Human•Life•Words•Thinker Voice in People Tweet 世界的平和への道をつくるプロセスのヒントになる話 を収録 これまでに戦争と平和を巡る人類の救済への道を探り示してきた先人たちと現代を生きるその先導者たちの埋もれた提言を発掘し、ここに集約していく。 人間は、平和な世界を作るための方法などの多くのヒントを既に沢山示してきている。 我々は、それらの世界中に埋もれてしまっている提言を世界に発信していないだけなのだ。 ここに、発掘する文章の多くは、人類の平和への道を導き出す為の方法や優れた提言などに重点を置いて平和な世界を創造していく為のヒントになるものを中心に載せている。世界の平和への道を作り出す為に、これらの話を寄り合わせ、共通して見出される平和への方法をここから編み出していって欲しい。 Human Nature とは、自然の一部である人間を見出す言葉である。人間は、自然の一部の部分に過ぎない存在だが、それは同時に、宇宙という全体そのものでもあるという循環する存在を示したものである。 人々が世界の中に表出させながら埋もれさせてしまっている導く力を秘めた言葉をここに発掘し、幸せな世界への光として再び発信することで、これを読む一人一人の人々が自ら現代を生きる未来への道を創造していって欲しい。 juneabeppo(@ChuChu♪) 全記事の一覧は【Archives】をクリックすると一覧が表示されます。 Human Nature: アーカイブ - https://juneabeppo.tumblr.com/archive
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
「ポピュリズムとポピュラリズム──トランプとスペインのポデモスは似ているのか」
2016年11月16日 Yahoo!
米大統領選の結果を受け、スペインでは、ポデモスのパブロ・イグレシアス党首とドナルド・トランプを比較する人々が出て来たので、イグレシアスはこれに憤慨し、「ポピュリストとはアウトサイダー���ことであり、似たようなメソッドを使うことはあるものの、それは右翼でも、左翼でもあり得るし、ウルトラ・リベラルの場合も、保護主義者の場合もある」と主張していると『エル・バイス』(El Pais)紙が伝えている。
ポピュラリズムとは大衆迎合主義なのか
パブロ・イグレシアスは、「ポピュリスト」の概念についてこう語っている。
ポピュラリズムとは、イデオロギーでも一連の政策でもない。「アウトサイド」から政治を構築するやり方のことであり、それは政治が危機に瀕した時節に拡大してくる。
ポピュラリズムは政治的選択を定義するものではない。政治的時節を定義するものだ。
(『エル・バイス』2016年11月11日)
スペインは今年(2016年)6月に再総選挙を行ったが、昨年末の総選挙同様に議席が二大政党と新興二党に分裂したまま政権樹立に至らなかった。その上、最大野党の社会労働党が内部クーデターが起きるなどしてゴタつき、ラホイ首相続投の是非を問う信任投票で棄権したため、結局は国民党が政権に返り咲いている。イグレシアスは社会労働党のふがいなさを激しく非難しており、ポデモスは野党第一党になる黄金のチャンスを掴んでいるとも報告されている。「妥協をしながら国家制度のかなで地位を確立するポデモス」と「左派ポピュリズムとしてのポデモス」との折り合いをどうつけるかという以前からあった問題が、いよいよ切実なものになってきたようだ。イグレシアスはこう言っている。
これからの数カ月、議論しなければならないのは、ポデモスはポピュリストのムーヴメントとして存在し続けるべきか否かということだ。 (同前)
「ポピュリズム」という言葉は、日本では「大衆迎合主義」と訳されたりして頭ごなしに悪いもののように言われがちだが、Oxford Learner's Dictionaries のサイトに行くと、「庶民の意見や願いを代表することを標榜する政治のタイプ」とシンプルに書かれている。一九世紀末に米国で農民たちの蜂起から生まれた政党の名前がポピュリスト(人民党)だった。これは populace に由来する言葉だ。一方、 popular から派生したポピュラリズムは最近よく政治記事で使われるようになってきた言葉だが、昔から音楽関係の英文記事を読んでいる人は目にしたことがあると思う。クラシックに大衆音楽の要素を混入したり、インデ���ー系の知る人ぞ知るアーティストがポップアルバムを出したりするときに、評論家たちは「ポピュラリズム」と呼んできた。
「ポピュリズムの行き過ぎたものがポピュラリズム」という解釈もあるが、ポピュリズムは大前提として「下側」(イグレシアス風に言えば「アウトサイド」)の政治勢力たらんとすることで、テレビに出ている有名なタレントを選挙に出馬させたりする手法は単なるポピュラリズム(大衆迎合主義)だ。そのタレントが下側(アウトサイド)の声を代表するつもりかどうかはわからないからである。
左派と地べたの乖離
EU離脱、米大統領選の結果を受けて、新たな左派ポピュリズムの必要性を説いているのは『ガーディアン』のオーウェン・ジョーンズだ。
「統計の数学を見れば低所得者がトランプ支持というのは間違い」という意見も出ているが、ジョーンズは年収三万ドル以下の最低所得者層に注目している。他の収入層では、2012年の大統領選と今回とでは、民主党、共和党ともに票数の増減パーセンテージは一桁台しか違わない。だが、年収三万ドル以下の最低所得層では、共和党が16%の票を伸ばしている(『ニューヨークタイムズ』2016年11月8日)。票数ではわずかにトランプ票がクリントン票に負けているものの、最低所得層では、前回は初の黒人大統領をこぞって支持した人々の多くが、今回はレイシスト的発言をするトランプに入れたのだ。英国でも、下層の街に暮らしていると、界隈の人々が(彼らなりの主義を曲げることなく)左から右に唐突にジャンプする感じは肌感覚でわかる。これを「何も考えていないバカたち」と左派は批判しがちだが、実はそう罵���せざるを得ないのは、彼らのことがわからないという事実にムカつくからではないだろうか。
ラディカルな左派のスタイルと文化は、大卒の若者(僕も含む)によって形成されることが多い。〔中略〕だが、その優先順位や、レトリックや、物の見方は、イングランドやフランスや米国の小さな町に住む年上のワーキングクラスの人々とは劇的に異なる。〔中略〕多様化したロンドンの街から、昔は工場が立ち並んでいた北部の街まで、左派がワーキングクラスのコミュニティに根差さないことには、かつては左派の支持者だった人々に響く言葉を語らなければ、そして、労働者階級の人々の価値観やゆいへの侮辱を取り除かなければ、左派に政治的な未来はない。
(『ガーディアン』2016年11月10日)
右派ポピュリズムを止められるのは左派ポピュリズムだけ?
『エル・バイス』は、ポデモスとトランプは三つのタイプの似たような支持者を獲得していると書いている。
一 グローバル危機の結果、負け犬にされたと感じている人々。
二 グローバリゼーションによって、自分たちの文化的、国家的アイデンティティが脅かされていると思う人々。
三 エスタブリッシュメントを罰したいと思っている人々。
「品がない」と言われるビジネスマンのトランプと、英語で言うならオックスフォードのような大学の教授だったイグレシアスが、同じ層を支持者に取り込むことに成功しているのは興味深い。
マドリード自治大学のマリアン・マルティネス=バスクナンは、ポデモスとトランプが相似ている点は「語りかけ」だと指摘する(『エル・バイス』2016年11月11日)。「トランプには理念があるわけではなく、彼の言葉は、ヘイトや、オバマ大統領が象徴するすべてへの反動に基づいています。人々の感情を弄び、極左や極右がするように、共通のアイデンティティを創出しようとします。問題は、人々の情熱がどのように利用されているかということなのです」と彼女は話している。
感情と言葉の側面については、英国のオーウェン・ジョーンズもこう書いている。
プログレッシヴな左派は、ファクトを並べて叫べば人々を説き伏せることができると信じている。だが人間は感情の動物だ。我々は感情的に突き動かされるストーリーを求めている。一方、クリントンの演説は、銀行幹部の役職に応募しようとしている人のように聞こえた。(略)左派も感情を動かすヴィジョンを伝えなけばならない。ただ事実を述べてわかってくれるだろうと期待しているだけでは、右派の勢いを鈍らせることも、プログレッシヴな勢力の連合も築けないとわかったのだから。
(『ガーディアン』2016年11月10日)
ポデモスの幹部たちは「右派ポピュリズムを止められるのは左派ポピュリズムだけ」と言ったベルギーの政治学者、シャンタル・ムフに影響を受けているという。『エル・バイス』によれば、スペインは欧州国としては珍しく、英国のナイジェル・ファラージのUKIPや、フランスのマリーヌ・ルペンの国民戦線のような右派ポピュリズムがまだ出現していない。
ちょっと希望の押しつけ過ぎではないかとも思うが、オーウェン・ジョーンズが「ポデモスが崩れたら欧州の左派に未来はない」と言うのも、右派ポピュリズムへの抑止力として機能している左派ポピュリズムが他に見あたらないからだろう。
『ヨーロッパ・コーリング・リターンズ──社会・政治時評クロニクル 2014-2021』ブレイディみかこ 著 岩波現代文庫 2021年11月12日発行
著者 ブレイディみかこ(Mikako Brady)
ライター・コラムニスト。1965年福岡市生まれ。1996年から英国ブライトン在住。2017年、『子どもたちの階級闘争──ブロークン・ブリテンの無料託児所から』���みすず書房)で新潮ドキュメント賞を受賞。2019年、『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社)で毎日出版文化賞特別賞、本屋大賞ノンフィクション本大賞などを受賞。『女たちのテロル』(岩波書店)、『ブロークン・ブリテンに聞け Listen to Broken Britain』(講談社)、『女たちのポリティクス──台頭する世界の女性政治家たち』(幻冬舎新書)、『他者の靴を履く──アナーキック・エンパシーのすすめ』(文藝春秋)など、著書多数。
1 note
·
View note
Text
『テクノロジーとロシアとファシズムの関係』
ティモシー・スナイダー(Timothy Snyder 歴史家)
インタビュー・編 吉成真由美
ティモシー・スナイダー(Timothy Snyder 歴史家)イエール大学教授(中東欧史、ホロコースト史)。著書に『ブラッドランド』『ブラックアース』『The Road to Unfreedom』(未翻訳)『暴政:20世紀の歴史に学ぶ20のレッスン』など。ハンナ・アーレント賞他受賞。
「最大の暴力は『考える』ことをせずに素直に指示に従ってしまう善良な一般人によって行われる」──ハンナ・アーレント(1906 - 1975 政治理論家)
人間は多種多様であるという事実を受け入れなければならない。人間であるためには、いろんなやり方があるものだ。完全なる独立を求めず、「快い相互依存」をしよう。完全なる独立には、幸福ではなく無意味な人生と想像���超えた退屈だけが待っている。──ジグムント・バウマン(ポーランド出身の社会学者)
ティモシー・スナイダーの『ブラッドランド──ヒトラーとスターリン、大虐殺の真実(上・下)』(2010年)と『ブラックアース──ホロコーストの歴史と警告(上・下)』(2015年)は、冷戦時代に「鉄のカーテン」でブロックされていた東欧側の膨大な資料に基づいて書かれたもので、世界中に衝撃を与えた。それによると1400万人に上る犠牲者を出したホロコースト(大虐殺)は、ドイツ国内でドイツ人によって行われたのではなく、ドイツ人が侵略する以前にソ連によって国家破壊が行われた東欧で、「市民権を失った人々」が殺され、しかも、ソ連のNKVD(スターリンの下でソ連の秘密警察や諜報機関を統括していた内務人民委員部)やドイツのSS(ヒトラー率いるナチ政権の武装親衛隊)のみならず、多くの地域住民によって大量殺戮が実行されたのだった。
そしてファシズムは、1920年代に当時のグローバル資本主義と共産主義へのアンチテーゼとして、イタリアで誕生したが、今日再び、世界各地でポピュリズムや極右政党の台頭が見られる。今後グローバリゼーションによって引き起こされた富の格差問題や難民問題を解決するため、そして福祉国家を建設するためという、当時とまったく同じ理由によって、ファシズムが台頭する可能性が大いにありはしないか。
スナイダーは、情報寡占大企業が支配するインタ���ネットが、ファシズムや暴政の温床になりつつあることを指摘して現代社会に警鐘を鳴らすとともに、リベラル派がとってきた「すべては意見の違い」で片づけてしまおうとする態度も鋭く批判し、民主主義を守り暴政を避けるための具体的な20のレッスンを提示している。
民主主義とは多数決のことかと思っていた、というような人も少なからずいるわけで、スナイダーは、民主主義の本質とは何か、私たちにとって大切なこと、重要なこととは一体なんなのか、という基本的な部分を、実にわかりやすく説明する。民主主義とは、「法の支配」のもと、何度も間違いを犯すことを可能にする制度であり、国家が「時間」を稼ぐためのシステムだからこそ、不完全であることを許容し、多様性を内包できて、社会が次第に安定していくのだと。
そして、全体主義やファシズムに流されないためには、基本的な考え方ができていればいいのであって、個々人の小さな踏みとどまる意志や真実を大事にしようとする小さな抵抗が、結果として大きな力をもつのだということを、期待させてもくれる���
インタビューは、オーストリアの、街中に音楽があふれるウィーン市にある「人間科学研究所 Das Institute fur die Wissenschaften vom Menschen (IWM)」の所長室で行われた。この研究所は、人文科学および社会科学の独立した高等研究所で、もともと東欧と西欧の学術交流、学術分野と社会との交流、ならびに学術的な研究などを目指して、オーストリア政府、ウィーン市、ポーランド政府、チェコ政府からの基金により、1982年に設立された。近年はヨーロッパやアメリカのみならず、アジアやグローバルサウス(南半球の発展途上国)へもその研究領域を広げてきており、毎年のべ100人くらいの研究者たちがここで研究に勤しんでいる、(2018年10月収録)
「テクノロジーとロシアとファシズムの関係」
●格差問題是正がファシズムにつながる理由
──ファシズムはしばしば他の権威主義と関連して認識されています。たとえば全体主義や、ナチズム、国粋主義、民族主義などですね。あなたはファシズムをどのようにとらえておられますか。
スナイダー ファシズムというのは基本的に、われわれは個々の人間ではなく、グループであり、一族であり、民族であり、種族であると考えます。ファシズムにおける政治��、「われわれには何が共通しているか」から始まるのではなく、「敵を選ぶ」というところから始まるのです。まず敵が誰であるかを認識するところから始まる。
さらにファシズムは、世界の現状やグローバリゼーションの影響などを見て、そこに「問題や課題がある」の考えるのではなく、誰かによる「陰謀の結果だ」のいうふうに考えます。政策によって解決すべき問題だととらえるのではなく、特定のグループによる攻撃の結果だととらえる。ファシズムとは政治形態の一つであり、グローバリゼーションへの対処の一方法でもあります。
そしてファシズムの基本には「神話」があります。「われわれの良識」と「世界の現実」を脇におしのけて、そこにできた空間に「神話」を押し込むのです。「われわれはグループとして互いによく似ていて、リーダーと神秘的な関係を結んでおり、われわれが『神話』を作り、それを変えていくことをリーダーが指導する」というストーリーですね。
──ファシズムは、1920年代にグローバル資本主義と共産主義へのアンチテーゼとしてイタリアで生まれたわけですが、そもそもイタリアのファシズムは、民族主義的なナチズムとは大きく異なっていて、強い政府の統制のもと、当時のグローバリゼーションによって引き起こされた富の格差を解消すべく、福祉国家の建設を目指して誕生したというふうに理解しています。
そうだとすると、今日の世界でも、「グローバリゼーションによって引き起こされた富の格差問題を解消するため」、そして「福祉国家を建設するため」というまったく同じ理由によって、ファシズムが台頭する可能性が大いにあるということになりませんか。
スナイダー それは実に興味深い質問です。イタリアをはじめとしてファシズムは、「富の再分配」を主眼に置いていました。ファシストたちが言ったのは、格差があるのはマイノリティのせ��だ、ユダヤ人のせいだと。だから再分配のための最良策は、国家による産業を立ち上げると同時に、他の人たちから富を奪うことだと。ファシズムには確かに「再分配」の概念が含まれていますし、資本主義の失敗もファシズム台頭の理由の一つです。
2008年(世界的な経済破綻)以降、確かに一般的に収入格差が広がって、人々は「自分の問題はメキシコ人や中国人やユダヤ人たちによって引き起こされたんだ」といった言説に惑わされてしまう傾向にあります。トランプ氏のような政治家は、こういった状況を都合よく利用して、たとえば「グローバリゼーションはプロセスの問題ではなく、人々の問題だ」と言うわけです。グローバリゼーションには顔があって、われわれはその顔をブーツで踏みつぶしてやるんだ、と。これが彼の政治観です。
トランプ氏もプーチン氏も1920年代、30年代のアイディアや手法、つまり嘘をばらまいたり「神話」を繰り返し唱えたりといった手法をとり入れていますが、違いは、彼らは「再分配」にはまったく興味がないということですね。この点は大きな違いです。プーチン氏やトランプ氏は、彼ら自身がオリガーク(寡頭財閥人)で、彼ら自身が大金持ちだということです。プーチン氏は本当の大金持ちですし、トランプ氏は大金持ちになりたい人です。彼らは「再分配」したい人たちではないし、するつもりもまったくない。そこが大きな違いですね。
●ポピュリズムは「法」や「体制」をなし崩しにする
──では、ポーランドやハンガリー、オーストリア、ドイツ、フランス、そしてアメリカでも、ポピュリズムや極右政党の台頭が見られます。これはファシズムにつながる現象ととらえて心配すべきなのでしょうか。
スナイダー 民主主義を大切にしたいから心配すべきですが、それよりも根本問題は、「一体われわれは何を望んでいるのか、何がなくなることを心配しているのか」という内容のほうです。
私自身は「法の支配」や「民主主義」「個人の権利」が摩減していくことを心配しています。ポピュリズムや権威主義、ファシズムは、これらの素晴らしいものをわれわれから奪ってしまうという理由で、大きな懸念材料です。
問題は、脅威や懸念材料については大いに話題にされるけれども、一体何が素晴らしいもので、何をわれわれは望んでいるのか、なぜそれらが素晴らしいのかという肝心な事柄について、深く議論したり考察したりしないというところにあります。
「ポピュリズム」が、人々に声を与えるという意味であれば、それはOKですが、「ポピュリズム」が、人々に嘘をばらまくことを意味するなら問題ですし、「ポピュリズム」が、「人々」という名のもとにシステムのルールを破壊することを意味するのであれば、最悪です。このことを私は心配しています。
ポピュリズムによって出てきたある人物が、「自分は人々の声の体現者である」と言いつのることによって、その人と人々との間にある「法」や「体制」といったものが意味不明を失っていき、それらは単なる障害物と化してしまって、それらが払拭されることにつながっていってしまう。これこそが危険であると思いますし、こうしてポピュリズムはある種のファシズムに変化していくのだと考えています。
──グローバル企業をコントロールして富の再分配をするためには、世界政府を作って制御していく必要があると考える経済学者たちもいます。それは人々にとって新たな脅威となる可能性も大きいわけで、それならむしろグローバル企業による寡頭支配のほうがまだましなのではないかという気もしてしまうのですが。
スナイダー 世界政府でもなくグローバル企業による寡頭支配でもない、別の方法はどうですか(笑)。
一つの解決法としては、「法」や「市場」を真剣にとらえるということです。
プーチン氏やトランプ氏が支配する世界では、市場は「法の支配」を免れますし、市場が「法の支配」をまったく受けないゾーンがいつくも存在します。オフショア(規則のみゆるい海外)の銀行口座やオフショアの企業、匿名の取引、といったものがトランプ氏を作ったのです。「作った」というのは、彼が金儲けをすることを可能にしたという意味であり、彼の世界観を形成したという意味でもあります。つまり「法」は冗談であり、金や権力のみが重要であるという考え方ですね。これはトランプ氏とプーチン氏に共通するもので、プーチン氏もそのように考えています。ロシア全体が、アメリカ資本主義の末端にあるグレーゾーン(合法か違法かスレスレの領域)部分に匹敵すると言ってもいいでしょう。
たとえばグローバル企業が、税金逃れをせずに、タックスヘイブン(租税回避値)を避けて、匿名の取引も行わない、という真っ当なやり方だってあるわけです。これは世界政府という方向ではありませんが、こうすることでオリガーキー(寡頭財閥)を制御することにもなる。なぜなら真の問題は、オリガーク(寡頭財閥人)たちが国の力を逃れていることにあるからです。そして、彼らが国の力を手にした場合、今度は自分たちが国の力から逃れられるようにもっていくために、その力を利用する。
プーチン氏はロシアの国をコントロールしていますが、それを何に使っているかというと、たとえば自分の友だちのチェロ奏者に20億ドルあげるために使っている。これは国のコントロールを逃れたものです。トランプ氏は国の力を手にしていますが、それを何に使っているかというと、自分が世界中にホテルを作るための資金調達に使っている。国の力から逃れるために国の力を利用している。ですから、問題の核心は、国々がどうやってこれを制御していくかということになります。
ロシアと中国問題
●ロシアは「前近代的」国家だ
──そのロシアですが、以前ロシアを「マフィア国家」だと言っておられましたが、ロシアはどういう観点から見てマフィア国家のなのでしょうか。
スナイダー 多くの人がそのフレーズを使ってきていますが、私自身はどちらかというと「オリガーキー(財閥による寡頭制)」というフレーズを使いたい。そのほうがギリシャ時代にさかのぼる歴史的な意味合いが含まれますから。古代の民主主義の議論では、オリガーキーというのは民主主義がうまく機能しなくなると台頭してきます。アリストテレスは、民主主義のリスクの一つとして、金持ちがそうでない階級を欺くために民主主義を使うこともあると言っていますが、現実にもそっくりそのまま当てはまりますね、
ロシアの特徴は、富が限られた人々に集中していて動かないという点にあります。そのために、ロシアには従来の意味での「法の支配」というものがありません。そのことをもって「マフィア国家」と表現するのであれば、そのとおりです。���法」が機能しないことと、社会的な流動性がないことが、ロシアの大きな特徴になります。
この場合、権力を握っている人々は、このやり方が唯一の方法なのだと市民を説得することでのみ、自分たちがサバイブしていくことができる。この部分が、マフィアという比喩では十分でなくなります。マフィアは、「他のやり方はない」というような説得はしませんね。ロシアのような国家は、他の選択肢はないと主張するわけです。力のある者が統治し、富める者が��治する。他のどこの国でもこれが自然の成り行きというものなのだから、現状に満足しなさいと説得するわけです。
──さらにリーダーは常に自分に対する「忠誠」を要求しますよね。
スナイダー まったくそのとおりです。「忠誠」の要求はトランプ氏とプーチン氏の大きな特徴でもあります。大事なのは「ルール(法)」ではなく個人的な「忠誠」であると。その点では確かにマフィアですが、一歩下がって見てみると、彼らのやり方は「前近代的」だという見方もできます。国家ができる以前の状態ですね。
国家ができる前は、一族というものがあった。一族の中では、特定個人に忠誠を誓うことが大事だったし、忠誠を誓った人たちは、さまざまな報酬が配られた。プーチン氏やトランプ氏には、こういうモデルが最もしっくりくるんですね。
しかし近代政治の歴史は、人々がこのモデルから抜け出すために努力して作り上げられてきたのです。一族のリーダーに忠誠を誓わなくともいいように、政治的にも経済的にも人々が自由に移動することができるようなプリンシプル(原理原則)を作り上げてきたのです。
──ちなみになぜロシアでは、性的指向(セクシュアル・オリエンテーション)の話題が大きな問題として取ませんとり上げられるのでしょうか。イワン・イリン(プーチンが信奉するロシア出身の哲学者、1883 - 1954)のファシスト的な哲学の影響があるからですか。
スナイダー イワン・イリンの影響はそれほど大きくないと思います。むしろ自分たちと彼らとを区別するいい方法だからでしょう。腐敗しているのは彼らのほうで、われわれは清く正しいということを強調するための方便ですね。もちろんファシズムとも関連しています。ファシズムは非常にはっきりとした男女の役割を提示しますから、とくに現代ロシアの男性的なものに対する崇拝という気運ともしっくり合っているからですね。
●ロシアにとっての本当の威厳は中国だ
──プーチン氏の「ユーラシア経済連合」構想は、ロシアがユーラシア全体のリーダーとなり、中心となるべきだと提案しています。ロシアの「ユーラシア経済連合」構想と中国の「一帯一路」構想とは、双方ともスケールの大きなものですが、どのように対照して見ておられますか。
スナイダー 私自身は中国よりもロシアについてよりよく知っていますが、両者の主な違いは、中国には、自国のパワーを広げていくための、影響力を増していくための、ある種のプランがあるように見えます。対してロシアには、自国のパワーを広げていくためのプランはないですね。ロシアのプランは、他国のパワーを下げることです。ヨーロッパを弱くすることで、ドイツやフランスの力を弱くすることです。自国を強くするより、西側の国々の力を現在よりも弱めたい。
両者の構想をつき合わせて見てみると、明らかなのは、ロシアがやろうとしているのは地政学的な自殺だということです。なぜなら、長期的にはロシアにとっての本当の問題は、フィンランドでもスイスでもスペインでもなくて、中国だからです。ロシアは、西欧の力を弱めようとしているわけで、いちばん自分たちの味方になる可能性がある国々を攻撃しようとしていることになります。
西欧の力を弱くするというのは、自分たちのエゴを満足させます。だからそうしているわけで、気分のいい派手な騒ぎを起こすことになるし、自分たちの権力を正当化させることになるし、自分たちに力があるように感じることができるし、市民に自分たちの力を宣伝することにもなる。シリアを爆撃したりウクライナを侵略したり、アメリカの大統領選挙を攪乱すれば、自分たちはスーパーパワーであると感じることもできる。しかし実際には、墓穴を掘っているようなものです。
ロシア国家がサバイブしていくためには、西欧と中国とのバランスをとることが必須になりますから、西欧を攻撃することは、このバランスを自ら崩すことになってしまいます。ロシアのやり方は、一人の終身独裁者のために短期的な勝利を求めている、ということですね。
中国のほうは、ある経済政策を展開して、長期的にはロシアを追い詰めることを狙っているとも言えるでしょうし、確実に彼らはそうするでしょうね。そこが大きな違いです。
──中国のどのような点が、ロシアにとって深刻な脅威なのでしょうか。
スナイダー むしろ中国がロシアにとって脅威でない点があるだろうか、というくらいですよね。
人口統計を見ても、ロシアの人口(約1億4400万人)に対して、中国は桁違いに多い(14億人)。投資額を見ても、中国のほうがロシアよりも多くシベリアに投資しています。資源の点では、中国は天然ガスと水が必要ですし、将来的には食料も必要になるでしょう。ロシアにはそれらがすべてあります。現時点では、中国はロシアのエリートたちを買収することでこれらを手に入れていますが、将来的には中国は別の方法でこれらを入手することになるかもしれない。ロシアのエリートを買収するのか、直接奪取するのか、あるいはロシアの南側にある国々を中国側につけることによって入手するのかはわかりませんが、中国は確実に資源獲得に乗り出してくるわけです。
西欧はロシアにとって実際には、痛くもかゆくもないフェイクな敵であって、本当の脅威は中国なのです。
「テクノユートピア」と民主主義
●嘘は、人々から抵抗力を奪う
──カリフォルニア大学バークレー校の人類学者アレクセイ・ユルチャクは、1950年代から80年代の終わりにかけてのソ連社会の状況を、「ハイパー・ノーマリゼーション」と呼んでいます。システムが機能していないことを誰もが知っているにもかかわらず、代案を思いつかないので、政治家も市民もシステムが機能しているという嘘を信じるようになり、社会に嘘が蔓延して、人々が嘘に慣れてしまうという状況です。
社会に嘘が蔓延していると、一体何が本当で、何が嘘なのかがまったくわからなくなってしまうので、人々は抵抗する意欲そのものを失ってしまいます。この「嘘をばらまく」という手法は、ロシア政府がコントロール手法として、自国内のみならず世界中で実行しているやり方なのでしょうか。
スナイダー そのとおりです。しかも、おっしゃるように特定の嘘をばらまくだけではなく、すべての人々を常に不信感で満たすというやり方です。そして、確実な事柄なんてあるんだろうか、という疑いの気持ちを人々に植えつける。
不信感をぬぐえない場合、人々は家にこもる。私はこれを「カウチ(長椅子)ファシズム」と呼んでいます。旧来のファシズムでは、外に出て行進しなければならなかったけれども、プーチン氏もトランプ氏も人々に行進などしてもらいたくはない。
それよりもむしろ家にこもって、「ホントかどうかちょっとわからない。嘘かもしれない。だからテレビを見てみよう、インターネットを見てみよう」となる。そういう状況にもっていければ、彼らの勝ちです。
旧来のファシズムでは、真実を払拭して生まれた空間に「神話」を押し込むわけですが、この場合の「神話」とは、「この土地を侵略すべきだ」といったような具体的な行動を伴うものでした。現在のそれは、「何も真実ではない、だから何も行動すべきではない」というものに変わっています。われわれがすべてのお金を獲得して、われわれのやりたいようにやるから、あなた方は家にこもっていなさい、と。確かにこれは非常に効果的な策略で、使っているほうは、その効果を十分に承知しながら使っています。
では、これに対抗する唯一の方法は何か。それはつまり、
「知識は重要だ」
「確認できる事実はある」
「事実は大事だ」
という倫理的な立場をしっかり認識することです。
われわれは自己防衛のために消極的な態度をとってきていて、それは確実に権威主義を下支えすることになっています。すべては単なる意見の違いだとか、あなたの意見も私の意見も両方ともいい、と言ってしまう。地球は平らだ──いや丸い、チョコレートは甘い──いやレモンのようだ、など、(明らかに事実と違っていることでも)みんなさまざまな意見をもっているんだ、ということで放っておく。リベラルな人たちや左側の人たちは、現実の世界というものに無関心で、事実をしっかりと確認することから逃げてきた。一方で、金持ちやメディア操作に長けている人たちが、こういった態度を利用して、リベラルを攻撃することに用いてきたのです。
ですからここで今一度古いやり方に戻って、事実を見つめ、現実をしっかりと手中に取り戻さなければならないと考えています。
●完全な「透明さ」とは全体主義のこと
──これらを踏まえて、インターネットについて伺いたいと思います。
IT産業に携わっている人たちは、テクノロジーは個人の力を増して、分散型社会をもたらし、それによって世界はより安全に、より透明に、そしてより民主的になっていくと言います。「テクノユートピア」と呼ばれる考え方です。彼らによると、より多くの人々がソーシャル・ネットワークを使ってつながり合うことで、恐怖や、外国人恐怖症、偏見、差別といったことから解放されていくと言います。
しかし現実には、インターネットは個人ではなく、ますますもってごく少数の大規模情報企業やプラットフォーム会社によってコントロールされていますし、マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究者が行った大規模なツイッターアカウント追跡調査結果によると、インターネット上では、嘘は真実より70%もリツイートされる可能性が高く、6倍も速く広く深く伝わることが明らかにされました(Science, March 8, 2018)。
しかも、インターネットの普及率は2006年の20%から、2018年には50%まで上がっているのですが(Statista:Global internet access rate 2005-2018)、ポピュリズムの人気も2000年には8%だったものが2018年には25%まで上がっていて(Milken Institute Symposium, Europe: Past Tense, Future Perfect?, July, 2018, Yascha Mounk [ハーバード大学]の発言)、インターネットの普及が必ずしも民主主義を下支えすることになっていないわけです。
あなたは「情報の分野で成功した人たちは、むしろナイーブな世界観をもっている」(Big Think, Sept 18, 2018)とおっしゃっています。
スナイダー つまり「なぜ『ナイーブ』という表現を使って、『悪徳 sinister』という表現を使わなかったのか」という質問ですか(笑)?
確かに初期のころは「ナイーブ」な人たちもいました。インターネットはできるだけ自由にしておいて、広告費で運営するという形でいいと無邪気に考えていたまじめな「リバタリアン(個人的な自由と経済的自由を求める、自由至上主義者)」たちがいたのも確かです。
ただ、ある時期を越えたら、たとえば最初の10億ドルを稼いだ後は、もはや無邪気であるとは言えませんね。若いころそのように考えていて、ソーシャル・プラットフォームを立ち上げ、世界で屈指の金持ちになったら、もはや「ナイーブ」とは言えない。その時点ですでに「悪徳」です。「善良さ」を偽った悪徳ですね。あるいは「オプティミスト(楽観主義者)」を装った「悪徳」です。
インターネットの��題としてあなたがあげたことはすべてそのとおりです。インターネットの根本問題は、「透明さ」が必ずしも良いとは限らないという点です。われわれが自由であるためには、自分の一部はプライベートでなければならない。(集団としてではない)自分自身の夢をもっていなければならないし、自分の行動や性質のパターンは自分のものでなければならないし、人間関係の一部は外から覗いただけでは理解できないようなものでなければならない。
完全な「透明さ」とはすなわち全体主義のことです。全体主義とは、パブリックな部分とプライベートな部分の区別がないという意味です。「自由」が存在するためには、プライベートとパブリックの区別が存在していなければならない。ですから、社会のすべてが、「透明になる」というのは恐ろしい予測です。ロシアのどこかにあるマシーンが私の脳の化学変化を分析するというのは、考えただかでも恐ろしいシナリオです。でもわれわれは他人のプライベートライフについては興味があるので、このシナリオに乗ってしまう。そうすると結局、自分たちのプライベートライフも、よく考えずに公開してしまうことになる。これが「透明になる」ということが意味するものです。
もう一つあなたがあげた「恐怖」は、重要なポイントです。ソーシャル・プラットフォームは、何がわれわれを不安にさせるのか、何がわれわれに恐怖を感じさせるのかということを探知するのに長けています。しかもそれを使って、ますますわれわれを不安や恐怖に陥れ、インターネットにより多くの時間を使って広告を目にするよう仕向ける。そうなるとわれわれは、ある意味で自分自身のパロディ(滑稽な分身)と化してしまうのです。
私の知っている人たちがそうなってしまったのを、この目で見ています。あなたもおそらくそういう人を身近に知っているでしょう。かなり複雑で深い世界観をもっていた人たちが、ある種の恐怖にからめとられてからは、それがますます重要なことになって、そればかり話題にするようになってしまった。それがインターネットがもたらす影響なのです。
さらに根本的なことを言えば、「インターネットは人間ではない」ということです(笑)。
インターネットはそのほとんどがアルゴリズム、つまりコンピューター・プログラムなわけですね。そしてこれは誰も言わないけれども、非常に本質的な点なのですが、「インターネットはわれわれのことを親身になって心配していない」ということです。全然、まったく(笑)。
インターネットは、海や宇宙がわれわれのことを心配してなどいないように、まったくもって気にかけていない。子猫や、子犬が画面に現れて、一見親しみやすそうに見えますが、プログラムはわれわれのことなどまったく無関心なわけです。
──確かに非常に興味深い点です。
●インターネットはスパイの温床になる
──では、インターネット上で行われている、サイバー戦争についてはどうですか。アメリカは2016年のサイバー戦争でロシアに完敗したということですが、その原因はテクノロジーと人々の生活の関係が変わったために、ロシアの諜報機関が得意とするいわゆる「積極工作 active measures(さまざまな心理操作やメディア操作により、敵を攪乱・分断・崩壊させることを目的とした諜報活動)」の活動員たちに、大きなアドバンテージを与えることになったからだというものです。でもこのやり方は、アメリカの諜報機関がずっと世界中で行ってきたことではないですか。なぜロシアにとくにアドバンテージがあるとお考えですか。
スナイダー まず言っておきたいのは、ロシアがアメリカの大統領選挙で勝利したという本を読んだからといって、それでわれわれ(アメリカ人)のほうは無実だと言いたいわけではありません。私自身が最も嫌うものの一つは、「自分たちは何も悪いことはしていない、相手がひどいことをしただけだ」というような「無実」についての主張や議論です。もちろんアメリカも他の国の選挙に干渉してきました。これはひどいことです。どこの国であろうと、他国のみ選挙に干渉するのは倫理的にやってはいけないことです。だから、アメリカが中南米の国々の選挙に干渉するのは、ひどいことですし、ロシアがアメリカの選挙に干渉するのも、ひどいことです。一市民として、これらは忌避すべきことであると考えています。
こう前置きしたうえで、2016年のアメリカ大統領選挙へのロシアの干渉についてですが、特筆すべきなのは、われわれのオープンかつナイーブなインターネットに対する態度というものが、おっしゃったような旧来の諜報活動メカニズムが働くための大きな通路をひらいたということです。
「積極工作」という旧来の手法は、まずあなたの心理についてよく研究して、それを今度はあなたを陥れるために利用する、というものです。一見良さそうに見えるけれども、よく考えてみたらあなたにとっては不利なことだったというような結果を招くわけです。
ただこの「積極工作」を、従来のように人間同士の間で実行するのは容易なことではありません。人間同士の関係性を築いて、最終的にはあなたが夢にも思わなかったようなことをあなたにさせるようにもっていく。非常に難しいことですね。ところがテクノロジーをもってすれば、これがかなり容易くなるのです。スケールを大きくすることでこれが実行できるようになってしまう。
もし現実世界で「積極工作」をあなたに仕掛けようとするなら、いろいろな周囲の人間関係を巻き込んで、さまざまなシナリオを築き上げなければならないわけで、それらをすべてが破綻しないようにもっていくのは至難の業です。
ところが、この「積極工作」の対象が、あなた個人ではなく1億4000万人(フェイスブックを通じてロシアのプロパガンダに接した人の数)以上のアメリカ人ということになると、このスケールの大きさを利用して、これらの人々に働きかけることになります。そうなると、すべての人々を説得する必要はまったくなくて、その中のごく一部の人々を説得して自分たちの望む方向に誘導すればいい。それだけで選挙結果を左右して、自分たちに都合のいい勝利をもたらすことができるのです。
そしてこれは重要な点ですが、その際彼らが私を「信用する」必要などまったくないのです。
従来の「積極工作」の場合、あなたが工作員を信用する必要があります。「あなたに自分の利益に反する行動をとらせる」という最終目的に達するまでのシナリオを、あなたがすべて信用しないことには成り立たないからです。
ところがコンピュータの場合、人々はなぜかコンピュータを信用してしまうんですね。
自分で作ったものでもないのに、自分のコンピュータだと思ってしまう。インターネットも自分のものだと勘違いしてしまう。しかも画面上に出てくるウェブサイトは、自分がそれを選択しているのだと錯覚する。実際には彼ら自身が選択したものではなくて、広告会社や宣伝目的で雇われたひとが、ユーザーの性向や嗜好をフォローして、あらかじめより分けて提供しているのです。
ロシアはフェイスブックを通して、あなたの好みを把握すると同時に、それらを使って人々をある方向に誘導し、社会を攪乱・分断させた。これが実際に起こったことです。
テクノロジーは、悪意をもってわれわれを操作しようとする人々の前に、われわれを容赦なく裸でさらしたのです。今後はこれを教訓として、国家のみならず個人のレベルでも、こういった操作に容易に引っかからないようになることを願っています。
──確かに私たちはインターネットに対して非常にナイーブで、もたらす結果の重要性をあまり考えずに、自分たちを簡単にネット上にオープンにしてしまいます。
スナイダー そうです。
すべての国は長所と短所を備えているわけで、アメリカはどちらかというと相手をすぐ信用する「高信用社会」ですね。アメリカ人がある領域で素晴らしい能力を発揮するのは、あるレベルの相手をすすんで信用するという性質があるから。ロシアとは異なります。ロシアは相手をなかなか信用しない「低信用社会」です。
アメリカでは、自分とある程度似ている他の人を信用する傾向があって、それがビジネスに役立ってきたのです。ロシアはインターネット上に、アメリカ人が自分たちと似た人たちがいると錯覚するようなサイトをたくさんでっち上げた。もっぱらアメリカ人をターゲットにして、彼らの興味や嗜好に合わせて別々のサイトを用意しました。黒人用のサイト、白人至上主義者用のサイト、南部の人たち用のサイトをそれぞれ作って、彼らが自分たちと似たような人たちとコミュニケーションしているんだと錯覚するように操作した。だから人々はそれらに引っかかったのです。
これはバカだったとしか言いようがありません。アメリカ人にとっていちばん難しいのは、自分たちが騙されたことを正直に認めることです。誤りを犯した、インターネットに騙された、ロシア政府に一杯食わされた、と素直に認めるのが本当に難しい。だからそうする代わりに、これはロシアがやったことではなくて、自分がこれを信用して選んだんだ、というふうに自己納得させようとします。
これはアメリカ人に限ったことではありません。われわれは誰もが、インターネット上で騙された経験をもっているはずです。まずそれを認めることが重要です。
最悪の暴力と「良い不完全」
●市民ではなくなった時に、最悪の悲劇が起こる
──ご著書について少し質問させてください。
『ブラッドランド』と『ブラックアース』は、これまでのホロコースト観を大きく変えるインパクトをもたらしました。
まず「1933年から1945年の間に、バルト海と黒海の間そしてベルリンとモスクワとの間の地域で、約1400万人の人々が意図的に殺害された」わけですが、ご著書によると、次のような一般に知られていなかった点を指摘されています。
①「反ユダヤ主義」が戦争の主な原因ではなく、食料を確保するために農耕地を求めたことが主理由であって、当時の食料は現在の石油のような重要性をもっていた。
②ホロコーストは、ドイツ人国内でドイツ人によって行われたのではなく、むしろドイツ人が侵略する以前にソ連によって大規模な侵略殺害が行われた東ヨーロッパの地域でこそ、主に実行に移された。
③大量殺害は、ソ連のNKVDやドイツのSSによって行われたのみならず、多くの地域住民によって実行された。彼らは自らサバイバルを懸けて、ドイツのために働く以前はソ連のために働いていた。
これらを踏まえて、なぜある国々ではユダヤ人はほぼ生き残って、別の国々ではその多くが殺されてしまうことになったのか *1、お話しいただけますか。
*1 エストニアでは99%のユダヤ人が殺され、オランダでも75%のユダヤ人が殺されたが、デンマークでは親ナチ政権だったにもかかわらず99%のユダヤ人が生き残り、フランスでも75%のユダヤ人が生き残った。
スナイダー 『ブラッドランド』では、誰がどこで死んだのかを記録しようとしました。「ホロコースト」には地理部分が欠落していましたから、一体どこでユダヤ人たちが死んだのかを検証したわけです。そして、ユダヤ人たちが死んだ地域では、他の東たちも何百万という単位で死んでいった。その背景には理由があるはずだと考えたんですね。
たとえば、ドイツもソ連も(食料確保の目的のために)肥沃なウクライナに大いに関心があった。ウクライナには多くのユダヤ人が住んでいて、ドイツがウクライナに侵攻するには、さらに多くのユダヤ人たちが住んでいたポーランド領域を通る必要があった。
私の論点は、ヒトラーはユダヤ人を最終的な敵として見ていたけれども、実際に戦争を始めるまでは、彼らを殺害するには至らなかった。で、その戦争はウクライナの領地をめぐってのものでした。ですから二つの事柄が同時に起きたことになります。ドイツは食料確保のためにある他国の領地をコントロールしようとしたけれども、その領地にはたまたま多くのユダヤ人が住んでいた。戦争がひどくなっていくに従って、次第に領地のコントロールよりも、ユダヤ人殺害そのものが目的となっていった、ということです。
『ブラックアース』で言いたかったのは、人々を殺害するための条件を整えようとする場合、最初に行われるのは、インスティテューション(国家や組織といった体制)をとり除いてしまうことです。権威主義や国家主義というものは、それだけでは大量殺戮には直接つながらないということを言いたかった。大量殺戮とは、別の国がもっている権力を払拭することで、まず人々を一挙に脆弱にし、その後で国家権力を行使する形で行われるのです。
これは少し説明がいります。われわれは、強い国家権力はその市民を虐げると思いがちですね。それもそのとおりで、たとえば現在中国は、実際ウイグル人のイスラム教市民を抑圧し、彼らをキャンプに収容していますし、ミャンマーでも、イスラム教市民が抑圧されている。これらは強力な国家権力が、自国市民を抑圧している例です。ですから、そういうことも確かに起こります。
しかし最悪の暴力とは、ある国家が別の国家の領地に侵入していって、その領地そして国家を破壊したうえで行使される時のものです。このやり方がヨーロッパにおける帝国主義の全歴史です。ドイツが、ここにはポーランドは存在しない、ソ連も存在しない、だからこの土地にいる人々をどうしようとまったく構わないのだと宣言した、そういう条件がそろった状況で初めて、ユダヤ人の大量殺害が可能になったのです。
ある国はもはや存在しない、とドイツが宣言した地域においてはユダヤ人の大量殺戮が実行されたけれども、ドイツの同盟国では、多くのユダヤ人が生き残った。そういう国が、たとえ権威主義国家や、極右支配国家や、親ナチ国家だったとしても、国家権力が自国の市民を殺害するとなると、これは一挙に難しくなるからです。
つまり、国家がある国によって破壊されると、別の国がその地域を蹂躙してホロコーストを始めることを促進することになる。二度の侵略を受けた地域では、ユダヤ人は非常に高い確率で消滅していった一方、国家が存続していたところに住んでいたユダヤ人は、高い確率で生き残ったのです。
──ヒトラーとスターリンは、両者とも領地と食料を求めて戦争をしていたわけですが、どういった点が大きく異なっていたのでしょうか。
スナイダー 二人は似たところがありました。グローバリゼーションに対処するアイディアというものをもっていた点、一党独裁で国家を運営していくことが可能だと考えていた点、そして両者ともあらゆることを、つまり歴史や時間というものを加速度的に進めようとした点。
違いは、スターリンの敵は資本主義でしたが、ヒトラーは民族ということに焦点を絞っていて、ユダヤ人による陰謀ということを考えていた。とくに30~40年代、スターリンは大きな領域をコントロールしようとしたのに対し、ヒトラーは大きな領域を変えようとしていた。そしてスターリンは自国領の末端部分の人々を殺したけれども、ヒトラーはポーランドとソ連と戦争をしながら、その領域で主に殺戮を行ったわけです。
●「われわれ VS 彼ら」という対立構図を避けよう
──ナチ党の主要指導者の一人であったヘルマン・ゲーリングは、こう言っています。
「もちろん人々は誰も戦争などしたくはない。しかし、政策決定するのは国の指導者たちなのであって、それが民主主義だろうとファシスト独裁主義だろうと議会制だろうと共産主義独裁だろうとまったく関係なく、人々を(戦争に)同意させるのはいつも簡単なこと��のだ。単に、われわれは攻撃されたんだと言いふらし、平和主義者たちを、国に危機をもたらす愛国心を欠いた卑怯者だと言って貶めればいいだけのことだ。どの国でもこの方法は必ずうまくいく」(Nuremberg Diary, Gustave Gilbert, 1947)
つまり、人々の「生き残り本能」を刺激すれば、彼らの意見や意志を変えることなど朝飯前だというわけです。確かに9・11後のアメリカで、2003年にイラク戦争を始める際には、この方法が効力を発揮しました。
このような落とし穴に落ちないようにするには、どうしたらいいのでしょうか。
スナイダー まず初めに、いかなる場合でも「われわれ VS 彼ら」という対立構図を作る政治のやり方は大いに危険であると、常に意識していることが大事ですね。確かにありとあらゆるシステムでこの(ゲーリングが指摘した)やり方が可能ですが、その効果には差があって、この方法が容易く実行できてしまうシステムと、そうでないシステムもあります。
市民権が弱く、報道機関が脆弱な国ほど、この手法が効果を発揮する。たとえば今日のアメリカでは、トランプ氏は、メキシコや中国への過激発言をすることで、かなり多くの人々を煽動することができますが、すべての人々を動かすことはできないし、明日メキシコを侵略するぞと宣言しても、すぐにそれに対する強力な不支持に突き当たることになります。
ですから、ゲーリングの言っていることはある程度正しいのですが、いつも必ず効力を発揮するとは限りません。肝心なのは、「われわれ VS 彼ら」という対立思考に代わるものとして、一体どのような考えを人々の中に広めていったらいいのか、という点ですね。これは先ほど話に出た「事実を探求すること」につながります。事実の探求は、「われわれ VS 彼ら」という単純な対立構図をずっと複雑なものにします。
それと、「ポジティブで倫理的な民主主義」とはどういうものかということを、積極的に考えてみることが大事です。民主主義とは、単にわれわれがもっている制度だというふうにとらえるのではなく、政党や労働組合やさまざまな組織を通じて人々を社会的につなげる制度であるととらえる。そうすることによって、状況は複雑になり、人々が「われわれ VS 彼ら」という単純な構図をとりにくくするわけです。もしメキシコ人が同じ労働組合や教会のメンバーだったら、それだけですでに、われわれが善いほうで彼らが悪いほうだという「われわれ VS 彼ら」という区別をするのを少しためらうでしょう。
加えて、権力の分散が重要です。トランプ氏は、もし彼自身が指さすだけで、ある国や地域を侵略することができるのだったら、大喜びでしょう。ホワイトハウスで働く人たちが証言していることですが、トランプ氏は、実際にそうしようとしたことがすでに何度もあるようですね。そうさせないよう彼を説得したと。権力の分散は、大統領でさえそれによって制約されることを意味します。メキシコの例に戻るならば、もしトランプ氏が実際にメキシコを侵略しようとしても、現在の分断した米国議会でさえ、(共和党と民主党が)そろって阻止しようとするでしょうし、他の公的機関も阻止するでしょう。
ゲーリングの言ったことはそのとおりです。これはいつの時代でも起こりうることですし、その傾向はいつの時代にもあります。大事なのは、われわれは、社会が多様性を包容できるようにもっていくことができるのか、社会がプロパガンダに対して懐疑的になるようにもっていくことができるのか、ということですね。
●国家はサイエンスに投資すべきだ
──『ブラックアース』の結論部分で、「ホロコーストを理解することは、おそらく人類存続のための最後のチャンスになるだろう。••••••国家というものは、将来について冷静に思考するためにサイエンスに投資すべきだ。時間が思考を支え、思考が時間を支える。構造が多様性を支え、多様性が構造を支える」と書かれていますが、「ホロコースト」はどのような新たなレッスン(教訓)を今日の世界に提供できるのでしょうか。また、国家はなぜサイエンスに投資するべきなのか、お話しいただけますか。
スナイダー あの本は2014年に書いたものですが、未来をわれわれ自身の手でなんとかしなければならないという強い思いがあって、将来、気候変動問題がさらに深刻化して、資源確保をめぐっての競争が激しくなり、食料や水、領地をめぐって、人々の恐怖意識と闘争意識が高まっていって、「われわれ VS 彼ら」という対立が際立ってくるだろうという危機感がありました。
未来を考えるにあたって、二つのやり方があります。まず、ヒトラーが言ったように未来とは「避けられない闘争」であると考えるのか、それとも「われわれ人間は理性的に世界をとらえて、道具を創造し、それらの道具が時間を生み出すことを可能にする。それによって将来の悪いシナリオを避けることが可能となり、2年、5年、10年、20年という時間がわれわれに与えられ、子どもを作って、その彼らにも未来があるのだと想像することを可能にする」と考えるのか、ということです。
これまであまり注意が払われてこなかったのですが、この本で指摘したかったのは、ヒトラーがサイエンスに反対していたという点です。ヒトラーは「サイエンスが未来を作るというのは、ユダヤ人が生み出した幻想だ。テクノロジーは使えるかもしれないが、それによって『われわれ人間は闘争する存在だ』という原理原則が揺らぐようなことはない」のだと言っていました。
サイエンスは重要です。それは歴史と同じく、原因と結果についての研究で、そこには過去と現在と未来という軸があります。サイエンスは、われわれ人間に未来というものを期待させてくれるから重要なのです。
もしサイエンスを支持するのであれば、そこには原因と結果があると認識することになる。現在の状況には過去の決断の影響があると認めることになり、現在のわれわれの決断が未来に影響を与えるということを認めることになります。サイエンスは多くの事柄の基本です。
現アメリカ大統領と行政府は、サイエンスと人文科学の両方に対して非常に敵対する態度をとっています。人文科学はどこに問題があるかを指摘し、サイエンスがそれをどのようにして解決するかを提示するのですが、現行政府は(問題を解決するどころか)次々と新たな問題を生み出しているというのが現状です。
●民主主義は時間を稼ぐ
──では、その大統領を選出した民主主義についてですが、「最も不完全な民主主義でも、最も完全な独裁主義よりまだはるかにましだ」と言う人もいますが、賛同されますか。
また、「民主主義とは、何度も間違いを犯すことを可能にする制度であり、国家が『時間』を稼ぐためのシステムだ」とおっしゃっていますが、なぜ繰り返しやり直すことができることがそれほど重要なのでしょうか。
スナイダー これは世界を基本的にどうとらえるかということと関係しています。
私自身は「完全(パーフェクト)な独裁主義」などありえないと考えます。なぜならパーフェクトな独裁者など存在しないからです。いちばんいい時でも、われわれは誰一人としてパーフェクトではありえない。完全な独裁主義がありえない理由は、世界全体を把握するアイディアというようなものは、決して作りえないからです。そのような完全さはありえない。
われわれに必要なのは、「良い不完全」というものです。あなたも私も、誰もがしばしば間違いを犯すのであって、あなたの倫理観と私のそれとは異なっていて、一致してはいないということを、オープンに言うことができるシステムです。どのようなシステムが、ひどい犠牲を払わずに「不完全」であることを許容できるのか。自分とは倫理観の異なる人たちを踏みつぶすことなく、自分の倫理観を表現できるのか。実はこれらこそ「民主主義」や「多元主義」が可能にしている事柄なのです。
これらのシステムでは、われわれは自分を表現することができて、勝つこともあれば負けることもあるし、自分の倫理観に基づいて投票することはできても、ほとんどの場合、自分の意見を他人に強要することはできません。世界が不完全だからこそ、「民主主義」が良いシステムなのです。
良い民主主義のもとでは、多様性というものが祝福されます。あなたと私とは常に異なる人格をもった人間だという認識、個人主義というものが祝福される。これはいいことです。ある特定の人物があなたや私を完全に代表することはできません。(たとえば国家といった)インスティテューションこそが、多様性を許し、表現の自由を許すのです。だから民主主義が良いシステムなのです。
そらから、神でない限り、いかなる独裁者も必ず死にます。そのことだけでも完全な独裁者というものが存在しないことは明白ですね。誰でも必ず老いて死ぬわけだから。そして老い際に、システム全体も道連れにして崩壊させることになります。独裁主義のもとでは、特定の個人そのものがシステムだからです。
民主主義はもっとカジュアルです。民主主義のもとでも、人々は病気になったりして死にますし、選挙に負けたりもする。それでも「手続き」というものが存在していて、その「手続き」が時間を稼ぐのです。そうすることで、たとえリーダーが亡くなっても(選挙によって代わりの人を立てることができるし、人が交替してもシステムそのものは機能しつづけるので)、続けて国家も一緒に崩壊してしまうのではないかと心配している人々がパニックを起こすようなことは避けられます。この点が重要なのです。
──ちょうど種の多様性の増大が、地球を安定化させてその耐性を高めてきたことと似ていますね。
スナイダー それはいい例です。
暴政を避けるためのレッスン
●忖度による服従をするな
──あなたの『暴政:20世紀の歴史に学ぶ20のレッスン』(2017年)は、とても身につまされ励まされるものでした。たとえば、
「言葉を大切に」は、貧しい言葉が全体主義を招くというジョージ・オーウェルの『1984年』の世界を思い起こさせますし、「真実を大切にせよ」と「よく調べよ」は、嘘を遠ざけて自由を守るためには必須の態度ですし、「職業倫理を忘れるな」と「できうる限り勇気を持て」、いずれも実行するのはそう簡単ではないですが、常に意識していないと、つい不本意なことに引きずられる結果となってしまいます。
で、まず第一にあなたがあげた「忖度による服従をするな」というレッスンについてですが、アメリカの社会心理学者スタンレー・ミルグラム(1933ー1984)の実験 *2 を紹介していました。それによると、人々は、「命令に従うことが、社会をより良くするために自分が果たすべき責任である」と信じた場合、いかに残酷な命令であっても良心の呵責をまったく感ずることなくそれに従うことができる、と。
そしてご存じのように、ハンナ・アーレントは『エルサレムのアイヒマン���の中で、アイヒマン個人は、「『反ユダヤ人』という考えをまったく持っておらず」「検察側のありとあらゆる努力にもかかわらず、誰の目似も明らかなのは、この男(アイヒマン)は『モンスター』などではまったくないということだ」と語っています。すなわち誰でもアイヒマンになる可能性があるのだと。
私たちには優れた想像力というものが備わっているので、ごく自然に他人が一体何を欲しているのかを知ろうとします。それは幼児や老人や病人の世話をする際には、とても素晴らしい働きをしますが、同時に「忖度による服従」というような行動を生むことにもなってしまうわけです。
一体どうやってこのごく自然な人間の性向というものに抵抗したらいいのでしょうか。
*2 アメリカの社会心理学者スタンレー・ミルグラムによる「隷属行動の研究」実験は、一般市民が特定の命令のもとでは非常に残酷な行為を平気で行うことができることを証明するもの。教師の役を与えられた被検者は、壁の向こう側にいる生徒役の人物に簡単な単語問題を出し、生徒が間違えると生徒に電気ショックを与えるよう指示される。電圧は15Vから始まって最大450Vまで15Vずつ上げていくことができ、加圧量に従って、生徒に反応する声が聞こえるように設定してある。生徒役には実際の被害はないのだが、被検者にはそれがわからず、本物としか思えない声が聞こえてくる。実際生徒の、痛みを訴える声から、絶叫、そして苦悶の金切り声、失神して無反応になる、まで聞かされるのだが、指導者から静かにかつケンイテキニ実験継続を施されると、驚いたことに、生徒が絶叫して実験中止を懇願する300Vまでは、なんと100%の被検者が加圧し続け、最大の450Vまでスイッチを入れた者は65%にものぼった
スナイダー 今おっしゃったことの中にすでに答えがあります。市民であるということは、自分が置かれている状況がどのようなものなのかをしっかりと識別するということです。
たとえば街の会合(タウンミーティング)に行くとします。まず会場に入って椅子に座る。これは誰もがやっていることだから、そうすべきことですね。しかし数人が手をあげて、「町の工場が汚染された廃液を川に流しているけれども、それは許容範囲だ」というような発言をした場合、たとえ大勢の人が許容側であったとしても、「とんでもない、それは許容できない」と、しっかり反対意見を言うべきなのです。重要なのは、椅子に座るという皆と同調した行為と、肝心な時には反対意見を述べるという行為との違いを、はっきり認識するということです。
先ほどの「多様性」の話に戻りますが、たとえば野球を観にいくと、みんなと同じように声援を送りますが、時には他の観衆とはまったく反対の行為をすることもあるわけです(たとえばヤンキー・スタジアムで、並みいるヤンキースファンの中で、レッドソックスを応援するようなもの)。個人として自立するためには、これら両者の違いがわかる必要があります。
それこそがわれわれをして独立した個人たらしめるものです。この違いがわかるためには、繰り返し練習する必要があります。どこで線を引くのかということですが、誰もが同じところで線引きをする必要もありません。でも線を引くことができなければならない。だから第一レッスンが「忖度による服従をするな」ということなのです。
場合によっては、「これは今の私にとって普通(ノーマル)じゃない」と、しっかり言うことができなければならない。すべてのことをノーマルだと許容するのであれば、結果として権威主義を許容することになってしまうからです。
●組織や制度を守れ
──20のレッスンの中で、とてもユニークなものの一つは、「組織や制度を守れ」というものです。この「組織」の中には、いかなるサイズの組織も含まれるのでしょうか。たとえば宗教組織とか結婚なども。
スナイダー それは面白い点です。私が意味した「組織」とは、政府組織や、さまざまな非政府組織のことです。「ホロコースト」研究からみちびかれた結論は、これはちょっと保守的に聞こえるかもしれませんが、どんなに不十分な組織であっても、まったくないよりはましだということです。そして、うまく機能していない組織があった場合、それを壊してしまうよりは、改良して使えるようにするほうが望ましい。
たとえば、私自身はアメリカの最高裁判所が下した判決に対して大いに不満をもっていますが、だからといって憲法まで破棄してしまおうとは思わない。一般的に言って、国家の組織は、物事が急激に変わってしまうのを防ぐ役割を果たします。これによって体制が激変しないよう防御すると同時に、個人が孤立してしまうのを防ぐ役割も果たします。
アメリカでは現在人々が選挙に立候補していますが(2018年11月の中間選挙)、立候補することで彼らは「議会制度」を守っているのです。票を集めるために、他の人たちと一緒に活動することになるからです。非政府組織も同じです。労働組合でもボーイスカウトでもローカルな野球チームでも、そしておそらく結婚でも、それらの組織や制度は、人々が一人になってしまうことを防いでくれる。人間はまったく一人になってしまったら、完全に負けです。
アメリカにおける「自由」のコンセプトは誤解を招きやすいところがあります。たとえば���くアメリカ映画に出てくるのは、たった一人のヒーローが最後に世界を救うというようなストーリーで、宇宙からの敵を相手にするにしろ何にしろ、いつもたった一人のヒーローが救済するわけですが、実際には、たった一人になったヒーローは必ず負けてしまうのです。言い換えると、一人にしてしまえばその人を必ず敗北させることができるということでもあります。
組織は、われわれは一緒だということを自覚させてくれます。その中で初めて、個人が一人で何かをするということが可能になる。ですから国家組織と非国家組織の両方ですね。
──宗教組織もですか。
スナイダー (躊躇しつつ)一つ以上存在することを許すなら、ですね(笑)。
●相手の目を見て世間話をせよ
──もう一つのユニークなレッスンは、「相手の目を見なさい。そして世間話(スモールトーク)をしなさい」というものです。私たちはどちらかというと「世間話」というのはとるに足らないものだと教わってきましたし、インターネットを通じたコミュニケーションが増えることで、ますます相手の目を見つめる機会が少なくなってきています。なぜ相手の目を見ることと世間話をすることが重要なのでしょうか。
スナイダー このレッスンについては、ほとんどすべての人が質問してきます(笑)。
おそらくほとんどの人が、これは真実だと直感的にわかっているからでしょう。お互いに相手が人間であることを認識し合うことが大事だと知っているからだと思います。このレッスンの本質はここにあります。
コンピュータと目を見つめ合うことはできません。目線を向けることはできても、見つめ合うことはできない。コンピュータは見つめ返してくれません。動物たちと見つめ合うことはできるし、人間同士見つめ合うこともできます。見つめ合うということは、相手がそこにいることを認識することであり、エレベーターの中でも、バーにいても、誰かが目を見つめたら、必ずわかります。目を見つめられたら、それを無視することは非常に難しい。
なぜこのレッスンを入れたかというと、人々が分裂してしまうことや細分化してしまうことをできるだけ避けたいと思っているからです。現実の世界で実際に他の人たちと直接接触できる貴重な機会があった場合には、それらの人たちと一緒にいるということを実感したい。
目を見つめるということは、同時に肯定することも意味します。政治が悪いほうに傾いてきて、人々が孤独を感じたり��圧されていると感じたりする場合、彼らの目を見つめることは、彼らを認識することにつながるわけです。「避けて通る」ことの逆が「目を見つめる」ということになります。
世間話をするのも、相手がリアルな存在だと受け入れることを意味します。現在アメリカでは世間話をするのはとても大事です。なぜなら、重要な話(ビッグトーク)はしにくい状況になっていますから(笑)。
自分とは異なる視点をもった人たちともつながろうとするなら、他のさまざまなトピックについても話ができなければならない。「真実でない事柄」を信じている人たちとコミュニケートするには、まずお互いに人間であると認め合うところから始める必要があります。直裁に「真実でない事柄」の部分から話を始めるわけにはいかないからです。
まず、その人たちが大切に思っていること、たとえば天候や食べ物や子どものことといった普通のことを、あなたも大切に思っているんだと伝えます。その後で、彼らとは異なる意見の部分を提示する。それでも彼らは同意するとは限りませんが、少なくともあなたを人間だと認めることになりますし、異なる意見をもった別の人間の存在を認識することでになります。
●愛国者(パトリオット)は歓迎するが、国粋主義者(ナショナリスト)は願い下げ
──レッスンの一つは「愛国者であれ」というものですが、オルダス・ハクスリー(1849ー1963)は、「愛国心というものの最大の魅力の一つは、自分たち自身は深く善良であると感じながら、相手をいじめたり欺いたりするという、われわれの最悪の欲望をみたすことができるからだ」と言っていますし、バートランド・ラッセル(1872ー1970)も、「愛国心というものは、つまらない理由のために殺したり殺されたりする意志のことだ」と言っています。
あなたはどうやってハクスリーとラッセルを説得しますか。
スナイダー オスカー・ワイルド(1854ー1900)も「愛国心とは悪党の最後の砦だ」と言っていますし、リストはまだまだ続きます(笑)。
「原則」の問題と「実践」の問題を考えています。
まず原則について考えてみましょう。自分自身のアイデンティティが自分の外側に向かっていくことによって集団の原則となるわけです。「愛国心」と言った場合、自分の国が正しいとか誤っている、といったようなことを問題にしているのではないですね。私はある原則というものをもっていて、それは国家の原則でもあるべきだ、というふうに考えるのが「愛国者」です。
アメリカではたとえば「自由」がこの原則に当てはまります。そして愛国者は、個人だけでなく国家もこの原則に従うべきだと考える。この意味での愛国者は、決して満足するということはないですし、「リーダーがやることはなんでもOKで自分はそれに従う」などとも言いません。
アメリカの原則を「自由」だとするなら、愛国者だったら、国旗に対して��礼をしなければならないと考えるのか、それとも(たとえば大統領の態度に反対して国旗に敬礼しないという態度をとるような)抵抗を示してもいいと考えるのか。もし原則が「自由」ならば、もちろん抵抗してもいいというふうに考えるはずですよね。抵抗することはむしろ歓迎されるべきことになるはずです。愛国者というのは、国をしてある方向に向かわせようと努力する人々のことだと理解しています。
これに対して「国粋主義者」のほうには、あなたがおっしゃった事柄がすべて当てはまります。国粋主義者は、リーダーの言うことにすべて従うことはOKで、これは私の国で、私の国は常に正しく、グループの名のもとに抑圧行為をしても許されると考えるのです。
原則として、万能な人間などいないですし、完全に純粋な人間も存在しません。可能なのは、自分が所属するグループをある共通するスタンダードにもっていこうと努力すること、これが愛国心です。「愛国者であれ」というのは、「国粋主義者にはなるな」という意味でもあります。
「実践」の問題としては、もし人々が自分の国について、つまり実際の政治が行われるところについて、そして愛国心というものについて、語り合うことを躊躇するならば、結果として国に対する良い感情を逆の側(極右側)に利用されることになります。これはまったくの愚策ですね。自分の国に対してなんらかの発言をすることを躊躇していると、極右側にいい口実を与えてしまうことになる。「左側や中道派の連中は自分の国を恥じているんだ」と極右側が主張するのを助けることになってしまいます。
私自身は、自分の国を恥じてはいないし、自分の国を愛していると、ハッキリ言えます。今よりずっとましな国であるべきだとは思いますが(笑)。
そしてそのために政治というものがあるのです。政治とは、「自分の国は瑕疵のない素晴らしい国だ」と言いまくることじゃない、それは政治ではなく怠慢です。
政治とは、「われわれはこれらの事柄を大事にしているし、この国を愛している。だからこの国にはこれらの良い制作やアイディアを採用してもらいたいし、この国に住むさまざまな人々にとって、そして次の世代にとって、より良い国になっていってもらいたい」というふうに言うことです。これが私がこのレッスンで意図したところです。
●歴史を学ぶことが未来を生み、民主主義を支える
──最後に、歴史を学ぶ重要性についてお話いただけますか。
スナイダー われわれには歴史が必要です。なぜならわれわれには「時間」というものが必要だからです。われわれの後ろには、これまで人類が営々と構築してきた大きな遺産があるということを意識する必要があります。われわれはこの瞬間にのみ生きているのではなくて、われわれの存在は海の波のようなものです。海の波がこの瞬間に打ち寄せるのは、それ以前に何千キロメートルにもわたる波の構築があるからですね。この波が打ち寄せるまで、ずーっとその波は続いてきたし、さまざまな周囲の影響があって初めて、この波はこの時この場所で打ち寄せるわけです。
われわれの現在というものは、この波のようなものです。われわれは、何かが起こると驚くわけですが、もし現在というものがこれまでの長い過去の蓄積の上にあると理解すれば、それほど驚くことにはならないでしょう。過去を知れば知るほど、現状に対して冷静に対処することができるようになります。
同時に、われわれには未来が必要だから、歴史が必要なのです。
「歴史の終わり」を宣言することの問題点は、そうすることで「未来の終わり」をも意味してしまうからです。実際に1989年(東欧革命:東欧の共産主義政権崩壊が起こり、アメリカの覇権が現実になった年)以降、西欧では「歴史の終わり」ということがさかんに言われた。やはり選択肢というものはないのだと。そういう見方の問題点は、いったん「過去」について考察することをやめてしまうと、つまり過去が現在とどのようにつながっているのかという流れを感じることができなくなると、「未来」についても考えることができなくなってしまうということです。考えられるのは「現在」だけになってしまう。そして想像できる未来像が貧弱になってしまい、想像できる未来とは、単なる現在の続きとしてのそれだけに限られてしまうのです。
インターネットが良い例です。インターネットの一体どこが未来的なのでしょうか。現在の最も重要なテクノロジーですが、これらがもたらしたことといえば、われわれを以前よりやや野蛮にしたということです。
そこには何も未来的な要素がありません。インターネットのことを話題にしている人々は、実際にどのような未来像をわれわれに提供しているのでしょうか。
彼らの描く未来像とは、太平洋に彼らだけのための人工島を作ったり、彼らだけが火星に移住したり、彼らだけが永遠の命を手にすることができたり、かくせんそうになったら彼らだけニュージーランドの核シェルターに入ることができたりするもので、これらを「未来」と呼ぶことはできません。
歴史を把握しないと、可能な未来像というものが見えなくなります。これはわれわれを圧倒的に品質にしてしまう。社会を貧弱にするのみならず、民主主義を困難にしてしまう。民主主義というのは未来に対する「賭け」であるべきだからです。ある候補者やある党に投票するのは、彼らが将来これらの政策を施行してくれる可能性がありそうだし、それは将来われわれにとっていいことだと思うからです。
もし現在にのみとらわれて、未来のことを考えないようになったら、権威主義者が勝利してしまいます。未来がないのであれば、権威主義者たちは、過去にあった脅威に焦点を当てたり現在の感情に焦点を当てることになるからで、「過去」と「現在」だけが政治の対象になったら、権威主義がはびこってしまいます。民主主義が残っていくためには、「未来」への展望がなければならない。
歴史こそが、未来に向かった考察というものを可能にするのです。歴史は、過去にどのような選択肢が可能だったのかを見せてくれますし、時間の流れる方向を示してくれます。未来は明確なものではないですが、少なくともわれわれが影響を及ぼすことのできる「未来」が存在する、ということを実感ささせてくれるのです。
歴史とは、人々が感じているよりもずっとじゅかな役割を果たしています。
歴史が重要でなくなることと民主主義の衰退とは強く関連していると思います。原因と結果という関係にあると。
「嘘と孤独とテクノロジー──知の巨人に聞く」
著者 吉成真由美(インタビュー・編)
(株)集英社インターナショナル
2020年4月12日発行(インターナショナル新書)第二章ティモシー・スナイダー「テクノロジーのロシアとファシズムの関係」より
吉成真由美(よしなりまゆみ)
サイエンスライター。マサチューセッツ工科大学卒業、ハーバード大学大学院修士課程修了。元NHKディレクター。著書に『知の逆転』『知の英断』『人間の未来AI、経済、民主主義』(インタビュー・編、すべてNHK出版新書)、『進化とは何か:リチャード・ドーキンス博士の特別講義』(編集・翻訳、早川書房)等。
1 note
·
View note
Text
THE TE OF PIGLET by Benjamin Hoff, 1992.
何千年もの昔、人間は自然界のほかのものたちと調和して生きていた。今日ぼくたちが〈テレパシー〉と呼んでいるものをつかって、人間は動物、植物、その他のかたちの生命と心をかよわせていた。ほかの生きものを自分〈より下〉とみなすようなことはまったくなく、ただちがうはたらきをする、ちがうものと思っていた。人間は大地の守り神や自然の精霊とともに力をあわせて働いた。ともに世界を守る責任をわかちあっていたんだ。
大気はいまとはまるでちがっていて、植物を養う水分をはるかにたっぷり含んでいた。ものすごくいろいろな種類の野菜、くだもの、種子、穀類が手に入った。そういう食べものがあって、不自然な緊張がないから、人間の寿命は今日の寿命の何倍も長かった。食べるためや、〈スポーツ〉のために動物を殺すなんてことは考えられなかった。人間は人間自身とも、ほかのさまざまな生きものともいっしょに平和に暮らし、ほかの生きてものを先生とも友だちとも思っていた。
けれど、最初はそろそろ、やがてぐんぐん強力に、人間の〈エゴ〉が自己主張をはじめた。とうとう、そいつがいろいろ不愉快な事件を引きこしたもので、人間は自分だけで世のなかへ出ていって必要な教訓を学べばいいんだ、とみんなの意見が一致した。絆は断たれた。
ひとりになって、生まれた世界から疎外され、思うぞんぶんあじわっていた豊かさからも切り離され、人間はもうしあわせではなかった。そして、失われた幸福をさがしはじめた。なにかそれを思い出させるものを見つけると、人間はそれを自分のものにし、もっとたくさんためこもうとした──こうして〈ストレス〉が生活に入りこんだ。しかし、長くつづく幸福を求めて、その一時的な代用品を山と積んでも、まるで満足はなかった。
もうほかの生きものがいっていることを聞いてもわからないから、かれらの行動を見て理解しようとするしかなかったが、人間はしばしばその解釈をまちがえた。いまは大地の守り神や自然の精霊とみんなの利益のために協力することもなく、自分のためだけに大地の力をあやつろうとしていたから、植物はしおれて枯れはじめた。水分を吸いあげて蒸散させる草や木が少なくなると、地球の大気も乾燥してきて、砂漠があらわれた。生き残った植物の種類はそれほど多くなく、時とともに小さくかたくなっていった。ついには祖先にあったような燦然と輝く色彩も失せ、たわわに実る果実も消えた。それとともに人間の寿命も短くなりはじめ、病気が発生してひろがった。手に入る食べものの種類が少なくなったので──ますます感受性が���ってきたせいもあるが──人間は友である動物を殺して食べるようになった。動物たちはまもなく近寄ってくる人間から逃げることをおぼえ、しだいに警戒心をつのらせて、人間の動機や行動を疑うようになった。そうして〈分裂〉はひろがった。何世代かたつと、かつての生活がどんなふうだったか知るひともほとんどいなくなった。
人間がますます暴力的に地球をいじりまわすようになり、その社会的、精神的世界が人類だけのものにせばめられていくにつれ、人間は自分の同胞に対してもますます暴力的、操作的になっていった。たがいに殺しあい、奴隷にしあい、軍隊や帝国をつくりだし、自分たちとはちがう姿、話し方、考え方、行動をするものたちを屈伏させ、自分たちが最善と思っているものを押しつけた。
人生があまりにも悲惨になってしまったので、およそ二、三千年前、ほとんど忘れ去られている真理を教えようと、完全なる精霊たちが人間のかたちをとって地球上に生まれてくるようになった。が、そのころまでに人間性はあまりにも分裂してしまい、自然界を動かしている宇宙の法則にもきわめて鈍感になっていたから、これらの真理のほんの部分的にしか理解されなかった。
時がたつにつれて、完全なる精霊の教えは、政治的理由とでもいうべきもののために、それを受け継いだあまりにも人間的な組織によって変えられていった。組織内の重要な地位についた連中はほかのものを支配しようとした。かれらは人間以外の生きものの重要性をみくびり、これらの生きものにも魂と知恵があり聖なる存在なのだというくだりを──それから、かれらがふれている天国というのは〈聖杯〉と〈一体化〉した状態で、だれでも自分のエゴを捨てて宇宙の法則にしたがうなら到達できる、というところも──教えから削除した。権力に飢えた連中はかれらの信者に、天国は一部の人々が──人間だけが──死後におもむく場所で、かれらの組織の承認を受けた者のみが行くことのできるところだと信じさせようとした。そういうわけで、完全なる精霊さえ、人間のエゴに邪魔されて、真理の全体をもとどおりにすることはできなかった。
〈大分裂〉とそれにさきだつ〈黄金時代〉の話は、感受性豊かで賢明な人々によって何世紀にもわたり伝えられてきた。今日の工業化された西洋では、単なる伝説か神話──だまされやすく世慣れていない人々が信じこむファンタジーとか、想像力と感性だけにもとづいた物語──とみなされている。大地の守り神や自然の精霊に会って心をかよわせている少数のひとがいて、複数の霊的な共同体がかれらと協力し、その指示にしたがって、すばらしくおいしい野菜やくだものを育てているという事実があるにもかかわらず、こうした存在に関する描写は一般に〈おとぎばなし〉として片づけられている。また世界の諸宗教の聖典に、〈大分裂〉を潤色し、単純化した記述を見受けるが、これらの宗教の信者のどれほどがそれを本気で信じているものか疑わしい。
それでも〈分裂〉前の技術や、考え、ならわしの一部は保たれた。北アメリカ大陸では先住民の、いわゆる〈インディアン〉の教えとして残っているもののなかにいくらか伝わっている。ヨーロッパではほとんど滅んでしまったが、ストーン・サークルとか、地のエネルギーが集結するチャンネルである〈レイ・ライン〉(中国人は〈龍の脈〉と呼ぶ)など比較的新しい現象に、その影響の痕跡をいまも見ることができる。チベットでは、共産主義者の侵攻まで、古いしきたりがチベット仏教のなかに残されていたが、その秘伝やならわしの多くは仏教に何千年も先行していた。日本でも、神道の儀式や信仰になにがしか見つけることができる。中国で、それらはタオイズムを通じて伝えられた。そして、中国共産党の猛反対にもかかわらず、伝えられつづけて今日に至っている。
簡単にいえば、タオイズムは宇宙の道タオと調和して生きる生き方で、タオの特徴は自然界のいとなみにあらわれている。タオイズムは哲学とも宗教ともいえそうで、そのどちらでもない。というのは、それはさまざまなかたちをとり、哲学とか宗教とかいうときの西洋的な考えや定義にそぐわないのだ。
中国におけるタオイズムは儒教の均衡勢力と呼んでいいだろう。儒教というのは孔子(西洋ではコンフューシャスというほうが通りがいいが)の教えを成文化、儀式化したものだ。西洋的な意味あいの宗教ではないけれど、人間中心的で自然無視の態度、厳格な服従重視、そして権威主義的な、つべこべいわせない姿勢など、清教徒(ピューリタン)のキリスト教にどことなく似ているといっていい。儒教が気にかけるのはあらかた人間関係で、社会的、政治的な決まりやヒエラルキーだ。主として、政治、ビジネス、家族・親族関係、祖先崇敬などの分野で貢献している。とくに不可欠な原理は、高潔、礼儀正しさ、慈愛、忠義、誠実、義務、そして正義だ。ひとことでいうと、儒教は集団のなかの個人の立場をあつかう。
それとは対照的に、タオイズムはおもに個人の、世界との関係をあつかう。タオイズムはだいたいにおいて科学的、芸術的、精神的なところで貢献している。タオイズムから中国の科学、医学、農芸、山水画、そして自然をよんだ詩が生まれた。主要な原理は、自然な素朴さ、無為、自発性、そして思いやりだ。儒教とタオイズムのもっとも簡単にわかるちがいは感性面、気持ちの差だ。儒教がきびしく、画一的、家父長的で、しばしば苛酷なら、タオイズムは幸福で、おだやかで、子どもっぽく、澄んでいる。そのおきにいりのシンボル、流れる水のように。
タオイズムは古典的には三人の人物の教えとして考えられている。二千五百年ほど昔に書かれたといわれる、タオの古典中の古典『道徳経』の著者、老子。数冊の書をあらわし、約二千年前の戦国時代に作家、哲学者の一派の開祖となった荘子。そして四千五百年以上昔に中国を治めていたなかば伝説的な黄帝。さまざまな瞑想的、錬金術的、医術的な原理が黄帝に発するといわれる。これら三者はタオ思想の始祖というより、むしろそれを系統だてて伝えた偉人たちだった。というのは、前にもいったように、いまタオイズムとして知られているものは、まだ三人とも生まれる前、荘子という〈完全な徳の世〉にはじまったのだ。
完全な徳(〈至徳(しとく)〉)の世、人間は大きな家族の仲間としてけものや鳥といっしょに暮らしていた。ひとりの人、あるいはひとつの生物をほかと隔てる〈優劣〉の区別はま���たくなかった。みな生まれながらの徳を保ち、純粋に素朴な状態で暮らしていた。・・・・・・
完全な徳の世には、知恵や才能が特別視されることはなかった。賢い人々はただ、太陽にほんの少し近い、人間性という木の上のほうの枝にいるにすぎなかった。人々はなにが正しく礼儀にかなっているかも知らぬまま、まちがいなくふるまった。愛しあい、敬いあい、それを慈愛と呼ぶ必要もなかった。誠実で正直だから、忠誠など考えもしなかった。約束を守り、信用のことなど考える必要もなかった。日常生活では助けあい、あてにしあって、義務など考えなかった。かれらが正義に無縁だったのは、不正がまったくなかったからだ。かれらは自身とも、互いにも、また世界とも調和して生きていたから、そのふるまいはなんの痕も残さず、そのためかれらがいたという物的証拠はない。
〈大分裂〉以来ずっとタオイストたちは、タオとの調和を阻むものをすべて捨て去ることによって、完全な徳、至徳の境地に到達しようと心がけてきた。
※〈徳〉(te)の発音は、普通話(北京官話)では〈テ〉ないし〈トゥ〉となるようです。ここでは〈デ〉と発音し、終わりに〈r〉の音をそえて〈デァ〉や〈ドゥァ〉の中間の発音という向きもある。
この〈徳〉の古典的中国語の書き方は二段階あって、まず〈まっすぐ(直)〉という漢字に〈心〉という漢字を足して、それで徳という意味のつくりになる、次に、その漢字に加えるのが〈左足〉のぎょうにんべん。中国語では〈踏み出す〉という意味をもつ。というわけで、行動する徳という意味になる。
徳は、英語でいう美徳が連想させるような、基本的にその持ち主とかかわりなくおなじとみなされる、いわばフリーサイズの、善行あるいは立派な行動とはちがう。そのかわり、そこには、特別の性格、特別の強さ、あるいはその個人に特有の隠された力といった性質──ものごとの内なる自然から出てくるなにか──がある。さらに、その持ち主が知らずにもっているなにかだと、つけくわえてもいい。
ここでぼくたちは、タオイストが昔から〈とてもちいさい動物〉を好んでいることに注目してもいいだろう。いわゆる動物はべつとして──これを儒教はただ食べるか、犠牲(いけにえ)にするか、あるいは犂(すき)や車を引かせるだけのものとみなしているが──儒教が支配する伝統的な中国社会で〈とても小さい動物〉というと、女と子ども、それに貧しい人々だった。
強欲な商人、地主、役人に踏みつけにされて、貧乏人は儒教的社会の最低辺にいた。いい方をかえれば、待った数に入っていなかった。女たちは、たとえ裕福な家庭の女性でも──とりわけ裕福な家庭の女性こそ──しあわせな暮らしだったとはいえない。女性に対してあまりに抑圧的で今日の西洋ではだれひとり理解できないような、親が決める結婚、一夫多妻、纏足(てんそく:事実は足の破壊だ)、その他もろもろの慣習を儒家がとりしきっていたからだ。子どもたちだってそうそう愉快にやっていたわけではない。堅実な儒家にとって、子とは家系を継続させるため、なんであれ無条件に親にしたがい、親が老いればあらゆる世話をするために存在していた──自分なりの考え、理想、興味などもってはならないのだ。儒教のもとでは、父親が自分にしたがわない息子、名誉を傷つけた息子を殺しても当然とされた。子のそうした行ないは犯罪同然とみなされたのだ。
それに対し、タオイズムでは、尊敬は当人しだいと考えられていて、もし親父さんに正しくないふるまいがあれば、家族には逆らう権利があった。それは皇帝とその〈家族〉──臣民──にもいえた。もし皇帝が暴君なら、人民は彼を王座から追いはらう権利がある。儒家の政府高官は、タオイストや仏教徒の影響を受けたい秘密結社にいつもびくびくしていた。それらは、事態が耐えがたくなればいつでも、踏みつけにされている者たちを守って王座をひっくり返そうとしており、それもめずらしいことではなかったからだ。
タオイストはいつも〈負け犬〉に共感していた──中国社会から見捨てられた悲運の人々だ。なかには腐敗した商人や役人の策略にかかって経済的に破滅して、やむなく〈緑林(りょくりん)の兄弟〉(法的な保護を剥奪された者)となり、〈江湖(こうこ)の客〉(漂泊者)となった者もいた。中国武術は主としてタオイストと仏教僧が、身をまもる手段のない人々を守り、自衛させるために発達させた。武術というより反(アンチ)武術と呼んだほうがいいかもしれない。というのも、それは弱者に剣を抜く者がいるところ、武装した盗賊はもちろん将軍やお上の兵士に向かってもつかわれたのだから。仏教武術が防衛の〈ハード〉な手法(そこから力をつかって直接攻める空手とテコンドーが出た)に集中しがちなのに対し、タオイストは〈ソフト〉な手法に専念する傾向があり、たとえば、流動的で間接的な太極拳や八卦掌(はっけしょう:柔道や合気道に似ているが、もっと洗練されている)などがある。
権力の乱用と思われるものをやっつけるのに、タオ作家はその文章術をつかって、タオ武術家が相手の攻撃力を消し去る動きやツボをつかってしたのとおなじことをした。文学的な真実と虚構を武器に、かれらは権力者の非行を公表し、よこしまな者、傲慢な者、尊大な者、残虐な者を嘲笑した。閉口した儒家は何度もこうした文書を取り締まろうとしたのだが、多くのばあい、成功しなかった。庶民の共感を得られなかったからだ。
位(くらい)も高く権力もある儒家が一般にほとんど動物に敬意を払わないこと、また、ときどき中国の〈劣った〉人々を〈豚〉や〈犬〉よばわりしていることを見れば、タオ作家が多くの動物譚(たん)──実際のできごとの記述も、想像上の話もあるが──を記録したのも不思議ではない。そこではネズミ、蛇、猛禽(もうきん)など嫌われものの生きものが、〈高級な人々〉も見習ったほうがいい有徳のふるまいを見せる。これらの話では、動物たちの勇気、愛情、誠実、正直が、富裕な地主、商人、役人の思いあがりや偽善と対比される。古い例だが、荘子はこう書いた。
祭礼を司る神官が礼服をまとって豚小屋へ行き、豚に問いかけた。「なにをぶうぶういっている? これから3カ月穀物を食べさせてやろう。それから私は十日断食をする──おまえたちは食べているのにだ──そしてそのあと三日、私はおまえたちの不寝番をしよう。それから新しい敷物を広げ、おまえたちを霊界へ送り出すに先立って、彫刻をほどこした犠牲(いけにえ)の台に置いてやるのだ。私がしてやることをみな考えてみなさい。それでどうしていやがるのだ?」
もし神官がほんとうに豚のしあわせを気にしていたら、ぬかともみ殻を与えて、放っておいたろう。しかし、彼はおのれの威信という観点から事を見ていた。神主は──自分が死んだら、見事な天蓋(てんがい)が棺の上に広げられ、墓まできらびやかに運ばれると知っていて──特権的役職の装束を身につけ、飾りたてた乗り物に乗るのがうれしいのだ。もし豚のしあわせを気づかうなら、こうしたことは重要ではないとわかっただろうが。
タオ作家の攻撃目標は、裕福な儒家だけではなかった。マルクス兄弟やスタン・ローレルとオリバー・ハーディーのように、タオイストは社会のどういうレベルであれ、もったいぶったエゴを風刺した。この傾向は以下の物語に見ることができる。清朝の作家蒲松齢(ほしょうれい)の『梨(なし)の種』だ。
めかしこんだ農夫が町の市場で梨を売っていた。梨は大きくて、おいしくて、農夫はたちまちちょっとばかりの金をもうけていた。つぎだらけの木綿を着て、小さい鋤(すき)を背負った道士(タオイスト)が通りかかり、農夫の車のかたわらに立ち止まると、梨を一個無心した。農夫は失せろといった。道士は行こうとしなかった。農夫は怒ったのなんの。とうとう大声でどなりはじめた。
「だが、あなたの車には何百という梨がおありだ」と、道士はおだやかにいった。
「ほんの一個でいいのに。なにをそんなにうろたえるのです?」
騒ぎを聞きつけて、どんどん大勢の人が集まってきた。見物人のなかには傷ものの梨を貧しい人に投げてやりなさいと、農夫にいう者もいた。農夫はきかなかった。とうとう、この騒動が騒乱になりかけたところで、だれかが一個梨を買って道士に与えた。恩人に心から感謝すると、道士は群衆のほうを向いた。
「われわれ道にしたがう者は、けちな強欲を憎んでおります」と、道士は語った。
「この美しい果実を、ご親切なみなさんと分けることにしましょう」
だれひとり、その梨の一切れを受け取る者はなかった。見物の人たちは、自分で食べなさいといいはった。
「わたしには植える種が一粒あればいいのです」と、道士は答えた。「そうしたら、みなさんにお返しができるでしょう」。彼はその実を食べると、小さな種を一粒残した。小さい鋤で穴を掘り、種を穴のなかに落とすと、また土をかけた。それからお湯を頼んだ。だれかが近くの店からお湯をもらってきた。道士がそれを種を植えた地面にかけるあいだ、群衆は興味津々で見まもった。
突然、小さな芽が顔を出し、ぐんぐん伸びて木になった。枝や葉がわさわさ広がった。花が咲き、それから大きくてうまそうな匂いの実がたわわに実った。
道士はその実を見物の人たちに配った。実はほどなくすっかりなくなった。すると、小さい鋤でその木を切り倒した。群衆に手を振り、その木をひきずって、道士はしあわせそうに去っていった。
この間ずっと、あの欲ばり農夫は口をぽかんとあけて眺めていた。そしていま、自分の梨をふり返れば、ひとつ残らずなくなっているではないか。道士にかけられたまじないをふり払うと、農夫はなにが起きたか悟った。車の引き具の棒が一部──〈梨の木〉の幹と同じ太さだ──切り取られていた。
必死で探しまわって、農夫は壁に立てかけてある棒を見つけた。道士がそこに置いていったのだ。当の道士の姿はどこにもなかった。群衆はその冗談めいた教えを喜んで大笑いした。
負け犬に加勢するタオイストを理解するには、宇宙の力をはじめ、力というものに対するタオイストの態度を理解する必要がある。ほかのことでもそうだが、タオイストの見方は歴史を通じ大なり小なり儒家の対極にあった。
天の力という儒家の概念は、かなりあいまいだが、旧約聖書の神のイメージに近いものがある。儒家はそれを天──〈空〉〈天界〉、あるいは〈最高統治者〉──と呼んだ。天は男性視されていて、ときにおそろしいほど、猛々(たげだけ)しい。だから供犠(くぎ)や儀式によってなだめなくてはならなかった。それは一方の肩をもち権限を付与した。それは天の息子、皇帝に統治権を直接伝えた。支配は天子から下へ外へ──もっとも位の高い役人からもっとも下位の者へ、中心的な一族からとるにたらない家族へ──とひろがった。天は光り輝くすがたと想像されていた(ゆえに皇族や大貴族は華麗な色彩を用いた)。それはほうびとして物質的な繁栄をさずけるといわれた(ゆえに儒家は富すなわち善と考える)。ひとことでいえば、それは畏怖すべきもの──愛するよりは恐れるべきなにかだと(ゆえに上位者に対する無条件の服従が強調され���儒家の用語には思いやりといったことばがない)みなされた。
儒家が庶民に示した天の力のイメージとはそういうものだった。社会レベルで、それは法廷における訴人、証人、被告人のあつかいに見ることができる。法にもとづいた相談や弁護はなんびとにも許されず、みんな長官の前に出て硬い床に(ときには鎖につながれて)ひざまずか���ばならなかった。長官は、地方政府における皇帝の代理で、証言や自白を拷門によって引き出す権限があった(ゆえに中国の拷門が発達)。この種の脅しが何世紀もつづいたせいで、大多数の中国人は官僚的な行政とのかかわりを極力避けるようになった。不幸なことに、この〈公然参加嫌い〉がつぎからつぎと──現在の全体主義的官僚政治も含めて──専制君主に国民支配をゆだね、維持させてしまっている。
儒家とはちがい、タオイストは天の力を男性と女性の両性と見た。円が曲線によって陽と陰、あるいは男と女、の半々に分けられている、タオイストのシンボル太極のように。しかし、自然界にはたらいている天の力は──老子のいう〈万物の母〉だが──その行動がきわめて女性的だとタオイストはいつも考えていた。それは流れる水のように、やさしい、やってくるすべてのものを養う肥沃な谷のように、つつましく、惜しげない。霧の向こうにかいま見た風景のように、隠されていて、とらえがたく、神秘的だ。それはどちらの肩をもつでもなく、なんの権限も授けない。それは供犠や儀式で左右することも、なだめることもできない。法を行なうにあたっては、すべてにおいてそうなのだが、それは軽いタッチで、見えざる手をつかう。老子がいったように、「天の網は目が粗いが、なにひとつもらさない(天網恢恢疎(てんもうかいかいそ)にして漏らさず)」のだ。
おごりやうぬぼれをひけらかさないよう用心しながら、それがもっとも深い神秘を伝える相手は、政府高官でも、もったいぶった学者でも、富裕な地主でもなくて、一文なしの僧、小さい子ども、動物、そして〈愚弄される者たち〉だ。なんらかのえこひいきがあるとするなら、つつましい者、弱い者、小さい者に味方しているところだろう。
だれにでもわかるとおり、とても小さい動物だと不利なところがある。そういう弱点のひとつが、より大きい動物に利用されるところだ。
小さい動物は──ひとかどのものになりたいと切望しながら、想像やおそれにひきとめられていて──なんであれ重要なことを達成しそうな期待がもてる動物ではまずない。それでもやはり彼はヒーローになりうる器だ。勇敢な救助者、堂々たる闘士、あるいは偉業をなしとげたひと、どれでもいい。よくよく見れば、そのびくともしない外面の下に、ほとんどのばあい彼が見つかる。それは、歴史を見ても明らかなように、いつもそうだったし、きっとこれからもずっとそうにちがいない。
いろいろの点で、彼は変化し、成長し、最初のころより大きくなるのは、ひとり彼だけだ。そしてついには、自分が小さいことを否定せず、それを活用して、ほかのもののためにそれをなしとげる。〈大きいエゴ〉を蓄積することなく、内側では〈とても小さい動物〉のまま、なしとげる──それも以前とはちがった種類の〈とても小さい動物〉として。
引っこみじあんの 小さい動物だから
大きく大胆になりたいと 夢見ながら
きみはためらう 感じやすさのかたまりになって
生きるチャンスを 待ちながら
時はどんどん 走ってく
好機は来て また消えていく
それでもきみは待っていて なにもしない
羽があるのに 飛ぼうとしない鳥
けれど きみが願っている〈きみ〉は
いまも これからも きみにはならない
きみのなかで待っている 特別のことをするひとは
ほかにだれもいないんだもの
きみは導きの星になれる
もしきみ自身を生かすことができれば
いま はずかしがっている感じやすさだって
成長したら 隠されている扉を見つけるだろう
まだ だれも行ったことのない場所への 扉を
ひそかにきみが感じている誇りは
きみをだめにしたりなんかしない
それは〈小さい〉ってことのなかに
〈大きい〉とこを見つけてくれる
ぼくたちひとりひとりのうちに、なんだか不幸になりたがっているものがある。それは想像のなかで、まだ存在していない問題をつくりだす──そして実現させることもかなり多い。それはすでにある問題を拡張する。低い自己評価をさらに低く、他者への尊敬をますます失わせる。腕前、整頓、清潔さに対する誇りを破壊する。集いを対決に、期待を不安に、機会を危険に、踏み石をつまずきの石に変える。そのはたらきぶりは、顔面筋肉をつっぱらせ、老化のプロセスを速めるしかめっつらのひそめ眉にうかがうことができる。その顔のうしろでそいつは否定的エネルギーで心を汚染し、外に向かって病気のようにひろがる。それから、ほかのひとたちの不幸をうつしてもどってくる。そしてまたそれがつづく。
『サタデー・レヴュー』の主筆を三十年以上務めたノーマン・カズンスは、その雑誌の廃刊後に書いたある記事で、その作用をこういいあらわした。
『サタデー・レヴュー』がいかなる成功をおさめたとしても、それは精神生活についておける思想と芸術の役割に対する敬意とじかに結びついていた。近ごろ国民文化を冒している低俗さに照らすとき、このことは特別の重要性を帯びてくる。とくに興行界と出版界には、趣味の梯子のよりいっそう低い段を見つけようとする熾烈な競争があるようだ。・・・・・・
自由が下層社会の隠語とどういうわけか同義だとする奇妙な考えがある。かつて芸術にたずさわる人々は、社会の不正や横暴を攻撃する思想を伝達する能力を互いに自慢しあったものだった。いまは、わいせつな言葉を充分使うことさえできれば、人間性に一撃を与えたと感じる人々が一部にいるらしい。・・・・・・
言語の品位を落とすことは、礼儀正しさの忘却を繁栄するばかりか、つくりだしてもいる。ささいな食い違いをきっかけに、暴力的な反応がひき起こされるようになった。テレビに教育されたアメリカの一世代がこぞって、侮辱に対する正しい反応はだれかの顔面にパンチをくらわすことだと信じこまされている。
これは、社会的に認知されたあらゆる否定的現象に見られる。たとえばますます増えている老けた若者の支配的な哲学はこうらしい。〈うまく行くもんか。だったら、なぜやるんだ?〉。
かれらがもっているのは、おそれだ。かれらはおそれる──思いきって肯定的な感情表現をすること、肯定的な行動をとること、なんであれエゴを超えているものに肯定的にかかわることをおそれる。かれらにいわせれば、そういうことは愚かで、かれらは愚かに見られたくない(かれらは恐怖に身がすくんでいるように見えるのはかまわないらしい──ただ、愚かに見えるのがいやなのだ)。周囲の人間にはあいにくだが、愚痴をいうことなら、かれらたちはおそれずにする。ちっぽけな器をしぶしぶ命の泉まで運んでおきながら、少ししか入れてもらえないと文句をいう。
かれらたちは現実主義者だ、というひとがいる。でも、現実っていうのは、ひとがつくるものだ。そして否定的な現実をどんどん育て、ひき起こしていけば、それは多くなるいっぽうだ。かれらたちは自分たちが見たいものしか見ない。・・・・・・たとえば、歴史的に見て、いまほど個人に変化を起こす力と機会が与えられたことはない。あたりをとっくり見まわせば、この主張はたやすく立証されるだろう。しかし、その作用はかなり多くの人々に、自分たちは無力だと信じこませている。そしてそうと信じているから、かれらは無力だ。
困難がなければ、人生は岩もカーブもない流れのようなものだ──おもしろいことコンクリート並み。問題がなければ、人間的成長も、グループによる目的の達成も、人類の進化もない。しかし、問題に関して問題になるのは、そこでなにをするかなんだ。かれらたちは問題を克服しない。そう、あべこべだ。
かれらたちは、いいかえれば〈こぼし屋〉だ。かれらは否定的なものを信じていて、肯定的なものは信じない。悪いことばかりで頭がいっぱいなもので、人生に〈良いこと〉があっても、かれらの目には止まらず通りすぎてしまう。それならかれらは、この世がどんなものか正確に説明してくれるひとたちだろうか。もし宇宙が〈彼ら的姿勢〉に支配されていたら、すべてはとっくの昔に崩壊していただろう。創造された万物は、飛びつづけるハチドリから自転する惑星まで、〈やれば、できる〉という信念にもとづいて運行しているのだ。
ウイリアム・ブレイクを引用すれば「太陽と月がもし疑いを抱くなら/ただちに消えてなくなるだろう」。
というわけで、長続きしたかったら、どんな社会も彼らたちに支配させてはならない。というのは、彼らたちは、生存と繁栄のためにもっとも必要とされているまさにそのものをあざ笑うからだ。老子は書いた。
道を開くと
最も高い心はそれを実践し
並の心はそれを考慮して
少しは試してみたりもするが
最も低い心は笑いものにする
もし笑いものにされなければ
それは道ではない
身のまわりの彼らたちを少し見てみよう。最初は〈否定的ニュース・メディア〉と呼んでいるやつだ。ヘンリー・デイビッド・ソロー��、『森の生活』にこう書いた。
新聞で印象的な記事というものをまったく読んだことがない、と確かに思う。だれかが強盗にあったか、殺害されたか、事故死をとげたと、あるいはどこかの家が焼け、船舶が座礁し、蒸気船が爆発し、牛が西部鉄道でひかれ、狂犬が殺され、冬にバッタの大群が出たと一回読めば──もうそれ以上読む必要はない。一度でたくさんだ。
今日、否定的ニュース・メディアのおかげで、ぼくたちはほとんどなにもできない問題について過剰に知らされている。
0 notes
Text
禅 - ZEN 愛と力
一粒の砂に世界を見、
一輪の野の花に天を見る。
汝の掌に無限を捉え、
一時の中に永遠を見よ。
(ブレイク)
泉のささやきにより、
いと小さい枝の葉ずれの音により、
日の神が眠りにつく時
開いた葉を閉じる雛菊により、
蔭なす木により、灌木により、
彼女はわたしに伝えることができる。
自然の一切の美が、
誰かほかの、もっと賢い人に伝え得るよりもっと多くのことを。(ウィザー)
数多くのキリスト教会、仏教寺院、ユダヤ教会堂、回教寺院、それに実質的、精神的な教育機関にもかかわらず、われわれの多くは、無知で、愚かで、全く自我中心的にすぎるということである。これが、時に、悟れる者を失望落胆させる。あまたの仏像、聖像に、われわれはその跡を見出すことができる。
シンシナティの Van Meter Ames 博士は言う、
「まったくの貧困と絶望的事態においては、無感覚が一番よいのかもしれない。だが、それがおよそ人間の生活が到り得る最大のものだと思うのは、悲しい迷いである。」
博士はまったく正しい。人間が人間であるかぎり、かれはその周囲に起きるさまざまな出来事に、無感覚でいることはできない。人口の密集した都会の真中で原子爆弾が炸裂したのちの、あらゆる人間の苦痛、苦悶、悲惨を目にする時、かれの神経は千々に引き裂かれる。
そしてもっともいけないことは、人はこれらの苦の前にまったく無力だということである。人が持ち得る唯一の救いは、もしそれがかなうことならば、無感覚の福音であろう。何と非人間的なことではないか。われわれの団体活動はすべて、個人の考えや行為の集積であると自分は考えたいのだが、以上の事柄は、みな絶望的にわれわれ個人の制御を越えるものである。このことを思う時、自分は神に次のような独り言をいわせた聖書の著者に、深く共鳴せずにはいられない。
「エホバ、人の地に大なると、其心の思念の都て図維る所の恒に唯だ悪きのみなるを見たまへり。是に於て、エホバ、知の上に人を造りしことを悔いて、心に憂へたまり。エホバ言たまひけるは、我が創造りし人を我が地の面より拭去ん。人より獣、昆虫、天空の鳥にいたるまでほろぼさん。
其は我れ之を造りしことを悔ればなり。」(「創世記」第六章五-七節)
神は今、地上から人を拭い去る大事業に専心従事しているのであろうか。まさにそのようである。それならば、人間は人間であるかぎり、この事態に対処する態度を持たねばならぬ。
『愛と力』
いまだかつて、人類の歴史において、現代の世界におけるほど精神の指導者ならびに精神的価値の高揚が差し迫って必要だったことはない。前世紀から今世紀にかけて、われわれは人類の福祉の増進のために幾多の輝かしい成果をおさめてきた。しかし、おかしなことに、われわれは、人類の福祉が主として精神上の智恵と訓練によるものであることを忘れていたようである。今日、世界が憎しみと暴力、恐怖と不実の腐敗した空気に満たされているのは、ひとえに、われわれがこのことを充分に認識しなかったことによる。実際、われわれは、個人としてのみでなく、国際的にもまた民族的にも、おたがいの破滅のためにいよいよ力をつくそうとしているかのごとくである。
今日、われわれの考え得る、そして、その実現をねがうさまざまの精神的価値のうち、何よりも切望せられるものは “愛” である。
生命を創造するのは愛である。愛なくしては、生命はおのれを保持することができない。今日の、憎悪と恐怖の、汚れた、息のつまるような雰囲気は、慈しみと四海同胞の精神の欠如によってもたらされたものと、自分は確信する。
この息苦しさは、人間社会というものが複雑遠大この上ない相互依存の網の目である、という事実の無自覚から起きていることは、言をまたない。
個人主義の道徳の教えは、さまざまの意義ある成果を生んで、まことに結構である。しかし、個人は他の人々から孤立し、その属している集団──それは生物的な集団、政治的な集団、宇宙論的な集団など、さまざまあろうが──から切り離される時、もはや存在しないということを忘れてはならない。数学的にいうならば、一という数は、無限に存する他の数と関係しないかぎり、一ではない、それ自身ではあり得ない。一つの数それ自体の存在などということは考えられない。これを道徳的もしくは精神的にいえば、それぞれの個人の存在は、その事実を意識すると否とにかかわらず、無限にひろがり一切を包む愛の関係網に、何らかのおかげをこうむっているということである。そしてその愛の関係網は、われわれのみならず、存在するものすべてを漏らさず摂取する。実にこの世は一大家族にして、われわれひとりひとりがそのメンバーなのである。
人間の思想の造型に、地理がどれほど関係あるものか、自分にはわからない。だが、事実、七世紀の頃、“華厳哲学” として知られる一つの思想体系が開花したのは、極東の地においてであった。華厳(けごん)は、たがいに融通し、たがいに滲透し、たがいに関連し、たがいにさまたぐることなしという考え方に基づく。
この一切の相依相関を説く哲学が正しく理解される時に、“愛” が目覚める。なぜならば、愛とは他を認めることであり、生活のあらゆる面において他に思いを致すことだからである。「すべての人に為(せ)られんと思うことは、人にもまたそのごとくせよ。」これが愛の要旨であり、これは相依相関の認識からおのずと生まれてくることである。
たがいに関係をもち、たがいに思いやるという考え方は、力の観念を排除する。力とは、内的関係の体制の中に外から持ち込まれるものだからである。力の行使はつねに、専断、独裁、疎外に向かう。
近頃、われわれが憂慮するのはほかでもない、力の本性を見抜けないで、したがって、それを全体の利益のために用いることのできぬや̀か̀ら̀が、力の概念を不当に買いかぶって主張することである。
愛とは、われわれに外から与えられる命令ではない。外からの命令には、力の意味がふくまれている。行きすぎた個人主義は、力の思いを育てはぐくむ温床である。なぜならば、それは自己中心的なものであって、ひとたび外にむかって動き出し、他人を支配しようとしはじめると、はなはだ尊大に、またしばしば、はげしい手段をもって自己を主張する。
それに反して、愛は、相依相関の心から生まれ、自我中心、自己強調とはほど遠い。力が、表面は強く、抵抗しがたく見えながら、実はみずからを枯渇させるものであるのに反し、愛は自己否定を通して、つねに創造的である。愛は、外部の全能なるものを待たずして、みずから働く。愛は生命、生命は愛である。
生命は、かぎりなく錯綜した相依相関の網であるから、愛の支えなくしては生命たり得ない。愛は、生命に形を与えようとして、さまざまのす̀が̀た̀に自己を実現する。形は必然的に個別的である。そして分別する知性は、とかく形を究極の実体とみなしがちである。力の概念はここから生まれる。知性が発達し、その独自の道を進んで、人間活動の実利的分野でおのれがおさめた成功に夢中になってくると、力が暴れ狂い、周囲を破壊しまわる。
愛は肯定である。創造的肯定である。愛はけっして破壊と絶滅には赴かない。なぜならば、それは力とは異なって、一切を抱擁し、一切を許すからである。愛はその対象の中に入り、それと一つになる。しかるに、力は、その特質として二元的、差別的であるから、自己に相対するものをことごとく粉砕し、しからずんば、征服して奴隷的従属物と化さねばやまぬ。
力は、科学ならびにそれに属するすべてのものを利用する。科学は、分析的であるにとどまり、無限に多様な差別相とその量的測定の学たることを越えないかぎり、とうてい創造的ではあり得ない。科学において創造的なものは、その探究の精神であるが、それは愛によって鼓舞されるものであって、力によってではない。力と科学の間に何らかの協力が行なわれる時には、その結果は、いつでも、さまざまの災害と破壊の手段を考え出すことになる。
愛と創造力とは一つの実体の両面のすがたであるが��創造力はしばしば愛から切り離される。この不幸な分離が行なわれる時、創造力は力と結びつくことになる。力は実は、愛や創造力よりも下位のものである。力が創造力をわがものとする時、それはあらゆる禍いをひきおこす危険きわまりない要因となる。
前述のように、力の観念は、実在の二元的解釈から必然的に生まれる。二元論が、その背後に統合する原理のあることを認めようとしない時、その生来の破壊的傾向は、奔放に、ほしいままに露呈される。
この力の誇示のもっとも顕著な一例が、西欧の人々の自然に対する態度にみられる。かれらは自然を征̀服̀す̀る̀といって、けっして自然を友̀と̀す̀る̀とはいわない。かれらは高い山に登っては、山を征服したと公言する。天のかたに向かってある種の発射物を打ち上げることに成功すると、今度は空を征服したと主張する。なぜかれらは、いまやわれわれは自然とよりいっそう親しくなった、とは言わないのか。不幸なことに、敵対観念が世界のすみずみにまで滲透して、人々は「支配」、「征服」、「管制」等々を口にする。
力の観念は、人格とか、相互依存とか、感謝とか、その他さまざまの相互関係の心を斥ける。われわれは、科学の進歩、たえず改善される技術、ならびに工業化一般によっていかなる恩恵を引き出そうとも、みながひとしくその恩恵にあずかることは許されない。なぜならば、力は、われわれ人類同胞の間にひとしく恩恵を分配しないで、それを独占しがちだからである。
力はつねに尊大で、独断的で、排他的である。それに反して、愛はおのれを低うし、一切を包括する。力は破壊を意味し、自己破壊をさえあえてする。愛の創造性とはまったく反対である。愛は死に、そしてふたたび生きる。しかるに力は殺し、そして殺される。
力とは人を物に変えるち̀か̀ら̀である、と定義したのは、シモーヌ・ウェイルだったと思う。自分は、愛とは物を人に変えるち̀か̀ら̀である、と定義したい。かくして、愛は力と根本的に対立するもののようにもみえる。愛と力はたがいに排除し合い、したがって、力のあるところには愛の影さえささず、また愛のあるところには力はまったく立ち入る余地もないと考えられる。
これは、ある程度までは正しい。だが真実には、愛は力に対立するものではない。愛は力よりも高い世界に属し、愛に対立すると思い込んでいるのは、力の方だけである。まことに、愛は一切をつつみか、一切を許す。それは一切を和らげ、かぎりなく創造して尽きるところを知らぬ。力はつねに二元的である。したがって固定的で、自我を主張し、破壊におもむき、すべてを滅却する。そしてもはや征服すべきものがなくなると、おのれに鉾先を向け、おのれを滅ぼすに到る。力とはこのような性質上のものであるが、これは、今日われわれの目撃するところではないか。それは国際問題において殊に顕著である。
愛は盲目というが、盲目なのは愛ではなくて、力である。けだし、力は、おのれの存在が何か他のものに依ることをまったく見落としている。それは、自己とはくらぶべくもない大いなる何ものかにおのれを結びつけることによって、はじめてそれ自身であり得ることを認めようとしない。この事実を知らぬままに、力は自滅の淵に一直線に飛び込んでゆく。力が悟りを体験するには、まず、その眼を覆うと̀ば̀り̀を取り除かなければならない。この体験なくしては、力の近視眼的ま̀な̀こ̀には、真のす̀が̀た̀は一切うつらない。
ま̀な̀こ̀があ̀る̀が̀ま̀ま̀の実在、すなわち実相を見得ない時、恐怖と疑念の雲が、見るものすべてを覆う。実在の真相を見ることあたわずして、ま̀な̀こ̀はみずからをあざむく。相対するものをことごとく疑いはじめ、破壊しようとほっする。こうしてたがいに疑ってとどまるところを知らず、こうなっては、いかに説明しようとも、対立緊張を和らげることはできない。双方がありとあらゆる詭弁、奸策を弄する。これが国際政治では、外交という名の下に行なわれる。だが、相互の信頼と、愛と、和解の精神の存せぬかぎり、いかなる外交も、みずからのか̀ら̀く̀り̀によって創り出した緊張状態を緩和することはできないであろう。
力に酔った人々は、力が人を盲目にし、しだいにせばまる視界に人を閉じ込めるものだということに気づかない。こうして力は知性と結びつき、あらゆる方法でそれを利用する。だが、愛は力を超越する。なぜならば、愛は実在の核心に滲透し、知性の有限性をはるかに越えて、無限そのものであるからである。愛なくしては、人は、無限にひろがる関係の網、すなわち実在を見ることはできない。あるいは、これを逆に言えば、実在の無限の網なくしては、真に愛を体験することはできない。
愛は信頼する。つねに肯定し、一切を抱擁する。愛は生命である。ゆえに創造する。その触れるところ、ことごとく生命を与えられ、新たな成長へと向かう。あなたが動物を愛すれば、それはしだいに賢くなる。あなたが植物を愛すれば、あなたはその欲するところを見抜くことができる。愛はけっして盲目ではない。それは無限の光の泉である。
ま̀な̀こ̀盲(めしい)、みずからを限定するがゆえに、力は実在をその真相において見ることができない。したがって、その見るところのものは虚妄である。力それ自体もまた虚妄である。そこで、これに触れるものも、またすべて虚妄性と化する。力は虚妄の世界にのみ栄え、かくて、偽善と虚偽の象徴となる。
終りにあたり、くりかえして言う。実在するものすべての相依相関の真理に目覚め、たがいに協力する時、はじめてわれわれは栄えるのだという事実を、まず自覚しようではないか。そして、力と征服の考えに死して、一切を抱擁し、一切を許す愛の永遠の創造によみがえろうではないか。愛は、実在をあ̀る̀が̀ま̀ま̀に̀正しく見ることから流れ出る。そこで、われわれに次のことを教えてくれるのも、また愛である。すなわち、われわれ──個別的に言えばわれわれのひとりひとり、集合的に言えばわれわれのすべて──は、善にあれ悪にあれ、この人間社会に行なわれることの一切に責任がある。だから、われわれは、人類の福祉と智慧の全体的発展を妨げるような条件を、ことごとく改善もしくは除去するように努めなければならないのである。
『愛と力』鈴木大拙(1958年にブラッセル万国博覧会で読まれたメッセージ)邦訳 工藤澄子1965年2月25日(筑摩書房刊)『禅』(筑摩文庫1987年9月29日発行)より。
鈴木大拙(すずきだいせつ)
1870年(明治3年)、金沢市に生まれる。国際的に著名な仏教哲学者。本名は貞太郎。1891年(明治24年)、東京に遊学。東京大学選科に学びつつ、鎌倉円覚寺の今北洪川、釈宗演の下で参禅。1897年(明治30年)、一元論的実証主義者P.ケーラスをシカゴにたずね、11年間とどまる。1909年(明治42年)帰国、禅を広く海外に紹介し、大乗仏教の国際性を宣布した。1949年(昭和24年)、文化勲章受賞。1966年(昭和41年)死去。主著『楞伽経研究』『日本的霊性』『禅と日本文化』ほか。
1 note
·
View note
Text
『The Face of the War.(戦争の顔)』──Thomas Wolfe(トマス・ウルフ)
「戦争の顔」は、元来トマス・ウルフ(Thomas Wolfe 1900─38)の『天使よ故郷を見よ』の一部をなすものだったが、1935年6月雑誌『モダン・マンスリー』(Modern Monthly)に掲載された。ちなみに、この号は戦争特集号で、「アメリカが戦ったら 私はどうするか」というテーマのシンポジウムの企画があって、これにはシャーラウッド・アンダソン(Sherwood Anderson)、ヴァン・ワイク・ブルックス(Van Wyck Brooks)、ジョン・デューイー(John Dewey)などの興味ある顔ぶれが寄稿している。 さて、同誌に載ったウルフの作品は、第一次大戦の最後の年、1918年の夏の南部を舞台にして戦争につきものの四つの出来事を描いたもので、これは取りも直さず、戦争の暗い悲劇的な顔なのである。 ある飛行場の請負工事現場で白人の監督者から非道な打擲(ちょうちゃく)を受けて半殺しにされる黒人の話、同じ飛行場にある秘密軍用機の格納庫へ知らずに近づいたために、見張りの兵隊から罵られ暴行される三人の若者の話は、卑怯者が権威をかさに着て充足させようとする殺人への衝動、欲望を描破している。ある黒人貧民窟に建て���れた間に合わせのバラックで、狩り集められた慰安婦と水兵をまじえる男たちとの間でそそくさと行なわれる売春行為は、人間の獣的欲望の赤裸々な姿であるし、最後のある軍港での場景は、戦争につきものの瞬間的価値判断から生じる不条理と残忍さのドラマである。戦争はこうした人の心の闇の奥に潜む動物的衝動の引き金を引く。そして個人は「戦争の大渦巻きの中に──アメリカの巨大な暗い深淵と、雑踏する混乱の中に、そして残酷で冷淡な魔法の国に」投げ込まれる。そこではすべての者が互いに他人として生き、矮小で孤独で見捨てられたまま生きるのである。 The Lost Boy. The Lost Girl. この世には、世界中のいたる所に少年の死があり、少女の死がある。 One of the Girls in our Party. 私たち一行の一人 The Far and the Near. 遠きもの、近きもの The Web of Earth. 大地の蜘蛛の巣
0 notes
Text
achieve the perfect work-life balance(仕事と人生の完全なバランス)
完璧なワーク・ライフ・バランスを獲得する方法は一つしかない。働かないことだ。仕事(ワーク)と人生(ライフ)が別々の器に盛ってあるとすれば、すでに何かが間違っている。偉大な画家や、詩人、舞踏家、その他あらゆるアーティスト、起業家といったクリエイティブな人たちは、まず自分の生き方を選ぶ。その生き方に合わせて、どうやって食べていくか考えるのだ。自分に満足を与える人生を選ぶのであって社会的な要請を満たすために人生を選ぶのでは、話が逆だ。自分が書いているとき、描いているとき、または踊っているときでも何でもいいのだが、このような人たちはそのとき、嘘偽りのない自分でいられるという人たちなのだ。他のことなんかしている暇はないのである。 ビート・ジェネレーションの象徴的存在であるハンター・S・トンプソンは、一生書き続ける人生を望んだ。そこで彼はジャーナリズムで生計を立てながら、『ラスベガスをやっつけろ』等の小説を書いた。トンプソンは、大儲けもしなかったが貧乏だったこともなく、望み通りの人生だった。作家としての人生を生き切ったと言える。死後、葬式に際してトンプソンの灰は、号砲1発、大砲の弾とともに大空に打ち上げられた。彼らしいはなむけの1発だった。 ハンター・S・トンプソンが、走り書きのメモでこんな助言を友人に寄せている。「つまり、あくまで私の見た感じでは、人生の公式があるとすれば、こんなようなことだと思う。人は道を選ぶ。選んだ道は、自分の欲望を満たすために自分の才能を最大限に発揮させてくれる道でなければならない」。そしてこう結んでいる。「つまり、こういうことだ。前もって決められたゴールに到達するために人生を捧げるのではなく、楽しそうな道を選んだ方が得ってことさ」。トンプソンは、まさにそのような道を歩んだのだ。ジャーナリストとしてカツカツだったことがあっても、トンプソンは書き続けた。それが自分の信じた道であり、それ以外のことは、どうでもよかったのだ。 クリエイティブな人にとって、仕事と人生は合わせて一つなのであって、別々のものではない。自分自身が仕事なのだ。セットで一つなのだから、バランスもへったくれもない。一度仕事と人生が泣き別れになったら、あなたの人生は分裂してしまう。もしあなたが今、仕事を休んでどこかに出かけたいと思っているようなら、ただちに人生そのものを変えなければならない。 ──「仕事とお楽しみのバランスをとった方がいいと思っているのなら、やるだけ無駄でしょう。それよりも、仕事をお楽しみにした方がいいですよ」──ドナルド・トランプ [ 不動産王 ] THE ART OF CREATIVE THINKING by Rod Judkins 2015
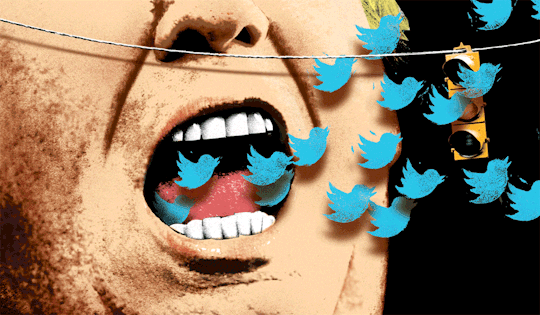
0 notes
Text
if something doesn't need improving, improve it(改良の必要がないからこそ改良してみる)
誰もが今ある普通の方法で満足しているときにこそ、より良い方法を探してみる。現状というものは当初の意味を失っても、集団の序列の序列の中で維持されてしまうものだ。より良い方法は常に存在する。人は、前からやっているという理由だけで、どうしてもあらかじめ決められた方法に従ってしまう。普通と思われているものに流されてしまうのだが、本当はそのやり方を発展させたり改良する点を探すべきなのだ。何度も試されうまくいくと保障されている方法に常に挑戦する心を持とう。どんなに長い間、同じことを同じやり方でやっていたにしても、そこには必ず改良の余地があるのだから。 ──「同じことを繰り返すというのは、前に進むというより熱を起こしてしまうという意味では、摩擦と同じなのです」──ジョージ・エリオット[小説家]
0 notes
Text
get into what you're into(カップの気持ちになる)
何かをするときに、私たちは外側から覗き込んでいるだけのことも多い。遠くから観察しているだけ。あなたと、あなたがやることの間にある距離が遠すぎる。人生を無駄にしないために、そして仕事を無駄にしないためには、内側に入り込んだ方が良い。興味があったら、臆せず入り込んでいこう。自分自身が、企画の対象に「なる」のだ。その対象がカップなら、カップの気持ちになってみる。手にとられるということ、熱湯を注ぎこまれるということ、珈琲の香り、皿洗い機に入れられるということ、誤って傷つけられ、縁が欠けてしまうというのはどういうことか、想像してみるのだ。相手になりきって、中から外を見てみるのだ。 ──「身の回りの環境に身を沈めて、自然を隅々まで観察しなければならない。または、対象に身を沈めて、その対象をどうやって再現するか理解しなければ」──ポール・セザンヌ[画家]
0 notes
Text
be a beginner, for ever(生涯初心者)
経験が浅いということを最大限に活かそう。初心者の視点は新鮮なのだ。素人は新しいアイデアに対して心が閉じていない。だから、できることは何でもやってみる。「ちゃんとしたやり方」を知らないのだから、ある方法論でがんじがらめになっていないのだ。何が「正しい」か知らないというのは、何が「間違い」か知らないということでもあるのだ。 専門家になってしまわないということ。権威になってしまわないということはとても重要だ。その道の大家は、常に過去の体験を参照する。一度うまくいった方法を繰り返す。せっかくの知識を儀式に変えてしまう。豊富な専門知識は、堅固な拘束具になってしまうのだ。その道何十年のベテランといっても、実はある1年分の経験を繰り返しているにすぎない。そして、自分のやり方を脅かす新しい方法が現れたら、揉み消しでしまおうとする。 あなた自身に、そしてあなたの仕事場に新しい風を吹かせるために、今日1日「あなたの仕事じゃないこと」を試してみるのもいい。仕事を交換してみると、イノベーションを推奨する環境��生まれる。いつも新しいやり方を探す。わかりきったやり方を繰り返さない。普通のやり方など捨てて、普通じゃないやり方で試してみよう。 ──「やり方を知っているということは、もう、それを1回やってしまったということだ。だから私はいつも、やり方がわからないことをやり続けなければならない」──エドゥアルド・チリーダ[彫刻家]
0 notes
Text
go from A to B via Z(AからZ経由でBに行く)
いつも同じ道ばかり歩いていれば、自分がどこにいるのか迷うことはない代わりに、自分を見失ってしまう。同じことを同じようにやってばかりいては、いつも同じ結果しか得られない。職場でも、同じことを同じようにやってカビの生えたような結果を出し続けるという罠に落ちてしまいがちだ。何かを変えればいいことがある。机の向きを変えるとか、コピー機を移動して見るとかでも構わない。成長は痛みを伴う。しかしそれも、間違った場所に居続けることの苦痛には敵わない。何かを同じようにやる回数が多ければ多いほど、やり方を変えるのが難しくなってしまう。どんなことでも、今居る A から B へと移動して風景を変えてみなければならないときが必ずくる。でも、どうせなら遠回りして木星経由で行ってみよう。 「オリジナリティが習慣を打ち負かした結果が、クリエイティビティなのだ」──アーサー・ケストラー[作家・ジャーナリスト]
1 note
·
View note
Text
look over the horizon(地平線のそのまた向こうを見る)
壮大なビジョンを持って未来を見据える人たち。彼らには未来が見えているわけではない。その代わり、自分が活動する分野にどのような展開があるかをしっかり見据えている。そして来るべき変化を一番乗りで迎えるのだ。ほとんどの人は目の前の雑事に追われて首を上げる暇もないが、その隙に彼らは地平線の彼方を見ているのである。 「ビジョンを持っているというのは、未来が見えるということだ。あるいは未来が見えたような気がするだけかもしれない。私の場合、見えた通りにやってみると、その通りになる。しかし、白昼夢とか夜の夢に未来を幻視するわけではない。市場を理解し、世界を理解し、人というものを良く理解して、明日はどっちに向かいそうかを知ることで、ビジョンが見えてくるのだ」──レナード・ローダー[エスティ・ローダー社 元社長・会長]
0 notes
Text
『贅沢に慣れてしまうなんて、そんなに悲しいことは他にないと思う』──チャーリー・チャップリン[映画監督・役者]
ラルフ・ワォンド・エマーソン、エミリー・ディキンソン、ヘンリー・デイヴィッド・ソローをはじめとして、数えきれない思想家や詩人たちも、孤独の中に豊かなひらめきの種を見出した。物の少ないオフィスやアトリエは、脳の働きを鋭く保ってくれる。今やっていることに意識を完全に集中するので、ありのままを見ることができるのだ。拡散していた力が一束に収束し、より力強くなるかのように。人の心はさまよいがちなのだ。目移りするものを取り払って、心を一点に留めておこう。
1 note
·
View note
Text
架空の講義『メディア・リテラシーとは? 講師:高橋 利枝』講義メモ:ChuChu♪
『メディア・リテラシーとは?』 レン・マスターマンは、メディア・リテラシーの目的を「多くの人が力をつけ(empowerment)、社会の民主主義的構造を強化すること」(Masterman, L. 1995)としている。 「メディア・リテラシーとは、どのように機能するか、メディアはどのように意味を作りだすか、メディアの企業や産業はどのように組織されているか、メディアは現実をどのように構成するかなどについて学び、理解と楽しみを促進する目的で行う教育的な取り組みである。メディア・リテラシーの目標には、市民が自らメディアを創りだす力の獲得も含まれる」(鈴木みどり 1997) 「メディア・リテラシーとは、市民がメディアにアクセスし、分析し、評価し、多様な形態でコミュニケーションを創り出す能力を指す。この力には、文字を中心に考える従来のリテラシー概念を超えて、映像および電子形態のコミュニケーションを理解し、創りだす力も含まれる」(鈴木みどり 1997) メディアリテラシー欧州憲章(European Charter for Media Literacy)による7つの能力(Livingston, S. 2009) 1.個人やコミュニティのニーズや利益にあったコンテンツにアクセスしたり、蓄えたり、取り戻したり、共有するためにメディアを効果的に利用する。 2.異なる文化的・制度的資源から幅広いメディアの形式とコンテンツにアクセスし、情報選択をする。 3.どのように、そしてなぜメディア・コンテンツが作られたのかを理解する。 4.メディアによって使われているテクニックや言語、慣例やメッセージを批判的に分析する。 5.アイデアや情報、意見を表現したり、コミュニケーションするために積極的にメディアを利用する。 6.不快で有害なメディアのコンテンツやサービスを特定したり、避けたり、挑戦したりする。 7.民主主義的な権利や市民の責任の実践のためにメディアを効果的に利用する。 「メディア・リテラシーとは、 第一に、メディアに対する批判的(クリティカル)な読み書き能力であり、批判的(クリティカル)思考能力は主権者として生きる上で必要不可欠な能力である。 第二に、メディア・リテラシーはメディアを創造し、発表し、コミュニケートするスキルや能力である。単にメディアを利用する能力ではなく、多様なコミュニケーションへとメディアを活用する能力を含んでいる。 第三に、メディアについての基本的人権や社会責任を自覚し、多様なメディアを活用し、メディアが作り出す新しい公共圏に参加して、コミュニケーションする能力を民主主義社会の形成に寄与する力である。」(坂本旬 2009) デジタル・リテラシーとは、「デジタル社会において生きる力」であり、そのために必要な能力は「アクセス」「クリティカル(分析・評価・解釈)」「コミュニケーション能力(表現・創造・参加)」の3つに集約することができる。 ・クリティカル(分析・判断・利用・解釈) (高橋利枝) デジタル・リテラシーとは、デジタル社会を生きるための力だけではなく、「世界とつながり、グローバル社会を共に創る力」であり、言い換えるとデジタル・リテラシーとは、「グローバル社会に参加する基礎的な力」なのである。(高橋利枝) 「グローカリゼーション」とは、「グローバルなローカリゼーション」すなわち「グローバルなるものとローカルなるもの、あるいは、より抽象的なもの──普遍主義と個別主義〔•••〕の相互浸透」(Robertson, R. 1995) テキスト: 『デジタルウィズダムの時代へ──若者とデジタルメディアのエンゲージメント』高橋 利枝 著 新曜社2016年10月7日発行より一部抜粋。 高橋 利枝(たかはし としえ) 早稲田大学文学学術院教授。英国 LSE 大学でソニア・リビングストーン教授に師事し博士号を取得。オックスフォード大学やバーバード大学と「若者とデジタル・メディア」に関する国際共同研究を行う。東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会テクノロジー諮問委員会委員。
0 notes
Text
架空の講義『「デザイン思考の一例」講師:佐宗邦威先生とMIT Media Lab 石井裕先生』講義メモ:ChuChu♪
『自分が見ていた世界と違う幅の世界に触れる──佐宗邦威(SASO KUNITAKE )』 普段自分が無意識に接している世界とまったく違う振れ幅の世界に触れることで、発想をひろげること。 たとえば、以下のような軸で幅をつくることができます。
・人間横断:自分とはまったく違う環境の人の生活や人生に触れる(共感) ・分断横断:共通項を持ちながらまったく違った分野での例に触れる ・地理横断:世界のまったく違った場所でおこっていることに触れる ・時間横断:歴史的な観点から時代を経ておこっている違いと共通点を知る
『発想を飛躍させる:ジャンプ・プロセス』 重要そうなものから一見関係なさそうなものまで、たくさんインプットしたら次は、新しくユニークな切り口を生むために発想をジャンプさせる。様々なアイデア発想法の方法論、このプロセスでのデザイナーの思考は大きく分けて、様々な組合せを結びつける「新結合」、一見違うものに共通点を見出す「アナロジー思考」、前提となるルールを変えてしまう「前提を壊す思考」の3つがある。
『強制発想マトリックスを使った発想』 一見違う要素を無理やり結びつけて発想を生む、新結合による発想法。様々な組���合せを使った発想法「統合(シンセサス)」
『固定観念(メンタルモデル)から離れ、意図的に発想をジャンプさせるためのアナロジー思考』 アナロジーとは、日本語で「類推」と訳されますが、一見違うように見えることに共通点を見出すことを指します。 新しいことを発想する上では、すでに知っている身近な世界である自分の知識を、未知の世界の知識と結びつけることで新たねアイデアを生むことができます。 伝える場面では、新たなアイデアを、はじめてそれを見開きする人が知っていることに結びつけます。つまりら「知っている世界」と「未知の世界」との間を2回、行き来する事が必要になります。「まったく違うように見えるけれど、何か共通点を探す」というアナロジー思考になります。
『アナロジー思考』 1.発想のためのアナロジー(自分の身近なものと結びつける:Make strange familiar) 2.伝えるためのアナロジー(自分の身近なものをまったく違うものと結びつける:Make familiar strange)
MIT Media Lab 石井裕先生
『シンプルに感情に訴えかける体験デザインを行うアウトプット』 伝えたい要素を凝縮していかにシンプルにし、受け手に合ったかたちでドラマ性のある体験を実現し、感情を揺り動かすか。 これには、凝縮フォーマット、ストーリーテリング、体験デザインという3つの要素がある。
0 notes
Text
『双方の対立を超えて問題解決策を編み出す方法──意見の衝突や論争を鎮め、答えを出すためのヒント』
──想像力とは結びつきを見つけることにすぎない、。創造的な人々は、どうやったのかを尋ねられたら、少し後ろめたい思いを抱くだろう。なぜなら、実際には何もしなかったから。ただ、見ただけだ。すると、明らかになってくるんだ。それは、これまでの経験を結びつけて、新しいものを合成できたからだ。それができたのは、人よりも多くの経験をしてきたか、自分の経験について他の人よりも考えてきたおかげだ。──スティーブ・ジョブズ(1996年ワイアード誌インタビューより) 『双方の対立を超えて問題解決策を編み出す方法──意見の衝突や論争を鎮め、答えを出すためのヒント』 ・受動的に話を聞く(パッシブ・リスニング) ・ところどころに集中して聞いている(セレクティブ・リスニング) ・相手が心を開き、もっと話したいと思うような積極的な聞き方(アクティブ・リスニング) 『アンソニー・サッチマン博士(Anthony L. Suchman)』──(以下2012年12月3日Ron Friedman, PhD氏がサッチマン博士に行ったインタビューより一部抜粋) 共感と受容(バリデーション) 人間が進化する過程で、恐怖への反射的な反応は大きく役立った。おかげで近づいてくる捕食者から身を守り、子孫を残せるまでに生き長らえることができたのである。だが現代の職場では、即座に恐怖に反応すれば、周囲と協力して働く妨げになる。それが感情的になるほど、双方が相手の話に耳を傾けなくなる理由の一つだ。 感情がこじれそうになる事態をどう収めればいいのだろうか。 サッチマンは、まず最初に、仕事と人間関係のチャンネルを分けることだと述べている。 「対立は、たいていどちらかが相手の反応を個人的な攻撃と受け取ることで起こる」「わたしの考えに賛成するのは、わたしが好きだから。わたしの考えに反対するのはわたしがきらいだから。そう考えるのだ。そうなると、仕事のチャンネルが塞がれ、率直な意見が伝えづらくなる」 わたしたちの脳の処理能力には限りがある、とサッチマンは指摘する。わたしたちは仕事か人間関係かのどいらかのチャンネルにしか専心できない。2つが交錯してしまうと、建設的な協力は難しくなる。 対立からくる緊張を和らげる1つの方法は、人間関係のチャンネルに意識的に集中し、それを大切にするのを再確認することだ。そうすれば、本当は何が議論の的になっているのかを見誤らずにすむ。ほんのしばらく、人間関係に意識を集中すると、仕事の話から個人的感情が切り離される。 サッチマンは、絆を強め、対話を生産的にするために、次のような表現(頭文字をとってPEARLS)を使うように勧めている。 協力(Partnership) 「あなたとこの仕事に取り組みたいと心から思っています」 「きっと一緒に解決策を見つけられますよ」 共感(Empathy) 「あなたの話から熱意が伝わってきます」 「心配しているのがわかります」 承認(Acknowledgement) 「ずいぶんがんばったんですね」 「努力したんですね。それが現れていますよ」 尊敬(Respect) あなたの創造性はすばらしいといつも思っています」 「これについてあなたが詳しいのは間違いありません」 正当化(Legitimation) 「これは誰でも苦労しますよ」 「これでは誰もが不安になりますよね」 応援(Support) 「力になりたいです」 「あなたの成功を願っています」 PEARLS 協力(Partnership)・共感(Empathy)・承認(Acknowledgement)・尊敬(Respect)・正当化(Legitimation)・応援(Support) つながりを求める気持ちを大切にすれば、会話の質を高めることができる。議論が激しくなるほど、そうした表現が重要になる。 判断を避ける──じっくり時間をかけて近づく──共感を示す──結束する THE BEST PLACE TO WORK ──The Art and Science of Creating an Extraordinary Workplace by Ron Friedman, PhD ©2014
0 notes
Text
『ホモ・サピエンスと言葉』話:ユヴァル・ノア・ハラリ(歴史学者)2017
──「みんなにとっての物語(story)は、オバマ大統領が広島演説で語ったstoryにも繋がるstory」──ChuChu♪ 大切なのは物語と現実を分けて考えること。物語そのものが悪いわけではない。それがなければ社会は機能しないのですから、人々が金銭を信じなければ経済は崩壊するでしょう。大事名のは、物語を私たちの役に立たせること。私たちが物語の奴隷ににされてはならないのです。信じる物語が違うからといって戦争で殺し合うようなことになってはいけない。 イスラエルとパレスチナは何十年にもわたって争いを続けています。この紛争は領土をめぐるものでも、食糧をめぐるものでもなく、物語をめぐる争いです。イスラエルにはイスラエルの物語があり、パレスチナにはパレスチナの物語がある。合意できないから戦う。こうなってしまうと、物語は私たちの役に立ちません。大事なのは現実と物語を峻別すること。それには、様々な方法がありますが、私にとっていちばん良い試金石は「痛み」があるかどうか。何が「現実」で何が「物語」かを識別するためには、痛みを感じるかどうかを考えてみる。たとえば、金は痛むか、国家は痛むか。敗戦によって国家は苦しむと思うかもしれないけれど、痛むのは国民であって国家ではない。日本が第二次世界大戦に負けたとき、苦しんだのは国家ではなくて日本の人々です。つまり、人や動物は痛むから現実だけど、金や国は発明された物語でしかない。人間にとっての良い物語とは、世界の痛みを減らすものです。パレスチナとイスラエルの物語を語るとき、公平に客観的に話をする、イスラエル寄りの立場をとらない。 あるグループの中で育ち、そっちの側の物語をずっと聞かされて、他方の物語を知らなければ、無意識に一方の物語が現実で他方は嘘だと思いがちです。直接関係ない地域の物語なら客観的になれますが、ことが自分の属するグループとなると、努めて客観的な立場をとるようにしないとどうしても偏ってしまいます。──ユヴァル・ノア・ハラリ『ホモ・サピエンスと言葉』(新潮社・季刊誌『考える人』No.59 2017年冬号スペシャルインタビューより一部抜粋) ユヴァル・ノア・ハラリ(Yuval Noah Harari) 1976年生まれのイスラエル人歴史学者。エルサレムのヘブライ大学教授。英オックスフォード大学より博士号取得(中世史、軍事史)。『サピエンス全史 文明の構造と人類の幸福』(河出書房新社刊)は48ヵ国語に翻訳刊行される世界的ベストセラーとなった。)
1 note
·
View note
Text
人道的介入のための規準──ピーター・シンガー(One World:the ethics of globalization second edition ©2002 @2004 by Peter Singer)
残虐行為がおこなわれたとき犯人を処罰することは、そうすることが正義の要求にかなっているとの信念から、ほとんどの人が支持している。公利(功利)主義の観点からすれば、過去に罪を犯した者を処罰するのは、同様のことをするかもしれない他の者たちに対して、正義からの逃げ場のないことを教えて、新たな罪を犯すことを思いとどまらせるためである。しかしながら、処罰に対する恐怖が犯罪防止のためにつねに十分であるというわけではないから、介入の〔是非に関する〕問題が依然として生じることになる。処罰が正当化できるなら、いまおこなわれようとしている犯罪や現におこなわれている犯罪を止めることも正当化できるだろう。残虐な行為がおこなわれているときに介入する権利があるだけでなく、介入するための方法が他国に進攻することしかないとしたら──ある著名な国際委員会が2001年にその報告書のタイトルで示唆したように──「保護する責任」もあるのだろうか。しかし、そのような責任があるとしても、各国はどのような状況の場合にそのような責任にもとづいて行動するべきなのだろうか。 哲学者がこの問題を取り上げることは何も新しいことではない。カントは、『永遠平和のために』と題する「哲学的素描」を書いたが、そこで彼は、いかなる国家も他国の政体や政府に武力によって干渉してはならないと論じた。また彼は戦争の準備を進めている国家は、平和の可能性について哲学者の意見を求めるべきだとも考えていた。ジョン・ステュアート・ミルは、「自らは攻撃を受けていない国が戦争を始めてよいのはいつか」という問題以外に、哲学者が関心を持つべき問題はほとんどないと述べた。ミルは、「他国の問題に介入することの正当性と、介入を控えることの正当性(これは前者の正当性とはまったく同様に疑わしい場合もある)を明確かつ合理的に評価するための何らかの規則ないしは規準」の確立を哲学者が模索するべきだと考えていた。 どのような場合に介入が正当であ��また義務でさえあるのか、あるいはどのような場合にそうではないのかを、ミルが言うように「明確かつ合理的に評価する」ための規則や規準とはどのようなものだろうか。この問題に関連してよく聞かれるのは、国際法に関するラッサ〔ラサ〕・オッペンハイムの有力な論文に出てくる次のような語句である。 国家は、その人的および領土的支配権によって、自国民を自らの裁量に従って扱うことができるという一般的な同意がある。しかし、そのような裁量には限界があるという見解を支持する相当数の意見や慣行が存在する。すなわち、国家が自国民の基本的権利を否定し、しかも人類の良心に衝撃を与えるような仕方で、自国民に対して残虐な行為を犯して迫害するとき、人道のための介入をすることは法的に許される。 マイケル・ウォルツァーは、この規準を受け入れ、『正しい戦争と不正な戦争』において、以下のように書いている。 人道的介入が正当化されるのは、それが「人類の道徳的良心に衝撃を与える」行為に対する(成功する見込みが十分にある)対応である場合である。この古めかしい文言は、私には完全に正しいと思われる。••••••この文言が言及しているのは、普通の男女が日々の生活の中でえた道徳的確信である。また、そうした道徳的確信によって説得的な議論が展開できるとすれば、国連を待つ(世界国家を待つ、救世主を待つ••••••)といった受け身の態度をとる道徳的理由は何もないと考えられる。 この文が書かれたのは1977年である。この間、救世主は現れなかったが、国連は──その活動が厳しい批判にさらされ、切望されているほどつねに迅速かつ効果的だというわけではなかったが──活動できることを示してきた。ウォルツァーは、この「良心に衝撃を与える」という規準を支持し続けていて、次のように指摘している。 「死体が死後硬直する前にカメラ・クルーが到着する」時代においては、人類の良心に衝撃を与える行為は──私たちがそうした行為と密接に結びついているために──以前よりもいっそう衝撃的なものになっている。 そうだとしてもウォルツァーは介入に反対する強い確信は持ち続けるべきだと主張する。ウォルツァーが特に否定するのは、人権侵害だけで介入を正当化する十分な根拠になるとか、民主主義のために介入することは正当なことだといった考えである。あるところでウォルツァーは、介入に反対する強い推定の根拠を擁護しているが、それは国家において、国民が共同生活を送ることができて、その国家の社会構造の内部においてその国民なりの仕方で自由を求めて戦うことができる場合には、その国家の主権を守ることは重要であるという観点からのものである。他のところでは彼の議論はもっと実際的なものである。すなわち、ローマ時代以来、帝国主義列強は、内戦に介入して版図を拡大しようとしてきたことを忘れてはならない。介入は、それがどのような形のものであれ、いとも簡単に併合のための口実になるということである。ウォルツァーは、正当なものであったと彼が考える介入の例をいくつかは挙げている。1971年のインドによる当時の東パキスタン──現バングラディッシュ──への介入、1979年のタンザニアによるウガンダのイディ・アミン体制に対する介入、同じ年のベトナムによるカンボジアへの介入である。しかし彼によれば、全体として一国の国民には「帝国の助けなしに、国民自身で自らの困難を解決することが認められなければならない」。 ウォルツァーが「人類の良心」という規準に訴えていることの問題点は、この良心が、さまざまな時代や場所において、異なる人種間での性行為、無神論、混浴などによって衝撃を受けてきたことである。皮肉なことに、ナチス自身が「国民の健全な感性」を法規範の地位にまで引き上げ、同性愛の抑圧に用いたのである。国際的な法律家たちが人類の良心の衝撃を与える行為について語るとき、彼らがそのようなことを言っているのではないことはわかるが、どうすれば彼らが言おうとしていることを正確に特定できるだろうか。 国連事務総長コフィ・アナンは、介入が正当化されるのは、「死と苦しみが多くの人びとに加えられていて、しかも名目上支配している政府が、それを止めることができない、もしくは止めようとしないときである」と述べている。彼はこの見解を擁護して、国連憲章の目的は「個々人の権利を守ることであって、個々人を虐待する者を守ることではない」という。「人類の良心に衝撃を与える」という規準に比べて、アナンの規準にはより具体的であるという利点がある。しかしながら、アナンの規準をさらに正確なものにするには、「苦しみ」という個所をもっと具体的な危害の一覧表に代えなければならない。これを行ったのは、1948年の集団虐殺罪の防止および処罰に関する条約をはじめとするさまざまな国際的法律文書であって、この条約の考え方は、1988年の国際刑事裁判所に関するローマ規程にも受け継がれている。同条約の第二条は、集団虐殺の犯罪を以下のように定義している。 集団虐殺とは、国民的、民族的、人種的または宗教的集団に対して、その全部ないしは一部を破壊する意図を持っておこなわれる次の行為のいずれをも意味する。 (a)集団の構成員を殺すこと。 (b)集団の構成員に重大な肉体的または精神的危害を加えること。 (c)集団の全部または一部の成員の身体を破壊することを企図した生活条件を当該集団に故意に課すこと。 (d)集団内における出生を意図的に阻止するための措置を強制すること。 (e)集団の子どもを他の集団に強制移送すること。 これらすべての行為が犯罪とされるべきであり、また、それをおこなう者は、可能な場合には常に訴追されるべきであるが、これらの行為の間に区別を設けることは可能である。軍事的介入は広範囲に被害をもたらす危険があるのだから、集団内における出生を意図的に阻止するための措置を強制することや、集団の子どもを他の集団に強制移送すること��、それ自体としては軍事的介入を正当化するには不十分であろう。もちろん、こうした措置には一般に肉体的な暴力がともない、集団の構成員に対して深刻な精神的危害を与える可能性もある。したがって、こうした状況は、集団虐殺に関する定義の他の項目も満たすことになって、軍事的介入を正当なものにするかもしれない。さらに、これらの行為が特定の国民的、人種的、民族的または宗教的集団に対しておこなわれたかどうかは、これらの犯罪を「集団虐殺」と認定する役割を果たすにすぎない。同じくらい多数の罪のない人びとに向けられたら手あたり次第の暴力は「人道に対する罪」になり、それらもまた、正当な介入の引き金になるだろう。 「人道に対する罪」の定義は、「集団虐殺」の定義ほど確定的なものではない。しかし国際刑事裁判所に関するローマ規程では次のような定義が用いられている。 「人道に対する罪」とは、一般市民に対する広範な、または組織的な攻撃の一部として、それを知りつつ実行された場合の、以下のいずれの行為をも意味する。 (a)殺人。 (b)殲滅。 (c)奴隷化。 (d)住民の追放または強制移送。 (e)国際法の基本ルールに違反した拘禁、または他の肉体的自由の極度の剥奪。 (f)拷問。 (g)レイプ、性的奴隷化、強制売春、強制妊娠、強制不妊、もしくは他のいかなる形態のものであれこれらと同程度の性的暴力。 (h)この項で言及されたいずれかの行為、または本裁判所の管轄権内のいずれかの犯罪と結びついて実行された、特定可能な集団あるいは共同体に対する迫害で、政治、人権、国民、民族、文化、宗教、第三項で定義されているジェンダーなど、国際法の下で普遍的に許容されないと認められている根拠によるもの。 (i)人を強制的に失踪させること。 (j)アパルトヘイトの罪。 (k)同様の性格を持つその他の非人道的行為で、多大の苦しみ、すなわち、身体、または精神的もしくは身体的健康に対する重大な害を意図的にもたらすもの。 私たちが軍事的介入を正当化する要因を求めているなら、ここでも、これらの犯罪の広範かつはなはだしい例に焦点を当てる必要がある。 今や私たちは、ウォルツアーとアナンの規準に加えて、「集団虐殺と人道に対する罪」のこれらの定義を利用して、次のように、言うことができる。 人道的介入が正当化されるのは、多数の人びとに対して、殺人に及んだり、重大な身体的または精神的な危害を加えたり、あるいは身体的破壊を起こすような生活条件を意図的に課したりする行為への(成功する見込みが十分ある)対応の場合である。さらに、名目上支配している政府が、そうした行為を止めることができないか、もしくは、止めようとしない場合である。 たしかに、この定義は答えよりも疑問のほうを多くもたらす。「多数」というのはどのくらい多くの人びとなのか。身体的または精神的な危害はどの程度重大なものでなければならないのか。多数の人びとに身体的破壊をもたらす生活条件が意図的に課せられたのはいつであるかを誰が判断するのか。人道的介入が正当化されるのは、この規準が満たされたときだとしても、それと同時に、他の国々にも介入する義務が生じるのだろうか。多数の人びとを殺すような環境汚染をそうと知りながら引き起こすことや、止めようとしないことも、この定義を満たすことと見なされうるのだろうか。問題となるのは人類に対してなされた行為だけなのか。何万頭ものチンパンジーを殺すことや、かけがえのない生態系を破壊し、それによって多くの生物種を絶滅させることも、介入のための根拠になる日がいつか来るのだろうか。 これらの疑問に答えることは困難であり、──あまりにも困難であるために──予見可能な将来における政治的行動のための基礎とはなりえないだろう。2000年にカナダ政府によって設立された「介入と国家主権に関する国際委員会」がその『保護する責任』という報告書でおこなったように、控えめなところから始めるほうがよい。この委員会は、オーストラリア元外相のギャレス・エバンズとアルジェリアのベテラン外交官のモハメド・サヌーンが共同議長となり、12カ国から集められた12人の著名な専門家によって構成されたものであったが、彼らが注意を払ったのは同委員会の勧告が政府的に実行可能なものでなければならないということであった。その目的のために同委員会は、正当と認められる軍事的行動の規準を二つにまで絞った。 A:大規模な生命の損失。現実のものであるか、それとも懸念されるもので、集団虐殺の意図の有無は問題ではなく、国家による意図的な行為、国家の怠慢ないしは無能力、あるいは国家機能の不全状態のいずれかの産物である場合。 または、 B:大規模な「民族浄化」。現実のものであるか、それとも懸念されるもので、殺害、強制追放、テロ、レイプによるもの。 同委員会は、これらの規準が満たされたときには、介入する権利があるだけでなく、これらの行為の犠牲者である人びと、あるいは犠牲者となる危険が差し迫っている人びとを保護する国際的な責任があると述べている。この介入のための条件は、人道に対する罪に関する国際刑事裁判所の定義による条件よりもいくつかの点で狭くなっているので、介入のための規準が満たされにくくなっていると考えられるかもしれない。しかしある重要な点で、同委員会の第一の規準は、人道に対する罪に関する国際刑事裁判所の定義を優に越えている。すなわち、介入の引き金となる「大規模な生命の損失」は、意図的な人間の行為の結果である必要はない。同委員会は、人びとが餓死するのを防ぐための介入が、国家が人びとを援助できなかったり、援助するのを怠ったりする場合には、正当化できると述べているのである。 これら二つの規準は、国際社会がある状況への介入を検討しているとき、少なくとも、適切な出発点として使えるように思われる。したがって、次の問題に関心を移すことにしよう。介入のための規準──これら二つの規準であれ、他の一組の規準であれ──が満たされたのはいつであるかを誰が判断するべきなのだろうか。実際のところ、この疑問に対する答えは介入のための権威ある手続を定めることができるのではないかと思われるグローバルな機関が、世界に一つだけ存在する。
1 note
·
View note