Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
九頭八岐蛇竜婚姻譚
※胸糞話※
【クズヤマノオロチ伝承】の裏側です。
草薙の前世(転生前)にあたる話です。現在の草薙には思い出せない記憶。
真の姿は名の通り大きな大きな九頭の大蛇。人間化はこういうイメージ。

小さな神子のために、一生懸命化ける練習したそうな。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
山を流れる命の川。その化身たる九頭八岐大蛇に仕える者たちが居た。
力を持ちながらも平和を愛す竜の一族。
中でも比類なき才に恵まれ、凛とした若き神子……名は叢雲といった。
幼き日から不可視の神と触れ合える異能を持っていた叢雲。
大蛇は久方ぶりの話し相手を歓迎し、彼女の成長を見守った。
ぐうたら酒仙だが頼れる大蛇。聡明で世話好きな叢雲。互いに惹かれ合った二人はやがて、つがいとなった。
「足が縺れる」と文句を言いながらも、彼女の体温を身近に感じるため人の姿に化けた大蛇は、つがいの印として自らの蛇皮で編んだ首巻を贈った。
時に小さな喧嘩をしながらも、仲睦まじく手を取り合い、豊作と平穏を守ってきた大蛇と叢雲。
しかし、幸せな時間は長くは続かなかった。
世界戦争。激しい争いの焔は当然この地にも及んだ。
命の川を以てしても消せぬ業火は、木々や生き物だけでなく、一番恐ろしいものを燃やした。
人の心である。
叢雲には双子の姉『天(アマノ)』がおり、彼女は平和呆けした一族に辟易していた。
特に妹の叢雲が疎ましかった。
同じくして産まれたのに、瞳に宿るとされる神通力は叢雲だけのもの。
天が持つ武勇の才は、「平穏を望む人々」には評価されなかった。
落ちこぼれと罵られ、種の保存……その器としてぞんざいに扱われる自分。
対して、清らかな妹は神様にだって愛されたという。
仔犬のように無邪気に慕ってくる叢雲。
自分から全てを奪った妹の、星空のように輝く瞳が大嫌いだった。
そんな最中起こった戦争。熱い血潮を持て余した者にはこれ以上無い好機。
天は徒��を組み、待望の戦火の中へ身を投じて行った。
相見える相手が、天敵である妖精帝國軍であるとも知らずに。
かくして数多の死傷者を出した大蛇山であったが、叢雲は傷ついた者と穢された川を悼み、祈りと供物を捧げ続けていた。
川の汚染に比例して化身たる大蛇も衰弱し、山を去るよう伝えたのを最後に姿を保てなくなった。
瞳を潤ませ、救いを乞う叢雲。その姿が遂に姉の逆鱗へ触れた。
「貴重な食料をどこにやる。虚空に向かって話しかける不気味な女め」
「皆の者見ろ、戦いもせずただただ食い扶持を減らすクズだ」
「祈りの神子だと言うのなら、その身を以てこの戦火を消して見せよ」
「御神酒の代わりに血を、果実の代わりに肉を。 人の祈りを込めた神子を、いま大蛇様へ捧げよう」
燃え盛る焔に追い詰められ、叢雲は彼の漣川へと落とされた。
何よりも守りたかった命が、体内で溺れ息絶える感覚。
蛇の悲痛な叫びは、誰の耳にも届かなかった。
そして物語は伝承へと還る。
麓の女性こそ叢雲の姉、天。
そして彼女が産んだ奇形の赤子。
絞首痕を這う蛇の紋様、抉り取られた右の眼窩。
川へ落ちた直前、叢雲が負った傷をそのままに産まれた赤子こそ、復讐のために人へ堕ちた大蛇神そのものだった。
赤子と目が合い、天が叫ぶ。「早くその子を、あの山へ」
幾年月、復讐は果たされたり。
しかし大蛇の心は満たされることは無く、それどころか飢餓感は増すばかりだった。
息絶えた天、叢雲と同じ顔に思わず息を飲む。
しかし気がつけば、彼女は腹の中だった。
混濁する自我。心が、乖離していくのを感じた。
「人の血を川、屍を山とし全てを喰らう。暴飲暴食の悪しき神よ」
呑めども呑めども乾きは癒えず、喰えども喰えども満たされず。
命が喉を通り過ぎて行く度に、漣川の記憶が蘇る。
「お身体に障りますよ」と酒を取り上げ、窘める叢雲。
まだ呑み足りないと文句を言えば、困ったような笑顔でぽんぽんと膝を叩く。
そんな日々が帰ってこない事実を、突きつけられるようだった。
思い出の首巻を寒空の慰めとし、途方も無く歩き出す大蛇。
足が縺れ、頽れた泥の味さえ、もう分からなかった。
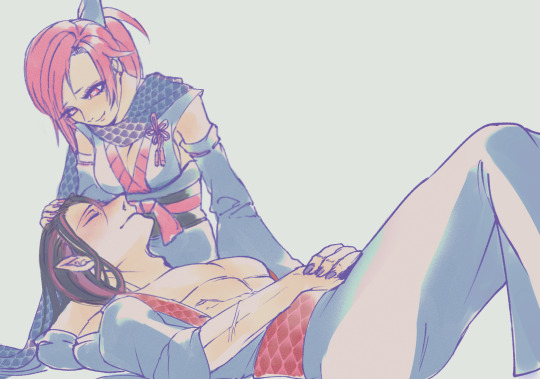
0 notes
Text
柘榴山昔話
ぷつん。
裂けた皮膚から血液が這い出る様子は、羽化を迎えた蛹のようだ。
しかし億劫なそれは翅を広げることなく、背を丸めては固くなる。
そうして出来上がった紅く光る石を丁寧に削ぎ落とす。
昨日は腹、今日は腕、明日は脚、明後日は背中。
塞がったばかりの傷口を順繰りに花開かせていく。
摩耗した心にはどこか他人事のように映ったが、それは確かに僕の体で繰り返されている__だった。

◆◆◆
人里から遠く離れた場所に、狐たちが棲む山があった。
その山は鉱石を多く有し、特に焔石と呼ばれる石が強い輝きを放っていた。
触れた者は加護を賜ると言い伝えがあり、彼らは大切にその石を守ってきた。
しかし焔石の強い光は外界の者をも惹き寄せ、不成者たちが山を無遠慮に踏み荒らし、切り拓いた。
開拓により顕になった山肌に、紅石をぎっしりと実らせた様子からいつしか『柘榴山』と呼ばれるようになった。
狐たちは怒り、持てる力全てで人間を追い払った。
そして包帯で傷口を覆い隠すように、霧の結界を張り巡らせて柘榴山を人目から遠ざけた。
白濁にじんわりと滲む誇り高き紅。
その姿に胸を詰まらせた彼らは戒律を立てた。
「二度とその山に余所者を入れてはならない」
「法を破る者は、柘榴山の痛みを知ることになるだろう」
◆◆◆
それから狐と人、それぞれが何世代にも渡り歴史を紡いだ。
伝説を信じ、語り継ぐ者の減少と比例するように、柘榴山も少しずつベールを脱ぎ、再びその顔を空に覗かせた。
◆◆◆
外の世界が見てみたかった。
好奇心というものは天邪鬼で、ダメだと云われる毎にぐんぐん育つ。
ちょっとだけ、すぐに帰ればいい。きっと誰も気づかない。
ある日僕は、山をこっそり抜け出した。
そして、彼と出会った。
最初は狐の子だと思った。でもよく見ると尻尾が無い。そこで漸く気がついた。
“人間は恐ろしい”ずっとそう教えられてきたけど、オトナってやっぱりウソつきだ。
話してみると、僕らと何にも変わらない。
“外の世界は穢れている”それもウソだった。
彼が連れて行ってくれたウミ。そこで初めて見た色が忘れられない。何と云ったっけ……そうだ、アオ色。
山の足元にウミがある事だって知らなかった。濃い霧が隠してしまっていたから。
人間が面白いやつだって事も知らなかった。オトナたちが遠ざけたから。
だから僕は自分の目で見たものを信じようと思った。
オトナたちの目を盗んでは、彼と会い“人間”を知った。
あんなに楽しいのは、随分久しぶりだった。
ある日僕は戒律を破り、彼を住処に招き入れた。
怪我をした彼の手当をしてあげたかった。
僕と同じ紅を、滲ませていたから。
「これがあればどんな怪我も治せる。
でもね、二人だけの秘密だよ」
彼の傷口に、紅く光る石を翳した。
0 notes