Text
Contents Design 第15回
今更書いてもきっと誰も見てないだろうってくらい書くの忘れてて今提出する(2020/02/07)。
なんで遅れたの?って思うかもしれないけど、個人的にインターンに行こうと思ってて、それのポートフォリオを作ろうと2年次の振り返りをしてたらふと思い出したんだよ。まぁこれはヤベえな。ここまで頑張ってきて最後やらかした蛇足蛇足。竜頭蛇尾。
こんなタイミングで書いてるから、先生方やSA・TAの方々はきっと見てないんだろうなとか、次のCDの子に見られたりすんのかなとか、そういうことを考えながら書いている。あっ���そういうば俺、CDのSAに選ばれたんだよ〜〜嬉しい〜〜名誉〜〜〜〜。(もしこれがBLOG NAVIのとこに貼られてて見てるならここじゃなくて第14回までのを参考にしてね頼むから)
一旦ポートフォリオやめてこっち書こうかなってつらつら書いてるんだけど、今思えば半年間のグループワーク楽しかったな。喧嘩とか雰囲気悪くなるみたいなのって半年も一緒にやってれば絶対あるから、まぁそういうことがあったら一歩引いて全体を見てみるとか落ち着くとかそうやって出来たらなぁって思って取り組んだけど、当事者になるとまぁ難しいよねそういうの。しょうがない。それを経て大人になるのだー、多分。
とか書きながらポートフォリオを思い出し焦ってる俺。マジで会社に見せられる作品なんてないぞ...。「そもそも学生身分で偉そうにパンフレットを制作しましただの、ポスターを作りましただの言って良いのか?いや良くない。」ってさっきからやはかは反語表現繰り返しまくりで全く進まないんすよね。自分に自信が持てない。去年、作ったポスターを友達経由で面識のない喋ったことも見たこともない大人に見せ(られ)たんだけど、「う〜ん、学生感丸出しだね」ってコメントされ、それがトラウマ。学生感ってなんだ?チープなのか?子供っぽい?大人になりきれてない?うわあああああああああああああああああああ...。
まぁ四の五の言わずにまとめてみるか。
0 notes
Text
Contents Design 第14回
今回は私用によって授業を欠席した。その分授業に授業に出てくれたグループのメンバーから今回やったことやコンテンツの進捗などを教えてもらい、状況を把握した。
次回は成人の日で休み。再来週にはもう最後の授業、すなわち最終発表だ。長かったようですごい短かった気がする。みんなの夏課題を見たのが昨日のことのようで仕方がない。集中しているとこんなにも時が過ぎるのは早いのかと思い知った。
もしかしたら一足早いかもしれないが、書くこともないのでこの授業で思い知らされたことを少しだけ...。それは現場に足を運ぶこと、ペルソナとしている相手にテストを行なってもらいブラッシュアップすることの大事さは特に思い知らされた。この授業での小学校訪問にて収集した情報とユーザビリティテストのフィードバックはコンテンツの底上げになったと感じる。これはこの授業で習い、これからも私にとって武器となる知識だろうと思う。誰かに何かを依頼され、自分が新たなものを作る時、この知識を用いて積極的に足を運んで行こうと思う。
まぁあんまり書きすぎても次回書くことなくなりそうなのでこれくらいで。写真は欠席したので、このTumblr用に写真をいじって作った画像でも置いておく。


0 notes
Text
Contents Design 第13回
第2回登戸小学校訪問、ユーザビリティテスト!今回に関しては小学生のパワーとかスタミナじゃなくて、早起きでやられた。もはや起きれる気がせず、オールした。私以外でオールして小学校訪問に臨んだ人も結構多いんじゃないか…?朝超寒い中バカデケェおもちゃを運び、小学生の圧倒的な体力にやられ、しかし午後はタコパとCDの授業の組み方も飴と鞭が上手いこと、上手いこと…。
・どんなことをしたのか
前述した通り、登戸小学校にてユーザビリティテストを行った。1セッション35分(?)を4回ほど行い、様々な小学生におもちゃを体験してもらい、口頭ではあったがフィードバックをもらった。ここでもう一度私のグループのおもちゃの流れをおさらいすると、
まずはこのおもちゃの概要→百聞は一見にしかず、まずはやってみよう→1,2回ほどやったら次は高いところからやってみようと促す→1度高いところからやったら次は重い物を入れてみようと促す→ここまでの全4回の試行が終わったら5回目もう一度自由にやらせる(高さ設定、重さ設定は子供達の自由に)→5回終わったら学習のおさらい。→ここまでで恐らく時間が余るので(ほぼ確定)、あと2,3度やらせる。→全(7or8)回の試行が終わったらそれらを得点化し、ランキングに載るか否か、載った場合その順位はどれくらいかを楽しむ。
という流れになっている。子供達は私たちの考えた通りの流れに沿ってやってくれた。中には暴走する子や飽きてしまう子も見られた。1セッションが終わると、そのセッションで遊びに来てくれた小学生たちがフィードバックをいただいて撤収という形になる。
午後は午前に行った登戸小学校訪問の振り返りを各グループで行い、5限はタコパ!思って以上に楽しかったぞ。
・授業を通して何を感じたか
小学生たちの意見は真っ直ぐで純粋なものであった。私のグループに一番多かったのは難しいという意見だった。でも私は諸学校訪問全体を見て、この難易度設定に間違いはないと思っている。何故なら難しすぎて飽きちゃう子は一人しか見受けられなかったからだ。その子が意見してくれた子の一人で、もう一人の意見してくれた子は難しくて点数が取れず、ランキングに載れなかった子だった。後者の意見はシンプルに悔しさから出たものだろうと思う。ランキングに載るというのはそう簡単なものではないぞ、少女よ。少し脱線したが、その一人のために難易度を下げてしまうのは個人的に勿体無いと思う。大帝の子は難しいと感じながらも、どう点数を取ろうか何度も飽きずに試行錯誤してくれた。その結果ポイントが取れた時は非常に嬉しそうに見えた。私はこの難易度の高さが子供たちをこのおもちゃから離させない一つの要因だと考えている。
ただポイントを取る以前に、車が山の傾斜の途中で脱線してしまうのは非常に良くない。これは高さや重さとは関係のないミスで、子供達の試行錯誤の邪魔になる。修正すべきポイントだ。
(↓ 全日本カークラッシュ協会代表審査員 相原)

(↓ カークラッシュ協会公認臨時審査員 田島さんと大石さん)

上記を踏まえても、今回の小学校訪問は成功だったと個人的には言える。何故なら楽しんでくれた子が多かったからだ。遊んでくれた中でも、数人の「あっちのやつやりたい」という発言には心が折れそうに���ったがその数人を除いた他の全員は時間になってもあと一回、あと一回と遊んでくれた。これにはあと数回の授業を乗り切るモチベーションの支えになってくれた..。
最後のタコパは楽しかった、以上!良いお年を。
・次回までにやってくること
・Webサイト制作:これはグループの課題、Webサイト実装得意じゃないけどWebサイトの構造くらいは頑張ろうと思う。
0 notes
Text
Contents Design 第12回
小学生大丈夫かな…。どうやらインフルエンザが流行り始めてるみたいで怖い。朝電���で老若男女問わずとんでもねぇ数の人と同じ密閉空間で空気を共有してると思うと、インフルエンザ怖いより吐き気がしてきた。来週に伸びたユーザビリティテストだけど、今週も頑張りましたとさ。
・どんなことをしたのか
今日は急遽、CSでの作業となった。前回と同様、冒頭にやるべきことの説明(こういうのこれからやるからねってやつ)をしてその後は各グループで個人作業。今日説明されたことはブックレット、パンフレット、Webサイト。個人的に重要というかやらなきゃいけないのはここら辺だと聞いてて思った。説明は以上おしまい!
各グループでの作業において、私は今回もポスター制作。タイトルの方は終わったので、コンセプトの方のポスターに取り組んだ。2枚目大変だけど、やりたい事をやらせてもらっているので、構わんです。ただまぁ仕事量に差があるのはおかしいけどな。
・授業を通して何を感じたか
ブックレットは個人的に楽しみである。まぁこんな拙く汚い言葉遣いではきっと選出されないだろうが、それでも他のみんながどのような思いでこの授業に取り組んだのかはとても気になるので楽しみである。パンフレットは何とか提出出来た。だが、修正点が見つかり星野先生のお世話になってしまった。AiはIxdとこの授業のおかげで基礎の基礎ぐらいは理解しているが、Psに関してはまだまだ分からない事ばかりである。しかし、Psも使えたらデザイナーとしてさらに引く手が増えるのでぜひ習得したい気持ちはある。Webサイトであるが、これは前半にたくさん仕事をした人の比重は軽くして、贔屓目に見てもあまり仕事をしていない人にやっていただきたい。とは言っても丸投げは良くないので、サイトの構成や構造は一緒になって考えたいと思う。Ixdの時もそうだったが、ビジュアル面での理想は高いが、それをそのままサイトに落とし込めず、理想と現実の差分が嫌になるのでコーディングは非常に苦手だ。やれば出来るようになると言われたが、今だにやらないので出来ていない。もししなきゃいけない日が来ても、きっとこの世の中にはコーディング出来るけどビジュアル面が弱い人も居ると思うので、そういう人とタッグを組んで頑張りたい。今回はグループのメンバーと協力することにする。
ポスターに関しては不幸中の幸いか、ちょうどグラフィックデザインでGrid Systemについて習ったばかりだ。まだまだ身についていない部分ばかりだが、何とか見やすい配置を探して行こうと思う。
(↓ 授業外活動中の私のグループ)

・次回までにやってくること
ポスターの完成:2枚とも印刷、カットまで頑張る。(個人)
コンテンツの改善:基本的には出来ているが、よりね。(グループ全体)
0 notes
Text
Contents Design 第11回
前回は疲れた…。ひたすら小学生の圧にやられた。今回はその振り返りと次回の登戸小学校訪問への準備だ。何もない回だがこういう回が実は一番重要だったりするかもしれない。
・どんなことをしたのか
授業が始まってすぐにポスターを設置する台の使い方のレクチャーが始まった。次回の登戸小学校訪問で使うものだ。当日の準備時間は30分しかないのでこれに時間をかけるわけにはいかない。4人誰でも組めるよう、見てるだけの人間が出ないように全員で取り組んだ。
その後は各グループに分かれて作業。私はポスターの修正を行った。ただの雲だと面白みに欠けるのでシェイプをスウォッチしてパターン化したものを雲の柄にした。
時間いっぱいまで作業した後は次回までに準備することを取り決め、大学近くに住む杉山の家にコンテンツを持ち運んだ。
・授業を通して何を感じたか
まず感じたのが次回の登戸小学校訪問時の準備時間の短さだ。朝早くに小学校に行き、30分で準備する。正直前回のような調整している時間はない。前日までに調整して当日パパッと準備できるようにしなければ。全員が出来ないということがないように、当日までにしておく必要がある。
私はポスターを担当していたので授業時間はポスター制作に勤しんだわけだが、ポスターは2枚必要になる。1枚はイラストを中心とした子供向けのもの、もう1枚は保護者や大人に向けた説明口調のもの。2枚作るのは相当しんどいという甘えが2枚めの大人向けのものをグループの佐々木に仕事を任せる口実になったのだが、これがまぁ悲惨だった。俺の判断ミスです。努力したことは認めるので敢闘賞を送ろう。でも彼がやったのは本当にグラフィックデザインや情報デザインを受けた生徒のものなのか?というものだった。まぁ絵の上手い下手はしょうがない。俺もそんなに上手くないし。でもだったら下手なりにトレースとかしたら?って感じのイラストだった。これじゃまるで説明と絵が一致せず何のこっちゃ実際に見ないとプロセスが分からん。それと説明。一回説明文書き出して必要な情報とそうじゃない情報の取捨選択した??ってくらい情報がまとまっておらず無駄に長い文章、イラスト分の説明文の大きさを無理に埋めただけ。俺がやれば良かった…まぁとりあえず基盤となるものにはなったしまぁいいか。ていうかなぁ!?「ごめん」って謝るくらいならやってやるから金をくれ。最初から胸張れるくらいに頑張ってくれよ。指摘したとこ全部俺の言いなりじゃん。お前が作ったんだろ?そこにお前の意思はないのか?自分が作ったものボロクソ言われて悔しくないのか?
ああ…良くない癖が。自分の熱量と他人の熱量を比べちゃいかん。同じ熱量で取り組みたかったが仕方ない。プロジェクトは楽しみにしている。とりあえずポスター2枚目も作るか…。
・次回までにやってくること
・ポスター2枚目の制作と印刷:辛いよ… 時間ないよ… でも悔しいので頑張る。
(↓ パンフレット用宣材写真)

0 notes
Text
Contents Design 第10回
今日は色んな意味で待望のユーザビリティテストだ!怖い…でも楽しみでもある。近くの学童の児童たちが来てくれる訳だが熱気に負けないように気を引き締めて行こう。
・どんなことをしたのか
前述したように今回は学童の子たちによるユーザビリティテスト、まぁいわゆるターゲットにしている人たちに実際に試作で遊んでもらいテストする時間だ。ユーザビリティテストの流れは今までに何回か行った相互評価に似ていて、いくつかのグループ(小学生側)に分かれて1セッション20分前後で行い、各グループ(我々)を順番に回ると言うものだ。まぁ案の定、場はカオスになり1セッションという概念は計画通りに行かず、好きなタイミングでグルグル回るみたいなものだった。授業ギリギリまで行い、学童の子達が帰った後、20分くらい簡易フィードバック会議を行い次回に向けて振り返りを行った。
・授業を通して何を感じたか
私は予想していたよりも子供達が私のグループのコンテンツに対して前向きな、積極的な反応をしてくれたと考えている。あまり争いは好きではないが、クラスの中でも大分盛り上がっていたのではないだろうか。その点においては非常に嬉しい。残す授業は数少なくなってきてはいるが、モチベーションに繋がった。また男子だけではなく、女子にもウケていた。これもかなり嬉しい。メンバーが男子しかいないがゆえに、生み出したアイデアも男っぽいものばかりだと感じていたが、しっかりとしたブレインストーミングやKJ法によりカバー出来ていた。もう少しディティールアップしてより男女どちらにもウケるコンテンツに仕上げて行きたい。ただ成功していた部分もあれば、失敗、修正すべき部分も浮き彫りとなった。それはコンテンツの内容に当たる部分である。私のグループはプロダクトに時間ばかりをかけていて、コンテンツの内容に当たる部分が大分おろそかになっていた。何とか形に無理やりしたようなものであったのだ。子供達に学びを構築させる時間であったり、静と動の緩急であったりが小学生に圧倒されてしまい、あまり上手くいかなかった。それでも大分何とかしたがこれでは本番である科学館でのワークショップ時には不安が残る。修正すべき部分だ。気合いで乗り切るのは高校生まで。大学生は狡猾に仕切るのだ。
(↓ ユーザビリティテストに向けて準備する私のグループ)

コンテンツとは別に個人的に制作したポスターだが、そこそこのウケだった。まぁ悪くない。田島さんにも褒められたしね。良かったな俺。ただ見返すと確かに形にはなっているがひねりがない。誰もが想像できるような在り来たりなものになってしまっている。これでは同じポスター制作者が並んだ時に頭一つ抜きんでることは出来ない。インパクトを与えつつ、細かい部分に目が行き長い時間見たくなるようなポスター制作をするためには、今のステージからもうワンステップ、ツーステップ踏み出せなければならない。私は私であるがゆえを作るために平凡なままではいたくない、私を私であると誰かに気づかせるためにひねりを加えなければ…。
(↓ 私の制作したポスター(左側))

・次回までにやってくること
・今回の授業を踏まえた修正…?:とりあえず修正する部分はたくさんある。頑張るぞ。
0 notes
Text
Contents Design 第9回
もう最近は忙しい、めっちゃ忙しい。CDのタスクもさる事ながら他の授業での課題も忙しい。でもまぁみんな忙しいしやるしかないのだ!フレ!フレ!俺!(千鳥のニッポンハッピーチャンネル参照) 今回は前回のフィードバックをもとに本制作へ入るための振り返りみたいなもの。次回は学童の子らが来るらしい。初めて子供の手に触れる瞬間だ。
・どんなことをしたのか
今回は書き込めるようなことはほとんどしてない。強いて言えば本制作に入るための振り返り会議と制作を行なった。私個人では次回の学童の子たちに見せるポスターの原案を考えて形にした。絵を描くのは好きで、特に先週だか先々週だかのグラフィックデザインの時に見た本授業TAの田島さんが制作したポスターを見て、すげぇと思い頑張ろうと決めたのだ。私もああいうの作ってみたい。マジですごい。
(↓ 原案書いてる私)

(↓ 原案完成させた私)

・授業を通して何を感じたか
いよいよ本制作に入るためにさらに思考を一段階深く掘り下げてコンテンツをより良いものにしていくタームに入ったわけで、より頑張って行こうと心を引き締め、腹をくくった。また本記事冒頭でも前述したがとにかく忙しいが、どの課題も手を抜かずに取り組んで行きたいとも思う。正直に言うとしんどいが、自分以上にしんどい人はいるだろうし、しんどい中頑張れば何かを掴めるかもしれない。仮にこの授業頑張れたとしても他の授業を落とさなきゃ頑張れないようじゃまだまだである。まぁ少なくとも1単位も落とさずに頑張っていこうぜ俺と思いながら頑張っていこうと思う。
・次回までにやってくること
・子供たちに壊されないようなコンテンツにする:これはグループ目標。壊されたら負け、楽しんでなくても負け、壊されずに楽しませられたら勝ち。
・ポスター完成:これは個人目標。まぁとりあえずは形にするけど今後修正していくと思う。
(↓ プロトタイプの時に活躍してくれたJackの車)

0 notes
Text
Contents Design 第8回
今回はなんともう中間発表だ。これまでの7回で積み上げ、形にしたものを一旦発表する。前後半に分かれ、後半には小学校の先生も来る緊張の回だった。
・どんなことをしたか
単純明快発表会。4限目:前半はコンテンツの最終調整。私のグループは形こそ出来上がっているもののコンテンツのプロセスを調整する時間に欠けていた(もっと集まって作業すべきだった)。まぁ4人それぞれ違うスケジュールで動いているので仕方のないことだが、それでもそんな言い訳している暇あったら作業は進めた方がいい。そんなこんなで当日の前半の時間はほとんどを上手く機能するようにひたすら微調整を繰り返した。U字で返すか、L字で曲げるか… はたまたゲーム性を削ってとりあえず今日を乗り切るか。まぁ最後のは無しにしてもとにかく色々考えた。3人寄れば文殊の知恵。後述するが実はうちの班には自ら何も行動を起こさない人が1人いる。薄々気づいていたが確信を持ったのも今日だ。彼についてもどうにかしなければならない。問題を抱えながらも何とか調整は終了し、5限の発表には間に合った。
(↓ 発表に向けて準備をする私のグループ)

5限目:後半は発表だった。基本的には今までの相互発表同様にグループを2つに分断して、各チーム他の3グループを周り評価するというものだ。だが今までと違うのはポスターを用意し、各々のコンテンツに出会うところから行う。つまり今まで最も本番に近いやり方だ。ここで私はある事を確認すべく前述した彼とチームを組んだ。彼とはNE30-0108D佐々木一樹だ。今までの7回で、正直に、直接的に言うと彼はグループ内で浮いていた。彼は意見を出さなければ、反応もなく、作業も自ら行わない。全てにおいて受け身の姿勢なのだ。また私のグループはメンバーのスケジュールを考えて、4人または最低でも3人集まれるように木曜の2限の時間、土曜の3限の時間に集まって作業している(場合によっては日程変更あり)。木2は良いが土3の方、彼はバイトで来れない。まぁバイトは仕方ない。かく言う私も土曜はバイトがあるので切り上げる時間は決めている。だが、彼は自分が来れない日または来れなかった日に何があったのかを全く聞いてこない。私を含む他のメンバーのTumblrを毎回チェックしているのか? …私は彼の超受け身姿勢は上記の何も聞いてこないことを含め、このグループのメンバーでありながら何も分かっていないが故のものなのではないかと予想した。それを確かめるために今回は彼とチームを組み、彼の発表を見ることにした。ここまで一緒に会議やコンテンツ内容を決めておいて一人で発表出来ないのは正直やる気が感じられないと私は思う(それは他の2人もそうだし、私も同じ)。いざ発表すると予想通り、彼はポスターと向き合って発表し、全体の流れは酷いものだった。1回目の発表が終わると彼は傍観している私に、「俺、土曜来れてないから分からないとこあるし一人じゃ無理だよ。」と抗議して来た。はっきり言ってめちゃくちゃ腹が立った。思っていることを全てぶつけてやろうかと思ったが、場の空気を悪くしたくないし、彼に怒って無駄な体力を使いくない。結局彼一人では発表できなかったのだ(質疑応答の返答なんて全部俺がやったしね)。別に彼が嫌いなわけではない、ていうか嫌いだったらもう何も言わないし、ここにも書かない。どうせ私のグループにいるのだったら彼に変わって欲しいのだ。高校生までの受け身の授業からいい加減離れて大学生として積極的に、自発的に行動して欲しいのだ。いつまでも間違いを恐れていたら前には進めないし、良いものも出来ない。今失敗せずにいつ失敗するのか。大学生は最後の失敗できる期間だと何故気付かないのか。まぁこんなとこに書いても何も進展しないのは分かっているが、どうか彼が見てくれることを祈ってこれを書いたことを許して欲しい。(今回今まで以上に優しくではなく直接話したので多分変わってくれると思うが…無理だったらもう言ってしまおう…。)
全6回の発表からは学生を含め、訪問してくれた小学校の先生からも様々なフィードバックを得ることが出来た。これは次回以降、コンテンツのアップグレードに繋がるぞ!まだまだ気合い入れて頑張っていこうというモチベーションにも繋がった。
・授業を通して何を感じたか
様々なフィードバックからたくさんのものを得られた。中でも特に小学校の先生の意見は上平先生、栗芝先生、星野先生、TA,SAの方々とは違った小学生に最も近い立場としてとても参考になるものであった。しかし一番に感じたことはまた別にあって、それは今一度この折り返し地点でグループ内の各メンバーの考えやこうしたいという思いを合わせるべきだと私は感じた。この先、より良い会議や制作を行うためにメンバーに様々な意見を出してもらいたい。そのためにはやはり足並みを揃える必要がある。分からないところを補完しあうのもまた一つ大事なことである。もしかしたら私がこんな事を言うせいで、グループ内の仲が崩れるかもしれない。でも1人が遅れてその分を他の3人が愚痴りながら取り戻すくらいなら一度ぶっ壊して立て直した方が良いと私は思う。
・フィードバックまとめ
以下は発表を通して来訪者の方々からいただいたフィードバックをまとめたもの、またそれらのフィードバックを読み私たちのグループが導き出した改善案のまとめである。
・発射台に工夫があるとよい
・ハーフパイプにすると面白いかも
・レーンに線を描いた方が高さを意識することができる
・一連の道にして固定するとよい
・おもりを選ばせる
・おもりの有無の違いをもっと分かりやすいものを考える
・ピンの大きさを考えたほうが良い
・車の精度を上げたほうが良い
・車でものを倒すのは倫理的にどうか
・車である必要性はあるか
・説明の時に言葉だけではなく、実際にやって見せながらわかりやすく導入できるとよい
・体験が分かりにくい
・そのまま受け取って遊ぶと子供の試行錯誤がなくなってしまう
・テーマ性がない
・もう少し全体的なプロセスの長さを用意する
・遊びに寄りすぎているという意見と学習に執着しすぎなくてもよいという意見がある
↓ それらに対して話し合いで出した改善案 ↓
・レールをつける:車が変な方向に行かないようにするため
・発射台を工夫する:楽しさを向上させるため
・おもりについてはもう少し話し合ってどうするかを決める:おもりの有無によるスピードの変化は今のところわかりづらい。おもりの要素は必要かどうかを今後話し合って決めることにする
・ピンを大きくする:ピンが小さくてあたらない、インパクトが小さいのを改善するため
・車の強度を上げる:強度を上げて壊れるのを防ぐため
・車の先にカメラを付ける:楽しさ、理解しやすさ向上のため。しかし、今のままではカメラが壊れてしまう可能性が高いため、話し合いが必要
・自発性を増やす:子供の試行錯誤を増やして考えさせるため
・世界観を考える:子供たちが理解しやすいようにするため
・次回までにやってくること
・プロトタイプの修正:もはやこれは毎回のこと。
・フィードバックから情報を収集:大事。活かせることや今の自分たちに大事なことをしっかり抜き出す。
・足並みを揃える:本当はチームを崩すなんてやりたくないけどやるしかない。
0 notes
Text
Contents Design 第7回
今回は前回行ったダーティプロトの検証とそのフィードバックからプロトタイプを制作し、それをグループごとに相互評価して修正・改善し、次回の中間発表に備��る回である。
・どんなことをしたか
これまでのブログを見てきた方ならもう分かるだろうが、私のグループは力と運動というテーマで特に、高さエネルギーと運動エネルギーの分野に絞り、高さや重さが運動に対してどのような作用を引き起こすのかについておもちゃにしようと奮起してきた。そして私たちは先週のダーティプロトに修正・改善を加え、また設定もより深くして何とかプロトタイプへと昇華させた。相互評価は各グループ二手に別れて前後半に分かれて設定された他の3グループに評価に行くものであった。何度やっても他のグループの過程を見たり聞いたり、自分たちのグループの評価がもらえるのは制作の糧になると感じた。相互評価が終わり次第各グループはフィードバックをもとに改善点や気づきを見つけ次回の中間発表に備えるという感じだ。
(↓ 相互評価中の私の班)

(↓ 相互評価後の会議)

・授業を通して何を感じたか
今回は非常に様々なことを感じた。自分たちが考え出した制作物が初めて形とな���、メンバー以外の人の手で試されるという非常に大きな、貴重な時間だったと私は感じている。相互評価はそこそこの結果で、私がメインで製作した車は男女とも(特に一部の女子)には好評で個人的には車は男子が喜ぶと考えていたので褒められた喜びと同時に驚きも少し感じた。台に関しては傾斜が急なのと私を含めてメンバーの技量の低さが斜面の傾斜を完璧には出来ず、まっすぐ転がすのが非常に困難なものになってしまった。だがそれでも相互評価に来てくれた大部分の人が楽しんでくれてたように見える。ただ課題点はたくさん見つかった。その中でも特に大きかったのはおもちゃの不変性(ここではおもちゃ全体のプロセスに変化がない、つまり見たまんまのおもちゃでやり方にも遊び方にもこれといった工夫が施されてないという意味)であった。ここで前々回(第5回)を思い出してほしい。実はこのおもちゃは元々カスタマイズ性、選択肢に富んだ変化に溢れるものであった。しかし私たちは多すぎる選択肢は学びと容易さを遠ざけると判断し、その要素を減らした、いや減らし過ぎてしまったのだ。この部分は今回の相互評価とそれから得たフィードバックによる気づきであった。また、私自身が他のグループの評価に行った時に2つ強力型、1つは対戦型というものであったが個人的(男子目線的)には対戦型のおもちゃの方が圧倒的に面白かった。また、そのグループのおもちゃは大人と子供という差から生まれるハンディキャップをほとんど感じさせないようなおもちゃを制作していた。圧倒され、焦り、悔しいと感じ、俺もやってやるぞとバネにした。
・次回までにやってくること
・プロトタイプ修正:今あるプロトタイプをより良いものに…
・発表の準備:え~もう次回発表??はっやくない??もう半分まで来たの??
0 notes
Text
Contents Design 第6回
今回は先週の授業と授業外で集まって行なったグループ会議にて絞った二つの案のダーティプロトタイプを制作し、グループ内でお互いのダーティプロトタイプを実際に使ってみて、気づきであったり修正点であったりを見付け出した。
・どんなことをしたか
前述した通り、ダーティプロトタイプの検証を行った。私のグループは2:2で分かれて「位置エネルギーや運動エネルギーを題材としたおもちゃ」と「摩擦を題材としたおもちゃ」の2つの制作を行った。私は前者の制作を行った。基本的に必要なパーツは位置エネルギーと運動エネルギーを実際に体現する物体とそれを滑らす台である。私は物体担当だった。この段階ではカスタマイズ性というのを重視していたので車をモチーフとして、車体を二つ、そしてタイヤを三つほど制作した。もちろん付け替え可能である。しかしいざ検証を行うと様々な問題点が見つかった。カスタマイズ性で子供達が学びという趣旨からズレてしまったりするんではないか。そもそも位置エネルギーや運動エネルギーが目的なのにタイヤの変化による摩擦力の変化にも頭を周すのは厳しいのではないか。そもそも車というモチーフに新鮮味がない。など様々な改善点が見つかった。授業時間が過ぎても私たちは夢中で話し合ったが結局まとまりがつかなかったのでキリのいいところで中断し、再び授業外で集まって会議することにした。
(↓会議中に書き出したホワイトボード)


…少し話は逸れるが、もう一つの案は早い段階でボツとなった。ダーティプロトタイプを二人が別々に作ってきて話にならなかったり、そもそも実現性が低かったりと問題点ばかりだったのだ…;;
・授業を通じて何を感じたか
私が一番感じたことはダーティプロトタイプの重要度の高さである。前述したがダーティプロトタイプを制作して気づいたことがたくさんあった。私はそのことに驚きが隠せなかった。何故ならそんな簡単なことがどうして制作前の会議で分からなかったのかと作ってみてから気づいたことがたくさんあったからである。実際に形にしてそれを見て触ってやってみてという行程を経て気づくことの重要さに驚きを隠せなかった。
また誰かの意見に引っ張られるのは良くないということが改めて分かった。今回の授業で大池さんであったり、内藤さんであったり、大石さんであったり、上平先生であったりとたくさんの人が私のグループを訪れ、会議内容を拝見してアドバイスであったり方向性であったりを伝授してくれた。もちろん一致するアドバイスもあったが、ほとんどがバラバラであった。しかし誰がが正解というわけでもなく、何なら正解などないのだ。正直に言うと私のグループ、特に私がアドバイスによって意見がブレて会議を長引かせてしまったと個人的には感じている。本当に申し訳ない、メンバーたち。以後芯を強く生きます。
・次回までにやってくること
・プロトタイプの制作:今度はダーティとは違ってもっとしっかりとしたものを作ってくる。
・シナリオを書く:ペルソナがそのおもちゃに出会う所から課題が解決されるところまでをシナリオ化する。
0 notes
Text
Contents Design 第5回
今回は前回行ったKJ法を授業外にグループで更に深め、そこから得た新たな気づきや繋がりを基に一人一人が個々に5つずつアイデアを考えアイデアシートに書いてくる。それを相互評価しグループ内でイケそうなものを決めて今度はグループで相互評価するというものだ。
・どんなことをしたか
前述した通り、まずは第4回にて書いた授業外にグループで会議してKJ法を更に深化させたものを基に考えてきたアイデアをグループで相互評価するというものであったが、これがまぁ大変だった。今回は私も苦戦してIxDの時ほど斬新なアイデアが思い浮かばず平凡なものばかりになってしまったが、班員にはそれ以下の意見もあった。このブログを班員が見てないと踏んでこの部分を書くが、ホッケーゲームとかいうアイデアだったり、凧のようなものというアイデアだったりと没ネタどころかこれはダメだろというものばかりで悲惨だった。結局勝負に出せるアイデアは全部で6個のみだった(私:2, S山:3, S々木:1 K藤:0)。そんなこんなで私の班はその6つを提げてグループ間での相互評価に挑んだ訳だ。
グループ間での相互評価の方法は前半後半にグループ内で分かれ、前半では前半組が、後半では後半組が自分たちのグループで話し合っていた席に残り他の班からの来訪者に対して自分たちのアイデアを説明しフィードバックをもらうという感じだ。(私の班は4人なので)残っている2人は他の2グループにアイデアを評価しに行くというシステムである。アイデアの説明は上手く行ったと思う。まぁもともと自分のアイデアも多かったので説明しやすかったし余すことなくアイデアの説明が出来たので正確なフィードバックをしてもらえた。他のグループへの評価はとても面白かった。私が訪ねた班はどちらも私の班とは違うテーマだったので客観的に意見を言えたし非常に興味深いアイデアもあった。でも少し安心したのは息をのむほどすごいアイデアはなかったということだ。
(↓他グループにアイデアを発表する私とグループメンバー)

グループ間の相互評価の後はそのフィードバックを基に更にそこから自分たちのグループのアイデアを2つにまで絞るということであった。フィードバックと先生方、SAさん方のアドバイスによって正直ここは割とトントン拍子で進んだと私個人は感じている。しかし授業時に固まったのは1つだけであった。何とかものになりそうなアイデアを2つ合わせて形には出来たのだがその日は体力的にも班員は限界だったと思う。なので後日集まってもう一つの案を固めることにした。
10/24(木)、私の班は集まって何とか2つ目の案は固まった。あぶね~~~。
・授業を通して何を感じたか
私が先週の授業を休んでしまったというのもあってか、個人的にはKJ法を突き詰めきれなかった気がする。これは本当に申し訳ない。遅れを取り戻そうと家で個人的にKJ法を行ってみたりしたが、記憶が正しければこれは複数でやるから効果が出るのであって一人でやっても意味がないのであった...;; まぁともかく何とか2つの意見が出たのは一安心だ。ただまだスタートしたに過ぎない。ここからやっと始まって行くのだと思うとまだまだ道は長い。真剣に取り組んでいきたいと改めて感じた。
(↓自宅で行なったKJ法)

・次回までにやっておくこと
・ダーティプロトタイプの作成:次回の授業は絞ったアイデアのダーティプロトの”検証”から始まる。つまり授業時には完成してなければならない。メンバー間の連絡をたくさん行なってズレなくしっかり2つ作って来れるようにしたいと思う。
0 notes
Text
Contents Design 第4回
私は今週の第4回、低気圧による体調不良で欠席してしまった。多少無理してでも行こうかと思ったが、班のメンバーや周りに気を使わせるのも嫌だし体調不良の状態で楽しく出来る気がしないので欠席を選択した。メンバーには申し訳ないことをしたので、今週の課題と次回で挽回したい。
どんなことをしたのかは写真と班のメンバーの説明で何となく把握した。当日先週先々週と既に2度休んでいる2限の授業には出席して、その時に班のメンバーに自分のポストイットを託し帰宅した。
班のメンバーが書いた数十枚のポストイットをグループ化してる写真から授業でやったことの概要を把握し、班のメンバーから詳細のことを聞いた。どうやら次回の授業までに集まらなければならないらしい。相談した結果、木曜2限の時間帯に集まることになったのでその時改めてもう一度授業内容を聞くのと、その時にやる深層化?に向けて写真をもう一度見直して授業時にメンバーがまとめたポストイットを把握しておかなければならない。
・会議を通して
私の班は10/17(木)に集まりポストイットを改変した。元々の出来が良かったので位置関係であったり関係の深いものをまとめた。またそれらの素から新たな気づきであったりヒントを探し出した。以下がそれらである。
・非日常の体験が自発的行動を誘発するということが分かった
・物事をシンプルに考える発想力が行動につながることが分かった
・競うことがあるということは協力することもあるということが分かった
・競うことと機能面と動くものは関係性があることが分かった
・男子は機能面、女子はデザインを重視することが分かった
・協力することは競うことより飽きやすいのではないかことが分かった
・自発的行動の理由の根本は何かを知ろうとする動きがあるということが分かった
・楽しく学ぶためには複数の人と行動することが大切ということが分かった
・コンテンツにたどり着くまでの思考の関係が分かった
・未知と競争をキーワードになるかもしれないということが分かった
・子供は負けることに恥じらいがないということが分かった
・学んでもらうには自発的に行動して学んでもらうことが大切であるということが分かった
・競うことに飽きることはないため、競うことは大事であるということが分かった
・良いデザインが自発的行動を誘発することが分かった
・小学生は物事を複雑に考えないということが分かった
・共有を積極的にすることは楽しいということがわかった
・競技性が機能面に対して何かのサイクルを生み出していることが分かった
・動かないものは飽きやすいということが分かった
・競うことが好きなため、勝敗要素を取り入れることが良いかもしれないということが分かった
・既知のことは飽きを生み出すということが分かった
・未知のことでも自分たちに関係ないことには興味を持たないということが分かった
(↓班で集まっての会議)


・次回までにやってくること
・アイデアシートの作成:この会議の時に知ったがどうやらKJ法で気づいたことやヒントを元に5つのアイデアを生み出しアイデアシートにまとめて来なければならないらしい!これは困った困った大変だ...。
0 notes
Text
Contents Design 第3回
今回は午前中に登戸小学校に訪問しワークショップを行い、午後の講義の時間では午前中の小学校訪問の振り返りと様々なデジタルファブリケーションのレクチャーが行われた。小学校訪問ではCDのメイン課題である科学キットの制作にあたっての情報収集であったり小学生を間近で観察する機会であったりと小学校に訪れて授業を共に行うというとても希少な時間であった。またデジタルファブリケーションではプロトタイプの制作や発表時などに活用できる重要なレクチャーであった。
・どんなことをしたのか
午前中の小学校訪問では、小学生たちが実際に授業で習った作りたいものの設計図を各々(中には複数人が共同で)書いてきて、それを軸に制作を行うのを手伝うというものであった。1人1班(男女2人ずつで計4人)体制で行った。私が担当した班の子達の設計図は男子二人とも同じで輪ゴムと紙コップ、プラコップを使ったロケットを各々が制作、女子は共同で磁石を使ったレースの制作を行なっていた。最初はやはり私が男だからか男子とはすぐに打ち解けて刃物を使った作業の同伴だけでなく、他に手伝って欲しいことや学校の話であったりも作業しながら話してくれた。女子は最初、刃物を使う作業の同伴だけだったが次第に打ち解けて色々な話をしてくれた(だが基本的に作業の手伝いのお願いはされなかった)。正直私は小学2年生をなめていた。もっと不器用で下手くそでたくさん手伝いを要求されると思ったいたが、(私が小学校低学年の時とは違い)とてもしっかりしていた。刃物を使う作業の同伴以外の要求はほとんど無くて、私が能動的に何か行動を起こさなければ何もしなくて良いくらいに自ら制作しトライアンドエラーを繰り返して自分なりのやり方を見つけようと模索していた。ここだけの話後半は暇すぎて、子供達が作っている創作物と同じものを作って俺の方が飛ぶぞと比べっこしていた。子供達は比べるのが大好きで私がこれをする前も同じものを作ってる子同士で俺の方がすげぇよと比べっこしていた。高校から文系だった私は科学はおろか物理にも弱いが、紙コップロケットだったりするのを作るのが好きだったので何とか子供達には負けないくらいのものを作ったがそれでも僅差だった、すごい。奴らはすごい、脅威だ。
(↓訪問した登戸小学校の下駄箱)

午後の講義では、今後のCDの授業においてはもちろん、個人でも使えるファブリケーションにおけるツールの紹介であったり使い方のレクチャーであったりと個人的に非常に充実した講義であった。記録の取り方、木工、材料と素材、撮影、大型プリンター、3Dプリンター、レーザーカッター、カッティングマシンの計8項目のレクチャーを受けた。
・小学校訪問&レクチャーを通して���じたこと
廊下を行き多目的室に入るまでの歩いている時間、私はノスタルジックな気持ちに浸っていた。何かを飼っている虫かご水槽、夏休みの課題か何か分からないけど全て手書きで所々親に手伝ってもらったであろう痕跡の残るポスター、輪郭がいびつな自分たちの似顔絵、場所は違えど小学校そのものはどこも似たり寄ったりなんだなと思いながら自分の小学校時代を思い出していた。ただ実際に授業に同伴すると怖さすらも感じるくらいに子供達はしっかりとしていて、ビックリした。基本的には先生だろうが大学生だろうが頼らず自分たちの力で制作を行なっていき、ある程度進んだら他の友達の元に行って作ったものを比べてみたりしていた。始まる前私は彼らを舐めきっていた、しかしそれは私の考えと知識の浅さゆえのものだった。また私たち大学生に質問をしてきたこともあった。今は私たちと違い、小学校低学年でもみんなスマホは当たり前のような時代になってきている。だからなのかは分からないが、質問の内容も良い意味で子供っぽくないものもあったりした。たった10年だが今の10年は常識も世界も変わる、そんな時代に生まれてきてしまったのだ。それもあって制作物を子どもに向けて作るのでは甘いんじゃないかというのは一番感じた。もちろん対象年齢は小学校低学年向けの科学キットではあるが、私たち大学生でも楽しいと思えるようなものでなければ今の小学生は真に楽しんでくれないんじゃないかと考えている。そう一番最初に感じた時、不安な気持ちもあったが同時にやってやんぞという気持ちも高まった。
午後の講義におけるレクチャーはそれぞれ8人の違う人たちによるものだった。それぞれが個性的でまとめて書こうとすると難しいので箇条書きで書きたいと思う。
記録の取り方 by 内藤さん:主にTumblrについてレクチャーしてくれた。Tumblrは内容、写真の観点から3段階評価に分かれる。しっかりとした内容と複数枚の写真があるかどうかで決まるそうだ。しかし内藤さんは評価を気にしすぎて堅い文章になるよりかは自由に書いた方が評価する側も見てて楽しいし、何より後で見返したときに堅い文章だと思い出しづらいし面白くないよというアドバイスをくれた。私は第一回から割と自由に書いているのであまり気にししてはいないがそれでも改めて意識しておこうと思った。また内藤さんはCD履修者として、制作物を先生に見せる時がいつか来るが三人とも個性が強いからきっとバラバラの意見を言って来るかもしれない。それに振り回されずに自分の芯を持って制作に取り組むことが大事。だからと言って先生の意見はないがしろにせず、しっかり聞き入ること。とアドバイスをくれた。分かってはいるが人間、迷うと誰かに頼りたくなってしまう。いつか路頭に迷った時にまたこのブログを見直そうと思う。
木工 by 上平先生:主にワーキングスペースで使える木工関係の工具についてレクチャーしてくれた。丸ノコや電ノコ、グルーガンや万力など様々なツールについて説明していただいた、その中でも木材調達についての話が一番記憶に残っている。上平先生は木材調達において廃材の利用にこだわっていた。理由はいくつかあり、手に入りやすい、規格化されたものでは味がないという理由から廃材を推していた。廃材は木工関係のお店やホームセンターで廃材をくださいと言うと無料で手に入る。何故なら廃材は使えない(売り物にならない)のと処理にお金がかかるからである。また規格化されたものだと木材という自然溢れる材料を使っていてもどこか人工的な部分が出たりしてしまう、しかもものすごく高い。前期のIxdでプロトタイプを制作していた時に木材を購入したがビックリするほど高かった。もう少し大きいものを買って分断すれば安く済んだが当時の私が加工できる手段といえば手動ノコギリしかなかった。高くつくよりも汚くなる、綺麗に加工できない方が嫌だった私は高くても綺麗にカットされた木材を購入した。しかし今回レクチャーを受けたことによって、綺麗に加工する知識を習得した。すぐに上手くはいかないが、何度も挑戦して知識を技術に昇華させたい。
材料と素材 by 大石さん:主にプロトタイプ制作時などに決める材料の使い所と似たようなものの違いについてレクチャーしてくれた。発泡スチロール、スチレン、プラバン、ダンボール、木材などなど実演を通して様々な材料の違いとメリットデメリットについて説明していただいた。ほとんどの材料は100均で調達可能だから近くの100均をいくつか回って集めるのも良いかもしれないともおっしゃっていた。また大石さんもCD履修者なので、CD履修の先輩として些細なことでも例え必要じゃないかもと思っていても気づきであったり何か引っかかること思いついたことがあれば必ずポストイットすること、アイデア出しは最初のポストイットが肝心で文字通りあればあるほど強みになる。もし本当にいらなかったら後で捨てれば良い。とアドバイスをくれた。私もその通りだと思う。私の班は男4人なので意見が出しづらいとかは基本的にはないと思うが、全員が全員私みたいにおしゃべりではないのでしっかり一歩引いて場を見れるように意識はしている。
撮影 by 大池さん:主にブツ撮りであったりの撮影の技法であったり基本的な知識についてレクチャーしてくれた。私は個人的に写真だったり動画だったりの撮影が好きでカメラを所有しているので基本的な知識についての部分は大池さんの説明で改めてそうだったそうだったという感じであった(にしても大池さんの例え話は上手かった)。後はレンズであったり、もしカメラを買うなら一旦ここに行こうというお店の名前であったりととても面白かった。個人的に一番記憶に残っているのは大池さんの「少し写真を撮ることにこだわりがあったりする人は初心者にああした方がいい、こうした方がいいと言いがちだがもっと自由に撮っていいと思う。綺麗な構図、場面によって変える値とかはあるかもしれないが、自分が撮りたい写真であったりお気に入りのものが出来たならそれでいい」というような言葉である。私の知り合いにも悪気はないんだろうが、知り合いのコミュニティで一番最初に一眼に触れたというのもあってか一眼の話題になるとすぐにマウントを取りたがる人がいる。私はいつもその人がやりたいようにやれば良いんじゃないか。と不思議に思っていたので、大池さんの言葉にはすごく感動したし共感した。
大型プリンター by 田島さん:主に大型プリンターの使い方や注意事項についてレクチャーしてくれた。大型プリンターという存在は知っていたがイマイチ分からなかったし接点もなかったので無視していたが今回の田島さんの説明でCD演習中に必ず使えるようになってプロジェクトなどにも活かそうと感じた。最初の設定はめんどくさいがやり方を覚えれば後は簡単というイメージだった。でも何より無料なのが個人的には魅力だった。また田島さんもCD履修者の先輩として、ポスターのインパクトはでかいからこだわろう、カラフル・ポップ・キャッチーなのが印象に残る、タイトルにもこだわると良いぞとアドバイスをくれた。田島さんが実際にCD履修時に作ったポスターは確かにアドバイスしてくれた3つの全てがぎっしり詰まっていてとても素晴らしいものだった。私の班は男ばかりなのビジュアルに欠けがちになるかも知れないが、そういうことにはより一層気を使って仕上げていきたいと思う。
3Dプリンター by 星野先生:主に3Dプリンターについてのレクチャーをしてくれた。3Dプリンターの使い方、注意すべきこと、メリットデメリットなど。正直、私には縁の遠い話だと思っていたが、想像していたよりも簡単で私にも出来そうと感じた。また3Dプリンターは使える(使っている)学生が少ないので大型プリンターとは違い、予約も必要じゃない。この点も非常に便利だ。問題は3DCGソフトが扱えるかどうかというところに帰結するわけだが、前々から触りたいとは思っていたのでこれを機に後期は空いた時間を3DCGソフトに使ってみようと思った。今は無料で優秀な3DCGソフトがあるので始めやすい、きっかけもあるのでこれを逃さずにはいられない。またこちらも無料で使える(厳密には学費の一部で整備している)のが非常に魅力的だ。今度何かオブジェクトみたいなものを作ってみようと思う。
レーザーカッター by 栗芝先生:主にレーザーカッターについてのレクチャーをしてくれた。個人的には3Dプリンター同様、私には関係のない話だと思っていたが、そうでもない。もちろん危険なツールだが、想像しているほど難しくはなかった。またレーザーカッター自体は他の大学にもあるみたいだが学生が自由に使えるのは専修大学だけらしい。他の大学はレーザーカッター専用の事務員に渡さなきゃいけない、しかも有料。うちは無料、すごい。ただその分学生側は注意事項をしっかり守り気をつけて使わなければ1号館ごと火の海になるかも知れないことを忘れてはならない。あくまでもそういうことが起きる可能性は十分にあるツールなのだということを忘れてはいけない。ただもしこのツールも3Dプリンターも使えるようになればこれ以上の武器はないだろうというくらいすごいツールだ。是非ともこの後期CD履修の間に最低一度多ければたくさん使ってみたいと思う。
カッティングマシン by 前嶋さん:主にカッティングマシンの操作と注意事項についてレクチャーしてくれた。このマシンは特に紙をカッティングするのにフォーカスしているマシンでデータを送ったらそれ通りに切ってくれるという非常に便利なマシンだ。特に手動カットではやりづらい曲線などが出てきた時に活用できるだろうと感じた。前嶋さんもCD履修者で、しかも4年生。聞きたいことがあったら聞いてくれと言われ、私は就活について質問した。就活は自分のペースでやるべき、確かにインターンは行った方が良いが周りが行ってるからと言って焦るべきではない。それは内定も同様で自分のペースで自分のすべきことをしっかりやっていれば必ず結果はついてくる。周りに振り回されるな。とアドバイスをしてくれた。私の中学、高校からの友達もう既に2年の夏にインターンに行ったという人らが数名いる。正直私は焦った。なぜなら3年からでも間に合うし、今年はもっと他のことをやって力をつけたいと思っていたからだ。だから私は前嶋さんの言葉に少し救われた。ありがとうございます。自分を失っちゃいけない。
(↓大池さんが書いた撮影のレクチャー時のホワイトボード)

・次回までにやってくること
・ポストイット:次回の単位化において最も重要な要素。個人的には最低でも30~50は出しておきたい。現在(10/11 11:30)ではまだ18枚ほど...頑張らなければ。プリントには単位化と書いてあるが、個人的に単位化までやっておくべきか...要プリント確認。
・他は前回同様。
0 notes
Text
Contents Design 第2回
今回は特別講義としてジャパンGEMSセンターより”かもさん”が来訪し、ワークショップを行った。小学生くらいを対象とした勉強ではなく学び、知識は与えられるものではなく考え発見するもの。と言ったようなプログラムで、小学生だったらどのように感じるのか、また純粋に大学生としてこのプログラムをどう感じたかなどを考えながらワークショップを行った。
・どんなことをしたのか
”新しいつよい動物を作ろう”という目標を掲げてプログラムは行われた。しかし、その前にまず息抜きとして飴を賭けた競蛙が行われた。ルールは簡単で1~12の好きな数に自分の手持ちの飴を1つBETする、自分の賭けた数字の蛙が一番最初にゴールしたら勝ちだ。しかし蛙は自分では動けない。サイコロを2つ振って出た目の合計した数字の蛙がひとマス進めるのだ(例えばサイコロを振って2と5が出たら合計は7なので7番の蛙がひとマス進む)。サイコロに不正が無いように一人が振ったら隣の人が次を振る、そしたら次の人と順番に振っていくシステムだ。私は隣に居た杉山と相談し”1″にBETすることにした。一番人気は8、次に人気が6だっただろうか。私(と杉山)が賭けた1は大穴も大穴、私たち以外誰も賭けて居なかった。まぁもう大学生ならお気付きのことだろうが出目の合計は最低でも2(1+1)、絶対に勝てるわけがない。しかしそれでも私たちは途中で何か起きることを信じ1に賭けた。カヲルくんも言ってだろう?「希望は残っているよ、どんな時にもね」と。結果は”9″の勝利、1はひとマスも進めなかった。レース中に2つのサイコロの出目の合計が1になるという概念の崩壊は起きなかったのだ。まぁおふざけはここまでにして、この勝負において確率的に一番勝率が高いと思われるのは、”7″。次に”6″,”8″と続き(7=1+6, 2+5, 3+4, 4+3, 5+2, 6+1で6/36=1/6、6=1+5, 2+4, 3+3, 4+2, 5+2、8=2+6, 5+3, 4+4, 3+5, 6+2で5/36)、もっとも低いのが”2″,”12″(2=1+1, 12=6+6で1/36)となる。あまり数学が得意でない私でもこれくらいはレース前にパッと計算できた。しかし実際は一番勝率の高い”7″ではなく”9″が勝利した。この事からかもさんは、
”確率という知識はあくまでこうなるだろうという予測を立てる道具に過ぎない。実際に大人になり社会に出ると教科書通りの事例はまずないし、実際に起きるのは今やったレースのような事例外の事ばかりだ。���かに得た知識によって大方の予測がつけられるようになるのは確かだが、それだけでは役に立たない。”
と教えてくれた。また今のワンレースで何度もサイコロの出目を足す計算をした、また、自然と確率というものを習っていなくても1という合計数にはならない事や7が一番出やすいという事にもこのゲームを通して気づくかもしれない。それは我々大学生にとっては造作もない事だが小学生にとってそれらをプリントの上でと考えたらしんどいだろう、でも遊びを交えながらだったらいくらでも出来るんだ。大事なのは答えを知ることでも効率よく答えにたどり着くことでもない。情報が0の状況からでもまずは自分で考えて試してみる勇気、力を養うことが大事、ともおっしゃっていた。私は昔から強制される勉強ほど身につかないものはない、教科書通りにいく現実など多くは存在しないとどちらも強く感じていた。そんな私はこの時点で既にもうかもさんの、このプログラムの虜だったのかもしれない。
(↓ジャパンGEMSセンターのかもさん)

その後は今回のメインである”新しいつよい動物を作ろう”を行った。かもさんが用意した世界で一番弱い生き物に何を足したらティラノサウルスに襲われずに生き抜けるかということをテーマに各々が羽を生やしたり、足を速くしてみたり、人型にしてみたりと試行錯誤していた。各々が新しいつよい動物を作りある程度の説明を加え、自分の作品としお互いの作品を鑑賞した。自分がこういうの作ってみようかなと思っていて作らなかった作品が別の人に作られていたり、そういう手があったのか!と思わせられたりととても楽しかった。この課題に不正解はない、各々が考えて作り出した全てが正解の形なのだ。
(↓新しいつよい動物を生み出し戦闘デモンストレーションしている私の班)

これはワークショップとは別の話...ワークショップが終わった後、今日までの課題であった各班のフラッグ制作の一口評価by上平先生が行われた。私の班は私が自ら制作担当を買った。私の班は今期唯一の女子なし男4人の班(第1回でのTumblrで言及したが他の班には最低でも男女が一人ずついる)であったので、テーマは一瞬でThe Beatlesか時計仕掛けのオレンジのアレックス率いるドルーグ集団のどちらかであった。結局選んだの超有名なThe BeatlesのAbbey Roadのジャケ写の構図である(本当はドルーグであったが背景を真っ黒にするのはダメっぽかったので諦めた)。Abbey Roadの構図はやはりThe Beatles、過去にも何度かあったらしいがタイトルにまでこだわっていたのは初めてだと評価をいただいた。しかし、人物と名前の表記が離れているので誰が誰だか分からないとダメ出しもくらった。その指摘は班員からも出ていて別バージョンで頭の上に名前を置いたバージョンも作ってあったが、個人的美観にそぐわなかったのでボツにしたのだがそちらが正解だったようだ。正直悔しかったが、私個人が今回の演習で(勝手に)設定した”アートからデザインへの広域化”と言うテーマにあるように、自分で勝手に満足して完結しているようではまだまだアートに過ぎない。誰かに伝わるようにデザインしなければならないのだ。決してアートを否定してるわけではない、ただアートは自分の趣味でやれば良い。
(↓私の班であるTeamHのフラッグ)

・ワークショップを通して感じたこと
ワークショップが始まる前に「今回行うのは小学生向けのプログラムで、どう言うものなのかじっくりものにしましょう」的な説明が入った時に私は、「あぁ遊びね笑」と正直舐めきっていた。まずは楽しむのがメイン、でそっから何を学ぶかと言うよくあるパターンだろうと思っていた。そのパターンであることは間違いではなかった。ただ、それが自分の想像を超える高いレベルで行われたのだ。恥ずかしながら小学生向けのプログラムに本気で取り組み心から楽しんでしまった私がいた(私だけかと思っていたが、写真を見たらみんなめっちゃ笑顔だった)。我々のような大学生でも楽しめたのは綿密に計算され、長い経験から臨機応変に対応できるかもさんの腕によるものだろう。
また、かもさんの全体の雰囲気作りも素晴らしいものだと感じた。かもさんは自己紹介から締めの挨拶まで終始にこやかで良い意味で緩い雰囲気を全体に流し続けていた。それにより普段目立ちたくないので思ってても手を挙げない私を含めみんなが自ら挙手したり、指されても動じずに自分の思っていることを発言していた。これは一見簡単そうに見えてとても難しい。緩過ぎれば場に一体感がなくなりみんなが良くない自由を楽しみだす。逆に厳格な雰囲気を醸し出せばみんなが強張り意見は全く出ず気まずい雰囲気が漂う。それをかもさんは難なくこなしていた。これは近い将来で言えば、来週の月曜日(10/7)に行う登戸小学校の訪問時に活用できると思うし、これから先グループワーク時などの話し合いの時にも活用できると考える。決して簡単な技ではないが、この意識を忘れてはいけない。またかもさん自身もワークショップを楽しみ、授業のような一方的な影響ではなく相互的に影響し合うと言うのも強く作用してると感じた。これは授業とは違うワークショップというシステムによるものだが、非常に重要なことだと考える。
このワークショップで密かに思い出していたのは第1回に上平先生が行った外での即興演劇、サンキューゲームである。あれはお互いの表現を否定せずあらゆる角度から新たな捉え方をし、伝わればサンキューと言う非常にピースフルなゲームであった。あの場に漂っていた様々な意見を受け入れると言う雰囲気が今回のワークショップでも漂っていたと私は感じる。だからみんな恥ずかしがらずに自分の思ってること、言いたいことをアウトプット出来たのだと私は考える。
・次回までにやってくること
・訪問に向けてスリッパの準備:登戸小学校訪問時に使うスリッパの購入
・既にあるコンテンツを越えるための調査:CD演習通しての課題は小学生を対象にしたサイエンスキットの制作。しかしその制作も生半可なものでは許されないし何よりそんな妥協したくない。なので制作のための調査を行う。新しい革新的なアイデアはちょっとしたひらめきから来るものだが、そのひらめきも膨大なインプット、情報がなければ生まれない。(なんかデジャヴ...似たようなセリフ、前にも言ったっけ?)
・収集したデータの単位化:要はたくさんのデータを雑多に集めても見づらいので整理しましょうねってことだと思ってる。多分そう。
0 notes
Text
Contents Design 課外授業
今回は課外授業ということで、かわさき宙と緑の科学館ワークショップを行った。大学の裏すぐの生田緑地の中にある博物館で、名前の通りに自然であったり宇宙であったりの資料や情報を知れたりワークショップを体験することが出来る。今日私たちが行ったワークショップは、「実際に生田緑地を歩き、地層を目で見て触れる」と「椀がけ法を用いた鉱物の採集と観察」であった。大学生ながらどちらも非常に楽しいものであった。
・どんなワークショップだったのか
まず最初に行ったのが「実際に生田緑地を歩き、地層を目で見て触れる」ワークショップであった。生田緑地は平面ではなく凹凸のある緑地が広がる。現に近くにある専修大学は丘(小さな山)の上にある。生田緑地の一番高い場所からは新宿が拝めるほどだ。そんな生田緑地の入り口すぐの脇道を登りながら3つの地層を観察し、登頂後降りつつ3つの地層を観察する、計6つの観察ポイントを巡るワークショップである。そこからどのようにして地層が変動したのかやその地層から得れる情報は一体何なのかなどを文面上だけでなく、実際に観察することで習得するというのが1つ目のワークショップの目的である。
(↓1つ目のワークショップの断面観察)

次に行ったのが「椀がけ法を用いた鉱物の採集と観察」ワークショップである。これは先ほど紹介した生田緑地を歩き地層を見て触れるワークショップにて出てくる”多摩ローム層(別名ゴマ塩軽石層)”と呼ばれる火山灰にて出来た層を椀がけという手法で洗い出し、中に含まれる白と黒の鉱物を取り出しファーブルで観察するというものである。見た目は茶色だが実際にゴマ塩と呼ばれる所以である白と黒の鉱物が含まれていることをより親身に知るためのワークショップである。これが2つ目のワークショップの目的だろう。
(↓実際に私が採集した鉱石をファーブルで拡大したもの)

・ワークショップにて感じたこと
まず感じたのはやはり文面上で説明されるより実際に歩いて触って何かを感じた方が楽しいということである。もう今年で20になるがつまらないどころか楽しく感じた。特に2つ目のワークショップは何だか懐かしい気持ちにもなって楽しかった。また、大地の話になると何十万年前の地層や火山の噴火で飛んできた火山灰といったワードが出てくるが今の私たちや小学生には全く身近に感じられない。しかしそれが地元で直に確認できると認めざるを得ないし、そんな壮大な話が生まれた土地で起きてると知れば自然と興味が湧くのかもと思った。
やはり勉強が一番楽しく感じれる瞬間はインプットしたものをアウトプットした瞬間だと私は考える。言語も知識も頭の中で溜め込むのではなく、実際に活用出来てやっと勉強してて良かったと感じるのではないだろうか。それが小さい頃に感じれなかった子達は自然と勉強してる意味が分からなくなっていくのではないだろうかと私は思う。
0 notes
Text
ContentsDesign 第一回
ついに始まった後期応用演習”ContentsDesign”。毎週このようなブログ形式でTumblrに授業内容や感じたことをテキストで落とし込んでいくわけだが私はこのようなテキストに落とし込むのがあまり得意じゃないので、この作業を通して少しでも上達したらと思いながら書いていこうと思う。
・何を議論して、何が決まったのか?
班編成は4人、全員男子。他のグループは大概というか私の班以外全て(比率はバラバラ)男女混合だ。女性というのは難しい生き物なので少し救われたと同時に男(特に私のような人間)には思い浮かびづらいアイデアが思いつきやすいと思うと少し残念な気もする。しかしまぁ男子4人であれば他の班よりすぐ結束力は高まるしお互いに意見しやすいという点では良い班編成だと思う。
最初に議論したことは半年間かけて作り上げる科学キットのテーマだ。「力と運動」「電磁力」「光と音」「環境」「大地」とかだったと思う。メンバーで最初に合致した意見は、”「環境」と「大地」はやめよう”というものだった。私も心から同意だった、何故なら中学の時の科学分野での苦手科目が生物、地理学だったからだ。”苦手科目から逃げる”というのは良くないが、この際自分たちの得意なものを深く掘り下げたいという気持ちの方が強くあったのだ。そんなこんなで私たちのテーマは「力と運動」に決まった。(というのも本当の希望は「光と音」であったが、私の圧倒的ジャンケン力が物申し負けた)
私は映像や音楽が大好きなので、「光と音」で制作を行いたかったが負けてしまっては仕方ないので「力と運動」というテーマに全力で向き合っていこうと思う。もしかしたらここで習得したことが将来の創作活動に活きるかもしれない、と思うと自分の本来の希望のテーマでなくても手を抜いてられない。全力で挑もうと思う。
・自分はこの演習を通して、どうありたい?
質問が難しいのか私の理解力が乏しいのか分からないがこの質問に適当な答えを返せる自信がない。強いて言えばこの演習を通して様々なモノ、ヒトに触れ価値観を深めたい。新しい世界を知りたい。と考えている。この演習は一人で何かを考え誰かのために制作するのではなく、あらゆる場所へ赴き様々なコミュニティに触れ、制作物を中心に様々な人や物を巻き込んで制作を行うと聞いた。アートではなくデザインなのだと感じた。ある時は誰かの受け手として、ある時は何かの伝え手として、人と人や人と物の間に入りそれぞれ感情や思考、情報を受け取って感じて考えて伝えれるように私はなりたい。
・次回までに何をしてくれば良いのか?
・フラッグ制作:自らやりたいと挙手したので頑張って作らなければ。(自ら手を挙げたが、めんどくさくなってきた...) まぁでもどうせやるなら自分が納得できるものを作る。
・Tumblr1回目投稿:今やってるこれ。
・資料を読む:先ほどDirectに送られてきた。より良いアイデアを出すためには膨大なインプットが必要なので、まずはこれに目を通す。後は少しズレるが身の回りに起きている不思議なことにも気づけるように目を配っておく。
・次回は特別講義なので眠くならないように前日早めの就寝でしっかり睡眠を取る。
(↓制作フラッグのための撮影)
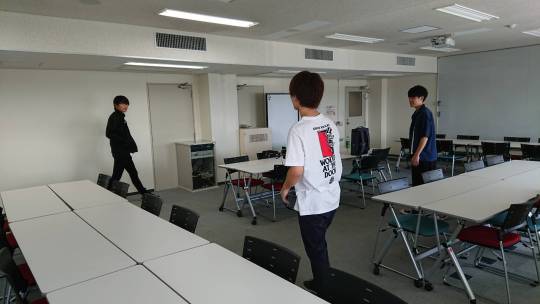
1 note
·
View note