Text
眞人の自傷について/『君たちはどう生きるか』(2023)
傷を作った犯人は誰だ、と迫るお父さんに眞人が鼻白んだような顔をするところ、彼の失望と幼稚な甘えのどちらもが表れている気がしてすごく好きでした。作中の「悪意」という言葉を用いるなら、眞人がこめかみに傷を作る行為は、同級生よりむしろお父さんに向けた悪意の意味合いが大きかったんじゃないかと思います。
疎開してきた子どもが車で学校に乗りつけたらどうなるか、眞人であれば十分予想できたであろうし、それは観客側にとっても同��ではないかと思います。ほとんど暗黙のうちに了解されていた喧嘩のシーンは、引きの構図で、かなりあっさりと描写されます。 眞人の心情に寄り添って考えるなら、同級生との不和よりも、その直前、父と夏子さんのキスを目撃したことや、車での登校に夏子さんも一枚嚙んでいたことの方が面白くなかったんじゃないかな。もちろん、自分の行為によって同級生が「加害者」になることも想定していたのではないかと思います(ところで、前半部の彼は想定の中で動きがちだ。とにかく相談というものをしない)。ただ、眞人があそこで傷つけに行った相手はお父さんなんじゃないかな。眞人は勝一さんに傷ついてほしかったんじゃなかろうか……。帰路につく眞人の足取りはいやにまっすぐなんですよね。
「傷つけられた」眞人を見た勝一は、ケアにつとめるでも、自身の迂闊さを顧みるでもなく、やり返してやると意気込む。このときの眞人の、「この人ってこうなんだな」みたいな表情が好き!という話でした。眞人の自傷は、自分をないがしろにした(ように見えた)お父さんへの当てこすりでもあった。し、傷ついてしまえばいい、そして自分がどんなに傷ついたか思い知ればいい、というような甘えでSOSだったのかなと思います。
追記 『君たちはどう生きるか』でもうひとつ好きなシーンは、夏子さんが眞人に「大嫌い」と言い放つところです。「父さんの好きな人」「姉さんに顔向けできない」と、第三者を経由してやっと関係していたかのように思われた2人も、傷を作りあっていたと判明するのがグッとくる!
0 notes
Text
本屋
ひさびさに本屋に行きました。 漫画の新刊やもともと興味のあった本を通販で適宜買い足すのが習慣になって久し��ためか、たまに本屋に行った日は印象深い日になります。よく言われていることですが、書店も図書館も、棚を眺めるのが面白いですね。話題の新刊コーナーや新着本もそうですし、普段なら絶対読まないジャンルの棚で、背表紙の文字を追っていくのも楽しい。 友達や知り合いの本棚を見るのも好きです。何に興味があるのかとか、どんな並べ方をしてるのかとか。雑然としている部分を見つけて、最近はこのへんを読んでいるのかなと想像してみたり……。
本屋に行った話に戻します。今回は旅行ガイドが目当てだったのですが、妙に旅の本の向かいにあった平積みコーナーが気になりました。積まれていたのは「仕事も人生もうまくいく〇ヶ条」といようなもの。おいちょっと!大丈夫か!? という感じですね。普段であれば、幸福論をテーマにした書物が世に溢れているのはうんぬんかんぬん……なんて理屈をオートでこねだすところですが(最悪?)、その時は素直に魅了される自分が半分、そのような自分への驚きが半分、でした。
今日の出来事にはひとまず、興味のなかった事柄に興味を持てたという評価と、興味のステップをぶっ飛ばしすぎているという評価の両方を付加してみることにしました。 今まで通りのやり方ではうまくいかないと感じたときは、新しい知識や関心ごとを少しずつ取り入れてみています。しかし、自分の中の基軸に軽微な修正を加え続けるのが面倒になったとき、もしくは悩みごとがパターン化したとき、全くの新機軸を打ちたてたくなる。「すっごく変わってみるのはどう?」(宝石の国のダイヤちゃん)ですね。書店で目に入った本によって、そうした変身願望を刺激されたのだと思います。
書店を去って、ご飯を食べて友達としゃべるうちに、本への関心は薄らいでいきました。今は、隣りあう棚を移動するように、少しずつ関心の幅を広げていく方に心が向いています。いつも通りの状態です。変わらない自分に少し安心したと同時に、あんなにあの本に引き付けられたのは何であったのだろう、という不思議さが残りました。
もしかすると、いつかは正反対の考え方をしだすかもしれません。そのときはそのときで、ぶっ飛んでいく楽しさを享受したいですね。
0 notes
Text
買ってよかったもの2022+α
大晦日ですね。 体調を崩してしまい外には出ておりませんが、街ではあちらこちらから良いお年を、という挨拶が聞こえてくることでしょう。そうした年の瀬の雰囲気が好きです。 私も年の瀬ムードに参加すべく、買ってよかったと感じたものを紹介しようと思います。
書籍編
新潮社 新潮美術文庫シリーズ
作家ごとに刊行されている、小さな画集です。定規で測ってみたところ、横13センチ、縦20センチほどでした。それぞれの本に1人執筆者がついており、掲載作品や作家の解説を行ってくれます。 私が今年買ったのはコロー、ユトリロ、クレーの3冊です。特にクレーは、解説の部分も含め読みごたえがありおすすめです。 手ごろなわりに満足感もあったので、ちょっとずつ集めていきたいなあと思っています。日本の作家に限定した新潮日本美術文庫というのもあるみたいなので、そちらも気になっている。
東京美術 ヴィルヘルム・ハマスホイ 静寂の詩人
こちらはごく最近(たしか12月のはじめとかに)買ったものですが、かなり良かったので共有です。 Twitterか何かでハマスホイの室内画を見かけて「素敵すぎ!?」となり、そのまま大きい書店へ絵の載っている本を探しに行きました。 平凡社から出ているものと迷いましたが、1枚1枚の絵が大きく集中もしやすそう、という理由で東京美術の方を選びました。平凡社の方は、参考図版が充実していた印象です。 普段は電子か通販で本を買うことが多いため、久々に店頭で吟味したという意味でも印象的でした。
食料品編
茅乃舎 和風だし塩
マイ万能調味料とでも言うべきものがあるとすれば、私の場合はこれです。 魚のうま味と程よい塩味であらゆる素材がいい感じの味に仕上がります。私はおにぎりに使うのが1番好き。 湿気で中身が固まりやすいので、小さなお皿やフタに適量をとってから湯気の立つ料理に振りかけるようにしています。
KALDI クラフトジンジャー
辛いジンジャーエールが大好きで、中でも特に好みに合致しました。 喉にカ~ッとくる辛さと言うよりは、生姜感が強く舌の上でピリピリする感じです。 シロップとビールをまぜて作ったシャンディガフも美味しかったです。好きなお酒が増えて嬉しい!
その他編
RANDEBOO Bucket bag
A4もノートPCも入る。 デカいバッグはあればあるほどいいです。
Mattel ウノ ミニマリスタ
持っていくとオシャレ~と言ってもらえて嬉しかったです。でしょ~。 関係ないのですが、ウノがマテルという会社でつくられていたことも、マテルが世界最大規模の玩具メーカーであるらしいこともこの記事を書いて初めて知りました。超大手玩具メーカーってフィクションの中ではたまに見るけど本当にあるものなんだ。そりゃあるか……。
番外編 買ったけど活用できなかったもの
無印良品 週刊誌4コマノート・ミニ
フィルムスタディーに使おうと思い購入しましたが、ToDoリストと化しています。 しかもノートを開く習慣がないので、今やお守りのようなアイテムになってしまいました。 さいきん自分の中に「中長期の目標を立て、達成に向けて日々を細分化した方がいいに決まってる」という気持ちが芽生えてきたので、このノートの使い方を見直してみたいです。 構図も学習したいので、本来想定していた���途にも揺り戻したい。
フィルムアート社 類語辞典シリーズ
創作活動のサポートを前提に、様々な感情、性格、場面設定……がインデックスされています。最近刊行された「対立・葛藤類語辞典 上巻」以外の6冊をまとめ買いしてみました。 それぞれの項目の解説だけでなく、関連・派生する状況や、先行する作品例などもバランスよく記載されており驚きの充実度です。 自分の良くない性質として、既知の事柄の確認に終始してしまう、というのがあります。来年は自分の知らないこと・考えてこなかったことにも目を向け、その手助けとして類語辞典シリーズも活用できればいいな。
ここまでお読みいただきありがとうございました。 お風邪など召されませぬようお過ごしください。 来年もどうぞよろしくお願いいたします!
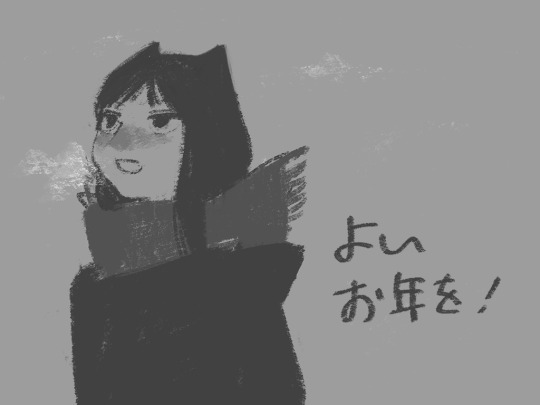
0 notes
Text
離別と道徳/川上弘美『神様』
「抱擁を交わしていただけますか」 くまは言った。 「親しい人と別れるときの故郷の習慣なのです。もしお嫌ならもちろんいいのですが」 わ��しは承知した。
川上弘美『神様』17頁
川上弘美『神様』(中央公論社、2001)は、「わたし」の語りで綴られた9つの短編からなる。表題作「神様」と、その続編「草上の昼食」では、「わたし」と「くま」のあたたかな交流がえがかれる。
くまとは文字通り、熊だ。「雄の成熟した」、大きな動物。 くま自身も「今のところ名はありませんし」と、「くま」以外であろうとはしない。何やら様々な事情を抱えているらしいが、「わたし」はそれを聞き出そうとはしない。 語り手である「わたし」にも不明な点が多い。『神様』の中に散らばった「三つ隣の305号室」「隣の隣の304号室」といった記述から、ある集合住宅の302号室に住んでいることはわかる。が、職業や年齢、経歴は一切明かされない。短編同士の時間軸もすっぽり抜け落ちている。実のところ、それぞれの短編における「わたし」が常に同じ「わたし」であるかどうかも、定かではない。
そんなくまと「わたし」が抱擁という交点を持ったのが、冒頭で引用した部分だ。くまに別れを告げられた日、「わたし」は「あのときの抱擁は、おずおずとした抱擁だった」と回想する。不明な二者がゆるくつながり、互いを開示しないまま交流を終えていく。自己開示の未完了は、ここでは良識に類する。
「結局馴染みきれなかったんでしょう」目を細めて、くまは答えた。 馴染んでいたように思っていたけど。言おうとしたが、言えなかった。ほんの少しなめたワインのせいだろうか、くまの息は荒いだけでなく熱くなっている。 わたしも馴染まないところがある。そう思ったが、それも言えなかった。かんたんに、くらべられるものではないだろう。
同書、184頁
彼らは、彼らのあいだに横たわった一線、とでも言うべきものを踏み越えなかった。 自身の境遇や苦しみを洗いざらい話してしまうことによって、あるいは他者と対決し和合することによって、ドラマチックな物語は生起する。しかし「わたし」は、そうした物語からは距離を取る。代わりに、ごくごく素朴な思いやりを他者に向け、離別の痛みを引き受ける。
寝床で、眠りに入る前に熊の神様にお祈りをした。人の神様にも少しお祈りをした。ずっと机の奥にしまわれているだろうくま宛の手紙のことを思いながら、深い眠りに入っていった。
同書、192頁
「わたし」はくまの他にも、様々な不思議な生きものたちと出会う。彼らは説明もなしにぽんと現れ出でて、当たり前に生活する。不明であることが了解されながら、「わたし」と彼らの関係は進行する。
「夏休み」「離さない」は他と少し違った印象も受けるが、根底にあるものは同じであろう。「わたし」は、自己と他者が同一化しそうなほどに強く結びつく痛みを退け、つないだ手を離す痛みを受け入れ続ける。 謎は謎のままに、別れの時が訪れるまで付き合っていく。自己と他者とが分かたれているからこそ、自分のできうる範囲で相手を思いやる。これが作品全体に貫かれた、誠実であたたかな態度であるように思われる。
くまの手紙を読んだ日、「わたし」はどんな夢を見ただろう。 くまと一緒に草原で寝ころぶ夢だったかもしれないし、全く違う夢だったかもしれない。 いずれにせよ、「わたし」にはそれを話す動機はない。目が覚めたら、いつも通りの一日を過ごしていくのではないだろうか。
参考文献 川上弘美『神様』(中央公論新社、2001年) 大塚英二『サブカルチャー文学論』(朝日新聞社、2004年)
0 notes
Text
横光利一「機械」
https://www.aozora.gr.jp/cards/000168/files/907_54297.html
Webページ上で文章全体を表示してまず驚く。改行が極端に少ない。句点も少ない。 そうした体裁上の特徴に加え、「私」の語りがややこしいのが内容の理解を困難にする。「私」は、他人の思惑や感情など、知り得る筈のない事柄についても断定口調で語る。直前で述べたことと真逆のことさえ言い出す。語りに根拠もなければ、一貫性もない。 面白いのは、「私」が語りの信用できなさにどこか自覚的である点、そして「機械」という小説が、メチャクチャな語りを有していながら破綻してはいない点だ。 「私たちの間には一切が明瞭に分かっているかのごとき見えざる機械が絶えず私たちを計っていてその計ったままにまた私たちを押し進めてくれている」という文章がある。「見えざる機械」とは、重クロム酸アンモニアという伏線であり、主人が必ず金を落とす約束事だと解釈した。すなわち、小説そのものの仕組み・機能、とでも言うべきものだ。 「私」の語りには「私」の主観が大いに反映されている。し��し、完全にプレーンな「ありのまま」が投げ出されているわけではない。事実、文章は裁断機にかけられたがごとく数度改行され、事後的に・順序良く情報が並べられている。 小説を構成しているのは「私」の語りだが、「私」はそれが信用ならないと知っている。信用ならずとも、小説としては成立する。そんな小説のはたらきも、「私」はうっすらと感知している。奇妙な入れ子構造を有した、技巧的な作品である。
0 notes
Text
海野十三「人体解剖を看るの記」
https://www.aozora.gr.jp/cards/000160/files/43839_18747.html
緊張と緩和、麻痺と覚醒がうつろう様子をうまく描写している。 メスが入れられると、少年の屍体からは人格がたちまち消去され、死因の解明を待つオブジェクトと化す。ただし、あくまでそれは、比喩の世界でそのように感じられた、というだけ。少年は人形に、魚に、教本でみた解剖図に喩えられる。既にイメージとして知っているものの反復は人を緩ませる。が、それらを「直視」したとき、再び不快な緊張感に見舞われる。 警察医が慣れた手つきで解剖を行った、という点がポイントのように思われる。彼にとってそれは、ごくごく日常の、繰り返された動作に過ぎない。簡便なオノマトペが屍体解剖を淡白に印象づける。科学とはいったい、このように地味で平凡な姿をしているのだろう、と思わされる。
0 notes
Text
雑に描いた絵
雑に描いた絵をテキトーに仕舞ってもらいたい! と思うことがあります。 もう少し詳しく書くと、気ままにすばやく描いた絵を、その場にいた誰かに手渡したい。内容をさらったあとは、授業中に回ってくるあのメモみたく、カバンの底にでも押し込んでほしい。学期末には、底にたまったレシート類と一緒にくずかごに投げ入れて構わない。なんとなく捨てづらいものを一時的に保管している例の場所、そこに放り込んでもいい。 ようは、私が雑に描いた絵を、きちんと雑に扱ってもらいたいのだと思います。
私が中学生のとき、どういう脈絡だったかは忘れましたが、ヒステリックな芸術家の寸劇をすることになりました。「絵をこちらで用意するから、それを役者に破ってもらおう」という私の提案が通ったので、画用紙に適当な図柄を描きました。 本番が終わったあと、クラスメイトのみんなが破かれた紙片を拾い集め、セロテープで繋ぎ合わせていたのをよく覚えています。彼らはつぎはぎの紙を私に手渡し「素敵な絵なのにもったいないよ」と言いました。役者の子はばつの悪そうな顔をしてた。書いてて思ったけど、本当にかわいくてやさしくて良い子たちだ。思い出すと胸がギュッとなります。 それはそれ、当時の私は奇妙な気分になりました。最初から破るのが目的だったのだから、あの絵はちゃんと役目を果たし終えたのだから、それでいいじゃないかと。保存を全く想定していなかったので、ちょっと面食らったのだと思います。
すこし前、Twitterからフリート機能がなくなりました。私はこの機能が大好きで、よく使っていました。24時間たてば投稿が自動で消去されるので、その日食べたごはんや出先の写真、落書きなんかを気軽に公開することができます。 現在はサブアカウントに作業進捗や落書きを投稿していますが、やっぱりフリートとは勝手が違うな、と感じることが多いです。ツイートとして投稿された絵は地層のように積み重なっていきます。一方フリートには、およそ時間軸と言えるようなものがない。その時その場にしかない絵が点々と散らばっている。今思えば独特の心地よさがあったように思います。 フリート、復活しないかな~。
冒頭の話の続きをします。 気ままにすばやく絵を描くとなると、必然そのとき置かれていた状況に影響されやすくなると思います。そうした日記未満の絵を、その場で誰かと共有してみたい。そこで大方の目的は達成されるので、あとはどうなってもOKです。むしろ処分されることが、逆説的に私の絵の任務を完了させている気すらする。 とはいっても、例えば一時的な保管庫から引っ張り出された紙切れが、当時の思い出を蘇らせたとしたら、きっと超うれしいだろうなあ、とも思います。
0 notes