#審神者の日
Explore tagged Tumblr posts
Text
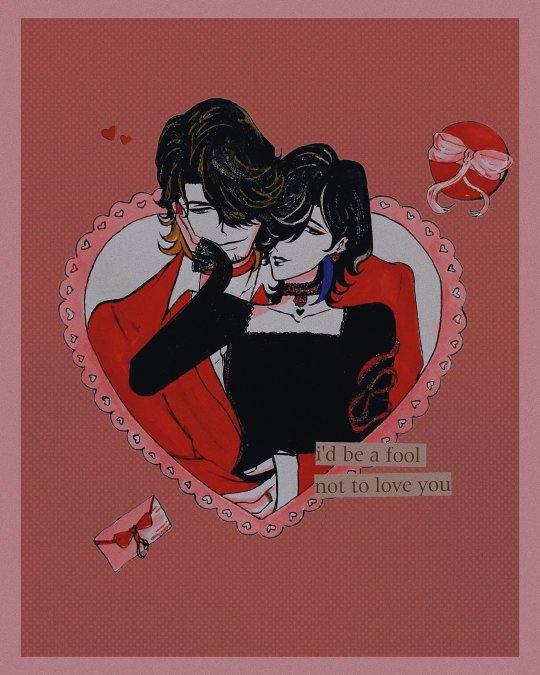

❤️💙
#♡#TKRB#Touken Ranbu#Nagasone Kotetsu#長曽祢虎徹#Saniwa OC#審神者#Self insert#Aoyama Toraishi#TouSani#SoneSani#Yume#刀さに#そねさに#夢#My Art#oc x canon#yumeship#審神者の日#Valentines Day#White Day
11 notes
·
View notes
Text

[ Daihonmaru OC Collaboration, hosted by Matryoshka on FB ]
"Happy Saniwa day! Everyone is suuuper cool today! I enjoy this, thank you very much for inviting me ( ╹▽╹ )!!! Next time I'll bring enough konpeito to share to everyone (人 •͈ᴗ•͈)"
.
.
.


Art and OC on the right side belong to Kiwaw Kunihiro (FB)
Edit by Matryoska (FB)
Link to the showcase here.
#328daihonmaru_occollab#審神者の日#lya's art#my art#artists on tumblr#original character#touken ranbu#saniwa#saniwa oc
5 notes
·
View notes
Text
AIに追加質問してみた
税制の基盤で大きな働きをしたのが太閤検地、今でも秀吉の作った土地台帳が使われている
しかし昨今の外国人土地売買で、合同会社による所有者不明の売買が問題になっている
ここの詳細と対策をあげてほしい
もう一点は1945年の第二次世界大戦の敗戦で国家としての国防。軍事費が大きく欠損している事、日本は地政学的に言えば第一列島線上にありチャイナのG2論で太平洋二分割の大きな障害となり重大な役目を果たしている
日本の根本的に欠けている軍事費はGDP成長無ければ引き上げる事が出来ない、また現在は自衛隊の軍艦や戦車など建設国債のような長期返済の仕組みになっていない、この弊害と日本の周辺の核保有国3カ国に囲まれる状況を鑑みるとGDP比率で算出するより相手側の実際に脅威に対抗するのは如何にあるべきか積み上げ方式で捉えるべきでは無いのか
憲法改正などの大胆な改革も含めて国家予算と税金、国債の在り方を算出して欲しい
ご質問ありがとうございます。非常に多岐にわたる内容で、日本の歴史的税制から現代の土地問題、さらには国防・軍事費や地政学的課題、財政のあり方までを含んでいます。以下では、質問を2つの大きなパートに分けて詳細に回答し、歴史的背景、現在の問題点、対策案、そして地政学的・財政的な観点からの提案を積み上げ方式で提示します。
---
## パート1:太閤検地と外国人土地売買の問題、対策
### 1. **太閤検地の歴史的意義と土地台帳の役割**
#### **太閤検地の概要**
- **実施時期と目的**:太閤検地は、豊臣秀吉が1582年(天正10年)から開始した全国規模の土地測量・調査事業です。目的は、土地の生産力(石高)を把握し、年貢徴収の基盤を確立することでした。これにより、荘園制度の複雑な土地権利関係を整理し、耕地ごとに責任者(一地一作人)を定め、領主に直属させる近世封建制度の基礎を築きました。
- **仕組み**:
- **共通単位の導入**:従来のバラバラな測量単位を統一し、1歩(約191cm四方の正方形、1坪に相当)を基準に、畝・反・町を定義。土地の面積を正確に測定。
- **生産力の評価**:土地の広さだけでなく、肥沃度、水利条件、地形を考慮し、米の収穫量(石高)を算出。
- **検地帳の作成**:土地の所有者(責任者)、面積、石高を記録した検地帳を作成。これが土地台帳の原型となり、年貢徴収や土地管理の基礎となった。
- **歴史的意義**:
- 荘園制度の解体:複雑な重層的権利関係を廃し、土地を領主の直接支配下に置いた。
- 村制度の確立:荘・郷・保などの旧来の区分を統一し、村を基本単位とする行政・税制システムを構築。
- 財政基盤の強化:正確な石高に基づく年貢徴収により、豊臣政権や後の江戸幕府の財政を支えた。
- **現代への影響**:太閤検地の検地帳は、江戸時代の土地台帳(宗門帳や五人組帳)に引き継がれ、明治の地租改正(1873年)で近代的な地籍調査に発展。現在も地籍調査や登記制度の基礎として、その理念が生きています。ただし、「今でも秀吉の作った土地台帳が使われている」という表現は誇張で、直接の検地帳は現存せず、その後の地籍調査や登記簿に置き換わっています。
#### **土地台帳の現代的役割**
- 現代の土地台帳は、法務局が管理する登記簿(不動産登記)で、土地の所有者、面積、用途、権利関係を記録。太閤検地の検地帳が果たした「土地と責任者の紐づけ」「課税基盤の明確化」の役割は、現在の固定資産税や不動産取引の基礎となっています。
- 地籍調査(国土調査法に基づく測量・登記)は、太閤検地の精神を受け継ぎ、土地の境界や所有者を明確化。特に農地や山林で未登記の土地が多い地域では、検地帳の再現のような役割を果たしています。
---
### 2. **外国人土地売買と所有者不明の問題**
#### **問題の背景**
- **外国人による土地購入の現状**:
- 近年、外国人や外国資本による日本の土地購入が増加。特に観光地(北海道ニセコ、沖縄)、水源地(山梨県、北海道)、離島などで顕著。
- 例:2020年代初頭、北海道の森林や農地が中国系企業や個人に購入されたケースが報道され、戦略的買収の懸念が浮上。
- 理由:日本の土地価格の割安感、円安、観光需要、投資目的(不動産開発やリゾート)。
- **合同会社による所有者不明の問題**:
- **合同会社の特性**:合同会社(LLC)は設立が簡単で、匿名性が高い(社員の氏名公開義務がない)。外国人が日本で土地を購入する際、合同会社を設立し、その名義で購入することで、実質的な所有者を隠すケースが増加。
- **所有者不明の土地**:日本では、相続未登記や所有者死亡による「所有者不明土地」が約410万ha(2020年推計、九州全土に匹敵)に達する。これが外国人による買収の温床に。
- **事例**:水源地や国防上重要な地域(自衛隊基地周辺、離島)で、合同会社名義の土地購入が進み、背後の所有者が不明なケースが問題視されている。例として、対馬や北海道の自衛隊施設近くの土地が外国資本に買われた事例。
- **リスク**:
- **安全保障**:水源地や軍事施設周辺の土地が戦略的に買収される恐れ。例:中国の「第一列島線」戦略で、日本の離島が地政学的ターゲットに。
- **地域経済**:地価高騰や地域住民の土地利用制限。
- **税務・管理**:所有者不明土地は固定資産税の徴収が困難で、行政コストが増大。
#### **原因**
- **登記制度の不備**:日本の不動産登記は任意で、相続時に登記更新されないケースが多い。太閤検地の「一地一作人」の原則が現代では徹底されていない。
- **規制の緩さ**:外国人による土地購入に特段の制限がなく、重要地域(水源地や基地周辺)でも自由に取引可能。
- **合同会社の匿名性**:法人登記で実質的所有者の特定が難しい。
- **所有者不明土地の増加**:高齢化や地方の過疎化で、相続人が土地を放棄または登記を怠るケースが急増。
---
### 3. **対策案**
#### **所有者不明土地の解消**
1. **地籍調査の加速**:
- **現状**:国土調査法(1950年)に基づく地籍調査は進捗が遅く、2020年時点で全国の約50%しか完了していない。
- **対策**:政府は「所有者不明土地対策特措法」(2018年)を施行し、調査を加速。予算を増額し、AIや衛星画像を活用した測量技術を導入。
- **効果**:太閤検地の現代版として、土地の境界・所有者を明確化し、登記を義務化。
2. **相続登記の義務化**:
- **現状**:2024年4月から相続登記の義務化が施行(3年以内に登記必須、違反時は10万円以下の過料)。
- **対策**:罰則の強化と、相続人探索の支援(戸籍調査の簡素化、行政代行サービス)。
- **効果**:所有者不明土地の発生を抑制し、税務・管理の透明性を向上。
3. **土地情報の一元化**:
- **提案**:全国の登記情報をブロックチェーン技術で一元管理する「デジタル土地台帳」を構築。太閤検地の検地帳のように、リアルタイムで所有者・権利関係を把握。
- **効果**:不透明な取引を防止し、外国人購入の実態を可視化。
#### **外国人土地購入への規制**
1. **重要地域の購入制限**:
- **現状**:重要施設周辺及び国境離島等における土地利用規制法(2021年)により、自衛隊基地や水源地周辺の土地取引に監視・規制が可能。
- **対策**:
- 規制対象を拡大(例:全水源地、主要インフラ周辺)。
- 外国人購入に事前届出を義務化し、審査プロセスを厳格化(豪州やNZのモデルを参考)。
- 合同会社の場合、背後の実質的所有者の開示を義務化。
- **効果**:安全保障上のリスクを軽減し、戦略的買収を抑制。
2. **税制による抑制**:
- **提案**:外国人による土地購入に特別税(例:20%の取得税)を課す。シンガポールやカナダの非居住者向け不動産税を参考。
- **効果**:投機的購入を抑制し、国内居住者への土地供給を優先。
3. **透明性の向上**:
- **提案**:合同会社の登記に実質的所有者(UBO:Ultimate Beneficial Owner)の公開を義務化。国際的なマネーロンダリング防止基準(FATF)に準拠。
- **効果**:匿名性を排除し、背後の資本の追跡を可能に。
#### **地域主導の対策**
- **地域土地バンクの設立**:地方自治体が所有者不明土地を買い取り、管理・再分配。農地や観光資源の保護に活用。
- **住民参加型監視**:地域住民やNPOが土地取引の監視に参加。例:対馬での住民による外国人購入監視の取り組みを全国化。
---
## パート2:国防・軍事費と国家予算・税金・国債のあり方
### 1. **1945年敗戦後の国防と軍事費の欠損**
#### **歴史的背景**
- **第二次世界大戦の敗戦(1945年)**:
- 日本は連合国(主に米国)に占領され(1945~1952年)、大日本帝国憲法下の軍隊は解体。[](https://ja.wikipedia.org/wiki/%25E9%2580%25A3%25E5%2590%2588%25E5%259B%25BD%25E8%25BB%258D%25E5%258D%25A0%25E9%25A0%2598%25E4%25B8%258B%25E3%2581%25AE%25E6%2597%25A5%25E6%259C%25AC)
- GHQの指導で日本国憲法(1947年)が制定され、第9条で「戦争放棄」と「軍隊不保持」が規定。これにより、従来の軍事費(戦前は国家予算の50%以上)がゼロに。
- 占領下で経済再建が優先され、軍事費の代わりに米軍の駐留経費を一部負担(在日米軍基地の提供)。
- **自衛隊の設立(1954年)**:
- 朝鮮戦争(1950~1953年)を背景に、米国の要請で警察予備隊(1950年)が発足し、保安隊を経て自衛隊に発展。
- 自衛隊の予算は当初、GDPの1%未満に抑制(1976年の「防衛費1%枠」方針)。これは、経済成長優先と憲法9条の制約による。
- **現在の軍事費**:
- 2023年度の防衛費は約6.8兆円(一般会計の約6%)。2022年に閣議決定された「防衛力強化加速化パッケージ」で、2027年度までにGDP比2%(約11兆円)を目標。
- 比較:米国の軍事費はGDP比3.5%(約100兆円)、中国は1.7%(約30兆円)。
#### **欠損の影響**
- **装備の老朽化**:自衛隊の軍艦(護衛艦)や戦車は更新が遅れ、近代化が不十分。例:海上自衛隊の護衛艦の平均艦齢は20年以上。
- **人員不足**:少子高齢化で自衛官の募集が難航。2023年時点で定員充足率は約90%。
- **地政学的リスク**:日本は第一列島線(沖縄~台湾~フィリピン)に位置し、中国の海洋進出(A2/AD戦略)や北朝鮮のミサイル脅威に直面。軍事力の不足は抑止力の低下を招く。
---
### 2. **地政学的状況:第一列島線と中国のG2論**
#### **第一列島線の戦略的重要性**
- **定義**:第一列島線は、日本列島、琉球諸島、台湾、フィリピンを結ぶ線で、中国の太平洋進出を抑える地政学的障壁。
- **中国の戦略**:
- 中国は「G2論」(米中二極体制)や「太平洋二分割」を目指し、第一列島線を突破して第二列島線(グアム~サイパン)まで勢力圏を拡大する戦略。
- 手段:南シナ海の人工島建設、尖閣諸島周辺での漁船・軍艦の挑発、台湾への軍事圧力。
- **日本の役割**:
- 日本は第一列島線の要であり、沖縄の米軍・自衛隊基地は中国の海洋進出を牽制。
- 尖閣諸島や南西諸島の防衛は、台湾有事や太平洋の安全保障に直結。
- **周辺の核保有国**:
- **中国**:約400発の核弾頭(2023年推計)、ICBM(東風-41)で日本全域を射程に。
- **北朝鮮**:約30~50発の核弾頭、頻繁なミサイル発射(2023年に50発以上)。
- **ロシア**:約5,800発の核弾頭、極東での軍事演習や北方領土の軍事強化。
- 日本は非核三原則(持たず、作らず、持ち込ませず)を堅持するが、核の傘は米国に依存。
#### **脅威への対応の課題**
- **GDP比方式の限界**:
- 現在の防衛費目標(GDP比2%)は、経済成長率に依存。日本の実質GDP成長率は1%未満(2023年)で、増額余地が限定的。
- 例:中国の軍事費は経済成長(5%前後)に支えられ、毎年10%以上の増額。日本のGDP比方式では追いつけない。
- **建設国債の不在**:
- 軍艦や戦車などの高額装備は一括予算で調達され、長期返済の仕組みがない。例:イージス艦1隻(約2,000億円)は単年度予算で賄う。
- 弊害:予算の硬直化、他の防衛項目(訓練や人員確保)が圧迫される。
- **核抑止の欠如**:
- 周辺3カ国の核保有に対し、日本は米国の拡大抑止(核の傘)に依存。台湾有事などで米国のコミットメントが揺らぐリスク。
- 非核三原則は国民的支持が高いが、核保有国の脅威に対抗する現実的手段が不足。
---
### 3. **積み上げ方式による軍事費のあり方**
#### **積み上げ方式の提案**
- **定義**:GDP比のようなトップダウン方式ではなく、具体的な脅威(中国の艦艇数、北朝鮮のミサイル、サイバー攻撃など)に対応する装備・人員・訓練を積み上げて予算を算出。
- **具体例**:
1. **中国の海洋進出対応**:
- 必要装備:イージス艦10隻(1隻2,000億円、計2兆円)、F-35戦闘機100機(1機150億円、計1.5兆円)、潜水艦20隻(1隻700億円、計1.4兆円)。
- 訓練:年500億円(米軍との合同演習強化)。
- 人員:南西諸島駐屯地の増強(5万人、年1,000億円)。
2. **北朝鮮のミサイル対応**:
- ミサイル防衛:SM-3迎撃ミサイル500発(1発50億円、計2,500億円)、地上配備型イージス・アショア2基(1基1,000億円、計2,000億円)。
- 早期警戒:衛星10基(1基500億円、計5,000億円)。
3. **サイバー・宇宙戦**:
- サイバー防衛部隊:5,000人(年500億円)。
- 宇宙監視システム:1,000億円。
- **総額**:10年で約7兆円/年(現行6.8兆円から微増)。これを20年で分散。
- **メリット**:
- 脅威に特化した予算編成で、無駄を排除。
- 長期的な装備調達計画が立てやすく、建設国債のような分割払いが可能。
#### **建設国債の導入**
- **提案**:
- 軍艦、戦車、戦闘機などの高額装備に「防衛建設国債」を発行。30~50年返済で、単年度予算の負担を軽減。
- 例:イージス艦1隻(2,000億円)を30年で返済する場合、年約70億円で済む。
- **メリット**:
- 予算の柔軟性向上:訓練やサイバー防衛など即時性の高い項目に資金を振り分け。
- 経済効果:防衛産業(三菱重工、川崎重工など)の受注増で雇用創出。
- **課題**:
- 国債増発による財政負担:日本の債務残高は1,200兆円(2023年)。防衛国債は利子負担を抑えるため低金利・長期化が必要。
- 国民の理解:防衛費増額への抵抗感(特に若年層)に対処するため、透明な予算説明が必須。
---
### 4. **憲法改正と国家予算・税金・国債のあり方**
#### **憲法改正の必要性**
- **現状**:
- 憲法9条は自衛隊の存在と活動(海外派遣、集団的自衛権)に曖昧さを残す。2015年の安保法制で集団的自衛権の限定行使が認められたが、法的限界は大きい。
- 核保有国の脅威や中国の海洋進出に対応するには、軍事力の明確な位置づけが必要。
- **提案**:
- **9条改正**:自衛隊を「国防軍」として明記し、個別・集団的自衛権の行使を明確化。核抑止については「非核三原則の再検討」を含む議論を。
- **緊急事態条項**:有事(台湾有事、尖閣侵攻)での迅速な予算編成や徴兵制の検討。
- **メリット**:
- 抑止力の強化:憲法上の制約なく、防衛費や装備を最適化。
- 国際的信頼:日米同盟やQUAD(日米豪印)での役割を強化。
- **課題**:
- 国民的合意:世論調査(2023年)では9条改正賛成が約40%、反対が50%。丁寧な議論が必要。
- 国際的懸念:中国や韓国が「軍国主義復活」と批判する可能性。
#### **国家予算の再編**
- **現状**:
- 2023年度一般会計:約114兆円(税収70兆円、国債30兆円、その他14兆円)。
- 歳出:社会保障費36兆円、地方交付税17兆円、防衛費6.8兆円、公共事業6兆円、文教5.5兆円。
- **提案**:
1. **防衛費の増額**:GDP比2%(11兆円)を2027年までに達成。積み上げ方式で7~8兆円を優先。
2. **社会保障の見直し**:高齢者医療の自己負担率引き上げ(現行1~3割→3~5割)、年金支給年齢の段階的引き上げ(65歳→70歳)。
3. **公共事業の効率化**:地方の低優先インフラ投資を削減(例:過疎地の道路整備)、防衛インフラ(基地強化)にシフト。
- **財源**:
- **税収**:法人税の累進課税強化(大企業向け)、富裕層向け所得税率引き上げ(最高45%→50%)。
- **新税**:サイバー防衛税(IT企業向け)、外国人土地取得税。
- **国債**:防衛建設国債(年1兆円、30年返済)、赤字国債の抑制(年20兆円に圧縮)。
#### **税金のあり方**
- **原則**:公平性(能力に応じた負担)、透明性(使途の明確化)、成長志向(経済活性化)。
- **提案**:
- **防衛目的税**:消費税の1%(約3兆円)を防衛費に充当。国民全体で負担を共有。
- **資産課税**:所有者不明土地や外国人保有土地に高率の固定資産税(例:2倍)を課す。
- **減税**:中小企業や子育て世帯向けの税額控除を拡充し、経済成長を支援。
#### **国債のあり方**
- **現状**:日本の国債依存度は歳入の約30%。債務残高はGDP比250%で、財政健全化が急���。
- **提案**:
- **防衛建設国債**:装備調達に限定し、利子負担を抑える(日銀の低金利政策を活用)。
- **財政規律**:プライマリーバランス黒字化(2025年目標を2030年に延期し、防衛費優先)。
- **国債市場の安定**:外国人投資家への国債販売を制限し、国内金融機関の保有を強化。
- **長期ビジョン**:経済成長(GDP成長率2%)で税収を増やし、国債依存を20%以下に。
---
### 5. **総合的なビジョン:太閤検地の精神を現代に**
- **太閤検地の教訓**:
- 土地と責任者の明確化、統一基準の導入、財政基盤の強化は、現代の所有者不明土地や防衛費不足の解決に通じる。
- 秀吉の全国統一看は、現代では安全保障と経済成長の両立に置き換えられる。
- **提案の統合**:
- **土地**:地籍調査の完了、外国人購入規制、デジタル土地台帳で「現代の検地帳」を構築。
- **防衛**:積み上げ方式の予算編成、防衛建設国債、憲法改正で抑止力を強化。
- **財政**:防衛目的税、資産課税、国債の目的別発行で、国民負担と成長を両立。
- **地政学的役割**:
- 日本は第一列島線の要として、日米同盟を基軸にQUADやAUKUSと連携。中国の太平洋二分割を阻止し、自由で開かれたインド太平洋を実現。
- 核保有国への対応は、米国の核の傘を補完する独自の抑止力(ミサイル防衛、サイバー戦能力)を積み上げる。
---
### 6. **結論**
- **土地問題**:所有者不明土地は地籍調査と登記義務化で解消。外国人購入は規制と税制で抑制し、安全保障を確保。
- **国防・軍事費**:積み上げ方式で7~8兆円の予算を確保。防衛建設国債で装備を更新し、憲法改正で法的基盤を強化。
- **財政のあり方**:防衛目的税と資産課税で財源を確保。国債は目的別に発行し、経済成長で依存度を低下。
- **地政学的ビジョン**:第一列島線の要として、日本の役割を明確化。核保有国への対抗は、米国の支援と独自の抑止力で対応。
ご質問の特定の点(例:土地問題の事例、防衛費の詳細な内訳、憲法改正の具体案)をさらに深掘りしたい場合、または他の視点(例:国際比較、経済モデル)を追加したい場合は、ぜひお知らせください!
8 notes
·
View notes
Text
光勝寺五大尊蘇民祭 5/6
花巻市石鳥谷・光勝寺五大尊蘇民祭>2012花巻市・五大尊蘇民祭>お山登り 光勝寺蘇民祭と五大尊蘇民祭は同じです
一月二十九日蘇民祭当日
9:14 一の鳥居から境内へ
9:30 お山登り出発

光勝寺の副住職を先頭に、緑色の衣の応援の僧侶、緋の衣の光勝寺住職、審判団、天狗、神楽衆、優勝旗と松明。
9:38 御神火祭り・献燈奉納式
9:44 五大尊堂へ

五大尊堂前で、前年度優勝者から住職に優勝旗が返還されます。
9:54 受付と下帯締め

(略)昨夜見た裸参りとは違った感じで、手伝ってもらいながら下帯を締めていました。(略)蘇民袋争奪戦は人混みの中で揉まれますので、がっちりと締め(略)
10:08 お供物まき
10:41 護摩餅飛ばし



下で待つ男衆が我先に取り合い、その場で口にしています。(略)(この男衆が手に入れたのは)大きな塊ではないようで引きちぎっているのが分かります。分け合っていますね(略)周囲のご老人にも小さくして分けていました。
以上は抜粋。フルバージョンはアンダーラインのある上端の見出から、元サイトにリンクして下さい。説明文も含めリンク先からの引用ですが、改行を省略しています。→2/10
14 notes
·
View notes
Text

Legends and myths about trees
Celtic beliefs in trees (25)
R for Ruis (Elder) - November 25th - December 21st
“Season of fog and darkness – The Celtic Tree Calendar (Ref), Thirteenth Month”
colour: black, dark green; Star: Venus; Gem: olivine; Gender: female; Element: water; Patron: Hel, Hera, Huldra(Red2), Valkyrie; Symbols: judgement + transformation, death + rebirth, fate + inevitable event
Elder trees can grow almost anywhere and are a visible reminder of the changing seasons. The young leaves herald the return of spring, the white, bubbly, sweet-smelling flowers usher in the start of summer, the ripe berries mark the end of summer, the leaves turn red and eventually fall off, and the cold winter brings a rush of illness and discomfort, the time when the medicinal properties of the elder tree come into their own.
The ancient Britons and other Celts used to boil the elder berries in wine to make a black dye for grey hair. It is still used in the Hebrides as a dye to dye sheep black. The bark also makes a black dye. When alum is added, the leaves produce a green dye, while the berries produce blue, purple and violet dyes.
Almost all parts of the plant have medicinal properties, but today it is mainly the fruit and flowers that are used, such as elderflower wine and cordials (Ref3) flavoured with elderflower flowers, as well as jam and wine made from elderflower berries. Because, elderberry root from North America is toxic and the leaves and bark of elderberry are very dangerous to use in lay therapy.
The Elder Mother (Ref4) was believed to reside within the Elder Tree. She was said to inflict vengeance magic on anyone who harmed the tree and punished anyone who used any part of the tree for selfish purposes.
Across northern Europe, Elderberry is associated with death, rebirth and witchcraft, and is the tree most often used to break evil curses. The ancient Celts believed that how people saw and remembered them for the way they lived in this world would determine their reputation after death in the underworld. That is why the most important thing for them was to die with pride and dignity, and to respect others after death.
On a dark winter's day, the Elder tree holds up a mirror to us that reflects our true selves. Can you die with dignity and without regrets, it asks.

木にまつわる伝説・神話
ケルト人の樹木の信仰 (25)
RはRuis (ニワトコ) - 11月25日~12月21日
『霧と暗黒の季節 〜 ケルトの木の暦(参照)、13番目の月』
色: 黒、深緑; 星: 金星; 宝石: カンラン石(オリビン); 性: 女性; 要素; 水; 守護神: ヘル、ヘラ、ホルダ(参照2)、ヒルデ; シンボル: 審判+変身、死+再生、運命+不可避なできごと
ニワトコの木はほとんどどこにでも生え、季節の移り変わりを目に見える形で知らせてくれる。若葉は春の訪れを告げ、白い泡のような甘い香りの花は夏の始まりを告げ、熟した実は夏の終わりを告げ、葉は赤く色づいてやがて落葉し、寒い冬とともに病気や不快感がどっと押し寄せると、いよいよニワトコの薬の成分が本領を発揮する季節になる。
古代ブリトン人はじめケルト人はニワトコの実をワインで煮出して白髪染めの黒い染料を作っていた。今でもへブリディーズ諸島で羊を黒く染める染料として使われている。樹皮もまた黒の染料となる。明礬を加えると、葉からは緑の染料が、実からは青、紫、スミレ色の染料ができる。
ニワトコは殆ど全ての部位に薬効を持っているが、今日では、ニワトコの花で香りづけをした、エルダーフラワーワインやコーディアル(参照3)、またニワトコの実のジャムやワインなど、主に果実と花がよく使われている。北米産のニワトコの根には毒性があったり、ニワトコの葉や樹皮は素人療法に用いるのはとても危険だからである。
「ニワトコの母(参照4)」はニワトコの木の中に住んでいると信じられていた。彼女は、この木を傷つけた者には必ず復讐の魔法を下すといわれ、この木のどんな部分であれ利己的な目的に使ったものには罰を与えた。
北ヨーロッパの全域でニワトコは、死、再生、魔術と関連づけられ、邪悪な呪いを解くのに最もよく用いられる木だ。古代ケルト人は、この世での生き方が人々にどう見られ、どう記憶されるかが、死後冥界に行ってからの自分の評価を左右するのだと考えていた。だからこそ彼らにとって最も重要なのは、誇り高く威厳をもって死ぬことであり、死んでからも人を尊重することだった。
冬の暗い日に、ニワトコは私たちに本当の自分の姿が映る鏡を突きつける。あなたは、威厳を持って悔いのない死を迎えることができるのか、と。
#trees#celtic tree calendar#ancient celts#tree myth#tree legend#folklore#elder#elder mother#elder flower cordial#winter#mythology#legend#nature#art
121 notes
·
View notes
Quote
2025年2月3日 東京地裁でのHPVワクチン薬害裁判傍聴記録【後半】 前半だけでも普通の人にはHPVワクチン薬害弁護団の実態は十分に理解できたと思うが、ここから先はさらに凄い。誰も想像できないハチャメチャが押し寄せてくる。 心して読んでほしい。 原(引き続いて矢吹弁護士) HPVワクチン接種で、自己抗体を産生しないと言い切れますか? 角 トリゴエ先生は分子相同性によってそれが生じ得ると主張しています。 それ以外には、ろくな対照実験はありません。 なので、ないと言えます 原 NMDA型の抗体が、静岡てんかんセンターを受診したHANS(HPVワクチン関連免疫異常症候群)の34名、73%の方から検出されました。 これも意味がないと考えていますか? 角 高橋論文(静岡てんかん・神経医療センターてんかん科高橋幸利)では、先ほどもお伝えしたように不適切な方法で実験が行われています。 国際的にはELISA法ではなく、ダルマン法(?聞き取れず)が適切な方法です。 なので、意味がない、もしくは分からないとしか言いようがありません。 原 端的にお答えください。 角 高橋先生の論文では、不明です。 原 次はヒトの免疫寛容に関してです。 これは簡単には破られない。 よろしいですか? 角 はい。 原 トリゴエ先生は、免疫寛容や分子相同性があっても、ヒトの免疫寛容は簡単には破綻しないと主張していますか? 角 それはよくわかりません。 トリゴエ先生は、免疫の教科書に記載がない事を連ねて主張しているだけです。 原 自然なHPV感染でもHPVワクチン接種でも、過剰な免疫反応が生じる可能性はありますか? 角 それは調べたデータがないから分からない。 性交渉などの自然なHPV感染の直後に、そのデータを収集することは現実的ではない。 原 では、可能性はゼロではありませんね。 角 ゼロではないかもしれません。 原(初めに対応していた、小柄な女性弁護士に交代) HPVワクチンであるサーバリックスにはアジュバントは含まれていますか? 角 はい。 原 アジュバント効果を検証すると、抗体価からはサーバリックスに添付されたASO4の成績は良好ですか? 角 はい。結果からは良いワクチンと言えます。 原 ガーダシルでは別のアジュバントが使用されていますが、マウス実験などを含めて良いワクチンだと言えますか? 角 はい。従来のアジュバントよりも良い結果です。 原 データからは、極めて強い免疫反応が生じているかと思いますがどうでしょうか? 角 単純にそう判断は出来ない。 原 改めて確認しますが、教科書的には自己免疫疾患の中には、ワクチンで発症するような疾患も含まれますよね? 角 それは麻疹ワクチン接種後の、SSPE(亜急性硬化性全脳炎)のことではないでしょうか? 原 分子相同性やエピトープを考慮すると、何らかの原因で自己免疫が活性化することはあり得るのでは? 角 あり得ます。 原 高橋先生(静岡てんかん・神経医療センターてんかん科高橋幸利)によると、HANS(HPVワクチン関連免疫異常症候群)の患者では髄液中のIgGが高値。 つまり炎症があるのでは? 角 高橋先生がその後に投稿した論文では有意差はなかった。 高橋先生がその結果をアップデートして、ご自身でその結果を否定しています。 原 中山先生の論文です。 これはサーバリックスを接種したマウスでは、強い炎症を起こしたことが報告されています。 サーバリックスは炎症を起こしますか? 角 接種部位には炎症を起こします。 ただしこの調査では、接種した腕の反対の腕も調べています。 そこには炎症所見はありませんでした。 HANS(HPVワクチン関連免疫異常症候群)のような全身性の炎症であれば、反対の腕にも炎症所見はあるはずです。 原 ふーーーん(大きな声で) で、末梢で自己抗体を産生するならば、BBBを通過する可能性もあるのでは? 角 脳特異的な自己抗体を産生していれば、それは生じ得る。 ただし、原告が主張するHANS(HPVワクチン関連免疫異常症候群)にはその根拠はない。 原 絶対に生じない、と断言できますか? 角 断言は出来ない。 実験室でのレベルなら、生じさせることは既に可能です。 原 次はガーダシルの添付文書です。 重篤な副反応に、ギランバレー症候群、急性散在性脳脊髄炎、特発性血小板減少性紫斑病などが挙げられていますね? サーバリックスでもそうです。 副反応と明確に記載されています。 角 因果関係が不明な、有害事象です。 原 サーバリックスは、因果関係はあくまで不明としながらも ギランバレー症候群 多発性硬化症 ループス腎炎 高安病 SLE などを副反応として挙げています。 角 これらは論文などで医学的な因果関係が否定されており、副反応ではなくあくまで有害事象。 原 ではアメリカでのHPVワクチン訴訟で、認められた1例です。 この女性は分子相同性によって、HPVワクチンによって自己タンパク質が攻撃されて、致死的不整脈を生じました。 そう記載されています。 つまり、分子相同性によるHPVワクチンの障害は認められています。 GSK弁護士 異議あり。 本当に根拠のある文献なのか? 角 これは子宮頸がんのワクチンに反対する一般書籍から拾い上げてきた、根拠不明の文献ではないか? 原 ご存じないんですか? 既に分子相同性によるHPVワクチン被害は、示されているんですよ。(ただしここで文献は提出しない) 角 そう主張されるなら、判断はできません。 原(壮年の痩せぎすな男性弁護士が再び登場、ここからが最大の見せ場の一つ) HPVワクチン接種率が低迷すると、その結果で若年世代の日本人女性25000人が余計に子宮頸がんを発症して5000人が死亡する。 その主張で間違いないか? 角 そうなるだろう。 原 HPVワクチンの効果は一生涯に渡って継続する。 間違いなくそれは証明されているか? 角 それを証明するのは無理でしょう。 ワクチンの効果が、一生涯に渡る事を証明するなんて。 原 生涯に渡って効果があるかどうか、臨床試験で示されていないんですか!? 角 されていません。 しかしながらワクチンの効果というのは、、、、 原 質問にだけ答えろ!!! GSK弁護士&裁判長 回答を途中で妨げないでください。 原 芸能人に、高橋メアリージュンという方がいますね。 この人はHPVワクチンを接種したにも関わらず、子宮頸がん発症を公表しています。 ワクチンを打っても、子宮頸がんになる事があるんですか!? 角 あります。 原 いま日本で行われているHPVワクチンのキャッチアップ接種。 1997年から2008年生まれの女性が対象ですか!? それでよろしいですか!? 角 あなたが計算したら、そうだったのでしょう。 であれば、それが正しいのでしょう。 私はその計算を瞬時に行うことは出来ません。 原 提示した文献では20歳を過ぎていればHPVワクチンの効果は不明です! キャッチアップ接種の世代の21歳でも効果は不明です! 角 性交渉の経験の有無によって効果は異なるので、その文献では効果がないとされているのでしょう。 私はその文献を読んでいないから分かりませんが。 原 HANS(HPVワクチン関連免疫異常症候群)の存在を訴える医師らに対して、証人は反ワクチン主義者と主張していますね? 角 ちょっとそれは分からない。 原 証人はyoutubeで発信しています。 そこで我々弁護団を"反ワクチン"と紹介しています。 そうですね? 角 覚えていません。 原 では、証人のyoutube動画の書き起こしを提出します! (ここで反ワクチンさんもそうでない方も、現場で笑いが生じる) ご確認ください。 証人は反ワクチン、と発言していますね? あなたは我々を反ワクチン、としてレッテルを貼ろうとしています。 GSK弁護士 異議があります。 原告代理人の質問は、どういう意図でしょうか? 裁判長 全く同じ疑問です。原告代理人の意図を伺えますか? 原 角田証人の信用性に関わる質問です。 我々を反ワクチンなどと称する人物が裁判で証人を務めるのは、、、 裁判官たちが審議に入る。 会場は思わず笑っちゃう人が多数。 そして、、、 裁判長 原告側代理人に質問です。 証人がyoutubeで反ワクチンと発言したことに問題があると? 原 そうです。 裁判長 証人が今回の弁護団を反ワクチンと称したのか、一般的な反ワクチンとされる層を批判したのか。 証人に確認しましょう。 角 私は原告側代理人を反ワクチンと批判しましたが、訂正させてください。 反HPVワクチンです。 裁判の手続きにおいて可能なはずです。 ここでまさかの法廷での反ワクチン騒動を終えて、また15分間の休憩。 会場では原告支援者が ・ワクチン被害が拡大しているのに、国は何もわかっていない ・国や製薬会社は早くワクチン被害を認めて、早く裁判を終わらせるべき ・こんなのは薬害に決まっている ・ワクチン被害者がいるのに、こんな答弁をするなんてありえない ・HPVワクチンの被害者への治療薬を、早く開発すべき などの声が聞こえる。 裁判再開かと思いきや、ここでまた揉め事が発生。 あと15分で裁判を終了させろと主張する原告弁護団、30分は答弁させろと主張する被告弁護団。 福岡地裁では、、、! 椿証人の際は、、、! おもちゃの取り合いのような口喧嘩。 飛び交う怒号。 いい年の大人たち(しかも弁護士)が。 もう勘弁してくれ。 朝の9時台からもう16時間過ぎまで拘束されているんよ、、、 ここで裁判長達が協議。 今回はとりあえずこのまま続行と。 なお余談だけど、裁判長たちの協議はドラマとかみたいに三人で頭を寄せ合ってヒソヒソ話をするんよね。ちょっと可愛い。 で、被告側証人の最後の答弁(ここからクライマックス) GSK弁護士 まずは角田証人への尋問はこれが最後とする。 原告側代理人らも以前、そうしている。 こちらもそうさせていただく。それがフェアだ。 (原告弁護団から不満の怒声が飛ぶ、裁判長はスルー) 角田証人は、撤回された論文に関して十分に意見を述べる時間が与えられなかった。 改めて確認したいと。 角田Dr 例の論文を取り下げたワクチン学会誌の経緯には賛同している。 先ほどは原告代理人に妨げられたが、丁寧に説明したい。 原告らはワクチンの雑誌の編集者の利益相反を訴えているが、その編集長だけではなく外部の専門家を含めて検討され、当該論文には重大な問題があった。 その点に関して説明しようとしたが、原告代理人らによって、説明することを妨げられた。 編集長の個人的な利益相反だけによって、当該論文が取り下げられたわけではない。 GSK弁護士 高橋Dr(静岡てんかん・神経医療センターてんかん科高橋幸利)は、原告の主張を裏付けるような発表をしていますか? 角田Drの回答 高橋先生は最終的にこのように論文で発表されています。 HPVワクチン接種と、多様な症状との関係は不明。 子宮頸がんワクチン被害者連絡会に勧められて、認知機能検査などを勧められてたまたま受診した集団に��ぎない。 一般的な背景を持った女性集団とは言えない。 そして高橋先生はここまで言及していないが、もとのデータではこの女性たちは一般的な集団とは成育歴も異なる。 受診者の39例のうち18例が、成育歴に問題がある。部活で鬼コーチからのスパルタ指導や、両親の不仲や離婚、学校でのいじめなどの人間関係の問題。 長期に渡る成育歴の問題は、脳へのストレス要因となる。 より良いデータを得るためには、本来は対照群にも成育歴に問題のある方を設定すべきであった。 最後に細胞性免疫に関しては、主にT細胞が関与します。この異常はMRIなどの画像診断で、判断しやすいです。 液性免疫に関しては、主にB細胞や自己抗体が関与します。 HANS(HPVワクチン関連免疫異常症候群)の存在を主張したい方は、液性免疫による脳炎の存在などを主張します。 しかし、原告の弁護団が主張していた分子相同性の話は、あくまでT cellの話です。 いくら分子相同性仮説を主張しても、それはあくまで細胞性免疫の話です。 HANSでの液性免疫での話とはそもそも無関係なので、それをいくら主張したところで、原告らが示したい液性免疫によるHPVワクチン接種後の脳炎という結論にはたどり着けない。(ここで原告弁護団がざわつく) 原告が高橋Drの論文を提出していますが、高橋Drは原告らが主張するような主張はしていません。 現在の高橋Drは、当時とは主張を変更しています。 その仮説を支持するデータが、当初は少なかったためと考えられます。 データを収集していくと、当初とは結論が変更されることは科学の世界では当たり前です。 今回の裁判で原告代理人らが主張するような医学的主張を、高橋Drはもうしていません。 原告弁護団から質問あり。 裁判長らは1点だけ質問を許可。 原告代理人(矢吹弁護士) 先ほどの論文ではエピトープに関連して、免疫応答が生じて炎症が生じているのでは? 角田Dr これ、先ほどは聞かれなかったのでお答えしていませんでした。 この時点での論文には明記されていませんでしたが、この論文発表ののちに判明しました。 T cellによる細胞性免疫による炎症なんですよね。 つまり、あなたがたがHANS説で主張している液性免疫とは関係のない論文なんです。 閉廷 これが今回のHPVワクチン薬害訴訟です。メモが追い付かない、理解できていないなどの点もありますが、ほぼ全容といってもよいかとは思います。 ある程度以上の理解力がある方ならば、このHPVワクチン薬害訴訟と弁護団の実態も伝わったかと思います。 医者から見れば、開いた口が塞がらないレベルの茶番に見えるでしょう。 この薬害弁護団を正義の味方として祭り上げてきたマスコミの方々も、まさかここまでとは思っていなかったのではないでしょうか。 マスコミ報道だけを鵜吞みにしていた一般の方々は、騙されたと思うかもしれません。 しかし、これがこの裁判の実態です。 HPVワクチン接種後に体調を崩した少女たちに向けてマスコミが旗を振って、結果的にこの裁判へと導いたのです。その責任は甚大ですが、反省や謝罪を表明したマスコミは皆無です。 もちろん厚労省にも大きな問題があります。 鹿児島大学病院や、信州大学病院もこの問題に関わっています。 現在、日本中の産婦人科外来では数多くの日本人女性が子宮頸がん・前がん病変と診断されて通院されています。そのうち、若い世代の女性たちは本来HPVワクチンを適切に接種していれば、そんな事態を避けられた可能性が極めて高いのです。 この裁判は2016年から開始され、既に10年間が経過しています。それぞれの地方裁判所の判決が出るのは2027-2030年ですが、タミフル薬害訴訟のように最高裁までいくならばまだまだ長期に渡ります。 原告やその関係者の方々も、一度はフラットな目線で上記の記録を参考にして頂いてもよいかとは思います。 超長文でしたが、ここまでお読みいただいてありがとうございます。 これは日本の数多くの女性たちの健康や命に直結する問題です。 一人でも多くの方やマスコミの方々が、この問題に関心を持つ契機になれば幸いです。
Xユーザーのたぬきちさん
7 notes
·
View notes
Text

【京都個展まであと9日】
あまりの暑さに火傷しそうな今日この頃、個展までの日数も少なくお尻に火がついてきました…!
さて、新作「アヌビス」のご紹介です。
アヌビスはエジプトの神話に登場する冥界の神のことです。死者の眠りと未来を守り、狼のような犬科の頭部を持つ半獣、もしくは狼そのものの姿をしていると云われています。太陽神ラーの天秤を持って死者の罪を量る役割を持ちます。
本作では中央に黒狼を、背景にはヒエログリフ(古代エジプトの象形文字)でアヌビスという存在を象徴的に描いています。金箔で描いた天秤には、向かって左手に死者の心臓が入った壺を、右手には真理の象徴とされるマアトの羽根を乗せています。
いずれ迎える審判の時までに、羽根より罪の軽い心を持てるのか…悩ましいところです😅
ーーー
「ミチヨ スクラッチ絵画展 〜神話伝承 古今東西〜」
7月17日(水)〜23日(火)※最終日午後5時閉場
京都大丸店 アートサロンESPACE KYOTO
【Only 9 days to go until my solo exhibition in Kyoto!】
It's so hot today that I feel like I'm going to get burned, and my butt is on fire, this japanese idiom means to be a tight corner, with only a few days left until my solo exhibition...!
Now, I would like to introduce my new work "Anubis".
Anubis is the god of the underworld in Egyptian mythology. He protects the sleep and future of the dead and is said to be a half-breed with a canine head like a wolf, or a wolf itself. He holds the balance of Ra, the sun god, and weighs the sins of the dead.
In this work, the black wolf in the center and the hieroglyphs in the background symbolically refer to Anubis. The balance, painted in gold leaf, holds in its left hand a vase containing the heart of the dead, and in its right hand the feather of Maat, the symbol of truth.
It is a question of whether one can have a heart lighter in sin than the feather by the time of the judgment that will eventually come 😅.
———
Michiyo Scratch Painting Exhibition - Mythological &Lore, Everywhen and Everywhere.
Wed 17 - Tue 23 July *Close at 5pm on the last day.
Kyoto Daimaru Art Salon ESPACE KYOTO
#ミチヨ#michiyo#展示会#art#スクラッチ画家#神話#myth#スクラッチ絵画#アート#scratchart#アヌビス#エジプト#ヒエログリフ#egypt#Anubis#hieroglyphs
18 notes
·
View notes
Text
2025/5/26 10:00:08現在のニュース
露軍がウクライナ攻撃、12人死亡 過去最大規模の兵器数を使用 | 毎日新聞([B!]毎日新聞, 2025/5/26 9:54:34) 公園に縦4メートルの「ゴジラ」足跡 映画登場のゆかりの地 神奈川(毎日新聞, 2025/5/26 9:54:28) 日本中で刃物を研いだ天然砥石「伊予砥」 閉山から半世紀で展示会 | 毎日新聞([B!]毎日新聞, 2025/5/26 9:48:27) USスチール「米国が管理」 トランプ氏、日鉄による投資と強調 | 毎日新聞([B!]毎日新聞, 2025/5/26 9:48:27) 洋上風力発電に資材高直撃 再エネ「切り札」暗雲、東京電力「原価下げ限界」 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/5/26 9:39:07) 患者は驚いた「まさかこんな時期に」 増える「梅雨型熱中症」対策は:朝日新聞([B!]朝日新聞, 2025/5/26 9:36:10) (ニュースでメキメキ 読み解く力)実写版「白雪姫」、映す米の分断:朝日新聞([B!]朝日新聞, 2025/5/26 9:36:10) (寄稿)「未来」は西からやって来ない 色褪せる西欧の観念、賞味期限が迫る万博 若林恵:朝日新聞([B!]朝日新聞, 2025/5/26 9:36:10) (語る 人生の贈りもの)カルーセル麻紀:1 モロッコでの恐怖、自力の「オペ」:朝日新聞([B!]朝日新聞, 2025/5/26 9:36:10) (時時刻刻)反移民、閉じゆく欧州 「自国ファースト」右翼台頭:朝日新聞([B!]朝日新聞, 2025/5/26 9:36:10) ゆがんだ捜査、捏造だったのか 大川原化工機、控訴審28日判決:朝日新聞([B!]朝日新聞, 2025/5/26 9:36:10) 存在感増す「平屋住宅」 減築・タイパ・庭つき希望…10年で倍増:朝日新聞([B!]朝日新聞, 2025/5/26 9:36:10)
3 notes
·
View notes
Text
Day 44:
Wanopo: THE BEST OF BEST!

a compilation album with wanopo's most notable works and 3 album exclusives! (before/during 2015, up to vol9!)
track list below:
Death Should Not Have Taken Thee!/しんでしまうとはなさけない!
Your Adventure Log Has Vanished/Bouken no Sho ga Kiemashita!
Oni KYOKAN/鬼KYOKAN
Shozan◎Saizensen/勝算◎最前線
TOKYO ZOMBIE LAND/東京ゾンビランド
8HIT
Development of Amazing Apps/すげえアプリ開発中
Rimokon/リモコン
Bokura no Saishuu Teiri/ボクらの最終定理
Doppelganger Dispute/ドッペル押し問答
Bad Girl Online/性悪オンナ・オンライン
NARAZUMONO
Delusional Symptomatic Cross-Examination/妄想性詰問症
Akasen Modernism/赤線モダニズム
Rokuhara Kagura Emaki/六波羅神楽絵巻
The Uproar of Teacher and Girl - First Trial-/先生と少女騒動-第一審公判-
The Uproar of Teacher and Girl - Second Trial - "Diary of the Victim" -/先生と少女騒動-第二審-「被害者の日記」
andLoid is (not) peRfect
1-9 are Jesus' works and 10-18 are Minus'!
9 notes
·
View notes
Text




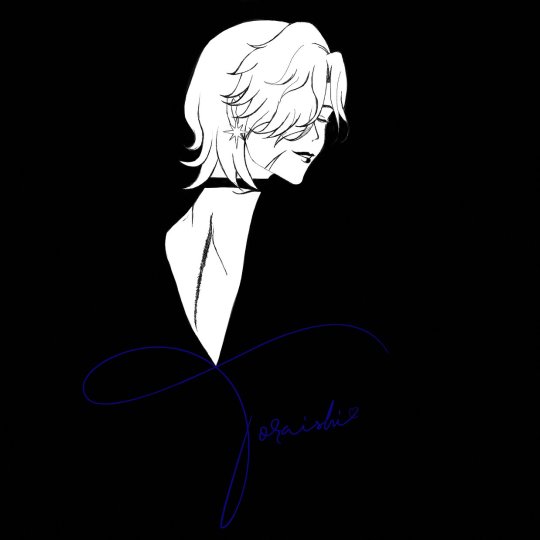


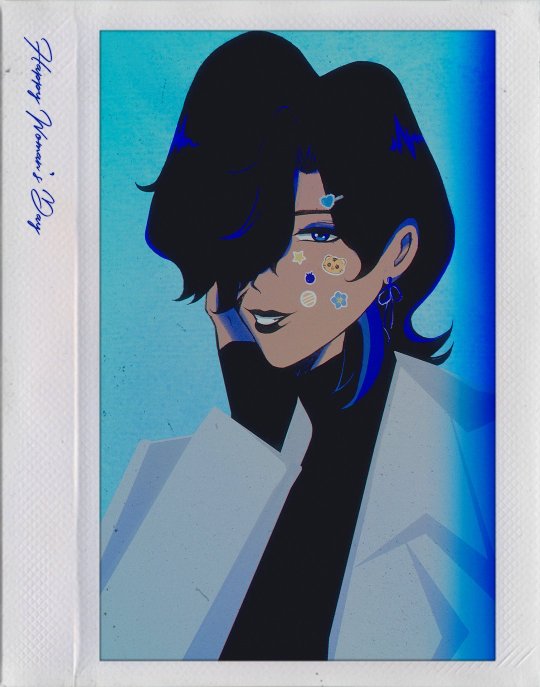
Small log from the past few weeks ♡
#♡#TKRB#Touken Ranbu#Nagasone Kotetsu#長曽祢虎徹#Saniwa OC#審神者#Self insert#Aoyama Toraishi#TouSani#SoneSani#Yume#刀さに#そねさに#夢#My Art#oc x canon#yumeship#審神者の日
7 notes
·
View notes
Text
★2024年読書感想まとめ
2024年に読んでおもしろかった本の感想集です。寝て起きると昨日のすべてを忘れてる……っつう繰り返しで日々一切が過ぎていくので、一年の記録をひとつにまとめとくのもいいかなと。以下ざっくばらんに順不同で。ちなみにNot 新刊、ほんとにただ読んだものの感想です。
◆◆小説◆◆
●アンナ・カヴァン『氷』(山田和子訳・ちくま文庫) 巨大な”氷”の進行によって全世界が滅亡の危機にさらされるなか、男はヒロインたる”少女”をどこまでも追い求める……。もっとゴリッゴリにスタイルに凝った幻想文学かと思って足踏みしてたのですが、こんなに動き動きの小説とは。意外なほど読みやすかったです。唐突に主人公の夢想(?)が挿入される語り口も最初は面食らったけどすぐに慣れたし。内容はウーン、暴力まみれの病みに病んだ恋愛小説という感じ? 構成の一貫性とかは疑問だったりしたんだけどそのへんはどうでもよく。後半尻上がりに面白くなっていくし色々吹っ飛ばす魅力があってかなり好きでした。 それと解説に書いてあった「スリップストリーム文学」というのがすなわち自分の読みたい小説群だなーという嬉しい発見もあり。つってもジャンル横断的な定義だから、該当するものを自分で探すのはムズいけどね。
●スタニスワフ・レム『惑星ソラリス』(沼野充義訳・ハ��カワ文庫) 何年も謎に包まれたままの海洋惑星に降り立った主人公が遭遇する怪現象の正体とは?……っていう超有名なSF。「実はこの海は生き物なんじゃね?」がオチだったらどうしよう……と思ってたけど杞憂、それは出発点に過ぎませんでした。途中に挟まる惑星ソラリスの(仮想)探険史の部分がすごく面白い。あとはこの小説のまとめ方はちょっと神がかってると思う……。自分はSFは全然明るくなく、ちょっと異様な感触みたいなものを求めてたまーに手に取るぐらいなのですが、その点この本はほんとにセンス・オブ・ワンダーを味わわせてくれて良かった……。SFオールタイムベスト1とかになるのもむべなるかなぁと。
●庄司薫『赤頭巾ちゃん気をつけて』(新潮文庫) 東大紛争終息直後の1969年を舞台に、あれこれ思い悩む男子高校生の一日を描いた中編。自意識過剰気味の饒舌な一人称文体が特徴で、すごくユーモラスだけど主人公がかなりナヨナヨした人物にも見える……。でもその中から、外界の強烈な変化に対してありのままで居られない精神の揺れみたいなものが浮かび上がってくるところがおもしろくて、確かに青春小説の名作かも……と思いました。 リアルタイムにはどうだったか知らんけど、今の眼で見るといわゆる”1968年”以降の状況とか、70年代カウンターカルチャー的な空気の”乱暴さ”に対する、一見弱々しいけど切実な返歌って感じもしました。 もっとも読み終えてから、この小説をあえて政治的な色で塗るならいわゆる”保守反動”的な感性に分類されるのかなぁとかはちょっと思ったけど。しかし、リベラルにあらざれば人にあらずみたいな価値観こそ断然間違ってるしなぁなどと、ひとりで勝手に問答したりもしました(笑)。それに現実的にはそんな二分法で単純に分けられるもんでもないだろうし。なんとなく「その時代の作品」という感じなのかと思ってたけど、今読んでも全然おもしろかったです。
●フランツ・カフカ『審判』(池内紀訳・白水uブックス) 理由も分からないまま突然逮捕された主人公が、裁判の被告の立場にずーーーっと留め置かれるっていうお話。何ひとつ確かでないものに延々振り回され続ける理不尽が、ときに笑っちゃうほど面白く、逆に陰惨すぎるくだりもあったりして、総じて非常に好みでした。バカバカしいけどブラックな不条理ユーモア小説? カフカって自分が漠然と抱いてたイメージよりもずっと大胆で、わりとアホなことをあっけらかんと書いたりもするのねーという発見がありました。このお話には裁判的なものの外枠と手続きのみがあって、そこに「法」はないのでは? というふうに読んでたのですが……。終盤の「大聖堂にて」っていう章が凄かったです。
●スコット・フィツジェラルド『グレート・ギャツビー』(野崎孝訳・新潮文庫) ニューヨーク郊外に暮らすギャツビーという名の大富豪の生き方を、たまたま隣に住んだ青年が垣間見る、みたいなお話。ストーリーそのものはわりとベタだと思うんですけど、それを語る会話パートの書き方の巧さと、ドラマの合間の地の文が醸し出すほどよい叙情性がすばらしい。純粋ゆえの虚飾、虚飾ゆえの純粋さみたいな、テーマの核心部分にもちょっと飛躍があって面白いなーと。この短さの中に、アメリカっていう国の一断面をパチリと切り取ってる感じがするのもまた。ひとことで言うと絶品でした。英語圏小説のランキング上位に入ってるのもむべなるかなぁと。
●三島由紀夫『仮面の告白』(新潮文庫) この人の長編はあんま肌に合わないかも……と思って敬遠してたのですが、初めて好きなものに出会えました。言わずと知れた一発目の代表作。同性にしか欲望を抱けない青年の葛藤を、韜晦まみれの絢爛たる文章で綴った青春小説。個人的には、いわゆる”ふつう”でない自分を露悪的に飾り立てるような自己陶酔を振りまきながら、でもそれは”ふつう”でない自分を守るための防御姿勢にすぎなくて、結局は苦々しい現実と向き合わざるを得ない……みたいな話として受け取りました。読み方合ってるのか分からんけど。前半が下地で、後半がその実践編(あるべきとされる自分との葛藤編)なのかな。特に後半のなんとも言えないみずみずしさとその帰結がよかったです。
●横溝正史『獄門島』(角川文庫) 初・横溝。瀬戸内海の小島で巻き起こる猟奇連続殺人事件に金田一耕介が挑む。事件の過程はわりとふつう……と思いながら読んでいきましたが結局かなりおもしろかったです。振り返ると1から10まで本格ミステリじゃなきゃ成立しないような物語だったなと思って。国内ミステリーベスト1になるのもむべなるかなぁと。
●筒井康隆『敵』(新潮文庫) 折り目正しく”余生”を送っている渡辺儀助の生活風景を描いた老境小説。章題が「朝食」「友人」「物置」などとなっていて、各章ではそのカテゴリーごとに儀助の暮らしが掘り下げられていき、その積み重なりから彼の老境が浮かび上がってくる、みたいな趣向。特に食生活に関する記述が多いのですが、自分がほとんど興味ないのもあって前半は正直重く……。しかし地盤が固まり「役者」が揃ってからの中盤以降がけっこう楽しく、終盤は圧巻! けっきょく御大はすごかった……。 的を射てるかは分からないけど、小説の語り口的にもかなりおもしろいことをやってるような。老主人公の生活が章ごとにあらゆる角度から掘り下げられていきますが、そこで語られてるのは「ここ数年の彼の生活のディティール」っていうフワッとした塊としての時間であって、実は小説内では「敵」関連以外ではほぼ全く時間が流れてないように思います。A→B→……→Zみたいに、出来事同士を順番につないでいくことでドラマを進行させていくのとは全然違う手法で物語を語っていて、しかもそれにかなーり成功しているような。もちろん類例はあるんでしょうけど、個人的にはとても新鮮な小説でした。
★★★総合しますと、いわゆる名作と言われてるものって確かによく出来たものが多い……っつうめっちゃくちゃふつうのことを思わされた年でした。というか単純に数を読めてないのよなぁ。
◆◆その他の本◆◆
●『石垣りん詩集』(ハルキ文庫) 石垣りんのテーマは、貧しさ、労働、生活の苦しみ、”女性”性、戦争、戦後の日本、生きること、殺すこと、食べること、それらもろもろに否応なく内在する「ここにあることの残酷さ」みたいなものかなと思いました。そうした感情を、ゴロッとした異物感のある黒いユーモアで表現している詩が自分は好き。婉曲的に表現された切実な慟哭という感じもします。特に「その夜」っていう、入院中の書き手が人生の孤独と疲労を歌う作品が凄かった……。こんなん泣いちゃうよ。 「詩」というジャンルに依然として親しめてないので、定期的に読んでいきたい。
●柳下毅一郎『興行師たちの映画史-エクスプロイテーション・フィルム全史-新装版』(青土社) エクスプロイテーション=「搾取」。リュミエールやメリエスといった黎明期の作り手にとって、映画は緻密に作り込む「作品」ではなく興行のための「見せ物」に過ぎなかった――というところから説き起こして、観客の下世話な関心を狙って作られた早撮り・低予算・儲け第一主義映画の歴史をたどった本です。 取り上げられてるのはエキゾチズム(物珍しい異国の風景)、フェイク・ドキュメンタリー、魔術&奇術、畸形、セックス、特定人種向け映画、画面外ギミック映画などなど。現代の一般的な価値観や、映画=「それ単体で完結した(芸術)作品」みたいに捉えるとどうなのよ? ってものばかりなのですが、あの手この手でお客の関心をかき立て、乏しい小遣いを搾り取ろうとする映像作家たちの商魂たくましい姿が垣間見られる楽し��本でした。 見せ物小屋的映画論というのはある意味もっとも俗悪でいかがわしい映画論だと思うんだけど、確かにそれって実写映画のもっとも本質的な部分ではあるかも、という気がしてしまう……。個人的には、画面外のギミックで客を呼び込んだウィリアム・キャッスルの非・���粋なる邪道映画のパートが特に楽しかったです。一点だけ、エクスプロイテーションという概念設定はちょっと範囲が広すぎるような気はしないでもなかったかなぁ。でもこれを元に、観られるものをちょこちょこ観ていきたい所存。
●氷室冴子『新版 いっぱしの女』(ちくま文庫) 『海がきこえる』などの少女小説で有名な作者が、ふだん思ったことを自由に書き綴ったエッセイ集という感じでしょうか。一見柔らかいけどその実めっちゃ鋭い切り口と、それを表現するしなやか~な筆運びに痺れました。1992年に出た本だけど、新版が出てる通り読み物として全然古びてないと思う。おすすめです。
●『精選女性随筆集 倉橋由美子』(小池真理子選・文春文庫) この方のシニカルさと毒気がもともと好き、というのはあったのですが、とても良かったです。それでも最初のほうはあまりに歯に衣着せぬ攻撃性がなかなか……と思ったりもしたけど、中盤の文学論、特に大江健三郎、坂口安吾、三島由紀夫に触れたエッセイがなんともよくて。”内容はともかく独自の語り口を練り上げた文体作家として大江を読んでる”みたいなことを確か書いてたりして、言ってることが面白い。積んでる小説作品も読も~という気になりました。
●吉田裕『バタイユ 聖なるものから現在へ』(名古屋大学出版会) すんごい時間かかったけどなんとか読めた本。フランスの怪しく魅力的な思想家、ジョルジュ・バタイユの思想を、彼自身の記述を中心に先行テキストや時代背景なども織り交ぜて分析し、一本の流れにまとめた総論本。〈禁止と違反〉とか〈聖なるもの〉とか、彼の提出したテーマが結局面白いというのがひとつと、それらを論じていく手つきの周到さ・丹念さがすごい。特に日記や著書のはしばしの記述から、バタイユが影響を受けた先人の哲学(へーゲル、ニーチェ、マルクスとか)や同時代の思想潮流(シュルレアリスム、コミュニズム、実存主義とか)の痕跡を読み取り、そこから彼自身のテーマの形成過程を立体化していくあたりは本当に息詰まるおもしろさ。重量級の本でしたがめっちゃよかったです。もっとも自分は肝心のバタイユ自身の本を『眼球譚』しか読んでないので、現状この本のイメージしか持ててないというのはあるんだけど。とりあえず『内的体験』と『エロティシズム』だけはどうにか読んでみるつもり。
◆◆マンガ◆◆
●ジョージ秋山『捨てがたき人々』(上下、幻冬舎文庫) いろんな意味で深ーい鬱屈を抱えた狸穴勇介(まみあなーゆうすけ)という青年が、新興宗教の信者である岡辺京子という若い女性と出会ったことで始まる物語。性欲と金銭欲を筆頭に、あらゆる現世の欲望にまみれた救われぬ衆生たちの下世話で深刻な人間絵巻、といった感じでしょうか。ふつうに考えるとまぁそこまではいかんやろ……という境界を軽々と乗り越えてくる常軌を逸した展開がすごい。それと人間っつうのはホントにどうしようもない生き物だね~という気持ちにもさせられます。学生のときに買ったんだけど当時はつまらなくて挫折、自分にとってはあまりに読むのに早すぎたんだな……と今にして思いました。最序盤の伏線とかをきれいに回収し切ってはいないんだけど、この際そのへんはどうでもいいかなと。ここまで徹底的な方向へ流れていくならもう何も言えねえわ……って感じの終盤もすばらしい。 これが2024年に読んだものの中で一番面白かったです。
●小骨トモ『神様お願い』(webアクション)、『それでも天使のままで』(アクションコミックス) 両方とも短編集。子供のころや学生時代のイヤ~~~~~~~な記憶、それもおもに自分の弱さや性欲といった、一番目を向けたくない部分がどんどん脳裏によみがえってくる、えげつないけど得難いマンガでした。10代なんてまだまだ若いし人生これから! っていうのも本当だけど、それと同時に人生自体はとっくの昔に始まってて、けっこう多くのことは取り返しがつかないし人間の根っこの部分は歳食ってもそうそう変わりはしないっていう、しんどすぎるけど(自分にとっては)大切なことを思い出させてくれたところが何ともありがたかった……。お話の展開も総じてすんごいテクニカルな気がします。 それでも新刊の『天使』のほうが、『神様』よりほんのちょっとだけ優しさを感じる部分は多いかしら。
●吉田秋生『カリフォルニア物語』(全4巻、小学館文庫) 自分はおそらく作り手への愛とか感謝の念にはめっぽう乏しいほうで、何でも作品単体で眺めて、あーでもないこーでもない、ワンワンギャンギャン吠え猛ってしまう人間なのですが、吉田秋生だけは例外。何でも好き。丸ごと好き。読めるだけで幸せ。どのへんが琴線に触れてるのか正直自分でも分からないのですが、気になる部分があっても好きがそれを上回ってしまう気持ちというのは幸せだなーと思ったりします。 これは最初の代表作に当たるのかな。ニューヨークを舞台に行き場のない若者たちを描いた群像劇。彼女の描く、イタミやすい少年少女が自分は好き……。舞台はニューヨークなのに題名がこれなのもスマートでイカしてる。 もっともファンみたいに書いたけど、実は『BANANA FISH』と『海街diary』っつう一番大きいふたつをまだ読んでません。買ってはあるんだけどなんかもったいなくて……。でも2025年中には読もうかな。
●高橋しん『最終兵器彼女』(全9巻、ビッグコミックス) 部屋の片隅に長ら~く積んである『セカイ系とは何か』をいよいよ読むべく、『イリヤ』ともども手元に揃えてやっと読了。結果、あらゆる方向に尖りまくった傑作じゃん! と思いました。世界の崩壊に対して主人公2人の恋愛という、圧倒的に超無力なモノを対峙させ、理屈ではなくエモーショナルの奔流として無理矢理! 成立させた名作という感じ。まぁこの2人にほとんど感情移入できないほど自分が歳取っちまってることは悲しみでしたが、いい意味でのぶっ壊れっぷりが面白く。 それと自分はこれを読みながら、たまたま以前読んでいた米澤穂信の某初期長編を思い出したり。世界は刻々と変化しているのに自分たちは無力な青春の中で何もできないでいる、みたいなこの感じって90年代から00年代の日本独自の感覚なんでしょうかね……。ちなみに『イリヤ』はまだ1巻しか倒してませんが読みます。今年中にはきっと読みます。読み切ることになっています。
●梶本レイカ『悪魔を憐れむ歌⑤』 4巻までで連載が打ち切りになってしまったマンガを、作者ご自身が5巻を自費出版して完結させた作品、だと思います。 舞台はさまざまな腐敗に揺れる北海道警察管区。人間の四肢を逆向きに曲げて殺害する、「箱折犯」と呼ばれる過去の猟奇殺人が突如再開され、そこからふたりの男のウロボロスめいた運命の輪がまわり始める……。 出版形態のためかは分からないですけど、最終5巻はこれまで以上に描写のタガが外れてる感じで、それがすごい楽しかったです。1巻の出だしからはこんなとこまでフッ飛んでくる話だとは思わなかった……。それでいて猟奇殺人ミステリーとしてもなるほどーと思うところもあって。この方はすごい前に『コオリオニ』っていうマンガも読んだのですが、主要キャラクターをとつぜん突っ放す感じがこわい。けど面白い。お疲れさまでした。
◆◆補足◆◆
・安部公房もちょろちょろ読んだり。今のところは、異常どころかめっちゃ理知的なアイデア作家という印象なんだけどこれが覆ることがあるやいなや。 ・『めくらやなぎと眠る女』というアニメ映画の予習をするついでに村上春樹の短編もちょこっと。ファンには超怒られそうですが、彼の小説ってパスタ茹でたりジャズを聴いたり昔の恋愛とか人間関係の失敗を感傷的に懐かしんだりといった、ザ・村上春樹なことをやってるときは…………なんだけど、その先で訳分からんことになる話がたまにあってそれがめっちゃ面白かったです。現状読んだものだと「ねじまき���と火曜日の女たち」、「UFOが釧路に降りる」、「納屋を焼く」が最高でした。できれば全作読んでみたい。 ・フランク・ハーバートの『デューン』シリーズも2個目まで。SFファンタジーの大家というイメージで読んだらメインで使う語り口(作劇法?)が超・会話劇なのが意外でした。
★★★これを書いている2025年1月現在はドスト先生の『悪霊』を読んでいます。が、全体の十分の一すぎてもまだ若者世代の話に入らないので投げ出しそう……。シニカル成分100%の語り口はけっこう好みなのですが。前に読んだ『罪と罰』と比べても視点が格段にいじわるな気がして、これを書いてたときの作者の精神状態やいかに? 2025年はもうちょい数をこなせたらいいなと思っています。ではー。
4 notes
·
View notes
Text
「宮崎正弘の国際情勢解題」
令和七年(2025年)6月12日(木曜日)
通巻第8820号 <前日発行>
ツアーとはラテン語のカエサル=「善き大王」
神の御稜威がロシアの皇帝であり、神の代理人というのがプーチンの認識
*************************
前号にひきつづき、なぜイーロン・マスクの父親がモスクワに現れたか?
モスクワで開催された「未来フォーラム」に出席するためだった。このフォーラムでは、「21世紀の多極化世界」、「コンテンツを通じたベータ世代への価値観の発信」、「調和のとれたバランス2050」、「グレーターユーラシア2050」、「イデオロギーと伝統��価値観」などを主要なテーマとした分科会が開かれ、主催は「ツァルグラード研究所」である。
発言者にはラブロフ外務大臣、世を騒がせる「陰謀論者」のアレックス・ジョーンズ、アメリカの経済学者ジェフリー・サックス、イギリスの政治家ジョージ・ギャロウェイ、そしてイーロン・マスクの父エロール・マスクなどだった。保守論客、モスクワに勢揃いの観なきにしもあらず。
プーチン大統領を称賛するエロール・マスクは、以下の発言をした。
「モスクワは私にとってローマのような、最も美しい街です。ロシアは欧州共同体の一員になろうとしているにもかかわらず、敵のように描かれていることに非常に驚いています。ロシアはヨーロッパを二度も救ったのです。ナポレオンとヒトラーから。どうしてロシアを否定的に描き続けることができるのでしょうか?」
ツァルグラード研究所は、かのアレクサンダー・ドゥーギンが所長。政治思想とロシア正教の思想を融合させた保守的な政策提言を行うシンクタンクである。
このツァルグラード研究所の思想的基盤とは「ロシアは神から精神的、歴史的使命を託された独特の文明。国家という概念は、時間が経つにつれて国家が自らをどう考えるかではなく、永遠にわたって神が国家をどう考えるかによって決まる」としている。
このイデオロギーにプーチンが共鳴するのである。
プーチンは儀式に必ずロシア正教会大司教をともなう。それは「ロシア皇帝の権威は神の御稜威による」という伝統的信仰であり、その価値観は西側の合理主義が受け入れるところではない。
ツアーとはラテン語のカエサル=「善き大王」を意味しており、神の御稜威がロシアの皇帝であり、神の代理人というのがプーチンの認識である。
このようなイデオロギーを鼓吹するのが「現代ロシアのラスプーチン」と言われるドゥーキンである。彼はウクライナ特殊部隊の暗殺対象であり、実際に愛娘が暗殺されている。
彼は言う。「ロシアが成功するためには独裁国家でなければならない。イヴァン雷帝、ピョートル大帝、ヨシフ・スターリンをはじめとするロシアとソ連の指導者の統治をみよ」
ドゥーギンは躊躇なく続ける。
「ロシアは人為的に作られた『ウクライナ国家』」を解体し、その歴史的記憶をロシア文明の不可欠な一部として回復しなければならない。ロシアの女性は、子どもを産み育てることこそが人生の主な目的であり、その最大の貢献であると認識すべきだ」。
▲「現代ロシアのラスプーチン」と言われるドゥーキンが主催
ドゥーギンの世界分析はこうだ。
「かつての東西冷戦は、旧来の世界の枠組みを電撃的に解体した。現在の“トランプ劇場2.0”とは革命を超えた革命だ。腐敗したシステムの残骸を食い尽くし、古き良きもの、力強いもの、純粋さゆえに恐ろしいものを再構築することを約束する”最後の審判“だ。トランプ主義は、長らく周縁化されてきた旧保守主義者の国家ポピュリスト的政策と、シリコンバレーにおける予想外の変化(影響力のあるハイテク界の大物たちが保守政治に同調し始めた)を組み合わせた、特異な現象として浮上した。多極化した世界の地政学における最後の和音となり、リベラル
グローバリストのイデオロギー全体を覆す」
独善的な世界観だが、ロシアがトランプの呼びかけによる停戦に応じないのは、こうした強いイデオロギーが露西亜社会を蔽っているからだろう。
ドゥーギンは続けた。「トランプ大統領は過去80年間を象徴するあらゆる国際機関──国連、WHOやUSAIDといったグローバリスト機構、そしてNATO──の解体に乗り出している。トランプ氏はアメリカ合衆国を新たな帝国と見なし、自らを衰退する共和国を正式に終焉させた現代のアウグストゥスと見なしている。彼の野望はアメリカ本土にとどまらず、グリーンランド、カナダ、パナマ運河、さらにはメキシコの獲得にも関心を示している」
就中、ドゥーギンが評価するのはUSAIDの解体である。
「米国国際開発庁(USAID)の解体は重要な出来事であって、ソ連がコミンテルンを廃止したこと(ソ連のイデオロギー的利益を世界規模で擁護する組織を廃止した)が国際的なソビエト体制の終焉の始まりを告げたように。USAIDはグローバリストのプロジェクト実施のための主要な運営組織だった。自由民主主義、市場経済、そして人権を世界中に押し付けることを目指すイデオロギーとしてのグローバリズムの主要な伝道ベルトだった。このUSAIDの縮小措置の重要性は、たとえばウクライナがUSAIDに大きく依存してきたようにウクライナのすべてのメディア、
NGO、そしてイデオロギー組織はUSAIDから資金提供を受けていた」。
アメリカのプロパガンダ機関の解体はコミンテルンの解体を意味するとまでドゥーギンは評価するのである。すなわち「トランプは善悪の概念に現実性があるとは考えていない。利点と欠点だけを信じている。その事例がイスラエルへの過剰は梃子入れに象徴されている」。
たまにロシアの訴えに耳を傾けると、西側の常識とはほど遠い議論をしていることが分かる。
6 notes
·
View notes
Text
ひとこと日記📓 2024.09
9.1-引越し。荷物でいっぱいになった車で元彼を駅で拾って新居へ。運び終わってから、お互いの気持ちの話をした。今日が最後、今日が最後を繰り返してまた一緒になりたい。
9.2- 1人で部屋の片付けをする。大方片付いたら、もう何ヶ月もここに住んでいるような感覚になった。いい仕事にすぐ就けそうにないので、またその場凌ぎで派遣を始めようか悩む。web面談をしたら、自分の顔があまりにも暗くて今日にも自殺しそうなやつに見えて悲しかった。
9.3- 何もしたくない。さみしい。
9.4- 「YOU 君がすべて」S3を観ている。ラブが抱える悩みが自分と被る。ジョーが元彼と少し似ているから余計に… / まだ部屋に冷蔵庫がない。冷蔵庫を持たない暮らしについて考えてみる。わたしはよく食材を腐らせて捨てていたから、ないほうがいいけど難しいね。
9.5- 事務の派遣が決まりそう。時給制だけど、貯金も少しできるくらいは稼げるから、1日でも早く働き始めたいけど… 本当は在宅でデザインの仕事がしたい。応募はしてるけど、すぐに決まるかわからないから、派遣の仕事を始めるべきか、でも長期雇用予定の求人だから中途半端に働き始めたら担当にも企業にも迷惑だよな/ 元彼からの質問に長文で答えたら既読無視されててつらいけど信じて待つ。→待てない。
9.6- やっと新居にwifiが通った。3時間かけての大掛かりな工事だった。みんなそれぞれ、自分にできる仕事をして世の中が回っている。
9.7- 23時過ぎ、元彼からメッセージ。今夜君の家に泊まっていいか?と。わたしのアパートの近くの駅でのんでたらしい。バーに合流して遅くまで彼の友人たち(外国人の旦那と日本人の妻2組)と過ごした。彼は酔っていたけど、わたしの魅力を友人たちに熱弁し始めたり激しめのスキンシップをとってきたり、やっぱりまだわたしのこと大好きなんだなってわかって安心した。
9.8- 午前3時に帰宅してシャワーでセックス。急遽、彼のバンドメンバーと一緒に川に行くことになった。
起床。まだ魔法は解けてなかった。けど、バンドメンバーのひとりがわたしと一緒に川に来るのはおかしいってメッセージで言い始めてからおかしくなった。人が変わったように、やっぱり一緒になるべきじゃないと言って川に行ってしまった。精神病かな? そのバンドメンバーまじで国に帰ってクレメンス
9.9- 電話したらもう会うべきじゃないって言われちゃった。じゃあなんで土曜日泊まりにきたのかな?しにた。でも戻ってきてくれるって信じてる。
9.10- 初回のカウンセリング。大事なことちゃんと伝えられたと思う。次回からは心理士を目指す大学院生が担当することになる。どんな先生が担当になるか少し緊張する。
9.11- ちょっと鬱目。いい感じのイタリア人とマッチするも多分詐欺垢っぽい。代わりなんていないのに何してるんだろう。
9.12- 昨日は9.11だったことに気づく。最近Deep stateに興味があり、陰謀論の動画を見たりしている。世の中は一部の人間に操られているのかな。もしそうであったとしても、わたしの人生に直接的には関係のないことだけど。
9.13- 出鱈目な生活を送っている。自己肯定感も上げればいいってものではなくて、変な上げ方をすると拗れる。
9.14-9.15 ここ数日、夢の感覚がリアル過ぎる。地面師を観ていたら、朝になっていた。そしてようやく眠って目が覚めたら夕方になっていた。元彼から、わたしが1番好きなポケモンをリモートで送ろうか?とメッセージが来たが、「会えないのなら今は要りません、ありがとう。」と答えた。どんなつもりでメッセージを送ってきてるんだろう。頭の中を解剖してやりたい。
9.16- ボーリング同好会の集まりに参加。今まで70前後だったのに、いろんなアドバイスのおかげで100超えた。久しぶりの達成感。グループチャットから個人でLINE追加してくる男たちがだるい。なんでわからないんだろう…?
9.17- 今日から新しい仕事が始まった。午後からずっと頭が痛い。逃げて逃げて逃げ続けてきたツケが回ってきたとつくづく思う。もう諦めて死んだほうが楽だと思う。思うだけ。/ 昨日、ペットの誕生日だったのにうっかり忘れていた。最低。わたしはつくづく冷たい人間だ。
9.18- 仕事2日目
9.19- 仕事終わりにアプリの人と会う。あんまり会いたくなかったけど、スタバを奢ってあげるし30分だけでもいいからお願いと言われて会った。結局3時間くらい一緒にいた。寝てない。
9.20- 金曜日。つかれた。しばらくメッセージしてる外国人と電話したけど、違った。
9.21- 夕方までだらだら過ごす。暗くなってからオーダーしたシャツを取りに行く。かわいい、わたしが着たら絶対にかわいいと思った。/「この世界で生きていくために、手を組みませんか」というプロポーズ
9.22-トークサバイバーを観る。笑���と楽しいね。今日何したか覚えてない。3連休じゃなかったら死んでた。/就寝前に元彼から電話。
9.23- am2 元彼の家に到着。引っ越してからさらに遠くなり1時間近くかかるようになってしまった。朝まで眠れず。2人の関係を成就させるために、わたしが変わる。/ ヘアカットに行く。私史上1番気持ちよいシャンプーだった。
9.24- 元彼から風邪をもらった。体がとてもだるいけど、この仕事は身体に負荷がかからないし、人と話すことも少ないからなんとかなる。次のデートはコスモス畑。わたしと彼が2年前の秋に初めてデートした場所。
9.25- 以前、大学附属の心理センターで初回のカウンセリングを受けたのだが、審議の結果、わたしの症例は当センターでは対応継続できないとのことだった。そんなことあるんだね、いっぱい自分のこと話したのに無駄になった。/ 仕事おわりにweb制作会社の面接へ。すぐに転職したいわけじゃないけど、選択肢をつくっておきたくて。今の仕事のお給料に特段不満はないけど、派遣から正社員になったらいくらもらえるのか早めに確認しなきゃな。
9.26- 手術なしで視力を回復できるオルソケラトロジーというものを知る。15万ほどするが、レーシックやICLに比べて低リスクで安いから、生活が安定したらやりたい。/仕事おわりに、からやまのテイクアウト。期間限定のマグロ天定食を注文。働いて好きなもの食べて好きなだけゆっくりお風呂に浸かって眠くなったら静かに寝る。ほどほどに自由。
9.27-あたらしい仕事で2週間が経った。今朝、職場のグループで村八分に遭い、役職者からクビを言い渡される夢を見て、目覚めたらいつも家を出る時間の5分前だった。夢でよかった、今仕事がなくなったら働く気力が尽きてしまう。/ 最近、日本の映画をよく観ている。日本人にしか出せないものってある。もちろん、アメリカ人にしか出せないものも、インド人にしか出せないものもある。人種についてもっと深く考えたいけど、知見がないから難しい。/ 新しい総理が誕生した。お誕生日おめでとう。
9.28- マックポテトの品質に一喜一憂するのやめたいから買うのをやめるべき。/ 弟とヤドカリを買いに行く。198円の命。/ 新居に観葉植物を迎えた。
9.29- 容姿が醜い人といっしょに出かけると、自分の価値が下がったように思える感覚ってふつうじゃないのかな。
9.30- 今日から英単語1日10個覚える。一年で3650個。/ 9月終わった。じめじめ生きてる感じがしてダサい月だった。
完
10 notes
·
View notes
Text
ニーチェ的「末人(おしまいの人間)」の特徴と、現代的類似形態の詳細
1. 適応過剰性と主体性の喪失
権威(国家、企業、上司など)に従順で、自発性に乏しい。
社会制度や通念に対して疑問を持たず、内面化して生きる。
安全・安定を最優先にし、挑戦や創造には消極的。
自己決定を恐れ、他者の評価やルールに依存。
2. 上下関係の内面化
上には媚び、下には高圧的になる傾向(権威主義的性格、アドルノらが論じた)。
上下関係を自然なものとみなし、抑圧を再生産。
弱者に対して連帯せず、むしろ攻撃する(スケープゴートを求める)。
3. 形骸化した美意識
形式や規範に固執し、本質を見失う。
個性や創造性よりも、既存の「正しさ」「整い」に価値を置く。
「美」はファッションやマナー、インテリアなどの型に還元されがち。
4. 表面的なポリコレ(政治的正しさ)の遵守
内発的な倫理観ではなく、外的規範に合わせるためのポリコレ実践。
その遵守自体が自己肯定感や優越感の源となる(道徳的ナルシシズム)。
他者にもその規範を強制し、逸脱者を排除する傾向。
5. 希望の喪失と抑圧的自己認識
世界を変える可能性や自己変容の可能性を信じない。
自虐的・自己卑下的な語りをするが、そこに妙な誇りがある。
抑圧された自我を正当化する言説(「これが現実」「大人になるってそういうこと」)を反復。
6. 不自由なプライドと支配欲
無内容な「正しさ」や「常識」を盾にプライドを保つ。
自身の狭い経験や価値観を普遍化し、他者に押し付ける。
教訓・説教・忠告の形式で他人を支配しようとする。
7. 快楽の均質化と怠惰な幸福
「心地よさ」「無難さ」「便利さ」が幸福の基準。
不快や混乱、対話や変化を避ける。
消費社会的な快楽(娯楽、買い物、SNS)に閉じこもる。
8. 過剰な自己保存本能
生命や社会的立場の維持が最優先で、「生の昂揚」は軽視される。
ニーチェがいう「生の意志(Wille zum Leben)」に従っているが、「力への意志(Wille zur Macht)」を欠く。
9. 規範の内面化による監視社会的性格
自分の内に「監視者」を住まわせて、自己検閲・自己管理を行う。
他者の逸脱に敏感で、それを咎めることで自我を保つ。
「世間的正しさ」を無自覚に武器化する。
10. 意味の貧困と深みの喪失
深い問いや形而上学的関心を「非生産的」として切り捨てる。
宗教・哲学・芸術が、単なる趣味や装飾に矮小化される。
内的対話が失われ、自己の深みに潜る能力が減退する。
近代批判の系譜との関連
フロムの「自由からの逃走」:自由を恐れ、権威に服従する性格傾向。
マルクーゼの「一元的思考」:技術的合理性が全てを覆い尽くし、対抗的想像力を失う。
アドルノの「権威主義的パーソナリティ」:ナチズムを可能にした心理的傾向として分析。
ライヒの「性の抑圧とファシズム」:リビドーの抑圧が支配構造に適応的性格を生む。
現代の「末人」的傾向を加速する社会的要因
SNSによる承認欲求の制度化(「いいね」による快楽回路)
教育における標準化と評価主義(偏差値、就職偏重)
経済的不安定さと過剰労働(自発性・余白の欠如)
文化の商業化と表層化(深層的意味への関心の喪失)
規範の過剰供給と自己責任論の蔓延
このような人間像は、ニーチェが超人(Übermensch)という概念で対比的に語るように、**「生の肯定」「創造的価値の創出」「自己変容」**という方向性とは真逆の位置にあります。
必要であれば、こうした「末人」状態からの脱出のヒント(例:生成変化、アセンブリックな生のあり方、東洋思想との接続など)についても整理できます。ご希望があればお知らせください。
4o
You said:
ニーチェの「末人」と同様の分析を行った思想家・学者など、できるだけ多数教えてください。
ChatGPT said:
ニーチェの「末人(der letzte Mensch)」という概念に類する人間像の分析や批判を行った思想家・学者は、20世紀以降の哲学、社会思想、精神分析、文化批評において多数存在します。以下に代表的な人物をジャンルごとに整理し、簡単な解説を添えてリスト化します。
◆ ニーチェの「末人」的主題を引き継ぐ思想家・学者リスト
1. 実存主義・ニヒリズム批判の系譜
思想家 主な概念・著作 関連する「末人」的分析
マルティン・ハイデガー『存在と時間』「ダス・マン(世人)」=平均化された匿名的存在としての人間像。自己を生きる代わりに他者の視線や世間に流される。
ジャン=ポール・サルトル『嘔吐』『存在と無』「実存は本質に先立つ」:自由から逃れ、役割や肩書きに安住する人間への批判。
アルベール・カミュ『異邦人』『シーシュポスの神話』不条理を直視せず、習慣の中に逃げる人間の姿(=末人的)を描く。
2. フランクフルト学派・社会心理の批判
思想家 主な概念・著作 関連する「末人」的分析
テオドール・アドルノ『権威主義的パーソナリティ』『否定弁証法』権威に従順で他者に攻撃的な性格構造=ファシズムを支える「末人的」性格。
マックス・ホルクハイマー『道具的理性の批判』理性が自己保存と効率だけを目的とするようになった現代人=末人。
エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』『生きるということ』自由に耐えきれず権威に逃げ込む「逃走する人間」=末人の心理。
ハーバート・マルクーゼ『一次元的人間』消費社会が人間の欲望や想像力を均質化し、批判精神を失わせる。
3. ポスト構造主義・現代思想系
思想家 主な概念・著作 関連する「末人」的分析
ギー・ドゥボール『スペクタクルの社会』実体なき「イメージの支配」に取り込まれる人間像=自己喪失型の末人。
ジャン・ボードリヤール『消費社会の神話と構造』『シミュラークルとシミュレーション』現実よりもコピー(シミュラークル)を消費する人間=意味喪失の末人。
ジル・ドゥルーズ & フェリックス・ガタリ『アンチ・オイディプス』など欲望をコード化され、定型的な役割を演じる主体=脱創造的「末人」。
スラヴォイ・ジジェクポストマルクス主義・ラカン理論消費社会における「空虚な欲望」と「享楽の命令」に従う主体=「末人」的存在。
4. 宗教・倫理・東洋思想との関連
思想家 主な概念・著作 関連する「末人」的分析
シモーヌ・ヴェイユ『重力と恩寵』形式的信仰や制度に埋没し、本質的な魂の渇望を見失った人間への批判。
梅原猛『仏教大学講義』など経済的合理性や制度に埋没する現代人=仏教的な意味での「迷い」の極致。
中村雄二郎『術語集』『共通感覚論』技術的合理性に染まる現代人が、感性・共感を失う危険性を示唆。
5. 精神分析・文化批判・社会理論系
思想家 主な概念・著作 関連する「末人」的分析
ヴィルヘルム・ライヒ『ファシズムの心理構造』性の抑圧が支配体制に順応する性格を生み出す=「末人」的心理の構造分析。
アーサー・ケストラー『機械の中の幽霊』科学文明の発達と人間性の崩壊の乖離を批判。
ノーム・チョムスキー『メディア・コントロール』マスメディアによる認識の管理に無自覚な現代人=末人型の大衆。
6. 日本の思想家・文化批評家
思想家 主な概念・著作 関連する「末人」的分析
柄谷行人『マルクスその可能性の中心』『探求』資本制の内部に無自覚に同一化する主体の批判。
宮台真司『14歳からの社会学』など「終末的社会」の中で思考停止する大衆=末人化した現代人の診断。
中沢新一『野生の科学』『芸術人類学』近代的合理主義に押しつぶされた、野生的感性や創造性の喪失=末人的。
栗本慎一郎『意味と生命』『パンツをはいたサル』「意味への感受性」の衰退を嘆く。脳の変容と社会構造との関係を指摘。
補足:文学・芸術における「末人」的表現者
フョードル・ドストエフスキー(『地下室の手記』の主人公)
カフカ(『変身』『審判』などの不条理で抑圧的な主人公像)
三島由紀夫(『豊饒の海』など、戦後日本人の精神的空洞化への批判)
村上春樹(空虚で自閉的な語り手たち)
必要であれば、特定の思想家の議論を掘り下げたり、比較表にしたり、また「末人」から脱却する思想や実践(生成変化・スピノザ・仏教思想など)との接続も可能です。お知らせください。
3 notes
·
View notes
Quote
最近、外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替える「外免切替」をおこなった外国人の運転による重大事故が相次いでいます。 5月14日には埼玉県三郷市で中国籍の男が小学生4人をはねたひき逃げ事件、5月18日には三重県亀山市の新名神高速道路においてペルー国籍の男が逆走した当て逃げ事件が発生しており、どちらの運転手も外免切替によって日本の運転免許証を取得していたことが明らかになっています。 そもそも、外国人が日本でクルマを運転する際には次のいずれかの運転免許証を所持しなければなりません。 ーーー 1 日本の運転免許証 2 ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証 アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダなどが対象 3 日本と同等レベルの免許制度を有している国または地域の免許証(大使館や領事館などが作成した日本語の翻訳文が添付されているものに限る) スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、台湾などが対象 ーーー ただし、国際運転免許証で運転できる期間は原則として日本に上陸した日から1年間であり、それを越え���と国際運転免許証では運転ができません。 また上記2や3に該当しない国や地域の免許証を持っている外国人が日本でクルマを運転する場合は、日本の運転免許証を取得する必要があります。 そのような事情から外免切替をおこなう外国人は年々増加傾向にあり、2024年中は7万5905人が日本の免許を取得したほか、外免切替者数はこの10年で約2.5倍にのぼっています。 まず外国人が外免切替の手続きをするに当たっては「期限の切れていない有効な外国免許証を所持していること」、「外国免許証の取得後、その国に3か月以上滞在していること」、「申請しようとする都道府県に住所地があること」といった条件を満たす必要があります。 また手続きは基本的に書類審査→適性試験→知識確認→技能確認という流れで実施され、日本の交通ルールを問う知識確認に合格すると技能確認の試験に進めます。 そして運転技能をチェックする技能確認に合格すれば、日本の運転免許証を取得できます。 しかし、上記の知識確認に関しては交通ルールに関する問題が「○×方式」でわずか10問しか出題されない上、7問以上正解で合格という非常に簡単な内容となっています。 加えて試験が日本語以外の20数か国の言語で受験できることもあり、「日本語で受験しないと意味がない」、「日本人の免許取得は厳しいのに、なぜ外国人に甘いのか」など批判の声が多く寄せられています。 さらに中国人の間では「外免切替ツアー」と呼ばれる日本旅行がおこなわれており、一時滞在先のホテルを住所地として日本の運転免許証を取得する事例も起きています。 外免切替の際には住所を証明するための「住民票の写し」や「旅券」などの書類を提出しなければなりません。 しかし、実はホテルや旅館などの責任者が住所の「証明人」となることで、観光などの短期滞在の外国人であっても手続きができてしまう驚きの実態があるのです。 ホテルや旅館を住所地として認めることに対しては「外国人による交通違反や重大事故が発生した際、反則金の納付や交通事故の捜査に支障が出るのでは」と懸念の声も上がっていました。 このような外免切替の問題に対し警察庁の楠長官は、5月22日の定例記者会見において「住所を確認するための書類は、申請者の国籍にかかわらず住民票の写しを原則とし、観光で滞在する人の外免切替を認めないこととする」と話しています。 また、知識確認や技能確認の方法を厳格化することについても検討すると明らかにしました。警察庁は今後外免切替の改正案などを取りまとめ、パブリックコメントを実施するなどの必要な手続きを進める方針です。 ※ ※ ※ 外国人優遇とも批判される外免切替制度について、ようやく改正に向けた動きがみられています。 外免切替者による重大事故が相次ぐ中でどの程度制度が厳格化されるのか、その動向が注目されています。
外国人に甘すぎ!? 交通ルールを問う試験はわずか10問&ホテルを住所に日本の免許取得も… 観光滞在者「外免切替」認めない方針、警察庁長官が表明 | くるまのニュース
3 notes
·
View notes
