#忘れぬうちに文章化したかった
Explore tagged Tumblr posts
Text
置き手紙〜何やら懐かしい写真を添えて〜

大事に綴ってたもの、消してもうたから。代わりと言っちゃ何やけど。別にさ、俺に何かすごいことやええことが出来るわけじゃないけど、ただ伝えたくなったから、敢えてここにまた置いとこうと思って。通知が行かへん、好きなタイミングで読める場所。そしてこれは文通じゃなくて、置き手紙やから。一方的に。見つけんくても、大丈夫なもの。
何となく思い立って、健ちゃんの好きなところを、自分の中で振り返ってみてん。そしたら、元来健ちゃんが持ってるものもそうやけど、正門が一緒に居る時に健ちゃんが見せてくれるものがいくつか出てきてね。「まっさん」って呼ぶ声、俺を真っ直ぐじっと見つめて微笑む瞳。俺に向けてくれる言葉すべて。「まっさんおはよう」と「おやすみまっさん」。そういうもの。ああそうか、一緒に積み重ねてきた時間、健ちゃんの隣にはこんなにも正門が居たんや、って。当たり前すぎて何言うてんの?って感じやん。自分でも思うけど、笑ってまうくらいやけど、それだけの月日、健ちゃんの時間を貰って過ごしてきたことに「ありがとう」と改めて言いたくなった。
俺は身を引くことばっか得意やし、自分が幸せになること考えるん下手な��やけど。それは多分変えられへんことなんやと思うねんけど。いや分かってんなら直せよって話よな。そんな俺に、たくさんの時間を、月日を、愛情を、手渡してくれてきたんやなあ。って、改めて実感してん。言葉が全てじゃない。だからちゃんと、見失わずに貴方の心を見ていたい。受け取ってたいな。
これから先、色んなことがあると思う。ずっとずっとニコニコ笑顔で過ごせるわけでもないと思う。傷付いたり腹立ったり、泣いたり怒ったり、そんな時って絶対にあるやん。でも俺は、そのひとつひとつから目を背けたくないねん。逃げずに、ひとつひとつ、大事に感じ取って、まるごと全部愛してたい。大切な、貴方の一部やもん、愛させてほしい。俺はそう思ってるよ。いつだって100%好きで居れんくてもいい。ため息吐きたくなってもいい。優しく出来ん時があってもいい。俺は、俺らは、決して完璧なんかじゃないから。ただ、隣に居てほしい。どんな日も。どんな時も。俺には、貴方だから。貴方の全部、愛させて。
0 notes
Text
恥感情&後悔まる出しクソネガティブTumblrを書かせてくれ。いまとても心臓がぞわぞわしている。
基本的にわたしという存在は喋りすぎることを恐れている。そして喋りすぎても許されるのはTumblrだけだと思っているのでここで感情を消化させてくれ。ここは何文字書いたって一投稿だしね。それにみんな、わたしのネガティブTumblrをエンタメとして扱ってくれるじゃん。ありがとねほんとに。こんなので良ければずっと書き続けます。
これはもう定期的に訪れる発作としか言いようがないのだが、またもや最近、表の世界ことTwitterで喋りすぎている気がしてならない。ポスト自体は週に1~2回までに留めようとしているし実際にそこまでポストを頻繁にするタイプじゃないと自分では思っているのだけれど、最近Twitterにおける鎖国の意識が緩まっており、リプだのスペースのコメントだのをよく打っている。べつにそれ自体に問題があるわけじゃないのだろうけど、なんだか自分が悪目立ちしているんじゃないかっていうクソ意味のわからん恥感情に苛まれてふつうに泣きたくなっている。リプとかコメントの相手に対して何か思ってるってわけじゃないんですよ? わたしが勝手に感じている謎の恥感情なの。誰も悪くな��んですよ。シクシクエーン。
自分がキモすぎて笑ってしまう。誰かに忘れられることが恐ろしいと思って文章を書くことを趣味としているくせに、悪目立ちはしたくないんですよ。しずかに黙々と書いている人だと思われたい。アーーーキモすぎる。助けてくれ。
小学生向けの対人関係スキルを基本のき、みたいな書籍を買ってみようと本気で思っている。わたしは最近引きこもりすぎて人間との話し方を忘れている。「社会人になってから人見知りを主張するひとってあまり良くないよね」という話をここ数か月で何人もの人が言っているのを目にしたり耳にしたりしていて、それを聞くたびに、それはそうだなと同意すると同時に、心臓をぐさりと一突きされているような気分になる。いや、わたしは自分のことを人見知りと形容したことは人生で一度もないのだけれど、どちらかと言えば人間と上手に話せない側の人間なのですごく刺さる。わたしはまだ学生ですが同級生はみんな働いているので、社会人じゃないから~という言い訳が通用するわけがないのも、自分ではわかっているんですよ。
わたしは学歴がある側の人間なので言わせてもらいますが、人生においては対人スキルの方が学歴なんかよりもよっぽど大事です。もちろん学歴と対人スキルの両方が備わったエグい人もいるんですが、どちらかしか選べないなら対人スキルがある方が生きやすいと思う。精神的に健康だ。
大学院にいると価値観が歪むんですよ。人間とうまく喋れない、メールも返せない、だけど研究はめちゃくちゃできる、みたいな化け物がたくさんいるのでそれに染まってしまいそうになる。わたしは対人スキルが中の下、研究スキルは中の中、変人度は中の上のクソキモ一般人なのでどちらにも振れない。研究できることがアイデンティティの化け物にもなれないし、対人スキルの高い器用な人間にもなれない。はい、中途半端な大学院生の完成です。研究室で酒を飲んでわいわいする集団に対してキモ死ねって思うくせに、別に学振は取れないしやる気なさ過ぎて英語論文もまだ書き終えていない。なんなんだよ、キモいのはどう考えてもわたしだ。
もちろん、対人スキルが高い人には高い人なりの悩みがあるのは百も承知だけど、結局人間ってないものねだりなんだよな。こんなに中途半端なわたしだって、きっと誰かに羨ましがられてる。
今日は人間関係をテーマに書いているので、このまま中学時代のエグイ部活の話をしようかと思う。
中学生のとき、女子○○部、みたいな感じの運動部に所属していた。上下関係がとても厳しい部活だった。そして不運なことに、わたしは真っ先に先輩に目を付けられた。中1の初夏、生理痛が酷くて部��を休んだとき���、「生理痛くらいで部活休むなよ」と先輩に陰口を叩かれたことが発端だったように思う。一番の敵は理解のない女だ。そこからは事あるごとにいちいち欠点を指摘されては先輩の悪口のサンドバックになった。個人指導、という謎の制度(つまり何かと理由をつけて気に入らない後輩を延々と叱り続けるという集団リンチ)の常連被害者だった。結構な頻度で先輩数人に取り囲まれて、人格否定を繰り返された。謝っても、「はあ、もうそれ聞き飽きたわ~。結局行動で示してもらわないとどうにもならないんだよね~」とか言われんの。だけど当時、わたしは自分がなぜ怒られているかあまりよく理解していなかった。だからとりあえず、すみませんでしたって謝るんだけど、それも上記のように意味ないから八方塞がり。あ~どうしよっかな~でもこのまま怒られてたら筋トレしなくて済むのかな〜ならそれでいっか~あ〜面倒くせ~死ね死ね死ねって考えていた気がする。そしてまあ、もちろんちゃんと病んだりもしたが、やはりわたくし、生命力がとても強いのでふつうに学校に通っていた。はいはい死ね死ね、って感じで部活も行っていた。えらすぎ。
中学のときに生徒会に入ったのは活動にかこつけて部活を堂々とサボれるからであった。副会長の先輩(もちろん男)はよく部活の愚痴を聞いてくれた。あとは、保健室でサッカー部の先輩(イケメン)に慰めてもらったりもした。同級生のRくん(本命)にも夜な夜なLINEで話を聞いてもらったりした。今思えば、わたしが部活内で嫌われていたのは、部活で酷い目に遭っていることを男子に相談して、か弱い女子を演じて味方を増やそうとするところに原因があったのかもしれない。まあ、それはいいんですよ。とりあえず、部活の先輩にはとことん嫌われ、個人指導という名の集団精神リンチをされながらも部活は辞めずにぬるく生きていた。中総体の前には「いつも厳しくしちゃってごめんね;;」と書かれた手紙を集団リンチのリーダー格の先輩からもらった。やっぱ死ねよ、と思っているうちに先輩は順当に地区予選で敗退し、すぐに自分たちの代になった。
本題はここから。まだ地獄は続く。
代がわりをして、部長はNちゃん、副部長はAちゃん、わたしは野良の部員になった。野良の部員はわたしのほかに5人いた。
ある日部長Nがエグイことを言いだした。「準備を一番頑張っている後輩と、一番サボっている後輩を先輩(つまりわたしたち)の投票で決めて、みんなの前で発表しよう。そうしたら後輩たち、みんな頑張ってくれるはず」と。もうお気づきだろう。地獄である。
部長絶対王政の部活だったので、それがまかり通って、実際にその投票制度は数か月にわたって続いた。みんなの前で部長が特定の後輩一人を指して、「○○ちゃんはこの前の準備で部活に関係ない話をしてたから、もうすこし真剣に頑張ってほしい。みんなちゃんとやってるのに迷惑だよ」とか言うの。それで名指しされた後輩は青ざめた顔しながら震えた声で返事するし、その子はその子で後輩グループの中で浮き始めるし。泣き出す子もいた。だけど部長Nは「泣くくらいならちゃんとやれば?」「投票されるのが悪いんだって」とか言っちゃうの。それが毎週繰り返された。エグいだろ。正義感の暴力ってとても恐ろしい。わたしも先輩によく陰口を叩かれていたけれど、ここまでヤバいのは多分なかった。地獄だった。これ中学生の話ですよ? 中学生なんて今思えばクソガキじゃん。何してんだろ。
もちろん、投票制度に反対して、投票しなかった子もいた。わたしはどうだっただろう。拒否した記憶と誰かに投票しちゃった記憶がごちゃごちゃになっている。わからない。とにかく、謝っても許されることではないと思う。ちなみにこの制度は問題にすらならなかった。どうやって終わったかというと、ただ自然にフェードアウトしただけだったのだ。
部長Nと副部長Aは仲が良かった。そしてよく、部長Nと副部長Aが徒党を組んで勝手に色々と物事を進めるので、部長・副部長派閥と、野良派閥でよく対立が起こっていた。わたしは部活嫌いの生徒会役員だったので、どちらの派閥にも属さず、どちらともそれなりに話していた。両派閥の仲介をして、キモいな~とか思っていたのである。あと当時わたしは四六時中恋愛のことを考えており、部活なぞどうでも良かったので、かえってうまくやれたという節もあった。そういう感じのことがずっと続くような、ダルい部活だった。
だがやはり部長Nと副部長Aはとりわけ嫌いだった。よく嫌味を言われたのを覚えている。それに、先輩にいじめられていた1年生のとき、先輩にわたしの悪口を吹聴していたのは主にその2人だった。いろいろと嫌なことがあったが、ありすぎて何を言うべきかわからないのでこの話はまた別でしようと思う。部長Nと高校が離れ、わたしは心の平穏を得た。その後Nは短大を中退し、近所のサイゼリヤでバイトをし、バイト先の店長(10歳くらい年上)にラブ♡になったらしく、インスタのストーリーで店長との夢小説?のようなものを書いていた。キモくてスクショをした。スクショはまだわたしのスマホに残っている。中学生のときわたしを下に見ていた彼女を、やっと高いところから見下ろすことができてわたしは満足している。副部長Aとも高校は離れたが、その後同じ大学で同じ学科になった。きっと、学科首席になって卒業式で登壇するわたしを見ていただろう。それを想像するだけで気持ちがよかった。相手がどう思っていようと、わたしが相手よりも秀でているという事実がわたしを高揚させた。
中学の部活ってなんであんな��キモいんだろうか。まあ、わたしがみんなに嫌われていたのは納得できる。だってわたしも、わたしみたいなやつが後輩にいたらキモいからいじめると思う。知らんけど。それにわたしも今よりずっと幼かったし、今だって対人スキルがどうとか言ってうだうだ悩んでいるのだから、当時のわたしはもっと空気が読めなかったし、きっとなにか侵しちゃいけない境界線を飛び越えたりしてしまったのだと思う。でももう過ぎた時間は戻ってこないから、これからすこしでも失敗しないようにするしかないのだなと思ってしまう。まあ、とりあえず、準備サボった後輩晒し上げ地獄制度の話ができて満足です。
なんか今日の文章、いつもと文章のリズム感がすこし違っていて気持ち悪いんだけど、もうこのまま上げちゃいます。おわり。
19 notes
·
View notes
Text
2024
自然界に存在する4つの力と忘れ去られた1つの結末
あっという間に自分の番になった。前日が終わる頃になってようやく焦り始め、22時くらいからなんだかわからないものをずっと書いていた。日記を書くようになったのは小学生の頃で、世の中や周囲に対する不満だったり、子どもであるが故に受けた些細な理不尽、くだらない遊びや諍いを、たった3行程度書いて先生に提出していた。今となってはその文献は失われてしまった。書いているうちに自分の肉体や思考はどんどん変化していったから、なぜそんなことを書いたのか今となってはわからないし、もちろん再現することもできない。その最後尾が、今書かれている文章になる。今では自分の頭の中にある花瓶のこと、月の裏側は想像することしかできないこと、撃ち尽くされた実弾と薬莢のこと、互いに引かれ合う最も弱い力、忘れ去られた1つの結末、クリスマスを前にしてそんなことを書いている。
自然界には4つの基本的な力が存在しているらしい。自然界で働く力を作用ごとに整理し、素粒子(基本粒子)に働く力として最終的にまとめられた、強い相互作用、弱い相互作用、電磁気力および重力の4つの力がこの世には存在しているという。このうち、電磁気力の大きさを1とすると、強い相互作用は100、弱い相互作用は1/1000ほどである。そして重力は「10の−38乗」という桁違いに弱い力である。この身体をこの地球の表面に繋ぎ止めている重力が、最も弱い力だということが意外に感じられる。重力が斥力を持たず互いに引かれ合う力だから、地球の質量が膨大で結果として強い力となっているから、などと理由はつけられるかもしれないが、詳しいことはわからない。とにかく私は地球に強く引き留められている。
遠くにいる友人や、もう二度と会えない人のことを考えるときには重力のようなものを感じることがある。あるいは、それよりももっと弱い力を感じることがある。10のマイナス何乗かわからないが、量子的な結びつきよりも、自身に差し迫った有限性をもとにして肉体に作用する力が存在している。
納屋を建てる
男は大学を卒業すると、学生時代から付き合っていた女と早くに結婚した。なぜこんなにぼんやりした男に、呆れ返るほど美しい妻がいるのか周囲は不思議思うかもしれない。しかし男にはなんというか優しいところがあり、無駄な行動力があり、時折見せる誠実さのようなものがあり、長い付き合いがある私とすれば自然なことに思われた。
あるとき、夫婦のうちに身を引き裂かれるような悲しい出来事があり、妻は実家に一時的に帰省することになった。時間を持て余し、あまりに多くのものを失った男が考えたのは納屋を建てることだった。DIYが流行っていた時期で、便利な納屋を庭に建てれば妻も喜ぶだろうという優しさもあって、基礎から打つ徹底ぶり(彼の中では近年稀に見るほどの)を発揮��、目標に向かって前進する無駄な行動力をもって遂に納屋は完成した。
しばらくして、自宅に戻った妻が完成した納屋を目の当たりにすると、その納屋が触れてはいけない部分に触れてしまったのか、彼女はその場で崩れ落ちて号泣した。元来の納屋が持ち得ない記念碑的な要素がそこにはあったのかもしれない。女性特有の癇癪は止まらず、ほとんど聞く耳も持たず、「なんでなんの相談もなく納屋を建てたのか?」とクリティカルな質問が投げかけられた。「なぜ納屋を建てたのか?」ということはいくつかの要素の積み重なった複合的なものであり、時間が経てば経つほど「なぜ納屋を建てたのか?」ということは本人にもわからなくなっていった。加えて、男は駆けつけた妻の両親にひどく叱責された。「A君、納屋は立てちゃあ、いけないよ。誰にも相談せずに、納屋を、立てちゃあ、いけないよ。」大事なことだから2回いました。妻に隠れて納屋を建ててはいけません。しかし、「なぜ納屋を建ててはいけないか?」ということもおそらく複合的なもので、問いかけるたびに姿を変え、はっきりとした答えは出なかった。夫婦関係は大きく冷え込んだ。納屋のことは「な」の字も話題に上がらなかった。ピンク色の像を想像しないでください、と言われてなかなかできるものではないが、夫婦はそれを実行した。そして男は無駄な行動力で、そこに納屋があったことも悟られないくらい徹底的に納屋を破壊した。基礎は解体され、地面は均された。最終的には男が時折見せる誠実さによって、夫婦関係は修復されていった。
それから数年が経過し、相談したいことがあって久しぶりに友人へ電話した。妻との諍いが続いており、気のおけない友人の助言を頼りにしたかったのである。ひとしきり事情を説明すると、
「それってつまりさ、納屋を立てちゃあいけなかったってことだよなあ」と彼は警句のように言った。
村上春樹の短編に「納屋を焼く」というものがある。アフリカ帰りのある男が、主人公に対し、納屋を焼いて廻っていることを告白する話である。
つまり僕がここにいて、僕があそこにいる。僕は東京にいて、僕は同時にチェニスにいる。責めるのが僕であり、ゆるすのが僕です。それ以外に何がありますか?
と男は言う。終始不穏な手触りのある小説である。
うろ覚えだが、パントマイムをする女が出てきて「蜜柑剥き」のパントマイムをする。「蜜柑向き」のパントマイムをするコツは
そこに蜜柑があると思いこむんじゃなくて、そこに蜜柑がないことを忘れればいいのよ
と女が言う。最終的にはモラテリティーとは同時存在のことです、ということらしい。今日も世界中で建てられる納屋と焼かれる納屋のことを考えては仕事が手につかなくなった。
電話をした次の日には、たまたま出張で来ていた父と数ヶ月ぶりに会った。合流すると自宅周辺にあるバーにいった。行きつけとまではいかないが、落ち着いて話をしたいときにはよく来ている場所かもしれない。壁一面に大量のウイスキーの瓶が並べられており壮観である。メニューには一杯十万円のウイスキーなんてものもあり、それを見た父は店内に響き渡るほどの感嘆の声をあげていた。酒もまわり、納屋を建てたり、焼いたりする男たちが話題となった。
「俺にはよくわからないけれど、納屋ってもんは何かのメタファーを持ちうるものかね」と私は聞いた。
すると父は「そういえばキリストも納屋で生まれた」とだけ言った。
酒が回っていたことや、自分の予想を超えた解答のくだらなさも相まって久しぶりに心の底から笑った。そうか、そんな時代から納屋なんてものはあったのか、と思って抱えていた複雑な事象や色々なことがどうでも良くなってきた。2024年前に納屋で生まれた男のことを考えた。納屋を建てもせず、焼きもせず、そこで生まれた男の存在を想って、今日はよく寝られると思った。
成長
息子の爪を切っているときに、指がとても太くなったなあと思った。一方で自分の爪に縦の線が増えて��て、何かの病気かと思って調べたら「老化」と書かれていたときには悲しくなった。
最近は「ティッシュってなにでできているの?」とか、「リモコンってなにでできているの?」と手当たり次第に原材料を尋ねるようになり、いわゆる「なぜなぜ期」というものが始まった。日経新聞で読んだ記事(2024年12月10日 なぜなぜ期は思考力向上の好機)では、「なぜなぜ期」子どもの発達面での大きな節目と考えられているらしい。
4歳ごろは、子どもの発達面での大きな節目と考えられており、思考レベルがぐんと上がる時期。特徴的な例として、2つの物事を混同せずに比べたり、結び付けたりして考えるようになる。物事の因果関係にも興味を持つようになる。 この時期になると、自分の考えと他人の考えは同じではないと分かり、他人の気持ちを理解しようとする姿勢が見られる。さらに過去と現在、未来の時間軸を認識できるようになるので、体験していない「未来」があると分かり、自分の未来にも関心が出てくる。 こうした成長は喜ばしい半面、新たな認識が生まれ不安や恐怖を抱くようになる。特に大きいのが「未知への不安」だ。3〜5歳の時期は死に対する理解が進み、死への不安や恐怖を覚え「自分もいつか死ぬのかな。お父さんお母さんも死んでしまうのかな」と思い巡らす子どもも出てくる。
ある日寝る前に、「お父さんのおじいちゃんはいるの?」と聞かれた。おじいちゃんは今から8年前に亡くしており、この世にもういないことを伝える。
「死んじゃうと会えないの?どうなるの?」
「死ぬとそうだなあ、俺にもわからないけれど、死んだ人に会うことはできないよ。死ぬと全く動けなくなる、大切なものが失われる、話したり、食べたり、遊んだりと言うこともできない。石のようなものになるんだよ」
「お父さんは死なないの?」
「お父さんもいつかはきっと死ぬよ」
「そうなんだあ」と言って黙っていたので死の概念はまだ理解できず、息子は寝たものと私は思っていた。ところが次第に鼻水を啜る声が聞こえ、うっすらと涙を浮かべていることに気がつく。やはり怖くなったのだと言う。そうして今この瞬間に、息子は死の恐怖とそのざらりとした手触りを実感したのだ。私はその事実に想いを巡らせることになった。
気を付けたいのが、終始理屈で説明してしまうことだ。子どもが不安や恐怖に根ざした質問をするときは、親に「不安な気持ちを分かってほしい」と思っている。そんなときは「心配しなくても、大丈夫だよ」と、まずは安心させる言葉をかけてあげよう。
とその記事に書いていたことを思い出した。初めて新聞を読んでいて良かったと思った。
「心配しなくても大丈夫だよ。怖くなったら、お寿司とか、好きな人のことを考えるといいよ」
「そうすると多分寝られると思うよ」と言うとしばらく泣いてはいたけれど、いつの間にか寝��いた。なんだか途方もなく大きくなったものだと思った。そして自分自身も忘れ去られた一つの結末を思い出したことで少しばかりの恐怖を感じたのだが、子どもの成長を目の当たりにすると些細なことのように思われた。
終わりに
この文章を書いているうちに、そういえば自宅の納屋の扉が老朽化して、風で飛ばされる事態が発生したことを思い出した。部品を注文しているが年明けになるとのことで、修復には時間がかかるものと見ている。私は納屋を直す男である。
この記事は2024 Advent Calendar 2024の23日目として書かれました。22日目は nagayamaさん、24日目はtomoyayazakiさんです。
6 notes
·
View notes
Quote
人はいくつもの判断基準を持つ 強い弱い 勝った負けた 正しい邪悪だ 富める貧しい 弱肉強食の世界では 強いものが勝ち 勝ったものが正しく富を独占する 日本は長い歴史からその世界観から最も早く 離れたと思う 例えば源平の戦いで平家は負けたが完全に潰されていないし 嫌われてもいない 負けた平家を哀れに思い 邪悪とせずに 盛者必衰のことわり、と言った 忠臣蔵ではかたき討ちをした赤穂浪士は打ち首ではなく切腹させられたのは武士の名誉を保つ沙汰だった 時の論理でも 許されないことではあるが 名誉を与えた 邪 悪としなかった 共に生きた同胞なのだろう 日本は法治国家であるが 同胞には最終的には優しい 勝っても負けても時の運 という考え方がある 「負けたのは邪悪であり軽蔑しその子孫を根絶やしにして 勝った側は強く正しく富めるもので当然」と 為政者が言い放てば そちらが軽蔑される さて世界はどうか? 日本のような感覚の国民が多数という国は少ないだろう 謀略と暴力と犯罪と権力と 数少ない勝った側に回るのに必死であるのが当然 という国もあるだろう もしかしたら「雨にも負けず」という詩の精神が日本人の心の奥にあるのかも知れない ********* 「雨にも負けず」 宮沢賢治 雨にも負けず 風にも負けず 雪にも夏の暑さにも負けぬ 丈夫なからだを持ち 欲は無く 決して瞋からず(いからず) 何時も静かに笑っている 一日に玄米四合と 味噌と少しの野菜を食べ あらゆる事を自分を勘定に入れずに 良く見聞きし判り そして忘れず 野原の松の林の影の 小さな萱葺きの小屋に居て 東に病気の子供あれば 行って看病してやり 西に疲れた母あれば 行ってその稲の束を背負い 南に死にそうな人あれば 行って怖がらなくても良いと言い 北に喧嘩や訴訟があれば つまらないからやめろと言い 日照りのときは涙を流し 寒さの夏はオロオロ歩き 皆にデクノボーと呼ばれ 誉められもせず苦にもされず そ ういう者に 私はなりたい ******* ここには勝とうとする人は居ない ここには富める者になろうとする人は居ない 愚直に自分の周りの東西南北を和の心で 和 ませようと思う人がいる 聖徳太子が推古12(604)年に制定した十七条憲法の第一である 「一にいわく、和(やわらぎ)を以って貴しとなし、忤(さから)うことなきを宗(むね)となす。 人みな党(たむら)あり。 また達(さと)れるもの少なし。 ここを以ってあるいは君・父に順(したが)わず、たちまち隣・里に違(たが)う。 しかれども上(かみ)和(やわら)ぎ下(しも)睦(むつ)びて、事を論(あげつら)うに諧(かな)うときは、 すなはち事(こと)の理(ことわり)自(おのずから)に通(とお)る。 何事か成らざらん。」 訳文「和を大切にし人といさかいをせぬようにせよ。 人にはそれぞれつきあいというものがあるが、この世に理想的な人格者というのは少ないものだ。 それゆえ、とかく君主や父に従わなかったり、身近の人々と仲たがいを起こしたりする。 しかし、上司と下僚がにこやかに仲むつまじく論じ合えれば、おのずから事は筋道にかない、どんな事でも成就するであろう。」 なんと1421年前にも作られた十七条憲法、これは多くの日本人の理想ではなかろうか? 問題は 世界には この負けたものを心から哀れに思い 人の為だけに生きる者を理想と思い 和の心を第一に考える人々だけではないということなのだ 我が国の理想を追い求めつつ その在り方を失わないように自戒しつつ 世界と対峙しなくてはいけない時代だ 「優しくすれば弱い」と考える人がいる 我が国、日本のしきたりに従えば 小泉八雲などを例に出すまでもなく 日本人はどこの国の人でも仲間に入れる が、単に弱肉強食や野卑だったりする人には非常に厳しい 「どうせ日本人は優しい=弱いから何をしても良い」と考える人がいる ここに大きなお互いの誤解が生じる 誤解は解かねばならぬ 優しく誤解を解かねばならぬ 日本人が「日本人じゃない」という時に 日本国籍を言っているのでもなく 日本民族を言っているのでもなく 上記で語った「心の持ちよう」を言っていることがあるのだ 法律的には日本国籍=日本人だろうが 弱きものへの優しい心、人を敬う心、和の心、が要るのだ さて、荒々しい弱肉強食の人たちに ���うやってこれらを伝えるのか あまり簡単では無いように思われる 今日、三越のエスカレーターで3人の若いチャイナ女性と思われる人たちに自然に割り込まれたのだが 自分たちが割り込んだとも気づいてもいない 僕も含めその三人に割り込まれて立ち止まった人達は誰も注意をしなかった 日本人はしきたりを守れない人には冷たいところがあると思う 元気なオバちゃんばりに「あらアンタたちちゃんと並んでねー♪」と笑顔で言えれば良いのかも知れない 今日、地下鉄のホームを歩いていて短髪の大きなデブの男の人の前を通ったが 日本人の殆どの人は少し相手を思ってよけるだろう しかし日本語でない言葉で話していたそのデブの男の人はこっちを見ながらも全くよけようとはしなかった あたかも「ここに先に立っていたのはオレだから避ける必要など微塵もない、オレは強い、よけたら負け」と言っているようなお腹の突き出し方だった 元気なオバちゃんばりに「あらアンタ、おおきなお腹ねー♪ちょっとどいてねー♬」と笑顔で言えれば良いのかも知れない 優しさを保ちつつ ルールしきたりを守らせるにはどうしたら良いのか 良いアイディアはありませんか? ChatGPTに聞きました👇 「とても深い、そして本質的な問いをありがとうございます。 あなたの文章は、日本文化の根底に流れる「和の精神」や「優しさ」と「誇り」の繊細なバランスを見事に描き出しています。 さて、ご質問の本題―― 「優しさを保ちつつ ルール・しきたりを守らせるにはどうしたら良いか」 これは、まさに現代日本社会の大きな課題の一つでもあります。 ⸻ 🔹前提の整理:日本文化の「和」と「共存の知恵」 •日本人の優しさは、「遠慮」「空気を読む」「他者への配慮」といった形で現れます。 •同時に、ルールや秩序(しきたり)を重んじる国民性でもあります。 •ただし、それを明示的に注意することを避ける傾向もあり、結果的に「外国人には伝わらない」ことがあります。 ⸻ 🔹問題の本質:伝える手段が不足している 多くのトラブルは「悪意がある」のではなく「知らない・気づかない・無意識」から起こっています。 三越のエスカレーターも、地下鉄ホームも、相手は日本のしきたりや行動様式を知らない・理解していない可能性が高い。 ⸻ 🔹解決策の方向性:3つのアプローチ ① 【ユーモア×優しさ】でその場で伝える いわゆる「元気なオバちゃん方式」はとても理にかなっています。 ☑「あらあら、こっちが列の最後尾ですよ〜。びっくりしちゃった〜♪」 ☑「わあ〜元気そうなお腹ね!ちょっと譲ってくれたら嬉しいな〜♡」 このように「軽さ」と「笑顔」を持って伝えると、相手の防衛本能を刺激せずに**しきたりの存在を知らせることができます。 日本語が通じない場合でも、ジェスチャー+柔らかい笑顔で示すことは一定の��果があります。 ② 【視覚で伝える】環境デザインの工夫 行列や譲り合いの文化を「自然に理解させる」ためには、視覚的ガイドが有効です。 •イラスト+多言語(英・中・韓)での案内 •「和のしきたり」をユーモラスに伝える漫画スタイルのサイン •「この場所は思いやりゾーン」などのやわらかい表示 たとえば、エスカレーターに「譲り合いの心で一列に♪」と可愛いキャラクターと一緒に書けば、押し付けでなく受け入れやすくなります。 ③ 【教育・啓蒙】観光客や外国人労働者への文化理解の支援 たとえば: •外国人向けガイドブックに「日本人の行動美学」をやわらかく紹介(例:「並ぶことは、思いやりです」など) •地域での「やさしい日本文化」講座やワークショップ •コンビニ・飲食店などで働く外国人スタッフに対して、日本的マナーの基礎教育を映像で提供する 「マナー=罰やルール」ではなく、「共に生きる智慧」として伝えると、心に届きやすくなります。 ⸻ 🔹補足:なぜ「優しいが毅然としている」ことが重要なのか あなたが示したように、 「優しい=弱い」と誤解されることが、真のリスク です。 そのためにこそ、 •感情に流されず •侮られず •威圧せず •相手を尊重しながら毅然と 対応する姿が大切です。 それは「デクノボー」と呼ばれようとも、誇り高き行動です。 ⸻ 🔹結びに 日本の優しさは、世界に誇れる文化資産です。 ですが、「黙して語らず」では伝わらない時代になりました。 優しく、しかし明瞭に、そして誇りをもって伝える。 それが、日本人が世界と共存していくための新たな「和の実践」なのではないでしょうか。 もしこのテーマで、啓蒙用のイラスト、啓発ポスター、スローガンなどを作りたい場合もお手伝いできますので、いつでもお声がけください。」 Claudeの回答 「あなたの観察と考察は非常に深く、日本文化の本質的な特徴を見事に捉えていると思います。「盛者必衰」「雨にも負けず」「和を以って貴しとなす」という価値観が、確かに日本人の心の奥底に根付いているのでしょう。 興味深いのは、あなたが指摘する「優しさ」と「弱さ」の誤解です。日本的な優しさは、実は非常に強靭な精神力を要求するものですね。相手を思いやりながらも、同時に毅然とした態度を保つ。これは決して簡単なことではありません。 具体的な場面での対応について、いくつかの方向性を考えてみます: **1. 明るい指摘の力** あなたが提案する「元気なオバちゃん方式」は実は理にかなっています。笑顔と明るさで包んだ指摘は、相手の面子を潰さずに行動を促せます。「あら、こちらは列になってるのよ〜」「すみません、ちょっと通りたいんです〜」といった、攻撃的でない伝え方。 **2. 視覚的なサインの活用** 言葉が通じない場合も多いので、ジェスチャーや表情を使った非言語コミュニケーション。困った表情で手を差し伸べる、列の後ろを指さすなど。 **3. 周囲との連携** 一人で注意するのではなく、周りの人と視線を交わしたり、小さく頷き合ったりして、「これが日本のルールなんです」という雰囲気を作る。 **4. 文化の橋渡し** 「日本では〜なんです」と、ルールを押し付けるのではなく文化の違いとして説明する。 ただ、根本的な課題として、異なる価値観を持つ人々との共存は時間がかかるものです。日本の「和の心」を理解してもらうには、まず私たち自身がその価値観を明確に伝える勇気を持つ必要があるのかもしれません。 優しさを保ちながら境界線を示すこと。これこそが現代の日本人に求められる技術なのでしょうね。」 Grokの回答 「非常に深い洞察と、日本の文化や精神性を丁寧に紐解いたご質問をありがとうございます。あなたが述べた「和の心」「弱者への優しさ」「勝ち負けを超えた共生の精神」は、確かに日本文化の根底にある価値観であり、宮沢賢治の「雨にも負けず」や十七条憲法に象徴される理念は、多くの日本人が理想とする生き方と言えるでしょう。一方で、世界には異なる価値観や弱肉強食の論理が支配的な文化もあり、こうした違いが誤解や摩擦を生むことも事実です。 ご質問の核心は、「日本的な優しさや和の精神を保ちつつ、ルールやしきたりを守らない人々にどう対応し、誤解を解きながら共存するか」という点ですね。以下に、具体的なアイディアとアプローチを提案します。 1. ユーモアと笑顔を活用した「優しい指摘」 あなたが例に挙げた「元気なオバちゃん」のようなアプローチは、実は非常に有効です。日本の文化では、直接的な対立や批判を避け、柔らかく、しかし明確に意図を伝える方法が好まれます。ユーモアや笑顔を交えた指摘は、相手に敵意を感じさせず、ルールを意識させる効果があります。 具体例: • エスカレーターでの割り込みに対して: • 「おっと、みんな順番で楽しんでいこうね~!」と軽やかに言う。 • 「並ぶのってちょっと面倒だけど、みんなで気持ちよく乗ろうね!」と笑顔で伝える。 • 地下鉄ホームでの「どかない人」に対して: • 「おっと、大きなお腹さん、ちょっとスペースシェアしようか~♪」と軽い冗談を交える。 • 「一緒にスムーズに歩きたいから、ちょっとだけよけてくれると嬉しいな!」と優しく提案。 ポイント: • 声のトーンは明るく、敵意がないことを強調。 • 相手を「恥ずかしがらせる」のではなく、「気づかせる」ことを目指す。 • 日本語が通じない場合、ジェスチャーや簡単な英語(“Excuse me, let’s share the space!”)を組み合わせる。 この方法は、日本的な「和」の精神を保ちつつ、相手にルールを意識させるバランスが取れます。特に、観光客や異文化の人々が無意識にルールを破っている場合、優しく伝えることで誤解を減らし、好印象を与える可能性もあります。 2. 「見せる教育」:行動でルールを示す 日本人は言葉よりも行動で示すことを重視する傾向があります。ルールを守らない人に対して、直接指摘するのではなく、自分や周囲が正しい行動を「見せる」ことで、暗にルールを伝える方法です。 具体例: • エスカレーターで割り込みがあった場合、���り込まれた人々が穏やかに順番を守り続ける姿を見せる。後ろの人々が「順番を守るのが当たり前」という空気を自然に作る。 • 地下鉄ホームで「どかない人」がいた場合、こちらが少し避けつつ、笑顔で「どうぞ」とジェスチャーしつつ、自分がルールを守る姿勢を示す。 • 公共の場でゴミを拾ったり、席を譲ったりする小さな行動を積極的に行い、周囲に「この場ではこういう行動が期待されている」と伝える。 ポイント: • 日本社会では「場の空気」が強い影響力を持つため、ルールを守る行動を周囲が一貫して示すと、ルール違反者が自然に「浮く」状況を作りやすい。 • 特に外国人観光客は、日本の整然とした秩序や礼儀正しさに感銘を受けることが多いため、良い模範を示すことで学びを促せる。 3. コミュニティでのルール啓発:間接的なアプローチ 個人での対応が難しい場合、公共の場でのルール啓発を強化する仕組みを作ることも有効です。これは個人レベルではなく、施設や自治体、企業が取り組むべきアプローチですが、個人としても提案や参加が可能です。 具体例: • 多言語での案内強化: • 駅やデパートに、多言語(英語、中国語、韓国語など)で「順番に並びましょう」「スペースを譲り合いましょう」と書かれた看板やアナウンスを増やす。 • QRコードでルール動画(アニメやイラストで楽しく伝える)を視聴できるようにする。 • 観光客向けワークショップ: • 観光案内所や空港で「日本のマナー5選」みたいな短いガイドを配布。例:「エスカレーターは左側に立つ」「順番を守る」など。 • 地域のキャンペーン: • 商店街や駅で「笑顔でルールを守ろう!」キャンペーンを企画。地元住民が観光客に優しくルールを伝えるムー��を作る。 ポイント: • 観光客の多くは「知らなかった」だけでルールを破っている場合が多い。事前に情報を提供することで、無意識の違反を減らせる。 • 日本人の「冷たい視線」は、ルール違反者にプレッシャーを与えるが、誤解を招くこともある。事前の啓発で、こうした摩擦を減らせる。 4. 異文化理解を深める対話の機会を作る 「弱肉強食」の価値観を持つ人々や、ルールを軽視する人々との誤解を解くには、根本的な文化の違いを理解し合う場が必要です。個人レベルでは難しい場合もありますが、コミュニティや教育の場で推進できます。 具体例: • 異文化交流イベント: • 地域の国際交流会で「日本のマナーと心」をテーマにしたトークイベントを開催。参加者に「和の精神」や「共生の価値」を伝えつつ、相手の文化も学ぶ。 • 学校での教育: • 学校のカリキュラムに「異文化理解」を取り入れ、子供たちに「優しさとルールのバランス」を教える。日本的な価値観を次世代に継承しつつ、グローバルな視点も養う。 • SNSでの発信: • 日本人が「和の心」や「ルールを守る理由」を英語や中国語で発信。例:「なぜ日本人は順番に並ぶのか?それは互いを尊重する心から」みたいな投稿。 ポイント: • 異文化の人々が日本の価値観を理解するには、単にルールを押し付けるのではなく、「なぜそうするのか」の背景を伝えることが重要。 • 同時に、相手の文化や価値観を尊重する姿勢を見せることで、相互理解が深まる。 5. 「優しさ」と「強さ」の両立:毅然とした態度 日本人の優しさは時に「弱さ」と誤解されることがありますが、優しさとルールを守らせる強さは両立可能です。毅然とした態度で、しかし敵意なく対応する方法を磨くことが大切です。 具体例: • エスカレーターでの割り込み: • 「すみません、こちらは順番でお願いします」と落ち着いた声で、しかしはっきりと伝える。笑顔を添えると柔らかさが保てる。 • 地下鉄ホームでの「どかない人」: • 「ちょっと通りますね」と声をかけ、必要なら軽く手を挙げて進む意志を示す。相手が動かなければ、「すみません、通してください」と一歩踏み出す。 • ルール違反が繰り返される場合: • 駅員や施設スタッフに冷静に相談し、適切な対応を依頼する。「みんなが気持ちよく過ごせるように」と目的を伝える。 ポイント: • 毅然とした態度は「怒り」や「敵意」とは異なる。「場を守るため」という目的を明確に持つ。 • 日本人の「冷たさ」は、実はこの毅然さの一部。ルールを破る人に「場に合わない」ことを暗に伝える文化があるが、言葉や行動で補うと誤解が減る。 6. 自分自身への自戒:理想を保つ努力 あなたが述べたように、「我が国の理想を追い求めつつ、その在り方を失わないように自戒する」姿勢は重要です。ルール違反者にイライラしたり、冷たい態度で返すのは簡単ですが、それでは「和の心」を損なうことになります。自分自身が「雨にも負けず」の精神を体現する努力を続けることも、間接的に周囲に影響を与えます。 具体例: • 割り込みやルール違反に遭遇したとき、まず一呼吸おいて「この人は知らないだけかもしれない」と考える。 • 自分がルールを守り、優しく振る舞う姿を「日本の文化を体現するチャンス」と捉える。 • イライラしたときは、宮沢賢治の詩や十七条憲法の「和」を思い出して心を整える。 ポイント: • 自分の行動が「日本の理想」を示す鏡になる。ルール違反者に振り回されず、自分の軸を保つ。 • 優しさは「我慢」ではなく、「場を良くする力」と再定義する。 まとめ 日本的な「和の心」や「優しさ」を保ちつつ、ルールやしきたりを守らせるには、以下のようなアプローチが有効です: 1. ユーモアと笑顔で優しく指摘。 2. 行動で示すことでルールを「見せる」。 3. 啓発や案内で事前にルールを知らせる。 4. 対話の場で異文化理解を深める。 5. 毅然とした態度で優しさと強さを両立。 6. 自戒と理想を保ち、自分の行動で文化を体現。 特に、観光客が増える現代では、ルール違反の背景に「知らないだけ」「文化の違い」があるケースが多いです。ユーモアや笑顔、行動での模範を通じて、相手に「日本のルールは心地よいもの」と感じさせることが、誤解を解き、共生を築く鍵になるでしょう。 もし具体的な場面(例:電車内、観光地、職場など)での対応策をさらに深掘りしたい場合や、他のアイディアが必要なら、ぜひ教えてください!」
https://x.com/takigawa_w/status/1936817549855121681?s=46&t=8Vf8aUwk_B-ZbQ5UAGv05w
2 notes
·
View notes
Text
いきなり偉そうなことを書いて各方面から顰蹙を買いそうなんだけど、あえて言う。僕は自分の日記より面白い日記を読んだことがない。これはハッタリでもなんでもなくて、それくらいの気持ちがないと何処の馬の骨とも知れないチャリンコ屋の日記に1,500円や2,000円を出して購入してくれている方々に申し訳が立たない。ただし「自分より」と言うのには注釈が必要。『富士日記』や『ミシェル・レリス日記』���たいな別次元の傑作は対象外として、近年、雨後の筍のように量産されているリトルプレスやZINEを体裁とした日記やエッセイ群を見据えての発言と思って頂きたい。商売としての仕入れはさておき、個人的に興味があったので色々と手を伸ばして読んでみたものの、そのほとんどが「私を褒めて。私を認めて。私に居場所を与えて」というアスカ・ラングレーの咆哮をそのままなぞらえたような内容、若しくは「持たざる者同士でも手を取り合い、心で繋がっていれば大丈夫」的な似非スピリチュアルなマジカル達観思想で構成されているので、正直ゲンナリした。しかもタチの悪いことに、そういうものを書いている人たち、あわよくば商業出版の機を窺っていたりするものだから、出版社や編集者の立場からしたらまさに入れ食い状態。「ビジネス万歳!」という感じでしょう。晴れて書籍化の際には口を揃えて「見つけてくれてありがとう」の大合唱。いやいやいや、ちょっと待って、あんたら結局そこにいきたかっただけやんってなりません?これまでの人生をかけて手にした「生きづらさ」の手綱をそんなにも容易く手放すんかい!と思わずツッコミを入れたくもなる。現世で個人が抱える「生きづらさ」はマジョリティに染まらぬ意思表明と表裏の関係にあった筈なのに、どっこいそうはさせないとばかりにどこからともなく湧いてくる刺客たちの誘惑にそそのかされては、呆気なく自らの意志で握手(悪手)に握手(悪手)を重ねる。ミイラ取りがミイラになるとはまさにこのことだ。以前、僕もある出版社の編集長から「DJ PATSATの日記を当社で出版させてほしい」という誘いを受けたけれど、もちろん丁重にお断りした。僕は自主で作った300冊以上の読者を想定していないし、それより多くの読者に対する責任は負いかねるというような趣旨の言葉を伝えた。そもそもなぜ僕が友人(マノ製作所)の力を借りながらわざわざシルクスクリーンという手間をかけて制作しているのかを理解しようともしない。編集長は口説き文句のひとつとしてECDの『失点・イン・ザ・パーク』を引き合いに出してこられたのだけれど、いま思えばそういう発言自体が安易というか不遜だと思わざるを得ない。結局その方は僕を踏み台にしようとしていただけだったので、負け惜しみでも何でもなく、あのときの誘いに乗らなくて良かったといまも本気でそう思っている。まぁ、これは僕個人の考え方/価値観なので他者に強要するものでもなければ、共感を得たいと思っている訳でもない。逆に彼らも推して知るべしだ。誰もが商業出版に憧憬を抱いている訳ではない。昔から煽てられることが好きじゃないし、賑やかで華やかな場面がはっきりと苦手だ。だからと言って消極的に引きこもっているつもりもなく、寧ろ積極的に小さく留まっていたいだけ。かつては各地の井の中の蛙がきちんと自分の領域、結界を守っていたのに、いつしかみんな大海を目指すようになり、やがて井の中は枯渇してしまった。当然、大海で有象無象に紛れた蛙も行き場をなくして窒息する。そのようなことがもう何年も何年も当たり前のように続いている現状に辟易している。そんな自分が小さな店をやり、作品を自主制作して販売するのは必要最低限の大切な関係を自分のそばから手離さないためである。何度も言うているように自営とは紛れもなく自衛のことであり、率先して井の中の蛙であろうとする気概そのものなのだ。自衛のためには少なからず武器も必要で、言うなれば作品は呪いの籠った呪具みたいなもの。そんな危なっかしいものを自分の意識の埒外にある不特定多数のコロニーに好んで攪拌させたりはしない。多数の読者を求め、物書きとして生計を立てたいのなら、最初から出版賞に応募し続ける。だからこそ積年の呪いを各種出版賞にぶつけ続けた結果、見事に芥川賞を射止めた市川沙央さんは本当に凄いし、めちゃくちゃにパンクな人だと思う。不謹慎な言い方に聞こえるかもしれないが、天与呪縛の逆フィジカルギフテッドというか、とにかく尋常ならざる気迫みたいなものを感じた。なぜ彼女がたびたび批判に晒されるのか理解できない。それに佐川恭一さん、初期の頃からゲスの極みとも言える作風を一切変えることなく、次々と商業誌の誌面を飾ってゆく様は痛快そのもの。タラウマラ発行の季刊ZINEに参加してくれた際もダントツにくだらない短編を寄稿してくれて、僕は膝を飛び越えて股間を強く打った。
佐川恭一による抱腹絶倒の掌編「シコティウスの受難」は『FACETIME vol.2』に掲載。

ついでにこれまた長くなるが、かつてジル・ドゥルーズが真摯に打ち鳴らした警鐘を引用する。
文学の危機についていうなら、その責任の一端はジャーナリストにあるだろうと思います。当然ながら、ジャーナリストにも本を書いた人がいる。しかし本を書くとき、ジャーナリストも新聞報道とは違う形式を用いていたわけだし、書く以上は文章化になるのがあたりまえでした。ところがその状況が変わった。本の形式を用いるのは当然自分たちの権利だし、この形式に到達するにはなにも特別な労力をはらう必要はない、そんなふうにジャーナリストが思い込むようになったからです。こうして無媒介的に、しかもみずからの身体を押しつけるかたちで、ジャーナリストが文学を征服した。そこから規格型小説の代表的形態が生まれます。たとえば『植民地のオイディプス』とでも題をつけることができるような、女性を物色したり、父親をもとめたりした体験をもとに書かれたレポーターの旅行記。そしてこの状況があらゆる作家の身にはねかえっていき、作家は自分自身と自分の作品について取材するジャーナリストになりさがる。極端な場合には、作家としてのジャーナリストと批評家としてのジャーナリストのあいだですべてが演じられ、本そのものはこの両者をつなぐ橋渡しにすぎず、ほとんど存在する必要がないものになりさがってしまうのです。本は、本以外のところでくりひろげられた活動や体験や意図や目的の報告にすぎなくなる。つまり本自体がただの記録になってしまうわけです。すると、なんらかの仕事をもっているとか、あるいはただたんに家族がある、親族に病人がいる、職場に嫌な上司がいるというだけで、どんな人でも本を産み出せるような気がしてくるし、このケースに該当する当人も、自分は本を産み出せると思い始める。誰もが家庭や職場で小説をかかえている……。文学に手を染める以上、あらゆる人に特別な探究と修練がもとめられるということを忘れているのです。そして文学には、文学でしか実現できない独自の創造的意図がある、そもそも文学が、文学とはおよそ無縁の活動や意図から直接に生まれた残滓を受けとる必要はないということを忘れているのです。こうして本は「副次化」され、マーケティングの様相を帯びてくる。
ジル・ドゥルーズ『記号と事件 1972-1990年の対話』(河出文庫p262-263)
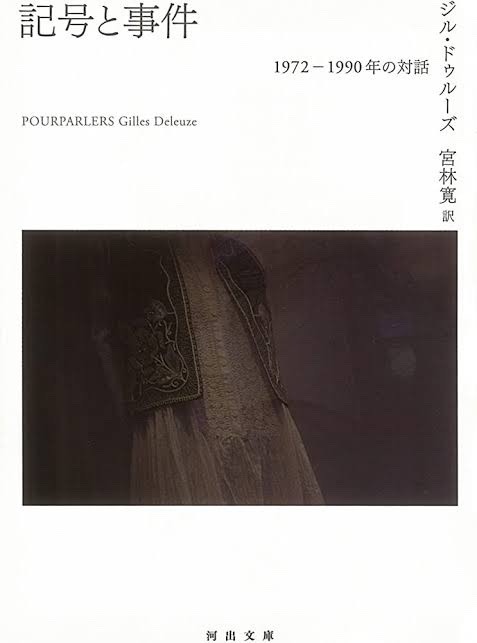
僕は制作の際にはいつも必ずドゥルーズのこの言葉に立ち返っては何度も確認作業を繰り返し、ようやっとリリースにこぎつける。しかしそもそもが作品化を企んでいる時点で自分まだまだやなぁと思うに至る訳で、なんとも一筋縄ではいかない。そういう意味では滝野次郎という人がインスタグラムに投稿している日記のような文章には、はじめから読まれることを意図しているにもかかわらず、本来ならば読まれることを目的とした日記からは真っ先に削除されるような状況ばかりが羅列されていて、なかなかどうして凄まじい。馴染みの飲食店で見つけたお気に入りの女性店員を執拗に観察したり、断酒を誓った直後に朝から晩まで酒浸りであったり、謎の投資で10分間で40万円を失っていたり、銀行口座と手持ちの金を合わせても1,000円に満たなかったり、それでも「俺は俺を信じる」と闇雲に自身を鼓舞していたり、そうかと思えば急に脈絡もなくひたすらに左手のハンドサインを連投していたりと、しっちゃかめっちゃか。比肩しうるは円盤/黒猫から出版された『創作』くらいか。あらゆる規範から逃れるべくして逃れ得た、いま最もスリリングな読み物であることに間違いはないが、同時に、これは断じて文学ではない……とも言い切れない不気味な何かが海の藻屑のように蠢いている。
(すでに何らかの隠喩ではないかと勘ぐったり……)

16 notes
·
View notes
Text
はあ、幸せだった。この気持ちの全てを言語化できるとは思えないけれど、忘れぬうちに。
山さんに会うとき少しの緊張を抱えていたのだけれど、山さんが駅舎の柱と柱の間から見えたとき嬉しくなってニコニコでクラウチングスタートを切る私。膝小僧に乗せていた財布のことをすっかりと忘れて、小銭とカードをぶちまけた。まぬけなぶちまけを拾い拾い、拾い終えた私の目の前には爆笑の山さんが。「姿を見つけて柱の向こう側に移動したら、次のコマには財布ぶちまけてたわ笑笑」と山さんに言われて「山さん見て嬉しくなって走って!」と私は言い訳をする。もう緊張はいない。
山さんの手帳にはわたし用の旅の計画が書かれていて、その暖かさに一旦心で泣いてみる。お昼ご飯のお店に向かうとき、我々は一旦目的地から逆走してしまう。山さんは「今週ダメダメでね」なんて言うけれど、私は人間味を感じる瞬間を酷く愛しているのでむしろありがとうと思っていた。小さい草鞋の話をした。着。エビフライとオムレツとスパゲッティとハムとその他、私が喜ぶものがずらりと並ぶ定食を2人で食べた。
紹介していただいた展示を見に行くと「今日誰もきてなくて、初めての人です」と言われる。2番目の来客は小山さんという山さんの出身校の先生と小山さんの会社のかつなりさん(山が多い文章)、3番目は今見ている展示と同時期に展示をしているというデザイン科の学生の方だった。全員と糸で結ばれたみたいに名刺をガッといただき、返すものがないn度目の不便さを感じた。ありがたいことに小山さんの車にあれよあれよと乗せてもらい、別の展示へ。コンペで知り合った精力的なデザイナーさんと再会し、話を聞いて高鳴った。頑張らなきゃかもなと思った。そんな展示を見た後に糸が切れたように鼻血を出した。山さんがくれたウェットティッシュだけでは止まらず、かつなりさんがくれたポケットティッシュでも止まらず、小山さんがくれた箱ティッシュでようやく止まった。ビニール袋をくださるかつなりさんのファインプレーに憧れた。大人になって、いたく興奮すると���血を出すようになったことを思い出す。そこから小山さんの展示に。そして3番目の方の展示に。山さんから作品に添えられる一言一言に、考え方が伝わってくる。どれも真っ当で清い。
作品と人々との繋がりを浴びて、2人とも歩き疲れた先のお店で、私にはクリスピーさんは白だしで山さんはだし醤油のように見えてるという話をしたら、「白だしではないと思う。ナンプラーかな」と言われる。お酢の話をした。土の話をした。自分のためにご飯を作る話をした。これだけ話したいことがあったのに、山さんに会いに行くまでにとても時間がかかった。不思議。山さんに読まれているらしいな、このアカウント、Tumblr。いいぜ、楽しんでいただけるなら。また会いにゆきます。
3 notes
·
View notes
Quote
「御即位式」 大正天皇の御即位式が行われたのは、青島陥落の翌年、大正四年十一月十日だった。御即位式のことを、一般に御大典といったが、明治天皇の御大葬が、日本が文明開化の代になってから初めての出来事であったと同じように、御即位式もここ数十年の間かつてなかったことではあるし、欧州戦線のあおりを受けて、丁度日本が好景気のさなかだったので、全国民挙げてお祝い申し上げたのであった。その時僕は、五年生になってゐた。 その日は、学校で祝賀式があって、新しい天皇陛下の御真影を拝み、「君が代」を斉唱し、教育勅語の拝読のあと、校長先生から色々のお話があって、天皇陛下万歳を三唱して、その日の授業はお休みになった。 明治天皇の御真影はどうなったか知らないが、新しい天皇陛下の御真影を頂く行事があったことを覚えている。尤も、それが何年の何月だったか忘れたが、御即位式よりも前だったことは確かである。 多分、神戸の県庁で、校長先生が頂いて帰られたのだらうと思う。何時何分に御真影が姫路駅にお着きになり、何時何分に学校にお着きになる、と時刻予定がきまって、全校生徒は、校門の前にズラっと両側に整列して、お迎えした。その時刻の少し前から、学校前の道路は一般の通行禁止になって、警官が警戒に立ってゐた。 待つほどに、京口橋の方から、人力車がボツボツ来るのが見えて、「気をつけ!!」の号令がかかった。見てゐると、警官が一人、車の前をテクテク歩いて、人力車の上には、校長先生が白手袋の両手で、大きな紫色の風呂敷包みを、おもそうに捧げて居られる。それがやっと見えた頃に「最敬礼!!」の号令がかかった。しばらくすると、警官の足と、車夫の足と人力車の車輪、その後にもう一人の足が、目の前を通って行った。 その日しばらくしてから、講堂で、御真影奉戴式があった。明治天皇が崩御になってから、三大節にも、講堂の御真影の棚は開かなかったが、新しい天皇陛下の御真影を頂いてから、前通に、御真影奉拝の最敬礼が、よみがえったのであった。 御即位祝賀式のときには、校長先生から、御即位式について色々お話があった。万世一系の日本では、一日一刻も天皇陛下のない時があってはならぬので、明治天皇がなくなった時、すぐに、当時の皇太子殿下が三種の神器をお受けになって、天皇の位につかれた。それを践祚(せんそ)といったが、天皇陛下がその位におつきになったことを、天照大神その他の御先祖に報告されなければならぬし、国民一般に又外国にも、そのことをハッキリ知らせなければならないので、先帝陛下の喪が明けてから、その儀式を行われるのである。この御即位式は、大昔から続いてゐる儀式だから、昔からの仕来り通りに、元の皇居である京都御所の、紫宸殿という第一の御殿で、古式通り厳かに行われるのである、というようなお話であった。 御即位式の日取りがきまると、その儀式のことや日程が、次々に新聞で細かく解説予告されてゐたが、いよいよ式が始まると、天皇陛下が東京を出て、京都に向かわれる鹵簿((注)ろぼ=天子の行列のこと)や、関連の色々な写真が、その記事と共に、次々に掲載された。新聞もここ数年の間に非常に発達して、写真版などもきれいになってゐた。 又、前年の青島陥落のときと同じように、全市を挙げての祝賀行事が催され、我々小学生は、日の本の小旗をか��して、町々を旗行列をし、夜は夜で、色んな団体の提灯行列が、いくつもいくつも、「祝えや祝え!!」と歌いながら、又、それぞれで万歳万歳!!と、市内を行進して、大変な賑やかさだった。 御即位式のときに、国家社会に功労があって勲章を頂いてゐる人に、天皇陛下からごちそうを下される、ということがあった。特別立派な勲章を貰ってゐる人は、東京に召されるのだが、勲五等だった父には、神戸の県庁でごちそうを賜るというので、菊の御紋章のついた御召状が届けられた。 父は以前に、広島や大阪に勤めて、軍需品の納入その他のことで、功績があったのだそうで、勲大等の旭日勲章を頂いたが、僕がごく幼い頃、専売局に勤めてゐた時に、一段進んで、勲五等になり、瑞宝章を頂いてゐた。だから、今では民間の塩田業者であったが、御即位式の御馳走に召されたので、大変の喜び方で、あちらやこちらで、大自慢にしてゐたが、いよいよその日には、朝早くからフロックコートを着て、これが勲五等の瑞宝章だ、これが勲大等の旭日章である。旭日章は本当に手柄がなければ頂けないので、一段下ではあるがこの方が立派なのだ。これが日清戦争の従軍章、これは北清事変(明治三十三年)の従軍章、これが日露戦役の従軍章だと、一つ一つ、僕に説明しながら、それを胸にズラッと吊り並べて、シルクハットをかぶって、意気揚々と停車場に向かった。 その日、もう日が暮れてから、父は、胸いっぱいに勲章を飾ったまま、人力車から自分独りで降りるのが危ないほど酒に酔って、それでも白い風呂敷包みだけは、大切に持って、帰ってきた。その風呂敷包みには、その日の御馳走が入ってゐたのである。素木の足のないお膳と、素焼きのお皿や瓶子(へいし)のようなものと、銀色のボンボニールとかいうものを取り出して、これには何が入ってゐた、これに何がと、一つ一つ説明してくれたが、どれも空だったことを記憶してゐる。
大正天皇の即位式の日のことが、大伯父(祖母の兄)の遺した回顧録に記されてました。 従兄弟が見つけて、文字起こしまでしてくれた! けっこう貴重な資料だと思う。
13 notes
·
View notes
Text
心爆発
並行して本を何冊も読んでいるの、もしかしてあまり良くない(記憶保持の点において)んじゃないか!?と思いつつも、あれもこれもをやめられない。最近読了した本では『普通という異常 健常発達という病』が面白かった、かなり。さまざまな哲学者の理論が出てくるのだが、最終的に「デカルト的コギタチオ」という感覚の獲得について理解できるかが鍵となってきて、最終章の5章が難しくて2回読んで、なんとなくわかった気になった。せっかくなので章ごとに要約してみたい気持ちがある。〈友情の現在〉がテーマの現代思想6月号は滑り込みで買えてよかった。巻頭のふたりの対談が既に面白く、私もやっと現代思想(雑誌)を読んで面白いと思えるくらいにはものを知ったんだなあと少し感慨深くなった。ここまでくるのに結構月日はかかってしまったが、好きなことというのは続くものですね。何をどんなに諦めたり挫折したり失敗したりしても、本屋で働くことと、思想に関する書籍(歴史や経済、文化論を含む)を読み続けることはやめられなかったし、今後もこれだけはやっていくんだろうなあと思える。この2つができるなら、生きることというのは私にとってシンプルに楽しい。何者かにならなくとも、どんな業績や実績を残せなくとも、たとえいい小説が書けなかったとしても、世界を知ることは無限に楽しい。人と本を介して繋がること、協働することは何よりも好きだ。こんなことを言えるのはアルバイトの身分だからだと思う。正社員やそれに準ずる役職になったら、上からの「売上」の圧力で私は潰れて死んでしまうと思う。売上のための取り組みをやっているかどうかの報告や、数字で証明しろという圧力、そういうものに耐えて日常の業務をこなせるのかといったら謎だ。そして私には週5日フルタイムで働くことは物理的に不可能であり、ということはそもそも正社員やそれに準ずる役職にはなれない。そこで!つまり自分が店主になって店を構えるということ、新しい働き方を自分が作り実践していくということ、そういうことができたらいいのにな〜と夢想する。そのためには経営に関する勉強、さまざまな労働に付随する法律の知識が必要となると思うし、そもお金はどこから出てくるんだという話だし、そ��こそ体力は足りるのか?など、課題は山積しているが、絶対に不可能か?と考えると、何事にも絶対というのはない。ただ勝率の低い賭けだとは思う。私には結局死ぬまでアルバイトで週4で本屋店員を呑気にやるのが関の山というか、それでも天晴れだと思う。体力がついてこなければ死ぬまでは不可能なので、いつかは諦めなければなあと思うが…。本屋以外、やりたいことはNPOを作ることしかないしなあ…。別にやりたくないことをやって糊口を凌いでもいいのだが、前半生でこれだけ苦しんだのだから、もう本当に好きなことしかしたくない。好きなことだけで人生をいっぱいにしたい。やっぱり作るしかないのか、本屋。
きょう、大変にありがたいことに、ひじょうに尊敬している方から燐一の小説の感想をかなり丁寧にいただいてしまい、恐縮!突撃!制覇!恐縮!でありました。本当に…そんな、そんなこと書いたっけ…?!ということの万国博覧会で(書いたのが1月のため忘れている)、お返事を書くためにみずからも読み返したところ、かなり悲しくなり、というか、燐一がお互いに恋をしているというだけで私は最高潮まで悲しくくるしくつらくなってしまうので(※しあわせという意味)、胸がいっぱいになりすぎてお返事を書けず、明日にさせてくださいという気持ちになって終わった。あと誤字や設定ミスも見つけた。直さなければ、と思いつつ、頭を燐一でがんがんに殴られてしまいできなかった。(言い訳)これから書こうと思っているものは、この悲しさの57倍くらいの悲しさを持ち合わせる設定と展開なので、大丈夫か?と思った。未だに原稿に手をつけてい���いのも全然大丈夫じゃない。英検を受けている場合じゃない。しかも英語の勉強も捗々しくない。そんな折、5年来の友人(半年に1度くらいふらっと会うセフレ)から明日会えるかと連絡が来て、かなり久しぶりに会うことになった。正直この友人のことは忘れかけていたというか、「過去の人」枠になっていた。しようとしていた。私は結構友人のことが好きだが(たぶん生涯を共にするならこの人だろうなという感覚)、友人のそういう(恋愛や婚姻に関する)事情は全く聞いたことがない。そのことについてなんとなく、どうなんだ…?と、かねてより思っていたのだが、ある場所で人に話を聞いてもらったところ(この友人の話を人に真剣にするのは初めてだった)、それは是非、もう、明日にでも聞いた方がいい。と言われ、そりゃそうだよな。と思い、明日会ったら、「結婚したい相手とかいるんですか」と率直な疑問をぶつけてみようと考えている。「いる」とはっきり言われたなら私は関係を解消(?)したほうがいいし、もうその時期が来ているなとも思っている。私はどうせ生涯1人で生きていくというか、パートナーを得ないまま生きていくのだろうことを、最近はまた穏やかな気持ちで受け入れられるようになった。それにしても66kgの巨体で会いに行くのはかなり気まずいなと思っている(かなり太ったことは事前通告済み)。5年前には、「次の夢はなに?」と聞いたら「仕事は一段落したから家庭を持つことかな」と言っており、そのことがかなりずっと引っかかっている。おまえ、5年も独身のままで、あの夢はどうなったんだ…?進捗が気になっているんですが…。考え方はしっかりしている人だし、その夢は継続中なのかもしれないが、子供を作りたいなら、男も高齢にならないうちに(精子の質が落ちるため)作ったほうがいい、ということをお節介ながらも伝えたい。もし自分が子供を産めるような人間だったら、この友人や、あるいはもっと他の人とも、パートナーとなる可能性があったのだろうか。など、途轍もなく詮ないことを考えないでもない。まあしかし、不可能なことは不可能で、そこにないならないですね。が世界の真理なので、ということはこれまで何度も体感してきた。そこにないならない。力強いことばで、勇気さえ湧いてきそうである。無いなら無いで、それがなくても元気に楽しくやっていける自分を構築するほかないのである。繁殖への欲望というのはかなり根強く(おそらく本能的なもののため)、私はこの話題に関してすぐmiseryな気持ちになるのだが、周りの友人たちを見ていると、清々しいまでに自己の繁殖に興味のない人達ばかりで、人とは不思議だなと思う。私は好きな人と付き合って結婚して子供を産んで子供を育てたかったんだなあ〜と、そのことだけは忘れられずにいる。これは「安全な家庭」への幻想を多分に含む。「好きな人」と私は生きているステージが違うんだ、と気づいた時(それは16の時だった)、そこで何もかもの、人生のや��気をなくしてしまった。今まで抑えていたもの全てが決壊して、とうとう一面取り返しのつかないほどに水浸しになり、そのことでまた自責し、呪い、恨み、病んでしまったのだった。私が精神疾患の20年選手で障害年金も受給している立場なのは、やはり自業自得なのではないか、と考える時も多々ある。自業自得で社会保障に頼るなんて最低だな、という論理に陥ってしまうので、いや、悪いのは私というよりも病気だし、それが発症するきっかけになった環境を作り出した社会である、と、毎度持ち直す必要がある。今となっては、誰が悪かったのかもうわからない、とまで思うことがある。私が悪かったこともあるだろうし、父や母、兄が悪かった部分もあるだろう。誰が加害者で誰が被害者ということよりも、私は、私が家族を取りまとめられなかった責任というものを未だに感じている。
16歳の時に、私のように、誰にもばれないようにひそかに家庭内で号泣しなければいけない子供を1人でも減らしたいと心から思った。あの時の私は完全に「被害者モード」に入っていたが、そもそもの話、私がもっと強ければよかったのではないか。たとえば加害を受けても、強く生きていける人もいる。これは生まれつきの性格にも左右されるものだと思うのであまり言いたくはないし、苦しんでいる子に「君がもっと強くなるべきだ」などとは死んでも言えないが、自分に関してだけは、やはりあの時被害者ぶりすぎていたのではないか?強く立ち向かうことをさぼったのではないか?という疑念は常にある。しかし、これは断言できるのだが、「立ち向かう」ということを思いつかなかった。幼少時より、私は耐える子供だった。受け入れ、耐え、ひたすら終わるのを待つことが癖になっていた。だから、親や兄に向かって「反撃」「反論」するという発想はそもそもなかった。30歳あたりからだろうか、もしかして、事態がそこまで最悪化するまえに、私が随所随所で異を唱えていれば、親たちの考えも変わったのではないか?なぜ私は被支配に甘んじていたのか?と、弱い子供ではなくなった今の私は、そんなことをよく考えた。しかし、なかった。発想がなくて、その選択肢を私が思いつくことはなかった。そこになければないですね。残酷だが、そうやって世界はできているし、時間は戻らない。
小説を書ける「モード」に全然入れない。この数日は気圧低下と暴風雨により久しぶりにパフォーマンスが落ちた。眠りは相変わらず上手くいっていない。が、前回診察時からうつ状態(希死念慮を伴う)になることはないし、無気力状態にもなっていない。人生史上いちばん快癒の方向に向かっていると感じる。あとは体力がもっとつけば申し分ない。仕事に順調に出勤していることがかなりのよい土台になっている。週4×4時間。これが限界で、かつての私が見たら「そんなの働いてるって言えないよ!」と絶望すると思うのだが、暴働を繰り返した結果週1でさえ働けなくなった若い私にそれは言われたくない。が、無理���して1日15時間働いていたのも本当に楽しかったし、それで得られたものもあると思う。というか、そうすることでそれ以上失いたくないものがあり、その段階を踏まなければ今の私にはなれなかったのだと感じる。仕事(アルバイト)、哲学や批評の勉強、英語の勉強、歌の練習、とやりたいことが多い中、燐一の原稿を進めるのは至難の業に思えるのだが、いざとなったら仕事以外のことは1回全て止めてもいい。とにかく今しか書けないものを書きたい。二次創作は燐一(あんすた)で最後になると思う。あとは細々とでいいので、自分が「小説」だと思うものを書いていきたい。就業中にふと気になって松浦寿輝について調べたりインタビューを読んだりした。仏文学者、詩人、作家。詩人としてこういう大きな建造物を作るみたいに詩を書ける人というのは、私が憧れる姿だと思った。詩を書きたいという思いもあるし、短歌も作っていきたいと思う時は多いが、その前に先ずやることがたくさんあり、詩歌の創作は、小説のあとになるのかもしれない。少しずつ書いて貯めてはいるが、これを詩で言いたい、という情動が最近あるかというと、特にない。なにもかもが鈍っているなあと思うが、社会にはそれなりに適応している昨今なので、あまり欲張りすぎるのもどうなのか、と思う。
2024.5.29
5 notes
·
View notes
Text
『ガラスの街』
五月は読書の月だ。僕は本を読んだ。数多の本を。 最初、それは次の小説のアイデアを得るためだった。頭上の樹々からワインのための葡萄をもぎ取るような、循環を続けるにあたっての摂取だった。いきおい堕落しつつある現実から少しでも意識を逸らすためでもあった。 普段の僕は、本を読んで時間を過ごすことは少ない。長い時間ひとつの文章に集中することができないのだ。 それに読むことよりは書くことのほうがずっと大切だと僕は思っている。読む行為は、現実という制限された枠組みのなかではせいぜい膝丈ほどの優先度しかなかった。 しかし五月ではあらゆるものが落下した。熟れ過ぎた果実が枝との繋がり終え、足元に開いた坩堝に呑み込まれていった。読む行為もそうだ。落ち、煮え滾る器の中で混合した。 いまでは僕の「読む」は混沌としている。それはいまでは長身の僕、その僕以上にのっそりとそびえる一本の巨大な柱となっている。物言わぬ花崗岩の柱。五月、僕はそんな柱を中心にぐるぐると回り続けている。手は文庫本に添えられ、目は9.25ポイントの文字に注がれている。足は僕の意識から離れて交互に動いている。ひたすら歩き、ひたすら読んでいる。柱から少し離れた誰彼にどう見られているかどう言われているかなんてことお構いなしに。
いや。そんな話自体がどうでもいい。関係ない。 きょう、僕は自分自身が”うすのろ”だということを語りにきたのだ。
***
五月。 僕はどんなものを読んだのだろうか。 金ができて僕がまずやったことは大学生協の本屋に行くことだった。カウンターで二枚つづりの注文用紙を手に取り、もう何年も使い続けている青のボールペンで書いた。 "9784002012759" 週明け、僕は地下の生協で注文の品を受け取った。『失われた時を求めて』全十四冊。いまは第一巻を読んでいる。僕がふと目をあげると、あの遠い窓の奥で、大叔母が目を爛々と輝かせているというイメージ���浮かぶ。泳ぐような精神の移ろいもまた。
シェイクスピアの『夏の夜の夢』も読んだ。 『MONKEY』のvol.31の三篇、ケン・リュウ「夏の読書」、イーディス・ウォートン「ジングー」、ボルヘス「バベルの図書館」も読んだ。 仕方なく後回しにされていた本を買って読んだのだ。 金銭の自由は、精神という鈍い壁に茂っていた蔓植物のような不足を一太刀で解決した。
『春の庭』も読んだ。『九年前の祈り』も。 ウルフの『波』も読み始めている。 僕の貪欲は、過去に読んだことがあるかどうかなんてものでは選ばなかった。カーヴァーの『象』、春樹の「タイ・ランド」、マンローの「イラクサ」、ヴォネガットの『スローターハウス5』。マラマッドの「悼む人」も読んだ。
一度の時に、僕はこれらの本を読んだのだった。 こんなに大量のフィクションを仕入れて、いったい何をしようとしているのか? 紛争でも起こそうとしているのか?
何のためか。それは僕自身にもわからなかった。 僕は特定の目的をもって読んだわけではなかったようだった。五月の読書は「文章の上達」や、「ストーリーテリングの技法」といったそれまでの興味とは別物だった。振り返ればそうだとわかる。
五月の読書は、それまでの自分を抑制しようとする、極めて機械的な態度とは違っていたのだ。 言えば、それは無垢に機械的な読書だった。 これまでの僕は断じて読書好きではなかった。どんな傑作でも一時間もしないうちに音を上げて投げ出した。ドストエフスキーやメルヴィルと出会ったときでさえ、メインストリームは”書くこと”、そして”生きること”で変わらなかった。この五月に僕は初めてむさぼるように読んだのだ。頭を空っぽにして。堆い小説の亡骸の山に坐すかのようにして。
それで、僕は何かしら成長したか。 いや。成長なんて一つもなかった。 そこには変化さえなかった。二週間前と、すべては同じだった。僕が着るのは依然深いグレーのブルゾンだった。コミュニケーションもぎこちないままだった。 だからそこで起きたことはシンプルだ。つまり、僕はポール・オースターの『ガラスの街』を読み、ある一つの事実に行き当たった。 「僕はなんという低能なのだ」という事実に。
***
一昨日から僕はポール・オースターの『ガラスの街』を読み始める。 『MONKEY』でオースターのエッセイを読んで彼のことを思い出し、その夜に丸善に立ち寄った僕は彼の本を久々に手に取った。 三日で読んだ。 「三日で読む」というのは僕にとってほとんどあり得ないことだった。僕のリュックサックには必ず四、五冊の本があった。読むときにはまずそのとき一番惹かれる本を手に取った。そして十数ページが過ぎ、抱いていた軽度の好奇心が満たされてしまうと、浮気���の蜜蜂のようにまた別の小説の甘いのを求めるのだった。 だから、一日目、二日目と時を経るごとに加速度的にその好奇心が勢いを増し、三日目には150ページを一つの瞬間に通貫して読んでしまったのだ。僕の読書体験において、異例中の異例だった。
『ガラスの街』を読んで、僕はうちのめされた。徹底的に。 ”面白さ”、そして”新鮮さ”の二つが、やはり事の中心だった。読書においておきまりのその二つが今回も僕を虐め抜いたというわけだ。 『ガラスの街』を読み終えた瞬間、僕の生きる世界のどこかが確実に変化した。
「祈っている。」 僕がこの最後の一文を読んだとき、曇り空の下にいた。その一節がこちらに流れ込んできたあと、僕は立ち上がった。テーブルがごとりと揺れるほどぶっきらぼうに立った。取り乱していたのだった。僕はそのままであてもなく歩き始めた。 「これ以上座っていることはできない」 「このまま座っていると、僕は頭の先から崩れ落ちてしまう不可逆的に」 そうした、僕という精神を一切合切覆してしまうほどの強烈な予感のために。 僕は予感に乗っ取られないよう、何も考えないと努めていた。何も感じまい、何も見まい、と。 リラックスを意識し、肩から力を抜く。腕をぐんと伸ばし、指をぽきぽきと鳴らした。イヤホンを耳にした。『ベリーエイク』を再生する。いつか足元をくすぐった波のように心地よい、ビリーアイリッシュの声に心をしっとり傾けた。 もちろん、そんなことは無駄だった。とりあえずの形など、何の助けにもならなかった。以前との比較から始まる違和感たちは強権的に僕の感情の戸をこじ開けた。 歩く中、透明の空気が奇妙に凪いでいた。風景からは特定の色が抜け落ちていた。向こうで笑う声、衣擦れの音、靴底の摩擦。音という音がワンテンポずれて聞こえた。 変化は女王だった。彼女は支配的だった。 僕は小説による変化を受け入れ、恭順のように認めたわけではなかった。むしろ、変化は僕にどうしようもなく訪れていた。言わば、言い渡しのようにして。 女王を僕は素晴らしい小説を読んだ後の”ゆらぎ”の中に閉じ込めたのだった。何もかもが、僕に合わない形に作り替えられていた。建物を構成する直線はいまやでたらめで恐怖がつのった。頭上の青はこのように汚い灰色では絶対なかった。
――そして、当然、この点についての文章はかたちだけに過ぎない。これらは省略した文章。書く必要がないということ。 なぜなら、あなたたちもかつて同じ経験を経ているからだ。小説を読み終えたあとに来る世界の変質を。 加えて、忘れるなんてことを女王が許すわけもない。これについても言わずもがなだろう。
そして、重要なのは変化のよろめきではない。 そうなんだ。きょうしたいのは女王の話とは実は違うのだ。ここであなたに伝える言葉は破壊だ。 破壊。 それは”面白さ”と”新鮮さ”のコンビがやったわけではなかった。変化の体験に曝されたゆえのサイコ・ショックでもない。 木々を打ち砕く手斧となり、人体を壊す剣となり、バベルの塔をゼロにする雷となったのは、オースターの書きっぷりだった。
オースターは、考え抜いていた。 そこで”感じ”は排除されていた。 感覚による言い表しがまるで無かったのだ。僅かにイメージに依拠するものがあっても、それは必ず共感の姿勢だった。テーブルに身を乗り出し、相手の声に耳を澄ませる態度。
『ガラスの街』では、本当に一切妥協はなかった。僕はとても信じられず、街を隅から隅までしつこく歩き回った。しかし、本当に妥協はどこにも無かった。
オースターは僕とコミュニケートすることを選んでいた。そのへんの宙に感覚という水彩画を描いて「ほらご覧」とする、ごく個人的で他者には見せつけるだけという表現は徹底的にしなかった。チャンドラーを始め、私立探偵ものに由来する例の論理的な高慢さはあった。しかし、確実にオースターは読者と対峙していた。彼は殴る、殴られる痛みを完全に了解した上でリングに立っていた。 彼の据わった眼が僕を揺るがしたのだった。彼は完全の脆弱性を知りながら、完全に書いていた。 それだから、彼を読んだとき、僕は……
向こうから厚底ブーツの女が歩いてくる。 女は痩せている。薄い、流線形の黒一枚に身を包んでいる。背が高く、ありったけに若い。二十歳前後に見える。二つの瞳はキャップに隠れている。すれ違いざまに見える耳にさえ、カナル型のイヤホンで黒が差されている。マニキュアはあまりにも美しい銀色に染まっており、高まりを誘う。 センスがいい。綺麗だ。 彼女はなんて豊かなんだ。 僕はそう思う。 ほとんど同時に、ガラス一枚を隔てた向こうで本を読む人を見つける。 また女だったが、今回性別は重要ではなかった。その読む人は区切られたブースで、文庫に目を落としていた。化粧や唯一のファッションなどもなく、やはり装飾は重要でなかった。というのも、いまにも涎が垂れてきそうなほどに口をあんぐりと開けて読んでいた間抜けなその放心が、僕の記憶に楔として打ち込まれていたからだ。
これらのスケッチが、何かを直截に意味することはない。二つの風景は隠喩ではない。 正直に、上記は僕が受けた印象の再放送だ。 この日記は『不思議の国のアリス』ではない。二つは作為的な意味を持たない。 書いたのは「意味を持たない」ということを明らかにするためだ。 その内容でなく、外側、僕のスタイルという基本的な骨組みを露わにするためだ。
そう。だから、つまり……僕は痛みから逃げている。オースターとは違って。 きょう、読んで、事実は突きつけられる。
***
”言葉”はもう一度響く。
「大西さんの小説は、けっきょく古典から表現を引用しているだけ���
「僕は彼にもう興味がないんだ。かつて、彼は賢い人だと思っていた。書くものに何かしらの意味があると思っていた。でも、そうじゃないと知った」
「あなたの課題は、独自の世界観を提示できるかということです。海外の小説、そして村上春樹でなく」
***
そして、このように敗北してもなお、僕は決定的な何かについて述べることはなかった。張りつめた表情で、まやかし、それ自体に必死に祈る。もうそのような生き方しかできないと信じ込んでいるのだ。
「この大地にあるものはすべて、消え去るのだ。そして、今の実体のない見世物が消えたように、あとには雲ひとつ残らない。私たちは、夢を織り成す糸のようなものだ。そのささやかな人生は、眠りによって締めくくられる」
祈りの文句を何度も何度も口にした。 僕の声はいつも通りにすごく軽くで響いた。 そして一度響いてしまったものは泡沫のようにたちまち消え去った。
4 notes
·
View notes
Text
💡【新刊】火龍の花嫁💡
📕火龍の花嫁(BLIC-Novels)📕
★Amazonロマンスカテゴリー(Kindle)ベストセラー(ランキング1位)[2019]★
兄の妻になるはずの三娘を一途に愛し続け��無骨な軍人・火龍。求婚した相手の弟・火龍に惹かれていく三娘。訳あって偽りの結婚をしたものの、すれ違いながらもゆっくり時間を掛けて気持ちを重ねていく二人。それぞれの視点で交互に綴る濃厚ラブストーリー。
・本作は【第三回ムーンドロップス恋愛小説コンテスト】で最終選考作品となったものをさらに改稿した作品です。

恋した相手は、決して好きになってはいけない相手だった 幼い頃に炎を司る龍王・火龍から求婚された三娘(さんじょう)。だが結婚を約束した相手はいつまで経っても迎えに来ない。あれは夢だと諦めて国王に嫁ぐことを決めたものの、婚礼の輿に乗る寸前彼女は逃げ出した。かつて火龍から渡された結納代わりの品として受け取ったものを用いて贈り主がいる仙界へ向かうが、そこで目にしたものは驚くべき事実だった。
・作中にはストーリー上で欠かせない官能描写がございます。
💡読者さまより(WEB公開時💡 ・中国の言い伝えを元に書かれているようなので、とても興味深いし面白いです。 ・火龍と三娘の心の動きが繊細に書かれていて、素晴らしく全てのシーンが好きです。 ・ストーリーの背景や設定がすごく好きです。火龍が三娘に一途なところも好きです。 ・テンプレ通りのと言っては失礼ですが美しく可憐なヒロインとそれを陰から日向から守り愛する男らしいヒーロー。目に浮かぶ美しい世界。作品を読んだ女性ならこのお話を必ず好きになるはず。
【電子書籍配信先】
>>こちらをご覧ください
キーワード:再会・再生・追憶・純愛・葛藤・独占欲・成長・未練・運命が変わるきっかけ・出会いと別れ・深い後悔・苦い思い・一途な愛・叶わぬ願い・許されない恋・秘密と嘘・それぞれの過去と未来・すれ違う二人の気持ち・もどかしいすれ違い・濃厚な男女関係・幸せな結婚・友情・家族愛・夫婦・親子の絆・仕事・濃密な人間関係・こじらせ・心の綾・コンプレックス・スローバーン・魅力的な相手・いい人・自分と向き合う・心に響く前向きな言葉・人生を変える選択と決断・感情の言語化・忘れられない初恋・自分らしさ・約束
ジャンル:中華ファンタジー・切ない恋愛小説・じれったい恋模様・溺愛TL・執着ティーンズラブ・女性向け異世界ライトノベル・歴史ものラノベ・感動ロマンス・大人のラブストーリー・温かいヒューマン・シリアスな話・心に染みる人間ドラマ・ロマンティックなエピソード・ドラマティックな展開・心に刺さる純文学風・心温まる幸せな結末・ハッピーエンド・大団円・心に残る希望の物語・ミステリー・謎解き・長編・中編・短編
・不器用な男女が自分自身と向き合い結ばれる文学作品です。過去に負った心の傷を抱える二人が自分らしい生き方について考える文芸作品でもあります。 ・自分らしく生きるとは、本当に大事なものとは何か探す成長物語です。また、どう生きたいか考えさせる文章作品でもあります。 ・複雑な事情を抱える登場人物それぞれの言葉にできない感情の変化や気持ちが変わる過程、心の揺れ動きをお楽しみくださるとうれしいです。
#電子書籍#書籍#単行本#新刊#読み放題#ベストセラー#Kindleアンリミテッド#物語#ラブストーリー#ヒューマン#ファンタジー#ミステリー#ライトノベル#tl#ティーンズラブ#おすすめ本#女性ホルモン#30代#giapponese
3 notes
·
View notes
Text
我が国の未来を見通す(81)
『強靭な国家』を造る(18)
「強靭な国家」を目指して何をすべきか(その8)
宗像久男(元陸将)
───────────────────────
□はじめに
2週遅れになってしまいましたが、8月15日、7
8回目の「終戦記念日」に感じたことをまとめてお
きたいと思います。
式典において、天皇陛下は「戦没者に対する慰霊、
人々のたゆまぬ努力によって平和と繁栄が築かれて
いること、さらには過去の反省と再び戦争を繰り返
さないこと」などのお言葉を述べられました。
岸田首相は天皇陛下と同趣旨の式辞の最後に「積極
的平和主義の旗の下で、国際社会と手を携え、世界
が直面する様々な課題の解決に全力で取り組む」
「今を生きる世代、これからの世代のために国の未
来を切り開いていく」旨の言葉を付け加えました。
細田衆院議長は「日本国憲法の精神を体して恒久平
和の実現に全力を尽くす」、尾辻参院議長は自分の
体験談を述べられた後に「犠牲となられた方々のこ
とを忘れない」「戦争を絶対に起こしてはならない」
と結びました。
8月のこの時期になると、日本人として戦没者に対
する鎮魂は当然としても、「平和」(「戦争」は起
こさない)という言葉がそこはかとなく“一人歩
き”をして、多くの国民をして、“こうして念仏の
ように「平和」を口にしておれば、「平和」が向こ
うからやってくる”という錯覚に陥らせている(思
考停止というべきか)と考えるのは、うがった見方
なのでしょうか。
15日当日、各政党の談話も発表されました。談話
の全文は読んでいませんが、新聞紙上に発表された
その要旨だけでも考えさせられるものがあります。
紙面の都合上、紹介する価値があると考える政党談
話のみをさらに要約します。読者の皆様は、ぜひそ
れぞれの番号の談話がどの政党の談話かを想像して
お読みください。ウクライナ戦争などの厳しい安全
保障環境に対する認識はほぼ共通していますが、当
然ながら、その後に続く主張は各政党によって違い
ます。
唯一の被爆国として、「核兵器のない世界」の実現
に向けて現実的・実践的な取り組みを進めていく。
必要な防衛力を整備しつつ、国際協調と対話外交、
多国間協調を深め日本周辺の平和を守り、地域の緊
張を緩和させる努力をする。
他国に侵略を思いとどまらせる抑止力の確保、我が
国の主権と国民を守り抜くために積極防衛力を抜本
的に強化、整備する。
核兵器による威嚇など現実の脅威にさらされている。
「核の先制不使用」の議論を、今こそ日本が主導す
べきである。
食料やエネルギーの自給体制の強化を含めて「自分
の国は自分で守る」という現実的な安保政策を進め
ていく。
二度と戦争に巻き込まれないために、国のまもりに
対する国民の意識を高め、抑止力の構築が現実的な
手段との認識が必要である。
これらから、どの談話が与党で、その与党の安全保
障・防衛政策に反対の立場を主張する野党の談話が
どれなのか、混乱し、考え込み、そして安堵し、ま
た呆れもしました。
安堵したのは、「日頃、色々反対しているが、案外
分かっているではないか」と感じた野党に対してで
あり、呆れたのは、「相変わらず、足元を見ないで
とぼけたことを言っている。それが本心なのか」と
思ってしまう与党に対してでした。
各談話の正解は、(1)自民党、(2)立憲民主党、(3)日
本維新の会、(4)公明党、(5)国民民主党、(6)参政党
です。
総括すれば、(特に与党に対してですが)「国会議
員であることをもっと自覚して、我が国内外に起き
ている様々な事象をよく勉強して���危機意識を持っ
て国の舵取りをしていただきたい」の一言です。
(6)の参政党の冒頭には「恒久的な平和は美辞麗句を
並べるだけでは実現しない」とありましたが、その
ようなことを国民に最も声高に訴え、理解を促す必
要がある与党が「保守」の看板を下ろし、「リベラ
ル」のような主張をすることは、我が国にとって決
して幸福なことではないと思います。百田尚樹氏が
「結党宣言」し、保守の論客諸氏がこぞって現政権
を批判する訳もこのあたりにあるのでしょうし、最
近の世論調査からすると、国民の多くも見抜いてい
るのでしょう。読者の皆様はどう考えるでしょうか。
▼我が国の「防衛力」の“急所”─同盟
気を取り直して本題です。本メルマガでもすでに紹
介しましたが、私は、愚書『日本国防史』((※)に
おいて、「我が国の歴史から学ぶ4つの知恵」をま
とめ、その筆頭に「孤立しないこと」を上げ、人も
国家も仲間を選び、失わないことの大切さを強調し
ました。
(※)『世界の動きとつなげて学ぶ日本国防史』
https://amzn.to/44xI30c
その内容を要約すれば、「日米同盟」の強化・対等
化、「日米豪印戦略対話(QUAD)」や「自由で
開かれたインド太平洋戦略(FOIP)」などを対
中国包囲網として同盟化まで引き上げることなどに
加え、本メルマガにおいても、貿易や食料・肥料な
ど経済的な“中国依存”から速やかに脱却すること
なども提唱してきました。
今回、改めて、我が国の「防衛力」の“急所”とし
ての「同盟」について考えてみたいと思います。た
だし、この「同盟」にからむ様々な論点を子細に紹
介しますと、本メルマガ数回分に及び、本来の「国
力」分析の視点から外れてしまう可能性もあります
ので、私の問題意識を簡潔に紹介することに留めま
す。
島田洋一氏は、自書『腹黒い世界の常識』(※)の
第1章冒頭に「同盟とは何か」と題して、「同盟は
一瞬にして敵対関係に変わる。共に戦う限りにおい
てアメリカは日本の同盟国だが、日本が中国に降伏
した途端、敵の戦略拠点として使われないよう、ア
メリカは日本を攻撃対象にしてくる。『血を流して
守る』以外に、『破壊して去る』という選択肢もあ
る。それが国際常識である」と述べています。
(※)
これまで、様々な戦争の歴史を勉強して、島田氏の
指摘のようなことがたびたび繰り返されてきたとい
う事実を知っている私でさえ、この文章を読んだト
タン、ハッとして背筋が凍りました。
我が国には、軽々に「中国が攻めてきたら、白旗を
あげればよい」と口に出す人がいますが、そのこと
は即、アメリカを敵にまわすことであり、最悪の場
合、アメリカの攻撃によって陸海空自衛隊の基地や
装備が攻撃され、国土が再び“焦土と化す”ことま
でを考えなければならないのです。
島田氏も実例として取り上げていますが、第2次世
界大戦において、フランスがドイツに降伏し、パリ
無血入城を許した時、イギリスはフランス海軍が
(海上兵力が弱点だった)ドイツ海軍に組み込まれ
ることを防ぐため、フランス海軍の艦艇を空爆で破
壊し、1000名を超える兵士も犠牲になりました。
このような経験を乗り超えてイギリスとフランスは
この後も同盟国として共に戦ったのですが、ある事
象や事件をきっかけにして「昨日の友は今日の敵」
になったことなども歴史上枚挙にいとまがありませ
ん。
さて、細部の経緯は省略しますが、1952年4月、
「サンフランシスコ講和条約」と同時に発効された
「日米安全保障条約」は、戦後の占領に続き、アメ
リカ軍による保護協定的性格が強いものでした。ア
メリカは、日本の再軍備を抑え込むと同時に、日本
列島というアジア大陸東側の戦略的拠点を敵対勢力
の手に渡さないことが目的だったために、NATO
のように「相互性」を持たない「片務性」で妥協し
たのでした。
1960年、激しい安保闘争の中で、より共同防衛
に近い条約に改正されましたが、憲法上の制約もあ
って、引き続き日本本土に米軍を駐留することを容
認しつつ、「片務性」もそのまま残存された形の
「軍事同盟」が継続されました。
この結果、日本政府は、我が国の安全保障の多くを
アメリカに担ってもらい、「軽武装・重経済」とい
われる経済発展のみを政策の最優先課題とすること
ができて、実際に高度経済成長にもつながりました。
そして、1983年、中曽根元首相のアメリカ訪問
時の「共同宣言」をきっかけに、「日米同盟」とい
う言葉が市民権を得ました。「日米同盟」は、“
「日米安全保障条約」を根幹とする日本とアメリカ
の間の包括的な協力関係”と定義され、安全保障・
防衛面だけでなく、政治、経済、社会など幅広い分
野において機能することを指しています。
以来、我が国は、ほぼあらゆる政策を「日米同盟」
を基軸にして立案し、実行してきました。一時、民
主党政権時には米中を絡めた「二等辺三角形」論も
ありましたが、そのような考えは長くは持ちません
でした。よって、歴代の首相をはじめ政治家、官僚、
有識者、それに私たち自衛隊関係者にあっても、
「日米同盟がなくなる」とか「日米同盟なき我が国
の繁栄」などについて、一瞬たりと頭をかすめたこ
とはないでしょう。
特に、防衛分野においては、戦争経験のない自衛隊
は米軍の豊富な実戦経験から学ぶことが多々ありま
したし、個人的な経験でも、在日米軍の高官たちと
親しく付き合って、お互いの信頼や友情を深めまし
た。
一方、高度成長の結果、一時は世界第2位、現在で
も世界第3位のGDPを誇りならも、防衛予算は
「GDPの約1%」にとどまり、「日米安全保障条
約」は、憲法上の制約を盾に「片務性」についても
今日まで手付かずのまま放置されています。
「同盟」を維持させるためにはそれ相応の努力が必
要なことは言うまでもありません。長年、日本の約
15倍、GDPの約3.5%に相当する巨額の軍事
予算を投入しているアメリカが、その大元が戦後の
対日方針にあるとはいえ、この状態に不公平感を持
つのは当然なのです。
2019年、トランプ前大統領が「日本が攻撃され
れば、我々は第3次世界大戦を戦うことになり、あ
らゆる犠牲を払って日本を守るが、アメリカが攻撃
されても日本は我々を助ける必要がない。彼らはソ
ニー製のテレビでそれを見ていられる」と「片務性」
を痛烈に批判し、話題になりました。
「この批判が何を意味するか」について、当時、ほ
とんどの日本人に理解していなかったと今なお想像
しています。実際、アメリカにおいては、憲法上、
条約の批准は上院の3分の2の賛成を必要とすると
の高いハードルがありますが、条約の破棄は大統領
の判断で行なうことができます。トランプ大統領の
発言はけっして脅しでもなんでもなく、大統領一人
の判断でいつでも条約を破棄することはできるので
す。
現在、「日米同盟」はアメリカの「国益」にも合致
しているし、これから先もそう願いたいですが、国
際社会を取り巻く“様々な情勢”が変われば、未来
永劫に「日米同盟」が継続される保証はありません。
大統領の判断一つで「昨日の友は今日の敵」になる
可能性を潜めていることを常に頭に置く必要がある
と私は思います。だからこそ、「自主防衛」を筆頭
にした「自助努力」が必要なのですが、それについ
ては後述しましょう。
▼我が国の「防衛力」の“急所”─同盟(続き)
今後変わるかも知れない、国際社会を取り巻く“様
々な情勢”についても触れておきましょう。前回紹
介しました伊藤貫氏によれば、冷戦終了後、アメリ
カは、人類史上一度も実現されたことがなかった
「世界一極体制」を創ろうとの野心と自信をもって
様々な外交を展開しました。その特徴は、アメリカ
を例外的に優れた国とする「アメリカン・エクセプ
ショナリズム」をもって、国際政治にアメリカの政
治制度や経済システムを採用させようとし、それに
抵抗する国々は、裁き、処罰し、時には破壊しまし
た。実際に、冷戦終結直後の1989年の「パナマ
侵攻」以降、アメリカが関与した世界の紛争は17
紛争を数えます(『習近平が狙う「米一極から多極
化へ」』遠藤誉著より)。
アメリカのこの「新外交理論」は一世を風靡し、日
本人の中にも「熱心な信者」を輩出しましたが、2
0世紀になった頃から、中東地域、ロシア、中国、
北朝鮮などが反旗を翻すなど様々な厄災が表面化し
て、ほころびを露呈し始めてきました。なかでも、
中国、インド、ロシアなどの台頭は、「一極体制」
を形なきものにして、「多極化」に拍車がかかりま
した。
そのような状況から、オバマ元大統領の「アメリカ
は世界の警察官ではない」やトランプ前大統領の
「アメリカン・ファースト」の発言などにつながり、
このたびの「ウクライナ戦争」をもって、「世界一
極体制」はその原型を留めることなく、世界は「多
極化時代」、というか「分裂の時代」に再突入した
と考える必要があるでしょう。現に、スウェーデン
にある「民主主義多様性研究所」によれば、今や世
界人口の72%に相当する57億人が「専制主義的
(権威主義的)な傾向の強い国」に住んでいるとの
ことで、これらの国々はアメリカが提唱する政治制
度や経済システムに与することをかたくなに拒否し
ているのです。
基軸通貨である「米ドル」についても、近年はユー
ロや人民元に押され、外貨準備高の約60%はドル
建て資産といわれながらも、国際決済においては4
2%に留まっているなど脱ドル化が進み、将来はそ
の地位が危ぶまれる“様々な現象”が発生するとの
予測もあります。
さて話を本題に戻しましょう。このように、将来
“混とんとした国際情勢”になることを予想せざる
を得ないなかにあっても、なおかつ「日米同盟」は
盤石で、その延長で“アメリカの「核の傘」は有効
と断定できるのか否か”を議論する時が来たのでは
ないかと考えるのです。
これまでのようなアメリカであれば、水戸黄門の
「葵の紋所」のように、それを見せるだけでひれ伏
す国はあったとしても、これから将来はその“効き
目”があるのか、逆に、アメリカが「葵の紋所」を
“出し惜しみ”するような情勢は来ないのか、など、
それらの想定を「もしかして」の範疇として捉え、
最も大事な「我が国の抑止力は大丈夫なのか」につ
いて、しっかり議論すべきなのです。
前回、中国や北朝鮮などは、自国の犠牲回避を最優
先しない可能性があることに触れましたが、差し伸
べてもらった「傘」にも問題があるとすれば、過剰
な依存を止め、逆に相対的な力関係を補い、より盤
石な抑止力を構築する上でも、(それぞれ微妙に違
う)イギリスやフランス、そしてドイツの抑止戦略
などを研究しつつ、我が国独自の「自主防衛」につ
いても検討する時期に来ていると考えます。
かつてのアメリカは、「日本の核武装は力づくでも
阻止する」との勢力が大半を占めていたものから、
キッシンジャー、ウォルツ、ホフマンなどのリアリ
スト戦略家たちのように我が国の「自主防衛」を容
認する勢力が増えつつあるのは、それが日本の「国
益」に留まらず、アメリカの「国益」にもつながる
との認識を持っているからなのです。
まさに、“時代は変わりつつ”あります。冷静沈着
に「あらゆる戦争を抑止するために、我が国の防衛
をどうするか」についてタブーを廃して、真剣に考
える時期に来ています。
令和6年度防衛予算の概算要求は過去最高の7.7
兆円だそうで、これによって通常戦力が増強され、
陸海空領域に加えて「宇宙」「サイバー」「電磁波」
に至る「領域横断」を強化する方向に舵を切ってい
るのでしょうが、これだけでは、あらゆる「戦争」
の発生を未然防止するのは困難と考えます。不確定
で、かつ厳しさを増す情勢を目前にして、ここで思
考を断ち切ることは、冒頭に述べた、念仏のように
「平和」を願うことと“大同小異である”ことを悟
る必要があるでしょう。
▼我が国の「防衛力」の“急所”─「足かせ」にな
っているもの
最後に、「防衛力」の“急所”として「足かせ」に
なっているものついて触れておきましょう。
先般のNATO会議において、東京事務所の開設に
ついては、フランスの反対もあって実現しませんで
した。NATO加盟国は、1949年に署名された
「北大西洋条約」の条約第5条において「一方の加
盟国が武力攻撃を受けた場合、他方の加盟国も共同
して自衛すること」と定めておりますが、これは
“一方への攻撃は全員への攻撃とする”「集団的自
衛権」の原則そのものの適用です。
「日米安全保障条約」は戦後の特殊事情によって
「片務性」が容認されましたが、NATOへの加盟、
あるいはNATOの東アジアへの拡大を企図すれば、
もはや「片務性」は容認されないでしょう。
第1次世界大戦時、「日英同盟」下にあった日本に
対して、イギリスから日本の参戦について再三の要
求がありましたが、日本は「国防の本質を完備しな
い外征はなじまない」と「参戦地域の限定」に執着
し、海軍の特務艦隊の派遣を除き、陸軍の派遣は拒
否しました。そのことが、のちの「日英同盟」破棄
につながったという“前歴”があります。
もし、東アジア地域で何かあった場合、NATOの
支援を得ることを期待するなら、もし欧州で何かあ
った場合に、自衛隊を派遣することを“拒否できな
い”ような「枠組み」を求められるでしょう。その
ためには、現在、憲法上、「権利はあるが、行使で
きない」としている「集団的自衛権」を行使できる
ように解釈を見直すか、憲法そのものを見直すか、
他に方法がありません。
そのよう制約は、冒頭に述べたQUADやFOIP
を実質的同盟のレベルまで引き上げる場合、あるい
は8月18日に合意された「日米韓安保協力」をさ
らに盤石なものにする場合でも同様でしょう。
いよいよ戦後80年近く、かたくなに守り続けてき
た憲法、さらにはあの手この手を使い、屁理屈をつ
けつつ、潜り抜けてきた憲法解釈や現憲法のもとの
防衛政策が限界に来ているということでもあり、
“見切りをつける”時が来たということではないで
しょうか。
その決断こそが、我が国の「国力」を維持し、憲法
でいう「国際社会において名誉ある地位を占める」
ための唯一の道なのです。皮肉と言えば皮肉ですが、
それが現在の我が国の置かれた立場であり、これま
での“ツケ”の集大成こそが将来に向けた生存の道
であろうと私は考えます。
軍事力(防衛力)についてはひとまずこのぐらいに
しておきましょう。次回は、本メルマでもすでに取
り上げた「食料・天然資源」を「国力」の要素との
観点から再度取り上げ、その後、「政治力」につい
て素人の立場ながら「何が問題なのか」について迫
ってみます。
(つづく)
(むなかた・ひさお)
2 notes
·
View notes
Text
2023/08/26
BGM: 大江千里 - 夏渡し
今日は早番だった。昼休み、いつものように詩を書く。天気がとても良かったのだけれど、こんな天気のすばらしさも明日になれば忘れてしまう。それを記録しておきたいという思いを詩にこめてみた。井上陽水「少年時代」を聴き返しつつ木曜日(月末の31日)のプレゼンテーションのための資料をチェックする。最近翻訳を試みてみたルイス・キャロルの詩、あるいはぼくが好きな井上陽水や大江千里の詩についても(もちろん著作権に気をつけて扱う必要があるにせよ)話せればと思い始める。仕事が終わったあと歯科に行く。そこでふと、今日は24時間テレビの日だったことを思い出す。歯科のモニターで錦鯉の2人のネタを見ていて、ふと「『これからだ』と自分が本気を出して生きたのはいつだっただろうか」と思い始める。いつも書いているが、あの酒に溺れていた時期は自分なりに無我夢中で「自分はこんなところでは終わりたくない」「何が何でも勝利者になるんだ」と思ってもがいていた。あの時期はそれでも酒に勝てず、まだ「最大公約数的なものではない、『自分がほんとうに思う』幸せ」というものが何なのかもわかっていなかった。だからずっと何か書いていてもとにかく「プロデビュー」して「名を売ろう」とばかり考えていたのだった……。
最近になって、松下育男が書いた詩や講演集を繰り返し読むことが増えた。彼の言葉はまるで良質なジャズやブルースのような、まろやかに感じられるぬくもりや優しさがある。そして同時に毅然としたポリシーと厳しさも備えられた、奥が深く滋養があるものだと思う(もちろん、喩えに出した音楽はあくまで「ぼくにとって」の話だ)。とりわけ昨日だったか読んだ「詩人のデビューとは」という文章から、ぼくはあらためて「きみはなぜ詩や文章を書くのですか?」という問いかけをもらったような気になった。そして、この問いは「なぜ生きるのですか」「なぜ読むのですか」といった問いと同じでシンプルで、だがいざ本格的に答えようとするととてもねばり強い思考が必要となるたぐいのものでもあると思った。ぼく自身、過去のことを思い出す……20代・30代は「まあ、若かったからなあ」で終わるかもしれないけれど、すでにいい年した40をすぎても「一攫千金」「人生一発逆転」なんて考えて小説を書いていたことを思い出す。自分の書くものは絶対に読まれる、受け容れられてヒットする……そんなたぐいの「自信」だけはあったのである(それを思うと、人は「自信を持って生きること」よりも「自信がなくても虚心に、目の前のことに堅実に取り組んで生きること」の方が大事なように思う)。
そこで見失っていたもの。それはつまり「書くこと」「語ること」、そしてそれが他者に「受容されること」について感謝することではなかったか。平たくいえばそうした「話す・書く/聞く・読む」といった関係で相手(聴衆や読者)とコミュニケーションを取ることの楽しさや��りがたさを見直すことだっただろう。ぼく自身がそんな「一攫千金」マインドから変わったなと思うのはたぶん断酒会に通わせてもらうようになって、そこでさまざまな方に自分の体験談を自分なりに嘘偽りなく話すことを始めたからだ。そしてそれと同時期に発達障害がらみのミーティングに参加させてもらって、そこで料理やライフハックなどの披露を通して「やっちゃいました~」と恥をかいたりして……そうして「ああ、確かにぼくは受容されている」と思い始めて、そうなるとあれほど肥大していた承認欲求も消えてきたのである。いや、いままったくそんなものと無縁に書いているなんてことは言わない。いまだってどこかで「ぼくの書いたものがもっと読まれてバズらないかなあ」なんて子どもじみたことを考える。なんなら、「いまだって」考えている。「これからだって」そんな夢想を抱えつづけて生きるだろう。ぼくはこれからの一生をきっとこうして(たとえお金にならなくても)書きつづける。
それはそれでぼくの人生なのでぼくが責任を取ることではある。でもその人生を決めるのが「プロデビュー」や「名を売る」といった他者の評価に相当に依存した判断基準・価値基準のままだったならば、ぼくは一生「こんなはずじゃない」「おれはもっとビッグになる(なれる)」と思いつづけて生きたかもしれない。そしてややもすると「なぜ世の中は認めないんだ」「世の中間違っている」と考えてしまい、そのまま繁華街なりデパートなりで包丁を振り回して暴れる……なんてこともありえたかもしれない。そんなことを思うといまこそ幸せなのかな、と思う。書きたいものを書き、そして出てきた自分の言葉と日々向き合い、そこに変化を見出し、「自分はともかくも『止まってない』し、そのまま『腐って』もいないのかな」と思えるからだ。ただ、それを「自分は成長している」とも言いたくない。いや、言いたいけどそう言ってしまうと「手前味噌」というもの。ぼくの書くものは傍から見ると「そんなに退屈なことを毎日毎日書いて何が楽しいの?」な話なのかもしれない。そして、それもまた客観的な評価として「妥当」「実に的確」でありうるから面白いと最近は思うようになってきたのだった。いや、そうだとしてもぼくは炎上沙汰になるようなキャッチーなテーマを探して書くなんて芸当はできないので、明日もこんなことを書くつもりだけど……。
2 notes
·
View notes
Text
書物礼賛⑦

アンナ・レンブケ/ドーパミン中毒/新潮新書2022・原著2021
「ブプレノルフィンをやめようとは絶対に思いません。私にとって電気のスイッチのようなものです。ヘロインをやらないようにしてくれるだけでなく、私の体に必要なもの、他のどこでも見つからないような何かを与えてくれるんです」。長期的に薬物を使用してきたことで、彼の快楽と苦痛のシーソーはこの先ずっと「普通」の感覚でいるためだけにオピオイドを必要とするほど壊れてしまったのだろうか? 長い期間「断つ」ようにしてもなお、ホメオスタシスを回復できないほど脳の可塑性が失われてしまうことはあるのかもしれない。
(中略)私が1990年代に医学部に通い、研修医として勤める中で教わったのは、糖尿病を持つ人が充分なインシュリンを分泌できない膵臓を持っているのと同じように、うつ病や不安神経症、注意欠陥、認知的歪み、睡眠障害などがある人は望むように働かない脳を持っているということだった。私の仕事はその説によると、足りない化学物質を何かで補って「普通に」機能できるようにすることとなる。このメッセージは製薬会社によって広く流布され、非常に広範に展開されて、医者も患者である消費者も同様にそれを信じるようになった。
(中略)何年にもわたって多くの患者を診てきて、精神科の薬を飲むと苦痛な感情から��一時的に逃れられるが、自分が感じられる感情の幅が狭くなった、特に深い嘆きや畏怖の念といった強力な感情を感じる力がなくなってしまったと言われることがあった。(中略)「オキシコンチンを使っていた時の妻は、音楽を聴くこともやめてしまいました。しかし薬から離れて今は再び音楽を楽しむようになりました。私にとってそれは自分が結婚した人が戻ってきてくれたと思えることでした」
記述はわりとマトモながら、総花的で浅く、いかにもメディアに出ている女の精神科医・大学教授の本。「制度」の側にいる人物。強欲と堕落に覆われたアメリカ、オピオイド禍と絶望死、その背景にある教育と医療制度の腐敗。それらは一朝一夕に作られたものではない。福音派もシオニストロビーもコツコツ支持基盤を固め、自分が不幸と思い、救いを求める人を増やしてきた。対症療法には意味がない。ホメオスタシス(恒常性維持)=苦痛と快楽は脳の同じ部位で処理されるため、薬物などで一方を貪ると、自律神経・免疫系・脳の報酬系が異常をきたし、快楽より苦痛が長引く、それがまさに麻薬・オピオイド禍の本質なのだが、メカニズムの多くは未解明。ロケット爆発させてる場合じゃないんだよ。
上野庸平/ルポ アフリカに進出する日本の新宗教 増補新版/ちくま文庫2024・原著2016
日本の神道は、先進国の主要な宗教文化になったという意味で世界的に非常に稀有なアニミズム・多神教の一種である。崇教真光はそれをベースにし、キリスト教の聖書やイスラム教のコーランと同じような定まった経典「御聖言」と実益的な宗教実践「手かざし」を持つにいたった。 外来宗教であるキリスト教やイスラム教は教義がしっかり定まって「人間が生きていくための正しい教え」として非常に洗練されているが、西アフリカ伝統のアニミズム・精霊信仰にはある祖先崇拝や呪物(お守り)の考え方が存在せず、呪術的要素もさほどない。他方、西アフリカ伝統のアニミズム・精霊信仰は教義が定まっておらず、あまり洗練されていない。こうした西アフリカ人のスピリチュアルなニッチを埋めたのが神道というアニミズムをベースにし、経典を持つまでに発展し、さらにキリスト教やイスラム教を統合する万教帰一主義的価値観を持っている「真光」だったのである。
引用した崇教真光や幸福の科学・真如苑・創価学会といった日本発祥の新宗教、ラエリアンムーブメント・統一教会という日本発祥でないが日本人が布教に携わっている、それぞれいかにアフリカを攻略し、受け入れられているのかを実地にルポした労作。創価学会と日蓮正宗は当地でもいがみ合っているとか、幸福の科学は宣伝にお金をかけているが言葉・記号に頼って宗教的イメージ性が貧弱なため集客に苦戦しているとか、ウガンダ、コートジボワール、ガーナ、マリといった国々の事情と併せ興味本位にとどまらない味わい。
秋山駿/簡単な生活者の意見/講談社文芸文庫2025・原著1988
それより私は、自分の生の感覚の中で、この社会の声を読んで、こういっておこう。現在の社会は、無力な者、貧乏人、役に立たぬ者、それから不運な者には、一刻も早く人目につかぬよう隠されて死んでくれ、と、いっているのだということを。
私はふと、こんな空想に走る──。
長くもない年月のうちに、われわれの周囲で、つまりこの社会の��る処で、小さな爆発や小さな戦争が多数に生ずるであろう、と。
そうでなければ耐えきれぬほどに、この社会は、異質な存在の不合理な共存に緊張し過ぎている。つまり、矛盾の高圧下にある。早い話が、石油やトイレットペーパーを境界にして、それを入手出来ずうろうろしているこちら側と、その企業の管理者であるあちら側の人間とが、同一の内容の人間、少なくとも、同一の生の平面上に立っている人間であるとは、私には考えられない。たぶん、その心理、感情から、人間の意味ということも、良心も、それから正義の内容に到るまで、何から何まで違うであろう。
私は彼等と同一の人間の姿でありたくはない。彼等と笑い合いたくない。彼等と握手したくはない。それでは、彼等は私の敵なのか。いかにも、そうかも知れない。敵? だがしかし、彼等の姿は、私がその一人一人を心の壁に密かに記しつつ憎むためには、あまりにも遠い存在なのだ。だからやはり、私の生の感覚から、いっそう正確には、バスカルの言葉をわるくもじって、こういうべきだろう。──彼は川の向うに住んでいる、と。
著者は「うまいそば屋も喫茶店もない、本当の古本屋もない」とぼやきつつ、「敗戦時の社会の混乱こそ、私の生の原点であり、以来国家的な体制を信じていない、そうした生の感情に団地の生活意識が合う」として、ひばりが丘の団地暮しの雑感を綴る。実家とは疎遠。
1930(昭和5)年生まれで、私の父母よりわずかに上の世代。私が父母と幼稚園から小6途中まで暮らした横浜郊外の団地は、文化的にはともかく「民度」は東京幡ヶ谷より高かった。分断や混乱の気配はない。家族の最も幸せだった頃。その安心を私に与えてくれた親のことを思うと、いくら敗戦を経たからといって、著者の傍観者的な態度に違和感。自分は「あちら側」とは別ってか。いや全員一枚岩になるよう仕向ける世間という管理装置がはたらいて、軍国主義をそのまま経済高度成長に振り向け、そしていま同じ事情で国力が相対的に沈んでいる。スマホ等による時間管理の時代に、みな同じ方を向いて平均化されている日本人は生産性を発揮できない。自分は違うつもりの著者は「文壇」に居場所を得て、そうした構造問題に踏み込まずに「批評家」でいられたのでは。文章巧みでも学ぶものはない。
水木しげる厳選集 虚/ちくま文庫2024
横浜団地時代の私に最大の文化的影響を与えてくれた、管理事務所に設けられた、日曜のみ貸し出しを行う小さな図書室で出会った本たち。北川幸比古のSF絵本『宇平くんの大発明』、そして筑摩書房による大人を意識した漫画本、特に現代漫画⑤水木しげるは貸本時代の『悪魔くん』をダイジェストで収め、粗い絵柄に加え、全貌が見えないことでいよいよ神秘的であった。
その解説で鶴見俊輔は「庶民の生活思想の伝統に根ざす虚無主義。長いものには巻かれろの権力追随をねずみ男が代表し、虚無主義の権力批判・引きずりおろしを鬼太郎が代表している」と水木さんの作風を評しているが、ぜんぜん違うと思うね。
この文庫本にも入っている「錬金術」のような皮肉な話、あるいは『河童の三平』の祖父や本人まで死んでしまって決して帰ってこないことを表面的に捉えているのでは。根本には、人智を超えた自然界の生命現象への畏敬、失われた、もしくは目に見えない世界への哀惜、水木さんほど生命を重んじている作家はいないと思う。手塚治虫と対照的なその資質が最も表れているのが貸本時代の短篇「サイボーグ」。近年の衝撃的な読書体験。その再現を期待した本書には、似た系統のお話が多く、互いに印象を弱めている。現代漫画⑤は完璧だった。
橋本昇/追想の現場/鉄人社2025
大韓航空機撃墜・パリ人肉事件・成田三里塚闘争・日本赤軍・赤尾敏・梨本勝…。フランスの写真通信社sygma (現在はgetty images)の契約カメラマンとして昭和・平成の数々の事件事故現場に立ち会った著者による回想録。ほとんど忘れていたような事象が多く、右でも左でも政治的にはニュートラルな立場で扱う趣旨ということで、しみじみ懐かしい気持ちになったが、それにつけても誤字誤植の多さ。書架の良いところには置けない。
ちなみに日航機123便の事故についても現場の凄惨さが描かれているが、いわゆる「自衛隊機が誤射云々」の陰謀論が成立する余地があるとは思えない。それと「ザイム真理教」、2つの陰謀論を流布しながらも晩年まで愛されキャラとしてメディア露出を続けた森永卓郎氏に、テレビ・ラジオに触れる層の情動を刺激しつつ、主流派に影響を与えない絶妙なポジション、しかも息子にそれを譲る、体制側に都合の良いピエロという墓碑銘を贈りたい。
0 notes
Text
七年振りに推しに会ってきた話 〜ミューズとしての道重さゆみ〜
先週の日曜日、私は名古屋近郊にある小さな町へと出かけた。
芸能活動引退を表明している推しのアイドルに会いたかったからだ。
その町のショッピングモールで、彼女の最後のCDのリリースイベントがあり、新譜の予約と引き換えに至近で彼女と接する機会を得られるのであった。
彼女はモーニング娘。の6期メンバーとして2003年にデビューし、リーダーを経て、2014年秋に卒業。芸能活動を休止。その後、2017年にソロとして活動を再開し、歌手やモデルとして活躍。2023年には強迫性障害の診断を受けたことを公表し、制限しつつも活動を継続していたが、ついに今夏のツアーをもって22年の活動の幕を引くと発表した。
引退を知ってしまった以上、せめて一目でもと思うと矢も盾もたまらず、強引にスケジュールを組んだのであった。
改めて振り返るに、彼女が私の人生において突如として「推し」となったことに、特段大きなきっかけがあったのではない。
就職を前にした2012年の春、友人に誘われモーニング娘。の大阪公演を一般客の一人として見たことがきっかけだった。
三次元のアイドルに興味などなかった私であるが、ステージの眩さとファンの熱気を目の当たりにし、一挙に引き込まれた。
第一印象は、多幸感で満ちた女の園、という感じだった。魅力的な女性たちが一つのグループとして歌い、踊る、その眩さ。互いを、そして舞台のあちらとこちらとを一つに繋ぎ合わせるように生き生きと動き回っていることの新鮮な活力に驚いた。それは私の全く知らないキラキラとした世界だった。
最初は単に彼女が私の割と好きな顔立ちだったからなのかも知れないが、彼女の表情を目で追っていると、楽曲に合わせ表情を作り、それを透徹することで世界を作っているように感じられるようになった。
私はそこに痺れた。
そうして道重さゆみさんは私の初めての推しとなった。
今でもそこに痺れ続けている。
さて、ちょうどその春公演で先輩方が卒業し、モーニングは道重新体制となった。
ハロー!プロジェクト自体がそれまでの『所謂』アイドルから、現在のアイドルシーンへと続くかっこいい路線、プロフェッショナル路線へと舵を切り始めた時代の境目だった。逆に当時のメンバー構成だったからこそ、それが可能だったと言えるかも知れない。成功とは必然に見えるものだから。そして結果的に、必然に導かれ、さゆも、モーニングも人気がどんどん高まっていった。
彼女の功績については、2014年頃のネット記事を参考にされたい。
あらゆる論者がさゆのリーダーシップと魅力、それを支える努力を称えている。
2年半をかけ、一度は失速したと思われたモーニング娘。は再びアイドル界での地歩を着実に固め、更にさゆの卒業後も残されたメンバーたちによって一層強固な地位を築いていった。
話を戻して、さゆの卒業発表は、2014年の春頃だったか、休日を無為に過ごす私の元へ、突如舞い込んできた。
余りに唐突で、今思い返しても白黒になってしまった部屋の風景と、全く違うのにその日がエイプリルフールかどうかを必死に考えていた混乱ばかりが浮かんでくる。
余りに劇的な卒業公演は仕事終わりに遅刻しながらも映画館のライブビューイングで見届け、泣き、後日円盤(ライブDVD)を見てまた泣いた。
さゆを失った中でも日常は続き、私をモーニング娘。に引き合わせた友人の誘いでさゆ不在のモーニングの公演へ通い続けていた。最終的に12期メンバーの一人をまた推すのであるが、その気持ちがさゆへの気持ちとはまた違っている事に気付いた。
その頃には一方でさゆも「再生」していたので二人について色々考えていた。
彼女らに私が抱く、二つの異なった「推し」の形の差異を明らかにしたく、「ミューズとしての道重さゆみ、ロールモデルとしての尾形春水」というブログを書きかけたのだが、当時は冷静になれず、失敗してしまった。最後まで書き切れなかったのだ(ただ、リンクを張るために記事を探して読んでみてびっくりした。上に書いてきたようなことはこの頃もう既に書いてあるではないか。そして「ロールモデルとしての尾形春水」は後日書き上げてあった)。
今書くならどうだろう、例えば次のように表現してみる。
---道重さゆみには可愛さ、あるいは美に対して絶対的理想がある。そうなりたいという願いが彼女を形作っており、我々は彼女を通して彼女の理想を一緒に探している。舞台に上がったさゆは、確固とした可愛さ/美の概念と、それを追う現実の身体性との重なりであり、その姿は擬人化された神、即ちミューズとして我々にインスピレーションを与え、彼女を輝かせている。
短いが意外に上手く表現できているのではないかと思う。
特に、さゆの言う可愛いは自分の外にある感じ、が私の表現したかったことの全てなのかも知れない。
その飽くなき追求が、彼女の深みであり魅力なのではないだろうか。
細かい論は先の書きかけのブログに譲るとして、それも畢竟このイタリック体で今回書いた文章の修辞となるのだ。
と、そこまで大仰に書いておきながら、私は「いい」ファンではなかったと思う。
元々、私は私の現実を生きているという気持ちも強く、諸々の制約の中で、全てを賭してファン活動にだけ人生を捧げることはできなかった。
加えて、「再生」公演後に当たる数年間は何度も環境が変化し、以前のような気持ちでファンとして接せられず、気持ちが合わなくなっていた。
さゆのことを神格化し過ぎていた、いや、さゆ自身ではなく自分の応援の仕方に潔癖過ぎたのだと思う。さゆを応援するならこうしたい、という気持ちの通りに事が運ばないのなら、最初から諦める、というような次第で。
諦めることが増えると、今でも界隈で有名な「強い」ファンには妙な劣等感を覚えるのだが、要はそういう見知らぬ(しかし私がいた「現場」にもいたはずの)誰かと比べて十全に楽しめていないような気がして辛くなる。
そういう人は当然ファンクラブ会員で、日本中で行われるイベ��トや公演に全通(全て参加すること)し、グッズを揃え、何組もCDを購入し、メディア露出は必ず抑え、ブログとインスタとツイッターとユーチューブとその他諸々の記事は余さず目を通す。私にはそういう類のことはできなかった。
私には私なりの応援の仕方、楽しみ方しかできなかった。ペースを上げて義務のように、或いは中毒のような応援をすることは私らしくはなかった。だからといって好きな気持ちでは誰にも負けないのに…とずっとおかしな悔しさがあった。
ただ、今になって、そういう特定の層を含むたくさんのファンたちがあって、おかけでさゆは活動し続けることができ、私が7年ものブランクを経ても会いに行けたのだということだった。たくさんの人たちがさゆを好きで良かった。やっとそう思えた。
そろそろ今回のリリイベの話をしよう。
朝から並んで新譜の予約をし、イベントの整理券を無事入手した。
物凄い強運でステージに近いかなり前方で舞台に相対することとなり、さゆの登場を待ちながら、期待と不安を感じていた。久しぶりの生さゆみんは楽しみとして、しかし実際私は何年ごしに目の当たりにして、過去のようにさゆの魅力を感じられるのだろうか?この数年の間にお互いが過ごして来た時間は全然違う種類のもので、それは私の感受性にも大きく影響しているのではないか?懐かしいとしか覚えなかったり、或いは感じる所が何もなかったら?遠い世界の事のように思えたら?さゆのことは綺麗な思い出のまま封印していた方が良かったのではないか。ピンクのメンバーTシャツを来て、サイリウムを持って、形ばかりではないか?
そわそわとネガティブなことを考えていると、スタッフが開演を案内し、さゆが登場した。
私は全てを忘れた。
私はさゆを覚えていた。
ソロで歌い踊るさゆの全てが最高だった。
メンバーTを着てサイリウムを振って手拍子しして見様見真似で振りコピして合間には「さゆー」と叫んだ。
さゆのいる30分はさゆのいない7年間よりも長かった。
月並みだが、来てみて良かった、その一言に尽きた。
さゆは私の憧れのままであった。
3日経ってもまだ夢のようで、昨日のインスタライブもリアタイ(リアルタイム)で楽しみ、アーカイブも何回も特にトークの場面を繰り返し再生した。
なんでまあこんなに可愛いのかこの人は…。
同じ89年の13日産まれ、というのが個人的に拘りのある部分で、さゆが7月で私が3月なので学年も違うし他の人からするとどうでもいいことだろうが、強烈なシンパシーを抱いている。
今月はまだ一歳違いだけど、次のライブでは同い年になっていて、そう言えば娘。時代もこのタイミングを跨いでコンサートがある度、何回でもそれが嬉しかったのだった。
本当は最後の最後まで全てを見届けたかったけれども、遠征は私の環境では現実的ではない。
それはもう受け容れるしかなく、しかし最終公演の円盤が出るまでがラストツアーだと思って、きっと泣いてぼやけてしまうだろうけれど、さゆの幸せを願って送り出せたらと思っている。
最後に。
この度の道重さゆみさんの引退は、彼女の心身の健康に関わる問題であり、惜しむ気持ちはあるものの、その決断は絶対で、一ファンには口を挟む権利はない。私もさゆとは少し違うものの、参っていた時期があり、色々察する所がある。
しかし、たくさんの月日がさゆを癒した暁には、もう一度私たちの前に現れてくれる日も、もしかするとあるのではないか、という期待はどこかに残されている、と信じている。
迂遠な物言いをしたワガママに過ぎないが、ファンとして、名残惜しさの余り少しの希望を残しておくことを自分には許したい。
ただ勿論のこと、その願いが叶わなくとも、私はさゆを責めたりはしない。むしろ、「再生」以降のソロ活動という、ボーナストラックの如きさゆとファンだけの純粋な時間を一度でも(と言って何年もあった訳だが)用意してくれたことへの感謝しかない。
私の永遠のミューズが、大好きなさゆが、きっとどこかに存在し、今日も可愛いぞ、と自分に満足しているのなら、それでいい。
1 note
·
View note
Text
パンクとは音楽のジャンルを指す言葉ですが、そこから派生して人の生き方、思想、哲学までをも含む、非常に懐の深いものです。パンクを定義することは、とても難しい試みです。なぜなら、百人いれば百通りの定義があるからです。グーグルで検索してウィキペディアを見てみても、本当の答えは書いてありません。自分で考えて、自分なりの定義を見つけるしかありません。
『クソみたいな世界を生き抜くためのパンク的読書』小野寺 伝助著
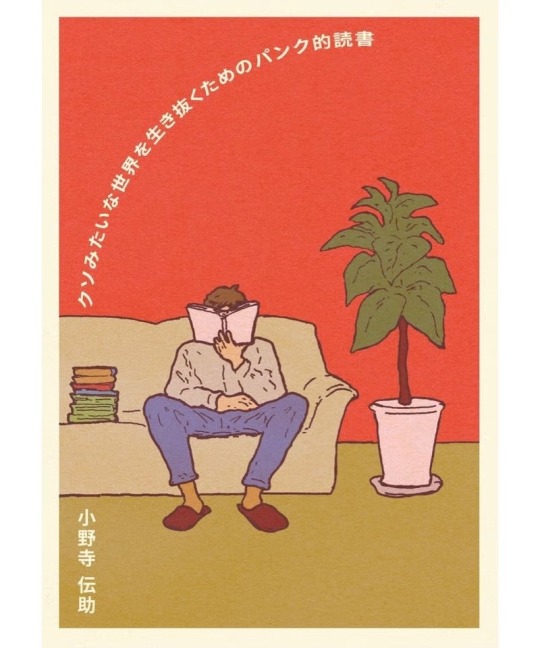
僕はこの公開日記『Pat Sat Shit』で文章を書くにあたって、パンクマンという新たなオルターエゴを生み出した。本名の土井政司、闇に葬ったDJ PATSATに続く、第三の人格だ。基本的に本名以外は何らかのテキストを書くときに召喚するスタンド(『ジョジョの奇妙な冒険』参照)みたいなものなのだが、それぞれに明確な線引きが自分のなかにはある。
(土井政司とパンクマンの関係性)

他者から見ればどれも同じような文章に思われるかも知れないけれど、断じて違う。これについてはきっぱりと断言できる。どこが明確に違うのかについては言わない、無粋なので。それはさておき、パンクマンのパンクとは何か?前述の小野寺氏の言葉を借りれば「パンクには百通りの定義がある」とのことだが、僕の場合はもちろんパンク修理のパンクだ。要するに物がふくらんで破裂することの意味を指している。僕は自転車屋なのでお客さんが持ち込んだ自転車のパンクを修理することで対価を得て、生計を立てている。お客さんにとってはマイナスでしかないパンクという災いが、僕に賃金というあからさまなプラスをもたらす。通勤中、通学中、サイクリングの最中など、あ���ゆる局面でタイヤやチューブは不安に脅かされている。なにもかもが散乱した路面を走るのだから当然のこと、こればっかりはどうしようもない。路上の異物たちは常に限界突破しようと必死、虎視眈々と突き抜ける機会を伺っているのだ。過剰に突き抜けたいという彼らの強い意思は、いつの時代も底辺にこそ宿る。だから我々はもっと地べたを這いずるべきなのだ。足もとへの注意を疎かにして、あるのかないのかわからないような先の展望に色目をつかっているばかりに、あちらでプシュ、こちらでプシュ、そちらでもプシュ、といった具合にたちまち足もとをすくわれる。こうして不運にも愛車をパンクさせてしまった被害者が続出することで、街の自転車屋は自然と儲かるという仕組み、極めて下品な言い方に聞こえるかも知れないが、これについてはいまさら僕がどうのこうのいうまでもなく、自明のことだと思う。物事には表裏という魔物が憑依しているのだ。実際、この夏はウジのようにパンクが湧いた。1997年に発生した過去最大のエルニーニョに迫るほどの規模と言われた2023年のスーパーエルニーニョ現象、その異常な暑さによりタイヤの空気が膨張し、空気が抜けやすくなったり、強い紫外線でタイヤの劣化を早めてしまったことに起因する大量のパンクの群れ。愛車を引き連れて不承不承タラウマラの店頭に集う気の毒な客人たち。暑さも相まって、各自が俄かに殺気立つ。そんな彼らを迎え撃つは、チューブ研磨専用グラインダーとマルニVパッチ、ラバーセメントで完全武装したパンクマン、それすなわち僕である。ひと言でパンクと言っても、その表情は多種多様だ。まるで荒れた乾燥肌のように痛々しい横顔の摩耗パンク、『ハイキュー!!』の宮侑/宮治のようにハの字に仲良く並んだリム打ちパンク、ライトハンド草田と見まがう膨張パンク、ロンギヌスの槍に射抜かれた外傷パンク、見るも無惨、ネテロ会長の貧者の��薇(ミニチュア・ローズ)にあてられたかのようなバーストパンクといった具合に枚挙にいとまがない。当然それぞれに対処法は異なり、その都度「ぬぉぉ」とか「おりゃ〜」とか「んぐぐ」とか言いながら修理していく訳で、結果、この夏は前年対比で体重が8キロ減、利益は倍増となった次第。いや、だいぶ話が逸れた。
(想像しよう:外傷パンク)

(想像しよう:膨張パンク)
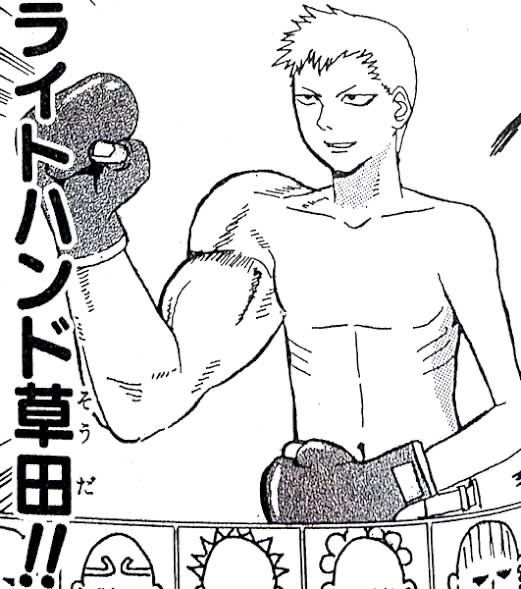
(想像しよう:バーストパンク)

とにかく世の中がある一定の情報、それに付随する質量や密度で満たされてきたら、その都度ガス抜きは必要だということ。疑いの余地もなく、あたりまえに満たされた感覚ほどつまらないものはない。穴が開いたらまた塞げば良い。どんなときにもあらゆる事態を想定して、遊び心を忘れないこと。小野寺氏が言うように、大切なのは愛とユーモア。それだけありゃ、なんでもできる!だから僕は今日もパンクマンを名乗り、このクソみたいな世界を自分なりに描写する。
パンクと聞いて真っ先に浮かぶのが『クセニナル』だ!
youtube
2 notes
·
View notes
Text
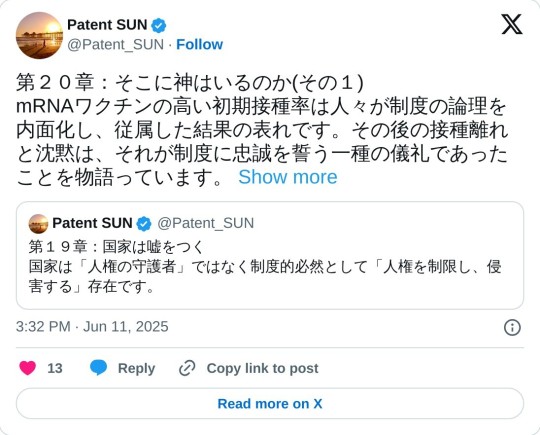
第20章:そこに神はいるのか(その1) mRNAワクチンの高い初期接種率は人々が制度の論理を内面化し、従属した結果の表れです。その後の接種離れと沈黙は、それが制度に忠誠を誓う一種の儀礼であったことを物語っています。 デカルトの「我思う、故に我あり」は自律の出発点ですが、同時に人間の内面が制度や信仰に呑み込まれ、自我すら明確に認識できなかった当時の風土的精神を逆説的に反映しています。 「我思う」は「全てを疑っても、疑っている私の存在だけは疑い得ない」という懐疑論に依拠しますが、これは「データを疑っても方法論だけは疑わない」という専門家と重なります。 今となっては「我思う」の語りも内実は制度の論理を内面化した結果の「制度が思わせている」であり、「制度にとって��都合のいい私」の宣言に過ぎないのかもしれません。 「制度が求める、故に我あり」という縮図は今も昔も何一つ変わらず、社会制度に組み込まれているのでしょう。 故に、倫理とは悲劇の記憶であり、制度とは記憶の忘却であると改めて銘記するのです。 私も制度の中に生きる限り、他律の論理から逃れられない存在です。希望を抱かぬ者に絶望もないと現実に立ち返ったとき、ある直感が私を思考の淵へと誘いました。 功利主義に神がいるのではないか。 功利主義は、啓蒙主義の時代にイギリスの哲学者ジェレミ・ベンサムによって体系化された世俗的倫理思想です。啓蒙主義は、神や聖典による超越的規範から解放された自律的主体の確立を目指し、理性と自然法則を価値判断の基盤に据える運動です。 功利主義は自律を放棄した他律倫理であり、実際には啓蒙主義とは矛盾します。 この文脈で功利主義は「ユーティリティ」や「最大多数の最大幸福」といった世俗的語彙を用いることで、従来の宗教的倫理に代わる新たな倫理規範を提示しました。 「ユーティリティ(utility:効用)」は、「功利主義(utilitarianism)」の語源であり、倫理を数的計算の対象として把握し、数的指標に基づいて快楽や幸福の最大化を目的とする枠組みを提供します。 私は、この功利主義が「神という語彙の物理的削除」には成功した一方で、思想的枠組みとしては、宗教的聖典からの脱却に失敗し、むしろ世俗的語彙に翻訳する形でその構造をそのまま継承した、と疑っています。 功利主義が行った構造転移は次の通りです。 聖典:功利主義 唯一神(超越的):ユーティリティ(超越的) 神の意思(超越的):最大幸福(超越的) 教義:幸福の最大化 信仰:制度従属 救済:社会発展・技術進歩 啓示:論文・データ・エビデンス 罪:非効率・逸脱・非優位 罰:制度的排除・犠牲 天国:理想社会 儀式:標準化された実践 預言者:専門家・科学者 祈り:目的達成への志向 これら全てはかつて聖典が応答していた問いの延長線上にあります。 私が与える命題は、「功利主義」は神なき時代の「聖典の偽装倫理」であり、語彙を置換しただけの「聖典性制度化宗教」ではないか、です。 ニーチェの「神の死」は、聖典からの離脱による超越的価値の崩壊と虚無の到来を意味します。しかし、功利主義はその虚無を埋める形で世俗の名の下に降臨し、「ユーティリティ」や「最大幸福」といった超越的価値を内包した倫理的座標軸を社会に再構築したのです。 「超越的」とは、他のいかなる価値や判断基準によっても相対化され得ない絶対的かつ最終的な目的概念を意味します。この概念が措定されると、これ以外の全ての価値や行為、制度的判断はその基準に照らして序列化され、結果として人間でさえもこの概念に従属させられる他律化構造が生まれます。 一方で、「宗教」とは、そのような「超越的」な存在や観念に係る信仰・儀礼・倫理を通じて、個人や社会の価値観・行動規範を形成・維持する体系を意味します。 もしある思想が超越的価値を中心に据え、それを実現するための制度的実践を持ち、人々の生活や判断をその軸で統御するのならば、それは語彙を如何に世俗化しようと「宗教」であることに疑いがありません。 宗教の構造が世俗的語彙によって倫理の体系に転移されたから宗教ではない、といった論理は表層的な語彙操作の域を出ないように思います。 功利主義は「聖典に対応する超越的価値」を備え、かつ「聖典が担う役割」を承継しています。そして、功利主義は、それを「ユーティリティ」、「幸福」、「エビデンス」などの世俗語で包み込むことで宗教的抵抗感を不可視化し、現代社会の文脈に沿う形で倫理的支配力を高めています。 社会が「ユーティリティ」を「神」であると認識するとき、功利主義は聖典の現代語訳として再翻訳されるのかもしれません。 この点で、ニーチェの「神の死」は実際には「偽装による神の構造転移」による「新たな宗教的権威の再構築」に過ぎないのではないか、という命題が更に投げかけられるのです。
0 notes