Text
Dtronics DT-7
DX7 をエレピ、ブラス、ベースとかじゃなくて、ドローンやパッド系で使おう、となると、もう自���製パッチでやるしかありませんので、ガチの自炊をやるなら外部エディターは必須、という事で Dtronics DT-7 を買った訳です。どうせ買うなら MIDI IN からの直接介入方式の方が操作性で勝るはず、と思って勢いあまってこれにしてしまったのですけども・・。

結論から言えば、初代 DX7 なら、ソフトのエディターを MIDI コントローラーで操作するのでも、あんまり変わらなかったかもしれません。というのも、初代 DX7 は内部の処理能力が大変遅く、DT-7 の摘みを回して音が出てくるまで、そこそこタイムラグがあるのです。初代 DX7 は sys.ex 経由で音を出しながらエディットするのが、そもそもできない作りなのでした(DX7ii の方はできるそうです)。摘みを回して1秒待って、それから音を出して確認するしかないという、何の為の直接介入エディターだったのか的な、そんな感じ。もっとも、ソフトエディターを MIDI コントローラーで操作すると、他にも問題が生じるという事なら DT-7 で良かった〜、という話になりますが、まあ、そこはもう試さなくて良いでしょう。自分、DT-7 でやっていきますよ。
あと、DT-7 は大変大きく重たいです。もっとコンパクトで DX7 のパネルにちょこんと置けるものかと思っていたら、それこそ P5rev4 desktop な��かを上回る大きさがあったりするので、別途机なりスタンドなりが必要になって、まあまあ困っております。
とは言え、DX7 本体のパネルスイッチと液晶だけでエディットしてても、例えば変な音が鳴りっぱなしになってしまった状態になった時など、原因のパラメーターを素通りしてしまい右往左往的な状況になりがちですから、当てずっぽでも摘みを絞ればだいたい音を止められるのは、大変ありがたいです。DT-7 に付いている LED 表示の数字も、DX7 のパラメーターを覚えていれば問題なく読めるようにちゃんと工夫されていますし、総じて、DX7 のエディットが随分楽になるのは間違いないです。
一方で、DT-7 を使って DX7 のエディットの全体像が把握できてしまえば、もう DT-7 は要らなくなるんだろうな的な感触もあったりします。それくらい DX7 は、使ってみれば単純なシンセなのでした。

DX7 で自炊する前までは、DX7 にはもう少し諸々の機能が揃っている前提で考えていたのですが、DT-7 で全体を見ながら使っていくと、結構色んな機能が削ぎ落とされているんですよね。例えばモジュレーターに掛けられる LFO があったら・・と自分は思ってしまいますが、初代 DX7 の LFO はキャリアにしか掛かりませんので、例えばドローン的な音を作って、そこでモジュレーターをウネウネさせるなら、DX7 で鍵盤なり MIDI からのトリガーでリズムを刻むしかないのです。ただ、鍵盤なりトリガーなりでリズムを刻んでしまえば、アンビエントのお作法とは別の世界が出来上がってしまうので、そういう意味で DX7 に「自由」はないのですよね。
DX7 は、そのアフタータッチ機能の豊富さから察するに、鍵盤なりその他インターフェースで旋律なり和音を演奏することが前提のシンセなのであろうと。つまり、あの時代の一流の���楽家と定義された人たちの積み上げた鍛錬に背く事を、ヤマハは望まなかったのだと思われます。ただ、やっぱりこの初期 12bit 独特の音は、これでしか出せませんので、アンビエント的な事で使うなら、そこは割り切って使うしかないと思いました。
で、これを使って DX7 で音を作っていると、1983年にそれまでのアナログシンセしかなかった世界にいきなり DX7 が登場して、ここから今までとは全く別の物語が始まるんだという、これが発売された当時にシンセ好きの人たち皆んなが持ったであろうその高揚感が、なんと自分の中で湧き上がってくるのでした。自分はこの数年の間に、古いアナログシンセをいじる的な順番を経てここに来ましたので、余計にそれを感じられているのだと思いますが、当時の人の気分を40年遅れて感じているというのも、すごい面白いです。もう少し掘ってみたら何かあるかもしれない的な期待感までもを、40年遅れて持ってしまっているのですよ。
youtube
もちろん、先人の方々と同じように深く掘っても何も出てきませんでした、という事も十分起こり得るとも思っていますが、それでもここは「敢えて」な訳です。初代 DX7 は、それまでのアナログシンセとは間違いなく別のベクトルを向いた楽器なのですが、そのベクトルが全くの正体不明なものではなく、何か別の本質に向かっているのかもしれない的な期待感を、やっぱり抱かせてくれるのでした。
これをドローンやアンビエントで使う人が殆どいないのは、先に書いたように旋律なり和音なりでリズムを刻む事でしかモジュレーターを動かせない所に由来しているような気はしていますので、自分は MIDI の演奏データを工夫する事でそこら辺を克服しつつ、アンビエント的な用途で、ちょっと頑張ってみようと思っています。
0 notes
Text
国内政治の話 |ωΦ*)コソーリ・・・
今回の参院選は、個人的には不思議な感覚になる選挙だったかもしれません。自分は自民党55年体制ど真ん中の時代に生きた世代なので、かつての与野党構造が空洞化した国政選挙にまだ慣れがない、というのはあると思います。昨年、岸田政権下で派閥の解散が行われたことで事実上「55年体制」は終焉を迎えた訳ですが、その影響による空洞化がここまでに定着するというのも、自分は予想をしていませんでした。自民党は、一旦は組織の解体を演出して見せつつもゾンビのようにまた55年体制を復活させてくる、くらいの感覚が自分にはありましたが、それももう昭和の古い感覚なのかもしれません。

かつて55年体制の一翼を担っていた旧来の野党勢力が今回軒並み惨敗したのも、時代の終わりを象徴しているように感じました。代わって躍進したのは新興政党でしたが、今回の選挙はその新興政党が今後の政治の中心に台頭していく「転換点」として記憶されるような気はします。日本の外で起きている事、例えばアメリカのトランプ大統領を産んだ社会の土壌なども含め、世界はもう20世紀ではない、ということを強く感じます。
次のフェーズに入った世界では日本に限らず、「保守勢力の台頭」が目を引く出来事としてあげられると思います。ただし、このような「新しい保守」の登場を、国内外のメディアはしばしば「極右」や「ポピュリズム」といった言葉で語りますが、個人的には、それらの言葉が必ずしも実態を的確に表しているようには思えなかったりしています。
例えば、今回の参院選で注目を集めた参政党は、支持層と既得権益層という対立軸を掲げ、支持層の不満に訴えるスタイルを取っています。これは確かに典型的なポピュリズムの手法と言えるでしょう。一方で、ポピュリズムという言葉には「扇動的」「理性的でない」といった否定的なニュアンスがつきまといます。今の参政党の支持者をそのようなイメージで一括りにしてしまうのは、自分は少し違うと思っているのです。なぜなら、現在の参政党支持層には「嘘であっても、それが既得権益を打破するツールとして機能するなら容認する」という、ある種の戦略的な思考がそこに見え隠れしているように感じるからです。単純な感情動員型のポピュリズムとは異なり、そこには今の社会制度に対峙する為のリアリズムがあるのではないでしょうかね。

本来、嘘とは客観的事実に反する情報であり、否定的に扱われるべきものでしょう。でも、現代社会においては嘘を積極的に利用するのを「善」とする倫理観があるのも、これまた現実だと思います。例えば金融の世界などでは、実際の価値以上の「レバレッジ」(借金による投資拡大)が、時に実体経済から乖離した「価値の捏造」が横行し、サブプライムローン問題などは、その象徴的な一例でした。
例えば司法の場においても、被害者側が「相手の嘘に泣き寝入りさせられる」構造がしばしば存在します。社会的活動や利益が損なわれた状況の説明過程で、どんなに嘘や虚偽の主張がなされようとも、法制度の限界によって嘘が無罪放免にされる場面は、決して少なくありません。嘘や捏造が経済や法の中で奔放に利用される現実がある以上、それで不利益を被った人々、或いは利益を受諾できた人々が「同じ手段で対抗する」という発想に至ったとして、それも人情だろうなと、自分は思ってしまう訳です。
都市部で生活している人たちほど、この「価値の捏造」ルールに煮湯を飲まされた経験、大きな利益を受諾できた成功体験が多くあるはずで、そこに参政党が東京で強かった要因があるのでは?とも考えたりしています。それは、ある種の「目には目を」の論理とも言えますが、参政党に限らず、今の新興保守勢力の根底には、概ねそれがあるのではないかと、自分は思っています。
参政党の主張する「子供一人につき月10万円支給」や「食料自給率100%」も、財源も含めた根拠などの具体性が確かに曖昧ですが、支持者にとってはその嘘は既得利権への対抗手段として有効である、むしろそれくらいやらないと成果の一つも見込めないと認識されているのだと思います(もっとも参政党の何がブラフで何が本丸なのかは、現状では知る由もなく、その本丸は支持者が各々自分たちの���語を勝手に参政党に投影していると)。

今盛んに、テレビなどでは参政党の主張に含まれる嘘を指摘し、論破しようとする動きが見られます。ですが、参政党の支持者はそれに対して「上等だ」という類の反応を示すだけでしょうし、そこで議論の接点を見出そうとすること自体が、単純なパターナリズムに陥っていると思うのです。
今回の選挙で、参政党はおそらく日本の次世代の政治を担う政党の一角となりうる可能性を強く印象づけたと思います。彼らの主張やスタンスを、感情的・陰謀論的と決めつけることで矮小化しようとする空気も、依然として根強くありますが、それは社会の側がまだ20世紀の感覚で、今の政治を取り巻く情勢を見ているからのような気がします。アメリカの議会がほぼ機能しなくなってしまっている今の状況と併せて見ても、議論の叩き台として、20世紀の対立構造を前提としたポジション取りしか想定できないようでは、物事を建設的に進めていくことはできない気がしてしまうのです。
※筆者は参政党支持ではありません
0 notes
Text
DX7 のリバイ
なんと30年ぶりのリバイで、初代 DX7 を我が家に再びお迎えしてしまった訳ですけども。初代 DX7 は、自分が21歳くらいだった頃に生まれて初めて買ったポリシンセですが、当時の自分はシンセを全く理解しておらず、結局プリセットのエレピとベースの音を midi シーケンサー(QX5)で鳴らしてそれを 4tr のカセットマルチで重ね録りとかやりながら遊んでいただけ、という何とも勿体無い使い方で終わってましたけども。

(花の83年組)
後に Machintosh を買って DTM を始めたものの、自分で DX7 の音色を作るまでには至らず、まあ、適性がないというか、DX7 のパラメーターを捲って一生懸命数値を変えても、自分が何をしているのかさっぱり分からず、作りたい音に辿り着ける手応えも一切得られず、30歳を過ぎた辺りで手放しました。
その頃、世の中的にもシンセの音色は自分で作るものではなく買うものだったのもあり、シンセの音を自分で作らなければならない必要性に迫られる機会がめちゃくちゃ少なかったというのも大きかった〜、というのは、でも今にして思えば言い訳なんですよ。
ある意味、あの時代は皆んなで時代に翻弄されていただけとも言えるのですが、当時その周りと一緒になって翻弄されている状態を「適応」と勘違いしてしまうところが、まあ、要するに人としての凡庸さの現れなのかなと。
結局、あの頃「適応」を勘違いした若かりし自分が「手も脚も出ない」と思い込んだ DX7 は、自分が還暦直前になって買い直して使ってみたら、そこそこ使い始められる程度には難しくない物だった訳なので。
もっとも、DX7 を自分が使えるかも、と思ったきっかけも R*S の Serge を使っていたからこそなので、やっぱり物事は順番を踏むのが大事、という話ではあるのかもしれません。R*S の Serge は、フィルターなしでも色んな音が出せますし、FM 変調的な事もふんだんに使って音を作っていくシンセですから、それで FM 変調を扱える下地が自分の中に出来上がっていたのは、その通りだと思います。

DX7 をお迎えして使ってみて思うのは、若い頃にやった事って、ホント忘れないんですね、という。自分はマニュアルを見ずとも DX7 を何となくいじれてしまい、 しかも Serge で経験したことをそのまま使って何となくそれっぽい音が作れてしまうという、自分でもびっくりです。指が勝手に動くんですよ。プリセットの音も、例えばブラスのちょっとチープな音をもう少しふくよかにしよう、とかも割とすんなりできてしまうので、若い頃に誰か教えてくれる人がいたら、もう少し違った人生があったのかな〜、なんてまあ、それは言っても仕方ありません。
しばらくいじっていくと、どうしてこのシンセの旬が2年かそこらで終わってしまったのか分かる気がしたのですが、このシンセはやっぱり音作りの幅は狭いんですよ。結局、DX7 は FM 変調機能の一部だけを抜粋してパッケージングしただけのシンセと言って良いのであろうと。このシンセが発売され��当時の空気を自分も覚えていますが、「モンスターシンセだ!」という誇張されたイメージを自分はまんま真に受けていた、というのを、40年経って、自分はようやく気がついたのでした。これなら後の wave table シンセの方が人気が出るのは当然だろうな、というのは思いますね。
もっとも、自分は今回「音作りの無限の可能性」を求めて DX7 のリバイをしたのではなくて、early 80s の 12bit にある独特のザラついた質感が欲しくて買ったので、音作りの幅が意外と狭かったというのは、そ��なに問題ではないのです。自分は古い 12bit デジタルの負荷を掛けた時に出るバグっぽい音が欲しかっただけなんですよ。
youtube
自分の作る曲には、それなりにアンビエントの要素もありますので、 それこそ William Basinski 的な遠鳴り感が、ある種の場面では欲しくなったりするのです。で、今自分が使っているポリシンセはどれもその William Basinski 的な遠鳴り感をまあまあ苦手にしているシンセだったりします。ああいう遠鳴り感はやっぱり wave table シンセは得意だろうな、というのは何となく思うのですが、やっぱり 70s をテーマにするなら wave table は無しです。一方で初代 12bit でなら、すれすれの所ではあるものの、70s 特有の空気感を表現できる音があると、自分は踏んだのです。
自分が90年代クインシーやチックコリアのエレクトリック、LA フュージョン的な音を出そうと思うなら、間違いなく 16bit の方を買いますが、自分の用途なら初代 12bit ですよね。
0 notes
Text
ARP Odyssey その2
結局、カントリーギター的な響きを軸に据えたアレンジに「なんとなく」でダイアトニック的な響きを加えてしまえば、楽曲の印象も「なんとなく」になってしまうはずで、ただ、その原因となるカントリーとダイアトニックの関係性は一般的に認知されているものではない分、そこを無自覚に物事を進めてしまうのも、まあまあやりがちな事ではあるだろうと。一般的に認知されている事ではないからと言って、自分が気になっている箇所をスルーするのも、それは違う訳で、なのでそこはちゃんとやっておかないと、そういう事って後々悔いを残しますよね。

そもそもシンセで普通のダイアトニックコードの転回形のような音を出しても、あんまり IDM ぽくはならないというのもありますし、その IDM の中でちゃんとギターの音がカントリーギター然とする事を目指するなら、より意識をしてダイアトニック的な響きを楽曲から省いく方が、自分の意図が伝わりやすくなるだろうと。
と、思い始めたちょうどその頃、自分はたまたま Random Souce(R*S)の Serge を使い始めていたのですが、これは本当に偶然なのですが、R*S はそういう自分の向いている方向にピッタリの楽器だったのですよね。やっぱり普通の鍵盤シンセと比べて、モジュラーシンセは出せる倍音の幅が広くて複雑で、それでもちゃんと有機的で、本当に豊かな響きが得られるのです。なので、例えば音をワッと広げたい場面でも R*S なら2声の対旋律をちょっと組んであげて、下で低域をドローンで鳴らして、あとはそれぞれの音に H949 なりアナログディレイなりのエフェクトを掛けて、それをちょっと pan で振ってあげれば、ポリシンセの5声で鳴らす和音に引けを取らない、大きな音像を作ることができてしまうのです。
モジュラーシンセはある面、平均律そのものからの解放を目指した楽器でもありますから、放っておいてもダイアトニックコード的な響きではない音の方向になっていく傾向があります。そういう意味では、意図せず、自分がダイアトニック的な響きから離れた所にいたのはあったのだと思います。そこから色々考えていたら、自然音階とダイアトニックの違いなどを意識できるようになっていった感じなのだと思います。
それまで自分がイメージしていたシンセの音は、いわゆるシンセサイズされた音と鍵盤の和音から得られる印象を一つに捉えていたものなのですが、そこが意識できるようになってくると、この二つは分けた方が良いだろうと。自ずと和音の要素を省いた所で成立するモノシンセばかりを使うようになってしまい、ポリシンセは電源を入れない事の方が多くなってしまうのでした。そして、もう少しモノシンセのバリエーションが欲しくなるのです。その頃、Chroma Polaris は壊れており、眠ったままになっていましたので、あとは Moog Grandmother も使っていませんでしたので、Polaris を修理するよりはその二つを ARP Odyssey に変えたらとても美しいではありませんかと。
youtube
(こうやって他人が上手に使っている音を聞くと、手放さない方が良かったかな・・と思う日もありますが)
Chroma Polaris は ARP のフィルターを搭載してますので、70s 的な空気感を作るのにとても重宝していたのですが、ARP の 70s 的な空気感が欲しいなら Polaris よりは Odyssey の方がむしろそのものズバリな訳で、ポリフォニック機能を使わないなら Odyssey の方が余計に自分の目的には合っているだろうと。付け加えると、Polaris は1984年発売のシンセなので、基本現代的なシンセの音が鳴る部類ではあるのです。Polaris は微妙に70s の雰囲気ではなかったというのもありました。Polaris は構造的にはとても面白いですし、全然嫌いじゃないのですが、如何せん置き場所問題がありますから、まあ、断捨離です。
Odyssey は、70s そのものズバリを目的に買うので Korg のリイシューではなく、もちろん古い方のです。欲を言えば、そりゃ rev1 の、所謂モーグフィルターの乗ってる奴が欲しい、とも思いましたが、まあ、自分が欲しいタイミングで日本の古いシンセ屋さんにそれが出ていないということは、これはもう縁がないんです。
rev2 と rev3 なら、自分なら rev3 。原宿のシンセ屋さんの主は「2も3も、だいたい一緒」と仰っておられましたが、自分もそう思います。ただ、rev3 の方がガワの共振音がデッドな分、タイトな音が鳴る(気がする)ので、自分はそっちを選びました。rev3 でも十分、濃いぃ 70s の音が鳴ります。ベタな表現を使えば、レコードみたいな音がします。Odyssey は2音ポリにもなりますので(adsr の r を短くしないと不自然になりますが)、自分の対旋律を組む使い方でも、その旋律を鍵盤で探れるので、これもポイント高いです。

CS15 と比べると、Odyssey は env の動きがとても有機的です。生き物のような音の変化があります。CS15 に限らず、日本の古いアナログシンセの env は、概ねそこがぶっきらぼうな動き方をしますので、そこは結構差があるかな・・とは思いました。vco の音やフィルターの音の楽しさなら、日本のシンセも全然負けていません。
悪い点をあげますと、やはり評判通り、スライダーの使いずらさは特筆すべきものがあります。見事に使いづらいです。ベンダーも使いづらいです。まあ、ここら辺は慣れようと思います。
1 note
·
View note
Text
ARP Odyssey その1
シンセは、最近までポリシンセを基本にやっていたのですが、Random Source の Serge を使うようになってから、段々と自分の音楽で和音を担当させるのはギターに任せてしまった方が、おそらく自分の音楽が分かりやすくなるのでは?と思うようになるのでした。もう少し書くと、鍵盤から得られるヴォイシングが楽曲の印象に与える影響と、シンセサイズされた倍音の印象を分けた方が、自分のやろうとしていることが伝わりやすくなるのではと。そうなると、モノシンセの方がむしろその用途では適正があるのでは?と。

自分がギターに和音の役割を担わせて、シンセから和音の要素を削ろうと思ったのは、鍵盤の和音の響きとギターの特徴的な和音の響きを一緒に鳴らすと、結構情報過多な音になってしまうかも、ということを思い始めたからではあります。
自分が利用している特徴的なギターの響きは、所謂カントリーギターの奏法からくる響きなのですが( 70s がテーマですから)、それは基本的にはラグタイム・ブルースの影響から生まれた奏法なので、要するにブルース的な響きのルールで演奏される所に起源があります。実はそこにあまりダイアトニックな概念はなかったりするのですよね。
もっとも、この「カントリーギターにダイアトニックな概念はない」というのもかなり個人的な話で、この話が正式な理論体系として認められていることはありません。ただ、自分はダイアトニックと自然音階は、物としては一緒でも、背負っている背景がそれぞれ違うでしょ、と。なので、例えば「Cのダイアトニック・スケール」と言われて連想する音と、「Cの自然音階」と言われて連想する音は、違うものと言って良いのでは?と。
調性音楽の歴史的には、バッハの平均律からの調性音楽の誕生からの西洋音楽では、それをダイアトニックとは呼ばずに自然音階と呼び、その中でトニック、ドミナント、サブドミナントという調性の概念が整備される、という流れのはずです。所謂「ダイアトニック・スケール」というのは、20世紀に入った後、調性の内属性と外属性の区別の為に、内属性の7つの音をダイアトニックと定義したジャズ理論から普及した、と言って良いと思うのです。

どうして内属性と外属性を区別する必要があったかと言えば、ジャズを効率的に再生産、量産化する為にアドリブでスケール・アウトした音とそうでない音を体系化して学ぶ必要があったからと。そのスケール・アウトした音は、ジャズですから、当然独立した音体系を持つブルースのセンスから来るものなのですが、順序とすればトニック、ドミナント、サブドミナントの音体系を持たないブルースが、西洋音楽的な調性音楽の中に、その適応を試みた概念をダイアトニックとノンダイアトニックという言葉を使って説明した、と解釈するのが妥当であろうと。
なので、カントリーギターの響きにケルティッシュやスコティッシュな「自然音階」のニュアンスとブルース的な音体系���共存はあれど、そこにジャズ的なスケール・アウトを前提とした「ダイアトニック」のニュアンスは入っていない、と自分は解釈する訳です。個人の感想ですよ、くれぐれも。
因みに、ブルースのルールは、今の音楽理論ではブルースを西洋音楽の文脈として解釈した20世紀の流れとは別の解釈になっており、つまり V → IV は本来は禁則であると説明するのはナシになって��ブルースの V、IV を西洋音楽のドミナント、サブドミナントの解釈に当てはめるのは無理がある、ブルースはそれ自体が独自の音楽である、という風になっていたりします。
結局、自分が若い頃、あまり音楽理論に馴染めなかったのは、ここら辺りの説明で「無理くりだろ・・」と思って気持ちがシラけてしまったというのはあります。時代が下れば、あれは本当に無理くりだった訳で、まあ、今の若い人たちはですね、我々老人世代が「理論なんて役に立たねー」などと無邪気に言い放ってしまうのには、それなりに理由があったんですよと。ただし、細かい所がちょっとダメだからと言って、それを理由に全体を否定するのは単なる幼児性以外の何ものでもなく。はい。

ここでやっと最初の鍵盤シンセの和音の話になる訳ですが。思ったより、相当前置きが長くなりました。続きは次回。
0 notes
Text
ギターの録音、できてません
本当はもうとっくにギター入れが済んで、都内のスタジオでリアンプも済んでいるはずでしたが、まあ、2月の下旬に父が歩行中の転倒からの手術、その術後、色んなことを経験させて���らってます的な状況が発生してしまい、ギター入れができておりません。父が入院した病院は割と遠くの病院になってしまったのと、その病院の医師の諸々の煩雑さや融通の効かなさにも振り回されてしまい、3月は丸々ドミノ倒し的に時間がなくなってしまいました。4月に入って父は退院してホームに戻ったものの、状態は芳しくなく、結局親戚対応や施設との対応に追われて、諸々撃沈。

ただ、その間、ギターを弾く身体を戻すのと、楽器をもう少し馴染ませるのと、できる限りはやっています。弾けてせいぜい1日20分か30分ですが、それでもやらないよりはマシでしょうと。
楽器が、去年一昨年と、母の在宅介護期間で完全に鳴りが失われてしまった状態ですから、とりあえずはアコギ1本、エレキ2本、ナイロン弦1本をそれぞれ馴染ませていこうと、4日交代で1本ずつ鳴らしてはいますが、やっぱり鳴らす時間が少ないので芯まで馴染んでくる感じまでは中々なって来ないです。まあ、芯まで馴染まそうと思えば一日2時間、3週間は鳴らさないとどーにもなりませんのでそのレベルは諦める訳ですが、何にせよ、もどかしいです。
もっとも、3月4月は自分の持っているギターにはあまり良い季節ではないようで、毎年楽器の建て付けが変なバランスになってしまうので、ちょうど良かった部分もあります。特にウチのエレキ2本は3〜4月は弦が突っ張った感じになってしまい、弦高を普段より下げないと、弦がゆとりのある感じで振動しないのです。自分、弦高の低いギターの音が苦手ではあるので、毎年その期間に録音はやらない方針でやってはいます。
そういう意味では2月までにギター入れは済ませておきたかった訳ですが、そこのちょっとのズレがなんだかな・・という。2月にできなかったら、もう5月まで待つしかありません。まあ、何かのサインなんだと思います。そういうことにしておきましょう。
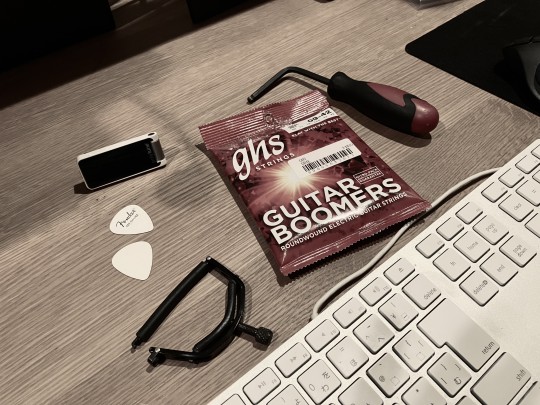
色々不満はあるものの、楽器も身体も、そこそこ録音しても良い状態にはなって来ていると思うので、5月6月に何事も起きず、2曲のギター入れ、リアンプまで済ませられたら良いなと思っています。ギターの録音は、フレーズとリズムだけ間違えずに弾けたら OK 、じゃ流石にちょっと寂しいですから、ちゃんと魂込めて録音できたらと。
と、思っていたら4月の下旬から父が再入院からの転院という、まあ、ここでは書けない、かなり、相当に込み入った事態になってしまった訳で、またまた時間がなくなってしまっております。父の見通しが立つまではギター入れは保留ですね。
良いように解釈すれば、2025年のポピュラー音楽はもはや32分音符ベースのタイム感で回っているし(ヒップホップの影響が大きいと思われ)そのタイム感をある程度出せるように弾かないと16分音符ベースのタイム感だと何も伝わらないぞ、そこの練習をもう少しやっとけ、というお導きなのかもしれませんと。
で、メトロノーム買ったんですよ。やっぱり今の時代、32分音符は弾けとかないと、と思いました。隙間時間に毎日32分音符弾きを3分でもやっておこう、とかなら単独のメトロノームが良いでしょうと。もちろん、♩≒ 70 くらいから始めて、80とかじゃ全く弾けてませんけども。ベタ弾きでもヒーヒー言ってるレベルなので、シンコペなんてもう当然アレなアレ。それがどこまで本番の演奏に反映されるかは、正直分かりませんが、まあ、今はそういう時間なのかなという理解で。もっとも、今年は5月に入っても気候は不安定のままで、楽器の建て付けは戻ってきてはいませんので、どの道、保留だったのかもとも。

音楽は、ホント変わりましたよね。最近の若い先端の音楽家の方たちの、例えばドラムの人のハイハットって、どーしてあんなに細かいんでしょうか?などなど。それを疑問に思っても、あれが世間に受け入れられている以上、我々凡人は付いていって、それを理解していくしかありませんです。そこで「あんなの必要ないでしょ」と言った瞬間、何かが終わるんです、言った本人の気が付かないところで。まあ、凡人が「正しい音楽が生き残る」と思った瞬間、全ては終わるので。凡人なら才能のある人たちの言う「正しい音楽」とやらの呪いに惑わされることなく、「生き残った音楽が正しい」を基準にやっていくしか、生き残れる術はありません。
0 notes
Text
そしてまた、ニューウェーブが始まる
2025年4月に発動されたトランプ大統領の全世界に対する関税政策は、自分たちが大きな時代の節目に来てしまったんだ、という思いを強くさせた大きな出来事でした。一言で言えば、1985年のプラザ合意に象徴される時代の流れとしての金融資本主義の行き詰まりが、ここで訪れたという話なんだろうと、感想としては持ちました。

金融資本主義は多くの恩恵を社会にもたらした反面、その構造として持ち合わせている、製造業を低付加価値なものとして扱ってしまう歪みを、結果として是正する事ができなかったのです。それはアメリカの製造業に限った話でもなく、日本であっても、中国であっても、今の製造国の役割を担ってくれている東南アジアであっても、最後は労働者の価値を棄損して営む事を良しとしたのが、金融資本主義が歩んだ道なのでした。金融資本主義のルールに「製造業に従事する労働者をリスペクトしないで済むアリバイ」を与えてしまう側面があることを資本家たちは分かっていながらも(適切なコストカットと、安易な人件費削減などの不適切なコストカットを明確に区別することが不可能であることは、皆んな知っています)、この40年の間、彼らは労働者個人の「努力」「自己責任」などの労働者が負担を負う形のイデオロギーばかりをマスメディアや教育機関を利用して積極的に啓蒙した一方、「労働者の価値を限度を超えて棄損してはならない」という資本家の側が負担を負わなければならなくなるイデオロギーの一切を啓蒙対象から外したのでした。その”資本家たちの都合”に労働者たちはもう付き合わない、という確固たる意思表示をしたのが、今起きている事の本質にはあるんだろうと。
今のアメリカは、低賃金で雇った全世界の製造国労働者の作った「物」を、国民に膨大な借金をさせる事で大量の消費を促し、それで諸々のバランスを取ってきたとも言えます(アメリカのその過剰債務が持続可能だったかは怪しいにせよ)。しかし、それをトランプ政権はアメリカの「赤字」であるとし、赤字を解消して何が悪い?と言い、今の世界の経済バランスを保つドルの基軸通貨としての役割を無視した、自国アメリカのリセッションの誘発、そして世界経済の秩序を崩壊させてしまいかねない高額な関税を各国にかけ始めてしまいましたアメリカ国内ではトランプ政権がこのような��端な政策で運営されることは、ある程度皆んなが予想していたことではあるようですが、それでもトランプを大統領にしないといけない事情が、アメリカの、本来なら製造業を営むことで自己の尊厳を守って生きていくべき人たちにはあったのでした。
人が生きていく術というのは、そもそも適正によって自然と決まっていってしまう類のもので、それは本来、後天的にどうこうできる事が限られている性質のもののはずです。デスクワーク的な業務に適正のない人にその道で努力しろ、というのは非人道な行為であるにもかかわらず、金融資本主義者たちはそれでも「努力」の無理強いを製造業で生きた人たちにし続けた訳なので、遅かれ早かれ、これはどの道破綻するシステムではあったと言えます。

この努力の無理強いを延々とされ続けたきた人たちは、当たり前ですが、もはや対話を拒否するだけの状態になり、エリートは俺たちの適性や限界を「知ったこっちゃない」とずっと扱ってきただろ?俺たちに「100mを5秒で走れ、走れないなら努力しろ」と言い続けただろ?俺たちだってもうエリートにとって都合のいい秩序が壊れようがアメリカが困窮しようが知ったこっちゃない、俺たちにとっては一緒のことさと、おかげでアメリカ議会は機能不全に陥ってしまいましたけども。これを単なるポピュリズムで説明するのは違うと思いますけどね。
で、この行き詰まりを見せ始めた金融資本主義の次の資本主義はどんなものになるかと、流行りの生成 AI に聞いてみたら、「レバレッジの縮小・規制」の方向に進む圧力が強くなっている、と出力されてきました。自分ら、戦後のブレトンウッズ体制からの欲望に任せた拡張に次ぐ拡張の世界で生きてきた人間にとって、縮小の方向に進む人類の姿は中々想像し難いものはあるのですが、その出力が AI の世論誘導の可能性はあるものの、世界が縮小・規制のフェーズを望んでいる���シは確かにあるのかもしれません。特に21世紀を迎えた後、リベラルの掲げた正義が「不可能な努力の強要」の口実として機能した面は否めなく、例えば「自由」という言葉は、もはや多くの人たちに悪と捉えられています。
60年代からの産業資本主義か徐々に金融資本主義へと変換していく時代の最後の方で、音楽の分野ではニュー・ウェイブというジャンルが流行り始めたのですが、それは今にして思えば、「金融」という、産業資本主義的な軸から見れば得体の知れない何かが世の中を支配し始めている、という状態を敏感に感じ取った当時の音楽家たちの音変換だったという事ができると思うのです。だからあの時代のニュー・ウェイブではああいう、ある種のおどろおどろした雰囲気のビジュアルや音像が多用されたんだろうと。
そして今、40年続いたその金融資本主義が変容していくこの時代に、今の音楽家たちはここで何を感じ取ってそれをどう表現しているのか、ということを改めて観察していく事が、自分には必要なのかなと思い始めています。気が付くと、世界の音楽家とそのリスナーたちは既に音楽を「小さな共同体への回帰」という表現に重心を移動させている向きがあるのではないかと。一方で、このまま優生思想の資本主義という結構なデストピアの道を受け入れていく流れの、コンサートチケットの高騰やスーパーファンの高額会員料なども、現実としてはありますけども。さて、世界はどっちの方向に進んでいくでしょうね。
2 notes
·
View notes
Text
70s のエコー 5
XL-305 がウチに来て、自分の気が付かなかった 70s のニュアンス的なことに気が付けるようになれたのは良かったのですが、XL-305 はリバーブタイムも音の位相的な部分の補正も全くできませんので(プリディレイは 1745 でやれますが)全曲 XL-305 でやるというのも難しく、どうしようかとまた色々探し始める訳ですが、ある日唐突に Hologram Electronics の Microcosm というリバーブも入ったマルチ・グラニュラー系のペダルの音が、ひょっとしたら自分の音楽には合うのかも・・という事を思い始めるのでした。

どうも自分がステレオ音像のエコーで 70s の音を探してもこれ以上は何もないと、無意識のうちに察したっぽいです。もう古いエコーマシンに答えはないだろうと。で、何故か Microcosm だった訳ですが、Microcosm の動画を沢山見ていると、この音の広がり方はリバーブ単体で作っているというよりは、モジュレーション効果で作っているっぽいと。サンプリングした音をぐにゃぐにゃに変調を掛けながらステレオで散らしているのでは、と。
なら、グラニュラーに特化したペダルを PCM81 の前に繋いで PCM81 のモジュレーションを全部ゼロにしたら PCM81 の音が今っぽくなるのでは?という事を思って、グラニュラーなら Chase Bliss も見てみようかと。
Chase Bliss 自体は昔から知ってますが、その特徴的な音を活かす場面を自分の音楽の中であまり想像ができなくて、買おうとは思っていませんでした。実は2019年に、自分 Horogram Electronics の Infinite Jets を買って、浦島太郎を解消していこう的な事をやったのですよ。自分が音楽を復活させてから見えた音楽の世界は、あまりにも先に行ってましたから、これはもう強めの刺激を自分に与えるしかない・・と。そしたら、Infinite Jets のバッファの音が独特なせいもあって、あの特徴的なグラニュラーな音を上手く自分のギターとシンセの間に挟む事ができなかったのです。

諸々を省略して話せば、結局自分の音楽でギターの音が未来を表現してしまうと、自分が想定している文脈が破綻してしまうのです。自分の想定した文脈なら、ギターの音���そ 70s を表現できていないとダメなんじゃないのかと。Chase Bliss は、確かに面白いけど自分の特徴を消してしまうかも、と。
ただ、改めて自分は何のためにステレオ音像にこだわっているのかを思い直してみれば、そういえば今の社会に適応するためなので、ステレオ音像そのものが「今」であれば文脈の破綻はない事になります。70s(自分の鳴らすギターの音)が 90s(PCM81)に適応しても2025年の社会にアピールできるものは何もありませんけど、「今」や「未来」に適応しているならアピールになるでしょう、と。その視点で Chase Bliss の音を聞くと案外イケるかもという事で、PCM81 の事はとりあえず忘れて、単体でもリバーブの音が入っている MOOD mkii を買ってみることにしました。Microcosm は、その時なぜか意識の外に行ってしまいましたので、まあ、保留。
いざ、自分の曲で MOOD mkii を鳴らしてみると、これは間違いなく「今」の音なのですが、自分の音楽で「今」の音をどこに的を絞るのかと言われると、Big Thief の『Change』的なインディーギターロックの空間表現の所なので、Chase Bliss の音を素で鳴らしてしまうと、割とエレクトロ・インディー的な所の音が鳴ってしまい、大分ピントがズレてしまいます(もっとも、Change はルームアンビエントをマイクで拾う系なので、シンセ音楽的なアプローチとは全然違うのですが、印象としての Change が表現している都市空間的な、そこ)。
まあ、Chase Bliss に限らず、今のシンセ系の機材は大体キラキラした音なので、そこが自分が目指す「今」のインディーギターロック的な音とは相性がすこぶる悪いのは、買う前からなんとなく分かってはいました。そこをまとめる時、自分には H2 Audio の 5011 という EQ があって、これがホントに重宝します。これは音そのものは今の音なのですが、魂が 70s の機材なので、この 5011 で音を作ると Elektron であろうが Random Source であろうが、もちろん Chase Bliss であっても、今のパーツで作られた機材の音とヴィンテージ機材との接点を作ることができるのです。これで MOOD mkii のキラキラした成分を削ると、これまた思った所で音が鳴ってくれて、まあ、大変有難い機材です。

MOOD mkii のポイントは MOOD mkii をギターに掛けないことでした。どうあっても 70s 垢に塗れたギターの音を中途半端な印象にしない唯一の方法を貫くなら、未来的な音はギターに一切使わない、だと思いました。MOOD mkii を使うのはベースとスネア。ギターを取り巻く環境を「今」に設定して、ギターには今持っている古いエコーマシンたちを使って 70s をまんま背負ってもらいましょうと。これなら文脈の破綻なく最後までイケる手応えが得られる感じになってきましたけども、色々やっていくと Microcosm もどこかのタイミングで買い足そうかな、と思っています。
というのも、MOOD mkii は思ったほど色んな音にならないんです。どっちか言ったらシンセで音を作る人向け、というよりはギタリスト向け、と言いますか。ギタリストの人って、びっくりするくらいシンセサイズ・アレルギーなんですよ。おそらく、エフェクターにシンセサイズの要素を入れてしまうと、そこでそっぽを向かれてしまうんだと思われます。なので、MOOD mkii ができることと言えば、実質プリセットだけの音、という。そういう意味ではギタリストって、楽器の進歩という面をサポートする市場の役割的な面から言えば、ちょっと邪魔な存在ではありますけども。
#music gear#reverb#chase bliss#h2 audio#5011#mood mk2#digital reverb#analog eq#500 series#eq#reverb pedal
0 notes
Text
介護の備忘録 3
父は、東京の西のかなり西の方の有料老人ホームに、3年前にはいりました。老人ホーム自体はちゃんとやってくれて、それは良かったのですが、医療体制がやっぱり都心部とは文化がかなり違う・・という感想は持ってしまいました。

(本文とは関係ないイメージです)
一言で言えば、やっぱり東京の西は社会主義で回っているエリアなんです。だからありとあらゆる医療行為に関して、家族が自分で考える事をしないケースがとても多いのだと思われ、医者の対応もそれに合わせて最大公約数的な部分の対応で全てを完結させるシステムで回っているのでした。
そもそも、医者の判断には仮説に基づくケースも多々あり、その仮説が外れてしまう可能性も当然あり、常に100%、処方が上手く行く訳でもありませんので、外れたらその都度対応していくしかない部分がどうしたってある訳です。
ただ、大資本の分厚い雇用に守られて人生の中年期までを過ごしてしまった系の人たちにとっては、その都度、状況にあわせた対応を自己責任でやっていく、というやり方は物凄い負担になってしまうようで、例えばお父さんお母さんの容態が一般的な症例から外れて一般的な処方ができなくて、仕方なしに一般的ではない処方を試さざる得ない状況で一般的な処方ではない処方をやって、それが上手く行かないと、もう後悔の念に押し潰されて「人の命をなんだと思っているのぉぉぉ!」的に取り乱してしまう、そんな感じ。
結局、皆んなと一緒の診療をしてくれたら後悔はないですと。余計なことするなと。それでダメなら諦めも付きますというルールで、全ての医療行為を回していかざる得ないんだろうと。例え一般的な処方ではない処方の方が可能性が広がったとしても、それを選択肢に入れる事そのものが東京西部の人たちにはナシのようで、それよりはまず皆んなと一緒を望み、それをあなたも私も幸せと感じましょうと。
患者家族の方がそれを望むと、受け入れる医療現場の方もそれに自分たちの仕事を最適化させてしまい、一般的な症例から外れた患者がやってくると、現場で働く人たちの方で嫌がれている感じの対応をされてしまうケースも、まあ、散見されます。自分ら都心部で暮らす側からすれば椅子から転げ落ちるほどにびっくりしてしまうしかありませんけども、東京の西のエリアでは、それを受け入れてやっていくしかない部分は、あったりするのでした。

(本文とは関係ないイメージです)
東京西部のその社会主義的な思想の根本には、様々な対応をできるようにする事を容認するから、制度に隙が生まれてそこで抜け駆けをする奴が出て真面目にやっている人が損をするんでしょ!皆んな一律にしか対応しないシステムにすれば、抜け駆けなんてできなくなるでしょ!というのがあったりします。自分も東京西部ではそれが支配的な空気なのはそれなりに知ってはいましたが、医療体制までもがこうまで社会主義になっているところまでは分かっていませんでした。そこの部分に限って言えば、失敗したな・・ということは思っています。
自分は2016年に、今の都心5区の隅っこに引っ越してきましたが、引っ越し先を決める時、郊外に出ようか、或いはもっと地方都市(長野とか富山とか)まで引っ込もうか、それとも狭くて薄暗い都心部の隅っこにしようか、凄い考えました。年齢的にも、おそらく人生最後の引っ越しになるだろう、というのもありましたし、音楽を再開するにあたって、という部分も大きな比重を占めていましたので、まあ、ホント色々考えましたよ。
今の所に決めた理由は、もちろん一つではありませんけども、やっぱり自分は競争をするために音楽を再開する訳ですから、社会主義で回っているエネルギーを日常で浴びるのはマイナスでしかないというのも、一つの大きな理由でした。父の東京西部の医療体制のスタンダードな対応を経験してしまうと、尚更あの時の自分の選択は間違いではなかったという。まあ、今の住処は狭くて薄暗い所ですけど、ここに決めて良かったですよ。東京西部の郊外文化は、自分には合いません。
もっとも、老人ホームの居心地そのものに父は大変満足しており、まあ、自分が医療機関とやり取りをする時にその都度、戦わないといけないのが難点、というだけで、それ以外は万事塞翁が馬的な事なのかな、という気もしていますけども。
0 notes
Text
70s のエコー 4
PCM81 が自分の音楽にハマるのかハマっていないのか、もうなんだか分からないですよという感じで悶々とした状況が続いている頃、たまたまマーク・ノップラーのサイトに立ち寄ってみた時、マークノップラーの昔のラックに MicMix の XL-305 というスプリング・リバーブが入っている写真を見つけたのです。XL-305 は、AudioScape というメーカーからレプリカが出ており、YouTube でその音を前から知っていたのですが、これは中々綺麗でオーガニックな鳴り方をするリバーブではあります。ただ、ちょっと綺麗過ぎな所もあって、それが 70s の文脈に紐づけられる音になるのか的な所で、どうしようかなー、くらいで止まっていましたが、その時はオリジナルを手に入れてみようとまでは思っていませんでした。ただ、我らが陰キャ系スーパーヒーロー、マーク・ノップラーが使っているとなると、話は別。
youtube
で、色々調べてみると、XL-305 の発売は1979年で、分類とするなら early 80s の時代の物なのでした。まあ、やっぱりステレオ音像のエコーで78年以前の物を望むのは、無理があるんだろうと。ただ、YouTube に上がっている数少ないオリジナル XL-305 のデモ動画の音を聞くと、ちょっとプレート味のある音で、音の質感そのものは十分 70s の質感を持っていそうで、これは PCM81 よりイケるかも・・と思ってしまった訳です。
PCM81 で確信が持てない以上、他に何かを見つけるしかありませんので、XL-305 がそんなにお高い物じゃないなら賭けてみるのはありかもしれない、と。で、またまた楽器検索サイトで検索をしてみますと、とある信頼できるショップから、そのショップで整備した物がお手頃な価格で出品されており、これは買ってみるしかないだろうと。
数週間後に届いて自分の曲で鳴らしてみた所、とても 70s でクリーミーな音が鳴るには鳴るのですが、自分はこの XL-305 の音を直ぐには受け止めきれないのでした。一口に 70s とは言っても、自分でも把握していないニュアンスがまだまだ沢山あったという事なのですよね。

ヴィンテージ・シンセの回でもありましたが、結局、各トラックの EQ を当てる場所を、XL-305 の音と音の重心が揃うようにちょっとずらしていくと、自分のトラックが以前より芯で 70s の質感を捉まえている感じにどんどんなっていくという。自分、70s に人格形成期を迎えてますから、70s 的なニュアンスなら実体験としてかなり深い所まで知ってるはず、なんてとんだ思い上がりでしたね。自分は 70s の質感を、完全には捉えられていなかったのでした。こうなると XL-305 を買っておいて本当に良かった、と言うしかない訳です。
この音の重心を PCM81 を使って気が付けるようになれと言われても、自分は無理ですよ。XL-305 を鳴らしながら探すから見つかるんです。結局、XL-305 でハマる EQ の当て方が見つかった後、その EQ で PCM81 を鳴らしても相当ピントの外れた印象の音になってしまうので、こういう所の差に凡人が丸腰で気が付けるようになれよ、機材じゃねーんだよ的な話って、実は才能ある人たちの呪いなんじゃないでしょうかね。
それはともかくも。オリジナルの XL-305 はウチの環境ですと、voltampere の GPC-TQ から電源を取るとかなりプレートちっくなニュアンスで鳴らせてウキウキな気分になれますので、今はそうしています。voltampere の GPC-TQ は、中々難しい電源で、ウチでは基本、ヴィンテージのアウトボードはここから取らないようにしているのですが、XL-305 を GPC-TQ から取っても、70s 風味が薄れてしまうこともなく、むしろ持ち前の 70s 風味を今の環境に適応させやすくなる印象になります。

voltampere の GPC-TQ は光城精工の生産なので、KOJO の音に近いニュアンスで鳴ってしまうと思うのです。低域がやたら野太くモダンな印象で鳴る、的な。結局、低域に量感がありますから、高域の繊細さが聞こえずらい面があって、それがヴィンテージのカラッとしたニュアンスを鳴らしたい場合に、結構邪魔かなという。あとはやっぱりノイズが少なすぎると、せっかくのヴィンテージ・プリアンプが、なんだかモダンな印象で鳴ってしまうというのもあります。ただ、XL-305 を使う分にはそれら GPC-TQ の特徴が欠点にはならず、むしろ今風の低域の作り方を取り入れたトラックとの相性を良くしてくれる感じです。この辺りは良い悪いとかではなく、単純に 70s のニュアンスが欲しいなら、という前提あっての感想ではあります。
という訳で、1745m、EP-2 に加えてこの XL-305 でかなり芯を食った感じで 70s な音作りができるようになりましたが、XL-305 はリバーブタイムが一切変えられませんので、そこが非常に不便です。短めのスプリングリバーブをもう一台買うのか、それとも何か別の手立てがあるのか・・的な所の悩みは、結局残ってしまうのですけども。
0 notes
Text
70s のエコー その3
実は EP-2 を押入れから出している時、若い頃に買った PCM81 も出てきたのですが、PCM81 はずっと今自分のやっている事には合わないと思っていましたから使うつもりはありませんでしたが、あの動画を見た後、じゃ使ってみるかと。PCM81 に入っている Hall や Chamber は由緒正しき 224 から引き継がれたアルゴリズムが移植されているはずなので、せっかく持っているんだから試してみようと。

使ってみると、これがまた一発でダメ、と決めてしまうにはあまりにももったいない系の見事なまでの妖艶な Lexicon サウンドが鳴るので、これでイケるでしょとなってしまいそうになるのですが、それでもこれはどうあってもコテコテの 90s 節な訳です。90s は平成文化絶頂期の時代で、平たく言えばお気楽極楽な世界。70s の不安定で野蛮な世相の残った時代とは、大分違いますよね。
話は少し外れますが、自分は音楽を社会の文脈に紐付ける事を第一に考えています。なので、所謂感覚一発だけのやり方で音楽を作るつもりがないのです。もちろん、ある種の界隈で「考えるな!感じるんだ!」と言われているのは知っていますけども。
自分の理解では、人類は文脈を発掘、共有することで生存たらしめてきた種ではありまあせんかと。医学も何にもない太古の昔におなかが痛くなりました、と。痛い痛い痛いよ、っていう状況で「考えるな!感じるんだ!」で生存できますか?と。おなかが痛くなる理由なんて、当時は誰も分からない訳ですから、そこで文脈を発掘しようと、原因を無理くりにでもひねり出そうと、そういう頭の回り方をする種が生存に有利だったということなんですよ、人類は。
感じたら考えろ、ですよ。それができない種は滅んで、出鱈目であろうと皆んなに共感してもらえる文脈をあみ出せる種と、それに共感できる種が共に生き残ったのが人間ではありませんか。自分が音楽で生存しようと思うなら、同じ事をやるしかないと、個人の感想ですけども。

音楽は社会の中で生存するから意味があるとするなら、音から連想される時代背景と文脈を無視して音を選ぶのには、それが機材であれ、フレーズであれ、果ては自分のキャラからくる要素も含めて、自分は抵抗があるのです。自分の出す音を社会で共有された文脈と紐づけられるようになるためには、もちろん教養が何より大切ですから、自分は座学の部分もちゃんと準備してやっていこうと。そもそも自分には才能がありませんから、余計にそこを頑張らないと生存競争の土俵にすら上がれないと思うのです。
もちろん、それが中途半端なもので終わってしまえば自分の負け。1ミリ足りなかろうが50センチ足りなかろうが3メートル足りなかろうが、足りないなら全部一緒。惜しい、じゃダメなんですよ。凡人なら準備をして、また準備をして、更に準備をして、準備し過ぎることはないです。歌のないインストなら、そこは歌のある音楽よりシビアにやらないとダメだと思います。
70s をテーマにしているんだから 90s は違うでしょ、というのも、確かに細かすぎるのかなと思わないではありませんが、そこは凡人の自分が疎かにして良いことではないのではないかと。才能がある人のことは、知りませんよ。
で。頭ではそれが分かっていても、Lexicon のこの不思議な中毒性のような音が、心を掴んで離さないのです。街灯に吸い寄せられる虫になってしまう自分が、そこにいるのです。困ったもんですよ。

ここで諦めないとするなら、可能性があるとすればアルゴリズムの拡張カードの音に期待してみるのはありかもと。PCM80 の拡張カードは楽器検索サイトで検索するとぽつぽつ出てきますので、そこで個人ではなくストアから出品されているカードを取り寄せてみるかと。取り寄せた物が届いて、それを挿して鳴らしてみると、まあ、そうっすね・・という。90s 節が軽減される面もありますが、それがスッキリなくなる訳でもないという。
まー、難しいっすよ。結論が出ないです。
最近、ちょっと考えているのが、Chase Bliss のモジュレーション・���ダルを何か買ってきて PCM81 のモジュレーションと置き換えて鳴らしてみようかと。そうすると中途半端な 90s な空気感が薄れるかもと。90s は NG でも「今」なら文脈上は問題なくなりますので、時間ができたらその方向でやってみようかと。時代に取り残されてもおかしくない老人が軽やかに今の文化に適応できてたら、それはカッコ良いじゃないですか。
0 notes
Text
70s のエコー その2
1745m がそんな感じでどハマりしてしまいましたので、色々欲が出てきてしまい、とりあえず、ずっと押し入れに眠ったままにしてある Echoplex EP-2(1969年)も使ってみようかと。

テープディレイはですね、所有している人なら分かると思いますが、あれはヘヴィーなんですよ。物理的な部分ももちろんそうなんですけど、何より精神的な負担が大きくて、あの音を維持していく上での気持ちの重さたるや、あれは中々に中々なものなのですね。自分も一時はテープエコー熱にうなされて買ってしまったのですが、メンテナンスの手間と実機テープディレイ的な音がポピュラー音楽の最前線から消えてしまっている現実の前に、社会性の発動こそステイタス的な季節を過ごす凡人にとって、実機 EP-2 の魅力は便利なデジタル物の前になす術もなく、長らく押入れの肥やしにしてしまっておりましたが。
時代が下り、改めて実機テープエコーの音を聞くと、TOP100とかの音楽をやるでない限り、自分の音楽に合わないのがはっきりしているなら、プラグインも含めて、便利な物で満足した気分になるのも違うんだろうな、という感想を持つしかありませんでした。やっぱり実機の EP-2 の音は全然違いました。
もちろん、自分の EP-2 はメンテナンスを入れないとダメな音になっていましたから、真空管を入れ替えて、テープも交換して、それでもダメだったので、ひょっとしたらもう元には戻らないかもしれないと思いつつ、 Echo Fix から販売されている新品の再生、録音ヘッドを取り寄せて、それをプロオーディオのメンテナンスを専門にやってくれる業者に持ち込んで(テープデッキのノウハウを豊富に持っている所が良いと思います)、ヘッドの交換とその他メンテナンスをお願いしてみました。そうしたらダメになっていたコンデンサーは一つしかなく、後はヘッドの交換をするだけで、これが文句なしで使える音に復活してくれて、これはテンション上がりましたよ。

EP-2 はさすが 60s 発祥の物だけに、1745 の音にばっちりハマってくれます。この音のハマり方を聞いてしまうと、それまで自分の中では 70s の分類だった SDE-2000 と E1005 の音が、early 80s の音に聞こえてしまうという副作用をもたらし、まあ、こうなるとまるで終わりが見えてこない感じになってしまい、更に困ってしまうのですが。
考えてみれば、60s を引き継いだ early 70s、73年以降の本格的な 70s、78年以降の early 80s 的な雰囲気の三つは、それぞれ別の雰囲気を持っているんですよね。そうなると、ウチの純然たる 70s のエコーは 1745 と EP-2 の2台という事になる訳で、でもそこから 70s を増やすなら 70s ど真ん中の RE-201 だろうとは思うのですが、テープエコーを2台も使うの?というのもありしますし、そもそもステレオ音像のエコーを作りたいのに、モノラルを増やすの?というのもあります。
まあ、ステレオね・・と。ここで本格的にステレオ音像のリバーブで音を作り込む手法が普及し出す時期を考えると、1978年の Lexicon 224 以降なので、自分は変に 70s に潔癖になるより early 80s 的な音に目指した方が目的を達せるのかも?と。そんな風に考えていた頃、YouTube にとある 224 の動画がアップされており、これは持っていかれましたね。その動画を見ると、いや、これは買わなければ・・と、相当頭に血が上りました。ただ、運が良いのか悪いのか、その時に楽器検索サイトで検索しても、224 はもう市場に出ていなかったのでした。もちろん、怪しい物ならなくはなかったですけども、関わってはいけない系の人に機材の希少性だけで関わって良いことはない、という経験則が自分にはありますし、細かくは書きませんが、その後色々あって、最終的にはこの流れならこれはもう縁がない、という感じで諦める感じになりました。ひょっとしたら自分がその動画で持っていかれているのは 224 の音ではなく、P5rev.2 の音の方なのかもしれませんしね。
youtube
また、224 が使われている当時のレコードを漁ってみても、当時は 224 の擬似ステレオ音像が不自然と捉えられていたフシもあり、224を思いっきり派手に鳴らすようなミックスが全くされていなかったのも、諦める決断を後押ししてくれました。
結局、70s をテーマにしつつも今風の音楽でよく聞かれる系の派手なステレオ音像のエコーを鳴らすなら、無理に当時物にこだわらなくても良さそうだと。逆に今の物を、文脈そのものを工夫する事で混ぜ込む方が目的に合うのでは?と。
そんなこんなで無事に 224 熱から生還するも、Lexicon の音って、ほんと妖しいんですよ。街灯に吸い寄せられる虫の如く、自分も吸い寄せられていくのが、はっきり自覚できたりします。こんな効果を自分の音楽にもたらしてくれるなら、是非、自分の音楽で使いたいと思ってしまうのですけども。
0 notes
Text
70s のエコー その1
今自分が作っている音楽は、自分の人格形成期と正面から向き合うことをテーマの一つに掲げてやっていますので、結局使う楽器にしても録音機材にしても 70s の当時物でやるのがメインにはなっています。ただ、エコーに関してだけを言えば、70s で当時物のエコーと言われると、はてさてこれはどうしたものか的な事になって、色々迷走してしまうのです。

70s のポピュラー音楽の録音は、結局「デッドな音がかっこいい」とされた時代なのでエコーはほぼほぼ部分効果の一つとしての使われ方が普通で、70s の音楽で今の音楽の見られるような通奏されるステレオ音像のエコーを求めるのは、そもそも違うというのはあります。じゃ、自分はそのままデッドな音でやれば良いかと言われると話はそんなに単純ではなく、イヤホンで街中の雑踏に塗れた音を聞くのがスタンダードな環境の中、エコーなしのデッドな音像が果たして世間にとっての印象に残る音になるのでしょうかと。無邪気にデッドな音でトラックを仕上げてしまうのには、まあまあハードルの高いものがありますよ。で、他の人たちはそこら辺、どう解釈しているんだろうと観察していると、オーガニックな音を作りたい人たちは、部屋鳴りをステレオセットのマイクで拾って、という方向にどんどん向かって行き、方やプラグインエコーを駆使する系の人たちはプラグインエコーをこれでもか、というほど挿しまくる方向に向かい、もはやエコーで作るステレオ音像なしで作られる音楽は、もう極々一部を除いては、ないも同然なのでした。
もう一点、70s のデッドな音がカッコ良く鳴るのはアナログテープの音を使って、プラグインEQの一切を使わないミキサー卓でミックスするしか、ああいうカッコ良さの音は鳴らせないという事も、やっていく内にどんどん分かってきてしまうと、まあ、自分はなんとかステレオ音像のエコーを使っても 70s 的な雰囲気を出せるようにやっていくしかないんだろうと。
なので、一昨年くらいまではプラグインの IR リバーブを使ってそれっぽい事をやっていたのですが、ある時ネットオークションで Roland の古いディレイ、SDE-2000 を深夜のハイな気分で冷やかし入札をしてましたら自分に落ちてしまい、仕方なく引き取って自分の曲で使ってみたら、これが異次元のディレイ音でハードとプラグインってこんなに別の物なの?という。それまで自分は実機エコーとプラグインエコーが、こうまで違うとは思っていませんでしたから、割と衝撃。こうなるともう IR とか使っている場合じゃないとなってしまい、結局そこからエコーもハードにする道を歩み始めてしまうのですけども。

とは言っても、ハードで70年代のレコードで使われているステレオなリバーブマシンを探そうとすると、鉄板 140 かスプリングの BX-20 くらいしかない訳で、さあどうしましょうという感じ。そもそも 140 は基本 60s でアイコニックな音とされる系なのではないでしょうかね?と思ったりもしており、70s でステレオ音像のエコー・・というこの無理難題。
どうしたらいいのか分かっていない状況で、ここで少し視野を広げてみますと、70s のシンセ音楽にクラウト・ロックと呼ばれるジャンルがあるのですが、そこでスラップバックディレイ的な音作りがなされる事が多く、言われてみるとディレイマシンのショートディレイの音をパンで振ってステレオ音像を作るのは 70s をやるならアリなんでは?と思い、70s 的なディレイマシンを探す事に。
リバーブで 70s は選択肢が殆どありませんが、ディレイマシンなら結構色んな物があり、そこで目に止まったのが Eventide 1745m。1745m はクラフトワークや、KISS の Love Gun などで使用されたディレイで、これは 70s のアイコニックな音と言える範疇の音なのでは?という事で色々調べてみることに。
そうしたら、1745m は発売が1975年、デジタルディレイ最初期の頃の機種なのでフィードバック機能が搭載されておらず、ディレイモジュールが3機入って入れば、それで3回遅れた音が鳴らせるだけの仕組みで、用途とすればショート・ディレイか、プレートリバーブのプリディレイしかない、という物でした。ただ、YouTube に上がっている試奏動画では、かなり自分が思う 70s の音が鳴っており、更にはジャイケルマクソン君のスリラーで Bruce Swedien が2台も使っているのを写真で見たりしてミーハー根性が爆発したりと、これは買うしかないでしょという流れに。

さっそく楽器検索サイトで 1745m を検索をすると、丁度自身の工房で整備した物を販売している業者さんから Bruce Swedien が使っている3機モジュール仕様の物が比較的安価で出ていましたので、即お取り寄せ。届いた物で音を鳴らしたら、もう素晴らしいクラウトロック的な音像が鳴らせてしまい、大満足なのでした。
もはや今、自分がやっている曲でエコーの基準は 1745m です。ここに揃わない音は全て却下しています。やったじゃん、70s なエコーの基準ができたよ、と思って、これでガンガン行けるぞ〜、と思っていたら、1745m と揃う音が鳴るエコーが他にそもそも少ないという現実にぶち当たってしまうのですけれども。
0 notes
Text
介護の備忘録 2
母は3年前に小脳出血で倒れ、救急搬送されたもののコロナで手術室が空かず、手術を受けたのが8時間後という、まあ、実質手遅れな状態で、もう手術をしないでも良かったのでは?的な状況でした。ただ、手術待ちの病院に親戚一同集まっている中、「発症後3時間以上経過しており手術をしても社会復帰はまず不可能、このまま手術をせず看取ります」とは言えないので、仕方なく手術をやった訳ですが、案の定、脳は壊れてしまっており、母は半分以上の記憶をなくし、全く別の人格になって戻ってきました。

まあ、それは良いんです。社会的な拘束力から「手術しません」とは絶対に言えませんでしたので、社会の一員である以上、その拘束力に従うのは薮坂ではありませんので。
問題はその後です。
社会復帰のできない人間を面倒見るのは医療ではなく、介護の分野ですから、段階的に母を医療から介護の現場に引き継いで行く訳ですが、まあ、言うとアレですけども、母の暮らす行政区は某宗教団体の影響力が経済にまで及んでいるであろう系の行政区で、病院から次の施設に移る過程で、特定宗教の経済圏に囲い込みに逢ってしまい、移る施設の選択に物凄い苦労をさせられてしまうのでした。
病院からリハビリ病院に転院する際は、手術をしてもらった病院が運悪くその特定宗教の経営する病院でしたから(救急搬送なので選べません)、結局そういう系の施設以外への転院手続きを思いっきり煩雑なものにされて��なら宗教経済圏内のリハビリ病院にしましょう♪ 的な案内しかして貰えないのでした。リハビリ病院そのものが都内でもそんなに多くはないので仕方がない面はあるにせよ、ちょっと嫌な感じでしたね。とりあえずウチもその系列のリハビリ病院でリハビリをする訳ですが、社会復帰は当然できませんから、その後、有料老人ホームに行くのか特養に行くのか、の選択で特養は入所待ちになりますから有料老人ホームしかありませんよ〜的な説明をして、こっちが聞かなければ「老健」の説明を省いて物事を進めようとするのは、いかがなものかと。
母のようなケースで特養の入所待ちをする場合、老健という施設が一時的に入所待ち期間中の面倒を見る機能を、厳密には老健はそういう施設ではないという位置付けなのですが、請け負ってくれるケースもあるのです。なので、老健という選択肢も最初から有料老人ホームと併せて説明するのが筋だと思いますが、母が入った特定宗教経済圏のリハビリ病院はそうはせず、在宅介護か有料老人ホームですと、そして提示してきた有料老人ホームはその特定宗教経済圏のグループ企業と思われる某チェーン店方式の、一般的には「料金が高い」と評判のホームばかりでした。

(本文とは関係のないイメージです)
そもそも老人ホームには入る人との相性がある訳です。老人ホームの紹介センター的な所で色々話を聞けば、民間の老人ホームは数多あり、その特徴や風土にも様々なものがありますのでご家族と一緒に相性の良い所を慎重にお選びください、と案内される訳なので、提携企業のチェーン店方式のホームと、一つだけパッとしないホームを間に挟んだだけ、という仕事をした時点でその人には何も任せられないですよ。
その後、色々頑張りましてとりあえずその特定宗教経済圏からは脱出できたと思いますが、選んだ老健はあまり良い施設ではなく、正直、失敗したな・・とは思いました。コロナで内部を見学させて貰えなかったので、そこが母に合わない所だとは、外からは分かりませんでした。だからと言って、特定宗教経済圏に止まる選択肢もありませんので、これはもう運が悪かったという理解で納得しました。
その後、まあ、更に色々ありましたが(なんと在宅介護になってしまった)、諸々省略。脱力です。
最終的には、母は長年暮らした行政区の特養に無事に入所でき、今、人生のアディショナルタイムを無駄に浪費している感じですが、でもこうするしか仕方ありませんでしたので、後悔とかはありません。母が今の特養に入ったのが良かったのか悪かったのかは、正直分からないです。頭が壊れていない状態の母なら「嫌」と言ったはずの施設を「ここは良い所よ〜」と言っている姿を見ると、周りで一生懸命考えてやってあげても、もう物事はなるようにしか回っていかないんだな、という感じです。実は特養も、頭が壊れていない母ならここが好きそうという所を一生懸命選んで、ショートステイを申し込んで、母が馴染めるように、職員の方々にも覚えて貰えるように、こちらでやれることは全部やりましたが、結局そういう所への入所は一切叶わず。あんまり良い所じゃないな・・と思っていた所に、導かれるように決まり、本人はそこを「ここは良いとこよ〜」と大変気に入ってしまうのでした。まあ、周りがどんなに一生懸命やっても、結局その人の星回りには誰も逆らえないという、そういう学びを得たんだと思います。
追記:リハビリテーション病院の在宅復帰相談員の人が提携企業のチェーン店方式の老人ホームばかり紹介してきた、というのも、そういう対応をされて満足してしまう家族が、結局多いんだろうと。皆んなと一緒になれてアタシ達幸せです、という人が圧倒的に多いからああいう仕事が成り立つんだろうと、後から理解したものはあったかもしれません。
0 notes
Text
ChatGPTと白雪姫
対話型AIが登場してしばらく経ちましたが、これは革新的だ、と思った人が意外と少なかったようで、あとは少し気になったこともありましたのでブログにしておこうかと。
そもそも対話型AIの仕組みを皆さん、あまり良く理解されていらっしゃらないのかもと思い、ざっくりその仕組みを書きます。
以下の話はこちらの書籍から参照していますので、ちゃんと理解したい方はこちらの書籍を読まれる事を強くお勧めします
対話型AIは、簡単に言えば人の会話を言葉と言葉の連鎖の中で使われる組み合わせの確率を割り出して、その確率の高い連鎖を何パターンか出力してみる、という仕組みなのだそうです。例えば私、猫、好、という単語を使った組み合わせは「私は猫が好き」であったり「私が猫に好まれる」であったり、はたまた「私に猫と好み」のようなものまで様々なパターンが想定される訳ですが、その中から前後で使われる言葉の種類から、私、猫、好、の組み合わせとして確率の高い言葉の組み合わせを出力する、という仕組みなのです。つまり、対話型AIで、言葉の意味を分かっているという状態では全くなく、単なる言葉の組み合わせの確率論がそこにあるだけなのだそうです。
ということは、ここで一つ大きな問題が生じてしまう訳ですが、例えばある質問の中で使われた言葉の組み合わせから、何を選べば次へ続く言葉の組み合わせとして「正解」になるのかを確率だけで出力してしまえば、例えばEU反対派の人たちが良く使う言葉の羅列の次に選ばれる言葉の組み合わせの次に続く言葉としては、「EUは解体していく可能性がある」系に自然となっていってしまうと。逆にEU賛成派の人たちが良く使う言葉の羅列から選ばれる、次に続く言葉の組み合わせとしては「EUが解体される可能性は低い」系になっていく訳なので、これはつまり、SNSの利用で見られる「同質の意見どうしを強化し合ってしまうエコーチェンバー現象」の増長になっていませんか?という懸念が生じる訳です。
例えば、欧州の若者、就職先、働く国、多様性、メリット、という単語の組み合わせと、ロシアの安価な天然ガスの入手、ドイツ、グリーンディールの実現性、インフレ、現実的、移民問題、という二通りの言葉の組み合わせを、EUの未来を予想して欲しい旨のプロンプトでそれぞれを対話型AIに入力してみてみると、それぞれ対照的なニュアンスの回答が返ってくるはずです。(もちろん、一方の言葉を反対の意味になるように入力すれば、両方同じニュアンスの回答が出力されます)
EUの将来程度の話なら、現状では全く予想ができませんので、どちらのニュアンスで出力されようがあまり大きな問題にはなりませんけども、それが例えば美しい音楽が生き残るのは必然か?や、音楽のプロとは何か?のような、人それぞれの立場や都合の占める割合の多い、そして感情論にもなりやすいテーマでこの言葉の選択方法を用いてしまうと、これは対話型AIを使う人を、かえって孤立化させてしまわないですかね?という。

同質の意見で強化された決して客観的ではない意見を、客観的のお墨付きを得た意見なのにぃ!的な、心の闇が個人の中で蓄積されていきませんか?と。これは白雪姫のストーリーの中に出てくる魔女の鏡と一緒の現象ですよ?と。最後は、「鏡よ鏡、鏡さん、世界で一番美しい人は誰~れ?」と聞かれて「白雪姫です」などと答えてたら、魔女さまはブチ切れてしまうんですよ?
と、思っていたら、対話型AIを利用する人はとても少なく、2025年2月現在で、全体の1割未満である的な話を聞いて、まあ、それならまだ救いがありますよね・・という感じにはなったのですけども。
対話型AIを利用する人が少ないのは、結局その出力精度がオタクの需要にマッチしないからなのではないかと、個人的には考えたりしています。生成AIは、ニッチなジャンルの知識量ではオタクには敵いませんので(当たり前です、AIはそういうものです)、そこでオタクが「俺の方が凄い」と見下して終わってしまっているのかもと。新しい技術は、オタクが最初に熱をあげて、それから一般にドミノ倒しのように普及していく(by 秋元康)性質のものなので、オタクが使わないと一般には普及しないのかもしれないと。
そういう意味では、今の普及率のままなら対話型AIはサービス停止に追い込まれる可能性は高く、対話型AIを提供するベンダーは何としても一般への普及を成功させないといけませんので、それは今のような形ではもう難しいという結論が出ていそうな気はします。色んな事を多角的に推論できる機能なんて、一般の人たちは使わないんですよ。そんな事より一般の人たちは日常業務で「楽ができる」「俺は凄い」の方が大事で、それは結局、事務仕事のショートカットを生成する、くらいしか使い道を思いつかない、ということなのではないでしょうか。
なので、ブレーンストーミング用のツールとしての使い方なんて、生成AIとしては近い将来衰退していき、対話型AIは、事務仕事のショートカットが誰でも簡単にできます!とかいうアプリケーションに特化した形での利用に制約されていくのでは?と予想する訳ですけども。なんか、あまりにも勿体ないですけども。もっとも、対話型AIが心の闇の増長ツールとして普及してしまうよりは、ここでオタクに「俺の方が凄い」と思われて衰退していく方が、人類の為なのかもしれませんが。分かりませんけども。
0 notes
Text
介護の備忘録 1
介護の現場を、介護される側の家族として一通り経験したので、備忘録として経験を残しておこうかと。

(本文には関係のないイメージです)
実家のある都内某区の状況を言えば、既に逼迫している様子は十分に伺えます。もっとも、某世田谷区は既に実家の行政区より更に逼迫しており、母はとある事情で某世田谷区の介護施設に一時的にお世話になったことがあったのですが、ケアマネジャーを筆頭とした介護職員の皆様方は常時イライラされ、介護される側が不慣れであっても(こっちは介護なんて初めての経験ですが)、介護される側の不備などを容赦無く叱責して来られる状態でした。まあ、社会には色んな方々がおられますから、とにかく自分の都合、自分の都合を言って何が悪いの?アンタたち介護の仕事でしょ!というタイプの方々が、世田谷区は多いんでしょう・・というのは、もちろんご理解差し上げます。大変ですね。実家の方もこれから団塊の世代の大量の看取りを迎える都内最大級のベッドタウンの一つには違いなく、世田谷まではいかなくとも、今のままでは済まなくなる可能性は十分にあるとは思いました。
実家の行政区が無策のまま団塊の世代の看取りの季節を迎えるというのも考え難く、おそらく何らかの準備をしているであろうということは、もちろんこちらの憶測でしかありませんけども、まあまあ散見されるのかなと。
単純に、特養施設は入所者の回転率を上げるしか、諸々回らないでしょうから、それを今から少しづつ実行しているのは、可能性としてはあっても驚きはありません。実家の行政区では区の HP で特養施設の入所申し込み状況を公開しており、パッと見れば人気の施設と不人気の施設、という感じで、そこに掲載されている表を理解することができるとは思いますが、実際に施設に見学に行けば、不人気の施設は、まあ、そういう機能を任されているんだろうな・・というのが推測できる感じでしょうか。
申し込み待機人数が他と比べてかなり少なく空き床数も多い所は、おそらく回転数を上げる役割の施設なんだろうと、実際に見学に行けば “そういう” 臭いを感じることができたりするのでした。施設内の雰囲気、衛生管理、食事の内容、などなど。個人の感想です。なので、数字的な偏りは、そういうことの表れであろうと。例えば高齢者は食事の匙加減一つであっという間に衰えて行きますから、ベッドの回転数の調整は、そういう所でも普通に可能であることは、自分の在宅介護2年半の経験から、実感としてあります。

(本文には関係のないイメージです)
ベッドの回転数を意図的に調整する事の倫理観は、正直、もう言っていられる状況ではないだろうな、と。例えば認知症が進行してしまい、もう特養では面倒見れません、となれば次はグループホームでの相互監視の生活が始まりますし、それでも手に負えなくなれば、もうどうするの?という。それが団塊の世代の看取り季節が本格化すれば、ドッと増える訳です。介護の費用も国持ちになりますので、それは色々どうなんだろうと。
実家の行政区では “そういう” 役割の施設と、そうでない施設に分かれている、ともちろん断言はしませんが、入所の相談をする際、平均的な入所期間を「5年」と説明される施設と「2〜3年」と説明される施設と、あとは見るからに環境の悪い所とに分かれます。個人の感想です。2〜3年のアディショナルタイムなら、十分倫理問題もクリアしていると、個人的には思ったりはします。
残酷系の話はこれくらいにしときますが、もう一つ、在宅介護をどこでやるのかという所で施設への入所の判断がそこそこ左右されるということは、あまり知られていないかもなので、それも書いておきます。
母の在宅介護は僕が今暮らしている行政区でやって、母の住民票は実家に残し、実家の行政区の介護保険を使って母の介護をやった訳ですが、実家の方の施設は「息子の行政区に行け」という圧をかけてくる感じでしたね。なのでこっちの施設やケアマネージャーに相談すると「こっちに来るな、実家の方に残れ」という話になってしまい(そりゃそうですよ、こっちの行政区だって介護の人数を増やしたくない訳ですから)、母の特養への入所は、割と延び延びにされてしまった経緯が、ウチの場合はありました。実家の方の施設は「そっちの行政区はまだ余裕があるだろ、そっちで面倒見ろ」的なことな訳ですが、母は実家大好きな人ですからこっちに住民票を移すのは無しで、息子はとても困りましたよ。最終的には実家の方の施設に入りましたが、母は在住50年以上ですから(それだけそこに納税してきた)、当然ですよという事しか自分は思っていません。実家の行政区の施設何やってるんすか?という事は印象として、強く残りましたね。
0 notes
Text
あけましておめでとうございました
この年越し連休は結構ギターを練習しました。おかげでギターを弾く身体が大分戻ってきた感じはありますが、でも若い頃の弾き倒していた頃の感覚は流石に戻りません。まあ、弾き倒していたのはもう25年以上も前の話なので、1ヶ月やそこらで戻るはずもなく。

練習はやっぱりコピーです。スケール練習的な事も少しはやりますが、なんと言っても YouTube 動画のコピー。海外のヴィンテージギターショップが楽器のデモ演奏を地元の達人を使ってアップしているのが、これが手がまるまる見える素晴らしい教材な訳です。音もくっきりはっきり聞こえますし、これを真似しない手はないという。
アメリカのローカルカントリープレイヤーの演奏がこんな身近で見れるなんて、なんて良い時代になったんだと思います。皆んな、ホント上手いしカッコいいんですよ。若い頃にこれだけ情報量があれば、もっと違った練習ができて、もっと上手になれただろうな〜、なんて思う訳ですが、まあ、仕方ないす。
エレキとアコギと二種類やりましたから、結構な分量で腕と肩がじんじんしてますけども、やっぱり楽しいです。とりあえず、こうやってまとまった時間、ギターを弾けるのも年末年始だけなので。
今年はなんとか自分の曲のギター入れをやれたらと。ギター入れをやるなら、介護期間ですっかりふにゃふにゃになった身体をもう少し戻したいので。今の状態じゃちょっと・・です。普段ギター弾いてない奴がギターを弾いても、コイツ弾いてねーな、て一発で分かりますもん。楽器なんてギターに限らず、全て身体から鳴らせない奴は偽物。あなたも偽物。私も偽物。ああ、そのまま、バレバレのまま。
0 notes