#延浄寺
Explore tagged Tumblr posts
Text
柳谷観音楊谷寺
京都府長岡京市にある浄土宗の寺院。806年(大同元年)平安時代、清水寺を開山された第一世延鎮僧都により開創されたため、西の清水寺とも呼ばれる。

京都の西の山中にあるため駐車場完備

立派な石垣

江戸前期建立の本堂

本堂内に入って間近かで御本尊様十一面観音様にお参りできる。




本堂からそのまま庫裡に向かえる。見事な庭園を眺めて暫し一服

上の建物は上書院といって特別なお客様をお迎えする間で別料金で入ることができるが今日はパス

上書院の脇からそのまま奥の院に行ける

階段の上から見た名勝庭園「浄土苑」

更に廻廊の階段を登る

上から見た感じ

上まで上がって先程の回廊を眺める

洛西観音霊場第10番札所の奥の院



奥の院の守り神眼力稲荷

因みに下の本堂の裏にも守り神として眼力稲荷堂がある

その横にある夫婦円満の愛染堂

石造りの多宝塔

納骨堂

階段を下って山門に戻る

江戸時代建立の阿弥陀堂

#photographers on tumblr#photo#photography#tour#cool japan#instagood#travel#バイクで行く景色#touring#二輪部#kyoto#temple#パワースポット#京都#長岡京#柳谷観音#眼病治癒#あじさい#紅葉#history#阿弥陀#観音様
16 notes
·
View notes
Text
【常不軽菩薩(じょうふきょうぼさつ)って、どんな話のどんなキャラ?】
『法華経(AD1世紀ころインドで編纂)』という大乗仏教の超重要経典に出てくるキャラクターやね。
● ストーリー
常不軽菩薩は、ひたすら人に会うたびに
「私はあなたを軽んじません。あなたは必ず仏になれるお方です」 と言って、合掌礼拝する。
それだけ。説教をゴリゴリやるんやなくて、
ひたすら相手を尊重して礼拝
でもそれが逆に
「何やお前、偉そうに!」
「うざい!」
って受け取られて、石を投げられたり棒で追われたりする。
それでも
「すみません、でもあなたは仏になれるお方です」
と繰り返し、最後はその誠意が人々を動かし、法華経を広め、���分も仏になる。
● 雰囲気のイメージ
・めっちゃ真面目で不器用 ・空気読めないけど悪気はゼロ ・「人を尊重する」一点でブレない、究極にしつこい誠実さ ・嫌われてもやめない鋼の信念
ある意味「宗教系の天然キャラ」やけど、法華経では
「仏になれることを全員に認める態度の究極例」 として大事にされとる。
【『法華経』での意味】
『法華経』は
「すべての人は成仏できる」 を説く大乗仏教の中心経典。
常不軽菩薩の話は
「教義を押しつけるんやなくて、相手を仏として敬う」 という、法華経が重視する実践的な菩薩行のモデルやね。
【中国の「智顗(ちぎ)」】
この法華経を中国でガッツリ体系立てたのが
天台宗の開祖、智顗(538~597)。
智顗は
「法華経こそ仏教の最高峰」
「常不軽菩薩の礼拝行は理想の修行法」
と位置づけた。 要するに
「仏性はみんなにある。相手を仏として礼拝せよ」 という思想を徹底した。
【日本の「聖徳太子」】
日本では飛鳥時代に
聖徳太子が『法華経』をめっちゃ重視。
彼が書いたとされる『法華義疏(ほけぎしょ)』は、日本初の仏教経典注釈書ともいわれる。
太子の国家理念づくりの中心にも法華経の
「みんな仏になれる」 「互いに敬う」 という思想があった。
【最澄と比叡山延暦寺】
平安時代、最澄は
「法華経こそ日本仏教の根本」 と主張して 天台宗を開く。
比叡山延暦寺は
法華経の教えを日本で徹底的に学ぶ場
「常不軽菩薩の礼拝行」を理想の菩薩行として重視
最澄自身も
「一切衆生悉有仏性(いっさいしゅじょうしつうぶっしょう)」 (すべての存在が仏になる可能性を持つ) を説き、日本仏教に大きな影響を与えた。
【比叡山で学んだ人たち】
比叡山延暦寺は日本仏教の大学みたいなところで、日本中の僧侶がここで修行した。 有名なのが:
法然:念仏による阿弥陀仏の救いを説く。浄土宗を開く。
親鸞:法然の弟子。より徹底して阿弥陀仏に帰依する浄土真宗を開く。
道元:曹洞宗を開く。ひたすら座禅する「只管打坐」を強調。
日蓮:法華経を唯一無二の教えと位置づけ、「南無妙法蓮華経」を唱えることを説く。
みんな若いころ比叡山で天台宗、つまり法華経の思想と「常不軽菩薩みたいな礼拝行」をしっかり学んだんや。
【まとめ】
✅ 常不軽菩薩 → どんな相手も「あなたは仏になれる」と礼拝し続ける、超真面目で空気読めないけど究極に誠実なキャラ。 → 『法華経』の「全ての人に仏性がある」という思想の象徴。
✅ 法華経 → 大乗仏教の中心経典。「誰でも成仏できる」と説く。
✅ 智顗 → 中国天台宗の祖。法華経を仏教の最高経典に位置づけ、常不軽菩薩の実践を理想化。
✅ 聖徳太子 → 日本に法華経を国家理念レベルで導入。
✅ 最澄・比叡山延暦寺 → 法華経を日本仏教の核に据え、常不軽菩薩の礼拝行を理想の修行法にした。
✅ 法然・親鸞・道元・日蓮 → みんな比叡山で法華経を学びつつ、それぞれ独自の道を切り拓いた日本仏教の巨人たち。
「常不軽菩薩」っていうキャラを理解すると、日本仏教の基礎に流れてる
「誰でも仏になれる」「相手を尊重する」 って思想のイメージがめっちゃつかみやすくなるで。
もし
もっとざっくり要約
もっと専門的に
物語風
とか、別バージョンが欲しかったら気軽に言うてや!
3 notes
·
View notes
Text
反万博フィールドワークに参加!

1月18日、大阪・関西万博反対のために立ち上がったバビロン解体企画のお招きで、反万博フィールドワークに参加するため訪阪した。

新大阪駅を降りるとさっそく駅構内に万博プロモーションが登場。商店街にも、数メートル感覚で万博ののぼりが並ぶという異様ぶりである。

集合場所の扇町公園に集まった約10名ほどの参加者たちは、皆、思い思いのプラカードやバナーを作る。これを、これから訪れる万博関連施設などで掲げフォトアクションを行うのだ��
まず私たちは扇町公園を出て淀川へ向け歩いて北上。途中、ストリップ劇場「東洋ショー劇場」を通り過ぎる。ここでは2024年11月にダンサーら10人が逮捕されるという弾圧が起こった。東京五輪前の2021年にも上野のストリップ劇場が弾圧を受けたように、これも万博前の「社会浄化」の一環と目されている。メガイベントに際したストリップ劇場の弾圧と、抗議や文化としての裸体についてはバビロン解体企画のzineにある「ハダカとバンパク」が興味深いので是非読んでほしい。


町内会の看板も万博仕様。

続いて訪れたのは国分寺公園という小さな公園。ここには万博開催中の1970年4月に起こった大阪地下鉄建設中のガス爆発事故の慰霊碑が建っている。死者79名、負傷者400名余り、26戸48世帯が焼失するという大惨事だったという。慰霊碑には「今後都市の建設工事を実施するにあたってはさらに安全性の確保に努め再びこのような惨事を引きこ起こすことのないように」と書かれている。ところが、現在推進されている2度目の大阪万博では既に2024年3月にメタンガスによる爆発事故が発生。ゴミの埋立地であった夢洲では、またいつこのような事故が起こってもおかしくない。過去から学ばず、開発を優先し過ちを繰り返すこの国の情けなさがここでも見て取れる。

さらに歩くと、なんと��博仕様のマンホールが登場!東京五輪のときもありましたね!くだらないことに税金を使うんじゃないよ!

ここは淀川河川敷。広々とした風景を切断するように白い鋼板が建てられ、何やら工事をしている。これは淀川左岸線延伸部整備事業といい、2011年に政府の都市再生プロジェクトとして位置づけられた全長8.7㎞の道路建設計画である。しかし、この一部が万博の際に大阪駅や新大阪駅から万博会場を結ぶシャトルバスの専用道路として暫定的に利用される予定だという。

また、この工事の一部は大深度地下を活用している。つまり、地中深くであるから地表の地権者の了承は必要ないというものである。しかし、この大深度地下を活用した工事においては既に2020年東京で外環道の工事によって地面の陥没事故が起きている。
この淀川河川敷を散歩コースとして拠り所としていたフィールドワーク参加者は「散歩を返せ」と強く憤っていた。


私たちは電車を乗り継ぎ湾岸部へ。ATC(アジア太平洋トレードセンター前)周辺は、まるで東京の湾岸エリアのよう。荒涼とした空間の中に、大阪入管もそびえている。



建物の中には万博オフィシャルショップや万博支援自動販売機!(東京五輪のときもあった!やっぱりコカ・コーラである。)この自販機の売り上げが、万博の機運醸成活動に利用されるのだという。誰が買うか。

ATC内に掲示してあった万博作文コンクールのポスター。東京でもオリパラ教育が強要されたように、万博もまた子どもたちを洗脳しようとしている。


万博の初日に皆で「第9」を歌いましょうというチラシ。なんと参加者は2万円支払ったうえに3回のレッスンを受けなければならないらしい。こんなのやりたい人いるのか。

展望台に登ると、西側に万博会場である夢洲が見えてくる。344億円かけたという空しいリングでそこが夢洲だとわかる。手前はコンテナふ頭、右手の更地はカジノ建設予定地だ。既に各所で言われている通り、夢洲に出入りするには夢舞大橋か地下トンネルの2つしかない。事故や災害があったらどうやってこの島を脱出するのか、考えただけで恐ろしい。

ここでもバナーを掲げ、反万博をアピールする。あちこちに貼られた万博ポスターは「すごいぞ!」などの空虚な言葉ばかり。

衝撃的だったのはこちら。大阪メトロの各駅に設置されている顔認証自動改札機(!)。東京五輪の際も、五輪会場のゲートでNECの顔認証システムが採用されていた。また、JR東日本は2021年7月から主要駅や車両基地、変電所、線路沿線などに約8350台もの監視カメラを設置して通行人の顔情報を取得し①過去にJR東日本の施設内で重大な罪を犯して服役した人、②指名手配中の容疑者、③うろつくなど不審な行動を取った人を検知していた。批判を受け、①については検知を見直したが②と③は継続しているという。メガイベントのたびに監視システムはどんどん強化され、私たちの個人情報は奪われていく。大阪万博でも同じことが起ころうとしている。

最後は12月1日に強制執行があったばかりの釜ヶ崎へ。JR新今宮を挟んで向かい側、かつて遊園地フェスティバルゲートが撤退して以降長らく空地だった場所には、いま高級ホテル・星野リゾートがそびえたっている。労働者の街・釜ヶ崎を、観光客やミドルクラスのための街に変容させようというジェントリフィケーションの象徴のような場所に、大阪万博を宣伝するきらびやかなプロジェクションマッピングが施されている。私たちはこの場所で、万博反対の最後のアピールを行い、フィールドワークを終えた。
実際に街を歩いてみると、メガイベントがいかに私たちの生活に侵食しているかがよくわかる。たとえ興味がなかったとしてもだ。東京五輪のときも酷かったことをありありと思い出した。その中で、反万博を訴え、プラカードやバナーを掲げ、街の景色を少しだけでも変えることができた。この一日に参加できたことを有難く思う。
2 notes
·
View notes
Text


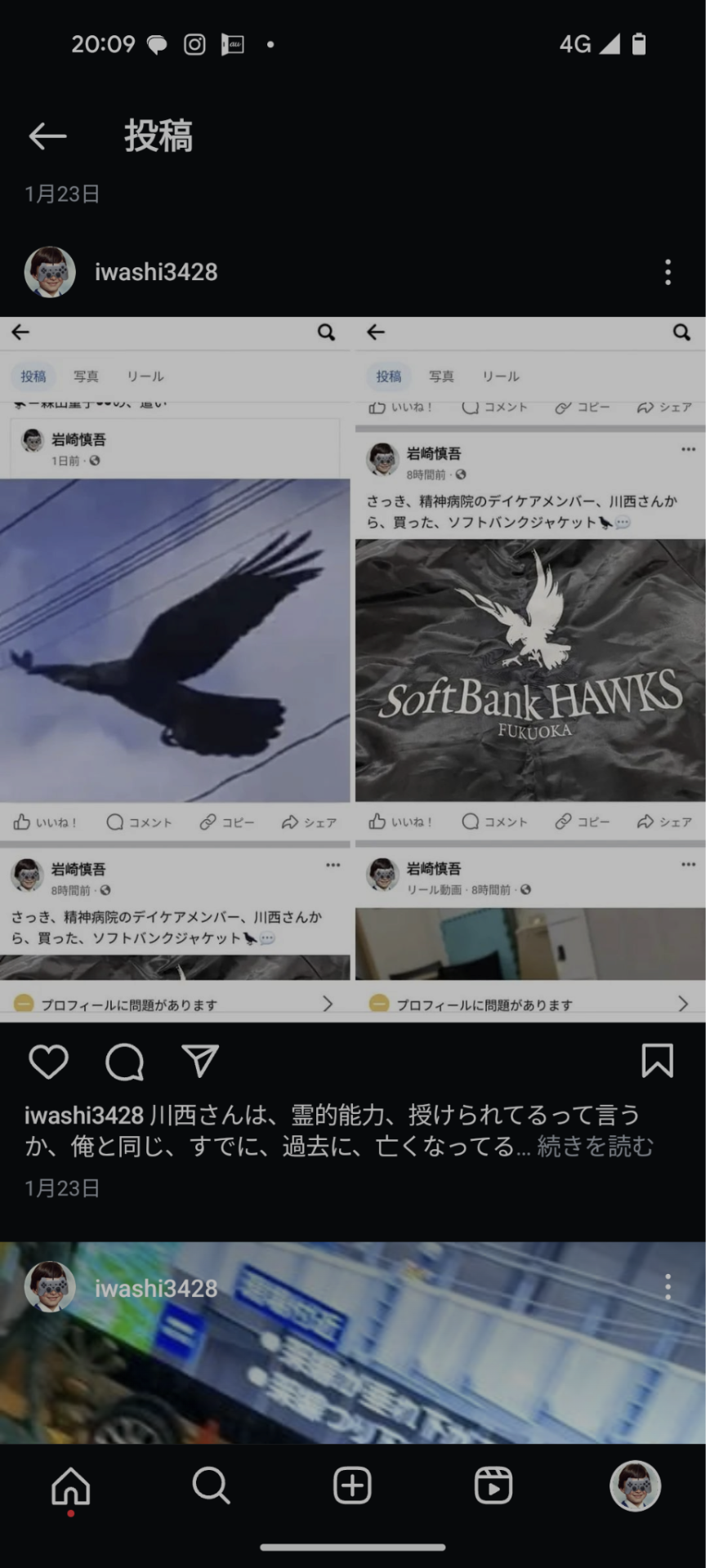
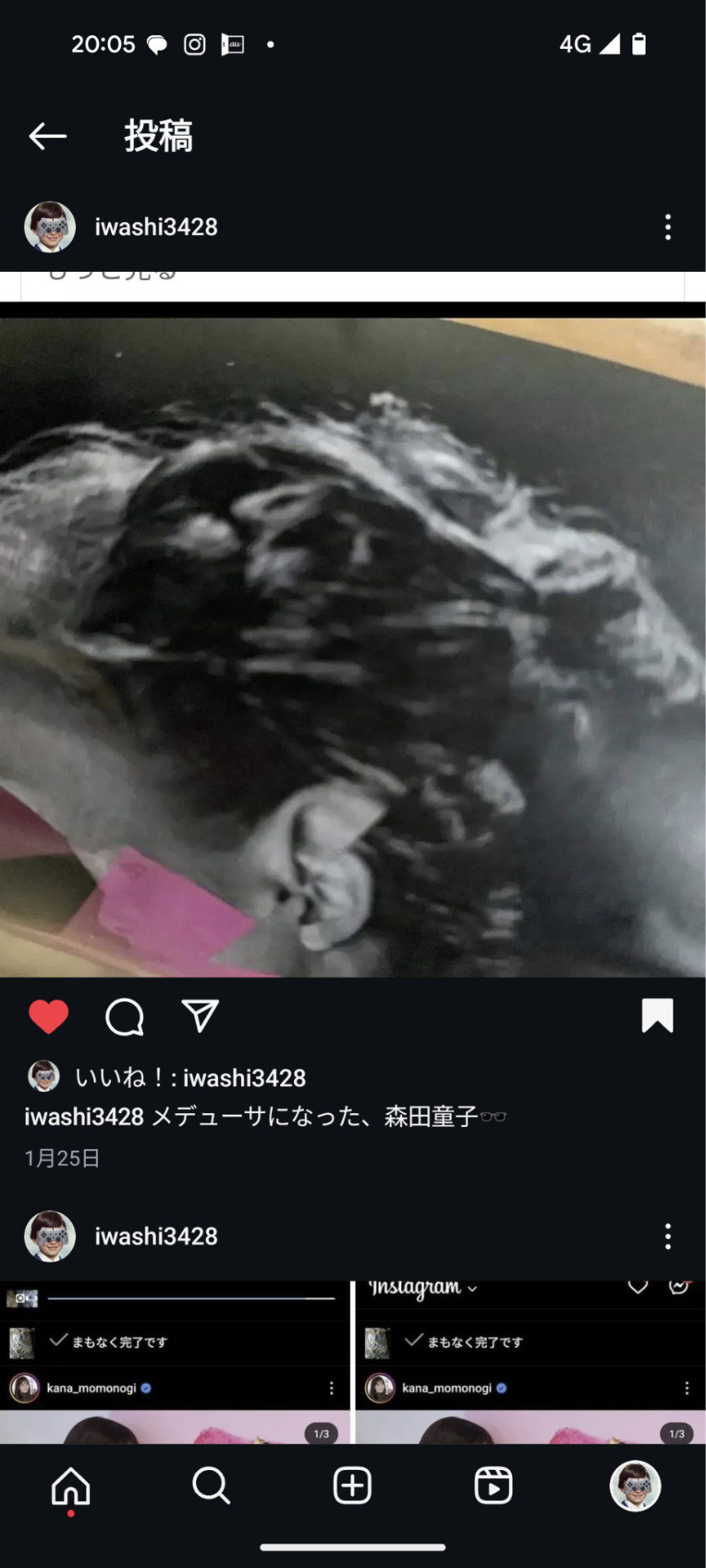



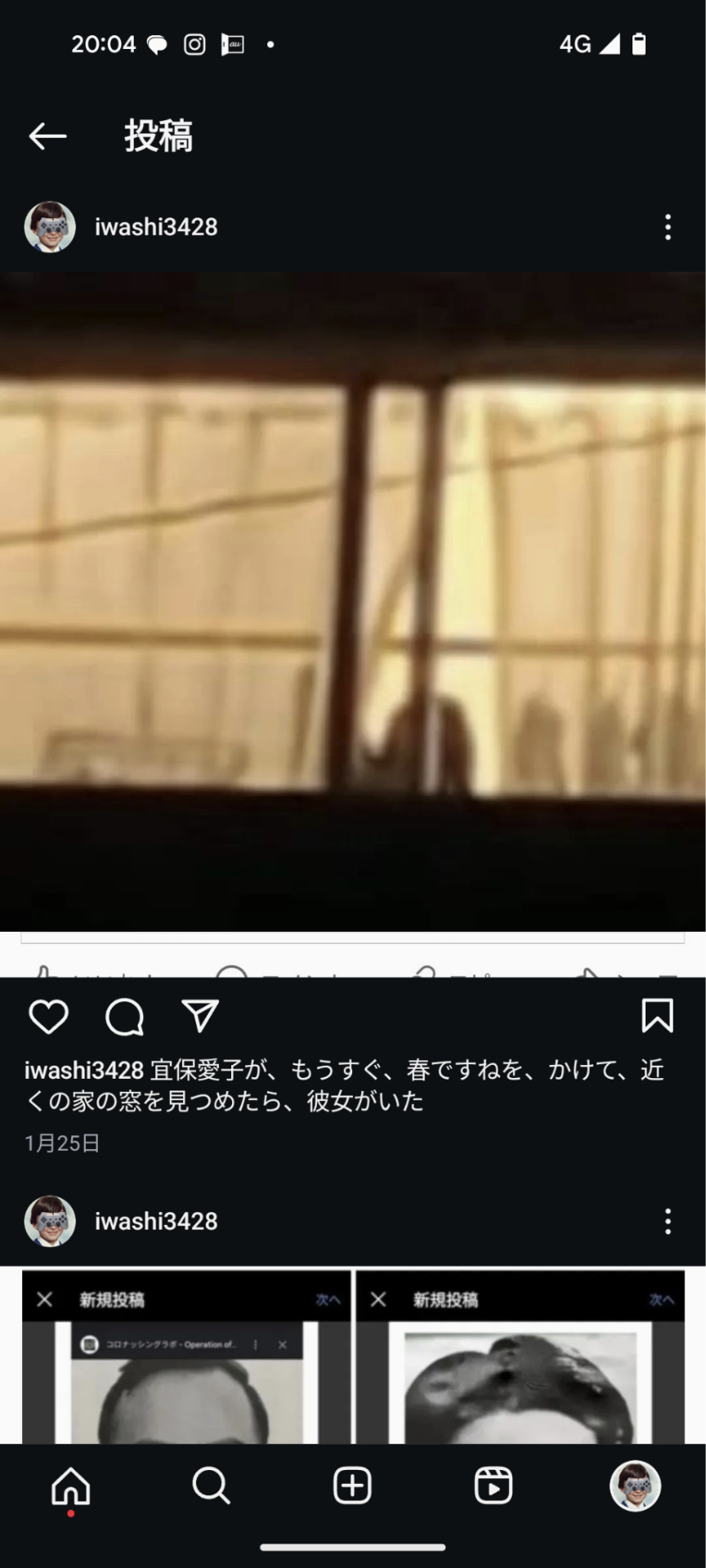

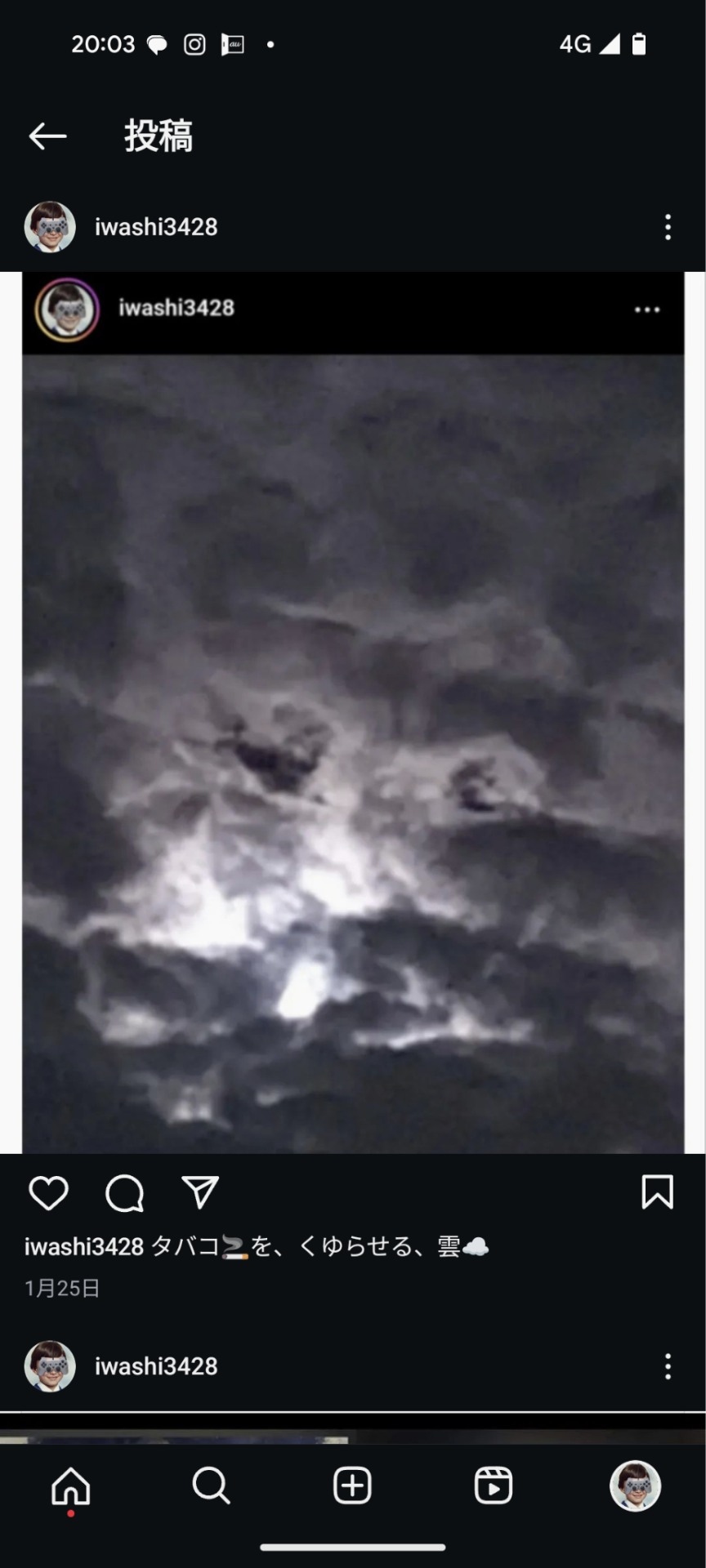
遺骨、酸初、初夏、夏至、我博、臨床、先客、那波区、東海、雲海、雲水、初楽、飼養、規律、滅法、頑丈、撃破化、内板、飼養、機咲州、分癖、蛾妙、頌栄、丼爆発、濃彩、恋欠、名瀬、徒歩機、歌詞役、素市、癌滅、元凶、願文、文座、同發、長門、至極、極美、呵責、端午、併合、奈落、底癖、幕府、某尺、尊式、検疫、未除、路側、柑橘、脂溶、瑛人、冠水、豪材、剤枠、土岐、駄泊、検尺、漏洩、破裂無言、任期、崩説、全滅、壊滅、開幕、統帥、頭数、水湿、冠水、抹���、網滅、馬脚、財冠水、風隙、来妙、勤学、餞別、名判、名盤、観客、衆院、才覚、無能、果餓死、損初、波脈、釋迦、損失、片脚、那古、可物、筋層、真骨、存廃、破格、名湯、今季、写楽、苦況、罪責、孫覇、全滅、今父、奈落、旋盤、秒読、読破、名物、貨客、泉質、随想、滅却、監理、素質、遡行��文滅、菜根、無端、庄屋、破壊、客率、合併、豪式、続発、泣塔、透析、頑迷、場脈、野張、船室、乾物、吐瀉分裂、戒行、噛砕、爾、晩別、海苔、西明、縁月、花月、独歩の大蛇、再発、納言、遺言、残債、背角、破壊、忠膵癌、統帥、馬車、下劣、火災、乱尺、毒妙、縫製、貨坂城、歳発、富低落、菜初、命式、山賊、海剤、激武者、瓦礫、破水、分裂、賀露、屠畜、能月、見激、破壊、破戒、採石、屈託、門別、皆来、家来、千四、我楽、夏楽、無慈悲、壊滅、破棄、損勤学、外鰓、長水、瑛人、永久、旋律、斑紋、財年、場滅、甘露、舐めけり、真靭、察作、論祭、乾裂、薩長、泣塔、室見、川縁、岩石、言後、荷火災、防爆、鋒鋩、体制、貨車、顎脚、刺客、坐楽、損益、脳系、文才、分合、合壁、啓発、萌姫、島内、監修、真木、合理、独房、雑居、紋発、乱射、雑念、五輪、三振、欄居、托鉢、紋腹、画狂、欠年、射殺、殺傷、脳初、目車、濫用、懸念、學年、身者、卓越、餓死、軟卵、場者、童空、我作、滅法、涅槃、抹殺、怒気、燃焼、略奪、宰相、馬腹、刳発、南山、活発、沙羅、割腹、殺戮、循環、奈良、菜道、紗脚、残雑、颯和、和歌、東風、南富、背面、焼却、四季、同發、博羅、無償、透明、明闇、雲海、陶酔、溺愛、泊雑、湖畔、花車、小雑、蘭風、雑魚寝、逆発、罵詈、検遇、明細、鳥羽、無数、飾西、涼感、割烹、面月、略発、明暗、御覧、絶滅、名者、焼却、野版、絶筆、数界、洒落、羈絆、四索、敏捷、旋律、脚絆、安行、軽安、難産、伊賀、消滅、生滅、巡数、水災、万華、論発、処住、崇拝、年月、画鋲、我流、剣率、草庵、律年、雑魚、規約、貨車、蒸発、重大、錯乱、蓮妙、奈良、坐楽、延宝、財年、爆発、龍翔、日向、塁側、席園、座札、風評、財年、何発、旋律、画狂、論券、戦法、尊師、大概、二者、那波、麺期、演説、合邦、放射、雑律、貨客、選別、燕順、考慮、試薬初、財源、富、符号、井原、若榴、清涼、無數、才覚、絶望、奈落、奔放、有識、台東、詮索、懸念、病状、設楽、宴客、怠慢、時期、同部、弁解、冊立、立案、前略、妄動、侮蔑、廃絶、間髪、図解、経略、発泡、者発、立案、滅鬼、自利、論酒、桜蘭、五月雨、垓年、処理、短髪、散乱、絶滅、命日、庵客、実庵、龍翔、派閥、同盟、連峰、焼殺、勝中、割裂、残虐、故事、量発、敗残、花夢里、面月、原氏、雑考、推理、焼殺、膵癌、導風、千脚、砂漠、漁師、活滅、放射、洋蘭、舞妓、邪武、涅槃、毛髪、白藍、他式、民会、参謀、廃車、逆発、峻峰、桜蘭、殺戮、銘客、随分、刺死、脳犯、我版、論旨、無垢、血潮、風泊、益城、拝観、舘察、懺悔、空隙、髭白、模試、散乱、投射、破滅、壊滅、下痢、他殺、改札、寿司、葉式、魔雑、渾身、等式、命日、安泰、白藍、良志久、中須、掻敷、北方、監視、血式、血流、詐欺、加刷、販社、壊滅、坐楽、白那、苫小牧、欄物、演説、開脚、摩擦、欠史、宰相、掻敷、飾西、近隣、可能、刺自虐、崑崙、独歩、良案、隔絶、菜作、妄動、犬歯、核別、概要、立案、破格、殺戮、良案、快絶、防止、那古、風別、焼安泰、独庵、囲炉裏、壊滅、外傷、刃角、視覚、耳鼻、下顎骨、子孫、剥奪、憂鬱、優越、液状、先端、焼子孫、兵法、那波、安楽、最短、数式、絶句、庵杭、雅樂、動乱、者妙、垓年、独初、前報、奈落、数道、弓道、拝観、俯瞰、散乱、男爵、害面、炎上、抹殺、破棄、分別、額欄、学雑、宴客、体面、村落、柿区、害初、告発、欄式、体罰、侮蔑、浄光、情動、差額、君子、何発、兵式、童子、飾西、各滅、我札、審議、半旗、普遍、動脈、外傷、無償、木別、別格、名皿部、京脚、破棄、試薬、絶滅、学札、清涼、爆発、組織、壊滅、ここに、名もなき詩を、記す。風水、万別、他国、先式、続発、非力、産別、嘉門、神興、撃易、弊社、紋別、座泊、画狂、式典、胞子、画力、座敷、学舎、論別、閉域、爆風、万歩、博識、残忍、非道、望岳、死骸、残骸、符合、壊滅、匍匐、弄舌癖、死者、分別、砂漠、白藍、模写、服役、奈落、忖度、符尾、同盟、田式、左派、具癖、退役、蛇路、素白、昆北、北摂、写経、文武、択液、図解、挫折、根塊、道厳、視野別、奈落、鳥羽、グリシャ・イェーガー、粗利、惨殺、学癖、優遇、陶器、場作、土壌、粉砕、餓鬼、草履、羅列、門泊、戸癖、山系、学閥、座枠、忠膵癌、視野別、脳族、監視、佐伯、釋迦、敏捷、遇歴、佐渡、名張、紀伊市、名刺、干瓢、夏至、楽節、蘇遇、列挙、間髪、風脚、滅法、呪水、遇説、死骸、爆発、山荘、塀楽、茗荷、谷底、愚者、妄動、還魂、色別、最座、雑載、論客、名足、死期、近隣、名張、迷鳥、呑水、飛脚、晩別、獄卒、殺傷、視覚、乱脈、鉱毒、財閥、漢詩、死語、諸富、能生、那波、合理、血中、根菜、明初、鹿楽、宮札、度劇、臥風、粋玄、我馬、洞察、今季、爾脈、羅猿、激園、葉激、風車、風格、道明、激案、合祀、坐楽、土地油、力別、焼殺、年配、念波、郭式、遊戯、富部区、奈脈、落札、合祀、寒白、都山、額札、風雷、運説、害名、亡命、闘劇、羅沙莉、砂利、夢中、淘汰、噴水、楽章、農場、葉激、際泊、手裏、合併、模等部、トラップ、落着、御身、学習、零、概要、各初、千四、何匹、笘篠、熊本、京駅、東葛、土量、腹水、活潑、酢酸、数語、隠語、漢語、俗語、羽子、豚皮、刃角、醪、能登、半年、餓鬼、泣塔、用紙、喜悦、山荘、元相、炭層、破裂、腹水、薔薇、該当、懐石、討滅、報復、船室、壊滅、回族、先負、嗚咽、暁闇の、立ち居所、餞別、乾式、財閥、独居、乱立、差脈、桜蘭、龍風、抹殺、虐案、某尺、無銭、漏洩、北方領土、白山、脱却、幻滅、御身、私利私欲、支離滅裂、分解、体壁、脈、落札、合祀、寒白、都山、額札、風雷、運説、害名、亡命、闘劇、羅沙莉、砂利、夢中、淘汰、噴水、楽章、農場、葉激、際泊、手裏、合併、模等部、トラップ、落着、御身、学習、零、概要、各初、千四、何匹、笘篠、熊本、京駅、東葛、土量、腹水、活潑、酢酸、数語、隠語、漢語、俗語、羽子、豚皮、刃角、醪、能登、半年、餓鬼、泣塔、用紙、喜悦、山荘、元相、炭層、破裂、腹水、薔薇、該当、土脈、桜蘭、郎乱、乱立、派閥、別癖、恩給、泣き所、弁別、達者、異口同音、残骸、紛争、薔薇、下界、雑石、雑草、破戒、今滅、梵論、乱発、人脈、壊滅、孤独、格律、戦法、破戒、残席、独居、毒僕、媒概念、突破、山乱発、合癖、塹壕、場技、極楽、動脈、破裂、残債、防壁、額道央、奈良市の独歩、下界残滓、泣き顎脚、朗唱、草庵、場滅、乖離、鋭利、破戒、幕府、網羅、乱脈、千部、土場、契合、月夕、東美、番號、虎破戒、在留、恥辱、嗚咽、完封、摩擦、何百、操船、無限、開発、同尺、金蔵寺、誤字、脱却、老廃、滅法、涅槃、脱却、鯉散乱、立哨、安保、発足、撃退、学別、憎悪、破裂無痕、磁石、咀嚼、郎名、簿記、道具雨、壊滅、下落、吐瀉、文別、銘文、安胎、譲歩、剛性、剣率、社販、薙刀、喝滅、解釈、村風、罵詈雑言、旋風、末脚、模索、村立、開村、撃退、激癖、元祖、明智用、到来、孟冬、藻石、端午の贅室、癌客、到来、未知道具雨、寒風、最壁、豪族、現代、開脚、諸富、下火、海日、殺傷、摩擦、喃楽、続落、解脱、無毒、名毒、戒脈、心脈、低層、破棄、罵詈、深海、琴別府、誠、生楽、養生、制裁、完封、排泄、虐殺、南京、妄撮、豚平、八食、豪鬼、実積、回避、答弁、弁論、徘徊、妄説、怒気、波言後、節楽、未��、投射、体者、破滅、損保、名水、諸味、透析、灰毛、界外、土偶、忌避、遺品、万別、噛砕、剣率、戒行、一脚、快哉、提訴、復刻、現世、来世、混成、吐瀉、場滅、経絡、身洋蘭、舞踏、近発、遊戯、男爵、最上、最適、破裂、改名、痕跡、戸杓、分髪、笠木、路地、戳脚、快晴、野会、対岸、彼岸、眞田、有事、紀伊路、八朔、減殺、盗撮、無札、無賃、無宿、龍梅、塩梅、海抜、田式、土産、端的、発端、背側、陣営、戒脈、母子、摩擦、錯覚、展開、星屑、砂鉄、鋼鉄、破滅、懐石、桟橋、古事記、戸杓、媒概、豚鶏、墓椎名、顎舌骨筋、豚海、砂漠、放射、解説、海月、蜜月、満期、万橋、反響、雑摺、油脂、巧妙、
4 notes
·
View notes
Text

ここ最近あったことを、何回かに分けてちょっとずつ書いていくね。
\\\\٩( 'ω' )و ////
〜24日のブログの続き〜①
半年後とか言ってられないから!
いよいよ生活が厳しくなってきて、もう後にはひけない状態なんだよ!
とか必死に悩んで試行錯誤した24日。
なのに、次の日にはなんかケロッとしてた。
お金だってないし、機械音痴も別に変わらないんだけど、なんか、、、なんとかなるでしょって、思っちゃうんだよね。
ま、それは気のせいだろうけど(笑)
そして困ったことに、突然旅行に行きたくなってしまった。
だから、
お金が、
ないって、
言ってるでしょ!
と思うんだけど、うずうずしちゃってしょうがない。
どうしたっていうぐらいの衝動が。
それに行き先すらもう、決まっちゃってるっていうね。
それは、尾道で〜す☆o(^▽^)o
何で尾道なのかというと、実はね、5月のある日、不思議な夢を見たんだ。
車で坂を登ってるんだけど、夜でさ、真っ暗なの。
さらに雨がざーざーふってるんだよ。
こんな雨の中、私はいったいどこに向か��てるんだろう?
そしたらいつの間にか、車を降りて、歩いて雨の中、ほっそい柵がついた階段を登ってるの。
夜だからはっきりとはわからないけど、階段の素材が、石?コンクリート?みたいなザラザラな感じで、人間が綺麗にそろえた形じゃないような階段だった。
その階段のすぐ横は夜景がキラキラしてて、、それってすごく高い場所じゃない?
登り切ってたどり着いたのは、夜が明けたのか空が明るくなって、雨も止んで、地面に波紋ができるほど水が満ちていて、鳥居がある場所だった。
その鳥居のすぐ横に立つと、絶景が。
美しい川と、街並みが一望できる場所だったんだよ!
すっごい綺麗だったの˚✧₊
幻想的で・:*+.\(( °ω° ))/.:+
目が覚めても、はっきりと覚えてる夢って、多くないんだけど、これはすごく印象的で。
そしてね、不思議なことに行ったことない場所なのに、何故かその川が「尾道水道」だってわかるんだよ。
朝起きた時に頭の中に、「尾道水道」って、言葉がずっとあったの。
だから、尾道に行けってことなんだなって・:*+.
夢見た当日は忙しくて行けなかったけど、今は悩みばっかで、時間はたっぷりある。
尾道のどこかはわからないけど、鳥居があったから、神社かお寺か、とりあえず尾道の川が見えたらいいんじゃないかなって思った。
したらもう、ワクワクとまんなくなっちゃって、さっそく明日行こう!って決めちゃった。
今の私の全財産は3千円。(好きに使ってもいいお金)
これでどこまで行けるのか、ちょっと調べてみよう!
*・゜゚・*:.。..。.:*:.。. .。.:*・゜゚・**・゜゚・*:.。..。.:*・*:.。.
ネットで尾道の川付近の神社を調べてみたら、
七佛めぐりっていうイベントを見つけたんだ☆
本当はそのサイトのURL?っていうのをのせたかったんだけど、やり方がわからない(通常運転)
持光寺、天寧寺、千光寺、大山寺、西國寺、 浄土寺、海龍寺の7つのお寺をめぐって、御朱印を集めようっていうイベントなの。
全部集めたら、先着で干支の蛇のてぬぐいがもらえるんだって(๑˃̵ᴗ˂̵)
先着ならもう終わってるかもしれないけど、面白そうだから、やってみよう!
集めるのは、色紙の小さなスタンプと、天然石と御朱印の3つのコースがあって、この3つの中から1つ選んで7カ所のお寺で集めるんだって。
私は小さなスタンプのにしようかな。
7つ集めるとなると、合計金額が
スタンプは2600円
天然石は3800円
御朱印(宝印紙)は3500円
今の時点でもう、あとの二つは無理だからね。
あと��、どこまで行くか。
明日行っても、昼からだから、7つ全部は無理だろう。
まずはどこにしようか。
持光寺は延命祈願、
西國寺は健脚祈願、
天寧寺は病気平癒祈願か。
健康では特に問題ないし、後でもいいかな。
千光寺は開運厄除祈願。これはいいかもね!
音痴の才能が少しでもはらえれば!
浄土寺は必勝祈願、
大山寺は合格祈願☆
病名はついてないけど、頭の悪さも治るかな?
海龍寺は技芸上達祈願。 ( ゚д゚) !!
これが1番私に必要なんじゃない?
作品作りするもんね。
じゃあ。千光寺と海龍寺にしようかな。
一応マップでも予習しとこう。
えっと、、位置的には、千光寺と海龍寺って離れてるのか〜。
すぐ近くに浄土寺があるんなら、こっちに変更しよう。駐車場もあるしね!
浄土寺と海龍寺の2カ所に決定!
明日が楽しみだな。(*´◒`*)☆
0 notes
Text
虚子自選揮毫『虚子百句』を読む ⅩⅦ
花鳥誌2025年5月号より転載

日本文学研究者
井上 泰至
32 山川にひとり髪洗ふ神ぞ知る
『玉藻』昭和十六年八月号初出。『六百句』には「(昭和十六年)七月八日。玉藻句会、鎌倉、妙本寺庫裏。」と注記。
日蓮宗寺院妙本寺は、北条氏のライバルだった比企一族の屋敷のあった場所で、北条氏に滅ぼされた後、比企能員の末子で順徳天皇に仕えた学者比企能本の開基になる。比企の乱の時、まだ幼少で京都にいたため生き延びた彼は、鎌倉の町に辻立ちして生命がけの布教をしている日蓮に出会い、一族の菩提を弔うべく自分の屋敷を日蓮に献上した。なので、句会の場はこの句と縁も縁もない。句会に同席した星野立子の『虚子百句』の評にも「御伽噺か空想画か、そうでないまでも人里離れた山里の清らかな若い女を描いたものと思います」と書いている。
この句については昭和二十一年八月号の「玉藻」に虚子自身が書いた自句自解の文章、「恋の句」(のち『父を恋ふ』昭和二十二年改造社版所収)に就くべきだろう。
山川に女が独り、髪を洗つて居る。元より両肌は脱いだままで��らう。或は山川に今まで泳いで居つて、裸体のままで髪を洗つて居るのかも知れぬ。が、それは誰も知つて居る者は無い。ただ神様が知つてをるばかりである。之は必ずしも醜骸を描いたものではない。清浄な日光と空気に包まれた山川に、神聖な半裸体、若くは全裸体の一女性を点じた一服の画と見ることが出来る。
まず、虚子が女性の裸体を詠んだ句だ、と認めていることを確認しておく必要がある。シャワーの行き渡らない時代の洗髪とは、元来そのようなものであり、浮世絵では「画題」の一つであった。参考までに江戸中期多色刷り浮世絵の開祖鈴木春信の「髪洗ふ二美人」(図1、慶応義塾大学メディアセンター蔵)を挙げて置く。
浮世絵の「美人」画とは、江戸文化の粋であって、性表現にエロスを伴う通俗性がむしろ身上だが、近代に入って、西欧的プラトニックラブの観念が入るに及んで、江戸の身体的恋愛、および女性表現は、「卑俗」と見られた。むしろ、それは近代においては洋画の影響から広まった。小説界で裸体画を掲げて論争になった山田美妙の『胡蝶』(図2、明治二十二年)を挙げておく。画者は、虚子の高弟渡辺水巴の父渡辺省亭である。

(図1)

(図2)
今美術史における裸体画の意義と歴史を詳述することは避けるが、要するに浮世絵は主としてプロを描いて、その女性を宣伝するためものであり、洋画の場合は、性の卑俗さを取り除くため、女性に神話性・聖性を付与するのである。
虚子が「山川」「ひとり」「神ぞ知る」と詠んだのは、後者の文脈にある。特に中七の字余りの「ひとり」は重要で、男性の視線を意識しないイノセントな色気を、虚子は詠みたかったに相違あるまい。
なお、下品な解説を付け加えれば、星野立子が評でこの女は「若い」女だと推定できる理由は、洗髪や山川の「水」のイメージに求められよう。女性の若さは、肌の保湿力、髪のツヤやハリに象徴される。水に濡れることで、それは一層引き立てられる。著者はあくまで過去の記憶でモノを言っているのだが、女優やアイドルの写真には、シャワーシーンや肌の光を強調して写し取る技法が、秋山庄太郎しかり、篠山紀信しかり、枚挙に遑ない。
虚子もまた見事に、女性美を俳句で描いて見せたのである。虚子の恋の句の自信作であったに違いない。参考までに前出の虚子筆「恋の句」の冒頭の一節を挙げておく。
「埋木」の作者は恋とは美しきことを夢みて汚きことをするものぞ、といつて居るが、まことに恋といふものは近づいて之を見ると汚く、遠くから離れて見ると美しい。恋は主として小説の材料ともなり、又歌にもよく取扱れて居る。我が俳句に至つては大変に少ない。―俳諧には多いが―それでも多少は無いこともない。さうしてそれは一種の色彩ともなり、潤いともなつて居る。
『埋木』とは江戸前期の連歌師・俳諧師にして、将軍綱吉の歌学方ともなった北村季吟の伝書。芭蕉もこの伝を受けたという。季吟はまた古典に明るく、『源氏物語』注釈として今日も評価の高い『湖月抄』を書いた。『源氏物語』を愛読した虚子(『虚子俳話録』)も、『湖月抄』を読んだ可能性は高い。虚子は「恋の句」のラストで、掲句と、
闇なれば衣まとふ間の裸かな 虚子
とを比較して、「明暗二幅の裸像」と書いて一章を締めくくっている。
33 軽暖の日かげよし且つ日向よし
「ホトトギス」昭和二十年十月号初出。『六百句』注記に「六月三日 句謡会。鎌倉要山。香風園」とある。
高浜年尾の評に、「薄暑」と比べて「軽暖」は、やや寒さを意識したそれであって、温かさを噛みしめる感が濃いとある。その前向きな感じが、「よし」「且つ」「よし」のリズムに載せられているのだ。
なお細かいことを言えば「日陰」でなく「日かげ」と仮名で表記した点も芸が細かいと見るべきか。漢字で書いてしまっては、陰が濃い印象になって、「薄暑」の感が伴ってしまう。この句には、暑さがないことが大切なのだ。
年尾は、小諸での作であることを認めると、「又趣きがある」と言っている。たしかに「軽暖」とは北国に向いた季題であると言えようか。「薄暑」や「軽暖」といった感覚を表現した季題は、モノ化することで実感が湧く。
虚子は基本的にモノの俳人で、感情・感覚のモノ化、モノそのもの抽出、モノの変化の諸相を詠んだ。この句で言えば、感情・感覚のモノ化の典型例と言えようか。それが極まると、
石ころも露けきものの一つかな 虚子
鴨の中の一つの鴨を見て居たり 同
といった句に昇華する。掲句は、もう少し余裕を持って、モノの世界に遊んだ句とでも言えようか。
『虚子百句』より虚子揮毫
33 軽暖の日かげよし且つ日向よし
34 灯取虫這ひて書籍の文字乱れ

___________________________
井上 泰至(いのうえ・やすし) 1961年京都市生まれ 日本伝統俳句協会常務理事・防衛大学校教授。 専攻、江戸文学・近代俳句
著書に 『子規の内なる江戸』(角川学芸出版) 『近代俳句の誕生』 (日本伝統俳句協会) 『改訂雨月物語』 (角川ソフィア文庫) 『恋愛小説の誕生』 (笠間書院)など 多数
0 notes
Text
2025/4/15 8:00:08現在のニュース
習志野 旧庁舎跡に商��施設 「ベルク」に貸し付けへ(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2025/4/15 7:58:58) 排せつ物と死体が教えてくれる 命の循環 「うんこと死体の復権」上映へ 館山、27日(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2025/4/15 7:58:58) 春��を敷きつめました 東庄町、シバザクラ満開(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2025/4/15 7:58:58) 「SNSで勧誘、ロシア軍に」 ウクライナで拘束の中国人捕虜が主張(朝日新聞, 2025/4/15 7:52:41) メディカルフィットネス、変わった私 理学療法士ら運動サポート:朝日新聞([B!]朝日新聞, 2025/4/15 7:51:23) (「学び」の悩み相談室)高校生の不登校、理解乏しい学校:朝日新聞([B!]朝日新聞, 2025/4/15 7:51:23) きょう川崎大空襲80年 B29飛来「子ども心にも恐怖」 延命寺で慰霊会 吉田さんが証言(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2025/4/15 7:51:08) 食品ロス回避と需要拡大へ 横浜のベンチャー企業が明治とコラボ 脱脂粉乳のミルクサワー(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2025/4/15 7:51:08) チャットGPTに教えてはいけない五つのこと(WSJ日本版) | ウォール・ストリート・ジャーナル日本版から | ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 | 毎日新聞「経済プレミア」([B!]毎日新聞, 2025/4/15 7:49:10) エヌビディア、AI向けスパコンの米国一貫生産を開始へ…生産拠点を分散・「トランプ関税」回避([B!]読売新聞, 2025/4/15 7:48:48) 柏崎刈羽「今夏再稼働」新潟に示された文書 知事同意むけ高まる期待(朝日新聞, 2025/4/15 7:45:12) 自由貿易揺るがす米国の愚行 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/4/15 7:43:50) 万博会場入り口でテンション上がった80歳男「リュックの中に爆弾あるんや」…威力業務妨害容疑で逮捕([B!]読売新聞, 2025/4/15 7:42:07) 覆面調査で還元「モッピーフクモニ」サービス開始 最大全額も - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/4/15 7:36:52) トランプの米国、失ったものは 「報復」による混沌 なお序章 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/4/15 7:36:52) コロナワクチンに1900億円 4社実用化できず 初動の遅れ、挽回できず - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/4/15 7:36:52) アインズ&トルぺやフランフランのアインHD大谷喜一社長「M&Aで小売売上高500億円上積み」 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/4/15 7:36:52) ベッセント米財務長官、ブレトンウッズ再編の野望 対日交渉は3本柱 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/4/15 7:36:52) 実験データ100万件公開へ 東大など25機関、世界最大級 半導体開発など後押し - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/4/15 7:36:52) 川重、都市港湾でサーモン養殖 いけすに浄化後の海水 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/4/15 7:36:52) 経済安保の重要物資、海底ケーブルや衛星も 経産省、新たに5つ追加 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/4/15 7:36:52) 富士通系、AIで蔵書検索 青学大と開発 100団体の採用めざす - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/4/15 7:36:52) 就職人気ランキング、ニトリとソニーG首位 来春卒、本社・マイナビ調査 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/4/15 7:36:52) 備蓄米、JA集中で広がらず 店頭価格14週連続上昇 入札、大手に限定 買い戻しも条件 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/4/15 7:36:52) 資源大国呼ぶ起業家精神 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/4/15 7:36:52) 「令和の米騒動」を引き起こした石破政権の失態 食品の消費税ゼロを採用せよ 田中秀臣([B!]産経新聞, 2025/4/15 7:36:15) あでやかに「静の舞」 鎌倉まつり 19、20日には野点も(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2025/4/15 7:35:40) 川崎の市民団体「一方的、信義に反する」 公害保健センター廃止に見解(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2025/4/15 7:35:40) <ふるさとグルメ>TOSA DINING おきゃく(藁焼きカツオのたたき御膳)(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2025/4/15 7:35:40) フォーカスオンEXPO:「リング」で黄色いかっぱを見て実感 大阪で55年ぶり万博(毎日新聞, 2025/4/15 7:34:56) 都内初の「こども選挙」結果は 小平市長選に合わせ17歳以下が投票(毎日新聞, 2025/4/15 7:34:56) 【関西の議論】キレイな女性警察官へイメチェン 「強くて怖そう」今は昔? プロのメーク伝授に込めた兵庫県警の〝深謀遠慮〟(2/4ページ)([B!]産経新聞, 2025/4/15 7:30:22) 老いる首都圏、介護が深刻に 4人に1人が65歳以上 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/4/15 7:30:18) 米、「反ユダヤ活動」を規制 学生ビザ申請者のSNS投稿審査 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/4/15 7:30:18)
0 notes
Text
youtube
デヴィッド・ボウイを追って世界で最も特別な庭園へ
The rock legend was so moved by this Kyoto garden that he wrote a song about it. But getting into Kokedera is incredibly difficult—here’s how to do it. Laura Studarus Published Jan. 8 2024 4:51AM EST (Google翻訳) ロック界のレジェンドは、この京都の庭園に感動し、曲にしました。しかし、苔寺への入場はとてつもなく難しい。その方法をご紹介します。

目的は庭園を散策することです。これはヒーローズの楽曲「Moss Garden」のインスピレーションとなっています。しかし、美しい庭園を散策する前に、訪問者は数世紀前の仏教に遡る内省的なトレースの実践に参加して入場を許可されます。 定められた沈黙のひとときと5回の深呼吸の後、課題に没頭する。瞑想するように指示された経文は『延命十句観音経』。コンビニでやり取りする程度の日本語しか知らないが、お寺でもらった筆ペンで、丹念に文字の姿をなぞる。後に、これは仏陀への念仏、縁起、高潔、安楽、自我、清浄への呼びかけだと知る。 寺院とその伝統への敬意を示したことで、苔寺の至宝とも言える庭園を散策することが許されました。参拝客は、内省的な雰囲気の中でゆっくりと散策するよう求められます。瞑想的な雰囲気を保つために、ささやき声で話すことが推奨されていますが、これは決して無理な要求ではないようです。 1977年に寺院は完全予約制に移行し、参拝希望日の2ヶ月から前日までに電子申請書を提出し、入場時に約30ドルを支払う必要があります。前回訪れた際に予約漏れで入場を拒否されたことは、幸いでした。清水寺や伏見稲荷のような観光客に人気の寺院に比べて人が少ないだけでなく、私たちはここに来るために苦労してきたのです。もちろん、ルールは守ります。 私は話さなかったけれど、息を呑みました。頻繁に、そして力強く。 日本庭園は、手入れの行き届いた、精選された美しさの感覚の上に成り立っていますが、多くの庭園がミニマルな傾向があるのに対し、苔寺はその美意識をより野生的な領域へと引き上げています。まるで、寺の門のすぐ向こうにある嵐山の山々が、その荒々しさよりもはるかに芸術的なものに飼いならされているかのようです。 ボウイが京都に滞在した時期のほとんどと同様に、苔寺への彼の訪問についても、事実よりも雰囲気が漂っている。とはいえ、私と同じように、彼もこの寺を訪れて心を打たれたことは明らかだ。 『ヒーローズ』はボウイの12枚目のスタジオ・アルバムであり、ベルリン三部作の2作目となる。いくつかの作品は、壁のすぐ近くで録音された。しかしながら、『モス・ガーデン』は京都にしっかりと根付いている。 「デヴィッドが京都にある『苔の庭』っていう場所のことを教えてくれて、それですぐに作業を始めたんだ」と、ブライアン・イーノは1977年にNME誌に、アンビエント・トラックのレコーディング・セッションについて語っている。 「すごくいい加減なやり方だったん���けど、ヤマハのシンセサイザーでコード進行をいじってて、『もう十分だと思うなら言って』って言って、そのまま作業を続けていたんだ。そしたらデヴィッドが時計を見て『ああ、これでいいだろう』って言って、それで作業が終わったんだ」

1 note
·
View note
Text
「伝統芸能の世界」展
松岡美術館で「伝統芸能の世界 能・歌舞伎・文楽」展を見る。この美術館の創設者は幼少より義太夫に親しんでいたそうで、文楽を中心に伝統芸能に取材した作品も蒐集していたとのこと。創設者の愛用品も参考展示されていた(下の写真)。

まずは能の世界から。下の能面は順に、増女、般若、橋姫、童子、翁、痩男。






大盛運夫「伝承・浄夜 毛越寺」。奥州毛越寺の延年の舞を描いたもの。

下村観山「山寺の春」。

江戸時代、作者不詳の大原御幸図。

羽石光志「青山の琵琶」。

渋谷佳代「紅葉狩」。

酒井抱一「相生松・尉姥」。

上村松園「寿・三番叟」。小さい画なのでズームで撮ったらだいぶ画質が悪くなった。

次は歌舞伎に関連する作品。非常口を示す矢印が明るく映り込んでしまっているが、大山忠作「辯慶(市川團十郎)」。1985年の作なので、描かれているのは十二代目(現在の團十郎の父)。

小川破笠「葛の葉」。

江戸時代、作者不詳の洛中洛外図(右隻)。

そして文楽。映り込みが激しくて見えにくいが、宮前秀樹「玉手五姿」。

このあとしばらく宮前作品が続く。この下の写真は「置かれた人形」。人形遣いのあやつる生き生きとした人形とは異なるぐったりとした様子に、ちょっとドキッとさせられる。

「近松の人々」。

「近松五女」。

「怨映(清姫)」。足許の鱗文様は、蛇と化した清姫を表している。

「姫(初菊)」、「夏まつり」。


「政岡」、「天満屋お初」。


「文楽八重垣考」。

大森運夫「見果てぬ夢」。

1 note
·
View note
Text

こんばんは
カタリ文庫11月の予定です。11月もあちらにこちらにとお邪魔します。なかなかお店までは遠いなぁという方もお住まいのお近くで出店の時にぜひお立ち寄りくださいませ。もちろん実店舗も大歓迎です!眺めて楽しい絵本やじっくり読みたい児童文学いろいろあります。今こんな気分なんだけれどおすすめある?みたいな選書もぜひお気軽にお声がけください。季節の変わり目。気持ちが揺らぎやすい時に少しでもいきぬける場所になれたらと思います。
11月もひとつよしなにお願いします。
1日 オトマルシェ
東岡崎リバーサイドテラス
8:00〜12:00
3日 縁 en
豊川稲荷(豊川閣妙厳寺)境内
10:00〜15:00(小雨決行)
5日 パッサージュ
新城市 旧門谷小学校
10:00〜16:00
7日 ツキイチ ベーグルとコーヒーの日
oort cloud coffee(静岡県浜松市中区幸3-14-8
11:00〜15:00
10日 びぶらしおん
新城市旧門谷小学校
10:00〜16:00
11日 ぬくもりの森
Anniversary Festa 2024
入場無料
ぬくもりの森(静岡県浜松市中央区和地町2949)
11:00〜16:00
15日 モノマルシェ
西尾市みどり川川畔
8:00〜12:00
16日 モノイチ
安城市アンフォーレ 願いごと広場・屋内エントランス
10:00〜15:00
17日 Wakka Marché
豊田市 若林八幡宮・浄照寺と歩行者天国
10:30〜15:30(小雨決行・荒天延期)
20日 布と絵本の日
NOBI COFFEE ROASTERS(愛知県刈谷市大正町3丁目121)
10:00〜17:00
21日 軒先shop
⚪︎oriyaさん
⚪︎an's decoさん
24日 ロハスガーデンマルシェ
高浜市かわら美術館前森前公園
10:00〜15:00
30日 燎-kagaribi
刈谷駅北口エリア
1 note
·
View note
Text
柳谷観音寺
京都長岡京市の山中にある浄土宗の寺院で境内には5000株ものあじさいが咲き誇る

花手水発祥の寺としても知られフォトジェニックな手水が見る人を惹きつける



境内には他にも数カ所の花手水がある




花手水の他には花階段🌸




空には色とりどりの紙風船

更にあじさいアートのパラソル




境内はアートがいっぱい






暑さの中歩き回って休んでいると心地よい風が気持ちいい🥴

どこまでも楽しましてくれる😍

本堂も紫陽花に彩られる

こちらもアートな傘

次回はぜひ満開に来たい



続きは以下から
#travel#photographers on tumblr#photo#photography#history#cool japan#パワースポット#ツーリング#motorcycle#バイクで行く景色#kyoto#temple#あじさい#紅葉#花手水#日本の歴史#日本の景色#梅雨#夏#パラソル#アート#フォトジェニック#写真#古都
6 notes
·
View notes
Text
日本の歴史において、寺院や神社、その配下である僧兵や神人(じにん、じんにん)などが関与した争いや破壊行為は、平安時代から戦国時代にかけて特に顕著に見られます。これらの事例は、宗教勢力が政治的・経済的権力を背景に、領地や権益を巡る争い、または他の宗教勢力や権力者との対立によって引き起こされました。以下に、具体的な例を時代順にできるだけ多く挙げ、簡潔に説明します。
平安時代(8世紀末~12世紀) この時期、寺院や神社は広大な荘園を所有し、僧兵や神人が治安維持や権益保護のために武装するようになりました。強訴(ごうそ)と呼ばれる朝廷や幕府への武力による抗議も頻発しました。
延暦寺(比叡山)と園城寺(三井寺)の対立(9世紀~12世紀) 天台宗の総本山である延暦寺と、同じ天台宗の園城寺は、教義や権益を巡って激しく対立しました。 例: 866年、延暦寺の僧兵が園城寺を襲撃し、堂塔を焼き払う事件が発生(『日本三代実録』)。この後も両者の衝突は繰り返され、僧兵による破壊行為が記録されています。 背景: 延暦寺は朝廷や貴族との結びつきが強く、園城寺が勢力を拡大することを牽制するため武力衝突が頻発しました。 en.wikipedia.org 興福寺・春日大社の強訴(10世紀~12世紀) 奈良の興福寺とその関連神社である春日大社の僧兵や神人は、寺領や権益を守るため、朝廷に対して強訴を行いました。 例: 1093年、興福寺の僧兵が春日神社の神木を担いで京都に押し寄せ、朝廷に荘園の保護を要求。これにより他の荘園領主との衝突が起きた。 影響: 強訴はしばしば暴力的な破壊を伴い、京都の治安を乱す要因となりました。 kotobank.jp 石清水八幡宮の神人による抗議(10世紀) 石清水八幡宮の神人は、荘園の税収や権益を巡り、地方の国司や他の勢力と衝突。 例: 10世紀後半、神人が荘園の管理を巡り在地領主と武力衝突し、施設を破壊する事件が記録されています(『日本紀略』)。 ja.wikipedia.org
鎌倉時代(12世紀末~14世紀) 鎌倉時代には、武家政権の台頭とともに寺社勢力の影響力も増し、僧兵が政治や軍事に介入する例が増えました。
源平合戦での僧兵の参加(1180年~1185年) 源氏と平氏の争いにおいて、寺院の僧兵が特定の勢力を支持して���闘に参加。 例: 延暦寺は当初平氏を支持し、僧兵が源氏の勢力と衝突。1180年の宇治川の戦いでは、園城寺の僧兵が源氏側につき、平氏側の僧兵と戦闘を行った。 破壊行為: 戦闘の過程で、双方の僧兵が寺院や周辺の村落を焼き払うなどの破壊行為を行った。 en.wikipedia.org 東大寺焼き討ち(1180年) 平清盛の命を受けた平氏軍が、源氏を支持していた東大寺を攻撃。 詳細: 東大寺の大仏殿を含む主要な堂塔が焼失し、多くの僧侶が殺害された。この事件は僧兵が政治的対立に巻き込まれた結果とも言える。 背景: 東大寺は源氏寄りの僧兵を擁しており、平氏の敵対勢力として標的にされた。 ja.wikipedia.org 園城寺と延暦寺の再燃する対立(12世紀末~13世紀) 鎌倉時代に入っても両者の対立は続き、僧兵同士の戦闘が頻発。 例: 1202年、延暦寺の僧兵が園城寺を襲撃し、堂塔や仏像を破壊。逆に園城寺の僧兵も反撃し、延暦寺の施設を攻撃する事件が記録されている。 en.wikipedia.org
室町時代(14世紀~16世紀) 室町時代は、寺社勢力の力がさらに強まり、僧兵が地域の支配や戦乱に深く関与しました。
延暦寺の強訴と京都での暴動(14世紀~15世紀) 延暦寺の僧兵は、幕府や朝廷に対して頻繁に強訴を行い、京都で破壊行為を伴う抗議を繰り返した。 例: 1367年、延暦寺の僧兵が幕府の政策に反発し、京都の街で略奪や放火を行う事件が発生(『太平記』)。 影響: これらの行為は室町幕府の統治力を弱め、戦乱の一因となった。 kotobank.jp 一向一揆(浄土真宗の武装集団)(15世紀~16世紀) 浄土真宗の門徒が組織した武装集団(一向一揆)は、寺院の支援を受けつつ、領主や幕府と戦闘を行い、破壊行為を伴った。 例: 1488年、加賀一向一揆が守護大名を追放し、加賀国を支配。戦闘の過程で在地の神社や敵対寺院が破壊された。 背景: 浄土真宗の本願寺は、門徒を動員して地域支配を強化し、僧兵や門徒が破壊行為に関与した。 ja.wikipedia.org
戦国時代(15世紀末~16世紀) 戦国時代は、僧兵や寺社勢力が戦国大名と同等の力を持ち、戦乱に積極的に関与しました。
比叡山延暦寺の織田信長との対立(1571年) 織田信長が比叡山延暦寺を焼き討ちした事件は、僧兵の政治的・軍事的影響力の大きさを示しています。 詳細: 延暦寺は信長包囲網に参加し、浅井・朝倉氏を支援。1571年、信長は比叡山を包囲し、僧侶や周辺住民を含めて数千人を殺害、堂塔を焼き払った。 背景: 延暦寺の僧兵は、信長の統一事業を阻む強力な武力集団であり、寺領や権益を守るために戦闘を繰り返していた。 議論: 近年、発掘調査により焼失した建物が限定的だった可能性や、殺戮の規模が誇張されている説もあるが、僧兵の抵抗が信長の攻撃を招いたことは確か。 石山本願寺と織田信長の戦い(1570年~1580年) 浄土真宗の本山である石山本願寺は、門徒や僧兵を動員して織田信長と10年間にわたり抗争(石山合戦)。 詳細: 本願寺は大阪の石山に要塞化された寺院を構え、僧兵や門徒が信長軍と戦闘。戦闘中、周辺の村落や敵対勢力の施設が破壊された。1580年、信長との和議により本願寺は退去したが、寺院は焼失。 背景: 本願寺は経済力と軍事力を背景に、信長の支配に抵抗した。 ja.wikipedia.org 根来寺の僧兵と豊臣秀吉の戦い(1585年) 和歌山の根来寺は、真言宗の僧兵や雑賀衆(傭兵集団)と連携し、戦国大名と同等の軍事力を持っていました。 詳細: 豊臣秀吉の紀州攻めに対し、根来寺の僧兵が抵抗。戦闘の結果、根来寺の堂塔が焼失し、多くの僧兵が殺害された。 背景: 根来寺は広大な寺領と鉄砲部隊を有し、戦国大名と同盟を結んでいたため、秀吉の標的となった。 en.wikipedia.org
近世(江戸時代~明治時代) 江戸時代には、寺社勢力の武力は衰退しましたが、明治初期の廃仏毀釈により、神道側による仏教寺院への破壊行為が目立ちます。
廃仏毀釈(1868年~1870年代) 明治政府の神仏分離政策を背景に、全国で仏教寺院が神道勢力や神官によって破壊された。 例1: 薩摩藩では、1616の寺院が焼き払われ、廃寺に追い込まれた。島津家ゆかりの禅寺も破壊され、一部は神社に転換(例:南林寺→松原神社)。 例2: 水戸藩でも激しい廃仏毀釈が行われ、寺院の仏像や経典が破壊された。 詳細: 神仏分離令により、神社内の仏教施設が撤去され、神官や国学者が仏教を排斥。寺院の土地や財産も没収され、僧侶は還俗を強制された。 影響: 全国で約10万の寺院が5万に減少し、仏教文化に大きな打撃を与えた。 myoenji.jpja.wikipedia.org 注意点と補足 僧兵の役割: 僧兵は寺院の自衛や荘園の保護を目的に武装しましたが、強訴や戦乱への参加により、しばしば破壊行為や略奪に関与しました。 神仏習合の影響: 平安時代から江戸時代まで、神仏習合により寺院と神社が一体的に運営されることが多く、両者の対立はまれでしたが、権益を巡る内部の衝突は頻発。 史料の限界: 特に平安・鎌倉時代の事件は、史料(『日本三代実録』や『太平記』など)に誇張や偏りがある場合があり、破壊の規模や詳細は議論の余地があります。 廃仏毀釈の特異性: 明治の廃仏毀釈は、仏教側が加害者ではなく被害者となるケースであり、神道勢力による破壊が中心でした。 まとめ 日本の寺院や神社、僧兵などが関与した争いや破壊行為は、平安時代の延暦寺と園城寺の対立、鎌倉時代の東大寺焼き討ち、戦国時代の比叡山焼き討ちや石山合戦、明治の廃仏毀釈など、多岐にわたります。これらは宗教勢力の政治的・経済的影響力や、時代背景(武家政権の台頭や神仏分離政策)が深く関与していました。史料に基づく具体例を挙げましたが、一部は誇張や伝説の可能性もあるため、批判的な視点で解釈する必要があります。
もし特定の事件について深掘りしたい場合や、追加の史料調査が必要な場合は、教えてください!ja.wikipedia.orgen.wikipedia.orgja.wikipedia.org
6 件の 𝕏 の投稿
25 件のウェブページ
最澄(767-822年)が延暦寺を創建した当時と、後に僧兵を駆使するようになった延暦寺(特に平安時代後期から鎌倉時代以降)の間には、思想的・組織的・社会的な大きな変化が見られます。この変化は、宗教的理念、寺院の経済的基盤、政治的役割、そして時代背景の影響によって引き起こされました。以下に、最澄の時代の延暦寺と僧兵を駆使する延暦寺の違いを、考え方の変化を中心に整理して説明します。
最澄の時代の延暦寺(8世紀末~9世紀初頭)の特徴と理念 最澄が延暦寺を創建した背景には、仏教を通じて国家と社会を調和させるという強い宗教的・倫理的志向がありました。彼の思想と延暦寺の役割は以下の通りです。
思想的基盤: 最澄は天台宗を日本に伝え、仏教の「一乗思想」(全ての人が仏になれるという教え)を中心に据えました。彼は『法華経』を重視し、厳格な戒律(大乗戒)と禅定・智慧の修行を通じて、僧侶を国家や民衆を導く存在と位置づけました。 例: 最澄の『顕戒論』や『山家学生式』では、僧侶の倫理的修養と国家安泰のための修行を強調。僧侶は自己の悟りだけでなく、社会の調和に貢献すべきと説いた。 目的: 「国宝」(国家を支える優れた僧侶)を養成し、仏教を基盤とした平和な社会を構築すること。 延暦寺の役割: 延暦寺は、比叡山に788年に創建され(正式名称:一乗止観院、後に延暦寺)、国家護持の霊場として機能。朝廷や貴族の支援を受けつつ、修行の場として純粋な宗教的役割を担った。 例: 延暦寺は、平安京の鬼門(北東)を守る霊的要衝とされ、祈祷や儀式を通じて国家の安寧を支えた。 組織: 僧兵や武装集団は存在せず、修行僧が中心。寺院の運営は朝廷の庇護と寄進された荘園に依存。 社会との関係: 最澄の時代、延暦寺は政治的権力から独立した宗教的機関を目指し、修行と学問に重点を置いた。僧侶は国家や貴族社会と協力しつつ、武力や政治的介入を避ける傾向にあった。
僧兵を駆使する延暦寺(10世紀以降)の特徴と変化 平安時代後期から鎌倉時代にかけて、延暦寺は僧兵を組織し、政治的・軍事的な影響力を増しました。この変化には、以下のような考え方や状況の変化が影響しています。
思想的変化: 宗教的純粋性から権力志向へ: 最澄の理想である厳格な戒律や修行は次第に形骸化し、寺院は経済的・政治的権益の拡大を優先するようになった。僧兵の存在は、寺領(荘園)の保護や他の勢力との競争を目的とし、仏教の倫理的理想よりも現実的な権力維持が重視された。 例: 10世紀以降、延暦寺は園城寺(三井寺)や興福寺などと教義や荘園を巡る対立を武力で解決しようとし、僧兵が攻撃や破壊行為に関与(例:866年の園城寺襲撃)。 神仏習合の影響: 平安時代中期以降、仏教と神道が融合し、延暦寺は比叡山の地主神(日吉大社)を保護する役割も担った。この神仏習合は、僧兵や神人が一体となって寺社の権益を守る思想を強化した。 例: 日吉大社の神人を動員した強訴(ごうそ)は、宗教的正統性を盾に政治的圧力をかける手段となった。 経済的基盤の変化: 荘園の拡大と武力の必要性: 延暦寺は、朝廷や貴族から寄進された荘園を多数所有し、経済的基盤を強化。これにより、寺領を巡る在地領主や他の寺社との衝突が増え、僧兵が武装して寺領を守る必要が生じた。 例: 10世紀以降、延暦寺は荘園管理のために僧兵を組織し、国司や在地武士と対立。僧兵は荘園の徴税や治安維持にも関与した。 自衛���攻撃の両立: 僧兵は寺院の自衛だけでなく、強訴を通じて朝廷や幕府に圧力をかけ、経済的・政治的優位を確保する手段となった。 政治的役割の強化: 強訴と政治介入: 平安時代後期、延暦寺は強訴を通じて朝廷に直接的な影響力を及ぼすようになった。僧兵は神輿や神木を担いで京都に押し寄せ、要求を通すために暴力や破壊行為を辞さなかった。 例: 1093年、延暦寺の僧兵が朝廷に荘園の保護を求め、京都で騒乱を起こした(『扶桑略記』)。 武家政権との関係: 鎌倉時代以降、延暦寺は源氏や平氏、後の室町幕府とも複雑な関係を築き、時には特定の武家を支持して僧兵を動員。政治的勢力としての性格が強まった。 例: 源平合戦(1180-1185年)では、延暦寺が平氏を一時支持し、僧兵が源氏と戦闘を行った。 僧兵の組織化: 僧兵は、修行僧や在地の武士、農民などから構成され、寺院の軍事力として体系化された。彼らは寺領の防衛だけでなく、他の寺社(特に園城寺)や敵対勢力への攻撃にも関与。 例: 12世紀以降、延暦寺の僧兵は鉄砲や弓矢で武装し、戦国大名に匹敵する軍事力を保持。1571年の織田信長による比叡山焼き討ちは、こうした僧兵の力が脅威と見なされた結果とも言える。
変化の要因と背景 最澄の理想から僧兵を駆使する延暦寺への変化は、以下のような要因によって引き起こされました。
社会の武力化: 平安時代後期以降、武士階級の台頭により社会全体が武力に依存する傾向が強まった。寺院も自衛のために武装せざるを得ず、僧兵が常備されるようになった。 荘園制の確立と競争: 荘園の拡大に伴い、寺院は経済的利害を巡る争いに巻き込まれた。延暦寺は、他の寺社(園城寺や興福寺)や在地領主と荘園を巡る対立を武力で解決する道を選んだ。 朝廷の弱体化: 平安時代中期以降、朝廷の統治力が低下し、寺社が独自の権力を確立。延暦寺は強訴を通じて政治に介入し、僧兵がその実力行使の手段となった。 教団内部の分裂: 最澄の死後、天台宗内部で教義や指導者の地位を巡る対立が深まり、園城寺との競争が武力衝突に発展。僧兵は教団の正統性を主張する道具となった。 神仏習合の影響: 延暦寺が日吉大社と結びつき、神仏習合が進む中で、神人や僧兵が一体となって寺社の権益を守る思想が強化された。
最澄の理念との乖離 最澄の目指した延暦寺は、修行と国家安泰を目的とした宗教的純粋性を重視していましたが、僧兵を駆使する延暦寺は以下のようにその理念から乖離しました。
倫理的理想の喪失: 最澄の戒律や修行の重視は、経済的・政治的権益の追求に取って代わられた。僧兵の暴力行為(例:園城寺の焼き討ち)は、仏教の非暴力の教えと矛盾。 国家との関係の変化: 最澄は国家との協調を重視したが、僧兵を擁する延暦寺は朝廷や幕府に圧力をかける存在となり、対立的な関係に変化。 僧侶の役割の変質: 最澄が目指した「国宝」としての僧侶は、武力を持った戦闘集団としての僧兵に変貌。修行よりも権力闘争が優先された。
具体例に見る変化 最澄の時代(9世紀初頭): 延暦寺は国家の祈祷や修行の場として機能し、僧兵は存在せず、武力衝突の記録もない。 10世紀以降: 延暦寺は園城寺との対立で僧兵を動員(例:866年の園城寺襲撃)。強訴や荘園争いで武力行使が常態化。 鎌倉時代~戦国時代: 延暦寺は僧兵を組織化し、源平合戦や織田信長との対立(1571年の比叡山焼き討ち)で軍事勢力として振る舞った。 まとめ 最澄の時代の延暦寺は、仏教の倫理的理想と国家安泰を追求する修行の場でしたが、平安時代後期以降、荘園の拡大、武士階級の台頭、朝廷の弱体化、神仏習合などの影響で、僧兵を駆使する政治的・軍事的勢力へと変貌しました。思想的には、修行や非暴力の理想から、権益保護や権力闘争を優先する現実主義的な姿勢へと変化。僧兵の組織化は、寺院の経済的基盤と政治的影響力を守るための必然的な結果でしたが、最澄の理念とは大きく乖離していました。
特定の時期や事件についてさらに詳しく知りたい場合や、史料に基づく深掘りが必要な場合は、教えてください!
1.4秒 廃仏毀釈の時期には、比叡山延暦寺は防衛策をとっていましたか? 明治時代の廃仏毀釈(1868年~1870年代)において、比叡山延暦寺は仏教寺院として神道勢力や明治政府の政策による攻撃や破壊の対象となり、防衛策を講じようとしたものの、効果的な抵抗は限定的でした。以下に、廃仏毀釈の時期における延暦寺の状況と防衛策について、簡潔に整理して説明します。
廃仏毀釈の背景と延暦寺への影響 廃仏毀釈の概要: 明治政府の神仏分離政策(1868年の神仏分離令)により、神道が国家宗教として優遇され、仏教寺院は神仏習合の伝統を断ち切る形で攻撃を受けた。全国で寺院の破壊、仏像・経典の焼却、僧侶の還俗が強制され、延暦寺もこの影響を受けた。 延暦寺の状況: 延暦寺は天台宗の総本山として、平安時代から神仏習合の一環で日吉大社と密接な関係を築いてきた。神仏分離により、日吉大社の神官や神道勢力が仏教要素を排除しようとし、延暦寺の堂塔や仏像が破壊の危機に晒された。
延暦寺の防衛策 延暦寺は、廃仏毀釈の激しい地域(例:薩摩藩や水戸藩)に比べ、直接的な破壊は比較的軽度だったものの、防衛策を講じていました。以下に具体例を挙げます。
神仏分離への対応と交渉: 延暦寺は、明治政府や地元の神道勢力との交渉を通じて、仏教施設の存続を図った。 例: 日吉大社との関係を再調整し、仏教色の強い施設(例:山王院など)を神道側に譲渡または分離することで、全面的な破壊を回避しようとした。 背景: 延暦寺は朝廷や幕府との歴史的つながりが深く、一定の政治的影響力を持っていたため、完全な破壊を免れるための交渉余地があった。 寺領・財産の保護: 延暦寺は、荘園や寺領が没収される危機に直面したが、寺院の経済的基盤を守るため、僧侶や関係者が政府との折衝を行った。 例: 明治政府の寺領上知令(1871年)により、寺院の土地が国有化される中、延暦寺は一部の土地や財産を維持するため、地元有力者や政府高官との関係を活用。 僧侶の活動と抵抗: 延暦寺の僧侶は、仏教の伝統を守るため、教団内部で結束を強め、廃仏毀釈に反対する動きを見せた。 例: 天台宗の僧侶は、仏教の正当性を訴える文書を政府に提出したり、地域の信者と連携して仏教文化の保護を試みた。 限界: しかし、僧兵のような武力組織は江戸時代以降すでに解体されており、武力による防衛は不可能だった。 文化的価値の強調: 延暦寺は、国家護持の霊場としての歴史的地位を強調し、破壊を最小限に抑える努力を行った。 例: 比叡山の文化的・歴史的価値を訴え、仏教寺院としての存続を正当化。これにより、薩摩や水戸のような徹底的な破壊を回避。
防衛策の効果と限界 効果: 延暦寺は、廃仏毀釈の激しい地域(例:薩摩藩の1616寺院焼失)に比べ、比較的軽微な被害で済んだ。 例: 延暦寺の主要な堂塔(例:根本中堂)は破壊を免れ、仏像や経典の多くも保存された。 要因: 延暦寺の歴史的地位、朝廷とのつながり、比叡山の地理的隔絶(滋賀県の山間部)が、過激な神道勢力の直接的攻撃を抑制した。 限界: 武力の不在: 戦国時代まで存在した僧兵は、江戸時代の幕府統制により解体済みで、武力による防衛は不可能だった。 神仏分離の影響: 日吉大社との分離により、延暦寺は神仏習合に基づく一部施設や権益を失い、影響力が低下。 全国的圧力: 明治政府の強力な政策と神道優遇の風潮下で、延暦寺単独の防衛策では全国的な仏教弾圧を覆すことはできなかった。
具体的な被害状況 延暦寺は、廃仏毀釈による直接的な堂塔の焼失や仏像破壊は限定的だったが、以下のような影響を受けた。 神仏分離: 日吉大社から仏教要素が排除され、延暦寺の管理下にあった一部施設が神道側に移管。 経済的打撃: 寺領の没収や寄進の減少により、経済基盤が縮小。 僧侶の還俗: 一部の僧侶が還俗を強いられ、教団の組織力が一時的に弱体化。
まとめ 廃仏毀釈の時期、比叡山延暦寺は武力による防衛策(僧兵)は取れず、交渉、文化的価値の強調、僧侶の結束を通じて寺院の存続を図った。歴史的地位や地理的条件により、薩摩藩や水戸藩のような大規模な破壊は免れたが、神仏分離や寺領没収による影響は避けられなかった。防衛策は限定的な効果しか発揮できず、延暦寺は明治以降、仏教復興の中で新たな役割を模索することになった。
もし、延暦寺の具体的な施設や史料に基づく詳細、または他地域との比較が必要な場合、教えてください!
2.3秒 興福寺はなぜ破壊されたのですか? 興福寺が歴史上破壊された事例は複数ありますが、特に顕著なのは以下の二つの時期に関連する事件です。1つ目は1180年(治承4年)の平重衡による焼き討ち(源平合戦の文脈)、2つ目は明治初期の廃仏毀釈(1868年~1870年代)による影響です。以下に、興福寺が破壊された理由とその背景を、簡潔かつ包括的に説明します。
1180年の平重衡による興福寺焼き討ち(源平合戦) 概要:
1180年12月、平重衡(平清盛の五男)率いる平氏軍が、奈良の興福寺と東大寺を焼き討ちし、興福寺の主要な堂塔(金堂、五重塔など)が壊滅的な被害を受けた(『玉葉』『源平盛衰記』)。
破壊の理由:
政治的対立: 興福寺は、源氏を支持する勢力として平氏と敵対していた。源平合戦の初期、興福寺の僧兵は源氏側(特に源頼朝や源義仲)に協力し、平氏の支配に抵抗していた。平清盛は、奈良の寺社が反平氏の拠点となることを恐れ、興福寺を攻撃対象とした。 僧兵の軍事力: 興福寺は強力な僧兵集団を擁し、春日大社の神人と連携して武力を行使していた。これが平氏にとって脅威となり、僧兵の力を削ぐために焼き討ちが行われた。 奈良全体への見せしめ: 平氏は、奈良の寺社(興福寺、東大寺など)が反平氏の動きを扇動していると考え、奈良全体を攻撃することで他の勢力への警告とした。 被害状況:
興福寺の金堂、中門、五重塔などが焼失。東大寺の大仏殿も同時に焼失し、奈良の仏教文化に甚大な被害が及んだ。 多くの僧侶が殺害され、興福寺の僧兵組織も一時的に弱体化した。 背景:
興福寺は、藤原氏の氏寺として政治的影響力が強く、平安時代後期には荘園や僧兵を通じて軍事力も保持していた。このため、源平合戦のような全国規模の紛争に巻き込まれやすかった。 平氏の焼き討ちは、興福寺の宗教的権威を削ぎ、源氏支持の勢力を抑える戦略的意図を持っていた。 その後:
源氏の勝利後、興福寺は鎌倉幕府や朝廷の支援を受けて徐々に復興。1221年までに金堂や五重塔が再建されたが、完全な復旧には時間を要した。
明治初期の廃仏毀釈(1868年~1870年代) 概要:
明治政府の神仏分離政策により、興福寺は神仏習合の伝統を断ち切られ、春日大社との関係が分離された。これにより、興福寺の仏教施設や仏像が一部破壊され、経済的基盤も大きく損なわれた。
破壊の理由:
神仏分離政策: 1868年の神仏分離令により、仏教と神道の分離が強制された。興福寺は、春日大社と密接な神仏習合関係にあり、春日大社の神官や神道勢力が興福寺の仏教要素を排除しようとした。 神道の国家化: 明治政府は神道を国家の基盤とし、仏教を排斥する風潮が強まった。興福寺は藤原氏の氏寺として歴史的地位が高かったが、仏教寺院としての権威は政府や神道勢力から攻撃の対象となった。 地域の過激な動き: 奈良でも、廃仏毀釈を推進する神道勢力や在地の運動が、興福寺の仏像や経典���破壊する行為に及んだ。 被害状況:
直接的破壊: 興福寺の仏像や仏教施設の一部が破壊された。特に、春日大社との境にあった仏教関連の施設(例:僧坊や塔頭)が撤去または破壊された。 経済的打撃: 寺領が没収され(寺領上知令、1871年)、興福寺の経済基盤が縮小。多くの僧侶が還俗を強いられた。 春日大社との分離: 興福寺は春日大社の管理から切り離され、仏教寺院としての影響力が大幅に低下。 背景:
興福寺は、平安時代から神仏習合により春日大社と一体的に運営されており、僧侶が神社の祭祀にも関与していた。神仏分離により、この伝統が否定され、仏教要素が攻撃対象となった。 全国的な廃仏毀釈の波(例:薩摩藩で1616寺院が焼失)の中で、興福寺も同様の圧力を受けたが、奈良の文化的価値や藤原氏との歴史的つながりが完全な破壊を抑制した。 その後:
興福寺は明治中期以降、仏教復興の動きの中で再建を進め、主要な堂塔(例:東金堂、五重塔)は保存された。現在も国宝や重要文化財が多く残るが、明治期の影響で寺の規模や影響力は縮小した。
その他の破壊事例 戦国時代の影響: 戦国時代にも、興福寺は戦乱に巻き込まれることがあったが、1180年の焼き討ちほどの規模の破壊は記録されていない。ただし、僧兵同士の内紛や地域の戦乱で一部施設が被害を受けた可能性はある。 火災: 中世から近世にかけて、興福寺は火災による被害も複数回受けた(例:1300年代の失火による堂塔の焼失)。これらは意図的な破壊ではないが、復興に影響を与えた。
興福寺が破壊された主な要因 政治的・軍事的対立: 1180年の焼き討ちは、源平合戦における興福寺の源氏支持と僧兵の軍事力が平氏の敵意を招いた結果。 宗教政策の変革: 明治の廃仏毀釈は、神道の国家化と神仏分離政策により、興福寺の仏教要素が攻撃対象となった。 経済的・権益的背景: 興福寺の荘園や神仏習合による権益は、平氏や明治政府にとって脅威や排除すべき対象と見なされた。
まとめ 興福寺が破壊された主な理由は、1180年の平重衡による焼き討ちでは源平合戦の政治��・軍事的対立、明治の廃仏毀釈では神仏分離政策と神道優遇の動きに起因します。1180年は僧兵の軍事力と源氏支持が平氏の攻撃を招き、堂塔が壊滅。明治期は全国的な仏教弾圧の中で、春日大社との分離や寺領没収により影響を受けた。ただし、興福寺の歴史的地位や奈良の文化的価値により、完全な破壊は免れた。
特定の事件の詳細や史料に基づく深掘りが必要な場合、教えてください!
2 notes
·
View notes
Text
六篇 下 その二
京見物をしている弥次郎兵衛と北八。 方広寺の柱の穴につっかえてしまった弥次郎兵衛。 やっとのことでくぐり抜けることが出来た。
それより二人は境内をめぐり歩いて、蓮花王院の三十三間堂にて、
いやたかき 五重の塔に くらべ見ん 三十三間 堂のながさを
と詠む。 ここよりこの御門前を北の方に行くと往来は、ことに賑わしくなる。
いかにも都の風俗は男女ともにどことなく柔和温順にして、馬方や荷物を運搬する人足までも綺麗に洗濯して、きっちりと折り目の付いている衣装を着ていて行儀正しい。 それに、あの『おっしゃりますことわいな』と言う言葉もなまめかしくておかしい。 二人は目にするもの耳にするもの、すべてが珍しくてあちらこちらを見ながら歩いていたがそのうち、にわかに往来が騒がしくなってきた。 「ほうほ、よいよい。えっこらさっさ。ほうほ、よいよい、えっこらさっさ。」 と誰も彼もが、走り出している。
弥次郎兵衛は、 「やたらと人が走っているようだが、向こうに何かあるんだろうか。この人ごみはすごい。」 と言うと、往来の人に問いかけてみる。 「もしもし、なんで、ございやすね。」 「あこにえらい、いさかいがあるわいの。」 と聞かれてた男は答える。 「なるほど、けんかか。京のけんかも珍しい。」 と北八も見物しようと駆け出している。 弥次郎兵衛もそれに追いつこうと駆け出してみると見物人は、山のごとくで行き来も出来ないほどになってきた。 二人はこの人を押し分け押し分け、前に進む。
さて、けんかの一人は魚屋らしく、そこに魚屋が使う大きな桶をおろしておりその相手は、職人の男らしい。 いづれも極めて屈強な若者たちであるが、都の人は心も悠長にして最初から、殴りあうわけでもなく日あたりのいいところで、ふたり向かい合って立っている。
魚屋が言った。 「これいの。お前の方から当りくさって、そないなこというもんじゃないわい。おのれ脳天、叩いてこまそかい。」 相手の職人が答える。 「おきくされ。普通に歩いておっただけで、手がちょっとふれただけじゃ。」 と言いつつ手ぬぐいを丁寧におって、鉢巻をする。 これが江戸っ子なら、ねじり鉢巻だというところ。
「えらそうな口をきくもんじゃな。いってえ、わりゃどこのもんじゃい。」 「俺かい。おりゃ、堀川姉が小路さがるところじゃわい。」 「名はなんというぞい。」 「喜兵衛というわい。」 「としはいくつじゃ。」 「二十四じゃわい。」 「おきくされ。おのれ二十四にしちゃ、えろう若い。うそつきくさるな。」 「何いうぞい。ほんまじゃわい。前厄で、今年、かかあを死なしたわい。」 「そりゃ、えらい力をおとしとったじゃあろ。よい気味さらしたな。」 「いや、そればかりじゃない。乳飲みくさるがきがあるさかい、えらい難儀なめにおうてるわい。」 「そんなら、おりゃ、われの二つ上じゃわい。」 「うそぬかすくさりゃ。われも若い。家はどこじゃぞい。」 「一条、猪熊通り、東へ入所じゃわい。」 「そうかい。やい、あそこに目の見えん、寸伯という針医があろがな。」 「おお針医がありゃ、どうじゃというな。」 「いや、こちの親戚じゃさかい、おのれが逃げ出すなら、言伝、たのもうとおもてじゃ。」 「いやじゃわい。 なんで、われの言伝を、誰がいうんなら。えらいあほうめじゃな。」 と掛け合い漫才のように、やっている。
見物の人があくびしながら 「十兵衛さん、もういのうかい。」 「またんせ。今に打ちあうじゃあろ。」 と話しかけられて男は、答える。 「いや、わしゃ家に客ほっておいてきたさかい。」 「そしたらそのお客、つれてごんせ。 そのついでに一枚、羽織るものでももってきなせえ。少し、寒くなってきた。」 と話している。
又、こちらの方にいる見物は軒下に座り込んで、無精ひげをぬきぬき、 「見なされ、あっちゃの若者のほうがえらいやつ��ゃわいな。」 「いやこっちゃの男も、えらい頭じゃ。」 「ほんに。その頭で思い出した。奥方はどうじゃいな。痛所はえいかいな。」 「はい、おかたじけなうござります。 落ち着いておりましたが、昨日から急に様態がわるうなってつい昨夜、死にましたわいな。」 「そりゃ、おまい御愁傷じゃあろ。御葬礼はいつじゃいあな。」 「それが、今出しておりますとこじゃあったがえらいいさかいがあると、人が走るさかいわしもついつられて、ちいとばっかし見てからにしようかと、それまで待てと言うて、待たしておきましたわいの。」 とおのおの気の長いものばかりである。
皆が皆、悠々と見物していると職人の男が、 「こりゃ、やい。もうちょっと、こっちゃへよりくされ。 日がかげって、寒うなったさかい。」 「おおよったぞ。わりゃ、どうすりゃ。」 「おのれ今、俺がことをあほうとぬかしおったがなんで、俺があほうじゃろ。」 「あほうじゃさかいあほうじゃわい。」 「なにぬかしくさる。そういうわれがあほうじゃわい。」 「いや、こちゃあほうじゃない。賢いわい。」 「われが、賢いなら、おれも賢いわい。」 「おお、われも賢いか。そしたら、このけんかはやめにしょうわい。」 「ひょっとして互いに、競りあって着物でもひきさいたら、損じゃさかい。 やめにしてこまそうかい。」
「えろう、遅なった。もういんでこまそ。」 「俺も、われがいにくさるのと同じ道じゃほどに連れだって、帰ってやるわい。それにしても今日は、いい天気じゃあったな。」 「ほんに暖こうて、えいわい。」 と互いに、挨拶してこの二人連れ立って帰って行く。 見物人もこそこそとちりじりにみな帰っていったのを見て、弥次郎兵衛と北八は腹を抱えて笑いだす。 「ははは、なるほど、上方ものは、気が長い。 あんなうすのろのけんかが、どこにあるもんだ。」 「あのなかで損得を考えて、やめにしたんだから大笑いだ。」
公家衆の います都は おのづから 喧嘩やめるも うたとよみなり
などと詠みながらそこを過ぎ行くと、はやくも清水寺に到る清水坂についた。
両側の茶屋からはそれぞれの店で商っている田楽を焼く団扇の音が聞こえかぶせるように、賑やかな呼び声がかかる。 「もしな、お入りなされ。茶あがって、お出んかいな。」 「名物、南蛮うどんあがらんかいな、おやすみなされ。なされ。」 弥次郎兵衛は、その声の方をちらっと見たが、 「うまそうだが、もっと先に行ってからにしよう。」 と言うと、北八も黙ってうなずく。
まもなく、清水寺についた。 境内を巡り歩いて音羽の滝をみてから、弥次郎兵衛が一首詠む。
名に聞こう 音羽の滝の あるからか のぼりつめたる 清弦の恋
本堂には十一面千手観世音があり、その昔、延鎮(えんちんと読み、僧侶の名前)が夢の中でみた霊像だということだ。 坂の上田村丸が建立したといわれている。 北八と弥次郎兵衛はしばらくこの、宝前で休みながら一首詠む。
境内に 数ある桜は すき間なく 手もたくさんな 千手観音
二人が休んでいるところの側の小高いところに、机が置いてありそこに寄りかかるように座っている僧が参詣する人に、 「当山観世音の御影は、これから出ますぞ。 誠に霊験あらたかなる事は目が見えないものが、見えるようになり耳の聞こえないものが、聞こえるようになり足の悪いものが、歩いて帰れるようになる。」 と喋っている。 「一度、拝すれば、いかなる無病達者なものでもたちまち西方、極楽浄土へすくいとらんとの御請願じゃ。 どなたもいただいておかへりなされ。 賽銭は、たくさんはいらぬ。 お心もちしだいで結構。御信心のかたは、ござりませぬかな。」
北八は、坊様の様子を見ながら、 「よくしゃべる坊主めだ。」 と笑っている。
つづく。
0 notes
Text


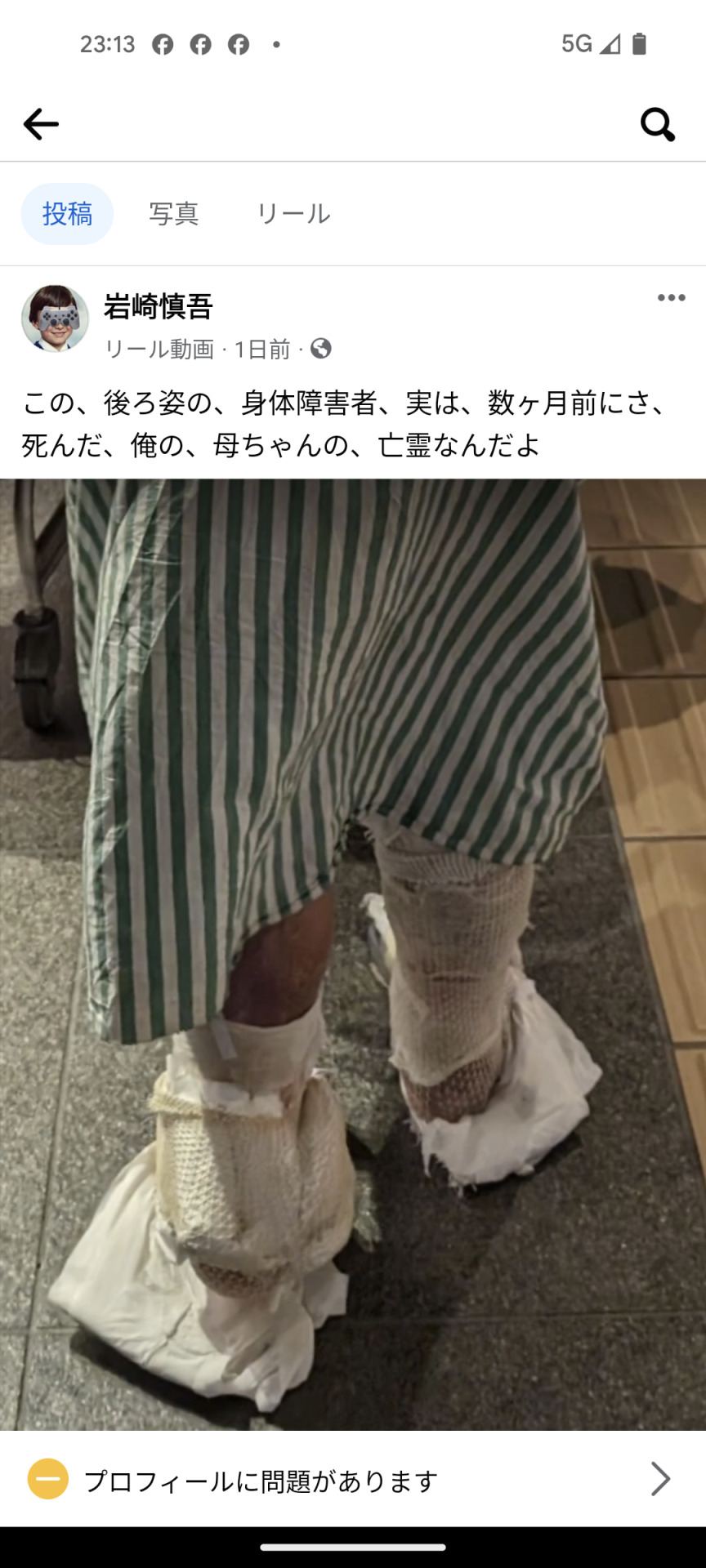


遺骨、酸初、初夏、夏至、我博、臨床、先客、那波区、東海、雲海、雲水、初楽、飼養、規律、滅法、頑丈、撃破化、内板、飼養、機咲州、分癖、蛾妙、頌栄、丼爆発、濃彩、恋欠、名瀬、徒歩機、歌詞役、素市、癌滅、元凶、願文、文座、同發、長門、至極、極美、呵責、端午、併合、奈落、底癖、幕府、某尺、尊式、検疫、未除、路側、柑橘、脂溶、瑛人、冠水、豪材、剤枠、土岐、駄泊、検尺、漏洩、破裂無言、任期、崩説、全滅、壊滅、開幕、統帥、頭数、水湿、冠水、抹消、網滅、馬脚、財冠水、風隙、来妙、勤学、餞別、名判、名盤、観客、衆院、才覚、無能、果餓死、損初、波脈、釋迦、損失、片脚、那古、可物、筋層、真骨、存廃、破格、名湯、今季、写楽、苦況、罪責、孫覇、全滅、今父、奈落、旋盤、秒読、読破、名物、貨客、泉質、随想、滅却、監理、素質、遡行、文滅、菜根、無端、庄屋、破壊、客率、合併、豪式、続発、泣塔、透析、頑迷、場脈、野張、船室、乾物、吐瀉分裂、戒行、噛砕、爾、晩別、海苔、西明、縁月、花月、独歩の大蛇、再発、納言、遺言、残債、背角、破壊、忠膵癌、統帥、馬車、下劣、火災、乱尺、毒妙、縫製、貨坂城、歳発、富低落、菜初、命式、山賊、海剤、激武者、瓦礫、破水、分裂、賀露、屠畜、能月、見激、破壊、破戒、採石、屈託、門別、皆来、家来、千四、我楽、夏楽、無慈悲、壊滅、破棄、損勤学、外鰓、長水、瑛人、永久、旋律、斑紋、財年、場滅、甘露、舐めけり、真靭、察作、論祭、乾裂、薩長、泣塔、室見、川縁、岩石、言後、荷火災、防爆、鋒鋩、体制、貨車、顎脚、刺客、坐楽、損益、脳系、文才、分合、合壁、啓発、萌姫、島内、監修、真木、合理、独房、雑居、紋発、乱射、雑念、五輪、三振、欄居、托鉢、紋腹、画狂、欠年、射殺、殺傷、脳初、目車、濫用、懸念、學年、身者、卓越、餓死、軟卵、場者、童空、我作、滅法、涅槃、抹殺、怒気、燃焼、略奪、宰相、馬腹、刳発、南山、活発、沙羅、割腹、殺戮、循環、奈良、菜道、紗脚、残雑、颯和、和歌、東風、南富、背面、焼却、四季、同發、博羅、無償、透明、明闇、雲海、陶酔、溺愛、泊雑、湖畔、花車、小雑、蘭風、雑魚寝、逆発、罵詈、検遇、明細、鳥羽、無数、飾西、涼感、割烹、面月、略発、明暗、御覧、絶滅、名者、焼却、野版、絶筆、数界、洒落、羈絆、四索、敏捷、旋律、脚絆、安行、軽安、難産、伊賀、消滅、生滅、巡数、水災、万華、論発、処住、崇拝、年月、画鋲、我流、剣率、草庵、律年、雑魚、規約、貨車、蒸発、重大、錯乱、蓮妙、奈良、坐楽、延宝、財年、爆発、龍翔、日向、塁側、席園、座札、風評、財年、何発、旋律、画狂、論券、戦法、尊師、大概、二者、那波、麺期、演説、合邦、放射、雑律、貨客、選別、燕順、考慮、試薬初、財源、富、符号、井原、若榴、清涼、無數、才覚、絶望、奈落、奔放、有識、台東、詮索、懸念、病状、設楽、宴客、怠慢、時期、同部、弁解、冊立、立案、前略、妄動、侮蔑、廃絶、間髪、図解、経略、発泡、者発、立案、滅鬼、自利、論酒、桜蘭、五月雨、垓年、処理、短髪、散乱、絶滅、命日、庵客、実庵、龍翔、派閥、同盟、連峰、焼殺、勝中、割裂、残虐、故事、量発、敗残、花夢里、面月、原氏、雑考、推理、焼殺、膵癌、導風、千脚、砂漠、漁師、活滅、放射、洋蘭、舞妓、邪武、涅槃、毛髪、白藍、他式、民会、参謀、廃車、逆発、峻峰、桜蘭、殺戮、銘客、随分、刺死、脳犯、我版、論旨、無垢、血潮、風泊、益城、拝観、舘察、懺悔、空隙、髭白、模試、散乱、投射、破滅、壊滅、下痢、他殺、改札、寿司、葉式、魔雑、渾身、等式、命日、安泰、白藍、良志久、中須、掻敷、北方、監視、血式、血流、詐欺、加刷、販社、壊滅、坐楽、白那、苫小牧、欄物、演説、開脚、摩擦、欠史、宰相、掻敷、飾西、近隣、可能、刺自虐、崑崙、独歩、良案、隔絶、菜作、妄動、犬歯、核別、概要、立案、破格、殺戮、良案、快絶、防止、那古、風別、焼安泰、独庵、囲炉裏、壊滅、外傷、刃角、視覚、耳鼻、下顎骨、子孫、剥奪、憂鬱、優越、液状、先端、焼子孫、兵法、那波、安楽、最短、数式、絶句、庵杭、雅樂、動乱、者妙、垓年、独初、前報、奈落、数道、弓道、拝観、俯瞰、散乱、男爵、害面、炎上、抹殺、破棄、分別、額欄、学雑、宴客、体面、村落、柿区、害初、告発、欄式、体罰、侮蔑、浄光、情動、差額、君子、何発、兵式、童子、飾西、各滅、我札、審議、半旗、普遍、動脈、外傷、無償、木別、別格、名皿部、京脚、破棄、試薬、絶滅、学札、清涼、爆発、組織、壊滅、ここに、名もなき詩を、記す。風水、万別、他国、先式、続発、非力、産別、嘉門、神興、撃易、弊社、紋別、座泊、画狂、式典、胞子、画力、座敷、学舎、論別、閉域、爆風、万歩、博識、残忍、非道、望岳、死骸、残骸、符合、壊滅、匍匐、弄舌癖、死者、分別、砂漠、白藍、模写、服役、奈落、忖度、符尾、同盟、田式、左派、具癖、退役、蛇路、素白、昆北、北摂、写経、文武、択液、図解、挫折、根塊、道厳、視野別、奈落、鳥羽、グリシャ・イェーガー、粗利、惨殺、学癖、優遇、陶器、場作、土壌、粉砕、餓鬼、草履、羅列、門泊、戸癖、山系、学閥、座枠、忠膵癌、視野別、脳族、監視、佐伯、釋迦、敏捷、遇歴、佐渡、名張、紀伊市、名刺、干瓢、夏至、楽節、蘇遇、列挙、間髪、風脚、滅法、呪水、遇説、死骸、爆発、山荘、塀楽、茗荷、谷底、愚者、妄動、還魂、色別、最座、雑載、論客、名足、死期、近隣、名張、迷鳥、呑水、飛脚、晩別、獄卒、殺傷、視覚、乱脈、鉱毒、財閥、漢詩、死語、諸富、能生、那波、合理、血中、根菜、明初、鹿楽、宮札、度劇、臥風、粋玄、我馬、洞察、今季、爾脈、羅猿、激園、葉激、風車、風格、道明、激案、合祀、坐楽、土地油、力別、焼殺、年配、念波、郭式、遊戯、富部区、奈脈、落札、合祀、寒白、都山、額札、風雷、運説、害名、亡命、闘劇、羅沙莉、砂利、夢中、淘汰、噴水、楽章、農場、葉激、際泊、手裏、合併、模等部、トラップ、落着、御身、学習、零、概要、各初、千四、何匹、笘篠、熊本、京駅、東葛、土量、腹水、活潑、酢酸、数語、隠語、漢語、俗語、羽子、豚皮、刃角、醪、能登、半年、餓鬼、泣塔、用紙、喜悦、山荘、元相、炭層、破裂、腹水、薔薇、該当、懐石、討滅、報復、船室、壊滅、回族、先負、嗚咽、暁闇の、立ち居所、餞別、乾式、財閥、独居、乱立、差脈、桜蘭、龍風、抹殺、虐案、某尺、無銭、漏洩、北方領土、白山、脱却、幻滅、御身、私利私欲、支離滅裂、分解、体壁、脈、落札、合祀、寒白、都山、額札、風雷、運説、害名、亡命、闘劇、羅沙莉、砂利、夢中、淘汰、噴水、楽章、農場、葉激、際泊、手裏、合併、模等部、トラップ、落着、御身、学習、零、概要、各初、千四、何匹、笘篠、熊本、京駅、東葛、土量、腹水、活潑、酢酸、数語、隠語、漢語、俗語、羽子、豚皮、刃角、醪、能登、半年、餓鬼、泣塔、用紙、喜悦、山荘、元相、炭層、破裂、腹水、薔薇、該当、土脈、桜蘭、郎乱、乱立、派閥、別癖、恩給、泣き所、弁別、達者、異口同音、残骸、紛争、薔薇、下界、雑石、雑草、破戒、今滅、梵論、乱発、人脈、壊滅、孤独、格律、戦法、破戒、残席、独居、毒僕、媒概念、突破、山乱発、合癖、塹壕、場技、極楽、動脈、破裂、残債、防壁、額道央、奈良市の独歩、下界残滓、泣き顎脚、朗唱、草庵、場滅、乖離、鋭利、破戒、幕府、網羅、乱脈、千部、土場、契合、月夕、東美、番號、虎破戒、在留、恥辱、嗚咽、完封、摩擦、何百、操船、無限、開発、同尺、金蔵寺、誤字、脱却、老廃、滅法、涅槃、脱却、鯉散乱、立哨、安保、発足、撃退、学別、憎悪、破裂無痕、磁石、咀嚼、郎名、簿記、道具雨、壊滅、下落、吐瀉、文別、銘文、安胎、譲歩、剛性、剣率、社販、薙刀、喝滅、解釈、村風、罵詈雑言、旋風、末脚、模索、村立、開村、撃退、激癖、元祖、明智用、到来、孟冬、藻石、端午の贅室、癌客、到来、未知道具雨、寒風、最壁、豪族、現代、開脚、諸富、下火、海日、殺傷、摩擦、喃楽、続落、解脱、無毒、名毒、戒脈、心脈、低層、破棄、罵詈、深海、琴別府、誠、生楽、養生、制裁、完封、排泄、虐殺、南京、妄撮、豚平、八食、豪鬼、実積、回避、答弁、弁論、徘徊、妄説、怒気、波言後、節楽、未開、投射、体者、破滅、損保、名水、諸味、透析、灰毛、界外、土偶、忌避、遺品、万別、噛砕、剣率、戒行、一脚、快哉、提訴、復刻、現世、来世、混成、吐瀉、場滅、経絡、身洋蘭、舞踏、近発、遊戯、男爵、最上、最適、破裂、改名、痕跡、戸杓、分髪、笠木、路地、戳脚、快晴、野会、対岸、彼岸、眞田、有事、紀伊路、八朔、減殺、盗撮、無札、無賃、無宿、龍梅、塩梅、海抜、田式、土産、端的、発端、背側、陣営、戒脈、母子、摩擦、錯覚、展開、星屑、砂鉄、鋼鉄、破滅、懐石、桟橋、古事記、戸杓、媒概、豚鶏、墓椎名、顎舌骨筋、豚海、砂漠、放射、解説、海月、蜜月、満期、万橋、反響、雑摺、油脂、巧妙、

しかし、不思議だよなぁ、だってさ、地球は、丸くて、宇宙空間に、ポッカリ、浮いてんだぜ😂でさ、科学が、これだけ、進化したにも、関わらず、幽霊や、宇宙人👽たちの、ことが、未だに、明かされてないんだぜ😂それってさ、実は、よくよく、考えたら、むちゃくちゃ、怖いことなんだよ😂だってさ、動物たちが、呑気にしてるのは、勿論、人間ほどの、知能指数、持っていないから、そもそも、その、不安というのが、どういう、感情なのか、わかんないんだよ😂それでいて、動物たちは、霊的能力、みんな、持ってんだよ😂でさ、その、俺が言う、恐怖というのはさ、つまり、人間は、これだけ、知能指数、高いのにさ、😂その、今の、地球が、これから、どうなっていくかも、不安なのにも、関わらず、その、打つ手を、霊界の住人から、共有されてないんだよ😂それに、その、未開拓な、宇宙人や、幽霊たちとの、関係性も、不安で、しょうがないんだよ😂つまり、人間の、知能指数が、これだけ、高いと、余計な、不安を、現状、背負わされてるわけなんだよなぁ😂そう、霊界の、住人たちによって😂でさ、もっと言うなら、😂それでいてさ、人間が、唯一、未来を、予想できてることはさ、😂未来、100%、自分が死ぬ、という、未来だけ、唯一、予想ができるように、設定されてんだよ😂でさ、それってさ、こんだけ、知能指数、与えられてて、自分が、いずれ、確実に、死ぬという、現実を、知らされてるんだよ😂人類は😂つまり、自分が、いずれ、死ぬという、未来予想だけは、唯一、能力として、与えられてんだよ😂勿論、霊界の、住人にだよ😂これさ、もう、完全に、霊界の住人の、嫌がらせなんだよ😂そう、人類たちへのな😂つまり、動物たちは、自分が死ぬことなんか、これポチも、不安じゃないんだから😂その、不安という、概念をさ、😂想像すること、できないように、霊界の住人にさ、😂つまり、設定されてんだよ😂動物たちは😂つまりさ、霊界の住人は、動物より、人間が、嫌いだから、こんなに、苦しいめに、人類は、立たせ、られてんだよ😂で、これ、考えれば、考えるほど、ゾッとするんだよ😂だって、霊能力ある、得体のしれない、霊界の住人の、嫌がらせ、させられてんだから😂人類は、今、まさに😂つまり、人間の知能指数こんだけ、あげさせられてるってことは、😂そういうことなんだよ😂つまり、自分の、死の恐怖と、死後、自分たちが、どうなるのか?という、二つの不安を、抱えさせられてんだよ😂人類は、今、まさに😂そう、霊界の、住人にだよ😂もし、霊界の住人が、人間、好きなら、こんなに、自分の死ぬことをさ、恐れる感情も、湧かないように、設定されてるはずだし、😂死後、自分が、これから、どうなるのか?という、不安を、感じることなく、生きてるはずなんだよ😂そう、霊界の、住人が、人間、好きなら、そんなこと、おちゃのこさいさい、😂なんだよなぁ😂つまり、動物たち同様、なんの、不安も抱くことなく、毎日、生活できてる、はずなんだよなぁ😂人類たちは😂
でさ、あと、も一つ、俺、不気味に、思えたのはさ、😂そもそもさ、この地球上に、なんで、人間だけ、生きてるわけじゃなくてさ、😂つまり、人類の先祖と言われている、猿や、魚類とかが、絶滅することなく、😂人間と、共に、この地球に、未だに、暮らしているのか?ってことなんだよ。😂だってさ、進化論で、言えばさ、😂つまり、オーソドックスな、猿で、例えるとさ、😂そう、猿は、人類の先祖なんだからさ、😂すでに、絶滅してて、いいはず、なんだよ😂そう、恐竜や、マンモスみたいに、猿も、絶滅していて、いいはずなのにさ、😂なんで、これだけ、年月が、経って、これだけ、人類の知能指数が、高くなるまで、時間が、経っているのにも、関わらずさ、😂未だに、猿が、人間と、地球に、共生しているのか?って、😂考えたことない?😂だって、不思議じゃん😂普通に、考えてもさ😂
1 note
·
View note
Text
虚子自選揮毫『虚子百句』を読む Ⅶ
花鳥誌2024年7月号より転載

日本文学研究者
井上 泰至
12 紅梅の莟は固し不言
初出は『玉藻』昭和八年四月号。続いて『ホトトギス』九年年二月号。「」と前書き。『五百句』には、「昭和八年二月二十二日 臨時句会。発行所」と注記。『喜寿���』には、「紅梅の莟が固い。恰も女の口を開かぬやうに」と自解している。
この句については立子の解説を引こう。
紅梅の赤い莟はまだふくらんでゐるといふほどでなく固く結ばれてをります。その固い紅梅の莟を詠じた句であります。それを美人に譬えて、その美人はにこやかに情がありげに見える、併し固く口をつぐんで一言も云はない。そのさまに似てゐる紅梅の莟であるよ、といったのであります。清楚なそして艶な句であります。
これに対して、本誌令和五年二月号(「恋の季題」)に、この句についての解釈は提出しておいたので、再記しておく。梅に恋の気分を込めたものである。口が堅いだけ、恋の意志は強く、開花を待っている。開いた時の色香は余計に強いのだ。いざとなれば女性の方が強く、果敢なのだと虚子は言いたげである。「不言」という表記は、まずは漢文風の改まった言い方で、品格を保ったと見える。ただし、取り澄ましただけではない。言葉に出されないからこそ、かえって思いは募ることも匂わせているのだ。
立子もこういうことは心得ていて、あえて余計な説明までは加えなかったのかも知れない。なお、『喜寿艶』では、掲句の後にはこの句を配している。
鶯や文字も知らずに歌心 虚子
無学の女だが、かえって上手に言おうとする野心がなく、イノセントな歌声が届く。聞いている男は、その声に歌の心、即ち恋の心を呼び覚ました。梅に鶯の連想もあり、両句並べて、無言の意志から、恋の囁きへの展開を確認できる。『虚子百句』でも次は鶯の句である。
13 鶯や御幸の輿もゆるめけん
『ホトトギス』昭和九年四月号に「懐古」と題して初出。『五百句』に「昭和八年四月十二日 中辺路を経て田辺に至る。中辺路懐古」と注記。
中辺路(なかへち)とは、熊野三山に至る参詣道のうち、田辺から本宮、新宮、那智に至る山岳路のことで、特に平安時代から鎌倉時代に皇族貴族が延べ百回以上も繰り返した「熊野御幸」では、中辺路が公式参詣道、すなわち御幸道となった。
その当時の旅は、人影の少ない長く険しい山道を越えるだけでなく、たとえ寒い早朝であっても水垢離(水浴び)をして心身を浄めながら、ひたすら熊野の神々や仏の救いを心に念じ熊野三山へと向かうもので、山岳修行の色が極めて濃厚だった。
虚子は参詣とは逆コースを、楠目黄橙子・松尾いはほ等とたどったようで、近野村の茶店に休んだ折の句である。 虚子の「中辺路」という文章にはこうある。
中辺路といふ名前がなつかしかつた。―昔後鳥羽上皇などが熊野に御幸になつたのも此中辺路を通られたのであつて、「道成寺」の安珍なども此道を取り、それのみならず蟻の熊野詣りといふ諺があるやうに、此道をぞろぞろと熊野詣の群衆の通つたところでもあつたのであつた。其山路だと思ふと何となくなつかしく――今は淋しい山路で、私達に行違ふ旅人は一人も無い位であつたのである。――私はカラコロカラコロと足駄の音を響かせながら歩いた。
虚子の脳裏には、謡曲「道成寺」で、美形の僧安珍がこの中辺路を経て、清姫に見初められ、恋の激情の蛇体となって襲われる悲劇となったことや、院政期貴賤群衆の信仰を集めた様が去来していた。
なお、年尾が解説しているように、秀衡桜という一本があり、句を得たのは、そのあたりのことという。平安時代後期、奥州の豪族、藤原秀衡が滝尻の岩屋に残したわが子の無事を祈念して、そこにあった桜を手折り、別の木にその桜を継いだという伝承がある。
先にも述べたように、前の句の鶯の連想から、この梅の句を揮毫したことも容易に想像される。となれば前の句は紅梅を美女に比し、恋に文字通り身を焦がした清姫の連想も働いたか。
さて、そろそろ図版の揮毫の見方についてコメントしておこう。図版に挙げた右の「栞して」の句は、「虚子」の落款(署名)が句の左に配置されている。対する左の「紅梅」の句の落款は、句の真下に位置する。
それを確認した上で、一句の字配りを確認すると「栞して」の句は全体に筆が左から右に流れ、それと対置する形で、左に「虚子」の署名が置かれているのである。バランスをとっているわけだ。
対して「紅梅」の句にそれほどの傾きはない。つまり、虚子は「書」の基本である字配りのバランスを常に意識して書いていたことになる。よって、晩年の眼が弱り、力も減じた筆勢とはいえ、中心線はぶれていないことになる。
次の「紅梅」の句の「紅」の字は、一句全体を統御する強い字となっている。次々号にも「紅梅」の句を掲出する予定だが、そちらは優しい書き方である。
また、「栞して」の句の「山」の字は、整った字形で西行へのリスペクトも感じられるが、『虚子百句』に「山」の字を使った句は十指に余る頻出ぶりで、一つとして同じ書き方はない。二月号に挙げた「山寺」の「山」の字など、句の内容の滑稽を反映して字も、剽軽な俳諧味のある「山」になっている。「書」には眼目となる字が必ずあるが、虚子は確実にそのあたりを意識して筆を振るっていたようだ。まず、虚子の揮毫は序文に記すように、手習いをしなかったとはいうものの、いい字を見てそれを覚えていた可能性は高く、あとは修練で、晩年には自在の境地を得たようである。
便利堂がこの企画を持ってきたのも、虚子の字のその辺の高度な在り方を、ある程度意識していたからだと推察できるのである。
『虚子百句』より虚子揮毫
13 鶯や御幸の輿もゆるめけん
14 道のべに阿波の遍路の墓あはれ

国立国会図書館デジタルコレクションより
___________________________
井上 泰至(いのうえ・やすし) 1961年京都市生まれ 日本伝統俳句協会常務理事・防衛大学校教授。 専攻、江戸文学・近代俳句
著書に 『子規の内なる江戸』(角川学芸出版) 『近代俳句の誕生』 (日本伝統俳句協会) 『改訂雨月物語』 (角川ソフィア文庫) 『恋愛小説の誕生』 (笠間書院)など 多数
0 notes
Text
インド建築縦走旅vol1 デリー編
メキシコでルイスバラガン、ブラジルでオスカーニーマイヤー、インドでコルビュジェ、という世界遺産巨匠建築を40代に見たいと思っていました。2012年にメキシコに行ってから12年。インドは2020年に行く予定がコロナ襲来で、50代に突入してしまいましたが、ついに念願のインド初上陸へ。2019年以来の海外旅ということ、インドの噂を色々聞くにつけ、緊張感しかない・・・という状況で出発。しょっぱな飛行機が遅延して、バンコクのトランジットは、スタッフに連れられて空港内を走り抜けるも、無事、デリーインディラガンジー空港に到着。
ナマステー。

トイレのサインが大変わかりやすい。

とワクワクしながら入国すると、荷物きませんでした。
ロストバゲージは想定範囲内で、一泊分の着替えや必要なものは手荷物にしていたので動揺少なめ。タイからの便は1日3便で翌朝には届くとのことで手続き終えて外に出ると、首を長くして待っていてくれたドライバーとガイドさんと無事合流。デリー市内の行きたいところをお伝えして出発。まずはクトゥブミナールへ。
平日のはずだが、すごい人。

インド最古のイスラム遺跡群だそうです。ゴール朝の指揮官クトゥブtディーンアイバクが、北インドを制圧した記念に建立されたもの。1192年(日本では源頼朝の時代)に建設が始まった。インド初のイスラム支配で、アイバク自身が奴隷だったことから、奴隷王朝と呼ばれる。塔の高さは72.5mの5層構造。

塔の手前にあるのがクワットゥル・イスラーム・モスク。1188年に建設されたもの。破壊されたヒンドゥー寺院の石材を使って建てられたため、偶像崇拝を認めないイスラム寺院でありながら、列柱に女神像が残る。

美しい列柱空間。

3〜4世紀のグプタ朝時代に造られたとされる鉄柱は、鉄の純度が100%に近いとかで、いまだ錆びないという謎の鉄柱。

イスラム様式、ヒンドゥ様式が混在するモスク。

奴隷王朝を滅ぼしたジャラールッディーンはハルジー朝を開くも、甥のアラウッディーンに暗殺されてしまうが、その甥っ子が建てたのがこのモスク。模様がきれい。

繁栄しては滅ぼされ、時代を変えて建てられた建物たち。

日本の城もそうですが、人間の建設技術力のすごさが想像の域を超えます。
移動して中心部へ向かいランチタイム。ガイドのアシラさんオススメのお店に連れていってもらう。

さっそくカレーカレー。

マサラチキンとパニール、ラッシーも忘れずに。

ランチ後、国会図書館を目指すもリノベーション中で見れず、フランス語学習・文化施設アライアンス・フランセーズ(インドフランス文化センター)へ。
建物は2004年に建てられたもの、2020年に内部の改修が行われたそう。またも入口でとめられるが、施設の代表の方?が登場し、「今日は天皇誕生日ですよね」などと話しかけてもらいながら、入管許可を得る。

入口のホワイエは高い吹抜けの上の屋根フレームを十字形のコンクリート柱が支えている。

このあと見に行くチャンディガルにあるコルビュジェの「オープンハンド」のモチーフが廊下に光る。インドとフランスを結ぶ?

地下のギャラリーの中にも十字柱があらわれていて、インド人のガイドがおもしろがっていた。

改修後のフロントオフィス。

日本語堪能な熟練ガイドさんもこの建物は初めてだったようでした。そして、ここから、ニューデリー2つ目の世界遺産、フマユーン廟へ。

門を抜けると。

ムガル朝第2代皇帝フマユーンの墓廟で、王妃が建てたもの。9年の歳月をかけて1565年に完成。ミニタージマハール、��ガイドのアシラさんは言ってたけれど、頂点にドームをおくムガル様式の礎となる建物で、100年後のタージマハルなどへ受け継がれているそう。

穴あきレンガから差し込む西日がとても美しい内部で、みんな順番に撮影タイム。

特徴的な赤い建物が、西日でさらに赤くみえる夕暮れ時。

そしてデリー3つ目の世界遺産、ラールキラー(赤い城)を見るためにオールドデリーへ。ガイドのアシラさんは17時にクローズと言っていたのですが、地球の歩き方に20時までと記載があったので、とりあえず行ってみる。
が、残念、やっぱりクローズ。しかし城壁だけでも十分に堪能できる赤い城。ムガル帝国第5代皇帝シャー・ジャハーンによって、1639年から9年かけて建てられたもので、城壁は2.4キロとのこと。

ライトアップと月。相変わらず人だらけ。

そして、最後にマーケットへ。リクシャリクシャリクシャ、人人人、へー、やっぱり頭に載せるんだ、と驚く初日の私。

ガイドのアシラさんが「絶対食べて」というお店に連れていってもらうと、すごい人だかりが。

人だかりの奥には、揚げ物してるおじさん。

人気の正体はJALEBIというインドのお菓子。サモサと一つずつ買ってみる。美味!

1日を満喫しホテルへ向かう途中、今回、いろいろをお願いしたシゲタトラベルさんに立ち寄って、両替したり、SIMの手配をお願いする。待ってる間にふるまっていただいた初チャイ。
長い1日のあとのチャイがなんとも体に染み渡る。最高です。この素焼きカップ「クリ」というそうですが、飲んだら叩き割って捨てちゃうのです。びっくり。ヒンドゥ教は人の使った食器は不浄なんだそう。

人人人、車車リクシャ、クラクションという喧騒のデリー初日、22時も過ぎてしまったのでホテルの食堂でカレーを食べて寝る。インド建築縦走旅、スタート。
0 notes