#手漉き紙
Explore tagged Tumblr posts
Text
カミスキ

紙漉きとは、植物繊維を水に溶かして漉き取ることで紙を作る伝統的な製紙法です。和紙を作る際に用いられる手法で、その歴史は古く、日本では7世紀頃にはすでに紙漉きが行われていたと言われています。工程は、大きく分けて「原料の準備」、「煮込み」、「叩き」、「漉き」、「乾燥」の5つの段階で構成されます。伝統的な手法であり、職人の技術や経験が紙の品質に大きく影響します。手漉き和紙は独特の風合いや美しさを持つため、書道や絵画、工芸品などの材料としてだけでなく、照明やインテリアなどさまざまな用途で使われています。
手抜きイラスト集
#紙漉き#paper making#fabbricazione della carta#fabricación de papel#Papierherstellung#fabrication du papier#手抜きイラスト#Japonais#bearbench#art#artwork#illustration#painting
1 note
·
View note
Text
手漉き?機械漉き? それぞれの良さから知る和紙の世界/Understanding the Difference Between Handmade and Machine-made Washi

手漉き和紙と機械漉き和紙の違いに焦点を当て、あまり知られていないそれぞれの強みや、製法による見た目の違いについて解説。それぞれの和紙が持つ特徴を知ることで、和紙選びの視野が広がります。
手漉き?機械漉き? それぞれの良さから知る和紙の世界
0 notes
Text











Decorative Sunday
There are 440 Washi-producing centers throughout Japan. It is widely produced not only as traditional paper using pure kozo, mitsumata, and gampi, but also as more contemporary paper used in art, crafts, folkcrafts, casting, and molding. Washi is an intangible cultural asset and traditional craft product of Japan.
The examples shown here are from Washi, Handmade Paper of Japan (日本の紙 : 全国手漉き和紙見本帖), a specimen book of 307 Washi paper samples in a binder, produced at Ino, Agawa District, Kōchi Prefecture, Japan by Zenkoku Tesuki Washi Rengōka in 1997. Shown here from the top:
Ecchu Washi, Katazomeshi (Stencil Printed Paper): A resist is applied onto the kozo base paper through a stencil. The paper is then dyed, and then the resist paste is washed away to reveal the image.
Mino Washi: Flowers and butterflies are embedded in kozo paper, used for handicrafts and interior decoration.
Echizen Washi, Seikaiha (semicircular repeated wave patterns): mitsumata paper with gold leaf.
Mino Washi: Kozo with embedded butterfly.
Echizen Washi, Kiriasa: Mitsumata paper.
Echizen Washi, Hiryushi: Mitsumata paper.
Sakishu Washi: Unbleached kozo paper is processed by folding the paper and dipping the edge into dyes to create a variety of colors and patterns.
Tosa Washi: Made from kozo and Manila hemp.
Kurotani Washi, Bingata-somegami: Made from kozo, Bingata was produced as one of the folkcrafts in Ryukyu, using a dye and resist method.
Our copy is another donation from our late friend Jerry Buff (1931-2025).
View more posts on decorative papers.
View more Decorative Sunday posts.
#Decorative Sunday#decorative plates#decorative art#patterns#patterned papers#decorative paper#Washi#Handmade Paper of Japan#kozo#mitsumata#gampi#Japanese paper#specimen books#paper specimens#paper
127 notes
·
View notes
Text
雑草たべてみた展

とちぎ花センターで「雑草たべてみた展」を見る。「食糧難に備えてそのへんの草 食べてみました」と銘打っている。
入口の手前に、雑草を食べる前の心得が明示してある。入口の左右には「雑草という草はない」という有名なことばの幟。


この企画展の主役の雑草の皆さん。

ちゃんと名前がついている。

「あなたが食べるべき雑草がわかる! 雑草チャート」。ちなみに自分は(まあ食べるべきとか言われても食べる気はないけど)ノゲシになった。

いよいよ「とちぎ花センターの自称カリスマ主婦たち渾身の雑草レシピ」が登場する。

一週間分の献立になっているのがすごい。

よくスーパーに置いてある写真入りレシピカード、あれを連想した。


「これからは食卓に雑草を!」……じゃあないんだよ。

でも、無責任に勧めるのではないところに専門家の矜持と良心を感じる。

スギナ推しコーナーがあった。

スギナの皆さん。

スギナ染め。媒染によって色目が変わる。

スギナで紙を漉いて作ったノート。ものすごくザラザラした質感で、墨やインクなどが盛大に滲みそうな雰囲気だったが、残念ながら試し書きはできない仕様。


雑草つながりで、埼玉県立熊谷農業高校の野菜昆虫部の雑草標本の展示。野菜昆虫部の活動内容が気になる。



顔ハメ撮影スポット。自撮りもOK。

追記。NHK宇都宮放送局のニュースがこの企画展を取り上げていた。映像には食レポもあり。
32 notes
·
View notes
Text
Papermaking

Swords and the Law
I learned how to make paper. I was fine even when I had to work my hands
In cold water in the middle of winter. But now I don't make paper. I get so cold that I need water to warm my hands. I wouldn't be able to make paper in Russia like this.
Rei Morishita
紙漉き
私は紙漉きを学んだ。 真冬に冷たい水の中で 手を動かしても へっちゃらだった。 だが今、紙漉きをやらない。 手を温める水が必要なほど 寒がりだ。 これではロシアでは 紙を漉けないな。
森下礼
صناعة الورق
لقد تعلمت كيفية صنع الورق. في الماء البارد في منتصف الشتاء حتى لو حركت يدي كان مثير للاشمئزاز. لكنني الآن لا أصنع الورق. أحتاج إلى الماء لتدفئة يدي أنا بردان. الآن في روسيا لا أستطيع صنع الورق.
ري موريشيتا
изготовление бумаги
Я научился делать бумагу. В холодной воде посреди зимы Даже если я двигаю руками Это было отвратительно. Но сейчас я не делаю бумагу. Мне нужна вода, чтобы согреть руки Мне холодно. Сейчас в России Я не умею делать бумагу.
Рей Моришита
#Papermaking#cold water#middle of winter#water to warm my hands#Russia#rei morishita#森下礼#Swords and the Law
2 notes
·
View notes
Text
和紙のポストカードづくり
こんにちは!しのわくスクールです。
先日、和紙のポストカードづくりを実施したので、その様子をお伝えします。
今回講師をしてくださったのは、和紙ラボTOKYOの篠田佳穂さん。

台東区の下町御徒町にショップ兼工房を構えており、外国人の方や小学生に向けてワークショップ等もおこなっております。
今回はガーセをいれたかわいいポストカードを作りました♪

日本の伝統工芸として知られる和紙ですが、そもそも何からできているかご存じですか?
和紙は、楮(こうぞ)という植物からできており、柔らかい状態にしてから皮の部分だけを削いで原料が作られています。
ただ、これだけでは和紙はうまく作れず、トロロアオイという植物の根っこから抽出する『ねり』が必要不可欠です。
この『ねり』があることで、楮の繊維が水に沈殿せず、均等にならされて綺麗な和紙が完成するそうです!和紙ができるまでには、職人さんの高い技術によって丁寧に、そして時間をかけて作られているのですね。
そんな和紙ではありますが、実は身近にある植物からも作ることができるそうです!!
すると、先生がもみじのような葉の形をした梶の木(かじのき)という植物を見せてくれました。

クワは上野公園の不忍池にも生えているようで、子ども達も『そんなにすぐ近くからとれるの!?』と驚いていました。
気軽に見ることができるので、散歩がてらお子さんと一緒に探してみてください♪
先生から和紙のお話を聞いた後は、ポストカードづくりに挑戦!
3人3チームにわかれて、下の役割を順番におこないました。
1番手:「簀桁(すげた)」という和紙を漉く道具を持って揺らす
2番手:原料が入ったボウルを簀桁に流しいれる
3番手:ボウルに溜まった水を戻す
繊維がよく混ざるように原料の容器をよく振ってから、何回かに分けて流しいれると、あとはスピード勝負!

ゆっくり揺らすと和紙が乾いてきてしまうので、均等になるようにすばやく簀桁を揺らしていきます。
隅まで原料がいきわたるように、簀桁を揺らすのが意外と難しく、初めての漉く作業に子ども達も少し緊張した様子でした☺


和紙を漉いたら、最後は圧搾という作業。
上から板で重みをかけて水分を絞り出すことで、和紙がよく締まり強度を増すそうです。

最後に、和紙を窓に貼り付けたら、自然乾燥させて完成を待つのみ!
後日、完成した和紙を子ども達に渡すと、『けっこう固い!』『ちゃんと紙になっている!!』と嬉しそうにしていました♪

普段は完成した和紙をみることが多いですが、今回のプログラムを通じて和紙がどのように作られていて、どんな職人さんが関わ��ているのか、裏側を知ることができました。
自分達でつくったからこそ、ものづくりの楽しさだけでなく、和紙づくりの難しさや大変さも知ることができたのではないかと思います。
このプログラムを通じて、子ども達が和紙や日本の伝統工芸に興味をもったり、ここでの発見や学びが子ども達の将来に少しでも繋がれば幸いです。今回、プログラムに協力してくださった和紙ラボTOKYOの篠田さん、ありがとうございました!
2 notes
·
View notes
Text
2023年10月27日に発売予定の翻訳書
10月27日(金)には33冊の翻訳書が発売予定です。うちハーパーコリンズ・ジャパンが14冊です。
叫びの穴
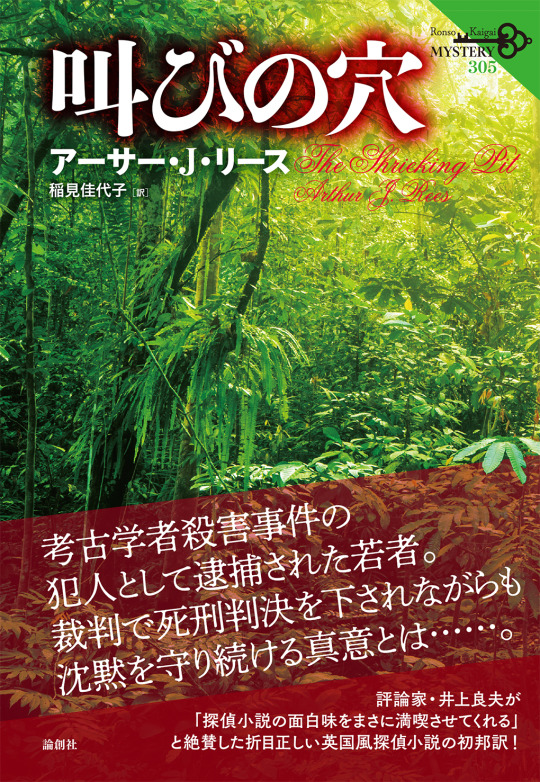
アーサー・J・リース/著 稲見佳代子/翻訳
論創社
自立的で相互依存的な学習者を育てる コレクティブ・エフィカシー
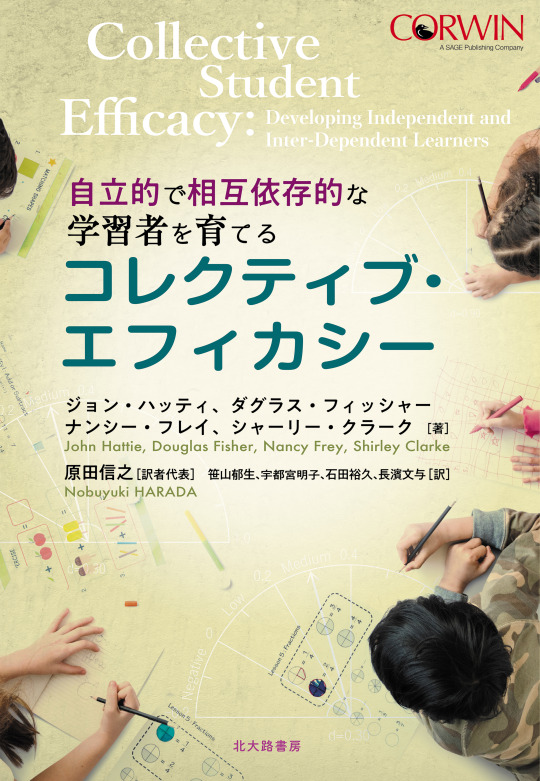
ジョン・ハッティ/著 ダグラス・フィッシャー/著 ナンシー・フレイ/著 シャーリー・クラーク/著 ほか
北大路書房
ビートルズ ’66

スティーヴ・ターナー/著 奥田祐士/翻訳
DU BOOKS
[ザ・シーダーズ]神々の帰還(下) : 秘められし宇宙テクノロジーの大開示
エレナ・ダナーン/著 佐野美代子/翻訳 アレックス・コリエー/著
ヒカルランド
パディントンのクリスマスの手紙 : Paddington's Christmas Post
マイケル・ボンド/イラスト R・W・アリー/イラスト 関根麻里/翻訳
文化学園 文化出版局
ギャリー・カーツ マジック・コレクション
リチャード・カウフマン/著 角矢幸繁/翻訳
東京堂出版
飼育下パンダの野生復帰
張和民ほか/著 岩谷季久子/翻訳
科学出版社東京
1930年代の只中で : 名も無きフランス人たちの言葉
アラン・コルバン/著 寺田寅彦/翻訳 實谷総一郎/翻訳
藤原書店
中国手漉竹紙製造技術
陳剛/著 稲葉政満/監修 白戸満喜子/翻訳
科学出版社東京
なぜ私たちは燃え尽きてしまうのか
ジョナサン・マレシック/著 吉嶺英美/翻訳
青土社
Pythonによる時系列予測
Marco Peixeiro/著 株式会社クイープ/翻訳
マイナビ出版
富豪に仕える : 華やかな消費世界を支える陰の労働者たち
アリゼ・デルピエール/著 ダコスタ吉村花子/翻訳
新評論
中国仏性論
頼永海/著 何燕生/翻訳
法藏館
新版 地図とデータで見る水の世界ハンドブック
ダヴィド・ブランション/著 吉田春美/翻訳
原書房
第二次世界大戦 運命の決断 : あなたの選択で歴史はどう変わるのか
ジョン・バックレー/著 辻元よしふみ/翻訳
河出書房新社
「自信がない」という価値
トマス・チャモロ=プリミュージク/著 桜田直美/翻訳
河出書房新社
生物学大図鑑 : 世界を知る新しい教科書
メアリ・アージェント=カトワラ/著 左巻健男/監修 黒輪篤嗣/翻訳
河出書房新社
ジンジャーとピクルスのおはなし
ビアトリクス・ポター/著 川上未映子/翻訳
早川書房
パイがふたつあったおはなし
ビアトリクス・ポター/著 川上未映子/翻訳
早川書房
路地裏で拾われたプリンセス
ロレイン・ホール/著 中野恵/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
一夜の夢が覚めたとき
マヤ・バンクス/著 庭植奈穂子/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
愛は一夜だけ
キム・ローレンス/著 山本翔子/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
伯爵夫人の出自
ニコラ・コーニック/著 田中淑子/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
シンデレラの十六年の秘密
ソフィー・ペンブローク/著 川合りりこ/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
天使の誘惑
ジャクリーン・バード/著 柊羊子/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
目覚めたら恋人同士
ペニー・ジョーダン/著 雨宮朱里/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
禁じられた言葉
キム・ローレンス/著 柿原日出子/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
捨てられた花嫁の究極の献身
ダニー・コリンズ/著 久保奈緒実/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
街角のシンデレラ
リン・グレアム/著 萩原ちさと/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
侯爵と雨の淑女と秘密の子
ダイアン・ガストン/著 藤倉詩音/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
身代わりのシンデレラ
エマ・ダーシー/著 柿沼摩耶/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
悲しみの館
ヘレン・ブルックス/著 駒月雅子/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
薔薇色の明日
レベッカ・ウインターズ/著 有森ジュン/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
2 notes
·
View notes
Text
KMNR™ exhibition「紙標」カミナリ "SIRUSI" 2023.9.16 Sat - 10.8 Sun

この度VOILLDは、谷口弦、桜井祐、金田遼平によるアーティスト・コレクティブ、KMNR™(カミナリ)の新作個展「紙標(しるし)」を開催致します。本展は2022年に開催された個展「PAUSE」 に続く、VOILLDでは二度目の新作展となります。
谷口弦は1990年佐賀県に生まれ、江戸時代より300年以上続く和紙工房、名尾手すき和紙の七代目として家業を継ぎ伝統を守りながら、様々な技法や素材を手漉き和紙の技術と掛け合わせ、和紙を用いたプロダクトの開発や先鋭的な作品を制作しています。桜井祐は1983年兵庫県に生まれ、現在は福岡を拠点に自身が設立したクリエイティブ・フォース TISSUE Inc.にて編集者としてアートブックの出版や幅広いメディアの企画・編集・ディレクションを行い、並行して九州産業大学芸術学部ソーシャルデザイン学科の准教授を務めています。金田遼平は1986年神奈川県に生まれ、独学でデザインを学び渡英。グルーヴィジョンズへの所属を経てデザインスタジオYESを設立し、東京を拠点にグラッフィクデザイナー・アートディレクターとして活動をしており、三者三様に国内各地で多彩なプロジェクトを手掛けています。カミナリは2020年にこの3名から結成され、国内外での展覧会の開催やグループ展への出展、企業への作品提供など、精力的に作品の発表を行っています。
カミナリは伝統的な手すき和紙の技術を用いて再生された紙「還魂紙」を使って、様々な時代の「物」に宿る魂やストーリーを紙にすき込み、先人達が積み重ねてきた和紙という歴史を現代の観点で解体し、新たな価値を吹き込み再構築した平面、立体作品を制作しています。江戸時代以前、反故紙を用いて漉き直された再生紙は、原料の古紙に宿っていた魂や情報が内包されていると考えられていたことから還魂紙と呼ばれていました。カミナリは、その還魂紙を活動のコンセプトであると同時に軸となるマテリアルとして用いること��、過去と現在、変化し続ける未来、そして異なる文脈の物事を繋ぎ合わせるという役目を持たせています。素材の持つ歴史と特性を熟知し、様々な要素を重ね作品に投影することで、和紙の歴史を通観するものとしても捉えることができるのです。
「紙標(しるし)」と題された本展では、近年制作している関守石をモチーフとした立体作品「PAUSE」のシリーズに続き、石をモチーフとしたオブジェクトをさまざまに組み合わせ紐で結び上げた立体作品を発表いたします。和紙とは人間が人間のために作った「記録」や「記憶」を残すための媒体でありながら、近年のデジタルやインターネットの普及によりその在り方は形を変えてきており、紙を使うこと自体がまるで儀式のような特別な意味を持つようになってきているとカミナリは言います。そして石とは、物質が長い年月をかけ積み重なりできた「時間」や「歴史」の象徴と言えます。その二つを組み合わせることで、生きてきた証や過去の思い出といった、形にしがたいものたちを可視化し、そこに置くことで気付き、立ち返れるものとして一連の作品が制作されました。印象的な結び目は、日本古来の結びなどから着想を得て、しめ縄や結界、魔除けのような想いを込めながらひとつひとつ結び上げられています。物理的な法則と独自の感性、立体としての美しさと均衡が巧妙に作用しながら制作された作品は、それぞれが独立しながらも、有機的に結びついているのです��伝統と芸術、過去と現在、そして未来へと往来しながら、道具を使わず手作業のみで結び上げられた作品群は現代の民芸的作品とも言えるのではないでしょうか。
作品と行動を介して、歴史とはなにか、人の記憶とはなんなのかという根本的な疑問を投げかけながら、新鮮な角度から思考と実践を重ね練り上げた、およそ20点に及ぶ作品群を展示いたします。カミナリの新たな展開となる本展を是非ご高覧頂ければ幸いです。皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。
ー
忘れていた。 初めて触れたと思っていた感情や感覚の多くは、実はすでに経験したことだった。
にもかかわらず僕らは、ときにその事実をも忘却のあちら側へと線引きしてしまう。 だからこそ人は石木を刻み、土に楔打ち、紙に記録してきた。
形のないものに形を与える行為はつくる者の体内に原始の感覚を、経験していないはずの記憶を呼び起こす。 その瞬間、僕らは確かに“思い出している”のだ。
ーKMNR™


KMNR™ |カミナリ 2020年、佐賀県名尾地区において300年以上の歴史を持つ名尾手すき和紙の7代目・谷口弦、編集者の桜井祐、アートディレクターの金田遼平によって結成されたコレクティブ。伝統的な手すき和紙の技術を用いることで、新たな文脈を持ったメディウムとしての「還魂紙」を生み出し、作品制作を行う。 IG: @kmnrtm ー谷口弦 名尾手すき和紙7代目。1990年佐賀県生まれ。関西大学心理学科卒業後、アパレル会社勤務を経て、江戸時代より300年以上続く和紙工房の名尾手すき和紙に参画。家業として伝統的な和紙制作を行うかたわら、2020年ごろよりKMNR™主宰として作品制作を開始。 HP: naowashi.com ー桜井祐 編集者。1983年兵庫県生まれ。大阪外国語大学大学院博士前期課程修了後、出版社勤務などを経て、2017年クリエイティブディレクションを中心に行うTISSUE Inc./出版レーベルTISSUE PAPERSを設立。紙・WEB・空間など、幅広い領域において企画・編集・ディレクションを行う。九州産業大学芸術学部ソーシャルデザイン学科准教授。 HP: tissuepapers.stores.jp ー金田遼平 グラフィックデザイナー/アートディレクター。1986年神奈川県小田原市生まれ乙女座。法政大学在学時に独学でデザイン制作を始め、卒業後に渡英。帰国後、2013年よりグルーヴィジョンズ所属。2018年よりフリーランス、2019年デザインスタジオYES設立。 HP: kanedaryohei.com Exhibitions:
2023 アートフェア「EASTEAST_TOKYO 2023」at 科学技術館
2022 グループ展「LIGHT」at VOILLD グループ展「8」at VOILLD 個展「PAUSE」at VOILLD
2021 出展「祈りのインターフェイス展」at BONUS TRACK GALLERY 個展「TIMESCAPE」at Muracekai 個展「秘事」at ニューGEN GEN AN幻 / OUCHI 出展「Kyushu New ART 2021」at 博多阪急8F催事場 作品提供「紙糸靴下|Paper Fiber Socks」for Goldwin 2020 長崎アートプロジェクト「じかんのちそう」招聘作家

KMNR™「紙標」 会期:2023年9月16日(土)~10月8日(日) オープニングレセプション: 9月15日(金)18:00 – 21:00 開廊時間:12:00 - 18:00 休廊日:月曜、火曜 ー 16th Sat Sep. 2023 - 8th Sun Oct. Open: 12-6pm Closed: Mon&Tue



1 note
·
View note
Text

ローラ・オーウェンズ
《無題》、2014年(部分)。
インク、シルクスクリーンインク、ビニールペイント、アクリル、油彩、パステル、紙、木材、溶剤転写、ステッカー、手漉き紙、糸、板、接着剤をリネンとポリエステルに使用。
5部構成。
全体サイズ:350.8cm × 270.5cm × 6.7cm。
ホイットニー美術館(ニューヨーク)。ジョナサン・ソーベル2014.281aeの資金による購入。© ローラ・オーウェンズ
0 notes
Text
木炭と没食子インクと羽ペンとフィキサチーフを作るワークショップ
時は2025年5月のゴールデンウィーク。 以前、奥深い洋画材の世界という実に大変面白すぎる展示をされていたギャラリー・エスパス・ラポルトさんで、今度は古典的石膏デッサンとその画材展を開催し、そのワークショップとして「作って試そう!木炭・インク・フェキサチーフ」を開催するというので参加してみました。 その備忘録です。
正直、4種類も画材作るのって欲張りすぎない!!??って思ったけれども、ちゃんとできました! ただ、ワークショップの時系列のまま記事を書くとカオスになりそうなので、画材ごとに分けてざっくり体験記録として残しておきます。
1.木炭作り
今回使うものはブドウとホオの木。 木炭に使われる木の説明も色々ありましたが、デッサンとか常に放棄してるし、木炭は高校の時に1回使ったっきりの自分がこのワークショップに参加して良かったのかなぁ……とか、きっと他の人は美術の道を歩んでる人達なんだろうなぁ……とかちょっと気が引けてたりし���ソワソワしたりして話に集中出来なかったのは内緒である。
とりあえず、なんでブドウの木がよく使われるのかは成る程納得した。
と言うわけでブドウ。 焼く前のブドウの枝とか、ホオノキの枝の写真を撮り忘れました。


左は表面の皮を剥く前。 右は表面の皮を軽く剥いた後。 こちらは比較的簡単に剥けました。

こちらはホオ。 ものすごく柔らかい鉛筆削りのような、ゴボウのささがきのようなそんな気持ち。 ほぉ……ってダジャレを何度も脳内で繰り返していた模様。 ほぉほぉ。

缶缶に詰めます。 本当は縦に、みっちり詰めた方が良いらしいのですが、今回のワークショップの人数的にこんな感じに。


焼きます。 缶のロットにばらつきがあるのか、蓋が開きそうになったり(本来は針金とかで縛っておくと良い)、巡回パトカーがやってきて怪しまれたらどうしよう!とか、外人さんからこの集団は何だ!?って見られたり、参加者たちでわいわいしながら焼きました。

こちらはホオ。 ちょっとヤニが出たそうです。 ブドウは生焼けの写真しかなかったのでカット。😢

できたものをデッサン紙に描いてみました。 しっかり描けて嬉しい。
今回は焼く温度やその他いろいろの条件で柔らかめの木炭になったので、うっかり折れてしまいましたが、楽しかったです。 (なお、反射的に半紙みたいにつるっとした方に描いてしまったが、デッサン紙は紙目がある方が表だった😇)
2.フィキサチーフ作り
今回は、シェラックを使ったフィキサチーフを作りました。 と言いたいところですが、ほぼ見てるだけで終了です🤣

こちらがシェラック。 こちら��アルコールに溶かすだけ!簡単!
まぁ我が輩、お酒飲めないし、消毒液の臭いだけで無理なか弱い人間ですので、地味に難易度高いんですけどね😭 (アンモニアの臭いは良いのに、アルコールは駄目なんだね……)
ですが、今回のワークショップの一番最初に溶かす作業に入ったのに、最後まで溶け切りませんでした!😂 (ちなみに全員分を一括で作ってます。なので自分はただみてるだけ)
このワニスの良いところは、アルコールなのですぐに揮発するので、重ね塗りしやすいところだそうです。 フィキサチーフとしてだけでなく、DIYにも良いとのこと。 その代わり、油彩画には使えないそう。
アルコール苦手ではあるものの、スプレー缶が苦手(捨てるとき困るし、真夏に暑すぎて爆発したらどうしようとか確率の低い心配をしている)な自分としては、このフィキサチーフの方が安心安全である。 アルコールは化粧品用のがちょうどあるし。
で、この溶かしてできたフィキサチーフを霧吹きで木炭画とかに吹きかけるわけですが、画像がなくてごめんなさい。 (自分のモノは写真に撮れないし、他人を勝手に取るのもアレだし)
代わりにこちら。

右の金属の謎のL字型の棒。 コレが霧吹きです。 なんか思ってたのと違うって? 画材の霧吹きと言えばコレデショ???(すっとぼけ)
2つあるのは、片方は手持ちのもの(ホルベイン) 上にある、吹き口が黒くなっているものが今回ワークショップのお土産品です。 買うとき1,000円くらいした気がしてたけど、いま世界堂のページ見てたら500円くらいだったorz
使い方はホルベインのサイト見てくだせぇ。

で、上の写真の話に戻そう。 フィキサチーフは色が付かないし、お持ち帰りはなかったので、普通に水彩で霧吹きしてみました。
こんな感じに定着する、と思っていただければ。 (なんとなくお土産の方が綺麗に広がってる)
水彩のラメとか、仕上げの色鉛筆とかパステル使うときにちょっと試してみたいかもですね。 このフィキサチーフ。
3.没食子インク作り

今回一番楽しみにしていた没食子インク作りです。 この写真の丸いものが没食子。
作り方は簡単! ・没食子(虫こぶ)を砕く! ・砕いたものを水で煮る ・スチールウールをお酢に漬けて媒染液を作る ・煮た没食子を漉して、媒染液を垂らす ・粘度調整用にアラビアゴム溶液をちょっと入れる はい完成!
道具と材料があればね、簡単だけどね、用意するのがね、っていうやつ。

と言うわけで、こちら先ずは砕きます! ハンマーでえいや!と。ストレス発散!


ハンマーで砕いたものを乳鉢でさらに細かく。

煮ます。 一番手前が我が輩のもの。 ちなみに、この容器はステンレス。 大抵の金属はタンニンが反応してしまうので、ホーローとかガラスとかステンレスでないと駄目です。

しばらく煮て冷ましたら、お茶パックで漉していきます。

ちなみにこちら、アラビアゴム溶液作り。 アラビアゴムは水に溶けるのですが、少し時間がかかるので、温めて溶かすのですが、今思うと、自分でアラビアゴム溶液作る時って、絶対直火は使わなくて湯煎にするんですよね…………
何が言いたいかというと、焦げました😂
アラビアゴム、直火駄目、絶対!
アラビアゴム使うって教えてくれれば、手持ちの粉末持っていったのに。 (今回使用したものはザラメタイプでした)


気を取り直してスチールウールに酢酸投入! しばらくするとシュワシュワしてきます。

こうして材料ができました!
後はこの没食子の液体に、媒染液を垂らしていきます。

媒染液を垂らしてゆらゆら揺らしてしばらくしたら黒っぽくなりました。

瓶に詰めて完成!
4.羽ペン作り

今回はダチョウの羽だそうです。 (ちなみに右上の紫がかった線とかが没食子インクを羽ペンで試し書きしたもの)
はい、羽の下の方をむしって、根っこを炙って先っちょをナイフで切って羽管完成!
って言いたいところだけど、炙るの怖いのでスルー。 綺麗に切れないし、難しい!
切り方はもはやそれっぽくなればいいやの精神で切ってました🤣 一応、ぱっと見た感じはチェンニーニのやり方とほとんど変わらなそうでした。
ちなみに、なんでワークショップに羽ペン作りが入っているかというと、没食子インクは金属のペン先が使えないので没食子インク用として用意されたのですが、何ならガラスペンや割り箸ペンでも良いとのこと。
以上、ワークショップの思い出でした。 木炭作りは(アレやコレやで)思った以上に楽しかったし、没食子インク手作りできて嬉しいし、シェラックを使ったフィキサチーフは今後自分でも何か使えそうな気がしてきたし、非常に思い出に残るワークショップでした。 講師の鳥越さん、松川さん、そしてギャラリーオーナーの佐藤さん、ありがとうございました!
途中、お隣の駄菓子屋さん開けていただいて、麩菓子食べたりしたのも楽しい思い出。 久しぶりに食べた麩菓子はうまし。 川越生まれの血が麩菓子を求めるのだ……(←関係ない)
余談。 ワークショップ終了後、クサカベ2025アキーラ展限定色のきっかわさん絡みの色、鳥越さん、松川さんに興味持っていただいてわいわいやってましたが、伊研の木炭色、なんの木炭なのかに疑問が行くのが流石だなぁ!って思っちゃいました。
自分は普通に折れちゃったものとか、品質は良いけど木炭としては売れないもののごちゃ混ぜ品かなーとか適当な事思ってしまいました。 でも、伊研の商品に、柳の炭精粉ってのがあるっぽいので、案外柳だったりして。
1 note
·
View note
Text
札幌 襖交換
札幌の障子張替え、費用の内訳と目安 札幌で障子の張替えを依頼する場合、費用がどのくらいかかるのかは気になるところです。料金は主に「障子紙の材料費」と「張替えの工賃」で構成されます。障子紙は、前述の通り種類によって価格が大きく異なります。一般的な普及品が最も安価で、強化紙やプラスチック障子、手漉き和紙などは高価になります。工賃は、障子のサイズ(高さや幅)や、桟の形状(通常の格子か、雪見障子かなど)によって変わるのが一般的です。また、業者によっては最低依頼枚数が設定されていたり、枚数が多いと割引になったりする場合もあります。出張費が別途必要な場合もあるので、見積もり時に総額を確認することが大切です。札幌市内の複数の業者から見積もりを取り、料金とサー���ス内容を比較検討することをお勧めします。現代の多様なライフスタイルは、住まいに対する要求も変化させています。「金沢屋手稲石狩店」は、襖、障子、網戸、畳の張替えにおいて、単に古くなったものを新しくするだけでなく、現代的な生活課題に対応する機能的なソリューションを提供しています。例えば、小さなお子様がいて障子の破れに悩むご家庭には、強度が高く破れにくいタイプの障子紙を提案。ペットを飼っていて襖の引っ掻き傷が気になる場合には、耐久性の高いペット対応の襖紙を選ぶことができます。また、外からの視線が気になるリビングの窓には、プライバシーを守りつつ採光も確保できるガラスフィルムを施工するなど、具体的な「お困りごと」に寄り添った提案力が魅力です。札幌市手稲区及び近郊エリアのお客様の生活状況を丁寧にヒアリングし、豊富な選択肢の中から最適な素材や機能を選定。伝統的な技術と現代的なニーズを融合させ、より安全で快適な住まいづくりをサポートしています。
「札幌 障子張替」ならここ!
0 notes
Text
消えゆく和紙の灯を絶やさないために-私たちにできること/What We Can Do to Safeguard the Future of Washi


古来より受け継がれてきた美しい和紙。しかし、その輝きは年々失われつつあります。このままでは、私たちの大切な和紙が消えてしまうかもしれません。
それでも、和紙の未来に希望の光がないわけではありません。
下記の記事では、和紙の未来を守るために、私たち一人ひとりにできることを共に考えていきます。小さな一歩が、やがて大きな光となるはずです。 和紙の未来を共に考える-危機に瀕する和紙産地に希望の光を見出す
0 notes
Text
KASOKEKI lamp(カソケキランプ)の口コミ・評判をもとに、和紙ランプの魅力やモデル別の違い、おすすめの選び方まで徹底解説。
自然素材と職人技が生み出す癒しの灯りを、実体験レビューで紹介します。
0 notes



