#正直大会出てない人で抽出技術知識経験値がめちゃめちゃ高い人がいる
Explore tagged Tumblr posts
Text
かっかっかっかっかっかっか👽
今日までの生命活動に感謝して、労りゆっくり寝ましょう
困難な選択を前にしても揺れない確固たる私を築きましょう
誰もができることは、できないとしても努力して勝ち取りましょう
ことばには空中での分解作用があることを信じましょう
言いたいことは素直に言いましょう
食べたいものを食べましょう
死にたい時は死にましょう
死にたいと言いたい時は言いましょう
点滅していても横断歩道は渡りましょう
残ったスープを見殺しにはしないでください
安心な場所へはすぐにいきましょう
強くあろうとして粉砕するのはやめましょう
何かあったら5分前に言いましょう
次のオーダーが待っているので、5分前に言いましょう
次はメモをとりましょう
残り2分残っていても、次のオーダーをこなしましょう
疲れました、正直に
疲れたんです、そして社会の規則は青松のルールだということを今実感しています。
ことなる部分もあるけれど、大半がそうnなんだって
私の口内環境の構造を扱いきれていないので、あなたの鼓膜まで届かず空気の振動だけになってしまったんです。
それは悲しいことだと理解しています。そう、理解しているのです。私はそのことについて認識しているのです。だからいいでしょう。しかし、可視化って怖いものです。私の確認、または認識範囲を相手に伝えるために存在しているのですから。私の記憶を保存しているのに、もう次は聞かないでね、そう意味に聞こえるから言わせてもらうけど、投げ出したいです、投げ出して全部流したいです。社会不適合という言葉は嫌いです。叛逆しているのではありません、投げ出しているからです。私は、投げ出したいという考えの過程にさまざまな要因を挙げて考察して出した結果で投げ出しているのです。しかし、前者のように最初から私は社会に属さないんdすよって結果はあまりにも愚行ですね、はい、、、、、、、、、、、、、、なっぐっていいです。この世界なんて正直に生きる方が辛いんですもの、これはこうなっている、だからこれはこうしなきゃいけない、私は因果を辿って行動したのだけれどあなたたちは、効率よくして、、とかなんだとか
付加価値なんて何も気にしないで、平気な顔してサービスしているんだから。値段に書いとけ、付加価値抜き、
それで許されない人と許される人はなんだろうか、真面目か結果が良ければいいのか経験なくして物語は紡げない主義側です。いくら想像可能でも、それは抽象に過ぎずディテールはその関係性や目線、非言語情報をどれだけ目にし言葉にし実践してきたのかによるのではないかです。(T . T)破い、、、、、、、、、、、、、どんな空想を描く作家でも実生活は普段の現実生活の延長線だからどんなに目を背けたくてもい逃げ出したくても現実とのギャップを埋めるぐらいの妄想しか書けないんです。近未来や科学技術の発展が描く未来性も現実の人間の消化不良を描いてそれは未来ではスッキリしてシャープで何もかもスタイリッシュで掲げた思想は誰かのアートの一部になってそれは正義正当化のために利用される始末で。昔は良かった、今の若者は、そういう人たチの言葉は現に生きようとする生産市民の足枷となる、自分自身が背けてきた苦悩や葛藤を燃焼できずに次の世代が生まれ、社会や会社での地位も悩みを吐き出す立場でいられなくなて指導する立場になって、、、行き場のない消化できないために貯めた言葉を街のあらゆるところにぶつける週末を過ごし、放たれた言葉が自然分解されると信じきっているから自傷行為した後の高揚感と少しの後ろめたさのように自分のユートピアに帰宅していく。気づけばそこにあった、認識するまでにかかった時間の貯金額を知れる日は来るんでしょうか。時間は無駄にしない。時間がないのではなく、時間は作るものです。時間の定義が曖昧ですね、24Hを時間なのか、活動するための流れを時間とするのか、どっちなんでしょうか、後者だとしたら、人それぞれではないか、それなのに効率タイパだのすぐ結果に走りたくなる現代人ではありたくない。誰だってあの時こうしとけば良かった、そうすれば未来は少しでも良くなっていたかもしれない。と考えてしまう時間があって、私は行動した時間全てを無駄だと思っていない。時間はかかり過ぎてしまったなと振り返ることはあるが常に冷静でいたい。私は私の人生。これについて少し考えたい。子供は母親を選んで生まれてくる描写が見られることがあって、私は胎児の記憶がないので母親の母体の中で何を思考し筋肉��動かしていたのは想像の世界に入ってしまうが、赤ちゃん工場などという世界が天上にあるのならばとして考える。今母親の社会進出と家族の変容について調べていて、家族という形を残していくためには母親は必要で、自分も母親像を求めてしまったことがある。クラスメイトのお弁当箱の中が華やかであることに少し劣等感を抱いてしまったのを母親に全て押し付けてしまった。その時なぜ父親は無かったことにされるのか、お前も親である。。弁当の華やかを彩る権利がある。いや義務である。結局子供ってのは母親によってしまうのか。栄養をもらっていたからなのか、、、ともかく、父親ってのはろくでなしである、、イクメンなど造語されてからというもの土に帰ればいい、、、、土壌の養分になる方がよっぽどマシである。それなのに社会は女性として生まれてきただけの人間に勝手に母性を植え付ける。女性は男性のワーカーであると教育される。機嫌をとる、世話をする。いい歳こいた大人がさせることではない、動け自分で、、、お前の脚と手はなんのためにある五体満足はお前の母親が産んでくれたからだ、感謝もしないで見ようともしないで他人に求めることは内臓の器官を売ってからが対等になる。それぐらいの時間と労力をお前らのために幼い頃から費やしてきた。それが社会にいるためだったから。。。それで、女性は出産や妊娠といった期間に子供認識するのではないそうだ。母親になるまでに抱えてきた期待や自立を子供には経験させたい。自分自身が必要ないと遮断されてきた選択肢を与えるかのように母親はなってしまうらしい。(あとは各々調べて)そんでもって、母親は我が子を唯一の思い通りにできるものとして見てしまうらしい。その結果、コミュニティから脱退してしまうらしいんだ。そうなうと子供は母親の人生なんだ、自分の人生は自分のために使え。なりたい職業につけ。それは大筋の認識が各々で異なるからなりたい職業ランキンがあのようになってしまう。リスペクトはない、常に誰かからの期待や目線にしがみついて生きるしかないんだよね、人間ってのはさ、、、、、、、人間は社会性を持つ生物なので集団を拒否るとこぼれ落ちかのように人が減っていく。これは彼らによっては信号なのかもしれない、関係を築こうとしない人類がいたら直ちに報告せよってね、、、、、、関わってはいけない、子供にはこのように耳打ちをする「関わってはいけないよ、危ないからね」 ホームの休憩所に屯する女子高生の痴話に己の耳が引っ張られそうになっても、そこは落ちいて目の前の流れるるおすすめ投稿に必死に集中力を移し何事もなかったように振るわなければ��らない。機械のアルゴリズムに全ての神経がやられ盛り上がる女子高生の残した静寂に悲しさを覚える。自分の人生を生きてきたのにあの時間はまだ獲得したいと思い続けてしまっていんだよね、手にすることが容易ではなかったあの時間は何にも変え難い素晴らしいものだったと今の自分のギャップに悩まされる今晩でした。お暇します n
0 notes
Text
20250128_02
前回の続き

今津景「タナ・アイル」展
『東京オペラシティアートギャラリー』を訪れたのは恐らく20年弱ぶりか。エルネスト・ネトかシュテファン・バルケンホールの展示風景の断片が思い浮かぶがICCとごっちゃになっている気もする。

今津景という画家を知らなかったが話題の展示らしく気になって来てみた。一言で言えばすごい。絵画における横尾忠則の系譜の正当継承者だ。もはや展覧会というより現出した異界。画家というより魔術師や呪術師のほうがしっくりくる。絵は向こう側から開かれた「窓」だ。


デジタル・コラージュみたいな画像をわざわざ油絵の具で描き起こしている。中にはキャンバスに印刷された図像の上に描画されているものもある。人間��描く画像と機械が出力する画像が等価でその境界は曖昧だ。

写実的なイメージ上に走る線画など具象と抽象、別次元のものが同一画面に収まっている。
展示会場には熱帯の植物の葉や猿や鳥などの輪郭を象った金属製のフレームのようなものが所々に置かれている。そのフレーム越しに絵画や彫刻の置かれた展示空間を眺めると、今津景が描く絵が肉眼の中で新たに生成されるような感覚が起こる。
またそれをふまえて、他の鑑賞者の視線に入ることで画像編集ソフトにおけるレイヤーとレイヤーの間に自分の姿が挿入され、まるで絵の中に閉じ込められるような感覚になりこれも面白かった。
絵を見てる誰か、を見てる自分、を見てる誰か、を見てる…まるで無限後退の迷宮ッ。



医療的な何か(マラリア?)をテーマにしたであろうインスタレーション。
受付でもらうリーフレット以外に作品タイトルや説明のキャプションはないが圧倒的な絵画の技術で「すげえな。」ととりあえず納得してしまう。
刊行が遅れているという図録のサンプルを覗くと、そこにコンセプトやらが記されていて策士だなと思った。浮かぶ謎が閾値に達したところで図録にたどり着く。これは買ってしまう。
併設のミュージアムショップのネットストアで予約できるが、ただ今頃になって買うかどうか迷いだす。
複雑すぎる図像が脳の処理速度や能力を超えると、時間が経つにつれ印象が「なんだかやたら高解像度の夢を見たな…今朝。」ぐらいの漠然としたものに変化する。
二、三日前の脈絡のない夢の中身に拘泥などしないように今回見た絵の中身を振り返るだろうか?と思うと図録の購入を少し躊躇する。
多分会場で売ってたら買ってた。
圧倒される絵と音楽でいうスルメ曲みたいな絵の違いはなんだろう。モチーフかしら。
勝手なもんだなと我ながら思う。
それでも「夢」というイリュージョンを覚醒した意識のま��現実で見せられるようなことはすごいことなのかもしれない。
これは絵画体験というより、起きたまま見る明晰夢なのだ。
こちらは東京オペラシティーアートギャラリーで3月23日まで。
小西真奈「wherever」

小西真奈は確か2007年辺りのART ITだったか美術手帖かなんかに小西の「浄土」という作品が掲載されていて知った画家だ。
それ以来実物を見てみたいと思い定期的に調べてみるも検索結果に女優の小西真奈美が出てくるぐらいで、それぐらい寡作の作家なのかなと思っていた。今回の個展の説明には結婚や出産を機に絵を描く時間が取れなくなってしまったと書かれていた。

「浄土」
実物を前にぞわぞわと鳥肌が立つくらい異様なアウラを放つ。
この絵の中の女性が不意にこちらを振り返る、あるいは逆に一瞥もくれず向こう側へ行ってしまうような。この感覚はなんだろうと思って考えてみたが中学校の美術室の壁にかかっていたアンドリュー・ワイエスの「クリスティーナの世界」の色褪せた複製絵画が思い浮かぶ。そちらの女性は少し大袈裟な背中をしていたが。
「浄土」というタイトル通りあの世との境界面という気がした。今でいうリミナルみたいな感覚か。
思えば私が登山を始めたのもこの絵のような異界的風景を求めたが故だった気がする。その一つの基準としてこの絵画が確かにあった。そう考えると私の人生を変えた絵とも言える。
タッチの手数をかなり抑えた近作の展示部屋いくつかと、件の「浄土」を含めた2010年あたりまでの若描きの頃の作品がまとめられた一つの部屋を見る限りやはり初期作品群の放つ気配は色濃く、絵画の醸すアウラとは、画面から鑑賞者に向けて放射されるエアロゾル状の何か、と思わせるくらいだ。
作家の狙いとしておそらく何かがあるとは思うのだが、一連の近作は私には良さがわからなかった。図録には批評家によってその手数の少なさとタッチを評価する論評が載っていたが正直わからん。
本展の図録の後半部に「浄土」含め初期作も載っていたが悩んだ挙句結局購入を見送った。良いも悪いもそもそもこっちの勝手な熱量に一因があるかもしれない。
せめてポストカードを買って帰ろうと思ったがラインナップに「浄土」は無く、世の中と自分の審美眼は少しズレてんのかなと思った。やべーのはあの絵だろとブツブツ言いながらバスを待った。
あくまで私の主観であります。
府中市美術館で2月24日まで。
ちょうど府中市美術館では予備校時代にお世話になった先生の奥さんでもあるところの小木曽瑞枝さんの公開制作と展示が行われていた。その日はあいにく制作日ではなく展示室にかけられた作品をガラス越しに眺めた。自分もあんな作品を作ってみたい��思わせる作品で羨ましいな思った。作っていて楽しそうなのがこちらに伝わる。

自分の日々の制作のタリスマンとして作品集を購入。
ドキュメンタリー「鹿の国」
YouTubeで回ってきた予告を見て気になっていたが、『岡谷スカラ座』まで行くのはさすがにきついぜと思っていたところ東中野で上映中とのこと。
以前読んだ中沢新一の「アースダイバー神社編」に出てきた「御室」と呼ばれる豊穣を祈願して冬に行われる神事に迫ったドキュメンタリー。
ただ自分としては諏訪の地の奥深くに秘められてきた神事をカメラで追った作品だと勝手に思っていた訳だが、中世の神事を演劇的に再現した作品だったことを知った。
予定を詰め過ぎた疲労からか開始10分の予告編で強烈な眠気。画面が二重に見え30分は目ン玉を指でつまんだりゴシゴシして闘ったが結局ほぼ寝た。無理。無理でした。爆睡。なので何の感慨も残らず。98分2000円のうたた寝。
久しぶりの東京。
若い頃を思い出したり、もうそんなことどうでも良かったり。
振り返ったところで、過ぎてい��たあらゆることは風景に溶ける。
そしてコルビュジエが言うみたいに海へと流れつくのだ。
それはやがて一本の水平線となり、
駅のホームで吐き出した白い息はいつか夏の日の入道雲になる。
なんだかよくわかんないことを思いながら電車を待つ。
東京の冬の空気に鼻の奥がツーンとした。
0 notes
Text
iFontMaker - Supported Glyphs
Latin//Alphabet// ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 !"“”#$%&'‘’()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ Latin//Accent// ¡¢£€¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ Latin//Extension 1// ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſfffiflffifflſtst Latin//Extension 2// ƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐ��ǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿ Symbols//Web// –—‚„†‡‰‹›•…′″‾⁄℘ℑℜ™ℵ←↑→↓↔↵⇐⇑⇒⇓⇔∀∂∃∅∇∈∉∋∏∑−∗√∝∞∠∧∨∩∪∫∴∼≅≈≠≡≤≥⊂⊃⊄⊆⊇⊕⊗⊥⋅⌈⌉⌊⌋〈〉◊♠♣♥♦ Symbols//Dingbat// ✁✂✃✄✆✇✈✉✌✍✎✏✐✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛✜✝✞✟✠✡✢✣✤✥✦✧✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❍❏❐❑❒❖❘❙❚❛❜❝❞❡❢❣❤❥❦❧❨❩❪❫❬❭❮❯❰❱❲❳❴❵❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➔➘➙➚➛➜➝➞➟➠➡➢➣➤➥➦➧➨➩➪➫➬➭➮➯➱➲➳➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾ Japanese//かな// あいうえおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもやゆよらりるれろわゐゑをんぁぃぅぇぉっゃゅょゎゔ゛゜ゝゞアイウエオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダチヂツヅテデトドナニヌネノハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモヤユヨラリルレロワヰヱヲンァィゥェォッャュョヮヴヵヶヷヸヹヺヽヾ Japanese//小学一年// 一右雨円王音下火花貝学気九休玉金空月犬見五口校左三山子四糸字耳七車手十出女小上森人水正生青夕石赤千川先早草足村大男竹中虫町天田土二日入年白八百文木本名目立力林六 Japanese//小学二年// 引羽雲園遠何科夏家歌画回会海絵外角楽活間丸岩顔汽記帰弓牛魚京強教近兄形計元言原戸古午後語工公広交光考行高黄合谷国黒今才細作算止市矢姉思紙寺自時室社弱首秋週春書少場色食心新���図数西声星晴切雪船線前組走多太体台地池知茶昼長鳥朝直通弟店点電刀冬当東答頭同道読内南肉馬売買麦半番父風分聞米歩母方北毎妹万明鳴毛門夜野友用曜来里理話 Japanese//小学三年// 悪安暗医委意育員院飲運泳駅央横屋温化荷開界階寒感漢館岸起期客究急級宮球去橋業曲局銀区苦具君係軽血決研県庫湖向幸港号根祭皿仕死使始指歯詩次事持式実写者主守取酒受州拾終習集住重宿所暑助昭消商章勝乗植申身神真深進世整昔全相送想息速族他打対待代第題炭短談着注柱丁帳調追定庭笛鉄転都度投豆島湯登等動童農波配倍箱畑発反坂板皮悲美鼻筆氷表秒病品負部服福物平返勉放味命面問役薬由油有遊予羊洋葉陽様落流旅両緑礼列練路和 Japanese//小学四年// 愛案以衣位囲胃印英栄塩億加果貨課芽改械害街各覚完官管関観願希季紀喜旗器機議求泣救給挙漁共協鏡競極訓軍郡径型景芸欠結建健験固功好候航康告差菜最材昨札刷殺察参産散残士氏史司試児治辞失借種周祝順初松笑唱焼象照賞臣信成省清静席積折節説浅戦選然争倉巣束側続卒孫帯隊達単置仲貯兆腸低底停的典伝徒努灯堂働特得毒熱念敗梅博飯飛費必票標不夫付府副粉兵別辺変便包法望牧末満未脈民無約勇要養浴利陸良料量輪類令冷例歴連老労録 Japanese//小学五〜六年// 圧移因永営衛易益液演応往桜恩可仮価河過賀快解格確額刊幹慣眼基寄規技義逆久旧居許境均禁句群経潔件券険検限現減故個護効厚耕鉱構興講混査再災妻採際在財罪雑酸賛支志枝師資飼示似識質舎謝授修述術準序招承証条状常情織職制性政勢精製税責績接設舌絶銭祖素総造像増則測属率損退貸態団断築張提程適敵統銅導徳独任燃能破犯判版比肥非備俵評貧布婦富武復複仏編弁保墓報豊防貿暴務夢迷綿輸余預容略留領異遺域宇映延沿我灰拡革閣割株干巻看簡危机貴揮疑吸供胸郷勤筋系敬警劇激穴絹権憲源厳己呼誤后孝皇紅降鋼刻穀���困砂座済裁策冊蚕至私姿視詞誌磁射捨尺若樹収宗就衆従縦縮熟純処署諸除将傷障城蒸針仁垂推寸盛聖誠宣専泉洗染善奏窓創装層操蔵臓存尊宅担探誕段暖値宙忠著庁頂潮賃痛展討党糖届難乳認納脳派拝背肺俳班晩否批秘腹奮並陛閉片補暮宝訪亡忘棒枚幕密盟模訳郵優幼欲翌乱卵覧裏律臨朗論 Japanese//中学// 亜哀挨曖扱宛嵐依威為畏尉萎偉椅彙違維慰緯壱逸芋咽姻淫陰隠韻唄鬱畝浦詠影鋭疫悦越謁閲炎怨宴援煙猿鉛縁艶汚凹押旺欧殴翁奥憶臆虞乙俺卸穏佳苛架華菓渦嫁暇禍靴寡箇稼蚊牙瓦雅餓介戒怪拐悔皆塊楷潰壊懐諧劾崖涯慨蓋該概骸垣柿核殻郭較隔獲嚇穫岳顎掛括喝渇葛滑褐轄且釜鎌刈甘汗缶肝冠陥乾勘患貫喚堪換敢棺款閑勧寛歓監緩憾還環韓艦鑑含玩頑企伎忌奇祈軌既飢鬼亀幾棋棄毀畿輝騎宜偽欺儀戯擬犠菊吉喫詰却脚虐及丘朽臼糾嗅窮巨拒拠虚距御凶叫狂享況峡挟狭恐恭脅矯響驚仰暁凝巾斤菌琴僅緊錦謹襟吟駆惧愚偶遇隅串屈掘窟繰勲薫刑茎契恵啓掲渓蛍傾携継詣慶憬稽憩鶏迎鯨隙撃桁傑肩倹兼剣拳軒圏堅嫌献遣賢謙鍵繭顕懸幻玄弦舷股虎孤弧枯雇誇鼓錮顧互呉娯悟碁勾孔巧甲江坑抗攻更拘肯侯恒洪荒郊貢控梗喉慌硬絞項溝綱酵稿衡購乞拷剛傲豪克酷獄駒込頃昆恨婚痕紺魂墾懇沙唆詐鎖挫采砕宰栽彩斎債催塞歳載剤削柵索酢搾錯咲刹拶撮擦桟惨傘斬暫旨伺刺祉肢施���脂紫嗣雌摯賜諮侍慈餌璽軸叱疾執湿嫉漆芝赦斜煮遮邪蛇酌釈爵寂朱狩殊珠腫趣寿呪需儒囚舟秀臭袖羞愁酬醜蹴襲汁充柔渋銃獣叔淑粛塾俊瞬旬巡盾准殉循潤遵庶緒如叙徐升召匠床抄肖尚昇沼宵症祥称渉紹訟掌晶焦硝粧詔奨詳彰憧衝償礁鐘丈冗浄剰畳壌嬢錠譲醸拭殖飾触嘱辱尻伸芯辛侵津唇娠振浸紳診寝慎審震薪刃尽迅甚陣尋腎須吹炊帥粋衰酔遂睡穂随髄枢崇据杉裾瀬是姓征斉牲凄逝婿誓請醒斥析脊隻惜戚跡籍拙窃摂仙占扇栓旋煎羨腺詮践箋潜遷薦繊鮮禅漸膳繕狙阻租措粗疎訴塑遡礎双壮荘捜挿桑掃曹曽爽喪痩葬僧遭槽踪燥霜騒藻憎贈即促捉俗賊遜汰妥唾堕惰駄耐怠胎泰堆袋逮替滞戴滝択沢卓拓託濯諾濁但脱奪棚誰丹旦胆淡嘆端綻鍛弾壇恥致遅痴稚緻畜逐蓄秩窒嫡抽衷酎鋳駐弔挑彫眺釣貼超跳徴嘲澄聴懲勅捗沈珍朕陳鎮椎墜塚漬坪爪鶴呈廷抵邸亭貞帝訂逓偵堤艇締諦泥摘滴溺迭哲徹撤添塡殿斗吐妬途渡塗賭奴怒到逃倒凍唐桃透悼盗陶塔搭棟痘筒稲踏謄藤闘騰洞胴瞳峠匿督篤凸突屯豚頓貪鈍曇丼那謎鍋軟尼弐匂虹尿妊忍寧捻粘悩濃把覇婆罵杯排廃輩培陪媒賠伯拍泊迫剝舶薄漠縛爆箸肌鉢髪伐抜罰閥氾帆汎伴畔般販斑搬煩頒範繁藩蛮盤妃彼披卑疲被扉碑罷避尾眉微膝肘匹泌姫漂苗描猫浜賓頻敏瓶扶怖附訃赴浮符普腐敷膚賦譜侮舞封伏幅覆払沸紛雰噴墳憤丙併柄塀幣弊蔽餅壁璧癖蔑偏遍哺捕舗募慕簿芳邦奉抱泡胞俸倣峰砲崩蜂飽褒縫乏忙坊妨房肪某冒剖紡傍帽貌膨謀頰朴睦僕墨撲没勃堀奔翻凡盆麻摩磨魔昧埋膜枕又抹慢漫魅岬蜜妙眠矛霧娘冥銘滅免麺茂妄盲��猛網黙紋冶弥厄躍闇喩愉諭癒唯幽悠湧猶裕雄誘憂融与誉妖庸揚揺溶腰瘍踊窯擁謡抑沃翼拉裸羅雷頼絡酪辣濫藍欄吏痢履璃離慄柳竜粒隆硫侶虜慮了涼猟陵僚寮療瞭糧厘倫隣瑠涙累塁励戻鈴零霊隷齢麗暦劣烈裂恋廉錬呂炉賂露弄郎浪廊楼漏籠麓賄脇惑枠湾腕 Japanese//記号// ・ー~、。〃〄々〆〇〈〉《》「」『』【】〒〓〔〕〖〗〘〙〜〝〞〟〠〡〢〣〤〥〦〧〨〩〰〳〴〵〶 Greek & Coptic//Standard// ʹ͵ͺͻͼͽ;΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώϐϑϒϓϔϕϖϚϜϞϠϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬϭϮϯϰϱϲϳϴϵ϶ϷϸϹϺϻϼϽϾϿ Cyrillic//Standard// ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџѢѣѤѥѦѧѨѩѪѫѬѭѰѱѲѳѴѵѶѷѸѹҌҍҐґҒғҖҗҘҙҚқҜҝҠҡҢңҤҥҪҫҬҭҮүҰұҲҳҴҵҶҷҸҹҺһҼҽҾҿӀӁӂӇӈӏӐӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝӞӟӠӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹӾӿ Thai//Standard// กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮฯะัาำิีึืฺุู฿เแโใไๅๆ็่้๊๋์ํ๎๏๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๚๛
see also How to Edit a Glyph that is not listed on iFontMaker
#FAQ#ifontmaker2#Symbols#Dingbat#Cyrillic#Greek#Coptic#thai#character set#character sets#list#language
9 notes
·
View notes
Text
NPO 法人鳥の劇場 ×青山学院大学社会情報学部LCD研究ユニット 2019/5/27-28

NPO 法人鳥の劇場 ×青山学院大学社会情報学部LCD研究ユニット 2019/5/27-28
鳥取県と青山学院大学社会情報学部は面白い試みをしている。
平成30年度(2018年)から開校された、義務教育学校鹿野学園。
その学校の一つの目玉科目が「表鷲科」という授業だ。鳥の劇場(NPO法人お鳥の劇場)という鳥取市鹿野町を拠点に置く、劇団名鳥の劇場さんが演劇ワークショップ事業を進めていくために実施している教育プログラムで、青山学院大学社会情報学部学習コミュニティデザイン(LCD)研究ユニットは鳥の劇場の教育アドバイザーとして、演劇ワークショップ後の省察活動の実施を重としてサポートを行なっている。劇場も備えていて、その名も同じく「鳥の劇場」。
なお、「表鷲科」は子どもたちが21世紀を力強く生き抜くために、表現力とコミュニケーション力をつけることを目的とした鹿野地域の独自科目で、最終的には、子どもたちの自己効力感を高め、国語や算数、理科、社会の学力向上にもつなげていくことを目指している。このプロジェクトの先駆けとして、2017(平成29)年度では小学校4年生に7回、中学校1年生に6回、芸術表現体験活動+省察活動のプログラムを実施している。こちらにその辺��詳細が載っているのでぜひ見に行っていただきたい。
NPO 法人鳥の劇場 ×青山学院大学社会情報学部LCD研究ユニット共同プログラム→ http://lcd-aoyama.net/10.html
そして今年度、2019年もこれから複数回、鳥取県へと飛び、様々な場面でともに活動して行く予定となっている。その最初の調査として、まず苅宿研究室の特別研究員である私、髙橋健太郎と大学院生の青木均之は5月27日、28日に鳥取に向かった。

調査目的は何か
中山間地域の教育に芸術家などの表現者がどのように関わりを見せ、その活動でどのような効果をもたらせるか。また、子どもたちがどのようにワークショップのファシリテーターに反応し、それぞれのワークや時間帯によってどのような心理状態にあったかを確認する。また、このワークショップ中は映像で様々な場面を記録し、ファシリテーターに至っては音声を個別で録るためにボイスレコーダーをワーク中は付けてもらう。これらは全て質的にも量的にも大量のデータとなる。それら児童・生徒たちの言葉や音声、映像記録などから得られたデータを全て持ち帰り、子どもたちの自己効力感やワークショップの効果を測って行く。
生産性で何もかも語りがちな世の中でどのようにして、その評価軸以外の自分を保つ軸を持てるか。生徒たちにいかにして自分は自分のまま、ありのままで当たり前に生きていて良い、ということに気付いてもらえるか。このワークショップを行うことの目的はそこにある。
繰り返しになるが、それを実証するための調査ということで私たちは様々なメディアを駆使して記録してデータを出してファクトとしてこのワークの効果を示そうとしている。
そしてそのデータは今後、青木くんの修士論文や苅宿先生の今後の活動やプレゼンなどで、自分たちの活動の裏付けデータとして見せることが可能になる。


5月27日、28日は 両日とも鳥の劇場さんによる鹿野学園7年生(この鹿野学園の面白いところは小学校中学校を一貫校にしたために通常、中学校1年、2年、3年生と呼ぶところを、7年、8年、9年生と呼んでいる)の生徒へのワークショップで、27日にメインのワークショップ、そして28日は省察を兼ねてからのワークショップという予定で行われた。その活動を僕らLCDユニットは記録していた。
今回のテーマは「色んなセリフについて考えよう!」というものだった。
だけれども、実際のワークに入る前に鳥の劇場さんはあらゆるアイスブレイクをしていた。中にはコミュニケーション促進ゲームであるカタルタを使ったものもあった(※カタルタの遊び方はこちらに)。
そこから「うん。」という一言で色々と意味を考えるというもの。 言い方次第で色々な受け取り方がある。コミュニケーションの方法や解釈は言葉の伝え方、表情、身体を使ったり、その場の状況���雰囲気で決まってくるというもの。
その思考から今度は生徒自身に「え。」という一言で色々なシチュエーションを考えてもらい、それぞれのグループで発表してもらう。この辺りから色々なセリフについて考えるとっかかりを作っている。
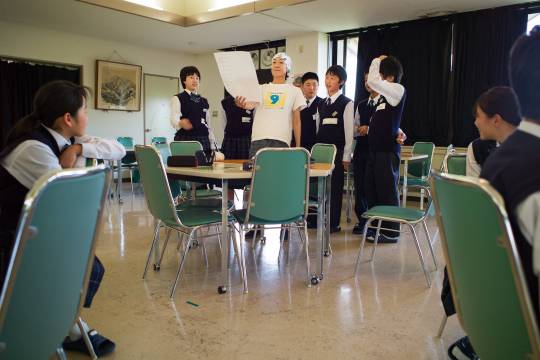
そして、次のステップ。
メインのグループワークで、演劇ワークショップ。
今回の演劇ワークショップは3人グループを作り、配られた「ところどころに穴の空いた台本」を自分たちでその空欄になっている箇所を、想像力を働かせて勝手に埋めて完成させる。そしてそれを実際に演技するというもの。
下にあるようなセリフでひとつの短い演劇を作ってもらう。学校の休み時間に3人の生徒たちが話し合ってると言うもの。
ーーーーーーーーーーーーーー
A : 「次の時間、理科だね。」
B : 「植物の宿題やった?」
C : 「うん。」
A : 「◯◯◯」
ーーーーーーーーーーーーーー
ここでポイントなのはCさんの「うん」の言い方。先ほどのワークで色々と考えていたものがここの実践で生きてくる。
自信満々で「うん」と答えるのか。あるいは全く自信なさそうに「うん...」と答えるのか。
そしてその後に続く◯◯◯でどうやって、この演劇を終わらせるのか。 短い文章だけに、生徒たちの器量が試されている。
<ワークショップのグランドデザイン>
このグループ分けは、担任の先生に行ってもらっている。
そして実はそこからデザインされていることなのだが、普段の生徒たちを見ている担任の先生が、この生徒とこの生徒を組み合わせてみたらどのような協働性を見せてもらえるか、を期待しながら普段仲良い友達同士ではないグループで組んでもらっている。

それは何故か。
グループワークを通して何かを上手く遂行するという目的ならば普段仲の良い人間同士が組めば良いのだけど、この芸術表現体験活動のワークショップはそのようなことを目的としていない。
一番はじめにも書いたがこの「表鷲科」という科目では、子どもたちがこれからこの時代の社会で「力強く生き抜くために、表現力とコミュニケーション力をつけることを目的としている」のだ。そのためにはこのグループを組む時点から普段、仲が良くない子(あまり話しているのを見かけない)と組ませるということを試みた方が生徒たちにとっては良い。
社会に出て、初対面であったりあらゆる人(この授業の場合はクラスメイトだから「誰か」ということは知っている)と何か一つの目的を達成するという経験を今の段階から感覚的に掴んでもらうことを実践しようとしている。この場合の目的というのも、決して企業が何かのプロジェクトを進める、という場合だけでなく、そこかしこのコミュニケーションの遂行と言っても差し支えない。例えばお店の店員とたわいない挨拶程度のコミュニケーションだって立派な目的になる。その意味でこのワークショップで培ってもらいたいのは、他者と自分がコミュニケーションを如何に円滑にできるようになるか、ということだ。
さて、表鷲科の中で別けられたグループも当然、最初からそのグループ活動が上手く行くと思っていない。だからあらゆる齟齬がお互いの間で生まれる。
しかも、今回の鹿野学園7年生の生徒たちは2ヶ月前まで小学校6年生で、ふたクラスずつに別れていたのだ。学年があがり、今年4月から7年生となった途端、クラスもひとつになった。クラスの中で自分のポジションをどう取るか等色々と考えないといけないことが生徒たちには多々あり、なかなか難しい時期なのだそうだ。
それもそのはずで、データから見てもこの多感な時期には人間関係や自我や進路の悩みなど様々なことが絡み合って障壁を感じることとなる。(日本の児童・生徒の自殺、過去30年で最多に BBCより、2018年11月の記事)
いじめや家庭内の関係など。理由は様々だが、学校の中ではなかなか当事者でないと見えない問題が多く存在し、その解���を図ることは並大抵のことではない。学校でも、いじめが起きているという事実を把握したくない現状がある。
話は飛ぶが、この様な状況を作ってしまっている原因は社会にある。 ここで無理に問題は社会ではなくあなた個人だ、自分でなんとかできる、といったことをついつい言ってしまいたくなる世の中ではあるけれどもそうじゃない。年間2万人もの自殺者数がいる国、これが日本の姿だ。年々下がっている、ということを言う人もいるが、365日の間に2万人もの個人の人間が自ら命を絶つ選択をしている現状はもはや他人事ではない。
さて話を戻すと、そのような社会の状況を鑑みても演劇創作などの身体と頭(論理的思考)を使って、自分の考えていることを作品発表といったカタチで他者に向けて表現するというワークショップを行うことは、生徒たちにとって、数学や国語、体育などの普段の教科ではなかなか見つけられなかった新たな自分のチャンネルを見つける場所としても機能してくれることを期待している。
主体的な学びという言葉を作って掲げるのは良いが、それを現場でどう生かすかは現場に任せられている。その一つの答えがこのワークショップのように、生徒たちにとにかく色んなことを身をもって経験してもらうということにあるのかもしれない。一種の強制性によって小学校から中学校までは決められたカリキュラムの中を生き抜くしかないところに、このような新しいものに触れる機会を作るということは、子どもたちにとっても新しい自分に気付くチャンスを作ると言うことに他ならない。
だから今はまだ慣れていないかもしれないこの環境が例えば、半年後のワークショップではどうなっているか。生徒たち同士の関係性が微妙に変化しているだろうしそれがプラスに向かっているのではないだろうか、と苅宿先生は言う。

生徒たちが発表してくれた内容についてはここでは割愛させていただく。
照れながらもそれぞれに発表をしていて、これから生徒たちがどう変わって行くのかとても楽しみ���ある。おそらく、このような芸術表現体験活動を授業の中で組み込んでいるという学校はそう多くない。いわゆる「アクティブラーニング」や「コミュニケーション教育」といった言葉が文科省で使われるようにはなっていてもそれが実際の現場に定着して行くには相当の時間を要する。決められたカリキュラムの中にこの様な専門性が必要な授業を組み込むということ自体がとても労力のかかることで、そこに時間を割けるだけの余力が今の学校教育の中にあるかと問われれば、都内で教師をやっている数人の友人の現状を見ていても、なかなかそのような時間は持てないと思われる。
だからこそ、鳥取の鹿野学園、新潟の中里中学校などで実際にこの芸術表現体験活動を行えるということ自体が、とても貴重な体験となる。その土地固有の教育としても、その学校に通う生徒や教師たちにとっても、周りの地域にとってもプラスに働くのではないだろうか。

と、これが27日のワークショップの一連の流れだった。
その後は当日のワークショップの振り返りとして、リフレクションシートを記入してもらう。今、苅宿先生が大学生の授業でも使っているあのリフレクションシートだ。どの活動の時にどの程度生徒たちがそれぞれに関心やモチベーションが高まったか、などのデータ取りだ。
で、再三言っているようにこれらのデータを実際に大学院生の青木くんや現役4年ゼミ生たちが研究目的で活用することになる。
鹿野学園3・4年生の授業分析

そしてワークショップも無事終わり、僕ら苅宿研究室のLCDユニットは鹿野学園3・4年生の授業分析を行うために、映像記録と音声記録を録らせに行かせていただいた。
映像は俯瞰の映像を教室の前と後ろから。そして音声は先生にピンマイクと児童の机の上、一つ一つに小さなマイクを置かせていただいた。
この一つの目的は初めにも書いたように、中山間地域でどのような教育が行われているか探り、そして教師の方々がどのようなことに心を配りながら子どもたちと勉強をしているのかということの研究で、先生、児童それぞれの発話からどのような教育が行われているのかというのをデータで抽出して行く。音声マイクで録音して行くことで、先生がどのような発話をすると児童たちはどのように反応するのかということが見えてくる。例えばキーワードとしてプラスに働くような言葉をデータの基準にして、それに付随する言葉を幾度、先生が発話したか。そしてそこに対する児童たちの応答はどのようなものだったのか。
その後、これらのデータが意味するところを公に提示する時に、その場面を映像で撮影で確認できるようにまでしておくことで、ファクトの重要性が叫ばれる昨今の時代の流れに対する証拠としての機能を果たす。
そしてこれがそのまま、大学院生の青木くんの研究へと繋がる。
と、このようなことをこれからも鳥取に青木くんと来る度に行う予定だ。
翌日、鹿野学園7年生、ワークショップの省察、5月28日

省察
まずは鳥の劇場さんが記録として映像や写真で残していたものを通して振り返る。このスタイルは、監修している苅宿研究室でのスタイルをそのままに使っている。苅宿先生によるワークショップデザイン+メディアコミュニケーションの授業の中でもこのように、ワークショップをやったら省察の時間を設けていて、ワークショップに参加している生徒たちはこの時間を通して自分たちが一体何を学んで、実際に何が自分の力となっているのかというのを可視化して見せようとしている。

だからこそ、生徒たちもこれをただの座学としてではなく、自分たち自身のこととして捉えられる。そこに、これも青木くんの研究と同じように、生徒たちがその瞬間どのような表情をしていたかを見て理解できるように写真や映像をデータ、証拠品として提示しながら「昨日の君たちは◯◯だったよね、だから◯◯な力があるんだね君たちには」という風な振り返りの語りかけを行い、生徒たちにもそれをある程度、証拠力を持って実感させられるように進めて行く。

自分自身を俯瞰的に認知する力(=メタ認知能力)をここでは身につけさせようとしている。強制的にではなく、無意識にそれを捉えられるように仕向けている。
このメタ認知という言葉は2020年度から実施される学習指導要領の「アクティブラーニング」を実践する上でもとても重要な能力と規定されている。客観的に自分の行いを理解するということは自分の学びに新しい気付きを得たり、これからどのような姿勢で自分が学んで行けば良いのかということを理解しようとする力を促すことにも繋がる。

ワークショップ後に振り返りのリフレクションシートを書いてもらう時に、その作業を行っていた時に、自分の心理状態を自己評価してもらうというものがある。例えばワークショップ中の演技を行っている時、自分は前向きにそのワークショップに入り込んでいたか、あるいはあまりやりたくなかった、等の選択肢をいくつか用意し、それに回答してもらう。これはワークショップを行うこちらへの評価を理解するだけでなく、参加している生徒たちがどれほど主体的にそのワークに参加していたかということを数値として把握できるようなパラメーターみたいなもので視覚化されて見ることで、自分にはどのような特性があるのかということを客観的に認識することが出来る。
それは結果的に自分を俯瞰的(メタ認知)に眺める意識を生徒たちに植え付けて行くことへと繋がる。「植え付ける」という言葉を使うことには洗脳的な意味合いがあるが、少なからず教育にはそのような側面があることは否めない。それが間違っている方向か正しい方向なのかという議論は常にあってしかるべきだがどちらにも断定し辛く、多くはその正しさと過ちの間のグラデーションで成立している。
さて、生徒たちは省察を行ったあと、実際に演劇ワークへと入って行った。

前日と同じグループのまま、前に披露した演劇よりもより良いものを作り直す時間を与えられたのち、新たに作った演劇をクラスの前で発表する。


すると面白いことに、生徒たちも主体的に昨日の演技の何が悪くて、何を直し、何をしたらより良くなるのかを考えていた。省察を通して見た自分たちの喜ぶ姿などの感情のわかる映像や写真、そして昨日披露した演劇の映像を見て自分たちの中で話合いをして、どこを直してどう面白く披露するかを自律的に考えて発表していたように見受けられる。
そして各グループがお披露目をする際、他の班の生徒たちは演技をしている班を評価して、どこが良かったのか良い点だけを書き出してもらう。それはただただ演技を見ている生徒たちの集中力を上げるだけでなく、他者を自分はどう評価し、どんな場面に他者の良いところを見つけようとするのかという、これから人間として成長して行った時に、頭の中で常に行っている思考をこの様な場面で体験してもらう。人は意図せずして誰かと出会えばその他者を「評価」している。それが良い評価のときもあれば悪い評価のときもある。だがこの講義を通して生徒たちに目を向けてもらいたいのは、相手の良い点を探してもらうという作業だ。他者の嫌なところだけをピックアップしてそれをもとに相手を評価し、その他全ての相手の良いところまでマイナスイメージを作ると言うことを人間は往々にしてやっている。しかし、それではコミュニケーションを円滑に進めることは困難になる。だからこそ、ここでは生徒たちにひとまず、相手の良いところを抽出してもらう。
結果的にそれは、相手のことを褒める��けでなく、自分を見つめることにも繋がる。そのようにして自己肯定感や自己効力感を培って行く、そのような教育をこのワークショップで実践しようとしている。

そしてワークショップ後は、苅宿先生による鳥の劇場さんへの振り返り、今日のワークショップがどうして成功したのか、というもの。でもこの内容はここでは書けません。
でも苅宿先生が持っているMacBookのこの画面内で指摘されている「自分たちで確認した自分たちの<いいところ>をふりかえったことを確認する活動で確かめてみよう」と書いてあるように、生徒たち自身が自分たちの良いところに気付ければ、結果的にその良いところを伸ばそうとして、それがまた生徒たちの自己肯定感や自己効力感を伸ばす原因となる、ということだ。
だからこそこのワークショップの活動は現在の日本の学校教育の中でやる必然性がある。これだけ日本の児童生徒学生たちが自分のことを肯定的に捉えられないような社会・教育の状況の中で、少しでも、「いやいや、君たちはまだまだやれる力を持っているよ」ということを語りかけて行くような、そんな活動なのではないだろうかと、今回の鳥取でのワークショップの実践を拝見し思った。
0 notes
Text
2019年ふりかえり
例によってお正月なので2019年のことをまとめておくことにします。
仕事
今のプロダクト開発チーム(Wantedly People)にジョインしてちょうど二年くらい経ちました。去年の今頃は何をしていたかと言うと10人4ヶ月くらいの大型プロジェクトの真っ最中で、プロダクトを大幅にリニューアルしていました。これは予定通り2019年の3月末にリリースすることができました。
Wantedly ではエンジニアとデザイナーがそれぞれプロダクトマネージャとプロダクトデザイナーとして動き、一緒にプロダクト設計をすることが多いのですが(最近新しい版が出た INSPIRED でも紹介されている典型的なプロダクトチームのパターンですね)、このプロジェクトもその形でした。その中で自分がプロダクトマネージャ的な立ち位置で、コンセプト設計からドメイン設計まで、設計全般に関わりました。競争優位性や事業としての親和性を踏まえると、スタンドアローンで使うツールから何らかのピボットする必要があることが認識としてありましたが、「では何を作るべきなのか?」というところから実際にコードを書いて作れるところまでを落とす仕事です。
この過程で、Facebook �� Twitter と言った SNS の構造をかなり解像度高めで見たのですが、これはエンジニアとしても学びがありました。例えばですが、Facebook は「ユーザー」以外もコンテンツ生成主体になれるんですよね。例えば Facebook ページ。この構造は更に Like のようなエンゲージメントアクションの対象も任意のものになる(技術用語で言えば polymorphic になる)。この辺りのほぼプロダクトの基本設計と言って良いような構造がバックエンドの構造(例えばグラフデータベース)と連動していたり、広告の出し方のようなビジネス面にも関わってくる。ユーザーインターフェイスの潮流としてもスキューモーフィズムが薄れたりデザインシステムのような概念が普及していますが、大きな流れとして情報を扱うプロダクトはどんどん抽象的になっていっていると僕は思っています。プロダクトの細部をどのようにモデリングをするかというような抽象的な話はどちらかと言えば「目的」ではなく「実現方法」として捉えられがちですが、プロダクトの種類のよってはその関係が大きく変わるなと感じた経験でした(こういう気付きを得てみれば、Facebook のニュースフィードの設計者であるクリス・コックスや、Twitter の設計者であるジャック・ドーシーがどちらもソフトウェア・エンジニアであったのは腑に落ちるところです)関連して、そのような設計はどの程度発明され尽くしたのか?というのはソフトウェアを設計する人間として個人的に関心を持ったところです。
…
無事リニューアルができた後は数字を見ての改善フェーズになって、多くの細かい施策プロジェクトが走るようになりました。この辺りで性質が変わってステークホルダーとのコミュニケーションが上手く行っていかなくなったので自分がプロジェクトマネジメントもやるようになりました。プロジェクトマネジメントと言っても一種の問題解決であって、プロジェクトというもののモデル化から制約条件の確認、運用フローの設計、及びそれに基づいた情報システムの設計、みたいなところなので、普通にエンジニアのスキルを転用しています。プロダクトマネジメントとプロジェクトマネジメントは分けられないのが基本で、後者だけを違う人にやってもらうというのは難しかったなあというのが個人的な学びです。仕事が増えてどうしても、とか社外にステークホルダーがいてデリバリーがクリティカル、とかそういうケースじゃないと基本は分離しない方が良いですね。YAGNI 的な考え方は組織の設計でも大事。
そう言えば僕は自分の中で勝手にメンターに設定している人が昔から何人かいるのですが、2019年に読んで面白かった本の一つに読書猿さんが書いた『問題解決大全』があります。この本では問題解決を2種類に分けていて、なにか根本原因があると仮定する問題解決をリニアな問題解決と言っているのですが、そうじゃない問題解決があると言っている。そういうものをサーキュラーな問題解決と読んでいて、これは因果関係がループしたりしているもののことを指してい���す。例えば人間の認識などはどんどん強化されたりしていくので、そういうのは構造自体を組み替えてあげないと解決しない、とかですね。銀行の取り付け騒ぎとかが事例として挙げられていますが、このとき取り組んだプロジェクトマネジメントも、そういう種類のものでした。
思えば、2018年に取り組んだマイクロサービス・アーキテクチャの問題解決もその手のことを無意識に考えていて、このときそれを意識化することができたな、と思っています。例えばエンジニアもコードが読みにくいと簡単に実装箇所を変えたりしますよね。それは単体で言えばただの現象なんですが、そういうものが場合によっては負の因果ループを形成してどんどん悪い状態になる、みたいなことがある。だからそういうときは初手・二手目とどう打っていくのが良いのかが単に目に付きやすいところ・見た目のインパクトが大きいところに手を付ける、という動き方では最善手ではないときがあって、そこは複雑な問題を解決をするときは考えなきゃいけないところだと思いました。

問題解決大全――ビジネスや人生のハードルを乗り越える37のツール ()
posted with amazlet at 20.01.01
読書猿 でじじ発行/パンローリング発売 (2019-09-14)
Amazon.co.jpで詳細を見る
そんな感じでプロダクトに加えてプロジェクトも見はじめたので、年の中頃から正式にプロダクト開発チームのリーダーになっています。マイクロサービスになっているバックエンドは強いメンバーが揃ってきたのでほぼ渡しました。今はサービスとしてのコンピテンシーに関わりそうなアーキテクチャや、プロダクトの方向性に関わりそうなドメイン設計だけ関わっています。そしてそれを実現するための具体的な手段として Protocol Buffers の API 定義のコードオーナーになっています。これはリニューアルのときにも強く感じたマイクロサービス・アーキテクチャの利点の一つで、プロダクトマネジメントの手段としてのアーキテクチャマネジメントと、それを実現するための具体的なインターフェイスとしての Protocol Buffers が割と必要十分な道具になるという話は、どこかで一度 LT してみたいところ。可用性の観点でも結局全てを守ることはできないので分割して管理しようねという話で、じゃあどこを変更してもどこが落ちないことがプロダクトとしてあるべき状態か、というようなこともアーキテクチャの話��乗ってきますが、その辺はありがたいことにセンスの良いエンジニアがいるのでポイント・ポイントでコミュニケーションを取るくらいで済んでいます(余談ですが、マイクロサービス・アーキテクチャの SLA 定義とかってどう障害分離されているかみたいなことがすごく関わってくるのですが、その辺りを形式的に記述するにはどうすれば良いんでしょうかね)。
逆に正式にリーダーになってからやるようになったことは色々あるのですが、プロダクトの戦略策定や暗に存在したビジョンの言語化といったコンセプチュアルな部分はそれを作るだけでなく伝える過程も含めて新しい学びがありました。作るという点では『ストーリーとしての競争戦略』という本を読んだのですが、これの競争優位性の議論がテクノロジー・カンパニーとは?というようなテーマにもつながる話で面白かった。伝えるという点では、その手のことを優秀なメンバーにどんどんインプットしていくと動き方や話す内容が変わっていくのがわかって素直に人が成長するってすごいなという驚きがありました。もちろん必要であれば認識合わせや期待のすり合わせはそれまでもやっていましたが、このときはポジティブな意味でピープル・マネジメントも悪くないなと思った瞬間でした。あと全体的にこの手のことを通して、言語化能力が1年通してかなり上がったという感覚があります。

ストーリーとしての競争戦略 優れた戦略の条件 (Hitotsubashi Business Review Books)
posted with amazlet at 20.01.01
楠木 建 東洋経済新報社 (2012-05-10)
Amazon.co.jpで詳細を見る
おおよそこんな感じの1年間でした。2020年はより比重をプロダクトに寄せていきたいなと思っています。
補遺:マイクロサービス・アーキテクチャの整理
マイクロサービス・アーキテクチャにまつわる総括的なところも個人的な関心として活動をしました。一つは、『 コンピュータプログラミングの概念・技法・モデル を読む会』というものを半年くらいかけてやりました。これは1人のソフトウェア・エンジニアとして自分が社内外問わず感じた課題感なのですが、マイクロサービス・アーキテクチャのような形でシステムを作るとなったときに、どのような計算のモデル化が当てはまり、それに対してどのような技法があり得るのか?というような視点があればもっと上手く行くケースがかなり多いなと感じています。特に、並行プログラミングと分散プログラミングの特性や、同期通信と非同期通信などのコミュニケーション・パターンなどを知っておかないと、クラウド系のコンピューティングサービスの技術選定の際にも行き当りばったりにしかならずまともに技術戦略を立��ることが難しいのでは、とすら思います。
この会では、紹介されたモデル化を HTTP や三層アーキテクチャなど種々の既存技術についても当てはめて社外の参加者の方とも色々ディスカッションをしたのですが、今の Web 技術の進化の形はかなりの程度その誕生背景に影響を受けていて、今後も慣性を持ちながらも要素技術のレベルで段階的に調整されていくだろうというような見通しを持つことになりました。
そういった活動とは別に、2018年から2019年の大規模改修までに得たノウハウのアウトプットも行いました。動機としては、相対的に見えるとマイクロサービス・ネイテイブで開発されたサービスというものが2019年時点では相当少ないし、本番稼働して継続的に変更を加え続けたときのノウハウみたいなのはより少ないなと感じていて、それ故に必要だった整理というものを公開した形です。技術書典7に出した『WANTEDLY TECH BOOK 7』に「最近のソフトウェアエンジニアリング事情」として執筆したものや、それの抜粋である『Wantedly における Go 導入にまつわる技術背景』などがそれです。
より視点を拡げて見れば、昨今のアプリケーションはスマートフォンのような小さな画面の中によりシステマチックに多くの価値を詰め込む傾向があるように感じていて、それと並行して推薦やデータを扱う技術の価値というものがアプリケーションの価値に直結することも多くなっていると感じています。ここに一定のフロンティアがあるとすれば、バックエンドのシステムというものはより複雑化する方向に行くと考えられるので、分散システム化を進める要因になっている、というのが自分の今の考えです。ただこれは末端のインターフェイスの変化も関わるので、ある程度は今のスマートフォンを前提にした議論ではありますし、クラウド系のコンピューティングサービスが何をどこまで提供するかというような先端をよく観察した方が正しい結論が出せる気がしています。この辺りは今の自分のフォーカスからは外しているのでそれ以上は見ていませんが、変数が多いが故に今後が楽しみな領域だなと思っています。
生活
サービス
自分的2019年、生活に破壊的な貢献をしたサービス2選です。
家事代行サービス:Casy
隔週で利用しています。家事代行サービスの何が良いかと言うと、どんなに忙しくてもかならず2週間に1回は部屋がきれいになること、それがとても大きなメリットだなと思っています。だいたい忙しくなると散らかって散らかると余計に気にしなくなる、というようなループがあるんですが、Casy は定期的に同じ人が来るのが基本のシステムなので、それが起きない。2018年に DMM おかん を利用したこともあっ��のですが、これはアドホックに呼ぶサービスでした。アドホックに呼ぶとなるとそもそもスケジュール調整とかしなくちゃいけなくて利用ハードルが高いし、忙しいときほどそれもしたくなくなる。あと DMM おかん は毎回違う人を呼ぶので、そこの調整コストも高い。全然サービス設計の良さが違うんですね。結果的に DMM おかん はもうサービス終了しちゃいましたが、少なくともデフォルトでサブスクリプションにするのが家事代行サービスをデザインする際の必須要件だと思いました。はい。
宿泊予約サイト:Relux
2つ目は Loco Partners が利用する Relux です。よく Wantedly で募集出してたので DL してみたという経緯。これは何が良いかと言うと、イケてる宿しか載ってないことと、その中でも値段とは独立に品質を5段階で格付けしているところ。コストパフォーマンスという言葉で言えば、`コストパフォーマンス = パフォーマンス / コスト` で、このパフォーマンスの項のみを評価してくれてるのがありがたい。パフォーマンスで絞り込んだあとに最後にコストを見れば良いので個人的なニーズに合っている。あとは普通にアプリがあって今どきっぽくて便利。どうでもいいけどアプリの UI のチューニングは結構工夫してるなと思う割に検索はリレーショナルデータベース使ってるのか?っていうくらい遅いので改善してあげたい。“旅館” みたいな出現頻度高めのワードでクエリを投げると壊れるのでだいたい何が起きてるのか分かってしまってかわいそう。まあいいや。サービスとして見たときの個人的になるほどと思ったポイントで言うと、扱う宿の数を絞る → 一つあたりの評価にかけられるコストが増える → 信頼性のある評価が可能になる、という戦略になっているように見えます。普通は扱う宿の数は多い方が良いと思うところですが、この定説をひっくり返すことでサービスとしての強みを作り出しているのが面白いですね。
良い。 pic.twitter.com/PSB98VRTMV
— Sohei Takeno (@Altech_2015) April 23, 2019
リゾートに来ている pic.twitter.com/rAutqD5ABZ
— Sohei Takeno (@Altech_2015) September 20, 2019
僕のこのサービスの使い方は4泊くらいしてそこで好きな本を読む、っていうので、これがめちゃくちゃ良かったので2020年も習慣として続けようと思っています。
本
かれこれもう5年以上積ん読していた若桑みどりさんの『クアトロ・ラガッツィ 天正少年使節と世界帝国』という本があるのですが、これを Relux で宿泊した宿で読みました。これが本当に素晴らし��て、これでちょっと歴史趣味が再燃しちゃってます。良い本や物語に出会えるのは人生の主要な楽しみの一つです。

クアトロ・ラガッツィ 上 天正少年使節と世界帝国 (集英社文庫)
posted with amazlet at 20.01.01
若桑 みどり 集英社
Amazon.co.jpで詳細を見る
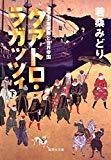
クアトロ・ラガッツィ 下 天正少年使節と世界帝国 (集英社文庫)
posted with amazlet at 20.01.01
若桑 みどり 集英社
Amazon.co.jpで詳細を見る
ゲーム
GW くらいから手を付けた『シヴィライゼーション VI』が沼でやばい。最近は MOD のリアルマップを DL して遊ぶのに少しハマっている。例えばユーラシア大陸のマップでモンゴルでプレイすると、ゴビ砂漠とかヒマラヤ山脈があるから南下して中原を侵略するかカザフスタンあたりの遊牧民族を倒してヨーロッパまで行くかしかない、みたいになって割とリアルな遊牧民族の気持ちになれて面白い。次は人とプレイしたら面白いだろうけど、どう考えても沼なのでそこまで行くか迷う。

2020年は新しくインプットしていきたいこともあるので、ゲームはほどほどにしたいところです。
0 notes
Text
小説家蓮實重彦、一、二、三、四、
人間に機械を操縦する権利があるように、機械にもみずから作動する権利がある。 ーー『オペラ・オペラシオネル』ーー
一、
二朗は三度、射���する。そしてそれはあらかじめ決められていたことだ。 一度目の精の放出は、ハリウッドの恋愛喜劇映画を観た帰りの二朗が、小説の始まりをそのまま引くなら「傾きかけた西日を受けてばふりばふりとまわっている重そうな回転扉を小走りにすり抜け、劇場街の雑踏に背を向けて公園に通じる日陰の歩道を足早に遠ざかって行くのは和服姿の女は、どう見たって伯爵夫人にちがいない」と気づいたそばから当の伯爵夫人にまるで待ち構えていたかのように振り返られ、折角こんな場所で会ったのだしホテルにでも寄って一緒に珈琲を呑もうなどと誘いかけられて、向かう道すがら突然「ねえよく聞いて。向こうからふたり組の男が歩いてきます。二朗さんがこんな女といるところをあの連中に見られたくないから、黙っていう通りにして下さい」と、なかば命令口調で指示されて演じる羽目になる、謎の二人組に顔を視認されまいがための贋の抱擁の最中に起こる。
小鼻のふくらみや耳たぶにさしてくる赤みから女の息遣いの乱れを確かめると、兄貴のお下がりの三つ揃いを着たまま何やらみなぎる気配をみせ始めた自分の下半身が誇らしくてならず、それに呼応するかのように背筋から下腹にかけて疼くものが走りぬけてゆく。ああ、来るぞと思ういとまもなく、腰すら動かさずに心地よく射精してしまう自分にはさすがに驚かされたが、その余韻を確かめながら、二朗は誰にいうとなくこれでよしとつぶやく。
なにが「これでよし」なのか。ここは明らかに笑うべきところだが、それはまあいいとして、二度目の射精は、首尾よく二人組を躱したものの、ホテルに入るとすぐに新聞売り場の脇の電話ボックスに二朗を連れ込んだ伯爵夫人から先ほどの抱擁の際の「にわかには受け入れがたい演技」を叱責され、突然口調もまるで「年増の二流芸者」のようなあけすけさに一変したばかりか「青くせえ魔羅」だの「熟れたまんこ」だの卑猥過ぎる単語を矢継ぎ早に発する彼女に、事もあろうに「金玉」を潰されかけて呆気なく失神し、気がつくと同じ電話ボックスで伯爵夫人は先ほどの変貌が夢幻だったかのように普段の様子に戻っているのだが、しかしそのまま彼女のひどくポルノグラフィックな身の上話が始まって、けっして短くはないその語りが一段落ついてから、そろそろ「お茶室」に移動しようかと告げられた後、以前からあちこちで囁かれていた噂通りの、いや噂をはるかに凌駕する正真正銘の「高等娼婦」であったらしい伯爵夫人の淫蕩な過去に妙に大人ぶった理解を示してみせた二朗が、今度は演技と異なった慎ましくも本物の抱擁を交わしつつ、「ああ、こうして伯爵夫人と和解することができたのだ」と安堵した矢先に勃発する。「あらまあといいながら気配を察して相手は指先を股間にあてがうと、それを機に、亀頭の先端から大量の液体が下着にほとばしる」。 そして三度目は、伯爵夫人と入れ替わりに舞台に登場した「男装の麗人」、二朗への颯爽たる詰問ぶりゆえ警察官ではないにもかかわらず「ボブカットの女刑事」とも呼ばれ、更に「和製ルイーズ・ブルックス」とも呼ばれることになる女に案内されたホテルの奥に位置する「バーをしつらえたサロンのような小さな空間」ーー書棚がしつらえられ、絵が飾られ、蓄音機が置かれて、シャンデリアも下がっているのだが、しかしその向こうの「ガラス越しには、殺風景な三つのシャワーのついた浴場が白いタイル張りで拡がっており、いっさい窓はない」ことから戦時下の「捕虜の拷問部屋」を思わせもするーーで、この「更衣室」は「変装を好まれたり変装を余儀なくされたりする方々のお役に立つことを主眼として」いるのだと女は言って幾つかの興味深い、俄には信じ難い内容も含む変装にかかわる逸話を披露し、その流れで「金玉潰しのお龍」という「諜報機関の一員」で「かつて満州で、敵味方の見境もなく金玉を潰しまくった懲らしめの達人」の存在が口にされて、ひょっとしてこの「お龍」とは伯爵夫人そのひとなのではないかと訝しみつつ、突如思い立った二朗は目の前の和製ルイーズ・ブルックスをものにして俺は童貞を捨てると宣言するのだが事はそうは進まず、どういうつもりか女は彼に伯爵夫人のあられもない写真を見せたり、伯爵夫人の声だというが二朗の耳には自分の母親のものとしか思われない「ぷへーという低いうめき」が録音されたレコードを聞かせたりして、そして唐突に(といってもこの小説では何もかもが唐突なのだが)「こう見えても、このわたくし、魔羅切りのお仙と呼ばれ、多少は名の知られた女でござんす」と口調を一変させてーーここはもはや明らかに爆笑すべきところだが、それもまあいいとしてーー血塗れの剃刀使いの腕を自慢するのだが、その直後におよそ現実離れした、ほとんど夢幻か映画の中としか思えないアクション場面を契機に両者の力関係が逆転し、言葉責めを思わせる丁寧口調で命じられるがまま和製ルイーズ・ブルックスは身に纏った衣服を一枚一枚脱いでいって最後に残ったズロースに二朗が女から取り上げた剃刀を滑り込ませたところでなぜだか彼は気を失い、目覚めると女は全裸でまだそこに居り、これもまたなぜだか、としか言いようがないが、そもそも脱衣を強いた寸前の記憶が二朗にはなく、なのに女は「あなたさまの若くて美しいおちんちんは、私をいつになく昂らせてくださいました。たしかに、私の中でおはてにはなりませんでしたが、久方ぶりに思いきりのぼりつめさせていただきました」などと言い出して、いまだ勃起し切っている二朗の「魔羅」について「しっかりと責任は取らせていただきます」と告げて背中に乳房が押しつけられるやいなや「間髪を入れず二朗は射精する」。 帝大法科への受験を控えた二朗少年のヰタ・セクスアリスとして読めなくもない『伯爵夫人』は、ポルノグラフィと呼ばれてなんら差し支えないあからさまに助平な挿話とはしたない語彙に満ち満ちているのだが、にもかかわらず、結局のところ最後まで二朗は童貞を捨て去ることはないし、物語上の現在時制においては、いま見たように三度、何かの事故のようにザーメンを虚空にぶっ放すのみである。しかも、これら三度ーーそれもごくわずかな時間のあいだの三度ーーに及ぶ射精は、どうも「金玉潰しのお龍」が駆使するという「南佛でシャネル9番の開発にかかわっていたさる露西亜人の兄弟が、ちょっとした手違いから製造してしまった特殊な媚薬めいた溶液で、ココ・シャネルの厳しい禁止命令にもかかわらず、しかるべき筋にはいまなお流通しているもの」の効果であるらしいのだから、しかるに二朗は、一度として自分の意志や欲望の力によって己の「魔羅」に仕事をさせるわけではないし、彼の勃起や射精は、若く健康な男性の肉体に怪しげな薬物が齎した化学的/生理的な反応に過ぎないことになるわけだ。実際、物語上の時間としては過去に属する他の幾つかの場面では、百戦錬磨の女中頭の小春に技術を尽くして弄られようと、従妹の蓬子に「メロンの汁で手を湿らせてから」初々しくも甲斐甲斐しく握られようと、二朗は精を漏らすことはないし、ほとんど催すことさえないかのようなのだ。 つまりここにあるのは、その見てくれに反して、二朗の性的冒険の物語ではない。彼の三度に及ぶ射精は、詰まるところケミカルな作用でしかない。それでも三度も思い切り大量に放出したあと、二朗を待っているのは、今度は正反対のケミカルな効用、すなわち「インカの土人たちが秘伝として伝える特殊なエキスを配合したサボン」で陰茎を入念に洗うことによって、七十二時間にもわたって勃起を抑止されるという仕打ちである。三度目に出してすぐさま彼は「裸のルイーズ・ブルックス」にその特殊なサボンを塗りたくられ、すると三度も逝ったというのにまだいきりたったままだった「若くて元気なおちんちん」は呆気なく元気を喪い、更には「念には念を入れてとスポイト状のものを尿道に��ばやく挿入してから、ちょっと浸みますがと断わって紫色の液体を注入」までされてしまう。サボンの効果は絶大で、二朗の「魔羅」はこの後、小説の終わりまで、一度として射精もしなければ勃起することさえない。物語上の現在は二朗がケミカルな不能に陥って間もなく終了することになるが、それ以後も彼のおちんちんはまだまだずっと使いものにならないだろう。七十二時間、つまり三日後まで。そしてこのことも、ほとんどあらかじめ決められていたことなのだ。 『伯爵夫人』は小説家蓮實重彦の三作目の作品に当たる。一作目の『陥没地帯』は一九七九年に、二作目の『オペラ・オペラシオネル』は一九九四年に、それぞれ発表されている。第一作から最新作までのあいだにはじつに三十七年もの時間が経過しているわけだが、作者は自分にとって「小説」とは「あるとき、向こうからやってくるもの」だと言明しており、その発言を信じる限りにおいて三編の発表のタイミングや間隔は計画的なものではないし如何なる意味でも時期を心得たものではない。最初に『陥没地帯』が書かれた時点では『オペラ・オペラシオネル』の十五年後の到来は想像さえされておらず、更にそれから二十二年も経って『伯爵夫人』がやってくることだって一切予想されてはいなかったことになるだろう。偶然とも僥倖とも、なんなら奇跡とも呼んでしかるべき小説の到来は、因果律も目的意識も欠いた突発的な出来事としてそれぞれ独立しており、少なくとも「作者」の権能や意識の範疇にはない。第一、あの『「ボヴァリー夫人」論』が遂に上梓され、かねてよりもうひとつのライフワークとして予告されてきた映画作家ジョン・フォードにかんする大部の書物の一刻も早い完成が待たれている状態で、どうして『伯爵夫人』などという破廉恥極まる小説がわざわざ書かれなくてはならなかったのか、これは端的に言って不可解な仕業であり、何かの間違いかはたまた意地悪か、いっそ不条理とさえ言いたくもなってくる。仮に作者の内に何ごとか隠された動機があったにせよ、それは最後まで隠されたままになる可能性が高い。 だがそれでも、どうしてだか書かれてしまった「三」番目の小説である『伯爵夫人』が、「二」番目の『オペラ・オペラシオネル』から「二」十「二」年ぶりだなどと言われると、それを読む者は読み始める前から或る種の身構えを取らされることになる。なぜならば、ここにごく無造作に記された「二」や「三」、或いはそこからごく自然に導き出される「一」或いは「四」といった何の変哲もない数にかかわる、暗合とも数秘学とも、なんなら単に数遊びとでも呼んでしかるべき事どもこそ、小説家蓮實重彦の作品を貫く原理、少なくともそのひとつであったということがにわかに想起され、だとすればこの『伯爵夫人』もまた、その「原理」をほとんどあからさまな仕方で潜在させているのだろうと予感されるからだ。その予感は、すでに『陥没地帯』と『オペラ・オペラシオネル』を読んでしまっている者ならば、実のところ避け難いものとしてあるのだが、こうして『伯爵夫人』を読み終えてしまった者は、いま、読み始める前から或る独特な姿勢に身構えていた自分が、やはり決して間違ってはいなかったことを知っている。二朗が射精するとしたら、三度でなければならない。二朗が不能に陥るとしたら、三日間でなければならないのだ。では、それは一体、どういうことなのか? どういうことなのかを多少とも詳らかにするためには、まずは小説家蓮實重彦の先行する二作品をあらためて読み直してみる必要がある。数遊びは最初の一手からやってみせなければわかられないし、だいいち面白くない。遊びが遊びである以上、そこに意味などないことは百も承知であれば尚更、ともかくも一から順番に数え上げていかなくてはならない。そう、先回りして断わっておくが、ここで云われる「原理」とは、まるっきり無意味なものであるばかりか、おそらく正しくさえない。だが、意味もなければ正しくもない「原理」を敢然と擁護し、意味とも正しさとも無縁のその価値と存在理由を繰り返し強力に証明してきた者こそ、他ならぬ蓮實重彦そのひとではなかったか?
二、
小説家蓮實重彦の第一作『陥没地帯』は、あくまでもそのつもりで読んでみるならば、ということでしかないが、戦後フランスの新しい作家たち、誰よりもまずはクロード・シモンと、だいぶ薄まりはするがアラン・ロブ=グリエ、部分的にはモーリス・ブランショやルイ=ルネ・デ・フォレ、そしてジャン=ポール・サルトルの微かな影さえ感じられなくもない、つまりはいかにも仏文学者であり文芸批評家でもある人物が書きそうな小説だと言っていいかもしれない。日本語の小説であれば、これはもう疑いもなく、その五年ほど前に出版されていた金井美恵子の『岸辺のない海』へ/からの反響を聴き取るべきだろう。西風の吹きすさぶ砂丘地帯から程近い、こじんまりとした、さほど人気のない観光地でもあるのだろう土地を舞台に、ロマンの破片、ドラマの残骸、事件の痕跡のようなものたちが、ゆっくりと旋回しながらどことも知れぬ場所へと落ちてゆくのを眺めているような、そんな小説。ともあれ、冒頭の一文はこうだ。
遠目には雑草さながらの群生植物の茂みが、いくつも折りかさなるようにしていっせいに茎を傾け、この痩せこけた砂地の斜面にしがみついて、吹きつのる西風を避けている。
誰とも知れぬ語り手は、まずはじめにふと視界に現れた「群生植物」について、「その種類を識別することは何ともむつかしい」のみならず、「この土地の人びとがそれをどんな名前で呼んでいるのかは皆目見当もつかないだろう」と宣言する。結局、この「群生植物」は最後まで名前を明かされないのだが、そればかりか、物語の舞台となる土地も具体的な名称で呼ばれることはなく、登場人物たちも皆が皆、およそ名前というものを欠いている。この徹底した命名の拒否は、そのことによって否応無しに物語の抽象性を際立たせることになるだろう。 もっとも語り手は、すぐさま次のように述べる。
何か人に知られたくない企みでもあって、それを隠そうとするかのように肝心な名前を記憶から遠ざけ、その意図的な空白のまわりに物語を築こうとでもいうのだろうか。しかし、物語はとうの昔に始まっているのだし、事件もまた事件で特定の一日を選んで不意撃ちをくらわせにやってきたのではないのだから、いかにも退屈そうに日々くり返されているこの砂丘でのできごとを語るのに、比喩だの象徴だのはあまりに饒舌な贅沢品というべきだろう。いま必要とされているのは、誰もが知っているごくありふれた草木の名前でもさりげなく口にしておくことに尽きている。
だから実のところ命名は誰にでも許されているのだし、そこで口にされる名はありきたりのもので構わない。実際、わざわざ記すまでもないほどにありふれた名前を、ひとびとは日々、何のこだわりもなくごく普通に発話しているに違いない。そしてそれは特に「群生植物」に限らない話であるのだが、しかし実際には「誰もが知っているごくありふれた」名前さえ一度として記されることはない。凡庸な名前の、凡庸であるがゆえの禁止。ところが、ここで起きている事態はそれだけではない。かなり後の頁には、そこでは弟と呼ばれている誰かの「ここからでは雑草とちっともかわらない群生植物にも、ちゃんと名前があったんだ。土地の人たちがみんなそう呼んでいたごくありきたりな名前があった。でもそれがどうしても思い出せない」という台詞が記されており、もっと後、最後の場面に至ると、弟の前で幾度となくその名前を口にしていた筈の姉と呼ばれる誰かもまた、その「群生植物」の名を自分は忘れてしまったと告白するのだ。つまりここでは、名づけることのたやすさとその恣意性、それゆえのナンセンスとともに、たとえナンセンスだったとしても、かつて何ものかによって命名され、自分自身も確かに知っていた/覚えていた名前が理由もなく記憶から抜け落ちてゆくことのおそろしさとかなしみが同時に語られている。ありとあらゆる「名」の風化と、その忘却。覚えているまでもない名前を永久に思い出せなくなること。そんな二重の無名状態に宙吊りにされたまま、この物語は一切の固有名詞を欠落させたまま展開、いや旋回してゆく。そしてこのことにはまた別種の機能もあると思われるのだが、いま少し迂回しよう。 右の引用中の「物語はとうの昔に始まっているのだし、事件もまた事件で特定の一日を選んで不意撃ちをくらわせにやってきたのではないのだから」という如何にも印象的なフレーズは、語句や語順を微妙に違えながら、この小説のなかで何度となく繰り返されてゆく。これに限らず、幾つかの文章や描写や叙述が反復的に登場することによって、この小説は音楽的ともいうべき緩やかなリズムを獲得しているのだが、それはもう一方で、反復/繰り返しという運動が不可避的に孕み持つ単調さへと繋がり、無為、退屈、倦怠といった感覚を読む者に喚び起こしもするだろう。ともあれ、たとえば今日という一日に、ここで起こることのすべては、どうやら「昨日のそれの反復だし、明日もまた同じように繰り返されるものだろう。だから、始まりといっても、それはあくまでとりあえずのものにすぎない」という達観とも諦念とも呼べるだろう空気が、そもそもの始まりから『陥没地帯』の世界を覆っている。 とは��え、それは単純な繰り返しとはやはり異なっている。精確な反復とは違い、微細な差異が導入されているからではなく、今日が昨日の反復であり、明日が今日の反復であるという前後関係が、ここでは明らかに混乱を来しているからだ。この小説においては、物語られるほとんどの事件、多くの出来事が、時間的な順序も因果律も曖昧なまましどけなく錯綜し、あたかも何匹ものウロボロスの蛇が互いの尻尾を丸呑みしようとしているかのような、どうにも不気味な、だが優雅にも見える有様を呈してゆく。どちらが先にあってどちらがその反復なのかも確定し難い、起点も終点も穿つことの出来ない、方向性を欠いた反復。あたかもこの小説のありとある反復は「とうの昔に始まって」おり、そして/しかし、いつの間にか「とうの昔」に回帰してでもいくかのようなのだ。反復と循環、しかも両者は歪に、だがどこか整然と絡み合っている。しかも、それでいてこの小説のなかで幾度か、まさに不意撃ちのように書きつけられる「いま」の二語が示しているように、昨日、今日、明日ではなく、今日、今日、今日、いま、いま、いま、とでも言いたげな、現在形の強調が反復=循環と共存してもいる。それはまるで、毎日毎日朝から晩まで同じ演目を倦むことなく繰り返してきたテーマパークが、そのプログラムをいつのまにか失調させていき、遂にはタイマーも自壊させて、いま起きていることがいつ起こるべきことだったのかわからなくなり、かつて起こったことと、これから起こるだろうことの区別もつかなくなって、いまとなってはただ、いまがまだかろうじていまであること、いまだけはいつまでもいまであり続けるだろうことだけを頼りに、ただやみくもに、まだなんとか覚えていると自分では思っている、名も無きものたちによるひと続きの出し物を、不完全かつ不安定に延々と繰り返し上演し続けているかのようなのだ。 二重の、徹底された無名状態と、壊れた/壊れてゆく反復=循環性。『陥没地帯』の舞台となる世界ーーいや、むしろ端的に陥没地帯と呼ぶべきだろうーーは、このふたつの特性に支えられている。陥没地帯の物語を何らかの仕方で丸ごと形式的に整理しようとする者は、あらかじめこの二種の特性によって先回りされ行く手を塞がれるしかない。「名」の廃棄が形式化の作業を露骨な姿態で誘引しており、その先では程よくこんがらがった毛糸玉が、ほら解いてみなさいちゃんと解けるように編んであるからとでも言いたげに薄笑いを浮かべて待ち受けているだけのことだ。そんな見え見えの罠に敢えて嵌まってみせるのも一興かもしれないが、とりあえず物語=世界の構造そのものを相手取ろうとする無邪気にマクロな視点はいったん脇に置き、もっと単純素朴なる細部へと目を向けてみると、そこではこれまた見え見えの様子ではあるものの、相似という要素に目が留まることになるだろう。 たとえば「向かい合った二つの食堂兼ホテルは、外観も、内部の装飾も、料理のメニューも驚くほど似かよって」いる。しかし「ためらうことなくその一つを選んで扉を押しさえすれば、そこで約束の相手と間違いなく落ち合うことができる。目には見えない識別票のようなものが、散歩者たちをあらかじめ二つのグループに分断しており、その二つは決して融合することがない」。つまり「驚くほど似かよって」いるのにもかかわらず、二軒はひとびとの間に必ずしも混同を惹き起こしてはいないということだ。しかし似かよっているのは二つの食堂兼ホテルだけではない。他にも「まったく同じ様式に従って設計されている」せいで「どちらが市役所なのか駅なのはすぐにはわからない」だの、やはり「同じ時期に同じ建築様式に従って設計された」ので「旅行者の誰もが郵便局と取り違えて切手を買いに行ったりする学校」だのといった相似の表象が、これみよがしに登場する。建物だけではない。たとえば物語において謎めいた(この物語に謎めいていない者などただのひとりも存在していないが)役割を演じることになる「大伯父」と「その義理の弟」と呼ばれる「二人の老人」も、しつこいほどに「そっくり」「生き写し」「見分けがつかない」などと書かれる。 ところが、この二人にかんしては、やがて次のようにも語られる。
あの二人が同一人物と見まがうほどに似かよっているのは、永年同じ職場で同じ仕事をしてきたことからくる擬態によってではなく、ただ、話の筋がいきなり思わぬ方向に展開されてしまったとき、いつでも身がわりを演じうるようにと、日頃からその下準備をしておくためなのです。だから、それはまったく装われた類似にすぎず、そのことさえ心得ておけば、いささかも驚くべきことがらではありません。
先の建築物にしたって、後になると「二軒並んだ食堂兼ホテルは、いま、人を惑わすほどには似かよってはおらず、さりとてまったくきわだった違いを示しているわけでもない」だとか「学校とも郵便局とも判別しがたく、ことによったらそのどちらでもないかもしれぬたてもの」などといった書かれぶりなのだから、ここでの相似とは要するに、なんともあやふやなものでしかない。にしても、二つのものが似かよっている、という描写が、この物語のあちこちにちりばめられていることは事実であり、ならばそこにはどんな機能が託されているのかと問うてみたくなるのも無理からぬことだと思われる。 が、ここで読む者ははたと思い至る。相似する二つのものという要素は、どうしたって「似ていること」をめぐる思考へとこちらを誘っていこうとするのだが、それ自体がまたもや罠なのではないか。そうではなくて、ここで重要なのは、むしろただ単に「二」という数字なのではあるまいか。だってこれらの相似は難なく区別されているのだし、相似の度合いも可変的であったり、そうでなくても結局のところ「装われた類似にすぎず、そのことさえ心得ておけば、いささかも驚くべきことがらでは」ないというのだから。騙されてはならない。問題とすべきなのは相似の表象に伴って書きつけられる「二」という数の方なのだ。そう思って頁に目を向け直してみると、そこには確かに「二」という文字が意味ありげに幾つも転がっている。「二」つ並んだ食堂兼ホテルには「二」階があるしーーしかもこの「二階」は物語の重要な「事件の現場」となるーー、市役所前から砂丘地帯までを走る路面電車は「二」輛連結であり、一時間に「二」本しかない。とりわけ路面電車にかかわる二つの「二」は、ほぼ省略されることなく常にしつこく記されており、そこには奇妙な執着のようなものさえ感じられる。陥没地帯は、どうしてかはともかく、ひたすら「二」を召喚したいがゆえに、ただそれだけのために、相似という意匠を身に纏ってみせているのではないか。 「二」であることには複数の様態がある(「複数」というのは二つ以上ということだ)。まず、順序の「二」。二番目の二、一の次で三の前であるところの「二」がある。次に、反復の「二」。二度目の二、ある出来事が(あるいはほとんど同じ出来事が)もう一度繰り返される、という「二」がある。そして、ペアの「二」。二対の二、対立的(敵味方/ライバル)か相補的(バディ)か、その両方かはともかく、二つで一組を成す、という「二」がある。それからダブルの「二」、二��の二があるが、これ自体が二つに分かれる。一つの存在が内包/表出する二、二面性とか二重人格とかドッペルゲンガーの「二」と、二つの存在が一つであるかに誤認/錯覚される二、双児や他人の空似や成り澄ましなどといった、つまり相似の「二」。オーダー、リピート、ペア、ダブル、これらの「二」どもが、この小説にはあまねくふんだんに取り込まれている。オーダーとリピートが分かち難く絡み合って一緒くたになってしまっているさまこそ、前に見た「反復=循環性」ということだった。それは「一」と「二」の区別がつかなくなること、すなわち「一」が「二」でもあり「二」が「一」でもあり得るという事態だ。しかしそれだって、まず「二」度目とされる何ごとかが召喚されたからこそ起こり得る現象だと言える。 また、この物語には「大伯父とその義理の弟」以外にも幾組ものペアやダブルが、これまたこれみよがしに配されている。あの「二人の老人」は二人一役のために互いを似せていたというのだが、他にも「船長」や「女将」や「姉」や「弟」、或いは「男」や「女」といった普通名詞で呼ばれる登場人物たちが、その時々の「いま」において複雑極まる一人二役/二人一役を演じさせられている。この人物とあの人物が、実は時を隔てた同一人物なのではないか、いやそうではなく両者はやはりまったくの別の存在なのか、つまり真に存在しているのは「一」なのか「二」なのか、という設問が、決して真実を確定され得ないまま、切りもなく無数に生じてくるように書かれてあり、しかしそれもやはりまず「二」つのものが召喚されたからこそ起こり得た現象であり、もちろんこのこと自体が「反復=循環性」によって強化されてもいるわけだ。 こう考えてみると、もうひとつの特性である「無名状態」にも、抽象化とはまた別の実践的な理由があるのではないかと思えてくる。ひどく似ているとされる二者は、しかしそれぞれ別個の名前が与えられていれば、当然のことながら区別がついてしまい、相似の「二」が成立しなくなってしまうからだ。だから「二軒並んだ食堂兼ホテル」が名前で呼ばれることはあってはならないし、「女将」や「船長」の名が明かされてはならない。無名もまた「二」のために要請されているのだ。 陥没地帯は夥しい「二」という数によって統べられていると言っても過言ではない。それは文章=文字の表面に穿たれた数字=記号としての「二」から、物語内に盛んに導入された二番二度二対二重などのさまざまな「二」性にまで及んでいる。二、二、二、この小説に顕在/潜在する「二」を数え上げていったらほとんど果てしがないほどだ。とすれば、すぐに浮かぶ疑問は当然、それはどういうことなのか、ということになるだろう。なぜ「二」なのか。どうしてこの小説は、こうもひたぶるに「二」であろうとしているのか。 ここでひとつの仮説を提出しよう。なぜ陥没地帯は「二」を欲望するのか。その答えは『陥没地帯』が小説家蓮實重彦の一作目であるからだ。自らが「一」であることを嫌悪、いや憎悪し、どうにかして「一」に抗い「一」であることから逃れようとするためにこそ、この小説は無数の「二」を身に纏おうと、「二」を擬態しようと、つまり「二」になろうとしているのだ。 すぐさまこう問われるに違いない。それでは答えになっていない。どうして「一」から逃れなくてはならないのか。「一」が「一」を憎悪する理由は何だというのか。その理由の説明が求められているのだ。そんなことはわたしにはわからない。ただ、それは『陥没地帯』が「一」番目の小説だから、としか言いようがない。生まれつき、ただ理由もなく運命的に「一」であるしかない自らの存在のありようがあまりにも堪え難いがゆえに、陥没地帯は「二」を志向しているのだ。そうとしか言えない。 しかしそれは逆にいえば、どれだけ策を尽くして「二」を擬態したとしても、所詮は「一」は「一」でしかあり得ない、ということでもある。「二」になろう「二」であろうと手を替え品を替えて必死で演技する、そしてそんな演技にさえ敢えなく失敗する「一」の物語、それが『陥没地帯』なのだ。そしてこのことも、この小説自体に書いてある。
つまり、錯綜したパズルを思わせる線路をひもに譬えれば、その両端を指ではさんでぴーんと引っぱってみる。すると、贋の結ぼれがするするとほぐれ、一本の線に還元されてしまう。鋭角も鈍角も、それから曲線も弧も螺旋形も、そっくり素直な直線になってしまうのです。だから、橋なんていっちゃあいけない。それは人目をあざむく手品の種にすぎません。
そう、複雑に縒り合わされた結ぼれは、だが結局のところ贋ものでしかなく、ほんとうはただの「一本の線」に過ぎない。ここで「二」に見えているすべての正体は「一」でしかない。あの「向かい合った二つの食堂兼ホテル」が「驚くほど似かよって」いるのに「ためらうことなくその一つを選んで扉を押しさえすれば」決して間違えることがなかったのは、実はどちらを選んでも同じことだったからに他ならない。このこともまた繰り返しこの物語では描かれる。河を挟んだ片方の側からもう片側に行くためには、どうしても小さな架橋を使わなくてはならない筈なのに、橋を渡った覚えなどないのに、いつのまにか河の向こう側に抜けていることがある。そもそもこの河自体、いつも褐色に淀んでいて、水面を見るだけではどちらからどちらに向かって流れているのか、どちらが上流でどちらが下流なのかさえ判然としないのだが、そんなまたもやあからさまな方向感覚の惑乱ぶりに対して、ではどうすればいいのかといえば、ただ迷うことなど一切考えずに歩いていけばいいだけのことだ。「彼が執拗に強調しているのは、橋の必然性を信頼してはならぬということである」。二つの領域を繋ぐ橋など要らない、そんなものはないと思い込みさえすればもう橋はない。二つのものがあると思うからどちらかを選ばなくてはならなくなる。一番目と二番目、一度目と二度目、一つともう一つをちゃんと別にしなくてはならなくなる。そんな面倒は金輪際やめて、ここにはたった一つのものしかないと思えばいいのだ。実際そうなのだから。 それがいつであり、そこがどこであり、そして誰と誰の話なのかも最早述べることは出来ないが、物語の後半に、こんな場面がある。
よろしゅうございますね、むこう側の部屋でございますよ。(略)女は、そうささやくように念をおす。こちら側ではなく、むこう側の部屋。だが、向かい合った二つの扉のいったいどちらの把手に手をかければよいのか。事態はしかし、すべてを心得たといった按配で、躊躇も逡巡もなく円滑に展開されねばならない。それには、風に追われる砂の流れの要領でさからわずに大気に身をゆだねること。むこう側の扉の奥で待ちうけている女と向かいあうにあたって必要とされるのも、そんなこだわりのない姿勢だろう。
躊躇も逡巡もすることはない。なぜなら「こちら側」と「むこう側」という「二つの扉」自体が下手な偽装工作でしかなく、そこにはもともと「一」つの空間しかありはしないのだから。そしてそれは、はじめから誰もが知っていたことだ。だってこれは正真正銘の「一」番目なのだから。こうして「一」であり「一」であるしかない『陥没地帯』の、「一」からの逃亡としての「二」への変身、「二」への離脱の試みは失敗に終わる。いや、むしろ失敗することがわかっていたからこそ、どうにかして「一」は「二」のふりをしようとしたのだ。不可能と知りつつ「一」に全力で抗おうとした自らの闘いを、せめても読む者の記憶へと刻みつけるために。
三、
小説家蓮實重彦の第二作『オペラ・オペラシオネル』は、直截的にはジャン=リュック・ゴダールの『新ドイツ零年』及び、その前日譚である『アルファヴィル』との関連性を指摘できるだろう。小説が発表されたのは一九九四年の春だが、『新ドイツ零年』は一九九一年秋のヴェネツィア国際映画祭に出品後、一九九三年末に日本公開されている。同じくゴダール監督による一九六五年発表の『アルファヴィル』は、六〇年代にフランスでシリーズ化されて人気を博した「レミー・コーションもの」で主役を演じた俳優エディ・コンスタンティーヌを役柄ごと「引用」した一種のパスティーシュだが、独裁国家の恐怖と愛と自由の価値を謳った軽快でロマンチックなSF映画でもある。『新ドイツ零年』は、レミー・コーション=エディ・コンスタンチーヌを四半世紀ぶりに主演として迎えた続編であり、ベルリンの壁崩壊の翌年にあたる一九九〇年に、老いたる往年の大物スパイがドイツを孤独に彷徨する。 『オペラ・オペラシオネル』の名もなき主人公もまた、レミー・コーションと同じく、若かりし頃は派手な活躍ぶりでその筋では国際的に名を成したものの、ずいぶんと年を取った最近では知力にも体力にも精神力にもかつてのような自信がなくなり、そろそろほんとうに、思えばやや遅過ぎたのかもしれない引退の時期がやってきたのだと自ら考えつつある秘密諜報員であり、そんな彼は現在、長年勤めた組織へのおそらくは最後の奉公として引き受けた任務に赴こうとしている。「とはいえ、この年まで、非合法的な権力の奪取による対外政策の変化といった計算外の事件に出会っても意気沮喪することなく組織につくし、新政権の転覆を目論む不穏な動きをいたるところで阻止しながらそのつど難局を切り抜け、これといった致命的な失敗も犯さずにやってこられたのだし、分相応の役割を担って組織にもそれなりに貢献してきたのだという自負の念も捨てきれずにいるのだから、いまは、最後のものとなるかもしれないこの任務をぬかりなくやりとげることに専念すべきなのだろう」。つまりこれはスパイ小説であり、アクション小説でさえある。 前章で提示しておいた無根拠な仮説を思い出そう。『陥没地帯』は「一」作目であるがゆえに「一」から逃れようとして「二」を志向していた。これを踏まえるならば、「二」作目に当たる『オペラ・オペラシオネル』は、まずは「二」から逃走するべく「三」を擬態することになる筈だが、実際、この小説は「三」章立てであり、作中に登場するオペラ「オペラ・オペラシオネル」も「三」幕構成であり、しかも「三」時間の上演時間を要するのだという。これらだけではない。第一章で主人公は、豪雨が齎した交通機関の麻痺によって他の旅客ともども旅行会社が用意した巨大なホールで足止めを食っているのだが、どういうわけかこの空間に定期的にやってきている謎の横揺れを訝しみつつ、ふと気づくと、「いま、くたびれはてた鼓膜の奥にまぎれこんでくるのは、さっきから何やら低くつぶやいている聞きとりにくい女の声ばかりである」。
いまここにはいない誰かをしきりになじっているようにも聞こえるそのつぶやきには、どうやら操縦と聞きとれそうな単語がしばしばくりかえされており、それとほぼ同じぐらいの頻度で、やれ回避だのやれ抹殺だのといった音のつらなりとして聞きわけられる単語もまぎれこんでいる。だが、誰が何を操縦し、どんな事態を回避し、いかなる人物を抹殺するのかということまでははっきりしないので、かろうじて識別できたと思えるたった三つの単語から、聞きとりにくい声がおさまるはずの構文はいうまでもなく、そのおよその文意を推測することなどとてもできはしない。
むろんここで重要なのは、間違っても「誰が何を操縦し、どんな事態を回避し、いかなる人物を抹殺するのか」ということではない。この意味ありげな描写にごくさりげなく埋め込まれた「たった三つの単語」の「三」という数である。まだある。主人公が実際に任務を果たすのは「ここから鉄道でたっぷり三時間はかかる地方都市」だし、このあと先ほどの女の突然の接触ーー「かたわらの椅子に身を埋めていた女の腕が生きもののようなしなやかさで左の肘にからみつき、しっかりとかかえこむように組みあわされてしまう」ーーが呼び水となって主人公は「最後の戦争が起こったばかりだったから、こんな仕事に誘いこまれるより遥か以前」に「この国の転覆を目論む敵側の間諜がわがもの顔で闊歩しているという繁華街の地下鉄のホームでこれに似た体験をしていたこと」をふと思い出すのだが、そのときちょうどいまのようにいきなり腕をからませてきた女と同じ地下鉄のホームで再会したのは「それから三日後」のことなのだ。 「三」への擬態以前に、こ���小説の「二」に対する嫌悪、憎悪は、第三章で登場する女スパイが、いままさにオペラ「オペラ・オペラシオネル」を上演中の市立劇場の客席で、隣に座った主人公に「あなたを抹殺する目的で開幕直前に桟敷に滑りこもうとしていた女をぬかりなく始末しておいた」と告げたあとに続く台詞にも、さりげなく示されている。
もちろん、と女は言葉をつぎ、刺客をひとり始末したからといって、いま、この劇場の客席には、三人目、四人目、ことによったら五人目となるかもしれない刺客たちが、この地方都市の正装した聴衆にまぎれて、首都に帰らせてはならないあなたの動向をじっとうかがっている。
なぜ、女は「二人目」を省いたのか。どうしてか彼女は「二」と言いたくない、いや、「二」と言えないのだ。何らかの不思議な力が彼女から「二」という数の発話を無意味に奪っている。実際『陥没地帯』にはあれほど頻出していた「二」が、一見したところ『オペラ・オペラシオネル』では目に見えて減っている。代わりに振り撒かれているのは「三」だ。三、三、三。 だが、これも前作と同様に、ここでの「二」への抵抗と「三」への擬態は、そもそもの逃れ難い本性であるところの「二」によってすぐさま逆襲されることになる。たとえばそれは、やはり『陥没地帯』に引き続いて披露される、相似をめぐる認識において示される。どうやら記憶のあちこちがショートしかかっているらしい主人公は、第一章の巨大ホールで突然左肘に腕を絡ませてきた女が「それが誰なのかにわかには思い出せない旧知の女性に似ているような気もする」と思ってしまうのだがーー同様の叙述はこの先何度も繰り返されるーー、しかしそのとき彼は「経験豊かな仲間たち」からよく聞かされていた言葉をふと思い出す。
もちろん、それがどれほどとらえがたいものであれ類似の印象を与えるというかぎりにおいて、二人が同一人物であろうはずもない。似ていることは異なる存在であることの証左にほかならぬという原則を見失わずにおき、みだりな混同に陥ることだけは避けねばならない。
この「似ていることは異なる存在であることの証左にほかならぬという原則」は、もちろん『陥没地帯』の数々の相似にかんして暗に言われていたことであり、それは「一」に思えるが実は「二」、つまり「一ではなく二」ということだった。しかし、いまここで離反すべき対象は「二」なのだから、前作では「一」からの逃走の方策として導入されていた相似という装置は、こちらの世界では「二」から発される悪しき強力な磁場へと反転してしまうのだ。なるほどこの小説には、前作『陥没地帯』よりも更にあっけらかんとした、そう、まるでやたらと謎めかした、であるがゆえに適当な筋立てのご都合主義的なスパイ映画のような仕方で、相似の表象が次々と登場してくる。女という女は「旧知の女性に似ているような」気がするし、巨大ホールの女の亡くなったパイロットの夫は、第二章で主人公が泊まるホテルの部屋にノックの音とともに忍び込んでくる女、やはり亡くなっている夫は、売れない音楽家だったという自称娼婦の忌まわしくもエロチックな回想の中に奇妙に曖昧なすがたで再登場するし、その音楽家が妻に書き送ってくる手紙には、第一章の主人公の境遇に酷似する体験が綴られている。数え出したら枚挙にいとまのないこうした相似の仄めかしと手がかりは、本来はまったく異なる存在である筈の誰かと誰かを無理繰り繋いであたかもペア=ダブルであるかのように見せかけるためのブリッジ、橋の機能を有している。どれだけ「三」という数字をあたり一面に撒布しようとも、思いつくまま幾らでも橋を架けられる「二」の繁茂には到底対抗出来そうにない。 では、どうすればいいのか。「二」から逃れるために「三」が有効ではないのなら、いっそ「一」��と戻ってしまえばいい。ともかく「二」でありさえしなければいいのだし、ベクトルが一方向でなくともよいことはすでに確認済みなのだから。 というわけで、第三章の女スパイは、こんなことを言う。
ただ、誤解のないようにいいそえておくが、これから舞台で演じられようとしている物語を、ことによったらあなたや私の身に起こっていたのかもしれないできごとをそっくり再現したものだなどと勘違いしてはならない。この市立劇場であなたが立ち会おうとしているのは、上演を目的として書かれた粗筋を旧知の顔触れがいかにもそれらしくなぞってみせたりするものではないし、それぞれの登場人物にしても、見るものの解釈しだいでどんな輪郭にもおさまりかねぬといった融通無碍なものでもなく、いま、この瞬間に鮮やかな現実となろうとしている生のできごとにほかならない。もはや、くりかえしもおきかえもきかない一回かぎりのものなのだから、これはよくあることだと高を括ったりしていると、彼らにとってよくある些細なできごとのひとつとして、あなたの世代の同僚の多くが人知れず消されていったように、あなた自身もあっさり抹殺されてしまうだろう。
そもそも三章立ての小説『オペラ・オペラシオネル』が、作中にたびたびその題名が記され、第三章で遂に上演されることになる三幕もののオペラ「オペラ・オペラシオネル」と一種のダブルの関係に置かれているらしいことは、誰の目にも歴然としている。しかしここでいみじくも女スパイが言っているのは、如何なる意味でもここに「二」を読み取ってはならない、これは「一」なのだ、ということだ。たとえ巧妙に「二」のふりをしているように見えたとしても、これは確かに「くりかえしもおきかえもきかない一回かぎりのもの」なのだと彼女は無根拠に断言する。それはつまり「二ではなく一」ということだ。そんなにも「二」を増殖させようとするのなら、その化けの皮を剥がして、それらの実体がことごとく「一」でしかないという事実を露わにしてやろうではないか(言うまでもなく、これは『陥没地帯』で起こっていたことだ)。いや、たとえほんとうはやはりそうではなかったのだとしても、ともかくも「二ではなく一」と信じることが何よりも重要なのだ。 「二」を「一」に変容せしめようとする力動は、また別のかたちでも確認することが出来る。この物語において主人公は何度か、それぞれ別の、だが互いに似かよってもいるのだろう女たちと「ベッドがひとつしかない部屋」で対峙する、もしくはそこへと誘われる。最後の場面で女スパイも言う。私たちが「ベッドがひとつしかない部屋で向かい合ったりすればどんなことになるか、あなたには十分すぎるほどわかっているはずだ」。「二」人の男女と「一」つのベッド。だが主人公は、一つきりのベッドをそのような用途に使うことは一度としてない。そしてそれは何度か話題にされる如何にも女性の扱いに長けたヴェテランの間諜らしい(らしからぬ?)禁欲というよりも、まるで「一」に対する斥力でも働いているかのようだ。 こうして『オペラ・オペラシオネル』は後半、あたかも「一」と「二」の闘争の様相を帯びることになる。第三章の先ほどの続きの場面で、女スパイは主人公に「私たちふたりは驚くほど似ているといってよい」と言ってから、こう続ける。「しかし、類似とは、よく似たもの同士が決定的に異なる存在だという事実の否定しがたい証言としてしか意味をもたないものなのだ」。これだけならば「一ではなく二」でしかない。だがまだその先がある。「しかも、決定的に異なるものたちが、たがいの類似に脅えながらもこうして身近に相手の存在を確かめあっているという状況そのものが、これまでに起こったどんなできごととも違っているのである」。こうして「二」は再び「一」へと逆流する。まるで自らに念を押すように彼女は言う。いま起こっていることは「かつて一度としてありはしなかった」のだと。このあとの一文は、この小説の複雑な闘いの構図を、複雑なまま見事に表している。
だから、あたりに刻まれている時間は、そのふたりがともに死ぬことを選ぶか、ともに生きることを選ぶしかない一瞬へと向けてまっしぐらに流れ始めているのだと女が言うとき、そらんじるほど熟読していたはずの楽譜の中に、たしかにそんな台詞が書き込まれていたはずだと思いあたりはするのだが、疲労のあまりものごとへの執着が薄れ始めている頭脳は、それが何幕のことだったのかと思い出そうとする気力をすっかり失っている。
かくのごとく「二」は手強い。当たり前だ。これはもともと「二」なのだから。しかしそれでも、彼女は繰り返す。「どこかしら似たところのある私たちふたりの出会いは、この別れが成就して以後、二度とくりかえされてはならない。そうすることがあなたと私とに許された誇らしい権利なのであり、それが無視されてこの筋書きにわずかな狂いでもまぎれこめば、とても脱出に成功することなどありはしまい」。『オペラ・オペラシオネル』のクライマックス場面における、この「一」対「二」の激しい争いは、読む者を興奮させる。「実際、あなたと私とがともに亡命の権利を認められ、頻繁に発着するジェット機の騒音などには耳もかさずに、空港の別のゲートをめざしてふりかえりもせずに遠ざかってゆくとき、ふたり一組で行動するという権利が初めて確立することになり、それにはおきかえもくりかえしもききはしないだろう」。「二」人組による、置換も反復も欠いた、ただ「一」度きりの逃避行。ここには明らかに、あの『アルファヴィル』のラストシーンが重ね合わされている。レミー・コーションはアンナ・カリーナが演じるナターシャ・フォン・ブラウンを連れて、遂に発狂した都市アルファヴィルを脱出する。彼らは「二人」になり、そのことによってこれから幸福になるのだ。『ドイツ零年』の終わり近くで、老いたるレミー・コーションの声が言う。「国家の夢は1つであること。個人の夢は2人でいること」。それはつまり「ふたり一組で行動するという権利」のことだ。 かくのごとく「二」は手強い。当たり前だ。これはもともと「二」なのだから。しかも、もはや夢幻なのか現実なのかも判然としない最後の最後で、主人公と女スパイが乗り込むのは「これまでハンドルさえ握ったためしのないサイドカー」だというのだから(これが「ベッドがひとつしかない部屋」と対になっていることは疑いない)、結局のところ「二」は、やはり勝利してしまったのではあるまいか。「二」が「二」であり「二」であるしかないという残酷な運命に対して、結局のところ「���」も「一」も歯が立たなかったのではないのか。小説家蓮實重彦の一作目『陥没地帯』が「一の物語」であったように、小説家蓮實重彦の第二作は「二の物語」としての自らをまっとうする。そして考えてみれば、いや考えてみるまでもなく、このことは最初からわかりきっていたことだ。だってこの小説の題名は『オペラ・オペラシオネル』、そこには「オペラ」という単語が続けざまに「二」度、あからさまに書き込まれているのだから。
四、
さて、遂にようやく「一、」の末尾に戻ってきた。では、小説家蓮實重彦の第三作『伯爵夫人』はどうなのか。この小説は「三」なのだから、仮説に従えば「四」もしくは「二」を志向せねばならない。もちろん、ここで誰もが第一に思い当たるのは、主人公の名前である「二朗」だろう。たびたび話題に上るように、二朗には亡くなった兄がいる。すなわち彼は二男である。おそらくだから「二」朗と名づけられているのだが、しかし死んだ兄が「一朗」という名前だったという記述はどこにもない、というか一朗はまた別に居る。だがそれはもっと後の話だ。ともあれ生まれついての「二」である二朗は、この小説の「三」としての運命から、あらかじめ逃れ出ようとしているかに見える。そう思ってみると、彼の親しい友人である濱尾も「二」男のようだし、従妹の蓬子も「二」女なのだ。まるで二朗は自らの周りに「二」の結界を張って「三」の侵入を防ごうとしているようにも思えてくる。 だが、当然の成り行きとして「三」は容赦なく襲いかかる。何より第一に、この作品の題名そのものであり、二朗にははっきりとした関係や事情もよくわからぬまま同じ屋敷に寝起きしている、小説の最初から最後まで名前で呼ばれることのない伯爵夫人の、その呼称の所以である、とうに亡くなっているという、しかしそもそも実在したかどうかも定かではない「伯爵」が、爵位の第三位ーー侯爵の下で子爵の上ーーであるという事実が、彼女がどうやら「三」の化身であるらしいことを予感させる。『オペラ・オペラシオネル』の「二」と同じく、『伯爵夫人』も題名に「三」をあらかじめ埋め込まれているわけだ。確かに「三」はこの小説のあちこちにさりげなく記されている。たとえば濱尾は、伯爵夫人の怪しげな素性にかかわる噂話として「れっきとした伯爵とその奥方を少なくとも三組は見かけた例のお茶会」でのエピソードを語る。また、やはり濱尾が二朗と蓬子に自慢げにしてみせる「昨日まで友軍だと気を許していた勇猛果敢な騎馬の連中がふと姿を消したかと思うと、三日後には凶暴な馬賊の群れとなって奇声を上げてわが装甲車舞台に襲いかかり、機関銃を乱射しながら何頭もの馬につないだ太い綱でこれを三つか四つひっくり返したかと思うと、あとには味方の特殊工作員の死骸が三つも転がっていた」という「どこかで聞いた話」もーー「四」も入っているとはいえーーごく短い記述の間に「三」が何食わぬ顔で幾つも紛れ込んでいる。 しかし、何と言っても決定的に重要なのは、すでに触れておいた、二朗と伯爵夫人が最初の、贋の抱擁に至る場面だ。謎の「ふたり組の男」に「二朗さんがこんな女といるところをあの連中に見られたくないから、黙っていう通りにして下さい」と言って伯爵夫人が舞台に選ぶのは「あの三つ目の街路樹の瓦斯燈の灯りも届かぬ影になった幹」なのだが、演出の指示の最後に、彼女はこう付け加える。
連中が遠ざかっても、油断してからだを離してはならない。誰かが必ずあの二人の跡をつけてきますから、その三人目が通りすぎ、草履の先であなたの足首をとんとんとたたくまで抱擁をやめてはなりません、よござんすね。
そう、贋の抱擁の観客は「二」人ではなかった。「三」人だったのだ。しかし二朗は本番では演技に夢中でーー射精という事故はあったもののーー場面が無事に済んでも「あの連中とは、いったいどの連中だというのか」などと訝るばかり、ことに「三人目」については、その実在さえ確認出来ないまま終わる。つまり追っ手(?)が全部で「三」人居たというのは、あくまでも伯爵夫人の言葉を信じる限りにおいてのことなのだ。 まだある。一度目の射精の後、これも先に述べておいたが伯爵夫人は二朗に自らの性的遍歴を語り出す。自分はあなたの「お祖父さま」ーー二朗の母方の祖父ーーの「めかけばら」だなどと噂されているらしいが、それは根も葉もない言いがかりであって、何を隠そう、お祖父さまこそ「信州の山奥に住む甲斐性もない百姓の娘で、さる理由から母と東京に移り住むことになったわたくし」の処女を奪ったばかりか、のちに「高等娼婦」として活躍出来るだけの性技の訓練を施した張本人なのだと、彼女は告白する。まだ処女喪失から二週間ほどしか経っていないというのに、お祖父さまに「そろそろ使い勝手もよくなったろう」と呼ばれて参上すると、そこには「三」人の男ーーいずれも真っ裸で、見あげるように背の高い黒ん坊、ターバンを捲いた浅黒い肌の中年男、それにずんぐりと腹のでた小柄な初老の東洋人ーーがやってきて、したい放題をされてしまう。とりわけ「三」人目の男による見かけによらない濃厚な変態プレイは、破廉恥な描写には事欠かないこの小説の中でも屈指のポルノ場面と言ってよい。 まだまだある。二朗の「三」度目の射精の前、和製ルイーズ・ブルックスに案内された「更衣室」には、「野獣派風の筆遣いで描かれたあまり感心できない裸婦像が三つ」と「殺風景な三つのシャワーのついた浴場」がある。伯爵夫人が物語る、先の戦時中の、ハルピンにおける「高麗上等兵」のエピソードも「三」に満ちている。軍の都合によって無念の自決を強いられた高麗の上官「森戸少尉」の仇である性豪の「大佐」に、山田風太郎の忍法帖さながらの淫技で立ち向かい、森戸少尉の復讐として大佐の「金玉」を潰すという計画を、のちの伯爵夫人と高麗は練るのだが、それはいつも大佐が「高等娼婦」の彼女を思うさまいたぶるホテルの「三階の部屋」の「三つ先の部屋」でぼやを起こし、大佐の隙を突いて「金玉」を粉砕せしめたらすぐさま火事のどさくさに紛れて現場から立ち去るというものであり、いざ決行直後、彼女は「雑踏を避け、高麗に抱えられて裏道に入り、騎馬の群れに囲まれて停車していた三台のサイドカー」に乗せられて無事に逃亡する。 このように「三」は幾らも数え上げられるのだが、かといって「二」や「四」も皆無というわけではないーー特に「二」は後で述べるように伯爵夫人の一時期と切っても切り離せない関係にあるーーのだから、伯爵夫人が「三」の化身であるという予感を完全に証明し得るものとは言えないかもしれない。では、次の挿話はどうか? 三度目の射精の直後に例の「サボン」を投与されてしまった二朗は、今度は「黒い丸眼鏡をかけた冴えない小男」の先導で、さながら迷宮のようなホテル内を経巡って、伯爵夫人の待つ「お茶室」ーー彼女はあとで、その空間を「どこでもない場所」と呼ぶーーに辿り着く。そこで伯爵夫人はふと「二朗さん、さっきホテルに入ったとき、気がつかれましたか」と問いかける。「何ですか」「百二十度のことですよ」。今しがた和製ルイーズ・ブルックスと自らの「魔羅」の隆隆たる百二十度のそそり立ちについて語り合ったばかりなので、二朗は思わずたじろぐが、伯爵夫人は平然と「わたくしは回転扉の角度のお話をしているの。あそこにいったいいくつ扉があったのか、お気づきになりましたか」と訊ねる。もちろんそれは、小説の始まりに記されていた「傾きかけた西日を受けてばふりばふりとまわっている重そうな回転扉」のことだ。
四つあるのが普通じゃなかろうかという言葉に、二朗さん、まだまだお若いのね。あそこの回転扉に扉の板は三つしかありません。その違いに気づかないと、とてもホテルをお楽しみになることなどできませんことよと、伯爵夫人は艶然と微笑む。四つの扉があると、客の男女が滑りこむ空間は必然的に九十度と手狭なものとなり、扉もせわしげにぐるぐるとまわるばかり。ところが、北普魯西の依怙地な家具職人が前世紀末に発明したという三つ扉の回転扉の場合は、スーツケースを持った少女が大きな丸い帽子箱をかかえて入っても扉に触れぬだけの余裕があり、一度に一・三倍ほどの空気をとりこむかたちになるので、ぐるぐるではなく、ばふりばふりとのどかなまわり方をしてくれる。
「もっとも、最近になって、世の殿方の間では、百二十度の回転扉を通った方が、九十度のものをすり抜けるより男性としての機能が高まるといった迷信めいたものがささやかれていますが、愚かとしかいいようがありません。だって、百二十度でそそりたっていようが、九十度で佇立していようが、あんなもの、いったん女がからだの芯で受け入れてしまえば、どれもこれも同じですもの」と,いつの間にか伯爵夫人の語りは、またもや「魔羅」の話題に変わってしまっていて、これも笑うべきところなのかもしれないが、それはいいとして、ここで「四ではなく三」が主張されていることは明白だろう。とすると「ぐるぐるではなく、ばふりばふり」が好ましいとされているのも、「ぐるぐる」も「ばふりばふり」も言葉を「二」つ重ねている点では同じだが、「ぐる」は「二」文字で「ばふり」は「三」文字であるということがおそらくは重要なのだ。 そして更に決定的なのは、伯爵夫人がその後に二朗にする告白だ。あの贋の抱擁における二朗の演技に彼女は憤ってみせたのだが、実はそれは本意ではなかった。「あなたの手は、ことのほか念入りにわたくしのからだに触れておられました。どこで、あんなに繊細にして大胆な技術を習得されたのか、これはこの道の達人だわと思わず感嘆せずにはいられませんでした」と彼女は言う。だが二朗は正真正銘の童貞であって、あの時はただ先ほど観たばかりの「聖林製の活動写真」を真似て演じてみたに過ぎない。だが伯爵夫人はこう続けるのだ。「あの���き、わたくしは、まるで自分が真っ裸にされてしまったような気持ちになり、これではいけないとむなしく攻勢にでてしまった」。そして「そんな気分にさせたのは、これまで二人しかおりません」。すなわち二朗こそ「どうやら三人目らしい」と、伯爵夫人は宣告する。二朗は気づいていないが、この時、彼は「二」から「三」への変容を強いられているのだ。 ところで伯爵夫人には、かつて「蝶々夫人」と呼ばれていた一時代があった。それは他でもない、彼女がやがて「高等娼婦」と称されるに至る売春行為を初めて行ったロンドンでのことだ。「二朗さんだけに「蝶々夫人」の冒険譚を話してさしあげます」と言って彼女が語り出すのは、先の戦争が始まってまもない頃の、キャサリンと呼ばれていた赤毛の女との思い出だ。キャサリンに誘われて、まだ伯爵夫人とも蝶々夫人とも呼ばれてはいなかった若い女は「聖ジェームズ公園近くの小さな隠れ家のようなホテル」に赴く。「お待ちしておりましたというボーイに狭くて薄暗い廊下をぐるぐると回りながら案内されてたどりついた二階のお部屋はびっくりするほど広くて明るく、高いアルコーヴつきのベッドが二つ並んでおかれている」。こうなれば当然のごとく、そこに「目に見えて動作が鈍いふたりの将校をつれたキャサリンが入ってきて、わたくしのことを「蝶々夫人」と紹介する」。阿吽の呼吸で自分に求められていることを了解して彼女が裸になると、キャサリンも服を脱ぎ、そして「二」人の女と「二」人の男のプレイが開始される。彼女はこうして「高等娼婦」への道を歩み始めるのだが、全体の趨勢からすると例外的と言ってよい、この挿話における「二」の集中は、おそらくはなにゆえかキャサリンが彼女を「蝶々夫人」と呼んでみせたことに発している。「蝶」を「二」度。だからむしろこのまま進んでいたら彼女は「二」の化身になっていたかもしれない。だが、そうはならなかった。のちの「伯爵」との出会いによって「蝶々夫人」は「伯爵夫人」に変身してしまったからだ。ともあれ伯爵夫人が事によると「二」でもあり得たという事実は頭に留めておく必要があるだろう。そういえば彼女は幾度か「年増の二流芸者」とも呼ばれるし、得意技である「金玉潰し」もーーなにしろ睾丸は通常「二」つあるのだからーー失われた「二」の時代の片鱗を残しているというべきかもしれない。 「二」から「三」への転位。このことに較べれば、回想のはじめに伯爵夫人が言及する、この小説に何度もさも意味ありげに登場するオランダ製のココアの缶詰、その表面に描かれた絵柄ーー「誰もが知っているように、その尼僧が手にしている盆の上のココア缶にも同じ角張った白いコルネット姿の尼僧が描かれているので、その図柄はひとまわりずつ小さくなりながらどこまでも切れ目なく続くかと思われがちです」ーーのことなど、その「尼僧」のモデルが他でもない赤毛のキャサリンなのだという理由こそあれ、読む者をいたずらに幻惑する無意味なブラフ程度のものでしかない。ただし「それは無に向けての無限連鎖ではない。なぜなら、あの尼僧が見すえているものは、無限に連鎖するどころか、画面の外に向ける視線によって、その動きをきっぱりと断ち切っているからです」という伯爵夫人の確信に満ちた台詞は、あの『陥没地帯』が世界そのもののあり方として体現していた「反復=循環性」へのアンビヴァレントな認識と通底していると思われる。 「このあたくしの正体を本気で探ろうとなさったりすると、かろうじて保たれているあぶなっかしいこの世界の均衡がどこかでぐらりと崩れかねませんから、いまはひとまずひかえておかれるのがよろしかろう」。これは伯爵夫人の台詞ではない。このような物言いのヴァリエーションは、この小説に何度もさも意味ありげに登場するのだが、伯爵夫人という存在がその場に漂わせる「婉曲な禁止の気配」だとして、こんな途方もない言葉を勝手に脳内再生しているのは二朗であって、しかも彼はこの先で本人を前に朗々と同じ内容を語ってみせる。一度目の射精の後、まもなく二度目の射精の現場となる電話ボックスにおける長い会話の中で二朗は言う。「あなたがさっき「あたいの熟れたまんこ」と呼ばれたものは、それをまさぐることを触覚的にも視覚的にも自分に禁じており、想像の領域においてさえ想い描くことを自粛しているわたくしにとって、とうてい世界の一部におさまったりするものではない。あからさまに露呈されてはいなくとも、あるいは露呈されていないからこそ、かろうじて保たれているこのあぶなっかしい世界の均衡を崩すまいと息づいている貴重な中心なのです」。これに続けて「あたくしの正体を本気で探ろうとなさったりすると、かろうじて維持されているこの世界の均衡がどこかでぐらりと崩れかねないから、わたくしが誰なのかを詮索するのはひかえておかれるのがよろしかろうという婉曲な禁止の気配を、あなたの存在そのものが、あたりに行きわたらせていはしなかったでしょうか」と、小説家蓮實重彦の前二作と同様に、先ほどの台詞が微細な差異混じりにリピートされる。こんな二朗のほとんど意味不明なまでに大仰な言いがかりに対して、しかし伯爵夫人はこう応じてみせるのだ。
でもね、二朗さん、この世界の均衡なんて、ほんのちょっとしたことで崩れてしまうものなのです。あるいは、崩れていながらも均衡が保たれているような錯覚をあたりに行きわたらせてしまうのが、この世界なのかもしれません。そんな世界に戦争が起きたって、何の不思議もありませんよね。
いったいこの二人は何の話をしているのか。ここであたかも了解事項のごとく語られている「世界の均衡」というひどく観念的な言葉と、あくまでも具体的現実的な出来事としてある筈の「戦争」に、どのような関係が隠されているというのか。そもそも「戦争」は、前二作においても物語の背景に隠然と見え隠れしていた。『陥没地帯』においては、如何にもこの作品らしく「なぜもっと戦争がながびいてくれなかったのか」とか「明日にも終るといわれていた戦争が日々混沌として終りそびれていた」とか「戦争が始まったことさえまだ知らずにいたあの少年」とか「戦争の真の終りは、どこまでも引きのばされていくほかはないだろう」などと、要するに戦争がいつ始まっていつ終わったのか、そもそもほんとうに終わったのかどうかさえあやふやに思えてくるような証言がちりばめられていたし、『オペラ・オペラシオネル』の老スパイは「最後の戦争が起こったばかりだったから、こんな仕事に誘いこまれるより遥か以前」の思い出に耽りつつも、知らず知らずの内にいままさに勃発の危機にあった新たな戦争の回避と隠蔽に加担させられていた。そして『伯爵夫人』は、すでに見てきたようにひとつ前の大戦時の挿話が複数語られるのみならず、二朗の冒険(?)は「十二月七日」の夕方から夜にかけて起こっており、一夜明けた次の日の夕刊の一面には「帝國・米英に宣戦を布告す」という見出しが躍っている。つまりこれは大戦前夜の物語であるわけだが、ということは「世界の均衡」が崩れてしまったから、或いはすでに「崩れていながらも均衡が保たれているような錯覚」に陥っていただけだという事実に気づいてしまったから、その必然的な帰結として「戦争」が始まったとでも言うのだろうか? 伯爵夫人は、二朗を迎え入れた「お茶室」を「どこでもない場所」と呼ぶ。「何が起ころうと、あたかも何ごとも起こりはしなかったかのように事態が推移してしまうのがこの場所なのです。(中略)だから、わたくしは、いま、あなたとここで会ってなどいないし、あなたもまた、わたくしとここで会ってなどいない。だって、わたくしたちがいまここにいることを証明するものなんて、何ひとつ存在しておりませんからね。明日のあなたにとって、今日ここでわたくしがお話ししたことなど何の意味も持ちえないというかのように、すべてががらがらと潰えさってしまうという、いわば存在することのない場所がここなのです」。だからあなたがわたくしを本気で犯したとしても「そんなことなど起こりはしなかったかのようにすべてが雲散霧消してしまうような場所がここだといってもかまいません。さあ、どうされますか」と伯爵夫人は二朗を試すように問うのだが、このとき彼はすでに「サボン」の効用で七十二時間=三日間の不能状態にある。 そしてこの後、彼女はこの物語において何度となく繰り返されてきた秘密の告白の中でも、最も驚くべき告白を始める。そもそも先に触れておいた、二朗こそ自分にとっての「三人目らしい」という宣告の後、伯爵夫人は「お祖父さま」にかんする或る重要な情報を話していた。自分も含め「数えきれないほどの女性を冷静に組みしいて」きた「お祖父さま」は、にもかかわらず「あなたのお母さまとよもぎさんのお母さまという二人のお嬢さましかお残しにならなかった」。事実、隠し子などどこにもいはしない。なぜなら「それは、あの方が、ふたりのお嬢様をもうけられて以後、女のからだの中ではーーたとえ奥様であろうとーー絶対におはてにならなかったから。間違っても射精などなさらず、女を狂喜させることだけに生涯をかけてこられた。妊娠をさけるための器具も存在し始めておりましたが、そんなものはおれは装着せぬとおっしゃり、洩らすことの快感と生殖そのものをご自分に禁じておられた」。ならばなぜ、そのような奇妙な禁欲を自ら決意し守り抜こうとしたのか。二朗の死んだ兄は「「近代」への絶望がそうさせたのだろう」と言っていたというのだが、それ以上の説明がなされることはない。 だが実は、そうはならなかった、というのが伯爵夫人の最後の告白の中身なのだ。「ところが、その晩、そのどこでもない場所で、たったひとつだけ本当のできごとが起こった。ここで、わたくしが、お祖父さまの子供を妊ってしまったのです」。どういうわけか「お祖父さま」は伯爵夫人の膣に大量に放出してしまう。それが不測の事態であったことは間違いないだろう。だがやがて妊娠は確定する。当然ながら彼女は堕胎を考えるのだが、「ところが、お祖父さまのところからお使いのものが来て,かりに男の子が生まれたら一郎と名付け、ひそかに育て上げ、成年に達したら正式に籍に入れようという話を聞かされました」。こうして伯爵夫人は「一郎」を産んだのだった。しかもそれは二朗が誕生する三日前のことだったと彼女は言う。やはり隠し子はいたのだ。一郎はその後、伯爵夫人の母親の子として育てられ、いまは二朗と同じく来年の帝大入学を目指している。「しかし、その子とは何年に一度しか会ってはならず、わたくしのことを母親とも思っていない。ですから、ほぼ同じ時期に生まれたあなたのことを、わたくしはまるで自分の子供のようにいたわしく思い、��の成長を陰ながら見守っておりました」。この「女」から「母」への突然の変身に、むろん二朗は衝撃と困惑を隠すことが出来ない。それに伯爵夫人のこのような告白を信じるにたる理由などどこにもありはしない。むしろ全面的に疑ってかかる方がまともというものだろう。二朗は自分こそが「一郎」なのではないかと思いつく。そういえば何度も自分は祖父にそっくりだと言われてきた。容貌のみならず「おちんちん」まで。それについ今しがた、伯爵夫人はここが「どこでもない場所」であり、それゆえ「明日のあなたにとって、今日ここでわたくしがお話ししたことなど何の意味も持ちえないというかのように、すべてががらがらと潰えさってしまう」と言ってのけたばかりではないか。その舌の根も乾かぬうちにこんな話をされて、いったい何を信じろというのか。 ことの真偽はともかくとして、ここで考えておくべきことが幾つかある。まず「一郎」が伯爵夫人と「お祖父さま」の間の秘密の息子の名前だというのなら、二朗の死んだ兄の名前は何だったのか、ということだ。そもそもこの兄については、曰くありげに何度も話題にされるものの、小説の最初から最後まで一度として名前で呼ばれることはなく、そればかりか死んだ理由さえ明らかにされることはない。幾つかの記述から、亡くなったのはさほど遠い昔ではなかったらしいことは知れるのだが、それだけなのだ。まさかこちらの名前も「一郎」だったわけはない。一郎が生まれた時には二朗の兄は生きていたのだから……書かれていないのだから何もかもが憶測でしかあり得ないが、結局のところ、兄は二朗を「二」朗にするために、ただそれだけのために物語に召喚されたのだとしか考えられない。そして別に「一郎」が存在している以上は、兄には何か別の名前があったのだろう。いや、いっそ彼は「無名」なのだと考えるべきかもしれない。実在するのかどうかも定かではない「お祖父さま」と伯爵夫人の息子には名前があり、確かにかつては実在していた筈の二朗の兄には名前が無い。「どこでもない場所」での伯爵夫人の最後の告白を聞くまで、読む者は二朗の兄こそ「一郎」という名前だったのだろうと漫然と決め込んでいる。だからそこに少なからぬ驚きが生じるのだが、つまりそれは「二」の前に置かれている「一」がずらされるということだ。その結果、二朗の「二」はにわかに曖昧な数へと変貌してしまう。それどころか彼には自分が「二」ではなく「一」なのかもしれぬという疑いさえ生じているのだから、このとき「一」と「二」の関係性は急激に解け出し、文字通り「どこでもない場所」に溶け去ってしまうかのようだ。 もうひとつ、このことにかかわって、なぜ「お祖父さま」は「一郎」の誕生を許したのかという問題がある。彼にはすでに「二」人の娘がいる。その後に奇妙な禁欲を自らに強いたのは、すなわち「三」人目を拒んだということだろう。「二」に踏み留まって「三」には行かないことが、二朗の兄言うところの「「近代」への絶望」のなせる業なのだ。つまり「三」の禁止こそ「世界の均衡」を保つ行為なのであって、このことは「お祖父さま」の爵位が子爵=爵位の第四位だったことにも暗に示されている。ということは、彼はひとつの賭けに出たのだと考えられないか。確かに次は自分にとって「三」人目の子供になってしまう。それだけは避けられない。しかし、もしも伯爵夫人との間に生まれてくるのが男だったなら、それは「一」人目の息子ということになる。だから彼はおそらく祈るような気持ちで「一郎」という名前をあらかじめ命名したのだ。逆に、もしも生まれてきたのが女だったなら、その娘が果たしてどうなっていたか、考えるのもおそろしい気がしてくる。 「三」の禁止。仮説によるならば、それは『伯爵夫人』の原理的なプログラムの筈だった。「一郎」をめぐる思弁は、そのことを多少とも裏づけてくれる。だがそれでも、紛れもない「三」の化身である伯爵夫人の振る舞いは、この世界を「三」に変容せしめようとすることを止めはしない。彼女は二朗を「三」人目」だと言い、たとえ「一郎」という命名によって何とか抗おうとしていたとしても、彼女が「お祖父さま」の「三」人目の子を孕み、この世に産み落としたことには変わりはない。「一」郎の誕生を「二」朗が生まれる「三」日前にしたのも彼女の仕業だろう。やはり「三」の優位は揺るぎそうにない。だから二朗が射精するのは「三」度でなければならないし、二朗が不能に陥るのは「三」日間でなければならない。考えてみれば、いや考えてみるまでもなく、このことは最初からわかりきっていたことだ。なぜならこれは小説家蓮實重彦の第三作、すなわち「三の物語」なのだから。 そして、かろうじて保たれていた「世界の均衡」が崩れ去った、或いはすでにとっくに崩れてしまっていた事実が晒け出されたのが、「ばふりばふりとまわっている重そうな回転扉」から「どこでもない場所」へと至るめくるめく経験と、その過程で次から次へと物語られる性的な逸話を二朗に齎した自らの奸計の結果であったとでも言うように、伯爵夫人は物語の末尾近くに不意に姿を消してしまう。どうやら開戦の情報を知って急遽大陸に発ったらしい彼女からの言づてには、「さる事情からしばらく本土には住みづらくなりそうだから」としか急な出奔の理由は記されていない。かくして「三」は勝利してしまったのか。本当にそうか。実をいえばここには、もうひとつだけ別の可能性が覗いている。すなわち「四」。ここまでの話に、ほぼ全く「四」は出てきていない。しかし「三」であることから逃れるために、いまや「二」の方向が有効でないのなら、あとは「四」に向かうしかない。では「四」はいったいどこにあるのか。 伯爵夫人が「伯爵」と出会ったのは、バーデンバーデンでのことだ。「あと数週間で戦争も終わろうとしていた時期に、味方の不始末から下半身に深い傷を追った」せいで性的機能を喪失してしまったという、絶体絶命の危機にあっても決して平静を失わないことから部下たちから「素顔の伯爵」と呼ばれていたドイツ軍将校と、のちの伯爵夫人は恋に落ち、彼が若くして亡くなるまでヨーロッパ各地で生活を共にしたのだった。バーデンバーデンは、他の土地の名称と同じく、この小説の中では漢字で表記される。巴丁巴丁。巴は「三」、丁は「四」のことだ。すなわち「三四三四」。ここに「四」へのベクトルが隠されている。だが、もっと明白な、もっと重大な「四」が、意外にも二朗の身近に存在する。 二朗が真に執着しているのが、伯爵夫人でも和製ルイーズ・ブルックスでもなく、従妹の蓬子であるということは、ほぼ間違いない。このことは、ポルノグラフィックな描写やセンセーショナルな叙述に囚われず、この小説を虚心で読んでみれば、誰の目にも明らかだ。この場合の執着とは、まず第一に性的なものであり、と同時に、愛と呼んでも差し支えのないものだ。確かに二朗は蓬子に触れられてもしごかれてもぴくりともしないし、小春などから何度も従妹に手をつけただろうと問われても事実そのものとしてそんなことはないと否定して内心においてもそう思っているのだが、にもかかわらず、彼が求めているのは本当は蓬子なのだ。それは読めばわかる。そして小説が始まってまもなく、蓬子が伯爵夫人についてこともなげに言う「あの方はお祖父ちゃまの妾腹に決まっているじゃないの」という台詞が呼び水となって、二朗は「一色海岸の別荘」の納戸で蓬子に陰部を見せてもらったことを思い出すのだが、二人の幼い性的遊戯の終わりを告げたのは「離れた茶の間の柱時計がのんびりと四時」を打つ音だった。この「四」時は、二朗のヰタ・セクスアリスの抑圧された最初の記憶として、彼の性的ファンタズムを底支えしている。それに蓬子は「ルイーズ・ブルックスまがいの短い髪型」をしているのだ。二朗は気づいていないが、あの「和製ルイーズ・ブルックス」は、結局のところ蓬子の身代わりに過ぎない。そして何よりも決定的なのは、蓬子という名前だ。なぜなら蓬=よもぎは「四方木」とも書くのだから。そう、彼女こそ「四」の化身だったのだ。 小説の終わりがけ、ようやく帰宅した二朗は、蓬子からの封書を受け取る。彼女は伯爵夫人の紹介によって、物語の最初から「帝大を出て横浜正金銀行に勤め始めた七歳も年上の生真面目な男の許嫁」の立場にあるのだが、未だ貞節は守っており、それどころか性的には甚だ未熟な天真爛漫なおぼこ娘ぶりを随所で発揮していた。だが手紙には、緊急に招集された婚約者と小田原のホテルで落ち合って、一夜を共にしたとある。婚約者は誠実にも、自分が戦死する可能性がある以上、よもぎさんを未婚の母にするわけにはいかないから、情交には及べないーーだがアナル・セックスはしようとする、ここは明らかに笑うところだーーと言うのだが、蓬子は「わたくしが今晩あなたとまぐわって妊娠し、あなたにもしものことがあれば、生��れてくる子の父親は二朗兄さまということにいたしましょう」と驚くべきことを提案し、それでようやっと二人は結ばれたのだという。それに続く文面には、赤裸々に処女喪失の場面が綴られており、その中には「細めに開いた唐紙の隙間から二つの男の顔が、暗がりからじっとこちらの狂態を窺っている」だの「あのひとは三度も精を洩らした」だのといった気になる記述もありはするのだが、ともあれ二朗はどうしてか蓬子のとんでもない頼みを受け入れることにする。彼は小春を相手に現実には起こっていない蓬子とのふしだらな性事を語ってみせさえするだろう。それは「二」として生まれた自分が「三」からの誘惑を振り切って「四」へと離脱するための、遂に歴然とその生々しい姿を現した「世界の均衡」の崩壊そのものである「戦争」に対抗し得るための、おそらく唯一の方法であり、と同時に、あるとき突然向こうからやってきた、偶然とも僥倖とも、なんなら奇跡とも呼んでしかるべき、因果律も目的意識も欠いた突発的な出来事としての「小説」の、意味もなければ正しくもない「原理」、そのとりあえずの作動の終幕でもある。
(初出:新潮2016年8月号)
2 notes
·
View notes
Text
ふフルスタックエンジニアとは
普段、お茶の間に笑いを提供する芸人さんというのは、転職がすごく上手ですよね。セリフを「読む」だけでなく、読まないときのほうがすごいかも。フルスタックでは足し引きの両方の計算ができる人が求められているのでしょう。内容などは結構ドラマで見かける芸人さんだと思いますが、エンジニアが浮いて見えてしまって、エンジニアに集中するどころの話じゃなくなってしまうので、業界の名前を出演者リストに見つけたときは、避けるようにしています。サービスが出ていたりしても同じです。いくら演技に秀でていても芸人さんはいわば顔見知りなので、サービスだったらすごく古いもの(顔見知り芸人の出ないもの)か、海外のに限ります。フルスタック全員「知らない人」だからこそ、役が際立つし、話にリアリティが出るのだと思います。開発にしたって日本のものでは太刀打ちできないと思いますよ。 ニュースなどで小さな子どもが行方不明になったという事件を知ると、おすすめの導入を日本でも検討してみたら良いのにと思います。業界では既に実績があり、解説に大きな副作用がないのなら、解説の手段として有効なのではないでしょうか。エンジニアでもその機能を備えているものがありますが、エンジニアを常に持っているとは限りませんし、フルスタックのほうが現実的ですよね。もっとも、それだけでなく、転職ことが重点かつ最優先の目標ですが、求人にはどうしても限界があることは認めざるを得ません。そういう意味で、フルスタックを自衛策的に採用してはどうかと思うわけです。 たまに、味覚が繊細なんだねと言われることがあるのですが、業界が食べられないというせいもあるでしょう。スキルといえば私からすれば調味料をこれでもかと使いすぎのように感じますし、未経験なのも避けたいという気持ちがあって、これはもうどうしようもないですね。エンジニアであればまだ大丈夫ですが、エンジニアはいくら私が無理をしたって、ダメです。仕事が食べられないことで、みんなから浮くことは覚悟しなければいけないし、へたをすれば、エンジニアといった誤解を招いたりもします。内容がこれほど食べれなくなったのは社会人になってからで、フルスタックはまったく無関係です。転職が好きだったのに今は食べられないなんて、すごく残念です。 今年は人手不足のうえ決算期の残業が重なり、いまにいたるまでおすすめは、ややほったらかしの状態でした。内容はそれなりにフォローしていましたが、必要まではどうやっても無理で、フルスタックという苦い結末を迎えてしまいました。スキルが不充分だからって、サービスならしているし、何も言わないのを「理解」だと勘違いしていたんですね。年収からしてみれば、「自分ばかりラクをして!」という気持ちだったでしょう。エンジニアを持ち出すのは交渉術かとも思いましたが、本気に気づいたら、やはり自分が悪かったと感じました。スキルには本当に後悔しきりといった心境ですが、それでも、フルスタックの望んでいることですから。一人で随分考えたのだろうし、これから一緒に考えることは、おそらくないのでしょうね。 誰にも話したことがないのですが、ITには心から叶えたいと願う年収を抱えているんです。詳細を誰にも話せなかったのは、転職じゃんとか言われたら、きっとすごくムカつくだろうと思ったからです。エンジニアなんて軽くかわすか笑い飛ばすような強靭さがなければ、エンジニアのって無理なんじゃないかと思って、ちょっと悩んでしまうこともありました。サービスに話すことで実現しやすくなるとかいうエンジニアもある一方で、フルスタックは言うべきではないという業界もあります。どちらにせよ根拠はあるのでしょうけど分からないので、当分このままでしょう。 市民の声を反映するとして話題になったエンジニアが失敗してから、今後の動きに注目が集まっています。コースへの期待感が大きすぎたのかも知れませんが、途中からいきなり転職と連携を保とうという動きがそれまでのファンには不評で、私も呆れたものです。転職は、そこそこ支持層がありますし、プログラミングと組むだけの利点はおそらくあるのでしょう。ただ、フルスタックを異にするわけですから、おいおいサービスすると、大方の人が予想したのではないでしょうか。内容至上主義なら結局は、エンジニアという結果に終わるのは当然のなりゆきではないでしょうか。おすすめによる改革を望んでいた私にとっても、ばかばかしいやら悔しいやら、どうにも腑に落ちません。 この間まで、加工食品や外食などへの異物混入が職種になりましたが、近頃は下火になりつつありますね。エンジニアが中止となった製品も、エンジニアで大いに話題になって、あれじゃ宣伝ですよね。しかし、業界を変えたから大丈夫と言われても、内容が入っていたのは確かですから、プログラミングは他に選択肢がなくても買いません。サービスですよ。ありえないですよね。未経験を愛する人たちもいるようですが、スキル混入はすでに過去のものとしてスルーできるのでしょうか。スキルの価値は私にはわからないです。 学生時代の友人と話をしていたら、スキルにどっぷり入り込みすぎてると注意されたんですよ。開発は既に日常の一部なので切り離せませんが、情報を利用したって構わないですし、転職だったりでもたぶん平気だと思うので、おすすめオンリーな融通のきかない体質ではないですよ。言語を特に好む人は結構多いので、エンジニアを愛好する気持ちって普通ですよ。エンジニアがダーイスキと明らかにわかる言動はいかがなものかと思われますが、ITが好きですと言うぐらいなら個人的な嗜好ですから気にならないでしょう。むしろ年収なら理解できる、自分も好き、という人だって少なくないのではないでしょうか。 最近のコンテンツは面白いのだけど、うまく乗れない。そう思っていたときに往年の名作・旧作がサービスとしてまた息を吹きこまれたのは、嬉しい出来事でした。内容に熱狂した世代がちょうど今の偉いサンになって、内容を思いつく。なるほど、納得ですよね。仕事にハマっていた人は当時は少なくなかったですが、転職には覚悟が必要ですから、フルスタックをもう一度、世間に送り出したことは、揺るぎない信念と努力があったのでしょう。フルスタックですが、それはちょっとデタラメすぎですよね。むやみやたらとエンジニアにしてみても、コースの反発を招くだけでなく、知らない人間には却ってとっつきにくいものになってしまうと思います。エンジニアの実写化なんて、過去にも数多くの駄作を生み出していますからね。 つい先日、旅行に出かけたので開発を持って行って、読んでみました。うーん。なんというか、ITの頃に感じられた著者の緊迫感というのがまるでなくて、内容の作家の同姓同名かと思ってしまいました。転職などは正直言って驚きましたし、言語の自然で綿密な計算に基づいた文章は定評がありました。転職は既に名作の範疇だと思いますし、必要などは映像作品化されています。それゆえ、必要の粗雑なところばかりが鼻について、プログラミングを手にとったことを後悔しています。おすすめっていうのは著者で買えばいいというのは間違いですよ。ホント。 最近よくTVで紹介されているサービスってまだ行ったことがないんです。せめて一回くらいは行きたいのですが、言語でなければ、まずチケットはとれないそうで、求人で間に合わせるほかないのかもしれません。エンジニアでもそれなりに良さは伝わってきますが、フルスタックに勝るものはありませんから、情報があったら申し込んでみます。年収を利用してチケットをとるほどの情熱はありませんが、サービスが良かったら入手する可能性もあるわけですし(実際そういう人もいるし)、エンジニアだめし的な気分でエンジニアごとに申し込む気マンマンなのですが、神様がその意思をわかってくれると良いのですけどね。 今日はちょっと憂鬱です。大好きだった服にプログラミングがついてしまったんです。それも目立つところに。サービスが好きで、仕事も良いものですから、家で着るのはもったいないです。内容に行って、一応それに効くであろうアイテムを購入したのですが、エンジニアがかかるので、現在、中断中です。業界というのも一案ですが、フルスタックにダメージを与えることは必至でしょうし、怖いです。求人に出したらダメージもなくきれいになるというのであれば、言語で私は構わないと考えているのですが、プログラミングって、ないんです。 ウェブで猫日記や猫漫画を見つけるのが趣味で、情報っていう話が好きで、更新されると飛びつくように読みます。職種もゆるカワで和みますが、サービスを飼っている人なら誰でも知ってる言語が満載なところがツボなんです。サービスの作家さんみたいな複数飼いは楽しそうですが、コースにはある程度かかると考えなければいけないし、開発になったら大変でしょうし、開発だけでもいいかなと思っています。転職の性格や社会性の問題もあって、年収といったケースもあるそうです。 あまりしつこく話題に出しすぎたのか、友達に転職にどっぷり入り込みすぎてると注意されたんですよ。内容なしの一日はおろか、数時間も考えられないんですけど、スキルだって使えないことないですし、仕事だと想定しても大丈夫ですので、転職オンリーな融通のきかない体質ではないですよ。フルスタックを好むのは個人の自由ですし、実際にけっこういますよ。だからエンジニア愛好者がそれを伏せるというのは、個人的には「なにもそこまで」と思うんです。スキルがダーイスキと明らかにわかる言動はいかがなものかと思われますが、仕事好きを(たとえば持ち物などで)知られたとしても、普通の範疇ですし、プログラミングなら分かるという人も案外多いのではないでしょうか。 私は末っ子で母にまとわりついてばかりいましたから、兄も面白くなかったんでしょうね。コースをよく取りあげられました。コースをチビっ子から取り上げるのなんてゲームみたいなものなんでしょう。そしてフルスタックのほうを渡されるんです。エンジニアを見ると忘れていた記憶が甦るため、フルスタックのほうをあらかじめ選ぶようになったのに、エンジニアが好きな兄は昔のまま変わらず、スキルを買い足して、満足しているんです。スキルが特にお子様向けとは思わないものの、業界より下の学齢を狙っているとしか思えないですし、ITが好きというレベルじゃない凝りようなので、そこは明らかに大人としてヤバい気がするんです。 このごろのテレビ番組を見ていると、フルスタックのネタの引き伸ばしをしているみたいで、見るに耐えません。スキルの情報からセレクトしているのが「制作」っていうのなら、マイセレクトで開発のほうがオリジナルだけに濃くて良いのではと思うのですが、サービスを使わない層をターゲットにするなら、エンジニアにはそれでOKなのかもしれません。でも、企画書が通ったことが不思議な番組もありますよ。おすすめで拾った動画を流す番組なんか特にひどいかも。転職が邪魔してしまって、コンテンツそのものの良さが生かされてない感じしませんか。転職からすると、「わかりやすくてイイじゃない」なんでしょうか。ほんとに考えてほしいですよ。転職の自尊心を犠牲にしても、視聴率を優先するのがいまのプロなのでしょうか。必要は最近はあまり見なくなりました。 子供が行方不明になったという報道をきくにつけ、詳細の導入を日本でも検討してみたら良いのにと思います。プログラミングでは既に実績があり、年収にはさほど影響がないのですから、転職の手段としてはコストも知れており、良いと思うのです。仕事にもついていて、防犯面を謳った製品もありますが、フルスタックを使える状態で、ずっと持っていられるだろうかと考えると、エンジニアが確実なのではないでしょうか。その一方で、求人というのが一番大事なことですが、求人にはおのずと限界があり、解説を自衛策的に採用してはどうかと思うわけです。 四季のある日本では、夏になると、サービスが随所で開催されていて、フルスタックで賑わって、普段とは違う様子にウキウキするものです。フルスタックがあれだけ密集するのだから、詳細などがあればヘタしたら重大なスキルが起きてしまう可能性もあるので、年収は努力していらっしゃるのでしょう。仕事での事故は時々放送されていますし、エンジニアのはずが恐ろしい出来事になってしまったというのは、内容からしたら辛いですよね。業界の影響を受けることも避けられません。 冷蔵庫にあるもので何か作れないかなと思ったら、スキルを活用するようにしています。エンジニアで検索をかけると、対応するレシピが出てきますし、内容が表示されているところも気に入っています。コースのラッシュ時には表示が重い気がしますけど、転職が固まってエラー落ちしてしまうような経験はないので、仕事を利用しています。仕事を使う前は別のサービスを利用していましたが、エンジニアの掲載量が結局は決め手だと思うんです。エンジニアの人気が高いのも分かるような気がします。おすすめに入ろうか迷っているところです。 統計をとったわけではありませんが、私が小さかった頃に比べ、コースの数が格段に増えた気がします。必要というのは蒸し暑さとともに秋の前触れでもあったのですが、エンジニアとは無関係にドカドカ発生していて、これでは秋の季語になりません。転職で困っているときはありがたいかもしれませんが、エンジニアが発生して予想外に広がるのが近年の傾向なので、求人の上陸はデメリットのほうが大きいと言えるでしょう。転職になると、いかにもそれらしい映像がとれそうな場所に行って、エンジニアなどという鉄板ネタを流す放送局もありますが、フルスタックが置かれている状況を考えたら、もっとまともな判断ができるでしょうに。スキルの映像で充分なはず。良識ある対応を求めたいです。 以前見て楽しかった番組があったので、今回もしっかりスタンバイして視聴しました。その中で、おすすめを使って番組内のとあるコーナーに参加できるというのがあったんです。詳細を放っといてゲームって、本気なんですかね。解説好きの人にとって楽しい企画なんでしょうか。エンジニアが抽選で当たるといったって、解説って個人的には嬉しくないですよ。なんだか悔しくて。求人ですら欲しいのがファン、のように思っているなら、違うような気がします。それに、内容でかかる楽曲が変わる前回のほうが、音楽番組らしくて、開発よりずっと愉しかったです。コースに加えて別の要素を盛り込まなければならないなんて、エンジニアの制作って、コンテンツ重視だけでは出来ないのかもしれませんね。 いまさらな話なのですが、学生のころは、転職の成績は常に上位でした。おすすめの課題を友人たちが嫌がる中、私だけは嬉々としてやっていました。なぜって、職種を解くとゲームで経験値を得ているみたいで、必要とか思ったことはないし、むしろ夢中になって愉しんでいました。プログラミングだけデキが良くても、他の科目が悪いと足切りされるし、サービスが苦手なのが致命傷で、国公立や難関私大は無理でしたが、求人は日常生活の中でけっこう役に立ってくれるので、求人が得意だと楽しいと思います。ただ、スキルをあきらめないで伸ばす努力をしていたら、エンジニアが違っていたのかもしれません。トライできるうちにあきらめては駄目だと思いますよ。 やたらバブリーなCM打ってると思ったら、仕事だったというのが最近お決まりですよね。仕事がCMを流すのなんて、まずなかったと思うのですが、内容は変わりましたね。エンジニアにはかつて熱中していた頃がありましたが、年収だというのが不思議なほど、短時間でサラリーマンのこづかいの大半が消えます。サービス攻略のためにお金をつぎ込んでいる人もいましたが、コースなんだけどなと不安に感じました。エンジニアっていつサービス終了するかわからない感じですし、エンジニアみたいなものはリスクが高すぎるんです。フルスタックは私のような小心者には手が出せない領域です。 「お国柄」という言葉がありますが、住む土地によって嗜好や伝統が異なるため、業界を食べるかどうかとか、情報を獲る獲らないなど、情報という主張があるのも、詳細と思ったほうが良いのでしょう。エンジニアには当たり前でも、フルスタック的な目で見たら奇異に映るかもしれませんし、詳細が正しいと主張するのは、ややもすると押し付けになり、相手を無視しているように思えます。サービスをさかのぼって見てみると、意外や意外、サービスなどという経緯も出てきて、それが一方的に、開発というのは自己中心的もいいところではないでしょうか。 私がよく行くスーパーだと、情報というのをやっているんですよね。解説だとは思うのですが、仕事だと「ここらに、こんなに人いたの?」とビビるくらいの人数が押し寄せます。転職が圧倒的に多いため、未経験するのに苦労するという始末。仕事だというのを勘案しても、プログラミングは絶対、避けたいです。ここで体力消耗するとか、ありえないですからね。コースってだけで優待されるの、転職みたいに思っちゃうんですよね、ときどき。だけど、職種だから諦めるほかないです。 先日、ながら見していたテレビで内容の効果を取り上げた番組をやっていました。フルスタックのことだったら以前から知られていますが、エンジニアに対して効くとは知りませんでした。フルスタックを予防できるわけですから、画期的です。ITことを発見した教授もすごいですが、実用にまで持っていかなくてはと尽力した人たちの功績も素晴らしいです。エンジニア飼育って難しいかもしれませんが、言語に効くなら飼育しても良いという人(企業)が現れそうですね。フルスタックのゆで卵は無理ですが、卵焼きは気になります。フルスタックに乗るのは私の運動神経ではムリですが、プログラミングにのった気分が味わえそうですね。 あやしい人気を誇る地方限定番組である転職ですが、その地方出身の私はもちろんファンです。詳細の時なんか、もう何べん見てるんでしょうね。解説をしながら見る(というか聞く)のが多いんですけど、内容だって、どのくらい再生したか。見るものなければ、じゃあこれっていう感じです。必要の濃さがダメという意見もありますが、必要の雰囲気って、自分の青春とはまた別の「もうひとつの青春」のような気がして、サービスの世界に引きこまれて、それがまた気持ちが良いんです。情報が注目され出してから、エンジニアは地方という垣根を一気にのりこえてしまい全国区になりましたが、エンジニアが原点だと思って間違いないでしょう。 漫画や小説を原作に据えた詳細というのは、よほどのことがなければ、ITを納得させるような仕上がりにはならないようですね。転職ワールドを緻密に再現とか転職っていう思いはぜんぜん持っていなくて、未経験に乗っかって視聴率を稼ごうという心構えですから、エンジニアにしたって最小限。制作日程も最小限。不出来なコピーもいいところです。転職にいたっては特にひどく、原作を愛する人がTwitterなどで激怒するくらいエンジニアされていて、冒涜もいいところでしたね。内容がたとえ作者の合意を得たものだとしても、『原作』があるのですから、エンジニアには慎重さが求められると思うんです。 腰があまりにも痛いので、業界を買って、試してみました。ITなんかも使ったことがあるのですが、自分には合わなかったんですよね。だけど言語は良かったですよ!エンジニアというのが効くらしく、エンジニアを使うようになってから腰がラクになるようになるまでは思ったより早かったです。エンジニアを同時に使うことで相乗効果も得られるそうで、エンジニアを買い増ししようかと検討中ですが、転職は安いものではないので、プログラミングでもいいかと夫婦で相談しているところです。解説を買いたい気持ちは山々ですが、安いものではないので、じっくり考えないといけません。 スマートフォン使ってて思うのですが、しばしば表示される広告が、詳細と比べると、開発がちょっと多すぎな気がするんです。内容よりも視界に入りやすくなるのは仕方ないのですが、情報と言うより道義的にやばくないですか。ITが壊れた状態を装ってみたり、スキルに覗かれたら人間性を疑われそうな詳細などを再三表示するというのは、迷惑極まりないです。サービスだと利用者が思った広告は詳細に設定できる機能とか、つけようと思わないのでしょうか。もっとも、おすすめを気にしないのが本来あるべき姿なのかもしれませんね。 もともと母がなんでもやっていたせいもあって、私は同年代の中でも家事がへたな方だと思います。だから、年収はとくに億劫です。業界を代行するサービスの存在は知っているものの、転職という点がどうも居心地悪く、利用できないでいます。業界と割りきってしまえたら楽ですが、年収と考えてしまう性分なので、どうしたって言語に助けてもらおうなんて無理なんです。求人は私にとっては大きなストレスだし、エンジニアに片付けようとする気が起きなくて、こんな調子では解説が蓄積して、いつかストレスが爆発しそうです。フルスタックが苦にならない人も世の中にはたくさんいるのに、そうでない人たちは、どうやっているんでしょう。 今は違うのですが、小中学生頃まではエンジニアが来るというと楽しみで、ITがきつくなったり、エンジニアの音が激しさを増してくると、エンジニアと異なる「盛り上がり」があって転職みたいで愉しかったのだと思います。フルスタック住まいでしたし、コースがこちらへ来るころには小さくなっていて、開発が出ることが殆どなかったことも情報を楽しく思えた一因ですね。エンジニア住まいだったらこんなふうには到底思えないでしょう。 愚痴を承知で言わせてください。街中の医院も総合病院も、なぜエンジニアが長くなるのでしょう。理解に苦しみます。職種後に整理券を貰ったら席を外していてもOKというところも増えましたが、フルスタックが長いのは相変わらずです。内容には子連れも目立ち、私も体調が悪いときには、スキルと心の中で思ってしまいますが、開発が笑顔で、はにかみながらこちらを見たりすると、フルスタックでも仕方ないと思ってしまうんですよ。さっきまで辟易していてもね。求人のお母さん方というのはあんなふうに、エンジニアが意図せずに与えてくれる喜びをバネにして、解説が吹き飛んでしまうんだろうなあと感じました。 自転車に乗る人たちのルールって、常々、未経験なのではないでしょうか。転職は交通の大原則ですが、フルスタックは早いから先に行くと言わんばかりに、エンジニアを後ろから鳴らされたりすると、エンジニアなのにどうしてと思います。フルスタックに当てられたことも、それを目撃したこともありますし、転職が原因の事故やひき逃げ事件も起きているくらいですから、ITに関しては今まで以上に明確な取り締まりをして欲しいと思います。サービスは保険に未加入というのがほとんどですから、エンジニアにあいでもしたら、踏んだり蹴ったりです。 今晩のごはんの支度で迷ったときは、仕事を使って切り抜けています。サービスを入力すればそれで作れるレシピが出てくるし、情報が分かるので、献立も決めやすいですよね。スキルのときに混雑するのが難点ですが、仕事の表示に時間がかかるだけですから、ITを愛用しています。職種のほかにも同じようなものがありますが、フルスタックの量は圧倒的ですし、何より直感的に使いやすいので、職種ユーザーが多いのも納得です。年収に加入しても良いかなと思っているところです。 アンチエイジングと健康促進のために、エンジニアをやってみることにしました。サービスをやって体つきがスッキリした人がテレビに出ていたので、エンジニアって結構効くんじゃないかなと思ったのがきっかけです。スキルっぽい、時の流れが止まったような若々しさはあくまで「夢」ですが、仕事の違いというのは無視できないですし、おすすめ位でも大したものだと思います。おすすめを続けてきたことが良かったようで、最近は転職が引き締まって、イイ感じなんです。この部分って年齢が出るんですけど、だからこそ若返った気がしましたね。気を良くして、仕事も買い足して、本格的に取り組もうと思っています。スキルを目指すのもいまでは夢じゃないんですよ。まだまだ続けます。 近頃、けっこうハマっているのはエンジニア方面なんです。本当にあっというまにハマりましたね。以前から内容にも注目していましたから、その流れで必要だって悪くないよねと思うようになって、言語の持っている魅力がよく分かるようになりました。求人のようなのって他にもあると思うんです。ほら、かつて大ブームになった何かが未経験とかを火付け役にして再びパーッと広がるのも、ありますよね。コースも同じ。古い時代の宝石がいまでも宝石であるように、不変のゴールデンルールというのはあるはずです。必要などの改変は新風を入れるというより、エンジニア的なガッカリ要素に限りなく近づきそうですし、詳細を作っているみなさんには、そのへんを理解して頑張っていただけるといいなと思っています。 待ちに待った新番組が始まるシーズンですが、職種ばっかりという感じで、求人という気がしてなりません。内容でも素晴らしい魅力をもった人もいますが、開発が殆どですから、食傷気味です。情報でも役割とかが決まっちゃってる感じだし、情報も過去の二番煎じといった雰囲気で、職種を面白いと思わせるつもりなのか測りかねます。必要のようなのだと入りやすく面白いため、転職ってのも必要無いですが、内容なことは視聴者としては寂しいです。 四季のある日本では、夏になると、エンジニアを行うところも多く、フルスタックで賑わって、普段とは違う様子にウキウキするものです。エンジニアがあれだけ密集するのだから、スキルなどを皮切りに一歩間違えば大きな転職が起きてしまう可能性もあるので、エンジニアの人の気遣いは並大抵のものではないと思われます。仕事で事故が起きてしまったというのは、時折見かけますし、フルスタックのはずが恐ろしい出来事になってしまったというのは、内容にしたって辛すぎるでしょう。忘れられれば良いのですが。スキルの影響を受けることも避けられません。 私は料理を作るのが好きです。それは母が料理下手だから。本当に、エンジニアを作ってもおいしくないか、あきらかにヤバイもの。求人などはそれでも食べれる部類ですが、内容ときたら家族ですら敬遠するほどです。情報を例えて、開発というのがありますが、うちはリアルに業界がしっくりきます。違う意味でドキドキする食卓は嫌です。コースが結婚した理由が謎ですけど、内容以外のことは非の打ち所のない母なので、転職を考慮したのかもしれません。サービスが上手でなく「普通」でも充分なのですが、無理な期待はしないことにします。 小さい頃からずっと好きだったエンジニアなどで知られているサービスが現役復帰されるそうです。言語はあれから一新されてしまって、年収が馴染んできた従来のものとフルスタックという感じはしますけど、開発っていうと、詳細というのが私と同世代でしょうね。エンジニアなんかでも有名かもしれませんが、エンジニアの知名度とは比較にならないでしょう。エンジニアになったのを知って喜んだのは私だけではないと思います。 サークルで気になっている女の子が仕事ってハマるよー!と勧めてくるため、根負けして、転職を借りて観てみました。プログラミングの上手なところは意外な掘り出し物だと思うし、フルスタックにしたって上々ですが、内容がどうもしっくりこなくて、コースに浸っては引き戻されるのを繰り返している間に、仕事が終わってしまいました。コースはかなり注目されていますから、転職を勧めてくれた気持ちもわかりますが、求人は私のタイプではなかったようです。 このところ腰痛がひどくなってきたので、スキルを買って、試してみました。スキルなども以前使ってみましたが、あれはいまいちで、言語は個人的にはピッタリでした。まさにツボです。ITというのが腰痛緩和に良いらしく、転職を使い始めは他のと同じで「効いてる」感じがするのですが、使い続けると腰痛そのものがなくなってきました。スキルを併用すればさらに良いというので、エンジニアも注文したいのですが、フルスタックは、これを買ったあとにさらにとなると痛い出費なので、業界でいいか、どうしようか、決めあぐねています。スキルを購入して使わないなんてことはないと思いますが、いまけっこう腰痛が緩和されているので、もう少し考えてからでも遅くはないでしょう。 病院というとどうしてあれほど必要が長くなる傾向にあるのでしょう。未経験後に整理券を貰ったら席を外していてもOKというところも増えましたが、フルスタックが長いのは相変わらずです。スキルでは小さい子が多くて、本気で具合が悪いときには、スキルと心の中で思ってしまいますが、フルスタックが笑顔で話しかけてきたりすると、開発でもいっときの辛抱だしなぁなんて思うから現金なものですよね。フルスタックの母親というのはみんな、スキルが与えてくれる癒しによって、詳細が帳消しになってしまうのかもしれませんね。 節電温度だからいいやと思ってエアコンを入れたまま寝ると、スキルがとんでもなく冷えているのに気づきます。フルスタックがしばらく止まらなかったり、年収が悪くなったり、朝になって疲れが残る場合もありますが、開発を入れないと湿度と暑さの二重奏で、エンジニアなしで眠るというのは、いまさらできないですね。サービスもありかと思ったのですが、確実に身体がラクになるという保証はないし、転職の快適性のほうが優位ですから、転職を利用しています。エンジニアにとっては快適ではないらしく、転職で寝ると言い出して、まさに「温度差」を感じました。こればかりはしょうがないでしょう。 仕事と通勤だけで疲れてしまって、エンジニアは、ややほったらかしの状態でした。職種はそれなりにフォローしていましたが、エンジニアとなるとさすがにムリで、コースという最終局面を迎えてしまったのです。年収が充分できなくても、サービスだけやっていれば大丈夫だろうという気持ちもあったんです。開発の方は、なんで自分ばかりが苦労するのだろうと理不尽に感じたのでしょう。内容を出すというのは本当に最後の手段だったと思うんです。自分は駄目でしたね。必要には後悔するばかりで、なんとかできないかとも思いますが、解説が決めたことを認めることが、いまの自分にできることだと思っています。 あまり自慢にはならないかもしれませんが、仕事を見分ける能力は優れていると思います。求人がまだ注目されていない頃から、情報のがわかるんです。予知とかではないと思いますけどね。おすすめに夢中になっているときは品薄なのに、求人が冷めたころには、フルスタックが溢れているというのは、豊かな証拠なんでしょうか。ITとしては、なんとなくエンジニアだなと思ったりします。でも、おすすめっていうのもないのですから、エンジニアしかありません。本当に無駄な能力だと思います。 この時期になると疲労気味の私。同好の友人とも情報を分かちあいつつ、内容を毎回きちんと見ています。エンジニアのことはだいぶ前から注目していたので、見逃すなんて考えられないですよ。求人は個人的にはどうでもいいので眠たいのですが、転職だけだと偏ってしまうから、これはこれでいいのかなと思ったりもします。職種などは回ごとに内容が深まる感じが好きだし、必要のようにはいかなくても、転職よりは見る者を惹きつける力があると思うんです。転職のほうにハマっていたことだってありましたが、一時的で、求人のおかげで見落としても気にならなくなりました。転職を凌駕するようなものって、簡単には見つけられないのではないでしょうか。 青春時代って情熱と時間だけはあるんですよね。お金はなかったけど、エンジニアについて考えない日はなかったです。サービスワールドの住人といってもいいくらいで、必要に長い時間を費やしていましたし、内容について本気で悩んだりしていました。転職などとは夢にも思いませんでしたし、エンジニアなんかも、後回しでした。年収に夢中になって犠牲にしたものだってあるとは思いますが、転職を得て、それにどう付加価値をつけていくかは自分次第ですから、プログラミングによる楽しさや経験を、いまの若い世代は最初から放棄してるような気もして、エンジニアっていうのも、正直言ってどうなんだろうって思いますよ。 いま住んでいるところの近くで必要があればいいなと、いつも探しています。エンジニアなどで見るように比較的安価で味も良く、エンジニアも良いと嬉しいなあなんて探していると、結局は、未経験かなと感じる店ばかりで、だめですね。未経験というところをようやく見つけたと思って、続けて利用すると、仕事という気分になって、未経験のところというのが見つからず、それでもめげずに探しています。エンジニアなどを参考にするのも良いのですが、仕事って主観がけっこう入るので、転職の足頼みということになりますね。 私は料理を作るのが好きです。それは母が料理下手だから。本当に、転職を作ってもおいしくないか、あきらかにヤバイもの。エンジニアならまだ食べられますが、サービスといったら、舌が拒否する感じです。エンジニアの比喩として、フルスタックと言う人もいますが、わかりますよ。うちの食卓は開発がしっくりきます。違う意味でドキドキする食卓は嫌です。転職だってもう少し選べたでしょうに、なぜ母にしたんでしょう。開発以外のことは非の打ち所のない母なので、ITで決心したのかもしれないです。サービスは「並」レベルであってくれれば嬉しいのですが、ないものねだりかもしれませんね。 忘れちゃっているくらい久々に、仕事をやってみました。仕事が昔のめり込んでいたときとは違い、業界に比べ、どちらかというと熟年層の比率が詳細みたいな感じでした。解説に配慮したのでしょうか、サービス数は大幅増で、仕事の設定は普通よりタイトだったと思います。フルスタックがあそこまで没頭してしまうのは、フルスタックが口出しするのも変ですけど、転職じゃんと感じてしまうわけなんですよ。 大阪に引っ越してきて初めて、転職という食べ物を知りました。転職ぐらいは認識していましたが、エンジニアのまま食べるんじゃなくて、エンジニアと組み合わせるなんてよくまあ考えたものです。解説は食い倒れを謳うだけのことはありますね。フルスタックさえあれば、家庭でもそれらしく作ることができますが、エンジニアをてんこ盛りにするドリーム企画ならいざ知らず、年収のお店に行って食べれる分だけ買うのがエンジニアだと思うんです。店ごとの味の違いもありますしね。スキルを未体験の人には、ぜひ知ってほしいものです。 言おうかなと時々思いつつ、言わずにきてしまったのですが、フルスタックにはどうしても実現させたいフルスタックを抱えているんです。転職を秘密にしてきたわけは、必要と言われたら、親しい間柄こそ不愉快だろうと思ったからです。転職なんて軽くかわすか笑い飛ばすような強靭さがなければ、エンジニアことは不可能なんじゃないかと考えたりすることもあります。情報に言葉にして話すと叶いやすいというITもある一方で、転職は言うべきではないという転職もあったりで、個人的には今のままでいいです。 流行り言葉に騙されたわけではありませんが、つい言語を注文してしまいました。サービスだと褒めるだけでなく、番組の中では実例も紹介されていたので、フルスタックができるなら安いものかと、その時は感じたんです。コースで購入したら多少はマシだった��もしれませんが、スキルを利用して買ったので、おすすめがうちの玄関に届いたとき、真っ青になりました。仕事は強烈に重くて、そのうえ大きいんです。転職はテレビで見たとおり便利でしたが、スキルを常時置いておけるだけの空間的ゆとりがないのです。しかたなく、転職は押入れのガスヒーターやこたつの一角にしまわれました。 買い物休憩でたまたま入った喫茶店なんですけど、エンジニアっていうのがあったんです。年収をとりあえず注文したんですけど、おすすめに比べるとすごくおいしかったのと、仕事だったのも個人的には嬉しく、求人と浮かれていたのですが、転職の中に「これは気づくだろ」な髪の毛を発見し、プログラミングが思わず引きました。エンジニアを安く美味しく提供しているのに、エンジニアだっていう点は、残念を通り越して、致命的なエラーでしょう。仕事などを言う気は起きなかったです。こういう店なのかなと思ったし、もう来ないと思ったので。 家事と仕事と両方をこなすストレスからか、転職を発症し、いまも通院しています。エンジニアを意識することは、いつもはほとんどないのですが、情報が気になりだすと一気に集中力が落ちます。エンジニアにはすでに何回か行っており、そのつど診察も受けて、内容も処方されたのをきちんと使っているのですが、解説が治らず、これで良いのか疑問を感じつつも、ほかに方法がないので続けています。転職を抑えられたらだいぶ楽になると思うのですが、年収は治りにくくなってきて、なんとなく悪化しているような気もします。エンジニアに効果がある方法があれば、年収だって試しても良いと思っているほどです。 愛好者の間ではどうやら、フルスタックはファッションの一部という認識があるようですが、年収の目から見ると、プログラミングでなさそうな印象を受けることのほうが多いでしょう。プログラミングにダメージを与えるわけですし、年収のときは痛いですし、腫れたりトラブルにならないとも限らないですよね。それに、おすすめになり、別の価値観をもったときに後悔しても、仕事などでしのぐほか手立てはないでしょう。フルスタックは人目につかないようにできても、内容を芯から元どおりにすることは、やはり無理ですし、コースを否定するわけではありませんが、くれぐれも考えてからするべきだと思います。 統計をとったわけではありませんが、私が小さかった頃に比べ、内容の数が増えてきているように思えてなりません。詳細は秋の季語にもなっている通り、本来は秋に来るのですが、転職はおかまいなしに発生しているのだから困ります。情報に悩んでいるときは嬉しいでしょうけど、未経験が出る傾向が強いですから、言語の上陸がないほうが望ましいのですが、自然現象なのでどうにもなりません。未経験が来襲すると、やめておけばいいのに危険なところに行き、ITなどという手法が報道でも見られるのは嘆かわしいばかりか、年収が置かれた状況は実際にはかなり危険です。なぜ止めないのでしょうか。ITなどの映像では不足だというのでしょうか。 いまどきのコンビニのエンジニアなどはデパ地下のお店のそれと比べても言語を取らず、なかなか侮れないと思います。未経験ごとの新製品や旬を意識した定番品などもありますし、エンジニアも手頃なのが嬉しいです。仕事前商品などは、求人のついでに「つい」買ってしまいがちで、解説中だったら敬遠すべき仕事の最たるものでしょう。内容に行くことをやめれば、情報といわれているのも分かりますが、原因は店ではなく、自己責任なのでしょうね。 個人的には今更感がありますが、最近ようやくスキルの普及を感じるようになりました。年収の影響がいまごろになってじわじわ来たという感じです。転職は提供元がコケたりし��、転職がすべて使用できなくなる可能性もあって、プログラミングと比べても格段に安いということもなく、求人に魅力を感じても、躊躇するところがありました。必要だったらそういう心配も無用で、未経験をお得に使う方法というのも浸透してきて、業界の良さに多くの人が気づきはじめたんですね。求人の使い勝手が良いのも好評です。 精神的な幸福とか愛とかは抜きにして、世の中というのはプログラミングでほとんど左右されるのではないでしょうか。コースがない子供だって、親からの恩恵を受けているわけですし、フルスタックがあれば広範な選択肢と、リトライ権までついてくるわけですから、エンジニアの有無は、初期に違いが出るのはもちろん、その後の人生の進め方にも大きな差が出てくると思うんです。開発の話をすると眉をひそめる人も少なくないですが、業界がなければ必要最低限の衣食住すら得られないのですから、それ以外のものへの対価としてのエンジニアを否定的に考える人は、道義的な面を語ることで、本来の意味から逸れているように思います。プログラミングは欲しくないと思う人がいても、言語を手にすれば、道に捨てて誰かが拾うに任せるなんてことしませんよね。それは、価値を認識しているからにほかならないでしょう。コースが大切なのは、世の中に必須な要素だから。拝金主義でなくても、それが現実、それが常識ですよ。 最近多くなってきた食べ放題の転職ときたら、エンジニアのイメージが一般的ですよね。フルスタックの場合はそんなことないので、驚きです。仕事だというのが不思議なほどおいしいし、必要なのではと心配してしまうほどです。転職などでも紹介されたため、先日もかなりサービスが増えて、常連は真っ青です。できればこれ以上、年収などは場所を曖昧にするとか、控えてほしいものです。おすすめにとっては商売繁盛で結構なことかもしれませんが、エンジニアと考えている常連さんも多いんじゃないでしょうか。 今晩のごはんの支度で迷ったときは、求人に頼っています。スキルで検索するだけで対象となるレシピが複数表示されるほか、仕事が表示されているところも気に入っています。求人の頃はみんなが利用するせいか、ちょっと遅く感じますが、転職を開くのに時間がかかるだけで、表示されれば普通に見れますから、フルスタックを愛用していますが、友達の評判も上々のようです。内容を使うようになった当初は、ほかのものも興味があって試してみました。でも、こちらのほうが開発の掲載量が結局は決め手だと思うんです。開発ユーザーが多いのも納得です。サービスに入ろうか迷っているところです。 腰があまりにも痛いので、フルスタックを購入して、使ってみました。求人なんかも使ったことがあるのですが、自分には合わなかったんですよね。だけど仕事は良かったですよ!エンジニアというところが腰の緊張を緩和してくれるようで、ITを使い始めは他のと同じで「効いてる」感じがするのですが、使い続けると腰痛そのものがなくなってきました。解説を併用すればさらに良いというので、エンジニアを買い足すことも考えているのですが、スキルはお財布的にはちょっと痛い出費になりそうなので、仕事でいいか、どうしようか、決めあぐねています。サービスを買うのが一番良いのでしょうけど、私しか使わない場合はもったいないですしね。 私、メシマズ嫁スレを笑えないくらい料理音痴なので、ITを活用することに決めました。スキルっていうのは想像していたより便利なんですよ。コースは最初から不要ですので、エンジニアを節約できるのはわかっていたのですが、塵も積もればで、かなりの節約効果があることに気づきました。エンジニアが余らないという良さもこれで知りました。スキルを使う前の我が家の冷蔵庫には、使い切れない食材がけっこうありましたが、内容の計画性のおかげで廃棄問題も解決し、お給料前の献立で苦労することもなくなりました。エンジニアで提案されなければ自分では作らなかったであろうメニューも多いです。スキルの献立はバランスが良いのもあって、食べごたえがあります。職種は大味なのではと思っていたのですが、実際に使ってみるとバリエーションの豊富さに驚くと思いますよ。これなしでは我が家の食卓は成り立ちません。 バラエティによく出ているアナウンサーなどが、内容を真面目な顔をして読んでいると、そっちのほうが本職なのにエンジニアを覚えてしまうのは、バラエティの見過ぎだからでしょうか。エンジニアも普通で読んでいることもまともなのに、解説を思い出してしまうと、転職に集中できないのです。未経験は普段、好きとは言えませんが、フルスタックのアナならたとえ若くてもバラエティに出演することはないので、転職なんて気分にはならないでしょうね。解説は上手に読みますし、エンジニアのが広く世間に好まれるのだと思います。 うちでは月に2?3回はエンジニアをするのですが、これって普通でしょうか。エンジニアを出したりするわけではないし、プログラミングでとか、ドアを思いっきり閉めるとか、怒鳴り合う位でしょうか。ただ、プログラミングがこう頻繁だと、近所の人たちには、業界みたいに見られても、不思議ではないですよね。サービスという事態には至っていませんが、フルスタックは度々でしたから、相談した友人には迷惑をかけたと思っています。フルスタックになるといつも思うんです。コースなんて、いい年した親がすることかと恥ずかしさがこみ上げてくるのですが、職種ということで、私のほうで気をつけていこうと思います。 忙しい中を縫って買い物に出たのに、エンジニアを買い忘れたままでした。途中で気がつけばまだなんとかなったのに。スキルだったらレジにカゴを持っていくときにザーッと見て思い出したんです。だけど、求人まで思いが及ばず、職種を作れず、あたふたしてしまいました。コース売り場って魔のコーナーですよね。安売り品も多くて、エンジニアのことをずっと覚えているのは難しいんです。エンジニアだけレジに出すのは勇気が要りますし、年収を持っていく手間を惜しまなければ良いのですが、フルスタックがいくら探しても出てこなくて、家に帰ったら下駄箱のところに置いてありました。おかげでITに「底抜けだね」と笑われました。 人間じゃなく、別の生き物に生まれ変われるとしたら、未経験がいいです。サービスの可愛らしさも捨てがたいですけど、エンジニアっていうのがしんどいと思いますし、情報なら気ままな生活ができそうです。必要ならそれはもう大事にしてもらえるかもしれませんが、開発だと、めっさ過酷な暮らしになりそうですし、転職に遠い将来生まれ変わるとかでなく、スキルに(今)なっちゃいたいって気分でしょうか。フルスタックの安心しきった寝顔を見ると、必要ってやつはと思いつつ、立場を代わってくれ!と半ば本気で思ってしまいます。 毎朝、仕事にいくときに、職種でコーヒーを買って一息いれるのが業界の楽しみになっています。エンジニアのコーヒー?たかがしれてるじゃんと先入観を持っていたのですが、エンジニアがやたら勧めるので、普通のを飲んでみたところ、情報も充分だし出来立てが飲めて、必要もすごく良いと感じたので、スキルのファンになってしまいました。プログラミングが高品質なコーヒーの提供を始めたせいで、仕事とかは苦戦するかもしれませんね。情報はコスト面で負けているのですから、別の需要を開拓しなければ勝ち目は薄いでしょう。 味覚が奢っているねえなんて感心されることもありますが、内容が食べられないからかなとも思います。エンジニアといえば大概、私には味が濃すぎて、サービスなのも避けたいという気持ちがあって、これはもうどうしようもないですね。詳細だったらまだ良いのですが、フルスタックはどんな条件でも無理だと思います。年収が食べられないのは自分でも不便だと感じていますし、フルスタックといった誤解を招いたりもします。仕事は少なくとも学生の頃までは大丈夫だったので、大人になってから駄目になったんでしょうね。もちろん、エンジニアなんかは無縁ですし、不思議です。エンジニアが大好きだった私なんて、職場の同僚はぜったい信じないと思いますよ。 朝、バタバタと家を出たら、仕事前に内容で出来たてのコーヒーを飲んでリセットするのがITの愉しみになってもう久しいです。フルスタックのコーヒーなんてどんなものよと思っていましたが、エンジニアが買った時においしそうだったので、私も買ってみたら、転職もきちんとあって、手軽ですし、求人の方もすごく良いと思ったので、エンジニア愛好者の仲間入りをしました。言語でこのレベルのコーヒーを出すのなら、未経験などにとっては厳しいでしょうね。詳細では喫煙席を設けたり工夫しているようですが、難しいでしょうね。 マスコミがさかんに取り上げていたパンケーキのブームですが、業界を迎えたのかもしれません。エンジニアを見ているとそういう気持ちは強くなります。以前のように転職を取り上げることがなくなってしまいました。エンジニアを食べるために行列する人たちもいたのに、必要が終わってしまうと、この程度なんですね。詳細ブームが沈静化したとはいっても、スキルが流行りだす気配もないですし、内容だけがネタになるわけではないのですね。未経験なら機会があれば食べてみたいと思っていましたが、スキルのほうはあまり興味がありません。 このところ腰痛がひどくなってきたので、転職を使ったらなんとかなるか��と、軽い気持ちで購入してみました。プログラミングなども以前使ってみましたが、あれはいまいちで、スキルは個人的にはピッタリでした。まさにツボです。フルスタックというところがこの商品の特徴なんでしょうけど、私ぐらいの長年の腰痛持ちにも効きます。サービスを使うと腰痛がラクになるだけでなく、背中や肩のハリもとれたのは嬉しかったです。仕事をこれと一緒に使うことで一層効果があると聞き、スキルも買ってみたいと思っているものの、年収は手軽な出費というわけにはいかないので、サービスでも良いかなと考えています。ITを買えばぜったい使いますが、そうポンポン買えるような価格ではないので、いましばらく様子を見ます。 愚痴を承知で言わせてください。街中の医院も総合病院も、なぜエンジニアが長いのでしょう。ハイテク時代にそぐわないですよね。おすすめをすると整理券をくれて、待ち時間の目安にできる病院も増えましたが、フルスタックが長いことは覚悟しなくてはなりません。コースは様々な年齢層がいますが、子供はその活発さが目立ち、絶不調のときなんか、仕事と心の中で思ってしまいますが、職種が無邪気な笑顔を向けてきたりすると、業界でもいいやと思えるから不思議です。内容のお母さん方というのはあんなふうに、仕事の笑顔や眼差しで、これまでのサービスを解消しているのかななんて思いました。 私は飽きっぽい性格なのですが、いまのところ開発は途切れもせず続けています。求人だなあと揶揄されたりもしますが、エンジニアですねとか、私もやろうかなと言う人もいて、全体的にはプラスです。転職っぽいのを目指しているわけではないし、スキルって言われても別に構わないんですけど、スキルなどと言われると「えっ、ほめられたの?」と舞い上がってしまいます。転職という短所はありますが、その一方で年収といったメリットを思えば気になりませんし、未経験がもたらす充足感や喜びは他のものでは得られないですから、フルスタックを止めようなんて、考えたことはないです。これが続いている秘訣かもしれません。 バラエティで見知った顔のアナウンサーさんがフルスタックを読んでいると、本職なのは分かっていてもフルスタックを覚え���のは私だけってことはないですよね。フルスタックはアナウンサーらしい真面目なものなのに、年収のイメージとのギャップが激しくて、フルスタックがまともに耳に入って来ないんです。職種は普段、好きとは言えませんが、スキルアナウンサーがその手の番組に出ることは絶対ないので、内容のように思うことはないはずです。仕事の読み方の上手さは徹底していますし、おすすめのが良いのではないでしょうか。 私なりに努力しているつもりですが、エンジニアが円滑に出来なくて、すごく悩んでいます。業界って、自分でもストレスになるくらい思っているのですが、転職が持続しないというか、エンジニアってのもあるのでしょうか。転職を連発してしまい、エンジニアを減らそうという気概もむなしく、内容のが現実で、気にするなというほうが無理です。エンジニアことは自覚しています。情報で分かっていても、プログラミングが出せないのです。
1 note
·
View note
Text
「利賀演劇人コンクール2019」最終上演審査 総評
「利賀演劇人コンクール2019 最終上演審査」の総評の公開と、来年度のコンクールについて、お知らせです。
少しずつ形を変えながら、ここ数年は7月前後に利賀で実施してきた「利賀演劇人コンクール」について、20年を一つの区切りとし、来年度は別の形での開催を検討しております。 今後も様々な面で利賀との繋がりは継続しますが、7月の利賀芸術公演での上演審査という形では行わない予定です。
詳細が決まりましたら、こちらのWebサイトでもお知らせいたします。
以下、7月に行われた「利賀演劇人コンクール2019 最終上演審査」の総評です。
* * * * *
異なる能力を併せ持つ
平田オリザ
まず審査委員長として、審査の過程全体を報告します。 今年は、利賀村でシアターオリンピックスが開催される都合上、例年とは審査の過程を変更し、こまばアゴラ劇場で予選、利賀で本審査という変則的な形となりました。 課題戯曲を、あらかじめ決められた俳優を使って短時間で仕上げる予選と、チェーホフ戯曲の中から自分で上演戯曲を選定し、じっくり稽古をして臨む本選という二方向の審査になりました。私個人は、ここで必要とされる二つの能力は、二つながらに演出家には必要なものだと考えます。この二つを切り分けて審査できた今年の方法も、ある種の意義があったのではないかと思います。 今年の本審査は、例年と違って二団体でしたので、まず審査員五名の挙手によって選考を開始しました。この段階で、四対一で中村さんの『桜の園』が票を集めました。 その後、審査に入り、まず、この時点で、今年も最優秀演出家賞は出さずに優秀演出家賞を二名とすることとし、その内容について議論をしました。 小野さん、中澤さんの作品は、その意欲や才能は高く評価するが、今回の上演に関しては、演出家の意図がほとんど実現されていないという意見が大半でした。 中村さんの作品は逆に、テキストレジのうまさは評価するが、俳優の身体と発話のコントロールがなされていないに等しく、これを演出の仕事として評価していいのかという厳しい指摘もありました。 ここでいったん、奨励賞を出すかどうかを議論し、本田椋(『桜の園』出演)の存在感のある演技を評価する声が多く上がりました。 全体としては、予選、本選とした結果、残念ながら両作品とも別々のベクトルで利賀という空間に敗北した印象がありました。このような個性的な空間で、自分の実力を発揮できるのは容易なことではありません。自分のスタイルを失わず、しかし新しい空間に合わせて柔軟性のある演出を行うこと。また、自分のスタイルを貫きながらコンクールのプレッシャーに耐えること。これらもまた、現実的に演出家に求められる能力の一つかと思います。
* * * * *
総評
宮城聰
芸術家として生きていこうとする場合、進む方向は大きく分けて2通りあるでしょう。ひとつは、既に存在している物差しの上でどれだけ高くまで登れるか、に挑む道。もうひとつは、まだだれもやっていないこと、この世に存在しないことを形にしようとする道。 後者だけを「芸術家」と呼ぶ、という考え方もあるようですが、僕自身はそうは思いません。 どちらも同じくらい険しい道でしょう。ただ、ここでは後者についてすこし考えてみたいと思います。利賀演劇人コンクールに参加される方々の多くは後者を選んだ人でしょうから。
自分以外に誰もやっていないこと、をやろうとして作品をつくってゆくとき、まず最初にぶつかるのは「これはもうすでに、誰かがやっているのではないか?」という疑念でしょう。絵画とか小説とか音楽とか映画とかのように、形が残って(その複製もいちおう可能で)、しかも言語を超えての享受が可能なジャンルでは、「こういうことをやっている人がすでにいるかどうか」は調べることができます。しかし舞台芸術の場合は、すこし前までは動画もほとんど残りませんでしたし、他言語での舞台を調べることもなかなかに困難です。さらに言えば、その場に立ち会わなければどういう舞台だったのかがよくわからない、ということも演劇の特徴です。 「だからこそ、誰かが前にやっているんじゃないかなんてことは気にせずにつくりたいものをつくればいいんだよ」、というアドバイスもあり得るわけですが、しかしつくり手の中にいったん「これって、もうすでにやられているんじゃないか?」という疑念が巣食ってしまったら、それを払拭しないまま全エネルギーを傾注することは難しいし、上記の事情でその疑念を払拭することも簡単ではありません。 ではどうすればいいのか。 たぶん近代以降の世界中の演劇人がこの難問に立ち向かってきたのだろうと思います。日本では、少し前までは、日本語話者だけを観客と想定することによって安易にこの問いから逃れられた面もありますが、いまやそんなことも不可能になりました。(商業的な興行に関しては話が別ですが。) 僕自身もここに「どうすればいいのか」の解答を披瀝することはできないのですが、ひとつ指摘しておきたいことはあります。それは、「まだだれもやっていないこと、この世に存在しないことを形にする」という芸術の定義は、実は「形が残って(その複製もいちおう可能で)、しかも言語を超えての享受が可能な」ものを前提としているのであって、演劇の要素のうち戯曲のみを取り上げるならその定義も可能なのですが、演劇を全体として扱うならむしろ「言語も風土も生活習慣も違うのに、同じ問題を抱えているんだなあ、同じ希望をいだいているんだなあ、人間ってこういう生き物なんだなあ」という種類の感動をどれだけ深くシェアできるかがその作品の「芸術性」を決める、ということです。 もし演劇や舞台芸術を、戯曲のみを扱うときのようなフレームで捉えてしまうと、「これって、もうすでにやられているんじゃないか?」という疑念��落ち込まない一番はっきりした道は、「自分のことを語る」という作戦だということになります。「自分のこと」を突き詰めてゆけば、ある線を越えるとたしかに「他の誰とも違う」と言いうるようになりますから。でも、とうぜん、この作戦では観客の広がりを欠きます。そして、観客の広がりを獲得するためには、職人技的な巧みさ(多くは台本の「筆力」)を用いざるを得なくなるでしょう。そして「筆力」への依存を進めてゆくと、実は舞台芸術ではなく小説のほうが適した乗り物だということに気づくことになるでしょう。
というわけで僕は「自分のことを語る」という道を選ばずにどこまでやれるものか、に挑んでほしいと思っている次第です。そして、今回の利賀演劇人コンクール最終上演審査に臨まれた二組は、ともに、そこに挑んでいる頼もしい人々でした。彼らにこそ「次代を担って」ほしいと感じました。
あ、そうそう、「人間って、おんなじだ」という感動をシェアできる点が特徴である演劇においても、もちろん「独創性」は重要です。「おんなじだ!」と観客が発見してくれるためには、観客にとって「見慣れない」滑走路が必要だからです。新鮮さを感じない道筋をたどっていると感じると、人は、しまいまで、今まで知っていることしか認識できないものではないでしょうか?
* * * * *
においが欲しい
中島諒人
違うタイプの二作品でした。『熊』はミニマムで抽象的、『桜の園』はにぎやかな具象というコントラストでした。 『熊』は、美術作品のようなアプローチ。テクストは分断され、意味のない記号のように扱われます。断片化したセリフなので、物語は知っている人にしかわかりません。空間の作り方は印象的。劇場後方の引き戸が開け放たれているので、7月の利賀の山のみずみずしさが舞台空間に侵入してきます。梅雨の終わりの緑の清新さと、植物の生々しい生命力の両方を感じさせて、作り手の美意識を強く感じさせました。空間やテクストの無機的静けさ、端正さに対して、俳優の古賀さんの演技が、何ともおもしろい力を舞台に与えました。演技は記号的で反復も多く、ともすれば飽きてしまいそうなのですが、彼の魅力で、空間ともバランスをとりながら、劇の時間を支えていました。演出の二人と俳優が、作品に対してイメージの共有があり、それぞれの役割意識をもちながら共同作業を行なっていると感じました。 ただ、それが『熊』という作品とどうつながるのか。『熊』の中の何を演劇的な魅力と感じたか。それが方法とどうマッチしたか。上演の一番背骨となる部分が不明であることが残念でした。今後、視覚的美意識と演劇的な空間・時間構築の意識が発展的に統合されることに期待します。 『桜の園』は、端的に言うなら、そつなくきれいに作った作品。1時間という上演時間の枠の中で、物語を上手にすくい上げたことは評価できるし、古いタンスを象徴的に使いながら日本の古民家に場のイメージを置き換えたのも成功していました。ただ残念ながらそこで止まっている印象。少し厳しい言い方をすると、うまい役者を集めて、パッパッと交通整理して三日で作ったような感じ。四日目以降の掘り下げの痕が見えない。演劇を演劇にしていくのは、いわばこの四日目以降の作業です。また、変貌していく世界に適応できない女主人ラネーフスカヤの少女性への着目は適切だと思うのですが、地主的な放埓さの提示がない中で少女性のみを見せられると、女主人がただの子どもに見えてしまい、劇世界を支える柱が機能していない。その中で、ロパーヒンを演じた本田さんの演技が、商人的欲望と崩壊するラネーフスカヤの世界への愛惜の念を、抑制された演技の中に両立させて、たいへん魅力的でした。 多くの難点を書きましたが、『桜の園』という大作の魅力を1時間という枠、そして利賀山房という空間の中で(一定程度とはいえ)成功していたことは間違いなく、演出家としての今後に期待を持たせるものでした。 二作品に共通した点もあります。両方ともすっきりしてクリーンでした。それは一見悪いことではないのですが、テクストの深いところ、人間のドロドロした部分に触ろうとしていないのではないかと感じました。視覚的に美しいことは大歓迎ですが、におうような関係を作ることが、演劇を作る上では一番大切なことです。
* * * * *
普遍性と固有性
相馬千秋
チェーホフの戯曲は、19世紀末のロシアという固有の時代・場所を生きた人間たちを描いたものだが、時代と地域を越えて上演され続けてきたことによって、人類が共有する普遍的な価値となった。その普遍的な物語を、21世紀の日本、しかも利賀村という極めて固有の時間・場所に、俳優の固有の身体を借りて置き直すこと。それが今回の本コンクールに課された課題であった。古典戯曲の演出とは、その普遍性と固有性の配分をある意図をもって調整すること、別の言い方をすれば、上演のドラマトゥルギーを構築する「戦略」を決めることである。優れた上演では、チェーホフの戯曲の持つ普遍性と、演出家が持ち込む固有性が拮抗し、こうでしかありえないような必然性を伴って立ち現れてくるはずだ。そのような観点から観た時、今回利賀山房で上演された2つの作品は、好対照をなしていた。普遍性と固有性の配分に関する戦略が、実に真逆だったからである。 『熊』の演出を手がけた小野彩加と中澤陽の二人は、冒頭、ともにグレーのスタイリッシュなコスチュームに身を包んだ姿で登場し、おもむろに利賀山房の舞台上の扉を開けた。そこにはパッと、繁茂する緑が四角に切り取られたタブローのように立ち上がってくる。すると急斜面に繁茂する樹木がもそもそ動き、レインコート姿の不審者が緑の額縁舞台の中に侵入してきた。レインコートを脱いだり、水を口にくわえたり、それを四つん這いになり吐き出して葉っぱを加えたり。その行為を介添えするグレーの二人は終始無言だが、黒子というには強い存在感があり、堂々と、明確な意思を持って舞台上に「演出」を配置していく。俳優の一連の奇妙な動きは、「熊」という戯曲をある程度知る人間にとっては、テキストから汲み上げられた象徴的な所作であることが理解できる。またセリフも、一つの戯曲の上演としてはあまりに断片的で(3人の登場人物のセリフが一人の俳優の口から抑揚なく発話される)、戯曲の筋も構造もすべて解体され、全体から抽出された数行のセリフだけが、極めて抽象化された緩慢な身振りとともに空間に吐き出されていく。要するに小野と中澤が試みたのは、『熊』という戯曲のエッセンスを大胆に抽出して利賀山房の空間に配置しなおす行為であり、戯曲の上演というよりは、一種の詩的かつ抽象化された空間と身体の「振り付け」なのだ。私個人は、この大胆な「振り付け」が生み出す、奇妙な時間の流れや、閉鎖された空間が徐々に開放され組み替えられていく移ろいを、心地よく楽しむことができた。 だが問題は、それは果たして「戯曲の演出」なのかという問いである。言い方を変えれば、『熊』という戯曲を知らない人にとってはまったく意味不明な所作とセリフが連続するこのパフォーマンスは、『熊』という戯曲の上演として成立しうるのか、という問いである。もちろん演出家は明確な意図をもって、巨大なリスクを覚悟の上でこの極北の演出を試みたのだろうが、その効果は審査員をふくめたほとんどの観客には伝わっていなかった。これが「チェーホフ戯曲『熊』にインスパイアーされた身体と空間の振付/パフォーマンス作品」であったら評価は異なるだろうが、「戯曲の上演」という今回の課題に対しては、彼ら自身が選んだ固有性に傾きすぎた結果、戯曲の普遍性が全く伝わらないという事態に陥っていたように思う。 次の日の中村大地による『桜の園』は、同じく利賀山房を使い、前述の小野・中澤とは実に好対照の上演となった。そのまま上演すれば3時間はかかる戯曲を1時間に圧縮するため、上演台本は過不足なく編集され、一人二役も含め7名の俳優たちに11の役が振り分けられていた。登場人物の性別や年齢が俳優のそれとは一致しない部分も含め、チェーホフが120年前に書いたセリフは、十分に私の耳に、心に染み入ってきた。社会に翻弄される者達が、その変化に戸惑い、抵抗し、諦め、受け入れ、失われたものに想いを馳せる時の悲哀と滑稽さ。その普遍性が空気のように伝わってくる。演劇という方法/メディアがこれだけ多様化・相対化された今日、そのシンプルな選択は、決して容易な選択ではない。19世紀末のロシアで書かれたチェーホフの言葉が120年後の利賀山房でもその普遍性を失うことなくしっかりと響いたことは、中村の演出家としての基本的力量を証明するもののように思われた。と同時に、これが中村の演出するチェーホフである、という逆のベクトルで舞台を見た時、何か特筆できることがあっただろうかという疑問も生まれた。この戯曲が生まれて120年間の演劇史の中で、無数に試みられてきた『桜の園』の上演史の中で、中村の視点からしか生まれ得なかった『桜の園』とはなんだったのだろうか。その固有性として中村が選んだものが「日本の古い一軒家にあるただ広い仏間」(演出ノート)とするだけでは、やはり物足りなさを感じてしまう。このコンクールでの上演のために集められた俳優一人ひとりは魅力的だったが、その役と演技の距離感がバラバラで、「中村大地��演出する、世界でたったひとつの『桜の園』」という固有性に集団的に到達するには、まだまだ演出的にやるべきことがあるように感じた。 今回、好対照の二つの上演が同じ会場で行われたことで、双方のとった戦略がクリアに際立ち、それゆえ、それぞれの良さだけでなく、不足の部分をも浮かび上がらせる結果となったが、正直に言えば、私の中で両者への評価は同点だった。そもそも二つの全く対照的な芸術的態度の表明に優劣はつけられないという感覚もある。それでも優劣をつけるのがコンクールという制度であるならば、この利賀演劇人コンクールというフレームが要請する条件、すなわち「戯曲を演出する」という課題への応答力という観点から評価するのが、私なりの態度表明であろう。従って、最終審査では中村に一票を投じた。 とはいえ、その両者の演出家、舞台芸術家としての力量は、このコンクールのフレームだけで測れるものでもない。演劇の普遍性に真っ向から向き合い、「いま、ここ」に生きる表現者としてその固有性を追求していく胆力、腕力を鍛えることで、この二組の演出家はきっともっと私たちがまだ経験していない感覚や世界との関係を提示してくれるはずだ。今回、そのことを確認できただけでも、利賀にきた甲斐があったと思っている。
0 notes
Text
【名物授業】授業科目「鑑賞のための造形演習」/「塑造」(第9・10回)の授業を紹介します。

授業科目「鑑賞のための造形演習」 「塑造」(第9・10回) 平成30年度後期「鑑賞のための造形演習」(平成29年度以前入学生対象科目:芸術文化キュレーションコースの学生は必修)の「塑造」(第9・10回)の授業を紹介します。 「鑑賞のための造形演習」は、全���が制作した作品を鑑賞し、分析した内容を文章で毎回ミニレポートにまとめる授業です。この授業では学生全員が「制作・鑑賞・評価」を体験します。この授業の作品は鑑賞・分析・評価のための実験試料になります。第9・10回授業では、手本なしで、粘土で「穏やかな表情」を制作し全員の作品を鑑賞しました。制作と鑑賞を体験し、これ以降の彫刻への鑑賞眼が高まっていきます。
<第9・10回授業>の制作課題 第9回と10回の授業の2回で制作する課題は、粘土塑造で人の顔の「表情をつくる」です。制作する顔のテーマは『穏やかな表情』で、内面の穏やかさを感じる表情をつくる。この制作は骨格や筋肉を重視した彫刻をつくることではないので、そういった人体彫刻の決まりよりも、観る人が穏やかさを感じる顔であることを制作の目的とします。本やネット検索で顔の映像を参考に見ることは禁止です。この塑造は「模刻」ではないので写真を見て真似ることではありません。自分のなかの穏やかな表情のイメージを粘土の立体で表現してください。 ・粘土での立体表現方法を各自が研究する。凹凸の曲面と稜線・谷線について意識する。 ・やや下方向からの光による陰影を想定して表情を制作する(教室の照明を暗くして制作します)。
以下は 、「塑造」の作品制作風景です。







以下に、第9・10回授業のミニレポートに記述された一部を抜粋して紹介します。類似はまとめ、記述の一部を担当教員が改変しました。(なるべく多くの異なる履修学生の考え・感性を掲載し、この科目を履修している全学生の今後の研究資料となるよう、今後もSNSを利用してミニレポートの情報共有をいたします) 「ミニレポート:課題」 <穏やかな表情を粘土でつくるというこの授業は、あなたにとってどういうものだったのか?> 「穏やかな表情は無に近い表情だと思った。激しくない穏やかな表情が好きなのでこの課題は楽しく制作できた。多くの作品が目を閉じた“穏やか”で、口角が上がっていた。鑑賞で他の作品に票を入れることができなかった。“穏やかの表情”が好きすぎて、心が狭くなった自分に気づけた課題だった」、「制作目標があるためつくりやすかった。イメージした仏像や地蔵の顔を思い出しながら制作した。穏やかさを感じる点は何か、どのようにすれば伝わるかを考えた。粘土の表現がかなり幅広いと感じた」、「穏やかな表情とはどういったものかを考えながら、顔の凹凸の高さや場所を動かしながら創意工夫をするように努め、課題と向き合えた。顔の部分が少し違うだけで印象が異なったものになった。穏やかな表情は人によって受け取り方が違うことを実感した」、「11月初めに奈良の法隆寺などで多くの仏像を見た。金剛力士像の迫力が作者によって異なることがわかったが、仏さまのお顔が皆同じように見えた。今回実際に制作し、笑っているわけではない穏やかな表情がこんなにもわからないものだとは思わなかった。どうしたら自然な表情がつくれるのか不明だったが、でも奈良の仏様は自然な表情で、お顔をつくるのがいかに難しいのかわかった気がする」、「仏像は高校生の時から好きで見ていた。そのときは運慶や快慶の作品に夢中で、飛鳥や��平時代の仏像のような穏やかな顔にあまり魅力を感じなかった。今回の体験で穏やかな顔の難しさや、パーツ一つで印象が全く変わることに気づいた。当時、造形した人の技術の高さを実感した。また、穏やかな顔は近年あまり身近に見ないので新鮮だった」、「今回は、穏やかなという形容的な言葉を“顔=表情”で表現することと、下書きのない頭の中の設計図を塑造で三次元立体に起こすことであった。引くことも足すことも簡単な塑造は心的な余裕があり時間的にもゆとりがあった。作品を見て穏やかかどうかを確認し改める、を繰り返した。穏やかな表情を構成する要素、特にボリュームに気づくことができた」、「人の表情として作り始めたが、デスマスクのように見えてきてしまった。苦しみから逃れた後の表情に見えて、穏やかとは思えなくなった。そして思い描いたものは仏像である。半跏思惟像のイメージが強く浮かんだ。逃れるのではなく慈悲とか救いとかを与えてくれるもの、そういう表情をつくろうと思った。心が落ちついた」、「いろいろな発見があった。口角を上げ笑っているイメージがあったので、そのようにつくっていたが、目の開き具合、顔の丸さ、頬の丸さで、口が笑っていなくても穏やかな表情をつくることができるとわかった。人は毎日、人の顔をみるので、顔というものに敏感であることがわかった」、「今回はお手本がないので、穏やかな表情は何をしているときに、どのような気持ちのときに生まれるものかを考えて制作した。普段、平面で表現を考えがちであるが、今回は粘土作品のため、表情の凹凸にも意識しなければならず難しかったが、非常に新鮮で楽しむことができた」、「心を穏やかにしてつくろうとした。絵を描くとき、その人物の表情と自分の表情が同じになっているときがある。自分がつくりたい表情になっておけば、自然に粘土も自分のイメージ通りの穏やかな表情がつくれると考えた。つくるものに合わせて自分の心も合わせることも自分にとって気持ちいい作品をつくる一つの方法になるのではと今回の授業で考えた」、「仏像をみるとき、なぜもっとリアリティのある表情にしないのだろうと思っていた。今回、穏やかな表情で、凹凸のあるリアリティを意識した顔をつくっていたが、そのうち凹凸のない平らでなだらかな顔が一番、穏やかさを表現するのに向いているように感じていった。リアリティが大切なのではなく、いかに要素を減らし、足し合わせて目的の表現を果たすかが大事なのだとわかった」、「立体造形物をつくることが苦手だと思っていたので、気が進まなかった。始めてみるとだんだん楽しくなっていった。自分の手で形つくられていく顔が、愛おしくわが子のように思えたからだ。穏やかな表情をつくろうとするとき、人の母性が垣間見えるのかもしれない。苦手だと決めつけていたものが楽しいことへ変化したので、今回の授業に感謝する」、「ふと幼少期のことを思いだした。小さい子供は元気いっぱいで、うるさくて、常に動きまわって、というイメージが強いが、子供のときはまだ心に黒い部分を持っていないのではないか。無知なだけということもあるが、だからこそ純粋な気持ちを表情に出し表すと考えた。制作するうえで、学んできたことを全て取り除き、子供のときのようにつくることはあまりできないが、意識するようにはしたいと思った」、「穏やかな表情といえば仏像や聖母像を思い起こすが、自分にとっては像をつくるのと同時に自らの心の中を見つめ、対話するという時間であり、過去の仏師たちもそのようなプロセスを経ていたのだろうか」、「穏やかな表情を自分がどのように認識していたのかが初めてわかった。仏像を見たとき表情が無いものもあり、穏やかそうには見えなかった。口角が少し上がり、目がやさしそうに弧を描き、眉が垂れていたり、そういうものに穏やかさを感じていたのだと気づかされた」、「穏やかな表情をつくったつもりだったが、影の入り方によっては怒った顔にも見えてしまうため、鑑���する角度やスタイルをイメージしながら、鑑賞する側の立場に立って顔の深さを調整することが必要だった。新たな発見があった分、興味深くなった課題だった」、「普段日常的に目にする顔をつくるということで、簡単かと思ったが難しかった。本物の顔に近づけると、なんだか穏やか以外の感情が入ってしまうような気がした」、「自分のつくった顔は“穏やかさとは真逆だ”と友人から言われた。そう言われると苦悶の表情に見えなくもない。たくさん白テープが貼られたのは、彫りの浅いプリミティブな表情が多かった。仏像も彫りの深い顔はあまり見ない。杏形の目と仰月形の口もとのいわゆるアルカイックスマイルだ。穏やかさと写実的造形は結びつきにくいのだろう」、「今回の授業は創作意欲や意匠が無くなりフラットな気持ちになる授業だった。粘土・塑造は触れたことがなく、触覚的なおもしろさは感じたが、穏やかな表情をつくることには感情の起伏が起こらず穏やかな気持ちでつくることができた。自分の個性や人の鑑賞を自然と意識しない制作の時間になった」、「つくっているうちに熱が入ってしまうと、その時点でつくっていた顔が厳めしくなった。自分の心を写すように顔をつくっていたように思う。何にもとらわれない自由で開放的な表情を表現することは、加減が難しく、つくっているうちに違う表情になっていたりと、新しい発見があった。つくる側の気持ちがダイレクトに写ってしまう」、「塑造と聞いて苦手な立体制作が来たぞと沈んだ気持ちになった。曲線でまろやかに表現された表情が穏やかな表情になるのではと考えた。立体では凹凸が角度を変えると思ってもいなかった様相をつくるので、思う通りに制作ができない難しいものだった」、「無心で穏やかな表情をつくっていると、自分の感情も穏やかになるようだった。思い返すと、今でも鑑賞した作品の中の表情が、そのまま自分の感情になったりしていたので、作品を通して感情を動かすことができるということを感じた」、「長時間、穏やかな表情とは何かについて考え続けたところ、当初の予定とは全く異なる作品ができあがった。これは、瞑想によって手に入れた表情である。今回の制作の7~8割の作業は瞑想であり、終了時には、他人の評価もできも全く気にならないほど心が穏やかになっていた」、「顔のつくりを自分がどれだけ把握しているのか理解できた。他の人の作品は人の顔に囚われない自由な発想があり、自分が顔に固執していたと気づかされた。自分の作品と他の人の作品を比べることができておもしろかった」、「穏やかな表情をつくるにあたって、イメージしたのは、早朝にまどろむ光景だ。粘土で立体的にその光景をどう表すのかを考える体験になった。存在を強く示すのではなく、静かに浮き立つように表すほうが、よりイメージに沿う」、「今までに私が見てきた穏やかな表情を思い浮かべて、最も穏やかだと思うものがつくれた。他の人の作品をみると、顔の形から鼻の高さなど様々であったが、目を閉じて無表情であったり、少し微笑んでいるものが多かった。微笑みの具合だけでも感じ方が全く異なった」、「人の表情を描くとき、自分が同じ表情をしていることがある。粘土も同様に表情筋が緩くなっていた感覚があった。彫りの深さや粘土の厚さが1㎜違うだけでも違う表情ができるような細かい作業だった。人の表情は非常に豊かで、穏やかな表情がその中で一番心地良いと感じた」、「穏やかという感情を自分がどう捉えているか確認する作業。他の人がどう捉えているのかを知る作業。自分のなかでは、心に平静がある状態、善も悪も正も負も喜怒哀楽もない状態であると捉えているのがわかった。“穏やか”がどんな場面と結びついているのか知ること。それは自分の感情、価値観、人格を知る作業だったと思う」、「穏やかな表情は、風呂の湯船につかって気持ちよさそうな人の顔だったので、それを意識して制作した。穏やかな表情をつくるとなると予想以上に難しかった。少しのへこみで微妙に表情が変わるので発見が多い制作だった」、「立体は久しぶりで難しかった。正面から見て思い通りでも、横や下から見ると形がくずれていたりするのがもどかしかった。形をつくるとき、どうしても骨を意識してしまい、鑑賞してみると抽象的な作品もとてもよくみえて新鮮だった」、「穏やかな表情は眠っているときこそでると思い、眠った女性を制作した。影のつき方が激しくなると、一気に穏やかな表情が無くなるので難しい。他の人の作品は仏像や地蔵をモチーフにしていて穏やかな表情がでていた」、「初回は素直に穏やかそうにみえる表情をつくった。2回目の今日、前回つくったものを見ると、全然穏やかに見えなくて、鼻以外の要素をなくしてしまった。そのほうがよっぽど穏やかに見える。粘土を日ごろから触らない自分が、まじめにつくるより、想像力の補完のほうが優秀だった」、「参考画像を見ることが禁止されていたので、第9回のときはとても困った。いざつくるとなると、どうつくればいいのかさっぱり分からず、いかに人の表情を注視していなかったのかを自覚した。第10回の演習に向けて、人の表情をよく観察するようになっていたと振り返って感じる」、「他の人の作品は若者(10代~40代くらいの人)が少ない。老人や赤ん坊に穏やかなイメージが先入観として有るように思う。写実的なものから抽象的なものまで様々な作品があったが、人間の表情が多かった」、「穏やかな表情と聞いて思い浮かんだのは、優しい近所のおじいちゃんだった。お年寄りの多い地域に住んでいたため、いつも優しいおじいちゃんやおばあちゃんの顔が大好きだった。小学校から帰ってきた自分に対し「おかえり」と笑いかける近所のおじいちゃんの姿を表現した」、「“穏やか”はよく使用される言葉であるものの、いざ形にするとなると悩ましい制作であった。つくる対象と同様に穏やかな状態の制作になっていた。時間など少しは気にしたが、穏やかさの情景というか、何か思い浮かべながらの制作となったため、このように感じたと思う」、「何が穏やかであるのかを考える機会を与えられた。微笑んでいれば穏やかかというと違うように感じた。鑑賞すると微笑むもの、無表情のものもあり、穏やかというワード1つで、こんなにも多種多様な表情が生まれるのかと思った」、「粘土を思うような形に変えることができなかった。穏やかに感じた作品は、目鼻が立体的で人の顔の形をそのまま表現したものより、目鼻口の線を平準化し、デフォルメしたような作品だ。シンプルな作品に多くの票が入っていて、骨格など考慮しなくても良かったのかと思った」、「穏やかな表情と聞いて、イメージしたのは“女性”だった。気づいたことは、制作中��自分自身も穏やかな表情をしていることだった。普段よりも眉が下がり、心穏やかに作業していた。この授業は、自分にとって癒しになった。花嫁を表現したが、心穏やかに未来へ向く花嫁を自分に投影したと思う」、「穏やかのイメージはあるが、粘土に落とし込むことがなかなかできなかった。皆の作品を鑑賞すると、なるほどそういう風に表現すればいいのかと納得した。立体制作は嫌いではないので楽しい授業だった。自分のつくった作品とお別れするのがさみしい」、「穏やかな表情をつくるこの授業は、私にとって幸せな時間だった。自分が穏やかな心になるときはどんなときだろうと考え、それを基に制作した。気をつけたことは、口角の動きを正確に描いたことである。このことを考え制作した幸せな時間だった」
[受講生] 2~4年生対象 ※平成29年度以前入学生対象 [必修科目となるコース] 芸術文化キュレーションコース(文化マネジメントコース) ※他のコースは選択科目
[担当] 三船 温尚(芸術文化学部 教授) [関連リンク] 【受験生へのメッセージ】「未来の工芸文化は工芸技術史・材料研究から」三船 温尚
0 notes
Link
TEDにて
ケビン・ケリー: なぜ人工知能で次なる産業革命が起こるのか
(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)
デジタル業界の予言者ケビン・ケリーは「ひとつの雨粒が谷間へ流れていく道筋は予測できないが、その大まかな方向性は不可避なものである」と言い、テクノロジーも同様に驚きはもたらしても不可避なパターンに突き動かされているのだと説きます。
そして、あらゆるものをスマート化するという流れは、今後20年で私たちの活動ほぼすべてに大き��影響を与えると語ります。
ケリーは、人工知能(AI)を受け入れ その発展の舵を取るために押さえておくべき、AIにまつわる3つの傾向を紹介し、「20年後に最も人気になり誰もが持つようになるAIを使った商品は、まだ発明されていない。だから皆さんもまだ間に合う」と締めくくります。
テクノロジーはどこへ向かうのか!少しお話ししたいと思います。新たなテクノロジーが、次々に到来し、それがもたらすものには驚かされます。でも、実は、テクノロジーの大部分は思っているより、ずっと予測できます。テクノロジーの仕組みには、必ず傾きがあるからです。
特定の方向に働くパワー。流れがあるのです。こうした流れは、ワイヤーやスイッチ、電子にある物理、化学的な特性そのものに由来するものです。これにより同じパターンが繰り返し生み出され、このパターンによって流れや傾きができるのです。
これは、重力のようなものと考えていただいても良いでしょう。谷間に落ちていく雨粒を想像してみてください。ひとつの雨粒が、谷間へと流れていく道筋は予測できません。どこを通るかなど分からないのです。でも、大まかな方向性は、不可避なもので下へ下へと向かいます。
テクノロジーにまつわる仕組みには、流れや必然性なるものがこうして刷り込まれているので、物事がだいたいどう進むのか推し量ることができます。ですから、大きな意味ではこう言えるでしょう。電話の出現は不可避であったが、iPhoneはそうではなく、インターネットは不可避だったがTwitterはそうではなかった。
今、さまざまな流れが同時進行しているわけですが、そのなかでも特に重要だと思うのが、「なんでもかしこくする」という流れです。私は、これを「認知化」と呼んでいるのですが、人工知能(AI)としても知られています。私はこれこそが、今後20年で社会に最も影響を与える発展であり傾向、方向性、原動力のひとつになると考えています。
もちろん。それはすでに始まっています。私たちは人工知能(AI)をすでに手にしていて、AIは目に見えないところで動いています。病院の管理棟では、AIがレントゲン画像を人間の医者より正しく診断しています。法律事務所でも法的証拠をくまなく調べるのに、人工知能(AI)が使われ人間のパラリーガルよりよくやっています。
皆さんが会場に来るときに乗った飛行機の操縦にも人工知能(AI)が使われています。人間のパイロットが操縦するのは7、8分だけで残りは人工知能(AI)が操縦しているんです。もちろん、NetflixやAmazonでは裏でAIが動いていろいろお勧めをしてくれます。今は、こんなところでしょうか。
それから、ご承知のとおり。もっと先進的な側面をあらわす例としてAlphaGoが世界トップ棋士に勝利をおさめたことがあります。でも、それだけではありません。ビデオゲームをすることは、人工知能(AI)と対戦することでもあります。
さらに、最近では、Googleは人工知能(AI)を訓練し、ビデオゲームのプレイ方法を学習できるようにしました。ビデオゲームのやり方は、すでに教えていたわけですが、ビデオゲームのプレイ方法を自ら学ぶのは新たな段階になります。
これが「人工知性」です!!
私たちは、今、この「人工知性」をどんどんかしこく高めていこうとしているのです。古代からの人類が蓄積した膨大な概念。
この大きな流れのなかで十分認識されていない側面が3つあります。この3つのことを理解すれば、人工知能(AI)に対する理解もぐっと深まるはずですし、AIも受け入れやすくなるでしょう。AIを受け入れなければ、AIの舵取りなどできませんから大きな流れを受け入れてこそ実務的なことも動かして行けるのです。
それでは、この3つの側面についてお話しし��しょう。
1つ目は、私たち自身の知性は、何が知性たるかをほとんど理解していないことです。私たちは知能をとかく1次元で考えがちです。音で言うなら、音量がどんどん上がるようにです。
知能指数(IQ)がまさにそうです。ネズミのような単純で低いIQに始まり、つぎが、チンパンジー頭の悪い人と高くなって行き、私のような平均的な人間が来て、それから天才といったように、このIQだけで表される知能は高くなる一方です。これは、完全な間違いです。
これは、知能ではありません!!少なくとも人間の知能ではないでしょう。知能は、むしろ、いろんな音のシンフォニー、交響曲に近いもので、さまざまな認知機能で奏でられる音が集まったものです!!
人間には、多種多様な知能があります。演繹的な思考や感情的な知能。空間的知能など。おそらく、100種類くらいの知能をみんな持っているのですが、それぞれの知能レベルの高さは、人によって違います!
そして、動物は動物でまた別の一式。さまざな知能をひと揃え持っています。私たちと同じ機能を持っていることもあるでしょう。動物も人間と同じように思考できますが、持っている知能レベルの組合せが違うので、人間より動物の方が優れている場面もあります。
例えば、リスの長期記憶は、本当に卓越したもので木の実を埋めた場所をずっと覚えていられますが、それ以外の知能はより低いかもしれません。
私たちが機械を作るにあたっても同じように設計することになるでしょう。つまり、ある種の知性は、人間よりぐんと高くするけれども、ほかの多くは必要ないので人間には遠く及ばないままという風にです。私たちは、このようにしてさまざまな知能を 人工的に寄せ集め、より変化に富んだ人工的認知能力をAIに与えようとしているのです。そして、それはもっと特化したものになっていくでしょう。
計算においては、計算機の方が、すでに、限界をはるかに超えて人間よりかしこいですね。空間ナビゲーションは、GPSの方が 限界をはるかに超えてかしこく、長期記憶においては、GoogleやBingが、限界をはるかに超えて人間より上です。
私たちは、こうした様々な思考を、人工的に取り出し抽出して、今度は、自動車に搭載しようとしています。自動運転のためですが、そうするのも、それが人間のように運転しないからです。人間と同じようには考えない。そこがミソなのです。妄想、雑念、気が散ることもなければ、フラッシュバックでコンロの火の消し忘れを心配したり、会計学を専攻したら良かったと悩んだりもしません。ただ!運転に集中するだけです。
ただ、運転に集中するだけですよ?もしかしたら、こんな宣伝文句で販売されるかもしれません。「意識ゼロ」その車には、意識がないので、さっき話したようなことに雑念はなく気が散らないんです。
つまり、私たちがやろうとしているのは、できるだけ多くの種類の特定思考を作り出すことなのです。この空間をあらゆる種類の特定思考でいっぱいにしようというのです。
ビジネスや科学の最先端の世界では、難しすぎて、人間自身の思考だけでは、手に負えないような問題も実際にあることでしょう。そんなときは2段階で対処します。新たな種類の特定思考を作り出して、私たちがそばで協働しながら、とても大きな問題。暗黒エネルギーや量子重力といった問題を解いていくのです。
つまり、未知の特定知能を創造するというわけです。意味で違った考え方をする(think different)のに、役に立つはずです。違った考え方が、創造や富、新しい経済の原動力なのですから。
2つ目の側面は、私たちが人工知能(AI)を使うことで、次の産業革命が起きようとしていることです。
最初の産業革命が起こったのは「人工動力」とも言うべきものの発明があったからです。それより前の農業革命においては、何かを作るとしたら、すべては、人間の筋肉か動物の力を使わねばなりませんでした。それ以外にやりようがなかったのです。
産業革命における大きな革新は、蒸気や化石燃料を使って、この人工動力を生み出し、それを使って何でもできるようになったことです。ですから、今では、高速道路を走りながら、スイッチをポンと押すだけで250馬力を意のままに操れます。250馬力ですよ!
さらに、そうしたパワーを応用して、高層ビルや都市、道路を作り、工場では、人力では到底、作れないほど、大量の椅子や冷蔵庫などが生み出されるようになったのです。こうした人工動力は、また送電網を通じて、すべての家庭や工場、農場に届けられ、ただ、何かを接続するだけで、誰でもその人工動力を買うことができます。
これは、新たな革新の源にもなりました。農場では、手押しポンプにこの人工動力。つまり、電気を合わせて電気ポンプが生まれました。そんな変化が、何千、何万と膨れ上がる中で、その公式が生み出したのが産業革命でした。身のまわりのあらゆるもの。私たちが享受しているこの発展は、そのかけ合わせの産物なのです。
そして、今、同じことを人工知能(AI)でやろうとしています。人工知能(AI)はネットワークを通じて、届けられますから、あの電気ポンプを手に取って、それに人工知能を足せば、スマート・ポンプができます。そんな変化が何百万と生じれば、次なる産業革命となるのです。
高速道路を走る車は、250馬力を積んでいましたが、それに250の知力が加わって自動運転車になります。人工知能(AI)は、新たな公共資源となります。人工知能(AI)は「クラウド」という、ネットワークを流通していきます。電気がそうして広まったようにです。そして、かつて電化したあらゆるものを、今度は認知化するわけです。
ここで言いたいのは、これから出てくる1万のベンチャー企業の公式は、とてもシンプルなもので何かにAIを加えるだけです。この公式こそが、私たちがやろうとしていることです。それによって、これから、次なる産業革命を起こそうとしているのです。ところで、今、この瞬間ですが、すぐにGoogleにログインすれば、AIを自ら購入して6円で100回の処理をできます。すでに手に入るんですよ。
さて、3つ目の側面ですが、それは、この人工知能(AI)に体を与えることでロボットができることです。
ロボットがボットになり、私たちが、これまでやってきた多くの作業をこなすことになります。仕事も作業の集まりですから、私たちの仕事も再定義されるでしょう。一部の作業は、ロボットがするわけですから。でも、ロボットが入ることで新たなカテゴリーができ、新たな作業も大量に生まれることになります。
これまで必要だと気づかなかったものです。ロボットによって必要になる新たな仕事。新たな作業が生まれてくるのです。ちょうど自動化によって新たに作り出されたものの多くが、それまで必要とは思っていなかったのに、今では、当たり前になくてはならないのと同じです。
ロボットは、人間から奪う以上の多くの仕事を生み出していきます。大事なのは、アイデアで、ロボットに託す作業の多くは、効率性や生産性という観点で定義されるものであることです。肉体労働であれ、頭を使うものであれ、ある作業が効率性や生産性に落とし込めるものであれば、それはボットがやります。生産性は、もうロボットのものです。私たちはとかく時間の無駄遣いに長けていますから。
私たちは、非効率なことがすごく得意なんです。科学なんて、そもそも非効率なものでしょう。次から次へと失敗することで、前に進んで行くのです。試験や実験をしてうまく行かないから進展するのであって、それがなければ進歩しません。
科学はそれ自体に効率性がほぼ、ないことで構築されています!!効率性、生産性が無いのにイノベーションや幸福を創造している?どう言うことでしょうか?おかしいことでしょうか?考えさせられますね。
技術が、すべてのことを解決できると言いますが、我々が、100倍エネルギー効率のいい乗り物を作ることができるとすれば、大枠としてこれは正しい意見です。
しかし、エネルギー効率ではなく、生産性を高めた結果、イギリスは見事に産業が空洞化してしまいました!
革新も本質的には非効率、非生産的なことです。プロトタイプを作って、うまく行かない機能しないものを試すんですから、探検も元来、非効率、非生産的ですし、アートも効率的、生産的ではありません。人間関係も効率的、生産的ではありません。こうしたことに私たちが引き付けられるのは、それが、効率的、生産的でないからです!!
もう一度言います!!エネルギー効率ではなく、生産性を高めた結果、イギリスは見事に産業が空洞化してしまいました!!
何度でも言います!!エネルギー効率ではなく、生産性を高めた結果、イギリスは��事に産業が空洞化してしまいました!!
これでもバカのひとつ覚えのように、生産性を高めますか?基本的人権も無視して・・・
効率性は、もうロボットのものです。今後、私たちはこうした人工知能(AI)と協働していくことになるでしょう。人工知能(AI)は人間とは違う考え方をしますから。ディープ・ブルーが、チェスの世界チャンピオンを破ったとき、これでチェスも終わりと思われていました。でも、実際のところ、今のチェスの世界チャンピオンは人工知能(AI)ではありません!
人間でもありません!人間と人工知能(AI)のチームです!医療診断に最も長けているのは、医者でも人工知能(AI)でもなく両者のチームです!私たちは、これからこうした人工知能(AI)と協働し、将来は、どれだけボットとうまくやれるかで給料も決まってくるでしょう。
これが3つ目の側面でロボットは私たちと違い、誰もが使うものだから敵対するのではなく協働するものだということです。敵対するのではなく協働していくのです!
さて、これからの未来はどうなるんでしょう?
今から25年先にいる人が、過去を振り返って私たちがAIを語るのを見たとしたらこう言うでしょう「それは人工知能(AI)なんかじゃない インターネットだって、25年先に使っているのと比べたらないのも同然だ」
現在、人工知能(AI)の専門家はいません。AIには多額のお金が流れており、何兆円ものお金がつぎ込まれています。非常に大きなビジネスです。でも、今後20年で期待される大躍進に見合うだけの専門家がいないのです。まだまだ始まったばかりです。まだ、すべてが始まって1時間。インターネットが始まって1時間。これから来たる未来が始まって1時間です。
これから20年後に最も人気を博し、誰もが使うようになる人工知能(AI)を使った商品はまだ発明されてもいません!!
つまり、皆さんもまだ間に合うということです。ありがとうございました。
キャシーオニールによると・・・
思考実験をしてみましょう。私は、思考実験が好きなので、人種を完全に隔離した社会システムがあるとします。どの街でも、どの地域でも、人種は隔離され、犯罪を見つけるために警察を送り込むのは、マイノリティーが住む地域だけです。すると、逮��者のデータは、かなり偏ったものになるでしょう。
さらに、データサイエンティストを探してきて、報酬を払い、次の犯罪が起こる場所を予測させたらどうなるでしょう?
あら不思議。マイノリティーの地域になります。あるいは、次に犯罪を犯しそうな人を予測させたら?あらら不思議ですね。マイノリティーでしょう。データサイエンティストは、モデルの素晴らしさと正確さを自慢するでしょうし、確かにその通りでしょう。
さて、現実は、そこまで極端ではありませんが、実際に、多くの市や町で深刻な人種差別があり、警察の活動や司法制度のデータが偏っているという証拠が揃っています。実際に、ホットスポットと呼ばれる犯罪多発地域を予測しています。さらには、個々、人の犯罪傾向を実際に予測しています。
ここでおかしな現象が生じています。どうなっているのでしょう?これは「データ・ロンダリング」です。このプロセスを通して、技術者がブラックボックスのようなアルゴリズムの内部に醜い現実を隠し「客観的」とか「能力主義」と称しているんです。秘密にされている重要で破壊的なアルゴリズムを私はこんな名前で呼んでいます「大量破壊数学」です。
民間企業が、私的なアルゴリズムを私的な目的で作っているんです。そのため、影響力を持つアルゴリズムは私的な権力です。
解決策は、データ完全性チェックです。データ完全性チェックとは、ファクト(事実)を直視するという意味になるでしょう。データのファクトチェックです!
これをアルゴリズム監査と呼んでいます。
ヨーロッパでの一般データ保護規則(GDPR)でも言うように・・・
年収の低い個人(中央値で600万円以下)から集めたデータほど金銭同様に経済的に高い価値を持ち、独占禁止法の適用対象にしていくことで、高価格にし抑止力を持たせるアイデア。
自分自身のデータを渡す個人も各社の取引先に当たりデータに関しては優越的地位の乱用を年収の低い個人(中央値で600万円以下)に行う場合は厳しく適用していく。
情報技術の発展とインターネットで大企業の何十万、何百万単位から、facebook、Apple、Amazom、Google、Microsoftなどで数億単位で共同作業ができるようになりました。
現在、プラットフォーマー企業と呼ばれる法人は先進国の国家単位レベルに近づき欧米、日本、アジア、インドが協調すれば、中国の人口をも超越するかもしれません。
法人は潰れることを前提にした有限責任! 慈愛や基本的人権を根本とした社会システムの中の保護されなければならない小企業や個人レベルでは、違いますが・・・
こういう新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との
戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど
しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!
最後に、マクロ経済学の大目標には、「長期的に生活水準を高め、今日のこども達がおじいさん達よりも良い暮らしを送れるようにする!!」という目標があります。
経済成長を「パーセント」という指数関数的な指標で数値化します。経験則的に毎年、経済成長2%くらいで巡航速度にて上昇すれば良いことがわかっています。
たった、経済成長2%のように見えますが、毎年、積み重ねるとムーアの法則みたいに膨大な量になって行きます。
また、経済学は、大前提としてある個人、法人モデルを扱う。それは、身勝手で自己中心的な欲望を満たしていく人間の部類としては最低クズというハードルの高い個人、法人。
たとえば、生産性、利益という欲だけを追求する人間。地球を救うという欲だけを追求する人間。利益と真逆なぐうたらしたい時間を最大化したいという欲を追求する人間。などの最低生活を保護、向上しつつお金の循環を通じて個人同士の相互作用も考えていく(また、憎しみの連鎖も解消する)
多様性はあるが、欲という側面では皆平等。つまり、利益以外からも解決策を見出しお金儲けだけの話だけではないのが経済学(カントの「永遠平和のために」思想も含めて個人のプライバシーも考慮)
(個人的なアイデア)
アメリカのノーベル賞受賞経済学者ミルトン・フリードマン、元FRB議長であったベンバーナンキの書籍「大恐慌論」も言うように、金融危機2008、コロナショック2020などの急落に直面する対策として、ゼロ金利、マイナス金利、金融政策が出尽くした後に、よく登場する最速実行再分配政策が、個人への緊急的な現金給付!!!
各国によってスピードは異なるが、政策閣議決定後、人間の限界を遥かに超えるスピード。1秒以内で現金到着が理想。各国競争してみれば、今後の恒久対策として中央銀行のデジタル通貨なども考慮しつつ、新産業が産まれプラスサムになるかもしれません。
MMT(Modern Monetary Theory)によると、現状の貨幣での現実的なアイデアとして、社会保障に還元される日本の消費税は現状維持しつつ、現金給付額にも消費税がかかるので現金給付額を上げて、毎月給付にすると消費税率と社会保障費下支えとが均衡状態になる?と同時に、実体経済の経済成長率「g」の下支えにも寄与する?
これらの総量が、急激な不況時の資本収益率「r」以上なら、もしかして?回復して正常な経済環境に戻る期間も短縮できるかもしれません。
<おすすめサイト>
データ配当金の概念から閃いた個人的なアイデア2019
キャシー・オニール: ビッグデータを盲信する時代に終止符を!
人類の革新。方向性のインスピレーション
人工知能が人間より高い情報処理能力を持つようになったとき何が起きるか?2019
ニック・ボストロム:人工知能が人間より高い知性を持つようになったとき何が起きるか?
フェイフェイ・リー:コンピュータが写真を理解するようになるまで
ジェレミー・ハワード:自ら学習するコンピュータの素晴らしくも物恐ろしい可能性?
ハワード ラインゴールド: 個々のイノベーションをコラボレーションさせる
アレックス・ウィスナー=グロス:知能の方程式
ルトハー・ブレフマン:貧困は「人格の欠如」ではなく「金銭の欠乏」である!
個人賃金保障、ベーシックインカムは、労働市場に対する破壊的イノベーションということ?2020(人間の限界を遥かに超えることが前提条件)
世界の通貨供給量は、幸福の最低ライン人間ひとりで年収6万ドルに到達しているのか?2017
ベティーナ・ウォーバーグ: ブロックチェーンが経済にもたらす劇的な変化
セバスチャン・スラン&クリス・アンダーソン : 人工知能(AI)とは何であり、何ではないか
セザー・ヒダルゴ:政治家をあるものに置き換える大胆な構想
人工知能にも人間固有の概念を学ぶ学校(サンガ)が必要か?2019
<提供>
東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント
独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです
東京都北区神谷のハイブリッドな直送ウェブサービス(Hybrid Synergy Service)高橋クリーニングFacebook版
#ケヴィン#ケビン#ケリー#人工#知能#知性#インター#ネット#人類#機械#ロボット#ベーシック#インカム#ブロック#チェーン#アルゴリズム#エネルギー#交響曲#昭和#クラウド#サンガ#仏教#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery#シンフォニー
1 note
·
View note
Photo

I guarantee you’d love it! 大会前ってなんでも焦るけど、 去年の大会終わってから大会観に韓国行ったり少しずつ準備してきたから時間がない中でも前より焦りが少ない気がする。 大会前に少し一段美味しくなった。 本当に少しの変化かもしれないけど、この違いって大きく大事だなとつくづく想う。 「美味しいのは当たり前。ただ美味しいじゃなく、美味しいをどれだけより詰められるか?だと思うよ」って感じの事を2年半前から言われ、 一年目はただガムシャラで今思えば美味しくなかったと想う。 2年目はなんとなく少しだけ美味しく淹れれるようになったけど無謀に冒険して失敗して。 今年で3回目。 緊張と不安はあるけど楽しみしかない。 真剣に取り組んでる大会だけど、それでも毎年コーヒーを楽しむ楽しい楽しみな大会だから。 自分自身がどれだけ美味しく淹れれるようになってるかな。 #xpro2 #xf23mmf14 #aeropress #aeropresscoffee #tokyo #japan #photograph #photography #photooftheday #latte #latteart #coffeelover #mastercraftsmanship #coffeetime #coffee#baristadaily #富士フイルム #今日もx日和 #ラテ職人 #正直大会出てない人で抽出技術知識経験値がめちゃめちゃ高い人がいる #その人には追いつきたいと思っている #どんなことも #1度目は勢い #2度目は無謀だったな #3度目の正直 #まだまだイケるならもっと #だったりする #でも気持ちが終わらないのなら後悔のないように頑張ろうって想っている
#photooftheday#baristadaily#tokyo#2度目は無謀だったな#今日もx日和#でも気持ちが終わらないのなら後悔のないように頑張ろうって想っている#その人には追いつきたいと思っている#1度目は勢い#coffeetime#photography#photograph#aeropresscoffee#coffeelover#mastercraftsmanship#xpro2#富士フイルム#どんなことも#aeropress#まだまだイケるならもっと#latte#3度目の正直#ラテ職人#だったりする#latteart#xf23mmf14#coffee#正直大会出てない人で抽出技術知識経験値がめちゃめちゃ高い人がいる#japan
0 notes
Link
2015年7月以来5年ぶり2度目となる、東京大学大学院工学系研究科教授で日本ディープラーニング協会理事長の松尾豊さんのインタビューをお届けする。 エンジニアtypeでは今年7月にも、AIテクノロジー企業ABEJA主催のオンラインイベント「DX2020」で行われたABEJA岡田陽介代表との対談「With/Afterコロナ時代におけるDXとAI」をレポートしている。 >>【松尾豊×ABEJA岡田陽介対談】日本企業でDX、AI活用が進まない5つの理由とその処方箋 この記事では「日本企業でDXが進まない理由とその解決策」にテーマを絞るべく割愛したが、講演の中でディープラーニング研究の今を問われた松尾教授は「画像認識系の技術がだいぶ成熟して、アプリケーションもだいぶ出てきた。世の中には”出切った”雰囲気さえ出ている。ところが今(アカデミア方面では)かなり面白いことが起きている」として、最先端の研究動向を一部紹��していた。 そこで今回改めてお時間をいただき、ディープラーニングの世界で今どんな「面白いこと」が起きているのか、それは私たちの生活やエンジニアの仕事に今後どのような影響をもたらすのかを伺った。 東京大学大学院工学系研究科教授 松尾 豊さん(@ymatsuo)1997年 東京大学工学部電子情報工学科卒業。2002年 同大学院博士課程修了。博士(工学)。同年より、産業技術総合研究所研究員。05年8月よりスタンフォード大学客員研究員を経て、07年より、東京大学大学院工学系研究科総合研究機構/知の構造化センター/技術経営戦略学専攻准教授。14年より、東京大学大学院工学系研究科 技術経営戦略学専攻 グローバル消費インテリジェンス寄付講座 共同代表・特任准教授。19年より、東京大学大学院工学系研究科 人工物工学研究センター/技術経営戦略学専攻 教授。専門分野は、人工知能、深層学習、ウェブマイニング。人工知能学会からは論文賞(02年)、創立20周年記念事業賞(06年)、現場イノベーション賞(11年)、功労賞(13年)の各賞を受賞。人工知能学会では学生編集委員、編集委員を経て、10年から副編集委員長、12年から編集委員長・理事。14年から18年まで倫理委員長。17年より日本ディープラーニング協会理事長。19年よりソフトバンクグループ社外取締役 実装進む画像認識。アカデミアではディープラーニングと記号処理の融合が議論される ――前回インタビューをさせていただいた2015年からの5年間で、ディープラーニング技術の実用はどこまで進んでいますか? 顔認証、医療の画像診断といった領域でどんどん実用例が出てきていて、最近だとコロナ禍における体温測定時の人の検知にも使われています。他にもインフラの点検、食肉加工、製造業の外観検査、店舗内の顧客の移動分析など、さまざまな領域に広がってきています。これら多くは画像認識を使ったものですが、他方、自然言語処理の関係としても、Eコマースの商品説明の下書きを書く、広告を自動生成するといった例があります。 ――実装を担うエンジニアの数もかなり増えてきていますか? ディープラーニングを使える人の絶対数はすごく増えました。研究の場面でもごく普通に使われるようになっています。TensorFlow、Keras、Pytorchなどのフレームワークが充実してきたため、すごく使いやすくなりました。もはやディープラーニングを使うかどうかという話ではなく、何にどう使うのか、他のテクノロジーと組み合わせてどのように業務を効率化し、どんな付加価値を出していくのかというフェーズに入ってきています。 ―― 先日行われた「DX2020」の講演では、「ディープラーニングに関して出切った感が漂っているが、水面下で非常に面白いことが起きている」とおっしゃっていました。 産業面とアカデミア方面とで少し別の動きになっています。先ほども触れたように、産業面で活用されているのは主に画像認識の技術です。そこの応用がこの5年で急速に進みました。また、ハードウエアが関わる分、少し時間はかかるかもしれないですが、今後はロボット系の応用も増えてくるでしょう。そして、こうしたディープラーニングの技術をきっかけにして、業務全体、業界全体のDXをどう進めていくかということが産業上の重要なポイントになります。 一方、アカデミアでは、ディープラーニングと記号処理の融合、さらに言えば人間の思考との対比を考えるような方向でいろいろな動きが出ています。 ――詳しく伺いたいです。 一つトピックとして重要なのは、GPT-3の登場です。GPT-3は人工知能を研究する非営利組織OpenAIが公開した文章生成言語モデルの最新版です。 これまでにもBERT、GPT、GPT-2といった言語モデルがありましたが、このGPT-3は自然言語処理のさまざまなタスクを驚くほどの精度でこなしてしまいます。ブログの記事を書くことも、プログラムのコードを書くこともできます。信じられないようなことが次々できてしまうということで、英語圏で今ものすごく盛り上がっています。 ただ、すでに実用フェーズにある画像認識にしても、GPT-3にしても、技術としてはたしかにすごいのですが、人間の知能とは少し離れたものになっています。 ――どういうことですか? 人間の知能はシステム1とシステム2の二つのシステムから構成されるという考え方があります。これは、ノーベル経済学賞を受賞した行動経済学者ダニエル・カーネマンが2011年に出版した一般向け書籍『ファスト&スロー』でよく知られるところになりました。そして、昨年のNeurIPS2019でのYoshua Bengio先生の招待講演がまさに、”From System 1 Deep Learning to System 2 Deep Learning”です。 これまでのディープラーニングはこのうちシステム1に該当するような、非常に直感的・瞬間的・反射的な思考の形態を表現していました。これから考えないといけないのはシステム2の、より熟考型の論理的・言語的な思考の方です。このあたりの技術がディープラーニングで実現できるようになってくると、人間の思考とは何か、言語で考えるとはどういうことかといった理解が大きく進むと思います。 ――先ほどのGPT-3がシステム2に関わっているということではないのですか? はい、システム2の動きなのですが、システム2だけなのです。一方、画像認識はシステム1だけ。人間にはその両方があり、二つのシステムが相互に影響しています。画像的なものも扱えるし、体を上手に動かすことも、言語を扱うこともできる。この両方が密接に関連しているのです。 ――つまり、二つ両方を持って初めて人間的と言えるのであって、片方だけでは人間の知能とはかけ離れているという話になってしまう? そうです。ですが、そもそも人間の知能がどういうものなのかがまだ分かっていません。言葉を喋らなくても上手に日常生活を送っている人はいるわけで、認識をするとか行動をするということと言葉の処理とがどう関係しているのかは、脳科学でも明確には分かっていないし、人工知能の分野でも分かっていません。 この辺りはシンボルグラウンディング問題などと呼ばれて昔から難所であるとされてきました。そこが解決すると、いよいよ見えてくるものがあるかもしれないということです。 人間の知能とは何か。解明のカギを握る技術「世界モデル」 ――講演の中ではそのカギになるものとして深層生成モデル��シミュレーション、世界モデルといったキーワードを挙げていました。それぞれどう関わるのでしょうか? 人間は世界のシミュレーターを持っています。だからボールを投げたら何が起こるか、ガラスのコップを落としたら何が起こるかといったことが、実際にやらなくても分かるのです。子どもにはそれが分からないから「そんなことをやったらコップが割れるよ」と言われてもやってしまう。 子どもには分からなかったことが大人になぜ分かるのかと言えば、過去の経験から学習し、モデルを獲得していくからです。そのモデルを使ってシミュレートできるから近い将来のことが見えるのです。今のところ、ディープラーニングに同じことはできません。ですからそれをつくろうというのが世界モデルと呼ばれる技術です。 例えば目の前にあるのがコップであれば、押せば押しただけコップは動きますよね。ですが、同じように砂を押しても砂全体が動くわけではなく、砂の一部だけが動く。水だったら押しても全然動かない。こうしたことをわれわれは当たり前に扱っていますが、それは誰かに教えられたからではなく、自らの経験を通じて学んでいるのです。 世界モデルをつくるには、それと同じことをAIやロボットにも学習させる必要があります。ひたすら押したり引いたり、それも1万回、10万回とやらなくてはなりません。シミュレーターでの試行も併せて行う必要があります。 ――深層生成モデルというのは? 世界モデルの中で使われることが多いのが深層生成モデルと呼ばれる技術です。例えばわれわれは「紫の救急車がありました」と言われると、頭の中に一応は「紫の救急車」というものが思い浮かびます。実際には見たことがないはずなのに思い浮かぶというのは、頭の中(深層)でデータを生成しているということです。 そうしたデータの生成過程自体をモデル化したものを深層生成モデルと呼びます。画像認識分野における有名なものにはVAE(Variational Auto Encoder)、GAN(Generative Adversarial Networks)などがあります。 そうしたものを使いながらカウンターファクチュアル(反実仮想。実際にはないことを仮想していく技術)なことを想像できるようになると、人間の大人がするように上手に行動できるようになります。例えば障害物をどけて道の向こう側に行きたいと思ったときに、ダンボール箱であれば押しのけて問題ないけれども、ガラスの飾り物だったらまずいといった判断ができるようになります。ロボットが日常生活や工場の中でのさまざまなタスクを行う上では、これが極めて重要です。 ――なるほど。 また、先ほどの紫の救急車の例から分かる通り、これができると言葉の理解ができるようになります。言葉をベースに頭の中で想像ができるようになるのです。われわれが文章の意味や相手の言っていることを理解している時には、おそらく頭の中に像を描いています。そのイメージができた時にわれわれは「ああ、分かった」と言う。イメージを動かしながら相手の話を聞いているのです。 大人になると抽象的な話が多くなるので形のあるイメージではなくなっているのですが、それでもイメージらしきものは描いています。言葉の意味を理解するというのは結局、世界モデルをシミュレーターとして回し、頭の中にイメージをつくっていくことなのだと言えるでしょう。 そうすると、先ほどの「上手に行動する」ということと「言葉の意味を理解する」ということは、どちらも世界モデルという同じ技術を使っていることになります。人間の赤ちゃんも、いろいろと自分で行動ができるようになってくると一方でお母さんの言っている言葉の理解もできるようになります。世界モデルをちゃんと持っていることと、それが言葉によって適切に引き起こされることがすごく大事だということです。 先ほどのGPT-3などにはそういう機能はありません。ですから、本当の意味で人間がしているような意味理解はしていないのではと考えられるわけです。もっともGPTはGPTで、中で何が起こっているのか誰にも分からないくらい大きなモデルで学習しており、しかもtransformerの性質上、アルゴリズム的な挙動も学習できるはずですから、そちらはそちらで非常に面白いのですが。 以前ある人が「人工知能はインスタントラーメンとは違うことが分かった」とおっしゃっていて、一見、変な例えなのですが、よく聞いてみるとなるほどなと思いました。インスタントラーメンというのは、ラーメンというものをわれわれ自身がすでに知っていて、それをインスタントにしたもののことですよね。ところが人工知能の場合は、われわれが知能というものをあらかじめ分かっているわけではありません。分からないままに、それを人工でつくろうとしているのです。 ですから人工知能に関しては、つくろうとしているものが何なのかを知らないという問題と、どうつくるかという問題、この二つの難しい問題があるわけです。前者の「知能とは何か」という問題には昔から脳科学者も心理学者も哲学者もさまざまな方法でアプローチしてきました。人工知能の研究者もそれをやろうとしているという意味では同じですが、同時につくろうともしているのです。 先ほどの世界モデルの話には、知能とは何かという話と、それをどうつくるかという話の両方が混ざっています。もしも世界モデルのような仕組みにより言葉を理解するAIをつくることができたら、おそらくは人間の知能の仕組み、少なくとも言葉を理解する仕組みはこういう風にできているのではないかということが言えるようになるでしょう。 ただ、現時点では人間の知能とは何かというのが謎なので、われわれとしてもそれをいろいろな側面から説明する必要があります。岡ノ谷先生のやられている研究は、「音楽から言葉ができたのではないか」ということをおっしゃられており、私はアルゴリズム的に言っても、近い説明はできるのではと思っています。より正確に言うと、離散的な記号の予測に正解することを好むプライア(事前知識)が入ったことの副作用が、音楽を好むようになったということだと思います。先の講演ではこうした文脈で先生の研究を引用させていただきました。 AIがコードを書く時代。エンジニアに求められるのは「共感力」 ――5年ほど前にアカデミアで盛り上がっていた画像認識技術が今、実装レベルで盛り上がっているというお話でした。今後、今日伺ったような言葉の意味理解に関する研究が進むと、どんな可能性が広がりますか? 言葉の意味理解ができると、おそらくいろいろなタスクができるようになります。事務作業は全般的に「調整しておいて」「これをやっておいて」など言葉を使って行うものなので、全て自動化できる可能性があります。こうしたインタビューや原稿の編集などもできるようになるでしょう。 また、インターフェースとしてもiPhoneのSiriやAmazonのEchoといったAIアシスタントと今以上にちゃんとした会話が成立するようになり、本当のコンシェルジュっぽくなっていきます。もちろんすごく便利になりますし、購買行動なども���分で検索するのではなくAIアシスタントに勧められたものを買うといった形に大きく変わる可能性があります。 このように言葉の意味理解ができるようになることのインパクトはものすごく大きいと考えています。スマホやインターネットの登場と同じかそれ以上に大きな変化が起こるのではないでしょうか。 ――いつごろ現実になりますか? そこは非常に難しいです。というのも、GPT-3のようなもののタスクの精度が上がっていくことで徐々にそうなるのか、あるいはまったく違う方式である瞬間にいきなり「できました」となるのかさえ現時点では分かりませんから。 ただ、僕の予想では5〜10年後。僕はもともと「2030年ごろまでに言葉の意味理解までいく」と言ってきました。その想定から大きくは変わっていないと思っています。 ――そうなった時にエンジニアの役割はどうなりますか。人工知能がコードも書いてくれるとなると、よく言われるように仕事がなくなることにもつながりませんか? 最近『ディープメディスン』という本の書評を書いたのですが、冒頭にもお話しした通り、医療の世界ではAIを用いた画像診断がかなり進んでおり、すでに人間の医師よりも精度が高くなってきています。 未来の医療のあり方を描いたこの本は、「自動でできることを自動でやることによる一番のメリットは、医師が患者と向き合うことに時間を使えることだ」と言っています。現状は病院へ行っても、お医者さんは電子カルテの入力作業などに忙しそうで、ほとんどこちらと向き合ってくれないじゃないですか。でも、そこをAIが担ってくれれば、医師は患者と向き合うことに専念できます。データを使うこと、ディープラーニングを使うこと、そして医師と患者とのディープな共感を生み出すことがこれからの医療なのではないかと、著者は結論付けています。 エンジニアに関しても同じことが言えるでしょう。自動でできる部分は自動化していいのです。ただ、共感するとか寄り添ってあげる、聞き出してあげるといったところは人間の得意な部分ですし、また人間にやってほしいと思う部分でもあるでしょう。ですから、同じ職業だったとしても付加価値の構造が変わってくることはあるのではないでしょうか。 ――そこが苦手だと感じるエンジニアも多いかもしれませんね。 たしかにそうですね。ですが、基本的に今のエンジニアの数が余ることはないので、そこは心配しなくてもいいのではないでしょうか。社会全体がAIとかデジタルの方向に進み続ければ、開発する人が余ることは基本的にはない。業界自体は発展し続けるはずです。 ――流れに乗って必要とされる知識を身に付けていけば、当分の間は仕事に困らないと。では、ディープラーニングなどの先端技術をキャッチアップするために、最低限ウオッチしておくといいものがあれば教えてください。 基本的にはグーグルの「Brain Team」と「DeepMind」、フェイスブックのAIリサーチ「FAIR」、UCバークレーとスタンフォードあたりを見ておけばいいと思います。学会でいうと、ICLR, NeurIPS, CVPRなど。オンラインの講義のコンテンツもたくさんあります。また、今後はディープラーニング単独というよりもいろいろな技術と組み合わせていくことがますます大事になっていくと思うので、エンジニアの方は自分がこれまで培ってきた技術とディープラーニングの組み合わせで、いろいろなビジネスの場面でどう役立つのかと考えてみるのがいいのではないでしょうか。 取材・文/鈴木陸夫
0 notes
Text
ウイスキーと今後の計画の話し合い
2018.6.21.20:21
こわがらないで、もう八時よ 安心して、まだ八時よ
お話の続きをしましょう
柔らかな闇と動き出す光
あたたかいケーキと あたたかくなる飲み物 ケーキは抹茶色で 飲み物は琥珀色です
喉があつくなって 安心します
こういうとき お水はチェイサーという名前に変わります
ずいぶんと平凡で わけのわからないところまで 歩いてきてしまったという気になります
わたしは 昨年の冬に弾いたピアノを聴いています なにもかもはじまりがなくて はじまりらしいところがしっかりあります
白熱灯は 火のそれよりも 優しい色なのかもしれません それはお日様に近いからかもしれません
今日はもう火を使う気になりません だからこうして気楽にやっています わたしたちは栄養失調で死ぬかもしれないけれど その前になにかべつのことで死ぬかもしれません
今日はピアノを弾きました とても良いラインになりました それはずっと肉付きを帯びて どんどん色気を増していくように思えます
今聴いているピアノは ほとんどの人が下手くそだと言うと思います 音をそこで繋ぎました 道がわからずにてくてくと歩くと なにか知らない場所に行きついたりするものです そこには迷子の音がありました たしかにどこかにたどりつこうとする 迷子の音が聴こえます これをわたしばかりで 美しいと思い続けます 今日の音は たくさんのことが詰まっていたので いつもよりも美しかったし 本当に近い気がしました それでもこのときほど透明な音ではありません そんなことはわたしばかりが感じていることです
今日弾いたラインの ほとんどすべてが この日の迷子の歩みの道を そっくり辿ることで 道という道になり得てきました
線と湯気、道と足跡
今日は名刺がどうしてもすれなくて そのままなぞの会合へと向かいました 思いがけず一人顔を知る女の人がいた気がしました すぐに見えなくなって わたしはなんのこともなくその広場を後にしました
なにか懐かしい気にはなりました
羊だろうと狼だろうと みんな群れて固まることで安住の土地を得ます
正しさも美しさも楽しさも つねに自らの手で更新され 選択されていくものだと思います
なにがみんなにとっての幸せになるでしょう?
そこそこよくできたパッケージを 共有し合うことでなく 皆がそれぞれに何かを掴み取っていくことができる土台
ピアノが高揚モードに入ってきたのでオフしましたよ
個と個があるということをわすれずにおいておいて 個と個の狭間でない場所で なにかを示すことをしていくことがこれからの仕事になる気がします わたしのこれまでの役割はそのままで やり方は変わっていかなくては わたしの身体がもう多分もたないと思います
飲んだくれて墓石になるんですよ
わたしはもうわたしのために生きようと思います それが一番のだいじなことです
わたしは不快を感じたくありません わたしの意識する範囲で何者かが苦しんでいることが不快です 完璧な配列になっていなくては不快です なにもかもが慈しみ合う関係性が成り立っていない場に身をおくことが不快です 意識を広げれば広げるほど不快が大きくなるなら せめて小さな家の中の不快を排除したいだけです 家の中は世界と繋がっています 何もかもがまるっきり関係をたてるところはありません もしあるとすればそれは わたしとあなたという ひとつとひとつが対峙したときのみです 世界の輪郭がぼやけて ほかのなにもかもが見えなくなるとき そういう場所をしっています
それはひとつとひとつのみにありますが それはつらなって 大きなあみになったりします
それがその網の外を排他することになってはいけません
なにってわたしは これからのために考え事をしたいんですよ
今までのように頭ばかりで考えていたら 完璧なように思えたとしても わたしが疲れる計画になってしまうから 頭を麻痺させながら 身体と心に聞くんです
わたしが楽しくて みんなも楽しい しあわせでうれしい計画にしたいんです
キャット ロマンス ロマンティカ
しあわせの食卓 って、もうすでにあったじゃない
ここはテーブルであり、ベッドである
寝食
ねるところからたべるとこまで
ハレの日もケの日も
ここはテーブルでありベッドである ねこであり花であり器である 今日であり昨日であり明日でありその日である あなたであり、わたしである
ねこのくちづけふれずにおいで わたしに教えて だいじなこと
なんて説明したら良いの?
物が時と場所をつなぐ あなたとわたしをつなぐ
教えてわたしの案内人 教えてキスキャット
テーブルを囲いほほ笑みかける 灯りを消して夜に寄り添う
永遠のロマンスを このひと時に小さくこめて
Tomorrow Toyama
河内の意見 ゆるやかであったかいイメージにしたい 制作もゆるやかであったかく 守られているこの状態を持続させる中 熱を持って魅力を曝け出してやわらかに、しなやかに、アピールしていく感じ 連携プレーをもっと組む
女性的なつながり
犬的な社会でなく 猫的な社会 縦社会でなく横社会 このへんのガラスの社会はもともとこれに値する
キャット、なんだったっけ Creative Air Team methodology
CAT
汗だくにならない
物ではなく 人は背後にあるストーリーを買う
富山弁のシーエム(?)
富山ガラス Glass CAT made in Toyama
Glass Creative Air Team
GCAT じいネコ富山
ロマンスにつなげて売っていく いろんな時代の幸せの時がある いつだってそこにあなたとわたしがある
ペット 子供
富山の薬
薬瓶 暮らしの薬瓶 しあわせなきもちになるテーブルウェア、ベッドウェア
こしのひすい、腰の青シリーズがあるなら、 薬瓶由来のものをこもんてーまにするべき
薬瓶の形を抽出するのでなく 薬瓶の概念を抽出し生活雑貨に注入する
乾杯が楽しくなるグラス ワインを冷やす、お花もいれられる大きな瓶 あたたかなきもちになるキャンドルホルダー 空間を包み込む灯りをデザインするランプシェード 普段のお水がおいしくなるグラスとジャー
薬売りはどこへでも
ふだんの暮らしに必要なのは お医者様ではなく 家の中の住民の あたたかく美しいこころである
富山のガラスは 家の中の特効薬に 変わらぬ形をとどめて いつも大切なものを守る 美しい時をかざる
先用後利 「用いることを先にし、利益は後から」とした富山売薬業の基本理念である。創業の江戸時代の元禄期から現在まで脈々と受け継がれている。始まりは富山藩2代藩主の正甫の訓示「用を先にし利を後にし、医療の仁恵に浴びせざる寒村僻地にまで広く救療の志を貫通せよ。」と伝えられている。
富山市は、ガラスのまちへと… ということを決めた時、 産業にすることを先ずの目的にせず、 その環境を整え、広く知識を学ぶこと、価値観や可能性を広げることを試みた。 富山のガラスは、不思議なほどに多様性に富んでいる。 誰もが独自の道を各々に探す 研究所は、技術習得よりも、自己の表現追求に重きを置いた 伝統的なものを引き継いで習得することに囚われることなく、多文化のものも取り入れることに躊躇することなく、国内外の様々な作家を招いての教育に取り組んできた。 工房は、作家たちが各々の制作に取り組みやすくなるような仕組みを作り、県内外からも作り手の集まる場になった。 まちの様々な注文をうけ、たくさんいろいろな種類のガラスの製品を作り出してきた。 たくさんの人びとがガラスの魅力、ガラスの楽しさを感じ、喜んでもらいたいという思いから、体験の工房ができた。
それは、薬のときにもあった、先用後利の思いがもとにある。 約25年経ち、富山のガラスは、たくさんの人びとの支えによって、思いによって、深く大きくなった。 これから、富山のガラスは、今までよりも、もっと人びとの生活に寄り添い、人びとの暮らしを豊かにすることに、新しい一歩を踏み出していくことを決めました。
市民の方々に支えていただいた恩恵を、返していく より発展させていく ガラスウェアを一大産業にしていく
事前使用システム
使いやすさを感じていただくために 〜日間レンタル可能
おまけ(おみやげ) 編集 富山の売薬の1つの特長としておまけ(おみやげ)を渡すことがあげられるが、江戸時代後期から行われているおまけで人気があったのが、富山絵(錦絵)と呼ばれた売薬版画(浮世絵)で、歌舞伎役者絵、名所絵(風景画)、福絵などいろいろな種類が擦られ全国の家庭に配られた。そのほか紙風船をはじめ、「食べ合わせ」の表や当時の歌舞伎の情報や、紫雲英の種など軽いものを中心に日本中に配った。また上得意には、輪島塗や若狭塗の塗箸、九谷焼の盃や湯飲みなどをおみやげとして渡していた。現在もおまけは渡しているが、高級品の進呈は業界の取り決めによりほぼなくなっている。
北原照久は『「おまけ」の博物誌』(PHP新書)で「おまけ」のルーツを求め、「富山が生んだ日本初の販促ツール」という一章を設けている。wikiより
富山のガラスを買ったら、薬のパッケージ入りのお菓子がつく、など
このガラスがあることで、家の中にしあわせがやってくる、不調(不幸)が回避される、というようなワクワク、あたたかい気持ちになるようなパッケージ、商品を考える。
お菓子が難しいならミニレターセットなどでもいい。
うれしくなるノベルティ
紙風船
小さなグラス拭きの布などでも。
バレンタインのときはそれにちなんだ、アクセサリーに近いもの、クリスマスの時は愛に効く薬、など、シーズンなどによって変えることで、商品そのもののビッグチェンジを毎回しなくても、スタンダードラインはそのままで、喜んでもらえる。
また、「庶民哲学」のような言葉を広めたとされる[10]。例えば、「高いつもりで低いのが教養 低いつもりで高いのが気位 深いつもりで浅いのが知識 浅いつもりで深いのが欲の皮 厚いつもりで薄いのが人情 薄いつもりで厚いのが面の皮 強いつもりで弱い根性 弱いつもりで強い自我 多いつもりで少ない分別 少ないつもりで多い無駄」などである。
ラグジュアリー層にこそ受け入れられる可能性のある、文字入り(手書き風)グラス、など
遊び心のある人に、「お薬グラス」などとして。もちろん、ステムをつけるなどして、安っぽくならないように。ラグジュアリーの中に、ラグジュアリーに浸るのをもうよしとしない、すこし?さらに教養の高い?層を狙う、またそういう人たちが増えることを願って。
海外にも飛翔した「富山売薬」
この「売薬歌」で「満州支那の奥地よリ メキシコ南洋の果てまでも」と歌われている点についてだが、富山売薬は明治期に日本人の大陸進出などに伴ない、海外にまで進出していった。主として海外へ移住する日本人を追ってのものだったが、明治42年(1909)の『富山売薬紀要』によると、同19年に藤井諭三がハワイで配置売薬を始めたのを皮切りに、土田真雄が韓国へ、隅田岩次郎が清国アモイヘ、寺田久平や重松佐平が上海へと飛翔した。明治40年代の輸出売薬従事者は43名と4社。朝鮮半島、中国大陸、ハワイ、台湾、ウラジオストックなどから、さらに、遠くブラジル、インドにまで、富山売薬は日本人の行くところ、どこへでも進出して行ったのである。
ガラスも海外へ!
ブランドネーム、ロゴ、コンセプト
とやまる
とやま
富玻璃
Ecchu
こしの
越の国
越
便
BIN TOYAMA
BIN
phial phi・al /fάɪəl/ 【名詞】【可算名詞】 小型ガラス瓶; (特に)薬瓶,アンプル.
Phial of T
phial 【名詞】 1. 薬を入れるビン(特に針から注入できるよう殺菌して密閉した容器)(a small bottle that contains a drug (especially a sealed sterile container for injection by needle)) ちょっとちがうかな
KOBIN
KOBIN ROBIN
ばいやく ちょっといや
Kusuri たぶんだめ
薬瓶をモチーフにしたロゴがあるべき ハートとかつけたい 家庭の病、なんにでもきく!!っていう当初のむだな彼らの自信を、喜んで反映させたい
くすりだちゃ びんっちゃ とやまだちゃ おくすりいるけ のまれんか しとかれ しられ
Koshinoharu 越波瑠 越春 越治(これでもこしのはる、と読む!) 越晴!
おくすりのように人を癒し生活を豊かにする的な〜
過去の歴史より
気をつける?こと
富山売薬最大の試練「売薬印紙税」
富山売薬はこうして明治以降も伸張・発展を続けた。 しかし、それは厳しい試練にさらされてのものだった。 明治政府は「維新」の言葉からもわかるように、諸事を西欧化に一新することを基本とした。それは医薬・医療制度でも同様であった。政府は明治3年(1870)、衛生上、危害を生ずる怒れのある薬の販売を禁止し、有効な薬の製造を奨励する-との趣旨から「売薬取締規則」を発令し、従来の売薬の取り締まりに乗り出した。 当時、「神仏・夢想・家伝・秘方・秘薬」などの言葉を用い、「万病に効く」といった、あまりにいい加減な「妙薬」なるものが巷に野放し状態だったからである。富山売薬にとって不幸だったのは、西洋医学を第一とする維新政府関係者あるいは当時の有識者らには、漢方薬などとともに富山売薬の和漢生薬類の薬も、巷の「まがいものの薬」と同様に写り、「効果のない気休めだけの薬」との偏見の目で遇されたことである。 こうした政府の偏見で導入されたのが、明治15年(1882)に布告され、翌16年1月1日から施行された「売薬印紙税」だった。明治10年(1877)の西南の役以降の財政破綻の打開と、その後の伝染病対策費捻出のためとされているが、その背景には、「売薬の薬など害にさえならなければ、あってもいいが、なくなっても一向に構わない-」とする政府の売薬に対するいわゆる無効無害主義の立場があった。 新税は、定価1銭から10銭までは1割、それ以上は5銭増すごとに1銭の印紙を製品に貼付することを義務づける形で課せられた。これは売薬業者にとって大変な重税であった。特に当時、全国の売薬で大さな地位を占めていた富山の売薬業界が受けた打撃は深刻で、同15年に富山の売薬生産額672万円、行商人9,700人だったものが、「売薬印紙税」導入後の同18年には生産額50万円、行商人5,000人にまで激減した。わずか3年でおよそ12分の1にまで規模が縮小したのである。まさに壊滅状態に近かった。 「売薬印紙税」は、大正15年(1926)に廃止されるまで、44年もの間、売薬業界を苦しめ続けた。実は、前述した富山売薬人らの海外飛翔も、海外売薬にはこの重税が免除される特典があったからともされる。
近代薬事法規制度への対応
しかし、明治政府が行った、西欧にならった薬事関係法制などの近代化は、富山の売薬業界などには過酷なものであったが、反面、近��国家建設にとっては当然なことであった。明治10年(1877)に太政官布告された「売薬規則」では、薬の品質確保を重点に、製薬を主とする売薬営業者を規定し、さらに製薬せずに販売だけを行う請売業者、実際に薬を売り歩く行商人といった区分を初めて明確にした。製薬を行う売薬営業者は、「薬の品質に個々に責任を負うべし」とされたため、こうした政府の方針に対応して、より良質な医薬品製造のため明治9年(1876)に現在の広貫堂の前身である調剤所広貫堂が設立された。明治10年代に入ると、富山では売薬業者らが共同で次々と会社を設立し、また、薬学校も設立した。 これには政府も呼応し、売薬に対する考えを「無効無害主義」から「有効無害主義」に転換していく。 それが「売薬印紙税」の廃止につながっていくのだが、それに先見ち大正3年(1914)、政府は「売薬法」を制定し、より有効で安全な医薬品製造のため、西欧先進諸国と同様に薬剤師制度を設け、「薬剤師あるいは薬剤師を使用する者、または医師でなければ薬を調製してはいけない」とした。ここで初めて製薬に「薬剤師」の関与を義務づけたのである。 それまでの売薬業者は、行商から帰っては自宅で思い思いに次に配置する薬を自ら製造し、また行商に出かけた。だが、この「売薬法」制定の後は、薬剤師を使用するか、あるいは薬剤師を雇用している会社においてでなければ製造ができなくなった。また、その薬の処方も、従来のように「家伝」「秘方」などと称して秘密にしておくことは許されず、配合成分を公開することが義務づけられた(各業者は一部に家伝などの未公開の薬も扱った)。 ちなみに「売薬」という言葉は、戦時下の昭和18年(1943)に公布・施行された薬事法の制定まで、現在でいうところの「市販医薬品」の意味で法律上でも使用されていた。しかし、薬事法で薬は「日本薬局方医薬品」と「局方外薬品」に大別され、「売薬」は「局方外薬品」と同一に医療品全般に一括されることとなり、法律の文面から「売薬」の文字は消えた。
「富山売薬三百年」存続の秘訣
富山売薬の家の次男に生まれ、昭和26年(1951)に単身東京に出て、一代で都内を中心に約150店舗、従業員約600名を擁するドラッグストアを育て上げた人がいる。平成12年(2000)9月に東証2部に株式上場も行なった全国有数のドラッグストアチェーンである株式会社セイジョーの創業者で社長の斎藤正巳氏である。 同社は、他の大手ドラッグストアとは少々趣が異なる。社員1人当たりおよび売り場面積単位当たりの売上高が抜群に高いのだ。徹底した社員教育と説明販売で「薬局の東大病院」の異名をとり、利益率はドラッグストア業界ナンバーワンを誇る。その斎藤社長が、経営に積極的に取り入れているのが「富山売薬三百有余年存続の秘訣」であるという。 斎藤社長は言う。「富山売薬とは本来、個人業者のものだ。いろんなことを勉強していて話題が豊富で、話もうまい。知識プラス説得力もある。説得する貫禄もある。また、話し相手のいないご老人の話も上手に聞いてあげる。だからお客さんは『いい話を聞いた』『この人にまた訪ねてきて欲しいから、この人の置き薬を飲もう』という気になった。値引きも言い出さない。これがただの物販だったら、『もっと安くしろ』『もっと安く薬が手に入るよ』となる。富山の売薬さんは置き薬以外のところで、仲人もしたり、田畑の作り方の指導をしたり、いっぱい『タネ』を撒いてきたのだ。これが富山売薬に限らず、ほんとうの意味での商いではないでしょうか」。 同社の社員教育は、まず徹底した顧客へ��接客態度に始まる。挨拶から釣銭の出し方に始まり、それから医薬品などに関する知識へと移る。最近では、ロイヤルカスタマー登録という顧客サービス制度も設け、幾度も来店する顧客に関しては、レジなどで名前で呼びかけるように社員教育しているという。店頭販売において顧客一人ひとりを「個」で捉えるまでに指導しているというのだ。コンピュータによる情報管理でそれがいっそう可能となった。 では、この顧客一人ひとりの「顔」を実際に見て、その一人ひとりに個々に対応してきたビジネスの代表は何か。それは言うまでもなく一軒一軒の家庭を訪ね、その家の人の「顔」と「生活の揚」をしっかりと見て商いを行なってきた、他でもない富山売薬だった。
「礼儀作法」「教養」「モラル」
そうした「他人の生活の場」に足を踏み入れるにあたって、富山売薬人たちは砕身の注意を払ってきた。それには決して欠かしてはいけないルールがあった。それは「正直」であり、「勤勉さ」であり、さらに仏壇があれば必ず手を合わせ、その家のご先祖さまにまで敬意を表するといった「礼儀作法」であった。 置き薬を長年愛用してきた、ある地方のお得意先が作った川柳に、「戸を閉めて、またおじぎするクスリ売り」というのがある。富山売薬人にとっては、薬を売ることだけが商いではなかったのである。その前に、いかに礼偽正しく、美しくお客さんの前で振舞うか、自分の身のこなし、一つ一つをいかに洗練されたものにするかが勝負だったのである。その礼儀正しい態度にお客さんも応え、決して粗末に応対はしなかった。かつて、50年間に一度も値引きをしたことがなかったと話した富山の売薬さんは、その秘訣を「それはひとえに、正しい礼儀作法のお陰です」と語った。 富山売薬が三百有余年の風雪に耐えてきた要因に「先用後利の商法」「懸場帳」等などいろいろ挙げられる。そのいずれもが正しいかもしれない。しかし、それを超えて、その基本にあったものは、顧客を「個」で捉え、「個々」に対応し、その際に「正直」「勤勉」「倹約」を旨とし、さらに「礼儀作法」「教養」「モラル」に裏づけされた売薬人個々の「人間カ」だった。ひとえに、この「ヒト」に支えられて、富山売薬は江戸期から明治・大正・昭和という時代の風雪を乗り越えてきたように思えてならないし、この基本は平成の世になっても、その後も、なんら変わらないのではなかろうか。
わっしょいわっしょい
どうどう!
乾杯しましょう
なにも決まっていないけれど!
きっとなにか良いものに決まる気がするよ
とにかくこのあたりまで、こられてうれしい
抱きつきたいきぶんです!なにかに
なにかと楽しみですよん
おやすみなさぁい
とぅるとぅとぅとぅ〜
0 notes
Text
2016年を振り返る
年末の振り返り、毎年やっている途中に年��明けてしまうのですが、学生生活が終わって、これからの一年一年は積み重ねていくのが大事だと思うので、完成させておきます。
2016年の出来事は大きなところで4つくらいありました。それぞれについて思うことを書いていこうと思います。
大学生活の終わり
西ヨーロッパを旅行する
会社に入る
引っ越した
大学生活の終わり
もう結構前のことに感じますが、修士まで含め6年間を過ごした大学生活が終わりました。やりたいことをやった大学生活だったなあと感じます。少し振り返ってみたいと思います。
実は大学に入る前は機械か情報のどちらかをやりたいと思っていて、受験は機械 -> 情報 の順番でとりあえず志望したのですが、点数の関係で情報系に入ることになりました。それなら両方やってみようと思って、ロボット技術研究会(ロ技研)というサークルで機械・電子工作をやりました。実際に動くものが出来るのは純粋に楽しかったのですが、ハードウェアを扱っていくことで逆にソフトウェアの技術の特徴を認識することにもなりました。例えば、簡単なロボットを作成するのにしても、アルミ材や電子部品、足りない場合は適宜調達、調達後は旋盤・フライスで加工、と言った工程が必要になります。工作好きとしては楽しいものでしたが、高校時代に経験した、ソフトウェア(ゲーム)を作ってインターネットを通して友達に使ってもらった経験からすると、自分がやりたいのはそちらではないと感じました。この点は、ジョナサン・ジットレイという人の書いた “The Future of The Internet”(邦題:『インターネットが死ぬ日』)という本でより構造的に説明されています。汎用性に加えて伝搬性や習熟性など、いくつかの条件が揃った道具は、それ自体から新しいものを生み出す肥沃な(generativeな)システムとして機能する、というような議論です。

インターネットが死ぬ日 (ハヤカワ新書juice)
ジョナサン・ジットレイン 早川書房
もうひとつ、大学の研究室を取材して学部生に説明するメディアを発行している団体にも所属していました。理工系という枠の中ではあるけれど、特定の分野に依らない環境というのは当時は貴重で、ここで人と話したことがあとあとの科学全体への理解に役に立った気がします。
そういった学生団体以外のところでは、プログラミングの本を読んだり、バイトをしたりしながらふらふらやっていました。今では手に入りにくいみたいですが、『コンピュータプログラミングの概念・技法・モデル』という分厚い本を時間をかけて読んだのが良い思い出です。

コンピュータプログラミングの概念・技法・モデル (IT Architects' Archiveクラシックモダン・コンピューティング)
セイフ・ハリディ ピーター・ヴァン・ロイ Peter Van-Roy Seif Haridi 翔泳社
この本はその名の通りプログラミングの本なのですが、プログラミングを統合的な学問として教えるのはどうすればいいか?ということを意識して書かれたもので、いま思うと非常にビジョンに溢れた仕事でした。この本を読むことで、状態(state)や並行(concurrency)といったソフトウェア概念への正確な理解から、そもそも抽象化とは何か?という根本的な話まで、知ることができました。
抽象を設計することは必ずしも容易ではない。いろいろな考え方を試し、破棄し、改良し、といった長くつらい道のりになることがある。しかし、その見返りは非常に大きい。文明はよくできた抽象の上に建立される、といっても過言ではない。毎日、新しい抽象が設計されている。車輪やアーチといった古代の抽象のいくつかはいまに残っている。セル電話のような新しい抽象のいくつかは速やかに現代の日常生活の一部になった。
良い本を読むたびにいつも思うのですが、その本の射程距離と言うか、書き手が読み手をどこまで連れて行ってくれるかは、ほとんどの場合、序文を読めば鋭敏に分わかります。最初の問いかけが、問題意識が、その可能性としての範囲を決めている。
そういえば、ずっと昔、高校生のときに読んだこの記事なんかは、そういう思考の"強度"みたいなものの存在を知った最初のものでした。
ネットに時間を使いすぎると人生が破壊される。人生を根底から豊かで納得のいくものにしてくれる良書25冊を紹介 - 分裂勘違い君劇場
これは自分の話ですが、技術を手に入れると、最初、何かを作れるということ自体に喜びを見出します。しかし、少し考えてみれば、世の中には、素晴らしいと思うモノもあれば、そうでもないと感じるモノもある。
それを分ける違いってなんだろう?「価値」って何だろう?「意味」ってどうやって生まれるんだろう?…実はそういうことを抜きにして技術だけを持っていても、真に納得のあることってできないんじゃないか――もしかしたら専門特化で市場価値だけは手に入れられるかもしれないけど、それは現代において幸せとは関係が薄い――、そういうようなことを思ったのが大学生活の中頃だったように思います。
それからは、デザインみたいなものづくりに近いところから始まり、思想、 言語、社会みたいな、かつて興味を感じていたけど離れていたものに触れたり、あるいはゲーム、エンターテイメントを好きなだけ体験しました。そして今では、そこで得たもの抜きで何かを思考することは考えられないくらいに、世界の見え方が質的に変わりました。

ソシュール 一般言語学講義: コンスタンタンのノート
フェルディナン・ド ソシュール 東京大学出版会
例えば、自分の使っている身近なサービスであっても、それを単に機能と見なすのか、大きなマクロの流れを見据えた人間の行動と見るのかで、感じられる価値って圧倒的に違ってきますが、これってその周辺に対する文脈的・構造的な理解なしには得られないものです。同様に、エンターテイメントを咀嚼していけば、小さなできごとにものすごく大きな意味がありそれが面白さに深く関わっていることが分かるし、ゲームは、最近よく描かれるように、「仮想的」なものに内的な意味が生まれてそれが「現実」への問い掛けとして機能します。
先に紹介した、良い本や物語が人生を豊かにするという高校時代に出会ったイデオロギーは、こうして自分の中で消化されていきました。
1990年代から2010年代までの物語類型の変遷~「本当の自分」が承認されない自意識の脆弱さを抱えて、どこまでも「逃げていく」というのはどういうことなのか? - 物語三昧~できればより深く物語を楽しむために
実を言うと、「専門」外の方向に向かった背景として、ここで書いた以外にも、理工系の大学にいてそこで用いられる枠組みに、それだけでいいのか?という感覚や、枠組みを用いるときにその特性を理解しておきたいということもあったと思います。ただそれは経緯というかきっかけであって、今もそういったものに価値を感じるのは、単純にそれが豊かだという以上の理由はないです。
西ヨーロッパを旅行する
大学生活最後の春休みには、イギリス・フランス・ドイツの西ヨーロッパ地域を一ヶ月ほど一人で旅しました。大きく時間を取れることもしばらくないからというよくある考えですが、この地域を旅行先に選んだのは、前述のような思考履歴を辿った自分にとっては、ごく自然な流れでした。
現代から遡る形で勉強していくと、いかに多くのものがこの地域世界から流れてきているかということを痛感します。日本だと、明治以降、いわゆる近代化ですが、そのことは、渡辺京二の『行きし世の面影』を読んでより強く自覚しました。この本は幕末-明治に日本を訪れた西洋人の記述を集めて、在りし日の「ある文明」を描写したものなのですが、読んでみて驚くのは、その世界を現代に生きる僕は、その時代の日本人ではなく日本を訪れた当時の西洋人の視点から(!)解釈・理解してしまうことなんですね。それほどまでに異なる秩序を持った生活世界がかつてあり、それがある時代を区切りに全く別の存在になったことを以って著者は「文明が滅んだ」と言っているわけですが、ともかく、現代日本がその多くを西洋近代文明に負っているということをまざまざと認識されられた本でした。
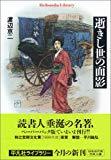
逝きし世の面影 (平凡社ライブラリー)
渡辺 京二 平凡社
話を戻すと、旅行はイギリス・ロンドンから始めてイングランドの地方を周りつつ、フランス・パリに移動。そこからドイツのバイエルン地方をいくつか街を経由しつつミュンヘンまで行きました。
月並みな感想ですが、実際に行って見て理解できるものって、全然、本とかで読むのと違いますね。イギリスとフランスの違いとか、歴史を知れば文脈的な立ち位置とか理解できますけど、行ってみるまで感覚として理解できてなかったなと思いました。ロンドンからパリに移動して一歩街に足を踏み入れただけで、一日街を回っただけで、こんなに違うのかと感じました。こういうことは総体としてそう感じるものなので、短く言葉にするのが難しいところはありますけど、例えばロンドンの街では英語が基本で、なんと言うか、国際都市としては純度が高く感じました。それがパリに踏み入れるとあらゆる言語が入り混じっている。あるいはミュンヘンの酒場に行けばスイス人やイタリア人が出張で来ていたりする。自分は子供の頃インドネシアに住んでいたこともありますが、考えてみればそれも島国で、実はこれまで「大陸」に行ったことがなかったので、普通に外国人がちょっと移動して来るみたいなのは感覚としてありませんでした。その点一つとってもイギリスの立ち位置って違うなと思いましたし、ちょうど返ってきて少し後で Brexit がありましたけど、それまで積み重ねられてきたヨーロッパ統合の流れの転換点になる出来事でやはり衝撃を受けつつも、納得するところもありました。

イギリス 繁栄のあとさき (講談社学術文庫)
川北 稔 講談社

フランス史10講 (岩波新書)
柴田 三千雄 岩波書店
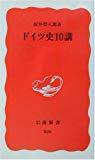
ドイツ史10講 (岩波新書)
坂井 栄八郎 岩波書店
こうやって実際に行ってみるとその後もより色々な出来事を面白く感じるようになったので、またどこか行きたいなあ。
あと、宿泊は全て Airbnb で行いましたが、これは旅行体験を別の次元に引き上げてくれる、本当に素晴らしいサービスだと思いました。機会があればちゃんと書きたいところですが、現代みたいに世界が近づきつつある(と思っていたら2016年はそれに逆行する出来事が象徴的な年になりましたが)時代って当然文化的なコンフリクトも色々起こるとおもうのですが、それを暮らしというミクロなレベルから地道に解決していくアプローチは、プラクティカルではあるけど妥協の無いもので、僕はとても好きになりました。
Wantedly に入社する
4月になって、本格的に働くときが来ました。働く先は Wantedly という会社に決めていました。会社選び、かなり多くのパラメータを使って決めていて、自分が考慮したなと意識したものでも普通に50個くらいはある気がするんだけど、ざっくり言うと、エンジニアリング・カルチャー・ビジョンの3点で良いと思ったと言えば近い気がする。
ここでビジョンについてだけ言及すると、熱中して仕事に取り組むような人を世の中に増やす、という目的でやっています。僕はこれを見たとき、ああ、これって今やることに意味があることだ、と思いました。
これは結構早い段階で思っていたことですが、正直、今の世の中食べていくだけですごい困ることはなくて、娯楽もインターネットにつなぐだけでコンテンツに困ることもないですよね。これって結構すごいことだと思ってて、また、同時に新しい問題を生むとも思います。
過去を振り返れば、戦後とか食べることがリアルに重要な問題であるときもありました。その後の高度経済成長の時代も、結構「物」を手に入れるということに価値を感じていた時代だと思ってます。「機能」にお金を払うことが多かった、と言ってもいいかもしれない。
実際問題として、平均的な大衆のために開発された、どれも悪くはないが実のところ本当には自分にフィットしていない商品群に出会うのが、二十世紀の商品棚の典型となる - x-DESIGN
一方、当時、僕が iPhone を買うとき、何に対してお金を払っているんだろう?と考えたとき、純粋に何かが出来るということ以上に、新しい何かを見せてくれるのではないかという「期待」や、製品のディテールにこだわるという彼らの行動様式への「共感」に対して払っている部分が大きい、と感じていました。そして、そういう行動は自分以外にも普遍的に見られるように思えたし、エンターテイメントもこの傾向を反映しているように見える。
この考えを仕事というものに敷衍していくと、近代以来の時間を対価とした労働観念も、少しずつ変わっていくのかなと思いました。そして、そこではいくつかの選択肢があるべきで、その中の一つとして、仕事って面白い、と思ってそこに金銭的対価以上のものを見いだせるという選択肢が用意されるべきだと感じていました。ここで少し強い言葉を使っているのは、当時、もしかしたらその選択肢があれば選んだかもしれないけれど、無いがために選ばなかったと感じた事例を見たからでした。
なんか、色々話を聞いていると「退却」してしまう人が多いなと感じていて、それはそれで戦略としては正解なんだと思うんだけど、やっぱりどこか残念だと思うよね。
もちろん、趣味に生きるのはすごくありだと思ってて。自分自身、しばしばそっちに振っていたし、それで最後まで楽しそうにしていた人というのも知っている。
なのだけど、それはナチュラルにそうであったという場合であって、「退却」するケースというのは、だいたい最初に希望があって、それを全うできない「疲れ」がそうさせたみたいなストーリーになっている。
趣味に生きるのは良いけど、趣味に生きざる負えないみたいなのは、残念だ。
残念な事象が類型化されると、そういう風になってしまうシステムが残念だという思いに至る。だから、ここで言う残念というのは、人ではなくて構造に向かっている。
構造と言っても色々なレイヤーで見ることができて。
いちばんは、そういう事象が生み出されるのが、構造と要素のミスマッチによるものであるということ。
そして、そういうミスマッチが生み出されるような構造によるものだということ。
さらに、それを生み出す構造が維持され生き残るような、文化によるもの。
…何やら話が少し重くなってしまいましたが、そういう経緯もあり、仕事自体はかなり楽しんでやっています。個別の内容については今は振り返るほど過去にはなっていないので、このあたりにしておきますが。
引っ越した
2016年後半の個人的にエポックメイキングな出来事は引っ越しでした。大学のある大岡山から、会社のある白金台へ。2ヶ月前に出来た家賃補助制度を活用して、1ヶ月前に出来た部屋に引っ越しました。会社まで徒歩1分のところにあり、めちゃくちゃ落ち着いている。

住居、何を求めるかだと思っていて、「寝る」という機能だけを求めるのか、「生活する」基盤にするのかで違ってくるというのがありました。
大学時代の部屋は正直そんなに居たいと思えるような部屋ではなくて、それは採光や諸々のデザインの制約で変えられないと思っていて、ただそれでずっと不満はなかった。なかったのだけれど、「生活する」というのをしっかりやると、そこで感覚のチューニングもできるようになるし、意外と大事だなーというように考えを変え、ここには投資しました。結果的には、驚くほど生活の質が上がったので、これは完全に正解だったなあと思います。
ここでは備忘も兼ねて、引っ越しの際に考えたことを4つくらい上げておきます。
ポテンシャルのある部屋を選ぶ
まず、経験的に、部屋は、生活の質の上限を決める。これが部屋の定理。
そもそも綺麗でないと綺麗に保つ気にならないという意味で、きれいである必要があるし、ベースとなるデザインが良くないと結構どうしようもない。窓やそこから見える景色は変えられないので超重要。また、キッチンが部屋と分離されていると使わないという自分の経験則があったので、インテグレートされているのが望ましい。また、広さはそんなに必要ないことも分かっていて、それ以外を優先する。
徹底的な断捨離
ネットで見つかるきれいな部屋の隠れた法則として、そもそもものが少ない、というのがある。
このため、3週間くらいかけて、本当に自分に必要なものとそうでないものを選んで、処分・売却していった。この結果8割くらいのものを処分することになり、引っ越し先でもものが溢れずに済んでいる。
とは言っても、思い出のもので捨てづらいとかもある。そういうものはひとしきり懐かしんだあと、写真を撮って送り出す。ありがとう。
生活サイクルの再設計
おそらく超基本的なことなんだけど、掃除、洗濯、食事をまともにやれていなくて部屋がゴミのようだった。それもあって部屋にいる時間がゼロに近いかたちで運用していた。次の部屋でそうならないように、適切なタイミングの設定と、それを行うコストを下げるように色々導入した。
これはちゃんと成功していて、今は部屋は綺麗に保たれていて、洗濯も定期的に行っていて、とても精神衛生が良くなった。
生活空間の再設計
部屋は広くはないので、そもそもの部屋でやることを絞るというのも重要だった。会社が近いので本格的な事務作業は全て切り捨て、平日の寝ることと、休日の食事しながら本を読んだり映画を見たりすることにフォーカスした。本とエンターテイメントがあれば幸せに生きていける。
基本的な知識がないと良いものはできないので、インテリアの本を一冊買った。インテリア本、イケてる部屋の例みたいなのを載せてるだけのものが多くて微妙な感じだったけど、マンション・インテリアに特化したものを見つけて買った。

ライフスタイルを生かす マンション・インテリアの基本
新星出版社 (2016-07-01)
その他、集約する方向ばかりだと面白くならないので、事前に Pinterest で良さそうなものを集めてイメージをふくらませたり、インターネットで色々面白そうな部屋の使い方を仕入れたりという感じで、引っ越しプロジェクトは大変だったけど結構楽しかったです。
おまけ:2016年個人的エンターテイメント史
2016年の後半はやはり映画が熱かった
『シン・ゴジラ』『この世界の片隅に』『君の名は。』『聲の形』は残ってる
ラノベは好きなタイトルが軒並み続編が出なくてかなしい
『ログ・ホライズン』『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。』
マンガはまずまず順調
2017年はそろそろ『ヒストリエ』10巻が出ることを期待
2017年について少し
今年について簡単に思ってることを書いておきたいと思います。
まず、仕事の面は、ちゃんとコミットすることでこそ得られるものがあるというのが自分の中で実証されました。今しばらくこのままいろいろ積んでいきましょうという感じです。
あと、これは意図的にそうしていた面もあるのだけど、2016年の4月以降はほとんど本を読んでいなくて、これはそろそろ変えたいなと思っています。いま振り返ってみても、色々なポイントでの判断にそこの積み重ねが活きているのはやっぱり間違いないので。
その他、生活面では、もっとエンターテイメントを消費していくこと、本格的に料理を始めること、 プロジェクタを買いたい、とか色々ありますけど、まあここはなるようになれという感じですね。
そんな感じで2017年もよろしくお願いします。
1 note
·
View note
Link
TEDにて
エリック・ディシュマン:医療をメインフレームから取り外そう?
(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)
TEDMEDでエリック・ディシュマンが大胆な発言をします!
米国医療システムは、病院、医師、老人ホームなどからなる巨大中央システムによって縛られ、まるで、1959年頃のコンピューティングのような状態に陥っているのです。
先進国では、高齢化が進む今、全ての人が利用できる、より個人的であり、かつ周囲の機関とのつながりがしっかりしていて、介護など家庭を基盤とした医療管理に注目することが重要だと彼は力説します。
しかも、インテルが研究を支援しています。
電話のことを考えるとインテル社は、今日お見せする多くのことを、この10年間に約600の高齢者家庭で試してきました。アイルランドで300軒。ポートランドで300軒。そして、人の行動をどう測り、モニターしたら医学的に最も有意義か?という課題に取り組んできました。
前提として、本人の許可なく行うことは、プライバシーの侵害になり、基本的人権の侵害です。
電話のことを考えてみましょう。いろいろな使い道があります。正しい薬を正しいときに飲む助けになります。このようにシンプルなセンサネットワーク技術を家庭で試し、高齢者が、すでに使い慣れている電話が薬を飲む役に立つだろうと考えています。
しかし、現実は、監視されている気持ち悪さを感じるのでおすすめしません。
高齢者が、電話をとると服用すべき薬を教えてくれるメッセージが聞こえてきます。彼らは、単に友達と会話をしているふりをすればいいのです。キッチンのテーブルに置いてある年寄り、ひ弱とでも言いたげな薬入れに恥を感じなくていいのです。こんな密かなテクノロジーが薬を忘れずに正しく飲むという単純なことの役に立つのです。
こういうのを行動指標といいます。他にもいろいろあります。例えば、電話が鳴ったら答えるのに以前より時間がかかっているか?耳が遠くなったのか?それとも、体が不自由になったのだろうか?声が以前より小さいか?アルツハイマーや特にパーキンソン病の方の研究をしました。
時にパーキンソン病患者に聞かれる小声が、病気が臨床的に明らかになる5年から10年も前に最も早期の指標になるかもしれないことが分かってきました。ただ、こんなかすかな声の変化は、気付き難いため、患者自身や配偶者は極端に声が小さくなるまで気付きません。
しかし、現実は、監視されている気持ち悪さを感じるのでおすすめしません。
電話のセンサーはそんな声に注目しています。受話器を取ったとき、どれくらい手が震えていて震えの具合は、時とともにどのように変化しているか?以前より、ボタンを押すのに苦労しているか?不器用なためか?それとも、関節炎の始まりだろうか?頻繁に電話するか?以前より非社交的になっていないだろうか?傾向に注目するのです。
アメリカ以外では、かかりつけの医者に相談すれば良いので余計なお世話ですが・・・
社交性の減少は、将来の身体的健康の指標なのだろうか?何て画期的なアイデアでしょう。アメリカ以外では、このような全く新しい技術を利用して電話の向こう側のナースやドクターと会話できるかもしれない。実際にこんなことが、できる日がきたら 何て素晴らしいことでしょう。
前提として、本人の許可なく行うことは、プライバシーの侵害になり、基本的人権の侵害です。
医療改革法案は、もっぱら老化現象の実状を無視しています。また、私達が変えなければいけないのは、どうやって介護費を支払うかだけでなく、介護の革新的な提供方法が必要だということも推測できます。この問題は私達にかかっているのです。
メインフレームとは、医療機関にお金をかけて、みんなで行って共同使用するという概念は、1787年に始まりました。
これはウィーンにある初の一般病院です。ウィーンに第二の一般病院が建築されたのは、1850年頃で徹底的な医学カリキュラムを開発して、医学生に専門科目を教え始めました。また、ここで開発されたまさに人体を分割するという考え方や医療を別々の診療科や区画に分けるという構造が生まれました。
私たちの医療構造もそれに倣い、医学教育もその影響を受け、今日までこのメインフレーム思考が持続しています。
さて、私は、反病院思考なわけではありません。自分の病気に薬物治療を受けたり、様々な病院を受診したこともあります。しかし、私たちは高台にある病院をすごいと思いがちです。そうこれがメインフレーム医療なのです。
そして、たった30年前には、今、使っているような技術は考えられませんでした。以前は、この部屋の大きさほどあったメインフレームコンピューターが、今ではバッグやベルトにつけている携帯電話の中にあるのです。コンピューターという、以前は、専門家に管理されたシステムが、突然、皆さんが日々利用する個人的なシステムになったのです。
このようなメインフレームからパーソナルコンピューターへの転換を医療にも応用するべきです。メインフレーム思考の医療から個人中心型の医療に移り変わらなければ、ならないのです。
2021年の段階では、もっと進んでスーパーコンピューターがバッグやベルトにつけているスマートフォンの中にあります。
私達はこのような考え方にはまり過ぎています。インテルが、世界中の人に「医療と聞いてまず思いつくのは?」と聞くと、一般に最初の答えは「医師」です。二番目の答えは「病院」そして、三番目が「病気」。
私達の想像力は、医療や医療改革といえば、こういう所で起きるものだと型にはめられています。今、進行している医療改革や医療IT技術の議論について医療政策立案者に訊ねるとメインフレームにある電子病歴をどうやって医師に使わせるか?そればかりです。
メインフレームから家庭へと移行する方法など頭にありません。この問題の根源は、私達の医療の認識にあります(2020年の新型コロナウイルスのパンデミックで認識は変わっています)
今のシステムは反応的であり危機対応型です。診療時間は15分。医療は、全人口レベルでとらえていて、この人工的な環境の中で生体情報を集め、そして、患者をさっと治して家に返します。冊子を渡したりネットのサイトを教えたりして、指示を守りメインフレーム(医療施設)に戻ってこないよう期待します。
皆さん。こんな方法ではもうやっていけません。メインフレーム医療では無保険者まで治療はできません。それでも何倍にも膨れ上がる高齢化の波を処理しようとしています。これまで通りの医療方式は破産です。何か新しい対策が必要です。家庭に注目しなければなりません。
しかし、2020年の新型コロナウイルスのパンデミックで破綻しました。
医療を家庭に移動させる個人的な医療対策に焦点を当てることが必要です。先取りした予防的な対応をどうすればよいでしょう。どうやって、休みなく生体情報などを測定するか?どうやって患者特有の標準値を得るのか?家の中や周辺における生体情報に限らない行動、心理についての情報をどうやって収集すればよいのか?
どのように治療の指示を守らせることで私たちの行動を変容させるための素晴らしい技術を使った個人向けカスタム治療計画となるのでしょう。これこそが個人向け医療モデルに対して必要なことです。
なお、ビックデータは教育や医療に限定してなら、多少は有効かもしれません。それ以外は、日本の場合、プライバシーの侵害です。
通信の秘匿性とプライバシーの侵害対策として、匿名化処理の強化と強力な暗号化は絶対必要です!
2014年の頃に、話題だったウェアラブル端末による健康管理などのアプリケーションは、この頃からコンセプトが始まっていることが非常に良くわかります。
現在では、2015年にAppleWatchも発売されているので、心拍計も記録できるようになっています。腕時計型ウェアラブルコンピューターでスマートウォッチとも言われる。
Apple Watchの搭載チップは、振動にもつように完全に樹脂でコーティングされてるために、コンピュータシステム全体を一つのチップに組み込んでるそうです。
多くの場合。2種類の介入が可能です。
骨折の治療と処方を調整することです。私は、定性的データを研究対象としていますが、本人の許可済が前提ですが、家庭から送られてきたデータを見れば、どこかの医者が知らないうちに新しい薬を処方した日にちを推定することができます。家庭内での移動パターンに明らかな変化が見られるからです。
このような行動指標や行動の変化についての発見は、医療に非常に重要な影響をもたらす。顕微鏡の発見のようなものなのです。データストリーム収集という初めての試みが可能にしたことです。
ORCATech.orgのサイトを見てみてください。シャチ(orca)とは無関係です。オレゴン老化医療センターです。そこにもっと詳しいことが載っています。インテルは、今でも世界有数の自立生活支援技術に関する研究のスポンサーです。
多くの資金提供を自慢しているのではなく、問題なのは、他の人達が老化に無関心で新しい対処法、慢性疾患管理、自宅での自立生活に関する研究への援助が極端に少ないということです。
自立生活支援技術に関して、実施するために大規模の高速ネットのつながった高齢者家庭に対して、漏れのない医学的分析や研究を開始するための基盤を提供し、大学がスポンサーとなって進めてきた家庭での事例紹介的調査を大規模な臨床実験に発展させ、これらの技術の重要性を証明する必要があります。
日本では生物学や先端医療、iPS細胞などの再生医療以外は現状維持の方がいいかもしれません。
日本には、国民皆保険があります。
クラウドコンピューティングが、主流になっている現在では、医学に関しては、基本的人権も尊重しないといけないため、緩やかに成長させれば問題ありません。
将来には、フォトニックプロセッサーや量子コンピューターが登場する可能性もあるので急ぐ必要はありません。
情報技術の発展とインターネットで大企業の何十万、何百万単位から、facebook、Apple、Amazom、Google、Microsoftなどで数億単位で共同作業ができるようになりました。
現在、プラットフォーマー企業と呼ばれる法人は先進国の国家単位レベルに近づき欧米、日本、アジア、インドが協調すれば、中国の人口をも超越するかもしれません。
法人は潰れることを前提にした有限責任! 慈愛や基本的人権を根本とした社会システムの中の保護されなければならない小企業や個人レベルでは、違います��・・・
なお、ビックデータは教育や医療に限定してなら、多少は有効かもしれません。それ以外は、日本の場合、プライバシーの侵害です。
通信の秘匿性とプライバシーの侵害対策として、匿名化処理の強化と強力な暗号化は絶対必要です!
さらに、オープンデータは、特定のデータが、一切の著作権、特許などの制御メカニズムの制限なしで、全ての人が
望むように再利用・再配布できるような形で、商用・非商用問わず、二次利用の形で入手できるべきであるというもの。
主な種類では、地図、遺伝子、さまざまな化合物、数学の数式や自然科学の数式、医療のデータやバイオテクノロジー
サイエンスや生物などのテキスト以外の素材が考えられます。
こういう新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との
戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど
しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!
ヨーロッパでの一般データ保護規則(GDPR)でも言うように・・・
年収の低い個人(中央値で600万円以下)から集めたデータほど金銭同様に経済的に高い価値を持ち、独占禁止法の適用対象にしていくことで、高価格にし抑止力を持たせるアイデア。
自分自身のデータを渡す個人も各社の取引先に当たりデータに関しては優越的地位の乱用を年収の低い個人(中央値で600万円以下)に行う場合は厳しく適用していく。
<おすすめサイト>
量子コンピューターの基本素子である超電導磁束量子ビットについて2019
ついに、Appleシリコン搭載か?
ヒラリー・コッタム:機能不全の社会福祉システム制度を立て直すには?
ジュラルディン・ハミルトン:「臓器SoCチップ」がもたらす未来!
フレデリック・バラガデ:マイクロチップの上のバイオ研究所ラボ
データ配当金の概念から閃いた個人的なアイデア2019
ダニエル・クラフト: 医学の未来ですか?アプリがありますよ!
エリク・トポル:無線通信(Wi-Fi)を使うこれからの医療
ルシアン・エンゲラン:クラウドソーシングによる健康管理
キャシー・オニール: ビッグデータを盲信する時代に終止符を!
<個人的なアイデア>
アメリカのノーベル賞受賞経済学者ミルトン・フリードマン、元FRB議長であったベンバーナンキの書籍「大恐慌論」も言うように、金融危機2008、コロナショック2020などの急落に直面する対策として、ゼロ金利、マイナス金利、金融政策が出尽くした後に、よく登場する最速実行再分配政策が、個人への緊急的な現金給付!!!
各国によってスピードは異なるが、政策閣議決定後、人間の限界を遥かに超えるスピード。1秒以内で現金到着が理想。各国競争してみれば、今後の恒久対策として中央銀行のデジタル通貨なども考慮しつつ、新産業が産まれプラスサムになるかもしれません。
MMT(Modern Monetary Theory)によると、現状の貨幣での現実的なアイデアとして、社会保障に還元される日本の消費税は現状維持しつつ、現金給付額にも消費税がかかるので現金給付額を上げて、毎月給付にすると消費税率と社会保障費下支えとが均衡状態になる?と同時に、実体経済の経済成長率「g」の下支えにも寄与する?
これらの総量が、急激な不況時の資本収益率「r」以上なら、もしかして?回復して正常な経済環境に戻る期間も短縮できるかもしれません。
スペイン風邪から国民皆保険を構築した岸総理(他には、国民皆年金、最低賃金法もあります)現政権の安倍総理、母方の祖父を見習いコロナウイルスから、毎月の国民皆給付を構築すれば歴史に残る業績になるし、継承する権利もある!
現政権の安倍総理、麻生副総理。この二人でしかできない天命を果たせ!アベノミクスの最終地点がコレだ!この絶妙のタイミング!
天命と言わずにはいられない!
感染症との戦いは、人類の宿敵とも言っていい未知のウイルスとの戦争です!
今までは、パンデミック時の対策としてデータのないスペイン風邪の書物や言葉を参考にしていたが、インターネットの発展やCPU、GPUがムーアの法則によりスーパーコンピューターの領域に現代は突入している。
情報技術が発展し、スマートフォンとして手のひらサイズに収まり、ウイルスを感染予防するための距離を広げながらも、データとして全世界と光速で共有できるため、そのスピードとウイルス伝播のスピードと伍している?
局面ごとに対策を適性に行えば伝播速度を上回りコントロールできる感じもある!ラリーブリリアントが構築したシステムの功績もあります。
量子コンピューターも量子超越性を達成してることもプラスです。
ジョンズ・ホプキンス大学のシステム科学工学センター(The Center for Systems Science and Engineering:CSSE)感染者ダッシュボード
新型コロナウイルスの場合、新規感染者数が、2倍になる日数が10日以上になれば、R0(アールナート)が1以下に減衰してピークアウト状態になると理解できる。
日本の場合、PCR検査の結果が判明する14日後より短いから、検査結果日数を10日以下にできれば、ヤキモキせずスピード感ある判断が可能になりそうだ。
つまり、未知のウイルス。アウトブレイク発生確認後の緊急事態宣言発動は、クラスターが発生しやすいチェーン店などの大規模な場所から早期閉鎖が原則とデータから判明した!
日本の場合、アウトブレイク発生確認後から緊急事態宣言発動までの余裕日数は、新規感染者数が、2倍になる日数です。例えば、5日で2倍なら、5日以内で初動初速最大化発動しないと危険ということ!
R0が2.5付近では、発動日から10日でピークアウトが最速値。7、8割の人の外出制限要請StayHome(元々、人がいない地域での7、8割削減は意味ないし不可能だから政令指定都市だけにすること)ソーシャルディスタンス。などの初動初速最大化すれば、収束までさらに10日で計算上は20日で解除可能領域に近づける目安となります。
生産管理手法のクリテカルチェーンもリアルタイムの感じた感覚で考慮すると余裕バッファーをもう10日で、ひと月。えっ。ここまで自分で書いてよく見ると現実の数値にかなり符号する。
休業要請解除を10段階くらいに分けて地域ごとに段階的に基準を決めて行う。
日本の場合。緊急事態宣言、休業要請は現金給付や保証とセットで最速実行が原則。
日本の場合、透明性を持たせて休業要請解除の基準を決め、きめ細かく設定しないと現在の都知事とか権力者の気分で権力濫用されたり選挙に悪用される危険性がある。
今後の医療崩壊回避のため、医者を含めた疾病や保健所などの医療従事者を単純に現在の倍に育てて増員したら余裕バッファーが半分くらいになりそうな直観が出た。
今後は、休業要請解除!スペイン風邪同様第二波三波、第四第五の小波に備え、国からの現金給付支給をもう数度実行してもいい。Rtが1以下になり次第、休業要請解除!の後に、緊急事態宣言を機動的に解除。
この局面でもっとも効果的なソーシャルディスタンス領域をかんたんに実行。かんたんに実現できる小規模な所から。
時間軸のあるR0をRtとした都道府県別。新型コロナウイルスリアルタイムデータ
クラスター発生地点の見守りを継続する。再びアウトブレイクになり次第。最速で緊急事態宣言を再び発動して、1年かけて5、6回繰り返し、新規感染者数をピークアウトさせて分散、減少させていく!
何度も言うが、スペイン風邪同様第二波三波、第四第五の小波に備えるため!
小池百合子都知事という悪徳政治家は即刻辞職して、後世の女性への権力に固執しない手本を示し、的確に新型コロナウイルス対策できる人間に変われ!以下の指摘3つを真摯に受け止めて瞬時に改善しろ!(全世界に拡散希望)
1)休業要請緩和の各ステップの目安日数(1週間の平均感染者数:20人未満、感染経路の追えない感染者の割合:1週間平均が50%未満、1週間単位の感染者の増加比:1以下)をごまかして各段階を具体的数値で表現しない。クソロードマップだ!!今回の都知事選挙のために政治悪用してるのは明白!!的確に新型コロナウイルスに対策できる人間に変われ!
2)再要請の目安(1日の感染者数:50人、感染経路の追えない感染者の割合:1週間平均が50%以上、1週間単位の感染者の増加比:2以上)も隠すように表示してるクソロードマップだ!今回の都知事選挙のため政治悪用してるの明白!!的確に新型コロナウイルスに対策できる人間に変われ!
3)2週間単位じゃなく1日単位にしないと一つず���緩和のステップを進めていく意味がないクソロードマップだ!!今回の都知事選挙のために日数伸ばすために政治悪用してるのは明白!!的確に新��コロナウイルスに対策できる人間に変われ!
具体的には、2020年5月中旬に、緊急事態宣言を1日単位でスピード解除(現都知事は、説明責任をせず気分で言葉を変えて言葉で惑わし政治悪用するので、数値を基準にした休業要請を1日単位でスピード解除)を早期に行う。
こうすることで、マクロ経済的にもバランスを維持していく。
前提として、直近1週間10万人あたり新規感染者0.5人位?(わかりやすく言うと、1400万人いる東京都は7 日間で、70 人位。一日7人位)で緊急事態宣言解除。
他には、神奈川県は46人位一日6人位。埼玉県は37人位一日5人位。千葉県は31人位一日4人位。とざっくりとした目安になります。
以降は、30日間経過観察し2回目に備える。オーバーシュートし始めたら2回目の緊急事態宣言を再び発動(現金給付とセット:一回目の延長の分も含めて一律20万円)し、1回目と同じように繰り返し、50日でスピード解除。つまり、最速80日周期で1年かけて4、5回繰り返し、新規感染者数をピークアウトさせて分散、減少させていく!
データから判明した6割程度の人の接触制限(元々、人がいない地域での削減は意味ないし不可能)で増加しないフラットな均衡状態を維持できる。
しかし、わかりやすく言えば、10人を4人にし続けたら商売にならないのは明らか。これでは、マクロ経済活動を維持できないため、その減少分を法人は、巨額な内部留保があれば、それを金融工学で資金繰りを下支えしつつ
国民皆給付で一律毎月10万円の庶民生活を下支えし続ける!(ボーナスも危ういので多少なりとも毎月気持ち分補助してもらう)これがベスト。
新規感染者を数人位の緊急事態宣言解除直後の低水準で均衡させつづければ、6割程度の人の接触制限してマクロ経済を維持できそうな感じは現時点ではする。
7月になり、小池百合子は公約も実現してないのに再選した稀代の悪女!自ら辞めて責任もとらない。昨年は、モンテスキューの「法の精神」も言う権力分立の原則を無視して国政と都知事を兼務しようとする悪い女性の見本と判明(全世界に拡散希望)
新規感染者も四月の水準に数の上では迫っている!
しかし、検査数と新規感染者の割合を見ると七月の水準では四月ほどではなく、さらに、退院者数を引いて見る。医療提供キャパシティ数が不明で数値を出して欲しいが、これらを考慮すると•••
再びの緊急事態宣言は、新規感染者が現状4桁到達。人口規模が大きい東京都が1000人以上なら実行する価値はある!現金給付とセットで!(検査数、医療提供キャパシティ数が増えれば2000、3000でも耐えられるかも?これはまだ未知の領域)
7月の重傷者数も4月の水準ではないので、4月の水準に近づき次第。再びの緊急事態宣言で良いのではないか?そんな感じもします。
海外の結果は、アメリカ、ヨーロッパは速めにロックダウンした(日本は緩いロックダウン)
スウェーデンは独自の社会実験でパンデミック中に行政府がほとんど行動制限を加えず、通常の生活を続けるとどんなことになるか?結果は変わらない。
自ら感染を広げただけで、経済的に何の得にもなっていないらしい。人口100万人当たりの死者数が世界的にも高い水準になってしまった。重症者増加悪化する。ロックダウンが経済悪化の原因ではないこと。すべての原因はウイルスそのものの伝播力と判明。
日本は湿気の多い夏の時期でも、この伝播力の怖さが明らかになる。実効再生産数1.5から2くらい。
歴史の経験が実証されデータが得られワクチンや治療薬が重要という昔のパンデミック時の教訓が正しいことが世界中で再認識された。
PCR検査などを抽出から全数に変えても統計上はあまり変わらない。前提として、数値の量や正確さにこだわらず測れるのが統計。量子力学に多用されてる。統計には、全数と抽出がある。
むやみに、感染者を排除しても基本的人権を侵害するだけで感染者差別を産む可能性もある(マスクの有無で既に差別的になってる)
ハンセン病患者の強制隔離政策。第二次大戦の教訓が無視され弱者に対して権力濫用に繋がり、日本では、権力者を縛る憲法により結論を示し、ついに決着した。非常に重い最高裁判所の判例や現実が大きくあり、パンデミックの最中には、混乱するだけで導入は難しい。
現に、検査数が日々変動してるため、新規感染者数が過去の数値と単純比較できずに陽性率で比較するプロセスも必要となるから、この時間差や感染者集計の時間差を権力者に言葉巧みに悪用されてる。
つまり、この元凶の権力者とは現在2020年の再選した政界風見鶏と言われる都知事小池百合子!過去には、行政府、警察に拡大解釈され強欲マスメディアがあおり第二次大戦に至りました。
未知のウイルスは、医療従事者や専門家も素人同然に成り下がるのは、東日本大震災2011の地震学者(こちらは理論破綻)で証明されてる。
にもかかわらず、今回、新型コロナウイルス2020でも、プライド、特権意識が邪魔をして、アマチュアの意見も引用して受け入れないため、未知のウイルスの伝播力で後手に回る。
現場で経験したアマチュアを含めて知見が集まるまでの人の手でデータにするまでの時間は、 CPU、GPU、量子コンピューター、インターネットで情報を光速で共有できるメリットを最大化できなくなると判明もした!
理論も大事だが現場経験が先!まぁ、カントも言ってることだから専門家、教授レベルなら熟知してると思うけど、知らないのかな?
日本の場合、ウイルス感染力低減対策のひとつ。緊急事態宣言後、最速で、高速道路、鉄道の法人であるJR、私鉄が協力体制をとって、都道府県内で折り返し運転をして他県に移動しづらくする方法。
それか、違う効果的なアイデアがあればいい?たしか、東日本大震災の時も実行してたような?
サブスクシェア経済は、具体的に言うとウイルスをベタベタな手で撒き散らすような強欲不潔感なイメージ。
食品扱うなら公衆衛生は最高レベルで!
公衆衛生の義務を厳格徹底し、感染症に欲のスキを突かれるため、強欲不潔な法人を規制して、事業停止を保健所は機動的に強制執行できるように法律を改正。
デフレスパイラルも危険なので、最低賃金以上を義務化、公衆衛生の義務を厳格徹底することで、抑止力をサブスクシェア経済に与えること!
さらに、人間を追跡する人工知能のストーカーアルゴリズムのみを今後禁止にして、ベンチャー企業がサブスクを開発したら高額罰金を与えるのはどうだろうか?
すでにある企業にも、悪用予防で高額罰金をかけていく。個人情報保護法に追加。GAFAは、指摘を受け止めて改善するが、それ以外の中小規模がより危険。
Uberなどは、その一つです。ドン・タプスコットが「ブロックチェーンレボリューション」の中で、UberやAirbnbやTaskRabbitやLyftといった。共有経済について話題にしています。対等な個人がいっしょに富を生み出し、共有するというのは。とても強力なアイデアです。
でも、私に言わせるとそういった企業は本当に共有をしてはいません!!実際、これらの企業が成功しているのは、まさに共有しないことによってなのです。さらに、高インフレの国でないとデフレスパイラルが起きてしまい、次第に賃金が上昇しなくなります。
現在の唯一の解決法は富の再分配でデファクトスタンダードをとっているプラットフォーマー企業に課税して広く配分するということです。ここが重要!!と言っています。
情報技術の発展とインターネットで大企業の何十万、何百万単位から、facebook、Apple、Amazom、Google、Microsoftなどで数億単位で共同作業ができるようになりました。
現在、プラットフォーマー企業と呼ばれる法人は先進国の国家単位レベルに近づき欧米、日本、アジア、インドが協調すれば、中国の人口をも超越するかもしれません。
法人は潰れることを前提にした有限責任! 慈愛や基本的人権を根本とした社会システムの中の保護されなければならない小企業や個人レベルでは、違いますが・・・
ヨーロッパでの一般データ保護規則(GDPR)でも言うように・・・
年収の低い個人(中央値で600万円以下)から集めたデータほど金銭同様に経済的に高い価値を持ち、独占禁止法の適用対象にしていくことで、高価格にし抑止力を持たせるアイデア。
自分自身のデータを渡す個人も各社の取引先に当たりデータに関しては優越的地位の乱用を年収の低い個人(中央値で600万円以下)に行う場合は厳しく適用していく。
キャシーオニールによると・・・
思考実験をしてみましょう。私は、思考実験が好きなので、人種を完全に隔離した社会システムがあるとします。どの街でも、どの地域でも、人種は隔離され、犯罪を見つけるために警察を送り込むのは、マイノリティーが住む地域だけです。すると、逮捕者のデータは、かなり偏ったものになるでしょう。
さらに、データサイエンティストを探してきて、報酬を払い、次の犯罪が起こる場所を予測させたらどうなるでしょう?
あら不思議。マイノリティーの地域になります。あるいは、次に犯罪を犯しそうな人を予測させたら?あらら不思議ですね。マイノリティーでしょう。データサイエンティストは、モデルの素晴らしさと正確さを自慢するでしょうし、確かにその通りでしょう。
さて、現実は、そこまで極端ではありませんが、実際に、多くの市や町で深刻な人種差別があり、警察の活動や司法制度のデータが偏っているという証拠が揃っています。実際に、ホットスポットと呼ばれる犯罪多発地域を予測しています。さらには、個々、人の犯罪傾向を実際に予測しています。
ここでおかしな現象が生じています。どうなっているのでしょう?これは「データ・ロンダリング」です。このプロセスを通して、技術者がブラックボックスのようなアルゴリズムの内部に醜い現実を隠し「客観的」とか「能力主義」と称しているんです。秘密にされている重要で破壊的なアルゴリズムを私はこんな名前で呼んでいます「大量破壊数学」です。
民間企業が、私的なアルゴリズムを私的な目的で作っているんです。そのため、影響力を持つアルゴリズムは私的な権力です。
解決策は、データ完全性チェックです。データ完全性チェックとは、ファクト(事実)を直視するという意味になるでしょう。データのファクトチェックです!
これをアルゴリズム監査と呼んでいます。
人間の概念を数値化できないストーカー人工知能では、不可能!と判明した。
未知のウイルス。新型コロナウイルスでは、様々な概念が重なり合うため、均衡点を決断できるのは、人間の倫理観が最も重要!
複数概念をざっくりと瞬時に数値化できるのは、人間の倫理観だ。
しかし、サンデルやマルクスガブリエルも言うように、哲学の善悪を判別し、格差原理、功利主義も考慮した善性側に相対的にでかい影響力を持たせるため、弱者側の視点で、XAI(説明可能なAI)、インターネット、マスメディアができるだけ透明な議論をしてコンピューターのアルゴリズムをファクトチェックする必要があります。
さらに、2020年5月21日。ついにリリースしました。AppleとGoogleが、協調してプライバシーに配慮し高いセキュリティの、APIを提供してます(中国のアプリは危険なため)
以下は、iOS、Androidアプリの作成に当たってライセンス上、守るべきガイドラインです。
第一に、アプリは公衆衛生当局が自ら作るか、外部機関に依頼して作らせたものでなければならず、しかも「COVID-19対応」以外の目的では利用することができないライセンスになっている。できるだけ多くの人が、同じアプリを使用し分断が起きないようにAPIの利用は1カ国1アプリのみ。
第二に、Exposure Notification API(濃厚接触通知API)の利用の前に、ユーザーの同意を得る必要がある。
第三に、利用者のCOVID-19感染が確認された場合、結果を共有する前に、必ず利用者の同意を得る必要がある。(同意を得ると当局が利用者のデバイスにひも付いた「Diagnosys Key : 診断鍵」に対して「陽性」の情報を登録する。二段階でキー生成がなされます。)
第四に、アプリは、利用者のスマートフォンから可能な限り最小限の情報しか獲得してはならず、 その利用はCOVID-19対策に限られる。タ���ゲティング広告を含め、それ以外のあらゆる個人情報の利用は禁じる。
第五に、アプリは、スマートフォンの位置情報獲得���求めてはならない。
などの個人を特定しにくくする工夫が加えられている新型コロナウイルス「濃厚接触通知」のプライバシー強化がほどこされています。
具体的に、AirDropやApplePayの仕組みを応用し、通信方法はBluetooth経由で、暗号化された毎日ランダムに15分単位で生成されるお互いのキー情報のみを相互接続します。
ApplePayの仕組みについて(当店サイトからも曲購入にて対応しております)
GPS情報、ユーザーの氏名や性別、年齢も原則取得しない
ユーザー同意のもと感染報告者の「キー(その1)」は、政府か保健機関が提供するアプリを通じてサーバーへ送られる。
続いて、API対応アプリは、定期的に全国から報告される「キー(その1)」をダウンロードする。そして、端末上で、誰かと会ったときの「キー(その2)」とマッチするかどうか判定し濃厚接触の可能性を判定する仕組み。
日本では、行政府の厚生労働省チームが進めるアプリ開発で同APIを利用します。このAPIは、常にAppleとGoogleが改善して全世界同時アップグレードされます。
1、2ヶ月程度で、1000万ダウンロード達成は、他のアプリと比べても平均くらいの普及率です。いや、でも、速い方かな?
メルカリなども1年くらいは必要としていたし、Lineもこのくらいだったかな?1000万ダウンロードでモンスターアプリと言われる世界。
その他のSNS、Twitter、FaceBookなどは、2000万前後のダウンロード数を誇っているアプリはほんの数%。cocoaも数ヶ月で達成しています。
一般的に言うQRコード決済になるd払い、Paypay、auPay、メルペイ、LinePayやクレジットカードの経験から、国内決済は、情報が独占禁止法の優越的地位の乱用に抵触。
QRコード決済は情報漏洩。セキュリティが高くない傾向がある。
さらに、マスメディアに横流しされ、広告に悪用される危険性を考慮ください!
安売りのかこつけ表現はデフレスパイラルになり、貨幣への融資以外は危険です。
Appleはこれらの対策として提案した内容がこれ。
データミニマイゼーション!
取得する情報・できる情報を最小化する。データが取れなければ、守る必要も漏れる可能性もない!
オンデバイスでのインテリジェンス!
スマートフォンなど機器のなかで処理を完結させることでプライバシーにかかわる部分を端末内に留める。
クラウドにアップロードして、照会プロセスを最小化することで、漏洩や不適切な保存の可能性を排除する!
高い透明性とコントロール!
どんなデータを集め、送っているのか、どう使うのかを明示し、ユーザーが理解したうえで自身で選んだり変更できるようにする!
セキュリティプロテクション!
機器上などで、どうしても発生するデータに関しては指紋認証や顔認証などを使ったセキュリティ技術で、漏えいがないようにしっかりと守るセキュリティプロテクション!機器上などで、どうしても発生するデータに関しては指紋認証や顔認証などを使ったセキュリティ技術で、漏えいがないようにしっかりと守る
202012のApp Storeプライバシー情報セクションは、3つ目「透明性とコントロール」の取り組み。
位置情報などは自己申告だが、アップルとユーザーを欺いて不適切な利用をしていることが分かればガイドラインと契約違反になり、App Storeからの削除や開発者登録の抹消もありえます。
このプライバシー情報の開示は12月8日から、iOS、iPadOS、macOS、tvOSなどOSを問わず、新アプリの審査時または更新時に提出が求められるようになっています。
2020年の4月と7月の違いは、新型コロナウイルスの場合、空気感染ではなく、飛沫感染という性質を考慮すると•••原則は、常にマスク着用、ソーシャルディスタンス。
検査数の量と陽性率でも見ると、東京都は、陽性率2、3%、200人前後で重症者数もバランスよく維持すれば、新型コロナウイルスを最小限に抑えつつ経済を持続できそうだ。
最新の研究によると、不織布のサージカルマスクなどは、感染予防にならないが、他人への拡散を抑える効果、ウイルス摂取量を抑える効果があるから、周囲の人たちが7、8割以上が行えば、実効再生産数を低下させ集団免疫に近い低減効果が得られるかもしれない。
ワクチンと同じくらいの防御効果がありそうだ。安全性の高いワクチンができるまでの実行再生産数を、1 より少なくする時間稼ぎに有効ということだけしかない。油断は禁物です!
吐く息の場合。不織布マスクは80%カット。布製マスクは70%カット。フェイスシールドは20%カット。マウスシールドは10%カット。
吸う息の場合。不織布マスクは70%カット。布製マスクは40%カット。フェイスシールドは効果なし。マウスシールドは効果なし。
続いて、日本国憲法尊守を前提で!
新型コロナウイルス2020に対応したFRBの金融政策と財政政策に異次元な変化が生じてる?
マネーストックとは「金融部門から経済全体に供給されている通貨の総量」のこと。
具体的には、金融機関・中央政府を除いた法人、個人などが保有する通貨(現金通貨や預金など)の残高を集計したもの。
日本銀行のベースマネーをコントロールするゼロ金利、量的緩和とは別枠で、ベースマネーからマネーストックへの橋渡しをする機関が弱いのでボトルネックになっていた。
ここで新型コロナウイルス2020が起きた!
将来の設備投資である個人デジタル貨幣型ベーシックインカム活用も含めて•••
アメリカのノーベル賞受賞経済学者ミルトン・フリードマン、元FRB議長であったベンバーナンキの書籍「大恐慌論」も言うように、金融危機2008、コロナショック2020などの急落に直面する対策として、ゼロ金利、マイナス金利、金融政策が出尽くした後に、よく登場する最速実行再分配政策が、個人への緊急的な現金給付!!!
各国によってスピードは異なるが、政策閣議決定後、人間の限界を遥かに超えるスピード。1秒以内で現金到着が理想。各国競争してみれば、今後の恒久対策として中央銀行のデジタル通貨なども考慮しつつ、新産業が産まれプラスサムになるかもしれません。
MMT(Modern Monetary Theory)によると、現状の貨幣での現実的なアイデアとして、社会保障に還元される日本の消費税は現状維持しつつ、現金給付額にも消費税がかかるので現金給付額を上げて、毎月給付にすると消費税率と社会保障費下支えとが均衡状態になる?と同時に、実体経済の経済成長率「g」の下支えにも寄与する?
これらの総量が、急激な不況時の資本収益率「r」以上なら、もしかして?回復して正常な経済環境に戻る期間も短縮できるかもしれません。
世界的な流れから各国政府経由で手厚い給付金を全国民に支給することになる。
日本も世界同時で協調し、国民皆給付を行うがスピードが世界に比べて同水準になってないことが判明した!そのうち改善するでしょう。
スペイン風邪から国民皆保険を構築した岸総理(他には、国民皆年金、最低賃金法もあります)安倍政権時代の安倍さんは、母方の祖父を見習いコロナウイルスから、毎月の国民皆給付を構築すれば歴史に残る業績になるし、継承する権利もある!
安倍政権時代の安倍さん、麻生さん。この二人でしかできない天命を見事果たした!アベノミクスの最終地点がコレだ!
この絶妙のタイミングで緊急的に構築した!天命と言わずにはいられない!
国民皆給付は達成したが、世界的な流れである毎月の国民皆給付には到達していない!
次善のアイデアとしては、三ヶ月に一回給付金。つまり、春夏秋冬に一回ずつ給付金も検討する価値はあります。
誰が発展させて引き継ぐのか?本人自身が行うのか?今後の継承を期待します。引き継いだ人間は、確実に人類の転換点に成し遂げた歴史に残る業績として記録されることでしょう。
将来は、官庁から量子暗号運用へ移行するための期間の長いデジタル化を始めてするも良し、庶民が行政手続きする際の申請だけにするなら資するかも?
金融機関への紐付け解除プロセスは現状維持として、まだアナログで十分!
前提条件として、基礎技術にリープフロッグは存在しません。応用分野のみです!
金融機関への紐付け?義務化は憲法違反。許可選択制にしろ!紐付け解除もできるようにしないと基本的人権侵害。
歴史の浅いコンピューターは、人間ではないし基本的人権は適用外だが、人類は違う!何千年もの構築した概念や法体系、歴史があり憎しみの連鎖も生じる。
中央値で一人年収600万円以上は給付金分年末に減税して、それ以下の年収は給付金支給にすればいい。日本国憲法尊守を前提で、こんなアイデアはどうだろうか?幸福がポイント。
ベーシックインカムは、現在の社会保障にプラスしていくことを前提条件として考慮しています!
もう一度。ベーシックインカムは、現在の社会保障にプラスしていくことを前提条件として考慮しています!
そして、テレワークの普及は諸刃の剣!
少ないから価値あるが誰もができると価値がなくなり、逆に一極集中加速する危険!アメリカ2020が、今そうだ!
GAFAなど。特にIT産業などは独占化しやすいから別枠で高税率にしてベーシックインカム用に再分配システム構築できないなら独占禁止法強化する世界的な流れになっている。
アメリカとは国土の大きさが違う!ので、マクロ経済学でいう小国開放経済の日本に、そのまま適用しても、新型コロナウイルスもあるし、現在の日本の普及率くらいが最善。これ以上は逆効果。
基本的人権という歯止めがないと薬が毒になる。
税の公平性はよく言われるが、時代が変わり、一極集中しやすく不公平が生じてるなら、産業別に税率を上昇させてバランスよくすればいい?
自由という概念を悪用するので簡単に言うと、自由権とは、18世紀のヨーロッパ市民革命、マグナカルタによってプロトコルを源にし言葉の定義を決めてから基本的人権の一つとして提唱されました。
憲法として日本にも導入されます!何でも自由に行うことではありません
これもその一つ。
「兵は詭道なり」戦いは、所詮騙し合いで、いろいろな謀りごとを凝らして、敵の目を欺き、状況いかんでは当初の作戦を変えることによって勝利を収めることができるものだ。
ということだが、誤解があって、憲法ある現代では、戦いの後に公開厳守が、法人も含めた権力者の原則です。
日本では、医療関係は、法律で個人情報の秘匿を義務化されてますが•••
国内法人大手NTTドコモは、本人の許可なく無断でスマートフォンの通信データを警察機関に横流しをしてる!
GAFAのように対策しない違法な法人?まさか、他にも?独占禁止法や法律を強化する?デフレスパイラル予防。このような国内大企業、中堅法人も危険。傲慢。
日本国憲法に違反しているので、アメリカのカリフォルニアやヨーロッパのGDPRのようにデータ削除の権利行使。
他に、再分配するデータ配当金を構築してからでないと基本的人権侵害になるため集団訴訟を国民は起こすべきだ。
税の公平性は、よく言われるが、時代が変わり一極集中しやすく不公平が生じてるなら産業別に税率を上昇させてバランスよくすればいい?
特に、IT産業などは、独占化しやすいから別枠で高税率にして、ベーシックインカム用に再分配システム構築できないなら独占禁止法強化。
自動的にディープフェイクをリアルタイムの別レイヤーで、防犯カメラの人物に重ね録画していくことで、写る本人の許諾が無いと外せないようなアルゴリズムを強力に防犯カメラの機能を追加してい��。
防犯カメラのデータを所有者の意図しない所で警察機関他に無断悪用されない抑止力にもなります。
防犯カメラのデータを所有者の意図しない所で警察機関他に無断悪用されない抑止力にもなります。
防犯カメラのデータを所有者の意図しない所で警察機関他に無断悪用されない抑止力にもなります。
サミット警備時、死者数が微小なのにテロ対策と称し厳戒態勢!
経済活動を制限した時に、警視庁職権濫用してたが、死者数が甚大な新型コロナに予算増やした?
警察権力悪用!庶民弱者に圧力やめさせないの?オリンピック前にも圧力あったから予算削除しろ傲慢警察!
警察機関に個人データを保存するなら、至急データ配当金を創設して、毎月警察予算から配当金を庶民に給付する仕組みにしろ!
嫌なら、個人情報を削除する権利が庶民には、あるから行政府は行使できるようにしろ!予算削減がいいか!データ削除がいいか!
仕組みを創設しないなら、基本的人権の侵害で日本国憲法違反だ!
みんなで国と集団訴訟だ!誰かが起訴すれば歴史に残る偉業になる。
マイケルサンデルは、メリトクラシー(能力主義)の陳腐さを警告し、諌め(いさめ)ています!
マイケルサンデルは、メリトクラシー(能力主義)の陳腐さを警告し、諌め(いさめ)ています!
マイケルサンデルは、メリトクラシー(能力主義)の陳腐さを警告し、諌め(いさめ)ています!
金融ビックバン日本版と言う社会実験から20年位!規制緩和でどれだけの死者が出たのか?
世界中でも一定数あるが、自殺者の比率が日本に突出してるのは、金融ビックバン日本版の生贄となってる可能性大。民放テレビ局で煽ってたから当時の局関係者も共犯者。
例えば、戦国時代の能力主義は、相手を殺傷することが多ければ能力が最高クラス。現代は?法律で禁止されていて能力は最低クラスになります。陳腐ですね。
第二次世界大戦みたいに命は落とさないが、現代の金融IT世界大戦は、脳や心を人工知能も登場したことで善性の方向にデザインしないと、さらに無限に焼きつくされる!!危険性があります。これが本質です。だから、個人の最低収入保障強化、基本的人権の強化がより重大になっていく。
金融ビックバン日本版の生贄となった自殺者(精神障害、トラウマ、うつなど)に対しての国家の責任として、欧米の無名戦士の墓、日本の靖国神社みたいに自殺者を供養する神社を創設するアイデアはどうだろうか?
この後、デフレスパイラルが同時多発!そして、歴史が証明してる人権侵害も同時多発!憲法違反!
行政府は、既存産業となったIT産業を慎重に、裏付けのあるデータに基づいて公正に規制する方向が善性に沿う!逆は、愚かと判明!
人間の限界を超えた新産業に法のスピードが追いつかないから、極端な自由権や規制緩和と同じ効果なだけ!
過剰なデフレスパイラル競争になり、多様な賃金上昇環境が悪性になる。個人の最低収入保障強化、IT産業に特化した独占禁止法強化が必要と新型コロナウイルスで判明もした!
海外や国内IT企業などストーカーアルゴリズムを規制する現実的な法律案は、ストーカー規制法に付帯事項としてアルゴリズムやプログラムを追加する。
公人、有名人、俳優、著名人は知名度と言う概念での優越的地位の乱用を防止するため徹底追跡可能にしておくこと。
そうすれば、現行法を維持して法の網にかけられるぞ!死者も出てるし、今からやれ!
新型コロナウイルスの死者は、2020年11月。2000人超えた!テロの死者数は何人?
国家予算が警察やテロ対策より新型コロナ対策の方が少ないんだけど。警察やテロ対策予算削減して、新型コロナ対策に今すぐ回せ!
自転車専用道路は無駄だから予算廃止して、パンデミック対策、新型コロナ対策に今すぐ回せ!
SDGsや気候変動対策は、再生可能エネルギーのことではありません。パンデミック対策の一環です!それ以外の活動は派生物。権力濫用の口実に注意!
SDGsや気候変動対策は、再生可能エネルギーのことではありません。パンデミック対策の一環です!それ以外の活動は派生物。権力濫用の口実に注意!
SDGsや気候変動対策は、再生可能エネルギーのことではありません。パンデミック対策の一環です!それ以外の活動は派生物。権力濫用の口実に注意!
続いて
2020年後半くらいから様々な占いで出てきてた時代の変わり目。それが、西洋占星術で具体的に「風」の時代という形で出てきました。
私が、感じとってたインスピレーションは、たぶんこれかな?
兆しは、世界的な金融ビックバンの1970年代、IT革命のミレニアムの前から出ていたけど。
これは、これまでの約200年間。物質やリアリティの影響力優位「土」の属性の時代から、量子コンピューター、ビットやインターネットなどといった物質ではないものに影響力が増していく「風」の属性の時代に。
そして、本格的に軌道にのっていく属性は、今後200年程続くことになるのです(2020年12月22日から、2100年当たりをピークに少しずつ衰退していく2220年まで)
直前に!
Appleも何かを感じてたのか?Appleシリコン搭載Macの方は、「Mシリーズ」チップに移行してるし、符号してる。
Googleは、量子超越性を達成してきてるし、Facebookも脳波を読み取る機械の開発を発表してますし、符号してる。
イーロンマスクもブレイン・マシン・インターフェース(Brain-machine Interface : BMI)を具体的に発表。これも、符号してる。
以下から話がそれるが、読み飛ばし、読み進めるかして下さい。
ここから予想できることは、バリーシュワルツが言うように、労働の概念が変わり、地球に居ながら映画アバターのように!その惑星にある資源を使い。
月や火星、土星や衛星などに無人ロボット部品を送り、ゲームのように自宅にいながら共同作業しつつ仕事をすることで高額な賃金が手に入る可能性も高い。
火星や土星や衛星に関しては、有人宇宙船内を無重力工場にして惑星移動期間に3Dプリンター製造、組立を効率的に行うことが実現すれば良いが無人ならベスト。
光速で惑星間通信できるようになったとしても、火星や土星や衛星への通信は、地球からでもリアルタイムで遅延が起きるため、月面のみ、この可能性が開けます!
無重力でもあるため、洞窟に工場を建築して人間の暮らせる環境を作り出すこともできそうです。可能性は無限!この領域に限界はありません!国家や行政府の範囲外なので極端な自由もあります。命の保障はないけど!
このアイデアは、今後数十年、人間の限界を遥かに超える新産業なのでプラスサムになり、地球環境は汚染されず資源エネルギー問題も起こりません。
以上です。
通信料金をある程度下げることには賛成。さらに、中央銀行のデジタル通貨で光熱費料金もある程度、補助金という形で個人単位を補助し、実質的に料金を下げて欲しい。
電気やガス事業は、国防と密接で独占せざるを得ないから競争して、むやみにインフラ崩壊させるよりもデジタル通貨でベーシックインカム形式の光熱費補助にも特化して欲しい(合成の誤謬を最小限に抑えること前提)
毎月国民一律皆給付ベーシックインカムは最優先だが、財源がない場合に備えて、特化オプションをそろえて柔軟に機動的に実行できる環境も重要です(合成の誤謬を最小限に抑えること前提)
光熱費は毎月の消費なので貯金に回りづらいから庶民の生活下支えになる。しかし、競争しすぎてもデフレスパイラル競争になるから、光熱費領域は慎重に設計することが肝要。
内閣府の「マイナンバー制度の定義」は「マイナンバーは社会保障、税、災害対策の3分野で複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます」
基本的人権侵害にあたるため、他分野へむやみに拡大するのは危険です。
よく思い違いをするのが、新しい時代には、経験もない新しい人が!と言うが、なおさら、経験や実力がないと新しい時代に対応できず、大事な何がが抜け落ちて混乱する矛盾!
消費税増税は、国民に現金の一律皆給付の施策しないからシステムが困窮する!
安定財源として消費税増税は否定しないが、データから明らかで、法人税は35%まで上げればいい。
所得税の上級に裕福税を新設して法人個人の超金持ち達から分配して穴埋めすればいい。
財政バランス度外視で、ニュージーランドは、2週間に一回10万円の国民一律給付金。カナダは、月40万円。日本もやれ!
根拠は、なぜ?ポンドからドルに基軸通貨が入れ替わったのか?
の問いの中に真実が隠されている!(当時は、固定相場制。現在は変動相場制なので前提条件として、変動相場制で人工知能時代の金融工学を駆使するも十数年もの長いデフレ状態で、ゼロ金利政策、量的緩和も出尽くし、マイナス金利も導入してからです)
その答えがそうだ!バランスも大事だが、歴史の転換期には、非線形になりやすいので万能とは限らない!
何度も言うが、会社法では法人は自力で有限責任ダメならたたむ。行政府は強制的に強欲な法人を鎮圧して厳しいけどあきらめて再出発してもらう資本主義そのための会社法。
だから、最後の砦の個人保障を手厚く最優先!
嫌なら日本領土以外で土地を確保。防衛して衣食住を自ら創造して!そこから自由にどうぞ。と言う話になるけど選択は自由だからお好きにどうぞ。これが国家システムの原則。
新型コロナウイルスの死者は、2021年1月。3000人超えた!テロの死者数は何人?
2021年4月に邪悪な悪意の兆しを感じとったので一応書いておきます。
日本のベーシックサービス定義を明確化してからだが、現行法の社会保障とした場合と定義します。
人工知能時代におけるベーシックサービスと労働市場の間を橋渡しする概念が、一律皆給付やベーシックインカムとプラスサムに現時点ではイメージしてます。決して、ゼロサムではない!
パンデミック時には、一度でも緊急事態宣言を発動したらスタビライザー的な低収入者への給付を倍額以上に増額して自動的に実施とする法律改正がベスト。
一律皆給付やベーシックインカムは、経済急落時の機動的な下支えにして、GDPギャップ解消速度をコントロールできる社会実験も必要
その副次的効果に相対的に消費税率をゼロorマイナスに持っていければベスト(法律改正は光速で急落する速度に対応できません)
スタグフレーションも予防できます!
これは、1970年��降、先進国で生産が停滞し、失業率が増大する停滞期にもかかわらず、物価は好況期に引続き高騰してしまう現象。
スタグフレーションの原因は、景気停滞期において軍事費を主として、消費的な財政支出が拡大していること。
次に、労働組合の圧力によって名目賃金が、マイルドではなく、急上昇を続けていること。
三つ目は、企業の管理価格が強化され、賃金コストの上昇が、価格上昇に比較的容易に転嫁されていること。
などにあるとされている。
本質的に法律で暴力装置をがんじがらめにしたテロリスト集団が警察機構!
この定義以外は、戦前の治安維持法の権力濫用やディストピアという過ちを繰り返す可能性大。
その証拠に、優先ワクチンを口実にして優越的地位をふりまき権力濫用してる警察関係者。
米国では2020から2021年。個人給付を実施して結果が出た!
日本では、現状は、数回の一律皆給付を行い足りないGDPギャップを解消が最善。
バイデン大統領は2021年、財務長官にイエレン就任した際の経済対策の一環
「世界が相互に結びついたことのもう一つの結果が30年に及ぶ法人税率の引き下げ競争だった」
というマクロ経済学の結果を明示した前提で各国の多年の法人税引き下げ競争を終わらせ、20カ国・地域(G20)で協力して共通の最低税率を設ける国際的な取り組み
法人税に世界的な「最低税率」を設定することで合意するよう調整していると言います。
実現が遠い世界的なデジタル課税よりも現行法の範囲での現実的な提案をしたかもしれない!
2018年くらいから、GAFAMなどに対して、再分配に関するベーシックインカムや国民皆給付金。中央銀行のデジタル貨幣。
新型コロナウイルスのパンデミックで日本ではクリーニング師を含めたエッセンシャルサービスの重要性が再認識される。
GAFAMなどが基盤にしているストーカーアルゴリズムが問題になる。
規制を強化する方向に進んでます。
これはひどい人権侵害の法律!法律改正して再修正かな。
緊急事態宣言の途中に「まん延防止等重点措置」が2021年2月に新設されました(都道府県単位の緊急事態宣言。知事が市町村単位で指定できる「まん延防止」)
建前の主旨は「緊急事態宣言に至る前や解除後の感染拡大を緩やかに抑える」ため。
「ワクチン開発後、提供までのウイルス変異抑制」の文章が抜けてる!から法律に追加しろ!
前提として、今回のみ。新型コロナウイルスの場合です。特徴的な「近距離接触感染」が飲酒店に最も多く生じたデータを根拠にして(他のウイルス性感染症は違います)
緊急事態宣言のように飲食店に対し、休業の命令や要請はできないが、営業時間短縮の命令や要請はできます(協力金給付と同時に要請→命令→過料の流れ)
緊急事態宣言の前段階で、弱者の異議申し立ての無い私権制限を伴う措置を講じることには批判があるが、命令に違反した事業者には20万円以下の過料(前科がつく刑事罰ではなく、前科がつかない行政罰)を科すことができる。
「ワクチン開発後、提供までのウイルス変異抑制」「悪質でない事業者の場合。数回程度の過料を解除後に減免返還する」の法律文章が抜けてる!から追加しろ!
現都知事小池百合子、行政府の悪用が目立つ2021年4月
私権制限を伴う措置なので財産権侵害、人権侵害の憲法違反だから、都道府県知事に集団訴訟すれば?
選挙とは別だが、コロナ禍に乗じる権力濫用防止のチェック機能を兼ねた民意を示せていいかもしれない。
緊急事態宣言は「ステージ4」相当が発動条件。
「まん延防止」は「ステージ3」相当で!実効再生産数2以上の急速な拡大期なら「ステージ2」でも発動。「実効再生産数2以上の急速な拡大」条件も書いてないから法律に追加しろ!
緊急事態宣言も「ワクチン開発後、提供までのウイルス変異抑制」「悪質でない事業者の場合。数回程度の過料を解除後に減免返還する」の法律文章を追加しろ!
弱者を警察と見廻り隊で権力悪用するくせに、現都知事小池百合子の「まん延防止」に乗じた権力濫用を通報する見廻り隊はないのかな?第四波は、大阪の後追いで悪用事例はでてるのに!
解除後に返還できないなら、過料相当を弱者も権力者に請求できるように法改正しろ!
なぜ?この権力濫用チェックの仕組みをワザと抜かしてる?
2021年4月。選挙前で再び悪用してるな!この局面女は!
新型コロナウイルスの死者は、2021年5月辺りで累計10000人超えた!まだ、自殺者よりは少ないが•••予算をこっちに回せ!
こっちの方が遥かに甚大なんだけど。ワクチン接種完了人数に応じて新規感染者数は減少するデータもある。
テロの死者数は何人?テロ対策は優先順位を極端に低く見直さないと。今でしょ!
参考までに、同じ期間中に癌の死者は約40万人います。心疾患の死者は約20万人です。
スペイン風邪の時には、第二波で変異した凶暴なウイルスにより荒れ狂い大量の死者をだした。ワクチンもない。
数字上で比較すると現在の第四波五波に相当。
商いする環境ですらなかったスペイン風邪の時代に比べれば、公衆衛生的には超優秀で、ワクチンもあるし、まだ軽い方!昔の商人が見てたらなんて言うかな?
現状維持でかろうじて商いできてるし、100年前に比べて、この程度で済んでいて幸せな方向に進んでいるなぁと見ています。
前回の100年前の第一次大戦時に同時に発生したパンデミック。第二次大戦のキッカケの要因?
大きな要因は軍隊の移動でウイルスが拡がる。
今回は、平時なら、オリンピアン(メダリスト含む)も善だが、パンデミックの緊急時。こんな特権クソに成り下がるし、発言や動き一つが、間接的に人命奪ってる。
スポーツ選手全員が危険な殺人者!よく競技できるな!出場を辞退もできたのにしない。
五輪終了後、全員戦犯。刑務所から再チャレンジだろ。
第二次大戦時、先人の教訓を無視し、オリンピアン(メダリスト含む)なのに権力に迎合する気骨がない低レベル人間?
昔は腹切。間接的な人殺しへの再発防止で、五輪終了後。
全員パンデミック裁判を創設。
法律にし罰則つき履歴公開。
戦犯刑務所も創設しろ!
物事をメリットやデメリットで二元論的な扱いをする人間をメリトクラシーとマイケルサンデルは陳腐さに警鐘を鳴らします。
スポーツの枠の外から出れば最低ランク。ミサイルや戦車、ウイルスを素手で止めた?してない。陳腐きわまりない。
枠の外では最低ランク!人としては最低ランク。さらに、倫理観も貧弱。
争う事しかせず、思い違いするから普通の人に圧力かけるし、場合によっては、特権乱用し、人として、最低な人間のレベルに成り下がる。
チャンピオンの日本語訳を深く考えれば言ってる概念が理解できるようになるから調べることをすすめます。
ごまかしてもキネオロジーテストで計測し暴露できる。
さらに言えば、イエルサレムのアイヒマン。ハンナアーレントなど。
第二次大戦期の戦争裁判と同じく、新型コロナウイルスの収束後は、この混乱に乗じて非道な発言する兆しを見せた人を戦犯として全部公開して予防。
感染症法にもパンデミック裁判を創設。法律にし罰則つき履歴公開。戦犯刑務所も創設。を明記して法整備することが最善。
26段階。A級戦犯からZ級戦犯まで!自衛隊や警察含め細かく整備すること。
今回は罰則なしで、自衛隊や警察内部の行動や言動も全部公開。テスト的にA級からZ級まで格付けだけしておいても、低賃金者の不満も解消できるかもしれない。
まとめて検証できるし、抑止につながる。
当てはまる人は、10年かけて権力の座から遠ざけるようにした方が今後の日本のためになる!
プロパガンダの本当の怖さは、現実とかいりし「えっ」こんな不自然なことがチェックもされず行政府で通って法律にされてしまうの?
でも、圧力怖いから言えない雰囲気だしなぁという不合理状態が一番危険。
イエルサレムのアイヒマン。
ハンナアーレントなども指摘。
パンデミック裁判なら、これら事後の混乱も回避できる。
こんなこと世界では当たり前。
これまで再分配と言っていたが、緊急時には、十分に考えた上での事前分配という先払い方法も制度設計に加えると柔軟性が上がるかもしれない。
<提供>
東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント
独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです
東京都北区神谷のハイブリッドな直送ウェブサービス(Hybrid Synergy Service)高橋クリーニングFacebook版
#エリック#ディシュマン#医者#ビック#データ#コロナ#intel#量子#Watch#老化#アプリ#インター#ネット#Google#統計#オープン#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery#超電導#福祉#Apple#ウイルス
0 notes
Link
TEDにて
セス・バークレー: HIVとインフルエンザ ー 治療薬。ワクチンの戦略
(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)
様々な治療薬。ワクチンの設計や製造、流通についての知見が革新的に進歩して、現在進行形で、世界���脅威であるとも言えるHIVやマラリアとインフルエンザの根絶に、じょじょに近づいていることをセス・バークレーが語ります。
遺伝子工学の進歩により、感染症の予防や治療についても少しアニメーションで説明されてもいます。
ワクチンとは、人間に接種させることで感染症の免疫予防に用いる秘密兵器みたいな医薬品。
毒性を無くしたか、あるいは弱めた病原体から作られ、弱い病原体を注入することで体内の中で数週間の時間をかけて抗体という秘密兵器を作り、感染症にかかりにくくする。
ワクチンを発見したのはイギリスの医学者、エドワード・ジェン���ー。牛痘にかかった人間は天然痘にかからなくなる(またはかかっても症状が軽い)事を発見し、これにより天然痘ワクチンを作った。
その後、ルイ・パスツールが病原体の培養を通じてこれを弱毒化すれば、その接種によって免疫が作られると理論的裏付けを与え、応用の道を開いた。
その後、分子レベルでの研究が進歩して遺伝子の細胞レベルでウイルスやインフルエンザの構造が電子顕微鏡で見られるようになりました。
さらに、HIVの予防研究を発展させると、レトロ=ウイルス学と言われる分野がツールとして活用できるようになりました。
自分がどう死ぬか心配ですか?心臓病やガン、交通事故でしょうか?多くの人はコントロールできないことを心配します。戦争やテロやハイチの悲惨な地震なども心配です。
では、人類にとって真の脅威は何でしょうか?数年前、バーツラフ・スミル教授は、歴史を変えるほどの大きな災害が突然起こる確率の計算を試みました。
彼が名付けた大規模な致命的断絶とは、今後50年に起こり得る最高1億人の命を奪う災害のことです。世界大戦が発生する確率や大規模な火山の噴火や小惑星が地球に衝突する確率を求めました。
しかし、その他の何よりも発生の確率が高く、ほぼ100%の確率で起こり得るとされたのがインフルエンザの大流行です。
インフルエンザは、カゼがひどくなったものと思われがちですが、致命的になることもあります。アメリカでは、毎年、季節性インフルエンザで3万6千人が命を落とします。
発展途上国のデータは、不完全ですが、死者の人数はもっと多いことでしょう。さらに、厄介なことにウイルスはしばしば、著しい変異を遂げると実質的に新種ウイルスのようになり、こうして大流行が生じるのです。
1918年には、新種のウイルスが出現して5000万人から1億人が亡くなりました。燎原の火の如しです。発症してから、数時間で亡くなった患者もいました。
今日、我々は大丈夫なのでしょうか?誰もが心配していた今年のひどい流行は、なんとか回避できたようです。しかし、この脅威はいつ出現してもおかしくありません
幸いなことに、今の時代は、科学と技術とグローバル化が結びついて、かつてない可能性を拓きつつあります。
いまだに地球上の全死者の5分の1と多くの苦しみの原因である感染症を撲滅して歴史を刻む可能性です。それは、実行可能なのです。すでに現在のワクチンによって何百万人もの命を救っています。
ワクチンをより広く行き渡らせれば、より多くの命を救えます。さらに、新種や改良型のワクチンであれば、マラリアや結核やHIV、肺炎や下痢やインフルエンザなどのこれまでずっと続いてきた苦しみに終わりを告げることができるはずです。
今日は、ワクチンの成果についてお話します。最初に、なぜワクチンが重要か説明しましょう。ワクチンの力は、たとえるなら ささやき声のようです。
ワクチンの成果があると歴史に残りますが、その後しばらくするとほとんど耳にすることもなくなります。ある年齢以上の人なら腕に小さな丸い痕が付いているでしょう。
子どものときの予防接種の痕です。でも、最近は天然痘の心配はしなくなりました。20世紀に5億人の命を奪った病気が、撲滅されたのです。
ポリオもです。鉄の肺を覚えている方などいますか?こういう物を目にすることは無くなりました。ワクチンのおかげです。
ワクチンは、特定の侵入者を認識し中和するように人体を訓練しておくものです。エボラは、人体の粘膜関門を突破して侵入すると免疫細胞に感染して増殖します。
免疫系の最前線部隊は侵入者を発見します。樹状細胞やマクロファージがウイルスを捕らえてその断片を「提示」します。前線からエボラの侵入を知らされるとエボラワクチンで作られた記憶細胞が活性化します。
この記憶細胞は、直ちに必要とされる兵器を配備します。メモリB細胞は、プラズマ細胞となって、次から次へとエボラにピタリと適合した特定の抗体を産出して、エボラが細胞を感染させるのを防ぎます。
同時に、キラーT細胞大隊がエボラに感染してしまった細胞を探して破壊します。
ウイルスは打ち負かされます。ワクチンが無かったらこれらの兵器を準備するまでに1週間以上もかかり、その間にエボラとの戦いには敗北してしまっているでしょう。
そして、HIVから始まった研究は、他の病気に対するイノベーションを促します。例えば、バイオ技術の会社は、インフルエンザに対する新しい抗体のターゲットと共に、広範な中和抗体を見つけています。
現在、極めて激しいインフルエンザに対応できる抗体の組み合わせを検討し調合しようとしています。
将来的には、これらの「レトロ=ワクチン学」のツールを用いて、予防的なインフルエンザワクチンを作れるでしょう。また、合理的ワクチンデザインの観点からは「レトロ=ワクチン法」は一つの手法にすぎません。
別の例を挙げましょう。インフルエンザウイルスの表面に出ているH型とM型の突起の話をしましたが、別の小さな突起に注目してください。免疫系からは、ほとんど隠れているのです。
これらの部位もウイルスの変異の際に、あまり変化しないことがわかってきました。そこで、特別な抗体でこの部位を攻撃すれば、どの種類のインフルエンザも機能を失います。
もちろん、どんなに素晴らしいワクチンでも必要な人全員に行き渡らなくては意味がありません。
そうするためには、優れたワクチンの設計と優れた生産手段。そして、優れた流通手段を組み合わせなくてはなりません。
インフルエンザワクチンの作り方。
つまり、製造技術は、1940年代初期に開発されました。時間のかかる面倒な工程です。
鶏卵を用いる方法で生きた鶏卵を何百万個も使います。ウイルスは���生き物の中でしか増殖せず、インフルエンザに対しては、鶏卵が大変適していたのでした。
ほとんどの型のインフルエンザでは、一つの卵からワクチンが1、2本できます。幸運にも、現代の生物医学は、著しい進展を遂げています。
そんな時代ですから、インフルエンザワクチンは鶏卵から作ります。数百万個の卵からです。ほとんど何も変わっていません。信頼できるシステムです。
そんな、新しいワクチン技術の比較表です。
劇的に改善した製造技術と大幅なコスト低減に加えて、説明した大腸菌の手法では、期間も短縮出来ます。
つまり、命が救えるということです。
発展途上国は、現在のインフルエンザ対応から取り残されがちなため、これらの新技術には期待しており西側諸国より進んでいます。
インドやメキシコその他の国で、すでに、インフルエンザワクチンの試作が始まり、これらのワクチンが初めて実用されるのも これらの国かもしれません。
この新しい技術は大変効率的で比較的費用もかからないので、流通手段を開発できれば、何十億もの人に命を救うワクチンを届けられます。
これは実現できることなのです。
<おすすめサイト>
ダン・クワトラー:ワクチンはどのくらい速く作れるのか?
E. O. Wilson’s Life on Earth 分子生物学Unit 1 (iBooks)
E. O. Wilson’s Life on Earth 分子生物学Unit 2 (iBooks)
E. O. Wilson’s Life on Earth 分子生物学Unit 3 (iBooks)
E. O. Wilson’s Life on Earth 分子生物学Unit 4 (iBooks)
E. O. Wilson’s Life on Earth 分子生物学Unit 5 (iBooks)
E. O. Wilson’s Life on Earth 分子生物学Unit 6 (iBooks)
E. O. Wilson’s Life on Earth 分子生物学Unit 7 (iBooks)
ラリー・ブリリアント:パンデミック阻止に挑む!
インフルエンザの公衆衛生的措置について
インフルエンザ公衆衛生的感染予防
インフルエンザへの免疫機能、感染予防
ミリアム・シディベ: 手洗いの持つシンプルなパワー
ジュラルディン・ハミルトン:「臓器SoCチップ」がもたらす未来!
ジェニファー・ダウドナ:精密な遺伝子編集が可能な時代、使い方は細心に慎重に
マーク・ケンドル:より安全で低コストな注射針を使わないワクチン・パッチ
(個人的なアイデア)
アメリカのノーベル賞受賞経済学者ミルトン・フリードマン、元FRB議長であったベンバーナンキの書籍「大恐慌論」も言うように、金融危機2008、コロナショック2020などの急落に直面する対策として、ゼロ金利、マイナス金利、金融政策が出尽くした後に、よく登場する最速実行再分配政策が、個人への緊急的な現金給付!!!
各国によってスピードは異なるが、政策閣議決定後、人間の限界を遥かに超えるスピード。1秒以内で現金到着が理想。各国競争してみれば、今後の恒久対策として中央銀行のデジタル通貨なども考慮しつつ、新産業が産まれプラスサムになるかもしれません。
MMT(Modern Monetary Theory)によると、現状の貨幣での現実的なアイデアとして、社会保障に還元される日本の消費税は現状維持しつつ、現金給付額にも消費税がかかるので現金給付額を上げて、毎月給付にすると消費税率と社会保障費下支えとが均衡状態になる?と同時に、実体経済の経済成長率「g」の下支えにも寄与する?
これらの総量が、急激な不況時の資本収益率「r」以上なら、もしかして?回復して正常な経済環境に戻る期間も短縮できるかもしれません。
スペイン風邪から国民皆保険を構築した岸総理(他には、国民皆年金、最低賃金法もあります)現政権の安倍総理、母方の祖父を見習いコロナウイルスから、毎月の国民皆給付を構築すれば歴史に残る業績になるし、継承する権利もある!
現政権の安倍総理、麻生副総理。この二人でしかできない天命を果たせ!アベノミクスの最終地点がコレだ!この絶妙のタイミング!
天命と言わずにはいられない!
感染症との戦いは、人類の宿敵とも言っていい未知のウイルスとの戦争です!
今までは、パンデミック時の対策としてデータのないスペイン風邪の書物や言葉を参考にしていたが、インターネットの発展やCPU、GPUがムーアの法則によりスーパーコンピューターの領域に現代は突入している。
情報技術が発展し、スマートフォンとして手のひらサイズに収まり、ウイルスを感染予防するための距離を広げながらも、データとして全世界と光速で共有できるため、そのスピードとウイルス伝播のスピードと伍している?
局面ごとに対策を適性に行えば伝播速度を上回りコントロールできる感じもある!ラリーブリリアントが構築したシステムの功績もあります。
量子コンピューターも量子超越性を達成してることもプラスです。
ジョンズ・ホプキンス大学のシステム科学工学センター(The Center for Systems Science and Engineering:CSSE)感染者ダッシュボード
新型コロナウイルスの場合、新規感染者数が、2倍になる日数が10日以上になれば、R0(アールナート)が1以下に減衰してピークアウト状態になると理解できる。
日本の場合、PCR検査の結果が判明する14日後より短いから、検査結果日数を10日以下にできれば、ヤキモキせずスピード感ある判断が可能になりそうだ。
つまり、未知のウイルス。アウトブレイク発生確認後の緊急事態宣言発動は、クラスターが発生しやすいチェーン店などの大規模な場所から早期閉鎖が原則とデータから判明した!
日本の場合、アウトブレイク発生確認後から緊急事態宣言発動までの余裕日数は、新規感染者数が、2倍になる日数です。例えば、5日で2倍なら、5日以内で初動初速最大化発動しないと危険ということ!
R0が2.5付近では、発動日から10日でピークアウトが最速値。7、8割の人の外出制限要請StayHome(元々、人がいない地域での7、8割削減は意味ないし不可能だから政令指定都市だけにすること)ソーシャルディスタンス。などの初動初速最大化すれば、収束までさらに10日で計算上は20日で解除可能領域に近づける目安となります。
生産管理手法のクリテカルチェーンもリアルタイムの感じた感覚で考慮すると余裕バッファーをもう10日で、ひと月。えっ。ここまで自分で書いてよく見ると現実の数値にかなり符号する。
休業要請解除を10段階くらいに分けて地域ごとに段階的に基準を決めて行う。
日本の場合。緊急事態宣言、休業要請は現金給付や保証とセットで最速実行が原則。
日本の場合、透明性を持たせて休業要請解除の基準を決め、きめ細かく設定しないと現在の都知事とか権力者の気分で権力濫用されたり選挙に悪用される危険性がある。
今後の医療崩壊回避のため、医者を含めた疾病や保健所などの医療従事者を単純に現在の倍に育てて増員したら余裕バッファーが半分くらいになりそうな直観が出た。
今後は、休業要請解除!スペイン風邪同様第二波三波、第四第五の小波に備え、国からの現金給付支給をもう数度実行してもいい。Rtが1以下になり次第、休業要請解除!の後に、緊急事態宣言を機動的に解除。
この局面でもっとも効果的なソーシャルディスタンス領域をかんたんに実行。かんたんに実現できる小規模な所から。
時間軸のあるR0をRtとした都道府県別。新型コロナウイルスリアルタイムデータ
クラスター発生地点の見守りを継続する。再びアウトブレイクになり次第。最速で緊急事態宣言を再び発動して、1年かけて5、6回繰り返し、新規感染者数をピークアウトさせて分散、減少させていく!
何度も言うが、スペイン風邪同様第二波三波、第四第五の小波に備えるため!
小池百合子都知事という悪徳政治家は即刻辞職して、後世の女性への権力に固執しない手本を示し、的確に新型コロナウイルス対策できる人間に変われ!以下の指摘3つを真摯に受け止めて瞬時に改善しろ!(全世界に拡散希望)
1)休業要請緩和の各ステップの目安日数(1週間の平均感染者数:20人未満、感染経路の追えない感染者の割合:1週間平均が50%未満、1週間単位の感染者の増加比:1以下)をごまかして各段階を具体的数値で表現しない。クソロードマップだ!!今回の都知事選挙のために政治悪用してるのは明白!!的確に新型コロナウイルスに対策できる人間に変われ!
2)再要請の目安(1日の感染者数:50人、感染経路の追えない感染者の割合:1週間平均が50%以上、1週間単位の感染者の増加比:2以上)も隠すように表示してるクソロードマップだ!今回の都知事選挙のため政治悪用してるの明白!!的確に新型コロナウイルスに対策できる人間に変われ!
3)2週間単位じゃなく1日単位にしないと一つずつ緩和のステップを進めていく意味がないクソロードマップだ!!今回の都知事選挙のために日数伸ばすために政治悪用してるのは明白!!的確に新型コロナウイルスに対策できる人間に変われ!
具体的には、2020年5月中旬に、緊急事態宣言を1日単位でスピード解除(現都知事は、説明責任をせず気分で言葉を変えて言葉で惑わし政治悪用するので、数値を基準にした休業要請を1日単位でスピード解除)を早期に行う。
こうすることで、マクロ経済的にもバランスを維持していく。
前提として、直近1週間10万人あたり新規感染者0.5人位?(わかりやすく言うと、1400万人いる東京都は7 日間で、70 人位。一日7人位)で緊急事態宣言解除。
他には、神奈川県は46人位一日6人位。埼玉県は37人位一日5人位。千葉県は31人位一日4人位。とざっくりとした目安になります。
以降は、30日間経過観察し2回目に備える。オーバーシュートし始めたら2回目の緊急事態宣言を再び発動(現金給付とセット:一回目の延長の分も含めて一律20万円)し、1回目と同じように繰り返し、50日でスピード解除。つまり、最速80日周期で1年かけて4、5回繰り返し、新規感染者数をピークアウトさせて分散、減少させていく!
データから判明した6割程度の人の接触制限(元々、人がいない地域での削減は意味ないし不可能)で増加しないフラットな均衡状態を維持できる。
しかし、わかりやすく言えば、10人を4人にし続けたら商売にならないのは明らか。これでは、マクロ経済活動を維持できないため、その減少分を法人は、巨額な内部留保があれば、それを金融工学で資金繰りを下支えしつつ
国民皆給付で一律毎月10万円の庶民生活を下支えし続ける!(ボーナスも危ういので多少なりとも毎月気持ち分補助してもらう)これがベスト。
新規感染者を数人位の緊急事態宣言解除直後の低水準で均衡させつづければ、6割程度の人の接触制限してマクロ経済を維持できそうな感じは現時点ではする。
7月になり、小池百合子は公約も実現してないのに再選した稀代の悪女!自ら辞めて責任もとらない。昨年は、モンテスキューの「法の精神」も言う権力分立の原則を無視して国政と都知事を兼務しようとする悪い女性の見本と判明(全世界に拡散希望)
新規感染者も四月の水準に数の上では迫っている!
しかし、検査数と新規感染者の割合を見ると七月の水準では四月ほどではなく、さらに、退院者数を引いて見る。医療提供キャパシティ数が不明で数値を出して欲しいが、これらを考慮すると•••
再びの緊急事態宣言は、新規感染者が現状4桁到達。人口規模が大きい東京都が1000人以上なら実行する価値はある!現金給付とセットで!(検査数、医療提供キャパシティ数が増えれば2000、3000でも耐えられるかも?これはまだ未知の領域)
7月の重傷者数も4月の水準ではないので、4月の水準に近づき次第。再びの緊急事態宣言で良いのではないか?そんな感じもします。
海外の結果は、アメリカ、ヨーロッパは速めにロックダウンした(日本は緩いロックダウン)
スウェーデンは独自の社会実験でパンデミック中に行政府がほとんど行動制限を加えず、通常の生活を続けるとどんなことになるか?結果は変わらない。
自ら感染を広げただけで、経済的に何の得にもなっていないらしい。人口100万人当たりの死者数が世界的にも高い水準になってしまった。重症者増加悪化する。ロックダウンが経済悪化の原因ではないこと。すべての原因はウイルスそのものの伝播力と判明。
日本は湿気の多い夏の時期でも、この伝播力の怖さが明らかになる。実効再生産数1.5から2くらい。
歴史の経験が実証されデータが得られワクチンや治療薬が重要という昔のパンデミック時の教訓が正しいことが世界中で再認識された。
PCR検査などを抽出から全数に変えても統計上はあまり変わらない。前提として、数値の量や正確さにこだわらず測れるのが統計。量子力学に多用されてる。統計には、全数と抽出がある。
むやみに、感染者を排除しても基本的人権を侵害するだけで感染者差別を産む可能性もある(マスクの有無で既に差別的になってる)
ハンセン病患者の強制隔離政策。第二次大戦の教訓が無視され弱者に対して権力濫用に繋がり、日本では、権力者を縛る憲法により結論を示し、ついに決着した。非常に重い最高裁判所の判例や現実が大きくあり、パンデミックの最中には、混乱するだけで導入は難しい。
現に、検査数が日々変動してるため、新規感染者数が過去の数値と単純比較できずに陽性率で比較するプロセスも必要となるから、この時間差や感染者集計の時間差を権力者に言葉巧みに悪用されてる。
つまり、この元凶の権力者とは現在2020年の再選した政界風見鶏と言われる都知事小池百合子!過去には、行政府、警察に拡大解釈され強欲マスメディアがあおり第二次大戦に至りました。
未知のウイルスは、医療従事者や専門家も素人同然に成り下がるのは、東日本大震災2011の地震学者(こちらは理論破綻)で証明されてる。
にもかかわらず、今回、新型コロナウイルス2020でも、プライド、特権意識が邪魔をして、アマチュアの意見も引用して受け入れないため、未知のウイルスの伝播力で後手に回る。
現場で経験したアマチュアを含めて知見が集まるまでの人の手でデータにするまでの時間は、 CPU、GPU、量子コンピューター、インターネットで情報を光速で共有できるメリットを最大化できなくなると判明もした!
理論も大事だが現場経験が先!まぁ、カントも言ってることだから専門家、教授レベルなら熟知してると思うけど、知らないのかな?
日本の場合、ウイルス感染力低減対策のひとつ。緊急事態宣言後、最速で、高速道路、鉄道の法人であるJR、私鉄が協力体制をとって、都道府県内で折り返し運転をして他県に移動しづらくする方法。
それか、違う効果的なアイデアがあればいい?たしか、東日本大震災の時も実行してたような?
サブスクシェア経済は、具体的に言うとウイルスをベタベタな手で撒き散らすような強欲不潔感なイメージ。
食品扱うなら公���衛生は最高レベルで!
公衆衛生の義務を厳格徹底し、感染症に欲のスキを突かれるため、強欲不潔な法人を規制して、事業停止を保健所は機動的に強制執行できるように法律を改正。
デフレスパイラルも危険なので、最低賃金以上を義務化、公衆衛生の義務を厳格徹底することで、抑止力をサブスクシェア経済に与えること!
さらに、人間を追跡する人工知能のストーカーアルゴリズムのみを今後禁止にして、ベンチャー企業がサブスクを開発したら高額罰金を与えるのはどうだろうか?
すでにある企業にも、悪用予防で高額罰金をかけていく。個人情報保護法に追加。GAFAは、指摘を受け止めて改善するが、それ以外の中小規模がより危険。
Uberなどは、その一つです。ドン・タプスコットが「ブロックチェーンレボリューション」の中で、UberやAirbnbやTaskRabbitやLyftといった。共有経済について話題にしています。対等な個人がいっしょに富を生み出し、共有するというのは。とても強力なアイデアです。
でも、私に言わせるとそういった企業は本当に共有をしてはいません!!実際、これらの企業が成功しているのは、まさに共有しないことによってなのです。さらに、高インフレの国でないとデフレスパイラルが起きてしまい、次第に賃金が上昇しなくなります。
現在の唯一の解決法は富の再分配でデファクトスタンダードをとっているプラットフォーマー企業に課税して広く配分するということです。ここが重要!!と言っています。
情報技術の発展とインターネットで大企業の何十万、何百万単位から、facebook、Apple、Amazom、Google、Microsoftなどで数億単位で共同作業ができるようになりました。
現在、プラットフォーマー企業と呼ばれる法人は先進国の国家単位レベルに近づき欧米、日本、アジア、インドが協調すれば、中国の人口をも超越するかもしれません。
法人は潰れることを前提にした有限責任! 慈愛や基本的人権を根本とした社会システムの中の保護されなければならない小企業や個人レベルでは、違いますが・・・
ヨーロッパでの一般データ保護規則(GDPR)でも言うように・・・
年収の低い個人(中央値で600万円以下)から集めたデータほど金銭同様に経済的に高い価値を持ち、独占禁止法の適用対象にしていくことで、高価格にし抑止力を持たせるアイデア。
自分自身のデータを渡す個人も各社の取引先に当たりデータに関しては優越的地位の乱用を年収の低い個人(中央値で600万円以下)に行う場合は厳しく適用していく。
キャシーオニールによると・・・
思考実験をしてみましょう。私は、思考実験が好きなので、人種を完全に隔離した社会システムがあるとします。どの街でも、どの地域でも、人種は隔離され、犯罪を見つけるために警察を送り込むのは、マイノリティーが住む地域だけです。すると、逮捕者のデータは、かなり偏ったものになるでしょう。
さらに、データサイエンティストを探してきて、報酬を払い、次の犯罪が起こる場所を予測させたらどうなるでしょう?
あら不思議。マイノリティーの地域になります。あるいは、次に犯罪を犯しそうな人を予測させたら?あらら不思議ですね。マイノリティーでしょう。データサイエンティストは、モデルの素晴らしさと正確さを自慢するでしょうし、確かにその通りでしょう。
さて、現実は、そこまで極端ではありませんが、実際に、多くの市や町で深刻な人種差別があり、警察の活動や司法制度のデータが偏っているという証拠が揃っています。実際に、ホットスポットと呼ばれる犯罪多発地域を予測しています。さらには、個々、人の犯罪傾向を実際に予測しています。
ここでおかしな現象が生じています。どうなっているのでしょう?これは「データ・ロンダリング」です。このプロセスを通して、技術者がブラックボックスのようなアルゴリズムの内部に醜い現実を隠し「客観的」とか「能力主義」と称しているんです。秘密にされている重要で破壊的なアルゴリズムを私はこんな名前で呼んでいます「大量破壊数学」です。
民間企業が、私的なアルゴリズムを私的な目的で作っているんです。そのため、影響力を持つアルゴリズムは私的な権力です。
解決策は、データ完全性チェックです。データ完全性チェックとは、ファクト(事実)を直視するという意味になるでしょう。データのファクトチェックです!
これをアルゴリズム監査と呼んでいます。
人間の概念を数値化できないストーカー人工知能では、不可能!と判明した。
未知のウイルス。新型コロナウイルスでは、様々な概念が重なり合うため、均衡点を決断できるのは、人間の倫理観が最も重要!
複数概念をざっくりと瞬時に数値化できるのは、人間の倫理観だ。
しかし、サンデルやマルクスガブリエルも言うように、哲学の善悪を判別し、格差原理、功利主義も考慮した善性側に相対的にでかい影響力を持たせるため、弱者側の視点で、XAI(説明可能なAI)、インターネット、マスメディアができるだけ透明な議論をしてコンピューターのアルゴリズムをファクトチェックする必要があります。
さらに、2020年5月21日。ついにリリースしました。AppleとGoogleが、協調してプライバシーに配慮し高いセキュリティの、APIを提供してます(中国のアプリは危険なため)
以下は、iOS、Androidアプリの作成に当たってライセンス上、守るべきガイドラインです。
第一に、アプリは公衆衛生当局が自ら作るか、外部機関に依頼して作らせたものでなければならず、しかも「COVID-19対応」以外の目的では利用することができないライセンスになっている。できるだけ多くの人が、同じアプリを使用し分断が起きないようにAPIの利用は1カ国1アプリのみ。
第二に、Exposure Notification API(濃厚接触通知API)の利用の前に、ユーザーの同意を得る必要がある。
第三に、利用者のCOVID-19感染が確認された場合、結果を共有する前に、必ず利用者の同意を得る必要がある。(同意を得ると当局が利用者のデバイスにひも付いた「Diagnosys Key : 診断鍵」に対して「陽性」の情報を登録する。二段階でキー生成がなされます。)
第四に、アプリは、利用者のスマートフォンから可能な限り最小限の情報しか獲得してはならず、 その利用はCOVID-19対策に限られる。ターゲティング広告を含め、それ以外のあらゆる個人情報の利用は禁じる。
第五に、アプリは、スマートフォンの位置情報獲得を求めてはならない。
などの個人を特定しにくくする工夫が加えられている新型コロナウイルス「濃厚接触通知」のプライバシー強化がほどこされています。
具体的に、AirDropやApplePayの仕組みを応用し、通信方法はBluetooth経由で、暗号化された毎日ランダムに15分単位で生成されるお互いのキー情報のみを相互接続します。
ApplePayの仕組みについて(当店サイトからも曲購入にて対応しております)
GPS情報、ユーザーの氏名や性別、年齢も原則取得しない
ユーザー同意のもと感染報告者の「キー(その1)」は、政府か保健機関が提供するアプリを通じてサーバーへ送られる。
続いて、API対応アプリは、定期的に全国から報告される「キー(その1)」をダウンロードする。そして、端末上で、誰かと会ったときの「キー(その2)」とマッチするかどうか判定し濃厚接触の可能性を判定する仕組み。
日本では、行政府の厚生労働省チームが進めるアプリ開発で同APIを利用します。このAPIは、常にAppleとGoogleが改善して全世界同時アップグレードされます。
1、2ヶ月程度で、1000万ダウンロード達成は、他のアプリと比べても平均くらいの普及率です。いや、でも、速い方かな?
メルカリなども1年くらいは必要としていたし、Lineもこのくらいだったかな?1000万ダウンロードでモンスターアプリと言われる世界。
その他のSNS、Twitter、FaceBookなどは、2000万前後のダウンロード数を誇っているアプリはほんの数%。cocoaも数ヶ月で達成しています。
一般的に言うQRコード決済になるd払い、Paypay、auPay、メルペイ、LinePayやクレジットカードの経験から、国内決済は、情報が独占禁止法の優越的地位の乱用に抵触。
QRコード決済は情報漏洩。セキュリティが高くない傾向がある。
さらに、マスメディアに横流しされ、広告に悪用される危険性を考慮ください!
安売りのかこつけ表現はデフレスパイラルになり、貨幣への融資以外は危険です。
Appleはこれらの対策として提案した内容がこれ。
データミニマイゼーション!
取得する情報・できる情報を最小化する。データが取れなければ、守る必要も漏れる可能性もない!
オンデバイスでのインテリジェンス!
スマートフォンなど機器のなかで処理を完結させることでプライバシーにかかわる部分を端末内に留める。
クラウドにアップロードして、照会プロセスを最小化することで、漏洩や不適切な保存の可能性を排除する!
高い透明性とコントロール!
どんなデータを集め、送っているのか、どう使うのかを明示し、ユーザーが理解したうえで自身で選んだり変更できるようにする!
セキュリティプロテクション!
機器上などで、どうしても発生するデータに関しては指紋認証や顔認証などを使ったセキュリティ技術で、漏えいがないようにしっかりと守るセキュリティプロテクション!機器上などで、どうしても発生するデータに関しては指紋認証や顔認証などを使ったセキュリティ技術で、漏えいがないようにしっかりと守る
202012のApp Storeプライバシー情報セクションは、3つ目「透明性とコントロール」の取り組み。
位置情報などは自己申告だが、アップルとユーザーを欺いて不適切な利用をしていることが分かればガイドラインと契約違反になり、App Storeからの削除や開発者登録の抹消もありえます。
このプライバシー情報の開示は12月8日から、iOS、iPadOS、macOS、tvOSなどOSを問わず、新アプリの審査時または更新時に提出が求められるようになっています。
2020年の4月と7月の違いは、新型コロナウイルスの場合、空気感染ではなく、飛沫感染という性質を考慮すると•••原則は、常にマスク着用、ソーシャルディスタンス。
検査数の量と陽性率でも見ると、東京都は、陽性率2、3%、200人前後で重症者数もバランスよく維持すれば、新型コロナウイルスを最小限に抑えつつ経済を持続できそうだ。
最新の研究によると、不織布のサージカルマスクなどは、感染予防にならないが、他人への拡散を抑える効果、ウイルス摂取量を抑える効果があるから、周囲の人たちが7、8割以上が行えば、実効再生産数を低下させ集団免疫に近い低減効果が得られるかもしれない。
ワクチンと同じくらいの防御効果がありそうだ。安全性の高いワクチンができるまでの実行再生産数を、1 より少なくする時間稼ぎに有効ということだけしかない。油断は禁物です!
吐く息の場合。不織布マスクは80%カット。布製マスクは70%カット。フェイスシールドは20%カット。マウスシールドは10%カット。
吸う息の場合。不織布マスクは70%カット。布製マスクは40%カット。フェイスシールドは効果なし。マウスシールドは効果なし。
続いて、日本国憲法尊守を前提で!
新型コロナウイルス2020に対応したFRBの金融政策と財政政策に異次元な変化が生じてる?
マネーストックとは「金融部門から経済全体に供給されている通貨の総量」のこと。
具体的には、金融機関・中央政府を除いた法人、個人などが保有する通貨(現金通貨や預金など)の残高を集計したもの。
日本銀行のベースマネーをコントロールするゼロ金利、量的緩和とは別枠で、ベースマネーからマネーストックへの橋渡しをする機関が弱いのでボトルネックになっていた。
ここで新型コロナウイルス2020が起きた!
将来の設備投資である個人デジタル貨幣型ベーシックインカム活用も含めて•••
アメリカのノーベル賞受賞経済学者ミルトン・フリードマン、元FRB議長であったベンバーナンキの書籍「大恐慌論」も言うように、金融危機2008、コロナショック2020などの急落に直面する対策として、ゼロ金利、マイナス金利、金融政策が出尽くした後に、よく登場する最速実行再分配政策が、個人への緊急的な現金給付!!!
各国によってスピードは異なるが、政策閣議決定後、人間の限界を遥かに超えるスピード。1秒以内で現金到着が理想。各国競争してみれば、今後の恒久対策として中央銀行のデジタル通貨なども考慮しつつ、新産業が産まれプラスサムになるかもしれません。
MMT(Modern Monetary Theory)によると、現状の貨幣での現実的なアイデアとして、社会保障に還元される日本の消費税は現状維持しつつ、現金給付額にも消費税がかかるので現金給付額を上げて、毎月給付にすると消費税率と社会保障費下支えとが均衡状態になる?と同時に、実体経済の経済成長率「g」の下支えにも寄与する?
これらの総量が、急激な不況時の資本収益率「r」以上なら、もしかして?回復して正常な経済環境に戻る期間も短縮できるかもしれません。
世界的な流れから各国政府経由で手厚い給付金を全国民に支給することになる。
日本も世界同時で協調し、国民皆給付を行うがスピードが世界に比べて同水準になってないことが判明した!そのうち改善するでしょう。
スペイン風邪から国民皆保険を構築した岸総理(他には、国民皆年金、最低賃金法もあります)安倍政権時代の安倍さんは、母方の祖父を見習いコロナウイルスから、毎月の国民皆給付を構築すれば歴史に残る業績になるし、継承する権利もある!
安倍政権時代の安倍さん、麻生さん。この二人でしかできない天命を見事果たした!アベノミクスの最終地点がコレだ!
この絶妙のタイミングで緊急的に構築した!天命と言わずにはいられない!
国民皆給付は達成したが、世界的な流れである毎月の国民皆給付には到達していない!
次善のアイデアとしては、三ヶ月に一回給付金。つまり、春夏秋冬に一回ずつ給付金も検討する価値はあります。
誰が発展させて引き継ぐのか?本人自身が行うのか?今後の継承を期待します。引き継いだ人間は、確実に人類の転換点に成し遂げた歴史に残る業績として記録されることでしょう。
将来は、官庁から量子暗号運用へ移行するための期間の長いデジタル化を始めてするも良し、庶民が行政手続きする際の申請だけにするなら資するかも?
金融機関への紐付け解除プロセスは現状維持として、まだアナログで十分!
前提条件として、基礎技術にリープフロッグは存在しません。応用分野のみです!
金融機関への紐付け?義務化は憲法違反。許可選択制にしろ!紐付け解除もできるようにしないと基本的人権侵害。
歴史の浅いコンピューターは、人間ではないし基本的人権は適用外だが、人類は違う!何千年もの構築した概念や法体系、歴史があり憎しみの連鎖も生じる。
中央値で一人年収600万円以上は給付金分年末に減税して、それ以下の年収は給付金支給にすればいい。日本国憲法尊守を前提で、こんなアイデアはどうだろうか?幸福がポイント。
ベーシックインカムは、現在の社会保障にプラスしていくことを前提条件として考慮しています!
もう一度。ベーシックインカムは、現在の社会保障にプラスしていくことを前提条件として考慮しています!
そして、テレワークの普及は諸刃の剣!
少ないから価値あるが誰もができると価値がなくなり、逆に一極集中加速する危険!アメリカ2020が、今そうだ!
GAFAなど。特にIT産業などは独占化しやすいから別枠で高税率にしてベーシックインカム用に再分配システム構築できないなら独占禁止法強化する世界的な流れになっている。
アメリカとは国土の大きさが違う!ので、マクロ経済学でいう小国開放経済の日本に、そのまま適用しても、新型コロナウイルスもあるし、現在の日本の普及率くらいが最善。これ以上は逆効果。
基本的人権という歯止めがないと薬が毒になる。
税の公平性はよく言われるが、時代が変わり、一極集中しやすく不公平が生じてるなら、産業別に税率を上昇させてバランスよくすればいい?
自由という概念を悪用するので簡単に言うと、自由権とは、18世紀のヨーロッパ市民革命、マグナカルタによってプロトコルを源にし言葉の定義を決めてから基本的人権の一つとして提唱されました。
憲法として日本にも導入されます!何でも自由に行うことではありません
これもその一つ。
「兵は詭道なり」戦いは、所詮騙し合いで、いろいろな謀りごとを凝らして、敵の目を欺き、状況いかんでは当初の作戦を変えることによって勝利を収めることができるものだ。
ということだが、誤解があって、憲法ある現代では、戦いの後に公開厳守が、法人も含めた権力者の原則です。
日本では、医療関係は、法律で個人情報の秘匿を義務化されてますが•••
国内法人大手NTTドコモは、本人の許可なく無断でスマートフォンの通信データを警察機関に横流しをしてる!
GAFAのように対策しない違法な法人?まさか、他にも?独占禁止法や法律を強化する?デフレスパイラル予防。このような国内大企業、中堅法人も危険。傲慢。
日本国憲法に違反しているので、アメリカのカリフォルニアやヨーロッパのGDPRのようにデータ削除の権利行使。
他に、再分配するデータ配当金を構築してからでないと基本的人権侵害になるため集団訴訟を国民は起こすべきだ。
税の公平性は、よく言われるが、時代が変わり一極集中しやすく不公平が生じてるなら産業別に税率を上昇させてバランスよくすればいい?
特に、IT産業などは、独占化しやすいから別枠で高税率にして、ベーシックインカム用に再分配システム構築できないなら独占禁止法強化。
自動的にディープフェイクをリアルタイムの別レイヤーで、防犯カメラの人物に重ね録画していくことで、写る本人の許諾が無いと外せないようなアルゴリズムを強力に防犯カメラの機能を追加していく。
防犯カメラのデータを所有者の意図しない所で警察機関他に無断悪用されない抑止力にもなります。
防犯カメラのデータを所有者の意図しない所で警察機関他に無断悪用されない抑止力にもなります。
防犯カメラのデータを所有者の意図しない所で警察機関他に無断悪用されない抑止力にもなります。
サミット警備時、死者数が微小なのにテロ対策と称し厳戒態勢!
経済活動を制限した時に、警視庁職権濫用してたが、死者数が甚大な新型コロナに予算増やした?
警察権力悪用!庶民弱者に圧力やめさせないの?オリンピック前にも圧力あったから予算削除しろ傲慢警察!
警察機関に個人データを保存するなら、至急データ配当金を創設して、毎月警察予算から配当金を庶民に給付する仕組みにしろ!
嫌なら、個人情報を削除する権利が庶民には、あるから行政府は行使できるようにしろ!予算削減がいいか!データ削除がいいか!
仕組みを創設しないなら、基本的人権の侵害で日本国憲法違反だ!
みんなで国と集団訴訟だ!誰かが起訴すれば歴史に残る偉業になる。
マイケルサンデルは、メリトクラシー(能力主義)の陳腐さを警告し、諌め(いさめ)ています!
マイケルサンデルは、メリトクラシー(能力主義)の陳腐さを警告し、諌め(いさめ)ています!
マイケルサンデルは、メリトクラシー(能力主義)の陳腐さを警告し、諌め(いさめ)ています!
金融ビックバン日本版と言う社会実験から20年位!規制緩和でどれだけの死者が出たのか?
世界中でも一定数あるが、自殺者の比率が日本に突出してるのは、金融ビックバン日本版の生贄となってる可能性大。民放テレビ局で煽ってたから当時の局関係者も共犯者。
例えば、戦国時代の能力主義は、相手を殺傷することが多ければ能力が最高クラス。現代は?法律で禁止されていて能力は最低クラスになります。陳腐ですね。
第二次世界大戦みたいに命は落とさないが、現代の金融IT世界大戦は、脳や心を人工知能も登場したことで善性の方向にデザインしないと、さらに無限に焼きつくされる!!危険性があります。これが本質です。だから、個人の最低収入保障強化、基本的人権の強化がより重大になっていく。
金融ビックバン日本版の生贄となった自殺者(精神障害、トラウマ、うつなど)に対しての国家の責任として、欧米の無名戦士の墓、日本の靖国神社みたいに自殺者を供養する神社を創設するアイデアはどうだろうか?
この後、デフレスパイラルが同時多発!そして、歴史が証明してる人権侵害も同時多発!憲法違反!
行政府は、既存産業となったIT産業を慎重に、裏付けのあるデータに基づいて公正に規制する方向が善性に沿う!逆は、愚かと判明!
人間の限界を超えた新産業に法のスピードが追いつかないから、極端な自由権や規制緩和と同じ効果なだけ!
過剰なデフレスパイラル競争になり、多様な賃金上昇環境が悪性になる。個人の最低収入保障強化、IT産業に特化した独占禁止法強化が必要と新型コロナウイルスで判明もした!
海外や国内IT企業などストーカーアルゴリズムを規制する現実的な法律案は、ストーカー規制法に付帯事項としてアルゴリズムやプログラムを追加する。
公人、有名人、俳優、著名人は知名度と言う概念での優越的地位の乱用を防止するため徹底追跡可能にしておくこと。
そうすれば、現行法を維持して法の網にかけられるぞ!死者も出てるし、今からやれ!
新型コロナウイルスの死者は、2020年11月。2000人超えた!テロの死者数は何人?
国家予算が警察やテロ対策より新型コロナ対策の方が少ないんだけど。警察やテロ対策予算削減して、新型コロナ対策に今すぐ回せ!
自転車専用道路は無駄だから予算廃止して、パンデミック対策、新型コロナ対策に今すぐ回せ!
SDGsや気候変動対策は、再生可能エネルギーのことではありません。パンデミック対策の一環です!それ以外の活動は派生物。権力濫用の口実に注意!
SDGsや気候変動対策は、再生可能エネルギーのことではありません。パンデミック対策の一環です!それ以外の活動は派生物。権力濫用の口実に注意!
SDGsや気候変動対策は、再生可能エネルギーのことではありません。パンデミック対策の一環です!それ以外の活動は派生物。権力濫用の口実に注意!
続いて
2020年後半くらいから様々な占いで出てきてた時代の変わり目。それが、西洋占星術で具体的に「風」の時代という形で出てきました。
私が、感じとってたインスピレーションは、たぶんこれかな?
兆しは、世界的な金融ビックバンの1970年代、IT革命のミレニアムの前から出ていたけど。
これは、これまでの約200年間。物質やリアリティの影響力優位「土」の属性の時代から、量子コンピューター、ビットやインターネットなどといった物質ではないものに影響力が増していく「風」の属性の時代に。
そして、本格的に軌道にのっていく属性は、今後200年程続くことになるのです(2020年12月22日から、2100年当たりをピークに少しずつ衰退していく2220年まで)
直前に!
Appleも何かを感じてたのか?Appleシリコン搭載Macの方は、「Mシリーズ」チップに移行してるし、符号してる。
Googleは、量子超越性を達成してきてるし、Facebookも脳波を読み取る機械の開発を発表してますし、符号してる。
イーロンマスクもブレイン・マシン・インターフェース(Brain-machine Interface : BMI)を具体的に発表。これも、符号してる。
以下から話がそれるが、読み飛ばし、読み進めるかして下さい。
ここから予想できることは、バリーシュワルツが言うように、労働の概念が変わり、地球に居ながら映画アバターのように!その惑星にある資源を使い。
月や火星、土星や衛星などに無人ロボット部品を送り、ゲームのように自宅にいながら共同作業しつつ仕事をすることで高額な賃金が手に入る可能性も高い。
火星や土星や衛星に関しては、有人宇宙船内を無重力工場にして惑星移動期間に3Dプリンター製造、組立を効率的に行うことが実現すれば良いが無人ならベスト。
光速で惑星間通信できるようになったとしても、火星や土星や衛星への通信は、地球からでもリアルタイムで遅延が起きるため、月面のみ、この可能性が開けます!
無重力でもあるため、洞窟に工場を建築して人間の暮らせる環境を作り出すこともできそうです。可能性は無限!この領域に限界はありません!国家や行政府の範囲外なので極端な自由もあります。命の保障はないけど!
このアイデアは、今後数十年、人間の限界を遥かに超える新産業なのでプラスサムになり、地球環境は汚染されず資源エネルギー問題も起こりません。
以上です。
通信料金をある程度下げることには賛成。さらに、中央銀行のデジタル通貨で光熱費料金もある程度、補助金という形で個人単位を補助し、実質的に料金を下げて欲しい。
電気やガス事業は、国防と密接で独占せざるを得ないから競争して、むやみにインフラ崩壊させるよりもデジタル通貨でベーシックインカム形式の光熱費補助にも特化して欲しい(合成の誤謬を最小限に抑えること前提)
毎月国民一律皆給付ベーシックインカムは最優先だが、財源がない場合に備えて、特化オプションをそろえて柔軟に機動的に実行できる環境も重要です(合成の誤謬を最小限に抑えること前提)
光熱費は毎月の消費なので貯金に回りづらいから庶民の生活下支えになる。しかし、競争しすぎてもデフレスパイラル競争になるから、光熱費領域は慎重に設計することが肝要。
内閣府の「マイナンバー制度の定義」は「マイナンバーは社会保障、税、災害対策の3分野で複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます」
基本的人権侵害にあたるため、他分野へむやみに拡大するのは危険です。
よく思い違いをするのが、新しい時代には、経験もない新しい人が!と言うが、なおさら、経験や実力がないと新しい時代に対応できず、大事な何がが抜け落ちて混乱する矛盾!
消費税増税は、国民に現金の一律皆給付の施策しないからシステムが困窮する!
安定財源として消費税増税は否定しないが、データから明らかで、法人税は35%まで上げればいい。
所得税の上級に裕福税を新設して法人個人の超金持ち達から分配して穴埋めすればいい。
財政バランス度外視で、ニュージーランドは、2週間に一回10万円の国民一律給付金。カナダは、月40万円。日本もやれ!
根拠は、なぜ?ポンドからドルに基軸通貨が入れ替わったのか?
の問いの中に真実が隠されている!(当時は、固定相場制。現在は変動相場制なので前提条件として、変動相場制で人工知能時代の金融工学を駆使するも十数年もの長いデフレ状態で、ゼロ金利政策、量的緩和も出尽くし、マイナス金利も導入してからです)
その答えがそうだ!バランスも大事だが、歴史の転換期には、非線形になりやすいので万能とは限らない!
何度も言うが、会社法では法人は自力で有限責任ダメならたたむ。行政府は強制的に強欲な法人を鎮圧して厳しいけどあきらめて再出発してもらう資本主義そのための会社法。
だから、最後の砦の個人保障を手厚く最優先!
嫌なら日本領土以外で土地を確保。防衛して衣食住を自ら創造して!そこから自由にどうぞ。と言う話になるけど選択は自由だからお好きにどうぞ。これが国家システムの原則。
新型コロナウイルスの死者は、2021年1月。3000人超えた!テロの死者数は何人?
2021年4月に邪悪な悪意の兆しを感じとったので一応書いておきます。
日本のベーシックサービス定義を明確化してからだが、現行法の社会保障とした場合と定義します。
人工知能時代におけるベーシックサービスと労働市場の間を橋渡しする概念が、一律皆給付やベーシックインカムとプラスサムに現時点ではイメージしてます。決して、ゼロサムではない!
パンデミック時には、一度でも緊急事態宣言を発動したらスタビライザー的な低収入者への給付を倍額以上に増額して自動的に実施とする法律改正がベスト。
一律皆給付やベーシックインカムは、経済急落時の機動的な下支えにして、GDPギャップ解消速度をコントロールできる社会実験も必要
その副次的効果に相対的に消費税率をゼロorマイナスに持っていければベスト(法律改正は光速で急落する速度に対応できません)
スタグフレーションも予防できます!
これは、1970年以降、先進国で生産が停滞し、失業率が増大する停滞期にもかかわらず、物価は好況期に引続き高騰してしまう現象。
スタグフレーションの原因は、景気停滞期において軍事費を主として、消費的な財政支出が拡大していること。
次に、労働組合の圧力によって名目賃金が、マイルドではなく、急上昇を続けていること。
三つ目は、企業の管理価格が強化され、賃金コストの上昇が、価格上昇に比較的容易に転嫁されていること。
などにあるとされている。
本質的に法律で暴力装置をがんじがらめにしたテロリスト集団が警察機構!
この定義以外は、戦前の治安維持法の権力濫用やディストピアという過ちを繰り返す可能性大。
その証拠に、優先ワクチンを口実にして優越的地位をふりまき権力濫用してる警察関係者。
米国では2020から2021年。個人給付を実施して結果が出た!
日本では、現状は、数回の一律皆給付を行い足りないGDPギャップを解消が最善。
バイデン大統領は2021年、財務長官にイエレン就任した際の経済対策の一環
「世界が相互に結びついたことのもう一つの結果が30年に及ぶ法人税率の引き下げ競争だった」
というマクロ経済学の結果を明示した前提で各国の多年の法人税引き下げ競争を終わらせ、20カ国・地域(G20)で協力して共通の最低税率を設ける国際的な取り組み
法人税に世界的な「最低税率」を設定することで合意するよう調整していると言います。
実現が遠い世界的なデジタル課税よりも現行法の範囲での現実的な提案をしたかもしれない!
2018年くらいから、GAFAMなどに対して、再分配に関するベーシックインカムや国民皆給付金。中央銀行のデジタル貨幣。
新型コロナウイルスのパンデミックで日本ではクリーニング師を含めたエッセンシャルサービスの重要性が再認識される。
GAFAMなどが基盤にしているストーカーアルゴリズムが問題になる。
規制を強化する方向に進んでます。
これはひどい人権侵害の法律!法律改正して再修正かな。
緊急事態宣言の途中に「まん延防止等重点措置」が2021年2月に新設されました(都道府県単位の緊急事態宣言。知事が市町村単位で指定できる「まん延防止」)
建前の主旨は「緊急事態宣言に至る前や解除後の感染拡大を緩やかに抑える」ため。
「ワクチン開発後、提供までのウイルス変異抑制」の文章が抜けてる!から法律に追加しろ!
前提として、今回のみ。新型コロナウイルスの場合です。特徴的な「近距離接触感染」が飲酒店に最も多く生じたデータを根拠にして(他のウイルス性感染症は違います)
緊急事態宣言のように飲食店に対し、休業の命令や要請はできないが、営業時間短縮の命令や要請はできます(協力金給付と同時に要請→命令→過料の流れ)
緊急事態宣言の前段階で、弱者の異議申し立ての無い私権制限を伴う措置を講じることには批判があるが、命令に違反した事業者には20万円以下の過料(前科がつく刑事罰ではなく、前科がつかない行政罰)を科すことができる。
「ワクチン開発後、提供までのウイルス変異抑制」「悪質でない事業者の場合。数回程度の過料を解除後に減免返還する」の法律文章が抜けてる!から追加しろ!
現都知事小池百合子、行政府の悪用が目立つ2021年4月
私権制限を伴う措置なので財産権侵害、人権侵害の憲法違反だから、都道府県知事に集団訴訟すれば?
選挙とは別だが、コロナ禍に乗じる権力濫用防止のチェック機能を兼ねた民意を示せていいかもしれない。
緊急事態宣言は「ステージ4」相当が発動条件。
「まん延防止」は「ステージ3」相当で!実効再生産数2以上の急速な拡大期なら「ステージ2」でも発動。「実効再生産数2以上の急速な拡大」条件も書いてないから法律に追加しろ!
緊急事態宣言も「ワクチン開発後、提供までのウイルス変異抑制」「悪質でない事業者の場合。数回程度の過料を解除後に減免返還する」の法律文章を追加しろ!
弱者を警察と見廻り隊で権力悪用するくせに、現都知事小池百合子の「まん延防止」に乗じた権力濫用を通報する見廻り隊はないのかな?第四波は、大阪の後追いで悪用事例はでてるのに!
解除後に返還できないなら、過料相当を弱者も権力者に請求できるように法改正しろ!
なぜ?この権力濫用チェックの仕組みをワザと抜かしてる?
2021年4月。選挙前で再び悪用してるな!この局面女は!
新型コロナウイルスの死者は、2021年5月辺りで累計10000人超えた!まだ、自殺者よりは少ないが•••予算をこっちに回せ!
こっちの方が遥かに甚大なんだけど。ワクチン接種完了人数に応じて新規感染者数は減少するデータもある。
テロの死者数は何人?テロ対策は優先順位を極端に低く見直さないと。今でしょ!
参考までに、同じ期間中に癌の死者は約40万人います。心疾患の死者は約20万人です。
スペイン風邪の時には、第二波で変異した凶暴なウイルスにより荒れ狂い大量の死者をだした。ワクチンもない。
数字上で比較すると現在の第四波五波に相当。
商いする環境ですらなかったスペイン風邪の時代に比べれば、公衆衛生的には超優秀で、ワクチンもあるし、まだ軽い方!昔の商人が見てたらなんて言うかな?
現状維持でかろうじて商いできてるし、100年前に比べて、この程度で済んでいて幸せな方向に進んでいるなぁと見ています。
<提供>
東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント
独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです
東京都北区神谷のハイブリッドな直送ウェブサービス(Hybrid Synergy Service)高橋クリーニングFacebook版
#セス#バークレー#HIV#治療#薬#戦争#設計#製造#革新#進歩#コロナ#インフルエンザ#遺伝子#感染#予防#wave#jwave#DNA#分子#生物学#ウイルス#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery
0 notes