#特に冬は頭に雪が積もったりすればそれはやっぱりずっと濡れていることになろうて
Explore tagged Tumblr posts
Text
青と金色
■サイレンス
この部屋のインターフォンも灰色のボタンも、だいぶ見慣れてきた。指で押し込めて戻すと、ピーンポーンと内側に引っ込んだような軽い電子音が鳴る。まだこの地に来た頃はこうやって部屋主を呼び出して待つのが不思議な気分だった。鍵は開かれていたし、裏口だって知っていたから。 「…さむっ」 ひゅうう、と冷たい風が横から吹き込んで、思わずそう呟いて肩を縮めた。今週十二月に入ったばかりなのに、日が落ちると驚くほど冷え込む。今日に限って天気予報を観ていなかったけれど、今夜はいつもと比べても一段と寒いらしい。 近いし、どうせすぐだからと、ろくに防寒のことを考えずに部屋を出てきたのは失敗だった。目についた適当なトレーナーとパンツに着替え、いつものモッズコートを羽織った。おかげで厚みは足りないし、むき出しの両手は指先が赤くなるほど冷えてしまっている。こんなに寒いのならもっとしっかりと重ね着してこれば良かった。口元が埋まるくらいマフラーをぐるぐるに巻いてきたのは正解だったけれど。 いつもどおりインターフォンが繋がる気配はないけれど、その代わりに扉の奥からかすかに足音が近付く。カシャリ、と内側から錠の回る音がして目の前の扉が開かれた。 「おつかれ、ハル」 部屋の主は片手で押すように扉を開いたまま、咎めることも大仰に出迎えることもなく、あたたかい灯りを背にして、ただ静かにそこに佇んでいた。 「やっと来たか」 「はは、レポートなかなか終わらなくって…。遅くなっちゃってごめんね」 マフラー越しに笑いかけると、遙は小さく息をついたみたいだった。一歩進んで内側に入り、重たく閉じかける扉を押さえてゆっくりと閉める。 「あ、ここで渡しちゃうからいいよ」 そのまま部屋の奥に進もうとする遙を呼び止めて、玄関のたたきでリュックサックを開けようと背から下ろした。 遙に借りていたのはスポーツ心理学に関する本とテキストだった。レポート課題を進めるのに内容がちょうど良かったものの自分の大学の図書館では既に貸し出し中で、書店で買うにも版元から取り寄せるのに時間がかかるとのことだった。週明けの午後の講義で遙が使うからそれまでには返す、お互いの都合がつく日曜日の夕方頃に部屋に渡しに行く、と約束していたのだ。行きつけのラーメン屋で並んで麺を啜っていた、週の頭のことだった。 「いいから上がれよ」遙は小さく振り返りながら促した。奥からほわんとあたたかい空気が流れてくる。そこには食べ物や��との生活の匂いが確かに混じっていて、色に例えるなら、まろやかなクリーム色とか、ちょうど先日食べたラーメンのスープみたいなあたたかい黄金色をしている。それにひとたび触れてしまうと、またすぐに冷えた屋外を出て歩くために膨らませていた気力が、しるしるとしぼんでしまうのだ。 雪のたくさん降る場所に生まれ育ったくせに、寒いのは昔から得意じゃない。遙だってそのことはよく知っている。もちろん、帰ってやるべきことはまだ残っている。けれどここは少しだけ優しさに甘えようと決めた。 「…うん、そうだね。ありがと、ハル」 お邪魔しまーす。そう小さく呟いて、脱いだ靴を揃える。脇には見慣れたスニーカーと、濃い色の革のショートブーツが並んでいた。首に巻いたマフラーを緩めながら短い廊下を歩き進むうちに、程よくあたためられた空気に撫ぜられ、冷えきった指先や頬がぴりぴりと痺れて少しだけ痒くなる。 キッチンの前を通るときに、流しに置かれた洗いかけの食器や小鍋が目に入った。どうやら夕食はもう食べ終えたらしい。家を出てくる前までは課題に夢中だったけれど、意識すると、空っぽの胃袋が悲しげにきゅうと鳴った。昼は簡単な麺類で済ませてしまったから、帰りにがっつり肉の入ったお弁当でも買って帰ろう。しぼんだ胃袋をなぐさめるようにそう心に決めた。 「外、風出てきたから結構寒くってさ。ちょっと歩いてきただけなのに冷えちゃった」 「下旬並だってテレビで言ってた。わざわざ来させて悪かったな」 「ううん、これ貸してもらって助かったよ。レポートもあと少しで終わるから、今日はちゃんと寝られそう……」 遙に続いてリビングに足を踏み入れ、そこまで口にしたところで言葉が詰まってしまった。ぱちり、ぱちりと大きく瞬きをして眼下の光景を捉え直す。 部屋の真ん中に陣取って置かれているのは、彼の実家のものより一回り以上小さいサイズの炬燵だ。遙らしい大人しい色合いの炬燵布団と毛布が二重にして掛けられていて、丸みがかった正方形の天板が上に乗っている。その上にはカバーに入ったティッシュ箱だけがちょんとひとつ置かれていた。前回部屋に訪れたときにはなかったものだ。去年は持っていなくて、今年は買いたいと言っていたことを思い出す。けれど、それはさして驚くようなことでもない。 目を奪われたのは、その場所に半分身を埋めて横になり、座布団を枕にして寝息を立てている人物のことだった。 「…えっ、ええっ? 凛!?」 目の前で眠っているのは、紛れもなく、あ��松岡凛だった。普段はオーストラリアにいるはずの、同郷の大切な仲間。凛とはこの夏、日本国内の大会に出ていた時期に会って以来、メールやメディア越しにしか会えていなかった。 「でかい声出すな、凛が起きる」 しいっと遙が小声で咎めてくる。あっ、と慌てたけれど、当の凛は起きるどころか身じろぐこともなく、ぐっすりと深く眠ってしまっているようだった。ほっと胸を撫で下ろす。 「ああ、ご、ごめんね…」 口をついて出たものの、誰に、何に対してのごめんなのか自分でもよく分からない。凛がここにいるとは予想だにしていなかったから、ひどく驚いてしまった。 凛は今までも、自分を含め東京に住んでいる友達の部屋に泊まっていくことがあった。凛は東京に住まいを持たない。合宿や招待されたものならば宿が用意されるらしいけれど、そうでない用事で東京に訪れることもしばしばあるのだそうだ。その際には、自費で安いビジネスホテルを使うことになる。一泊や二泊ならともかく、それ以上連泊になると財布への負担も大きいことは想像に難くない。 東京には少なくとも同級生だけで遙と貴澄と自分が住んでいる。貴澄は一人暮らしでないからきっと勝手も違うのだろうが、遙と自分はその点都合が良い。特に遙は同じ道を歩む選手同士だ。凛自身はよく遠慮もするけれど、彼の夢のために、できるだけの協力はしてやりたい。それはきっと、隣に並ぶ遙も同じ気持ちなのだと思う。 とはいえ、凛が来ているのだと知っていれば、もう少し訪問の日時も考えたのに。休日の夜の、一番くつろげる時間帯。遙ひとりだと思っていたから、あまり気も遣わず来てしまったのに。 「ハル、一言くらい言ってくれればいいのに」 強く非難する気はなかったけれど、つい口をついて本音が出てしまった。あえて黙っていた遙にじとりと視線を向ける。遙はぱちり、ぱちりと目を瞬かせると、きゅっと小さく眉根を寄せ、唇を引き結んだ。 「別に…それが断わる理由にはならないだろ」 そう答えて視線を外す遙の表情には少し苦い色が含まれていて、それでまた一歩、確信に近付いたような気がした。近くで、このごろはちょっと離れて、ずっと見てきたふたりのこと。けれど今はそっと閉じて黙っておく。決してふたりを責めたてたいわけではないのだ。 「…ん、そうだね」 漂う空気を曖昧にぼかして脇にやり、「でも、びっくりしたなぁ」と声のトーンを上げた。遙は少しばつが悪そうにしていたけれど、ちらりと視線を戻してくる。困らせたかな、ごめんね、と心の中で語りかけた。 「凛がこの時期に帰ってくるなんて珍しいよね。前に連絡取り合ったときには言ってなかったのに」 「ああ…俺も、数日前に聞いた。こっちで雑誌だかテレビだかの取材を受けるとかで呼ばれたらしい」 なんでも、その取材自体は週明けに予定されていて、主催側で宿も用意してくれているらしい。凛はその予定の数日前、週の終わり際に東京にやって来て、この週末は遙の部屋に泊まっているのだそうだ。今は確かオフシーズンだけれど、かといってあちこち遊びに行けるほど暇な立場ではないのだろうし、凛自身の性格からしても、基本的に空いた時間は練習に費やそうとするはずだ。メインは公的な用事とはいえ、今回の東京訪問は彼にとってちょっとした息抜きも兼ねているのだろう。 「次に帰ってくるとしたら年末だもんね。早めの休みでハルにも会えて、ちょうど良かったんじゃない」 「それは、そうだろうけど…」 遙は炬燵の傍にしゃがみこんで、凛に視線を向けた。 「ろくに連絡せずに急に押しかけてきて…本当に勝手なやつ」 すうすうと寝息を立てる凛を見やって、遙は小さく溜め息をついた。それでも、見つめるその眼差しはやわらかい。そっと細められた瞳が何もかもを物語っている気がする。凛は、見ている限り相変わらずみたいだけれど。ふたりのそんな姿を見ていると自然と笑みがこぼれた。 ハル、あのね。心の中でこっそり語りかけながら、胸の内側にほこほことあたたかい感情が沸き上がり広がっていくのが分かった。 凛って、どんなに急でもかならず前もって連絡を取って、ちゃんと予定を確認してくるんだよ。押しかけてくるなんて、きっとそんなのハルにだけじゃないかなぁ。 なんて考えながら、それを遙に伝えるのはやめておく。凛の名誉のためだった。 視線に気付いた遙が顔を上げて、お返しとばかりにじとりとした視線を向けた。 「真琴、なんかニヤニヤしてないか」 「そんなことないよ」 つい嬉しくなって口元がほころんでいたらしい。 凛と、遙。そっと順番に視線を移して、少しだけ目を伏せる。 「ふたりとも相変わらずで本当、良かったなぁと思って」 「…なんだそれ」 遙は怪訝そうに言って、また浅く息をついた。
しばらくしておもむろに立ち上がった遙はキッチンに移動して、何か飲むか、と視線を寄こした。 「ついでに夕飯も食っていくか? さっきの余りなら出せる」 夕飯、と聞いて胃が声を上げそうになる。けれど、ここは早めにお暇しなければ。軽く手を振って遠慮のポーズをとった。 「あ、いいよいいよ。まだレポート途中だし、すぐに帰るからさ。飲み物だけもらっていい?」 遙は少し不満そうに唇をへの字に曲げてみせたけれど、「分かった、ちょっと待ってろ」と冷蔵庫を開け始めた。 逆に気を遣わせただろうか。なんだか申し訳ない気持ちを抱きながら、炬燵のほうを見やる。凛はいまだによく眠ったままだった。半分に折り畳んだ座布団を枕にして横向きに背を縮めていて、呼吸に合わせて規則正しく肩が上下している。力の抜けた唇は薄く開いていて、その無防備な寝顔はいつもよりずっと幼く、あどけないとさえ感じられた。いつもあんなにしゃんとしていて、周りを惹きつけて格好いいのに。目の前にいるのはまるで小さな子供みたいで、眺めていると思わず顔がほころんでしま��。 「凛、よく寝てるね」 「一日連れ回したから疲れたんだろ。あんまりじっと見てやるな」 あ、また。遙は何げなく言ったつもりなのだろう。けれど、やっぱり見つけてしまった。「そうだね」と笑って、また触れずに黙っておくけれど。 仕切り直すように、努めて明るく、遙に投げかけた。 「でも、取材を受けに来日するなんて、なんか凛、すっかり芸能人みたいだね」 凄いなぁ。大仰にそう言って視線を送ると、遙は、うん、と喉だけで小さく返事をした。視線は手元に落とされていながら、その瞳はどこか遠くを見つめていた。コンロのツマミを捻り、カチチ、ボッと青い火のつく音がする。静かなその横顔は、きっと凛のことを考えている。岩鳶の家で居間からよく見つめた、少し懐かしい顔だった。 こんなとき、いまここに、目の前にいるのに、とそんな野暮なことはとても言えない。近くにいるのにずっと遠くに沈んでいた頃の遙は、まだ完全には色褪せない。簡単に遠い過去に押しやって忘れることはできなかった。 しばらく黙って待っていると遙はリビングに戻って来て、手に持ったマグカップをひとつ差し出した。淹れたてのコーヒーに牛乳を混ぜたもので、あたたかく優しい色合いをしていた。 「ありがとう」 「あとこれも、良かったら食え」 貰いものだ、と小さく個包装されたバウムクーヘンを二切れ分、炬燵の上に置いた。背の部分にホワイトチョコがコーティングしてあって、コーヒーによく合いそうだった。 「ハルは優しいね」 そう言って微笑むと、遙は「余らせて���だけだ」と視線を逸らした。 冷えきった両の手のひらをあたためながらマグカップを傾ける。冷たい牛乳を入れたおかげで飲みやすい温度になっていて、すぐに口をつけることができた。遙は座布団を移動させて、眠っている凛の横に座った。そうして湯気を立てるブラックのコーヒーを少しずつ傾けていた。 「この休みはふたりでどこか行ってきたの?」 遙はこくんと頷いて、手元の黒い水面を見つめながらぽつぽつと語り始めた。 「公園に連れて行って…買い物と、あと、昨日は凛が何か観たいって言うから、映画に」 タイトルを訊いたけれど、遙の記憶が曖昧で何だかよく分からなかったから半券を見せてもらった。CM予告だけ見かけたことのある洋画で、話を聞くに、実在した人物の波乱万丈な人生を追ったサクセスストーリーのようだった。 「終盤ずっと隣で泣かれたから、どうしようかと思った」 遙はそう言って溜め息をついていたけれど、きっとそのときは気が気ではなかったはずだ。声を押し殺して感動の涙を流す凛と、その隣で映画の内容どころではなくハラハラと様子を見守る遙。その光景がありありと眼前に浮かんで思わず吹き出してしまった。 「散々泣いてたくせに、終わった後は強がっているし」 「あはは、凛らしいね」 俺が泣かせたみたいで困った、と呆れた顔をしてコーヒーを口に運ぶ遙に、あらためて笑みを向けた。 「よかったね、ハル」 「…何がだ」 ふいっと背けられた顔は、やっぱり少し赤らんでいた。
そうやってしばらく話しているうちにコーヒーは底をつき、バウムクーヘンもあっという間に胃袋に消えてしまった。空になったマグカップを遙に預け、さて、と膝を立てる。 「おれ、そろそろ帰るね。コーヒーごちそうさま」 「ああ」 遙は玄関まで見送ってくれた。振り返って最後にもう一度奥を見やる。やはり、凛はまだ起きていないようだった。 「凛、ほんとにぐっすりだね。なんか珍しい」 「ああ。でも風呂がまだだから、そろそろ起こさないと」 遙はそう言って小さく息をついたけれど、あんまり困っているふうには見えなかった。 「あ、凛には来てたこと内緒にしておいてね」 念のため、そう言い添えておいた。隠すようなことではないけれど、きっと多分、凛は困るだろうから。遙は小さく首を傾げたけれど、「分かった」と一言だけ答えた。 「真琴、ちょっと待て」 錠を開けようとすると、思い出したみたいに遙はそう言って踵を返し、そうしてすぐに赤いパッケージを手にリビングから戻ってきた。 「貼るカイロ」 大きく書かれた商品名をそのまま口にする。その場で袋を開けて中身を取り出したので、貼っていけ、ということらしい。貼らずにポケットに入れるものよりも少し大きめのサイズだった。 「寒がりなんだから、もっと厚着しろよ」 確かに、今日のことに関しては反論のしようがない。完全に油断だったのだから。 「でも、ハルも結構薄着だし、人のこと言えないだろ」 着ぶくれするのが煩わしいのか、遙は昔からあまり着こまない。大して寒がる様子も見せないけれど、かつては年に一度くらい、盛大に風邪を引いていたのも知っている。 「年末に向けて風邪引かないように気を付けなよ」 「俺は大丈夫だ、こっちでもちゃんと鯖を食べてるから」 「どういう理屈だよ…って、わあっ」 「いいから。何枚着てるんだ」 言い合っているうちに遙が手荒く背中をめくってくる。「ここに貼っとくぞ」とインナーの上から腰の上あたりに、平手でぐっと押すように貼り付けられた。気が置けないといえばそうだし、扱いに変な遠慮がないというか何というか。すぐ傍で、それこそ兄弟みたいに一緒に育ってきたのだから。きっと凛には、こんな風にはしないんだろうなぁ。ふとそんな考えが頭をもたげた。 遙はなんだか満足げな顔をしていた。まぁ、きっとお互い様なんだな。そう考えながら、また少し笑ってしまった。 「じゃあまたね、おやすみ」 「ああ。気を付けて」
急にひとりになると、より強く冷たく風が吹きつける気がする。けれど、次々沸き上がるように笑みが浮かんで、足取りは来る前よりずっと軽かった。 空を仰ぐと、小さく星が見えた。深く吐いた息は霧のように白く広がった。 ほくほく、ほろほろ、それがじわじわと身体中に広がっていくみたいに。先ほど貼ってもらったカイロのせいだろうか。それもあるけれど、胸の内側、全体があたたかい。やわらかくて、ちょっと苦さもあるけれど、うんとあたたかい。ハルが、ハルちゃんが嬉しそうで、良かった。こちらまで笑みがこぼれてしまうくらいに。東京の冬の夜を、そうやってひとり歩き渡っていた。
■ハレーション
キンとどこかで音がするくらいに空気は冷えきっていた。昨日より一段と寒い、冬の早い朝のこと。 日陰になった裏道を通ると、浅く吐く息さえも白いことに気が付く。凛は相変わらず少し先を歩いて、ときどき振り返っては「はやく来いよ」と軽く急かすように先を促した。別に急ぐような用事ではないのに。ためらいのない足取りでぐんぐんと歩き進んで、凛はいつもそう言う。こちらに来いと。心のどこかでは、勝手なやつだと溜め息をついているのに、それでも身体はするすると引き寄せられていく。自然と足が前へと歩を進めていく。 たとえばブラックホールや磁石みたいな、抗いようのないものなのだと思うのは容易いことだった。手繰り寄せられるのを振りほどかない、そもそもほどけないものなのだと。そんな風に考えていたこともあった気がする。けれど、あの頃から見える世界がぐんと広がって、凛とこうやって過ごすうちに、それだけではないのかもしれないと感じ始めた。 あの場所で、凛は行こうと言った。数年も前の夏のことだ。 深い色をした長いコートの裾を揺らして、小さく靴音を鳴らして、凛は眩い光の中を歩いていく。 格好が良いな、と思う。手放しに褒めるのはなんだか恥ずかしいし、悔しいから言わないけれど。それにあまり面と向かって言葉にするのも得意ではない。 それでもどうしても、たとえばこういうとき、波のように胸に押し寄せる。海辺みたいだ。ざっと寄せて引くと濡れた跡が残って、繰り返し繰り返し、どうしようもなくそこにあるものに気付かされる。そうやって確かに、この生きものに惚れているのだと気付かされる。
目的地の公園は、住んでいるアパートから歩いて十分ほどのところにある。出入りのできる開けた場所には等間隔で二本、石造りの太い車止めが植わるように並んでいて、それを凛はするりと避けて入っていった。しなやかな動きはまるで猫のようで、見えない尻尾や耳がそこにあるみたいだった。「なんか面白いもんでもあったか?」「いや、別に」口元がゆるみかけたのをごまかすためにとっさに顔ごと、視線を脇に逸らす。「なんだよ」凛は怪訝そうな、何か言いたげな表情をしたけれど、それ以上追及することはなくふたたび前を向いた。 道を歩き進むと広場に出た。ここは小さな公園やグラウンドのような一面砂色をした地面ではなく、芝生の広場になっている。遊具がない代わりにこの辺りでは一番広い敷地なので、思う存分ボール投げをしたり走り回ったりすることができる。子供たちやペットを連れた人たちが多く訪れる場所だった。 芝生といっても人工芝のように一面青々としたものではなく、薄い色をした芝生と土がまだらになっているつくりだった。見渡すと、地面がところどころ波打ったようにでこぼこしている。区によって管理され定期的に整備されているけれど、ここはずいぶん古くからある場所なのだそうだ。どこもかしこもよく使い込まれていて、人工物でさえも経年のせいでくすんで景観に馴染んでいる。 まだらで色褪せた地面も、長い時間をかけて踏み固められていると考えれば、落ち着いてもの静かな印象を受ける。手つかずの新品のものよりかは、自分にとって居心地が良くて好ましいと思えた。 広場を囲んで手前から奥に向かい、大きく輪になるようにイチョウの木々が連なって並んでいる。凛は傍近くの木の前に足を止め、見上げるなり、すげぇなと感嘆の声を漏らした。 「一面、金色だ」 立ち止まった凛の隣に並び、倣って顔を上げる。そこには確かに、すっかり金に色付いたイチョウの葉が広がっていた。冬の薄い青空の真下に、まだ真南に昇りきらない眩い光をたっぷりと受けてきらきらと、存在を主張している。 きんいろ、と凛の言葉を小さく繰り返した。心の中でもう一度唱えてみる。なんだか自分よりも凛が口にするほうが似つかわしいように思えた。 周囲に視線を巡らせると、少し離れた木々の元で、幼い子供ふたりが高い声を上げて追いかけっこをしていた。まだ幼稚園児くらいの年の頃だろうか、頭一個分くらい身の丈の異なる男の子ふたりだった。少し離れて、その父親と母親と思しき大人が並んでその様子を見守っている。だとすると、あのふたりは兄弟だろうか。大人たちの向ける眼差しはあたたかく優しげで、眩しいものを見るみたいに細められていた。 「な、あっち歩こうぜ」 凛が視線で合図して、広場を囲む遊歩道へと促した。舗装されて整備されているそこは木々に囲まれて日陰になっているところが多い。ここはいつも湿った匂いがして、鳥の鳴き声もすぐ近くから降りそそぐように聞こえてくる。よく晴れた今日はところどころ木漏れ日が差し込み、コンクリートの地面を点々と照らしていた。 休日の朝ということもあって、犬の散歩やジャージ姿でランニングに励む人も少なくなかった。向かいから来てすれ違ったり後ろから追い越されたり。そしてその度に凛に一瞥をくれる人が少なくないことにも気付かされる。 決して目立つ服を着ているわけでもなく、髪型や風貌が特に奇抜なわけでもないのに、凛はよく人目を惹く。それは地元にいたときにも薄っすらと浮かんでいた考えだけれど、一緒に人通りの多い街を歩いたときに確信した。凛はいつだって際立っていて、埋没しない。それは自分以外の誰にとってもきっとそうなのだろう。 いい場所だなぁ。凛は何でもないみたいにそう口にして、ゆったりとした足取りで隣を歩いている。木々の向こう側、走り回る子供たちを遠く見つめていたかと思えば、すぐ脇に設けられている木のベンチに視線を巡らせ、散歩中の犬を見て顔をほころばせては楽しそうに視線で追っている。公園までの道中は「はやく」と振り返って急かしたくせに、今の凛はのんびりとしていて、景色を眺めているうちに気が付けば足を止めている。こっそり振り返りながらも小さく先を歩いていると、ぽつぽつとついてきて、すうと寄せるようにしてまた隣に並ぶ。 その横顔をちらりと伺い見る。まるで何かを確かめるかのように視線をあちらこちらに向けてはいるものの、特にこれといって変わったところもなく、そこにいるのはいつも通りの凛そのものだった。 見られるという行為は、意識してしまえば、少なくとも自分にとってはあまり居心地が良いものではない。時にそれは煩わしさが伴う。凛にとってはどうなのだろう。改まって尋ねたことはないけれど、良くも悪くも凛はそれに慣れているような気がする。誰にとっても、誰に対しても。凛はいつだって中心にいるから。そう考えると苦い水を飲み下したような気持ちになって、なんだか少し面白くなかった。
遊歩道の脇につくられた水飲み場は、衛生のためだろう、周りのものよりずっと真新しかった。そこだけ浮き上がったみたいに、綺麗に背を伸ばしてそこに佇んでいた。 凛はそれを一瞥するなり近付いて、側面の蛇口を捻った。ゆるくふき出した水を見て、「お、出た」と呟いたけれど、すぐに絞って口にはしなかった。 「もっと寒くなったら、凍っちまうのかな」 「どうだろうな」 東京も、うんと冷えた朝には水溜まりが凍るし、年によっては積もるほど雪が降ることだってある。水道管だって凍る日もあるかもしれない。さすがに冬ごとに凍って壊れるようなつくりにはしていないと思うけれど。そう答えると凛は、「なるほどなぁ」と頷いて小さく笑った。 それからしばらくの間、言葉を交わすことなく歩いた。凛がまた少し先を歩いて、付かず離れずその後ろを追った。ときどき距離がひらいたことに気付くと、凛はコートの裾を揺らして振り返り、静かにそこに佇んで待っていた。 秋の頃までは天を覆うほど生い茂っていた木々の葉は、しなびた色をしてはらはらと散り始めていた。きっとあの金色のイチョウの葉も、程なくして散り落ちて枝木ばかりになってしまうのだろう。 「だいぶ日が高くなってきたな」 木々の間から大きく陽が差し込んで、少し離れたその横顔を明るく照らしている。 「あっちのほうまできらきらしてる」 中央の広場の方を指し示しながら、凛が楽しげに声を上げた。示す先に、冷えた空気が陽を受け、乱反射して光っている。 「すげぇ、綺麗」 そう言って目を細めた。 綺麗だった。息を呑んで見惚れてしまうほどに。いっぱいに注がれて満ちる光の中で、すらりと伸びる立ち姿が綺麗だった。 時折見せる熱っぽい顔とは縁遠い、冴えた空気の中で照らされた頬が白く光っていた。横顔を見ていると、なめらかで美しい線なのだとあらためて気付かされる。額から眉頭への曲線、薄く開いた唇のかたち。その鼻筋をなぞってみたい。���に溶け込むと輪郭が白くぼやけて曖昧になる。眩しそうに細めた目を瞬かせて、長い睫毛がしぱしぱ、と上下した。���が散って、これも金色なのだと思った。 そうしているうちに、やがて凛のほうからおもむろに振り返って、近付いた。 「なぁ、ハル」少し咎めるような口調だった。「さっきからなんだよ」 ぴん、と少しだけ背筋が伸びる。身構えながらも努めて平静を装い、「なにって、何だ」と問い返した。心当たりは半分あるけれど、半分ない。 そんな態度に呆れたのか凛は小さく息をついて、言った。じっと瞳の奥を見つめながら、唇で軽く転がすみたいな声色で。 「おれのこと、ずっと見てんじゃん」 どきっと心臓が跳ねた。思わず息を呑んでしまう。目を盗んでこっそり伺い見ていたのに、気付かれていないと思っていたのに、気付かれていた。ずっと、という一言にすべてを暴かれてしまったみたいで、ひどく心を乱される。崩れかけた表情を必死で繕いながら、顔ごと大きく視線を逸らした。 「み、見てない」 「見てる」 「見てない」 「おい逃げんな。見てんだろ」 「見てないって、言ってる」 押し問答に焦れたらしく凛は、「ホントかぁ?」と疑り深く呟いて眉根を寄せてみせる。探るような眼差しが心地悪い。ずい、と覗き込むようにいっそう顔を近付けられて、身体の温度が上がったのを感じた。あからさまに視線を泳がせてしまったのが自分でも分かって、舌打ちしたくなる。 「別に何でもない。普段ここへは一人で来るから、今日は凛がいるって、思って」 だから気になって、それだけだ。言い訳にもならなかったけれど、無理矢理にそう結んでこれ以上の追及を免れようとした。 ふうん、と唇を尖らせて、凛はじとりとした視線を向け続ける。 しかしやがて諦めたのか、「ま、いいけどさ」と浅くため息をついて身を翻した。 顔が熱い。心臓がはやい。上がってしまった熱を冷まそうと、マフラーを緩めて首筋に冷気を送り込んだ。
それからしばらく歩いていくうちに遊歩道を一周して、最初の出入り口に戻ってきた。凛は足を止めると振り返り、ゆっくりと、ふたたび口を開いた。 「なぁ、ハル」今度は歩きながら歌を紡ぐみたいな、そんな調子で。 「さっきは良いっつったけどさ、おれ」 そう前置きするなり、凛はくすぐったそうに笑った。小さく喉を鳴らして、凛にしては珍しく、照れてはにかんだみたいに。 「ハルにじっと見つめられると、やっぱちょっと恥ずかしいんだよな」 なんかさ、ドキドキしちまう。 なんだよ、それ。心の中で悪態をつきながらも、瞬間、胸の内側が鷲摑みされたみたいにきゅうとしぼられた。そして少しだけ、ちくちくした。それは時にくるしいとさえ感じられるのに、その笑顔はずっと見ていたかった。目が離せずに、そのひとときだけ、時が止まったみたいだった。この生きものに、どうしようもなく惚れてしまっているのだった。 「あー…えっと、腹減ったなぁ。一旦家帰ろうぜ」 凛はわざとらしく声のトーンを上げ、くるりと背を向けた。 「…ああ」 少し早められた足取り、その後ろ姿に続いて歩いていく。 コンクリートの上でコートの裾が揺れている。陽がかかった部分の髪の色が明るい。視界の端にはイチョウの木々が並んできらめいていた。 「朝飯、やっぱ鯖?」 ���に並ぶなり凛がそっと訊ねてきた。 「ロースハム、ベーコン、粗挽きソーセージ」 冷蔵庫の中身を次々と列挙すると、凛はこぼれるように声を立てて笑ってみせた。整った顔をくしゃりとくずして、とても楽しそうに。つられて口元がほころんだ。 笑うと金色が弾けて眩しい。くすみのない、透明で、綺麗な色。まばたきの度に眼前に散って、瞼の裏にまで届いた。 やっぱり凛によく似ている。きっとそれは、凛そのものに似つかわしいのだった。
(2017/12/30)
3 notes
·
View notes
Text
自殺未遂
何度も死のうとしている。
これからその話をする。
自殺未遂は私の人生の一部である。一本の線の上にボツボツと真っ黒な丸を描くように、その記憶は存在している。
だけど誰にも話せない。タブーだからだ。重たくて悲しくて忌み嫌われる話題だからだ。皆それぞれ苦労しているから、人の悲しみを背負う余裕なんてないのだ。
だから私は嘘をつく。その時代を語る時、何もなかったふりをする。引かれたり、陰口を言われたり、そういう人だとレッテルを貼られたりするのが怖いから。誰かの重荷になるのが怖いから。
一人で抱える秘密は、重たい。自分のしたことが、当時の感情が、ずっしりと肩にのしかかる。
私は楽になるために、自白しようと思う。黙って平気な顔をしているのに、もう疲れてしまった。これからは場を選んで、私は私の人生を正直に語ってゆきたい。
十六歳の時、初めての自殺未遂をした。
五年間の不登校生活を脱し高校に進学したものの、面白いくらい馴染めなかった。天真爛漫に女子高生を満喫する宇宙人のようなクラスメイトと、同じ空気を吸い続けることは不可能だと悟ったのだ。その結果、私は三ヶ月で中退した。
自信を失い家に引きこもる。どんよりと暗い台所でパソコンをいじり続ける。将来が怖くて、自分が情けなくて、見えない何かにぺしゃんこに潰されてしまいそうだった。家庭は荒れ、母は一日中家にいる私に「普通の暮らしがしたい」と呟いた。自分が親を苦しめている。かといって、この先どこに行っても上手くやっていける気がしない。悶々としているうちに十キロ痩せ、���理が止まった。肋が浮いた胸で死のうと決めた。冬だった。
夜。親が寝静まるのを待ちそっと家を出る。雨が降っているのにも関わらず月が照っている。青い光が濁った視界を切り裂き、この世の終わりみたいに美しい。近所の河原まで歩き、濡れた土手を下り、キンキンに冷えた真冬の水に全身を浸す。凍傷になれば数分で死に至ることができると聞いた。このままもう少しだけ耐えればいい。
寒い!私の体は震える。寒い!あっという間に歯の根が合わなくなる。頭のてっぺんから爪先までギリギリと痛みが駆け抜け、三秒と持たずに陸へ這い上がった。寒い、寒いと呟きながら、体を擦り擦り帰路を辿る。ずっしりと水を含んだジャージが未来のように重たい。
風呂場で音を立てぬよう泥を洗い流す。白いタイルが砂利に汚されてゆく。私は死ぬことすらできない。妙な落胆が頭を埋めつくした。入水自殺は無事、失敗。
二度目の自殺未遂は十七歳の時だ。
その頃私は再入学した高校での人間関係と、精神不安定な母との軋轢に悩まされていた。学校に行けば複雑な家庭で育った友人達の、無視合戦や泥沼恋愛に巻き込まれる。あの子が嫌いだから無視をするだのしないだの、彼氏を奪っただの浮気をしているだの、親が殴ってくるだの実はスカトロ好きのゲイだだの、裏のコンビニで喫煙しているだの先生への舌打ちだの⋯⋯。距離感に不器用な子達が多く、いつもどこかしらで誰かが傷つけ合っていた。教室には無気力と混乱が煙幕のように立ち込め、普通に勉強し真面目でいることが難しく感じられた。
家に帰れば母が宗教のマインドコントロールを引きずり「地獄に落ちるかもしれない」などと泣きついてくる。以前意地悪な信者の婆さんに、子どもが不登校になったのは前世の因縁が影響していて、きちんと祈らないと地獄に落ちる、と吹き込まれたのをまだ信じているのだ。そうでない時は「きちんと家事をしなくちゃ」と呪いさながらに繰り返し、髪を振り乱して床を磨いている。毎日手の込んだフランス料理が出てくるし、近所の人が買い物先までつけてくるとうわ言を言っている。どう考えても母は頭がおかしい。なのに父は「お母さんは大丈夫だ」の一点張りで、そのくせ彼女の相手を私に丸投げするのだ。
胸糞の悪い映画さながらの日々であった。現実の歯車がミシミシと音を立てて狂ってゆく。いつの間にやら天井のシミが人の顔をして私を見つめてくる。暗がりにうずくまる家具が腐り果てた死体に見えてくる。階段を昇っていると後ろから得体の知れない化け物が追いかけてくるような気がする。親が私の部屋にカメラを仕掛け、居間で監視しているのではないかと心配になる。ホラー映画を見ている最中のような不気味な感覚が付きまとい、それから逃れたくて酒を買い吐くまで酔い潰れ手首を切り刻む。ついには幻聴が聞こえ始め、もう一人の自分から「お前なんか死んだ方がいい」と四六時中罵られるようになった。
登下校のために電車を待つ。自分が電車に飛び込む幻が見える。車体にすり潰されズタズタになる自分の四肢。飛び込む。粉々になる。飛び込む。足元が真っ赤に染まる。そんな映像が何度も何度も巻き戻される。駅のホームは、どこまでも続く線路は、私にとって黄泉への入口であった。ここから線路に倒れ込むだけで天国に行ける。気の狂った現実から楽になれる。しかし実行しようとすると私の足は震え、手には冷や汗が滲んだ。私は高校を卒業するまでの四年間、映像に重なれぬまま一人電車を待ち続けた。飛び込み自殺も無事、失敗。
三度目の自殺未遂は二十四歳、私は大学四年生だった。
大学に入学してすぐ、執拗な幻聴に耐えかね精神科を受診した。セロクエルを服用し始めた瞬間、意地悪な声は掻き消えた。久しぶりの静寂に手足がふにゃふにゃと溶け出しそうになるくらい、ほっとする。しかし。副作用で猛烈に眠い。人が傍にいると一睡もできないたちの私が、満員の講義室でよだれを垂らして眠りこけてしまう。合う薬を模索する中サインバルタで躁転し、一ヶ月ほど過活動に勤しんだりしつつも、どうにか普通の顔を装いキャンパスにへばりついていた。
三年経っても服薬や通院への嫌悪感は拭えなかった。生き生きと大人に近づいていく友人と、薬なしでは生活できない自分とを見比べ、常に劣等感を感じていた。特に冬に体調が悪くなり、課題が重なると疲れ果てて寝込んでしまう。人混みに出ると頭がザワザワとして不安になるため、酒盛りもアルバイトもサークル活動もできない。鬱屈とした毎日が続き闘病に嫌気がさした私は、四年の秋に通院を中断してしまう。精神薬が抜けた影響で揺り返しが起こったこと、卒業制作に追われていたこと、就職活動に行き詰まっていたこと、それらを誰にも相談できなかったことが積み重なり、私は鬱へと転がり落ちてゆく。
卒業制作の絵本を拵える一方で遺品を整理した。洋服を売り、物を捨て、遺書を書き、ネット通販でヘリウムガスを手に入れた。どうして卒制に遅れそうな友達の面倒を見ながら遺品整理をしているのか分からない。自分が真っ二つに割れてしまっている。混乱しながらもよたよたと気力で突き進む。なけなしの努力も虚しく、卒業制作の提出を逃してしまった。両親に高額な学費を負担させていた負い目もあり、留年するぐらいなら死のうとこりずに決意した。
クローゼットに眠っていたヘリウムガス缶が起爆した。私は人の頭ほどの大きさのそれを担いで、ありったけの精神薬と一緒に車に積み込んだ。それから山へ向かった。死ぬのなら山がいい。夜なら誰であれ深くまで足を踏み入れないし、展望台であれば車が一台停まっていたところで不審に思われない。車内で死ねば腐っていたとしても車ごと処分できる。
展望台の駐車場に車を突っ込み、無我夢中でガス缶にチューブを繋ぎポリ袋の空気を抜く。本気で死にたいのなら袋の酸素濃度を極限まで減らさなければならない。真空状態に近い状態のポリ袋を被り、そこにガスを流し込めば、酸素不足で苦しまずに死に至ることができるのだ。大量の薬を水なしで飲み下し、袋を被り、うつらうつらしながら缶のコックをひねる。シューッと気体が満ちる音、ツンとした臭い。視界が白く透き通ってゆく。死ぬ時、人の意識は暗転ではなくホワイトアウトするのだ。寒い。手足がキンと冷たい。心臓が耳の奥にある。ハツカネズミと同じ速度でトクトクと脈動している。ふとシャンプーを切らしていたことを思い出し、買わなくちゃと考える。遠のいてゆく意識の中、日用品の心配をしている自分が滑稽で、でも、もういいや。と呟く。肺が詰まる感覚と共に、私は意識を失う。
気がつくと後部座席に転がっている。目覚めてしまった。昏倒した私は暴れ、自分でポリ袋をはぎ取ったらしい。無意識の私は生きたがっている。本当に死ぬつもりなら、こうならぬように手首を後ろできつく縛るべきだったのだ。私は自分が目覚めると、知っていた。嫌な臭いがする。股間が冷たい。どうやら漏らしたようだ。フロントガラスに薄らと雪が積もっている。空っぽの薬のシートがバラバラと散乱している。指先が傷だらけだ。チューブをセットする際、夢中になるあまり切ったことに気がつかなかったようだ。手の感覚がない。鈍く頭痛がする。目の前がぼやけてよく見えない。麻痺が残ったらどうしよう。恐ろしさにぶるぶると震える。さっきまで何もかもどうでも良いと思っていたはずなのに、急に体のことが心配になる。
後始末をする。白い視界で運転をする。缶は大学のゴミ捨て場に捨てる。帰宅し、後部座席を雑巾で拭き、薬のシートをかき集めて処分する。ふらふらのままベッドに倒れ込み、失神する。
その後私は、卒業制作の締切を逃したことで教授と両親から怒られる。翌日、何事もなかったふりをして大学へ行き、卒制の再提出の交渉する。病院に保護してもらえばよかったのだがその発想もなく、ぼろ切れのようなメンタルで卒業制作展の受付に立つ。ガス自殺も無事、失敗。
四度目は二十六歳の時だ。
何とか大学卒業にこぎつけた私は、入社試験がないという安易な理由でホテルに就職し一人暮らしを始めた。手始めに新入社員研修で三日間自衛隊に入隊させられた。それが終わると八時間ほぼぶっ続けで宴会場を走り回る日々が待っていた。典型的な古き良き体育会系の職場であった。
朝十時に出社し夜の十一時に退社する。夜露に湿ったコンクリートの匂いをかぎながら浮腫んだ足をズルズルと引きずり、アパートの玄関にぐしゃりと倒れ込む。ほとんど意識のないままシャワーを浴びレトルト食品を貪り寝床に倒れ泥のように眠る。翌日、朝六時に起床し筋肉痛に膝を軋ませよれよれと出社する。不安定なシフトと不慣れな肉体労働で病状は悪化し、働いて二年目の夏、まずいことに躁転してしまった。私は臨機応変を求められる場面でパニックを起こすようになり、三十分トイレにこもって泣く、エレベーターで支離滅裂な言葉を叫ぶなどの奇行を繰り返す、モンスター社員と化してしまった。人事に持て余され部署をたらい回しにされる。私の世話をしていた先輩が一人、ストレスのあまり退社していった。
躁とは恐ろしいもので人を巻き込む。プライベートもめちゃくちゃになった。男友達が性的逸脱症状の餌食となった。五年続いた彼氏と別れた。よき理解者だった友と言い争うようになり、立ち直れぬほどこっぴどく傷つけ合った。携帯電話をハイヒールで踏みつけバキバキに破壊し、コンビニのゴミ箱に投げ捨てる。出鱈目なエネルギーが毛穴という毛穴からテポドンの如く噴出していた。手足や口がばね仕掛けになり、己の意思を無視して動いているようで気味が悪かった。
寝る前はそれらの所業を思い返し罪悪感で窒息しそうになる。人に迷惑をかけていることは自覚していたが、自分ではどうにもできなかった。どこに頼ればいいのか分からない、生きているだけで迷惑をかけてしまう。思い詰め寝床から出られなくなり、勤務先に泣きながら休養の電話をかけるようになった。
会社を休んだ日は正常な思考が働かなくなる。近所のマンションに侵入し飛び降りようか悩む。落ちたら死ねる高さの建物を、砂漠でオアシスを探すジプシーさながらに彷徨い歩いた。自分がアパートの窓から落下してゆく幻を見るようになった。だが、無理だった。できなかった。あんなに人に迷惑をかけておきながら、私の足は恥ずかしくも地べたに根を張り微動だにしないのだった。
アパートの部屋はムッと蒸し暑い。家賃を払えなければ追い出される、ここにいるだけで税金をむしり取られる、息をするのにも金がかかる。明日の食い扶持を稼ぐことができない、それなのに腹は減るし喉も乾く、こんなに汗が滴り落ちる、憎らしいほど生きている。何も考えたくなくて、感じたくなくて、精神薬をウイスキーで流し込み昏倒した。
翌日の朝六時、朦朧と覚醒する。会社に体調不良で休む旨を伝え、再び精神薬とウイスキーで失神する。目覚めて電話して失神、目覚めて電話して失神。夢と現を行き来しながら、手元に転がっていたカッターで身体中を切り刻み、吐瀉し、意識を失う。そんな生活が七日間続いた。
一週間目の早朝に意識を取り戻した私は、このままでは死ぬと悟った。にわかに生存本能のスイッチがオンになる。軽くなった内臓を引っさげ這うように病院へと駆け込み、看護師に声をかける。
「あのう。一週間ほど薬と酒以外何も食べていません」
「そう。それじゃあ辛いでしょう。ベッドに寝ておいで」
優しく誘導され、白いシーツに倒れ込む。消毒液の香る毛布を抱きしめていると、ぞろぞろと数名の看護師と医師がやってきて取り囲まれた。若い男性医師に質問される。
「切ったの?」
「切りました」
「どこを?」
「身体中⋯⋯」
「ごめんね。少し見させて」
服をめくられる。私の腹を確認した彼は、
「ああ。これは入院だな」
と呟いた。私は妙に冷めた頭で聞く。
「今すぐですか」
「うん、すぐ。準備できるかな」
「はい。日用品を持ってきます」
私はびっくりするほどまともに帰宅し、もろもろを鞄に詰め込んで病院にトンボ帰りした。閉鎖病棟に入る。病室のベッドの周りに荷物を並べながら、私よりももっと辛い人間がいるはずなのにこれくらいで入院だなんておかしな話だ、とくるくる考えた。一度狂うと現実を測る尺度までもが狂うようだ。
二週間入院する。名も知らぬ睡眠薬と精神安定剤を処方され、飲む。夜、病室の窓から街を眺め、この先どうなるのかと不安になる。私の主治医は「君はいつかこうなると思ってたよ」と笑った。以前から通院をサポートする人間がいないのを心配していたのだろう。
退院後、人事からパート降格を言い渡され会社を辞めた。後に勤めた職場でも上手くいかず、一人暮らしを断念し実家に戻った。飛び降り自殺、餓死自殺、無事、失敗。
五度目は二十九歳の時だ。
四つめの転職先が幸いにも人と関わらぬ仕事であったため、二年ほど通い続けることができた。落ち込むことはあるものの病状も安定していた。しかしそのタイミングで主治医が代わった。新たな主治医は物腰柔らかな男性だったが、私は病状を相談することができなかった。前の医師は言葉を引き出すのが上手く、その環境に甘えきっていたのだ。
時給千円で四時間働き、月収は六万から八万。いい歳をして脛をかじっているのが忍びなく、実家に家賃を一、二万入れていたので、自由になる金は���万から七万。地元に友人がいないため交際費はかからない、年金は全額免除の申請をした、それでもカツカツだ。大きな買い物は当然できない。小さくとも出費があると貯金残高がチラつき、小一時間は今月のやりくりで頭がいっぱいになる。こんな額しか稼げずに、この先どうなってしまうのだろう。親が死んだらどうすればいいのだろう。同じ年代の人達は順調にキャリアを積んでいるだろう。資格も学歴もないのにズルズルとパート勤務を続けて、まともな企業に転職できるのだろうか。先行きが見えず、暇な時間は一人で悶々と考え込んでしまう。
何度目かの落ち込みがやってきた時、私は愚かにも再び通院を自己中断してしまう。病気を隠し続けること、精神疾患をオープンにすれば低所得をやむなくされることがプレッシャーだった。私も「普通の生活」を手に入れてみたかったのだ。案の定病状は悪化し、練炭を購入するも思い留まり返品。ふらりと立ち寄ったホームセンターで首吊りの紐を買い、クローゼットにしまう。私は鬱になると時限爆弾を買い込む習性があるらしい。覚えておかなければならない。
その職場を退職した後、さらに三度の転職をする。ある職場は椅子に座っているだけで涙が出るようになり退社した。別の職場は人手不足の影響で仕事内容が変わり、人事と揉めた挙句退社した。最後の転職先にも馴染めず八方塞がりになった私は、家族と会社に何も告げずに家を飛び出し、三日間帰らなかった。雪の降る中、車中泊をして、寒すぎると眠れないことを知った。家族は私を探し回り、ラインの通知は「帰っておいで」のメッセージで埋め尽くされた。漫画喫茶のジャンクな食事で口が荒れ、睡眠不足で小間切れにうたた寝をするようになった頃、音を上げてふらふらと帰宅した。勤務先に電話をかけると人事に静かな声で叱られた。情けなかった。私は退社を申し出た。気がつけば一年で四度も職を代わっていた。
無職になった。気分の浮き沈みが激しくコントロールできない。父の「この先どうするんだ」の言葉に「私にも分からないよ!」と怒鳴り返し、部屋のものをめちゃくちゃに壊して暴れた。仕事を辞める度に無力感に襲われ、ハローワークに行くことが恐ろしくてたまらなくなる。履歴書を書けばぐちゃぐちゃの職歴欄に現実を突きつけられる。自分はどこにも適応できないのではないか、この先まともに生きてゆくことはできないのではないか、誰かに迷惑をかけ続けるのではないか。思い詰め、寝室の柱に時限爆弾をぶら下げた。クローゼットの紐で首を吊ったのだ。
紐がめり込み喉仏がゴキゴキと軋む。舌が押しつぶされグエッと声が出る。三秒ぶら下がっただけなのに目の前に火花が散り、苦しくてたまらなくなる。何度か試したが思い切れず、紐を握り締め泣きじゃくる。学校に行く、仕事をする、たったそれだけのことができない、人間としての義務を果たせない、税金も払えない、親の負担になっている、役立たずなのにここまで生き延びている。生きられない。死ねない。どこにも行けない。私はどうすればいいのだろう。釘がくい込んだ柱が私の重みでひび割れている。
泣きながら襖を開けると、ペットの兎が小さな足を踏ん張り私を見上げていた。黒くて可愛らしい目だった。私は自分勝手な絶望でこの子を捨てようとした。撫でようとすると、彼はきゅっと身を縮めた。可愛い、愛する子。どんな私でいても拒否せず撫でさせてくれる、大切な子。私の身勝手さで彼が粗末にされることだけはあってはならない、絶対に。ごめんね、ごめんね。柔らかな毛並みを撫でながら、何度も謝った。
この出来事をきっかけに通院を再開し、障害者手帳を取得する。医療費控除も障害者年金も申請した。精神疾患を持つ人々が社会復帰を目指すための施設、デイケアにも通い始めた。どん底まで落ちて、自分一人ではどうにもならないと悟ったのだ。今まさに社会復帰支援を通し、誰かに頼り、悩みを相談する方法を勉強している最中だ。
病院通いが本格化してからというもの、私は「まとも」を諦めた。私の指す「まとも」とは、周りが満足する状態まで自分を持ってゆくことであった。人生のイベントが喜びと結びつくものだと実感できぬまま、漠然としたゴールを目指して走り続けた。ただそれをこなすことが人間の義務なの��と思い込んでいた。
自殺未遂を繰り返しながら、それを誰にも打ち明けず、悟らせず、発見されずに生きてきた。約二十年もの間、母の精神不安定、学校生活や社会生活の不自由さ、病気との付き合いに苦しみ、それら全てから解放されたいと願っていた。
今、なぜ私が生きているか。苦痛を克服したからではない。死ねなかったから生きている。死ぬほど苦しく、何度もこの世からいなくなろうとしたが、失敗し続けた。だから私は生きている。何をやっても死ねないのなら、どうにか生き延びる方法を探らなければならない。だから薬を飲み、障害者となり、誰かの世話になり、こうしてしぶとくも息をしている。
高校の同級生は精神障害の果てに自ら命を絶った。彼は先に行ってしまった。自殺を推奨するわけではないが、彼は死ぬことができたから、今ここにいない。一歩タイミングが違えば私もそうなっていたかもしれない。彼は今、天国で穏やかに暮らしていることだろう。望むものを全て手に入れて。そうであってほしい。彼はたくさん苦しんだのだから。
私は強くなんてない。辛くなる度、たくさんの自分を殺した。命を絶つことのできる場所全てに、私の死体が引っかかっていた。ガードレールに。家の軒に。柱に。駅のホームの崖っぷちに。近所の河原に。陸橋に。あのアパートに。一人暮らしの二階の部屋から見下ろした地面に。電線に。道路を走る車の前に⋯⋯。怖かった。震えるほど寂しかった。誰かに苦しんでいる私を見つけてもらいたかった。心配され、慰められ��抱きしめられてみたかった。一度目の自殺未遂の時、誰かに生きていてほしいと声をかけてもらえたら、もしくは誰かに死にたくないと泣きつくことができたら、私はこんなにも自分を痛めつけなくて済んだのかもしれない。けれど時間は戻ってこない。この先はこれらの記憶を受け止め、癒す作業が待っているのだろう。
きっとまた何かの拍子に、生き延びたことを後悔するだろう。あの暗闇がやってきて、私を容赦なく覆い隠すだろう。あの時死んでいればよかったと、脳裏でうずくまり呟くだろう。それが私の病で、これからももう一人の自分と戦い続けるだろう。
思い出話にしてはあまりに重い。医療機関に寄りかかりながら、この世に適応する人間達には打ち明けられぬ人生を、ともすれば誰とも心を分かち合えぬ孤独を、蛇の尾のように引きずる。刹那の光と闇に揉まれ、暗い水底をゆったりと泳ぐ。静かに、誰にも知られず、時には仲間と共に、穏やかに。
海は広く、私は小さい。けれど生きている。まだ生きている。
4 notes
·
View notes
Photo


ぽつん感… 寄ってみた。 さすがにここまで庇の下だと雨にも雪にも当たらないね。 おかげでまったく緑青が浮いてない。やっぱりか。 あとお掃除の人に横のガラスと一緒に拭いてもらってそう。 メモリアル88ハイツ 札幌市白石区東札幌4条6丁目4-12 1985年竣工 2017年4月21日撮影
0 notes
Text
妹のために、妹のために、妹のために。(推敲中)
ふたなり怪力娘もの。血なまぐさいので注意。
扠、ここはある民家の一室、凡そ八畳程の広さの中に机が二つ、二段ベッドが一つ、その他本棚や観葉植物などが置いてある、言つてしまえば普通の部屋に男が二人顔を突き合はせ何やらヒソヒソと、いや、別に小声で話してゐるわけではないのであるが何者かに気づかれないよう静かに話し合つてゐる。一人は少し痩せ型の、黒い髪の毛に黒い縁のメガネが聡明な印象を与へる、如何にも生真面目さうな好青年で、もう一人は少し恰幅の良い、短く切られた髪の毛に色の濃い肌が健康な印象を与へる、如何にも運動が得意さうな好青年である。前者の名は那央と言ひ、後者の名は詩乃と言ふ、見た目も性格の型も違えど同じ高校に通つてゐる仲の良い兄弟である。二人の間にはノートの切れ端と思しきメモと、丁度半月ほど前に買つた十キロのダンベルが、そのシャフトを「く」の字に曲げ事切れたやうにして床���寝そべつてゐた。
何故メモがあるのか、何故ダンベルのシャフトが「く」の字に曲がつてゐるのか、何故二人の兄弟がそれらを囲んで真剣な話し合ひをしてゐるのか、その説明をするにはもう一つ紹介しておかねばならぬ事があるのであるが、恐らく大層な話を聞かずとも直ぐに状況を何となく分かつて頂けるであらう。其れと云ふのも二人にはもう一人血を同じくする、一五〇センチに満たぬ身の丈に、ぷにぷにとした餅のやうな頬、風でさらさらと棚引き陽の光をあちこちに返す黒い髪、触つた此方が溶け落ちるほど柔らかな肌、此れからの成長を予感させる胸の膨らみ、長いまつ毛に真珠を嵌めたやうな黒目を持った、--------少々変はつてゐる所と言へば女性なのに男性器が付いてゐるくらゐの、非常に可愛らしい中学一年生の妹が居るのである。名前は心百合と言ふ。成る程、ふたなりの妹が居るなら話は早い、メモもダンベルも話し合ひも、全てこの妹が原因であらう。実際、メモにはやたら達筆な字でかうあつた。-----------
前々から言ってきたけど、こんな軽いウェイトでやっても意味が無いと思うから、使わないように。次はちゃんと、最低でも一〇〇キロはあるダンベルを買ってください。私も力加減の練習がしたいのでお願いします。曲げたのは直すので、これを読んだら持ってきてください。
あと全部解き終わったので、先週から借りてた那央にぃの数学の問題集を返しました。机の上に置いてあります。全然手応えが無かったから、ちょっと優しすぎると思います。新しく買ったらまた言ってください。
心百合より
このメモは「く」の字に曲がつたシャフトの丁度折り目に置かれてあつて、凡そ午前九時に起床した詩乃がまず最初に見つけ、其の時は寝ぼけてゐたせいもありダンベルの惨状に気を取られメモを読まないまま、折角値の張る買ひ物をしたのにどうして、一体何が起きてこんなことに、…………と悲嘆に暮れてゐたのであるが、そんな簡単に風で飛ぶような物でも無いし、それに落ちたとしても直径二センチ以上ある金属がさう易易と曲がるわけでも無いから何者かが手を加えたに違ひ無く、自然と犯人の顔が思ひ浮かんでくるのであつた。わざわざ此れを言ひたいがためにダンベルを使ひ物にならなくしたのか。俺たちにとつては一〇キロでもそこそこ重さを感じると云ふのに、一〇〇キロなんて持ち上げられるわけが無い、しかもその一〇〇キロも、"最低でも"だとか、"力加減"だとか書かれてゐるので妹はもつと重いダンベルを御所望であるのか。確かにふたなりからすると、一〇〇キロも二〇〇キロも軽いと感じるだらうが、此れは俺たちが自分の体を鍛えるための道具であるからそつとしておいて欲しい。さう彼は文句を言ひたくなるものの、未だ中学一年生とは言へ、本来車でも打つから無ければ曲がるはずも無いシャフトを綺麗に曲げてしまつたと云ふ事実に、ただひたすら恐怖を感じ震える手でこめかみあたりに垂れてきた冷ややかな汗を拭ふのであつた。
一体全体、ふたなりの女の子は力が強いのである。そして其れは心百合も例外では無く、生まれて間もない時から異常な怪力ぶりを発揮してきた。例へば此れはある日の朝のことであつたか、彼ら彼女の父親が出勤しようとしてガレージのシャッターを開けると、何の恥ずかしげもなく無断駐車してゐる車の、後ろ数十センチが見えてゐたことがあつた。幸ひにも丁度車一台分通れるくらゐの隙間はあるし、其れに父親の向かふ方向とは逆の位置にあつたので、何とか避けて車を出せさうではあつたのであるが、如何せん狭いガレージと、狭い通りと、幅のある車であるから、ふとした拍子で擦つてしまふかもしれない。かと言つて警察やらレッカーやらを呼ぶ時間も手間も勿体無い。仕方が無いので父親は、当時十四歳であつた那央と、当時十二歳であつた詩乃を呼び出して、ほんの数センチでも良いからこの車を向かふ側へ押せないかと、提案して自身も全身を奮ひ立たせたのであるが当然の如く動く気配は無かつた。ならばせめて角度だけでもつけようと思ひ、三人で掛け声をかけ少しでも摩擦を減らさうと車の後ろ半分を浮かせようと頑張つたものの、此れまた持ち上がる気配も無くたつた数秒程度で皆バテてしまつた。さうして諦めた父親は携帯を取り出し、諦めた二人の兄弟は数歩離れたところにある壁に凭れ、こんなん無理やろ、何が入つてんねん、と那央が言つたのをきつかけに談笑し始めた丁度其の時、登校しようと玄関から出てきた心百合が近寄つてきて、どうしたの? さつきから何やつてたの? と声をかけてきた。そこで詩乃が其の頭を撫でながら事情を説明して、ま、無理なものは無理だし、今日こそ親父は遅刻するかもな、と笑ひながら言ふと心百合は、
「んー、………じゃあ私がやってみてもいい?」
と言ひながらランドセルを那央に押し付け、唖然とする兄たちを余所に例の車へ向かつて行く。そしてトランクにまでたどり着くと、屈んで持ち易く力の入れ易い箇所を探しだす。----------当時彼女は小学三年生、僅か九歳である。自分の背丈と同じくらゐの高さの車を持ち上げようと、九歳の女の子がトランクの下を漁つてゐるのである。流石に兄たちも其の様子を黙つて見てゐられなくなり駆け寄つて、ついでに電話を掛けてゐる最中の父親も駆け付けて来て、結局左から順に父親、心百合、詩乃、那央の並びでもう一度車と相対することになつたのであるが、那央が、せえの! と声を掛け皆で一斉に力を入れる前に、よつと、と云ふ可愛らしい声が車の周りに小さく響いた。かと思ひきや次の瞬間には、グググ、と車体が浮き上がりたうたう後輪が地面から離れ初め、男たちが顔を見合はせ何���起きてゐるのか理解するうちに、一〇センチ、一五センチは持ち上がつてしまつた。男たちのどよめきを聞きながら、心百合は未だ六割程度しか力を入れてゐないことに少しばかり拍子抜けして、これならと思ひ、
「お父さんも、お兄ちゃんたちも、もう大丈夫だから手を離していいよ」
と言ふと、片手を離しひらひらと振り、余裕である旨を大して役に立つてゐない他の皆に伝え背筋を伸ばした。
「それで、これどうしたらいいの?」
男たちが恐る恐る手を離し、すつかり一人で車の後部を持ち上げてゐる状態になつた頃、娘が其のやうに聞いて来たので一寸だけ前に寄せてくれたら良いと、父親が答えると心百合は、分かつた、とだけ言つてから、そのまま足を踏み出して前へ進もうとした。すると、初めの方こそ靴が滑つて上手く進めなかつたのであるが、心百合も勝手が分かつて来たのか、しつかりと足に全体重と車の重量を掛け思ひ切り踏ん張つてゐると遂には、タイヤと地面の擦れる非常に耳障りな音を立てて車が前へと動き出したのである。そして、家の前だと邪魔になるだらうから、このまま公園の方まで持つて行くねと言つて、公園の側にある少し道が広がつてゐる所、家から凡そ三〇メートル程離れてゐる所まで、車を持ち上げたままゆつくりと押して行つてしまつた。
あれから四年、恐らく妹の力はさらに強くなつてゐるであらう。日常では兎に角優しく、優しく触る事を心がけてゐるらしいから俺たちは怪我をしないで済んでゐる、いやもつと云ふと、五体満足で、しかも生きてゐる。だが今まで何度も危ない時はあつた。喧嘩は全然しない、と云ふより一度も歪みあつたことは無いけれども、昼寝をしてゐる妹の邪魔をしたりだとか、凡ミスのせいでテストで満点を逃し機嫌が悪い時に何時もの調子で話しかけたりだとか、手を繋いでゐる最中に妹が何か、------例へば彼女の趣味である古典文学の展示に夢中になつたりだとか、さういう時は腕の一本や二本覚悟しなければならず打ち震えてゐたのであるが、なんと情けない話であらう。俺たちは妹の機嫌一つ、力加減一つで恐怖を覚えてしまふ。俺たちにはあの未発達で肉付きの良い手が人の命を刈り取る鎌に見える。俺たちにはあの産毛すら見えず芸術品かと思はれる程美しい太腿も、人の肉を潰したがつてゐる万力のやうに見える。……………本来さう云つた恐怖に少しでも対抗しようとダンベルを買つたのであるが、丸切り無駄であつた、矢張り妹には勝てぬのか。直接手を下されたわけでも無いのに、またしても負けてしまふのか。もう身体能力だけでなく、学力も大きな差をつけられたと云ふのに。---------------心百合は元々、小学校のテストでは常に満点を、…………少しドジなところがあるからたまにせうもない間違ひを犯すことがあるが、其れは仕方ないとして試験は常に満点を取り続けてをり、ある日学校から帰つて来るや、授業が暇で暇で、暇で仕方がないからお兄ちゃん何とかしてと言ふので、有らう事か俺たちは、其れならどん��ん先の内容をこつそりと予習すると良い、と教えてしまつた。其れから心百合は教室だけでなく家でも勉強を進め、タガが外れたやうにもう恐ろしい早さで知識を吸収したつた一週間か二週間かで其の学年、-----確か小学四年生の教科書を読み終えると、兄から譲り受けた教科書を使って次の学年、次の次の学年、次の次の次の学年、…………といつたやうに、兄たちの言ふ通りどんどん先の内容を理解していき、一年も経たぬ間に高校入試の問題が全て解けるようになつてゐた。かと思えば、那央の持つてゐる高校の教科書やら問題集やら参考書やらを、兄の迷惑にならぬよう借りて勉強を推し進め、今度は半年程度で大学入試の問題をネットから引つ張り、遊び半分で解いてゐたのである。そして此方が分からないと言つてゐるのに答え合はせをして欲しいと頼んで来たり、又ある時は那央が置きつぱなしにしてゐた模試を勝手に解いては、簡単な問題ばかりで詰まんなかつた、お兄ちゃんでも全部解けたでせう? この程度の問題は、と云ふ。そんなだから中学一年生の今ではもはや、勉強をしてゐるうちに好きになつた古典文学を読み漁りながら、受験を控えた那央の勉強を教えるためにも、彼が過去問題集に取り組む前にはまず、心百合が一度目を通し、一度問題を全て解き感想を言つて、時間をかけるべきか、さうでないかの判断の手助けをしてゐるのである。先のメモにあつた後半の内容はまさに此の事で、どんなに難しさうな問題集を持つて行つても簡単だから考へ直すべしと言はれ凹む那央を見てゐると、詩乃は二年後の自分が果たしてまともな精神で居られるのかどうか、不安になつて来るのであつた。
さうすると此の兄弟が妹に勝つている点は何であらうか、多分身長以外には無い気がするが、もう後数年もすると頭一つ分超えられてしまふだらう。聞くところに寄ると、ふたなりは第二次成長期が落ち着き始める一四、五歳頃から突然第三次成長期を迎え、一八歳になる頃には平均して身長一八七センチに達すると云ふのである。実際、那央のクラスにも一人ふたなりの子が居るのであるが、一年生の初め頃にはまだ辛うじて見下ろせた其の顔も今では、首を天井に向けるが如く顔を上げないと目が合はないのである。だが彼らは未だに、こんな胸元にすつぽりと収まる可愛い可愛い妹が、まさか見上げるほど背を高くしないであらうと、愚かにも思つてゐるのであるがしかし、さうでも思はないとふたなりの妹が近くに居ること自体怖くて怖くて仕方なく、心百合を家に残しどこか遠い場所で生活をしたい衝動に駆られるのであつた。
扠、読者の中には恐らくふたなりをよくご存知でない方が何名かいらつしやるであらうから、どうして此の兄弟が、可愛い、たつた一人だけの、愛しい、よく出来た妹にここまで恐怖を感じるのか説明しておかねばならぬのであるが、恐らく其れには引き続き三人の兄妹の話をするだけで事足りるであらう。何分其処に大体の理由は詰まつてゐる。-------------
ふたなりによる男性への強姦事件は��々ニュースになるし、其れに世の男達なら全員、中学校の保健体育で習つた記憶がどこかにあるから皆知つてゐるだらう。本日未明、〇〇県〇〇市在住の路上で男性が倒れてゐるのを誰々が発見し、現場に残された体液から警察は近くに住む何たら言ふ名前の女性を逮捕した。-----例へばさう云ふニュースの事である。凡そ犯人の側に「体液」と「女性」などと云つた語が出てきたら其れはふたなりによる強姦を意味するのであるが、世の中に伝えられる話は、実際に起きた出来事にオブラートにオブラートを重ね、さらに其の上からオブラートで包み込んだやうな話であつて、もはやお伽噺となつてゐる。考へてみると、大人になれば一九〇センチ近い身長に、ダンベルのシャフトのやうな金属すら曲げる怪力を持つ女性が今日の男性を暴行し無理やり犯せば、そもそも人の形が残るかどうかも怪しくなるのは容易に想像できる。実際、幾つか例を挙げてみると、ふたなりの"体液"を口から注ぎ込まれ腹が破裂し死亡した男や、行方不明になつてゐたかと思えば四肢が完全に握りつぶされ、そしてお尻の穴が完全に破壊された状態でゴミのやうに捨てられてゐた男や、ふたなりの"ソレ"に耐えきれず喉が裂け窒息死した男や、彼女たちの異常な性欲を解消するための道具と成り果て精液のみで生きる男、……………挙げだすとキリがない。二人の兄弟は、ふたなりの妹が居るからと言つて昔からさう云ふ話を両親から嫌と言ふほど聞いて来たのであるが、恐ろしいのはほとんどの被害者が家族、特に歳を近くする兄弟である事と、ふたなりが居る家庭は一つの例外なく崩壊してゐる事であつた。と云つても此の世の大多数の人間と同じやうに、彼らも話を言伝されるくらゐではふたなりの恐ろしさと云ふ物を、其れこそお伽噺程度にしか感じてゐなかつたのであるが、一年前、小学六年生の妹に、高校生二年と中学三年の兄二人が揃つて勉強を教えてもらつてゐたある夜、机の間を行つたり来たりするうちに何故かセーラー服のスカートを押し上げてしまつた心百合の、男の"モノ"を見た時、彼らの考へは変はり初めた。其の、スカートから覗く自分たちの二倍、三倍、いや、もう少しあらうか、兎に角妹の体格に全く不釣り合いな男性器に、兄たちが気を取られてゐると心百合は少し早口で、
「しばらくしたら収まると思うから見ないでよ。えっち。それよりこの文章、声に出して読んでみた? 文法間違いが多くて全然自然に読めないでしょ? 一度は自分で音読してみるべしだよ、えっちなお兄ちゃん。でも単語は覚えてないと仕方ないね。じゃあ、来週までに、この単語帳にある単語と、この文法書の内容を全部覚えて来ること。----------」
と顔を真赤にして云ふと、下の兄に高校入試を模して作つた問題を解かせつつ、上の兄が書いた英文の添削を再開してしまつた。が、ほんの数分もしないうちに息を荒げ出し、そして巨大な肉���の先端から、とろとろと透明な液体を漏らし淫猥な香りを部屋中に漂はせ初めると、
「ど、どうしよう、…………いつもは勝手に収まるのに。………………」
と言つて兄たちに助けを求める。どうやら彼女は五〇センチ近い巨大な肉棒を持ちながら其の時未だ、射精を味はつた事が無かつたやうである。そこで、ふたなりの射精量は尋常ではないと聞いていた那央は、あれの仕方を教えてあげてと、詩乃に言ふと急いでバケツと、絶対に要らないだろうとは思ひつつもしかしたらと思つて、ゴミ袋を一つ手に取り部屋に戻つたところ、中はすでに妹が前かがみになりながら両手を使つて激しく自分のモノを扱き、其の様子を弟が恍惚とした表情で見守ると云ふ状況になつてゐる。----------何だ此れは、此れは俺の知る自慰では無い。此れがふたなりの自慰なのか。………………さうは思ひながら、ぼたぼたと垂れて床を濡らしてゐる液体を受け止めるよう、バケツを丁度肉棒の先の下に置くと、そのまま棒立ちで妹の自慰を見守つた。そしていよいよ、心百合が肉棒の先端をバケツに向け其の手の動きを激しくしだしたかと思えば、
「あっ、あっ、お兄ちゃん! 何これ! ああぁあんっ!!」
と云ふ、ひどくいやらしい声と共に、パツクリと開いた鈴口から消防車のやうに精液が吹き出初め、射精とは思へないほどおぞましい音が聞こえて来る。そしてあれよあれよと云ふ間にバケツは満杯になり、床に白くドロドロとした精液が広がり始めたので、那央は慌ててゴミ袋を妹のモノに宛てがつて、袋が射精の勢ひで吹き飛ばぬよう、又自分自身も射精の勢ひで弾き飛ばされぬよう肉棒にしがみついた。-------
結局心百合はバケツ一杯分と、二〇リットルのゴミ袋半分程の精液を出して射精を終え、ベタベタになつた手と肉棒をティッシュで拭いてから、呆然と立ちすくんでゐる兄たちに声をかけた。
「お兄ちゃん? おにいちゃーん? 大丈夫?」
「あ、あぁ。…………大丈夫。………………」
「しぃにぃは?」
彼女は詩乃の事をさう呼ぶ。幼い頃はきちんと「しのおにいちゃん」と読んでゐたのであるが、いつしか「しのにぃ」となつて、今では「の」が略されて「しぃにぃ」となつてゐる。舌足らずな彼女の声を考へると、「しーにー」と書いたほうが近いか。
「……………」
「おい、詩乃、大丈夫か?」
「お、………おう。大丈夫。ちょっとぼーっとしてただけ。………………」
「もう、お兄ちゃんたちしっかりしてよ。特にしぃにぃは最初以外何もしてなかったでしょ。……………て、いうか私が一番恥ずかしいはずなのに、何でお兄ちゃんたちがダメージ受けてるのん。………………」
心百合はさう言ふと、本当に恥ずかしくなつてきたのか、まだまだ大きいが萎えつつある肉棒をスカートの中に隠すと、さつとパンツの中にしまつてしまつた。
「とりあえず、片付けるか。…………」
「おう。……………」
「お兄ちゃんたち部屋汚しちゃってごめん。私も手伝わせて」
「いいよ、いいよ。俺たちがやっておくから、心百合はお風呂にでも入っておいで。------」
このやうにして性欲の解消を覚えた心百合は、毎日風呂に入る前に自慰をし最近ではバケツ数杯分の精液を出すのであつたが、そのまま流すとあつと言ふ間に配管が詰まるので、其の始末は那央と詩乃がやつてをり、彼女が湯に浸かつてゐるあひだ、夜の闇に紛れて家から徒歩数分の所にある川へ、音を立てぬよう、白い色が残らないよう、ゆつくりと妹の種を放つてゐるのであつた。空になつたバケツを見て二人の兄弟は思ふ。------------いつかここにあつた精液が、ふとしたきつかけで体に注がれたら俺たちの体はどうなる? そもそも其の前に、あの同じ男性器とは思へないほど巨大な肉棒が、口やお尻に突つ込まれでもしたらたら俺たちの体はどうなる? いや、其れ以前に、あの怪力が俺たちの身に降り掛かつたらどうなる? ふたなりによる強姦の被害者の話は嘘ではない。腹の中で射精されて体が爆発しただなんて、昔は笑いものにしてゐたけれども何一つ笑へる要素などありはしない、あの量を、あの勢いで注がれたら俺たち男の体なんて軽く吹き飛ぶ。其れにあんなのが口に、お尻に入り込まうとするなんて、想像するだけでも恐ろしくつて手が震えてくる。聞けば、顎の骨を砕かうが、骨盤を割らうが、其んな事お構ひなしにねじ込んで来ると云ふではないか。此れから先、何を犠牲にしてでも妹の機嫌を取らなくては、…………其れが駄目ならせめて手でやるくらゐで我慢してもらはねば。…………………
だが彼らは此れもまた、わざわざ時間を割いてまでして兄の勉強を見てくれるほど情に満ちた妹のことだから、まさかさう云ふ展開にはならないであらうと、間抜けにも程があると云ふのに思つてゐるのであるが、そろそろなのである。ふたなりの女の子が豹変するあの時期が、そろそろ彼らの妹にも来ようとしているのである。其れ以降は何を言つても無駄になるのである。だから今しかチャンスは無いのである。俺たちを犯さないでくださいと、お願ひするのは今しか無いのである。そして、其の願ひを叶えてくれる確率が零で無いのは今だけなのである。
「------もうこれ以上引き伸ばしても駄目だ。言いに行くぞ」
ダンベルとメモを持ち、勢ひよく立つた那央がさう云ふ。
「だけど、………それ言ったら言ったらで、ふたなりを刺激するんだろ?!」
「あぁ。…………でも、少しでも確率があるならやらないと。このままだと、遅かれ早かれ後数年もしないうちに死ぬぞ。俺ら。………………」
「くっ、…………クソッ。……………」
「大丈夫、もし妹がその気になっても、あっちは一人で、こっちは二人なんだから上手くやればなんとかなるさ、……………たぶん。………………」
「最後の「たぶん」は余計だわ。……………」
「あと心百合を信じよう。大丈夫だって、あんなに優しい妹じゃないか。きっと、真剣に頼めば聞いてくれるはず。……………」
「兄貴って、たまにそういう根拠のない自信を持つよな。………」
さう言ふと、詩乃も立ち上がり一つ深呼吸をすると、兄と共に部屋を後にするのであつた。
心百合の部屋は、兄たちの部屋に比べると少しばかり狭いが其れでも一人で過ごすには物寂しさを感じる程度には広い、よく風が通つて夏は涼しく、よく日が当たつて冬は暖かく、東側にある窓からは枯れ葉に花を添えるやうはらはらと山に降り積もる雪が、南側にある窓からはずつと遠くに活気ある大阪の街が見える、非常に快適で感性を刺激する角部屋であつた。そこに彼女は本棚を此れでも��と云ふほど敷き詰めて新たな壁とし、嘗ての文豪の全集を筆頭に、古い物は源氏物語から諸々の文芸作品を入れ、哲学書を入れ、社会思想本を入れ、経済学書を入れ、そして目を閉じて適当に選んだ評論などを入れてゐるのであるが、最近では文系の本だけでは釣り合ひが取れてない気がすると言ひ初め、つい一ヶ月か二ヶ月前に、家から三駅ほど離れた大学までふらりと遊びに行つて、お兄ちゃんのためと云ふ建前で、解析学やら電磁気学やら位相空間論やらと云つた、一年か二年の理系大学生が使ふであらう教科書と、あとさう云ふ系統の雑誌を、合わせて十冊買つて来たのであつた。そして、春までには読み終はらせておくから、お兄ちゃんが必要になつたらいつでも言つてねと、那央には伝えてゐたのであつたが、意外に面白くてもう大方読んでしまつたし、途中の計算はまだし終えてないけれども問題はほとんど解き終はつてしまつた。またもう一歩背伸びをして新しく本を買いに行きたいが、前回大量にレジへ持つて行き過ぎたせいで、大学生協の店員にえらく不思議さうな顔をされたのが何だか癪に障つて、自分ではもう行きたくない。早くなおにぃの受験が終はつてくれないかしらん。さうしたら彼処にある本を買つて来てもらへるのに。それか二年後と言はず今すぐにでも飛び級させてくれたらいいのに。…………と、まだ真新しい装丁をしてゐる本を眺めては思ふのであつた。
なので那央が大学生になるまで数学やら物理学は封印しようと、一回読んだきりでもはや文鎮と化してゐた本たちを本棚にしまひ、昨日電子書籍として買つてみた源氏物語の訳書を、暇つぶしとしてベッドの上に寝転びながら読んでゐると、コンコンコン、…………と、部屋の扉をノックする音が聞こえて来た。
「はーい、なにー?」
「心百合、入ってもいいか?」
少し澄んだ声をしてゐるから那央であらう。
「いいよー」
ガチャリと開いたドアから那央が、朝に軽いイタズラとして曲げたダンベルと、その時残しておいたメモを手に持つて入つて来たかと思えば、其の後ろから、何やら真剣な表情を浮かべて居る詩乃も部屋に入つて来る。
「あれ? しぃにぃも? どったの二人とも?」
タブレットを枕の横に投げ出すと心百合は体を起こし、お尻をずるりとベッドの縁まで滑らせ、もう目の前までやつて来てゐる兄二人と対峙するやうにして座つた。
「あぁ、…………えとな。…………」
「ん?」
「えっと、………お、おい、詩乃、……代わりに言ってくれ。…………」
「えっ、………ちょっと、兄貴。俺は嫌だよ。…………」
「俺だって嫌だよ。後で飯おごってやるから頼む。……………」
「………言い出しっぺは兄貴なんだから、兄貴がしてくれよ。…………」
あんなに真剣な表情をしてゐた兄たちが何故かしどろもどろ、………と、云ふよりグジグジと醜い言ひ争ひをし始めたので、心百合は居心地が悪くなり一つため息をつくと、
「もう、それ元通りにして欲しくて来たんじゃないの?」
と言つて、那央の持つてゐるダンベルに手を伸ばし、トン��ンと叩く。が、那央も詩乃も、キュッと体を縮こませ、
「えっと、…………それは、…………ち、ちが、ちがってて…………」
などと云ふ声にならぬ声を出すばかりで一向にダンベルを渡してくれない。一体何が違つてゐるのだらう、………ま、ダンベルを持つて来たのだから直して欲しいには違ひない、と、云ふより直すと書いたのだから直してあげないと、------などと思つて、重りの部分に手をかけると、半ば引つたくるやうにして無理やりダンベルを奪ひ去つた。
「いくらお兄ちゃんたちに力が無いって言っても、こんな指の体操にもならないウェイトだと意味無いでしょ。今度はちゃんとしたの買いなよ」
さう云ふと、心百合はまず手の平を上にして「く」の字に曲がつたシャフトを、一辺一辺順に掴んでから、ひ弱な兄たちに見せつけるよう軽く手を伸ばし、一言、よく見ててね、と言つた。そして彼女が目を瞑つて、グッ…と其の手と腕に力を込め始めると、二人の兄弟がいくら頑張つても、--------時には詩乃が勝手に父親の車に乗り込んで轢いてみても、其の素振りすら見せなかつたシャフトが植物の繊維が裂けるやうな音と共にゆつくりと反り返つていき、どんどん元の状態に戻つて行く。其の様子はまるで熱した飴の形を整えてゐるやうであつて、彼らには決して太い金属の棒を曲げてゐるやうには見えなかつた。しかもさつきまで目を閉じてゐた妹が、いつの間にか此方に向かつて笑みを浮かべてゐる。……………其のあまりの呆気なさに、そして其のあまりの可愛いさに、彼らは己の中にある恐怖心が、少しばかり薄らいだやうな気がするのであつたが、ミシリ、ミシリ、と嫌に耳につく金属の悲鳴を聞いてゐると矢張り、目の前に居る一人の可憐で繊細で、人々の理想とも形容すべき美しい少女が、何か恐ろしい怪物のやうに見えてくるのであつた。
「はい、直ったよ。曲がってた所は熱いから気をつけてね」
すつかり元通りになつたダンベルを、真ん中には触れないやう気をつけながら受け取ると、那央はすぐに違和感に気がついた。一体どう云ふ事だ、このシャフトはこんなにでこぼこしてゐただらうか。---------まさかと思つて、さつきの妹の持ち方を真似してダンベルを持つてみると、多少合はないとは言え、シャフトのへこんでゐる箇所が自分の手の平にもぴつたりと当てはまる。其れにギュッと握つてみると、指先にも若干の凹凸を感じる。もしかして、--------もしかして、この手の平に感じるへこみだとか、指先に感じるでこぼこは、もしかして、もしかして、妹の手の跡だと云ふのであらうか。まさか、あの小さく、柔らかく、暖かく、ずつと触れてゐたくなるやうなほど触り心地の良い、���の手そのものに、この頑丈な金属の棒が負けてしまつたとでも云ふのであらうか。彼はさう思いつつ、もしかしたらと自分も出来るかもしれないと思つて力を入れてみたが、ダンベルは何の反応もせずただ自分の手が痛くなるばかりであつた。
「で、他に何か話があるんだよね。何なの?」
「あ、…………えっ、と。…………」
「もう、何なの。言いたいことはちゃんと言わないと分からないよ。特に、なおにぃはもう大学生なんだから、ちゃんとしなきゃ」
と五歳も年下の妹に諭されても、情けないことに兄がダンベルを見つめたまま固まつてゐるので、恐怖心を押さえつけ��らか平静になつた詩乃が、意を決して口を開けた。
「それはだな。…………えっと、……心百合って、ふたなりだろ? だからさ、今後気が高ぶっても俺らでやらないで欲しい。……………」
ついに言つてしまつた、だけどこれで、…………と詩乃はどこか安堵した気がするのであつたが、
「えっ、…………いや、それはちょっと無理かも。………だって。…………………」
心百合がさう云ふと、少し足を開いた。すると那央と詩乃の鼻孔にまで、いやに生々しい匂ひが漂ふ。
「………だって、お兄ちゃんたちが可愛くって、最近この子勝手にこうなるんだもん」
心百合がスカートの上からもぞもぞと股の間をいじると、ぬらぬらと輝く巨大な"ソレ"が勢いよく姿を現し、そして自分自信の力で血をめぐらせるかのやうに、ビクン、ビクン、と跳ねつつ天井へ伸びて行く。
「ねっ、お兄ちゃん、私ちょっと"気が高ぶった"から、お尻貸してくれない?」
「い、いや、………それは。…………」
「心百合、……………落ちつい、--------」
「ねっ、ねっ、お願いっ! ちょっとだけでいいから! 先っぽしか挿れないからお尻貸して!!」
心百合は弾むやうにして立ち上がると、詩乃の手首を握つた。と、その時、ゴトリ、と云ふ重い物が落ちる音がしたかと思ひきや、那央が扉に向かつて駆けて行く様子が、詩乃の肩越しに見えた。
「あっ、なおにぃどこ行くの!」
心百合は詩乃をベッドの上に投げ捨て、今にもドアノブに手をかけようとしてゐた那央に、勢ひよく後ろから抱きつく。
「あああああああああああ!!!!!!」
「ふふん、なおにぃ捕まえた~」
ほんの少し強く抱きしめただけで心地よく絶叫してくれる那央に、彼女はますます"気を高ぶらせ"、
「しぃにぃを放って、どこに行こうとしていたのかなぁ? ねぇ、那央お兄ちゃん?」
と云ひ、彼が今まで味はつたことすら無い力ではあるが、出来るだけ怪我をさせないような軽い力で壁に向かつて投げつけると、たつたそれだけでぐつたりとし起き上がらなくなつてしまつた。
「もしかして気絶しちゃったのん? 情けないなぁ。………仕方ないから、しぃにぃから先にやっちゃお」
ベッドに染み付いてゐる妹の、甘く芳しい匂いで思考が止まりかけてゐた詩乃は、其の言葉を聞くや、何とかベッドから這い出て、四つん這ひの体勢のまま何とか逃げようとしたのであるが、ふと眼の前にひどく熱つぽい物を感じるたかと思えば、ぶじゅっ、と云ふ下品な音と共に、透明な液体が床にぼとりと落ちて行くのが見えた。--------あゝ、失敗した。もう逃げられぬ。もう文字通り、目と鼻の先に"アレ"がある。俺は今から僅か十三歳の幼い、其れも実の妹に何の抵抗も出来ぬまま犯されてしまふ。泣かうが喚かうが、体が破壊されようが関係なく犯されてしまふ。あゝ、でも良かつた。最後の最後に、こんな天上に御はします高潔な少女に使つて頂けるなんて、なんと光栄な死に方であらうか。-----------------
「しぃにぃ、よく見てよ、私のおちんちん。お兄ちゃんを見てるだけでもうこんなに大きくなつたんだよ?」
さう云ふと、心百合は詩乃の髪を雑に掴んで顔を上げさせ、自身の腕よりもずつとずつと太い肉棒を無理やり見せると、其の手が汚れるのも構はずに、まるで我が子��頭を撫でるかのやうな愛ほしい手付きで、ズルリと皮の剥けた雁首を撫でる。だが彼には其の様子は見えない。見えるのはドクドクと脈打つ指のやうな血管と、男性器に沿つて真つ直ぐ走るホースのやうな尿道と、たらりたらりと垂れて床を濡らすカウパー液のみである。其れと云ふのも当然であらう、亀頭の部分は持ち主の顔と同じ高さの場所にあるのである。------まだ大きくなつてゐたのか。…………彼にはもう、久しぶりに会ふことになつた妹の陰茎が、もはや自分の心臓を串刺しにする鉄の杭にしか見えなかつたのであるがしかし、其のあまりにも艶めかしい佇まひに、其のあまりにも圧倒的な存在感に、手が打ち震えるほど惹かれてしまつてもうどんなに嫌だと思つても目が離せなかつた。
「んふふ、……お兄ちゃんには、この子がそんなに美味しそうに見えるのん?」
「………そ、そんな、……そんなことは、ない。…………」
さうは云ふものの、詩乃は瞬きすらしない。
「でもさ、------」
心百合はさう云ふと、自身の肉棒を上から押さえつけて、亀頭を彼の口に触れるか触れないかの位置で止める。
「------お兄ちゃんのお口だと、先っぽも入らないかもねぇ」
と妹が云ふので、もしかしたらこの、俺の握りこぶしよりも大きい亀頭の餌食にならないで済むかもしれない、…………と詩乃は哀れにも少しだけ期待するのであつたが、ふいに、ぴゅるっと口の中に何やら熱い液体が入り込んで来る。あゝ、もしかしてこれは。………………
「………けど、そんなに美味しそうな顔されたら諦めるのも悪いよねっ。じゃあ、お兄ちゃん、お口開けて? ………ほら、もっと大きく開けないと大変なことになるよ? たぶん」
「あっ、………やっ、………やめ、やめやめ、いゃ、ややめ、あが、………………」
………まだ彼は、心百合が途中で行為を中断してくれると心のどこかで思つてゐたのであらう、カタカタと震える唇で一言、やめてくださいと、言ほうとしてゐるのであつた。だがさうやつてアワアワ云ふのも束の間、腰を引かせた妹に両肩を掴まれ、愉悦と期待に満ちた表情で微笑まれ、クスクスとこそばゆい声で笑はれ、そしてトドメと言はんばかりに首を可愛らしくかしげられると、もう諦めてしまつたのか静かになり、遂には顔が醜くなるほど口を大きく開けてしまつた。
「んふ、もっと力抜いて? …………そうそう、そういう感じ。じゃあ息を吸ってー。………止めてー。………はい、お兄ちゃんお待ちかね、心百合のおちんちんだよ。よく味わってねー」
其の声はいつもと変はらない、中学生にしては舌つ足らずな甚く可愛いらしい声であつたが、詩乃が其の余韻に浸る前に、彼の眼の前にあつた男性器はもう前歯に当たつてゐた。かと思えばソレはゆつくりと口の中へ侵入し、頬を裂し血を滴らせるほどに顎をこじ開け、瞬きをするあひだに喉まで辿り着くと、
「ゴリュゴリュゴリュ………! 」
と云ふ、凡そ人体から発生するべきでは無い肉の潰れる音を部屋中に響き渡らせ始める。そして、彼が必死の形相で肉棒を恵方巻きのやうに持つて細やかな抵抗してゐるうちに、妹のソレはどんどん口の中へ入つていき、ボコリ、ボコリとまず首を膨らませ、鎖骨を浮き上がらせ、肋骨を左右に開かせ、あつと云ふ間にみぞおちの辺りまで自身の存在を示し出してしまつた。もうこれ以上は死んでしまふ、死んでしまふから!止めてください!! ———と彼は、酸素の薄れ行く頭で思ふのであつたが恐ろしい事に、其れでも彼女のモノはまだ半分程度口の外に残り、ドクンドクンと血管を脈打たせてゐる。いや、詩乃にとつてもつと恐ろしいのは次の瞬間であつた。彼が其の鼓動を唇に数回感じた頃合ひ、もう兄を気遣うことも面倒くさくなつた心百合が、もともと肩に痛いほど食い込んでゐた手に骨を握りつぶさんとさらに力を入れ、此れからの行為で彼の体が動かないようにすると、
「ふぅ、………そろそろ動いても良い? まぁ、駄目って言ってもやるんだけどね。良いよね、お兄ちゃん?」
と云ひ、突き抜かれて動かない首を懸命に震はせる兄の返事など無視して、そのまま本能に身を任せ自分の思ふがまま腰を振り始めてしまつたのである。
「〜〜〜???!!!! 〜〜〜〜〜〜〜!!!!!!」
「んー? なぁに、お兄ちゃん。しぃにぃも高校生なんだから、ちゃんと言わないと誰にも伝わらないよぉ? 」
「〜〜〜〜〜!!!!!!!」
「あはっ、お兄ちゃん死にかけのカエルみたい。惨めだねぇ、実の妹にお口を犯されるのはどんな気分? 悔しい? それとも嬉しい?」
心百合は残酷にも、気道など完全に潰しているのに優しく惚けた声でさう問ひかける。問ひかけつつ、
「ごぎゅ! ごぎゅ! ずちゅり! ……ぐぼぁ!…………」
などと、耳を覆いたくなるやうな、腹の中をカリでぐちゃぐちゃにかき乱し、喉を潰し、口の中をズタズタにする音を立てながら兄を犯してゐる。度々聞こえてくる下品な音は、彼女の陰茎に押されて肺の中の空気が出てくる音であらうか。詩乃は心百合の問ひかけに何も答えられず、ただ彼女の動きに合はせて首を長くしたり、短くしたりするばかりであつたが、そもそもそんな音が耳元で鳴り響いてゐては、妹の可愛らしい声も聞こえてゐなかつたのであらう。
もちろん、彼もまた男の端くれであるので、たつた十三歳の妹にやられつぱなしというわけではなく、なんとか対抗しようとしてはゐる。現に今も、肩やら胸やら腹のあたりに感じる激痛に耐へて、力の入らぬ手を、心百合の未だくびれの無い未成熟な脇腹に当て、渾身の力で其の体を押し返そうとしてゐるのである。………が、如何せん力の差がありすぎて、全くもつて妹には届いてゐない。其の上、触れた場所がかなり悪かつた。
「何その手は。私、腰触られるとムズムズするから嫌だって昔言ったよね? お兄ちゃん頭悪いからもう忘れちゃったの? -----------
……………あ、分かった。もしかしてもっと突っ込んでほしいんだ!」
心百合はさう云ふと、腰の動きを止め、一つ、涙と鼻水でぐしゃぐしゃになり怯えきつてゐる兄の顔を至極愛ほしさうに撫でる。そして、
「もう、お兄ちゃん、そんなに心百合のおちんちんが好きだなんて早く言ってくれたらよかったのに。昔、精通した時に怯えてたから嫌いなんだと思ってた。…………
--------んふ、んふふ、…………じゃあ心置きなくやっ��ゃってもいいんだね?」
と変はらず詩乃の頭を撫でながら云つて、彼を四つん這いの状態から正座に近い体勢にし、自身は其の体に覆いかぶさるよう前かがみになると、必死で妹の男性器を引き抜こうと踏ん張る彼の頭を両手で掴み、鼠径部が彼の鼻に当たるまで一気に、自身のモノを押し込んだ。
「~~~~~~~??????!!!!!!!!!!」
「あんっ、……お兄ちゃんのお口の中気持ちいい。…………うん? お口? お腹? ………どっちでもいいや。---------」
心百合は恍惚(ルビは「うっとり」)とした表情で、陰茎に絡みつく絶妙な快感に酔ひしれた。どうしてもつと早く此の気持ちよさを味ははなかつたのだらう。なおにぃも、しぃにぃも、ただ年齢が上なだけで、もはや何をやつても私の後追ひになつてゐるのに、私がちょつと睨んだだけで土下座をして来る勢ひで謝つて来るくせに、私がどんなに仕様もないお願いをしても、まるでフリスビーを追ふ犬のやうにすぐに飛んでいくのに、-----------特に、二人共どうしてこんなに勉強が出来ないのだらうか。私が小学生の頃に楽々と解いてゐた問題が二人には解答を理解することすら難しいらしい、それに、そもそも理解力も無ければ記憶力も無いから、一週間、時には二週間も時間をあげてるのに本一つ覚えてこなければ、読んでくることすら出来ず、しかもこちらが言つてることもすぐには分かつてくれないから、毎回毎回、何度も何度も同じ説明をするハメになる。高校で習う内容の何がそんなに難しいのだらうか、私には分からぬ。そんなだから、あまりにも物分りの悪い兄たちに向かつて、手を上げる衝動に襲われたことも何度かあるのではあるけれども、別にやつてもよかつた。其れこそあの、精通をむかえたあの夜に、二人揃つて犯しておけばよかつた。あれから二人の顔を見る度にムクムクと大きくなつて来るので、軽く手を強く握ったり、わざと不機嫌な真似をして怯えさせたりした時の顔を思ひ出して自慰をし、自分の中にもくもくと膨らんでくる加虐心を発散させてゐるのであるが、最近では押さえが効かなくなつてもう何度、二人の部屋に押し入つてやらうかしらんと、思つたことか。さう云へば他のクラスに一人だけ居るふたなりの友達が数ヶ月前に、兄を嬲つて嬲つて嬲つて最後はお尻に突つ込んでるよ、と云つてゐるのを聞いて、本当にそんな事をして良いのかと戸惑つてゐたが、いざやつてみると自分の体が快楽を貪るために、自然と兄の頭を押さえつけてしまふももである。このなんと気持ちの良いことであらう、那央にぃもまずはお口から犯してあげよう、さうしよう。…………………
と、心百合は夢心地で思ふのであつたが、詩乃にとつて此の行為は地獄であらう。さつきまで彼女の腰を掴んでゐた手は、すでにだらんと床に力無く垂れてゐる。それに彼女の鼠径部がもろに当たる鼻は、-------恐らく彼女は手だけ力を加減してゐるのであらう、其の衝撃に耐えきれずに潰れてしまつてゐる。とてもではないが、彼に未だ意識があるとは思えないし、未だ生きてゐるかどうかも分からない。が、心百合の手の間からときたま見える目はまだ開いてをり、意外にもしつかりと彼女のお臍の辺りを眺めてゐるのであつた。しかも其の目には恐怖の他に、どこか心百合と同じやうな悦��を蓄えてゐるやうに見える。口を引き裂かれ、喉を拡げられ、内臓を痛めつけられ、息をすることすら奪われてゐるのに、彼は心の奥底では喜んでゐる。…………これがふたなりに屈した者の末路なのであらう、四歳離れた中学生の妹に気持ちよくなつて頂けてゐる、其れは彼にとつて、死を感じる苦痛以上に重要なことであり、別に自分の体がどうなろとも知つたことではない。実は、心百合が俺たちに対して呆れてゐるのは分かつてゐたけれども、一体彼女に何を差し上げると、それに何をしてあげると喜んでくれるのか分からなかつたし、それに間違つて逆鱗に触れてしまつたらどうしようかと悩んで、何も出来なかつた。だが、かうして彼女の役に立つてみるとなんと満たされることか。やはり俺たち兄弟はあの夜、自慰のやり方を教へるのではなく、口を差し出し尻を差し出し、犯されれば良かつたのだ。さうすればもつと早く妹に気持ちよくなつてもらえたのに、……………あゝ、だけどやつぱり命は惜しい、未だしたい事は山程ある、けど今はこの感覚を全身に染み込ませなければ、もうこんなことは二度と無いかもしれぬ。-------さう思ふと気を失ふわけにはいかず、幼い顔つきからは想像もできないほど卑猥な吐息を漏らす妹を彼は其の目に焼き付けるのであつた。
「お兄ちゃん、そろそろ出るよぉ? 準備はいーい? かるーく出すだけにしておいたげるから、耐えるんだよ?」
心百合はさう云ふと、腰を細かく震わせるやうに振つて、いよいよ絶頂への最後の一歩を踏み出そうとする。そして間もなくすると、目をギュッと閉じ、体をキュッと縮こませ、そして、
「んっ、………」
と短く声を漏らし快楽に身を震はせた。と、同時に、薄つすら筋肉の筋が見える、詩乃の見事なお腹が小さくぽつこりと膨らんだかと思ひきや、其れは風船のやうにどんどん広がつて行き、男なのに妊婦のやうな膨らみになつて遂には、ほんの少し針で突つつけば破裂してしまふのではないのかと疑はれるほど大きくなつてしまつた。軽く出すからね、と云ふ妹の言葉は嘘では無いのだが、其れでも腹部に感じる異常な腹のハリに詩乃はあの、腹が爆発して死んでしまつた強姦被害者の話を思ひ出して、もう限界だ、やめてくださいと、言葉に出す代はりに彼女の腕を数回弱々しく叩いた。
「えー、………もう終わり? お兄ちゃんいつもあんなにご飯食べてるのに、私の精液はこれだけしか入らないの?」
とは云ひつつ詩乃の肩に手をかけて、其の肉棒を引き抜き始める。
「ま、いいや、お尻もやらなきゃいけないし、その分、余裕を持たせておかなきゃね」
そしてそのままズルズルと、未だ跳ね上がる肉棒をゆつくり引き抜いていくのであるが、根本から先つぽまで様々な液体で濡れた彼女の男性器は、心なしか入れる前よりおぞましさを増してゐるやうに見える。さうして最後、心百合は喉に引つかかつた雁首を少々強引に引つこ抜くと、
「あっ、ごめ、もうちょっと出る。…………」
と云つて、"最後の一滴"を詩乃の顔にかけてから手を離した。
「ぐげぇぇぇぇぇぇぇ…………………!!!!お”、お”え”ぇぇぇぇぇぇぇぇ!!!!!」
一体どこからそんな音を発してゐるのか、詩乃が人間とは思へない声を出しながら体に入り切らぬ妹の精子たちを、己の血と共に吐き出して行く。が、心百合はそんな彼の事など気にも止めずもう一つの標的、つまり壁の側で倒れてゐる那央に向かつて歩みを進めてゐた。
「なおにぃ、いつまで寝たフリしてるの? もしかしてバレてないとでも思ってた?」
「あ、…………え、…………や、やめ。…………」
「えへへ、やめるとでも思ってるのん? しぃにぃはちゃんと私の愛を受け止めてくれたんだよ、………ちょっと死にかけてるけど。 なおにぃはどうなるかな?」
那央は体を起こし、そのまま尻もちをついた状態で後ずさろうとしたものの、哀れなことに後ろは壁であつた。
「お、お願いします、………やめ、やめてください。お願いします。………………」
「んー? お兄ちゃんは自分に拒否権があると思ってるのん? それに、私は今、"気持ちが高ぶってる"んだから、お兄ちゃんがするべきなのは、そんな逃げ回るゴキブリみたいに壁を這うことじゃなくて、首を立てに振ることだよ」
だが裂けた口から精子を吐き出し続けてゐる弟を見て、誰が首を縦に振れようか、ヒクヒクとうごめく鈴口からカウパー液を放出し続けてゐる肉棒を見て、誰がうんと頷けようか。彼に選択権は無いとは言つても、命乞ひくらゐはさせても良いであらう。
「お兄ちゃんさ、情けないと思わない? 妹にハグされただけで絶叫して、妹に軽く投げられただけで気絶して、妹に敬語を使いながら怯えてさ、……………そんなにこの子の餌食になりたいのん?」
「こ、心百合、……………頼む。…………頼むから落ち着いてくれ。……………」
「んふふ、お兄ちゃんって諦めが悪いよね。でも嫌いじゃないよ、そういうところ。------」
「あ、あ、…………や、やめて、…………ああぁ、や、やめてくださ…………………」
「もう、しぃにぃと同じ反応しないで! お兄ちゃんでしょ? 弟の方がまだ潔くて男の子らしかったよ? っていうかさっき私に、犯さないで、って言ったのもしぃにぃだったじゃん」
心百合は土下座のやうに下を向く那央の頭を上げさせ、肉棒の先つぽを軽く口の中へねじ込む。
「あ、あが、………。ひ、ひや。……………」
「だからぁ、………バツとしてなおにぃを犯す時は、遠慮しないことにしよっかな。-----えへへ、大丈夫だって、しぃにぃはまだ生きてるし、大丈夫大丈夫。----------」
さうして彼女は本当に容赦なく、那央の頭を手で掴み固定して、一気に自身のモノの半分ほどを突つ込んだ。そして、前のめりになつて暴れる兄の体に背中から覆いかぶさるように抱きしめると、
「よっ、と。………」
と軽い掛け声をかけ、そのままスツと、まるでお腹にボールでも抱えてゐるかのやうに、何事も無く男一人を抱えて立ち上がつた。体勢としては、妹の男性器に串刺しにされた那央が、逆立ちするやうに足を天井へ向けて、心百合に抱きかかえられてゐる、と云へば伝はるであらうか、兎に角、小学生と言はれても不自然ではない小柄な体格の女の子に、標準体型の男が上下を逆にして抱えられてゐると云ふ、見慣れぬ人にとつては異様な状況である。
「~~!!!~~~~~~!!!!!!!」
「こら、暴れないで。いや暴れてもいいけど、その分どんどん入って行くから、お兄ちゃんが困ることになるよ?」
其の言葉通り、那央が暴れれば暴れるほど彼の体は、自身の体重で深く深く心百合のモノに突き刺さつて行く。が、其れでも精一杯抵抗しようと足をジタバタ動かしてしまひ、結局彼女のモノが全部入るのにあまり時間はかからなかつた。
「もう諦めよっ? お兄ちゃんはこれから私を慰めるための玩具になるんだから、玩具は玩具らしく黙って使われてたら良いの」
だがやはり、那央は必死で心百合の太腿を掴んで彼女の男性器を引き抜こうとしてゐる。なのでもう呆れきつてしまひ、一つ、ため息をつくと、
「いい加減に、………」
と云ひながら、彼の肋骨を拉げさせつつ二、三十センチほど持ち上げ、そして、
「………して!」
と、彼の体重も利用して腕の中にある体を振り下ろし、再び腹の奥の奥にまで男性器を突つ込ませた。
「っっっっっっ!!!!!」
「あぁんっ! やっぱり男の人のお口はさいこぉ、…………!」
心百合はよだれを垂らすほどに気持ち良ささうな顔でさう云ふのであるが、反対に、自分では到底抵抗できぬ力で体を揺さぶられた那央は、其の一発で何もかもを諦めたのか手をだらりと垂れ下げ出来るだけ喉が痛くならないように脱力すると、もう静かになつてしまつた。
「んふ、…………そうそう、それでいいんだよ。お兄ちゃんはもう私の玩具なの、分かった?」
さう云ひながらポンポンと優しくお腹を叩き、そのまま兄を抱えてベッドまで向かふ。途中、未だにケロケロと精液を吐き出してゐる詩乃がゐたが、邪魔だつたので今度は彼を壁際まで蹴飛ばしてからベッドに腰掛けた。そして、
「ちゃんと気持ちよくしてね」
と簡単に云つて、彼の腰の辺りを雑に掴み直すと、人を一人持ち上げてゐるとは思へ無いほど軽やかに、------まさに人をオナホールか何かだと勘違ひさせるやうな激しい動きで、兄の体を上下させて自身の肉棒を扱き出したのであつた。股を開き局部を露出してなお、上品さを失はずに顔を赤くし甘い息を吐き綺羅びやかな黒髪を乱す其の姿は、いくら彼女が稚い顔つきをしてゐると云へ万人の股ぐらをいきり立たせるであらう。勿論其れは実の兄である詩乃も例外ではない。どころか、彼はもう随分と妹の精液を吐き出しいくらか落ち着いてきてゐたので心百合と那央の行為を薄れていく意識の中見てゐたのであるが、自身の兄をぶらぶらと、力任せに上へ下へと上下させて快楽を貪る実の妹に対しこの上なく興奮してしまつてゐるのである。なんと麗しいお姿であらうか、たとへ我が妹が俺たちを死に追ひやる世にも恐ろしい存在であらうとも、ある種女神のやうに見えてくる。そして其の女神のやうな高貴な少女が、俺たち兄弟を道具として使ひ快楽に溺れてゐる。………なんと二律背反的で、背徳的で、屈辱的な光景であらう、人生の中でこれほど美しく、尊く、猥りがましく感じた瞬間はない。------彼はもう我慢できなくなつて、密かに片手を股にやり、ズボンの上から己の粗末なモノを刺激し初めたのであるが、ふと視線に気がついてグッと上を向くと、心百合が此方を見てニタニタと其の顔を歪ませ笑つてゐた。
「くすくす、……………お兄ちゃんの変態。もしかして、なおにぃが犯されてるの見て興奮してたの?」
心百合はもう那央の体を支えてゐなかつたが、其れでも其の体は床に垂直なまま足をぶらつかせてゐる。
「ほら、お兄ちゃんも出しなよ、出して扱きなよ。知ってるよ私、お兄ちゃんが密かに私の部屋に入って、枕とか布団とかパジャマとかの匂いを嗅ぎながら自慰��てるの。全部許したげるからさ、見せてよ、お兄ちゃんのおちんちん」
「あっ、………えっ、…………?」
自分の変態行為を全部知られてゐた、-----其の事に詩乃は頭を殴られたかのやうな衝撃を受け、ベルトを外すことすらままならないほど手を震えさせてしまひ、しかしさらに自身のモノが固くなるのを感じた。
「ほら早く、早く、-----------」
心百合はもう待ちきれないと云ふ様子である。其れは年相応にワクワクしてゐる、と云ふよりは獲物を見つけて何時飛びかかろうかと身を潜める肉食動物のやうである。
「ま、まって、…………」
と、詩乃が云ふと間もなく、ボロンとすつかり大きくなつた、しかし妹のソレからすると無視できる程小さい男の、男のモノがズボンから顔を出した。
「あははははっ、なにそれ! それで本当に大きくなってるの?」
「う、……��っ…………!」
「まぁ、いいや。お兄ちゃんはそこでそのおちんちん? をシコシコしていなよ。もう痛いほど大きくなってるんでしょ? 小さすぎて全然分かんないけど」
と云つて心百合は那央の体を掴み、再びおぞましい音を立てながら"自慰"に戻つた。そして詩乃もまた、彼女に言われるがまま自身の粗末な男性器を握ると悔しさやら惨めさやらで泣きそうになつたが、矢張り妹の圧倒的な巨根を見てゐると呼吸も出来ないほどに興奮して来てしまひ、ガシガシと赴くがまま手を動かすのであつた。だが一寸して、
「あ、しぃにぃ、見て見て、-------」
と、心百合が嬉しさうな声をかけてくる。………其の手は空中で軽く閉じられてをり、那央の体はまたもや妹のモノだけで支えられてゐる。------と思つてゐたら突然、ビクン! と其の体が暴れた。いや、其れは彼が自分から暴れたのではなく、何かに激しく揺さぶられたやうだと、詩乃は感じた。
「ほらほら、------」
ビクン、ビクンと那央の体が中身の無い人形のやうに暴れる。
「------お兄ちゃんのちっちゃい、よわよわおちんちんじゃ、こんなこと出来ないでしょ」
ベッドに後ろ手をつきながら、心百合がニコニコと微笑んでさう云つてきて、やうやく詩乃にも何が起きてゐるのか理解できたやうであつた。まさか妹は人を一人、其の恐ろしい陰茎で支えるのみならず、右へ左へとあの激しさで揺れ動かしてゐるとでも云ふのであらうか。いや、頭では分かつてはゐるけれども、全然理解が追ひつかない。いや、いや、ちやつと待つてくれ、其れよりもあんなに激しく暴れさせられて兄貴は無事であらうか。もう見てゐる限りでは全然手に力が入つて無く、足もただ体に合はせて動くだけ、しかも、かなり長いあひだ呼吸を肉棒で押さえつけられてゐる。……………もう死んでしまつたのでは。----------
「んぁ? なおにぃもう死にそうなの? ………………仕方ないなぁ、ちょっと早いけどここで一発出しとくね」
男性器を体に突つ込んでゐる心百合には分かるのであらう、まだ那央が死んでゐないといふ事実に詩乃は安心するのであつたが、先程自分の中に流し込まれた大量の精液を思ふと、途中で無理矢理にでも止めねば本当に兄が死んでしまふやうな気がした。
「んっ、…………あっ、来た来たっ……………」
心百合はさう云ふとより強く、より包むように那央を抱きしめ、其の体の中に精を放ち始める。が、もう彼の腹がパンパンに張らうとした頃、邪魔が入つた。
「やめ、………心百合、もうやめ、…………!」
「なに?」
見ると詩乃がゾンビのやうに床を這ひ、必死の力でベッドに手をかけ、もう片方の手で此方の腕を握って、しかもほとんど残つてゐない��を食ひしばつて、射精を止(や)めさせようとしてゐるではないか。兄のために喉を潰されても声をあげ、兄のために激痛で力の入らぬ足で此方まで歩き、兄のために勝ち目など無いと云ふのに手を伸ばして妹を止めようとする献身的な詩乃の姿勢に、心百合は少なからず感動を覚えるのであつたが、残念なことに彼女の腕を握つてゐる手は自身の肉棒を触つた手であつた。
「お兄ちゃん? その手はさっきまで何を触ってた手だったっけ?」
と云ふと、那央がどうなるのかも考えずに無理やり肉棒を引き抜きベシャリと其の体を床に投げつけ、未だ汚い手で腕を握つてくる詩乃の襟首を掴んで、ベッドから立ち上がる。
「手、離して」
「は、はい。………」
「謝って」
「あ、あぁ、……ご、ごご、ごめんなさい。……………」
「んふ、…………妹をそんな化物でも見るみたいな目で見ないでもいいんじゃないのん? 私だって普通の女の子なんだよ?」
「……………」
「ちょっとおちんちんが生えてて、ちょっと力持ちで、ちょっと頭が良いだけなんだよ。それなのにさ、みんなお兄ちゃんみたいに怯えてさ、……………」
「心百合、…………」
「------本当に、たまらないよね」
「えっ?」
「でも良かったぁ、……………もう最近、お兄ちゃんたちだけじゃなくて、友達の怯えた表情を見てると勃ってしょうがなかったんだもん。……………」
「こ、心百合、…………」
「だからさ、今日お兄ちゃんたちが部屋に入ってきて、犯さないで、って言った時、もう我慢しなくて良いんだって思ったんだよ。だって、お兄ちゃんも知ってるんでしょ? ふたなりにそういう事を言うと逆効果だって。知ってて言ったんでしょ? -------」
「まって、……そんなことは。…………」
「んふ、……暴れても無駄だよ、お兄ちゃん。もう何もかも遅いんだよ、もう逃れられないんだよ、もう諦めるしかないんだよ、分かった?」
「ぐっ!うああ!!!」
「あはは、男の人って本当に弱いよね。みーんな軽く手を握るだけで叫んでさ、ふたなりじゃなくっても女の子の方が、今の世の中強いよ、やっぱり。お兄ちゃんも運動部に入ってるならもっと鍛えないと、中学生どころか小学生にすら勝てないよ? …………あぁ、でもそっか、そう云えば、この間の試合は負けたんだっけ? 聞かなくてもあんな顔して夜ご飯食べてたら誰だって分かっちゃうよ」
心百合はさう云ふと、片手で詩乃を壁に投げつけた。
「ぐえっ、…………」
「-----ま、そういう事は置いといて、中途半端に無理やり出しちゃって気持ち悪いから、さっさとお尻に挿れちゃうね。しぃにぃは後でやってあげるから、そこで見てて」
詩乃が何かを云ふ前に心百合は、ひどい咳と共に精液と血を吐き出し床にうずくまる那央を抱えて、無理やり四つん這いの体勢にする。そしてジャージの腰の部分に手をかけて剥ぎ取るように下ろすと、其処にはまるで此れからの行為を期待するかのやうにヒクヒクと収縮するお尻の穴と、ピクピクと跳ねる那央のモノが見えた。
「なぁに? なおにぃも私にお口を犯されて興奮してたのん?」
「ぢ、ぢが、……ぢがう。………」
と那央が云ふけれども激しく嘔吐しながらも自身のモノを大きくすると云ふことは、さう云ふ事なのであらう。
「んふふ、じゃあもう待ちきれないんだ。いいよ、それなら早く挿れてあげるよ。準備はいーい?」
さながら接吻のやうに心百合の男性器と、那央の肛門がそつと触れ合ふ。が、少なく見積もつても肛門の直径より四倍は太い彼女のモノが其処に入るとは到底思へない。
「だめ、だめ、だ、だめ、………あ”ぁ、ゃ、………」
那央は必死に、赤ん坊がハイハイする要領で心百合から逃げようとしてゐるのであるが、彼女に腰を掴まれてしまつては無意味であらう、ただ手と足とがツルツルと床を滑るのみである。しかし其のあひだにも心百合のモノはじつとりと品定めするかのやうに、肛門付近を舐め回して来て、何時突つ込まれるか分からない恐怖で体が震えて来る。一体どれほどの痛みが体に走るのであらうか。一体どれほどの精液を放たれるのであらうか。妹はすでに、俺たち二人の腹を満杯にするまで射精をしてゐるけれども、未だ普段行われる自慰の一回分にも達してをらず、相当我慢してゐることはこの足りない脳みそで考へても分かる。分かるが故に恐ろしい、今のうちに出来る限り彼女の精液を吐き出しておかないと大変な事になつてしまふ。凡そ"気が高ぶった"ふたなりが情けをかけ射精の途中で其の肉棒を引き抜いてくれるなんて甘い希望を持つてはいけない。況してや先つぽだけで我慢してくれるなど、夢のまた夢であらう。…………あゝ、こんなことになるなら初めからダンベルなど放つておけばよかつた、どうしてあの時詩乃に、云ひに行くぞ、などと持ちかけてしまつたのか、あのまま何も行動を起こさなければ後数年、いや、後数日は生きていけさうであつたのに。あゝ、どうして。-------さう悲嘆に暮れてゐると、遊びもここまでなのか、心百合が自身のモノの先端を、グイと此方の肛門に押し付けて来た。そして、
「んふ、ちょっと痛いかもしれないけど、我慢してね。-------」
と云ふ悦びに打ち震えた優しい声をかけられ、腰を掴んでいる手に力が込められ、メコリと肛門が広がる感覚が走れば直ぐ其の後、気を失ふかと思はれる程の激痛で目の前が真暗になつた。
「ぐごっ、…………ごげっ、ぐぁ、……………」
絶叫しようにも、舌が喉に詰まつて声が出てこない。だけどそんな空気の漏れる音を立ててゐるうちにも妹のソレはどんどん那央の中へ入つて来て、もう一時間もしたかと彼が思つた頃合ひにふと其の動きが止まり、次いで腰を握りつぶしてゐた手の力も抜けていき、たうたう全部入つたんだ、何とか耐えきつた、と安堵して息を吸つたのであるが、しかし心百合の言葉は彼を絶望させるのに十分であつた。
「------ちょっと先っぽだけ入れてみたけど、どう? 気持ちいい?」
「ぅご、………う、嘘だろ…………」
「嘘じゃないよ。じゃ、どんどん入れてくね」
「あがああああああああああっ、がっ、あっ、…………」
那央の絶叫は心百合に再び腰を掴まれ、メリメリメリ、………と骨が軋む音が再びし始めるとすつかり無くなつてしまつた。彼は激痛からもはや目も見えず声も出ず考へることすら出来ない状態なのだが、此れが人間の本能と云ふやつなのであらう、其れでも手を前に出し足を上げ、一人の可憐な少女から逃げようとしてゐるのである。が、いつしか手が空を切り膝が宙に浮くやうになるともう何が起きてゐるのか訳が分からなくなり、心無い者に突然抱きかかえられた猫のやうに手足をジタバタと暴れさせるだけになつてしまふ。そして、さうやつて訳が分からぬうちにも心百合の陰茎は無慈悲に入つて行き、体の中心に赤々と光る鉄の棒を突つ込まれたかのやうに全身が熱くなり汗が止まらなくなり初めた頃、いよいよお尻に柔らかい彼女の鼠径部の感触が広がつた。広がつてしまつた。
「んふふ、どう、お兄ちゃん? 気持ちいーい?」
「………………」
「黙ってたら分からないよぉ?」
と、云ひつつ心百合は腰を掴んでゐた手で那央の体を捻り其の顔を覗き込む。
「あがっ、…………」
「私はお兄ちゃんに気持ち良いかどうか、聞いてるんだけど」
「こ、こゆ、…………」
「んー?」
那央は黙つて首を横に振つた。当然であらう、自分の拳ほどの太さの陰茎を尻にねじ込まれ、体が動かないようにと腰を掴んでゐた手でいつの間にか持ち上げられ、内蔵を滅茶苦茶にしてきた陰茎で体を支えられ、もう今では中指の先しか手が床に付かないのである。例へ激痛が無くとも、腹に感じる違和感や、極度に感じる死の恐怖や、逃げられぬ絶望感から決して首を縦に振ることは出来ないであらう。
「そっか、気持ちよくないんだ。…………」
「はやく抜いてく、…………」
「------ま、関係無いけどね」
気にしないで、気にしないで、ちやんと気持ちよくしてあげるから、と続けて云ふと心百合は再び那央の腰を掴み直す。
「こ、こゆり!!! やめて!!!」
「うるさい! 女の子みたいな名前して、おちんちんで突かれたぐらいで文句言わないで!」
この言葉を切掛に、心百合は骨にヒビが入るほど其の手に力を入れ、陰茎を半分ほど引き抜いていく。そして支えを失つてもはや力なくだらりと垂れる兄を見、
「んふ、………」
と妖艶に色づいた息を漏らすと、彼のお尻に勢ひよく腰を打ち付けた。
「ぐがあぁ!!!!!」
「あぁん、お尻もさいこぉ。……………お兄ちゃんの悲鳴も聞こえるし、お口より良いかも、…………」
さう云ふと、もう止まらない。兄がどんなに泣き叫ぼうが、どんなに暴れようが自身の怪力で全て押さえ込み、其の体を己の腰使ひでもつて何度も何度も貫いて行く。そして初めこそ腰を動かして快楽を貪つてゐたが、次第に那央の事が本当に性欲を満たすための道具に見えてくると、今度は自分が動くのでは無くさつきと同じやうに彼の体を、腕の力だけで振り回して肉棒を刺激してやる。
「あぎゃっ! いぎぃ! おごぉっ!!-------」
「あはっ、お兄ちゃん気持ちよさそう。…………良かったねぇ、妹に気持ちよくし���もらえて。嬉しいでしょ?」
「こ、ごゆぅっ!! ごゆり”っ!!! ぐあぁっ!!!」
「なぁに、お兄ちゃん? 止めてなんて言わないでよね。いつもお勉強教えてあげてるのにあんな反抗的な目で見てきて、悔しかったのか知らないけど、どれだけ私が我慢してたか分かる?」
「じぬっ!! じぬがら!!! ゃめ!!!」
「…………んふ、もう大変だったんだから。毎日毎日、お風呂に入る前の一回だけで満足しなきゃいけなかった身にもなってよ」
「ぐぎぃっ!!こゆっ!!あ”あ”ぁっ!!!」
「でもさ、思うんだけど、どうしてあんな簡単な入試問題すら解けないのん? 私あの程度だったら教科書を読んだら、すぐに解けるようになってたよ? しかも小学生の頃に。入試まで後一ヶ月も無いのに大丈夫?
……………もうお兄ちゃんの代わりに大学行ったげるからさ、このままこんな風に私の玩具として生きなよ。そっちの方が頭の悪いお兄ちゃんにはお似合いだよ、きっと、たぶん、いやぜったい」
傷だらけの喉をさらに傷つけながら全力で叫ぶ那央を余所に、心百合は普段言ひたくて言ひたくて仕方無かつた事を吐露していくのであつたが、さうしてゐると自分でも驚くほどあつと云ふ間に絶頂へ向かつてしまつて、後数回も陰茎を刺激すると射精してしまひさうである。全く、この出来損ないの兄は妹一人満足させることが出来ないとでも云ふのであらうか。本当はこのまま快感の赴くがままに精液を彼の腹の中に入れてやりたい所だけど、折角手に入れた玩具を死なせてしまつては此方としても嫌だから、途中で射精を止めなければならぬ。いや、未だ壁の側で蹲つてゐるしぃにぃが居るではないか、と云ふかもしれないが人の腹の容量などたかが知れてゐて、満杯にした所で未だ未だ此の体の中には精液が波打つてゐる。-------あゝ、ほんの一合程度しか出ない男の人が羨ましい。見ると、なおにぃの股の下辺りに白い点々が着いてゐるのは多分彼の精液なのだと思ふが、なんと少ないことか。私もあのくらいしか出ないのであれば、心置き無く此の情けない体の中に精を放つことが出来るのに。……………
「------そろそろ、……そろそろ出るよ、お兄ちゃん。ちゃんと私の愛、受け止めてあげてね」
さう云ふと心百合は今までの動きが準備体操であつたかの如く、那央の体を激しく揺さぶり始める。そして最後、那央のお尻に自分のモノを全て入れきり目を閉じたかと思ひきや、
「んっ、んっ、………んん~~~。…………」
と、其の身を震わせて精子を実の兄の体の中で泳がせるのであつた。が、矢張り彼女にもどこか優しさが残つてゐたのか数秒もしないうちに、じゅるん、と男のモノを引き抜き那央を床に捨て、どろり、どろりと、止めきれ無かつた精液を其の体の上にかけると、でも矢張りどこか不満であつたのか壁際で自身の小さな小さなモノを扱いてゐたもう一人の兄の方を見た。
「しぃにぃ、おまたせ。早くしよっ」
其の軽い声とは逆に、彼女の肉棒はもう我慢出来ないと言はんばかりに、そして未だ未だ満足ではないと云はんばかりに大きく跳ね床に精液を撒き散らしてゐる。一体、妹の小さな体のどこにそんな体力があるのか、もうすでに男を滅茶苦茶に嬲り、中途半端とは云へ三回も射精をしてゐると云ふのに、此のキラキラと輝くやうな笑顔を振りまく少女は全く疲れてなどゐないのか、これがふたなりなのか。-----------
「あ、えぁ、…………」
「? どうしたの? なにか言いたげだけど。………」
「そ、その、きゅ、きゅうけい。…………」
「--------んふ、何か言った? 休憩? 私、休憩なんて必要ないよ。それにお兄ちゃんも十分休んだんだから良いでしょ。……ねっ、早くっ、早くお尻出して?」
「い、いや、いや、…………………」
起き上がつてドアまで駆け、そして妹に捕まえられる前に部屋を後にする、……………さう云ふ算段を詩乃は立ててゐたのであるが、まず起き上がることが出来ない。なぜだ、足に力が入らない、----と思つたが、かうしてゐる内にも心百合は近づいて来てゐる。其の肉棒を跳ね上げさせながらこちらに向かつて来てゐる。-------もうじつとしてなど居られない。何とか扉まで這つて行き、縋り付くやうにしてドアノブに手をかける。が、其の時、背中に火傷するかと思はれるほど熱い突起物が押し付けられたかと思つたら、ふわりと、甘い甘い、でも決して淑やかさを失ふことの無い甚く魅惑的な匂ひに襲はれ、次いで、背後から優しく、優しく、包み込まれるやうにして抱きしめられてゐた。そして首筋に体がピクリと反応するほどこそばゆい吐息を感じると、
「おにーちゃんっ、どこに行こうとしてるのん? まさか逃げようとしてたのん?」
と言はれ、ギュウゥゥ、………と腕に力を入れられてしまふ。
「ぐえぇ、………ぁがっ!………」
「-----んふふ、もう逃げられないよぉ。しぃにぃは今から私に、……この子に襲われちゃうの。襲われてたくさん私の種を吐き出されちゃうの。------ふふっ、男の子なのに妊娠しちゃうかもね」
「ご、ごゆり、…………あがっ、………だれかたすけて。……………」
と云ふが、ふいにお腹に回されてゐた手が膝の裏に来たかと思へば、いつの間にかゆつくりと体が宙に浮いて行くやうな感じがした。そして顔のちやつと下に只ならぬ存在感を感じて目を下に向けると、すぐ其処には嫌にぬめりつつビクビクと此方を見つめて来る妹の男性器が目に留まる。そして、足を曲げて座つた体勢だと云ふのに遥か遠くに床が見え、背中には意外と大きい心百合の胸の感触が広がる。…………と云ふことはもしかして俺は今、妹に逆駅弁の体位で後ろから抱きかかえられて、情けなく股を開いて男のモノを入れられるのを待つてゐる状態であるのだらうか。まさか男が女に、しかも実の妹に逆駅弁の体勢にされるとは誰が想像できよう、しかし彼女は俺の膝を抱え、俺の背中をお腹で支えて男一人を持ち上げてしまつてゐる。兄貴は心百合のモノが見えなかつたからまだマシだつただらうが、俺の場合は彼女の男性器がまるで自分のモノかのやうに股から生えてゐて、……………怖い、ただひたすらに怖い、こんなのが今から俺の尻に入らうとしてゐるのか。------
「あれ? お兄ちゃんのおちんちんは? どこ?」
詩乃はさつき自身のモノをしまふことすら忘れて扉に向かつたため、本来ならば逆駅弁の体位になつて下を向くと彼の陰茎が見えてゐるはずなのだが、可哀想なことに心百合のモノにすつぽりと隠れてしまつて全く見えなかつた。
「あっ、もしかしてこの根本に感じてる、細くて柔らかいのがそうなのかな? いや、全然分かんないけど」
心百合のモノがゆらゆらと動く度に詩乃のモノも動く。
「本当に小さいよね、お兄ちゃんのおちんちん、というか男の人のおちんちんは。私まだ中学一年生なのにもう三倍、四倍くらい?は大きいかな。…………ほんと、精液の量も少ないし、こんなのでよく人類は絶滅しなかったなぁって思うよ。-----まぁ、だから女の人って皆ふたなりさんと結婚していくんだけどね。お兄ちゃんも見てくれは良いのによく振られるのはそういうことなの気がついてる? 女の人って分かるんだよ、人間としての魅力ってものがさ。------」
「こゆり、…………下ろして。…………」
「あはは、役立たずの象徴を私のおちんちんで潰されてなに今更お願いしてるのん? ふたなりに比べて数が多いってだけで人権を与えられてる男のくせに。お兄ちゃんは、お兄ちゃんとして生まれた時点で、もう運命が決まってたんだよ。…………んふ、大丈夫大丈夫、心配しないで。もしお兄ちゃん達に人権が無くなっても、私がちゃんと飼ってあげるから、私がちゃんとお兄ちゃんにご飯を食べさせてあげるからさ、そんな不安そうな顔する必要ないよ、全然。--------」
「こゆ、り。…………」
「だって私、お兄ちゃんたちのこと大好きなんだもん。なおにぃにはあんなこと言ったけど、なんていうか二人とも、ペット? みたいで可愛いんだもん。だから普通の男の人よりは良い生活をさせてあげるから、さ、-----」
と、其の時、詩乃の体がさらに浮き始める。
「…………その代わりに使わせてね、お兄ちゃんたちの体。--------」
さう云ふと心百合は、早速兄の体を使おうと一息に詩乃を頭上へ持ち上げて、彼の尻穴と自身の雁首を触れ合はせる。意外にも詩乃が大人しいのはもう諦めてしまつたからなのか、其れとも油断させておいて逃げるつもりだからなのか。どちらにせよ動くと一番困るのは内蔵をかき乱される兄の方なのだから静かに其の時を待つてゐるのが一番賢いであらう。
「んふ、…………じゃあ、挿れるね。--------」
詩乃は其の言葉を聞くや、突然大人しく待つてなど居られなくなつたのであるが、直ぐにメリメリと骨の抉じ開けられる音が聞こえ、そして股から体が裂けていくやうな鈍い痛みが伝わりだすと、体全体が痙攣したやうに震えてしまひもはや指の一本すら云ふことを聞いてくれなかつた。其れでも懸命に手足を動かそうとするものの体勢が体勢だけにそもそも力が入らず、ひつくり返された亀のやうに妹の腹の上でしなしなと動くだけである。だがさうしてゐるうちにも、心百合は力ずくで彼の体に男のモノを入れていき、もう其の半分ほどが入つてしまつてゐた。
「そんな無駄な抵抗してないで、自分のお腹を触ってみたら? きっと感じるよ、私のおちんちん」
妹に言はれるがまま、詩乃はみぞおち辺りを手で触れる。すると、筍が地面から生えてゐるやうにぽつこりと、心百合の男性器が腹を突き破らうと山を作り、そして何やら蠢いてゐるのが分かつた。
「あっ、……はっ、………はは、俺の、俺の腹に、あぁ、……………」
「んふふ、感じた? 昔こういうの映画にあったよね、化物の子供が腹を裂いて出てくるの。私怖くて、お兄ちゃんに抱きついて見れなかったけど、こんな感じだった?」
「-----ふへ、………ふへへ、心百合の、こゆり、………こゆ、…………」
「あはっ、お兄ちゃんもう駄目になっちゃった? しょうがないなぁ、………」
と云ふと、心百合は腰を引いて詩乃の体から陰茎を少し引き抜く。
「-----じゃあ、私が目を覚まさせてあげる、………よっ!」
「っおごぁっっっ!!!!!」
其のあまりにも強烈な一撃に、詩乃は顔を天井に上げ目を白くし裂けた口から舌を出して、死んだやうに手をだらんと垂れ下げてしまつた。果たして俺は人間であるのか、其れとも妹を気持ちよくさせるための道具であるのか、いや、前者はあり得ない、俺はもう、もう、…………さう思つてゐると二発目が来る。
「ぐごげぇえええっっっっ!!!!!」
「んー、…………まだ目が醒めない? もしもーし、お兄ちゃん?」
「うぐぇ、……げほっ、げほっ、………」
「まだっぽい? じゃあ、もう一発、………もう一発しよう。そしたら後はもうちょっと優しくしたげるから!」
すると、腹の中から巨大な異物が引き抜かれていく嫌な感覚がし、次いで、彼女も興奮しだしたのか背後から艶つぽい吐息が聞こえてくるようになつた。だけど、どういふ訳か其の息に心臓を打たせてゐると安心して来て、滅茶苦茶に掻き回された頭の中が少しずつ整頓され、遂には声が出るようになつた。
「こ、こゆり。………」
「うん? なぁに、お兄ちゃん」
「も、も、ももっと、もっと、…………」
もつと優しくしてください、と云ふつもりであつた。しかし、
「えっ、もっと激しくして欲しいのん? しぃにぃ、本当に良いのん?」
「い、いや、ちが、ちが、…………」
「----しょうがないなぁ。ほんと、しぃにぃって変態なんだから。……でもさすがに死んじゃうからちょっとだけね、ちょっとだけ。-------」
さう云ふと心百合は、今度は腰を引かせるだけでなく詩乃の体を持ち上げるまでして自身の陰茎を大方引き抜くと、其のまま動きを止めてふるふると其の体を揺する。
「準備は良い? もっと激しくって言ったのはお兄ちゃんなんだからね、どうなっても後で文句は言わないでね」
「あっ、あっ、こゆり、ぃゃ、……」
「んふ、-------」
と、何時も彼女が愉快な心地をする際に漏らす悩ましい声が聞こえるや、詩乃は床に落ちていつた。かと思えば、バチン! と云ふ音を立てて、お尻がゴムのやうに固くも柔らかくもある彼女の鼠径部に打ち付けられ、体が跳ね、そして其の勢ひのまま再び持ち上げられ、再度落下し、心百合の鼠径部に打ち付けられる。-------此れが幾度となく繰り返されるのであつた。もはや其の光景は遊園地��ある絶叫系のアトラクシオンやうであり、物凄い勢ひでもつて男が上下してゐる様は傍から見てゐても恐怖を感じる。だが実際に体験をしてゐる本人からするとそんな物は恐怖とは云へない。彼は自分ではどうすることも出来ない力でもつて体を振り回され、腹の中に巨大な異物を入れられ、肛門を引き裂かれ、骨盤を割られ、さう云ふ死の苦痛に耐えきれず力の限り叫び、さう云ふ死の恐怖から神のやうな少女に命乞ひをしてゐるのである。だが心百合は止まらない。止まるどころか彼の絶叫を聞いてさらに己を興奮させ、ちやつと、と云つたのも忘れてしまつたかの如く実の兄の体をさらに荒々しく持ち上げては落とし、持ち上げては落とし、其の巨大な陰茎を刺激してゐるのであつた。
「あがあぁぁぁ!!!こゆ”り”っっっっ!!!!ぅごぉあああああっぁぁ!!!!」
「えへへ、気持ちいーい?」
「こゆりっっ!!こゆり”っ!!!!!こゆっ!!!!」
「んー? なぁに? もっと激しくって言ったのはお兄ちゃんでしょう?」
「あぁがぁぁっっ!!!ごゆ”り”っ!!!」
「んふふ、しぃにぃは本当に私のこと好きなんだねぇ。いくら家族でも、ちょっとドキドキしちゃうな、そこまで思ってくれると。------」
腰を性交のやうに振つて、男を一人持ち上げ、しかも其の体を激しく上下させてなお、彼女は息を乱すこともなく淡々と快楽を味はつてゐる。が、其の快楽を与えてゐる側、------詩乃はもう為すがまま陵辱され、彼女の名前を叫ぶばかりで息を吸えてをらず、わなわなと震えてゐる唇からは血の流れを感じられず、黒く開ききつてゐる瞳孔からは生の活力が感じられず、もはや処女を奪はれた生娘のやうに肛門から鮮血を垂れ流しつつ体を妹の陰茎に突き抜かれるばかり。でも、其れでも、幸せを感じてゐるやうである。何故かと云つて、彼ら兄弟は本当に妹を愛してゐるのである。其の愛とは家族愛でもあると同時に、恋ひ人に向ける愛でもあるし、崇敬愛でもあるのである。そしてそこまで愛してゐる妹が自分の体を使つて喜んでくれてゐる、いや彼の言葉を借りると、喜んで頂けてゐるのである。…………此の事がどれほど彼にとつて嬉しいか、凡そ此の世に喜ぶ妹を見て嬉しくならない兄など居ないけれども、死の淵に追ひ込まれても幸せを感じるのには感服せざるを得ない。彼を只の被虐趣味のある変態だと思ふのは間違ひであり、もしさう思つたのなら反省すべきである。なんと美しい愛であらうか。---------
「んっ、………そろそろ出そう。……………」
さうかうしてゐると、心百合はどんどん絶頂へと向かつて行き、たうたう、と云ふより、此れ以上快感を得てしまつては途中で射精を止める事が出来ない気がしたので、さつさと逝つてしまはうと其の腰の動きをさらに激しくする。
「ひぎぃ!!うぐぇ!!ごゆりっ!!じぬ”っ!!!じぬ”ぅっっっっ!!!!」
死ぬ、と、詩乃が云つた其の時、一つ、心百合のモノが暴れたかと思ひきや、唯でさへ口を犯された際の名残で大きく膨れてゐた彼の腹がさらに膨らみ、そして行き場を失つた精液が肛門をさらに切り裂きながら吹き出て来て、床に落ちるとさながら溶岩のやうに流れていく。
「あっ、あっ、ちょっ、…………そんなに出たら、………あぁ、もう! 」
心百合は急いで詩乃の体から男性器を取り出し床に捨てると、本棚に向かつて流れていく精液を兄の体を使つて堰き止め、ついでにもう殆ど動いてゐない那央を雑巾のやうに扱つて軽く床を拭き、ほつとしたやうに一息ついた。
「まだ出したり無いけど、ま、この辺にしておこうかな。………これ以上は本が濡れちゃう。-------」
続けて、
「なおにぃ、しぃにぃ、起きて起きて、-------」
だが二人とも、上と下の口から白くどろどろとした液体を吐き出し倒れたままである。
「-----ねっ、早く起きて片付けてよ。でないともう一度やっちゃうよ?」
と云つて彼らの襟を背中側から持ち、猫をつまむやうにして無理やり膝立ちにさせると、那央も詩乃も一言も声を出してくれなかつたがやがてもぞもぞと動き始め部屋の隅にある、彼女がいつも精液を出してゐるバケツを手に取り、まずは床に溜まつてゐる彼女の種を手で掬い取つては其の中に入れ、掬い取つては其の入れて"行為"の後片付けをし始めたので、其の様子を見届けながら彼女もウェットティッシュで血やら精液やらですつかり汚れてしまつた肉棒を綺麗にすると、ゴロンとベッドに寝転び、実の兄としてしまつた性交の余韻に、顔を赤くして浸るのであつた。
那央たち兄弟は体中に感じる激痛で立つことすら出来ず、ある程度心百合の精液をバケツに入れた後は這つて家の中を移動し、雑巾を取つて来て床を拭いてゐたのであるが、途中何度も何度も気を失ひかけてしまひ中々進まなかつた。なんと惨めな姿であらう、妹の精液まみれの体で、妹の精液がへばり付いた床を雑巾で拭き、妹の精液が溜まつてゐるバケツの中へ絞り出す。こんな風に心百合の精液を片付けることなど何時もやつてゐるけれども、彼女に犯されボロ雑巾のやうな姿となつた今では、自分たちが妹の奴隷として働いてゐるやうな気がして、枯れ果てた涙が自然と出て来る。-------あゝ、此の涙も拭かなくては、…………一つの拭き残しも残してしまつては、俺たちは奴隷ですらない、人間でもない、本当に妹の玩具になつてしまふ。だがいくら拭いても拭いても、自分の体が通つた場所にはナメクジのやうな軌跡が残り、其れを拭こうとして後ろへ下がるとまた跡が出来る。もう単純な掃除ですら俺たちは満足に出来ないのか。異様に眠いから早く終はらせたいのに全く進まなくて腹が立つて来る。が、読書に戻つて上機嫌に鼻歌を歌ふ妹のスカートからは、蛇のやうに”ソレ”が、未だにビクリ、ビクリと、此方を狙つてゐるかの如く動いてゐて、とてもではないがここで性交の後片付けを投げ出す事など出来やしない。いや、そもそもあれほど清らかな妹にこんな汚い仕事などさせたくない。心百合には決して染み一つつけてなるものか、決して其の体を汚してなるものか、汚れるのは俺たち奴隷のやうな兄だけで良い。-------さう思ふと急にやる気が出てきて、二人の兄達は動かない体を無理やり動かし、其れでも時間はかかつたが綺麗に、床に飛び散つた精液やら血やらを片付けてしまつた。
「心百合、………終わったよ。-----」
「おっ、やっと終わった? ありがとう」
「ごめんな、邪魔してしまって。…………」
「んふ、………いいよいいよ、その分気持ちよかったし。-------」
さう心百合が云ふのを聞いてから、兄二人は先程まで開けることすら出来なかつた扉から出て行こうとする。
「あ、お兄ちゃん、------」
心百合が二人を呼び止めた。そして、
「-----また明日もしようね」
とはにかみながら云ひ二三回手を振つたのであるが、那央も詩乃も怯えきつた顔をさらに怯えさせただけで、何も言はずそそくさと部屋から出ていつてしまつた。
「詩乃、…………すまん。…………」
心百合の部屋を後にして扉を閉めた後、さう那央が詩乃に対して云つたけれども、云はれた本人は此れにも特に反応せず自分の部屋に、妹の精液が入つたバケツと共に入りほんの一時間前まで全ての切掛となつたダンベルがあつた位置に座り込んだ。其のダンベルと云へば、結局心百合の部屋から出る時に那央が持つてゐたのであるが、自室に入る際に階段を転げ落ちてゐく音がしたから多分、兄と一緒に踊り場にでも転がつてゐるのであらう。もう其れを心配する気力も起きなければ、此れ以上動く体力も無い。なのに体中に纏わりつく心百合の精液は冬の冷気でどんどん冷え、さらに体力を奪つて来てゐる。ふとバケツの方に目を向けると、二人の血でほんのりと赤みがかつた妹の精液が半分ほど溜まつてゐるのが見える。-------一体これだけでも俺たち男の何倍、何十倍の量なのであらうか。一体俺たちがどれだけ射精すれば此の量に辿り着けるのであらうか。一体どれほどの時間をかければ人の腹を全て精液で満たすことが出来るのであらうか。しかも此の液体の中では、男の何百、何千倍と云ふ密度で妹の精子が泳いでゐると云ふではないか。…………恐ろしすぎる、もはやこの、精液で満たされぱんぱんに張つた腹が彼女の子供を授かつた妊婦の腹のやうに見えてくる。もし本当にさうなら、なんと愛ほしいお腹なのであらうか。………だが残念なことに、男は受精が出来ないから俺たちは心百合の子供を生むことなど出来ぬ。其れに比べて彼女の子供を授かれる女性の羨ましさよ、あの美しい女神と本来の意味で体を交はらせ、血を分かち合ひ、そして新たな生命を生み出す、-------実の妹の嬲り者として生まれた俺たち兄弟とは違ひ、なんと素晴らしい人生を歩めるのであらう。だが俺たちの人生も丸切無駄では無いはずである。なんせ俺達は未だ生きてゐる。生きてゐる限り心百合に使つて頂き喜んで頂ける。もう其れだけで十分有意義である。詩乃はパキパキと、すつかり乾きつつある心百合の精液を床に落としながら立ち上がると、バケツに手をつけた。
--------と、丁度其の時、妹の部屋の方向から、ガチャリと扉の開く音がしたかと思えば、トントントン…………、と階段を降りていく軽い音が聞こえてきた。さう云へば、ふたなりも男と同じで射精をした後はトイレが近くなるらしいから、階段下のトイレに向かつたのであらう。と、詩乃は思ひながら其の足音を聞いてゐたのであるが、なぜか途方もない恐怖を感じてしまひ、心百合が階段を降りきるまで一切の身動きすら取らず、静かに息を潜めて心百合が戻つて来るのを待つた。----今ここで扉を開けてしまつては何か恐ろしいことになる気がする。…………其れは確かに、今しがた瀕死になるまで犯された者の「感」と云ふものであつたがしかし、もし本当に其の感の云ふ通りであるならば、先程階段を転げ落ちていつた那央はどうなるのであらう。多分兄貴も俺と同じやうに全く体が動かせずに階段下で蹲つてゐるとは思ふが、もし其処に心百合がやつて来たら? いや、いや、あの心優しい心百合の事だし、しかももう満足さうな顔をしてゐたのだから、運が良ければ介抱してくれてゐるのかもしれない。————が、もし運が悪ければ? 此の感が伝えてゐるのは後者の方である、何か、とんでもなく悪い事が起こつてゐるやうな気がする。さう思ふと詩乃は居ても立つても居られず、静かに静かに決して音を立てぬようそつと扉を開けると、ほとんど滑り落ちながら階段を降りて行く。途中、那央が居るであらう踊り場に妹の精液��跡があつたが、兄は居なかつた。でも其の後(ご)もずつと精液の跡は続いてゐたので何とか階段を降りきつたのであらうと一安心して、自身も階段を降りきると、確かに跡はまだあるのであるが、其処から先は足を引きずつたやうな跡であり、決して体を引きずつたやうな跡ではなくなつてゐる。…………と云ふことは、兄はもしかして壁伝いに歩いたのだらうか、------と思つてゐたら、ふいに浴室の方から声が聞こえてきたやうな気がした。最初は虫でも飛んでゐるのかと思つたけれども、耳を澄ますと矢張り、毎日のやうに聞いてゐる、少し舌足らずで可愛いらしい声が、冬の静寂の中を伝はつて確かに浴室から聞こえてくる。そしてよく見れば、兄の痕跡は其の浴室へ向かつて伸びてゐる。------いや、もしかしたら精液まみれで汚れてしまつた那央を綺麗にしようと、心百合がシャワーを浴びせてゐるのかもしれない、それに自分もティッシュで拭くだけでは肉棒を綺麗にした気がせず、もしかするとお風呂にでも浸かつてゐるのかもしれない。…………が、浴室に近づけば近づくほど嫌な予感が強くなつてくる。しかも脱衣所の扉を開けると、ビシュビシュと何やら液体が、無理やり細い管から出てくるやうな音、-----毎夜、妹の部屋から聞こえてくる、兄弟たちを虜にしてやまない"あの"音が聞こえてくる。
「あ、あぁ、…………」
と声を漏らして詩乃は、膝立ちになり恐る恐る浴室の折戸を引いた。すると心百合は其処に居た。此方に背を向け少し前のめりになり、鮮やかな紺色のスカートをはためかせながら、腕を大きく動かして甘い声を出して、確かに其処に居た。-----
「こ、こゆり。……………」
「うん? もしかして、しぃにぃ?」
心百合が此方に振り向くと、変はらずとろけ落ちさうなほど可愛い彼女の顔が見え、そして彼女の手によつて扱かれてゐる、変はらず悪夢に出て来さうなほどおぞましい"ソレ"も見え、そして、
「あんっ、…………」
と、甲高い声が浴室に響いたかと思えば腕よりも太い肉棒の先から白い液体が、ドビュルルル! と天井にまで噴き上がる。
「あぇ、こゆり、………どうして、…………」
「んふ、やっぱり中途半端って良くないよね。もうムラムラしてどうしようも無かったから、いっその事、我慢しないことにしたんだぁ。……………」
其の歪んだ麗しい微笑みの奥にある浴槽からは、彼女の言葉を物語るかのやうに入り切らなかつた精液がどろどろと床へと流れ落ちていつてゐる。……………いや其れよりも、其の精液風呂から覗かせてゐる黒いボールのやうな物は、其れに縁にある拳のやうな赤い塊は、もしかして、-------もしかして。………………
「あ、兄貴、…………」
もう詩乃には何が起きてゐたのか分かつてしまつた。矢張り、良くないことが起きてゐた。其れも、最悪の出来事が起きてゐた。-------射精は途中で無理やり止めたものの合計で四回も絶頂へ達せられたし、其れなりに出せて満足した心百合は、兄たちが"行為"の後片付けをしてゐる最中に読書を再開したけれども、矢張りどこか不満であつたのか、鼻歌を歌ふほど上機嫌になりつつも悶々としてゐたのであらう。何しろあの時妹の肉棒は、惨めに床を拭く俺たちを狙ふかのやうに跳ねてゐたのである。其れで、兄たちが居なくなりやうやく静かになつて、高ぶつた気もついでに静まるかと思つたのだが、意外にもさうはならない、むしろ妹の男性器はどんどん上を向いていく。あゝ、やつぱりお兄ちゃんたちの顔と叫びは最高だつた。あれをおかずにもう一発出したい。………と思つても、兄たちがバケツを持つていつてしまつたので処理をしようにも出来ず、結局我慢しなければならなかつたが其のうちすつかり興奮しきつてしまひ、ベッドから起き上がつて、一体どうしたものかと悩んだ。------いや別に、バケツはあと一つ残つて居るのだから今ここで出してもよいのだけれども、其れだけで収まつてくれる筈がない。お風呂も詰まつてはいけないとお兄ちゃん達が云ふから駄目だし、外でするなんて、夜ならまだしもまだ太陽が顔を覗かせてゐる今は絶対にやりたくない。そもそも外でおちんちんを出して自慰をするなぞ其れこそ捕まつてしまふ。どうしよう。…………さう云へばさつき、さういえば階段からひどい音が聞こえたのは少し心配である。もう二人は歩くことも出来ないのかしらん。可哀想に、歩くことも出来ないなんて其れは、其れは、……………もはや捕まえて欲しいと自分から云つてゐるやうなものではないか。さうか、お兄ちゃんたちをもう一回犯せば良いんだ。どつちが階段を下りていつたのかは知らないが、歩くことも出来ないのだから下の階には二人のうちどちらかが未だ居るはず、いや、もしかしたら二人共居るかもしれない。-------と、考へると早速部屋から出て、階段を下り、下で倒れてゐた那央を見つけると服を汚さぬよう慎重に風呂場まで運んで、そして、----ここから先は想像するのも嫌であるが、心置きなく犯して犯して犯して犯したのであらう。浴室に散乱するシャンプーやらの容器から那央が必死で抵抗したのは確かであり、其れを己の力で捻じ伏せ陵辱する様は地獄絵図であつたに違いない。いや、地獄絵図なのは今も変はりは無い。何故かと云つて心百合のモノは此方を見てきてゐるのである。ビクビクと自身を跳ね上げつつ、ヒクヒクと鈴口を蠢かしてゐるのである。此の後起こることなんて直ぐ分かる。-------逃げなくては、逃げなくては、………逃げなくてはならぬが、心百合がほんのりと頬を赤くし愉快な顔で微笑んで来てゐる。あゝ、可愛い、………駄目だ、怖い、怖くて足が動かない。…………と、突つ立つてゐると心百合の手が伸びてくる。そして、抱きしめられるやうにして腰を掴まれるとやうやく、手が動くようになり床に手を付けた。が、もう遅い。ずるずると、信じられない力で彼の体は浴槽の中へ引きずり込まれていく。どれだけ彼が力強く床に手を付けようとも、どれだけ彼が腰に回された手を退けようとも、ゆつくりと確実に引きずり込まれていく。そして、またたく間に足が、腰が、腹が、胸が、肩が、頭が、腕が、どんどん浴室の中へと入つて行き、遂に戸枠にしがみつく指だけが外に出てゐる状態となつた。が、其の指も、
「次はしぃにぃの番だよ? 逃げないで。男でしょ?」
と云はれより強く引つ張られてしまふと、耐えきれずにたうたう離してしまつた。
「やめてええええええええええええええええええええええ!!!!!!!!!!!!!!!!!」
心百合と云ふたつた一三歳の、未だぷにぷにと幼い顔立ちをした妹の力に全く抗えず、浴室に引きずり込まれた詩乃はさう雄叫びを上げたが、其の絶叫も浴室の戸が閉まると共に小さくなり、
「んふ、………まずはお口から。-------」
と、思はず恍惚としてしまふほど麗しい声がしたかと思ひきや、もう聞こえなくなつてしまつた。
(をはり)
3 notes
·
View notes
Text
『とあるねじれたせかいのものがたり』
一
歪んでる、それが正しい、あの子の世界。
その女の子は、一面が銀色に輝く雪原のはじっこに住ん��いる。剛毛の赤毛に、とろりと溶けるような垂れた黒色の目に短く切り揃えられたような睫毛。同年代の子供で背の順に並べば一番前を陣取るようなこじんまりとした背丈。決して美人とは言えないその女の子は、毎日大きな書庫の隅に置かれた机で本を読んでいた。書庫は壁全体に張り付いているような巨大な本棚をいくつも揃えている。無論壁だけでなく部屋全体に美しく並べられ、その一つ一つが様々な書物でびっしりと埋まっている。思わず前のめりになってしまう胸が躍る冒険譚も、大人でも読むのに苦労するだろう分厚い辞書のような物語も、どこかに住む見たことのない生物が全頁に描かれている図鑑も、幼子も心をときめかせるカラフルな絵本も、彼女の望む全ての本が揃っていた。そこで年がら年中四六時中読書に耽っていた。 女の子はたった一人でその家に住んでいた。丸太で頑丈に造られたその家は、人間だって簡単に吹き飛ばされてしまいそうな猛烈な吹雪にあてられてもびくともしない。数か所に設けられた窓も三重構造になっているから、寒さにも風にも強い。ただ、換気をしようとするときに不便なだけ。 お腹が空いたら彼女は台所へ向かう。冷蔵庫の中身は誰かがこっそり補充しているかのように常に満杯だった。それを女の子は不思議に思ったことはない。今日もまっしろで雪玉みたいな卵を二つ。慣れた手つきで殻を割って、ボウルに落とされるは二つの黄色いまる。いくつかの調味料を目分量で加えてかき混ぜる。これで準備は万端。長方形のフライパンにフライ返しと取り皿を乗せて右手に、ボウルを左手に。小さな両手でたくさんの荷物を引きつれて、煌々と燃える居間の暖炉へと。煉瓦で囲まれた大きな暖炉にフライパンを翳して温めたら、卵を流す。じゅう、と耳に心地良い音。静寂を掻き分けるようなこの音が女の子は好きだった。火力が強いために加減が難しいが、上手く溶き卵をひっくり返していく。慣れた手つきで、あっという間にふっくらふんわり卵焼きのできあがり。まだ熱い間にいただきます。暖炉の前のテーブルに卵焼きと箸を並べて、彼女は手を合わせる。それから箸で卵焼きを裂く。その隙間から、冬に吐きだす白い息のような湯気がもくもくもくと溢れだしてきて、女の子はにんまり笑みを浮かべる。美しい断面図、黄色の層。一口サイズにして口の中に放り込む。控えめな味付けだけど、甘い卵の味がしっかりと口の中いっぱいに染み渡っていった。はふはふと熱さに口の中で卵焼きを転がしながら、それでも我慢できなくて噛んでいく。そのたびに味が広がっていく。卵焼きは彼女が大好きで大得意な料理だった。 満たされたらまた書庫へと戻る。書庫は居間よりも何倍も大きくて、まるで家に図書館が併設されているかのようだった。部屋には真っ赤な絨毯が敷かれ、女の子の平凡な容姿とは裏腹の、どこか高級な気風を兼ね備えている。木製の本棚に並べられた本は乱雑で、高さもまったく揃っていない。それを彼女は気にしなかった。むしろそのざわめいているような雰囲気が彼女にとっては心地良かった。まるで、一人きりじゃないみたいだったから。一冊一冊無造作に読み進めている感覚がたまらなく愛おしかったから。 食事をとる前に読了して机に置きっぱなしにしていた本を手に取り、適当な隙間に押し込める。こうしてまた仲間の元に戻っていく。溢れんばかりの物語の渦に引き込まれて、一つになる。おかえり、ただいま。そんな言葉が聞こえてきそうだった。さよなら、またね。女の子は愛しげに細い指で背表紙をなぞる。心を動かす物語を、ありがとう。 次に読む本を決めていないのが女の子の特徴だ。棚いっぱいに広がっている背表紙の森を眺めて、呼ばれるように一冊の本に指をかける。今日もそうして一つの本棚の前に立ち、黒い瞳で無数の題名を受け止めていく。と、視線の動きが止まる。すぐに書庫の大きな扉の傍まで戻ると、自分の何倍もの背丈のハシゴを手に取った。幼い身体に対してあまりに長く、運びづらい。本棚に這わせるようにゆっくりゆっくり連れて行くと、目的の場所に立てかけた。ハシゴは天井まで突き刺さりそうな高さだった。実際、本棚は丁度天井まで届いているため、そのくらいの高さが無いと意味が無い。女の子はハシゴが安定していることを何度も確認すると、意を決して登っていく。一段一段、丁寧に手をかけ、足をかけていく。いくつもの本を横目にひたすら上へと向かっていき、一番上の段までやってくる。おはよう、よろしくね。手を伸ばして、蜂蜜色のハードカバーの一冊を取り出す。いってきます、いってらっしゃい。そうして森の中で一輪の花を摘む。脇に挟み込むと、行きよりも慎重に降りていく。幸運なことに未だ落ちたことは一度も無いが、足を滑らせれば、ハシゴがバランスを崩せば、小さな命の灯など一瞬で吹き飛ばされてしまうのだろう。それが女の子はどうしようもなく怖かった。油断すると足を掬われる。本が教えてくれたことだ。石橋を叩いて渡るように緊張を保っていくと、気付いたら床に足がついていた。やれやれ、今日も無事に乗り越えられたようだ。女の子は本を両腕で包み込みながら安堵の息をついた。 ハシゴを定位置に戻し、すぐに机へと向かう。窓の向こう側から差し込んでくる白い光を明かりにして、本を前にする。『麦』という余計なものを全て削ぎ取ったような端的な題名。本を開くと、古びた一ページ目が顔を出す。あなたはどんなものをわたしに与えてくれるの、楽しみにしているね。 文字の一つ一つを撫でるように読み進めていく。紙を捲る乾いた音が、大聖堂で楽器を鳴らすように書庫に響く。外界の音は厳重なガラス戸が一寸の漏れなく遮断しているため、その音だけが唯一この家に残された光のようだった。他には何も無い、無音の世界。女の子はそれに寂しさを覚えない。別の世界に心を委ねているから、気にも留めない。 小さな窓の外からの明かりは何時の間にかおとなしくなっていき、文字が読めないほどに暗くなってきた頃に息を吹き返したかのように顔を上げた。架空の世界から現実の世界へと戻ってきた彼女は、余韻に脳が痺れたまま徐に立ち上がる。『麦』に薄い木片の栞を挟み込んで閉じると、机の上に残して彼女は書庫を後にする。 書庫と居間は短く真っ直ぐとした廊下で繋がれている。この家にある部屋は、ベッドが置かれただけの寝室と、台所を取り込んだ居間と、書庫のたった三つだけだった。それだけで彼女には十分だった。 居間の暖炉の前の椅子に腰かけると、女の子は一日を戦いきった後のように長い溜息をついた。息を吐くと同時に、空腹感も増幅してくる。また卵焼きでも作ろうか、それとも別のものを作るかと思案する。妙な倦怠感が全身に覆いかぶさって、なされるがままに彼女はテーブルに伏せる。なんだか、とても疲れていた。『麦』は一人の女の子の生き様を描いている物語なのだが、まるで筆者が直接書いた自伝のような生々しさがあった。他の本とは何か違う。うまく言葉で形容できないのが彼女は非常にもどかしかったのだが、とにかく違う、そんな引力のある書物だった。だからか、いつもよりも余計に力を吸い取られていた。 疲労の海に抵抗なく浸かっていると、彼女はいつの間にか目を閉じ、夢の世界へと旅立ってしまっていた。
二
女の子は、聞き覚えの無い音に目を覚ました。こんこん、と何かを叩いている音だ。硬いその音は小さなものだったが、沈黙を当然とする家を揺らすように響いている。眠気まなこを擦りつつ、女の子は震源を探ろうと周りを見渡す。が、いつも通り暖炉で火が燃えているだけ。部屋の中に特に異変は無い。不思議に思いながら椅子から立ち上がって、耳からの情報を分���して少しでも音が大きく感じる方向へと歩いていく。そうすると彼女は一度として開けたことのない形ばかりの外への扉の前に辿り着いていた。明らかにここから――正しく言えばこのすぐ外から音は発信されている。彼女は木の重い扉の取っ手をとり、力いっぱい引く。びゅおう、と猛烈な風が部屋に吹き込んできて、まだ夢の中にいるような浮遊感が走り去っていった。細めた視界に入ったのは、扉の向こうにいたのは、彼女が初めて見る、彼女によく似た形をした生物だった。 「え……」 一体いつ以来、彼女は声帯をこれだけ震わせたのだろう。小さな感嘆符が零れ落ちて、目の前にいる人物に穴を開けんとしているかのように見上げていた。自分よりずっと大きな体つき。がっしりと肩が広く、闇夜から生まれたかのような真っ黒に染まった服を身に纏っている。男のひとだ、と彼女ははっきりと断言した。何度か見たことがある――それは本が由来だった。本の挿絵で見たような男性像が目の前にリアルな姿として存在している。 男性は女の子より一回り歳を取ったような、しかしまだ活力が十分に身に余っているそんな若者だった。扉が開けられたことに驚いたのか目を見開きながら、雪崩れ込むように女の子の横を擦り抜け、居間へと突入していった。というよりも、倒れ込んでいった。女の子は息を呑む。本を落とすよりもずっと重量感のある音が床を揺らす。女の子は顔を硬直させながら、恐る恐る目の前にいる若者の目を閉じた顔に指先で触れた。まるで雪のような冷たさに指が痙攣する。と、若者の眉間がぐっと歪む。些細な変化にも驚いて女の子は仰け反るが、若者には身体を動かす力も殆ど残されていないらしい。 とりあえず、扉を締めなければ家の中にまで雪が積もってきてしまいそうだった。女の子は若者の足を無理矢理引き摺って家の中に押し込めると、扉を閉める。ずっと使われておらず形式上のものであった外と中の境界線は、錆び付いたように重い。 若者は今にも凍え死んでしまいそうなことは、幼い女の子でもすぐに理解できた。すぐに暖炉の前に連れていて、温めてあげなければ。女の子は小さな身体で若者の体を引こうとするが、びくともしない。彼女が考えていたより人間の身体というのは重い。それでも、何もしないわけにはいかない。彼女はまず吹雪に晒されてしまい彼にかかった雪を叩き落とし、近くにあったタオルで濡れた部分をゆっくりと拭いていく。死人のように青白い顔をしているが、まだ息はしている。彼女は何度も何度も彼の顔を優しく拭いた。目を覚ますのを、じっと待っていた。 その甲斐あってか、しばらくしてから彼の目が薄らと姿を現す。女の子は息を呑み、身を乗り出した。自分と同じ黒い瞳をしている。改めて見ると、逞しいというよりは、優しくおっとりとした印象を持たせる。けれど鼻がぴんと美しいラインを描いており、整っている顔つきだった。若者は現状を理解できず、相変わらず生気が抜けた表情で固まっていた。 女の子は一度その場を離れ、台所へと向かう。慣れた手つきでティーポットとティーカップ、それからハーブを一枚用意する。小鍋に水を注ぐと、暖炉の前へと移動しその火を利用して沸騰を待つ。その間積極的に後ろを振り返り、若者の様子を伺っていた。若者は一応は目を覚ましたものの、凍り付いたような体を動かすことができないでいた。珍しいものを見る目で眺めているうちに、手元のお湯は沸騰する。慌てて台所へと戻ると、ポットの中にハーブを落とし、湯を注ぐ。ハーブの香りが彼女の鼻腔を刺激し、充満していく。心が穏やかになる爽やかな香りだ。ハーブの成分が浸透するのを待つ間に、女の子は若者の傍に戻る。 「……ごめん……ありがとう……」 若者は女の子を視界にいれるや否や、そう彼女に声をかけた。女の子は肩を跳ねさせ、直立する。相手は人間なのだ、喋るのは当然だ。そうと解っていても、胸がどきどきとして、一気に緊張してくる。 凍ったような体を無理に動かそうとする若者を見て我に返った女の子は、急いでその傍に寄る。彼女のか弱い体で若者を支えられようもないが、その健気さに若者は微笑みを取り戻した。力が湧いてきたように、体を引き摺るようにして暖炉のもとへと向かう。ゆっくりゆっくり、時間をかけて、歯をがちがちと鳴らしながら息を切らしながら体の痛みに耐え、炎の前に辿り着いた。そこでようやく、若者は安堵の息をついた。同時に女の子も胸を撫で下ろす。 ふと、ハーブティーのことを思い出し、一目散に女の子は台所に入る。ティーポットからハーブを取り出すと、ティーカップと共に暖炉の前へ戻る。まさか、二つのティーカップを同時に使うときがやってこようとは夢にも思わなかった。床にカップを並べると、ゆっくりとハーブティーを注いでいく。白銀の湯気が空気に溶けていき、同時に昇ってくるハーブの香りに若者の固まった頬は綻んだ。手をついてそこに体重をかけながら上半身を起き上がらせ、彼女からカップが渡されるのを待つ。 女の子は恐る恐るハーブティーを彼に差し出す。 「ありがとう」 先程よりもはっきりとした口調で律儀に若者は対応し、震える両手でティーカップを包み込む。掌から感じられる温もりは癒しそのもの。水面に映る若者の顔は揺れている。端に唇をつけ、少しずつ喉に流し込んでいく。冷えた歯に熱々の紅茶は痛みを呼び起こしたが、すぐにそれは打ち消される。さっぱりとした味わいだった。濃さもちょうどよく、飲みやすい。芯まで冷え込んだ身体に心地良く熱が浸透していくのを感じる。ふと視線を女の子にやると、彼女は黒い目を大きく開けて若者を凝視していた。何故そんなに見てくるのか不思議だったが、やがて気付いたように若者は口を開く。 「……とても、美味しい。とっても」 女の子はぱっと表情を明るくさせた。年相応の愛くるしい笑顔に、若者の心も和らぐ。 それから女の子は思いついたように立ち上がり、台所に戻る。不思議そうに取り残された若者は、きょろきょろと居間の様子を見回す。木造のあたたかい色合いの壁に床。部屋の中心に赤い絨毯が敷かれ、その上にはテーブルに椅子が置かれている。そして、彼の目の前にある暖炉。それだけしかそこには無かった。随分と広いのに、場所を持て余しているようだった。やがて、女の子が戻ってきたのに気が付く。彼女は卵焼きを作る体勢でいた。若者には調理用具の意味が分からず、不審気に眉を顰める。しかし次の瞬間、目の前で繰り広げられる料理に驚嘆せざるを得なかった。自分よりも一回りも小さい女の子が、いとも簡単に美しい卵焼きを作り上げていく。あっという間だった。黄金の輝きと出来たての湯気を放つそれは、若者の萎えていた食欲を刺激した。女の子は箸で一口分に切ると、彼の口の前に持っていった。それは予想だにしていなかった若者だったが、生憎彼の手は箸を器用に扱えるほど回復していない。幼い子供に「あーん」をされるなんて恥ずかしい以外の何物でもなかったが、相手の輝く瞳を見ていては断ることもできない。仕方なく口を開けると、卵焼きが放り込まれる。紅茶のおかげで温もっている口内に、とろりと染み出る素材の甘さ。調味の加減も控えめながら、卵本来の味を引き立てているようだった。たかが卵焼き、されど卵焼き。特に体が弱った彼にとってはどんな高級料理よりも絶品だと断言できた。 「美味しい!」 我慢できず、嬉しそうな声が彼から飛び出していた。一気に元気が湧いてきたかのようだった。 女の子は喜び、次々と彼の口の大きさに合うよう卵焼きを切っていく。 「君は、小さいのにしっかりしているね……お母さんはいないの?」 ようやく思考がはっきりとしてきたのだろう、若者はそう尋ねる。 対する女の子はぽかんと目を丸くする。お母さん、という言葉を噛み砕き、本で読んできた母親像を思い出す。子供を産み、育てる女性。気付いた頃には――最初から一人だった女の子には関係の無い存在だった。結果、彼女は首を横に振る。 「お父さんは?」 彼女の行動は変わらない。 「一人でこんなところに住んでいるの?」 そこでようやく彼女は大きく頷いた。すごいなあ、と感嘆の声をあげる。女の子にとっては当然のことであったから、何をそんなに驚かれるのかよくわからない。 「……俺は柊っていうんだ。外の吹雪に巻き込まれちゃってね……本当に助かったよ、君が出てくれて」 ひいらぎ。女の子は心の中で繰り返した。文字はきっと、柊。木へんに、冬。ひいらぎ。女の子はこの言葉を何度か本で見てきたが、微風が流れるような穏やかな音の響きが快くて、好きな言葉の一つだった。 同時に、優しい声だな、と女の子は思った。低くてしっかりとしているのだけど、鼓膜を撫でるような綿みたいに優しい声だ。きっと、ずっと聴いていても飽きないのだろう。子守唄でも歌われたら、どんなに目が覚めていてもすぐに眠ることができそうだ。それか、聴いていようと夢中になって無理矢理起きているかの、どっちか。 「君の名前は?」 不意に問われて、女の子は思考を停止させる。彼女には名前というものが存在しない。一人で生活し他人とまったく出会うことのない彼女には、必要無いものである。けれど、名乗ったら、名乗り返す。物語ではよくあるパターンだ。このタイミングで言わないのもおかしいだろう。あまり、変な子だと思われたくない。どうしようと考え始めて、最初に出てきた単語をいつのまにか口に出していた。 「……む、ぎ」 「麦?」 拙い声を彼は聞き取ってくれたらしい。女の子は――麦は、大きく縦に頷いた。 麦かあ、麦。いいね、麦かあ。何が嬉しいのか、柊は頬を綻ばせた。本当は先程まで読んでいた本のタイトルから引用しただけの偽りの名前だが、そうやって何度も繰り返されると何故かとても唇のあたりがむず痒くなる。 そこで沈黙���訪れる。柊はハーブティーを口にし、麦は彼の口が落ち着いた頃に卵焼きを差し出した。僅かずつではあるが、彼の胃は満たされていく。幸せを具現化したようなその味に、逐一柊は美味しいと感想を述べた。そのたびに麦は嬉しくなって、他にも御馳走してあげたい気持ちに駆られる。けれどそれ以上に、麦は今、この瞬間を柊と過ごしていたいと思うのだった。初めて出会った人間。心優しい大人。読書からは感じたことのない楽しさに胸が躍っていた。 麦はうまく喋れない子だと柊はすぐに理解した。だから会話といっても基本的に彼から喋り、麦はそれに身振り手振りで返すといった風である。言葉を発するのは不得意だけど、しかし麦は読書で培ってきたおかげなのか頭がいい。柊の言葉をほとんど理解することができたため、不器用なようで、しかし円滑にコミュニケーションがとることができたのである。 「卵焼き、好きなの?」 こくりと頷く。 「俺もまあ、好きだけど、普通って感じかな。でもさ、麦の卵焼きは特別だなあ。俺の母さんが作るものよりずっと美味しいよ」 唇を噛んで、恥ずかしげに顔を俯かせる。 「というか、こんなところに住んでるのによく食材なんて調達できるね。外、かなり雪が積もってるけど」 ふるふると横に振る。 「ん? 雪、得意なの?」 ふるふる。 「んーと……そっか。まあ、どうにかしてるんだよね」 こくり。柊は苦笑を浮かべた。初対面であるおかげでもあるだろうが、無闇に踏み込んでこないのも麦には丁度良かった。 先程の柊の言葉にどう答えたらいいのか、麦には分からない。冷蔵庫に詰め込まれた食材は常に補充されていて、困ることが無い。それが普通だと思っていた。でも、そういえば本の中でも食材を買いに出かけている描写はいくつも見てきた。そういうものなのかもしれない。自分の方が、不思議なのかもしれない。けれど、それを柊に説明しようもない。それに柊はあまり気にしない風にいてくれるから、まあいいや、と流すことができる。 「吹雪、やまないね」 柊は三重に守られた窓の外を見ながら、ぼんやりと呟く。 「今夜中はずっとああなんだろうな」 こくり。 「ごめんね。急に入ってきちゃって」 ふるふる。 「麦は優しい子だな」 ふるふる。 自分よりも、こうして構ってくれる柊の方がずっと優しい。美味しい美味しいと言ってくれる柊の方がずっとずっと優しい。そう言いたかった。 「そこにつけこむようでなんだか悪いんだけど、今夜はここに泊まっていってもいいか?」 こくりこくり、こくり。 勿論です。 力強く何度も頷いた麦に、柊は思わず噴き出した。 「ありがとう。なに、なんか嬉しそうだね」 見透かされたみたいで、麦は隠れるように自分に淹れたハーブティーを口にした。不思議。いつもと同じハーブでいつもと同じくらいの時間だけ浸けたのに、なんだかいつもよりずっと、おいしい。卵焼きはいつの間にか無くなってしまっていた。全部柊がたいらげてくれた。自分の作った料理を誰かが幸せそうにたいらげてくれるのは、こんなにも快いものなんだと麦は知る。 それからもいくつか会話は続いていく。いつもならとっくに夕食を済ませて書庫に戻って読書に耽っている頃だが、麦の頭に読書のことはまるで蝋燭の火が消えてしまったように無くなっていた。夢中になっているといつのまにか時間が過ぎていってしまうのは、読書と同じだった。本が好きなことも、柊に告げた。どんなことが好きか、という問いに対し、ほん、という単語は言いやすいのか、すらりと言うことが出来た。その年で読書家かあ、と柊は笑った。誇らしげな顔で何度も頷く。本当に好きなんだね。その言葉に、強い肯定を示した。どこか誇らしげな顔をしていたのが、柊の瞳に焼き付いた。 本に関する柊からの質問攻めが終わった後、ふと、思い出すように柊は声をあげた。 「そういえば、今日って十月三十一日だっけ」 じゅうがつさんじゅういちにち。何の暗号かと思考を巡らせる。と、思い至る。日付だ。今日という日を定める記号。本の中では時間の動きを明確にするために記しているものもある。麦には日付感覚というものが存在しない。日々同じ時間を同じようにを繰り返すだけなのだ。けれど麦はきっとそうなんだ、今日は十月三十一日なんだと思い込み、彼の言葉を肯定する。そうだよね、うんうん、ああ、でも。柊は顔を顰めた。些細な表情変化にすら、何か悪いことをしただろうかと麦は怯えてしまう。返答が良くなかっただろうか。肯定してはいけなかっただろうか。 柊には麦の動揺が伝わったらしい。 「いやさ、折角のハロウィンだっていうのに、俺お菓子もなんにも持ってないなーって思って、なんか申し訳ないや」 ハロウィン? 麦は光の速さで頭の中の辞書を捲っていく。が、その単語は彼女の聞き知らぬものであった。本でもそんなものを題材にしたものがあっただろうか? 忘れただけだろうか。いくら卓越した読書量を誇る麦でも、読んできた本以上に読んでいない本がまだ途方も無いくらい多いのだから、知らないものがあってもおかしくはない。そう自分に言い聞かせながらも、やはり気になる。 「というか、今回の場合俺が家に訪問してるし、なんか何もかもかっこつかないなあ。うーん情けない大人だ」 柊が何を言っているか、さっぱり解らない。必死に理解しようと脳をフル回転するものの、結果は良くない。白旗だ。お手上げだ。 そんな麦の様子を敏感に察した柊は、首を傾げた。 「ハロウィン。……Trick or treat」 流暢な英語が彼の口から滑るが、彼女は顔をぽかんとさせたままである。今までなんらかの返答をしてきた麦が、初めて見せた「わからない」だった。 「トリックオアトリート。知らないのか?」 「とり……」 「トリック、オア、トリート。お菓子をくれなきゃいたずらするぞ、っていう意味」 麦の表情は相変わらずである。 本当に分かってないんだなあ、と柊は微笑を浮かべる。 「子供は今日、十月三十一日――ハロウィンの夜、一軒一軒家を回って大人にそう言ってお菓子をねだるんだ。愉しいお祭りだよ。子供の持てる小さな鞄いっぱいに美味しいお菓子を詰めるから、その後毎日お菓子を食べられる。やっぱりお菓子って、子供にとっちゃ宝みたいなものでしょ」 麦は頬を紅潮させて、やや興奮気味に頷く。なんだかよく分からないけど、しかしとても魅力的な話だった。あまーいお菓子を貰いに、人々に出会っていく。そしてきっと、後で毎日大切に大切に消費していくのだ。お祭りというその言葉の響きだけでもわくわくさせられる。 「とり、あー……」 麦は頑張って発音しようとするが、理解してもいない単語を放出するのは、彼女にはあまりにも難しい。 「トリック、オア、トリート」 「とり、おあ」 「トリック、オア」 「とりっく、おあ」 「そうそう。トリック、オア、トリート」 「とりっく、おあ、とりーと」 「おおっいけたね! でもごめん俺、お菓子が無いんだよ。いたずら確定だ」 けらけらと笑う柊だったが、麦は慌てて否定する。いたずらなんて、できっこない。根気強く自分のペースに合わせてくれるこの人に、危害なんて与えられるわけがない。麦の必死な様子を見ていると、柊は穢れなき穏やかな気持ちでいられた。 「……もう俺はそんなのをする歳じゃないけど、麦なら余裕だなあ」 しみじみと、水が布に浸透していくような静かな言い方。 淋しそうな表情だな、と麦は思った。きっとこの人は、大人になってしまい、戻れない子供だった時代に恋い焦がれるような思いに晒されているのだ。懐古の思いにとらわれて苦しむ人の物語を、麦はいくつか目にしてきた。この人もきっと、同じなんだ。 「……麦は外にはいかないのか?」 その問いに麦は首を横に振って応える。そっか、と柊は目を俯かせた。 「そっか。それならハロウィンを知らないのも納得かな……でもさ、それって、淋しくはないか?」 少し間を置いて、再び麦は首を横に振った。淋しくはない。いつも彼女の傍には身に余る本がある。本が友達のようなものだったから、飽きることも淋しくなることもない。そういった感情をまったく持ち合わせたことが無かった。 「でもやっぱり、勿体ないよ。こんなとこにたった一人で住んでるなんて、可哀そうだ」 可哀そう? 何が可哀そうだというのだろう。彼女はここでの生活を受け入れ、満足していた。その気持ちは真実そのものである。それなのに柊はなんだか憐れむような目で麦を見つめてくるのだ。ハロウィンを知らない彼女を、他人という存在に疎い彼女を、本に囲まれ幸せである彼女を、可哀そうだと。 「俺さ、今の吹雪が止んだらここを出ていくから、試しでさ、一緒に外に出てみないか?」 誘い。 一瞬だけ、ほんの少しだけ、彼女の心が揺らいだ。彼は、いずれこの家を発つ身。ここに留まってほしいなんて、彼女は言えない。幸せな時間は終わってしまう。それはきっとそう遠くない。でも、行ってほしく���い。なら、彼についていくという案はひどく魅力的なように思えた。 その瞬間、脳を突き刺す痛みに顔を歪めた。だめ、と強く叩かれたかのようだった。だめ、ダメ、駄目。そんな声が聞こえてきそうだった。麦はまた首を横に振る。否定。拒絶。行かない。行っちゃいけない。理由は解らないけど、自分はここに居なくちゃいけないから。誰にも教えられていないけど、それは使命であり運命であるかのように麦の中に元来根付いていた。 「……麦?」 優しい声。麦を癒してくれる音。 「大丈夫か、なんだか顔色が急に悪くなったけど」 平気だと返事しようとしたが、秒を追うごとに痛みが酷くなっていくようで、麦は頭を抱え込んだ。頭のはじっこが、熱い。ずきんずきんと痛んで、苦しい。耐えられなくなって、遂に前のめりに倒れ込んだところを、柊の温かくなった身体が難なく受け止めた。なんて力強く頑丈な胸板だろうか。ひ弱で幼い自分の体とはまるで別物だった。麦は彼の大きな腕の中から、恐る恐る彼の顔を覗き込んだ。さっきよりずっと近いところで、柊は変わらぬ笑顔を浮かべていた。 「疲れたんだね。ごめん、変なこと言って。今日はもう休んだ方がいい。寝室はどこ?」 嫌だ、もう少し、話していたい。麦の本音はそうだった��、その欲がはっきりと彼女の心に浮かびあったとたんに、打ち消すように大きな響きが頭を支配する。痛い。やめて。益々苦痛に歪んでいる様子は、柊を戸惑わせる。その顔が、決定打だった。もう終わりだ。困っているのに、我儘は言えない。 麦は項垂れ、暖炉の左奥にある扉を指差した。寝室のある部屋なのだと理解し、柊はぐったりとしている麦をおぶると、彼女の寝室だという部屋へ入る。扉を開くと出窓に置かれた蝋燭が部屋を照らしている。一見あまりにも儚く不十分な光のようだが、この部屋はとても狭く、ベッドしか置かれていない。読書灯としての役割を果たせていれば十分なのだろう。柊は皺無く整えられた布団を捲りあげ、頭痛に苦しむ麦をあまり揺らさないようにゆっくりとベッドに座らせる。頭に手を当てたまま人形のように動かない麦を見て、柊は仕方なさそうに腕を伸ばす。麦はとても、軽い。いとも簡単に持ち上げることができる。背中と足を包み込むように持ち上げて、麦の身体を布団の下へと滑らせる。ようやく横になった麦にふかふかの布団をそうっとかけると、彼女の臆病な顔だけがよく見えた。愛玩動物を扱うのと同じような要領で柔らかい赤毛を骨ばった大きな手で撫でると、麦の表情は不意に綻んだ。 「……ひい、らぎ」 あまりにも拙い声だ。言葉を口にするというその行為自体に慣れていないことがあまりにも分かりやすい。 「ひいらぎ」 彼の名前を呼ぶ。 「ひいらぎ、ひいらぎ」 何度も呼ぶ。 「ひいらぎ、ひいらぎ、……柊」 何度も、何度も呼ぶ。 どうして名前を連呼するのか、それになんの意味があるのか読み取れず、ただ単純に恥ずかしくなって柊は目を逸らす。それは、先程自己紹介をして、柊が何度も彼女の名前を呼んだ時と同じような光景だった。 「ほら、頭痛いんだろ。ゆっくり休んで、明日も本を読むんだろ」 柊は身を乗り出し、出窓にある蝋燭を吹き消す。居間から零れてくる光だけが寝室を照らしているが、麦の視界では一気に柊の顔は逆光で闇に塗りつぶされてしまった。それでもなんとなく感じ取れるのだ。暗闇の中で、彼が穏やかな笑みを浮かべている。彼女の目には鮮明に柊の表情が映っていた。 「おやすみ」 軽くそう声をかけると、柊は麦に背を向ける。居間に足を踏み入れると、音を立てないようにそうっと慎重に扉を閉めていく。光の線がどんどん狭まっていく。完全に消えて無くなってしまうその瞬間まで惜しむように、麦は瞬きもせずに目を凝らし続けていた。
三
柊の足はこの家において一番の面積を占める書庫へと向かっていた。他人の家を詮索するのはよくないと分かっていながらも、明日にでも発つ身だ。その前に、麦の生活の全てだという読書の間を一目見てみたかった。居間から続く廊下を歩くとすぐに突き当りに辿り着く。そこに佇んでいる重い扉を開くと、柊は思わず息を止めた。 点けたままにして放置されていたのか、待ち受けていたように淡い黄金の電灯が照らしている中で、二階分に相当するだろう天井の高さまで伸びた本棚が数十と並べられ、それを余すことなく本が埋め尽くしている。書物が生み出す独特の渇いた匂いで部屋が満ち満ちており、明らかに居間や寝室とは別格のものであると確信した。扉を閉めると、柊は一人穴に突き落とされたような気分にさせられた。圧倒されているのだ。シックな色合いの真っ赤な絨毯は柔らかく、足音はいとも簡単に吸収される。どこか高級感を思わせる厳格な色合いの部屋だが、柊は同時に不気味さも抱える。これだけ大量の書物がどうして周りに何も無い雪原にあるのだろう。いくら一日の大半を読書に費やしているといっても、一生かかっても全てを読破するのは無理ではないだろうか。 柊は棚に並べられた本の群を眺める。高さがまったく揃っていない様子は、整理整頓に関しては麦が無頓着であることをそのまま示している。殆ど物が置かれていない居間や皺のまったく無かったベッドの置いてある寝室を思い返すと、どこかが僅かにずれた不協和音のようだった。何か知っている本でもないものかと探してみるが、彼の知らないタイトルばかりだった。読むのが億劫になりそうな固い雰囲気のものもあり、自分よりずっと小さな麦がこのような本と日々向き合っているのかと思うとただ圧巻されるばかりである。言葉を知らない幼子のように見えていたが、実は途方もない量の知識を溜め込んでいるのではないだろうか。むしろ何故ハロウィンを知らなかったのかが益々疑問である。 ぼんやりとした調子でいると、やがて窓に面した古い机に辿り着いた。机の上には、小さなランプといくつかの辞書、そして栞を挟んでいるところから読みかけであると思われる蜂蜜色のハードカバーの本が一冊、椅子の前に置かれていた。薄らいだ表紙の文字に目をやると、『麦』と書かれていた。彼女と同じ名前の題名だとまず思った。だから彼女は手に取ったのかもしれない。自分の名前と同じ作家はそれだけで何故か親近感が湧いたり、気になったりするのと同じことだ。なかなか可愛らしい人間味のある麦の一面をこっそり垣間見て、まるで夜の学校にでも忍び込んでいるような不思議な緊張と高揚で満たされる。 しかし、そこで柊は気が付いた。この本には著者名が明記されていないのだ。表紙にも、背表紙にも、そして表紙を捲った一ページ目にも無い。当然のように『麦』というその一文字だけが印刷されているだけ。不審に思った柊は、『麦』を手に取ったまま、周囲の本棚にしまってある本を確認する。さすがにハシゴを使って上まで確認しようという勇気は湧いてこなかったが、歩き回ったところ、殆どは著者がはっきりと書いてある。殆どは、だ。片手で数えられるほどだが、『麦』と同じように著者名が載っていない本も存在していた。そしてそれらは決まって蜂蜜色のハードカバーの本であった。そういうシリーズなんだろうかと考えるものの、なんとなく納得がいかない。何故だろう、気味が悪い。得体の知れない空気がこの図書館のような書庫全体に漂っていた。誤魔化そうとしていても拭い切れず鼻につく臭いのよう。 そうして『麦』に視線を落としている時。 唐突に、書庫を照らしていた光が、全て消え去る。 柊はハッと視線を上げた。しかし一点の光も無く真っ黒に塗りつぶされた視界では何も捉えることはできないし理解することもできない。急に奈落の底に連れて行かれたかのようだが、手を伸ばすと傍に本棚があり、場所は変わっていないことを確認する。 が。 ふわり、と、薄いシルクの布のようなものが、本棚についたその彼の左手に覆いかぶさる。 ぞわりと柊の全身に猛烈な寒気が迸り、反射的に腕を引いた。今のは一体なんだった? 一体自分の身に何が降りかかった? 真っ暗闇の視界では皆目見当がつかず、恐怖が一気に増幅されていった。本棚に触れてはいけないとそれだけは把握し、柊は逃げるようにその場を離れる。方向感覚はまったく正常でないが、立ち止まっていられるほど悠長で鈍感な精神を持ち合わせてはいない。もがくように動き回っていなければ誤魔化せない。とにかくまずは明かりを点けなければ。入ってきた扉は、どこだ。本棚と本棚の間を走り抜けていくと、彼は出入り口ではなく麦の机の前に辿り着いていた。夜中だが、窓から零れてくるのは雪の光か、ほんの僅かだが青白い光が注がれていた。時を経て暗順応が機能してきたこともあり、闇の中でも視界が安定してくる。彼は焦燥に肩を激しく上下したまま、ゆっくりとその場で振り向いた。 身体が固まる。 塗りつぶされた暗闇の中で、更に濃い影が、黒い本棚から染み出るように蠢いている。ふわりふわり、海月のように、微風に揺れるカーテンのように、生きているように、湧き出ている。異形が、異様な風景を作り上げ、彼を闇の底へと誘う。それが一体なんなのか、柊にはまったく理解することができない。動揺に眼が眩んでいるが、彼の頭に響く危険信号が戻ってはいけないと叫んでいる。単純な生理的拒絶。あれは、触れてはいけない。そう確信した瞬間、足が竦み、いよいよ彼は身動きがとれなくなってしまった。 と、さわ、と何かが鼓膜を擦る。耳元で吐息を吹きかけられたようなこそばゆさに、神経が極限まで逆立っていた柊の体は反射的に仰け反った。あの影がすぐ近くまで音も立てずに忍び寄ったのかと危惧したが、少なくとも自分の手の届く範囲には見当たらない。なら、なんだったのか。柊は耳を守るように手を翳して、震える息で耳をすました。戸の隙間からそっと暗室を窺うように、心の準備をしながら感覚をとぎらせてみる。さわ、さわ。さわ、ざわ。鼓膜が揺らぐ。全身に鳥肌が立っていくようだった。囁くように鳴いているような何かは、誰かの声。 にん、げんだ。ふふ。さわざわ。に、んげん。ふふ、ひい、ぎ、ら、ひい、らぎ、うふふ。まよ、って、あは。ひいらぎ。 靄のような雑音が混ざったたどたどしい言葉。何かに引っかかっているような、壊れたレコードのような音。柊は無意識に、あまりにも不器用でたどたどしい麦の声を連想した。違う。彼は即座に否定する。これは麦の声じゃない。彼女はもっとあたたかい色を帯びている。浅はかな自らの想像力に感じるのは、麦に対する後ろめたさ。 ――ニンゲン。 霧雨のようなざわめきに圧し掛かるようにあまりにも唐突に、どこからか、ぐんと低く鉛のように重い脅すような声が響く。 耳を包み震えていた柊の手が、萎縮のあまり硬直する。 ――人間……人の魂。 ――僅かな綻びから穢れた足で踏み入った、愚かな人の魂。 何かがこそこそと発している囁きと違い、この低い声は投げかけてきているのか明確に聞きとることができた。しかし、その声が何を暗示しているのか、やはり柊にはすぐに理解できなかった。少なくとも分かるのは、脳内に直接語りかけてくるその声は、はっきりと聞き取れる代わりに頭を痺れさせるような残響を以て抉ってくるということだ。 ゆらりゆらり本棚を揺蕩う影。段々と成長しているかのように伸びている。まるで深海で揺れる海藻のよう��った。 ――此処は唯一であり、何とも交わらぬ世界。貴様のような者の踏み入れて良い領域ではない。故に排除する。 突如として突き出された宣告を柊は瞬時に反芻し、大きく目を見開いた。 「!? 排除って……どういう……!」 動揺と畏怖が混ざり合った震えた声で、柊はどこから発しているかも分からない声に向かって戸惑いをぶつける。 「なんなんだ、さっきからわけがわからないことばかり……ここは麦の家だろう。俺は吹雪で迷い込んできただけで……!」 ――ならば貴様に問う。貴様、何故ここに入った。 「何故って」 すぐに言い返すために柊は自分という存在を顧みようとした。しかし彼の脳内に浮かんできたのは、いつしかの思い出でもここに至る映像でもなく、新品のノートのように美しくまっさらでまっしろな記憶だけだった。 あれ。 そういえば、俺はどこから来たんだ。 俺は、どうして吹雪の中にいたんだ。 卵焼きを作ってくれた、母さんってどんな顔だったんだ。 ハロウィンの記憶は、一体どこで誰と紡いだ記憶なんだ。 何も覚えていない。 まっさらでまっしろで、なにもない。 俺は一体、なんだ。 ――貴様は迷い彷徨い続け、最早藻屑に等しい魂。それ故にこの世界に繋がる僅かな隙間を抜けてきたのだろう。自分でも気が付いていないとは、なんと滑稽で愚劣なことか。 呆れたような声が収束するや否やくすくす、と嗤う声が大きくなった。子供や、女や、男、或いは全く別の生き物の、様々な声が折り重なって、柊に降り注いでくる。全身の毛を逆立てる、声の群集。耳元から聞こえてくるようにも、遠くから聞こえてくるようにも思われる。 明らかに自分の感覚がおかしくなってきている。柊は塞ごうとしても使い物にならない手を胸に当て、振動する深呼吸をした。とりっく、おあ、とりーと。極限状態で、麦の言葉が蘇る。まったく、これはいたずらどころの話ではない。なんてハロウィンだ。 ここは、危ない。逃げなくてはならない。しかし、どうしたらいい。外は夜、加えて荒れ狂う猛吹雪。窓を開けて外に出たところで、逃げることはできるかもしれないが別の危険が牙を向けて立ちはだかっている。そもそも、厳重な三重の窓を悠長に一つ一つ開けていられるような余裕などない。ならば、この道をまっすぐ走り抜けるか。出入り口に向かって影に捕まらず逃げ切ることができるか。彼は速まる鼓動を胸に、なるべく冷静になれと自分に言い聞かせる。パニックになってはいけない。先程まで自分の歩いていた書庫の道を本棚の配置を頭の中に描け。最初来てから、この机に至るまでの道順、方向。思い出せ。組み立てるんだ。 ――塵如きが神体に触れるなど、余計な知識を与えるなど、決して許されぬ。 神体? なんの話だろうか。 惑わせられてはならない、耳を傾けてはならないと思いつつも自然と柊の思考は傾いていく。だが、塵という単語が自分を指しているのは流れで汲み取れたが、そうなれば自分が触れたという神体というのは、人間とは相容れぬ存在であろう存在というのは、まさか。 ――身を以てその愚行を恥ずべし。 「待て! 麦が……麦が神様って、どういうことだ!?」 思い当たった答えはほぼ確信。しかし麦という幼い少女と神の称号はあまりにも彼には不釣り合いなように思われ、当たって砕けろとも言わんばかりに叫んでいた。同時に、自分を殺そうとする相手を引き留める、時間稼ぎでもあった。なんでもいい、生き延びるために、崖に手で掴まっているようなぎりぎりの状態を少しでも延ばすしかない。 「麦……麦は……」 狼狽えた声で、場を繋ごうとする。その最中、彼の中で渦巻いていたものがゆっくりと顔を出す。短時間にして、麦と、麦の家に対する抱いた謎、疑念。これは、この声は、恐らくこの家の鍵となる何か。麦を取り巻く異変の理由を知る何か。いや、もしかしたら、真実そのもの。そう考えたら、止まらなくなる。 自身の記憶には無くとも、彼は、元来好奇心に魅せられると、夢中になって身を捧げる性をもっていた。純粋な、真実への拘り。それが柊という魂の性であり、本質であった。自分で気付かぬほど既に柊自身がひどく歪んでいても、揺らぐことなく彼の中に在り続けていた。 それが彼を、突き動かしていく。 「というか、麦はどうしてこんな人里離れた雪原に住んでいるんだ。たった一人で、あんなに小さい子供がどうして生活できている」 「外に出たことがないというのに、どうして切らすことなく食べ物が用意されているんだ」 「汚い話だけど、便所も無かった。風呂も無い。居間と、寝室と、この書庫。この家自体、広い割に生活するには決定的に欠けている」 「どこから電気が通っている。どうして暖炉の炎は消えない」 「一生かかっても読み切れないだろう大量の本は、一体誰が、どうやってここに押し込めたんだ」 「麦はこの家からどうして外に出たことがないんだ」 「一体ここはなんなんだ。麦は一体――なんなんだ」 柊の口からは、短時間にして溢れ出てきた疑問――この空間、麦の世界の歪みを問う言葉が自然と溢れ出ていた。おかしい。何もかもが、おかしい。得体の知れない、理由が見えない歪に柊は気付かぬはずが無かった。ただそれを、麦に直接言及することが躊躇われただけで。 歯を食い縛り、影の返答を持つ。その沈黙が、切迫した環境下にある彼には異様に長く感じられた。 ――神は、此処に存在している、其れこそが力。其れこそが世界。 ――外界に触れること、あってはならない。他に意志を向けてはならない。 静寂。 まともな返答にもなっていない。ただぼやかしているだけ。 『麦』が彼の手から滑り落ちる。挿まれていた栞は衝撃のままに飛び出し絨毯の上に転がり、乱雑に開かれたまま本は静止する。未だ止まらない嗤い声と誰とも知らぬ低い声を遮る音は、絨毯でも吸収しきれない。 柊の拳は震えていた。恐怖とは異質の、胸の奥から競り上がってくるどろどろと混濁した感情だった。麦の淹れてくれた心も体も温まるハーブティーの味が、ふんわりと甘い卵焼きの味が、まだ口の中に残っている。ハロウィンの話を身を前のめりにして耳を傾けている映像はまだ新しい。外に出ようと試しに誘ってみたものの、拒絶と共に苦しげに歪めた表情は切実で、痛みが直に伝わってくるようだった。あまりにも軽い身体を持ち上げた時の感覚は忘れない。自分の名前を何度も何度も呼ぶ、嬉しそうに呼ぶ、その声が、耳に残っている。最後に見せた精一杯の微笑みが、目に焼き付いて離れない。麦は良い子だった。可愛らしく愛らしい、不器用な女の子だった。吹雪で荒んだ自分の体と心を一瞬で溶かしてしまう、そんな力があった。 彼女は何か理不尽なものに捕われているのではないのだろうか。ここに閉じ込められ、それに本人すら気が付かぬまま、時を過ごしている。この家で彼女を見張る、この得体の知れない影が、彼女を縛っているのではないだろうか。 だとしたら、なんて歪みだろう。 「そんなの、間違っている」 正しさを望む柊は断言した。影を真っ向から否定した。 「外を知ってはいけない? そんなの、ただの監禁じゃないか。あんな小さな女の子を閉じ込めて、一体どうしようっていうんだ」 ――つい先程迷い込んできた歪み如きが、解ったような口をきくか。貴様は何も理解していない。実に愚かしい。 「何が理解だ。そっちの都合なんて最初から解ってやるつもりもない」 ――余程魅せられ心を奪われたか……仮にも魔除けの力を持つ名を持っているというのに。貴様のような者の身勝手な甘言が神体を壊すことに繋がるとも知らないで、平和なことよ。 「壊す……? 麦を苦しめているのは、あの子の世界を歪めているのは、お前達だろう!?」 ――嗚呼、実に憐れ。強情は若さ故か。貴様の言うかの苦しみは貴様等のような者が生み出すのだと、解らぬとは。 影の声が明らかに増幅し、苛立ちを部屋中に吹雪の如く降り注いだ。 本棚から溢れる影の成長速度が突如加速する。恐怖が一抹も無いというわけではない。だが、柊の中にある柊の正義が、勇気が、怒りが、拘りが、彼を奮い立たせる。怖がってはいけない。麦を連れて今すぐにでもここから出ていこう。外の世界に連れ出そう。一刻も早く、彼女を呪縛から解き放たないと。こんな危険で歪な場所に彼女一人を置いていけるはずがない。 柊は遂に走り出した。頭に描き抜いた地図を信じ、唯一の光源である背後の窓から離れ、真っ赤な絨毯を勢いよく蹴り、真っ直ぐ本棚と本棚の間の道を抜けていく。瞬間、見逃すはずもなく影が彼を掴みとろうと一気に手を伸ばす。彼は自分の中から湧き出てくる力に驚きすら感じていた。今なら全てを弾き飛ばせそうだった。肌に一瞬で鳥肌を立たせるような気味の悪い影が触れようとしても、まるで何かが柊を守っているかのように弾き返す。擦り抜けていく。行ける。逃げ切る。逃げ切って、麦のあの細い手をとる。この家を飛び出て、彼女を解放する。きっとそのために自分はここに迷い込んできたのだ。 途中で道を左に曲がる。そして真っ直ぐいけば出入り口が待っている。鍵がかけられるような仕組みにはなっていなかったはず。このまま突入するのみ。この書庫から出ることさえできれば、恐らく勝ち。 しかしその直後のことだ。彼のその数歩先で、とてつもない雪崩れが転がり込んできたかのような壮絶な音が響いた。柊は目を見開き、急ブレーキをかけた。暗闇の中でも分かる。あまりに背の高い本棚に詰め込まれた大小色とりどりの本が濁流の如く彼の前で転がり落ちたのだ。いっちゃだめ、いっちゃだめ。そう言っているかのように。茫然とその様子を柊の瞳は捉える。彼は大量の本が無造作に積み重なっていく様子を見守る他無かった。彼女の拠り所である本ですら敵と化すのか。文字通り本の山に行く手を一瞬で���まれた柊に残されるのは、勇気でも、怒りでも、恐怖でもなく、何も無くなり、絶望が顔を出す。 動揺は停止を呼んだ。柊の思考は鈍り、その隙に彼の身体を掬うように影が纏わりついてきた。我に返りそれを解こうと身を振るった柊だったが、次々に容赦なく襲い掛かってくる影の布は、最早小さな彼ひとりで対処できるレベルを超えていた。柊を守っていた何かは、もう息を引き取ったかのように機能しない。隙間無く柊を蝕もうとするように影は巻き付いていく。豪速で体中の隙間から柊の体内に侵入して、息の音を止めていく。筋肉は痙攣して、ぴくりとも動けなくなる。形すら残すまいとするように、外から内から喰われていく。黒に蝕まれていく。暗闇に取り込まれていく。影に成り果てていく。 圧倒的な力を前に、成す術もない。 声は聞こえない。 在るのは、沈黙のみ。
四
朝。麦は平凡な一日の始まりに、すぐに異変を察知した。 彼が居ない。昨夜ここに訪れた、柊が居ない。本来なら柊の方が異変であったはずなのに、麦にとっては今のこの状況の方が非日常であるかのようだった。 いつもと変わらないはずの居間はやけに静かだった。やはり柊の姿は見当たらない。まるで昨夜のことが全て物語のように架空の世界で、自分の妄想が創り出した嘘の産物のように思えたが、それにしてはあまりにも実感として強く彼女の中に残っている。彼の声も彼の力強い腕も、麦自身がよく覚えている。麦は真ん中のテーブルに目を留め、唾を呑んだ。二つのティーカップと小皿。嘘なんかじゃない。確かに柊はここに居た。ここでハーブティーを飲み、卵焼きを食べたんだ。美味しいって何度も笑ってくれたんだ。 柊の姿を求めて、彼女はこの家のもう一つの部屋である書庫へと向かった。黄金の光に照らされた本の森は、いつものように高さの揃っていないまま佇んでいる。日常そのものの形を保っている。歩いて見回ってみたものの、柊の姿は塵も見当たらない。読書の定位置である机の近くまでいくと、ふと外の吹雪が止んでいることに気が付いた。吹雪がやんだら出ていくと言っていた。もしかしたら、直接別れを告げるのが気恥ずかしくて、麦に何も言わずに勝手に出ていったのかもしれない。今まで読んできた文章の中で、あのくらいの年頃の男性がそうやって一人で旅に出ていこうとする描写があった。所詮、数時間だけの付き合いだ。そのくらい呆気ないものでも仕方が無いかもしれない。けれど麦は淋しかった。……そう、とても、淋しかった。彼女は自分で自分に驚愕する。そうか、これが淋しいという感覚なんだ。理解し、痛む胸を手で押さえる。柊は、ひどい。私を置いて、さっさとどこかに行ってしまった。もっと沢山お話をしたかったのに。もっと一緒に居たかったのに。 と、麦は足元に『麦』が落ちていることに気が付いた。栞が飛び出して、どこまで読んだか分からなくなってしまっている。そっと拾い上げてぱらぱらとページを捲るものの、まるで情報が頭に入ってこない。こんな感覚は抱いたことがなかった。こんな風に文字をぞんざいに扱ったことは、一度も無かった。麦は『麦』を閉じる。栞を机の上に置き去りにして、出入り口へと向かった。『麦』を取ったときと同じように本を脇に挟んで、ハシゴを移動させる。頭痛からは解放されていたが、身体がやたらと怠い。のろのろととある本棚に立てかける。それは『麦』の入っていた棚だった。読み切っていないが、とても今は続きを読もうと思う気分じゃなかった。どんなに難易度の高い本でも辞書を駆使して何日もかけて読破するのが信条であったのに、それを覆す行為である。この二日で、彼女にはあまりにも「初めて」が多すぎた。きっと麦は自分の心を制御できないでいるのだろう。 ハシゴを一段ずつ登っていく。自分の体重に震えるハシゴを伝い、確実に上へと向かっていく。麦の瞳はぼんやりとしていて、何かをきっかけに落ちてしまいそうな足取りだった。やがて『麦』があったところまできて、彼女は蜂蜜色のその本を適当に戻した。ごめんね。彼女は謝るしかなかった。ごめんね、ごめんね。なんだか涙が出てきそうだった。経験したことのない感情、途中で投げ出してしまった後ろめたさ、柊の声。いろんなものが彼女の中で渦巻いて、いつもなら耳に届いてくる本の声もそっぽを向いたかのように聞こえなくて、まったく訳が分からなくなる。 彼女はまた少しずつ降りていく。 荷物が無い分、帰りの方が楽だ。 それで視界が広がっていたのだろうか、彼女の目に、とある蜂蜜色のハードカバーが映る。 テンポ良く動かしていた足を彼女はふと止めた。 その本から目を離せなくなった。心が奪われてしまった。 題名を――『柊』。 著者名は、無し。 麦は無意識に手を伸ばしていた。そうすれば、届く距離だった。 指先に本が触れる。古くなった『麦』と違って、まだ真新しい触感だった。それを引き抜こうと、体重を寄せる。 バランスが崩れる。 身体が空中に投げ出される。 油断をすれば、足を掬われる。 本と共に、『柊』と共に、落ちていく。
赤毛が更に紅く染まっている。色鮮やかな赤ずきんを被っているように頭は真っ赤。頭だけじゃない、全身が強���打ちつけられ、止めどなく血が彼女の体から抜けていく。 真っ赤な絨毯とまったく同じ色。 柔らかな毛は麦の鮮血を吸っていく。色は上塗りされていく。
書庫に潜むそれは思った。 ――嗚呼、これで、幾度目だろうか。 と。
『柊』から影が伸びる。 優しく、柔らかく、彼女を抱きしめた。
五
朝。女の子は目を覚ました。 彼女は毎日読書をしていた。居間に並列している図書館のような書庫は、天井まで突き抜けんとする本棚がいくつも並んでいて、その一つ一つに本が所狭しと並んでいる。無数にある物語に身を委ねるのが好きだった。彼女はそれだけで満足できた。他には何も望んでいないし、望もうともしていない。ただ、目の前にある、この大量の書物を読み進めていくことこそ、生き甲斐そのものだった。 ずっと読み続けてもきっと永遠に読み切ることができないその本の森が、彼女を縛り続ける。彼女をここに留まらせ続ける。
ここに存在することこそが力。ここに留まることで、世界を保つことができる神様。外へ出ていけば、世界は消えてしまう。同時に神様も消えてしまう。神様が世界であり、世界は神様そのもの。だから、彼女はここに生きる。害をなす可能性は全て淘汰された世界で、自分でも理解せぬままにページをめくる。たとえ死んでも、また生まれる、神様の入った仮初めの身体で。 そうして世界は永遠に保たれるのだ。
歪んでる、それが正しい、あの子の世界。
歪んでも、それに気付かぬ、あの子の世界。
彼女は今日もその世界で、本を読む。
了
お題:本の高さが揃ってない本棚、ハーブティー、卵焼き、ハシゴ、ハロウィン、赤ずきん
作成:2014年10月
0 notes
Text
鎮寒
ずっと埋もれていた。雪の中に。大粒の雪の降る日だった。長時間の昼夜交代勤のおかげで体とメンタルはぼろぼろになり、車を駐車場に停めワイパーを上げて家まで歩いているとき、一面に積もった真っ白な雪が布団のように見えて飛び込んでから、ど��くらい時間がたったのだろうか。別にそこで永遠に寝るつもりで飛び込んだわけじゃないのに、心身すべてを漂白してくれそうな気がして、目を閉じてしまった。意識を閉じて体を氷に預けたらどうなるか、この世に無数にある物語の中でよくありすぎてわかりきったことなのに、預けてしまった。表面に積もった新しい雪は僕の体をやわらくうけとめて、一瞬だけ暖かかったけど、すぐに露出してる顔とを手を冷やし、やがてやけどしているみたいに痛くなってきた。そして意識せずに、おそらく意識せずに意識をなくしていった。
でも死ななかった。ずぼっと頭を上げ、体をひっくり返すと雪が振り落ち、全身はびしょ濡れで、下着も肌に張り付いていたのに、なぜかまったく痛くなかった。ああ、ここは天国なのかな、と思ってあたりを見渡したが、景色はいつもの雪に埋もれた帰り道だった。おかしい、なら幽霊か、と思ったが、足があった。頭を触ってみるけど、三角巾や輪っかの感触もなかった。「おかしい」と思うと気配を感じ横を見ると、この雪景色に黄緑色のワンピースをきた見知らぬ女性が立っていて、「で、でた」と心臓がとびでる気がした。やはりあの世だ僕は死んだんだと思った半面、心臓がまだ動いていることも奇妙だった。
「おはようございます。よく眠れましたか?」と彼女は言う。女性らしい高い声で、よくある幽霊らしいうしろ暗いニュアンスはなく、さわやかで透き通ってすらあった。
「えーと、よく眠れました」と、おどおどしながらとりあえず返す。
「よかった。死んだかと思い、心配しました」と返ってくる。
「えっと、死んでないんですか、僕は」
「死んでませんよ。私が救いました」
「えっ、救ってくれたんですか」
「私がおまじないをかけました」
彼女は指で目の前に円を描いた。印を結んだのだろうか。
「おまじない?それはどういう?」
「寒さを感じなくするおまじないです」
「えっ?」
それから彼女はうすら笑った。その顔は、どこか見覚えがあった。
「そうですね、あなたの皮膚が、寒さを跳ね返すようになったと思います」
ふと自分の体を見ると、ズボンから湯気が上がっていた。それだけじゃなく、雪に突っ込んでいた手を見てみると、赤くも痛くもなく、ましてや少し湯気が上がっていた。
「え、なんだこれ・・」
「しばらく、そのおまじないは続きます」
「え」ちょっとわけがわからなかったが、続けて聞いてみた。
「あなたは、雪女なのですか?そんな寒そうな恰好で・・」
「うーん、そういうわけでもありませんが、そのようなものです。私も同じく寒くありませんが、でも気を失いそうです」
「どっち・・」少し可笑しかった。そして雪がまた降り始めた。
「とにかく、あなたにひとつお願いがあります。鳥が鳴き始めたら、おまじないは解けます。そうしたら、私の愛する人に伝えてください」
「なにを?」
「私も愛しています、だけを」
「え?それだけ?」
「それだけです」
「ちょっとまって、どういう・・。鳥って、ひとって・・えっ?いつ?」僕はうろたえたが、
「時期がきたら、ここへ来てください。そうすればわかります。では。よろしくお願いします」
そう言って、彼女はもう一度笑って、後ろへ振り向いた。そのとき、嗅いだことのあるような香りがふあっとして、降る雪に埋もれていくようにゆっくりと姿を消した。
「このほろ苦い香り・・。てか、どういう・・」僕は困惑したが、とりあえず立ち上がり、むちゃくちゃに手足を動かしてみた。ジャンプもしてみると、雪に足を取られて転んだ。
「うえっ」すぐ飛び起きた、そうして違和に気づく。
「体が、軽い」
直感がぴきーんと鳴った。あっ、これならいける、と思った。寒さを全く感じない。寒さは良くなくて、仕事場でも体も頭もぎこちなくなり、集中力が落ちて能率が落ちる。そして家に帰ればなんにもする気にならない。それが今までの疲れの原因だったんだ。よし、雪女、と呼べばいいのだろうか、雪女さん、ありがとう。これをチャンスにちょっと頑張ってみる。鳥の鳴く頃って、春のことかな。そうか、約束は果たすよ。それまで、力を借りるよ。しかし雪女にまでよろしくお願いされるなんて、世の中はどこまで世間なんだろうか。
それからの僕は、水を得た魚、八面六臂、なんでもござれの正露丸のような働きぷりだった。まず手をつけたのは部屋掃除。夏物の服、冬物の服、本や漫画、書類やペットボトルや紙屑とずれたシーツの布団が混然一体になった部屋を、ストーブもつけずにあれよあれよと片付けた。部屋が寒いと動けない、を言い訳にしてた日々はこれでさようなら。窓を開けて掃除機もかけて、心地いい部屋に変わった。動けば動くほど汗が滴り、畳を濡らして、霧がかかった。
部屋が汚いと運気が入ってこない、と大工の父親はよく言うが、僕は坂口安吾なんだ、と言い聞かせて蓋をしてた悩みにさようなら。運気はともかく、部屋の散らかりは精神の散らかりとリンクしていて、緩慢なボディブローのように起きても寝ててもジワジワメンタルを削ってくる。ついでになんと確定申告も終わらせた。毎年ギリギリな自分がうそのようだった。部屋が汚ければ源泉徴収の用紙も散り散りになりますます書けず、どこに本物があるかわからないのでごみも捨てれない。部屋のきれいな人にきっとわからない連鎖の理である。
埋もれている間はちょうど仕事が休みの日だった。出勤すれば、いつも寒さでやる気のない自分ではなく、体がうごくうごく。担当のプラスチック部品を手早く組み立て、ラインに流す、不良品は別に溜めてあとで検品する、その繰り返しをいつもより手早くできた。そして体もほてれば頭もほてる。よく笑い、よく報告し、よく怒られたのは変わらないが、よく立ち直れた。なぜなら俺は真夏だから、雨はすぐ乾く。
コミュニケーションがうまくいけば、仕事もしやすくなる。以前よりよく仕事が回るようになった。が、時間給は上がることはなかった。どうせ上がらないので時間給通りのクオリティの仕事をすればよく、それ以上のことを自分にもとめるのは自由だけど人に求めてはいけない、という冷静さも戻ってきた。でもそれだと同僚たちの間でどっちの味方なのか揺れることになるが、熱いギャグで回避した。これでいいのだ。なにごとも環境が大事。負の連鎖はいったん環境を整えてからじゃないとなかなか切れない。私は生き返ったのだ。ウォームビズだとかでそんな暖かくない休憩所で半袖でアイスを食べているのを引いた眼で見られていても、幼少期はハバロフスクですごしたということにしておけば万事解決するほどの勢いがあった。
恋愛もうまくいった。それまでは負の連鎖の中で冴えない顔をした男だった僕は自信のオーラをまとえるようになり、同僚の女性の目もきらつき始めた。そのうちの一人をフレンチに誘って、そのあといい感じになり付き合い始めた。正直気はそんなに合わないけど、よく笑う人でなんとなく楽しかったし、僕の高い体温は人間電気アンカとして重宝されていたが、一月ほど後に彼女は元カレの元へ戻っていった。しかし僕はその時も泣きながら彼女の幸せを祝福する度量があった。がさすがに傷心したところに、シングルマザーの女性といい感じになった。手足が冷えるとよくないからと温めたら、大きな赤ちゃんを抱いてるみたいとよくわからないことを言って、ぐっすり眠っていたが、なんとなくそれきりだった。うまくいっているようには見えないが、人をあたためることができたことは幸せだった。
ホーホケキョ
ウグイスが鳴いたころ、僕のおまじないが解けた。休みの日の昼に、その声をきいたとき、急に、突然に、肌が寒くなった。
「さむっ」
積もっていた雪は氷のごとく硬く、太陽はいつもより多めに雪を照らしまぶしかった。すずめらしい鳥もチュンチュン鳴き、またあちらこちらから水がちょろちょろ流れ出す音がして、道を歩けば泥と雪がまじりあい、雪に幽閉されてた杉の葉っぱも散らかっていた。しかし人が通らないところは今もうずたかく雪が積もっていて、まだ溶けそうになかった。急な斜面は雪がずり落ちて、灰色の濡れた植物がべっとりと垂れ下がっていた。水は道を流れるので、道との際は削られて家の廂のように浮いてみえた。
「すううううう・・・・はあ」
息を大きく吸って吐いた。体をさすような冷たさが懐かしく、吐けば久しぶりに白く、体から熱が抜けていき、身震いした。うーん、やはり寒い。毎年秋にやってくる、暖かい日が続いていたのに急に寒い日が来て、真冬に比べれば全然なのに、体がまだ寒さについていってないから異常に寒く感じる、という感じ。それはもう経験していたはずなのに。でも日差しはあたたかく、それで立ち上る土の匂いのせいなのだろうか、体の底からあっちの興奮に似たうずきを感じることがあり、やっぱり、この感じは春。では、さあ、あの時の雪女の約束を果たす時が来た。とりあえず足を彼女と会った場所へと運ぶ。でも彼女はいない。いったいどうやって何すればいいのか。ここに来ればわかるといった。
すると小さい羽ばたきが目の前にやってきて、目の前の小さな木に止まった。そしてこちらを見て、こういった。
ホーホケキョ
「あ・・」ピンときた。その羽の色、うぐいす餡の色、だ。黄緑っぽい色。あの日に彼女にあったときの、ワンピースの色はこんな感じだった。僕は理解した。ああ、そうか、あなたは
「おーい」
いきなり横で呼ばれてびっくりした。知らない男の人が立っていた。
「え??誰??あっ・・」
また同じ黄緑色の服をきた、しかし今度は男の人が立っていた。
「君かあ」彼は言った。はっ、と思った。彼女と同じような、透き通った音がしている。
「え?あなたは・・雪女・・いや、雪男さん?」
「あははっ、ちがうよ」
「あっ、愛してますっ」
「おっと、初対面の男に告白するなんて、のぼせやすい人なのかな?」
「いや、ちがいます。えーと、ここで会った女の人からそう伝えてくれって」焦りすぎたので、息を一つ飲み込んで応えた。頭より胸が冷えた。
「えっ、それって、僕と同じような服を着た人かい?」
「そうです」
「それでなんて?」
「だから、愛してますって・・」
「・・それは君の気持ちじゃないのかい?」
「・・ち、違いますよ」ちょっとそんな好みは持っていなかった
「そうか、残念だね、君はいい目をしてるから、ちょっと残念だね」彼ははにかんだ。さっきは気づかなかったけど、その顔はあの女とすこし似ていた。
「あの、すみません、僕は違うので」二重の意味を込めたつもりだ。
「はは、からかってごめん。・・ありがとう。満足したよ。重要な役目をありがとう」
「あ・・はい」
「じゃあ」彼は振り向いて立ち去ろうとする。あっさりすぎて慌てた。
「えっと、あなたたちはウグイスなんですか?」そういえば、さっきのウグイスの姿は見当たらなかった。
「ああ、ちがうよ。君がここにきたのを教えてくれたのは彼らだけどね」
「ええ・・じゃあ・・」
「私たちは、これだよ」彼はまた笑う、その顔・・何かを思い出させる。そして、あたりにほろ苦い香りがひらく。あっ、この香りも・・知ってる・・
「あっ・・ふきのとう」
そして彼の体は、黄緑色だけのこして消える。消えたと思ったら、その色は丸まって、あわてて僕が差し出した両掌の上に結晶し、小さくコロン、と転がった。それはとてもかわいい卵型で、若草色をして、一部分に添えられた紫色がかえって鮮やかにしていた。裂けた先端から中を覗くと、独特の香りとともに、外の皮に大切に守られるように、柔らかい花のつぼみが閉じ込められているのが見えた。ああ、この顔・・既視感の源はこれだった。でもふと気にかかった。
「えっ、でも・・これ・・死んじゃうよ、あんた」
するとどこからともなく男の声がした。
「死にはしないよ。それは花だからね、私のきもは土の中。まあ、それも大事なものだけど、でも彼女がもういないんじゃ、今回はもういいかな。だからちょっとした礼だよ、君に私をたべてほしい。そそるだろう」
「・・たく、浮気はよくないですよ」余裕ができたので、冗談で返す。
「はは・・参ったね」
「もうそんな時期ですか。みんなそわそわしてるだろうな」
「そうだね。君たちは目ざといからね、いや、特にしわのよった君たちのほうかな。どうせ取られてしまうだろう。去年運がよかっただけかな」
僕が少し笑うと、彼は続ける。
「彼女は今年で最後だったんだ。そのとき、僕と一緒になろうと誓ったんだよ。でも、雪が降る前にとられちゃったからね、ほんとは僕と・・」
「今年で最後?」
「君たちが何度花を取ったって、また次の年には咲くさ。でも疲れてきちゃうから、そのうち死ぬよ。だから種を残すんだ。僕の素を受けて、彼女が綿毛を飛ばすんだ」
「しらなかった。たんぽぽみたい」
「そうかもね、、私はいくよ・・じゃあね、また」
ホーホケキョ
なにかの合図のように、ウグイスは鳴いた。なんとなく、彼の意識が消えたのが分かった。
「・・伝えたよ、雪女さん」
手の上のふきのとうを見る。ああ、そういえば僕は以前、食べたことがある。秋、雪が積もる前、ふきのとうはひっそり顔を出していることがある。春のものより小さくて風味は少ないけど、味は確かにふきのとうだった。春まで待てないひとは、珍味としてとることがあった。だから、つまり最後だと悟った年の前、運悪くつぼみを取られてしまった女が絶えるとき、約束した男にメッセージを伝えたかったのだろう。あんなおまじないなんて使えるほどの、僕の体温なんか目じゃない、演歌のような熱い情念を知ってしまったら、時期だというのに、大好きなのに、とてもふきのとうなんて、これでさえ食えないよ。
とはいえさて、雪はゆるみ魔法は解けた。でも環境は整った。おまじないのある時にできた体の動かし方で、もう一度世間に向かっていこう。そう思えること自体、見違えった感じがして、ほんとうにあの時僕は一回死んで生き返ったのかもしれない。ありがとう、ますます食べられないよ、困ったね。でも帰ったらこれ一個だけ味噌あえにして食べよう、今年はそれで十分。急いで帰る僕の吐く息はまだ白く、どこかで鶯がまた鳴いた。
0 notes
Text
26/淡い夢には染まれない(2h)
(CoC ※身内向けシナリオバレ含む)
(大体)二時間ライティング。これは試験導入です
~レギュレーション(仮)~
・1話二時間でライティング(プロットを含む) 尚、校閲については時間外に加算(だってクソ文そのまま出すの恥ずかしくない?)
・目安~3000字(私の速度が1500字/hなので) これはね、守れてない
・タイトルをお題サイトから適当に1つ、キーワードを歳時記からランダムに3つ選択し、それをベースに即興で物語を汲む
・キーワードは1つ以上を使用すれば、3つ全ては使わなくても良い
・+して各話のランダム要素として適当に相手に何か聞いて提示してもらったものを組み込む
~ここまでレギュレーション
●キーワード ・燕(乙鳥、玄鳥、飛燕、燕)夏 ・更衣(ころもがえ、俳句の世界では夏の衣服に着替えることを言う)夏 ・鬼灯(6~7月には淡い花が咲く)秋
●タイトル ・「淡い夢には染まれない」 元:√9
前半:春の雨は全てを雪ぐなら、(中坪と今井野と次の季節の話) 後半:海の底に、亡骸が沈んでいる(神楽坂と×××と��明け前の話)
記事内リンクできないのでスクロールしてください。
.
(1.とうしょー)
雨音で目が覚めた。窓の外を見て、それが人を目覚めさせるような粒の大きさでもないことを知って、たまらなく嫌な気持ちになった。
ガラス張りの窓いっぱいに着いた水滴は、まるで雲の中を泳いだ後のように風景を隠して、寝室と外の世界とを隔てていた。雨に濡れてもいないのに、全身は微かに濡れて湿っていた。 ゆっくりと息を吐く。 スマートフォンのサイドボタンを押す。午前二時半を少しだけ過ぎた時間。人は、この時間を真夜中と呼ぶ。 ひそやかに息を吸う。 (……嫌な夢、) 酷な、幻を見た。ひどく懐かしい邂逅だった。 死んだ人の、夢を見たのだ。けれど、ここ最近は見ていないものでもあった。だからこそ余計、せり上がってくる酸を堪えるのに必死だった。目を覚ました瞬間に嘔吐しないだけ、以前よりいくらかまともになれているのかもしれない。 伏せた瞼の裏に、忘れるなと言いたげな残像が焼き付いていた。閉じかけた目を薄らと開く。苦い表情が零れる。
迷う指先でスマートフォンの画��を撫でようとしては、躊躇って引っ込める。しばらく逡巡して、結局真っ暗な画面をお守りのように握りしめるだけに留まった。 翔子は湿った夜着のまま、ベランダの窓をそっと開けた。霞のような輪郭が無い雨が世界を包んでいる。右手を宙に投げ出してみると、肌に当たる雨粒は柔らかく、優しく、手のひらを濡らしているというのに、息が詰まるほど生暖かった。 冬の名残は、どこにもない。
春が嫌いだった。全てが色づき始める季節だから。全てが、始まる季節だったから。
強制的に、あらゆる全てを初めからやり直させてしまう世界のシステムだとすら思っていた。 灰ばんでいた空はいつのまにか青くふんわりと宇宙へ向かって伸びやかに揺れ始めるし、枯れた下生えの隙間から若葉色の新芽は空に追いつこうとどんどん背を伸ばすし、その内に冬鳥はそっと氷河を渡り消え、木々花々は匂やかに揺れ、ありとあらゆる全てが柔らかく、美しく歌い出す。幸福な季節には違いない。 只人であれば、尚のこときっと、そう思うのだろう。悲しいことを濯ぐための機構であるのなら。そのために必要なことなのであれば。 しかし、前の季節に留め置かれたものは、そうではない。春の雨には縋れない。 だとすれば、どこへ流れて行けば良いのだろう。何度も彼女は考えた。幾ら蹲って考えても、行き先の解は得られないままだった。行き先が無いまま溶けてしまえば、どこにだって居場所は見つからない。
閉じた冬の装いのまま、人々の中を縫うように行う呼吸は翔子の肺を確かに焼いた。春を待たずに動かなくなってしまった美しい鳥の亡骸を抱いて、翼を畳なわらせて、一緒に白くなってしまいたかっただけだったのに。それすら春は無慈悲に雨を注いで、溶かしてしまった。 もういない、六花一つ残されていない。 追い縋ることさえ、できなかった。 時間だけが、無為に流れて行った。雪解け水のように。 心は確かにまだ吹雪の内側に取り残されたままなのに、がらんどうの身体だけが芽吹きの季節を迎える。そうして、終ぞ何にもなれなかった。 何になることも、許されなかった。 だからこそ、春という存在が、痛哭に至るほど嫌いだった。
深夜のベッドの上には、旧い記憶の扉が開く音だけが波打ったシーツに遺されていた。 そうだ、彼女の夢を見たのだ。
思い出の中と寸分違わない、輝血のような目をしていた。 彼女はただ、何も言わないまま翔子を見ていた。見ているだけだった。相対して二人佇むだけの、不思議な明晰夢だった。 鬼灯の萼みたいに穴の空いた二つの目で、翔子の目をじっと見つめるだけだった。責め苛むことも、忘れないでと縋ることもせず、ただ網膜の隙間から、ひっそりと赤い色を向けるだけだった。 夢の中で、零れそうになる謝罪を、せり上がる嗚咽を、飲み込んで腑の中にもう一度落とすことの苦痛を知って尚、翔子はただ沈黙を保っていた。ここが、夢だと判っていたからこそ。 どうせなら、罵声の一つでも投げつけられたほうが、余程楽だというのに。凍り付いた冬の名残ばっかりが、喉元にずっと刺さっているから、こんなに苦しいのだというのに。 けれど、それでも。 ――それでも。
不意に、握りしめたスマートフォンがけたたましく鳴って、翔子は「うひゃっ」と変な声を上げて、電話を取り落とした。慌てて拾い直そうとして、表示されている名前を目にした瞬間、微かに肩が跳ねる。 どうして、と思う気持ちより先に、途方もないものが溢れた。
恐る恐る、受話を押す。 「……もしもし?」 『翔子さん!? オレです! 中坪ですけど!』 「……、……」
不意打ちの音量が鼓膜を思った以上に揺さぶって、翔子は思わず眉間に皺を寄せた。煩い以外に、上等な形容があるのであれば教えてほしい。 唸るように息を吐いてから、首を振る。耳から携帯を少し離すように持って、その声を噛み締める。 『あれっ!? 翔子さん!? もしもし!?』 「落ち、落ち着いて。……聞こえてる。冬次でしょ、解ってるよ。……名前、登録してるんだから」 『あ、そっか。……や、そーいうことじゃなくて! オレオレ詐欺とかだったらどうするんスか!?』 「またベタな問いを……。嫌、その前に、詐欺する奴らが、こんな妙な時間に電話してくることないだろ。ATMだって閉まってるし……。今、何時だと思ってるか知らないけど」 『……確かに?』 そもそも、登録しているのは携帯の番号だ。いずれにせよ、そんなものが他人の手に渡っている時点で割ととんでもない状況だという前提が必要であることを、翔子は思いついても敢えて口には出さなかった。
窓を閉めて、ベッドに座った。コイルスプリングが柔らかく沈んだ。 「えっと、どうしたの、こんな時間に」 あ。と電話口から声が漏れた。言葉を選ぶように、無音を探るような呼吸が聞こえる。 『や、うーん。……別段どうした、ってのは特にないんですけど』 「珍しく言い濁るね、きみにしては」 『あはは。いや、なんか嫌な感じがして! なんつーのかな、勘みたいな?』 「勘?」 『うん。なんか、翔子さんが泣いてるような気がして』
羽根を撫でるような、そんな声音だった。 静寂。春霞が、窓ガラスを叩く音さえ部屋に響くような。柔らかなふちを持った残響。夜が、嫋やかに濡って行く音だった。
『……っつーか、こんな夜中に突然電話して、起こして、それこそどうすんだよって感じっスよね! ……ごめんなさい、迷惑だった?』 「や、」 反射的に声を出すと、喉が詰まるような感覚を覚えて、翔子はたまらず二、三度ほど咳き込んだ。 「……びっ、くりはしたけれど、たまたま起きてはいたから、別に」 『あ、ホント!? 良かった!』 「うん。だから、迷惑とかじゃないよ。それは、平気」 それは嘘ではない。むしろ。 『えと、でもなんかやっぱり、声、元気ねー気がするけど、大丈夫スか』 「大丈、」 そこまで言って、舌が縺れた。
翔子は、喉に支えた冷たいものを、融かすように、ゆっくりと唾液を飲み込んだ。小鳥のような細やかな呼吸を一対すると、微かに目を伏せる。――そうして、誰見る人も居ないというのに、瞑目したまま、ふっと笑みを零した。 「……大丈夫、……では、なかったから、助かった」 『え』 「ありがと冬次。電話貰えて、嬉しかった」 『うぇ? ん? よくわかんないけど、ナイスタイミングだった感じ?』 「うん」 『おー。……へへ、良かった! なんか、力になれたみたいで』 照れたように弾む声を聴きながらふと窓の外を見ると、あれほど燻っていた霞の群れは、いつの間にか止んでいた。薄雲は未だ空を漂っているものの、霽月は冴え冴えと淡く濡れて、輝いていた。とろりと艶やかで、柔らかな黒い闇が世界を包んでいた。 「もう春時雨が降るような季節だったか」 『ん? そっち、雨降ってたんスか?』 「ああ、もう止んだみたいだ。雨なのかなんなのか、はっきりしないくらい細かいやつだったけどね」 『霧雨みたいな』 「霧は秋の言葉だよ」 『えー……じゃあ、霧吹きみたいな雨』 「……うん、まあ、誤りではない」 窓を開けると、湿った夜風が優しい手つきで頬を撫でた。不意の心地よさに目を細める。
月と雲の間に、鳥の群れが飛んでいた。黒い影を思わず目で追った。 長い尾を翻して、空気を裂く羽ばたきは力強く、それは生命の息吹を伴って夜空を飛んでいた。 ツバメの群れだ。 五、六羽ほどの影が、黙したまま雨の名残の中を、すうっと横切っていった。 思わず吐息が漏れた。春なのだなと思う。翔子は自分の喉元を撫でた。 冷たい違和感は、どこにだってない。
「あのさ」 『うん?』 「蒸し返すみたいに感じたら、ごめんね。えっと、あれから私、何回か考えたのだけれど、」 『あれから、って?』 「夢の中のことの話さ」 ふと、思い出したように苦笑混じりの声を零す。疑問符を浮かべるような瞬きが、電話越しに聞こえたような気がした。 立ち上がって、パソコンデスクに向かう。伏せられたままの写真立てを、そっと起こした。縁についた埃を払う。写真自体は褪せもせず、いつかの記憶の中と同じ色を保っていた。
写真の中の少女は、ただ一人で笑っている。 暗がりの中でも、自分と良く似た赤い二つ目の色だけは、炎のように明るく燃えている。
逢いに行こう。とふと思い立った。 考えるだけで足が竦むけれど、雪が溶けた後の大地でなら、残された花弁のひとひらくらい拾うことができるかもしれない。
「やっぱりさ、ツバメには春のほうが良く似合うよ」
銀世界に零れ落としてきた、花の完爾を思う。 窓の外に冬の名残は、やはりどこにももう無かった。
/.
(2.かぐさが)
神楽坂がそこに向かった理由は簡単だ。庁舎の屋上から植え込みにしゃがみ込むそれを小一時間以上も眺めていて、その間、彼女が微動だにしないものだから、興味を引かれて降りていっただけだった。 夜は、やおら白みかけていた。黒と、紺と、あいまいな赤が入り混じって、暗いのに、どうしてか白色に光っているように思えるのだ。 夜明け前に、世界は一番暗くなる。そのことが、この上なく不思議だった。明かされる前の夜が前日の遺したものを含めて、一度咀嚼して、内側へ連れて行ってしまうからだろうか。
がらんどうの朝である。 空は這うような速さで明るくなっていくのに、空気だけが未だ暗いままだった。まるで、薄墨の中を泳いでいるようだ。歩いた跡の宙空に、影が緒を引くように濁って、揺れている。
神楽坂が相模原の前に現れると、彼女は瞬時に形容し難い顔をした 「うわっ……、……神楽坂さん」 「ううん、その反応は想定していなかった。……流石の私でも傷つくな」 「また、そんなこと言う。……思ってもいないくせに、良くそんな言葉ぽんぽん出てきますね」 「手厳しいなあ。でも、どうだろう? 私も君が思っているよりは恐らく人間なのだろうから、邪険にされると揺れる心の一つや二つ、持ち合わせているさ」 相模原は瞼を薄く伏せると、地面に目をやった。 朝闇の中に目を凝らすと、彼女がじっと見ていたのは、一羽の小鳥の死骸であることがすぐに理解できた。小鳥の瞼は閉じていて、うす黄色い足が縮こまって小枝のように固まっている。長い燕尾は萎れて、翼が貝のように閉じていた。
「君がね、一体何を見ているのかと思ったんだ。小一時間、身動き一つしないものだから」 神楽坂の問うような独白が、溶けるように輪郭を滲ませた。
相模原は、顔を上げなかった。 彼女は二時間の間、ずっと沈黙を留めていた両手をようやく動かして、小鳥の亡骸を恭しく掬い上げた。羽毛は神楽坂が見ているだけでも、まるで雪のように柔らかだった。汚れらしい汚れもない。その艶のある幼い両翼が、だらけるように相模原の手のひらから零れた。嘴の端から、涙のような赤が数滴、彼女の薬指を濡らした。
「眠っているだけかと思ったんですよね」 返答、と言うよりは、言い訳のように独り言ちて、両掌の棺に雛燕を収めたまま、相模原はどこか宛てがあるような足取りで、茂みの中に分け入っていった。 神楽坂も無言でそれを追った。藪の中は折り重なった青葉が一層闇を深めていて、草葉の緑すら曖昧模糊としていた。 足の長い下生えと放り出された蘖が足取りを阻んだが、少し奥に分け入ったあたりに、まるで獣道のように秘め踏み固められた小さな路が奥へ続いていることに、神楽坂は気が付いた。 相模原は野良猫の如く訳知った風で、その獣道を往く。 夏木立は底の無い陰をより深めていた。まるで、海の底を歩いているような暗さだ。世界でたった一カ所、この場所だけが、未だ夜の中に取り残されてしまっているのかと思うほど。お互いがお互い、誰であるか、わからなくなるほど。 相模原は、一瞬神楽坂を振り返った。 それだけだった。
やがて、彼女は雑然と茂る数多の緑の中の一つにたどり着いて、迷い無くその根元を掘り始めた。堆積した腐葉土は柔らかく除けられ、土の下から雨上がりのような、湿った匂いがした。 背高く生えた緑の、茎の隙間に、白い蕾がまどろむような面持ちでいくつか揺れているのが見える。 「これは……?」 「ああ、鬼灯ですよ、これ」 神楽坂が興味深げに指先で蕾に触れると、相模原は顔も上げずに答えた。 「好きなんです、鬼灯。あたしによく似てるから」
程なくして出来た十数センチくらいの円形の縦穴に、相模原は巣立ち雛を葬った。からっぽの土のゆりかごの中に、冷たい羽毛はすぐに沈んで見えなくなった。地面は子燕の体積ぶん、僅かにまるい弧を描いて、鬼灯の茎を埋もれさせた。相模原の指には土が着いたままで、それは薄墨の中、行き場を無くして漂っていた。 「手���を、持ってくるべきだったな」 神楽坂はまるで後悔するように呟いて、相模原の手を取り、そのまま着いた土を払った。僅かに相模原の両手が動揺を見せて固まった。「はい」と言って、差し出された彼のハンカチを、少し迷って、相模原は諦めたように受け取る。 「……すみません」 「いいや、気にしないで欲しい。手袋も、私が持っていれば君にスマートに差し出せたのだろうから」 「……、や、唐突に土掘り出すような想定して、手袋持ち歩いてるほうが、よっぽど稀有だと思うんですけど」 「はは、そうだとしても、相模原がそういうことをするのであれば、持っていたほうがいいだろ?」 神楽坂は温顔のまま笑った。押し込まれるようにして、相模原は影を探すように俯いた。泡を吐くような呼吸が、木の葉擦れの音に掻き消された。 二人の足元で、鬼灯の小さな花がぎこちなく揺れた。晩夏にはきっと、珊瑚の玉のように煌びやかな、赤い実を結ぶのだ。
「ねえ、神楽坂さん。もう止めましょうよ。こんな不毛なこと」 まるで、朝凪のような弱々しい声が漏れた。ゆっくりと伏せていた顔を上げて、彼女はまるで途方に暮れたように笑った。 「何も無いんですよ、ここには」 土で汚れた指先のまま、相模原は自分の胸の中心をそっと撫でた。ネクタイの結ばれた胸元には穴も空虚も無く、土で僅かに汚れた白いシャツが見えた。悲鳴のように掠れた声が、乾ききった唾を飲み込んで震えた。
「そう思っているのは、相模原だけだよ」 けろりと悩んだ風もなく神楽坂はそう返して、相模原はいよいよ苦い物を噛んだように顔色を崩した。 「何の音だって、聞こえたことが無いのに」 「まだ眠っているだけさ」 「……そうやって、根拠の無い事を言うの、おじょーずですね」 「そうでもないよ?」 後退するように引っ込めた彼女の両手を少々強引に引き寄せて、神楽坂は未だ汚れたままの掌に、唇を寄せる振りをした。言葉に詰まる相模原の顔を手の向こうに見て、冴え冴えと明るい両目で笑う。 その掌から、燕の死臭はしなかった。
息が詰まった顔のまま、相模原は手を引いた。彼は易々と両手を離して、笑顔を崩さないまま「そろそろ戻らないと。随分長い気分転換になってしまった」と、迷うことなく庁舎のほうへ歩き出した。 無言で彼女もそれに続く。深海のような暗闇の中に、木の葉の擦れる音だけが波のようにざわめいていた。
「海の底だって、ここよりかもうちょっと息しやすいと思うんですよね」 苦しそうな独り言が聞こえた。こぽりと音を立てるように、忌々しげに相模原が泡を吐く。 神楽坂は薄く笑って、微かに頭上を仰いだ。 木下から夜明けの空が零れている。深海のような空気の中で、いつの間にか空は海の青と同じ色に染まり始めていた。
.
0 notes
Text
妹のために、妹のために、妹のために。(推敲中)
ふたなり怪力娘もの。わりかし血なまぐさいので注意。
扠、ここはある民家の一室、凡そ八畳程の広さの中に机が二つ、二段ベッドが一つ、その他本棚や観葉植物などが置いてある、言つてしまえば普通の部屋に男が二人顔を突き合はせ何やらヒソヒソと、いや、別に小声で話してゐるわけではないのであるが何者かに気づかれないよう静かに話し合つてゐる。一人は少し痩せ型の、黒い髪の毛に黒い縁のメガネが聡明な印象を与へる、如何にも生真面目さうな好青年で、もう一人は少し恰幅の良い、短く切られた髪の毛に色の濃い肌が健康な印象を与へる、如何にも運動が得意さうな好青年である。前者の名は那央と言ひ、後者の名は詩乃と言ふ、見た目も性格の型も違えど同じ高校に通つてゐる仲の良い兄弟である。二人の間にはノートの切れ端と思しきメモと、丁度半月ほど前に買つた十キロのダンベルが、そのシャフトを「く」の字に曲げ事切れたやうにして床に寝そべつてゐた。
何故メモがあるのか、何故ダンベルのシャフトが「く」の字に曲がつてゐるのか、何故二人の兄弟がそれらを囲んで真剣な話し合ひをしてゐるのか、その説明をするにはもう一つ紹介しておかねばならぬ事があるのであるが、恐らく大層な話を聞かずとも直ぐに状況を何となく分かつて頂けるであらう。其れと云ふのも二人にはもう一人血を同じくする、一五〇センチに満たぬ身の丈に、ぷにぷにとした餅のやうな頬、風でさらさらと棚引き陽の光をあちこちに返す黒い髪、触つた此方が溶け落ちるほど柔らかな肌、此れからの成長を予感させる胸の膨らみ、長いまつ毛に真珠を嵌めたやうな黒目を持った、--------少々変はつてゐる所と言へば女性なのに男性器が付いてゐるくらゐの、非常に可愛らしい中学一年生の妹が居るのである。名前は心百合と言ふ。成る程、ふたなりの妹が居るなら話は早い、メモもダンベルも話し合ひも、全てこの妹が原因であらう。実際、メモにはやたら達筆な字でかうあつた。-----------
前々から言ってきたけど、こんな軽いウェイトでやっても意味が無いと思うから、使わないように。次はちゃんと、最低でも一〇〇キロはあるダンベルを買ってください。私も力加減の練習がしたいのでお願いします。曲げたのは直すので、これを読んだら持ってきてください。
あと全部解き終わったので、先週から借りてた那央にぃの数学の問題集を返しました。机の上に置いてあります。全然手応えが無かったから、ちょっと優しすぎると思います。新しく買ったらまた言ってください。
心百合より
このメモは「く」の字に曲がつたシャフトの丁度折り目に置かれてあつて、凡そ午前九時に起床した詩乃がまず最初に見つけ、其の時は寝ぼけてゐたせいもありダンベルの惨状に気を取られメモを読まないまま、折角値の張る買ひ物をしたのにどうして、一体何が起きてこんなことに、…………と悲嘆に暮れてゐたのであるが、そんな簡単に風で飛ぶような物でも無いし、それに落ちたとしても直径二センチ以上ある金属がさう易易と曲がるわけでも無いから何者かが手を加えたに違ひ無く、自然と犯人の顔が思ひ浮かんでくるのであつた。わざわざ此れを言ひたいがためにダンベルを使ひ物にならなくしたのか。俺たちにとつては一〇キロでもそこそこ重さを感じると云ふのに、一〇〇キロなんて持ち上げられるわけが無い、しかもその一〇〇キロも、"最低でも"だとか、"力加減"だとか書かれてゐるので妹はもつと重いダンベルを御所望であるのか。確かにふたなりからすると、一〇〇キロも二〇〇キロも軽いと感じるだらうが、此れは俺たちが自分の体を鍛えるための道具であるからそつとしておいて欲しい。さう彼は文句を言ひたくなるものの、未だ中学一年生とは言へ、本来車でも打つから無ければ曲がるはずも無いシャフトを綺麗に曲げてしまつたと云ふ事実に、ただひたすら恐怖を感じ震える手でこめかみあたりに垂れてきた冷ややかな汗を拭ふのであつた。
一体全体、ふたなりの女の子は力が強いのである。そして其れは心百合も例外では無く、生まれて間もない時から異常な怪力ぶりを発揮してきた。例へば此れはある日の朝のことであつたか、彼ら彼女の父親が出勤しようとしてガレージのシャッターを開けると、何の恥ずかしげもなく無断駐車してゐる車の、後ろ数十センチが見えてゐたことがあつた。幸ひにも丁度車一台分通れるくらゐの隙間はあるし、其れに父親の向かふ方向とは逆の位置にあつたので、何とか避けて車を出せさうではあつたのであるが、如何せん狭いガレージと、狭い通りと、幅のある車であるから、ふとした拍子で擦つてしまふかもしれない。かと言って警察やらレッカーやらを呼ぶ時間も手間も勿体無い。仕方が無いので父親は、当時十四歳であつた那央と、当時十二歳であつた詩乃を呼び出して、ほんの数センチでも良いからこの車を向かふ側へ押せないかと、提案して自身も全身を奮ひ立たせたのであるが当然の如く動く気配は無かつた。ならばせめて角度だけでもつけようと思ひ、三人で掛け声をかけ少しでも摩擦を減らさうと車の後ろ半分を浮かせようと頑張つたものの、此れまた持ち上がる気配も無くたつた数秒程度で皆バテてしまつた。さうして諦めた父親は携帯を取り出し、諦めた二人の兄弟は数歩離れたところにある壁に凭れ、こんなん無理やろ、何が入つてんねん、と那央が言つたのをきつかけに談笑し始めた丁度其の時、登校しようと玄関から出てきた心百合が近寄つてきて、どうしたの? さつきから何やつてたの? と声をかけてきた。そこで詩乃が其の頭を撫でながら事情を説明して、ま、無理なものは無理だし、今日こそ親父は遅刻するかもな、と笑ひながら言ふと心百合は、
「んー、………じゃあ私がやってみてもいい?」
と言ひながらランドセルを那央に押し付け、唖然とする兄たちを余所に例の車へ向かつて行く。そしてトランクにまでたどり着くと、屈んで持ち易く力の入れ易い箇所を探しだす。----------当時彼女は小学三年生、僅か九歳である。自分の背丈と同じくらゐの高さの車を持ち上げようと、九歳の女の子がトランクの下を漁つてゐるのである。流石に兄たちも其の様子を黙つて見てゐられなくなり駆け寄つて、ついでに電話を掛けてゐる最中の父親も駆け付けて来て、結局左から順に父親、心百合、詩乃、那央の並びでもう一度車と相対することになつたのであるが、那央が、せえの! と声を掛け皆で一斉に力を入れる前に、よつと、と云ふ可愛らしい声が車の周りに小さく響いた。かと思ひきや次の瞬間には、グググ、と車体が浮き上がりたうたう後輪が地面から離れ初め、男たちが顔を見合はせ何が起きてゐるのか理解するうちに、一〇センチ、一五センチは持ち上がつてしまつた。男たちのどよめきを聞きながら、心百合は未だ六割程度しか力を入れてゐないことに少しばかり拍子抜けして、これならと思ひ、
「お父さんも、お兄ちゃんたちも、もう大丈夫だから手を離していいよ」
と言ふと、片手を離しひらひらと振り、余裕である旨を大して役に立つてゐ���い他の皆に伝え背筋を伸ばした。
「それで、これどうしたらいいの?」
男たちが恐る恐る手を離し、すつかり一人で車の後部を持ち上げてゐる状態になつた頃、娘が其のやうに聞いて来たので一寸だけ前に寄せてくれたら良いと、父親が答えると心百合は、分かつた、とだけ言つてから、そのまま足を踏み出して前へ進もうとした。すると、初めの方こそ靴が滑つて上手く進めなかつたのであるが、心百合も勝手が分かつて来たのか、しつかりと足に全体重と車の重量を掛け思ひ切り踏ん張つてゐると遂には、タイヤと地面の擦れる非常に耳障りな音を立てて車が前へと動き出したのである。そして、家の前だと邪魔になるだらうから、このまま公園の方まで持つて行くねと言つて、公園の側にある少し道が広がつてゐる所、家から凡そ三〇メートル程離れてゐる所まで、車を持ち上げたままゆつくりと押して行つてしまつた。
あれから四年、恐らく妹の力はさらに強くなつてゐるであらう。日常では兎に角優しく、優しく触る事を心がけてゐるらしいから俺たちは怪我をしないで済んでゐる、いやもつと云ふと、五体満足で、しかも生きてゐる。だが今まで何度も危ない時はあつた。喧嘩は全然しない、と云ふより一度も歪みあつたことは無いけれども、昼寝をしてゐる妹の邪魔をしたりだとか、凡ミスのせいでテストで満点を逃し機嫌が悪い時に何時もの調子で話しかけたりだとか、手を繋いでゐる最中に妹が何か、------例へば彼女の趣味である古典文学の展示に夢中になつたりだとか、さういう時は腕の一本や二本覚悟しなければならず打ち震えてゐたのであるが、なんと情けない話であらう。俺たちは妹の機嫌一つ、力加減一つで恐怖を覚えてしまふ。俺たちにはあの未発達で肉付きの良い手が人の命を刈り取る鎌に見える。俺たちにはあの産毛すら見えず芸術品かと思はれる程美しい太腿も、人の肉を潰したがつてゐる万力のやうに見える。……………本来さう云つた恐怖に少しでも対抗しようとダンベルを買つたのであるが、丸切り無駄であつた、矢張り妹には勝てぬのか。直接手を下されたわけでも無いのに、またしても負けてしまふのか。もう身体能力だけでなく、学力も大きな差をつけられたと云ふのに。---------------心百合は元々、小学校のテストでは常に満点を、…………少しドジなところがあるからたまにせうもない間違ひを犯すことがあるが、其れは仕方ないとして試験は常に満点を取り続けてをり、ある日学校から帰つて来るや、授業が暇で暇で、暇で仕方がないからお兄ちゃん何とかしてと言ふので、有らう事か俺たちは、其れならどんどん先の内容をこつそりと予習すると良い、と教えてしまつた。其れから心百合は教室だけでなく家でも勉強を進め、タガが外れたやうにもう恐ろしい早さで知識を吸収したつた一週間か二週間かで其の学年、-----確か小学四年生の教科書を読み終えると、兄から譲り受けた教科書を使って次の学年、次の次の学年、次の次の次の学年、…………といつたやうに、兄たちの言ふ通りどんどん先の内容を理解していき、一年も経たぬ間に高校入試の問題が全て解けるようになつてゐた。かと思えば、那央の持つてゐる高校の教科書やら問題集やら参考書やらを、兄の迷惑にならぬよう借りて勉強を推し進め、今度は半年程度で大学入試の問題をネットから引つ張り、遊び半分で解いてゐたのである。そして此方が分からないと言つてゐるのに答え合はせをして欲しいと頼んで来たり、又ある時は那央が置きつぱなしにしてゐた模試を勝手に解いては、簡単な問題ばかりで詰まんなかつた、お兄ちゃんでも全部解けたでせう? この程度の問題は、と云ふ。そんなだから中学一年生の今ではもはや、勉強をしてゐるうちに好きになつた古典文学を読み漁りながら、受験を控えた那央の勉強を教えるためにも、彼が過去問題集に取り組む前にはまず、心百合が一度目を通し、一度問題を全て解き感想を言つて、時間をかけるべきか、さうでないかの判断の手助けをしてゐるのである。先のメモにあつた後半の内容はまさに此の事で、どんなに難しさうな問題集を持つて行つても簡単だから考へ直すべしと言はれ凹む那央を見てゐると、詩乃は二年後の自分が果たしてまともな精神で居られるのかどうか、不安になつて来るのであつた。
さうすると此の兄弟が妹に勝つている点は何であらうか、多分身長以外には無い気がするが、もう後数年もすると頭一つ分超えられてしまふだらう。聞くところに寄ると、ふたなりは第二次成長期が落ち着き始める一四、五歳頃から突然第三次成長期を迎え、一八歳になる頃には平均して身長一八七センチに達すると云ふのである。実際、那央のクラスにも一人ふたなりの子が居るのであるが、一年生の初め頃にはまだ辛うじて見下ろせた其の顔も今では、首を天井に向けるが如く顔を上げないと目が合はないのである。だが彼らは未だに、こんな胸元にすつぽりと収まる可愛い可愛い妹が、まさか見上げるほど背を高くしないであらうと、愚かにも思つてゐるのであるがしかし、さうでも思はないとふたなりの妹が近くに居ること自体怖くて怖くて仕方なく、心百合を家に残しどこか遠い場所で生活をしたい衝動に駆られるのであつた。
扠、読者の中には恐らくふたなりをよくご存知でない方が何名かいらつしやるであらうから、どうして此の兄弟が、可愛い、たつた一人だけの、愛しい、よく出来た妹にここまで恐怖を感じるのか説明しておかねばならぬのであるが、恐らく其れには引き続き三人の兄妹の話をするだけで事足りるであらう。何分其処に大体の理由は詰まつてゐる。-------------
ふたなりによる男性への強姦事件は度々ニュースになるし、其れに世の男達なら全員、中学校の保健体育で習つた記憶がどこかにあるから皆知つてゐるだらう。本日未明、〇〇県〇〇市在住の路上で男性が倒れてゐるのを誰々が発見し、現場に残された体液から警察は近くに住む何たら言ふ名前の女性を逮捕した。-----例へばさう云ふニュースの事である。凡そ犯人の側に「体液」と「女性」などと云つた語が出てきたら其れはふたなりによる強姦を意味するのであるが、世の中に伝えられる話は、実際に起きた出来事にオブラートにオブラートを重ね、さらに其の上からオブラートで包み込んだやうな話であつて、もはやお伽噺となつてゐる。考へてみると、大人になれば一九〇センチ近い身長に、ダンベルのシャフトのやうな金属すら曲げる怪力を持つ女性が今日の男性を暴行し無理やり犯せば、そもそも人の形が残るかどうかも怪しくなるのは容易に想像できる。実際、幾つか例を挙げてみると、ふたなりの"体液"を口から注ぎ込まれ腹が破裂し死亡した男や、行方不明になつてゐたかと思えば四肢が完全に握りつぶされ、そしてお尻の穴が完全に破壊された状態でゴミのやうに捨てられてゐた男や、ふたなりの"ソレ"に耐えきれず喉が裂け窒息死した男や、彼女たちの異常な性欲を解消するための道具と成り果て精液のみで生きる男、……………挙げだすとキリがない。二人の兄弟は、ふたなりの妹が居るからと言つて昔からさう云ふ話を親から嫌と言ふほど聞いて来たのであるが、恐ろしいのはほとんどの被害者が家族、特に歳を近くする兄弟である事と、ふたなりが居る家庭は一つの例外なく崩壊してゐる事であつた。と云つても此の世の大多数の人間と同じやうに、彼らも話を言伝されるくらゐではふたなりの恐ろしさと云ふ物を、其れこそお伽噺程度にしか感じてゐなかつたのであるが、一年前、小学六年生の妹に、高校生二年と中学三年の兄二人が揃つて勉強を教えてもらつてゐたある夜、机の間を行つたり来たりするうちに何故かセーラー服のスカートを押し上げてしまつた心百合の、男の"モノ"を見た時、彼らの考へは変はり初めた。其の、スカートから覗く自分たちの二倍、三倍、いや、もう少しあらうか、兎に角妹の体格に全く不釣り合いな男性器に、兄たちが気を取られてゐると心百合は少し早口で、
「しばらくしたら収まると思うから見ないでよ。えっち。それよりこの文章、声に出して読んでみた? 文法間違いが多くて全然自然に読めないでしょ? 一度は自分で音読してみるべしだよ、えっちなお兄ちゃん。でも単語は覚えてないと仕方ないね。じゃあ、来週までに、この単語帳にある単語と、この文法書の内容を全部覚えて来ること。----------」
と顔を真赤にして云ふと、下の兄に高校入試を模して作つた問題を解かせつつ、上の兄が書いた英文の添削を再開してしまつた。が、ほんの数分もしないうちに息を荒げ出し、そして巨大な肉棒の先端から、とろとろと透明な液体を漏らし淫猥な香りを部屋中に漂はせ初めると、
「ど、どうしよう、…………いつもは勝手に収まるのに。………………」
と言つて兄たちに助けを求める。どうやら彼女は五〇センチ近い巨大な肉棒を持ちながら其の時未だ、射精を味はつた事が無かつたやうである。そこで、ふたなりの射精量は尋常ではないと聞いていた那央は、あれの仕方を教えてあげてと、詩乃に言ふと急いでバケツと、絶対に要らないだろうとは思ひつつもしかしたらと思つて、ゴミ袋を一つ手に取り部屋に戻つたところ、中はすでに妹が前かがみになりながら両手を使つて激しく自分のモノを扱き、其の様子を弟が恍惚とした表情で見守ると云ふ状況になつてゐる。----------何だ此れは、此れは俺の知る自慰では無い。此れがふたなりの自慰なのか。………………さうは思ひながら、ぼたぼたと垂れて床を濡らしてゐる液体を受け止めるよう、バケツを丁度肉棒の先の下に置くと、そのまま棒立ちで妹の自慰を見守つた。そしていよいよ、心百合が肉棒の先端をバケツに向け其の手の動きを激しくしだしたかと思えば、
「あっ、あっ、お兄ちゃん! 何これ! ああぁあんっ!!」
と云ふ、ひどくいやらしい声と共に、パツクリと開いた尿道から消防車のやうに精液が吹き出初め、射精とは思へないほどおぞましい音が聞こえて来る。そしてあれよあれよと云ふ間にバケツは満杯になり、床に白くドロドロとした精液が広がり始めたので、那央は慌ててゴミ袋を妹のモノに宛てがつて、袋が射精の勢ひで吹き飛ばぬよう、又自分自身も射精の勢ひで弾き飛ばされぬよう肉棒にしがみついた。-------
結局心百合はバケツ一杯分と、二〇リットルのゴミ袋半分程の精液を出して射精を終え、ベタベタになつた手と肉棒をティッシュで拭いてから、呆然と立ちすくんでゐる兄たちに声をかけた。
「お兄ちゃん? おにいちゃーん? 大丈夫?」
「あ、あぁ。…………大丈夫。………………」
「しぃにぃは?」
彼女は詩乃の事をさう呼ぶ。幼い頃はきちんと「しのにいちゃん」と読んでゐたのであるが、いつしか「しのにぃ」となつて、今では「の」が略されて「しぃにぃ」となつてゐる。
「……………」
「おい、詩乃、大丈夫か?」
「お、………おう。大丈夫。ちょっとぼーっとしてただけ。………………」
「もう、お兄ちゃんたちしっかりしてよ。特にしぃにぃは最初以外何もしてなかったでしょ。……………て、いうか私が一番恥ずかしいはずなのに、何でお兄ちゃんたちがダメージ受けてるのん。………………」
心百合はさう言ふと、本当に恥ずかしくなつてきたのか、まだまだ大きいが萎えつつある肉棒をスカートの中に隠すと、さつとパンツの中にしまつてしまつた。
「とりあえず、片付けるか。…………」
「おう。……………」
「お兄ちゃんたち部屋汚しちゃってごめん。私も手伝わせて」
「いいよ、いいよ。俺たちがやっておくから、心百合はお風呂にでも入っておいで。------」
このやうにして性欲の解消を覚えた心百合は、毎日風呂に入る前に自慰をし最近ではバケツ数杯分の精液を出すのであつたが、そのまま流すとあつと言ふ間に配管が詰まるので、其の始末は那央と詩乃がやつてをり、彼女が湯に浸かつてゐるあひだ、夜の闇に紛れて家から徒歩数分の所にある川へ、音を立てぬよう、白い色が残らないよう、ゆつくりと妹の種を放つてゐるのであつた。空になつたバケツを見て二人の兄弟は思ふ。------------いつかここにあつた精液が、ふとしたきつかけで体に注がれたら俺たちの体はどうなる? そもそも其の前に、あの同じ男性器とは思へないほど巨大な肉棒が、口やお尻に突つ込まれでもしたらたら俺たちの体はどうなる? いや、其れ以前に、あの怪力が俺たちの身に降り掛かつたらどうなる? ふたなりによる強姦の被害者の話は嘘ではない。腹の中で射精されて体が爆発しただなんて、昔は笑いものにしてゐたけれども何一つ笑へる要素などありはしない、あの量を、あの勢いで注がれたら俺たち男の体なんて軽く吹き飛ぶ。其れにあんなのが口に、お尻に入り込まうとするなんて、想像するだけでも恐ろしくつて手が震えてくる。聞けば、顎の骨を砕かうが、骨盤を割らうが、其んな事お構ひなしにねじ込んで来ると���ふではないか。此れから先、何を犠牲にしてでも妹の機嫌を取らなくては、…………其れが駄目ならせめて手でやるくらゐで我慢してもらはねば。…………………
だが彼らは此れもまた、わざわざ時間を割いてまでして兄の勉強を見てくれるほど情に満ちた妹のことだから、まさかさう云ふ展開にはならないであらうと、間抜けにも程があると云ふのに思つてゐるのであるが、そろそろなのである。ふたなりの女の子が豹変するあの時期が、そろそろ彼らの妹にも来ようとしているのである。其れ以降は何を言つても無駄になるのである。だから今しかチャンスは無いのである。俺たちを犯さないでくださいと、お願ひするのは今しか無いのである。そして、其の願ひを叶えてくれる確率が零で無いのは今だけなのである。
「------もうこれ以上引き伸ばしても駄目だ。言いに行くぞ」
ダンベルとメモを持ち、勢ひよく立つた那央がさう云ふ。
「だけど、………それ言ったら言ったらで、ふたなりを刺激するんだろ?!」
「あぁ。…………でも、少しでも確率があるならやらないと。このままだと、遅かれ早かれ後数年もしないうちに死ぬぞ。俺ら。………………」
「くっ、…………クソッ。……………」
「大丈夫、もし妹がその気になっても、あっちは一人で、こっちは二人なんだから上手くやればなんとかなるさ、……………たぶん。………………」
「最後の「たぶん」は余計だわ。……………」
「あと心百合を信じよう。大丈夫だって、あんなに優しい妹じゃないか。きっと、真剣に頼めば聞いてくれるはず。……………」
「兄貴って、たまにそういう根拠のない自信を持つよな。………」
さう言ふと、詩乃も立ち上がり一つ深呼吸をすると、兄と共に部屋を後にするのであつた。
心百合の部屋は、兄たちの部屋に比べると少しばかり狭いが其れでも一人で過ごすには物寂しさを感じる程度には広い、よく風が通つて夏は涼しく、よく日が当たつて冬は暖かく、東側にある窓からは枯れ葉に花を添えるやうはらはらと山に降り積もる雪が、南側にある窓からはずつと遠くに活気ある大阪の街が見える、非常に快適で感性を刺激する角部屋であつた。そこに彼女は本棚を此れでもかと云ふほど敷き詰めて新たな壁とし、嘗ての文豪の全集を筆頭に、古い物は源氏物語から諸々の文芸作品を入れ、哲学書を入れ、社会思想本を入れ、経済学書を入れ、そして目を閉じて適当に選んだ評論などを入れてゐるのであるが、最近では文系の本だけでは釣り合ひが取れてない気がすると言ひ初め、つい一ヶ月か二ヶ月前に、家から三駅ほど離れた大学までふらりと遊びに行つて、お兄ちゃんのためと云ふ建前で、解析学やら電磁気学やら位相空間論やらと云つた、一年か二年の理系大学生が使ふであらう教科書と、あとさう云ふ系統の雑誌を、合わせて十冊買つて来たのであつた。そして、春までには読み終はらせておくから、お兄ちゃんが必要になつたらいつでも言つてねと、那央には伝えてゐたのであつたが、意外に面白くてもう大方読んでしまつたし、計算も終えてしまつたし、問題もほとんど解き終はつてしまつた。またもう一歩背伸びをして新しく本を買いに行きたいが、前回大量にレジへ持つて行き過ぎたせいで、大学生協の店員にえらく不思議さうな顔をされたのが何だか癪に障つて、自分ではもう行きたくない。早く那央にぃの受験が終はつてくれないかしらん。さうしたら彼処にある本を買つて来てもらへるのに。それか二年後と言はず今すぐにでも飛び級させてくれたらいいのに。…………と、まだ真新しい装丁をしてゐる本を眺めては思ふのであつた。
なので那央が大学生になるまで数学やら物理学は封印しようと、一回読んだきりでもはや文鎮と化してゐた本たちを本棚にしまひ、昨日電子書籍として買つてみた源氏物語の訳書を、暇つぶしとしてベッドの上に寝転びながら読んでゐると、コンコンコン、…………と、部屋の扉をノックする音が聞こえて来た。
「はーい、なにー?」
「心百合、入ってもいいか?」
少し澄んだ声をしてゐるから那央であらう。
「いいよー」
ガチャリと開いたドアから那央が、朝に軽いイタズラとして曲げたダンベルと、その時残しておいたメモを手に持つて入つて来たかと思えば、其の後ろから、何やら真剣な表情を浮かべて居る詩乃も部屋に入つて来る。
「あれ? しぃにぃも? どったの二人とも?」
タブレットを枕の横に投げ出すと心百合は体を起こし、お尻をずるりとベッドの縁まで滑らせ、もう目の前までやつて来てゐる兄二人と対峙するやうにして座つた。
「あぁ、…………えとな。…………」
「ん?」
「えっと、………お、おい、詩乃、……代わりに言ってくれ。…………」
「えっ、………ちょっと、兄貴。俺は嫌だよ。…………」
「俺だって嫌だよ。後で飯おごってやるから頼む。……………」
「………言い出しっぺは兄貴なんだから、兄貴がしてくれよ。…………」
あんなに真剣な表情をしてゐた兄たちが何故かしどろもどろ、………と、云ふよりグジグジと醜い言ひ争ひをし始めたので、心百合は居心地が悪くなり一つため息をつくと、
「もう、それ元通りにして欲しくて来たんじゃないの?」
と言つて、那央の持つてゐるダンベルに手を伸ばし、トントンと叩く。が、那央も詩乃も、キュッと体を縮こませ、
「えっと、…………それは、…………ち、ちが、ちがってて…………」
などと云ふ声にならぬ声を出すばかりで一向にダンベルを渡してくれない。一体何が違つてゐるのだらう、………ま、ダンベルを持つて来たのだから直して欲しいには違ひない、と、云ふより直すと書いたのだから直してあげないと、------などと思つて、重りの部分に手をかけると、半ば引つたくるやうにして無理やりダンベルを奪ひ去つた。
「いくらお兄ちゃんたちに力が無いって言っても、こんな指の体操にもならないウェイトだと意味無いでしょ。今度はちゃんとしたの買いなよ」
さう云ふと、心百合はまず手の平を上にして「く」の字に曲がつたシャフトを、一辺一辺順に掴んでから、ひ弱な兄たちに見せつけるよう軽く手を伸ばし、一言、よく見ててね、と言つた。そして彼女が目を瞑つて、グッ…と其の手と腕に力を込め始めると、二人の兄弟がいくら頑張つても、--------時には詩乃が勝手に父親の車に乗り込んで轢いてみても、其の素振りすら見せなかつたシャフトが植物の繊維が裂けるやうな音と共にゆつくりと反り返つていき、どんどん元の状態に戻つて行く。其の様子はまるで熱した飴の形を整えてゐるやうであつて、彼らには決して太い金属の棒を曲げてゐるやうには見えなかつた。しかもさつきまで目を閉じてゐた妹が、いつの間にか此方に向かつて笑みを浮かべてゐる。……………其のあまりの呆気なさに、そして其のあまりの可愛いさに、彼らは己の中にある恐怖心が、少しばかり薄らいだやうな気がするのであつたが、ミシリ、ミシリ、と嫌に耳につく金属の悲鳴を聞いてゐると矢張り、目の前に居る一人の可憐で繊細で、人々の理想とも形容すべき美しい少女が、何か恐ろしい怪物のやうに見えてくるのであつた。
「はい、直ったよ。曲がってた所は熱いから気をつけてね」
すつかり元通りになつたダンベルを、真ん中には触れないやう気をつけながら受け取ると、那央はすぐに違和感に気がついた。一体どう云ふ事だ、このシャフトはこんなにでこぼこしてゐただらうか。---------まさかと思つて、さつきの妹の持ち方を真似してダンベルを持つてみると、多少合はないとは言え、シャフトのへこんでゐる箇所が自分の手の平にもぴつたりと当てはまる。其れにギュッと握つてみると、指先にも若干の凹凸を感じる。もしかして、--------もしかして、この手の平に感じるへこみだとか、指先に感じるでこぼこは、もしかして、もしかして、妹の手の跡だと云ふのであらうか。まさか、あの小さく、柔らかく、暖かく、ずつと触れてゐたくなるやうなほど触り心地の良い、妹の手そのものに、この頑丈な金属の棒が負けてしまつたとでも云ふのであらうか。彼はさう思いつつ、もしかしたらと自分も出来るかもしれないと思つて力を入れてみたが、ダンベルは何の反応もせずただ自分の手が痛くなるばかりであつた。
「で、他に何か話があるんだよね。何なの?」
「あ、…………えっ、と。…………」
「もう、何なの。言いたいことはちゃんと言わないと分からないよ。特に、なおにぃはもう大学生なんだから、ちゃんとしなきゃ」
と五歳も年下の妹に諭されても、情けないことに兄がダンベルを眺めたまま固まつてゐるので、恐怖心を押さえつけ幾らか平静になつた詩乃が、意を決して口を開けた。
「それはだな。…………えっと、……心百合って、ふたなりだろ? だからさ、今後気が高ぶっても俺らでやらないで欲しい。……………」
ついに言つてしまつた、だけどこれで、…………と詩乃はどこか安堵した気がするのであつたが、
「えっ、…………いや、それはちょっと無理かも。………だって。…………………」
心百合がさう云ふと、少し足を開いた。すると那央と詩乃の鼻孔にまで、いやに生々しい匂ひが漂ふ。
「………だって、お兄ちゃんたちが可愛くって、最近この子勝手にこうなるんだもん」
心百合がスカートの上からもぞもぞと股の間をいじると、ぬらぬらと輝く巨大な"ソレ"が勢いよく姿を現し、そして自分自信の力で血をめぐらせるかのやうに、ビクン、ビクン、と跳ねつつ天井へ伸びて行く。
「ねっ、お兄ちゃん、私ちょっと"気が高ぶった"から、お尻貸してくれない?」
「い、いや、………それは。…………」
「心百合、……………落ちついt。……………」
「ねっ、ねっ、お願いっ! ちょっとだけでいいから! 先っぽしか挿れないからお尻貸して!!」
心百合は弾むやうにして立ち上がると、詩乃の手首を握つた。と、その時、ゴトリ、と云ふ重い物が落ちる音がしたかと思ひきや、那央が扉に向かつて駆けて行く様子が、詩乃の肩越しに見えた。
「あっ、なおにぃどこ行くの!」
心百合は詩乃をベッドの上に投げ捨て、今にもドアノブに手をかけようとしてゐた那央に、勢ひよく後ろから抱きつく。
「あああああああああああ!!!!!!」
「ふふん、なおにぃ捕まえた~」
ほんの少し強く抱きしめただけで心地よく絶叫してくれる那央に、彼女はますます"気を高ぶらせ"、
「しぃにぃを放って、どこに行こうとしていたのかなぁ? ねぇ、那央お兄ちゃん?」
と云ひ、彼が今まで味はつたことすら無い力ではあるが、出来るだけ怪我をさせないような軽い力で壁に向かつて投げつけると、たつたそれだけでぐつたりとし起き上がらなくなつてしまつた。
「もしかして気絶しちゃったのん? 情けないなぁ。………仕方ないから、しぃにぃから先にやっちゃお」
ベッドに染み付いてゐる妹の、甘く芳しい匂いで思考が止まりかけてゐた詩乃は、其の言葉を聞くや、何とかベッドから這い出て、四つん這ひの体勢のまま何とか逃げようとしたのであるが、ふと眼の前にひどく熱つぽい物を感じるたかと思えば、ぶじゅっ、と云ふ下品な音と共に、透明な液体が床にぼとりと落ちて行くのが見えた。--------あゝ、失敗した。もう逃げられぬ。もう文字通り、目と鼻の先に"アレ"がある。俺は今から僅か十三歳の幼い、其れも実の妹に何の抵抗も出来ぬまま犯されてしまふ。泣かうが喚かうが、体が破壊されようが関係なく犯されてしまふ。あゝ、でも良かつた。最後の最後に、こんな天上に御はします高潔な少女に使つて頂けるなんて、なんと光栄な死に方であらうか。-----------------
「しぃにぃ、よく見てよ、私のおちんちん。お兄ちゃんを見てるだけでもうこんなに大きくなつたんだよ?」
さう云ふと、心百合は詩乃の髪を雑に掴んで顔を上げさせ、自身の腕よりもずつとずつと太い肉棒を無理やり見せると、其の手が汚れるのも構はずに、まるで我が子の頭を撫でるかのやうな愛ほしい手付きで、ズルリと皮の剥けた雁首を撫でる。だが彼には其の様子は見えない。見えるのはドクドクと脈打つ指のやうな血管と、男性器に沿つて真つ直ぐ走るホースのやうな尿道と、たらりたらりと垂れて床を濡らすカウパー液のみである。其れと云ふのも���然であらう、亀頭の部分は持ち主の顔と同じ高さの場所にあるのである。------まだ大きくなつてゐたのか。…………彼にはもう、久しぶりに会ふことになつた妹の陰茎が、もはや自分の心臓を串刺しにする鉄の杭にしか見えなかつたのであるがしかし、其のあまりにも艶めかしい佇まひに、其のあまりにも圧倒的な存在感に、手が打ち震えるほど惹かれてしまつてもうどんなに嫌だと思つても目が離せなかつた。
「んふふ、……お兄ちゃんには、この子がそんなに美味しそうに見えるのん?」
「………そ、そんな、……そんなことは、ない。…………」
さうは云ふものの、詩乃は瞬きすらしない。
「でもさ、------」
心百合はさう云ふと、自身の肉棒を上から押さえつけて、亀頭を彼の口に触れるか触れないかの位置で止める。
「------お兄ちゃんのお口だと、先っぽも入らないかもねぇ」
と妹が云ふので、もしかしたらこの、俺の握りこぶしよりも大きい亀頭の餌食にならないで済むかもしれない、…………と詩乃は少しだけ期待するのであつたが、ふいに、ぴゅるっと口の中に何やら熱い液体が入り込んで来る。あゝ、もしかしてこれは。………………
「………けど、そんなに美味しそうな顔されたら諦めるのも悪いよねっ。じゃあ、お兄ちゃん、お口開けて? ………ほら、もっと大きく開けないと大変なことになるよ? たぶん」
「あっ、………やっ、………やめ、やめやめ、いゃ、ややめ、あが、………………」
………まだ彼は、心百合が途中で行為を中断してくれると心のどこかで思つてゐたのであらう、カタカタと震える唇で一言、やめてくださいと、言ほうとしてゐるのであつた。だがさうやつてアワアワ云ふのも束の間、腰を引かせた妹に両肩を掴まれ、愉悦と期待に満ちた表情で微笑まれ、クスクスとこそばゆい声で笑はれ、そしてトドメと言はんばかりに首を可愛らしくかしげられると、もう諦めてしまつたのか静かになり、遂には顔が醜くなるほど口を大きく開けてしまつた。
「んふ、もっと力抜いて? …………そうそう、そういう感じ。じゃあ息を吸ってー。………止めてー。………はい、お兄ちゃんお待ちかね、心百合のおちんちんだよ。よく味わってねー」
其の声はいつもと変はらない、中学生にしては舌つ足らずな甚く可愛いらしい声であつたが、詩乃が其の余韻に浸る前に、彼の眼の前にあつた男性器はもう前歯に当たつてゐた。かと思えばソレはゆつくりと口の中へ侵入し、頬を裂し血を滴らせるほどに顎をこじ開け、瞬きをするあひだに喉まで辿り着くと、
「ゴリュゴリュゴリュ………! 」
と云ふ、凡そ人体から発生するべきでは無い肉の潰れる音を部屋中に響き渡らせ始める。そして、彼が必死の形相で肉棒を恵方巻きのやうに持つて細やかな抵抗してゐるうちに、妹のソレはどんどん口の中へ入つていき、ボコリ、ボコリとまず首を膨らませ、鎖骨を浮き上がらせ、肋骨を左右に開かせ、あつと云ふ間にみぞおちの辺りまで自身の存在を示し出してしまつた。もうこれ以上は死んでしまふ、死んでしまふから!止めてください!! ———と彼は、酸素の薄れ行く頭で思ふのであつたが恐ろしい事に、其れでも彼女のモノはまだ半分程度口の外に残り、ドクンドクンと血管を脈打たせてゐる。いや、詩乃にとつてもつと恐ろしいのは次の瞬間であつた。彼が其の鼓動を唇に数回感じた頃合ひ、もう兄を気遣うことも面倒くさくなつた心百合が、もともと肩に痛いほど食い込んでゐた手に骨を握りつぶさんとさらに力を入れ、此れからの行為で彼の体が動かないようにすると、
「ふぅ、………そろそろ動いても良い? まぁ、駄目って言ってもやるんだけどね。良いよね、お兄ちゃん?」
と云ひ、突き抜かれて動かない首を懸命に震はせる兄の返事など無視して、そのまま本能に身を任せ自分の思ふがまま腰を振り始めてしまつたのである。
「〜〜〜???!!!! 〜〜〜〜〜〜〜!!!!!!」
「んー? なぁに、お兄ちゃん。しぃにぃも高校生なんだから、ちゃんと言わないと誰にも伝わらないよぉ? 」
「〜〜〜〜〜!!!!!!!」
「あはっ、お兄ちゃん死にかけのカエルみたい。惨めだねぇ、実の妹にお口を犯されるのはどんな気分? 悔しい? それとも嬉しい?」
心百合は残酷にも、気道など完全に潰しているのに優しく惚けた声でさう問ひかける。問ひかけつつ、
「ごぎゅ! ごぎゅ! ずちゅり! ……ぐぼぁ!…………」
などと、耳を覆いたくなるやうな、腹の中をカリでぐちゃぐちゃにかき乱し、喉を潰し、口の中をズタズタにする音を立てながら兄を犯してゐる。度々聞こえてくる下品な音は、彼女の陰茎に押されて肺の中の空気が出てくる音であらうか。詩乃は心百合の問ひかけに何も答えられず、ただ彼女の動きに合はせて首を長くしたり、短くしたりするばかりであつたが、そもそもそんな音が耳元で鳴り響いてゐては、妹の可愛らしい声も聞こえてゐなかつたのであらう。
もちろん、彼もまた男の端くれであるので、たつた十三歳の妹にやられつぱなしというわけではなく、なんとか対抗しようとしてはゐる。現に今も、肩やら胸やら腹のあたりに感じる激痛に耐へて、力の入らぬ手を、心百合の未だくびれの無い未成熟な脇腹に当て、渾身の力で其の体を押し返そうとしてゐるのである。………が、如何せん力の差がありすぎて、全くもつて妹には届いてゐない。其の上、触れた場所がかなり悪かつた。
「何その手は。私、腰触られるとムズムズするから嫌だって昔言ったよね? お兄ちゃん頭悪いからもう忘れちゃったの? -----------
……………あ、分かった。もしかしてもっと突っ込んでほしいんだ!」
心百合はさう云ふと、腰の動きを止め、一つ、涙と鼻水でぐしゃぐしゃになり怯えきつてゐる兄の顔を至極愛ほしさうに撫でる。そして、
「もう、お兄ちゃん、そんなに心百合のおちんちんが好きだなんて早く言ってくれたらよかったのに。昔、精通した時に怯えてたから嫌いなんだと思ってた。…………
--------んふ、んふふ、…………じゃあ心置きなくやっちゃってもいいんだね?」
と変はらず詩乃の頭を撫でながら云つて、彼を四つん這いの状態から正座に近い体勢にし、自身は其の体に覆いかぶさるよう前かがみになると、必死で妹の男性器を引き抜こうと踏ん張る彼の頭を両手で掴み、鼠径部が彼の鼻に当たるまで一気に、自身のモノを押し込んだ。
「~~~~~~~??????!!!!!!!!!!」
「あんっ、……お兄ちゃんのお口の中気持ちいい。…………うん? お口? お腹? ………どっちでもいいや。---------」
心百合は恍惚(ルビは「うっとり」)とした表情で、陰茎に絡みつく絶妙な快感に酔ひしれた。どうしてもつと早く此の気持ちよさを味ははなかつたのだらう。なおにぃも、しぃにぃも、ただ年齢が上なだけで、もはや何をやつても私の後追ひになつてゐるのに、私がちょつと睨んだだけで土下座をして来る勢ひで謝つて来るくせに、私がどんなに仕様もないお願いをしても、まるでフリスビーを追ふ犬のやうにすぐに飛んでいくのに、-----------特に、二人共どうしてこんなに勉強が出来ないのだらうか。私が小学生の頃に楽々と解いてゐた問題が二人には解答を理解することすら難しいらしい、それに、そもそも理解力も無ければ記憶力も無いから、一週間、時には二週間も時間をあげてるのに本一つ覚えてこなければ、読んでくることすら出来ず、しかもこちらが言つてることもすぐには分かつてくれないから、毎回毎回、何度も何度も同じ説明をするハメになる。高校で習う内容の何がそんなに難しいのだらうか、私には分からぬ。そんなだから、あまりにも物分りの悪い兄たちに向かつて、手を上げる衝動に襲われたことも何度かあるのではあるけれども、別にやつてもよかつた。其れこそあの、精通をむかえたあの夜に、二人揃つて犯しておけばよかつた。あれから二人の顔を見る度にムクムクと大きくなつて来るので、軽く手を強く握ったり、わざと不機嫌な真似をして怯えさせたりした時の顔を思ひ出して自慰をし、自分の中にもくもくと膨らんでくる加虐心を発散させてゐるのであるが、最近では押さえが効かなくなつてもう何度、二人の部屋に押し入つてやらうかしらんと、思つたことか。さう云へば他のクラスに一人だけ居るふたなりの友達が数ヶ月前に、兄を嬲つて嬲つて嬲つて最後はお尻に突つ込んでるよ、と云つてゐるのを聞いて、本当にそんな事をして良いのかと戸惑つてゐたが、いざやつてみると自分の体が快楽を貪るために、自然と兄の頭を押さえつけてしまふももである。このなんと気持ちの良いことであらう、那央にぃもまずはお口から犯してあげよう、さうしよう。…………………
と、心百合は夢心地で思ふのであつたが、詩乃にとつて此の行為は地獄であらう。さつきまで彼女の腰を掴んでゐた手は、すでにだらんと床に力無く垂れてゐる。それに彼女の鼠径部がもろに当たる鼻は、-------恐らく彼女は手だけ力を加減してゐるのであらう、其の衝撃に耐えきれずに潰れてしまつてゐる。とてもではないが、彼に未だ意識があるとは思えないし、未だ生きてゐるかどうかも分からない。が、心百合の手の間からときたま見える目はまだ開いてをり、意外にもしつかりと彼女のお臍の辺りを眺めてゐるのであつた。しかも其の目には恐怖の他に、どこか心百合と同じやうな悦びを蓄えてゐるやうに見える。口を引き裂かれ、喉を拡げられ、内臓を痛めつけられ、息をすることすら奪われてゐるのに、彼は心の奥底では喜んでゐる。…………これがふたなりに屈した者の末路なのであらう、四歳離れた中学生の妹に気持ちよくなつて頂けてゐる、其れは彼にとつて、死を感じる苦痛以上に重要なことであり、別に自分の体がどうなろとも知つたことではない。実は、心百合が俺たちに対して呆れてゐるのは分かつてゐたけれども、一体彼女に何を差し上げると、それに何をしてあげると喜んでくれるのか分からなかつたし、それに間違つて逆鱗に触れてしまつたらどうしようかと悩んで、何も出来なかつた。だが、かうして彼女の役に立つてみるとなんと満たされることか。やはり俺たち兄弟はあの夜、自慰のやり方を教へるのではなく、口を差し出し尻を差し出し、犯されれば良かつたのだ。さうすればもつと早く妹に気持ちよくなつてもらえたのに、……………あゝ、だけどやつぱり命は惜しい、未だしたい事は山程ある、けど今はこの感覚を全身に染み込ませなければ、もうこんなことは二度と無いかもしれぬ。-------さう思ふと気を失ふわけにはいかず、幼い顔つきからは想像もできないほど卑猥な吐息を漏らす妹を彼は其の目に焼き付けるのであつた。
「お兄ちゃん、そろそろ出るよぉ? 準備はいーい? かるーく出すだけにしておいたげるから、耐えるんだよ?」
心百合はさう云ふと、腰を細かく震わせるやうに振つて、いよいよ絶頂への最後の一歩を踏み出そうとする。そして間もなくすると、目をギュッと閉じ、体をキュッと縮こませ、そして、
「んっ、………」
と短く声を漏らし快楽に身を震はせた。と、同時に、薄つすら筋肉の筋が見える、詩乃の見事なお腹が小さくぽつこりと膨らんだかと思ひきや、其れは風船のやうにどんどん広がつて行き、男なのに妊婦のやうな膨らみになつて遂には、ほんの少し針で突つつけば破裂してしまふのではないのかと疑はれるほど大きくなつてしまつた。軽く出すからね、と云ふ妹の言葉は嘘では無いのだが、其れでも腹部に感じる異常な腹のハリに詩乃はあの、腹が爆発して死んでしまつた強姦被害者の話を思ひ出して、もう限界だ、やめてくださいと、言葉に出す代はりに彼女の腕を数回弱々しく叩いた。
「えー、………もう終わり? お兄ちゃんいつもあんなにご飯食べてるのに、私の精液はこれだけしか入らないの?」
とは云ひつつ詩乃の肩に手をかけて、其の肉棒を引き抜き始める。
「ま、いいや、お尻もやらなきゃいけないし、その分、余裕を持たせておかなきゃね」
そしてそのままズルズルと、未だ跳ね上がる肉棒をゆつくり引き抜いていくのであるが、根本から先つぽまで様々な液体で濡れた彼女の男性器は、心なしか入れる前よりおぞましさを増してゐるやうに見える。さうして最後、心百合は喉に引つかかつた雁首を少々強引に引つこ抜くと、
「あっ、ごめ、もうちょっと出る。…………」
と云つて、"最後の一滴"を詩乃の顔にかけてから手を離した。
「ぐげぇぇぇぇぇぇぇ…………………!!!!お”、お”え”ぇぇぇぇぇぇぇぇ!!!!!」
一体どこからそんな音を発してゐるのか、詩乃が人間とは思へない声を出しながら体に入り切らぬ妹の精子たちを、己の血と共に吐き出して行く。が、心百合はそんな彼の事など気にも止めずもう一つの標的、つまり壁の側で倒れてゐる那央に向かつて歩みを進めてゐた。
「なおにぃ、いつまで寝たフリしてるの? もしかしてバレてないとでも思ってた?」
「あ、…………え、…………や、やめ。…………」
「えへへ、やめるとでも思ってるのん? しぃにぃはちゃんと私の愛を受け止めてくれたんだよ、………ちょっと死にかけてるけど。 なおにぃはどうなるかな?」
那央は体を起こし、そのまま尻もちをついた状態で後ずさろうとしたものの、哀れなことに後ろは壁であつた。
「お、お願いします、………やめ、やめてください。お願いします。………………」
「んー? お兄ちゃんは自分に拒否権があると思ってるのん? それに、私は今、"気持ちが高ぶってる"んだから、お兄ちゃんがするべきなのは、そんな逃げ回るゴキブリみたいに壁を這うことじゃなくて、首を立てに振ることだよ」
だが裂けた口から精子を吐き出し続けてゐる弟を見て、誰が首を縦に振れようか、ヒクヒクとうごめく尿道からカウパー液を放出し続けてゐる肉棒を見て、誰がうんと頷けようか。彼に選択権は無いとは言つても、命乞ひくらゐはさせても良いであらう。
「お兄ちゃんさ、情けないと思わない? 妹にハグされただけで絶叫して、妹に軽く投げられただけで気絶して、妹に敬語を使いながら怯えてさ、……………そんなにこの子の餌食になりたいのん?」
「こ、心百合、……………頼む。…………頼むから落ち着いてくれ。……………」
「んふふ、お兄ちゃんって諦めが悪いよね。でも嫌いじゃないよ、そういうところ。------」
「あ、あ、…………や、やめて、…………ああぁ、や、やめてくださ…………………」
「もう、しぃにぃと同じ反応しないで! お兄ちゃんでしょ? 弟の方がまだ潔くて男の子らしかったよ? っていうかさっき私に、犯さないで、って言ったのもしぃにぃだったじゃん」
心百合は土下座のやうに下を向く那央の頭を上げさせ、肉棒の先つぽを軽く口の中へねじ込む。
「あ、あが、………。ひ、ひや。……………」
「だからぁ、………バツとしてなおにぃを犯す時は、遠慮しないことにしよっかな。-----えへへ、大丈夫だって、しぃにぃはまだ生きてるし、大丈夫大丈夫。----------」
さうして彼女は本当に容赦なく、那央の頭を手で掴み固定して、一気に自身のモノの半分ほどを突つ込んだ。そして、前のめりになつて暴れる兄の体に背中から覆いかぶさるように抱きしめると、
「よっ、と。………」
と軽い掛け声をかけ、そのままスツと、まるでお腹にボールでも抱えてゐるかのやうに、何事も無く男一人を抱えて立ち上がつた。体勢としては、妹の男性器に串刺しにされた那央が、逆立ちするやうに足を天井へ向けて、心百合に抱きかかえられてゐる、と云へば伝はるであらうか、兎に角、小学生と言はれても不自然ではない小柄な体格の女の子に、標準体型の男が上下を逆にして抱えられてゐると云ふ、見慣れぬ人にとつては異様な状況である。
「~~!!!~~~~~~!!!!!!!」
「こら、暴れないで。いや暴れてもいいけど、その分どんどん入って行くから、お兄ちゃんが困ることになるよ?」
其の言葉通り、那央が暴れれば暴れるほど彼の体は、自身の体重で深く深く心百合のモノに突き刺さつて行く。が、其れでも精一杯抵抗しようと足をジタバタ動かしてしまひ、結局彼女のモノが全部入るのにあまり時間はかからなかつた。
「もう諦めよっ? お兄ちゃんはこれから私を慰めるための玩具になるんだから、玩具は玩具らしく黙って使われてたら良いの」
だがやはり、那央は必死で心百合の太腿を掴んで彼女の男性器を引き抜こうとしてゐる。なのでもう呆れきつてしまひ、一つ、ため息をつくと、
「いい加減に、………」
と云ひながら、彼の肋骨を拉げさせつつ二、三十センチほど持ち上げ、そして、
「………して!」
と、彼の体重も利用して腕の中にある体を振り下ろし、再び腹の奥の奥にまで男性器を突つ込ませた。
「っっっっっっ!!!!!」
「あぁんっ! やっぱり男の人のお口はさいこぉ、…………!」
心百合はよだれを垂らすほどに気持ち良ささうな顔でさう云ふのであるが、反対に、自分では到底抵抗できぬ力で体を揺さぶられた那央は、其の一発で何もかもを諦めたのか手をだらりと垂れ下げ出来るだけ喉が痛くならないように脱力すると、もう静かになつてしまつた。
「んふ、…………そうそう、それでいいんだよ。お兄ちゃんはもう私の玩具なの、分かった?」
さう云ひながらポンポンと優しくお腹を叩き、そのまま兄を抱えてベッドまで向かふ。途中、未だにケロケロと精液を吐き出してゐる詩乃がゐたが、邪魔だつたので今度は彼を壁際まで蹴飛ばしてからベッドに腰掛けた。そして、
「ちゃんと気持ちよくしてね」
と簡単に云つて、彼の腰の辺りを雑に掴み直すと、人を一人持ち上げてゐるとは思へ無いほど軽やかに、------まさに人をオナホールか何かだと勘違ひさせるやうな激しい動きで、兄の体を上下させて自身の肉棒を扱き出したのであつた。股を開き局部を露出してなお、上品さを失はずに顔を赤くし甘い息を吐き綺羅びやかな黒髪を乱す其の姿は、いくら彼女が稚い顔つきをしてゐると云へども万人の股ぐらをいきり立たせるであらう。勿論其れは実の兄である詩乃も例外ではない。どころか、彼はもう随分と妹の精液を吐き出しいくらか落ち着いてきてゐたので心百合と那央の行為を薄れていく意識の中見てゐたのであるが、自身の兄をぶらぶらと、力任せに上へ下へと上下させて快楽を貪る実の妹に対しこの上なく興奮してしまつてゐるのである。なんと麗しいお姿であらうか、たとへ我が妹が俺たちを死に追ひやる世にも恐ろしい存在であらうとも、ある種女神のやうに見えてくる。そして其の女神のやうな高貴な少女が、俺たち兄弟を道具として使ひ快楽に溺れてゐる。………なんと二律背反的で、背徳的で、屈辱的な光景であらう、人生の中でこれほど美しく、尊く、猥りがましく感じた瞬間はない。------彼はもう我慢できなくなつて、密かに片手を股にやり、ズボンの上から己の粗末なモノを刺激し初めたのであるが、ふと視線に気がついてグッと上を向くと、心百合が此方を見てニタニタと其の顔を歪ませ笑つてゐた。
「くすくす、……………お兄ちゃんの変態。もしかして、なおにぃが犯されてるの見て興奮してたの?」
心百合はもう那央の体を支えてゐなかつたが、其れでも其の体は床に垂直なまま足をぶらつかせてゐる。
「ほら、お兄ちゃんも出しなよ、出して扱きなよ。知ってるよ私、お兄ちゃんが密かに私の部屋に入って、枕とか布団とかパジャマとかの匂いを嗅ぎながら自慰してるの。全部許したげるからさ、見せてよ、お兄ちゃんのおちんちん」
「あっ、………えっ、…………?」
自分の変態行為を全部知られてゐた、-----其の事に詩乃は頭を殴られたかのやうな衝撃を受け、ベルトを外すことすらままならないほど手を震えさせてしまひ、しかしさらに自身のモノが固くなるのを感じた。
「ほら早く、早く、-----------」
心百合はもう待ちきれないと云ふ様子である。其れは年相応にワクワクしてゐる、と云ふよりは獲物を見つけて何時飛びかかろうかと身を潜める肉食動物のやうである。
「ま、まって、…………」
と、詩乃が云ふと間もなく、ボロンとすつかり大きくなつた、しかし妹のソレからすると無視できる程小さい男の、男のモノがズボンから顔を出した。
「あははははっ、なにそれ! それで本当に大きくなってるの?」
「う、……ぐっ…………!」
「まぁ、いいや。お兄ちゃんはそこでそのおちんちん? をシコシコしていなよ。もう痛いほど大きくなってるんでしょ? 小さすぎて全然分かんないけど」
と云つて心百合は那央の体を掴み、再びおぞましい音を立てながら"自慰"に戻つた。そして詩乃もまた、彼女に言われるがまま自身の粗末な男性器を握ると悔しさやら惨めさやらで泣きそうになつたが、矢張り妹の圧倒的な巨根を見てゐると呼吸も出来ないほどに興奮して来てしまひ、ガシガシと赴くがまま手を動かすのであつた。だが一寸して、
「あ、しぃにぃ、見て見て、-------」
と、心百合が嬉しさうな声をかけてくる。………其の手は空中で軽く閉じられてをり、那央の体はまたもや妹のモノだけで支えられてゐる。------と思つてゐたら突然、ビクン! と其の体が暴れた。いや、其れは彼が自分から暴れたのではなく、何かに激しく揺さぶられたやうだと、詩乃は感じた。
「ほらほら、------」
ビクン、ビクンと那央の体が中身の無い人形のやうに暴れる。
「------お兄ちゃんのちっちゃい、よわよわおちんちんじゃ、こんなこと出来ないでしょ」
ベッドに後ろ手をつきながら、心百合がニコニコと微笑んでさう云つてきて、やうやく詩乃にも何が起きてゐるのか理解できたやうであつた。まさか妹は人を一人、其の恐ろしい陰茎で支えるのみならず、右へ左へとあの激しさで揺れ動かしてゐるとでも云ふのであらうか。いや、頭では分かつてはゐるけれども、全然理解が追ひつかない。いや、いや、ちやつと待つてくれ、其れよりもあんなに激しく暴れさせられて兄貴は無事であらうか。もう見てゐる限りでは全然手に力が入つて無く、足もただ体に合はせて動くだけ、しかも、かなり長いあひだ呼吸を肉棒で押さえつけられてゐる。……………もう死んでしまつたのでは。----------
「んぁ? なおにぃもう死にそうなの? ………………仕方ないなぁ、ちょっと早いけどここで一発出しとくね」
男性器を体に突つ込んでゐる心百合には分かるのであらう、まだ那央が死んでゐないといふ事実に詩乃は安心するのであつたが、先程自分の中に流し込まれた大量の精液を思ふと、途中で無理矢理にでも止めねば本当に兄が死んでしまふやうな気がした。
「んっ、…………あっ、来た来たっ……………」
心百合はさう云ふとより強く、より包むように那央を抱きしめ、其の体の中に精を放ち始める。が、もう彼の腹がパンパンに張らうとした頃、邪魔が入つた。
「やめ、………心百合、もうやめ、…………!」
「なに?」
見ると詩乃がゾンビのやうに床を這ひ、必死の力でベッドに手をかけ、もう片方の手で此方の腕を握って、しかもほとんど残つてゐない歯を食ひしばつて、射精を止(や)めさせようとしてゐるではないか。兄のために喉を潰されても声をあげ、兄のために激痛で力の入らぬ足で此方まで歩き、兄のために勝ち目など無いと云ふのに手を伸ばして妹を止めようとする献身的な詩乃の姿勢に、心百合は少なからず感動を覚えるのであつたが、残念なことに彼女の腕を握つてゐる手は自身の肉棒を触つた手であつた。
「お兄ちゃん? その手はさっきまで何を触ってた手だったっけ?」
と云ふと、那央がどうなるのかも考えずに無理やり肉棒を引き抜きベシャリと其の体を床に投げつけ、未だ汚い手で腕を握つてくる詩乃の襟首を掴んで、ベッドから立ち上がる。
「手、離して」
「は、はい。………」
「謝って」
「あ、あぁ、……ご、ごご、ごめんなさい。……………」
「んふ、…………妹をそんな化物でも見るみたいな目で見ないでもいいんじゃないのん? 私だって普通の女の子なんだよ?」
「……………」
「ちょっとおちんちんが生えてて、ちょっと力持ちで、ちょっと頭が良いだけなんだよ。それなのにさ、みんなお兄ちゃんみたいに怯えてさ、……………」
「心百合、…………」
「------本当に、たまらないよね」
「えっ?」
「でも良かったぁ、……………もう最近、お兄ちゃんたちだけじゃなくて、友達の怯えた表情を見てると勃ってしょうがなかったんだもん。……………」
「こ、心百合、…………」
「だからさ、今日お兄ちゃん��ちが部屋に入ってきて、犯さないで、って言った時、もう我慢しなくて良いんだって思ったんだよ。だって、お兄ちゃんも知ってるんでしょ? ふたなりにそういう事を言うと逆効果だって。知ってて言ったんでしょ? -------」
「まって、……そんなことは。…………」
「んふ、……暴れても無駄だよ、お兄ちゃん。もう何もかも遅いんだよ、もう逃れられないんだよ、もう諦めるしかないんだよ、分かった?」
「ぐっ!うああ!!!」
「あはは、男の人って本当に弱いよね。みーんな軽く手を握るだけで叫んでさ、ふたなりじゃなくっても女の子の方が、今の世の中強いよ、やっぱり。お兄ちゃんも運動部に入ってるならもっと鍛えないと、中学生どころか小学生にすら勝てないよ? …………あぁ、でもそっか、そう云えば、この間の試合は負けたんだっけ? 聞かなくてもあんな顔して夜ご飯食べてたら誰だって分かっちゃうよ」
心百合はさう云ふと、片手で詩乃を壁に投げつけた。
「ぐえっ、…………」
「-----ま、そういう事は置いといて、中途半端に無理やり出しちゃって気持ち悪いから、さっさとお尻に挿れちゃうね。しぃにぃは後でやってあげるから、そこで見てて」
詩乃が何かを云ふ前に心百合は、ひどい咳と共に精液と血を吐き出し床にうずくまる那央を抱えて、無理やり四つん這いの体勢にする。そしてジャージの腰の部分に手をかけて剥ぎ取るように下ろすと、其処にはまるで此れからの行為を期待するかのやうにヒクヒクと収縮するお尻の穴と、ピクピクと跳ねる那央のモノが見えた。
「なぁに? なおにぃも私にお口を犯されて興奮してたのん?」
「ぢ、ぢが、……ぢがう。………」
と那央が云ふけれども激しく嘔吐しながらも自身のモノを大きくすると云ふことは、さう云ふ事なのであらう。
「んふふ、じゃあもう待ちきれないんだ。いいよ、それなら早く挿れてあげるよ。準備はいーい?」
さながら接吻のやうに心百合の男性器と、那央の肛門がそつと触れ合ふ。が、少なく見積もつても肛門の直径より四倍は太い彼女のモノが其処に入るとは到底思へない。
「だめ、だめ、だ、だめ、………あ”ぁ、ゃ、………」
那央は必死に、赤ん坊がハイハイする要領で心百合から逃げようとしてゐるのであるが、彼女に腰を掴まれてしまつては無意味であらう、ただ手と足とがツルツルと床を滑るのみである。しかし其のあひだにも心百合のモノはじつとりと品定めするかのやうに、肛門付近を舐め回して来て、何時突つ込まれるか分からない恐怖で体が震えて来る。一体どれほどの痛みが体に走るのであらうか。一体どれほどの精液を放たれるのであらうか。妹はすでに、俺たち二人の腹を満杯にするまで射精をしてゐるけれども、未だ普段行われる自慰の一回分にも達してをらず、相当我慢してゐることはこの足りない脳みそで考へても分かる。分かるが故に恐ろしい、今のうちに出来る限り彼女の精液を吐き出しておかないと大変な事になつてしまふ。凡そ"気が高ぶった"ふたなりが情けをかけ射精の途中で其の肉棒を引き抜いてくれるなんて甘い希望を持つてはいけない。況してや先つぽだけで我慢してくれるなど、夢のまた夢であらう。…………あゝ、こんなことになるなら初めからダンベルなど放つておけばよかつた、どうしてあの時詩乃に、云ひに行くぞ、などと持ちかけてしまつたのか、あのまま何も行動を起こさなければ後数年、いや、後数日は生きていけさうであつたのに。あゝ、どうして。-------さう悲嘆に暮れてゐると、遊びもここまでなのか、心百合が自身のモノの先端を、グイと此方の肛門に押し付けて来た。そして、
「んふ、ちょっと痛いかもしれないけど、我慢してね。-------」
と云ふ悦びに打ち震えた優しい声をかけられ、腰を掴んでいる手に力が込められ、メコリと肛門が広がる感覚が走れば直ぐ其の後、気を失ふかと思はれる程の激痛で目の前が真暗になつた。
「ぐごっ、…………ごげっ、ぐぁ、……………」
絶叫しようにも、舌が喉に詰まつて声が出てこない。だけどそんな空気の漏れる音を立ててゐるうちにも妹のソレはどんどん那央の中へ入つて来て、もう一時間もしたかと思はれる頃合ひにふと其の動きが止まり、次いで腰を握りつぶしてゐた手の力も抜けていき、たうたう全部入つたんだ、何とか耐えきつた、と安堵して息を吸つたのであるが、しかし心百合の言葉は彼を絶望させるのに十分であつた。
「------ちょっと先っぽだけ入れてみたけど、どう? 気持ちいい?」
「ぅご、………う、嘘だろ…………」
「嘘じゃないよ。じゃ、どんどん入れてくね」
「あがああああああああああっ、がっ、…………」
那央の絶叫は心百合に再び腰を掴まれ、メリメリメリ、………と骨が軋む音が再びし始めるとすつかり無くなつてしまつた。彼は激痛からもはや目も見えず声も出ず考へることすら出来ない状態なのだが、此れが人間の本能と云ふやつなのであらう、其れでも手を前に出し足を上げ、一人の可憐な少女から逃げようとしてゐるのである。が、いつしか手が空を切り膝が宙に浮くやうになるともう何が起きてゐるのか訳が分からなくなり、心無い者に突然抱きかかえられた猫のやうに手足をジタバタと暴れさせるだけになつてしまふ。そして、さうやつて訳が分からぬうちにも心百合の陰茎は無慈悲に入つて行き、体の中心に赤々と光る鉄の棒を突つ込まれたかのやうに全身が熱くなり汗が止まらなくなり初めた頃、いよいよお尻に柔らかい彼女の鼠径部の感触が広がつた。広がつてしまつた。
「んふふ、どう、お兄ちゃん? 気持ちいーい?」
「………………」
「黙ってたら分からないよぉ?」
と、云ひつつ心百合は腰を掴んでゐた手で那央の体を捻り其の顔を覗き込む。
「あがっ、…………」
「私はお兄ちゃんに気持ち良いかどうか、聞いてるんだけど」
「こ、こゆ、…………」
「んー?」
那央は黙つて首を横に振つた。当然であらう、自分の拳ほどの太さの陰茎を尻にねじ込まれ、体が動かないようにと腰を掴んでゐた手でいつの間にか持ち上げられ、内蔵を滅茶苦茶にしてきた陰茎で体を支えられ、もう今では中指の先しか手が床に付かないのである。例へ激痛が無くとも、腹に感じる違和感や、極度に感じる死の恐怖や、逃げられぬ絶望感から決して首を縦に振ることは出来ないであらう。
「そっか、気持ちよくないんだ。…………」
「はやく抜いてく、…………」
「------ま、関係無いけどね」
気にしないで、気にしないで、ちやんと気持ちよくしてあげるから、と続けて云ふと心百合は再び那央の腰を掴み直す。
「こ、こゆり!!! やめて!!!」
「うるさい! 女の子みたいな名前して、おちんちんで突かれたぐらいで文句言わないで!」
この言葉を切掛に、心百合は骨にヒビが入るほど其の手に力を入れ、陰茎を半分ほど引き抜いていく。そして支えを失つてもはや力なくだらりと垂れる兄を見、
「んふ、………」
と妖艶に色づいた息を漏らすと、彼のお尻に勢ひよく腰を打ち付けた。
「ぐがあぁ!!!!!」
「あぁん、お尻もさいこぉ。……………お兄ちゃんの悲鳴も聞こえるし、お口より良いかも、…………」
さう云ふと、もう止まらない。兄がどんなに泣き叫ぼうが、どんなに暴れようが自身の怪力で全て押さえ込み、其の体を己の腰使ひでもつて何度も何度も貫いて行く。そして初めこそ腰を動かして快楽を貪つてゐたが、次第に那央の事が本当に性欲を満たすための道具に見えてくると、今度は自分が動くのでは無くさつきと同じやうに彼の体を、腕の力だけで振り回して肉棒を刺激してやる。
「あぎゃっ! いぎぃ! おごぉっ!!-------」
「あはっ、お兄ちゃん気持ちよさそう。…………良かったねぇ、妹に気持ちよくしてもらえて。嬉しいでしょ?」
「こ、ごゆぅっ!! ごゆり”っ!!! ぐあぁっ!!!」
「なぁに、お兄ちゃん? 止めてなんて言わないでよね。いつもお勉強教えてあげてるのにあんな反抗的な目で見てきて、悔しかったのか知らないけど、どれだけ私が我慢してたか分かる?」
「じぬっ!! じぬがら!!! ゃめ!!!」
だが其の悲痛な叫びもまた、間接的に彼女の肉棒を刺激するのである。
「------んふ、もう大変だったんだから。毎日毎日、お風呂に入る前の一回だけで満足しなきゃいけなかった身にもなってよ」
「ぐぎぃっ!!こゆっ!!あ”あ”ぁっ!!!」
「でもさ、思うんだけど、どうしてあんな簡単な入試問題すら解けないのん? 私あの程度だったら教科書を読んだら、すぐに解けるようになってたよ? しかも小学生の頃に。入試まで後一ヶ月も無いのに大丈夫?
……………もうお兄ちゃんの代わりに大学行ったげるからさ、このままこんな感じで私の玩具として生きなよ。そっちの方が頭の悪いお兄ちゃんにはお似合いだよ、きっと、たぶん、いやぜったい」
傷だらけの喉をさらに傷つけながら全力で叫ぶ那央を余所に、心百合は普段言ひたくて言ひたくて仕方無かつた事を吐露していくのであつたが、さうしてゐると自分でも驚くほどあつと云ふ間に絶頂へ向かつてしまつて、後数回も陰茎を刺激すると射精してしまひさうである。全く、この出来損ないの兄は妹一人満足させることが出来ないとでも云ふのであらうか。本当はこのまま快感の赴くがままに精液を彼の腹の中に入れてやりたい所だけど、折角手に入れた玩具を死なせてしまつては此方としても嫌だから、途中で射精を止めなければならぬ。いや、未だ壁の側で蹲つてゐるしぃにぃが居るではないか、と云ふかもしれないが人の腹の容量などたかが知れてゐて、満杯にした所で未だ未だ此の体の中には精液が波打つてゐる。-------あゝ、ほんの一合程度しか出ない男の人が羨ましい。見ると、なおにぃの股の下辺りに白い点々が着いてゐるのは多分彼の精液なのだと思ふが、なんと少ないことか。私もあのくらいしか出ないのであれば、心置き無く此の情けない体の中に精を放つことが出来るのに。……………
「------そろそろ、……そろそろ出るよ、お兄ちゃん。ちゃんと私の愛、受け止めてあげてね」
さう云ふと心百合は今までの動きが準備体操であつたかの如く、那央の体を激しく揺さぶり始める。そして最後、那央のお尻に自分のモノを全て入れきり目を閉じたかと思ひきや、
「んっ、んっ、………んん~~~。…………」
と、其の身を震わせて精子を実の兄の体の中で泳がせるのであつた。が、矢張り彼女にもどこか優しさが残つてゐたのか数秒もしないうちに、じゅるん、と男のモノを引き抜き那央を床に捨て、どろり、どろりと、止めきれ無かつた精液を其の体の上にかけると、でも矢張りどこか不満であつたのか壁際で自身の小さな小さなモノを扱いてゐたもう一人の兄の方を見た。
「しぃにぃ、おまたせ。早くしよっ」
其の軽い声とは逆に、彼女の肉棒はもう我慢出来ないと言はんばかりに、そして未だ未だ満足ではないと云はんばかりに大きく跳ね床に精液を撒き散らしてゐる。一体、妹の小さな体のどこにそんな体力があるのか、もうすでに男を滅茶苦茶に嬲り、中途半端とは云へ三回も射精をしてゐると云ふのに、此のキラキラと輝くやうな笑顔を振りまく少女は全く疲れてなどゐないのか、これがふたなりなのか。-----------
「あ、えぁ、…………」
「? どうしたの? なにか言いたげだけど。………」
「そ、その、きゅ、きゅうけい。…………」
「--------んふ、何か言った? 休憩? 私、休憩なんて必要ないよ。それにお兄ちゃんも十分休んだんだから良いでしょ。……ねっ、早くっ、早くお尻出して?」
「い、いや、いや、…………………」
起き上がつてドアまで駆け、そして妹に捕まえられる前に部屋を後にする、……………さう云ふ算段を詩乃は立ててゐたのであるが、まず起き上がることが出来ない。なぜだ、足に力が入らない、----と思つたが、かうしてゐる内にも心百合は近づいて来てゐる。-------もうじつとしてなど居られぬ。何とか扉まで這つて行き、縋り付くやうにしてドアノブに手をかける。が、其の時、背中に火傷するかと思はれるほど熱い突起物が押し付けられたかと思つたら、ふわりと、甘い甘い、でも決して淑やかさを失ふことの無い甚く魅惑的な匂ひに襲はれ、次いで、背後から優しく、優しく、包み込まれるやうにして抱きしめられてゐた。そして首筋に体がピクリと反応するほどこそばゆい吐息を感じると、
「おにーちゃんっ、どこに行こうとしてるのん? まさか逃げようとしてたのん?」
と言はれ、ギュウゥゥ、………と腕に力を入れられてしまふ。
「ぐえぇ、………ぁがっ!………」
「-----んふふ、もう逃げられないよ。しぃにぃは今から私に、……この子に襲われちゃうの。襲われてたくさん私の種を吐き出されちゃうの。------ふふっ、男の子なのに妊娠しちゃうかもね」
「ご、ごゆり、…………あがっ、………だれかたすけて。……………」
と云ふが、ふいにお腹に回されてゐた手が膝の裏に来たかと思へば、いつの間にかゆつくりと体が宙に浮いて行くやうな感じがした。そして顔のちやつと下に只ならぬ存在感を感じて目を下に向けると、すぐ其処には嫌にぬめりつつビクビクと此方を見つめて来る妹の男性器が目に留まる。そして、足を曲げて座つた体勢だと云ふのに遥か遠くに床が見え、背中には意外と大きい心百合の胸の感触が広がる。…………と云ふことはもしかして俺は今、妹に逆駅弁の体位で後ろから抱きかかえられて、情けなく股を開いて男のモノを入れられるのを待つてゐる状態であるのだらうか。まさか男が女に、しかも実の妹に逆駅弁の体勢にされるとは誰が想像できよう、しかし彼女は俺の膝を抱え、俺の背中をお腹で支えて男一人を持ち上げてしまつてゐる。兄貴は心百合のモノが見えなかつたからまだマシだつただらうが、俺の場合は彼女の男性器がまるで自分のモノかのやうに股から生えてゐて、……………怖い、ただひたすらに怖い、こんなのが今から俺の尻に入らうとしてゐるのか。------
「あれ? お兄ちゃんのおちんちんは? どこ?」
詩乃はさつき自身のモノをしまふことすら忘れて扉に向かつたため、本来ならば逆駅弁の体位になつて下を向くと彼の陰茎が見えてゐるはずなのだが、可哀想なことに心百合のモノにすつぽりと隠れてしまつて全く見えなかつた。
「あっ、もしかしてこの根本に感じてる、細くて柔らかいのがそうなのかな? いや、全然分かんないけど」
心百合のモノがゆらゆらと動く度に詩乃のモノも動く。
「本当に小さいよね、お兄ちゃんのおちんちん、というか男の人のおちんちんは。私まだ中学一年生なのにもう三倍、四倍くらい?は大きいかな。…………ほんと、精液の量も少ないし、こんなのでよく人類は絶滅しなかったなぁって思うよ。-----まぁ、だから女の人って皆ふたなりさんと結婚していくんだけどね。お兄ちゃんも見てくれは良いのによく振られるのはそういうことなの気がついてる? 女の人って分かるんだよ、人間としての魅力ってものがさ。------」
「こゆり、…………下ろして。…………」
「あはは、役立たずの象徴を私のおちんちんで潰されて何今更お願いしてるのん? ふたなりに比べて数が多いってだけで人権を与えられてる男のくせに。お兄ちゃんは、お兄ちゃんとして生まれた時点で、もう運命が決まってたんだよ。…………んふ、大丈夫大丈夫、心配しないで。もしお兄ちゃん達に人権が無くなっても、私がちゃんと飼ってあげるから、私がちゃんとお兄ちゃんにご飯を食べさせてあげるからさ、そんな不安そうな顔する必要ないよ、全然。--------」
「こゆ、り。…………」
「…………でもその代わりに使わせてね、お兄ちゃん達の体。--------」
さう云ふと心百合は、早速兄の体を使おうと詩乃をさらに高く持ち上げて、彼の尻穴と自身の雁首を触れ合はせる。意外にも詩乃が大人しいのはもう諦めてしまつたからなのか、其れとも油断させておいて逃げるつもりだからなのか。どちらにせよ動くと一番困るのは内蔵をかき乱される兄の方なのだから静かに其の時を待つてゐるのが一番賢いであらう。
「んふ、…………じゃあ、挿れるね。--------」
詩乃は其の言葉を聞くや、突然大人しく待つてなど居られなくなつたのであるが、直ぐにメリメリと骨の抉じ開けられる音が聞こえ、そして股から体が裂けていくやうな鈍い痛みが伝わりだすと、体全体が痙攣したやうに震えてしまひもはや指の一本すら云ふことを聞いてくれなかつた。其れでも懸命に手足を動かそうとするものの体勢が体勢だけにそもそも力が入らず、ひつくり返された亀のやうに妹の腹の上でしなしなと動くだけである。だがさうしてゐるうちにも、心百合は力ずくで彼の体に男のモノを入れていき、もう其の半分ほどが入つてしまつてゐた。
「そんな無駄な抵抗してないで、自分のお腹を触ってみたら? きっと感じるよ、私のおちんちん」
妹に言はれるがまま、詩乃はみぞおち辺りを手で擦つた。すると、筍が地面から生えてゐるやうにぽつこりと、心百合の男性器が腹を突き破らうと山を作り何やら蠢いてゐるのが分かる。
「あっ、……はっ、………はは、俺の、俺の腹に、あぁ、……………」
「んふふ、感じた? 昔こういうの映画にあったよね、化物の子供が腹を裂いて出てくるの。私怖くて、お兄ちゃんに抱きついて見れなかったけど、こんな感じだった?」
「-----ふへ、………ふへへ、心百合の、こゆり、………こゆ、…………」
「あはっ、お兄ちゃんもう駄目になっちゃった? しょうがないなぁ、………」
と云ふと、心百合は腰を引いて詩乃の体から陰茎を少し引き抜く。
「-----じゃあ、私が目を覚まさせてあげる、………よっ!」
「っおごぁっっっ!!!!!」
其のあまりにも強烈な一撃に、詩乃は顔を天井に上げ目を白くし裂けた口から舌を出して、死んだやうに手をだらんと垂れ下げてしまつた。果たして俺は人間であるのか、其れとも妹を気持ちよくさせるための道具であるのか、いや、前者はあり得ない、俺はもう、もう、…………さう思つてゐると二発目が来る。
「ぐごげぇえええっっっっ!!!!!」
「んー、…………まだ目が醒めない? もしもーし、お兄ちゃん?」
「うぐぇ、……げほっ、げほっ、………」
「まだっぽい? じゃあ、もう一発、………もう一発しよう。そしたら後はもうちょっと優しくしたげるから!」
すると、腹の中から巨大な異物が引き抜かれていく嫌な感覚がし、次いで、彼女も興奮しだしたのか背後から艶つぽい吐息が聞こえてくるようになつた。だけど、どういふ訳か其の息に心臓を打たせてゐると安心して来て、滅茶苦茶に掻き回された頭の中が少しずつ整頓され、やつと声が出るようになつた。
「こ、こゆり。………」
「うん? なぁに、お兄ちゃん」
「も、も、ももっと、もっと、…………」
もつと優しくしてください、と云ふつもりであつた。しかし、
「えっ、もっと激しくして欲しいのん? しぃにぃ、本当に良いのん?」
「い、いや、ちが、ちが、…………」
「----しょうがないなぁ。ほんと、しぃにぃって変態なんだから。……でもさすがに死んじゃうからちょっとだけね、ちょっとだけ。-------」
さう云ふと心百合は、今度は腰を引かせるだけでなく詩乃の体を持ち上げるまでして自身の陰茎を大方引き抜くと、其のまま動きを止めてふるふると其の体を揺する。
「準備は良い? もっと激しくって言ったのはお兄ちゃんなんだからね、どうなっても後で文句は言わないでね」
「あっ、あっ、こゆり、ぃゃ、……」
「んふ、-------」
と、何時も彼女が愉快な心地をする際に漏らす悩ましい声が聞こえるや、詩乃は床に落ちていつた。かと思えば、バチン! と云ふ音を立てて、お尻がゴムのやうに固くも柔らかくもある彼女の鼠径部に打ち付けられ、体が跳ね、そして其の勢ひのまま再び持ち上げられ、再度落下し、心百合の鼠径部に打ち付けられる。-------此れが幾度となく繰り返されるのであつた。もはや其の光景は遊園地にある絶叫系のアトラクシオンやうであり、物凄い勢ひでもつて男が上下してゐる様は傍から見てゐても恐怖を感じる。だが実際に体験をしてゐる本人からするとそんな物は恐怖とは云へない。彼は自分ではどうすることも出来ない力でもつて体を振り回され、腹の中に巨大な異物を入れられ、肛門を引き裂かれ、骨盤を割られ、さう云ふ死の苦痛に耐えきれず力の限り叫び、さう云ふ死の恐怖から神のやうな少女に命乞ひをしてゐるのである。だが心百合は止まらない。止まるどころか彼の絶叫を聞いてさらに己を興奮させ、ちやつと、と云つたのも忘れてしまつたかの如く実の兄の体をさらに荒々しく持ち上げては落とし、持ち上げては落とし、其の巨大な陰茎を刺激してゐるのであつた。
「あがあぁぁぁ!!!こゆ”り”っっっっ!!!!ぅごぉあああああっぁぁ!!!!」
「えへへ、気持ちいーい? 」
「こゆりっっ!!こゆり”っ!!!!!こゆっ!!!!」
「んー? なぁに? もっと激しくって言ったのはお兄ちゃんでしょう?」
「あぁがぁぁっっ!!!ごゆ”り”っ!!!」
「んふふ、しぃにぃは本当に私のこと好きなんだねぇ。いくら家族でも、ちょっとドキドキしちゃうな、そこまで思ってくれると。------」
腰を性交のやうに振つて、男を一人持ち上げ、しかも其の体を激しく上下させてなお、彼女は息を乱すこともなく淡々と快楽を味はつてゐる。が、其の快楽を与えてゐる側、------詩乃はもう為すがまま陵辱され、彼女の名前を叫ぶばかりで息を吸えてをらず、わなわなと震えてゐる唇からは血の流れを感じられず、黒く開ききつてゐる瞳孔からは生の活力が感じられず、もはや処女を奪はれた生娘のやうに肛門から鮮血を垂れ流しつつ体を妹の陰茎に突き抜かれるばかり。でも、其れでも、幸せを感じてゐるやうである。何故かと云つて、彼ら兄弟は本当に妹を愛してゐるのである。其の愛とは家族愛でもあると同時に、恋ひ人に向ける愛でもあるし、崇敬愛でもあるのである。そしてそこまで愛してゐる妹が自分の体を使つて喜んでくれてゐる、いや彼の言葉を借りると、喜んで頂けてゐるのである。…………此の事がどれほど彼にとつて嬉しいか、凡そ此の世に喜ぶ妹を見て嬉しくならない兄など居ないけれども、死の淵に追ひ込まれても幸せを感じるのには感服せざるを得ない。彼を只の被虐趣味のある変態だと思ふのは間違ひであり、もしさう思つたのなら反省すべきである。なんと美しい愛であらうか。---------
「んっ、………そろそろ出そう。……………」
さうかうしてゐると、心百合はどんどん絶頂へと向かつて行き、たうたう、と、云ふより此れ以上快感を得てしまつては途中で射精を止める事が出来ない気がしたので、さつさと逝つてしまはうと其の腰の動きをさらに激しくする。
「ひぎぃ!!うぐぇ!!ごゆりっ!!じぬ”っ!!!じぬ”ぅっっっっ!!!!」
死ぬ、と、詩乃が云つた其の時、一つ、心百合のモノが暴れたかと思ひきや、唯でさへ口を犯された際の名残で大きく膨れてゐた彼の腹がさらに膨らみ、そして行き場を失つた精液が肛門をさらに切り裂きながら吹き出て来て、床に落ちるとさながら溶岩のやうに流れていく。
「あっ、あっ、ちょっ、…………そんなに出たら、………あぁ、もう! 」
心百合は急いで詩乃の体から男性器を取り出し床に捨てると、本棚に向かつて流れていく精液を兄の体を使つて堰き止め、ついでにもう殆ど動いてゐない那央を雑巾のやうに扱つて軽く床を拭き、ほつとしたやうに一息ついた。
「まだ出したり無いけど、ま、この辺にしておこうかな。………これ以上は本が濡れちゃう。-------」
続けて、
「なおにぃ、しぃにぃ、起きて起きて、-------」
だが二人とも、上と下の口から白くどろどろとした液体を吐き出し倒れたままである。
「-----ねっ、早く起きて片付けてよ。でないともう一度やっちゃうよ?」
と云つて彼らの襟を背中側から持ち、猫をつまむやうにして無理やり膝立ちにさせると、那央も詩乃も一言も声を出してくれなかつたがやがてもぞもぞと動き始め部屋の隅にある、彼女がいつも精液を出してゐるバケツを手に取り、まずは床に溜まつてゐる彼女の種を手で掬い取つては其の中に入れ、掬い取つては其の入れて"行為"の後片付けをし始めたので、其の様子を見届けながら彼女もウェットテ��ッシュで血やら精液やらですつかり汚れてしまつた肉棒を綺麗にすると、ゴロンとベッドに寝転び、実の兄としてしまつた性交の余韻に、顔を赤くして浸るのであつた。
那央たち兄弟は体中に感じる激痛で立つことすら出来ず、ある程度心百合の精液をバケツに入れた後は這つて家の中を移動し、雑巾を取つて来て床を拭いてゐたのであるが、途中何度も何度も気を失ひかけてしまひ中々進まなかつた。なんと惨めな姿であらう、妹の精液まみれの体で、妹の精液がへばり付いた床を雑巾で拭き、妹の精液が溜まつてゐるバケツの中へ絞り出す。こんな風に心百合の精液を片付けることなど何時もやつてゐるけれども、彼女に犯されボロ雑巾のやうな姿となつた今では、自分たちが妹の奴隷として働いてゐるやうな気がして、枯れ果てた涙が自然と出て来る。-------あゝ、此の涙も拭かなくては、…………一つの拭き残しも残してしまつては、俺たちは奴隷ですらない、人間でもない、本当に妹の玩具になつてしまふ。だがいくら拭いても拭いても、自分の体が通つた場所にはナメクジのやうな軌跡が残り、其れを拭こうとして後ろへ下がるとまた跡が出来る。もう単純な掃除ですら俺たちは満足に出来ないのか。異様に眠いから早く終はらせたいのに全く進まなくて腹が立つて来る。が、読書に戻つて上機嫌に鼻歌を歌ふ妹のスカートからは、蛇のやうに”ソレ”が、未だにビクリ、ビクリと、此方を狙つてゐるかの如く動いてゐて、とてもではないがここで性交の後片付けを投げ出す事など出来やしない。いや、そもそもあれほど清らかな妹にこんな汚い仕事などさせたくない。心百合には決して染み一つつけてなるものか、決して其の体を汚してなるものか、汚れるのは俺たち奴隷のやうな兄だけで良い。-------さう思ふと急にやる気が出てきて、二人の兄達は動かない体を無理やり動かし、其れでも時間はかかつたが綺麗に、床に飛び散つた精液やら血やらを片付けてしまつた。
「心百合、………終わったよ。-----」
「おっ、やっと終わった? ありがとう」
「ごめんな、邪魔してしまって。…………」
「んふ、いいよいいよ、その分気持ちよかったし。-------」
さう心百合が云ふのを聞いてから、兄二人は先程まで開けることすら出来なかつた扉から出て行こうとする。
「あ、お兄ちゃん、------」
心百合が二人を呼び止めた。そして、
「-----また明日もしようね」
とはにかみながら云ひ二三回手を振つたのであるが、那央も詩乃も怯えきつた顔をさらに怯えさせただけで、何も言はずそそくさと部屋から出ていつてしまつた。
「詩乃、…………すまん。…………」
心百合の部屋を後にして扉を閉めた後、さう那央が詩乃に対して云つたけれども、云はれた本人は此れにも特に反応せず自分の部屋に、妹の精液が入つたバケツと共に入りほんの一時間前まで全ての切掛となつたダンベルがあつた位置に座り込んだ。其のダンベルと云へば、結局心百合の部屋から出る時に那央が手に持つてゐたのであるが、詩乃が自室に入る際に階段を転げ落ちてゐく音がしたから多分、兄と一緒に踊り場にでも転がつてゐるのであらう。もう其れを心配する気力も起きなければ、此れ以上動く体力も無い。なのに体中に纏わりつく心百合の精液は冬の冷気でどんどん冷え、さらに体力を奪つて来てゐる。ふとバケツの方に目を向けると、二人の血でほんのりと赤みがかつた妹の精液が半分ほど溜まつてゐるのが見える。-------一体これだけでも俺たち男の何倍、何十倍の量なのであらうか。一体俺たちがどれだけ射精すれば此の量に辿り着けるのであらうか。一体どれほどの時間をかければ人の腹を全て精液で満たすことが出来るのであらうか。しかも其の精液の中では、男の何百、何千倍と云ふ密度で妹の精子が泳いでゐると云ふではないか。…………恐ろしすぎる、もはやこの、精液で満たされぱんぱんに張つた腹が彼女の子供を授かつた妊婦の腹のやうに見えてくる。もし本当にさうなら、なんと愛ほしいお腹なのであらう。………が、残念なことに、男は受精が出来ないから俺たちは心百合の子供を生むことなど出来ぬ。其れに比べて彼女の子供を授かれる女性の羨ましさよ、あの美しい女神と本来の意味で体を交はらせ、血を分かち合ひ、そして新たな生命を生み出す、-------実の妹の嬲り者として生まれた俺たち兄弟とは違ひ、なんと素晴らしい人生を歩めるのであらう。だが俺たちの人生も丸切無駄では無いはずである。なんせ俺達は未だ生きてゐる。生きてゐる限り心百合に使つて頂き喜んで頂ける。もう其れだけで十分有意義である。詩乃はパキパキと、すつかり乾きつつある心百合の精液を床に落としながら立ち上がると、バケツに手をつけた。
--------と、丁度其の時、妹の部屋の方向から、ガチャリと扉の開く音がしたかと思えば、トントントン…………、と階段を降りていく軽い音が聞こえてきた。さう云へば、ふたなりも男と同じで射精をした後はトイレが近くなるらしいから、階段下のトイレに向かつたのであらう。と、詩乃は思ひながら其の足音を聞いてゐたのであるが、なぜか途方もない恐怖を感じてしまひ、心百合が階段を降りきるまで一切の身動きすら取らず、静かに息を潜めて心百合が戻つて来るのを待つた。----今ここで扉を開けてしまつては何か恐ろしいことになる気がする。…………其れは確かに、今しがた瀕死になるまで犯された者の「感」と云ふものであつたがしかし、もし本当に其の感の云ふ通りであるならば、先程階段を転げ落ちていつた那央はどうなるのであらう。多分兄貴も俺と同じやうに全く体が動かせずに階段下で蹲つてゐるとは思ふが、もし其処に心百合がやつて来たら? いや、いや、あの心優しい心百合の事だし、しかももう満足さうな顔をしてゐたのだから、運が良ければ介抱してくれてゐるのかもしれない。————が、もし運が悪ければ? 此の感が伝えてゐるのは後者の方である、何か、とんでもなく悪い事が起こつてゐるやうな気がする。さう思ふと詩乃は居ても立つても居られず、静かに静かに決して音を立てぬようそっと扉を開けると、ほとんど滑り落ちながら階段を降りて行く。途中、那央が居るであらう踊り場に妹の精液の跡があつたが、兄は居なかつた。でも其の後(ご)もずつと精液の跡は続いてゐたので何とか階段を降りきつたのであらうと一安心して、自身も階段を降りきると、確かに跡はまだあるのであるが、其処から先は足を引きずつたやうな跡であり、決して体を引きずつたやうな跡ではなくなつてゐる。…………と云ふことは、兄はもしかして壁伝いに歩いたのだらうか、------と思つてゐたら、ふいに浴室の方から声が聞こえてきたやうな気がした。最初は虫でも飛んでゐるのかと思つたけれども、耳を澄ますと矢張り、毎日のやうに聞いてゐる、少し舌足らずで可愛いらしい声が、冬の静寂の中を伝はつて確かに浴室から聞こえてくる。そしてよく見れば、兄の痕跡は其の浴室へ向かつて伸びてゐる。------いや、もしかしたら精液まみれで汚れてしまつた那央を綺麗にしようと、心百合がシャワーを浴びせてゐるのかもしれない、それに自分もティッシュで拭くだけでは肉棒を綺麗にした気がせず、もしかするとお風呂にでも浸かつてゐるのかもしれない。…………が、浴室に近づけば近づくほど嫌な予感が強くなつてくる。しかも脱衣所の扉を開けると、ビシュビシュと何やら液体が、無理やり細い管から出てくるやうな音、-----毎夜、妹の部屋から聞こえてくる、兄弟たちを虜にしてやまない"あの"音が聞こえてくる。
「あ、あぁ、…………」
と声を漏らして詩乃は、膝立ちになり恐る恐る浴室の折戸を引いた。すると心百合は其処に居た。此方に背を向け少し前のめりになり、鮮やかな紺色のスカートをはためかせながら、腕を大きく動かして甘い声を出して、確かに其処に居た。-----
「こ、こゆり。……………」
「うん? もしかして、しぃにぃ?」
心百合が此方に振り向くと、変はらずとろけ落ちさうなほど可愛い彼女の顔が見え、そして彼女の手によつて扱かれてゐる、変はらず悪夢に出て来さうなほどおぞましい"ソレ"も見え、そして、
「あんっ、…………」
と、甲高い声が浴室に響いたかと思えば腕よりも太い肉棒の先から白い液体が、ドビュルルル! と天井にまで噴き上がる。
「あぇ、こゆり、………どうして、…………」
「んふ、やっぱり中途半端って良くないよね。もうムラムラしてどうしようも無かったから、いっその事、我慢しないことにしたんだぁ。……………」
其の歪んだ麗しい微笑みの奥にある浴槽からは、彼女の言葉を物語るかのやうに入り切らなかつた精液がどろどろと床へと流れ落ちていつてゐる。……………いや其れよりも、其の精液風呂から覗かせてゐる黒いボールのやうな物は、其れに縁にある拳のやうな赤い塊は、もしかして、-------もしかして。………………
「あ、兄貴、…………」
もう詩乃には何が起きてゐたのか分かつてしまつた。矢張り、良くないことが起きてゐた。其れも、最悪の出来事が起きてゐた。-------射精は途中で無理やり止めたものの合計で四回も絶頂へ達せられたし、其れなりに出せて満足した心百合は、兄たちが"行為"の後片付けをしてゐる最中に読書を再開したけれども、矢張りどこか不満であつたのか、鼻歌を歌ふほど上機嫌になりつつも悶々としてゐたのであらう。何しろあの時妹の肉棒は、惨めに床を拭く俺たちを狙ふかのやうに跳ねてゐたのである。其れで、兄たちが居なくなりやうやく静かになつて、高ぶつた気もついでに静まるかと思つたのだが、意外にもさうはならない、むしろ妹の男性器はどんどん上を向いていく。あゝ、やつぱりお兄ちゃんたちの顔と叫びは最高だつた。あれをおかずにもう一発出したい。………と思つても、兄たちがバケツを持つていつてしまつたので処理をしようにも出来ず、結局我慢しなければならなかつたが其のうちすつかり興奮しきつてしまひ、ベッドから起き上がつて、一体どうしたものかと悩んだ。------いや別に、バケツはあと一つ残つて居るのだから今ここで出してもよいのだけれども、其れだけで収まつてくれる筈がない。お風呂も詰まつてはいけないとお兄ちゃん達が云ふから駄目だし、外でするなんて、夜ならまだしもまだ太陽が顔を覗かせてゐる今は絶対にやりたくない。そもそも外でおちんちんを出して自慰をするなぞ其れこそ捕まつてしまふ。どうしよう。…………さう云へばさつき、さういえば階段からひどい音が聞こえたのは少し心配である。もう二人は歩くことも出来ないのかしらん。可哀想に、歩くことも出来ないなんて其れは、其れは、……………もはや捕まえて欲しいと自分から云つてゐるやうなものではないか。さうか、お兄ちゃんたちをもう一回犯せば良いんだ。どつちが階段を下りていつたのかは知らないが、歩くことも出来ないのだから下の階には二人のうちどちらかが居るはず、いや、もしかしたら二人共居るかもしれない。-------と、考へると早速部屋から出て、階段を下り、下で倒れてゐた那央を見つけると服を汚さぬよう慎重に風呂場まで運んで、そして、----ここから先は想像するのも嫌であるが、心置きなく犯して犯して犯して犯したのであらう。浴室に散乱するシャンプーやらの容器から那央が必死で抵抗したのは確かであり、其れを己の力で捻じ伏せ陵辱する様は地獄絵図であつたに違いない。いや、地獄絵図なのは今も変はりは無い。何故かと云つて心百合のモノは此方を見てきてゐるのである。ビクビクと自身を跳ね上げつつ、ヒクヒクと尿道を蠢かしてゐるのである。此の後起こることなんて直ぐ分かる。-------逃げなくては、逃げなくては、………逃げなくてはならぬが、心百合が頬を赤くし愉快な顔で微笑んで来てゐる。あゝ、可愛い、………駄目だ、怖い、怖くて足が動かない。…………と、突つ立つてゐると心百合の手が伸びてくる。そして、抱きしめられるやうにして腰を掴まれるとやうやく、手が動くようになり床に手を付けた。が、もう遅い。ずるずると、信じられない力で彼の体は浴槽の中へ引きずり込まれていく。どれだけ彼が力強く床に手を付けようとも、どれだけ彼が腰に回された手を退けようとも、ゆつくりと確実に引きずり込まれていく。そして、またたく間に足が、腰が、腹が、胸が、肩が、頭が、腕が、どんどん浴室の中へと入つて行き、遂に戸枠にしがみつく指だけが外に出てゐる状態となつた。が、其の指も、
「次はしぃにぃの番だよ? 逃げないで。男でしょ?」
と云はれより強く引つ張られてしまふと、たうたう離してしまつた。
「やめてええええええええええええええええええええええ!!!!!!!!!!!!!!!!!」
心百合と云ふたつた一三歳の、未だぷにぷにと幼い顔立ちをした妹の力に全く抗えず、浴室に引きずり込まれた詩乃はさう雄叫���を上げたが、其の絶叫も浴室の戸が閉まると共に小さくなり、
「んふ、………まずはお口から。-------」
と、思はず恍惚としてしまふほど麗しい声がしたかと思ひきや、もう聞こえなくなつてしまつた。
(をはり)
0 notes
Text
【小説】鳴かない (下)
大学四年生の郡田さんは単位が不足していて、そのせいで卒業が危うかった。
長い長い夏休みが終わって大学がまた始まると、彼からくる連絡は、遊びの誘いではなくて、朝、授業に間に合うように起こしに来てくれ、というものになった。
お互いのアパートが近かった私は、郡田さんの部屋の合鍵を預かり、講義の時間に間に合うように彼の部屋へ行き、布団をひっぺがして起こさなくていけなかった。
郡田さんの部屋は散らかってはいるものの、物が多いという印象はなく、生活に必要最低限の物だけがかき集められているという感じがした。寝ている人、しかも年上の男性の部屋に、鍵を開けて堂々と踏み込むというのは、なんだか心のどこかに引っ掛かるものを覚えた。
夏が終わっても郡田さんは相変わらずで、ベッドの中には、裸同然の格好をした女性が一緒にいることも多かったけれど、いつの間にか慣れた。いつまでも不慣れなのは連れ込まれた女性の方で、朝、突然鍵を開けてやって来た私を、彼の本命の彼女なのだと勘違いして、しどろもどろに慌て始めることがしょっちゅうだった。彼の部屋で同じ女性と鉢合わせになることは一度もなく、私は毎回、素っ裸かそれに近い下着姿の女性に、初めまして郡田さんのサークルの後輩です、恋人ではないのでご安心を、という挨拶をしなければならなかった。
肝心の郡田さんはいつも通り飄々としていて、まだ寝惚けているのだろう、起こしてくれてありがとう、なんて言いながら、全裸のまま私に抱きついたりすることもあった。
人の裸というものは、日頃は見る機会もなく、見えたとしても決して見てはいけないという気持ちになるが、見慣れればどうってことはない。素っ裸のまま布団に包まって眠っていた彼らよりも、そんな彼らの部屋にずけずけと踏み込み、布団を引き剥がす私という存在の方が、よっぽど恥ずべき生き物のような気がした。
郡田さんは起きるとさっさと女性を部屋から退出させて、シャワーを浴びる。その間に私は台所を拝借し、冷蔵庫の中の残り物で何か適当に朝食を作った。郡田さんはそれをいつも美味しそうに食べ、私に感謝の言葉を述べた。軽いハグが、その言葉とセットの時もあった。私はその度に、自分の身体が不自然にぎくしゃくと軋む音を立てているような気がした。
郡田さんの身支度が済むと一緒に部屋を出る。大学までの道を、二人並んでゆらゆらと歩いた。秋の光に照らされた朝の景色は、いつもどこか白くきらきらと瞬いていて、濃厚な金木犀の甘ったるいにおいに頭がくらくらした。少しずつ冷えていく風の温度に、私はいつも少しだけ泣きたくなった。
休みの日は夏と変わらず、私と鷹谷はよく郡田さんに誘われて飲みに行ったり遊びに行ったりした。他の部員が一緒に来る時もあれば、三人だけで集まることもあったけれど、郡田さんが私に手を出してくることはやっぱりなかった。せいぜい酔っ払ってもたれかかってくるくらいで、無理にお酒を飲ませてどうこうしようということはなかった。彼はこの頃、部の飲み会で女の子に手を出すということをしなくなっていた。私以外の女子には全員、手を出した後だったからだ。
女の子を連れ帰らなくなった郡田さんは、飲み会でへろへろに酔っ払うようになった。家が近所で、合鍵も預かっている私が、彼を送ることが増えた。時々、彼は自分の家ではなく私の家に行きたいと言って聞かず、渋々部屋へ上げることもあった。けれどそんな時も郡田さんは私が来客用の布団を敷くのを大人しく待ち、その布団にころんと横になってすぐに眠った。
一度だけ、急に冷え込んだ秋の夜、郡田さんは私を抱き締めたまま眠ったことがあった。優しい力で私を腕に抱いたまま、しばらくこうさせて、と言ったきり、そのまま眠ってしまったのだ。けれど、その晩もそれ以上何かしてくるということはなかった。
彼の腕に抱かれていると、身体が不自然にねじ切れていくような錯覚を覚えた。眠れないまま、暗闇にじっと目を凝ら��、私はあの花火の夜のことを思い出していた。あの夏の蝉たちは、皆ひとりぼっちから抜け出せたのだろうか。
あの時、交わした言葉について、その後彼と語ることはなかった。あの子供のようなくちづけの意味も、すきだよという声の重みも。
鷹谷はそんな私と郡田さんの関係を、少しばかり心配していた。鷹谷は、私が酔った彼を送って帰る度、何か言いたげな表情をしていたけれど、結局は何も意見しなかった。
「大丈夫か」
鷹谷はそんな一言で私に問いかけた。
「大丈夫だよ」
私はいつもそう返した。鷹谷が何についてそう尋ね、私は何についてそう答えたのか、何もわからないまま、だけど必ずそう返事をした。
郡田さんがどう思っているのか、私にはわからなかった。誰かにこの話をすれば、彼は美茂咲のことが本当に大切で、だから手を出さないのだ、美茂咲だけは抱かれないのだ、と言う人と、美茂咲は都合良く使われているだけだ、遊ばれているだけなのだ、と言う人がいた。
どちらの意見にも賛同できなかった。いつものように優しく笑う郡田さんを見ていると、前者の意見のような気がして、酔った夜に私の前だけで見せる、何かを失ってしまった悲しみに囚われているような儚い笑い方をする彼を見ていると、後者のような気がした。
「郡田さんは私のこと、どう思っているんですか」
そう本人に問いかけることができたのは、十一月が終わる頃だった。その日私は、特にこれといった用もないのに、郡田さんの部屋でだらだらと過ごしていた。彼は友達から借りてきたのだというテレビゲームをしており、私はそれをぼんやり眺めていた。
私の言葉に、うん、と彼は返事をした。
「魚原は、そうだね、頭は良いし真面目なんだけど、時々、妙に抜けてるよね」
「そうですか」
「たまにリュックの肩紐がねじれてるの、気になるんだよなぁ」
「言って下さいよ、それは」
私が顔をしかめてそう言うと、彼はコントローラーを握り、画面を見つめたまま、うん、そうするね、と言った。画面の中では郡田さんは極悪非道人になっていて、ヘリコプターを強奪すると、夜景の上を飛びながら、暗殺対象がいるビル目がけてミサイルを発射していた。
「魚原は、俺のことどう思ってるの」
爆音、建物が崩壊する音、人々の悲鳴。凝った音響を聞きながら、それでも彼は容赦なく二発目のミサイルを撃つ。
「郡田さんは――」
画面の中でビルが完全に崩れ去る。よくやった、引き返せ、という次の指令が画面下に字幕となって表示される。けれど彼は、瓦礫の山となった、粉塵をまとうビルの残骸に向けて、さらにもう一発、ミサイルを落とす。
「――変な人です」
「どう変なの」
「次々違う女の人を引っかけてきては、すぐ寝るし」
「うん」
「サークルの女の子全員に手を出すし」
「全員っていうのは言いすぎ。まだ魚原には手ぇ出してないでしょ」
「それも変です」
「変? どうして?」
ビルの残骸が燃えていた。真っ赤な火柱がわっと立ち上がる。次々と街が燃えていく。漆黒の中の銀河のような煌めきが、夜景が、人々の営みが、全て炎の中へと飲み込まれていく。郡田さんの操縦するヘリはゆっくりと上昇し踵を返す。来た道を引き返すように飛んでいく。
「魚原に手を出してないことが、どう変なの」
「どうして、私だけなんですか」
「魚原だけじゃなかったら、いいの」
郡田さんはそこでちらりと画面から目を離した。画面の中で、ビルを崩壊させ、街に火を放ったその目で、私のことを見た。
「魚原以外にも、手を出してない女の子が他にいれば、それで良かった?」
私は、答えられなかった。
ずっと気になっていた。どうして彼は私を抱かないのか。その機会はいくらでもあるのに、どうしてそうしないのか。私のことをどう思っているのか。
けれど、その問いを持つ度、口に出す度、こうして郡田さんに質問で返される度、どうしたらいいのかわからなくなる。私はどうしたいのだろうか。その問いの答えを知りたいのだろうか。真実を知りたい、そうなのかもしれない。でも本当に、そうなのだろうか。
本当のことを知りたいのであれば何故、郡田さんが口を開くことが、その口から零れ落ちてくる言葉を私の耳が拾い上げることが、こんなにも恐ろしいのだろう。郡田さんの目を見つめることが、こんなにも怖いのだろう。
私は、何を求めているのだろう。
彼に抱かれたいのだろうか。彼に抱かれなかったことを不満に思っているのだろうか。どうして私だけ、と彼を責めているのだろうか。抱かれたいのであれば、どうして抱かれたいのだろう。彼に抱かれたら、何か変わるのだろうか。
彼がどんな答えを出してくれることを、私は望んでいるんだろう。一体何を、彼に尋ねたいのだろう。
何も答えられないでいると、郡田さんはゲームの手を止めた。彼の両腕が伸びてくる。最初は、押し倒されるのかと思った。けれどそうじゃなかった。彼は私のことを抱き寄せ、その両腕の中にすっぽりと私を片付けてしまった。
「泣くなよ」
「……泣いてません」
「悪かった、泣かないでくれ」
郡田さんの声が、頭の上からする。
「どうしても抱かれたいなら、抱かないこともないけど」
私はその言葉に首をぶんぶんと横に振った。考えて言葉を紡ぐより先に、身体がそう反応した。うん、と郡田さんはまた返事をする。
「俺の態度の何かが、魚原を傷つけているのはわかるよ。でも俺は、それがなんなのかよくわからないんだよ」
そんなことを言われたって困る。私がそれを訊きたいぐらいだ。
「俺がいろんな女の子と寝てるのが悪いの?」
私は、郡田さんが多くの女性と肉体関係を持つことに、傷ついているのだろうか。彼に誰とも寝てほしくないのだろうか。
「魚原のことは、ちゃんと女の子として見てるよ。異性として、意識してる。でも、抱かなくてもいいんだ」
郡田さんの言葉に、胸が苦しくなる。どうして苦しくなるんだろう。
理由もわからないままに零れていく涙を、郡田さんのシャツが吸い込んでいく。濡らしてごめんなさい、と言おうと口を開いたけれど、嗚咽が混じった私の言葉は、自分の耳ですら上手く聞き取れなかった。それでも、うん、と郡田さんは返事をしてくれる。
「俺が悪いんだろうな。ごめんね」
私はまた首を横に振ろうとして、振れなかった。
「魚原は、俺のことがすき?」
もう首を縦にも横にも振れなかった。肯定も否定もできない。郡田さんは、そんな何もできない私の頭を撫でた。
「俺は魚原がすきだよ」
そんな言葉が降ってくる。だけれどもう私には、それにどう答えていいのか、何もわからなかった。
こんな男、最低だ。
涙を拭って、そう思った。
顔を上げ、思わず彼の頬を平手打ちした。郡田さんは一瞬、呆気に取られたような顔をして、けれど、すぐに困ったような表情で笑った。
私はこみ上げてくる涙を堪えることもできずに、郡田さんの胸元を濡らした。
彼の優しさは罪だった。彼の優しさは私を蝕んだ。ぎしぎしと心が軋んだ。ずきずきと胸が痛んだ。
ちくしょう。
思わず、そんな言葉が私の口を突いて出てくる。
悔しくて、情けなくて、こんなに憎たらしいのに、こんなに憎みたいのに、悲しいほどに、この人を憎めない。
泣き止むまでずっと抱き締めていてくれた彼の腕の中で、私は郡田さんが嫌いになった。
クリスマスが近付いてきた頃、私の処女を奪ったのは、郡田さんではなく、鷹谷だった。
あの一件以来、私と郡田さんは少し距離を置くようになった。それは意図的な、心理的な理由ももちろんあったけれど、郡田さんが卒論と就職活動に追われ、他人をかまう暇があまりなくなってしまったということが、大きな要因だった。よくよく考えてみれば、四年生の彼が、夏休みあんなに遊び呆けていられるはずはなく、そのしわ寄せが全てこの冬にやって来たのだった。
郡田さんが遊びに誘ってこなくなっても、私と鷹谷は二人で飲みに行ったり、遊びに出掛けたりしていた。
何気ない雑談をしながら居酒屋で飲み、もう一軒どこかへ行きたいねと私が言うと、鷹谷は時計をちらりと見やり、「もう十一時半だ、帰れ」と低く断った。店を出て、送る、と言って歩き出した鷹谷に半ば無理矢理引きずられるようにして家へ帰った私は、完全にただの酔っ払いだった。
私は鷹谷が酔ったところを見たことがない。私がいくら酔っ払っていても、同じ量、時には私よりもずっと多く酒を飲んだはずの彼は、いつもと全く変わらない。顔も赤くならないし、足元がふらつくなんてこともない。言動も感情の起伏も、全て素面の時のままだ。
その日、私はとても酔っていて、部屋まで送ってくれた彼の腕にしがみついて、嫌だ帰らないでと泣いた。鷹谷と二人で飲んでいても、不意に郡田さんのことを思い出して、突然胸の奥の方から、言いようのない感情が湧き上がってくる。今まではそれをじっと我慢していたが、自分の部屋に帰ってきて、最後の最後、感情が爆発したのかもしれない。
鷹谷はそんな私を、まるで小さな子供でも見ているかのような、どうしたらいいのかわからないという、困った表情をしていたが、延々と泣き止まない私を見て何を思ったのか、それとも、実は鷹谷も相当に酔っていたのか、唐突に私を押し倒した。驚いた私が思わず動けずにいると、仏頂面の男友達の口から聞こえてきたのは、すまん、という一言だった。
「魚原は、郡田さんのことが好きなんだろう」
全てが終わると、さっさと元通りに服を着た鷹谷は、まだ布団の中、裸のまま毛布に包まっている私に温かい飲み物を淹れてくれながら、確かにそう言った。
「なのにどうして、郡田さんを嫌うんだ」
「……私、彼のことが好きなのかな」
未だに起き上がれない私がぽつりとつぶやくようにそう言うと、鷹谷は台所に立ったまま、怪訝そうに眉間の皺をより深くした。
「好きじゃないのか」
「そう思う?」
「そうとしか思えん」
「どうして?」
「そうにしか見えん」
鷹谷はマグカップを二つ持ってやって来て、私にホットミルクを差し出した。私がなんとか起き上がってそれを受け取ると、彼は布団の側に腰を降ろし、自分のマグカップを口元へと運んだ。中身は見えなかったが、においでわかった、コーヒーだ。
鷹谷はいつも、コーヒーをブラックで飲む。まだ出会ったばかりの頃、渋いね、大人だね、と私が言うと、彼が「砂糖とかミルクとか、正直よくわからん」と返事をしたの���思い出す。
「すまなかった」
「何が?」
「こういうことは、合意の上でするべきだった」
鷹谷が苦い顔をしてコーヒーを飲んだ。そうだね、と私は返してミルクを口へ運ぶ。
もうこれで、郡田さんのことを何も責められない。
いくら酔っていたとはいえ、抵抗しようと思えば、いくらでもできたはずだ。鷹谷に押し倒された時、彼のことを突き飛ばさなかったのは、私がそれを望んでいたから、なのだろうか。嫌ではなかったから、彼のことを拒まなかったのか。では嫌ではなかったら、私はなんでも受け入れるのだろうか。
郡田さんのことを考えている時のような、何かもやもやとした黒い霧が、頭の中に立ち込め、胸元で渦を巻き、私の息を詰まらせ、苦しくさせる。また涙が零れた。名前も付けられない感情が、心を滅茶苦茶にかき乱す。
ああそうか。
名前だ。この感情に、名前を付けたい。名前を付けるよりも先に、行為ばかりが、行動ばかりが先へ進むから、いつもこんなにも苦しくなるのだ。
郡田さんがどうして私を抱かないのかを考えるよりも先に、郡田さんのことが好きなんだと思えれば良かった。鷹谷のことを受け入れるか拒絶するか考えるより先に、私のことが好きなのかと、一言問えば良かった。どうしてそんな、簡単なことに気がつかなかったのだろう。
私たちは、距離が近すぎた。少し身体を動かせば、お互いの身体が触れ合うくらい、距離が近かった。相手のことをどう思っているかなんて、考える暇は与えられなかった。お互いの身体がぶつからないように気を遣うことで精いっぱいで、ぶつかればぶつかったで、そのことに思い悩んだ。相手のことをじっくりと見つめる時間も、自分のことを見つめ直す余裕もなかった。
「大丈夫か」
鷹谷が私の涙に気付いて、そう尋ねる。私はそれに何度も頷いた。
「大丈夫だよ」
鷹谷が何についてそう尋ねたのかは、やっぱりわからない。わからないけれど、それでも大丈夫だと思えた。
鷹谷は泣く私を抱き締めることなんかしなかった。すきだよ、なんて言わなかった。きっと彼は、郡田さんのように優しい力の使い方なんてできないのだろう。でもそのことが、今の私には最も優しいことのように思えた。
ホットミルクが、酒ばかりに溺れていた私の内臓にじんわりと染みていくのを感じた。ゆっくり深呼吸をひとつすると、部屋の中の空気は、もう冬のにおいがした。
郡田さんは卒論を書き上げ、内定も無事に手に入れた。
連絡があったのは、雪がたくさん降った翌日で、久しぶりに私たちは三人で集まり、彼の部屋でトマトチーズ鍋をすることになった。郡田さんの家でごはんを食べることは、今までにも何度かあった。こういう時、買い出しに行くのは後輩である私と鷹谷と決まっていたのだけれど、この時、鷹谷は出掛けるのを渋った。
「魚原は家が近いからいいけど、俺はここまで来るのに雪をかき分けて大変だった。できればもうしばらくは出掛けたくない。買い出しは、二人で行って来て下さい」
雪がほとんど降らない海沿いの地域から、大学進学を機にこの街にやって来た鷹谷は、不機嫌そうな表情でそんなことを言って、私と郡田さんを追い出した。鷹谷の態度は、本気で怒っているように見えたけれど、気を遣ってくれたんだろう、ということはすぐにわかった。私が郡田さんと二人で話ができるように、彼なりに配慮してくれたのだ。
「なんだか、久しぶりだね」
まだ雪が多く積もっている道を歩きながら、郡田さんはそう言った。彼のことを嫌いになって以来、部室で会えば挨拶程度の言葉は交わしていたが、こうやってお互いにゆっくり向かい合うのは、初めてだった。といっても、せいぜい一ヶ月しか経っていない。けれど夏休みの始めに親しくなって以来、私たちは一ヶ月間も関係が希薄だったことなんかなかった。
「私がいなくても、ちゃんと朝起きれてましたか?」
「うん、まぁ、なんとかね。目覚まし時計、新しく二つ買ったんだよ」
「ああそうだ、内定、おめでとうございます」
「ありがとう。春からは、東京だ」
「今度は、社内の女性全員に手を出すんですか?」
「ははは、即クビになりそうだなぁ」
私が冗談めかして言った言葉に、郡田さんは白い息を吐いて笑った。それから私をまっすぐに見つめて、言う。
「もう、不特定多数の女の人と寝るのはやめたよ」
やめるよ、ではなく、やめたよ、であることに気がついて、私は少しだけ驚いた。忙しくて、そんな暇がなかったのかもしれない、とすぐに思った。
「そうですか」
私の口から出た言葉は、やけに淡泊だった。うん、と郡田さんが頷く。
「もう魚原が泣くの、見たくないからね」
「泣いてなどいません」
「嘘つけ」
私が睨むと、郡田さんは困ったような表情をしていた。その顔を見て思わず微笑むと、私の表情を見て、彼も口元を緩めた。
郡田さんは右手を差し出してきた。私は黙って、左手を絡める。私の指先は冷え切っていたのに、彼の手は温かかった。いつも人より少しだけ温度が高い、この人の持つ熱量を思い出して、私はそれを懐かしく思った。
何も話さないまま、二人手を繋いで、雪の道を歩いた。
私の歩調に合わせてくれているのを感じながら、それでも私は転ばないように、雪に足を取られないように、下ばかりを向いて歩いた。郡田さんが時々思い出したかのようにくちずさむ鼻歌は、どれも知らない曲ばかりで、聞いたそばからどんな歌だったか忘れてしまった。
吹く風は冷たかった。冷気に晒された鼻先がじんと痛くなり、私はときどき鼻をすすった。
今日、寒いね。風邪でも引いたの?
郡田さんは私を振り向きもせず、そんなことを言った。なんでもないです、大丈夫です、と答えて、私は涙を誤魔化した。
どんなに鼻水が垂れてきそうになっても、視界が水気を帯びてぐちゃぐちゃになっても、それでも拭うことはしなかった。荷物を持っていない方の手は、郡田さんが握ってくれていたから。
その晩は、今までで一番楽しい夜となった。
私も郡田さんもすっかり酔っ払ってしまって、ほんの小さなつまらないことでも、馬鹿みたいにげらげらと笑っては肩を寄せ合ってじゃれていた。いくら酒を飲んでも変化のない鷹谷も、この晩だけは、眉間の皺を緩めて、穏やかな表情をしていた。
途中で郡田さんは眠ってしまい、わー、郡田さん寝ちゃやだよぉ、なんて言っているうちに私も寝てしまったようだった。目が覚めた時、部屋の中は恐ろしく片付いていて、私と郡田さんは仲良く同じベッドの中に寝かされていた。ふと見れば、鷹谷はひとり、大きな身体を折り曲げるようにして、炬燵に肩まで潜って眠っている。私たちが眠りに落ちた後、鷹谷が何から何まで全部やってくれたんだとすぐにわかった。
いくら飲んでも平気な鷹谷が羨ましい、と思っていたけれど、酒で潰れることのない人間は、それはそれで損な役回りをしているのかもしれない。
この夜以降は、夏休みに逆戻りだった。
郡田さんは、また積極的に私たちを遊びに誘ってくれるようになった。もうじき卒業してこの街を去ってしまう彼と過ごせる時間を惜しむかのように、年末年始も三人とも帰省などせず、一月、二月、三月と、毎日のように顔を合わせた。もちろんそれは三人きりだけではなかったけれど、他の誰がいたとしても、この三人のうちの誰かがいないということはまずなかった。
その頃になってようやく、郡田さんの優しさが、毒ではなくなった。彼に触れられることも怖くなくなった。彼に触れられると、感情がひどくかき乱されていたけれど、もうそんなことはなかった。
彼が女性と寝なくなったことが、そのことに関係しているのかはわからない。けれど彼が私に言う「すき」という言葉や、柔らかいハグや、頬やおでこに落としてくれるついばむようなくちづけを、受け入れることができるようになった。
その変化に比べれば、私と鷹谷の関係は、ほとんど何も変化していなかった。一度は肉体関係を持った私と鷹谷だったけれど、最も親しい友人だという認識は変わらなかったし、再び身体を重ね合うことはなかった。そういう、男と女の艶っぽい雰囲気になることもなかった。
私と鷹谷は郡田さんの引っ越しの準備も手伝って、退居当日の荷物の運び出しまで一緒にやった。
いろんな思い出の詰まった郡田さんの家はみるみる空っぽになっていった。最後、何もなくなってしまった彼の部屋で、この部屋はこんなに広かっただろうか、と思った。家具どころか絨毯もカーテンさえない部屋は、もはやどこにも郡田さんの面影を見つけることなどできず、ただただ無機質な空間が広がっているだけだった。
大学を卒業し、東京で新しい生活を始めた彼を訪ねることは一度もしなかった。郡田さんがこっちへ足を運ぶこともなかった。
私は郡田さんと連絡を取らなかった。郡田さんも私に連絡してくることはなかった。私は、彼が今どこでどうしているのかを知らない。知らなくていいとすら思っていた。知るべき時が来たら、知るだろうと思った。その時までは、記憶の中に、三人で過ごした日々をそっと仕舞っておきたかった。
郡田さんの存在はいつの間にかサークル内ではタブーとされるようになり、誰もが彼のことを忘れようとしていた。在学中は部員にあれだけ慕われていたのが嘘のようだった。
大学二年生に上がる頃、部室のアルバムから、郡田さんの写真を一枚、拝借したのは、彼のことを、ずっと心の中に留めておきたいと思ったからだ。
私はあと何回、郡田さんと関われるのだろう。私の人生に、もう一度彼が関与することがあるのかすら、わからない。もしかしたら、もう二度と関われないのかもしれない。
わからないけれど、どんな未来が待っているにせよ、彼のことを忘れる日だけは来てほしくなかった。私はそっと郡田さんの写真を手帳に挟め、春が来て手帳を新しくする度に、写真を静かに挟め直した。
***
写真を見つめていたら電話の音がして、はっと我に返る。
ポケットに入れっぱなしだったスマートフォンを取り出して、操作する。画面に表示された鷹谷篤という三文字に、急いで電話に出た。
「もしもし?」
「紡紀は」
電話口で開口一番、ぶっきらぼうにそう言った友人に思わず笑いそうになりながら、私は後ろを振り返る。後輩の彼は、酒のせいだろうか、わんわんと泣き出して、今は泣き疲れたのか布団に突っ伏すようにして眠っていた。
「寝てるよ。ついさっき眠ったとこ」
「魚原が寝る場所は」
「大丈夫、布団もう一組敷くから」
「話したのか」
「何を?」
「写真」
「ああ、うん……」
「そうか」
鷹谷の声には溜め息が混じっていた。吐き出された息がノ��ズとなって、私の耳元でざらつく。
「紡紀には、つらいかもしれんな」
この後輩が、私に少なからず好意を抱いていることは、その態度からなんとなく感付いてはいた。彼は私をよく慕ってくれている。声をかければ、飲み会だろうがカラオケだろうが、彼は私について来る。郡田さんに対する私と鷹谷が、以前そうであったように。
そして自分が、彼の気持ちに応えようとしないであろうということも、私は知っていた。どんなに一緒にいたとしても、私の心の中に、彼が腰を降ろせる椅子はない。
郡田さんがこの街を去って以来、心の中にある椅子は、しばらく誰にも使われてはいないけれども、それでもその椅子にこの後輩が座ることは、きっと一生ないだろう。
「二次会、終わったの?」
時計を見ればもうすぐ日付が変わるところだった。うちのサークルにしては、二次会が終わる時間には早い。電話口の向こうに大勢の人の気配がしなかったので、もう解散したのだろうか、と思っての質問だった。
「いや、早めに抜けた。明日、面接だから」
「ああそうか、就活。頑張ってね」
「ありがとう」
私はもう内定をもらっていて、春からの就職を決めていた。鷹谷の方は、いくつか内定は得たものの、本当にやりたい仕事ではないと、他の企業の面接に回っているのだった。鷹谷の真面目さとひたむきさには、本当に身が締まる思いがする。そのくせ、面接の前日に、飲み会の二次会にまで参加する彼の律儀さと神経の図太さにも、心が震える。
「大丈夫か」
鷹谷がそう訊く。
「大丈夫だよ」
私はそう答える。
もう何度も繰り返したこのやりとりを、私はあと何回、繰り返すのだろう。少しは私の「大丈夫だよ」に、鷹谷を安心させる響きが含まれているだろうか。
何かあったら遠慮せず電話しろ、とだけ言い残して、おやすみも言わせずに鷹谷は通話を切った。不器用な優しさが、そんなところにまで滲み出ている。
いつの間にか室内はすっかり冷え切り、半袖のTシャツ一枚の私には少し寒いくらいだった。リモコンを操作してエアコンを止め、寝ている後輩を踏まないようにベランダに向かい、網戸を全開にした。
夏の熱気がむわっと室内へと流れ込んでくる。聞こえてくる蝉の声に改めて気付いた。ああ、夏だ、と思う。孤独から抜け出そうと、闇の中、ただ声を枯らして叫ぶ、夏。
息を大きく吸い込んだら、火薬のにおいがした。こんな真夜中にどこかで、誰かが花火をしているんだろうか。
思い出す、あの夏の日。
すきだよ、と言ってくれた、郡田さんの声。
今でも耳にこびりついて、取れない。
結局、私は一度も、郡田さんに自分の気持ちを伝えなかった。伝えなくても、伝わっていたかもしれない、と思うのは、慢心だろうか。けれど、この気持ちを好きという言葉で表現することが、本当に正しいことなのか、私自身、今もわからない。
彼が卒業してこの街を発ってしまったことを、三年も経つのに私は未だに実感できない。今でも朝早くに彼のアパートに行けば、そこで彼が眠っているような気がする。部室にも飲み会にもすっかり顔を出さなくなってしまったけれど、まだ大学構内のどこかに、彼がいるような気がする。
彼に会えなくて寂しいだなんて、一度も思わなかった。連絡も取っていない、顔も見ていない。けれども私の心の中の最も身近なところに、まだ彼はいる。
――軽々しく好きと口にできるほど、それは気安い感情ではなかった。好きの二文字に圧縮できるほど、薄っぺらくもなかった。
一体なんという言葉が、この感情を呼ぶのに適切なのか、私は知らない。
名前を付けられないうちは、まだ行動を起こしたくなかった。あと何回、私の人生に機会が残っているのかはわからない。けれど、私という存在がぐちゃぐちゃに歪んでしまわないように、生きていたいと思った。
蝉が鳴いている。
まだ見ぬ誰かを求めて、蝉が鳴いている。
いつかこの感情に名前を付けることができたら、私も郡田さんに伝えよう。だからそれまでは、全部仕舞っておくのだ。心のずっと奥の方に、けれど、決して忘れてしまわないように。
私はそう思って、静かに手帳を閉じた。
<了>
1 note
·
View note
Text
aaaaa
そろそろ有給消化しないと消えちゃうので2連休をとったのだが、ただ家でゴロゴロするのはもったいないので旅行にでも行こうかなと。台湾とか行ってみたいなと思ったんだけど、調べていると2泊はほしかったし、一人旅よりかは数人で行く場所かなーっと。


LCCのHPを見比べていたらバニラエアの新千歳行きの飛行機が相当安かったので北海道へ行くことに。成田で飛行機に乗りこみ、滑走路へ向かう途中でなぜか急ブレーキ。他の乗客も一体何事かとおもったが特にアナウンスは無し…。そして一応無事に離陸してしばらくしたら機長アナウンスがあり、今操縦している操縦士は試験に合格してこの便で初操縦との紹介があった。客室では拍手が起こり、先の程の急ブレーキもちょっと納得した。急ブレーキ以外はほぼ完璧で、流石だね!(まぁほぼオートパオロットだろうけど)。
新千歳へは10時ころ到着、鉄道で移動して12時前には札幌駅に到着。札幌駅直結のステラプレイス6Fにある回転寿司「根室花まる」で昼食をとろうと思ったのだが、あろうことか設備点検のために2日間閉店中!ここの回転寿司けっこう有名なので残念。昼食は回転寿司と決めきっていたので、札幌駅から15分ほど歩くけど「トリトン」というお店へ。回転寿司といえども、やはり北海道のは全くあなどれない。中トロもうまかったけど、一番感動したのは平目の昆布〆かな。口の中で旨味の余韻がずっと続く。サーモンも味濃かったなー。
さてここからは登山。旅行に来てわざわざ山に登るのかよと思われるかもしれないが、札幌には市民のsoul mountainともいうべき有名な藻岩山がすぐ近くにある。高尾山みたいにロープェイやケーブルカーが整備されていて、誰でも簡単に登ってこれる。しかも山頂からは札幌市が一望でき特に夜景は素晴らしいとのこと。おまけに大都市のすぐ近くなのに登山道は原始林。近くにこんな自然があるなんて。
回転寿司��ら札幌駅に戻り、バスターミナルから啓明ターミナル(終点)まで30分くらいだったか?そこから10分ほど歩いて慈啓会病院裏の登山道へ向かう。藻岩山の登山道は4つあるが、ここからのコースが最もポピュラーらしい。登山道入り口にはトイレと泥を洗い流す水場が備えられている。
【コースタイム】登山道入り口(1430)→リフト跡(1450)→山頂(1530)→休憩→下山開始(1600)→登山口(1655)
道がひどい・・・雨でもうぐちゃぐちゃ。ゲイターもってくるんだったな。登山靴が泥だらけになってしまった。低山とはいえ、北海道の紅葉の時期は過ぎていてもう冬の様相。気温は5℃より少し高い程度だったけど、動いているので寒くない。ちなみにこのときの装備は上:レインウェア、JK、ネックウォーマーの下着。下:長ズボン、ネックウォーマータイツ。ほかは手袋と首元に目出し帽みたいなやつ。富士山と同等の装備を用意してきたけど、フリース出すまでではなかった。
藻岩山中腹には日本で最初に作られたというスキー用のリフトの台座が残っている。慈啓会病院裏のコースの途中にあるので、ここから登らないとたどり着けない。
登山道は始めの30~40分は土(本日は泥)の道で、残りは岩の道となる。もしかしてこれが名前の由来?岩の道になった頃にはなんかガスってきたし。
登り始めて約1時間で山頂に到着。展望台 兼 RW駅で、中にはレストランも備えられている。夜景が見れる時間に合わせてきたのだが、日没が16時20分なので1時間くらい時間がある。せっかくだからレストランで一服していきたかったのだが、今日は閉まってるみたい。というか、この日を含めて2週間はRWが点検してるためレストランもRWも動いていないんだって!帰りの足にしようと思っていたのに・・・。根室花まるといい、藻岩山RWといい、なんでこんなに重なるのよ。またさっきのぐちょぐちょの道を戻らなければならないということでだいぶテンション下がる。
まぁ気を取り直して展望台に上がってみると、えっ、何これすごすぎない!?札幌市一望!!!藻岩山、低山とはいえ侮ることなかれ。かなりの絶景に驚いた。視界全部に街じゃん!
夕暮れの時間なので空が少しだけ赤い。天気悪いけど雲がいい感じにかかっている。雲の流れが意外と早く、街が霞んだり霧が晴れたり、そのたびに日本海(写真左上 中央左)と幌内山たち?(写真左上 中央)が見え隠れする。この天気だし、RWも運休してるため山頂展望台には自分以外にカップルの2人しかいない。ほぼ独り占め。ちなみに車に乗っても山頂まで来れる。
今年は11月になっても北海道で雪がふらないとニュースになっていたが、どうやらこの日には雪が降った模様。山頂に薄っすらと積もっていたところに誰かが「はつ雪」と書いたのが残っていた。ただ残念ながら、市内の方では確認できなかったのか、初雪の発表はもう数日後であった。
RW動いていなくても、晴れていれば夜景が見れるまで待機できなくはなかった。ただしこの空模様ではいつ天気が崩れてもおかしくないので、残念だけど少しでも明るいうちに下山することに。夜景なら一応下山中にちょっと見ることはできた、かなり木々に邪魔されたけど。きっと綺麗だったんだろうなぁ、あれだけすごい景色だったんだもの。最近新調したLEDヘッドライトは大変役に立ちました。軽いし明るいし、これで1000円台だからいい買い物したな。
結局下山中に雨が降ってきて、登山道入り口にたどり着いたときには本降りとなっていた。これだけ雨に振られても、防水対策はしっかりしているので服の中はまったく濡れず快適。雨具のフードかぶるよりも、いつも使っているつばのある帽子かぶったほうが視界も確保できるし動きやすいな。登山道は相変わらずぐっちゃぐちゃ!山頂で一回泥落としたんだけど(RW乗れると思って)、また泥だらけになってしまったので登山口の水道を借りることに。気温も5℃くらいまで下がっていたと思うけど、動いていたので寒さを感じることはまったくなかった。
本日の宿はすすきのに近い「SOCIAL HOSTEL 365」。ドミトリーで一泊2800円だったかな(平日料金)。2段ベッドになっているのだが、スペースは布団1.5倍分だけ横に長い約2畳。普通の2段ベッドに比べるとやや広く、しかも周りが木の壁で囲まれているので半個室のような感じ。また、明かりは裸電球でけっこう落ち着く空間となっており居心地が良い。コンセントは2つ。建物の1FはBARとなっており、これは夕食後に利用することに。2F,3Fが客室で、各階に水洗トイレ、シャワー、談話スペース、キッチンが設けられている。コンパクトだけど、まぁ一人旅なんだし十分。ここのスタッフの男性、中東出身ぽく、顔の彫りが深くてかっこいい。後述だけど、BARもいい感じて、このゲストハウスにして大正解だった。個室もあるけどベッドで十分。
夕食は特に行き先を決めず、とりあえずすすきのへ向かう。一通りお店を見たところで、どのお店も良さそうで選べない。 結局自分の目ではなくグーグルさんに載ってる評価で決める。 夕食に決めたのは「北海番屋やっとこ」という居酒屋。平日だからか、客は5人くらいしかいなかった。せ��かくだからここでしか食べらなさそうなものばかり注文してみる。タコの白子、にしんの刺し身など。タコの白子は、要はタコの卵。食感は生のホタルイカとかなり似ている。こいつ単体の味はあまり感じなかった。
ジンギスカンは明日も食べる予定だったんだけど、一応お店の自慢らしかったから注文した。自分で焼くスタイル。にしんの刺し身はアジのサッパリ感とブリのネットリ感の中間の食感。味はまぁ美味というよりも、見た目通りの普通の味かな。
美味しいもので腹8分目くらいまでなり、宿のBARへ。なんとこのBARではシーシャ(水タバコ)を体験することができる。多分スタッフが中東出身(推測)だから、自国の文化を紹介しようと始めたんじゃないかなと思っている。タバコとか吸ったこと無いし吸うつもりも毛頭ないけど、シーシャはウィスキーと合うことからちょっと興味があった。1500円で体験でき、アルコールも付いてくるということでお得な感じするんだが。ということで人生初の煙をやってみる。
炭に火をつけ、50cmくらいのシーシャの先端にフレーバーと一緒に置く。フレーバーの種類たくさんあって迷ったんだが、とりあえずシトラスにしてみる。吸い込むときはなんともないけど、煙を吐くときに喉がいがいがしてむせる。鼻から抜かないと香りを感じない。水を通った煙を吸うので熱くない。シトラスなのか…?って感じだけど、雰囲気は十分に堪能できた笑。炭を継ぎ足せば2時間くらいは楽しめるとのこと。けどやはり、むせそうになる。けど確かに、ウィスキーとの相性は良いかも!チョコ系の甘いフレーバーのほうが相性いいかもしれないな。ちなみにこのBARは宿泊客以外でも利用できる。
翌日は二条市場で朝食。平日でそんなに混んでいなかったけど、外国人は多かった。その場で食べたいもの選んで購入、捌いてくれる。牡蠣がすっごいうまかった!!2つの産地のを1つずつ食べたんだけど、味がぜんぜん違うし、とてもクリーミー。ぶっちゃけこんなに美味しい牡蠣食べたの初めて。しかもかなり大きいのに1つ150円というwwwもう笑うしかない。アワビは500円だったかな、〆たてでコリコリした歯ごたえ。焼きタラバガニは自分で食べたい足を選び、一度蒸してからバーナーで炙る。何も味付けないほうが、カニの風味を感じられる。
昼食へ向かったのはサッポロビール園。二条市場から徒歩で向かったので25分くらい歩いたのでは?ビール園の芝は昨日の雨で輝いていた。到着したのは開園10分前だったが、まぁ結果的に徒歩で来てよかったかな、バス使ってたらもっと前に到着して待ち時間退屈してた。
大学生のころにも一人旅でここに来たけど、レストランに入ったのは初めて。あのときはお金あんま無かったから、大人になったらまた来たいなーと思っていたっけ。今は財力あるからお高いレストランも入れます。
ラムブロシェットと鹿肉のなんちゃら(忘れた)。自分しいたけが食べれないんだけど、今回串に刺さって出てきた焼きしいたけが美味しそうで、つい食べてしまったら全然いけた!けどやっぱ美味いとは言えないが(笑)。
空港へはビール園から直行のバスが出ており、わざわざ札幌駅に戻る必要が無いのが非常に便利。バスを待っている間外でブラブラしていたら、気がつけば虹が出ていた。自然の虹ってでかいよなー。
帰りの新千歳空港の保安検査で、念のためにもってきていた18本歯付きのチェーンを没収された。成田ではなにも言われなかったのに、「三��の形がX線で見えたからダメ」という理論。・・・は?尖っているものは全てダメというなら鍵も杖もダメじゃね?ましてやアイゼンみたいな歯があるわけでもなく1~2cmくらいのちょこんとした歯でどうやって人を傷つけるわけ?1500円くらいで買った安物なのでいい勉強代になったよ。多分ストックはアウトになる可能性大きいので、これから飛行機で登山遠征行くときはリュックは受託したほうが無難だね。テントのポールとかもダメって言われそう。てか、調理用のミニナイフやガスとかは当然アカンから、やっぱ預けないとだめだわ。
ということで以上、「せっかくの有給だけど行くとこないから適当に札幌一人旅しようと思っていたら美味しいものたくさん食べれました」でした。
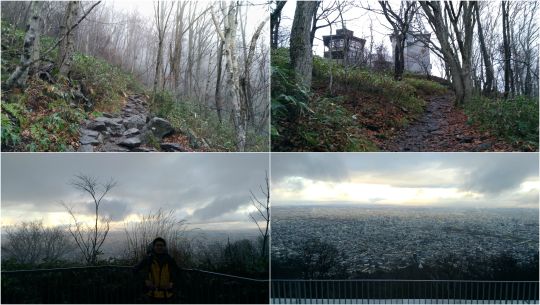
0 notes
Text
「六道の辻に迷うなよ」プレイログ/PC歌仙兼定
ねこのすけ卓様作シナリオ集「怪物の手記」より シナリオ「六道の辻に迷うなよ」プレイログ
KP:かずみ様/@kazumi_coc PL:スミ/PC:歌仙兼定
当然ですが内容にはシナリオのネタバレを多分に含みますので、プレイの予定がある方はご注意ください。
PLが初心者であったため、シナリオの指示以上に、KP、NPCが分かりやすいように誘導する場面があります。必要以上にうろうろ探索してしまったため、得に意味のない動きをしているシーン・台詞もあります。その辺りは気にしないで読める方向けです。RPが走りに走った末、元シナリオとは関係のない設定等も生えております。
※CoCTRPGの性質上、もちろんどのような展開でも受容できる懐の深い審神者向けです※
プレイログを元に、PC視点の小説風にまとめたものをプライベッターに掲載しております。気が向いたら読んでみてね!
「六道の辻に迷うなよ」リプレイ/PC歌仙兼定
【壱】http://privatter.net/p/2294483
---
かずみ:あ、念のためダイスなんでもいいので降って頂けますか!
歌仙兼定:CCB<=80 日本刀(打刀) Cthulhu : (1D100<=80) → 100 → 致命的失敗
かずみ:機能ちょっと事故が発生したので…!
歌仙兼定:wwwwwwww
かずみ:wwwwwwwwwwwww
すずぱか:wwwww
かずみ:振っておいてよかったwwwwwwww
KP:BGM:待機
歌仙兼定:僕の余りある雅が暴走してしまったよ
かずみ:みやびっょぃ
KP:さて
KP:では、「六道の辻に迷うなよ」セッション開始とさせて頂きます!
歌仙兼定:よろしくお願いします!
かずみ:よろしくおねがいします!
KP:では導入から行きますね
歌仙兼定:はい
KP:刀剣男士。それがあなたたちの呼び名です。
KP:刀剣男士は、審神者が霊力を込めて打った刀剣を媒介に、名刀の付喪神が受肉した存在。
KP:審神者を中心とした本丸に所属し、みな家族のような絆で結ばれている。
KP:心に刀を持ち、戦場を駆け抜け、審神者と家族の元へ戻れることが、刀剣男士の誇りである。
KP:人の身で経験するあらゆる事象は「物」であった頃の自分には想像もできなかったことばかり。
KP:あなたは「人」と同じように言葉を交わし、食事を楽しみ、美しさを愛で、そして、「人」と同じように、眠る。
かずみ:こちらが、このシナリオでの刀剣男士の解釈となります
かずみ:色々な行動、思考、RPの際に参考にしていただければと思います。
かずみ:共有メモの方にも後ほど貼っておきますね
KP:BGM:停止
KP:あなたは目を覚ます。
KP:板張りの床に倒れていたようで、鼻先が冷たい。
KP:部屋全体を包む刺すような寒さに、その身を震わせることでしょう。
KP:体を起こしたあなたはあることに気付きます。
KP:あなたは眠る前に何をしていたのか、どうにも思い出せません。
KP:わかるのは自分が 刀剣男士であることだけで、自分の本丸の仲間のことを全く覚えていません。
KP:それどころか、審神者のことも曖昧にしか思い出 せませんでした。
KP:/
KP:BGM:探索
かずみ:さて、ここから探索となります。
かずみ:行動宣言、RPなどよろしくお願いします〜!
歌仙兼定:「おや?ここはどこだろう?ぼくはどうしていたんだっけ……?」
歌仙兼定:とりあえず当たりを見回します/
KP:かしこまりました
KP:真っ白な壁に囲まれたこじんまりとした部屋です。
KP:周りの壁の一方に障子戸がありました。
KP:全体的に薄暗い印象ですが、障子の向こうは外なのか明るくなっています。
KP:部屋の中央には布団が一組敷かれていて、その傍らには走馬灯がぼんやりと光を漏らしていました。
KP:身のまわりを確認すると、 靴を履いておらず、刀剣以外は持ち合わせていませんでした。
KP:/
歌仙兼定:服はきています?
KP:きてますね。
KP:靴のパーツだけない、と考えていただければと思います!
歌仙兼定:了解です!
歌仙兼定:「ふむ、靴がないと足が寒いね」お布団inしてみます/
KP:歌仙兼定が足を入れたのは、使った形跡のない布団でした。
KP:中は冷えております。/
歌仙兼定:「……冷たいじゃないか……💢」掛け布団をめくります/
KP:猛る歌仙が布団をめくりますが、特に何もありません。
KP:少し布団にシワがよったくらいですね。/
歌仙兼定:「(思わず猛ってしまったよ……)」猛る気持ちが収まらず敷布団もめくります/
KP:歌仙がどれほど怒れども、やはり特に何もありません。
KP:布団がとてもシワシワになりました。/
歌仙兼定:「ふん、これくらいにしておいてやるか」走馬灯をよく見てみます/
KP:かしこまりました。
KP:大小さまざまな円が描かれた美しい走馬灯です。
KP:落ち着いた水色に塗り染められた外郭の内側で、ほんのりとした灯りが影絵を照らしています。
KP:走馬灯は二重構造の���篭です。内側の面が回転して、外側の面へ影絵を映し出すように細工されています。
KP:ここで、アイデアをどうぞ/
歌仙兼定:CCB<=75 アイデア Cthulhu : (1D100<=75) → 9 → スペシャル
かずみ:良い出目!
歌仙兼定:「ぼくの雅が囁いている……!」/
KP:布団を存分に弄り倒した歌仙は、ふと、穏やかな走馬灯の光を見てこの部屋に来たことがあるような気がしました。
KP:具体的なことは思い出せませんでしたが、覚えがあることで少しだけ安心しました。/
KP:ここで、オカルトを振ることも出来ます。
KP:/
歌仙兼定:初期値ですがオカルト振ります/
KP:では、お願いします
歌仙兼定:CCB<=5 オカルト Cthulhu : (1D100<=5) → 57 → 失敗
かずみ:初期値ですからねえ
KP:特に分かることはありませんでした。
歌仙兼定:立ち絵のような顔をしていますね……
かずみ:wwwww
歌仙兼定:走馬灯は二重構造で回転するものということですが、今動いてますか?/
KP:内側の面が動いております。
KP:/
歌仙兼定:なるほど、では手にとってみても先程以上に気がつくことはありませんか?可能なら裏面等ひっくりかえしたりして見てみます/
KP:特に走馬灯からこれ以上わかることはありませんね。
KP:ひっくり返してしまうと、ちょっと……壊れる可能性が……というところです。/
歌仙兼定:あ、はい、STR22なのでそっとしておきます
歌仙兼定:部屋を一周し、気がつくことがなければ障子の方へ近づきます
歌仙兼定:/
KP:特に気付くことはございません、そのまま障子の方へ歌仙は向かうでしょう。
KP:障子は、普段和室にある極々一般的な障子です。/
歌仙兼定:一応聞き耳ふってみます
歌仙兼定:/
KP:お願いします
歌仙兼定:CCB<=25 聞き耳 Cthulhu : (1D100<=25) → 27 → 失敗
かずみ:おしい!
KP:辺りは静かだと感じるでしょう。
歌仙兼定:「クッ……」/
歌仙兼定:そっとあけてみます/
KP:かしこまりました。
KP:当たりの様子を警戒しつつ、歌仙が障子を開けると、その先にあったのは庭のような印象の場所でした。
KP:庭にしては殺風景で植え込みや装飾といったものはありません。あなたの目に映ったのは、降り注いでいる小さくて白いもの。
KP:雪だ。頬を掠める空気は冷たく、吐く息は白い。
KP:地面には砂利が敷かれていて、その上には足跡ひとつない雪がうっすらと積もっています。
KP:辺りを見渡してみると、周囲を白い壁に囲まれているのに気付きます。そして正面の壁にだけ引き戸があるのが見えました。
KP:足元はちょうど縁側のようになっていて、足置き石があります。
KP:頭上を確認した所、広がっているのは白んだ空。しかし妙な圧迫感を見て取ります。空は何処までも高く続いているはずなのに、
KP:有限を感じました。まるで見えない天井があるような感覚です。
KP:/
歌仙兼定:「雪、かな?」履物等は見当たりませんか?今歌仙ちゃん足袋ないから裸足のままですよね/
KP:履物は見当たりません。素足で行くしか無いと、歌仙は気付くことでしょう。
KP:/
歌仙兼定:砂利をひとつ拾ってみます/
KP:雪に埋もれた、小さな砂利です。
KP:踏んでも怪我をしない程度の、丸い飾り石ですね。/
歌仙兼定:「ふむ、ここでこうしていても仕方ない、一面の白と足の跡というのもなかなか風流、行ってみるとしよう」刀をしっかり持って、足を踏み出し、遮るものがなければ、静かに正面の引き戸へ/
KP:歌仙が警戒しながら引き戸へ近づくと、張り紙がしてあるのに気付きます。
KP:読みますか?
歌仙兼定:読みます
KP:雑な字で短い文章が書かれていました。
KP:「帰りたければ 鍵を探せ
KP:鍵は お前らには 使えない
KP:使い方は 炎の精が 知っている」
KP:/
かずみ:共有メモにもはりますね!
歌仙兼定:「雑な字だね、書いたものに今度指南してやらねば」持って帰る気満々で張り紙を剥がそうとします/
KP:張り紙は綺麗に歌仙の手元へ収まりました。/
KP:ここで、目星をお願い致します/
歌仙兼定:はい
歌仙兼定:CCB<=70 目星 Cthulhu : (1D100<=70) → 46 → 成功
KP:雑な字だと、張り紙を詳しく観察していた歌仙は、裏面も文章が書かれており、透けていることに気が付きます。
KP:/
歌仙兼定:「なんだい、裏紙なんて、ケチなこと、ますます書いた者に一言言ってやらねば気が済まないよ」読みます/
KP:「じっくり 待てばいい
KP:利口なやつは そうするのさ」
KP:と、同じ字で書いてありました、/
かずみ:共有メモに追加します!
歌仙兼定:「いや、ぼくはこれを書いた者に一秒だって速く指南をしなくてはならないんだ💢どこかに隠れているんのではないだろうね!?」改めて周囲を見回します/
KP:では、辺りを詳しく観察した歌仙の眼には、空の様子がとまるでしょう。
KP:空からの光には方向性があるようです。
KP:明るい方を目で追うと、障子を背にして右手側の天井に光源があるようだとわかるでしょう。
KP:知識、アイデア、天文学、のいずれかが振れます/
歌仙兼定:引き戸のある壁の右上あたりの天井で間違いないでしょうか?アイデアが振りたいです/
KP��そうなります。アイデアどうぞ!
歌仙兼定:CCB<=75 アイデア Cthulhu : (1D100<=75) → 65 → 成功
KP:/
KP:天上をじっと見つめていた歌仙はひらめきます。これか、゙「朝日」のように見える゙と。
KP:/
かずみ:(天井ですね)
KP:それ以外には歌仙にとって特に気になるところはないでしょう。/
歌仙兼定:「朝日……」得に太陽とか見えるわけではないけど、なんとなくひらめいたって感じですかね?/
KP:そんな感じですね、(あ、なんか朝日っぽい……)という位の感覚ですかと。/
歌仙兼定:ありがとうございます。では一応、引き戸に聞き耳をふってみたいです/
KP:お願いします。/
歌仙兼定:CCB<=25 聞き耳 Cthulhu : (1D100<=25) → 90 → 失敗
KP:引き戸の先は静かだと感じます。/
かずみ:出目が雅
歌仙兼定:「な、何か今ちょっと危ないような気がしたけど気のせいだったよ!!!!」雅にそっとあけてみましょう/
KP:歌仙が警戒しつつ引き戸を開けると自然とほっとしたことでしょう。庭とは違い寒くありません。どうやら室内のようです。
KP:しかし、続いて人影があることに気付きます。
KP:部屋の中央に卓があり、あなたの方を向いて卓についている見知らぬ青年がいました。/
歌仙兼定:「やあ、こんにちは、ここはあたたかいんだね」寒いので普通に入ります。青年に挨拶します/
青年:「……俺に言っているのか?」
KP:ここでアイデアをお願いします/
歌仙兼定:CCB<=75 アイデア Cthulhu : (1D100<=75) → 25 → 成功
KP:歌仙は不思議な感覚を青年に対して覚えます。
KP:何となくではあるものの、青年に悪意はないと感じさせるものでした。
KP:そして、警戒しながら部屋に入った歌仙の目には、部屋の様子が映ります。
KP:部屋は古い家のような造りです。
KP:砂利敷きの地面から一段上がった所が板の間になっていて、青年はそこに座っています。
KP:板の間に上がるための足置き石もあ りました。
KP:四方を囲む白い壁には、ひび割れや落雷を思わせるような黒い模様が描かれています。
KP:左右の壁にはそれぞれ引き 戸があり、奥の壁には更に奥へ行くための通路がありました。/
歌仙兼定:「きみ以外、ここに誰かいるのかい?」戸口で話しかけて青年の反応を待ちます/
青年:「ここには……いない、だろう」
青年:「ほかは知らない」
KP:/
歌仙兼定:「であれば、今ここでは僕はきみに話しかけたと理解するのが筋だろう。外は寒いのだけど上がってもかまわないかな?足が少し濡れている、ふくものがあればお借りしたい」話しかけます/
青年:「それも、そうか……」
青年:「上がるのは構わない」
青年:「ただ、ふく物は……この本くらいか」
KP:青年が、卓の上から一冊の和綴じの本を手にとります。/
歌仙兼定:「きみ、正気か、本は読むためのもので足を拭くものではない💢」仕方ないので適当に手で足の露をはらって部屋へあがります、青年に近づき手に持った本を見ます/
青年:「そう、なのか……」
KP:青年は怒っている歌仙に少し驚いている様子です。
KP:歌仙が板の間に上がると、左奥の壁際にギヤマン(ガラス)皿の上に蝋燭が載せられていること、右奥 の壁には絵が三枚飾ってあることに気がつくでしょう。
KP:そしてあちこちに走馬灯がおかれていますが、さほど明るくはありません。
KP:青年の持っている本には「枕草子」との表題が書かれております。/
歌仙兼定:「価値のわからぬものの手にあっては書も泣いていることだろう、その気持ちはぼくらにはよくわかるだろうに」(刀剣男士付喪神的な感じで自然に出てしまった、という感じの台詞で大丈夫でしょうか?
歌仙兼定:青年から本をとりあげパラパラとひらいてみたいです/
かずみ:問題ないです!
青年:「……? そうなのか」
KP:青年はイマイチぴんと来ていない様子です。
KP:では、知識をどうぞ。
KP:/
歌仙兼定:CCB<=60 知識 Cthulhu : (1D100<=60) → 42 → 成功
歌仙兼定:(目利きはまかせてくれ✨)/
KP:文系刀である歌仙は、こちらの本の事を当然知っているでしょう。
KP:有名な随筆です。
KP:春はあけぼの、夏は夜、秋は夕暮れ、冬はつとめて。
KP:春は日の出前、夏は夜、秋は夕暮れ、冬は早朝、それぞれの季節 ごとに姿を変えていく景色の美しさをやんごとない文体で綴っています。/
かずみ:共有メモ追加しました!
歌仙兼定:「冬は……つとめて……」PC的に先程の寒い庭とピンときて良いでしょうか/
KP:さすが文系名刀、現在の状況といい、何か勘づくものがあったようです。/
かずみ:オッケーーです!
歌仙兼定:「なるほど……」
歌仙兼定:「きみ、この本のこともよくわかっていないようだけど、この部屋にあるものについても理解は無いということかな」そうですね、手近にあるなら3枚の絵に視線をうつしたいです/
青年:「そうだな……気がついたら、ここにいた」
青年:「この本はなんだ?」
KP:青年は本に興味を示しております。
KP:絵はここからでも十分に見える距離ですね。
KP:一枚目は、鉛筆��゙描かれた虫のように見える何か。
KP:二枚目は、水彩で描かれた魚。三枚目は、油絵の具で描かれた猿。
KP:どれも額縁に入れられて飾られています。
KP:ここで、知識を-15の補正つきで振って下さいませ/
歌仙兼定:CCB<=45 知識 Cthulhu : (1D100<=45) → 26 → 成功
KP:審神者から借りて読んだことがあったのかもしれません。
KP:どこかの本に書いてあった内容を思い出します。
KP:赤子は母親の腹の中で夢を見るのだという。
KP:微生物に始まり、魚を経て、猿になり、ようやく人間になる、進化の夢。
KP:これは進化の過程を記した絵なのではないか、と歌仙は思い至ります。
KP:/
歌仙兼定:「かいつまんで言えば春夏秋冬の良さについての書だが、この美しい随筆について講説をはじめると1日では足りない。ここから出られたら気の済むまでいくらでも話してやろう」
歌仙兼定:「きみも気がついたらここにいた、と言ったな。それはここではないどこかから来たという認識があるということだ。その点に関してはぼくも同じだ」
歌仙兼定:「ぼくはここから出たい。きみはどうか?」/
青年:「俺は……よくわからない」
青年:「だが、おまえについていこう」
青年:「しかし、お前はその本の中身を知っているのか」
青年:「貸してくれ、読みたい」
KP:青年は歌仙へ向かって手を伸ばしています。/
歌仙兼定:「書に興味を持つことは良いことだ、丁寧に扱うように」本は返してあげます/
青年:「わかった」
KP:頷く青年に本を渡すと、彼はパラパラとページをめくって音読を始めます。
KP:最初は拙くひらがなを選んで読んでいるようなのですが、数 ページめくる頃には、すらすらと漢字も読めるようになっています。
KP:そして冊子を歌仙に返し、
青年:「これでお前と同じになっただろうか」
KP:と、少し得意げです。/
歌仙兼定:「……ここから出たらもっとたくさん書を読むと良い。話はそれからだ」進化?のようなものを目の当たりにして少しおどきますが平静を装って返事します。
歌仙兼定:歌仙的には青年以上に部屋の中にあるものにも興味があると思うので左奥壁際のギヤマン皿とろうそくを見に行きたいです/
青年:「そうだな、そうする」
KP:それでは、青年も歌仙の後ろを立ち上がってついてくるでしょう。
KP:二人が蝋燭の前に立つと、大きな蝋燭が赤々と燃えていることがわかります。
KP:���゙ヤマンの皿は固定してあるので動かすことはできません。
KP:知識、またはアイデアを振ることが出来ます。/
歌仙兼定:アイデアでお願いします/
KP:かしこまりました、お願いします。.
KP:/
歌仙兼定:CCB<=75 アイデア Cthulhu : (1D100<=75) → 10 → スペシャル
KP:それは、歌仙には後約2時間で燃え尽きてしまうとわかります。/
かずみ:(ゲーム内時間です)
歌仙兼定:「この蝋燭はあとニ時間はもちそうだ、かえの蝋燭はこの部屋にあるかい?」青年に確認しつつ見回します/
青年:「ここにはなさそうだな」
KP:青年も歌仙も周囲を見回しますが、代えの蝋燭はありませんでした。/
歌仙兼定:その部屋の光源はその蝋燭ですか?/
KP:その蝋燭に加えて、あちこちに走馬灯が置かれております。
KP:さほど明るくはない様子です。
KP:/
歌仙兼定:なるほど、さっきの庭のように不思議ななんか明るいアレがあるわけではないと/
KP:はい、そんな感じでございます/
歌仙兼定:走馬灯は先程みたものと同じですか?/
KP:いえ、ただの光源としての意味しかもたないものですね。
KP:装飾などがありません。/
歌仙兼定:ありがとうございます、では視線をうつして壁の黒い模様をよく見てみたいです/
KP:壁の模様から得られる情報は特にありませんね。
KP:先程出た描写以上のことは特に読み取ることはできないでしょう。/
歌仙兼定:なるほど。
歌仙兼定:「きみ、この部屋からは出てみたりしてないのかい?ここには奥へ続く通路や戸があるけれど」青年にききます/
青年:「気がついたらここに居たからな」
青年:「どこにも動いてはいない」
KP:青年は答えます/
歌仙兼定:「やれやれ、怠慢なことだな、そんなことではまた怒られ……?うん、誰が怒るのだったかな?」記憶は曖昧なんですよね?/
KP:そうですね、本丸の仲間は勿論、審神者の事も曖昧にしか思い出せない形です。/
KP:青年は「何を言っているんだ……?」という形で首を歌仙を見ています。/
かずみ:(首は見ていないですね!!)
かずみ:(歌仙を見ています)
歌仙兼定:「……とりあえず、この部屋から出てみよう」思い出せないことに多少不安を感じつつ、左の引き戸に……聞き耳をしますよ!!/
青年:「わかった」
KP:頷く青年は左の引き戸へ向かう歌仙に付いていきます。
KP:思い出せないことへの不安があるのか、警戒心強く、歌仙は聞き耳を立てた。
KP:振って下さいませ〜!/
歌仙兼定:CCB<=25 聞き耳 Cthulhu : (1D100<=25) → 9 → 成功
かずみ:おお!
歌仙兼定:(ほとばしる僕の雅)/
KP:では、研ぎ澄まされた歌仙の耳には、小さな鳥の鳴き声が聞こえてくることでしょう。/
かずみ:ドバドバ雅
歌仙兼定:「鳥の声……?」聞き覚えがあったり、何の鳥かわかったりはしませんか?/
KP:鳴き声だけでの判定は、知識と聞き耳の組合せロールとなりますかね/
歌仙兼定:ふむ、じゃあ、まあおいておきましょう、さも思慮深いような顔をして頷いたあと、右の引き戸に向かい聞き耳したいです/
KP:青年も後ろからついてきます。振って下さいませ!/
歌仙兼定:CCB<=25 聞き耳 Cthulhu : (1D100<=25) → 19 → 成功
歌仙兼定:(聞き耳とか雅があれば初期値で十分ってヤツですわ)/
KP:では、戸の向こう側は至って静かであると感じるでしょう。/
かずみ:これが歌仙の雅Power……
歌仙兼定:では右の引き戸をあけてしまいましょう/
KP:かしこまりました、描写します。
KP:歌仙が引き戸を開けると、部屋全体が今までの部屋と比べて、更に暗いことに気が付きます。
KP:今までの部屋は窓から光が差していましたが、この部屋の窓の外は真っ暗でした。
KP:窓には格子がはめられているため、外の様子はよくわかりません。
KP:部屋の中には蛍がふわふわと飛んでいます。静かな虫の声がしました。
KP:部屋の中央には卓があり、奥には調理場があるのが見えます。
KP:壁際に幾つかの棚が備えられていて、食器や食材などが収め られていました。
KP:薄明かりですが走馬灯が照らしているため、問題なく探索はできそうです。/
KP:アイデアをここで振って下さいませ/
歌仙兼定:CCB<=75 アイデア Cthulhu : (1D100<=75) → 72 → 成功
歌仙兼定:(おっと……)/
KP:では歌仙は窓から見える真っ暗な様子を見て、この部屋が月のない夜、新月なのだと気付くでしょう。
KP:/
かずみ:成功なら全部雅の勝ちですね!
歌仙兼定:「やあ、なるほど、夏というわけだな?」部屋に入りましょう。調理場を見て落ち着いていられないでしょうしww/
KP:青年もついていきます。部屋の様子は先程の描写くらいなものですね。/
かずみ:調理場! 調理場!
歌仙兼定:奥が調理場ということなので、そこへ行くまでに一番手前には卓(机的な感じ?)があるのでしょうか?であれば、見てみます/
KP:(そんな感じです)
KP:通りがかりに卓を見た歌仙は、奇妙な物を見つけます。
KP:黒い液体で卓いっぱいに描かれた魔法陣と、一枚の便箋です。
KP:/
かずみ:/忘れすみません!
歌仙兼定:黒い液体はかわいていますか?魔法陣に触らないで便箋を手に取れるなら手にとって見てみます/
KP:乾いている様子はありませんね。便箋は手にとれます。
KP:質のいいシンプルな便箋に、インクで書かれた美しい文字が並んでいます。
KP:読みますか?/
歌仙兼定:美しい文字は読みますね/
かずみ:さすが文系名刀
KP:「誰も 彼も 信じるべきではない」
KP:と、表面にかかれております。/
歌仙兼定:「ふむ、流麗な文字とおよそ似つかわしいとは言えない内容だね」裏も見てみます。/
KP:「特に
KP:角が二本ある奴を信じるなんて 愚かだ」
KP:同じく流麗な文字で綴られております。/
かずみ:共有メモにもはりました!
歌仙兼定:「角が二本……鬼でも出るというのか?」口に出します。そうですね、メモは音読していて青年にも内容は聞こえていたという感じでお願いできますか?共有メモありがとうございます!/
歌仙兼定:めもじゃない、便箋の内容を、です/
青年:「鬼……? そんなものが現れるのか」
KP:(了解しました!)
KP:ここでアイデアをどうぞ!/
歌仙兼定:CCB<=75 アイデア Cthulhu : (1D100<=75) → 9 → スペシャル
歌仙兼定:(奮う雅止まらない)/
すずぱか:雅力・・・
KP:歌仙は一瞬、青年が怯えるような表情をしたように思えた。
KP:恐らく青年は無意識のようで、そんな自分には気付いていない様子です。/
かずみ:雅こそ力!!
歌仙兼定:表情の変化におや?とは思いますが、触れません。魔法陣に見覚えはありますか?乾いてないということはなんだかべったりしている??んでしょうか???/
KP:見覚えは特に無いですね。粘性を持った液体だと感じられます。
KP:/
歌仙兼定:ねちょねちょには触りたくないのでそっとしときましょう……奥へいきます。途中に窓があれば除きますが、先程の描写以上のことはわからないですかね?/
KP:そうですね、特に分かることはございません。歌仙は青年と共に調理場の前へつきました。
KP:調理場は、至って普通の一般的なものです。
KP:何か調理するのに支障はなさそうです。/
歌仙兼定:まず壁際の棚をみます。ふんわりで申し訳ないですが、不自然な食器や食材はありますか?/
KP:そうですね、歌仙が中を検分すると、綺麗な食器や新鮮な食材があります。
KP:特に違和感などもない、普通の食材であるということがわかりました。
KP:こちらでは、欲しいものを宣言して《幸運》に成功すれば、可能な範囲で出てきます。
KP:/
歌仙兼定:あの、ちなみに、持ち物の、鮎20匹は……/
かずみ:ふふふふふふwwwwwwwwwwwwww
KP:残念ながら、今手元にございません。
KP:この棚を探せば、あるかもしれませんよ!/
かずみ:20匹も持ってたんですか!?wwww 確認しそびれてたwwwwww
歌仙兼定:じゃあ鮎探しますwwwwwww/
かずみ:干物だし普段から20匹持ち歩いていてもイケルイケル
KP:はい、幸運をどうぞ!
歌仙兼定:CCB<=60 幸運 Cthulhu : (1D100<=60) → 50 → 成功
歌仙兼定:あったwwwwwwww/
KP:鮎がたくさん出てきました!/
かずみ:美味しい鮎が、どーんどーーーん!
歌仙兼定:「なかなか良い鮎がそろっている、が……ぼく、自分が獲ってきたものでないと不満なんだよね……せめて私が育てました!みたいな、アレ、あるだろ、アレが欲しい」
KP:幸運をどうぞ!
KP:/
歌仙兼定:wwwww
歌仙兼定:CCB<=60 幸運 Cthulhu : (1D100<=60) → 92 → 失敗
KP:��産者証明は付いておりませんでした。/
かずみ:あっ /見逃してたすみません!
歌仙兼定:不満なので、鮎ちょっとおいときましょうwwwww芸術死に技能になるの悲しいけど、あんまりここにあるもの食べたくないんですよね……調理場には流し台もありますか?水道ついてます?/
歌仙兼定:あとお腹が空くような感じはしますか?/
かずみ:まあ、安全な食材であることは確かですがね!
KP:流しも水道も完備されております。そうですね、歌仙は特に空腹を感じていないでしょう。/
歌仙兼定:「空腹が一番の調味料だ、あとで腹が減ったらぼくの料理を披露してやろう」蛇口ひねってみます/
青年:「料理……俺は食事をした覚えが、ないな……」
KP:首をかしげる青年はともかく、新鮮な水が出てきます。/
歌仙兼定:あっ、さんざん鮎探しといてなんですけど、瓶(2つ)と、肉を縛るタコ糸、油はありますか?/
KP:幸運に成功すればあります、どうぞ!/
歌仙兼定:CCB<=60 幸運 Cthulhu : (1D100<=60) → 17 → 成功
KP:無事見つかりました!
KP:/
歌仙兼定:それでは、瓶の一つにお水をいれて蓋をし、もう一つには油をいれて持っていきます/
歌仙兼定:タコ糸も懐へ/
KP:かしこまりました、持ち歩けます/
歌仙兼定:だいたい調理場は見られるところは見た感じでしょうか?/
KP:そうですね、現状見られるものは全て見ました。/
歌仙兼定:この奥に扉や通路はないんでしたよね?そしたらもと居た部屋へ帰ろうかな……帰り際に卓の裏側が見られる造りなら見ていきます/
KP:はい、特にございません。卓の裏側を見ておいた歌仙ですが、特に何もありませんでした。
KP:では歌仙は最初に青年の居た部屋に戻ります。青年も後ろからついております。
KP:/
歌仙兼定:では最初の部屋で、そういえば、3枚の絵の裏なんかも調べられるのなら外してみたいです。作者の目利きをしたいので/
KP:3枚の絵の裏には特に何も書かれていませんね。/
歌仙兼定:あっこれ、この部屋も中央に卓があったのかな、だったら見てない気がするので見たいです/
KP:きょろきょろする歌仙ですが、卓には枕草子が乗っていた以外には特に気になるところは見受けられません。/
歌仙兼定:「……///なんでもないよ、次の部屋に行こうか」鳥の声のした左の引き戸へ向かいあけます/
青年:「わかった」
KP:青年は歌仙の言葉に頷き、やはりついてくる様子です。
KP:歌仙が引き戸を開くと、まず、目線より上にある格子がはまった隙間かに目が行きました。
KP:そこは僅かばかりの隙間ですが、床にある走馬灯の他に部屋を照らす灯りになっ ていました。
KP:差し込んでいるのは橙色の光。夕暮れだろうか。
KP:室内には、本の詰まった書棚があります。
KP:書棚だけではなく、床にも沢山の本が積み上げられ、積みあがった本の上にはせきれいの入った鳥かごが一つ乗せられています。
KP:先程から鳴いていた声の主でしょう。
KP:また、入って右手の壁には見取り図らしきものが貼られていました。
KP:/
歌仙兼定:「おや、鳥の声、といえば春かと思ったんだが、夕暮れか……」右手の壁の見取り図に目が行きます/
青年:「枕草子、か……」
KP:青年は夕暮れの光に目を細めながらつぶやくでしょう。
青年:「今もまだ、よくはわからんが」
青年:「こう……美しいとは、思う」
KP:青年がつぶやく合間に見取り図の位置へ到着しました。
KP:右上の角、左上の角で壁に貼られています。
KP:雪の降っていた部屋は「冬の部屋」
KP:中央の部屋は「春の部屋」
KP:今いる本棚のある部屋が「秋の部屋」
KP:春の部屋の右隣が「夏の部屋」
KP:通路の奥にある部屋には「鍵の部屋」と記されています。/
かずみ:(アアッ コマが何故か動かせない奴……)
かずみ:ありがとうございます…! そして青年のコマを登場させるのをうっかり忘れてましたのでそっと後ろに添えておきました……!
歌仙兼定:「ああ、まずは感じることができれば上々だ。表現等、あとから自然についてくる」雅を理解してくれそうな相手なので気分良いですね!
歌仙兼定:(適宜自分でコマ動かすようにしますね!)
かずみ:ニコニコ歌仙ちゃん!
かずみ:(お願いします…!)
歌仙兼定:「しかし、この部屋、このように陽の当たる場所に、乱雑に書物を床に積むのは、よくない」床の本を見てみたいのですが、すごい量でしょうか?/
青年:「そういうものなのか」
KP:青年は歌仙に褒められて心なしか嬉しそうです。
KP:本はすごい量ですね! しかもそこらにあるのは外来語のものばかりです。/
歌仙兼定:「外来語……漢詩なら心得があるが、それ以外はなあ……きみはどうだい?」きいてみます/
青年:「外来語……あまり、知らんな」
KP:青年は眉を寄せております。
KP:ここでアイデアをお願いします/
歌仙兼定:CCB<=75 アイデア Cthulhu : (1D100<=75) → 89 → 失敗
歌仙兼定:(ウッ……)/
KP:では、特に気がつくことはなかったでしょう。/
かずみ:ざんねん!
歌仙兼定:「だろうね」
歌仙兼定:「ああ、あれもよくない、本の上に物、しかも鳥かごをのせるとは!」鳥かごを持ってよく見てみます/
KP:止まり木にとまっていて、時々元気にちょこちょこ動いているせきれいですね。特に変わった点はありません。/
歌仙兼定:「ふむ、可愛らしいものだね、美しい声で囀るこの子に罪はない」鳥かごの下敷きになっていた本は何かかわったことはないですか?/
KP:特に何も変わりないですね。/
歌仙兼定:「本の上にも置けないが、床に置くわけにもいくまい、きみ、ちょっと持っててくれたまえ」青年に鳥かごをおしつけます/
青年:「わ、わかった」
KP:青年は戸惑いながらも了解します。中の鳥を興味深げに覗き込んでいます。/
歌仙兼定:「食べるんじゃないぞ」棚の本も見ます、こちらも外来語で読めそうにないですか?/
青年:「そ、それくらいはわかっている!」
KP:叫ぶ青年を尻目に歌仙は棚へ向かう形ですね? となると、目星を一つお願いします、/
歌仙兼定:はい
歌仙兼定:CCB<=70 目星 Cthulhu : (1D100<=70) → 85 → 失敗
歌仙兼定:オッフ/
KP:では、次にアイデアを/
歌仙兼定:CCB<=75 アイデア Cthulhu : (1D100<=75) → 89 → 失敗
かずみ:ふふwwww
歌仙兼定:(ンッフwwwwww)
KP:では、歌仙は何も気づかず本棚一直線ですね!
KP:では、棚の本ですが、やはり外来語の本が多く、殆どが読めない本です。
KP:背表紙を眺めた印象だと、なんとなくですがジャンルは限定されていないようです。
KP:本棚を調べるならば、目星で「読める本を探す」ことになります。
KP:/
歌仙兼定:ではまず、目星をふってみたいです/
KP:どうぞ!
歌仙兼定:CCB<=70 目星 Cthulhu : (1D100<=70) → 4 → 決定的成功/スペシャル
かずみ:ふふふふふwwwwwwww
歌仙兼定:(雅ーーーーーーーー)
かずみ:雅強い!
KP:では、歌仙は文化や食生活に関する本や、古い冒険譚まで様々な本があることに気が付きます。
KP:そしてその中から抜き出した一冊の本をパラパラと捲ると、偶然にも日本語のページを見つけることができました。
KP:西洋の悪魔を思わせるような、立派な双角の山羊の挿絵がされたページ。
KP:読みますか?
KP:/
歌仙兼定:読みましょう!/
KP:BGM:停止
KP:わかりました。
KP:BGM:疑惑
KP:そこにはこんなことが書かれています。
KP: 人間になる方法
KP: 我がしもべを喰えば
KP: 願いをかなえることが出来るだろう
KP:我がしもべ
KP:「豊穣の獣」を呼び出し 喰らうのだ
KP: 我こそは「豊穣の女神」
KP: あらゆる生命の権化
KP:我を讃え 我に跪き
KP:我が恩恵をその身に宿せ
KP:さすればお前は
KP:人間になることもできよう
KP:「人間になる方法」と表題のされたその内容に、歌仙は冒涜的なおぞましさを感じずにはいられません。
KP:《SAN 値チェック》1/1D3
KP:お願いします。
KP:/
かずみ:共有メモにもぺたり
歌仙兼定:CCB<=60 SANチェック Cthulhu : (1D100<=60) → 90 → 失敗
歌仙兼定:アウ
かずみ:あらん
歌仙兼定:1D3 Cthulhu : (1D3) → 2
かずみ:歌仙兼定のSAN値が(SAN:60→58)になりました
KP:おぞましい内容に驚く歌仙。
KP:まだ、ページには続きがあります。
KP:読みますか?/
歌仙兼定:「あまり気持ちの良い本ではないが……」うーん、他に読めるものもなさそうなので読んでみましょう/
KP:歌仙が更にページをめくると「豊穣の獣の召喚方法」という記述を発見します。
KP: 豊穣の獣の召喚方法
KP: 新月の夜
KP: 祭壇や魔法陣に血を捧げて行う
KP: 血を捧げたものが呪文を唱えることで
KP: 豊穣の獣は現れる
KP:そのページには、儀式に使う祭壇や魔法陣の図と共に、発音さえ不確かな寒気のするような呪文の文言が書き連ねられていま す。
KP:また、血を捧げる際に HP を 1D3 点消費しなければなりません。
KP:ここまで読みきった歌仙は、追加で SAN 値チェックが発生します。
KP:《SAN 値チェック》1D3/1D6+1
KP:どうぞ!/
歌仙兼定:CCB<=58 SANチェック Cthulhu : (1D100<=58) → 88 → 失敗
歌仙兼定:アッちょ
かずみ:あらら……
歌仙兼定:いきます……
歌仙兼定:1D6+1 Cthulhu : (1D6+1) → 1[1]+1 → 2
かずみ:おおお!!!!
歌仙兼定:(圧倒的雅ーーーーーーーーー)
かずみ:歌仙兼定のSAN値が(SAN:58→56)になりました
かずみ:やりましたね!
歌仙兼定:(あぶなかったですね……合計4……)
KP:恐怖に打ち勝った歌仙は、1点のクトゥルフ神話技能を得ます。
KP:追加しておいて下さいませ〜!
かずみ:下手したら一次発狂でしたね……
KP:さて
KP:歌仙が読み終えた本を思わず閉じると、ピーっという甲高い悲鳴のような鳥の鳴き声が聞こえてきました。
KP:それに続いて何かが次々に落ちる音がします。
KP:いかがしますか?/
歌仙兼定:「(食べるのなと念をおしたのに……!!)」音の方へ向かいます/
KP:歌仙が唇を噛んで音のした方を見に行くと、崩れた本の山とその下敷きになってひしゃげている鳥 籠が目に入ります。
KP:そして籠を手放し、本を手にしている青年の姿がありました。
KP:彼は、こちらへ来た歌仙をに視線を上げ、
青年:「ああ、すまない、うるさかったか」
KP:と口にしました。
KP:/
歌仙兼定:「ぼくは鳥かごをきみに頼んだ、本を読めとは言っていないぞ」可能なら本を取り上げます/
青年:「食ってはいない、落ちただけだろう」
KP:青年は眉をしかめながらも、歌仙が手を伸ばせば素直に本を手放します。/
歌仙兼定:「ぼくは二回同じことを言うのは好きではない。一回で理解しないやつも同様だ。ぼくは鳥かごをきみにもっているように頼んだ」鳥の無事を確かめられますか?/
青年:「なるほど……それは悪かった」
青年:「落とすべきではなかったのか」
KP:青年は少しピントのぼけた謝罪をしてきますね。
KP:一冊ずつ本を退けていくと、本の下敷きになりひしゃげてしまった鳥籠が出てきます。中を覗くことが出来ます。/
歌仙兼定:ああー…のぞきます;;;/
KP:中を見るとせきれいは止まり木から落ちて ぐったりしていました。
KP:上から乱雑に落とされた本と共に落ちた衝撃にどこかをぶつけてしまったらしく、特に技能の必要なく、もう手の施しようがないことがわかります。
KP:青年は、そんな歌仙の行動に対して、不思議なものを見るような視線を向けました。
KP:/
歌仙兼定:まず鳥かごから出して、状態を確認したあとに息を引き取るのを確認した感じでおkでしょうか?/
KP:その形で大丈夫です、青年が、歌仙が何をしているのかよく理解していない様子でそれを見ています。/
歌仙兼定:「この子が何をしたというんだ……」返答は求めない独り言としてつぶやきます。小鳥を、袖か外套をちぎって包んであげられますか?/
青年:「何か問題があったのか? 何故お前はその鳥を包んでいるんだ?」
KP:というわけで、不思議そうに歌仙に聞く青年を尻目に包めました。/
歌仙兼定:「命、とりわけ喪失には畏敬をもって接するべきだ……わからないのであれば、これ以上は言わない」鳥ちゃんどっかに埋めてあげたいのでとりあえず、これ以上傷まないようにもってけますか?/
青年:「喪失……? その鳥は、失われてしまったのか? 何故だ?」
KP:青年は喪失という言葉に眉をしかめ、歌仙に尋ね続けます。
KP:懐に大事に入れられますよ!/
歌仙兼定:「……さわってごらん、壊さないように、優しく」懐へしまう前に青年に鳥の亡骸に触れさせます。
歌仙兼定:「まだ暖かいが、じき冷たくなって��崩れていく。この責任の一端がきみにある」
歌仙兼定:「失われた物はもう戻らない。言っても仕方ないことだから、これ以上きみを責めることはしない」/
青年:「この鳥は……俺のせいで、失われるのか」
青年:「さっきまで動いて鳴いていたのに」
青年:「確かに、目の前にあるのに」
青年:「失われるのか」
青年:「これは、なんだ?」
青年:「目の前にあるのに、失われるというのを、何と言うんだ?」
KP:青年は、あと一歩というところで腑に落ちないようで、歌仙の答えを縋るように待っています/
歌仙兼定:「ひとは、これを『死』と呼ぶ」こたえます/
青年:「死……そうか、死か」
青年:「この鳥は、俺が死なせてしまうのか」
青年:「……それは、すまないことをした」
KP:青年は、布にくるまれ動かなくなったせきれいに小さく謝罪し、そっと手を離しました。
KP:/
歌仙兼定:「……」返事はしませんが、わかってくれたようで少しほっと(?)します。とりあえずこの部屋でこれ以上気がつくことは無いでしょうか?/
KP:そうですね……後は、青年が先程手に取っていた本くらいなものでしょうか。/
歌仙兼定:アッ……とりあえず、取り上げたのを見ます……歌仙ちゃんに読める言語でしょうか?/
KP:ちゃんと日本語のようです!
KP:飾り気のない黒一色の本で、表題は「怪物の手記」とあります。/
歌仙兼定:おっと……さっきのチェックから一時間全然たってないですよね……?/
KP:そうですね、一時間経ってはいませんね!
KP:しかし不定の狂気にはまだ遠いかな、という印象ですが!
KP:/
歌仙兼定:見た感じ嫌な感じとかはないですか?さっきの本からした嫌な感じとかしない?(表紙時点で)/
KP:特にそういう意味で嫌な感じはしませんね。ただの黒い本です。/
歌仙兼定:「……何故この本を読んでいたんだい?」まず聞いてみます/
青年:「何故……」
青年:「わからない」
青年:「黒かったから目に付いたのだろうか」
KP:青年は首を傾げます。/
歌仙兼定:あ、てか、一気に5減らなかったら大丈夫なのか、動画で見てた一時間で5のハウスルールと混ざってました……不定(?)は私48とか?ですよね?/
かずみ:ああ、なるほど! はい、48なので今のところそんなに問題ないですよ〜!/
歌仙兼定:あ、じゃあ読みます!!!!/
かずみ:はーい!
KP:歌仙が、先程青年から取り上げた本を開く。
KP:まず、目に入ったのは「幾星霜を越え、遂に私は人になる夢を叶えた。」という文字列だった。
KP:そして、ページは続く。
KP:「怪物であった自分が今の私を見たらどう思うだろうか。
KP:少なくとも怪物であったときの自分は、このような喜びに触れることはおろか、それが幸せなことであると考えさえしなかったのだ。
KP:私はそれまで食事の必要がなかった。
KP:故に酷くまばゆい経験だった。頬張り、触感と、うまみを楽しんで、噛み砕き、飲み込む。
KP:たったそれだけのことだが、食事とは奥深く、そして幸せなものだった。
KP:気の合う友人達や大切な家族と共に卓を囲み、食事をする。
KP:怪物はこの心地よさを知らぬのだ。
KP:そして、眠ること。
KP:人に成って初めて、この大切さを知った。
KP:無防備に安心して眠れるのは大切なことである。
KP:寒くて寝付けない日も良いだろう、暑くて寝苦しい日も良いだろう。それも四季の美しさなのだ。
KP:季節が廻り別れがおとずれても、寂寞や悲しみに心が震えることなど、今まではなかった。
KP:命に終わりがあることも、人の宿命である。喪う悲しささえ自分が人である証明のようで、愛おしい。」
KP:と言った内容が書かれていました。/
かずみ:共有メモにはりました!
歌仙兼定:「きみは、これを読んだのかい」途中でとりあげちゃったのもあるので、改めてききます/
青年:「読んだ、な」
KP:そう答える青年は、自らの背の辺りを撫でている。
青年:「お前も食事をしたり、眠ったり、悲しんだり、喜んだりするのか」
青年:「俺は……あの本のようなことを、したことも感じたこともない」
青年:「俺は、人間ではないのだろうか」
青年:「だったら俺は……なんだ? 怪物なのか?」
青年:「俺は……人間に、人間になりたい」
青年:「お前たちがしていることを、してみたい……」
KP:青年は、矢継ぎ早に歌仙へ訴えます。/
歌仙兼定:「そう、ぼくは……ぼくも、そのようにしていた、食事をしたり、眠ったり、悲しんだり、喜んだりしていた、と思う。ここではない、ところで」
歌仙兼定:「きみはさきほど、秋の夕暮れの日差しを美しいと感じ、この小鳥の亡骸に謝罪した」
歌仙兼定:「ぼくにはこの上もないほど、「人」と同じように感じたよ」
歌仙兼定:「取り上げて悪かったね」本は全部読んでしまったのなら、青年に差し出します/
青年:「しかし……食事はとったことがないし、眠ったこともない……それで、人とは言えないだろう……」
KP:青年は、うつむきながら、差し出された本を受け取りました。/
歌仙兼定:「ぼくは、形を真似するよりも大事な「人」の在り方というものが、別にあると思うよ」小鳥を布で包みなおして懐に大事しまって部屋を出ましょう/
青年:「そう、なのだろうか……しかし、なりたいんだ……お前と、同じに……」
KP:青年もうつむきながら付いていきますね。
KP:ここで幸運をお願いします。/
歌仙兼定:KOWAI……
歌仙兼定:CCB<=60 幸運 Cthulhu : (1D100<=60) → 72 → 失敗
かずみ:(´∀`*)ウフフ
歌仙兼定:アアアッ/
かずみ:あらら
KP:シークレットダイス
歌仙兼定:ンンーKOWAI;;;;/
KP:シークレットダイス
青年:「……あれは、なんだ?」
KP:ふと、気が付いたように青年が見取り図を指差します。
KP:歌仙の視線も、自然とそこへ誘導されるでしょう。目星をどうぞ!
KP:/
歌仙兼定:CCB<=70 目星 Cthulhu : (1D100<=70) → 3 → 決定的成功/スペシャル
かずみ:ふふふwwwww
歌仙兼定:(ここでーーーーーーww)
KP:青年の指で指し示されたからか、歌仙は見取り図の違和感に気がつく。
KP:鍵の部屋の鍵の文字はそこだけ顔料のようなものを塗られた 上に書かれていました。
KP:不自然な場所に手を触れるとぽろぽろと顔料が剥がれ落ち、本来書いてあった文字が姿を現します。
KP:下に書かれていた文字は「命」でした。
KP:その部屋は鍵の部屋ではなく「命の部屋」であるということがわかります。
KP:/
歌仙兼定:(あっこれもしかしてNPCが気付いてくれたやつ……??さっき怒ってごめんな……?)
歌仙兼定:「命の……部屋……?」ちなみに見取り図はがせますか?/
青年:「鍵の部屋では、なく……?」
KP:剥がせるものではない感じですね!/
歌仙兼定:なるほど、じゃあ、お互いに命の文字に気が付いた感じなら部屋を出ましょう/
KP:はい、では歌仙は青年と連れ立って春の部屋へと戻りました。
KP:/
歌仙兼定:まず、あの殺気忘れてた蝋燭、見たいです!!!残り!!!/
歌仙兼定:殺気✕さっき○
KP:はい、知識またはアイデアをどうぞ!/
歌仙兼定:アイデアで!
歌仙兼定:CCB<=75 アイデア Cthulhu : (1D100<=75) → 11 → スペシャル
KP:では後1時間半ほど、の感じですね!/
かずみ:(あれ、コマ動かせた……)
歌仙兼定:け、けっこうあったよかった/
歌仙兼定:(動かせましたね…ありがとうございます)
歌仙兼定:ちなみに夏の部屋とか虫鳴いてましたが床は土だったりはしない?/
かずみ:時間使った箇所がせきれいの話をしていたシーンくらいでしたからね
かずみ:土ではないですね! 調理場とかがあるくらいなので!
KP:土ではないですね! 調理場とかがあるくらいなので!
KP:/
歌仙兼定:冬の部屋は玉砂利?ですもんね……うーんじゃあ、奥の通路いきますか……暗いですか?/
KP:暗くはないです!/
歌仙兼定:なるほど
歌仙兼定:「きみは、食事をしたことがないのかい?」
歌仙兼定:青年にききます/
青年:「ああ、気がついたらここにいたんだ」
青年:「一度だって、ないだろう」
KP:青年は答えます/
歌仙兼定:「食事をしてみたいと思うのかい?」続けて聞きます/
青年:「! できることなら、してみたい」
青年:「お前たちと同じことが、してみたい」
KP:青年はパッと顔を上げ、勢い良く答えます/
かずみ:(勢い良く、というより強く、ですかね)
歌仙兼定:(私(よしきた!))
かずみ:(おやこれは……?)
歌仙兼定:「ついておいで」調理場へいきましょう!!!!鮎のところへ!!!/
かずみ:鮎だーーーーーーー!!!!
青年:「ああ!」
KP:心なしか嬉しそうに青年はついていきます。背中に当てていた手を離しています。/
歌仙兼定:背中に手……?と若干不審に思いながらも、調理場へいきましょう……!そして芸術「鮎の塩焼き」を振りたいです!!!/
KP:はーい! 材料は、先程探したときにあったようです!
KP:で、料理なのですが
KP:《DEX*3》+《芸術:鮎の塩焼き》
KP:との判定になっております!
KP:/
KP:もしかしなくとも……自動成功なのでは!/
KP:BGM:停止
歌仙兼定:あっ、DEXと足し算なんですね……DEX判定が別にいるのかと思って一瞬焦りましたが成功?で良いのかな?/
KP:BGM:調理
KP:はい、自動成功です!
すずぱか:BGM
KP:歌仙は実に慣れたもので、鮮やかに塩で鮎を包みます。
歌仙兼定:(メッッチャクッキングしてる)
KP:そして、七輪にかけ、じっくりと焼き上げます。
KP:待つこと数分。
KP:いや、多分もうちょっと長い、数十分ほど。
KP:香ばしい海の臭いがあたりに立ち込め
KP:BGM:停止
歌仙兼定:(あ、ちょ、こんなところで時間が……wwwww)
KP:実に美味しそうな! 鮎の塩焼きが出来ました!!
KP:BGM:探索
KP:/
かずみ:クッキングBGMはやはりこれかと……
歌仙兼定:「さあ、ぼくの渾身の鮎の塩焼き!食ると良い!」バーン!!!!!!!てします/
KP:青年は口を開き、目を輝かせ、焼きたての鮎の塩焼きを口いっぱいに頬張ります。
KP:溢れ出る魚の油、程よい塩気。
KP:青年はほかほかと湯気を立てる鮎を、喉を鳴らして飲み込む。
KP:そして、また一口。
KP:1尾まるまる、あっという間に青年は完食しました。
KP:/
歌仙兼定:「どうだい、おいしいかい、いやおいしかっただろう!!」食べっぷりがよかったようなのでフフン♪って感じです!/
青年:「……ああ……おいしい? そうだな、おいしかった、のだろう……」
KP:青年の返答に遅れが出ます。卓の前で、頭を前後にゆら、ゆら、と揺らしております。/
歌仙兼定:「なんだい、歯切れがよくないね、あの食べっぷりでまずかったとは言わせないぞ」と言いながらなんか変だなとは思って注意深く様子を見守ります/
青年:「いや……うまかった……ああ……うん……」
KP:青年は揺らしてた頭をほとんど止め、卓に突っ伏す寸前といった所です、/
歌仙兼定:「!?なんだ?どうした!?鮎にあたったのか!?」倒れ込みそう?なら?肩を揺する?大丈夫か!?みたいな感じで覗き込みます/
KP:歌仙が青年の肩を取り、よくよく様子を見ると、彼の目がとろんとしていることに気付けます。
KP:/
歌仙兼定:「もしかして……眠いのか?」何もしないとそこに倒れちゃいそうですか?/
青年:「いや……そうなのか……? 眠い、のか……」
KP:そうですね、放っておくとそのまま卓へ突っ伏して寝てしまいます。/
歌仙兼定:これは……あの……抱きあげたりおぶったりとか……できますか?STR22/
KP:青年は歌仙よりちょっと背が高いくらいなものなので、大丈夫ですよ!/
かずみ:STR22がじわじわくるんだよなあ……
歌仙兼定:「まったく、世話のやける……!」颯爽と抱き上げて布団の部屋へいきたいのですが、できますか?/
KP:勿論大丈夫です!
KP:シークレットダイス
KP:青年を抱き上げた際、歌仙は彼の寝言のような声を聞きます。
青年:「すまない」
青年:「怖かったんだ」
KP:という、小さな声でした。
KP:/
歌仙兼定:「人なら、そういうものさ」起こさない程度の小声で返して、布団に寝かしてやります/
KP:青年はお布団に入って、ぐっすり眠りにつきました。/
歌仙兼定:ぐっすり寝てしまったどうしよう……
かずみ:wwwww
歌仙兼定:様子を見てても起きそうにないですか?/
KP:しばらくは寝続けるだろう、というところですね。/
歌仙兼定:鼻をつまんでみます/
KP:むにゃむにゃと言いながら眉をしかめますね。/
歌仙兼定:こりゃだめだ!という確信を得たので、一人で歩きまわってみようかな。命の部屋に続く通路に行きたいです/
KP:むにゃむにゃ言っている青年を残し、命の部屋の通路前へ歌仙は来ました。
KP:板張りの通路が引き戸の前まで走っており、通路の左右は一段下がっていて水が敷かれていることがわかります。/
歌仙兼定:水に不自然な感じはないですか?よく見てみます/
KP:不自然なところは見受けられません。歌仙が覗き込んでよくよく観察すると、深さは脛ほどまでしかなく、底は白い砂が敷かれていて透き通った水に自分の姿が映っている事がわかります。/
歌仙兼定:「なかなか風流な趣向ではあるね……」引き戸に聞き耳ふりたいです/
KP:引き戸の前まで行く形ですかね?
KP:/
歌仙兼定:う、うーん?どうしよ、ちょっと怖いかな……蝋燭確認に戻っても良いですかね/
KP:はい、ではアイデアをどうぞ!
KP:/
歌仙兼定:CCB<=75 アイデア Cthulhu : (1D100<=75) → 92 → 失敗
歌仙兼定:おおんwwwww
KP:それなりに短くなっていることはわかりますね!/
かずみ:ファンブルじゃなくてよかった…!
歌仙兼定:今、蝋燭をよく見てみたが、短くなっている以外に気がつくことはなかったって感じでしょうか/
KP:そうですね、まだ少し余裕はありそうかな? という形です/
歌仙兼定:うーん他に見るものが思いつかないな……青年起きてくる気配ないですよね/
KP:そうですね、まだしばらく寝ているでしょう。
KP:時間進めちゃうことも可能ですよ。/
歌仙兼定:とりあえず、さっきせっかく瓶と糸と油みつけたので、アルコールランプの要領で蝋燭の炎をうつしてみたいんですが、できますか?/
KP:DEX×5の判定で行きましょう!
歌仙兼定:(優しい😭)
KP:失敗したら、ちょっと上手いこと火が移ってくれない、と言うかたちで!
歌仙兼定:CCB<=60 DEX*5 Cthulhu : (1D100<=60) → 39 → 成功
KP:成功値60ですね、どうぞ!
KP:お!
KP:では歌仙は手際よく火を瓶に移せました!
KP:/
歌仙兼定:だからといってこれで何をするとかまったくないんですが……!!持って歩くのは何か判定いりますか?/
KP:そうですね、DEX-1とかですかね…… そして、左右どちらかの手が使えなくなる形でどうでしょうか?
KP:/
歌仙兼定:ですよね……得に明確に持ち歩く目的がないうちは、春の部屋の卓の上においておきましょう……
KP:では、春の部屋の卓周りがちょっぴり明るくなりました/
歌仙兼定:蝋燭がまだ燃え落ちていないのならお布団の部屋へいって起きるのを待ってみます/
KP:わかりました、青年が起きるまで待つ形ですね?/
歌仙兼定:二人で行動するほうが良さそうなので……待ちます!枕元に座ってうとうとしてましょう/
KP:かしこまりました!
KP:歌仙が青年の枕元へ戻り、うつらうつらと船を漕ぐ。
KP:しばらくして、青年は目覚めるでしょう。
KP:歌仙が枕元にいることに、少々安心したような笑みを浮かべて、青年は起き上がります。
KP:/
歌仙兼定:「やあ、やっと起きたか……床に転がすんじゃあんまりだと思って、ここまで運んできてやったんだから感謝してくれよ」/
青年:「そうか……ありがとう」
KP:青年は素直に礼を言って、へにゃりと笑います。
KP:ここで、アイデアをどうぞ!
歌仙兼定:CCB<=75 アイデア Cthulhu : (1D100<=75) → 59 → 成功
KP:では、青年の長かった髪がかなり短くなっていることに気が付きますね。
KP:具体的に言うと、束ねていた髪留めが解けて、項が隠れる程度の長さになっております。
KP:/
歌仙兼定:(青年の容姿気にして無さすぎやったわwwwwという顔してます)
かずみ:んんんwwwww
歌仙兼定:「きみ、髪が……??まあ、よく眠れたようだから、それでいいか……」髪留めは近くに落ちていたりしますか?/
青年:「……? ……ああ、だから背が寒くなっていたんだな」
KP:青年は歌仙の言葉に納得した顔をしております。
KP:髪留めは、パッと見どこにも見当たらないでしょうね。/
KP:まるではじめからそれが自然であったかのように、なくなっております。/
歌仙兼定:今更ですが、改めて、青年の容姿をまじまじと見てみます……具体的なイケメン的な数値等を……/
KP:そうですね、白い襦袢を一枚着た、とっても平均的な顔立ちの青年となっております。
KP:際立った特徴はほとんどありません。/
歌仙兼定:(APP18とかじゃなくてよかったという顔)
かずみ:wwwwwwwwwwwwwwwwwwww
かずみ:思わず思い切り草を生やしてしまった
歌仙兼定:「すっきりしたみたいだし、また、一緒にここを見て回ってくれないか?一人で探すより、二人の方が良いだろう」と聞いてみます/
青年:「ああ、お前がそう言うなら俺も付き合おう」
KP:さて
KP:二人が起き抜けに和やかに団欒していると、背後、鍵の部屋の方からカチャリと何かが開く音がしました。/
歌仙兼定:「おや?今の音……早速だが、見に行こうか」青年を促します/
青年:「ああ、行くぞ」
KP:青年は歌仙についていく姿勢です。
KP:鍵の部屋へ、向かいますか?/
歌仙兼定:はい!まっすぐは向かいますが、一応他にも異変がないかは気を配っておきます/
KP:なるほど、それならば向かう途中で目星をお願いします!
歌仙兼定:唸れぼくの目利き!!
歌仙兼定:目星ふります
KP:はーい!/
歌仙兼定:CCB<=70 目星 Cthulhu : (1D100<=70) → 68 → 成功
かずみ:ギリギリ唸った!
歌仙兼定:(た、足りた!!!)
KP:では、さり気なく警戒しながら歩みを進めていた歌仙には、蝋燭の火が見るだけで残りもうわずかだという事がわかります。
KP:このまま鍵の部屋の戸まで行きますか?
KP:/
歌仙兼定:行きます!早足でいきましょう!!!/
KP:はーい!
KP:では、通路の頭上に頭上には紺色の闇が広がって いることに歌仙たちは気がつくでしょう。
KP:まるで星のない夜空のようです。
KP:そのまま進むと、2つの水路の間を通って、引き戸の前へ難なく二人はたどり着くでしょう。
KP:/
歌仙兼定:引き戸はぱっとみなにかかわったところはありますか?/
KP:特に別段気になるところもない、一般的な引き戸のようです。/
歌仙兼定:多少様子を伺う余裕はあるかな、聞き耳は一応ふりたいです。さっき突然鍵の音?がしましたし…/
KP:では、聞き耳どうぞ〜!/
歌仙兼定:CCB<=25 聞き耳 Cthulhu : (1D100<=25) → 61 → 失敗
KP:部屋の中から物音はしませんね。/
歌仙兼定:青年はなにか気付いたような様子はないですか!!!!チラッチラッ/
KP:シークレットダイス
青年:「静かだな」
KP:特になさそうです!/
歌仙兼定:「ぼくもそう思っていたところだ」
歌仙兼定:引き戸をあけましょう/
KP:BGM:停止
KP:かしこまりました。
KP:歌仙は、引き戸を開ける。
KP:「鍵」
KP:引き戸の先は、鍵の部屋。
KP:その部屋には、何もありませんでした。
KP:「鍵」といわれて思い浮かぶものは、何も。
KP:ゆえに、あなたは、絶句してしまう。
KP:部屋の中心にあったのは、
KP:今まさに打ち上がったであろう、一振りの刀剣でした。
KP:あなたは思い出す。
KP:この部屋が「命の部屋」であるということを。
KP:青年に感じていた、不思議な感覚を。
KP:BGM:危険
KP:歌仙が一振りの刀剣に目を奪われていた刹那。
KP:突如、背後から轟音が響きます。
KP:春の部屋の卓の真上が真っ赤な閃光と共に燃え立ちました。
KP:渦を巻く赤い稲妻がまばゆく輝いて、まぶしくてそれを直視するこ とさえ困難です。
KP:しかしそれでも、あなたは見てしまう。
KP:まるで生き物のような炎。光と熱の塊。
KP:煮えたぎるような火炎の光が「鍵」を差し出せというように伸ばされている。
KP:。この意思持つ火炎こそが「炎の精」であると理解 することでしょう。
KP:これは刀剣男士の生まれる場所にして、数多の刀剣の死する場所。
KP:生と死の体現者にあなたは恐怖する。
KP:《SAN 値チェック》1D5/1D10 の減少
KP:お願いします。/
歌仙兼定:(大きい……!)
歌仙兼定:CCB<=56 SANチェック Cthulhu : (1D100<=56) → 6 → スペシャル
かずみ:がんばれー! がんばれー!
かずみ:うおおお!?!?
歌仙兼定:(雅isパワー)
かずみ:がんばってる……
KP:1d5,お願いします!
KP:/
歌仙兼定:1D5 Cthulhu : (1D5) → 2
かずみ:歌仙兼定のSAN値が(SAN:56→54)になりました
歌仙兼定:(雅ほんと強いな
かずみ:少ない!
かずみ:さすが雅Power
歌仙兼定:「ちょっとびっくりしたけど大丈夫だったよ!!」青年は大丈夫ですか/
KP:怯んでも仕方のない所を耐えた歌仙。
KP:前に進むどころか、その場にとどまることさえ難しい熱風が吹き荒れます。
KP:春の部屋は焼け爛れ、戻れるような状態ではありま せん。
KP:蝋燭の炎もまた激しくなり融解が加速しています。
KP:もしこの炎の精と接触してしまったら、刀剣男士といえど只ではすまないだろうと直感することでしょう。
KP:炎の真っ赤な腕が「鍵」を求めてあなたたちを追い詰めます。
KP:あなたは青年と共に、鍵の部屋の方にじりじりと追いやられる形になります。
KP:余りのまばゆさに炎の精を直視することがかなわず、青年は視線を周囲の水面へと向けています。
青年:「あれが鍵なら渡せばいい!」
KP:青年は、叫びます。
KP:ここで、幸運をどうぞ/
歌仙兼定:はい
歌仙兼定:CCB<=60 幸運 Cthulhu : (1D100<=60) → 89 → 失敗
歌仙兼定:(雅が……)
すずぱか:雅尽きた
KP:歌仙は、突然の焔の勢い、そして青年の様子で手一杯のようです。/
かずみ:雅ィ……
歌仙兼定:鍵の部屋にあった刀剣が「歌仙兼定」でないことはわかりますか/
KP:歌仙兼定でないことは、確かですね。/
歌仙兼定:誰かを目利きすることは咄嗟には無理ですかね/
KP:そうですね、あまりに危険な状況であること、そして大きな焔に赤く照らされておりますのでとっさに判断することは難しいでしょう。/
かずみ:(あ、コマ忘れてた……ありがとうございます……!!)
歌仙兼定:なるほど、とりあえず、命の部屋と一振りの刀剣で歌仙はピンときているようなので
歌仙兼定:「あれを差し出すわけにはいかない」と返答をします/
青年:「……わかった」
KP:状況の把握しきれていない青年は、歌仙の静かな言葉に返答します。
KP:では、刀剣を炎の精に渡さないということでよろしいでしょうか?/
歌仙兼定:ううーん、とりあえず、刀剣を渡さずにいると現状維持でじりじり追い詰められているという感じでしょうか?/
歌仙兼定:(どうしよ全然わからん
歌仙兼定:)/
KP:いえ、ここは分岐のようなものでして。
KP:決断次第で、進行が変わります/
歌仙兼定:なるほど、では差し出さないです。この状況で安易に差し出せないと思うので/
KP:かしこまりました。
KP:歌仙と青年は、刀剣を背後へかばうようにして炎の精と対峙するでしょう。
KP:敵対、という程ではない。
KP:しかし、これは渡せない。そう二人は決断し、刀剣を背後へと庇った。
KP:BGM:停止
KP:そのとき。
KP:しゅぼ、と音を立てて、大きな蝋燭の火が燃え尽きました。
KP:やがて沢山の走馬灯のあかりが一つ一つ消え去っていきます。
KP:蛍も、夕焼けも、全ては真っ暗な闇の中に。
KP:目の前にあった真っ赤な炎の精も嘘のように静まり返りました。
KP:忌々しげな舌打ちを最後に、あなたの視界は真っ黒に塗り潰されます。
KP:何もかもが真っ暗な闇に包み込まれたとき。静かに、あなたのすぐ近くから、声が届きます。
青年:「……ありがとう」
青年:「お前が来てくれて、よかった」
KP:BGM:終了
KP:歌仙は勢いよく目を見開いた。
KP:見知った天井。見知った場所。鍛刀場にほど近い、庭に面した縁側で、あなたは目を覚ましました。
KP:徐々に、夢の中で思い出せなかったことを思い出してきます。
KP:自分が駆け出しの本丸に在籍していること。所属しているのは、 あなたの他にほんの僅かしかいない。本当に始まったばかりの本丸。
KP:そして、新しい刀剣男士を生み出すべく、審神者が刀を打ったことを思い出す。
KP:打ちあがるまでの時間を、新しい家族が目覚 めるまでの時間を、あなたは待っていたのです。
KP:眠ってしまうとは何という不覚だろう。夢まで見るなんて。
KP:そんなあなたの元へ審神者がかけてくる。
KP:新しい刀剣男士が、生まれたことを知らせに。
KP:審神者の後ろに、刀剣男士が一振り、立っている。
KP:紫の引き締まった洋装。
KP:品の良い、彩度の抑えられた黄金にたなびくカソック。
KP:薄灰茶の、短くきりそろえられた髪、薄紫の瞳。
へし切長谷部:「へし切長谷部、と言います」
へし切長谷部:「主命とあらば、何でもこなしますよ」
KP:そう名乗った刀剣男士にあなたは見覚えがあるだろう。
KP:もっとも、夢の中のぼんやりした彼とは、その佇まいはだいぶ違うもの となっているけれど。
KP:彼はあなたに向かって、右手を差し出します。
KP:/
歌仙兼定:「ああ……」
歌仙兼定:「僕は歌仙兼定。風流を愛する文系名刀さ。どうぞよろしく」
歌仙兼定:差し出された手を握り返します/
へし切長谷部:「その手……」
KP:しっかりと握り返しながら、へし切長谷部は苦笑します。
へし切長谷部:「また、鼻を摘むのだけは、勘弁してくれ」
KP:あれは案外苦しかった、そう笑う長谷部と、歌仙、そして審神者を穏やかな春の陽光が包む。
KP:庭では、黒い稲妻のような枝を伸ばした桜が、沢山の花びらを抱き。
KP:空にはせきれいがはばたいて、澄み渡る声を響かせておりました。
KP:ここは、まだ始まったばかりの本丸。
KP:彼らは、審神者の元で切磋琢磨しあい、大きく成長していくことでしょう。
KP:ただ、ただ。
KP:このへし切長谷部は、きっとよい塩梅に焼けた鮎の塩焼きが好物だろうし
KP:きっと、文学に興味を持ちつつ、寝る時は、ほんのちょっぴり鼻を警戒する。
KP:そんな、刀剣男士として育っていくのでしょう。
KP:この、歌仙兼定と共に。
KP:END1:焔の絆
0 notes
Text
23
23歳だった。誕生日だった。その日は冷たく光る雨が降って���僕は前日から遠い海の名前のお酒を飲んでいた。CDプレーヤーの冷静な緑色のデジタル文字が00:00を示し、僕は自分の年齢が変わったと知った。00:01に間宮から「誕生日おめでとう。これからもよろしくね」とメールが来た。僕はオーディオテクニカの分厚いヘッドホンを外した。ニルヴァーナの鋭いギターリフの隙間に静寂が入り込んできて、それはすぐにエアコンのざーっという低い音に変わった。僕は「ありがとう」と返信を送ってケータイの電源を切った。それからガラスのコップに入れた安いワインで眠剤を飲んだ。何錠だったかは数えなかったけれど、多分8,9錠くらいだったんじゃないかと思う。後ろめたさが喉を過ぎていって胃に達する頃には自己肯定に変わっている。やわらかい。身体は海に近くなる。 遠のいていった記憶が実は僕自身だったのではないかと思う。詭弁。生きることは過程の推移に過ぎないのかな。それにしても。長く生きすぎたと思った。20歳になったとき、僕は確かにこれから生きるのだ、何故なら今まで自分はまともには生きてこられなかったのだから、と思っていた。しかしそれから三年間で積み上げてきたもの、そして今ここに残っているものは、ざらついて青ざめた自分の顔と、荒れた喉、常に痛みで存在感を発し続けている胃、それから傷の上に傷を重ねられてケロイド化した左腕だけだ。時間は積み重なることを知らない。しかしそれは決して新しくなることはない。始まった時から、全ては終わりを目指している。 僕は再びヘッドホンを耳に当てる。エイフェックス・ツインの暴力的に優しい、壊れた心拍音のようなビートが頭の中いっぱいに拡がっていく。全ては終わっている。もう十代のうちに終わっている。それなのに僕は生きている。僕は人生に飽きている。ワインを注ぎ足す。これから車を駆って公道を130キロぐらいで走って、それで死刑になったらいいなと思う。全ては終わっている。騒音に似た音がずっとしている。 一時期、僕は詩を書いていたことがある。それは慰めと言うよりは……、例えば彼らは、何をして生きているのだろう、何を見ているのだろう、それから間宮は? 彼女は詩を書いている、その場所に僕は行きたかった。どうしようもなく気持ちよくなるときがあった。僕はただ、終わりの音楽がいつまでもいつまでも鳴り響いている場所、そこに生きたかった。何日か、間宮と一緒に家を出て、お金が無くなるぎりぎりまで遠くに行ってみたことがある。そうして、多分どんなひとの言葉もあらゆるものがフィルターにかけられて「過去」という場所から響いてくるように聞こえる、銀色の山あいの道に二人車を止めて、目眩のするような、鳥や虫たちしか降りていけないような谷(その底には川のようなものが流れていた。でもそれは水ではなくて、そこに降りていけるような言葉を僕たちは持たなかったのでそれを暫定的に川と呼んだ。僕らは草の生えた地面に寝ころんで、シャツの背中が砂粒に濡れるのも気にせずに手を繋いだ)を見下ろす場所で、「お互いにこれが最後だとしたら」とどちらともなく呟いて(いや、二人も何も言わなかったのだ)、それからキスみたいなものをした。お互い、感じていたのは繋がりよりも、隙間だった。何の音楽もなかった。 22歳だった昨日、僕は綾嶺さんと彼女の部屋でお酒を飲みながら話した。彼女は誰も来るつもりじゃなかったから、と言って、机の上の本を取り敢えず、危なっかしく胸の前に抱えて部屋の隅に持って行った。その本の山は、雨の多い季節を待っている、足のない虫たちのように、間からは紙片が飛び出していたり、表紙の無い本があったりした。でも僕を呼んだのは彼女なのだ。彼女の部屋では、常に先を先を急いでいるようによろけながらも(合わない靴を履いているので)全速力で行き先も分からず一心不乱に走っているようなアークティック・モンキーズの‘テディー・ピッカー’が部屋の空気を突き抜けるように流れていた。綾嶺さんはふたこと目には「死にたい」と言う。それが冗談では無いことを僕は知っている。彼女は27歳で切実に死にたがっている。何の仕事もしていなくて、親のお金で(それもやっとせびって満たしているようなものなのだ)それまでを生きてきていた。申し訳ない申し訳ないといつも彼女は言う。だから僕は淡い禁酒中の彼女に4本目のビールを勧めた。それから彼女は「みんな死んでしまえ」まず私から、いや、みんなだ、みんな、みんなみんなみんな! と言った。僕は窓を開けた、冷たい風が吹き込んで、見える星、あ、あそこは熱いな、ここは冷たいなとても、と僕は思った。綾嶺さんは「間宮ちゃんはどうよ。最近あなた達会ってる? それからセックスしてる?」と言った。僕は「会ってます。セックスはしていません」と言った。それから「セックスって何ですかね?」と言った。彼女は「セックスは恥ずかしいものだよ、とても」と言った。それから僕は綾嶺さんとセックスをしなかった。ただ、ぺたぺた触れあって、お酒を飲んだ。「今私は、あなたの生身に触れている。あなたは私の乳房に触れた。服越しなのでした。それはセックスではないのでした。過去形でね。でも何なんだろうね」と言った。分からなかったので、僕は持ってきていたワインを開けた。飲むつもりは無かったのだけど、間が保たなかったのだ。彼女はボタンを一番上まできちんと留めて、それから洗面所で髪も整えてきて、それから「やっぱりいいや」と言って、背の低いテーブル越しに一瞬同じ瞬間に笑い合い、彼女は彼女は髪をまとめて頭の上でくくった。それから彼女は「あんたは私をずっと好きでいてくれると約束してくれる?」と言った。僕は「前提として僕は綾嶺さんが好きなのでしょうか?」と言った。 「好きじゃないの?」 「好きですよ。そりゃ」 「じゃ、何でそんなこと言うのよ」 「好きって何か分からないからです」 「あんたは私が好きじゃないの?」 「好きですよ」 「ずっとね」 「ずっとです」 「嘘ね」 「嘘じゃありません」 「そう。じゃああんたはきっと馬鹿だ」 僕は、嘘じゃありません、と口の中で言ったけど本当は嘘だったのだけれど、そう言ったら、僕は泣いてしまうし、彼女は死んでしまうのかも知れなかった。綾嶺さんは横を向いて肩に付いた何かを弄っていた。それから歌うように、私は、どうせ、あー、あれだ、あれ、何だろうな、あー、わからない…、と呟き続けた。endless, endless, endless... 帰ってきて、まだ酔いの醒めない頭の焦点をセンター試験の過去問題集に並んだ、不可思議な英語の文字列に合わせようと思ったけれど、それは英語でもない何かにしかならなかった。僕は諦めてベッドに潜り込んだ。生活音が聞こえた。それは僕の不安が具体的になったような音だった。僕は生きるのかも知れないと思う。生きるのかも知れない。怖い。大学に行ったらもっともっと怖いだろう。僕はこれ以上の勉強はもう勘弁だと思っていた。けれども僕はひとのいる場所に行きたかった。僕は18歳のときに一度大学に入っていて、それは一年でやめた。その頃には僕は酷い鬱病で、ただ薬とワインと、間宮へ送る「死にたい」と間宮からの「死ぬなよ。死んじゃ嫌だよ」で、生きていた。たまに「じゃあ死ねよ」と返ってきて、そう、そのあとは三ヶ月くらいケータイの電源を切っていたんだ。そうだった、僕は三年間ずっと間宮にどれだけのお礼も、何にもしていなかった。僕は当たり前のように生き残ってしまって、間宮はいつもいつものように僕に笑いかけてくれた。 一年前に僕はそれまでは休学扱いだった大学を正式に止めることにした。それはひどくあっけなく受理された。誰も引き留めたりしなかった。誰も僕に何かをしろといなかった。誰も彼もが僕にただ生きていればいい、そうすれば何かが出来るかも知れないしと言った。僕は何も出来ないかも知れないと思ったけれど、取り敢えずは寝て過ごすことにした。ただただ何もかもが急速に老いていった。僕は毎日一度は死のうと思った。 誕生日の朝、雨は雪に変わり、昼頃になって煙草が切れかけているときに間宮が突然家にやってきた。「これ、プレゼント」と言って手渡されたのは一カートンのラッキー・ストライクと缶入りのピースだった。缶を開けると、実在しない森のような香りがした。彼女は体型にぴったりと合った、冬の温度がその周りだけ少し厳しさを失うような感じの淡いピンク色のセーターを着て、もこっとした感じのブーツの丈を短くしたような合成皮革の靴を履いていた。珍しく赤いフレームの眼鏡をかけていて、それが短めの髪にとても合っていた。玄関で、丁寧に紐を解きながら、 「どう、小説は書いている?」 と何気なく言った。 僕は、 「書けないんだ」 と言って、それから先は続かなかった。外から入ってきた空気が、僕の胸の中の空気と排斥し合うようで、軽い立ちくらみを感じた。 彼女は「そう。でも、時間はたくさん、たくさんあると思うよ。それにね、書けないからと言って私は亜紀を嫌いになったりしないから心配ないんだよ」と言った。 彼女が言うとまるで本当みたいに思えた。でもきっと本当のことのひとつひとつは見つめてしまってはならないし、留めて置くことも出来ないんだ。 僕は「ありがとう」と言った。 彼女は「どういたしまして」と言ってから、「もうひとつ、本当はこっちがプレゼント」と言って、僕に小さなリボンの付いた紙袋をそっと手渡した。柔らかいものが入っていた。 「それはマフラーなの。ありきたりでごめんね。私、下手だから、半分くらいは、ううん、もっとかもしれない、妹が編んだの」 僕は袋を開けた。それはクリーム色で、少し長めで、とても丁寧に編まれていた。僕はそれを折りたたみ直して、頬に当ててみた。柔らかく、それは熱いくらいの感触で、僕はそれを鼻に当てた。とてもいい匂いがした。 「ねえ、僕は君にどれくらい感謝しなくちゃいけないんだろう。ありがとう、すごくすごく嬉しい」 彼女はやっと立ち上がって、「伝わらないかもしれないけどね」と言って僕の身体に腕を回した。それから耳元で、 「嬉しいのはずっとずっと私の方なんだよ」 と呟いた。 僕の部屋にはいると、まず彼女は戸口のところで立ち止まって、「うわぁ、前よりも本増えてるね」と言った。 僕は「読んでないから」と言って、台所からコップを持ってきた。炭酸入りの紅茶も冷蔵庫から出してきた。 間宮は僕の机の上に拡げてあった、大学入試問題の数学のテキストをぱらぱらとめくっていた。本の方に目は向けたままで「やっぱり大学には行くの?」と言った。 僕は紅茶を均等に注ぎながら、 「うん。分からないけれど、今のところ、もし僕が生きるのだとしたら、語学の勉強が合っていると思うから」 と言った。半分くらいは嘘だった。僕は薬とお酒を飲んで、音楽を聴いているのが一番幸せだった。幸せというより、他の何一つしたいことがなかった。それから煙草を吸いながら、僕は一生がずっと今日なら、死ぬのと同じくらい生きているのもいいと思えた。だから大学になんか行きたくなかった。でも、生きていくための方便として、大学にまた行くくらいしか、他には思いつかなかったのだ。まず、両親がいまの生活を続けることを許してくれるだろうとは思わなかったし、バイトで生活を制限されるくらいなら、外国語の辞書でもめくっていた方がいい、みたいな完全な消去法だった。 「それに、バンドを作るのは、ここでは無理だから」 間宮はコップを取って、唇の先に紅茶をちょっと付けるようにして「おいしいね」と言った。 「ふーん、亜紀がバンドを作りたいなんてね」 と寂しそうに笑って。彼女は壁に立て掛けたレスポールを取って、ベッドに座って弾く真似をした。「たった六弦で音楽を作れるなんて、私には信じられないな。アキには特別な才能があるんだよ。ギターを弾くのが楽しいってだけで」 と念押しするようにはっきりとした口調で言った。 「それは買い被りすぎだよ。いくらなんでも。ギターなんて誰でも弾ける」 僕は紅茶を、喉を鳴らして飲んだ。 間宮はふふと笑って、ギターの指板をばらばらな手つきで押さえて、右手でじゃらりと鳴らした。孵ったばかりの小鳥が呻くような音が出て「これでも?」と笑った。 「それは」僕は言って、間宮からギターを受け取って、「KID A」のリフを弾いた。間宮は「気持ちいい音」と言って、コップを額に当てて、それからベッドに仰向けになった。 「この曲はジョン・メイヤーが弾いていたんだけれど、弦はたった二本しか使っていないんだよ」 と僕は説明した。 間宮は起き上がって、「違うんだよ」と言った。 「あたしはね。ギターを見てると、指を這わせるよりも叩き壊したくなるんだ」 「それは…」 というのをさえぎって彼女は、 「ううん。わかってる。それはわかってるよ。でも亜紀はギタリストで、私は本質的にギタリストじゃないのよ。それはどうしても」 僕にはそうは思えなかった。それは単に慣れの問題だと言おうとした。けれど、何かそれを言いたくないような感情があって、僕は黙っていた。それにギターを叩き壊したいのは、本当は僕だって同じなのだ。 その日の夜、僕たちは二人で綾嶺さんの家に行った。彼女は昨日のままの格好でやっとのことで戸口まで這ってきたようだった。 「入りなよ」と言った。 「おじゃまします」と言って間宮はさっさと入っていった。僕が靴を脱ごうとしていると、綾嶺さんが僕の足にしがみついてきたので倒れそうになって、彼女の肩に軽く手をついてしまった。綾嶺さんの身体は、そのまま壊れてしまいそうに力なく床に倒れた。僕は壁に危うくもう一方の手を付けてバランスを取った。 「ごめんね」僕が口を開く前に綾嶺さんが言った。 「私なんかのために」 僕は綾嶺さんを壁に凭せ掛けてから、靴を脱いだ。間宮が居間のドアから顔を出して、 「綾嶺ちゃん飲み過ぎだよ。いるだけで酔うよ、この部屋」と言った。 それから、くたっとしている綾嶺さんを見て、僕の方へ歩いてきて 「何やってんの」と言った。それから小声でわざとらしく「おお、このままほっといたら綾嶺ちゃん死にそうだね」 「さあね」 「死んだらあたしたち捕まるかな」 「さあね」 「あのさ」綾嶺さんが言った。 「丸聞こえなんだけど」 間宮は「知ってる」と言って、くすくす笑った。 綾嶺さんは自力で立ち上がって、立ち上がるとまるで全然お酒なんか飲んでないみたいにすたすたと居間の方へ歩いていった。 綾嶺さんの部屋は昨日よりもずっと乱雑としていた。本棚に並んでいた百冊ほどの本が、全て床に払い落とされていた。その上に飲みかけのワインのボトルが横たわっていて、ファッション雑誌の表紙の女の子の顔が半分赤く染まり波打っていた。何冊かはもう永遠のアルコール中毒の最中にいた。窓が開いていて、カーテンが何か宿命的な陰鬱を訴えるように重たげに揺れていた。スピーカーから、何かうめき声のような、ざらざらした音が漏れていた。 「みんな捨ててしまおうと思ってね」 綾嶺さんは床に置かれた赤い座椅子に崩れるように座って言った。それから二、三回咳をして、「煙草、吸ってもいい?」と言った。 僕は、自分のライターで綾嶺さんのくわえたマールボロに火を着けてあげた。 彼女は煙を吸ってから吐くのに、時間がかかった。 「雨が降っているのね」 僕はこれが部屋にかかっているのが何の音楽なのか聞こうとしたけれど、間宮がスピーカーに付いたつまみを回すと、うめき声は、遠くから聞こえてくる鳥の声に変わった。 「私は昔、宇宙飛行士になろうとしていたんだ。十年くらい前まではね、結構本気で思っていたんだよ。成績も悪くなかったし、ううん、とても良かったと言ってもいい、体力にも自信があった。頭がやられる前まではね。私は、空を見上げて、星座の名前を覚えるのが何より嫌いだった。ただ、あそこには空間と光だけがあるんだ。星座なんてのは、あくまで地上にへばりついた人間達の、局地的な土臭いお遊びみたいなものだ。地球なんて、本当にちっぽけで、そこにしがみついている人間がぶざまだと思った。私はそれを見下ろしたかったんだな、見上げるんじゃなくて、みんなみんな見下ろしてしまいたかった。私は何も知ろうとしなかった。結局、地上の、小さなひとつひとつのことを、ひとは存外に大切にしていて、宇宙までも言葉に還元してしまおう、なんていう、でもそのいじましい努力を、知らなければ、私はひとのなかでは生きていけない、そういう当たり前のことを、私は知らなかった。みんな、とても現実的にアレンジされた夢の中に生きているのね。本当に夢を見られるのは限られた人間だけだし、私にはその資格があると思った。私は社会がいかに馬鹿馬鹿しいかの受け売りをしたかった訳じゃないの。間宮は分かってるだろうけれど、アキトくんは知らないと思う。私ってね、まともじゃないの。大学に入った時には正直絶望しきっていたわ。私が他人の感情、というか生活かな、にはほとんど不干渉であるのに、彼らは私を避けていた。多分、恐れてさえいた。私はね、現実的だし、自己中心的であることに自覚がありすぎたのよ。それでも純粋な好意があることは知っていた。ケータイにもほとんど用がないくらい、私には友だちがいなかった。せいぜい、仲のいいふりをするか、独りでもまだ気高くいられればよかったんだけどね。でも私は独りでいることしか出来ない癖に、独りでいることに耐えられない人間だった。彼らは、ひとに何らかの価値を求めているの。アキトくんだっていくらかはそうだよ。ときどきは私に出来ないこと、表情、とかを求めたりもするでしょう? でも、あなたは私が私でいることを求めていてくれる。痛いくらいに。きっとあなたは私がおばあさんになっても友だちでいてくれるわね。そういうのって嬉しいと言いたいけれど、怖いな。甘えてしまいそうなのよ……」 眠ってしまった綾嶺さんを見ながら、僕たちはしばらく大陸風のような、ざわめきに耳を傾けていた。そのうちに、風は湿っぽくなり、段々水の流れのようになっていった。その流れは耳の中で落ち着いた静けさを作りだした。 「なんだか泣きたくなるね」 間宮は言った。透明な声で。 昼頃また来ます、と書き置いて、僕たちは外に出た。
(2010)
0 notes
Text
てならいはじめ_壱
春は好きではなかった。
冬の間は息を潜めていた幾つもの花が咲き競い、大地から沸き立つ噎せ返るような生命の息吹は、病弱な身には息苦しかった。 明るく弾んだ人の声や百鳥の囀りはそこかしこから聞こえてくるのに、一つとしてこの蔀戸を越えて入ってくることはない。 あたり一面春の中、この部屋だけが季節に置き去りにされたように静かで、寒くて、寂しい。
_____春は好きではなかったのだ。
夜半の寒さに出た咳で目が覚めれば、大気に常と違う香りが混じっている。 少しの甘さを含んだ、寒さの中できんと冴えるような清い香り__梅の香りだ。
あぁ、咲いたのだな、今年も。
ごそごそと身を起こし、綿入れを頭からすっぽりと被り戸から頭だけくぐらせれば、外は墨を流したような暗闇が広がっている。 そのままじっと戸にもたれかかっていると、やがて目が慣れてきて、見慣れた庭の様子がぼんやりと見えてくる。 寒さの厳しい大寒の最中、如月の朔日。庭には雪が降り積もっていて、その雪に幽かに反射する星明りの中に仄かな紅色が見えた。 まだ数えるほどしか目にしていないが、物心つく前からずっとそこにあるという、紅い梅の木。 都でもまだ珍しい鮮やかな紅色は、侍読であった曽祖父が帝から賜ったものだという。
『阿呼、梅は菅原の家にとって、何より大切な木なのだ』 『だからいつも見守ってくれるよう、阿呼の部屋を此処にしましたよ』
父も子供の頃過ごしたのだという部屋は、正面にその木を臨む大きな蔀戸がある。 鮮やかな紅色に触れてみたくて手を伸ばすが、子供の腕ではとても届かなかった。 熱が下がらず寝ているようにと叱られた身、雪の降り積もる庭に素足で出るのはためらわれて、 それでも諦めきれずに、未練がましく綿入れを被り直してその場に座り込んだ。
「きれい、」
ほう、と発した声は白い息となり、ふわりと消えた。
「きれいでかわいいのう、梅の花は。阿呼の顔につけて飾ったなら、少しは元気に見えるだろうか」
父は文章博士としての仕事で忙しく、母は家のことにかかりきりで、同じ家に居ながらあまり会うことが叶わない。 兄弟はおらず、病気がちで、家から出られぬ身には当然のように友もいない。 家どころか、一度熱が出ると部屋から出ることすら難しく、日々の大半をこの部屋で書に囲まれて過ごしている。 物心ついた頃からずっとそうで、これからも、きっとそうなのだと半ば諦めていた。
だから部屋の窓から眺める外の風景はいつも嫌いだった。 塀の向こうを行き交う人々の喧騒、鳥の鳴き声、それらは僅かな距離であっても決して自分には手が届かない。 外が活気付けば付くほど、ひとりきりのこの部屋の静かさが増して行くようで___特に春は苦手だった。 ずっと冬のまま、静かなままでいればよいのだ。自分も、世間も。
そんな中で、窓を越えて香りを届けてくれるこの梅の花のことだけは何故か嫌いになれなかった。 春の盛りになればきっと届かぬような香りも、冬ならば他の花の香りに邪魔されることもなく、梅の香りだけが届く。 自分と同じように孤独であるにもかかわらず、寒さの中に花を咲かせ、春を待ち望む全てのものを勇気付けるその姿に、 どれだけ羨ましく、こうあることができたらと憧れを募らせたことか。
元気に見えたなら、外に出られるだろうか。 外に出たなら、春の中に自分も入れるだろうか。 ________春を、好きになれるだろうか。
そうして伸ばした手はやはり空を切ったのだけれど、不思議と寂しい気持ちにはならなかった。
「おやすみ、梅の花」
最後に胸いっぱいに香りを吸い込んで、乳母に戸を開けていたことが見つからないようにしっかりと閉める。 褥に伏せてもまだ香りが傍に居てくれるようで、不思議と胸が暖かく、 肺腑に突き刺さる冷気も和らいだような気がして、その夜はそのまま咳のひとつも出さずに眠りに就いた。
「さま…阿呼さま」
「ん、すずなり…」
「あら、今朝は随分と顔色がよろしいこと」
すっかり眠り込んでいたようで、額に触れて、髪を梳いてくれる乳母の手つきでぼんやりと意識が戻る。 乳母の鈴生(すずなり)は、怒りっぽいがよくよく自分の身を案じて世話を焼いてくれる。 今朝は苦しくないのだと告げれば、そうでしょうとも、と呆れたように笑う。 その返事の意味を測りかねて首をかしげると、だって、と続けられた言葉に目を見開いた。
「外の梅の枝を手折って来るほどにお元気なのですから」
ほら、と示す指の先は己の枕元____そこには鮮やかな花とよく膨らんだ蕾をいっぱいに付けた、小ぶりな梅の枝がひとつ。
それほどお元気なのだから朝餉は残してはいけませんよ。その言葉には返事ができなかった。 枕元に転がる、鮮やかな紅梅の一枝は、解けた雪の雫が花弁の上できらりと光っている。 そろりと手を伸ばし、指に触れた花弁のしっとりと濡れた様子が、まるで人の肌に触れたようで思わず取り落としかけた。 きてくれたのか。応えるはずのない問いかけに、乳母が首をかしげるが、何も気にならなかった。
「うん___今に、元気になるのじゃ」
しっかりと手に持ち直し、小さな枝に頬を寄せると、あの香りがした。
0 notes
Text
24/青い鳥小鳥
(しょたろぎとちびゆきの話)
(※CoCシナリオ「ストックホルムに愛を唄え」のネタバレがあります)
晴れた空はつきぬけるほどにたかくまで、あおくふかく、ほかのどんないろもゆるさないといいたげに、りんとすみわたっていた。いえいえのあいまに、木のこずえに、どんなところにもぎんいろをした、雪がふり満ちている。まるでそれらは、鏡をくだいて、そのかけらひとつひとつをふりまいたようにきらきらとさざめいて、ゆらいで、うたっている。
幼いこどもの目には、眩暈を覚えるほど、眩しい風景だった。 明るくて、美しくて、――救いようがないほど、冷たい世界だった。
未明、東京には珍しく、雪が降っていた。水をあまり含まない、ぱさぱさした雪だった。静かに、しかし確かに体積を町に埋め続けたそれは、夜のしじまでは物足りないと言わんばかりに、町の音という音をむさぼり尽くし、たった一夜のあっという間に、世界を真っ白に塗りつぶしたのだった。 とはいえ、都内の人の営みは、それらを厄介に思ったり足止めを食らったりすると言え、こんなもので遮られるほどにひ弱でない。朝も早い時間から、アスファルトの上に降り積もった白はその大多数が踏み潰され、びちゃびちゃに湿り、踏み固められた靴跡や轍が幾つも残っていた。 自宅から離れた、それなりに閑静で大きな家がたくさんあるこのあたりでも、車が通れるくらいの大きさの道路には、雪はもう殆ど残っていない。薄い残雪は、水分で溢れており、夜に冷え込んだらきっと氷になるのだろう。 黄色と緑の両目が、アスファルトを伝う雪水をぼんやりと見つめていた。
空木晴は踏み荒らされた雪の合間を縫って、わずかに残された綺麗な雪のかけらを丁寧に丁寧に、集めて歩いていた。両の手に抱える程の雪が留められていた。彼は、雪だるまを作りたかったのだ。 誰のためと言うわけではない。ただ、雪が積もってする遊びといえば、彼の中にはそれしかなかっただけのことだった。 最初、家のベランダで作ろうとしたのだけれど、邪魔だからと言う理由で止められた。素直に外に飛び出てみても、遊べるような綺麗な雪は、マンションの他の子供たちにもう荒らされてしまっていた。 だから、あてどなく歩いた。 無垢な雪の残りを探して、ただ街を歩いていた。 いくら晴れているとはいえ、真冬の空の下は、きんきんと光るように寒かった。手袋のない手のひらはやがて赤く腫れ、じんじんと痺れ、剥き出しの頬は、刃物で切られるように痛かった。 行けども行けども、住宅街にも、踏み荒らされた積雪にも、終わりはなかった。 冬休みの今、どの家も子供たちは外に飛び出す機会を穴ぐらの子ぎつねのように伺っていたようで、綺麗な雪はもうあらかた誰かに占領されており、晴ひとりが息を潜めて遊ぶことができる場所なんて、どこにもなかった。 塀の片隅に、電信柱の陰に、草むらの上に。誰の手にも触れられていない雪を一すくいずつ集めては、胸に抱えた。 どこか、誰に邪魔されることもない場所で、雪だるまを作るために。 ただ、そのためだけに。
ほうぼう彷徨って、やがて、一つの公園にたどり着いた。そこは、家のない部分を小さく区切って作った、空き地のような場所だった。ベンチと、一人漕ぎのブランコがある以外に、何もない場所だった。幸いにも、周囲には誰の気配だってない。遠くで、タイヤが水っぽい雪を掻き分けるときの、がしゃがしゃという音が響いている。 腕いっぱいに抱えた雪を地面に下ろすと、融けかけの塊はどさりと音をたて、公園の美しい無垢の上に寝転がった。ジャンパーの胸のところが冷たく濡れていた。 息を短く吸う。肺がきりきりと痛んだ。晴は赤く凍える手で、回りの雪をかき集めては、せっせとならし、凹凸のある肌をなめらかにならしていった。胴ができれば、次は頭を。柔らかな表層をすくい取って、手で丸くして、胴に乗せて、素手でならす。指が曲げる度に痛みを帯び、爪の先には少しずつ力が入らなくなっても、晴はただそれを繰り返していた。 ただ、ひとりで延々と、そうしていた。
「――星のおうじさま?」
突然、音のないはずの公園で、後ろから声がした。 思わず振り向いてみると、一人の少女が後ろのベンチの上に立ちながら、じっと晴の姿を見下ろしている。肩で綺麗に切りそろえられた髪は、冬の河底のような密やかな青をしており、銀河色をした大きな瞳が、興味深そうに晴の姿をとらえているのだった。 「ん? や、ちゃうな。おうじさまのかみの毛は、麦の穂ぉのきんいろやったしな……」 声は、独特の抑揚を持っている。この辺りでは、まず聞かないアクセントだった。 少女はそんな調子でぶつぶつ独り言をつぶやきながら、ベンチからぴょんと飛び降り、雪を踏みしめて、晴のところまでてくてくと歩いてくる。 若葉色のゴムぐつが白を割って刺さるたび、まるでそこだけが春の日差しを受けて草花が伸び、生の息吹を受けて眠りから目覚めるようだった。 「あ、かみの毛ぎんいろ」 「、っ」 「じゃあ、雪のおうじさまなんかな?」 晴は、つい身を竦めさせた。 怖いくらい、どきどきしていた。 容姿に触れられたことが、まずひとつ。もうひとつは、公園に来たとき、誰もいなかったはずだったから。公園には誰の足跡もなく、気配もなく、息の音もなかった。今、さっきまで。彼女は音もなくそっと晴の背後に忍び寄り、ベンチの上から猫のように晴のことを見ていたのだ。 公園の反対側の入り口には、迷いなく真っ直ぐ、ベンチまで伸びる小さな足跡が一人分あった。きっと、向こうの入り口からやってきたのだろう。 「……」 晴は固まって、少女がこちらに近づいてくるのを怯えながら見ていた。少女の紺色のコートが、マフラーの裾が、ふわふわと揺れていた。彼女は晴の傍までずんずんと近づいてくると、固まっている晴の顔を覗き込んで、まじまじとその色の異なる両目をまっすぐに見つめる。 「うん。お星さまより、おひさまの下の雪みたいなかみの毛しとうもんね。でも、きみ、目ぇも綺麗やなあ! お空から降ってきた、宝石みたいや!」 少女はそう、屈託の無い笑顔で言って、ただにこにこ笑っている。 晴は。
――晴は、いよいよいたたまれなくなって、冷たい両手で、自分の顔を覆った。これ以上見られないように、夏の雨のように突然体を打ち据えた恐怖ごと隠すように、じりじりと二、三歩後ずさる。少女は「えっ」と驚いた声を上げて、夜空のような瞳をまん丸くして、その星図を広げる。しかし、逃げられた分の距離を、若草色のゴムぐつは迷うことなく歩を詰める。 「やだ」 「? なんて?」 「……きれいでも、なんでもないのに、なんでほめるの」
どうして、この人、きもちわるいところなんて、ほめるの。
「だって、きれいやん」 彼の声の震えに気付かなかったのか、少女はきょとんとした顔で言った。星が大気の内側で歌うように、その銀河もまた息を吸って、ふるふると揺れる。逃げる意味を解釈することができないと言いたげに、困惑した表情を浮かべて、小鳥のように首を傾げる。 「やだ、」 晴はただひたすらに、ぞっとした。背筋にぴりっとした電流が走ったようだった。じり、と後ずさり、少女と距離をとる。小さな雪だるまの後ろに逃げ込むようにして、顔を、体を隠そうとする。 「なんで隠れんの!」 「や、だ!」 逃げた。 逃げるとは言っても、雪だるまを挟んで追いかけ合うだけだった。恐怖心が先立って足は縺れるし、混乱した頭では、公園の外へ飛び出すことなんて考えられなかった。少女は負けじと追ってくるし、諦める気配も無いようだった。 「待ってって言うとるやん!」 延々と続くかと思われた小さな鬼ごっこは、少女が晴の服の裾を問答無用でひっつかんだことで、あっけなく終わりを迎えた。二人がさんざん踏み散らかした雪の上に、晴がべしゃり、音を立てて転ぶ。 「あ、ごめ……」 「……ぅ」 雪の上に、じわりと涙がにじむ。 痛みからではない。どうしたらいいか、わからなかったからだ。そんな顔も見せたくなくて、暫く雪の上に伏せたままだった。冷たい両手は、鞭うたれたように痺れていた。 そんなところに、目の前に手が伸びてくる。それは、手袋に覆われた、少女の手だった。しゃがんで、申し訳なさそうに晴の顔を見ている。 真っ直ぐに、見つめている。 「ごめんなぁ? ……たてる?」 「……」 「だいじょうぶ?」 晴はただ、固まっていた。少女はじっと手を差し伸べたまま、動かない。冷たい風が、二人の前髪をさらさらと揺らした。どこかの木の枝から、やわらかく融けた雪の、落ちる音が聞こえた。 「……」 しばらく時間が経って、少女が寒さにふるりと身を震わせたころ、ほんとうに、ゆっくり、おずおずと、戸惑うように、躊躇うように、――晴が、少女に向けて手を伸ばした。彼女はそれを受けて、晴の体を引っ張り上げる。握られた指は鳴るように痛んだ。手袋の繊維の一本一本ですら、自分を攻撃しているような気分になった。 二人とも並んで立つと、少女の方が僅かに背が高かった。「ごめんなあ」としきりに謝りながら、ぱたぱたと晴の体についた雪や滴を払っていく。その様子を、晴は不安げなもどかしさを浮かべながら見ていた。 「……なんで、やさしくして���れるの?」 「へあ?」 「……みんなぼくのこと、きもちわるいっていうのに」 「んなことあらへんよ」 「……なんで?」 「なんで、って……うちがきれいや思たもんにきれいって言うて、どーしてダメやって言われなあかんねん。うちはきれいだとおもたで。それで、ええことやないん?」 少女は「はい、もっときれいになった」と言って、もう一度すっくと立ち上がる。そうして、不意に思い出したように、自分の手袋を脱ぎ、素手のまま晴の両手を取った。突然手の指に重なるあたたかな人の体温に、晴の体が総毛立って硬直する。 「うわひゃっこ! なんでこんなんなるまで手袋せえへんの!?」 「……て、てぶくろ、ない」 「なんで!?」 晴がおろおろと眉根をよせて、ただ身を竦ませているのを見ると、彼女は大きく溜め息をついてから、とった両手を自分の顔の高さまで持ち上げた。そのまま、晴の両手にはあ、と息を吹きかけて、ゆっくりと摩(さす)った。 摩る、重ねられた手もまた、白く、小さな手のひらだった。赤く凍えて、濡れた皮膚を愛撫するように、少女は真剣な表情で晴の両手を温め続けた。晴は身を固くして、何度も手を引っ込めようとした。だが、少女の目があまりにも真摯だったので、何をすることもできなかった。 やがて、手のひらの冷たさは平等に二人の間に行き渡り、少女の手指が微かに赤らんだころ「はい」と言って彼女は自分の手袋を差し出した。 「はい。貸したる」 「……でも、ぼくがつけたら、寒くなっちゃうよ」 「だいじょーぶ、うち、替えのやつあるから。それに、うちがつけとったやつのほーが、ぬくいやろ」 躊躇していると、痺れを切らした彼女が無理矢理に手袋を嵌めてきた。抗おうとしても、両手で片手を握られてはたまらない。結局、晴の両手には、少女の手袋がすっぽりと被せられた。内側に、少女の体温が残されたままだった。誰かの寝ていた布団の中に、手を差し込んだ時のような暖かさだった。 晴がどうふるまったものか思案した挙句、そのままおずおずと雪だるまに手をつけ直すと、その様子を少女はじっと見つめていた。 「……雪であそぶの、すき?」 「……すき」 晴が頷くと、少女はどこか嬉しそうに、赤らんだ頬を緩めてにんまり笑った。 「うち、なまえな、“ゆきみつ”言うねん。いまあそんどる雪に、いっぱいになるっていういみの、満。で、ゆきみつ。みょーじがお風呂場にある鏡で、かがみゆきみつ」 自分を指さして言う。思わず、晴も指の指すほうに目線を吸い寄せられた。 「ゆき、みつ、……ちゃん」 「ゆき、でええよ。……きみは?」 「……はる。うつろぎはる」 「はるくんな!」 そう行って、雪満が差し出した右手の意味を、晴は理解できずに瞬きした。焦れたように、雪満が唇を尖らせて「あくしゅ」と言うと、晴はますます顔を曇らせる。 「あくしゅ?」 「ともだちになったら、そらあくしゅするやろ」 「……、……」 「どないした?」 「ともだちに、……なってくれるの?」 「うん? せやよ」 「……ほんとにほんとに、ともだちになって、くれるの」 「うん。だって、なまえ教えっこしたら、もうともだちやん」 「……、……、……やった……」 硬いつぼみが解けるような音を立てて、晴の目がきらきらと光る。焼けた石のような色をしていた。火に焼(く)べて融け出した、宝石の色だ。 そろそろと、ぎこちなく手を握る。雪満はその仕草に首を傾げてから、満足げに手をぶんぶんと上下させた。 「なあ、そんな小ちゃい雪だるまなんて作らんで、もっとおっきいやつ作ろや!」 「え」 「こーんなん!」 雪満が両手を大きく広げる。晴は目を大きく広げ、背伸びする雪満を目で追う。胸を張る雪満を、困ったように見上げた。 「え、でも、……おっきいのつくっても、こわされちゃうよ」 「そうなん? じゃあ、うちの庭につくればええ」 こっち。と言いながら、強引に手を引く。慌ててついていけば、公園を少し過ぎたところに、庭のある大きな邸宅が目に入った。塀は高く、門は優美で、前庭には常緑樹が茂っていた。表札を見上げる。晴にその漢字の意味はわからなかったが、苗字が一文字なのだということだけはわかった。 門は黒く、細いめっきのされた鉄で編まれていた。開いている。玄関に繋がるアプローチは、きちんと雪かきがされていた。
周辺に公園ほど綺麗な雪は残っていなかったけれど、庭先には木から零れ落ちた雪が積もっていた。 それらを集めて、小さな雪玉をつくって二人で転がした。庭先には、雪玉の形にそって、除雪された道がくねくねと作り出される。土が混じり、茶色くなった雪玉は、限界まで転がした結果、二人の肩以上に大きくなった。葉っぱの切れ端や、小石が混じったせいで、雪だるまはでこぼこだらけの上、無骨で、どう評価したとしても不細工としか形容できない有様だったが、それは門の脇の木陰に堂々と聳え立っていた。 しかし、大きくなりすぎて、一つ問題ができてしまう。 「あかん! これじゃあたま、乗っけられへん!」 「どうしよう」 「うちがはるくんのことかたぐるましても、雪玉持てへんしな」 晴はおろおろと雪満と、土まみれの雪だるまを交互に見る。当の雪満は難しそうな顔をしながら、何かを考えていたが、暫く顔をもんもんとさせた後、 「うん、よし、むり。おとんにやってもらお」 と、あっけなく諦めた。 「えっ」 「おとーん! 雪だるま作ったから! 頭乗せてー!」 唐突に踵を返して、家の中へ向かって、高らかに吼える。 晴があっけにとられていると、雪満はそれを気にせず彼を引っ張って玄関へ走った。父親のことを呼びながら。晴は動転していたものの、雪満の手を握る力が強すぎて、振りほどくこともできなかった。 父親、家族。しかも、他人の。ぐるぐると晴の目が回る。落ち着いていたはずの胸が、またぎりぎりと締め付けられるようだった。 玄関ポーチの前まで来ると、中から呆れたような溜め息を吐きながら、彼女の父親らしき男性が姿を現す。晴が肩を跳ねさせた。 「なんやねんな……あ~、また日陰にえらいごっつい雪玉作りよって……」 「雪玉やないもん! 雪だるまやもん! はるくんと一緒に作ったんやで! どや、すごいやろ」 「はるくん……?」 「うん、おともだち」 ほら。と言って、雪満が手を引っ張る。晴は、おどおどと眉を下げたまま、萎縮したように体を小さくした。男性の目が、どこか品定めするように晴を舐める。思わず俯いて、足下を見た。 一瞬のような無限の時間、裁きを待つ罪人のような心持ちで天啓を待ちわびていると、「おーそか。雪満と遊んでもろてすまんなあ」と、思った以上に軽い声が降ってきて、思わず顔を上げた。 「お前らどんだけ遊び回っとったか知らんけど、全身びちゃびちゃにしとるやん……ほれ、おかんからタオルもろてきて拭いとき。風邪引いたら、たまらんで」 「そうする! おとん、雪だるまかっこよくしといてな!」 「顔くらい自分で作っとかんかい」 「ご近所でいっとーべっぴんにして!」 「オスにしたらええのかメスしたらええのか、わからへんぞそれ」 彼女らがするそんなやりとりを、あっけにとられて眺めていた。 また、ぐいと手が引かれる。雪満はほくほくとした顔で、晴の手を離さないまま、玄関の扉をくぐって家の中へ入っていった。腕の先の晴が萎縮していることに気がついているのかいないのか、雪満は「ただいまあ」と間の抜けた声を出した。 屋根の下の玄関も、庭に見合って広い。晴にとって、三人以上の人間が立って入ることのできる玄関なんて、マンションのロビーくらいなものだった。ほう、と息が出る。外界との空気が遮断されて初めて、体が芯まで冷え切っていることに気がついた。繋いだ腕がぷるぷると震える。 「お帰り。……誰やその子、ご近所の子?」 「せや! 雪のおうじさまやで!」 「アホな事言うとらんと。あんたに王子様なんておるわけないやろ」 「ちゃうてー! 外に積もっとうほーやてー!」 「はいはい。……んで、何くんやったけ」 「、はる、です」 母親からすっと目線を移されて、思わず体がぴんと張る。彼女は一瞬だけ顔の色を無くしたが、すぐにはあ、と息を吐いて、呆れたように笑った。 「はるくんも雪満も、全身びちゃびちゃやん。タオルやるから、ちゃんと服着替えて、身体拭いてき」 「おかん、おとんと同じこと言うとるな」 「やかまし。はよ着替えてきんさい」 「はぁい」 雪満がぽいぽい、と手早くマフラー、ゴムぐつを脱ぎ捨てて、玄関を上がろうとすると、ぐいと後ろにつんのめる。慌てて振り返ると、晴は困ったような顔をして立ち尽くしていた。母親と雪満が同じように不思議そうな顔をした。 「ぼく、きがえもってないよ」 「! パンツまでびちょびちょなんか!?」 「ち、ちがうけど、でも、おうちにとりにいかないと、」 「え、うちのパジャマのズボンくらいなら貸したるて」 「でも……」 「ええから! カゼ引くよりはまーし!」 それからは、追い剥ぎのようなありさまだった。濡れたジャンパーも、靴下も、ズボンまでが引っぺがされ、恥ずかしがる暇すらなく、タオルと替えのズボンを渡される。泡を食いながらも、流石に濡れた素肌では室内でも鳥肌が立ってしまうほどだったので、晴はしどろもどろになりながら、それらを身につけた。 柔らかな繊維からは先の先まで、柔軟剤の華やかな匂いがしていた。自分の家のものとは、全く異なる香りだった。 現状がめまぐるしすぎて、呼吸の仕方すら忘れそうだった。なぜ彼女の母親が、赤の他人の、それも今さっき自分の存在を知ったばかりなのに、手厚くもてなして、まるで“母親のように”自分に溜め息をつき、手を出してくれるのか全く理解の外にあった。
着替えが終わると、雪満は彼を台所に引っ張って行った。そうして、二人で母親が淹れてくれたココアを飲んだ。暖かな甘さが、痛い��どに優しかった。目に見えないほど深い所の傷口に、沁みるような味をしていた。 「なあ、はるくんて、いましょーがくせー?」 「四月から、しょうがくせい」 「うちも! おないどしやん」 「いっしょのがっこう?」 「ご近所やったら、多分いっしょ! あそこの、かどまがったとこのピアノ教室をすぎたとこの……」 「あ、おんなじ」 「やった! じゃあ、春からもはるくんとあそべるんやね、うれしなあ」 雪満は上機嫌でココアを飲み干す。爪の先でマグを弾くと、きん、と高い音が響いた。 「ね、はるくんは他におともだちおらんの」 「……、いない……」 「きょーだいは?」 「お兄ちゃんが、……ぼくは、お兄ちゃんだと思ってるけど、」 「なか、良くない?」 その言葉には小さく頷いた。 正直に返すと、胸がじんじんと痛んで、思わず自分の膝を見た。冷たさに、心まで真っ赤に腫れ上がってしまったのだろうか。 寂しい子供だと、思われただろうか。やはり、彼女もまた、そんな独りぼっちで雪玉を固めて遊ぶ奴なんて、よくよく考えてみたら気持ちが悪いと、思っただろうか。マグカップを握る手に力が入る。 ぽっと出た杞憂の芽は、ふふふ、と隣から、堪えきれない笑いがこぼれたことでつまみ出される。
「ほんなら、今はるくんのなかで、うちがいちばんやん」 雪満は目を細めて、にやにやと、漏れ出る喜びを抑えきれないといった顔で笑う。晴は驚いた後、二度くらいゆっくりと瞬きをして、――彼女の笑いに釣られて、照れくさそうにへにゃ、と表情を歪めた。 それは笑ったわけではなく、反射的に口角が歪んだだけだったのかもしれない。上手な笑顔の作り方は、まだ彼にはわからなかったからだ。 「うちもねえ、まだ引っ越してきたばっかでともだちおらんし、一人っこやから、はるくんがいちばんやで」 「ほんとう? ……、……ぼくが、いちばん?」 「そー。うちら、いちばんどうしやね」 「……! うん!」
軒先の雪が、固まって地面に落ちた。 窓の向こうに、くぐもった音で響いていた。壁のこちら側には、届かない。
外は相も変わらず、底意地悪いほど青一色に晴れ渡っていたけれど、冷たい空気から室内の温さに染められてしまった二人は、ココアを飲んで肩を寄せ合って、他愛のないお互いの話に、面白そうに笑うばかりだった。 晴の赤かった指先は、いつの間にか血の気を取り戻し、柔らかくなっていた。痺れはなく、痛みも無かった。前髪だけが、少し水気に曝されて湿っているばかりだった。 雪満がマグカップを持って椅子を飛び降りる。晴もそれに続いて、流しにそれを押し込んだあと、雪満がくるりと晴を振り向いて自信たっぷりな顔で笑った。 「ね、うちの部屋いこ!」 「ゆきちゃんのおへや?」 「うん。はるくんが雪であそぶのすきなんなら、うちもうちのすきなこと教えたる」 「、うん!」 雪満の部屋は二階の、東側の部屋だった。朝の日差しが取り込めるように、東の壁が大きく出窓になっていて、水色の柔らかな色をしたカーテンが、ふっくら揺れていた。部屋の中はまだ越してきたばかりと言うこともあるのか、クリーニングの匂いがした。 ただ、それ以上に、紙の香りが溢れている。まるで森の中のようだと思った。暗い山の奥から厳かに運び出され、漂白され、苗を植え付けられた、白い森の中にいるようだった。 「うちねえ、本読むのすきなん」 「ご本?」 「そーやで」 招かれた部屋の中は、エアコンでこんこんと暖められていて廊下のような冷たさはない。足下から上ってくる冷えに耐えきれず、二人はそそくさと部屋の中に入った。淡い色のカーペットは足が長く、腰を下ろすと気持ちが良さそうだった。 真新しい勉強机が一つ、それについた椅子が一つ、ベッドが一つ。 それ以上に、晴が目を引かれたのは、部屋にぎっしり所狭しと押し込められた、本棚の群れだ。 「すごいやろ」 おおよそ、小学生に上がる子供の部屋とは思えないほどの蔵書量だった。本棚の足下にはキャスターがついており、左右に移動が容易だった。棚を動かしたその奥にも更に本が詰まっており、その中には晴にはまだ読めないくらい、難しい字のものもあった。 訳の分からない背表紙を一冊引き抜いて、小難しそうな表紙を開いてみる。中にある文字もまた、よくわからないものだった。本当に難しい字にはふりがながついているけれど、小学校で習うのであろう漢字には、ルビも何もついていない。 「よめない!」 「それはちょっとむつかしーやつやんな。うちもたまによめないもじある」 「ゆきちゃん、こんなのよんでるの……!?」 「せやで。ふふん、うちのこと、おねえちゃん扱いする気になったやろ」 「なった! すごい!」 本たちは整然と並べられている。文庫は文庫、菊判は菊��、四六判は四六判で、多少の背の違いはあれ、皆大人しく自分の与えられた隙間でじっと押し黙っていた。 雪満は本たちの背表紙を、そろりとなぞる。書棚の中でも下のほうには、子供向けの、判型がいっそう不ぞろいな絵本たちがわらわらと押し込まれていた。後ろからそれを眺めている晴にも、そのやたらめったら彩色が派手で嫌が応にも目を引くような、ページ数の薄くて紙の厚い本たちの存在は、ぴしっと背の揃った他の本たちに比べて、わやくちゃで、不ぞろいで、どこか親しみやすいものだった。 雪満はその中から、数冊の本を抜き出しては横に重ね、そうしてそれを胸に抱えて、ベッドに座る。自分の右側のスペースをぽんぽんと叩いて、晴を招いた。 「おねえちゃんらしく、うちがはるくんにご本よんであげよー」 「なによんでくれるの?」 「なにがええかなあ。いっこずつよんでこ」 「うん」 さんざん迷って、吟味して、白い小さな手はやがて恭しく一冊の本を持ち上げた。勿体ぶって、仰々しくページを開く。小さな紙面を、二人で覗き込むようにして、肩を寄せ合って、絵本を眺める。雪満の唇が、メーテルリンクの青い文字をなぞった。 「むかしむかし……」
†
子供部屋は、やおら静かになっていった。
そっと雪満の部屋のドアを開くと、エアコンが暖気を吐き出す音だけがごうごうと静かに囁いていた。晴と雪満は、二人揃ってベッドの上で丸くなり、寝息を立てている。絵本や、子供向け文学書や、たぶん、晴にはよくわからないような書籍なども、片づけられもせずその辺に転がっていた。 本を読みながら寝てしまったらしい。 母親は、雪満が頬を乗せている開いたままのヘンゼルとグレーテルの本をそっと抜いて、ページを閉じた。空っぽの絵本棚に戻す。
幸せそうに寝息を立てるふたりのこどもを見下ろす目には、色も感情も、何もかもが、なかった。 ただ、底知れない目だった。 少なくとも、子供をもつ母親の目とは形容しがたかった。こんな目で、子供を見下ろす母親が、どのくらいこの世界にいるのだろうと、背筋の凍えるような、そんな眼差しだった。
どこか値踏みするように一瞬息を止めた後、彼女は二人を起こさないように、ゆっくりと部屋を下がる。扉の音がしないよう、慎重に扉を閉め、廊下に立つと、その隣で父親がナイフで手遊びしながら、声を潜めて聞いた。 「殺らないんか?」 母親は目配せして、肩を竦めた。 「こんな引っ越してすぐ、ご近所の子ぉに手ぇ出したら、流石に足がつくで」 「まぁ、そうやのうても雪満が探すわなあ。恰好の獲物やったんに、流石うちらの子ぉ言うか、めざとい言うか」 「あの感じやと、おらんくなっても親も本腰入れて探さんやろ。一度相手の親御さんにもご挨拶しとかんとなあ」 「生まれながらに蚊帳の外っちゅうことか。けったいやのお」 「そういう家(の)がおるから、うちらみたいなんが居れるんやけどなあ」 二人して、にたにたと下卑た笑いを浮かべる。そうして、母親が何か思いついたような顔をして、より顔の皺をくしゃっと深めて、笑った。 「優しゅうされたことない子ぉはなあ、扱いやすいからなあ。きっとよう懐いてくれるやろなあ」 「お前、なんか悪いこと思いついたやろ」 「いやぁ? でも、せやなあ。ウチにしたら妙案やと思うわぁ。あの子、殺さんでおいて、大事に大事にしたるのも、ええんやないかって思っただけやで」 「またそら、どうして」 母親は、底知れない宇宙のような黒い目を、三日月のように細くした。
「そら、子供は肥らせたほうが、美味いやろお」
魔女が食うもんなんやったら、余計なあ。
たった一枚の扉だけを隔てて、廊下は寒々しく、血も凍るほどに冷たく。暖かな部屋の内側で二人はそんなことも知らず、ただ寄り添って夢を見ていた。 温い、柔らかな日だまりのようなこの夢が、どこまで続くかも知らないまま、ただゆらゆらと、まどろんでいた。 定められた最果てが、道行の無い断崖だなんてまだ知らない。 ただ、それだけ。それだけのこと。
/
0 notes