#美容の最先端を名古屋から発信
Explore tagged Tumblr posts
Text
スイスで見た博物館・美術館 備忘録
栄華で罪深い過去と共に。
いろんなヨーロッパ絵画や歴史的史料を見るなかで、少しだけヨーロッパやスイスのイメージが具体的になってよかったな。
ぜんぶ素人の適当な感想なので、気軽な旅行気分で流し読みしていただければ幸いです。
ラ・ショー・ドゥ・フォン
時計博物館
Lorelei and the Laser Eyesに出てきそうな大きく複雑で謎めいた時計がたくさん見られて楽しかった。歴史的な展示もされていて、最初は日時計・砂時計から始まるのだけれど、最後正確性を求めるうちに、メカメカしい原子時計までいくのが面白かった。
時を、航路を、労働を、計り刻む合理性の象徴としての時計。
写真は複雑なアナログ時計と精密な原子時計。


ヌーシャテル
美術・歴史博物館
地域のちょっとした歴史資料館見るのが好きなので。トラベルパスという共通観光チケットがあれば無料で見られるのも気軽でよい。(多くの博物館・美術館も同様)
小規模だけれど、全体的にまじめに作られていて好印象。精巧な自動人形が見られたのも楽しかった。緻密な絵を描いてくれる!
建物も立派。スイスは町中に豪華で立派で石造りの重い建物がずっとのこっている。


「植民地主義者の銅像をどうしますか?私たちは公共の場で何を、どのように覚えておきたいのでしょうか?」
印象的だったのは、地域の名士の銅像をどうすべきかという展示。ヌーシャテル中心部に立っている町の発展に寄与した名士は、実は奴隷貿易や三角貿易で富を得た人物であり、現代において彼を称える銅像が町にあるのは是か非か、市民はどう考えるのかという展示。地域の歴史紹介や美術家や歴史家など専門家のオピニオンビデオ、市民への公開アンケートなどを用いて多角的に議論の素材を提供する。正解はないけど、とりあえずみんなで過去を踏まえて考えて議論して、今後決めていこうというスタンス。
過去の他地域への搾取とそこから得た富・美を現在どう扱うべきかというテーマは、このちいさな地域の郷土資料館をはじめ、後述するようにほかの美術館当でも見られて、スイスやヨーロッパ全体での時流でもあるのかもしれない。
ベルン
パウル・クレー・センター
クレーの作品は今まで散発的に見たことあるだけでそんなに興味なかったのだけれど、作品をまとめて見られて、なんとなくよさがわかってよかった。作品保護の観点から、展示点数は規模のわりに少なめ。
限られた二次元の色と線という手法でいかに現実を描きうるかという自由で多様な実験みたいな作品が楽しい。絵単体というより、そのいろんな試みが自分には興味深かった。

晩年の、勢いを増すナチス・ドイツの勢力から逃れて故郷ベルンに戻ったのち、なぜか線と色に迷いが消え、寡黙で内省的で象徴性を増していくなぞめいた作品群が個人的には好みだった。
ローザンヌ
リュミエーヌ宮・自然博物館
たまたま休憩に立ち寄った立派な旧宮殿内に、無料で市民開放されている博物館があったので。
おおきなマンモスの化石があった!ほかにもたくさんの剥製(絶滅種も含む)や鉱物・化石が展示されていて、時間なくてゆっくり見て回れなかったけれど、思いがけず充実した展示があり楽しかった。ここも建物が古くて立派。

チューリッヒ
チューリッヒ美術館
中世から現代美術までいろいろなヨーロッパの美術作品がたくさん集まっている。自分の精神は近代で止まったままなので、いろいろな近代絵画が間近で見られてうれしかった。ほかの美術館等と違いトラベルパスは対象外で、別途入館料が必要なので要注意。
マグリットやキリコやフランシス・ベーコンの作品が近くで見られる!やった!!



ムンクのこの絵も、線と色合いの構成がしっかりしたふつうの風景画だけれど、見てるとつらくなってくるような感じがあってよかった。

現代美術
バングラデシュ・ダッカ出身の非営利コレクティブが作ったインスタレーションがよかった。少しだけダッカという地域と縁があったので。


急速な経済発展と社会の変化、押し寄せるたくさんの海外資本・商品・文化と市場社会、そのなかで抱える戸惑いや経済発展への期待や先進国への不信感。作品で表された、現地産業であるニットで編まれたキャンベル缶や粗末な屋台に並ぶたくさんの商品≒危険物��なかに、わずかに知っていたバングラデシュに住む彼らの思いを、芸術作品を通して改めて知れたようでよかったと思う。
デモによる政権交代後、みんなどうなるのかな。無事であるといいのだけれど。
ジャコメッティ作品
スイス出身の作家ということで、こちらも今まであまりよくわからなかった人なのだけれど、この機会にまとめて作品を見ることができてすごくよかった。人間性の衰弱と危機のなかでの抗い、というモダニズムなテーマよかったな。フランシス・ベーコンや河原温とかもそうだけど、モダニズムのなかで人体の徹底的な解体と再構成を描こうとする作品が好きなのかもしれない。


存在だけ再構成されたよろよろしてる犬。かわいいね。

企画展
チューリッヒ美術館のコレクションに多大な貢献をした武器商人「Sammlung Emil Bührle氏」の所蔵コレクションの今後の在り方について問うもの。
戦争という場を利用し、武器の販売で得た多額の富により築かれたコレクション。ここに飾られる絵画の額のすべてには「Sammlung E.G. Bührle」と刻印がされている。モネのきれいな睡蓮などもこの額に囲われ、周辺情報が気になって作品単体の鑑賞が難しい展示。




なお、ほんの一部にナチス・ドイツがユダヤ人から押収した作品も含まれており、こちらについては返還手続きを進めており、展示不可となっているとのこと。
だから作品すべての来歴を明らかにし、それはQRコードで開示されてい���。展示自体がこれらの周辺情報含めて、たくさんの犠牲とそこから得た利益という過去のうえに築かれたコレクションをどう維持し、どういう文脈とともに展示していくか問題提起し、議論するための場となっている。

非常に難しい問いかけであり、自分にはどういう方向性に進むのがいいのかわからないし、作品鑑賞の場としては周辺情報が多すぎるし、けれど無視できない・そうすべきでない問題なのもわかる。過去からは逃れられないけれど、いつか作品そのものをちゃんと鑑賞できる環境が整えられる日が来るんだろうか。
日本では、国立近代博物館の戦争画展示や藤井光氏の展示などが、自分が知っている中では社会的・歴史的経緯に取りまかれる芸術と展示の問題を取り扱っていて、たまに気になって見に行く。
(チューリッヒ美術館まとめ)
いろんなお金と美術と考えが集まる場所なので、ものすごく駆け足に1時間半で見たら大変でした!
ジュネーブ
ルソーの像・ルソーと文学の家
ルソーの諧謔と矛盾に満ちた「孤独な散歩者の夢想」が好きなので、ルソー詣でをしてきた。
家のほうはふつうに1Fでカフェを営業していたのが意外。テーマごとにおしゃれでコンパクトな展示となっていて、日本語ガイドのレンタルもありで見やすい。「孤独な散歩者の夢想」展示が見られたので満足!



国際宗教改革博物館
小ぶりな建物ながら、展示はきれいで整理され、非常に充実・意欲的な内容でよかったな。特設Wi-Fiで接続できるホームページから多言語対応されていて、しっかり翻訳された日本語で見やすく展示解説が読めるのも、ちゃんと説明しようというやる気を感じた。
当然プロテスタントの視点からの展示だけれど、あまり宗派に偏らず、比較的フラットに解説されている印象(自分がキリスト教に不明のためわからないだけかもしれないけれど)
聖書がラテン語からドイツ語・フランス語・英語に翻訳されることで、書物が権力��係を変え、そして社会が変わっていったことを、当時の書物を通して少しだけ思いを馳せることができるようでよかった。
写真はラテン語から英語やドイツ語など様々な言語に翻訳された、宗教改革当時の聖書。




ジュネーブに滞在し、宗教改革で大きな役割を果たしたカルヴァンについては、偶像崇拝を厳しく禁じていたため、彼が使ったといわれてるコップしか遺物が残ってなくて、それが展示されているのがおもしろかった。
宗教改革でよりモダンな形に切り替わったキリスト教が商業主義・物質主義に取り込まれていくこと、女性や疎外された人々がプロテスタントの教義について議論する演劇をもとにした映像作品、そして今日的な「プロテスト」の在り方など、意欲的な展示構成も見ていて楽しかった。時間の都合上、駆け足でしか見られなくて残念。


ざっくりまとめ
海外でもGoogle翻訳のカメラ機能で展示解説をおおむね読むことができるので本当に助かる。ホームページやガイド端末で日本語含めた多言語対応しているところも意外とあった。
自分が行った場所はどこに行っても古く重い石造りの建物が残っていて、重く逃れられない過去のなかにずっといるようで印象的だった。
小さいけれど、伝えたいことがちゃんとあって、資料の保存や展示の意義を問い続けるような博物館・資料館は、国内外問わず見ごたえあっていいなと思う。大きな美術館や公設の資料館とかもそれぞれ姿勢に違いがあって、いろいろ見られて勉強になった。
最後にいい感じの湖の写真で終わります。湖は最高。

5 notes
·
View notes
Text
世の中は空前のサウナブームらしい。各種情報メディアを駆使して街の銭湯にたどり着いた全国の猛者たちが昼夜問わず約50 - 120 ℃の高温室内で肌を触れ合わせる姿を想像してゾッとしない訳がない。合言葉は「整いました」とのことで、僕はこれを珍奇サウナ偏愛者による「型に嵌ったフロー」と誤読して勝手に溜飲を下げている。チンコだけに、風呂だけに。これはなにもサウナ好きを揶揄しているのではない。むしろ彼らは街の銭湯の隆盛に大いに貢献している。そんなサウナブームを皮切りにして、いまでは銭湯での音楽ライブやDJイベント、更にレコードや書籍を販売する催事までもが行われて、みな一様にそれなりの賑わいをみせているようだ。この数年で銭湯を舞台にしたMVや楽曲がどれだけ製作されたことだろう。これについても、関わった人たちは広義の意味でのリノベーションに一役買っている。公共性の再編とでも形容しておこうか。因みにカセットテープレーベル”Ital.”を主催するケイタくんはサウナ好きではなく、古参にして無類の(ただの)風呂好きである。とある書籍の記述により誤解を招いている可能性があったので、一応。かくいう僕も幼少期に住んでいた家の並びに銭湯があったので週の半分くらいは利用していた。お尻に石鹸を塗りたくって誰が一番速く床を滑ることができるかを競い合う「尻軽レース」に挑戦したり、友人とタッグを組んで肩車をする、もしくは自力で壁をよじ登って女湯を覗くなどの愚行三昧で、いずれも店主にこっぴどく叱られた。16-18歳の頃にはいまも豊津駅の近くにある福助温泉で深夜の清掃アルバイトもさせてもらっていた。誰もいない時間帯の業務目的とは言え、禁断の女湯に足を踏み入れるのは、性欲みなぎる多感な時期の男子として、当たり前にドギマギした記憶がある。ロッカーの片隅に置き去りにされた下着を見つけたときは興奮を抑えきれなかった。いま思い返せば老婆が使用している類の肌色のそれであったが、当時の自分としては貧相な妄想に薪をくべるものであれば、なんでも良かったのだ。バイト終わりにはトイレにこもって自身の陰茎を握り締めた。そんな日の翌朝は決まって寝坊してしまい、定刻の登校に間に合わなかった。そういう小さな欲望の積み重ねが、人を大人にするのだ。僕はいまでも家族で福助温泉に通っている。番台では当時と変わらぬ寡黙な女将さんが節目がちに帳面を捲っている。いまも昔もこの人に向かって性器をさらしているかと思うと、未熟な僕は今更ながらに不思議な感慨に浸ってしまう。女将さん、俺はちゃんとやれただろうか?やるべきこと、果たすべきことを全うできましたか?女将さんは大人になった僕を認識している筈だが、なにも言わない。もともと極端に口数の少ない方だったので、僕の方からも敢えて話題を持ち出すこともない。30年前、父親と一緒に股間を露わにしていた僕がいつしか父親になり、今度は自分の息子たちと共に股間を露わにしている。女将さんはすべてを見て、知っている。心底かなわないと思う。数十年間ずっと変わらぬ姿勢でペンを握る女将さんの手許にある帳面、あそこに世界の秘密、いや、もっと言えば「世紀の発見」がしたためられているのではないかと勘繰らせるほどの圧倒的な寡黙。安易に適温を求めてはならない。静寂の裏側で、湯は激しく沸いている。

もう一件、自分が子どもの頃から足繁く通い、お世話になっていた近所の銭湯、新泉温泉があったのだが、昨年惜しくも閉館してしまった。電気風呂の横に鯉が泳ぐ大きな水槽があって、息子たちも一番のお気に入りだったので、残念で仕方がない。隆盛と没落。この��の均衡が保たれたことなど、かつて一度もなかった筈だ。そもそもフロー(風呂)強者が言うほど簡単に物事が整う訳がない。新泉温泉の最終営業日、もちろん親子で最後の湯に浸かりに行った。しかしそんな日に限って長男がロッカーの鍵を紛失してしまい、浴室や脱衣場を血眼になって探し回るも見つからない。僕ら家族の異変に気がついた店主やその場にいたお客さんも誰が言い出すともなく、一緒になって鍵を探してくれた。床を這いずって探しているうちに銭湯の老朽を伴う歴史が手のひらを通じて伝わってくる。今日限りでもうこの場所には通うことができないことがわかっているので、自ずと込み上げてくるものがあった。鍵は古びた体重計の裏側から発見された。その瞬間、店主以外の全員が全裸のまま快哉を叫びハイタッチした。長男もほっと胸を撫で下ろしていた。これこそが裸の付き合いというものだ。帰り際、息子たちは自分たちで描いた新泉温泉の絵と手紙を店主に手渡した。僕は「実は子どもの頃から通っていたんです」と伝えると店主は「わかってたよ、自転車屋さんのとこの」と言ってくれた。適温を求めてはならない。いつだって現実は血反吐が出るほど残酷だ。それでも僕たちは新泉温泉の湯を忘れない。店主はその日の入浴料を受け取らなかった。

このように僕個人にとっても銭湯には様々な思い入れがあり、いまでも大好きな場所に変わりはないが、それは昨今のサウナブームとはまったく関係がないし、死んでも「整いました」とか言いたくない。そもそもが自分の性器を他者にさらすことも、他者によってさらされた性器を目の当たりにすることも得意ではない。むしろはっきりと苦手だ。世の男性の数だけ多種多様な性器が存在する。サイズ、形状、カラーバリエーション、味、ニオイ等々、どれをとってもふたつとして同じものがない。股の間にぶら下がっているという設置条件がこれまた滑稽で、あのルックスのあの人にあんな性器が、とか、あのガタイのあの人にあんな性器が……みたいな、得たくもない新規情報が視覚を通して脳内に流し込まれるので、煩わしいことこの上ない。挨拶を交わす程度だった近隣の人々とばったり銭湯で遭遇してしまったら、その日を境にして、顔を合わせるたびに性器が脳裏にチラついてしまう。実際に息子の同級生の父親数名と銭湯でチンコの鉢合わせしてしまったのだが、以降、なかなかパパたちのチンコの造形を払拭できなくなる。これはまさに不慮の追突事故、ごっチンコというやつだ。会社員時代、憧れの上司と出張先で入浴を共にする機会があったのだが、どちらかと言えば華奢に分類されるであろう上司の股間には目を覆いたくなるくらいに巨大なふたつのフグリがblah blah blah、いや垂れ下がっていたのだ。洗髪の際にバスチェアに腰掛けておられたが、信じられないことに巨大すぎるフグリはべちゃりと床に接地していた。以来、上司がどれほどの正論を振りかざそうが、客先でのプレゼン時に切れ味鋭くポインターを振り回そうが、どうしたってスラックスの内側で窒息しかけているであろう巨大なフグリを想起してしまう。程なく僕は退職した。とにかく性器というのにはそこにあるが故に素通りすることが難しく、極めて厄介なシロモノである。それが「ない」ことで逆に「有して」しまう諸問題と真摯に向き合��たOBATA LEOの最新作『目下茫洋』は、数多あるフェミニズム関連のテキストとは一線を画する。あまりにグロテスクでおぞましい、だからこそ美しいなどという常套句を粉砕する「弱さ」に貫かれた思考の遍歴。貫く我々♂ではなく、貫かれる♀の身体から滴る分泌液で書かれた紋様のようで、誌面に一定の形状で留められている訳ではない。読む者の素養に左右されるようにして、その形状は刻一刻と微細に変化するだろう。こちらは無数に排泄するが、あちらはたったひとつで対峙している。なにも戦地は彼の地だけではない。戦場は僕やあなたのすぐそばで、いまもネバっこく股を開けている。

臍の下に埋め込まれた爆弾を抉りとるための努力を続けながら、同時にあるのかわからない最終地点に向けて爆弾を運ぶ。本当は抉り取ることはできないとわかっていても、背骨を曲げて運び続けることが、すなわち生きることになっている。『目下茫洋』
8 notes
·
View notes
Text
【小説】コーヒーとふたり (上)
休日に喫茶店へ行くことは、加治木零果にとって唯一、趣味と呼べる行動である。
喫茶店へ行き、コーヒーを飲む。時刻はだいたい午後二時から三時。誰かと連れ立って行くことはない。常にひとりだ。行き先も、決まった店という訳ではない。その時の気分、もしくはその日の予定によって変える。
頼むのは、コーヒーを一杯。豆の銘柄やどのブレンドにするかは店によってだが、基本的にブラック。砂糖もミルクも好まない。軽食やスイーツを注文するということも滅多にない。ただ一杯のコーヒーを飲む、それだけ。
彼女は喫茶店では本を読まないし、パソコンも開かない。スマートフォンにさえ触れないこともある。コーヒーを飲み終えたら、すぐに店を出て行く。たとえその一杯がどんなに美味でも、二杯目を頼むことはない。時間にすればほんの数十分間。一時間もいない。それでも彼女は休日になると、喫茶店へ行き、コーヒーを飲む。
零果がその店を訪れたのは二回目だった。最初に訪れたのは、かれこれ半年近く前のことだ。
た��たま通りかかった時にその店を見つけた。「こんなところに喫茶店があったのか」と思った。喫茶店があるのは二階で、一階は不動産屋。賃貸マンションの間取り図がびっしりと貼り付けられているガラス窓の隣に、申し訳なさ程度に喫茶店の看板が出ていた。
細く狭い階段を上った先にその店はあり、店内は狭いながらも落ち着きのある雰囲気だった。歴史のある店なのか、年老いたマスター同様に古びた趣があるのが気に入った。コーヒーも決して不味くはなかった。出されたカップもアンティーク調で素敵だと思った。
しかしその後、零果の喫茶店リストの中で、その店はなかなか選ばれなかった。その店の立地が、彼女のアパートの最寄り駅から微妙に離れた駅の近くだったからだ。「わざわざあの駅で降りるのはちょっとな……」と思っていた。けれど、最近同じ店に行ってばかりだ。今週末は、普段あまり行かない店に行こう。それでその日、その店を選んだ。
けれど、その選択は失敗だった。
「あれ? 加治木さん?」
そう声をかけられた時、零果は運ばれて来たばかりのコーヒーをひと口飲もうとしているところだった。カップの縁に唇を付けたまま、彼女はそちらへと目を向ける。
その人物はちょうど、この店に入って来たところだった。そして偶然にも、零果は店の入り口に最も近い席に案内されていた。入店して真っ先に目につく席に知人が座っているのだか���、彼が声をかけてきたのは当然と言えば当然だった。しかし、零果は彼――営業部二課の戸瀬健吾に声をかけられたことが衝撃だった。
「こんなところで会うなんて、奇遇だね」
戸瀬はいつもの人当たりの良い笑みを浮かべてそう言ったが、零果は反応できなかった。驚きのあまり、何も言葉が出て来ない。しかし彼女の無言に気を悪くした様子はなかった。
「俺はよくこの店にコーヒーを飲みに来るんだけど、加治木さんもよく来るの?」
笑顔で尋ねてくる戸瀬に、零果はカップを口元から離してソーサーの上へと戻しながら、「いえ、その……たまに……」と、かろうじて答える。この店に来たのは二度目だったが、そう答えるのはなんとなく抵抗があった。あまり自分のことを他人に明かしたくない、という彼女の無意識が、曖昧な表現を選んでいた。
「そうなんだ。ここのコーヒー、美味いよね。あ、じゃあ、また」
やっと店の奥から店員が現れ、戸瀬は空いている席へと案内されて行った。幸いなことに、彼の席は零果から離れているようだ。大きな古めかしい本棚の向こう側である。
戸瀬の姿が見えなくなってから、零果はほっと息をついた。休日に同僚と顔を合わせることになるとは、なんて不運なのだろう。その上、場所が喫茶店だというところがツイていない。
改めてコーヒーを口元へ運んだが、未だ動揺が収まらない。半年前に来店した時は悪くなかったはずのブルーマウンテンブレンドだが、戸瀬の顔を見た後の今となっては、味の良し悪しなどわからなかった。香りも風味も台無しだ。コーヒーカップのブルーストライプ柄でさえ、「さっき彼が似たような柄のシャツを着ていなかったか?」と思うと途端にダサく思えてくる。
それに加えて、戸瀬は先程、こう言った、「俺はよくこの店にコーヒーを飲みに来るんだけど、加治木さんもよく来るの?」。
その言葉で、彼女の喫茶店リストから、この店が二重線を引かれ消されていく。
同僚が常連客となっている喫茶店に足を運ぶなんて御免だ。二度目の来店でその事実を確認できたことは、不幸中の幸いだったと思うしかない。数回通い、この店で嗜むコーヒーの魅力に気付いてしまってからでは、店をリストから削除することが心苦しかったはずだ。ある意味、今日は幸運だった。この店は最初からハズレだったのだ。
零果は自分にそう言い聞かせながらコーヒーを飲む。味わうのではなく、ただ飲む。液体を口に含み、喉奥へと流す。せっかく、いい店を見つけたと思ったのに。うちの最寄りから、五駅離れているのに。飲み込んだ端から、落胆とも悔しさとも区別できない感情がふつふつと沸き上がってくる。その感情ごと、コーヒーを流し込む。
早くこの店を出よう。零果は、一刻も早くコーヒーを飲み干してこの店を出ること、そのことに意識を集中させていた。
コーヒーを残して店を出ればいいのだが、出されたコーヒーを残すという選択肢はなかった。彼女は今まで、たとえどんなに不味い店に当たってしまっても、必ずコーヒーを飲み干してきた。零果にとってそれはルールであり、そのルールを順守しようとするのが彼女の性格の表れだった。
先程入店したばかりの客が熱々のコーヒーを急いで飲み干してカウンターの前に現れても、店の主人は特に驚いた様子を見せなかった。慣れた手つきで零果にお釣りを渡す。
「ごちそうさまでした」
財布をショルダーバッグに仕舞いながら、零果は店を出て行く。「またのお越しを」という声を背中で受け止め、もう二度とこの店に足を運ぶことはないだろうな、と思い、そのことを残念に思った。深い溜め息をついて階段を降り、駅までの道を歩き出す。
店の雰囲気は悪くなかった。コーヒーだって悪くない。ただ、戸瀬の行きつけの店だった。
否、それは戸瀬個人に問題があるという意味ではない。彼の物腰柔らかで人当たりの良い態度や、その温厚な性格は職場内でも定評があるし、営業職としての優秀さについても、零果はよくわかっている。
そうではなく、零果はただ、同僚に会いたくないだけなのだ。休日に喫茶店でコーヒーを飲んでいる時だけは。唯一、彼女にとって趣味と呼べるであろう、その時間だけは。知り合いには誰とも会うことなく、ひとりでいたい。平日の書類とメールの山に抹殺されそうな多忙さを忘れ、心も身体も落ち着かせたい。そのためには極力、同僚の顔��見ないで過ごしたい。
駅に着くと、ちょうど零果のアパートの最寄り駅方面へ向かう電車が、ホームに入って来たところだった。このまま家に帰るだけというのも味気ない、と思いかけていた零果であったが、目の前に停車した電車を目にし、「これはもう、家に帰れということかもしれない」と思い直した。もうこの後は、家で大人しく過ごすとしよう。
そう思って、電車に乗り込む。車両の中にはすでに数人の乗客が座っており、発車までの数分を待っている様子であった。零果は空いていた座席に腰を降ろそうとし、そこで、自分の腰の辺りで振動を感じた。バッグに入れてあるスマートフォンだ、と気付いた。その一瞬、彼女はスマホを手に取ることを躊躇った。
バイブレーションの長さから、それがメールやアプリの通知ではなく着信を知らせるものだということはわかっていた。休日の零果に電話をかけてくる相手というのは限られている。候補になりそうな数人の顔を思い浮かべてみたが、誰からの着信であっても嬉しいニュースであるとは思えない。
座席に腰を降ろし、スマートフォンを取り出す。そこで、バイブレーションは止まった。零果が呼び出しに応じなかったので、相手が電話を切ったのだ。不在着信を示すアイコンをタップすると、発信者の名前が表示された。
有武朋洋という、その名前を見た途端、めまいを覚えた。ちょうど、午後四時になろうとしているところだった。判断に迷う時間帯ではあったが、この電話は恐らく、今夜食事に誘おうとしている内容ではないだろうと、零果は確信していた。
膝の上でショルダーバッグを抱き締めたまま、メッセージアプリを開き、有武に「すみません、今、電車なんです」とだけ入力して恐る恐る送信する。瞬時に、零果が見ている目の前で、画面に「既読」の文字が現れた。恐らくは今、彼もどこかでこのアプリを開いて同じ文面を見つめているに違いなかった。案の定、間髪入れずに返信が表示される。
「突然悪いんだけどさ、ちょっと会社来れる?」
零果が思った通りだった。有武の、「悪いんだけどさ」と言いながら、ちっとも悪びれている様子がない、いつものあの口調を思い出す。
「今からですか?」
今からなんだろうな、と思いながら、零果はそう返信する。
「そう、今から」
「今日って休日ですよね?」
休日でも構わず職場に来いってことなんだろうな、と思いながら、それでもそう返信をせずにはいられない。
「そう、休日」
何を当たり前のこと言ってんだよ、って顔してるんだろうな、有武さん。少しの間も空けることなく送られて来る返信を見ながら、零果は休日の人気がないオフィスでひとり舌打ちをしている彼の様子を思い浮かべる。
「それって、私が行かないと駄目ですか?」
駄目なんだろうな、と思いながらそう返信して、座席から立ち上がる。
駅のホームには発車のベルが鳴り響いている。零果が車両からホームに戻ったのは、ドアが閉まりますご注意下さい、というアナウンスが流れ始めた時だった。背後で車両のドアが閉まり、彼女を��せなかった電車は走り出していく。
家に帰るつもりだったのにな。零果は諦めと絶望が入り混じった瞳でその電車を見送った。握ったままのスマートフォンの画面には、「加治木さんじゃなきゃ駄目だから言ってるんでしょーよ」という、有武からの返信が表示されている。
「…………ですよね」
思わずひとり言が漏れた。ホームの階段を上りながら、「今から向かいます」と入力し、文末にドクロマークの絵文字を付けて送信してみたものの、有武からは「了解」という簡素な返信が来ただけだ。あの男には絵文字に込められた零果の感情なんて届くはずもない。
再び溜め息を盛大についてから、重くなった足取りで反対側のホームに向かう。なんて言うか、今日は最大級にツイてない。休日に、一度ではなく二度までも、同僚と顔を合わせることになるとは。しかも突然の呼び出しの上、休日出勤。
ただひとりで、好きなコーヒーを飲んで時間を過ごしたいだけなのに。たったそれだけのことなのに。
心穏やかな休日には程遠い現状に、零果はただ、肩を落とした。
「加治木さん、お疲れ様」
そう声をかけられた時、思わず椅子から飛び上がりそうになった。咄嗟にデスクに置いてあるデジタル時計を見る。金曜日、午前十一時十五分。まだ約束した時間まで四十五分あるぞ、と思いながら零果は自分のデスクの横に立つ「彼」を見上げ、そこでようやく、声をかけてきたのが「彼」ではなく、営業部の戸瀬だったと気が付いた。
「あ……お疲れ様です」
作成中の資料のことで頭がいっぱいで、零果は戸瀬に穏やかな笑顔を見つめられても、上手い言葉が出て来ない。五四二六三、五万四千二百六十三、と、零果の頭の中は次に入力するはずだった数値がぐるぐると回転している。キーボードに置かれたままになっている右手の人差し指が、五のキーの辺りを右往左往する。
当然、戸瀬には彼女の脳内など見える訳もなく、いつもの優しげな口調で話しかけてきた。
「この間の土曜日は、びっくりしたね。まさかあんなところで加治木さんに会うなんて」
土曜日、と言われても、零果はなんのことか一瞬わからなかった。それから、「ああ、そう言えば、喫茶店で戸瀬さんに会ったんだった」と思い出す。
「でも、聞いたよ。あの後、有武さんに呼び出されて休日出勤になっちゃったんだって? 加治木さん、いつの間にかお店から消えてるから、おかしいなって思ってたんだけど、呼び出されて急いで出てったんでしょ?」
零果は思わず、返事に困った。急いで店を出たのは戸瀬に会って気まずかったからだが、まさか目の前にいる本人にそう伝える訳にもいかない。有武の呼び出しのせいにするというのも、なんだか違うような気もするが、しかし、戸瀬がそう思い込んでいるのだから、そういうことにしておいた方が得策かもしれない。
「えっと、まぁ、あの、そうですね」などと、よくわからない返事をしながら、零果の右手は五のキーをそっと押した。正直、今は戸瀬と会話している場合ではない。
「有武��んもひどいよね、休日に会社に呼び出すなんて。そもそも、加治木さんは有武さんのアシスタントじゃないんだから、仕事を手伝う必要なんてないんだよ?」
戸瀬の表情が珍しく曇った。いつも穏やかな彼の眉間に、小さく皺が寄っている。本気で心配している、というのが伝わる表情だった。けれど今の零果は、「はぁ、まぁ、そうですよね」と曖昧に頷くことしかできない。四のキーを指先で押しつつ、彼女の視線は戸瀬とパソコンの画面との間を行ったり来たりしている。休日出勤させられたことを心配してくれるのはありがたいが、正午までにこの資料を完成させなければいけない現状を憂いてほしい。零果にはもう猶予がない。
「なんかごめんね、加治木さん、忙しいタイミングだったみたいだね」
戸瀬は彼女の切羽詰まった様子に勘付いたようだ。
こつん、と小さな音を立てて、机に何かが置かれた。それはカフェラテの缶だった。見覚えのあるパッケージから、社内の自動販売機に並んでいる缶飲料だとわかる。零果が見やると、彼は同じカフェラテをもうひとつ、右手に握っていた。
「仕事がひと段落したら、それ飲んで休憩して。俺、このカフェラテが好きなんだ」
そう言って微笑む戸瀬の、口元から覗く歯の白さがまぶしい。「あ、あの、ありがとうございます」と零果は慌ててお礼を言ったが、彼は「全然いいよー」とはにかむように左手を振って、「それじゃ、また」と離れて行った。
気を遣われてしまった。なんだか申し訳ない気持ちになる。恐ら���戸瀬は、休日に呼び出され仕事に駆り出された零果のことを心から労わってくれているに違いなかった。そんな彼に対して、自身の態度は不適切ではなかったか。いくら切羽詰まっているとはいえ、もう少し仕事の手を止めて向き合うべきだったのではないか。
そこで零果は、周りの女子社員たちの妙に冷たい目線に気が付いた。「営業部の戸瀬さんが心配して話しかけてくれているのに、その態度はなんなのよ」という、彼女たちの心の声が聞こえてきそうなその目に、身がすくむような気持ちになる。
しょうがないではないか。自分は今、それどころではないのだから……。
パソコンに向き直る。目の前の画面の数字に意識を集中する。しかし、視界の隅に見える、カフェラテの缶。それがどこか、零果の心にちくちくと、後悔の棘を刺してくる。あとで、戸瀬にはお詫びをしよう。零果はカフェラテを見つめながら、心に黄色い付箋を貼り付ける。それにしても、カフェラテというのが、また……。
「資料できたー?」
唐突にそう声をかけられ、彼女は今度こそ椅子から飛び上がった。気付けば、側には「彼」が――日焼けした浅黒い肌。伸びすぎて後ろで結わえられている髪は艶もなくパサついていて、社内でも不評な無精髭は今日も整えられている様子がない。スーツを着用する営業職の中では珍しく、背広でもジャケットでもなく、作業服をワイシャツの上に羽織っているが、その上着がいつ見ても薄汚れているの��また、彼が不潔だと言われる理由である。ただ、零果がいつも思うのは、彼は瞳が異様に澄んでいて、まるで少年のようであり、それでいて目線は鋭く、獲物を探す猛禽類のようでもある、ということだ――、有武朋洋が立っていて、零果の肩越しにパソコンのディスプレイを覗き込んでいた。
「あれ? 何、まだ出来てないの?」
咄嗟に時刻を確認する。戸瀬に声をかけられてから、もう十分近くも経過している。なんてことだ。しかし、約束の時間まではあと三十五分残されている。今の時点で資料が完成していないことを責められる理由はない。それでも零果が「すみません」と口にした途端、有武は「あー、いいよいいよ」と片手を横に振った。
「謝らなくていいよ。謝ったところで、仕事が早く進む訳じゃないから」
斬って捨てるような口調であったが、これが彼の平常だ。嫌味のように聞こえる言葉も、彼にとっては気遣って口にしたに過ぎない。
「時間には間に合いそう?」
「それは、必ず」
「そう、必ずね」
零果は画面に向き直り、資料作りを再開する。ふと、煙草の臭いがした。有武はヘビースモーカーだ。羽織っている作業着の胸ポケットには、必ず煙草とライターが入っている。煙草臭いのも、社内外問わず不評だ。しかし有武本人は、それを変える気はないようである。
「うん……大丈夫そうだ。本当に、正午までには出来上がりそうだね。さすがだなぁ、加治木さんは」
零果が返事もせずにキーボードを叩いていると、彼の右手が横からすっと伸びてきて、机の上のカフェラテの缶を取った。零果が「あ、それは……」と言った時、缶のプルタブが開けられた音が響く。
「これ、飲んでもいい?」
「…………はぁ」
どうして、缶を開けてから訊くのか。順序がおかしいとは思わないのだろうか。
「飲んでいいの?」
「……どうぞ」
「ありがと」
有武は遠慮する様子をまったく見せず、戸瀬が置いて行ったカフェラテをごくごくと飲んだ。本当に、喉がごくごくと鳴っていた。それから、「うわ、何これ、ゲロ甘い」と文句を言い、缶に記載されている原材料名をしげしげと眺めている。人がもらった飲み物を勝手に飲んで文句を言うな。零果はそう思いながらも、目の前の資料作成に集中しようとする。どうしてこんな人のために、せっせと資料を作らねばならないのだろうか。
「じゃ、加治木さん。それ出来たらメールで送って。よろしくね」
そう言い残し、カフェラテの缶を片手に有武は去って行く。鼻歌でも歌い出しそうなほど軽い彼の足取りに、思わず怒りが込み上げる。階段で足を踏み外してしまえばいい。呪詛の言葉を心の中で吐いておく。
有武がいなくなったのを見計らったように、後輩の岡本沙希が気まずそうに無言のまま、書類の束を抱えて近付いて来た。零果がチェックしなければならない書類だ。
「ごめんね、後でよく見るから、とりあえずそこに置いてもらえるかな」
後輩の顔を見上げ、微笑んでみたつもりではあったが、上手く笑顔が作れたかどうかは疑問だった。岡本は何か悪いことをした訳でもないだろうに、「すみません、すみません」と書類���置いて逃げるように立ち去る。そんなに怖い顔をしているのだろうか。零果は右のこめかみ辺りを親指で揉む。忙しくなると必ず痛み出すのだ。
時計を見つめる。約束の時間まで、あと三十分。どうやら、ここが今日の正念場のようだ。
「メールを送信しました」という表示が出た時、時計は確かに、午前十一時五十九分だった。受信する側は何時何分にメールが届いたことになるのだろう、という考えが一瞬過ぎったが、そんなことを考えてももう手遅れである。
なんとか終わった。間に合った。厳密には一分くらい超過していたかもしれないが、有武がそこまで時刻に厳密な人間ではないことも、この資料の完成が一分遅れたところで、今日の午後三時から始まる会議になんの影響もないこともわかっていた。
零果はパソコンの前、椅子に腰かけたまま、天を仰いでいた。彼女が所属する事務部は五階建ての社屋の二階にあるため、見上げたところで青空が見える訳はない。ただ天井を見上げる形になるだけだ。
正午を告げるチャイムが館内放送で流れていた。周りの女子社員たちがそれを合図にぞろぞろと席を立って行く。呆然と天井を見つめるだけの零果を、彼女たちが気に留める様子はない。それはある意味、日常茶飯事の、毎日のように見る光景だからである。魂が抜けたように動かないでいた零果であったが、パソコンからメールの着信を知らせる電子音が鳴り、目線を画面へと戻した。
メールの送信者は有武だった。本文には、零果の苦労を労う言葉も感謝の言葉もなく、ただ、「確認オッケー。午後二時半までに五十部印刷しておいて」とだけ書かれていた。やっぱりなぁ。そうくると思ったんだよなぁ。当たらないでほしい予想というのは、なぜかつくづく当たるものだ。嫌な予感だけは的中する。
十四時半までには、まだ時間がある。とりあえず今は、休憩に入ろう。
零果は立ち上がり、同じフロア内にある女子トイレへと向かった。四つ並んだうちの一番奥の個室に入る。用を足していると、扉が閉まっていたはずの手前の個室から人が出て行く気配がした。その後すぐ、水を流す音と、扉がもうひとつ開かれた音が続く。
「ねぇ、さっきのあれさぁ……」
「あー、さっきの、加治木さんでしょ?」
手洗い場の前から会話が聞こえてくる。
零果は思わず動きを止めた。声のする方へと目線を向ける。扉の向こうが透視できる訳ではないが、声から人物を特定することはできる。ふたりとも、同じフロアに席を置いている事務員だ。正直、零果と親しい間柄ではない。
「戸瀬さんがせっかく話しかけてくれてるのに、あの態度はないよね」
「そう、なんなの、あの態度。見てて腹立っちゃったよ」
蛇口が捻られ、手を洗う音。零果は音を立てずにじっとしていた。戸瀬ファンクラブ所属のふたりか。恐らく、ここに零果本人がいるということを、ふたりは知らないに違いない。
「戸瀬さんもさ、なんで加治木さんなんか気にかけるんだろうね?」
「仕事が大変そうな女子社員を放っておけないんじゃな��? 戸瀬さんって、誰にでも優しいから」
「加治木さんが大変な目に遭ってるのは、有武のせいでしょ?」
きゅっ、と蛇口が閉められた音が、妙に大きく響いた。その時、零果は自分の胸元も締め付けられたような気がした。
「そうそう、有武が仕事を頼むから」
「加治木さんも断ればいいのにね。なんで受けちゃうんだろう。もう有武のアシスタントじゃないのにさ」
「さぁ……。営業アシスタントだった過去にプライドでもあるんじゃない?」
ふたりのうちのどちらかが、笑ったのが聞こえた。
「うつ病になってアシスタント辞めたくせに、事務員になってもプライド高いとか、ちょっとねぇ……。自分で仕事引き受けて、それで忙しくって大変なんですって顔で働かれてもさぁ……」
足音と共に、ふたりの会話も遠ざかっていく。どうやら、女子トイレから出て行ったようだ。
ふたりの声が完全に聞こえなくなるのを待ってから、零果は大きく息を吐いた。「……有武さんのことだけは、呼び捨てなんだ」と、思わずひとり言が漏れた。そんなことはどうでもいい。どうでもいいけれど、言葉にできる感想はそれくらいしか思い付かなかった。
他の事務員から陰で言われているであろうことは、薄々わかってはいた。同じ内容を、言葉を選んで、もっともらしい言い方で、面と向かって言う上司もいる。同僚たちに特別好かれているとは思っていなかった。しかし、本人には届かないだろうと思って発せられる言葉というのは、こんなものなのか。
水を流し、個室から出た。鏡に映る自分の顔の疲弊具合に気分はますます陰鬱になる。腹の底まで冷え切っているように感じる。
同じ階にある休憩室へ向かおうと思っていたが、先程のふたりもそこにいるのだろうと思うと、足を向ける気にはならなかった。さっきの会話の続きを、今もしているかもしれない。
自分の席に戻って仕事を再開するというのも考えたが、こんな疲れた顔で休憩も取らず仕事をしているところを、誰かに見られるのも嫌だった。
結局、零果は四階に向かうことにした。階段で四階まで上ると、営業部が机を並べているフロアと、会議室が両側に並ぶ廊下を足早に通り過ぎる。外出していることが多い営業部だが、昼の休憩時間に突入しているこの時間は、いつにも増して人の姿がない。零果は何も躊躇することなく、通路の突き当り、外階段へと続く重い鉄の扉を開けた。
非常時の利用を目的に作られた外階段を、普段利用する社員はほぼいない。喫煙室以外の場所で煙草を吸おうとする不届き者ぐらいだ。外階段だけあって、雨風が吹き荒れ、もしくは日射しが照り付け、夏は暑く冬は寒いその場所に、わざわざ足を運ぶ理由。それは「彼」に会いたいからだ。
「おー、お疲れ」
鉄製の手すりにもたれるようにして、「彼」――有武朋洋がそこにいた。いつも通り、その右手には煙草がある。有武は、この外階段でよく煙草を吸っている。社内に喫煙室が設けられてはいるが、外がよほどの嵐でない限り、彼はここで煙草をふかしている。
「……お疲れ様です」
挨拶を返しながら、鉄の扉を閉め、有武の吐く煙を避けるため風上に移動する。向かい合うように立ちながらも、零果の目線は決して彼の顔を見ようとはしない。それもいつものことだ。有武も、そのこと自体を問うことはしない。ましてや、喫煙者でもない彼女が何をしにここまで来たのかなんて、尋ねたりもしない。
「何、どうしたの。元気ないじゃん。なんか嫌なことでもあった?」
口から大量の煙を吐きながら、有武はそう尋ねた。零果は「まぁ……」と言葉を濁しただけだったが、彼は妙に納得したような顔で頷く。
「まー、嫌なこともあるよな」
「……そうです、嫌なこともあります」
「だよな」
「せっかくの休日に呼び出されて仕事させられたり」
「…………」
「今日だって、あと二時間で会議の資料を作ってくれって言われたり」
「…………」
「その資料がやっとできたと思ったら、それを五十部印刷しろって言われたり」
「何、こないだの土曜日のこと、まだ怒ってんの?」
有武が小さく鼻で笑った。これは、この男の癖��。この男は、上司でも取引先でも、誰の前でも平気で鼻で笑うのだ。
「土曜日は呼び出して悪かったって。でもあの時にテンプレート作って用意しておいたから、今日の資料作りがたった二時間でできたってことだろ?」
「……なんとかギリギリ、二時間でできたんです」
「でも、ちゃんと時間までに完成しただろ」
有武は、今度は鼻だけでなく、声に出して笑った。
「加治木さんはできるんだよ。俺は、できると思ったことしか頼まない。で、本当にちゃんとできるんだ、俺が見込んだ通りに」
「…………」
零果は下を向いたままだ。そんな彼女を見つめる有武の瞳は、からかうように笑っている。
「別に気にすることないだろ。周りからなんて言われたのかは知らないが、加治木さんは他の人ではできないことを――」
「私はもう、あなたの営業アシスタントじゃありません」
遮るように言った彼女の言葉に、有武が吐く煙の流れも一度途切れた。
「もう、私に……」
仕事を頼まないでください。そう言えばいい。零果が苦労ばかりしているのは、この男の仕事を引き受けるからだ。それを断ってしまえばいい。幸いなことに今の彼女は、それを咎められることのない職に就いている。もうアシスタントではない。ただの事務員だ。同僚たちが言う通りだ。
わかっている。頭ではわかっているのに、零果はどうしても、その続きを口にすることができない。うつむいたまま、口をつぐむ。
ふたりの間には沈黙が流れる。有武は煙草を咥えたまま、零果が言葉を発するのを待っているようだった。しかし、いつまでも話そうとしない彼女を見かねてか、短くなった煙草を携帯灰皿へと捨ててから、一歩、歩み寄って来た。
「加治木さんは、俺のアシスタントだよ。今も昔も、ずっと」
彼の身体に染み付いた煙草の臭いが、零果の鼻にまで届く。もう何年になるのだろう、この臭いをずっと、側で嗅いできた。いくつもの案件を、汗だくになったり、走り回ったりしながらこなしてきた。無理難題ばかりに直面し、関係部署に頭を下げ、時には上司に激昂され、取引先に土下座までして、それでも零果は、この男と仕事をしてきた。いくつもの記憶が一瞬で脳裏によみがえる。
「仕事を頼まないでください」なんて、言えるはずがなかった。どうして彼が自分に仕事を依頼するのか、本当は誰よりもわかっていた。
大きく息を吐く。肩に入っていた力を抜いた。
「有武さん」
「何」
「……コーヒー、奢ってください」
「は?」
「それで許してあげます」
零果の言葉に、ぷっ、と彼は吹き出した。
「コーヒーでいいの? どうせなら、焼き肉とか寿司とか言いなって」
まぁ言われたところで奢らないけどね。そう言いながら、有武はげらげらと笑う。零果は下を向いたまま、むっとした顔をしていたが、内心、少しほっとしていた。零果が多少、感情的な言い方をしてもこの男は動じないのだ。
「あ、ちょっと待ってて」
有武は唐突にそう言うと、外階段から廊下へと繋がる扉を開け、四階のフロアへと戻って行った。ひとり残された零果が呆然としていると、有武はあっという間に戻って来た。
「ほい、これ」
差し出されたその手には、缶コーヒーが握られている。社内の自動販売機に並んでいるものだ。どうやら、有武はこれを買いに行っていたらしい。零果は受け取ってから、その黒一色のパッケージの缶が、好きな無糖のブラックコーヒーだと気が付いた。
「それはコーヒーを奢ったって訳じゃないよ。さっき、デスクにあったカフェオレもらったから、そのお礼ね」
「もらったって言うか、有武さんが勝手に飲んだんじゃないですか……。あと、カフェオレではなく、カフェラテです」
「オレでもラテでも、どっちでもいいよ。飲んでやったんだろー。加治木さんがコーヒーはブラックの無糖しか飲まないの、知ってるんだから」
その言葉に、ずっと下を向いたままだった零果が一瞬、顔を上げて有武を見た。戸瀬から缶飲料をもらった時、「よりにもよってカフェラテか……」と思ったことが、バレているのではないかとさえ思う。そのくらい、目が合った途端、得意げに笑う有武の顔。憎たらしいことこの上ない。零果はすぐに目を逸らした。
「……やっぱ、許さないかも」
「は?」
「なんでもないです」
有武は肩をすくめた。作業服の胸ポケットから煙草の箱を取り出し、一本咥えて火を点ける。吐き出された煙は吹く風に流され、あっと言う間に目では追えなくなった。
いただきます、と小さく声に出してから、零果は缶コーヒーのプルタブを開けた。冷たいコーヒーをひと口流し込んでから、喉が渇いていたことに気が付いた。
疲れたな。改めてそう思う。百円で買える缶コーヒーの味わいにさえ、癒されていくように感じる。
今日は良い天気だ。この外階段に吹く風も、日射しも心地良い。ここから見下ろせる、なんてことのない街並みも。この男との何気ない会話も。ここにあるものすべてが、冷え切っていた零果の心を解きほぐしていくような気がする。
「加治木さん、昼飯はもう食ったの?」
煙を吐きながら、有武がそう訊いた。
「いえ……」
「何、また食ってないの? ちゃんと食わないと、身体に良くないよ」
「……有武さんは?」
「俺は今日、三時から会議で、終わったらその後に会食だから。昼飯は食わなくてもいいかなーって」
「会食までに、お腹空いちゃうんじゃないですか?」
「何か軽くは食べるけどね。会議中に腹が鳴っても締まらないし。ただ、四十歳過ぎるとね、やっぱ食った分は太るんだわ」
そう言う有武は、今年で四十一歳のはずだが、まったく太っていない。零果は七年前から彼を知っているが、出会った頃から体型が変化したとは思えない。ただ、それは本人が体型を維持する努力をしているからだろう。
そして、そういう努力ができるのであれば、もう少しこまめ��髪を切ったり髭を整えたりしてもいいのではないか、とも思う。特に最近の有武は、髪にも髭にも白髪が混じるようになった。もう少し身なりを整えれば、印象もまた変わると思うのだが。
「あ、そういえば、もらったアンパンがあるんだった。アンパン、半分食う?」
「いえ……あの、今本当に、食欲がなくて……」
零果はそう言いながら、無意識のうちにみぞおちの辺りをさすっていた。トイレで聞いてしまった、同僚たちの会話。無遠慮に吐き出された彼女たちの言葉、その声音の棘が、零果の胃の辺りに突き刺さっている。とてもじゃないが今は、何か固形物を口にしようという気にはならなかった。
「ふうん、あ、そう」
と、有武は煙草をふかしながら返事をした。零果の様子を特に気に留めている様子も、提案を断られて落ち込むような様子もない。そうやって、無関心を装う節がこの男にはある。
「じゃ、今度は喫茶店にでも行こうか」
有武が煙草を吸い終わった頃、零果も缶コーヒーを飲み終えたところだった。
「コーヒー奢るよ。どこか行きたい店ある? 俺の好きな店でもいい?」
「どこでもいいですよ」
「了解。また連絡するわ」
有武が外階段とフロアを繋ぐ、重たい扉を開ける。開けたまま待ってくれている彼に、小さく会釈をしながら零果が先に通る。触れそうなほどすぐ近くに寄ると、煙草の臭いをはっきりと感じる。今は吸った直後なので、臭いはなおさら強烈だ。
「くっさ……」
「あ?」
零果の口から思わず零れた言葉に、彼は即座に睨んでくる。
「すみません、つい、本音が……」
「悪かったな、煙草臭くて」
有武は舌打ちをしながら零果に続いてフロアへ戻り、外階段への扉を閉めた。
「有武さんは禁煙しようとは思わないですか?」
「思わないねー。だから俺が臭いのはこれからも我慢してねー」
「…………」
臭いと口走ってしまったことを根に持っているのか、有武は不機嫌そうな顔だ。
「あ、有武くん!」
並んで廊下を歩いていると、突然、背後から声をかけられた。振り向くと、通り過ぎた会議室から、ひとりの女性が廊下へ顔を覗かせている。
肩につかない長さで切り揃えられた黒髪。前髪がセンターで分けられているので、その丸さがはっきりとわかる額。染みも皺もない白い肌には弾力がある。彼女が今年で四十歳になるのだと聞いても、信じる人はまずいないだろう。零果より頭ひとつ分、小柄なことも相まって、彼女――桃山美澄は、二十代に間違えられることも少なくない。
実年齢よりも若く見られる桃山は、実際は経験豊富な中堅社員である。そして何より、ずば抜けて優秀な社員として、社内外で有名だ。営業アシスタントとして三人の営業マンの補佐についているが、「桃山本人が営業職になったら、売上額が過去最高になるのではないか」という憶測は、かれこれ十五年前から上層部で囁かれている、らしい。有武の営業アシスタントを務めているのも彼女である。零果は仕事を手伝わ���れているに過ぎず、本業は事務職であり、有武の本来のアシスタントは桃山なのだ。
桃山の顔を一目見るなり、有武は露骨に嫌そうな顔をした。しかし、それを気にする様子もなく、彼女は近付いて来る。
「有武くん、探したんだよ。午後の会議の資料の進捗はどう? 間に合いそう?」
「あー、それなら大丈夫。加治木さんに頼んでるから」
桃山は有武の隣に並ぶ零果を見やり、申し訳なさそうに眉尻を下げた。
「ごめんね加治木さん、また面倒な仕事、有武くんに頼まれちゃったね」
「いえ、あの、大丈夫です」
零果はいつも、桃山を前にすると困惑してしまう。謝る彼女に対して、なんて言葉を返せばいいのか、わからない。
「資料は? どのくらい出来てるの? 続きは私が代わろうか」
「あの、もう、完成はしていて、あとは印刷するだけなんですが……」
「本当に? もう出来てるの? すごいね加治木さん、やっぱり優秀だね」
「いえ、そんなことは……」
桃山はにこにこと、朗らかな笑顔だ。嫌味なところは感じさせない。実際、嫌味など微塵も込めていないということは、零果もわかっている。返す言葉に悩んでしまうのは、そうやって本心から褒めてくれる存在がそれだけ稀少だからだ。
「じゃあ、資料の印刷はこっちでやるよ。月末も近いし、加治木さん、自分の仕事も忙しいでしょう?」
「そんなことは……」
そんなことはありません、と言おうとして、後輩の女子社員から書類の束を受け取っていたことを思い出す。そうだ、あの書類をチェックしなくてはいけないのだ。思わず言葉に詰まってしまう。桃山はそれを見逃さなかった。
「うん、資料の印刷は私がするね。もう有武くんにメールで送ってくれてるんだよね? 有武くん、私のアドレスに転送してもらっていいかな?」
「はいはい、わかりましたよ」
有武は窓の外に目線を向けたまま、そう返事をした。彼のそんな態度にも、桃山は顔色ひとつ変えることはない。柔和な笑みのまま、零果に向き直った。
「加治木さん、忙しいのにいつもありがとうね。本当は私がやらなくちゃいけないことだから、こんな風に言うのはおかしいんだけど、有武くんは加治木さんと仕事をするのが本当に楽しいみたいで」
「い、いえ、あの……」
桃山は続けて言う。
「でも、加治木さんには事務職としての仕事もあるんだから、しんどかったり、難しかったりする時は、いつでも私に言ってね。有武くんだって、それで加治木さんのことを悪く思ったりはしないからね。私も、有武くんも、いつだって加治木��んの味方だから。無理はしないでね」
その言葉に、零果は頷くことしかできない。気を抜くと、泣いてしまうかもしれない、とさえ思った。桃山が自分の上司だったら良かったのに。零果は今の上司である、事務長の顔を思い出しながらそんなことを思う。桃山が上司だったら、毎日、もっと楽しく働けるかもしれないのに。
けれど、と思い直す。
桃山はかつて、零果の先輩だった。同じ営業アシスタントだった。三年前までそうだった。零果は彼女の下に就き、多くのことを学んだ。彼女の元から離れたのは、自分なのだ。そのことを、零果は今も悔やんでいる。
「それとね、」
桃山は一歩、零果に近付くと、声を潜めて言った。
「加治木さんが有武くんから直接仕事を任されていることは、事務長も、営業アシスタント長も、営業部長も合意している事柄だよ。それなのに、加治木さんのことを悪く言う人が事務員の中にいるみたいだね?」
脳裏を過ぎったのは、女子トイレで聞いた会話の内容だった。同僚の言葉が、耳元でよみがえる。
零果は思わず、桃山の顔を見た。先程まで朗らかに笑っていたはずの彼女は、もう笑ってはいない。口元は笑みを浮かべたままだったが、その瞳には鋭い光があった。それはぞっとするほど、冷たい目だった。
「うちの営業アシスタント長は、そっちの事務長と仲が良いからね。私が事務長に言っておいてあげようか? 『部下をよく指導しておいてもらえませんか』って。加治木さんは有武くんの仕事をサポートしてくれているのに、それを邪魔されたら困っちゃうんだよ」
桃山には、こういうところがある。普段は温厚なのに、時折、何かの弾みでとてつもなく冷酷な表情を見せる。
零果は慌てて、首を横に振った。
「そんな、大丈夫です」
「そうかな? 私はそうは思わないけどな。加治木さんのことを悪く言う社員が同じ事務の中にいるなんて、とてもじゃないけど――」
「桃山、もういいって」
ずっと上の空でいるように見えた有武が、突然、会話に割って入った。
「加治木さんが大丈夫って言ってるんだから、とりあえずは大丈夫なんだろ。もし何かあったら、桃山に相談するよ」
「…………」
桃山はしばらく無言で有武を見上げていたが、やがて再びにっこりと笑った。それから、零果へと向き直る。
「うん、加治木さん、何かあったら遠慮なく相談してね。いつでも聞くからね」
「いえ、あの、お気遣い、ありがとうございます」
何度も頭を下げる零果に、桃山はにこにこと微笑む。
「ううん。逆に、気を悪くしていたらごめんね」
「いいえ、気を悪くするなんて、そんな……」
「私はこれでも、営業アシスタントだから。有武くんが気持ち良く仕事をするために、私にできることは全部したいんだ」
そう、桃山の目的は、あくまでも「それ」だ。営業アシスタントとしての職務を全うしたいだけなのだ。零果のことを気遣っているかのように聞こえる言葉も、すべては有武の仕事を円滑に進ませるため。反対に、彼の仕事ぶりを邪魔するものを、すべて排除したいだけ。
有武から仕事を頼まれた零果がその意欲を削がれることがないように、彼女のことを悪く言う同僚を排除しようと考えているのだ。その点、桃山は零果のことを「有武の仕事にとって有益にはたらくもの」と認識しているようだ。そうでなければ、零果に仕事を依頼していることを許したりはしないだろう。
「何かあったら言ってね」と言い、「それじゃあ」と手を振って、桃山は営業部のフロアへと向かって行った。
桃山の姿が見えなくなると、その途端、有武は大きく息を吐く。
「はーあ、おっかない女……」
「桃山さんのことを、そんな風に言わなくても……」
普段は飄々としている有武も、桃山を前にするとどこか緊張しているように見えるから不思議だ。そう思いながら、零果は有武の顔を見上げ、
「あ……」
「あ?」
「いえ、なんでもありません……」
反射的に目を逸らした零果を、彼が気にする様子はなかった。ただ、「加治木さん、俺の正式な営業アシスタントに早く戻ってくれよ」と、どこか冗談めかした口調で言った。
その言葉に、零果は何も答えなかった。うつむいたままの彼女の左肩をぽんぽんと、軽く二回叩いて、「じゃ、また」と、有武も営業フロアへと消えて行った。
「…………無理ですよ」
有武の背中も見えなくなってから、ひとり残された零果はそうつぶやく。
事務部に異動して二年。今となって��、営業アシスタントとして働いていた過去が、すべて夢だったのではないかとすら思える。あの頃は、毎日必死だった。ただがむしゃらに仕事をこなしていた。どうしてあんなに夢中だったのだろう。零果はもう、当時の感情を思い出すことができない。 二階の事務部フロアに向かって歩き出す。所属も業務内容も変わったが、今も零果には戦場が与えられている。運動不足解消のためにエレベーターを使うのではなく階段を降りながら、頭の中では午後の仕事について、すでに思考が回り始めていた。今の自分には、やるべき業務がたくさんある。戦うべき雑務がある。そのことが、何よりも救いだった。
※『コーヒーとふたり』(下) (https://kurihara-yumeko.tumblr.com/post/746474804830519296/)へと続く
3 notes
·
View notes
Quote
11日発売の「週刊文春」(文藝春秋)記事は、宝塚歌劇団の宙組トップスター・真風涼帆(まかぜすずほ)が、宙組トップ娘役だった星風まどか(現花組トップ娘役)に侮蔑的な言葉を浴びせるなど陰湿なイジメを行っていたと報じた。宝塚歌劇団をめぐっては昨年12月発売の「文春」記事で、演出家・原田諒氏がトップスターや演出助手だった女性スタッフらにハラスメント行為を行っていたと報じられ、原田氏が退団するという出来事が起きたばかりだったが、たて続けに不祥事が発覚する宝塚歌劇団の内部で今、何が起こっているのだろうか――。 一昨年の2021年に創立100周年を迎えた宝塚歌劇団は、「タカラジェンヌ」と呼ばれる劇団員が全員女性で、彼女たちが男役・女役を務め、花組・月組・雪組・星組・宙組の計5組と専科で構成されることが大きな特徴。歴代のトップスター、トップ娘役からは大地真央、黒木瞳、天海祐希、真矢ミキをはじめ今も第一線で活躍する女優が数多く生まれるなど、芸能界の貴重な人材育成機関としての顔も持つ。 「組それぞれカラーや特徴があり、公演も組ごとで行われる。たとえば宙組は真風涼帆のスタイルに象徴されるとおり、ステージでは長身のトップスターをはじめ男役たちがスリムなスーツを着こなす姿が印象的。また、月組は『芝居の月組』といわれ、女優の大地真央、黒木瞳、涼風真世、天海祐希、真琴つばさ、紫吹淳らを輩出してきた。ちなみに黒木はトップスターではなくトップ娘役だったが、トップスターとトップ娘役のコンビ内には厳しい上下関係があり、年次も基本的にはトップスターのほうが上。それが影響しているのかどうかは定かではないが、退団後に人気女優として息長く活躍するOGにはトップスター経験者が多い印象。 また、団員は5年目までは宝塚歌劇団の正社員という扱いで、給料やボーナス、退職金も支払われるというのは日本の劇団では珍しく、これも大きな特徴といえる」(宝塚歌劇団に詳しい週刊誌記者) トップスターとトップ娘役の関係性 その宝塚歌劇団には今、試練が訪れている。今月に入り、関係者から新型コロナウイルス感染者が出た影響ですでに花組、星組、宙組の公演が中止に追い込まれるという不運に見舞われるなか、前述のとおり内部の不祥事がたて続けに発覚し、宝塚ブランドが失墜しかねない事態に陥っているのだ。 「劇場の最寄り駅である宝塚駅では、先輩が乗ろうとする電車に後輩は乗らずに『お見送り』をしたり、宝塚線の線路沿いでは先輩が乗っていると思われる電車が通るだけで後輩が立ち止まって礼をしたり、宝塚音楽学校では上級生と下級生が班をつくって校舎の隅々まで完璧に掃除をするといった『鉄の掟』が有名だが、今ではそうしたルールはかなり緩和されている模様。それでも上下関係が厳しいのは確かだが、トップスターとトップ娘役の関係性というのは、コンビによってまちまち。 トップスターは相手役のトップ娘役の指導係の役割も担うので、基本的には明確な上下関係が存在するが、大地真央と黒木瞳のように熱い師弟愛で結ばれているケースや、特に最近では友だち関係に近かいケース、逆に真風と星風のように険悪なケースもあると聞く。トップスターの性格や考え方による部分が大きいが、歌劇団に所属するタカラジェンヌは総勢で約400人おり、各組のトップスターはおおむね3~5年で交代していくので、一概に『こう』というのはいえない。もっとも、真風の例はかなりレアといえるだろう。稽古中などに大勢の劇団員やスタッフがいる前でトップスターがトップ娘役を叱るというのは珍しくはないが、真風のように容姿を批判したり演技ができないと言い出すような凄惨なイジメは聞いたことがない」(同) 渦巻く嫉妬 そんな団員・スタッフたちが鉄壁の絆で結ばれているかにみえる宝塚歌劇団で、なぜイジメやハラスメントが起きているのだろうか。『自己正当化という病』の著者で精神科医の片田珠美氏はいう。 「宝塚もそうですが、一般に閉鎖的な空間ほど不祥事が起きやすいのです。しかも、私自身も中学生の頃に『ベルばら』ブームを経験した影響で、宝塚に憧れていましたが、このように憧憬や羨望の対象になっている組織では、理不尽な仕打ちを受けても告発をためらう傾向が強くなります。なぜかといえば、その組織に入ることができ、所属していること自体にブランド価値がありますので、自分が排除されることへの恐怖ゆえに、声を上げにくいからです。 ですから、最近宝���の不祥事が『文春』によって立て続けに報じられていますが、必ずしもここ数年でとくに増えたというわけではないと思います。以前から同様��不祥事はあったものの、誰も声を上げることができなかっただけではないでしょうか。 しかも、宝塚は『女の園』で同性の集まりですから、どうしても嫉妬が渦巻きやすくなります。おまけに、男役トップスター、あるいはトップ娘役の座を目指してしのぎを削る世界なので、嫉妬の炎が燃え上がるのは当然でしょう。上級生が、自分の立場を脅かしかねない下級生に嫉妬を抱き、陰湿ないじめを繰り返すことがあったとしても不思議ではありません。 今回の報道で引っかかるのは、男役トップスターの真風涼帆さんが自分の相手役だったトップ娘役の星風まどかさんをいじめていたという点です。真風さんは男役で、星風さんは娘役ですから、普通に考えると星風さんが真風さんの立場を脅かす存在とはいえません。第一、真風さんは175センチと高身長のうえ端正な顔立ちであり、圧倒的な人気を誇っていますから、嫉妬する必要などないように思います。もっとも、それでも生まれてしまうのが嫉妬の怖いところで、星風さんの若さや歌唱力に嫉妬したのかもしれません。 もう1つ考えられるのは、真風さんが同じようないじめを過去に受けていた可能性です。真風さんは、星風さんを幹部部屋に呼び出し、反省するよう1時間の正座を命じたと『文春』で報じられましたが、真風さん自身も同様の仕打ちを上級生から受けたことがあったのかもしれません。宝塚には『軍隊並み』と称されるほど厳しい上下関係があり、上級生の言葉は絶対ということですから、真風さんが同じように正座させられたことがあった可能性は十分考えられます。 こういう場合、『自分も上級生からされたのだから、同じことを下級生にしてもいい』と自己正当化しやすくなります。また、『攻撃者との同一視』というメカニズムが働くことも少なくありません。 これは、自分の胸中に不安や恐怖、怒りや無力感などをかき立てた人物の攻撃を模倣し、自身が攻撃者の立場に立つことによって、屈辱的な体験を乗り越えようとする防衛メカニズムです。フロイトの娘、アンナ・フロイトが見出しました。 このメカニズムは、さまざまな場面で働きます。たとえば、学校の運動部で『鍛えるため』という名目で先輩からいじめに近い過酷なしごきを受けた人が、自分が先輩の立場になったとたん、今度は後輩に同じことを繰り返します。同様のことは職場でも起こります。お局様から陰湿な嫌がらせを受けた女性社員が、今度は女性の新入社員に同様の嫌がらせをするようになるわけです。 この『攻撃者との同一視』が宝塚では起きやすいように見えます。しかも、『舞台を素晴らしいものにするため』という口実があれば、正当化されやすいでしょう。ですから、同様の不祥事は実はいくらでもあり、今後も声を上げる人がいれば、表に出てくるのではないでしょうか」 ちなみに当サイトは今回、複数の宝塚歌劇団元関係者や日頃からメディアを通じて宝塚に関する情報を発信している人々に取材を申し込んだが、軒並み拒否されてしまった。 「全国紙をはじめ主要メディア各社には宝塚の担当記者がいるほど、メディアとのつながりは深い。日本中に数多くの熱心な宝塚ファンがおり、宝塚はメディアにとっても強力なコンテンツの一つと化していることから��好な関係を築いている。さらに、宝塚関連の書籍や雑誌の特集なども多く、宝塚の元関係者であったり強いパイプを持っていたりすれば、それだけでいろいろな仕事につながるという人もおり、意外にも宝塚批判というのはタブー視されている面がある」(前出・週刊誌記者) (文=編集部、協力=片田珠美/精神科医)
宝塚歌劇団ブランド失墜、トップスターが凄惨イジメ、文春報道…不祥事生む組織体質 | ビジネスジャーナル
5 notes
·
View notes
Text
"Kill them with kindness" Wrong. CURSE OF MINATOMO NO YORITOMO
アイウエオカキクケコガギグゲゴサシスセソザジズゼゾタチツテトダ ヂ ヅ デ ドナニヌネノハヒフヘホバ ビ ブ ベ ボパ ピ プ ペ ポマミムメモヤユヨrラリルレロワヰヱヲあいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわゐゑを日一国会人年大十二本中長出三同時政事自行社見月分議後前民生連五発間対上部東者党地合市業内相方四定今回新場金員九入選立開手米力学問高代明実円関決子動京全目表戦経通外最言氏現理調体化田当八六約主題下首意法不来作性的要用制治度務強気小七成期公持野協取都和統以機平総加山思家話世受区領多県続進正安設保改数記院女初北午指権心界支第産結百派点教報済書府活原先共得解名交資予川向際査勝面委告軍文反元重近千考判認画海参売利組知案道信策集在件団別物側任引使求所次水半品昨論計死官増係感特情投示変打男基私各始島直両朝革価式確村提運終挙果西勢減台広容必応演電歳住争談能無再位置企真流格有疑口過局少放税検藤町常校料沢裁状工建語球営空職証土与急止送援供可役構木割聞身費付施切由説転食比難防補車優夫研収断井何南石足違消境神番規術護展態導鮮備宅害配副算視条幹独警宮究育席輸訪楽起万着乗店述残想線率病農州武声質念待試族象銀域助労例衛然早張映限親額監環験追審商葉義伝働形景落欧担好退準賞訴辺造英被株頭技低毎医復仕去姿味負閣韓渡失移差衆個門写評課末守若脳極種美岡影命含福蔵量望松非撃佐核観察整段横融型白深字答夜製票況音申様財港識注呼渉達良響阪帰針専推谷古候史天階程満敗管値歌買突兵接請器士光討路悪科攻崎督授催細効図週積丸他及湾録処省旧室憲太橋歩離岸客風紙激否周師摘材登系批郎母易健黒火戸速存花春飛殺央券赤号単盟座青破編捜竹除完降超責並療従右修捕隊危採織森競拡故館振給屋介読弁根色友苦就迎走販園具左異歴辞将秋因献厳馬愛幅休維富浜父遺彼般未塁貿講邦舞林装諸夏素亡劇河遣航抗冷模雄適婦鉄寄益込顔緊類児余禁印逆王返標換久短油妻暴輪占宣背昭廃植熱宿薬伊江清習険頼僚覚吉盛船倍均億途圧芸許皇臨踏駅署抜壊債便伸留罪停興爆陸玉源儀波創障継筋狙帯延羽努固闘精則葬乱避普散司康測豊洋静善逮婚厚喜齢囲卒迫略承浮惑崩順紀聴脱旅絶級幸岩練押軽倒了庁博城患締等救執層版老令角絡損房募曲撤裏払削密庭徒措仏績築貨志混載昇池陣我勤為血遅抑幕居染温雑招奈季困星傷永択秀著徴誌庫弾償刊像功拠香欠更秘拒刑坂刻底賛塚致抱繰服犯尾描布恐寺鈴盤息宇項喪伴遠養懸戻街巨震願絵希越契掲躍棄欲痛触邸依籍汚縮還枚属笑互複慮郵束仲栄札枠似夕恵板列露沖探逃借緩節需骨射傾届曜遊迷夢巻購揮君燃充雨閉緒跡包駐貢鹿弱却端賃折紹獲郡併草徹飲貴埼衝焦奪雇災浦暮替析預焼簡譲称肉納樹挑章臓律誘紛貸至宗促慎控贈智握照宙酒俊銭薄堂渋群銃悲秒操携奥診詰託晴撮誕侵括掛謝双孝刺到駆寝透津壁稲仮暗裂敏鳥純是飯排裕堅訳盗芝綱吸典賀扱顧弘看訟戒祉誉歓勉奏勧騒翌陽閥甲快縄片郷敬揺免既薦隣悩華泉御範隠冬徳皮哲漁杉里釈己荒貯硬妥威豪熊歯滞微隆埋症暫忠倉昼茶彦肝柱喚沿妙唱祭袋阿索誠忘襲雪筆吹訓懇浴俳童宝柄驚麻封胸娘砂李塩浩誤剤瀬趣陥斎貫仙慰賢序弟旬腕兼聖旨即洗柳舎偽較覇兆床畑慣詳毛緑尊抵脅祝礼窓柔茂犠旗距雅飾網竜詩昔繁殿濃翼牛茨潟敵魅嫌魚斉液貧敷擁衣肩圏零酸兄罰怒滅泳礎腐祖幼脚菱荷潮梅泊尽杯僕桜滑孤黄煕炎賠句寿鋼頑甘臣鎖彩摩浅励掃雲掘縦輝蓄軸巡疲稼瞬捨皆砲軟噴沈誇祥牲秩帝宏唆鳴阻泰賄撲凍堀腹菊絞乳煙縁唯膨矢耐恋塾漏紅慶猛芳懲郊剣腰炭踊幌彰棋丁冊恒眠揚冒之勇曽械倫陳憶怖犬菜耳潜珍
“kill them with kindness” Wrong. CURSE OF RA 𓀀 𓀁 𓀂 𓀃 𓀄 𓀅 𓀆 𓀇 𓀈 𓀉 𓀊 𓀋 𓀌 𓀍 𓀎 𓀏 𓀐 𓀑 𓀒 𓀓 𓀔 𓀕 𓀖 𓀗 𓀘 𓀙 𓀚 𓀛 𓀜 𓀝 𓀞 𓀟 𓀠 𓀡 𓀢 𓀣 𓀤 𓀥 𓀦 𓀧 𓀨 𓀩 𓀪 𓀫 𓀬 𓀭 𓀮 𓀯 𓀰 𓀱 𓀲 𓀳 𓀴 𓀵 𓀶 𓀷 𓀸 𓀹 𓀺 𓀻 𓀼 𓀽 𓀾 𓀿 𓁀 𓁁 𓁂 𓁃 𓁄 𓁅 𓁆 𓁇 𓁈 𓁉 𓁊 𓁋 𓁌 𓁍 𓁎 𓁏 𓁐 𓁑 𓀄 𓀅 𓀆
207K notes
·
View notes
Text
遅。役者紹介の遅刻について
最上です。
遅刻しました。ごめんなさい。
エブリデイの役者紹介と、
37期に適当に一言あててます。
毎日がエブリデイ!
とろんとろん
スタミナ無限人間。
一日に何回も同じ場面の練習をして、しっかり大きい声出して演技してるのに、クオリティが落ちない。すごい。
表情とか、立ち振る舞いとか、喋り方とか、稽古の度に小泉進次郎に近づいていってる。近づきすぎてもはや小泉進次郎そのもの。なんなら純一郎。
ーーーーーーーーーーーーー
めっちゃボケる。けど、たまに真面目。
けど、それ以上にめっちゃボケる。たまに誰も拾いきれない時ある。
彼は昼飯をゼリーにすることが多い。というかゼリー以外を食べてるのを見た記憶が無い……そんなことはない。言い過ぎた。
しらたま琉師
エブリデイが産んだ化け物。
初めはかわいい演劇オタクだったのが、数多の試練を経て、無事に化け物に進化。昆虫で言うところの、完全変態。
rrrrるーしーが完全変態を遂げたのは、もちろんrrrr本人の努力の賜物。熱心に演出さんの言うことを聞いて、自分からアドバイスを聞きに行ったりもして、それを確実に自分の中に落とし込んでいった。
rrrは向上心が凄まじい。それが周りにも伝わってきたから、演出さんや演補さんがrrrを魔改造したんだと思う。
ーーーーーーーーーーーー
僕(最上)とRRRは、演出上の絡みが多い。その割には、僕はRRRのことをあまり知らない気がする。
話す機会は多かったけど、ほとんどが演技の話だったような…
芹田にな
エブリデイが産んだ化け物その2……になるはずだった人。
なんで体調崩してんねん
レイは、滑舌が良い。
ダンスが上手い。
努力家でもある。
稽古の度に成長してるのを、ひしひしと感じる。
なんで体調崩してんねん。
ふざけんな。
ふざけては無いか。
はよ元気になって戻ってこい
君の演技が見たいんや
MO・GA
最上です。
錫蘭リーフ
完成度の暴力
役を理解して、自分の動きに落とし込むのがとてつもなく上手い。
本番に近づくにつれてセイロンさんの演技にも少しずつ変化があったけど、それはあくまで状況に応じて演技の幅を広げただけ。って感じがする。
引き出しが無限にあるんだと思う。きっとセイロンさんの引き出しを覗いたら、4次元空間が広がってるんだろう。
ーーーーーーーーーーーーー
よく笑ってくれる。だから、いっぱいふざけちゃう。
でも、まだまだいけると思ってる。気に触れない程度に、どこまで絡んでいいのか探っていきたい。
白
名誉演補補。
rrrルーシー化け物化計画の一端を担った重要な人物。
もちろん演技も、めっちゃいい。声がね、合ってるんすよ。
声に、渋みと深みがある。
でもね、ぶらんさんは声だけじゃない。話し方とか、立ち方とか、顔のむけ方とか、ちゃんと「おじ」なんです。
ーーーーーーーーーーーー
ぶらんさんと言えば、なんか話しかけたくなる、で有名です(僕の中で)。
なんでこんなに絡みたくなるんやろ。
多分、そういう化学物質が皮膚から放出されてるんだと思います。
苔丸
人間の皮を被ったホスピタリティ。
苔丸さんは、めっちゃ上手い。
演技が上手な人って、「演技してる感」が無い。
母役じゃなくて、母。
目立たないシーンでは、ほんとに目立たない。
他の役を映えさせるためのセリフを、自身の魅力を抑えながら発する。
それが、苔丸さんが持ってる技術であり、役者のあるべき姿である。
僕はそう思う。
ーーーーーーーーーーーー
ホスピタリティポイントその1
苔丸さんはよく、グループLINE上で送られた連絡事項や報告に、リアクションの絵文字をつける。
通称、リアクション芸人。
ちゃうかには、片手で数えられる程の人数、存在する。
僕もリアクション芸人なので、苔丸さんには親近感を感じている。
苔さん曰く、
「自分が送ったメッセージにリアクションがついてると、『ちゃんと読んでもらえてるんだぁ』ってなって嬉しいでしょ。」
だそうだ。
う〜ん、ホスピタリティ。
ホスピタリティポイントその2
稽古期間中、様々な部署から、事務連絡とか、アンケート回答依頼とか、が立て続けに送られてきた時期があった。
8件ぐらいあったんじゃなかろうか。
正直僕は、全ては把握しきれていなかった。
メッセージ送信後からそこそこ期間が経ってしまって、ラインの上の方に埋もれちゃった話もあった。
そんな時、ホスピタリティ神から手が差し伸べられた。
LINEで、ホス神によって、[平民のto do]というタイトルでノートが投稿された。
そこでは、これまで送られてきた依頼等の、
対象者
期限日
その依頼の責任者
などが、めっちゃめちゃわかりやすくまとめてあった。
感動した。
ちゃうかの団員の皆さんは是非、
LINEの検索欄で「平民」と入力して、ホス神のホスピタリティを再確認してください。
ホスピタリティポイントその3 (最後)
7/7前後の期間に、ちゃうかで、七夕企画が行われた。
楽屋に笹が設置され、短冊、こより、ネームペンが準備された。
もう一度言おう。
楽屋に笹が設置された。
???
???
もちろんホス神こと苔丸さんの仕業だった。
ホス神がホス神である所以は、「短冊、こより、ネームペンを準備する」という所にある気もする。
ある別の日には、参加費を会計の人に渡すための封筒とマスキングテープが、ホス神によって楽屋に設置されたこともあった。
人が必要としていることにいち早く気づいて、それを実行に移しちゃうのが、ほんとにすごい。
気づい��ら、37期よりも沢山書いてしまった。
早乙女レジェル
努力の人
さすがに練習量えぐい
本番1週間前に代役を言い渡されて、本番でちゃんと形に出来るのまじですごい。
稽古時間外に、1人でセリフ読みの練習してるの、何回か見た。多分動きの練習も、稽古時間外でやってたんだと思う。
努力の「努」の漢字の左上の、「女」の部分はえるさんが担当してるんじゃないでしょうか
しかも、レイの演じ方を踏襲してプワをやってるから、「レイの存在にも意味があった」 って思える。
高校生A 花灯
日常会話劇のスペシャリスト
流石に上手い。
溢れ出る日常会話感。
普段から意味わかんない会話してるんだろうなこの人…って思わせるような、完璧な演技。
ーーーーーーーーーーー
実際どうなんでしょうね。なびやさんとほぼ喋ったことないから分かんないけど、普通の人じゃなさそうな気はする。
失礼なこと言いました。ごめんなさい。
園堂香莉
近隣住民
この場でなぽりさんを語るには、まず脚本の話からした方がいい。
エブリデイの脚本は、
ふざけ散らかしてる。
それなのに、
綺麗にまとまってる。
なんで?
天才なんすよ、なぽりさんは。
僕がオムニを全力で楽しめたのは、強調構文くんを生み出してくれたなぽりさんのおかげです。
あと、キャスパにフィリピンダンスのポーズ採用していただいたの、めっちゃ嬉しかった。
ーーーーーーーーーーーー
先日、家の近くの坂道でなぽりさんとばったり会いました。
これからもちょくちょく遭遇すると思います。よろしくお願いいたします。
中森ダリア
めっっっっちゃいい人。
演技、上手いです。
普段のひらりさんは、どっちかと言うと振り回す側の人間だと思ってます。
が、振り回される役も、とても良い。
ーーーーーーーーーーーー
ひらりさんは、リアクションが大きくて楽しいし、よく笑ってくれる。こういう人が1人いるだけで場の雰囲気がグッと明るくなる。
叶イブ
隠しきれない妹感
いつかどこかでやっていらっしゃった、プワの代役が頭から離れません。今回のオムニでは、出るシーンがかなり短かったけど、ほんとは凄い役者さんなんだと思います。外公、期待してます。
張潤玲
迫・力
えるさんが抜けても、エッホエッホの不気味さを保てたのは、マモさんの気迫、破壊力が大きかったからだと思います。
海泥波波美
最老にして最強
アサギさんには、芯が通ってる。
演補として指示を出す時、ほぼ確実に、その指示を出す理由を教えてくれる。
「俺は、るーしーを化け物にした方が見てて面白いと思うんだよな。だから、もっと動き増やしてみようぜ」
そんな感じ。
アサギさんの中でしっかり信念があって、それを元に発言してるんだろう。
だから、安心感があるし、ついていきたいと思える。
雨々単元気
優柔勇断
アサギさんが剛なら、てにさんは柔
柔軟性と包容力。
てにさんが演出だったおかげで、僕たち役者はのびのびと稽古できたし、稽古に行くのが楽しいと思えるようになりました。ありがとうございました!
てにさんが、稽古場の明るい雰囲気作りにおいて果たした役割は大きい。
てにさんは、演出を経て、人間として成長した気がします。
場当たりの期間あたりから、リーダーシップや決断力が増してきて、
「僕はこの人について行っていいんだ」
って思えるようになりました。
上から目線みたいな言い方になってすみません。でも、てにさんの「監督力」みたいなのの成長は、どうしても伝えておきたくって。
新入生なのでよく分からないですけど、なんか、そんな感じがします。
mmmmmmmmmmmmmm
以下、オペさんand37期に、適当に一言書いてます。
オペ
音響オペ
埖麦
寝相が、戦死体にしか見えない。
照明オペ
礼雅
あっ!!!
映像オペ
弖啼
酒強そうやし、強かった。
37期
目良鏡子
愛嬌とアイソレーション
六甲賽ロコ郎
世界の中心で賽を叫ぶ
モイLv1
溢れ出る優しさと、稀に出る狂気
かしぱん
将来はドライビングフォース
ティグ
図書館のパーマ男
水瀬奏
瞬間ハートビート(あえてのホロライブ)
ジン
Rainbow Smile
三船智
ウルトラソウル! Hey!
黒羽千絽瑠
通学琵琶湖
櫻井リン
黒を白には出来ないが、白を黒には出来る。(暗黒微笑)
諭吉
栄一
ソイ
もぎもぎ
ぷよテト
Oh! Dough! Good!
Rグレイ
夕暮れ色のグレイ
37期に一言あててるやつは、
実は本人にはわかる裏話があったり、なかったり、ダジャレだったりします。
以上、最上がお送りandお遅れしました。
1 note
·
View note
Text

CoC「ヤゼル」秀才 追記に詳細設定 ※シナリオのネタバレが含まれます
◆橘星蘭身上調査書
芸名:橘星蘭(たちばな せいらん) 本名:雪庭嵐(ゆきにわ らん) 愛称:ランちゃん 年齢:23歳 性別:女 血液型:B型 誕生日:4月4日 星座:おひつじ座 身長:158cm 体重:46kg 髪色:暗い紫、黄色のインナー 瞳の色:ヘーゼル 視力:左右1.0 きき腕:右 声の質:芯の通った澄んだ声 舞台の端まで声が通る icv.キルラキル皐月のときの柚木涼香 手術経験や虫歯、病気:子供の頃は食が細く病弱で、ガリガリで発育が悪かった 身体の傷、アザ、刺青:なし その他の身体的特徴(鼻や目の形、姿勢、乳房、足、ホクロなど):締まった細身 肉も筋肉もつきにくい セックス体験、恋愛、結婚観:恋愛に本気になったことがなく、基本的に自分の仕事を優先するため続かない 尊敬する人:ヒース・レジャー、トム・ハンクス、オードリー・ヘップバーン、ジョニー・デップ 恨んでる人:特になし 出身:富山県の田舎 職業:舞台女優 将来の夢:自分の劇団を持って脚本・監督も担当すること 恐怖:舞台の公演中止 癖:腕組み 酒癖:酒鬼強い ワク あまりに酒が強いのでベロベロになるまで飲みすぎることもある
*交流向け 一人称:私 二人称:あなた、君 呼び方:苗字+さん 仲良くなれば下の名前で呼び捨て
*概要
「劇団フルーツタルト」のトップスター。老若男女問わず人気があり、将来を期待される女優。ファンからの愛称は「ランちゃん」。
*性格
おおらかで魅力的、情熱と行動力ですぐ人気者になるタイプ。仲間内では気さくだが、時にずけずけ物を言いすぎることも。ストイックな努力の信奉者だが、すべての人がこれほど人生や生活を捧げる必要はないとも考えているため、好きでやっているものを他人に求める気はない。才能を信じず自ら獲得したもののみを信じる女。細身で小柄な体に飢えた獣のようなパワーを秘めている。 幼い頃は小さくガリガリの自分に自信が持てなかったが、思春期からいくつかのコンプレックスを自力で克服してきた。悲しみで涙は滅多に人に見せないが、苦しみの最中にいる人に同情しやすく涙もろい。 好きなもの(特に演劇)に関しては無邪気な愛情を感じており、それゆえに他人には理解しがたいほどの執着で勉学や修練に励む。贅沢が好きで度が過ぎた浪費をしてしまうこともしばしば。
*人間関係
舞台関係者には礼儀正しく、真正面からぶつかるコミュニケーションをする。劇団員との仲は良好で、組織のなかの政治を嫌うため誰とでも平等に接し、対等な友人のような関係を築いている。監督や脚本と意見がぶつかることはしばしばあるが、不思議と険悪になることはない。ファンには気前よくサービスする。 恋愛に関しては恋人にしたいと思った相手は狙って手に入れるタイプ。芸の肥やしのためにのめり込んで燃えるような恋愛をしたいと思っているが、芸の肥やしだと思っているためあまり長続きしない。そのわりに自分の容姿や肩書きだけを見る人間は嫌う。わがまま。
*家族関係、幼少期体験 父母と兄が健在。学生時代は非常に品行方正な優等生。 中学の頃たまたま観に行った「椿姫」の舞台に憧れて高校は演劇部に所属。短期大学を卒業してすぐ「劇団フルーツタルト」に入り、一気に演技の才能を開花させた。 しかし母方の祖父が演劇の道を目指し一時は売れたがその後落ち目になり失踪した件で家族が振り回された過去があり、母親は演劇と自分の父親を恥ずかしいものだと思っているため、嵐が演劇をやることに忌避感を覚えている。 だが同時に彼女の激しい気性も知っているため自分たちの言うことは聞かないだろうと思いつつ、母親は演劇を応援していないのが現状。多少気にしてはいるが、足枷には思っていない。
*能力
華やかな演劇の才能の持ち主。舞台上にいるとつい目で追ってしまうほど目立つ。小さな頃やっていた剣道と日本舞踊のおかげでタフで肺活量が高く、舞台上でまったく息を乱さず長時間セリフやダンス、アクションをこなすことができる。スマートな体型と中性的な声を活かした少年役も人気。 歳の割に老成した考えの持ち主であり、あらゆる女性の味方。健康的な美しさのために日々トレーニングなどの努力を続け、理論を学んで実践しては劇団内やSNSで共有している。食べてもあまり太れない体質で風邪を引きやすいため、体調管理が欠かせない。 あらゆる演劇や映像作品については、不朽の名作から最新作まで寝る時間を惜しんでもチェックしている演劇オタク。幅広いジャンルを愛する。
*劇団フルーツタルト 東京の小さな劇団でありながら粒揃いの才能の持ち主が集まり、ここ最近急激に成長する劇団。少数精鋭の脚本家、演出家、劇団員が集まり、大手の劇場ともたびたび契約する実力派。 「フルーツタルト野山劇場」とも言われる脚本家野山三郷の古典的な舞台の本筋を壊さず骨太なストーリーと仰々しいセリフ回し、それでいてケレン味たっぷりでポップさのある演者たちの軽妙な会話がエンターテイメント性の高い劇団。近年は美麗な衣装と橘星蘭の人気もあいまって数々の演劇賞を受賞し、演劇界を超えてメディアに露出しつつある。
【出演作品】 バニラ(娘B) 親孝行な娘たち(マルガリータ) アルルカン(王子) 若草物語(ジョー) いばらの冠(マグダラのマリア) オリエント急行の殺人(メアリー・デブナム) 完璧な息子(新庄清人) オズワルト(オズワルト) だれがコマドリを殺したか?(カメリア) 吸血鬼カーミラ(カーミラ)
*好きなもの 食べ物:握り寿司(特にブリとハマチ)、おでん(特にタコ)、釜飯、ホタルイカ、フルーツタルト、ブルボンのお菓子 得意料理:ちらし寿司、いなり寿司、煮付けなどの和食 里芋の唐揚げが絶品 小料理屋の父直伝のため美味しい 飲み物:カフェラテ、芋焼酎、ハイボール 季節:春 色:鮮やかでポップなカラー、シルバー 香り:ロクシタンのエルバヴェール 書籍:小説、あまり分野を問わず本屋を巡る よくお風呂で読む 動物:サモエド ファッション:少し変形のきいたクラシックな服が好き 場所:舞台の上、鑑賞席 愛用:シルバーのイヤリング、キャンディ(低血糖対策) 趣味:映画鑑賞、舞台鑑賞、台本読み
0 notes
Text
ある画家の手記if.81 雪村絢視点 告白
I’m singing’ in the rain Just singing’ in the rain, What a glorious feeling, And I’m happy again. I’m laughing at clouds So dark, up above, The sun’s in my heart And I’m ready for love…………
直にぃが「そろそろお昼ご飯にしようか」って三人分の食事作ってたから、ケータイで検索してピザとかかつ丼とかラーメンとかいろいろ片っ端に電話かけて出前とった。頼むときに一応マナーかなと思って「二人の分も注文する?」って聞いたらすごい勢いで首を横に振られた。 それから三人で食事しながら香澄のとなりに座って香澄を構い倒した。直にぃのほかにも心許せる人間がいたらいい、とかなんとかいう思惑はなくもなかったけど、それより香澄が口開けて笑ってるのを見れるのが嬉しかった。いつもはちょっと大人しくて照れぎみっていうか、まことくんちでも声をあげて笑い崩れたりってとこはまだ見たことなかったから。今も無理して明るく振舞ってるわけじゃなさそうだし、なら遠慮せずにいこうと思って俺も好き勝手やり放題だった。香澄もつられて笑った。 ーーー自傷は、無意識からの心理的な圧迫や抑圧のひとつの現れ方だ。真澄さんの話で俺の憶測はすこし確信めいてきた。なら心からの感情をなるべくたくさん自然に発露させてやるのは有効だ。核心部分につられて心理はほかの感情も圧迫するから、圧死する前に溜め込ませないで出させたほうがいい。普通に考えて、核心部分を圧迫できるのは核心部分そのものじゃなくてその外側にあるものだ。それを溶かしたい、そのあとで圧迫されなくなった無防備な核心部分を守るのはーーー俺の役目だ。 で、何で溶かせるか、これはフリや演技じゃ通じない、香澄を心から大事に想う人間がほんものの関係を築いていかないと。俺がなんでここまでゴチャゴチャ考えてるかって、香澄のことが大事だからだ、つまり俺は普通にしてればいい。 今のところは順調、特に俺の心理面はね。誰も無理しないで好循環を築くことが俺の当面の目的だ。
風呂に入ることにしたら「片付けは僕がやっておくよ」って直にぃが食べ散らかしたものをキッチンに引こうとした。 「待って直にぃ!それまだ食べかけ!」 眉に皺を寄せてソファの上から直にぃが皿を持った腕をすこし強めに掴んでとめた。直にぃは皿に乗ってた最後の一個のタコ焼きを串に刺して俺の口に入れてくれた。パクッと食いついてもぐもぐしながら直にぃの腕をパッと離した。 ここにきたとき香澄の向こうでわたわたしながら部屋の中を片付けてる直にぃが視界の端をかすめた。そのとき直にぃは今おろしてるシャツの袖まくってて、腕には引っかき傷のあとみたいなのがちらっと見えた。どれくらいの怪我かよく見えなかったけど、まぁ掴んでもまるで痛まない程度には治ってきてるっぽいな。 うっかりにしたって直にぃはもうすこし気をつけたほうがいいな。香澄を守ろうとしてんだろうけど、それで直にぃが傷つくと香澄は自分を守られること自体に否定的になりかねない、もうなってるか? だから直にぃがそばについてても、いや、そばにいるほうが自傷悪化するかもな、今は。帰る前にチャンスがあれば説教しとくか。それか様子によってはしばらく香澄と俺だけで旅行でも行くかな。多分二人にそういう発想ないし。 もぐもぐし終えてタコ焼きを飲み込んだら先に風呂場にいこうとしてた香澄の背中に助走つけて飛び乗った。 「わ、絢まってまって、落ちるって」 香澄が俺の両脚を慌てて抱える、香澄の背中に乗っかりながらおんぶされて笑いながら言う。 「脚がいたむ~歩けない~」 「えっほんとに?!」香澄がさらに慌てたから香澄の顔の横から風呂場をビシッと指差した。 「すすめ香澄号!身体的弱者のために!」 「もう…絢の冗談しゃれにならないよ」 香澄が俺をおんぶして脱衣所で下ろした。 「有効な対処方法が見つかったって言ったじゃん。俺の脚なんてもうジョークのネタくらいにしか使えないね」 俺が服を脱ぎながら笑い飛ばしたら香澄はどこか安心したような笑みを浮かべてた。 焼き殺されかけたんだもんな、それを香澄が助けてくれた。 俺はもう大丈夫だよ。そんな感情を込めて、にっこり俺も笑って見せた。
香澄と一緒に読んだ「星の王子さま」の本は直にぃの私物らしい。原著じゃなくて和訳だった。 俺ははじめて訳したときからあの本の新訳が出るたびに全部に目を通してた。ずっと一定の人気を誇る本だから新訳がどんどん出る。サン=テグジュペリの描いた挿絵がすげーかわいいから書店でもすぐ目につく。直にぃが持ってた本は相当古いやつで今はネットとかじゃないとなかなか手に入らない、訳も日本語の言い回しも古めかしくてサンテックスの生きた時代を連想できる俺の好きなやつだった。
「おお~浴槽でか!�� 風呂に入って浴槽のサイズにビビる。真澄さんとこのも標準より大きめだと思うけど。 「直人サイズだからね」 「この部屋って直にぃが購ったの?」 「うん。画家だった頃のアトリエを後輩に譲ってここに移ったの」 「なるほどね」 ここに住み始めたのと画家をやめたのは同時期で合ってるらしい。真澄さんが調べやすいように追加情報まとめてあとで報告するかな。しなくてもあの人ならこれくらいのことは割り出せてるかもな。
風呂の中で香澄とお互いの体を確認し合う。 香澄の体に新しい怪我は増えてなかった。それを褒めるみたいに香澄の頭をポンポン撫でて手と手を絡ませる。香澄の指先を指の腹でさりげなく撫でた。会ったときから気になった、やけに爪を短く切り込んでるから、いつ切ったのか切り口の感触で伺う。昨日今日、ってわけじゃないな。とするとこれは切ってから伸びてきてようやくこの長さってことか。直にぃの腕の傷はそれでか。 「香澄、爪切りすぎたろ」 目を細めてにまーっと意地悪く笑って言ったら正面の香澄がおたおたした。 「えと…寝てる間見ててくれてた直人の腕引っ掻いちゃって、なら爪切ったらいいかなって」 「切りすぎ。直にぃのこと守ろうとすると香澄は視野が欠けがちになるんだから、直にぃを傷つけたくないとか守りたいって思ったときは、思いついても行動する前に一度5分くらい深呼吸してみな。本当にしなきゃいけないこととその加減が見えてくるかもよ」 説教っぽくなりすぎないように向かい合って手を絡めて一緒に手遊びしながら笑ってそう言ったら香澄は素直に頷いた。 「絢、ありがと」
身体洗いあって二人で湯船に浸かって、話がひと段落ついたとこで俺は目を閉じて湯気に向かって歌い出した。風呂の中で歌うの、音が響いて楽しいな。 「それなんて曲?」 「Singin’ In The Rain. ”雨に唄えば”だよ」 歌詞がないところのメロディは口笛にした。こんなこと名廊本家でやってたら殺されるな、シャレじゃなく。 香澄は隣で静かに俺が歌い終わるのを聴きながら待ってた。 歌い終わってから、すこし落ち着いた声で話す。 「俺の脚、雨が降ると痛んだり動かなくなるんだ。気圧だか湿度だか原因よく知らないけど。香澄をラブホで手当てしてから公園で倒れてまことくんに病院つれてってもらったけど、あれは帰ってる途中で雨が降り出しちゃって、脚が動かなかったから公園のゾウのお腹んとこに隠れてたの」 「ゾウのお腹?」 「こーいう丸い穴があって、潜れそうだったから」 腕を頭の上にあげて丸を作ってみせる。 「前は雨が降ったら俺はそこでお手上げだったけど、おとなしく本読む以外にも雨がやむまで歌うって手もあるよな~みたいな」 そこにいた頃は気づいてなかったけど前は相当たくさんの不可視の縛りがあった。あの頃は歌うって手段は頭のどこにも浮かばなかった。誰かに聞こえたら俺の分際で浮かれてでもいるのかってキレられるに決まってるし、雅人さんの家は沈黙に支配されてるような破っちゃいけない空気感があったから。 「絢、いまの曲もう一回歌って」 「いいよ」 ねだられてもう一回同じ曲を披露した。ジーン・ケリーほど美声じゃないしあそこまで声を張り上げるわけじゃないけど、音読するときと同じくらいの感じで、優しく湯気に乗せるみたいにして。 それから話は二転三転しつつ、『からっぽのいきもの』の訳の話になった。 あれって真澄さんが好きな本なのか、俺の訳が気に入ったのか、どっちなんだろ。 「それはたぶん絢の訳を好きって言ったんだよ。兄ちゃんあの絵本は好きじゃ無いから」 「そうなの」 「うん。なんて訳したの?」 「Ils font des animaux en ballons gonflables.」 まだあの本の内容は覚えてる。子供向けにしては意味深だったからつい暇なときリピートして考える。 あの物語の冒頭は”かれは ほんものをかうおかねが ありませんでした”だった。金銭で買えるどうぶつたち。みんなと同じようにかれに財産があったなら、自分のさびしさを使ってまでなにかを作ろうとは考えなかったかもしれない。かれをそらに運んでくれたどうぶつたちは、かれの作った尊く愛しいにせものたちだ。貧しさが、自分を高次へ導く豊かなものをもたらしてかれに生み出させた、宙に吐くだけじゃ霧散して消えるだけのかれの吐息が形になって、なにひとつ持ってないスタートラインから。 訳したときには、直にぃや理人さん、誠人さん、真澄さん、香澄…みんなに似てると思ってた。でもあれは俺の話でもあった。なにひとつ持たずに逃げ出して、残ったものもすべて捨ててそこから新しく始めた俺の。 どこまで高く上昇できるかは俺にかかってる。そして俺はあのとき上昇や浮上に無意識に墜落の未来を感じてた、でも ーーーー「物語にもただの日常にも無限の解き方があるけれど、絢も覚えておいで」 俺を俺だと分かってたときの理人さんがこっそり教えてくれたこと。 ”なぜあの犬は吠えなかったのか? …聞こえなかったこと、書かれていないもの、見えないもの、起こらなかったこと、決められた枠の外側に目を向けてみつけるんだよ、想像力をつかってね” つまり、あの物語はあそこまでしか明文化して書かれてないだけで、続いてたかもしれない。実際、最後はぷつんと切れたような形で特にここで終わりだなんて書かれてなかったし。 どう続けるのかは読み手次第ーーーかれも、俺も、香澄も、真澄さんも、直にぃも。どれだけそういう予測が立っても無残な墜落に終わるかは、書かれてないんだ。書かれなかったことに、作者の思いがあるかもしれない。…いま訳したらまた違う感じになるかもね。
「……さびしさは…彼の命なんだね」 となりで香澄が呟いた。 なにか考え込んでるみたいな顔してる。ーーーかれの、命… 「…香澄?」 香澄が俺の肩にもたれて頭を擦り付けてきた。ねこみたい。 「さっき絢は冗談みたいに言ってたけど…俺、ほんとに会いたいと思ってたよ。絢に」 「…………」 「会えてよかった。すごく大事なんだ…また…一緒にいられて、嬉しい。おかえり、絢」 凪いだ水面に広がる微かな波紋、 香澄の首に腕を回してぎゅっと体を抱き締めた。 触れた腕や体からざらざらした感触が伝わる、身体中にたくさん重なった傷跡、 …もう大丈夫だよ、俺がきたから 俺がついてるよ もう誰にも傷つけさせない、俺じゃなきゃだめなんだ、香澄にとって俺はもう”絢”だから それを嬉しく思う どこにもいかない ずっとついてる どんなときも俺がいて香澄が自分を守るのを助けるよ ”絢”は いらなくなんてない 「………俺もだよ」 香澄の首筋に頭を押しつけて静かに目を閉じた。嬉しくて、自然と口元が緩んで微笑んだ。 俺にもあった 俺が俺だったから、守れるものが 「…香澄が、すごく大事だ。…会えて、よかった、Je suis très heureux n'ai jamais été aussi vivant.…」
風呂から上がって夕飯作って、直にぃと香澄と三人でまた話しながら食べた。 話してて思う、直にぃもけっこう面白い本を読んでる、ずっと絵ばっかり描いてたってよく聞いたから何も共通の話題なんてないかと思ってたけど、案外俺と読んだ本で被ってるのもあった。 そして被ってる本は、正気だったときの理人さんに「読んでごらん」て俺が勧められたものだ。直にぃはきっと、雅人さんから勧められたか、借りて読んだ。 まだ本家で一緒に暮らしてて仲のいい兄弟だった頃、理人さんと雅人さんは一緒に同じ本を読んでたのかもしれない。そう思うと、嬉しかった。
それから直にぃを口先でいじりながら香澄と一緒に寝室に入った。 なんとなく歩くとき香澄の腕を引いて俺の前で絡ませるのがもう癖になってきた。なんだろ、落ち着く。香澄がうしろついてきてるからか? 絡ませた腕の上に俺も両手を置く。列車みたいにつながって歩く。香澄は俺の足踏まないようにしててちょっと歩きづらそうだけど。 かわいかったから鍋つかみに恐竜みたいな柄のやつ買ってきたら香澄はそれを見てえらく喜んでた。このキャラクター有名ななんかだったのか?? 香澄は丸くした目をきらきらさせてる。俺は鍋つかみを一度手にはめて、香澄の鼻にパクッて噛みつかせた。香澄は鼻を押さえられて笑ってた。花が咲いたみたいな笑顔だ。俺もにこにこする。 はしゃぐ香澄の手に鍋つかみをしっかり装着させて、香澄を寝かせる。以前やったみたいに、首筋を俺の体で守るようにして覆いかぶさった。優しく体を抱きしめて明かりを消す。 「香澄、おやすみなさい」 「うん、絢おやすみ」 俺の考えてた「具体的に試したいこと」ってのは、ここからだ。 入眠時の意識状態の行動には、起きている間の当人にいくら説得しても働きかけても効果は薄いだろう。カウンセラーとか臨床心理士とかちゃんとした人が専門知識持ってやるならそういうことも有効なのかもしれないけど、俺がそうじゃない以上俺にできることは別のことだ。 俺のフラッシュバックから生じる脚の痛みに燃えてもないのに水をかけて効果が出たとき思った、問題行動が起きた時が解決の契機にもなる、眠っている意識には、眠っている間に、俺が起きててずっと声をかけ続ければ…
…まだ眠たい もう少し寝てよう…あったかくて気持ちいいし… 「……。」 じゃないんだって!!!!! 「香澄、香澄!」 急いで体を起こして目の前で眠ってる香澄の肩を揺さぶる まさか眠ってたのか、初めてきた他人の家で? 今って、OMG、嘘だろ、部屋ん中もうすっかり明るい、まる一晩俺眠ってたのか?! 何しにきたんだよ?! 完全に脱力した俺の下敷きになってた香澄はぼんやり目を覚まして、俺の背中に回してた手をおそるおそる外した。 「……。」 「……。」 ……は?? 香澄も同じことを思ったのか、綺麗に嵌められたままの状態の鍋つかみをそーっと手から外してみる。…何もない。血の跡とか、指先が腫れてたり赤くなってもない。深爪ぎみだったから一晩中俺の背中を鍋つかみでこすってたとしたら爪の生え際にダメージあるはずだ。 「……。」 香澄の手をとってよく見る。香澄も自分の手じゃないみたいに目を丸くして俺と一緒に、見る。 ……何もない。 「………。」 「絢?!」 脱力してボスッと枕に顔面から倒れ込んだ。…マジか。論理的に現実だけ見て、理詰めで勝負しようとして挑んだら勝負開始のゴングが鳴るのと同時に俺がスヤスヤ眠りこんで、しくじったと思って見れば何も起きてすらなかった… ーーー惨敗。人間ってのは理屈でできてない。十分わかってたつもりだったんだけど… 「…っはは、」 腕をついて枕からゆっくり顔を上げて起き上がったらおかしくて笑いと一緒に目尻から涙でてきた。指先でそれを払う。 起き上がった香澄の体にぐたっと凭れたら重心がずれて香澄の膝の上に倒れた。 俺の顔を見下ろして覗き込んでくる香澄のぽかんとした顔を見て、その頰にそっと手を伸ばす。 俺ちょっと驕ってたかもね、頭使って情報揃えれば俺に事態をどうにかできるかも、なんて。俺の想定した希望より人間の可能性の方がひと回りもふた回りも大きなスケールで軌道を描いてた。人の命を生かす方向へ。 愛で人間の命は守れない、でも愛し合うことで人間が変わって、それが誰かや本人の命を守った。 惨敗だ。 俺が嬉しそうに声を立てて笑うのにつられたのか、香澄も笑い出した。 真澄さん、香澄は奇跡を起こしたよ、自分で。
そのあと一応全身を見てみて何も起きてないのを確認してから、香澄と一緒に寝室からリビングに出てった。 直にぃはもう朝ごはん作って俺たちを待ってた。俺のために何品目かをまだ追加で作ろうか迷ってたみたいだ。 俺が「じゃーん」て言って後ろから香澄の両手を掴んでバンザイさせて直にぃに見せたら、意味をすぐに察したのか直にぃは走り寄ってきて、香澄を抱きしめて泣いてた。幸せそうに笑いながら。
続き
0 notes
Text
愛なのに
まずはじめに「その着せ替え人形は恋をする」を皆さん見てますか?2022冬アニメのラインナップで、ぶっちぎりで1番面白いです。まだ未見の方は是非第3話までチェックしてほしいですが、第8話が神回だったのでもう一気に全話見て下さい笑 アニメ化から原作コミックスの売れ行きをいかに伸ばせるかがここ最近のアニメのバズってる指数になってますが、特に"着せ恋"の売れ方は半端じゃなくて、1ヶ月で100万部伸びたらしいです。騙すつもりはないですが、騙されたと思って一度見てみてください。

さて、今回は先月末から公開された「愛なのに」について。城定秀夫と今泉力哉がタッグを組み、お互いが書いた脚本をお互いが撮影するという企画"L/R15"より生まれた作品です。今作は監督が城定秀夫で脚本が今泉力哉。まずは城定秀夫について。数多くのピンク映画やVシネを世に生み出してきた城定秀夫の作品の中でも「アルプススタンドのはしの方」はすごく良い作品なのでこちらもチェックしてみて下さい。そして今泉力哉と言えば世間的には「愛がなんだ」が代表作とされていますが、個人的には違います。僕は下北沢を舞台に男1女4の設定で描いた青春群像劇の2020年公開の「街の上で」が1番だと思います。

若葉竜也が演じた主人公の荒川青も最高でしたが、ストーリーの中で1番心を惹かれたのは中田青渚演じるスタイリストの"城定イハ"でした。穂志もえか、萩原みのり、古川琴音よりも圧倒的に中田青渚に1票でした。劇中で映画の撮影を終え、下北での打ち上げ後にイハちゃんの家に行って、ただ談笑する長尺ワンカットシーンは本当に良いので見てほしい。関西弁の女の子ってやっぱりいいよな〜とも思わされるし、なんといってもイハちゃんが可愛すぎます。このシーン以外にも全編通して散りばめられている今泉節も最高の作品です。

あれ?城定? 気になった方は流石です。この役名は今泉力哉が城定秀夫をオマージュした役名なのです。それくらいリスペクト強めな先輩後輩の2人が作る映画がつまらないわけがないのです。単調な流れでも会話劇が抜群に面白い今泉力哉の脚本力と城定秀夫のカット割がとてもいい塩梅でした。見終わっての感想を軽く伝えるならば、予告編を見て抱く期待値を余裕で超えてくる位面白かったです。

ここからは毎度お馴染みのネタバレ有りな感想で作品を振り返ります。多少のネタバレは気にしない方向けです。嫌な方は鑑賞後に読んでもらえたら嬉しいです。

主人公は瀬戸康史演じる古本屋の店主の多田(ただ)。年齢はもうすぐ31歳。その多田を一方的に好きになり、しつこく求婚を迫る女子高生の矢野岬を演じたのが、今ブログで三回連続登場の河合優実(もう確実にファンです) 岬が店内から一冊の小説を万引きするところから物語は始まります。万引きの理由は自分の名前を覚えてほしかった事と、多田が読んでいる本が欲しかった為。間違いなく可愛くないと絶対に許されない理由でした笑 その日を境にして店に来る度にラブレターを持ってきては求婚を迫る岬。そんな彼女を邪険には扱えない性格の多田。犯罪になりかねない歳の差がもちろん壁になってますが、もう一つの壁が多田の過去の恋愛でした。この微笑ましい冒頭の2人のシーンでがっつり心掴まれました。
瀬戸君はアイドル俳優とばかり思ってましたが、歳を重ねていい味が出てきてますよね。この作品でその先入観は払拭されました。それよりも、河合優実に言い寄られる多田よ、、ただただ羨ましいぞ笑

多田の忘れられない女性の佐伯一花(いっか)を演じたのが、ゲス極のドラマーであり最近は女優としても活躍中のさとうほなみakaほな・いこか。佐伯は多田が岬と出会った頃には結婚式を控えていました。その相手である亮介は、2人を担当してくれているウェディングプランナーの美樹と結婚式が終わるまでの期間限定な不倫関係にありました。この亮介が不倫をしている事は予告を見た時点で既にネタバレしていたので、こっちの話はどうでもいいから、もっと多田と岬のシーンを見たい!と思ったのが序盤の感想です。でも、一花が亮介の不倫の尻尾を掴んでからが、この映画の始まりと言っても過言ではないです。
不倫をした事をあっさりと認める亮介。相手は美樹でなく、過去に自分の事を好いていた人物であると嘘をつきます。謝罪されても腹の虫がおさまらない一花が出した結論は「私も同じ事していい?」でした。つまり一花も過去に自分の事を好きだった多田と寝てくると。ここら辺から亮介を演じた中島歩のポンコツぶりを発揮する演技は思わず笑ってしまう事間違いなしです。

多田をホテルに呼び出した一花。結婚式を控えた花嫁である事を多田は知っていて、「こんな事は絶対に間違っている」と一花の決意を受け入れません。そんな多田に痺れを切らし「じゃあ違う男とやる」と洋服を着始める一花を見て、男としてのプライドが勝ってしまい遂に決意が固まった多田。ちなみにこの時のコンドームの件は最高でした笑 エロVシネを沢山撮ってきた城定監督の濡れ場に対するこだわりは半端じゃなかったです。並の濡れ場シーンとは比べ物にならない位に。そして、その城定監督の期待に間違いなく100%応えたであろうさとうほなみの演技は必見です。

これで亮介とウィンウィンな関係に戻れると思っていましたが、一花は多田と会ってから表情が晴れないまま。あーやっぱり���悪感が勝ってしまうパターンねと思いましたが、悩みの原因はそんなありきたりなものではなかったです。一花は多田とのSEXがあまりにも気持ち良すぎて忘れられなくなっていました。これだけ聞くとビッチで尻軽な奴ねとか、多田がとんでないテクニックの持ち主だったのかと考えてしまいます。でもそうじゃないのがこの脚本の面白い所。結論から言うと原因は亮介にあって、彼は超がつくほどSEXが下手クソだったのです。
その確信に触れるシーンは美樹との行為を終えた後にやってきます。男たる者、異性に言われたらずっと引きずってしまう「SEX下手くそですよね?」を美樹にマジなトーンで言われてしまいます。ここの掛け合いの亮介のポンコツっぷりは絶対に笑ってしまいます。その後、一花は多田との行為をアゲインしたくなり、もう一度だけ体を交わします。このシーンを見て僕はいやらしだけとは違う感情になってしまいました。鑑賞前の予想を大きく覆した中盤は完全に一花と亮介に話を持って行かれた展開でした。でもご安心下さい。ラストはちゃんと多田と岬のターンで幕を閉じます。

時は一花から連絡が来る前に戻ります。多田はいつもの様に岬から手紙を受け取りますが、その時は少し雰囲気が違いました。封筒の中には白紙の便箋だけが入っていて「多田さんの言葉が欲しい」と岬言われ、返事を書く約束を交わしました。でも16歳の女子高生に改めて何を書けば良いのか分からず筆が全く進みません。そんな時に一花からの連絡がありました。ずっと忘れられなかった相手と決着をつけた結果、多田は“愛”についての価値観が変わりました。岬に宛てた内容は、"これからも手紙を書いて欲しい。求婚をし続けてほしい。いつか岬の事を好きになれる気がする" その後、なんだかんだありながらも結婚する事を決めた一花から招待状が届きます。そして岬の両親が多田の家に怒鳴りにくる(当たり前)などあって迎えるラスト。

いつもの日課であるノラ猫のカンタにエサをあげている多田の所に手紙を持った岬がやってきます。親御さん問題は解決してないですが、こっそりとお店で会い続ける2人。一花の結婚式にはもちろん参列しなかった多田に友人が引き出物を渡しにやってきます。その中身は夫婦茶碗。その片方を岬にプレゼントし、「やった!」と岬が喜び幕は閉じます。
この後の展開は見た人に委ねる的な終わり方でしたが、僕はこの2人が将来結ばれる事はないのかなと。岬がこれから大人になっていく中で、色々な人との出逢いや価値観、世界観の変化が押し寄せてくるはずです。そして多田ではない別の誰かと結ばれた時には良き思い出の1つとして“ちょっと思い出しただけ”になるかもしれませんよね。この映画のキャッチコピーである「真っ直ぐで厄介で、否定できないこの想い」はとても素敵な言葉だなと見終わった後に思わせられました。
youtube
NARI
44 notes
·
View notes
Text
2021/7/24
朝、目覚ましより先に目を覚ます。相変わらず遠足が楽しみで早起きしてしまう子どもです。すると雨が降りはじめ、なぬ! と思っていると、��ぐに雨は止んで、むしろ陽射しが窓から注いでくる。浮きうきで支度をしていると、Nから連絡が来ている。Tが美容室に行くから午後からにしてほしいと。それならカリー食べられるじゃん、となり、予定通りに家を出る。今日も積雲の多い晴れ。上昇する夏のイマージュ。熱気球や光のきらめきを感化しながら、ふたりに会えるのが楽しみで仕方ない。
オープンと同時にOさんのお店に入る。今日は早いですねって驚かれる。この時間はいつもお客さんが少ないらしく、ほんとうにひとりもお客さんがやってこない。久しぶりに音楽談義に華を咲かせる。一昨日ひさしぶりに聴いたAC/DCが凄いかっこよかったってはなしから、Oさんは意外にもAC/DCの大ファンだと知れる。こう言っちゃあれですけど、AC/DCってバカのひとつ憶えっていうか、そんな感じだからバカにされがちだと思うんですけど、あの潔いギターがかっこいいですよねって。すると、Oさんも同じ意見で、そうなんですよ、アンガス・ヤングって腹くくってギター弾いてるんですよね、そういう姿勢に惹かれるんですよ、どの曲も同じような感じなんですけど、ある意味でミニマルミュージックなんですって、かなり良いことを言う。ものすごく共感する。アンガス・ヤングのように腹をくくっているギタリストをもうひとり思い付き、キース・リチャーズもそんな感じですよねって。すると、Oさんも同じ意見で、そうなんですよ、僕のなかではアンガスとキースは同類ですね、キースのギターもミニマルミュージック、ひとつのことをどこまでも突き詰めた職人芸ですよねって。お客さん、ほんとうに一人もやってこず、音楽談義が白熱する。
湘南新宿ラインで待ち合わせ。毎度のこと待ち合わせがめちゃくちゃ下手くそなわれわれ。時間を過ぎても誰とも会うことができず、平行世界(パラレルワールド)のことを考える、じぶんだけがいま待ち合わせの存在していない世界線にいるのではないか、と。偶然会うことは得意なのになぁ。そしたらNから連絡が来ていて、Nの居るらしいプラットホームの場所に向かう。Tにも連絡をする。遠足スタイルのNにようやく会うことができる。TからはOKサインがきている。ところが待てども待てどもTの姿が見えない。乗るつもりだった電車が行ってしまったそのあとすぐにTがひらひらとやってくる。バッド・タイミングすぎて、ある意味でグッド・タイミング。そんなのも関係なくTが久しぶりのNをわぁーーっと抱きすくめる。こんな光景を見られただけで大いに大満足で、わざわざこれから海に行かなくてもいいくらいに今日という一日を達成してしまう。これは勝手な偏見かもしれないけれど、ふたりはいい意味に左右対称というか左右非対称で、たぶん、おたがいに自覚していない長所をそれぞれに強く持ち合っている(コントラの感想もきれいさっぱり真逆だったし)。だから、ふたりが一緒にいると最強(最狂?)という感じがするし、ふたりはほんとうにいい友であると思う。
湘南新宿ラインのボックス席、昨日セブンでNに教えてもらったアンダー・ザ・シーをTも知っているかどうか5月8日のピアノの録音をTにも聴いてもらう。録音の日付を見ながら2カ月以上も気になり続けていたんだなぁと思う。電車で音が聴こえ辛いこともあってか、Tはまったくわからない模様。Nにも聴いてもらうと、すぐに昨日のあれねっとなる。Nとふたりでメロディを口ずさんでTに聴かせる。そんなこんなでディズニーやジブリのはなしになる。すでに何回も観ている映画にコメントを付けたり、ツッコミを入れながら観るやつやりたいなぁと思う。窓の外は積乱雲がものすごい。移動の時間が大好きだなぁとあらためて思う。どこかに行くっていう目的も目的でいいけれど、それに伴う移動の時間は目的に付随する二義的なものではなくて、むしろ、移動の時間のなかにこそ目的の限定的な立場からはみ出してそれを包摂するような自由な豊かさがあるような気がする。究極的には行って帰ってくるだけで充分なのかもしれない。
京急線に乗り換える。新幹線スタイルの座席、しかも、先頭車両の一番前の座席がロマンスカーのような展望座席になっている。生憎、展望座席は��まっていて、後方の席に三人横並びで座る。トンネルの多い路線、トンネルの影のアーチが見えてきて、列車がトンネルの外に走り出て車内がそぞろ明るくなるたびに『恋恋風塵』の冒頭のショットを思い出す。Nは席を離れて、展望座席の後ろから展望窓の風景を覗いている。Tが今日のNちゃんの後ろ姿って小学生の遠足みたいだよね~って。前々からNが何かに似ていると思い続けてきて、ついにこの謎が解けた、トトロだってことを打ち明ける。展望座席が空いたから、そっちに移動する。窓の外は積乱雲がものすごい。線路の周りは緑にあふれ、山間の町並みは茶畑のように段々に家々が連なっている。遠くのほうに海が見えてきそうで、なかなか見えない。停車駅のひとつで、Tがその町並みを眺めながら、すごーい外国に来たみたいって。それは言い過ぎかってすぐに撤回する。大笑いしながら、まあ、イオンあるからねって。ついに車窓から海の濃いブルーが見えて三人とも大はしゃぎ。
三崎口駅に到着。電車から降りると、線路の途切れる終着地がある。バスで水族館に行く。終着点の水族館の名前のバス停で下車すると、空き地みたいなところにマリモをでかくしたみたいな変な植物たちが疎らに群れをなしている。なにこれかわいいと三人とも大興奮。植物が生えているというより、植物のような動物がジッと立ち止まって群れをなしているというほうがピンとくる。もののけ姫のこだまみたいな感じでジッとこちらの様子を窺っている。基本的には疎らに群れをなしていながら、三体がぴったりくっついて仲良し三人組みたいになっているのもいる。マリモのなかからエノコログサが飛び出ている。Tが夜になったらきっとここには誰もいないよ、みんな森に帰っちゃうんだ、みたいのことを言う。大笑いしながら、ほんとうにそんなふうに思われる。水族館のバス停のはずなのに、水族館はまだ先にあって、しかも、けっこうな距離がある。なんで水族館の前まで行ってくれないのって何度もブーたれる。入園してすぐ、でっかいアシカが眠っている。アシカってこんなにでかいんだってびっくりする。Nはアシカにも似ているような気がする。なんだろう、ヒゲの雰囲気がそう感じさせるのかな。まずは、当水族館の押しであるらしいカワウソの森に行く。想像とだいぶ違っていて、カワウソも一匹しか見られず、ちょっとショックを受ける。自然公園みたいなところに野生のヘビに注意の看板が出ていて、さっそくハンターことTの心が燃え上がっている。ヘビ捕まえていいの?! って言うから、野生のヘビならいいんじゃないって。水族館の屋内に入る。入口のところにサメの口の骨のとげとげしい模型があって、すぐ近くまできて、その大きさにびっくりして思わず仰け反るような姿勢になると、Nになんで~って突っ込まれる、ずっと見えてたのにって。いや、近くまできたら思ったよりでかいのにびっくりしてって弁明する。館内に入るなり、いきなりでっかいチョウザメがいて目が点になる。数体の古代魚が水槽のなかでゆらゆらと身を踊らせている。それから個々の小さな水槽を順番に見てまわる。大勢の魚がスクランブル交差点のように錯綜と泳ぎまわっている水槽で、TかNのどっちだったかが全ての魚たちが誰ひとりとしてぶつかることなく泳ぎまわっていることに感心している。チンアナゴがエイリアンみたいな動きでおもしろい。二階に上る。二階は円形の壁沿いにぐるっと大きな水槽が張り巡らされていて、魚たちが回遊できるようになっている。水槽の上からは太陽の光が注いでいて、フロアのあっちこちに光や虹のきらめきが踊っている。サメが特に目を引く。凶悪そうなギザギザの口に、何よりも眼球がひっくり返ったような冷徹な目。鼻に瘤のようなものを付けているサメがいて、あれは何だろうとしばらく後を追ってみるも、よくわからない。ノコギリザメがいて、ふたりにも声をかける。ノコギリザメはけっこうかわいい感じ。見にいくとノコギリザメは泳ぐのやめて、ジッとこちらの様子を眺めている。その瞳の動きで三人を順番に見渡しているのがわかる。ノコギリザメから離れると、ノコギリザメのほうも泳ぐのを再開させる。一階に戻ると、シマ吉くんの催しが行なわれている。魚も芸を覚えることにびっくり仰天。シマ吉くんかわいい。館内を出て、キムタクみたいなペンギンを見に行く。からだを唐突にブルブルッと震わせたり、羽を暢気にひよひよさせたり、ペンギンの動きには変なメリハリがあって見応えがある。そしたら、一羽だけ気ちがいのようにからだを意味不明にくねらせながら泳いでいるペンギンがいる。意味不明に水飛沫を立てるその一羽に三人とも釘付けになる。Nが私もこんなふうに動いてみたいけど人間だからなぁ、みたいなことを残念そうに口にする。でも、Nはたまにいきなり唐突に、衝動的に常軌を逸したような動きを見せるよなぁと思う。件のことで警察署に行くまえ、小川のところで連絡待ちしているときに���いきなりNがわあああっと手に持っていた葉っぱを小川に投げつけたのはほんとうに美しかった。いったん駅に戻って、三戸浜を目指すことにする。なんでバスは水族館の前まで来てくれないんだって相変わらずブーたれながら歩いていると、車がきて道を開ける。車が過ぎて、遠いバス停に向けて再発進しようとすると、Nがいきなり手に持っていたエノコログサをわああっと振り乱しながら急接近してきて、うわわわっと腰を抜かしそうになる。なんで、なんで、いきなりそんなことするの?! Nは悪い笑みを浮かべ、だってKさん、とここでいったん絶妙な間を置き、素直にそのことを言うべきか言わないべきか迷っているような、あえて間を置くことでそのことを強調するような感じで、ビビりなんだも~ん! って。この野郎、ひとをバカにしやがって、いつかぜったい仕返ししてやるからなって心に強く思いつつ、ほんとうに最高だなって思う。ビビりなんだも~ん! いままでNからもらった言葉でいちばん嬉しいかもしれない。
バスで駅に戻り、三戸浜を目指す。収穫が済んで畑にきれいに整列しつつも朽ち果てている植物たちの残骸をTが戦時中の死体のようだと形容する。あるいは向日葵の蛍光色の質感、夜になったら光り出しそう。子猫の亡骸。急に夏の終わりが顕在化する。いまが夏でよかったと思う、すぐに骨に還ってしまうから。Nが持ち歩いていたエノコログサを子猫に捧げる。持ち歩いていて、よかったなぁと心の底から思う。ねこじゃらしはそこらへんにも普通に生えていて、すぐにでも摘んでこられるけども、これは人間側のエゴかもしれないけれど、大事に持っていたそれを捧げるというのはせめてもの救いになる。意気消沈しながらも海への歩みは止まらない。海への入口の畦道を通り抜けると、大きな海が広がっている。夕陽を受けた波のまにまが橙色の光のすじを浮かべている。三人とも大はしゃぎで海のほうに駆けてゆく。サンダルのNが早速パンツの裾をたくし上げて海のなかに入っていく。勢いのある波を受けたNがこっちへ振り返って驚きと喜びの入り混じったようなとってもいい笑顔をみせる。さらにずいずい海のほうに身を入れてゆく。Nのからだが踊っている。このあいだと同じくらいの時間なのに波の寄せ方がぜんぜん違っている、浜のかなり深いところまで波が来ていて、くつで歩ける場所がほとんどない。そればかりではなく、このあいだは空の高いところにずっと見えていた月がどこにも見当たらない、昨日の感じからして今日はおそらく満月だろうと思われるけれど。じぶんもスニーカーと靴下を脱いで波打ち際を歩く。波はけっこうな勢いで、裸足だからと油断していると下半身がびしょ濡れになってしまう。びしょ濡れになって色々諦めたらしいTがサンダルを脱いで裸足になる。Nも裸足のほうが気持ち良さそうとサンダルを脱ぐ。まずは廃墟を目指す。でっかい丸太が波打ち際に落ちている。海のほうに蹴ってみるものの、重すぎてぜんぜん動いてくれない。それだというのに、ひとたび波が丸太に届くと、波はいとも簡単に丸太をさらって、さらに次の波が丸太を波打ち際に叩きつける。あっぶな! と三人で丸太をよける。Tが海の殺意を感じるよーとはしゃいでいる。波打ち際をずいずい歩いていると、後ろのふたりから何これすごーい! 魔法使いみたいって歓喜の声があがる。何かと思えば、じぶんの足が濡れた砂浜に触れるたびに、フワッと空気の膨らみのようなのがあたりに拡がっている。まさに魔法使いが歩いているかのよう、もののけ姫のシシ神様の歩き方みたいってはなしにもなる。波の勢いにかなり苦戦しながらも廃墟が近づいてくる。廃墟の辺りを境に砂浜が岩場に変わっていて、岩にぶつかった波が壮絶な潮砕けとなって舞い上がっている、絶句して、ゴクンと唾を飲み込む。廃墟に到達。Tからもらったウエットティッシュで足の砂を落として靴下とスニーカーを履き直す。いざ、廃墟に潜入! 底の抜けた階段の脇をロッククライミングのように慎重によじ登る。続いてTも。続くNが半ばの空中で動けなくなってしまい、あわわ、あわわ、この次どこに足をもっていったらいいのー?! って。どうにかこうにか登りきる。廃墟にもかかわらず落書きなんかがいっさいない、純然たる野生の廃墟。下から見る限り、底が抜けそうな感じがしたけれど、踏んでみるかぎり最初のフロアは問題なさそう。ところが、その先に伸びている廊下は底抜けしそうというより、すでに床の木肌がひび割れて底が見えている。あっぶな! と咄嗟に引き下がって、そばに来ていたTにも注意を促す。ここで行きにも少し話題になった(そんなことはすっかり忘れていた)Nの「ばけたん」なるお化け探知機がついに初お目見えになる。「ばけたん」が赤く光れば悪霊がいる、青く光れば天使がいる、緑に光れば平常でとくに何もない。どう考えても赤く光りそうなシチュエーションでありながら、どういうわけか青く光る。底抜けの大丈夫そうな場所をひと通り探索して外にもどる。出るときもNは半ばの空中で動けなくなってしまい、あわわ、あわわ、どうにかこうにか地面に帰ってくることができる。続いて洞窟。入り口の岩場にはでっかいフナムシが無数に蠢いている。ふたりから虫がだめなのに、なんでフナムシは平気なのって不思議がられる。セミが夏の天使なように、フナムシは海の天使だからって思っていることを素直に応えながら、でも、だとしても何で平気なんだろうって不思議に思う。ひとりでは怖すぎて一歩しか中に入れなかった洞窟も三人いれば心強い。スマホのライトで先を照らしながら、ちょっとずつ、ちょっとずつ、中のほうに入ってゆく。洞窟の側面にも天井にも隙間なく無数のフナムシが蠢いている。Nがここでも「ばけたん」を発動させてみる、結果は緑の光。洞窟は大広間の先に細い小路が続いている。その入口まで行って引き返そうとすると、Tがこの先まで行ってみようよって。もう無理、もう無理、これ以上は無理って断ると、さすが度胸のあるTはひとりで小路に入ってゆく。小路の突き当たりまで行ってもどってくる。小路の突き当たりはさらに左右に枝分かれしているらしい。
夕陽は海上の雲にのまれ、空は暗くなりつつある。岩場をさらに進んでゆくと、一人キャンパーが三組だったか四組、おたがいに微妙に距離を取りながら座っている。焚火のいい匂いがする。岩場にはフナムシなかにカニもたくさんいる。そんな岩場の一角にどんなカニとも比べものにならないでっかいカニをTが発見、すぐさまハンターの心が燃え上がり、捕獲に向かう。カニの捕まえ方なんて知らないよ~(だったらヘビの捕まえ方は知っていたのか……)と弱音を吐きながらも果敢にカニに立ち向かってゆく。数分の格闘のすえ、見事にカニを捕獲、持っていたビニール袋に入れる。Nはその場に腰掛け、じぶんは岩場の先端のほうまで行き、Tはその中間くらいから三者三様に暮れてゆく空と海を眺める。岩にぶつかる波の潮砕けがもの凄い。しばらく経って、Nのいる地点まで戻ろうとすると、Nが大きく手を振る、大きく手を振り返す。ふたたび三人が集まると、Nが家が恋しくなっちゃうって泣きそうな声で言う。たしかにそうなのだ。こんな最果ての辺境で、しかも、もうすぐ夜が来ようとしている。どうして、じぶんはいつもこんなところにわざわざひとりで赴いているのかってことをこのとき初めて考える。それからNがいい写真撮れたよって、ふたりがそれぞれに海を眺めている写真を見せてくれる。そろそろ帰ろうか、来た道を引き返すことにする。廃墟の辺りで海を離れて、上の道路を歩くことにする。Nだけ足の砂を落としていなくてどこかで洗いたい、いちどは海に下りていこうとするけれど、あいだには砂浜があるから海で洗ってもまた砂だらけになってしまう。きっと、そこらへんに水道があるでしょってことになり、そのまま上の道路を歩いてゆく。しばらくすると、マリンスポーツの拠点みたいな施設がある。水道はありそうでなくて、人間はじぶんたちを除いて人っ子ひとりいない。そんな施設のさなかに芝生のお庭がある。芝生のお庭になら水道あるでしょって探すけど、水道はどこにもない代わりに芝生の隣に敷居に囲われたプールがある。その敷居は簡単に跨いでいける感じで、だあれもいないし、あのプールで洗っちゃえば。Tが敷���を跨ぐまでもなく普通に入口を発見して、勝手に入口の鍵みたいのを開けて中に入っている。足を洗ったNがプールの水すごいきれいだったって戻ってくる。ふふ。とうに日は暮れて、暗い夜の山道を駅に向かって引き返す。Nが暗いよぉ、怖いよぉと頻りに泣きそうな声で連呼する。そんなつもりじゃなかったけども、仕返しを無事に達成。Nのスマホのライトでできるでっかい影。とりわけ樹々の左右から覆い被さる真っ暗な坂道、ここで「ばけたん」をやってみようになるけれど、Nのかばんから「ばけたん」が消失してしまう。どこかに落としてきちゃったかなぁ。自動車のヘッドライトからほとばしる影に驚いたりしながら、街灯のある明るいところに移動して「ばけたん」の捜索。かばんを隈なくひっくり返しても見つからず、「ばけたん」の性能には半信半疑ながら三千えんのお買い物がたったの二日で消失してしまうのにはさすがに気の毒な感じがして、色んな可能性を示唆していると、かばんのポケットのひとつから「ばけたん」が発見される。よかったぁ。その場で「ばけたん」を発動させると緑色に光る。山道を経て、畑道のところまで来ると、びっくりするぐらい赤い光線を発する怪しい満月が空のかなり低いところにのぼっている。Tがどこかのタイミングで(たぶん廃墟だったかな)口走った『夕闇通り探検隊』の一言が胸に突き刺さる。月のなかを鉄塔の陰翳が横切る。
帰りの電車でも頻りに「ばけたん」のはなしになる。乗換駅でも発動させてみる。緑色。廃墟でいちどだけ出た青以外はぜんぶが平常の緑色を示す。Nから、こんな胡散臭い商品なのに何故か高評価のアマゾンのレビューを見せてもらう。それでもまだ胡散臭さは拭えなくて、いっぽうで廃墟のときだけ色が変わったことがどうも引っかかっている。帰り際になってNがぽろっと口にした「乱数の偏り」という言葉にアンテナがビビッと反応して、これはきっと何があるぞと思う。帰ったらじっくり調べてみようと心に決める。
1 note
·
View note
Photo

劇評など critic
作品をめぐるこれまでのテキスト ※敬称略 ※所属や肩書きは執筆当時のもの
カトリヒデトシ(2010) 平山富康(2010) 亀田恵子(2010) Marianne Bevand(2011) 間瀬幸江(2011) 唐津絵理(2011) 金山古都美(2012) 島貴之(2012)
/
カトリヒデトシ(エム・マッティーナ 主宰 舞台芸術批評)
「なぜ日本人がチェホフをやるのか?」と問うのは、かなりダサい。
今までの蓄積に付け加える、新しい文脈・意味を発見し提示するのだという優等生的な答えは間違っていると思っている。それでは、ヨーロッパ文化をきちんと学んだという模範解答になり、単なるレポートになってしまうだろう。
古典を何度でも取り上げることは、芸術の目指す「絶対的有」への敬虔な奉仕である。「有りて在るもの」への畏怖の気持ちは洋の東西といったものは関係ない。芸術へひざまづき、頭をたれることは、芸術家の基本的な資質であるし、それこそが歴史や文化的差異を超えようとする意思の現れにつながっていく。現代から古典を読み直し、古典から現在を照らすことにこそ、古典に取り組む大きな意味がある。
また、孔子は論語で「子は怪力乱神を語らず」といった。これは軽々しくそれについて語ってはならないと理解するべきで、超常現象にインテリは関わらないということではない。芸術は人間を超えた存在、「不可知な存在」を認知することが第一歩であろうから。
第七の演劇には、不可知が全体を包みこもうとする力。またそれに触れた人間の、根源的な「生」への畏怖がよく現れている。
それらの二点で第七劇場は大切な存在だとおもっている。 たとえば、今回の「かもめ」はチェホフの本質に迫ろうとする試みである。
ダメな人間がダメなことしかしないで、どんどんダメになっていってしまうのがチェホフ世界の典型である。そこには没落していく帝政時代の裕福な階級を描き続けた、彼の本質が現れている。
それはチェホフには、たれもが時代に「とり残されていく」、乗り遅れていく存在であるという認識があるからである。つまり、「いつも間に合わないこと」こそが人の本質なのだという考えである。
取り残されていくことは悲しい。何も変わらなければ既得権を維持できるものを、時代の変化によって、何もかもが「今まで通り」ではいかなくなる。チェホフはそれを、「われわれは絶えず間に合わず、遅れていく存在なのだ」と確信にみちて描く。苦い認識である。
人間はいつでも誰でも、既にできあがった世界の中に生み落とされる。誰もがすべてのものが現前している中にやってくる。個々人は、養育や教育によって適応をうながされるだけである。人は限りない可塑性をもって生まれるが、時代や地域や環境によって、むしろ何にでも成り得たはずの可能性をどんどん削ぎ落とされていく。
現在ではすたれてしまったが、日本には古代から連綿と続いた信仰に「御霊」というものがある。人は死んだ際に、現世に怨みを残して死ぬと、祟るものだという信仰である。「御霊」は、残った人たちに、天災を起こしたり、疫病を流行らせたりする。やがて人々は天災疫病が起こった時に、誰の「祟り」であろうと考えるようになる。それを畏れるために死んだものの魂が荒ぶらないように崇め拝めるようになっていく。人々に拝まれ、畏怖されるうちに、荒ぶった魂は落ち着いていき、「神」として今度は人々を護る存在へと変わっていく。だから「御霊」はおそろしいものであるだけではない。
「荒ぶる魂」を、第七は「かもめ」の登場人物たちの「遅れ」「取り残されていく」姿の絶望の結果に見る。舞台はその絶望からの荒ぶりに共振し、増幅し、畏怖を現す。
チェホフの持っていた、人に対する「諦観」を大きな包容力で抱え込んこんだ上に、零落していくことへの激しい動揺を、魂の「荒ぶり」として表現する。それは現在の私たちでは到底もち得ない、激しい「生」の身悶えである。
その方法として舞台に遠近法が援用される。 奥行き作り出すことによって、「位相=層=レイヤー」��作りだされる。 後景の美しいオブジェは遥かに遠い「自然」の層で、あたかも人の世を見つめ続ける「永遠」や「普遍」を感じさせる。そして中景は「六号室」のドールンのいる老練の世界、経験に基づいて生きる老人の世界である。患者たちは遊戯する体を持ち、永遠の世界を希求する。その三層を背負って、最前景で「かもめ」の世界が現れる。かれらは都会と田舎、人と人の現世の距離によって引き裂かれていき、苦しみ世界を生きるものとして描かれるのだ。
そう、日本人「にも」チェホフが描けるのではない。 日本人「にしか」描けないチェホフがあるのである。
/
平山富康(財団法人 名古屋市文化振興事業団 名古屋市千種文化小劇場 館長)
遡って2010年2月、名古屋市の千種文化小劇場で企画実施した演劇事業『千種セレクション』(同劇場の特徴的な“円形舞台”を充分に活用できそうな演出家・団体を集めた演劇祭)で、第七劇場の『かもめ』は上演されました。企画の立ち上がった頃には、第七劇場は『新装 四谷怪談』の名古屋公演を既に果たしていて、その空間演出力が注目されていた事から企画の趣旨に最適でした。参加団体は4つ、持ち時間は各60分。それぞれ会話劇・現代劇の再構成・半私小説的創作劇とラインナップが決まる中、第七劇場のプレゼンは“チェーホフの『かもめ』を始めとする幾つかの作品”との事…たったの60分で。一体、どんな手法で時間と空間の制約に収めるつもりなのか。当惑をよそに第七劇場が舞台に作ったのは、さしずめ「白い画布」でした。舞台は一面、真っ白なリノリウムが敷かれ、無骨な机や椅子との対照が、銅版画のように鋭利な空間を立ち上げていました。舞台と同じく白い衣装をまとった俳優(彼女らは『六号室』の患者たち)は静謐な余白のようです。が、幕が開いて、彼女らが見せる不安な彷徨と激した叫びが「鋭利な銅版画」の印象をより強めていきます。この画布が変化を見せるのは、チェーホフの他作品の人物たちが続々と舞台に位置を占めていく時でした。彼らは暗い色の衣装をまとって、これまでの描線とは異なる雰囲気です。こうして、既にある版画の上から幾人もの画家が新たな絵画を描くように芝居は進みました。幾つもの物語の人物が、互い���世界を触れあわせていく現場。彼らが発する言葉と声、静と動が入り混じる身体の動きは、新たな画材でした。時に水墨画、木炭、無機質なフェルトペン。余白を塗り込めたと思えば余白にはねのけられる「常に固定されない描画」のようにスリリングな作劇が、観客の前でリアルタイムに展開されたのです。終演後のアンケートでは“視覚的に美しい贅沢な構成” “話を追いそこねても目が離せなかった” “世界がつくられていく感覚” “難しい様で実はわかりやすい”と、中には観劇の枠に留まらない感想も多々あり、第七劇場が『千種セレクション』で残したのは、限られた空間で無限に絵画を描く様な演劇の可能性だった…というのが当時の記憶です。名古屋市の小劇場で室内実験のように生まれたその作品が、再び三重県で展開され、これから皆さまはどのように記憶されるか。非常に楽しみです。
/
亀田恵子(Arts&Theatre Literacy)
第七劇場の『かもめ』を見終わったあと、どうしようもなく胸高鳴る自分がいた。新しい表現の領域を見つけてしまったという心密かな喜びと、その現場に居合わせることの出来た幸運に震えた。彼らの『かもめ』は演劇作品に違いなかったが、別の何かだとも感じた。「ライブ・インスタレーション」という言葉がピタリと腹に落ちた。「インスタレーション」とは、主に現代美術の領域で用いられる言葉で、作家の意図によって空間を構成・変化させながら場所や空間全体を作品として観客に体験させる方法だ。元々パフォーミング・アーツの演出方法を巡る試行錯誤の中から独立した経緯があるというから、演劇との親和性は高いのだろう。しかし、すべての演劇作品が「インスタレーション」を感じさえるかといえばそうではない。
舞台を四方から客席が取り囲む独自な構造を持つ千種文化小劇場・通称“ちくさ座”(名古屋市)。この舞台に置かれていたのは白い天板の長テーブルが1つに、黒いイスが数客。天井からは白いブランコが1つと、羽を広げた“かもめ”のオブジェが吊られており、床は八角形状に白いパネルが敷き詰められていた。役者たちの衣装もモノトーンやベージュといった大人っぽい配色でまとめられ、全体としてスタイリッシュな印象だ。舞台セットの影響なのか、作品中のセリフでは、チェーホフの『六号室』や『ともしび』といった他の作品の一部も引用され、人間の生々しい欲望や絶望を色濃く孕むセリフが続くが、不思議と重苦しさに傾くことがない。むしろチェーホフの描く狂気や人生における悲しいズレが、役者の身体と現実の時間を手に入れ、終末に向かって疾走する快感へと変容していく。役者たちの独自の強い身体性が、無機質な空間の中で描く軌跡は、従来の演劇の魅力だけでは説明が難しい絶妙なバランスを生み出しているのだ。
第七劇場の『かもめ』は、演劇の枠だけで完結しなければ「インスタレーション」作品として押し黙っている存在でもない。戯曲に閉じ込められた時間を劇場という空間に新たにインストールし、生きた役者の身体によって再生する。それは観客との間に「今、この瞬間」を共有する「ライブ・インスタレーション」として新たな領域を創造する行為に他ならない。
「インスタレーション」は、観客の体験(見たり、聞いたり、感じたり、考えたり)する方法をどう変化させるかが肝らしい。この作品は優れた演劇作品であると同時に「インスタレーションの肝」そのものではないかと思うのである。
/
Marianne Bevand(フランス・舞台芸術プロデューサー)
2011年3月、パリで第七劇場の『かもめ』を観たとき、このよく知られたチェーホフの戯曲において何が問題となっているかを、はじめてよく理解できた機会だった。『かもめ』は昨年にあまり成功していないと感じるいくつかの演出版しか観ていなかったが、私の心を奪ったこのロシア演劇の日本人演出を私はたまたま観る機会を得た。
私は演出・鳴海康平の力量に感動した。深く人間性を表現できる俳優への的確な演出があり、とても美しいシーンを舞台上に構成していた。このすばらしいパフォーマンスの中で、私はある種の普遍性を感じた。私の演劇に関する感覚的な願いが実現するためには、この日本の第七劇場を待たなければならなかった。チェーホフ戯曲の人物を演じながら、偉大なる悲劇だけに可能な想像空間のひとつへと、私を連れ去ることに俳優たちは成功していた。この芝居の最初から私は現実の世界から引き離され、登場人物が衝動や欲求や悲しみによってつき動かされることに目を見張った。それは『かもめ』の中心となる感情である。
素晴らしい身体的なパフォーマンスを通して、俳優たちはコンテンポラリーダンスを想起させる一連のムーヴメントを創り、ときに印象的な間の中で静止する。手をあげる彼女たちは、まるで空を飛びその状況から逃げ出したしたいかのようである。しかし、閉じこめられているかのように最終的には彼女たちは地上に留まる。自由への抵抗の中で、もしくは自由が欠けた結果として、白い服を着た3人の女性の登場人物(訳者注:患者2人とニーナの3人)は、狂気の中へ落ちていくように見える。彼女たちは動きが速く、それは視覚的には、黒い服を着た他の人物たちの緩慢な動きと対照的である。舞台の中央から端へとぐるぐると回る彼女たちを見て、彼女たちは自分たちが生きている規定された世界を象徴するある種の領域を爆破したいかのようなイメージが私の心に浮かんだ。黒い服を着た人物たちは、外部の者に自分の居場所を思い出させる支配社会の象徴を思わせる。
このことは私に、チェーホフがこの作品でいかにアーティストが社会の外側に位置し、つらい時代を生きていたかを明らかにすることで当時のアーティスト状況の描写を試みたことを思い出させる。かもめにおいて、3人の女性の人物たちは、ある異なる精神状態の中で、そして目まぐるしい時空の中で彼らがいかに必死に生きるか、また彼女たちがいつもいかに社会の爪に捕えられているかを現している。
この芝居の終わりに私は自問した。「もしあなたが他の誰かとは異なるふるまいをするなら、あなたは気が狂っているとみなされるのだろうか?」いずれにせよ、第七劇場のパフォーマンスが国境を越えて、いくつかの問いを私に起こしたことは確かである。
この美しく芸術的な作品とともに第七劇場が受けるにふさわしい大きな成功を果たすことを、そしてあらゆる世界を横断し、さらに多くの観客の目と心を開くことを、私は願っている。
/
間瀬幸江(早稲田大学 文学学術院 助教)
チェーホフは世界を面や立体としてとらえていた。人物という点や、人間関係��いう線は、それじたい基幹的ではあるにせよ、作品世界全体の構成要素のひとつでしかない。作品世界のこの広がりから何を「切り出す」のかが、舞台づくりの鍵を握る。
今回、第七劇場の「かもめ」(シアタートラム、9月8日~11日 構成・演出・美術:鳴海康平)で中心的主題として切り出されたのは、トレープレフがニーナに演じさせる劇中劇「人も、動物も…」の部分である。母親のアルカージナに「デカダン」と嘲笑され、当の演者であるニーナにも「よく分からない」と距離を置かれてしまうこの一人芝居の内容は、人間がいかに「やさしく」接しようともいずれ寿命を迎えて消滅することが決まっている地球という惑星の命の時間から考えれば、まったき現実である。その「現実」が、舞台奥中央の老木のオブジェによって密やかに具象される。活人画を思わせるこのオブジェは、開場とともに舞台に姿を見せる、ニーナを思わせる4人の女たちの狂気を孕む無造作な動きはもちろんのこと、見やすい席の確保を願うささやかな「姑息さ」を抱えつつ舞台上の彼女たちを横目で眺める観客たちの動きも、暗がりから見つめ続けている。そして本編が始まり、いつからかそこに照明があてられ、雪のようなものがしんしんと降りだすころ、前景では「かもめ」のいくつかのシークエンスが狂乱的リズムで反復運動を始める。母親にも恋人にも振り向いてもらえずに絶望する青年の物語にせよ、成功という幻想にからめとられたまま一歩も進めない女の物語にせよ、息子を愛しながらその愛を届けることに不器用な母親の物語にせよ、ツルゲーネフには勝てないと感じる自意識の牢獄から逃れることのできない小説家の物語にせよ、個別の物語が抱え込む不毛な反復のエネルギーから発せられる絶叫は、しんしんと降り積もる雪の世界に消えていくしかない。トレープレフは、チェーホフの作った物語のとおり、最後にはピストルの引き金を引く。発射音は聞こえない。しかしそれは、弾丸が発せられなかったからではない。観客は、朽木に降り積もる雪の世界から、トレープレフの自殺や、ニーナの破滅を眺めている。人も動物もヒトデも消えうせた孤独な世界に、ピストル音が届くのは、何万光年も先なのだ。
2011年の日本で、「終わり」というブラックホールを概念としてではなく実体としてほんの一瞬でも覗き見てしまった私たちにとって、朽木の住まう冷えきった世界は、もはや象徴主義の産物ではなくなってしまった。しかし、この終末感を100年前にこの世を去ったチェーホフがすでに言いきっていたことにこそ、私たちはかすかな希望をみるのである。「三人姉妹」を演出したマチアス・ランゴフは、「私たちはチェーホフのずっと後ろを歩いているのです」と言った。それから20年が経過した今なお、チェーホフは私たちの少し前を歩いていて、たまにふと振り返りいささか悲しげに微笑んでみせるのである。鳴海康平は、劇中劇を「切り出す」ことで、無数の点と線とが錯綜して作られる立体的な時空間の表出に成功した。その数多の点や線を大事に拾い出しながらもう一度観てみたかったとの感慨を抱きつつ、9月11日のシアタートラムを後にした。演技者たちの凛とした佇まいも素晴らしかった。
/
唐津絵理(愛知芸術文化センター シニアディレクター)
私たちの深層心理に迫りくる懐かしさの気配、演劇を超えて広がる舞台芸術への希求、それが第七劇場『かもめ』初見の印象だった。
白のリノリウムが敷かれ、白紗幕が下がった劇場は、ブラックボックスでありながらも、ホワイトキューブ的展示室をも想像させる洗練された空間。そこにあるのは、白い長テーブルと幾つかの黒い椅子、天井から吊られた真っ白のブランコやかもめのオブジェ、そして座ったり蹲ったりしている俳優たちの身体だ。白い空間にじっと佇む身体は、彫刻作品のようでもある。上演中も俳優たちは役柄を演じるというより、配役のないコロス的身体性を表出させている。身体の匿名性は、観客自身が自らの身体の記憶と結び付けるための回路を作り出す。それは抽象度の高いダンスパフォーマンスと通ずる身体。前半は僅かに歩いたり、ゆすったりしていた身体が、後半になるにつれて、走ったり、体を払ったり、震わせたりと、より激しく痙攣的になっていく。演劇的マイム性とは一線を画したこれらの身振りが、絶望的に重苦しく表現主義的になりがちなロシアの物語を今日の日本に切り開いていると言ってもよいかもしれない。
怒涛のラストシーンまで、作品全編を演出家・鳴海の真摯さが貫いていく。しんしんと静かに降り積もる雪のように、一見穏やかに見える身体の佇まいの内には、静かな情熱の灯がいつまでも熱く燃え続けている。それがこの作品の確かな強度となっているのだと思う。
/
金山古都美(金沢市民芸術村ドラマ工房ディレクター)
2010年2月千種文化小劇場、12月三重県文化会館で第七劇場の「かもめ」を観劇。時の交錯を感じた千種、閉塞と決壊を感じた三重。どちらについてもその『観後感』は、まったく違っていて。鳴海氏の構築する世界は、その“場所”で変化し、その“人”で変化するようです。“人”とは、役者はもとより、スタッフ、劇場の人々、そして当日来られる観客、すべての“人”を包んでいます。実際観に行った私自身の変化も少なからず影響しあいながら「劇場」という空間が形成されていくのでは。そしてそれは建物の中だろうが、外だろうが、1人だろうが1万人だろうが変わらないのでは・・・違うな。変わらないのではなく、変わることも含めての「作品」なのです。白い床も、テーブルも椅子も、ブランコも「かもめ」のオブジェも、何一つ変わっていないようなのに・・・。そんな演劇のもつ『その場でしか出会えない幸せ』に皆さんで会いに行きましょう。
/
島貴之(aji 演出家)
金沢21世紀美術館にあるジェームズ・タレル作「ブルー・プラネット・スカイ」とい��作品を見た事がありますか?
四角い白色の天井の中央が四角くくり抜かれ、そこから空が見える。故郷へ帰る度に見上げる空。移ろいやすい金沢の空。晴天、夕刻、曇り空、雨。冬はそのグレイの穴から雪が舞い落ちるのです。
曇り空の四角いグレイのグラデーション。無彩色に見えるグレイに、私は何度もさまざまな色を見た事があります。それを見上げる人の心情がそこに色を齎すのです。天井の枠に囲われた今の自分が、その遠く向こうにあるものを見通す瞬間に—。
この作品では登場人物が纏う衣装を見渡すと白から黒へのグラデーションとなっています。そして劇中では、登場人物の性格や事象に伴う心情があらゆる要素により明確に描かれています。個としての居場所、表情、身体、言葉_そしてそれらが合わさりバランスを変化させる事で、その瞬間にしかない色が次々と生まれては消えて行くのです。
それは、移ろいやすい金沢の空のようであり、また、あなたの心情を映すあのグレイのグラデーションであってほしいと願うのです。
2011年の9月に私は第七劇場の「かもめ」を拝見しました。大胆に再構成されたこの舞台に流れる時間は、キリスト教的な時間感覚の、すでに始まったが未だ終わっていない「時のあいだ」を意識させるものでした。時間は、何分・何秒という座標を流れているとされる概念だけでなく、事件・タイミングによって認識される感覚との2つに分けて考えることができます。あのハイコントラストな世界は、ニーナの事件史のある時点なのだろうと納得して観ました。クロノスでなくケイロス、あるいはゲシヒテによって物語を紡ぐ方法は個に依った場合は有効で、むしろ本質的な問いは、なぜそのように構成したかにあると思われました。それが私には「かもめ」の本体をよく知るために境界線を明らかにしようとしているというだけではなく、ほんのりと漂うロマンチックな印象に隠されているような気がしています。舞台を構成するあらゆる要素は一見、清貧とも言えるほど禁欲的に佇み、それがある種の理想として観客に迫っていましたが、私達は同時にその内側にあるもっと柔らかで繊細なモノも見ていました。その存在が、内側からも外側からもこの作品の再演を促しているのではないかと思っています。
2 notes
·
View notes
Link
003年4月15日夜、福岡市中央区の日本語学校に魏と王、楊らが職員室に忍び込み、現金約五万円を盗んだ。そこは王が在籍していた学校だった。王、楊はその1月にも、同区のファストフード店に侵入し、現金230万円を盗んでいた。ここは楊のアルバイト先。4月9日には魏が別の中国人留学生2人と共謀し、中国人留学生から現金約26万円を奪うという事件も起こしている。 「3人で何かやろう」 5月上旬には、楊のアルバイト先だった同市博多区のラーメン店経営者襲撃を計画する。「面識があると発覚の危険性が高い」として断念したが、この時すでに「殺害して金を奪う」ことを念頭に置いていた。 http://yabusaka.moo.jp/fukuokaikka.htm
中国人留学生
王亮(ワンリャン 当時21歳)
出典福岡・一家4人殺人事件
吉林省出身。父親は土木会社を経営し、裕福な家庭に育った。02年春、日本の大学進学を目指して福岡市内の日本語学校に入学し、同級生とともに寮で暮らし始めた。当初授業の出席率は96%と高かった。(出席率が95%以下になれば入国管理局に報告されるという。さらに低くなると強制送還される)だが王はこの年の9月、同級生とトラブルを起こし、その時の学校の対応に不信感を抱き、ほとんど学校に出てこなくなった。同級生によるとこの頃から王の様子が変わっていったという。03年4月の時点で、王はMさん宅から700mほどのところにある家賃2万円のアパートに楊とともに住んでいた。5月15日に日本語学校から、このままで除籍処分になると通告された。就学生が除籍処分されると、就学ビザを取り消され不法滞在になる。王は1度中国に帰り、両親に再編入のための授業料の工面を依頼していた。だが、両親が王持たせたはずの授業料は学校に納めておらず、除籍処分となっていた。
楊寧(ヤンニン 当時23歳)
出典福岡・一家4人殺人事件
吉林省出身。父親は長春市の中日友好協会に勤め、母親は同市の製紙工場に勤務。王とは両親同市が古くからの知り合いだった。01年10月に就学ビザで来日し、日本語学校を卒業した後、私立大学国際商学部に入学し、アジアの貿易経済について学んだ。02年には1科目を履修しただけでさぼり、後期には病気と称して休学したが、実際は福岡市内のハンバーガーショップでアルバイトをしていた。03年4月に1度は復学したが、年間50万円余の学費が払えず、納入期限の6月末を前に「親から学費を受け取るために一旦帰国する」と大学側に説明して出国した。この時、実家には戻っていない。
魏巍(ウェイウェイ 当時23歳)
出典福岡・一家4人殺人事件
河南省出身。父は工場を経営する資産家。魏自身も高校卒業後、3年間人民軍(※)で班長を務めた。その後大連の外国語学院で日本語を学び、日本留学後は先端技術を学ぶという希望を持ち、01年4月、福岡の日本語学校に入学している。02年4月には予定通り、コンピューターの専門学校に入学した。ここでは成績もよく、奨学生候補だった。故郷には恋人もいて、ごく普通の学生だったが03年になると一転して学校を欠席がちになった。魏のアパートには中国人の女性が何人も出入りするようになり、4月には留学生仲間と中国人宅に押し入り、26万円を強奪、6月には知人の女性に暴力をふるったとして傷害容疑で逮捕された。この頃、インターネットカフェにしばしば通うようになり、王や楊と知り合った。4月9日にはかつて住んでいたアパートへ強盗を押しこんだこともある。また、他人名義で携帯電話を契約する詐欺も働いている。金にも対して困っていない優秀な学生だった彼が、03年春を境に突如犯罪行為を繰り返すようになっていた。
出典blog-imgs-34.fc2.com
福岡一家4人殺害事件
福岡一家4人殺害事件
Mさん一家
殺害されたMさん一家は、Mさん(41歳)、妻C子さん(40歳)、小学6年の長男K君(11歳)、小学3年生の長女H子ちゃん(8歳)の4人暮らし。 Mさんは1962年福岡市で生まれた。私立博多高校を中退し、中州のクラブ勤めを経て上京。東京・麻布十番の焼肉店などで修行した後、88年に福岡市中央区で韓国料理店をオープンさせた。この店は繁盛し、有名人なども多く来店、テレビでも紹介されるほど有名店になった。その後、東区にも別の焼肉店を開店し、売上も好調だった。 C子さんも福岡県出身。九州女子高校を卒業後、94年頃まで化粧品会社の美容部員として福岡空港の国際線ターミナル店で働いていた。MさんとC個さんは高校時代から交際しており、90年5月に結婚した。Kくん、H子ちゃんも生まれ、幸せ家庭を築いていた。 しかし、最初の悲劇が起こった。01年9月、BSE(牛海綿状脳症)騒動が起こり、その煽りを受けて経営していた両店は廃業に追い込まれたのである。 MさんはC子さんの親族と一緒に婦人服販売会社を始めるが、売上が低迷、さらに東区の焼肉店開店のために自宅を抵当に入れて借りた4000万円の返済も滞るようになった。 03年3月、夫婦は婦人服販売業の業績が上がらないことから、C子さんの親族から独立して、衣料品などをデパートに卸す仕事を始めた。その2ヶ月後、Mさんの知人から休眠中の会社「W」を継承して復活させた。C子さんを社長にして、衣料品販売業を本格的に乗り出した。 また失業し、金に困ったMさんは闇ビジネスと呼ばれる仕事にも手を広げていく。事件後、家宅捜索で福岡市中央区のマンションから大麻草が発見されている。Mさんは大麻草を栽培して、売りさばいていたとされている。 またMさん一家は94年から96年にかけて、外資系生保会社と、99年には国内の生保会社と、一家4人の生命保健契約を締結した。保健金額はMさんが1億2000万円、C子さんが2500万円、KくんとH子ちゃんが各2100万円の総額1億8700万円に上り、その月々の保険料は14万円近くになっていた。 ちなみにMさん一家は王、楊、魏の3人とは面識はなかった。 http://yabusaka.moo.jp/fukuokaikka.htm
強襲
凌遅刑
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%8C%E9%81%85%E5%88%91
凌遅刑(りょうちけい)とは、清の時代まで中国で行われた処刑の方法のひとつ。生身の人間の肉を少しずつ切り落とし、長時間苦痛を与えたうえで死に至らす刑。歴代中国王朝が科した刑罰の中でも最も重い刑とされ、反乱の首��者などに科された。また「水滸伝」にも凌遅刑の記述が記載されている。また、この刑に処された人間の人肉が漢方薬として売られることになっていたとされている。この刑罰は李氏朝鮮(朝鮮王朝)でも実施されていた。また、これに酷似したものとして隗肉刑がある。
Mさんの帰宅
日付が変わって翌午前1時40分頃、Mさんが帰宅してきた。愛車のベンツC200に乗って、自宅の車庫前まで帰ってきた時、携帯電話で友人と会話している。Mさんは「今、家についた。これから駐車場にいれるから、後でかけ直す」と電話を切ったが、その友人に再び電話がかかってくることはなかった。家に入ろうとしてきたMさんを犯人達は玄関で待ち伏せていた。工事現場から盗んできた鉄パイプを、いきなり後頭部を殴りつけた後、前に向かって横から額を殴り、さらに左目周辺や頬を殴ったり、全身を蹴ったりした。さらに犯人達は2階で失神していたH子ちゃんを担ぎ下ろし、父親の目の前でいたぶったり殴打しながら、Mさんに何かを聞き出そうとリンチを加え続けていた。だが、Mさんはなにも答えず、「用がなくなった」ということで、H子ちゃんの首を絞めて殺そうとした。Mさんは土下座して、「娘だけは助けてくれ」と言ったが、彼らはこれを嘲笑し、殺害した。さらにMさんの首を白いビニール紐で絞め、気を失った彼を浴槽に浸けて溺死させた。 3人は一家の遺体を運びやすくするため、まずMさんの両手に手錠をかけ、首から足にかけて工事現場で盗んできた太い電線で縛り、H子ちゃんを背負わせる格好で固定した。また、ちょうど血のついて放置しておけない玄関マットがあったので遺体を覆い隠すために持ち出し、車を乗り捨てる際に近くの草むらに捨てた。 3人は一家4人をベンツに乗せ、その車に一緒に乗りこんだ。 博多港箱崎埠頭の岸壁に到着した3人は遺体を海に沈めるために、前もって用意しておいた重りを1個ずつつけ始めた。Mさんの腕とH子ちゃんの足を手錠でつなぎ、その手錠のチェーンの部分に別の手錠をつないで、鉄アレイをつけるなど、万全を期した。C子さんとKくんはそれぞれ両手に手錠をかけ、鉄アレイをつけた。千加さんは服を着ていないので浮き上がりそうだったので、特別に鉄製の重りを針金で巻きつけていた。 遺体を捨てた後、Mさんのベンツを運転して久留米市に向かった。これはNシステム(自動車ナンバー自動読み取り装置)でも確認された。ベンツは「ブリジストン久留米工場」クラブハウスの専用駐車場に乗り捨ててあるのが発見されてい。3人はベンツ放置後、JR久留米駅から福岡に戻った。 20日午後、博多港箱崎埠頭付近の海中から一家の遺体が次々と発見された。これほど早く遺体が発見されることは、3人にとって誤算以外の何物でもなかったはずだ。 なお事件当日の行動については3人の供述をもとに書いたが、3人が責任をなすりつけ合ったり、供述そのものを変えているので、不確かな点も多い。 http://yabusaka.moo.jp/fukuokaikka.htm
3人の浮上
事件に使われた手錠は台湾製でレバー操作をすれば簡単に取り外しができる金属製のおもちゃ、鉄アレイは重量20kgのもので、それぞれ福岡市内にある量販店で売られていた。この店の防犯カメラにそれらを買った人物が映し出されていた。その映像から似顔絵が公開されると、日本語学校の生徒が「同級生(王)に酷似している」と証言、ここで王とその交友関係が洗われるようになった。ここで楊の存在が浮上し、楊の携帯電話の通話記録から魏の存在も明らかになった。 また、遺体に付けられていた直方体の鉄製の重り(重量30kg)は魏が過去に頻繁に出入りしていた女性宅がある福岡市博多区の賃貸マンションの所有会社が非常階段への鉄製扉を開放させておくために特別注文したものだった。 事件後、魏は出国2時間前に空港へ向かう途中の路上で、別の暴行事件により身柄を拘束された。だが、この時すでに王は楊とともに福岡空港から上海に出国していた。この航空券は犯行の3日前に楊が用意していた。2人は中国の公安当局に身柄を拘束されることになった。 供述 「窃盗目的で侵入した。黒幕は存在しない」(王、楊) 「Mさんは高級車を持っていて金持ちそうだったから狙った」 「5月下旬に王から『おまえは格闘技ができるだろう。それなりに荒っぽいが、カネになる仕事がある』と誘われ、楊を入れて3人でMさん一家を襲った。家族4人の首を絞めて殺した後、遺体をMさんのベンツでう実まで運んで投げ捨て、その車も遠くまで捨てに行った。王は誰かに殺しを依頼されていたようで、私は成功報酬として約1万円を受け取っただけだ。残りの報酬はまだもらっていない」 (魏) http://yabusaka.moo.jp/fukuokaikka.htm
出典kyushu.yomiuri.co.jp
公判を終え福岡地裁を出る魏被告
福岡一家4人殺害事件
王被告土下座にも消えぬ怒り 遺族、厳罰求める
出典kyushu.yomiuri.co.jp
福岡一家4人殺害事件
中級人民法院裏門で、通行人をチェックする職員
憤りは収まらなかった。昨年六月に起きた福岡市の松本真二郎さん一家四人殺害事件。遼寧省遼陽市の中級人民法院で十九日に開かれた初公判で、孫たちの命を奪った元留学生二人と初対面した遺族には、日本語での謝罪もむなしく響いた。「頭を下げれば済むと思っているのか」。一年四か月を経ても消えない激しい怒りが、異国の法廷に広がった。 王亮被告(22)は白いワイシャツ、白っぽい綿のズボン姿で法廷に姿を見せた。楊寧被告(24)は、黒いトレーナーに白っぽいズボンをはき、二人ともオレンジ色のベストを着ていた。両足には鎖、両手には手錠がかけられていた。 起訴状が読み上げられる間、楊被告は、検察側の質問に対し、はきはきと答えたが、何度もまばたきするなど緊張が見て取れた。王被告も時折、目元に手をやるなど、落ち着かない様子だった。 犯行現場となった松本さん宅の子供部屋や浴室、廊下に残された血痕などの写真がスクリーンに次々と映し出されると、王被告は終始目をそらし、楊被告も顔を上げようとしなかった。 静寂が破られたのは、王被告の意見陳述の途中だった。突然、後ろを振り返り、約三メートル離れた傍聴席の最前列に座っていた松本さんの妻千加さんの父親、梅津亮七さん(78)に向かって土下座し、約三十人いた傍聴席から驚きの声が上がった。さらに、裁判長に向き直った後、もう一度後ろを向き、日本語で三回、「すみません」と繰り返し頭を下げた。 数日前に遼陽市入りした梅津さんは、公安当局などを回り、両被告の逮捕に謝意を伝え、厳罰を要請したという。公判終了後、「頭を下げて済むものではない。それ以上にひどい目に遭わされた」と怒りが収まらない様子だった。 http://kyushu.yomiuri.co.jp/news-spe/20090427-462876/news/20090427-OYS1T00564.htm
裁判経過
楊寧被告人は1審で死刑判決を受け、控訴棄却を経て2005年7月12日に死刑執行された。一方、王亮被告人は遼寧省遼陽市人民検察院により無期懲役が確定した。 日本で逮捕起訴された魏巍被告人は1審の福岡地裁で事実を認めた後、ほぼ黙秘を通し、死刑判決を受けた。2審では、一転して動機や犯行過程、3人の役割、遺族への謝罪などを詳細に証言したが、控訴は棄却された。上告したが2011年10月20日に最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は上告を棄却して死刑が確定した。 2014年現在、魏巍は福岡拘置所に収監されている。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E4%B8%80%E5%AE%B64%E4%BA%BA%E6%AE%BA%E5%AE%B3%E4%BA%8B%E4%BB%B6
出典stat.ameba.jp
福岡一家4人殺害事件
福岡一家4人殺害事件
日中の捜査共助と問題点
同事件は主犯格2人が中国に逃亡したため、中国との捜査共助が最大の焦点となった。結果的には日本国内の反響の大きさに配慮した中国当局が積極的に協力したため、早期逮捕が実現したが、一方で他の事件では日中間の捜査協力がほとんどなされていない実態や、アメリカ、韓国以外と犯罪人引渡し条約が結ばれていない現状も指摘され、国際化する犯罪に各国捜査当局の対応が遅れている点が浮き彫りとなった。 また、福岡地裁で行われた魏巍被告人の公判では、中国公安当局が作成した王亮、楊寧両被告人の供述調書が日本の裁判で初めて証拠採用された。これまで日本の刑事裁判では、海外の捜査当局が作成した調書は「証拠能力なし」とされることが多かったため、この判断は「国際犯罪の捜査に道を開く」と評価されたが、黙秘権が存在しない中国の調書を問題視する意見もあり、議論を呼んだ。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E4%B8%80%E5%AE%B64%E4%BA%BA%E6%AE%BA%E5%AE%B3%E4%BA%8B%E4%BB%B6
8 notes
·
View notes
Text
目が休まらない
2020.06.25(木)雨のち曇り
いやな夢を見た。
わたしは電車に揺れている。緑の長椅子はまばらに席が空いていたから、多分昼過ぎくらいの設定だったんだと思う。何故か親子連れに挟まって座っている。しばらくすると、右手にいたお父さんらしきひとがうろたえ出した。見ると子どもを抱きしめて顔を覗き込みながら揺さぶっているのだが、子どもは目を閉じて全身の力が抜けているようだった。左手、席の端っこで手すりに体を預けて寝ているお母さんが徐に起きて、目に映った光景をようやく頭で処理できた瞬間、大声で泣き叫んでいた。
この前、親孝行のこととか孤独死のこととか考えちゃったからかしら。夜中地震速報も鳴ってたし、防災アプリが大雨注意で警報鳴ったし、寝覚めが悪い。起きてケータイの時計を見ると6時40分とかだった。友だちからメッセージ来ていて明るい内容だったから、それだけで気持ちが落ち着いた。本当に助かった。
突然に死んでしまったあの子は何歳くらいかはよく分からなかったんだけど、赤ん坊にしてもそれより大きい子どもだとしても、夢診断からするとどちらも良い知らせの予兆ではあるみたい。[参考:https://spicomi.net/media/articles/799]
あの子が赤ちゃんであれば生まれ変わりや成長の象徴(生まれ変わりの象徴って変な日本語)で、子どもであればあの子はわたし自身であり未熟さの象徴らしい。子ども(=未熟さ)が死ぬというとこは、わたしが過去を反省し、生まれ変わることを暗示しているとのこと。まあ言われてみれば。ちょっと悟るの遅いよね。
今日は有給をとってお芝居を観に行った。割と近所に住んでる子の知り合いが出てる演劇。演劇観るのもその子と会うのも久しぶりだ。会場のお客さんも舞台に立つ役者さんも若い子が多くて浮いていないか心配になった。若い女子たち、みんな洋服の袖が肩口あたりまでしかなくて、なんかフリフリしたのついてるし、なんかフリフリしたのはちょっと透ける素材で、二の腕をすらっと見せてた。見る立場だというのに、スマホのインナーカメラで仕切りに前髪をチェックしてる子もいた。わたしは絶賛半ズボン、化粧もしてない。
あれ…?この学校って…、去年まで女子高で、今���から男女共学になったんだよね…?なのにさ、どうして一人も女子居ないの…?いや、僕は別に、いいんだけどね、女子なんか居なくてもさ…。そうだよ、女子がたくさん居ると思ったからこの学校に入学した訳じゃないんだからさ。でもさ…、なんで居ないの?…それから、モテない男子たちによる、女子を探す冒険がはじまった。
未来演劇部公演「ドレミの歌〜男子校版〜」HPより
先生が誰かがいたずらで割った校舎の窓ガラスを片付けているシーンから始まった。その後、ドノウエという男の子、その後にソリマチ、レンゲくんと続々と学生が現れるのだけど、最初は上記のあらすじのように淡々と話していた理屈っぽいドノウエくんも、隠していた欲望という疑問が溢れ出して三人声を張り上げて「女性がいないこと」を嘆いていた。
「女子なんかか弱いし力がないから僕が手伝ってあげなきゃいけないんだー!!」
「邪魔だし、女子なんていたら進学出来なくなっちゃうー!!」
みたいな深夜ラジオの芸人のイケてないエピソードを地でいく感じ。ドノウエくんとレンゲくんは勉学が出来るがこじらせていて、ソリマチくんは良い具合に頭が足りてないから理解できず混乱する。絶叫に次ぐ絶叫、これが開始30分以内くらいかとにかく序盤なもんで、心配になった。役者陣の喉が。
ドノウエくんらはどうやら高校2年で、劇中は2学期の途中くらいの設定だった。学校の前には大きな壁が立ちはだかって外の様子は見えず、彼らは校舎の1階よりも上の階に上がったことがない。校則で禁止されている。でも、彼らが1年時に共学になったのだから、上の2学年は女子だけのはず。でも彼らは学校で女子を見たことがない。なので、ドノウエくんらは女子は上の階にいるのではないかと推測した。先生にも問い詰めるが、先生もよく分かってないようだった。でも、先生は女子を見かけたことがあるという。
ここら辺でミズノくんという風紀委員の男の子が出てくる。今から1時間は校舎から出たらいけないと言う。ドノウエくんらは「女子をそのうちに帰らせて僕たち男子とエンカウント出来ないようにしてるんだろ」と問い詰める。シラをきるミズノくんは風紀委員なので、校則を侵す者を許さない。冒頭の割れたガラスの片付けで残っていただけの先生すらも閉じ込めようとする。風紀委員は常にテストで10番以内に入らなければならず、そのうえ校長先生のお眼鏡に適わないといけない。その選考基準は校長の好みだそう。今出てる男の子らはイケてない役なのにみんな鼻が高くて眉を揃えた垢抜けた見た目なので「校長先生はジャニーさん的な立ち位置なのかな」と勘ぐってしまった。その勘はたぶん外れた。その後全然そんな描写は欠片も出て来なかった。わたしの頭がちょっと穢れてるだけだ。
でもかつてはミズノくんもエロ本を集めてる健全な男の子(中学が同じだったレンゲくん暴露)で、三人から説得され、冒頭の先生も何故か女子探しに巻き込まれる。ここらへんで青いツナギを着た納品業者が、これまた男性なのだけど、その人が荷物を届けに来る。段ボールに梱包されてるので中身は分からないが音楽の先生宛のもの。でも職員室も音楽室もドノウエくんが知ってる1階にはなく、女子が生息してるであろう2階以上。納品業者のためと称して未知の上の階を探索していく。
2階にフワくんという男の子が真っ直ぐ遠くを見つめながら歌っている。フワくんは転校生らしく、他のメンバーが白いシャツにネクタイ姿なのに彼は学ランだった。隣にはシロタくんという唯一白っぽい青という明るい髪色で、FILAの赤いジャージ姿にゴム手袋を両手に嵌めて、水詰まりを直すスッポンを持っていた。で、1階から2階に上がってきたドノウエくんらと出くわすのだ。今思うと、トイレ掃除係は上の階に行ってもいいのかしら。フワくんは転校生で校則のこと知らない��ら上の階にいたのかしら。ちょっとその辺は分からなかった。
フワくんは歌が好きで、モテたいなら合唱部に入れという。「ミスチルを歌え」と真面目にアドバイスするので笑ってしまった。生徒一人一人の名前を読んで、大声で返事するドノウエくんらの右頬を順番に殴り、「でもおれの拳の方が痛い!」と叫んだフワくんに期待した。みんな鬼の形相でドタンバタン暴れ回るのでめちゃめちゃ笑っちゃった。ここでタイトルの『ドレミの唄』がようやく出てきたので、歌が好きなフワくん、しかも転校生だから、ここは彼が中心になって学園、ていうか女性に興味ないふりして女体に興味しかないモテないくんたちを指揮して成長させていくアツい展開になる。そう思ってた。
2階には目当ての音楽の先生はいなかったので、3階に上がる。彼らの学園生活は残り1年と少しなので、1人1曲を完璧にマスターする時間はないと踏んだフワくんは、1人1音、幼稚園か小学校のハンドベル演奏みたいに、全員で音階をつくり演奏しようと提案した。ここで問題が発生、ドレミファソラシは7音なのに、ドノウエレンゲミズノフワソリマチシロタの6人しかいないのだ。先生を全力で説得しにかかるが応じない(部活動の顧問は言わばサービス残業に近いからだ)。何度も説得するのに先生の冷めっぷりは変わらず何故か納品業者の男が「やってあげましょうよ!」と立ち上がるパターンになった。しかも納品業者の男の名はランバシなので、確実にイケてないズの仲間になる奴なのだ。ランバシは納品業者からカントクになり段ボールの中から楽譜を取り出して配る。確か『天国と地獄』、運動会のかけっこでお馴染みのやつ。結局ランバシはカントクで歌わないので、先生を上手く口車にのせて合唱部に入らせた。
イケてないズが揉めているときに、隅の方で納品業者のランバシに「この学校には校歌がない」と先生が話していた。卒業式のときに締まらない、ドレミの歌の替え歌でいいから校歌をつくればいいのに。例えば、「ドはドリームのド」「レはレインボーのレ」などなど、夢と希望いっぱいのちょっとダサい替え歌(本人は至って真面目そうだが)。でも「シはなし!縁起悪いから!」と先生が言うと、イケてないズの中で全く女子に興味がなく合唱に魅かれて付いて来たようなシロタくんが熱く語り出した。彼だけは、未だ絶叫シーンがない。「シ=死」に付いてちゃんと向き合うことが生を感じること。「僕からすると『生まれ変わったら何になりたい』というのは今の人生から逃げている」うんぬんかんぬん。派手な髪もトイレ掃除で漂白剤に触れ過ぎだからというのも判明、見た目に反して敬語キャラであるシロタくん。わたしは結構気に入っている。
下の階から上の階に行く場面に変わるときに、舞台上には女子高生がふたり出てくる。彼女らの腰には数字が大きく載った紙がついている。たぶん紙の番号が「2」なら今のシーンは2階、「3」は3階にいるということなのだと思う。彼女らは一言も喋らないで、何か戯れて袖に消えていく。3階ではシャボン玉を飛ばし、4階では去り際に髪留めを落としていく。そのあとでドノウエくんたちがやって来る。
3階にも4階にも音楽の先生も女子たちもいない。上の階に登りながら「ド!」「ラ!」「シー!」とか担当の音階を張り上げながら『天国と地獄』を歌っている。わたしは益々役者陣の喉の調子が心配になる。ここまでしても女子の姿はない。怒るドノウエと仲間たち。が、ソリマチくんがシャボンの匂いに気づくと、「僕たちの合唱を聞いて気になってるのではないか」と彼らは歓喜。その上の階では女子が使いがちな髪留め、おそらく100均でよく見かける黒い針金みたいなやつを発見し、女子の本体に着実に近づいていることを感じる。
遂に、校舎の一番上の階まで来てしまった。でも彼らには女子を見つけられない。ここまで探したのに会うどころか視界にも映らないので、ドノウエくんらは愕然とするしかなかった。実はここで、うなだれて床しか見えなくなってるドノウエくんたちの後ろに女子2人が立っているのである。たった一人、シロタくんだけ気づいて、腕をあげちらちら指さして知らせようとするのだが、他の子たちも先生もランバシも気づかない。
「まだ屋上があるじゃないか」
ここで先生が言う。あれだけ合唱部に入るのに全く乗り気でなく、たまたまオフの日に忘れ物を取りに来たら騒動に巻き込まれただけの冷めた先生が、彼らと行動を共にしたことで意識が変わったのか、まさかそのセリフを言うとは思わなかった。立ち入り禁止のロープを外し、屋上へ。
ここで怒涛の合唱が始まる。ドからシまで横一列に並んで座る。観客と演者がまるで戦前のように対峙する。自分の音階を椅子から立ち上がって叫んで、また座る。しかもこの屋上での合唱は主旋律だけでなく、ハモリの部分とおそらく副旋律とかいうのも「ド!」とか「ラララララ」で表現している。大の男7人が黒ひげ危機一髪のように飛び上がりながら歌う、というか叫ぶ様子はもうすごい。なんか異様。上下の動きしかしていないのに、声はこちらに向ってすごい量のが来る。ギャートルズのロゴみたいな感じ。ここのシーンで笑いまくった。
歌いきり後ろを振り向いて、シロタくん以外の男子も、二人の女子に気づく。彼らは合唱が届いたのだと確信し、成長した己に気づき、同志を讃え合う。『蛍の光』がかかり、男子も下校していい時間になった。彼らは帰って行く。ここでゆっくり暗転し、合唱でも歌わず『蛍の光』でもなく、何か賛美歌のような歌が流れた。「アーメン」と最後に言うのが聞こえた。
ここで物語が終わるのかと思いきや、舞台が明るくなって先生と椅子に座っているランバシが立っている。ランバシは先ほどまでずっと着てた青い作業着ではなく、黒いジャケットで首からペンダントみたいのをぶら下げてピカピカの靴を履いてたから、最初誰だか分からなかった。「あ、このひともしかして校長だったのか!?」と思ったけど、どうなんだろう。何か違うっぽい。
奥から例の女子が2人出てくるが、先生は「ああごめん、もう合唱部は解散しちゃったんだ」と言ってたか、そう言うと女子生徒は帰っていった。ランバシも退出すると、急に先生の顔色が変わった。たまにはっきりした物言いはするけど喜怒哀楽どれにしても表情が変わらない、何を考えているか分からない人がいると思う。そういうひとは常識はあるので敬語を誰にでも使えるのだが、そんな感じの先生。その先生が苛立ちなのか不満なのか、強張った顔になって怖かった。次に何かを投げるジェスチャーをして、窓ガラスが割れる音がする。
「また閉じ込められちゃうよ」で、この物語は終わる。
セリフを一言一句覚えてるわけじゃないし、話を前後して覚えてしまってるかもしれないが、完全にコメディだと思ってたからこんな気味の悪い終わり方をするとは思わなかった。冒頭で割れた窓ガラスを掃除してる時点で、後で何か関わってくるじゃないかと思ったけど、まさか先生が自作自演してたなんて。なんで? なんでランバシは着替えたのか? 本当にただの納品業者だったのか? 何で女子は一言も言葉発さなかったのか、何で背後にいて見えなかったとはいえシロタくんしか最初女子の気配に気付けなかったのか。解散って卒業しちゃったってこと? 最後の暗転時に聞こえた「アーメン」は? 「閉じ込められる」の意味の本質は?
ひとつ気になるとどんどん引っかかるところが出てくる。正直合唱部なのに、わたしが学生時代に歌った合唱曲は1曲も出てこない。クラシック(オペラ?)を歌わせたのか。あまり意味はないのかもしれないけど、この学校、元々はキリスト教系の女学校か何かだったんじゃないか。わたしの穿った見方をすると、「アーメン」とか「閉じ込められた」とかそういう言葉から登場人物は誰か死んでいる設定なのだと思う。ドノウエたちは新入生、元は外部の人間だから生人だろう。2人の女子生徒は一言も喋らなかったから、単純に考えるとこの2人は死んで地縛霊かなにかなんじゃないか。シのシロタくん、しかもこの子は急に死生観を語り出したりしたので、この子は霊感を持っている。だから、最初シロタくんしか女子生徒の存在に気付けなかった、と辻褄が合う。けど、最後の合唱後にみんな女子生徒が見えるようになったこと、先生はこの探検の前から女子生徒を見たことがあったこと、「閉じ込められた」と言っているのは先生や男子生徒だったこと、これはまだ説明できないし「地縛霊が女子生徒」という推測から矛盾している。先生も見える人なのか? エクソシスト的な? うーん、わかんない。
こんだけ長く書いたのは、この説明でなんとか劇の大枠を考察してわたしと謎を解いてくれるひとを探しているからだ。物語が終わって、舞台に誘ってくれた子ともあーじゃないかこーじゃ���いかと探り合って見たけど、さっぱり分からなかった。謎は深まるばかりだ。すべてに意味を求めすぎて、こんがらがってるのかもしれない。
演劇が終わると、電車で仙川に行った。ふたりともこの周辺に住んでいるので、先日見つけたエモいリサイクルショップを見に行こうと話したのだ。仙川には演劇の学校があるってのもこの散歩で知った。意外となんでもあるぞ、この街。
残念ながらリサイクルショップはまだ空いてなかった。しかも今日までが閉店期間。明日だったら入れた。きーーー、タイミング悪い。「また今度リベンジしましょうねえ」と言って、とりあえず何か座って食べられそうなところを探すけど16時過ぎだからお酒を飲もうとするとまだ開いてないお店が多かった��行くあてもないので、おすすめのインドカレー屋さんに入った。16時代にだけどランチがやってて、そのランチをわたしたちは晩ご飯にした。ややこしい。こんな時間に晩ご飯なんて、おじいちゃん家に遊びに行ったみたい。
我慢できなくてビールを飲んだ。背徳感。しかもナン1枚おかわりして半分こして食べた。背徳感。わたしはランチセットのビール(+300円)にもう1本黒ビールを頼んじゃったので、ありとあらゆる大きさの小麦でお腹がパンパンになった。美味しかった。
それでもまだ18時前で胃袋の中身を消化すべくテキトーに二人で散歩した。向こうが聞き上手なので「最近、わたし世界史ベンキョーしてんすよ!」って話をしっかり聞いてくれてお酒も入ってたし気分が良くなってしまった。それでも気になることが満載で、世界史の最初の最初は歴史学のほかに考古学や地質学要素もあって、すごく面白かったんだもの。まだ最初も最初、ドリルの見開き2ページめ。ひとつ勉強すると、ちゃんと理解するために他のこともやりたくなるから、勉学というのは際限がない(元々知識量はないのもある)。
帰りの電車でゲームしたいと話した。わたしはゲーム機を一切持ってないけど、向こうは持ってるらしい。ゲーム強いひととゲームしたいから、気長に超内輪大会を待つことにする。
1 note
·
View note
Photo



Tumblrユーザーボイス: 福島県・株式会社BANKSさん。
家族がいつも暮らす家は、とっても大切なもの。快適で過ごしやすく、清潔で心休まる家がいいですね。今回のインタビューは、個人住宅や店舗の設計・施工のほかリフォームや什器・家具の製作なども手がけるBANKSさんです。ブログ「BANKS.inc」では、それぞれ進行中の住宅や店舗の施工状況について、たくさんの写真を交えながら解説されています。普段あまり見ることのない現場作業の様子や、家ができる/リフォームされて生まれ変わっていく様子をじっくりと見ることができる、まさにインテリア・建築好きにはたまらないブログです。どれだけ心を込めて家が作られているかを知れば、自然に愛着も湧くし、日々のお掃除にも熱が入るはず。愛情を込めて今も未来も価値のある家を残すべく日々活動する、BANKSさんのお話をどうぞ。
- BANKSさんの考える、理想の家とはどんなものでしょうか。
日本の建物は、1000年前から建っているものもあれば30年で壊されてしまうものまでさまざまです。価値があると思う人がいれば壊さずに次の世代にとっておけるものですが、ほとんどの建物は価値がないものとして壊されてしまいます。私たちの理想とする家は、今も未来も価値があると思ってもらえる家です。
では、価値がある家とは一体どういう家なのか。価値には3つのレイヤーがあると考えています。1つ目は、お客様から見た価値。2つ目は、私たちが価値があると思っているもの。3つ目は社会や地球環境という、当事者の外側から見たときの価値です。お客様も私たちも、お互いに自分本位になりすぎず、それでいて環境配慮や社会貢献をきちんと考えた、ものづくりの観点からも品質の高い家が理想です。
また、身の回りにある木や石や金属で無理なく家を建てるということも大切だと考えています。日本には豊かな自然があり、その自然を活用した清潔な住まいを発明した先祖の知恵には驚かされるばかりです。伝統の知恵を自分たちなりに消化し、少しでもその知恵を発展させるような家を建てることを目指しています。石油製品は非常に便利ですが、安易に石油に頼らなくともいい家を建てられる、もしくは頼らないほうがいい家になる、というようにしていくことも大切だと思います。

- 設立からまだ数年の若い会社ということですが、BANKSさんはどんな経緯で創設されたのですか?また、スタート後の率直な感想を聞かせてください。
前職で気のあった2人で独立しました。福島県は非常に住宅会社の多いエリアではあるのですが、自分たちが本当にいいなと思えるような家を作っている会社がなかったため、自分たちで始めることにしました。
周りの方にはたくさん「大変だよ」と言われましたが、おかげさまでいまだ大変な目には合わずにすんでいます。立ち上がりは事務所を作りながら仕事を並行してやっていました。不安や悩みを感じるようなことはなかったような気がします。忙しかったからでしょうか。
- 事業内容がとても幅広いですが、どのような規模・体制で一連のお仕事を行われているのですか?
弊社のスタッフは5名です。「住まいを作る」が仕事なので、家の建物だけでなく、家の中身(家具)と家の外見(庭)も含めて、トータルで作っています。既製品を取り付けるだけ、ということに抵抗があるため、家具も全て作れる体制を取っています。
具体的には、弊社で図面を描き、信用できる職人さんに製作を依頼しています。家具、建具、大工、左官、カーテンなど、それぞれに専門の職人がいて、独自に開拓しておつきあいをお願いしています。


- 日本は昔から地震など天災が絶えず、最近では大雨などの極端な悪天候も増えています。このような点について、人が住む家を作る会社としてどういう取り組み・心がけをされていますか?
地震と湿度は家の大敵です。大きな地震がきても構造的に心配のない家、これは建築屋として達成すべき当然のことです。建築基準法的に耐震クリアしているだけでなく、構造材も特別にこだわったものを使用しています。森林大国である日本では木を使って家を建てることが自然ですが、木は乾燥のさせ方によって割れやすさが変わります。BANKSでは広く普及されているKD材(人工乾燥材)よりも、木の割れにくさ、曲げ耐性など粘りのある天然乾燥材を構造材に使用しています。さらにプレカットではなく、大工さんによる手刻みで構造材を作り、伝統的な木組みで構造を作っています。地震をしなやかにかわし、木組みが外れないような知恵が詰まった、日本古来の家の建て方をしています。
湿度については、雨だけでなく結露などで湿気が壁の中に溜まってしまうと、構造材を腐らせたり、悪影響が強く出ます。特に最近の高断熱高気密の家は室外と室内の温度差が大きいため、壁体内結露が発生しやすくなります。また、浴室や料理などで発生した室内の水蒸気も、壁体内結露の原因の1つになります。弊社では、壁体内に通気層を設けて湿気を十分に外に逃がす機構と、調湿効果の高い素材(無垢材、漆喰、セルロースファイバー断熱材など)で家を作ることで、室内の快適と構造の安心を両立しています。調湿効果の高い素材で家を建てると、1年を通して室内湿度が50%前後で安定し、とても快適な空間になります。
- 最近は古民家などを自分でリフォームされる人も増えています。そのようなDIYの動きについてはどう思われますか?
DIYをすることで、家の建て方や素材について非常に理解が深まり、「プロに依頼すること」と「自分でできること」を区別する力が育まれます。この線引きが明確になることはとてもいいことだと思います。多くの友人たちがDIYで家づくりをやっていますが、要所要所でプロの力を借りており、これからの家づくりの1つのスタイルになると思います。
私たちの家の作り方は、専門職人による仕事の集積を大事にしているので、DIYで再現することは難しいです。今までのお客様には建築関係の方も多く、DIYもできる方がいらっしゃいましたが、そういった方にほど、より私たちの家の作り方を喜んでもらえたり感心してもらえたりするように感じています。

- 「今も未来も価値があると思ってもらえる家」を建てる上で、BANKSさんが心がけていることはどんなことですか?
住んで気持ちよく、見て美しい空間づくりです。性能は現代の最高基準を目指し、使う素材や技法は日本で伝統的に使われてきたものを積極的に取り入れています。100年後に、当時のベストだねと言われるような家を目指しています。そういったものづくりには、最新でなくなったとしても価値が宿ると信じています。
(画像:@banks-house)
136 notes
·
View notes
Photo
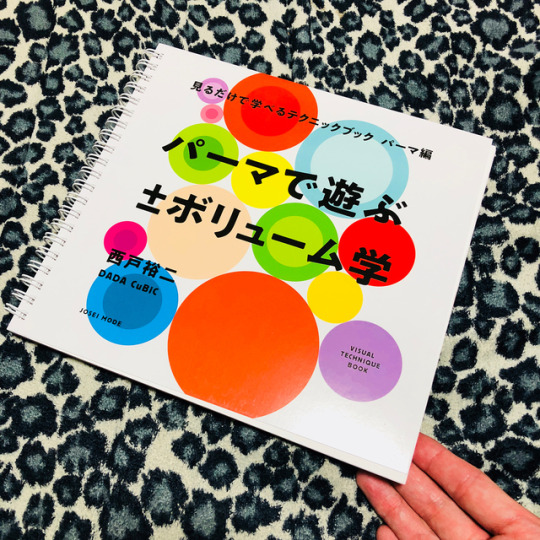
BOOKcollection📚 いつからだろう? こういう業界誌が好きになったの。 新しいのが出るとつい欲しくなる。 ✩ 技術系のテクニック本 ✩ 第一線で活躍する美容師の 頭脳を分析するもの。 ✩ 今を生きる美容師に必要な 要素を教えてくれる(~力)って 言う本 ✩ 1人のお客様を幸せにするためには 色々な力が必要で... 不器用な僕は頭で分からないと中々 行動���変えられない... だからこういう本をいっぱい読んで 色々な知識が増えていく。 もちろん全部が全部還元される訳 ではないけど...知らないことを 知ってるのが嬉しいだけで。 これからの時代はAIが色々な ところで活躍してくるだろうから AIなんかに負けない。 人間にしか出来ないっていう こだわりが大切な時代かな。 ✩ 作品掲載サイトが始まりました!! 今はまだ少ししかありませんが どんどん更新していきます。 インスタには載せきれてない 写真なども掲載していく予定です。 僕の創る世界観が好きな方!! 僕の創る世界観に興味がある方!! アンチはお断りです。 トップのリンクから飛べます。 作品見た方はコメントを是非 DMに下さい。 今後の作品の世界観の参考にします。 ✩ 実は、LINE@アカウントあります! LINE@ID @vci5997k @も忘れずにね!! お友達に是非追加よろしくお願いします。 一言メッセージいれてもらうと とても喜びます。 たくさんのお客様のヘアパートナーに なりたい!! ☆ ✩ ★ ♡ ♥ 最近TikTokにハマりすぎている(笑) Instagramサボり気味💦 △ ▼ ♢ ⿴ ⿻ ⿸ #愛知県名古屋市名東区の美容院 #ヘアメイクアーティスト #美容師的ポートレート #インスタグラマー #インフルエンサー美容師 #1日24時間365日美容師服部裕一 #マカロン掲載 #u1styleworld #ヘアアレンジ #おフェロ #フェミニスト #おフェロ系おフェミ系が得意です #テレビ出演したい #モデルみたいな美容師 #ヘアカタログに掲載されたい #自己顕示欲解放中 #ちなみに彼女全力で探し中 #撮影依頼受付中 #撮影モデル大大大募集中 #女の運命は髪で変わる #美容の最先端を名古屋から発信 #フォローミー💕 #インスタ映え #フォトジェニック #職業は美容師 #趣味はカメラ #iphoneカメラで撮る世界 #モデルさんと繋がりたい #instagram #instagood ✩ あなたの綺麗を叶える魔法の言葉 『インスタをみた。』ですよ。 あ〜美容師って最高で最幸かよっ✩ (Nagoya-shi, Aichi, Japan)
#インフルエンサー美容師#インスタ映え#フォローミー💕#ちなみに彼女全力で探し中#テレビ出演したい#美容の最先端を名古屋から発信#撮影モデル大大大募集中#女の運命は髪で変わる#美容師的ポートレート#モデルさんと繋がりたい#instagram#ヘアメイクアーティスト#自己顕示欲解放中#趣味はカメラ#ヘアアレンジ#フォトジェニック#iphoneカメラで撮る世界#愛知県名古屋市名東区の美容院#おフェロ系おフェミ系が得意です#撮影依頼受付中#インスタグラマー#職業は美容師#フェミニスト#マカロン掲載#u1styleworld#モデルみたいな美容師#ヘアカタログに掲載されたい#instagood#1日24時間365日美容師服部裕一#おフェロ
0 notes
Text
ある画家の手記if.54 告白
途方もないことなんだ、きっと
僕が水を取りにいった僅かな間に香澄は自分の部屋に入っていってしまった。
扉の前まできて、ドアノブに手をかけようとしたら内側から鍵の回る音がした。 ドア越しに香澄の謝る声が嗚咽に塗れてくぐもって届く。 僕は昔から怒るときは怒るから、慣れてて頭が冷えるのも早かった。でも香澄は明らかに慣れてない、大声で叫んだり、あんなにひどく泣いたり。 一人になって落ち着きたい…? 今日はもう疲れたから休みたい…? 「……………」 …自分から、部屋にこもったってことは今は僕と話したくもないし、話さなくたってただ寄り添ってるだけも、許してもらえない 閉め出されてしまった ほんとうに 脳裏によぎる 声が出なくなったアトリエ 香澄は咄嗟に自分の顔を傷つけた …ドアの向こうで今またそんなことに…なっていたら 「……香澄…」 ……約束 守ってくれるって 信じてここで待てばいいのか でも 香澄を守るためなら 香澄を疑ってかからないといけない? 香澄の口から自発的に出てこないたくさんのものを僕がすべて想像するのは無理だ だからちゃんと話したいんだ でも話してるって言えるのか、今の僕たちは 僕は勝手に言いたいことをなんとか言葉にしたけど きっとそれもうまく伝わらなかった どうして いつも伝えたいものは 言葉にならない? 香澄はどうして話してくれない? 僕を 巻き込まないため………
キッチンに戻って、遅いけど夕飯を一人分作った。香澄は食べてきてないようなことを言ってたから、お腹が空いたら食べられるように。 炒めたご飯をふわふわの卵で包んで形を整えてオムライスでかいじゅうくんの顔を作った。野菜で背びれを添えてケチャップで目や笑ってる口を書いた。林檎をうさぎの形に切って並べた。 他にもいくつか食べやすそうなものを作って、テーブルから香澄の部屋の方向に向くように全部きれいに配置して上から蓋をかぶせた。 メモ用紙にかいじゅうくんの泣いてる顔を書いて、一言「ごめんね」ってだけ文字で書いた。書いてる途中でぽたぽた目からテーブルに涙が落ちて、急いで拭った。
財布とケータイだけ持って、薄手のコートを引っかけて、深夜を回った暗い外に踏み出す。 ドアを閉める前に一度だけ部屋の中を振り返って、香澄の部屋のほうを見つめる 「…約束 守ってくれるって信じてるよ」 小さな声で震えるように囁いた 香澄が無事に部屋から出てくるのを確認できるまでずっとドアの横に座って待っていたかった。 でも香澄が出てきてくれても僕がなにか変わっていないと堂々巡りなんじゃないか。 そう思って、ただ部屋の中で待っているだけじゃ僕は何も変わらないと思って、でもどこへいけば、どうすれば、今の僕たちに必要なことを知れるのか、見当もつかなかった
そのままマンションを離れて、あても目的地もないけど夜道をなるべく明るいほうへ歩いた。そっちに希望でもあるみたいに。
しばらく歩いたところで、駅の裏あたりまで来たら道の端のほうで華奢で小柄な人影が地面に倒れていて、数人の大人の男に囲まれてるのを目にした。面白半分に体を靴でつつかれたりしている。 駅の強い照明で全部シルエットでしか分からなかったけど咄嗟に男たちの間に割り込んだ。僕の背が高いからわざわざ喧嘩沙汰にしなくても割り込むだけで退いてくれたり逃げてくれる場合も結構ある。 今回も僕に自然と見下ろされる角度になった男はまわりの数人を引き連れてさっさとどこかへいってくれた。 息をついて倒れてる人を見て「ーーーは…?」…思わず低い声が喉から出た。 人影はよろめきながら起き上がってとなりに転がっていたギターを掴んで立ちあがった。 「ん? んん? …なんだ、めいろーじゃん」 暗い中で僕の顔を凝視したと思ったら失望したみたいな声で不平を言われる。たしかに小柄で華奢…だけどこれに助けなんて必要なかった。 家から出てきてまで、僕なにやってるんだろ… 「! なんだお前んちこっから近いのかよ!今日泊めろ、降りる駅まちが「嫌だ。」 拒否。どんな事情があったって知るか、カルカッタの路上で転がってても平気で生き延びるやつだ。 「ちっ、つまんねーやつ」 僕だって。お前は嫌いだ。 以前となにも変わらない態度や仕草。僕はギターを担いだ小さな体に背を向けて、さっさと家のほうへ歩き出す。 「…………。」 「…〜♪」 「……。」 「〜〜♪」 僕の五メートル後ろくらいを歌声がつけてくる。 「なんでついてくるんだ、強引にうちへ来たって僕が絶対入れない!」 「前のアトリエは出入り自由だったじゃん、なんで急にケチってんだ」 「家族がいるから勝手に入ってほしくない、…っ、お前こそ…」振り返って睨みつける「なんなんだ…っ、七ちゃんが…死んだのに…!」 「まーたそれか」僕以外にも言われてるのか…当然といえば当然か いつもヘビみたいに���タニタ笑ってるやつがちょっと真顔になって続けた。 「それ天地は万物の逆旅にして光陰は百代の過客なり、しかして浮生は夢の如し、歓びを為すこと幾ばくぞ」 「……李白?」 「へえー元ネタ知ってんの? ひいじいちゃんのザユーのメーとかいうやつでほんとはもっとなげーんだけどあんなん覚えきれねえ。最初のとこだけは音がきれいだから覚えた」 僕が知ってるのは兄が教えてくれたからだ。 「……古人燭を秉りて夜遊ぶ、良に以有る也。…僕たちが夜中まで遊ぶ仲なもんか、なにが言いたい」 忌々しく小さな丸い頭を見下ろして聞く。 「そのまんま。時間はそう長くねーから」 「…僕はもう画家じゃない」 「おまえのそんな線引き知らね。誰だっていつだってなんだって可能だ。しかして浮生は夢のごとし、俺たちに与えられた時間は俺たちが作れる無限の美に比べて短すぎる、だから疾く、人生より疾く、疾ぶように生きるんだよ」 「……それもひいおじいさんの言葉?」 「ふはは、まあだいたいそんなかんじ。」 踊るように跳ねながら僕の後ろから横にきて、目の前に回り込んできて、真正面から見据えられる。 この目が苦手だ、大きく見開かれて爛々として、いつまでも永遠に燃える���火を振りかざしてるようで。柔らかな陽光じゃない、神の下から人間が欲して掠めとってきた炎。何もかもとっくに暴かれたあとみたいな気持ちになる 「ーーー伝えたいことがうまく伝えられない。伝わってたとしても僕になにも話してくれない。僕を守ろうとするから。一緒に守らせてくれない。僕はどう変わればいい」 勝手に口をついて考え続けてたことがそのまま出てきた。 するとあっけらかんと返された。 「なに焦ってんの?なんも知らねーけど手前が空回ってんのはビシビシ伝わる」 人生は短いなんて言った舌の根も乾かないうちにこうだ。焦るだって?僕が? 「伝わんねーときは聞く側の準備がまだ整ってねーから。なのにそこに伝えたい内容ばっか注ぎこんだら相手パニクるだろ。おまえが早く伝わってほしいだけなんじゃん?まずはちゃんと伝わるための足場が相手の中に組み上がるのを手伝いな」 「……………」 「ちゃんとキャンバスに地色塗ってマチエール作って次の色がより美しく映えるように地がしっかり乾くまで待つときは待つだろうが。絵を描いてたらおまえも自然にでき…てなかったかもなぁむちゃくちゃな速筆野郎だったの今思い出した、まんまかよ、やっぱ手前も変わったほうがいいな」 そこまで言ってひとしきり笑われたけど、ーーー香澄に僕の言葉がちゃんと伝わるためにはその前に香澄にも準備が……要る。僕は…とにかく話さないとってばかりで……香澄のことを…待ってないのか… 「チッ、ガラじゃねーこと言ったー」 「…自覚あるのか」 「守るの守りたいのなんて途方もねーこと言いだすからだぜ」 その目は珍しくどこか遠くを静かに見ていた。それだけで、失ってしまった人間なんだって痛いほど理解せざるを得なかった。戻らない、七ちゃん。 途方もないことなんだ、きっと 誰かを守りたいなんて それでも 僕はーーーー
日が昇ってあたりはすっかり明るくなった。 次の角の道で行屋は別の友人を道の向こうに見つけて、そっちに泊まると言って走り去った。 僕も家に戻る。マンションはすぐそこに見えてたから早く帰りたい…けど…ここで迂闊に走って怪我を悪くするのが僕の悪癖か…と思ってゆっくり体を労って歩く。 僕はまだ失ってない。まだ守れる。一生守る。 香澄と一緒に守っていきたい これまで二人で作ってきた、僕たちがこの先も一緒に居るための道を
「ーーーーー……」 帰り着いても部屋はしんとしていて、出てきたときのままみたいだった。 テーブルの食事も蓋を取ってみたけど手付かずだった。 香澄の部屋の前にいってドアノブを回したら、回った、鍵がかかってない… 「………」 ーーー僕はもうそばにいってもいい…? 寄り添うことを、許してくれる? 静かにノブを回して部屋に入る。ベッドに近寄ってみると香澄はおとなしく眠ってた。香澄の顔の隣、ベッドの横の床に座り込んで、香澄の顔にかかった前髪をはらう。 綺麗になった傷のない顔。閉じられた瞼の上あたりに少し名残があるくらい。ほんとうに別人みたいになったね。 実はまだ少し見慣れてなかったりする、今でも僕の頭に最初に浮かぶ香澄の像はあの傷痕を抱えた顔で。それでもこうやって髪の毛を撫でながら、ああ 愛しいなって気持ちでいっぱいになる。 腕を回して香澄の頭を横から大事に抱き込むみたいにして、体をベッドに寄りかからせて脱力して、夜通し歩いて疲れたのか、その姿勢のまま僕も一緒に緩やかに眠りに落ちていった。
香澄視点 続き
0 notes