54h4r4
82 posts
Don't wanna be here? Send us removal request.
Text
202506
29歳になってしまった。年を取ったってことは死に近づいたってことですよね。死、怖え~~~。
死が怖い。死が齎すであろうことを受け止めきれない。自身の死について、それが訪れた瞬間に過去も未来も無くなってしまうと考えている。事実は存在せずあるのは解釈だけであるというように、モノの存在とは自身という主体がそれを認識することにより成り立っている。死とは、その主体を失ってしまうことではないだろうか。死はあらゆる認識を僕から喪失させる。今この瞬間だって例外ではない。それが何よりも怖ろしい。
死が奪うのは未来だけではない。主体なき未来では過去を認識することもできない。だからそれは過去の己にも、見渡す限りの世界にも遍く行き届き、認識下におけるすべてを無に帰してしまう。そこは思考の限界であり、それ以上は語りえぬものである。故に想像による恐怖だけが残るのだ。
死��前提にした生の在り方を肯定できない。そのすべてを肯定してしまうことは今を生きる意味すら奪ってしまう。能動的に死を望むことは、それが未来のことであったとしても今の自分を殺すことに他ならない。だから今を生きたいと願うのならば、未来にも生き続ける意志を持たなければならず、未来に死ぬことを決めたのならば今すぐにでも死ななければならない。
公然の事実として、人には老衰や事故のような避けられない死がある。これまで書いたことを飲み込むのであれば、すべての人間は今すぐにでも死ななければいけないことになる。暴論、そんなものは知らない。避けられない未来には目を瞑るしかない。すべては今を生きていてもいい理由を手繰り寄せるための思索なのだから、そこに厳密性は必要ない。神の創った楽園に行こうとは思わないから、そこは曖昧にしておく。そうでもしなければ、これまでのすべてが無駄になってしまうではないか。
曖昧さは心地いい。けれどそれは己を脅かしもする。時折、現実逃避に過ぎないかもしれないとどうしようもなく自覚する瞬間がある。希釈を繰り返し誤魔化し続けても、それが溢れ出る源泉を止めることはできない。ゆえに焦点はずらしたままに留めておけばいい。その方が何かと都合がいいのだから。
0 notes
Text
202505
ずっと遅れて夢を見ている。
先月からの延長で、思っていたよりもだいぶ前に出るような仕事をしている。新しい領域に踏み込むときにはそれ相応の負荷がかかるもので、かなり久々に”詰め”の機会をいただくことがあった。圧力をかけられた際の特有の感覚といって伝わるだろうか。血の気が引くとともに体感時間が限りなく圧縮されてゆき、目の前の状況が幾重にも反芻されるあの感覚��ああ、たまらねえぜ。そのような胸がきりきりするような状況に対しても奮起できる性格でよかったと思う。挑戦を試されるような機会にはそれがある程度苦しいことであってもやってやろうという気概が湧いてくる。それが自身の成長に繋がると信じている。不確実な世の中だからこそ、己という最も確実な資産の投資に重要な意義を感じる。昨今はそういった理由で高学歴な人たちからコンサルタントのようなジェネラリスト職が人気らしい。VUCA時代が叫ばれるようになってから久しく、ポータブルスキルをキャッチアップすることの重要性はプレゼンスを増している。一つの仕事に安定を求められなくなった今、あらゆる環境でバリューを出していくために自身をストレッチしつづけることがキャリアデベロップメントにおけるリスクマネジメントのベストプラクティスとなるのだろう。本日のカタカナ語大会はここまで。
明確な目標に向かって走り続けることでしか生を実感できない。それでしか存在意義を感じられない。どうやら僕はそのような人間らしい。だから試されることに喜びを見出してしまう。幼いころから愛してやまないゲームはまさにそのようにして出来ている。ゲームとは、ストレスからの解放を楽しむ遊びだ。敵キャラクターや謎解きというストレスに対し、新たな力の獲得やストーリー展開のような明確な報酬がある。それらが次から次へと趣向を凝らしやってきて、プレイヤー、すなわち僕のことを試し続ける。そういうものに対して僕は異様な執念を燃やしてしまう。一度始めたストーリーはクリアするまでやめられないし、レート戦があれば上級者と言えるような階級に到達するまで戦場から撤退することはあり得ない。要は何かを追いかけているのが好きなのだ。それが届きそうで届かないものならなおさら。目の前に人参をぶら下げられた馬のように、遠ざかろうとする報酬があれば思わず走り出してしまうことを止められない。そうして地面を踏み鳴らすことだけでしか、この身が脈打っていることを実感できないのだ。
ふと、脳から分泌される麻薬が枯れたとき、いつまで自分は走り続けなければならないのかと我に返る時がある。苦しい思いばかりして一体何になるというのだろうか。何かに追い立てられることだけを縁に生きてしまう人間の辿る先は危うい。不意に立ち止まったとき、必死に走っていたはずの道が何だったのかすら分からなくなってしまいかねない。初めからそれだけでしか生きられない人などごく僅かだろうと思う。だが、日々を忙殺され続ければ走り続けること以外の余力など失われてゆく。ものの在り方を考えるというのは、ゆとりある者にのみ許された贅沢である。だから、走ること以外の余力が失われてしまったものにとっては、その慣性に従うことが精一杯の選択なのだ。そういった人々が有り合わせで掲げる理由が成長とかやりがいといった無形の報酬だ。人は誰しも、何かに縋らなければ生きていけない。それが自らの思想であれ、誰かの宗教であれ、危ない薬であれ、生きていくに足る理由がなければ途端に壊れてしまう。アウシュヴィッツ強制収容所で過酷な日々を送ったヴィクトール・フランクルは、極限の状況下であっても自らの存在には意味があると希望を持つことで耐え抜いたという。いかに悲観的な状況であれども、能動的な楽観視によって人はどのような状況をも受容することが出来るのだ。そのような人の持つ性質を素晴らしいと思う一方で、それが孕む無惨な可能性が僕にはあまりにも怖ろしい。
成長ややりがいといった言葉はあたかも我々の身に寄り添っているように聞こえる。だがその実はどうだろう。その道を走り続けることは本当に自身の成長につながるのか、そのやりがいは本当にあなた自身が感じているものなのか、その先に果たして幸福はあるのか。世の中は停滞することに対して厳しい。何も変わらないままでいるということは相対的な退化だ。だから、走り続けるものに対して社会がかける声は”まだ足りない”の一言だけだ。そういった言葉に真正面から向き合って耳を傾けてしまうような馬鹿正直な人間は、死ぬまで誰かが作った閉じた道を走り続けることになる。それは緩やかに足元までやってくる。強制収容所のように限界を超えるようなことを強要はしない。されど限界ぎりぎりのところを走り続けるよう巧みに人を誘う。人は誰しも劣等感を持っている。”もっとできるはず”と期待を込めた言葉はそれを強く煽る。はじめは自分の道を走っていたつもりでも、限界ぎりぎりで走り続けていればやがて正しい認知は歪められていく。それは悪しきも���であるとは限らない。だが、自らのあるべき幸福を追い求めたいという心理と、積み上げられたキャリアが生むサンクコストとが生み出す不協和が、自由であるべき自己を喪失させる。そうしていつしか、誰かの期待に応えることが生きがいであるかのようにすり替わる。それが悪いことだと言いたいわけではない。そこに当人による本来の意思が存在しないことが問題であり、故に僕はそれを畏怖の対象とするのだ。
誇りをもって生きたいのであれば、人は夢を持たなくてはならない。そして、それをどんな時も手放してはならない。空っぽな人間が駒となるのは世の摂理だ。自分の人生を生きていない人間が他人に利用されるのは当然の成り行きだろう。だから、邪な誘惑に唆されてはならない。走る道の舵を切るのはいつだって自分自身でなくてはならない。結果として、それが他者の思想や宗教と結びついても構わない。だが、そこには必ず自らの確固とした意志が介在していなければならない。走り抜けた先にある幸福は、自身で定義出来なければならない。そのために指針となる夢や希望を、人は無理矢理にでも自分の手で掴み取らなければならない。それが自らを由とするということなのだ。
自己実現のために何をすればいいか、それが見えてきている。普通の人と比べれば大きく出遅れてしまったかもしれない。だから未だに青臭いことばかりを繰り返している。だけど、もう少しだけこのモラトリアムを続けたい。美しさに触れていたい。熱を帯びていたい。点だけを散りばめてきた人生で、ようやく線を引くために走り出すことができたのだから。
好きなことで喜び、好きなことで悲しむ。そんな生き方に、初めから憧れていたんだと思う。
1 note
·
View note
Text
202504
優しい人間にならなくていい。
早いもので、転職をしてから1年半ほどが経つ。来たばかりだと思っていた現場でも矢面に立つ動きを任されるようになり、新しく入ってきた人の面倒も見るようになってきた。そうした変化は当然僕だけに限らず、僕の上に立つ人もまた新しい人となった。
その人は真面目を絵にかいたような人で、肩の力が入っているのがオンライン越しにも伝わるような人だ。二言目にはごめんと口をつくのが癖になっていて、いつも慌ただしく、話すとき妙にへらへらすることがある。1を聞くと10の回答が返ってくるような人で、心配性なのかマネジメントがきめ細やかだと他の同僚たちの間でも評判である。
お察しの通り、僕はその人が苦手だ。打ち合わせをできるだけ端的に済ませてあとは自走したい僕にはあまり仕事のスタイルが合わないんだと思う。ただこれも仕方のない側面があり、その人は管理職一歩手前の職位だから昇進のために不慣れながらも張り切っているのだろう。何かの折に過去にもマネジメントに挑戦したが心を病んでしまいうまくいかなかった過去があると言っていた。その時の失敗を取り返そうとして、それが空回りしてしまっているのだと思う。などと聞こえのいいように書いたが、思いつきのままに全てを喋り散らかしていくのだけは聞く側の負担が大きいからやめてくれ、頼む、まじで、ほんとに。
そんな風に悪感情を持って接していると、指示に対して不服な気持ちになるなど敬意を失ってしまうことがある。単純に言えば心の中でその人のことを心底舐めている瞬間がある。振り返ってそれを自覚するとき、自身にそのような感情があることを嫌悪する。
他者を軽んじてしまうのは何故だろう。言葉を詰まらせながら機嫌を伺う姿、相手を無条件に肯定し受け入れ続ける姿、それらが当たり前になったとき、その姿は無様で見苦しいものとして目に映る。意思をはっきりと示せない惰弱で頼りない存在、周りに合わせてばかりの退屈で空っぽな存在。そういう人間を人は無意識に下に見る。過剰な謙遜が、慎み深い卑下が相手の立場を上げすぎている。そうして驕りや不遜を相手の無意識に植え付けている。人と人は自然なままでは対等にいられない。それはひどく悲しいことだ。
目の前の人間の期待に応えようと無理をしてしまう人がいる。他者の心情を思いやれるほどの慈しみと、自らを顧みないほどの献身性と、主体的に物事を捉えることの出来る責任感。それら人として尊重されるべき要素を、不運にも持ち合わせすぎてしまったばかりに許容限界を超えてしまう人。そうして壊れてしまった後、その人の元に一体何が残るというのだろうか。そういった要素を優しさと呼ぶべきではなかったか。優しい人間になりなさいと世の道徳は示しているはずなのに、どうしてそれに準じたはずの心ある人が憂き目にあわなければならないのだろうか。
上下の格付けでしか他者と関係を築けない人がいる。目に映るすべてが敵である世界に生まれてしまったが故に、他者を貶めてでも己の覇道を突き進むことを厭わない人々。勝ち負けの執着に囚われ、嫉妬に塗れているその存在は哀れで救いがない。だが同時にこうも思う。そのような厳しい精神性こそが人を高みへと導くのだと。競争の原理が支配的に働く中で、他者の利益を優先することは確かに尊ぶべきことだろう。だが勘違いをしてはいけない。施しを与えてよいのはそれに見合う強さを持った存在だけだ。身を削るだけの自己犠牲には限界がある。大事なのは何よりも結果だ。善とその紛い物、偽善、独善、自己満足について。それらを識別するのは単純で、結果が伴うかどうかだ。どれだけ他者を思っていようが、自己を顧みず周りに尽くそうが、それが結果として実らなかったのであればそれは紛い物となる。周りを優先して得られるものなどたかが知れている。そうして大事なものを取り逃した後に何を言おうがそれはすべて言い訳でしかない。過程は他者のためにはならず、そこに気持ちや思いがいくら詰め込まれていたところで何の意味もない。だから優しいだけの人間が損をするのは至極当然の事なのだ。思いを口にすることなど誰にでもできる。そもそもこれだけ文化レベルが向上した世の中では良い人など五万と巡り合える。そんな中で優しさが取り柄となってしまうような人間は現状に甘んじているだけの愚か者だ。さらに言えば本当の意味で他者に優しくある人などほんの一握りで、多くの場合は能力や自信の無さを都合良く解釈しているだけだ。責任を取りたくないから遠慮をして、嫌われたくないから相手に同調している。にも関わらず耳障りの良い綺麗事ばかりを論い、リスクを取らない自分を肯定するための免罪符としている。そのような弱さを優しさと履き違えてはいけない。優しいだけの無能よりも、厳しい有能のほうがよっぽど価値がある。ポケモンの性格で「まじめ」とか「がんばりや」といった無難な性格のグループが、何の能力値も突出しないがために対戦では役に立ちづらいということは重要なことを示唆していると思う。
昔から人の気持ちをうまく考えることができずに失敗ばかりをしてきた。その度に周りに色々と教わりながら自身を矯正してきた。これまでの僕は普遍的なものばかりを有難がっていたから、その教えに従うままに人間らしい振る舞いを模倣していた。だがどうしても、言動と心情の間には歪みがあって、後になってずれた過去の辻褄を合わせるようなことばかりだった。そうして自分自身が奇妙な形に象られていくことを気持ち悪く感じていた。
“いい人”でいなくていい。一人になったことで、そう思うようになってきている。興味のないことに興味のあるふりをしなくてもいい。共感できないことに共感したふりをしなくてもいい。そんな風にしていると誰からも好かれないとこれまでに色んな人から優しい言葉をたくさんかけてもらった。それは幸運なことだったのだろう。恵まれた環境と言えたのだろう。だが、今の僕にはその陽だまりのような優しさが身を焦がして忌々しいのだ。ありのままに生きたことで誰も寄り付かなくなってしまったとしても、それは仕方のないことだ。いっそ己が何か気味の悪い生物であれば楽だったのかもしれないとさえ思う。当然そんな現実逃避は許されるはずもないから、僕は人として気味の悪い存在になるしかない。彼も人、我も人、ならば両者は本来対等であるべきで、それはあらゆる報いの責任が己に帰属することを意味する。それは持たざる者にとってあまりに厳しく残酷な事実だ。そのような機械的な正論が戒めとなって自らを突き刺す度に、その理由を繰り返し問いかけている。悪いことなんてないはずだから恨むべきは己の無力で、納得するための理由なんてものはただそれだけでいい。だから僕は自己救済のために利己を追求する。そうでなければあまりに悔しいままではないか。案外、自分の人生を生きるというのはそういうことなのかもしれない。そうして他者を貶めることになろうとも都合の良い解釈で誤魔化しもしないこともここに誓う。他人を消費していることにすらも気が付かなくなり、都合の良い部分だけを享受して、見たくない部分は周りのせいにして生きていく。そんな風にはなりたくない。たとえ悪の道を辿ることになったとしても、この道理だけは失ってはいけない。この揺るがない意思こそ、僕自身に残された唯一の人間らしさだと信じている。
いい人であろうとしたことも決して無駄ではなかったと思う。そのおかげで人間らしい穏やかな幸せはもう十分に享受させてもらった。僕の名前には優という字が入っている。優しい人間になってほしいという願いを込めたのだろう。その願いにずっと呪われていた。そんな僕の名を優秀の優だといってくれた人がいた。きっと、それはこんな僕を対等な人間として見てくれたこれ以上ないほどの優しさで、その奥ゆかしい理性にいつも救われていたんだと今になって思う。
1 note
·
View note
Text
202503
何にも隷属してはならない。 今日、多くの人が生きていくのに困らない生活を送れるようになってきている。それは文明の発展による高度な統制の賜物だと思う。一方でそのような秩序にも当然綻びはある。すべての人が幸福になれるルールを作ることは極めて難しいから、当然隙間が生じる。もし皆が皆、自分さえよければいいという考えで動いてしまえばたちまち世の中は壊乱してしまうだろう。多くの人がそれを分かっているから、瞬間的に得られる利益の誘惑を振り切って細く長い長期的な利益を選んでいる。それは善意と呼ぶべきものだと思う。そのような善意で世の中は均衡を保っている。そしてそれ故に、ごく一部が好き放題できる余地を与えてしまっている。 自分勝手に生きるのは悪いことだろうか。僕はそうは思わない。個としての存在を突き詰めるものとそうでないものとでは、決して相容れない思想の違いがある。自分の人生は何にも代えられないのだから自身の幸福を最優先にすべきで、それ以外のことなど些末な事象に過ぎない。責任、義理、誠実さ。いずれも自らを安く売る愚行ではないか。倫理、道徳、社会通念、そんなものは自らの意思を持たない奴隷のための手引きだろう。不遜であれ、傲慢であれ、己が人生こそ至高であり、横に並んでよいものなどありはしない。 ならば善意の提供者は利用されているのだろうか。真面目に生きている人間は馬鹿を見ているのだろうか。自分勝手に生きられる地盤というものは、全体最適のために多くの人が他者貢献を優先した結果により成されている。その事実がありながらも、まるで生きるのが下手とさえ扱われてしまうことは絶対に間違っていると思う。だが、僕にそれを糾弾する権利はない。何故なら僕もまた世の中の優しさにただ乗りしている側なのだから。 国というシステムは後世が発展することを前提にその仕組みが決まっている。そのインフラは遍く国民に与えられており、当然僕もその対象となっている。しかしながら、僕は後世を発展させるようなつもりはない。にも関わらず僕はその恩恵を享受している。そこに知らぬ存ぜぬは通用しない。僕は公共の福祉という善意を都合よく消費しているのだ。遠くない未来に、次世代に割を食わせてしまうことだろうと思う。どうしようもなく自分勝手な人間だ。 一部の身勝手な人間によって損をする人々がいることを嘆かわしく感じる。それでもなお、僕に出来ることはその事実から目を背けずにいることだけなんだと思う。誰も悪くなんてない。それが自然の摂理というやつで、原理はもっと単純なんだと思う。生活が脅かされるようなことはないものの、水準が上がっているだけで相対的な弱者がいることに変わりはない。弱者の立場にある者は否応なく搾取される。それは人の意思を超えた不変にして普遍の法則なのだ。だから、あえて悪いことがあるとするならそれは弱いことだ。憤るべきは世の不条理ではなく己の弱さなのだ。
自身のすべてを以てしても敵わないことがある。あらゆる手を尽くしても届かないものがある。それが齎すのは如何様にも覆せない決定的な敗北である。負けること自体は何も恥ずべきことではない。何もない人間であるよりは、負けた人間になれたならば重畳だろう。最も怖ろしいのは負け犬の自覚を失くすほどに飼いならされてしまうことだ。負けを受け入れることは耐え難い屈辱だけれど、その先にあったものが大切であればあるほど向き合わなくてはならない。自らの信念にさえも準じることができないのであれば何を以てして今この瞬間を己の生と言えるだろうか。隷属してはならない。統制による庇護にも、福祉による恩恵にも、敗北の屈辱にも、そして自らに与えられた生にも。 これを書いている今は、少しずつ暖かくなってきて季節の移ろいを感じる時分となっている。ふと、目に映る景色が刻々と変わることに心がざわつくのを感じた。この思いが凪いだ時、初めてすべてが過去になるんだと思う。
0 notes
Text
202502
生活の変化に伴い、これまで住んでいた家に住み続ける訳にもいかなくなったので引っ越しをした。住宅に関係する業界というのは情報格差をいいことに消費者への搾取が横行している。特に、原状回復のための修繕費請求は悪徳業者によるぼったくりが発生しやすい構造になっている。聞いた話では強面の男の人が不透明な理由で大金を要求し、よく分からないままにサインさせようとしてくるなんてこともあるらしい。旧居は新築物件だったということもあり、そのような手合いにとっては格好の狩場なのではという一抹の懸念があった。
――よろしい、ならば戦争だ。予期される敵の襲来を丸腰のまま受け入れるなど、喜劇にも満たん愚劣な茶番であろうが。牙を研げ、叛逆せよ、その手は武器を取るためにある。いつの時代にも生物の営みから闘争が絶えることなどありはしなかっただろう。ならばこそ、この修羅道で相見えた者同士高らかに人間讃歌を謳いあげようではないか。剣林弾雨の奏でる讃美歌は我らを祝福している。ジークハイル、ジークハイルヴィクトーリア。というわけで理論武装のために素人が色々調べたことを書き留めておきます。内容に関して一切の責任は取れませんが…。
修繕費は国土交通省のガイドライン(https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf)に従い、適切に算出されたものかを確認しましょう。重要だと思った点をまとめます。
・原状回復とは入居開始当時の状態に戻すことではない。したがって過失により破損させてしまった箇所の修繕費負担のみが妥当である
・日焼け跡のような時間の経過による自然な損耗(経年変化)の負担は必要ない
・画鋲の穴のような通常の利用による小さな損耗(通常損耗)の負担は必要ない
・負担すべきは退居日時点の住居の価値(残存価格)に対する修繕費のみでよい
・修繕に関わる費用は最低限でよい。例えば、タイル一枚の破損であればその分の費用のみを負担すべきであり、壁一枚分の修繕費を負担する必要はない
また、負担が必要なものに関しても賃貸契約と同時に加入しているはずの火災保険が適用される可能性があります。発生時期、破損個所、原因となった家具についての情報があれば申請できるはずです。退去立ち合い以降の申請は認可されない可能性が高いため必ず事前に確認しておきましょう。ちなみに、保険適用対象は発生日から2年以内とされていることが多いです。また、軽微な損傷のみでは保険適用となる可能性が低いです。勘の良い諸君らの検討を祈る。ところで結果なんですが軽微な指摘一個だけで何なら敷金が返ってきました。対戦ありがとうございました。
知恵と知識だけは何が起こっても自分を裏切らない資産である。いつ何時も自分だけは自分の味方でいなければいけないと思う。引っ越しに関しては、インターネットの回線速度を勝手に低速で契約させられたなど他にも色々とあった中、保険会社のNさんだけは僕の味方でした。おそらく業務外であろうことまで相談に乗ってくれて本当にありがとうございました。質問攻めにしてすみません。なんだかんだ、世の中はそういう優しさで回っています。
2 notes
·
View notes
Text
202501
報われたいという気持ちを抱えていた。これまで辿った軌跡が実を結ぶ実感を得たいと思っていた。それを期待という形で望んでしまうことは過ちだった。
ゲームの主人公は世界を救って英雄になった。特撮の主人公は悪を倒して平和を守った。アニメの主人公はヒロインが抱える問題を解決してハッピーエンドを迎えた。では、僕は?
多くを望むことは難しいと諦めていたつもりだった。そんなものはあり得ない、分不相応だと言葉にしながらも、心のどこかでは創作で見た結末に憧れたまま、ずれた気持ちから目を背けていた。そうして空っぽになってしまった分自身の存在意義を外側に作りながらも、内側では方向性のない意思を募らせていた。そんな風に性根が下らないから人に認められることを心では望んでいた。その果てにあったのは誰にとっても不誠実な結末だった。それが、そんなものがこれまでの人生だった。私欲を滅して奉公することの出来る精神を持ち合わせていたのであれば、あるいはそうなれたのかもしれない。誰かの希望を満たすことのみが本当に自身の存在意義であるならば、心に違和感は無いはずだった。奴隷が望んでよいのは、奴隷で在り続けること以外にありはしなかった。幸福を外側に定義できるほど、僕は優しい人間ではなかった。自分で自分を認められなければいけない。されど、自分が無いままでは自分を認めることもままならない。
年末年始以降、仕事以外の殆どの時間を一人で過ごしている。今はとにかく内側への意識を研ぎ澄ませたいから、他者という外乱を可能な限り除去している。さながら成虫を迎える蛹のように、閉じていくことで自らを確かなものとしている。一人になるべきだった。報いは己が己に与えられなければいけない。自らの手で繭を破れない蛹は腐り落ちてゆくだけなのだから。
まずは過去への未練をすべて捨て去って、悪いもの、そして良いものからもすべて決別しなければならない。報われたいと思うのはこれまでにしなければいけない。自分軸のない空っぽな動機で行ってきたことなど、何もしていないに等しい。故にそんなものに意味はなく、報いなど受けられようはずもない。僕は主人公でもなければ、端役です���もなかった。何もしていない人間に居場所など無い。自らの意思で生きていない人間はどこにも存在できない。所属感の欠如の真因はここにあったのだ。すべてを捨て去っても良いと思えるようになってようやく気付くことができた。過去の全てを否定はしない、それでも手放さなくてはならない。本当の意味で何もない状態から始めなければいけない。それでも最後に少しばかり名残惜しいから、過去の僕をこの場を以て供養したとさせて欲しい。そういえば、源泉徴収票を見たら社会人を始めるとき目標にしていた額に届いていた。よく頑張りました。
1 note
·
View note
Text
202412
僕には何も無い。その悔しさがずっと胸に重くのしかかっている。
己の内に眠っていた執着と向き合った一年だった。欲を曝け出すこと、我儘であること、死にたいと思うこと、嫉妬すること、劣等感に苛まれること、そして悔しいと思うこと。これら負の感情は不要で無駄であり、現状をありのままに受け入れることこそが生きやすくあるために重要だと考えていた。合理主義を徹底することが己にとって正しいと信じていた。おそらく、現代を生きる多くの人にとってはそうなのだろうと思う。
自分として生きている実感を渇望している。幼いころから貧困を憎んでいたから、物質的な豊かさに目が眩んでいた。そうやって培われた平穏な自由は尊いものではあれど、僕に空虚さばかりを齎していた。自らの望みを置き去りにした生活には彩がなかった。
そうやって何者でもない存在としてただ生存を繰り返していくことは、少しずつ己が消費されていく感覚だった。環境が少しずつ変化するにつれ自分に向き合う機会が増えて、このまま生きていていいのだろうかと考えるようになった。僕が僕として生きていることが何も残らず、やってきたことはすべてただの徒労となって死んでいく。そんなものは嫌だと思った。
己の存在意義を考えてしまうような誇大自己を抱えていながら、後世に何かを託すこともしない。そんな僕のような人間は、何者かになれなければ一生不幸なままなのだ。これは承認欲求とかプライドと呼ばれるような薄汚れたものかもしれない。けれど、己の内側にあるこれらの感情は目先に映っている世界よりも色付いて感じた。
一方で、僕は自分を示せるような価値あるものを何も持ち合わせていない。誰かに響かせられるような魅力が何もない。それが惨めで悔しい。足るを知り、安定を選び、無味無色な日々を過ごしていた人間がつまらないのは至極当然のことだろう。変わりたいと思う。なりたい自分になるために欲を出していくべきだと思う。これは今の僕にとって呪いかもしれない。でもいつか、この呪いを祝福に変えることが出来ると信じている。
ルームメイトと同居を解消し、離婚をした。なりたい自分でいるためにはそれまでの共同生活は僕にとって窮屈なものとなってしまった。それは僕自身の振る舞いによって生まれたものであるから、何かを責めるつもりは全くない。勝手に変わったのは僕のほうだ。穏やかで静かな時間だった。それを喜びと感じるには、僕はまだ自分の人生を生きられていなかった。普通、情動に身を任せた結果失敗を繰り返して穏やかになっていくのだろうと思う。お利口に生きてきた僕には、その経験が不足していた。平穏を生きていけるほど、僕は成熟しきれていなかった。
多くの人間関係を終わらせた年になった。バンドをしていた友人たち、家族、そしてルームメイト。そうして身寄りが一人もいなくなってしまった。冷静に考えれば28にもなってこんな体たらくなのには目も当てられない。全部逃げ出してしまいたくもなるけれど、駄々をこねるようにして生き恥を晒しながら何とか生きながらえている。自分を大事にしてこなかったツケなんだと思う。それでもなお、これまでの行動や出会いに後悔はない。無駄だと思うこともない。無駄にしないためにも、また一から始めていく。
「これだけ不義理を働いて何も為せませんでしたは流石にやばいぞお前」と、来年以降の僕に今のうちに言っておく。
3 notes
·
View notes
Text
202411
自分を大切にしたい。
最近Tumblrに薄暗いことを書きすぎているためか友人が気を利かせてご飯の席を用意してくれ、その中で温かい言葉をかけていただく機会があった。その節は本当にありがとうございました。きちんとお礼を言えてなくてすみません。
人の純粋な優しさに改めて触れて感じたことがある。なぜ僕は自分を大切にしていないのだろうか。なぜ自分の意思を尊重しないのだろうか。なぜ自分を信じていないのだろうか。
僕も人から優しいと言われることがある。しかし、今の僕のそれは自身が持つただの道具としての価値を切り売りしているに過ぎない。そこに自身への敬意はなく、それしか出来ないからそうしているだけだ。そのような優しさのことを媚びと呼ぶのだろうと思う。自分が無いから他者が優先されているだけで、その優先順位の決定に思いやりの意志は介在していない。
何かを我慢をしているわけではなくて、元から多くを諦めている。家族のために生きられればいいと、自分の意志を蔑ろにしてきた。そうして奴隷のように生きることを肯定していた。そんな風に生きていればそれ相応のものしか得られないのは当然であり、都合のいい存在としてすり減らされるだけだ。それはこちら側の振る舞いにも非があって、粗悪とする自身を差し出したところで雑に扱われてしまうのは道理だろう。自分すら否定する自分を誰が肯定するだろうか。そんな存在がどうして他者と対等にいられようか。
家族に縁を切ると宣言した。金銭の催促に関する話が発端だった。いつも通りお金が足りないらしく、いくら貸せそうかとこちら側に尋ねてくる形だった。その質問はおかしいと思った。いつもなら違和感を覚えなかったかもしれないが、その時僕ははっきりと自分が軽んじられていることを理解した。だから縁��切ることにした。もう十分やるべきことはやったと思う。何もかも遅すぎたくらいだ。
もっと自分自身に誇りを持つべきなんだと思う。それは他人軸で生きてきた僕にとっては怖いことで、自身の価値を他者に委ねないことを意味する。だからこそ向き合わなくてはいけない。それこそが僕自身の持つ歪みの原因であるから、自分で自分を承認していかなければいけない。自分に心を許して、自分を信じて、自分を大切にしていかなくてはならない。もう誰にも自分のことを傷つけさせないし、誰にも尊厳を踏み躙らせはしない。
多くの人は程よく誰かのために生きている。子供を育てたり社会貢献をしたりして、自身の外側に存在意義を見出している。それは何も悪いことではないし、むしろ多くの人がそのようにして生きているからこそ今の社会はうまく回っているんだと思う。僕の場合そうではなかった。自分の気持ちに嘘を吐いたまま、肥大していく空虚な自己が喉の奥に詰まったままでは生きていくことができなかった。消極的な遠慮を積み重ねてしまうことは、自らの人生を生きていくことの主体性を放棄している。いい加減日々を両腕よりも外側で消費していてはいけない。能動的に掴み取っていくべきだし、そこに何の遠慮もいらない。自分勝手な人間のほうがよっぽど真面目に自分の人生を生きている。今更根本は変えられないんだからそのくらいでちょうどいいんじゃないだろうか。
0 notes
Text
202410
自身に価値を感じられない。鬱屈とした劣等感を拭えない。やること為すことが下らなく思えて仕方ない。自分自身を取るに足らない存在だと捉えると、その延長にあるものすら程度が低く思えてしまう。
自分の価値について再考する。
自身の最大の長所は自走力の高さにあると考えている。何か課題に行き当たったとき、情報を集めて自分なりの仮説を構築し解を見出す主体性と思考力を有している。また、仮説が誤っていた場合に試行錯誤を繰り返し解の精度を高めてゆくことの出来る精神力もある。こういった能力は課題解決が中心となる仕事においては重宝される。昨今ではそのような頭脳労働の方が資本主義社会における価値の代替である金銭を稼ぎやすくなっている。そういう意味では“市場価値”というものさしにおいて自身は価値があるという自負がある。
しかし、それを考慮しても僕は僕自身に魅力を感じない。市場価値なんていうものは、所詮労働者としてどれだけ使いやすいかという指標でしかない。道具としての価値はあるかもしれないが、人としての魅力がそこにはない。そう、僕は人としての魅力に欠けている。これまでの人生を物語としてみたならば、主人公のキャラクター性があまりにも淡白すぎる。過去のTumblrを読み返しているとそのことを痛感する。これまでに何度も考えてきたことではあるが、僕はコンテンツ性に乏しい。自分を自分たらしめる独自性に欠けている。なんて退屈でつまらない存在だろうか。
苦しくはあるものの、現状に絶望はしていない。おそらくこれは瞑眩反応のようなもので、今になってこんな思春期の少年少女のようなことを考えるのは、自身の境遇の変化や決意によってようやく本当の意味で自分のために生きようとする意志を持ちはじめたことに起因すると考えている。自分への優先度が上がったことで、これまでどうでもいいと諦めてしまっていた自分自身の問題に向き合うことが出来るようになったのではないかと思う。聞くところによると、ミッドライフクライシスといって仕事や子育てが落ち着いた年中者にも思春期のような心理状況がしばしばみられるらしい。オレはまだ20代だが…。(追記 : 20代後半にもクォーターライフクライシスといってよく見られることらしい。何ならより広く、アイデンティティクライシスという言葉すらある。人類、血迷いすぎている。)
自分らしさを手に入れてそれがコンテンツ性を帯びたとき、はじめて心が安らかになるんだと思う。この願望が叶えられることはないのかもしれない。人の欲求は無尽蔵であるから、結局その先で届かないものに手を伸ばし始めてしまうのかもしれない。全部諦めてしまうこともできる。彩のないまま生きていくことも決して悪いことではない。でも僕にとってそれは、自分として存在している実感が得られないままに空虚な日々を過ごしていくことを意味する。そんな風に生きていくぐらいなら、死んでいるほうがましだと思う。
3 notes
·
View notes
Text
202409
さらなる幸福を求めている。それを認知したことにより鬱々とした日々を過ごしている。何かを望むことは、同時にそれが無いことによる絶望を知ることでもある。現状が不幸であるとは思わない。それでもどうしても足りていない。
ここ数年間、満たされない感覚が脳裏を支配していた。何をしてもここにいるべきでないという違和感が日増しに強くなっていた。それらの正体は、振り返ってみれば自分らしく幸福でありたいという心の声に他ならなかったのだと思う。足るを知る精神で生きていた。地に足の着いた苦しみのない平穏を求めてきた。だがそれは環境によって外側から与えられた欲求でしかなく、自らを起点として望んでいたものではなかった。
幸福とは何だろうか。哲学者たちが永遠の相や永劫回帰と呼ぶものは共通して、現在を生きるものは幸福であると示唆している。未来を考えず、過去に囚われず、今この瞬間をありのままに肯定して集中することができればその時点でいつだって幸福になれるという。確かに、僕はずっと安定した未来だけを想像して生きてきた。そんな人生は、端的に言ってしまえばつまらない。それは決して悪いことではない。だが今の僕には、わざわざそんな生き方だけをしていくことに意義を見出せない。
刹那的な生き様に憧れがある。何にも縛られず、自らの望みを従順に、耽美的に、破滅的に、残酷に追及する。そんな生き方に目を惹かれる。要は無い物ねだりなのだ。手元にないものばかりを見て、相対的な価値を追いかけ続けている。でもそれでいい。しばらくは衝動に身を委ねていたい。これまでの行いが無駄だとは思わない。全部手に入れたい。傲慢でありたい。
お金も時間も人間関係もこれまでより好き放題やるようになった。心の声を聴いて、まずは自分がどうしたいと思うのかを考えてから行動する。直感や好奇心のような原始的な欲求を大切にしている。その先の自分がどうなろうが、他人がどう思おうがそれは二の次でしかない。そうやって過ごしているうちに、自分のためだけに生きるのはとても寂しいということに気がついた。さらに、自分はその寂しさへの耐性がまるで無いことにも気が付いた。これまでは他者に関心を向けることで気を紛らわしていたんだと思う。そんなときは手慰みにギターで弾き語りをしたり絵を描いたりプログラムを書いたりする。少しでも生産的なことに集中している間は満たされている感覚がある。内側から出てくるものを形にしたい。思えば、こうやって言葉を書き連ねているのもその一環だったのだろう。望みはずっと内側に存在してくれていたんだ。
1 note
·
View note
Text
202408
これまでの人生は無駄なことばかりだったのではないか。今月はそんなことを考えていた。
中学の頃に家庭環境が悪化し、自分が何とかしなければと決意した。それから自分なりに精一杯頑張って今では余裕を持って過ごせるくらいにはなった。色々しんどい思いをしながらも、この今を何とか掴み取って家族を支えられるようになったことを誇らしくも思っていた。けれど、実際はそんなふうに僕が頑張らなくても何とかなっていたんだと思う。
カフカの変身で、主人公グレゴールの稼ぎがなくなってからもしばらくして家族が勤勉さを取り戻し何とかなったように、僕がすべてを投げ出していたとしてもその分家族が頑張ってくれていたんだと思う。むしろ、家族が頑張ることを阻害すらしてしまっていたのかもしれない。その他にも、国からの補助でうまくやっていけたかもしれないし、運よく手を差し伸べてくれる誰かが現れていたかもしれない。
そう考えるうちに、自分のやってきたことは全て意味のないことだったのかもしれないと考えるようになった。やりたくないことなんてやらなくてもよかったし、自分が好きなことを自分のためだけにしていたほうがよかった。そうしていれば、今こうして満たされない気持ちを抱えたまま苦しむことなんてなかったのではないか。それに気が付けないまま、自己確立出来ていない空っぽな人間として歳を重ねてしまった。僕が精一杯やってきたことは愚かで無駄なことだった。それがあまりに惨めで受け入れ難いから、早く全部終わりにしてしまいたい。そんな、考えても仕方のないことをぐるぐると考え続けてこの先働いていくことにも意義を見出せなくなってしまっていた。
そうなった場合をイメージしてみる。僕が全部やめてしまったところで、誰もそれを必要以上に怒ったりはしないだろうし、生活も意外となんとかなることを知っている。はじめは罪悪感を覚えるかもしれないけれど、そのうち慣れて何も感じなくなると思う。裕福な暮らしは出来ないだろうけど、そもそも僕はあまり物や金を必要としない性分だ。なんだ、悲しいくらい丸く収まってしまうじゃないか。僕が大事に握りしめていたものは、どうやら簡単に手放しても大して困らないものだったらしい。それでいい、それでよかった。意地になっていただけで、本当は大して重要なものではなかったんだ。果たしてそうだろうか。本当にそれで良いのだろうか。
どれほど楽観的に考えても、イメージしたifの僕に、今の僕は心から納得ができなかった。きっと僕のような意志の弱い人間がそのようにして生きた場合、与えられることが当たり前になってしまう。そうして自分以外のものを消費し擦り減らしていく存在になってしまうことだろう。それを続けた先にあるのは誰からも信頼されない孤独な人生ではないだろうか。
人と信頼でつながっていたい。少なくとも今の僕はそう考える。そのためにも信頼される存在になりたい。人を信じたいから、人から信じてもらえるように行動していたい。そうだ、家族のためという動機だけではなく、はじめから僕は自分のために頑張っていたんだ。自分らしく生きるためにこの今を自らの意思で選び取っていたんだ。全部無駄になんかしないし、意味がなかったなんて思わない。これからも僕は大切なことを、ものを、言葉を、人を信じ続けたい。
0 notes
Text
202407
アイデンティティを自己の内側に確立すること。問題ではなくまず気持ちに寄り添うこと。楽しく生きること。
3 notes
·
View notes
Text
202406
尊敬する人物が誰か考えたとき、一番初めにカービィやスマブラの生みの親である桜井政博氏が思い浮かぶ。ゲーム自体が素晴らしい作品であることは言わずもがな、氏が提唱するゲーム作りにおけるロジックは僕の目にとても魅力的に映る。ゲーム作りのほぼ全てを担当されてきているのでそのロジックにも様々あるのだが、特に尊敬するのは企画における課題設定から解決に至るまでのプロセスと、それらを生み出しているゲームに関する膨大な量のインプットである。詳しくはYouTubeチャンネルを見てください。
自分の人生は面白いゲームを作ることで完成するかもしれない。最近はそんなことを考えている。今月は「NHKにようこそ!」というアニメを見ていた。その中でゲームは総合芸術だと登場人物が発する瞬間があり、それほど重要なシーンではないにも関わらずそのさりげないセリフに確かにと考えさせられた。音楽や絵、文学からIT技術に至るまで様々なメディアをミックスさせて構成されているゲームを単なる娯楽品として消費するだけでは勿体ない。それらを芸術として捉え、自らの血肉にしたい。そして、自らも誰かが面白いと感じてくれるようなゲームを生み出したい。
これまで度々月記でも出てきているように、桜井氏には及ばないがやってきたゲームの量や種類ならかなりのものである自負がある。それだけではなく、バンドで音楽をやってきたこと、コンピュータサイエンスに関心を持ち続けてきたこと、課題解決型の仕事を続けていること、絵を描き始めたこと。これらすべてをゲーム作りに活かせるかもしれない。そうして、自分のこれまでの行いに一貫した意味を与えられるかもしれない。それこそが僕にとっての自己実現の形だと今強く思う。それを達成できたとき、今もなお頭の中を占有している焦りや喪失感、空虚に満たされている感覚を拭い去ることができるかもしれない。そうあって欲しいと願っているのかもしれない。
そういえば、小学生のとき将来の夢を考えましょうと紙を渡され、何も考えずにただゲームが好きというだけでゲームクリエイターと書いた覚えがある。20年間色々考えて、僕はまたゲームを作りたいと考えるようになりましたよ。
2 notes
·
View notes
Text
202405
ルームメイトがNISAを始めたいらしく、自分もかねてより興味を持っていたことからNISAに関する投資の勉強をし、ついでに今後の仕事のための練習として資料にまとめてプレゼンした。以下がスライドの1ページ目です。思想~~~。
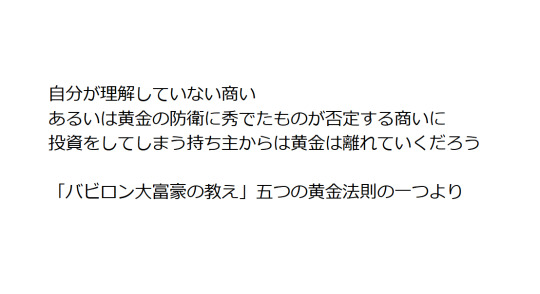
長期投資に取り組むためには必然的に遠い未来を考えることになるのだが、自分はどうしてもそれだけの時間を生きることに前向きになれない。
この先、仕事では裁量や責任が増え日々の業務がきつくなっていくことだろう。プライベートでも体は老いて不自由は増えていき、色々な所で肩身も狭くなっていくのだろうと思う。そして何より家族の介護など面倒を見なければいけないことが増え今よりも負担は増していく一方な気がしている。今月、兄からスマホの調子が悪いとの連絡があり、ちょうど自分のスマホを新調したこともあり元々使っていたものを譲るために久々に実家に帰った。最近どう、と母親に聞くと家賃の支払いが滞ってしまっており、月末までに払えない場合は家を引き払うことを誓約する書類にサインまでしている状況のようだった。話の振りの軽さに対し、返ってくる内容が重たすぎる。
目先のこの問題に関しては僕の手持ちですぐに工面できたが、この先はそんな単純な話ではなくなってしまうかもしれない。仕方のないことではあるものの、そんな未来で何を希望として生きていけばいいのか分からない。
・・・などと長ったらしく述べたが、こんなものは御託でしかない。そもそもこの話は以前DCの商品選びをするときにも考えたことで、結局は生きる前提で過ごしていくしかない。ならばやるべきことは御託を並べることではなく、それらに勝るほどの生きがいを見つけ出し没頭することのみなのだ。おそらく今後もこういったことを考えてしまうことになるとは思うが、今を生きている以上はこの姿勢を貫いていく他ない。
正確には4月末のことだが、人生初の音楽フェスに参加した。きっかけはバンド友達とそろそろ何かしたいねという話になり半ば突発的にチケットを予約したことだった。
フェスといえば事前にどこを回るか仲間内でわいわい話し合うのが醍醐味だと思っていたが、あいも変わらず周りは話し合いを進めたがらなかったので共同編集できるファイルを作成し草案を盛り込むなどして出来るだけ話し合いが進みやすいように立ち回っていた。旅行をしない僕はプライベートで人と計画を立てた経験があまりないのだが、自分がそういうことをきちんとやりたがるタイプであるというのは新しい発見だった。
好きなアーティストが複数参加していたこともあり思い出に残る体験ができたと思う。そもそも、プロのライブにきちんと参加したのも初めてだったのでライブパフォーマンスなど直接その場にいるからこそ味わえる空気感のようなものを体感することができたのもよかった。
一方で、消費的な活動に時間を費やしていていいのだろうかという不安が反芻され心が穏やかでない瞬間もあった。ステージとの隔たりを超えて一緒になって盛り上がっていても、自分は何故こちら側なんだろうなどと烏滸がましくも考えてしまい自身の中途半端さに情けなくなっていた。皆と折角一緒に来ているのにそんなふうに自分のことばかり考えているのにも嫌気が差していた。
昔から、何をやってもどこにいてもここにいるべきではないと感じる瞬間がある。そう感じるのはこれまでに浮ついた行動を繰り返してきたことの現れでしかない。何に対しても真摯に向き合わない人間はどこにも存在することが出来ないのだろうと思う。いい加減自分はどうありたいのか、悠長に考えていられる時間はとっくに過ぎ去っている。
2 notes
·
View notes
Text
202404
今月はモルフォ人体デッサンという人体を描くための本を読んだ。教本も読書にカウントしていいらしいですよ。
まずは作りを正しく理解するところから始めているので、頭一つ描くのにだいぶ時間をかけてしまっている。絵の勉強を始めてから物の在り方を新しく学ぶ度に、世界を正しく認識していなかったことに気づかされている。我々はどうにも思い込みで世界を見ているらしい。経験に基づいた脳による情報の補正は良くも悪くも知覚に影響を及ぼしている。機械学習を利用したアプリケーションが学習モデルによって出力結果に大きな差異を生む原理は、紙とペンを使って人間が絵を描くという原始的な行いにおいても変わらないのだ。すみません、興が乗り衒学活動をしてしまったのでお詫びに僕が描いた可愛い頭蓋骨でも見ていってください。

自身の魅力の無さを恥じることの多い月だった。コンテンツ性に乏しい自分は誰かに特別な印象を与えることが出来ない。そうして誰の記憶にも強く刻まれていないことが虚しいし、みじめに思う。
こんな風にネガティブなことを考えるようになったのは、ある意味で余裕が出てきたからなんだと思う。おそらく、今の自分は生活が整って仕事が安定してきたことで新たな欲求を抱き始めている。マイナスな感情を認知し始めたのは、その欲求を叶えるために必要な能力を求めて心が反応しているからなのだろう。これまでの欲求よりも上位に位置している��れはおそらく承認欲求と呼ばれていて、今の自分はその段階に踏み込もうとしているのだと思う。マズローの自己実現理論は確かな予言であることが、自らの境遇によって少なくとも主観的には実証された。また衒学活動をしてしまいました、もっと頑張ります。
1 note
·
View note
Text
202403
今月は「反応しない練習」というビジネス書的なやつを読んだ。この読書習慣を始めてからというもの、小説エッセイに次いでビジネス書と来ました。僕は一体どこに向かおうとしているんですか?
この本を読もうとした理由は公私に分けて二つある。
一つ目は業務コミュニケーションに心理的負荷がかかりすぎていると感じているためである。仕事で依頼をするときや意見を伝えたとき相手の心情を気にしすぎてしまうことや、成果物に対する他者からの反応を気にして心労が絶えない時がある。
二つ目は他者から自身に向く悪意に敏感過ぎる時があると感じるためである。自身を脅かすかもしれないと感じる対象を自己防衛のために疑いすぎてしまう傾向にある。
このような過剰な反応を抑止できるヒントになればよいと思いずっと積んでいた本だった。
内容としては目の前のことを勝手に判断して感情的になるなということをあの手この手で教えてくれている本だった。求めていた内容も書いてあるにはあったが、どちらかというと嫉妬や憎悪などのネガティブな感情を抱きやすい人向けの本だったので、自分にとってはあまり効果が無かった。合理的に物事を考えるのであれば、そういったものはすべて無駄な反応であるというのには概ね同意であった。
一方で、ここ数か月で仲良くなった創作活動をしている友人らと関わる中では、悔しいと感じる瞬間についての話を方々から耳にする。どうにも、そういった劣等感と心が苦しくなるまで向かい合うことで創作の糧とするらしい。そこでふと気が付いたのは、自分はこれまでにそのような思いをしたことがない。勝負ごとに負けたとしても、勝つためにやるべきこと以外を考えることは無いと思うし、そもそもこれまでの人生はほどほどに見切りをつけてきたことばかりだった。このように、こだわりを持って努力をしたことがないから悔しいと感じることがないのだと思う。良く言えば潔いが、悪く言えば何にも執着がないつまらない人間だと思う。
ネガティブな感情というのは基本的に考えてもどうしようもないことでしかない。それらに執着したところで自身の外側にある原因に影響を及ぼすことは出来ない。故にそれらは意味のないことだと見向きせずに生きてきたが、そのような負の側面と向かい合うことが場合によっては自身に良い影響を与えることだってあるんだと思う。そんな誰しもが気づいていそうなことに齢27にして気が付いた。多少の執着こそが人間の輪郭を彩るのかもしれないと思った。
1 note
·
View note
Text
202402
今月はオードリー若林が書いたナナメの夕暮れというエッセイ本を読んだ。繰り返し出てきた等身大の自分を受け入れるといったエピソードに、これまで彼が努力を積み重ねる中でどれだけ劣等感に苛まれてきたかが垣間見え、自分の大学院時代を思い出し色々と考えさせられた。自分は何も為せず折れてしまった側だが、自身に配られたカードを把握して戦略を立てていくことは何事においても大事だと改めて思った。
新しい職場では初の上司と目標設定の話し合いがあり転職してからこれまでの動きについてフィードバックをもらう中、即戦力だと言ってもらえたのが嬉しかった。そもそもの期待値が低かったのだろうということはさておき、異なる環境においても価値を認めてもらえる存在になるというのは自身のなりたい像の一つであったので小さいながらも印象深い出来事だった。とはいえ、評価されているのは概ねこれまでやってきたことの延長にあるものなので、新しい領域の業務に携わるようになってから期待外れとならないよう今後も頑張ろうと思う。ところで、今の会社はハードに働かせていただけるということで有名であるのだが、最近徐々にその頭角を現してきているのを感じる。この先生き残れるだろうか、そうご期待。
1 note
·
View note