Text
戦略会議 #028 アートマーケット/韓国のアートフェア出展
海外から帰ってくると、決まって食べたくなって行っていたのは地元の先輩の店のチャーハンだったが、今回は亡くなった妻とよく行っていた蕎麦屋だった。当時毎週何回かは足を運んでいたのだが、妻の病気が進行して以来3年半ほど行けていなかった。久しぶりの蕎麦を食べながら、この数ヶ月の喧騒を振り返った。
9月アタマのソウルは台風だと言うのにアートの熱がすごかった。アートバーゼルと並び世界最大級のアートフェアを開催するFriezeが韓国の老舗アートフェアと5年間の業務提携をし、ソウルの大規模展示施設COEXを分けあった形でアートフェアを行っていた。 5月末にサポートをしてほしいと頼まれた仕事はソウルでこの同じ時期に行われるサテライト的なアートフェアへの参加に関してであった。会期まで2ヶ月となった7月から実際には動き始め、11名のアーティストの作品をロンドン発祥のアートフェアで、ソウルでは初めての開催となるStART ART FAIR SEOULというアートフェアへ出展へと準備をはじめた。 今後立ち上げを予定している「THE TEN」というアートスペースとしての参加となる。スタッフとして手伝わせてもらっているギャラリー、自身がアーティストとして参加した台湾、バーゼルのアートフェアの経験はあるものの当初はなんとかなるとは思いながらも、思いもしない問題だらけで膨大なストレス��日々であった。大学院在学中にお世話になった人のサポートがなかったら、もうちょっと早めにもうやめようと思っていただろうと思う。
8月末からソウル入りし、巨大なふたブースに11人のすばらしいアーティストたちの作品をかけるインストールがはじまった。会期の2週間前になってようやく出てきた展示ブースのレイアウトにあわせ、事前に綿密にCGで展示をシミュレーションしていたおかげで、現地での展示は比較的スムーズに行われた。

韓国のインストーラーはとても優秀で、思いのほかたのしく設営は進んだ。30日の午後、31日の午前という計8時間の間に、48作品60点の作品をかけ、31日の夕方からVIPプレビューが行われた。

Frieze、KIAFのプレビューが2日からで会期はFriezeが5日、KIAFとStART ART FAIR SEOULが6日までなのはそれぞれのアートフェアのチカラ関係をそのままにあ��わしている。つまりFrieze目当てのコレクターが前後で溢れることを見越しているのだ。今回のStART ART FAIR SEOULへの参加は当然このFriezeとKIAFに沸くソウルの熱による相乗効果というものを期待しての参加であった。が、これはまったくといっていいほどその効果はなかった。会場の距離そのものはそれほどないのだが、ソウルの街の特徴的な形状である川を挟んでいることから移動が非常に困難で、最低でも4、50分かかる。そして、ソウルではタクシーの供給が圧倒的に足りていない。道でまともにタクシーは拾えないような状態であった。そもそもにソウルではGoogle Mapがまともに機能せず、Kakao Talk関連のアプリを使いこなせないと移動すらままならい。
これらのことから、VIPのプレビューに多くの人が訪れたがFriezeに足を運ぶであろうようなコレクターらしき人は皆無であった。飛ぶように売れると言われて来ただけに、これはかなりの問題である翌日から一般公開となったが、そこからどうやって販売するかを考える時間となった。

1日の1日をかけて、何が誰に売れるのかを考えた。アート作品はふらっと来て買うモノではない。誰かが買ってくれるのではなく買える人は限られている。戦略的に話を進め、この人しかいないという人にしっかりと作品を紹介できるかどうかである。
翌日交渉の末、ゼミ仲間であるアリカワコウヘイ!の大作(提示価格$61,000)はヨーロッパのコレクターによってコレクションされることが決まった。


その後、児嶋啓多や谷村メイチン・ロマーナの作品など数点が販売され、7日間の会期で提示価格にして$78,000分の作品を販売した。2日に開幕したKIAFでの販売が$10,000から$20,000の作品についてARTNETでニュースになっていることを考えると、これはわりと凄いことだったと思う。
With a Little Help From Frieze Seoul, Longstanding Korean Art Fair KIAF Comes Roaring Back
それだけの取引があるアートフェアであるということは出展者にとっては魅力になるのだから、このあたりを事件にするべきだと思うのだが、これができないあたりがアートフェアのチカラのなさだろうと思う。
アート作品は勝手に売れるモノではない。ほとんどの作品は市場的にも無価値だし、コレクターは欲しいもの以外は絶対に買わない。2011年に当時の京都造形芸術大学に入学���、アーティストを目指したころからずっとマーケットのことをギャラリーのオーナーの寵愛を受けながら、自身もコレクションもするし、アートフェアも何度も足を運んで作品を見続けてきた。そうやって学んできたことが間違いなく今の目を育てただろうなとありがたくは思ったが、けっしてやりたい仕事ではないなと思う。 台風直撃の5日にお客さんも少なかったためブースを現地のスタッフに任せ、Friezeを訪れることにした。


台風でStART ART FAIR SEOULはもぬけのからにも関わらず、Friezeは人だらけだ!着いた瞬間に2019年まで欠かさず訪れていたアートバーゼル香港を思い出し、気持ちがざわつく。台湾の台北當代よりもクオリティは上だ。








来年の東京現代がどうなるかだが、、、これを見るとソウルはこの5年で圧倒的にアジアのアートマーケットの中心地になるだろうということは容易に想像がつく。���なアートフェアに出展している場合ではなかったなという思いが込み上げる。研究者としてはこちらをくまなく観る方がよほどに得るものが多い。来年はお客としてソウルにこようと思う。
この夏で妻が亡くなって3年になる。それより前に何をしていたか少し忘れかけていたが、今回のFriezeに行って思い出してきた。何が好きで、何に夢中になって何を考えていたのか。そう、この蕎麦屋の安定しないクオリティがすごく好きだったんだ。
0 notes
Text
戦略会議 #02 展示まわり/「Ohter rooms | 狩野志歩、橋本晶子」
久しぶりに終日展覧会をまわる1日を過ごした。国立近代美術館の「ゲルハルト・リヒター展」、TALION GALLERYでの二人(宇田川直寛、横田大輔)による「石が降る」とともに楽しみにして訪れたのが大学院のゼミ仲間が企画した「Ohter rooms | 狩野志歩、橋本晶子」である。 LOKO GALLERYのレジデンスルームで行われた共に武蔵野美術大学卒の狩野志歩、橋本晶子による展示であった。 会場に着くと注意事項と作品リストが書かれた1枚の紙を渡され、展覧会趣旨を説明された。部屋には二脚の椅子があり、座っていただいても構いませんとのことであったが、作品には触れないでくださいいうことだった。展覧会の場所を案内をされ、会場となる部屋へと入っていった。

いわゆる「アート作品」となるいくつかのドローイングと映像作品を映し出したモニタはすぐに目につくものの一見すれば、ごく普通の部屋である。リストを見ながら部屋を見渡して、映像作品に目を向ける。この展覧会は予約制となっていて、90分という時間の枠を使って「ひとり」で展覧会会場にいることになっている。 これらいくつかの環境設定とアーティストの展示によって、部屋に入ってしばらくするといくつかの自分の中のことが転倒しはじめる。展覧会会期もまだありこれから見に行く人もいると思うので、作品について詳しくというよりは僕自身の経験したことを簡単に書いておくに留めておきたいと思う。 絵画に「図と地」があるように、展覧会にも作品という「図」と展覧会会場という「地」というものがある。僕の博士課程での研究対象でもあるコンテンポラリーアートのアーティストであるワリード・ベシュティは90年代のある意味での写真暗黒期の状況を作品が美術館やギャラリーと一体化し、建築の一部となったと述べていたことはやや大袈裟な話だとしても皮肉が効いている。本来、美術館やギャラリーで鑑賞者は「図」となる作品に意味を求めるものであり「地」である壁そのものや部屋自体には元々そこにある以上の何かを雄弁には語らせようとはしない。 今回の狩野志歩、橋本晶子の展覧会「Ohter rooms」において、いわゆる「アート作品」というものは映像作品とドローイングがそれにあたると思う。程よくその存在を観賞者に向けて主張しつつも、展示方法の工夫とその数やサイズ、作品の質が部屋である「地」に90年代の写真とは違った意味で溶け込ませており、「作品を観る」という展覧会の半ば強制的な制度から一時的にではあれ、気持ちを解放させてくれる。アート作品がそこにあって当たり前かのように思い始めてくるにつれ、部屋の中のさまざまな違和感が逆に際立ってくる。あちこちに貼られたマスキングテープは作品を貼り付けたものと同じものであるし、天井から下がったチェーンは照明のものでも天窓を操作するものでもない。作品を照らすように置かれたスタンドライトの下や脇に重ねられた本は背表紙がが壁側に向いていて読みづらくなっていて、「作品に触れてはいけない」と言われたことがここで急に意味を持ちはじめるを感じた。。。 あれ?この本は作品か?

一度「図と地」が転倒し始めると「地」であると思い込んでいた部屋そのものが急に前傾化してくる。履いてしまったが、スリッパは作品で履いたらダメだったか?と思わず元の位置に戻してしまったりした。アーティストふたりの作品はマルセル・デュシャンの「R.Mutt 1917」のサインとして機能し、部屋全体をレディメイド作品に変えるようでもあり、本来同じ階層で比べられることのない異なる二つの次元にあったものが、ひとつの空間的コラージュとなって部屋そのものへの僕の思い込みは脱臼させられる。そして「図と地」の関係は解消、もしくは、コラージュという意味ではその中間地点に意味と価値を考えるように思考を向けさせることとなる。つまり、部屋そのもの、そこにあるもの全てが意味の可能性に開かれるのである。 何が意味を持ち、何に価値が与えられるのか?ということは向き合ったその人次第だということ。世界が意味に溢れていたかつての魔術的な世界へと一時的に迷い込んだ感覚となる。
いわゆるホワイトキューブに対してオルタナティブなスペースでの展示というものは増えてきているように思える。場所性を取り込んだ「サイト・スペシフィック」なものというのも意識されることは多いだろうし、作品が場所のために機能するように控えめなものというのもおそらく存在すると思う。しかし、ここでの体験は単なる観賞ではなかったし、アート作品がこれでもかと置かれたホテルでの滞在でもなかった。慣れたアート作品に囲まれた自宅ともちがうし、アート作品を飾った友人宅を訪れるのでもない。「ひとりで90分間いられる」という設定は鑑賞者とこの展覧会を親密にさせたうえで、意味は果てしなく遠くに置かれていることに気がつくにも十分機能し、特異な時間を作り出す。その特異な時間は鑑賞者を何かと何かの間にできた例えようのない思考の割れ目に浮かべてみせるのだ。
Other Rooms アーティスト:狩野志歩、橋本晶子 会期:2022年6月1日から19日(休:月火) https://bit.ly/3zsBcsT
1 note
·
View note
Text
戦略会議 #09 アートについてのひとりごと/映画「ハンナ・アーレント」
先日の大学のゼミナールで今日から国立近代美術館ではじまるゲルハルト・リヒターの展覧会について紹介があった。近いうちに観に行くつもりではいる。今回日本初公開となる大作《ビルケナウ(937-1)》(2014年)が話題の作品となっている。
ビルケナウとは80年前の世界を巻き込んだ戦争のうち、ヨーロッパ起きた悲劇を象徴するアウシュビッツ強制収容所のあったポーランド村の名前である。リヒターがそれを作品として作った背景が簡単に説明され、元となった4枚の写真についての話がされた。その中で興味をもったのがハンナ・アーレントであった。 アーレントは、ユダヤ人であり、戦時中勾留地から脱走してアメリカに亡命した哲学者で、ハイデガーの愛弟子。「悪」について思考し続けた哲学者であった。 映画があったらしいので観てみた。 ハンナ・アーレント http://www.cetera.co.jp/h_arendt/
youtube
アーレントが、1960年に逃亡先でイスラエル諜報特務庁(モサド)によって逮捕された元ナチスの親衛隊アイヒマンが裁かれる裁判を傍聴し、ニューヨーカー誌に『エルサレムのアインヒマンー悪の陳腐さについての報告』を発表し大論争を起こすこととなった物語だ。 世界が極悪人を想像し、そうであることを前提に進められた裁判を目の前で起きたことを感情論に流されず正確に記述しアイヒマンを「根源的な悪」ではなく「凡庸な悪」であるとした。さらに被迫害者であるユダヤ人の指導者たちの中には(立場上仕方ないにしたとしても)アイヒマンに協力するものもいたとし、「ユダヤ人にとって同胞の破滅に指導者が果たした役割は暗黒の物語における最も暗い一章だ」と記した。このことが、世界中からの批判を集め、大学の職や友人たちを失うこととなる。 映画の演出に誘導されているとも思うが同調圧力は再び「凡庸な悪」として彼女の前に現れているように思えた。 アーレントが言い続けたことの本質はひとつだけだ。 「思考し、人間であることを放棄するな」と。 おもしろかった。 紀要論文書いて時間ができたら難しいらしいが、本も読んでみるか? さて、自分はちゃんとリヒターの作品に自分の思考で向き合えるのかな?
4 notes
·
View notes
Text
戦略会議 #21 アートライティング/多和田有希 @MtK Contemporary Art
急遽参加となった京都で大学院のゼミナール終了後、当初の目的であった展覧会をゼミ仲間たちと訪れた。「ゆだねながら語り合うこと/響き合う思考法」@MtK Contemporary Artである。
「写真は変成する MUTANT(S) on POST/PHOTOGRAPHY」にて非常にお世話になっており、昨年度書いた大学院紀要「シャーロット・コットン『写真は魔術』の再検討による「POST/PHOTOGRAPHY」論」でも取り上げさせてもらった多和田有希先生の作品を観ることが目的だ。 今回の展覧会ではふた方向の表現(《Family Ritual》と《ID》、《transition》… 《transition》は別かな?)の作品が展示されていた。これまでも京都や東京、浜松、高崎などで何度か観てきた作品たちではあったが、今回の展示で少し自分なりの解釈として掴み取れそうなところがあった。 作品群がいくつかという問題はいったん置いておいたとしても今回のこの展覧会に向けた多和田先生の「思考法」というものは全作品を通して共通するものを感じた。


《Family Ritual》は最低限これが人物写真(タイトルから察するに家族写真、家族の誰かが写った写真)であるとわかるように両目と口、そして身体の輪郭にあたる部分はプリミティブな紋様のようにも見える線の集積として残し、それ以外は焼き落とされたフォトグラフィック・オブジェクトとなっている。焼き落として削っているにも関わらず、逆に人物が糸の絡み合いによって創造されているようにさえ見える。焼かれた穴を通して写真は印画紙の向こう側も見えるため、現実空間における物理的なイメージの重なりによってイメージは単写真では持ちえなかった複雑な構造を持つようになる。焼き落とされたことによって、写真はもはや四角い矩形の画面ではなくなり、不安定な構造物となる一方、それによって物理的自由な身体を得るため、ひとつのイメージ内にいた二人の人物の距離感は現実世界で再編され、一人の人物の輪郭は別の写真の助けによって成立させられる。


一方、《ID》と《transition》は桜を撮影した写真のプリント表面を削るなどして傷をつけ、イメージ内に作家の行為を介入させている。桜の写真というある種の凡庸なイメージに一見すると白い花びらが舞っているかのよう見えるものはプリントそのものを削って捲れ上がった印画紙それ自体である《transition》は桜の写真が徐々に白くなる様を4枚のプリントで見せている。しかし、この4つの写真の「差」はイメージの明暗やコントラストのコントロールといったイメージ内で起きたものではない。この表面の物理的欠損の量によって生まれた変化によるものである。《ID》はそれらの単一イメージをより大きなプリントで見せており(《ID》のひとつは《transition》を反復している)、削られ剥がれた痕跡だけではなく、表面が剥がれてはいないこすったような跡などもその表面には複雑に残されている。
両方向の作品に通底する点は「イメージ(人物・桜)」と「物理的なアクションの痕跡(燃やす・削る)」のどちらもを等価に扱っていることである。つまり「写真の表象」と「写真の物質的欠損」という次元の異なるものをどちらも表現の素材として最終的にフォトグラフィック•オブジェクトを構築するものとして扱っている。写真的には「破壊」である行為もフォトグラフィック•オブジェクトにとっては「創造」になるというパラドックスが作品の下敷きになっており、それが異なる空間を共存させ、鑑賞者が自身の思考の中で再構築することを促す。 非常に身体的で、手業の痕跡が重要であるにも関わらず、ここで、最近再読したレフ・マノビッチの『ニューメディアの言語』にあったテキストを思い出させられた。
いまやその別の空間内に完全に位置づけられている。あるいは、より正確を期すなら、2つの空間ー現実の物理的空間と、仮想のシミュレートされた空間ーが共存しているとも言える。 レフ・マノビッチ『ニューメディアの言語』、みすず書房、2013年、p158
写真はこのことに今後より深く関与していくことは間違いない。 さら興味深い点は、表象として「現実らしいもの」こそ「シミュレートされたもの」で、(写真におけるアレ•ブレ•ボケに代表されるような)抽象的で「イメージ世界のものに見えるもの」こそが「ミートスペースに実在するもの」というここにもパラドックスが重ねられており、思考を転倒させられていて非常に面白い。 本来、ぶつかり合うはずのなかったものがぶつかり合ったのを目の当たりにした時、私たちがそれをどう理解をし、再構築して考えるのか…その「間」にどんなものを見るのか?中間地点にこそ価値生成の可能性があるのではないかと最近考えている僕としては非常に刺激となる作品であった。
そして、ゼミ仲間と観に行き、作品について話したことで思考の奥にあったものを引きずり出したことが今回はとてもよかった。
「ゆだねながら語り合うこと/響き合う思考法」 :2022年5月3日−2022年6月5日 :MtK Contemporary Art
0 notes
Text
戦略会議 #02 展示まわり/PRIVATE HOUSE 生きられた家
会期後半のギリギリの平日に予約をとって「PRIVATE HOUSE 生きられた家」へお邪魔してきた。展覧会のコンセプト上、どこまで勝手に語って良いのかわからないので、軽く触れる程度に書いておく。 展覧会は練馬区のあるお宅で行われていたもので、僕らのゼミの教授である後藤繁雄が主催するSUPERSCHOOL onlineというオンラインのアートスクールのメンバーでキュレーションされ、展示されたものであった。昭和12年に建てた日本家屋で85年の歴史ある家屋だ。 写真を表現としてもの、嗅覚に訴えるコンセプチュアルアート、音声を媒介として現代における死というものを再考させるような場づくりがされたもの、文字を解体した現代絵画などなどその表現手法はさまざまであったが「これは何です」と一言で説明できない複雑性を内包した作品群とこの家によって成立する展覧会であった。作品はどれもこの「家」とのつながりの中で生み出されていて、ある意味での外部記憶メディアもしくは記憶の翻訳者として機能しているように思えた。 「生きられた家」というタイトル「生きられた」ということばの含む二重性というか、捉え方次第でどちらともとれるいい具合に馴染みのない言い回しが二律背反する何かをそのまま受け入れてたいい意味での不安定さをより際立たせる。 生きているまま死ぬこと、死んでいるのに生きているようにすること。 ���のどちらもこれからはできるようになっていくのだろうな…とぼんやり考えながら掠れたテープレコーダーの声を聞いていた。 ますますこれからはある意味で完全には死ねない時代だ。 僕はこの何年間か「生きられた」のか?そんなことを考える展覧会であった。
0 notes
Text
戦略会議 #27 超域Podcast / 「展覧会は写真か?」という問いと思考の中間地点の重要性。
修士時代に所属していて、現在非常勤とTAをさせてもらっている通信制大学院のゼミの在校生、卒業生とともにコロナ禍の最中に行われていた拡散型の対話を行う勉強会を理想形として、2月からポッドキャストの番組をはじめた。
超域Podcast: https://gotolabochoikipodcast.wordpress.com/ 4ヶ月経って、コンテンツが増えてきたこともあり収録と配信そのものはだいぶ慣れてきた。
現在6つ目のテーマである「展覧会どうみる?」というシリーズが最新として配信されているのだが、自分自身でその配信を聞き直して思うところをいくつか書いておきたい。 ゼミ仲間の水田さんをゲストに迎えた今回、展覧会をつくるプロフェッショナルを入れての対話であったこともあり、いつにも増して対話は深く深くマニアックに拡散を続けた。思わず夢中になって「写真」に対しての現時点までの自分の思考を思いっきり吐き出してしまったりもした。足並みを揃えてみんなでせーのと「なるほど」を共有する勉強会もいいが、僕自身としては、ゼミの教授の突き抜けた講義に慣れてきているせいか…参加者を思いっきり置いてきぼりにする対話の中にこそ「学び」の価値を感じてしまっている。僕ら人間の想像力はスタート地点にもゴール地点にもなく、その中間地点に表れるものなのだということを最近改めて考えさせられているからだろう。特に現代になってますますその傾向が強いように思える。 ポッドキャストの対話はほとんど、ぶつけ本番で行われ、収録した��のままのものを配信用のコンテンツとして使っている。対話は即興的に行われていて、それぞれこれまでに学んできた知識を総動員して誰かの言葉に反応する。これが結構大事で、このタイミングで(知っているだけだった)「知識」を自身の対話の「道具」として使うことになる。残念なことに浅い「知識」は自身の道具に成り切っていないので上手いこといかないものである。「付け焼き刃」とは上手いことをいったもので、「道具」に成り切っていない、つまり包丁になっていない知識はただの鉄であり、生み出されてくる会話を上手くは捌けていない。 ただ、重要なのは上手く捌くことばかりではない。一度「道具」として使ってみることそれ自体が重要なのだと思う。勉強会配信のポッドキャストの利点は自分が「知識を道具として使えているのか?」ということを確かめることができる。要するに自己フィードバックが出来ることである。 あー本当はこんなことが言いたかったわけじゃないんだけどな…とか、こっちの考え方で話した方が正しかったかな…とか…実は結構上手く行っていないことも多々ある…でも、それでいいのだと思う。
誰かが生み出したある点とそれが向かう先の別のどこかとの間に反射的に生まれた思考に「それはちがうよ!」って自分にツッコミを入れながら思考をアップデートする。何でもわかった気になれる時代、誰かの思考をまるで自分のもののように感じれてしまう時代において価値も意味も実は、中間地点に表れる。今回の配信でいえば「遠くにいるからできること、考えられることがあっていい。目の前の大変に目がむくでいいのじゃないか?」って今回の対話の中で言ったのだけど。本当に言いたかったのはそういうことではない。体験が伴わない他者の痛みに思考の全てを向けすぎるのはいかがなものかというのが本質で、シミュレーションの中には現実はない。他者が作った結論だけを自分の知識にすることにはあまり気が進まないということなのかなと思う。最終的に自分自身に引きつけた検討が成せるのも、反射的に自分自身がことばを絞り出しているからであり、自分が作り出した中間地点にツッコメるからこそだ。 水田さんとの間で出てきた「展覧会は写真か?」という問いはこの中間地点に関することそのものに関するのでさらに興味深い。
後編の最後あたりの話に出てきた韓国の岸壁の壁画の話。実物がどのくらいあるのかはわからないがきっと現場では一望はできないものなのだろうと思う。そうすると全体像を把握しようとするためにはあちこちを走査することになる。つまり、鑑賞者は部分部分をスキャンしながら解釈を創造するわけだ。一望できないというのは結構ポイントで、一度に把握できない壁画は全体の時間を空間化していることになりその中を移動しながらモンタージュを作ることになる。そして、その空間的モンタージュは鑑賞者にそれぞれに独自の時間性をもたらすこととなり、そのインタラクトすることによって意味が生成されることとなる。つまり、それぞれに独自のナラティブを生成する。これは
1920年代以降、映画のモンタージュのような新しい語りの技法によって、観客は互いに関連のない画像のあいだの精神的なギャップをすばやく埋めることを強いられた。 レフ・マノヴィッチ 『ニューメディアの言語』 p107
とマノヴィッチが言っていることであり、それは展覧会の中で作品と作品との間に起こることにあたるのだろうし、そういう意味で展覧会が映画的もしくはゲーム的であるとも言える。そして、そこを経由して行くと確かに展覧会も写真的である(写真性を持っている)ともいえるように思える。配信内では「ポジフィルムに長時間露光」と例えたが、実際は空間的モンタージュなので「長時間露光の多重露光」という方がより正確だろうかとは思う。 ごちゃごちゃと書いてきたが、いいたいことは大きくはふたつ。 現代における人間のできる価値生成は中間地点で起こるということ。たぶんこのことをさまざまな人がさまざまな言い方でいっている。FLOWとか流動性とか、不確定性とか、マイナーな言語もそうだろう…僕は「間質的なもの」としているが、これ自体がそもそもアートのキモだ。 その価値生成を理解して世界を捉えるには人が作った「知識」を自分自身の「道具」としてちゃんと使えるようにすること。その訓練には対話のアウトプットとフィードバックの仕組みがあることが最適だということ。
【超域Podcast】シーズン6「展覧会どうみてる?」 https://bit.ly/3a9YPvI
0 notes
Text
戦略会議 #27 超域Podcast/ 「私たち問題」と「倫理」について
コロナ禍がはじまって以来、2年間続いている週3回のゼミの勉強会。この勉強会は当時コロナ禍で年8回という限られたスクーリングの機会がオンラインへと移行したことを補って余りあるほどに機能したもので、モリス・バーマンの『デカルトからベイトソンへ——世界の再魔術化』がゼミの必読書でもあったこともあり、積極的な「参加」の意識が生み出す集合知というもののチカラを目の当たりにするものであった。今年に入り、2月のアタマからそのゼミの勉強会の様子を月1回(現在は2回)収録し、ポッドキャスト(参照:「超域Podcast」)として公開することを試し始めた。僕としてはこれはヴィレム・フルッサーの「文化的コミュニケーション」についての理論の実践だと思っている。
情報操作のプ��セスは「コミュニケーション」と呼ばれますが、二つの段階に分かれます。第一段階では情報が作り出され、第二段階では記憶にもたらされ、そこで貯蔵されます。第一段階は「対話」と呼ばれ、第二段階は「言説」と呼ばれます。(中略)対話��作られた情報は、言説において流通します。 ヴィレム・フルッサー『写真の哲学のために』、深川雅文訳、勁草書房、1998年、p65
大学院も4月から五期目に入り、学びが充実してきたこと。そして、僕としてはゼミでの対話によって生まれた「情報」は「価値あるもの」だと思うようになってきたこと。それぞれ問題意識をもって入学してきた社会人がコンテンポラリーアートを通しての学びの中で変化した視点や考え方、経験というのはとても魅力的で、常にちょっとずつ新しい「何か」を生み出し続けているということ。そして、これらのことから考えこの学びを「言説化」しておくべきだろうということに至ったのだ。タイミングよく人に薦められてどハマりした「超相対性理論」というポッドキャストをヒントにしてフルッサーの言うところの4つの言説の方法のうち、空間へ放散する大衆化という方法を選んだということになる。ちなみに、これは「写真の流通」とも同じ方法で、現代写真アートにおける言説のひとつの方法とも言える。そして、参照元の「超相対性理論」のメンバーも配信の中で言っていたが、この方法は非常に充実した学びをもたらす。まだまだニッチなコンテンツなこともあってか、Apple Podcastランキングでカテゴリーのランキングでは常に割と上位にいて、総合5位まで上がったこともあったことからも視聴者にとっても多少は意味あるコンテンツとなっているのではないかとも思える。
毎回、Slackにガーッとトークテーマをあげた中から事前に選んで、収録の日にフリーで対話をする。多くはゼミの中でも度々登場するキーワードであったり、誰かしらがその時に気になっている問題であったりする。今のところどんなテーマであっても話が前に進まないことはない。これはそれぞれが何かしらを共有しているからでもあり、テーマとしてあげられた時点でそれなりに共有すべき同時代的なことであるということなのだろうと思う。 先日新しいシリーズとなるテーマ「私たち問題」について卒業生3人で対話をした。今回のこの「私たち」というテーマも事前にあげたうちの中から選ばれたひとつであった。このテーマをあげた背景としては、つい先日卒業した人たちの昨年度の修士論文で直接的には触れていないが、何人かの背景でゆるく繋がる共通の問題として現れているように思たこと、2020年の展覧会においてオラファー・エリアソンが「Little Sun」を使った体験型の作品《Sunlight Graffiti》において「私 I」と「私たち We」の問題を取り上げていたこと、それにユク・ホイの『再帰性と偶然性』を先日読み終わって考えたこと、さらにはゼミの別プロジェクトに関連してテキストを書いているワリード・ベシュティ��ETHICS』を読んでいたことなどが複雑に頭の中で絡み合って…いや、「倫理」「アート」「私たち」「西洋思想」はもしかしたら絡み合う問題なのではなかろうか?同時に考える問題なのではなかろうか?という仮説が立ち現れてきて、それが何の問題であるのか?という、つまり「西洋思想の限界」とか言われるものであったり、現状の国際状況などという現象的なこととがどう繋がるのか…繋がらないのか…そんなことがぼんやり思えてきて、とても自分ひとりだけでは昇華し切れないテーマとなっていた「私たち」を対話のテーマにしたいと考えたものであった。結果から言えば、充実した勉強会となり、お互いに共有したことはたくさんある。そして、僕は僕なりに上手いことはまとまらないかもしれないが、前に進んだ今思う部分を少し書いておこうかなと思う。
大学院に入って以降、カントにはじまり、フルッサーの『サブジェクトからプロジェクトへ』、マイケル・フリード「芸術の客体性」、モリス・バーマンの『デカルトからベイトソンへ——世界の再魔術化』と何かとこの「主体と客体」という二元論の問題は過去にもブログで書いたが(参照:「戦略会議 #21 論文研究準備/ 主体と客体」)、良かれ悪かれ常に登場する問題であった。「主体」とは対象世界である「客体」から区別して「ワタシ」を認識するという…西洋近代を支えた思考のある意味での限界が「西洋の没落」みたいなものを生み出し、東洋の思想へと接近が生まれる背景となっているとも言える。 一方で、ワリード・ベシュティが前述した『ETHICS』で
An aesthetics of ethics offers the possibility of distinguishing between means and ends by enacting a shift from a hermeneutic approach, which emphasizes decoding, to the study of the means by which that thing being examined comes into being and is circulated, in short, how the work creates conditions of reception, how it makes whatever its message is perceivable. Walead Besthy,”ETHICS”,Whitechapel Gallery, 2015, p12 (倫理学の美学は、解読に重点を置く解釈学的アプローチから、調査対象が存在し、流通するための手段、つまり、作品がどのように受容の条件を作り出し、どのようにそのメッセージを知覚可能にするかという研究への転換を実現することによって、手���と目的の区別の可能性を提供します。)
と述べるように「関係性の美学」以降のコンテンポラリーアートはプロジェクト型ではないオブジェクトワークであったとしても鑑賞者への受容やその流通の条件をどう作り出すのかという点が重要視されはじめている。デュシャンが思考の芸術として提示したレディメイドは鑑賞者との関係性という形で今日結実している。アート、つまり美的言説はどこに発生するのかという問いに対する答えは「鑑賞者の経験の中に」と言うのがコンテンポラリーアートにおける今時点でのひとつの重要な解答である。このことから言えることは、コンテンポラリーアートとはある意味で、鑑賞者にとって他者であるアーティストの問題、自分ではない他者の問題を鑑賞者である「私」がどう引き受けるか、どう「自分ごと」にするのかという「感覚的ものの分有」の問題であり、要するに「あなた」の問題を「私たち」の問題としてどう受容するのかということだ。つまり、芸術の受容の問題は「私たち問題」でもあるということなのだ。
英語など欧米の言語ほど主語の存在が厳密ではない日本人の僕としてはこれまであまり「私たち」を概念として意識したことがない。逆に「私たち」と強調して表現されることに対してはその政治的な側面、権威的な側面が気になってしまうといったネガティブな受け止め方をしていた。一方で「私たち We」というのは「私 I」以上に曖昧で抽象的である。どこまでを「私たち」とするのか?「私たち」とはそもそもなんなのか?今回の勉強会で「私たち」について話したことでこのあたりのことがだいぶ整理された。 「私たち」という概念は「アプリオリ(より先なるものから、の意)」ではなく、倫理的経験とその判断によってもたらされる「アポステリオリ(より後なるものから、の意)」なものであり、常に他者からの満たされない要求によって立ちあらわれる倫理的主体の問題である。
先行きの見えない不安定な世界情勢、すさまじいスピードで進歩するテクノロジー、コロナ禍というこれまでのアタリマエの通用しない日常…コミュニティや非人間の問題、新しい資本主義の問題、環境問題にいたるまで、今日の問題の多くは「私たち」の範囲設定の問題、つまり再領土化の問題だ。テクノロジーに関してはまさにユク・ホイが『再帰性と偶然性』で書いていた通りである。そして、それぞれに道徳的規範に沿って考えるということではなく、時代にあった倫理的判断を求められている。 なぜ今「私たち」について考える必要があるのか?「私たち」を考えるということはそれが何を示すのかということの解読と判断が常に必要で、倫理的な判断を下し続ける必要があるということだ。そして、このことこそが、実は西洋の二元論的な限界の超克へと繋がる方法として捉えられているのではないかということが今時点では考えられる。つまり、おそらく「倫理」「アート」「私たち」「西洋思想」というものは同じ問題意識に向かうピースとして考えられる。 と、ここまでめんどくさく複雑に書いてきたが、実際の収録した対話は和気あいあいとライトに対話がなされている。4月26日より3週にわたり毎週火曜日に配信の予定��� 【超域Podcast】 https://gotolabochoikipodcast.wordpress.com/

0 notes
Text
戦略会議 #21 アートライティング / ジェスパー・ジャスト 「SEMINARIUM」@PERROTIN
六本木のPERROTIN TOKYOで12月28日まで開催のジェスパー・ジャストの展覧会「SEMINARIUM」を観てきた。この展覧会はヴィデオインスタレーション作品である《Seminarium》と写真作品のシリーズ《Interpassivities》によって構成された展示であった。

主には4つの映像作品によって構成されたヴィデオインスタレーション《Seminarium》について感じたことを書いておきたいと思う。最初の部屋に展示された4つの作品はそれぞれ���組み立て式のLEDスクリーンによって立体的に組まれ、紫色に発光する女性の身体を映し出す映像と、理科の実験器具のようにも見えるガラスの花瓶とそれに水栽培されている植物と花瓶に取り付けられたプラスチック製のチューブと水を循環させるモーターそれに電源という構成になっている。 作品の展示形式的にはこの組み立て式のLEDスクリーンの展示はジェスパー・ジャストは近年NYのPERROTINなどの展示でも行っているようで、NYでの展示ではバレエのダンサーが本来筋肉系の治療などで使う低周波治療器(EMS)に音楽データを変換した電気を流し、それによって「動かされた」身体によってパフォーマンスを行うビデオ作品を展開したようである。奥の部屋にはこの映像作品と同様の内容での写真作品が展開されている。


最初の4つの映像作品もこの映像と同様の作品のものかと思ったが、どうやら違った映像で、4つの作品のうちひとつに映し出された女性は意味深なナレーションを発している。 植物はスクリーンに向かって茎を伸ば���、花瓶の中で根を伸ばしている。一方で、スクリーンの中の身体は組み立て式のLEDスクリーンと過去の彼の作品の展示も合間って、分解可能なものとして提示されているように思える。

LEDスクリーンと水栽培の水を循環させるモーターは同じ電源からとられており、スクリーン上で「再生される」女性とスクリーンの前の植物は、ある意味で同じ電源をその生命の動力源(エネルギー)としていることとなる。また、紫に発光した女性の身体は植物が光合成をするために必要な光となっており、LEDスクリーンが立体的に配置されているのはより効率的に光を植物にあて、光合成を促すためだと考えられる。この並置された植物とスクリーン内の女性はこの光合成とエネルギーを共有していることである種の共生をしており小さなエコロジーを形成している。メディアを通した奇妙さは感じられるものの、これは地球の縮図である。その意味でアーティストは創造主のようでもあり、種をコントロールするオーガナイザーのようでもある。 スマートフォンのカメラによって何もかもがイメージ化され、オンライン上にアップされた私たちの生は全てが複製可能、何もかもがコピーアンドペースト可能な時代へと向かっている。そうなった時、私たちの生とはなんなのか?身体的な経験と存在の価値とはなんなのか?そういった根源的な問いが彼の作品に通底し内包されているように思える。

0 notes
Text
戦略会議 #25 アタラシイアタリマエノカタチ / アタラシイアタリマエノカタチ京都巡回展「丼」展本日閉幕→オンラインへ
2020年4月、世界がCOVID-19、いわゆるコロナ禍によって混乱の真っ只中にある時に同期で京都芸術大学大学院に入学した博士課程4名、修士課程2名によって企画した展覧会が「アタラシイアタリマエノカタチ展」であった。 人類はコロナウイルスという脅威とどう共存しながらの生活をしていくのかという新たな命題に向けて登場した「ニューノーマル」という言葉によって今までの生活が「ノーマル」であるということを強く自覚させられる期間であったと思う。CIVID-19は様々なこれまでの「アタリマエ」に揺さぶりをかけ、つまりそれは本当に「アタリマエ」なのか?という問いを私たちに突きつけたのだった。今思えは、これは本来はアートや思想、哲学など人間自身が行わなくてはいけない仕事であったのではないかとも思える。何でも知った気になれる時代である情報化社会の中で思考停止になってしまった私たちが、もう一度世界との付き合い方を考える必要がある時代なのだと思う。 私たちは2020年4月に大学院入学したものの、大学の講義も含め全ての活動が後期の授業のはじまる10月までまったく顔を合わせることもなくすべてオンライン上で行われた。従来の「アタリマエ」であれば出来ていたであろう友人や大学キャンパスでの経験などはよほど積極的に動かない限りは失われてしまったのであった。 オンラインで行われた最初の講義後の時間を使わせてもらい、僕らは合わないながらも横のつながりを何とかして作れないか?つまり、講義室で隣に座れば何となく出来ていた友人関係や仲間というものを、この時代にどう作るのか?ということを模索したのだった。当初は緩く、広い範囲でオンライン上のSNSで集まった仲間の中に大学の助成金を使って「展覧会を企画しないか?」という呼びかけがきっかけとなってこの「アタラシイアタリマエノカタチ」はスタートした。その後ほとんどをオンライン上でのミーティングで進め、2020年11月に埼玉県プラザノース、2021年8月に長野県東急蓼科リゾート内、そして2021年11月ついに母校での開催となったのが今回の「アタラシイアタリマエノカタチ丼」ということになる。

過去2回の展覧会で展示した作品とそれをアップデートした作品などをそれぞれに持ち込み、大学院Pr PROJECTS Roomにて11月18日-23日の間で展示をした。4名の博士課程のメンバーのうち2名は博士課程を「制作・研究」で行っているためまったくの同期間で開催の大学院 「博士課程1・2粘性制作展 D#展 2021」にも作品を展示していた。どうせやるならぶつけようという今回の試みは、当人たちは大変そうであったが、結果としてなかなか集まれないメンバーの多くを母校である京都芸術大学に集まらせることとなった。
僕は大学院では「研究」のみなため、こちらの展覧会の会場にいる時間は自身の研究で生まれた問題意識と作品との接続点、距離感などをじっくりと考える時間となった。特に今回他の博士課程メンバーの作品のことも時間をかけて考えたことは非常に意義深いものであった。 先日も書いたことだが(参照:「戦略会議 #25 アタラシイアタリマエノカタチ/京都巡回展「丼展」」)、僕の現在の問題意識である「写真の物質性」の問題は
「写真(イメージ)の物質性」というものを考えた時、写真とはすでに物質世界を2次元平面の世界へと変換することには止まっていない。
多くのイメージは3次元へと容易に形を変えるようになってきて、図案を起こし、大理石を掘る手仕事が不可欠だった時代を考えると、隔世の感がある。ポスト・プロダクションの時代では、何かがつくられるというのは、ほぼ例外なく、イメージ(単一であれ、複数であれ)を経由した上での創造��為を意味している。
ヒト・シュタイエル『デューティーフリー・アート:課されるものなき芸術 星を覆う内戦時代のアート』、大森俊克訳、フィルムアート社、2021年、p270
というところへと繋がっていく。 今回の作品《The World as Blueprint:設計図としての世界 ーPetite Galerie Le Louvre》もオンライン上のイメージを設計図とし、世界のある一部を少数空間においてレプリカとしてコピペしてみせるという試みの中にある。 世界の全てがイメージかされアップロードされ、コピペとして利用される時代に私たちはそれに向き合った時に何を思うのか?そのことの実践を問いとして見せれないかというのが僕の問題意識である。 同様に、博士課程の他のふたりはそんな時代にあって、オリジナルや唯一無二であるということの価値とは何か?そして世界と触れるということはどういうことなのか?ということを問うものである。


同時代の抱える問題を別のアプローチで考え、次の「アタリマエ」となる今ここにはまだない考え方を考えてみようというのが僕らのやってきたことなのだろうと思う。
アタラシイアタリマエノカタチ展は実際の展覧会をメディウムとして最終的には本とオンラインでの展示というものが最終のアウトプットとなる。この美的言説の流通形態が前提であったことも僕の研究には非常に刺激のあるものであった。 今年の展覧会も、アーカイブして下記サイトへとアップする予定。 追って発表したいと思う。 アタラシイアタリマエノカタチ https://アタラシイアタリマエノカタチ.com
0 notes
Text
戦略会議 #02 展示まわり/西本春佳 個展「半年展」について
朝一京都から滋賀県の雄琴温泉の近くにある集落に向かっていった。目的はゼミの後輩の西本はるかの個展に行くためである。彼女は「人がいかに豊かな人生を送るか」という普遍的な問題に自身の実践を通して「絶対的私」という概念を構築し、観客論として書いて卒業した優秀な後輩である。
今回の展示は卒業後、移住し、現在彼女が住んでいる古民家の家屋を使ったインスタレーション展示であった。会場となった古民家は勉強会などで聞いて、想像していたよりはずっと綺麗な田舎の風景の中にある立派な古民家で、普段は月子茶屋というカフェとして使われているスペースを利用しての展覧会ということであった。

縁側の外の庭にはお茶会が出来るよ��にテーブルが出されており、到着した時にはそこに本人がいたのだが、一瞬誰だかわからず、開場と同時に着いたのにもう先客がいて、手を振っているのもこっちには入れないよ!と親切なおばあさんが教えてくれているのだと思ったぐらいであった。リアルな現実の手触りがイマイチ曖昧になっている。知っているようでいろんなことを実際は知らないのだなと思いながら車を停めて会場に向かった。
本人は不思議と高いテンションで迎えてくれた。いよいよ展示がはじまって、気持ちが昂っているのがよくわか��。玄関を入ったところの土間を上がったところの最初のエリアには彼女が在学中から書いているnoteからのテキストの出力が床に敷き詰められており、手前には
私はあなたの背中を押すつもりはありませんが これからのあなたの行為は否定も肯定もしません 全てあなたによって肯定してください
との文字が床に貼られたテープの上に書かれている。

このような言葉が家中のそこかしこに書かれている。縁側のガラスには、この集落での生活において感じたと思われる言葉が表裏の両方から書かれていたりここに住み始めてから半年の生活を垣間見せる。この入ってすぐのこの言葉だけは他と違うものであったのだということは後になって気がつく。 床に敷き詰められたテキストの出力の奥の居間にあるテーブルには本やぬいぐるみ、PCなどがテーブルに置かれており、座椅子と毛布が無造作に床に置かれている。床の間の面以外の3面にはピンク色の養生テープが貼られており、本人は「要塞」と読んでいたが、まるで「結界」のようだなと感じた。


畑仕事をしているのを知っていたので畑も見せてもらったが、無農薬故に自分が知っている畑というものとはその様相は異なるもので、だいぶカオスな感じであった。だが、それ以上にカオスになっていたのはWifiのルーターなどを含むコード類であった。明らかにこの家を含む集落というハードウェアと世界のデジタル化とのスピードが合っていないことがこいうところに現れるのだなと思えて少し面白かった。

自身が生み出してきたアウトプットにあたるブログの記事や論文集、トイレットペーパーの写真、図録、言葉などはピンクの「結界」の外にあることに対して、自身を作ってきたインプットにあたるものがこの「結界」のようなエリアの中にあるのが面白いと思えたが、現場ではそれ以上に感じ取れることはなかった。何かを大袈裟にこの展示のために作って空回りすることなく、これまでの自身の経験を編集して見せることで見事に仕上げている感じはおもしろいとは思ったが、ニュータウン育ちで人間嫌い、人の家に上がるのが苦手な僕としてはとにかく不得意なことが多すぎる空間であった。


小一時間滞在し、お茶を飲んでから会場を後にして大学へと向かった。 この日は、大学で自身の展示の設営をし、夜は大学の先生らと会って、翌日また大学で設営をしてから帰路についた…
京都を出て、車を運転しながらふと、あのピンクの養生テープに囲われた「結界」のような空間のことを考えていた。修士論文は観客論を書き、それは世界に対してどのように触れていくのか?という見事な手引き書となっていた、今回の展覧会はそれを実践してみせたというものであった。
結局あのピンクの「結界」はなんだったのだろう。。。 何かを思い違いしていたのではないかという考えが徐々に頭をよぎりはじめる。果たしてあれは本当に結界だったのだろうか?と。
少なくとも目の前に立った時にはそう思ったのだが、「入口の言葉」とこの結界内にあった予備の養生テープ…あのエリアを結界のように僕に見せていたのは果たして何だったのだろうか…


ギリシア哲学が対話によるものであることに対し、ブッダは自問自答によって世界の真理に辿り着いたといったような内容の話を聞いていたこともあり、思わず「なるほど」と声が出た。
あの展示空間は彼女の作り出した世界観ということではなく、僕に対しての世界そのものである。様々な仕掛けによって「あなたはこの状況でどういう選択をしますか?」という問い、つまり世界がどう見えていますか?ということを問うことを問うてきていたのだ。 つまりピンクの養生によって「結界」のように見せられたものは僕自身がそれを「結界」として見せているのだ。パーソナルスペースに対する意識が強く、気の強い子犬のような性格をしている僕としてはあの「結界」に足を踏み入れるということはよほどのことがない限りは有り得ない。。。それ故に張られた養生テープは拒絶の象徴となるのだ。おそらく、どのような方法であれ、内部に侵入することを本人は否定しないどころかむしろ喜んだのだろうということが1日半経ってようやく理解に結びつく。「絶対的私」の概念をもとに世界に向けてどのような観客になるのか?という画期的な論文同様、このインスタレーションも自分自身がどのような観客であるのか?ということを自問自答させられる仕組みになっていたのだ。 入口の言葉
私はあなたの背中を押すつもりはありませんが これからのあなたの行為は否定も肯定もしません 全てあなたによって肯定してください
はこの世界のルール設定だ。このルール設定によって、この展示空間は現実世界から切り離され、ある意味でここを舞台とするのだ。
この半年の集落での経験や畑仕事という世界との触れ合いなどおそらく、様々な点で「私」と「世界」との関係が揺らぐ経験をしてきたからこその展示だったのだと思う。自身の経験をメディウムとして、その境界線の���れを鑑賞者自身に追体験、自問自答させてみせるのだ。
0 notes
Text
戦略会議 #09 アートについてのひとりごと /エキソニモ 「CONNECT THE RANDOM DOTS」NFT作品アタリスギタ...
11月の4-7日の間、京都ではArt Collaboration Kyoto(参照:「戦略会議 #21 アートライティング/ Wade Guyton @Art Collaboration Kyoto」)が行われていた一方の東京では、ART WEEK TOKYOというイベントが行われていた。Art Collaboration Kyotoは日本のギャラリーがホストとなり、海外のギャラリーを受け入れて展示をしているアートフェアであったのに対し、ART WEEK TOKYOの方は都内4つのコースを回るアートバスが周回し、各エリアのギャラリー、美術館を巡るもので、バスの中でだけ聞ける音声によるアート作品を体験しながら、各地の展覧会を巡るというものであった。CADANとART BASELがサポートした新しいアートイベントとなる。
事前に行こうと検討していた中で、行きたかったSCAI THE BATHHOUSEが予約制となっていて行けなかったが、概ね行こうと思っていたところには訪れることができたが、移動を含むためそれほどの数を回れるものではなかった。 今回一番一番面白かった展示はwatingroomで行われていたエキソニモ「CONNECT THE RANDOM DOTS」であった。エキソニモはインターネットアートを中心にすばらしい作品を創り出すアーティストで、昨年の都写美での展示は本当にすばらしかった(参照:「戦略会議 #21 アートライティング/エキソニモ「UN-DEAD-LINK」東京都写真美術館」)。watingroomはアートフェアなどでは度々ブースを訪れることはあっても実際のギャラリーに訪れるのははじめてであった。 アートバスを降りて、少し歩いたところにギャラリーはあった。 ギャラリーの壁にはそれほど大きくはない白いペーパーがいくつかは直接壁に直張されており、別のものはその白いペーパーが黒いフレームに額装されて順番は一見するとランダムに掛けられていた。ペーパーにはどれも小さな黒いドットと数字が打たれており、そのドットを鉛筆のようなもの繋いでいったようなドローイングがなされている。ドットの数は入り口から部屋の奥に向かって倍々に増え、奥の壁に設置されたモニタを挟んで倍々に減っていくという形になっているように見える。それによって、入口から奥に向かって指数的に黒くなる深い海の底に潜るようなグラデーションがペーパーを跨いで構築されている。つまり奥のモニターの真っ黒さが谷の一番深いところのような構成となっている。


ドットと数字の位置はその白い紙の中で固定されておらず、紙ごとにいないため、これらはおそらくランダムに生成されたものであろうということは想像がつくのだが、それ以上の解釈をつくるのは作品解説を読む中で広がっていった。

実にシンプルに見える展示であったが、この展示「CONNECT THE RANDOM DOTS」はランダムにドットを生み出すアルゴリズムによって生成された数字の順にドットと数字、いわゆる「ドットつなぎ」のためのドットと数字によって構成された本のページでそれを繋いだものが展示されているのだ。
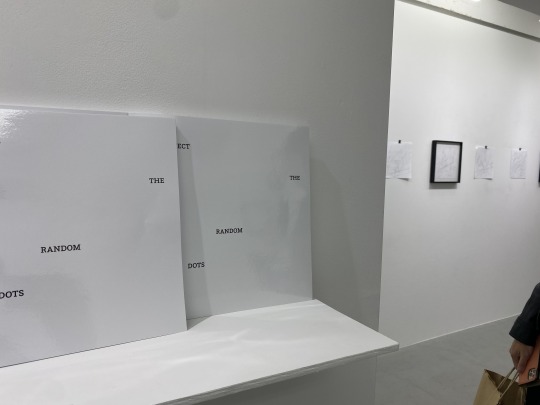
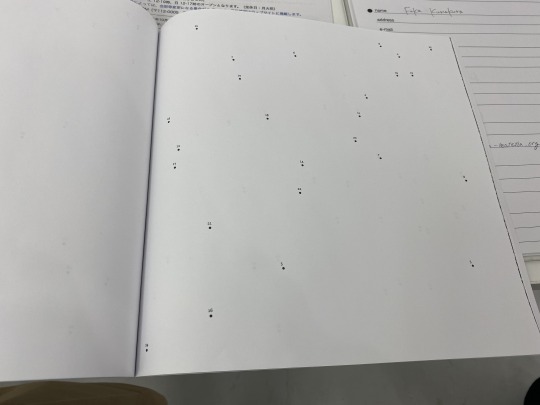
つまり、まずこの「ドットつなぎ」の本があり、それをエキソニモが実際に繋いだものがドローイングとなってそれが展示されているということだ。さらに、このドローイングは前述したようにページのあたまから徐々に指数的にドットの数を増やし、真ん中のページを挟んで、徐々に指数的に減っていくという構成になっている。この前半、後半でのドローイングは前半はしっかりと数字の順に、後半はランダムにとにかく点を繋いていくというようにドローイングのされ方が違っている。その違いは、ドットと線をメタファーとしてオンラインやSNSの発展もありどんどんと複雑化した人々の関係性が、ある地点今で言えばCOVID-19(コロナ禍)において見直す必要性を迫られ、新たな方法で線(関係性)を引き、再構築している様のようでもあった。

そして、この作品の最大の特長はこれらのドローイングによって構成され制作される本のページの所有権がNFTとして販売されているという点である。つまり、物資酢世界におけるオリジナルのオブジェクトが展示された「展示会場」、複製芸術となる「本」、そして非物質化された本のページの権利である「NFT」という3つの異なる階層によって構成された作品世界というものが作り出されている。実に複雑かつ階層的に「ドットと線」というシンプルに描き出されたアートの「価値」というものを問われている。何に自分自身が「価値」を感じるのか?ということである。ページの所有権となるNFTは会期中応募を受け付け、会期後に抽選によってランダムに当選者を決めて販売されることとなっている。応募には制限はなく、どれを選ぶか?どう応募するか?にも鑑賞者がどうそれに価値を感じたのかが現れる。 単に非物質的なもののオリジナルを証明するわけでもなく、単にアルゴリズムによるジェネラティブに自動生成されたイメージの価値を問うわけでもなく、大きな余白を残して、実に価値あることを考える機会を与えられていることを実感する。今回こそはじめてNFTを買い、コレクションする機会だと思えたので、応募することとしたのだった。 会期が終わり、いっしょに展覧会をまわった友人から「残念ながらはずれてしまった」という連絡をもらった。そういえばと自分のメールボックスを確認すると確かに「[CONNECT THE RANDOM DOTS] Lottery Result 抽選結果!!!!!」という件名のメールが来ていた。結果を確認する。

… なんと8点も当選している! どうしても今回コレクションしたかったので、全作品応募したのだが、 ランダム関数による厳正な抽選によって、8点も当選してしまった! なんと「ランダム」に愛された結果だろう。 明らかにアタリスギだ。 抽選の様子はギャラリストとエキソニモのふたりによってオンラインで行われ、その様子がYoutubeに公開されている。 https://youtu.be/IhqZHgfJ1i0 Youtubeを確認すると全作品応募しているのは僕だけだ。 「どう応募するか?にも鑑賞者がどうそれに価値を感じたのかが現れる」という意味では自分が意外と特殊なタイプの人間であることをやや自覚させられる。 応募時に名前を記載したのだが、、、それにしても「KEIJU KITA」出過ぎてる。そして、アタリスギテイル…変なとこで悪目立ちしまった。 けどまあ、いいにする。 全部は買えないので、さらに厳正に選んで購入の申し込みをした。 とにかく当たってうれしい。
0 notes
Text
戦略会議 #25 アタラシイアタリマエノカタチ/京都巡回展「丼展」
映画「イミテーションゲーム」からはじまり、Wade Guytonの作品(参照:「戦略会議 #21 アートライティング/ Wade Guyton @Art Collaboration Kyoto」)や、ヒト・シュタエルの本の表紙、最近何かと登場するアラン・チューリング。実はもうひとつがっつりと関わっていることがある。
今年の8月、長野県の蓼科にて展覧会を行った「アタラシイアタリマエノカタチ 2021」(参照:「戦略会議 #25 アタラシイアタリマエノカタチ/設営完了-僕らはまかない丼である。」)のポスターのデザインは実はチューリングパターンによるものであった。古いアタリマエと新しいアタリマエが混ざり合いながら、安定していき本当の意味でのアタラシイアタリマエというカタチを形作っていくということを示していたのだなと今更に理解をする。とてもいいデザインだったと思う。

昨日会場のペンキ塗りをし、今日明日で搬入する形で京都巡回展「アタラシイアタリマエノカタチ丼」展を11月18日(木)〜23日(火)の間で行う。2020年度大学院同期入学仲間の博士課程4名、修士課程2名というメンバーによる3回目の展示となる。修士課程の優秀なふたりが今年卒業してしまうので、このメンバーでの展示はもしかすると最後になるかもしれない。個性的な作品が不思議な調和を持って混ざり合おうとしていいところでこちらも安定している。 先日の大学のゼミで全然上手いこと作品についてプレゼンテーションができなかったので、少々整理してステートメントを書いた。今回の展示は昨年、今年展示したものの中から1作品づつの2作品。どちらも自身の博士課程の研究の中で生まれた問題意識をスタートとして作品化したものだ。

《The World as Blueprint:設計図としての世界 ーPetite Galerie Le Louvre》
2021 230×230×30cm フルカラーダイレクト昇華印刷、トロマット(ポリエステル)、アルミスタンド、樹脂
「写真(イメージ)の物質性」というものを考えた時、写真とはすでに物質世界を2次元平面の世界へと変換することには止まっていない。
多くのイメージは3次元へと容易に形を変えるようになってきて、図案を起こし、大理石を掘る手仕事が不可欠だった時代を考えると、隔世の感がある。ポスト・プロダクションの時代では、何かがつくられるというのは、ほぼ例外なく、イメージ(単一であれ、複数であれ)を経由した上での創造行為を意味している。 ヒト・シュタイエル『デューティーフリー・アート:課されるものなき芸術 星を覆う内戦時代のアート』、大森俊克訳、フィルムアート社、2021年、p270
と現代が置かれる世界の状況を鋭く描写するアーティスト、ヒト・シュタイエルは著書に記している。 オンラインに接続されたスマートフォンのカメラが世界の隅々までを撮影し、私たちが世界をイメージとして捉えるようになり、テクノロジーの進歩が様々な形式での出力を可能にした。これらの条件が整った現代において、写真(イメージ)はイメージ世界から物質世界をつくる設計図となっているということをヒト・シュタイエルは示しているのである。 2019年末から世界中を襲ったCOVID-19、いわゆるコロナ禍は私たちの生活から、人々の接触や接近というものの除外を迫った。それにより人が集まる場所は閉���を余儀なくされ、多くの活動の場が半強制的にオンラインへと移行した。美術館もその例外に漏れず、準備されていた展覧会は壁に作品がかけられたものの延期、場合によっては中止などということとなった。そんな状況の中、各美術館はバーチャル・ヴューイングなどを準備し、日本国内、さらには自宅に居ながらにしてオンライン上で世界中の様々な展覧会を訪れることが出来るようになったのである。これはオンライン上に物質世界とは異なったイメージ世界における体験を創造したと言える。一方で、冒頭のヒト・シュタイエルの話に戻れば、これは世界を再構築する新たなイメージ、つまり「設計図」が公開されたのだとという見方も可能である。 本作品《The World as Blueprint ー 設計図としての世界》はこのCOVID-19の期間に新たに構築されたイメージ世界を設計図とし、現実世界を再構築したものである。つまりコピー&ペーストするかのようにして、閉鎖され誰もが訪れることが叶わなかった美術館の壁を実物大の壁として現実世界へとプリントアウトしているのである。

《A.o.M(Aesthetics of Media)|Zoom 913 9757 4204》 2020 サイズ可変 ミクストメディア PC、プロジェクター、アクリル
《A.o.M(Aesthetics of Media)|Zoom 913 9757 4204》はCOVID-19、いわゆる「コロナ禍」の中で一躍世間に浸透したオンライン会議アプリである「Zoom®」を用いた作品である。
緊急事態宣言など人々の生活に制限が加わった2020年日本において、「不要不急」という言葉と並んで世の中に認知されたのは「テレワーク」であり、その実現の一旦を担った「Zoom」ではないかと考える。「コロナ禍」による人々が集まらない新しい生活様式はZoom®などのオンライン会議メディアを直接的なコミュニケーション��代替とした。日常生活でそれほどITやテクノロジーに頼ってこなかった人々の生活にですら突如として必要不可欠なものとして侵食してきたのである。「直接会わないとダメだ」と登場当初コミュニケーション不全を指摘する摩擦も起きたが、いずれ世の中に浸透しメディアがその存在感を違和感として示すことはなくなるであろうかと考える。そうなる前に、Zoom®そのものに自らの姿を晒させることでZoom®というメディアの知性や美学に触れることを試みたのが本作《A.o.M(Aesthetics of Media)|Zoom 913 9757 4204》である。
Zoom®は本来モニタ上部に設置された内臓カメラなどを使って利用者同士が自身を撮影しモニタ越しに双方の顔を見ながらテレビ電話のようにコミュニケーションを機能させるメディアである。本作ではUSBに接続した外部のウェブカメラにて「Zoom®」に「Zoom®自身(モニタ)」を撮らせて配信をしたものとなっている。つまりZoom®のセルフィー配信である。
カメラで自分自身を撮ったZoom®は合わせ鏡のなかのトンネルのように自らが配信しているイメージを反復させ、イメージの連続としての動画を生み出しつづける。この作品もアーティストはモニタとカメラの位置のみ設定をするが、それ以降はZoom®というメディアが本来のソフトウェアの特徴を活かし、展覧会会場と鑑賞者いうリアルの環境とオンライン上のZoomミーティングへの参加という二つの関係性を取り込みながら映像を変化させ抽象的なイメージを生み出し続ける。
ダン・グラハムの《Two-Way Mirror Power》やナム・ジュン・パイクの《TV 仏陀》、オラファー・エリアソン《Self-loop》といった先人たちの鏡やビデオカメラ、モニタを使った作品をリファレンス、アップデートした作品とも言える。本作品はそれらと同様に瞑想的な空間を作り出す。 本作品《A.o.M(Aesthetics of Media)|Zoom 913 9757 4204》には遠隔で下記からも参加可能:
https://us06web.zoom.us/j/91397574204 ミーティングID: 913 9757 4204 ※2021年11月18日〜23日 全日 12:30-1730の間利用可能

博士課程の研究発表展である「D#展」もギャルリ・オーブで開催されており「アタラシイアタリマエノカタチ」メンバーの博士課程のうち2人は両方に出展している。併せてご覧いただければ一層楽しめるかと思う。 さて、展示できたよ。 「アタラシイアタリマエノカタチ 丼」 京都芸術大学未来館2階PRルーム DATE:2021年11月18日(木)〜23日(火) OPEN:12:30-17:30
0 notes
Text
戦略会議 #26 POST/PHOTOGRAPHY/2022年度大学院紀要リポジトリ公開。「シャーロット・コットン『写真は魔術』の再検討による「POST/PHOTOGRAPHY」論」
2022年度の京都芸術大学大学院紀要のリポジトリがいよいよ公開になった。

昨年に続き、今年もエントリーした。昨年はワリード・ベシュティというコンテンポラリーアートのアーティストについて自信が観てきた作品を事例として作家研究をし、かなりラディカルに写真というものに向き合うことでわかってくる写真表現の領域拡張に関する論文となった。写真というメディアにおいて、デジタル化のみならず領域拡張が進んでいることは誰しもが少なからず感じているのだろうことは論文リポジトリの閲覧の多さ、ダウンロードの多さからも伺い知ることが出来た。少しは写真の議論を前に進めることに役に立てただろうか?と日々自問自答する。(参照:「戦略会議 #23 ワリード・ベシュティ/ 何者でもなくなっていく自分と紀要論文の現在」)
今年はこの写真表現の拡張にいち早く対応し、コンテンポラリーアートの写真を牽引してきたロンドンの写真キュレーターであるシャーロット・コットンの新しい著書『The Photography as Contemporary Art』(2021)を参照しながら、同じく彼女の著書『写真は魔術』(2015)における「写真の物質性」というものを事例をあげながら再考した。
この本はアートの中における写真の現在の状況、その文化的地位をある一つの視点から考えます。(中略)この文脈でもっとも重要なのは、写真の物質性(マテリアリティ)が経験されうる方法、またそれが表し促すものが極めて自由で、様々なものを包括しながら同時に拡張しているという点なのです。
シャーロット・コットン、『写真は魔術』、深井佐和子訳、光村推古書院、2015 年、 p. 7
自分としては我ながらなかなか興味深い写真論、ポスト・フォトグラフィ論の一部を書けたと思っている。この部分について今ならばどんな視点に立ち、写真の地平に何をコットンが示そうとしていたのか少しだけ理解できるようになったのではないか?と思える。 以下に今回公開されたリポジトリを共有しておきます。お時間ある時にぜひ。 京都芸術大学 学術機関リポジトリ 京都芸術大学大学院紀要 2号「シャーロット・コットン『写真は魔術』の再検討による「POST/PHOTOGRAPHY」論」 論文執筆にあたり、画像掲載のご協力を快く受けていただいた、横田大輔さん、多和田有希先生、RICOH ART GALLRYにはこの場を借りて、重ねてお礼を述べたいと思う。 論文公開されると自分自身の思考が客観視されるし、なんとなく身が引き締まる。。。
1 note
·
View note
Text
戦略会議 #21 アートライティング/ Wade Guyton @Art Collaboration Kyoto
開催決定からずっと楽しみにしていたアートフェアを訪れるため、弾丸日帰りで京都へ向かった。目的地は国立京都国際会館で行われている「Art Collaboration Kyoto」である。 「Art Collaboration Kyoto」の特徴は、日本を代表するコンテンポラリーアートのギャラリーがホストとなり、関わりのある海外のギャラリーのアート作品を京都へと誘致するという形式をとったこれまでにない新しいアートフェアとなっている点である。世界的なアートマーケットのサーキットの外側に位置する日本。香港などに比べて小さいと言われるアート市場の規模とその割に高いブース代との兼ね合。その他、様々な要素(ハードル)がこの形式によってある程度クリアされ、メガギャラリーの名前こそないが、海外の尖ったギャラリーの数々が名を連ね、日本においてかつてないほどのクオリティを担保したアートフェアになっていたと思う。今後も是非継続していってくれることを切に願う。
今回一番楽しみにしていたのが、日本のTaka Ishii GalleryとケルンのGalerie Gisela CapitainのコラボレーションによるWade Guytonの作品である。Wade Guytonについては、京都芸術大学の通信制大学院の後藤繁雄ゼミに在籍中、講義の中で紹介されたWhitney Museumで展示していた真っ黒い出力に覆われた壁の作品を見たのが最初であった。Guytonは出力機を意図的に誤用し、イメージにノイズを発生させ、そこに非人間的な装置の意思のようなものを浮かび上がらせる。はじめて実際の作品と対面したのは2019年3月のART BASEL HongKongであったと記憶している。プリンターに流し込まれたリネンに出力されたイメージによるよるもので、かなり衝撃を受けたのを覚えている。僕自身の作品シリーズ、《A.o.M(Aesthetics of Media)−メディアの声に耳を傾ける試み》はこの展示を観たことをきっかけとしてスタートしたと言ってもいいと思う。(参照:「戦略会議 #25 アタラシイアタリマエノカタチ/北 桂樹|A.o.M(Aesthetics of Media)ーメディアの声に耳を傾ける試み。」)

今回のTaka Ishii GalleryとGalerie Gisela Capitainで展示されていた作品はGuytonがパンデミック中に制作した新作であるとのことであった。作品は縦90 cm程度の3つの作品と縦200cm程度の1つの大型作品からなる。キャンバス地にインクジェット印刷をしたものをフレームに固定したもので、イメージは厚さ3cmほどの側面までプリントされている。

これらの4点の作品は右から、 ① 床や壁面にGuyton自身の作品が見える「スタジオイメージ」 ② 紫という色と他のイメージが介入してきている「(おそらく)スタジオイメージ」 ③ ぼぼ画面全体を覆った「チューリング・パターン」で、底面に黒字に白文字で「/232.8M」という文字がみえることからスクリーンキャプチャであると考えられるもの ④白地に「チューリング・パターン」と何かのイメージが重ねれたもの、印刷の掠れのようなもので構成されたもの という4点の構成になっている。


①の「スタジオイメージ」や③の「チューリング・パターン」はこれまでもGuytonは他の作品でも反復して使っている特徴的なモチーフである。抜群にかっこいいのだが、これらがどんなことを示した作品であるのか?というのを考えるのはいつも通り、なかなかに難解であった。
今回も使われている「チューリング・パターン」とは先の対戦中、ドイツ軍の暗号機「エニグマ」を解析し、現在のコンピューターにつながる電子計算機の基礎を作ったイギリスの数学者アラン・チューリングが1952年に理論的存在が示された自発的な空間パターンのことである。詳しくないのでざっくりとした補足をすると
「ふたつの仮想的な物質が混ざり合う時、それは均一には混ざらず、濃い部分と薄い部分を作りながら空間に繰り返すパターン(反応拡散波)を作って安定する」 というものらしい。チーターやヒョウ、シマウマのなどの模様などの規則性もそれにあたるとされているようである。今回はこの「チュー��ング・パターン」をモチーフとして現代社会の様相を示した作品であると考えられる。 2017年にロンドンのサーペンタインギャラリーで行われた展覧会の図録を持っているのだが、実はこれがかつてないほどに理解不能なものであった。『Zeichnungen von Drama und Frühstück im Atelier Vol.Ⅱ』と題されたこの展覧会の作品は全て同ポジションで撮影されたイメージで、床に重ねられていく破かれた印刷物のページが重ねられ、重ねられ順と逆ににページネーションされた構成となっている。そして、表紙はまさに「チューチング・パターン」がデザインされている。


今回の「Art Collaboration Kyoto」での展示と共通するモチーフを使ったこの『Zeichnungen von Drama und Frühstück im Atelier Vol.Ⅱ(ドラマのドローイングとスタジオでの朝食 Vol.2)』と題されたその作品はスタジオの足元で展開された現代のドラマであったのだろうということが今回の展示を観て少し触れられた気がする。 小一時間作品の前に居て、①から④の作品の順番はおそらくこの順で展示をするようにというのはアーティストの意思であろうと思ったので、ギャラリーの人に確認すると、やはりアーティストからの指示でこの順番になっているとのことであった。このことから考えるにこの作品にも現実の「物質世界」に近い①のスタジオイメージからはじまり、④のコンポジットされたイメージに向かうある種の方向性が存在する。
④の作品内でクッキリと印刷された「チューリング・パターン」と何かが重ねられた2つのイメージは他の3点の作品とほぼ同サイズでプリントされている。このことによって、この壁面上には5つの作品がかけられているかのようにも見える。つまり、一番大きな作品の背景の白地を作品ではなく展示会場の壁面としてみることで「物質世界」と「イメージ世界」もしくは「バーチャルなオンライン上の世界」は④作品の中、もしくは展示壁面全体で一度境界線が曖昧にさせられ、再度混ぜ合わせれ安定する。つまり、この「作品か壁面か」という「図と地」の転倒は壁面展示上において「物質世界」と「イメージ世界」という2つの世界が様々な位相で濃淡をもって混ざり合いを引き起こす。まさしく「チューリング・パターン」が示すものそものものである。 4点のうち1点がこのサイズであることはおそらく戦略的なことであったのだろう。 帰宅後確認すると、『Zeichnungen von Drama und Frühstück im Atelier Vol.Ⅱ』でもおそらく同じことを示そうとしていたのだろうということが伝わってくる。モネの図録から破り取られた紙や新聞など様々な印刷物が重ねられていっているのだが、そこにはオンライン上の情報(Apple Air Podsのページなど)が重ねられている。「物質世界」の印刷物の情報に「バーチャルなオンライン上の世界」の情報が介入している。その状態こそが真の意味での「現実世界」なのだということをたびたび挟み込んでくる「チューチング・パターン」によっておそらく示していたのだろう。これこそが現実のドラマであり、「現実世界」はもはや「物質世界」のみでは語れないということなのだろう。 Covid-19が引き起こしたパンデミックはこの現実を私たちにより強烈に感じさせる出来事であったということは僕自身も思うことである。対面とオンライン、様々な場面でこのふたつの現実の境界線は曖昧になっている。 ちなみに、現在読んでいる、ヒト・シュタイエルの著書『デューティーフリー・アート課されるものなき芸術 星を覆う内戦時代のアート Duty Free Art: Art in the Age of Planerary Civil War』の表紙も「チューリング・パターン」でデザインされている。内容もまさに世界をインターネット世界と物質世界との境界線を行き来しながら現実世界を考える思考の必要を迫るものである。「物質世界」だけで「現実世界」を理解しようとしてもGuytonの④の作品内のイメージ同様「チューチング・パターン」が重ねられたように「現実世界」は見えなくなってしまう。彼らは「チューチング・パターン」を2つの仮想的な物質ではなく2つの世界がもつリアリティの混ざり合いのメタファーとして現在に適用している。

「Art Collaboration Kyoto」非常に興味深い作品を観れて満足であった。Guytonに関してはじめて少しだけ指先が触れた感じがする。引き続き研究していこうと思う。
===
Art Collaboration Kyoto https://a-c-k.jp/ 2021年11月5−7日 国立京都国際会館イベントホール
#21#アートライティング#Wade Guyton#Art Collaboration Kyoto#taka ishii gallery#ArtCollaborationKyoto WadeGuyton Comtenporaryart ACK
0 notes
Text
戦略会議 #21 アートライティング/ホー・ツーニェン「百鬼夜行」@豊田市美術館
豊田市美術館、京都芸術センターとホー・ツーニェンの展覧会を周り、金沢21世紀美術館のダグ・エイケンへ向かうという映像作品を巡る週末であった。京都、水戸と巡回したピピロティ・リストの展覧会(参照:戦略会議 #21 アートライティング/ピピロッティ・リスト:Your Eye Is My Island -あなたの眼はわたしの島- @京都国立近代美術館)といい今年は映像作品が当たり年である。

シンガポールのアーティスト、ホー・ツーニェンに関しては今年の5月に山口情報芸術センター(YCAM)での「ヴォイス・オブ・ヴォイドー虚無の声」が僕にとっては今年イチの展覧会であったことからも自ずと期待が高まる展覧会であった。(参照:戦略会議 #21 アートライティング/ホー・ツーニェン《ヴォイス・オブ・ヴォイドー虚無の声》@YCAM)
今回の「百鬼夜行」は美術館の4つの展示室を使ったヴィデオインスタレーション作品で、それぞれかなり暗くセッティングされた展示会場に関連性がありながらも異なった見せ方をした一連の作品によって構成された展覧会であった。
最初の展示室に展開されていた《100の妖怪》は2つのプロジェクターによって映し出された大型な横長の映像作品と少し��れた位置に平行するように4分の1程度の大きさ、網状のハーフトランスペアレンシーの床置きのスクリーンに映し出された映像という二つの映像によって構成されたヴィデオインスタレーションである。横長の巨大なスクリーンの映像はおそらく、平安もしくは鎌倉時代あたりから現代もしくは未来までの(シンガポールに見える)風景へとスクロールし、続く背景の中を次々と個性的かつ奇妙な姿をした妖怪たちがその特徴を時折見せながら左から右へと練り歩くアニメーション作品であった。

深夜に徘徊する鬼や妖怪の群れ、およびそれらの行動を示すのが「百鬼夜行」であり、背景こそ特徴的ではあるものの、まさにこの映像はそれにあたる。特徴的なのはタイガーマスクと思わしき姿のものなどもちらほらと散見されていた点であろう。この辺りは他の作品を鑑賞することで明らかになっていく。

手前の半透明のスクリーンには日本の平安、鎌倉時代の身分の高そうな貴族のような男(配布資料によれば病床の源頼朝)からはじまり、着物の人、軍人やこども、オタクのような人までさまざまな時代の日本人の寝ている姿がモーフィングするアニメーションで映し出される。そのスクリーン越しに百鬼夜行の様を透かし、二つのスクリーンをレイヤー構造として重ねて見ることで、妖怪たちが私たちが寝静まった深夜に想像するよりもずっと堂々と盛大に行われているということを思わせる。源頼朝こそ起きている状態であるためその存在に気づいているようではあるが、他の時代の人々はその存在には気づかずに寝てしまっているように見える。

2階の展示室へと進むと《36の妖怪》が展示されている。これも暗幕を潜り、暗い部屋でのプロジェクション作品となる。高さ3mほど、幅5mほどのスクリーンに《100の妖怪》にも登場した妖怪のうち36の妖怪がおどろおどろしいBGMに合わせた解説とともに次々と姿を表してはモーフィングアニメーションによって次の妖怪へと姿を変ながら紹介される。日本の統一にあらがうとされいる土蜘蛛(つちぐも)からはじまり、鵺(ぬえ)など自然への畏敬の念、人々の怨念、言葉の中、人々の感情の中などから生まれた妖怪などが登場する。

解説は妖怪の登場当時の内容を平易な言葉で解説をし、妖怪というものがどのように私たち人間社会に登場し、関わるのかを考えさせられる内容ではあるが、妖怪によっては現代社会でもその姿を変えて存在するのではないかと考えさせられるものも多く含まれている。百目(ひゃくめ)などは情報化が進んだ現代の監視社会の姿そのものである。

また、これらの中には人間へと姿を変えて私たちの知る歴史に関与してきたと紹介される妖怪もいくつかいた。この妖怪を次々に紹介するという形式は江戸時代の遊びで「百物語」を模倣している。「百物語」では妖怪の登場する怪談をひとつ語り終える度に提灯の灯りをひとつづ消してゆき、最後のあかりを消した時にそこに本当の妖怪が姿をみせるととされていた。明治以降西洋的な思想が持ち込まれていこう日本では妖怪の存在というものをオカルトとして空想上のものとして扱い、現実世界から排除していった。みえないもの、いないものとして教育されてきたわたしたちには科学では説明のつかないことだけではなく、歴史的出来事、災害や厄災、事故や事件など日常に関わる様々なことに妖怪が関わっていたとしてもそこには気がつけなくなってしまっている。ここで紹介された妖怪のうちいくつか、のっぺらぼうやぬらりひょんなどは人間に姿を変え、第二次世界大戦に向かった日本の歴史に関わっていると紹介されている。

彼らは戦後そのまま社会へと溶け込んだという。最終の部屋の外で書籍資料の展示にて配布されていた展覧会資料には99の妖怪の紹介がされている。100はこの展示内で登場したちょうちんなのだと思っていたが、ちょうちんは妖怪ではなくやはり「百物語」で使われていた灯りとして登場したようだ。100に関してはこのあたりからも考えさせられる問題である。この作品では最後に登場するちょうちんが消えると展示室の照明が明るくなり、これまでスクリーンだったところが鏡となって鑑賞者を映し出す。これは現代社会を生きる私たちの中にも妖怪が含まれているということを示唆している。

3つ目の展示室以降は原作のある映画を加工したアニメーション作品である。そのため写真撮影が禁止されている。《1人もしくは2人のスパイ》は裏面から史実に基づいた画像や白黒の映画(おそらく「マライの虎」)をぼやけた映像で、表面からそれらを元に製作されたカラーのアニメーションを一枚のスクリーンを挟んで両面から投影しているヴィデオインスタレーション作品。アニメーションでは歴史上の実在する人物たちが《36の妖怪》でも紹介されたのっぺらぼうとして上書きされる。1938年に設立された「陸軍中野学校」では各部隊、大学から秘密裏に推薦された選りすぐりの者たちで、入学と同時に本名を捨て、過去と決別をする。このこれまでの自分の過去とのつながりの断絶が彼らをだれでもないのっぺらぼうとし、のっぺらぼうとなった彼らはその後、藤原少佐を長として組織された「F機関」の構成メンバーとなり、アジアの民族独立の支援と日本軍への協力のための諜報活動を行ったとしている。プロバガンダのために作られた映画そのものを素材、下敷きとし、そのプロバガンダによって作り出されているストーリーとしての歴史を妖怪の関与という大胆なフィクションによって上書きをする。1枚のスクリーンを挟んで前後から投影され重ねられ、時に大きくズレながら揺らぎを見せるこの映像作品は、まさしく歴史の表裏を見せており、京都学派をモチーフに1930、40年代の日本の思想界に語られてきた歴史と違う角度から光を当てて鑑賞者に歴史そのものの構造を見せた「ヴォイス・オブ・ヴォイドー虚無の声」を作ったホー・ツーニェンらしい作品であると感じた。こちらの作品も「歴史」そのものがモチーフである。
4つ目の展示室には2つのプロジェクション映像によって構成された《1人もしくは2人の虎》という作品。アジア全域に生息しではいたが、実際には日本はせいそくしなかった「虎」であるが、日本でも室町以降強さの象徴としてたびたび描かれてきた。アジアの人々を植民地支配から救う活動をした2人の日本人がいる。シンガポール攻略時の山下泰文大将とマレーで暴れ回った盗賊である谷豊である。谷は現地の貧民や弱者の味方をする義賊的英雄として敬われ、恐れられたと言われる。谷は「F機関」の勧誘によりスパイとなったとされている。その谷をモデルに1960年代に人気をはくしたテレビ番組が「怪傑ハリマオ」である。「ハリマオ」はマレー語で虎を意味し、強さの象徴として名付けられた。1980年代になると谷は映画「ハリマオ」として再び蘇る。アジア的な強さの象徴としての「虎」はその後もアニメ、タイガーマスクやうる星やつらのラムちゃんなど多様なキャラクターとして歴史に度々舞い戻ってきている。「マレーの虎」となった2人の日本人の話を室町以降描かれてきた日本画に現れる虎を切り抜き、パーツごと動かしたアニメーションと《1人もしくは2人のスパイ》のように史実の映像、映画にアニメーションを合成することで表現している。その映像からは2人の「マレーの虎」の登場にも妖怪たちが暗躍したことがうかがえる。
ホー・ツーニェンは「歴史」というものは固定されたものでなく、何かしらの目的をもって編み込まれ作られてきたものであるということ。その歴史を構成する要素へと分解しひとつひとつを丁寧に見せ、目の前で編み直してみせてくる。「歴史」とは過去そのものではなく、後から作られるものなのだ。その歴史へのアプローチを大胆なフィクションを用いてどのように触れるのかを私たちに提示する。またその際に、映像コンテンツをその内容だけでなく、映像メディアというものの特徴を活かし、視覚化し歴史の構造を見せるための装置としてうまく機能させていることが彼の作品の特筆する点であると考える。3つ目の展示室の《1人もしくは2人のスパイ》などがわかりやすいとは思う。史実に基づいた映像、映画にアニメーションを重ね合わせるだけであれば、最終のアプトプットをコンポジット(映像を合成した状態)で出すのでも問題はないはずである。しかしあえて、ホー・ツーニェンは透けたスクリーンに両面から投影するという形でこの展示を実行している。つまり、この映像には「表と裏とがある」というメディアの構造そのものも映像の内容だけでなく作品の意味を伝える上で重要な役割を果たしているということになる。歴史の2面性は映像の中身だけでなく、メディアの構造によっても示されているのだ。マクルーハンが言ったように「メディアはメッセージ」なのである。
3つ目の展示室《1人もしくは2人のスパイ》、4つ目の展示室《1人もしくは2人の虎》という作品こそが彼の示そうとした戦象前後の日本とアジアの「歴史」をモチーフとした作品であると思うが、「妖怪が関与した歴史」という下敷きを広くとったことで、これまでの歴史すべてをテーブルにあげ、歴史再考を私たちに可能性として提示して見せている点が素晴らしかった。必見の展覧会である。
0 notes
Text
戦略会議 #23 ワリード・ベシュティ/ 何者でもなくなっていく自分と紀要論文の現在
(予定では)3年間となる博士課程気がつけば折り返し地点を過ぎた。入学と同時にCovid-19が世界中に蔓延し、僕ら学生だけでなく大学もおそらく多くのイレギュラーな出来事を内包しながらとにかく学びを前進させる1年半であったと思う。この間、仕事もそこそこに思った以上に研究・学業にのめり込んできたので数年前までは「映像屋」だと思っていた自分が今は何屋かよくわからなくなってきてもいる。映像制作を辞めてはいないが、いい意味でそれだけでは自分自身が何者なのかを説明できなくなってきているということだ。カテゴライズ、何かしらの基準に規定する���いうのは簡単なことで、何者でもない状態でいることの方がむずかしいと思うのだが、今はこの状態がとても心地よい。このような状態はある意味でこの1年半のいわゆるコロナ禍という状況の中で判断してきたことがいい方向に出ているということなのだろうと思う。
自分自身を映像屋という枠組みから引き離し、何者でもない状態でいられるようにと別の側面をのある意味でのブランディングの一環として「researchmap」というのの情報を整理していた。「researchmap」研究者を検索するためのポータルサイトだ。所属を記載し、論文情報をCiNiiから引っ張って…と思ったら!

昨年の京都芸術大学大学院紀要で書いた論文「ワリード・ベシュティの思考の先に見る「これからの写真」。。。統計期間がこの1年なので相対的なものではあるが、京都芸術大学の学術機関リポジトリでまさかの閲覧1位になっている! 記憶している限りではたぶん、人生ではじめて1位になったぞ。いや、高校の地学のテスト以来か?たくさんの閲覧ありがとうございます。指導教官の教授のおかげでとてもいい感じに書けたのは間違いなかったのでうれしいな。 引き続きよろしくお願いします。今年度の論文も公開されたら共有いたします。 『ワリード・ベシュティの思考にみる「これからの写真」』 https://bit.ly/3ruOGNH 通信制大学院に入ってからの学びは本当に人生を変えている。明日の夕方から京都芸術大学の通信制大学院 後藤ラボの公開講座が行われます。ご興味ある方は下記から事前登録していただければ参加ができます。ぜひ! 【通信制大学院】10/16(土)16:20〜 後藤繁雄ラボ 公開スクーリング https://bit.ly/3aC0mI1
1 note
·
View note
Text
戦略会議 #26 POST/PHOTOGRAPHY/イメージの物質性ーラファエル・ローゼンダール|Calm @Takuro Someya Contemporary Art
今年度の大学院紀要は提出期限がかなり厳しく苦戦したが7月の末に最終的な内容でなんとか提出をした。今回の紀要論文は博論として「ポスト・フォトグラフィ論」を書き上げることを目指す中で、重要なパラダイムシフトのポイントであり、今後の議論のスタート地点となる「写真の物質性」について考えるものとした。
「写真の物質性」はライターであり、写真のキュレーターであるシャーロット・コットンが2015年の著書『写真は魔術』の中で
この本はアートの中における写真の現在の状況、その文化的地位をある一つの視点から考えます。(中略)この文脈でもっとも重要なのは、写真の物質性(マテリアリティ)が経験されうる方法、またそれが表し促すものが極めて自由で、様々なものを包括しながら同時に拡張しているという点なのです。 ーシャーロット・コットン、『写真は魔術』、深井佐和子訳、光村推古書院、2015年、 p. 7
と紹介したものである。コットンの名著『現代写真論』の後に出版された『写真は魔術』は80名以上(ほぼ1970年以降に生まれた)のアーティスの作品とシャーロット・コットンのエッセイ「写真は魔術」によって構成されたものであった。観客の目の前で行われるテーブルマジックを現代写真のメタファーとして取り上げ展開されたこのエッセイは、非常に示唆に富んだ豊かなものではあったものの、当時の僕にはどこか本質が捉えきれないものであった。そこから6年経った2021年、現在の視点をもってこの「写真の物質性」というものが何を示しているのか?ということを再検討し、「ポスト・フォトグラフィ」への道筋をつけ、イメージだけで語られることの多い写真に関しての議論を一歩先に進めることを目指したのが今回の紀要論文となる。 「写真の物質性」ということに関して、当初写真における「イメージ」と「オブジェ」の問題、つまり「イメージではなく写真を見ている」ということを中心に進めていこうと考えていたのだが、写真というメディアの特性なのか、どうしてもこの議論はイメージ優位の従来の議論を突破する破壊力を持つところまでには至らずにもがいていたというのが提出期限の1週間前という感じであった。徹夜明けの指導教官との論文指導の時間の後、ある展覧会に意識が朦朧とする中、足を運んでだことで展開は一変した。
翌朝駅へと向かう移動の中「今年はもしかしたらいいもの書けないかもしれないな…」とやや弱気に思っていた時にふと頭に降りてくるものがあった。
「これはスネ夫の髪型の問題なのかもしれない」
「写真の物質性」というものをこれまでの写真の考え方で捉えてきた。しかし既に議論の中心地はそこにはないのかもしれない。そこの前提を変えて思考してみることで、途端に様々なことが降りてきたのだった。これまでに書いていた内容の前提を大きく変更し、溢れるように出てくる言葉を紡ぎ、これまで苦しんでいたことが嘘のように論文を仕上げていった。詳しい内容は今年の紀要のリポジトリが公開されたら共有をする。
論文を仕上げて「写真の物質性」ということに理解が進んだことで、この問題がフルッサーの言うテクノ画像、いわゆる写真だけでなく様々なメディア、表現の問題に関わっているということが見えてくることとなった。この拡張こそが清水穣さんの言う「写真性」というところになるのだろうかと思う。。。
この忙しかった夏の期間に観た展覧会について少し書いておこうと思う。論文提出後の7月中旬からTakuro Someya Contemporary Artで開催中のラファエル・ローゼンダールの展覧会へ何度も足を運んだ。この世の中の状況的にそれほどの数を訪れたわけではないが個展としてはこの夏、文句なしの最高のものであった。
ラファエル・ローゼンダールはオランダ出身で、レンチキュラーの作品や、インターネットアートなどインターネットを発送の場として作品を制作し、ポストインターネットを代表するアーティストである。
■ラファエル・ローゼンダール|Calm 17 July - 28 August, 2021 Venue : Takuro Someya Contemporary Art

ギャラリー入り口に飾られたノートPCを開いたような壁面作品が印象的なこの展覧会では、2つの方向性(出力)によって制作されたものが展示されていた。ひとつは描画七宝(ペイント・エナメル)を用いた「Mechanical Painting」、もうひとつはプレキシグラスの「Extra Nervous」というシリーズである。どちらのシリーズもシンプルな平面構成によって構成された模様、もしくは壁にある窓や扉、エレベーターの出入口とったような境界線となるものをモチーフにしたイメージをもったものとなっている。
「Mechanical Painting」はエナメル・ペイント、つまりホーローであり、ガラス質の釉薬を支持体に焼き付けて作られた焼き物の作品ということになる。一見するとヌメっとしていて、艶やかな表面は丁寧に均一な表面に仕上げられたアクリルを透明のメジウムでコーティングしたようにも見える。作品は大きめで、焼き物であると聞いて急に作品の重さを感じるようになった。

一方、「Extra Nervous」は小さめのカラーのプレキシグラスにミラーの裏打ちをし、鑑賞者が作品の中に映り込むような作品であった。

これらの作品がいったい何であるのか…イメージは色面を構成した模様的であるため、何が描かれているかから何かを考えることは難��く、マテリアルとそのマテリアリティの体験から考察することにした。
どちらのシリーズも元々はローゼンダールがPC内で構成した色面の組み合わせであり同じ種類のデータである。テクノロジーのデジタル化の進歩によって、どちらもデータから出力によって制作することが可能となっている。つまり、印画紙ではないがこれらはどちらもプリント(出力)作品ということになる。その意味で僕としてはこれも「写真性」によって拡張された写真作品であろうと考える。しかし、これららの作品はプリント作品ではるものの、あくまでローゼンダールが作り出した、イメージ世界のものでありデータが見せるイメージは現実世界には由来したものではない。つまり、これらがもつリアリティはイメージ世界にのみ存在するものである。
これは僕が今回の紀要論文にて触れた「写真の物質性」と同様の問題を孕んでいる。それぞれの作品を生み出すイメージは同様のデータであることは、作品における鑑賞者の物質的な体験の差はイメージ世界のリアリティを現実世界へと持ち込む際に生まれる物質的な質量の問題によるものであるということになる。問題は出力の差、つまりアーティストの「選択」によって鑑賞者である私たちは同様のデータの持つ「イメージの物質性」の体験に差が生じることである。この差によってコットンが言っていた「写真の物質性(ローゼンダールの場合はイメージの物質性)」の体験がなされることとなる。 わかりやすい例をあげよう。「Mechanical Painting」において、色面の「境界線」はエナメルの釉薬の「重なり」によって表現される。つまりこの作品場合、青い釉薬の上に赤い釉薬が重なる、つまりレイヤー構造によって生み出されている。

一方で、「Extra Nervous」において、色面の「境界線」は色の境界線をそれぞれ異なったパーツの構成によって作り出すため、プレキシガラスとプレキシガラスの「接触」によって生まれることとなる。

これに限らず、出力の差によって様々な表現の差が現れる。これらのことが示すことが何であるのかということを考えるのがこの作品のおもしろさであった。 つまり、イメージ世界のリアリティを現実世界へと持ち込むということはこれまで、三次元世界を二次元平面に変換すると考えられてきた写真であったが、実際には二次元世界から三次元世界、つまり「現実世界をシュミレートする」ことこそが現段階での写真表現の主戦場であり、コットンが示した「写真の物質性」が経験されうる方法についての話なのだということだ。「写真の物質性」とは三次元世界にある写真という物質の話ではない。イメージ世界に私たちが感じる物質性の話であり、それをどう扱うのか?という問題である。
ここから考えられることは、テクノロジーの急速な進歩により、ローゼンダールのような作品も含む写真表現の世界はイメージだけでは語れなくなってきているというこである。さまざまな出力が可能となっているということは、「出力の選択」も「表現」となることを示している。写真が装置が生み出す「テクノ画像」以上、アーティストの思考やイメージが伝える内容だけでは作品の写真というメディアの本質には本来は辿り着けない。この点が写真の難しくもあり面白い点である。写真とは元来メディアアートなのだ。同様のことは写真の領域に限らず様々な領域を横断する形で同時多発的に発生している。そしてこれはまさに「スネ夫の髪型の問題」なのである。
0 notes