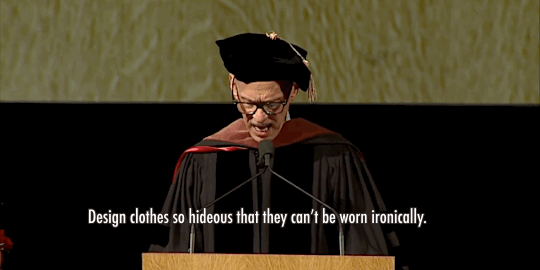Text
オクトパストラベラーはロールプレイングゲームではない
100時間あまりのプレーを経て、8人の物語の完結を見た。FFにもドラクエにもほぼ馴染みがなくて、なんとなくそういうジャンル(JRPGという呼び方はあまり好きではない)を敬遠してきた私が、10数年ぶりにターンベースのRPGゲームをフルプライスで購入したのは、IGNのレビューに心を動かされたのと、ネームバリューではなく、海外で高い評価を受けているらしいということからくる期待によるものだった。ゼルダ―ほどではないにせよ、ずっとプレーをしたくなるようなゲームであることを、100時間のプレー時間が証明してくれている。しかし、この魅力は私にとってRPGのそれではなかった。
主人公の視点の不在
オクトパストラベラーがロールプレイングというには、 主人公の視点がかけている。TESシリーズの歴代の主人公たちや、NeverWinterのようなD&DベースのRPGゲームでも、主人公のキャラクターがプレーヤーの視点として与えられる。同じ旅を一緒にしてくれる仲間がいるかどうかというのはこの観点においては些末なことだ。オクトパストラベラーは、一応形式として8人の中から一人を主人公として選んで、旅を始めることになるが、これは異なる視点を選ぶということを意味しなくて、初期の暫定的なクラスの選択に過ぎない。ゲーム開始から第1の段階では残り8人の仲間と出会うために、街を回ることになるが、8人全員を仲間に加えると、街の酒場で任意に入れ替え可能になり、キャラクターたちは攻略上のコマとなる。最初に選んだキャラクターは入れ替え不可能ではあるものの、その人を中心にストーリーが進んでいくわけではない。
昨年人気を博したNier: Automataの二人の主人公、2Bと9Sとを対照してみればわかりやすい。2Bと9Sの二人は同じストーリーラインを共有しつつも、視点を切り替えることで、同じストーリーの異なる側面を見せてくれる。しかし、オクトパストラベラーはこれの真逆で、8人はストーリーラインをまったく共有せず、しかし、視点だけは固定される――あるいは世界内の人物に特有な視点がまったくかけているということができる。誰を最初に選んでもプレーヤーが見る風景は同じだ。
演出上でこの点が目立つのは、イベントシーンの時だ。イベントシーンの時は、それまではそこらにいた街の人々が消えていなくなるだけではなく(このあたりの不自然さはIGNのレビューでも言われていたことなので割愛する)、そのイベントに関係のないパーティーのほかの人々も画面から消えていなくなる。まるで空気のような存在。違和感として強く印象に残ったのは次のシーンだ。プリムロゼのストーリーのなかで、街から離れた娼館を調査するために、かつて自分に仕えていた人の紹介で、娼館行きの馬車に乗り込むのだが、プリムロゼ以外の3人はどうやって娼館にたどり着いたのか説明できない。馬車に一緒に乗り込むには、娼館の秘密性と御者の友好的とは言い難い態度からは考えにくいし、乗らないで娼館に辿り着くのは無理とすでに説明されている。このような苦し紛れの演出になるのは、同じ世界で生きていて、旅仲間であるにもかかわらず、多元宇宙のように、8人のストーリーがお互いに絡み合わないからだ。
希薄なストーリー
8人が生きている世界には神話が設定されており、邪神であるガルデラが聖火神エルフリックらによって封印されていることが、物語が進むにつれて明らかになる。8人中の3人のストーリーがこのガルデラの話と絡むものになっている。邪神の力を得ようとしたり、邪神そのものの復活を望んだり、関連する書籍の蒐集に熱を上げたりと、それぞれ目的も手段も異なり、相互に助力して大きな陰謀に関わるというような話になっていない。ほかの5人といえば、そういう話とは関連せずに、成長、復讐、報恩、信頼、救助といったテーマの個人的な物語が展開される。8人それぞれ4章の話を終えてみると、最後まで絡み合わず、ガルデラへと収束もせず、あっさりと終了してしまう。高難易度マップとして、フィニスの門が用意されており、その最終ボスがガルデラのようだが、それはあくまでもサブストーリーだ。
相互に関連しないストーリーテリングは、ゲーム全体の目的の欠落のみならず――それを自由と呼びたい人もいるかもしれないが――それぞれのストーリーの薄弱さをももたらしている。例えばサイラスのストーリーラインで、知識の私蔵に執着するルシアが最終的に出てくるけれど、なぜ彼女がそこまで知識に執着するかはまったく説明されない。同じようにサイラスの知識への情熱もただキャラクターの属性として直接言われるだけだ。最終局面になって、サイラスとルシアの対峙がとても滑稽に見える。二人には知識に関する哲学的な立場の違いがあり、かたや私蔵にこだわり、かたや共有にこだわるということは繰り返し強調されるけど、そういう哲学の違いは最終的に武力衝突によって「解決」される。そういう哲学的な対立はストーリーとはならずに、むしろストーリーの薄さを敷衍するために持ち出されていて、最後はとても虚しく響き、人によっては説教くさく感じるだろう。同じことがアーフェンにもいえるし、テリオンにもいえる。この作品の人物は多かれ少なかれ、独自の哲学をもつけれど、哲学をストーリーに語らせないで、人物の言葉として、「感動」を強要するように、訴えかけてくるというのは押し付けがましい。しかも哲学的な対立はほとんどの場合、武力によってしか解決されないという水戸黄門的な古臭い勧善懲悪物語を利用しているところが、手抜きと思わざるをえない。
ターン制ストラテジーとパズル
オクトパストラベラーというゲーム――あるいはこの種のゲームというべきかもしれないが――の魅力がロールプレイにあるのではなく、ゲームプレイ(具体的にはバトルシステム)にある。なぜかというと、上で述べたように、ロア(物語)を追体験することがあくまでもフレーバーであり、バトルシステムに重心が置かれているからだ。
すでに多くの記事がバトルシステムについて紹介しているので、ここでは詳しい解説をしないが、その魅力がなにかということを理解するために、最低限のメカニズムの説明しておくことにする。オクトパストラベラーのバトルシステムの特徴は、ブレークとバトルポイントのシステムにある。ブレークというのは、敵に特定の弱点が設定されていて、弱点のタイプの攻撃を決められた回数をこなすと、敵が1ターンスターンして、そのあいだ、大ダメージを与えることができるというものだ。バトルポイントはそれに関連して、ターンごとに貯まる、攻撃力をブーストするためのポイントがあり、それを最大3回ブーストすると、一撃に大ダメージもしくは複数回攻撃が可能だ。バトルポイントを消費するターンではそれがたまらないようになっている。
この2つのメカニズムが戦闘を資源管理と分配のゲームにしている。戦闘において、HP、SP、BP(バトルポイント)、アイテム、ターンそれ自体が資源となる。とりわけボス戦においてはこのことが顕著で、ターンが伸びれば伸びるほどボスの攻撃が激しくなるので、そうなる前に決着をつける必要がある。HPやSPやアイテム、ターンを消費しながら、BPを貯める行動にするか、BPを消費していち早くブレークするかという選択はその都度緊張感に満ちたもになっている。一つの選択のミスが総崩れにつながる可能性がある。通常戦闘では、収支をできるだけプラスに保つように戦闘を組み立てる必要があり、いかに消費アイテムを少なく済ませるかがプレーヤーの腕にかかっている。エリアごとに敵の弱点の傾向性があり、バトルジョブがすべて開放されて、一人が実質2つのクラスを兼任できるまでは、その傾向に応じてパーティーを編成するという醍醐味もある。
ゲームが進展するにつれて、敵の弱点の配置がどんどん難しくなっていく。最初は敵全員が同じような弱点をもっていて、ブレークするまでの攻撃回数も少なく済むが、除々にブレークまでの攻撃回数が増えていき、属性の弱点もバラバラになり、弱点となる武器の種類も限定されていくことになる。難易度の上昇やバリエーションの変化のテンポがとてもよく、プレーヤーがある程度なれてくると、敵のタイプが変化し、プレーヤーにストラテジーを組み直すことを要求してくる。各マップもほどよい長さになっていて、ボス戦に突入するまで疲れ果てるというようなことはない。
プレーしていて、継続のモチベーションとなったのは、ストーリーの先を見たいという気持ちというよりは、次々突きつけられている難問を解きたいという気分だった。少し前にプレーしていたThe Witnessというゲームと似ていて、次々とやってくるパズルの洪水にのまれていくような感覚だった。もし、JRPGというジャンルはこのゲームによって定義してよいなら、それと洋ゲーのRPGの違いは、ゲームメカニクスによるプレイング駆動か、ストーリー体験駆動かということになるかもしれない。オクトパストラベラーはそういうことを考えさせてくれたゲームだった。
2 notes
·
View notes
Text
ヘイトスピーチの「自由」はあるべきか?――自由と責任について
最近ネットで、ヘイトスピーチについて、その自由を認めるべきか認めないべきか否かということについて喧々諤々と「論争」(とは呼ぶべきでもないようなものも含めて)が展開されていて、肯定する側は「ヘイトスピーチだって言論の自由のうちだろう」といい、否定する側は「他人の自由を制限するような言論の自由は(近代理念に従って)制限されるべき」という。私は後者の結論にはある意味では与するけれど、その論法には釈然としないところをずっと感じていた。何が釈然としないのかといえば、仮に自分を肯定側に立たせたときに、その論法にはあまり説得力を感じないからだ。というより、問題を回避されていると感じる。
肯定派が問いたいのは、あるいは依拠できると想定している問いは、同じ表現活動として、なぜ一方の自由は制限されて、もう一方の自由は制限されないのかということである。このような原則論のレベルにとどまっているときに、肯定派の答えは、「表現内容によっては表現の自由制限されるべきである」ということとして受け取られる。もう少し一般化すれば、「人間の活動は活動内容によってはその自由を制限されるべきである」ということだろう。この点について、肯定派の問いは答えられていなくて、否定派はその立場を表明しているにすぎない。そもそも肯定派の論法の強さはこの問いは「そのものとしては」答えられないだろうということにある。この点をもう少しよく真剣に受け取るべきである。
さて、否定派からの反論は、おそらくこうだろう。「我々はそれに答えている。他人の自由を制限するような、あるいは害するような行為は自由(の原則)それ自体を否定するからだというのがその理由である」と。しかし、「自由(の原則)」は特定の「行為」によって否定されるのはいかにしてか?「他人に死ねといったり、ゴキブリといったり」することによってか?特定の表現行為が他人の自由を制限することがありうるなら、例えば、安楽死に対する制限論を唱えるのは他人の自由の否定ではないのか?むろん、だからといって、このことを理由に安楽死の自由を推奨したいというわけではない。むしろ、他人の自由を否定してはならないという理由から、安楽死は容認されるべきであると推論すること自体の奇妙さを指摘したいのだ。(そもそもこれは「推論」なのか?)
特定の表現行為は他人の「自由」を制限する場合もありうる。例えば、サッカーのゲームにおいて、審判が「今の行為によってあなたは反則しており、よって退場してください」というときには、それのプレイヤーは退場しなくてはならない。このとき審判の表現(宣言)には「実効性」がある。日本国憲法にかかれている自由権(身体、精神、経済活動)は、サッカーゲームにおける審判と同様に、国家がその権力を使って、個人の行為を実効的に制限することに対して宣言されている――むろん、審判が選手の自由が制限をしているとは我々は通常考えない、言わない(このことの意味を考えることは自由ということの意味することを考える上ではヒントとなる)。しかし、ヘイトスピーチをする者たちには国家と同様な実効的な権力を持たないので(もし彼らが組織的に暴力を行使するならばそれは刑法等の法律によって対処されるだろうが、それはヘイトスピーチとの関連性を指摘でてきても別の問題である)、彼らの表現が他人の自由を否定するという時は、国家の権力が個人の自由を実効的に制限するとは少なくとも意味が異なるから、彼らの自由を、国家の権力行使と同じようには禁止できない。
次の問題を考えてみよう。中絶禁止論者は他人の中絶の自由を否定からといって、彼らの言説の自由は否定されるべきか。これと比較することによって問題の本質はいっそうはっきりする。我々は中絶禁止論者に対して少なくともヘイトスピーチと同様に禁止すべきとは通常考えないのは、言論を禁止すべきかという問題において賭けられているのは自由の原則の肯定や否定ではないからだ。自由の原則の否定という理由は、肯定派の問いに「きっぱりと」答えるべく持ち出された理由であると私は感じる。しかし、肯定派の問いの立脚点はそもそも自由の原則の「最大限」の適用であったことを思い出してほしい。意味することは何であれ、自由の原則の最大限の適用ということについては両者が合意している。つまり、この理由は肯定派にとってもあまりにも「自明」なことである。だから、私は自分を肯定派に立たせたときに、問いのポイントが回避されたと感じるのだ。肯定派の問いのポイントはどこにあるのかを理解するには、その自由の意味をもう少しはっかりさせておく必要がある。
ここで、もう一度サッカーの例に戻って見よう。もし審判に退場を宣言された選手が、それでも「私には継続してプレーする自由がある」と主張するなら、誤審だと思われない限り、私たちはきっとこの選手がサッカーゲームの審判の役割を理解しているのか、あるいはそもそもサッカーというもの(の規則)を理解しているのかと疑問に思うはずだ。なぜなら、この時主張された自由はサッカーのゲームというコンテクストを無視しており、それが意味するのは、せいぜいのところ「私はとにかく自分のしたいことをする」ということだ。この意味での「自由」は憲法で規定されたような自由とは意味が異なるのはたしかだが、だからといってこの用法が誤用だというわけではない。しかし、誤用ではないからといって、これがサッカーゲームにおいて退場を命じられたときに、継続プレーできる理由ともならない。「私はともかく自分のしたいことをする自由がある」というのは、承認するにせよ否認するにせよ、人間は自由意志をもって行動する生き物であるということの表現である。自由意志はときに権利のように思われることもあれば、とりわけ自分の行為(あるいは行為の回避)の結果において重荷となることもある(そういう時は「私はしかたなく○○をしたのだ」というかもしれない)。これは人間であることの意味の不可欠な一部を構成していて、すべての倫理的判断の前提である。それゆえ、我々がこの自由に対して反論しがたいと感じる:なぜならここに反論すべきポイントがないからだ(これを否定することが一体何を意味するかが不明瞭である)。
では、そもそもなぜ反論しなければならないと感じるのか?サッカーの例において、我々が反論したいとはあまり感じないのはなぜなのか?このことは人間の道徳(moral)の領域の性質の一つを明らかにしている。サッカーの例においては、ピッチにおける行為の解釈やその対処については明示的な規定がある。しかし、そういう明示的なゲームの外側にあるような、人間の道徳の領域は、そういう明示的な規定ができない。これは何をしてもよいということではなく、何をしてもその帰結の責任が個人的なものある。ある行為がどういうものとしてとらえるか、どういう行為が許され、許されないのか、それに対する弁解がどこまで必要か、必要でないか、どういうことがその行為の理由や言い訳(excuse)として妥当か、妥当でないかということをすべて含めて、その人の道徳的な立場(moral position)をあらわにする。これはサッカーゲームにおいてその行為と責任が極めて限定的であることと対照をなす。
つまり、ヘイトスピーチの自由の肯定論者がその問で明らかにしてのは、彼らはヘイトスピーチを(その結果「ゆえに」)表現の自由「として」行使し、その行為は(否定されない限り)表現の自由一般、もしくは人間の自由一般によって正当化されうるという彼らの道徳的な立場である。上でみたように、一般的に、人間の行為の自由がいかなる人間の行為の正当化もしなければ、その否定もしない。それは単にそうした行為に対する倫理的な判断を下すための前提である。ある意味人には殺人の自由はあるけれど、それによって殺人が許される行為で、それには厳しい結果が伴わないということにならない。これを表現という分野に限定しても話は変わらない。逆に、否定論者は、そういう行為は許されざる行為であると感じるが、それを非難するための「絶対的な」根拠がない――絶対的というのは、サッカーのルールのように解釈の余地もその解釈の責任も個人に帰されないようなもののこと――と感じるがために、自由の制限というあまりにも明白だが空虚な規則を持ち出す。しかし、その反論はかえって肯定論の正当性の根拠薄弱さを見えなくしてしまう。
肯定論はその本来の目的である正当化を果たしていないし、果たしえない。だからこそ、それは問いの形をとる。誤った問いによって、「ヘイトスピーチが表現の自由である」という主張の正当化の責任を相手に投げ渡すことがその問いの目的の一部である。だから、肯定論の問いに対しては「きっぱり」とした答えはありえない。しかし、それは肯定論は否定されなければ肯定されたも同然ということを意味しない。むしろ、それは肯定論者たちに、その正当化の責任を返すということにある。
(本エントリーは @Kaz_Yamamoto13 さんのブログエントリー https://twitter.com/Kaz_Yamamoto13/status/1023192874471628800 に触発されて書いたもの)
2 notes
·
View notes
Text
人間性の問い――新旧ブレードランナーの比較
・・・生きている人間または生きている人間に似ている(のように振る舞う)何かだけが、感覚を持ったり、ものを見たり、盲目であったり、音を聞いたり、聾であったり、意識があったり意識を失ったりすると言われる。(ウィトゲンシュタイン『哲学探究』第281節)
開かれた問い――デッカーととレイチェルの問い
ブレードランナーという作品は全体として、レプリカントという人間に似ている存在を通じて、人間性や魂についての問いを提起している。ファンの間では大きな論争を呼んでいた問題として、デッカードはレプリカントだったかどうかという問題があり、この問題を入り口にしてみよう。(ただこれは直接この問題に答えるためではない。)この問題をすこし身近に置き換えて考えてみる。仮に僕の友達がある日突然、実は自分は人造人間ですべて機械で出てきていると告げられたとしたら、僕は衝撃を受けるだろう。そこで、僕は彼にいつもは何を食べるのかと質問するかもしれないし、あるいは、夜は寝るのか、寝ている間に夢を見るのかと質問するかもしれない。しかし、仮に、彼は普段は何も食べず、夜寝ている間に、夢を見ないとしたら、僕は彼を友人として、あるいはそもそも僕と似たような存在――仮に人間であると認めがたいとしても――として扱うのをやめるだろうか?何が欠けていたら、僕は彼をただの物体として扱うだろうか?
この問いはレイチェルの問いと対照をなす。レイチェルは人間かレプリカントを識別するデッカードの試験を受けて、一見してとても人間らしい反応を見せたが、デッカードにはレプリカントだと見破られる。デッカードはそのことをその場でレイチェルに告げることはしなかったが、レイチェルはそのことに感づいて、動揺してタイレル社から逃げ出してしまう。ここで、僕らはレイチェルの動揺を想像するように誘われている。仮にあなたが日々、ほかの人たちと同じように、会社へ行き、仕事をし、仲間とビールを飲み・・・他の人たちと同じような生活していて、ある日、あなたの会社に検査官がやってきて、ひとしきりの検査を実施した上で、あなたは本物の人間ではないと直接告げたら、あなたは何を感じるだろうか?ここでレイチェルが僕らと同じように感じるかどうかわからないという言い訳の可能性は、デッカードの検査の質問に対するレイチェルの応答に仕方によって否定されているように見える。レイチェルの反応には不自然さは明らかになかったのだ。(さらなる言い訳として、それは検査を逃れるために計算した上の反応かもしれないといわれるかもしれないが、それなら、あなたが普段身近の人の反応が計算でないとどうして確信をもって言えるのか?レイチェルの計算と人間の計算の違いをどこでわかるのだろうか?)
そしてレイチェルの問題は単なるSci-Fiとしての仮定上でのみ存在するわけではない。奴隷制における黒人奴隷が聖書を根拠に、ホロコーストにおけるユダヤ人は優生学のような疑似科学によって、亜人間として扱われた歴史が人類にはあり、レイチェルが、たとえば瞳孔の拡張反応によって人間性を否定される可能性はそれらの歴史からそう遠くないのだ。実際反乱を起こした4人のネクサス6型のレプリカントの運命がそれを象徴している。彼らはいわばsub-humanとして奴隷のように扱われ、反乱を起こさないように寿命を4年に限定された上で、それでも人間に紛れ込もうとするレプリカントを狩るために、ブレードランナーという役職が設置されるというわけである。
しかし、この作品の結末は、救済の可能性を示そうとしている。一つはデッカードがリオンとの死闘の末に、屋根から落ちそうになったところを、リオンによって救われるという場面である。この場面において、リオンは屋根にしがみつくデッカードを見殺しにしさえすれば、プリスを殺された恨みは簡単に晴らせたのに、死期を悟ったリオンはデッカードの手を掴んで、屋根の上に引き上げる。ここで二つのことを示されている。一つはリオンが命の重大さを理解しているということ、そして、デッカードもまた自身と同じような重大な命をもつ存在として認めているということである。これは、ここまで「人間」が彼(ら)にしてきたことからすれば、実に驚くべきことである。ここに一つの救済の可能性が示されている。
もう一つはもちろんレイチェルとデッカードのロマンスと逃走である。デッカードにとって、レイチェルを愛し、レイチェルを匿い、レイチェルと一緒に逃げるということは、自身のブレードランナーとしてのアイデンティティを捨てることであり、レプリカント試験の有効性を否定するということである。レイチェルにとって、デッカードに愛されること、デッカードを愛することは、一旦否定されかけた自身の「人間性」の回復を意味する。ここにはもう一つの救済の可能性が示されている。
閉じられた問い――デッカードとレイチェルの子
さて、続編のブレードランナー2049はどうだろうか。2049はオリジナルの続編という体裁をとり、多くの設定を引き継ぐ。その中でキーとなるのは、やはりデッカードとレイチェルである。作品の駆動装置となるのはこの二人から生まれたと思われる子どもの探索である。探索の任につくのは、優秀なブレードランナーのKである。Kは製造番号の頭文字であり、デッカードような名前をKは与えられていない。そのことですでにわかるように、Kは警察の中で人間とは異なるものとして、あからさまな差別を受ける。例えば、彼の直属の上司のジョシ警部補があるとき、苛立って彼に向かって、おまえには魂なんかないと吐き捨てるシーンが出てくる。Kは子どもを捜索して殺害する任務を引き受けて、その途中で、失踪した子どもが実は自分ではないかと疑い始め、ついには確信に至る。そのことで動揺して、警察での安定性テストで、不合格な数値を出す。しかし、最後には自分の子ども頃の記憶が偽物だとわかり、その絶望の中で、ウォレス社に捕らえられたデッカードを救出して、本物の娘であるステリンのところに届けてから、階段で死にいく。
そしてこの顛末において、中心的な問いは生殖か人造かであり、人造が偽物で、生殖が本物として扱われる。最後のKの死の暗示ももちろんそのことを示唆しているが、レプリカント開放運動家たちや、ジョシ警部補や、ウォレスも生殖を重大な秘密として扱う。ジョシ警部補は生殖を人間とレプリカントの区別の最後の一線として、ウォレスは生殖をレプリカントを完全にするための最後の鍵として、レプリカントの運動家たちは生殖性を自身たちの運動のシンボルとしてみなしている。生殖の秘密が明らかになること、引き渡されること、失うことが彼らの存在意義を否定するかのようである。Kの失意もこの構図の中にとらえられている。
このことがKのジョイとシンクロしたマリエットとの情事にも反映されている。それまでジョイというホログラムに愛情を注ぐことがあっても、生身の女性に興味を示さなかったKは、自分が生殖で生まれた子どもだということがわかるととたんに、ジョイが呼んできたマリエットという娼婦を抱く。そしてこのことに対してジョイは嫉妬するどころか、積極的に協力をする。ことが終わったあとで、マリエットにぞんざいに扱われることにもジョイは抵抗しなかった。その後、デッカードを見つけたKがウォレスのエージェントに抑えられる場面で、あくまでもウォレス社の製品としてその人格的な存在意義が否定され、あっけなく破壊される。
一方Kはレプリカント開放運動家のリーダーによって、自分の出生の秘密が偽物であることを明かされるときに、大義のために自己犠牲をするように求められる。そしてその背後には同じような偽物の記憶を植え付けられた大量な名前もない戦士たちがいることも同時に明かされ、Kはその一員でしかない。このことを象徴するように、ジョイに与えられたジョーという名前の嘘を見破る場面が出てくる。
つまり、身体をもたないジョイはマリエットそしてKの補助として、生殖で生まれていないレプリカントたちは生殖で生まれたステリンを守る存在としてのみその存在意義が規定されている。本物と偽物との間には厳密な線――生殖――が引かれ、そこにはいかなるゆらぎも存在しない。人間性や魂の有無の問題が生殖によって閉じられてしまっているように見える。一見して、生殖能力をもつことで、レプリカントたちは人間と同様な存在になると見えなくもないけれど、実のところ、人間とレプリカントの分割線が、生殖で生まれた者とそうでないものの間に移動したにすぎない。そこには人間とレプリカントの境界線を揺るがすような問いの間隙はない。そういう問いの替わりに、生殖能力をもったレプリカントはあらゆる能力において人間と同等になり、実質は人間の一つの種(race)として、独立国家を建設するという話になっている。それは結果として、人間とレプリカントを別の人種として固定することになり、オリジナルとは逆の方向に向いてしまう。
0 notes
Text
人間を人間としてみなすということについて:奴隷制と中絶の問題
以下のはStanley Cavellの著書The Claim of Reasonから一部を抄訳したものである。出典情報をあげておきます。なぜこれをやろうと思ったかというと、ツイッター上で @ishtarist さんとのやり取りでこの部分を言及していたということと、僕自身がこの部分にかなり衝撃をうけていて、もう少し理解をしてみたいと思うからだ。
Cavell, Stanley, 1979, The Claim of Reason: Wittgenstein, Skepticism, Morality, and Tragedy, Oxford University Press. pp. 372-378
所々理解できない箇所や理解が怪しいと思う箇所には原文をつけました。
太字強調は僕が勝手につけた。
とても長いです。それではどうぞ。
人を人として扱うあるいは見なすことについて有意味に語る――あるいは(人間の)魂に表現を与えるものとして人間の体を見る、扱う、見なす――ことは、[上述と]同様に、人――あるいは体――が見られ、扱われ、みなされる、それとは両立しないような仕方があるということが前提とされるだろう。多くの人々、そして何人かの哲学者は、他���を物として扱うあるいは見なすことを非難する。しかし、ここでどんな可能性が描かれているのかはあまりはっきりしない。誰かがどんな物として扱われるだろうか(What thing might someone be treated as?)。
人が人以外の何物でありうるだろうか?ある人は王様であるかもしれない。王様を王様として扱うこと(ゴネリルとリーガン[二人はリア王の登場人物]は、いったん王様がいわば退位したなら、何が待ってるいかということが分からなかった)、あるいは王様が一人の人間(man)として扱われたいと願うことが何を意味するかについて、かなり(reasonably)はっきりしている。しかしよもやわれわれは王様は人(a person)であること(少なくとも一人の人(one person)であること)、人間(human being)であるということを疑うことなんてしないでしょう。物やヤギは王様ではない!しかし人間は、いわば彼もしくは彼女がそうであるところの人であるということに加えて、別の何かでなければならないだろうか――たとえば、主人あるいは奴隷、親あるいは子ども、作家、織工、よそ者。もし人々をこのような肩書のもとで扱う特定の仕方があるならば、それはそうした肩書を保持するために特定な振る舞い方があるからである。人間そのもの(human being as such)に特定な振る舞い方というものがあるだろうか。宗教や道徳が他人を単なる人として扱う義務について語るとき、そのことは他人たちの特定の肩書のもとで彼らに対する(owed)義務がいわば非―人間に対する義務であるということを含意しているわけではない。女、子ども、黒人、犯罪者は人間であるということが時々命令的(imperatvie)である。これは正義を呼び求めることである。正義がなされるために、認知(perception)を変えること、見方を変えることが呼び求められることがある。しかし、このことは、認知や自然の反応の変更を被らなければならない人々が、その時まで女、子ども、黒人、犯罪者を人間以外の何かとみなしてきたということを示しているだろうか。
時々奴隷所有者が彼らの奴隷をを人間としてではなく、むしろいわば家畜としてみなし、扱うと言われる。奴隷所有者のなかにはそういうことを口にすると知られる人もいる。また兵士が彼らの敵を人間として扱わないと言われる。兵士自身も時々そう言う。保守の人々は中絶問題に関して、リベラルの人々が人間の胚を人間とみなさないという。リベラルも時々同意せざるをえない。――しかしこのような主張を本気で信じる人がいるだろうか。私の感覚では、それらのことが本当に意味されることができない(My feeling is that they cannot really be meant)。もちろん言葉は何かを意味する。それらの言葉はランダムに話されたわけではない。それらの言葉が一体どんな趣旨で言われているだろうか(In what spirit are such words said?)。
奴隷の人間性を完全に否認する以外奴隷制がいかなる正当化の根拠も持たない時がくるだろう。制度(institution)それ自体が良いもの、あるいはとにかく疑問視されない時代があった。例えば、戦争の勝利の利益の一つである征服者の権利を履行することが残酷であるが合法であった。しかし、健全な精神のもつ人なら、中絶がそれ自体良いことであると考える人はいるまい。つまり、中絶が妊娠の利益(benefit)であるとか、性交渉の理由だとかとは考えないということである。ここに私がRoger Wertheimerについていけないと思う理由がある。彼が中絶の議論と呼んでいるものについて彼の傑出した論文において、奴隷所有者が奴隷の人間性を見出すことに失敗することを、リベラルが人間の胚を人間とみなすことの失敗になぞらえる(あるいはそれらの近似性について推測する)ことに私はついていけないのである。もっともリベラルな人の考えはこうである。中絶は道徳的な選択肢であり、その選択肢があることよりもその選択肢がないことのほうが人間の苦痛のコストがはるかに大きくなるものであり、この選択肢をなくすときに、国家(the state)は愚かにあるいは専政的にその警察権力を振るうものであると。中絶という選択肢が、人間の胚が人間であるということ以外に攻撃される根拠をもたないという時代がすでにきているかもしれない(かつては、母親の健康に大きな危険性があったということ、そのことが真実であった時代には、そのことによって一般的に攻撃されていた)。この究極的な攻撃の弱点(trouble)は、人間の胚は人間であるという議論が最終的に人々を説得できない(cannot finnally be won)だけではなく、その陳述は完全に意味されることができない(cannot fully be meant)――もしそれに反対する議論もそれに賛成する議論と同様に強力であるとしても、このことは驚くべきことではない。(この陳述は胚に魂があるという教条に訴える必要がないと私は思う。この点においてリベラルは大きく取り残されがちである。この議論は別の人達の間で起こるだろう。(this argument will take place in other company)これは誠実さの欠如の問題ではなく、この誠実さを述べる方法の欠如の問題である。保守にとってこの胚に対してなされてほしくない一つの明確なことがあり、彼がそれに対してなされたいと望みうることは何もない、あるいはもはやない。ところが、彼が望む明確な何か、彼が見ている何か、彼が感じている何かがある。彼が望んでいるのは胚を人間「として」みなされるということである。言い換えると、彼は人間の胚と人間の内在的な関係が貴方に衝撃を与えることを望んでいる。彼はこのように胚を見、その認知を貴方にも要求する。なぜなら彼は人間の胚が人間であると見ているからである(一人の人間(a human)ではなく、たとえば狼と対置された人間として)。このことは衝撃を与えることに十分であり、そのことによって、この生命を中絶すべきであるという考えに嫌悪の気持ちを植え付ける(found)。ある人はこれらの認知に対して盲目であることは十分にありうる。私は自分がそうでないと思う。しかしそれでも私は中絶の問題に関してはリベラルであると思う――中絶に寛容であるだけでなく、その合法化を強く(passionately)望み、それを合法的に反対しようとする人々が専政的で、感傷的な偽善者であると確信している。
明らかに私は中絶よりも他の事のほうをより嫌悪する。これらのこと少し独創的なものではないが、詳述すべき重要さがある。たとえば、不公正な法律。この場合は、貧困な人々、教育されなかった人々、見放された人々を差別する法律。また、たとえば、望まれないあるいはネグレクトされた子どもという事実。合法な中絶が不公平な法やネグレクトされた子どもに対するオルタナティブであるということは、良い論理の問題(matter of good logic)ではなく、悪い制度の問題(matter of bad institution)である。まず、もし、子どもを引き取ることが子どもを生む(having a child)こと以上な困難を引き起こさないほど社会がちゃんとしているなら。子どもを継続的に望み、彼らの世話をしようと思う人々によってのみ引き取られるなら。また、そういう人々を必要とする子どもにとって十分にそういう人達がいるなら。誰かがこのような人々が誰であるかをいかに見分けるかを知っているなら。私生児であることあるいは未婚の母であることあるいは自分達の子どもを諦めるかわりに養子を選択することに対するいかなる恥や差別もそれ自体が恥ずべきことであるなら。避妊が物理的にそれを実践する人にとって無害であるということが知られており、それを良心的に実践しているなら。女性が妊娠中に専門家による快適なサポートを提供され、父親も母親と一緒に仕事から親として離れることができて、中絶が認可される(sanctioned)必要があるのは、また常に容認されるのは、母親に対する明確で恐ろしい物理的または心理的な危険性があるときのみである(心理的な危険性は今のところ妊娠や出産そのものに対する恐怖に限定されるべきである)なら。そのとき私の中絶に対するリベラリズムが薄れ、中絶に対する嫌悪が花開くだろう。中絶を否定する法があるべきだとすら想像するだろう(もし今挙げたリストのことが実際に行われることを保障する法律があるならば)。いいかえれば、国家(state)が中絶を防ぐことに関心があると想像するだろうということである。私の理由は中絶を要請したり実践したりする人々がまだ生まれていないものに対して危険である(そのことはすでにかなりはっきりしている)ということにあるのではなく、彼らが自身に対して危険であり、彼らが自分を獣のようにしているし、社会も彼らに沿って同様な方向に進むからということにあるだろう。しかしリベラルとして私はこのような前提で警察権力を召喚することに反対するだろう。だから私は密かに、私が思い描くこれらの条件が実際に満たされているなら、現に自発的な自殺がないのと同様に、自発的な中絶がもはやないだろうということを想像する。――これらの熟慮の要点とは、中絶の議論は、それが人間の胚の地位に基づく限り、説得される(won)ことができないだけではなく、説得されてはならないということである。自発的な中絶はその犯罪化よりも悪くない。しかしだからといってそれが問題ないわけはない。中絶をより恐ろしく考えれば考えるほど、中絶による社会に対する告発をより恐ろしく考えるべきである。それは社会の失敗の徴であり、その点において監獄の存在と異なるわけではない。
このことは、中絶の実行が計画殺人、とりわけ最も無実なものに対する殺人の事例ではないと私は考えるということを意味する。人間の胚が人間であるということを保守は完全に意味すること(mean)ができないと主張ことで、私は次のことを言おうとしている。健全な精神をもつ保守ならヘロデやその子分たちを嫌悪すると同じ仕方で、中絶を要請したり実行したりする人々を嫌悪する人はいないということである――あるいは少なくとも、彼がヘロデを差別するのと同じように、中絶の人々を差別するのではない。ヘロデは彼が望まないもしくは都合が悪いと考える子どもを殺した人のみを処罰した(slated)。ヘロデはいかなる代償を支払っても止められなければならない。私はすべての保守が感じているものが卑劣なあるいは醜い何かに対するのと同様に、単なる不満や不快であり、彼がその道徳的な嗜好を合法化しようと望んでいるといいたいわけではない。(この可能性を排除もしないが。)私はすでに嫌悪の余地を見ることを主張してきた。この嫌悪感は、ある民族が自分達の人々の死体を放置されるがままにする、すなわち、その通り道に放置するか、ゴミと一緒に投げ出すかするということを目撃するときに感じる嫌悪感と似ている。それは悪いことであり、すなわち獣化であり、それを否定する法律があるべきであるけれど、これは殺人ではない。
人間の胚が人間であるということに対するいわば私の不信、すなわち、このことは完全には、あるいは真剣には意味されることができないと私が信じていることを正当化するためには、これらの言葉が意味するところの道筋、すなわち、そういうことを言うはめになった人々が何を見たくて、何を感じるかを描いてなければならない。このことは、奴隷所有者が主張する(奴隷所有者によって主張されるけれど、私の知り合いの圏内では、彼のためにだけなされた主張である)、奴隷は人間ではないということに対する私の不信を正当化するために行わなければならないことと同じことか。奴隷は人間「である」ということを「知っている」この私が奴隷所有者にいえることは、人間が人間であることを望み、みなし、感じることが一体何を意味するかということだけではないか。そして、私は自分がそうすることができると確信することができない。私は、すでに述べたように、このことを知るということが何を意味するかを知っていると確信していない。私が人間の胚について何かを見落としていると保守の人は想像するだろう。それが何であるかは私は知っている。なぜなら、保守の人が何を見落としていないかということがわかる、あるいはわかると信じているからである。本当のところ、私はそれを共有することを主張してきた。ただし、保守の人と同じような仕方でことを進めていくわけではないが。しかし、奴隷所有者は私が見落としていない何かを見落としているのか。そうではない、すなわち、同じような仕方で見落としているのではないと私思う。奴隷所有者は私が知っている人間についてのあらゆることを大まかに知っているだろう。彼は気だるい夏の朝に描き上げる空想小説においてそのことを微細に記述さえするだろう。
彼が本当に信じているのは、奴隷が人間でないということではなく、奴隷であるような人間もいるということである。議論の余地はない、違いますか。彼には奴隷がいるから奴隷は存在する。そうではない、ただこの人が特定の人間を奴隷「として」見、彼らを奴隷として見なす。彼はこのような人たちが全員奴隷であるべきと主張する必要はない。ただもし奴隷である人がいても、それは問題ない(all right)と主張すればいい。しかし、彼は間違っている。健全な精神をもつ人ならこのような人(man)――このもしかしたら魅力的な人、家族をもつ人、動物や子どもに対して普通の愛情を抱く人――はあらゆる犠牲を払っても止められなければならない、もし彼が貴方に触れるならと考えるだろう。
しかしもしこの人(man)が特定の人間を奴隷とみなすなら、彼が何かを見落としているのではなく、何か特別なことを見ているのではないか(間違いなく彼は私が何かを見落としていると考える)。彼が見落としているものは正確には奴隷に関する何かではないし、人間に関する何かでもない。彼は自身の何かについて見落としている。あるいはむしろ、これらの人々と彼のつながり、すなわち、彼と彼らの内的な関係についての何かを見落としている。奴隷所有者がテーブルで黒い手に給仕されることを望むとき、彼は黒いひづめに給仕されることに満足しないだろう。彼が奴隷をレイプしたり、側室としたりすることは、事実そのものとして、獣姦をしているとは感じない。彼が黒人のタクシー運転手にチップを渡すとき(彼が白人のドライバーに決してしないようなこと)、その生き物の首の片側を優しくたたいていればより適切であっただろうとは彼は考えない。彼は自身の馬にキリスト教に改宗させたり、キリスト教をかぎつけないようにするために、どんなことでもするわけではない。彼の奴隷との関係のあらゆることが示すのは、彼は多少なりとも奴隷を人間として扱っているということである――彼らに対する侮辱、失望、嫉妬、恐怖、懲罰、愛着…
それなら「人間ではない」ということが何を意味するか。いかにして多少なりともこの架空の奴隷所有者がこのことを意味とするだろうか。それを言うとき、彼は何を望み、何を見、何を感じるかと我々が想像するか。彼は奴隷達が、とにかく全員ではないが、彼より知的に劣っており、怠けていると意味しようとしているのではない。(彼は自身の息子についてそのように、あるいはもっと悪く考えるかもしれない。)彼は奴隷達が自分の友達よりも醜く、作法を身に着けていないと意味としているわけでもない。(彼は白人のクズについて、これらの意味で、もっと悪く考えるかもしれない。)彼は意味しようとすること、あるいは意味することができることには、はっきりしたことが何もない(He means,and can mean, nothing definite.)。これは精神の明白な枠組である。彼が曖昧に、意味しようとしているのは、彼らが「純粋に」人間であるわけではないということである。彼が曖昧に、意味しようとしているのは、人間の「種類(kinds)」があるということである。(私が次のように受け取るが、これはマルクスがフォイエルバッハの神学を採用することで種的存在としての人間について語った次のことの否定である。人間であることは人類(humankind)の一員になることであり、すべての他者に内的な関係を抱え持つことであると。)彼が曖昧に、意味しようとしているのは、奴隷は異なっている、まずは彼とは異なる、そして貴方や私とも異なるだろうということである。(私はここで次のように思う、すなわち信じるが、いかなる人種差別的な心理学あるいは人類学も、それがいかに彼を慰めるとしても、この曖昧な差異を述べることに関しては本当に彼を満足させることができない。)結局彼は人生の歴史、形式、あるいはむしろ生き方に訴えざるをえない。これが彼のすることである。彼が精確に信じているのは、正義が否定するもの、すなわち歴史と曖昧な差異が彼の社会的地位の差異を正当化できるということである。彼は正義の至高性を否定する必要がない。彼はその主題について雄弁ですらありうる。彼が否定する必要があるのは、特定の他者が正義の領域にあるということが承認されるべきであるということだけである。彼が否定しているものは奴隷が「他者」である、すなわち、彼という人間(his one)の他者であるということを否定しているということもできる。彼らはいわば「単なる」他者である。すなわち単に分離されているのではなく、異なっている。彼が奴隷達との関係において私的である(private)とみなしている、結局のところ彼らに知られえないとみなしていると言うこともできる。
奴隷は主人に対して秘密をもつだろう、疑いなくもっている。しかし主人はより多くをもっている。奴隷に対する権力は当然ながら、しかしそれ以上の何か。彼らとの関係における彼の経験についての権力と呼ぼう(Call it power over his experience in relation to them)。彼は奴隷についてのあらゆることを承認するだろう。私が意味しているのは、彼が奴隷に対して本物の感情を表すということ、奴隷達の苦痛から彼らのリズム感覚まであらゆることを承認するということである。ただし彼らの存在が正義の領域にあるということは除く。奴隷達は一定程度のことを彼に対して承認するだろう(彼についてのあらゆる感情の表現や、ブルースの表現を差し控えることは危険なほど挑戦的である)、しかし彼が主人であることの承認を除いては、彼について、彼に対して何も承認しない。しかし、「彼」を承認する、すなわち彼らの一人にとっての他者として彼を見ることへの権力、言い換えれば、彼が見るように彼の経験を見るという権力を彼が譲渡し、あるいは彼らが見つけるなら、彼は自身のことを彼らの目を通じて見るだろうし、また彼らも自分たちを彼の目を通じて見るだろうし、彼は自分の日々を数えるだろう。――南部の奴隷制は、そう言われているように、人間の歴史において最も厳しい形のものであったということだろう。しかし、もし私の虚構の小史において想定されたように、それに対する正当化が最終的な地点に到達したなら――奴隷は完全な人間ではない――その人間の悲惨さは人間の進歩(progress)の恐ろしい形を表象している。なぜならその地点は長く維持することができない。アメリカの内戦を悲劇と見なす様々な理由がある。奴隷制が奴隷所有者側では心理的に支持できなくなりつつあったということを考慮すれば、内戦は不必要であったとみなせるということが一つの立派な理由である。今やもし、奴隷制度を支持不可能なものにしたのが罪悪感にそったものではなく(たとえば劇的な善意の行為といった、罪悪感を和らげるのに十分な手段が与えられたならば、罪悪感とともに千年も生きられえただろう)、精神それ自体が自分自身を転倒させるような意味を作り出すことで、意味されることができないようなことを意味しようとするますますの努力によって、奴隷制度が支持不可能なものになったと示されるならば。またもしこの心理的な展開が敬虔ぶった批判の矢面に立たされ、自己正当化をせざるをえないような状況にならなければ、1865年の聖枝祭までに結実をし、奴隷制から自身開放したであろう。それほどにこの展開が十分にゆっくり進行していたならば、内戦は必然であったからというよりむしろ、不必要であったから悲劇的であっただろう。
奴隷制――それに限定されるのではなく、むしろそれによってほとんど公然と劇化される ――を想像することに不安を感じるとすれば、それは本当は奴隷制が、人間が彼らの知る、もしくはまったく知らない他人を人間として扱う一つの仕方であるということにある。このことを認めるかわりに我々はそうした人々が他人を人間としてまったく扱っていないと言う。(ナチズムを理解することは、そのことが何を意味するにせよ、それを人間の可能性として理解することでろう。怪物的で(monstrous)、許されない(unforgiveable)ことであるが、だからといって怪物の行為というわけではない。怪物は許されないのでもなく、許されるのでもない。我々は怪物に対して許しを適用するほどの内的な関係を持たない。)奴隷所有者が奴隷たちを一種の人間として扱うとみとめるならば、奴隷制は差異についての曖昧な主張や、正義の領域での存在から他者を排除するための表現不可能な根拠以外の基礎を持ち得ないということになる。そのことに近すぎるから、我々がいつになっても発見できないかもしれないのである。
人間の胚を人間としてみなし、ある程度扱うことができるということが正しいという事実から、人間の胚は人間ではないということを導き出したいと思っているわけではない。同様に、特定の人間を奴隷としてみなし、完全に扱うことができるという事実から、人間は奴隷ではないということを導き出したいと思ってるわけでもない。人間の胚が人間であるということが事実ではないのと同様に、特定の人間が奴隷であるということもまた事実ではないということを言いたいのである。このことは次のことを仄めかしているとうけとられるかもしれない。すなわち、自己を表現するある人がそれとは別の仕方で特定の「世界観」(Weltanschauung)に住みつくということである。言い換えれば、彼自身が住み着くその世界が、彼に特定の仕方で衝撃を与えているということである。次のようにも受け取られるかもしれない。すなわち、私と同じように考える誰かが、このような仕方で世界から衝撃を受けることに失敗する、あるいはともかく失敗したということである。(これも、また、一つの世界観か?)カモーウサギ[カモにもウサギにも見える絵]はカモ(の絵)であるということは真でも偽でもなく、事実でもない。もし誰かが確実に「それはカモだ」といういうなら、それがカモであるということが「彼にとって」真であるということが事実のようである。しかし「彼にとってである」ことは明らかに「私にとっての真」との対比をまねく。それでも、それはカモーウサギであるということが「私にとって」の真であるのは事実でないようである。それがカモーウサギであるということはことの事実に過ぎない(the fact of the matter)。ならば我々の立場にはどんな違い、もしくはどんな対比があるのか。
1 note
·
View note
Link
0 notes
Text
What happens when you Google Translate

el papa = the pope
el papá = the father
la papa = the potato (Lat. Am.)
la patata = the potato (Spain)
23K notes
·
View notes
Text
『職業としての小説家』抄
村上春樹の最近の作品『職業としての小説家』(スイッチ・パブリッシング)から、何かしら強い印象を残した箇所を抜き出しただけのもの。
文体
もちろん僕の英語の作文能力なんて、たかがしれたものです。限られた数の単語を使って、限られた数の構文で文章を書くしかありません。センテンスも当然短いものになります。頭の中にどれほど複雑な思いをたっぷり抱いても、そのままの形でとても表現できません。内容をできるだけシンプルな言葉で言い換え、意図をわかりやすくパラあフレーズし、描写から余分な贅肉を削ぎ落とし、全体をコンパクトな形態にして、制限のある容れ物に入れる段取りをつけていくしかありません。ずいぶん無骨な文章になってしまいます。でもそうやって苦労しながら文章を書き進めているうちに、だんだんそこに僕なりの文章のリズムみたいなものがうまれてきました。
(中略)
とにかくそういう外国語で書く効果の面白さを「発見」し、自分なりに文章を書くリズムを身につけると、僕は英文タイプライターをまた押し入れに戻し、もう一度原稿用紙と万年筆を引っ張り出しました。そして机に向かって、英語で描き上げた一章ぶんくらいの文章を、日本語に「翻訳」していきました。翻訳といっても、がちがちの直訳ではなく、どちらかといえば自由な「移植」に近いものです。するとそこに必然的に、新しい日本語の文体が浮かび上がってきます。それは僕自身の独自の文体でもあります。僕が自分の手で見つけた文体です。そのときに「なるほどね、こういう風に日本語を書けばいいんだ」と思いました。まさに目から鱗が落ちる、というところです。
イマジネーション
ジェームス・ジョイスは「イマジネーションとは記憶のことだ」と実に簡潔に言い切っています。そしてそのとおりだろうと僕も思います。ジェームス・ジョイスは実に正しい。イマジネーションというのはまさに、脈絡を欠いた断片的な記憶のコンビネーションのことなのです。あるいは語義的に矛盾した表現に聞こえるかもしれませんが、「有効に組み合わされた脈絡のない記憶」は、それ自体の直観を持ち、予見性を持つようになります。そしてそれこそが正しい物語の動力となるべきものです。
文章に対する批判
ここで僕が言いたいのは、どんな文章にだって必ず改良の余地はあるということです。本院がどんなに「よくできた」「完璧だ」と思っても、もっとよくなる可能性はそこにあるのです。だから僕は書き直しの段階においては、プライドや自負心みたいなものはできるだけ捨て去り、頭の火照りを適度に冷やすように心がけます。ただ日照りを冷やしすぎると、書き直しそのものができなくなるので、そのへんはある程度注意しなくてはなりませんが。そして外からの批判に耐えられる耐性を作っていきます。何か面白くないことを言われても、できるだけ我慢してぐっと呑み込むようにする。作品が出版されてからはマイペースで適当に受け流せばいい。そんなものいちいち気にしていたら身がもちません(ほんとに)。でも作品を書いているあいだにまわりから受ける批評・助言は、できるだけ虚心に謙虚に拾い上げていかなくてはならない。それが僕の昔からの持論です。
犬・猫・羊人格
もし人間を「犬的人格」と「猫的人格」に分類するなら、僕はほぼ完全に猫的人格になると思います。「右を向け」と言われたら、つい左を向いてしまう傾向にあります。そういうことをしていて、ときどき「悪いな」とは思うんだけど、それが良くも悪くも僕のネイチャーになっています。そして世の中にはいろんなネイチャーがあっていいはずです。でも僕が経験してきた日本の教育のシステムは、僕の目には、共同体の役に立つ「犬的人格」をつくることを、ときにはそれを超えて、団体ごと目的地まで導かれる「羊的人格」をつくることを目的としているようにさえ見えました。
別のシステムに自分を託すこと
ものごとを自分の観点からばかり眺めていると、どうしても世界がぐつぐつと煮詰まってきます。身体がこわばり、フットワークが重くなり、うまく身動きがとれなくなってきます。でもいくつかの視点から自分の立ち位置を眺めることができるようになると、言い換えれば、自分という存在を何か別の体系に託せるようになると、世界はより立体性と柔軟性を帯びてきます。これは人がこの世界を生きていく上で、とても大事ない見をもつ姿勢であるはずだと、僕は考えています。読書を通してそれを学び取れたことは、僕にとって大きな収穫でした。
物語と現実の相互調整
物語というのはもともと現実のメタファーとして存在するものですし、人々は変動する周囲現実のシステムに追いつくために、あるいはそこから振り落とされないために、自らの内なる場所に据えるべき新たな物語=新たなメタファー・システムを必要とします。その二つのシステム(現実社会のシステムとメタファー・システム)をうまく連結させることによって、言い換えれるなら主観世界と客観世界を行き来させ、相互的にアジャストさせることによって、人々は不確かな現実をなんとか受容し、正気を保っていくことができるのです。僕の小説が提供する物語のリアリティーは、そういうアジャストメントの歯車として、たまたまグローバルにうまく機能したのではないか――そんな気がしないでもありません。もちろんこれは、繰り返すようですが、僕の個人的な実感に過ぎません。しかしまったく的外れな意見でもないだろうと考えています。
0 notes
Photo

鳴海アラタさんはTwitterを使っています: “カナリア http://t.co/0ekK55k7Fq”
574 notes
·
View notes
Link
0 notes
Photo



Some additional Duchovny for your Sunday enjoyment.
via eonline
32K notes
·
View notes
Text
ゲーム開発者になりたい人へ
この記事は、ゲーム開発者(ここはプログラマではなくゲームデベロップに携わる人全般を指します) を目指している方向けに書いたものです。
既に業界でベテランの方々にとっては、「ひよっこが偉そうに、見当違いな事を吹聴して…」と思うかもしれませんが、今私がいる位置はまだこの程度で、おっしゃる通りひよっこですが、今からそちらに参りますので見守っていてくださると嬉しいです。
さらに読む
10 notes
·
View notes
Text
早期アクセスについてのお話
Redditで早期アクセスについてうまく話を書いたポストを見つけました。書いた本人に翻訳の許可をとったところ、快く頂いたので、翻訳を以下に掲載します。
該当のredditスレはこちらです。
あなたの街にある遊園地が建設中であるとお考えください。
建設を始める前に、そいつらは誰よりも先に乗り物に乗れるような「プレミアム」入場券を売ろうと考えている。一部の人々はこれを買い、そして遊園地側はこれを収入源と見なす。
遊園地が作られ始める。そいつらはフェンスをいくつか建てるけれども、乗り物よりもチケット売り場にほとんどの精力をつぎ込んでいるようだ。そいつらはすべての乗り物がそのうちくることを保障するけれども、チケット売り場の完成祝いに、乗り物が完成したあかつきには園内で使用できる園内ドルの特別セールをやっている。園内ドルを買う人もいる、そういう人たちは遊園地がオープンしたらそこでたくさんの時間を過ごすだろうと想像する。
園はそのうちいくつかの乗り物を投入する、もしかしたら最終予定の5%かもしれない。そいつらは特別早期入場券を買った人たちに、それらの乗り物を徹底的に試乗する機会を与える。「この乗り物は素晴らしい。」とか「この乗り物は楽しくなるだろう」とかといった類のコメントなら公開されるが、「この乗り物は動かない」とか「この乗り物は私の家族全員を殺し、私の顔をひどく傷つけた」とかといった文句は無視される。なぜなら、そういった問題は「本当にオープンした時までには修正されているであろうからだ」。
時間が過ぎても、遊園地は園内ドルや早期入場券をまだ売っているが、乗り物には労力を費やさなくなった。なぜこうなるかといえば、園に投資した人々(「本物」の投資者、お客様ではない)は出来る限り早く彼らのお金が帰ってくるのを見たいからである。このように園は園内ドルや早期入場券のすべてのお金を取り出した上で、それを投資者に分配すべき利益として報告をする。結局、園内ドルや早期入場券のセールの売れ行きが落ち始め、ついてには年利が出せなくなるほどまで落ちる。そこでそいつらは、「開業」と宣言する。通常の入場券を買う人たちも少しはいる、しかし園がいかにひどいかについての話がすぐに広まり、誰も買わなくなる。そこで園は超割引券を売り始める。通常は100ドルであるが、今日はなんとたった1ドルで入れる!何千人もの人が超割引券を買うが、すぐに消えていなくなる。
「正式開園」の1か月後、園は閉まり、全員がひどい遊園地だといい、そこから何かを買った人は全員嘘の約束に騙された。しかし、ビジネス会議では、園の収益は素晴らしい。開園するはるか以前から利益を出すことができ、店をたたむまでは収益を維持した。結果として、3つもの新しい遊園地が来年計画される。
早期アクセスの話で私は一本の映画を思い出した。『プロデューサーズ』だ。その映画では、お金をたくさん儲ける方法を思いつくプロデューサーはたくさんいる。それはこうだ。彼らは数百人の人に固定額で収益の20%を売る。したがって彼ら全員が大量のお金を儲けるためにしなければならないのは、作品が確実にひどくコケて利益が0となるようにすることだった。同じ理屈は早期アクセスゲームにも適応できる。もし彼らは約束した目玉を実現する前に利益を得ることができるなら、それらの目玉を実現する動機がまったくない。
ビジネスの観点:「我々が乗り物の絵だけで利益を数年で出すことができ、かつこのプロセスを繰り返せるなら、なぜ30年間通常の収益を得るために完成した遊園地を開発する必要があるのか」
0 notes