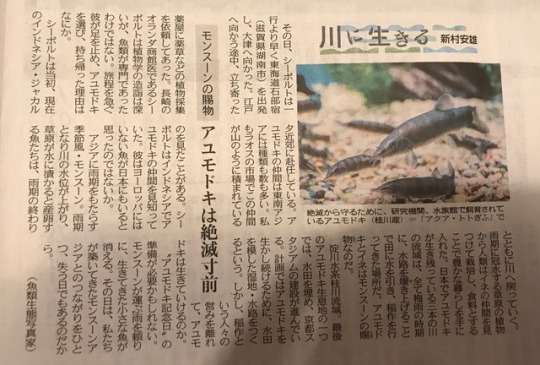Photo

「首相は保守の政治家とされるが、保守は、本来、急激な変化を好まず、積み重ねてきた歴史を大切にする。(中略)安倍政権は『戦後レジームからの脱却』を掲げ、戦後積み上げてきた事を水の泡にしようとしている。ある意味、革命政権とも言える」…確かに!
0 notes
Text
'Killing Commendatore' a shift from loss to renewal: Haruki Murakami interview
World-renowned writer Haruki Murakami, whose newest novel, "Kishidancho goroshi" ("Killing Commendatore"), was released in February, spoke recently with the Mainichi Shimbun and other media outlets about his latest work and the role of the novelist in the world today. "Killing Commendatore" is Murakami's first multivolume work since "1Q84," which came out 2009-2010 in Japan. The first volume is titled "Arawaru Idea" (Emerging Idea) and the second volume, "Utsurou metaphor" (Moving metaphor). The novel marks the first time in a while that Murakami has written in the first person. It is written in the voice of a 36-year-old painter whose wife left him abruptly. "At first, I always wrote in the first person, and gradually shifted to the third person," Murakami said. "Having achieved a novel totally in the third-person with '1Q84,' I felt the urge to return to the first person. There was a strong sense that I was returning to my roots, but I think there was a certain maturing of the protagonist as well." The "commendatore" originates with the Commendatore from Mozart's opera, "Don Giovanni," who is killed at the outset of the drama. Murakami said that the title, "Killing Commendatore," came to him before he even began writing the novel. "I was drawn to the peculiarity of the words," he said. "What I had first was the title, and the place where the story takes place, which is atop a hill in (the Kanagawa Prefecture city of) Odawara. The protagonist became a painter as I was writing." The painter -- separated from his wife and searching for something to paint amid his feelings of loss -- finds himself living in a house which belongs to the father of a friend. The father, aged 92, is a renowned Japanese-style painter who now lives in a seniors' home, thus leaving his house empty and available for the protagonist. It is after the protagonist discovers a painting titled "Killing Commendatore" in the attic that he becomes entangled in a cryptic series of events. The protagonist is commissioned to paint a portrait by a man with the unusual surname Menshiki. Aged 54, the mysterious Menshiki is a successful businessman living alone in a huge mansion on a hilltop across the valley from the protagonist. According to Murakami, the character was "a type of homage" to the 1925 American classic "The Great Gatsby" by F. Scott Fitzgerald, which Murakami has translated into Japanese. The protagonist hears a bell ringing in the middle of the night, and in his search for the source of the sound, he comes upon a well-like hole in the ground. With Menshiki's cooperation, the protagonist unseals the hole, in which he finds an old bell, the likes of which would be found in a Buddhist altar. As is addressed in the novel itself, the story surrounding the bell is a motif taken from Edo-period novelist Ueda Akinari's short story, "Nise no Enishi" ("A bond for two lifetimes"), which is included in Ueda's collection of short stories, "Harusame Monogatari" ("The tale of spring rain"). "The classics are valuable when they are cited or referenced," Murakami said. "I reference a lot of things, and that makes it fun. Remarkable tales have power as repositories, and are effective when referenced." Once the hole is unsealed, an enigmatic figure called "Idea," who looks exactly like Commendatore in the painting, appears. What unfolds afterward is a world in which good and evil are enmeshed, and bloodshed ensues. The protagonist is led into an underground darkness by figures in the painting, at which point Murakami fans will recognize and savor the signature maze-like elements of the novelist's tales. After the protagonist undergoes a gamut of trials and tribulations, he resumes life with his wife, and raises the child his wife became pregnant with while the two were apart. At the end of the book, the story jumps a few years to the period immediately after the 2011 Great East Japan Earthquake, and ends with the protagonist discussing his beliefs as to how he will live his life. The ending marks a shift from loss to renewal. "My novels are open-ended, or have mostly ended with the stories still wide open," Murakami explained. "This time, I realized that I'd begun to need a 'sense of closure.' For me, the fact that the protagonist decides at the end to live with the child is to suggest a new kind of conclusion." The backdrop against which this shift occurred was a trip that Murakami took in the fall of 2015, in which he drove along the coast from Fukushima to Miyagi prefectures, the area hit hardest by the March 2011 earthquake and tsunami. "That was a significant experience. It's linked to the sense of renewal, to the feeling that I must create new things. It may also have to do with the responsibility I feel because of my age," the 68-year-old Murakami stated. "I believe the disaster in the Tohoku region left a huge scar on the Japanese people's psyche. To portray the psyche of the people who lived through this particular time without parts that overlap (with the disaster) is unrealistic." At the same time, however, the historical scars left by massacres such as the Holocaust and the Nanjing Massacre cast a shadow on the painting, "Killing Commendatore." What was Murakami's intent in inserting references to such historical events? "Because history is the collective memory of a nation, I think it is a grave mistake to forget about the past or to replace memory with something else. We must fight against (historical revisionism). Novelists are limited in what we can do, but it is possible for us to fight such forces in the form of storytelling," he said.
0 notes
Text
新作『騎士団長殺し』 震災、再生への転換 一人称に戻る/新しい結論
毎日新聞 2017年4月2日 東京朝刊 2月に長編小説『騎士団長殺し』(第1、2部、新潮社)を刊行した作家の村上春樹さんが、毎日新聞などのインタビューに応じた。新作に込めた思いや小説家の役割について聞いた。【構成・大井浩一】 複数巻にわたる大長編としては『1Q84』(2009~10年)以来。400字詰め原稿用紙で2000枚に及ぶ。第1部が「顕(あらわ)れるイデア編」、第2部は「遷(うつ)ろうメタファー編」と題されている。 主人公は画家で、妻に突然別れを告げられた36歳の時の体験を中心として、一人称「私」で語られている。村上作品の長編では、久しぶりの一人称小説だ。 「僕は最初、一人称でずっと書いてきて、少しずつ三人称に移行していった。『1Q84』を純粋な三人称で書ききったことで達成でき、もう一回、一人称に戻りたい気持ちがあった。元のフィールドに戻ってきたという感じは強かったが、ある種の主人公の成熟はあると思う」 「騎士団長」はモーツァルトのオペラ「ドン・ジョバンニ」の登場人物に由来する。オペラの冒頭で殺されるシーンがあるが、執筆前にまず『騎士団長殺し』というタイトルが浮かんだという。 「言葉の感触の奇妙さに引かれた。最初にあったのはタイトルと、(主人公が住む神奈川・)小田原の山の上というシチュエーション。画家というのは書いているうちに出てきた」 妻と別れ、喪失感の中で描くべき絵を求める主人公が住んだ山の上の家は、友人の父親で高名な日本画家のもの。92歳の日本画家は高齢者養護施設に入っており、空き家になっていた。その屋根裏で「騎士団長殺し」と題する絵を発見した後、主人公は不可解な出来事に巻き込まれていく。 また、谷間を隔てた向かい側に住む「免色(めんしき)」という変わった姓の人物から、肖像画を依頼される。免色はビジネスの成功者で54歳。広大な邸宅に一人で住む謎の人物だ。その設定は著者が愛読し、自ら翻訳も手がけた米文学、スコット・フィッツジェラルド『グレート・ギャツビー』(1925年)を意識したものだ。「これは一種のオマージュ」と話した。 真夜中に鈴の音を耳にした主人公はその音の元をたどるうち、井戸のような穴を見いだす。免色の協力を得て、その穴を開放すると、中には古い仏具のような鈴があった。作中でも言及されるが、これは「(江戸時代の作家)上田秋成の『春雨物語』に収められている『二世(にせ)の縁(えにし)』という話をモチーフとして使った」と語る。 「古典というのは引用されることに価値がある。僕もいろんなものを引用するし、それが楽しい。優れた物語は入れ物としても力を持っているし、(引用は)有用なことだ」 穴を開放した結果、絵の騎士団長と同じ格好をした「イデア」と名乗る不思議な存在が登場する。善と悪が複雑に絡みあう世界が繰り広げられ、血も流される���絵の中の人物たちに導かれて主人公が地下の暗闇を巡る展開もあり、従来の村上作品でおなじみの道具立てが登場するのはファンにとって楽しみだろう。 主人公はさまざまな試練を経た後、妻と再び生活を始めるが、離れている間に妻が身ごもった子供を自分の子として育てていく。物語の最後、時間は数年後の東日本大震災の直後に飛び、主人公が生き方への信念を語って終わる。喪失から再生への転換が描かれる。 「僕の小説はオープンエンドというか、話がオープンになったまま終わるというケースがほとんどだったが、今回は『閉じる感覚』が僕にも必要になってきたという気持ちがあった。最後に主人公が子供と一緒に生きていくのは、僕にとっては新しい一つの結論を示唆するものだ」 そうした変化の背景には、一昨年秋に自ら車で福島県から宮城県にかけての沿岸を回った体験もあるという。 「その経験は大きかった。再生につながっていく気持ちにも関連している。新しいものを作っていかないといけないなと。年齢的な責任感もあるのかもしれない」 「東北の震災は、今の日本人のサイキ(精神)にものすごく大きい傷痕を残した事件だと思う。その時代を生きた人のサイキを書くには、(震災と)重なり合う部分がないとリアルではない」 一方、「騎士団長殺し」と題する絵の背景には、ナチスのホロコーストや南京虐殺事件にまつわる歴史の傷も影を落としている。どのような著者の思いが込められているのか。 「歴史というのは国にとっての集合的記憶だから、それを過去のものとして忘れたり、すり替えたりすることは非常に間違ったことだと思う。(歴史修正主義的な動きとは)闘っていかなくてはいけない。小説家にできることは限られているけれど、物語という形で闘っていくことは可能だ」
0 notes
Text
NHK WORLD Daily News
2. India, Malaysia to strengthen economic ties The prime ministers of India and Malaysia have decided to cooperate to strengthen economic ties, including investment in IT industry and infrastructure construction. India's Prime Minister Narendra Modi met with his Malaysian counterpart Najib Razak in New Delhi on Saturday. At a joint news conference after the meeting, the prime ministers said the 2 countries will further cooperate in building infrastructure, such as railways and roads. They also said that efforts will be made to help more companies make inroads into each other's industries. They mentioned IT and pharmaceutical firms. Modi said Malaysia is India's important partner in the Asian region, and that India wants to deepen strategic relations between the 2 countries. Since his inauguration 3 years ago Modi has expressed his intention to boost his country's involvement in East and Southeast Asia. Experts note Modi regards Malaysia as a stepping stone to accelerate India's investment in the entire ASEAN countries. The two nations have historically close ties and 2.7 million ethnic Indians live in Malaysia. Both are heterogeneous countries.
0 notes
Quote
NHK WORLD Daily News 20170402 1. New Chinese work permit system to rank foreigners The Chinese government has introduced a new ranking system for foreign nationals applying for working permits. The new system took effect on Saturday. Expatriates are classified into 3 categories -- A, B and C. Class A, the highest rank, includes recipients of internationally-known awards or executives of major corporations. They are eligible for simplified procedures to get work permits. Class B is for managers and professional technicians of foreign firms with bachelors' degrees or higher. They also need at least 2 years work experience. Class C workers include seasonal workers admitted under intergovernmental agreements. Expats who do not meet these criteria will also be evaluated and given points on 9 elements, including age, Chinese language proficiency, and income. Those who accumulate 85 or higher out of 120 points will be given an A ranking. Those with 60 to 84 points fall into the B category. Applicants 60 years old or over will be given zero points for the age qualification. Those with lower incomes will get fewer points. This has raised concerns among small- and medium-sized companies that their employees could have difficulty to get a work permit. An executive at a Japanese consulting firm, Naohiro Tanabe, is an expert on business in China. He says the new system will have a little impact on large firms, but smaller ones will have to find ways to cope, perhaps improving their workers' proficiency in Mandarin.
0 notes
Text
村上春樹さん「騎士団長殺し」語る 「私」新たな一人称 朝日新聞2017/4/2
『騎士団長殺し』(全2冊、新潮社)を出した作家の村上春樹さん(68)が、東京都内で朝日新聞などのインタビューに応じた。執筆の経緯や過去の作品、東日本大震災への思いまで、率直な言葉で語った。
「騎士団長殺しというタイトルが、まず最初にあったんです」。この奇妙な題名の小説について、村上さんはそう切り出した。 騎士団長は、モーツァルトのオペラ「ドン・ジョバンニ」の登場人物。「聴くたびに、騎士団長って何だろうって思ってたんです。僕は言葉の感触の奇妙さにひかれる。騎士団長殺しっていう小説があったらどういう話になるだろう、という好奇心が頭をもたげる」 語り手の「私」は無名の画家。もともと村上作品は「僕」という一人称の語りが定番だった。だが、『海辺のカフカ』で一人称と三人称を併用し、『1Q84』で純粋な三人称に移行した。そのなかで小説の幅を広げてきた経緯がある。 「でも『1Q84』を書ききって、また一人称に戻りたい気持ちがあった」と村上さん。「ただ『僕』からは離れようと。『私』という新しい一人称になって、主人公のある種の成熟を感じています」 執筆時、過去の作品と比べて技術的に向上していることを実感したという。 「『世界の終(おわ)りとハードボイルド・ワンダーランド』は、もどかしかった。物語はどんどん湧いてくるけど、それを制御する文体がなかったから。『ノルウェイの森』をリアリズムで書ききったのが転換点。そのあとの『ねじまき鳥クロニクル』で、リアリズムと非リアリズムのかみ合わせが、初めてうまくいった」 その『ねじまき鳥クロニクル』から、はや20年以上。「自分で言うのも何だけれど、20年の差を感じた。昔書けなかったことが書ける手応えがある」 物語は「むろ」という子の誕生とともに結末を迎える。やはり妻がいなくなる物語だった『ねじまき鳥クロニクル』には、なかった展開だ。「僕はこれまで、家族を書いてこなかった。でも今回は、一種の家族という機能がここで始まる」 村上作品は失われたもの、消えてしまったものを描いていると言われてきた。でも今作には、その一歩先に歩みを進めたような印象がある。 「僕自身が年をとってきたからかもしれないけど、何かを引き継いでほしいという気持ちがあるんです。それが何なのか、自分でもよくわからないけれど」 続編を期待する声は多い。「うーん。『ねじまき鳥クロニクル』も『1Q84』も続きはないって言って書いちゃったから、何とも言えないですよ。時間をおかないと、わからない」 今回の小説は、東日本大震災より前の9カ月間を、震災後の未来から回想する設定。村上さんは作品執筆中だった一昨年の秋、福島県で開かれた文学イベントに参加した際に、東北の沿岸を一人、車で走った。「この物語の中の人は、いろいろな意味で傷を負っている。日本という国全体が受けた被害は、それとある意味で重なってくる。小説家は���れについて、あまり何もできないけれど、僕なりに何かをしたかった」 人類が負った戦争という深い傷も、重要な意味を持つ。ナチスのオーストリア併合と日本軍による南京大虐殺、西洋と東洋でほぼ同時期に起こった暴力が、謎の絵を描いた老画家と、次第に結びついていく。「歴史は集合的な記憶だから、過去のものとして忘れたり、作り替えたりすることは間違ったこと。責任を持って、すべての人が背負っていかなければならないと思う」 昨年デンマークで開かれたハンス・クリスチャン・アンデルセン文学賞の授賞式で、「どれほど高い壁を築いて侵入者を防ごうとしても、そのような行為は我々自身を損ない、傷つけるだけ」と語った。 「最近世界各地で見られる、異物を排除すれば世の中よくなるという考え方へのおそれが、すごく強い。社会の影の部分を何でも排除しようという流れが強くなってる。ただ僕はそういうことを、政治的なステートメントとしてはあまり言いたくない。物語という形で語っていきたいんです」 「長編小説はツイッターとかフェイスブックみたいな、いわゆるSNSとは対極にある。短い発信ばかりが消費されていくのが今の時代。読み始めたらやめられないものを書くのが、僕には大事なことです」。村上さんはそう語った。 「物語は即効力を持たないけれど、時間を味方にして必ず人に力を与えると、僕は信じている。そして、できればよい力を与えられたらいいなと希望しています」(柏崎歓) ■『騎士団長殺し』あらすじ 肖像画を得意とする画家の「私」は妻に離婚を切り出され、雨田具彦(あまだともひこ)という画家の旧宅で暮らし始める。屋根裏から見つかった謎の絵の意味は。破格の額で肖像画を依頼してきた免色(めんしき)という男の意図は――。様々な謎をはらみながら、計約1千ページの物語は進む。
0 notes
Text
ホセ・ムヒカ インタビュー後編
■これ以上もてば、不幸になる
――日本人にメッセージは伝わったと思いますか。
「まさに文字通りに、私のことを『世界でいちばん貧しい大統領』だと受け取った人もいただろう。貧困を擁護していると感じた人も、いたかもしれない。だが、そうじゃないんだ。私は貧しくなんかない。貧乏でいい、なんて言ったことは一度もない」
「幸せだと感じるモノは、私はすべて持っている。これ以上のモノを持てば、とても不幸になってしまうから持っていないだけなんだよ」
「私が言っているのは、質素がいい、ということだ。浪費を避けること。言葉にすれば『質素』であって『貧困』ではない。貧困とは闘わなければならない」
「もし君がゲリラで、山に潜んでいたとしよう。山で快適に生きていくには多くのモノが必要だが、あまりに多くのモノをリュックに詰め込んでいけば、今度は歩くことができなくなる。人生とは長いゲリラ戦と同じだ。リュックは軽くしておかないと、歩き続けることができないんだよ」
――ムヒカさんは土地と建物を提供して地元に農学校をつくったそうですね。その生徒たちについて、東京外大での講演の最後に、「私たちは子どもをつくることができなかったけれども、地元で走り回っている彼らは私たちの子どもです」と言ったとき、会場で聴いていた奥さま(ルシア・トポランスキー上院議員)は泣いていました。
「なぜなら、私たちはとても努力をしてきたからだよ。農学校は私たちが暮らしている地元につくった。私たちは地域の人々のことをよく知っているし、畑のこともよく知っている。何か助けになることをしたいと思ったんだ。よく知っている人には、もっと何かをしたいと思うものだ。だからといって、この世の中が何か大きく変わるわけではないが、少なくとも私たち夫婦が暮らしている地元を、より良くすることはできる」
――世界はこれから、どうなっていくんでしょう。
「もっとも深刻な問題は、富の分配がうまくいっていないことだ。世界各地で、富があまりにも一部の人間に集中している。資本が生む利潤のほうが、経済成長のペースを上回っている。だから豊かな家庭に生まれたら、貯蓄して投資する能力を早くから身につけたほうがいい世の中なんだ。つまり人生のスタート時点から、巨大な富を持って生まれた者がさらに大きく、強くなっていく。この先の世界にあるのは、紛争だよ」
「放っておけば、富は集中する。今後も、ますます集中していくだろう。この問題は日本でも、ウルグアイでも、米国でも、世界中で起きていることだ。どうすれば正せるのかはわからない。だが将来、紛争の原因になっていくことは間違いない」(聞き手・萩一晶)
◇
3回にわたるインタビューの詳細と、元武装ゲリラのホセ・ムヒカさんが大統領になった背景については、12月の新刊「ホセ・ムヒカ 日本人に伝えたい本当のメッセージ」(朝日新書)で読めます。
0 notes
Text
ホセ・ムヒカ氏インタビューその1
南米ウルグアイから、前大統領のホセ・ムヒカさんが初めて日本にやって来たのは今年4月のことだった。1週間の滞在中、東京や大阪の下町を歩き、多くの学生とも触れあったムヒカさん。帰国後は、日本や日本人についてスピーチのなかで触れる機会が増えたという。「清貧」を貫く哲人政治家の目に、日本の何が、どう映ったのか。これから世界は、どう変わるのか。今春に続き、9月に再び、首都モンテビデオにムヒカさんに会いに行った。 世界一貧しい大統領と呼ばれた男 ムヒカさんの幸福論 ■ロボットは消費をしない ――日本訪問の1カ月前、ムヒカさんは私の取材に、「日本のいまを、よく知りたい。日本で起きていることのなかに、未来を知る手がかりがあるように思う」と話していました。実際、日本を訪ねてみて何か見えてくるものがありましたか。 「ひとつ心配なことがある。というのは、日本は技術がとても発達した国で、しかも周辺には労働賃金の安い国がたくさんある。だから日本は経済上の必要から、他国と競争するために、ロボットの仕事を増やさないといけない。技術も資本もあるから、今後はロボットを大衆化していく最初の国になっていくのだろう。ただ、それに伴って、これから日本では様々な社会問題が表面化してくるだろう。いずれ世界のどの先進国も抱えることになる、最先端の問題だ。確かに、ロボットは素晴らしいよ。でも、消費はしないんだから」 ――日本では道行くたくさんの人から声をかけられていました。日本の人々について、どんな印象を持ちましたか。 「とても親切で、優しくて、礼儀正しかった。強く印象に残ったのが、日本人の勤勉さだ。世界で一番、勤勉な国民はドイツ人だと、これまで思っていたが、私の間違いだった。日本人が世界一だね。たとえば、レストランに入ったら、店員がみんな叫びながら働いているんだから」 ――どこか印象に残った街がありましたか。 「京都だ。素晴らしいと思った。日本はあの文化、あの歴史を失ってはいけない」 「ただ、京都で泊まったホテルで、『日本人はイカれている!』と思わず叫んでしまった夜がある。トイレに入ったら、便器のふたが勝手に開いたり閉じたりするんだから。あんなことのために知恵を絞るなんて、まさに資本主義の競争マニアの仕業だね。電動歯ブラシも見て驚いた。なんで、あんなものが必要なんだ? 自分の手を動かして磨けば済む話だろう。無駄なことに、とらわれすぎているように思えたね。それに、あまりにも過度な便利さは、人間を弱くすると思う」 「とても長い、独自の歴史と文化を持つ国民なのに、なぜ、あそこまで西洋化したのだろう。衣類にしても、建物にしても。広告のモデルも西洋系だったし。あらゆる面で西洋的なものを採り入れてしまったように見えた。そのなかには、いいものもあるが、よくないものもある。日本には独自の、とても洗練されていて、粗野なとこ��のない、西洋よりよっぽど繊細な文化があるのに。その歴史が、いまの日本のどこに生きているんだろうかと、つい疑問に思うこともあった」 ■豊かな国ほど幸福について心配する ――2015年に大統領を退いてから訪れた国で、人々の反応は日本と同じでしたか。 「退任後に行ったのはトルコ、ドイツ、英国、イタリア、スペイン、ブラジル、メキシコ、米国だ。行った先で私はよく大学を訪れる。年老いてはいるが、なぜか若者たちとは、うまくいくんだ」 「そこで気がついたんだが、どこに行っても、多くの人が幸福について考え始めている。日本だけではない。どこの国もそうなんだよ」 「豊かな国であればあるほど、幸福について考え、心配し始めている。南米では、私たちはまだショーウィンドーの前に突っ立って、『ああ、いい商品だなあ』って間抜け面をしているけれど、すでにたくさんのモノを持っている国々では、たくさん働いて車を買い替えることなんかには、もはや飽きた人が出始めているようだ」 ――人々が幸福について考え、心配し始めているのは、なぜでしょうか。 「おそらく、自分たちは幸せではない、人生が足早に過ぎ去ってしまっている、と感じているからだと思う。昔の古い世界では、宗教に安らぎを感じる人もいた。だが世俗化した現代では、信心がなくなったから」 ――「世界幸福度ランキング」だと、日本は53位だそうです。 「東京は犯罪は少ないが、自殺が多い。それは日本社会があまりにも競争社会だからだろう。必死に仕事をするばかりで、ちゃんと生きるための時間が残っていないから。家族や子どもたちや友人たちとの時間を犠牲にしているから、だろう。働き過ぎなんだよ」 「もう少し働く時間を減らし、もう少し家族や友人と過ごす時間を増やしたらどうだろう。あまりにも仕事に追われているように見えるから。人生は一度きりで、すぐに過ぎ去ってしまうんだよ」
0 notes
Text
原子力賠償制度 電力会社の賠償責任無制限を維持で合意
原子力発電所などで事故が起きた際の賠償制度の見直しを議論している国の原子力委員会の専門部会は、電力会社の賠償責任を無制限としているいまの制度を維持する方向で合意し、今後事故に備えた資金の増額など詳しい制度設計を議論することにしています。 いまの原子力事故に対する損害賠償制度は、電力会社に過失がなくても損害額に応じて無制限の責任を負うとしていますが、福島第一原発の事故で損害が巨額になったことや、電力自由化で電力会社の経営環境が厳しくなることなどを踏まえて、国の原子力委員会は去年5月から有識者による専門部会で制度の見直しを議論しています。 この中で、賠償責任に上限を設けるかについて、委員からは賠償額が上限を超えると、被害者の請求先が国に変わり、電力会社が賠償への責任を持たなくなることなどに地元住民や国民の理解は得られないといった意見が相次ぎ、電力会社の賠償責任を無制限としている今の制度を維持する方向で合意しました。 一方、今の制度で電力会社は保険に加入し、賠償にあてる資金として最大1200億円を確保しておくとしていますが、これについては増額を検討し、その分電力料金が値上がりする可能性があることから、詳しい制度設計を議論することにしています。 賠償責任の制限をめぐっては「電力会社のリスクが大きすぎ、国が負担すべき部分もある」といった意見の一方で、「国の責任を重くすれば、国民の負担が増える」といった意見もあり、大きな論点となっています。
0 notes
Text
Nuclear accident compensation system to be kept
A panel of experts has agreed that the compensation system for nuclear accidents should be maintained. It imposes unlimited responsibility on power companies. The system states that utilities bear unlimited liability for damages even if they are not at fault in nuclear accidents. The government's Atomic Energy Commission set up a committee of experts to review the system. That's because the amount of compensation has become huge in connection with the 2011 Fukushima Daiichi accident, and a harsher business environment was expected after deregulation of the electricity market. The experts started discussions in May 2015. At a meeting on Wednesday, many participants opposed establishing a cap on utility liability and having the shortfall covered by the government. They said residents near nuclear plants and the general public will not accept it. Some observers say the current system creates too massive risks for utilities. Others argue the public will have to shoulder the burden if the government takes some responsibility. The committee will also discuss an increase in the amount that power companies are required to reserve for possible compensation from about 1 billion dollars. The increase could lead to a rise in electricity rates.
0 notes
Text
ひげ姿で乗務、私の自由だ 憲法頼みに大阪市と争う男性
ふだんは身近に感じにくい憲法。でも、私たちを守ってくれることがある。憲法改正をめぐる議論が動き始めるなか、3日で公布から70年となる。個人の権利を守りたいと考え、憲法に行き着いた人たちは、その価値をかみしめている。 ◇ 「ひげ禁止は憲法違反」 地下鉄運転士、大阪市を提訴 【憲法13条】すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 ◇ 2日朝、大阪市営地下鉄の運転士、河野英司さん(54)は自宅で、いつも通り口の周りのひげを短く整えた。20代で先輩に影響されて生やすようになり、ひげ姿での乗務は20年以上。「自分にはひげが合ってるし、あるのが当たり前」 ところが橋下徹前市長時代の2012年、市交通局は乗客に好感を持ってもらう狙いで、職員の身だしなみ基準を作り、「ひげは伸ばさずきれいに剃(そ)ること」と規定。河野さんも上司から剃るよう指導されたが、手入れを怠ったこともなく納得できない。「ひげを生やす自由があるのでは」と従わなかった。その後、人事評価は2年連続で5段階の最低とされた。 今年3月、「ひげを生やして勤務していることを理由に人事評価を下げられたのは憲法違反」として、ひげを認める職場環境や慰謝料を市に求める訴訟を大阪地裁に起こした。個人の尊重や幸福追求権を定めた13条に違反するとの主張だ。 すぐに憲法が思い浮かんだわけではなかった。戦争放棄を定めた9条は知っていたが、「憲法を実感したことはないし考えたこともなかった」。そんな時、ネットであるブログにたどり着いた。ひげを生やす自由は13条で保障される――。その説明で、ひげと憲法がつながった。 以前読んだ裁判の新聞記事も思い出した。ひげを理由に人事評価を下げられたとして会社に損害賠償を求めた会社員男性が勝訴したという内容だった。「自分も同じように判断してもらえるかも」。そう思い、弁護士に相談して提訴を決めた。 市側は裁判で「公務員として客に不快感を抱かせないように、ひげを含めた身だしなみを整えるための合理的制約は許容される」と反論。ひげ以外にも評価を下げるべき理由があったとも主張している。 河野さんは今も憲法を理解できたとは思わないが、「国民が幸せに暮らせるように守ってくれるもの」という印象を持っている。河野さんの代理人の村田浩治弁護士は今回の訴訟について「裁判で勝っても負けても、社会に問題提起することができる」と話す。ひげを生やすのを我慢している河野さんの同僚も、裁判の行方に注目しているという。 ログイン前の続き■アイドルの恋愛「尊重を」 元アイドルの女性(24)は、自身の恋愛をめぐる訴訟で、憲法に救われた。 アイドルとして活動していた時、所属会社との契約に反してファンの男性と交際したとして、この男性らとともに昨年、会社から約990万円の損害賠償を求める訴訟を起こされた。驚き、どうしていいのかわからず、弁護士に相談した。 しかし、東京地裁は今年1月、「アイドルの交際禁止」に一定の合理性を認める一方、「交際は人生を自分らしく豊かに生きる自己決定権そのもの。幸福を追求する自由の一つで、損害賠償をもって禁じるのは行きすぎ」との判断を示し、会社側の請求を棄却した。会社側は控訴している。 女性側の代理人を務める中島俊輔弁護士は「幸福を追求する自由とは明らかに憲法13条のこと。裁判でこちらが持ち出さなかった憲法が、アイドルの私生活での交際の自由を尊重するという判断の根拠とされて驚いた」と振り返る。芸能界のほかの恋愛禁止規約への影響も出る可能性があるとみている。 女性にとって憲法は「学校の授業で習った記憶があるくらい」のものだった。中島弁護士が憲法に守られた形となったことを伝えると、「ほっとした。交際しただけで何百万ものお金を請求されるのはやりすぎだと思う」と話したという。(佐藤恵子) ◇ 【憲法21条1項】集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ■PTAに入らぬ自由訴え 熊本市の岡本英利さん(60)は7年前、引っ越し先の市内の小学校に子どもが転入した際、PTAの会則などが書かれた冊子を受け取った。そこには「会則の配布をもって入会を了承していただく」とあったが、当時読んだ記憶はない。数年後、運営方法や会費の使い方に疑問を抱く。 中学時代は制服を強要されるのが嫌で、内側に禁止された柄物シャツを着て登校した。基本的人権を保障する憲法を授業で習い、何となく気になった記憶がある。 それから約40年。「そもそもPTAの加入方法が強制的でおかしい。憲法的に問題ではないか」。憲法の全文を読み、ネットで調べると、PTAは任意加入で、「結社の自由」を規定した憲法21条が根拠とされていることを知る。入る自由もあれば入らない自由もあるという解釈だ。 「受け身でいては自由は守られない」。無料法律相談会に行くと裁判を勧められ、加入したつもりはないとしてPTA会費の返還などを求めて提訴。だが一審判決では加入していたとされ、請求を棄却された。控訴し、今は高裁で和解協議中だ。加入が任意だという認識はPTA側も同じだが、岡本さんは保護者に任意だとはっきり伝わる入会手続きにするよう求めている。「強制加入だと思う人は少なくない。PTAが積極的に説明しないと21条の規定が守れない」 岡本さんが裁判の状況を発信するブログには、PTA問題で悩む親から「裁判が多くの人にとってPTAを考える機会になってほしい」などの反応が寄せられている。岡本さんは「敗訴しても、PTA加入は任意だと広く知らせることができれば、大きな役割を果たせるのでは」。そんな思いでブログにつづり続けている。
0 notes
Text
げんさんな人達(原産協会役・職員によるショートエッセイ)◇地層処分は時間かせぎ◇
げんさんな人達(原産協会役・職員によるショートエッセイ)
◇地層処分は時間かせぎ◇
高レベル放射性廃棄物の地層処分は、人工バリアを施した廃棄物を長い時間地下深い地層に埋め、安全を確保するものである。そこで重要なことは、地層が時間かせぎの役割を果たしていることだ。 廃棄物は永久に地層の中にあるのではなく、いずれは地下水によって地上まで運ばれてくると考えられている。それでも安全が確保できるというのが地層処分の考え方だ。なぜなら、廃棄物が地層を通って地上に運ばれてくるまでには時間がかかり、その間に廃棄物は減衰によって放射能が下がるからである。まさに地層に埋めることは、廃棄物が無害になるまでの時間かせぎをすることだともいえる。人工バリアを施すのはかせぐ時間をさらに長くするためだ。
つまり地層処分とは、有害の廃棄物が無害になるまでの対策をとることであり、廃棄物対策として完結した方法なのである。減衰することなく永久に存在し続け、地上近くで管理するしか手立てのない他の有害廃棄物と比べその対策の違いは明らかだ。 このような地層処分が、廃棄物対策としてきわめて優れた方法であることはもっと強調されてよいのではないか。(ST)
◎「原産協会メールマガジン」2016年8月号 (2016年8月25日発行)
http://www.jaif.or.jp/mailmagazine/2016-08/#8
0 notes
Text
(憲法を考える)自民改憲草案・ハンガリーで読む:上 「伝統回帰」似通う思想
「ドナウの真珠」。そう呼ばれるハンガリーの首都ブダペストは、中央をドナウ川がゆったりと流れる美しい街だ。 この街を訪ねようと思ったのは、総選挙で3分の2の議席を取ったオルバン政権が5年前、野党の反対を押し切り、憲法を丸ごと書き換えたと聞いたからだ。しかも、中身が自民党の日本国憲法改正草案と似ている。 前文を読み比べてみる。 〈自民草案〉「日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴(いただ)く国家」「良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する」 〈ハンガリー新憲法〉「我々は、我々の王、聖イシュトバーンが千年前に、堅固な基礎の上にハンガリー国家を築き」「我々の子供及び孫が、その才能、粘り強さ及び精神的な力により、再びハンガリーを偉大にすると考える」 相通じるのは、過去への憧憬(しょうけい)であり、歴史と伝統の上にある「国柄」を次世代へ引き継いでいこうとする発想である。 ハンガリーは、苦難に満ちた複雑な歴史を歩んできた。 16世紀にオスマン帝国、17世紀末からオーストリアに支配され、1867年にオーストリア・ハンガリー二重帝国に。第1次大戦に敗れると、トリアノン条約で国土の3分の2と人口の5分の3を失う。領土を取り戻そうと第2次大戦では枢軸国側として戦い、再び敗れた。 民族を散り散りにした敗戦が、ハンガリーの人々にもたらした喪失感と屈辱感――。オルバン政権は2010年、トリアノン条約が締結された6月4日を「国民連帯の日」とした。国民国家の枠を超えて民族の一体感を強めようと、自国の外で暮らす在外ハンガリー系住民にもハンガリー国籍を与えた。 新憲法の前文では、王国時代、国家を象徴する存在だった「聖なる王冠」に敬意を表するよう、国民に命じる。 王冠は第2次大戦中に国外に持ち出され、78年に米国から戻ってきた。国立博物館で保管されていたが、第1次オルバン政権時代に、国会議事堂へと移された。「権力の象徴」を、我が手に取り戻そうということなのか。ブダペストで会った政治学者は、新憲法は、第2次大戦以降の歴史を「負の歴史」として否定し、王冠が権威を持った古い歴史と「伝統あるハンガリー」へと回帰する思想に貫かれている、と言う。 伝統回帰という点では、自民草案でも「長い歴史と固有の文化」を持つ「美しい国土」が強調される。草案Q&A集によると、改憲の動機は「占領体制から脱却し、日本を主権国家にふさわしい国にするため」。安倍晋三首相も著書「美しい国へ」で、憲法前文の一節を指し「敗戦国としての連合国に対する“詫(わ)び証文”」と書いている。 米国の歴史学者、ジョン・ダワー氏の言葉を借りれば、敗戦と占領、憲法が制定された時代は、草案の起草者には、「自由な選択が制限され、外国のモデルが強制された、圧倒的に屈辱的な時代」(「敗北を抱きしめて」)と映るのだろう。 ハンガリー新憲法と自民草案はもう一つ、共通の背景を持っている。グローバル化で、国家や国民のアイデンティティーが揺らいでいることへの危機感だ。(編集委員・豊秀一)
0 notes