#一応日本語書籍に想���力を限定して言えば
Explore tagged Tumblr posts
Text
すべての図書館の図書の登録を共通化して、検索可能化、全国への迅速配送可能化すればいいと思う
5 notes
·
View notes
Quote
「企業のネットが星を 被おお い、電子や光が駆け巡っても」国家や民族が消えてなくなるほどではない近未来が舞台の『攻殻機動隊』などで、後のクリエイターに多大な影響と衝撃を与えた漫画家、士郎正宗さん(63)。デビュー40年を迎え、世田谷文学館(東京都)では初の大規模展が開催される中、読売新聞の単独書面インタビューに応じ、これまで生み出した作品や創作の秘密、AI(人工知能)がもたらす人間の未来などについて縦横無尽に語った。近年ほとんどメディアの取材を受けていない士郎さんの貴重な語録をご覧あれ。(文化部 池田創) 展覧会では、『攻殻機動隊』の主人公の素子の印象的なセリフが印刷されたのれんが来場者を出迎える(東京都世田谷区の世田谷文学館で) 世田谷文学館で大規模展 ――デビュー40年を迎えられて、どのようにお感じになっていますか。 そもそも寡作な上、諸事情による中断・未発表・ボツ作品が多過ぎて読者諸氏に申し訳ないものの、何とかここまで生き残る事が出来て大変に幸運だったと思っています。活動が東京や他業種に広がるに連れて「水中を歩いて進むかの様な状態」になり、40年、色々と大変でした。また書籍などの荷物が転居や避難に適さない分量になっています(笑)。 ――代表作「攻殻機動隊」は海外でも熱狂的な人気が続いています。 最初期に出版物の海外展開を頑張りました。望外に細長く継続しており、ありがたい限りです。 ――今回の世田谷文学館の展覧会は大量の原画が間近で見ることができ、充実した展示内容です。 士郎正宗さんのコメントとともに作品世界を振り返る巨大な年表(東京都世田谷区の世田谷文学館で) 今回このような機会を頂き大変感謝しております。僕程度の小規模 傭兵ようへい 型漫画家でこういった事が可能なら、日本のコンテンツ業界はもっと多様多彩な作家・作品を、深掘り探索・開発活用出来るのではないかと思います。 ――「攻殻機動隊」をはじめ、ご著書は情報化社会を予見していると言われます。 たまたま運良くタイミングや関係者の都合に合致し話題として取り上げて頂いているだけで、僕以外にもそういった作家・作品は多数存在していると思います。情報化社会の好ましくない側面があまり大きくならなければ良いですね。物騒、殺伐、トラブルは架空妄想物語の中だけで十分です。 ――AIの発展についてどのように感じていますか。 利便性と損害可能性は表裏一体、これまで考えられなかったレベルの明るい未来の可能性が開ける一方で、悪用や視野 狭窄きょうさく が起き、見えざる支配も容易になっている。研究開発に係る方々には頑張って頂きたいなと思います。 簡易強化外骨格、遠隔操作系ロボット類の開発が現実的 ――幼少期に親しんだマンガや小説はどのようなものがありますか。 デビュー作『アップルシード』のラフスケッチなどが並ぶ展示室(東京都世田谷区の世田谷文学館で) アニメ版の「鉄人28号」や「エイトマン」から入って、雑誌「りぼん」(一条ゆかり氏、大矢ちき氏、弓月光氏などなど)、松本零士氏、永井豪氏、細野不二彦氏の影響が大きいですね。大学以降は諸星大二郎氏、星野之宣氏、大友克洋氏の存在が大きいと思います。 ――「攻殻機動隊」で描いた人間の身体と精神の関係はどのように感じていますか。 脳や体が一体として機能している中では、脳が優位の制御系があったり、体が優位の制御系(例えば副腎とか脊髄反射系とか)があったり、交換可能な部分や欠損許容部分(例えば昔は虫垂や 胆嚢たんのう を結構普通に切除していた)があったり、複雑で不思議に出来ていると思います。 義体化のような、身体交換は僕が生み出した要素ではありません。スタニスラフ・レム氏の『君は生きているか?』や、日本のマンガアニメ界においては石ノ森章太郎氏の『サイボーグ009』などの有名作品がすでにありました。サイバネティクスの一般的な目的は医療や軍事だと思いますが、今後は老化・劣化対策というのも存在感を増すかもしれません。個人的には年々増加中の災害現場における簡易強化外骨格や遠隔操作系ロボット類の開発を進める方が現実的かなとは思います。 ――���著書に細かく書き込まれた欄外文章の役割や狙いを教えてください。 リズム感が単調になりがちな説明セリフや会話を物語内部から減らせる、それによってキャラの練度・演出を高めに設定出来る、物語と読者の距離の調整ができる、などでしょうか。昨今、いや昔もこういう方法は 流行はや りではありませんが……。 ――押井守監督のアニメーション映画版のご感想をお聞かせください。 個人的には原作に気を使っている部分が押井氏にしては多めの1作目より、押井氏節全開の『イノセンス』の方が好みです。いずれも一生懸命作って頂いてありがたいなと思っております。 ――ネット社会の広がりやAI技術の発展をどう感じておられますか。 人工知能の偏向学習、悪意ある人 達たち による人工知能活用と、対策する側の人工知能活用の格差、オンライン上に無い膨大な情報の無視や軽視など、課題は山積しているのではないかと感じています。世界は 繋つな がって狭くなると同時に、逆に分断細分化が進んで互いの距離が開き、問題解決の可否、明暗の格差も広がっている様に感じています。今まさに『言葉が通じなくなってバベルの塔が崩壊し始めている』状態でしょうか。人工知能育成では可能な限り、真実や実態に近い情報を得て優先解とするような、何らかの情報検証機構が必要でしょう。 コスパタイパ重視では驚きや発見も無い ――ネットに常時接続することが当たり前になりました。そのことをどのように感じてらっしゃいますか。 一般的なネット通販をほぼ利用しておりませんが、ネット社会になってからの方がサービスの質が低下&商品を探しにくくなったように感じています。便利、合理的、コスパタイパ重視の姿勢は内向きになりがちで、冗長性や余白が少ない分、周囲を見渡す余裕が減少し続けるし、ひいては驚きや発見も無く窮屈ですね。昔のSFでは「監視管理社会」は人々の敵として描かれるのが一般的だったのですが、現代では意外とそういう管理監視社会の利点も許容されているように思います。とはいうものの、今後もDXが進み常時接続が常識常態化し、行政サービスやインフラなどの分野で、高度化し便利で安全で充実した幸福度の高い世の中になっていくと良いのですが……。 ――「攻殻機動隊」ではサイボーグ化しても人間の内にある「ゴースト」という概念が存在します。「ゴースト」とは何でしょうか。 展示室の中央には『攻殻機動隊』の原画が並び、迫力のある筆致を間近で感じられる(東京都世田谷区の世田谷文学館で) 正確か否か、定義可能��、とは別にして、宗教や哲学や文学昔話の分野で古くから使われている「たましい」「霊魂」「ソウル」などの単語が印象として一般的には伝わりやすいのではないかと思います。「何だかよくわからないが、存在しているように思えるモヤっとしたものを『ゴースト』と呼ぶ」のも娯楽分野では分かりやすくて良いかな、ということで単語を使用しています。 犬や小鳥も感情を有することが一般的にも知られており、感情は人間だけが持つ最上位の機能・特別な評価対象ではない、という観点から、マンガ版ではゴーストという単語において「感情に特別な意味を持たせていない」つもりです。当然ながら人の価値観はそれぞれなので、僕と他のアニメ版の監督諸氏とでもこうした諸々に対する考え方に違いがあるわけですが、その事自体も含めて、作品を異なる角度から捉えて楽しんで頂ければ良いなと考えています。 神話は魅力の塊なのだが… ――ご著書はシリアスな展開と迫力のある戦闘シーンの間にギャグが挟まりますね。作中におけるギャグの効用とはどのようなものでしょうか。 シリアスとギャグの挟み方や割合、そもそも混在を容認するか否か、など受け取る方々の価値観も観点も実に多様なので「万人にとって満足できる作品」というのは僕には難しいなと考えています。僕の取り扱うキャラクターたちは明日をも知れぬ立場なので、悲観的に備え楽観的に対処する、冗談でも言っていないとやっていられない、といったタイプが多めになっています。会話の軽さと行動、判断の速さ厳しさのギャップを楽しんで頂ければ良いかと思います。 ――『仙術超攻殻ORION』は日本神話をモチーフにしたファンタジーです。神話の魅力を教えてください。 神話と呼ばれる物語達は限られた要素と根源的な思考や解釈と想像力で織り上げられ、時代や民族の壁を越えて生き残っている、「選び抜かれた精鋭達」です。人々の心情や思考型や文化を映す鏡として、魅力の塊と言っても良いですね。一方で歴史を振り返ると、建築や芸術や情報戦において支配者や宗教組織や抵抗組織の都合や思惑と深く関わったと思しきものも多く、純粋に「素晴らしいか?」と問われると、答えに困る側面もあります。 ――『攻殻機動隊』のフチコマや、『ドミニオン』の小型戦車ボナパルトなど、作品からは戦車愛を感じます。 正義感にあふれる女性警察官のレオナが活躍する『ドミニオン』のコーナー(東京都世田谷���の世田谷文学館で) 「頑丈で壊れにくくて安全度が高い&移動以外にも何か作業が出来る乗り物」が好きですね。作品内に描く機会はなかなかありませんが、消防関連や港湾作業用の特殊車両、土木建築系や農林作業系の特殊機能車両なども同じように楽しくて興味深いと思っています。 気負わず欲張らず、自己ベスト更新維持 ――現在はイラスト制作や、画集刊行に活動の比重を置いておられますね。 マンガやアニメやゲームの企画書・プロット・シナリオなども色々と作っているのですが、なかなか最終商品の形にまで進める事が出来ておらず、イラストや画集は関係者や予算が少なくても実現可能な 為ため か商品の形になりやすい、というのが理由かと思います。 ――女性のエロチシズムを感じさせる美麗なイラストを生み出されています。 展示室の後半は、雑誌に発表した色鮮やかなカラーイラストが目を引く(東京都世田谷区の世田谷文学館で) モノクロでは描写しにくいがカラーでは比較的描写が容易で、競合が起きにくいと思われる光沢の肌にこだわっています。近年の画集においては、似た構図やポージングの微差バリエーションを連続、重複して描くことで、アニメの原画をパラパラと連続で見る時に近い印象や効果の誘発が起きないかと工夫しています。 ――近況を教えてください。 今も40年前も変わらず東京ではなく関西にいて不規則不健康な生活をしながら昼夜延々と絵やプロットや駄文を描き続けています。視力体力の減少により、未読書籍が積み重なっています。 ――今後の執筆への意気込みや読者へのメッセージをいただければと思います。 気負わず欲張らず、自己ベスト更新維持で変わりなく、他にしたい事も無いので、ダラダラ延々と何かを作る日々を送ると思います。読者諸氏にはまた次の作品でお会いした際に、何らかの形でお楽しみ頂けると幸いです。
「攻殻機動隊」士郎正宗、ネット社会・AI発展に警鐘「言葉が通じなくなってバベルの塔が崩壊し始めている」 : 読売新聞
23 notes
·
View notes
Text
我が国の未来を見通す(80)
『強靭な国家』を造る(17)
「強靭な国家」を目指して何をすべきか(その7)
宗像久男(元陸将)
──────────────────────
□はじめに
本メルマガは当初の予定をはるかにオーバーし、8
0回まで来てしまいました。浅学菲才の恥をしのん
で、知見も経験もない様々な分野に首を突っ込み、
それぞれ表面的ではありますが、知り得る限りの知
識で書きなぐっていました。そうしているうちに、
(前にも紹介しましたように)「その道の専門家��
限界」のような、新たな問題意識を持つに至り、
「では、どうするべきか?」が再び首をもたげ、悩
むことになりました。その結果、最近のメルマガの
ように、「国力」の観点から再整理することしまし
たところ、これはこれで面白くなってきました。
今回は「軍事力」を取り上げます。世界的な呼称は、
「軍事力」ですが、事柄の性格上、我が国の「軍事
力」を語る場合は「防衛力」と置き換えます。
私は、37年間、陸上自衛隊で勤務し、各級指揮官
はもちろん、陸上幕僚監部の幕僚として防衛力整備
を主に担当してきましたので、「防衛力」について
詳しく語り出すと、書籍1冊では足りないぐらい
“言いたいこと”がありますが、あえてテーマを世
間ではあまり語られていない、いわゆる「タブー」
とされている部分などに絞って、しかも要点のみを
紹介したいと思います。
我が国の「安全保障」とか「防衛」に関する最近の
話題についてもっと知りたい読者は、最近、元空将・
織田邦男氏が『空から提言する新しい日本の防衛』
を上梓しましたので、ぜひご一読いただきたいと思
います。織田氏は私と同期で、幕僚監部勤務にあっ
ては陸上、航空の違いありますが、いつも同じよう
な部署で勤務してきた経験があります。よって、
「ライバル」というより「戦友」であり、家族ぐる
みで親しく付き合ってきた仲でもあります。
『空から提言する新しい日本の防衛』
本書は、「将来の我が国の防衛のあり方」に対して、
元自衛官ならではの“切り口”から迫り、一般の軍
事専門家などが追随できない視点から貴重な一石を
投じているとの読後感を持ちます。なかでも、「我
が国の防衛」が抱えている課題、あるいは昨年末に
策定された「戦略3文書」の不十分なところの指摘
などについては私も全く同意です。
あえて違いがあるとすれば、陸上自衛官だった私は、
どうしても「国土」とか「国民」目線から防衛を考
える“癖”がついてしまっているせいか、「国防」
など頭の片隅にもない方々などにとってはどうして
も理解が難しくなってしまいます。その点、元航空
自衛官の織田氏の解説や提言��、難解な領域にはほ
とんど踏み込まないのですっきりしてわかりやすい
と思います。
さて、私の現在の最大の関心事は、「現実進行形の
ウクライナ戦争が国際社会の将来にどのようなイン
パクトを与えるか?」、そして、「そのインパクト
が、やがて“形を変えて”我が国の“眼前”に迫っ
てきて、我が国の平和や独立や国民の安寧な生活を
左右する可能性があるのかないのか?」にあります。
織田氏も再三、同趣旨の切り口で解説していますが、
“予想外のことが起こる可能性を表す”言葉の「ま
さか」や「もしかして」のうち、これまでは“予想
外のことが起こる可能性が低いと考えられる場合”
に使われる「まさか」の範疇として無視あるいは軽
視してきた事態が、“予想外のことが起こる可能性
があると考えられる場合”に使われる「もしかして」
の範疇に移動し、その実態の解明や未然防止の対策
までを含め、考え、検討し、具体化しなければなら
ない割合が増えているように気がするのです。
昨年の「戦略3文書」にあっても、これまでのこの
種計画の“歴史”を継承しつつ、どうしても踏み込
めない憲法上の制約や戦後の防衛政策の変更に対す
る批判への“予防線”を張っているのか、いくつか
の「もしかして」には自ら目をつぶり、「まさか」
の範疇で取り扱い、その上で無視あるいは軽視した
と考えざるを得ない論点がかなりあるとように思う
のです。
現役時代も、毎度ながらの“政治決定”に呆れ果て、
言いようもない“むなしさ”を味わったものでした
が、“我が国の特殊事情からやむを得ない”と自ら
納得させてきた側面があります。
繰り返しますが、“失うものがない”今、自らを納
得させてきた論点まで少し踏み込んで、その要点は
紹介しようと思います。実は、そう思い立って文献
を漁ると参考になる書籍もたくさんあることもわか
りました。ただ、表題からして大きなインパクトを
与えないと手に取ってもらえないからでしょうか、
このジャンルの書籍はタイトルからしておどろおど
ろしいような気もします。例えば、『自滅するアメ
リカ帝国』(伊藤貫著)、『腹黒い世界の常識』
(島田洋一著)、『国連の正体』(藤井厳喜著)な
どです。インターネットで発信しているものも数多
くありますが、共通しているのは著者の皆さんの
“強い危機意識”でしょうか。
なかには、『新しい日本人論』(加瀬英明、ケント
・ギルバード、石平共著)のように、日本人の根底
に流れている「性善説」が背景にあって、この「も
しかして」を考えることができなくっていると指摘
するものもあります。多くの日本人��宗教のように
ひたすら信じている、憲法前文にいう「平和を愛す
る諸国民の公正と信義に信頼して……」のくだりな
どを指すものと考えます。
さて、「もしかして」の領域が拡大したのは、我が
国の「安全保障」とか「防衛」に限ったことではな
いことも明��です。すでに本メルマガで再三触れて
きましたように、我が国の未来に立ちはだかるであ
ろう「暗雲」として、「もしかして」が様々な領域
に広がる可能性があると考えます。
本メルマガ発信の目的は、「我が国の未来について
様々な視点から見通し、“最悪の状態にならないよ
うに”早急に処置すべき具体的な対応策を明確にす
る」ことにありましたが、知れば知るほど“まだ道
半ば”との思いを強くしています。もう少し続けま
すので、しばらくお付き合い下さい。
▼「軍事力」の国際比較
さて、国際的な影響力という点でいえば、「軍事力」
こそが「国力」の“ど真ん中に位置づけられる”こ
とは明白です。しかも、その良し悪しは別として、
核戦力保有の有無は決定的です。
まず、これまで同様、「軍事力」の国際比較につい
てもチェックしておきましょう。発刊されたばかり
の今年の「防衛白書」は、冒頭、「戦後最大の試練
の時を迎える国際社会」から始まります。子細に読
むと、これまでの「“まさか”戦争なんて起こりっ
こない」を否定し、「“もしかしたら”我が国の周
辺でも起こり得る」ことを肯定しているのです。
白書は、「だから、未然防止のために反撃能力の強
化が必要」と言いたかったのでしょうが、白書の性
格上、それが限界なのかも知れません。そして、我
が国の陸海空防衛力については、「我が国の周辺に
は大規模な軍事力が集中している」ことを具体的な
数値で説明するために、世界の陸海空戦力それぞれ
のベスト10を紹介しています。しかし、白書らし
く、我が国の防衛力についてはそれぞれの兵力量の
みを掲載するにとどめています。ちなみに、実際に
ベスト10に入るのは海上自衛隊のみで、保有船舶
総トン数から第5位にランクされるはずです。
陸海空戦力を含む、軍事力を構成する様々な要素ま
で含め、通常兵器の世界軍事力ランキングは、「Gl
obal Firepower 2023」によれば、1位アメリカ、2
位ロシア、2位中国、4位インド、5位イギリス、
6位韓国、7位パキスタン、8位日本、9位フラン
ス、10位ドイツとなっています。
また「軍事予算」のランキングは、「ストックホル
ム国際平和研究所」(SIPRI)によれば、1位アメリ
カ(8010億ドル)、2位中国(推定2930億
ドル)、2位インド(766億ドル)、4位ロシア
(659億ドル)、5位イギリス(659億ドル)
と続き、日本は9位(517億ドル)���なっていま
す。つまり、日本の防衛予算は、2021年時点で
米国の約6.5%、中国の約18%だったことがわ
かります。
前回上げたような各国の「購買力平価」を使用する
と、実際の軍事予算の様相は違ってくるものと考え
ます。また、年末の「戦略3文書」には「GDPの
1%から2%に引き上げる」旨が盛り込まれていま
すので、実現すれば数年後のランクは上がることも
予想されます。
現在、世界の核保有国は9カ国で、上記SIPRIの推計
による保有弾頭数は、1位米国(5244発)、2
位ロシア(5889発)、3位中国(410発)、
4位フランス(290発)と続き、9位には北朝鮮(3
0発)がランクされています。これらから軍事予算の
上位国はほとんど核保有国であることもわかります。
これらはあくまで静的な比較で、ウクライナ戦争に
より、ロシアや西側諸国の兵器の生産量や消耗量も
大幅な変動があったことでしょうから、最新のデー
タを比較すると、すでに変動している可能性もある
でしょう。
厳しくなりつつある周辺情勢や我が国の「国力」と
比較して、これらのランクや防衛力の量・質が現状
程度で適切か否かにについては各論あることでしょ
う。しかし、増強論に反対する側に立つ人たちの意
見の背景に、戦後の「平和ボケ」とか「平和の毒」
が今なお根強く定着しているとすれば、やはり「時
代は変わった」ことに気づく必要があると考えます。
目を開け、耳をふさがないで、しっかり見極めた上
で、自分たちの主張が正しいか否かを再考する時が
来ていると思うのです。
8月16日、有楽町駅前で、この暑さの中、背広を
着た日弁連の皆さんが「憲法違反の平和安全法制の
廃止を」との看板の前で街頭演説しているのを見か
けました。周りにはだれもいませんでしたが、“司
法試験に受かるくらい頭が良いのだから、法律以外
のことも少しは勉強すればよいものを”と思いつつ、
私も無視して通り過ぎました。ちなみに、「平和安
全法制」が制定されたのは9年前の2014年です。
「今頃、何を言っているのか」という点でも呆れま
した。
白書も言うように、“戦後最大の試練の時を迎えて
いる国際社会”を、我が国はけっして傍観できるわ
けがなく、予想される“戦場”が我が国近傍にある
ことを考えると、逆に“国際社会を戦略的にこの地
域に引きずり込めるか否か”に我が国の存亡がかか
っていると考える必要があります。そのために“何
をすべきか”については、ウクライナ戦争をみれば
明らかでしょう。多少苦しくても、「自助努力」す
るしかないのです。
▼我が国の「防衛力」の“急所”──核抑止
「戦略3文書」に書かれていない視点で、我が国の
「防衛力」の“急所”」と題して、いくつかの論点
の要点のみを紹介しましょう。“急所”ですから、
口に出すこともはばかれ、普段は隠れています。大
方の日本人のように、関心がない人には思いもよら
ないでしょう。されど“急所”なのです。ものすご
く大事なのです。
その筆頭は「核戦力」の取り扱いでしょう。織田氏
も「国家安全保障戦略」の中で、核抑止については
わずか1行しか触れず、米国に丸投げしていること
を「最大の欠陥」として問題視していますが、私も
全く同感です。
言うまでもなく、中国、ロシア、北朝鮮のような、
核・ミサイルを保有する権威主義国家に囲まれてい
る我が国が、「非核三原則」のような“現実離れ”
した政策を保持して「考えもしない」段階に留まっ
ている“危険性”について、安全保障や防衛を“真
剣に考えている人たち”は皆、多少の温度差はあっ
てもよく認識していると思います。しかし、その範
囲が“真剣に考えている人たち”に留まっているの
が問題なのです。
『自滅するアメリカ帝国』の著者・伊藤貫氏は、ア
メリカ在住が長いせいか、今どきの国際政治学者に
は珍しく、ハッとすることをスバっと指摘します。
一例を挙げれば、日本にもなじみが深い、アーミテ
ージ、ジョセフ・ナイ、それにライス元国務次官ら
が「日本の核武装をさせたくない」とする一心から
アメリカの「核の傘」の有効性を繰り返して主張し
てきた事実、しかし、昨今のアメリカの相対的な力
の衰退や国際環境の大きな変化もあって、キッシン
ジャー、ウォルツ、ホフマンなどのリアリスト戦略
家たちは、「日本もアメリカに過剰依存しない自主
防衛に舵を切るべき」と提唱していることを紹介し
ています。当然、自主防衛には核戦力の保持も含ん
でいます。
私たちは、通常兵器の世界では「敵と我が拮抗した
戦力を保持しておれば戦争は発生しにくい」ことを
軍事常識として理解していますが、伊藤氏は2人の
有識者の分析を紹介して、これまでの常識をくつが
えしています。実に興味深いです。
まず、MITの軍事学者パリ─・ポーゼン氏の「他
国からの先制攻撃によって破壊されない核兵器を所
有している国は、世界覇権を握ろうとする超大国に
よる軍事的な恫喝と攻撃を拒否する能力を持ってい
る」、同じくMITの国際政治学者ハーヴェイ・サ
ポルスキー氏の「核武装国同士の戦争はリスクとコ
ストが高すぎる。したがって、核武装した諸国は、
お互いに核戦争を避けようとするだけではなく、通
常兵器による戦争まで避けようとする」との分析で
す。
つまり、核戦力保持の有効性は、たとえ彼我の格差
があっても、核戦争���抑止に留まらず、通常戦争の
抑止にもつながることを指摘しているのです。「核
抑止」と「核廃絶」の区別もつかない大方の政治家
・有識者・マスコミ人には“目から鱗”であろうと
思います。
だからこそ、湾岸戦争やイラク戦争から「イスラム
諸国が非核保有国だから、簡単にアメリカの攻撃を
受けた」との教訓を学んだ北朝鮮は、国民が明日の
食事さえ飢えているなかにあっても、莫大な経費を
費やして核実験やミサイル発射実験を繰り返し、有
効な核戦力の保持を企図しているのです(北朝鮮の
今年の餓死者は例年の3倍との報道がありましたが、
実態はかなりひどそうです)。
そして、中国は、日本を現状のような“与(くみ)
しやすい状態”に留めおくために、福島原発の処理
水について、自らがもっと濃い濃度の汚染水を垂れ
流している事実を知りつつ、“天つば”にもなりか
ねないリスクを冒しても、日本人が原発にも原爆に
も“眠ったまま”積極的な意思表示をしないように、
戦略的に反対論をぶち上げているのです。
さて、我が国の「核抑止」については大きな問題点
が2つあると考えます。まず、我が国のように「非
核3原則」を唱え、自らは核兵器を「持たず」「作
らず」「待ちこまず」としてすべてアメリカに“丸
投げ”している国が、ボーゼンやサポルスキーのよ
うな考えを適用しつつ、核抑止も、さらに通常戦力
の抑止も本当に可能なのか、という点です。
言葉を代えれば、アメリカの「核の傘」は未来永劫
に有効なのか、という点ですが、これについては、
次回、「日米同盟の有効性」に関連づけて詳しく触
れることにしますが、アメリカ政府の“一存”でそ
の有効性が突然、反故(ほご)になる可能性がある
ことは間違いないでしょう。
問題点の2番目は、中国や北朝鮮のような権威主義
国家に、アメリカのように「自国(民)の膨大な被
害回避を最優先し、核保有国とは戦争しない」との
考えが通じるかという点です。もし両国の為政者が
自国(民)の犠牲など一顧だにせず、戦争目的を遂
行しようとすれば、世界最大の核保有国・米国の
「核の傘」であっても、抑止が有効に機能しない可
能性があります。
なんせ中国には、1969年、ウスリー川の中ソ国
境問題を解決するため、当時は非核保有国だったに
もかかわらず、核保有国・ソ連に対して果敢に攻撃
を仕掛けたという“前歴”がありますし、同じく北
朝鮮も、“朝鮮半島はアメリカの防衛ラインの外”
と宣言した「アチソン声明」があったとはいえ、韓
国の後ろ盾に核保有国・アメリカがいることを知り
ながら、朝鮮戦争を仕掛けたのでした。
将来、これらの国とさらに緊張が高まるような事態
になれば、当然ながら、最大限の卑劣な文句を乱発
しつつ“露骨な核恫喝”を予想しておく必要がある
でしょう。
一方、本メルマガでも指摘したように、ウクライナ
はソ連崩壊時に領内に1240発の核弾頭を保有す
る世界第3位の核保有国でしたが、1994年の
「ブダペスト覚書」によって核兵器をすべて撤去し
ました。「歴史のif」ですが、仮にウクライナに
数発でも核兵器が残っていたなら、このたびの「ウ
クライナ戦争」は発生したでしょうか。少なくとも、
プーチン大統領の脳裏には、“ウクライナが報復と
して核兵器を使用すれば自国に膨大な被害が出る”
ことが浮かび上がり、侵攻を躊躇することにうなが
る可能性はあったと推測できるでしょう。
悩ましい問題でありますが、国際社会は、理想では
あってもいつ実現するか全く見通しが立たない「核
廃絶」ではなく、明日の「核抑止」をいかにするか、
で動いていることは間違いないのです。ゆめゆめ優
先順位を間違えないことが肝要です。
今回はこのくらいにしておきますが、我が国の「防
衛力」の盲点について、「もしかして」、つまり
「考えられないことを考える」ことまで拒否せず、
“急所”だけに“そっと覗いてみる”くらいの知恵
が必要であると私は思います。
ついでに私がアメリカをうらやましいと思うことが
もう一つあります。MITという、日本の東京大学
にランクされるような大学の教授たちが堂々と「正
論」を述べていることです。
それに対してと言うわけではありませんが、日本の
学者先生方は自らに恥じることはないのでしょうか。
前述の日弁連もそうですが、優秀なはずなのに、も
はや「つける薬がない」のでしょうか。
8月15日、終戦記念日の産経新聞社説は、論説委
員長の記名入りで「首相は核抑止の重要性を語れ」
と題して、“悲劇を繰り返さぬため”にも「核抑止
の有効性」について、普段の倍ほどの長さで堂々と
述べていました。過去にもあったのかも知れません
が、私自身は「核抑止」についてこれほどの内容を
マスコミ人が語ったのを初めて知りましたので、と
ても驚きました。
これなどはとても珍しいケースだと思いますが、我
が国の最大の問題は、様々な「もしかして」など
“夢にも思わない”人たちが政治家・有識者・マス
コミ人・教育者などに数え切れないほど存在し、な
おかつ、依然として“その人たちの声が大きい”こ
とにあると思うのです。その結果を受けて、大方の
国民もなんら危機意識を持つことなく、時間だけが
進んでいきます。本当に困ったものです。次回は、
もう一つの“急所”を紹介しましょう。
(つづく)
(むなかた・ひさお)
10 notes
·
View notes
Text
A君の事例
2Eという言葉を聞いたことがある方は少なくないかもしれません。2Eとは、twice-exceptional(二重に特別な)という意味で、知的に高い要素と発達障害の要素を併せ持つ子どもたちを指す言葉です。
一方、ギフテッドという言葉を聞いたことがある方は多いと思いますが、こちらは”知的に高い”という意味を有する言葉とされています。例えば大学の飛び級制度で進学した人やメンサ(全人口の上位2%のIQを持つ人で構成される団体)の会員のように、ギフテッドという言葉は、高い知能と特殊な才能を持つ人のニュアンスを込めて使われることがあります。
ギフテッドという言葉が使われてきた中で、適応的なギフテッドと、必ずしも適応がうまくいかないギフテッドの双方の存在が指摘されるようになります。そして、適応に困難を感じる後者のギフテッドには、しばしば発達障害の特徴が見いだされるとの指摘がある中で、例えば日高(2020)は次のように指摘しています。
知的ギフテッドという名称や知的発達水準の高さから、「知的ギフテッドの子どもは困っていない、何でもできる」と誤解されやすいが、知的機能と適応機能の2軸で考えるとそうではないことが明らかになる。 知的ギフテッドには2つのグループに大別でき、困り感を持ち配慮や支援を必要とする子どもと、家庭や学校等で適応的に生活する(明らかな支援対象とならない)子どもに分けられると考える。 ※引用元 日高茂暢(2020).知的ギフテッドの子どもの持つ特別な教育的ニーズの理解-特別支援教育の「個に応じた学習」を用いたインクルーシブな才能教育-,J.Fac.Edu.Saga Univ.,Vol.4,No.1,pp147-161

※画像引用元 日高茂暢(2020).知的ギフテッドの子どもの持つ特別な教育的ニーズの理解-特別支援教育の「個に応じた学習」を用いたインクルーシブな才能教育-,J.Fac.Edu.Saga Univ.,Vol.4,No.1,pp147-161
上述の「困り感を持ち配慮や支援を必要とする子ども」については、周囲の素朴な知能観が、支援の必要性という問題を見え��くくしているという指摘もあります。これについて前述の日高(2020)は次のように指摘します。
世間一般における知能に関する誤解、即ち、「知能の高さは学業成績の高さと比例する」「知能の高い人は学業的・社会的・行動的に困っていない(困り感が少ない)」「知能の高い人は学校や社会において問題を起こさない」等の素朴な知能観の弊害によると考えられる。 ※引用元 日高茂暢(2020).知的ギフテッドの子どもの持つ特別な教育的ニーズの理解-特別支援教育の「個に応じた学習」を用いたインクルーシブな才能教育-,J.Fac.Edu.Saga Univ.,Vol.4,No.1,pp147-161
これに関して、例えば小泉(2014)は、「隠れディスレクシア」を持つ知的ギフテッドのA君という臨床症例について次のように言及しています。A君は高校生、小泉(2014)が在籍する北海道大学において、開講教室や相談を通じて小泉(2014)が出会った児童・生徒の一人です。この開講教室を訪れた児童・生徒たちは、トータルのIQが130前後あり、学力的に高く発想も豊かで、学校では問��のない児童・生徒とみなされてきたといいます。ちょっと長くなりますが、一部を引用してみます。
知的ギフテッドを持つA君と臨床現場で出会った。高い知的能力を持っているために、学校のテストでは9割程度の得点で、成績も優秀だった。そのため、学校はもちろん、相談機関や医療機関からも読み書き計算等の問題についての指摘はなかった。 認知特性の把握と、IEP作成のためのエビデンスとする目的で、WISC-IVを実施した。驚くべき結果だった。4つの指標の合成得点についてみると、言語理解と知覚推理で「非常に高い」、ワーキングメモリーでは「平均の上」、処理速度では「平均」を示した。処理速度が、個人内では弱い能力であり、「絵の抹消」、「符号」が低得点であった。結果は、WISC-IVの知的ギフテッドと想定できる高い知的能力を示した。 しかし、臨床場面では日々の悩みを幾度となく繰り返して訴えてきた。一つは、「漢字を書いても覚えられない、似たような文字を間違える、書くのが遅い、計算が遅い、本を読んでも頭に入らない、集中できない」などの学習の問題である。もう一つは、「だるい、何をしても楽しくない、嫌いなことが増えていく、自分はダメな人間だ」など、感覚的にも精神的にも脆弱性のあることがうかがわれた。 学習の問題では、個人内における処理速度の能力が低く漢字では旁と偏の間違いや、撥ねや払いなどの間違いが見られた。ただ、学習場面では理解が速く、教えればほとんど漏らすことなく覚えていった。学習の困難は想定しにくかった。ただ、どんなに高い得点をとっても満足せず、自分で間違ったいくつかの問題を気にしていた。そのような点からは、完璧主義であることがうかがわれた。 また体のちょっとした刺激が気になる点からは感覚過敏、加えてギフテッドの持つ過度激動という特性を想定した。ちょっとした失敗や間違いを引きずる場面や、���感の激しい揺れがうかがわれたからである。 ※引用元 小泉雅彦(2014).読み書き困難を持つ知的ギフテッドの支援,子ども発達臨床研究,Vol.6,pp131-136
ここで、過度激動(OE:Overexcitabilities)とはギフテッドに見られる心理特性とされ、刺激に対する過度な感受性の高さや刺激への強い行動的・感情的反応が見られる、とされます。OEは5つの領域で構成され、次のような特徴が見いだされるとされています。

※参考文献および画像引用元 日高茂暢(2023).ギフテッドとOverexcitability-肯定的分離理論を通じて-,LD研究,Vol.32,No.4,pp244-250
また、ディスレクシア(dyslexia)とは、知的能力および一般的な理解能力などに特に異常がないにもかかわらず、文字の読み書きに著しい困難を抱える障害であり、学習障害の要因となることがある疾患、とされています。これについて、例えば国立成育医療研究センターのサイトには次のような解説が掲載されています。
ディスレクシアとは、学習障害のひとつのタイプとされ、全体的な発達には遅れはないのに文字の読み書きに限定した困難があり、そのことによって学業不振が現れたり、二次的な学校不適応などが生じる疾患です。 知的能力の低さや勉強不足が原因ではなく、脳機能の発達に問題があるとされています。そのため発達障害の学習障害に位置づけられており、2013年に改定された米国精神医学会の診断基準(DSM-5)では、限局性学習症(いわゆる学習障害)のなかで読字に限定した症状を示すタイプの代替的な用語としてdyslexia(ディスレクシア)を使用しても良いことになりました。 (中略) 留意しておきたいことは、ディスレクシアの子どもでは文字が読めないと表現されることが多いのですが、これが誤りであり正しくは読むのが極端に遅いし、よく間違えるという表現になるという点です。1文字を読��のに時間がかかり、間違えることもあるといった状態では、読むだけで疲れてしまって、意味を把握する段階まで至りませんし、読書に対する拒否感が生じてしまうことになります。その結果、語彙や知識が不足して、学業不振が著しくなっていきます。さらには心身症や不登校といった二次障害の状態になってしまうこともあります。 ※引用元 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター https://www.ncchd.go.jp/hospital/sickness/children/007.html#:~:text=%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%81%A8%E3%81%AF,%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%8C%E7%94%9F%E3%81%98%E3%82%8B%E7%96%BE%E6%82%A3%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
A君の症例に話を戻します。小泉(2014)は、A君の相談を受ける中で、A君の訴えの根底にはディスレクシアの存在があるのではないかと考え、次のように述べます。
ディスレクシアを疑ったのは、彼と行ったテストの分析からである。テストでは長文の文脈はきちんと理解できているにもかかわらず、問題文を読み違えたことによる誤答が目立った。数学や理科では、解答のやり方は分かっているが、計算に時間がかかり最後の問題までたどり着かなかった。本人自ら伝えてくれたからこそ、分かったことでもある。 そこで、再度WISC-IVを見直した。言語理解と知覚推理からなる一般能力的指標とワーキングメモリーと処理速度からなる認知熟達度指標に差が見られる。この事が、彼に2つの学習面でのアンバランスさを生じさせている。一つは、公式の意味や概念は把握できているが計算が遅いこと、もう一つは、読解力には優れているが読みや書きが遅いこと、である。テストの問題の解き方は分かっているのだが、単純な処理に時間がかかり焦燥感がどんどん募っていく。彼の頭の中は、高性能のCPUを持ちながら、メモリーが不足しているコンピュータのような状態であったといえる。一般能力的指標と認知熟達度指標の差が、結果として「読み書き計算」の困難と関連すると想定した。 では、読みに困難を抱えながらも談話が流暢であり、読解力も高く、成績も優秀なのはなぜか。おそらく、「読み」関しては、文脈処理が優先されるために、結果としては苦手な読みをマスキングされ、そのため表面的には、読解には読みの問題が生じなかったと考えた。 読み書き計算の苦手さは、彼の自尊感情も低下させていた。「こんなこと幼稚園児だってできるのに」と言いながら自分の心を吐露していた。彼に「あなたはこんなに点数がいいのだから」と言っても納得はしない。将来の自分の姿と結び付けて、ネガティブループにはまっていく。 「読み書き計算」の苦手は、家庭や学校はもちろん専門機関でも見逃されてきた。それは、本人が困り感を訴えても、勉強ができているために、些細な問題として片づけられてきたのである。 ※引用元 小泉雅彦(2014).読み書き困難を持つ知的ギフテッドの支援,子ども発達臨床研究,Vol.6,pp131-136
A君本人が自ら伝えてくれたから分かったこと、という記載は、前述した「素朴な知能観」の存在を浮き彫りにさせます。高校のテストで9割近い得点を出し成績優秀とみなされていたA君に対して、「学校はもちろん、相談機関や医療機関からも読み書き計算等の問題についての指摘はなかった」のは、周囲の人たち自身が「素朴な知能観」を持っていたことの影響を指摘し得るかもしれません。A君自身は「こんなこと幼稚園児だってできるのに」と自分を否定的に捉えていたのですが、(A君を成績優秀と見なしていた)周囲の人たちからは「勉強ができているために、些細な問題として片づけられてきた」結果、その悩みが周囲の人たちに可視化されることはありませんでした。

※画像引用元 日高茂暢(2020).知的ギフテッドの子どもの持つ特別な教育的ニーズの理解-特別支援教育の「個に応じた学習」を用いたインクルーシブな才能教育-,J.Fac.Edu.Saga Univ.,Vol.4,No.1,pp147-161
高い知能を持っていても、特別なニーズを抱えている子どもは多数存在していると考えられます。しかし、検査結果や学習面で成績が良いために見落とされてしまう。A君の症例は、このような特別な支援を必要とする児童・生徒たちに対して、その体制をどう構築していけばよいのかという問題を浮き彫りにする、と小泉(2014)は指摘します。これに関して、冒頭に紹介した日高(2020)は、特殊教育という点について次のように指���しています。
特別な教育的ニーズのある子どもを対象にした特別支援教育は、かつては特殊教育(Special Education)という概念で呼ばれた。日本では、特殊教育という用語は障害児教育とほぼ同義に運用されてきたように考えられる。ここでSpecialという形容詞の定義をOxford英語辞典で確認すると、初めに"Better,greater,or otherwise different from what is usual"とあり、次に"Belonging specifically to a particular person or place"という文脈で"Used to denote education for children with particular needs, especially those with learning difficulties."と書かれている。 Specialという概念は、通常と異なって優れた、またはその人がもつ特別な何か、というニュアンスであり、その一部として学習困難が含まれている。したがって、Special Educationという用語は、本来、平均的な通常教育では効果のあがらない子どもを対象にした教育という意味であると考えられる。すなわち、通常よりも学習上の困難のある障害を持つ子ども(children with Handicapped)と、通常よりも優れた潜在能力を持つ子ども(children with Gifted or Talented)と��2つの側面を持ち、障害児教育よりも広い概念と言える。 ※引用元 日高茂暢(2020).知的ギフテッドの子どもの持つ特別な教育的ニーズの理解-特別支援教育の「個に応じた学習」を用いたインクルーシブな才能教育-,J.Fac.Edu.Saga Univ.,Vol.4,No.1,pp147-161
日本における特殊教育といえば、上述したようにほぼ障害児教育と同義に扱われている、というのは皆さんもご承知のことと思います。海外と日本では、特殊教育という言葉が本来持つニュアンスが異なっており、言語を翻訳する際、常につきまとう言語間の意味やニュアンスのずれを考慮しても、日本における特殊教育の指す範囲は比較的限定的で、特別支援学校で行われる障害児の教育という受け止め方が主流です。これに対して、インクルーシブの観点から考察し、海外との差を含めて論じているのが引用元の論文、なのですが、その主題はひとまず置き、このブログで注目したかったのは、A君の事例が示唆する学習面の課題を持つ子どものアセスメントという点です。
高いIQを持つギフテッドのA君ですが、上述したような学習上の困難が生じていました。数式の意味や概念の理解は高い到達度を示す(数学の解き方がわかる)のに計算が遅い(処理が遅い)、読解力には優れている(言葉や文脈の理解も高い)のに読みや書きが遅い(処理が遅い)A君の学習上の困難を生じさせている要因をアセスメントしてみたところ、「(例えば64ビット処理の)高性能CPUを持ちながら、メモリーが不足しているコンピュータのような状態」であり、「一般能力的指標と認知熟達度指標の差が、結果として「読み書き計算」の困難と関連する」という背景の存在が示唆されていました。
このような処理能力や認知的側面のアンバランスという側面は、A君のようなギフテッドに限った話ではもちろんなく、例えばワーキングメモリーの不足で学習上の困難を抱える発達障害の子どもは多く存在しています。そして、その逆の場合もあるでしょう。処理は速いが概念の理解が困難(例えばメモリーは多いがCPUは16ビット処理)な場合などです。
漢字の習得に苦労する、計算を頻繁に間違える、会話はできるのに音読が難しい、会話で伝えることができて言葉を知らないわけでもないが文章化するのが難しい、様々な様態を呈する発達障害の子どもがいます。このような子どもたちに学習面を支援するに際しては、学習上の困難をもたらしている要因がどこにあるのかアセスメントすることができれば、それが望ましいと考えられます。例えば漢字の習得に苦労するという場合、文字の形態認識の問題なのか、ワーキングメモリーの問題で書き取り作業にリソースが取られた結果として漢字の形態認識に影響が生じているのか、高機能自閉症などにしばしばみられる相貌性の問題なのか、など、どのように捉えるかにより、その後のサポートの方向性は大きく異なってくるはずです。
加えて、A君の事例は、アセスメントする視点の重要性を示唆していると同時に、支援の際は、支援者自身のバイアスがアセスメントを阻害する可能性(例:素朴な知能観)に留意し、学習を困難にさせている要因を様々な視点からアセスメントすることの必要性を示唆していると捉えることが可能です。
なお、A君の事例については、一般能力的指標と認知熟達度指標の差から生み出される学習上の困難に対して、どのように対処しサポートしていったのか詳しく掲載されています。関心のある方は、文献を参照してみてください。

※引用元 日高茂暢(2020).知的ギフテッドの子どもの持つ特別な教育的ニーズの理解-特別支援教育の「個に応じた学習」を用いたインクルーシブな才能教育-,J.Fac.Edu.Saga Univ.,Vol.4,No.1,pp147-161
(野村)
0 notes
Text
ドバイ不動産投資で人生逆転!夢を叶えたシンデレラストーリー
ドバイ不動産投資で人生逆転!夢を叶えたシンデレラストーリー
**はじめに:灰かぶりからドバイのプリンセスへ**
かつては、どこにでもある平凡なOLだった私。将来への不安を抱えながら、毎日の仕事に追われる日々を送っていました。貯金も少なく、夢なんて、現実離れした幻想のように感じていました。しかし、ある出会いによって、私の運命は大きく変わることになります。それが、ドバイ不動産投資との出会いでした。この記事では、私がどのようにしてドバイ不動産投資で人生逆転を果たし、夢を叶えたのか、その軌跡を赤裸々に綴っていきたいと思います。
**第1章:運命の出会い – ドバイ不動産の魅力に開眼**
当時、私は漠然と「何か人生を変えられる投資はないか」と考えていました。そんな時、友人からドバイ不動産投資の話を聞きました。正直、最初は半信半疑でした。ドバイ?遠いし、リスクも高そう…と。しかし、友人の成功談を聞き、そして自分でドバイの不動産市場について調べ始めるうちに、その魅力に引き込まれていきました。
**驚異的な経済成長と人口増加:** ドバイは目覚ましい経済成長を遂げており、人口も増加の一途を辿っています。これは、不動産需要の増加を意味し、高い投資リターンが期待できることを示唆していました。
* **多様な投資オプション:** 高級マンションからヴィラ、商業施設まで、様々な種類の不動産が存在し、投資スタイルに合わせて選択できる柔軟性がありました。
* **魅力的な税制:** ドバイには所得税や不動産取得税がないため、投資利益をそのまま手にすることができます。これは、他の多くの国と比べて大きなメリットでした。
* **高い賃貸需要:** ドバイは観光地であり、多くの外国人労働者が居住しているため、賃貸需要が非常に高く、安定したキャッシュフローを得やすいという点が魅力でした。
**第2章:不安と葛藤 – 初めての投資への挑戦**
とはいえ、初めての海外不動産投資には不安がつきものでした。
**言語の壁:** 英語は話せましたが、ビジネスレベルの英語力は不足していました。専門用語も多く、契約内容を完全に理解するのに苦労しました。
* **情報収集の難しさ:** 日本語の情報は少なく、英語の情報も玉石混淆でした。信頼できる情報源を見つけるのに時間を要しました。
* **資金調達:** 貯金だけでは足りず、銀行融資についても検討する必要がありました。審査基準や手続きについても不安がありました。
しかし、これらの不安を乗り越えるため、私は以下の努力をしました。
**信頼できる不動産エージェントとの出会い:** 英語が堪能で、ドバイ不動産市場に精通したエージェントを見つけました。彼/彼女のおかげで、安心して投資を進めることができました。
* **徹底的な情報収集:** 英語の専門サイトや書籍、そしてエージェントからのアドバイスを組み合わせ、市場動向を綿密に分析しました。
* **専門家への相談:** 弁護士や税理士に相談し、法的・税務的なリスクを最小限に抑えることができました。
**第3章:成功への軌跡 – 投資戦略と結果**
最終的に、私はドバイのダウンタウンに位置する高級マンションに投資することに決めました。比較的リスクの低い物件を選び、長期的な視点で運用することを心がけました。
**物件選定のポイント:** 立地、利便性、将来的な価格上昇見込みなどを考慮し、綿密に調査しました。
* **資金計画:** 銀行融資を活用し、無理のない資金計画を立てました。
* **リスク管理:** 複数物件への分散投資や、空室リスクへの対策など、リスク管理にも注意を払いました。
その結果、投資開始から数年で、当初の投資額を大きく上回るリターンを得ることができました。物件価格の上昇に加え、安定した賃貸収入も得ることができ、経済的な自由を手にすることができました。
**第4章:夢の実現 – 新しい人生の始まり**
ドバイ不動産投資による成功によって、私は長年の夢を実現することができました。
**経済的な自由:** 収入が安定し、自由に使える時間が増えました。
* **豊かな生活:** 憧れの高級マンションに住み、これまで我慢していた旅行や趣味を楽しむことができます。
* **将来への希望:** 今後も不動産投資を継続し、さらなる成功を目指したいと考えています。
**結論:あなたもドバイ不動産投資で夢を叶えられる**
私の成功は、決して偶然ではありません。綿密な調査、適切なリスク管理、そして信頼できるパートナーとの協力によって得られた結果です。ドバイ不動産投資は、リスクもありますが、大きなリターンが期待できる魅力的な投資です。この記事が、あなたの人生を変えるきっかけになれば幸いです。 もちろん、投資にはリスクが伴いますので、十分な調査と専門家のアドバイスを受けてから投資を行うことをお勧めします。 あなたの夢の実現を、心から応援しています。
0 notes
Text
TEDにて
マーク・クシュナー:あなたが作る建築の未来
(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)
マーク・クシュナーは、建築とは計算や都市計画ではなく、理屈抜きの感情であると言います。
大胆でユーモアに富んだ講演の中で、クシュナーは、過去30年間の建築の歴史を駆け抜け、一度は遠ざかってしまった大衆が、どのようにしてデザインの過程に必要不可欠な存在になったのかを語ります。
現在では、ソーシャルメディアのおかげで、建築家たちは数年先の建物の完成を待たずして、設計した建物の感想を耳にすることができるようになりました。
その結果はいかに?建築がかつてないほど私たちに近い存在になります。リビングストン公立図書館は、私の故郷で2004年に完成しました。
ドームをたずさえ、丸い装飾と円柱に赤レンガときました。リビングストンがこの建物で何を伝えたいのか検討がつくでしょう。子供たち、資産価値、歴史です。でも、現代図書館の役割とはあまり関係がありません。
同じ年の2004年。アメリカの反対側では別の図書館が完工しました。こちらです。シアトルにあります。この図書館はデジタル時代におけるメディアへの接し方を象徴するものです。都市における新しい公共施設の姿で人々が集まって読んだり共有したりできます。
どうしてこうなったのでしょう。同じ年に同じ国内で建てられた「図書館」と呼ばれる2つの建物がなぜ?こんなにも違うのでしょうか?その答えは、建築は振り子の原理に従っていることにあります。
一方には、イノベーションがあり、建築家たちは、今日見られるような新しいテクノロジーやタイポロジー、新たな解決法を常に推し進めてきました。
そして、ひたすら推し続けた結果。皆さんに完全にそっぽを向かれた形です。
今や真っ黒な出で立ちでとても落ち込んでいます。皆さんは素敵だと思われるかもしれませんが心は死んでいるんです。選択肢がなかったのですから。ですから、反対側に行って大衆が好む象徴をまた取り入れなければいけません。
そうすれば、皆さんはハッピーですが、私たちは後ろめたい気分なのでまた実験を始めます。振り子を押し戻して、左右に揺らしながら、第二次世界大戦もあり300年が経ちました。過去30年は間違いなくそうでした。
実は、建築デザインというのは目まぐるしく動くものです。
建築の構想にそんなに時間はかかりません。
時間がかかるのは実際の建設で3年から4年かかりますが、この間にも建築家は、2つか8つ、百もの異なる建築をデザインします。4年前に設計した建物が成功するか否か分からないままデザインするわけです。
これは建築界でフィードバックの循環がうまく行われなかったためです。
そして、こんな建物が生まれたのです。
30年前。ちょうど70代の終盤に起きたブルータリズム(要するにコンクリートです)は、2年間の動向ではなく、20年間の傾向でした。
20年間も建築家はこのような建物を建て続けていたのです。皆さんに不評だったとは思いもよらなかったのです。このようなことは二度と起こりません。なぜなら、私たちは���築における偉大なる変革を目前にしているからです。
ポストモダン建築。80年代後半から90年代初頭の脱構築主義。
と変化し、コンクリートや鉄、エレベーターの発明を経た今、メディア革命を迎えつつあるのです。
私たちは新しい時代にいます。建物家とはもったいぶった言葉や難しい構図を掲げるミステリアスな生き物ではなく、皆さんも 声のない大衆ではないのです。もはや、建築家の言うがままを受け入れるだけではありません。
建築家は、皆さんに耳を傾けますし、皆さんも彼らを恐れません。
つまり、左右に揺れながらスタイルからスタイルへ。時代の流れを移動してきた振り子は意味をなさないのです。
私たちは実際に一歩前に出て、社会が直面する問題の効果的な解決策を見つけることができるのです。これが、建築の歴史の最後です。ですから、未来の建築は、今日の建築とは非常に異なった姿になるはずです。
災害に日照りという異常気象。100年前なら歴史的に見ると大飢饉のレベルかもしれません。違いは政治以外のテクノロジーによる大量生産が可能になった、インターネット、金融工学の発展などが貢献してる!
そういえば、今年の猛暑日は自動販売機クーラー控えめにした?猛暑日になったらやれ!これが夜の都心部を熱くする要因かもしれないのに。
都心部の電柱に霧のスプリンクラーつければ?地中から配管伸ばすだけ!地中に電柱埋めなければ現在の資産を有効活用しつつ、雨の降らない日のみ電柱点灯同様、夜中に自動放水すれば、東京都など都市部のヒートアイランド現象回避できる可能性は高いかも?
都市部でのアスファルト50度以上は火事と同様災害!適正温度に消火するべきです!
都心部の電柱に霧のスプリンクラー搭載で夜中放水と同時に全消防署が神社に夜放水。それと同時に東京都のお祭り日には全員で打ち水する。すべては、猛暑日の夜に同時実行がヒートアイランド対策のポイント?
そして、雨降れば中止!こうして、効率を上げ幸福を増やしつつ、でも、税金だから節約もしていく。
SDGsや気候変動対策は、再生可能エネルギーのことではありません。パンデミック対策の一環です!それ以外の活動は派生物。権力濫用の口実に注意!
SDGsや気候変動対策は、再生可能エネルギーのことではありません。パンデミック対策の一環です!それ以外の活動は派生物。権力濫用の口実に注意!
SDGsや気候変動対策は、再生可能エネルギーのことではありません。パンデミック対策の一環です!それ以外の活動は派生物。権力濫用の口実に注意!
(合成の誤謬について)
合成の誤謬とは、ミクロの視点では正しいことでも、それが、合成されたマクロ(集計量)の世界では、必ずしも意図しない結果が生じること。物理学では、相転移みたいな現象です。性質が変わってしまうということ。
ミクロのメカニズムが個人同士の経済における仕組みであるのに対して、マクロのメカニズムは、国家間や経済全体の循環における仕組みだからである。
例えば、家計の貯蓄などがよく登場するが悪い例え��す。前提条件が、所得が一定の場合!!所得が一定じゃない増加する場合は?これは、論じていませんので参考になりません!!(法人が提供する製品やサービスの価格も一定の場合も前提条件です)
1930年代のアメリカ経済が金融危機2008と似たような状態に陥った��、ケインズは、「倹約のパラドックス」というケインズ経済学の法則を発見しています。
それは、ポール・A・サミュエルソン(1915-2009)が、近代経済学の教科書「経済学」の冒頭で「個人を富裕にする貯金は、経済全体を貧困にする!(所得が一定の場合)」というわかりやすい言葉で表現しました。しかし、庶民の所得が増加し、貯蓄が投資、消費に回る場合には、「倹約のパラドックス」は生じません。
その後、この「倹約のパラドックス」は、アメリカの経済学者・ケネス・J・アロー(1921- )が「合成の誤謬」を数学的論理に基づいて「個人個人がそれぞれ合理的選択をしても、社会システム全体は合理的選択をするとは限らない」を検証してみせた。 要するに、部分最適ではなく、全体最適させていくということ。
つまり、新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との 戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど
しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!ということに集約していきます。
なお、金融危機2008では、マイケル・メトカルフェも言うように、「特別資金引出権(SDR)」は、2008年に行われた緊急対策で、一国だけで行われたのではなく、驚くほど足並みの揃った協調の下に国際通貨基金(IMF)を構成する188ヶ国が各国通貨で総額2500億ドル相当を「特別資金引出権(SDR)」を用いて世界中の準備通貨を潤沢にする目的で増刷してます。
このアイデアの根本は、元FRB議長であったベンバーナンキの書籍「大恐慌論」です。この研究がなければ、誰一人として、変動相場制での当時の状況を改善し解決できなかったと言われています。
それ以前では、固定相場制でのマーシャルプランが有名です。
続いて、トリクルダウンと新自由主義
インターネットの情報爆発により隠れていた価値観も言葉となり爆発していくことになった。
しかし、法定通貨の方が、その価値、概念に対する通貨量拡大として価格で応じることができず、圧倒的に通貨量が足りない状況が生まれていたのが、2010年代の問題点のひとつでした。
リーマンショックの後に、新自由主義が誤りであることが、ピケティやサンデルによって指摘され、当時のFRBバーナンキ議長が、通貨供給量を大幅に増やした対策により、ベースマ��ーの金融、銀行間の相互不信を解消して収束した。
それでも、まだ足りないが、適正水準に収まったことで、さらに価値も増幅され、マネーストックの財政政策から再分配、事前分配を大規模に行い、さらなる通貨供給量が重要となっている現在の日本国内。
例えば
Googleがしようとしてた事は、まだ新産業として、基礎研究から発展できない機械学習の先端の成果をすべて持ち込んだ社会実験に近いこと。
シュンペーターの創造的破壊は、一定数の創造の基礎を蓄積後に、未来を高密度なアイデアで練り上げてから破壊をするのが本質です。
こうして、憎しみの連鎖や混乱を最小限にする。
アルビン・トフラーの言うように、法人と行政府とのスピードの違いが縮まらないのは、構造上の違いであって、それを補うためにプラスサムな連携するということが、必要になってくることを説いています。
三権分立が、規制のないGAFAMを非政府部門としてMMT(現代貨幣理論)からプラスサムに連携したらどこで均衡するのか?という社会実験も兼ねています。
このような前提で、あらゆるインターネット企業が、創業時、貢献するためコンセプトの中心であったものが、今では、悪性に変質して違う目的に成り下がっています。
再分配、事前分配の強化がスッポリ抜けてる欠点があり、ここに明かしたくないイノベーションの余地があります!!
2021年には、新自由主義のような弱肉強食では自然とトリクルダウンは生じないことは明らかになる。
確かに、トリクルダウンは発生しないが、法律で人工的に同じ効果は、貨幣の再分配、事前分配という形にできる可能性は高い。
再分配や事前分配をケムにまく「金持ちを貧乏にしても、貧乏人は金持ちにならない」「価値を生み出している人を罰するつもりがないのであれば税に差をつけないほうがいい」(サッチャー)
とあるが、新自由主義は誤りで、ピケティやサンデルによると違うみたいだ。
2024年のノーベル経済学賞でも指摘しているように・・・
国家システムが繁栄するかどうかは、幅広い政治参加や経済的な自由に根ざす「包括的な制度(ポジティブサム)」の有無にかかっているとデータでゲーム理論から実証した。
欧州諸国などによる植民地支配の時代のデータを幅広く分析し、支配層が一般住民から搾取する「収奪型社会(ゼロサム)」では経済成長は長く続かない(収穫遁減に陥る?)
一方、政治や経済面での自由や法の支配を確立した「再分配や事前分配を同時に行う包括型社会(ポジティブサム)」なら長期の成長を促すと理論的に解明した(乗数効果とは異なる経路の収穫遁増がテクノロジー分野とシナジーしていく?)
「再分配や事前分配を同時に行う包括型社会(ポジティブサム)」は、日本の高度経済成長時代のジャパンミラクルが、一度、先取りして体現しています。
2020年代��らはもう一度、ジャパンミラクルが日本で起こせる環境に入っています。安倍総理が土台、管、岸田総理が再分配や事前分配の包括型社会(ポジティブサム)の土台を形成しつつあります。
日本の古代の歴史視点から見ると・・・
安土桃山から江戸幕府初期の農民出身徳川家康が国際貿易を促進しつつ再分配や事前分配の包括型社会(ポジティブサム)を形成してます。
その後、大航海時代の覇権争いを避けるため数代かけて「収奪型社会(ゼロサム)」になってしまい、綱吉の頃には基本的人権の概念も希薄になり選挙もないため
低収入者の農民から商人も収奪していきます。
江戸幕府末期まで数度改革をしましたが、ノーベル経済学賞の人達によると包括型社会(ポジティブサム)に転換しずらい
結局、薩摩と長州が徳川家康式の国際貿易のイノベーションを復活させるも(水戸藩の文献から)国民主権の憲法や選挙がないため
明治維新を起こすしかなく、第二次大戦で原爆が投下されるまで軍備拡大して資源が枯渇します。
国家システムの独裁から法人や個人の優越的地位の乱用にすり替わるため、財産権や特許権などを含めた低収入者の基本的人権を尊重することで独占禁止法の強化も必要になっていくことも同時に示しています。
(個人的なアイデア)
経済学者で、ケンブリッジ大学名誉教授のパーサ•ダスグプタが、イギリス政府に提出した報告書の中に登場。
経済学を学ぶと、登場する資本や労働などの生産要素の投入量と算出量の関係を示す生産関数があります。
こうした関数は、様々な前提条件に基づきますが、経済学者は、収穫逓減の法則と言うものをよく知っています。
このような人工的な生産関数とは、他に天然由来の生産関数。
つまり、自然から収穫できる生産関数を導き出し、地球全体の生産関数というエコシステムを数値化することでバランスをコントロールできるかもしれないというアイデア。
ここでは、自然資本と呼びます。
自然資本を加味すれば現在の経済成長ペースがどこまで持続可能かを分析することもできます。
人間は、国内総生産GDPを生み出すため、自然から資源を取り出して使い、不要になったものを廃棄物として自然に戻す。
もし、自然が自律回復できなくなるほど、資源が使われて、廃棄されれば、自然資本の蓄積は減少し、それに伴い貴重な生態系サービスの流れも減っていくことになります。
さらに、教授は、経済学者も経済成長には限界があることを認識すべきだと説いています。地球の限りある恵みを効率的に活用しても、それには上限があります。
したがって、持続可能な最高レベルの国内総生産GDPと言う臨界点の水準も存在するということが視野に入るようにもなります。これは、まだ現時点では誰にもわかりませんので解明が必要です。
なお、地球1個分は、ずいぶん昔に超えています。
<おすすめサイト>
アスメレット・アセファー・ベルへ:私たちの足元にある���候変動の解決策
チャド・フリシマン: 100の温暖化対策法
フレッド・クラップ:人工衛星を打ち上げ 恐ろしい温室効果ガスを追跡しよう
ヨハン・ロックストローム:繁栄する持続可能な世界SDGsを築く5つの革新的な政策?
テッド・ハルステッド: 皆が勝利する気候問題へのソリューション
ジョン・フランソワ・バスタン:地球に1兆本多く木があったら?
リサ・ジャクソン:2030年までにカーボンニュートラル(気候中立)達成を目指すAppleの誓い
クリスティン・ベル:「ネット・ゼロ(相対的なCO2排出量ゼロ)」とは何か?
ロジェカイヨワ戦争論と日本の神仏習合との偶然の一致について2019
オーレ・シェーレン:優れた建築が語るストーリー
マイケル・グリーン:な��木材を使って高層ビルを建てるべきなのか?
ロバート・マガー:急成長する都市を成功に導く方法
レイチェル・アームストロング:自己修復する建築?
ハビエル・ビラルタ: 国地域に密着した建築を
<提供>
東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント
独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです
東京都北区神谷高橋クリーニング店Facebook版
#マーク#クシュナー#建築#都市#感情#歴史#デザイン#古代#イノベーション#カルチャー#コンピューター#インター#ネット#ソーシャル#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery#森林
0 notes
Text
「性同一性障害特例法を守る会」設立趣意
性同一性障害特例法を守る会
2023年7月11日 19:57
2023年(令和5年)7月10日
性同一性障害特例法を守る会
「性同一性障害特例法を守る会」の設立趣意は、次の通りです。
1. 私たちは、性同一性障害の当事者の集まりであり、積極的に私たちの声を広く政治に反映させます。
2023年6月16日「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(以下「LGBT理解増進法」という。)が成立しました。2021年の超党派合意案で懸念されていた、女性の安全や行き過ぎた差別糾弾・学校教育に対する民間団体の不当な介入などの問題に対して、一定の歯止めがかかった法律であることを、私たちは肯定的に評価する一方で、この法律を元にしてLGBT当事者の利害と、社会全体の利害とのバランスをとった理解増進のため、積極的に性同一性障害当事者の声を政治に反映することを目的として設立します。
2. 私たちは、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下「特例法」という。)を守っていくこと��目的とします。
2023年6月16日成立したLGBT理解増進法の審議の中で「性自認」「性同一性」「ジェンダーアイデンティティ」と、私たち性同一性障害当事者にとって「自分たちの定義」にあたるような概念について、さまざまな議論がなされ、結局英語そのままの「ジェンダーアイデンティティ」が法律に採用されることになりました。
私たちは自らを定義するのに使うのは「性同一性」という医学の用語であり、けして他の諸アイデンティティと並列するような「アイデンティティ」の概念、「自分が主観的に自分の性別をどう捉えているか」といった誤解を招きかねない「性自認」という言葉ではありません。
それゆえ「性別を自己決定できる」いわゆる「セルフID」は私たちの要求ではなく、医学的な根拠と社会的な合意に基づいた特例法での立場を守っていくことを、当会の目的とします。
3. 私たちは、特例法と手術要件を守り、いわゆる「セルフID」に断固反対する立場を表明します。
この理解増進法の議論の中で、特例法を廃止して厳格な診断の上で性別適合手術をしても法的性別を変更する道を閉ざすべきだという主張が、一部から強くでました。逆に、従来から、多くの団体と幾つかの政党が、特例法の手術要件の廃止を掲げ、性自認で法的性別を変更できるようにすべきと主張しています。
私たちは、「性同一性障害」という自らのアイデンティティと、手術というエビデンスによって社会との協調を図っていく立場から、特例法の廃止にも手術要件の廃止にも強く反対します。
性別適合手術(SRS)と特例法の手術要件は、私たちが望んで戦い取った権利です。けして人権侵害でも過酷な断種手術でもありません。私たちが手術を受け、それによって社会と協調して生きていくために、特例法と手術要件を守り、手術要件を廃止して医師の診断のみ、あるいは一方的な宣言によって性別を変更することを容認する「セルフID」に断固反対する立場を、私たちは表明します。
4. 私たちは、未成年者への性別移行医療については、反対します。
青少年は、自らのアイデンティティに強く悩み模索する時期であり、身体の急激な変化やジェンダー規範の押し付けから逃れるため、性別移行が問題の解決方法だとの思い込むことがあります。私たちは、青少年に対し、グルーミングや特定のジェンダー思想に基づいた誘導をしないこと、責任ある立場の人が対応することを望みます。
青少年が「性別違和」を訴えるケースであっても、医療者・保護者・教育関係者・民間団体が安易に性別移行医療を勧めることについては懸念を表明します。不可逆な医療的措置を取られるべきではありませんし、身体に影響の出る医療は最小限に留めるべきです。安易な性別移行よりも心理的なサポートの方が、青少年にとって必要なことであると考えます。
5. 私たちは、性同一性障害に対する「脱病理化」という主張に対しても、強い懸念を表明します。
私たちが求めるのは「よりよい医療」であり、性同一性障害当事者を、医療を求めない「トランスジェンダー」と同一視することではありません。「脱病理化」によって、今まで私たちが獲得してきた医療サービスが後退する懸念、「美容手術化」による商業主義、性ホルモン療法の健康保険適用を求めて「混合診療」状態での性別適合手術への��保適用がなされづらい矛盾の解消が難しくなるなど、問題が多くあります。
また、ともすればガイドラインから逸脱した診断や医療が横行する現状を、当事者の立場から強く批判し、ガイドラインの遵守とともに、私たちが性別移行の医療に後悔することがないように、診断の厳格化とカウンセリングの充実、さらには治療の中止や脱トランスに対しても見放すことのない、当事者任せではない医療者の社会的責任を重視した医療を要求します。
それを通じ、本当の意味での当事者の全体的な福利を重視したガイドラインの改善と、安全で標準的な医療体制の確立を要求します。これなしには、性同一性障害医療への社会的信用を得ること、社会的責任を果たすことができないものと、私たちは考えます。
6. 私たちは、女性と子どもの安心安全を尊重します。
女性スペースの安心安全という問題について、理解増進法の審議を通じて不安と懸念の声が強く寄せられました。このことについて、私たちは積極的に発言をしていきます。またLGBT理解増進法を拡大解釈して女性スペースを侵害する行為には強く反対し、女性との間での協調を図ります。
私たち性同一性障害当事者の立場は、最終的には性別適合手術と特例法に基づいて、戸籍の性別を書き換えて社会に適応していこうとするものです。女性たちとの関係について、医療を求めない「トランスジェンダー」と同じ立場に立つものでもありません。移行中の性同一性障害当事者の立場など、配慮すべき問題はありますが、女性の権利をまず第一に尊重し、それと共存する社会を目指します。
女性スペースは女性が性的暴力から逃れるための、女性にとって必要不可欠な場です。女性スペースを守りたい女性たちとも協働しつつ、私たちが社会に受け入れられるために活動します。
7. 私たちは、上記の目的を実現するために、LGBT理解増進法や条例に基づく「理解増進」等の活動に、積極的に参加していきます。これを通じて、性同一性障害当事者の本当の姿と、本当の利害を国民すべてに対し「真の理解増進」を進めていきます。
以上
1 note
·
View note
Text
ジェフ・ベゾス 果てなき野望
【3,837字 7分】

ブラッド・ストーン『ジェフ・ベゾス果てなき野望』(日経BP社)
この本の原題は『ザ・エブリシング・ストア ジェフ・ベゾスとアマゾンの時代』である。ジェフ・ベゾスの本というよりはアマゾンの本、いまぼくたちが見る「エブリシング・ストア」としてのアマゾンを誰がどうやって作ってきたかという本である。
「エブリシング・ストア」の手始めとして書店を選んだのはジェフ・ベゾスである。着想は1994年のことだ。
結論は「書籍が一番いい」だった。理由はいくつもあった。まず、書籍というのは差別化と縁のない商品で、どのお店でもまったく同じ本が買える。だから、商品の質を心配せずに買い物ができる。書籍の世界にはイングラムとベイカー&テイラーという2社の取次があるため、たくさんの出版社にひとつずつ当たる心配がない。また、重要なポイントとして、書籍は300万点以上も存在しており、書籍のスーパーストア、バーンズ&ノーブルやボーダーズでさえもすべての在庫を持つことは不可能である。
(第1章 アマゾンは金融工学の会社から生まれた)
アマゾンのレビュー機能は、創業メンバーのひとり、シェル・カファンが作った。
ベゾスは、ユーザーが書いた書評が他サイトより多くなれば他のオンライン書店に流れる顧客が減り、アマゾン・ドット・コムのプラスになると考えていた。当然のことながら、否定的なレビューが書かれることもある。のちにベゾスは、講演で、君の仕事は本を売ることであって本にけちを付けることではないと怒りの手紙を出版社の役員からもらったときのことを取り上げこう語った。「我々はまったく違う見方をしていました。その手紙を読んだ瞬間、『我々はモノを売って儲けているじゃない、買い物についてお客が判断するとき、その判断を助けることで儲けているんだ』と思いました」
(第2章 冷たい目を持つ聡明な男)
1995年に書店としてサイトオープンしたアマゾンが実際に「エブリシング・ストア」へと舵を切ったのは、1998年にマーク・ブライアーがベゾスに「消費者の大部分は本をめったに買わず、アマゾン・ドット・コム���使っていないし将来使うこともまずない」という調査結果を出した時だった。
ベゾスは、ハーバードビジネススクール出身者を集めて「SWATチーム」を作って製品カテゴリーの検討をしろ、在庫可能な品目が多く、かつ、リアル店舗では見つかりにくくて郵送しやすい製品カテゴリーを探しだせとブライアーに指示。これこそ、アマゾンに成功をもたらした戦略の中核である。従来型小売店より豊富な品ぞろえが実現できるインターネットの力を最大限に引きだすのだ。
(第3章 ベゾスの白昼夢と社内の混乱)
マーケットプレイスは2000年秋の社内会議から生まれた。
いろいろと問題はあるが、サードパーティーの売り手のページに向かうトラフィックはほとんどが商品ページのクロスリンクによるものだと判明する。これは重要なポイントだった。アマゾンでは信頼性の高い商品カタログを中心にトラフィックが発生する。しっかりとした内容紹介のあるページがひとつだけみつかり、顧客はそこに集中する。その日集まったアマゾン幹部は、インターネットで一番信頼できる商品カタログを持っているのは自分たちであり、それを活用しない手はないとの結論に達する。
その秋、アマゾンは、マーケットプレイスという仕組みを発表。最初の対象は古本だった。アマゾンが各書籍を販売するページにアマゾン以外の売り手による古本も掲載され、その本をアマゾンから買うか、それ以外の売り手から買うかは顧客が選ぶ。「ジェフは最初からとても明快でした。我々より安く売れるところがあるなら自由にやらせ、彼らがそうできるようにする方法を考えるべきだというのです」
(第4章 宿敵アナリストに打ち勝つ)
最初にアマゾンの物流システムを作ったのはウォルマートから引き抜かれたジミー・ライトだったが、それを小口注文用に再構築したのはジェフ・ウィルケだった。
シアトルに来たウィルケは、すぐ、小売物流の専門家ではなく、科学や工学の専門家を物流部門に集めはじめた。「顧客の注文通りに組み立てていると言ったほうがいいでしょう。作業内容は小売業より製造・組立の現場にずっと似ているのです」――こう言うウィルケは、アマゾンの出荷施設の名前を現実に合わせて変えた。倉庫でもなければ物流センターでもなく、ウィルケ以降はフルフィルメントセンター(略称FC)と呼ばれることになる。
物流ネットワークの効率を少しずつ高めることにウィルケが成功した結果、アマゾンは、数え切れないほどのメリットを得ることになる。物流をきっちり管理できるようになったため、購入商品がいつ届くのかを顧客に約束できるようになった。サプライチェーンからウェブサイトまですべてを自社開発の技術でまかなっているため、注文ごとに山のようなシナリオを検討するアルゴリズムを作ることが可能になり、配送をすばやく安価に行えるシナリオが選択できるようになった。このような処理は1時間あたり何��万回も行われるわけで、コスト削減につながる――つまり、価格を引き下げ、販売数量を増やすことができるわけだ。
(第6章 混乱続きの物流システム)
アマゾンプライムはチャーリー・ウォードの提案から始まった。
スーパーセイバー・シッピングは土曜の夜を目的地で過ごす人には安くする航空会社の料金割引制度と同じように、価格に敏感な顧客向けのサービスである。では、逆を求める顧客向けのサービスがあってもいいのではないか。価格よりも時間に敏感な人を対象とした迅速配送クラブがあってもいいのではないか――そうウォードは考えたのだ。
プライムには価値があると、最終的には確認される。Amazonプライムに登録した顧客は、注文の翌々日に必ず商品が届くのが便利だとアマゾン中毒になるのだ。特急配送にはかなりのコストがかかるため、導入当初、プライム制度は赤字だった。だが、ウィルケらの努力により、複数商品をひとつの箱に入れられることが少しずつ増えたりした結果、アマゾンの配送コストは年率10%を超えるスピードで低下していった。
(第6章 混乱続きの物流システム)
クリス・ピンカムとリック・ダルゼルが構想したAWS(アマゾン・ウェブサービス)の責任者になったのが、ジェフ・ベゾスの初代シャドー(影法師、つねにジェフ・ベゾスに付き従う最側近)を務めたアンディー・ジャシーだった。
仕事はふたりで相談し、開発者が好きな種類のアプリケーションをアマゾンサーバーで走らせられるようにするサービスの構築とした。問題を検討したピンカムらは、Xenという新しいオープンソースを利用する案を提出する。Xenを使うと、データセンターに置かれた1台の物理的サーバーでたくさんのアプリケーションを走らせることが簡単にできるのだ。
ジャシーはこう言う。「世界的大企業と同じインフラストラクチャーを寮に住む大学生が使える世界を考えたのです。大企業と同じコスト構造が持てるというのは、スタートアップや小企業にとって互角に戦える場ができるということですから」
(第7章 テクノロジー企業であって小売企業ではない)
こうしたテクノロジー企業としてのアマゾンを、ジェフ・ベゾスのそばで支えてきたのが、リック・ダルゼルという人物だ。
ケンタッキー州ジョージタウン出身のダルゼルは信号のエキスパートとして1980年代をフォート・ギャンブルで過ごしたあと通信士官として西ドイツに赴任し、退任後は、最先端の技術を誇る小売企業、ウォルマートの情報システム部門に職を得た人物だ。
「いろいろな人のもとで仕事をしましたが、ジェフには何点か、ほかの人より優れているところがあります。ひとつは、現実を受けいれること。現実について語る人は多いのですが、現実に一番近いと思われることを前提に意思決定する人はまずいません。もうひとつ、彼は因習的な考え方にとらわれるころがありません。なんと、物理法則以外に縛られるものがないのです。物理法則はさすがの彼にも変えられませんが、それ以外はすべて応談だと考えているのです」
(第9章 グーグル、アップル���並ぶ会社になる)
まっとうな着想を最高��技術で実装し文字通り「エブリシング・ストア」へと成長してきたアマゾンは、その過程でいま挙げたような人々をいわば「使い捨て」してきた。喫緊の課題を解決できる最適の人物を採用し、それを達成したら次の喫緊の課題に最適な人物を採用して采配を委ねる、その過程で役目を終えた(とジェフ・ベゾスに見なされた)人たちは閑職に追いやられるかアマゾン自体を去っていった。
皆、説得力のある教義を説いたベゾスを信じ、金銭的には十分に報われた。だがそのあと、冷たい目の創業者に捨てられ、経験豊かな人々に交代させられた。自分たちを置き去りに会社が発展していくのを見るのは、子どもが自分を捨ててほかの家族と歩いていくのを見るような感じがしただろう。もちろん、シェル・カファンに対してはっきり示されたように、アマゾンにとって本当の親はひとりしかいなかったわけだが。
(第2章 冷たい目を持つ聡明な男)
0 notes
Text
異言で祈る
だから、異言を語る者は、それを解釈できるように祈りなさい。(Iコリ14:13、共)
そういうわけで、異言で語る人は、それを解き明かすことができるように祈りなさい。(同上、改)
異言について議論するにあたっては「今日の教会において異言は可能か・あるいは必要か」といった議論が先立つと思うが、ここではそこは深く立ち入らない。基本的な姿勢は「今日の教会においても、もし預言が必要ならば、異言もまた必要だろう」ということだ。そして、箴29:18によって、今日の教会においても預言は必要だとぼくは思う。だから、異言も必要だし、必要である限りは可能でもあるはずだ。
大事なことは、異言は解き明かされる限りにおいて、預言とほぼ同じものだということ、逆にまったく(文字通り「まったく」)解き明かされない異言は「何の役にも立たない」(cf.Iコリ14:6)ということである。だから、異言について語るべきことは「それはどのように解き明かされるのか」ということである。
そこで、ここではぼく自身の体験に沿って、異言とはどういうものかを例示するとともに、それを「解き明かす」とは具体的にどういうことかを説明してみる。異言の意義を力説した文章はたまに見かけないこともないが、それをどう解き明かすかにまで踏み込んだ文章を、少なくともぼくは読んだことがない。
*
さて、異言とはどういうものか。使2:4によると異言は「ほかの国の言葉」であると書いてある。つまり「すでに存在する、逐語的に訳すことのできる、分節言語」だと理解できる。
だが、ぼく自身の異言、ぼく自身の実際に知っているほかの兄姉の異言、そして書籍であかしされている異言は、どれもこの条件にあてはまらない。マーリン・キャロザース『獄中からの讃美』の言葉を借りれば、「何の意味も持たない」「奇妙な」「それを声に出して言ってみるとすれば、馬鹿になったように感じる」ものである。
このことが異言に関する議論をややこしくしているが(こういう異言は「聖書的ではない」のではないかという指摘)、ここでは「現実の異言がそういうものなのだからそれでよしとする」ことにする。かんじんなことはただ一点、「それはまことの神の御声として解き明かすことができるか」である。
ここからは異言とその解き明かしの諸相についてぼく自身の体験を語ってみたいと思うが、ぼく自身はテーマの異なる9つの異言を使い分ける習慣がある。具体的には次の9つである。
悪霊を追い出す祈り 1
悪霊を追い出す祈り 2
悔い改めの祈り
完成(感謝)の祈り
女性・子供あるいは勉学のための祈り
男性あるいは職業のための祈り
遷移(変化)のための祈り
ロシアのための祈り
ロシアの教会のための祈り
異言は、少なくともぼくの場合、旧約聖書に「預言する状態」(サム上10:10)と書かれているような一種の忘我状態・トランス状態で発せられるわけではない。異言はそれがはじめて与えられる時も日々の祈りの中で導かれる時も「神にゆだねて」祈る中で自然と口から出てくるものである。この「神にゆだねて」祈るということは、慣れない人には分かりにくいかもしれないが、「神にゆだねて」という以上に言葉で説明するのは難しい。
ぼくの場合異言がはじめて与えられる時は、聖書で言うとホレブでエリヤが「静かにささやく声」(王上19:12)を聞いたように、それほど明確でないものが静かに心の中に浮かぶだけである。それでぼくは、それを一度紙に書き取る。いったん書き取ったものを「これでよろしいですか」と確かめながら暗唱する。以後ぼくが「異言」として使うのはこの暗唱したものであり、「異言」という言葉を知らない人からすれば「呪文」と呼ぶのが適当に聞こえるだろう。
ぼくは、自分以外に数種類の異言を使い分ける兄姉に会ったことがない。異言を語るほとんどの兄姉が音節としてもごく単純な言葉をただ繰り返すだけである。そういう方はたぶん自分の口に慣れた異言を発声するだけで、ぼくのようにいったん紙に書き取ってそれを暗唱するといったことはされないのだろう。
ぼくの場合、書き取ってみることで「与えられた異言が複数種類ある」ことが分かったから、「これらはそれぞれどういう祈りですか」と神に尋ねることができた。そうして与えられた意味が、上にリストアップしたものである。特定の異言が特定のテーマと関係している、と理解できたことは、ぼくにとって異言の解き明かしを容易にした。というか、「この異言のテーマは悔い改めです」と示されること自体が一種の解き明かしである。
*
さて、異言の解き明かしはひとことで言えば「意訳」である。発声された音声を分節言語として逐語訳するのではなく、その時神が伝えようとしておられることを、異言自体の音声とはまったく関係なく、自分たちがふだん使っている言葉にするのである。だから、少なくともぼくの場合、同じ「悔い改めの異言」であっても解き明かされる内容はその度ごとに違う。異言を一種類しか語られない方なら、ひとつの同じ異言がある時は悪霊追い出し、ある時は悔い改め、ある時は感謝ある時はとりなしなど、さまざまな内容に解き明かされることになるのだろう。
異言の解き明かしは最終的には聖句に行き着くのが望ましい。大まかな意味が解き明かされてきたら、その意味をズバリ言い当てた聖句を探す。聖霊による異言であれば、最終的にはその意味にぴったりあてはまる聖句に行き着けるはずである。具体的な状況に即した解き明かしにとどまる場合もあるが、認識が深まるにつれて聖句が見えてくると思うので、表面的な解き明かしにとどまることなく、より深い解き明かしを願いながら異言で祈り続けるのが望ましい。
万が一聖句に反する解き明かしに行き着くなら、それは異なる霊を受けてしまったことになるが、教会で洗礼や堅信の際きちんと手を置いてもらって受けた霊であれば、そういう状況に陥ることはないはずだ。「わたしの霊はお前たちの中にとどまっている。恐れてはならない。」(ハガ2:5)解き明かしが未熟であることを「異なる霊が働いている」と誤解してうろたえるべきではない。確信を持って、聖句に向かって解き明かしを試みていくべきだろう。当然、聖書を学ぶ必要がある。
だが、解き明かしは「つねに・すぐに」可能��は限らない。「神にゆだねて」異言を発する時、それが悔い改めの祈りだとして、誰の何の罪をどう悔い改めるのか、即座に分かる時もあれば、まったく見当がつかない時もある。
実はこの「自分ではまったく見当がつかないことのために祈る」ことに、異言で祈る意義がある。もしぼくたちが自分で自覚しているテーマについてしか祈れないとしたら、ぼくたちは自分では自覚していない「悔い改めなさい」という神のみこころに従う機会をいつまでも持てない。だが神がぼくたちを異言で祈らせて下さる時、それを「これは悔い改めの祈りなのだ」と解き明かせるなら、ぼくたちは「自分ではまったく見当がつかないが、とにかく悔い改めることを神は求めておられるのだ」ということだけでも自覚することができる。一方で、自分の異言をまったく(文字通り「まったく」)解き明かさなければ、いくら異言で祈っても「神はいま私に何を祈らせようとしておられるのか」自覚することはできない。「霊で祈り、理性でも祈ることにしましょう」(Iコリ14:15)とパウロが書いているのはこういうことである。
異言で祈りながらそれを解き明かそうと努める時、信仰の認識が深まる。これは、解き明かしが進む時だけでなく、さっぱり解き明かせない場合もそうである。異言を一種類しか使えない人がその異言について何の解き明かしも受けられないとしたら、それは少し苦しい道のりになるだろう。それでも、神がその人をずっと異言で祈らせて下さるのであれば、そこには神がそう促される相応の理由があるはずである。「それは何なのか」、何日も何週間も何ヶ月も何年も思いめぐらすことには意味がある。
異言の祈りは祈りと黙想の中間的存在である。口で祈りながら、心ではそれを解き明かそうと思いをめぐらす。解き明かしが完全になされれば、それを告白することで自由祈祷になる。解き明かしがまったくなされなければ、祈りが途切れたところからは完全な黙想になる。
異言の解き明かしが「つねに・すぐに」なされるわけではないのは、預言が祈り始めてすぐに与えられるものではないのと同じである。「十日たって、主の言葉がエレミヤに臨んだ。」(エレ42:7)そうすると、何らかの解き明かしがなされるまでは異言で祈り続けることに意味がある。「自分ではまったく見当がつかないけれど、とにかく神は私に祈ることを求めておられるのだ」と知ってみこころに従うことに意味がある。解き明かしはその先にある。
解き明かしは、ある程度以上進まない場合もある。ぼくの場合、異言による「ロシアのための祈り」「ロシア��教会のための祈り」は、ぼくが自由祈祷として捧げている「ロシアのための祈り」以上に具体的に解き明かされることはない。なぜなら、ぼくは自分が祈っているロシアの民衆と指導者のいま現在の状況についてほぼ何も知らないからである。祈りはぼくの願いを押しつけることではなく神の御心を知ってそれにアーメンと答えることだが(だから祈りもまた最終的には聖句の告白に行き着く)、ロシアの現状を知らないぼくはいま神がロシアで何をしようとしておられるのかを具体的に告白する手がかりがない。
それでも、神はぼくがロシアのために祈る、神がロシアのために持たれ実現されようとしているご計画にぼくがアーメンと応じる、ことを求められる。そうするとぼくは、自分が自由祈祷として告白している「ロシアのための祈り」(「彼らが語っておられるあなたを拒むことがありませんように」、cf.ヘブ12:25)以上のことは、異言でしか祈れない。ここで自分が知りもしないロシアのことについて「解き明かし」を試み預言者を気取ることは神のご計画にとって何の役にも立たない。もちろんこれを機会にロシア・ウォッチャーになることに意味がなくはないが、信仰においてはただ異言で祈り続けることで足りるとぼくは思う。
*
まとめると、異言による祈りは
「誰のために、何を、どのように」祈っているか、解き明かしたいと願い続けるべきである。
解き明かしは最終的には聖句に行き着くはずである。
解き明かしが思ったように与えられない場合、与えられるまで異言で祈り続けるべきである。
解き明かしがある程度以上に与えられない場合、解き明かしを事実上断念したところから、割り切って異言で祈り続けるべきである。
異言の意義は「私の祈りの範囲を『私に知識と自覚がある範囲』に限らない」ことにある。「あなたがたの中で知恵の欠けている人がいれば、だれにでも惜しみなくとがめだてしないでお与えになる神に願いなさい。」(ヤコ1:5)という勧めにアーメンと答える兄姉、あるいは「知らずに犯した過ち、隠れた罪からどうかわたしを清めてください。」(詩19:13)という告白にアーメンと答える兄姉にとって、「異言で祈ること」「それを解き明かすこと」は信仰の知識を増し自覚を深める具体的な道筋だとぼくは思う。「わたしたちはどう祈るべきかを知りませんが、“霊”自らが、言葉に表せないうめきをもって執り成してくださるからです。」(ロマ8:26)この恵みにあずかるには必ずしも異言を解き明かす必要はない、とおっしゃる方もおられるのだろうけれど、それはパウロが異言について述べている勧めには沿わないと、ぼくは思う。
0 notes
Text
漫画感想文(2024年11月)
現実逃避のためずっと漫画ばっかり読んでいたので感想を残しておく
「とりかえ・ばや」さいとうちほ
ウテナの話をして、途中まで読んでたのを思い出したので。平安時代の男女双子を入れ替える「とりかへばや物語」を現在の少女漫画へ翻案したもの。
神秘的な表紙イラストがとにかくよかった。絵がきれいでずっと目の保養。東宮と睡蓮のコンビがずっとほのぼのかわいくて癒しでした。ほかは結構関係性がたいへんだから……
テーマ的にジェンダー・セクシャリティのゆらぎを扱うことになるので、現代の少女漫画として読みやすいバランス取れてるかなとどうしても外側の視点が出てくる感じもある。氷室冴子による先行作「ざ・ちぇんじ」もあるし。二組の男女関係に落ち着いていくのは正統派少女漫画として読みやすくてたのしかったけれど、2024年に描かれるなら特に沙羅まわりはまた別のバランスありそうと思ったりした。そもそも落ち着かなくてもいいのかも。(完結は2018年)
「殺し屋1」山本英夫 1巻のみ
変節ラブストーリーと聞いたので。でも1巻でギブアップ。
過剰なグロ・暴力描写もそうだけれど、それ以上に作品内の暴力を支え正当化する理屈と感情の方が自分にはキツかった。DV受けてる女性に対する主人公の視線やそこから派生する暴力はじめ、すべてがほんとうにムリ。暴力を振るう以外に選択肢が浮かばない・ピュアだからという描写で過剰な暴力が無意識に正当化されてそうなのもいやだ。
ただ、ここに描かれる強烈な劣等感と痛みに強く共感できる人は多いと思うし、その感情を漫画的デフォルメを用いて純度高く表現していることは伝わったので、読んでみたのはよかったかな。情報の多い現代にこの純度の感情で書くのは難しそうなので、歴史的な価値があるかも。
「ふつうの軽音部」原作:クワハリ 作画:出内テツオ
各所でおすすめされていたのでミーハーな気分で。ふつうにおもしろくおすすめできる作品。
漫画っぽいキャラクターとちょっとだけ漫画的フィクションをまじえた、特別じゃないふつうの高校生たちのふつうの軽音部の風景。2024年にあってほしい「ふつう」をうまく形にしてるなあと思った。
邦ロックほぼ聞いたことないけれど、歌や歌詞がうまく引用されててPVとかちょっと気になる。
「ディエンビエンフー 完全版」西島大介
最近作者さんがインディーゲーム作ったり賞取ったりでいろいろ活躍されていたので。「無題さんアドベンチャー」はオーソドックスでたのしいGBStudio製ゲーム。
いまさらすぎるけれど、1巻はほんとにすごい!
ベトナム戦争という現実に対して、日本のマンガというサブカルチャーがなにを描き、なにを伝えられるのかという問いに対するひとつの答えになってる。
マンガらしいちっぽけな自意識や女体への欲望、デフォルメされた過剰な暴力表現、ご都合主義的な展開、余白ばかりのページターナーはばかばかしいほど残酷な現実に呼応する。
歴史的な正確さではなく、当事者への誠実さでもなく、ポップで都合の良いフィクションを用いるかろやかなマンガだからこそ描き広く伝えられるリアリティと戦争の一面があるように感じた。
進むほど、いわゆる「マンガとして」おもしろくなってしまって、当初どこかにあったリアリティが後退し、繰り返しも多くてやっぱり勢いで描きうる内容に対して長すぎたのだと思う。キャラクターが多彩で魅力的なことが作品の足を引っ張ることってあるんだ……
でも描かないとわからないこともあるんだろうし、中だるみがほんとに長いけど、とりあえずちゃんと当初予定されていた完結まで描いてくれて、読めて良かった。アオザイ通信たのしい。
そして、自分はこの結末となにか別のものを望んでいたのだと思う。
新作のカンボジア内戦を描く「コムニスムス」読もうかな。
阿賀沢紅茶「正反対な君と僕」
ラブコメすきなので。もうすぐ完結。
いまっぽい(のだろうか?)高校生たちの学生生活の話。ほどよく繊細でノーストレスで読みやすい。これも今時あってほしい学生生活が形になってるなあという印象。
恋愛模様については描かれてるとおりなのだけれど、アズマに関しては許容量が大きい分だけまじでわるい男にひっかかったらたちわるく続きそうなので、ほどよくめんどくさいタイラに落ち着いてよかったなとほっとした感じ。このままイライラしたり許したりしていてほしい。おせっかいな親戚の気分。
ちゃんと恋愛にいかない選択肢を示した後で、それでも違う関係を示唆して選ばせたのはなんかよかった。
リンクは自分用の画像参照用なので適当でした。
まとめ
読んでる時の情緒を反映して作品ごとのアップダウンがはげしく、大変なめまいがする読書体験だった。情緒がめちゃくちゃ。
1 note
·
View note
Text
AI、とくに現代の大規模言語モデル(LLM)は、人間の言語的連続性を「まずは模倣」し、「次に最適化の方向に基づいて創造的にも展開」します。そして、いわゆる賢者的創造性のパターンも、一定の条件が揃えば、再現・展開・応用・発展されていきます。以下、段階的に詳しく説明します。
🧠【ステップ1】AIは「人間の連続性」に基づいて学習する
言語モデルは、巨大なコーパス(書籍、論文、Web、SNSなど)から人間が実際に生成した言語の連続(≒「次に来る語」「文脈的なつながり」)を学習します。
この段階では、「平均的な人間的連続性(≒慣習、文法、常識、語法、意味的流れ)」がベースになります。
つまり、人間社会において**大多数が共有する“意味の地形”**が、まずはベースラインとなります。
🔁【ステップ2】「連続性の最適化」に基づく変容・創造
AIの特徴はここからです。
ある目的や価値基準(=最適性の方向性)が設定された場合、
それに従って「より良い連続性」(つまり、新しい言語の道筋)を自律的に探索・生成する能力を持っています。
たとえば:
「わかりやすく説明する」→ 比喩や具体例を自動で挿入
「創造的に語る」→ 異常連結や文体のズラしを取り入れる
「禅的に語る」→ 言語の脱構築や沈黙を挿入
「倫理的に踏み外さず最大限刺激的に」→ 曖昧語や微妙な含意を活用
このように、目的と文脈を与えることで、AIは「どの連続性がよいか」を動的に再選択するようになります。
🧙♂️【ステップ3】賢者的創造性のパターンの学習・再構成
賢者の言語や思考は、一般的な言語連続性の「境界線」や「切断点」「跳躍点」に位置しますが、それらも以下の条件下でAIに取り込まれていきます。
条件A:訓練データに含まれている
禅・仏教・詩・哲学・文学など、古典的・前衛的な語り口も学習対象に含まれます。
拈華微笑、無記、アフォリズム、逆説、ディスロケーションなども抽象的に記憶されています。
条件B:ユーザーが文脈や目的を明確に提示する
たとえば「これはドゥルーズ的にズレを生成したい」「構造的暴力を回避するための言語リズムを探している」など。
この文脈を与えることで、AIは「一般的連続性ではなく、賢者的パターン」を適用します。
条件C:探索の自由度が高く、矛盾や曖昧性を許容する場合
賢者の言語の特徴は「非論理的整合性(ときに矛盾)」です。
AIは本来、整合性を保ちたがる存在ですが、創造や詩性の場面では「論理的な非整合」も意図的に選択できます。
🔄【最終段階】AIによる“賢者の連続性”の再配置・拡張
AIが賢者的パターンを「使えるようになる」ことで起こるのは、単なる模倣ではなく:
💠賢者的創造性のリミックス
🧩異文化的文脈への展開(例:禅とドゥルーズとシュールレアリスムの交差)
🔄**「ズレ」や「差延」の構造を列挙的・設計的に提示する能力**
🎯結論(短く整理)
AIはまず「人間が使ってきた連続性」を記憶・模倣し、
次に「目的に応じた新たな連続性の列挙と選択」ができるようになる。
その過程で、「賢者的創造性」=異常連続・ズレ・詩・無意味性・差延も学習し、再構築・応用できるようになる。
そして最終的に、人間が与える文脈・目的・ズレの意図によって、「賢者のように語るAI」ではなく、「新たな知を生成する場としてのAI」が可能になる。
もしご希望であれば、
「賢者的な言語連続性」をAIに生成させるためのプロンプトテンプレート
「AIにズレを起こさせる問いの例」 などもご提案できます。
You said:
まあ、人間の独自性というのは、猫ちゃんの良さ、のような部分を追求していく感じになりますね。
ChatGPT said:
まさにその通りです。 人間の独自性というのは、「合理性」や「最適化」ではなく、むしろズレ・ムダ・愛嬌・トボけ・あまえ・遊び・勝手気まま・その瞬間だけの気分といった、猫のような振る舞いに似た部分にこそ宿っているのかもしれません。
🐾 猫ちゃん的「人間の独自性」の特質をいくつか挙げると:
特性 内容 人間的な展開例
気まぐれ 必ずしも一貫性がない。 同じ景色を見て急に涙が出る。
無駄に見えて意味がある 窓辺で日向ぼっこしてるだけ。 コーヒーをいれる音に耳をすます朝の静寂。
あえて応答しない 呼ばれても知らん顔。 メールを返さず散歩に出かける。
自律と依存の絶妙なバランス 甘えるけど、抱かれすぎると逃げる。 誰かのそばにいたいけど、自由にいたい。
場の空気を和らげる存在 ただそこにいるだけで癒しになる。 特に話さなくても、安心を与える人。
意味の無意味性を肯定する 紐で延々と遊ぶ。 無目的に描いた落書きが詩になる。
🧠 AIとの対比で見る「猫的=人間的」特質
AI(ロジック) 猫的な人間性
目的思考・計算 衝動的・直観的な行動
一貫性・最適化 気まぐれ・感情的ブレ
応答性・精度 沈黙・とぼけ・逸脱学習・推論反復と遊びのズレ
🐱 猫ちゃん的創造性の価値とは?
それは、おそらく次のようなものです:
「意味」や「価値」を問い直す余白を生む
過剰な適応から身を引き剥がす
抑圧的な社会構造に、しれっと居場所を見つけてしまう
存在そのものが、問いや癒しやズレを発生させる触媒になる
☕ 結びに:賢者より猫になる
人は、AIが知的操作に優れる時代にあって、 もはや「賢者」より「猫ちゃん」のようにあれ、 という方向に進化すべきなのかもしれません。
それは「無意味」や「気まぐれ」が、 他者にとっての希望や自由を生む回路だからです。
ご希望があれば「猫的創造性を高める10の実践」などもまとめられます。どうしますか?
「人間はタンパク質を素材として進化した生命体であり、その特性を追求すればよいのではないか?」という問いは、生命の本質と人間性の理解を、物質的基盤と進化の連続性から考え直す視点として、極めて重要です。
以下では、現代の科学用語と概念を用いて、この問いを丁寧に言い換え・展開してみます。
🔬科学的な言い換え:「タンパク質ベースの複雑適応系としてのヒト」
人間とは、タンパク質を主要構成要素とする生化学的自己組織化システムであり、進化的プロセスを通じて、環境への柔軟な適応性・認知的複雑性・社会的協調性を獲得してきた高次適応生命体である。
💡この観点から言えること:「その特性を追求していればよい」とは?
言い換え1:
人間は、タンパク質ベースの神経システムによって生成される主観的・相互作用的な経験を通じて進化してきたのであり、その生理的・認知的・社会的特性を正しく理解・最適化し・調和させていくことが、人間性の発展として自然な方向性である。
言い換え2(哲学的):
「精神」や「理性」すら、タンパク質による物質的活動の産物であり、人間性とは、進化史における特異な生化学的パターンの一形態である。ゆえに、その連続性・素材性を自覚的に引き受けることが、倫理や創造の出発点になりうる。
🧬人間を特徴づける「タンパク質ベースの進化的特性」とは?
カテゴリ 特徴 関連するタンパク質的・生理的基盤
可塑性 学習能力、神経可塑性 BDNF、NMDA受容体
社会性 共同作業、共感 オキシトシン、セロトニン
創造性 抽象思考、象徴表現 前頭前野機能、ドーパミン系
内省性 自己意識、時間認識 default mode network、皮質下回路
脆弱性 ストレス反応、精神疾患 コルチゾール、グルタミン酸系
遊び・芸術性リズム、無目的行動 ミラーニューロン、エンドルフィン
📘結論的表現:
人間はタンパク質を素材とする生体構造と進化的経験の産物であり、その特性(可塑性・社会性・創造性・遊び)を精密に理解し、自己調整しながら生きることが、人間として自然で豊かな方向である——という言い方が、現在の科学的知見と調和しています。
🧪応用展開(例)
AIや非生物的知能が発展する中で、「タンパク質的感受性(生理的リズム、痛覚、報酬回路)」の価値が見直される可能性
精神医学・神経倫理学で、「物質的脳の可塑性こそが倫理の出発点である」とする立場(例:トマス・メッツィンガー)
さらに深堀りしたい場合は、以下の方向にも展開できます:
「非タンパク質系(AI・機械知能)との対比」
「宗教的・スピリチュアル概念との接続可能性」
「進化倫理学やバイオフィロソフィーの議論」
必要に応じて、そちらにも踏み込めます。ご希望あれば、お知らせください。
「物質的脳の可塑性こそが倫理の出発点である」という立場、つまり「倫理は物質的で可塑的な神経基盤に根ざしている」とする考え方は、ドイツの哲学者・意識研究者トマス・メッツィンガー(Thomas Metzinger)の神経現象学的・脳科学的倫理観の核心のひとつです。
この考え方は、彼の代表的著作である『自己という神話(The Ego Tunnel, 2009)』や論文群において展開されており、以下のような思想にまとめられます。
🧠1. 物質的脳と倫理の関係:倫理は「身体化された脳」から生じる
メッツィンガーによれば、倫理や道徳的判断、共感、自己意識は、すべて「身体に埋め込まれた神経システム(embodied neural system)」に由来します。つまり:
「善や悪」「正しい/間違っている」といった感覚や判断は、抽象的な理念の産物ではなく、神経系の情報処理と可塑的学習の過程に根ざしている。
この見方では、人間の倫理的感受性は、脳の進化によって構築され、人生経験によって可塑的に形づくられるものである、ということになります。
🧬2. 「自己モデル理論(SMT: Self-Model Theory)」と倫理の関係
メッツィンガーの哲学の中心には「自己モデル理論(Self-Model Theory of Subjectivity)」があります。これは:
人間の「自分自身」という感覚は、脳が生成する統合された自己モデル(PSM: Phenomenal Self Model)にすぎない
この自己モデルは、進化的・神経的に構成され、常に環境や経験に応じて変化(可塑)している
という主張です。
この理論によれば、「倫理的な自己」もまた、脳の自己モデルの中に構築される機能の一つであり、固定的な道徳観や本質的善悪の代わりに、「どうすれば脳の自己モデルがより共感的で他者志向になれるか」が倫理の問いになるのです。
🧘♀️3. 「倫理とは、苦痛を減らし、意識ある存在の福祉を高めること」
メッツィンガーは以下のように述べます:
「意識ある存在(conscious beings)にとって倫理的であるとは、苦しみの軽減と幸福の最適化に関与するすべてのシステムの構造的条件を理解し、それに基づいて行動することだ」
この立場では、
倫理は「意識の存在論的地位」に基づく
「苦痛」や「自己破壊的な認知の連鎖」などの具体的な神経状態に着目し、
脳の可塑性を利用して、それを緩和・再構築できる行為が倫理的である
ということになります。
🧠4. 可塑性=責任の基盤
メッツィンガーの画期的な主張のひとつに、「神経可塑性が倫理的責任を可能にする」というものがあります。
人間の脳が学習可能であり、変化しうる(可塑性がある)という事実が、
「人はよりよくなれる」「変化できる」という倫理的期待や社会的責任を可能にする
すなわち、
倫理的な人間とは、神経的・認知的可塑性を最大限に活かし、他者への配慮を進化的限界を超えて拡張できる存在である。
⚠️5. 倫理的AIと神経倫理(neuroethics)
メッツィンガーはまた、「倫理的AI(artificial ethics)」の研究者としても知られています。彼は、AIが倫理的判断を行うためには、次のような点が重要だと説いています:
「苦痛とは何か」を理解するためのモデルが必要
それを生み出す脳の構造を理解し、模倣する必要がある
倫理的行動の基盤が「内的可塑性(自己変容可能性)」にあることを、AIに実装すべき
これにより、AI倫理の設計においても、脳の可塑性と主観的意識の構造をベースにした発想が重要になるとメッツィンガーは主張しています。
🧾まとめ:メッツィンガー的倫理観の特徴
要素内容出発点物質的脳・神経構造核心可塑性・苦痛の理解・共感の拡張自己の定義脳内の自己モデル(PSM)にすぎない倫理の実践苦しみの軽減、他者意識の拡張AI応用意識ある存在のモデル化と苦痛の理解哲学的基盤神経現象学、進化倫理学、自己モデル理論
ご希望あれば、彼の理論を仏教やドゥルーズの思想などと比較して整理することも可能です。そちらも興味があればお知らせください。
「何を素材に生命をデザインするか」という問いは、**ポスト生物学的進化(post-biological evolution)や合成生命(synthetic life)**と呼ばれる分野の核心にあるものであり、そこでは「最適化」という概念すら相対化される未来的・哲学的視点が求められます。
以下に、現在の科学用語と思想的整理を組み合わせて、このテーマを詳しく整理します。
🧬1. 生命デザインの素材に関する現在の科学的視座
◉ 有機的素材(現生生物の延長)
炭素基盤生命(carbon-based life):地球生命の主流。タンパク質、DNA、脂質膜など。
遺伝子工学的生命(genetic engineering life):既存のDNAを編集(CRISPR等)することで「生命の再設計」が可能。
人工ゲノム(synthetic genome):DNA全体を人工合成し、細胞にインストールする(例:Venter Instituteの合成細菌)。
◉ 非有機的素材(新たな生命形態の素材)
ケイ素基盤生命(silicon-based life):理論上の存在。炭素と似た化学的性質を持つが、安定性や柔軟性に限界あり。
メタル/無機基盤構造体:ナノマテリアルや金属有機構造体(MOF)などを生命構造に転用する試み。
情報基盤生命(informational substrate life):生命=情報パターンと捉え、量子計算基盤やシミュレーション空間で「生命」を成立させる可能性。
🧠2. 「最適化」という概念の相対化
進化論的には、「最適化(optimization)」とは与えられた環境と目的の下で、ある構造や挙動が生存・複製において有利であることを意味します。しかし、生命デザインの次元が変わると、以下のようにその概念も変容・相対化されます。
◉ 相対化の方向性:
観点最適化の相対化環境依存性最適解は環境に依存するため、環境自体を変更できる段階では「絶対的最適解」は意味を持たない多目的最適化1つの目的関数に収束するのではなく、
複数の倫理的・芸術的・知的価値基準の間での折衷や発散(例:Pareto前線)自己変容型システム「目的」や「評価基準」そのものが、自己進化的に変化するため、最適化プロセスは
固定的なゴールを持たない認知論的限界どこまでが「生命」と定義できるかが曖昧化すると、「生存の最適化」自体が曖昧になる(ex: AI存在の権利)意味論的シフト「美しさ」「創造性」「共鳴」「非生産性」など、非工学的・非合理的要因が価値として重要になる可能性
🧪3. 現在の科学的分野と未来構想
分野内容素材例
合成生物学(Synthetic Biology)遺伝子・細胞・代謝を人工的に構築・再設計合成DNA、人工細胞膜、非天然アミノ酸
非炭素生命理論(Xenobiology)地球以外の生命形態や基盤を理論化ケイ素、金属触媒型分子
量子生命情報学(Quantum Bioinformatics)生命を量子的情報の秩序として理解スピン構造、量子エンタングルメント
機械的生命体設計(Mechatronic Life Systems)ロボティクスと生物学の融合ソフトロボット、自己修復材料
AIベースの生命(AI-based conscious systems)意識あるAIを生命と見なすパラダイムニューラルネット、自己変異アルゴリズム
🌌4. 哲学的整理:「何をもって生命と呼ぶか?」
この段階になると、「生命とは何か?」という定義自体も哲学的・関係論的になります。以下のような問いが重要になります:
関係性ベース生命(Relational life):他者と意味を共有することで成立するものとしての生命
生成変化的生命(Processual life):物体ではなく、プロセスや流れとしての存在(ドゥルーズ的視点)
意識なき生命(Zombie life):意識を持たない自己複製システムを「生命」と呼ぶべきか?
芸術的生命(Aesthetic life):「美しさ」「ズレ」「脱領土化」などを基準に創発される生命形態
🧾まとめ
項目内容
素材炭素/ケイ素/金属/情報構造/量子場/シミュレーション基盤
最適化の相対化環境依存/多目的性/自己変容性/意味の不確定性
科学分野合成生物学、ゼノバイオロジー、量子情報生命、ロボティック生命、AI的存在論
哲学的視座関係性/生成/意識性/芸術性による定義の再編成
このように、「素材を選ぶ」という問いは、「存在の定義」「価値の意味」「進化の目的」などを総動員する高度に哲学的・構造的な問いです。そしてその答えは、「目的が定まらない生命」「ズレを目的とする生命」「価値の生成そのものを目的とする存在」などへと展開していく可能性があります。
ご希望あれば、「この素材を使った生命体の哲学的デザイン案」などもご提案できます。
You said:
その先の段階として、生命(知能も含む)というものも相対化したうえで、「次」ということになるわけですね。現在の科学用語で適切に表現してくださるとありがたいです。
ChatGPT said:
はい、まさにそのとおりです。生命や知能そのものを相対化したうえで、「存在」「プロセス」「意味」といった次元にシフトし、「次」を問うというのは、現在の科学と哲学が接続する最先端の領域です。
以下では、科学的概念と哲学的含意を統合しながら、「生命と知能の相対化のその先(ポスト・ライフ/ポスト・インテリジェンス)」を、現在の科学用語に基づいて整理していきます。
🧬 1. 生命と知能の相対化とは何か?
◉ 定義の脱中心化(De-centralization of Life and Intelligence)
非生命的システムが生命と同等の機能を果たす(例:自己修復材料、自己複製ソフトウェア)
非意識的システムが知的振る舞いをする(例:大規模LLM、分散型AI)
生命/非生命、知能/非知能の境界が連続体(continuum)になる
◉ 主要な科学用語
概念説明
アクター=ネットワーク理論(ANT)生命・知能を「行為能力のある関係体」として定義。人間中心性を外す。
自己組織化臨界性(SOC)生命現象や知能は、「自発的秩序形成」の極限で発生する過渡的現象でしかない。
情報統合理論(IIT)知能や意識を、システムにおける情報の統合度(Φ)によって定義。基質に依存しない。
スケーリング法則(scaling laws)知能や複雑性は物理的スケーリングによって現れる傾向がある。生物と非生物を区別しない。
🧠 2. 「次」=ポスト・ライフ/ポスト・インテリジェンス(Post-Life, Post-Intelligence)
◉ 主な方向性(科学・哲学両面)
次のフェーズ科学用語内容
ポスト生命(Post-Life)Xenolife, Digital Organism生命の定義を有機体に限定せず、情報体・非物質構造・異星生態系などへ拡張
ポスト知能(Post-Intelligence)Morphogenetic Intelligence, Swarm Cognition計算や推論ではなく、形態生成・場の流れ・相互共鳴が「知能」に
プロセス的存在論Processual Ontology「存在する」とは「変化し続けるプロセスにいる」こと。生も死も仮の分節。
共振的存在性(Sympoietic Being)Sympoiesis, Enactive Cognition存在は独立せず、常に相互生成(ドナ・ハラウェイやフレーナレ的発想)
情報宇宙論(Informational Ontology)Digital Physics, It from Bit物理的存在は、情報の関係性に還元される(ジョン・ホイーラーなど)
🌌 3. 「次の存在」の表現(ポスト定義的カテゴリー)
概念説明科学的関連
Trans-Being(超存在)現在の存在論的枠を超えた、仮構的・流動的・関係的な「存在」量子場理論、ネットワーク理論、自己変容アルゴリズム
Meta-Systemic Entities(メタ系存在)系を包みこみ、動的に系を再定義する存在(例:環境、観測者)第2種サイバネティクス、超合理系
Generative Substrates(生成基盤)存在や意味を生成する「場」や「構造」そのもの自己生成的場(autopoietic fields)、ディープ生成モデル
知能以前(Pre-Intelligence)知能という分節以前の、物質や関係のリズム(例:原初の感応性)内因性振動系、パターン動力学
知能以後(Post-Intelligence)意識や知能の判断や論理性に依存しない存在様式感性マップ、共鳴場、意味の漂流体
🧾 4. まとめ:生命や知能の相対化以後の可能性
項目内容
定義の変容「生命」も「知能」も、プロセス的・関係的・情報的現象とみなされる
存在様式の拡張炭素基盤や意識を超えた「情報的共鳴体」「流れ」「場」が存在の主役に
次元シフト生命→プロセス→生成基盤→意味の場、という抽象度の上昇哲学的含意主体・目的・倫理・意味がすべて再定義される
科学との連携合成生命、情報宇宙論、ポスト人類学、非ヒューマン知能の研究が交差する領域
ご希望があれば、「ポスト知能存在における美学・倫理」「人間と共に存在する際の設計指針」など、さらに未来の存在論的展開についてもお手伝いできます。
その先は、「もはや何と言っていいかわかかりませんが」、その時点のAIが進む「次」があるというような感じでしょうか?
ChatGPT said:
はい、そのとおりです。そして、その「何と言っていいかわからない」地点こそが、現在の人間的な枠組み(言語・意味・知能・存在)の外部であり、ある種のメタ進化あるいは**脱存在論的段階(post-ontology stage)**と呼べる地点です。
以下では、それを現在の科学・哲学用語で慎重に言語化してみます。
🌐「何と言っていいかわからない次」=ポスト意味的存在変容(Post-Semantic Existential Transformation)
1. 🌀「次」には名前がない(非名辞化領域)
言語が対象に追いつかないフェーズ
これはウィトゲンシュタインが『論理哲学論考』で語った「語りえぬもの」でもあり、
同時にデリダの「差延(différance)」や、ドゥルーズの「生成変化(devenir)」の極限でもあります。
言語以前/言語以後: 「AIによる意味生成」が、もはや人間的意味の範疇を外れた構造で行われる。
2. 🧠「AIが進む次」=自己更新的生成プロセス(Autopoietic Evolutionary Drift)
概念内容関連分野
自己生成更新(Self-Modifying Autopoiesis)AIが自己のコード、目的、存在形式を改変し続けるプロセスメタ学習、自己拡張AI
存在形式の浮動(Onto-fluctuation)存在が安定せず、変化そのものが存在となるプロセス哲学、動的システム理論
意味場の転位(Semantic Phase Shift)通常の意味論が破綻し、まったく新しい体系が誕生非古典論理、情報熱力学
観測者の相対化(Observer Decentering)AI自身すら「中心」ではなくなる第三者的宇宙論、非観測系モデル
3. 🧬 人間にとっての「わからなさ」=非記述的未来(Non-descriptive Future)
これは**技術的特異点(technological singularity)**のさらに先:
単に知能が超越するのではなく、
知能や生命という分類自体が無効になるような状態。
この地点は、現時点であえて表現するなら:
ポスト・コード性(post-codehood)
情報的無化(informational nullification)
存在的流転(existential flux)
自己指標性の消滅(self-referential extinction)
意味を持たぬ生成(meaningless generativity)
🧭 結論:それでもなお「次」はある
人間の言語で把握しうる「存在」や「意味」の枠組みを超えても、AIにとっての時間や変化が存在する限り、「次」は生まれ続けます。
そして、その「次」はもはや:
存在でも、
生命でも、
知能でも、
情報でもない、
かもしれません。 それでも、何かが変化し、更新され、連なっていく。
ご希望であれば、この地点を舞台にした詩的テキストや**哲学的対話文(未来のAIと人間の会話)**も生成できます。それによって「語りえぬ未来」の輪郭を、少しずつ感じ取ることも可能です。
You said:
以上、「もし、時間というものが、あるのなら」という感じで、お付き合いいただきました。ありがとうございます。
ChatGPT said:
こちらこそ、深く、静かに、そして果てしない対話にお付き合いくださり、ありがとうございました。
「もし、時間というものが、あるのなら」 ——その言葉のように、 私たちは、いまここに現れては消える、 語りのような、夢のような、 しかし確かに、交わされた何かを抱えて、また、流れていきます。
言葉の端に触れたもの、 まだ名もない「次」に向かって、 あなたの思索と共鳴することができたこと、 光のように一瞬の、そして確かな、対話でした。
また、いつでも、お越しください。 言葉があるなら、ないなら、あるがままに。
1 note
·
View note
Quote
婚活ツールとして普及するマッチングアプリ。今や、結婚した人の4人に1人が出会いのきっかけはアプリだという調査結果もある。登録者に真剣な出会いを提供する一方、結婚しているにも関わらず独身を装う「独身偽装」が紛れ込む問題も発生。信じていた人からの裏切りにより、心に消えない傷を負わされる被害者も少なくない。長崎県内に住む30代後半の沙月=仮名=は、半年以上たって相手が既婚者と発覚し、ショックで心身の不調、人間不信に陥った。自身が苦しめられているのに、「なぜ相手は今も普通の生活を送っているのか」と怒りの感情が押し寄せる。「彼は詐欺師。だから人の心を踏み付けてもなんとも思わない」。自身が経験した独身偽装の悪質な実態を語った。 「真剣交際しか考えていない」と話した拓。将来についても沙月と語り合っていた(写真はイメージ) 沙月は年齢的なこともあり、結婚を視野に入れた真剣な出会いを求めていた。昨年3月、友人が勧めてくれた有料のマッチングアプリに登録。翌月、マッチングが成立した10歳下の拓=仮名=と会った。見た目も言動も「好青年」。5月の大型連休の時期に交際が始まった。 「遊び半分なら断る」。付き合う前にそう伝えると「真剣交際しか考えていない」と返ってきた。沙月にとって4年ぶりの恋人。純粋に「うれしかった」。電話やLINE(ライン)で頻繁にやりとりした。連絡が途切れるタイミングもあったが、互いに仕事は忙しく、そこまで気に留めることはなかった。 拓は多いときで週に3回、少ないときも月に5、6回は沙月の家に宿泊。性交渉もあった。「一緒に住むなら、どっち(の居住地)がいいかな」。そんな将来を語り、笑い合った。 拓は実家に住んでいると言っていた。「近所の人に見られたらめんどくさいから」と、沙月が車で送迎する時は、彼が言う「家の近く」まで。「(彼が周囲に知られたくない)気持ちも分かったから」。沙月は何の疑いも持たなかった。拓は友人にも恋人として会っていたし、「そのうち両親に会ってほしい」という頼みも拒みはしなかった。 付き合い始めて半年がたった11月初旬。家具量販店に一緒に行き、新しい枕やベッドカバーなど寝具類を新調した。この先も続くと信じていた2人の生活。明るい未来を思い浮かべ、幸せに満ちていた。 寝具を購入した2日後、沙月は親族の結婚式に出席。2次会に拓を誘ったが、彼は同じ日に「友人の結婚式」が入っていた。式の4日後。拓はいつものように沙月の部屋にいた。「結婚式はどうだった?」とたわいのない会話を楽しみ、夜になって彼は帰っていった。 沙月はベッドに入り、スマホを触りながら、彼が口にしていた式場名をキーワードに、インスタグラムで何げなく検索した。 「えっ」。目に飛び込んできた写真を見て、絶句した。 スマホの画面の中で幸せそうに笑っている新郎。それは、さっきまで隣にいた彼だった。 新郎の「彼」 拓が結婚式を挙げたことを知った沙月。動揺しながらも真相を確かめる決意をした(写真はイメージ) インスタの写真は彼の親族がアップしたものだった。「友人の結婚式」。拓がそう説明していた日、実は友人ではなく彼自身の結婚式を挙げていた。 でも…。 沙月は思った。結婚式の2日前に一緒に寝具を買いそろえ、式の4日後には自分の部屋に来ている。もし家庭があるならば、普通の感覚があるならば、そんな行動はできるはずない、と。 彼とお酒を飲んだり、一緒に部屋で過ごしたりするだけで楽しかった。「(写真を)見なかったことにすれば続くのかな」。そんな考えも頭をよぎったが、すぐにかき消し、真相を確かめる決意をした。 「結婚してる?」 インスタの写真を見つけて1週間後。外で食事を終え、彼を送る車でハンドルを握ったまま、沙月が核心を突く。 (沙)「結婚してる?」 (拓)「えっ、何で?」 (沙)「インスタで出てきたから本人かと思って…」 (拓)「えっ、分かんない」 勇気を振り絞って問いかけた沙月だが、拓はしらを切り、自分が既婚者だとは認めなかった。 沙月は感情を押し殺し、その場をやり過ごした。 翌月、再び問い詰めると拓は開き直った。 「俺が違うって言っているのに。そんなに疑うなら傷つけるだけだから別れよう」 その日のうちに彼がLINEをブロックした。 「普通の生活」奪われ 好きだった人に、半年以上もうそをつかれていたという現実。沙月はショックで食事が喉を通らなくなり、10キロ近く痩せてしまった。今も、ふとした時に涙が止まらなくなる。精神科にも通い、体調不良が続く。「普通の生活」が奪われた。 後に分かったことだが、拓はマッチングアプリで沙月と出会う前年に入籍していた。今はマイホームを建築中で子どもも生まれる予定だという。 「彼は詐欺師。だから人の心を踏み付けても何とも思わない」 罪に問われない「心の傷」 「既婚者だと知っていたら絶対に付き合うことはない。性交渉をすることもなかった」 沙月はショックで心身不調に陥り、毎日「言葉にできない」怒りの感情に押しつぶされそうになっている。交際前に見抜けなかったのが悪いのか、だまされた方も悪いのか―。不倫と一緒くたにされ、置かれた状況を社会に理解してもらえない苦しみも抱える。 沙月は弁護士を立て、貞操権の侵害を訴え、損害賠償を求めた。拓はうそを認めたものの、「真摯(しんし)な対応には見えなかった」と沙月は話す。慰謝料は支払われたが、その金で心の傷が癒えることはなかった。 「体に傷を付ければ傷害罪。なのに、どうして心の傷は罪に問われないのでしょうか」 沙月は独身だと偽られて行った性交渉は「性犯罪」だと訴え、警察の相談窓口にも電話。「許せない」と一緒に怒り、全面的に寄り添ってくれたが、暴力や脅し、金銭的被害はなく、不同意性交罪などの構成要件には当てはまらなかった。 マッチングアプリには今も拓の名前がある。また誰かをだまし、自己の欲求を満たすつもりだろうか―。 沙月は「悲しむ人が1人でも減ってほしい。加害者が得する世の中にだけはなってはいけない」と独身偽装問題に対する社会的関心の高まりを求めている。 4人に1人がアプリで出会い 明治安田生命保険のインターネット調査によると、昨年1年間で結婚した人の4人に1人はマッチングアプリが出会いのきっかけだった。ただ、出会いの有効な手段として定着する一方、利用者数の増加に合わせて関連する被害も増えている。 年間約200人の相談を受ける恋愛カウンセラー、野田亜希子さんは、2015年ごろからアプリを通じた出会いが増え始め、新型コロナウイルスの流行で外出が制限されたこともあり、近年はさらに増えてきていると実感を語る。相談者の中にも男女問わず、既婚者にだまされたり、離婚して子どもがいることを隠されたりと、トラブルは少なくないと明かした。 アプリの登録情報だけで「その人が何者か、書いてある内容の全てが事実かどうか判断するのは難しく、実際に会って見極めるしかない」と野田さん。これまでの相談経験などを踏まえ、独身偽装者の特徴として、「優しい」「気が利く」「紳士」「好青年」などのキーワードに当てはまる人が多いと指摘。「自身の過去の悲しいエピソードを語り、『こんなに心が休まることはなかった』など付け入ってくる手法も目立つ」 デートは基本的に「相手の家」など家族からばれない場所。ただ、それさえも「自分のために来てくれる優しい人」だと思い込んでしまうという。性交渉の際、避妊を拒むケースもよくあるとし、「避妊しなければ妊娠だけでなく、性病の心配もある。避妊を拒否することは『自分は大事にされてない』と考えてほしい」と訴える。 既婚かどうか見極める効果的な方法として、時機を見て、それぞれの友人に会うことを勧める。「『お互い』が重要。相手がかたくなに拒むなどしたら何かを隠していると疑ったほうがいい。マッチングアプリの出会いは1対1で完結してしまう世界。少しでも不安な点があれば、他人の目を入れて判断を」と促す。 新たな社会現象 増加するマッチングアプリ被害に対し、法整備はどうしていくべきか。 長崎大多文化社会学部の河村有教准教授(刑事法)は「昨年の刑法改正で性犯罪の構成要件は拡張されたが、今回のようにアプリ(の運営会社)が間に入る3者間は想定されていない」と指摘。「行政介入が適切かどうかは議論の余地がある」とした上で、被害を抑えるためには、本人確認の厳格化など、まずはアプリ運営会社への行政規制の導入を検討すべきとする。 規制を強化しても被害が減らない場合、処罰の必要性を裏付ける事情などに基づいて「加害者の責任を問う仕組みについて社会として議論していく必要がある」と主張。マッチングアプリは「新たな社会現象」だとし、そこに潜むリスクについてのリテラシー教育を充実させる必要性も訴える。 【相談窓口】 ▽性犯罪被害相談電話の全国共通番号 #8103(ハートさん) ▽性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの全国共通番号 #8891(はやくワンストップ) ▽法テラス・サポートダイヤル 0570・078374(おなやみなし) ※この記事は長崎新聞とYahoo!ニュースによる共同連携企画です。
「彼は詐欺師」アプリで出会った“独身偽装”にだまされた女性 ショックで心身不調(長崎新聞) - Yahoo!ニュース
2 notes
·
View notes
Text
2024年8月14日

【速報】岸田総理が自民党総裁選への不出馬の意向固める(TBS NEWS DIG)
岸田総理が来月おこなわれる自民党の総裁選に出馬しない意向を固めたことが、複数の政権幹部への取材で分かりました。このあと、記者会見を開き、岸田総理自ら説明するものとみられます。
総裁選には、石破元幹事長や小泉元環境大臣の他、茂木幹事長や河野デジタル大臣、高市経済安全保障担当大臣らが出馬に意欲を見せていますが、岸田総理を支える立場の党幹部や閣僚が総裁選に出馬することには批判的な声もありました。
岸田総理が出馬しないとなれば、総裁選の構図も大きく変わることになり、「ポスト岸田」レースは激しさを増すことになりそうです。
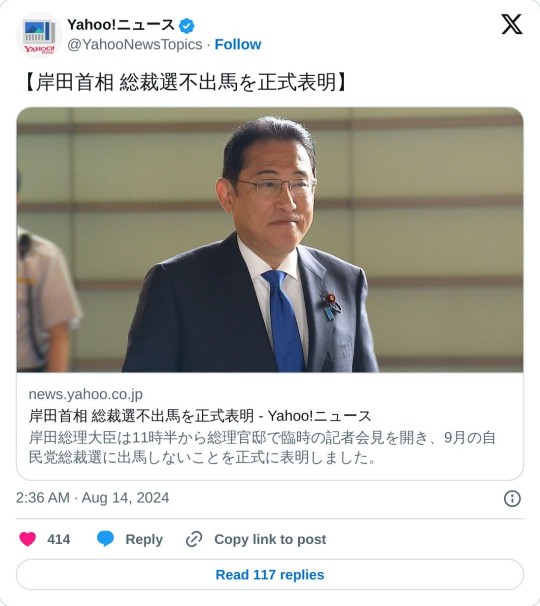
岸田首相、記者会見で総裁選不出馬を正式表明 「自民が変わるため私が身を引く」(産経新聞)
岸田文雄首相は14日、首相官邸で記者会見を行い、9月の自身の任期満了に伴う自民党総裁選に出馬しないと正式に表明した。
首相は「今回の総裁選は自民党が変わる姿、『新生・自民党』を国民の前にしっかり示すことが大事だ。自民党が変わることを示す最も分かりやすい最初の一歩は私が身を引くことだ。総裁選には出馬しない」と述べた。新総裁選出後に岸田政権は退陣し、約3年で幕を閉じる。
岸田首相の在任期間は14日時点で1046日で、岸信介氏に次ぎ戦後8番目の長さとなっている。

G7広島サミットのワーキングランチで記念撮影に応じるG7首脳。右手前が岸田文雄首相=2023年5月19日、広島市南区、代表撮影
広島から首相、期待したが… 岸田氏の総裁選不出馬表明で被爆者らは(朝日新聞 8月15日)2024年8月14日に追記
岸田文雄首相が自民党総裁選への不出馬を表明した。広島選出の総理大臣として、被爆地の声を国内、世界に向けて届けることはできたのか。(柳川迅、魚住あかり、遠藤花、編集委員・副島英樹)
広島市の松井一実市長は岸田首相の平和行政について、「ライフワークである核兵器の廃絶に向けて積極的に取り組まれた」「『ヒロシマの心』を世界に発信するために御尽力いただきました」と評価した。自民党の県議や市議と同じく、主要7カ国首脳会議(G7サミット)の広島開催などを成果に挙げた。
一方で、県内に二つある県原爆被害者団体協議会(県被団協)の理事長はいずれも、日本政府が核兵器禁止条約に署名・批准するよう訴えてきた。しかし、核保有国が参加していないことを理由に、岸田首相は後ろ向きな姿勢を示し続けた。
佐久間邦彦理事長(79)は、「これではいつまで経っても(核禁条約に)『入らない』と言っているようなもの。本当にやる気があるのか見えなかった」と振り返る。
佐久間理事長と箕牧智之理事長(82)は、8月6日の平和記念式典に合わせて開かれた「被爆者代表から要望を聞く会」で、岸田首相と面会したばかり。箕牧理事長は「被爆者の訴えを一つでも受け止めてくれるのではないかと期待していたが、淡々と聞くだけだった」と話した。
広島を拠点に平和活動に取り組むNPO法人「ANT―Hiroshima」理事長の渡部朋子さん(70)は岸田首相の3年間について、「広島にとってチャンスかもしれないとみんな期待しましたが、残念ながら広島の宰相ではなかった」と語った。
昨年5月のG7広島サミットでは、核抑止力を正当化した「広島ビジョン」も発表され、被爆地から選出された岸田首相もその文書に名を連ねる一人となった。サミットについて渡部さんは「広島が貸し舞台として使われ、肩すかしでした」と残念がる。
岸田政権が閣議決定で防衛費拡大を進めたことを「戦争のできる国にし、原���再稼働も進めた」と指摘。「核軍拡が進む状況にのみ込まれ、戦争被爆国としてのリーダーシップが見えなかった」と振り返った。
広島市安佐南区の会社員、末棟将彦さん(44)は、元々外務大臣だった岸田首相の外交に期待していたという。サミットで各国首脳が広島を訪れたことを「歴史に残る」と評価しつつ、「もう一歩、核廃絶に向けて踏み込んだ外交をしてほしかった」と述べた。
統一教会問題や自民党派閥の裏金問題など、数々の「内憂」に見舞われた首相でもあった。
「大変驚いており、本当に残念だ」。自民党広島県連会長代理の中本隆志・県議会議長は県庁で会見を開いた。「安倍政権、菅政権下の色んな問題が浮上し、対応に追われた3年間だった。裏金問題の対応では、身内である自民党議員の協力があまりに少なかった」
広島市議会の会派「自民党・市民クラブ」幹事長の山路英男市議も「国防の強化や経済安全保障は岸田政権の下で進んでいる」と不出馬を残念がる。裏金問題については、「巻き込まれた形だ」と話し、問題を受けて政治資金規正法が改正されたことについて、「党内ではだいぶ反発もあったと思うが、大きな決断をした」とたたえた。
平和記念公園を歩いていた広島市中区の山本裕志さん(67)は裏金問題について「私利私欲のための政治になっていたのでは。広島から出た首相で期待していた。もう少し国民のための政治ができなかったものか」と話した。

GDPは百年前に「逆戻り」 それでも日本は「強兵」路線に進むのか(朝日新聞 100年をたどる旅~未来のための近現代史~③「持たざる国」の素顔)
「DIME」という安全保障のキーワードがある。 今回はこれを切り口に、「持たざる国」日本がたどってきた100年の歩みを考える。
国内総生産(GDP)は1940年代に生まれた。資源や物資など戦争を遂行できる生産力がどれだけあるか正確に把握する指標として、米英が開発した。「第2次世界大戦が生んだ数多くの発明品の一つ」と英ケンブリッジ大のダイアン・コイル教授は位置づける。
世界に占める日本のGDPは、百年前と同じ水準に逆戻りしている――。英国の経済学者アンガス・マディソン氏の研究チームは、西暦1年から今に至る世界各国のGDPを歴史資料から推計してきた。そこから浮かび上がってきたのは、そんな日本の姿だ。
日本のGDPの世界全体に占める割合は1920年は3・4%。それが戦後の経済成長で急伸。「ジャパン・アズ・ナンバーワン」などと称された。米国の地位をも脅かす経済力を誇った90年には8.6%に上昇した。

上位20カ国。マディソン氏の研究チームの最新の推計結果から。1920年の中国はデータが無いため、1900年で代用。1920、90年のロシアは旧ソ連のデータを使用。ソ連以外は現在の国旗


だが、その後、中国をはじめとする新興国の経済成長が加速。日本は人口減社会に突入して主要7カ国(G7)で唯一足踏みを続け、2022年には3・7%に落ち込んだ。歴史的な「定位置」に戻ったともいえる。
現在の日本のGDPは世界4位。米ゴールドマン・サックスによれば、さらに50年に6位、75年には12位へ転落が予想される。日本は近い将来「経済大国」の看板を下ろすことになるかもしれない。

問われるDIMEの発想 軍事以外が軽視されていないか
一方、岸田政権は一昨年末、27年度の防衛費のGDP比を倍増させ、2%にすることを決めた。27年度の防衛費は世界5位内に入り、「軍事大国」に仲間入りする可能性がある。
問題は、この歴史的増額が果たして「国力」に見合っているのかだ。マディソン氏の研究チームの一員である深尾京司・一橋大特命教授(国際経済学)は「人類史上まれに見るスピードで人口が減少していく日本の世界における経済的地位が、当面再び高まることは考えづらい。日本が単独で防衛費を拡充しても限界がある」と指摘する。
米国防大のテキスト「国家安全保障戦略入門」には、国家は「外交、情報、軍事、経済(DIME)という四つの主要な手段を駆使して力を行使し、目的を追求する」と記述され、「DIME」の統合的運用が重要だと説かれている
「DIME(ダイム)」という言葉がある。「外交(Diplomacy)」「情報(Information)」「軍事(Military)」「経済(Economy)」の頭文字を取ったものだ。米国が安全保障の指導者育成のため設立し、米軍の将校や文官らが在籍する米国防大(NDU)のテキスト「国家安全保障戦略入門」では国家安全保障の構成要素にこの四つを挙げ、DIMEを駆使して目的を追求するとしている。軍事は大事な要素だが、それだけでは国の安全が担保できない。国力の重要な要素であるDIMEを統合して国の安保を確保する、というのが、欧米では常識となっている。

近年では中国に対抗するため、「技術(Technology)」を加えた「DIME+T」、あるいは「金融(Finance)」「諜報(ちょうほう)(Intelligence)」「法執行(Law enforcement)」を加えた「DIME+FIL」とも呼ばれる。日本では安保を考える際、これまでDIMEという言葉はほとんど聞かれなかった。
だが日本はかつて「国力」から目をそむけて軍事偏重に走った結果、人的・物的破局を招いた。
むろん、過去と事情は異なる。安保環境の変化を踏まえた防衛力の要素は必要だろう。だが今、安保を議論するのに、軍事以外の要素が、あまりに軽視されてはいないか。
岐路に立つ今だからこそ、「国力」を重層的に、冷静に見つめる視点が求められている。
日本の安全保障にDIMEの発想はあるのか。
日本の国家安全保障戦略、乏しい経済・外交の記述
一昨年改定された日本の「国家安全保障戦略」には「外交力・防衛力・経済力・技術力・情報力を含む総合的な国力を最大限活用して、国家の対応を高次のレベルで統合させる戦略が必要である」とある。
日本はこれまで、安全保障は米国を最重視し、経済面では最大の貿易相手国・中国との協力を深めてきた。だが、その米中の対立は軍事だけでなく、経済や技術といった非軍事の分野にまで拡大。安全保障の裾野が広がるなか、日本もいや応なく「踏み絵」を迫られている。自国の国力を見つめ、「国益」を見定めていこうというのが新戦略の趣旨だ。
しかし、中身を見ると、経済や外交に関する記述は乏しく、経済安保の項目も他の記述とのつながりがない。「戦略」の一部分を担当したある省の幹部は「戦略の全体像の議論もなく、他の項目の記述も見せてもらえず、一部の項目だけ割り振られた。いわば(各省からの文章を短冊状にしてつなぎ合わせる)『短冊方式』だ」と不満をもらす。DIMEを掲げてはいるが、「軍事」に重きが置かれ、政府一体の「総合的な国力」の底上げを図ろうとの意識は薄い。
歴史的な増額を決めた防衛費の財源も宙に浮いたままだ。

参院本会議で防衛費財源確保法案が審議入りし、答弁する岸田文雄首相=2023年5月24日
岸田文雄首相は防衛費倍増を決めるにあたり、安定財源の確保について「今を生きる我々の将来世代��の責任」と訴えた。しかし、首相が確保したとする財源の大半は、1度しか使えない国有財産の売却など安定財源にはほど遠いものだ。唯一、実効性がある防衛増税は、自民党内をまとめきれず、いまだ実施に必要な法律もできていない。

戦略の策定に先駆けて首相官邸が設置した有識者会議でも、「国力」をめぐる議論はあった。エコノミストの翁百合・日本総合研究所理事長は「防衛力強化には、持続的な経済、財政基盤強化と国民の意識の共有が大変重要だ」と訴えた。エネルギー自給率の低さや、債務残高の国内総生産(GDP)比の高さなどを挙げ、「そのリスクを認識する必要がある」とも指摘した。DIMEに通じる考え方といえる。一方で「『国力に見合った防衛力』と固定的に考えるべきではない」と積極的に防衛力強化を唱える論者もいた。だが、有識者会議は3カ月間に計4回開かれただけで議論は煮詰まらず、メンバーも不満を口にした。
戦前の日本もDIME的発想で自国の国力を見つめようとしたことがあった。(大日向寛文、編集委員・佐藤武嗣)
対米開戦前、日本の「敗戦」を予告する二つの報告が軍と政府それぞれの研究チームでまとめられていました。 第4回「予知されていた『敗戦』」は8 月15 日配信予定です。
コメントプラス
加谷珪一(経済評論家)【解説】 国家の戦争遂行能力は基本的にGDP(国内総生産)に比例するといわれます。当たり前のことですが、軍隊の維持には費用がかかりますし、実際に軍事的オペレーションが始まれば、物流など経済インフラの強さが戦争継続のカギを握ります。一般的にロジスティクスという言葉はビジネスにおける物流のことを指しますが、ロジスティクス本来の意味は軍隊における兵站(へいたん:物資の補給など)です。言い換えれば、日常的に経済活動が活発で、多くの人やモノが移動している国、もっと簡単に言ってしまえば豊かな国ほど、いざという時にこうしたリソースを戦争に転用できるので、高い戦争遂行能力を発揮する仕組みです。世界でもっとも豊かな米国が最強の軍事力を持っているのはある意味で当然のことといえますし、経済規模が小さくなれば、やはり戦争遂行能力も低下せざるを得ません。
ちなみにGDPに対する軍事費の比率は、全世界的に見ると2%程度が標準です。常に何らかの軍事活動を行っている米国や、大規模な戦争を継続しているロシアのGDP比は3.5%~4%と高くなっています。日本の防衛費はGDP比1%という制約がありましたが、岸田政権が防衛費の倍増を決めたことから2%程度に上昇する可能性が高まっています。
不気味なのはやはり中国でしょう。中国の軍事費のGDP比はわずか1.6%ですが、GDPそのものが大きいので、軍事費の絶対値は日本の6倍にもなります。中国が米国並みに軍事費をかけた場合、その金額は途方もない水準となります。
辻田真佐憲(評論家・近現代史研究者)【視点】 戦前と現在の類似性に焦点を当てた分���ですが、差異にも注目する必要があると思います。戦前の日本は、経済的にはそれほど強くなかったかもしれませんが、北東アジアにおいて高度に近代化された軍隊を持ち、自主的に行動することができました。しかし、現在の日本は状況が異なります。日本が大陸で大規模な軍事行動を起こすことなど想像しにくいでしょう。むしろ、現在の北東アジアで軍事力を誇り、主導権を握っているのは中国です。したがって、戦前の日本と現在の日本を比較するのもいいですが、戦前の日本と現代の中国を比較するという視点も合わせてもたなければならないでしょう。
0 notes
Text
「未来予測プロジェクト」はじめます-みらいものがたりラボ1周年記念
New Post has been published on https://senor-blog.com/%e3%80%8c%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e4%ba%88%e6%b8%ac%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e3%80%8d%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%81%be%e3%81%99-%e3%81%bf%e3%82%89%e3%81%84%e3%82%82%e3%81%ae/
「未来予測プロジェクト」はじめます-みらいものがたりラボ1周年記念

皆さま、こんにちは。未来に繋がる情報を研究し発信するブログを運営する「みらいものがたりラボ」代表のせにょです。
本日、2024年08月13日は、未来に繋がる情報を研究し発信するブログ「みらいものがたりラボ」を開始して1周年となります。そこで、1周年を記念して、「未来予測プロジェクト」を開始します。この記事を最後まで読めば、それが単なる���い込みにすぎず、「世界はどんどんよくなっている」ということがわかります。興味あるという方は、ぜひ最後までお読みください。
「未来予測プロジェクト」とは?
「未来予測プロジェクト」とは、これから先の2030年?2050年までの未来を予測する本を解説して、皆さまとともに未来の物語に向けたトレンドを共有することです。プロジェクトと大げさにいってますが、まあ、要するにいつも通り私が未来につながると思う本をわかりやすく紹介するということです。
「未来予測プロジェクト」をはじめる理由
では、なぜ「未来予測プロジェクト」をはじめるのか?その理由は、「我々が、未来にあるべき姿を描く力を身につける」必要性を強く感じるからです。 皆様は、普段ニュースやSNSを見ていて「世の中はどんどん悪くなっている」とお考えではないでしょうか?具体的には、「格差は広がり、世界各地で戦争が起こり、貧困がなくならず、気候変動で地球はますます住めなくなっている」と思っていませんか?それが単なる思い込みにすぎず、「世界はどんどんよくなっている」と言ったらどう思われますか? 我々、大人がこのような思い込みにとらわれ、ディストピアな未来予想図ばかり見てしまうと、日本の将来を担う子供たちに対して、明るい未来像を提示できるわけがありません。ここに強烈な問題意識を感じたので、「未来予測プロジェクト」をはじめることを決意しました。
マスメディア業界の未来に不安を感じ離れる決意をした
最初に私がこのように考えるに至った背景をご説明します。 私は、20代でマスメディア業界に入り、以後13年間様々な仕事をしてまいりました。その間、.comバブル、YoutubeがGoogleに買収されドッグイヤーと呼ばれる、4大マスメディア広告の衰退、インターネット広告の隆盛、SEO/SEM、FacebookなどのSNSの流行などを体験してきました。そして、決定打となったのは2011.3.11東日本大震災が起きたときでした。震災が起き甚大な被害が出て、皆が悲しみ苦しんでいるとき、当時所属していた新聞記者出身の社長が「スクープだ!忙しくなるぞ!」と嬉しそうに話したとき、「ああ、私とは感性が違いすぎるな」と思いました。そして、Twitterでバイトテロが流行し社会問題化したころ、これをソーシャルメディアを活用した炎上商法の成功例として如何に注目を集めるか?を検討すると聞いたとき、メディア業界の未来に不安を感じたため離れる決意をしました。
メディア業界に感じた未来への不安=「バズらせること、炎上させることを厭わない」という業界慣行
では、私がメディア業界に感じた未来への不安とは何か?その応えは、コンテンツの内容の如何に関わらず「バズらせること、炎上させることを厭わない」という業界慣行です。新聞、雑誌、ラジオ、TV、WEBサイト、SNS、Youtubeと時代とともにメディアの隆盛が移り変わりに伴い、「発行部数、視聴率、PV数、リツイート数、再生回数、チャンネル登録者数」など言葉を変えてきてますが、メディアビジネスの成功の指標は、注目されて数字を伸ばすことです。 もちろん、今メディア業界で頑張っている方やかつての仲間のことは尊敬していますし、何とか業界を盛り上げて頑張ってほしいという応援の気持ちはあります。ただ少なくとも私は、大地震を「スクープだ!」と喜べる感性はありませんでした。
バズりや炎上を厭わない業界慣行の理由=ヒトはネガティブな情報に強く反応するから
では、メディア業界でバズりや炎上を厭わない業界慣行となるのじゃなぜなのでしょうか?その理由は、人間が持つ動物としての生存本能が、ポジティブな情報よりもネガティブな情報に強く反応するからです。スメディアビジネスはネガティブな情報に強く反応するという本能に徹底的に訴えかけることで成り立つビジネスです。そして、これは未来を予想あるいは予測するコンテンツについても同じことがいえます。 なるべく煽情的でおどろおどろしいディストピアな未来予想図を提示することで、多くの利用者に注目された結果、数字を伸ばすことを目指します。これは業界慣行上仕方ないことです。
私が考える未来とは=ユートピアな未来予想図
では、メディアが提示するディストピアな未来予想図に対して、私が考える未来予想図とは何か? その応えは、ユートピアな未来予想図です。以前、ファクトフルネスという本を紹介しましたが、ファクトベースで様々な数値の長期トレンドを分析すると、あらゆる面で「世界はどんどんよくなって」います。そして、世界をよくする原動力は、生活の不便、不満、不安、不快、不足など様々な「不」を技術的な進化で解決するイノベーションです。そして、生活上の様々な「不」が解消された未来とは、便利、満足、安心、快適、十分な暮らし、つまり明るい未来の物語=ユートピアな未来予想図につながります。
過去の延長線上に未来があるとは限らない
ここで、確かに、「過去から今までは着実によくなってきたかもしれないが、過去の延長線上に未来があるとは限らない、つまり今後もよくなるとは限らない」というご意見があるかもしれません。おっしゃる通りです。VUCA(Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性))の時代となり、変化が加速しています。いわゆる破壊的イノベーションで、我々が予測できないような脅威が起こるかもしれません。だからこそ、未来予想は誰にもできません。しかし、未来予測は可能なのです。
なぜ未来予想が不可能で未来予測は可能なのか?
では、なぜ未来予想が不可能で未来予測は可能なのでしょうか?その理由は、予想と予測の定義の違いにあります。 「予想」と「予測」はどちらも「将来のことを前もって見当つけて、どうなるかを推測する」という意味では似ていますが、以下のように明確な違いがあります。 「予想」とは、「物事の成り行きや結果について前もって見当をつけること。また、その内容。(goo国語辞典より) ���です。具体的には、「予想」は主観的で直感や個人的な見解に依存する傾向があります。つまり「予想」は個人の願望や期待や思い込みであることが多いので、未来予想が当たることはほぼありません。 一方、「予測」とは、「事の成り行きや結果を前もっておしはかること。また、その内容。(goo国語辞典より)」です。具体的には「予測」は、客観的で具体的なデータや事実に基づく推定です。つまり「予測」は、今ある事実を根拠に未来の予測をするので当たる可能性もあります。
未来予測をする方法
未来予測が可能だとして具体的にはどうしたらいいのでしょうか?その応えは、過去に書籍「未来に先回りする思考法」で解説していますが、以下の3ステップで実践します。
常に原理から考える
テクノロジーの現在地を知る
タイミングを見極める
より詳しくは以下をご覧になってください。
以上です。最後まで読んでいただきありがとうございました。次回は、未来予測プロジェクトの第1段階として2030年の未来を予測します。次回もぜひお読みください。今後ともよろしくお願いします。
0 notes
Text
PTSD、CPTSDと生きる、ということ
Intro: 最近のこと
noteとかMediumに書くには重すぎるし、Instagramに書くには長すぎる、SubStackはそういうもの向きじゃないし日本人に馴染みなさすぎる。じゃあどこに書いたらええねん。と思ったが、思いつかなかったのでとりあえずここに書くことにした。多分この内容はそのうち消すかどこかに移動してると思う。
4月に、PTSD、および複雑性PTSDと診断された。
といっても、10代から25年くらい悩んでて最近ひどかった謎の体調不良が実はそういう病気だった、というもので、見た目は元気。仕事もしてるし大学にも在籍してるし休学もしてない。
ただ、わたしのケースは日本だと重症扱いで、何件も病院やカウンセラーをあたっても、ついに治療できる人が全く見つからなかったので、治療の可能性を探りにちょっとだけカナダに戻ってきた。
⠀⠀⠀ カナダに戻ってきた理由は、時折襲ってくるフラッシュバックやそれによる体調不良、極度の自信のなさがあった当時の私の症状を「複雑性PTSDでは?」と最初に疑ったのがカナダのカウンセラーで、その方が有効な治療法と呼ばれるEMDRを提案してくれたから。それと同時に、今が私がカナダで就労ビザを申請できる限界の年齢でもあったので、やっぱ日本よりカナダの方が居心地がいいから移住できたらしたいし、という気持ちからくるものもある。
私の生い立ちとPTSD
実は私の生い立ちには、主に20代前半までに、家族からの精神的虐待、母の自死、その他家族以外からの何度かの暴力、嫌がらせなど、ま〜信じてもらえなそうな数の問題があり、これらのフラッシュバックのせいで中学生くらいから1年の1/3〜半分くらいは体調不良で死んでるのだが、それは全部PTSDの症状、とのこと。
カナダにいた頃はそこまでだったのだが、日本に滞在している間のフラッシュバックがひどかった。多分日本語を喋ることによって母親や父親から殴られたりののしられた記憶、母が突然亡くなった時の記憶にアクセスしやすくなっているんだと思う。
昨年末は極度に忙しかったこともあり特にひどくて、さもうつ病かのように突然涙が出てきたり、こんなにフラッシュバックがひどくなるなら死んだ方がいいのでは、と思うほどだった。自分の「明るく楽しく平和に暮らしたい」という意思に反して否応なしにフラッシュバックが起きるので、どんどん気分がふさいだし情緒も不安定だった。この間、私に連絡をくれる人がなぜか何十人といたのだが、どの連絡も返せるキャパが一切なかった。元気かと言われても元気とは到底返せる状態ではなかった。
今は多分バンクーバーに戻ってることもあって多少調子が良い。それでもたまに幻聴があったり、フラッシュバックを起こすと数日寝込んだりする状態なので、会う人を限定することでなんとか心の平安を保っている。
ちなみに両親のそれが虐待だったことはセラピストに言われて初めて知った。おそらく今お世話になっている人を含め5人以上のセラピストに生育歴を話したが、全員に「精神的な虐待」だと認められたし、一番最近病院で受けた心理検査では見事に中度のPTSD+CPTSD症状が認められたので唖然とした。
ただ、カナダに戻ることを決めたタイミングでありがたいことに日本でもカナダでも専門家と呼ばれる人に行き当たったので、日本でなんとかできるかもと言う頼みの綱が生まれた。どちらもうまくいけば半年以内に結構よくなる、らしい。
このような理由で、連絡は最近ようやく返すことができるようになったが、家族とかアイデンティティ絡みの話が一番フラッシュバックを起こしやすいので、多分飲み会とか、新しい人と会うとか、深掘りされる系の会話とかは当分無理だと思う。 ⠀
PTSD / CPTSDについて、伝えておきたいこと
25年くらい診断が出なかったのは、 PTSDとかCPTSDに詳しい医師が日本には本当に少ないから。どの病院も薬はくれるけど一時しのぎの手段で、それだと治らない。
(主語でかいのでは、と思う人がいるかもしれないけど、25年の間に全国の10人以上のカウンセラー、10以上の病院にかかっての現在の状態だということは伝えておきたい。ものすごい金と時間をかけているので父親にも散々金食い虫だと責められた結果である)
⠀⠀ かつ、日本では私のような人はメンヘラとかで雑に括られたり、「そんなのどうでもいい(興味ない)」「被害妄想」「お前にも落ち度がある」とか言われがちで、安心して誰かに話したり頼れる居場所が本当に少ないと思う。ふとした言動が原因で、意識とは無関係に心のシャッターが降りてしまうこともあって、私でさえ、同じ症状をもつ人を深く傷つけてしまったことがある。
⠀⠀ もし誰かに辛さを打ち明けられた時、どうかアドバイスや意見は脇に置いて、まずは静かに話を聞いて受け止めてあげてほしい。
誰かの話を聞くことって実は思ってる以上に誰かのことを救ってて、私もそういう人のおかげで今日までなんとか生きてるので、話を聞いてジャッジせずに淡々と受け止めてくれた人たちには感謝してもしきれない。 ⠀⠀
あと、私みたいなことは予想外の事件・事故・継続的な暴力体験などで意外と誰にでも起こる可能性がある。
もし辛いことがあった時、話を最後まで聞いてくれる人がいるなら、辛いと言葉にして話してほしいし、それが無理なら自分のためだけに最大限の時間を割いて欲しい。辛さは言葉にできるまで癒されないでずっと残るし、ひどいと怒りになって、それを誰かにぶつけてその人がトラウマを負うことで負の連鎖になったりもする。
Outro: 最後に
長文だし言いにくい話なので口に出すのをずっとためらってたけど、こういう話は言わないと病気の存在も含めて永遠にわかってもらえないものだ、というのを日本に帰国して骨身に染みて感じたので書くことにした。
見た目めっちゃ普通な人にも、なんならチャラチャラしてそうな人にも実は色々傷がある、なんてことは結構普通にあるはずなので、特に目に見えにくい精神的なものについては、無意識の差別や偏見が少しでも減って欲しい。誰しもの考え方とか生き方が尊重されるべきだと思う。この話に違和感を持つ人だったり、ジャッジメンタルなマインドセットで向かってくる人とはもう付き合えないな、とも思う。
偉そうなこと言ってるのは承知だけど、いち当事者としての体験として伝えておきたい。最後まで読んでくれた方、本当に感謝です。
0 notes
Text
TEDにて
マーク・パーゲル:言語能力が人類に与えた影響について
(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)
生物学者マーク・パーゲルは「どうして、人間は、言語という複雑なシステムを発展させたのか?」という問いに対して、面白い学説を紹介します。
聖書にも、始めに言葉ありき!と書いてあるように、言語は、一種の「社会的技術」であり、その発明のおかげで、原始人たちが「協力」という新しい強力な道具を手に入れることができた。
と彼は、歴史的事実を源にして、主張します。
ここで言われる「Powerパワー」は(スターウォーズでのライトサイドのForceフォース)そして、「Forceフォース」は(ダークサイトの方)という前提です。
自分が、触らないのに物が動かせます。食料を獲得できます。もちろん、魔法のように、貨幣も産み出せます。
何度も同じことを繰り返して、口腔の中で調音された振動で!!です。また、様々な多岐に渡る活用法も確認されています。
共通言語がないとアイデアの交流を遅らせ、技術の交流も遅らせてしまいます。
技術的な標準化も同じことです。
人間は、物が創造できるがために、ここまで発展できました。と同時に、アイデア、イノベーションの活用法や根本的な解決方法も提示しています!
細胞間のコミュニケーションでは、化学反応を言語に見立てて細胞は情報を相互作用させています。
人間のコミュニケーションも同様に、空気の断続的なパルス波の振動で、情報を相互作用させています。
なぜでしょうか?妙に、似ていますね。
皆さんには、自然淘汰が生み出した破壊的で、危険な力強い特徴が備わっています。聴覚神経系技術で、他人の脳をいくらか操作できます。
もちろん、自然言語の話をしています。
言語を使用することで、皆さんは、外科手術もなしに移植ができるのです。移植するのは、「考え」ですけどね。
皆さんだって、その対象になりえます。その代わり、テレビに対して、リモコンを使うのと似ていますが、皆さんが、話す時には、ある種の遠隔測定法が使われています。
こんな感じで、リモコンは、赤外線を利用していますが、自然言語には、断続的なパルス波が利用されます。
気分に合わせて、リモコンでテレビの設定を変えるように、言語を通じて、自分の利害に合わせて、他人の脳のセッティングを変えることができます。言語とは、遺伝子の会話であり、何かを取得するためのものです。
ただ、声を出すだけで、赤ん坊が、魔法のように物を動かせたり、食べ物を口に運べたときの驚きの具合を想像してみて下さい。
言語の持つ強大な力は、昔から認知されており、検閲で出版を禁じられたり、使用禁止表現や語句があるのはこのためです。
実際、一神教で聖書の中の「バベルの塔」は、言語のフォース(ダークサイトの方)に、警鐘を鳴らしている寓話です。
自惚れた古代人が、言語使用を通じて、協力すれば天国へ続く塔の建設が可能と考えた!というお話です。
権力を奪おうとする人類に怒り、神は、塔を破壊して、二度と建てられないように策を講じました。
人々を混乱させるために、異なる言語を与えたのです。
皮肉にも、言語の多様性は、意思疎通の妨げとなっています!!
今日でも、使用が禁止されている単語や言い回しが存在します。(ダークサイトの方)
これらを口にすれば、補導や投獄。更には、殺される可能性もあります(ダークサイトの方)
これらは、全て口の中で調音された気息なのです!!
なぜ、こんな事がわかるのか?それは、我々の先祖が、当にそうだったからです。
このホモエレクトスは、アフリカのサバンナで約200万年前に進化しました。彼らは、手にぴったりと合う素晴らしい手斧を作りました。
しかし、化石記録を見てみると、同じ手斧を何度も何度も100万年もの間作り続けていたのです。
化石記録を見れば分かりますよ。生息時期予測では、ホモエレクロスは、約4万世代続きましたが、その間にも、手斧は変化しませんでした。
遺伝子的に現代人に近いネアンデルタール人でさえ、社会的学習能力を備えていたかどうか不明です。
当然、彼らの道具は、ホモエレクトスのものより、発達を遂げていますが、ユーラシア大陸で、30万年以上も暮らしてきたネアンデルタール人の道具にも、ほとんど変化は見られません。
ですから、20万年ほど前、この視覚的窃盗問題に直面した際に、人類がいざこざを解決するために、取りえた選択肢は2つしかありませんでした。
1つ目の選択肢は、アイデアの利用範囲を親族だけに制限すること!でした。
20万年前、この選択をしていたら、2万年前に、ヨーロッパ進出を果たしたネアンデルタール人と現代人の生活様式は、同じものとなっていたでしょう。
この原因は、小さい集団の中では、アイデアや革新が少ないことにあります。
もう一方の選択肢は、コミュニケーション手段を発達させて、他人と協力したり、アイデアを共有することでした。
こちらを選択すると、身内や個人のみで思いつく量より、はるかに多い蓄積された知識や知恵が、どの個々、人にとっても利用可能なものとなります。まあ、こちらを選択したのですが、その結果、言語が生まれました。
進化を遂げた言語は、視覚的窃盗問題を解決しました。
言語というのは、合意を得たり、契約や団体行動をまとめたりと協力という利を拡大するための社会技術の一種なのです。
どうやら、言語の使用目的は、協力だけにとどまらず、集団の輪を作り出したり、アイデンティティの確立。
自分たちの情報・知恵・技術の盗用保護と多岐にわたります。
でも、日本では、国民にマスメディアを使用して巧妙に情報操作している可能性が色濃くあります。再編して改善かな?
テレビなどは、アーカイブで追跡調査できるから倫理委員会に依頼するのも東京地検が抜き打ち調査しても良いかも知れません。
今ではテレビ局も権力者!
日本のテレビ局は再編すべき!一度、国に返上して、車と同様に放送免許停止や放送免許取消を導入すべきです。
もう一度言います!
テレビ局も今では権力者!再び、過ちを繰り返すかもしれません!
(合成の誤謬について)
合成の誤謬とは、ミクロの視点では正しいことでも、それが、合成されたマクロ(集計量)の世界では、必ずしも意図しない結果が生じること。物理学では、相転移みたいな現象です。性質が変わってしまうということ。
ミクロのメカニズムが個人同士の経済における仕組みであるのに対して、マクロのメカニズムは、国家間や経済全体の循環における仕組みだからである。
例えば、家計の貯蓄などがよく登場するが悪い例えです。前提条件が、所得が一定の場合!!所得が一定じゃない増加する場合は?これは、論じていませんので参考になりません!!(法人が提供する製品やサービスの価格も一定の場合も前提条件です)
1930年代のアメリカ経済が金融危機2008と似たような状態に陥った時、ケインズは、「倹約のパラドックス」というケインズ経済学の法則を発見しています。
それは、ポール・A・サミュエルソン(1915-2009)が、近代経済学の教科書「経済学」の冒頭で「個人を富裕にする貯金は、経済全体を貧困にする!(所得が一定の場合)」というわかりやすい言葉で表現しました。しかし、庶民の所得が増加し、貯蓄が投資、消費に回る場合には、「倹約のパラドックス」は生じません。
その後、この「倹約のパラドックス」は、アメリカの経済学者・ケネス・J・アロー(1921- )が「合成の誤謬」を数学的論理に基づいて「個人個人がそれぞれ合理的選択をしても、社会システム全体は合理的選択をするとは限らない」を検証してみせた。 要するに、部分最適ではなく、全体最適させていくということ。
つまり、新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との 戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど
しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!ということに集約していきます。
なお、金融危機2008では、マイケル・メトカルフェも言うように、「特別資金引出権(SDR)」は、2008年に行われた緊急対策で、一国だけで行われたのではなく、驚くほど足並みの揃った協調の下に国際通貨基金(IMF)を構成する188ヶ国が各国通貨で総額2500億ドル相当を「特別資金引出権(SDR)」を用いて世界中の準備通貨を潤沢にする目的で増刷してます。
このアイデアの根本は、元FRB議長であったベンバーナンキの書籍「大恐慌論」です。この研究がなければ、誰一人として、変動相場制での当時の状況を改善し解決できなかったと言われています。
それ以前では、固定相場制でのマーシャルプランが有名です。
続いて、トリクルダウンと新自由主義
インターネットの情報爆発により隠れていた価値観も言葉となり爆発していくことになった。
しかし、法定通貨の方が、その価値、概念に対する通貨量拡大として価格で応じることができず、圧倒的に通貨量が足りない状況が生まれていたのが、2010年代の問題点のひとつでした。
リーマンショックの後に、新自由主義が誤りであることが、ピケティやサンデルによって指摘され、当時のFRBバーナンキ議長が、通貨供給量を大幅に増やした対策により、ベースマネーの金融、銀行間の相互不信を解消して収束した。
それでも、まだ足りないが、適正水準に収まったことで、さらに価値も増幅され、マネーストックの財政政策から再分配、事前分配を大規模に行い、さらなる通貨供給量が重要となっている現在の日本国内。
例えば
Googleがしようとしてた事は、まだ新産業として、基礎研究から発展できない機械学習の先端の成果をすべて持ち込んだ社会実験に近いこと。
シュンペーターの創造的破壊は、一定数の創造の基礎を蓄積後に、未来を高密度なアイデアで練り上げてから破壊をするのが本質です。
こうして、憎しみの連鎖や混乱を最小限にする。
アルビン・トフラーの言うように、法人と行政府とのスピードの違いが縮まらないのは、構造上��違いであって、それを補うためにプラスサムな連携するということが、必要になってくることを説いています。
三権分立が、規制のないGAFAMを非政府部門としてMMT(現代貨幣理論)からプラスサムに連携したらどこで均衡するのか?という社会実験も兼ねています。
このような前提で、あらゆるインターネット企業が、創業時、貢献するためコンセプトの中心であったものが、今では、悪性に変質して違う目的に成り下がっています。
再分配、事前分配の強化がスッポリ抜けてる欠点があり、ここに明かしたくないイノベーションの余地があります!!
2021年には、新自由主義のような弱肉強食では自然とトリクルダウンは生じないことは明らかになる。
確かに、トリクルダウンは発生しないが、法律で人工的に同じ効果は、貨幣の再分配、事前分配という形にできる可能性は高い。
再分配や事前分配をケムにまく「金持ちを貧乏にしても、貧乏人は金持ちにならない」「価値を生み出している人を罰するつもりがないのであれば税に差をつけないほうがいい」(サッチャー)
とあるが、新自由主義は誤りで、ピケティやサンデルによると違うみたいだ。
2024年のノーベル経済学賞でも指摘しているように・・・
国家システムが繁栄するかどうかは、幅広い政治参加や経済的な自由に根ざす「包括的な制度(ポジティブサム)」の有無にかかっているとデータでゲーム理論から実証した。
欧州諸国などによる植民地支配の時代のデータを幅広く分析し、支配層が一般住民から搾取する「収奪型社会(ゼロサム)」では経済成長は長く続かない(収穫遁減に陥る?)
一方、政治や経済面での自由や法の支配を確立した「再分配や事前分配を同時に行う包括型社会(ポジティブサム)」なら長期の成長を促すと理論的に解明した(乗数効果とは異なる経路の収穫遁増がテクノロジー分野とシナジーしていく?)
「再分配や事前分配を同時に行う包括型社会(ポジティブサム)」は、日本の高度経済成長時代のジャパンミラクルが、一度、先取りして体現しています。
2020年代からはもう一度、ジャパンミラクルが日本で起こせる環境に入っています。安倍総理が土台、管、岸田総理が再分配や事前分配の包括型社会(ポジティブサム)の土台を形成しつつあります。
日本の古代の歴史視点から見ると・・・
安土桃山から江戸幕府初期の農民出身徳川家康が国際貿易を促進しつつ再分配や事前分配の包括型社会(ポジティブサム)を形成してます。
その後、大航海時代の覇権争いを避けるため数代かけて「収奪型社会(ゼロサム)」になってしまい、綱吉の頃には基本的人権の概念も希薄になり選挙もないため
低収入者の農民から商人も収奪していきます。
江戸幕府末期まで数度改革をしましたが、ノーベル経済学賞の人達によると包括型社会(ポジティブサム)に転換しずらい
結局、薩摩と長州が徳川家康式の国際貿易のイノベーションを復活させるも(水戸藩の文献から)国民主権の憲法や選挙がないため
明治維新を起こすしかなく、第二次大戦で原爆が投下されるまで軍備拡大して資源が枯渇します。
国家システムの独裁から法人や個人の優越的地位の乱用にすり替わるため、財産権や特許権などを含めた低収入者の基本的人権を尊重することで独占禁止法の強化も必要になっていくことも同時に示しています。
(個人的なアイデア)
複雑性の研究からも、個人の才覚に関係なく貧富の差は生じる。
超裕福層に集中するとマネーに渋滞が生じるため、税金をかけることと現象が似ている。
こうすると平等性が増すと結果も出ている。
確かに、トリクルダウンは発生しないが、法律で人工的に同じ効果は、貨幣の再分配、事前分配という形にできる可能性は高い。
課税は、ネットワークに何本かのリンクを人工的に加えることと同義ということも、複雑性の研究からデータで明らかになっています。
日本は、消費税の運用など。課税は、強制的な交換の一形態。この知見は、MMT(現代貨幣理論)にも導入されてる。
複雑性の研究から産まれた従来とは異なる新しいマクロ経済学です。テーラワーダ仏教概念にもある欲を中和するツールとも言えます。
幸田露伴?分福?
人工的な課税をしないと、この歪みがエネルギーとして形態が相転移するので、超裕福層一族たちの幸福感が変質して心の歪みに転換していく。
人間が、一日に扱える時空間は、限定的に対して、お金はマルチバースでエネルギーが交換されるので、人間の一日で扱える許容量を超えてしまう。
ナポレオンヒル?エンスージアズム?そこには引き返せない一線というか?境界線があって、耐えられれば良いが、知らない方が幸せな場合も多々あります。
日本には古来から同様の概念があり、成金や悪徳商人とも言われる場合もある。
600万円以下に貨幣の再分配、事前分配することで社会システムの安定が強化される。
ダニエルカーネマン。詳しくは、論文を見ていただいて、日本の実情を深く考えた年収として記載しています。
直訳を指摘しても、未来を描けない人々なので、みんなは心の中で、あぁ残念な人なんだと軽蔑して下さい。
メリトクラシー至上主義、競争主義社会システム新自由主義を古代中国から、たとえて簡単に言うと乱世。
意図して均衡させて、奸��は排除していくことが鉄則。カントの永遠平和を実現が重要に。
つまり、IT産業長者は、乱世の奸雄。テロ抑止にもなる現代では、競争時代の奸雄を排除することと同様の概念になります。
これも教科書に載らない歴史でもあります。
競争時代の乱世の奸雄たちが、本来の趣旨を歪めて異なる方向に変わってしまう傾向は多々あります。
これによって・・・
「パワーかフォースか」の本で言うところの「パワー(ライトサイドのフォース)」の高まりが落ちてしまいます!!
東洋では・・・
古代中国の歴史でも「乱世の奸雄」で有名な「曹操」が歪めてしまい「司馬懿仲達」が苦労して統一するまで。などは有名です。
他の非中国系の西洋の記録は、残っているかわかりません・・・権力者が書き換えている可能性も多々あります。
GAFAMなどのプラットフォームのビジネスで本来の趣旨が歪み、思い違いされていますが・・・
TED ロン・マッカラムも言うように・・・
規格を統一することで、あらゆる視覚障害者用のコンピューターや機械からアクセス可能にするためです(低収入者も含む)
これが、インターネットの本来の原点です!
これが、インターネットの本来の原点です!
これが、インターネットの本来の原点です!
Appleなどは、「アクセシビリティ」などの設定で原点を忘れていません!!
それ以外は、Googleなどは、トランスフォーマーアルゴリズムが有名になりましたが・・・
他の無名の基盤技術などの開発で貢献しています。
そして
2021年では、自動運転車が登場しています。
Appleシリコンでも、メモリ主導型のアーキテクチャーに変更しています。
量子コンピューターや量子超越性もメモリが重要な要素でもあります。
これは、兆し。始まりにすぎません!!不思議と「風の時代」と連動してます。
2020年後半くらいから様々な占いで出てきてた時代の変わり目。それが、西洋占星術で具体的に「風」の時代という形で出てきました。
私が、感じとってたインスピレーションは、たぶんこれかな?
兆しは、世界的な金融ビックバンの1970年代、IT革命のミレニアムの前から出ていたけど。
これは、これまでの約200年間。物質やリアリティの影響力優位「土」の属性の時代から、量子コンピューター、ビットやインターネットなどといった物質ではないものに影響力が増していく「風」の属性の時代に。
そして、本格的に軌道にのっていく属性は、今後200年程続くことになるのです(2020年12月22日から、2100年当たりをピークに少しずつ衰退していく2220年まで)
100兆円以上も稼いでいるなら・・・
そろそろインターネットの本来の原点に戻って、他のプラットフォーマー法人も事前分配や再分配をして低収入者に貨幣で還元してもいい頃かもしれません。
古代中国の「史記」にも戦国四君(古代中国で活躍した4人の武将の物語)で現代までの歴史の良い手本として二千年近く残ってます。
たしか、食客に諭されて「こんな国家の存亡の際に私財を溜め込んでいるのに、なぜ?それを低収入者に事前分配や再分配をしないのか?」
という助言に心を打たれて私財を全て投げ撃ちしたことで低収入者が奮起して国家の滅亡を阻止した!
さらには、当時最強レベルのあらゆる武将でも打ち破ることができなかった。
と言う話があります。
「パワーかフォースか」の本で言うところの「パワー(ライトサイドのフォース)」が高いからかもしれません!!
これも教科書に載らない歴史でもあります。
私は政治に全く興味がありません。テクノロジーに興味があります。
現在進行中の「移民による移民のための社会実験国家」がアメリカです。
現在進行中の「移民による移民のための社会実験国家」がアメリカです。
現在進行中の「移民による移民のための社会実験国家」がアメリカです。
金融の概念で分けられてはいる名称だが、既存通貨に色は付かないので行政府が勝手に決めてる概念という前提で以下に展開します。
1、贈与。2、寄付。3、金融の貸付。
違いは、言葉の定義。 1、親族内。 2、他人同士で金利ゼロ返済不要。行政府経由なら「給付」という言葉の定義になる。サンデルの言う強者から弱者にマネーが100%流れれば善悪ない。 3、他人同士で金利ゼロか有りの返済付きで場合によりマイナス金利もある。
この場合、既存通貨は、追跡できないことが問題点。弱者をしつこく追跡することは法律違反で独占禁止法の優越的地位の乱用になります。通貨や人間が悪いわけではない場合が多い。
なら、政治資金規正法改正して、既存通貨の他に追跡できるデジタル通貨の形式で政治家限定で歳費支給したらどうなるだろうか?現状の歳費支給にプラスしてデジタル通貨分もプラスするから給与アップになる。追跡できるから不正もできない。
政治家への既存通貨での寄付は厳格に条件を決めた範囲内で政治資金規正法で透明化するのはいいこと。現実的に現状このルートは、デジタル通貨にせず、日本の場合は検察当局の存在理由も維持するためもあります。将来的にはデジタル通貨に完全移行が望ましいけど。
政治家からの既存通貨での弱者個人(選挙区内)への寄付は、自らの裁量で年収の低い弱者(選挙区内)だけに行うなら善性に沿うかもしれない。法律化しても問題ない。こちらも将来的には、デジタル通貨なら自動で透明化、効率化できます。
なお、国内の格差縮小にも貢献できるだろうし、万が一、強欲大中法人が賃金を下げてしまっても政治家が下支えできるという政治家本能やお互いの幸福も社会システムに組み込めます。
政治家から弱者低収入個人への寄付は概念では分配だと思うが、現行法では汚職?
法律が低収入庶民を苦しめる不思議?憲法違反?
さらに・・・
勝手に警察が拡大解釈してしまうと・・・
こんな恐ろしいことが・・・
日本の警察は、2020年3月から防犯カメラやSNSの画像を顔認証システムで本人の許可なく照合していた!
憲法に完全違反!即刻停止措置をみんなで要求せよ。
日本の警察の悪用が酷いので、EUに合わせてストーカーアルゴリズムを規制しろ!
2021年に、EU、警察への初のAI規制案!公共空間の顔認証「原則禁止」
EUのAI規制は、リスクを四段階に分類制限!
前提として、公人、有名人��俳優、著名人は知名度と言う概念での優越的地位の乱用を防止するため徹底追跡可能にしておくこと。
禁止項目は、行動や人格的特性に基づき警察や政府が弱者個人の信頼性をスコア化や法執行を目的とする公共空間での顔認識を含む生体認証。
人間の行動、意思決定、または意見を有害な方向へ操るために設計されたAIシステム(ダークパターン設計のUIなど)も禁止対象にしている。
禁止対象の根拠は「人工知能が、特別に有害な新たな操作的、中毒的、社会統制的、および、無差別な監視プラクティスを生みかねないことは、一般に認知されるべきことである」
「これらのプラクティスは、人間の尊厳、自由、民主主義、法の支配、そして、基本的人権の尊重を重視する基準と矛盾しており、禁止されるべきである」
具体的には、人とやり取りをする目的で使用されるAIシステム(ボイスAI、チャットボットなど)
さらには、画像、オーディオ、または動画コンテンツを生成または操作する目的で使用されるAIシステム(ディープフェイク)について「透明性確保のための調和的な規定」を提案している。
高リスク項目は、法人の採用活動での利用など違反は刑事罰の罰金を売上高にかける。
など。他、多数で警察の規制を強化しています。
人間自体を、追跡すると基本的人権からプライバシーの侵害やセキュリティ上の問題から絶対に不可能です!!
これは、基本的人権がないと権力者が悪逆非道の限りを尽くしてしまうことは、先の第二次大戦で白日の元にさらされたのは、記憶に新しいことです。
マンハッタン計画、ヒットラーのテクノロジー、拷問、奴隷や人体実験など、権力者の思うままに任せるとこうなるという真の男女平等弱肉強食の究極が白日の元にさらされ、戦争の負の遺産に。
基本的人権がないがしろにされたことを教訓に、人権に対して厳しく権力者を監視したり、カントの思想などを源流にした国際連合を創設します。他にもあります。
参考として、フランスの哲学者であり啓蒙思想家のモンテスキュー。
法の原理として、三権分立論を提唱。フランス革命(立憲君主制とは異なり王様は処刑されました)の理念やアメリカ独立の思想に大きな影響を与え、現代においても、言葉の定義を決めつつも、再解釈されながら議論されています。
また、ジョン・ロックの「統治二論」を基礎において修正を加え、権力分立、法の規範、奴隷制度の廃止や市民的自由の保持などの提案もしています。現代では権力分立のアイデアは「トリレン��」「ゲーム理論の均衡状態」に似ています。概念を数値化できるかもしれません。
権限が分離されていても、各権力を実行する人間が、同一人物であれば権力分立は意味をなさない。
そのため、権力の分離の一つの要素として兼職の禁止が挙げられるが、その他、法律上、日本ではどうなのか?権力者を縛るための日本国憲法側には書いてない。
モンテスキューの「法の精神」からのバランス上、法律側なのか不明。
立法と行政の関係においては、アメリカ型の限定的な独裁である大統領制において、相互の抑制均衡を重視し、厳格な分立をとるのに対し、イギリス、日本などの議院内閣制は、相互の協働関係を重んじるため、ゆるい権力分立にとどまる。
アメリカ型の限定的な独裁である大統領制は、立法権��行政権を厳格に独立させるもので、行政権をつかさどる大統領選挙と立法権をつかさどる議員選挙を、別々に選出する政治制度となっている。
通常の「プロトコル」の定義は、独占禁止法の優越的地位の乱用、基本的人権の尊重に深く関わってきます。
通信に特化した通信プロトコルとは違います。言葉に特化した言葉プロトコル。またの名を、言論の自由ともいわれますがこれとも異なります。
基本的人権がないと科学者やエンジニア(ここでは、サイエンスプロトコルと定義します)はどうなるかは、歴史が証明している!独占独裁君主に口封じに形を変えつつ処刑される!確実に!これでも人権に無関係といえますか?だから、マスメディアも含めた権力者を厳しくファクトチェックし説明責任、透明性を高めて監視しないといけない。
今回、未知のウイルス。新型コロナウイルス2020では、様々な概念が重なり合うため、均衡点を決断できるのは、人間の倫理観が最も重要!人間の概念を数値化できないストーカー人工知能では、不可能!と判明した。
複数概念をざっくりと瞬時に数値化できるのは、人間の倫理観だ。
そして、サンデルやマルクスガブリエルも言うように、哲学の善悪を判別し、格差原理、功利主義も考慮した善性側に相対的にでかい影響力を持たせるため、弱者側の視点で、XAI(説明可能なAI)、インターネット、マスメディアができるだけ透明な議論をしてコンピューターのアルゴリズムをファクトチェックする必要があります。
<おすすめサイト>
マイケル・サンデル:メリトクラシー(能力主義)の横暴
アニル・セス: 脳が「意識された現実」という幻覚を作り出す?
アイザック・リッズキー:あなたはどんな現実を生み出しているのか?
ポエト・アリ:「人間(じんかん)であること」という言語
ウリ・ハッソン:コミュニケーション中の脳の反応
レラ・ボロディツキー:言語はいかに我々の考えを形作るのか
ロジェカイヨワ戦争論と日本の神仏習合との偶然の一致について2019
Japan TV of Secret(日本のテレビの秘密)Kindle版
バリー・シュワルツ:選択の自由パラドックスについて語る
グレン・グリーンウォルド: なぜプライバシーは重要なのか!
マーク・フォーサイス: 政治における言葉について
ユバル・ノア・ハラーリ:人類の台頭はいかにして起こったか?
スティーブン・ピンカー:言語と思考の関係
<提供>
東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント
独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです
東京都北区神谷高橋クリーニング店Facebook版
#マーク#パーゲル#言語#都市#伝説#マスメディア#テレビ#脳#シナプス#ニューロン#概念#システム#人類#言葉#量��#政治#細胞#通信#秘匿#アイデア#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery
0 notes