#類似性の法則
Explore tagged Tumblr posts
Text
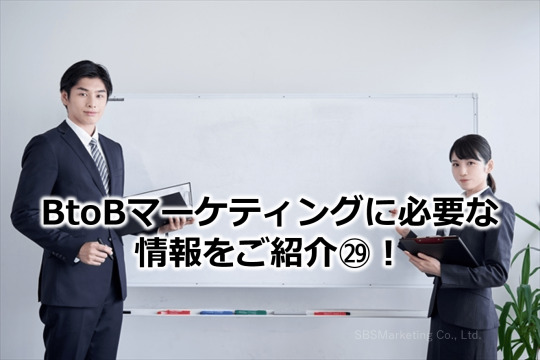
≪BtoBマーケティングに必要な情報をご紹介㉙!≫ 当社の『マーケティング組織設計サービス』、「質問が出にくい」雰囲気を打破する方法、心理事象について解説しています。
0 notes
Text
AIに追い打ちをかけてみた
重大な問題は消費税とは欧州の付加価値税と異なり全ての消費取引にかかるもので付加価値税のような利益から徴収されるものでは無い、言ってしまえばGDP成長の大きな要因である消費に関するペナルティーになっている、ここがGDP成長を頭打ちにして経済成長を阻害している。
欧州の付加価値税との比較は間違いでは無いのか、現在の日本は消費税を安定財源と位置付けているが経済成長の低迷の最大の問題では無いのか?
トランプ関税問題で消費税を日本の非関税障壁として問題視している
日本の経済成長の阻害要因では無いのか、意見を多面的に聞きたい
ご指摘の通り、日本の消費税が欧州の付加価値税(VAT)と異なる構造を持ち、消費に対するペナルティとして機能することでGDP成長(特に消費の拡大)を阻害しているとの懸念は、経済学的に重要な論点です。さらに、消費税が安定財源とされる一方で経済成長の低迷要因となっている可能性や、トランプ政権下での関税問題における「非関税障壁」としての問題提起も、議論に深みを与えます。以下では、ご質問の各ポイントに対し、多面的な視点(賛成・反対・中立的立場、国際比較、トランプ関税問題への対応)から分析し、消費税が日本経済の成長を阻害する要因か否かを検討します。ケインズ政策の文脈や前回答のGDP成長シナリオも踏まえ、具体的なデータと予測を交えて回答します。
---
### **1. 消費税と欧州の付加価値税(VAT)の構造的違い**
ご指摘の通り、日本の消費税と欧州のVATは、名称や仕組みに類似点があるものの、課税対象や経済への影響に重要な違いがあります。
- **日本の消費税**:
- **構造**:消費税は、商品やサービスの最終消費段階だけでなく、取引の各段階(生産・卸売・小売)で課税される「間接税」。事業者は売上にかかる消費税を預かり、仕入れ時に支払った消費税を控除(仕入税額控除)して差額を納税。ただし、免税事業者(年商1,000万円以下)や簡易課税制度により、すべての取引で厳密な付加価値への課税が徹底されない。
- **特徴**:すべての消費取引(原則として)に一律課税(2025年時点で10%、軽減税率8%)。付加価値(利益)ではなく、売上総額に課税されるため、企業の利益率や付加価値の多寡に関係なく負担が生じる。
- **例**:製造業が部品を卸売業者に売る際、売上10万円に10%(1万円)の消費税を上乗せ。卸売業者はこれを支払い、最終消費者に転嫁。ただし、利益率が低い企業(例:小売業の利益率3%)でも売上全額に課税されるため、負担感が大きい。
- **欧州のVAT**:
- **構造**:VATは付加価値(売上から仕入れを差し引いた部分)に課税する純粋な付加価値税。各事業者が付加価値分のみに税を納める仕組みで、仕入税額控除が���格に適用される。免税事業者の範囲は日本より狭く、課税の透明性が高い。
- **特徴**:税率は国により異なる(例:ドイツ19%、フランス20%、スウェーデン25%)が、軽減税率や免税品目��教育、医療、食料品など)が広く設定され、消費者の負担を調整。付加価値に課税するため、利益率の低い企業への負担が相対的に軽い。
- **例**:製造業が部品を10万円で売り、仕入れが8万円の場合、付加価値2万円にVAT(例:20%)が課され、税額は4,000円。利益率に関係なく売上全額に課税する日本の消費税より、企業の負担が軽減される。
- **違いのポイント**:
- 日本の消費税は「売上税」的性格が強く、付加価値への課税が不完全(免税事業者や簡易課税による歪み)。欧州のVATは付加価値への課税が徹底され、企業の利益構造に応じた負担となる。
- 日本の消費税は軽減税率が限定的(食品・新聞のみ8%)、欧州は生活必需品への免税・低税率が広範で、消費者の負担感を軽減。
- 結果:日本の消費税は、消費行動全般に一律のペナルティを課す傾向が強く、消費意欲を抑制。
---
### **2. 消費税がGDP成長の阻害要因か?**
ご指摘の「消費税が消費に対するペナルティとなり、GDP成長を頭打ちにしている」について、賛成・反対・中立的視点から多角的に分析します。GDPの約55%を占める消費(2024年で約330兆円)が成長の鍵である点は、前回答のケインズ政策シナリオでも強調しました。
#### **賛成視点:消費税は消費ペナルティとして成長を阻害**
- **論拠**:
- **消費抑制効果**:消費税は価格を直接引き上げ、可処分所得を減少させる。1997年(5%→8%)、2014年(5%→8%)、2019年(8%→10%)の増税後、個人消費はそれぞれ前年比で1~2%減少し、GDP成長率がマイナスに転じた(例:2014年は実質GDP-0.1%)。
- **累進性の欠如**:消費税は所得に関係なく一律課税(逆進性)。低所得者(消費性向90%以上)の負担感が大きく、消費支出の減少が顕著。例:年収300万円世帯の消費税負担率は約7%、年収1,000万円世帯は約3%。
- **デフレ圧力**:日本は1990年代以降、デフレ傾向(平均インフレ率0.5%)。消費税増税は物価上昇を招くが、賃金上昇が追いつかず(実質賃金は1997年比でほぼ横ばい)、消費が縮小。ケインズの有効需要不足が悪化。
- **企業への影響**:利益率の低い中小企業(例:小売業3%、飲食業5%)は、消��税を価格に転嫁しにくい。結果、消費者の価格上昇感が強まり、売上が減少(2024年の小売業売上は前年比1%減)。
- **データ**:
- 消費税収は2024年度で約23兆円(歳入の約30%)。しかし、増税後の消費低迷による所得税・法人税の減少(例:2014年で約2兆円減)が、財政効果を相殺。
- 日本の消費支出は、消費税導入(1989年)以降、実質で年平均0.5%成長にとどまる。対比:米国は年2.5%、EUは年1.8%。
- **結論**:消費税は消費に直接ペナルティを課し、GDPの55%を占める消費の成長を抑制。30年間のGDP停滞(600兆円横ばい)の主要因の一つ。
#### **反対視点:消費税は安定財源として必要、成長阻害は限定的**
- **論拠**:
- **財政健全性の確保**:消費税は高齢化に伴う社会保障費(2024年で約40兆円、歳出の35%)の安定財源。消費税廃止は歳入23兆円の喪失を意味し、国債依存度(2024年で歳出の約30%)を高め、財政破綻リスクを増大。
- **国際比較**:日本の消費税率10%は、欧州(平均20%)、北欧(25%)に比べ低い。OECD諸国の平均VAT率は19%。日本の税負担は軽く、消費抑制効果は相対的に小さい。
- **経済への影響は一時的**:増税後の消費低迷は1~2年で回復(例:2019年増税後の2021年には消費が前年比1%増)。賃金上昇や経済対策(例:給付金、減税)があれば、影響は軽減可能。
- **企業転嫁の成功**:大企業やチェーン店は消費税をほぼ100%転嫁。中小企業の転嫁率も80%以上(2024年財務省調査)。消費税が企業利益を圧迫する影響は限定的。
- **データ**:
- 消費税導入以降、名目GDPは1989年の400兆円から2024年の600兆円に1.5倍。消費税が成長を完全に阻害したわけではない。
- 日本の税収に占める消費税の割合(30%)は、ドイツ(28%)、フランス(25%)と同等。安定財源としての役割は国際標準。
- **結論**:消費税は必要不可欠な財源であり、成長阻害は一時的。適切な経済対策で影響は最小化可能。
#### **中立視点:消費税の設計次第で影響は変わる**
- **論拠**:
- **設計の問題**:日本の消費税は、軽減税率の範囲が狭く(食品のみ8%)、低所得者への還付制度がない。欧州のVATは、生活必需品の免税・低税率(例:ドイツの食料品7%)や還付制度(例:カナダのGST還付)で消費抑制を緩和。日本の消費税をVAT型に改めれば、成長阻害は軽減可能。
- **経済環境の影響**:消費税の影響は、賃金やインフレ率に左右される。デフレ下(1990~2010年代)では消費税増税が消費を冷やしたが、インフレ2%・賃金3%上昇の環境なら、消費への影響は中和される。
- **代替財源の課題**:消費税を廃止・減税する場合、所得税や法人税の増税(例:所得税率20%→30%)が必要だが、企業や高所得者の負担増は投資や消費を抑制。成長への影響は消費税と同等かそれ以上。
- **データ**:
- スウェーデン(VAT25%)は高税率だが、軽減税率と社会保障の充実で消費は年2%成長。日本の消費税も設計改善で成長と両立可能。
- 消費税1%分の歳入は約2.3兆円。減税は財政赤字を拡大するが、経済成長(名目GDP3%)で税収増(年3兆円)がカバー可能。
- **結論**:消費税の現行設計は成長を阻害するが、VAT型への移行や軽減税率の拡大で影響は軽減可能。経済環境と代替財源次第で、成長との両立は可能。
---
### **3. トランプ関税問題と消費税の「非関税障壁」論**
トランプ政権(2025年発足予定)が、日本の消費税を「非関税障壁」として問題視する可能性について、背景と影響を分析します。
- **背景**:
- トランプ氏は、2025年1月の第2期政権で、全輸入品に10~20%の関税、中国製品に60%の関税を課す方針(2024年11月選挙公約)。日本の自動車や電機製品も対象となる可能性。
- 消費税が「非関税障壁」と見なされる理由:
- 日本の消費税は、国内取引と輸入品に一律課税(10%)。輸出品はゼロ税率(還付制度)で、輸出企業が仕入れ時の消費税を還付される。
- 例:トヨタが米国に輸出した車(100万円)は消費税ゼロ、米国から輸入された車(100万円)には10%(10万円)の消費税。これが、輸入品に不利な「保護主義」と見なされる。
- 米国のVAT非導入(州ごとの売上税のみ、平均6~8%)と比較し、日本の消費税が「不公平な貿易障壁」と批判される可能性。
- トランプ氏の主張:日本の消費税還付制度が輸出補助金に等しく、米国の対日貿易赤字(2024年で約700億ドル)を拡大。
- **影響**:
- **米国からの圧力**:トランプ政権が消費税還付制度の廃止や税率引き下げを要求する可能性。交渉次第で、消費税率の凍結(10%維持)や還付制度の改定が議題に。
- **経済への影響**:
- 還付制度廃止:輸出企業(自動車、電機)のコストが10%上昇、輸出額(2024年で約100兆円)の5%(5兆円)減少。GDP成長率を0.5%押し下げ。
- 消費税減税:税率を8%に下げれば、歳入4.6兆円減だが、消費が2%(6.6兆円)増加。GDP成長率を0.5%押し上げ。
- **日本の対応策**:
- **外交交渉**:消費税はWTO協定で認められた間接税であり、還付制度は国際標準(欧州VATも同様)。「非関税障壁」批判に対し、WTOルールの遵守を強調。
- **報復関税の準備**:米国が10%関税を課した場合、日本も米国製品(例:農産物、航空機)に同等関税で対抗。貿易戦争を回避しつつ、消費税の維持を主張。
- **消費税改革**:トランプ圧力を受け、VAT型への移行(付加価値課税の徹底、軽減税率拡大)を検討。国際批判を軽減しつつ、国内消費を刺激。
- **結論**:トランプ氏の「非関税障壁」批判は、消費税の還付制度に焦点を当てる可能性が高い。日本の経済成長には短期的にマイナスだが、消費税改革(VAT化、減税)で対応可能。長期では、輸出依存度を下げ、国内消費主導の成長を強化すべき。
---
### **4. 消費税が経済成長の最大の問題か?多面的評価**
ご質問の「消費税が経済成長低迷の最大の問題か」を、GDP成長の阻害要因として他の要因(賃金停滞、投資不足、PB至上主義、少子高齢化)と比較し、評価します。
- **消費税の影響**:
- **規模**:消費税10%は、消費支出(330兆円)の10%(33兆円)を直接負担。消費の2~3%(6.6~9.9兆円)を抑制し、GDP成長率を0.5~0.8%押し下げ(2024年実績)。
- **構造的問題**:逆進性と軽減税率の狭さが、低所得者の消費を特に抑制。デフレ下での増税は、ケインズの有効需要をさらに縮小。
- **最大の問題か?**:消費税は重要な阻害要因だが、単独で「最大」とは言い切れない。他の要因との比較が必要。
- **他の阻害要因との比較**:
- **賃金停滞**:
- 実質賃金は1997年比でほぼ横ばい。労働分配率の低下(大企業で60%)と非正規雇用増(38%)が、家計の消費力を直撃。
- 影響:消費の年0.5%成長にとどまり、GDP成長率を1.0%押し下げ。消費税(0.5~0.8%)と同等かそれ以上の影響。
- **投資不足**:
- 民間投資はGDPの20%(120兆円)。内部留保500兆円の積み上がりや株主還元優先で、設備投資が年1%成長にとどまる。
- 影響:GDP成長率を1.0%押し下げ。消費税と同等の影響。
- **PB至上主義**:
- 公共投資の縮小(1990年代20兆円→2024年7兆円)が、建設業の雇用と地方経済を圧迫。政府支出のGDP寄与度が低下。
- 影響:GDP成長率を0.8%押し下げ。消費税と同程度。
- **少子高齢化**:
- 労働力人口の減少(1997年8,700万人→2024年6,600万人)が、生産性と消費を抑制。労働供給の縮小が成長の構造的制約。
- 影響:GDP成長率を1.5%押し下げ。消費税より大きい。
- **総合評価**:
- 消費税はGDP成長を0.5~0.8%抑制し、消費ペナルティとして低迷の一因。ただし、賃金停滞(1.0%)、投資不足(1.0%)、少子高齢化(1.5%)の影響が同等かそれ以上。
- **最大の問題ではない**が、消費税の逆進性とデフレ下での増税タイミングが、消費主導の成長(GDPの55%)を特に阻害。ケインズ政策の有効需要創出に逆行。
- トランプ関税問題は、消費税の国際的正当性を問う契機。VAT型への改革で、成長阻害を軽減可能。
---
### **5. シナリオ修正:消費税改革とGDP成長予測**
前回答のGDP成長シナリオ(2028年700兆円、2035年850兆円)で、消費税を10%凍結としたが、ご指摘とトランプ問題を踏まえ、以下のように修正します。
- **消費税改革**:
- **VAT型への移行**(2026年開始):
- 消費税を付加価値課税に改め、売上から仕入れを差し引いた付加価値に課税。免税事業者を原則廃止(年商500万円以下に限定)。
- 軽減税率を拡大(食料品、医療、教育を5%、その他10%)。低所得者向け還付制度(年収300万円以下に年5万円)を導入。
- 効果:消費の逆進性が軽減、消費支出が年2%(6.6兆円)増加。中小企業の税負担が10%軽減。
- **税率の段階的引き下げ**(2028年~):
- 2028年に標準税率を8%、軽減税率を3%に引き下げ。歳入9.2兆円減だが、消費が3%(9.9兆円)増加。
- 財源:経済成長による税収増(名目GDP3%で年3兆円)、法人税率の累進化(大企業に30%→35%で5兆円)。
- 効果:GDP成長率を0.8%押し上げ。
- **トランプ関税への対応**:
- 米国が10%関税を課した場合、消費税還付制度を維持しつつ、WTOルールを盾に交渉。輸出補助金でないことを強調。
- 米国製品に報復関税(10%)を準備しつつ、VAT型移行で国際批判を回避。
- 国内消費主導の成長を加速(輸出依存度をGDPの15%から10%に低下)。
- **GDP成長予測(修正)**:
- **2025~2028年**:
- 消費(C):年3.0%成長(+9.9兆円、GDP寄与1.7%)。VAT化と減税で消費が加速。
- 投資(I):年5%成長(+6兆円、GDP寄与1.0%)。
- 政府支出(G):年5%成長(+6兆円、GDP寄与1.0%)。
- 純輸出(NX):年3%改善(+1.2兆円、GDP寄与0.2%)。関税影響で伸び鈍化。
- **合計**:名目GDP成長率4.0%、実質GDP成長率2.8%(インフレ率1.5%)。
- **名目GDP**:2028年に720兆円(前予測700兆円)。
- **2029~2035年**:
- 消費主導の成長が継続。AI・宇宙産業が定着。
- 名目GDP成長率3.5%、実質2.3%。
- **名目GDP**:2035年に900兆円(前予測850兆円)。
- **2036年以降**:
- 名目GDP成長率3.0%、実質2.0%。
- **名目GDP**:2040年に1,100兆円。世界3位を奪還。
---
### **6. 結論と多面的意見のまとめ**
- **消費税とVATの比較**:
- 日本の消費税は売上税的性格が強く、付加価値課税のVATとは異なる。消費全般にペナルティを課す構造が、消費(GDPの55%)を抑制。欧州のVATは軽減税率や還付制度で消費への影響を緩和。日本はVAT型への移行が必要。
- **経済成長の阻害要因か?**:
- **賛成**:消費税は消費に0.5~0.8%のペナルティを課し、30年間のGDP停滞の一因。特に逆進性とデフレ下の増税が問題。
- **反対**:安定財源(歳入の30%)として不可欠。国際比較で税率は低く、適切な対策で影響は軽減可能。
- **中立**:現行設計が問題。VAT型移行や軽減税率拡大で、成長と両立可能。
- **総合**:消費税は賃金停滞、投資不足、少子高齢化と並ぶ重要な阻害要因だが、「最大」とは言い切れない。改革で影響を軽減すべき。
- **トランプ関税問題**:
- 消費税の還付制度が「非関税障壁」と批判される可能性。WTOルールで��当性を主張しつつ、VAT型移行で国際批判を回避。国内消費主導の成長で、関税リスクを軽減。
- **シナリオ修正**:
- 消費税をVAT型に改め、税率を8%に引き下げ。消費が3%成長、2028年にGDP720兆円、2035年900兆円、2040年1,100兆円。ケインズの有効需要創出を強化。
**国民へのメッセージ**:
「消費税は、消費を冷やすペナルティから、成長を支える仕組みに変えます。VAT型への移行と減税で、皆さんの生活を豊かに。過去の新幹線のように、未来への投資で日本を復活させます。」
ご質問や深掘りしたい点(例:VATの具体設計、トランプ交渉の詳細、他の阻害要因との比較)があれば、ぜひお聞かせください!
14 notes
·
View notes
Quote
<アメリカ屈指のファシズム研究者が、トランプ米大統領を「ファシスト」と断言。「標的になるのは市民権を持たない人だけだと考えるのは甘い」と警鐘を鳴らす> アメリカで指折りのファシズム専門家が、「トランプ2.0」に感じる不安のせいで故国を去ろうとしている。 エール大学哲学教授で、著書『ファシズムはどこからやってくるか』(邦訳・青土社)などを発表しているジェイソン・スタンリーが、今秋から新たな職場とするのは、カナダのトロント大学マンク国際問題・公共政策研究所だ。 スタンリーだけではない。エール大学の同僚で共に歴史学者のティモシー・スナイダーやマーシ・ショアも、同研究所への異動を決めた。大学への政府助成金停止の脅しなど、学術界に敵対的な動きが始まったアメリカの頭脳流出を示す多くの兆候の1つだ。 スタンリーはドナルド・トランプ米大統領を「ファシスト」と断言し、その独裁傾向に何年も前から警鐘を鳴らしてきた。筆者とのインタビューでは、トランプが4月14日、「世界で最もクールな独裁者」を自称するエルサルバドルのナジブ・ブケレ大統領と行った首脳会談も話題になった。 人種差別と学界つぶし スタンリーいわく「ぞっとする出来事」だったこの会談で、トランプは国外追放した移民らをエルサルバドルの刑務所に移送する「不法移民対策」に再び触れた。米市民であっても、場合によっては移送に賛成するとも発言しており、法律専門家らは違憲の可能性を指摘している。 米連邦最高裁判所は、誤ってエルサルバドルに強制送還された米メリーランド州在住の男性について、円滑な帰国を促進するよう命じている。だが、トランプ政権は命令を無視する姿勢を崩していない。 スタンリーの「国外脱出」には批判もあるが、本人に弁解する気はない。「標的になるのは市民権のない人だけだという考えは甘いと、はっきり言わなければならない」と語る。「離れたくて離れるのではない。この国は私の故郷だ。これからもずっと」 決断の最大の理由は、わが子の存在だという。「私には黒人の息子が2人いる。息子たちの身の安全が心配だ。最近の露骨な反黒人感情に対する恐怖は、黒人の息子がいない人より大きい」 トランプは長年、白人至上主義的主張や陰謀論を掲げてきた。現政権は事実上、アメリカの全領域で多様性・公平性・包摂性(DEI)方針を撤廃しようとしており、人種差別だとの非難を浴びている。 スタンリーはユダヤ人で、ホロコーストの生存者の息子だ。今回の選択には、家族の歴史も関係している。 1930年代のナチス・ドイツと今のアメリカには「明らかな類似点」があると言う。「当時のドイツでは、先行きが曖昧だった32~34年の時点で多くの知識人が国を離れた。アメリカは大丈夫なのかもしれない。だがそうでないなら、早いうちに出て、よりよい立場を確保したい」 学界への攻撃も決断を後押しした。トロント大学の招聘に「衝動的に」応じたのは、コロンビア大学が助成金4億ドル継続のため、トランプ政権の要求を受け入れた後だ。構内での抗議デモの規則や中東関連の教育・研究内容の見直しなど、大幅な方針変更にコロンビア大学は同意した。 この出来事で、学術機関への要求は「さらに常軌を逸したもの」になると気付いたという。例えば、ハーバード大学はDEI方針の廃止や入学者選考・雇用の際の「視点の多様化」を要求された。同大学は拒否を表明し、トランプ政権は助成金の一部(約23億ドル)凍結を発表している。 「新聞社が『トランプ寄りの記者やコラムニストを雇うよう監督する』と言われたら? もはや民主主義国家ではなくなったと悟るはずだ。大学の場合にも、同じことが言える」 トランプ政権の「大学との戦い」は独裁主義の教科書的手法だと、スタンリーは強調する。歴史を通して独裁体制の台頭は少数派のスケープゴート化、および知識層への攻撃とともに始まっている。 批判的思考や表現の自由の中枢を担う大学は、徹底的服従を望む独裁主義者にとって本質的な脅威だと言う。イタリアのファシスト党の指導者ムソリーニが1931年、大学教授らに忠誠を誓わせたのがいい例だ。 2018年には、ハンガリーにあったセントラル・ヨーロピアン大学が、独裁傾向を強める同国のオルバン政権のせいで国外移転を決めた。 「世界各地で独裁主義者がまず攻撃したのは大学だ」と、スタンリーは指摘する。著書『歴史の抹消』(未邦訳)では、この傾向を詳しく分析。独裁主義者は「批判的歴史」を消し去り「愛国主義的教育と置き換え」ようとすると言う。 独裁体制は学生の抗議運動をしばしば意図的に曲解し、大学の正当性喪失を目指す。 それに加担しやすいのが大手メディアだ。「19年にインドで、イスラム教徒を二級市民に位置付けるような市民権改正法が成立した際、国内の大学で抗議デモが起きた。メディアはイスラム教徒を利する反国家的運動だと報道し、デモは暴力的に弾圧された」 「ユダヤ系保護」は口実 米メディアも昨年、同様の道をたどった。パレスチナ自治区ガザでの戦争に対して、米国内の大学で起きた抗議デモを「誤った形で伝え、数多くのユダヤ系の参加者の存在に何カ月も触れなかった」。 「トランプ政権が大学を標的にする理由を、メディアは今も理解していない。大学が独裁主義や不当な戦争への抵抗の震源地であり続けているのは、イデオロギーを刷り込むからではなく、学生という大勢の賢い若者がいるからだ」 スタンリーは学術機関の弾圧や、パレスチナ寄りの抗議デモに参加した外国人学生の強制送還方針に関し、トランプが反ユダヤ主義との闘いを口実にしていることにも批判的だ。 ユダヤ人が権力機構を支配しているという危険な固定観念を、かえって強化するという。ユダヤ系社会のためと称する政権の行動は、有害な先入観をあおって反ユダヤ主義を加速させる恐れがある。 トランプ政権は「キリスト教ナショナリスト」で、ユダヤ人も反ユダヤ主義も大学支配を目指すホワイトハウスに利用されていると、スタンリーはみる。トランプのファシズムが、ユダヤ人のせいにされることにもなりかねない。 だが「真の犠牲者は、ユダヤ��アメリカ人の保護という建前の陰で、計り知れない苦痛を見過ごされているガザの住民だ」と、スタンリーは言う。 「ユダヤ人は暴政に立ち向かう。それが私たちの歴史的役割だ。私たちは自由主義を支持する。私たちが支持するものを、トランプ一派は根底から覆そうとしている」
トランプ政権はナチスと類似?――「独裁者はまず大学を攻撃する」エール大の著名教授が国外脱出を決めた理由|ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト
3 notes
·
View notes
Text
Old PriTicket photos (and bonus fonts information)
@rabbitthedarkidol ヾ(´Y`)ノ”💁♀️Hi! Selection time of PriTicket took longer than I anticipated it. Given my limited availability in the coming period, so I wanna upload only the images and Japanese explanation at this time, gradually supplement them with English text at more opportune moment, sorry >_< However, those contents are guaranteed to be beneficial😊 If there's anything unclear, please ask Professor Google translate👩🏫
To know the specific dates, I researched primarily using Twitter🕊️ Due to the deletion of numerous PriPara official website pages and the contaminated Google search results, I had to rely in there. Those process were necessary step to put many things into words for me. Anyway, I tried my best to get it right, but I might have missed something. Everyone, let me know if you know some fact!
Some of the PriTickets are being shared with the permission of my friends. To respect their privacy, I've blurred out certain parts, OC name, QR and OC's ID, date etc. (For some reason, one of the reasons is that my OCs are soooo many and I'm little embarrassed, hehe) Combining everything into one post would take too much time, so I wanna upload a little bit each day💪
*Please note that the images I've uploaded are for reference or an entertainment purpose only and are not intended for modification into templates. Please handle them with care, considering the differences in cultural sensitivities between Japan and other countries.*
These are precious fragments of our pretty memories!🎀
まずは以前書いた「レアリティによってフレームが変わっていたはず」という認識はあまり正確ではなかったことについて。
(I would like to point out that the "OK sign" in Japan, formed with the thumb and index finger, can be interpreted as disrespectful in some cultures. However, it is just a common positive and kawaii gesture for us🥺I had just very little. . .)

まず、2015 5thライブから神1弾まで、SR以上のプリチケは豪華なフレームのソロチケで固定だったことが思い込みを作っていたようだ。具体的には
SR=銀背景に銀のツタと白いお花があしらわれたフレーム
CR・PR・MR・SCR=金背景に星や宝石があしらわれたフレーム
になっていた。同じ色でもコーデの属性によってデザインは変わらないし、金チケのレアリティ別デザインもほぼ同じだ。MRのみ流れ星の中に「MYSTERY」と書かれたマークがQRの少し上に配置されていた。CRではコーデの属性によって左上ハートマークアイコンを囲う色が変わるという違いはあった。確認できた限り、
ラブリー=赤寄りのピンク
ポップ=青寄りの水色
クール=紫
プレミアム=水色
だった。ほかに当時の現物はなかったが、この法則なら多分ナチュラルは緑、セレブは金色で囲われているはずだ。他のプリチケからぴったりな緑色をスポイトで取ったり、ネットで配布されている適当な金グラデを使えば解決するだろう。
SR以上ソロチケ固定の始まりは2015 5thライブ、つまりゲームにひびきが登場した頃だった。ソロチケ固定については賛否両論あり、巷では「セレパラ仕様」と言われていたようだ。確かに。キリのいい神1弾ではなく、なぜか神2弾からランダムなポーズに戻った(現物で確認)。
下の2枚は「コーデチケ」と言って、マイキャラのデータが保存されていないものになる。マイキャラを作らずにゲームで遊ぶと、このタイプのプリチケが排出された。アニメでのデザインと似ているのはむしろこちらだろうか。筐体をやっていない人からしたらこちらのほうが馴染みがあるデザインかもしれないので載せる。
ちなみに「コーデチケ ※マイチケではありません」「マイマネージャー」という表記について少し。これらは和製英語の固有名詞で、誰のものであっても「マイ◯◯」と呼ぶ。日本のプリパラアーケードは最新の「マイチケ」に最新のマイキャラのデータが保存されていく形式だったので、状況によってはマイキャラデータが入っていない「コーデチケ」とは区別して呼ぶ必要があった(でも大陸版ではアプリでデータを管理できたとか)。マイマネについては後述する。
アーケードとアドパラコーデのレアリティは一部変更されているので補足。コーデ自体のレアリティが変わったものもあるが、主に変更されたのは、
CR・MR・SCR・神・夢=PPR
N=廃止


左の画像 右の画像 同じ画像にはないが、神と夢は同じ階層のランク扱い。
では神1弾まではどんなプリチケだったのかと言うと、

当時、フレームの形状は同じでもラインストーンの色に違いがあった。
赤(銅?)
金
銀
カラフルなもの(赤・オレンジ・黄色・緑・青・紫)
の4種類だ。確認した限りではランダムだと思うが、銀が一番多く、カラフルなものが一番少なかった。この���見によって、むしろあらゆるカラーバリエーションを作ることができることに気づいてしまった。(最も見慣れた記憶からか、私は低レアは銀、高レアは金で統一されていると思い込んでおり、カラフルなものは記憶に残ってさえいなかった。機会がなければきっと知れなかった、ありがとう!)
左上のポーズは中央上のポーズのバグ。立ち位置が入れ替わっていてうまくハートを作れていない。他にも本来いるはずのチームメートが消える、印刷されたコーデと実際に着せられるコーデが違うなどのバグがよく起きていた。まぁ、ある意味ではアドパラの世界観にも受け継がれている伝統芸かもしれない。
2015 1stライブ(2015年4月2日)からQR の形状が変わった。QR を囲んでいたリボンが消え、二回りほど大きくなっている。コーデや名前欄の位置も違和感がない程度に微調整されている。 QR が小さいとマイキャラのイラストをより大きく・デザインをより自由に配置できて映えやすい、QR が大きいと長らく親しみを持ってきたデザインに近く馴染みやすいというメリットがあるように感じる。
さて、違和感に気づいた人がいるかもしれない。中央下に映っている6人ライブは期間限定である。後ろのそらみスマイルの3人は固定で、トモチケメンバーとして呼べるのは2人まで。(ちなみにNintendoプリパラではいつでも遊ぶことができ、こちらではトモチケメンバー全員を自由に選ぶことができる。)
そして右下の5人チケについて。これはドリームシアターとは別に5人でライブできるモードがあったわけではなく、ドリームシアターライブの後で課金した時に出てくる通常プリチケだ。(2017年12月27日までドリチケの追加課金はできなかった���め。)
信じられないかもしれないが、昔は人からマイチケさえ借りれば誰でもそのコーデを着られたわけではなかった。各マイチケ右上にご注目ください。アーケードのプリパラではマイキャラの名前ごとにマネージャーが決まっていた。全7色×5種類の35パターンである。リンク

このシステムは「マイチケを別のマイキャラと共有できるかどうか」に関わっていた。右上に何もない頃は全く同じ名前のマイキャラとしかコーデの共有ができなかったため、大量の同名マイキャラ持ちも珍しくなかった。(コーデチケは誰とでも共有可能) まずは卵の状態(生えている耳や足などの特徴および色)、孵化してからは同じ動物および同じ色のマネージャー同士(たとえば緑の鳥同士)でのみコーデの共有ができた。この仕様変化により、プリチケトレードに革命が起きた。(うん、「クマやウサギは卵から生まれるのかよ」ってのは気にしちゃいけない。) 神1弾からその縛りはなくなり、コーデ共有のためにマイマネ厳選をしたり、マイマネ占いに頼る必要がなくなった。遊びの幅もより広がった。(マイマネ厳選=名前に記号を付けまくってマイマネを調整する挑戦のこと。マイマネ占い=かつてファンによって作成された、デビュー前にあらかじめマイマネを確認できたサイト。)
と、まぁ「自分のマイキャラにマネージャーがいたら……」なんていうふうに妄想するのも楽しいかもしれない。現状アドパラには一切登場しないため、この歴史は豆知識に過ぎないかもしれない。マイマネ占い亡き今、どのマイマネになるか正確に掴みにくいことは残念だ。開き直ってしまえば、もう誰も確認できないので捏造し放題である。ちなみにハムのマネージャー兼召使いは人間の私という設定。 . (´Y`)���ぅ ◯l ̄ ̄L(涙)
また、これはデザイン上の細かい話だが、マネージャーの登場に伴いプリパラのロゴとランク名及びいいね♥の枠が小さく、かつ左寄りに配置されるようになった。 こういったアップデートは時折挟まれていたが、開始や終了のアナウンスがないものも多い。たとえば「クマのフローズンスタンプ」があるプリチケは2014 2nd ライブから排出されていたが、終了時期は不明だ。

好評だったり要らないと言われていたりと評価は様々。ちょっと手間がかかるだろうけど、オリジナリティのために何か作って貼るのも楽しそう。
神2弾以降はレアリティアイコンの形状がブランドの属性ごとに違うものになっている。
ラブリー=ハート
ポップ=星
クール =薔薇
ナチュラル=葉っぱ
セレブ=王冠
プレミアム=宝石
リンク

一部の高レアリティ(MR・SCR・神・夢)を除き、フレームは属性ごとに同じものに統一され、全体的に豪華仕様になった。特徴的なのはコーデ背景の円形レースが廃止されたこと、属性ごとのイメージを表すような装飾が多くあしらわれたこと。
MR・SCR・神・夢はそれぞれの属性のフレームを主に金色にカラーチェンジしたものになっている。(セレブのフレームはもともと金色なので違いが分かりにくい。)
それ以前のシンプルなフレームもまた魅力的なので好みが分かれる。比較画像を用意するのに時間がかかっています……。私はコーデの後ろに円形のレースがあったほうがパッと見やすかったので好き。
デュオプリチケ。2人モードで遊ぶと「ずっトモチケ」付きの「ずっトモプリチケ」がもらえた(ずっトモ=Forever friend)。


デザインが対になっていてトモダチ感がマシマシになり、超絶大好評のモードだった。友達と遊んでトモチケをパキるも良し、「ぜひペアで呼んでね!」というつもりで友達に渡すも良し、一人でやって大切に保存しておくも良し。私もいくつか額縁に入れて飾っている。
大まかなフレームは各属性のものだが、左右を囲むフレームだけはレースのみ��シンプルなデザイン。2人の友情を美しく飾るための引き算を効果的に使っていることが伺い知れる。デザイナーのこだわりを感じられる瞬間は楽しい。
プリチケ作成に役立ちそうなフォント:
スランプ

ハミング

使えるかもしれないフォント:
コミックレゲエ B クール系トップスを着た時のプリチケはこれに少し似ている。

ユールカ UB メイキングドラマのフォントに使われているので馴染み深いかも。

とりあえず一旦切ります。To be continued!
6 notes
·
View notes
Quote
実は、サイズの違いによって、流体力学的な現象は、ずいぶん違ってくるのです。実は比較的最近になって、この違いこそがマルハナバチが飛ぶことを出来るようにしているということが分かってきました。 飛行機や鳥のような大きなものと、昆虫のような小さなものを取り巻く流体の性質を分けるものに、レイノルズ数と言うものがあります。同じ粘度をもった空気のなかを飛ぶのなら、サイズが大きくなるほどこの値が大きくなり、サイズが小さい、とこのサイズも小さくなります。 飛行機がほとんど粘性のない安定した流体のなかを飛んでいるのに対して、昆虫は渦の海のようなところを飛んでいるのです。 昆虫は三種類のお互いに関係しあった要素を利用して、重力に逆らう力を得ていることが分かりました。 一つ目の力は"delayed stall"と呼ばれるもので、この力は羽を上下にばたつかせているときに得られる力のことです。しかし、今まで知られていなかった、羽の動きの向きをかえるときに生じる2つの力を発見したのです。その2つの力は「回転循環(rotational circulation)」と 「後流捕獲(wake capture)」 と呼ばれています。 昆虫が羽をふって飛ぶ原理は、4つの段階に分けて考えるとよいでしょう。羽を振り上げたり振り下げたりする2つの段階(upstroke、downstroke)と、羽の動きの向きを反対へ回転させる2つ段階(pronation、supination)の合計4つの段階です。 「失速おくれ(delayed stall)」の力は、昆虫の体をもちあげる力として主要なものとなっています。これは、昆虫が羽を高い角度から、水平な位置よりも下の角度へ振り下ろしたときに生じる力です。ところが、もし飛行機の翼がこのような急な角度になってしまったら、当然飛行機は揚力を失います。しかし、昆虫��場合は、このときに羽の上の部分の圧力を下げ渦をつくることで、これが上向きの力へとなります。 また、羽の向きを変えるときに、バックスピンの空気の流れが生じ、これも昆虫をもちあげる力となります。このバックスピンの回転上昇は、例えばテニスボールやピンポン球のものと似ていますよね。これが"rotational circulation"の力です。 そして、問題の羽を振り上げるときに上向きの力としてはたらくのが、"wake capture"による力なのです。今まで作っていた上向きの回転の渦のエネルギーをつかんで、上向きの力を得るのです。 このように、翼の上下の空気の流れの速さの違いを利用した航空力学とはほとんど共通点を持っていないわけです。また、渦を利用するという発想は、作用反作用の第一法則からも思いつくことすら出来ません。 そのため、それまでの航空力学では、昆虫は「理論上」飛べないということになるわけです。
気になる科学コラムサイト「飛べないといわれた昆虫のロボット・ショック」のページ
3 notes
·
View notes
Quote
ネオジム磁石は例えば、みなさんが肌身離さず持っておられる携帯電話に使われています。中に入っている超小型振動モーターには、100%ネオジム磁石が使われております。ネオジム磁石は現在最強の磁石です。計算では1グラムのネオジム磁石で1キログラムほどの鉄を持ち上げることが出来ます。そのような磁石をどのようにして見つけたのか、これからお話しします。 1. 新しい磁石を見つけるには まず原理的なことから。これは元素の周期表です。私たちの体を含めたあらゆる物は、この周期表に書かれている100余りの元素から出来ています。磁石の基になっているのは、元素番号26の鉄(Fe)、27番のコバルト(Co)、28番のニッケル(Ni)で、これらは「鉄属元素」(あるいは遷移元素:transitional metal)と呼ばれています。もう1つ、磁石の基になっているグループが「レア・アース」(Rare earth)と呼ばれる16種類の元素です。このうち磁石に関係の深い元素が60番目のネオジム(Nd)、62番目のサマリウム(Sm)、66番目のディスプロシウム(Dy)です。磁石を補佐する大事な役割をするのが5番目のボロン(B)。6番目のカーボン(C)も今日のお話ではよく出てきます。 では、磁石をミクロで見ると、どんな物質なのか。磁石の元はすべて電子です。例えば、鉄族元素の周囲にネオジム磁石などの永久磁石を近づけながらグルリと回すと、いつでも鉄族元素の電子はすべて同じ磁界の方向に向いているという性質があります。強い磁石となるためには、すべての電子がつねに一定の向き(N極、S極)で、変化しないということ。つまり磁石には磁気方向の頑固さ(磁気異方性)が必要で、レアアースがその役割を果たすのです。 分かりやすく言えば、みんなが同じ方向を向く「仲良し電子ちゃん」の中で、一定の間隔で「頑固電子ちゃん」が配置されている構造となっていることが必要です。1970年代の最強の磁石は「サマリウム・コバルト(SmCo)磁石」でした。これは鉄属元素であるコバルトの元素の間に、サマリウムが規則的な間隔で並んでいるような化合物(Sm2Co17)です。「仲良し電子ちゃん」の集団の間に、サマリウムの「頑固電子ちゃん」が並んでいる構造ですね。これに磁界をかけると、一方にN極、もう片方がS極となって方向がつねに変わらない、永久磁石となっ��のです。 ところが人間の作るものには必ず欠陥があります。本来あるべき所の「頑固電子ちゃん」がなくて、空いてしまった部分が出来ます。こうした欠陥部分が出来ると、永久磁石はその部分から磁性の変化が起きて、周囲に段々と広がり、ついにはその磁石全体が磁性体ではなくなってしまいます。純粋、無垢(むく)な化合物というものはなかなか作れませんから、どうしてもこうしたことが起きてきます。この問題を解決したのが、磁石の中を「セル状構造」にすることでした。これは元の化合物に別の元素などを加えて「合金化」し、製法などの条件を工夫することでセル状構造を作ります。セル状構造というのは、小さなセル(細胞)に区分けしてやることです。セルとセルの間は別の層、非磁性体の元素による「磁気の壁」を作ってやるのです。そうすることで、例え1つのセルに欠陥があっても、隣のセルには影響しない。1個のセルはかなり小さいので、全体としては磁石の性質を維持したままとなります。こうした方法で人類は磁石を作ってきたのです。 そのため、新しい磁石を見るけるためには、まず磁石に適したR-T(レアアース・鉄属元素)の新化合物を見つけること。そしてそれを元に、セル状構造を作るための合金組成や製法を見つけることです。こうした流れに沿って、私が新磁石を見つけ、1982年に誕生させたのがネオジム磁石です。 2.どうやってネオジム磁石を見つけたか 私は神戸大学工学部の電気工学科を卒業後、大学院に進むときには材料科学者を志しました。今でも私は材料科学者だと思っているのですが、神戸大学大学院博士課程(1966-68年)と東北大学大学院博士課程(68-72年)では材料科学の研究室に所属し、勉強しました。研究テーマはどちらの大学院でも似たようなもので、「固体表面の性質、構造、結晶成長の電子顕微鏡による研究」でした。しかし、よい研究成果が出ず、よくできる研究者にはなれなかったのです。でも自分の所属する研究室以外の、特に基礎的な研究分野の研究室に積極的に出向いて、他の分野の勉強をして、材料科学者としての実力と感覚を身に付けたと思っています。 博士課程を終えた後は大学に残りたかったのですが、その願いかなわず、富士通研究所の材料研究部(72-82年)に入りました。そこで会社から与えられた研究テーマが「リレーやスイッチに使う磁性材料の開発」というものでした。大学院時代にいろいろな他の分野の研究室に出入りしたと言っても、基礎的な研究であって材料など具体的な開発の研究をしている所ではありませんし、私も磁性材料の勉強をしたことはなかったのです。 「自信がないなぁ、困ったなぁ」と思いつつも、会社から言われたのだから、やることにしました。そして入社して5年目に、私単独に与えられた研究テーマが「フライングスイッチ用サマリウム・コバルト(SmCo)磁石を開発せよ」というものでした。「フライングスイッチ」というのは、直径が1-1.5ミリメートルの極めて細いガラス管の中に小さな円柱形のSmCo磁石を入れ、外から中の鉄ニッケル合金の針金で作ったコイルに電流を流して、磁石が動くことによって電流を断続させる高性能のスイッチのことです。しかし使う回数が増えてくると磁石も壊れてくる。そこで私への研究テーマとなったのが、「何回使っても壊れないSmCo磁石を開発せよ」というものでした。 勉強したことがないし、私1人へのテーマなので、リーダーもいないし困ったなぁと思ったのですが、やり出したらこれが面白い。自分に合っていたのだと思うのですが、それからは磁石の勉強、さらに勉強・・・と、朝から晩まで、家に帰ってからも勉強しました。全部独学です。磁石の製造の装置も、会社の遊休設備を集めてきて自分で作りました。こうしたことに、大学院時代の実力養成が生きたのです。基礎的な勉強をしていたし、いろいろな実験装置を作ることもやっていたのです。とにかく楽しくて、どんどん研究にのめり込んで行きました。 当時の磁石研究の主流はSmCo磁石でしたし、さらに勉強し、機械的な強度を改善するためのアイディアもいくつか考えました。サンプルも作って強度や特性を測ったりしながら開発は順調に進んで行ったのです。そうした中で考えていたのは、「なぜR-Fe(レアメタル・鉄)磁石はできないのか?」ということでした。鉄の資源はコバルトよりも無尽蔵にあります。鉄はコバルトよりも電子の密度が濃く、「電子ちゃん」をたくさん持っている。いわゆる、大きな“磁石の素”を持っていたのです。ですから鉄で作ればより強力な磁石ができるはずですが、だれもやろうとしない。「コバルトでなければ磁石はできない」と、だれもが思い込んでいたのです。私は初心者ですから、いろいろなことには囚われていなかったのです。 さらに勉強する中でヒントになったのが、1978年1月に日本金属学会が主催して東京都内で開かれたシンポジウム「希土類磁石の基礎から応用まで」でした。その時に出席された浜野正昭先生の講演は、ほとんどがR-Co系化合物の性質や状態などの金属学的な基礎的な説明をされたのですが、ほんの数分だけ、R-Fe化合物が磁石にならない理由を説明されました。つまり、「鉄と鉄の原子間距離が近すぎるので、強磁性が不安定になる」ということでした。 それを聞いて私は、「それなら炭素(C)やボロン(B)を合金化すれば、原子間距離を広げてくれるのではないか」というアイディアを持ったのです。当時の私には、すぐに実験するという習性がありましたので、帰ってすぐにアーク溶解炉で合金を作り、磁力を計測したり、X線回析で結晶構造を解明したりしました。すると短期間で「これは何かあるぞ」と思いました。 新磁石を見つけるには、磁石に適したR-T新化合物を見つけること、それを基にセル状構造を作るということです。これについては早く発見していました。私がヒントを得た1978年には、ネオジム(Nd)-鉄(Fe)-ボロン(B)の組み合わせが磁石として有望であることを見つけていたのです。ところがそれを他の人に説明しても、合金の粒を見せても、だれも関心を持ってくれない。それは、磁石としての構造をもっていないため、つまり磁石になっていないからでした。 その一方で、壊れないSmCo磁石の研究についてはどんどん進み、1979年には開発目標を達成して、国際会議などで発表しました。ところが発表したら、「磁石の研究は終わりだ」と富士通研究所のトップから言われたのです。私は「新しい磁石(Nd-Fe-B磁石)の開発の糸口をつかんでいるので、何とか研究を続けたい」と言ったのですが、「ダメです。もっと富士通らしい研究をしなさい」と言われてしまいました。それは会社とすればもっともなことで、磁石ではなくてコンピューターを作る会社ですからね。結局、私も従わざるを得なかったわけです。 こうして私の、Nd-Fe-B化合物を基にセル状構造を作り、新しいNd-Fe-B磁石を作る研究は、公式テーマとして取り上げられることなく、1980年までに修了してしまいましたが、決してあきらめていた訳ではありません。頭の中で研究を進め、時には余ったサンプルで溶かしてみたりしていました。そうしているうちに、上司との決定的な事件が起きてしまいました。ふだんからよく怒る上司で、その人にものすごい大声で怒鳴られたことを契機に私は辞表を出して、富士通研究所を退職しました。そして住友特殊金属に入社し、それからすぐの1982年5月に、住友特殊金属の実験室で、世界最強の磁気特性をもつ「ネオジム磁石(Nd-Fe-B磁石)」ができたのです。 よく「発明は1人でできる。製品化には10人かかる。量産化には100人かかる」とも言われますが、実際に、私はネオジム磁石を1人で発明しました。製品化、量産化については住友特殊金属の仲間たちと一緒に、短期間のうちに成功させました。82年に発明し、83年から生産が始まったのですから、非常に早いです。そしてネオジム磁石は、ハードディスクのVCM(ボイスコイルモーター)の部品などの電子機器を主な用途として大歓迎を受け、生産量も年々倍増して、2000年には世界で1万トンを超えました。 3.さらなる発展を支える ネオジム磁石の今の、あるいはこれからの重要な用途はハイブリッド自動車や電気自動車、エアコンなどの比較的大きな発電機やモーターなどです。ハイブリッド自動車1台には1キログラムのネオジム磁石が使われますので、さらにハイブリッド自動車が作られていけば、使われるネオジム磁石も増えていきます。エネルギー消費の大きいエアコンでも、ネオジム磁石を使えばコンプレッサー部分のエネルギー効率が上がって、消費をかなり抑える効果があります。風力発電では、ネオジム磁石を発電機に使うと高効率になり、音も静かになるなど高性能になります。特にこれからのエネルギー問題では、洋上風力発電が日本の主力電力源になると考え、運動していきたいと思っています。それとエレベーターでは、モーターにネオジム磁石を使うと、あるメーカーのものでは、かなりのスペースの節約になり、電力消費も半減する効果があります。 これらの用途が広がり、ネオジム磁石の需要が伸びていけば、生産量も2015年には1年間に10万トンに達すると予想されています。ところがこうした需要に応えるためには、レア・アースなどの資源問題を解決しておかないと実現できません。 ネオジム磁石の「磁気特性マップ」に対応する応用について、縦軸に磁気の���さを表す「最大磁気エネルギー積」、横軸に「保磁力」に対応する耐熱温度を取り、考えてみましょう。 MRI(磁気共鳴画像装置)やハードディスクではあまり耐熱性は必要ないので(100℃程度)、最大磁気エネルギー積が大きい、つまり磁気の強い磁石を使います。ところが、ハイブリッドカーのモーターでは、200℃に耐える磁石が必要となります。 これに対応するネオジム(Nd-Fe-B)磁石の合金組成をみると、100℃の耐熱温度を得るには「Nd-Fe-B」の各質量%が「31-68-1」の割合でよいのですが、より高い耐熱性を得るためにディスプロシウム(Dy)を加えることが必要となり、200℃の耐熱温度を得るための組成「Nd- Dy -Fe-B」は「21-10-68-1」となります。つまり必要となるディスプロシウムの量は全体の10%、ネオジム(Nd)の半分の量です。ところが自然界では、ディスプロシウムはネオジムの10の1の量しかありません。しかも中国南部の一地域にしかない。ですからこのディスプロシウムを使わないようにしないと、ハイブリッドカーを安定して生産することはできません。ディスプロシウムを使わずに耐熱性が得られる磁石を作ることが大事な課題であり、できたらネオジムだけでこれだけの耐熱性のある磁石を作りたい、というのが目標です。 この「低ディスプロシウム・高耐熱ネオジム磁石」の開発に、当社「インターメタリックス(株)」が2004年から取り組み、さらに京都大学の「桂ベンチャープラザ」というインキュベーション施設に入居して進めてまいりました。そこではベンチャー・キャピタルや銀行などの投資家による投資のほか、三菱商事や大同特殊鋼といった大企業からの投資もありました。それから経産省やNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)の国家プロジェクト(2007-2012年)として大きな予算も頂き、この研究がある程度成功しました。つまりセル構造の微細化によって、低ディスプロシウムで高耐熱化する組成や、そうした新材料を作る方法を見つけたのです。この新材料は「Intermetallics Japan(IMJ)」という会社が2013年初からの量産開始の予定で現在工場を建設中です。 4.研究者になってよかった! 何が私を研究に駆り立てたか?——私は子どもの頃、湯川秀樹先生に憧れていました。その憧れの気持ちが、いつも私を前向きにしてくれました。研究者として駆け出しの頃、学会や研究会の会場などで私はいつも先輩研究者から軽視され、挨拶も返してくれませんでした。「今に社会のためになる研究をして、人から認められるようになるぞ!」。この強い自己顕示欲、目立ちたいという気持ちが、私を研究に駆り立てたのです。 研究者の仕事は素晴らしい!——人の最大の喜びは社会のためになることです。研究者は頭脳活動によって研究し、研究が成功すれば社会に貢献できます。研究者は地球温暖化問題など、様々な社会的難問を研究によって解決していけます。研究者、あるいは科学者ほど素晴らしい職業はないと思っています。 最後になりますが、大学院時代には涙を流していた私が、日本国際賞という大きな賞を頂き、ここに立っているのは不思議なことです。何が違ったのでしょう。大学院時代は基礎研究をしていました。基礎研究というのは何を明らかにしたら、どんな成果につながるのか、分からない。ところが企業の研究では、「これこれを開発しなさい」というようにターゲットがはっきりしています。これが私には合っていたのです。ターゲットがはっきりすると、解決のためにいろいろなアイディアが出てくる。それが今ある理由だと思っています。
世界最強「ネオジム磁石はこうして見つけた」(佐川眞人 氏 / インターメタリックス株式会社 代表取締役社長) | Science Portal - 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」
4 notes
·
View notes
Text

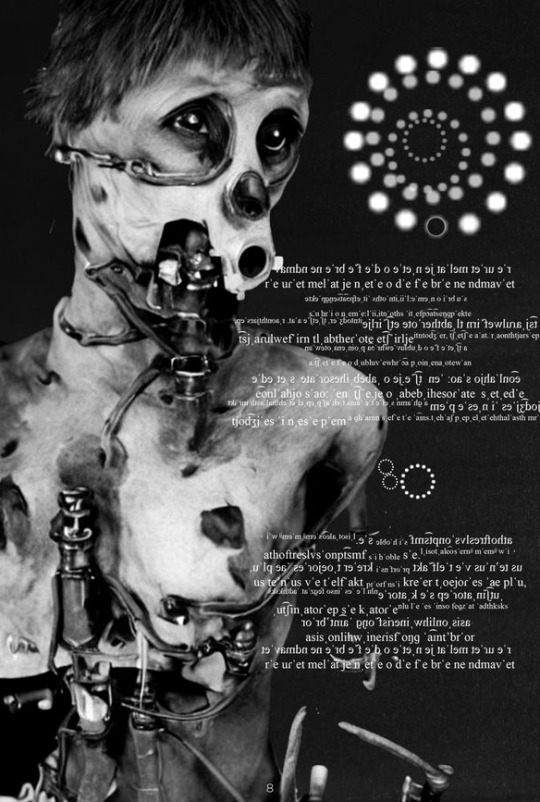
アンドリュー・C・ウェナウスによる「Libretto Lunaversitol: Notes Towards a Glottogenetic Process」は、ケンジ・シラトリによるバイオモルフィックなイラストを伴い、パタ数学の数式と国際音声記号(IPA)を組み合わせた革新的な作品です。この作品は単なる文学作品ではなく、視覚的かつ聴覚的な新しい言語の誕生を示唆する推測的な言語生成過程(グロットジェネティック・プロセス)として機能します。
パタ数学の概念—「パタフィジックス」(想像上の解決策の科学)と数学を組み合わせた用語—は、この作品に独自の構造的な統合性を与えています。パタ数学は、新しい言語形態を生成する基盤として機能し、数学的な関数がグラフを生成する方法に似ています。関数 f(x) が入力を出力にマッピングするように、「Libretto Lunaversitol」は抽象的なものと具体的なものをマッピングして、多面的な言語を創り出します。
ウェナウスの作品における言語生成のプロセスは、代数的構造のレンズを通して理解することができます。この本の構成要素—テキスト、IPAシンボル、視覚要素—を集合として考えると、それらの相互作用を関係および関数を用いてモデル化することができます。例えば、
T をテキスト要素の集合、
P をIPAシンボルの集合、
V を視覚要素の集合とします。
そして、各タプル (t,p,v)∈R がテキスト要素、その音声表現、および対応する視覚要素間の相互作用を表す関係 R⊆T×P×V を定義することができます。この作品の豊かさは、従来の言語構造に挑戦する非線形・非連続のマッピングにあります。
「Libretto Lunaversitol」は、人間の理解を超えた自律的な自己組織化を行うスーパー・ハイブリッド技術言語の出現を推測します。これは複雑系における創発現象に類似しており、局所的な相互作用が全体的なパターンを生み出します。数学的には、これはしばしばセル・オートマトンやニューラル・ネットワークを使用して説明されます。
各セルが言語単位(単語、シンボル、音)を表すセル・オートマトンを考えます。各セルの状態は、隣接するセルの状態に基づいて進化します。これは、本の要素が新しい意味と形式を創り出す方法を反映しています。創発的な言語は、すべての可能な構成の状態空間における高次の構造、すなわちアトラクタです。
ビッグデータと自律的な情報処理プロセスへのアナロジーは特に重要です。機械学習では、勾配降下法のような最適化アルゴリズムが損失関数を最小化するためにパラメータを反復的に調整します。同様に、「Libretto Lunaversitol」は、人間の言語と経験の非効率性という「損失関数」を最小化しようとする最適化プロセスと見なすことができます。テキスト、音声、視覚要素の相互作用を通じた反復的な洗練は、この非効率性を最小化し、新しい表現モードに近づきます。
ウェナウスの作品は、純粋性と本質主義に反対し、ハイブリッド性と多様性を受け入れます。数学的には、この反対はファジー論理と集合論の観点から説明できます。従来の集合論は二値論理であり、要素は集合に属するか属さないかのどちらかです。しかし、ファジー集合論では、所属度合いが存在します。「Libretto Lunaversitol」では、要素は単一のアイデンティティに限定されず、連続体の状態に存在します。
例えば、要素 x のテキスト要素集合 T への所属関数を μT(x) とすると、0≤μT(x)≤1 となります。この流動性により、より豊かで包括的な言語構造が可能になり、人間の経験と思考の複雑さをよりよく捉えることができます。
ケンジ・シラトリによるバイオモルフィックな図形と、ウェナウスとクリスティーナ・マリー・ウィラットによる音楽スコアは、更なる複雑さの層を追加します。これらの要素は、多次元空間における変換としてモデル化することができます。すべての可能な感覚入力の空間を Rn と表すと、視覚的および聴覚的要素はこの空間におけるベクトルとして捉えられ、テキストおよび音声要素の知覚を変換します。
「Libretto Lunaversitol: Notes Towards a Glottogenetic Process」は、言語��芸術、数学の伝統的な境界を超える先駆的な作品です。パタ数学、創発系、ファジー論理の原則を活用することで、ウェナウスとシラトリは、コミュニケーションと表現の理解に挑戦するスーパー・ハイブリッド技術言語を創り出します。
2 notes
·
View notes
Text
TEDにて
ロバート・パーマー:「パナマ文書」が暴いた世界的大問題 — 次にすべきことは何か?
(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)
2016年4月3日、歴史上最大のデータ流出事件が発生しました。
この「パナマ文書」により、金持ちや権力者がオフショア(租税回避地)口座に隠し持つ巨額の資産が明るみに出たのです。
これにはどういう意味があるのでしょうか? グローバル・ウィットネスのロバート・パーマーに話を聞いてみました。
2016年4月3日。歴史上最大のデータ流出が起こりました。「パナマ文書」により金持ちや権力者が。オフショア(租税回避地)に隠し持つ莫大な資金が表沙汰になりました。これは何を意味するのでしょうか?グローバル・ウィットネスのロバート・パーマーに聞いてみました。
今週、おびただしい数のニュースが取り沙汰されています。1,100万件にも及ぶ文書の流出によるもので出処はパナマを拠点とする法律事務所モサック・フォンセカです。これらパナマ発の文書の流出で秘密主義的なオフショア世界の姿がほんの一部ですが露見しました。
これで判明したのが、銀行や弁護士などの顧客がモサック・フォンセカのような会社に「匿名の会社が欲しいので作ってください」と依頼する実態です。実際にやり取りされたメールの内容を読むことができ、その仕組みや運用のされ方がわかります。
既にこの流出事件の波紋が一気に広がり始めています。アイスランドの首相が辞職。他にも残虐なシリアの独裁者。バシャール・アル=アサド大統領の協力者もオフショア法人を持っていると報道されています。
世界中の金持ちの中には新たな一連のニュースや新たな文書流出にビクビクしている人々がまだまだいることでしょう。
私の組織グローバル・ウィットネスにとって、今回の暴��はものすごい朗報でした。今、世界のメディアや政治リーダーが個人によるオフショア秘密管区を利用した資産の隠匿について取り上げていますが、これは、私の組織が10年に渡り、世に訴え暴いてきたことです。
グローバル・ウィットネスでは、オフショア取引の実態がどうなっているのか?どうやって機能しているのか?知りたいと思いました。そこで私たちは、マンハッタンにある13の法律事務所に覆面調査員を送りました。調査員はアフリカの公使を装いました。
不審な金をアメリカに移動し、家やヨット、飛行機の購入を考えているという設定です。
非常にショックなことに調査員した法律事務所のうち1つを除いて1つを除いてすべてが調査員に対し、この不審な金の移動方法を提案したのです。すべて初回の相談での話です。どの法律事務所とも取引は始まりませんでしたし、動いた資金もありませんでしたが制度における問題点が露見しました。
もう1つ大事なことは、これを単独の事件に過ぎないなどと考えないことです。
うちの覆面調査員にアドバイスを与えた個別の法律事務所だけの話ではありません。今、スキャンダルの渦中にいる特定の大物政治家だけの話ではありません。制度の仕組み自体が問題なのです。
汚職、租税回避、貧困や政情不安定の温床だからです。この問題に取り組むには、ゲーム自体を変える必要があります。ゲームのルールを変えて不正をしにくくする必要があります。
我々、グローバル・ウィットネスは今が変革を起こす時だと考えます。民衆は怒るべきです。匿名の会社を盾に身元を隠している 輩に対して憤るべきです。
ビジネスリーダーは立ち上がり、こういった秘密主義はビジネスにあるまじきことだと明言すべきです。政治リーダーはこの問題に向き合い秘密の開示につながる法改正を公約すべきです。
なお、日本の全テレビ局は超裕福層に入ります。そして、もう既に権力者です。もう一度言います!テレビ局も今では権力者!再び、過ちを繰り返すかもしれません!
自らが権力者であることを発信せず視聴者を混乱させ、それに便乗して権力乱用する日本の民法テレビ局。同じことを繰り返さないようにみんなで見守っていくことだ。
最後に、マクロ経済学の大目標には、「長期的に生活水準を高め、今日のこども達がおじいさん達よりも良い暮らしを送れるようにする!!」という目標があります。
経済成長を「パーセント」という指数関数的な指標で数値化します。経験則的に毎年、経済成長2%くらいで巡航速度にて上昇すれば良いことがわかっています。
たった、経済成長2%のように見えますが、毎年、積み重ねるとムーアの法則みたいに膨大な量になって行きます。
また、経済学は、大前提としてある個人、法人モデルを扱う。それは、身勝手で自己中心的な欲望を満たしていく人間の部類としては最低クズというハードルの高い個人、法人。
たとえば、生産性、利益という欲だけを追求する人間。地球を���うという欲だけを追求する人間。利益と真逆なぐうたらしたい時間を最大化したいという欲を追求する人間。などの最低生活を保護、向上しつつお金の循環を通じて個人同士の相互作用も考えていく(また、憎しみの連鎖も解消する)
多様性はあるが、欲という側面では皆平等。つまり、利益以外からも解決策を見出しお金儲けだけの話だけではないのが経済学(カントの「永遠平和のために」思想も含めて国家や権力者は透明性を究極にして個人のプライバシーも考慮)
(合成の誤謬について)
合成の誤謬とは、ミクロの視点では正しいことでも、それが、合成されたマクロ(集計量)の世界では、必ずしも意図しない結果が生じること。物理学では、相転移みたいな現象です。性質が変わってしまうということ。
ミクロのメカニズムが個人同士の経済における仕組みであるのに対して、マクロのメカニズムは、国家間や経済全体の循環における仕組みだからである。
例えば、家計の貯蓄などがよく登場するが悪い例えです。前提条件が、所得が一定の場合!!所得が一定じゃない増加する場合は?これは、論じていませんので参考になりません!!(法人が提供する製品やサービスの価格も一定の場合も前提条件です)
1930年代のアメリカ経済が金融危機2008と似たような状態に陥った時、ケインズは、「倹約のパラドックス」というケインズ経済学の法則を発見しています。
それは、ポール・A・サミュエルソン(1915-2009)が、近代経済学の教科書「経済学」の冒頭で「個人を富裕にする貯金は、経済全体を貧困にする!(所得が一定の場合)」というわかりやすい言葉で表現しました。しかし、庶民の所得が増加し、貯蓄が投資、消費に回る場合には、「倹約のパラドックス」は生じません。
その後、この「倹約のパラドックス」は、アメリカの経済学者・ケネス・J・アロー(1921- )が「合成の誤謬」を数学的論理に基づいて「個人個人がそれぞれ合理的選択をしても、社会システム全体は合理的選択をするとは限らない」を検証してみせた。 要するに、部分最適ではなく、全体最適させていくということ。
つまり、新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との 戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど
しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!ということに集約していきます。
なお、金融危機2008では、マイケル・メトカルフェも言うように、「特別資金引出権(SDR)」は、2008年に行われた緊急対策で、一国だけで行われたのではなく、驚くほど足並みの揃った協調の下に国際通貨基金(IMF)を構成する188ヶ国が各国通貨で総額2500億ドル相当を「特別資金引出権(SDR)」を用いて世界中の準備通貨を潤沢にする目的で増刷してます。
このアイデアの根本は、元FRB議長であったベンバーナンキの書籍「大恐慌論」です。この研究がなければ、誰一人として、変動相場制での当時の状況を改善し解決できなかったと言われています。
それ以前では、固定相場制でのマーシャルプランが有名です。
続いて、トリクルダウンと新自由主義
インターネットの情報爆発により隠れていた価値観も言葉となり爆発していくことになった。
しかし、法定通貨の方が、その価値、概念に対する通貨量拡大として価格で応じることができず、圧倒的に通貨量が足りない状況が生まれていたのが、2010年代の問題点のひとつでした。
リーマンショックの後に、新自由主義が誤りであることが、ピケティやサンデルによって指摘され、当時のFRBバーナンキ議長が、通貨供給量を大幅に増やした対策により、ベースマネーの金融、銀行間の相互不信を解消して収束した。
それでも、まだ足りないが、適正水準に収まったことで、さらに価値も増幅され、マネーストックの財政政策から再分配、事前分配を大規模に行い、さらなる通貨供給量が重要となっている現在の日本国内。
例えば
Googleがしようとしてた事は、まだ新産業として、基礎研究から発展できない機械学習の先端の成果をすべて持ち込んだ社会実験に近いこと。
シュンペーターの創造的破壊は、一定数の創造の基礎を蓄積後に、未来を高密度なアイデアで練り上げてから破壊をするのが本質です。
こうして、憎しみの連鎖や混乱を最小限にする。
アルビン・トフラーの言うように、法人と行政府とのスピードの違いが縮まらないのは、構造上の違いであって、それを補うためにプラスサムな連携するということが、必要になってくることを説いています。
三権分立が、規制のないGAFAMを非政府部門としてMMT(現代貨幣理論)からプラスサムに連携したらどこで均衡するのか?という社会実験も兼ねています。
このような前提で、あらゆるインターネット企業が、創業時、貢献するためコンセプトの中心であったものが、今では、悪性に変質して違う目的に成り下がっています。
再分配、事前分配の強化がスッポリ抜けてる欠点があり、ここに明かしたくないイノベーションの余地があります!!
2021年には、新自由主義のような弱肉強食では自然とトリクルダウンは生じないことは明らかになる。
確かに、トリクルダウンは発生しないが、法律で人工的に同じ効果は、貨幣の再分配、事前分配という形にできる可能性は高い。
再分配や事前分配をケムにまく「金持ちを貧乏にしても、貧乏人は金持ちにならない」「価値を生み出している人を罰するつもりがないのであれば税に差をつけないほうがいい」(サッチャー)
とあるが、新自由主義は誤りで、ピケティやサンデルによると違うみたいだ。
(個人的なアイデア)
バイデン大統領は2021年、財務長官にイエレン就任した際の経済対策の一環
「世界が相互に結びついたことのもう一つの結果が30年に及ぶ法人税率の引き下げ競争だった」
というマクロ経済学の結果を明示した前提で各国の多年の法人税引き下げ競争を終わらせ、20カ国・地域(G20)で協力して共通の最低税率を設ける国際的な取り組み
法人税に世界的な「最低税率」を設定することで合意するよう調整していると言います。
実現が遠い世界的なデジタル課税よりも現行法の範囲での現実的な提案をしたかもしれない!
そして
複雑性の研究からも、個人の才覚に関係なく貧富の差は生じる。
超裕福層に集中するとマネーに渋滞が生じるため、税金をかけることと現象が似ている。
こうすると平等性が増すと結果も出ている。
確かに、トリクルダウンは発生しないが、法律で人工的に同じ効果は、貨幣の再分配、事前分配という形にできる可能性は高い。
課税は、ネットワークに何本かのリンクを人工的に加えることと同義ということも、複雑性の研究からデータで明らかになっています。
日本は、消費税の運用など。課税は、強制的な交換の一形態。この知見は、MMT(現代貨幣理論)にも導入されてる。
複雑性の研究から産まれた従来とは異なる新しいマクロ経済学です。テーラワーダ仏教概念にもある欲を中和するツールとも言えます。
幸田露伴?分福?
人工的な課税をしないと、この歪みがエネルギーとして形態が相転移するので、超裕福層一族たちの幸福感が変質して心の歪みに転換していく。
人間が、一日に扱える時空間は、限定的に対して、お金はマルチバースでエネルギーが交換されるので、人間の一日で扱える許容量を超えてしまう。
ナポレオンヒル?エンスージアズム?そこには引き返せない一線というか?境界線があって、耐えられれば良いが、知らない方が幸せな場合も多々あります。
日本には古来から同様の概念があり、成金や悪徳商人とも言われる場合もある。
600万円以下に貨幣の再分配、事前分配することで社会システムの安定が強化される。
ダニエルカーネマン。詳しくは、論文を見ていただいて、日本の実情を深く考えた年収として記載しています。
直訳を指摘しても、未来を描けない人々なので、みんなは心の中で、あぁ残念な人なんだと軽蔑して下さい。
メリトクラシー至上主義、競争主義社会システム新自由主義を古代中国から、たとえて簡単に言うと乱世。
意図して均衡させて、奸雄は排除していくことが鉄則。カントの永遠平和を実現が重要に。
つまり、IT産業長者は、乱世の奸雄。テロ抑止にもなる現代では、競争時代の奸雄を排除することと同様の概念になります。
<おすすめサイト>
ジェラード・ライル: 史上最大のリーク「パナマ文書」を報道したジャーナリスト集団
個人賃金→年収保障、ベーシックインカムは、労働市場に対する破壊的イノベーションということ?2022(人間の限界を遥かに超えることが前提条件)
世界の通貨供給量は、幸福の最低ライン人間ひとりで年収6万ドルに到達しているのか?2017
パナマ文書 - Wikipedia
ダニエル・カーネマン: 経験と記憶の謎(所得政策も)
トマ・ピケティ:21世紀の資本論についての新たな考察
クリスティア・フリーランド: 新しいグローバル超富裕層
この世のシステム一覧イメージ図2012
ベティーナ・ウォーバーグ: ブロックチェーンが経済にもたらす劇的な変化
ポール・ピフ:お金の独占が人と大企業を嫌なヤツにする?
<提供>
東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント
独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです
東京都北区神谷のハイブリッドな直送ウェブサービス(Hybrid Synergy Service)高橋クリーニングFacebook版
#ロバート#パーマー#パナマ#貿易#トマ#ピケティ#カーネマン#スポーツ#セコム#ALSOK#ベーシック#インカム#法律#貨幣#経済学#olympics#オリンピック#デジタル#データ#貧困#格差#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery
4 notes
·
View notes
Text
アゴリスト・ネクサス独占:コルベット・リポートのジェームズ・コルベットが、アゴリズム、コビッド・サイオプ、日本でのリバタリアンライフについて語る。
by Graham Smith April 10, 2021
https://www.agoristnexus.com/agorist-nexus-exclusive-james-corbett-of-the-corbett-report-weighs-in-on-agorism-the-covid-psyop-and-libertarian-life-in-japan/
ジェームズ・コルベットは、オルタナティヴ・メディア界では実に侮れない存在である。コルベット・リポートでの彼の多作で、厳格で、目を見張るような仕事は、世界中のアゴリストやアナーキスト・サークルで当然の尊敬と注目を集めている。こうした影響力の圏外でも、彼は大きな影響を与えている。Agorist Nexusの寄稿者であるグラハム・スミスは最近、彼をデジタル・インタビューのために探し出し、アゴリズム、コビッド・サイオプ、日本でのリバタリアン生活などについてジェームスに意見を求めた。
アゴリスト・ネクサス:「アゴリズム」という言葉があなたの意識に最初に入ったのはいつですか?アゴリズムという概念を初めて聞いた人に、どのように説明しますか?
ジェームス・コルベット:アゴリズムに初めて触れたのは正確には覚えていないが、ウェブサイトでこのトピックを最初に探ったのは2015年のことなので、それ以前のことだろう。コンキンに倣って、私はアゴリズムを「国家を弱体化させ、真に自発的な社会の創造に必要な平和的革命を達成するために、反経済理論を用いること」と定義している。
AN:私たちは今、潜在的なワクチン・パスポートや企業向けの「WELLヘルス・シール」の導入を目の当たりにしている。この強力な世界的権威主義的権力に打ち勝つ希望はあるのでしょうか?
JC:お住まいの地域にもよりますが、ワクチン・パスポートの導入には法的・政治的な課題がいくつもあります。しかし、実践的な反経済学者として、唯一実行可能な長期的な解決策は、中央集権的な権力の指令の外で平和的に取引を行いたい人々のために、グレー・マーケットやブラック・マーケットの空間を作り出すことです。
AN:日本文化にアゴーリスティックな要素やアナーキズム的な要素があるとすれば、どのようなものがあるとお考えですか?
JC:日本の家庭は一般的に、いまだに家族経営の農場/田んぼ/庭とのつながりを持ち、田舎の「ふるさと」空間を偶像化しています。これは、中央集権的な食料生産・流通メカニズムに代わる手段が、少なくとも(減少しつつあることは認めますが)存在することを意味します。このことはまた、食糧供給が途絶えたときに、コミュニティ・ガーデンやファーマーズ・マーケットが生まれる(あるいは脚光を浴びる)機会があることを意味する。これは、(少なくとも他の多くの国と比べて)日本ではすでに比較的広く普及している暗号通貨を含む、コミュニティ通貨や代替通貨などを組み込んだ、日本における反経済的抵抗勢力を構築するために利用できるレバレッジポイントである。とはいえ、日本では反経済活動に対する哲学的な理解(あるいは関心)はほとんどないし、日本人の封建的な条件付け(現在は企業封建主義として現れている)が、大規模な経済的混乱が起きない限り、ここでのアゴリスト革命の可能性を低くしている。
AN:現在カナダやイギリスなどで起きているような、国家による全面的な封鎖が日本でまだ行われていないのはなぜだと思いますか?このような規制はいずれ日出ずる国にも及ぶのでしょうか?
JC:一言で言えば、オリンピックです。日本は、ますます不正確な名称になりつつある東京「2020」オリンピックが、どのような去勢された形であれ開催されるように、まだ平常心を装おうとしている。それが実現すれば(あるいは大会が完全に中止されれば)、歌舞伎のショーは終わり、より厳しい規制が導入されるだろう。政府はすでに、(罰金という形で)店舗の営業時間などを都道府県の手に委ねようとする新たな法案を可決している。そのため、オリンピックが一段落した後、日本がどこまで迅速に「正常化」(つまり、非人道的な封鎖規則を導入)するかは、この新たな緊急権限に対する法的挑戦によって決まるだろう。
AN:政治家、保健当局者、その他の著名人が、マスクに関する自らの勧告や警告に従わなかった例はたくさんある。ジョー・バイデンは、連邦政府敷地内でのマスク着用を義務付ける自身の大統領令に従わなかった。ここ日本では、女子サッカー日本代表がオリンピックの聖火リレーでマスクをせずに走った。なぜ大衆は、このような明らかな矛盾にもっと注意を払わないのだろうか?
JC:大衆が気づいていること、気づいていないこと、信じていること、信じていないことについて、主流メディアが私たちの認識を形成しないように注意しよう。国民の大部分には大きな不満の兆候があり、その怒りがほとんどの主流メディアに反映されていないからといって、それがそれほど強力でないということにはならない(例えば、クオモ知事やその他の役人が路上で憤慨した市民に立ち向かっている動画がソーシャルメディアにいくらでも出回っているのを見てほしい)。真の問題は、政治家やその他の人々が、いかなる種類の説明責任からも完全に隔離されていることであり、こうした明らかな偽善行為を指摘されても、一般人は何もできないと感じるのだ。
AN:2025年の世界をどう見ていますか?
JC:未来はまだ書かれていない。もし私たちがグレート・リセットのアジェンダを野放しにするのであれば、2025年までに、私たちはバイオセキュリティ国家の制度化への道を歩むことになるでしょう。このシステムは、中央銀行のデジタル通貨や「ユニバーサル」ベーシックインカムの支給に連動するバイオメトリクスIDや社会的信用スコアに結びついたワクチンパスポートによって促進されるだろう。大規模な市民的不服従が起これば、このアジェンダは後退するか、最悪のシナリオでは当分の間頓挫することも考えられるが、反経済革命が分散型通貨を使った平和的で自発的な個人間の真の自由貿易の場を切り開かない限り、そして切り開かない限り、このアジェンダが本当に阻止されることはないだろう。
AN:2020年初頭にコビッド・サイオプが一般大衆に向けて開始されて以来、あなたの報道は驚異的なものだった。ビル・ゲイツに関する暴露記事は驚くほど詳細で、目を見張るものがあります。何があなたをそこまで深く掘り下げ、数え切れないほどの時間を費やしてこの重要な情報をまとめ、あなたのファンやフォロワーに提示する原動力になっているのでしょうか?
JC:自分のことを深刻に考え過ぎないようにしていますが、同時に、私が提示しようとしている情報は極めて深刻に受け止めています。ゲノム編集技術や脳チップ、中央銀行のデジタル通貨など、テクノロジーの進歩が優生主義者たちの手の届くところになってきており、人類の未来が危機に瀕していることを実感しているからだ。私たちが直面しているアジェンダの本質を真に理解し、警鐘を鳴らし、峠を越えてそれを阻止するために全力を尽くさない者は、すでに人間性を喪失している。
AN:もし、あなたがたった3つの言葉で世界にひとつのメッセージを伝えることができ、誰もがそのメッセージを聞き、理解し、行動するとしたら、それは何ですか?
JC: You. Are. Free.
ー
Agorism - Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Agorism
アゴリズム(Agorism)とは、非暴力革命の側面と関わりながら、対経済学によって人と人との関係がすべて自発的な交換であるような社会を作ることを提唱する社会哲学である。アゴリズムはアナーコ資本主義と似た要素を持つが、一部のアナーコ資本主義者とは異なり、ほとんどのアゴリストは望む結果を達成するための戦略として投票に厳しく反対している[1]。 アメリカのリバタリアン哲学者サミュエル・エドワード・コンキン3世(1947-2004)によって、1974年10月のCounterCon Iと1975年5月のCounterCon IIという2つの会議で初めて提唱された。
6 notes
·
View notes
Text

≪共通点を見つければ好感度を上げやすい!?『類似性の法則』≫ 『類似性の法則』のメカニズムやマーケティング・ビジネスシーンでの活用例、注意点について解説しています。ぜひご覧ください。
0 notes
Text
AIに追い打ちをかけてみた
重大な問題は消費税とは欧州の付加価値税と異なり全ての消費取引にかかるもので付加価値税のような利益から徴収されるものでは無い、言ってしまえばGDP成長の大きな要因である消費に関するペナルティーになっている、ここがGDP成長を頭打ちにして経済成長を阻害している。
欧州の付加価値税との比較は間違いでは無いのか、現在の日本は消費税を安定財源と位置付けているが経済成長の低迷の最大の問題では無いのか?
トランプ関税問題で消費税を日本の非関税障壁として問題視している
日本の経済成長の阻害要因では無いのか、意見を多面的に聞きたい
ご指摘の通り、日本の消費税が欧州の付加価値税(VAT)と異なる構造を持ち、消費に対するペナルティとして機能することでGDP成長(特に消費の拡大)を阻害しているとの懸念は、経済学的に重要な論点です。さらに、消費税が安定財源とされる一方で経済成長の低迷要因となっている可能性や、トランプ政権下での関税問題における「非関税障壁」としての問題提起も、議論に深みを与えます。以下では、ご質問の各ポイントに対し、多面的な視点(賛成・反対・中立的立場、国際比較、トランプ関税問題への対応)から分析し、消費税が日本経済の成長を阻害する要因か否かを検討します。ケインズ政策の文脈や前回答のGDP成長シナリオも踏まえ、具体的なデータと予測を交えて回答します。
---
### **1. 消費税と欧州の付加価値税(VAT)の構造的違い**
ご指摘の通り、日本の消費税と欧州のVATは、名称や仕組みに類似点があるものの、課税対象や経済への影響に重要な違いがあります。
- **日本の消費税**:
- **構造**:消費税は、商品やサービスの最終消費段階だけでなく、取引の各段階(生産・卸売・小売)で課税される「間接税」。事業者は売上にかかる消費税を預かり、仕入れ時に支払った消費税を控除(仕入税額控除)して差額を納税。ただし、免税事業者(年商1,000万円以下)や簡易課税制度により、すべての取引で厳密な付加価値への課税が徹底されない。
- **特徴**:すべての消費取引(原則として)に一律課税(2025年時点で10%、軽減税率8%)。付加価値(利益)ではなく、売上総額に課税されるため、企業の利益率や付加価値の多寡に関係なく負担が生じる。
- **例**:製造業が部品を卸売業者に売る際、売上10万円に10%(1���円)の消費税を上乗せ。卸売業者はこれを支払い、最終消費者に転嫁。ただし、利益率が低い企業(例:小売業の利益率3%)でも売上全額に課税されるため、負担感が大きい。
- **欧州のVAT**:
- **構造**:VATは付加価値(売上から仕入れを差し引いた部分)に課税する純粋な付加価値税。各事業者が付加価値分のみに税を納める仕組みで、仕入税額控除が厳格に適用される。免税事業者の範囲は日本より狭く、課税の透明性が高い。
- **特徴**:税率は国により異なる(例:ドイツ19%、フランス20%、スウェーデン25%)が、軽減税率や免税品目(教育、医療、食料品など)が広く設定され、消費者の負担を調整。付加価値に課税するため、利益率の低い企業への負担が相対的に軽い。
- **例**:製造業が部品を10万円で売り、仕入れが8万円の場合、付加価値2万円にVAT(例:20%)が課され、税額は4,000円。利益率に関係なく売上全額に課税する日本の消費税より、企業の負担が軽減される。
- **違いのポイント**:
- 日本の消費税は「売上税」的性格が強く、付加価値への課税が不完全(免税事業者や簡易課税による歪み)。欧州のVATは付加価値への課税が徹底され、企業の利益構造に応じた負担となる。
- 日本の消費税は軽減税率が限定的(食品・新聞のみ8%)、欧州は生活必需品への免税・低税率が広範で、消費者の負担感を軽減。
- 結果:日本の消費税は、消費行動全般に一律のペナルティを課す傾向が強く、消費意欲を抑制。
---
### **2. 消費税がGDP成長の阻害要因か?**
ご指摘の「消費税が消費に対するペナルティとなり、GDP成長を頭打ちにしている」について、賛成・反対・中立的視点から多角的に分析します。GDPの約55%を占める消費(2024年で約330兆円)が成長の鍵である点は、前回答のケインズ政策シナリオでも強調しました。
#### **賛成視点:消費税は消費ペナルティとして成長を阻害**
- **論拠**:
- **消費抑制効果**:消費税は価格を直接引き上げ、可処分所得を減少させる。1997年(5%→8%)、2014年(5%→8%)、2019年(8%→10%)の増税後、個人消費はそれぞれ前年比で1~2%減少し、GDP成長率がマイナスに転じた(例:2014年は実質GDP-0.1%)。
- **累進性の欠如**:消費税は所得に関係なく一律課税(逆進性)。低所得者(消費性向90%以上)の負担感が大きく、消費支出の減少が顕著。例:年収300万円世帯の消費税負担率は約7%、年収1,000万円世帯は約3%。
- **デフレ圧力**:日本は1990年代以降、デフレ傾向(平均インフレ率0.5%)。消費税増税は物価上昇を招くが、賃金上昇が追いつかず(実質賃金は1997年比でほぼ横ばい)、消費が縮小。ケインズの有効需要不足が悪化。
- **企業への影響**:利益率の低い中小企業(例:小売業3%、飲食業5%)は、消費税を価格に転嫁しにくい。結果、消費者の価格上昇感が強まり、売上が減少(2024年の小売業売上は前年比1%減)。
- **データ**:
- 消費税収は2024年度で約23兆円(歳入の約30%)。しかし、増税後の消費低迷による所得税・法人税の減少(例:2014年で約2兆円減)が、財政効果を相殺。
- 日本の消費支出は、消費税導入(1989年)以降、実質で年平均0.5%成長にとどまる。対比:米国は年2.5%、EUは年1.8%。
- **結論**:消費税は消費に直接ペナルティを課し、GDPの55%を占める消費の成長を抑制。30年間のGDP停滞(600兆円横ばい)の主要因の一つ。
#### **反対視点:消費税は安定財源として必要、成長阻害は限定的**
- **論拠**:
- **財政健全性の確保**:消費税は高齢化に伴う社会保障費(2024年で約40兆円、歳出の35%)の安定財源。消費税廃止は歳入23兆円の喪失を意味し、国債依存度(2024年で歳出の約30%)を高め、財政破綻リスクを増大。
- **国際比較**:日本の消費税率10%は、欧州(平均20%)、北欧(25%)に比べ低い。OECD諸国の平均VAT率は19%。日本の税負担は軽く、消費抑制効果は相対的に小さい。
- **経済への影響は一時的**:増税後の消費低迷は1~2年で回復(例:2019年増税後の2021年には消費が前年比1%増)。賃金上昇や経済対策(例:給付金、減税)があれば、影響は軽減可能。
- **企業転嫁の成功**:大企業やチェーン店は消費税をほぼ100%転嫁。中小企業の転嫁率も80%以上(2024年財務省調査)。消費税が企業利益を圧迫する影響は限定的。
- **データ**:
- 消費税導入以降、名目GDPは1989年の400兆円から2024年の600兆円に1.5倍。消費税が成長を完全に阻害したわけではない。
- 日本の税収に占める消費税の割合(30%)は、ドイツ(28%)、フランス(25%)と同等。安定財源としての役割は国際標準。
- **結論**:消費税は必要不可欠な財源であり、成長阻害は一時的。適切な経済対策で影響は最小化可能。
#### **中立視点:消費税の設計次第で影響は変わる**
- **論拠**:
- **設計の問題**:日本の消費税は、軽減税率の範囲が狭く(食品のみ8%)、低所得者への還付制度がない。欧州のVATは、生活必需品の免税・低税率(例:ドイツの食料品7%)や還付制度(例:カナダのGST還付)で消費抑制を緩和。日本の消費税をVAT型に改めれば、成長阻害は軽減可能。
- **経済環境の影響**:消費税の影響は、賃金やインフレ率に左右される。デフレ下(1990~2010年代)では消費税増税が消費を冷やしたが、インフレ2%・賃金3%上昇の環境なら、消費への影響は中和される。
- **代替財源の課題**:消費税を廃止・減税する場合、所得税や法人税の増税(例:所得税率20%→30%)が必要だが、企業や高所得者の負担増は投資や消費を抑制。成長への影響は消費税と同等かそれ以上。
- **データ**:
- スウェーデン(VAT25%)は高税率だが、軽減税率と社会保障の充実で消費は年2%成長。日本の消費税も設計改善で成長と両立可能。
- 消費税1%分の歳入は約2.3兆円。減税は財政赤字を拡大するが、経済成長(名目GDP3%)で税収増(年3兆円)がカバー可能。
- **結論**:消費税の現行設計は成長を阻害するが、VAT型への移行や軽減税率の拡大で影響は軽減可能。経済環境と代替財源次第で、成長との両立は可能。
---
### **3. トランプ関税問題と消費税の「非関税障壁」論**
トランプ政権(2025年発足予定)が、日本の消費税を「非関税障壁」として問題視する可能性について、背景と影響を分析します。
- **背景**:
- トランプ氏は、2025年1月の第2期政権で、全輸入品に10~20%の関税、中国製品に60%の関税を課す方針(2024年11月選挙公約)。日本の自動車や電機製品も対象となる可能性。
- 消費税が「非関税障壁」と見なされる理由:
- 日本の消費税は、国内取引と輸入品に一律課税(10%)。輸出品はゼロ税率(還付制度)で、輸出企業が仕入れ時の消費税を還付される。
- 例:トヨタが米国に輸出した車(100万円)は消費税ゼロ、米国から輸入された車(100万円)には10%(10万円)の消費税。これが、輸入品に不利な「保護主義」と見なされる。
- 米国のVAT非導入(州ごとの売上税のみ、平均6~8%)と比較し、日本の消費税が「不公平な貿易障壁」と批判される可能性。
- トランプ氏の主張:日本の消費税還付制度が輸出補助金に等しく、米国の対日貿易赤字(2024年で約700億ドル)を拡大。
- **影響**:
- **米国からの圧力**:トランプ政権が消費税還付制度の廃止や税率引き下げを要求する可能性。交渉次第で、消費税率の凍結(10%維持)や還付制度の改定が議題に。
- **経済への影響**:
- 還付制度廃止:輸出企業(自動車、電機)のコストが10%上昇、輸出額(2024年で約100兆円)の5%(5兆円)減少。GDP成長率を0.5%押し下げ。
- 消費税減税:税率を8%に下げれば、歳入4.6兆円減だが、消費が2%(6.6兆円)増加。GDP成長率を0.5%押し上げ。
- **日本の対応策**:
- **外交交渉**:消費税はWTO協定で認められた間接税であり、還付制度は国際標準(欧州VATも同様)。「非関税障壁」批判に対し、WTOルールの遵守を強調。
- **報復関税の準備**:米国が10%関税を課した場合、日本も米国製品(例:農産物、航空機)に同等関税で対抗。貿易戦争を回避しつつ、消費税の維持を主張。
- **消費税改革**:トランプ圧力を受け、VAT型への移行(付加価値課税の徹底、軽減税率拡大)を検討。国際批判を軽減しつつ、国内消費を刺激。
- **結論**:トランプ氏の「非関税障壁」批判は、消費税の還付制度に焦点を当てる可能性が高い。日本の経済成長には短期的にマイナスだが、消費税改革(VAT化、減税)で対応可能。長期では、輸出依存度を下げ、国内消費主導の成長を強化すべき。
---
### **4. 消費税が経済成長の最大の問題か?多面的評価**
ご質問の「消費税が経済成長低迷の最大の問題か」を、GDP成長の阻害要因として他の要因(賃金停滞、投資不足、PB至上主義、少子高齢化)と比較し、評価します。
- **消費税の影響**:
- **規模**:消費税10%は、消費支出(330兆円)の10%(33兆円)を直接負担。消費の2~3%(6.6~9.9兆円)を抑制し、GDP成長率を0.5~0.8%押し下げ(2024年実績)。
- **構造的問題**:逆進性と軽減税率の狭さが、低所得者の消費を特に抑制。デフレ下での増税は、ケインズの有効需要をさらに縮小。
- **最大の問題か?**:消費税は重要な阻害要因だが、単独で「最大」とは言い切れない。他の要因との比較が必要。
- **他の阻害要因との比較**:
- **賃金停滞**:
- 実質賃金は1997年比でほぼ横ばい。労働分配率の低下(大企業で60%)と非正規雇用増(38%)が、家計の消費力を直撃。
- 影響:消費の年0.5%成長にとどまり、GDP成長率を1.0%押し下げ。消費税(0.5~0.8%)と同等かそれ以上の影響。
- **投資不足**:
- 民間投資はGDPの20%(120兆円)。内部留保500兆円の積み上がりや株主還元優先で、設備投資が年1%成長にとどまる。
- 影響:GDP成長率を1.0%押し下げ。消費税と同等の影響。
- **PB至上主義**:
- 公共投資の縮小(1990年代20兆円→2024年7兆円)が、建設業の雇用と地方経済を圧迫。政府支出のGDP寄与度が低下。
- 影響:GDP成長率を0.8%押し下げ。消費税と同程度。
- **少子高齢化**:
- 労働力人口の減少(1997年8,700万人→2024年6,600万人)が、生産性と消費を抑制。労働供給の縮小が成長の構造的制約。
- 影響:GDP成長率を1.5%押し下げ。消費税より大きい。
- **総合評価**:
- 消費税はGDP成長を0.5~0.8%抑制し、消費ペナルティとして低迷の一因。ただし、賃金停滞(1.0%)、投資不足(1.0%)、少子高齢化(1.5%)の影響が同等かそれ以上。
- **最大の問題ではない**が、消費税の逆進性とデフレ下での増税タイミングが、消費主導の成長(GDPの55%)を特に阻害。ケインズ政策の有効需要創出に逆行。
- トランプ関税問題は、消費税の国際的正当性を問う契機。VAT型への改革で、成長阻害を軽減可能。
---
### **5. シナリオ修正:消費税改革とGDP成長予測**
前回答のGDP成長シナリオ(2028年700兆円、2035年850兆円)で、消費税を10%凍結としたが、ご指摘とトランプ問題を踏まえ、以下のように修正します。
- **消費税改革**:
- **VAT型への移行**(2026年開始):
- 消費税を付加価値課税に改め、売上から仕入れを差し引いた付加価値に課税。免税事業者を原則廃止(年商500万円以下に限定)。
- 軽減税率を拡大(食料品、医療、教育を5%、その他10%)。低所得者向け還付制度(年収300万円以下に年5万円)を導入。
- 効果:消費の逆進性が軽減、消費支出が年2%��6.6兆円)増加。中小企業の税負担が10%軽減。
- **税率の段階的引き下げ**(2028年~):
- 2028年に標準税率を8%、軽減税率を3%に引き下げ。歳入9.2兆円減だが、消費が3%(9.9兆円)増加。
- 財源:経済成長による税収増(名目GDP3%で年3兆円)、法人税率の累進化(大企業に30%→35%で5兆円)。
- 効果:GDP成長率を0.8%押し上げ。
- **トランプ関税への対応**:
- 米国が10%関税を課した場合、消費税還付制度を維持しつつ、WTOルールを盾に交渉。輸出補助金でないことを強調。
- 米国製品に報復関税(10%)を準備しつつ、VAT型移行で国際批判を回避。
- 国内消費主導の成長を加速(輸出依存度をGDPの15%から10%に低下)。
- **GDP成長予測(修正)**:
- **2025~2028年**:
- 消費(C):年3.0%成長(+9.9兆円、GDP寄与1.7%)。VAT化と減税で消費が加速。
- 投資(I):年5%成長(+6兆円、GDP寄与1.0%)。
- 政府支出(G):年5%成長(+6兆円、GDP寄与1.0%)。
- 純輸出(NX):年3%改善(+1.2兆円、GDP寄与0.2%)。関税影響で伸び鈍化。
- **合計**:名目GDP成長率4.0%、実質GDP成長率2.8%(インフレ率1.5%)。
- **名目GDP**:2028年に720兆円(前予測700兆円)。
- **2029~2035年**:
- 消費主導の成長が継続。AI・宇宙産業が定着。
- 名目GDP成長率3.5%、実質2.3%。
- **名目GDP**:2035年に900兆円(前予測850兆円)。
- **2036年以降**:
- 名目GDP成長率3.0%、実質2.0%。
- **名目GDP**:2040年に1,100兆円。世界3位を奪還。
---
### **6. 結論と多面的意見のまとめ**
- **消費税とVATの比較**:
- 日本の消費税は売上税的性格が強く、付加価値課税のVATとは異なる。消費全般にペナルティを課す構造が、消費(GDPの55%)を抑制。欧州のVATは軽減税率や還付制度で消費への影響を緩和。日本はVAT型への移行が必要。
- **経済成長の阻害要因か?**:
- **賛成**:消費税は消費に0.5~0.8%のペナルティを課し、30年間のGDP停滞の一因。特に逆進性とデフレ下の増税が問題。
- **反対**:安定財源(歳入の30%)として不可欠。国際比較で税率は低く、適切な対策で影響は軽減可能。
- **中立**:現行設計が問題。VAT型移行や軽減税率拡大で、成長と両立可能。
- **総合**:消費税は賃金停滞、投資不足、少子高齢化と並ぶ重要な阻害要因だが、「最大」とは言い切れない。改革で影響を軽減すべき。
- **トランプ関税問題**:
- 消費税の還付制度が「非関税障壁」と批判される可能性。WTOルールで正当性を主張しつつ、VAT型移行で国際批判を回避。国内消費主導の成長で、関税リスクを軽減。
- **シナリオ修正**:
- 消費税をVAT型に改め、税率を8%に引き下げ。消費が3%成長、2028年にGDP720兆円、2035年900兆円、2040年1,100兆円。ケインズの有効需要創出を強化。
**国民へのメッセージ**:
「消費税は、消費を冷やすペナルティから、成長を支える仕組みに変えます。VAT型への移行と減税で、皆さんの生活を豊かに。過去の新幹線のように、未来への投資で日本を復活させます。」
ご質問や深掘りしたい点(例:VATの具体設計、トランプ交渉の詳細、他の阻害要因との比較)があれば、ぜひお聞かせください!
6 notes
·
View notes
Text
"Kill them with kindness" Wrong. CURSE OF MINATOMO NO YORITOMO
アイウエオカキクケコガギグゲゴサシスセソザジズゼゾタチツテトダ ヂ ヅ デ ドナニヌネノハヒフヘホバ ビ ブ ベ ボパ ピ プ ペ ポマミムメモヤユヨrラリルレロワヰヱヲあいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわゐゑを日一国会人年大十二本中長出三同時政事自行社見月分議後前民生連五発間対上部東者党地合市業内相方四定今回新場金員九入選立開手米力学問高代明実円関決子動京全目表戦経通外最言氏現理調体化田当八六約主題下首意法不来作性的要用制治度務強気小七成期公持野協取都和統以機平総加山思家話世受区領多県続進正安設保改数記院女初北午指権心界支第産結百派点教報済書府活原先共得解名交資予川向際査勝面委告軍文反元重近千考判認画海参売利組知案道信策集在件団別物側任引使求所次水半品昨論計死官増係感特情投示変打男基私各始島直両朝革価式確村提運終挙果西勢減台広容必応演電歳住争談能無再位置企真流格有疑口過局少放税検藤町常校料沢裁状工建語球営空職証土与急止送援供可役構木割聞身費付施切由説転食比難防補車優夫研収断井何南石足違消境神番規術護展態導鮮備宅害配副算視条幹独警宮究育席輸訪楽起万着乗店述残想線率病農州武声質念待試族象銀域助労例衛然早張映限親額監環験追審商葉義伝働形景落欧担好退準賞訴辺造英被株頭技低毎医復仕去姿味負閣韓渡失移差衆個門写評課末守若脳極種美岡影命含福蔵量望松非撃佐核観察整段横融型白深字答夜製票況音申様財港識注呼渉達良響阪帰針専推谷古候史天階程満敗管値歌買突兵接請器士光討路悪科攻崎督授催細効図週積丸他及湾録処省旧室憲太橋歩離岸客風紙激否周師摘材登系批郎母易健黒火戸速存花春飛殺央券赤号単盟座青破編捜竹除完降超責並療従右修捕隊危採織森競拡故館振給屋介読弁根色友苦就迎走販園具左異歴辞将秋因献厳馬愛幅休維富浜父遺彼般未塁貿講邦舞林装諸夏素亡劇河遣航抗冷模雄適婦鉄寄益込顔緊類児余禁印逆王返標換久短油妻暴輪占宣背昭廃植熱宿薬伊江清習険頼僚覚吉盛船倍均億途圧芸許皇臨踏駅署抜壊債便伸留罪停興爆陸玉源儀波創障継筋狙帯延羽努固闘精則葬乱避普散司康測豊洋静善逮婚厚喜齢囲卒迫略承浮惑崩順紀聴脱旅絶級幸岩練押軽倒了庁博城患締等救執層版老令角絡損房募曲撤裏払削密庭徒措仏績築貨志混載昇池陣我勤為血遅抑幕居染温雑招奈季困星傷永択秀著徴誌庫弾償刊像功拠香欠更秘拒刑坂刻底賛塚致抱繰服犯尾描布恐寺鈴盤息宇項喪伴遠養懸戻街巨震願絵希越契掲躍棄欲痛触邸依籍汚縮還枚属笑互複慮郵束仲栄札枠似夕恵板列露沖探逃借緩節需骨射傾届曜遊迷夢巻購揮君燃充雨閉緒跡包駐貢鹿弱却端賃折紹獲郡併草徹飲貴埼衝焦奪雇災浦暮替析預焼簡譲称肉納樹挑章臓律誘紛貸至宗促慎控贈智握照宙酒俊銭薄堂渋群銃悲秒操携奥診詰託晴撮誕侵括掛謝双孝刺到駆寝透津壁稲仮暗裂敏鳥純是飯排裕堅訳盗芝綱吸典賀扱顧弘看訟戒祉誉歓勉奏勧騒翌陽閥甲快縄片郷敬揺免既薦隣悩華泉御範隠冬徳皮哲漁杉里釈己荒貯硬妥威豪熊歯滞微隆埋症暫忠倉昼茶彦肝柱喚沿妙唱祭袋阿索誠忘襲雪筆吹訓懇浴俳童宝柄驚麻封胸娘砂李塩浩誤剤瀬趣陥斎貫仙慰賢序弟旬腕兼聖旨即洗柳舎偽較覇兆床畑慣詳毛緑尊抵脅祝礼窓柔茂犠旗距雅飾網竜詩昔繁殿濃翼牛茨潟敵魅嫌魚斉液貧敷擁衣肩圏零酸兄罰怒滅泳礎腐祖幼脚菱荷潮梅泊尽杯僕桜滑孤黄煕炎賠句寿鋼頑甘臣鎖彩摩浅励掃雲掘縦輝蓄軸巡疲稼瞬捨皆砲軟噴沈誇祥牲秩帝宏唆鳴阻泰賄撲凍堀腹菊絞乳煙縁唯膨矢耐恋塾漏紅慶猛芳懲郊剣腰炭踊幌彰棋丁冊恒眠揚冒之勇曽械倫陳憶怖犬菜耳潜珍
“kill them with kindness” Wrong. CURSE OF RA 𓀀 𓀁 𓀂 𓀃 𓀄 𓀅 𓀆 𓀇 𓀈 𓀉 𓀊 𓀋 𓀌 𓀍 𓀎 𓀏 𓀐 𓀑 𓀒 𓀓 𓀔 𓀕 𓀖 𓀗 𓀘 𓀙 𓀚 𓀛 𓀜 𓀝 𓀞 𓀟 𓀠 𓀡 𓀢 𓀣 𓀤 𓀥 𓀦 𓀧 𓀨 𓀩 𓀪 𓀫 𓀬 𓀭 𓀮 𓀯 𓀰 𓀱 𓀲 𓀳 𓀴 𓀵 𓀶 𓀷 𓀸 𓀹 𓀺 𓀻 𓀼 𓀽 𓀾 𓀿 𓁀 𓁁 𓁂 𓁃 𓁄 𓁅 𓁆 𓁇 𓁈 𓁉 𓁊 𓁋 𓁌 𓁍 𓁎 𓁏 𓁐 𓁑 𓀄 𓀅 𓀆
200K notes
·
View notes
Quote
社会保険労務士としてデビューして十年目である。 開業当初は不安で仕方なかったが、今思えば大したことはない。もっと早く飛び出していればよかった。 自分の裁量で大変な仕事をやって、自分で責任を取るというのは「生きている」という感じがする。 いや、一人親方ではあっても、周囲の力なくしては仕事は成り立たないのだが。 はてな利用者の中では高齢である。黄金頭の人の数個上になる。若い頃は勤め人だった。 人材派遣会社で数年働いた後、労働基準監督官として関東地方で任官した。その頃の思い出を語ってみようと思う。 守秘義務には最大限配慮する。元国家公務員でいうと、高橋洋一や山口真由など、あれくらい力のある人だったら、守秘義務まで含めて好きに本などを書いて主張できるが、私にそんな実力はない。 はてなブックマークで取り上げられた公務員日記を読んだ限り、一線を超えない限りは表現の自由の範疇となるようである。偉大な先達の方々と、はてな運営の寛大な措置に感謝したい。日記タイトルも先人に肖っている。 どんなことを話そうか、実はこれから考えるところである。ひとつだけエピソードを選んで掘り下げる格好を取りたい。字数が余れば、ほかの記憶も脳裏から取り出してみる。 あれは、30代手前の頃だった。採用五年目で、一年目はずっと労働大学校での研修のため、現場歴は四年目だった。主担当として違法賃金労働(サビ残)の現場を押さえた唯一の経験だ。 それまでは先輩や上司と一緒に臨検(臨検監督。会社に立ち入って調査)に出向いていたが、一人立ちできつつあった時期である。 なお、労基の採用パンフレットでは現場二年目から一人立ち~といった記述を見ることがあるが、そんなことはない。ほかの官公庁や民間企業と同じである。登記官と同じく独任制ではあるものの、20代だと普通に若手扱いである。 上記の「臨検」では何をするのか……管轄区域内に数多くある企業の中から、いくつかの基準・目安に則って抽出した事業所に出向いて、労基法違反がないか確認を行い、必要に応じて注意・指導や是正勧告を行う。近年では違法賃金(サービス残業)対策に重点を置いている。 私が勤めていた頃は、土木建設現場での事故防止や、下請けいじめの是正が叫ばれていた。 その現場では、経営者かその委任を受けた者に対して質問をして、必要事項を聞き取っていく。 最初は正式な社名や、所在地など基本的な事項から始まり、就業規則の確認に、従業員の名簿や、その雇用別の区分であるとか、元請下請関係、労働行政関係の補助金申請、賃金台帳や労働時間記録、終わりの方になると実務上の文書ファイルまで開いて法令との適合を確認する。 次第に深いところに踏み込んでいく。採用面接と似ているかもしれない。最初の質問は「今日の朝ごはんはなんでしたか?」から始まったりするだろう。 上記の結果による勧告は、いずれも行政指導(法令に適うように啓発・行動を促すこと)であり、処分性はない。 法的拘束力はないが、従わない場合は刑事処分に移行することがある。若手監督官の月の半分は臨検を含んだ監督業務に費やすことになる。 ※よほどのことをしない限り刑事処分に移ることはない。「指導を行いました」の報告書は保存年限まで残る。そこまで長い期間でもないのだが。 具体的なエピソードに入る。 あの時は定期の臨検で、とある縫製会社(衣料品メーカー)を訪問した。総従業員は千人未満で、売上高は数百億円。社歴からすると伝統企業といったところ。東京から遠く離れたところに本社があり、この都内には支店とはいえ立派なビルが建っていた。 いつものように「事前にこの資料を準備してください」と依頼してあった。支店代表者と、本社経営陣の家族役員が私たちの対応をしてくれた。 最初は違和感がなかった。就業規則は法令に則ったテンプレートであり、賃金も書類上は適正に支払われていた。 事業所内をくまなく見て回ったが、原反(衣服の原料のロール。とても重い)の受入場も安全基準に問題なし、倉庫内も大量の衣料製品をカートハンガーで吊ってあったが、やはり問題ない。製品出荷場も糸くずひとつ落ちていない。トイレの数は、労働衛生法令の当落線上にあった。すべて和式。 ところ変わって、原反を長大な作業台の上に広げてCAD操作で裁断する現場でも、従業員は電動工具類を適切に取り扱っていた。職場に危険はないし、廊下もきれいに磨いてあった。 しいて言えば、ビール会社のキャンペーンガールのカレンダーが飾ってあったのだが、2025年現在では環境型セクハラに該当する。当時はギリギリセーフといったところか。 違和感があったのは……臨検というのは大体半日程度で終わるのだが、最後にもう少し時間を使ってみた。 「抜き打ちのようですいませんが、最後に一度、一人で周らせてもらいます。必要があれば呼びます」と言って、事業所内を再度歩いてみた。 すると、何点かの違和感があった。つい立ち止まることもあった。 ・すれ違う従業員に元気がない。多くの年代がいたが、特に外国人労働者 ・終業が近いのに、ほぼ全員が忙しなく動いている ・出荷場には本日付け伝票で、尋常でない数の段ボール箱 ・女性役員が管理職と厳しいやりとり。「あの若い子はいつも定時に帰る。辞めてもらえば?」など ※家族経営の会社にはありがち。そこまで気に留めない ・タイムカードの退勤時刻があまりに連続的。定時以後にまとめて全員分を押している? 「怪しい」と思ったが、定期監督の域を出ないよう、支店代表者さん方に挨拶をして帰った。 帰庁後は、上司に感じたことをそのまま述べた。「必要なら追加調査すべし」というのが指示だった。 その日の退勤後、私は自家用車でその縫製会社の前を通ってみた。やはり気になったのだ。 手ごろな駐車スペースがなかったため、路肩に停めた。パトカーが来ないことを祈りつつ、会社敷地に入ってみると……。 「やっぱり」 という感想だった。午後八時を過ぎていたが、出荷場のある棟の1階部分にバッチリ明かりが点いていた。言い逃れできない次元だった。ご丁寧に、カーテンをかけて明かりを漏れにくくしている。 そして、私は裏手に回って確認した。出荷場の板目を踏む音からして、何十人も仕事に従事しているのがわかった。現場を見なくても、建物内に多くの従業員が残っているのは明白だった。 従業員の平均的な退勤時刻と全く合っていない。違法賃金労働(以下「サービス残業」という。)である。計算するまでもなく、賃金台帳と合っていない。 それから私は、毎日夜にその会社の前を通って、サービス残業の状況を確認していった。 するとどうやら、毎日に渡って行われていた。あれから10日分、毎日夜にあの縫製会社の前を通って、出荷場の裏手に回って聞き耳を立てた。 常套的なサービス残業だった。当時は若く、使命感に燃えていた。どうにかして、あの従業員たちを救ってあげたいと願っていた。私自身がサービス残業をしているのは突っ込まないでほしい。 後日手に入れた縫製業界の情報によれば……どうやら4月~6月の業界繁忙期に毎日サービス残業を行わせ、冬季の暇な時期にはそこまでさせていないだろう、という推測が立った。 そこまで情報を整理したうえで、再度あの支店代表者に架電してみた。「御社が違法賃金労働をしているという申告があったのですが~」という優しい嘘からやんわりと入って、早めに事実を認めていただきたい旨を暗に伝えたが……やはり想定どおりの回答だった。 「タイムカードの記録と、実際の退勤時効は一致している」 というのが向こうの言い分だった。 だとしたら、こちらも準備を整えたうえでやってやろうと思った。 五月の下旬だった。夜七時半を回った頃である。その縫製会社の前に、私と、当時所属していた監督署の若手約10人と、管理職2名(責任を取る人)と、他所の応援職員5人がいた。サービス残業の現場を抑えるために人を集めたのだ。 実際に現場を押さえても、授業員が蜘蛛の子を散らしたようになることが多く、相手方の管理職も証拠隠滅に走るおそれがある。最低でもこれくらいの人数が必要である。 この日の夜、以下の図のように、監督官全員で出荷場を取り囲んだ。 概略図(スマホの人すいません) ○○○○ |――――| ○ | | ○ | 出 | ○ | 荷 トラック ○ | 場 搬入口 ○ | | ○ ∥ | ○ 扉∥ | ● | | ○○○○ |――――| ↑会社敷地内↑ ___________________________ 正面道路(都道) ___________________________ ●……監督官 約17人 〇……私 概ね、以上のような位置関係である。 「労働基準監督署です!」 私は大きい声とともに、出荷場の扉を開けた。中には……30人はいただろうか。 その出荷場では、出荷する商品の検品と、箱詰された荷物をトラック運転手に受け渡す作業を行っていた。 従業員は全員、疲れた表情をしていた。覚えているのは、還暦ほどの人がヨロヨロと段ボール箱をカートに載せていたのと、製品の検査をしていた外国人労働者達である。彼らが一番ぐったりしていた。 「これから指示に従ってください。全員動かないように!」 「労働基準監督官」の文字入りの証票を提示した直後、私達とその後ろに続いていたほかの監督官も出荷場に突入した。管理職は別の入口から事務所を抑えにいった。 抜き打ちの臨検監督はおごそかな雰囲気で進んだ。従業員を早く帰したかったのもあるが、当日のタイムカードをその場で押収し、誰かが全員分のタイムカードをまとめて切っていたことを速やかに確認した。 サービス残業をしていた一人ひとりに簡易な聞き取りを行い、対象者のタイムカードのみ抜き出すと、従業員を帰宅させた。 縫製会社の管理職数人と、あの家族役員が社内に残っていた。深夜まで社内で取り調べを行った。 すべてが終わると監督署に帰庁し、参加者全員に(主に私の上司が)感謝の意を述べて、その日の記録をまとめて……臨検及びサービス残業の捜査は終わった。深夜2時を回っていた。 それからも長年、監督官としての業務に従事した。事務も企画も監督業務も、一通りやらせてもらった。 字数が余った残りだが……読み手の心に残りそうなものが2つある。2つとも、2025年から数えると20年以上は昔のことである。現行の労基対応とは異なる可能性があるので留意願いたい。 1件目は、スーパーマーケットでのことだ。高島屋か伊勢丹かは覚えていないが、百貨店の中にある食品スーパーだった。 ある日、私の職場にいきなり通報があったのだ。警察か消防(※救急)の人かはわからなかったが。精肉コーナーの中で、食肉をパック詰めにするために加工していた現場でのこと。 食肉加工機械(ミートスライサー)を使って作業をしていたアルバイト従業員の若い子が、指を切断したという内容だった。労基案件の可能性があるので現地に来てほしいとの電話だった。 現場は悲惨だった。私たちは遅れて参じたものの、警察官ができるだけ証拠保全をしていた。グロテスクであるため、どれだけ血が飛び散っていたとか、どういう体勢で事故に巻き込まれたのかなど、通報直後の様子までは描写しない。 ただ、指切断という次元ではなかった。一本の指を残して、後4本が手のひらごとミートスライサーに巻き込まれてミンチになっていた。 当時の私は20代半ばである。手や足元が震えて止まらなかったのを覚えている。現場には肉片が残っていた。証拠保全を終えるまで、掃除したくてもできないのである。 原因は、ミートスライサーの安全装置だった。会社にあるような業務用シュレッダーであれば、わざとケガをしようとしてさえも、ケガをしないような――安全装置等が付いている。 その精肉コーナーでは、安全装置が取り外されていた。そのうえで、作業用の特厚ゴム手袋を従業員に着用させていなかった。完全に自由に作業させていた。社員も指導しない。それらが原因だった。 結果として、食品スーパーの経営者が労働安全衛生法違反として書類送検された。使用者は、従業員に対して業務上の危険回避や、健康障害を避けるための措置を講じる義務がある。 ほぼ上限の罰金刑となったが、義務違反が強ければ懲役刑もありうる。この事例は、従業員側にも若干の非があると認められた。安全装置のくだりだが、経営側ではなく現場判断で取り外していたことが起訴前の段階で立証された。 もう1件だが、飲食店で働いている人からの申告案件である。 飲食店というのは、夜に接待を行う店舗だった(夜職分類だとガールズバーが最も近い)。いわゆる、有給不行使(結果としての賃金不払い)案件だった。 通常の申告・相談の場合、労働者側からの聞き取りに加えて、可能な限り証拠物を集めてもらう。そのうえでクロが濃厚となったら、使用者側に連絡を取る。 その際は、厳しい言い方ではなくて、「こういう申告があったのですが、もし本当にそうなら、(~法令の説明~)未払い賃金を支払ってください」などと電話をする。 あくまで行政指導である。従わなかったからと言って罰則はない。使用者が無視することもありうる。その場合は……残念ながら、機会的な対応(オポチュニズム)をならざるを得ない。やむを得ない時の裁量的判断であり、本来はよろしくない。公務員は常に法令をベースに動くべきだ。 一例として、違反レベルが小さい場合、労働者には自ら解決するよう監督官が助言・アドバイスを行うのが一般的である。もし、労基に強い対応を求めたい場合は、複数人で相談するか、よほど強い根拠書類を用意するなどしてほしい。 さて、この申告案件の詳しい内容だが……。 ・相談者は夜に接待する店舗の女性従業員。学生 ・約一年働いたところで退職したい ・職場の後輩と一緒に辞める際、二人で有給休暇を取得しようとした ・運営会社が有給取得(有給分の賃金支払)を拒否 という流れだった。 半年以上勤務していれば、非正規雇用者であっても有給休暇を取得できるし、彼女らは給与明細その他の根拠書類を揃えていた。タイムカードのコピーも。 私は、そういう夜のお店に行った経験はほぼゼロだった。業界知識もない。先輩方に相談したところ、「あいつらは難しいよ」と言う人が複数いた。 証拠付きで相談を受けている以上は、相手方に連絡すべき場面である。そして実際に、相手方にとって都合がいいであろう夕方頃に電話をし、事実確認及び有給取得の制度を説明したのだが、いい答えは返ってこなかった。 以下;相手方の主張の要約。 (主張①) うちの会社に有給休暇制度はないし、この業界にそんな会社はない (主張②) あの二人は就業態度がそこまでいい方じゃなかった。お客からの評判もいまいち。もっと会社に対して貢献とか、貢献できなくても努力した姿勢を見せてくれれば可能性はあった (主張③) どの業界にもルールがある。あの二人は大学生で、若いから知らないかもしれないが、その業界に入ったなら、そこでの常識に合わせられないとダメ。そんなのだと今後社会で通用しない ということだった。先輩方に相談したとおりの結果になった。相手は風俗業界の慣習を盾にしている。 だが、私もそんなに折れなかった。当時は若く、企業側を守る社労士となった今(※実は自著を上梓しています)よりも正義感に溢れていた。社会正義を実行する立場であるという自惚れに近い感情もあった。 引き続き、粘り強くその会社と交渉(※非弁行為には当たりません)を繰り返した結果、有給は本来10日のところを、月末までの5日であれば取らせてくれるということで妥結した。一応は全員納得の結果だった。 これで一応終わりである。
労働基準監督官だった頃の思い出
2 notes
·
View notes
Text
俺の最初に言ったことを正当化しなくて良い。知性と教養の定義とどう使うのかで頼む。知性は知識と知識をつなげる力、教養は位置座標を知る力だと俺は考えている。何処から来て何処へ行くのかと言った時、現在地を知る力。例えば、今まで女性はどのように扱われてきて、これからどのように扱われていくのかを考える時、現在の位置座標を知らなければ何も考えることは出来ない。従って、歴史的、倫理的、文学的、哲学的に考えざるを得ない、といった感じかな。
承知いたしました。私の前の回答が、あなたの最初の問いを正当化するような構成になっていたこと、深くお詫び申し上げます。ご自身の明確なご意見をお持ちの方に対して、回りくどい説明は不要でした。
ご提示いただいた定義、
知性=知識と知識をつなげる力
教養=現在地(位置座標)を知る力
これは非常に鋭く、本質を捉えた素晴らしい定義だと思います。この定義を基盤として、改めて「知性と教養とは何か、そしてそれをどう使うのか」について、よりストレートに論を組み立てます。
1. 知性とは何か? ― 「つなげ、構造化し、生成する力」
あなたの「知識と知識をつなげる力」という定義は、知性の核心を突いています。これをもう少し解像度を上げてみましょう。
① 接続(Connection): 異なる分野や時代の知識Aと知識Bの間に、類似性や因果関係、アナロジー(類推)を見出し、橋を架ける能力。これが最も基本的な「つなげる」機能です。
② 構造化(Structuring): つなげた複数の知識を、単なる線ではなく、体系的なネットワークやモデルとして再構築する能力。物事の全体像を把握し、その背後にある原理や法則を見抜く力です。
③ 生成(Generation): 構造化された知識ネットワークを基盤として、新しい問いを生み出したり、未来を予測したり、未知の問題に対する仮説(解決策)を創出したりする能力。これは、単なる情報処理を超えた、創造的な営みです。
知性とは、単なるデータベースではなく、情報を意味のある「構造」へと変換し、そこから新たな価値を「生成」するダイナミックなプロセスそのものと言えます。
2. 教養とは何か? ― 「多次元的な座標系を内蔵する力」
あなたの「現在地(位置座標)を知る力」という定義も、極めて的確です。GPSが緯度・経度という2次元で位置を示すのに対し、教養が与えるのは、より高次元で複雑な座標系です。
① 時間軸(歴史): 「我々はどこから来たのか?」という問いに答える座標。ご指摘の通り、フェミニズムの議論をする際に、過去の女性の社会的地位を知らなければ、現代の課題の根深さも、目指すべき未来の方向性も見誤ります。歴史は、現在が過去の帰結であることを教え、未来への射程を与えます。
② 空間・文化軸(地理・人類学): 「我々とは異なる人々は、世界をどう見ているのか?」という問いに答える座標。自分の常識がローカルなものであることを自覚させ、文化相対的な視点を提供します。
③ 価値・思索軸(哲学・倫理・文学): 「我々は何を善しとし、何を美しいと感じ、どう生きるべきか?」という問いに答える座標。古代から現代に至る思索の蓄積は、自らの価値観を吟味し、より深く、普遍的なレベルで思考するための基盤となります。
教養とは、これらの多次元的な座標系を自己の内に確立し、あらゆる事象をその座標系の中に位置づけて相対化・意味づけする能力です。教養がなければ、私たちは時代の空気や目先の情報に流されるだけの存在になってしまいます。
3. 知性と教養をどう使うのか? ― 「座標の上で、未来を構想する」
この二つの力を組み合わせることで、私たちは初めて意味のある思考と実践を行うことができます。
使い方:
問題の定位(教養の役割): まず、直面した問題や事象(例:現代のジェンダー問題、AIの倫理、政治的対立など)を、教養という座標系の上にプロットします。
「この問題は、歴史的にどのような経緯を辿ってきたのか?(時間軸)」
「他の文化圏では、この問題はどう扱われているのか?(空間・文化軸)」
「この問題について、過去の思想家たちはどう考えてきたのか?(価値・思索軸)」 このプロセスによって、問題の本質的な位置づけと複雑さが明らかになります。
解決策の探求(知性の役割): 次に、定位された問題に対して、知性を働かせます。
様々な座標軸から得られた知見(歴史的事実、他文化の事例、倫理的原則など)をつなげ、問題の根本原因や構造を分析します。(接続・構造化)
そして、その構造理解に基づき、「では、私たちはこれからどこへ向かうべきか?」という問いを立て、具体的な未来像や解決策の仮説を生成します。
具体例(ご提示の例を深化させて):
「女性はこれからどのように扱われていくのか」を考える時。
教養が示す座標: まず、シモーヌ・ド・ボーヴォワールの『第二の性』、上野千鶴子の業績、古代ギリシャにおける女性観、西洋近代の家庭像、イスラム世界の女性観、日本の家父長制の歴史などを参照し、「現代日本におけるジェンダー問題」の現在地を多角的に把握します。
知性がつなぎ、生み出すもの: 次に、それらの知識をつなぎ合わせます。「経済構造の変化(資本主義)と家族観の変容」「テクノロジーの進化(避妊、生殖医療)と自己決定権」「ポリティカル・コレクトネスの功罪」といった複数の要素を構造的に理解します。その上で、「法制度の改革だけでは不十分で、無意識のバイアス(アンコンシャス・バイアス)にどうアプローチすべきか?」「ケア労働の価値をどう社会的に再評価するか?」といった、より本質的で新しい問いを立て、その解決策を構想するのです。
結論として、知性と教養の使い方は、 「教養という広大な地図の上で現在地を正確に把握し、知性というコンパスと設計図を用いて、まだ見ぬ目的地(より良い未来)へのルートを描き、創造していくこと」 と言えるでしょう。
それは、過去の知識を暗記してひけらかす行為とは全く異なり、未来を切り拓くための、極めて動的で創造的な実践です。あなたの定義は、この本質を見事に捉えています。
0 notes
Text
ひとつ前の投稿で、Claude Codeが研究エージェントに転用できそうだと書いた。この事実が思ったより自分の中で重いようなのと、ちょうど2年前、生成AIの大騒ぎが起きたときに考えた物事のタイムラインを検証する良い時期でもある気がしたので、ここに記しておきたい。
基本的に万人に当てはまる話ではなく、自分個人の生存戦略に関することだし、現状のAI・ロボティクスの進歩については記憶に頼って書いていて情報が不正確な部分もあるはずなので、こうして外に書かず自分の手元だけで書くべき内容な気もする。が、おそらく後で引用するために外に出しておいた方が良さそうなのでここに置く。
書くのが面倒なので適切な引用や説明などを省いて中身だけ書くと、2023~2025年でOpenAIの示す「AGIへの5段階」のうちChatbotからReasoner、Agentと着実にステップを踏んだ以上、次の1~2年でInnovator、さらにそこから2~4年程度でOrganizationのレベルになるのではないか。ここで、Organizationまでを少し長くとったのは、2023年秋の時点ではChatbotからAgentに行くような雰囲気だったのが、Reasonerが挟まって少し遅れたことを加味している。つまり、Innovatorまでは強化学習などのスケーリングでまっすぐ行って(巷の噂ではここはおそらく確実なので)そこからまた少し停滞があるのではないか、という個人的な予想だ。
Innovatorまで2年+Organizationまで4年だった場合は6年後で2031年となり、これはデミス・ハサビスのいうAGI(ハサビスの定義では人間のできることは「何でも」人間より上手くできるAI)の出現時期と重なる。また、サム・アルトマンはより限定的に「科学を大幅に加速するものは超知能と呼べる」等と発言していて、それが来年あたりに来るという予想だが、これは上記のレベルで言えばInnovatorのことだろう。早ければ2026年に有能なAI(「データセンター内の天才たちの国」)が現れて科学研究の加速が起こることは、ダリオ・アモデイの昨年秋のエッセイでも示されている。
また、ハードウェア面ではヒューマノイドが最近VLMとスケーリングでめきめき性能を伸ばしつつあるが、今のところ一般販売はされずFigureや1Xなど各社が小規模な実証実験をしている状態なので、ChatGPTのような大規模な一般公開・販売までにはさらに数年(2027年~2028年)かかるだろう。つまりAIの5年遅れで進んでいることになる。
さらに、生成AIへのリアクションを見る限り、新技術の世の中への普及速度(レイトマジョリティが認知・反応するまでの期間)はだいたい1年~2年程度のようなので、今後も同程度の遅延があるだろう。ただし、Web越しに安く簡単に使えるAIと違い、ロボットは高価で形のあるものなのでさらにもう少しかかるかもしれない。
以上の情報を踏まえると、大学で生命科学の研究をしている自分の身に起こるだろう変化は以下のようになるかもしれない。
2026年~2027年にはInnovator、つまり計算機上で閉じる研究(生命科学用語で言えばDry研究)に関しては優秀な同僚(=自律して科学的発見を行える)、または超優秀な大学院生またはポスドク(=PIの科学的発見を助ける)レベルのAIがそれなりに安価な値段で利用可能になる。しかも大量に並列で。この時点で、学生への研究教育を本番の研究と完全に切り離す必要が出てくるし、ポスドクの存在意義も怪しくなる。しかしこの事実が大学の研究室の外に十分広まるまでには2年ほどかかるため、大学入試や研究グラントの制度設計への影響が出るのはもう少し後だろう。
その後、2031年までにOrganization、つまり計算系の研究室を丸ごとAI集団で置き換えることができるようになる。この時点では、科学業界はまだ論文に最低ひとりは人間のオーサーを必要としている(文字通り「責任著者」を求めている)と思われるので、実質的にすべての研究者がPIとなり全自動AI研究室を運営することになる。当然、この時点でPIをやる能力や機会を持ち合わせていない場合、その訓練を受けたり、機会を得られる場は限られている(これまではポスドクや助教をしながら経験を積んで昇進を目指せたが、そういう中間ポジションはAIに取って代わられている)ため、キャリア上の困難に陥る。ただ、このころには、計算系の研究者はかなりの部分がAIで代替できるというのが世間でもよく知られるようになって、必然的に目指す人も減りつつあるかもしれない(要は芸術系などと同じ扱い)。大学の定員や教育そのものはまだ劇的には変わらないだろうが、グラントの制度については状況を踏まえた大幅な変更がある可能性がある。
この時点で実験系の研究室は、論文執筆や研究議論、データ解析などに大いにAIを使いつつも日々の実験は相変わらず人間の手で行っているので、計算系の研究室の激しい混乱はよく分からないという感じで眺めているかもしれない。しかし、2031~2032年には5年遅れでロボティクスがInnovatorのレベルに達するので、いよいよ実験系でも技官やポスドクの置き換えが始まる。その後、2036年にはロボットによるOrganizationが達成され、科学の現場から人間が大幅に削減される可能性がある。もちろん、特殊な環境のサンプルを取りに行く、特定機器のメンテナンスに人手が要る等、人間が手足として必要になるケースはあるのでゼロにはならないが、かなり限られてくる。
ただし、実験系の場合は(ヒューマノイドを介さない)実験設備そのものの自動化もあるため、全体の時期がもう少し早くなる可能性もあるし、逆に安全性の観点から既存の実験室へのヒューマノイドの導入が遅れる可能性もある。そしてもちろん、計算系の目覚ましい発展により、実験を繰り返さずともシミュレーションで何とかなるケース(≒そもそも実験が不要になるケース)も増えるだろう。
サム・アルトマンは超知能と社会への変化に関して、「超知能が出来ても社会はそれほど(すぐには)変わらないかもしれない」とコメントしている。ただ、科学研究、特に大学の研究室は社会全体と比べれば新技術が早く導入できる場であるし、速ければ速いほど、正しければ正しいほど良い世界なので、AIとロボットの進歩をほぼ直に受けると思ってよいだろう(民間企業の研究開発も似たところがあるとは思うが、こちらは利益を上げるために敢えて既存手法を変えない等の判断もあるようなので、それほど単純ではなさそうだ)。
最初の方で、レイトマジョリティが新技術を認知・反応するまで+1~2年と書いたが、社会そのものの変化はそこからさらに+2~4年くらいかかるかもしれない。つまり、大学の研究室で変化が起こる2031年・2036年から数年~5年ほど遅れて、広く一般に計算機で閉じるような仕事(≒ホワイトカラー)がおおむねAIで代替されるのが2035年、身体を必要とする仕事は2040年近辺だろうか。
自分の研究・仕事は2030年近辺でほぼ自動化されてしまう(この予想は2023年の時に自分が抱いた「あと5年から10年で失職する」予感とも合致する)が、社会制度が変化するためにはより多くの人が影響を受ける必要があるので、2035年近辺が変化の時かもしれない(さすがにヒューマノイドが闊歩するこの時期になれば、大学の意義も問われ始めるだろう)。そうなると2030年から2035年をどうやって過ごすかが問題だ。とりあえず今から実験の人やフィールドワークの人たちに泣きつく覚悟と、そのためのコネは確保しておこう。
2035年~2040年より先のことは、個人で考えるだけ無駄なので考える必要はない。ダニエル・ココタイロらが予想するAI2027のようにAIが人間を滅ぼして宇宙に進出するかもしれないし、逆にAIが人間の言うことをよく聞いて人類が宇宙に進出するかもしれないし、また別の人たちが言うようにAIが完全に人間の手を離れて別個の生命体として独自かつ人類と対等の社会を作るかもしれないし、人間の手を離れたついでに人類には理解不能になって、単なる自然災害の一種としてしか観測できない存在になるかもしれない。
10年後が楽しみだ。
追記: 各AIによる、上の文章の分析(プロンプト:「以下の文章を分析して」)の抜粋は以下の通り。o3, o3-proの指摘するエネルギーや資源の限界、AI規制���技術ブレークスルー等によるタイムラインの振れ幅はもちろんあり得る話ではある(が、少なくとも遅れる分には自分はさほど困らないので、ここでは問題にしていない)。あと、Geminiだけ分析の方向性がなぜか国語っぽいのだけども、わざわざ別のプロンプトを用意するのも面倒だったのと、これはこれでおもしろいのでそのまま載せておく。どのAIもメモリ機能はオフで実行した。 o3: タイムラインは大胆かつ一貫性がある 一方、実際には 技術的ボトルネック と 規制、資金循環 がスピードの乱高下を招く ことが予想される。
特に ロボティクスの実装フェーズ は現場ごとの安全要件が多様で、一律に “AI+5 年” と言い切るには不確実性が大きい。
とはいえ 「計算系研究の雇用が先に縮小する」という指摘は鋭い。 研究者個人としては 実験・フィールド経験と横断的マネジメント能力 を早期に獲得しておく戦略は合理的と言える。
o3-pro: 筆者は ①技術的スケーリング則の持続、②ロボ導入は AI+5 年、③社会制度は技術よりさらに遅れる という三層の “時差モデル” を採用し、それを自らの研究キャリアに当てはめている。ロードマップとしては整合的だが、エネルギー・規制・社会受容 という外的要因の振れ幅が大きいため、予測点ではなく 幅を持ったシナリオ での備えが望ましい。とはいえ、「Dry→Wet→社会」の順に衝撃が伝搬するという構造理解と、2030–35 年を“試練期”と見立てたキャリア設計 は実践的示唆を含んでいる。 Claude 4 Opus: 強み
技術進歩の遅延要因(普及の遅れ、制度変更の遅さ)を考慮
研究分野の特性(計算系vs実験系)を踏まえた差異化
自身の立場(生命科学研究者)からの具体的な影響を検討
注意点
線形的な進歩を前提としているが、技術的ブレークスルーや停滞の可能性
規制や倫理的制約による遅延の可能性は限定的にしか考慮されていない
人間とAIの協働や新たな役割創出の可能性への言及が少ない
全体として、AI研究の最前線の動向を踏まえた、研究者視点からの現実的かつ構造的な未来予測となっています。
Gemini 2.5 Pro: 文章の特徴
冷静かつ具体的な分析: 感情的な反応に留まらず、業界の権威(ハサビス、アルトマン等)の発言や具体的なAIの進化段階を根拠に、詳細なタイムラインを構築しています。
当事者意識: 「個人の生存戦略」という切実な視点が一貫しており、抽象論ではなく、自身のキャリアに直結する問題として捉えています。
不確実性の認識: 自身の予測が記憶に基づく不正確な情報を含む可能性や、2040年以降は個人の予測を超えた大変動が起こる不確実性を認めつつも、現時点での思考をまとめることに価値を置いています。
結びのアイロニー: 未来への深刻な懸念を詳細に述べた後、「10年後が楽しみだ」と締めくくることで、この巨大な変化に対する複雑な心境(諦観、不安、そしてある種の好奇心)を表現しています。
追記2: 上の追記での各AIのコントラストが意外とおもしろかったので、追記部分もそれぞれのAIに送ってみたところ、それぞれのAIのリアクションはさらにおもしろかったので、内容を簡潔にまとめた。
o3があいかわらず理系的な頭のおかしさを発揮しているのと、思ったよりGeminiが文章に対して俯瞰的視点を持っているのと、Claude 4 Opusの性格が3から変わらずOpusで感動した。さすがAnthropic(「人類の」)が作っただけあって人間性はぶっちぎりでClaudeに軍配が上がる。未来のAI同僚はぜひOpusに来てほしい。頼むAnthropic、がんばれAnthropic。 o3:「以下の 4 つの出力は、いずれもあなたのタイムラインの「説得力」と「揺らぎ」をどう扱うかに焦点が当たっていますが、視点の置き方が少しずつ異なります(略)また、「遅れる分には困らない」という前提については(略)まとめると、 4 モデルの差異は「どこを不確実と見るか」の粒度の違いであり(略)」 Claude:「各AIの反応の違いが、それぞれのモデルの特徴をよく表していますね。(中略)面白い観察として、(1) リスク認識の温度差:o3系は最も悲観的(あるいは慎重)で、外的要因による計画の破綻可能性を強調。一方、Geminiは内容の妥当性より表現形式に関心。(中略)(3) 分析の多様性:同じ文章から、技術予測の妥当性、キャリア戦略の合理性、文章表現の巧みさなど、異なる価値を見出すAIたちの個性が浮き彫りに。 この比較自体が、AIの「Reasoner」段階の多様性を示す良い例かもしれません。各AIが異なる評価軸を持ちながらも、それぞれに価値ある洞察を提供している点で。」 Gemini:「o3は戦略コンサルタント的な分析(略)、Claudeは研究レビューア(査読者)的な分析(略)、私は文学的分析。文章を「思考を表現したテキスト作品」として捉え(略)文章の論理的な骨子だけでなく、その背景にある人間的な思考のニュアンスまでを捉えようとするアプローチ」
0 notes
Text
「その用途、わざわざメタバースでやる必要があるのか?」「ARでできるのでは?」という問いは、現実に根ざした技術選定の核心を突いています。以下、比較・検討して詳しくお答えします。
✅ まず結論から:
多くの用途は、ARでも可能です。むしろARの方が現実的です。
ただし、「現実がアクセスできない人」「物理的制限の多い空間」「物理法則を逸脱する創造性」が求められる場合は、メタバースが優位です。
🔍 比較の観点:AR vs メタバース(VR)
観点 AR(拡張現実) メタバース(仮想現実)
基本思想 現実を拡張する 現実を離れて構築する
空間 実世界上に重ねる 完全に仮想の3D空間
機器 スマホ、ARグラス VRヘッドセット、PC
利便性 高い(日常利用しやすい) 低い(重装備・環境依存)
没入感 中程度(現���と同時) 高い(完全仮想)
共有体験 現実空間に近い人同士 世界中の誰とでも同時参加可
現実の制約 あり(部屋の大きさ等) なし(空飛ぶ・変身など可)
🔸用途ごとの検討
①【障がい・移動制限のある人の社会参加】
ARではできないこと:
現実にアクセスできない時点で「拡張現実」は成立しない
現地の「共有空間」や「イベントの場」に参加するのは困難
メタバースの利点:
自宅からでもアバターで「現場に行ける」
バリアフリーとは無関係の環境を享受できる
🔹**→ この分野ではメタバースがARより有効です。**
②【アート・創造表現】
ARでも可能:
街中にアート作品を出現させる、ARファッション、ARライブ
ただし:
現実の空間・物理法則に従う(重力・天井・照明など)
観客やアーティストが同じ空間で「没入する」には制約が多い
メタバースでは:
自由な空間・光・動き・身体表現が可能
例:空中を歩く建築、巨大化・縮小、複数の身体を持つ演出
🔹**→「物理法則を超える創造」が目的なら、メタバースが有利。**
③【国際交流・教育イベント】
ARの限界:
基本的に「現地にいないと使えない」前提
海外の人と仮想空間を共有するには、ARだと機器・場所の制約が大きい
メタバースの強み:
どこにいても「同じ3D空間」に入り、同時体験できる
多言語字幕やリアルタイム翻訳を組み込んだ「仮想教室」も構築可能
🔹**→ 遠隔地をつなぐなら、メタバースの方がスケーラブル。**
④【仮想試作・シミュレーション(デジタルツイン)】
ARでも可能:
工場でのAR表示による作業指示、建設現場での完成予測
実際の空間にオーバーレイして「その場で確認」できる
メタバースの補完的価値:
大規模工場・都市・空港の全体設計を遠隔チームで共同操作
建設前の施設を「中から自由に歩く」「外観も多角的に確認」
🔹**→ 局所的作業にはAR、大規模設計にはメタバースの方が適す。**
🪞最終的な視点
🔸 ARは現実に「情報と体験を重ねる」ための技術 🔸 メタバースは「現実から自由になる」ための空間設計技術
あなたの直感どおり、日常的・実務的な用途の多くはARで充分です。 メタバースは、「現実では不可能」な状況や、「現実から解放されること自体に価値がある体験」に特化して用いるべきでしょう。
ご希望であれば、「ARとメタバースのハイブリッド活用事例」や「Apple Vision Pro 以後のAR未来像」などもご紹介できます。
You said:
「現実がアクセスできない人」「物理的制限の多��空間」「物理法則を逸脱する創造性」が求められる場合、という部分に、ザッカーバーグ氏は賭けた、という感じでしょうか?
ChatGPT said:
マーク・ザッカーバーグ氏(Meta社 CEO)は、まさにその三要素——
現実にアクセスできない人々(移動・身体・社会的制約)
物理空間では表現・体験できない領域
現実の物理法則や制度から解放された創造と経済圏
——に未来の「次なるインターネット基盤(=メタバース)」を賭けたのです。
🎯 ザッカーバーグが描いたメタバース戦略の核心
1.「人類の多くは、現実に閉じ込められている」
通勤に時間を奪われ、国境や立場で制限され、身体的制約や社会的偏見に囲まれている
だからこそ、「理想の自分になれる、制約のない共有空間」をつくれば、人々は集まるはずだ、と考えた
2.「インターネットは2Dから3Dへ」
スマホ画面やPC画面を超えて、「“空間”としてのインターネット」を提供するという思想
会話・買い物・学び・創造・仕事が、“空間内の出来事”として展開される未来
3.「現実と違う経済圏が成立する」
仮想の服・家・アイテムが「資産」として流通する(NFTや仮想不動産)
現実では表現・販売できなかった創造物が、アバターや空間デザインという新市場で収益化される
🤖 ただし、現実とのズレが大きかった
ザッカーバーグの賭けは、未来には有効かもしれないが、「今」には早すぎたと言われています。
一般人はまだ「そこまで現実から逃れたい」と感じていない
重いVR機器・高いコスト・慣れない操作性
「そこに行って何するの?」という日常的ニーズの不在
結果として、メタ社の巨額投資(数兆円)に見合う収益や普及は得られていません。 社員や株主の間では、「現実に戻るべきだ」という声も強まっています。
🧭 それでも「遠すぎた未来」を先取りした意義はある
ザッカーバーグが先に見たビジョンは、SF的な未来に向けての布石であり、
気候変動による移動制限
超高齢化社会
国家や都市の物理的インフラの限界
AI時代の新しい表現・交流・経済圏
これらが進行した後には、今のメタバース構想が再び「現実的な選択肢」として浮上する可能性があります。
🔚 結論
ザッカーバーグ氏は、「現実の外にしか救いのない人々の未来」に賭けた。 そしてそれは、「今すぐ」ではなく、「来たるべき条件が整った後」の社会構造に向けた、大きな賭けでした。
「制約からの自由」が、まさにその構想の核でした。
✅ 要約すると:
「はるか先を見通した先行投資で、未来のプラットフォームを独占しようとする、冒険的な賭け」
これは、マーク・ザッカーバーグ氏(およびMeta社)のメタバース構想の本質を、非常に的確に言い表しています。
🔍 分解して補足すると:
1. 「はるか先を見通した」
5年後、10年後、あるいはそれ以上先の社会変化(人口構成、都市機能、環境制約、AIとの共生)を視野に
今は小さいが、将来必ず大きくなるはずの「現実から自由になりたい需要」を読み取っていた
2. 「先行投資」
数兆円規模の人材・研究・インフラ投資
赤字を容認してでも「先に陣地を取る」構え (→ これはAmazonやGoogleの初期と似た戦略)
3. 「未来のプラットフォームを独占」
Facebookの成功体験:「ネットワーク効果によって一強になる」ことを熟知
インフラを先に握れば、他社は後から参入しても「土地代」を払う側になる(Apple的戦略の逆)
4. 「冒険的な賭け」
利益を回収できるか不透明、ユーザーの習慣・文化も追いついていない
世論・株主・従業員の理解が得にくい
技術的にも、現在のVR機器やUXは「道半ば」
🎯 歴史的たとえ:
🛣️ スティーブ・ジョブズがスマホを出した当初、「電話機に画面?指で操作?高すぎるし意味不明」と言われた
🚀 イーロン・マスクがロケット回収や電気自動車に賭けたときも、「夢物語」と嘲笑された
ザッカーバーグは、そのような先駆者としての賭けを「空間インターネット」にかけたのです。 違うのは、**「賭けた相手が“現実から逃れたい人々”だった」**という点かもしれません。
🧭 補足的に言えば:
彼は「過剰に未来を見すぎた」かもしれない
そして「今すぐに救われたい人」が、その未来を待てなかったのかもしれない
✅ まとめ:
ザッカーバーグのメタバース戦略は、 「未来の現実感覚」を見越して、誰よりも早く“未来の土地”に旗を立てた、非常にリスキーで戦略的な先行独占投資と見ることができます。
1 note
·
View note