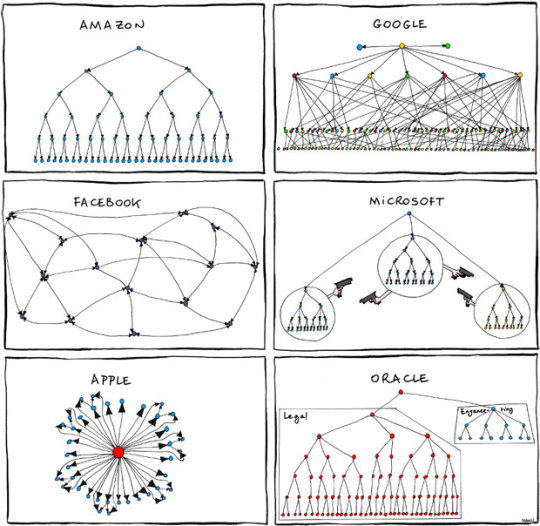Quote
水曜どうでしょう → 木曜ならいいでしょう? → 金曜なら夜は空いてるでしょう? → 土曜は休みでしょう? → 日曜もどうせ断るんでしょう? → 月曜なんて会ってくれないでしょう? → 火曜サスペンス劇場
Twitter / @1219hr (via june29)
16 notes
·
View notes
Text
[TED Air] レイチェル・ボッツマン:コラボ消費について
観た。
まぁ「シェア」とか「コラボ消費」とかももはやクリシェ化してるようにしか思わぬが、 最後の部分で「他者への評価付け」、「人間による人間への評価付け」の話に言及してる分、リアリティもあるし聞く価値あり。
というか、レイチェルボッツマンの本買った気がするけど、買ったかな、、 コラボ消費とか系のリファレンス、既存サービスのガイド的に読む価値あるかもと思わされました。
http://www.ted.com/talks/rachel_botsman_the_case_for_collaborative_consumption.html TED Air (http://goo.gl/2Aftm)
0 notes
Text
TED :ミック・エベリング:閉じ込め症候群のアーティストを解き放った発明
泣いてまうわ。 で、情けなくなるわ。
グラフィティ・アーティスト のTEMPTは、神経変性疾患で あるALSによって全身麻痺と なり、まばたきでしかコミュ ニケーション出来なくなりま した。起業家のミック・エベ リングがTEDActiveにおける 素晴らしいトークで、どのようにして共同制作者たち とオープンソースの発明品を作り上げ、TEMPTや同じ ような状況の人が再びアートをできるようにしたか紹 介します。
http://www.ted.com/talks/mick_ebeling_the_invention_that_unlocked_a_locked_in_artist.html TED Air (http://goo.gl/2Aftm)
3 notes
·
View notes
Text
[TED Air] TED講演をお勧めします。 ファビアン・ヘマート 「形が変化する未来の携帯」
なされる三つの提案は、 携帯電話に 1、重み(の変化)を与える 2、形の変化を与える 3、人間味を持たせる というもの。
3については、総じてコンピュータと機械の未来という話で、1と2のみが具体的な提案と呼べるけど、 1、の携帯電話に重みを与えることは、新たな一つのインタラクションを人間とデバイスの間に生んでくれる素晴らしいアイデアだと思った。
モーションキャプチャリングやセンシングなどで人間側の身体性を機械側に提供するという考え方のみではなく、 機械の持つ身体性をどのように人間側に伝達するか、 という視点から考えることは大切だと思った。
実は思いの外この観点からデザインされたプロダクトは少ないのではないだろうか、、(いつも通り荒川修作が想起される。同時に建築一般が。そして付加的にゲームのコントローラーが。)。
http://www.ted.com/talks/fabian_hemmert_the_shape_shifting_future_of_the_mobile_phone.html TED Air (http://goo.gl/2Aftm)
0 notes
Text
[TED Air] TED講演をお勧めします。 イーライ・パリザー:危険なインターネット上の「フィルターに囲まれた世界」
キャスサンスティーンが『インターネットは民主主義の敵か』で行っていた、見えざるアルゴリズムによる情報フィルタリングがもたらす、デモクラシーの危機への警鐘の焼き直し。 ひいては近代以降における個人という概念や、自由という概念を保守しようとする考え方。
もはやクリシェでしかないがクリシェであるが故に重要なもの。
ともあれ、Twitterのようなに、「人間」を情報フィルターとする方法論によって、純粋アルゴリズムによる完全なフィルタリングとは異なる、不確実性と拡がりの可能性を担保したフィルタリング在り方は模索可能であるとも思う。
http://www.ted.com/talk/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles.html TED Air (http://goo.gl/2Aftm)
1 note
·
View note
Text
TED: ジョン・アンダーコフラーが示すユーザインタフェースの未来
マイノリティリポートのUI を作成したアンダーコフラーによるトーク。 講演内では5年以内と言われたものは、kinnectを経験した今ではもっと近い未来だと思う。
皮肉なことにマイクロソフトが製品化して市場に投入したんやなぁ。
http://www.ted.com/talks/john_underkoffler_drive_3d_data_with_a_gesture.html TED Air (http://goo.gl/2Aftm)
0 notes
Text
TedTalks: Carlo Ratti: Architecture that senses and responds
センシング技術によって可能となる未来像がすげぇ。 8分頃からの水を利用した広告やファサードには色んな可能性を感じるし、 その前の2006ワールドカップの時の電話利用実態の調査もおもしろい。
http://www.ted.com/talks/carlo_ratti_architecture_that_senses_and_responds.html TED Air (http://goo.gl/2Aftm)
1 note
·
View note
Quote
「BANG 100 MILLION MINES」 同アプリは“社会貢献をゲーミフィケーション”したものだという。一種の位置ゲーであり、日本中にバーチャルな地雷1 件を1億個配置し、プレーヤーがそれを除去するのだが、この地雷除去と連動してカンボジアに存在する現実の地雷も除去されるという、マッチングギフトのような仕組みが想定されている。ソーシャルゲームが「お金を払ったことがむなしくなる。空中に消えていく」のに対し、清水氏は「自分が遊んだ分だけ地雷が除去されるのなら、こんなに達成感のあることはない」と、企画の実現に期待を込める。
http://www.itmedia.co.jp/promobile/articles/1106/14/news051_2.html
1 note
·
View note
Text
スマートグリッド・スマートシティ等資料個人的まとめ
書籍:「スマートグリッド」検索結果@Amazon
ウィキ:スマートグリッド(Wikipedia)
経産省:
スマートグリッドに関する国際標準化ロードマップについて(経済産業省)
スマートグリッド・スマートコミュニティについて(経済産業省)
各種資料:
横浜スマートシティプロジェクト・マスタープラン(2010)
ユビキタスパワーネットワーク(日本型先進スマートグリッドについて)
経済産業省産業構造審議会環境部会環境と産業小委員会:環境・エネルギー分野における有望技術を用いたまちづくりの海外先進事例(2009、経産省)
IBMスマートシティ:
「スマートシティ」検索結果@IBMホームページ
各種HP:
スマートグリッド展2011
スマートグリッド日本
0 notes
Quote
未来のネットワークでは、あらゆる人が誰が何をしているかを知ることができる。それは21世紀の中央情報局となる。ドン・タプスコットとアンソニー・D・ウィリアムズが2010年の著書『Macrowikinomics』で論じたように、今日の「ネットワーク諜報時代」の到来は、ルネサンスに匹敵するほどの「時代の転換期」を象徴している。
http://wired.jp/2011/06/07/%E3%80%8C%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E7%BD%A0_%E3%81%9D%E3%81%AE1/?utm_source=facebook&utm_medium=20110607
0 notes
Text
大澤真幸、連載「可能なる革命、友愛のコミューンと偽ソフィーの選択」『atプラス08:特集、瀕死の建築』:http://amzn.to/mQwdRC
本文要約。
-----------------
問題設定:
災害は「友愛のコミューン」(レベッカ・ソルニットの言う「災害ユートピア」)を生む。
そして、災害は往々にして革命へと転じていく。
では、「友愛のコミューン」が続いていく状況は「可能なる革命」と呼べる状況だと呼ぶことができるのではないか。
しかしながら、3.11後の日本社会を鑑みて、それが「可能なる革命」を生む社会状況を生んでいるとは見えない。
では、3.11という予測不可能な大災害は私たちが思考する「可能なる革命」についてどのような示唆をもたらしているのだろうか。
考察1:映画『ソフィーの選択』と「偽ソフィーの選択」から考える原発事故。
映画『ソフィーの選択』
ナチス支配下ユダヤ人強制収容所において、母親ソフィーが二人の息子の内一人を選ばされ、選ばれなかった息子はガス室へ送られ殺される。母親が選べないという選択をしたときは、ふたりともが殺される(ソフィーは結果として、弟を選択し兄をガス室へ送るという選択を行うが、発狂してしまう)。
「偽ソフィーの選択」
『ソフィーの選択』が、子どもとエアコンの選択であったら、置き換える。
その際私たちは倫理的に子どもを選択し、救うであろう。
福島原発問題は、究極的には「子ども」と「エアコン」の対比と近縁関係の問題と考えられるものであり、原発廃止へと向け思考することが穏当な解釈であろう。
考察2:リスク社会のリスク、について。
リスク社会のリスクの二つの性質。
第一:いったん生起すると、物的にも精神的にもきわめて深く広範な損害をもたらす、非常に大きな破局、である。
第二:リスクの生起確率が非常に小さく、ときに小さすぎて計算不能である。
これらの性格から、リスク社会におけるリスクや未曾有の大災害について、私たちは合理的に、確率論的に思考することは不可能である。
結論:
考察1と考察2を通じると、
原発問題を含めたリスク社会におけるリスク、さらには今回の「想定外」の天災(地震や津波)などに関して、実のところ「偽ソフィーの選択」程簡単な問題ではないということ、がわかる。
(要するに、ソフィーのように目の前に既に存在する子ども二人(or子どもとエアコン)について思考することがリスク社会のリスクについて思考することではなく、リスク社会のリスクについて思考することは、想像を超えて大きくかつ生起確率の低いことについて思考することである)
つまり、リスク社会のリスクや想定外の天災について思考することは、
1,どこまでの「われわれ」を想定すれば良いのか(広範すぎるリスクを引き受ける空間的な「われわれ」の範囲)、
2,いつまでの「われわれ」を想定すれば良いのか(生起確率が低く、千年や数万年などのレベルで想定されるべき時間的な「われわれ」の範囲)
についても考慮に入れるということ、となる。
そのため、災害によって生まれる「友愛のコミューン」が私たちに夢想させる「可能なる革命」について論じる際、この二つの困難が私たちには立ちはだかると言えるだろう。
(次回へ続く)
--------------
感想
1,レベッカ・ソルニット『災害のユートピア』って一時期話題になってたけど、震災前やった気がする。なんの時話題になってたっけ?と思いながら、読んどきたい本リストに追加せねば。
2,少なくともとりあえず、穏健ではあるが私自身が明確な反原発側の人間に立ち位置を改めるキッカケにはなった。ともあれもちろん、よくわからぬデモとかやってるのとか大して意味ないと思う。
映画『100,000年後の安全』もやはり観れば同様の考えを抱かせられるものなのだろうか。。
2 notes
·
View notes