#兄ちゃん 本物 小心者 猛犬注意
Link
7時15分配信します
YouTube世界に一つのシルバーアート【gansilverart】
Robot Animation『兄ちゃん達は本物の小心者』
https://youtube.com/shorts/6q5YRZq2HFM?sub_confirmation=1
こりゃ〜ちびロボちゃん
一枚上手やわぁ〜
▽作品に関してはこちら
gansilverart gallery store
https://gansilverart.stores.jp
YouTube世界に一つのシルバーアート【gansilverart】
https://www.youtube.com/@gansilverart01?sub_confirmation=1
0 notes
Text
iFontMaker - Supported Glyphs
Latin//Alphabet// ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 !"“”#$%&'‘’()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ Latin//Accent// ¡¢£€¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ Latin//Extension 1// ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſfffiflffifflſtst Latin//Extension 2// ƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿ Symbols//Web// –—‚„†‡‰‹›•…′″‾⁄℘ℑℜ™ℵ←↑→↓↔↵⇐⇑⇒⇓⇔∀∂∃∅∇∈∉∋∏∑−∗√∝∞∠∧∨∩∪∫∴∼≅≈≠≡≤≥⊂⊃⊄⊆⊇⊕⊗⊥⋅⌈⌉⌊⌋〈〉◊♠♣♥♦ Symbols//Dingbat// ✁✂✃✄✆✇✈✉✌✍✎✏✐✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛✜✝✞✟✠✡✢✣✤✥✦✧✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❍❏❐❑❒❖❘❙❚❛❜❝❞❡❢❣❤❥❦❧❨❩❪❫❬❭❮❯❰❱❲❳❴❵❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➔➘➙➚➛➜➝➞➟➠➡➢➣➤➥➦➧➨➩➪➫➬➭➮➯➱➲➳➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾ Japanese//かな// あいうえおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもやゆよらりるれろわゐゑをんぁぃぅぇぉっゃゅょゎゔ゛゜ゝゞアイウエオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダチヂツヅテデトドナニヌネノハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモヤユヨラリルレロワヰヱヲンァィゥェォッャュョヮヴヵヶヷヸヹヺヽヾ Japanese//小学一年// 一右雨円王音下火花貝学気九休玉金空月犬見五口校左三山子四糸字耳七車手十出女小上森人水正生青夕石赤千川先早草足村大男竹中虫町天田土二日入年白八百文木本名目立力林六 Japanese//小学二年// 引羽雲園遠何科夏家歌画回会海絵外角楽活間丸岩顔汽記帰弓牛魚京強教近兄形計元言原戸古午後語工公広交光考行高黄合谷国黒今才細作算止市矢姉思紙寺自時室社弱首秋週春書少場色食心新親図数西声星晴切雪船線前組走多太体台地池知茶昼長鳥朝直通弟店点電刀冬当東答頭同道読内南肉馬売買麦半番父風分聞米歩母方北毎妹万明鳴毛門夜野友用曜来里理話 Japanese//小学三年// 悪安暗医委意育員院飲運泳駅央横屋温化荷開界階寒感漢館岸起期客究急級宮球去橋業曲局銀区苦具君係軽血決研県庫湖向幸港号根祭皿仕死使始指歯詩次事持式実写者主守取酒受州拾終習集住重宿所暑助昭消商章勝乗植申身神真深進世整昔全相送想息速族他打対待代第題炭短談着注柱丁帳調追定庭笛鉄転都度投豆島湯登等動童農波配倍箱畑発反坂板皮悲美鼻筆氷表秒病品負部服福物平返勉放味命面問役薬由油有遊予羊洋葉陽様落流旅両緑礼列練路和 Japanese//小学四年// 愛案以衣位囲胃印英栄塩億加果貨課芽改械害街各覚完官管関観願希季紀喜旗器機議求泣救給挙漁共協鏡競極訓軍郡径型景芸欠結建健験固功好候航康告差菜最材昨札刷殺察参産散残士氏史司試児治辞失借種周祝順初松笑唱焼象照賞臣信成省清静席積折節説浅戦選然争倉巣束側続卒孫帯隊達単置仲貯兆腸低底停的典伝徒努灯堂働特得毒熱念敗梅博飯飛費必票標不夫付府副粉兵別辺変便包法望牧末満未脈民無約勇要養浴利陸良料量輪類令冷例歴連老労録 Japanese//小学五〜六年// 圧移因永営衛易益液演応往桜恩可仮価河過賀快解格確額刊幹慣眼基寄規技義逆久旧居許境均禁句群経潔件券険検限現減故個護効厚耕鉱構興講混査再災妻採際在財罪雑酸賛支志枝師資飼示似識質舎謝授修述術準序招承証条状常情織職制性政勢精製税責績接設舌絶銭祖素総造像増則測属率損退貸態団断築張提程適敵統銅導徳独任燃能破犯判版比肥非備俵評貧布婦富武復複仏編弁保墓報豊防貿暴務夢迷綿輸余預容略留領異遺域宇映延沿我灰拡革閣割株干巻看簡危机貴揮疑吸供胸郷勤筋系敬警劇激穴絹権憲源厳己呼誤后孝皇紅降鋼刻穀骨困砂座済裁策冊蚕至私姿視詞誌磁射捨尺若樹収宗就衆従縦縮熟純処署諸除将傷障城蒸針仁垂推寸盛聖誠宣専泉洗染善奏窓創装層操蔵臓存尊宅担探誕段暖値宙忠著庁頂潮賃痛展討党糖届難乳認納脳派拝背肺俳班晩否批秘腹奮並陛閉片補暮宝訪亡忘棒枚幕密盟模訳郵優幼欲翌乱卵覧裏律臨朗論 Japanese//中学// ���哀挨曖扱宛嵐依威為畏尉萎偉椅彙違維慰緯壱逸芋咽姻淫陰隠韻唄鬱畝浦詠影鋭疫悦越謁閲炎怨宴援煙猿鉛縁艶汚凹押旺欧殴翁奥憶臆虞乙俺卸穏佳苛架華菓渦嫁暇禍靴寡箇稼蚊牙瓦雅餓介戒怪拐悔皆塊楷潰壊懐諧劾崖涯慨蓋該概骸垣柿核殻郭較隔獲嚇穫岳顎掛括喝渇葛滑褐轄且釜鎌刈甘汗缶肝冠陥乾勘患貫喚堪換敢棺款閑勧寛歓監緩憾還環韓艦鑑含玩頑企伎忌奇祈軌既飢鬼亀幾棋棄毀畿輝騎宜偽欺儀戯擬犠菊吉喫詰却脚虐及丘朽臼糾嗅窮巨拒拠虚距御凶叫狂享況峡挟狭恐恭脅矯響驚仰暁凝巾斤菌琴僅緊錦謹襟吟駆惧愚偶遇隅串屈掘窟繰勲薫刑茎契恵啓掲渓蛍傾携継詣慶憬稽憩鶏迎鯨隙撃桁傑肩倹兼剣拳軒圏堅嫌献遣賢謙鍵繭顕懸幻玄弦舷股虎孤弧枯雇誇鼓錮顧互呉娯悟碁勾孔巧甲江坑抗攻更拘肯侯恒洪荒郊貢控梗喉慌硬絞項溝綱酵稿衡購乞拷剛傲豪克酷獄駒込頃昆恨婚痕紺魂墾懇沙唆詐鎖挫采砕宰栽彩斎債催塞歳載剤削柵索酢搾錯咲刹拶撮擦桟惨傘斬暫旨伺刺祉肢施恣脂紫嗣雌摯賜諮侍慈餌璽軸叱疾執湿嫉漆芝赦斜煮遮邪蛇酌釈爵寂朱狩殊珠腫趣寿呪需儒囚舟秀臭袖羞愁酬醜蹴襲汁充柔渋銃獣叔淑粛塾俊瞬旬巡盾准殉循潤遵庶緒如叙徐升召匠床抄肖尚昇沼宵症祥称渉紹訟掌晶焦硝粧詔奨詳彰憧衝償礁鐘丈冗浄剰畳壌嬢錠譲醸拭殖飾触嘱辱尻伸芯辛侵津唇娠振浸紳診寝慎審震薪刃尽迅甚陣尋腎須吹炊帥粋衰酔遂睡穂随髄枢崇据杉裾瀬是姓征斉牲凄逝婿誓請醒斥析脊隻惜戚跡籍拙窃摂仙占扇栓旋煎羨腺詮践箋潜遷薦繊鮮禅漸膳繕狙阻租措粗疎訴塑遡礎双壮荘捜挿桑掃曹曽爽喪痩葬僧遭槽踪燥霜騒藻憎贈即促捉俗賊遜汰妥唾堕惰駄耐怠胎泰堆袋逮替滞戴滝択沢卓拓託濯諾濁但脱奪棚誰丹旦胆淡嘆端綻鍛弾壇恥致遅痴稚緻畜逐蓄秩窒嫡抽衷酎鋳駐弔挑彫眺釣貼超跳徴嘲澄聴懲勅捗沈珍朕陳鎮椎墜塚漬坪爪鶴呈廷抵邸亭貞帝訂逓偵堤艇締諦泥摘滴溺迭哲徹撤添塡殿斗吐妬途渡塗賭奴怒到逃倒凍唐桃透悼盗陶塔搭棟痘筒稲踏謄藤闘騰洞胴瞳峠匿督篤凸突屯豚頓貪鈍曇丼那謎鍋軟尼弐匂虹尿妊忍寧捻粘悩濃把覇婆罵杯排廃輩培陪媒賠伯拍泊迫剝舶薄漠縛爆箸肌鉢髪伐抜罰閥氾帆汎伴畔般販斑搬煩頒範繁藩蛮盤妃彼披卑疲被扉碑罷避尾眉微膝肘匹泌姫漂苗描猫浜賓頻敏瓶扶怖附訃赴浮符普腐敷膚賦譜侮舞封伏幅覆払沸紛雰噴墳憤丙併柄塀幣弊蔽餅壁璧癖蔑偏遍哺捕舗募慕簿芳邦奉抱泡胞俸倣峰砲崩蜂飽褒縫乏忙坊妨房肪某冒剖紡傍帽貌膨謀頰朴睦僕墨撲没勃堀奔翻凡盆麻摩磨魔昧埋膜枕又抹慢漫魅岬蜜妙眠矛霧娘冥銘滅免麺茂妄盲耗猛網黙紋冶弥厄躍闇喩愉諭癒唯幽悠湧猶裕雄誘憂融与誉妖庸揚揺溶腰瘍踊窯擁謡抑沃翼拉裸羅雷頼絡酪辣濫藍欄吏痢履璃離慄柳竜粒隆硫侶虜慮了涼猟陵僚寮療瞭糧厘倫隣瑠涙累塁励戻鈴零霊隷齢麗暦劣烈裂恋廉錬呂炉賂露弄郎浪廊楼漏籠麓賄脇惑枠湾腕 Japanese//記号// ・ー~、。〃〄々〆〇〈〉《》「」『』【】〒〓〔〕〖〗〘〙〜〝〞〟〠〡〢〣〤〥〦〧〨〩〰〳〴〵〶 Greek & Coptic//Standard// ʹ͵ͺͻͼͽ;΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώϐϑϒϓϔϕϖϚϜϞϠϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬϭϮϯϰϱϲϳϴϵ϶ϷϸϹϺϻϼϽϾϿ Cyrillic//Standard// ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџѢѣѤѥѦѧѨѩѪѫѬѭѰѱѲѳѴѵѶѷѸѹҌҍҐґҒғҖҗҘҙҚқҜҝҠҡҢңҤҥҪҫҬҭҮүҰұҲҳҴҵҶҷҸҹҺһҼҽҾҿӀӁӂӇӈӏӐӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝӞӟӠӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹӾӿ Thai//Standard// กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮฯะัาำิีึืฺุู฿เแโใไๅๆ็่้๊๋์ํ๎๏๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๚๛
see also How to Edit a Glyph that is not listed on iFontMaker
#FAQ#ifontmaker2#Symbols#Dingbat#Cyrillic#Greek#Coptic#thai#character set#character sets#list#language
5 notes
·
View notes
Text
光の庭
!Fire Emblem Heros fan fiction!
・カミュとプリシラの話。名も無き森の夢語りの続き。
・独自解釈・ネタバレ・異世界交流を含みます。カップリング要素一切皆無。
Image song:光の庭(D)
00.
ある時、美しい真白の城に美しい姫君が居た。美しい姫君は、一人の王子様に恋をしていた。幼い頃に、出会った異国の王子様。だが、王子様は黄金郷を探しに長い長い旅に出てしまった。姫君は戻って来ない王子を慈しみ、会いたいと願った。だが、彼女の前に現れたのは、美しい悪魔だった。悪魔は言った。
「お前の願いを叶えてやろう」と。
01.
たまに愚痴りたい時もある。とかつて、この世界には居ない部下のロベルトが言っていた。王だって、王子だって――たまに不満を漏らしたい時もある。
アスク城にある酒場で、レンスターの王子はミルクを飲んでいた。
「不思議な感覚だな」
目の前に居るレンスターの王子はそう言い、椅子に座りながら此方を見ていた。
「この世界に来てから、驚きの連続だと思った。セリスの父上と母上が一緒に居て、アレスの父上と…伯母上もこの世界に居る。最初は夢だと思っていたけど、頬をつねっても、夢じゃない――本当の世界なんだなって」
「リーフ王子は、どう思いますか?」
「でも…この世界に来ていない父上と母上が来たら――僕は、どんな気持ちでいけばいいんだろうって。それが不安なんだ。フィンやナンナも、僕に気を遣ってくれているけど、僕は王の器に立つのが相応しいのかどうか、悩んでいるんだ」
リーフは王の立場であるが、王の立場に相応しいかどうかは――自分自身でも分からないのだ。幼い頃に国を追われ、若き騎士と、異国の王女と共に各地を帝国軍から逃げるように転々として来た日々。とある村でエーヴェルと言う女性に救われ、村の人達と、家族のように過ごしてきた日々。その平穏な日常が、ずっと続けばいい。その平穏が――帝国軍の襲来と共に終わった時。
自分にも見覚えがある筈だ。幼い双子の王子と王女も、立場が災いし、暗い、孤独のような日々を送ってきた。王族の頂点に立つのも、王族に生まれるのも、碌な事が起きない。それがリーフ自身が理解している事であり――黒騎士カミュの悲しみでもあった。
「貴方は貴方の道を進めばいい」
だから、自分なりの言葉を贈る事が、精一杯の類でもあった。
「王族であっても、貴方は貴方の道を進めばいいのです。誰の言葉に惑わされなくたっていい、自分の、信じる道を突き進めばいい」
それが――自分自身の答えでもあり、嘗て――自分自身が下したつらい決断でもあった。だが、目の前の王子は、
「…何だか、あなたの言葉に、救われた気がするよ…有難う、カミュ将軍」
――救われた、か。
自分は、誰かの助けになれたのだろうか。酒場からの帰路についている最中、自分自身はその言葉に悩んでいた。
『…それでも、人は何処へ行くのでしょうか』
トルバドールの女性のプリシラから言われたその言葉は――確かに、彼の胸に響いた。人は、死んだら何処へ行く。
「…カミュ将軍、聞こえていますか?」
リーフの護衛騎士であるフィンから、ハッと我に返った自分は彼の方を見た。
「先程、リーフ様と何かお話しされていましたが…どうしましたか?」
「あ、ああ…少し、彼の悩みについて相談したりしていた」
「…そうですか、有難う御座います」
フィンからいきなり感謝され、こちらも理解がイマイチ分からなかった。何故、感謝されてしまうのだろうか。
「…私でも時、リーフ様のお力に、なれない時があるのですよ。自分自身では耐えきれない、立場故や、ナンナ様の事――そして、キュアン様とエスリン様の悩みを抱えているのですから…ですが、こちらに来てから打ち明けられる人が居て、嬉しかったと思うのですよ。だからこそ――」
「いえ、いい…此方こそ、感謝する」
自分自身でもどうすることも出来ない悩みは――リーフやフィンだけが抱えているのではない、エレブ大陸の杖使いのプリシラも心配していたと言うのなら、自分は結局。一人で悩みを抱えているのだな。と苦笑しながら。
02.
「光と闇、どちらが正しいかなんて私には分からないんですが、どちらも間違っている、どちらも正しいって言うのは、人其々なんだと思います」
モノクルをクイッと片手で正し、闇魔導の使い手である彼――カナスはそう述べた。カナスの自室の書斎は彼にとって、宝庫であろう。ナーガ神についての伝承、ギムレーに関してのレポート、ラーマン経典、正の女神アスタルテの本…探究者である彼は、異国の騎士である自分にそう述べた。
「貴方が出会ったあの闇に堕ちた暗黒皇帝ハーディン…でしたっけ、彼は元々、善良な騎士だったと聞きます。オルレアンの方々から慕われていて、草原の民達からは希望だったと聞きました…例えるなら、闇に堕ちてしまえば、後は奈落の底――私は、堕ちてしまった人達を知っています」
黒い牙の者達の事を、述べたいであろう。剣を振るう『白狼』のロイド、獰猛な凶器を振るい、戦場を大暴れする『狂犬』ライナス――彼らの事を言いたげであった。自分は「何も言わなくていい」と告げ、カナスは「有難う御座います」と申し訳無さそうに言った。
「…闇は、必ずしも負の一面、悪とは限らないと、私は思うのです。歴史に葬り去られた、真実。語られざる、英雄の物語――それは、貴方が経験していると自分自身が物語っているからこそ、歴史が証明している。そう、例えばマルス王子が」
光の英雄なら、貴方は闇の英雄でしょうか。
「…妙な例え方だな、しっくり来る」
「でしょう?」とカナスは人差し指を振った。彼が椅子に座っており、机には色々書物が積み重なっていた。「バレンシア大陸の歴史」「ギムレー経典」「アステルテ経典」「魔石と魔王」「神竜ナーガとメディウスについて」知識を欲する彼が、異界の書物を欲するのも無理はない。と我ながら思う。するとカナスは、ある一冊の本を本棚から出した。
「英雄王マルスの物語」
知識を欲する彼が、この英雄譚に興味を持つのは珍しい事だ。自分の悩み故の決断力であろうか。
「マルス王子が、皆から慕われている光の英雄ならば、貴方とハーディンは闇の英雄です。ですが、彼と貴方の闇は、断然に差があり――違うのです。暗黒皇帝と化したハーディンは、心の闇に、呑まれた英雄。そして貴方は――例えるのは少し難しいのですが、歴史の闇に葬り去られた、英雄でしょう」
ああ、納得した。あの時の自分は黒騎士ではなく、ただの旅の者であった。カミュではなく、シリウスと名乗っていた。
「史実なき戦い、影に隠れた者――闇に葬り去られた者は、私の世界でも居ます。ですが…光と闇は、バランスが成り立たなければ存在意義を見出す事が出来ない。そして、貴方は――何を見出したのでしょうか。何を――」「カミュしょーぐん!マークス様とミシェイル様が呼んでるの!」
自分とカナスが振り返ると、ピエリとラズワルドが自室のドアを開けて、自分を呼び出しに来たのだろう。ラズワルドが「だ、大事な話をされていたのですね…!」と申し訳無さそうな表情をしたが、自分は「いや、良い」と手を振った。
「では、この話はまた、後程で」
まるで自分らしくない。と言い聞かせながら――自室のドアを、閉めた。
「…行ってしまいましたか」
カナスは、飛び出して行ったカミュを見つめ、ふぅ…と疲れた息を吐き出す。やはり、自分はこの世界でも探求を求めすぎている悪い癖が出てしまったようだ。
「…後で、ピエリさんとラズワルドさんに、お菓子でも贈っておきましょうか」
申し訳ない事をしてしまった表情をしたラズワルドに、お詫びの礼の品を考えておきながら、カナスは一つ、気になる事を呟いた。
「…それに、まるで彼女について話したくない素振りを、していた気がしますね…」
03.
「彼の王は泥から生まれた」
アカネイアの大陸一の弓騎士は、そう答えたという。泥から生まれた――その例えは、何処から来たのだろうか。レベッカはそう思った。
それは前、あの自分でさえも畏怖する力を持つ暗黒皇帝と相対していた時の事だ。ジョルジュやカミュが、苦虫を噛んだ表情をしていたのを忘れられない。それに、プリシラも、カミュやマークスについて余所余所しい態度をつい最近していたのも切っ掛けである。あまり他人の過去に突っ込みたくない(エリウッドや彼の御子息の有り難い御忠告である)のだが、ジョルジュと話をするタイミングが偶然にも弓を射る練習の休憩時に出来てしまったのだから。
「…ハーディンは、元々はオレルアン王の王弟だ。しかし、兄より劣る弟と言うのが災いなのか、少し心に歪があった」
ゼフィールもそうだった。彼は優秀過ぎるが故に、父親から忌み嫌われていた。とエリウッド様の御子息であるロイ様もそう仰っていたわね。とレベッカは納得の表情を浮かべた。それと同時に、遣る瀬無い感情が浮かび上がった。
「だが、アカネイアも元々は、高貴な血で建てられた国じゃない、それと同時に――神に守られし王国でもなかった。三種の神器を竜の神殿から盗み、其れを統治して出来上がった王国だった」
「こっちも、竜と人に歪な亀裂が入っていたのね」
「…人間、そう簡単に上手くいくもんじゃないがな。俺だってアカネイアの傲慢な貴族が嫌いだった。ラング将軍やエイベル将軍も、俺は死ぬほど嫌いだったが、アカネイアの為に、と何処かで逃げていた。現実逃避をしていたのかもしれない」
「こっちも大変なのね。ロイ様から、可愛らしいギネヴィア姫様が美しく成長したって言うから…もし会える機会があったら、見てみたかったなぁ」
「そうか…此方もニーナ様と出会える機会があったら、宜しく頼む」
分かった、約束するわ。とにこやかに微笑んだのだが――ジョルジュは口を開き、重たく、ある事を語る。
「――俺も、何時かはああなるだろう。と何処かで諦めていた」
「いつかは、ああなる…?」
「アカネイアの血を引く民が、他国の者達を蔑み、愚かだと嘲笑い、奴隷階級の者同士を戦わせ、動物の様な目でしか見ない剣闘士達の闘技場を見世物の様に観戦し…俺はそれが嫌いだった。だが、俺では何とかならなかった。ニーナ様は、その現状を変えようと必死に頑張っていた。だから俺は彼女の手伝いをしようと考えていた。だが、俺では役不足だったと…グルニア軍と戦う時に、気付いてしまった」
「あ…ああー…黒騎士の、カミュ将軍の事かしら?」
「だが、彼でしかニーナ様の心を開く事しか出来なかったんだろうな。敵国の騎士と、我々の国の王女、相容れない関係なのに、出会ってしまった。出会わなければ良かったのか、出会ってしまったのは必然だったのだろうか。それは今の俺にとっては分からない事だった」
ジョルジュの疑問に、レベッカはある事を口にしようとしたが――開けなかった。
――ね���、それはもう、必然だった方が良かったのじゃないかしら。辛い事や、悲しい事、楽しい事があるけれども、出会わなければ、何かが産まれなかったんじゃないかしら。
ニニアンの事を思いながら、レベッカの拳は固く握りしめた。
04.
ニノは歌を歌っている。古い、エレブに伝わる歌である。まだ幼さが残っている魔導士の少女は、アスク城のバルコニーの冷たい夜風に吹かれながらも、用意されている椅子に座って歌を歌っていた。
それを遠回しに見ていたカミュとミシェイルは、暗夜第一王女カミラの臣下である竜騎士の少女から貰った(彼女曰く、日頃レオンやマークスと接していたからそのお礼らしい)暗夜王国産のワインをグラスに注ぐ。
「何処か、遠い国の歌のように見えた」
とカミュはそう述べた。歌は、竜と人の物語を準えた叙事詩のようであった。竜と契約した者と、美しい少女の物語。エレブ大陸に伝わる、悲しい物語でもあった。
「あの少女は、雪を義理の兄と一緒に見た事があるらしい…俺も、ろくに妹であるマリアに、其れらしい事が出来なかったな」
王の激務に追われ、妹のマリアと一緒に、遊んだり一緒にお出かけする事が出来なかったらしい。その王位が、自らの父を手をかけた代償だったとしても、マリアはミシェイルが大好きだった。大好きな兄を、慕っていたのだ。
「…私も、同じ気持ちだ」
敬愛する王の子であるユミナ様とユベロ様と、一緒に遊んだり笑ったり、泣いたりする事はごく僅かで、彼等に何か残す事が出来たのか――後悔した事もあった。
カミュはそう、述べていたがミシェイルに至っては
「貴様はバレンシアであのリゲルの王子と楽しく接していたのではないか」と答えたが、カミュは首を横に振った。
(貴様は本当に優しすぎるな。それが仇となる時があるのだがな――)
ミシェイルはそう思う。マリアから見たら自分は「優しい兄」だと思うのであろう。だが、自分はそう優しい兄ではない。妹のミネルバから見たら「父親殺しの自分勝手な兄」と認識された事もあった。
ニノが歌を歌い終わり、立ち上がる。バルコニーの玄関に優しい兄であるロイドとライナス、大事な人であるジャファルが居て、ニノは駆け寄ってロイドに抱きしめる。
(兄である俺が、何をしてやれたんだろうな)
ミシェイルは思い悩む――すると、カミュは笑って誤魔化した。
「だとすれば、貴方も私も同じ悩みを抱えていたのではないか。優しい兄と、王子と王女に仕える騎士が、何をやれたのだろうか」
「お前は悩んでいるのか?」
「ええ、自分は――優しすぎるのではないのか。と思い悩む事があるのです。少し、コンウォル家の令嬢と出かけた時に」
あのトルバドールの少女の事か。とミシェイルはすぐに分かった。彼女は厳格な兄と、彼に使える優しげな、柔らかな声音をした修道士の従者が居る。
「…カミュ」
「…何だ」
「――ドルーアに従った者同士、同じ悩みを抱えているが…貴様も俺も、『どうしようもない大人同士』また、飲む事があったら悩みを打ち明けようか?」
「…それは遠慮しておきます」
やはりこいつは騎士であるが故に優しすぎるな。とミシェイルはそう思いながらも、最後の一杯であるワインを飲み干した。
05.
戦場を駆ける漆黒の駿馬、まるで父上の様だと最初は、そんな感想を自分の心に抱いていた。
「…おい、貴様」
プリシラはゲストルームで暗夜王国のあのドジなメイドのフェリシアが淹れた紅茶を飲んでいる最中に、ある人物と出会った。プリシラは唇をハンカチで上手に拭き取り、後ろの方を振り返る。やはり、最近召喚されたばかりの――師子王エルトシャンの息子であり、セリスやリーフと共にユグドラルの解放戦争を戦った仲でもある…。
――黒騎士アレス。父親譲りの剣裁きをし、戦場にその名を轟かせている聖騎士だった。
「はい、何でしょうか」
自分がそう答えると、アレスは「丁度良かった、貴様に話がある」とソファに腰掛けた。ベルクトといい、ミシェイルといい、兄と同じ融通が利かない人達と何気に縁があるのだろうか。とそう思っていると、アレスは意外なことを口にする。
「…最近、カミュについて気にしているのだな」
「えっ」プリシラはティーカップを落としそうになったのだが、アレスは「いや、忘れてくれ」とそっけなく答えた。これでは話になっていないのでは。思い切って、プリシラが思い当たる部分を考え、アレスに対してある事実を口にする。
「…貴方のお父様を、思い出しちゃったの?」
無言。どうやら図星のようだ。だが、アレスは「ああ、そうだ」と答えを口にする。プリシラは「やっぱり、そうなんですね」とふふっと笑う。早速だから、彼もお茶に誘ってしまおう。と、隣に居たジョーカーに、紅茶を頼んだ。
「エルトシャン殿下と、カミュ将軍は無茶をし過ぎなんだと思います」
毎回、シグルドとミシェイルが彼等を抱えて私やセーラさんの所に駆けつけて杖の治療を受けてしまうんです。と口にする。
「父上が、シグルド…様と本当に親友だったのか」やはり彼は敵討ちのシグルドに対して敬語をつけるかどうか、まだ迷っているみたいだった。
「で、カミュがミシェイルに抱えられているのは…どんな関係なんだ?歴史書だと、ドルーア側に就いたマケドニアとグルニアの総帥だったと聞いているが」
「…どんな関係、ですか」
確か、その時カミュの事を話していたミシェイルは、友人と言うか、親友とは言い難い…所謂、共犯者?の様な態度をしていた。
「ええっと…一緒に戦った、戦友?」
上手く誤魔化しておく事にした。彼等に首を突っ込むと、余計事態が悪化してしまう。
「そうか」とアレスは納得した表情をした。
「正直、思う。俺はずっと復讐の事を考えていたが…実は、父上の背中を追っていただけだろうな。と今は思ってる」
プリシラは、何も口にしない。アレスの話を、ただ聞いているだけだ。
「…父上は、立派な騎士だったと、母上から聞かされていた。高潔で、誇り高く、優しい騎士だったと聞いていた。俺はそんな父上に憧れていた」
だが、父上が死んだ時は――全てが変わった。とアレスは何処か暗い表情で語る。
「…そうですか、誇り高い黒騎士さんでも、弱音を吐く事はあるんですね」とプリシラは、ちょっと皮肉を込めた言葉を吐き出した。
「騎士である彼等は、誰かを守る為に戦っているんです。貴方のお父様やシグルド殿下、セリス様に、エリウッド公…それに、カミュ将軍や、ミネルバ王女も、前線で戦っている。人はいつか死にます…ですが、その何かを、また次の誰かが受け継いでいるのでしょう」
アレスは「そうか」と口にすると、ソファを棚代わりにして置いているミストルティンを構える。
「…この剣は、父上が俺を見守っている証だったんだな」
プリシラは、そんな彼を見て――ゆっくりと微笑んだ。
「私も貴方も、似たような悩みを抱えているんですね。だったら、一緒にお話ししましょうか」
「んで、俺が弓兵に狙われている若を守る為に、颯爽と弓兵を背後から攻撃して、若を助けたんですよ!」
「成程…今度、ミカヤが狙われた時にはその戦法を組み込む事も考えてみるか」
「じゃあ弓兵はあたしに任せるね!マシューは魔導士をお願い!」
「いやいやいや、俺は若様命だからな!じゃあ魔導士はガイア、お前に任せるぜ!レベッカー、期待してるぜー」
「何で俺!?おい、アズ…ラズワルド、笑いを堪えるな!」
ハハハ…と、食堂で弾んでいるマシュー達の姿を見て、ルーテは考える。プリシラがカミュについて気にしている。つまり、プリシラはカミュを見て何かを思い出した可能性は高い。だとしたら、カミュと関わりのある人物を探ってみる事にした。ジョルジュ、リンダ、ミシェイル、ミネルバ、マリア、パオラ、カチュア、エスト、ベルクト、アルム…思い当たる節が見当たらない。だとすれば、まだ可能性がある筈だ。此処はプリシラに尋ねるしか方法は無いだろう。ルーテが心の中でえいえいおー!と誓った途端に、カミュがミシェイルと一緒に、食堂に入って行った。
「いっつも行動しているのは、お友達なのかしら?」とラーチェルが困惑している表情をしていた。何時だったか、覚えていない。ふと、彼等の会話が聞き取れた。
「…で、最近その御令嬢が貴様を気にしていると?」
「ああ、そうだが……恐らくは、あの一件で」「そうか」
(つまり)
「一緒に出掛けた時に、彼女の言葉が…うん…」
(プリシラさんと出掛けた――つまり、彼女の方程式に考えると、ピクニックか何処かに行ってきたのでしょう。そして、彼女の言葉を考えると――やはり、カミュ将軍の過去に何か関係が?)
ルーテがその光景を見ていると――後ろからカナスが「何をやっているんですか?」と話しかけてきた。
「いえ、人間観察です」
「人間観察って…ああ、カミュ将軍の事ですか」とカナスは、何か納得した表情で見据えた。
「多分、彼等については、放っておいたほうがいいと思います」
「どうしてですか?私は非常に気になるのです」
するとカナスは――微笑み、こう答えた。
「あれが、彼等なりの答えなのですから」
(彼等なり、ですか)
恐らくは、自分が介入しなくても、無自覚に彼の善人さが――悩みを解決してくれるのだろう。ルーテはそう思い、魔導書を持ち、立ち上がる。
「カナスさん、有難う御座いました」
ルーテが立ち去った後、一人取り残されたカナスは――ちょうど部屋に帰ろうとしていたマシューを呼び出す。
「…マシュー、少し良いですか?」
「えぇ、何だぁ?」
「私の悩みも聞いてくれませんか」「は、はあ…」
恐らく、カミュについては…勝手に誰かが、悩みを解決してくれるのだろうから。
07.
「わぁー!雪だ!」
黒い天馬に乗っている軍師ルフレの娘と名乗る少女は、降り積もる雪を見て感想を述べた。護衛にはパオラが居るが、どうやら雪と聞いて駆け付けたターナと、追っかけてやって来たであろうフロリーナも参加した。ミシェイルは不満げに竜で空を飛んでいるが――そう言えば、雪なんて久々だろう。とこの時思った。
『貴様は、雪を見たと言っていたが――何時頃だ、アンリの道か?』
『アンリの道…確か、氷竜神殿に行く最中に、だ。ミシェイルは雪の中を行くと言うのか?』
『少しあの軍師の娘とやらが雪を見たいと言っていてな…全く、あの黒い牙の少女もそうだが、少しは危機感を…』
『いえ、それは構わないと思った方がいい――こんなに降り積もる雪の中で戦った時は、氷竜神殿で竜達と戦った時以来だったな。だが、こっちの方が、まだ暖かい』
『…まだ、暖かい?』
『あの時、猛吹雪で――凍えるような息吹を感じたが、ニフルで降り積もる雪は…暖かさを感じる。死を感じられない雪だ』
出発前のカミュとのやり取りを思い出す。自分が彼女らの護衛に立候補に参加したのは、マークが自分の末っ子の妹を思い出す故か、将又他の立候補役が彼女等を任せられない故なのか(ナーシェンやヴァルター)…。だが、ミシェイルはこの雪に、確かな暖かさを感じられたのは事実だった。
「…あの、ミシェイル様?どうなされましたか?」
「いや、少し昔の事を思い出してな」
「…昔の事、ですか?」
「もし、俺と貴様、どっちがマルス王子率いるアカネイア軍を討ち取れるかとしたら――貴様はどっちを選ぶ?」
カミュは自分の忽然とした問いかけに戸惑いを隠せずに居るが、『もし仮にマルス王子を討ち果たし、そしてガーネフを倒せるか』についてを答えるとしたら。まあ、小難しい問いかけに彼は答える事が出来ないだろう――と確信した矢先。
「…ミシェイル、陛下だろう」
驚きを隠せない答えだった。何故自分がマルス王子を倒せるか?とカミュに問いかけた。しかし彼は
「騎士として死ねるのなら、それでいい」と答えるだけだった。丁度その頃は、雪がしんしんと降り続いていた。
結局は、この戦いに何も意味がないと分かっていただろうか、それとも――あの双子の未来が掛かった戦い故の、結論だろうか。
この雪には何もいい思い出がない。が、カミュは気楽に答えた。勝者と敗者の答えなのか、それとも…まあ、いい。これが終わったらカミュにさっさと暖かい酒を寄越せと訴えかけてやろう――降り積もる雪に、舌打ちをしながら。
08.
あいつの顔を見る。高慢な性格のリゲルの王子であるベルクトから見た黒騎士さんについての物語と言うのを誰かはそう言う。俺は彼ではなく、リゲルにいた頃を思い返す。叔父上と話していた時に、今と違う笑い方をしていた。何となくだが、あの時は陰りがない顔をしていた――あのティータという女性と幸せそうに、睦まじく過ごして��た。だが、今の姿は――リゲルの騎士ではなく、���ルニアの黒騎士団を率いる騎士の姿だ。何処か、陰りが見えたような気がした。
「貴様からしたら、どうなんだ」「だが、彼が優れた騎士であるのは間違いないだろう」
ノディオンの騎士であるエルトシャンから見たら、自分から見たら優れた騎士である事を直ぐに見抜いた。若くして死んだ者であるが、シグルドの戦友である彼の下す判断は、流石はクロスナイツ騎士団長でありながら、ミストルティンを持つ(どうでもいいが、息子も優���た騎士であるが俺と似た性格をしている)騎士である判断であろう。
「優れた騎士でも、弱点を取られると直ぐに脆くなる」「例えば?」
エルトシャンは口ごもった。きっとあのノディオンの王女や妻の事を言いたいのだろう。自分はそう易々と言及する事は無かった。自分もリネアの事を思い返していたからだ。
「父上は、そう仰っていたのか」
「そうだ」
アレスは自分の問いかけに答え「そうか…」と悩める、思春期の少年らしさをまだ残している表情をしていた。すると会話している自分達の後ろでプリシラが絵本を持って何処かに行こうとしていた。
「おい、いったい何をしに行くつもりだ?」
「あれ、ベルクトさんに…アレスさん?珍しいですね。二人で何をしていたのですか?」
「ちょっとな…貴様こそ、何をするつもりだ?」
「ノノやミルラが絵本を読みたいって言うから、書斎から絵本を取り出してきたんです。この絵本が一番好きそうかなー…と考えてしまったんです。じゃあ、私は先を急いでますから」
それでは、失礼します。と言い、彼女は先に行ってしまった。
(分からない事だらけだ、結局は――自分は皇帝にはなれないと、何処かで感じてしまったのか。だが、あいつは…王になる器になんて持っていなかった。そう言えば、カミュも何時だったか、ある事を自虐していたな)
『私は騎士の器を持っているとは思えないのですが――王には、猶更向いていなかったのかもしれません』
(…似たもの同士、って事か)
急に用事があると言い、ベルクトが立ち去った後一人取り残されたアレスも自室に帰ろうとした瞬間、後ろから肩をポンポンと叩かれた。後ろを振り返ると――不機嫌な表情をした、従妹のナンナが居た。
嗚呼、これはまた説教のパターンか。と理解したのだが…ナンナは、意外な言葉を口にした。
「ちょっと、話があるの」
09.
「最近、プリシラと言うあのトルバドールの少女とよく話してるわね…私だけじゃ、相手にならないと思っているわけ?」
伯母上譲りの気の強さが得りなナンナの言葉に、アレスは言葉を詰まらせた。別にそう言う訳ではない、ただのお茶会仲間だ。と上手く話せば、ナンナは「…そう」と溜息を吐きながらそう言った。彼女と話をするのは久々だろうか?…いや、ナンナはいつもリーフと話をしていた。そりゃあ彼女はリーフの大事な人だから…幼い頃から一緒にいた仲だろう、仕方がないとは言え、彼女に詰め寄られては困る。「気の強いナンナ様」に言い寄られては、流石の黒騎士アレスもお手上げだろう。
「…そうだな、ナンナ。俺は今、悩んでいるんだ」
「…悩んでいる?どうしたの、らしくないわよ」
らしくない、か。そうだな。と確かに今の発言はまずかっただろうか。ふと考えると、ナンナにある事を尋ねた。
「…ナンナ、一ついいか?」
「どうかしたの?」
「…お前は、フィンの事をどう思ってる?」
えっ。まさかアレスから、フィンの事を尋ねられるとは思っていなかった。これは、答えに迷ってしまう。私はフィンのことを理解している母とは違うのだ…だが、ナンナははっきりと答えた。
「大切な人よ。私やリーフを、立派にエーヴェルと一緒に育ててくれて…エーヴェルが石化した時も、支えてくれた人」
そうか。とアレスは無表情で頷き、天井を見上げた。
…アレスと別れた後、ナンナは彼の行動に不可解を感じた。
(…でも、どうしてあんな事を。いつものアレスだったら――あれ?)
そう言えばプリシラと言えば、一つ気になる事がある。プリシラは別の異界で黒騎士と言われているカミュについて詳しく調べている様子が見受けられた。アレスも、プリシラとお茶会をしていたと言う訳ではなさそうだ。じゃあ、一体何の為に?とナンナが考えるとしたら――直接カミュ本人に問い質すしか無さそうだ。
「…でも、どうしてアレスは悩んでいたのかしら…あら?そういえば、カミュ将軍と、叔父上は一緒に出撃していたから…もしかして、そのせい…?」
ナンナは、やっぱりアレスの気持ちも考えた方が良いのかしら。とぼやいた。
10.
ざく、ざく、ざく。プリシラはニフルの土地を歩いていた。雪が降り積もるこの国は、雪合戦でも出来そうだ。と考える程だった。そう言えばカミュも、カナスに話をしていたらしく、自分も彼も、似た悩みを持っているのだな――と思いながら、雪がじゃりじゃりとなるこの地を足で踏みしめながら、前に――カミュと一緒に森を歩いていた事を思い出した。死んだら、魂はどこへ行くのだろうか。と問いかけていた。彼は、ニーナ王女の事を語っていた。救国の聖女。と何処かの記述ではそう記され、或いは傾国の魔女。と記されていた。他者を犠牲で成り立っている平和と言うのは、あまりにも残酷だったのだろう――ロイが語っていた『女王ギネヴィア』の物語――ゼフィールの豹変、そしてベルン動乱…竜と人が、分かり合える日は何時かは来るのだろうか。もし、そうだったとしたら…この冬景色を、竜達が見られる日が来るのかもしれない。
ふと、プリシラの足元に、誰かが居た――下を見たら、竜の少女であるファが、雪を見てキラキラと目を輝かせていた。
「ファ、雪を初めて見た!」「ふふふ、そうですね。これが雪なんですよ」
あのね、ニニアンお姉ちゃんからお話しをしてもらったの!イリアの雪はね、綺麗なんだって!と健気に話す姿は、とても楽しかった。
カミュとミシェイル、それに兄とルセアも一緒に連れて来て、ファと一緒に遊ぶのも考えたのだが――雪を見て、思った。
「カミュ将軍に――また、問いかけたい事があります」
この世界にきて、どう思ったのでしょうか。私はそれが、聞きたいです。
「…」
外でニフルの雪を見て、カミュは思う。自分は役目を果たしたからそれでいい。と何処かで思っていた。だが、バレンシアのアルムやベルクト、ティータを見て――一度は考え直した。生きると言うのは、とても残酷な事だ、だが、必死に生きていれば、結果が見えてくる事もある。と言うのも、事実だ。だが、一つだけ心残りがあるとすれば――。
「…この雪を、一度だけニーナに見せてもらいたかったな」
彼女がこの世界に来るのは、まだ遠い。
11.
真白のお姫様に王子様に会える対価というのは、人の心臓でした。人の心臓を悪魔に渡せば、お前の願いは叶えてあげる。そう、1000人の人間の心臓を私に渡せ。と。
お姫様は必死に人間の心臓を食らい続け、悪魔に献上をしました。そして残り一つの心臓を悪魔に上げれば、王子様に会える――しかし、現実は残酷でした。何故なら、残りの心臓は、王子様でしたから。
そう、お姫様は、王子様の国の民や、家族の心臓を喰らい、悪魔に献上したのです。
怒り狂った王子様は、国の民や家族を殺したお姫様にこう言ったのです。
「人殺し」と。
そうして真白のお姫様の心臓は剣で貫かれ、ドレスは真っ赤に血に染まったのです。
1 note
·
View note
Text
RDR2:37:悪い奴等は~天使の顔をして~♪
みたいなアーサーさんもいいと思うんですよね。人目のあるところでは天使だけど見ていなところだと悪魔、みたいな? でもそれって、ギャングらしいプレイを効率的に行うための必須ポイントですよね?
それはそれとして、……元ネタ分からない人のほうが多そうですがホントそれはそれとして。
クレメンスポイントのキャンプの近くで、通りかかると「脚を使うんだよ脚を! 手を上げて!!」とかいう声が聞こえてくる場所がありましてね? ダンスの練習でもしてんのかよと思いつつスルーしていました。
しかし今日、なにげなく双眼鏡で覗いてみたら……

KKKか(ㅍ_ㅍ) 儀式の十字架を立てるのにじたばたしてたのか。
で、十字架の下敷きになった白いの二人、0(:3 )~ =͟͟͞͞(’、3)_ヽ)_かな(ㅍ_ㅍ)ドウデモイイガ
それにしても、ストロベリーからの帰り道で見かけた連中といい、間抜けに描かれてますね。恐ろしげに描かない、間抜け・馬鹿として描くというのは、対象を否定させるためとしてはなかなか良い手法だと思います。悪魔に憧れる厨二あるいは馬鹿はいても、馬鹿に憧れる馬鹿以下はそうそういませんもの。

さて、キャンプでレニーに話しかけて、ミッションすることにしました。
レニーは20代前半くらい? まだまだ場数は踏んでいないけど、賢くて勇気もあって、それに思いやりもある普通に良い青年。なのに黒人ってだけで、解放奴隷の息子ってだけで、差別され馬鹿にされ嫌われたりして生きづらく、そんな自分を当たり前に仲間として受け入れてくれるダッチギャングに身を寄せて……。
気軽に話せる相手も、大半は同じ黒人とか、あるいは中国人とかみたいに白人以外の人たちなんだろうなぁ。

で、彼等から仕入れた情報で、軍人崩れのルモワン・レイダーズが、武器なんかを貯めてるアジトがある、と?
字幕で口元隠れてますけど、アーサーもちょっと微笑みながら聞いてるんですよね。レニーのやる気、がんばって貢献しようとしてるのが頼もしいって感じですかね。

白人であるアーサーは、直接自分がそういう差別をされることがないから、レニーの抱える生きづらさを本当の意味で分かることはできないわけで。「あんたには分からないよ。黒人の俺と一緒に馬を並べて走らせてたら、暴言吐かれたりするんだぜ」っていうレニー。
アーサーたちのような、肌の色なんかまったく関係なく、「なんでそんなことでおまえ嫌うのかさっぱり分からん」て兄貴分たちがいるのは、心強い拠り所でしょうなぁ。
レニーの台詞からすると、西部のほうはそういう差別があんましないのかな。無法者のまだ生き残ってる世界だから、力さえあれば一目置いてもらえるってことなのか。それもまた駆逐されていく世界なんだけっども。

おや……ここってこの間きるきるしてスケッチしてきた教会じゃないか。セイディとの買い出しのときに絡まれた連中の仲間かもしれないってことでしたが、そうか、ここにいた連中も仲間だったのか。どうやらレニーと来るときは、イベント的に無人になるのかな。
ちなみに通り道にあった戦場跡地はやっぱり南北戦争のものでした。
教会をちょっと調べてみよう、と言っていると、怪しげな馬車が通りかかります。どうやら火薬とかを積んでるっぽい? よし、旅人を装って、ちょっと距離をとって尾行だ!
そして辿り着いたのが、アジトだという噂の邸宅跡。

あの赤い箱、全部火薬か?
レニーに友好的なふりをして近づかせ、奴等を集めてアーサーが一気にころころするか、それとも派手に爆発させて暴れるかの選択。
え……ちょっと待って。友好的なふりして近づくのが俺ならともかく、おまえはたぶんまずいぞ。こいつら絶対レイシストだろ。
というわけで、派手に行こうぜ٩(。•ω<。)و
さくっと赤い箱を撃って付近の敵を一掃。あとはこつこつ潰していきます。

二階だか三階だかのガトリング野郎は俺に任せろ! てなもんで、相変わらず前衛は仲間に頼み、自分はスナイパースタイル。
ところで西部劇、ガトリングというと「拳銃では相手のできない恐ろしい武器」なわけですけど、RDR2のものは大した威力もないのであんまし怖くはありません。もちろん、射程内、遮蔽物もないとなったら即座に蜂の巣でしょうけど。……ガトリングというと、昨今では��グ7のプラットさんが思い浮かびますなぁ。ベタだけど好きなシーン(´ω`*) でもあの映画で一番「あらやだ素敵(´ω`*)」てなったのはビョンさまのセクシー加減でしたけど。もともと嫌いな俳優さんではないけど、マグ7のキャラが一番好きですね。
閑話休題。
一掃した後調べると、ふほほほほ武器がたんまりありますな。売ればいい金になるぜ。

帰り道、案の定ルモワンどもとかち合います。まあとりあえず穏便に「おまえさんらのとこと取引してきたんだよ」とか嘘言っときますけど……「黒人なんかと取引するわけがねぇ。北部人のおまえだってなんか怪しい」と。
……じゃあ、ちねば?(ㅍ_ㅍ)
迂闊に銃撃戦すると、馬車の火薬に当たるとかあるんじゃないですかね? 一応「武器がいっぱいだ」って話しかしてないけどさ。万一火薬も積まれてたら確実にやばいので、とっととデッドアイです。
最近ショーンががんばってるから、みたいなレニーです。そうか、年齢の近い若者組、大人組の一歩手前の彼等には、早く認めてもらいたいって思いもあるし、同世代として張り合う気持ちもあるんだな(´ω`*)
ショーンは大口野郎だから言ってること真に受けるなよ、とアーサー。なにより、レニーはすごくがんばってる。この間ビルも褒めてたよな。カラードだから一層がんばらないと認めてもらえないって思いがどこかにあるのか、それとも、こんな俺を仲間にしてくれてるからって思いなのか。
おまえは本当によくやってる、焦らなくていいんだぞ。いっぱい功績上げなかったら仲間じゃなくなるなんてことないんだ。
なんて具合に、アーサーさんとシンクロしてしまいますがな。レニー、おまえはほんとにええ子や。゚(゚´ω`゚)゚。
それに、ショーンのこともなんのかんの言って、生意気で大口叩いてうるさいけど、決して嫌いじゃないぽいアーサーさんです。レニーに比べて短絡的で危なっかしいから、なにかしでかさないかハラハラしてたりして、そのせいでつい怒ったりしてるんじゃないかなw

手に入れてきた武器の中から一本、失敬しとこ。
ほほう、ボルト式ライフルですな。てことは、高威力の単発銃? 見た目がかなり好きなので、これは近いうちに銃砲店でカスタムしてこよっと。それに、強い猛獣と戦うときに役立ちそうだしね。
ちなみにうちの親父という人が、ライフル射撃の国体選手だったこともあって、昔の実家にはライフルのストックなんかがありました。自分はほんの子供だったので漠然としか覚えていませんけど、その形状によく似てる気がするんですよね、これ。

軽口くらいは叩くけど、基本的に素直でがんばり屋のレニーには、アーサーも毒づいたりせず素直に接します。おじさんほんとおまえには期待してるけど、でも命は粗末にするんじゃないぞ(´・ω・`)イイナ?

法執行官とか相手にするより、無法者相手にドンパチやるほうが後ろめたさがなくていいなぁなんてことを思いつつ、暮れの川辺を眺めるアーサーさん。空のグラデ、樹木のシルエットが綺麗です。

モリーとダッチはここんとこ毎晩みたいに痴話喧嘩……テントが隣なので毎度筒抜けに聞こえてるんですけど……?
構ってほしいモリーと、今後のこととか考えてるから邪魔されたくないダッチ。あー……それでおまえ他の男つまみ食いしたんだろ? そうなんだろ? そういえばモリーの相談事って、あれっきりではないと思うのですが、こじれない内に話つけたほうがいいぞー? 荒事になって俺が駆り出されるのは正直迷惑なんだけどなー? 平和に暮らしたいんだしー?
そんな一夜が明けて、「手に入れたボルト式ライフルをカスタムしてこよう!」とローズの銃砲店にマーカーつけたアーサー。
しかし……キャンプから出る道に、ホゼアのいる場所の黄色いエリア印がはみ出てましてねぇ。これをシカトして出て行くのも心苦しいわけで。

ホゼアは、密造酒を本来の持ち主、ブレイスウェイト家に買い取らせることにしたようです。そのへんで見つけたってことにして……って少し無理がある気はするけど、そこを言いくるめたり、お互い本当のところは分かってはいても、取引に旨味があるようにして持ちかけるのが彼の得意技か。
そもそも密造酒なんて公にできないものなわけで、迂闊によそに売るよりも、元の持ち主、さばくルートなんかを持ってる相手に売り戻したほうが良かろうってことでもありますかな。隠しておくにはかさばるしね。

邸宅前の用心棒たちには、商談に来ただけだ、俺たちが怪しい振る舞いをしたら撃ってくれていいぞ、なんて言って、とりあえず中に入る許可ゲット。

あー……おばちゃんが当主? やだなぁ。こういう業突く張りの金持ちババアって、野郎の場合よりタチ悪いんだよ大抵……( ・ὢ・ )
これはそもそもうちのものなんだからそれを買う理由はないだろ、いやでも今は俺たちが持ってますよ? みたいなやりとりの末、どう思ったか、金を払ってやりなと命じたキャサリン? ファーストネームは字幕に出なかったし、さらっと聞き流してしまいましたけど、なんかそんな名前。
しかし受け取るんじゃなく、これをローズの町の、グレイ家の酒場=ホテルに持ち込んで客どもにタダでくれてやって、一日の商売を台無しにしてやりなという命令つき。
どんだけ嫌いなんだグレイ家のこと。

ローズの向かう馬車上でも、「あの2家はとことん憎み合ってる」とか話してます。日記からすると、イングランド系のグレイ家と、スコットランド系のブレイスウェイト家だったかな。まあ犬猿の仲ですね。
そしてホゼアの計画。「おまえはこれかぶってパイプくわえて、俺の弟でバカのふりして黙ってろ」。アーサーにこんなことさくっとさせられるのは、さすがホゼアw ……ところで弟ってのはちょっと無理が……いえなんでもありませーん:( •ᾥ•):
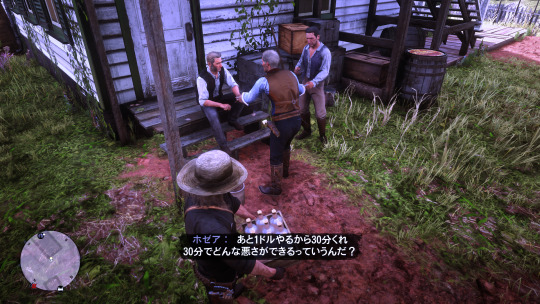
裏口にたむろしてる店員? あるいは用心棒? に小銭を渡してちょっと入れてくれよ、30分だけだからさー、と押し通るホゼア。

そして、密造酒の大盤振る舞い!!

アーサーはひたすら注ぐ係です。しかもプレイヤー、ちゃんと時々操作させられるw

ぐっでんぐでんになった人たち。普段は小粋なピアノを奏でてくれてるピアニストも椅子の上に立ってノリノリになってますw
だがしかし、そこにルモワンレイダーズが! それは俺たちの酒だろ、とか言ってきて、誤魔化そうにも通じず、はい銃撃戦。
えっと……ちょっと待って? ローズでドンパチ禁止じゃなかったっけ……?σ(๑• . •๑) しかもホゼアはグレイ保安官に会ってダッチとともにしばらく話し込んでたわけだし、やばいんじゃないの??

まあいいや。とりあえずホゼアを放せこの野郎( ・ὢ・ )

逃げてきた二人。
金はある程度貯まったけど、逃亡しきった後で安定した暮らしをするためには、もっと金がいる。その点ではホゼアもダッチと同意見なのか。
金、金、金……。金を追って、その金で買われた銃に追われて、追いつめられていくんじゃないのかね……? コーンウォールからピンカートンに大金が流れてもいるようで、コーンウォールという大資本を敵に回したヤバさはこれからますます募ってきそうです。

キャンプに戻ってダッチに報告。これからどうするのかと言うと、ダッチは、ブレイスウェイト、グレイ、双方に取り行って、いがみ合いを利用して相手の仕業と見せかけつついろいろといただこうと、そういう計画なようですが、あまりにも危ない橋。
……マイカ、おまえなんか吹き込んでんじゃないだろな? つーかダッチがなんでマイカを重用するのかが謎。……なんとなく、今のダッチが「聞きたい言葉」を言ってくれるからかもなって気はします。殺しや盗みを楽しめればいいから、この先どうなろうと知ったこっちゃないし、たぶんダッチギャングって場に愛着もないから、潰れたらよそに行くだけ。だから自分の好きな騒動と混沌が起こるように仕向けたい。だからハイリスクハイリターンで起死回生狙おうとしてるダッチを気軽に、無責任に焚き付けられる。違うかな。
この先のストーリー見ていけばもっと見えてくるものもあるのでしょう。ただ、それでもマイカに忠誠心があったとかは、絶対ない気がするw
個人的には、そういう本物のトラブルメーカー、凋落の決定的な引き金引く存在ってのが身内にいたほうが面白いと思います。誰も彼もが主人公に都合のいいことばっかり言ったりしたりする世界よりはずっと好き。
さて、次回は「世紀の銀行強盗」。派手なミッションタイトルなんだけど……メンバーがビルとレニーとカレン? それで「世紀の」? いや……ダッチが陣頭指揮取って、選りすぐりの精鋭でとかなら分かるけどさ?w
そしてこれもまた、「ボルト式ライフルを……」と思って馬の傍に行ったらビルがすぐそこにいて「アーサー」、「アーサー」ってしつっこく呼ぶのでね……つい話を聞いちゃった系でのスタートですw
1 note
·
View note
Text
世界にごめんなさい
あたし達は駅前の安っぽいチェーン店で、ハンバーガーを食べていた。この店は繁華街と通りを一本隔てた場所に建っている。横断歩道を渡れば、そこは猥雑な世界だ。ハイヒールのお姉さんが生足をブリブリ出して闊歩している。男どもが万札ばりばり言わして女を買いにきてる。まるで薄汚い森のようだ。あたし達はそんな大人の事情なんて知りませんよという顔をして、だらだら話をしていたんだ。制服から誇らしげに生やした太腿を、忙しなく組み替えながら。学校をさぼったわけではない。今はれっきとした放課後。ヤンチャが格好いいなんて価値観、もうダサいんだ。
「彼氏とのセックスが良くないんだよねえ」
とアコは言った。あたしは、
「当たり前じゃん」
と相槌をうつ。
「世の中、そういうもんなのだ」と、あたし。
「それでいいのだ」と、アコ。
「西から昇ったお日様が」
「違くて。そういうもんってどういうもんよ。ミイはすぐ煙に巻くような言い方するんだから」
「そういうもんなんだよ。愛に運命があるのと同じように、セックスにも運命があると思うのよね。あたしは二つ同時に当たりを引くなんてこと、まずないと思ってるの」
アコは「あ、そうなの」なんて、分かったような分かっていないような返事をする。仕方がない。アコは彼氏とのセックスの記憶をなぞるので忙しいのだ。あたしはアコに聞く。
「ていうかあんた、彼氏いたっけ?」
「向こうがそう言い張るからもしかして彼氏なのかなって」
「じゃあんたは心の底では、その人のことを彼氏だと思ってないんだ」
「めんどくさー。別にどうでもいいじゃん。彼氏なんてさ、セックスした相手に貼るレッテルよ」
そうね。ほんとそうだわ。あたし達はこの話題をゴミ箱に捨てた。
アコはチープな紙コップからコカコーラを啜っている。席を陣取るために飲み物頼んだのに、それじゃあすぐになくなっちゃうよ。それに見てみろ、このどす黒さ。見るからに不健康な色をしている。あたしは得体の知れない飲み物を美味しそうに啜ってるアコが信じられない。あたしはストローでオレンジジュースを掻き回しながら言う。
「そうして世の中回ってるのね。くるくるくるくる」
「だーかーら、それが分かんないの。全然納得いかないよ」
アコはぶりっと頬を膨らませる。可愛くねえ。
「あーあ、セックスがスーパーマン並に上手い男捕まえて、朝から晩までイかされたい。どっかにいると思うんだよね、そういうバカ野郎が」
「いねーよ」
あたし達はげらげら笑った。
アコは氷が溶けて地獄の釜のようになった紙コップをぐしゃっと握り潰した。あたし達はとっくに冷めてるテリヤキバーガーにかぶりつく。お腹は空いてないんだけど、それとこれとは関係がないんだ。あたし達は性欲のまま行きずりのサラリーマンとセックスするように、物を食べまくる。あたし達は満足するまで食べたいんだ。色んなものを。与えられるものがあったら、全部ぺろっとたいらげたいんだ。
「誰か与えてくれないかな。何かを」
あたしが呟くと、アコが神妙にうなずいた。おっかしいの。バンズの端っこから茶色い汁がこぼれ落ちる。アコはそれを人差し指ですくい上げ、べろっと舐める。
「アコ、あんたその仕草似合ってるよ」
「うそ。あたしエロい?」
「はは。それ、男の前で言えよ」
「そうねえ。確かに」
あたし達はしょっぱい唇をぺろぺろ舐めながら、チェーン店を後にした。
俗っぽい店に行った後は、こんな風景が頭に浮かぶ。ソースまみれの包み紙が、店員の手で無様に捨てられるの。あたしはその光景を思い浮かべると、少し興奮するんだ。それがあたしだったらいい。見知らぬ男のたくましい手で、骨まで丸めこまれて血みどろのまま捨てられたい。
「ねえねえ、あたしちょっとセックスしてくから、ミイ先に帰ってて」
目を離した隙に、アコは見知らぬサラリーマンと腕を組んでわくわくしている。いつもこんな調子だ。あたしは舌を出して言う。
「ばーか。殺されても知らないからな。えんじょこーさい、不倫、殺人事件だ、アホ」
「うわっ。ださー。九十年代的な退廃の香りがぷんぷんするよ」
「バブル崩壊の年ですからね、荒みもします。エヴァンゲリオン然り」
サラリーマンが口を挟む。うるせーお前は黙って七三になっていればいいんだよ。あたしはアコに囁く。
「その男、鞄に包丁忍ばせてるかもよ」
「な、何を言ってるんだ君は。ぼくは根っから真面目で爽やか彼女と妻を大事にする健全にスケベの……」
と、リーマン。うるせーっての。
「ホテル入った途端、後ろからぶすっ。あんたの動脈から血が噴き出るよ。ダブルベッドが血染め。大きな青いゴミ箱、満タンになっちゃうくらいの血液」
「うわあ、そしたらアコ、蝋人形みたいに青白くなっちゃうね。王子様のキスを待つ眠り姫みたい。最高にきれいじゃん。名前が可愛いからラプンツェルでもいいけどぉ」
「こいつはアコがあんまり美しいから、内臓ずるずる啜って、お尻の肉を持ち帰ってホルマリン漬けにして、毎日眺めながらオナニーしちゃうんだから」
「うひひ。何それ。あたしサイコホラー映画のヒロインになれるの? うれしー。ね、こいつのあだ名エド・ゲインにしようよ。3Pしながら羊たちの沈黙見よう?」
アコが背広に皺が寄るほど男の腕を抱きしめるから、サラリーマンはぎょっとして脂汗をかく。あたしはごめん、のポーズをする。
「遠慮しとく。想像したらお腹がもたれてきた」
「あそ。じゃね、ミイ。今日も黙って死ねよ」
「うん、アコも耳噛まれて死ねよ」
眠りって死と似てない? つまり、死ねはおやすみの挨拶。あたし達は毎日こうしてさよならするんだよ。年に何度も生命の終わりがくるのって、いいじゃん。
あたし達は壊れた人形みたいにぶらぶらと手を振りあった。男のよれよれした革靴と、アコの見せかけの純潔じみたピカピカのローファーが立ち去るのを見送りながら、あたしはコインパーキングにだらしなく生えてる雑草になりたいと思った。あーあ、めんどくさ。
兄ちゃんの部屋は男臭い。机にもベッドにも、わけ分からんものが山積み。兄ちゃん、教科書はどこにあんの? 辞書は? 鉛筆は? この人ちゃんと勉強してんのかなあ。山の中から煙草をパクってふかしていたら、兄ちゃんに後ろから蹴り飛ばされた。あたしは盛大にテーブルの角に頭をぶつける。
「いてーっ。死ねっ」
「オマエは二の句に死ね、だ。芸なし。つまんねー女」
「そりゃあんたの前ではつまんねー女だよ。面白さはとっておくんだ」
「知らん男のために? オマエの面白さって使い捨てなんだな」
「そりゃそうよ。言葉や価値観なんてツギハギで使い捨てなのよ。哲学者も心理学者もいっぱいいるんだから、どんな精神論だって替えがきくわよ。少し本読みゃね」
「まー確かに」
兄ちゃん拳骨であたしの後頭部を叩く。あたしはいてっと叫びながら、もっとしてと思う。あたしってヘンタイだ。
あたしってヘンタイだ。兄ちゃんに服を脱がされている。これからセックスするんだ。こういうのって気持ちいいんだよなあ。背徳的ってやつ? 法律なんてどうでもいい。こんなの当たり前だから。近親相姦なんて虐待や売春と同じで、常識という絨毯をめくれば白アリみたいにありふれてんだ。
「ねえ兄ちゃん」
「うるせー集中できないだろ」
頬を叩かれる。わーい、もっとして。
あたしの脱ぎ散らかしたスカートと兄ちゃんの学ランが、床の上で絡まりあっている。靴下の跡がかゆい。兄ちゃんの背中に腕を回す。熱くて湿ってる。何で兄ちゃんの背中はいつも湿っているんだろう? 一つ屋根の下に住んでいるのに、兄ちゃんって分かんないんだ。
兄ちゃんは眉間に皺を寄せてあたしを睨みながら交わる。だからあたしはいつも、兄ちゃんが気持ちいいのかそうでないのか分からなくなる。それでなくてもあたしは時々、観察されている気分になるんだよ。色んな人から標本みたいにね。
あたしは揺すぶられながら兄ちゃんを罵る。
「くず。くず。ばかばかばか。何十人もの彼女がいるのに妹と浮気する男のくず! バカ野郎、嬉しそうに腰ふってんじゃねーよ」
「そういうバカに抱かれて嬉しそうにしてるオマエは何なんだよ。ハツカネズミか。年中発情期か」
まあ性欲強いのは確かなことよ。真昼間の光の中で、あたしの体はよく見えているだろうか。あたしの肋や乳首やお尻のラインが、兄ちゃんの網膜に突き刺さって一生消えなくなればいい。兄ちゃんは制服のネクタイをあたしの首に巻きつけて、顔が鬱血するまでぎりぎり絞めあげる。
「兄ちゃん、こんなので興奮すんの? ヘンタイだね」
「悦んでるのはオマエじゃん」
「分かってらっしゃる」
「死ね、死ね、死ね。黙って死ね、このバカ女」
思いっきり絞め上げるから、あたしはげえげえ喘ぐ。色気も何もあったもんじゃない。けれども兄ちゃんだらだら汗かいてるし、まあいいか。
兄ちゃん、このまま殺してよ。あたしは誰からでもいい、愛されたまま死にたいんだ。目を瞑ってるうちにさ。抱きしめてもらってるうちにさ。あたしは人込みにいても、ぎゅうぎゅうの満員電車に乗っていても、体を冷たい風がひゅうひゅう通り抜けていくみたいなんだ。あたしの周りには常に小さな隙き間があって、それが疾風を呼び寄せる。
あたしは兄ちゃんの耳に頬を寄せて呟く。
「兄ちゃんも寂しい?」
「だからしたくねえやつとセックスしてんだよ」
ああ、兄ちゃん大好き。兄ちゃんの寂しさに包丁を突き立てて抉ってあげたい。兄ちゃんとあたしはキスして殴り合ってぶつかり合って静かにイきました。笑えます。
した後の朝日はだるい、ってどっかの歌人が詠んでたよ。あたしはセックスした後に朝日なんて見たことないな。だってするのってだいたい誰かのアパートかラブホテルか兄ちゃんの部屋だからさあ。アパートかホテルだったとしたら、さっさと家に帰ってだらだらして寝ちゃうからさあ。兄ちゃんと致す時は大抵お昼だしね。した後にピロートーク、そんな愛が詰まったお泊まりはしたことないんだ。
「愛なんていらねーよ」
ガン、また兄ちゃんからぶたれる。あたしは悦んでにこにこ笑いながら、心底、
「いらねーね」
と言う。あたしと兄ちゃんはこういうところで血が繋がっているんだなあ。神様いらんことしい。
兄ちゃんは毛布に包まって、まるで芋虫みたい。あたしはぐったりソファーに落ち着いている。お昼からどろどろに絡まり合うのって、気持ちのいいものなのよ。
明るい光に照らされて、身体中顕になるとあたしは、もう誤魔化しがきかないと思っちゃうんだ。あたしは紙の上のテリヤキバーガーで、色んなところから汁垂れ流しながら誰かに食べられる。兄ちゃんはあたしの肩を齧って歯型をつけるけれど��あたしは、そうされていると訳が分からなくなるんだ。あたしの腹に収納された小腸がもぞもぞもぞもぞ蠢き出すからさあ。
あたしは己の心の構造を突っつき回す度、いても立ってもいられなくなるんだ。あたしの心臓には歯がついていて、触れる人あらば噛みつこうとする。いつだってかっちかっちと牙が鳴る音が、胸のあたりから聞こえてくる。兄ちゃんもあたしの胸に頭を乗せて聞いてみてよ。
兄ちゃんはあたしが腕を突っついても振り向いてくれない。分かっている。つれない男だ。あたしはセックスした相手が思い通りにならないことにイライラして、こいつの気を引くのを諦める。
そうこうしてるうちに凶暴な心臓はどんどん歯を鳴らし始め、犬歯が刃になって、舌が三十センチも伸びた。あたしの心臓は下品な獣のように、舌をべろべろ出しながら涎を垂れ流している。全身がわなわな震えだす。あたしはたまらず兄ちゃんの腕にしがみつく。
寂しい。寂しい。兄ちゃん。寂しいよ。
こういう時だけ兄ちゃんは優しくて頭を撫でてくれるけれど、しばらくすると煙草吸いにどっか行く。突然放り出されたあたしの両腕、ドチンと地面に落ちる。
あたしは汗も流さずに外に出た。セックスしてる間にアコから連絡が来てた。やり終わったから踊ろうって。アマチュアかプロか分からない人がイキってる、クラブという煙たい場所で。あたし達は繁華街で合流する。アコがつまらなそうに言う。
「なーんだ。まだ生きてたの?」
あたしもやり返す。
「あんたこそ。この死に損ないっ」
虫食いだらけの街路樹が、あたしの肩に葉を落とす。やだ、全然しゃれてないんだな。そもそもこいつら、兵士みたいでいけすかないんだ。どこぞのエラい建築家が、景観がどうのとうそぶいて植えたけれど、夏になれば虫食いで茶色くなるし、秋になれば銀杏が臭う。冬は落ち葉の大洪水だ。だからおせっかいな市の職員が、定期的に丸ハゲにしちゃう。その結果みっともなくぽちょぽちょと葉がついているだけなので、景観を整えるという前提そのものがどこかにいっちまってる。この辺に巣食う太った芋虫、見捨てられた街路樹を食いつくしてよ。食いつくしたらパワーアップして、ビルの鉄骨も食べつくして、モスラになって飛んでってしまえ。
あたしの思考の如くもつれた電線を見上げながら歩いてたら、アコがぺちゃくちゃ喋りだした。
「またミイ、兄ちゃんとセックスしたんだね。残り香で分かるよ」
「んー」
あの電線が切れたらいいのに。あたし、それを噛んで感電死したい。山田かまちみたいにかっこよく死にたい。アーティスティックに死ねる人こそ、真の芸術家。
「ね、ミイ。さっきのサラリーマンとのセックスだけどね。気持ちよかったけど気持ちよくなかった」
「どゆこと?」
「分かんない。あのさあセックスって、してる間は相手のこと凄く好きだって思うけど、終わるとサーッと冷めるよね」
「あんたは男か」
「そうだったらよかったなあ。だって簡単じゃん。終わったら何もかもスカッと忘れてさ、どこへだって行けちゃうんだよ。あたしたちって穴ポコだから、洞窟に潜むナメクジみたいにうじうじするしかないじゃん。それに愛液とひだの形がそこはかとなくあの虫と似てるし」
「ははは。ばーか」
信号が凶暴な赤を点滅させ始めたので、あたし達は青を待つ。あたしは横断歩道のサイケな白黒が、シマウマを連想させるから好きなんだ。あたし達もシマウマと同じだから。孤独という猛獣から逃れるために、制服を着て普通の女の子のふりをして、コンクリートジャングルに溶け込もうとしている。保護色を必要としているから、同じ。
信号待ちの間、あたしもアコも横目で男を品定めしていた。そいつらの顔見るだけであたし、セックスしてるところを想像しちゃうんだ。どういう強さであたしのこと押さえつけるのかな、とか。アコも絶対そうだよ。
「あたし生まれ変わったらかっこいい男になる。地上にいる全ての女の子とやりまくって、無様に捨ててやるんだ」
お、それいいね、と振り向く。アコは魔法みたいにどこからか取り出したリップを唇に塗りたくっていた。その赤いいな。思いっきり下品で。
どうしてクラブの壁ってどこもマットな黒なんだろう。病院みたいな白でもいいじゃんかねえ。ま、見た目がどうであろうが、豚骨ラーメン屋に似た油の臭いがしてようが、何もかもふっとばしてくれる爆音が鳴ってればそれでいいよ。そうでしょ?
パッと見何人か分からないオーナーは、いつもあたし達に酒を奢ってくれる。この人絶対あたし達が高校生だと知ってるよな。いいんだけどね。あたし達はこっそり二人でトイレに篭って、コップの中身を便器にぶちまける。おしっこみたいに流されてゆくビールを見ながら、ざまあみろってケタケタ笑う。余計な優しさなんてクソったれだ。壊すのって面白い。それが大事なものほどね。
あたし達は踊り狂う。踊り狂う。発情モードに入った男がグラマーな女の尻を眺め回している。ああいいな。あたしもあの男に見つめられたいな。あたしは常に誰かに恋される人間になりたくなっちゃうんだ。誰もが愛する理想の女になりたい。セックスの相手が変わる度、あたしの体も変形するのならよかったのにな。あたし、そういうラブドールならよかった。
スピーカーから音の水を浴びながら、あたし達は狂ったように笑う。何もかもどーってことないみたいに。どーってことないんだけどさ。深刻な悩みがあるわけじゃないし。ミラーボール以外は床も壁も黒だ。黒、黒、黒。あたし達の制服がくっきりと浮かびあがる。あたしこのまま、光になって消えちゃいたい。
あたしが寂しがる、消えたがる、殺されたがる理由なら、シンリガクの本読みゃ理解できるんじゃないかな。だいたいの本には親が原因って書いてるよ。そうでなけりゃ肛門がどうとか。昔の人もたいがいスケベだよねえ。髭生やした爺ちゃんが赤ちゃんの下半身にばっかり注目して。そんなのってどうでもいい。いっそあたし達、下半身だけの化け物になっちゃえばいいんじゃない?
アコがふざけてあたしの腹をぶった。あたしもぶちかえす。アコは言う。
「ねえ、こないだあたしの彼氏貸したじゃん。どうだった?気持ちよかった?」
「それって今の彼氏? それとも前の? それとも前の前の……」
「えーと、分かんなくなっちゃった。いっか。誰だって同じだし」
「やっぱあたしら気が合うな」
ヘドバンしてると頭に脳内物質が溢れて、ボルチオ突かれるより気持ちよくなれるんだ。クソみたいな曲でも、そうしちゃえばどれも同じだよ。あたしもあなたも恋も愛も、爆弾で吹っ飛ばして塵にしてやる。
「アコ、あたしの彼氏はどうだった?」
「どうだったろ。ていうかどれだっけ」
「どれ」だって。笑える。
「ミイ。あたし達も数々の男に『どれ』って呼ばれてるのかな?」
「女子高生A、Bみたいに?」
「そうそう」
「そうだったらいいね。あたし、そうなりたいなあ」
「あたしも。あたし達、消えちゃいたいね」
「うん。消えて、きれいな思い出になりたい」
「天気のいい日だけきらきらして見えるハウスダストみたいにね」
「普段は濁っているのに、台風の後だけ半透明になる川の水みたいに」
「あたし、雫くんになりたい。知ってる? 絵本だよ。雫くんがさ、川に流されて海に到着して蒸発して、また雨になるの」
「それって話が違くなってない?」
「あ、そう?」
あたし達は全然センチメンタルじゃないダブステに貫かれながら手を繫いだ。アコの手のひらだけがあったかい。
あたし達はフライヤーをハリセンのように折り曲げ、互いの頭をはたきながら帰った。夜のネオンっていいよね。泣いてる時に見える風景みたいに潤んでてさ。ネオンを見ながらしみじみしてると、ひょっとしたらあたしも純情な女子高生なんじゃって思えてくるんだ。肩書き的には正真正銘の女子高生なんだけど、すれっからしだから、あたし達は。アコはにかっと笑い、尖った八重歯を両手の親指で押した。
「あたし、死んでもいいくらい好きな人ができたら、八重歯をペンチで引っこ抜いてプレゼントしたいな。世界一大好きな人に抜歯した箇所の神経ぺろぺろ舐めてほしい」
システマチックな街灯の光が、アコの横顔を照らしている。彼女はぼやっと言った。
「あたし愛されたいんだ。本当はね。それなのになぜか行きずりの人と寝ちゃうんだよねえ。あたし好きな人ができても、隣に男の人いたらエッチしちゃうんだろうなあ」
「別にそんなこと考えなくてもよくない? 無意味だよ。してる間、気持ちよければいいじゃん。黙ってりゃ誰も傷つかないし」
「んーまあそうなんだけど。あたし時々ね、どっちなのか分かんなくなるんだ。エッチして自分を悦ばせているのか、傷つけているのかがさ」
「大丈夫だよ。誰もアコのことなんかそこまで気にしてないから」
アコは子犬みたいな目であたしを見た。あ、地雷踏んだかも。アコがチワワのようにぷるぷる震えだしたので、あたしは彼女をそっと抱き寄せ、おでこを優しく撫でてあげた。
「ごめんね。あたしだけだよ。アコの気持ちを知ってるの。あたしだけがアコを見守ってあげるね。きれいだって思ってあげるね。アコが何人もの男から忘れられようとも、あたしは覚えててあげる。あたしに八重歯くれたら、あんたの望み通り神経舐めつくしてあげるよ」
「ほんと?」
アコはあたしの胸に頭をすり寄せてくる。この子を絶対に不感症のロボットなんかにさせないんだから。あたしはありったけの体温でアコを包み込む。この子が気持ち良さそうに目を細めてくれたらいい。そしたらあたし久々に、幸せってやつを味わうことができるから。
「あたしねえ、アコとセックスしたいな」
「あたしもミイとセックスしたい」
「しよっか」
「いえーい」
わはは、なんて簡単なんだろう。
「あたし、ミイを愛してる」
あたしはうんと返事をしようとして、黙った。愛がどういうものなのか分からなかったから。
ラブホテルのベッドでアコの体を舐めながら、色白いなあ、と思う。
「ミイ女の子とするの初めて? あたしは初めて」
「ふーん」
いつもスマホに貼り付いてる親指をがじがじ齧る。あ、ここだけ爪のびてる。
「ミイはどういうの好みなの?」
「どういうのって?」
「体位とか」
「うーん、何だろ、分かんない」
「兄ちゃんとしてる時ってどんな感じ?」
「あたしが上に乗るの」
「へえー、意外」
「意外もクソもある?」
「分かんないけどさ」
アコの耳を齧る。皮膚が歯茎に気持ちいい。アコは、あんた歯が痒い犬みたいだねえ、なんて言ってる。あんたも一度人を噛んでみろ。あたしがアコの胸をむにむにしていると、彼女はまた喋りだす。あたしの涎が潤滑油になってんのか、この子の口はさあ。
「兄ちゃん、あんたにどんなことするの?」
「スリッパでぶつよ」
「えっ」
「枕で窒息死させようとしてくる」
「それって気持ちいいの?」
「どうでもいいの。されてる間はさ。どうでもいい方が気持ちいいんだ」
「ミイが自分を粗末にするのって、近親相姦してることに罪悪感があるから?」
「何フロイトみたいなこと言ってんの。あたし、そういうのって嫌いなんだ。中学生の頃に腐るほど心理学の本読んだけど、読めば読むほどあたしを狂わせた原因が憎らしくなってくるからさ」
「えっ、憎らしくなるように書かれてんじゃないの、ああいう本って」
「マジ?」
「マジマジ。きっと昔の人はあたし達に親殺しさせようと思ってあの本書いてんだよ」
「それマジかもねえ、だったら面白いし」
「きゃはきゃは」
あー、くだらねえ。
「ねえねえ、じゃあやってみてよ。あたしの首、絞めてみて」
あたしは自分がアコの言葉にぎょっとしたことに気がついて、奇妙な気持ちになった。ああ、あたしってまだぎょっとするんだなあ。色んなセックスしててもさ。あたしは目をきらきらさせてるアコが無償に「愛おしく」なっちゃったりして、彼女の胸に顔を押し付けた。
「アコにはできないよ」
彼女はあたしの珍しく真面目で優しい声に目を丸くした。
「どおして?」
「うーん」
「あんた誰にでも残酷なことしそうなのにね」
「そうなんだけどねえ」
「どうしてあたしにはしてくれないの? あたしとするのが気持ちよくないとか? それともあたしが嫌いなの?」
アコは、嫌いにならないで、と泣きそうになる。ああ、そうじゃない。今この瞬間、彼女と一つになれたらいい。物理的に一つになって、ぐちゃぐちゃになって、疲れ果てるまで喚きあいたい。ああ、あたし男だったらよかったのに。そしたらアコのこと、一時しのぎでも悦ばせてあげられたのに。今ほどこう思うことってないよ。あたしはとりあえずデタラメな文句パテにして、二人の隙き間���埋める。
「だってアコの肌ってふわふわしててきれいだからさ。傷つけたくないんだもん」
「それを言ったらミイだって、殴られたりしてるわりに肌きれいじゃん。だからあたしの首を絞めても大丈夫だよ」
「嫌」
「どうして?」
あたしはアコをぎゅっと抱きしめた。そうすることしかできなかった。
「ミイがあたしの超絶技巧スーパーマンになってよ」きゃはきゃは。
まだ言ってるこいつ。バカだなあ。
これを愛と呼ぶのかどうなのか。あたし、世に蔓延るほとんどの概念が嫌いだけど、「愛」は殊更に嫌いなんだ。だって得体が知れないんだもの。
あたしは感情ってやつが嫌い。思考ってやつも嫌い。人間が地球にのさばる繁殖菌であるのなら、知能なんかなければよかったんだ。子供を作る行為をするために些細なことに頭を悩ませるなんて、全く時間の無駄すぎるよ。それが人間のいいところなんてセリフ、よく言えたもんだ。人間は動物達を見下す限り、地球に優しくなんてなれない。本来の優しさは無駄がなく、システマチックなものなんだ。
そうでしょ? 兄ちゃん。
「うわ、指先紫になってる。いい感じに動脈つかまえたかも」
手首に巻かれた紙紐が食い込んで痛いけど、それがまた興奮するんだなあ。兄ちゃんガンガン口の中で動かすから、思わずえずきそうになる。ここでゲロ吐いたらどんなに気持ちいいかしら。兄ちゃんは咳き込むあたしを足で踏み付けて、死ね、死ね、シネって怒鳴る。あたしは毛だらけの兄ちゃんの足首に縋り付く。
「兄ちゃん。殺して。今すぐ包丁持ってきてあたしを殺して」
「はいはい」
兄ちゃんは白けた目であたしをいなす。彼の瞳から放たれるレーザービームで粉々になりたいわ、あたし。
「兄ちゃん。あたしの心臓どうにかして。兄ちゃんがこいつを握り潰してくれたら、あたし、あたし」
あたしの喉がひいっと鳴いた。あたしはバーガーソースみたいな涙を滴らせながらズルズル泣いた。兄ちゃんが濡れた頬をぺろぺろ舐めてくれたので、あたしは少し嬉しくなった。
兄ちゃんは今に包丁を持ってくる。兄ちゃんも本心では死にたいんでしょ? 知ってるんだから。二人で汗だくになって死のうよ。それであたしを、あたしだけのものにして。
あたしは愛という建前に摩耗しないため、行きずりの男に抱かれる自分が嫌いなんだ。あたしは愛を忘れたいんだ。忘れたらもう苦しまなくてすむもん。兄ちゃん、アコ、あたしは、あたしのこの心臓は、いつか満たされる日がくるのかなあ。たくさんの人とセックスしたら、寂しくなくなる日がくるのかなあ。誰かを愛しいと思える日がくるのかなあ。キスをしたら少し楽になれるから、誰彼構わずキスをねだることも、それで長く続いた友情をぶち壊すことも、先生から不倫を強要されることもなくなるのかなあ。
あたしの皮膚は涙と一緒にズルズル溶け落ちてゆく。兄ちゃんが思いも寄らぬ優しさであたしを抱きしめて「泣くな」なんて言うから、あたしはますます感動してしまう。けれどその昂りもすぐ「ばからしー」に冷まされる。お願い兄ちゃん、早く包丁、としゃくりあげながら、あたしはこのまま永遠に彼に頭を撫でられていたいと思った。
兄ちゃん、煙草吸いに行かないで。ずっとあたしの傍にいて。
けれど兄ちゃん煙草吸いにきっとどっか行く。
0 notes
Text
父は脳腫瘍という病気を患い、手術を終えたあと50代にして視覚障がい者になった。
今は障がい者一級の認定を受け、基本的には何も見えない生活をしている。
最初は家族も私も戸惑ったし、ショックだったけど離れて住んでいたので病院にもいられなかったし、実感もわかず涙も出なかった。そうなんだ、これから大変になるね、とくらいしか言わなかったと思う。
そして、この件についてあまり人に積極的に話してこなかった。本当に気持ち的に距離の近い親友や、文脈として話さないと意味が通らない時しか発信しなかった情報である。※この件について知らなかった友人や近しい皆さん、デリケートな話題で話すにも気力が必要なので、話すかどうかはその時々の気分で決めていることがほとんどです。知らなかった=私があなたのことを大事と思っていないとは思わないでください。
父が手術を受ける直前に一度、出張ついでに私の住む横浜に遊びに来てくれたことがある。予約していた駅近の居酒屋に現地集合でいいだろうと思い、ラインでその連絡だけ入れてお店で待っていたが一向に現れない。
心配になり電話すると、「一人ではお店に行けない。横浜駅まで来てほしい」と言われて急いで駅まで戻った。
そこで再度電話をかけると、「改札口がわからない」と言っている。JRなのか京急なのか、どこにいるのか聞いても全然わからない様子だった。
短気な私は事態が飲み込めなさすぎて少しイラつき、「え?なにか上の看板に書いてない?」と聞いても上の看板って何?わからない。。というような返答でいやいやまいったなと思った。
とりあえずJRの改札にいるから駅員さんに聞いてそこまで来てほしいと伝えた。電話は切らずにつないでいると、改札のすぐ向こう側に父の姿が見えた。
電話越しに「パパいるの見えるよ、パパが今立ってるところからまっすぐのところにいるよ」と言い、普通ならすぐに気づくような距離だったが、全く気づかないでボーっとしている。
この時点で、なんかおかしいなと思った。注意力があまりにもないというか、視野がものすごく狭い。
周りの目は気になったが仕方ないので改札のそばにあった鉄の仕切りのようなものを拳で叩いて音を立て、「パパ!」と大きな声で呼んだ。
すると「おお、エミ」とか言ってた。すぐそばの改札を通ろうとすると、引っかかっている。マジかーと思いつつ、まずみどりの窓口で駅員に通れないって話してみて、と言ったがすぐそこに見えるみどりの窓口が、どこにあるのかわからないと言う。このエスカレーター超えたところにあるよと伝えて、すぐ出てくるだろうと思い電話を切って窓口の出口で父が出てくるのを待っていたら、またまた全然出てこない。というか姿が消えている。
焦った私は窓口にいる駅員さんに、たった今スーツケース引いてメガネをかけてる男性が改札通れないって聞いたと思うんですけど、どっちに出ましたか?と聞いた。すると「え、さすがにわかんないです」と言われ、正直「は?たった今のことも覚えてねーのかよ!」とキレそうになったがぐっと堪えてわかりました、いきなりすみませんと言って窓口を出た。
電話をかけても全然出ないので焦ったが、とりあえず私はあまり動かない方がいいかなと思いその場に留まることにした。
すると父が突然現れたので、目の前まで駆け寄って「パパどこにいたの?心配したんだよ」と言うとまだ遠くの方をキョロキョロ見渡している。目の前の私に気付いていないのだ。驚きながらも肩をトントンしてもう一度声をかけると、「ごめんごめん、京急に乗ってきたのにJRの改札から出ようとしちゃったのさ」と言っていた。
そういや羽田からはそりゃ京急だよな。。と自分がめちゃくちゃ焦っていたことにもここで気づいた。そして、父が前と同じようには行動できなくなっていることを確信した。
予約時間をかなり過ぎてから、ゆっくりゆっくり歩いてお店まで向かった。その途中、何度も電柱にぶつかりそうになっている。また、後ろから追い抜かしてくる人にも気付けず、さっと避けることもできないのでぶつかってしまっている(いや、ぶつかられている?)。
スーツケースは私が引いた。話を聞くと、空港の切符売り場でスーツケースを忘れて置いてきてしまうところだったらしい。ここでさらに、やばい、これはただごとじゃないと気づかされる。居酒屋で美味しい料理を食べながら2人で話していると、いつものパパだと思った。なんでも好きなもの頼みなさい、横浜でちゃんと頑張ってるんだねえ安心したよ、はなはボールを空中キャッチするようになったんだよ、と前と同じように話している。混乱したし、戸惑った。そしてまたゆっくりゆっくり歩いて電車に乗って、やっと家に着いた時には正直クタクタだった。脳腫瘍ってやばい病気だな、と実感した。
父は昔から仕事人間で、子どもの私たちと話す時もロジカルで、ただ「あれやりたい」「もうやめたい」だけじゃ通じない人だった。なんでそれをしたいのか、それをして何になるのか、今やめることがほんとに自分のためなのか?色々深く問いただされる。そして大体の場合、途中でこちらが折れることになるのだ。その結果犬や携帯電話、めちゃくちゃ厳しい部活をやめることなど、色んな物事を諦めた。
そんな中、私がどうしても諦めなかったのが海外留学だ。父は基本的に、私を自分の手元に置いておきたがった。高校生の間はずっと、「お前には弟と妹がいて、2人にもお金がかかるから大学は道内の国公立しか行かせない」と言われていた。私は生徒全員が必ず海外留学をする必要があるという秋田国際教養大に興味があったが、先述した内容や「そんな田舎に耐えられるのか」など色々言われ、確かにそもそも結構難しい大学だし、私田舎とか自然興味ないしなあと思い諦めた。
でも、国際教養大に行くつもりで数学Bの授業ではなく英語の授業を選択していた私は、進路の選択肢のほとんどが私大という状況だった。唯一の国立大の選択肢は数学2までとっていれば受験できる小樽商科大学、父の母校だ。父は浪人して入学した、当時、英語以外の教科は先生への愛想やキャラクターで成績をよくしていたと言っても過言ではない私にとってはそこそこチャレンジングな大学(国際教養大より下なんじゃ?と思うけど)。
そして私はセンター1ヶ月前というギリギリになってやっと1日12時間の猛勉強に取り組み、なんとか推薦で同大学に合格する。それを誰よりも喜んだのも父だった。「エミが俺の母校に入るのか〜」とよく言っていた。こっそり母から「自分の母校に入るのも嬉しいんだろうけど、札幌を離れず実家から大学に通ってくれることを一番喜んでるのさ」と聞かされる。そういうことかよとやっと気づく。私はいつも気づくのが遅い。
大学に入り、往復5時間かけて通学する日々が始まった。めちゃくちゃ遠い。朝めちゃくちゃ早い。めちゃくちゃ眠い。行き帰りだけで本当にクタクタで、なんでこんな大学に入ったんだろうと、通学中に関しては4年間ずっと思っていた。
ただ、それでも私は在学中勉学についてはそこそこ頑張った。英語のクラスを担当する教授に色々と機会をいただき、在札幌米国領事館が主催する英語のエッセイコンテストでジェンダーについて書き、特別賞でiPodと日本女性会議に出席(という名目の見学)する権利をもらった。
日本女性会議ではニューヨークの裁判官の女性と話し、女性から男性に対してのDVについてはどう対策すればよいと思うかを質問した。ただ、当時の私の英語力ではせっかくもらった回答の内容を理解できなかった。いい質問だと言われたことしか覚えていない。これは私の人生の中の最大の後悔の一つだ。
他にもオーストラリアの元衆議院議員の方との会食に同行させてもらったり、米国領事館のパーティーに参加したり、なんか色々やってた。単位は落とさずにいられた。サークルにも入らず固定のグループにも属さず、なんかよくわかんない子だったと思うが、友達にかなり恵まれ、みんなのおかげですごく楽しい大学生活を過ごせた。
大学2年の前期、私は最初の留学のチャンスを見送った。理由は元々父に言われたとおり、弟と妹にもお金がかかると思ったからだった。当時弟は受験生になっていた。それでなおさら、自分にだけお金をかけさせるわけにはいかないと思ったのだ。ただ両親は弟には道内国公立という条件を出さなかった。理由は弟が男だからだ。私はこれにマジギレした。多分人生で一番親にムカついたのはあの時だった。私の方が高校時代の成績も良かったのだ。私は絵に描いたような男尊女卑だと、親にめちゃくちゃキレた。
それで、私も留学する!!と勝手に決めたのだ。実は私は自分が見送ったtermで留学した他の子たちをめちゃくちゃうらやましく思っていたのだ。私の方が英語できる気がする、私の方が海外生活への挑戦意欲は絶対強いと思う、これまで頑張ってきた自分の力を試したい、と毎日毎日思っていた。そして親に留学を反対・阻止されないよう、TOEICやTOEFLの勉強をめちゃくちゃして、どちらも本番で過去最高得点を取った。そしてほとんど誰にも言わずに留学の学内選考に申し込み、勝手に合格してしまった。当時私にものすごく期待してくれていたアメリカ人の教授が親身に相談に乗ってくれて、志望理由の添削なども快く引き受けてくれた。そのおかげもあり、学内推薦の枠をとれた。
母には選考が始まった時点で留学のことも話しており、「そんなにやりたいならお金はなんとかするからやりなさい。きちんと努力する子には私は投資するよ」と言ってくれた。母は、いつも私の英語の勉強意欲や海外への憧れを認め、後押ししてくれた。そして、この言葉は今でも励みになっている。
問題は父である。昔から日本のものより海外のものに惹かれていた私を海外かぶれと呼び、アメリカをホワイトアングロサクソンが牛耳る国と表現し、なぜそんなところに憧れる!?と言われて育った。今思えば結構なレイシストだった。
絶対嫌がるだろうな、と思ったが、私にはあまり反対意見を言ってこず、受かってしまったものは仕方ないという感じで、銀行に通い教育ローンを組んで私をニュージーランドに送り出してくれた。アメリカは私の申し込んだtermの選択肢にはなかったので、消去法で唯一の英語圏だったニュージーランドを選んだのだ。
ニュージーランドでの2学期が私にとってどれほど楽しかったかは私を知る人はもう知っているだろうから話さない。とにかく人生最高の時間だった。初めて親元を離れたが、シェアハウスに住んでいたからかあんまり寂しくなかったし、親の目につかないところでちょっと悪いことをするのは最高に楽しかった。ただ、とにかく高い生活費や家賃を嫌な顔一つせず振り込んでくれる親への感謝は絶対忘れないよう決めていた。
後になって知ったことだが、父がすんなり承諾してくれたのは母の説得のおかげだった。父が「エミがボブサップみたいな黒人でも連れて帰ってきたらどうすんのよ!」と母に怒ると、母は「え〜。。ハーワーユーって言う。」と答え、さらに怒らせていたらしい。めちゃくちゃうちの母らしい。でも、やりたいことはやらせようよと頑張って説得してくれたんだと思う。そのおかげで、私はとにかく充実した時間を過ごして、自信をつけて家に帰ってこられた。ちなみに行きも帰りも母は空港で普通に結構泣いていた。行きは当時の彼氏も涙を必死で堪えていた。私だけが全く泣なず、これから始まる新生活への覚悟と期待ばかりが頭にあった。帰りの空港に彼は来なかった。当時は色々思ったが今思えば当たり前である。
帰国後足りない分の単位をとりながらバイトも再開して忙しくしていると、さらに就活も始まった。今思うと、新卒の就活はマジでクソみたいな行事だった。私は正直留学で燃え尽きていて、みんなと同じ格好をして綺麗事を並べる就活というものに疲れ切り、適当に受かった地元の会社に決めてしまった。
そこで働く間、両親は小学校高学年から英語の個人レッスンを受けさせてもらい、高校大学とずっと私の英語の勉強に投資し、応援してくれたのに、なんでそこで培ったスキルを活かす仕事につけるよう必死で頑張れなかったんだろうと、ずっとずっと後悔していた。あと当時の上司と先輩がめちゃくちゃ意地悪だったので、普通にやめたかった。
そして、父の病気はその会社に入って2年目の半ば頃に発覚した。当時福岡で単身赴任していた父は、なんとなく様子が変わっていた。まずあんなに大好きだった仕事が、全然楽しくなさそうだった。私は子供の頃から父から仕事の話を聞くのが好きで、よくわかんなくても色々聞いていた。福岡の前にいた島根では色々功績を残していたようで、その過程の話を聞くのはとてもワクワクしたし、娘として誇らしかった。でも福岡に行ってからは愚痴が増えた。というかあんまり楽しくない、としか言わない。それ以上は話したがらなかった。
また、なんか運転荒くなったな〜と思うようになった。いや元々荒い方なのだが、それにしても危なっかしい。注意散漫な感じだった。私は免許がないので運転のことがよくわからなかったが、毎日運転する母はめちゃくちゃびびっていて、危ない!と叫んだりするほどだった。あまりにも運転が荒すぎて、車酔いしやすい妹は父が運転するなら出かけないようにすらなった。
あんまり詳しく覚えてないけど、なんか他にも物忘れが激しくなったり、前は帰省の間毎日札幌ドームに野球観戦に行ってたのにぱたりと行かなくなったりと、色々おかしいなと思うことが増えていた。母がかなり心配するのを、私たち子供3人は元々危なっかしいところはあるよとか、天然だからねとか言って流していた。
しばらくしてから本人が病院に行くと言い出した。赤信号を無意識に無視しようとしてしまったらしい。病院で色々検査した結果、脳に拳大くらいのものすごく大きい腫瘍が見つかった。
それを最初聞いた時は、なんて思ったか正直覚えていない。多分ショックだったとは思うけど泣いた記憶はない。でも、何回目かの精密検査のあと、印刷された結果の紙に手術によって起こりうることみたいなのが一覧にして書いてあった。そこには脳梗塞とかなんか難しい漢字がたくさん並んでいて、失明というのもあった。それを見た瞬間、こんなにリスクがある病気なの?と母の前で泣いたのは覚えてる。それでも、父の病気のことであんまり泣いた記憶がない。私は普段かなり泣き虫なので、本当に泣けないほどショックだったのかもしれないな、と今となっては思う。
父の病気が発覚してから、色々考えることが増えた。父の病院の付き添いやお見舞いのため、会社を休むことも増えた。そのうち何回かは自分のためだった。色々気持ち的に疲れ、遊びに行くとかいう気持ちにもなれず、とりあえず犬と家にいたりした。でも会社や当時の上司はその辺はすごく理解してくれて、深く聞かずに協力してくださった。そこには本当に感謝している。
ちょいちょい会社も休みつつ、毎日色々ぐるぐる考えた結果、「私、結構親に恩返ししたいと思ってるんだな。その一番の方法って、ちゃんと英語のスキルを生かして楽しく働いて、親が私に投資した分を回収できるほど稼ぐことだ!」と気づいた(今思えばちょっと突っ込みどころもある)。
そして職場でも男尊女卑とか古い思考が蔓延しているのを感じ、基本不満しかないような状態になっていたので、本格的に転職活動を始めた。
転職活動は、新卒の就活よりチャンスは限られていた。有名な企業の求人にもとりあえず色々申し込んだが、新卒の時は当たり前のように通った書類審査でほとんど落ちた。でも、2年の経験で多少のスキルやマナーも身についていたおかげか、はたまたこの場から抜け出せれば人生やり直せるぞという強い希望からか、かなり高いモチベーションを保って行動できていた。平日の夜と土日はTOEICの勉強や企業研究、面接準備をしていて遊ぶ暇はなかった。けど、当時はそれを負担にすら感じないほどそれらに打ち込めていた。ある意味、こういう行動が辛い現実から目をそらす一つの方法だったのかもしれない。そんなときも自分の会社で面接官を担当したこともある父には、色々相談に乗ってもらった。
その結果、今働いている大きな会社から内定をもらえた。それまでわりと傍観していた、というかどの会社を受けているのかとかも多分よくわかっていなかった両親も、いざ転職が決定したとなると色々態度が変わった。当時私は色々あって両親(特に母)とあまり良好な関係を築けていなかったため、物件探しなどは全部一人で行った。というか23歳にもなり、これから一人暮らしするとなるとそれくらい一人でできないとダメだろうと思ってもいた。ただ、母は気まずそうに家具の買い出しや引っ越し手配などの手伝いを申し出てくれた。実際、そのおかげでかなり助かった。費用もかなり浮き、結局親の助けって大きいんだなと実感し始めた。父からはそういう類の協力は特になく、ただただ何回も「本当に横浜に行くの?」と聞いてきたり、「そうかあ、行っちゃうのかあ」とぼやいたりしていた。仕事中に「エミが横浜に行っちゃうのが寂しくて仕事にならない」とラインしてきたりもした。この人は本当に私のことを手放したくないんだなと思った。
子どものときから私はパパっ子だったし、父は実際私たち兄弟3人をめちゃくちゃ可愛がってくれたので、ここまで寂しがるのも仕方ないことなんだろうと思った。
それまでなんだこいつらと思っていた両親に対して、少しずつまた感謝の気持ちが湧くようになっていた。
そしてなんとか横浜や新しい会社での生活に少しずつ慣れてきた秋頃、ずっと保留にされていた父の手術が決行されることになった。いつ行われるのか、手術日直前までずっと計画が流動的だったので、飛行機を取るにも取れず、私は付き添うことはできずに当日も横浜で働いていた。まだ試用期間だったので本当はダメだったが、上司が在宅勤務にしてくれた。
手術は24時間以上かかり、母はずっと手術室の前で待っていた。普段父の愚痴ばかり言っていたのに、こういうことになると24時間とかでもあの固そうなベンチで待てるんだな、夫婦って謎だなと思った。
手術が終わった後、まだ腫瘍が残っているので来週また手術すると聞いた。どんだけ腫瘍あるんだよと思った。そりゃ運転なんかまともにできないよとか、その状態でずっと働いてくれてたんだなとか、色々思った。普段の私なら泣きそうな考え事だが、その時も泣けなかった。
そして2回目の手術も終わった後、母から顔がパンパンに腫れて管が繋がれた状態で、病院のベッドで寝ている父の写真が送られてきた。
正直、なんとも言えない気持ちだった。運動神経が悪く運動会を地獄と思っていた私だったが、運命走では父が毎年私を1位にしてくれた。仕事がめちゃくちゃ出来て、休日でも電話が鳴ると仕事モードになってテキパキ応答していた。友人関係で悩み学校にいけなくなった中学時代、忙しい中母と学校に出向いて先生に直接相談に行ってくれた。そんな父の姿が変わり果てた状態で札幌にある、とあんまり信じられなかった。
とりあえず親と妹に付き添いありがとうとだけは言ったと思うけど、なんか詳しいことはあんまり覚えてない。
その次の月に札幌に帰り、2週間ほど実家から在宅勤務させてもらうことにした。父が視覚障がい者になったことで、母の生活はとにかく大変になった。札幌を出るときにも感じたことだが、遠くから何もできない自分に対し自己嫌悪の気持ちを感じていた。一人だけ、大変な状況から逃げてきたような気持ちだった。それで今後後悔しないように上司やチームのメンバーに相談して快く受け入れてもらい、在宅勤務をさせてもらったのだ。
当時の父はほとんど何も自分ではできなかった。コップに水を入れることも、薬を包装のプラスチックから出すことも。何せ手術がおわり目を覚ましたら何も見えないのである。仕方ないと思い、みんな全部やってあげていた。
これがなかなか大変だった。普段通り続く仕事や父が障がい者になったことによる諸手続き、家事でも忙しいうえに、ずっと父のそばにいて余裕がなくなってきていた母と妹は、少しは自分で何かできるようにチャレンジだけでもしてほしいという気持ちでストレスを感じていた。また、それで父に優しくできない自分たちにも嫌悪感を感じてしまう。その時、本当にこのタイミングで札幌に帰ってきてよかったと思った。私はまだ気持ち的に余裕があったし、父のことをかわいそうに思う気持ちの方が強かったので、代わって父の相手や手伝いをしてあげられた。母が何度もお礼を言ってコーチのバッグとポーチまでプレゼントしてくれたが、私としては何もせずに傍観することで今後後悔したくないと思う、自分のための行動でもあったので、お礼を言われるようなことではないと思っていた。実際、終盤は私も疲れてきて、母と妹と3人でラーメン屋さんで父の横柄さや自己中さを愚痴りまくったりもしてしまったし。たしかにこれが日常なのはキツいと思った。
札幌から横浜に戻った後もしばらく、自分だけ逃げてきたような気持ちに苦しんでいた。特に、大好きでかわいい、しかも4つも年下の妹をあの大変な日常に置いてきてしまったことが辛かった。
それまで私は当時、彼氏にこの話をあんまりしたくなかった。しても楽しくないからだ。また、正直付き合って半年ほどの彼氏に話すには色々と重かった。だからずっと黙っていたが、なぜか横浜に帰ってきてから1ヶ月ほど経ったあとのクリスマスデートの準備中、とうとうこの罪悪感を打ち明けた(理由は、なんとなく今なら言えそうだなと思ったからである)。
すると「でも、エミちゃんは家族と離れているおかげで多少余裕を持って家族に接してあげられてると思うよ。全員が同じ場所にいたら、誰も家族の話を冷静に聞いてあげられる余裕がなかったと思うから、お母さんもみーちゃんも、エミちゃんに話聞いてもらってるだけで助かってると思うし、ここにいてよかったんだよ」と言ってくれた。正直、この時初めて結構泣きそうな気持ちになった。けどただでさえ変な空気にせざるを得ない話をし、その上泣いたらなんかマジで変な空気になるしなと思って、化粧をしながら平然を装ってありがとうと、今まで自分の殻に閉じこもってて本音を言わなくてごめん、と言った。一言だけ「俺はエミちゃんの話聞くくらいしかしてあげられへんから」と言ってくれたが、彼のいう通り、ただ話を聞いてくれるだけの人って、本当に助かるのだ。それを身をもって実感したことで、私も家族にとってのそういう存在になれてるのかもな、と思えた。それにより、やっと家族と離れていることへの罪悪感を消すことができた。慎重な私からすると、正直大丈夫なの!?と思うこともあるくらいいつも楽天的な彼だが、こういうことを偽りなくスラスラ言える優しさや前向きな気持ちを持つ人と一緒にいることが、私にとってどんなエリートや大富豪といるよりも最良の選択肢に感じた。そして今もそう思っている。
その間も、父の手助けをしたり一日中話し相手になる大変さを何度も二人からは聞いた。そう言われると辛いよね、ママやみー(妹)の立場だとそう思っちゃうよね、とか、なるべく相手の気持ちを汲んでいるような言葉遣いを意識した。前のわがまま女王の私には到底できなかったことである。
そして、父が函館の視覚障がい者向けの訓練センターに入ることになった。本当に少数の視覚障がい者と、色々と教えてくれるメンターの方しかいない施設だそうだ。
父は行きたがらなかった。施設どころか、自分の実家にも帰りたがらなかった。母が諸々の手続きを済ませるために家をあける間、また妹も仕事などでいない間、一人にしておけないので実家にいて、ついでに(少し休みたいのでとは言わないがそういう意味も込めて)今夜は泊まってきて、と頼んでも嫌がっていた。無理矢理行かせてもいつ迎えに来るんだと電話が来る始末だった。これはまじでキツいだろうなと思った。
父は仕事ももちろんまだ行けないので、一日中リビングの一人がけソファからトイレ以外は一歩も立たず、ずっとそこにいて話しかけてくるのだ。目が見えるとある程度読める空気も、読めないので仕方ない(元々かなりのkyおじさんなのもあるが)。本当に何もしようとしなかった。実際父も��トレスはかなりあっただろうから、無意識に嫌な言い方をされることも多く、色々書類を書いたり細かい手続きを済ませたりしないといけない母はクタクタだったし、妹も精神的にかなり疲れていた。父の無意識のきつい言葉に傷つき泣いたりもして、一緒にご飯食べたくないとも話していた。
そのため、母も妹も父の函館行きをある意味心待ちにしていた。ひどいように聞こえるかもしれないが、そうでもしないと二人とも身を入れて休めなかった。
父が函館に行ってから、母は生き生きしだした。自分の好きなことを好きなペースでできるようになったからだ。我が家の愛犬のはーちゃんも散歩嫌いを克服し、毎朝長い距離母を連れ回すようになった。それによって他の飼い主さんと仲良くなったり、友達とのランチやピラティスの時間もとれたり、母の生活が目に見えて充実し始めた。ずっと辛い話を聞いていた私はかなり安心できた。妹の電話口の声色もかなり明るくなり、みんな父のことが嫌いになったとかではなく、単にこれまでどうしても疲弊してしまう日々だったんだろうなと思った。
そんな中、突然父からラインが来た。え、ライン?と思った。なんせ前実家に手伝いに帰った時はiPhoneのロックを解除することもできなかったのだ。視覚障がい者用のモードに変更して、音声を頼りにパスコードを打つのがどうしてもうまくできず、イライラしてすぐ途中でやめていたし、基本的に携帯を触ろうともしなかった。そんな父から誤字脱字がほぼないラインを受け取り、本当に驚いた。と同時に訓練を一生懸命頑張ってることがわかり、とても嬉しかった。実は施設に入る直前に父と電話で大喧嘩したこともあったので、なんか色々安心した。
その頃、ニュージーランドでの1学期目の間、とても仲良くしてくれた香港人の友人と久々に連絡を取った。彼女は去年お父さまを突然亡くしたと話していた。とても賢く明るく、私と同じように男の子みたいにわんぱくな彼女だったが、ストレスで毎日浴びるようにお酒を飲み、円形脱毛症にもなったという。私も友人には積極的に話さなかった父の病気の経緯を初めてその子に打ち明けた。余談だが日本語だと言いにくいことも英語だと言いやすいことって結構ある。そして、「大変だったね。お父さんも家族もストレス溜まるよね。でも、エミがお父さんのことをちゃんと気にかけてあげていることは本人がわかるようにしてあげてね。じゃないと後悔するから」と言ってくれた。
それから私は毎週末、なるべく施設で訓練を受ける父にラインで連絡を入れるようになった。YouTubeの使い方を練習しているので、面白いラジオやいい音楽を教えてと頼まれて、私の大好きなオードリーのトークまとめと、父のために作ったプレイリストを送った。父もお気に入りの音楽を教えてくれたが、どれも命や周りの支えに感謝する歌だった。今の自分の気持ちにピッタリなんだと書いてあるのを見て、なんとなく父の内面的な変化も感じた。そして、やっぱり父は努力の人、やればなんでもできる人なんだと思い、誇らしかった。それは母も同じなようだった(ちなみに母にはラインに慣れてない頃、訳の分からない文章をたくさん送っていたらしい)。
しかしコロナウイルスの影響で父の訓練は中断され、一度札幌に帰ることになった。そしてこの後の訓練は札幌でやることになると言う。正直私たち3人はエッと思った。思っていたより二人が休める時間が縮むことを意味するからだ。ここからまた大変だな。。と思っていた。
それでもいざ訓練から戻ると、父はできることがだいぶ増えており、郵便屋さんからの荷物を自分で受け取り支払いも済ませたり、歩いて近所のスーパーに行ったりまでできるようになっていた。また、一人で部屋で過ごす時間も前より自然と取るようになり、妹は父のそういう進歩や変化について嬉しそうに話してくれた。
結局父はみずからやっぱり落ち着いたら函館にまた戻って訓練を受けると言い出した。実際、後続の訓練は札幌で、というのは父だけでなくセンターの方の意見でもあったので、なぜ函館に戻ると言い出したのかはわからない。でも、訓練を頑張りたいという意志は伝わってきて、手術後はあんなに色々と後ろ向きだった父が積極的に訓練に向き合ってくれたことがとても嬉しかった。
そして、函館での訓練を終えて帰ってきた父は、どうも色々性格的にも変化しているようである。元々理論派な仕事人間ながら天然でウケる部分もあった父だが、特に明るいタイプではなかった。失明してからは尚更で、無神経な物言いをしたりもしていたが、今はそういうことがかなり減ったらしい。なんとなく明るくなったと言う。この前は父から母に「今日は実家に泊まる。少し休めるしょ?」と言い出してくれたらしい。父も、自分の存在が負担ということではなく、単に母の疲れを感じ取って休みが必要だと配慮することができるようになったのだと思う。
夫婦生活を何十年としていると、最初にあった思いやりや配慮が薄れていくだけだと思っていたが、夫婦というものはいつになっても悪い方向だけでなく、いい方向に形を変えることも可能なのだと親を見ていて知ることができた。
はっきり言って、去年から今年にかけて私はかなり辛かった。涙こそ思っていたより出なかったけど、悲しみや精神的な疲れがいろんな形で出ていたと思う。それに、仕事の変化についていくのも大変だった。
そういう時、一緒にバカなことをして騒いだり、美味しいものを食べながら恋愛や仕事の話をしたりしてそういう悩みから気を逸らさせてくれた友達や、私の精神的疲労の弊害を受けながらも見捨てず、常に優しくそばにいてくれた彼氏にとても助けられた。
そして突然視覚障がい者になったことを、多少時間を要しても最終的に受け入れ、その生活に順応���る努力をする父、そしてそれを献身的にサポートする母や妹を心から尊敬する。あと、いつもみんなのストレスを無意識のうちに緩和し癒してくれる、犬のはなみちくんにもとっても感謝している。
こういう言い方をしてはなんだが、この事を通さないと分からなかった各人の良いところを知れた、いい機会でもあったとすら思えるようになってきた。
障がい者になること=マイナスではない。障がいを通じて、得られるプラスだってあるのだ。
せっかく色々書いたので、最後に一言。
話は少しずれるが、人種、セクシュアルオリエンテーション、宗教など、各分野でマジョリティ、マイノリティが存在し、その間での格差や差別、抗争が日々生まれている。こういった問題について、個人としてマジョリティ、マイノリティどちらも万人に受け入れられるべきであるとハッキリ言える人間になれたのは、ティーンの頃からこのような問題について国内外の同世代の友人とのディスカッションを通じて熟考したり、当事者とコミュニケーションを取ったりする機会の基盤にある、高度な教育を受けさせてくれた両親のおかげだと考え、心から感謝している。黒人、女性、同性愛者、トランスジェンダー、ムスリム、そして身体障がい者、またその他のすべてのマイノリティに属する人も、決して理不尽な迫害を受けるべきではない。すべての人間が人間として尊重されるべきである。この信念だけは決して曲げずに生きていく。
0 notes
Text
0:00
「あけましておめでとうございます。枢木さん」
ソファに横並びで『ゆく年来る年』を眺めていたルルーシュが、日付の切り替わりと同時にこちらへ向き直り、座面の上で正座になって三つ指を突いてくる。白無垢を纏った幻影が見えるほどの流麗なお辞儀に新年早々、文字通り本当に早々、心臓が鷲掴みにされる心地だ。
「あけましておめでとう、ルルーシュ。今年もよろしくね」
「はい、お願いします。……ふふ、平成三〇年の枢木スザクは男前ですねえ」
粛々とした顔つきを即座にふにゃりと緩ませ、胸の前で小さく拍手をするルルーシュの頬はほんのり、を通り越してなかなかに赤い。そこらの大学生よりも酒に弱い白人が存在するのだという事実を、スザクは目の前の可愛い同居人を通じて初めて知った。飲み慣れていないせいもあるのだろうか。なにせスザクが気合を入れたレストランで二十歳の誕生日を祝ったその席まで、ルルーシュがアルコールに口をつけたことは一度たりともなかったというのだから驚きだった。ルルーシュを見ていると事あるごとに、育ちが良いとはこういうことかとしみじみ思わされる。芸能界に足を踏み入れ立てでおまけに自分のファン、いかにもチョロそうだからさくっと抱いてモノにしてやろう、などと謀っていた三年前の自分を殴り倒しに行きたい。もっとも、ふわふわと心地良さそうにスザクの両手を取って無意味に振り、挙句ぽすんと胸元に倒れ込んでくるこの懐き具合に対して、これまでの戦績が口先だけのごく軽いキスひとつという今の体たらくの方が、過去の自分から張り倒されて然るべきといった話なのだが。
「眠いの? 寝るならちゃんとベッドに行かないと」
揃いのパジャマの胸元に顔を埋められ、こんなことでも童貞のように爆発寸前の下心を抑えながら頭を撫でる。さらさらとした黒髪の指通りを、指先から伝い全身全霊で愉しむことくらいは許してほしい。同じシャンプーを使っている筈なのに、どうしてこんなにも甘くやわらかな匂いがするのだろう。
「ルルーシュが寝るなら、俺も寝るし。明日のお雑煮作りも手伝うから」
「おぞうに……枢木さんは、おもち、何個食べますか?」
「んー、五つくらい? ほら、ルルーシュ立って」
「いつつかあ。いっぱい食べますねえ。いっぱい食べるひとはいいひとですよ」
「そうだね。ありがとう」
この瞬間もこれまでにも、襲ってしまおうと思えば容易に襲える場面がいくつもあった。今までベッドを共にしてきた女優なりモデルなりアイドルなり、凡百の相手であればとっくに抱き飽きている頃だろう。それをこの、五歳年下の男の子に限っては、酔ってふらついた身体を支えて唇が近づいた瞬間の、衝動的な一度の口づけしか為せていない。しかもそれを、同じ状況である今再び、今度こそは舌まで入れて奪ってやろう、などという気も臆病風で起こせない。あのキスの直後、真っ先に感じたのは圧倒的なまでの罪悪感だった。ルルーシュが嫌がっていない、というよりも「酔ってふざけてキスなんて大人だな、それも枢木スザクが相手なんて役得だ」程度にしか捉えていないのが丸分かりであったことで、「枢木スザクに生まれて良かった」という天から光射す気持ちプラス「どうして俺は枢木スザクなんだ、いっそただの顔が良くて才能と金のある一般人だったなら」という気持ちプラス「でも俺が枢木スザクでなければルルーシュはこんなに気を許してはくれないんだ」プラス「そうだ少なくとも俺はルルーシュにこんなに懐かれてるんだぞ見たか世界!」、イコールでこうして今もただの良い人、ルルーシュを愛し愛されるお兄さんポジションに甘んじている。与えた自室のベッドまで手を引いて先導し、布団を胸元まで掛けてやったルルーシュが「おやすみなさい」とこれ以上なく安心しきった声で言うのを聞いて、ようやく勃起を許した股間を開放すべくトイレへ向かった。二〇一八年の自慰初めだ。
9:00
「はい、熱いから気を付けてくださいね。いっぱいおかわりしていいですからね」
椀を手渡すルルーシュが着ている割烹着は、この日のためにスザクが購入した卸し立てだ。いつものエプロンももちろん至高だが、新年の朝には真っ白な割烹着と三角巾でお玉を片手に微笑むルルーシュがどうしても見たかった。今年の正月休みは三日の午前中まで、ルルーシュよりも半日分短いがその間はずっと一緒にいられる。どこにも行かず、何にも邪魔されることなく、ルルーシュの作った食事を三食食べて酒を飲んで――この世の春とはまさにこのこと。にやにやしながら雑煮の椀を片手にソファへ座ると、ルルーシュも後を追ってにこにこと身を寄せてきた。期待たっぷりに輝く瞳は、スザクがもう片方の手に持つお神酒の瓶へ向けられている。弱いと言っても酒好きの度合いにおいてはスザクどころか、『コードギアス』の打ち上げで目の当たりにしたシャルルのそれと並ぶほどのようだった。流石は親子、いや親子ではないのだが。シャルルとの共演回数はスザクの方が遥かに上回り、またルルーシュの実の両親ともそれなりに顔を合わせてきているというのに、未だに時折『ギアス』の世界が現実を侵食するような心地に襲われる。映画総集編の新規カットや宣材写真の撮影で仕事が継続しているから、という理由もあるがそれだけではなく、要はあまりにも強烈な体験だったのだ、『コードギアス』という現場は。あのドラマがスザクの人生を、比喩でも大袈裟でもなく変えた。思えば正月らしい正月を過ごしたいと考えたことなど、ほんの幼い頃以来ではないだろうか。
「お雑煮って、作るのも初めてだったんですけど、考えてみたら食べたこともほとんどないかもしれません。給食で出たかな……?くらいで」
「そっか、いつもはイギリスで過ごすんだもんね。イギリスの正月料理ってなんかあるの?」
「特にないですね……うちだと、ちょっと良い朝ご飯を食べるくらいです。あの、あれです、ラピュタのパンみたいな」
「あ、いいなあそれ。っていうかルルーシュ、ラピュタ見たことあるんだ?」
「映画という意味なら……」
「城本体は俺もないかな」
「ふふ、すみません」と、楽しくて仕方ないといったように笑い、角餅の端に齧りついて熱さに少し眉根を寄せるルルーシュをうっとり眺める。香り立つ湯気の向こうにルルーシュ、新しい年の陽射しに黒髪が透けて綺麗な茶色に映るルルーシュ、ああ今食べたのはスザクが型を抜いたお花のにんじん、椀を傾ける仕草もほんのり血色に染まった唇も完璧だ。
「そんなに意外ですか? 俺とジブリの取り合わせって」
「うーん、割と。なんか国内アニメとかって全然見ないで育ってきてそうな」
「それはそうですけどね。でもジブリは後学のためにも一通り観ましたよ。あ、あと、最近は移動中にあれとか観てました。けものフレンズ」
「なんだっけ、聞いたことあるなそれ……すごーい! ってやつだ」
「そうですそうです、すごーい! たのしーい! ってやつ」
かわいーい。心の中でしみじみ呟く。
「枢木さんとも観たいなあ、ラピュタとかトトロとか。ジブリって配信ないですもんね、借りてきますか?」と、雑煮のおかわりを取りに立ちながら提案してきたルルーシュに「えー、『正月は外に出ない計画』じゃん」と返す。「そうでしたね。あ、それじゃあそろそろ頼んでた神社が……」とルルーシュが言ったとほぼ同時、マンションコンシェルジュからのコールが鳴り響いた。
「わあ、ジャストタイミング。出ますね。……はい、枢木です。あけましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします……え? ……はい、ええ。少々お待ちいただけますか?」
空の椀を持ったまま、壁から取り上げた受話器を器用に押さえて「大きい荷物だから、配達員の方をそのまま上げてもいいか、って」と、ルルーシュはやや困惑顔でこちらを振り向く。頷いてやると、不思議そうながらも「……すみません、はい。お願いします。ありがとうございます」と丁寧に対応し、キッチンではなくスザクの傍に戻ってきた。
「そんな大きいもの、頼んでましたか? なんだろう、ゲンブさんからとか?」
「ないない。ああ、ハンコ押したらそのままでいいからね。俺が中まで運ぶから」
ますます首を捻るルルーシュだったが、ややあって聞こえたドアチャイムで弾かれるように再び立ち上がりインターホンまでぱたぱたと駆けていく。残りわずかだった雑煮を食べ終えてからゆっくり後を追えば、玄関にスザクが着いたときには配達員の姿がドアの向こうに消えたところで、ルルーシュが頬を紅潮させてスザクの方へ振り向いた。
「枢木さん、枢木さんこれ! これ、kotatsu!」
興奮のあまりかイントネーションが非日本語のそれになっているのを思わず笑いながら、「うん、炬燵。注文してたんだ。ルルーシュ、本物見たことないって言ってたから」と意識してさらりと伝える。ああ注がれる「枢木さんすごい! かっこいい!」の眼差し。
「すぐ組み立ててあげるから。炬燵でみかん食べてさ、おせちも食べて、一緒にテレビ見て、ごろごろしよう?」
さあ来い! 飛びついてハグ! 顔には出さず、しかし期待ではち切れんばかりの胸を脳内で大きく開く。ルルーシュの瞳がきらきらと輝き、勢いよく広げた両腕をがばりとスザクの首へ回して――近づく温度! 触れ合う胸!
「枢木さんっ、ありがとうございます! 大好きです!」
やったーーーーーーーーーーー!!!
15:00
予定通り炬燵と一緒に届いた神社のジオラマを組み立てるのには、予想以上に骨が折れ時間がかかった。ルルーシュと二人、お互いに細かい作業は得意だと自負していたが、出来上がったときにはどちらからともなくぐったりとした溜息が漏れたほどである。
「紙製だとは思えないですね。すごくしっかりしてる」
「そうだね、ちゃんと狛犬もいるし」
しかしジオラマと目線の高さを合わせ、炬燵の天板に顎をついて感嘆するルルーシュの美しい目瞬きと、その度に音を立てそうな睫毛を見ているだけでかなりの回復を感じるのだから安いものだ。否、この至近距離でルルーシュの素の表情を凝視できるという立場はどれだけの維持費がかかろうとも手放せない。このジオラマなんて二千円ほどの代物なのだ、むしろ神やら運命やらに莫大な額の値引きをしてもらっていると言える。
「でもちょっと、結構疲れましたね……今年の疲労初めだ」
「俺らジオラマを舐めてたね。あ、横になるならいいよ、膝」
「いいんですか? じゃあ、お言葉に甘えて」
炬燵に入ったまま横たわろうとするルルーシュに好機とばかり、だが極めて何気なく誘導をかけて、自身の膝に頭を置かせることにも大成功した。改めて見下ろせばなんて小さな頭、形の良い頭蓋だろう。そして髪の間から覗く、耳のやわらかく真っ白なことよ。指先でふにふにと耳殻を揉めば「くすぐったいですよ」と笑いながらの抗議が来た。
「ごめんごめん」
永遠にこの時間が続けばいいのに、と思うもルルーシュは早々に身を起こし、「だけどようやくこれで初詣が出来ますね。ほら、枢木さんも」と傍らに用意していた小箱を引き寄せる。中に入っていたのは賽銭箱を模した貯金箱で、スザクが「神社は混むし、どこに行っても人目が多すぎるから家で初詣をしよう」と提案したことに想像よりも遥かに喜んだルルーシュが買ってきたものだった。大学の友人に連れられて行ったヴィレッジヴァンガードで見つけたのだとか。前半は気に食わないが(男であれ女であれルルーシュと買い物をすることにデートの意味を見出さない人間などいるものか)、未だに場慣れしないという猥雑な雑貨店でおずおずとはしゃぐルルーシュの姿は想像するだに素晴らしいマスターベーションの供になる。
「二礼二拍手一礼、ですよね? お賽銭は先でしたっけ、後でしたっけ」
「合ってるよ。賽銭はよりけりだけど……まあそもそも手水とか鈴緒もないし、タイミングとかは気にしなくていいと思う」
「これね、見てください枢木さん。綺麗なのを用意したんです」
いそいそとルルーシュが取り出したのは五円玉が九枚で、「四十五円でしょう? 始終ご縁がありますように、って」とどこか自慢げに教えられる。
「すごいね、よく知ってるね」
チャンスとばかりに頭を撫でると、ルルーシュは一転して照れた笑みを満面に浮かべた。積もりに積もった欲望はもはや己の武器ともなっている。人間は進化する生き物だ。
「ご縁って、誰との?」
だが心温まっているだけの場合ではなく、ここはしっかり聞いておきたいところだ。これだけこちらからの想いを重ね、圧を込めておきながら、ルルーシュの恋愛観や好みのタイプといった情報を聞き出せたことはまるでない。ルルーシュの側からスザクに聞きたがることは多々あれど、反対にこちらからそうした話題を振るとルルーシュは本当に困ったようになってしまい、反応に窮してわずかに落ち込んでしまうのだ。
「そうですね、俺は特定の神を信仰している訳ではないんですが、何か大きな、上位存在のようなものはあるのかなと、ぼんやりですけど。それがもたらす運命だったり、チャンスだったり、そういうものとの良縁を、と思って」
ルルーシュは当然、性愛に無知というわけではない。仮にも二十歳の男子なのだ。この仕事をしている以上、扇情的なアピールを行うこともある。だがそれとは別の次元で、性の部分に希薄さを感じる、というのがこの三年間ルルーシュをじっとりと見てきた人間の所感だった。本人に確かめては勿論いないので、あくまで所感に過ぎないのだが。育ちの良さが影響しているのか、パーソナリティで片付けられるものなのか。ともかく、そのまっさらに見える惚れた腫れたの大地に芽吹きの気配があるのなら、早めに熟知し傾向と対策を――と思ったのだが、この様子ではまだ「優しくて大好きな枢木さん」に甘んじていられそうだ。
「――あとは、その。当たり前ですけど、枢木さんとのご縁も、ずっと続きますようにって」
枢木さんは何円入れますか? あっ、小銭って持ってないですよね。枢木さん、キャッシュレスの人だから。じゃあ、俺と一緒にこの四十五円、入れましょうね。半分ずつ二人で持って、せーのって。九枚だからどっちか一枚少なくなっちゃいますけど――ルルーシュの楽しそうに話す声を聞きながら、思わず目頭が熱くなったのを慌てて堪える。
炬燵の一辺に並んで座り、小さな神社を前にして二礼、二拍手、一礼。それぞれに目を閉じ、しばしの無言で願いを捧げる。神様、俺をずっと、ルルーシュの隣にいさせてください。セックスなんて出来ないままでもいい、いや今のは撤回、ルルーシュのおちんちんも見たいし舐めたいし触りたいし触ってほしいです。出来れば今年中にご査収願います。何卒。
「そうだ、おみくじもあるんですよ。初詣といえばおみくじですよね、今持ってきますね」
うきうきとした語調ながら名残惜しそうに炬燵を出てどうやらキッチンに向かい、バスケットを手に戻ってきたルルーシュがまた素早く炬燵に潜り込む。バスケットの中には人間の形をしたふわふわのパンが四つ、レーズンの目やボタンをつけられて可愛らしく鎮座していた。
「これって、あのラジオで言ってたやつ? えーと、」
「そうです、マナラ。美味しいですよ。では枢木さん、この中から好きなのをひとつ選んでくれますか?」
これがルルーシュの用意した「おみくじ」なのだろうか。なにやら誇らしげな顔で見守られ、カラフルなチョコレートで靴を履かされている一体を選んで手に取る。「裏返してみてください」と囁かれ、パンをひっくり返せばそこには、筆にチョコレートを取って書かれたと思しき、この手の装飾には異様なほど達筆な「大吉」の文字。
「おめでとうございます! 大吉ですよ! 枢木さんの二〇一八年は良い年になりますよ」
心底嬉しそうに楽しそうに、自分の食べるマナラを持って手を振るように動かすルルーシュ。こんな、スザクにおみくじを引かせるために、わざわざパンを焼いて、裏面に文字まで仕込んでわくわくと待っていたのか。抱き締めたい、猛烈に抱き寄せて深く深く口づけてしまいたい。可愛らしく振っていた手の部分から早速食べている唇を奪いたい。でろでろに愛しさで蕩けながら、スザクは大吉パンの頭に齧りつく。
21:00
「小腹が空いた気がします」
シャルルからの頂き物だというオリジナル日本酒『ルルーシュ』を大事そうに呑みつつ、毒にも薬にもならないような正月特番を微笑んで眺めていたルルーシュが突然、真剣な顔つきで報告してきた。
「枢木さん。俺は小腹が空きました」
むしろ宣誓と表現してもいいくらいの真面目な申告だった。「おせちのローストビーフ、確か残ってましたよね。枢木さんも食べますか。食べますよね」と静かな口調ながら言い募られ、「そうだね……ちょっとつまもうかな」とわずかに気圧されて答えると、ルルーシュの表情がぱあっと明るくなり、「にっこり」の図解として辞典に採用されそうな満面の笑みが浮かんだ。毎度思うがあまりにも顔が良い。
「取ってきますね! ローストビーフと、みかんのおかわりと、あと、ビールと」
浮き足立っているというよりほとんど千鳥足、これはかなり酔い始めているな、とキッチンへ向かう綿入れ半纏(こちらも着ているところが見たくて買った)の背中を目で追う。そして頬が緩む。炬燵机の上に置かれた、みかんの皮を広げて作った蛸にも口元がにやける。スザクが作ってみせてやったのを意気揚々と真似していたが、今見ると足が七本しかない。
「おせち、何が一番美味しかったですか?」
「一番? えー、難しいな……生春巻きかな。えびのやつ」
「あれは特にうまくいきましたね。もっとたくさん作れば良かったかな」
「また作ってよ。この前の餃子みたいにさ、大量に。次のおせちにも入れてね」
右手にローストビーフの皿、小脇にクッキーの細長い箱を抱え、左手に缶ビールの六缶パックをぶら下げつつみかん入りのネットを胸で抱えるという器用な格好で戻ってきたルルーシュへ、早々とかつ当たり前のように来年のリクエストを申告する。せっかく手作りするのだから互いの好きなものだけを入れたお重にしよう、とルルーシュからおせち料理の提案をされたときは自分でも度が過ぎていると思うほど大喜びしてしまった。大晦日の朝から並んで台所に立ち、ルルーシュのいつもながら鮮やかな手際に見惚れつつ、包丁捌きを褒められたり共に味見をして頷きあったり、あの楽しさはまるで子供の頃の自分までもが優しい手で抱き上げられたような心地だった。ただでさえ五つも年下で同性の相手に、ただ懸想するだけでなく母性まで求めるようになってはいよいよ終わりの始まりだと自覚してはいる。だが「あ、これたぶん甘いですよ。これもそうかな」とみかんを選別してこちらに寄せてくるルルーシュに、高鳴りとはまた違う、震えるほどの胸の衝動を覚えない男が果たしているだろうか。
「ミスターイトウのバタークッキーが昔から好きなんですよね。ムーンライトとかも美味しいけど、俺はやっぱりこの赤い箱に胸がときめく」
「ね、ルルーシュ」
「はーい。なんですか?」
酒に酔っていることもあり、出会った頃では考えられないほど気安くなってくれた反応。少し濡れたように瞬く睫毛、何にというでもなく、場の雰囲気に緩く笑んだ美しい唇の端。
「今年も、良い年になるといいね」
「はい。二人で、素敵な年にしましょうね。……あっ桃鉄! そうだ桃鉄やりませんか! 俺ね、結構いろいろ勉強したんですよ」
スザクの感傷を吹き飛ばさんばかりに勢いよく立ち上がり、「Wiiリモコンってこっちのチェストでしたっけ?」とわくわく探し始める姿に、思わず吹き出すように笑ってしまった。準備を手伝いに腰を上げ、「勝利パターンとか、カードの対策と使い方とか。もうやられっぱなしの俺じゃありませんよ、なんなら枢木さんに一泡吹かせてやりますからね」と意気込むルルーシュを軽くからかう。
「威勢がいいねえ。じゃあ罰ゲーム制にしよっか、ルルーシュが勝ったら何でも言うこと聞いてあげる。そのかわりあれだよ、負けたら俺にキスだからね」
「えっずるい! 俺もそれがいいです!」
明らかにふざけているとわかるような声色を作って言った台詞を食い気味に主張され、予期せぬ反応と勢いにぎょっとする。「俺が勝ったらー、枢木さんは俺に勝者のキスですからね」と続く語尾のふわふわした口ぶりは、完全に酔っ払い特有の様態。
「えっ……えっ、いいよ、うん」
鼻歌を歌いながらディスクを本体に飲み込ませるルルーシュには、自分が言ったことにどれだけ重みがあるか、いかに今スザクが動揺しているかもわかってはいないのだろう。スザクが勝ったらルルーシュとキスができて、スザクが負けたらルルーシュとキスができる? いや違う、負ければスザクからのキスだが勝てばルルーシュからのキス、両者は似て全く非なるものだ。恐らくルルーシュの中ではダチョウ倶楽部的な認識か下手をすればそれ未満だが、スザクにとってみれば瓢箪から駒の超特大級お年玉だ。
「何年でプレイしますか? 三十年……いや、五十年かな」
「三年決戦でいこう」
三年で片をつける。そして絶対に、ルルーシュの方からキスしてもらう。「えー、北海道大移動は起こさないんですか? そこも研究したのになあ」と可愛く不満を述べるルルーシュにクッキーを咥えさせて誤魔化し、スザクはリモコンを握る手にじっとりと汗を滲ませた。
結果として、我欲は人間を驚くほど弱くするもので、かのイカロスもただ飛ぶだけなら良かったものを太陽に届かんとしたその途端に翼を溶かしたというわけで、ものの見事にスザクは敗北を喫したのである。流石ルルーシュの「研究」は伊達ではなかったということか、いや運の部分ばかりはどうしようもない要素であって、やはり天がスザクの下心に味方をしなかったということなのだろうかしかし結局キスはできるのだから抜かったな天よ! なにせ前回の偶然から一ヶ月もせず再び巡ってきた、しかも今回は完全同意のチャンスである。酒に酔っての言動を同意とするのは人としてどうなのかという後ろめたさも小さじ程度ありつつ、もはやそんな理性を働かせてはいられないほど状況は切迫しているのだった。リモコンを静かに床へ置き、勝利に拳を掲げているルルーシュに向き直る。別にこれを機に関係を進めようだとか、ましてやそのまま押し倒してやろうだなどと思っているわけでは決してないのだ。ただ、人生に少しばかりのご褒美が欲しいだけ。ルルーシュという奇跡の存在と寝食を共にして、あまつさえその唇に触れるという極上の果実を「少しばかり」と形容するなどまさしく天をも恐れぬ所業だと自覚はしているが、それでも。
「ルルーシュ……」
好きだよ、と続けて甘く囁いたとしても、それが愛の告白だと受け取ってはもらえないこの身の切なさが、少しくらい報われてもいいじゃないか。
「あっ、そうですね! やったあ、じゃあお願いします」
――弾む口調で目を軽く閉じ、ルルーシュが自身の頬をとんとんと指差したことで、夢から醒めたように気付いた。そうだ、何もマウストゥマウスで、と指定されてはいなかったのだ。勝利のキスを頬に、というのは最近までやっていた番組名物のビストロコーナーでもお決まりの行為だった。なるほど、それならルルーシュが、いくら酔っているとはいえ自分からねだってくるのも理解の範疇内である。浮かれきっていた自分を内心、自嘲で笑い飛ばそうと努めながら、いやでもそれにしたってご褒美はご褒美に違いない、もうルルーシュのほっぺの感触を味わいつくしちゃうもんねとルルーシュの両肩に手を置く。近づく肌のきめ細かさと、香る黒髪の甘い匂い。はやる心臓が着地点を間違えないように、慎重に近づいて、
近づいて?
唇が。
ルルーシュの唇が、ルルーシュが瞼を一瞬開いて、またすぐに閉じて、顔を。
顔の角度を、変えて、スザクの唇に。
唇が、くちびるに。
「――ふふ、びっくりしました? この前のお返しです。なーんて」
放心しているスザクに、ルルーシュは悪戯が大成功した���いう笑顔で言う。「……あ、すみません、嫌だったですか?」と表情が翳りかけたのを慌てて勢いよく首を横に振り、「いやいやいや違うすごいびっくりしただけ、えっだってすごいブラフ……えっ待ってどこから?」と無意味にルルーシュの半纏の紐を結び直しながら返した。ルルーシュはほっとしたように頬を緩め、そしてまたにんまりと笑ってWiiリモコンを手遊びに振る。
「最初からです、最初に言ったときから。枢木さんが勝ってもそうしようって思ってたし、俺が勝ったら先制攻撃の不意打ちで、って。俺あのとき、誕生日のとき、すごくびっくりしたんですよ。だからお返しです。目には目を」
こんなところでハンムラビ法典を聞く試しがあるとは思わなかった。などと冷静に言ってはいられない。否もう、まるで冷静ではない。「そっかーいやほんとすごいびっくりした俺も、ルルーシュすごいねほんと良い役者、あー本職、俺も本職」と早口で並べ立て、無意味に手を握っては開き開いては握り、してやったり顔のルルーシュに爽やかな笑みを見せる。
「完全に騙されちゃったな。ああごめん、俺ちょっとトイレ行ってくるね」
「はい。すみません、俺も結構もう、眠くなってきたので……歯を磨いてきますね」
「オッケー。寝る前に声掛けて」
めいめいに立ち上がり、洗面所の前で別れて、ルルーシュが立った鏡越しの視界に映らない場所まで進んだところでトイレへダッシュする。短距離走者の本気の走り方だ。音が立ち過ぎないよう気をつけつつ急いでドアを閉め、息をつき、個室の中でしゃがみこむ。ぐうう、という音とも声ともつかないものが自分の喉の奥から漏れた。
「無理……好き……あー無理、超好き……どうしよう……好きです……」
ついに独り言が敬語になってしまった。ジーンズを下げてぼろんと飛び出す、元日にしてすでに今年最高ではないかという隆起を見せつける我が陰茎。そうだ今年は射精をする度に、赤十字社へ寄付をしよう。みなさんの二〇一八年が、どうぞ良きものでありますように。
1 note
·
View note
Text
【小説】ひとでなし
このひとでなしが。
兄は吐き捨てるようにそう言って、席を立った。
真っ赤な顔をして、数人の客と店員たちの視線を集めながら、テーブルの隙間を縫うように店を出て行く。
私は目だけでその背中を追った。ガラスの向こう、陽の光を浴びた彼の背広が滑らかな光沢を放っている。そのどこか品のない銀色の上着を見て、私は鰯の群れを連想していた。
魚料理にすればよかった。
この後、運ばれてくるはずの料理のことを思い出して、少し後悔する。
「お客様、大丈夫でございますか」
年配の店員が近付いて来て、私にそう声をかけた。
「ええ、大丈夫です」
「お召しものが汚れてしまわれましたね」
「ご心配なく。よくあることなのです」
私はそう答えながら、店員が差し出してくれたタオルでメロンソーダが滴っている頭を拭った。店員は濡れたテーブルをせっせと拭いている。
「先程のお客様が注文された料理ですが、注文を取り消し致しましょうか?」
「彼は、何を注文したんでしたっけ」
「鮭のムニエル定食をおひとつ」
「では、私が注文した和風ハンバーグ定食を取り消して、ムニエルの方を持って来てもらうことはできますか?」
「はい、かしこまりました」
年配の店員は恭しく頭を下げて、テーブルを離れて行く。空になってしまったメロンソーダのグラスをさりげなく片付けることも忘れなかった。
あの店員は、どうして兄が注文した方の料理を私が食べたいと思っているのか、不思議に思っているかもしれないな、と予想する。
再びひとりになった私は、窓から表の通りへと目をやる。すでに兄の姿はどこにもなかった。彼は昔から、道の途中で別れた後、決して後ろを振り返ったりしなかった。あの男とは違う。私の姿が見えなくなるまで、いつまでもそこに立ち尽くしている、あの男と、兄は違う。
去り際、兄が私の顔にぶっかけていったメロンソーダは、髪や顎をつたってワンピースの胸元まで緑色に染めていた。黄色の花柄の中に浮かび上がる淡い緑色は、葉のようにも見えなくはない。全身をまんべんなくこの緑色に染めたら、この染みも目立たなくなるだろう。そういう柄の洋服にしか見えなくなるはずだ。
だが、「メロンソーダをもっとかけてください」なんて、店員にも、ときどきこちらの様子を窺うように見つめてくる他の客たちにも頼めない。
服のことは諦めよう。この後、身なりを気にしなければならない相手と会う予定がある訳でもない。砂糖水のにおいがする頭髪も、化粧が崩れた顔も、濡れた衣服も、街ですれ違う人々は誰も気に留めない。そう思うとなんだかほっとして、私はテーブルの隅にあった灰皿を手元まで引き寄せ、煙草に火を点けた。
兄は、私が煙草を吸うのをひどく嫌がった。女のくせに、と罵った。だが、それは私が女だからではなくて、彼が嫌煙家だっただけだ。だから今まで吸えなかった。鼻から煙を出しながら、ニコチンが身体じゅうに浸透するのを待った。
テーブルに出しておいたスマートフォンのLEDが青白く点滅していることに気が付いたのは、その時だった。手に取ると、不在着信を示している。その時刻はほんの数分前、ちょうど、兄がメロンソーダをぶちまけた頃だった。電話がかかってきたことに、気付かないでしまったようだ。
後で必ずかけ直そう、と思いながら、煙草を親指で弾いて灰を落とす。
まだ午前中、昼前であることもあって、店の中は比較的空いていた。混んでくるのはこれからだろう。客が少ない時間帯でよかった。後ろの席に誰かいたら、メロンソーダの飛沫が飛んでいただろう。
煙を吐きながら、心の中の穴がじわじわと塞がっていくを感じていた。気分が落ち着いたのだ、と思い、今までの状況においても私は常に落ち着いていた、取り乱していたのは兄であって私ではなかった、とも思った。
彼は私を「ひとでなし」と言った。
ひとでなし。
小さく声に出してみる。唇に挟んだ煙草が転げ落ちそうになる。
私はひとではなくなってしまったのだろうか。真っ昼間、小さな洋食屋で罵声を浴びせられ、緑色した甘い液体をかけられるような私は、ろくでなしではあるけれど、まだひとであるはずだ。
短くなった煙草を灰皿へと擦りつける。二本目の煙草に手を伸ばしながら、兄は今どうしているだろう、と考えた。
私は今、泣いてもいないし怒りもしてない。彼が嫌った煙草を吸いながら、彼が注文し、彼が食べるはずだったムニエルが出てくるのを、彼がいなくなった席で待っている。
彼は今、泣いているのかもしれないし、怒り狂っているのかもしれない。道端で誰かの副流煙に顔をしかめ、空腹を抱えたまま、どこへ向かっているのだろう。
私たちは一生わかり合えないし、もう会うこともないのだろう。でもそれが、なんだかごく自然で、当たり前のことのように感じる。もっと早くこうなるべきだったような気さえする。
私は少しして運ばれてきたムニエルを前に、両手を揃えて祈った。
それは彼がどこかで幸福になりますように、という意味を込めての祈りだったが、私の口はさも当たり前のように「いただきます」とつぶやいた。
電話をかけてきた相手に折り返し連絡しようとスマートフォンを手に取ったのは、部屋に帰ってシャワーを浴びた後だった。
メロンソーダが染みになったワンピースを脱ぎ捨て、熱いシャワーを浴びて化粧さえも落としてしまうと、身も心も軽くなったような気がした。裸のままバスタ���ルに包まってベッドに転がる。シャワーを浴びた後は、こうしているのが心地良い。こうしていると、自分が日頃、いかに多くのものを身に着けているのかを考えさせられる。
あの男は私がこうして寝転んでいると、決まってセックスに持ち込んだ。私が誘っているとでも思っていたのだろうか。彼は事が終わるとすぐに衣服を着た。何も身に着けないでいることが、恐らく不安だったのだ。いつもこまごまとした多くのものを鞄に入れて持ち歩いていた。何も持たないことの快適さなんて、知らないのだろう。
そんなことを思い出しながらスマートフォンを操作し、着信履歴を見る。「達」とだけ登録してあるその人物からの、不在着信があったことが記録されていた。
たつ。
その名前をそっと声に出してみる。名前を呼ぶことも、なんだかずいぶん久しぶりだった。彼から電話がかかってきたことなんて、今まで数えるほどしかない。何かあったのかもしれない。そう思いながら、リダイヤルの文字をタップする。
呼び出し音は鳴らなかった。間髪入れずに、彼が電話に出たからだ。
「もしもし」
「もしもし、達?」
「律。今、もう一度かけようかと思ってたところ」
達は電話の向こうで、どこか安堵したような、呆れているような、疲労の色を感じさせる溜め息をついていた。最後に耳にした時と変わらない、懐かしい声。
「さっきは電話、出なくてごめんなさい」
「いや、いいよ。少し、気分転換に話がしたくなっただけだから」
妙な感じがした。彼が今までそんなことを言ってきた覚えがなかったからだ。やはり、何かあったのだ。私は無意識のうちに、身体に巻き付けていたバスタオルの胸元をぎゅっと握っていた。
「何かあったの?」
「少しね」
私の声がこわばったのを感じ取ったのであろう達は、ははは、と小さな笑い声を漏らした。彼はわかっている。自分が笑うと、私が少なからず安心するということを。だからときどき、私のために笑ってみせてくれる。
「もしかして、またお母さんと揉めたの?」
「あの女はいないよ」
達はそう言ってから、少し間を空けて、
「もういない」
と、言い直した。
「達、会いに行こうか?」
私がそう提案した時、彼はしばらく返事をしなかった。長い長い沈黙だった。通話の向こうから、パソコンのマウスをクリックしているような音だけが断続的に聞こえていて、それさえなければ、私は通話が途切れてしまったのではないかと思っただろう。
「達?」
「ああ、ごめん。うん……」
彼はそう言ってからまたしばらく考え込んだ様子で、たっぷり黙り込んだ後、
「そうだな、会おうか」
と、答えた。
彼がそう言ったので、私は心底ほっとした。
「今、何してるの? もしかして、仕事中?」
「ソリティアやってる」
「ソリティア? ああ、パソコンに入っている、トランプのゲームのこと?」
「そう」
「忙しい訳じゃないのね?」
「ソリティアで忙しいよ」
私は彼の冗談に笑った。それから時計を見た。まだ午後一時を回ったところだった。時間は、まだある。
「これから支度して電車に乗るよ。三時か、四時くらいには、そっちに着くから」
「今から来るの?」
「だって、早い方がいいでしょう?」
そこで、達は何かを言いかけたが、でもはっきりとした言葉にすることはなかった。今度はほんの少し黙った後で、
「わかった」
と、返事をした。
「それじゃあ、また後でね。電車の時間がわかったら、また連絡するから」
「うん。じゃあ」
通話を終えてから、私は大急ぎで支度に取りかかった。服を着て、軽く化粧をして髪を梳かす。放ってあった鞄を拾い上げ、忘れずにスマートフォンと部屋の鍵を仕舞う。ストッキングを穿く時間も惜しく、素足のままサンダルを突っかけて外に出た。
達は少し、様子がおかしい。
電話では口にしなかったが、やはり何か、電話をかけてくるだけのことが、彼の身に起こったということだろう。
駅までの道を駆けた。改札を通り、目的の電車があと十分もすれば来ることを電光掲示板で確認して、そこでやっと一息つくことができた。売店でミネラルウォーターと、たまたま目についた小説の文庫本を一冊買った。
達の住む街まで、ここからだと電車で二時間かかる。その間の暇潰しが必要だった。
電車に長く揺られる時は、いつも何か書籍を買うことにしている。駅で購入して、読み終えたら駅で捨ててしまう。今日手にした小説は、知らない作家の作品だった。題名にも聞き覚えがない。普段は読書をしないので、私が詳しくないというだけかもしれない。
「暇なら、本を読んだら」
そう私に提案したのは、あの男だった。彼は読書家で、多忙な時間の隙間を見つけては本を読んでいた。自室の書棚には零れ落ちそうなほど本が積み上げられていた。
「そうしようかな」
私がそう答えた時も、彼は分厚い本を膝に乗せ、ソファに行儀よく座っていた。
「何か、本を借りて行ってもいい?」
あの男は開いた本のページに目線を落としたまま、ただ黙って眉間に皺を寄せていた。彼は自分の持ちものが自らの管轄から外れ、どこか遠くへ行ってしまうことを嫌っていた。結局、彼は死ぬまで、私に一冊も本を借りることを許さなかった。
走って汗ばんだ背中に衣服が張り付いているのを感じながらミネラルウォーターを飲んでいると、電車は時間通りにやって来て目の前で停車した。開いたドアから乗客が降りてきて、入れ違うように私は乗り込んだ。
車両の中に乗客の姿はまばらで、午後の日射しを受け、心地良い暖かさに満ちている。
あと二時間。
どんなに気持ちが急いだところで、あと二時間、私はここで大人しく座っているしかない。その事実が私の焦燥感を少しばかり和らげた。早く会いに行かなくちゃと心は焦ってばかりいるのに、ゆったりと腰かけて二時間を過ごすなんて、不思議だ。
そうして走り出した電車の中で、私は文庫本を開く。
読み始めてわかったが、それは殺人事件を扱った小説だった。
河川敷で見つかった、ひとりの女子高生の死体。そこから始まった、少女ばかりを狙った連続殺人事件。主人公はその事件を追う刑事で、被害者と同じくらいの年齢のひとり娘が、別れた妻と一緒に暮らしている。殺された被害者の少女たちと、自分の娘を重ねつつ、犯人を追っていく。
『明日は私が殺されるかもしれない。今や、この街に住む誰もがそう思っていた』
そんな一文が、なぜか目に止まり、私はもう一度、その文章を目で追ってから、ページから目線を上げ、車両の中を見渡した。��学生らしい男性がひとりと、中年らしき女性が四人。お互い他人同士なのだろう、離れた席に座っていて、誰も口を利いていない。手元のスマートフォンを操作している人がふたり、ひとりは私と同じように何か書籍を読んでいて、最後のひとりは肩をすぼめるようにしてうとうととしている。
きっとこの車両の中には、明日自分が殺されるかもしれない、なんて不安に思っているような人間はいない。乗客たちは皆、落ち着き払った表情をして、のどかな午後を過ごしている。
誰も、自分が殺されるかもしれないなんて、普段は考えもしない。
街を歩いていたら突然、自動車が猛スピードで突っ込んでくるかもしれない。乗っていた電車が脱線して大事故を起こすかもしれない。人混みの中で通り魔に後ろから襲われることだってある。でも誰も、そんなことは考えない。この車両の中に、殺人犯がいるかもしれないなんて、思わない。
ああ、煙草が吸いたい。
私はそう思いながら、手元の文庫本を閉じた。本の内容に飽きてしまった。犯人がどこのどんなやつかなんて、興味がない。犯行の動機なんかどうだっていい。
窓の外に目をやった。ちょうど電車は川に架かる橋の上を走行していた。車窓の向こう、橋を構成する鉄骨の向こうに河川敷が見えた。小説の中では女子高生の死体が無残にも転がっているはずのそこは、西日をきらきらと反射する川面と、風にそよぐ青々とした草原、アスファルトで舗装された道を行く、犬を散歩させている老人の姿しかなかった。
もし今、私があの河川敷に立っていたら、きっと煙草を吸いたいなどとは思わなかっただろう。横たわる死体を前にして、もうすっかり満足するまで、いくらでもニコチンを吸っては吐き出すことができただろうから。
そう思いながら、私は座席に座り直し、殺人犯がいるかもしれない車両の中で忌々しく瞼を降ろした。
私の手の中にあるカードは機械に読み取られ、ぴっ、という短い音を立てた。帰りの電車賃がもう残っていないことを確認して、それでも開いた改札を出る。
「達」
「律」
電車は脱線することもなく無事に目的の駅に着き、私は改札の前に立っていた達と再会した。
彼は最後に会った時と変わらない、胸元がだらしなくたるんだ着古したTシャツと、すっかり色褪せて擦り切れそうなジーンズ姿だった。ただ、髪も髭も伸びすぎていた。目の下の濃い隈のせいで、まるで目玉が窪んでいるように見える。少しだけ、あの男の面影を思わせる容姿。
「早かったね」
「電車は時刻通りだったよ」
「うん。早かった」
そんな冗談にまた私が笑うと、達も少しだけ口元を緩めてみせた。彼は自分のために微笑んだりはしない。いつも誰かに笑顔を見せたくて、笑ったような表情をしてみせているだけだ。
「律、腹減ってない? 俺、まだ飯食ってなくて」
「そう。何か食べようか」
私はそう答えてから、胃の中にいるであろう鮭のことを思い出した。
「ファミレスでいい? 金ないから」
しかし、そう言いながら歩き出した彼に、私は何も伝えなかった。
達は、仕事を辞めてしまったのかもしれない。
根拠はわからないけれど、私はその時、そう思った。
「今日は、兄さんが訪ねて来たわ」
「へぇ」
「父が亡くなったんですって」
「そうなんだ」
達の声は、乾いていた。そこにはどんな感情にも濡れていない、まっすぐな響きがあった。
私は兄にメロンソーダをかけられて逆上された話をするべきか悩んだが、結局、口にはしなかった。きっと達は、そんな話をしたら不機嫌になるに違いなかった。
少し先を歩く彼の顔は、どこか遠くに思いを馳せているように見えた。私たちは一緒にいた頃から、あまり多くを語ってはこなかった。語る必要がなかったのだ。私たちは、とてもよく似た性質をしていたから。
駅を出てすぐのところにあるファミリーレストランに入った。安っぽいチャイムが私たちの存在を誰かに知らせている。いらっしゃいませ何名様ですか。二名で。お席の方、禁煙、喫煙、どちらになさいますか。きんえ、まで言いかけてから、達は、
「喫煙で」
と、答えた。私が喫煙者であるということを、その時思い出したのだろう。
午後四時を回ったファミリーレストランは、電車の車両のように人がまばらで、私たちは四人掛けの席に案内された。すぐ近くにふたり掛けのテーブルがあるにも関わらず。四人席が空いている時は、優先的にこちらへ振り分けされる仕組みなのだろうか。それがサービスというものなのかもしれないが、私も達も、まるで自身の半身を失ったかのように、隣を空席のままにして向かい合わなければならなかった。
私たちはメニューを開き、すべての品書きに目を通さないうちに注文したい料理を決めた。店員を呼ぶためのボタンを押したのは達だった。私は煙草に火を点けて、灰皿を引き寄せる。私はホットコーヒーを、達はエスカルゴの料理を頼んだ。
「エスカルゴ?」
店員が立ち去った後、私は煙を吐きながら達に尋ねた。
「好きなの?」
「不味いよ」
達はこちらを見もしないでそう答えた。今のは際どいジョークだった。私が思わず鼻で笑うと、彼も小さく笑ったので、それで冗談を言ったのだと気付いただけだ。
料理が運ばれて来るまでの間、会話はなかった。私たちは料理を待つこの時間が嫌いだった。酒を飲んでからアルコールが身体の隅々にまで回る、それまでの時間も同様に嫌っていた。私たちは不機嫌になると決まって口を閉ざし、そしてそれは、相手に対する最低限の誠意と優しさだった。
煙草が一本吸い終わった頃に料理は運ばれて来た。いただきます、と手を合わせ、達はお手拭きで乱暴に手を拭ってから、エスカルゴ料理に取りかかった。
「それで、一体何があったの?」
「人を殺したんだ」
彼はエスカルゴ料理を口へ運びながらそう言った。
そう、と私は返事をした。視界の隅、テーブルの上に達が指を拭いたお手拭きがくしゃくしゃに丸められて置かれており、それがまるでトマトソースでも拭き取ったかのように、うっすらと赤色に染まっていた。
「偶然ね、私もなの」
「律も?」
「そう」
「いつ?」
「今日」
「ふうん」
食事をしながらした会話は、それだけだった。
食事中は口を開くなと、あの男に厳格にしつけられた私たちは、今でもそれを守ろうとしている。達が母を殺し、私が父を殺した、今日でさえも。
食事の代金は、達がすべて払ってくれた。私たちは店を出て、川沿いにある寂びれたラブホテルまでの道を歩きながら、また少し言葉を交わした。
西日をさんさんと放っていた太陽はビル群の向こうに消え、空は幻想的なピンク色だった。吹いてくる風はどこか冷たく、私たちは下を向いて歩いた。まるで後ろめたいことでもあるかのように。
「殺して、どうだった?」
「別に何も」
「そう」
「うん」
道路を走る車の騒音に、私たちの会話は途切れ途切れになった。
ホテルのボーイは疲れた顔で私たちに部屋の鍵を渡した。ボーイが私と達の顔をほんの一瞬、交互に見比べていた。見比べたってわかるはずがない。私たちは二卵性で、外見は何も似ていないのだから。たとえ外見以外、すべてが非常に似通っているのだとしても。
部屋に入って、最初にシャワーを浴びたのは達だった。私は水が流れる音を聞きながら煙草を吸った。
今日は何回、シャワーを浴びることになるのだろう。頭からかけられたメロンソーダは、シャワーのうちに含まれるのだろうかと考えて、ひとりで可笑しくなった。
今日は二着もワンピースを駄目にした。どちらも服に染みをつけて。お気に入りのワンピースに染みついた血痕は、きっともう落ちないだろう。あれはあの男が、私が殺したあの父が、買ってくれたお気に入りだったのに。
私もシャワーを浴びてから、裸でふたり、シーツの中で遊びながら、また少しだけ会話をした。
「どうして殺したの?」
「理由なんてない」
「そうなんだ」
「そっちは、どうして?」
「どうしてかな……。何かちゃんと、理由があったような気がしたんだけど」
「理由っていうのは、行動する以前には必要だけれど、すべて終わってしまった後には、もうどうでもいいものだね」
「うん。確かに」
私たちの本質を覆い隠している膜が重なり合う。決して交わり合うことはないはずのその境界線が、不意に揺らぐ。溶けて、ほどけて、流れ出して。自在に動かせるはずの四肢は、自身の意思から遠く離れたところで、欲を貪る卑しい道具と化している。
こうしていると私はいつも、自分が粘土か何かになったような気分になる。人の手は容易く私をこね回し、形を変えていく。本来の形など、とっくに忘れた。抗おうと思えばそうできたはずなのに、私はただの土くれと化すばかりだ。兄の時も、父の時も、胎内で同じ時を過ごして共に産まれてきた、達が相手の時であっても。
こんな時、あの男は私のことを憐れんだ瞳で見下していた。父はいつもそうだった。可哀想なものばかり愛していた。喜劇よりも悲劇を好み、幸福よりも不幸を求めた。
夫に愛想を尽かされた妻。身体を交えた兄と妹。愛されなかった双子の片割れ。父に犯される娘。母を犯す息子。子供を猫のように捨てた親。子供に猫のように殺される親。
私たち双子はあの男に集められた、不幸の断片のひとつにすぎない。だから恐らく、これは私たちの意思ではなかった。
同じ親から同じ日に産まれた私たちが、偶然にも同じ日に、親を殺めた。
明日自分は殺されるかもしれない、なんて考える人はいない。同じように、明日自分は人を殺すかもしれないと考える人間も、またいない。私たちの生き死にと自らの意思が全く無関係であるように、私たちが自身の肉親を殺したこともまた、私たちの意思とは関係がない。
無責任だろうか。責任転嫁だろうか。
このひとでなしが。
兄に言われた言葉を思い出す。
遠くにサイレンが聞こえた。私たちの時間は、もう長くは残されていない。でも、私はまだ、ひとであるはずだ。
「ねぇ達、私はひとでなしだと思う?」
そう尋ねたのは、訊いてみたいと思ったからだ。私が唯一愛したこの同胞は、一体どう返事をするだろうか、と。
短い吐息と共に果てた私の弟は、のしかかるように身体を重ねたまま、つまらなそうに欠伸をしていた。それからおもむろに顔を上げ、私の顔をまじまじと見つめた。
「お前は、ひとでなしだよ」
あの男に少しだけ似た、私とは似ても似つかないその顔は、それから、ついばむようなキスをしてくれた。
了
0 notes
Text
chapter30
ソリチュードを出たのは昼少し前11時頃。
マルカルスまでのちょうど中盤の距離に位置するカースワステンで昼食をとり、また馬車に乗る。
スカイリムに派遣されて三年を少し過ぎ、最早見慣れた高原地帯の風景を横目に頭に浮かんだのはアナの顔だった。
出会って、一つ屋根の下で暮らし始めて五ヶ月。関係を持つようになってからは三ヶ月程。
今回のように長く家を空けるのはこれが初めてで、出張中も会議中にもかかわらずアナはどうしているだろうかとつい考えてしまった。
寂しいとは思ってくれているのだろうか。
出てくる時に名残惜しそうに抱きついてきた姿と、前日の夜に同じようにしがみついてきた顔が浮かぶ。情けない話だが、一週間も離れているとそこそこに溜まる。
アナは同じように思っているんだろうか。出会った時から考えると彼女は見違える程に俺に懐いてくれるようになった。が、正直未だにその気持ちを測りかねるところはある。
初めて家に来た時、淡々と服を脱ぎ俺のベッドに入って来た彼女を思い出す。温かい寝床と食事を提供してもらう代わりに、と店で金を払うように体を差し出してきた姿を。
今はあの頃とは違う。と、思いたい。
今日は?と、まるで「しなければならないこと」のように尋ねてきたり、そんなに毎日する必要はないと言えば、それじゃ口で、と言ってきたとしても。そんなことをする必要はないと言い聞かせるとアナはきょとんとした少し腑に落ちないといった顔で頷いた。
そんなアナを見ていると、自分の胸の中にも黒いものが湧いてくるのを感じた。
お前はアナを性欲処理の道具として見てはいないのか、本当に。一つ屋根の下にちょうどいい娘を手に入れて満足したのでは?という気持ちが。
それが湧くたびに頭を振って搔き消す。
違う。俺は大使館の、アナを食い物にしていた奴等とは違うと。
そんなことを考えていると、
「統括、マルカルスです。見えてきましたよ」
と、部下の兵士の一人に声を掛けられた。
幌から顔を出すとなるほど丘の向こうにそびえる岩の建物たちが見えた。
「あと二十分てとこですね」
御者の言葉に兵士達が降りる支度を始めるのを見て、俺も固まった上半身をほぐすように体を伸ばした。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
街の入り口に到着し、御者に金を払い荷物を卸す。今日は部下達も俺もこのまま直帰だ。時刻は夕方、街のそこかしこから夕餉の香りが漂ってくる。
家に続く石の階段を上りながら、なんとなくひりつくようなマジカの気配を感じた。
ドアを開けようとしたところで、
「おんどるまる!」
というアナの声と嬉しそうな顔が飛び込んできた。
「ただいま」
「おかえりなさい!」
アナの姿を見た瞬間、わかった。先程のマジカはこいつの物だ。
部屋の奥からにたりと笑いながら現れたベルナールの。
アナを抱きとめながら奴を睨むと、俺と同じ顔は三日月のように口の両端を吊り上げ歯を見せて笑った。
「よう。お帰りお兄様」
「…ああ」
「留守を見ててやった俺に土産は?ソリチュードのポートワインとか」
「無い」
「ふん、ケチめ」
ベルナールはひらひらと手を振り玄関に向かった。
「じゃあな。久しぶりに存分に可愛がってやれよ」
そう言って俺の肩を叩き、ばたんとドアを閉め出て行く。
「おんどるまる、ごはんさき?それともおふろ?」
「飯は?」
「もうできるよ!」
ぱたぱたとアナが向かったキッチンからはデミグラスソースのようないい匂いが���ていた。
「きょうはおんどるまるかえってくるひだから。ちょっとごちそうにしようとおもってひるからじゅんびしてたの」
「あいつと一緒にか?」
「え、」
ああ、こんな風に言うべきじゃないのはわかってる。もっと他にやりかたがあるだろう。
そう思いながらも喉から出てくる言葉を抑えられずアナを見下ろし、脱いだ制服のコートを傍らのソファに投げた。
「おんどるまる、」
「来い」
��あっ」
アナの腕を引き寝室に連れて行き、そのまま後ろ手に扉を閉めた。
「ひ、とめないと…」
「消したよ」
その通り、アナを引っ張りながら鍋の下の火に冷気魔法をひと投げしておいた。
「俺が気付かないとでも思ったか?」
「?なに…」
「ベルナールと寝たな?」
アナの黄金の瞳が一瞬驚きに大きく開き、すぐに伏せられる。
「なんで…」
「どうしてわかると思う?」
ベッドの近くに追い詰めたアナの肩を押し、そのままベッドに押し倒す。
「あっ、」
「あいつはご丁寧に跡を残さなかったと思ってたか?」
「…」
肩に置いた手で華奢な鎖骨から喉にかけてをなぞる。奴の。ベルナールの跡が俺にはくっきりと見えるそこを。
「お前の今の体はなアナ」
彼女の怯えたような上目遣いに、胸の奥で黒い欲が首をもたげる。
「体中びっしりとあいつのマジカの跡がついてるんだよ」
「えっ」
息を飲むアナの肩のブラウスをずり下げながら続けた。
「お前はマジカの感応力が低いから自分の体の奴の気配に気がつけないんだ」
手に取るようにわかったが、当然ベルナールはそれを見越してこの跡を残したのだろう。目に見える跡がなく俺に悟られないだろうとアナを安心させておいて、わざわざ俺の為に、俺だけにわかる印を残した。
「黙っていれば気付かれずに隠し通せると思ったか?」
「ちが…」
「そうだろ?」
わかっている。大方ベルナールに丸め込まれてこうなったんだろう。だがそれでも。それでもアナが俺以外の、それもあいつに抱かれたことが許せなかった。矛先を向ける相手を間違えているのはわかる。そう、ベルナールを殴りに行くべきだ。
ああそうだ俺はこう思っている。
アナをベルナールにかすめ取られたことが許せない。だから彼女に元通り、お前は俺のものだとわからせなければと。
頭の中は妙に冷えており、冷静な自分がおいおい何をしてると忠告していた。責めるべきはアナじゃない、ベルナールのほうだろうと。まず先に奴の胸ぐらを掴んで壁に叩きつけるべきだと。
が、それとは裏腹に俺の手はするすると胸から下に下り彼女の弾力のある太腿から尻にかけてを揉みしだく。押さえつけられたアナが軽く身じろぎした。
「こうやって俺が問い質さなかったら黙っているつもりだったというわけだな」
「そんな、」
「そうさ。そうすればお前とベルナールの二人だけの秘密だったのにな?」「おんどるまる…」
泣きそうな顔で見上げるアナはもうとっくに上半身をはだけられ、小ぶりな胸を露わにしている。そこを雑に揉みしだきながら我ながら嫌らしい嫌味が口をついた。
「言えよ。あいつと何回したのか」
「おんどるまる」
「俺が家を開けている間毎日か?このベッドで」
「べるのうちで…」
「ほう」
アナの泣きそうな顔とは裏腹に硬く立ち上がった乳首をきつくつねる。
「いたっ」
「行ったわけか。わざわざあいつの家に」
ぐにぐにと乱暴にこねくり回してやるとアナは下唇を噛みながらも太腿を擦り合わせて腰をくねらせる。表情とは裏腹に体は正直、というやつか。
「わざわざあいつの家に出向いて楽しんだと」
「ちがうよ…」
「何が違う?」
「ちがくて…」
健気にも俺を押し返そうとしてくるアナの両手首を掴み頭上に押し付ける。
「あっ」
「うるさいぞ」
それから拘束魔術でそこを固定した。アナはじたばたと体を捩らせる。
「なにこれ、やだ」
「お前が悪い」
ああ、もう駄目だ。俺は今、もはやどうしようもなく興奮している。半裸で自由を奪われたアナの姿を見て。彼女を気の済むまで犯し尽くしたいと。そう考えている。
その事実に愕然としているのは今アナの股間を撫で上げている俺ではなく、頭の中のもう一人の冷静な俺、オンドルマールではなく、サルモール司法高官統括としての俺だ。
アナの腰のベルトを外し、ホットパンツを足から引っこ抜く。膝を開かせると彼女特有のあのミルクのような香りがした。その匂いに欲望が刺激される。今組み敷いているこの娘を早く食い散らかしたいと。
下着の上からそこを親指で押してやると、浅ましい程に膨らませているのがわかった。思わず口の端が吊り上がる。
「これで嫌、か」
「んっ…ん、」
目を背けようとするアナの顎を掴んでこちらを向かせた。
「ベルナールはどうだった?」
「…」
「俺と同じ姿形の男に抱かれた感想はどうだ?」
硬く膨らんだ陰核を指先でぐりぐりと押しつぶすようにしてやると、アナの顔が一層切なげに歪む。ベルナールにもこの顔を見せたのかと思うと。一刻も早くこのアナの体中の跡を上書きしたくなった。お前は俺の。俺のものなんだアナ。
下着を脱がせて足を開かせる。先程から弄ってやったとはいえ、そこはまだ準備が足りないという風だ。
が、残念ながら俺はそうじゃない。
今すぐにこの娘を好き放題蹂躙したい。ベルトを外し、硬くなったそれを取り出す。
それを見て、足を広げられたままのアナは逃げるように腰を引いた。
「まって、おんどるまるまだ…」
「嫌だね」
入り口にあてがい、今にも舌舐めずりしそうな気持ちを持て余し深く息を吸った。
それから、一気に貫く。
「いっ…」
アナの顔が苦痛に歪む。だが悲しいことに俺にはまったくの逆効果だ。その表情は一層俺を刺激した。
中を味わうように動いてやるとアナは下唇を噛みきつく目を閉じた。いつもはもっと時間をかけてやる。彼女が自分からねだるようになるくらいまで。が、今日は違う。ろくに慣らさずに挿れられて辛いのだろう。
が、そんな顔も腰を持ち上げてやり上天井をごりごりと擦ってやるとすぐに解けてくる。ここを刺激してやるとアナはすぐに甘えた子犬のような声を出す。今まで何度も抱いてきて充分に知っている。
「んっ…あっ」
「何だ?無理矢理やられてる割にはよさそうだな?」
「ち、ちが…んっんんっあんっ、あ、あう」
「何が違うんだ?ん?」
相変わらずそこを擦りながらたまに腰を入れて最奥を突いてやるとアナの腰が堪らずにくねる。
「おんどるまる…」
「雌犬め」
ぐい、と体を押し付けて子宮口にぐりぐりと先端を押し付ける。今の俺は実に浅ましい顔をしているんだろう。俺の腰付きひとつで思いのまま鳴くこの娘が楽しくて仕方がない。
「あっ…あっ、あっ」
快楽に染まりつつある表情は、だがそれでも普段の俺を見上げてくるあの愛らしい顔じゃない。その黄金の瞳にはたっぷりと涙がたたえられていた。
その顔を見下ろしながら一度彼女の中から自身を引き抜き、背中を押し尻を高く上げさせる。
「んっ…」
そうしてまた貫く。
その細い腰を掴み、入り口近くまで引き抜きまた最奥を突き上げるような動きを何度も何度も繰り返す。シーツに顔を埋めたアナはその度くぐもった悲鳴を上げた。
思う存分それを堪能してから動きを早める。彼女の華奢な体を押しつぶすように体を押し付け、自分の欲を注ぐだけの動きに集中する。
そうして、彼女の中にその欲を吐き出した。俺が出ていったところから白濁液のそれがどろりとこぼれ落ちた。
アナははあはあと息をつきながらベッドに崩折れる。その姿を見ていると、昂ぶった胸の内が急速に冷えていくのがわかった。
ああ、くそ。情けない。
「…う、う…っく…」
アナがしゃくり上げる声がする。
「…すまない」
アナの顔を見ることも出来ず、片手で目を覆って言った。我ながら死ぬ程情けない。あんな風に楽しんでおきながらなんてザマだ。
「…」
のろのろと体を起こしたアナは未だ体に引っかかっていたブラウスを着直す。それから、俺に脱がされた下着とパンツを履く。その間、俺の顔を見ようとはせずに。当然だろう。
ちらりと見た彼女の目は泣き腫らして真っ赤だった。頰には幾筋も涙の跡が道を描いている。…そういえば、後半は殆ど泣きじゃくっていた。俺に突き上げられながらえずくように泣く声が耳に蘇る。
「アナ、」
そちらに体を向けた俺から逃げるようにアナはとん、とベッドから降りた。そうして、こちらを振り返らずにドアを開けて出ていく。彼女がドアを開けた瞬間、シチューのいい匂いが漂ってきた。その匂いを部屋に残してぱたんとドアが閉まる。それから、アナが自分の部屋に戻ったのだろう、またドアを開けて閉める音がした。
その音を聞いた瞬間猛烈な罪悪感が胸を這い上ってきた。大きくため息をつき項垂れる。 あいつの、アナの昔の話を聞いてから、俺は彼女を貪り食った男たちとは違うと思っていたのに。何も違いやしないじゃないか。泣きじゃくるアナを押さえつけて無理矢理に犯した。過去に何度となくされたように。
今の俺はアナにとって昔の客たちと何ら変わりなく見えているだろう。怯えながら見上げてくるあの黄金の瞳を思い出す。それから、やっと向けられるようになった屈託のない笑顔のことも。 もう俺の前であんな顔をしないかもしれないと思うと、周りの空間に押し潰されそうな気持ちになった。
言い訳はできない。
そう確かに俺は楽しんでいた。あのアナの表情に欲情していた。そして、普段から感じていた彼女への嗜虐心を剥き出しにしていた。
居た堪れなかった。あいつ、ベルナールは俺がこうなることも見越していたんだろう。あいつはそういう奴だ。
とりあえず俺が今やるべき最優先事項はあいつを殴ることで間違いない。アナには今は何をどう言い訳も出来ない。後で、彼女がまた俺のほうを向いてくれた時に話をしよう。
ベッドに張り付けられたように重苦しい体をなんとか引き剥がし、乱れたローブを直す。そうしてダイニングに置きっ放しだった制服のコートを羽織り再び街に出た。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「おお、どうしたよ?久々にペットを可愛がってやんなくていいのか?」
俺の顔を見たベルナールは開口一番いつもの皮肉たっぷりの表情でこう言った。
「あいにく手垢がついていてな。その犯人探しが先だ」
リビングのソファに制服のローブのまま寝転がっていたベルナールはふん、と鼻で笑い煙草をつけ、
「ほお」
器用に輪の形の煙を吐き出しながら続ける。
「どんな手垢?」
「ふざけた茶番に付き合わせるな。女を抱きながらあんな小細工とは恐れ入るな、ベルナール」
くつくつと喉の奥で笑いながらベルナールが身を起こした。
「そうだろ?」
そうして悠々と足を組み下から俺を睨め付ける。
「だが感謝して欲しいね。目に見える跡はつけるな、なんてあいつが健気なお願いをしてきやがるもんだからそれは叶えてやった。その代わりにああしたのさ」
「俺に見せつける為にか」
「その通り」
口の端を上げて笑うベルナールのその胸ぐらを掴んで立ち上がらせた。
「あぶね」
奴が持っていた煙草の先端がこぼれ落ちる。
「あぶねえな。落ち着けよお兄様」
「アナに手を出すなと言ったよな?」
「そうだな」
だがそれでもベルナールはその笑みを崩さない。
「でも今更だろ?今までだってあんたの女を俺が寝取ったことなんて何度となくあっただろうが」
「…」
「あの娘は特別か?」
「黙れ」
「あの伝説のドラゴンボーンを手中に収めて好きに出来る優越感てやつか」「黙れ!」
胸元を掴んだまま近くの壁にベルナールを叩きつける。
「いてっ…」
奴の手からこぼれ落ちた煙草を踏みにじり火を消した。
「痛えな」
「それ以上余計な口を聞くと痣が増えるぞ」
「は、勘違いすんなよ」
「何がだ」
「その前に手放せよ」
渋々離してやるとベルナールは足元の吸殻を拾い灰皿に押し入れる。
「ったく、人んち来て部屋汚すなよな」
「いいから早く話せ。何が言いたい」
先程まで押さえつけられていた壁にもたれながら、ベルナールは新しい煙草に火をつけた。
「お前は俺が無理矢理あの子とヤった風に言うがな。あの子からここに、俺の部屋に来たんだぜ?」
「何?」
「だからお前の家で無理矢理にじゃなくて、ここに来たアナちゃんをここで、具体的には向こうのベッドでおいしく頂いたんだっつうの」
「嘘つけ」
「嘘じゃねえよ」
くいくいと親指で寝室のほうを指すベルナールの横の壁を拳で叩く。
「アナがそんなことをするはずがない、か?どうだかな?」
脳裏にアナの顔が浮かんだ。
出張に出る前、俺に存分に甘えてきた姿を。確かに先程アナ本人の口からこいつの家にやってきたことは聞いた。が、大方こいつに無理に連れて来られたんだろうと、そう思っていた。
「あんたがいなくて寂しかったんじゃねえか?俺の上できゃんきゃん鳴いて腰振ってたよ。盛りのついた雌犬みてえにな」
「…」
先程まで目の前のこいつを殴り飛ばしたい衝動で熱されていた胸の内が急に冷えていくのがわかった。
本当に?本当にお前からこいつに、と頭の中のアナに問いただす。
しんとした室内で、ベルナールの吸う煙草の先端のじりじりという音がやけに耳についた。
壁から手を離し視線を落とす俺にベルナールはふう、と煙を吐きかける。
「しかし羨ましいね」
「?」
「あの子だよ。アナちゃん。ガキのくせにとんでもねえ名器だ」
うわの空になりかけていた心がじわじわと戻ってくる。
「最高だったよ」
「ベル」
「また貸してくれ。ああそうだ、今度三人でやろうぜ」
「ベルナール」
チリッ、と指先に青���電撃が走った。
「薬使ってさ、交代で…」
その瞬間。
俺の全身から電撃が迸り、半ば自動的に構えた右手に集中した。
それを見たベルナールは目を見開き、咥えていた煙草を落とす。
ベルナールの胸を目掛けて振り下ろされた右手が触れる寸前、そこを中心に展開されたマジカの盾が俺の稲妻を弾いた。裂くような音が静まり返っていた部屋に轟き渡る。
「ぐっ…」
俺と同じエメラルドグリーンの目が感情に燃えて俺に向けられる。
「てめえ‼︎殺す気か‼︎」
ベルナールが怒鳴った。
寸前で致命傷は避けられたようだが、ベルナールが盾を出した右掌からはしゅうしゅうと煙が立ち上り革の焼ける嫌な匂いがしている。
「ああ」
その掌を押さえて背を丸めているベルナールの胸ぐらを掴んで起こし、中指関節を突き出すように硬く握った拳で思い切り左頬を殴った。それと同時に掴まれていた手を離されベルナールは盛大にリビングの床に倒れ込む。
「…ってえ…」
唇を切ったらしく、拭ったところから擦れた血が奴の口元を汚していた。
「その程度で済んでよかったと思え」
ベルナールを見下ろし、瞬間爆発的に高まったマジカを抑えながら言う。
「あやうく殺すところだった」
「ふん、残念だったな。とどめを刺せなくてよ」
「おい‼︎すごい音がしたぞ⁉︎大丈夫か⁉︎」
睨み合う俺たちの間に不意に第三者の怒鳴り声が割って入る。
声のする玄関を開けると衛兵の後ろに数人の人だかりができていた。どうやら先程の騒ぎが家の外にまで丸聞こえだったらしい。
「あんたたちか。…兄弟喧嘩か?」
衛兵は後ろで床に座り込んでいるベルナールを覗き込んで半ば呆れたような声を出した。
「殺人未遂だ」
「黙れ。申し訳ない、ただの喧嘩だ。問題ない」
後ろで余計なことを言うベルナールを黙らせ、衛兵に頷く。
「そうか?あんたらエルフはやたらと派手な魔法を使うからな。どうしてもというなら街の外で頼むよ」
「ああ、騒がせてすまない。もう大丈夫だ。それでは」
衛兵を半ば外に押し出すようにしてまたドアを閉める。
「まったく俺んちで騒ぎを起こすな」
切れた唇に回復魔法の緑の光を浴びせながらベルナールが肩をすくめた。
「次やったらその程度で済まさんぞ。覚えておくんだな」
「は、あんたこそあのワンちゃんに愛想尽かされねえように気をつけな。俺に掻っ攫われねえようにな」
ベルナールの捨て台詞に鼻を鳴らし外に出ると、未だ家の前にいた数人の野次馬たちが一斉に俺を見た。
その視線を避けるように我が家へ戻る。
家への石段を登ろうとしたところで、玄関のドアを開けてこちらを見ていたアナと目が合った。おそらく先程の騒動を聞きつけて様子を伺っていたのだろう。だがその瞬間、ドアはばたんと音を立てて閉められる。
はあ、と思わずため息が漏れた。
家に戻ると、相変わらずリビングは数時間前俺が帰ってきた時のままになっていた。アナの部屋のドアはきっちりと閉められ、中からは何の物音もしない。
とりあえず腹が減った。昼から何も食べていないし今の諸々で多大なエネルギーを持っていかれた。
俺は再び息を吐き、アナが用意してくれていたシチューを温め直す為鍋に火をつけた。
0 notes
Text
父の死 連載第20回 4年と40年の歳月
屏風のような山々に囲まれた小さな村は、どこにいても風鈴の音が聞こえた。今月初旬に、佐賀県の磁器の里・伊万里の大川内山を訪れた。夏の風物詩「風鈴まつり」で、各窯の軒先に伊万里焼のそれがぶらさがっている。その涼やかな音色は、猛暑で萎えた体と心に潤いをもたらした。
食器、調理器具、装飾品・・・いろんな伊万里焼を目に焼きつけてきた。現代の伊万里焼は、何百年にわたって伝えられてきた技に、斬新な意匠が加わり、新しい命が吹き込まれている。観光客もまばらな静かな里で、色も形もさまざまな器を眺めながら、ここは桃源郷だなと思った。
伊万里は磁器の里に加え、梨の産地でもあった。道端の直売所で2キロほど買い求め、実家の母親に送った。翌日、母親から、梨が届いたこと、父親の命日が近づいてきたので仏壇に供えるとの連絡が入った。
大阪に帰り、ふと梨の送り状を見ると、届け先に私は父親の名前を書いていることに気付いた。自分でも驚いた。無意識に、すでにこの世にいない人物の名を記していたのだ。
連絡をくれた母親はそのことには触れなかったが、仏壇に供えるという言葉は、父親の名前を見たからなのか、とあとで思った。
父の死から丸4年が過ぎた。母親はいまだに父親が近所をうろうろしているような気がすると言う。それを聞くたびに私は、いつまで家の周辺を徘徊してんねん、と思う。
母親は父親が死んだ実感はないと言いながら、月命日には必ず墓に花を供え、住職のお参りを待つ。そしていないはずの父親に話しかける。願望と現実の双方を生きているのだ。
実家に帰ったとき、就寝前の母親が「お父ちゃん!」と”まぶたの夫”に声をかけているのを何度も聞いた。毎晩呼びかけているのだろう。ちょっと怖かった。
この4年のあいだに、母親と同年輩の何人かが鬼籍に入った。そのたびに母親は「お父ちゃんより〇歳若い」「〇級(学年)上や」と教えてくれる。闘病の末に亡くなくなったケースでは、「(遺族は死を)覚悟しとったやろうから、まだええわなあ」と嫉妬まじりに言う。大動脈瘤破裂で急死した父親は、あっけなく逝った。かける言葉が永遠に失われたので心残りなのだろう。
もっとも、長い闘病の末に旅立ったとしても、優しい言葉をかけていたかどうかは疑わしい。少しのしくじりでも「お父ちゃん、何しとんのよー!」と口うるさかったからである。
母方の祖母は晩年に痴呆症にかかっていたが、母親はおかしなことを言う祖母に、いちいち「それ、違うやろ!」「なんぼ言うたらわかんのん!」と大きな声で注意していた。中学生だった私は、それを聞くのが嫌で、 相手を否定しない 痴呆老人との付き合い方を記した本をコピーして渡したりしたが、効果はなかった。
長い闘病生活を続けていれば、父親は母親の小言を聞き続けなければならない。やはり父親は、数十秒でこの世を立ち去ることができてよかったのではないか、と私は思うのだ。
少年から青年にかけての私は、詮無きことを言う母親との折り合いが悪かった。口うるさくあれこれ言われるのが、私には鬱陶しかった。今になってそれは、母親の愛情であったかもしれないと思うのだが、反抗期の10代には”おせっかい”でしかなかった。
父親が亡くなり、主だった法事を終えると、母親や兄妹、親戚とも会う機会が減った。それでも独り暮らしの母親とだけは、2~3日に1回は、夕方から夜にかけて携帯電話に連絡をとる。
「こんばんわー」
長い呼び出し音に続き、いつも他人行儀なあいさつが返ってくる。「こんばんわ」と私も返す。そのあとは決まって、その日の天候が話題になる。「きょうは暑かったな~」「雨が降らんな~」「そっちはどうや?」。兵庫(母親)と大阪(私)の違いを確認する。播磨灘と大阪湾では、微妙に空模様が違うのだ。
ひとしきり天候の話題をしたあと、その日の出来事や近況報告がある。どこで誰々と会った。誰々が来てくれた。どんな会話をした。近所の知り合いの文鳥・ピーちゃんが弱ってきた。誰々が亡くなって、通夜に行って来た。朝からお寺の草むしりに行って汗を流した。秋祭りでおでんを〇人前つくった。余ったから持って帰ってきて食べた。畑で春菊がいっぱい獲れたので要るか? すぐに萎えるので要らん? そうか。大根送ったろか? 大阪でも安く買えるから要らんか。孫から電話があって嬉しかった。塾通いで忙しいらしい。勉強がようできるねんて。弱ってたピーちゃんが死んだ・・・。
地方紙にも載らない出来事を、元地方紙記者が聞く。最後はきまって「〇〇ちゃん(妻)によろしくな、モモ(飼い犬)にもよろしくな」と言って電話を切る。妻はまだしも、飼い犬によろしくと言われても、なんと伝えたらいいかわからない。後者は無視である。
母親の携帯電話をメール送信ができるタイプに買い換えたことは、以前にこのブログに書いた(2015年9月)。購入後にメールの送受信の仕方について、私が集中講義をおこなった。双方の努力の甲斐あって、今では1日3回はメール交換している。・・・というのはまったくの嘘で、この2年間で、母親からメールを受け取ったのは、たった1度だけである。「今は連絡できないので後でします」といった内容で、「へえ、ちゃんと送れてるやん」と感心したが、すぐあとに、何かの拍子で例文を誤って送信してきただけだったことがわかり、がっかりした。
けっきょく、80歳を超えた母親には、メールなど必要ないのだ。太い指で文字を入力する時間があったら、電話をかけたほうが早いということなのだろう。やはり”文字”よりも”声”なのだ。文明の利器を使わないと損、使ったら便利という私の考えは、余計なおせっかいに過ぎなかった。
父親が亡くなったちょうどその日が、私の50歳の誕生日だったことはすでに書いた。きりのいい”50”で、このブログを始めたことも。
あれから4度、季節はめぐり、私は54歳になった。その半分の年齢のころは、54歳と言えば、まるで別世界の人間だった。会社員だと順調にいけば、管理職に就く年齢である。周囲に慕われていればベテラン、そうでなければロートルと呼ばれているはずだ。加齢臭も半端ではない。ああ、オレもとうとうこんな年齢になったんか��とつくづく思う。
地方紙記者時代に、父親が60歳で定年を向かえ、自宅で小宴が開かれたことは当ブログでも触れた(2015年11月「酒よ」)。あと6年で、あのときの父親の年齢になると考えると、感慨深いものがある。
定年後の父親は、畑仕事をしたり、地元の自治会の役員をしたりして20年余りを過ごした。身内が言うのもナニだが、父親は周囲に敵をつくることなく、むしろ慕われ、頼りにされた。悪口を言う人はいない。敵が多い私とは、大違いである。
父親は長らく工場の脱臭装置の建設に携わり、現場監督を務めていた。叩き上げのエンジニアである。家の中で青焼きの設計図を広げ、仕事の準備・確認をしていた姿をしばしば目にしたことがある。
国内外に現場があったため、出張が多かった。私が中学生のとき、3者面談で珍しく学校に来てくれたことがあった。何らかの事情で、母親が来れなかったのだろう。
職場を抜け出してきたらしい父親は、放課後の午後4時ごろに自転車に乗って学校にやってきた。油が染み付いた灰色の作業服を着用し、安全靴を履いていた。お、かっこええな、と私は思った。働く父親の姿がそこにあった。私も大人になったら油にまみれ、身を粉にして働きたいものだと夢想した。
あれから40年ーー。私はエンジニアではなく、しがない物書きになった。油にもまみれず、身を粉にもせず、のほほんと生きている。(2017・8・14)
0 notes
Text
おとまりプロフィール
音尾光久(おとおみつひさ)オットー
31歳、179cm
貿易商社勤務
特技はトロンボーン(中学・高校と吹奏楽部だった)
早起き(よくマリーに「おじいさんか」って言われるくらい早い)
そろばん(お母さんがそろばん塾をやってた関係)
チェス(最初はインテリアとして買ったけどちょっとやってみたら面白かった)
趣味は裁縫(ミシン。親の代わりに弟妹のものを繕ってあげているうちに上手くなった)
渓流釣り(マイナスイオンを浴びに行くついでに晩ごはんのおかずもゲットできるから一石二鳥だよ)
柴犬グッズ集め(柴犬可愛いよね。あの尻尾が特に)
スポーツ観戦(頑張っている人たちを応援するのが好き。現地でもTVでも良い)
好きなものは石焼ビビンバ、南国のフルーツ(マンゴーとかパイナップルとか)、革製品(鞄とか靴とか)、綺麗な貝殻(海辺に行くとつい集めちゃう)
御燈商事で輸送機(船舶)部門の営業をしている。
二年前、営業中に事故に遭い、左目の視力のほとんどを失っている(明暗はかろうじて分かるくらい)。
※頭を強打したのと、割れたフロントガラスが目に刺さり角膜が傷ついたため。
右目は普通に見える。普段かけている眼鏡は左右の視力差を少しでも均等にするためのもの。
御燈商事には珍しい文化系。運動はそこまで得意じゃない。ただし根性はあるのでハードな外回りもこなせる。さすがに暑い夏場はちょっとへばってるけど。
でも日に焼けると真っ赤になってしまうので夏場でも長袖ワイシャツ。
家族構成は父、母、妹、妹、弟。四人兄弟の長男。なので小さい子供の相手には慣れてる。
名前の由来は『久方の光のどけき春の日に静心なく花の散るらむ』という紀友則の和歌。
ちなみに兄弟の名前も「春日(はるひ)」「静花(しずか)」「友紀(ゆうき)」と同じ和歌から取られている(弟は作者の名前からだけど)。
実は花鶏匡俊の従兄弟(花鶏の父親と音尾の母親が兄弟)。
ただし音尾の母は高校卒業後すぐに恋仲だった教諭と結婚するために駆け落ちをしているため、花鶏との面識はない。
従兄弟の存在は母から聞いてぼんやり知っている程度。花鶏も音尾家のことは知らない。
普段は物腰柔らかな好青年だが、怒らせると怖い。口調もかなり変わる。インテリヤンキー。
ただし怒りの沸点はかなり高いので、ほとんどの人はそのことを知らない。
彼が今まで本気でキレたのは人生で三回。二番目の妹をいじめていた男子生徒相手と、痴漢の現行犯で捕まえたのに往生際悪く言い逃れようとしたおっさんにと、繁南のことを噂して笑っていた同僚へ。
怒ると相手を壁際に追いつめてスラックスのポケットに両手を入れて後ろの壁をガッと蹴るくらいはやりそう(偏見)。
万里崎のことは事故前から好ましく思っていたが、事故を機にお互いすれ違ってしまい、淋しく思いながらずっと声をかけられずにいた。
音尾は音尾で「自分を庇って万里崎が大怪我をした」とずっと気にしていた。
自分だけあの日から解放されるのはフェアじゃない、と手術を受ければ視力が回復することを知りながらも、頑なに手術を受けずにいた。
が、万里崎に説得され、角膜移植手術を受ける。
手術をきっかけに少しずつ関係を修復し、恋人になるまでこぎつけたことをとても嬉しく思っている。
万里崎のことは大好きで、出来る限り甘やかしたい。でも恋人は自分のことは自分でやろうと無理をする(それが自分のためだと音尾は気づいていない)のでまだまだすれ違い気味。
意見が食い違うたびに言葉を重ねて分かり合う努力を欠かさないので、少しずつ相違は解消されていく(はず)。
多分わりとドS。
好きな人のいろんな顔を見たい。だから尿道ブジーとか買っちゃう。変態()
でもマリーが気持ち良くなることしかしないと心に決めている。
ただし過ぎた快楽は苦痛でしかないことに関しては気が回ってない。やっぱりドS。
万里崎知草(までさきちぐさ)27 マリー
27歳、175cm
貿易商社勤務
特技は日本の古い遊び(コマ回し、百人一首、けん玉など。特に得意なのはベーゴマ)
山菜の選別(実家の裏は山)
ボイスパーカッション(高校生の時に友達とハ○ネプに出た経験あり)
ワイシャツのアイロンかけ(中学生の頃から自分のは自分でやってた)
趣味はキックボクシング(退勤後の習い事&ストレス発散)
三味線(青森出身の母親の影響。最近は弾いてない)
油絵(独学。耳が悪くなってから三味線の代わりに始めた)
ウィンドゥショッピング(ハンナにつぐ衣装持ち。でもハンナとは違いなるべく低コストで済ます)
好きなものは大河ドラマ(真田丸むっちゃおもろかった!)、餃子、蜜柑(毎年冬は手のひらが黄色くなる)、猛獣(豹とかライオンとか。理由は格好いいから)
船舶営業部門で事務作業を行っている営業職。
元は営業で、音尾とペアを組んでいたが、二年前に交通事故に遭い受傷。一週間生死の境をさまよい、なんとか一命は取り留めたが聴力障害が残った。
※後遺障害等級7級3号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になる。
普段は残っている左耳の聴力を補聴器で補い、聞き取れない部分に関しては読唇と筆談で補っている。手話はまだ勉強中。
明るく朗らかなムードメーカーで、イベント大好き。船舶営業部門内でなにかやる時は大体この人が発起人。ハロウィンとか。
耳のことで一時期は腫れ物に触るような扱いを受けていたが、本人の元々の明朗さもあり、今ではほとんどの人間と問題なく接している。
ただ、本人は多少気にしている部分もあるようで、以前と比べると飲み会などに出かける頻度は減った。
※人ごみなど賑やかなところへ行くと話が聞き取りづらい&危険察知(車のクラクションなど)が遅れるので。
関西出身。実家は山奥の集落の寺。お経唱えられるよ。
耳が聞こえづらくなってからは一度も地元に帰っていない。
理由は、幼いころから見知っていた人たちの声が、前と同じように聞こえないことを思い知らされるのが怖いから。
そして、幼馴染たちに憐れまれるのが嫌だから(そんな人たちではないと知っていても)。
いつかは帰らなければ、と思っている。けれど踏ん切りがつかない。
名前の由来は『かくとだにえやはいぶきのさしも草さしも知らじな燃ゆる思ひを』という和歌から。
……というのは表向きの理由で、実際は名付け親の祖父が大の牡丹餅(おはぎ)好きだったため。おはぎ=萩=秋知草=知草。
「え、ちょい待ち、俺の名前おはぎから来てるん?」
ちなみにお兄さんは天香(あまか)さん。※お坊さんとしての名前は「てんきょう」さん。
これも表向きは『春過ぎて夏来にけらし白妙の衣干すてふ天の香具山』が由来。
だけど本当は『牡丹餅=牡丹=天香国色=天香』
「うちのじいさんどんだけ牡丹餅好きやったん?」
実家が和式だったため、高校生に進学するまで一度も洋式便器を使ったことがなかった。
ちなみに下宿のトイレは和式だったし、高校の校舎は新し目だったけど旧校舎側に和式便所があったのでなんとかなった。
今でも和式しか使えない。外出先では結構困る。なので知らない場所に行くのは渋る。和式便器があると分かっているなら行く。
音尾に対しては淡い恋心を抱いていたが、事故をきっかけに打ち明ける機会を逸し、以来ずっとぎこちない関係が続いていた。
相手車両の飛び出しが原因の事故だが、万里崎は「自分の不注意が原因だ」とずっと己を責め続けていた。
不注意で先輩の世界の一部分を奪った自分が、どの口で「あなたが好きです」などと言えるのだ、と。
手術をすれば音尾の視力が回復できると知り、手術を受けてくれと懇願したのは、音尾への贖罪もあるが、なにより自分を罪の意識から解き放つためには『何もなかった頃』に戻るしかないと思っていたから。
『先輩の世界を取り戻すこと』が罪悪感で押しつぶされそうになっていた万里崎の悲願だった。
「自分勝手でしょう、俺。先輩のためと言いながら、結局は自分が救われたいだけなんですよ」って寂しそうに笑うから抱き締めるしかない。
家族構成は父、母、兄。家族関係は良好。兄のことは「兄ちゃん」と呼んでいる。
でも最近ちょっと恥ずかしくなってきたので「兄貴」と呼んでみたら「今更どうしたんや、知草」と鼻で笑われた。
聴力障害の原因は聴神経の負傷だが、三半規管や耳小骨あたりもダメージを受けており、少しの刺激ですぐ気持ち悪くなる。
なので熱が出たりしたらまず歩けないし吐き気がすごい。ひどい船酔いみたいな状態になる。
でもなるべく他人の手は借りたくない。なのでいつもオットーとバトルになる。そして負ける。
オットーと思いが通じ合った後も「本当に自分でいいのか」「光久先輩にはも��と似合いの、五体満足のひとがいるんじゃないか」という不安で一杯。大好きだからこそ怖い。
その不安を悟られないように必要以上に明るく振舞ってしまう部分もある。優しくされると胸が痛くて、無性に泣きたくなる。泣かないけど。
自分が相手の重荷になっていないかをいつも気にしている。だからこそオットーの世話にならずに、出来る限り自分のことは自分でやりたい。
小さな頃から扁桃腺が弱く、わりとよく熱を出す。無茶は厳禁。
いつかはまた営業に戻りたいなぁと考えている。
0 notes
Text
ゼーユングフラウの戯言Ⅲ
その日は雨が降っていた。在り来たりな天気の一つである。
空から注ぐ猛攻を受けて、木陰で雨宿りをする青年は(花束が濡れるな)ということを考えていた。
文字通り彼の腕には、溢れんばかりの花が抱えられている。
その日は雨が降っていた。朝から変わらない、相変わらずの天気だった。
予定を立てていたわけではない。ただ、たまたま今日が雨で、たまたま休日で、たまたま早起きをして……つまり気分だった。
薄暗い蒼い空の下を歩く。
何の変哲もない傘に当たる水の音が間近に聞こえる。馬車が時たま通るたび、水溜りに警戒をして……また足を進める。その繰り返し。
雨は止みそうにない。今朝目を通した新聞にも、先日見かけた天気予報でも、今日は一日中雨だったはずだ。期待するだけ無駄なようだ。そもそも期待など微塵もしていないのだから、問題はない。
「すみません」
「あっ、いらっしゃいませ」
客と談笑していた店員に声を掛ける。嫌そうな顔もせず、彼女は営業スマイルを彼に向けた。
差していた傘を店先で畳めば、バシャバシャと足元へ遠慮なしに水が落ちる。
「あの、花束を適当に繕っていただけませんか」
「はい、構いませんよ。どのような花束かご希望はありますか?」
「あ……」
思わず青年は口ごもった。あまりこのようなことは得意でないらしい。花束を適当に、と行き成り声を掛ける程度なのだから当然だ。それを店員も察したのか、さりげなく助け船を出す。
「どなたかに捧げるものですか?」
「え」
キョトン。青年は暖色の目をパチクリとさせる。
彼の瞳は、ここ一帯を行き交うどの人々にもない、はちみつのような甘い色をしていた。
まさか真っ先にそのようなことを訊かれるとは思っていなかったのか、それとも図星だったのか……少なくとも、彼が動揺する理由がそこにはあったようだ。
どうやらこの青年、元々あまり口数が多い方ではないらしく、相変わらず笑顔の店員を見て思わず、すっ、と視線を伏せてしまった。
そして、彼は思い出す。
『それ』
『……なんだ』
目を伏せた途端に、彼は低い声音で短く言った。
それ、という指示語だけでは分からない。それも、目を向けていなかった青年は特に。
彼が渋々視線を上げると、眼前の少年はジッと自分を見つめていた。
『あんたは元々あんまり喋らないじゃないか。それに加えて目まで逸らされると、不安になる』
『しょうがないだろう。くせなんだ』
また目線を下げそうになって、留まった。そういえば、これをたった今指摘されたばかりではないかと。
結果、訝しげに視線を返すだけになった。
『目を見られることには慣れないんだ。それに僕は、自己表現があまり得意でない』
『陰気だよね、相変わらず』
『余計なお世話だ』
流石にそこまで言われると気分も害す。ムッとして少年を睨むと、微笑まれた。
思わぬ反応に、え、とキツネにつままれる。
『そうやってスウェイズが表情を変えてくれると、俺は安心するよ。折角綺麗な目をしているのに、向けてくれないなんて勿体無い』
『……君といると疲れる、ラファエル』
『あはは。そろそろ慣れたでしょう』
『開き直るな』
青年――スウェイズが指摘すると、また少年は笑ったのだった。
その笑顔と言葉があまりにむず痒く心を焦がしてくるものだから、また、スウェイズは思わず視線を外す。
――心臓が、どきどきと煩かった。
「お客様?」
「あの人に、」
ポツリ、と彼の唇から言葉が零れる。硝子越しの雨音に邪魔されることなく発せられた。
「慕う人に渡したい。それで構わないか……?」
「まぁ! はい、喜んで!」
女性というものは、いつの世も色恋が好物なのか。
スウェイズの言葉を聞いた途端、彼女はさかさかと動き始めた。
――近くの椅子に腰を掛けて、出来上がりを待つこと数十分。雨は止まない。
「お待たせしました」
「有り難う」
彼女が抱えていたのは、薔薇とかすみ草の花束だった。受け取ると、ガサガサと紙の刷れる音がする。
潰さないように注意を払って、スウェイズは花束を抱えた。
(……情熱的)
香りと色合いで存在を主張する荷物を一瞥して、そのような感想も抱いた。
「これ」
「えっ」
ポケットから適当に数枚の紙幣を差し出す。テーブルの上に置くと、彼女は妙に焦った。両手を横に振って、こんなにいらないと。
「いいんだ。どうせ使い道などあまりないんだ。感謝の気持ちだから」
ぐい、と半ば強制的に押し付ける。
そしてスウェイズは表の傘立てに突っ込んでいた持参物を取って、再び雨の中を歩きだした。
ただただ歩く。雨の中を歩く。ぼう、とあくる日の出来事を思い出してしまうのは仕方がないこと。
向う場所が、向かう場所だからだろうか。それは定かでない。
記憶の中の彼は言った。最近はどうしてるんだ、と。
どこかの野外カフェテラス。人気はまばら。湯気が微かに上るコーヒーと、洒落たティーセットが向かい側に置かれてる。
スウェイズの前に座っているのはラファエルだった。
「辺鄙な場所で保安活動。あまり物騒なことはないが、それなりに忙しない一日を過ごしてるよ」
「そうか」
頷いて、暖かなコーヒーを口に運ぶ。するとラファエルが「自分から聞いといて、それだけ?」と微苦笑を浮かべた。
う、とスウェイズが若干咽る。
「そ、そうか……」
「お、頑張る?」
ニヤニヤ。ラファエルが楽しそうにスウェイズを眺める。
何か言おう、何か言おうと彼は奮闘しているが……中々声は出てこない。プルプルと小さく震えていた。
「不便なことは、ない、か」
「ん? あぁ……」
やっと出てきた言葉に、ラエルの顔から笑みが引く。右手を左肩に沿えて、撫でた。
そこには本来あるはずの、腕がない。
「最初は慣れなかったけど、今は順応してるよ」
「そうか……」
先ほどと同じ返答。思わずラファエルはまた笑いそうになったが、堪えた。
「あんたこそどう? アドルフ兄さんとはうまくいってる? リンは変なことしてない?」
「…………」
「あれ」
シーン。
ラファエルの言葉にあからさまな沈黙を挟み、スウェイズはもう一度コーヒーを咽喉に流し込む。マグカップをテーブルに置いて、一言。
「アルフは先日、貴族屋敷の番犬と乱闘」
「おっと」
「リンは護衛で某研究所に赴いた際、変な物を食べたのか食中毒」
「……相変わらずだな」
再び苦笑いを浮かべるラファエル。迷惑そうにスウェイズの眉間にはシワが寄っていた。
次いで感情を露わにするかのように「はあ」とため息を吐く。
「番犬って、人間ならまだしも本当の犬だぞ。身分を考えろ……。リンは大方あの性格だ、勧められて断れなかったんだろうが……」
「だろうな。兄さんたちらしいよ」
「疲れる」
「苦労かけるな」
そう言って、ラファエルは紅茶を飲んだ。香りの強い紅茶だ。
チラリと彼の顔を見て、スウェイズは残りの質問に対する答えを続ける。
「上手くはやってるつもり」
「……そっか」
心底安堵でもしたのか、ラファエルは柔らかい笑みを返した。微かに肩の力が抜けたように見える。どうやらそれが一番気がかりだったようだ。
和やかな空気が流れるかと思いきや、「でも」とスウェイズがそれを遠ざける。
「僕は、君に居て欲しい」
「…………」
無言。
沈黙が続いて、それを破いたのはスウェイズ。
「戻ってこないのか」
「……ああ」
一言だけ、ラファエルは答えた。
先刻嫌と言うほど「そうか」と返していたスウェイズであるが、今回はそういかない。
食って掛かるように、溜め込んでいた思いを小出しにしてラファエルの説得に徹する。
「君だけの実力があれば、片腕のブランクなどあってないようなものだろう」
カップに口を付けて、彼の言葉をラファエルは黙って聞いていた。紅茶の水面に視線を落とし、落ち着いた様子で口を開く。
「俺が――"隻腕の仲間"という存在があんたたちの中にいるというだけで、きっと兄さんもスウェイズも無意識に俺を庇おうとする。そんなハンデを最初から負う必要はない。命を落とすぞ」
ジッとラファエルの碧眼がスウェイズを見た。片目の色が違う。
彼は幼少時代、右目に鉱石病という奇病なるものを患った。
書いて字の如く、なんと眼球が内側から物質・鉱石へと変化していくものである。奇病というだけあって未だ原因や治療法などが見つかっておらず、近年感染者は増えて行く一方。症状としては段々と視力が低下し、やがて失明する。
ラファエルの場合は他に類を見ないパターンで、なんと、鉱石病によって眼球が完全に侵されることなく病魔は消え失せた。
それでも彼の目は既に半分近く鉱石化をしており、結果として、定期健診を受けるだけに留まっている。
今の彼の右目に居座っているのは、本来の碧眼ではなく偽りの青い眼だ。
ただでさえ彼は右目に視力がなかったというのに、今度はとうとう、利き手であった左腕まで。
(ひとつくらい、僕に肩代わりさせてくれてもいいじゃないか)
ひとつ、ひとつ。失われていく彼に不安を抱いた。
いずれ彼は、本当に――奪われてしまうのではないのかと。ここから消えて、無くなってしまうのではないのかと。
だからせめて、安心させてほしかった。もっと触れられる距離に、目に見える場所にいてほしかったのだ。
「――当たり前だ」
「?」
ラファエルの言葉を受けても、尚スウェイズは引かない。それどころか力んでいた。
「君を見捨てるはずがない。君は知っているだろう、僕の……僕らの腕を」
「……熟知してるつもりだけど」
そう言って、ラファエルは紅茶を一口。
落ち着いているが故の余裕なのか、それとも逆か。
「君のことは守る。今更命を落とすことに恐れ戦く僕ではない。僕が君の失われた腕の代わりになる。だからもう一度」
「スウェイズ」
もう言わないでくれとばかりに、ラファエルが彼の台詞を遮った。
もしかすると、彼自身にも惑いがあったのかもしれない。
これ以上説得をされれば、傾いてしまいそうになる弱さがそこにはあったのかもしれない。
カチャン、と皿に乗せられたティーカップが鳴る。水面が揺れた。
「スウェイズ。ごめん」
「……」
自然と拳に力が入っていたが、それはスッと抜ける。
沈黙を口にして、視線を落とした。気にならなかった鳥の声がやけに大きく聞こえる。
ボソリと零れた声音はあまりに弱々しい。
「そんなに僕が頼りないのか」
「そうじゃない」
スウェイズが肩を落とすと、ラファエルはゆるゆると首を左右に振る。そして己の左肩に右手をやった。腕の無い左腕を撫でるようなしぐさをして、愛しそうに告げた。
「こんな俺でも、傍にいてほしいんだと言うやつがいるんだよ」
「!」
途端、スウェイズは目を見開いた。段々と冷静になったのか、それとも意味を噛み砕けたのか……瞳に色が戻る。
暫くの沈黙後、そういうことかと呟いた。
まだ残っているコーヒーにうつる彼の目にはどこか、悲しみに似た色が滲んでいる。
――己の醜さに反吐が出る。
膝の上に置かれた手に、再び力がこもった。彼の目にも、また別の感情が混ざる。
彼のことを思うなら、知っているからこそ、喜ばなければならない。
隻腕となってからの彼は、幾度となく自分を卑下する節があった。
元々そのような性格であることも知っている。その彼が、今の自分でも出来ることをやると言っているのに。
あの時の自分は、むしろ――。
「――ニャアァ」
「!」
真横から聞こえた猫の鳴き声に、ハッと我に返った。
相変わらず雨は酷い。
声の聞こえた方に目をやると、ふやけたダンボール箱が置かれていた。だいたい察しはつくが、近寄って箱を覗き込む。
すると、まだ小さな猫が箱の中をウロウロとしていた。クリーム色の毛色に包まれていながら、目元は茶色い。本来は毛が長い品種なのか、濡れ切った体毛は垂れ下がっていた。敷かれたタオルが雨水を吸い込んでグショグショだ。
それを見て、スウェイズは(見るんじゃなかったな)と僅かに後悔する。思わず目を逸らした。
「ニャー、ニャー、ニャアア」
目的地は近い。人気は少ない。このまま放置していては、恐らく――。
「……君、この辺には黒猫ばかりしかいないのに。タヌキみたいな品種なんて、珍しいな」
「フニャ?」
ふ、と、スウェイズは僅かに口元を緩めた。泳がせた視線が真上にいく。
水をはじく傘。少し揺らしてみれば、雨粒がボタボタと落ちてきた。これを失ったとしても、彼が死ぬことはない。だが、目の前の小さな命は別である。
「これで、勘弁してくれるか」
「ニャア……」
コートの内側に花束を入れて、持っていた傘を箱の上に置いた。気休めだ。
折り曲げた膝を伸ばし、猫を一瞥する。尚も変わらず必死に何かを訴えるように鳴いていたが、顔を逸らした。至る所を転々としている自分に、動物を養うことは出来ない。
精々彼に出来るのはこの程度であった。あるいは、
(一思いに殺してやるか、だな)
腰に下げられた得物を見やる。
このような場所には不釣り合いなほどに物騒な代物だ。しかし何故か、持ってないと不安なのだ。
むしろ持っているからこそよからぬことに巻き込まれかねないのだが。
(元来、こんなものは必要ないのだろう)
人を斬るための刃など。
雨に濡れることで、羽織っていたコートの色が段々と暗くなっていく。
流石に今の季節、こんな状況でノロノロとしていては風邪を引く。何より寒い。少し急ごうかと、スウェイズは足を速めた。
住宅街から離れ、丘の上。ポツポツと並んでいる石には人の手が入っている。
――墓地だった。
その中の一つに、スウェイズは近寄って行く。そして足を止めた。
あ、と思わず声が漏れる。ずっと雨から守るように持って来た花束だったが、供えてしまえば濡れてしまうではないか。
それに遅れて気が付いて、スウェイズは息を大きく吐き出す。
「……やはり、僕は媚を売るなんて器用なことは出来ないな」
あの時もそうだったように。今までも、そうだったように。
まだ小さな頃、リンと喧嘩をしたのだと彼が悩んでいたことがあった。
あまりにも泣きそうな顔で相談してくるものだから仲直りの仲介を行った。しかし本心はまったく別のことを考えていた。
君は、僕と喧嘩をしたら今と同じように悩んでくれるのか。泣きそうになってくれるのか。
……このまま仲直りなどしなければいいのに。どうせ放っておいても、君たちは仲が良いのだから和解するだろうに。
そのようなことを考えては、己を嫌悪し表情を隠した。
『この際だからハッキリ言わせてもらう』
『急に改まってどうした?』
我慢ならなかった。幼い頃からずっと彼を守ってきた。
リンと喧嘩したときも味方でいた。武具を片手に敵を掃討する時でさえも、彼の傍から離れることなどなかった。
ずっとそばにいた。
『僕は』
あの時の台詞を、今一度口にする。雨に濡れながら、ゆっくりと花束を差し出した。
「"僕は君が、好きだった"」
――告げると彼は驚いたように目を見開いて、そしてすべてを悟ったようにスウェイズを見つめた。
それは恋ではないんだよ、と言って。
ずっと守ってきていたものを奪われることが嫌になったのか、そうなのか。これは恋情ではなく、ただの独占欲というものか。
いいや、違う。違う。でも彼には。
届きさえもしなかった。
同性なのだから気持ち悪がられるだろうと、距離を置かれてしまうのではと少なからず畏怖はあった。
しかし彼は変わらず接してくれていた。本当に何事もなかったかのように、あれは本当に恋ではないと思っているように。
――それは拒絶されるよりも、断られることよりも、残酷な答えだった。
しかし皮肉にも、それが自分の想いを今一度考え直すきっかけにもなった。
「なぁ、アルフ」
「ん」
爪の手入れをしていたアドルフに声を掛ける。片手間だ。
「僕、多分ラファエルが好きだと思う」
「知ってる」
バチン。爪を切る音。本当に片手間である。しかしスウェイズは特に気にしていない。
最初から、アドルフが真面目に取り合うようことはないだろうと思っていた。
だからこそ爪の手入れをするアドルフに、今声を掛けたのだ。
「そうか……」
スウェイズは頬杖をついて目を瞑る。何かを思惟するように。
「ブラザーコンプレックスふたつも背負って、ラエルも大変ですね。君の場合はブラコンというより、過保護な保護者って感じですが……あ、切りすぎた。サエ、やすり取ってください」
「……そうか」
「おい、やすり」
「そうか」
「話聞けコラ」
「ん」
「っわ、投げんなよ」
手元にあった小さな細長い物体をアドルフに投げつける。
危なげにそれをキャッチしたアドルフは、偶然とはいえやっとスウェイズの方を見た。
話を聞けとは、どっちのことか。既にスウェイズは呆れているのか、それとも慣れているのか――あえて言及することはないが、目は語っている。
それを察したらしいアドルフは、面倒くさそうに本題に便乗したのだった。しかし相変わらず片手間である。
「ラエルは俺らの中では小柄ですし、自分で言うのもアレだが一番上の兄がこんなんなので、実質長男の役割を担ってくれていたわけですしね」
「君はちゃんと、彼らの……僕らの長男だと思うよ。他の誰よりも」
ピタリ。アドルフの手が止まる。僅かに視線をスウェイズに寄越して、また逸らしたのだった。
「……俺は見てるだけだ。それを言うなら、君の方が彼らの面倒を看ていると思いますよ。でも、あんまり保護者やって、反抗期迎えられても知りませんが」
「反抗期か。気を付ける」
適当に相槌を打っておくが、スウェイズはどこか釈然としない。会話がかみ合っていない気がするが、気のせいである。そう、気のせい。
パチン、と爪切りの音とアドルフの結論が耳に入る。
「それは恋ではないさ」
「……あぁ」
それだけ答えて、目を閉じた。
不毛な恋というものか。いいや、恋でないのなら不毛でもないのか。
否定。否定、否定、否定。否定。
――睫から雫が落ちる。既にびしょ濡れといったレベルだ。
瞬きをすれば視界が歪む。���るで泣いているような視界。
(あの後、リンとラファエルが葡萄酒を持って来て騒いで飲み明かして)
楽しかった。あの日々が続くのなら他には何も望んでなどいなかった。剣を振るうその先の願いも同じく。
「だというのに、君は関係のないところで逝ってしまったな。……それが、君が選んだことだったんだな」
これがアドルフの言っていた反抗期か、と自嘲するように笑う。
しかし反抗期なら、もっと可愛らしいものがよかったなとも思った。
――生きていてくれるなら、嫌われてもよかった。いっそ嫌われた方がマシだったのかもしれない。
「ただ、性別が違うというだけだったのに」
ずっとそばにいた。ずっと守っていた。ずっと、ずっと好きだった。
けれども君は、"傍にいてほしい人"という女性に連れられて逝ってしまったということなのか。
悔しかった。だからこそ、素直に喜ぶことが出来なかった。
いいや、素直なんてものではない。微塵も喜ぶことなど出来ていなかっただろう。きっとずっと仲が良かった。ずっと好いていた。なのにこの違いは一体なんだったのか。彼が恋慕した少女とは根本的に違う部分もあったのかもしれない。彼にしか分からない、彼の趣向というものもあったのかもしれない。
けれど第三者である自分にはそれが分からない。
(もし君が女性なら、僕を選んでくれたのだろうか)
なんて絵空事を描いてみる。
相手にはその気がないというのに、本当に、稀に性的な目で見てしまうことがあれば呑み込まれそうな罪悪感に苛まれ。ただ想いを伝えたいだけでも許されるかたちではない。彼の幸せを願うならば、報われないことが一番いい。そんなことも分かっていた。もし、もしも彼と結ばれるようなことがあったとしても……その先に明るいものはない。互いのことを想えば、結局。
――けれど。
「君を失うくらいなら、もっと早くに攫ってしまえばよかった。腕に閉じ込めてしまえばよかった」
それが本音だった。
ギリ……。奥歯を噛みしめる。
閑散としたこの場所なら、雨が降るという日なら、――君を失った今なら、吐き出しても許される気がした。
「僕だって、本当に、君のことを愛していたさ」
ゆっくりと花束を下ろす。それと同時に、腰に下げられた得物に手をやった。
柄を握り、鞘から細身の刀剣を引き抜く。
矛先を墓に向け、下に向けると――振り下ろした。
ザクッ! と、土に深々と刃が突き刺さる。
振り下ろすというよりも、突き立てたと表現した方がよかったかもしれない。
まずは剣士としての追悼を。
得物を手に取り、共に戦った同士として安らかな眠りを。――同時に、捧げる。
「これで君の愛した人を、しっかりと守っていけよ。君が、君でいられる理由だったんだろう」
――ツゥ、と生暖かい雫が頬を伝った。
堪えていたというのに、いつの間にか溢れていた。それを自覚した途端に、グチャグチャとした感情と涙がこみ上げてくる。
雨が酷い。
空が代わりに泣いている、などという表現はなんて図々しいのか。
「どうして。どうして……どうして、僕は……君は……どうして……」
何を問い質したいのかも分からない。
どうして彼は死んだのか。どうして彼はそのような人に惹かれたのか。どうして異性でなかったのか。どうして異性でなければならないのか。どうして。
「どうして僕は、君のことを好きになったんだろうな……」
それは他でない、君だったからで。
――不毛だ。
色の濁った瞳が、ゆるりと手元を見る。雨にしめった花束があった。
――とっくに雨なんか、上がっていた。
でもそういうことにしないと、泣いてるとバレてしまうから。
いつから泣いていたのかなんて分からない。もうずっと前から泣いていた。苦しくて、苦しくて、痛くて、泣いていたんだ。
しかしそれは自業自得。好きになってしまった自分が悪い。彼を守ることの出来なかった、自分の失態。
周りにバレないよう、彼に迷惑を掛けないよう、自分が胸中に思いを秘めて閉じ込めてしまえばいい。それだけのこと。だけどできなかった。
彼が死んだと知らされてから、本当はどうにかなりそうで。
それでも周りに気を遣い、似合わない笑顔を妙に取り繕ってみたりもして。――このまま平気になれたら。無理に笑うことで、どうにかなったら……なんて無責任な期待を抱いて。
悪あがきに過ぎなかったけれども。
(君のことを忘れるなんて、醜い僕には、やっぱり不可能みたいだ)
だから、せめて、どうか。
――この気持ちだけは、綺麗なままでいさせてくれないか。
ぎゅ、と花束を握りしめる。そして思い切り悪天候に向かって葬った。
拘束を失った花がバラけて、風に踊らされる。――花の香りに吐きそうだ。
降り雪ぐのは花の雨。そのまま醜い感情を消し去ってしまえばいい。ただ僕は純粋に、彼に別れを告げたいだけなのだから。
ただ、この花たちと共に恋心を散らせてくれ。
「ラファエル、ありがとう」
最後まで、僕を嫌わないでいてくれて。傍に置いていてくれて。
この気持ちを教えてくれたことも、苦しみを与えてくれたのも総て君なのだから。
ゆっくりと墓石に近付いて、傅く。
そうしてそっと、唇を触れさせた。本当に触れるか触れないかの、微かな口づけ。
好きでいさせてくれて、ありがとう。これできっと最後にする。
「君はこれを恋ではないと言ったけれど、――間違いなく、恋、だったよ」
確かに恋だった。不毛な恋だった。
実るはずなど最初からなくて、今となっては君もいなくて。
それでも僕は、君を追って死ぬことはしない。でも恐らく、君以上好きになる人もいないだろう。
「……さようなら」
またひとつ、頬を雫が滑り落ちていた。
――その日は雨が降っていた。在り来たりな天気の一つである。
濡れた顔をグシグシと拭う青年は、(酷い顔になってるんだろうなぁ)と、明日からまた顔を合わせる仲間に対する言い訳を考えていた。
彼の目蓋は赤く腫れ、目は未だに潤んでいる。
その日は雨が降っていた。朝から変わらない、相変わらずの天気だった。
しかし避けた雲間から――一筋の光が差し込む。恐らく明日は、晴天なのだろう。
頭に花びらを乗っけたまま、スウェイズは空を仰いで微かに笑んだのだった。
fin.
2013.2.26
0 notes
Text
■映画「クリーピー」などのメモ
▼DVDで「クリーピー」鑑賞。

▼黒沢映画については「CURE」をみて震撼して以来、刮目して観てきた。が、途中から映画をとりまく批評的磁場というか、カイエ・デュ・なんちゃら的なものというか、「これが分かんなきゃシネフィルじゃないよ」的なものがうっとおしくなったこともあり、また、「黒沢メソッド」的なものが勝手に分かった気になったのもあって、ある時期以降熱心に観てこなかった。
▼けれど、そんなことをどうのこうのいうには時も過ぎたし、今ならフラットに観られるんじゃないか、と思って観た。
▼やっぱすげえな…と再び震撼。
▼ちなみに、この映画の公開前後は、サイコパス映画というかモンスター映画というかが花盛りだったし、そのどれもが凄かった。
▼たとえば「ディストラクションベイビーズ」。

▼愛媛の小さな町に生まれものの、幼くして父も母もいなくなってしまい、弟の将太(村上虹郎)とともに、近所のおじさん(でんでん)に引き取られて育った泰良(柳楽優弥)。彼はある時から喧嘩に明け暮れ高校時代、地元の不良集団をボコボコにしたあげく、町を飛び出してしまう。
▼その後は、都会に繰り出し、からかってくる高校生たちにガチでファイティング。また、イキがってるバンドマンをみつけては背後から襲撃。返り討ちにあって鼻から血を出そうが、自分が勝つまで追いかけまわし滅多打ちにする。
▼さらには、町のキャバクラのガードマンのヤクザにも臆せず向かっていきノックアウト。その間、柳楽はほとんど無言。殴られても不敵に笑い、立ちあがり再び勝つまで拳をぶつけていく。
▼ただひたすら殴りかかる。壮絶な理不尽さ。殴る基準は何なのか?何のために殴るのか?何が不満なのか?…一切分からない。
▼そんな柳楽に惹かれていくのが、ヘタレ高校生の裕也(菅田将暉)。
▼柳楽の社会の外側にいるようなたたずまいを恐れながらも、ヘタレ故に社会の中で汲々とするしかない自分にはないものを持っていると感じ、彼に惹かれていく…。そんな裕也は、口八兆手八丁で寿良を手名付け、行動を共にする。そうすればヘタレな自分も強くなったような気がする。そして気がデカくなり自分より明らかに弱そうな町ゆく女性たちに襲い掛かる。普通なら「そんな恥ずかしいことするなよ」など言いそうだが、柳楽は何も言わない。
▼そんな2人は、いろいろあってキャバ嬢の那奈(小松奈々)を車に乗せて逃避行。その途中、スピードを上げすぎ対向車とクラッシュしてしまう。「救急車を呼ぼうか」そう言ってくれる車の主すらも殴り倒し、消えてしまう柳楽…
▼社会のルールなど眼中にないサイコパス=モンスターを描いた「脱社会的」映画にみえる。
▼だが地元高校生をボコる柳楽に「もうその辺でやめとけ」と制するでんでん
▼仲間のバンドマンを殴られ、「ふざけんなよ」と柳楽をボコるライブハウススタッフに対し「もうええから」と制するバンドマン。
▼猛スピードで自分の車にクラッシュして来た柳楽たちに対し怒りながらも「ええから。救急車呼んだるから」と助け船を示す運転手。
▼「もうええから」と制する人々の中に、逆説的に社会(街の掟、仲間の掟、最低限の人倫)が描かれる。同じ社会を生きる仲間なんだから、どれだけモメたってギリギリのところでは協力できる=「終わってない社会」がサイコパスの行動から逆照射して描き出される。
▼あるいは「ヒメノア~ル」

▼さえない童貞フリーターの岡田(浜田岳)はバイト先で変人すぎる先輩の、安藤(ムロツヨシ)と知り合い、彼の「片思いの恋物語」に巻き込まれる。
▼先輩は勤務先の近くにあるカフェの店員・ユカ(佐津川愛美)に恋しているが、彼女に彼がいるのか?も聞き出せないし、彼女をデートにも誘えない。
▼そこで「お前聞いてくれよ」と橋渡し役を頼まれるのだった。
▼そんな中、カフェで岡田はある人物を目にする。高校時代同級生だった森田(森田剛)だ。
▼彼は毎日のようにこのカフェを訪れユカのことをみているようだ。ストーカーなのか?真相を探るため岡田は、「久しぶりだね。飲みにいかない?」と誘い出す。
▼が、飲みに行くや、「一旦、底辺になってしまったヤツには浮ついた希望なんてないんだよ」と鬱になりそうなことしか言わない森田。
▼その後岡田は、安藤先輩の恋の橋渡しをするつもりが、いろいろあってユカとつきあうことに…
すると、それを知った森田が、「底辺なのに何浮ついてんだよ」と、彼らを殺しに動き回る。
▼その一方で、高校時代初めて殺しを一緒にやった元同級生で今は旅館の跡取り息子の和草(駒根木隆介)と、その恋人の旅館店員(山田真保)を殺したかと思えば、宿がほしくて民家を襲撃し主を殺してしまう…
▼容赦なく殺しまくる森田。
▼まさにサイコパス=モンスター的だが、彼の過去をたどると、高校時代のいじめにたどり着く。森田は浜田と共にいじめられていた。だが、ある時、浜田はいじめから逃れたいと、友人だった森田を売り、自分はいじめを回避する。
▼そのツケを払い、自分だけみんなの前でオナニーさせられる森田。その時、彼の中で何かが壊れ、サイコパス化がはじまった。社会の外側に出てルールなど無視するモンスター化がはじまった。
▼この社会は、人倫などあるようでなく「終わっている」。「腐っている」。だったらこっちも何だってやってやる…と言わんばかりのモンスターぶり。
▼だが、こちらも逆説的に「終わっていない社会」「腐っていない社会」が森田の中で前提にされている(浜田といっしょに家でゲームしているような小さな幸せに満ちた社会)。
▼あるいは、全く逆のアプローチだが「葛城事件」

▼男だったらある時期がきたら嫁を持って、2人くらい子供を産んで、自分の城である家を持つ。そして行きつけの店でも持って、人が来たら家の主として、いい感じでもてなす。そうやって家族を支え、長男にはパリッとしたスーツを着させ、ひとかどの男にする。次男は以下同様でがんばれ…。そんな家族の反映を願い「家長」の俺は自分の城の庭にすくすくと伸び行く木を植える…
▼映画は、昭和のある時期にだけ蔓延した「標準家族ウイルス」に感染した父(三浦友和)とそんな「一家の主」を持つ嫁(南果歩)、長男(新井浩文)、次男(若葉竜也)の「葛城一家」の物語。
▼ウイルスに感染してしまった父は、時代が変わり、その世界観が全く通用しなくなっているにも関わらず、感染したせいで見えてくる幻覚を、家族に押し付けてくる。
▼もはや父が変なウイルスに感染したゾンビにしかみえないので、逃げ回る家族。長男は嫁と結婚し家を出る。嫁(妻)は引きこもりの次男とともに父から逃げボロアパートに引っ越す。
▼しかし、ウイルスに感染した家長の元で長らく暮らしていたため、彼らも変わってしまった時代についていくことができない。
▼気の優しさゆえなのか、「ちゃんとやってれば努力は報われるin昭和」的思考ゆえなのか、頑張っても営業成績が伸びずリストラされ、それを嫁にも言えず、コンビニのレシートの裏に「すまない」と遺書を書いて自殺する兄。
▼引きこもりの末こじれてしまい「もう人生オワタ」と包丁を持って駅で無差別殺人を行う次男。
▼老人ホームのような施設でもうろうとするばかりの嫁。
▼こうしてウイルスのせいで「良かれと思って」したことが家族の破壊を招いた「一家の主」は、すくすくと伸び行く木に首を吊って責任を取るべく自殺…するが、木が折れてしまいできず…腹が減っていたのでコンビニで買ってきた麺をすする…
▼今はもうない「昭和社会」に内属しすぎることで、「平成社会」の外に出てしまう「脱・現社会的」三浦父…。それでも「終わってる昭和社会」を指摘することで、逆説的に「終わってない社会」が逆照射される。
▼しかし、「クリーピー」は言う。「(少なくとも近代社会において)終わっていない社会など可能だったのだろうか?」と。

▼この映画で描かれる社会からは、作中に登場するデカイ掃除機で吸い取られてしまったように、「人間の意思」が根こそぎ抜き取られてしまっている。
▼だから登場人物は意思をなくした亡霊のようであり、いつもどこかうつろで抜け殻のようだ。
▼脱走する凶悪犯罪者の説得に失敗し、刺されてしまい、それがきっかけで警察を辞めた主人公の高倉(西島秀俊)。彼は刑事をやめた後は、引っ越した自宅のリビングで椅子に座って窓の外からカーテン越しに吹き込んでくる風を浴びながら「平和だなあ」とまどろんでいる。その後、大学の教師の職を得るがそこでも授業が終わればあくび…
▼そんな彼の妻の康子(竹内結子)もまた日々、料理に、掃除にと、日々家事に忙しいが、自分からやっているというよりは単にタスクをこなしているだけのようにみえる。そもそも料理を作っているというが、自分が作ったスープをお隣におすそ分けする際に映るのは、ガラスのボールに入った薄気味悪い茶色い液体…。これは一体何を作っているのか?本当にそれを作ろうと意思して、作った結果がそれなのか?
▼加えて、彼の元部下だった野上(東出昌大)もまた、終始、目の焦点が定まらないような、どこかボーッとした風貌をしている…
▼また、高倉夫婦が引っ越した後、近所に手作りチョコを持って挨拶に行っても隣人は「そういう義理みたいなのは嫌で…近所づきあいはしてないんだ」とつれない。社会を作るうえで最低限の意思である、人と関わろうという気持ちがまるでない。
▼人々の意思(欲望)が「意味ある行為」を生み(●をしたいから×をしたんだ。無意味じゃないんだ。)、その意味ある行為の接続が、社会を作るという観点(ex:ウェーバー流社会学)からすれば、ここにはその起点となる意思がないため、社会もない。
▼その結果というべきか、映画に映る人々、建物、道具…あらゆるものが意味不明に満ちている。
▼映画は冒頭、8人を殺傷した連続殺人犯・松岡の取り調べ風景からはじまるが、彼が脱走した後、刑事達が彼を追いかける廊下は薄暗く、縦に長く、本当にここが刑務所なのか?と不思議に思えてくる作りになっている。
▼また逃げた彼を発見した場所には、無駄に多い来訪者たち。こんなに大勢部外者が刑務所に来るものなのか?
▼さらに、引っ越した高倉の隣に住む西野(香川照之)の家に至っては、玄関こそふつうだが、一歩、玄関から右に進めば、たちまち地下牢のような場所が現れ、鉄の扉さえある。この家は一体どんな間取りになっているのか?後にわかるが、香川は本物の西野さんを殺し、彼に成り代わっている存在。では本物の西野さんはなぜこんな鉄の扉がある家を建てたのか?
▼加えて、前述したように、妻康子が作っている料理も、「凝った味付けでしょ」などといっているが、一体何を作っているのかみていても全くわからない。「クスクス」など意表を突きすぎなアフリカ料理も出てくるし、ピーナッツのようなものをミキサーでクラッシュし液体にしもする。一体何が作りたいのか?
▼また高倉が務める大学では、窓の外にいつも大量の学生達が群がっている。そんなにたくさんやってきて、一体彼らは何をしているのか?
▼そして、映画では、前ぶれなく風が吹き、緑の木々やカーテンが揺れるし、突然、掃除機のけたたましい音や、ミキサーのうるさい音が鳴り響く。
▼我々にはあずかりしらないリズム(意味不明なリズム)で、世界のoff/onのスイッチがついたり、切れたりしているような印象。
▼映画に登場する全てが意味不明というか意味茫洋な感覚に満ちていて、そこが独特の不気味さを醸し出している。
▼これらのいくつかは、昔から黒沢映画で行われていたことかもしれないが、意味の蒸発感がもたらす社会の不在感がおそろしいことになっている。
▼だから「CURE」の時代には、サイコパスの萩原聖人が「お前は誰だ?」と尋ねればみんな「警察官だ」「教師だ」…と、社会における自分の役割を自信をもって答えていたが、「クリーピー」ならば、「お前は誰だ?」と聞かれても、「刑事かもしれないけど、さあ誰なんでしょう」と答えかねない勢いになっている。
▼だからといって皆、救済(CURE)されているようにはとてもみえないし、皆、もはや生きてすらいないようにみえる。
▼では、一体なぜこれほど社会から「意思」が吸い取られてしまったのか??それは2人のサイコパス=モンスターが教えてくれる、と映画は言う。
▼1人は、冒頭登場し脱走を図った末、撃ち殺される8人連続殺傷犯・松岡。
▼もう1人は、引っ越した高倉家の隣人で、他人の家族に近づいて彼らを洗脳し、一家の主を殺して自分がその代わりになりすます謎の犯罪者・西野(になりすました男)だ。
▼松岡は8人も殺しているが見た目はオレンジのTシャツを着こなした好青年。そんな彼は言う。
「俺、やりもしないであきらめるのは嫌いなんです。それよりもやった方がいいじゃないですか」
「なんでもいいんですよ。本人がやりがいを感じるならば」
▼それだけとれば自己啓発本にでも乗っていそうなフレーズだが、この論理で8人も人を殺している。高倉が「なんでもいいなら犯罪でもいいのか?」と水を向けると「そんなこと言ってないじゃないですか。ひどいな刑事さん。俺には俺のモラルがあるんです」とは言うが、その後、彼は脱走を図り、人質にとった通行人をあっさりナイフで切っている。
▼彼の「モラル」とは何なのか?おそらく欲望の実現までの手続きに関わるものだと思う。
▼ホルクハイマー=アドルノ、もしくは、ラカンの「サドとカントの同型性」についての議論を引く。
▼カントは、人間の理性の力を吟味することで「他者を手段として扱うのみならず目的としても扱え」などの「人間道徳の法則」を導き出した。
▼そして理性の力が「人間道徳」を生むのだから、その実現のためには理性以外の何物にも左右されてはならない。だから全ての能力や感情や欲望をも理性の力の支配下におくべきで、感情によって支配されてはならないと説く。これを「無感動の義務」と言う。
▼それは一見すると大変立派なことに思える。だからこそこうした考えは近代社会を支える行動規範の1つにもなっている。だが、SM小説の元祖、マルキ・ド・サドの小説に登場する「悪徳の追求者」ジュリエットはこんなことを言う。
▼「カントのその理性的な考えは、犯罪者が冷静な犯行計画をたて、良心の呵責を理性によって克服することと何が違うのか」と。
▼もっと言えば、欲望を達成するのに理性的に考え「AをしてBをしてCをすれば到達できる」という最短ルートがあった時、その間に、「殺人」や国家が「犯罪」と呼ぶものが挟まっていたとしても、そこで良心の呵責などの感情に左右されてはいけない。理性的に考えて最善のルートをとるべきだ…ということになるだろう。
▼「俺にもやっていいことと、いけないこととの区別くらいはつきます」と松岡は言っているが、おそらく彼の「やっていけないこと」は、国家が「犯罪」と位置付けていることと対応していない。むしろ、「国家が犯罪だと言っている」ことに良心の呵責を感じて欲望の実現ルートを迂回してしまうことこそ「やってはいけないこと」になっている。
▼同型の論理構成を持っている「道徳哲学」と「悪徳哲学」。その理性的で合理的な「道徳哲学」が、近代社会を支える重要な行動規範の1つになっているのなら、近代社会は同時に「悪徳哲学」をはらんでいることにもなる。近代社会はあらかじめ「松岡的」に、「サイコパス的に病んでいる」ともいえる。
▼そしてここで大事なのは「なんでもいいんですよ。本人がやりがいを感じるならば」と松岡が話すように、欲望そのものについてはまるで議論がないことだ。欲望の実現までの手続きに関しては感情に左右されるな…など、いろいろ御託はあるが、どうやったらどんな欲望が湧いてくるのか?などについ���は完全に蚊帳の外だ。
▼一方、西野はどうか?彼は高倉家の隣人で、「とある協会の理事」をしており、「娘」の澪(藤野涼子)と、病気で寝込んでいる「妻」の3人で暮らしている…ことになっている。
▼だが、映画が進むにつれ、その恐ろしい「正体」が明らかになってくる。彼は「西野」ではなく、高台から、(本物の)西野と妻と澪が暮らす家を眺め、「ターゲットとしてよさそうだ」と見定め、彼らに接触。友人関係になりながら、家族を口八丁手八丁で洗脳していき(本物の)西野を殺害。▼大型の布団乾燥機のような機械で西野を「パウチング」して部屋の床下に隠しながら、薬物入りの注射で妻をシャブ漬けに。
▼そして妻(母)を人質にとりながら娘・澪をコントロールし、西野家の財産を食いつぶしながら「家族生活」を営んでいたのだ。
▼そしてどうやら、このニセモノ西野は、これが初めてではなく、映画内で出てくる「日野市一家失踪事件」でも、同じように家族への接触→洗脳→主殺害→「ニセ家族生活」を行っていたようなのだ。
▼これだけ聞けば、「なんたる悪人か」と顔をそむけたくなる。だが、彼自身は「虫一匹殺せない」ような「か弱い」人間だ。だから彼は「ニセ家族実現」に必要な行動のうち「汚れ仕事」はほぼ自分でやらない。本物の西野の殺害も、彼のパウチングも、シャブ漬けになりすぎて使い物にならなくなった妻(母)の「処分」も…「それは自分たち家族でやってよ」と澪や妻など「西野家」に「アウトソース」してしまう。
▼その後、彼は高倉の妻・康子をも洗脳しにかかるが、その際も、彼女に薬剤入りの注射を打ち込み「意識朦朧」とさせたうえで、全ての行動を「康子さんの自由意思で決めたこと」にしてしまう。
▼「すべては彼(彼女)がやったのだ。彼(彼女)の自由意思でやったのだ。だから私は何もしていないのだ。何の責任もないのだ…」…行為も行為の責任も、自分以外の外部に「アウトソース」し続けるニセ西野。
▼ここには、「合理的」で「理性的」な「苦痛の回避」「労苦の回避」の思想がある。そしてこの「苦痛の回避」「労苦の回避」こそ、近代社会を支える大きな原理の1つだ。
▼たとえば「比較優位」を通じた「交換」の論理。
▼(近代)人はあれも、これも、それも…1人で生産する必要はなく、自分の能力の中で比較して一番得意なものに特化して生産。他に欲しいものは同様にして生産している他者と交換すればよいのだ、という思想。
▼経済学のベースになっている発想だが、これを支えているのは「不得手(労苦)なものは避けてよい」とする「労苦の回避」の思想だ。
▼そしてこの思想が「キツイ仕事はお金を通じてそれをやってくれる人に外注すればよい。彼だって無理にやらされているわけではない。お金が欲しくて自由意思でやっているのだから」という「分業の論理」、「アウトソースの論理」に発展していくし、その論理でまわっているのが近代社会だ。
▼だとすれば、ニセ西野が「不気味なサイコパス」的にみえるのなら、近代社会自体が「不気味なサイコパス」的なものをはらんでいるといえる。
▼合理的で理性的で感情に左右されない「欲望の追求」の手続きと、合理的で理性的で感情に左右されない「苦痛の回避」の手続き…近代社会に内在している「サイコパス的」なもの…
▼これらに共通しているのは徹底した「不合理な意思」の排除だ。
▼理性的に考えて合理的に計算すれば「最適な欲望達成」へのルート、「最適な苦痛回避」へのルートはほぼ1つに決まるはずだ。つまり、「誰がやっても同じようなルート、誰がやっても同じような行動」になるはずだ。
▼だとすれば、そこに「人間」はいるのか?最適行動だけをとる「機械人間」しかいなくなるのではないか?逆にいえば、もし人間がいるとすれば、「誰がやっても同じではない行動」、そいつにしか理解不能の「不合理な意思」がなくてはならないのではないか?
▼しかし、その排除こそが近代を作っているとすれば…まさに「不合理な意思」がデカイ掃除機で吸い取られた「抜け殻だらけ」の世界になるのではないか…「クリーピー」はそう言っているように思う。
▼映画のラスト。ニセ西野は、薬剤で洗脳された康子、その康子に不意打ちで薬剤を打ち込まれ意識朦朧とする高倉、そして「娘」澪と、犬のマックスとともに、「次なる寄生先」を探して国道16号線を進む。
▼そして、途中のドライブインの廃屋の屋上から街を覗きターゲットを発見。不気味に笑うニセ西野は、さっきできたばかりの「即席家族」の面々と、作戦会議を始める。
▼「そうだな。僕と澪は親子、で、高倉さんと康子さんはいとこ夫婦ってことにしよう。となると、ああ、この犬邪魔だな…」
▼そう言い出したニセ西野は、高倉に拳銃を渡し、この「犬を殺してくれ」とアウトソースする。
▼だが、そうやって拳銃を渡した次の瞬間、「これがあんたの落とし穴だ」…
▼高倉は銃をニセ西野に向け引き金を引く・・・「ええーー」…と、驚きながら銃殺されるニセ西野
▼「たとえ殺すことになろうとも、こんなやつの言いなりにはなってたまるか!」「俺は康子をとにかく何がなんでも守りたい!」そんな不合理な意思の力で高倉夫婦は洗脳状態から逃れることができたのだった。
▼その後の康子の「うわーーーーーー!」という張り裂けんばかりの泣き叫びこそ、そうした「不合理な意思」の象徴なのだろう。
▼だが。そうした近代社会の原理に真っ向から逆らう「不合理な意思」こそ、ISをはじめとするグローバルジハーディストたちの理解不能な行動の原動力になっているものではないか?
▼だとすれば、それを擁護することはどういうことになるのか?しかし、擁護しないとすればどういうことになるのか?
▼またも前触れのない風が吹き、落ち葉が風に舞う中、横たわるニセ西野の死体。この誰だか分からない男は一体誰なのか?
▼おそらく、押井守の作品によく出てくる「犯人だと思って捕まえたら誰かの操り人形」、そして「その“操り人”を捕まえても、また別の誰かの操り人形」そして「そのまた誰かを捕まえても…」ということになるのだろう。だからニセ西野は死んだとしても、ここが(ポスト)近代社会であるかぎり「クリーピー的隣人」、「となりのサイコさん」は消えないのだろう。だとすれば、何をどうすればよいのか?途方にくれるばかりだ…・。
0 notes
Text
【小説】真夜中の暗殺者 (下)
孤独で優しい魔法使い
Ⅱ.真夜中の暗殺者 (下)
「私は魔法使いだ」
感情のない、平坦な声音。だが、耳にした者をぞっとさせる、どこか冷酷な響き。やはり、その声は若々しく聞こえる。
リックの目には、この男の身体はまるで老人のように見えているのだが、声だけ聞けば若者だ。否、男の顔は、二十代であろう若者の顔をしている。顔と声は若者で、首から下は老人。そんなことがありえるだろうか。
「破滅の導師、不可能の術士、黒き無秩序…………私のことをそう呼ぶ者もいるが、私は魔法使いだ。昔の恋人の、魂の継承者を見守っている」
「魂の、継承者……?」
「俺が、スミキのかつての恋人の、生まれ変わりってことだ」
チルはリックに銃口を向けたままそう言った。顔色ひとつ変わらない。
魔法使いに、生まれ変わり。
リックには理解できそうにない。これは現実の話なのか。悪い夢の続きを見ているみたいだ。
だが、両手首に食い込む縄の感覚は、間違いなく現実のものだ。リックは今、地下室に囚われ、銃を向けられている。かつての仲間、一緒に育った兄貴分に、命を握られている。助けが来る見込みはない。部屋の中には同胞たちの亡骸が無残にも散らばっている。ここでこの有り様なのだ。「組織」の隠れ家は他にもあるが、他も似たような惨状が広がっているのではないか。
思えば、今回の任務は最初から妙だった。標的がひとりでいるはずのアパートの一室には、すでに刺客が待機していた。部屋に忍び込み、標的を抹殺するはずだった仲間は、返り討ちに遭い死んだ。路地で身を潜め待機していたリックは追手に見つかった。そして、追手たちに囲まれかけた時、リックを助けたのがチルと、このスミキという異様な男だ。チルに導かれるようにしてこの地下室へ来て、そして今、リックは彼に取り引きを持ちかけられている。
「組織」を裏切るか、ここで殺されるか。
偶然にしては、何もかもが出来すぎだ。否、何もかもが悪く運びすぎている。
チルは敵対勢力に今回の作戦のことを漏らしている。そうでなければ、ここまで作戦が失敗し続けるはずがない。
「チル、お前、殺されるぞ」
リックは自らに銃口を向けたままのチルへそう言った。「組織」を裏切り、敵対勢力へ「組織」を売ったところで、その敵がチルを生かしておくはずがない。「組織」が解体、もしくは、解体とまでいかずとも衰退した頃を見計らって、用済みのチルを始末するはずだ。
だが、チルは笑った。
「俺を殺すことはできない。スミキが付いている」
男はチルの背後で、首肯も笑いもしなかった。ただ黙っている。
リックは両手首を縛られたまま、腰のベルトから器用にナイフを一本引き抜く。それをチルたちからは見えないように背中に隠し、手首を縛る縄を少しずつ切断する。なるべく肩を動かさないように注意しながらだ。
このナイフの切れ味では、恐らくリックの手首の皮も多少切れてしまうだろうが、犬の餌にされることを考えれば、それくらい構わなかった。否、とリックは考え直し、ナイフの刃先の向きを少しばかり修正する。右手首を庇うような角度だ。代わりに、左手首に刃先が刺さる可能性があるが、リックの左手首は切れたりしない。
なぜならそこに、皮膚などないからだ。
「死ぬのはお前だ、リック。どうするんだ。ここで犬の餌になりたいのか」
「俺を殺したところで、どうせお前は死ぬことになるぞ、チル。『組織』を裏切ってどうする。世界のどこに逃げたところで、奴らは必ずお前を探し出して殺す」
「何度も言わせるな、俺は死な���い。リックだって見ただろう、スミキに銃弾が効かなかったのを」
路地裏で六人の男から一斉に射撃されたはずのこの異様な男は、弾が当たったにも関わらず、銃痕はひとつもなかった。衣服には穴も空いておらず、路地に弾丸は落ちなかった。銃弾は男に当たる直前、かき消えてしまった。
まるで魔法のように。
リックがナイフで喉元を斬りつけた時もそうだ。手応えは確かにあったのに、男の喉にはかすり傷ひとつつけられなかった。
あれが、魔法。
「確かにその男は魔法使いかもしれないが、お前は生身の人間だ」
リックはチルを見据えたままそう言い、両手首を縛る縄を断ち切った。チルはそのことに勘付いているだろうか。彼に気付かれなかったとしても、後ろの異様な男には気付かれているかもしれない。だがリックはそれ以上思案しない。不安が生じればそれは必ず表出する。心を無にする。感情を殺す。それが冷静さを失わないでいられる、唯一の手段だ。
「その男は不死身かもしれないが、お前は死ぬんだ、チル」
チルの指が唐突に引き金を引いたのを、リックの目は捉えていた。同時にリックは飛び上がるようにして身体を起こし、後方へと跳躍する。かつての同胞たちのはらわたを踏み潰すことになるが、構ってはいられない。足元が血で滑ることを計算に入れてさらに跳躍する。
リックには、チルの目の動き、銃口の向く先、腕の角度から、次にどこを狙って撃ってくるかのかが見えた。それは銃弾の軌跡が見えた時のようにはっきりと、空間を線となって走り抜けていく。その線を機敏にかわしながら、リックは右手で逆手に握っていたナイフを放った。
それが避けられてしまうことは、投げる前から予測できていた。リックは腰のベルトからさらにもう一本、ナイフを引き抜き、跳躍しながら投擲する。視覚より遥かに遅れて銃声が三発聞こえた。実際は一秒も経過していないはずだが、それだけリックの目の処理速度が加速しているのだ。弾は一発も当たらなかった。残弾はあと三発。
ナイフを投げた後、それが的に当たったか否かは確認しない。それは銃であっても同じだ。命中していようがいまいが、次の一発のことを考えていればいい。何かを期待したり安堵したりすることは、自らの命を危険に晒すことになる。リックにそう教えたのは、他でもないチルだった。だから、拳銃が床に落ちて滑るように回転する音を耳にした時、リックはすでに次に投擲するナイフを引き抜いていた。
血の滴る音。チルの呻き声。その手にすでに拳銃はなく、リックの投げたナイフが甲から手のひらまで貫通している。チルは痛みに顔を歪め、リックはゆっくりと動きながら問う。
「その魔法使いの魔法とやらは、お前には通用しないのか? チル」
「…………どういうことだ」
チルの苦痛に満ちた声はリックにではなく、背後に立つ異様な男へと向けられていた。
「スミキ、どうして俺を助けない?」
「どうしてお前を助ける必要がある?」
その男は、先程からぴくりとも動いていない。言葉を発しなければ、立ったまま死んでいるのではないかと疑ってしまうほどだ。
「その者の言う通りだ。チル、お前は生身の人間だ。お前は死ぬ」
「何を言っているんだスミキ。お前の身体にかかっているのと同じ魔法を、俺にもかければいい。それだけの話じゃないか」
「私にかかっているのと同じ魔法を、お前にもかける?」
魔法使いがそう言ってその口元を歪めた瞬間、リックは背筋が凍るような感覚��した。路地裏に突如としてこの男��現れた時と同じ、感じたその瞬間に、無意識的に身体がすくむような本能的な感覚。それは、恐怖。
その男が笑ったのを見たのは、それが初めてだった。否、感情らしい感情を露見させたのは、と言うべきだろうか。男の顔は笑っていた。
「ただの人間風情が。恥を知れ」
思わずぞっとする声音。リックは思い出しつつあった。この異様な男は、自分の生死など容易く決めることができるのだという、あまりにも圧倒的な絶望感。どうして忘れていたのだろう。チルに気を取られていたのか。さっきまで軽々と銃弾を避けていた四肢が、急激に重くなったように感じる。敵わない。この男に勝つことはできない。理屈ではない。直感的にそれがわかる。恐らく生きる者すべてが、この男を前にすれば自身の敗北を悟る。自らの死を祈る。せめてそれが、苦痛の少ない終末であるように。
そして、この異様な男に恐怖しているのは、チルも同様だった。血の滴る右手を押さえたまま、目を見開いて男を見ている。
「おい、どういうことだ、急にどうしたんだスミキ。お前はいつだって、俺のことを助けてくれたじゃないか。俺が、お前の恋人の生まれ変わりだから――」
「確かに、私はお前にいくつか魔法を授けた。酒代欲しさに両親が『組織』へ売り飛ばした赤子のお前に、生きていくための能力や技術を与えた。時には上部の人間たちでさえ知らない敵側の情報を、お前に伝えたこともあった。言われた通りに、追って来る者たちを殺した。だが、私はお前の命を救うことはしない。命乞いなどするだけ無駄だ。お前は死ぬ。それが、お前の星が定めた運命ならば」
「くそっ」
チルは忌々しげに地団太を踏んだ。リックの耳には、階上で鎖を引きずる音が聞こえる。軽快な足音。まるでチルの足音に反応したかのようだ。やはり、階上に何かいる。鎖に繋がれ、四足で歩く、何かが。
チルに悪態をつかれても、男は表情ひとつ変えず、眉ひとつ動かさない。淡々と言う。
「私はお前の命などどうでもいい。だが赤ん坊の頃から知っているよしみだ、ひとつ忠告する。チル、その者を殺すのはよせ。今、お前の運命を司る星が狂いつつある」
「俺だって殺したくはないさ、スミキ」
チルは手の甲を貫いているナイフを、勢いよく引き抜いた。表情は苦痛に歪んではいるが、その両眼は射抜くようにリックを見ている。
その目をよく知っている。憎しみに駆られた、殺意のある目だ。チルは子供の頃から、そういう目をしていた。決して、冷静に相手を殺すということはしなかった。いつも感情に駆られ、なぶるように、痛めつけるように殺してきた。施設にいた頃からそうだった。「組織」に所属してからも変わらない。
「だが、こいつは俺の手を噛んだ。飼い主の手を噛むような犬には、罰が必要だ。なぁ、そうだろう?」
それは唐突だった。べったりと血の付着したナイフは、チルの手から空間を切り裂くように放たれ、リックに向かって飛んでくる。リックは結果的にその投擲をかわしたが、一瞬の不意を突かれ、必要以上に大きな動作になってしまった。その隙をチルは狙っていたかのように飛び出し、全身で体当たりをして部屋の壁際までリックを吹っ飛ばすと、すぐに駆け出して床に落ちていた拳銃を手にした。受け身を取り損ね、無様に倒れたまま、リックがそれでもベルトから三本目のナイフを引き抜こうとした時、
「動くな!」
と、チルは鋭く叫んだ。向けられた銃口を見て、リックもそれ以上は動かない。その体勢では、反撃に出ることも、銃弾を避けることも困難だった。
「武器を出せ、すべて床に置け」
リックはすぐには応じなかった。
「武器を出して床に置けよ。俺が本気かどうか、痛い思いをしなくちゃわからないのか?」
チルの憎しみのこもった目。リックは黙ってその通りにした。身体を横にしたまま、ベルトに隠していたナイフを二本、揃えて床に置く。
「それでいい」
チルがそう言ったので、リックは左手の袖口の奥へは決して手を伸ばさなかった。チルは銃口をリックに向けたまま近付き、床のナイフを部屋の隅へと足蹴にした。そしてその足で、リックの横っ面を蹴り飛ばした。
「どっちが飼い主なのか、教えてやる」
崩れるように再び床に倒れたリックを、彼は蹴り続ける。急所は外し、しかし着実に痛めつけるように、執拗に、顔を、胸を、腹を、蹴り続けた。リックが声を上げることはなかった。幼い頃に叩き込まれた習慣は、今も健在なのだ。
子供の頃。それはリックにとって幸福な時代ではなかった。日々怯え、疲れ果て、しかし泣くことも許されなかった。その気力さえ奪われていたのかもしれない。
施設の子供がいなくなる度に、次にここからいなくなるのは自分かもしれないと思った。否、リックは実際、そうなりかけたことがある。あれは、チルが一足先に施設を抜けてすぐの頃だった。
大人たちに連れられて行った、暗い部屋。お仕置き専用の部屋だと知らされていたその部屋には、大きな檻がひとつあった。闇の中から聞こえる、鎖を引きずる音と、四つ足の生き物が歩く足音。荒い呼吸音と、液体が床に滴り落ちる音。
――リック、お前は「組織」に忠誠を誓えるか?
大人のひとりが、厳かな口調でそう言った。誓えます、とリックは答えた。恐怖心を決して表に出さないよう、細心の注意を払った。
――本当に誓えるのか?
先程の大人が、再び尋ねた。誓えます、と再度答えた。
――なら、左手をこの檻の中へ入れてみろ。
リックは躊躇しなかった。恐怖しなかった訳でも、予測できていなかった訳でもない。ただ、躊躇すれば、事態が悪化するとわかっていた。
鉄格子の隙間から、檻の中へと左手を入れた。檻の中の暗闇は、不気味なほどに生温かった。
――もっとだ。入るところまで全部、腕を檻の中へ入れろ。
肩が鉄格子に食い込むところまで、リックは腕を檻へと差し入れた。闇の中からは低い唸り声が聞こえてきた。獣の声だ。
――怖くないのか?
怖くありません、とリックは答えた。
――素晴らしい忠誠心だな、リック。
また別の大人が、感心したかのようにそう言った。
――我々は勘違いをしていた。お前は素晴らしい子供だよ。お仕置きしようと思ってここまで連れて来たが、ご褒美をあげるとしよう。
大人のひとりが不意に檻の奥、闇の中へ向き直り、ただ一言、「もういいぞ」と言った。
次の瞬間、「それ」は猛烈な勢いで闇の奥から飛び出してくると、一瞬の躊躇もなく、リックの左腕に食らいつき、肘から下をそのまま噛み千切った。リックはそれでも、悲鳴を上げることはしなかった。
闇の中、ふたつの目が光っている。口元を真っ赤に汚し、子供の左腕を口に咥えている「それ」は、大きな真っ黒の犬だった。
猛烈な痛みと出血で意識が遠のきつつあったリックの耳元で、大人のひとりがこう囁いた。
――忘れるなよリック。お前がその忠誠心を忘れた時、今度は片腕だけでは済まないぞ。
その日リックは、本当の意味で「組織」への忠誠を誓った。
その後、大人たちがリックに与えた「ご褒美」は、他の子供たちには与えらなかった物だった。
――誰にも勘付かれるな。これはごく一部の人間しか知らない、お前だけの「切り札」だ。
その後、「組織」に加入するまでの七年間、リックは死に物狂いだった。死に物狂いで、自身の左腕の肘から先がないという事実を、周囲に隠し続けなければならなかった。だがリックはそれを、隠し通してみせた。
与えられた義手の動かし方を徹底的に身体に叩き込み、不自然に見えない動きを完全に習得するのに三ヶ月かかった。左腕を使いこなすための特別な訓練も受けた。
チルがいなくなった今、他の子供たちよりも劣った成績しか残すことができないリックが、なんとか施設に踏みとどまり、「組織」に加入するためには、その左腕が必要だった。そしてそれは、忠誠心と引き替えに、「組織」が与えてくれた唯一のチャンスだった。
リックはそのチャンスを、掴んで決して離さなかった。
生きていくために。
生き残るために。
「どうだリック、そろそろわかってきたか?」
チルは思う存分リックを蹴りつけ、どこか満足したような口調でそう言った。
リックは腫れた顔で血を吐いた。折れた歯が口から血だまりへと転がり落ちる。
「お前は子供の頃から非力なやつだったな、リック。俺の助けがないとなんにもできない駄目なやつだった。俺はお前が鬱陶しかったよ。施設を出て、清々した。なのにまさかお前が、『組織』に加入するとはな。てっきり、そのうちお前を犬に食わせる業務が回ってくるんじゃないかと思ってたのに」
チルは拳銃を再びリックへと向けた。銃口を額へ突き付ける。リックは腫れ上がったまぶたの下で、なんとかその光景を捉えていた。
「これが本当に最後だ。『組織』を裏切って俺に付け。そしたら命だけは助けてやる」
「……俺は『組織』に忠誠を誓った」
リックはそれだけを答えた。それがすべてだった。
「そうか。お前も犬の餌になれ、リック。出来損ないの仲間たちが、先に天国で待っててくれてるさ」
チルはあっさりとそう言い、それから、階上に向け、「よし、いいぞ」と叫んだ。
その瞬間だった。
その刹那、その一瞬で、リックは左手の袖口の中へ右手を入れ、そこにあるスイッチを押し、左手首を引き抜いた。
銀色の刃が閃くように光った。易々と衣服を破り、皮膚に突き刺さり、そしてチルの心臓を貫く。
ほんの一瞬の出来事だった。
その一瞬で、十分だった。
恐らく、何が起きたのか理解できないまま、チルはその場で絶命した。
彼の胸に深々と刺さったのは、リックの左腕、義手に仕込まれていた刃渡りの長いナイフだ。上層部の大人たちから、仲間にさえも隠し通すように義務付けられた、リックの切り札。窮地に追い込まれた時に身を護るための最後の手段。
リックの耳に、あの嫌な鎖を引きずって駆けて来る音が聞こえた。それは軽やかに階段を降りて来る。瞬時にチルが持っていた拳銃を見つけ、それを拾い上げようとしたその時、リックの目の前、あの異様な男がしゃがみ込むようにして、そこにいた。
フードの下、真っ白い肌をした男の顔が目前にあり、リックは恐怖する。その残酷な色をした黒い両眼が、リックを見つめている。
「心配いらない」
男はただそう言って、音もなく立ち上がると、地上へと続く階段へと向き直った。鎖を引きずる音はだんだん近付いて来る。あの生臭い息を吐く呼吸音すら聞こえてきそうだ。
「もういい、忘れろ」
男は階段に向け、そう発した。その途端、鎖を引きずる音が止んだ。しばらく静寂が続いた後、鎖のじゃらじゃらとした金属音は、遠ざかって行った。再び階段を登って行ったようだ。やがてその音が聞こえなくなったのがわかると、リックは安堵した。いつであっても安堵してはいけないと叩き込まれたはずだったが、全身の力が抜け、床に仰向けに倒れ込む。
男はリックの方を向き、無表情に見下ろしている。
「俺を殺すか、魔法使い」
リックが尋ねると、男は首を横に振った。
「お前の命になど、興味はない」
「チルを、お前の恋人の生まれ変わりを、殺したのにか?」
「私はチルが死ぬのを見届けに来ただけだ」
「そうか。お前には最初からわかっていたんだな。チルがここで死ぬのが……」
リックは静かに息を吐いた。部屋の中は血と肉のにおいで充満している。心が落ち着くような状況ではないことは確かだが、不思議なことに、どこか穏やかな心境だった。すぐ側にこの異様な男が立っているというのに、恐怖心もない。チルが死んだからだろうか。
男は淡々とした口調で言う。
「チルの運命が死へ向かっているということはわかっていた。たとえチルが私の忠告を聞き入れていたとしても、お前が言っていた通り、遅かれ早かれ、殺されていただろう」
たとえリックが殺さなくても、チルはいずれ殺されていた。「組織」の残党か、もしくは、チルが寝返った敵対勢力によって。それは魔法使いでなくても、わかることだった。
「チルはお前のことを守護霊と言っていたが、お前はまるで、死神みたいだ。チルが死ぬのがわかっていて、助けなかったのか?」
「助けて何になる? 人間はいずれ死ぬ。不死身にでもしてやれとでも言うのか? チルが言った通り、弾丸が効かない魔法でもかけてやればいいのか? それとも、刃物で貫けなくなる魔法か?」
男は小馬鹿にするように鼻で笑ってそう言うと、横たわったままのリックから目線を外した。馬鹿馬鹿しい、と、声には出さなかったが、男の唇が確かにそう動いたのをリックの目は捉えた。そう、馬鹿馬鹿しい話だった。「チルを助けなかったのか」なんて質問をこの男にするのは、馬鹿馬鹿しい話だ。チルを殺したのは、他でもないリックなのだから。
施設から消えた子供たちのために、「組織」への復讐を誓っていたチル。
チルがそんなことを計画していたなんて、リックは思いもしなかった。仲間たちの復讐をしようなんて、そんな発想さえなかった。強い者だけが生き残り、弱い者は淘汰される。それが世の常だと思っていた。自らが残るためには、強くなるしか道は残されていない。だからこそリックは、「組織」への忠誠心と引き替えに、左腕に仕込み刀を入れる道を選んだ。否、それはリックが自ら望んだ結果ではなかったが、与えられた物を最大限に活かす努力はした。弱者のために何かを成そうだなんて、考えたこともなかった。常に自らが生き残ることを考え、そのために行動してきた。
そして、チルは絶命し、リックは生きている。
だが。
「俺もそのうち、殺されるんだろうな」
リックは天井を仰いだまま、そうつぶやくように言った。
チルの反逆行為によって、「組織」は恐らく、もう壊滅状態だろう。態勢を整えるとしても、短期間では無理だ。そうしている間に敵側の勢力範囲が広がり、「組織」は完全に解体させられるだろう。つまりは、皆殺しだ。
「お前にはお前の星のさだめがある。それを決めるのは、私ではない」
男はリックにそう言った。
星のさだめ。
星が定めた運命。
もし本当に、そんなものがあるのだとしたら、これは決められていた未来だったのだろうか。
「組織」の消滅によって、世界の均衡は崩れるだろう。また新たな勢力関係が生まれ、新たな争いが起き、そして新たな秩序によって再び統治される。多くの血が流され、多くの者が殺される。チルが果たそうとした復讐は、その小さな始まりにすぎない。こうなることを、彼は望んでいたのだろうか。仲間たちの仇を討つために、施設の同室で過ごしていたリックまで殺そうとしていた彼は、一体何を見つめ、何を手に入れようとしていたのだろう。
男はチルの死体の傍らに立ち、ただ見下ろしていた。その表情からは、なんの感情も読み取ることができない。かつての恋人の生まれ変わりだというチルの死を、どう受け止めているのか、リックには知る由もない。
「お前には、お前自身の運命もわかるのか? 魔法使い」
「いいや」
と、男は答えた。
「私は星の支配下から脱してしまった。死ぬことがないためだ」
「お前は本当に不死身なんだな。それは、その、魔法とやらのおかげか?」
「そうだ」
「お前はいつから不死身になった? 恋人の生まれ変わりを見守り続けていると言っていたな。そのために不死身になったのか?」
「いいや」
男は首を横に振り、それから僅かに、その表情を歪めた。まるで頭痛に襲われているかのような、苦しげな顔。それはほんの一瞬だったが、男はそんな表情をした。
「私がこうなったのは、アネッサに出会うずっと以前だ。今となっては、それがいつのことだったのかも、なんのためだったのかも、記憶が曖昧で思い返すことができない」
アネッサというのが、この男のかつての恋人の名前らしい。
リックはこの男の衣服の下に、たるんで皺が多い肌を見抜いたことを思い出し、顔と声は若者そのもののこの男は、実際は決して若くなどないのだろうと思った。思い出すことができないほどの長い時間を、この男は生きてきたのかもしれない。
「チルが死んで、お前はこれからどうするんだ、魔法使い」
「これまでと同じだ。次の生まれ変わりが現れるのを待つ」
そう答えてから、男は再度、リックを見た。
「そう言うお前は、どうする」
問われて、リックはただ苦笑する。
これからどうするのか。自分でもまったくわかっていなかった。
すると、男は外套の中から右手を差し出してきた。
「受け取れ」
革手袋に覆われたその手には、一枚の紙片が握られていた。それがなんなのかわからないまま、リックは半身を起こして受け取ってしまう。
それは切符だった。最寄りの港の名前が記してあり、それで船の切符だとわかった。行き先は、知らない港の名前だ。リックは頭の中にある地図をめくってみたが、地図からその地名を見つけ出すことはできなかった。
「それはチルが逃走用に用意していた切符だ。あと三時間後に船は出る。その船に乗れ。乗ってから四時間後、船はある港で一度停留する。そこで降りろ。駅に向かい、南へ向かう列車に乗れ。大きな川を渡る橋を渡ったら、次の駅で降りて、川辺の街まで引き返せ」
男の言葉を聞いていると、突然、リックの頭の中の地図上に、赤く輝く点が現れた。その点からは同じく赤い線が、まるで男の言う道のりを示しているように、あるひとつの街まで伸びていく。
それはどこか外国の、知らない街だった。リックが記憶していた地図に、異国の街までは載っていない。新しい地図が突如として、頭の中に浮かび上がってきた。まるで魔法のようだった。今の今まで知らない土地であったその街までの道のりを、何度も資料を読んで頭に叩き込んだ時のように、はっきりとイメージすることができる。
「その街には川の近くに大きな病院がある。その病院に勤めている、マーガレット・ヘイザーという女性を探せ」
リックの脳裏に突然、ある女の横顔が過ぎった。金髪の、青い瞳で、聡明そうな、知的な印象を与える顔つきの女。年齢は三十代だろうか。もしかしたら、もう少し年上かもしれない。知らない女だ。会ったこともなければ、写真や挿画で見たこともない。だがその顔がくっきりと頭の中に浮かび上がり、そして忘れられなくなった。
「その女性に伝えろ。『スミキに言われて会いに来た。助けてくれ』と。それだけで通じる」
「……この女は何者だ?」
「その病院に勤務していると言っただろう。看護師だ」
「看護師?」
「ああ、ちなみに、人妻だ」
「ふざけているのか?」
「冗談だ」
男は続けて言った。
「説明するとややこしいが、彼女は私の友人だ」
「魔法使い仲間ということか?」
「いや、彼女は普通の人間だ。さっき、看護師だと言ったはずだ」
「……堅気の人間なんだな?」
「だから、看護師だと言っているだろう」
一般市民に、リックのような生業の人間が気安く助けを求めていいものなのか。彼女の身に危険が及ぶことはないのか。そもそも、道中が安全なのかどうか、この魔法使いの言葉通り、その女を信用してもいいものなのか、判断することができない。
「彼女には私からも一報を入れておく。用心して港に向かえ」
男はそう言い残すと踵を返し、部屋を出て行こうとする。
「待て!」
リックがそう声を上げると、男は外套の裾をふわりと揺らし、立ち止まった。そして何も言わず、リックを見下ろしている。
「どうして、俺を助ける?」
「今まで、いろんな人間を見てきたが、私の首筋に斬りかかってきたのは、お前が初めてだ。特に、女ではな」
そう言われた瞬間、リックは頬が上気するのがわかった。
見破られていた。この男にはすべて、見抜かれていたのだ。それも当然なのかもしれない。だが、この魔法使いには何も通用しないとわかっていても、無性に悔しく、そして恥ずかしい。
「アネッサに初めて出会った時のことを思い出した。あの時は、心臓を弓矢で貫かれたものだが……。思い出すだけで胸の辺りがこそばゆい」
男は乾いた笑い声を上げた。表情は相変わらず無表情であったが、その声音はどこか楽しげであった。
「もう男の振りをして生きるのはよせ。女として生きた方が逃走も容易いだろう。せいぜい生き延びろ、百年ももたずに朽ちる命だ」
男はそう言って再び歩き出し、地上へと続く階段を上り始めた。やはり足音ひとつしない。すばやく立ち上がり、部屋の出入り口まで駆け寄ってリックは階段を仰いだが、そこにはすでに男の姿はなかった。まるで最初から、そんな男は存在していなかったかのようだった。
リックは船の切符を腰のベルトに隠し、それがそう簡単に落ちたりしないことを確かめた。
それから、血みどろの室内を振り返った。
倒れたままのチルの死体に近付き、その胸を片足で踏みつけると、突き刺さったままの、仕込み刀となっている左腕の義手を引き抜き、よく血を拭ってから元の通りに腕に装着した。そのカチンという金属音を聞いた時、リックは自らの任務が終焉を迎えたのだと思った。
チルの見開かれたままのまぶたを、そっと閉ざしてやる。彼の両眼は、まぶたの裏側の闇の中へ消える。もうその瞳に、光が灯ることはない。
チルは最後まで、気付かなかったようだ。リックの左腕に仕込まれていた武器のことも、ずっと一緒に過ごしてきた弟分が、本当は女なのだということも。
階段を上り、建物の外に出た時、世界は未だ夜中であった。街はすっかり寝静まっている。路地裏の死体はどうなったのだろう。窓から落ちた仲間の死体や、撃ち殺された六人の追手は。気がかりではあったが、詮索をする気は毛頭なかった。
脳内で地図を広げながら、港へ向かう道を慎重に歩き出す。
夜明けはまだ、遥か遠くにあった。
了
「Ⅲ.白昼の処罰者 (上) 」へ続く
0 notes