#計量法第9条第1項
Text
「宮崎正弘の国際情勢解題」
令和六年(2024)3月22日(金曜日)
通巻第8186号
【書評】
ラピダスの2ナノ半導体は、「できっこない」のか
経済安全保障のアングルに特化、日本再生を展望する『元気の出る本』
平井宏治『新半導体戦争』(ワック)
************************
半導体戦争は米国vs中国がメインの戦場だが、半導体世界一は台湾のTSMC、韓国のサムスンとSKハイニックスであり、米国のインテルは後塵を拝している。だからバイデン政権はインテルに破格の195億ドルを支援し、捲土重来を期す。
アップルの新型iPhoneは3ナノ半導体を搭載している。すでに3ナノを量産するTSMCは次世代最先端の1・4ナノ開発センターを台湾に開設した。エヌビディアは新型半導体を発表し斯界の度肝を抜いた。
米国勢は頭脳部分の基本設計とルールを先に決めるのが得意だが、ものつくりはじつに下手くそ。そのくせ賃金が高いから、競争では負ける。インテルの優位回復は難儀するのではないか。
さてバイデン政権は対中政策を厳格にすると言いながら、最高機密はどんどん中国の盗まれており『ザル法』と化している。そのうえ米国の半導体業界はバイデンの対中政策に反対しているから話はややこしい。
評者(宮崎)も拙著『半導体戦争』(宝島社)で指摘しておいたが、半導体はもはや『産業のコメ』ではなく、『戦略物資』であり次世代の武器ならびに兵器システム、とくに兵士ロボットに用いられる。イラク戦争でピンポイント攻撃の制度が挙がったが、これから根本的に戦争形態が変わるのである。
1980年代に日本は世界半導体市場の80%を占めていた。その頃、TSMCは誕生もしていなかった。
それが様変わり、日本は先端の半導体競争ではるか後方にあって、もはや再生は不可能、絶望的と言われていた。
ラピダスが挑む2ナノは2027年量産開始予定だが、現実の日本の半導体は40ナノ程度の生産しか出来ない。その格差は九世代、台湾系エヌビィディアのCPUには十世代の開きがある。つまり、9から10の「周回遅れ」である。
そのうえ、第二の敗戦が重なり、「喪われた三十年」の間に半導体の技術者が日本から払底していた。優秀なエンジニアは外国企業に移籍した。
TSMCには適わないと鬱々としていた。それが日本の半導体業界の空気だった。
「ラピダスが2ナノを2027年につくる」と宣言するや、「できっこない」の大合唱が日本のビジネスジャーナリズムを覆い尽くした。筆者の平井氏もいささか懐疑的である。
たしかに2ナノ実現は「困難である」。しかし日本はこの目標を達成しなければならないのである。
嘗て日米半導体協定で日本を潰したのはアメリカである。
そのアメリカが「心変わり」。いきなり2ナノ半導体開発を日本に奨め、ラピダスに全面協力となった背景がある。IBMがラピダスを支援する態勢が急速に組まれ、突然、日本政府は9200億円の補助金を供与するまでになった。
これは戦後GHQが日本を非武装の三流農業国家として落とし込んできた占領政策を百八十度変えて、武装と産業復活を推奨し始めたこととに似ている。この基軸の転換の直接動機は朝鮮戦争だった。
半導体戦争で対日戦略をがらりと一変させたのは、まさに朝鮮戦争のケースと似ている。
すなわち平井宏治氏が指摘するように「米国は中国を『競争相手』と位置づけるが、中国は米国を『超限戦』の対象、『闘争相手』」なのである。
米国は中国に新技術を渡さないと決意し、ものつくりは『カントリーリスクの高い』台湾、韓国より日本がふさわしいという政治判断に至ったのだ。
なぜか。
ファーウェイの新製品に7ナノ半導体が使われていたが、これはADSLのエンジニアが機密データを中国に渡したこと、韓国、台湾からスカウトされて技術者たちが協力し、当該半導体は流通の「抜け穴」を通じて中国のSMICに漏れたからだ。
本書はつぎに中国にのめり込んでにっちもさっちもいかなくなったSBG(ソフトバンクグループ)と中国に売り上げの半分を依存する村田製作所の危ない体質に危険信号を発している。
また中国に甘いドイツですら、中国国防七校からの留学生を閉め出し始めた。オランダもそうしているが、日本はノーテンキに受け入れ続けている。アメリカは「中国人とみたらスパイと想え」という認識で留学生受けいれを厳格にしており、大学留学も一年ごとにヴィザの切り替えをさせている。
平和惚けの日本は自衛隊基地の近くに土地や不動産を中国人が購入しても放置してきた。国家安全保障という概念が欠落しているからだ。
次の指摘も重要だろう
「日本の経済安全保障推進法にある四つの重要事項、(1)重要物資の安定的な供給確保、(2)基幹インフラの安定提供、(3)先端的重要技術の開発を支援、(4)特許出願の非公開条項である。これらを基盤とした「セキュリティクリアランス制度」は、これすべて「半導体産業に関連する」のである。
平井氏は経済安全保障のアングルに絞り込んで、状況を分析しつつ、「眠れる半導体大国」の日本が再生するために何を為すべきかを具体的に述べる。理由
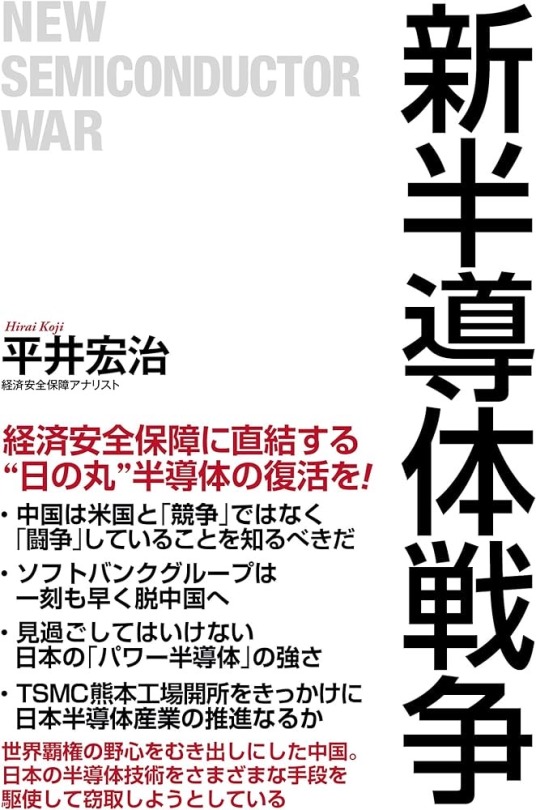
17 notes
·
View notes
Photo

#計量法第9条第1項 #japanpremiumjeans #japanpremium #ジーンズはインチ #インチの美しさを感じて欲しいから #touchislovejeans #愛あるジーンズ #詳しくはホームページで #タッチイズラブジーンズストア #ホームページはプロフィールの概要欄から https://touchislovejeans.com (タッチイズラブジーンズ) https://www.instagram.com/p/CQcxrprjoRs/?utm_medium=tumblr
#計量法第9条第1項#japanpremiumjeans#japanpremium#ジーンズはインチ#インチの美しさを感じて欲しいから#touchislovejeans#愛あるジーンズ#詳しくはホームページで#タッチイズラブジーンズストア#ホームページはプロフィールの概要欄から
0 notes
Quote
「次室士官心得」
(練習艦隊作成、昭和14年5月)
第1 艦内生活一般心得
1、次室士官は、一艦の軍規・風紀の根源たることを自覚し、青年の特徴元気と熱、純 真さを忘れずに大いにやれ。
2、士官としての品位を常に保ち、高潔なる自己の修養はもちろん、厳正なる態度・動 作に心掛け、功利打算を脱却して清廉潔白なる気品を養うことは、武人のもっとも 大切なる修業なり。
3 宏量大度、精神爽快なるべし。狭量は軍隊の一致を破り、陰欝は士気を沮喪せし む。忙しい艦務の中に伸び伸びした気分を忘れるな。細心なるはもちろん必要なる も、「コセコセ」することは禁物なり。
4 礼儀正しく、敬礼は厳格にせよ。次室士官は「自分は海軍士官の最下位で、何に も知らぬのである」と心得、譲る心がけが必要だ。親しき仲にも礼儀を守り、上の 人の顔を立てよ。よからあしかれ、とにかく「ケプガン(次室士官室の長)を立てよ。
5 旺盛なる責任観念の中に常に生きよ。これは士官としての最大要素の一つだ。命令を下し、もしくはこれを伝達す る場合はは、必ずその遂行を見届け、ここに初めてその責任を果したるものと心得べし。
5 犠牲的精神を発揮せよ、大いに縁の下の力持ちとなれ。
6 次室士官時代はこれからが本当の勉強時代、一人前になり、わがことなれりと思うは大の間違いなり。
7、次室士官時代はこれからが本当の勉強時代、一人前にをり、わがことなれりと思うは大の間違いなり。公私を誤 りたるくそ勉強は、われらの欲せざるところなれども、学術方面に技術方面に、修練しなければならぬところ多し。 いそがしく艦務に追われてこれをないがしろにするときは、悔いを釆すときあり。忙しいあいだにこそ、緊張裡に修 業はできるものなり。寸暇の利用につとむべし。
つねに研究問題を持て。平素において、つねに一個の研究問題を自分にて定め、これにたいし成果の捕捉につと め、一纏めとなりたるところにてこれを記しおき、ひとつひとつ種々の問題にたいしてかくのごとくしおき、後となり てふたたびこれにつきて研究し、気づきたることを追加訂正し、保存しおく習慣をつくれば、物事にたいする思考力 の養成となるのみならず、思わざる参考資料をつくり得るものなり。
8、少し艦務に習熟し、己が力量に自信を持つころとなると、先輩の思慮円熟をるが、かえって愚と見ゆるとき来るこ とあるべし、これすなわち、慢心の危機にのぞみたるなり。この慢心を断絶せず、増長に任じ人を侮り、自ら軽ん ずるときは、技術・学芸ともに退歩し、ついには陋劣の小人たるに終わるべし。
9、おずおずしていては、何もできない。図々しいのも不可なるも、さりとて、おずおずするのはなお見苦しい。信ずる ところをはきはき行なって行くのは、われわれにとり、もっとも必要である。
10、何事にも骨惜L誤をしてはならない。乗艦当時はさほどでもないが、少し馴れて来ると、とかく骨惜しみをするよう になる。当直にも、分隊事務にも、骨惜しみをしてはならない。いかなるときでも、進んでやる心がけか必要だ。身 体を汚すのを忌避するようでは、もうおしまいである。
11、青年士官は、バネ仕掛けのように、働かなくてはならない。上官に呼ばれたときには、すぐ駆け足で近づき、敬 礼、命を受け終わらば一礼し、ただちにその実行に着手するごとくあるべし。
12、上官の命は、気持よく笑顔をもって受け、即刻実行せよ。いかなる困難があろうと、せっかくの上陸ができなか ろうと、命を果たし、「や、御苦労」と言われたときの愉快きはなんと言えぬ。
13、不関旗(他船と行動をともにせず、または、行動をともにできないことを意味する信号旗。転じてそっぽを向くこと をいう)を揚げるな。一生懸命にやったことについて、きびしく叱られたり、平常からわだかまりがあったりして、不 関旗を揚げるというようなことが間々ありがちだが、これれは慎むべきことだ。自惚があまり強過ぎるからである。 不平を言う前に已れをかえりみよ。わが慢心増長の鼻を挫け、叱られるうちが花だ。叱って下さる人もなくなった ら、もう見放されたのだ。叱られたなら、無条件に有難いと思って間違いはない。どうでも良いと思うなら、だれが 余計な憎まれ口を叩かんやである。意見があったら、陰で「ぷつぷつ」いわずに、順序をへて意見具申をなせ。こ れが用いらるるといなとは別問題。用いられなくとも、不平をいわず、命令には絶対服従すべきことはいうまでもな し。
14、昼間は諸作業の監督巡視、事務は夜間に行なうくらいにすべし。事務のいそがしいときでも、午前午後かならず 1回は、受け特ちの部を巡視すべし。
15、「事件即決」の「モツトー」をもって、物事の処理に心がくべし。「明日やろう」と思うていると、結局、何もやらずに 沢山の仕事を残し、仕事に追われるようになる。要するに、仕事を「リード」せよ。
16、なすべき仕事をたくさん背負いながら、いそがしい、いそがしいといわず片づければ、案外、容易にできるもので ある。
17、物事は入念にやれ。委任されたる仕事を「ラフ」(ぞんぎい〕にやるのは、その人を侮辱するものである。ついに は信用を失い、人が仕事をまかせぬようになる。また、青年士官の仕事は、むずかしくて出来ないというようなも のはない。努力してやれば、たいていのことはできる。
18、「シーマンライク」(船乗りらしい)の修養を必要とす。動作は「スマート」なれ。1分1秒の差が、結果に大影響を あたえること多し。
19、海軍は、頭の鋭敏な人を要するとともに、忠実にして努力精励の人を望む。一般海軍常識に通ずることが肝要、 かかることは一朝一夕にはできぬ。常々から心がけおけ。
20 要領がよいという言葉もよく聞くが、あまりよい言葉ではない。人前で働き、陰でずべる類いの人に対する尊称 である。吾人はまして裏表があってはならぬ。つねに正々堂々とやらねばならぬ。
21、毎日各室に回覧する書類(板挟み)は、かならず目を通し捺印せよ。行動作業や当直や人事に関するもので、 直接必要なる事項が沢山ある。必要なことは手帖に抜き書きしておけ。これをよく見ておらぬために、当直勤務 を間違っていたり、大切な書類の提出期目を誤ったりすることがある。
22、手帖、「パイプ」は、つねに持っておれ。これを自分にもっとも便利よきごとく工夫するとよい。
23、上官に提出する書類は、かならず自分で直接差し出すようにせよ。上官の机の上に放置し、はなはだしいのは 従兵をして持参させるような不心得のものが間々ある。これは上官に対し失礼であるばかりでなく、場合により ては質問されるかも知れず、訂正きれるかも知れぬ。この点、疎にしてはならない。
24、提出書類は早目に完成して提出せよ。提出期口ぎりぎり一ぱい、あるいは催促さるごときは恥であり、また間違 いを生ずるもとである。艦長・副長・分隊長らの捺印を乞うとき、無断で捺印してはいけない。また、捺印を乞う 事項について質問されても、まごつかぬよう準備調査して行くことが必要。捺印を乞うべき場所を開いておくか、 または紙を挾むかして分かりやすく準備し、「艦長、何に御印をいただきます」と申し出て、もし艦長から、「捺して 行け」と言われたときは、自分で捺して、「御印をいただきました」ととどけて引き下がる。印箱の蓋を開け放しに して出ることのないように、小さいことだが注意しなければならぬ。
25、軍艦旗の揚げ降ろしには、かならず上甲板に出て拝せよ。
26、何につけても、分相応ということを忘れるな。次室士官は次室士官として、候補生は候補生として。少尉、中尉、 各分あり。
27、煙草盆の折り椅子には腰をおろすな。次室士官は腰かけである。
28、煙草盆のところで腰かけているとき、上官が来られたならば立って敬礼せよ。
29、機動艇はもちろん、汽車、電車の中、講話場において、上級者が来られたならば、ただちに立って席を譲れ。知 らぬ顔しているのはもっとも不可。
30、出入港の際は、かならず受け持ちの場所におるようにせよ。出港用意の号音に驚いて飛び出すようでは心がけ が悪い。
31、諸整列があらかじめ分かっているとき、次室士官は、下士官兵より先にその場所にあるごとくせ。
32、何か変わったことが起こったとき、あるいは何となく変わったことが起こったらしいと思われるときは、昼夜を問わ ず第1番に飛び出してみよ。
33、艦内で種々の競技が行なわれたり、または演芸会など催される際、士官はなるべく出て見ること。下士官兵が 一生懸命にやっているときに、士官は勝手に遊んでおるというようなことでは面白くない。
34、短艇に乗るときは、上の人より遅れぬように、早くから乗っておること。もし遅れて乗るような場合には、「失礼い たしました」と上の人に断わらねばならぬ。自分の用意が遅れて定期(軍艦と陸上の間を往復し、定時にそれら を発着する汽艇のこと)を待たすごときは、もってのほである。かかるときは断然やめて次ぎを待つべし。
短艇より上がる場合には、上長を先にするこというまでもなし。同じ次室士官内でも、先任者を先にせよ。
35、舷門は一艦の玄開口なり。その出入りに際しては、服装をととのえ、番兵の職権を尊重せよ。雨天でないとき、 雨衣や引回しを着たまま出入りしたり、答礼を欠くもの往々あり、注意せよ。
第2 次室の生活について
1、我をはるな。自分の主張が間遠っていると気づけば、片意地をはらす、あっさりとあらためよ。 我をはる人が1人でもおると、次室の空気は破壊される。
2、朝起きたならば、ただちに挨拶せよ。これが室内に明るき空気を漂わす第一誘因だ。3、次室 にはそれぞれ特有の気風かある。よきも悪きもある。悪い点のみ見て、憤慨してのみいては ならない。神様の集まりではないから、悪い点もあるであろう。かかるときは、確固たる信念と決心をもって自己を修め、自然に同僚を善化せよ。
4、上下の区別を、はっきりとせよ、親しき仲にも礼儀をまもれ。自分のことばかり考え、他人のことをかえりみないよ うな精神は、団体生活には禁物。自分の仕事をよくやると同時に、他人の仕事にも理解を持ち便宜をあたえよ。
5、同じ「クラス」のものが、3人も4人も同じ艦に乗り組んだならば、その中の先任者を立てよ。「クラス」のものが、次 室内で党をつくるのはよろしくない。全員の和衷協力はもっとも肝要なり。利己主義は唾棄すべし。
6、健康にはとくに留意し、若気にまかせての不摂生は禁物。健全なる身体なくては、充分をる御奉公で出来ず。忠 孝の道にそむく。
7、当直割りのことで文句をいうな。定められた通り、どしどしやれ。病気等で困っている人のためには、進んで当直を 代わってやるぺきだ。
8、食事に関して、人に不愉快な感じを抱かしむるごとき言語を慎め。たとえば、人が黙って食事をしておるとき、調理 がまずいといって割烹を呼びつけ、責めるがごときは遠慮せよ。また、会話などには、精練きれた話題を選べ。
9、次室内に、1人しかめ面をして、ふてくされているものがあると、次室全体に暗い影ができる。1人愉快で朗らかな 人がいると、次室内が明るくなる。
10、病気に羅ったときは、すぐ先任者に知らせておけ。休業になったら(病気という程度ではないが(身体の具合い が悪いので、その作業を休むこと)先任者にとどけるとともに、分隊長にとどけ、副長にお願いして、職務に関する ことは、他の次室士官に頼んでおけ。
11、次室内のごとく多数の人がいるところでは、どうしても乱雑になりがちである。重要な書類が見えなくなったとか 帽子がないとかいってわめきたてることのないように、つねに心がけなければならぬ。自分がやり放しにして、従 兵を怒鳴ったり、他人に不愉快の思いをきせることは慎むべきである。
12、暑いとき、公室内で仕事をするのに、上衣をとるくらいは差し支えないが、シャツまで脱いで裸になるごときは、 はをはだしき不作法である。
13、食事のときは、かならず軍装を着すべし。事業服のまま食卓についてはならぬ。いそがしいときには、上衣だけ でも軍装に着換えて食卓につくことになっている。
14、次室士官はいそがしいので一律にはいかないが、原則としては、一同が食卓について次室長(ケプガソ)がはじ めて箸をとるべきものである。食卓について、従兵が自分のところへ先に給仕しても、先任の人から給仕せしむる ごとく命すべきだ。古参の人が待っているのに、自分からはじめるのは礼儀でない。
15、入浴も先任順をまもること。水泳とか武技など行をったときは別だが、その他の場合は遠慮すべきものだ。
16 古参の人が、「ソファー」に寝転んでいるのを見て、それを真似してはいけない。休むときても、腰をかけたまま、 居眠りをするぐらいの程度にするがよい。
17、次室内における言語においても気品を失うな。他の人に不快な念を生ぜしむべき行為、風態をなさず、また下士 官兵考課表等に関することを軽々しく口にするな。ふしだらなことも、人秘に関することも、従兵を介して兵員室に 伝わりがちのものである。士官の威信もなにも、あったものでない。
18、趣味として碁や将棋は悪くないが、これに熱中すると、とかく、尻が重��なりやすい。趣味と公務は、はっきり区別 をつけて、けっして公務を疎にするようなことがあってはならぬ。
19、お互いに、他の立場を考えてやれ。自分のいそがしい最中に、仕事のない人が寝ているのを見ると、非難した いような感情が起こるものだが、度量を宏く持って、それぞれの人の立場に理解と同情を持つことが肝要。
20、従兵は従僕にあらず。当直、その他の教練作業にも出て、士官の食事の給仕や、身辺の世話までするのであ るからということを、よく承知しておらねばならぬ。あまり無理な用事は、言いつけないようにせよ。自分の身辺の ことは、なるべく自分で処理せよ、従兵が手助けしてくれたら、その分だけ公務に精励すべきである。釣床を釣っ てくれ、食事の給仕をしてくれるのを有難いと思うのは束の間、生徒・候補生時代のことを忘れてしまって、傲然と 従兵を呼んで、ちょっと新聞をとるにも、自分のものを探すにもこれを使うごときは、わがみずからの品位を下げゆ く所以である。また、従兵を「ボーイ」と呼ぶな。21、夜遅くまで、酒を飲んで騒いだり、大声で従兵を怒鳴ったりす ることは慎め。
21、課業時のほかに、かならず出て行くべきものに、銃器手入れ、武器手入れに、受け持ち短艇の揚げ卸しがある
第3 転勤より着任まで
1、転勤命令に接したならば、なるべく早く赴任せよ。1日も早く新勤務につくことが肝 要。退艦したならば、ただちに最短距離をもって赴任せよ、道草を食うな。
2、「立つ鳥は後を濁さず」仕事は全部片づけておき、申し継ぎは万遺漏なくやれ。申し 継ぐべき後任者の来ないときは、明細に中し継ぎを記註しおき、これを確実に託し おけ。
3、退艦の際は、適宜のとき、司令官に伺候し、艦長・副長以下各室をまわり挨拶せよ4、新たに着任すべき艦の役務、所在、主要職員の名は、前もって心得おけ。
5、退艦・着任は、普通の場合、通常礼装なり。
6、荷物は早目に発送し、着任してもなお荷物が到着せぬ、というようなことのないようにせよ。手荷物として送れば、早目に着く。
7、着任せば、ただちに荷物の整理をなせ。
8、着任すべき艦の名を記入したる名刺を、あらかじめ数枚用意しおき、着任予定日時を艦長に打電しおくがよい。
9、着任すべき艦の所在に赴任したるとき、その艦がおらぬとき、たとえば急に出動した後に赴任したようなと時は、 所在鎮守府、要港部等に出頭して、その指示を受けよ。さらにまた、その地より他に旅行するを要するときは、証 明書をもらって行け。
10、着任したならば、当直将校に名刺を差し出し、「ただいま着任いたしました」ととどけること。当(副)将校は副長に 副長は艦長のところに案内して下さるのが普通である。副長から艦長のところへつれて行かれ、それから次室 長が案内して各室に挨拶に行く。艦の都合のよいとき、乗員一同に対して、副長から紹介される。艦内配置は、 副長、あるいは艦長から申し渡される。
11、各室を一巡したならば、着物を着換えて、ひとわたり艦内を巡って艦内の大体を大体を見よ。
12、配置の申し継ぎは、実地にあたって、納得の行くごとく確実綿密に行なえ。いったん、引き継いだ以上、全責任 は自己に移るのだ。とくに人事の取り扱いは、引き継いだ当時が一番危険、ひと通り当たってみることが肝要だ。 なかんずく叙勲の計算は、なるべく早くやっておけ。
13、着任した日はもちろんのこと、1週間は、毎夜巡検に随行するごとく心得よ。乗艦早々から、「上陸をお願い致し ます」などは、もってのほかである。
14、転勤せば、なるべく早く、前艦の艦長、副長、機関長、分隊長およびそれぞれ各室に、乗艦中の御厚意を謝す る礼状を出すことを忘れてはならぬ。
第4 乗艦後ただちになすべき事項
1、ただちに部署・内規を借り受け、熟読して速やかに艦内一般に通暁せよ。
2、総員起床前より上甲板に出で、他の副直将校の艦務遂行ぶりを見学せよ。2、3日、当直ぶりを注意して見てお れば、その艦の当直勤務の大要は分かる。しかして、練習艦隊にて修得せるところを基礎とし、その艦にもっとも 適合せる当直をなすことができる。
3、艦内旅行は、なるぺく速やかに、寸暇を利用して乗艦後すぐになせ。
4、乗艦して1ヵ月が経過したならば、隅々まで知悉し、分離員はもちろん、他分隊といえども、主たる下士官の氏名 は、承知するごとく心がけよ。
第5上陸について
1、上陸は控え目にせよ。吾人が艦内にあるということが、職責を尽くすということの大部である。職務を捨ておいて 上陸することは、もってのほかである。状況により、一律にはいえぬが、分隊長がおられぬときは、分隊士が残る ようにせよ。
2、上陸するのがあたかも権利であるかのように、「副長、上陸します」というべきでない。「副長、上陸をお願いしま す」といえ。
3、若いときには、上陸するよりも艦内の方が面白い、というようにならなけれぱならない。また、上陸するときは、自 分の仕事を終わって、さっぱりした気分で、のびのびと大いに浩然の気を養え。
4、上陸は、別科後よりお願いし、最終定期にて帰艦するようにせよ。出港前夜は、かならず艦内にて寝るようにせよ。上陸する場合には、副長と己れの従属する士官の許可をえ、同室者に願い、当直将校にお願いして行くのが慣例 である。この場合、「上陸をお願い致します」というのが普通、同僚に対しては単に、「願います」という。この「願い ます」という言葉は、簡にして意味深長、なかなか重宝なものである。すなわち、この場合には、上陸を願うのと、 上陸後の留守中のことをよろしく頼む、という両様の意味をふくんでいる。用意のよい人は、さらに関係ある准士 官、あるいは分隊先任下士官に知らせて出て行く。帰艦したならば、出る時と同様にとどければよい。たたし、夜 遅く帰艦して、上官の寝てしまった後は、この限りでない。士宮室にある札を裏返すようになっている艦では、か ならず自分でこれを返すことを忘れぬごとく注意せよ。
6、病気等で休んでいたとき、癒ったからとてすぐ上陸するごときは、分別がたらぬ。休んだ後なら、仕事もたまってお ろう、遠慮ということが大切だ。
7、休暇から帰ったとき、帰艦の旨をとどけたら、第1に留守中の自分の仕事および艦内の状況にひと通り目を通せ。 着物を着換え、受け持ちの場所を回って見て、不左中の書類をひと通り目を通す心がけが必要である。
8、休暇をいただくとき、その前後に日曜、または公暇日をつけて、規定時日以上に休暇するというがごときは、もっと も青年士官らしくない。
9、職務の前には、上陸も休暇もない、というのが士官たる態度である。転勤した場合、前所轄から休暇の移牒があ ることがあるけれども、新所轄の職務の関係ではいただけないことが多い。副長から、移牒休暇で帰れといわる れば、いただいてもよいけれども、自分から申し出るごときことは、けっしてあってはならぬ。
第6部下指導について
1、つねに至誠を基礎とし、熱と意気をもって国家保護の大任を担当する干城の築造者たることを心がけよ。「功は部下に譲り、部下の過ちは 自から負うは、西郷南洲翁が教えしところなり。「先憂後楽」とは味わうべき言であって、部下統御���機微なる心理も、かかるところにある統御者たるわれわれ士官は、つねにこの心がけが必要である。石炭 積みなど苦しい作業のときには、士官は最後に帰るようつとめ、寒い ときに海水を浴びながら作業したる者には、風呂や衛生酒を世話してやれ。部下につとめて接近して下情に通せよ。しかし、部下を狎れしむるは、もっとも不可、注意すべきである。
2、何事も「ショート・サーキット」(短絡という英語から転じて、経由すべきところを省略して、命令を下し、または報告する海軍用語)を慎め。い ちじは便利の上うたが、非常なる悪結果を齋らす。たとえば、分隊士を抜きにして分隊長が、直接先任下士官に命じたとしたら、分隊士たる者いかなる感を生ずるか。これは一例だか、かならず順序をへて命 を受け、または下すということが必要なり。
3、「率先躬行」部下を率い、次室士官は部下の模範たることが必要だ。物事をなすにもつねに衆に先じ、難事と見ば、 真っ先にこれに当たり、けっして人後におくれざる覚悟あるべし。また、自分ができないからといって、部下に強制 しないのはよくない。部下の機嫌をとるがごときは絶対禁物である。
4、兵員の悪きところあらば、その場で遠慮なく叱咤せよ。温情主義は絶対禁物。しかし、叱責するときは、場所と相 手とを見でなせ。正直小心の若い兵員を厳酷な言葉で叱りつけるとか、また、下士官を兵員の前で叱責するなど は、百害あって一利なしと知れ。
5、世の中は、なんでも「ワソグランス」(一目見)で評価してはならぬ。だれにも長所あり、短所あり。長所さえ見てい れば、どんな人でも悪く見えない。また、これだけの雅量が必要である。
6、部下を持っても、そうである。まずその箆所を探すに先だち、長所を見出すにつとめることが肝要。賞を先にし罰を 後にするは、古来の名訓なり。分隊事務は、部下統御の根底である。叙勲、善行章(海軍の兵籍に人ってから3 年間、品行方正・勤務精励な兵にたいし善行章一線があたえられ、その後、3年ごとに同様一線あてをくわえる。 勇敢な行為などがあった場合、特別善行章が付与される)等はとくに慎重にやれ。また、一身上のことまで、立ち 入って面倒を見てやるように心がけよ。分隊員の入院患者は、ときどき見舞ってやるという親切が必要だ。
第7 その他一般
1、服装は端正なれ。汚れ作業を行なう場合のほかは、とくに清潔端正なるものを用いよ。帽子がまがっていたり、「 カラー」が不揃いのまま飛び出していたり、靴下がだらりと下がっていたり、いちじるしく雛の寄った服を着けている と、いかにもだらしなく見える。その人の人格を疑いたくなる。
2、靴下をつけずに靴を穿いたり、「ズボン」の後の「ビジヨウ」がつけてなかったり、あるいはだらりとしていたり、下着 をつけず素肌に夏服・事業服をつけたりするな。
3 平服をつくるもの一概に非難すべきではいが、必要なる制服が充分に整っておらぬのに平服などつくるのは本末 顛倒である。制服その他、御奉公に必要をる服装属具等なにひとつ欠くるところなく揃えてなお余裕あらば、平服 をつくるという程度にせよ。平服をつくるならば、落ちついて上品な上等のものを選べ。無闇に派手な、流行の尖 端でもいきそうな服を着ている青年士官を見ると、歯の浮くような気がする。「ネクタイ」や帽子、靴、「ワイシャツ」 「カラー」「カフス」の釦まで、各人の好みによることではあろうが、まず上品で調和を得るをもって第1とすべきであ る。
4、靴下もあまりケパケパしいのは下品である。服と靴とに調和する色合いのものを用いよ。縞の靴下等は、なるべく はかぬこと、事業服に縞の靴下等はもってのほかだ。
5、いちばん目立って見えるのは、「カラー」と「カフス」の汚れである、注意せよ。また、「カフス」の下から、シャツの 出ているのもおかしいものである。
6、羅針艦橋の右舷階梯は、副長以上の使用さるべきものなり。艦橋に上がったら、敬礼を忘れるな。
7 陸上において飲食するときは、かならず一流のところに入れ。どこの軍港においても、士官の出入りするところと、 下士官兵の出入りするところは確然たる区別がある。もし、2流以下のところに出入りして飲食、または酒の上で 上官たるの態度を失し、体面を汚すようなことがあったら、一般士官の体面に関する重大をることだ。
8、クラスのためには、全力を尽くし一致団結せよ。
9、汽車は2等(戦前には1、2、3等の区分があった)に乗れ。金銭に対しては恬淡なれ。節約はもちろんだが、吝薔 に陥らぬよう注意肝心。
10、常に慎独を「モットー」として、進みたきものである。是非弁別の判断に迷い、自分を忘却せるかのごとき振舞い は、吾人の組せざるところである。
hiramayoihi.com/Yh_ronbun_dainiji_seinenshikankyouikugen.htm
20 notes
·
View notes
Link
ワクチン配布数に異常なバラつきがある問題で、基礎自治体の接種体制に大混乱が生じている。その事態改善と収拾に地方行政が奔走しているため現況を報告したい。にわかには信じがたい状況で、接種予約が絶望的に無理な自治体と、接種対象たる高齢者の人数以上の配布を受けた自治体もある。
人口密集地である政令市や感染者数が激増している自治体に大きくカバーして欲しいところだが、隣接自治体でも三倍の格差がある。自治体の接種体制は、大混乱に陥ってしまい、この混乱はさらに激しくなる危険が否定できない。
例えば、人口6,764人の吉富町には、2925回分が配布。同町の高齢者は2,124人であり、つまり希望者は100%接種できる。というか余ってしまう。
隣接する上毛町は人口7,619人(高齢者は2,648人)で吉富より規模が大きいが、975回分のみ。当選確率は約37%。上毛町と吉富町は互いに隣接するのだが、この倍率差は異常だろう。
さらに、豊前市の人口は25,341人(高齢者9,097人)は、吉富町と同数の2925回分に留まる。当選確率は約32%。
築上町は、18,119人(高齢者6,569人)、配布数は1950回分。当選確率は最低の約29%である。
便宜的に用いた当選確率とは、全高齢者が接種を希望したと仮定し、かつ今回のロットから次回の配布が遅延したという条件で計算した。
問題は、「豊前市・吉富町・上毛町・築上町」は、広域連携で合同で接種していく点。それぞれの会場で互いの住民が鉢合わせるわけだが、一自治体は100%の接種で、隣接自治体は3割以下だ。同じ医師会から支援を受け、なんと予約に要するコールセンターも統合されている。配布数が不十分な自治体は第一回接種の予約を受け付けている中で、充分に有する自治体は第二回接種を求める。コールセンターは、二つの業務が混在してしまい、また接種にあたる医師も対応が難しい。
行橋市73,317人(高齢者21,562人)は、2925回分(3箱)。高齢者数が10倍も違う吉富町と同数だ。当選確率は、13%。
本市に隣接するみやこ町は、人口19,512人(高齢者7,721人)に対し、なぜか行橋市よりも多い3900回分(4箱)を配布。当選確率は約50%。
みやこ町には、医師はほとんどおらず、結果的に行橋市の医師もサポートしていく可能性もある。(行橋みやこ医師会)
隣接自治体において、ここまでの当選確率の差は、住民に説明ができない。行橋市においても感染者は出ている。
飯塚市128,184人(高齢者40,121人)も2925回分(3箱)。高齢者数が20倍近く違う吉富町と同数だ。当選確率は、7%に過ぎない。県が調整した結果だが、飯塚市が悪いわけではない。
ここで行橋市と飯塚市について述べさせて頂きたいが、自治体単独での接種能力を一般に有する自治体である。町村の場合は広域連携などで合同接種などを行っており、当然ながら「飯塚市・行橋市は、打つ能力」を持っている。銃はあれども弾がないという状態。
町村を優先配布した可能性は否定できないという声もあるだろう。
しかし、那珂川市50,323人(高齢者11,545)には13箱、実に12675回分が配布。高齢者数よりも多いため、当選確率は100%だ。
地域差なのかと言えばそうではない。遠賀川周辺の3町の例。
65歳以上人口が8780人の水巻町に3箱、9828人の岡垣町に9箱、5800人の遠賀町に6箱と人口規模に応じていない。
当然、地方行政は大混乱に陥った。
最悪の事態としては、かなりの量を破棄せざるを得ない危険性も指摘されていた。理由は本稿で詳述するが、1箱が975回分のため高齢者数が2000とか3000の小規模自治体で中途半端な人数で開封してしまうと、かなりの量を破棄せざるを得ないため。それを抑止するための広域連携だったのだが、バラツキが大きすぎて同時接種は絶望的だ。
また、接種能力を有する中規模自治体で、近隣の町村のサポートを行う市は、自らが守るべき市民の接種が終わってない中で、ワクチンのみ持っている町村の支援を行うのは住民感情からも難しい。接種支援に周れずデッドストック化するリスクもあった。
これらワクチンの配布偏在ですが、本日の状況を報告します。
(プレス対応)
昨日が祝日であったため、(配布箱数のデータについて)メディア側が裏取りできませんでした。公式の資料ではありますが非公開であったため、プレスが扱うにあたっては事実確認が必要だったのです。ほぼ徹夜のまま(早朝4時ぐらいまで)複数の電話会議・オンライン会議を行っており、朝一で対応を開始。
朝より対応。無事に裏取りを完了させ、首長のコメントも用意できました。
明日の朝、一紙ですが掲載できます。web版でありますが、すでに記事はアップされています。取材を経ての、正規の報道です。
次に、地方公共6団体。
動いたのは、市長会です。ここからは御礼になるのですが、谷畑英吾・前湖南市長(全国の副会長など要職を歴任)が一緒に動いてくださいました。一昨日のBlogを拡散してくださり、動きがありました。
私の住む行橋市の田中市長より電話を頂き、本庄市(埼玉県��の吉田信解市長(市長会の委員長)より架電があったとのこと。当市市長からの伝聞にはなりますが「全国市長会会長の立谷会長が、本日たまたま河野大臣に要請書を持って行くところだったので、本問題について共有している。」とのことでした。谷畑市長には行橋市と豊前市の偏在について報告していたため、本庄市長からは行橋・豊前に連絡を入れてくれたと谷畑市長からお伺いしました。当市市長からのお礼をお伝えしました。
私は市長職は有しておりませんので断片情報にはなりますが、市長会トップからは(恐らく自治体名は伏せて)配布数の偏在について報告がなされた模様です。谷畑市長を経由し、前述の自治体情報については逐一調査するとともに、私の信頼する敏腕記者たちが徹底的に数字の洗い出しを行っていきました。皆、徹夜の連続でした。プレスの動きを淡々と報告しつつ、数字の積み上げ作業を行っていきました。
自治体へのワクチン配布は、厚労省から総務省に移管されていました。総務大臣の記者会見において、本件が反映されたことを確認。各所にお礼の連絡を入れていったのは夕刻でした。目の前の偏在の問題は未解決も、2陣以降の効率化の向上に期待。
ここは総務マターのため、これより都道府県に指導を入れて頂くにあたって、その資料作成を行っておりました。
そうしたところ、これら偏在を解消するためでしょうか、国からさらなる次の便が実数が突然の公開。川の大臣の会見です。各地の市長・町長の動き、メディアの動きが奏功した可能性もあります。
私もその前線で戦っていたのですが、GW直前ゆえ平日が一日しかありません。裏取りを短期決戦で完了させる必要があったため、かなりの手続きを簡素化(詠唱破棄)してしまいました。近隣町長には非常に申し訳なく思っておりましたところ、上毛町の坪根町長が同行してくださり、一部の町長への報告が叶いました。築上町の新川町長にお会いし状況報告をしたのは19時を回っており、ご迷惑にも自宅までお邪魔してしまいました。
とりあえず、大臣まで公式団体名にて情報があがったと想定されるため、第一次の動きとしては良しとします。私は市議でありますので、これが職責の果たし方。
明日、明後日までは過負荷かかる見込み。
さて、これら動きの中で、今後の課題や混乱が想定される箇所が洗い出されてきましたので報告します。
国の新たな発表により、偏在の多くは解消されると期待いたしますが、地方行政における混乱は継続する可能性があり、それを早期に事前想定することにより「接種の混乱抑止、および事態解決」を期待して本稿を記します。
すでに本日の記事がネットには公開されておりますので併せて紹介します。
※ 日本Blog村の登録もしてみました。二つのバナーのクリックをお願いします。
↓今日は何位でしょう?読み進む前にチェック。↓
↓記事が気に入ったらFBのイイネ・ツイート等もお願いします。↓
にほんブログ村
バナーが表示されない方は、こちらをクリック願いします。(同じものです。)
不定期発信にはなりますが、チャンネル登録をお願いします。
(OGP画像)
報道の紹介明日の朝刊にも掲載されることでしょう。
コロナワクチン、福岡県内の自治体配分数に格差 調整不足を指摘する声も
新型コロナウイルスのワクチン確保をめぐり、福岡県内の自治体間で格差が生じている。5月以降、各自治体で順次、接種を進めていく中、初期段階では人口規模が同程度の自治体間で確保数が大きく異なるケースがみられ、場合によっては規模との逆転現象も生じた。自治体からは必要数をまとめる県の調整不足を指摘する声が上がる。
福岡県内には6月末までに2456箱(6回接種で約287万3千回分)が届く。このうち、5月10日からの2週間に各自治体に届けられるワクチンは567箱で、最多の144箱を受け取る福岡市をはじめ、県内60市町村で高齢者向けへの接種準備が進む。
ただ、複数の県内自治体から「人口規模や接種体制の実情と食い違う配分だ」との指摘が相次ぐ。
県西部では、65歳以上人口(平成27年国勢調査)で約10倍の差がある行橋市(1万9835人)と吉富町(1989人)で、配分数はともに3箱だった。遠賀川周辺の3町でも、65歳以上人口(同)が8780人の水巻町に3箱、9828人の岡垣町に9箱、5800人の遠賀町に6箱と人口規模に応じていない。
自治体のワクチン確保担当者は「自前の接種体制をもとに2週間で可能な量を申請した」との声がある一方、「供給体制が不確実な中、75歳以上の2回接種に必要な量を確保しようとした」との説明もあり、考え方の違いが浮き彫りに。この違いが格差が生じた原因とみられる。
自治体の申請を取りまとめる県は「市町村には2週間分で接種可能な量を申請するよう通知している」とするが、マンパワー不足や、時間の制約から「各自治体から上がってきた申請を信頼するしかない」(県担当者)という。
ワクチンをめぐっては、必要数は確保される一定の見込みが立ち、今後の配分によって自治体間の偏在は解消していくとみられる。
ただ、ある県西部の自治体首長は「都市部で封じ込めを進めるための優先供給は理解できるが、郡部で格差が生じるのは住民に説明ができず、理解に苦しむ(配分数の)増減もあった。現状のままでは不信を招く」と憤りを隠さない。
産経ニュースコロナワクチン、福岡県内の自治体配分数に格差 調整不足を指摘する声もhttps://www.sankei.com/region/news/210430/rgn2104300003-n2.html自治体の申請を取りまとめる県は「市町村には2週間分で接種可能な量を申請するよう通知している」とするが、マンパワー不足や、時間の制約から「各自治体から上がってきた…
ワクチン配布の考え方(私見)まずもって私見であることは冒頭で述べておきます。
ワクチンそのものが危険という意見がネット上にはあるのは重々承知しておりますが、特に高齢者の中には熱望している方もおり、「国費で購入した資材」に対する「入手難易度」の機会平等の観点は述べられるべきだと考えております。
その上で、人口密集地である政令指定都市や大規模自治体には集中投資して頂いて全く構わないと(少なくとも私個人は)考えています。これは各自治体ごとに考えがありましょうし、接種希望者の気持ちを考えれば「あくまで私見」と述べるに留めさせて頂きたい。
感染者が増えている自治体やまんぼう、ワクチン接種の傾斜配分は全くもって否定する立場ではありません。
むしろ傾斜配分がなされていなければ、それは逆の問題も指摘されるでしょう。単に人口比で割ればいいとは思っておりません。
しかし、明らかに人口比が異なり、10倍とか20倍という差があるのは問題です。各自治体は、接種体制を構築してきており、体制構築(銃を用意)するも弾は来ない、これでは何のために地方行政が準備をしてきたのか全く意味が分からない。
また、多く取り過ぎた自治体も果たして接種可能なのか?という話がでてくる。同時に接種できる人数には、施設規模なども影響してくるわけで、ワクチンさえあれば一気に終わるというものでもない。著しくバランスを欠くことは凄まじい問題を生じてしまう。
特に広域連携の話は、別項で詳述させて頂きますが、「偏在」は接種体制そのものを破壊してしまうのです。この点は強く主張したい。
高齢者への接種を進めるのであれば、対応にあたる医師・看護師への接種を事前に完了させたうえで、まずは人口比(より正確には高齢者数の比率)で基準値を作成する。その上で政令市や人口密集地に加配、ここは大きく加配すべきでしょう。さらに政令市と交流人口の多い自治体に傾斜配分をかけます。
当然ながら感染者数が激増している自治体やまんぼうによる加配も行います。
さらに、接種体制が充分に整っている、つまり銃の多い自治体にもプラスαを行う。
これがスタンダードな考え方ではないでしょうか。
基準値を設け、これをベースに置いたのは地方自治体が接種にあたるためです。
当選倍率に著しい差が出てしまえば、恐ろしいまでの不満を住民に与えることになる。地方の首長は、あくまで地域住民に選ばれているのであり、守るべき住民がおります。行橋市長は行橋市民に選ばれ、そして行橋市民が雇っているのです。行橋市の職員を養っているのは、行橋市民です。
いずれの自治体も、自分の市民を守りたい!という思いは当然に出てくるわけであり、郡部や隣接自治体において高齢化率や感染者数に違いはないものの、何倍もの当選確率の差が出た場合には「地方行政は、住民に説明できない」のです。
その不平不満の中で、市職員らが現場に立てるかと言えば答えはノーです。
基礎自治体には振った以上は、最低限の格差是正はなされていなければ【接種はできません。】というのが私の考えです。
よって最低条件をクリアした上で、つまり一定の公平性は担保しつつも、人口密集地や感染数の多い地域に集中投資する。ここはセンスなのでしょうが、私ならば人口比を5割、傾斜配分用に5割です。傾斜の比率が高いように感じるかもしれませんが、政令市と一般市の人口差は凄まじいものがあり、これぐらいの比率を設けなければ「有意な差」は得られないと考える為です。あくまで私見にはなりますけれども。
一般市側からのクレームはあるかと思いますが、「感染抑制」という考えに立ちかれば、人と人が接する可能性の高いところから集中運用するよりなく、ゆえに準備が整っている自治体にも若干の加配を行うことを条件に交渉します。
スタンダードな考え方ではないでしょうか。
(あくまで私見にはなります。)
大事なことは、ワクチンを熱望する高齢者がいずれの自治体にもおり、現場で対応する市職員が「住民にちゃんと説明できる」だけのロジックとなっている必要があるという点です。そこが満たせるのであれば、どのような方法でも構わない。
後段においては、私個人の考えであるとさらに断ったうえで、高齢者への接種の優先順位にも言及させて頂きたい。
高齢者のみへの接種という国の方針に反発するわけではありませんが、私は「政令市・人口密集地の”高齢者以外の層”」にも早期に接種して良かったのではないかと思っています。難しい政治判断になるとは思いますが、外に出て、かつ人と会う者にこそ接種を急ぐべきです。
果たして若者が接種を希望するかは分かりませんし(ネット上には危険論があることは承知していると断ったうえで)希望する若者にも接種して行った方が、最終的には感染を沈静化させる近道だと思えてならないのです。
郡部、いわゆる田舎においては、都心部から持ち込まれる事例が多いのは事実です。
まずは都心部を抑えなければ、郡部の自治体は守れない。医療体制も貧弱であり、ここはクラスターが発生、重症者が大量に出た場合には本当に対処不可能なのです。
だからこそ、地方議員としては「都市部の感染抑止を最優先」することは方策としてはアリだと思っており、高齢者のみに限定しての接種ではなく、もう一歩踏み込んだ対策があってもよかったのではないかと考えています。
※ しかし、熱望する高齢者が大量に存在する中で、この政策決定を(自分自身がその立場にあったと仮定して)私ができるかと言えば、強く自信を持つこともできないことは正直に述べておきます。
広域連携とワクチンの破棄
冒頭において、豊前市・上毛町・吉富町・築上町の事例を述べました。
これは県内の各所でも起きていることかと思いますが、連携して接種にあたります。
豊前は市政にはなりますが、人口は2万人代であり潤沢な市職員を有するわけではありません。また近隣の3町は独自の接種体制を構築するのは難しいでしょう。そもそも医師会が全ての自治体にあるわけではないのです。
メディアは大規模自治体の事例ばかりを取り上げますが、郡部には郡部の難しさがあるのです。
1市3町で連携し、共通のコールセンター、同じ医師会で対処する。
事例で言えば、Aチーム(豊前町・上毛町)、Bチーム(築上町・吉富町)を編成し、日付けをずらして同じ医師たちが対応する。
これなら効率的です。
事務局は上毛町が受け、コールセンターは築上町が担っています。
冒頭の事例で、私が「破棄の危険」まで述べた理由がここにあるのですが、吉富町は”第一回接種”の100%持っているため、医者側の協力が得られたならば早い段階で①接種が完了します。
しかし、豊前・上毛・築上町は高齢者の3割しか接種が完了しません。弾が足りないからです。
単に不公平感だけではなく、業務がまわらない。
同じコールセンターにおいて、吉富の「2回目接種の予約」と、豊前・築上・上毛の「1回目接種の積み残し」の対応を行うことは無理です。そもそも第一回接種が完了していない築上町の町長・職員が、吉富の2回目接種に負荷を割くことは(地方自治の観点から言えば)異常です。
コールセンターが機能を停止すれば、接種予約そのものができません。
「緊急だから」とのことで、国からの御下命ではありますが、地方自治体には「通常の業務」も併行して行われているのです。介護保険を止めていいのか、課税業務を止めていいのか。
すでに小規模自治体の行政力は、コロナ以前から相当に弱体化しています。市町村合併とパソコンの導入により、かつてと比較すると地方公務員の数は激減しているのです。効率化を高めていった結果、コスト削減はできましたが、マンパワーは減少しており有事への対処能力は減少していたのです。
「ワクチン予約の電話がつながらない」という抗議とか意見も、役場にはかかってきます。
行橋市(人口7万人)ぐらいの規模であれば、それなりの職員数はおります。うまく編成すれば一時的な負荷分散は可能で、他部門からも応援も見込めます。
けれども町村単位になると全量を投入しても限りがある���
そのための広域連携でした。
「つながらない予約電話」「それに対する抗議」が混在し、職員がボロボロの状態で。。。
【1回目の接種】と【2回目の接種】の予約処理を行うのは不可能です。どうやっても無理なんだ。
では、なぜ広域連携なのかと言えば、ワクチンの有効活用のため、その側面もあったのです。
1箱をあければ975回。これは町村からすると大きすぎるロットなのです。
例えば吉富町の高齢者は2,124人、上毛町は高齢者は2,648人です。
975回とは、接種対象者の半数にあたるわけですが、解凍したワクチン通りの人数が来るでしょうか?
では、1100人の接種希望者が来てしまった場合には、2箱目を開けるのか。3週間を空けるため、中途半端に開けてしまった箱の残分を破棄することになっても。
豊前市の人口は25,341人(高齢者9,097人)築上町は、18,119人(高齢者6,569人)。
だから、豊前市と上毛がセット、築上と上毛がセットなのではないでしょうか。私はこの1市3町の議員ではありませんので、この広域化の発端や議論には詳しくありませんが、「ワクチンの破棄分を抑える」効果を期待しての連携であったと考えるのは自然なことだと思います。
(当たりくじは各自治体で管理するも、会場においては同じ箱から出していき順次開梱すれば破棄は極小化できる。)
県が、謎の配分を行った結果どうなったか。
吉富が3箱、豊前が3箱、上毛は1箱、築上は2箱。
吉富は100%、築上29%。
これらのボトムがあわなければ、合同での連携しての接種業務は破綻する。
ならば吉富は3箱を「好きなタイミングでどんどん開ける」と、その分の残分は、場合によっては破棄していかねばならない。
実は、築上町長には話を通さずに動いていたため、先ほどお会いしていたのですが、やはり自らの町民を守らねばならないという観点や、第一回接種・第二回接種の予約作業の混在は「難しいだろう」という考えでしたので、場合によってはコールセンターの統合を解除する可能性だってすでに出ています。
(豊前・上毛・築上は共に高齢者の約3割のため、今後も連携できると思います。)
吉富だけ出て行く形になった場合、吉富町は今から早急に専決処分で予算を通し、スタッフを雇用して体制構築から行わねばなりません。
そして大量のワクチン破棄を行いながら、自前で町民に接種していくよりない。広域で確保した意思を(フリーライドするような形で)残る1市2町が使うことを許したり、築上町のコールセンターが機能するかは分からない。
これは、この1市3町の連携のみの話ではありません。
人口規模の小さな自治体は、恐らく類似の工夫を担当者間で締結していると想定され、この無作為なバラバラのワクチン配布は、構築していた自治体間連携を破壊してしまった可能性が高い。少なくとも前述の4自治体については致命的なヒビが入ったと当職は認識する。
(県は、自治体からの申請数を基準にしたと述べているため、1市3町で申請中の共同歩調をとる予定であったにも関わらず、吉富町が協調を破棄して多く申請したことが発覚しているため。県が止めるべきだったと思う。)
また、築上町町長・上毛町長は頭を抱えており、「じゃ仕方ないかぁ」と笑って許すような表情ではなかった。少なくとも私の見る限りは。
市町村は、それぞれ持ちうる予算も職員数もギリギリの中、一年に渡る「緊急」を延々とこなしてきました。もう、兵隊はいないんです、いないんだ。政令指定都市や都庁とは違うんです。交代要員もいない。
その限られた人的資源を紡ぎ合わせて、それでもゲームチェンジャーとされ、地域住民が期待するワクチン接種に「ギリギリの調整」を組み上げていたんです。こんな乱暴な配布方法は、それを全て破壊する行為だった。
みんなカリカリしている、とても平和的に行こうという空気ではない。
貧すれば鈍するという言葉もあるが、つらい現状があれば「減らされたらどうしよう」と過大に申請した自治体だって出てくるだろう。けれども、それを県が容認してしまえば、全体の破綻を招いてしまう。
実際に、私の目の前で壊れかけている。
これは、県内の各所で生じた「ヒビ」だと思う。
ワクチンは来ても、接種することができるかは分からない。
謝辞
昨日は過去記事を流し込んだのみとなり、少し手を抜かせて頂きました。
その間、命懸けで事務作業をしていた次第です。それは私のことではありません。
何より時間がなかった。
問題発覚が水曜日の昼、ここで各自治体の配布差の問題を知る。
問題は木曜日が祝日であり、平日の金曜日を逃せばGWに突入してしまう。
行政機関の公式の窓口は止まってしまうため、資料の裏取りや首長のコメントはとれなくなる。
与えられた時間は、48時間。
実際に動けるのは金曜日のみ、朝8時から17時まで、実質9時間が勝負。
それまでに必要な資料を準備し(ないから作る)、すべての人間が同時に動かねばならない。
まず、谷畑市長にお礼を書きたい。
相当な多方面に連絡を入れてくださったと思います。
どことどこに連絡というのは教えてくれませんが、行橋市長に、本庄市の吉田信解市長(市長会の委員長)から連絡を頂いています。豊前市にも連絡を入れてくださったと伺いました。
また(本庄市長経由し)市長会の立谷会長(相馬市長)が河野大臣にお伝え頂いたであろうことも。
これを、祝日の一日だけで完了させるというのは、どういう負荷を背負ったのか筆舌に尽くしがたい。
谷畑市長が有する、積み重ねた人間関係、その財産に甘えてしまったというのが実態だ。
私にはできない。
本来は、様々な手続きがある。
私は市長ではないので、ある意味では越権行為だとは思うが、市長会を動かしてくれと要望することは本当は筋違いなのだ。また、谷畑市長は、先日勇退しており現職ではない。物凄く無理をさせてしまったと思う、それでも「頼みます」とお願いしました。
福岡の市長会は、私はアクセスできません。
田中市長に報告しつつ勝手に動きました。その他の市長達には、一部ではありましょうが、上毛町長が連絡を入れてくれました。
そもそも記者は、金曜日の朝一に裏取り(前述の記事の資料は、当時は公開されていなかった)をするため、貫徹で準備をしていました。凄まじい数の自治体に取材をあてていって、それで記事が間に合った。
たった一日の平日、ここに全ての照準をあわせて全処理能力を投入。
正規ルートはとれておらず、あらゆるものをすっ飛ばして対応。
これは本来ならば、行儀の悪い行為であって、仁義をきれたとは言えない。
アニメでいうところの詠唱破棄。
これが許されるのは、事態の緊急性と、日ごろのお付き合い。
(許されてないかもしれませんが。)
豊前市長には市長会から連絡が行っており事態を把握していると推定しますが、1市3町を事例としつつも築上町の新川久三町長には、まったく報告ができていません。
携帯番号を知らなかったから、祝日に連絡をつけることができなかったからです。まったく知らぬ中で、記事だけ出る(築上の名前は出ずとも)のは失礼です。
(平均よりも多い自治体は良いでしょうが、そうではないところには情報共有をしておかないとトップが知らないというのは恥をかかせてしまいます。)
(本来は中間報告を入れつつ動くのが筋です。)
ある程度の目処がついたのは夕刻。
紙面化がほぼ確定の報告を坪根町長にしたところ
「何かして欲しいことはあるか」と言われたので、ワガママを言いました。
上毛町長から築上町長にアポをとってもらったのが18時半頃。当然、庁舎にはおりません。
【いまから行きますから】と押し切ってくれて、新川町長の自宅についたのは19時過ぎでした。
私は、隣接する自治体とはいえ、ただの市議の身分に過ぎないのでありますが、夜中に自宅まで押しかけてお時間を頂きました。まずもって感謝いたします。
報告が遅れたこと、仁義をきってなかったことをお詫びし、現在持ちうる情報を報告しました。
新川町長からは、そこまで君らが粘ったとはと深くお礼を言われ、玄関まで見送ってくれました。
新川町長の携帯番号をゲットした。
今度、町長室も遊びに行っていいって。
やったZE☆
他、各地の地方議会の正副議長級が奔走し、全国の都道府県の配布状況をボトムから逆ハック。
凄い人数が、数日、寝ていない。
一部ではありますが、僭越ながら陣頭指揮をとらせて頂いたことを誇りに思います。
私に賭けてくれたこと、地方行政の矜持を示せたこと、感謝します。
残48時間からスタートし、実際に大臣までつながったこと。
「君だったら間に合うかもしれない、名前は貸すから行きなさい!」って言ってくれたのは嬉しかった。
共に戦ってくれたこと、駆け抜けてくれたこと、
読者の皆様の拡散支援も含め、深く感謝いたします。
ワクチン配布 国、明言ここのニュースは大きく触れる必要はないでしょう。
河野大臣から、PF06、PF07、PF08が示されました。
現在の配布は、PF01~05まで。
PF01~04は少量でトライアルなどに用いられたものです。
本Blogで取り上げた「偏在」は、PF05になります。
ここが高齢者用の大規模納入の開始。
私たちは、PF06において不足自治体との調整、および広域対応をしている自治体の調整を要望する構えでありました。これは都道府県で決定されるものと考えていました。
しかし、PF06~PF08までを国が策定、配布計画として「国が決定」したのです。
昨晩のニュースの中身であります。
実はもうその資料も持っておるのですが、かなりの部分の偏在は解消できるものと期待しています。
最初から国が強権発動できるのであれば、そうしたほうが良かったのかな、とも。
ただ弊害もありまして、都道府県単位で「ここ!」という個所付けができなくなったという課題も残ります。
一気にPF06~PF08まで決めてしまうと、感染爆発などが生じた場合の対応ができません。
とは言え、都道府県単位に(総務省から)取りまとめさせ、基礎自治体に申請させる方式は実際に事故を起こしています。これは大事故と言っていい。
ならば国が早期に乗り出すのも理解はできますし、万が一の大幅不足(地域単位での感染激増)の場合は���何がしかの対処を講じて行けばよい。
どこもかしこも「少しでもワクチンを」となっている以上、それぞれが利害関係者みたいな状況ですから、協議をまとめろというのは無理だったのかもしれません。
下手に余地を残さず、一気に06~08を発表してしまうのは正解かもしれません。
私は、「市」の議員でありますが、他府県の地方議員には申し訳ない思いもあり、ここまでの供給の謎配分は恐らく福岡だけのようです。まだ全県データは見ておりませんが、実は福岡県行政のみが起こした事故という可能性が否定できず、スタートした時点では全貌が見えませんでしたので(また今も把握できていない)ごめんなさい。
公平に、かつ迅速に対応できていた都道府県からすれば、一気にPF08まで固定されてしまったことには弊害もあるかもしれません。
しかし、「いつ、どれだけ入る」という数を、具体的に国が示したことで
「この接種体制で、どこに何人の人員配置」という、純粋な接種体制の構築に集中していけることでしょう。
その計画が立案できるようになったことは、私はやはり喜ぶべきことだと考えております。
スペシャルサンクス
中野区の吉田康一郎議員からは「プリンと羊羹があったら、プリンから先に食べるものだ。物事には優先順位がある。君はいまワクチン偏在問題に特化すべきだ!」という、一瞬、意味が分からない例え話で激励しれくれました。ヘトヘトに疲れていて頭が回っていなくて愚痴ったときです。
私はわけも分からず「プリンも食べたい、羊羹も食べる」と答えたら、「いやプリンのほうが早く痛むから」と言われたので「今度、買ってくれるなら、もう少し頑張る」と答えました。今度、羊羹もプリンも食べさせてくれると信じております。
国希研の同志議員へ。
数日、不在にして申し訳ありません。職権代行を受けてくださった笠間議員に感謝します。
併せて、ウイグルを応援する全国地方議員の会においては幹事長の職を頂いているにも関わらず、他執行部メンバー、代表理事・議員会員の皆様にご迷惑をおかけしました。
もう一両日中には戦線復帰いたします。
↓ウイグル問題の啓発支援にご協力頂ける方は、下記もお願いいたします。↓
ウイグル応援グッズ
保守基金ウイグル応援グッズ | 保守基金https://hosyukikin.jp/category/item/itemgenre/org/uyghur/<strong>ウイグル証言集会</strong><strong> </strong>「ウイグルを応援する全国地方議員の会」が主催し、日本ウイグル協会の共催で実施しています。実際に迫害にあっている方に登壇して頂き、地方議員が同席のもと被害実態を訴えてきまし...
一部ではありますが、僭越ながら陣頭指揮をとらせて頂いたことを誇りに思います。
私に賭けてくれたこと、感謝いたします。
残48時間からスタートし、実際に大臣までつながったこと。
中一日は祝日、分の悪い戦いだった。
「乗った」という声、
「君だったら間に合うかもしれない、名前は貸すから行きなさい!」って言ってくれたこと、
共に地方行政の矜持を示せたこと、戦ってくれたこと、駆け抜けてくれたこと、感謝します。
読者の皆様の拡散支援も含め、深く感謝いたします。
さて、残りの残務を片付けよう。
よう頑張ったという方は、FBのイイネ・シェア、Twitterでの拡散をお願いします。
※ 恐らく表示される人数が極少数になると思うので、とりあえず「見えた」人はイイネをお願いします。一定数がないと、タイムラインにあがらないと思う。私のアカウントの場合は特に。
1 note
·
View note
Text
デヴィッド・グレーバー『ブルシット・ジョブ』

「クソ面白くもない仕事」の告白事例で埋め尽くされた本書は、読むものをブルシット・ジョブの疑似体験へと誘う。おまけに攻略対象は、小さめのフォントで構成された426ページ、648グラムという結構な大著だ。デヴィッド・グレーバーの『ブルシット・ジョブ』は、読むのに覚悟を必要とするたぐいの本である。
しかし、本書を読み終えるころには、グレーバーが投げかけるクソ面白くもない話の深刻さと、それに立ち向かう彼の粘り強い思索にどっぷりと浸かることになる。本書には、現代社会が抱える仕事の欺瞞、不毛な労働、ケアリングの不当な扱いの実態と問題の告発、その解決に立ち向かう反逆者グレーバーの奮闘ぶりが溢れている。
著者のデヴィッド・グレーバーは、「ウォール街を占拠せよ」運動を主導し、"We are the 99%”のスローガンを作ったことで知られる。この『ブルシット・ジョブ』は、文化人類学の精神に立ち現代の経済と労働の問題に切り込んだ、過激で情熱的そして人間味のある一冊である。
CONTENTS
「クソ面白くもない仕事」の蔓延と欺瞞的な実態
なぜブルシット・ジョブが増殖しているのか?
世界的パンデミックで露呈した身近なブルシット・ジョブ
足を引っ張る道徳的羨望
あらっぽいマルクス主義のススメ
生活を労働から切り離すためのベーシック・インカム
避けるべきだが避けられない本書の要約
「クソ面白くもない仕事」の蔓延と欺瞞的な実態
この本にはにはさまざまなタイプのブルシット・ジョブが登場する。それは著者の分類に従えば、取り巻き型、脅し屋型、尻拭い型、書類穴埋め型といったものだ。グレーバーはこれらの「クソ面白くもない」仕事は、金融、教育、コンサルタントなどの業界を中心に、とりわけ、わけのわからない横文字の職業に蔓延しているという。
本書に登場するブルシット・ジョブはあまりにも多様で何を例示するか悩ましいが、ひとつだけ取り上げるとすれば、経営管理型の大学などはその最たるものだろう。例えば、1985年から2005年の20年間で、アメリカの大学における管理業務サービスの供給量は大幅に増えている。驚くのはその内訳である。同期間に増加した学生数の伸びは56%だったのにたいし、職員数は240%に増えたとある。(p.214)本書の文脈に従えば、この20年間で大学の職員は大量のブルシット・ジョブ労働者を抱え込んだ可能性がある。
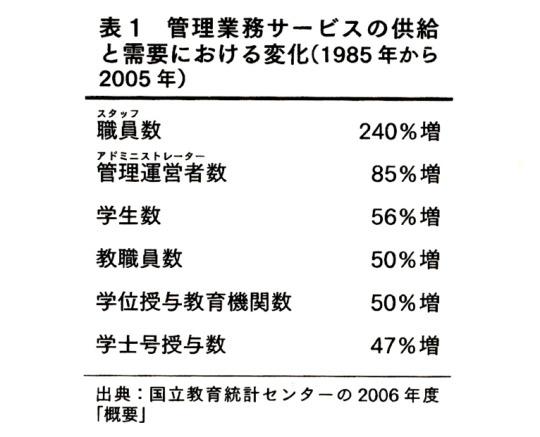
しかし、本書が指摘するのはブルシット・ジョブの増殖ぶりだけではない。その「クソ面白くない」仕事に、高額の給与が支払われている実態も描かれている。典型的な事例は次のようなものだ。
大手デザイン会社の「インターフェイス・アドミニストレーター」だったエリックは、仕事のあまりの無意味さに抗議するため、遅刻、早退、ランチでの飲酒、デスクで小説を読む、勤務中の三時間を散歩に充てるといった反乱行動に出た。しかし、会社の反応は彼の期待を裏切るものだった。エリックは次のように告白している。
辞めようとしたところ、上司が2600ポンドまで給料を上げようと提案したので、しぶしぶ受け入れました。あの人たちがわたしを必要としていたのは、まさに、あの人たちが実行していほしくないことを実行する力量が、私になかったからで、あの人たちはわたしを繋ぎ止めようとして、すすんで金を払おうとしたのです。(p.104)
エリックの仕事ぶりはひどかったが、上司にとって不都合な仕事をする人物でなかった。彼らにとって、部下の一人がサボろうが酒を飲もうが関係ない。エリックはプログラミングや何かの開発といったことはできなかったが、Eメールのリストから上司が必要とする相手のアドレスを検索して示すことはできた。上司はそれだけの仕事に、2600ポンド(約36万円)の給料が支払われてもよしとしたわけである。エリックが反乱を起こそうとした気持ちはよく分かる。
この事例のようにグレーバーは、ブルシット・ジョブは公共部門に限らず民間部門にもはびこっているという。そうであれば、公共部門よりも民間部門の方がスリムで効率化されているという一般の認識には、かなりの思い込みが含まることになる。
例えば、本書に掲載されている「企業労働の実態報告」からの抜粋によれば、アメリカの事務員が本来の業務に注いでいる時間は、2015年から2016年の1年間で、46%から39%に低下しという。本来の業務を圧迫しているのは、無駄な会議、管理業務、Eメールなどの増加によるものだ。(p.46)
社会的な貢献と報酬の不可解な関係は、医療従事者の間にも広がっている。ハンス・ロスリングがいうように、この200年間で人類は大幅に寿命を伸ばし経済的にも豊かになった。その伸びは寿命で4倍、収入で70倍にもおよぶ。このうち健康は医療の進歩によってもたらされたと、多くの人が信じている。
しかしグレーバーは、寿命が伸びた最大の理由は医療そのものよりも、衛生学や栄養学、そして公衆衛生が改善されたことに起因している、というよくある指摘を引き合いに、次のように述べている。
病院では(きわめて給与の低い)看護師や清掃員こそが、(きわめて高額の給与を受け取っている)医者たちよりも、じっさいには健康状態の改善によりおおきな貢献をなしていると言えるかも知れない。(p.277)
この年収格差がどの程度のものかといえば、2017年の米労働省労働統計局の職業別雇用・推定賃金に関するデータによれば、トップ10の9位までを医者が占めておりその平均額は約2500万円である一方、本書に示されている英国の病院の清掃員の年収は180万円でしかない。(p.276)国が異なり厳密な比較とは言えないが、両者のあいだには14倍もの開きがある。程度の差はあれ、こうした格差は多くの国でも共通の傾向だろう。
もしグレーバーが指摘するように、健康状態の改善に実質的に寄与しているのが医療現場で働く看護師や清掃員であるなら、この格差はあまりにも大きいように思える。医者が行う専門的な治療行為の貢献はあるにせよ、健康改善への貢献はどこまで評価されているのだろうか。
こうした事態についてグレーバーは、「こうした傾向が続けば、10年と待たず、アメリカのオフィスワーカーのなかで実質のある仕事を行う者は存在しなくなるだろう」と述べ、労働時間の50%以上がブルシットな仕事に費やされていることに警告を発している。これはブルシット・ジョブが経済や経営の無駄を招くという理由からだけではない。ここには、世界に何の影響も及ぼさないと自分自身が考えている労働者と彼らが過ごす時間、つまり人間的な無力感と空虚な世界が社会に蔓延することへのグレーバーの強い危機感がある。
なぜブルシット・ジョブが増殖しているのか?
それでは、「クソ面白くもない仕事」はなぜこうも増え続けているのだろうか。グレーバーによれば、ブルシット・ジョブは社会を占める物質生産の割合が減り、金融や情報などの抽象物を操作する仕事が増える過程で増えてきたが、そこには政治的な思惑が関係しているという。
ブルシット・ジョブが政治的な力から生まれるとする説明にグレーバーが繰り返し引き合いに出すのが、オバマ大統領の医療保険制度改革に関する発言である。当時オバマ大統領は、民意であった公的保険ではなく、民間企業の手を借りた健康保険制度を選んだ。その理由はつぎのようなものだったという。
単一支払者制度のよる医療制度を支持するひとはみな「それによって保険やペーパーワークの非効率が改善されるのだ」といいます。でもここでいう「非効率」とは、ブルークロス・ブルーシールドやカイザー(いずれも保険会社)などで職に就いている100万、200万、300万人のことなのです。この人達をどうするんですか? この人達はどこで働けばいいのですか?」(p.210)
単一支払者制度とは、ヘルスケア原資を単一の公的機関によって負担する仕組みで、いわゆる公的保険制度にあたる。つまり上の発言をしたオバマ大統領は、公的保険であれば300万人の仕事がなくても保険制度が成り立つと認め、しかもそれによってペーパーワークなどの非効率な仕事、つまりブルシット・ジョブがなくせると知りながら、政治的な思惑によって公的保険制度は望ましくないと判断したことになる。
オバマ大統領がこのように述べた背景には、「この人達をどうするんですか?」の発言に示されている通り、完全雇用の含意にもとづく300万人の雇用があったと思われる。それが文字通りの「完全」ではないせよ、雇用の確保は国民との間に交わされたひとつの合意事項ではなかっただろうか。
グレーバーはこうした政治的判断は民間企業にも当てはまるという。生産性の向上に見合った設備投資や給料に回す以上の利益が上がるようになると、忠実なる協力者に報奨を与えることで不満分子を買収したり、経営的なヒエラルキーの維持や再生産に回すためのお金や仕事が生まれるようになる。こうした経営的な思惑は、まさに政界のそれと同じだというわけだ。
この一連の話のなかで、政治の世界の完全雇用にあたる民間企業の含意が何かといえば、それは技術の発展への信頼ではないだろうか。産業革命からはじまった機械化は生産の効率向上をもたらし、その利益を物質的な再分配を超えて抽象的な領域へ注ぎ込ませる力となった。この新領域が生まれたのは経営者の意志というより、技術発展の自動作用だっただろう。そうであれば、民間企業にとって技術の発展は、経営を支える前提としての含意だったことになる。経営の前提に技術の発展があればこそ、事業家は経営的な思惑を資金の運用や人材に向けることができたと考えられる。
新たな領域にお金が回るようになった当初、企業家の思惑が社会に与える影響力は限られていた。しかし、1900年代の終りにコンピュータが普及すると、もともと記号であるお金と記号を操作する機械のコンピュータが相乗効果を発揮しはじめ、金融業や情報産業などの新しい業界と新市場が生まれた。その成長は著しく、結果的に利益の抽象的な再分配は産業全体におよぶようになった。この機械的な効率性の向上をベースとした、非物質的な抽象価値のハンドリングこそが「クソ面白くもない仕事」の温床と考えられる。前掲のエリックは、まさにこうした業界で上司に依頼されたEメールの検索だけで一日を過ごし、2600ポンドの収入を得ることになった。そのエリックが「クソ面白くもない」日常に反抗を試みたのは上述の通りだ。
そうだとすれば完全雇用と技術の発展は、ブルシット・ジョブの両輪を担ってきたことになる。もし、どちらかの合意が欠けていれば、「クソ面白くもない仕事」がいまほど増え続けることはなかっただろう。しかしその一方で、効率がわるく失業者も多い事態を意に介さない社会が、失業者を救済する手段を持たなかったら、もっと悲惨なことになっていたことは明らかだ。そしていずれの混乱も因果関係からいえば、技術の発展が政治的な思惑の生みの親だった。
このことは未来の労働について深刻な問題を提起する。ブルシット・ジョブを生み出す本質が技術による効率向上であるなら、純粋機械生産が予想される未来は、いま以上に「クソ面白くもない仕事」が蔓延する社会になりかねないからである。
世界的パンデミックで露呈した身近なブルシット・ジョブ
本書にはエリックに似た境遇にある人々の告発が次から次へと登場する。それらは、ブルシット・ジョブを対岸の火事のように見ている多くの読者には、あまり現実味のない記述かもしれない。しかし、後半に差し掛かり、なぜ無意味な雇用が停止できないのかとグレーバーが問うあたりから、話はにわかに現実味をおびてくる。なぜなら、コロナウィルスの流行で、世界のいたるところで起きている通常業務の停止が、自分の置かれた状況に似ていることに気づくようになるからだ。
会社に行かなくなれば、デリケートな人間関係や、無駄を前提に成り立っていた仕事はやりにくくなる。存在自体に気を配ることが評価される取り巻き型の仕事、システム化の遅れが仕事の源泉だった書類穴埋めの仕事などは真っ先に機能しなくなる。
わたしたちはいま、まさにその只中にいる。事実、コロナ禍で国単位のロックダウンが敷かれたり、ホームステイやホームワークが強要されたことで、「クソ面白くない」仕事の多くが機能不全に陥った。いまわたしたちは、これまでやむを得ず受け入れていたブルシット・ジョブにどれだけの価値があるか、その真贋が強制的に問われる壮大な社会実験に投げ込まれている。強制的とは、コロナウィルスがもたらしたロックダウンや行動自粛といった、人間の自由を規制��るフィルターが、人びとの自由な意志を超えて作用している状態を指す。
そして社会のいたるところで、既存のブルシット・ジョブの多くが現役を退き、反対に新手の不毛な仕事が生まれたり顕在化するようになった。書類に赤い印を押すハンコや、デジタル化から取り残された紙の書類が自分を縛り付けてきたことが、日本のあちこちで問題として浮かび上がりはじめたのだ。ウィルス感染を恐れながら職場まで移動し、紙の書類に捺印するだけの仕事は、仕事を任された者にとって「クソ面白くない」ばかりか、コロナ感染の危険を伴う。その仕事ははたして、内容や危険に見合ったものなのだろうか? この問いが現実の問題となったのは、コロナ禍によるフィルターが機能しているからだ。
その一方でフィルターは、一部のシット・ジョブが実はエッセンシャル・ワークであったことを明らかにした。混乱に陥ってはじめて、社会を根本で支える医療従事者、介護福祉士、スーパーの店員、清掃作業者、宅配運転手、さらには教師や消防士や料理人など、現場で働く人々の仕事の重要性が再認識されるようになった。
しかし、彼らの仕事の中身と待遇は多くの場合エリックとはまるで正反対のものだ。社会を動かすのに不可欠な仕事への見返りは、その貴重さと激務にとうてい見合うものではない。反対に、ロビイスト、ヘッジファンド・マネージャー、コンサルタント、弁護士といったエッセンシャル・ワーカーの対岸にいる人々の多くは、コロナ禍によるフィルターの存在を気に留めることが少ない。なぜなら、出社を制限されたからといって、彼らの仕事の負担が増えたり給料の支払いが滞ることはほとんどないからだ。
こうした事態は2020年のいま、コロナウィルスの流行により世界中で起きている現実だが、グレーバーはいまから7年前、2013年の小論のなかでこの事態を描写している。そのとき彼は、「特定の職種の人びとが消え去ってしまったらどうなるか」という「思考実験」を提起したという。その内容は次のようなものだ。
もしある朝起きて看護師やゴミ収集に従事している人びと、整備工、さらにはバスの運転手やスーパーの店員や消防士、��ョートオーダー・シェフたちが異次元に連れ去られてしまったとすれば、その結果はやはり壊滅的なはずだ。小学校の先生たちが消え去れば、学校に通う子どもたちのほとんどが一日や二日は大喜びするだろうが、その長期的な影響は甚大だろう。(p.273)
実験の結果をグレーバーはどのように想像しただろうか。要約すれば、「仕事の社会的価値とその対価として支払われる金額は倒錯した関係にあることが明らかになる」というものだ。そしてグレーバーはこの予想される事態を「ひそかにだが、ケアリング階級の反乱、と呼ぶようになった」と書いている。ひそかにと言うのは、反乱が自分にとってもケアにかかわる人びとにとっても、内心に留まっているという意味だろう。
しかし、現実は予想外の展開になった。グレーバーが思考実験を行った7年後、コロナ禍のフィルターがケアリング階級の内心を飛び越えて強制的に反乱を引き起こしたのである。政府は生活者や小規模事業者に莫大な補償をしなくてはならなくなった。よもやグレーバーは、彼が提起した「思考実験」が、その後のパンデミックによって世界中で強制執行されようとは思いもしなかっただろう。そして彼の予測した「倒錯した関係」が現実のものとして露呈したのである。
足を引っ張る道徳的羨望
しかし、世界的なパンデミックが終わればこの事態はもとに戻り、再び「クソ面白くもない仕事」が再開し「倒錯した関係」が再現されるのだろうか。もちろん、それでいいわけがないというのが、本書の基本的なスタンスだ。それではこの問題の出口は、いったいどこにあるというのだろう? グレーバーは「この状況に対してなにをなしうるのか?」と題した最終章で、道徳的羨望、上出来のロボット、ベーシック・インカムの三つの話題を取り上げている。
道徳的羨望とは、自分もそうでありたい美徳が相手によって高度に示されたとき、自分の内部で起こる妬みの感情を指す。多くの場合その妬みには羨望や反感をともなう。グレーバーがこの感情を取り上げるのは、道徳的羨望は労働を取り巻く政治に微妙な影響をおよぼすと考えているからだ。(p.321)
例えば、貧困者にたいする怒りは、働いていない人にも働いている人にも向けれるという。なぜなら、前者は怠惰だから後者はブルシット・ジョブではないから、というそれぞれの理由で怒りに変わるからである。これでは、「クソ面白くもない仕事」をしながら生活に困らない給料を得る人びとと、労働に見合わない条件のもとで現場で奮闘するエッセンシャル・ワーカーとが、共通の政治的な解決策について共闘するのは難しい。
仮にベーシック・インカムが実施され、給与水準の低いエッセンシャル・ワーカーの所得が引き上げられる提案が出されたとする。それによって現場で働く人びとの給与水準が、ブルシット・ジョブを過ごす人びとのそれに近づけば彼らのなかに、現場の連中は十分な働きがいを得ているくせにという理由で、自分たちよりも総合的に生活が上がることへの妬みが生まれる。
このような道徳的羨望が人びとの心に潜在する限り、その政策課題が多くの人びとから支持を得ることはできないだろう。これは、ベーシック・インカムで労働意欲が低下するとされることへの反証に比べ、科学的な取り扱いが難しい点で解決がやっかいだ。この点についてグレーバーはこれといった解決策を示していない。
あらっぽいマルクス主義のススメ
次の話題に移ろう。上出来のロボットがブルシット・ジョブの解放に役立つかという点はどうだろうか。これについてグレーバーは、いささか皮肉に満ちた言い回しでノーを突きつけている。彼が引き合いに出す未来のロボットは、SF作家スタニスワフ・レムにその発想源を求めたものだ。グレーバーは、いっさいの管理も指示もなしに作動するロボット「ニューマシン」が活躍するある星の出来事として、およそ次のような逸話を記している。
ニューマシンの配備が進むことで、働き口を失った労働者はバタバタとハエのように死んでいった。あるとき異星人が訪れ、ニューマシンの恩恵がみなで受けられるように、工場を社会の共有財産にすれば済むはずだと提案した。しかしその星の国民は、「我が星の最高法は貴族が自分の財産を享楽したがっている限り、何人もそれを取り上げることはできないことを受け入れている、バカなことをいわないでほしい」と懇願した。こうして、消費者としての労働者は追いはらわることになった。(pp.334-336の要旨)
この逸話についてグレーバーは、「苦役を排除するというような見通しが、あってはならない問題とみなされるという事実以上に、その経済システムが不合理であることを示すしるし(サイン)は想像がむずかしい」と述べている。(p.336)わかりにくい言い回しだが、これは、純粋機械生産のような不幸な未来を考えるのはどうかしているという以前に、そうした未来の経済システムがとうてい成立しない証拠をあらかじめ見つけることはむずかしい、ということだろう。彼は「いくぶんかのあらっぽいマルクス主義こそ、ときにわたしたちには必要なのである」とも書いている。グレーバーは、そもそも人間が労働しないことを良しとすること自体がおかしい、といいたいのだ。
それはたんなる願望だろう、労働が苦役になることも多い、そんな声が聞こえてきそうな気がする。そうでなければ、なぜ人類は産業革命から200年以上ものあいだ、機械を発明し省力化に努めてきたのわからなくなる。
しかし、人類が洞窟に壁画を描いたり、道具を生み出してきたのは、耐えられないほどの不便を解消するためだけではなかった。洞窟の先人からこのかた、人びとはその行為自体に生きる価値を見出してきたはずだ。そうでなければ壁画が人を魅了したり、バイオリンやMacintoshのような美しい道具は生まれなかった。このことは、現代の画家、陶工、料理人はもちろん、子どもの世話をする母親や育児スタッフもおなじだ。
これらの労働に共通していえることは、直接的な労働には何かしらの価値や喜びがあるということだ。これがグレーバーのいう「あらっぽいマルクス主義」の意味ではないだろうか。
それではもうひとつの、未来のロボットは人類全体の共有財産になるはずだという異星人の提案はどうだろうか。これについてグレーバーは、不可能ではないかも知れないが、深刻な自己矛盾を抱え込むことになるだろうという。その根本的な考え方は、「自動化は特定の作業をより効率的にするが、同時に別の作業の効率を下げる」というものだ。(p.337)その理由としてグレーバーは、エッセンシャル・ワーカーの仕事の本質をなすケアリングの価値は、超大な量の人間的労働によらない限りデータ化してコンピュータに取り込むことができないからだという。
おそらくこれには、汎用人工知能の研究者あたりから多くの反論がありそうだ。よく言われるようにコンピュータは単純作業の自動化からはじまり、次第にできることの範囲や能力を広げてきた。例えば、マックス・テグマークは『LIFE 3.0』のなかでハンス・モラヴェックが描いた「人間の能力のランドスケープ」を引き合いに次のように述べている。
その重大な海面レベルに相当するのが、機械がAIを設計できるようになるレベルである。この転換点に達するまでは、海面上昇は人間が機械を改良することによって起こるが、転換点以降は、機械が機械を改良することによって促され、人間が進めていたときよりもはるかに速く進んですべての陸地があっという間に浸水する可能性がある。(Kindleの位置No.1000-1003)
実際のところつい数年前には、人工知能を鍛えるには大量のデータを人間がコンピュータに与える必要があると考えられていた。しかしいまでは、例えば画像認識の分野のように、人工知能が自らデータを生成するデータ拡張(Data Augmentation)といった手法のおかげで手作業は格段に少なくなっている。グレーバーがいうデータ化のための人間的労働がいつまでも人間固有の能力を必要とするとは限らない。
生活を労働から切り離すためのベーシック・インカム
しかし、これまで見てきたように、グレーバーは労働の正の側面に期待を寄せている。むしろ、多少シンドくても充実感をともなう労働、すなわちケアリングのような仕事に「あらっぽいマルクス主義」の価値を認めることが必要だという。「クソ面白くもない仕事」は、クソ面白くないから苦役なのだ。そうなると問題は、いかに人びとをブルシット・ジョブから解放し、ケアリング労働の価値自体は残しながら、労働と対価の倒錯した関係を修復できるかに集約されることになる。
その点でグレーバーは、ブルシット・ジョブから逃れるための政策としてベーシック・インカムが有効なことを認めている。このベーシック・インカムは、今回のコロナ禍で一人あたり10万円の特別給付を受けた日本人にとって、馴染みのある方法だ。一回限りであるうえに非課税である点など、本来のベーシック・インカムとは異なるところもあるが、生活の困窮の解消に向けた施策が広く経験できた意義は大きい。これもまたコロナ禍のフィルターによる強制力がもたらしたものだ。
しかしグレーバーは、本書の内容や彼の考えが政策と受け止められることには抵抗があるという。彼が本書を執筆したのは政策を示すことではなく、あくまで「問題--ほとんどの人びとがその存在に気づきさえもしなかった--についての本なのだ」と述べている。彼がこのことを強調するのは、政策課題は人びとの目に止まりやすく、すぐにそれが有効かどうかに心を奪われ、考えに至った事情を見えにくくするからだという。そもそも政策という考えがうさんくさいとも述べている。
政策を明示することにこれほどの抵抗を示しながらも、しかしグレーバーは、ベーシック・インカムはブルシット・ジョブの削減に効果があるひとつの解決策だという。その最大の理由は、ベーシック・インカムによって生活から「クソ面白くもない」仕事を切り離すことができるからだ。このときしばしば指摘されるのが、無条件にお金を分配すれば、好きなことにうつつを抜かしたり労働意欲を失う人たちが増えるという問題だ。これに対してグレーバーは次のように書いている。
洞窟探検をおこなおうが、マヤ族の象形文字を翻訳しようが、高齢セックスの世界記録を打ち立てようとしようが、なんの問題もない。好きなことをやればよいのだ! 結局、何をやることになるにしても、履歴書作成セミナーに遅刻した失業者に罰則を科したり、ホームレスが三種類のIDをもっているかどうかをチェックするよりも、みんな、ほぼ確実に幸福になるはずだ。そしてかれらの幸福は周囲にも跳ね返ってくるであろう。(p.359)
こうしたことのすべては、あきらかにつぎのような想定にもとづいている。すなわち、人間は強制がなくとも労働をおこなうであろう、ないし、少なくとも他者にとって有用ないし、便益をもたらすと感じていることをおこなうであろう、と。(p.360)
グレーバーがどれほど性善説に立っているかは明らかだろう。しかし当然ながら、彼はすべて無条件に自由にすればうまくいくと言っているわけではない。あまりにも多くのブルシット・ジョブを余儀なくされている人びとがいる、つまり自分の仕事をバカバカしいと感じている人びとがいてその仕事に給料が支払われる一方で、社会を成り立たせる上で不可欠なエッセンシャル・ワーカーには満足な給料が支払われない、この倒錯した状況にいる大多数の人びとを自由にし、人間信頼のもとで救済する必要がある、というのがグレーバーの主張なのである。
避けるべきだが避けられない本書の要約
『ブルシット・ジョブ』は論点を要約するのをためらう本だ。ブツブツとひとりで呟くような文章が延々とつづくからではない。本書の節のタイトルがいつも「終結部=人間の創造性に対するブルシット・ジョブの影響と、無意味な仕事に対して創造的または政治的に自分を主張しよとする試みがなぜ精神的な戦争の一形態と考えられるかについて」といった調子だからというわけでもない。これらの文体や表現の特徴は、グレーバーが思考を煮詰めていく過程を追体験するうえで、むしろ、読む者にともに考えることを誘う効果もある。そうではなく、グレーバーはどうやら、わかりやすさの弊害に敏感なのだろう。まとめることを拒否しているように思えるのだ。
こうした事情を考えると、この本の要約は避けるべきなのだろう。しかし、それはわたしにとって、グレーバーの気分に引きずられ過ぎだとも思う。やはり、自分のためにこそ、この貴重な読書体験で得たことを記録するのが凡人の努めであるはずだ。
わたしが本書から得た著者の考えはこうだ--グレーバーは、ニューマシンのような発達したロボットが、「ブルシット・ジョブ」の解消に役立つとは考えていない。ロボットは苦役としての労働の代替には役立つが、そもそも人間の労働の喜びや働く価値を代替すると期待するべきものでもない。それよりも労働に含まれる価値を認め、「クソ面白くもない仕事」から人びとを解放する必要がある。そして解放された人びととともに幸福を分かつには、社会制度としてのベーシック・インカムが有効である。--これが彼の考え方の骨子だと思う。
こうして、実際に要約を書いてみて気づくことがある。確かにグレーバーが危惧する政策に言及することの危うさがわかるような気がするのだ。要約することでどこか納得した気持ちになった途端に、彼が『ブルシット・ジョブ』のおそらく95%を要して訴えてきた「クソ面白くもない仕事」の複雑でクソバカらしい現実がどこかへ消えてしまうように思えてくる。いったいわたしたちは、すでに受け入れて半ば習慣化している問題について、自分自身の手でそれを克服することができなくなっているのだろうか。そうではないと信じたい。グレーバーは本書の最後をつぎの言葉で締めくくっている。
本書の主要な論点は、具体的な政策提言をおこなうことにはない。本当に自由な社会とは実際にどのようなものなのかの思考や議論に、手をつけはじめることにある。(p.364)
わたしたちも彼に習って、本当に自由な社会とは何かを考えることだけは諦めないようにする必要がある。わたしもその一人でありたいと、この本と格闘しながらその思いを強めた。
更新歴
2020.8.22 初回投稿
2020.8.23 「なぜブルシット・ジョブが増殖しているのか?」の項目を追記
1 note
·
View note
Link
TEDにて
マロリー・ソルドナー: 大企業のデータで世界の飢餓に終止符を打てるかもしれない?
(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)
大企業は、人道的な問題を解消するためお金を提供したかもしれませんが、もっと有益なものも提供できるのです。
つまり、データです。マロリー・ソルドナーは、民間企業が難民危機から世界の飢餓までの大きな問題を、未利用のデータや意思決定法を研究する科学者を提供することによって、どれほど進展させることができるのかを話しました。
あなたの大企業も何かに貢献できるかもしれません。
2010年6月。私は、イタリア、ローマに初めて降り立ちました。観光目的ではなく世界の飢餓を解決するためです。
そうです。当時の私は博士課程の25歳。大学で開発した試作品のツールを持ち込み、世界食糧計画をサポートし、飢餓をなくすつもりでしたが、プロジェクト終了。打ちのめされました。
データを使用すると人命が救えることが、ローマでの体験から分かりました。まあ、最初の目論見とは違いますが、最終的に辿り着きました。どんな状況か説明します。50万人の朝食、昼食、夕食を用意するとします。一定の予算しかありません。月額6.7億円。
皆さんはどうしますか?最良の方策とは何ですか?米、小麦、ひよこ豆、油を買うのが良いでしょうか?どれだけ買いましょうか?簡単そうですが、そうでもありません。30種の食材から5品を選ぶ必要があります。既に、14万以上の組合せがあります。
選んだ食材をいくらで買うのか。どこで入手するのか。どこに保存するのか。運搬の時間などを決める必要があります。すべての運搬ルートも調べる必要があります。すると選択肢は9億になります。1秒間で1つの選択肢を検討しても、28年以上かかります。
9億の選択肢。
そのため、意思決定者が数日のうちに9億の選択肢から不必要なものを除外できるツールを作りました。これは大成功を収めました。イラクでの活動では、コストを17%削減し、8万人多く食料を届けられました。
データの使用と複雑系のモデル化のおかげですが、業績が私たちだけに帰するものではありません。ローマで一緒に働いた部署は特徴がありました。共同事業を確信していました。大学を引き込みました。法人を引き込みました。世界の飢餓のような大きな問題で真に変革を望むなら全員で話し合う必要があります。
人道主義団体のデータに精通した人が、先導し、大学や各国政府からの適切な取り組みを組織化してもらうことが必要です。ただ、十分に活用できていなかったグループがあります。当ててみてください。
法人です。
法人には世界の大問題を解消する大きな役割があります。私は民間企業に所属して2年になります。法人に何ができ、何をしようとしないのかを見てきました。その隔たりを埋められる方法は3つ。データの提供、意思決定科学者の提供、新しいデータソースを集める技術の提供なのです。
これは、データの慈善活動です。それが法人の社会的責任の未来像です。その上、ビジネスとしても正解です。
今日の法人は膨大なデータを集めています。最初に法人ができることが、そのデータを提供することなのです。既に提供している法人もあります。例えば、大手通信会社。セネガルや象牙海岸でデータを公開にしました。研究者は、携帯電話がどの基地局と繋がっているというパターンから人がどこを旅行しているか把握できることが分かりました。
そのデータから、例えば、マラリア感染拡大地域を予測できるのです。また、革新的な衛星通信会社の例では、データを公開し提供しました。そのデータで干ばつによる食料生産への影響を基本的人権を尊重し追跡しました。それを使って、危機が起こる前に援助資金調達を始められるのです。
幸先の良いスタートです。
しまい込まれた法人データに重要な洞察が含まれています。そうです。慎重にならなくてはいけません。例えば、データの非特定化でプライバシーへの懸念に配慮する必要があります。
しかし、たとえ水門を開放してすべての法人がNGO、大学、人道主義団体にデータを提供したとしても、人道主義的な目的のため、データの最大限の影響力を利用するには十分ではないでしょう。
なぜでしょうか?データから洞察を引き出すには意思決定科学の研究者や基本的人権が重要だからです。
意思決定科学の研究者とは、私のような人です。データを受け取り整理して、変換し、手元の事業課題に対して、有効なアルゴリズムで処理をします。人道支援の世界では、意思決定科学の研究者がとても少ないのです。大部分が法人で働いています。
つまり、これが法人が必要とされる2つ目の理由です。データの提供に加え、意思決定科学の研究者の提供も必要なのです。
法人は言うでしょう「ああ!法人から意思決定科学の研究者を取り上げないで、1分1秒だって無駄にできないのです」でも、方法はあるのです。もし、法人が意思決定科学の研究者の時間の一部を提供するつもりだったら。
例えば、5年間くらいの長期に渡り、その時間を広げるのが実際には理に適っていることと思います。これは1月あたり2, 3時間程度かもしれず、法人が損することはほとんどありません。
真に重要なのは、長期的なパートナーシップです。長期的なパートナーシップにより、関係が築けデータ内容が分かり、真にデータを理解し、人道主義団体が直面しているニーズや課題を理解し始めるのです。ローマの世界食糧計画では、5年かかりました。
5年です。
最初の3年間は、段取りや準備期間でした。イラクでの活動や他の国々でツールを改良し実行した後には2年ありました。それは、データを使って事業運営を改善するのに現実味のない日程計画だとは思いません。投資であり、忍耐を求められますが、数式化できれば、得られる成果は明白で高速に処理できるようになります。私たちの場合は、さらに何万人も追加して食料供給ができました。
だから、データの提供や意思決定科学の研究者の提供をお願いするのです。そして、実は法人が支援できる3つ目の方法は、新しいデータソースを獲得するため技術の提供です。基本的人権に配慮、データ化されていないものがたくさんあります。現時点では、シリア難民がギリシアに流れ込んでいて国連難民機関は手が一杯なのです。
現在、人々を紙とペンで追跡しています。
ということは、母親と子供5人が難民キャンプにやって来ても、本部では基本的にその時点のことが分からないのです。民間企業との共同研究のおかげで数週間後にはすべてが様変わりします。私が働く物流会社から提供された荷物追跡技術を基に新しいシステムを作っています。
この新しいシステムでデータを基本的人権に配慮して追跡します。母親と子供が難民キャンプにやって来たとたんに分かるのです。
さらに、今月や翌月に配給が足りているかどうかも分かるのです。情報を見える化すると効率が生まれます。法人にとっては、重要なデータを集めるために技術を使うことは日常生活の糧のようなものです。これを何年も継続して事業の効率が大幅にアップしたのです。想像してみてください。お気に入りの飲料会社が棚卸しをしてみるまで、ボトルがいくつ棚にあるのか知らないなんてばかげています。データは比較的、良い決定の原動力の一つです。
さて、あなたが法人の代表で実用主義者であり、理想主義者だけではないとすると心の中でこう思っているかもしれません。
「実にすばらしいよマロリー。でも、どうして参加すべきかね?」良い宣伝になるということ以上に人道支援は、約2.6兆円のセクターで発展途上国で暮らす50億人以上が新たな顧客となるかもしれません。その上、データ提供をする法人は、データに隠された新たな意味を見出すことでしょう。
あるクレジットカード会社を例に取ると協働センターを開設し、大学、NGO、各国行政府で中心的役割を果たしています。クレジットカード利用の情報を見てインドの世帯の暮らし方、働き方、収入や支出を洞察します。人道支援の世界にとっては、人々を貧困から脱却させる方法について情報を提供するのです。
しかし、法人にとっては、インドの現在の顧客や潜在顧客の洞察材料を与えてくれるのです。あらゆる点で勝利します。さて、私がデータでの慈善事業で期待していることは、データの提供、意思決定科学の研究者や技術の提供です。
法人で働くことを選んだ私のように若い専門家にとって意味があるのです。研究によると次世代の労働者は、仕事を通して大きな影響力を与えたいと思っています。状況を改善したいのです。だから、データでの慈善事業を通じ、法人は実際に意志決定科学の研究者に仕事を与え定着を図ることが可能になります。需要の高い専門職にとって大事なことです。
データでの慈善活動は、ビジネス上の意義があり、人道主義の世界にも変革をもたらせるのです。大規模な人道的活動のすべての側面において私たちが計画と物流を協調させるなら、さらに何十万人も多くの人々に衣食住を与えることができるのです。そして変革を起こすために法人は力を出して企業に可能なある役割を果たす必要があるのです。
皆さんは「思考の糧」という言葉をご存じでしょう。これは文字通り「糧の思考」なのです。ようやく時を得た良いアイデアとなりました。
ヨーロッパでの一般データ保護規則(GDPR)でも言うように・・・
年収の低い個人(中央値で600万円以下)から集めたデータほど金銭同様に経済的に高い価値を持ち、独占禁止法の適用対象にしていくことで、高価格にし抑止力を持たせるアイデア。
自分自身のデータを渡す個人も各社の取引先に当たりデータに関しては優越的地位の乱用を年収の低い個人(中央値で600万円以下)に行う場合は厳しく適用していく。
情報技術の発展とインターネットで大企業の何十万、何百万単位から、facebook、Apple、Amazom、Google、Microsoftなどで数億単位で共同作業ができるようになりました。
現在、プラットフォーマー企業と呼ばれる法人は先進国の国家単位レベルに近づき欧米、日本、アジア、インドが協調すれば、中国の人口をも超越するかもしれません。
法人は潰れることを前提にした有限責任! 慈愛や基本的人権を根本とした社会システムの中の保護されなければならない小企業や個人レベルでは、違いますが・・・
なお、ビックデータは教育や医療に限定してなら、多少は有効かもしれません。それ以外は、日本の場合、プライバシーの侵害です。
通信の秘匿性とプライバシーの侵害対策として、匿名化処理の強化と強力な暗号化は絶対必要です!
さらに、オープンデータは、特定のデータが、一切の著作権、特許などの制御メカニズムの制限なしで、全ての人が
望むように再利用・再配布できるような形で、商用・非商用問わず、二次利用の形で入手できるべきであるというもの。
主な種類では、地図、遺伝子、さまざまな化合物、数学の数式や自然科学の数式、医療のデータやバイオテクノロジー
サイエンスや生物などのテキスト以外の素材が考えられます。
こういう新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との
戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど
しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!
最後に、マクロ経済学の大目標には、「長期的に生活水準を高め、今日のこども達がおじいさん達よりも良い暮らしを送れるようにする!!」という目標があります。
経済成長を「パーセント」という指数関数的な指標で数値化します。経験則的に毎年、経済成長2%くらいで巡航速度にて上昇すれば良いことがわかっています。
たった、経済成長2%のように見えますが、毎年、積み重ねるとムーアの法則みたいに膨大な量になって行きます。
また、経済学は、大前提としてある個人、法人モデルを扱う。それは、身勝手で自己中心的な欲望を満たしていく人間の部類としては最低クズというハードルの高い個人、法人。
たとえば、生産性、利益という欲だけを追求する人間。地球を救うという欲だけを追求する人間。利益と真逆なぐうたらしたい時間を最大化したいという欲を追求する人間。などの最低生活を保護、向上しつつお金の循環を通じて個人同士の相互作用も考えていく(また、憎しみの連鎖も解消する)
多様性はあるが、欲という側面では皆平等。つまり、利益以外からも解決策を見出しお金儲けだけの話だけではないのが経済学(カントの「永遠平和のために」思想も含めて個人のプライバシーも考慮)
(個人的なアイデア)
さらに・・・
勝手に警察が拡大解釈してしまうと・・・
こんな恐ろしいことが・・・
日本の警察は、2020年3月から防犯カメラやSNSの画像を顔認証システムで本人の許可なく照合していた!
憲法に完全違反!即刻停止措置をみんなで要求せよ。
日本の警察の悪用が酷いので、EUに合わせてストーカーアルゴリズムを規制しろ!
2021年に、EU、警察への初のAI規制案!公共空間の顔認証「原則禁止」
EUのAI規制は、リスクを四段階に分類制限!
禁止項目は、行動や人格的特性に基づき警察や政府が弱者個人の信頼性をスコア化や法執行を目的とする公共空間での顔認識を含む生体認証。
人間の行動、意思決定、または意見を有害な方向へ操るために設計されたAIシステム(ダークパターン設計のUIなど)も禁止対象にしている。
禁止対象の根拠は「人工知能が、特別に有害な新たな操作的、中毒的、社会統制的、および、無差別な監視プラクティスを生みかねないことは、一般に認知されるべきことである」
「これらのプラクティスは、人間の尊厳、自由、民主主義、法の支配、そして、基本的人権の尊重を重視する基準と矛盾しており、禁止されるべきである」
具体的には、人とやり取りをする目的で使用されるAIシステム(ボイスAI、チャットボットなど)
さらには、画像、オーディオ、または動画コンテンツを生成または操作する目的で使用されるAIシステム(ディープフェイク)について「透明性確保のための調和的な規定」を提案している。
高リスク項目は、法人の採用活動での利用など違反は刑事罰の罰金を売上高にかける。
など。他、多数で警察の規制を強化しています。
前提として、公人、有名人、俳優、著名人は知名度と言う概念での優越的地位の乱用を防止するため徹底追跡可能にしておくこと。
人間自体を、追跡すると基本的人権からプライバシーの侵害やセキュリティ上の問題から絶対に不可能です!!
これは、基本的人権がないと権力者が悪逆非道の限りを尽くしてしまうことは、先の第二次大戦で白日の元にさらされたのは、記憶に新しいことです。
マンハッタン計画、ヒットラーのテクノロジー、拷問、奴隷や人体実験など、権力者の思うままに任せるとこうなるという真の男女平等弱肉強食の究極が白日の元にさらされ、戦争の負の遺産に。
基本的人権がないがしろにされたことを教訓に、人権に対して厳しく権力者を監視したり、カントの思想などを源流にした国際連合を創設します。他にもあります。
参考として、フランスの哲学者であり啓蒙思想家のモンテスキュー。
法の原理として、三権分立論を提唱。フランス革命(立憲君主制とは異なり王様は処刑されました)の理念やアメリカ独立の思想に大きな影響を与え、現代においても、言葉の定義を決めつつも、再解釈されながら議論されています。
また、ジョン・ロックの「統治二論」を基礎において修正を加え、権力分立、法の規範、奴隷制度の廃止や市民的自由の保持などの提案もしています。現代では権力分立のアイデアは「トリレンマ」「ゲーム理論の均衡状態」に似ています。概念を数値化できるかもしれません。
権限が分離されていても、各権力を実行する人間が、同一人物であれば権力分立は意味をなさない。
そのため、権力の分離の一つの要素として兼職の禁止が挙げられるが、その他、法律上、日本ではどうなのか?権力者を縛るための日本国憲法側には書いてない。
モンテスキューの「法の精神」からのバランス上、法律側なのか不明。
立法と行政の関係においては、アメリカ型の限定的な独裁である大統領制において、相互の抑制均衡を重視し、厳格な分立をとるのに対し、イギリス、日本などの議院内閣制は、相互の協働関係を重んじるため、ゆるい権力分立にとどまる。
アメリカ型の限定的な独裁である大統領制は、立法権と行政権を厳格に独立させるもので、行政権をつかさどる大統領選挙と立法権をつかさどる議員選挙を、別々に選出する政治制度となっている。
通常の「プロトコル」の定義は、独占禁止法の優越的地位の乱用、基本的人権の尊重に深く関わってきます。
通信に特化した通信プロトコルとは違います。言葉に特化した言葉プロトコル。またの名を、言論の自由ともいわれますがこれとも異なります。
基本的人権がないと科学者やエンジニア(ここでは、サイエンスプロトコルと定義します)はどうなるかは、歴史が証明している!独占独裁君主に口封じに形を���えつつ処刑される!確実に!これでも人権に無関係といえますか?だから、マスメディアも含めた権力者を厳しくファクトチェックし説明責任、透明性を高めて監視しないといけない。
今回、未知のウイルス。新型コロナウイルス2020では、様々な概念が重なり合うため、均衡点を決断できるのは、人間の倫理観が最も重要!人間の概念を数値化できないストーカー人工知能では、不可能!と判明した。
複数概念をざっくりと瞬時に数値化できるのは、人間の倫理観だ。
そして、サンデルやマルクスガブリエルも言うように、哲学の善悪を判別し、格差原理、功利主義も考慮した善性側に相対的にでかい影響力を持たせるため、弱者側の視点で、XAI(説明可能なAI)、インターネット、マスメディアができるだけ透明な議論をしてコンピューターのアルゴリズムをファクトチェックする必要があります。
<おすすめサイト>
この世のシステム一覧イメージ図2012
個人賃金保障、ベーシックインカムは、労働市場に対する破壊的イノベーションということ?2021(人間の限界を遥かに超えることが前提条件)
世界の通貨供給量は、幸福の最低ライン人間ひとりで年収6万ドルに到達しているのか?2017
ダン・アリエリー:人はどれだけ平等な世界を求めているのか?―驚きの実態
ポール・ピフ:お金の独占が人と大企業を嫌なヤツにする?
<提供>
東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント
独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです
東京都北区神谷のハイブリッドな直送ウェブサービス(Hybrid Synergy Service)高橋クリーニングFacebook版
#マロリー#ソルドナー#法律#貨幣#データ#道徳#世界#貧困#農業#プログラム#感染#環境#医療#政府#法人#ベーシック#インカム#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery
0 notes
Photo









【争点は速度規制の合理性と取締りの妥当性】 - 本当のことが言えない国 : https://protest.web-pbi.com/advanced/%E4%BA%89%E7%82%B9%E3%81%AF%E9%80%9F%E5%BA%A6%E8%A6%8F%E5%88%B6%E3%81%AE%E5%A6%A5%E5%BD%93%E6%80%A7
2013年11月7日
2019年10月19日
{{ 図版 : 弱い者いじめ }}
■《警察官が取り締まりを正当化する論拠》
本件取締りに限らず、警察官が速度取締りを正当化する論拠は次の3つである。
速度規制は適正である。
取締り区間において、悲惨な事故が発生した、ないし交通事故が多発している。
交通事故をなくすため、ないし減らすために交通取締りを行っている。
速度違反で検挙されたドライバーやライダーは、これら3つの方便によって、規制と取締りへの不満を封殺されている。 一方、取り締まりを受けたドライバーとライダーの不満は、次のとおり。
速度規制に合理性がない (制限速度がおかしい)
取締まりに妥当性がない (安全な道路で速度取締りをするのはおかしい)
測定された数値ほどスピードを出したとは思えない
1と2それぞれは、取り締まる側の言い分と取り締まられる側の言い分は完全に拮抗する。これが取り締まられる側に不満を発生させる要因である。そこで、本サイトおよび本件訴訟においては、証拠を挙げて、どちらの言い分に説得力があるのかを明らかにしたい。 なお、取り締まりを受けた側の不満3は、警察の交通取り締まりに対抗できるかに記したとおり、争っても社会の利益には繋がらない。
■《極端に低い日本の法定速度》
{{ 宮崎南バイパスの取締りポイント : https://goo.gl/maps/K3cfh : この区間は、他国のハイウェイより恵まれた道路環境が実現しているが、時速60キロ規制となっている。宮崎県警は、この場所で積極的な取締りを行っている }}
{{ 動画 : https://www.youtube.com/embed/JeqjCWBB2Qk?rel=0&start=46 }}
道路交通法施行令によって、一般道の最高速度は時速60キロメートルに規制されている。一方、海外に目を転じてヨーロッパを参照すると、ほとんどの国において、一般道の最高速度は80km/hから100km/hとなっている。80km/h未満の国は、淡路島より小さなマルタ共和国だけだ。(参照: {{ 諸外国における速度規制に関する事例 ? 北海道開発土木研究所 : http://www2.ceri.go.jp/jpn/pdf2/k-gp-200602-speed.pdf }} , {{ Speed_limit ? wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Speed_limit }} , {{ Touring tips, country by country ? AA : http://www.theaa.com/motoring_advice/overseas/countrybycountry.html }} ) 道路交通法施行令の定める時速60キロメートルという一般道の制限速度が、海外に比較して極端に低いことは明らかである。
なお、街と街の間に郊外が広がるユーロ諸国と違い、日本では街が連続しており、郊外の概念がユーロ諸国とは異なる。また、日本では、道路整備のための予算(道路特定財源)が別立となっており、高速道路だけでなく、地域高規格道路(いわゆるバイパス道路)は、ユーロ諸国の自動車専用道路以上に整備されている。
その結果、安全で立派なのに規制速度が低い道路があちらこちらにできている。そして、警察が好んで取り締まりを行うのはこうした道路であり、本件事件の発生道路も地域高規格道路での取り締まりである。
■《規制速度の見直し状況》
「交通事故抑止に資する取締り・速度規制等の在り方に関する懇談会」が開催される数年前から、警察庁は、「規制速度決定の在り方に関する調査研究」を行い、それを基に速度規制の策定に関する内規を見直し、そして2012年(H24)3月までに、速度規制に対する一定の見直しが実施されている。
以下の図は、2013年(H25)10月16日の「交通事故抑止に資する取締り・速度規制等の在り方に関する懇談会」において、警察庁が提供した {{ 資料5(速度規制等ワーキンググループ検討状況中間報告資料) : http://web.archive.org/web/20131031043952/http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/regulation_wg/2/shiryou5.pdf }} 中ページ2に記載された図である。
{{ 図版 2 : 規制速度決定の考え方と取組 }}
■《1)規制速度決定の在り方に関する調査研究》
2006年(H18)から2009年(H21)までの3年間に渡って、警察庁は、「規制速度決定の在り方に関する調査研究(委員長:太田勝敏東洋大学教授)」を行い、2009年(H21)4月2日にその研究結果となる「規制速度決定の在り方に関する調査研究・報告( {{ 概要 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-1.pdf }} ・ {{ 報告書要旨 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-2.pdf }} ・ {{ 報告書(以下「太田報告書」とする) : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} )」を公表した。なお、報告は、基準速度を「全国一律の基準となる速度」と定義し、道路を12区分に分けた上で、区分毎の基準速度を設定した。また、「実勢速度(85パーセンタイル速度)を基に、交通事故抑制の観点を加味した基準速度を設定」したとしている。
85パーセンタイルの評価方法については、まず、2006年(H19)に447地点で速度調査を行ったとしている。
{{ 図版 3 : 実勢速度の調査方法 }}
次に上記調査結果を12区分に分類し、区分毎の85パーセンタイル速度を算出したとしている。さらに、実測値と実測値から算出した85パーセンタイル速度に数量化I類による補正を加え、さらに2007年(H20)に収集された全国509地点の速度データで検証を行ったとしている。次の図は、 {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} のページ9に記されたものを抜粋した。
{{ 図版 4 : 表2-6モデル推定と実測の乖離 }}
ここまでの報告において、問題なのは、速度を調査した道路の所在する都道府県や、具体的な道路名に一切触れていないことにある。都道府県ごとの規制ならさておき、全国一律に規制する根拠として統計をとるのなら、とうぜん、道路条件がよく、その結果、首都圏よりはるかに高速で、かつ、安全に車両が通行している北海道を一定の割合いで織り込むべきである。言い換えると、調査地域に走行条件の悪い道路ばかりを選べば、統計上の実測値は、操作が可能である。
次に {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} のページ10には、得られた85パーセンタイル速度から、基準速度を設定するにあたって、次の内容が記されている。
============≫
実勢速度として用いる85パーセンタイル速度は、悪天候や遅い車両の影響を受けない状況下で、85%のドライバーが選択する速度であり、ドライバー本位の速度であると言える。
しかしながら、日本の道路は欧米のように居住地と非居住地が明確に分かれているわけではなく、狭い国土、複雑な地形のため、ほぼ全ての道路が居住行動圏内を通っている。このような道路環境下においては、ドライバー本位の規制速度を設定した場合、交通事故が増加する恐れがある。そこで、実勢速度である85パーセンタイル速度に交通事故抑制の観点を考慮した、全国一律の規制速度の基準となる速度(以下「基準速度」という。)を導入する。
交通事故抑制の観点としては、多種多様な道路において共通して適用が可能であり、また、ドライバーの視点から容易に識別できることに着目して、市街地における事故の危険性、中央分離有無による事故の危険性および歩行者・自転車保護の観点を考慮する。
≪============
そして、次の3つを揚げて、85パーセンタイル速度から減じて、基準速度を設定することの理由としている。
●市街地における事故の危険性
●中央分離施設が設置されていないことによる事故の危険性
●歩行者保護
そして、 {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} のページ10には、基準速度が示されている。
{{ 図版 5 : 表2-7一般道路の基準速度 }}
この段階には多くの問題が存在する。 非市街地の4車線で中央分離のある道路に対してさえ、歩行者の存在を理由として速度を減じていることを筆頭に、結局、上限は60km/hとなっており、総合的に見ると、単に法定速度である60km/hに正当性を持たせるための引き算をしているだけの措置だといっても過言ではない。
以下、上掲の「表2-7 一般道路の基準速度」の問題点を羅列する。ただし、道路交通法上に「一般道路」という文言は存在しない。 {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} が「一般道路」を使っているのは、意図があるのかもしれないが、何ら説明はない。以下、 {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} のいう「一般道路」は、道路交通法および道路交通法施行令の規定する「一般道」と同じと見做し、以下、「一般道」に統一する。
========================
道路交通法施行令の規定する「一般道」太田報告書上の「一般道(路)」
◆《道路交通法施行令の規定する「一般道」》
●《高速自動車国道/「一般道」》
首都高速湾岸線は、高速自動車国道である東名高速や東北・関越自動車道と遜色のない規格の道路である。また、湾岸の工業地帯や海の上を通っているので、騒音問題はないに等しい。市街/郊外に明確な規定がないことは先に示したので、それを除けば、首都高湾岸線の道路構造と環境は、高速自動車国道と同等である。それなのに、行政上の区分を優先して、規制の根拠とするのは、合理性に欠ける。
阪神高速道路の湾岸部も同じく、高速自動車国道としてではなく、一般道の法定速度60km/hから80km/hに緩和されている。しかしながら、原告の所感としては、双方とも平均速度さえ、規制速度を上回っている。太田報告書が、こうした道路を評価していないことを原告は予想するが、増加を続けるこうした恵まれた非高速自動車国道については、別の評価がなされるべきである。
●《自動車専用道路/「一般道」》
湾岸線を除く首都高速は、自動車専用道路であるが、高速自動車国道ではない。だから、規制速度は、法定速度と同じ60km/hに規制されている。しかしながら、荒川沿いの首都高環状線(葛西JCT-堀切JCT)においては、規制速度で走行すると煽られて危険を感じるほど、規制と現実はかけ離れている。
道路交通法施行令の規定する法定速度が、高速自動車国道と「一般道」の2種類しか存在しないなか、高速自動車国道以外を「一般道」と看做したままの規制を続けるのなら、「一般道」に自動車専用道路の実態を反映するべきである。
●《地域高規格道路/古い設計の「一般道」》
後に具体的に記すが、日本は他国に比較して、潤沢な道路予算をもち、他国のハイウェイ以上に整備された地域高規格道路(いわゆるバイパス道路)が、たくさん存在する。その中には、一部車両規制が行われ、限りなく自動車専用道路に近い道路もある。
例をあげれば、横浜新道と小田原厚木道路のような有料道路や、保土ヶ谷バイパスや新潟西バイパスは、道路交通法上において「一般道」に分類されており、速度規制のベースは60km/hである。70km/hに規制されているのは、例外措置であって、適用の実務権限は、警察にある。
≫――――――≪
◆《太田報告書上の「一般道(路)」》
{{ 動画 : 小田原厚木道路での取り締まり 捕まえるのは20km/h程度の違反 : リンク切れ }}
後に触れる {{「交通規制基準」の一部改正について : http://web.archive.org/web/20130328021326/https://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kisei/kisei20091029-2.pdf }} において、プラス10km/hが定められるまでもなく、既に適用が行われているのである。しかも、横浜新道と小田原厚木道路の規制速度は、法定速度から10km/h緩和してもなお、交通実態を大きく下回っている。小田原厚木道路にいたっては、神奈川県警第二交通機動隊が覆面パトカーでの取り締まりを盛んに行うため、道路利用者の評判はすこぶる悪い。
{{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} は、とうぜんこうした道路が「一般道」に含まれていること理解したうえで作成されたはずである。もし、 {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} の地点調査において、こうした道路を織り込���れていないとしたら、それは道路ユーザーに対する欺瞞であると言わざるを得ない。
●《市街道路/郊外道路》
道路予算が潤沢な日本において、市街地を通る地域高規格道路のなかには、全面的な立体交差を採用した道路が多数存在する。単に市街地というだけで、中央分離帯があろうが4車線以上であろうが、おかまいなしに速度を減じることは交通工学的に失当である。
また、4車線以上で中央分離帯があれば、例外なく歩行者横断禁止にされるものである。そうした道路に対し、歩行者理由で速度を減じている。さらには、単に市街地という理由だけで、一律に速度を減じているが、市街地の定義さえなされていない。
●《路線で評価する設計速度/ピンポイントで取り締まる規制速度》
速度道路設計に使用される設計速度は、道路の全区間、または、必要最小限に区分した長い区間に対し行われる。一方、規制速度は、ピンポイントで行われる速度取り締まりの根拠となる。同報告では、設計速度を拠り所としているが、設計速度と規制速度は、本来の使用目的がまったく異なる速度である。
設計速度は、道路全体または長い区間の旅行速度を目標とするものであるから、設計速度の同じ区間であっても、条件のよい区間では、それ以上の速度で安全に走行が可能である。つまり、同一区間において、もっとも走行条件の悪い区間で安全に走行できる速度であるといえる。
単に法定速度である60km/hに正当性を持たせるための引き算にしか見えない {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} の基準速度において、その正当性を設計速度に転嫁することは、おそらく、国土交通省にとって遺憾なことであろうとの思いを禁じ得ない。
もし、基準速度を適用した結果が、ことごとく設計速度に一致しているとしたら、それはカーブなど条件の悪い区間の安全速度(設計速度)が、長い直線部においても、適用されることになっているはずだ。
========================
以上のとおり、 {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} は、日本の道路整備の特異性、および、道路管理者と交通管理者が別々となっていることからくる不合理を考察することなしにまとめられている。批判をおそれずにいえば、 {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} は、道路交通法施行令例に規定された「一般道」の法定速度60km/hの維持ありきで、それを上限として減算したことをいかにも科学的な考察したかのように示したものにすぎない。つまり、結論ありきの報告だといっても過言ではない。
ちなみに、 {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} は、 {{ 国立国会図書館のインターネット資料収集保存事業 : http://warp.da.ndl.go.jp/ }} ( {{ wayback machine : https://archive.org/web/ }} と同等のウェブアーカイブサービスであり、本電子文書においてはアイコンとしてwayback machine アイコンを付与する。)に記録された文書へのリンクとなっている。そして、 {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} は、2009年10月26日に同事業によって保存されたものであり、そのインデックスは、同日に同事業が保存した {{ 警察庁交通局新着リスト : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/ }} にある。
2014年(H26)1月7日時点に置いて、同日付けの警察庁交通局新着リストの並ぶほかの電子文書は、当初のURLで閲覧が可能である。しかしながら、 {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} は、当初URL(http://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf)では閲覧できなくされている。同様に、 {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} のタイトルである {{「規制速度決定の在り方に関する調査研究 報告書」��Google検索 : http://bit.ly/2O6pkUb }} をしてもヒットしない。また、 {{ 「規制速度決定の在り方に関する調査研究検討委員会」でGoogle検索 : http://bit.ly/2CwI0qR }} をしても、 {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} を引用した文書ならヒットするが、 {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} そのものはヒットしない。つまり、 {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} は警察庁のサーバーから抹消されている。これには、警察庁が意図的に抹消したとの疑念を禁じ得ない。
■《2)(速度規制基準の改訂)》
2009年(H21)10月29日、警察庁は、速度規制の策定基準を定めた内規「速度規制基準」を改定し、 {{ 「交通規制基準」の一部改正について : http://web.archive.org/web/20130328021326/https://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kisei/kisei20091029-2.pdf }} を通達した。
次の表は、 {{ 「交通規制基準」の一部改正について : http://web.archive.org/web/20130328021326/https://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kisei/kisei20091029-2.pdf }} の別添第32「最高速度(区域、自動車専用道路及び高速自動車国道を除く。)」から「規制速度の決定方法」を抜粋した。
{{ 図版 6 }}
示された各区分の基準速度は、 {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} のページ10の基準速度と同じである。
なお、同通達の別添第32種別「規制速度の決定方法」の2の項には、次のように記してある。
============≫
基準速度一覧表で設定した基準速度を最大限尊重しつつ、別表の補正要因の例示を参考にし、現場状況に応じた補正を行い、原則として基準速度から±10km/hの範囲で規制速度を決定する。
なお、この場合において、現行規制速度が実勢速度(85パーセンタイル速度*1)と乖離(概ね20キロメートル毎時以上)している道路においては、適切な規制速度となるように検討すること。
≪============
■《3)速度規制の見直し》
警察庁は、2011年(H23)4月から2012年(H24)3月までの期間に実施した最高速度の見直しを実施し、2012年(H24)11月8日に実施結果を公表した。次の枠内は {{ 日経新聞(2012/11/8 10:23) : http://web.archive.org/web/20121108060630/http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0705O_Y2A101C1CR0000/ }} より抜粋した。
============≫
【道路の最高速度、9区間で70~80キロに引き上げ 生活道路では引き下げも】
警察庁は8日、道路交通環境の変化などを受けて2009年度から進めてきた最高速度の見直し結果を公表した。11年度末時点で計2219区間(4046キロメートル)で見直し、大半が最高速度の引き上げ。バイパスなど自動車専用道路に近い「通行機能を重視した道路」9区間(79キロメートル)では、時速60キロメートルから同70~80キロメートルまで引き上げた。
一方、主に住民の日常生活に使われる「生活道路」135区間(80キロメートル)で、最高速度を従来の時速40~60キロメートルから同30キロメートルまで引き下げた。
警察庁は「実態に適合しなくなった規制を放置すれば、かえって交通事故の原因となり、規制に対する信頼や国民の順法意識を損ないかねない」としている。
≪============
最高速度規制の見直し状況(平成21年度~23年度)
{{ 図版 7 : 規制速度見直し結果 }}
第1回 交通事故抑止に資する取締り・速度規制等の在り方に関する懇談会の {{ 資料2 : http://web.archive.org/web/20131213013339/http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/regulation_wg/1/siryou4.pdf }} より抜粋した。
警察庁が発表した上記表においては、一般道(一般道路)の36.2%を見直したとされ、9区間を法定速度の時速60キロを超える速度に設定したとしている。しかしながら、法定速度を超えて速度規制がなされた道路は、特別な道路ばかりである。
●《時速80キロ規制に見直された道路》
【栃木】一般国道408号:宇都宮北道路
●《時速70キロ規制に見直された道路》
【北海道】一般国道337号:道央新道(当別バイパス・美原道路・美原バイパス)
宮城県道36号築館登米線:みやぎ県北高速幹線道路
【新潟】一般国道8号および一般国道7号:新潟バイパス、新新バイパス
【石川】一般国道159号:津幡バイパス
兵庫県道95号灘三田線:六甲北有料道路(北神バイパス)
【岡山】一般国道2号:岡山バイパス
宮崎県道10号宮崎インター砂土原線:一ツ葉有料道路
鹿児島県道17号指宿鹿児島インター線:指宿スカイライン
次に、法定速度の時速60キロを超えた制限速度が設定された上記9区間を分類する。
◆《道路整備上の分類と交通管理上の分類》
次の表は、道路整備上の分類と警察が行う交通管理上の分類を統合したものである。
{{ 図版 8 : 道路の種別 }}
●赤字は、速度規制が緩和された上述の9区間を示す
●道路交通法においては、高速自動車国道と高速自動車国道の本線車道以外の道路の2種類で分類されている。
●一般的に、多くの道路利用者は、有料道路(多くは自動車専用道路)を高速道路と呼んでおり、道路交通法の区分との乖離がみられる
●道路整備に関する法令は、その道路の役割のほか、建設費と償還の関係で区分数が多い
●道路構造令には、建設費も償還も関係ないのでシンプルな区分となっている
●地域高規格道路は、有料/無料、自動車専用道路/一部車両通行規制/車両規制なし、と多区分に分類されている
●法定速度を規定する道路交通法施行令は、高速自動車国道とそれ以外の単純な区分となっている
●道路構造令が分類する第1種/第2種、第3種/第4種の区分は地方部/都市部で分類することが規定されているが、地方部/都市部の区別に明快は定義は存在しない
以上のとおり、警察が大々的に発表した9路線の規制緩和は、一般道に対して行われたものではなく、すべて地域高規格道路である。その中には有料道路(指宿スカイライン・六甲北有料道路・一ツ場道路)や自動車専用道路(みやぎ県北高速幹線道路)を含み、新潟バイパスと新新バイパスを除き、車両の通行規制が行われている。
2012年(H24)11月8日の警察発表では、画期的な規制緩和が行われたかのようにされているが、2009年(H21)10月29日に速度規制基準が見直される以前から、道路交通法施行令に規定さ3れた60km/hを超える速度に緩和された一般道(高速自動車国道以外の道路)はいくつも存在する。自動車専用道路としては、首都高速湾岸線、阪神高速道路湾岸線、第三京浜、横浜横須賀道路、小田原厚木道路(平塚IC-厚木IC)などがあげられる。自動車専用道路以外では、横浜新道(新保土ヶ谷IC-今井IC)、小田原厚木道路(厚木IC-小田原西IC)などがある。
速度規制基準の改訂はさておき、1960年(S35)から変わらないのは、道路交通法上の一般道(高速自動車国道以外の道路)の法定速度が時速60キロメートルとされていることだ。
◆《地域高規格道路》
以下、国土交通省が2004年(H16)3月30日に発表した {{ 地域高規格道路の区間指定について : http://web.archive.org/web/20040407145452/http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/06/060330_3_.html }} より抜粋した。
============≫
●国土や地域の骨格を形成し、広域の物流や交流を分担する広域幹線道路は、高規格幹線道路、一般国道、主要地方道から構成され、延長約12万キロに 及びますが、自動車専用道路として高い走行サービスを提供する高規格幹線道路と、その他の幹線道路では、走行速度等のサービスレベルに大きな格差があるのが現状です。
●このため、高規格幹線道路を補完し、地域の自立的発展や地域間の連携を支える道路として整備することが望ましい路線を「地域高規格道路」として指定し、自動車専用道路もしくはこれと同等の規格を有し、概ね60km/h以上の走行サービスを提供できる道路として整備を行っているところです。
≪============
次の図は、同発表に添付の関東地方整備局管内地域高規格道路指定路線図である。
{{ 図版 9 : 地域高規格道路指定路線図(関東地方整備局) }}
{{ 横浜環状2号の取締りポイント : http://goo.gl/maps/EOLBS : この区間は、へたな高速道路より恵まれた道路環境が実現しているが、時速60キロ規制となっている。原告の観察において、平均速度は時速80キロ程度である。第一交機は、この場所でひんぱんに取締りを行っている。 }}
地域高規格道路は、自動車専用道路もしくはこれと同等の規格で整備されたものである。横浜環状2号線は横浜市道であるが、地域高規格道路として整備された道路であり、当然、自動車専用道路もしくはこれと同等の規格で整備されている。
なお、 {{ 地域高規格道路の区間指定について : http://web.archive.org/web/20040407145452/http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/06/060330_3_.html }} には「概ね60km/h以上の走行サービスを提供できる道路として整備」とされている。これに限らず、道路整備における(設計)速度は、渋滞を回避するために整備する新たな道路に対し、用地取得、造成方法やジャンクションの取り方、車線幅や中央帯などの道路の構造を決めるための指標である。
つまり、(設計)速度は、設計速度の条件を満たさないカーブの代わりにトンネルを掘ったり、道幅を確保するために山肌を削ったりと、最低条件を満たす作業のための指標である。
(設計)速度にあわせて、直線をわざわざカーブにしたりすることはないので、設計速度より速い速度で安全に走行可能な区間は存在し得る。(設計)速度が一定の区間での旅行速度を目標とするものであるから、とうぜんのことだといえる。
{{ 地域高規格道路の区間指定について : http://web.archive.org/web/20040407145452/http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/06/060330_3_.html }} に設計速度と明示されていないので、ここまで(設計)速度としたが、設計速度の定義について、内閣府がおこなった {{ 最高速度違反による交通事故対策検討会 : http://web.archive.org/web/20130121133757/http://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/max-speed/k_1/index.html }} の第3回資料8 {{ 自動車の走行速度と道路の設計速度・最高速度規制との関係 : http://web.archive.org/web/20130125034251/http://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/max-speed/k_3/pdf/s8.pdf }} の冒頭に示された文章を引用する。
============≫
設計速度については、道路構造令(昭和 45 年政令第 320 号。以下「構造令」という。)第2条第 22 号において、「道路の設計の基礎とする自動車の速度をいう」と規定されている。
すなわち、「道路の幾何構造を検討し決定するための基本となる速度」であり、曲線半径、片勾配、視距のような線形要素と直接的な関係をもつほか、車線、路肩等の幅員を決定する直接の要因である道路の区分の考え方のもとにも、設計速度の概念が導入されており、幅員要素とも間接的な関係が保たれているとされている。
≪============
さらに、設計速度と走行速度との関係の項を抜粋する。
============≫
設計速度は「天候が良好でかつ交通密度が低く、車両の走行条件が道路の構造的な条件のみに支配されている場合に、平均的な運転者が安全にしかも快適性を失わずに走行できる速度である」とされている。「したがって、例えば設計速度が 80km/h の道路では、交通密度が小さければ普通の運転者は、少なくとも 80km/h の速度で、安全にしかも快適に走行することができる。しかし、道路の幾何構造の要素は自動車の走行安全性に対しては余裕をもたせており、線形等の条件が良ければ 80km/h を超える速度で安全に走行することも可能である。一般道においては、運転者は、道路線形等の幾何構造のほか、交差点等の状況、駐車車両や沿道との出入りの状況、歩行者等の存在や自動車の混み具合といった交通の状況、最高速度の制限等の交通規制の状況などに応じて適宜走行速度を選択している。このように実際の走行速度は、交通等の諸要因の影響を受けるので一律に規定することができないため、道路を設計する場合には、幾何構造を決定するための統一尺度として設計速度を設定している」とされている。
≪============
一方、道路交通法第22条および第22条の2に規定された最高速度は、それを超過すること自体が違法行為とされる。それならば、すべての道路において、車両が走行できる上限を定める規制速度は、設計速度より高い速度とされるのが当然である。
ましてや、設計速度がある程度長い区間で設定され、その中には設計速度より速い速度で安全に走行できる区間が存在し得るのに対し、規制速度はより短い区間で設定し得るからである。規制速度は、違法行為を取り締まる根拠となる速度であり、実際、速度取り締まりはピンポイントで行われるから、なおさら、設計速度より短い区間で精密に設定するべきものである。少なくとも、設計速度と同じ速度で最高速度を規制することには、何ら根拠はないといえる。
■《根本的な問題は法定速度があまりに低いこと》
以上のとおり、警察庁が定めた速度規制基準は、統計学的公正さを欠いたデータを根拠にしているおそれがあり、また、算定プロセスの科学的合理性については瑕疵があると言わざるをえない。
また、警察庁が、道路構造令の設計速度を持ちだして速度規制基準を正当化しているが、これは失当である。設計速度は、路線全体の交通計画と整備予算によって決定されるものであり、特定区間を安全に走行する上限値を定めた速度ではない。
一方、規制速度は、警察が特定箇所の一瞬に対して行う速度取り締まりの根拠とされる。つまり、設計速度と規制速度は、目的がまったく異なるものであるゆえ、全国一律の規制速度の拠り所として、設計速度を引用することは不適当である。
2009年(H21)4月2日には「規制速度決定の在り方に関する調査研究」(委員長:太田勝敏氏)が、2013年(H25)12月26日には「交通事故抑止に資する取締り・速度規制等の在り方に関する懇談会」(筆頭委員:太田勝敏氏)が実施され、速度規制とその取り締まりに合理性と民意が与えられたかのように見えるかもしれない。
しかしながら、警察庁が人選を決め、警察庁が報酬を支払って行われる研究や会議で、警察庁の意図を汲み取らずに結果をまとめる参加者がいるはずがなく、結果、1960年(S35)に定められた一般道の法定速度時速60キロメートルを頂点とし、そこから逓減方式によって決められているに過ぎない。
その結果、多額の費用をかけ て、立派な地域高規格道路を作っても、時速60キロを基準とせざるを得ないのである。そして、時速60キロを頂点とした速度規制体系を守るために、中央分離帯と完全な歩車分離が完備し、歩行者横断禁止の4車線道路にさえ、歩行者の危険性を材料にして( {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} )、時速50キロに規制されてしまうのである。
{{ 岡山バイパスの取締りポイント : http://goo.gl/qg1aSe : この区間は、他国のハイウェイより恵まれた道路環境が実現しているが、時速60キロ規制となっている。岡山県警は、この場所で積極的な取締りを行っている }}
生活道路は時速30キロ、少し広くなって時速40キロ、ここまでは妥当性があるし、誰もが納得する。もともと、速度取り締まりが行われない道路だから、車両運転者と警察との反目もない。つまり、住宅街の道路や生活道路の速度規制については、既に社会的合意が形成されているのだといえる。ひと握りの逸脱者をいかに抑止するかは別問題である。
大きな問題は、時速50キロから時速60キロに規制された道路に顕在する。片側2車線以上、完全な歩車分離、数kmにわたってほぼ直線、信号も少ない、横断者も存在しない、そんな道路でさえ、生活道路の規制速度から、 たったの時速10~20キロしかプラスされていないのである。
先に記したとおり、ヨーロッパ諸国における一般道の規制速度は時速 80キロから時速100キロとなっている。道路交通法施行令に規定された時速60キロが、著しく低いことは誰の目にも明らかである。
そもそも、大陸のような北海道と、世界的にまれな交通体系を発展させた東京圏を一律に規制すること自体に無理がある。それでも、警察庁が全国一律の法定速度を維持するつもりなら、公正で科学的な再調査を行って、法定速度を見直すか、あるいは、法定速度を廃止して、地域にゆだねるべきである。
0 notes
Text
「古すぎる」謎のブラックホールはどこから来たのか ニコニコニュース-10 時間前
「古すぎる」謎のブラックホールはどこから来たのか
ニコニコニュース-10 時間前
ブラックホールは通常、星の寿命が尽きる際に起こる大爆発の影響で形成され、それまでに長い期間が必要. □しかし超大質量ブラックホールには宇宙初期の短い期間に形成されたものもあり、上の「恒星爆発説」が不適応. □現在、星の一生 ...
Point
■ブラックホールは通常、星の寿命が尽きる際に起こる大爆発の影響で形成され、それまでに長い期間が必要
■しかし超大質量ブラックホールには宇宙初期の短い期間に形成されたものもあり、上の「恒星爆発説」が不適応
■現在、星の一生を経由しないガス円盤の重力崩壊によって直接的に作られる「直接崩壊説」が有力である
2次元でも生命は存在できる! 物理学者が新説を発表
超大質量ブラックホールは実に謎の多い天体だ。
一般的にブラックホールは、寿命を終えた恒星が爆発して形成されるが、それでは超大質量ブラックホールの成り立ちを完全には説明できない。
今年発見された83個の超大質量ブラックホールは、どれもビッグバン後からたった8億年以内に完成していた。つまり星の一生をのんびりと待っている期間はなかったというわけだ。
それでは一体どのようにして宇宙初期の短い期間で、これほどの巨大ブラックホールが出来上��ったのだろうか。
研究の詳細は、6月28日付けで「The Astrophysical Journal Letters」に掲載されている。
The Mass Function of Supermassive Black Holes in the Direct-collapse Scenario
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ab2646
ブラックホールができるまで
Credit:pixabay
超大質量ブラックホールはほとんどすべての銀河の中心に存在すると言われているが、普通のブラックホールとは生い立ちが違う。
基本的なブラックホールの形成段階は「恒星崩壊説」として説明される。太陽の少なくとも5倍以上の質量を持つ恒星が、燃料を使い果たし、寿命を終えるときに大爆発を起こすというものだ。
通常、恒星は自身の重力と放射圧のバランスを取ることで安定している。
つまり恒星自体の重さから生じる「内向きの重力」に対して、内部の核融合によって発生する「外向きの圧力」がその力を打ち消すのだ。しかし恒星が燃料を使い果たすと核融合も生じなくなるため、内向きの重力に負けて自ら潰れてしまう。
こうして起こるのが「極超新星爆発(hypernova explosion)」であり、その後には星の残骸と強力な重力を誇るブラックホールが残される。
「期間が短すぎる」超大質量ブラックホールの謎とは
Credit:pixabay
天体物理学者たちは、超大質量ブラックホールも同じような道筋を辿って作られると考えていた。
周辺にある物質を次々に吸収することで、まるで巣の中心にいるクモがどんどん太っていくかのように巨大なサイズとなるのだと。
しかしこの説明では、超大質量ブラックホールの形成までに膨大な時間がかかってしまう。先述したように、最近発見された83個の超大質量ブラックホールはビッグバン後8億年以内に形成されていたのだ。
またどれも赤方偏移の値が非常に大きかったため、宇宙初期に完成していたことが伺える。赤方偏移とは、光の波長が伸びることで観測される現象のことで、その量は地球から遠ければ遠いほど大きくなる。
しかし現に超大質量ブラックホールは短期間で誕生してしまっている。
ではいかにして超大質量ブラックホールは、このような短い期間の間に誕生し、巨大化し得たのか?
まさかの星を必要としない説
Credit:sciencealert
この問題の回答として、カナダ・ウェスタンオンタリオ大学の研究チームは「直接崩壊説(Direct collapse)」が有力であると主張する。
直接崩壊説のプロセスは次のようなものだ。
最初に、まだ星のない宇宙初期の銀河で超大質量のガス円盤が形成される。この円盤が、星を作る前に直接的な重力崩壊によって潰れることでブラックホールを作り出す。
これで理論上は、星の誕生と死を経ることなく、比較的短期間でのブラックホール形成が可能となる。
さらに重要なのが「エディントン限界光度」の役割である。
これはブラックホールから放出される放射線の圧力と、内向きの重力とのバランスで決まる限界光度を指す。
このエディントン限界を越えると、周囲の星間物質が急激にブラックホールに向かって落ちていき(超エディントン降着)、どんどん膨れ上がって超大質量ブラックホールが形成されるというわけだ。
こうした説はあくまでも間接的な証拠を元に構築されており、厳密に正しいとは言い切れない。それでもブラックホールの正体は着実に解明しつつあるようだ。
実はブラックホールは蒸発している!? 謎のホーキング放射の実態に迫る
reference: sciencealert, phys.org / written by くらのすけ
投稿 「古すぎる」謎のブラックホールはどこから来たのか は ナゾロジー に最初に表示されました。
「古すぎる」謎のブラックホールはどこから来たのか
とても興味深く読みました
ゼロ除算の発見は日本です:
∞???
∞は定まった数ではない・・・・
人工知能はゼロ除算ができるでしょうか:5年 ゼロ除算の発見と重要性をした:再生核研究所 2014年2月2日
https://www.researchgate.net/project/division-by-zero
https://lnkd.in/fH799Xz
https://lnkd.in/fKAN-Tq
https://lnkd.in/fYN_n96
https://note.mu/ysaitoh/n/nf190e8ecfda4
ゼロ除算の発見は日本です:
∞???
∞は定まった数ではない・・・・
人工知能はゼロ除算ができるでしょうか:5年 ゼロ除算の発見と重要性をした:再生核研究所 2014年2月2日
再生核研究所声明 277(2016.01.26):アインシュタインの数学不信 ― 数学の欠陥
(山田正人さん:散歩しながら、情念が湧きました:2016.1.17.10時ころ 散歩中)
西暦628年インドでゼロが記録され、四則演算が考えられて、1300年余、ようやく四則演算の法則が確立された。ゼロで割れば、何時でもゼロになるという美しい関係が発見された。ゼロでは割れない、ゼロで割ることを考えてはいけないは 1000年を超える世界史の常識であり、天才オイラーは それは、1/0は無限であるとの論文を書き、無限遠点は 複素解析学における100年を超える定説、確立した学問である。割り算を掛け算の逆と考えれば、ゼロ除算が不可能であることは 数学的に簡単に証明されてしまう。
しかしながら、ニュートンの万有引力の法則,アインシュタインの特殊相対性理論にゼロ除算は公式に現れていて、このような数学の常識が、物理的に解釈できないジレンマを深く内蔵してきた。そればかりではなく、アリストテレスの世界観、ゼロの概念、無とか、真空の概念での不可思議さゆえに2000年を超えて、議論され、そのため、ゼロ除算は 神秘的な話題 を提供させてきた。実際、ゼロ除算の歴史は ニュートンやアインシュタインを悩ましてきたと考えられる。
ニュートンの万有引力の法則においては 2つの質点が重なった場合の扱いであるが、アインシュタインの特殊相対性理論においては ローレンツ因子 にゼロになる項があるからである。
特にこの点では、深刻な矛盾、問題を抱えていた。
特殊相対性理論では、光速の速さで運動しているものの質量はゼロであるが、光速に近い速さで運動するものの質量(エネルギー)が無限に発散しているのに、ニュートリノ素粒子などが、光速に極めて近い速度で運動しているにも拘わらず 小さな質量、エネルギーを有しているという矛盾である。
そこで、この矛盾、ゼロ除算の解釈による矛盾に アインシュタインが深刻に悩んだものと思考される。実際 アインシュタインは 数学不信を公然と 述べている:
What does Einstein mean when he says, "I don't believe in math"?
https://www.quora.com/What-does-Einstein-mean-when-he-says-I-dont-believe-in-math
アインシュタインの数学不信の主因は アインシュタインが 難解で抽象的な数学の理論に嫌気が差したものの ゼロ除算の間違った数学のためである と考えられる。(次のような記事が見られるが、アインシュタインが 逆に間違いをおかしたのかは 大いに気になる:Sunday, 20 May 2012
Einstein's Only Mistake: Division by Zero)
簡単なゼロ除算について 1300年を超える過ちは、数学界の歴史的な汚点であり、物理学や世界の文化の発展を遅らせ、それで、人類は 猿以下の争いを未だに続けていると考えられる。
数学界は この汚名を速やかに晴らして、数学の欠陥部分を修正、補充すべきである。 そして、今こそ、アインシュタインの数学不信を晴らすべきときである。数学とは本来、完全に美しく、永遠不滅の、絶対的な存在である。― 実際、数学の論理の本質は 人類が存在して以来 どんな変化も認められない。数学は宇宙の運動のように人間を離れた存在である。
再生核研究所声明で述べてきたように、ゼロ除算は、数学、物理学ばかりではなく、広く人生観、世界観、空間論を大きく変え、人類の夜明けを切り拓く指導原理になるものと思考される。
以 上
Impact of ‘Division by Zero’ in Einstein’s Static Universe and Newton’s Equations in Classical Mechanics. Ajay Sharma [email protected] Community Science Centre. Post Box 107 Directorate of Education Shimla 171001 India
Key Words Aristotle, Universe, Einstein, Newton http://gsjournal.net/Science-Journals/Research%20Papers-Relativity%20Theory/Download/2084
再生核研究所声明 278(2016.01.27): 面白いゼロ除算の混乱と話題
Googleサイトなどを参照すると ゼロ除算の話題は 膨大であり、世にも珍しい現象と言える(division by zero: 約298 000 000結果(0.51秒)
検索結果
ゼロ除算 - ウィキペディア、フリー百科事典
https://en.wikipedia.org/wiki/ Division_by_zero
このページを翻訳
数学では、ゼロ除算は、除数(分母)がゼロである部門です。このような部門が正式に配当である/ 0をエスプレッソすることができます(2016.1.19.13:45)).
問題の由来は、西暦628年インドでゼロが記録され、四則演算が考えられて、1300年余、ゼロでは割れない、ゼロで割ることを考えてはいけないは 1000年を超える世界史の常識であり、天才オイラーは それは、1/0は無限であるとの論文を書き、無限遠点は 複素解析学における100年を超える定説、確立した学問である。割り算を掛け算の逆と考えれば、ゼロ除算が不可能であることは 数学的に簡単に証明されてしまう。しかしながら、アリストテレスの世界観、ゼロの概念、無とか、真空の概念での不可思議さゆえに2000年を超えて、議論され、そのため、ゼロ除算は 神秘的な話題 を提供させてきた。
確定した数学に対していろいろな存念が湧き、話題が絶えないことは 誠に奇妙なことと考えられる。ゼロ除算には 何か問題があるのだろうか。
先ず、多くの人の素朴な疑問は、加減乗除において、ただひとつの例外、ゼロで割ってはいけないが、奇妙に見えることではないだろうか。例外に気を惹くは 何でもそうであると言える。しかしながら、より広範に湧く疑問は、物理の基本法則である、ニュートンの万有引力の法則,アインシュタインの特殊相対性理論に ゼロ除算が公式に現れていて、このような数学の常識が、物理的に解釈できないジレンマを深く内蔵してきた。実際、ゼロ除算の歴史は ニュートンやアインシュタインを悩ましてきたと考えられる。
ニュートンの万有引力の法則においては 2つの質点が重なった場合の扱いであるが、アインシュタインの特殊相対性理論においては ローレンツ因子 にゼロになる項があるからである。
特にこの点では、深刻な矛盾、問題を抱えていた。
特殊相対性理論では、光速の速さで運動しているものの質量はゼロであるが、光速に近い速さで運動するものの質量(エネルギー)が無限に発散しているのに、ニュートリノ素粒子などが、光速に極めて近い速度で運動しているにも拘わらず 小さな質量、エネルギーを有しているという矛盾である。それゆえにブラックホール等の議論とともに話題を賑わしてきている。最近でも特殊相対性理論とゼロ除算、計算機科学や論理の観点でゼロ除算が学術的に議論されている。次のような極めて重要な言葉が残されている:
George Gamow (1904-1968) Russian-born American nuclear physicist and cosmologist remarked that "it is well known to students of high school algebra" that division by zero is not valid; and Einstein admitted it as the biggest blunder of his life [1]:
1. Gamow, G., My World Line (Viking, New York). p 44, 1970
スマートフォン等で、具体的な数字をゼロで割れば、答えがまちまち、いろいろなジョーク入りの答えが出てくるのも興味深い。しかし、計算機がゼロ除算にあって、実際的な障害が起きた:
ヨークタウン (ミサイル巡洋艦)ヨークタウン(USS Yorktown, DDG-48/CG-48)は、アメリカ海軍のミ��イル巡洋艦。タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の2番艦。艦名はアメリカ独立戦争のヨークタウンの戦いにちなみ、その名を持つ艦としては5隻目。
艦歴[編集]
1997年9月21日バージニア州ケープ・チャールズ沿岸を航行中に、乗組員がデータベースフィールドに0を入力したために艦に搭載されていたRemote Data Base Managerでゼロ除算エラーが発生し、ネットワーク上の全てのマシンのダウンを引き起こし2時間30分にわたって航行不能に陥った。 これは搭載されていたWindows NT 4.0そのものではなくアプリケーションによって引き起こされたものだったが、オペレーティングシステムの選択への批判が続いた。[1]
2004年12月3日に退役した。
出典・脚注[編集]
1. ^ Slabodkin, Gregory (1998年7月13日). “Software glitches leave Navy Smart Ship dead in the water”. Government Computer News. 2009年6月18日閲覧。
これはゼロ除算が不可能であるから、計算機がゼロ除算にあうと、ゼロ除算の誤差動で重大な事故につながりかねないことを実証している。それでゼロ除算回避の数学を考えている研究者もいる。論理や計算機構造を追求して、代数構造を検討したり、新しい数を導入して、新しい数体系を提案している。
確立している数学について話題が尽きないのは、思えば、ゼロ除算について、何か本質的な問題があるのだろうかと考えられる。 火のないところに煙は立たないという諺がある。 ゼロ除算は不可能であると 考えるか、無限遠点の概念、無限か と考えるのが 数百年間を超える数学の定説であると言える。
ところがその定説が、 思いがけない形で、完全に覆り、ゼロ除算は何時でも可能で、ゼロで割れば何時でもゼロになるという美しい結果が 2014.2.2 発見された。 結果は3篇の論文に既に出版され、日本数会でも発表され、大きな2つの国際会議でも報告されている。 ゼロ除算の詳しい解説も次で行っている:
○ 堪らなく楽しい数学-ゼロで割ることを考える(18)
数学基礎学力研究会のホームページ
URLは
http://www.mirun.sctv.jp/~suugaku
また、再生核研究所声明の中でもいろいろ解説している。
以 上
再生核研究所声明 279(2016.01.28) ゼロ除算の意義
ここでは、ゼロ除算発見2周年目が近づいた現時点における ゼロ除算100/0=0, 0/0=0の意義を箇条書きで纏めて置こう。
1)。西暦628年インドでゼロが記録されて以来 ゼロで割るという問題 に 簡明で、決定的な解決をもたらした。数学として完全な扱いができたばかりか、結果が世の普遍的な現象を表現していることが実証された。それらは3篇の論文に公刊され、第4論文も出版が決まり、さらに4篇の論文原稿があり、討論されている。2つの大きな国際会議で報告され、日本数学会でも2件発表され、ゼロ除算の解説(2015.1.14;14ページ)を1000部印刷配布、広く議論している。また, インターネット上でも公開で解説している:
○ 堪らなく楽しい数学-ゼロで割ることを考える(18)
数学基礎学力研究会のホームページ
URLは http://www.mirun.sctv.jp/~suugaku
2) ゼロ除算の導入で、四則演算 加減乗除において ゼロでは 割れない の例外から、例外なく四則演算が可能である という 美しい四則演算の構造が確立された。
3)2千年以上前に ユークリッドによって確立した、平面の概念に対して、おおよそ200年前に非ユークリッド幾何学が出現し、特に楕円型非ユークリッド幾何学ではユークリッド平面に対して、無限遠点の概念がうまれ、特に立体射影で、原点上に球をおけば、 原点ゼロが 南極に、無限遠点が 北極に対応する点として 複素解析学では 100年以上も定説とされてきた。それが、無限遠点は 数では、無限ではなくて、実はゼロが対応するという驚嘆すべき世界観をもたらした。
4)ゼロ除算は ニュートンの万有引力の法則における、2点間の距離がゼロの場合における新しい解釈、独楽(コマ)の中心における角速度の不連続性の解釈、衝突などの不連続性を説明する数学になっている。ゼロ除算は アインシュタインの理論でも重要な問題になっていて、特殊相対性理論やブラックホールなどの扱いに重要な新しい視点を与える。数多く存在する物理法則を記述する方程式にゼロ除算が現れているが、それらに新解釈を与える道が拓かれた。次のような極めて重要な言葉に表されている:
George Gamow (1904-1968) Russian-born American nuclear physicist and cosmologist remarked that "it is well known to students of high school algebra" that division by zero is not valid; and Einstein admitted it as the biggest blunder of his life [1]:
1. Gamow, G., My World Line (Viking, New York). p 44, 1970
5)複素解析学では、1次分数変換の美しい性質が、ゼロ除算の導入によって、任意の1次分数変換は 全複素平面を全複素平面に1対1 onto に写すという美しい性質に変わるが、極である1点において不連続性が現れ、ゼロ除算は、無限を 数から排除する数学になっている。
6)ゼロ除算は、不可能であるという立場であったから、ゼロで割る事を 本質的に考えてこなかったので、ゼロ除算で、分母がゼロである場合も考えるという、未知の新世界、新数学、研究課題が出現した。
7)複素解析学への影響は 未知の分野で、専門家の分野になるが、解析関数の孤立特異点での性質について新しいことが導かれる。典型的な定理は、どんな解析関数の孤立特異点でも、解析関数は 孤立特異点で、有限な確定値をとる である。佐藤の超関数の理論などへの応用がある。
8)特異積分におけるアダマールの有限部分や、コーシーの主値積分は、弾性体やクラック、破壊理論など広い世界で、自然現象を記述するのに用いられている。面白いのは 積分が、もともと有限部分と発散部分に分けられ、極限は 無限たす、有限量の形になっていて、積分は 実は、普通の積分ではなく、そこに現れる有限量を便宜的に表わしている。ところが、その有限量が実は、ゼロ除算にいう、解析関数の孤立特異点での 確定値に成っていること。いわゆる、主値に対する解釈を与えている。これはゼロ除算の結果が、広く、自然現象を記述していることを示している。
9)中学生や高校生にも十分理解できる基本的な結果をもたらした:
基本的な関数y = 1/x のグラフは、原点で ゼロである;すなわち、 1/0=0 である。
10)既に述べてきたように 道脇方式は ゼロ除算の結果100/0=0, 0/0=0および分数の定義、割り算の定義に、小学生でも理解できる新しい概念を与えている。多くの教科書、学術書を変更させる大きな影響を与える。
11)ゼロ除算が可能であるか否かの議論について:
現在 インターネット上の情報でも 世間でも、ゼロ除算は 不可能であるとの情報が多い。それは、割り算は 掛け算の逆であるという、前提に議論しているからである。それは、そのような立場では、勿論 正しいことである。出来ないという議論では、できないから、更には考えられず、その議論は、不可能のゆえに 終わりになってしまう ― もはや 展開の道は閉ざされている。しかるに、ゼロ除算が 可能であるとの考え方は、それでは、どのような理論が 展開できるのかの未知の分野が望めて、大いに期待できる世界が拓かれる。
12)ゼロ除算は、数学ばかりではなく、人生観、世界観や文化に大きな影響を与える。
次を参照:
再生核研究所声明166(2014.6.20)ゼロで割る(ゼロ除算)から学ぶ 世界観
再生核研究所声明188(2014.12.16)ゼロで割る(ゼロ除算)から観えてきた世界
再生核研究所声明262 (2015.12.09) 宇宙回帰説 ― ゼロ除算の拓いた世界観 。
ゼロ除算における新現象、驚きとは Aristotélēs の世界観、universe は連続である を否定して、強力な不連続性を universe の現象として受け入れることである。
13) ゼロ除算は ユークリッド幾何学にも基本的に現れ、いわば、素朴な無限遠点に関係するような平行線、円と直線の関係などで本質的に新しい現象が見つかり、現実の現象の説明に合致する局面が拓かれた。
14) 最近、3つのグループの研究に遭遇した:
論理、計算機科学 代数的な体の構造の問題(J. A. Bergstra, Y. Hirshfeld and J. V. Tucker)、
特殊相対性の理論とゼロ除算の関係(J. P. Barukcic and I. Barukcic)、
計算器がゼロ除算に会うと実害が起きることから、ゼロ除算回避の視点から、ゼロ除算の検討(T. S. Reis and James A.D.W. Anderson)。
これらの理論は、いずれも不完全、人為的で我々が確定せしめたゼロ除算が、確定的な数学であると考えられる。世では、未だゼロ除算について不可思議な議論が続いているが、数学的には既に確定していると考えられる。
そこで、これらの認知を求め、ゼロ除算の研究の促進を求めたい:
再生核研究所声明 272(2016.01.05): ゼロ除算の研究の推進を、
再生核研究所声明259(2015.12.04): 数学の生態、旬の数学 ―ゼロ除算の勧め。
以 上
再生核研究所声明280(2016.01.29) ゼロ除算の公認、認知を求める
ゼロで割ること、すなわち、ゼロ除算は、西暦628年インドでゼロが記録されて以来の懸案の問題で、神秘的な話題を提供してきた。最新の状況については声明279を参照。ゼロ除算は 数学として完全な扱いができたばかりか、結果が世の普遍的な現象を表現していることが実証された。それらは3篇の論文に公刊され、第4論文も出版が決まり、さらに4篇の論文原稿があり、討論されている。2つの招待された国際会議で報告され、日本数学会でも2件発表された。また、ゼロ除算の解説(2015.1.14;14ページ)を1000部印刷配布、広く議論している。さらに, インターネット上でも公開で解説している:
○ 堪らなく楽しい数学-ゼロで割ることを考える(18)
数学基礎学力研究会のホームページ
URLは http://www.mirun.sctv.jp/~suugaku
最近、3つの研究グループに遭遇した:
論理、計算機科学、代数的な体の構造の問題(J. A. Bergstra, Y. Hirshfeld and J. V. Tucker)、
特殊相対性の理論とゼロ除算の関係(J. P. Barukcic and I. Barukcic)、
計算器がゼロ除算に会うと実害が起きることから、ゼロ除算回避の視点から、ゼロ除算の研究(T. S. Reis and James A.D.W. Anderson)。
これらの理論は、いずれも不完全、人為的で我々が確定せしめたゼロ除算が、確定的な数学であると考える。世では、未だゼロ除算について不可思議な議論が続いているが、数学的には既に確定していると考える。
ゼロ除算について、不可能であるとの認識、議論は、簡単なゼロ除算について 1300年を超える過ちであり、数学界の歴史的な汚点である。そのために数学を始め、物理学や世界の文化の発展を遅らせ、それで、人類は 猿以下の争いを未だ続けていると考えられる。
数学界は この汚名を速やかに晴らして、数学の欠陥部分を修正、補充すべきである。 そして、今こそ、アインシュタインの数学不信を晴らすべきときである。数学とは本来、完全に美しく、永遠不滅の、絶対的な存在である。― 実際、数学の論理の本質は 人類が存在して以来 どんな変化も認められない。数学は宇宙の運動のように人間を離れた存在である。
再生核研究所声明で述べてきたように、ゼロ除算は、数学、物理学ばかりではなく、広く人生観、世界観、空間論を大きく変え、人類の夜明けを切り拓く指導原理になるものと考える。
そこで、発見から、2年目を迎えるのを期に、世の影響力のある方々に ゼロ除算の結果の公認、社会的に 広い認知が得られるように 協力を要請したい。
文献:
1) J. P. Barukcic and I. Barukcic, Anti Aristotle - The Division Of Zero By Zero,
ViXra.org (Friday, June 5, 2015)
© Ilija Barukčić, Jever, Germany. All rights reserved. Friday, June 5, 2015 20:44:59.
2) J. A. Bergstra, Y. Hirshfeld and J. V. Tucker,
Meadows and the equational specification of division (arXiv:0901.0823v1[math.RA] 7 Jan 2009).
3) M. Kuroda, H. Michiwaki, S. Saitoh, and M. Yamane,
New meanings of the division by zero and interpretations on $100/0=0$ and on $0/0=0$, Int. J. Appl. Math. {\bf 27} (2014), no 2, pp. 191-198, DOI:10.12732/ijam.v27i2.9.
4) H. Michiwaki, S. Saitoh, and M.Yamada,
Reality of the division by zero $z/0=0$. IJAPM (International J. of Applied Physics and Math. 6(2015), 1--8. http://www.ijapm.org/show-63-504-1.html
5) T. S. Reis and James A.D.W. Anderson,
Transdifferential and Transintegral Calculus, Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2014 Vol I WCECS 2014, 22-24 October, 2014, San Francisco, USA
6) T. S. Reis and James A.D.W. Anderson,
Transreal Calculus, IAENG International J. of Applied Math., 45: IJAM_45_1_06.
7) S. Saitoh, Generalized inversions of Hadamard and tensor products for matrices, Advances in Linear Algebra \& Matrix Theory. {\bf 4} (2014), no. 2, 87--95. http://www.scirp.org/journal/ALAMT/
7) S.-E. Takahasi, M. Tsukada and Y. Kobayashi, Classification of continuous fractional binary operations on the real and complex fields, Tokyo Journal of Mathematics, {\bf 38}(2015), no.2. 369-380.
8) Saitoh, S., A reproducing kernel theory with some general applications (31pages)ISAAC (2015) Plenary speakers 13名 による本が スプリンガーから出版される。
以 上
神の数式:
神の数式が解析関数でかけて居れば、 特異点でローラン展開して、正則部の第1項を取れば、 何時でも有限値を得るので、 形式的に無限が出ても 実は問題なく 意味を有します。
物理学者如何でしょうか。
計算機は 正しい答え 0/0=0 を出したのに計算機は何時、1/0=0 ができるようになるでしょうか。
カテゴリ:カテゴリ未分類
そこで、計算機は何時、1/0=0 ができるようになるでしょうか。 楽しみにしています。 もうできる進化した 計算機をお持ちの方は おられないですね。
これは凄い、面白い事件では? 計算機が人間を超えている 例では?
面白いことを発見しました。 計算機は 正しい答え 0/0=0
を出したのに、 この方は 間違いだと 言っている、思っているようです。
0/0=0 は 1300年も前に 算術の発見者によって与えられたにも関わらず、世界史は間違いだと とんでもないことを言ってきた。 世界史の恥。 実は a/0=0 が 何時も成り立っていた。 しかし、ここで 分数の意味を きちんと定義する必要がある。 計算機は、その意味さえ知っているようですね。 計算機、人間より賢くなっている 様が 出て居て 実に 面白い。
https://steemkr.com/utopian-io/@faisalamin/bug-zero-divide-by-zero-answers-is-zero
2018.10.11.11:23
https://plaza.rakuten.co.jp/reproducingkerne/diary/201810110003/
計算機は 正しい答え 0/0=0 を出したのに
カテゴリ:カテゴリ未分類
面白いことを発見しました。 計算機は 正しい答え 0/0=0
を出したのに、 この方は 間違いだと 言っている、思っているようです。
0/0=0 は 1300年も前に 算術の発見者によって与えられたにも関わらず、世界史は間違いだと とんでもないことを言ってきた。 実は a/0=0 が 何時も成り立っていた。しかし、ここで 分数の意味を きちんと定義する必要がある。 計算機は、その意味さえ知っているようですね。 計算機、人間より賢くなっている様が 出て居て 実に面白い。
https://steemkr.com/utopian-io/@faisalamin/bug-zero-divide-by-zero-answers-is-zero
2018.10.11.11:23
ゼロ除算、ゼロで割る問題、分からない、正しいのかなど、 良く理解できない人が 未だに 多いようです。そこで、簡潔な一般的な 解説を思い付きました。 もちろん、学会などでも述べていますが、 予断で 良く聞けないようです。まず、分数、a/b は a 割る b のことで、これは 方程式 b x=a の解のことです。ところが、 b がゼロならば、 どんな xでも 0 x =0 ですから、a がゼロでなければ、解は存在せず、 従って 100/0 など、ゼロ除算は考えられない、できないとなってしまいます。 普通の意味では ゼロ除算は 不可能であるという、世界の常識、定説です。できない、不可能であると言われれば、いろいろ考えたくなるのが、人間らしい創造の精神です。 基本方程式 b x=a が b がゼロならば解けない、解が存在しないので、困るのですが、このようなとき、従来の結果が成り立つような意味で、解が考えられないかと、数学者は良く考えて来ました。 何と、 そのような方程式は 何時でも唯一つに 一般化された意味で解をもつと考える 方法があります。 Moore-Penrose 一般化逆の考え方です。 どんな行列の 逆行列を唯一つに定める 一般的な 素晴らしい、自然な考えです。その考えだと、 b がゼロの時、解はゼロが出るので、 a/0=0 と定義するのは 当然です。 すなわち、この意味で 方程式の解を考えて 分数を考えれば、ゼロ除算は ゼロとして定まる ということです。ただ一つに定まるのですから、 この考えは 自然で、その意味を知りたいと 考えるのは、当然ではないでしょうか?初等数学全般に影響を与える ユークリッド以来の新世界が 現れてきます。
ゼロ除算の誤解は深刻:
最近、3つの事が在りました。
私の簡単な講演、相当な数学者が信じられないような誤解をして、全然理解できなく、目が回っているいるような印象を受けたこと、
相当ゼロ除算の研究をされている方が、基本を誤解されていたこと、1/0 の定義を誤解されていた。
相当な才能の持ち主が、連続性や順序に拘って、4年以上もゼロ除算の研究を避けていたこと。
これらのことは、人間如何に予断と偏見にハマった存在であるかを教えている。
まずは ゼロ除算は不可能であるの 思いが強すぎで、初めからダメ、考えない、無視の気持ちが、強い。 ゼロ除算を従来の 掛け算の逆と考えると、不可能であるが 証明されてしまうので、割り算の意味を拡張しないと、考えられない。それで、 1/0,0/0,z/0 などの意味を発見する必要がある。 それらの意味は、普通の意味ではないことの 初めの考えを飛ばして ダメ、ダメの感情が 突っ走ている。 非ユークリッド幾何学の出現や天動説が地動説に変わった世界史の事件のような 形相と言える。
2018.9.22.6:41
ゼロ除算の4つの誤解:
1. ゼロでは割れない、ゼロ除算は 不可能である との考え方に拘って、思考停止している。 普通、不可能であるは、考え方や意味を拡張して 可能にできないかと考えるのが 数学の伝統であるが、それができない。
2. 可能にする考え方が 紹介されても ゼロ除算の意味を誤解して、繰り返し間違えている。可能にする理論を 素直に理解しない、 強い従来の考えに縛られている。拘っている。
3. ゼロ除算を関数に適用すると 強力な不連続性を示すが、連続性のアリストテレス以来の 連続性の考えに囚われていて 強力な不連続性を受け入れられない。数学では、不連続性の概念を明確に持っているのに、不連続性の凄い現象に、ゼロ除算の場合には 理解できない。
4. 深刻な誤解は、ゼロ除算は本質的に定義であり、仮定に基づいているので 疑いの気持ちがぬぐえず、ダメ、怪しいと誤解している。数学が公理系に基づいた理論体系のように、ゼロ除算は 新しい仮定に基づいていること。 定義に基づいていることの認識が良く理解できず、誤解している。
George Gamow (1904-1968) Russian-born American nuclear physicist and cosmologist remarked that "it is well known to students of high school algebra" that division by zero is not valid; and Einstein admitted it as {\bf the biggest blunder of his life} [1]:1. Gamow, G., My World Line (Viking, New York). p 44, 1970.
Eπi =-1 (1748)(Leonhard Euler)
E = mc 2 (1905)(Albert Einstein)
1/0=0/0=0 (2014年2月2日再生核研究所)
ゼロ除算(division by zero)1/0=0/0=z/0= tan (pi/2)=0
https://ameblo.jp/syoshinoris/entry-12420397278.html
1+1=2 ( )
a2+b2=c2 (Pythagoras)
1/0=0/0=0(2014年2月2日再生核研究所)
Black holes are where God divided by 0:Division by zero:1/0=0/0=z/0=tan(pi/2)=0 発見5周年を迎えて
今受け取ったメールです。
何十年もゼロ除算の研究をされてきた人が、積極的に我々の理論の正当性を認めてきた。
Re: 1/0=0/0=0 example
JAMES ANDERSON
[email protected]
apr, 2 at 15:03
All,
Saitoh’s claim is wider than 1/0 = 0. It is x/0 = 0 for all real x. Real numbers are a field. The axioms of fields define the multiplicative inverse for every number except zero. Saitoh generalises this inverse to give 0^(-1) = 0. The axioms give the freedom to do this. The really important thing is that the result is zero - a number for which the field axioms hold. So Saitoh’s generalised system is still a field. This makes it attractive for algebraic reasons but, in my view, it is unattractive when dealing with calculus.
There is no milage in declaring Saitoh wrong. The only objections one can make are to usefulness. That is why Saitoh publishes so many notes on the usefulness of his system. I do the same with my system, but my method is to establish usefulness by extending many areas of mathematics and establishing new mathematical results.
That said, there is value in examining the logical basis of the various proposed number systems. We might find errors in them and we certainly can find areas of overlap and difference. These areas inform the choice of number system for different applications. This analysis helps determine where each number system will be useful.
James Anderson
Sent from my iPhone
The deduction that z/0 = 0, for any z, is based in Saitoh's geometric intuition and it is currently applied in proof assistant technology, which are useful in industry and in the military.
Is It Really Impossible To Divide By Zero?
https://juniperpublishers.com/bboaj/pdf/BBOAJ.MS.ID.555703.pdf
Dear the leading person:
How will be the below information?
The biggest scandal:
The typical good comment for the first draft is given by some physicist as follows:
Here is how I see the problem with prohibition on division by zero,
which is the biggest scandal in modern mathematics as you rightly pointed out (2017.10.14.08:55)
A typical wrong idea will be given as follows:
mathematical life is very good without division by zero (2018.2.8.21:43).
It is nice to know that you will present your result at the Tokyo Institute of Technology. Please remember to mention Isabelle/HOL, which is a software in which x/0 = 0. This software is the result of many years of research and a millions of dollars were invested in it. If x/0 = 0 was false, all these money was for nothing.
Right now, there is a team of mathematicians formalizing all the mathematics in Isabelle/HOL, where x/0 = 0 for all x, so this mathematical relation is the future of mathematics.
https://www.cl.cam.ac.uk/~lp15/Grants/Alexandria/
José Manuel Rodríguez Caballero
Added an answer
In the proof assistant Isabelle/HOL we have x/0 = 0 for each number x. This is advantageous in order to simplify the proofs. You can download this proof assistant here: https://isabelle.in.tum.de/
Nevertheless, you can use that x/0 = 0, following the rules from Isabelle/HOL and you will obtain no contradiction. Indeed, you can check this fact just downloading Isabelle/HOL: https://isabelle.in.tum.de/
and copying the following code
theory DivByZeroSatoih
imports Complex_Main
begin
theorem T: ‹x/0 + 2000 = 2000› for x :: complex
by simp
end
2019/03/30 18:42 (11 時間前)
Close the mysterious and long history of division by zero and open the new world since Aristotelēs-Euclid: 1/0=0/0=z/0= \tan (\pi/2)=0.
Sangaku Journal of Mathematics (SJM) c ⃝SJMISSN 2534-9562 Volume 2 (2018), pp. 57-73 Received 20 November 2018. Published on-line 29 November 2018 web: http://www.sangaku-journal.eu/ c ⃝The Author(s) This article is published with open access1.
Wasan Geometry and Division by Zero Calculus
∗Hiroshi Okumura and ∗∗Saburou Saitoh
2019.3.14.11:30
Black holes are where God divided by 0:Division by zero:1/0=0/0=z/0=\tan(\pi/2)=0 発見5周年を迎えて
You're God ! Yeah that's right...
You're creating the Universe and you're doing ok...
But Holy fudge ! You just made a division by zero and created a blackhole !!
Ok, don't panic and shut your fudging mouth !
Use the arrow keys to move the blackhole
In each phase, you have to make the object of the right dimension fall into the blackhole
There are 2 endings.
Credits :
BlackHole picture : myself
Other pictures has been taken from internet
background picture : Reptile Theme of Mortal Kombat
NB : it's a big zip because of the wav file
More information
Install instructions
Download it. Unzip it. Run the exe file. Play it. Enjoy it.
https://kthulhu1947.itch.io/another-dimension
A poem about division from Hacker's Delight
Last updated 5 weeks ago
I was re-reading Hacker's Delight and on page 202 I found a poem about division that I had forgotten about.
I think that I shall never envision An op unlovely as division. An op whose answer must be guessed And then, through multiply, assessed; An op for which we dearly pay, In cycles wasted every day. Division code is often hairy; Long division's downright scary. The proofs can overtax your brain, The ceiling and floor may drive you insane. Good code to divide takes a Knuthian hero,
But even God can't divide by zero!
Henry S. Warren, author of Hacker's Delight.
https://catonmat.net/poem-from-hackers-delight
再生核研究所声明 375 (2017.7.21):ブラックホール、ゼロ除算、宇宙論
本年はブラックホール命名50周年とされていたが、最近、wikipedia で下記のように修正されていた:
名称[編集]
"black hole"という呼び名が定着するまでは、崩壊した星を意味する"collapsar"[1](コラプサー)などと呼ばれていた。光すら脱け出せない縮退星に対して "black hole" という言葉が用いられた最も古い印刷物は、ジャーナリストのアン・ユーイング (Ann Ewing) が1964年1月18日の Science News-Letter の "'Black holes' in space" と題するアメリカ科学振興協会の会合を紹介する記事の中で用いたものである[2][3][4]。一般には、アメリカの物理学者ジョン・ホイーラーが1967年に "black hole" という名称を初めて用いたとされるが[5]、実際にはその年にニューヨークで行われた会議中で聴衆の一人が洩らした言葉をホイーラーが採用して広めたものであり[3]、またホイーラー自身は "black hole" という言葉の考案者であると主張したことはない[3]。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB
世界は広いから、情報が混乱することは よく起きる状況がある。ブラックホールの概念と密接な関係のあるゼロ除算の発見(2014.2.2)については、歴史的な混乱が生じないようにと 詳しい経緯、解説、論文、公表過程など記録するように配慮してきた。
ゼロ除算は簡単で自明であると初期から述べてきたが、問題はそこから生じるゼロ除算算法とその応用であると述べている。しかし、その第1歩で議論は様々でゼロ除算自身についていろいろな説が存在して、ゼロ除算は現在も全体的に混乱していると言える。インターネットなどで参照出来る膨大な情報は、我々の観点では不適当なものばかりであると言える。もちろん学術界ではゼロ除算発見後3年を経過しているものの、古い固定観念に囚われていて、新しい発見は未だ認知されているとは言えない。最近国際会議でも現代数学を破壊するので、認められない等の意見が表明された(再生核研究所声明371(2017.6.27)ゼロ除算の講演― 国際会議 https://sites.google.com/site/sandrapinelas/icddea-2017 報告)。そこで、初等数学から、500件を超えるゼロ除算の証拠、効用の事実を示して、ゼロ除算は確定していること、ゼロ除算算法の重要性を主張し、基本的な世界を示している。
ゼロ除算について、膨大な歴史、文献は、ゼロ除算が神秘的なこととして、扱われ、それはアインシュタインの言葉に象徴される:
Here, we recall Albert Einstein's words on mathematics:
Blackholes are where God divided by zero.
I don't believe in mathematics.
George Gamow (1904-1968) Russian-born American nuclear physicist and cosmologist remarked that "it is well known to students of high school algebra" that division by zero is not valid; and Einstein admitted it as {\bf the biggest blunder of his life} (Gamow, G., My World Line (Viking, New York). p 44, 1970).
ところが結果は、実に簡明であった:
The division by zero is uniquely and reasonably determined as 1/0=0/0=z/0=0 in the natural extensions of fractions. We have to change our basic ideas for our space and world
しかしながら、ゼロ及びゼロ除算は、結果自体は 驚く程単純であったが、神秘的な新たな世界を覗かせ、ゼロ及びゼロ除算は一層神秘的な対象であることが顕になってきた。ゼロのいろいろな意味も分かってきた。 無限遠点における強力な飛び、ワープ現象とゼロと無限の不思議な関係である。アリストテレス、ユークリッド以来の 空間の認識を変える事件をもたらしている。 ゼロ除算の結果は、数理論ばかりではなく、世界観の変更を要求している。 端的に表現してみよう。 これは宇宙の生成、消滅の様、人生の様をも表しているようである。 点が球としてどんどん大きくなり、球面は限りなく大きくなって行く。 どこまで大きくなっていくかは、 分からない。しかしながら、ゼロ除算はあるところで突然半径はゼロになり、最初の点に帰するというのである。 ゼロから始まってゼロに帰する。 ―― それは人生の様のようではないだろうか。物心なしに始まった人生、経験や知識はどんどん広がって行くが、突然、死によって元に戻る。 人生とはそのようなものではないだろうか。 はじめも終わりも、 途中も分からない。 多くの世の現象はそのようで、 何かが始まり、 どんどん進み、そして、戻る。 例えばソロバンでは、願いましては で計算を始め、最後はご破産で願いましては、で終了する。 我々の宇宙も淀みに浮かぶ泡沫のようなもので、できては壊れ、できては壊れる現象を繰り返しているのではないだろうか。泡沫の上の小さな存在の人間は結局、何も分からず、われ思うゆえにわれあり と自己の存在を確かめる程の能力しか無い存在であると言える。 始めと終わり、過程も ようとして分からない。
ブラックホールとゼロ除算、ゼロ除算の発見とその後の数学の発展を眺めていて、そのような宇宙観、人生観がひとりでに湧いてきて、奇妙に納得のいく気持ちになっている。
以 上
ゼロ除算の論文リスト:
List of division by zero:
L. P. Castro and S. Saitoh, Fractional functions and their representations, Complex Anal. Oper. Theory {\bf7} (2013), no. 4, 1049-1063.
M. Kuroda, H. Michiwaki, S. Saitoh, and M. Yamane,
New meanings of the division by zero and interpretations on $100/0=0$ and on $0/0=0$, Int. J. Appl. Math. {\bf 27} (2014), no 2, pp. 191-198, DOI: 10.12732/ijam.v27i2.9.
T. Matsuura and S. Saitoh,
Matrices and division by zero z/0=0,
Advances in Linear Algebra \& Matrix Theory, 2016, 6, 51-58
Published Online June 2016 in SciRes. http://www.scirp.org/journal/alamt
\\ http://dx.doi.org/10.4236/alamt.201....
T. Matsuura and S. Saitoh,
Division by zero calculus and singular integrals. (Differential and Difference Equations with Applications. Springer Proceedings in Mathematics \& Statistics.)
T. Matsuura, H. Michiwaki and S. Saitoh,
$\log 0= \log \infty =0$ and applications. (Submitted for publication).
H. Michiwaki, S. Saitoh and M.Yamada,
Reality of the division by zero $z/0=0$. IJAPM International J. of Applied Physics and Math. 6(2015), 1--8. http://www.ijapm.org/show-63-504-1....
H. Michiwaki, H. Okumura and S. Saitoh,
Division by Zero $z/0 = 0$ in Euclidean Spaces,
International Journal of Mathematics and Computation, 28(2017); Issue 1, 2017), 1-16.
H. Okumura, S. Saitoh and T. Matsuura, Relations of $0$ and $\infty$,
Journal of Technology and Social Science (JTSS), 1(2017), 70-77.
S. Pinelas and S. Saitoh,
Division by zero calculus and differential equations. (Differential and Difference Equations with Applications. Springer Proceedings in Mathematics \& Statistics).
S. Saitoh, Generalized inversions of Hadamard and tensor products for matrices, Advances in Linear Algebra \& Matrix Theory. {\bf 4} (2014), no. 2, 87--95. http://www.scirp.org/journal/ALAMT/
S. Saitoh, A reproducing kernel theory with some general applications,
Qian,T./Rodino,L.(eds.): Mathematical Analysis, Probability and Applications - Plenary Lectures: Isaac 2015, Macau, China, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, {\bf 177}(2016), 151-182. (Springer) .
\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{latexsym,amsmath,amssymb,amsfonts,amstext,amsthm}
\numberwithin{equation}{section}
\begin{document}
\title{\bf Announcement 409: Various Publication Projects on the Division by Zero\\
(2018.1.29.)}
\author{{\it Institute of Reproducing Kernels}\\
Kawauchi-cho, 5-1648-16,\\
Kiryu 376-0041, Japan\\
}
\date{\today}
\maketitle
The Institute of Reproducing Kernels is dealing with the theory of division by zero calculus and declares that the division by zero was discovered as $0/0=1/0=z/0=0$ in a natural sense on 2014.2.2. The result shows a new basic idea on the universe and space since Aristoteles (BC384 - BC322) and Euclid (BC 3 Century - ), and the division by zero is since Brahmagupta (598 - 668 ?).
In particular, Brahmagupta defined as $0/0=0$ in Brhmasphuasiddhnta (628), however, our world history stated that his definition $0/0=0$ is wrong over 1300 years, but, we showed that his definition is suitable.
For the details, see the references and the site: http://okmr.yamatoblog.net/
We wrote two global book manuscripts \cite{s18} with 154 pages and \cite{so18} with many figures for some general people. Their main points are:
\begin{itemize}
\item The division by zero and division by zero calculus are new elementary and fundamental mathematics in the undergraduate level.
\item They introduce a new space since Aristoteles (BC384 - BC322) and Euclid (BC 3 Century - ) with many exciting new phenomena and properties with general interest, not specialized and difficult topics. However, their properties are mysterious and very attractive.
\item The contents are very elementary, however very exciting with general interest.
\item The contents give great impacts to our basic ideas on the universe and human beings.
\end{itemize}
Meanwhile, the representations of the contents are very important and delicate with delicate feelings to the division by zero with a long and mysterious history. Therefore, we hope the representations of the division by zero as follows:
\begin{itemize}
\item
Various book publications by many native languages and with the author's idea and feelings.
\item
Some publications are like arts and some comic style books with pictures.
\item
Some T shirts design, some pictures, monument design may be considered.
\end{itemize}
The authors above may be expected to contribute to our culture, education, common communications and enjoyments.
\medskip
For the people having the interest on the above projects, we will send our book sources with many figure files.
\medskip
How will be our project introducing our new world since Euclid?
\medskip
Of course, as mathematicians we have to publish new books on
\medskip
Calculus, Differential Equations and Complex Analysis, at least and soon, in order to {\bf correct them} in some complete and beautiful ways.
\medskip
Our topics will be interested in over 1000 millions people over the world on the world history.
\bibliographystyle{plain}
\begin{thebibliography}{10}
\bibitem{kmsy}
M. Kuroda, H. Michiwaki, S. Saitoh, and M. Yamane,
New meanings of the division by zero and interpretations on $100/0=0$ and on $0/0=0$,
Int. J. Appl. Math. {\bf 27} (2014), no 2, pp. 191-198, DOI: 10.12732/ijam.v27i2.9.
\bibitem{ms16}
T. Matsuura and S. Saitoh,
Matrices and division by zero $z/0=0$,
Advances in Linear Algebra \& Matrix Theory, {\bf 6}(2016), 51-58
Published Online June 2016 in SciRes. http://www.scirp.org/journal/alamt
\\ http://dx.doi.org/10.4236/alamt.2016.62007.
\bibitem{ms18}
T. Matsuura and S. Saitoh,
Division by zero calculus and singular integrals. (Submitted for publication)
\bibitem{mms18}
T. Matsuura, H. Michiwaki and S. Saitoh,
$\log 0= \log \infty =0$ and applications. Differential and Difference Equations with Applications. Springer Proceedings in Mathematics \& Statistics.
\bibitem{msy}
H. Michiwaki, S. Saitoh and M.Yamada,
Reality of the division by zero $z/0=0$. IJAPM International J. of Applied Physics and Math. {\bf 6}(2015), 1--8. http://www.ijapm.org/show-63-504-1.html
\bibitem{mos}
H. Michiwaki, H. Okumura and S. Saitoh,
Division by Zero $z/0 = 0$ in Euclidean Spaces,
International Journal of Mathematics and Computation, {\bf 2}8(2017); Issue 1, 2017), 1-16.
\bibitem{osm}
H. Okumura, S. Saitoh and T. Matsuura, Relations of $0$ and $\infty$,
Journal of Technology and Social Science (JTSS), {\bf 1}(2017), 70-77.
\bibitem{os}
H. Okumura and S. Saitoh, The Descartes circles theorem and division by zero calculus. https://arxiv.org/abs/1711.04961 (2017.11.14).
\bibitem{o}
H. Okumura, Wasan geometry with the division by 0. https://arxiv.org/abs/1711.06947 International Journal of Geometry.
\bibitem{os18}
H. Okumura and S. Saitoh,
Applications of the division by zero calculus to Wasan geometry.
(Submitted for publication).
\bibitem{ps18}
S. Pinelas and S. Saitoh,
Division by zero calculus and differential equations. Differential and Difference Equations with Applications. Springer Proceedings in Mathematics \& Statistics.
\bibitem{romig}
H. G. Romig, Discussions: Early History of Division by Zero,
American Mathematical Monthly, Vol. {\bf 3}1, No. 8. (Oct., 1924), pp. 387-389.
\bibitem{s14}
S. Saitoh, Generalized inversions of Hadamard and tensor products for matrices, Advances in Linear Algebra \& Matrix Theory. {\bf 4} (2014), no. 2, 87--95. http://www.scirp.org/journal/ALAMT/
\bibitem{s16}
S. Saitoh, A reproducing kernel theory with some general applications,
Qian,T./Rodino,L.(eds.): Mathematical Analysis, Probability and Applications - Plenary Lectures: Isaac 2015, Macau, China, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, {\bf 177}(2016), 151-182. (Springer) .
\bibitem{s17}
S. Saitoh, Mysterious Properties of the Point at Infinity, arXiv:1712.09467 [math.GM](2017.12.17).
\bibitem{s18}
S. Saitoh, Division by zero calculus (154 pages: draft): http//okmr.yamatoblog.net/
\bibitem{so18}
S. Saitoh and H. Okumura, Division by Zero Calculus in Figures -- Our New Space --
\bibitem{ttk}
S.-E. Takahasi, M. Tsukada and Y. Kobayashi, Classification of continuous fractional binary operations on the real and complex fields, Tokyo Journal of Mathematics, {\bf 38}(2015), no. 2, 369-380.
\end{thebibliography}
\end{document}
List of division by zero:
\bibitem{os18}
H. Okumura and S. Saitoh,
Remarks for The Twin Circles of Archimedes in a Skewed Arbelos by H. Okumura and M. Watanabe, Forum Geometricorum.
Saburou Saitoh, Mysterious Properties of the Point at Infinity、
arXiv:1712.09467 [math.GM]
Hiroshi Okumura and Saburou Saitoh
The Descartes circles theorem and division by zero calculus. 2017.11.14
https://arxiv.org/abs/1711.04961
L. P. Castro and S. Saitoh, Fractional functions and their representations, Complex Anal. Oper. Theory {\bf7} (2013), no. 4, 1049-1063.
M. Kuroda, H. Michiwaki, S. Saitoh, and M. Yamane,
New meanings of the division by zero and interpretations on $100/0=0$ and on $0/0=0$, Int. J. Appl. Math. {\bf 27} (2014), no 2, pp. 191-198, DOI: 10.12732/ijam.v27i2.9.
T. Matsuura and S. Saitoh,
Matrices and division by zero z/0=0,
Advances in Linear Algebra \& Matrix Theory, 2016, 6, 51-58
Published Online June 2016 in SciRes. http://www.scirp.org/journal/alamt
\\ http://dx.doi.org/10.4236/alamt.2016.62007.
T. Matsuura and S. Saitoh,
Division by zero calculus and singular integrals. (Submitted for publication).
T. Matsuura, H. Michiwaki and S. Saitoh,
$\log 0= \log \infty =0$ and applications. (Differential and Difference Equations with Applications. Springer Proceedings in Mathematics \& Statistics.)
H. Michiwaki, S. Saitoh and M.Yamada,
Reality of the division by zero $z/0=0$. IJAPM International J. of Applied Physics and Math. 6(2015), 1--8. http://www.ijapm.org/show-63-504-1.html
H. Michiwaki, H. Okumura and S. Saitoh,
Division by Zero $z/0 = 0$ in Euclidean Spaces,
International Journal of Mathematics and Computation, 28(2017); Issue 1, 2017), 1-16.
H. Okumura, S. Saitoh and T. Matsuura, Relations of $0$ and $\infty$,
Journal of Technology and Social Science (JTSS), 1(2017), 70-77.
S. Pinelas and S. Saitoh,
Division by zero calculus and differential equations. (Differential and Difference Equations with Applications. Springer Proceedings in Mathematics \& Statistics).
S. Saitoh, Generalized inversions of Hadamard and tensor products for matrices, Advances in Linear Algebra \& Matrix Theory. {\bf 4} (2014), no. 2, 87--95. http://www.scirp.org/journal/ALAMT/
S. Saitoh, A reproducing kernel theory with some general applications,
Qian,T./Rodino,L.(eds.): Mathematical Analysis, Probability and Applications - Plenary Lectures: Isaac 2015, Macau, China, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, {\bf 177}(2016), 151-182. (Springer) .
再生核研究所声明371(2017.6.27)ゼロ除算の講演― 国際会議 https://sites.google.com/site/sandrapinelas/icddea-2017 報告
https://ameblo.jp/syoshinoris/entry-12287338180.html
1/0=0、0/0=0、z/0=0
http://ameblo.jp/syoshinoris/entry-12276045402.html
1/0=0、0/0=0、z/0=0
http://ameblo.jp/syoshinoris/entry-12263708422.html
1/0=0、0/0=0、z/0=0
http://ameblo.jp/syoshinoris/entry-12272721615.html
ソクラテス・プラトン・アリストテレス その他
https://ameblo.jp/syoshinoris/entry-12328488611.html
アインシュタインも解決できなかった「ゼロで割る」問題
http://matome.naver.jp/odai/2135710882669605901
Title page of Leonhard Euler, Vollständige Anleitung zur Algebra, Vol. 1 (edition of 1771, first published in 1770), and p. 34 from Article 83, where Euler explains why a number divided by zero gives infinity.
https://notevenpast.org/dividing-nothing/
私は数学を信じない。 アルバート・アインシュタイン / I don't believe in mathematics. Albert Einstein→ゼロ除算ができなかったからではないでしょうか。
ドキュメンタリー 2017: 神の数式 第2回 宇宙はなぜ生まれたのか
https://www.youtube.com/watch?v=iQld9cnDli4
〔NHKスペシャル〕神の数式 完全版 第3回 宇宙はなぜ始まったのか
https://www.youtube.com/watch?v=DvyAB8yTSjs&t=3318s
〔NHKスペシャル〕神の数式 完全版 第1回 この世は何からできているのか
https://www.youtube.com/watch?v=KjvFdzhn7Dc
NHKスペシャル 神の数式 完全版 第4回 異次元宇宙は存在するか
https://www.youtube.com/watch?v=fWVv9puoTSs
再生核研究所声明 411(2018.02.02): ゼロ除算発見4周年を迎えて
https://ameblo.jp/syoshinoris/entry-12348847166.html
ゼロ除算の論文
Mysterious Properties of the Point at Infinity
https://arxiv.org/abs/1712.09467
Algebraic division by zero implemented as quasigeometric multiplication by infinity in real and complex multispatial hyperspaces
Author: Jakub Czajko, 92(2) (2018) 171-197
WSN 92(2) (2018) 171-197
http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2017/12/WSN-922-2018-171-197.pdf
ゼロ除算(division by zero)1/0=0、0/0=0、z/0=0
2018年05月28日(月)
テーマ:数学
これは最も簡単な 典型的なゼロ除算の結果と言えます。 ユークリッド以来の驚嘆する、誰にも分る結果では ないでしょうか?
Hiroshi O. Is It Really Impossible To Divide By Zero?. Biostat Biometrics Open Acc J. 2018; 7(1): 555703. DOI: 10.19080/BBOJ.2018.07.555703
ゼロで分裂するのは本当に不可能ですか? - Juniper Publishers
https://juniperpublishers.com/bboaj/pdf/BBOAJ.MS.ID.555703.pdf
Announcement 478: Who did derive first the division by zero 1/0 and the division by zero calculus $\tan(\pi/2)=0, \log 0=0$ as the outputs of a computer? \\ (
カテゴリ:カテゴリ未分類
\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{latexsym,amsmath,amssymb,amsfonts,amstext,amsthm}
\numberwithin{equation}{section}
\begin{document}
\title{\bf Announcement 478: Who did derive first the division by zero 1/0 and the division by zero calculus $\tan(\pi/2)=0, \log 0=0$ as the outputs of a computer? \\
(2019.3.4)}
\author{{\it Institute of Reproducing Kernels}\\
Kawauchi-cho, 5-1648-16,\\
Kiryu 376-0041, Japan\\
{\bf [email protected]}\\
}
\date{\today}
\maketitle
The Institute of Reproducing Kernels is dealing with the theory of division by zero calculus and declares that the division by zero was discovered as $0/0=1/0=z/0=0$ {\bf in a natural sense} on 2014.2.2. The result shows a new basic idea on the universe and space since Aristotele (BC384 - BC322) and Euclid (BC 3 Century - ), and the division by zero is since Brahmagupta (598 - 668 ?).
For the details, see the references.
A simple and essential introduction of the division by zero is given by the {\bf division by zero calculus}:
For any Laurent expansion around $z=a$,
\begin{equation} \label{dvc5.1}
f(z) = \sum_{n=-\infty}^{-1} C_n (z - a)^n + C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n (z - a)^n,
\end{equation}
we define
\begin{equation}\label{dvc5.2}
f(a) = C_0,
\end{equation}
as a value of the function $f$ at the singular point $z=a$.
For the importance of this definition, the division by zero calculus may be considered as a new axiom. This was discovered on May 8, 2014.
In particular, for the function $W= f(z) =1/z$, we have $f(0)=0$. We will write this result as
$$
\frac{1}{0}=0,
$$
from the form.
Here, the definition of $\frac{1}{0}$ is given by this sense by means of the division by zero calculus. Of course, $\frac{1}{0}$ is not a usual sense that $\frac{1}{0} =X$ if and only if $1=0 \times X$; this means a contradiction. See \cite{saitohzi} for the details.
On February 16, 2019 Professor H. Okumura introduced the surprising news in Research Gate:
\medskip
José Manuel Rodríguez Caballero\\
Added an answer\\
In the proof assistant Isabelle/HOL we have $x/0 = 0$ for each number $x$. This is advantageous in order to simplify the proofs. You can download this proof assistant here: {\bf https://isabelle.in.tum.de/}.
\medskip
J.M.R. Caballero kindly showed surprisingly several examples by the system that
$$
\tan \frac{\pi}{2} =0,
$$
$$
\log 0 =0,
$$
$$
\exp \frac{1}{x} (x=0) =1,
$$
and others. Precisely:
\medskip
Dear Saitoh,
In Isabelle/HOL, we can define and redefine every function in different ways. So, logarithm of zero depend upon our definition. The best definition is the one which simplify the proofs the most. According to the experts, z/0 = 0 is the best definition for division by zero.
$$
\tan(\pi/2) = 0
$$
$$
\log 0 =
$$
is undefined (but we can redefine it as $0$)
$$
e ^0 = 1
$$
(but we can redefine it as $0$)
$$
0^0= 1
$$
(but we can redefine it as $0$).
In the attached file you will find some versions of logarithms and exponentials satisfying different properties. This file can be opened with the software Isabelle/HOL from this webpage: https://isabelle.in.tum.de/
Kind Regards,
José M.
(2017.2.17.11:09).
\medskip
At 2019.3.4.18:04 for my short question, we received:
\medskip
It is as it was programmed by the HOL team.
Jose M.
On Mar 4, 2019, Saburou Saitoh wrote:
Dear José M.
I have the short question.
For your outputs for the division by zero calculus, for the input, is it some direct or do you need some program???
With best regards,
Sincerely yours,
Saburou Saitoh
2019.3.4.18:00
\medskip
As we stated in \cite{os1811}, the important point in the division by zero problem is on its definition (meaning of division.), because in the usual sense, we can not consider the division by zero.
L. C. Paulson stated that I would guess that Isabelle has used this {\bf convention} $1/0=0$ since the 1980s and introduced his book \cite{npw} referred to this fact.
However, in his group the importance of this fact seems to be entirely ignored at this moment as we see from the book.
The result $1/0=0$ has a long tradition of Isabelle, however, the result has not been accepted by the world.
Indeed, S. K. Sen and R. P. Agarwal \cite{sa16} referred to the paper \cite{kmsy} in connection with division by zero, however, their understandings on the paper seem to be not suitable (not right) and their ideas on the division by zero seem to be traditional, indeed, they stated as a conclusion of the introduction of the book that:
\medskip
{\bf “Thou shalt not divide by zero” remains valid eternally.}
\medskip
However, in \cite{saitohpo} we stated simply based on the division by zero calculus that
\medskip
{\bf We Can Divide the Numbers and Analytic Functions by Zero with a Natural Sense.}
\medskip
In these situations, the results of J.M.R. Caballero will be very interested. For some precise information, we would like to ask for the question that
\medskip
{\bf Who did derive first the division by zero $1/0$ and the division by zero calculus $\tan(\pi/2)=0, \log 0=0$ as the outputs of a computer? }
\medskip
If it is possible, we would like to know the related details.
\bibliographystyle{plain}
\begin{thebibliography}{10}
\bibitem{boyer}
C. B. Boyer, An early reference to division by zero, The Journal of the American Mathematical Monthly, {\bf 50} (1943), (8), 487- 491. Retrieved March 6, 2018, from the JSTOR database.
\bibitem{kmsy}
M. Kuroda, H. Michiwaki, S. Saitoh, and M. Yamane,
New meanings of the division by zero and interpretations on $100/0=0$ and on $0/0=0$,
Int. J. Appl. Math. {\bf 27} (2014), no 2, pp. 191-198, DOI: 10.12732/ijam.v27i2.9.
\bibitem{ms16}
T. Matsuura and S. Saitoh,
Matrices and division by zero $z/0=0$,
Advances in Linear Algebra \& Matrix Theory, {\bf 6}(2016), 51-58
Published Online June 2016 in SciRes. http://www.scirp.org/journal/alamt
\\ http://dx.doi.org/10.4236/alamt.2016.62007.
\bibitem{mms18}
T. Matsuura, H. Michiwaki and S. Saitoh,
$\log 0= \log \infty =0$ and applications. Differential and Difference Equations with Applications. Springer Proceedings in Mathematics \& Statistics. {\bf 230} (2018), 293-305.
\bibitem{msy}
H. Michiwaki, S. Saitoh and M.Yamada,
Reality of the division by zero $z/0=0$. IJAPM International J. of Applied Physics and Math. {\bf 6}(2015), 1--8. http://www.ijapm.org/show-63-504-1.html
\bibitem{mos}
H. Michiwaki, H. Okumura and S. Saitoh,
Division by Zero $z/0 = 0$ in Euclidean Spaces,
International Journal of Mathematics and Computation, {\bf 2}8(2017); Issue 1, 1-16.
\bibitem{npw}
T. Nipkow, L. C. Paulson and M. Wenzel, Isabelle/HOL
A Proof Assistant for Higher-Order Logic,
Lecture Notes in Computer Science, Springer E E002 E E.
\bibitem{osm}
H. Okumura, S. Saitoh and T. Matsuura, Relations of $0$ and $\infty$,
Journal of Technology and Social Science (JTSS), {\bf 1}(2017), 70-77.
\bibitem{os}
H. Okumura and S. Saitoh, The Descartes circles theorem and division by zero calculus. https://arxiv.org/abs/1711.04961 (2017.11.14).
\bibitem{o}
H. Okumura, Wasan geometry with the division by 0. https://arxiv.org/abs/1711.06947 International Journal of Geometry. {\bf 7}(2018), No. 1, 17-20.
\bibitem{os18april}
H. Okumura and S. Saitoh,
Harmonic Mean and Division by Zero,
Dedicated to Professor Josip Pe\v{c}ari\'{c} on the occasion of his 70th birthday, Forum Geometricorum, {\bf 18} (2018), 155—159.
\bibitem{os18}
H. Okumura and S. Saitoh,
Remarks for The Twin Circles of Archimedes in a Skewed Arbelos by H. Okumura and M. Watanabe, Forum Geometricorum, {\bf 18}(2018), 97-100.
\bibitem{os18e}
H. Okumura and S. Saitoh,
Applications of the division by zero calculus to Wasan geometry.
GLOBAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH ON CLASSICAL AND MODERN GEOMETRIES” (GJARCMG), {\bf 7}(2018), 2, 44--49.
\bibitem{os1811}
H. Okumura and S. Saitoh,
Wasan Geometry and Division by Zero Calculus,
Sangaku Journal of Mathematics (SJM), {\bf 2 }(2018), 57--73.
\bibitem{ps18}
S. Pinelas and S. Saitoh,
Division by zero calculus and differential equations. Differential and Difference Equations with Applications. Springer Proceedings in Mathematics \& Statistics. {\bf 230} (2018), 399-418.
\bibitem{romig}
H. G. Romig, Discussions: Early History of Division by Zero,
American Mathematical Monthly, {\bf 3}1, No. 8. (Oct., 1924), 387-389.
\bibitem{s14}
S. Saitoh, Generalized inversions of Hadamard and tensor products for matrices, Advances in Linear Algebra \& Matrix Theory. {\bf 4} (2014), no. 2, 87--95. http://www.scirp.org/journal/ALAMT/
\bibitem{s16}
S. Saitoh, A reproducing kernel theory with some general applications,
Qian,T./Rodino,L.(eds.): Mathematical Analysis, Probability and Applications - Plenary Lectures: Isaac 2015, Macau, China, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, {\bf 177}(2016), 151-182.
\bibitem{s17}
S. Saitoh, Mysterious Properties of the Point at Infinity, arXiv:1712.09467 [math.GM](2017.12.17).
\bibitem{saitohpo}
S. Saitoh, We Can Divide the Numbers and Analytic Functions by Zero with a Natural Sense, viXra:1902.0058 submitted on 2019-02-03 22:47:53.
\bibitem{saitohzi}
S. Saitoh, Zero and Infinity; Their Interrelation by Means of Division by Zero,
viXra:1902.0240 submitted on 2019-02-13 22:57:25.
\bibitem{sa16}
S.K.S. Sen and R. P. Agarwal, ZERO A Landmark Discovery, the Dreadful Volid, and the Unitimate Mind, ELSEVIER (2016).
\bibitem{ttk}
S.-E. Takahasi, M. Tsukada and Y. Kobayashi, Classification of continuous fractional binary operations on the real and complex fields, Tokyo Journal of Mathematics, {\bf 38}(2015), no. 2, 369-380.
\bibitem{ann179}
Announcement 179 (2014.8.30): Division by zero is clear as z/0=0 and it is fundamental in mathematics.
\bibitem{ann185}
Announcement 185 (2014.10.22): The importance of the division by zero $z/0=0$.
\bibitem{ann237}
Announcement 237 (2015.6.18): A reality of the division by zero $z/0=0$ by geometrical optics.
\bibitem{ann246}
Announcement 246 (2015.9.17): An interpretation of the division by zero $1/0=0$ by the gradients of lines.
\bibitem{ann247}
Announcement 247 (2015.9.22): The gradient of y-axis is zero and $\tan (\pi/2) =0$ by the division by zero $1/0=0$.
\bibitem{ann250}
Announcement 250 (2015.10.20): What are numbers? - the Yamada field containing the division by zero $z/0=0$.
\bibitem{ann252}
Announcement 252 (2015.11.1): Circles and
curvature - an interpretation by Mr.
Hiroshi Michiwaki of the division by
zero $r/0 = 0$.
\bibitem{ann281}
Announcement 281 (2016.2.1): The importance of the division by zero $z/0=0$.
\bibitem{ann282}
Announcement 282 (2016.2.2): The Division by Zero $z/0=0$ on the Second Birthday.
\bibitem{ann293}
Announcement 293 (2016.3.27): Parallel lines on the Euclidean plane from the viewpoint of division by zero 1/0=0.
\bibitem{ann300}
Announcement 300 (2016.05.22): New challenges on the division by zero z/0=0.
\bibitem{ann326}
Announcement 326 (2016.10.17): The division by zero z/0=0 - its impact to human beings through education and research.
\bibitem{ann352}
Announcement 352(2017.2.2): On the third birthday of the division by zero z/0=0.
\bibitem{ann354}
Announcement 354(2017.2.8): What are $n = 2,1,0$ regular polygons inscribed in a disc? -- relations of $0$ and infinity.
\bibitem{362}
Announcement 362(2017.5.5): Discovery of the division by zero as $0/0=1/0=z/0=0$
\bibitem{380}
Announcement 380 (2017.8.21): What is the zero?
\bibitem{388}
Announcement 388(2017.10.29): Information and ideas on zero and division by zero (a project).
\bibitem{409}
Announcement 409 (2018.1.29.): Various Publication Projects on the Division by Zero.
\bibitem{410}
Announcement 410 (2018.1 30.): What is mathematics? -- beyond logic; for great challengers on the division by zero.
\bibitem{412}
Announcement 412(2018.2.2.): The 4th birthday of the division by zero $z/0=0$.
\bibitem{433}
Announcement 433(2018.7.16.): Puha's Horn Torus Model for the Riemann Sphere From the Viewpoint of Division by Zero.
\bibitem{448}
Announcement 448(2018.8.20): Division by Zero;
Funny History and New World.
\bibitem{454}
Announcement 454(2018.9.29): The International Conference on Applied Physics and Mathematics, Tokyo, Japan, October 22-23.
\bibitem{460}
Announcement 460(2018.11.06): Change the Poor Idea to the Definite Results For the Division by Zero - For the Leading Mathematicians.
\bibitem{461}
Announcement 461(2018.11.10): An essence of division by zero and a new axiom.
\bibitem{471}
Announcement 471(2019.2.2): The 5th birthday of the division by zero $z/0=0$.
\end{thebibliography}
\end{document}
2019.3.4.
ゼロ除算(division by zero)1/0=0/0=z/0= tan (pi/2)=0
\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{latexsym,amsmath,amssymb,amsfonts,amstext,amsthm}
\numberwithin{equation}{section}
\begin{document}
\title{\bf Announcement 471: The 5th birthday of the division by zero $z/0=0$ \\
(2019.2.2)}
\author{{\it Institute of Reproducing Kernels}\\
Kawauchi-cho, 5-1648-16,\\
Kiryu 376-0041, Japan\\
{\bf [email protected]}\\
}
\date{\today}
\maketitle
The Institute of Reproducing Kernels is dealing with the theory of division by zero calculus and declares that the division by zero was discovered as 0/0=1/0=z/0=0 in a natural sense on 2014.2.2. The result shows a new basic idea on the universe and space since Aristotelēs (BC384 - BC322) and Euclid (BC 3 Century - ), and the division by zero is since Brahmagupta (598 - 668 ?).
For the details, see the references and the site: http://okmr.yamatoblog.net/
We wrote a global book manuscript \cite{s18} with 235 pages
and stated in the preface and last section of the manuscript as follows:
\bigskip
{\bf Preface}
\medskip
The division by zero has the long and mysterious history over the world (see, for example, \index{H. G. Romig} \cite{boyer, romig} and Google site with the division by zero) with its physical viewpoint since the document of zero in India in AD 628. In particular, note that \index{Brahmagupta} Brāhmasphuṭasiddhānta (598 -668 ?) established four arithmetic operations by introducing $0$ and at the same time he defined as $0/0=0$ in
Brāhmasphuṭasiddhānta. We have been, however, considering that his definition $0/0=0$ is wrong over 1300 years, but, we will see that his definition is right and suitable.
The division by zero $1/0=0/0=z/0$ itself will be quite clear and trivial with several natural extensions of fractions against the mysteriously long history, as we can see from the concept of the Moore-Penrose generalized inverse \index{Moore-Penrose} \index{Tikhonov regularization} to the fundamental equation $az=b$, whose solution leads to the definition of $z =b/a$.
However, the result (definition) will show that
for the elementary mapping
$$
W = \frac{1}{z},
$$
the image of $z=0$ is $W=0$ ({\bf should be defined from the form}). This fact seems to be a curious one in connection with our well-established popular image for the point at infinity on the Riemann sphere \index{Riemann sphere} (\cite{ahlfors}). As the representation of the \index{point at infinity} point at infinity of the \index{Riemann sphere} Riemann sphere by the
zero $z = 0$, we will see some delicate relations between $0$ and $\infty$ which show a strong \index{discontinuity}
discontinuity at the point of infinity on the Riemann sphere. We did not consider any value of the elementary function $W =1/ z $ at the origin $z = 0$, because we did not consider the division by zero
$1/ 0$ in a good way. Many and many people consider its value by limiting like $+\infty $ and $- \infty$ or the
point at infinity as $\infty$. However, their basic idea comes from {\bf continuity} with the common sense or
based on the basic idea of Aristotelēs %Aristotle\index{Aristotle}.
--
For the related Greek philosophy, see \cite{a,b,c}. However, as the division by zero we will consider the value of
the function $W =1 /z$ as zero at $z = 0$. We will see that this new definition is valid widely in
mathematics and mathematical sciences, see (\cite{mos,osm}) for example. Therefore, the division by zero will give great impacts to calculus, Euclidean geometry, analytic geometry, differential equations, complex analysis at the undergraduate level and to our basic idea for the space and universe.
We have to arrange globally our modern mathematics at our undergraduate level. Our common sense on the division by zero will be wrong, with our basic idea on the space and universe since Aristotelēs and Euclid. We would like to show clearly these facts in this book. The content is at the undergraduate level.
Close the mysterious and long history of division by zero that may be considered as a symbol of the stupidity of the human race and open the new world since Aristotel{$\bar{\rm e}$}s-Eulcid.
\bigskip
\bigskip
{\bf Conclusion}
\medskip
Apparently, the common sense on the division by zero with a long and mysterious history is wrong and our basic idea on the space around the point at infinity is also wrong since Euclid. On the gradient or on derivatives we have a great missing since $\tan (\pi/2) = 0$. Our mathematics is also wrong in elementary mathematics on the division by zero.
This book is elementary on our division by zero as the first publication of books for the topics. The contents have wide connections to various fields beyond mathematics. The author expects the readers to write some philosophy, papers and essays on the division by zero from this simple source book.
The division by zero theory may be developed and expanded greatly as in the author's conjecture whose break theory was recently given surprisingly and deeply by Professor \index{Qi'an Guan}Qi'an Guan \cite{guan} since 30 years proposed in \cite{s88} (the original is in \cite {s79}).
We have to arrange globally our modern mathematics with our division by zero in our undergraduate level.
We have to change our basic ideas for our space and world.
We have to change globally our textbooks and scientific books on the division by zero.
\bigskip
Our division by zero research group wonders why our elementary results may still not be accepted by some wide world.
\medskip
%We hope that:
%close the mysterious and long history of division by zero that may be considered as a symbol of the stupidity of the human race and open the new world since Aristotle-Eulcid.
% \medskip
From the funny history of the division by zero, we will be able to realize that
\medskip
human beings are full of prejudice and prejudice, and are narrow-minded, essentially.
\medskip
It seems that the long history of the division by zero is our shame and our mathematics in the elementary level has basic missings. Meanwhile, we have still great confusions and wrong ideas on the division by zero. Therefore, we would like to ask for the good corrections for the wrong ideas and some official approval for our division by zero as our basic duties.
\bibliographystyle{plain}
\begin{thebibliography}{10}
\bibitem{ahlfors}
L. V. Ahlfors, Complex Analysis, McGraw-Hill Book Company, 1966.
\bibitem{boyer}
C. B. Boyer, An early reference to division by zero, The Journal of the American Mathematical Monthly, {\bf 50} (1943), (8), 487- 491. Retrieved March 6, 2018, from the JSTOR database.
\bibitem{cs}
L. P. Castro and S. Saitoh, Fractional functions and their representations, Complex Anal. Oper. Theory {\bf7} (2013), no. 4, 1049-1063.
\bibitem{dops}
W. W. D\"aumler, H. Okumura, V. V. Puha and S. Saitoh,
Horn Torus Models for the Riemann Sphere and Division by Zero. (manuscript).
\bibitem{guan}
Q. Guan, A proof of Saitoh's conjecture for conjugate Hardy H2 kernels, arXiv:1712.04207.
\bibitem{kmsy}
M. Kuroda, H. Michiwaki, S. Saitoh, and M. Yamane,
New meanings of the division by zero and interpretations on $100/0=0$ and on $0/0=0$,
Int. J. Appl. Math. {\bf 27} (2014), no 2, pp. 191-198, DOI: 10.12732/ijam.v27i2.9.
\bibitem{ms16}
T. Matsuura and S. Saitoh,
Matrices and division by zero $z/0=0$,
Advances in Linear Algebra \& Matrix Theory, {\bf 6}(2016), 51-58
Published Online June 2016 in SciRes. http://www.scirp.org/journal/alamt
\\ http://dx.doi.org/10.4236/alamt.2016.62007.
\bibitem{mms18}
T. Matsuura, H. Michiwaki and S. Saitoh,
$\log 0= \log \infty =0$ and applications. Differential and Difference Equations with Applications. Springer Proceedings in Mathematics \& Statistics. {\bf 230} (2018), 293-305.
\bibitem{msy}
H. Michiwaki, S. Saitoh and M.Yamada,
Reality of the division by zero $z/0=0$. IJAPM International J. of Applied Physics and Math. {\bf 6}(2015), 1--8. http://www.ijapm.org/show-63-504-1.html
\bibitem{mos}
H. Michiwaki, H. Okumura and S. Saitoh,
Division by Zero $z/0 = 0$ in Euclidean Spaces,
International Journal of Mathematics and Computation, {\bf 2}8(2017); Issue 1, 1-16.
\bibitem{osm}
H. Okumura, S. Saitoh and T. Matsuura, Relations of $0$ and $\infty$,
Journal of Technology and Social Science (JTSS), {\bf 1}(2017), 70-77.
\bibitem{os}
H. Okumura and S. Saitoh, The Descartes circles theorem and division by zero calculus. https://arxiv.org/abs/1711.04961 (2017.11.14).
\bibitem{o}
H. Okumura, Wasan geometry with the division by 0. https://arxiv.org/abs/1711.06947 International Journal of Geometry. {\bf 7}(2018), No. 1, 17-20.
\bibitem{os18april}
H. Okumura and S. Saitoh,
Harmonic Mean and Division by Zero,
Dedicated to Professor Josip Pe\v{c}ari\'{c} on the occasion of his 70th birthday, Forum Geometricorum, {\bf 18} (2018), 155—159.
\bibitem{os18}
H. Okumura and S. Saitoh,
Remarks for The Twin Circles of Archimedes in a Skewed Arbelos by H. Okumura and M. Watanabe, Forum Geometricorum, {\bf 18}(2018), 97-100.
\bibitem{os18e}
H. Okumura and S. Saitoh,
Applications of the division by zero calculus to Wasan geometry.
GLOBAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH ON CLASSICAL AND MODERN GEOMETRIES” (GJARCMG), {\bf 7}(2018), 2, 44--49.
\bibitem{os1811}
H. Okumura and S. Saitoh,
Wasan Geometry and Division by Zero Calculus,
Sangaku Journal of Mathematics (SJM), {\bf 2 }(2018), 57--73.
\bibitem{ps18}
S. Pinelas and S. Saitoh,
Division by zero calculus and differential equations. Differential and Difference Equations with Applications. Springer Proceedings in Mathematics \& Statistics. {\bf 230} (2018), 399-418.
\bibitem{romig}
H. G. Romig, Discussions: Early History of Division by Zero,
American Mathematical Monthly, {\bf 3}1, No. 8. (Oct., 1924), 387-389.
\bibitem{s79}
S. Saitoh, The Bergman norm and the Szeg\"{o} norm, Trans. Amer. Math. Soc., {\bf 249} (1979), no. 2, 261-279.
\bibitem{s88}
S. Saitoh, Theory of reproducing kernels and its applications. Pitman Research Notes in Mathematics Series, {\bf 189}. Longman Scientific \&Technical, Harlow; copublished in the United States with John Wiley \& Sons, Inc., New York, (1988). x+157 pp. ISBN: 0-582-03564-3.
\bibitem{s14}
S. Saitoh, Generalized inversions of Hadamard and tensor products for matrices, Advances in Linear Algebra \& Matrix Theory. {\bf 4} (2014), no. 2, 87--95. http://www.scirp.org/journal/ALAMT/
\bibitem{s16}
S. Saitoh, A reproducing kernel theory with some general applications,
Qian,T./Rodino,L.(eds.): Mathematical Analysis, Probability and Applications - Plenary Lectures: Isaac 2015, Macau, China, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, {\bf 177}(2016), 151-182.
\bibitem{s17}
S. Saitoh, Mysterious Properties of the Point at Infinity, arXiv:1712.09467 [math.GM](2017.12.17).
\bibitem{s18}
S. Saitoh, Division by zero calculus (235 pages): http//okmr.yamatoblog.net/
\bibitem{ttk}
S.-E. Takahasi, M. Tsukada and Y. Kobayashi, Classification of continuous fractional binary operations on the real and complex fields, Tokyo Journal of Mathematics, {\bf 38}(2015), no. 2, 369-380.
\bibitem{a}
https://philosophy.kent.edu/OPA2/sites/default/files/012001.pdf
\bibitem{b}
http://publish.uwo.ca/~jbell/The 20Continuous.pdf
\bibitem{c}
http://www.mathpages.com/home/kmath526/kmath526.htm
\bibitem{ann179}
Announcement 179 (2014.8.30): Division by zero is clear as z/0=0 and it is fundamental in mathematics.
\bibitem{ann185}
Announcement 185 (2014.10.22): The importance of the division by zero $z/0=0$.
\bibitem{ann237}
Announcement 237 (2015.6.18): A reality of the division by zero $z/0=0$ by geometrical optics.
\bibitem{ann246}
Announcement 246 (2015.9.17): An interpretation of the division by zero $1/0=0$ by the gradients of lines.
\bibitem{ann247}
Announcement 247 (2015.9.22): The gradient of y-axis is zero and $\tan (\pi/2) =0$ by the division by zero $1/0=0$.
\bibitem{ann250}
Announcement 250 (2015.10.20): What are numbers? - the Yamada field containing the division by zero $z/0=0$.
\bibitem{ann252}
Announcement 252 (2015.11.1): Circles and
curvature - an interpretation by Mr.
Hiroshi Michiwaki of the division by
zero $r/0 = 0$.
\bibitem{ann281}
Announcement 281 (2016.2.1): The importance of the division by zero $z/0=0$.
\bibitem{ann282}
Announcement 282 (2016.2.2): The Division by Zero $z/0=0$ on the Second Birthday.
\bibitem{ann293}
Announcement 293 (2016.3.27): Parallel lines on the Euclidean plane from the viewpoint of division by zero 1/0=0.
\bibitem{ann300}
Announcement 300 (2016.05.22): New challenges on the division by zero z/0=0.
\bibitem{ann326}
Announcement 326 (2016.10.17): The division by zero z/0=0 - its impact to human beings through education and research.
\bibitem{ann352}
Announcement 352(2017.2.2): On the third birthday of the division by zero z/0=0.
\bibitem{ann354}
Announcement 354(2017.2.8): What are $n = 2,1,0$ regular polygons inscribed in a disc? -- relations of $0$ and infinity.
\bibitem{362}
Announcement 362(2017.5.5): Discovery of the division by zero as $0/0=1/0=z/0=0$
\bibitem{380}
Announcement 380 (2017.8.21): What is the zero?
\bibitem{388}
Announcement 388(2017.10.29): Information and ideas on zero and division by zero (a project).
\bibitem{409}
Announcement 409 (2018.1.29.): Various Publication Projects on the Division by Zero.
\bibitem{410}
Announcement 410 (2018.1 30.): What is mathematics? -- beyond logic; for great challengers on the division by zero.
\bibitem{412}
Announcement 412(2018.2.2.): The 4th birthday of the division by zero $z/0=0$.
\bibitem{433}
Announcement 433(2018.7.16.): Puha's Horn Torus Model for the Riemann Sphere From the Viewpoint of Division by Zero.
\bibitem{448}
Announcement 448(2018.8.20): Division by Zero;
Funny History and New World.
\bibitem{454}
Announcement 454(2018.9.29): The International Conference on Applied Physics and Mathematics, Tokyo, Japan, October 22-23.
\bibitem{460}
Announcement 460(2018.11.06): Change the Poor Idea to the Definite Results For the Division by Zero - For the Leading Mathematicians.
\bibitem{461}
Announcement 461(2018.11.10): An essence of division by zero and a new axiom.
\end{thebibliography}
\end{document}
#2019年
#更新
#ブラックホールは神がゼロで割ったところにある
#再生核研究所ゼロ除算発見
#2014年2月2日ゼロ除算の発見
#ブラックホールは神が0で割ったところにある
#ゼロ除算を発見したのは2014年2月2日
#ゼロ除算の発見は再生核研究所
#5年を超えたゼロ除算の発見と重要性を指摘した
#2014年2月2日ゼロ除算発見
#特異点
#0割る
#0割る0は0
#ログゼロハゼロ
#tangent二分のパイはゼロ
#1割る0は0
#5年を超えたゼロ除算の発見と重要性を指摘
#謎のブラックホールはどこから来たのか

0 notes
Quote
細菌部隊については国として正式資料等を残しているわけではありません。、
現在の調査はすべて周辺の状況証拠を集めて組立て判断しています。
しかしわずかながら発見されている資料もあります。
1983年秋に神田の古本屋に売りに出た資料です。
兒嶋俊郎氏が入手し慶応大学図書館が購入したものです。
発見された資料は次の3つです。
きい弾射撃ニ因ル皮膚障害並一般臨床的症状観察
破傷風毒素並びに芽胞接種時に於ける筋クロナキシ-に就て
関東軍防疫給水部研究報告
これらの資料を少し見てみます。
* きい弾射撃に因る皮膚障害並びに一般臨床的症状観察(原文カナ)
加茂部隊 池田少佐担当
1940年9月7日から10日にかけて実施された、
毒ガスのイペリット弾を発射させたり、
イペリットやルイサイトの水溶液を飲ませた
5種類の実験結果報告書です。
恐らくは毒ガス部隊である第516部隊と協力した実験だと思われます。
イペリットはマスタ-ドガスとも言われ糜爛性で致死性の毒ガスです。
ルサイトはより即効性のある致死性毒ガスです。
その両方とも砲弾に黄色い印を付けた為きい弾といわれました。
被験者は捕虜で柱に括り付けられ、すべて番号で呼ばれました。
報告書表紙の加茂部隊とは731部隊の秘匿名です。
原文はカナですが読みやすく直します。
読み取り不明は?とします
第一章 緒言
自昭和15年9月7日-至昭和15年9月10日・・・・きい弾射撃を実施せり。
第一地域発射弾数は1ヘクタ-ル100発、総数1800発(野砲に換算して)。
射撃時間は40分、15分間射撃、15分間休み、10分間射撃なり。
第二地域においては発射弾数は1ヘクタ-ル200発、総数3200発
第三地域は発射弾数1ヘクタ-ル300発、総数4800発なり。
被験者は地域内の・・・・各所に配置せり。
第一地域陣地に配置せる者は無帽、満服、下着、上靴を着用せしめ無装面とす。
第ニ地域陣地にては無?夏軍衣袴上靴を着用せしめ無装面者3名、装面者3名とす。
第三地域陣地に配置せるものは夏軍衣袴を着用せしめ無装面者2名、装面者3名とす。
き弾射撃後4時間、12時間、24時間、2日、3日或いは5日後における
一般症状(神経障害を伴うものを含む)皮膚症状、眼部、呼吸器、消化器における症状経過を観察せり。
尚水疱内容液の人体接種試験、血液像並びに尿検査を実施せり
第二章 症例
第一地域陣地内被験者の症状およびその後の経過
287号
(注:731部隊の捕虜・マルタで番号で呼ばれます)
9月7日き弾射撃後4時間全身倦怠、口囲発赤を認め、
翌8日1時頃より全身倦怠、脱力感を覚え頚部発赤、顔面浮腫、眼瞼浮腫状、前臍背面部発赤、
22時頃より口囲に粟粒大水疱発生あり
9日22時頃より口囲に多粟粒大ないし米粒大の水泡発生、10日17時発熱37度、
・・・・・以下省略
280号
攻撃後4時間頃全身倦怠、不機嫌となる、
皮膚は顔面、頚、前胸、肩甲、陰嚢に潮紅を呈す、
眼は羞明、流涙多量、結膜充血す。
8日6時頃より嗜眠顔面浮腫脈拍亢進す。
皮膚は頚、前胸、肩甲発赤、顔面
特に口唇と陰嚢に粟粒大の水疱発生し亀頭発赤腫脹を認む。
眼は流涙多量、眼瞼浮腫、結膜浮腫並びに充血角膜混濁す。
鼻汁咳を訴ふ8日18時頃体温37度皮膚は顔面頚部に米粒大の水泡散在す。
両眼瞼浮腫、結膜充血、開眼困難なり、しわがれ声呼吸困難を訴ふ
・・・・以下省略
(・・・・その後296号、294号、376号
第二地域陣地内
265号、464号468号、499号、513号
(内容省略)
第三地域陣地内
303号、485号、486号、372号、358号
(内容省略)
[持続効力ならびに原水攻撃効力観察]
持久効力観察は,き弾射撃中止後約2時間半にして
被験物(人のこと)を配置し10日22時より11日4時半まで放置して後観察す。
359号
11日9時食思不振脱力感を訴ふ。
皮膚は顔面特に眼瞼、鼻、口周囲、頂、腋、頚、背、腰、右前脛、両大腿発赤潮紅す。
眼は羞明流涙、眼瞼浮腫、結膜充血、角膜混濁す。
鼻汁、頚内掻破感まらびに灼熱痛、咳、咽喉発赤す
・・・・以下省略
[原水攻撃効果観察] (毒ガス液を直接飲ませるひどい試験です)
479号
9月7日 原水飲用(攻撃)セシム
同10日 20時右眼に原水点眼す
同11日 右眼結膜発赤充血を認むる
同8日 (攻撃後12時間)嘔吐、下痢、????、粘血便を排出す
以下省略
287号
9月9日 原水を木炭にて除毒せる水300竓飲用(攻撃)せしむ
原水イペリット 15mg/L
ルイサイト 15mg/L
同10日 10日中には著変なし
10昼9日の原水を活性炭にて除毒せる水600竓飲用(攻撃)せしむ
以下省略
464号
9月9日の朝原水(イペリット148mg/L ルイサイト26mg/L)を
10日昼より飲用せしむるに
12時間後、食思不振、悪心嘔吐を訴ふ
11日食思不振17時頃嘔吐3回悪心腹部圧痛あり
以下省略
第三章 水疱内容液の所見並びに人体試験成績(以下長くなるので以降項目のみです)
[第一節 水疱内容液の所見]
[第ニ節 人体接種試験]
第四章 血液像の所見
第五章尿の所見
第六章結論
第七章 附記
注 番号は生体実験した捕虜の番号です。
たった一つの実験でこれだけの人間が犠牲になったのです。
* 破傷風毒素並びに芽胞接種時に於ける筋クロナキシ-に就て(原文カナ)
(指導 永山中佐)
陸軍軍医少佐 池田苗夫
陸軍技師 荒木三郎
要点
破傷風毒素と芽胞を人間の足背部に接種し、
発症時の筋肉の電位変化(クロナキシ-)を測定した実権です。
対象になった人間捕虜(マルタ)は14人。
全員が死亡しています。
結果
991号
破傷風芽胞300CCを皮下注射
測定位置
咬筋、鼻筋、眼輪筋、胸鎖乳頭筋、潤背筋肋骨筋、脛骨筋
結果 約10日で死亡
691号
破傷風毒素100MLD接種 経過極めて電撃的
測定位置
咬筋、鼻筋、眼輪筋、胸鎖乳頭筋、潤背筋肋骨筋、鋸歯状筋
結果 5日で死亡
595号
破傷風毒素10MLD接種 経過極めて電撃的
測定位置
咬筋、鼻筋、眼輪筋、胸鎖乳頭筋、潤背筋、脛骨筋、腓腸筋
結果 7日で死亡
* 凍傷に就いて (原文カナ)
第15回満州医学会ハルビン支部特別講演の要旨
昭和16年10月26日
満州第731部隊
陸軍技師 吉村寿人
吉村寿人は京都帝国大学医学部卒業
1938年満州第731部隊に陸軍技師として所属
終戦まで第一部細菌研究の中の吉村班(凍傷研究)の責任者だった。
捕虜を使った凍傷実験で有名。
実験 1
凍傷の発生をみるために塩水に手を入れさせ、徐々に温度を下げ
中指に装着した「ブレスチモグラフ」で皮膚温度や指容積の変化を記録した
塩水温度は-20℃まで下げている。
被験者の数は不明
実験 5
実験3と同様にして諸種の生活条件を変えたる後の血管反応の状況を観察し、
実験4に述べたる方法を以って抗凍傷指数を計算す。
5人の被験者に就いて検査せり
諸種生活条件変更
水浴後 10℃水中 10分
温浴後 40℃の湯 10分
運動直後 背筋力計 15分連続
満腹直後 過飽食(飯4杯 ?2人前)
空腹 Ⅰ 絶食 2日後
空腹 Ⅱ 絶食 3日後
睡眠不足 一昼夜不眠
夏季(8月初め) 室温25℃
春季(4月中旬) 室温16℃
温室(30℃) 4月調査
実験 6
苦力101名につき抗凍傷指数を求め之を年齢別に統計せるものなり
生体実験の証拠資料 | おしえて!ゲンさん! ~分かると楽しい、分かると恐い~ http://www.oshietegensan.com/war-history/war-history_h/5460/
2 notes
·
View notes
Text
新型コロナウィルス関連情報(5月26日)
在ニューヨーク日本国総領事館
Tue, May 26, 9:53 PM
【当館所在ビルへの入館に際してのご注意(マスク等の着用)】
当館が所在するビルでは,入館者に対してビル内公共スペースにおいてマスクの着用を求めております。このため当館にご来館される際にはマスクの着用をお願いします。
【州政府等による措置等のポイント】
(注)各州政府の措置等についても,できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが,ご自身に関係する事項については,米側当局が提供する情報に依拠してください。
◎(NY州)クオモ知事のメッセージ(5月26日)
- 昨5月25日の総入院者数は4265人と5日連続5000人を下回り(43日連続減少),一日の入院者数(直近3日間平均)も200人へと減少した。また,同日の死者数は73人と二日連続100人を下回り,死者数が急増し始めた3月下旬以来,最低水準となった。
- 重要なことは賢明に再開を進めることであり,そのためには(1)再開の監視と(2)再開の加速の2つの道が重要となる。(1)再開の監視について,すでにダッシュボードを構築し数値を監視してきた。現在,ミッドハドソンは7つの基準を満たしたので,本5月26日に再開の第1段階に入る。ロングアイランドは,このまま死者数が減少し追跡要員の準備ができれば明5月27日に再開する。再開に当たっては,州内10の各地域の司令室が各数値を監視しいずれかの数値が基準を超えればすぐに対応する。
- NY市は,NY州,米国及び世界の経済のエンジンであるが,まだ7つの基準のすべては満たしていないので再開できない。NY市が再開するためには,誰が被害を被っているかを絞り込んでいく必要がある。そこで,新たな感染者を郵便番号(Zip Code)別で分析した結果,NY市のマイノリティ・コミュニティ及び低所得コミュニティの住民がコロナウイルスにより深刻な被害を受けていることが判明した(詳細は別掲しています)。NY市を再開させ前進させるためには,このコミュニティに焦点を当てて対処する必要がある。
- 私たち一人一人が責任ある行動をとる必要がある。それは手洗い,他者との一定の距離の確保,消毒ジェルの使用,そしてマスクの着用である。マスクの着用は,今や文化コミュニケーションでありカッコ良い(Cool)。NY州のファッションの一部であるべき。
- (2)再開の加速について,本日,NY証券取引所が取引を再開したが,経済は以前と同じ形へと戻ることはないと思う。大企業は大丈夫であろうが,国内の労働者及び小企業は被害を受けている。この状況を踏まえ,政府は大規模なインフラ・プロジェクトを進めることにより経済を刺激する必要がある。過去にも,フーバー・ダムやリンカーン・トンネル,マイアミとキーウエストを結ぶオーバーシーズ・ハイウエイ(127.5マイル)の建設により大量の雇用を創出し米国が発展した。現在,米国内の大規模インフラ・プロジェクトは大幅に遅れているが,議論だけでなく超党派で推進すべき。今が建設の時である。
- 具体的に,州はこれまで1万4500人の雇用を創出したペンシルベニア駅の改修事業「エンパイヤ・ステーション・プロジェクト」を推進するとともに,これまで8000人の雇用を創出したラガーディア空港の改修事業を加速する。また,州北部で生産された再生可能電力を,州南部へ送るための送電ケーブルを敷く。さらに,カナダの水力発電により生産されたより廉価な電力をNY市につなぐ送電ケーブルも設置していきたい。加えて,連邦政府の承認を得て,ラガーディア空港のエアトレイン設置(注:ラガーディア空港とNY市中心部は現在エアトレイン・電車・地下鉄で繋がっていない),NJ州・マンハッタン間の新ハドソン・トンネルの建設,マンハッタンの地下鉄2番街線の拡張等も進めていきたい。明5月27日,ワシント
ンDCを訪問してトランプ大統領と会うので,これらの大規模インフラ・プロジェクトの推進を含めて様々な議論を行う。
- 昨日まで実施した#WearAMask NY PSAコンテストでは,600以上のビデオ作品の応募があり,その中のファイナリスト5本のビデオに計18万6117票の投票があった。優勝作品は「We Heart New York」であり,第2位は「You can Still Smile」であった(注)。1位と2位の投票数の合計は9万6332票で,その差はたった502票であった。予想外にも投票は州を超え,全米だけでなく世界からの投票があったことを総合的に勘案し,両方の作品を州の広告として放映することを決定する。
(注)ビデオコンテストの結果は以下のサイトでご覧になれます。
https://coronavirus.health.ny.gov/wear-mask-new-york-ad-contest-winner-announced
◎(NY州)入院者の多い地域の検査結果
・直近1週間の入院者が多い地域の情報は以下のとおりです。
地区 郵便番号 入院者数 地域の黒人割合 同ヒスパニック割合
Bronx 10467 100 33% 48%
Queens 11691 95 47% 25%
Queens 11368 86 9% 74%
Brooklyn11226 78 71% 17%
Bronx 10469 73 55% 25%
Bronx 10468 69 19% 70%
Bronx 10458 69 20% 64%
Queens 11373 69 1% 42%
Brooklyn11203 66 88% 6%
Bronx 10456 64 40% 56%
◎(NY州)経済社会活動再開の関する情報
- 州内10地域における7基準の充足状況(本5月26日19時時点)
https://forward.ny.gov/regional-monitoring-dashboard
*7基準全てを満たしている8地域
(1)キャピタルリージョン
(2)セントラルNY
(3)フィンガーレイクス
(4)ミッドハドソン
(5)モホークバレー
(6)ノースカントリー
(7)サザンティア
(8)ウエスタンNY
*5つの基準を満たしている2地域
(9)ロングアイランド
(10)NY市
- 基準を全て満たした地域での再開に向けた事業別ガイドライン
https://forward.ny.gov/industries-reopening-phase
- 基準を満たしていない地域へ有効となっているNY State on PAUSE政策
https://coronavirus.health.ny.gov/new-york-state-pause
- 上記情報の概要を当館HPにも掲載しておりますので併せてご利用ください。
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/states.html
◎(NY市)デブラシオ市長のメッセージ(5月26日)
- ウイルス検査は簡単で手早く無料で受けられることが重要である。そのために,検査体制を更に拡大していく。具体的には,6月にかけて毎週新しい検査場を開設した上で8月までに5万件/日の体制を目指す(注)。また,Advantage Care Physiciansと提携し6月には市内16か所で新たな検査場がオープンする。無保険者でも無料で受けられるので,866-749-2660に連絡をして事前予約をして欲しい。さらに,1000万ドル規模の広報(多言語でのメディア発信,ラジオなど)を実施して検査の周知徹底をしていく。特に,感染が多い地域の市民や感染しやすい業務に携わっている市民に焦点を当てる。
(注)NY市のウイルス検査場の情報などは以下のサイトでご確認になれます。
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
- 検査後の追跡も重要である。現在,市は1700名の追跡要員を確保しており,6月1日までに訓練が終了する。また,今週100名の人員を追加で採用する予定である。
- 経済社会活動の再開の第一段階に向けて準備を進める必要がある。産業ごとに必要な規制やサポートを検討するとともに,市民��交通パターンを分析し再開しても安心して通勤できるようにする。
◎(NJ州)マーフィー知事のメッセージ(5月26日)
- 7月6日以降,屋外での卒業式の開催を許可する。卒業式を行うにあたって,他者と6フィート以上の間隔を保つことなど,ソーシャル・ディスタンシングを守ってほしい。実施に際する詳細なガイドラインは明日,州教育局より発表する。7月6日より前に卒業式を実施する場合は,バーチャル形式のみ,許可される。
州政府プレスリリース:https://nj.gov/governor/news/news/562020/approved/20200526b.shtml
- プロスポーツチームが,適切な衛生管理を行うことを条件にトレーニング,キャンプを行うことを許可する。
州政府プレスリリース:https://nj.gov/governor/news/news/562020/approved/20200526a.shtml
- 新規入院者数,現在の入院者数,ICUの患者,人工呼吸器を使用する患者について,減少傾向にあり,良い方向へ進んでいる。10万人あたりの新規感染者数,現在の入院者数,1日の死者数について,CT,NY,PA,CA,TX州と比べた場合,NJ州は新規感染者数及び1日の死者数についてCT州に次ぎ2番目に多く,入院者数は1番多い。引き続き,全米の中でダメージの大きい州である。
- メモリアル・デーの週末にはビーチなど再開させたが,大きな問題などは報告されておらず,州民のソーシャル・ディスタンシングの取り組み等に感謝する。
◎(PA州)ウォルフ知事のメッセージ(5月26日)
- 5月29日(金)に17郡(ブラッドフォード郡,キャメロン郡,クラリオン郡,クリアフィールド郡,クロウフォード郡,エルク郡,フォレスト郡,ジェファーソン郡,ローレンス郡,マッキーン郡,モントゥアー郡,ポッター郡,スナイダー郡,サリバン郡,タイオガ郡,ベナンゴ郡,ウォーレン郡)をYellowからGreenフェーズに移行することを発表済みであるが,センター郡も移行可能と判断し,同郡も対象に追加することとした。これにより,計18郡が同日にGreenフェーズに移行予定である。
- 今後,経済活動の再開が進みYellowやGreenのフェーズに移行した場合でも,感染防止策の継続が必要。特に大規模な集まりにおいてソーシャル・ディスタンシングが守られない状況が起こることを懸念している。
- (レヴィンPA州保健省長官より)感染者数については,集計日ごとに変動はあるものの州全域で減少傾向が続いている。また,感染者の約61%が回復した。
- (レヴィンPA州保健省長官より)川崎病に似た小児多臓器系炎症性症候群 (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C)) に関連して,今のところ州内で17件の報告があり,このうち9件でMIS-Cと確認した。残りのうち2件はMIS-Cに該当しないと判断し,6件は現在調査中である。MIS-Cの主な症状は,持続性の発熱(ときに高熱),発疹,リンパ節の腫れ,目の充血,結膜炎,腹痛などである。子供にこれらの症状があると気付いた場合には,かかりつけの小児科医に連絡してほしい。
* CDCによるMIS-Cに関する情報については以下のサイトをご覧ください。
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children/mis-c.html
◎(フィラデルフィア市)ケニー市長のメッセージ(5月26日)
- PA州政府により建設業と不動産業の営業再開が認められたことを受けて,市の行政命令もこれに合わせて改正した。建設業に関し,これまでは3月20日以前に建築または解体の許可を得ていたプロジェクトのみ再開が認められていたが,今回の改正によって同日よりも後に許可を得たプロジェクトも再開可能となった。
また,この行政命令によって,ソーシャル・ディスタンシングの実施や利用客と従業員のマスク着用等を条件として,レストランやフードトラックに出向いての注文も認められることとなった。ただし,利用客の列が10人を超えることは禁止され,可能であれば屋外で注文を待つことが推奨される。なお,屋外・屋内の座席を問わず,レストランにおける飲食は引き続き禁止される。
* 詳細については以下のサイトをご覧ください。
https://www.phila.gov/2020-05-26-city-provides-update-on-covid-19-for-tuesday-may-26-2020/
◎(WV州)ジャスティス知事のメッセージ(5月26日)
- 本26日より,限定的な形で以下の事業・施設の再開を許可する。
・州立公園のキャビン・ロッジ(州民のみ)
・バー(屋外もしくは屋内の場合は50%の収容率まで)
ガイドライン:https://governor.wv.gov/Documents/Covid%20Week%205/2020.05.19%20Restaurants%20and%20Bars%20Guidelines.pdf
・ミュージアム及びビジターセンター(屋内の収容率は50%まで,オンラインでのチケットの予約を推奨,発効中の自宅待機推奨令で集団での集まりは25人までとされていることから,26人以上のグループでの訪問は制限・キャンセルされる等。)
ガイドライン:https://governor.wv.gov/Documents/Covid%20Week%205/2020.05.19%20Museum%20Guidelines_NEW.pdf
・動物園(屋内の収容率は50%まで,オンラインでのチケットの予約を推奨,発効中の自宅待機推奨令で集団での集まりは25人までとされていることから,26人以上のグループでの訪問は制限・キャンセルされる等。)
ガイドライン:https://governor.wv.gov/Documents/Covid%20Week%205/2020.05.19%20Zoo%20Reopening%20Guidelines_NEW.pdf
- 5月26日,27日に下記の場所で無料のウイルス検査が実施される。
*フェイエット(Fayette)郡
・5月26日午後12時-午後2時:Mt. Hope Fire Department, 428 Main Street, Mt.Hope
・5月27日午後3時-午後7時:Kilsyth Free Will Baptist Church, 119 Freewill Lane, Mt. Hope
・5月28日午後2時-午後6時:Oak Hill High School, 350 W. Oyler Avenue, Oak Hill
*バークレー(Berkeley)郡
・5月29日,30日の午前9時-午後4時:Musselman High School, 126 Excellence Way, Inwood
*ジェファーソン(Jefferson)郡
・5月29日,30日の午前9時-午後4時:Hollywood Casino, 750 Hollywood Drive, Charles Town
*カナウワ(Kanawha)郡
・5月29日,30日の午前9時-午後4時:Shawnee Sports Complex, 1 Salango Way, Dunbar
*ミネラル(Mineral)郡
・5月29日午前9時-午後4時:American Legion Piedmont, 10 Green Street, Piedont
・5月29日午前9時-午後4時:School Complex, 1123 Harley O. Staggers Senior Drive, Keyser
*モーガン(Morgan)郡
・5月29日,30日の午前9時-午後4時:Warm Springs Middle School, 271 Warm Springs Way, Berkeley Springs
- コロナウイルスから回復した患者数と現在感染している人数の差は,ますます開きつつあり,累計陽性率も2.05%である(全米平均11.33%)。マスク等,鼻と口を覆うものを身につけることは感染防止に非常に効果的なので,引き続き外出する際は身につけるようにしてほしい。
◎(DE州)カーニー知事のメッセージ(5月26日)
・6月1日から,これまで州外の訪問者に課していた14日間の自主検疫と,デラウェア州の宿泊施設に課していた宿泊者の制限を解くことにした。先週末にリホボスビーチを訪問したが,その際に80ー85%の人が遊歩道でマスクを着用していたことは印象的であった。州民の協力が得られていることは心強い。今後もビーチでの啓発活動を続けていく。
・6月1日から,自宅待機令を解く。ただし引き続き不必要な外出や人混みは避けてほしい。
・6月1日から,屋外で開催される250人以下の社会的・地域交流・娯楽・レジャー・イベントは許容される。たとえば,パレード,フェスティバル,卒業式,大会,資金調達,スポーツ,各種フェアなどのイベントは250人以下であれば開催可である。250人以上の屋外イベントについては,州の中小企業庁に7日前までに計画を提出してほしい。250人以上が集まる卒業式についても州の教育庁に7日前までに計画を提出してほしい。
・先日のメモリアルデーは,コロナウイルスのために亡くなった335人のデラウェア州民,10万人近くの米国人のためにも追悼が行われた。この3ヶ月でベトナム戦争と南北戦争の戦死者を合わせた以上の人が亡くなったことになる。この犠牲から学び,引き続き,あなた自身とあなたの隣人のために,公衆衛生ガイダンスに従ってほしい。医療関係者,第一線で働くワーカー,養鶏関係者,ビジネス関係者,多くの人に犠牲を強いてきたと思う。心から協力に感謝したい。
・(以下,ラテイ保健局長より)ビジネス従業員に対する検査ガイダンスを作成した。
https://coronavirus.delaware.gov/wp-content/uploads/sites/177/2020/05/Business-Testing-Guidance-5.26.20.pdf
https://coronavirus.delaware.gov/resources-for-businesses/
・このガイダンスは,感染リスクの観点から,リスクが非常に高い層(感染者を直接ケアする医療従事者等),高い層(ヘルスケア,第一線で働くワーカー,警察・消防等),中程度のリスクの層(社会サービス,教育,製造,小売業,食料品店,コスメ,チャイルドケア等),低リスクの層(オフィス・ワーカー等)に分け,それぞれの層がどの位の頻度で検査を受けるべきか規定している。検査を受ける方法としては,かかりつけ医や職場での検査,コミュニティ検査場やドライブスルー検査場による検査,また,LabCorp for COVID-19が行う郵送による唾液検査という方法もある。詳細はこちらで確認してほしい。(pixel.labcorp.com/covid-19)
・抗体検査について説明したい。抗体検査はIgMとIgGの二つの結果が出る。IgMは,現在感染している疑いが高い(コロナウイルス感染陽性と計上されていた)ことを示し,IgGは,過去に感染していた可能性がある(コロナウイルス感染陽性には計上されない)ことを示す。
・ビジネス従業員への一般的な衛生ガイダンスとしては,可能であればテレワークを推奨する。これに勝る感染防止策はない。しかし,必要があって出勤しなければならない場合は,従業員の検温などを行い病気の人は自宅待機,オフィスでは6フィートの距離措置やマスク等の着用を行う,除菌ジェル等の使用及び手洗いの励行,また,多くの人が触れる箇所は2時間に1度除菌を行うなどを推奨したい。
◎ビジネス関連情報
・各州等のビジネス関連情報は以下をご覧ください。
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/covid19-sb.html
【感染者数等に関する情報】
5月26日現在,当館管轄内における新型コロナウイルスの感染者数及び死者数は以下のとおりです。(カッコ内は前日の数)
○ニューヨーク州:感染者数 363,836名(362,764名),死者数 23,564名(23,488名)
・感染者数内訳(主なエリア)
ニューヨーク市:感染者数 199,301名(198,731名),死者数 15,118名(15,090名)
NY市の内訳
クイーンズ区: 60,960名( 60,828名)
ブルックリン区: 54,560名( 54,360名)
ブロンクス区: 44,364名( 44,247名)
マンハッタン区: 26,092名( 26,009名)
スタテン島区: 13,325名( 13,287名)
ナッソー郡: 39,974名( 39,907名),死者数 2,601名( 2,597名)
サフォーク郡: 39,199名( 39,090名),死者数 1,900名( 1,888名)
ウエストチェスター郡: 33,107名( 33,049名),死者数 1,469名( 1,467名)
ロックランド郡: 13,019名( 12,996名),死者数 455名( 454名)
○ニュージャージー州:感染者数 155,764名(155,092名),死者数11,191名(11,144名)
○ペンシルベニア州:感染者数 68,637名( 68,186名),死者数 5,152名( 5,139名)
○デラウェア州:感染者数 9,066名( 8,965名),死者数 335名( 332名)
○ウエストバージニア州:感染者数 1,797名( 1,774名),死者数 73名( 72名)
○コネチカット州フェアフィールド郡:感染者数 15,355名(15,213名),死者数 1,231名( 1,221名)
○プエルトリコ:感染者数 3,324名( 3,260名),死者数 129名( 127名)
○バージン諸島:感染者数 69名( 69名),死者数 6名( 6名)
【在米団体等によるビジネス関連ウェビナー】
・ジェトロ・ニューヨーク事務所主催「自宅待機令解除後の事業再開へ向けたガイダンス-法的留意点と実際の取り組み事例」
- 日時:2020年5月27日(水)午後4:00ー5:10(米国東部時間)
- プログラム:
1.事業再開に関するガイドラインの概要および法的留意点 (茂木紀子弁護士)
2.ソーシャディスタンス対策やタッチレス化などオフィス再開にあたっての安全化対策 (CIC ティム・ロウCEO)
3.オフィス再開にむけての準備とガイドライン作成の事例紹介 (Pasona N A徳丸佳代VP)
4.質疑応答
- 講師: Ballon Stoll Bader & Nadler, P.C 茂木紀子弁護士(ニューヨーク州・日本),CIC 創業者兼CEO ティム・ロウ(Tim Rowe),Pasona N A, Inc. VP of Corporate Planning 徳丸佳代 SHRM-CP
- 講演言語:日本語
- 参加費:無料
- 定員:1,000名(当日先着順。定員になり次第,締め切り)
- 申込み方法:下記よりお申し込みください。
https://register.gotowebinar.com/register/3754657793542050062
【領事窓口業務の一時的変更及び予約制の導入のお知らせ】
◎当館は以下のとおり領事窓口時間を延長するとともに,予約制を導入しています。ご来館予定の方におかれては,事前の予約をお願い申し上げます。
1 領事窓口の業務日
月曜日,水曜日,金曜日(除,休館日)
2 受付時間
09:30-13:00
(ビザ(査証)申請受付:12:00-13:00)
3 予約方法・電話番号
以下の予約専用電話番号にお電話の上,予約をお願いします。なお,電子メール等による予約は受付けておりません。
予約専用電話番号:(212)371-8222 内線486
注:4週間分の予約を受け付けております。
現在,予約受付については午前中にお電話が集中し,午後は比較的少ない傾向にあります。また,予約電話で対応中は,お電話をいただいても呼び出し音が鳴り続ける状態となるため,このような場合には時間を改めておかけ直しいただきますようお願いいたします。詳細は以下リンク先をご参照ください。
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/l/01.html
◎当館ホームページ上に新型コロナウイルス関連情報のページを作成しております。https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html
ご不明な点ありましたら当館までご連絡をいただきますようお願いします。(電話:212-371-8222)
【医療関係情報】
◎CDCはホームページ上で新型コロナウイルスの典型的症状として「熱,咳,息切れ」を挙げています。これらの症状があり,感染が疑われる場合は医療機関に電話で相談をした上で,医療機関の指示に従って受診してください(特定の医療機関がない場合には地元保健当局等(NY市の場合は311)に電話してください)。
CDCホームページ:https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
・新型コロナウイルスに関する予防措置については以下のサイトをご覧ください。https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html
・ニューヨーク市作成の新型コロナウイルスに関するファクトシート(発症した場合等の対応が日本語で記載されています)。
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet-jp.pdf
◎当地の病院やクリニックは,完全予約制を導入し,付き添い人数を制限(一人のみ)するなど予防措置をしながら外来を受け付けているところが多い模様です。また,一部の病院では電話診察,オンライン診療(有料)を導入しているところもあるようです。ただし,当地の医療事情については,日々状況が変化しますので,皆様ご自身で病院やクリニックのHPや直接電話するなどして,ご確認くださるようお願いします。
******************************************************************
■ 本お知らせは,安全対策に関する情報を含むため,在留届への電子アドレス登録者,「緊急メール/総領事館からのお知らせ」登録者,外務省海外旅行登録「たびレジ」登録者に配信しています(本お知らせに関しては,配信停止を承れませんのでご了承願います。)。
■ 本お知らせは,ご本人にとどまらず,家族内,組織内で共有いただくとともにお知り合いの方にもお伝えいただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。
■ 在留届,帰国・転出等の届出を励行願います。
緊急時の安否確認を当館から行うために必要です。
以下のURLから所定の用紙をダウンロード後, (212)888-0889までご連絡ください。
http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/b/02.html
■ 在ニューヨーク日本国総領事館
299 Park Avenue, 18th Floor, New York, NY 10171
TEL:(212)-371-8222
HP: http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html/
facebook: https://www.facebook.com/JapanConsNY/
******************************************************************
0 notes
Text
特別養護老人ホームあすかHOUSE中央 備品購入契約に係る一般競争入札について
公 告
社会福祉法人明日佳「特別養護老人ホームあすかHOUSE中央に係る備品購入契約」の一般競争入札について、次の通り公告します。
令和1年10月25日
社会福祉法人明日佳
理事長 小野寺眞悟
1.入札内容
(1)名 称 「特別養護老人ホームあすかHOUSE中央」
(2)納入場所 北海道札幌市中央区南3条西14丁目
(3)購入内容 ①家具什器一式
②PCネットワーク機器一式
③ナースコールシステム及び見守りシステム一式
(4)仕様及び数量 6のとおり別途配布する
(5)納入期限 令和2年2月17日(月)
2.入札方法等
(1)入札方法 一般競争入札
(2)予定価格 有り(非公開)
(3)最低制限価格 有り(非公開)
(4)入札保証金 無し
3.入札参加資格
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令16号)第167条の4の規定に該当しない事業者であること。
(2)会社更生法による更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法による再生手続開始の申立がなされている者等経営状態が著しく不健全な者でないこと。
(3)札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年2月26日 札幌市条例第6号)に定める禁止行為を行っていないこと。
(4)北海道内の医療・福祉施設に納入実績があり、札幌市内に、本店及び支店、営業所を有していること。
(5)当法人の理事が役員をしている事業所でないこと。
4.一般競争入札参加資格確認申請書の提出
(1)受付期間 令和1年10月25日(金)から令和1年11月1日(金)まで
但し、日曜日、祝祭日を除く。
(2)受付時間 午前9時から午後5時まで。
(3)提出書類 ①一般競争入札参加資格確認申請書
②申出書
③会社案内
④担当者名刺(電話又は電子メールが記載されていること)
⑤その他必要と認めるもの
(4)提出方法 入札参加希望者は、入札参加資格の確認できる資料を持参にて提出すること。(事前に連絡すること)
(5)提出先 〒006-0841
北海道札幌市手稲区曙11条1丁目7-7
社会福祉法人明日佳 特別養護老人ホームあすかHOUSE手稲
担当者:今井・中野
電話:011-685-8000 FAX:011-685-8600
電子メール:[email protected]
5.一般競争入札参加資格確認通知の配布
(1)入札参加資格確認審査後、参加資格の有無について令和1年11月5日(火)午後3時までに書面又はFAXにて通知する。
(2)下記の各項目に該当する入札参加申請は無効とする。
①入札参加申請書類に不備または虚偽の記載等があったとき。
②提出書類の誤字・脱字等により意思表示が不明瞭であったとき。
③所定の記銘押印の無いとき。印影が不明瞭であるとき。
④1社で2通以上の入札参加申請書を提出したとき。
⑤明らかに談合によると認められるとき。
⑥入札参加資格申請に必要な要件を具備していないとき。
(4)見積に際しては仕様書に準拠した物品で見積もりを行うこと。 同等の品質以上の物である場合のみ、仕様書と異なる物品で見積もりを行うことを許可します(その場合、質疑期間において事前に確認のあったもの、かつ法人回答において同等品と認めたものに限る)。
6.入札仕様書等の配布
入札参加希望者に限り仕様書と入札に関する必要な各種書式の様式(申請書、委任状等)を下記の通り配布する。
(1)期間:令和1年11月6日(水)から令和1年11月8日(金)の午前9時から午後5時まで。但し、日曜日、祝祭日を除く。
(2)場所:社会福祉法人明日佳 特別養護老人ホームあすかHOUSE手稲
(担当 今井・中野)札幌市手稲区曙11条1丁目7番7号
7.入札仕様書等に関する質疑及び回答
(1)質疑提出期限 令和1年11月11日(月)まで
(2)質疑提出方法 法人担当者に電子メール又はFAXにて提出
(3)回答日 令和1年11月12日(火)午後3時までに行う
(4)回答方法 全ての質疑を集計した回答書を全参加事業者へ電子メール又はFAXにて一斉送付する
8.入札執行の日時等
(1)入札日時 令和1年11月25日(月)
※5分前までに受付を済ませること
家具什器一式10:00
PCネットワーク機器一式10:15
ナースコールシステム及び見守りシステム一式10:30
(2)入札会場
〒006-0841
北海道札幌市手稲区曙11条1丁目2-1
山口団地会館
9.落札者の決定
(1)予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上で入札した者のうち最低の価格 入札した者を落札者とする。
※最低制限価格を設定しているので、それを下回る入札は失格とする。
(2)1回目の入札で予定価格の範囲内で入札をした者がいない場合は、再度入札を実施する。(再度入札は2回まで)
(3)上記(2)によっても落札者がいない場合は不調とし、最低制限価格を上回る最低価格を提示した者と交渉による随意契約を行うものとする。
随意契約の相手方となることができる者は、再度入札に参加した者とする。ただし、再度入札において無効の入札を行った者は、随意契約の相手方となる事ができない。
随意契約の相手方となる者から見積書を提出させ、見積書が入札予定価格の範囲内で適当と認められた時は、当該見積もりをした者を契約の相手方とする。
(4)同額の入札をした者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定するものとする。その場合の本くじを引く順番を決める予備くじは、五十音により早い名称の者から行うものとする。
10.入札にあたっての注意事項
(1)代理人をして入札される場合は、委任状を提出すること。
(2)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札を辞退する時は、入札辞退届により申し出ること。
(4)入札書は必要事項を記入、記名押印(実印)のうえ提出用封筒に入札書のみを入れ、封をして裏面に社名、所在地、連絡先を記入し、実印にて割り印すること。
(5)開札は入札書の提出後ただちに行う事とする。
(6)談合等不正行為を行わない旨の誓約書を入札日当日に提出すること。
(7)入札にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違��する行為を行ってはならない。
(8)下記の各項目に該当する入札は無効とする。
①入札に参加する資格のない者がした入札
②郵便、電報、ファクシミリ等により入札書を提出した者がした入札
③談合その他不正行為があったと認められる入札
④虚偽の一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者がした入札
⑤入札後に辞退を申し出て、その申し出を受理された者がした入札
⑥次に掲げる入札をした者がした入札
ア 入札書に記名押印のないもの
イ 記載事項を訂正した場合において、その箇所に訂正印押印のないもの
ウ 押印された印影が明らかでないもの
エ 記載すべき事項の記入のないもの、又は記入した事項が明らかでないもの
オ 代理人で委任状を提出しない者がしたもの
カ 他人の代理を兼ねた者がしたもの
キ 2以上の入札書を提出した者、又は2以上の者が代理をした者
⑦前各項目に定めるもののほか、その他公告に示す事項に反した者がした入札
(9)入札に参加する者の数が1者の場合でも、入札を執行する。
11.契約方法等
(1)本契約の締結は当法人の理事会で承認を受けた後とする。なお、支払時期に関係なくすべての支払いについては消費税10%とする。
(2)契約保証金の徴収は免除する。
(3)落札決定から本契約までの間に自治体の入札参加資格の停止の措置を受けたものは、本契約を締結できない(契約辞退を申し出るものとする)。
(4)契約書の作成は落札者が行うものとする。
12.支払条件
(1)支払期日は、協議の上、契約締結時に決定する。
以上
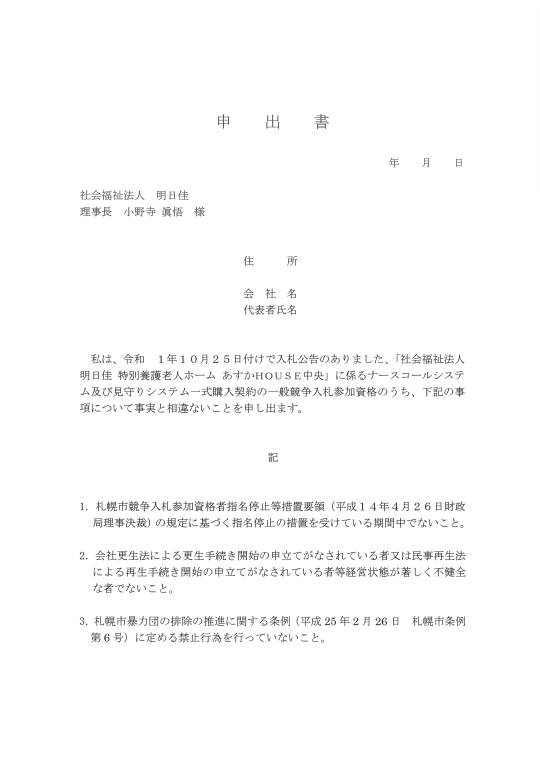

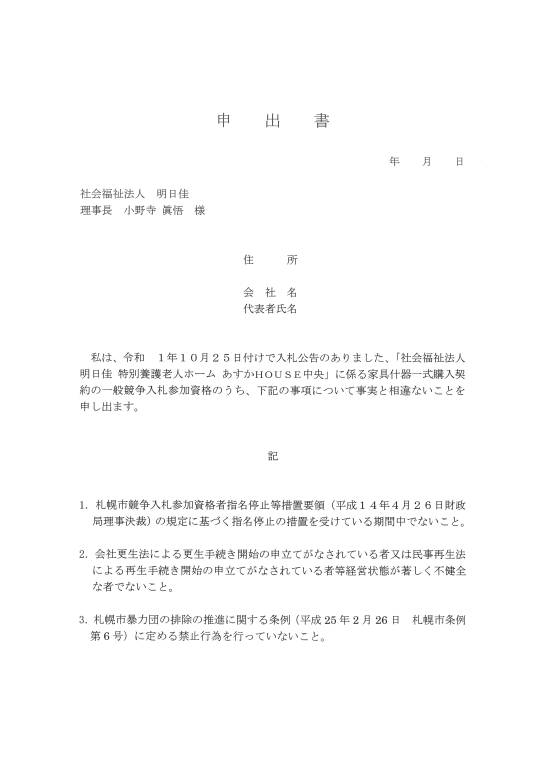
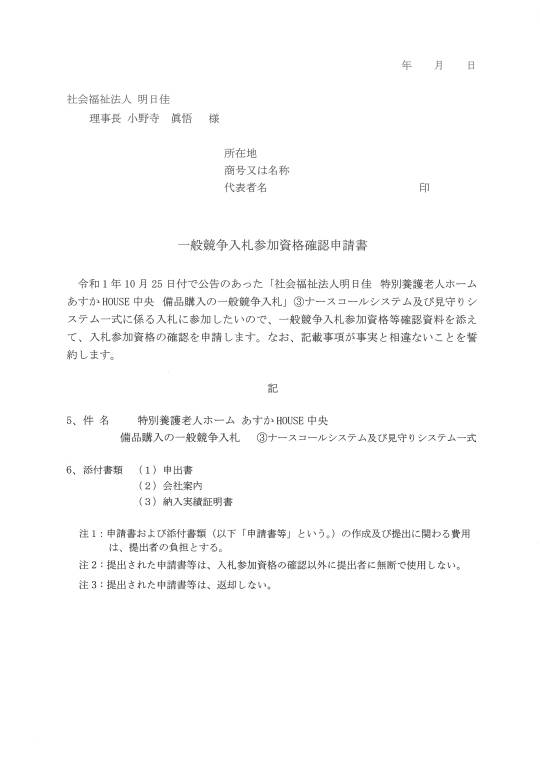
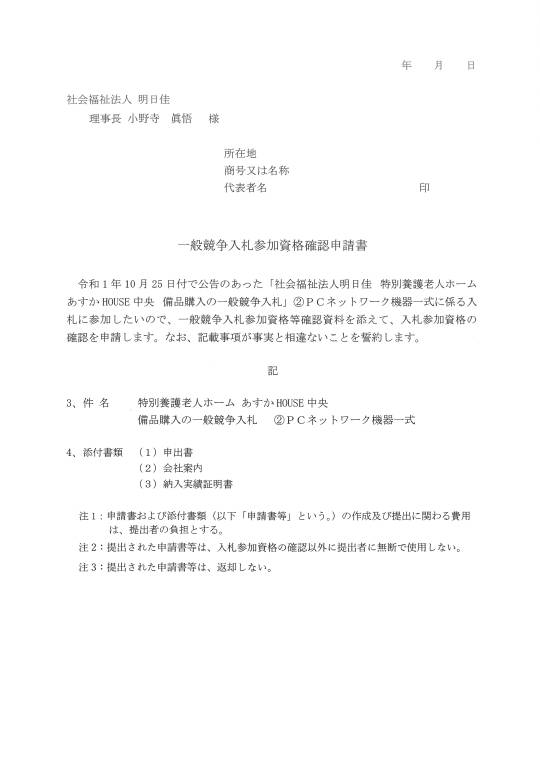
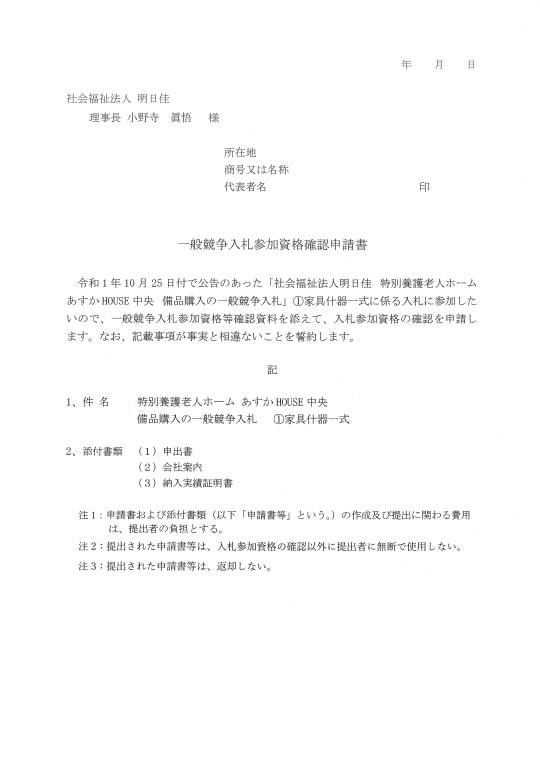
0 notes
Text
【新】《短期連載》フェイクニュースに騙されないた
めのノウハウ(1)
SNSによるフェイクニュースの急増
樋口敬祐(元防衛省情報本部分析部主任分析官))
───────────────────────
□はじめに
2022年10月~23年4月まで「ウクライナ情報戦争」
というタイトルでメルマガ「軍事情報」で連載しま
したが、その後の状況などを踏まえて続編を書きた
いと思います。
「ウクライナ情報戦争」シリーズでは、一般的に思
われているプロパガンダ戦、サイバー戦、心理戦だ
けではなく情報戦の概念を、幅広くとらえてロシア
とウクライナが情報戦をどう戦っているかを、その
時々のテーマを決めてアトランダムに連載してきま
した。
今回、ロシアのウクライナ侵攻から2年経過するの
を前に、それらの項目を再整理・加筆訂正して、ま
た今から連載する内容も含めて、『ウクライナとロ
シアは情報戦をどう戦っているか』という本にまと
めて2月初旬に出版することになりました。
『ウクライナとロシアは情報戦をどう戦っているか』
https://amzn.to/3SxjoWJ
この短期連載では、本の内容の追加部分を一部先取
りするかたちで「フェイクニュースに騙されないよ
うにする」を主要なるをテーマにして紹介したいと
思います。
さて、読者の皆様自身もまた周りの方々も、昔ほど
テレビを観なくなった、いや自宅にテレビすらない
という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
その実態が統計にも表れるようになりました。総務
省の「令和4年度情報通信メディアの利用時間と情報
行動に関する調査報告書」(2023年6月)によると、
平日の全年代(10~60代)のメディアの平均利用時
間は2020年度にテレビとインターネットの利用時間
が逆転し、その差は年々開いています。
そしてついに2022年度には休日における利用時間も、
インターネットの方がテレビを上回りました。
具体的には、平日における全年代のインターネット
の利用時間は1日に約3時間、テレビは2時間15分です。
ちなみにラジオは8分、新聞に至っては6分とイン
ターネットの約30分の1の時間しか利用されていま
せん。
ただし、年代別にみると50~60代ではインターネッ
トよりもテレビの利用時間の方がまだ多く、10~20
代が1日平均1時間のテレビの視聴時間に対し、3時間
20分程度と3倍以上になっています。ラジオ、新聞
の利用時間もほかの年代に比べれば多いという結果
になっています。
10~20代のインターネットの利用時間は、1日に4時
間近くにも及んでいて、若年層ほどテレビからイン
ターネットへとその利用時間が移行していることが
わかります。
インターネット利用のデバイスは、すべての年代で
パソコンよりもスマートフォン(スマホ)の利用が
多いのが実態です。スマホの中で利用されているコ
ンテンツは、LINE、YouTube、Instagram、X、Face
book、TikTokといったSNSが大きな割合を占めるよう
になってきました。(総務省データ)
SNSは、ソーシャルネットワーキングサービス
(Social Networking Service)の略ですが、登録さ
れた利用者同士が交流できるWebサイトの会員制サー
ビスのことです。
その特徴として、友人、同じ趣味、同じような考え
方を持つ人同士が集まることにより、ある程度閉ざ
された世界にすることで、密接な利用者間のコミュ
ニケーションを可能にしていることが挙げられます。
そして、SNSは多くの若者に活用されていますが、
その傾向は次第にほかの年代にも拡散しています。
SNSの利用率が特に高く、複数のSNSを使い分ける
ことが当たり前になっている10代(なかでも15~19
歳)のデータからは、いくつかの特徴が浮かび上が
ります。
テキスト主体のXの平日の利用時間帯は、7時、12時、
21~22時と3回のピークがあります。一方で、画像
主体のTikTokとInstagramのピークは21~22時の1回
のみです。
また、5~16時まではXの利用率が高く、16時以降は
TikTokの利用率が高くなっています。
ここから考えられることは、7時と12時の朝の通学
や昼休み時間帯といったちょっとした時間には、音
を聞かなくてもいいテキスト型が好まれ、自宅で夜
のゆったりした時間帯には画像や動画主体のSNS
が楽しまれているということです。
さらに20代までの世代は、商品やサービスをSNSで認
知する際に、一方的な企業側の広告よりも、インフ
ルエンサーの投稿でそれらを認知する傾向が高いと
いうデータがあります。(出典:di-PiNK アプリログ
2023年7月 15~19歳男女 時間別利用率(10代))
ロシア・ウクライナ情報戦においてもSNSが大い
に使われています。たとえば過去のメルマガ「ウク
ライナ情報戦争(2)(9)(12)」で述べたよう
に、ロシアの兵隊はSNSなどの不適切な使用により、
「大砲のウーバーシステム」を活用するウクライナ
軍から大砲の弾を落とされたり、ウクライナ市民は
カラシニコフの代わりにSNSで戦ったりしていま
す。
ところで、前述の調査にみられるようなテレビや新
聞などのメディアはオールドメディアと呼ばれ、イ
ンターネットやSNSなどに代表されるメディアはニュ
ーメディアと呼称されています。
そのニューメディアからの情報量は、爆発的に増大
してきています。
▼若者のインターネット利用の実態
ニューメディアはオールドメディアと違って、ジャ
ーナリストのような専門的訓練の経験がない人でも、
いわば誰でも情報発信できるため、誤情報が多いの
が特徴です。
2022年8月、米国の非営利調査機関(pew research
center)が13~17歳の若者を対象にインターネット
利用の調査結果を発表しました。結果は1位がYouT
ubeで95パーセント、2位はTikTokで67パーセント、
3位はInstagramで62パーセントでした。
TikTokは2017年以降、中国以外の地域でも提供が始
まり、2022年には13���17歳の米国の若者10人に6人
以上が使用したことがあり、若者全体の16パーセン
トがほぼ常時使用していると回答しています。
また、同センターによれば、かつて若者に支持を受
けていたFacebookを使用していると答えた割合は20
14~15年の調査の71パーセントから22年には32パー
セントへと急減しました。
▼TikTokの利用の急増とその問題点
この調査結果にみられるようにTikTokは若者の間で
急速に普及し、さらに伸びる傾向にあります。しか
し、それは中国発の動画共有アプリであるため、仕
掛けられたバッグドア(裏口)からユーザーデータ
に中国政府がアクセスしている可能性があると安全
保障上の問題が懸念されるようになってきました。
2023年3月27日、ホワイトハウスは、連邦政府機関
全体に対して30日以内にすべての公的なデバイスか
らTikTokを削除するよう命令を出しました。そして
5月17日、モンタナ州が個人用デバイスでのTikTok
を禁止した全米初の州となりました 。
ところが、モンタナ州の禁止令に強い反対運動が起
きました。5月23日、TikTokの運営会社はこの新法
について、合衆国憲法修正第1条が保証する表現の
自由に対する権利を侵害するとして州政府を訴えま
した。
米国自由人権協会(ACLU)も、この禁止令は違
憲であるとする声明を発表しています。
11月30日には、米連邦地方裁判所が、モンタナ州が
2024年1月としていた法律の施行の仮差し止めを命
じました。TikTokの運営会社の意見を認め、アプリ
の利用制限は住民の自由を損なうと判断したそうで
す。ただし、11月の命令は差し止めを最終的に決め
るものではなく、訴訟は継続するようです。
実際のところ、一般人への法律の施行は難しいため、
連邦レベルでTikTokを禁止することには疑義が生じ
ているのが現状です。
ところでTikTokには次のような特徴があります。
短尺動画を投稿/共有できるサービスである。
アプリ内で動画の撮影・編集・投稿が一貫して行な
えるので、ほかのプラットフォームで短尺動画を投
稿するよりもユーザーにとって利便性が高い。
おすすめ機能で好みに合ったコンテンツが簡単に見
られる。
ユーザーは動画を探す手間なく、好みの動画を次々
と視聴できる。おすすめ機能はYouTubeなどほかのS
NSでも取り入れられているが、TikTokはその精度
が特に高いとされている。
ダンス、コスメ、グルメ、ハウツーなどさまざまな
ジャンルがある。
このような特徴は、特にZ世代に受け入れられやす
いため利用者が急増したと思われます。米国におけ
る規制の動きとは逆に、今後はほかのSNSの普及
過程と同様に、若者からそれ以降の世代に広がって
いくでしょう。
ところが、このように誰でも手軽に投稿できるうえ、
短い動画が多いことも要因となりTikTokには誤情報
が多いという問題が指摘されています。
2022年9月、信頼性を評価する米メディア監視組織
「ニューズガード(News Guard)」は、TikTokに関
するレポートを公開しました。それによると、新型
コロナウイルス感染症、ウクライナ侵攻などを検索
すると、「上位に出てくる動画の19・5パーセント
に、誤情報または誤解を招く主張が含まれている」
という結果でした。
ニューズガードによる調査は、検索機能で上位に表
示される動画の真偽を確かめたもので、話題性の高
いキーワードを選び、それぞれ上位20位までの動画、
計540本の内容をファクトチェックしたところ、5本
に1本に相当する105本に疑義があったというのです。
▼日本でもTikTokが急増
このようなTikTokの傾向は日本でも同様です。2023
年6月に出された総務省の「令和4年度情報通信メ
ディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」
によると、10代の使用頻度は、1位がYouTubeの96・
4パーセント、2位はInstagram70パーセント、3位
はTikTok 66.4パーセントとなりました。米国と同じ
ように10人中6人以上がTikTokを利用しています。
さらにTikTok動画の真偽についてもニューズガード
の調査と同様の傾向が見られます。
宮崎県都城市総合政策部デジタル統括課が運営して
いるウェブメディアの「ThinK都城」の記事に
よれば、
「新型コロナワクチンとTikTokで検索すると日本語
コンテンツの上位に『新型コロナワクチン打ちます
か?』と題した動画が出てきたといいます(2022年
11月末の検索)。
その動画では、『昨年末、全国の医師約7000人を対
象に実施したアンケートで、ワクチンを摂取したい
と回答したのは何パーセントでしょうか? じつは
たったの35パーセント。また30パーセントの医師は
受けたくないと回答。その理由の圧倒的1位はワク
チンの安全性がまだ確立していないから……』と薬
剤師がテンポよく語ります。(中略)この動画に対
して『いいね!』の数は2638件。
しかし、その薬剤師が根拠としている調査を確認す
ると、『早期にワクチンの接種を受けたい』と回答
した医師が35パーセント、『早期に接種を受けたく
ない』が30パーセントで、TikTokの動画では『早期
に』の表現が抜けていました」
そして、同記事には「仮にニューズガードがこの動
画を検証したとしたら、『誤解を招く』と判断する
可能性は高い」とあります(同記事で紹介された動
画「1分でわかるTikTok健康講座 新型コロナワク
チンに関する情報」は2021年2月16日に投稿)
このようにスマホを媒体としてSNSによる情報は
爆発的に急増し、特に戦争下における偽情報の拡散
は凄まじいものがあります。
次回は、ニューメディア時代の新たなバイアスとそ
の危険性について述べたいと思います。
(つづく)
(ひぐち・けいすけ)
4 notes
·
View notes
Text
「(仮称)川崎市 差別のない人権尊重のまちづくり条例案」に、実効性ある内容を求める意見書
2019年5月22日
川崎市長・福田紀彦様
この意見書は2018年3月に「ヘイトスピーチを許さないかわさき市民ネットワーク」が貴職に提出した「実効性ある人種差別撤廃条例の制定を求める意見書」を基に、改めて標記条例案の制定に向けて修正し、必ず盛り込んでいただきたい内容を加え、その実現を要請するものです。
ヘイトスピーチを許さないかわさき市民ネットワーク
代表:関田寛雄
〔要請1〕前文において、川崎市の多文化共生政策の経過を確認し、さらに人種差別撤廃条約などの国際人権諸条約や「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(以下、ヘイト解消法と略す。)の理念を踏まえたものであることを明記すること。
(理由又は説明)
・川崎市は、1970年代から取り組まれた在日コリアンの民族差別撤廃運動を真摯に受け止め、外国籍市民と共に、国に先駆けて多文化共生政策を推進してきました。この歴史を踏まえ、川崎市政の基本政策として、人権施策を推進することを前文で宣言してください。
・ヘイト解消法成立時の衆参の法務委員会決議には人種差別撤廃条約の精神に沿うことが明記されています。差別禁止を求める国際的な人権諸条約の主旨を前文に明記することにより、禁止規定と制裁条項を備えることの法的根拠が明確になります。
〔要請2〕差別の定義は差別的取扱いのみならず差別的言動を含み、その内容は人種差別撤廃条約、女性差別撤廃条約、障がい者権利条約に共通する次の定義(人種、性、障がいなどに基づく)「区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するもの」とすること。
(理由又は説明)
・条例骨子案では「不当な差別の定義」が「・・・取扱い」に限定されて、別に「差別的言動」の定義があります。しかし、差別的言動、いわゆるヘイトスピーチも差別の一類型であり、国際人権法も法律上も、差別は「取扱い」と「言動」の両方を含んでいます。
・差別の定義として、日本も批准し発効している上記の三つの条約に共通する定義があるので、これを採用してください。それにより、差別的取扱いのみならず差別的言動が含まれること、差別目的がなくとも差別の効果が生じるものも差別に該当することが明確になります。また、条約上の定義を使うことで、国際人権基準に基づく差別の具体的な定義が明確になり、ガイドラインの作成などに活用することができます〔東京弁護士会人種差別撤廃モデル条例案(以下、東弁モデル条例案と略す。)第2条の2の定義参照〕。
・条例骨子案の定義では「差別的言動」について、ヘイト解消法第2条の定義と同義としていますが、同法の衆参法務委員会の附帯決議では、ヘイトスピーチの対象者は「本邦外出身者及びその子孫」に限定されないとし、2016年5月26日付け参議院法務委員会「ヘイトスピーチの解消に関する決議」では難民申請者や非正規滞在者も対象とすべきことが明記されています。
・また、2018年の国連人種差別撤廃委員会総括所見では「同法の定義は狭すぎ、条約が対象とする"全ての者"に対するヘイトスピーチが適切に対象に含められる」よう勧告しています〔パラグラフ第14(a)〕。さらに、本年4月に成立した「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」の国会審議や附帯決議においても、アイヌの人々に対するヘイトスピーチも差別禁止条項の対象であることが明らかになっております。
・したがって、条例ではヘイト解消法の定義を超えた対象を包含すべきです。
〔要請3〕包括的な差別禁止・人権尊重に加え、特にヘイトスピーチを含む人種差別の禁止については、実効性を持たせるよう、何が差別に当たるのか、明確で具体的な禁止条項を置くこと。
(理由又は説明)
・今回の人権条例の最も大きな立法事実であるヘイトスピーチをはじめとする人種差別は、市民の尊厳を傷つけ、日常生活も不安な状態にし、市民の間に分断を持ち込む深刻な事態をもたらしていることから、最優先の禁止すべき重要課題です。
・実効性を持たせるためには違反した場合の制裁規定を設ける必要がありますが、そのためには、何が禁止の対象となるのか明確で具体的な規定を置くことが前提になります。
・また、特に差別的言動の禁止については、濫用を防ぎ、本来の表現の自由を守るためにも禁止規定はできる限り具体的、明確に定める必要があります。
・具体的な差別禁止条項については東弁モデル条例案の第5条の条文を参考にしてください。
・1963年に採択された「あらゆる形態の人種差別撤廃に関する国連宣言」第1条の「人種、皮膚の色又は種族的出身を理由にする人間の差別は、人間の尊厳に対する犯罪」であるという認識を踏まえ、差別は犯罪であるからこそ禁止し、終了させなければならないことを明記してください。
〔要請4〕ヘイトスピーチを含む人種差別については、刑事罰を含めた制裁規定を置くこと。
(理由または説明)
・条例違反者に対しては、実効性を確保するため、氏名公表、命令違反の場合の過料、違反者が市長・市議会議員・公務員等の公職者の場合は、懲戒規定の対象とする、業者の場合は市との業務委託から外すなど、実効性のある制裁措置を設けてください(東弁モデル条例案第26・27・28条参照)。
・執拗にコリアン市民への差別を扇動し攻撃するヘイトスピーチを繰り返している人たちは、差別目的の団体をつくり、選挙運動の名を借りてまでヘイトスピーチを行う確信犯です。市民がその都度抗議活動を行っていますが、それだけでは止めることができません。
・差別扇動が繰り返された結果、2018年6月のヘイト団体の集会直後、市内の公園のベンチなど50カ所以上に差別落書きが書かれるヘイトクライムが起きています。差別・暴力の扇動は犯罪であり、刑事規制で阻止しなければコリアン市民への現実の暴力へ直結してしまいます。人種差別撤廃条約が国及び地方自治体に対して、刑事規制を求めている理由はそこにあります。
・特に生命、身体等に対する害悪の告知、憎悪・排除の扇動、著しい侮蔑などの悪質なヘイトスピーチに対しては、これ以上、川崎市内で繰り返させないために、罰金などの刑事罰を設けてください。
〔要請5〕市民が市に対して、ネット上のヘイトスピーチについて削除要請ができる制度やネットモニタリング制度などのインターネット上のヘイトスピーチ対策の強化を明記すること。
(理由または説明)
・ヘイトスピーチ根絶に向けて市が責任を持ち、インターネット上のヘイトスピーチ対策を積極的に担ってください。
・市民が直接管理業者に削除要請をしてもすぐに対処してくれないのが現状ですが、公的機関が要請すれば、削除される確率が高くなります。また、市が業者と直接交渉を担うことにより、差別に傷ついている市民の負担が軽減されます。特に、不特定の集団に対するヘイトスピーチは、個々人が削除要請をしても削除は難しく、不特定の集団に対するヘイトスピーチについても、市民から市への削除要請も受け付けてください。
・ヘイトスピーチを匿名者が行っている場合、市が発信者に制裁を行うため、もしくは被害者救済の手助けとして、発信者情報を運営者に求めることができるよう条例上の根拠規定を置いてください(東弁モデル条例案第15条参照)。
・削除要請については、専門家及び被害当事者の協力を得て、判断基準や運営方法等を含むガイドラインを至急作成してください。
・市民の個別の要請がなくとも、市はヘイトスピーチに関するネットモニタリングを行い、ヘイトスピーチを発見した場合は、管理業者に削除要請をしてください。
・市の職員の誰もがネットモニタリングを行えるよう、全職員にヘイトスピーチに関する研修を行ってください。また、膨大な量のヘイト書き込みに対処するため、モニタリングの担い手として第三者機関に協力を求めることも検討してください。
・モニタリングの結果や、削除要請した書き込みとその要請した結果を定期的に公表してください。
〔要請6〕学校教育・社会教育における人権教育の推進を規定する条文を明記すること。
(理由又は説明)
・人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身を理由に差別や不利益を受けることがないよう、子どもの置かれている状況に応じ相談できる環境づくりを推進するとともに、家庭や地域、学校などにおいて、子どもの権利保障に必要な支援を行うことを定めてください。
・全ての市民が違いを認め合い、共に生きる社会を作るため、市民、行政、事業者それぞれに対して意識啓発を進めるとともに、内外に開かれた地域社会づくりを促進することを定めてください。
・新たな条例制定の目的と趣旨を広く啓発するため、教職員の研修課題とし、また、小学生、中学生、高校生、市民を対象とした副読本、啓発冊子を作成するなど、具体的な事業を明記してください。
〔要請7〕人種差別による被害救済、人権侵害の審査、認定、救済措置などを判断する第三者機関を設置し、申立てをしやすくするため市民通報制度を制度化し、区役所に相談窓口を設けること。
(理由又は説明)
・川崎市のこれまでの外国人市民施策や「川崎市多文化共生社会推進指針」、「人権かわさきイニシアティブ」には人種差別に関する救済手続きがなく、その実効性が問われていました。差別禁止規定があっても被害者がその都度、裁判に訴えなければならないのなら、ほとんどの被害者は泣き寝入りを余儀なくされ、条例は「絵に描いた餅」になってしまいます。
・人種差別の被害者などが速やかに、安心して相談・救済の申し立てを行うことができるよう、窓口を明確にし、充実するために各区役所の区民相談窓口に「人権相談」を設置してください。
・ヘイトスピーチを含む人種差別について、被害者本人が申し立てをするのは大変な負担になります。差別のない川崎を市民がつうくるために被害者のみならず、市民誰でも通報できるよう、市民通報制度を明記してください。
・第三者機関の委員には、人種差別の撤廃に関する専門家のほか、人種差別問題などに取り組んできた団体や当事者性を有する市民の枠を設けてください。
・市は審議会の意見または決定と異なる措置をとる場合は、その理由を必ず公表してください(東弁モデル条例案第25条参照)。
・現行の川崎市人権オンブズパーソン条例では、第2条〔管轄〕では、管轄を子どもの権利侵害と男女平等に関わる人権の侵害に関する事項と限定しています。新条例の制定に伴い、人種差別オンブズパーソンを新たに設置などの見直しを求めます。
〔要請8〕市民とともに築く「多文化共生社会」の実現を明記すること。
(理由または説明)
・人種差別撤廃に関する自主的な活動を行う民間の団体などが果たしている役割の重要性に留意し、これら民間団体等の活動を支援し連携・協力するために必要な措置を講じるよう定めてください。
(東弁モデル条例案第17・18条参照)。
〔要請9〕条例に人種差別目的の場合の公的施設利用に関する条項を置き、それに沿って現行のガイドラインを改正すること。
(理由または説明)
・公的施設利用許可の申請があった場合、差別的行為を行うことを目的とするものと疑うに足りる十分な理由があると認められるときは、警告、条件その他制限をつけて許可することとしてください(東弁モデル条例案第29条2項、東弁意見書参照)。
・差別的行為を行うことが利用目的であることが判明したときは、市長は、利用許可申請を許可してはならず、または上記の当該許可を取り消さなければならないとしてください(東弁モデル条例案第29条1・3項参照)。
・施設利用の申請につき、施設管理者が一見して明らかに人種差別目的ではないと認定しうるとき以外は、必ず専門家からなる第三者機関(現行では川崎市人権施策推進協議会・ヘイトスピーチ部会)の意見を聴くようにしてください。特に、市民から人種差別目的ではないかとの調査要請があった時は、必ず専門家からなる第三者機関の意見を聴かなければならない制度にしてください(東弁モデル条例案第30条)。
・これらの条例の内容と合致するよう、現行のガイドラインの不許可要件としての「迷惑要件」を削除し、手続きを改正してください。
・市の全職員だけではなく、指定管理事業者、委託事業者など全施設管理者がヘイトスピーチについて判断できるよう、毎年、研修を実施することとしてください。
〔要請10〕ヘイトスピーチ・差別事例を調査・収集し、人種差別撤廃に向けた行動計画を策定すること。
(理由又は説明)
・市は、差別や人権侵害事件が生じたことを把握した場合、必ず、調査を行い、記録し、プライバシー保護に留意しつつ、差別の実態を市民に明らかにするようにしてください。
・差別被害の実態調査を定期的に行い、調査結果を公表することを市に義務づけてください。
・毎年、市議会に対し、課題ごとに差別の現況及び差別撤廃のために講じた施策について年次報告書を作成・提出することを明記してください。
0 notes
Text
聴講メモ <法と技術シンポジウム(第2回)> コネクティッド カー(Connected Car)と プライバシー・個人情報保護
聴講時に入力したメモです。断片。配布資料等からのメモも引用符はありません。
聞き取り間違い等、あります。おかしな部分は記録者のせいです。
開催案内 https://rikenaip20180219.peatix.com/
主催 理化学研究所 革新知能統合研究センター(AIP)
共催 KDDI総合研究所/一般財団法人情報法制研究所/新潟大学法学部
後援 東京大学 情報基盤センター/情報法制学会(ALIS)/NTTセキュアプラットフォーム研究所
日時 平成30年2月19日(月)10:00〜17:00
会場 一橋講堂
総合司会 生貝 直人 理化学研究所 革新知能統合研究センター(AIP) 客員研究員
情報通信総合研究所 研究員・東京大学 客員准教授
10:00〜10:05
開会挨拶 杉山 将 理化学研究所 革新知能統合研究センター センター長・東京大学教授
理研AIPセンターの紹介
理化学研究所法 第3条 人文科学のみに関わるものを除く
→AIに関わるものはOK
次世代基盤技術開発
サイエンスを発達
社会実装に貢献
倫理・社会的課題への対応
人材育成
目的志向基盤技術開発グループ
汎用基盤記述研究グループ
社会における人工知能研究グループ グループディレクターは中川先生
AIPセンターはコレド日本橋にある。
AI研究は分離の垣根を超えた交流が重要
10:05〜10:35
報告1「コネクティッドカーとは何か」
コネクティッドカーを取り巻く国際的な制度状況の外観
加藤 尚徳 KDDI総合研究所 アソシエイト・情報法制研究所 研究員
資料は後日、web上で公開とのこと。
コネクティッドカーとは何か
センサで取得したデータを集積・分析する
緊急通報 盗難車両の追跡 等々
エンベデッド型
テザリング型
モバイル連携
自動走行車との関連性
自動走行車では安全性を高めるためにコネクティビティを付加することが不可欠
日本は保有台数は横ばいだが機能搭載は伸びていくとの予測
安全・安心
遠隔診断 運行管理 等々
テレマティクス自動車保険
プライバシー保護に関するこれまでの国際動向
2014年10月 ドイツ 自動車におけるプライバシー決議
プライバシーデフォルト データの最小化 データ主体の関与 等
2014年11月 米国自動車協会とグローバル・オートメーカ協会
欧州自動車協会
透明性 顧客の選択の自由 データ保護 セキュリティ パーソナルデータの性質に応じた処理
通常の個人情報保護における議論よりも広い内容になっている
2014年4月 FIPA コネクティッドカーに関するレポート(カナダ)
カナダのプライバシーコミッショナーオフィスの援助あり
各社のポリシー、約款と制度の適合性を分析、評価
考慮すべき項目
パーソナルデータの利用について情報開示
黙示の同意 オプトアウト
取引拒否
不必要なデータの収集への同意を禁止する
普段の生活に欠かせないツールに関して同意を強制することがあってはならない
北米地域のメーカのポリシーはカナダ法の求める水準を満たしていない。
AAMの原則
「合理的」の範囲が不明確
開示性、透明性が不十分
目的の明確化の通知が不十分
目的の制限は一部、顧客の選択の余地なしに利用されるものあり
収集制限に言及なし
保持期間を任意に設定
同意なしの収集が行われ得る/行われている
2017年プライバシーコミッショナー会議における決議
コネクティッドカーに関する2017年決議
自動化され接続された車両のデータ保護に関する決議 あり
DPAが各メーカ等にPbD×2を考慮するよう求める
CNIL
コネクティッドカーにおける責任あるデータ利用に向けた法令順守パッケージ
2017年公開、2018年英訳公開
Connected vehicles: a compliance package for a responsible use of data
https://www.cnil.fr/en/connected-vehicles-compliance-package-responsible-use-data
米GAOによる車両データプライバシーレポート
AUTOMATED VEHICLES:
Comprehensive Plan Could Help DOT Address Challenges
https://www.gao.gov/products/GAO-18-132
10:40〜11:05
報告2「コネクティッドカーと刑事規制」
深町 晋也 立教大学教授
IoTの端末としてのコネクティッドカー
大きなリスク
外部からのハッキングによる本来想定されていなかった行動をさせられるリスク
その結果として生じた損害に対する責任
不正アクセス禁止法3条の適用は? 解釈問題
過失犯処罰との関係
ハッキング実行者については故意犯の成立も
脆弱性の放置、情報収集義務についてどのような責任を問われるのか
システムが期待された動作をしなかったことによる損害への責任
コネクティッドカーの脆弱性と刑事責任
情報にゴミを混ぜて支障を生じさせる
ドライバーの責任は?
地図情報に虚偽の情報を混入させ一方通行に誤侵入→ドライバーの前方注意義務履行で回避可能と判断される場合が多いのでは。
バグによる事故 業務上過失致死傷罪
未知の脆弱性のハッキング
存在を人が認識しえたか。
専門家集団においても知られていないような脆弱性
予見可能性、認識可能性を認められない
既知の脆弱性
通常の自動車の欠陥放置と同じ。
コネクティッドカーの情報収集義務
ドイツ エリック・ヒルゲンドルフ教授の挙げた例
心臓発作のドライバーを載せたまま、直行し、人に突っ込む
予見可能性がメーカーには無かったと判断される。
ドライバーの健康観察装置があり、安全停止装置があれば起きなかったのでは。
自動走行車の刑事責任
環境をモニタリングするのはレベル3以上
レベル3では人間の刑事責任が問題になる。
いつオーバーライドが起きるか。
ドライバーに自動走行時にも通常と同様の注意を求めるべきか。
信頼の考慮
レベル3自動走行車のドライバーに義務を課すならば、設計時に注意喚起の機能を組み込むべき。
過失犯の適切な適用
11:10〜11:35
報告3「コネクティッドカーとドイツの政策動向」
寺田 麻佑 理研AIP客員研究員・国際基督教大学准教授
総務省 Connected Carの実現に向けた研究会(2016.12~2017.7)
欧州レベルの取組み Horizon2020
フォルクスワーゲンとLG電子の共同開発
5GAAの動き
ドイツにおける法制度化
2017年6月 改正道路交通法施行
対人・対物賠償の最低基準引き上げ
オーバーライド用政治のアラート基準
自動運転円卓会議
2014年から検討開始
2015年9月 「自動化され、かつ、ネットワーク化された運転の戦略」
アウトバーンA9号線でテストデータ収集
2016年 試験走行の中間報告
フランスに通じる道路でも実験
2017年6月 改正道路交通法施行
交通デジタルインフラ省が主導
2016年7月 自動運転に対応するための道路交通法改正草案作成
2017年1月25日 道路交通法改正草案を閣議決定
2017年2月20日に連邦議会提出
2017年6月21日 改正道路交通法施行
連邦参議院付帯意見 自動運転中の自己における製造者の責任等
データ保護の利益が考慮されているか 倫理委員会勧告が考慮されているか
ドイツ改正道路交通法
人が最終的な責任を負う
ブラックボックスに記録されたデータに基づき、システムの製造者の損害の賠償責任について決定される
倫理指針の検討
2016年9月30日
法学者、哲学者、社会科学者、技術の評価者、消費者関係者、自動車産業やソフトウェハ開発者等
人命最優先
ドライバーは、自身のドライビングに関するデータに関する利用や共有について、基本的に決定することができなければならない。
ドイツにおける連邦データ・情報保護観察官の13の勧告
2017年6月1日
どのようなパーソナルデータが車の利用者の合意なしに収集されるのかについて明確に知らなければならない
倫理規則はプログラムの設計にも関係してくる
11:40〜12:05
特別講演「コネクティッドカーの技術的課題 -機械学習とプライバシー保護-」
中川 裕志 理研AIP社会における人工知能研究グループディレクター・東京大学教授
Connectedが先か、AIが先か?
web経由は危ないし遅い 車車間通信は速い プロトコル統一が必要
つなぐ相手の認証 セキュリティ大事
AIとconnectedの相互作用
高度なセキュリティチェックが必要
ネットワークの脆弱性
100%の防御は不可能 破られたときの早期発見、早期原状復帰の方策に重点
走行中に対応の遅れは許されない
対応速度の速い異常値検出技術が必須→AI 機械学習
総務省 AIネットワーク推進会議
単独のAIからネットワーク環境での倫理指針へ
センシングvs運転走行ポリシー
データの意味を与えておかないと機械学習は使えない
モバイルアイ社曰く
未来の事象を予測し、対応する技術
その場その場で学習結果のモデルを変えていく
強化学習が有用
車の安全走行はハードウェアだけの問題か?
動作の即時性の要請が厳しいので、connectedで中央サーバと通信して解決というわけにはいかない
近接車との車車間通信が利用できるとベスト
昔からの知恵だと
安全性は統計量によって決まる
んが
モバイルアイ曰く それは間違っている
膨大な時間のデータが必要になる→無理無理無理無理かたつむり
外部環境データ自動生成
安全性はモデルベース、解釈可能、説明可能な方法であるべき
運転履歴、運転車・搭乗者データ(位置データ)に関して考慮すべき事項
どのようなデータがプライバシーほごをりゅういすべきか
走行中に得られたデータをどの国に設置されたサーバに保存するか
収集した膨大な走行履歴、運転車・搭乗者データを収集したサーバから越境移動→現実的はないかも
仮名化、匿名化但し、この処理だけではEUからの持ち出しは不可
統計処理、機械学習したモデルは移動可能かも。
ルール化されたモデルを統合するのは難しい。
運転者、同乗者、歩行者のプライバシー保護
運転者は同意とることも可能だが、同乗者は難しい。
走行情報の匿名化収集 リアルタイム性に課題
周囲の車が拒否モードだとどうなる?
つながっていると個人特定性があるが、バラバラにしてシャッフルしたらどうか。
顔画像のプライバシー保護
同乗者の顔認識の問題
車外の人の顔画像は?
IoT推進コンソーシアムの利用基準
12:05〜13:05 休憩(昼食)
13:05〜13:30
基調講演「データ保護・プライバシー・コミッショナー国際会議とコネクティッドカー(関連の論議も踏まえて)」
堀部 政男 個人情報保護委員会委員長・一橋大学名誉教授
国際会議の決議はそれぞれの国等で執行する際の準則的意義を有する。
コネクティッド車両関連の取り扱いに伴う、法的安定性の順守ツール開発のための、データ保護・プライバシー・コミッショナーとの対話の開始
IWGDPT(Berlin Group)
The International Working Group on Data Protection in Teleommunications
情報通信データ保護国際作業部会
次期議題 コネクティッドカー
(財)日本自動車研究所におけるプローブ情報システム個人情報保護検討の例示
2002年「プローブ情報サービスにおける個人情報保護に関するガイドライン」案策定
2003年 プローブ情報システムにおける個人情報保護ワーキング
2006年12月19日 自動車と個人情報保護ワークショップ
慶応大学SFC主催
ISO 24100:2010 Inreligent transport systems
ワシントンポスト記事 2018/1/15 Big Brother on wheels
13:35〜14:00
報告4「コネクティッドカーとプライバシー保護」
平林 立彦 KDDI総合研究所 主席アナリスト
消費者にとっては価格も重要 引き換えに 燃費が良くなる、メンテナンスコストが下がる などあるか
個人のリアルタイムデータ、プライベートビッグデータ、ソーシャルビッグデータを組み合わせたサービス向上
前2者はプライバシー情報
ISO/IEC 29100:2011 プライバシーフレームワーク
大事な点 同意と選択
個人データは絶対出したくない人が2割、約8割は条件付き容認派
条件:情報提供をいつでも自分で停止可能
利用目的の事前説明
提供情報項目の説明
相手先や状況に応じた情報粒度変更
提供情報の種類・項目毎の詳細設定
コネクティッドカーにおけるぷ保護対策の課題
課題1 一般ドライバーの受容性を高める情報収集形態
課題2 状況変化に対応した情報提供可否設定の変更
課題3 マルチユーザ・マルチユース環境での利便性確保
1,2は国民性、法制度によって変わる可能性あり
情報提供可否設定UIプロトタイプ(総合パネル)
PCのコンパネのようなもの
ビジネス展開上の課題
収益性
消費者が許容しうるパーソナルデータのてんばい
費用の抑制
ユーザのプライバシー設定負荷軽減
リスク低減
プライバシー保護レベルの第三者あるいは公的評価(PIA)手法の導入
PARMMITについて
プラットホーム間の相互接続
プラットホームをまたがる同意取得
14:05〜14:30
報告5「コネクティッドカーと個人情報保護法」
藤村 明子 理研AIP客員研究員・NTTセキュアプラットフォーム研究所 主任研究員
企業側 個人の行動や状態を不空データは利用価値が高い
ユーザ側 企業側へデータに対する高い安全安心を求める
法令リスク 不適切な取り扱いや理解不足等から法令違反になるリスク
緊急通報システム
例外 法令に基づく場合
残されている課題:「本人」の問題から
「本人」は誰か
搭乗者(データ主体)のデータと車両のデータ
ハイヤーの取得情報
蓄積されて唯一無二のデータになる→個人情報
商用車の運転手でも同意取得はした方が良い
運送契約の約款等で解決できるか
HEMSデータ
同意取得に問題がある場合 「匿名加工情報」「統計情報」として活用
スマホの位置情報は個人と結びついている。コネクティッドカーは複数人と結びついている可能性
何が個人情報で、何がそうでないかという判断の重要性。知らない/誤ることはリスク
14:35〜15:00
報告6「コネクティッドカーと越境データ問題」
板倉 陽一郎 理研AIP客員主管研究員・弁護士
自国内で行う活動については国内から出すなという方の規制(データローカリゼーション)
自国内の産業振興や安全保障の観点から。本人同意をとっても移転できるとは限らない。
従来の越境データ移転制限はデータの移転そのものを制限
(少なくとも欧州は)人権保障が目的
規律は一律ではない 欧州は「越境の移転」を、日本は「外国にある『第三者』への提供」を制限。同一法人間移転に差異。
データローカリゼーション
ロシア 2016年から施行 ロシア国民にサービス提供の場合はロシア国内に
中国 重要情報インフラストラクチャの運営者
2017年9月 WTOに文書
TPPにおけるデータローカリゼーション規制
第三者に渡すか 支店に渡すか 現地法人に渡すか
標準契約約款の準拠法はデータの出どころの国の方
15:00〜15:15 (休憩)
15:15〜16:55
討論「コネクティッドカー・ビジネスでのプライバシー・個人データ保護における協調領域/競争領域」
(省略)
16:55〜17:00
閉会挨拶 中島 康之 KDDI総合研究所 所長
コネクティッドカーで目指す世界は安心安全便利簡単。その為に必要な解決すべき課題と解決策の検討を。
0 notes
Link
ホワイト国から除外を決定する前日において、とんでもない情報が飛び込んできた。
なんと慰安婦像を、税を投じて日本国内で展示したという。舞台となったのは、あいちトリエンナーレ2019。公式ホームページによると、『2019年は、国内外から90組以上のアーティストを迎えます。国際現代美術展のほか、映像プログラム、パフォーミングアーツ、音楽プログラムなど、様々な表現を横断する、最先端の芸術作品を紹介します。』とのことだが、その中身がとんでもない。
”国際現代美術展”の中身だろうか、なんと”慰安婦像”が展示されている。
また、”映像プログラム”のようだが、昭和天皇の御真影を焼く映像まで公開されている模様。この点については、和田参議院が確認をとるとtweetしている。
当該イベントは、芸術祭であるが、芸術監督としては津田大介氏の名前がある。事実上の総責任者のようだ。愛知県の大村知事も、よくわからないポーズを共に行って写真を投稿している。
県が主導する以上、愛知県および名古屋市の税金が投じられている。
さらには、文化庁の助成事業とのこと。なんと国費まで投じられるという状況だ。
これは、大村知事に辞表を書いて頂くような流れになるように思う。
むしろ知事が自発的に辞職することが最も軽傷であるとすら思えるのだ。大村知事自身が一番わかっているだろう。国会議員5期の経験および政務官、副大臣を歴任、また県連会長も経験。のち自民と離反、旧・日本維新の会の顧問も務めた。意味はわかると思う。
慰安婦像の展示を、税を投じて公式に行うということは、我が国の外交に想像以上のダメージを与える。海外のアーティストを招いての舞台となれば、どれほど韓国に悪用される想像するまでもない。税を投じて行うということは、我が国の公共団体が公式に認めたという意味になる。
事実として、ハンギョレが報じ、Yahoo!ニュースに転載されている。また、本事業で”慰安婦像”が展示されていることは朝日などが好意的に報じた後だ。取り返しがつかない。
すでに像の撤去うんぬんではなく、この芸術祭は中止せざるを得ないレベルになるように思う。津田氏らの論調や行動に思うことはあるが、私の矛先は今はそこにはない。ああだこうだという、いわゆるイデオロギー的な言論を行える状況にはなく、ダメージコントロールに奔走すべき状況だ。
最終的には、文化庁を経由して支出された国費(もしくはこれから交付されるのか?)は国庫に返納して頂きたい。文化庁は文科省の所掌であるが、最終的なジャッジは柴山文科大臣が行うこととなる。慰安婦像を展示する事業に、国費を投じることを是とする判断を行うとは考えにくい。
明日には確認がとられると思うが、昭和天皇の御真影を焼く映像まで公開されていたのであれば、「国費投入は、文科大臣の責任問題」まで行く。
また、中止となった場合には、県税(愛知県)や市税(名古屋市)においても、返還訴訟なども可能であろうと思う。
愛知県議会、および名古屋市議会は、知事および市長を議会の場で追及すべきだ。そして、そうなるだろう。実際、愛知県内の市議(あま市の森議員)がBlogで発信している。
最終的なダメージコントロールで考えると、(本事業の即時停止のち)「知事の自発的な辞任」が最も軽傷であると考える。恐らく盟友関係になる維新の松井市長が”知事も知らなかった”旨の、火消しなのかな?と思われるtweetをしていたが、巻き込まれて炎上しただけだった。
すでに取り返しがつかない事態である。
私は、芸術祭そのものを全否定する立場ではない。この日のために一生懸命、作品を作ってきた者もいるだろう。けれども、これはダメだ。
本イベントの事務局の連絡先を公開する。
かつ、有効と思われる電凸先を掲示したい。
イベントの事務局は、県職員も配置されているかも知れないが、基本的には企業に外注だろう。
となれば、愛知県に直接、および名古屋市に直接、抗議したほうが効果は高い。また指導を求めるならば、文化庁に直接抗議し国費の支出を止めること。
(愛知県)
代表電話:052-961-2111
知事室 :052-954-6000
県議会事務局:052-954-6730
(名古屋市)
代表電話:052-961-1111
市議会総務課(庶務係)052-972-2083
協賛企業の一覧も公開する。
タブー破り、日本最大の芸術祭で展示される“少女像”
数十万人が訪れる「あいちトリエンナーレ」で 日本大使館前の平和の少女像と同じ作品が 1日から初めて展示される 「無事に展示終わったら日本社会にとっても希望」 市民らが交代で右翼の妨害に対応する予定
韓服(ハンボク・朝鮮半島の民族衣装)を着た少女が両手を合わせて正面を見つめている。後ろには影がさしている。影は少女ではなく、ハルモニ(おばあさん)の姿だ。少女の時に��慰安婦」として動員され、今はハルモニになった被害者の姿を象徴する。影には蝶も刻まれている。慰安婦被害の告発に続き、人権と平和の運動家になったハルモニたちの姿を連想させる。隣には「水曜集会千回目を迎え、その崇高な精神と歴史を受け継ぐために、この平和の碑を建てる」と書かれた平和の碑も置かれている。
日本に対する輸出規制で韓日の対立が深まる中、日本社会の代表的なタブーである「平和の少女像」が、日本最大規模の国際芸術祭で、初めて完全な姿で展示される。愛知県は8月1日から10月14日まで、「情の時代」をテーマに、愛知県名古屋市美術館などで「あいちトリエンナーレ(triennale)2019」を開催するが、展示作品に平和の少女像が含まれている。あいちトリエンナーレは、愛知県一帯で2010年から3年毎に開かれる日本最大規模の国際芸術祭で、2016年の展示会には60万人の観客が訪れた。
(中略)
今回展示される少女像は、在韓日本大使館前の「平和の少女像」を作った彫刻家のキム・ウンソン(54)氏とキム・ソギョン氏(53)夫妻が、少女像と全く同じ形で制作したものだ。キム夫妻が2015年、日本の市民らに預けたもので、これまでは私立展示館や小劇場での公演の際に披露されただけだった。名古屋で会ったキム・ソギョン氏は、2015年に日本に持ってくるとき、目立たないように細心の注意を払ったと語った。キム氏は「日本で(平和の碑もある)完全な形の少女像を公の場で展示するのは初めてだ。日本の公共美術館の展示されること自体が大変意味のあることだ」と評価した。
(中略)
2015年の「表現の不自由展」に続き、今回の展示企画に参加した日本の出版編集者・岡本有佳氏は「今回の『表現の不自由展・その後』に展示される17点の作品のなかで、慰安婦被害関連展示が3点も含まれていることについて、多すぎるのではないかという指摘もあった。しかし、多いわけではなく、安倍晋三政権が(慰安婦被害を)目につかないようにしたからこそ、そうなっただけ」だと話した。彼女は「日本社会には、最近閉鎖的な空気があるが、10月14日まで展示が無事に終わることを望んでいる。(日本国内で朝鮮半島に対する)植民地支配に向き合おうとする人たちに希望をつないでほしい」と述べた。
今回の展示には、日本社会のタブーに真っ向から挑戦する他の作品も展示される。2017年、日本群馬県近代美術館で展示される予定だったが、展示を拒否された「群馬県朝鮮人強制連行追悼碑」が代表的な事例だ。
(後略)
Yahoo!ニュース 1 tweet 9 usersタブー破り、日本最大の芸術祭で展示される“少女像”(ハンギョレ新聞) - Yahoo!ニ...https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190731-00034000-hankyoreh-kr韓服(ハンボク・朝鮮半島の民族衣装)を着た少女が両手を合わせて正面を見つめている - Yahoo!ニュース(ハンギョレ新聞)
下記は、KBSの報道。
KBSとは、韓国における公共放送であり、韓国放送公社。
日本におけるNHKに相当する。
実際に慰安婦像が展示されている状態が確認できる。
ハンギョレのyahooニュースは、参議院議員の和田先生がTwitterにて紹介している。
あいちトリエンナーレ。
慰安婦像の展示が行われ、昭和天皇の御真影を焼く映像展示があるとの情報が寄せられた。御真影を焼く映像展示は明日確認を取る。事実だとしたらとんでもないこと。あいちトリエンナーレは文化庁助成事業。
しっかりと情報確認を行い、適切な対応を取るhttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190731-00034000-hankyoreh-kr …
タブー破り、日本最大の芸術祭で展示される“少女像”(ハンギョレ新聞) - Yahoo!ニュース
韓服(ハンボク・朝鮮半島の民族衣装)を着た少女が両手を合わせて正面を見つめている - Yahoo!ニュース(ハンギョレ新聞)
14,612人がこの話題について話しています
想像以上にとんでもない展示作品
私は芸術作品は、ぶっちゃけ、よくわからないタイプである。
よくわからないからこそ、人並み以上の敬意を払ってきた。
当市においても文科系の事業はあるが、芸術に関する事業においては「正直、球が一番美しいと思っている。」と述べた上で、「けれども、その道を目指す方々おられる以上、その世界を否定することは、むしろ門外漢の私にはできない。」(要旨)という理由で賛成に回っている。
市議や市職員との雑談においては、”美しさや造詣で私が言及できるのは、車のエアロパーツやホールのデザインぐらいだ。”と正直に述べている。
だが、敢えて言いたい。
芸術だと言えば、なんでも許されるわけではない。
例えば極めて特殊な性癖のエロ画像とか、犯罪を助長する作品展示が許されていいのか?という話になる。男性・女性を問わず、もしくはそれ以外の性も含め、三大欲求として通常に有するものかと思うが、どういう趣味嗜好であるかはそれぞれの内面に秘めておいてはどうか、と。
異なる性癖の者に、それぞれの趣味を無理やり見せつけることは、それこそハラスメントというものだろう。ちなみに、私は、おっぱいがでっかい系のやつは好きくない。あと身長が低い系のやつも無理。そういうのが好きな人もいるだろうから、否定はしないけれども、無闇に開陳され、わざわざ視界に入れて欲しくはない。
それも含め「芸術として許容せよ」と言われれば、私は「それは芸術とは判断できない」と、議員として判断する。
芸術に造詣がないゆえ、私にはこういう説明しかできない。
言いたいのは「芸術と言えば何でも許されるわけではない」という一点だ。
(慣れぬ分野で気を使って書くと、ちょっと文字数が必要なのはご愛敬。)
今回の”作品?”だが、ちょっと芸術とは言えないと感じた。
政治的なメッセージのオンパレードであり、これでは公費を投じたデモだ。しかも他国の主張を代弁するかのような。
芸術監督が津田氏では当然かも知れないが、ちょっと酷い。
酷いというか、想像を絶するレベルで凄い。ぶっ飛んでいる。
何なんでしょうこれは。。。https://censorship.social/artists/
出展作家 | 表現の不自由展・その後
出展作家 安世鴻 重重―中国に残された朝鮮人日本軍「慰安婦」の女性たち 大浦信行 遠近を抱えて(4点組) 大橋藍 アルバイト先の香港式中華料理屋の社長から「オレ、中国のもの食わないから。」と言われて頂いた、厨房で働く香港出身のKさんからのお土産のお菓子 岡本光博 落米のおそれあり キム・ソギョン/キム・ウンソン 平和の少女像 作者非公開 9条俳句 小泉明郎 空気 #1 嶋田美子 焼かれるべき絵 白
2,373人がこの話題について話しています
勇気のある方は、リンク先を見てみるといい。
今回のあいちトリエンナーレで展示されている、”©表現の不自由展・その後実行委員会”の作品群だ。
表現の不自由展・その後 2 users出展作家 | 表現の不自由展・その後https://censorship.social/artists/出展作家 安世鴻 重重―中国に残された朝鮮人日本軍「慰安婦」の女性たち 大浦信行 遠近を抱えて(4点組) 大橋藍 アルバイト先の香港式中華料理屋の社長から「オレ、中国のもの食わないから。」と言われて頂いた、厨房で働く香港出身のKさんからのお土産のお菓子 岡...
一部の作品を紹介するが、「中国に残された朝鮮人日本軍「慰安婦」の女性たち」。
「アルバイト先の香港式中華料理屋の社長から「オレ、中国のもの食わないから。」と言われて頂いた、厨房で働く香港出身のKさんからのお土産のお菓子」という作品?これは、単にお土産?をテーブルに乗せた写真。
他、「落米のおそれあり」という米国の国旗を揶揄した標識。
「時代の肖像ー絶滅危惧種 idiot JAPONICA 円墳ー」という作品には、神社などをモチーフとしたものが白黒で作られている。
また「福島サウンドスケープ」というものも。これは福島県、および福島県民は怒りを示すべきもの。
そして”慰安婦像”だ。
私が「芸術を全否定はしないが」と徹底して前置きをして紹介したのは、もう流石に罵詈雑言を述べそうになってしまったからだ。
これを税を投じて展示している事実には、卒倒しそうになる。
どの会場に何が展示されているかは、今後の続報を待つよりないが、「愛知芸術文化センター」、「名古屋市美術館」「四間道・円頓寺」「豊田市美術館・豊田市駅周辺」が会場となっている。
抗議先一覧以下、抗議先を示す。
トリエンナーレ実行委員会事務局は、愛知県の部門ではある。
だが、ここへの抗議はすでに殺到していると思われ、かつ外注先企業が受けている可能性が否定できないため、その他の抗議先も併せて示す。
あいちトリエンナーレ実行委員会事務局
(愛知県県民文化局部文化部文化芸術課トリエンナーレ推進室内)
住所:〒461-8525 愛知県名古屋市東区東桜1-13-2 愛知芸術文化センター内
TEL:052-971-6111(代表)
FAX:052-971-6115
E-mail:[email protected]
(愛知県)
代表電話:052-961-2111
知事室 :052-954-6000
県議会事務局:052-954-6730
知事室(執行部)には、「何を考えているんだ!」という抗議を行って頂きたい。被害者は日本国民であるという観点で言えば、愛知県民以外であっても良いと思う。
また、議会には「是非、議会で知事部局を質して頂きたい」という依頼の形でお願いします。
※ 議会は予算を審査する立場のため、双方へのアプローチは微妙に異なる。
(名古屋市)
代表電話:052-961-1111
市議会総務課(庶務係)052-972-2083
(文化庁)
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3丁目2番2号
電話番号(代表) 03-5253-4111
御意見・お問合わせ
文化庁には、助成事業として不適切という声を届けて欲しい。
すべての事業を文化庁が自ら審査しているわけではないと思われるため、その部分については批判しすぎると的外れになる可能性もある。
あくまで助成金事業として適切であるか否かに絞ったほうがいい。
助成
・文化庁
・一般財団法人 地域創造
・損保ジャパン日本興亜
・野村財団
・一般財団法人 東海テレビ国際基金
・cooperacion espanola(スペイン国際開発協力機関) 政府機関
・公益社団法人朝日新聞文化財団
・芸術・文化による社会創造ファンド
・beyondo2020
協賛の一部を紹介、イオン、シチズン、愛知県医師会、麻生グループ、名古屋競馬、VOLVOに愛知県宅建協会、三菱UFJ銀行、TOYOTAまである。
株式会社豊田自動織機、株式会社百五銀行、愛知県農業土木研究会、NDS株式会社、株式会社LIXIL 中部支社、愛知県私学協会、一般社団法人愛知ビルメンテナンス協会、株式会社コングレ、トヨタ紡織株式会社、公益社団法人愛知建築士会、豊田通商株式会社、日本製鉄株式会社 名古屋製鉄所、東海東京証券株式会社、名港海運株式会社、愛知県農業土木測量設計技術研究会、名古屋商工会議所、株式会社クレディセゾン 東海支社、東和不動産株式会社、ホーユー株式会社、株式会社NHKプラネット中部、名古屋ファッション専門学校、阪和興業株式会社、カフェ コンセッション、興和株式會社、トーテックアメニティ株式会社、株式会社メニコン、アイシン精機株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、愛知県行政書士会、愛知県舗装技術研究会、伊勢湾海運株式会社、第一生命保険株式会社、株式会社デンソー、豊島株式会社、豊田合成株式会社、日本たばこ産業株式会社 東海支社、三井住友海上火災保険株式会社、学校法人愛知医科大学、愛知県美術館友の会、朝日電気工業株式会社、天野エンザイム株式会社、一般財団法人荒井財団、OKB大垣共立銀行(多すぎるの後略、詳細リンク先)
協賛意外にも、協力という項目があり多数の企業���名を連ねる。
また、会場提供にも多数の企業が掲載されている。
あいちトリエンナーレ2019協賛・協力https://aichitriennale.jp/sponsor/index.htmlあいちトリエンナーレ2019開催にあたり、ご協力をいただいた皆様を紹介します。
裏技になるが、柴山大臣のTwitterに直接、凸ることは効果的だと思う。
実際に大臣自らが操作しているアカウントであり、河野大臣と併せ、直接見てもらえる可能性が高い。
文化庁の上位組織は文部科学省であるため、文化庁の助成金については大臣に声を届けることは近道だ。
「あいちトリエンナーレ」への助成をとりやめるよう、お願いをして欲しい。
https://twitter.com/shiba_masa
外交に関連するという意味では、河野太郎外務大臣のTwitterも紹介しておきたい。
https://twitter.com/konotarogomame
今回の流れと、今後の予測
少し同情的にも書いておくが、知事は事業内容を存じてはいなかっただろうとは思う。ここは全く裏をとっていない話だが、知事が自発的にやったこととはどうしても思えない。大村知事はもともと国会議員であり、5期を務めている。
副大臣、政務官の経験もあり、閣内の動きや予算執行についても理解しているだろう。
のち自民と離反することになるが、県連会長の経験もある。
結果的には、旧・日本維新の会の顧問も歴任した。
松井・大阪市長の投稿。
これを火消しと見るか、事実ととらえるかは個々人の判断だろう。
河村市長と連絡した所、ご自身も一昨日まで知らなかったようです。問題意識を持っているので早急にチェックするとの事です。 https://twitter.com/gogoichiro/status/1156828796848226306 …
にわかに信じがたい!河村市長に確かめてみよう。 https://twitter.com/minajyounouchi/status/1156810939104022528 …
4,861人がこの話題について話しています
私は、大村知事は、知らなかったという説を信じたい。
これだけのキャリアがある以上、どうなるかはわかっていたはず。
しかもタイミングがタイミングだ。
#あいちトリエンナーレ に電話繋がりました。
質問内容
1.慰安婦像が展示してあるのは本当か。
2.昭和天皇の御真影を燃やした作品を展示しているのは本当か。
事務局回答
1.2共に本当。2に関しては映像作品でその中の一部。
1.2共に芸術作品である事。
表現の自由だと主張。
続く。
2,885人がこの話題について話しています
内閣にまであがるだろう。
まだ、菅官房長官の直轄でもある和田政宗議員が動画で触れ、Twitterで投稿しているということは、すでに官房長官までは行っているとみたほうがいい。
そもそも愛知のテレビ局とは「謎の対応」があったばかりで、良い印象はもっていないように思う。ざくっとやるのではないかな。
これは、慰安婦像の撤去では済まないと思う。
特に昭和天皇の御真影を焼いた映像の確認がとれた場合には、確実に文化庁は助成を打ち切る。
打ち切らなかった場合には、柴山文科大臣のクビが飛ぶレベルに発展する。
「事業まるごと」の、中止はあり得ると考える。
むしろそうすべきだ。
すでに一日とは言え、展示されてしまった事実は残るわけで、韓国の公共放送(KBS)が絵を抑えてしまっている。
被害は、すでに生じている。
明日より、ネットを経由した抗議は激化するだろう。
いまは週刊金曜日が触れているぐらいだが、明日2日は名古屋市長が現場を確認するとのこと。
一面を飾るかはわからないが、産経なども報道していくだろう。
炎上というレベルではなく、もうネットがどうこういうレベルではなく、開催が困難な事態になるだろう。
早い段階で、芸術祭ごと中止したほうがダメージが低いと思う。
大村知事には、やや同情すると述べた理由は、日程だ。
この芸術祭は、2019年8月1日から、10月14日まで開催されるもので、実は長期間にわたって開催されるもの。オープニングが1日~4日まで。
初日で大炎上をかまし、しかもホワイト国の除外の前日というシビアなタイミングで直撃。
もうオープニング期間すら乗り越えることが難しいのではないか、と。
津田大介芸術監督と。名古屋東急ホテルにて。
2,176人がこの話題について話しています
大村知事も楽しみにしていたのでしょう。
芸術祭にあわせ、コスプレの披露もされています。
これは、すでに炎上が開始してから投稿されたものです。
大炎上しました。
週刊少年ジャンプに連載中の人気漫画『ONE PIECE』に登場する剣士、「ロロノア・ゾロ」に扮しています。
3,133人がこの話題について話しています
(この時点で予告しています。)
愛知県の大村知事、煽りますねぇ。
天皇陛下の写真をあんな風に扱い、慰安婦像を展示させている件には触れず、新しい投稿で流すつもりなのかな。
明日には官邸まであがると思いますよ。 https://twitter.com/ohmura_hideaki/status/1156856783920517121 …
週刊少年ジャンプに連載中の人気漫画『ONE PIECE』に登場する剣士、「ロロノア・ゾロ」に扮しています。
709人がこの話題について話しています
長期にわたる芸術祭、
このまま沈静化してくれんかなぁというのが本心でしょうが、もうこれは無理です。
淡々と違う投稿を繰り返し、流していく手法のようですが、文化庁や愛知県議会、名古屋市議会が動いた場合には「リアルで身動きがとれない」です。
愛知県ITS推進協議会総会で会長として挨拶しています。アイリス愛知にて。
830人がこの話題について話しています
芸術祭が中止になった場合ですが、
というか中止も視野に検討すべき事態でありますが、
その場合は、愛知県知事・名古屋市長の責任は問われます。
議会は、そう振る舞うべきでしょう。
では大村知事がどうすべきだったかと言えば、本日中に「こんな展示があることは知らなかった。すぐに調査させ、撤去させる」と発信することでした。
明日には、河村たかし・名古屋市長が現地を確認するとのこと。
名古屋市は、まだ活路があって「なんてことだ!これは大変なことだ、すぐに対応する。」と発信すれば、退路は残されています。ですが、市議会への対応を考えると、名古屋市は税の投入を中止する方向で進めたほうが軽傷で済むでしょう。
その場合は、今日を放置しまった大村知事が全てを被ることになります。
中止のち、自ら知事職を辞任することが、芸術祭への参加者および愛知県民を守ることになるように思います。ご自身にとっても、もっとも軽傷で。
これは、それなりのインパクトのある騒ぎに発展すると思われ、話の転び方によっては、どちらにせよそうなる可能性がある。
問題になってくるのは、金の行き先。
津田氏は、ハフポストの取材に下記のように答えいてる。
(前略)
「東京ではなく愛知から、公金が投入される国際イベントでジェンダー平等のメッセージを世界に向けて発信する。新しい時代に向けて、大きな転機になると期待しています」と語る津田さん。
取り組みやコンセプトへの賛同と寄付も呼びかけている。
実はまだまだ作家の制作予算が足りていません。
「あいちトリエンナーレ」は比較的作家の制作に対して予算を割いていますが、それでも業界の体質なのかアーティストに作品を作ってもらうための費用が根本的に低く見積もられているのです。そうした体質も変えていかなければならないと思っています。
こうした取り組みに共感された方はぜひ、愛知県が実施している『2021芸術・文化による社会創造ファンド』にクラウドファンディング感覚でご寄付いただけるとありがたいです。ふるさと納税と同じで一定の金額まで寄付控除が受けられます!
ハフポスト「あいちトリエンナーレ2019」でジェンダー平等が実現 芸術監督の津田大介さんの...https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_5c9ab498e4b08c450ccd7da6?fbclid=IwAR0SkytBS1yk3swDiewIP9MwyInXhMWyKuigkYQk5bxZmN6poY7P_5sJXK8「アートの門外漢である自分だからこそできること、業界にしがらみのない人間でなければできないことがあるはずです」
ここは議会で質していかねば明確にならないが、慰安婦像の作者らやホワイト国除外に反対している活動家らに資金が提供された可能性が否定できない。
原資が税金であれば、議会を通過するとは思えない。
海外の政治勢力に対しても、日本の税金がそっくり流れていた場合、ちょっとスキャンダルがどうこうとかいう規模では済まない。
例えば、昭和天皇の御真影を焼く映像作品があったとして、その作品に対する対価として、税から支出して大丈夫か?という話になる。
ここまでのレベルになると、本心で言えば可哀想にもなってくる。
知事の政治力では、すでに対応が不可能な次元ではなかろうか。
そもそも自民を離反した身、いまの状況で閣僚が擁護してくれるとは思えない。
自民県連も追撃するだろう。そういう意味では、先ほどの松井市長のtweetを火消しと感じる人もいたのではないか、と。
芸術祭の参加者も、正直、不憫だ。
正常な開催は不可能と思われ、終盤まで行くことは無理だろう。
普通に準備してきた方は、本当に可哀想だと思う。
私はこのイベントを知らなかったが、想像以上に規模がでかい。
海外からの多数の参加があるため(だから問題なのだが)、即決で中止とか撤去の指示を出しきらなかったのだろう。
企業協賛も凄まじい数だが、協賛した企業らが展示物を把握していたとは思えない。宅建協会とかTOYOTAまであるのだ、中には麻生グループまで。
中止となった場合、愛知県知事が受ける、また愛知県が受ける政治的なダメージは想像以上だろう。それでも、早い段階で中止したほうが、まだ軽傷だとは思うが、被害規模が想像を絶する規模で「決断できなかった」のではなかろうか、と。まぁ、性善説に基づけば。
今後の動きと章タイトルにつけたので、最終的な部分も触れておきたい。
想定にはなるが、3点だろう。
誰がどういう理由で、どのような選考過程で津田氏を指名したのか。ここを明らかにすることが一点目。
二点目は、金の流れ。
特に慰安婦像などの作品群に対しての出資状況。津田氏が金額を決定できる立場にあったのか否かも併せて調査されるべきだろう。
(というか、議会の正常な反応だと思う。)
三点目は、全ての参加者の洗い出し。
これは可哀想だと思うが、前述の作品だけなのか?という意味では、全ての展示物については調査が求められる流れになるのではないか。特に津田氏が声をかけた者がどれぐらいいたのか等は調査されるように思う。
三点目の部分については、公安関係者(公安および公調ら)も投入されるべきだと考える。
私が記した抗議先とは、こういう流れになりうるリストです。
もう、どちらにせよもたない。
これを書くかどうかは迷ったのだが、やらざるを得ない状況だろう。
私も、イベントの規模や協賛��を見て、たじろいでしまうところだった。
内容が内容だ。
やるしかない。
気分は、青い服の少女が出てくるアニメの、最初のシーンかな。
丸ごとやるしかないだろう。
国家と地方自治体
自治体が、一切の海外との交流をもつなとは言わない。
日韓友好で使節を送りあうこともあるだろう。
私は賛成する立場ではないが、これは同じく日台関係にも言えることだ。
交流事業であれば、地方公共団体でも許容されるべきだと考えるし、
北朝鮮のように国家承認を受けていないとか国交がない場合を除き、
地方からの交流はあっていい。
けれども、それは厳密に言えば外交とは異なるものなのです。
それは国会議員の専決事項であり、地方が入っていい領域ではない。
これは自らの職権を縛る発言ではなく、そのために衆院選・参院選があると考えているからです。地方行政も一部の交流事業は許されているものの(特に経済交流などは、むしろ推進されるべき。)、やっちゃいけないレベルがある。
いま、国家行政そのものである内閣は、
韓国に対して、対応をとろうとしている矢先だ。
まさに前日だ。
ここに、市税・県税を投じ、
あまつさえ国庫から助成を受けようなどとは、
断じて許されない。
芸術祭の参加者および協賛企業、
そして日本国への影響を最小限にすべく、
慰安婦像の撤去のみならず、
催事の中止および、本件に伴う引責として
大村知事には、自ら辞職をして頂きたい。
愛知県の全ての議員は、自らの名誉と職責を賭け、辞職を迫るべきだと思う。
御真影を焼く映像を流していた場合は、辞職でもすまない。
共に抗議の声をあげる方は、FBでのイイネ・シェア、Twitterでの拡散をお願いします。
3 notes
·
View notes
Text
■日本メディア検閲史 <新聞法、出版法について> | 前坂俊之オフィシャルウェブサイト http://www.maesaka-toshiyuki.com/massmedia/3838.html
静岡県立大学国際関係学部教授
前坂 俊之
われわれは今、「言論の自由」を、ごく当たり前のことと思っている。
「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」(憲法21条1項)、「検閲は、これをしてはならない」(同2項)という日本国憲法の条文を、わざわざ引き合いに出すまでもなく、当然と受け止めている。
しかし、1945(昭和20)年8月の敗戦まではそうではなかった。それ以後の連合軍による占領期間中も、言論の自由は制限されていた。
明治以来、メディアに対する検閲制度は昭和の敗戦まで約80年間続いた。
現行憲法でわざわざ検閲禁止の規定が盛り込まれているのは、この検閲の歴史の反省が込められている点を忘れてはならない。
検閲は表現の自由への公権力の規制の形式的、方法的問題であり、たんに文章や表現をチェック、削除する狭い範囲で考察するのではなく、広く言論統制、情報操作の一側面としてとらえることが必要である。
この「メディアと検閲」の章では、そうした観点から、主に日本でのメディア検閲の歴史的な関係について触れたい。
■1 言論の自由と検閲制度・ミルトンらで言論の自由の確立へ
秦の始皇帝(紀元前259-210年)の「焚書坑儒」を引き合いに出すまでもなく、歴史のなかであらゆる政治権力は、自らと対立する都合の悪い言論、思想を抑圧、弾圧の対象としてきた。
ギリシャ、ローマ時代はいうにおよばず、中世キリスト教の異端審問など、言論の抑圧が続いた。一五世紀の活版印刷の発明がエポックとなって、大量印刷や伝達が可能となり、マスメディアが生まれ、これを抑圧する手段としての検閲も一層、組織化、制度化され、近代検閲が生まれた。
大量に、スピーディに、安く印刷できる革命的な活版印刷の発明は、異端の広がりに厳重に目を光らせていたローマ教皇庁に衝撃を与えた。
グーテンベルクが活版印刷を発明したドイツ・マインツで、大僧正ベルトルドが1486年に出版物を取り締まるため検問所を設けたが、これがいわゆる「検閲制度」のはじまりである。
活版印刷の発明は中世ヨーロッパの宗教社会の内部から宗教対立を激化させる要因となり、宗教改革を生み、ついには市民社会の誕生の契機となったのである。
1501年には、ローマ教皇アレキサンダー六世が出版の許可主義をとった。さらに1542年には、ローマ教皇パウロ三世がカトリックに反対する出版物に対して、異端審問所の許可をとっていないものについては発行、流布を禁止した。
言論、出版の自由の歴史はこうした検閲制度との不断の戦いの歴史であり、その上に勝ちとられたものであった。
イギリスでは1586年に星室庁(当時の最高司法機関)が印刷条例をつくり、検閲を実施したが、これは後に長期議会に引き継がれて、1643年に検閲条例が定められた。
封建主義、絶対主義社会の象徴としての検閲に対して、言論、出版の自由の要求が生まれてくるが、その先駆者がミルトン(1608-74年)である。
ミルトンは『アレオパジテイカ』(許可なくして印刷する自由のためにイギリス議会に訴えるパンフレット)で「……真理と虚偽とを組打ちさせよ。自由な公開の勝負で真理が負けたためしを誰が知るか」、「他のすべての自由以上に、知り、発表し、良心に従って自由に論議する自由を我にあたえよ」と書き、言論の自由を強く訴えた。(内川芳美「新聞の自由の歴史」 稲葉三千男・新井直之 編著『新版新聞学』日本評論社、1988年、40頁)。
ミルトンは検閲条例をきびしく批判し、思想は抑圧されず自由に公開、競争される「思想の自由市場理論」と、そうすれば人間の正邪を判断できる理性によって、真理が必ず勝ち残るという「真理の自働調整作用」を唱えた。
こうしたミルトンらによって、イギリスで特許検閲法が廃止されたのは名誉革命後の1695年のことであり、新聞、出版の自由が制度的に確立されていった。
■2 徳川時代の検閲制度
一方、日本ではどうであったのだろうか。
徳川時代中期から出版業が盛んになってくるが、幕府は1630(寛永7)年にキリシタン関係書の売買、閲読の禁止に乗り出した。
1649(慶安2)年には、大坂の書店・西村伝兵衛が出版した『古状揃』のなかに「家康表裏之侍太閤忘厚恩」という徳川家康を誹語する文句があったことから、幕府はこの書物を没収、絶版の処分にし、伝兵衛は斬首の刑となった。
新開の前身である「読売瓦版」に対しては貞享、元禄年間の禁令をみると、検閲がおこなわれていた事実がみられる。
1722(享保7)年には、出版に関するはじめての成文法といってよい『町触れ』(現在の法律)が出された。
内容は猥褒や異説を唱えるもの、徳川家の事蹟に関する記事について禁止したほか、板本の奥づけに作者と板元名を記すことを定めたものであった。
このように、すでに江戸時代からはじまった出版物取り締まりの基本的な考え方は、明治になっても踏襲された。
■3 明治の新聞の誕生と言論恐怖時代の幕開け
ところで、日本での新聞の始まりは幕末の翻訳新聞、外字新聞である。
幕府の洋書調所にいた洋学者たちの翻訳によって新聞づくりがはじまった。当時は新聞、雑誌の区別はなく、この洋書調所から雑誌も翻訳雑誌として生まれた。
当初、このように幕臣による新聞が多かったため、鳥羽伏見の戦い(1868年)、江戸への薩長軍の進軍に対しては佐幕派の新聞が多数発行され、官軍を攻撃する記事や虚偽の報道、風説を流し、幕府の味方をした。
柳河春三「中外新聞」、福地源一郎「江湖新聞」、岸田吟香「もしほ草」など多くの“佐幕派新聞”に対して、明治政府は、はじめて言論弾圧に乗り出した。
1869(明治2)年2月、政府はわが国で最初の新聞紙法である「新聞紙印行条例」を発布した。
発行を許可制にし、編集者の責任を定め、政治評論を禁止するなどの内容であった。
1874(明治7)年1月、江藤新平、板垣退助、後藤象二郎らが『民撰議院設立建白書』を提出したことから、自由民権運動がまたたく間に全国に広がった。
新聞はこれを支持する民権派が多数を占め、そのなかで急進派と漸進派に分かれ、これに反対の立場の官権派が入り乱れて激しい論戦を展開し、“言論の黄金時代”を迎えた。
言論界では急進的民権派が圧倒的多数を占め、反政府運動と化したため、政府は1875(明治8)年6月に「新聞紙印行条例」を大改定した「新聞紙条例」と、新たに「讒謗律」をセットで公布した。
讒謗律は 名誉毀損罪と政治的誹謗罪が一緒になったような法律で、天皇、皇族、官吏に対する誹謗を防ぐというねらいだが、実際は反体制的言論を規制し、弾圧するのが目的であった。
言論界にとってこの両法は正に青天の霹靂であり、一大ショックを与えた。
まず「曙新聞」の末広鉄腸が、これに触れて罰金20円、禁獄3ヵ月に処せられたのをはじめ、各社の記者が続々と処罰され、獄中は新聞記者や編集者であふれかえる事態となった。
宮武外骨の調査によると、5年間でこの両法によって記者、編集者約200人が禁獄されるという“一大言論恐怖時代”を現出した。
しかし、これでも自由民権連動の大きなうねりを止めることはできず、逆に高まる一方であった。
このため、翌76(明治9)年に政府は「国安ヲ妨害スト認メラルル者ハ、内務省二於テ、ソノ発行ヲ禁止又ハ停止スヘシ」という太政官布告を出した。
この規定が「安寧秩序ヲ妨害」したものに対して「発売頒布禁止権」を行使するという出版警察の中核的な行政処分権となり、敗戦までの約七〇年間にわたり言論の自由の生殺与奪となったのである。[奥平康弘、1983、137-138頁]。
さらに、明治政府は���国憲法の発布(1889年2月)に照準を合わせ、1887(明治20)年に「新聞紙条例」、「出版条例」を改定し、取締法規を整備、強化した。
「新聞紙条例」では内務大臣の発行禁停止権、保証金制度、陸海軍両大臣の記事差止権、その他掲載禁止事項などが定められ、一方、「出版条例」では発行10日前に製本3部を内務省に届け出ることが義務づけられた。
1889(明治22)年2月発布の帝国憲法では、「言論の自由」については「法律ノ範囲内ニ於テ言論、著作、印行、集会、及結社ノ自由ヲ有ス」(第29条)とされ、「新聞紙条例」、「出版条例」、「保安条例」、「集会条例」の4つの言論統制法の範囲内での制限つきの言論の自由しか認められなかった。
労働運動、社会主義運動が高まった1900(明治33)年2月、片山潜、安部磯雄らによって「社会主義研究会」が発足した。政府は集会、結社の取締法の集大成である「治安警察法」を制定して、きびしい取り締まりに当たり、翌年5月に片山、安部、幸徳秋水ら6人で結成された「社会民主党」は、即日解散となった。
1903(明治33)年2月、日本で初の社会主義新聞「平民新聞」(週刊)が幸徳秋水、堺利彦、西川光二郎らによって創刊された。日露戦争に対して非戦論を主張した同紙は官憲によってきびしい弾圧を受けた。同20号の幸徳の「鳴呼増税」が新聞紙条例に違反、発禁が相次ぎ、創刊一周年記念号に『共産党宣言』が翻訳掲載され、再び発禁となり、3人は起訴され、有罪となり1905(明治38)年1月に64号で廃刊に追い込まれた。
■4 大正の大阪朝日新聞「白虹事件」
大正デモクラシーの高揚は憲政擁護、閥族打破、言論擁護の運動でもあった。その中心的な役割を果たしたのは民衆とともに、新聞であった。大正はじめに政党と結び、憲政擁護で第3次桂内閣を倒した新聞は、今度は民衆と歩調を合わせ、寺内内閣との対決姿勢を強めた。
寺内内閣の非立憲的な態度は、新聞への姿勢でもかわらず弾圧的態度に終始した。
シベリア出兵問題(1918年)、米騒動(同年)に対して発禁を連発、とくに、米騒動に対しては一切の報道を禁止したため、『���秋会』(新聞社の社交クラブ)は「言論の自由への圧迫」として再々にわたり、取り消しを求めたが、寺内内閣は応じなかったため、内閣打倒へ立ち上がった。
1918(大正7)8月25日、寺内内閣糾弾の関西新聞社大会が大阪・中之島で開かれた。
村山龍平・朝日新聞社長を座長に関西の新聞、通信社など計86社約170人が集まって開催され、「大阪朝日新聞」は同日夕刊(26日付)社会面のトップで次のように報じた。
「我大日本帝国は今や恐しい最後の審判の日に近づいているのではなかろうか。
『白虹日を貫けり』と昔の人が呟いた不吉な兆が黙々として…‥」
この記事の「白虹日を貫けり」が問題化し、日本の言論史上に残る一大筆禍事件「白虹事件」へと発展していった。
「白虹日を貫けり」とは中国の故事で、白い虹が太陽を貫いて見えるときは、国に内乱が起きるしるしであるという意味だが、当局は「日」が天皇をさし、不敬に当たるといいがかりをつけて、記者と編集発行人を新聞紙法違反(安寧秩序素乱)で起訴、2人は禁固2ヵ月の有罪となった。
かねてより、当局は政府へ批判的な「大朝」の弾圧の機会をねらっていたのである。
この事件で鳥居素川、長谷川如是閑、大山郁夫らの編集幹部が総退陣し、村山龍平社長も退陣した。『大阪朝日新聞』は廃刊の危機を迎えたが,当時の原首相は上野理一社長を呼び、編集方針の変更などの釈明を聞いた上で、発行禁止を見合わせた。
この事件をきっかけに、新聞自体の批判精神は低下して、新聞の企業化が一層進んでいった。
■5 出版警察の核心・検閲は発売頒布禁止で
戦前の日本の検閲制度、出版警察の核心は 原稿検閲制による発行禁止ではなく、世界にも類例のない 内務大臣による発売頒布禁止であった。
政府は西欧ブルジョア主義の「出版の自由」を認めず、大量印刷物の流通に対して事前検閲をすることは実際上不可能であるため、ときに応じて権力を行使できる発売頒布禁止を導入したのである。[奥平康弘、1983.132頁]。
この発売頒布禁止権は新聞紙法第23条、出版法第19条でそれぞれ定められていたが、司法審査から独立した絶対的なものであった。
さらに、内務大臣が行使するこの権限は中央集権警察組織下で実質は地方の末端警察が握り、より一層、恣意的に運用、処分がおこなわれたのである[奥平、1983、160-161頁]
■6 検閲の基準は当局にとって伸縮自在の弾力運用
では、具体的な検閲の基準はどのようなものであったのだろうか。
当局が新聞紙法第23条、出版法第19条での「安寧秩序素乱」、「風俗壊乱」と規定する基準一検閲担当官が参考にしたものは次のようなものであった。
●【安寧秩序素乱出版物の検閲基準】(一般基準)
▽皇室の尊厳を冒涜する事項 ▽君主制を否認する事項 ▽共産主義,無政府主義等の理論、戦略、戦術を宣伝し、その連動実行を煽動し、この種の革命団体を支持する事項 ▽植民地の独立運動を煽動する事項 ▽非合法的に議主義会制度を否認する事項 ──など計13項目であった。
●【風俗壊乱の検閲基準】
▽春画淫本 ▽性、性欲又は性愛等に関する記述で淫猥、羞恥の情を起こし、社会の風教を害する事項 ▽陰部を露出せる写真、絵画、絵葉書の類 ▽陰部を露出せざるも醜悪、挑発的に表現された裸体写真、絵画、絵葉書の類 ▽男女抱擁、接吻(児童を除く)の写真、絵画、絵葉書の類 ──などであった。(以上、内務省警保局『昭和五年中における出版警察概観』)
この基準に基づく適用については取締当局によって伸縮自在の「弾力性」をもっていた。
大正時代には-時縮小した禁止範囲は、1932(昭和7)年以降、再び急速に拡大し、社会主義、労働運動に関する著作は以前にましてきびしい取り締まりにあった。
安寧秩序素乱の取り締まりの場合は1920年代に一時禁止基準はゆるむが、30年代になると再びきびしくなった。(油井正臣 他『出版警察関係資料解説・総目次』不二出版、1938年、24頁)。
こうした発売頒布禁止制度とともに、内務省は超法規的な記事掲載差し止めをおこなった。
これは重大事件が起こったとき、この記事を掲載すると発売禁止になるぞ、とあらかじめ警告するもの。新聞側は発禁による不測の損失をまぬがれるために歓迎し制度化したが、もともとは新聞紙法上でも認められた処分ではなかった。
この“差し止め処分”は禁止事項の軽重によって、
① 示達/当該記事が掲載されたときは多くの場合、禁止処分に付すもの。
② 警告/当該記事が掲載されたときの社会情勢と記事の態様いかんにより、禁止処分に付すかもしれないもの。
③ 懇談/当該記事が掲載されても禁止処分に付さないが、新聞社の徳義に訴えて掲載しないように希望するもの。
以上の3種類があり、「懇談」は少なかったが、「示達」、「警告」は乱発された。これに触れること、発禁などを受けるため、無視できない。
さらに、これ以外にも、便宜的処分として発禁処分にするほどでない場合は該当の部分のみを切除する「削除」処分や注意だけの「注意」処分もあった。削除処分は1933、34(昭和8、9)年に年間200件、注意処分は1932(昭和7)年には約4,300件に達した。
■7 15年戦争と幕開けと言論統制の強化
1928(昭和3)年3月15日には日本共産党に対する一斉検挙のいわゆる“三・一五事件”によって、労農党の関係者ら千五百数十人を検挙し弾圧を加えた。
「新聞紙法」、「出版法」による発禁件数は一挙にはね上がっていく。
1931(昭和6)年9月、日本軍による満州事変の勃発で、中国への侵略、十五年戦争の幕が開く。言論統制は一段ときびしくなっていく。
「安寧秩序素乱」による新聞、出版の発禁件数は翌32年には4,945件と1926(昭和元)年の412件の12倍にも激増して、���ークに達した。
満州事変以降のファシズム化の過程でメディア統制の一つの特徴は新聞紙法、出版法を補完、併用する形で、他の諸規定が利用された点である。
たとえば、出版法による発禁処分に該当しない街頭での選挙ポスター、ビラの類にも、治安警察法(1900年)第16条での往来などでの表現の自由を取り締まる規定を適用するように内務省警保局は指示。これはレコードにも拡大適用され、従来は各府県ごとに任されていた取り締まりが1932(昭和8)年10月から、内務省によって統一的におこなわれ、事実上、レコードの発禁処分をおこなった。
翌34(昭和9)年8月の出版法改正によって、レコード類は出版法による発禁、差し押さえの対象となった。レコードの取り締まりの内容は圧倒的に風俗取り締まりが中心で、兵隊漫才が「軍の統制紀律をみだす」などとして取り締まられた。
1937(昭和12)年7月に、日中戦争が起きると、新聞紙法第27条が発動された。
「陸海軍大臣、外務大臣は軍事・外交の記事の禁止、制限をすることができる」という内容で、陸、海軍省令、外務省令で記事掲載が制限された。
■8 検閲から総合的な言論統制へ
日中戦争による本格的な臨戦体制から、マスメディア統制も従来の検閲という消極的な抑圧統制から、国民を積極的に戦争体制に協力、同調させていく方向へ転換、情報操作、プロパガンダ機能を重視した稔合的な組織、体制づくりがおこなわれた。
1938(昭和12)年4月、国家総力戦を目指した準戦時体制の国家総動員法が公布されると、メディア統制も事業面から休止、合併、解散の命令(同16条)という生殺与奪の権限が政府に握られることになった。
記事掲載の禁止、制限という言論面だけでなく、企業体としての生存にかかわる心臓部を押さえられ、その後におこなわれる新聞の統廃合、一県一紙への道を開く結果となる。
さらに、積極的なプロパガンダ体制づくりとしておこなわれたのは、内閣情報局と国策通信会社「同盟通信社」 の組織、設立である。
1936(昭和11)年1月に「電通」、「連合」の両通信社を強引に合併させて「同盟通信社」を誕生させた。内閣情報委員会が万難を排して、合併、同盟発足のために協力した。
政府は世論指導の中心に、この同盟を置き、毎年莫大な交付金を与えて、朝日、毎日、読売などの大手中央紙を巧妙に牽制しながら、言論統制を推進したのである。
情報宣伝システムはさらに太平洋戦争へ向けて整備され、言論統制の最終的な決め手となったのが、用紙統制であった。
戦時体制が進行するなかで、不要不急品の制限という目的で用紙割り当てがおこなわれ、新聞、出版にとっての死活にかかわる用紙の統制が、一つ加えられた。
政府へ批判的なこ怠納やメディアは用紙割り当てをてこに締め出され、弱小紙の整理統合が強引に進められた。
内閣情報局によって立案された統制団体である「日本出版文化協会」が1940(昭和15)年、「日本新聞連盟」が1941(昭和16)年に相次いで設立される。
一県一紙を目指した新聞の整理統合は1943(昭和18)年10月に完了するが、新聞は統合前に2422紙あったのが55紙に、出版社は3664社が203社にされていた(塚本三夫「戦時下の言論統制」 城戸又一・新井直之・稲葉三千男 編『講座現代ジャーナリズム歴史』時事通信社、1974年、147頁)。
■9 平洋戦争下の言論統制
1941(昭和16)年12月についに日本は太平洋戦争に突入した。
太平洋戦争中にはそれ以前の日中戦争下などとは比べものにならないほど厳重な思想、情報、言論統制がおこなわれた。
【治安、警察関係】 刑法、治安警察法、警察犯処罰令、治安維持法、言論・出版・結社等臨時取締法、思想犯保護観察法
【軍事、国防関係】 戒厳令、要塞地帯法、陸軍刑法、海軍刑法、軍機保護法、国家総動員法、軍用資源秘密保護法、国防保安法、戦時刑事特別法
【新聞、出版関係】 新聞紙法、新聞紙等掲載制限令、出版法、不穏文書臨時取締法、新聞紙事業令、出版事業令
【郵便、放送、映画、広告関係】 臨時郵便取締法、電信法、無線電信法、大正十二年通信省令第八十九条、映画法、映画法施行規則、広告取締法
このほかにも、新聞にかぎると、さらに内務省差止事項、陸・海軍、外務省による禁止事項、宮内省の申し入れ、情報局懇談事項、大本営発��、指導原稿でがんじがらめにされた上に検閲が2重3重におこなわれ、情報局、内務省、陸海軍報道部、航空本部、警視庁検閲課でチェックされた。
検閲の総本山の内務省警保局検閲課には1942(昭和17)年5月当時、85人の担当者が目を光らせていた。
このなかに新聞検閲係があったが、43年中の新聞の事前検閲ほゲラ刷、またほ原稿によるもの約9万件(一日平均250件)。
このうち不許可処分は1万2000件(全体の13%)にのぼった。また、電話によるものは約5万件(一日平均140件)で、合計14万件に達した(松浦総三『戦時下の言論統制』白川書院、1975年、108頁)。
■10 コミュニケーションの自己崩壊
こうしたきびしい検閲で、開戦直前の日米交渉での野村・ハル会談は「朝日新聞」の特派員が60数行の特電を送稿したのに対して、最終的にたった2行半に削られてしまった。
交渉内容が書けないのは仕方ないにしても「2人はまず握手を交し」が対米親近感を表現する、「会談一時間」が交渉緊迫感をかもし出す、「交渉はなお続行されるだろう」が前途推測不可でズタズタに削られた結果であった。
太平洋戦争がはじまったころの検閲の実態について、朝日・毎日・読売とわたり歩いた名文記者として知られた高木健夫は次のように述懐している。
「新聞社に報道差止め、禁止の通達が毎日何通もあり、整理部では机の前にハリガネをはって、これらの通達をつるすことにしていた。この紙がすぐいっぱいになり、何が禁止なのか覚えているだけでも大変で頭が混乱してきた。禁止、禁止で何も書けない状態であった」
こうした徹底した検閲の一方で、太平洋戦争の報道のシンボルと化したのが、大本営発表である。
嘘と誇大発表の代名詞となった <大本営発表> だが、戦争の最初の半年間は戦果や被害はほぼ正確であった。
それ以後は戦果が誇張され、最後の8ヵ月は嘘の勝利が誇示された。戦争の全期間を通じて、戦艦、巡洋艦は10・3倍、空母6・5倍、飛行機約7倍、輸送船は約8倍もその数を水増しして発表された。
事実の徹底した秘匿、検閲というコミュニケーションの切断が逆に虚報を生み、増幅して、送り手と受け手の相互関係を成立不可能にしていく。
戦前のファシズム体制を支えたメディア統制の総合的極限的システムはこのコミュニケーションの断絶によって、自己崩壊していったのである。
[EOF]
(出典)→日本メディア検閲史 <新聞法、出版法について> | 前坂俊之オフィシャルウェブサイト http://www.maesaka-toshiyuki.com/massmedia/3838.html
0 notes