#ふわもこ部うさぎ課垂れ耳係
Text
蜃気楼の境界 編(一二三四)

「渦とチェリー新聞」寄稿小説
連載中のシリーズ、第一話からの公開、第七話まで。第八話以降、朗読版に繋がり、最新話に辿り着けます。
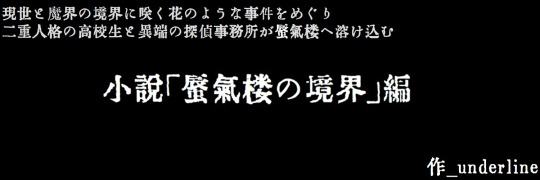
蜃気楼の境界 編(一)
序件
赤に黄を混ぜると橙になるとか、分子だとか原子だとか、決まりごとで世界を理解した気になれるとしている人達の視た光景が世界の基準になっていることがそもそも気に食わないと、二〇一六年春、高校一年生になったばかりの渡邉咲は思っている。彼女はやがてクラスに、背が高く視力の悪い市川忍という一見平凡な男子生徒がいることに気づくだろう。麗らかな新大久保、韓国料理店をはじめとした多国籍渦巻く通り、彼女よりも背の高い通行人達の隙間を縫いながら気分よく和楽器専門店へ向かう道すがら、迷いのない機敏さですれ違った、いつだったか見たような気のする少女に勘が働き、あとを追うと、二人の男が対立していたのだ。さっぱりとした面立ちの男が軽やかに束感ショートの若い警部補に、これは高橋さんお久しぶりです、と話しかけるが、その警部補は、探偵に用はないよ、と軽くあしらう。少女は、この探偵と警部補の間を通り過ぎ、可憐に立ち止まり、一、三、三十、千五百と口にしたのだ。新規上場企業連続殺人事件の際はな仲本慧きみのお世話になったが、警部補がいう、本当に高くついたよ闇のポケットマネーだった、今回の捜査はもう済んでいる高知県岡内村の淵に発見された男の水死体はここのホステスとの恋の縺れで半グレが実行したと調べがついている。ところが、探偵仲本慧は、隠れて話を聞いていた渡邉咲が耳を疑うようなことを坦々と喋りだしたのだ。少女崔凪が口にした数から推理するに、彼女の身長百五十センチが百五十万μm(マイクロメートル)だね、目視可能な基準五十μmより小さい花粉が三十μmで飛沫や通常マスクの捕獲サイズが三μmで細菌は一μm、零点三μmはN95マスク捕集サイズ、零点一μmはインフルエンザやコロナのウイルスサイズつまり著名なウイルスは人間の千五百万分の一の小ささでその一回り大きい細菌が百五十万倍の少女を視れば頭は火星にあり地球からの距離十三光分だね月までなら一点三光分、符号、十三、仲本慧が楕円を描くようにぐるぐる歩く、火星は周期七百八十日で地球に近づき月との接近を天上で愉しめるわけだが今年はそれに当たる、七百八十と十三に関係する郵便番号が高知市青柳町で、そこに住む犯人は七百八十日周期で男を殺しに東京を訪れる。
雑居ビルの階段下で警部補は少女崔凪を見、腰を低くし、初めまして警部補の高橋定蔵だ、二年前はお世話になったがきみは知ってるのかな、という。崔凪は強い瞳のまま無言。警部補は探偵に、依頼はしてないから助言と受け取るがどうして事件を追ってる。陰で話を聞きながら、渡邉咲は胸を熱くしている。着信音がする。それを無視した仲本慧、曰く、単なる不倫調査で慧探偵事務所の探偵チームはターゲットの男がある女とホテルへ入るところを写真に収めたが依頼の追加でその女のプロファイルを求められたという。追加依頼を探偵チームに投げようとしたとき事務所に遊びにきた崔凪が、一、三、三十、千五百と自ら口にしたのだ。推理から、と仲本慧はいう、写真に収めた女は、蜃気楼だと気づいた、真の不倫相手の女、つまり犯人が、虚の像を追わせたのさ、ここのホステスは事件の蜃気楼、無関係だね。渡邉咲は、どういうこと、と驚くが、何度か鳴っていた事務所からの着信を仲本慧が受けて、崔凪に、さぁ行こう、と告げ、去り際、ふと足元を見、ツバキの花は境界に咲くというが、現世と魔界の境界にも咲くんだね、と笑みを浮かべる。警部補は二人を追わず高知警察署へ連絡しているらしい。数日後、高知の青柳町に住む女、宮地散花が連続殺人容疑で逮捕されたことを渡邉咲はニュースで知り、午前の授業中はずっと雑居ビルの階段下でのやりとりの記憶に捕らわれ、探偵仲本慧の絡んだ事件の真相って境界の狭間に咲く花のよう、と夢見心地になるが、少女崔凪による真相は、甲乙ムの三文字の一体である鬼を抱く宮地散花が千五百年つまり明応九年に践祚した後柏原天皇の詠んだ歌、心だに西に向はば身の罪を写すかがみはさもあらばあれ、に心打たれるも意味を取り違え、三十人の男の供養を願ったことに始まる。その鬼の念、情景を歪ます程に強く、探偵や警察を巻き込み、一高校生渡邉咲さえ巻き込んだが、彼女は探偵仲本慧による更なる次元さえ加わった渦の中でときめいている。その様は、クラスメイトの市川忍の何かを揺るがしたのだ。窓の下、体育館でのバスケの授業をずっと眺めていた市川忍は、突然渡邉咲の存在に気づき、それは彼のもう一つの人格、仟燕色馨の方が先だったかもしれない。胸騒ぎだ。
蜃気楼の境界 編(二)
書乱
春の夕、上海汽車メーカーの黒い車が高田馬場駅は西、高校の校門を通過し、停車する。奇妙な車がよぎった、脳裏より声。授業も聞かず窓の下、体育館でのバスケの授業をぼんやりと眺めていたが、脳裏に響く声に高校一年生の市川忍、カジョウシキカ唐突に何だよ、と聞く。一昨年にきみを冗談交じりに犯人と疑ってみせた探偵がいたのを覚えてないか。そう問われたものの市川忍は思いだせず、それがどうかしたのと内側へ声を。すると、微かなタイヤの摩擦音と停車音の比較から目的地はすぐ側の一軒家だろうちらと見えた、運転手がその探偵だ、という。この七年前は二〇〇九年五月、関西の高校生から広く流行した新型インフルエンザ以降雨の日以外つねに窓が少し開けられている。空気は生ぬるい。チョークの音。市川忍、幾つか机の離れた席に座る渡邉咲に視線を送る。チャイムの音が鳴り、放課後、別のクラスの生徒、石川原郎がやってきて無造作に横の机に座り、市川おまえ高校はバスケ部入らないの。まあね。受け応えしながら机の中の教科書類を鞄にしまっていく。渡邉咲立ち上がり、教室の外へ。一書に曰く(あるふみにいわく)と仟燕色馨の声が響く、混沌のなか天が生まれ地が固まり神世七代最初の神、国常立尊が生まれたが日本書紀に現れない五柱の別天津神がそれより前にいて独神として身を隠したというのが古事記の始まりということは教科書にも書かれていたが先程の古文の教師はイザナギとイザナミの二神から説明した、これもまた一書に曰く、数多の異神生まれし中世ではアマテラスは男神ですらあり中世日本とは鎌倉時代からつまり末法の世まさに混乱した世の後で超自然思想は流行り無限の一書織り成す神話に鎮座し人々は何を視ているのか、きみが気にしている渡邉咲、退屈そうに探偵読本を机の中に置いていった、大方、探偵に夢を見、探偵業に失望したのだろう、数分の場所に探偵がいる。市川忍は脳裏に響くその声をきっかけにし会話一つ交わしたことがない渡邉咲のあとを必死で追う。走りながら、どう呼びかけるのかさえ決めていない。仟燕色馨のいう一軒家は平成に建てられた軽量鉄骨造で、渡邉咲が通り過ぎた頃合いで咄嗟にスマホを耳に当て、探偵が入っていった、と強く言う。驚き、振り返る渡邉咲。
目黒にて桜まじ、遊歩す影二つ。吹く風に逸れ、冷たし。怪異から死者が幾人、立入禁止とされた日本家屋をちら見し、一つの影、あァお兄様さらなる怪奇物件作りどういたしましょうと口元を手で隠し囁く明智珠子に兄、佐野豊房が陽炎のごとき声で私達はね共同幻想の虚空を幽霊のように漂っているんです、井戸の中で蛙は鬼神となりたむろする魍魎密集す地獄絵図の如き三千大千の井戸が各々の有限世界を四象限マトリクス等で語る似非仏陀の掌の架空認識から垂れ下がる糸に飛びつき課金ならぬ課魂する者達が世を牛耳りリードする妄想基盤の上で生活せざるを得ないならば、宇宙に地球あり水と大地と振動する生命しかない他のことは全て虚仮であるにもかかわらず。明智珠子がその美貌にして鼻息荒く、あの探偵とだけは決着を付けなければいけませんわ、家鳴の狂った解釈で恐怖させる等では物足りません残酷な形で五臓六腑ぶちまけさせなければ気が済みません。佐野豊房は、だがただ凍風を浴びるがままである。翌週は春暑し、件の探偵仲本慧はそれでも長袖で、奇妙な失踪調査依頼で外出している。我が探偵チームが二日で炙りだしたターゲットの潜伏ポイントは男人結界つまり男子禁制の聖域だからねと探偵事務所二番窓口女性職員橋本冷夏にいう、琉球神道ルーツの新興宗教だそうだ。いつも思うんですが年中長袖で暑くないんですか。東京中華街構想があった年と探偵仲本慧プロファイルを口にする、同士と約束したんだねハッタリ理由に青龍を肌に翔ばす気がなかったから年中長袖を着る決着にしたわけだ。えっ、一体何が。その会話を引き裂かんとついてきていた少女崔凪、突飛な言葉を口にする、卑弥呼は、自由じゃない。ハッとし振り返った仲本慧問いかける、今回の件、どう思う。崔凪、気分良さげにいう、男子禁制だから教えられない。生暖かい風が東京湾から。晴海アイランドトリトンスクエアをぐるっと回ってみたわけだが、と元の駐車場に踏み入った仲本慧、あれはかつて晴海団地があった土地だね、我が探偵チームが弾き出した潜入ポイントにも寄った方がいいかもしれないね。そうして訪ねた一軒家の門の外、仟燕色馨を秘める二重人格者は市川忍と、探偵仲本慧を気にする渡邉咲、二人の高校生が現れたのだ。
蜃気楼の境界 編(三)
朔密
白雨あったか地が陽を返す。探偵との声に驚き振り返る渡邉咲の前に市川忍。彼をクラスメイトと理解する迄に数秒。バスケ部上がりの忍は別世界の男子生徒に見えたし圧も弱く視野外にあったのだ。水溜りを踏んで市川忍は彼のもう一つの人格仟燕色馨と心の内側で会話をしている。探偵が入っていったとスマホを片手に口にしたが通話はしていない。咲に向け、ここで事件が起こっているから静かに、俺には知り合いに探偵カジョウシキカがいて今彼と話していると囁くように言い、表札にある「朔密教」と火と雫の紋章、白い香炉を模った像をちらと見、呼び鈴を鳴らす。片や探偵仲本慧はその軽量鉄骨造の一軒家の門の斜め向かい、車中にいる。突然現れた高校生の男女がターゲットの家の呼び鈴を鳴らしたことで注目する。ガチャと鳴り玄関から高齢の女、倉町桃江が姿を見せ咲を見ると、何か用ですか、と聞く。戸惑う咲の前に出、忍、朔密教���見学に来たのですが、というと、男子禁制ですから、そちらのお嬢さんだけでしたら。運転席の仲本慧とともに慧探偵事務所窓口職員橋本冷夏が後部座席から降りるが助手席に座る少女崔凪は出てこない。通り雨は天気予報になかったねと口にしながら歩み寄る仲本慧を間近に見た咲が紅潮する。仲本慧が高校生二人を一瞥し、倉町桃江をじっと見つめ、貴女がここの教主ですか、こちらの橋本冷夏が見学に来たのですが。ぬるい風に織り混ざる卦体。そうですか。倉町桃江は表情一つ変えず、弥古様はおられませんが、さ、どうぞ、屋内へ消える。門前に探偵と忍と咲が残る。脳裏の声に促されて忍、何か事件でもあったんですか、と慧に。素性を見抜かれた質問を受けた慧はほんの僅か忍を見、ああきみは以前事件のときに少し話かけた学生だね、とにっこり笑いながら名刺を差し出し、慧探偵事務所の仲本慧だ、困ったことがあればいつでも訪ねてくるといい金額は安くはないけどね、そう話を逸らす。スマホを耳にあてた忍は仲本慧の目をじっと見て、知り合いの探偵と連絡を取りあってるところでもしかしたら同じ事件を追ってるのかも、弥古様を、と挑発する。ここに、咲の目前で、二人の探偵の戦いの火蓋が切られたのだ。咲の気をひく為に市川忍によって仟燕色馨が探偵とされた顛末である。
門と玄関の境界の片隅、雨露に濡れるツバキの花に気づくのは、仲本慧のスマートフォンに朔密教内部に潜入した橋本冷夏から失踪調査対象は石文弥古の姿見当たらずとのメッセージが届き、車内の崔凪に視線を送った直後、片や、市川忍の視界には、はらはら雪が舞い、脳裏に津軽三味線の旋律流れ、声響く、曰く、表札に火と雫の紋章があったがイザナミが命を落とすきっかけ火の神カグツチを当てれば雫はその死悲しむイザナギの涙から生まれしナキサワメであり白と香炉を模った像から琉球の民族信仰にある火の神ヒヌカンを合わせれば朔密教の朔は月齢のゼロを意味し死と生と二極の火の神を炙り出せるだろう男子禁制からヒヌカンによる竈でのゼロの月の交信を弥古様は隠れて行い目的はイザナミの復活か、次元異なる宗教織り成す辺りの新宗教らしさから朔密の密を埋没神と見るなら竈は台所更には死した大いなる食物の神オホゲツヒメの復活とも関連し故に弥古様は台所を秘めたる住処、家としている。この象徴的絵解きのごとき推理の意味が市川忍は何も分からなかったが解が台所であることのみ理解しスマホへ向け成程仟燕色馨、君の言う通りだ敢行するしかないねと言い渡邉咲を見、ねぇ仟燕色馨から君にお願いがある、この中は男子禁制、だから、と耳元に。咲はこのとき、心を奪われたのだ、市川忍ではなく、仟燕色馨の方に。現場が男子禁制ゆえに崔凪の手助けが得られず動揺して仲本慧は自力で推理する。ここへ来る前に出向いたかつての晴海団地はダイニングキッチンが初導入されそれを一般家庭に普及させた歴史的土地で朔密教が琉球神道ルーツの新興宗教であることは調査班の報告で分かっているから潜入した橋本冷夏は台所へ案内されている筈、儀式は日々そこで行われるが石文弥古の姿はないという、ならどこに。その事務的に戸惑った様子が渡邉咲には探偵読本にもあった只の組織である商売人の探偵にしか見えなかったのだ。咲は仲本慧を背にして走り、玄関をくぐり、朔密教内部に潜入する。だが、濡れた車、助手席から出てきた少女崔凪が数字の羅列を呟き、仲本慧は、そうか分かったぞ、と声をあげて橋本冷夏に通話する。崔凪が、涼しい顔でのびのびと呟く、負けるくらいなら今だけ男子禁制じゃなくてもいいかな。

蜃気楼の境界 編(四)
你蜃
燻銀の月が空に二人の高校生公園で座る。笙の天音が鳴り、お母さんだ、とラインの返信をしながら渡邉咲、探偵カジョウシキカは推理で勝っていた、と市川忍を見、探偵仲本慧に出会ったきっかけはそもそもあの少女崔凪だったと思いだす。一昨年にこの公園で鼻歌交じりハーブの栽培をしてた子だ、だから見覚えがあったんだ、と。軽量鉄骨造一軒家、朔密教本部から出てきた探偵職員橋本冷夏に、今宵は重慶三巴湯と青島ビールで宴会だね、と上海汽車メーカーの黒い車へ去る仲本慧の側にいた少女崔凪が高校生の二人をちらと見ふっと笑う。市川忍は悔しがるだけで、だがその内側に潜むもう一つの人格仟燕色馨は市川忍の瞳を通し崔凪をじっと見つめる、夜の公園で仟燕色馨、只の勝負なら勝敗などは所詮遊戯それに君も渡邉咲と親しくなり目的は果たしているだろうしかし慧探偵事務所は現世と魔界裏返りし境界ありこれは魔族の矜持に触れるゆえ既に仕掛けをしている君も再戦を覚悟してほしい、と。その脳裏からの声の本意を掴めない市川忍に、咲、貴方のお知り合いの探偵さんはどう言ってるの。その輝く瞳妖しく、市川忍はときめく反面恐怖を覚え、無意識にポケットから作業用の黒ゴム手袋をとりだす。刹那、何故か海峡で波を荒らげる雪景色に鳴り響く津軽三味線の調べが聞こえ、再戦を望んでると伝えると、只ならぬ興奮を見せて咲は喜ぶのだ。先刻、朔密教内部へ駆けていった咲は、仟燕色馨の伝言、台所の真下に女の住居有り、を忍から受け儀式行われし白い炊事場を目指したとき、倉町桃江の脇で動揺する橋本冷夏の姿を見たが、その元に着信が入り中国語で会話を始め、瞳に青龍の華が光れば、香炉、水、塩、生花を払い除け床下収納庫の先に階段を見つけると、独房のような地下室で失踪調査対象である石文弥古を発見、最早咲は事の成り行きを見届けるのみ、異変の只中で、少女崔凪の存在が頭によぎったのだ、確かに探偵仲本慧は推理が届かず動揺していた、何か得体の知れない事が起きたのだ。それにしても、咲は思う、探偵仟燕色馨どのような人なのかな、市川忍という同級生がどうして魅力的な探偵さんとお知り合いなの、ふふ、取りだしたその黒ゴム手袋は何、月がきれい、まるで、私の住む世界のよう。
朔密教、明治に明日香良安が琉球神道系から分離し設立した新宗教である。分離したわけはスサノオに斬り殺されたとされるオホゲツヒメの復活を教義の核に据えた故で、同時期に大本で聖師とされる出口王仁三郎が日本書紀のみ一書から一度だけ名が述べられるイヅノメ神の復活を、同様に一書から一度だけ名が述べられるククリヒメの復活を八十八次元の塾から平成に得た明正昭平という内科医が朔密教に持ち込み妻の倉町桃江を二代教主に推薦し本部への男子禁制を導入、女埋没神の全復活によりイザナミ復活へ至る妻のお導きを深核とし今の形となる。女埋没神はイヅノメ神、オホゲツヒメ、ククリヒメの他に助かったクシナダヒメを除くヤマタノオロチの生贄とされた八稚女らがあり、更には、皆既日食により魔力が衰え殺されたとされる卑弥呼を天照大神と見定めての復活とも融合している。それらを依頼主に説明しながら仲本慧は殺風景な部屋で分厚い捜査費用を懐に入れ、他の探偵にも依頼してないかな、と冷えた目を向ける。依頼主である小さな芸プロのマネージャーは、業界に知られたくない件だから貴方を紹介して貰ったんだ、深入りはしない彼女どういう様子でしたと聞く。調査ではと仲本慧、社会にある数多の既存の道筋を歩めないという認識から石文弥古は芸能に道がないか訪ね、今は朔密教を訪ねているのだろうね、弟以外の人の来訪を絶ち鬼道を続けたとされる卑弥呼の形式で、倉町桃江の最低限の関わり以外を完全に断って地下で儀式を八十八日間続ける任務を受け入れた石文弥古は、我が優秀な女子社員いわく、自らの意志とのことだ。屋外へ出、仲本慧、通話し、高校生市川忍を調査して、という。崔凪の口にした数は、四四八、二四七、一三七。仲本慧はタワマン供給実績数を推理し晴海団地へ出向いたわけだがその推測は二〇二一年の上位三都府県に予知のごとく一致し、崔凪はのちに数列に隠していた八十八を付け足し、慧の推理は台所の地下へと変化したが、二四七が卑弥呼の日食の年を指すように、海とされるワタツミ三神がたとえ人智の蜃気楼であってもなくても推理と崔凪の真意とが違っても。仲本慧は思う、人々は、この街は大地は、紀元前、胡蝶の夢は一介の虚無主義ではない知が、華が、騒いでいる。
by _underline
蜃気楼の境界 編(五六七)へ
0 notes
Text
落石
Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside us while we live.
by Norman Cousins
〜序章 今〜
真っ白な中にいま僕はいる。周りは虚無とカオスが広がり、何もできない。ただ、いま自分が出来る最大限の努力は呼吸をし命をつなぎとめることだ。ゆっくり途方も無い道のりを重たい足で歩き続ける。歩き続けることがいつか、きっと僕にとって何か、良いことをもたらすのではないかと思いきかせた。白く、一点の濁りもない中をただひたすら飽きることなく足を動かすことを続けた。
不意にある人の事想う。ああ、あの人と結ばれたらな。いや、もうあれは過去だ。過ちだ。何を僕は引きずっているのだろう。幾度となく、偽りの意見を反芻させた。目を閉じ、呼吸を整えた。
漆黒の闇から急に現れた、たった1人の人間に狂い戸惑った。気づけば周りにはなにもかも手放していた。自分の、判断だし、決断でもあった。おかけで今なにも関わってくれる人も、動物もいない。そして、今僕は虚無にいる。全ては自業自得なのだ。
〜第2章 過ち〜
目が覚めた。どこか重たく、身体全体に痛みを生じた。目もなかなか、開けることができない。いつもの朝とは違い、日の光りを感じられない。そのせいか、起き上がるのに、10分以上はかかった。僕にとってはかなり遅い方だし、他の人と比べて寝起きはいい方だ。その日は休みだった。飲み過ぎても仕事に支障が出ないようにと、希望休をとっていた。変なところ真面目だよねと大衆に言われる所以がこのことなのかもしれない。
その日そんなに早く起きる必要はなかったがなぜか起きた。どこか気持ちが、心がいつもより落ち着かなかった。目を開けることにためらい、もう一度寝ることを考えた。しかし、いつもとはちがう、違和感を覚えた。僕の部屋はお世辞にいっても綺麗じゃない。ただ、今自分の嗅覚から感じるのはフローラルでとこか愛したくなる香りだった。当時、コーヒーを勉強していた僕は香りに敏感だった。今まで嗅いだことのない、落ち着いていて、どこか派手な綺麗で美しい香りだった。まるでアジア太平洋産の��ーヒーを思わせる、どこかどっしりとし荒々しいコクとハーブを感じるような繊細さを僕は感じた。
その香りは、確かに、自分の部屋から香ることのできない香りなのは明確だった。だからこそ、目を開ける勇気がなかった。あの繊細で、どこか悲しい香りは僕は感じたことない。多分、目を開けて現実を見てしまったら後悔することもわかっていた。しかし、僕はゆっくり目を開けた。どんな現実も受け入れることを僕は覚悟した。そこは真っ白でなんの変哲も無い白い天井だった。また、予想通り日光はカーテンから少し漏れるだけの光しかベッドには届いていなかった。そして僕は裸だった。スタイルがお世辞にもよくない身体がベットに放り込まれている。身体は重く、ベッドに根を生えているようにも思えた。この時点で少し飲み過ぎたことを、後悔した。気分と身体の両方の違和感に耐えきれず、少し寝返りをうった。その時何かを触った。柔かく、どこかハリがあり、触るといまにも跳ね返されそうな弾力だった。指先から伝わるシナプスが脳みそに達したが何かは特定できなかった。もう少し触りたかったが勇気がなかった。そして、一度そこで寝返りを止めた。正体を知ってしまったら、真実に追いつけず、自分の偽りの世界を作り逃避する気がしてならなかった。それが楽なのはわかっていたがどうしてもしたくなかった。向き合うことが僕の数少ない良い点の一つだと理解していたからだ。そしてそれを永遠に自分に自分の武器として、自分の存在を誇示するために持ち続けていたかった。
重たい体をゆっくりと左45度に傾け、現実を見ることを決意した。ぼんやりと映る姿にかすかに見覚えがある。どこかでみたことあり、僕の小さな脳で思い当たる節を探した。学生時代のそんなに多くない友人、ゴルフで出会った仲間、バンドなどで交流を持った人たちなどを当てはめたがどれもちがった。誰かはわからないが、確実にそこにあるものは女体だった。お世辞にも白とは言えない肌ではあるがハリときめ細かさはある。お尻もそれほどありかつひきしまっており、くびれがとても特徴的だ。乳房は少しお椀型でハリもあり乳首は程よく黒がかり僕の好みな形、色だった。髪色は明るめな茶色では、あるものの落ち着きがあり、ショートとロングの間、つまりミドルほどの長さだった。カーテンがなびいている下で、少し日に当たるその姿はどこか幻想的で魅力的で現実に存在する人間には思えないほどの美しさであった。まだ、誰かもわからないが見ていると落ち着くし、このまま時が止まってくれないかとおもった。もちろん、止めることなどできない。
気づいた時には深い眠りについていた。身体の重さは幾分なくなり悪酔いが冷めてきたのが、明らかに実感できた。さっきとは違い外界の光がもろにあたり、風も感じることができた。カーテンが顔なで今にも部屋全体の小物たちが起きなよ、と言わんばかりだ。今時間は何時だろう、ふと思い、また誰かわからない女体の隣でよく寝れたなと自分に驚く。
「おはよ」
聞いたことのある声が僕の背中を包んだ。どこか、優しくも冷徹な声が特徴的だ。恐ろしく、顔を見ることも、もちろん振り返ることもできない。畳み掛けるように女体は話す。
「昨日飲みすぎたようだけど大丈夫?」
やはりかと思った。今までにない酔いが朝遅い、違和感が心を包んだ。僕は平静を装いどこか洒落臭く返事をした。
「あんなんじゃ、酔わないよ」
僕は女体の顔見なくても笑っていることに気づいた。
「へぇー、毎日晩酌してるだけあるわね」
この時、いくつか女体の候補を絞ることができた。晩酌をしていることは少数人にしか告げてないし、なんなら幾分恥ずかしいことではあるから、大々的に自分から発信はしていない。かなり仲の良い、あるいは直近で会話をしている人に絞られる。
「最近そんなに飲んでないよ」
少しかまをかけて、発言した。最近の飲酒量は軒並み右課題上がりをし、来月の健康診断はもう絶望的だ。直近で会話している友人にはその話を何度も話をしている。
「最近飲むのふえてるじゃない。この前も電話した時酔いつぶれてたわよ」
ここで確信をついた。最近ある1人とよく通話をする。同じ職場の人だ。衝動を抑えきれず体の向きを変えて顔を見た。
女体はニヤっと笑った
「椿、、、」
「おはよ」
ドス
頭の中で何かが落ちた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
僕はそこそこ名前の知れている商社に勤務している。商社ではあるが、ほぼサービス業であるため平日やすみが基本だ。平日休みでの特権をまだ実感していない。強いてゆうのであれば、ふとした時にドライブなど外出するとき弊害があまりない。人混み、交通規制、こどもの泣き噦る声などストレスを与える要素がない。もちろんデメリットもある。友人関係が、がらっとかわった。だいたいの友人は土日休みであるため休みが合わず、交流する時間がなく連絡する頻度もすくなくなり疎遠気味になってしまった。また、ある友人は遊べる回数などがすぐなくなったからか、付き合いが悪いなどと吐き捨てられたこともあった。こうして、休日に過ごし方は狭い自宅で引きこもるか、職場仲間と軽くご飯に行くことしかできなかった。時々コミニュティーの狭さに驚愕し、過去自分の思い描いた誇らしき人生の理想との乖離に不安と絶望に日々打ちひしがれるのであった。
僕は時々死をも考えたこともある。富士の樹海で首を吊るいくつもの死体に憧れたこともあった。自分もそのうちの一つにどのようになれるか、考えたこともあった。でも、後一歩のところで勇気が出ずにいた。死ぬ勇気さえ僕には持てれなかった。僕が愚かであることは明確だった。
ただ、仕事での悩みは無いと言ったら嘘ではあるが、さほど気になるほどではなかった。横山と稲村の紛争を常に仲裁して、チームの空気が悪くならないようにいつも注意をしていた。仲間とのコミニケーションを常に積極的にとり、チームの不満やいわゆる膿を出す役割を僕はしていた。人からはそれらは重みでストレスのかかるものであると言うが、僕は気にならなかった。むしろチームが良い方向に前進していることを日々実感し、達成感に浸れた。それが仕事の一つのやりがいであることは否めないし、自分の一つの居場所であったことも確かだ。ただ、その居場所や仲裁に入るのもなかなか至難の技であった。
横山はチームリーダーとして、1年前に配属された。彼は、スタイルがよくイケメンと言う部類にはいり見た目はどこかアグレシッブで仕事に対して強いこだわりがありそうだった。ただ、その見た目とは相反するような過去を持っていた。
19XX年、横山はファッション系の仕事についていた。彼は現場に強くこだわった。彼が配属されたのは西山駅の正面にある、お店も売り上げもかなりボリュームのある店舗だった。店の正面には街のメインストリートがあり、土日には車両の通行が禁止される、謂わば歩行者天国になる。また、道の向かいには最大級のデパートがあり、平日土日関係なくいつも人でごった返している。店の周りにも競合店揃いのファッション系ブランドのお店が軒を連ねる。そこでその店は勝ち取っていかなければならなく、横山自身かなりのプレッシャーであった。前任のマネージャーは成果を出すことができなく半年で別の店舗に異動をした。左遷とも噂された。
横山は客の求めているものを的確に会話を通じて探し出し提案することを目標としていた。そのことを認められたか、前年よりも売り上げを伸ばし上層部にはかなり高い評価で認められた。��社にも評価され次期エリアマネージャー候補とも囁かれていた。横山は仕事にやりがいを感じ、通勤にも片道2時間という長いものであったが文句どころか、毎日が充実していた。
忘れもしない10月20日。いつもどおり横山は出勤した。大通りに群がるスーツをみにまとったサラリーマンをかき分け、店の正面まで歩く。あまりの人の多さで、後ろへ押し流されながら歩き続けるのは一苦労だ。店の鍵は全部で5つある。正面の扉が2枚あり、一枚の扉に上と下1つずつ鍵がある。鍵を開けると30秒以内に店の事務所のセキュリティの機械に鍵を取り付けないとアラームがなる仕組みだ。
この日もアラームを解き、オープン作業を一緒に行うパートの人を待った。作業が始まる9時30分にも来なかった。ここのお店に着任してからはじめての経験であった。パートの携帯に着信を入れたが冷酷な自動音声が聞こえる。
「ただいま電話に出ることはできません」
が横山の耳に響く。まるで暗く深い洞窟の中で聞こえるように。
几帳面で真面目で無断欠勤などするタイプではないため、怒りよりも心配がかった。事故か事件か、最悪の状況が頭をよぎる。とりあえず何事もないことを祈った。電話が早くかかってこないか、気にしながら開店作業を黙々と進めた。本社から送られてきた服や小物の納品物を片付け、陳列。店内の掃き掃除、また陳列されている服の整理、などいつもよりも同じ時間で2人分の作業をしなければならないため、時間の体感速度はかなりのものであった。店内に開店まであと5分のチャイムが鳴り響く。当然間に合うはずもなく、開店してから残った作業をすることにした。急いで、事務所に戻りレジの開局作業に取り掛かった。両替準備金を数え、パソコンに入力し、開局させた。もう、幾度となく行った作業のため、手慣れたものだ。毎日同じことの繰り返しであったが毎日同じモチベーションで仕事をすることができた。人はそれを、嘲笑い鼻でわらい社畜だと罵った。横山はそのことを何も感じもしないし、馬鹿にする方が馬鹿だと感じた。
そんなことを頭で回想をしていると気づくと1分前のチャイムが鳴る。横山は店の自動ドアの正面に背筋をのばして、客を迎い入れる準備をした。静寂の中を切り裂くように、店内アナウンスが入る。開店だ。深呼吸で心拍数を安定させる。今日も始まる。
横山は客に向かってしっかりと大きな挨拶をした。
「いらっしゃいませ」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
10月20日夜、街中の有名な居酒屋で団体グループのせいで予約がいっぱいだった。店もてんやわんやで、少ない人数で営業していた。キッチンには洗い物が山積みになり、ドリンクをテーブルまで提供するのに精一杯であった。従業員がベルトコンベアーで流されているかのように機械的にキッチンからドリンクがかなり乗ったトレイを持ち、テーブルまで運んだ。なぜか従業員には顔がない。じっくり見てもそこには何もなく、カオスで色も特徴もない。まるでロボットが店舗を運営しているように感じた。何も面白みも、魅力も感じないお店だ。多くの人が二度と行くことはないというだろう。実際その半年後お店は潰れたという。詳しくはわからない。
その日の団体の客は横山の働くお店の集まりだった。幹事の伊藤は重たい口を開け、淡々と話を始めた。
「ボイコットに参加してくれてありがとう」
参加者は息を飲む。この言葉は絶対に聞くことは覚悟していたし、ボイコットしたことも事実だ。しかし、改めて耳からその情報を聞くと様々な考えが頭をめぐり実感と責任感が心臓からゆっくりと湧き上がるのがわかった。まるで血液のようにその感情が身体中をめぐり次第に身体が硬直していくのがわかった。参加者のうち華奢な男の1人が口を開いた。
「これで横山も終わりだな。」
伊藤はその言葉をきき深く項垂れ、自分の今の行動がどの程度影響し波及していくのか想像するのができなかった。想像したくないのではなく伊藤の脳みそではキャパオーバーでこれからのことがわからなかった。どのようにこれから自分の立場が変わっていくのかも先を見越した行動ではなく瞬間的で能動的であったことは間違いない。そして、伊藤はこれにきづくことはなかった。
伊藤は何かを決心したかのようにまた鉄の扉のような唇を開けた。
「そうだな。祝おう。皆で。」
重苦しくどこか窮屈な空気の中冷やかしのようにグラス同士の冷たく乾いた音が部屋中に響き渡る。乾杯のこともそこに明るさはなく海の奥深く光の届かない場所にいるかと錯覚するぐらい暗く意味深なものであった。主婦がお酒を飲みながら現実を受け止めたかのように話をした。
「私、本当にボイコットしたのね」
伊藤がゆっくりと口を開いた。
「そうだよ。俺らはやったんだ。でもこれも全て横山がわるい」
「そうわよね。自業自得だわ。」
主婦はそう言い放ちグラスを空にした。無理やり流し込んだせいか咳こんだ。その音さえ虚しく聞こえる。
伊藤が息を吐き思いつめながら鍋をつついた。
鍋には色も何もないカオスが広がっていた。なぜだろう、食欲も湧かないしそこには何もない。物理的ではなく精神的に。
「明日からどうなるかな」
空虚な世界にその声だけ響いた。周りは静かに息を飲んだ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
枯葉が落ちある種のイルミネーションが広がっていた。自然が作り出すトンネルはどこかに吸い込まれ迷走しいずれ消えていくことを実感した。皆口を開け小さな頭の中で回想する。出口はどこなんだろう。
横山は会社に解雇された。ボイコットの日から次の日でだった。次の日も従業員は誰もこず、たった一人静かに営業した。現実、一人で営業することもできず、閉店を余儀なくされた。会社からボイコットについて、ヒアリングを幾度と無く横山に行なったが、何もわからなかった。事実、横山自身アルバイトたちによって遂行されたボイコットがなぜ行なわれたのか甚だ理解できなかったからである。横山は小さくか細い声で何度も連呼した。
「わからないです。すみません。」会議室はため息に包まれた。
彼が転職するのは、季節が幾度と無く変わった後だった。あのボイコットから仕事に対する熱意がまったくもてず、故郷である横浜に身を隠した。実家での居心地はよくはなかった。口うるさい親父と心配性な母親が彼に対して異常なまでに面倒を見ていたがそれが逆に狭く感じた。早く仕事をしないのかと部屋の扉をノックする音を毎日聞き、親父が酔った勢いで母親との馴れ初めを永遠と語るが興味がなかった。両親との生活は約2年だったがなぜ実家に戻ってきたか聞いてこなかったし知らない。彼らにそのことに興味が無かった。
そんな実家であったが一人で住むよりましであった。あのボイコットから人間不信になってしまった。外を出歩くといくつもの白と黒の目が彼自身を凝視し監視されているように思えた。また、このころ横山は人間の顔の表情が素直に受け入れることができず人間の後ろに何も無いカオスの顔が見えるようになっていた。そいつは口も鼻も目も耳も何もかも無い。しゃべることさえしず、ただ黙って横山をみていた。横山はそいつを見始め外に対しての絶望感と虚無さから外に出なくなった。少しでも安心した場所に行きたく実家へと移った。
横山の部屋は2階の角にあり風通しはかなりいい。部屋には小さな窓がある。埃がかぶっていて、窓のふちは錆付き重い。あるとき外界を覗いた。
家のしたに広がる商店街がにぎわっていた。
3 notes
·
View notes
Text
自殺未遂
何度も死のうとしている。
これからその話をする。
自殺未遂は私の人生の一部である。一本の線の上にボツボツと真っ黒な丸を描くように、その記憶は存在している。
だけど誰にも話せない。タブーだからだ。重たくて悲しくて忌み嫌われる話題だからだ。皆それぞれ苦労しているから、人の悲しみを背負う余裕なんてないのだ。
だから私は嘘をつく。その時代を語る時、何もなかったふりをする。引かれたり、陰口を言われたり、そういう人だとレッテルを貼られたりするのが怖いから。誰かの重荷になるのが怖いから。
一人で抱える秘密は、重たい。自分のしたことが、当時の感情が、ずっしりと肩にのしかかる。
私は楽になるために、自白しようと思う。黙って平気な顔をしているのに、もう疲れてしまった。これからは場を選んで、私は私の人生を正直に語ってゆきたい。
十六歳の時、初めての自殺未遂をした。
五年間の不登校生活を脱し高校に進学したものの、面白いくらい馴染めなかった。天真爛漫に女子高生を満喫する宇宙人のようなクラスメイトと、同じ空気を吸い続けることは不可能だと悟ったのだ。その結果、私は三ヶ月で中退した。
自信を失い家に引きこもる。どんよりと暗い台所でパソコンをいじり続ける。将来が怖くて、自分が情けなくて、見えない何かにぺしゃんこに潰されてしまいそうだった。家庭は荒れ、母は一日中家にいる私に「普通の暮らしがしたい」と呟いた。自分が親を苦しめている。かといって、この先どこに行っても上手くやっていける気がしない。悶々としているうちに十キロ痩せ、生理が止まった。肋が浮いた胸で死のうと決めた。冬だった。
夜。親が寝静まるのを待ちそっと家を出る。雨が降っているのにも関わらず月が照っている。青い光が濁った視界を切り裂き、この世の終わりみたいに美しい。近所の河原まで歩き、濡れた土手を下り、キンキンに冷えた真冬の水に全身を浸す。凍傷になれば数分で死に至ることができると聞いた。このままもう少しだけ耐えればいい。
寒い!私の体は震える。寒い!あっという間に歯の根が合わなくなる。頭のてっぺんから爪先までギリギリと痛みが駆け抜け、三秒と持たずに陸へ這い上がった。寒い、寒いと呟きながら、体を擦り擦り帰路を辿る。ずっしりと水を含んだジャージが未来のように重たい。
風呂場で音を立てぬよう泥を洗い流す。白いタイルが砂利に汚されてゆく。私は死ぬことすらできない。妙な落胆が頭を埋めつくした。入水自殺は無事、失敗。
二度目の自殺未遂は十七歳の時だ。
その頃私は再入学した高校での人間関係と、精神不安定な母との軋轢に悩まされていた。学校に行けば複雑な家庭で育った友人達の、無視合戦��泥沼恋愛に巻き込まれる。あの子が嫌いだから無視をするだのしないだの、彼氏を奪っただの浮気をしているだの、親が殴ってくるだの実はスカトロ好きのゲイだだの、裏のコンビニで喫煙しているだの先生への舌打ちだの⋯⋯。距離感に不器用な子達が多く、いつもどこかしらで誰かが傷つけ合っていた。教室には無気力と混乱が煙幕のように立ち込め、普通に勉強し真面目でいることが難しく感じられた。
家に帰れば母が宗教のマインドコントロールを引きずり「地獄に落ちるかもしれない」などと泣きついてくる。以前意地悪な信者の婆さんに、子どもが不登校になったのは前世の因縁が影響していて、きちんと祈らないと地獄に落ちる、と吹き込まれたのをまだ信じているのだ。そうでない時は「きちんと家事をしなくちゃ」と呪いさながらに繰り返し、髪を振り乱して床を磨いている。毎日手の込んだフランス料理が出てくるし、近所の人が買い物先までつけてくるとうわ言を言っている。どう考えても母は頭がおかしい。なのに父は「お母さんは大丈夫だ」の一点張りで、そのくせ彼女の相手を私に丸投げするのだ。
胸糞の悪い映画さながらの日々であった。現実の歯車がミシミシと音を立てて狂ってゆく。いつの間にやら天井のシミが人の顔をして私を見つめてくる。暗がりにうずくまる家具が腐り果てた死体に見えてくる。階段を昇っていると後ろから得体の知れない化け物が追いかけてくるような気がする。親が私の部屋にカメラを仕掛け、居間で監視しているのではないかと心配になる。ホラー映画を見ている最中のような不気味な感覚が付きまとい、それから逃れたくて酒を買い吐くまで酔い潰れ手首を切り刻む。ついには幻聴が聞こえ始め、もう一人の自分から「お前なんか死んだ方がいい」と四六時中罵られるようになった。
登下校のために電車を待つ。自分が電車に飛び込む幻が見える。車体にすり潰されズタズタになる自分の四肢。飛び込む。粉々になる。飛び込む。足元が真っ赤に染まる。そんな映像が何度も何度も巻き戻される。駅のホームは、どこまでも続く線路は、私にとって黄泉への入口であった。ここから線路に倒れ込むだけで天国に行ける。気の狂った現実から楽になれる。しかし実行しようとすると私の足は震え、手には冷や汗が滲んだ。私は高校を卒業するまでの四年間、映像に重なれぬまま一人電車を待ち続けた。飛び込み自殺も無事、失敗。
三度目の自殺未遂は二十四歳、私は大学四年生だった。
大学に入学してすぐ、執拗な幻聴に耐えかね精神科を受診した。セロクエルを服用し始めた瞬間、意地悪な声は掻き消えた。久しぶりの静寂に手足がふにゃふにゃと溶け出しそうになるくらい、ほっとする。しかし。副作用で猛烈に眠い。人が傍にいると一睡もできないたちの私が、満員の講義室でよだれを垂らして眠りこけてしまう。合う薬を模索する中サインバルタで躁転し、一ヶ月ほど過活動に勤しんだりしつつも、どうにか普通の顔を装いキャンパスにへばりついていた。
三年経っても服薬や通院への嫌悪感は拭えなかった。生き生きと大人に近づいていく友人と、薬なしでは生活できない自分とを見比べ、常に劣等感を感じていた。特に冬に体調が悪くなり、課題が重なると疲れ果てて寝込んでしまう。人混みに出ると頭がザワザワとして不安になるため、酒盛りもアルバイトもサークル活動もできない。鬱屈とした毎日が続き闘病に嫌気がさした私は、四年の秋に通院を中断してしまう。精神薬が抜けた影響で揺り返しが起こったこと、卒業制作に追われていたこと、就職活動に行き詰まっていたこと、それらを誰にも相談できなかったことが積み重なり、私は鬱へと転がり落ちてゆく。
卒業制作の絵本を拵える一方で遺品を整理した。洋服を売り、物を捨て、遺書を書き、ネット通販でヘリウムガスを手に入れた。どうして卒制に遅れそうな友達の面倒を見ながら遺品整理をしているのか分からない。自分が真っ二つに割れてしまっている。混乱しながらもよたよたと気力で突き進む。なけなしの努力も虚しく、卒業制作の提出を逃してしまった。両親に高額な学費を負担させていた負い目もあり、留年するぐらいなら死のうとこりずに決意した。
クローゼットに眠っていたヘリウムガス缶が起爆した。私は人の頭ほどの大きさのそれを担いで、ありったけの精神薬と一緒に車に積み込んだ。それから山へ向かった。死ぬのなら山がいい。夜なら誰であれ深くまで足を踏み入れないし、展望台であれば車が一台停まっていたところで不審に思われない。車内で死ねば腐っていたとしても車ごと処分できる。
展望台の駐車場に車を突っ込み、無我夢中でガス缶にチューブを繋ぎポリ袋の空気を抜く。本気で死にたいのなら袋の酸素濃度を極限まで減らさなければならない。真空状態に近い状態のポリ袋を被り、そこにガスを流し込めば、酸素不足で苦しまずに死に至ることができるのだ。大量の薬を水なしで飲み下し、袋を被り、うつらうつらしながら缶のコックをひねる。シューッと気体が満ちる音、ツンとした臭い。視界が白く透き通ってゆく。死ぬ時、人の意識は暗転ではなくホワイトアウトするのだ。寒い。手足がキンと冷たい。心臓が耳の奥にある。ハツカネズミと同じ速度でトクトクと脈動している。ふとシャンプーを切らしていたことを思い出し、買わなくちゃと考える。遠のいてゆく意識の中、日用品の心配をしている自分が滑稽で、でも、もういいや。と呟く。肺が詰まる感覚と共に、私は意識を失う。
気がつくと後部座席に転がっている。目覚めてしまった。昏倒した私は暴れ、自分でポリ袋をはぎ取ったらしい。無意識の私は生きたがっている。本当に死ぬつもりなら、こうならぬように手首を後ろできつく縛るべきだったのだ。私は自分が目覚めると、知っていた。嫌な臭いがする。股間が冷たい。どうやら漏らしたようだ。フロントガラスに薄らと雪が積もっている。空っぽの薬のシートがバラバラと散乱している。指先が傷だらけだ。チューブをセットする際、夢中になるあまり切ったことに気がつかなかったようだ。手の感覚がない。鈍く頭痛がする。目の前がぼやけてよく見えない。麻痺が残ったらどうしよう。恐ろしさにぶるぶると震える。さっきまで何もかもどうでも良いと思っていたはずなのに、急に体のことが心配になる。
後始末をする。白い視界で運転をする。缶は大学のゴミ捨て場に捨てる。帰宅し、後部座席を雑巾で拭き、薬のシートをかき集めて処分する。ふらふらのままベッドに倒れ込み、失神する。
その後私は、卒業制作の締切を逃したことで教授と両親から怒られる。翌日、何事もなかったふりをして大学へ行き、卒制の再提出の交渉する。病院に保護してもらえばよかったのだがその発想もなく、ぼろ切れのようなメンタルで卒業制作展の受付に立つ。ガス自殺も無事、失敗。
四度目は二十六歳の時だ。
何とか大学卒業にこぎつけた私は、入社試験がないという安易な理由でホテルに就職し一人暮らしを始めた。手始めに新入社員研修で三日間自衛隊に入隊させられた。それが終わると八時間ほぼぶっ続けで宴会場を走り回る日々が待っていた。典型的な古き良き体育会系の職場であった。
朝十時に出社し夜の十一時に退社する。夜露に湿ったコンクリートの匂いをかぎながら浮腫んだ足をズルズルと引きずり、アパートの玄関にぐしゃりと倒れ込む。ほとんど意識のないままシャワーを浴びレトルト食品を貪り寝床に倒れ泥のように眠る。翌日、朝六時に起床し筋肉痛に膝を軋ませよれよれと出社する。不安定なシフトと不慣れな肉体労働で病状は悪化し、働いて二年目の夏、まずいことに躁転してしまった。私は臨機応変を求められる場面でパニックを起こすようになり、三十分トイレにこもって泣く、エレベーターで支離滅裂な言葉を叫ぶなどの奇行を繰り返す、モンスター社員と化してしまった。人事に持て余され部署をたらい回しにされる。私の世話をしていた先輩が一人、ストレスのあまり退社していった。
躁とは恐ろしいもので人を巻き込む。プライベートもめちゃくちゃになった。男友達が性的逸脱症状の餌食となった。五年続いた彼氏と別れた。よき理解者だった友と言い争うようになり、立ち直れぬほどこっぴどく傷つけ合った。携帯電話をハイヒールで踏みつけバキバキに破壊し、コンビニのゴミ箱に投げ捨てる。出鱈目なエネルギーが毛穴という毛穴からテポドンの如く噴出していた。手足や口がばね仕掛けになり、己の意思を無視して動いているようで気味が悪かった。
寝る前はそれらの所業を思い返し罪悪感で窒息しそうになる。人に迷惑をかけていることは自覚していたが、自分ではどうにもできなかった。どこに頼ればいいのか分からない、生きているだけで迷惑をかけてしまう。思い詰め寝床から出られなくなり、勤務先に泣きながら休養の電話をかけるようになった。
会社を休んだ日は正常な思考が働かなくなる。近所のマンションに侵入し飛び降りようか悩む。落ちたら死ねる高さの建物を、砂漠でオアシスを探すジプシーさながらに彷徨い歩いた。自分がアパートの窓から落下してゆく幻を見るようになった。だが、無理だった。できなかった。あんなに人に迷惑をかけておきながら、私の足は恥ずかしくも地べたに根を張り微動だにしないのだった。
アパートの部屋はムッと蒸し暑い。家賃を払えなければ追い出される、ここにいるだけで税金をむしり取られる、息をするのにも金がかかる。明日の食い扶持を稼ぐことができない、それなのに腹は減るし喉も乾く、こんなに汗が滴り落ちる、憎らしいほど生きている。何も考えたくなくて、感じたくなくて、精神薬をウイスキーで流し込み昏倒した。
翌日の朝六時、朦朧と覚醒する。会社に体調不良で休む旨を伝え、再び精神薬とウイスキーで失神する。目覚めて電話して失神、目覚めて電話して失神。夢と現を行き来しながら、手元に転がっていたカッターで身体中を切り刻み、吐瀉し、意識を失う。そんな生活が七日間続いた。
一週間目の早朝に意識を取り戻した私は、このままでは死ぬと悟った。にわかに生存本能のスイッチがオンになる。軽くなった内臓を引っさげ這うように病院へと駆け込み、看護師に声をかける。
「あのう。一週間ほど薬と酒以外何も食べていません」
「そう。それじゃあ辛いでしょう。ベッドに寝ておいで」
優しく誘導され、白いシーツに倒れ込む。消毒液の香る毛布を抱きしめていると、ぞろぞろと数名の看護師と医師がやってきて取り囲まれた。若い男性医師に質問される。
「切ったの?」
「切りました」
「どこを?」
「身体中⋯⋯」
「ごめんね。少し見させて」
服をめくられる。私の腹を確認した彼は、
「ああ。これは入院だな」
と呟いた。私は妙に冷めた頭で聞く。
「今すぐですか」
「うん、すぐ。準備できるかな」
「はい。日用品を持ってきます」
私はびっくりするほどまともに帰宅し、もろもろを鞄に詰め込んで病院にトンボ帰りした。閉鎖病棟に入る。病室のベッドの周りに荷物を並べながら、私よりももっと辛い人間がいるはずなのにこれくらいで入院だなんておかしな話だ、とくるくる考えた。一度狂うと現実を測る尺度までもが狂うようだ。
二週間入院する。名も知らぬ睡眠薬と精神安定剤を処方され、飲む。夜、病室の窓から街を眺め、この先どうなるのかと不安になる。私の主治医は「君はいつかこうなると思ってたよ」と笑った。以前から通院をサポートする人間がいないのを心配していたのだろう。
退院後、人事からパート降格を言い渡され会社を辞めた。後に勤めた職場でも上手くいかず、一人暮らしを断念し実家に戻った。飛び降り自殺、餓死自殺、無事、失敗。
五度目は二十九歳の時だ。
四つめの転職先が幸いにも人と関わらぬ仕事であったため、二年ほど通い続けることができた。落ち込むことはあるものの病状も安定していた。しかしそのタイミングで主治医が代わった。新たな主治医は物腰柔らかな男性だったが、私は病状を相談することができなかった。前の医師は言葉を引き出すのが上手く、その環境に甘えきっていたのだ。
時給千円で四時間働き、月収は六万から八万。いい歳をして脛をかじっているのが忍びなく、実家に家賃を一、二万入れていたので、自由になる金は五万から七万。地元に友人がいないため交際費はかからない、年金は全額免除の申請をした、それでもカツカツだ。大きな買い物は当然できない。小さくとも出費があると貯金残高がチラつき、小一時間は��月のやりくりで頭がいっぱいになる。こんな額しか稼げずに、この先どうなってしまうのだろう。親が死んだらどうすればいいのだろう。同じ年代の人達は順調にキャリアを積んでいるだろう。資格も学歴もないのにズルズルとパート勤務を続けて、まともな企業に転職できるのだろうか。先行きが見えず、暇な時間は一人で悶々と考え込んでしまう。
何度目かの落ち込みがやってきた時、私は愚かにも再び通院を自己中断してしまう。病気を隠し続けること、精神疾患をオープンにすれば低所得をやむなくされることがプレッシャーだった。私も「普通の生活」を手に入れてみたかったのだ。案の定病状は悪化し、練炭を購入するも思い留まり返品。ふらりと立ち寄ったホームセンターで首吊りの紐を買い、クローゼットにしまう。私は鬱になると時限爆弾を買い込む習性があるらしい。覚えておかなければならない。
その職場を退職した後、さらに三度の転職をする。ある職場は椅子に座っているだけで涙が出るようになり退社した。別の職場は人手不足の影響で仕事内容が変わり、人事と揉めた挙句退社した。最後の転職先にも馴染めず八方塞がりになった私は、家族と会社に何も告げずに家を飛び出し、三日間帰らなかった。雪の降る中、車中泊をして、寒すぎると眠れないことを知った。家族は私を探し回り、ラインの通知は「帰っておいで」のメッセージで埋め尽くされた。漫画喫茶のジャンクな食事で口が荒れ、睡眠不足で小間切れにうたた寝をするようになった頃、音を上げてふらふらと帰宅した。勤務先に電話をかけると人事に静かな声で叱られた。情けなかった。私は退社を申し出た。気がつけば一年で四度も職を代わっていた。
無職になった。気分の浮き沈みが激しくコントロールできない。父の「この先どうするんだ」の言葉に「私にも分からないよ!」と怒鳴り返し、部屋のものをめちゃくちゃに壊して暴れた。仕事を辞める度に無力感に襲われ、ハローワークに行くことが恐ろしくてたまらなくなる。履歴書を書けばぐちゃぐちゃの職歴欄に現実を突きつけられる。自分はどこにも適応できないのではないか、この先まともに生きてゆくことはできないのではないか、誰かに迷惑をかけ続けるのではないか。思い詰め、寝室の柱に時限爆弾をぶら下げた。クローゼットの紐で首を吊ったのだ。
紐がめり込み喉仏がゴキゴキと軋む。舌が押しつぶされグエッと声が出る。三秒ぶら下がっただけなのに目の前に火花が散り、苦しくてたまらなくなる。何度か試したが思い切れず、紐を握り締め泣きじゃくる。学校に行く、仕事をする、たったそれだけのことができない、人間としての義務を果たせない、税金も払えない、親の負担になっている、役立たずなのにここまで生き延びている。生きられない。死ねない。どこにも行けない。私はどうすればいいのだろう。釘がくい込んだ柱が私の重みでひび割れている。
泣きながら襖を開けると、ペットの兎が小さな足を踏ん張り私を見上げていた。黒くて可愛らしい目だった。私は自分勝手な絶望でこの子を捨てようとした。撫でようとすると、彼はきゅっと身を縮めた。可愛い、愛する子。どんな私でいても拒否せず撫でさせてくれる、大切な子。私の身勝手さで彼が粗末にされることだけはあってはならない、絶対に。ごめんね、ごめんね。柔らかな毛並みを撫でながら、何度も謝った。
この出来事をきっかけに通院を再開し、障害者手帳を取得する。医療費控除も障害者年金も申請した。精神疾患を持つ人々が社会復帰を目指すための施設、デイケアにも通い始めた。どん底まで落ちて、自分一人ではどうにもならないと悟ったのだ。今まさに社会復帰支援を通し、誰かに頼り、悩みを相談する方法を勉強している最中だ。
病院通いが本格化してからというもの、私は「まとも」を諦めた。私の指す「まとも」とは、周りが満足する状態まで自分を持ってゆくことであった。人生のイベントが喜びと結びつくものだと実感できぬまま、漠然としたゴールを目指して走り続けた。ただそれをこなすことが人間の義務なのだと思い込んでいた。
自殺未遂を繰り返しながら、それを誰にも打ち明けず、悟らせず、発見されずに生きてきた。約二十年もの間、母の精神不安定、学校生活や社会生活の不自由さ、病気との付き合いに苦しみ、それら全てから解放されたいと願っていた。
今、なぜ私が生きているか。苦痛を克服したからではない。死ねなかったから生きている。死ぬほど苦しく、何度もこの世からいなくなろうとしたが、失敗し続けた。だから私は生きている。何をやっても死ねないのなら、どうにか生き延びる方法を探らなければならない。だから薬を飲み、障害者となり、誰かの世話になり、こうしてしぶとくも息をしている。
高校の同級生は精神障害の果てに自ら命を絶った。彼は先に行ってしまった。自殺を推奨するわけではないが、彼は死ぬことができたから、今ここにいない。一歩タイミングが違えば私もそうなっていたかもしれない。彼は今、天国で穏やかに暮らしていることだろう。望むものを全て手に入れて。そうであってほしい。彼はたくさん苦しんだのだから。
私は強くなんてない。辛くなる度、たくさんの自分を殺した。命を絶つことのできる場所全てに、私の死体が引っかかっていた。ガードレールに。家の軒に。柱に。駅のホームの崖っぷちに。近所の河原に。陸橋に。あのアパートに。一人暮らしの二階の部屋から見下ろした地面に。電線に。道路を走る車の前に⋯⋯。怖かった。震えるほど寂しかった。誰かに苦しんでいる私を見つけてもらいたかった。心配され、慰められ、抱きしめられてみたかった。一度目の自殺未遂の時、誰かに生きていてほしいと声をかけてもらえたら、もしくは誰かに死にたくないと泣きつくことができたら、私はこんなにも自分を痛めつけなくて済んだのかもしれない。けれど時間は戻ってこない。この先はこれらの記憶を受け止め、癒す作業が待っているのだろう。
きっとまた何かの拍子に、生き延びたことを後悔するだろう。あの暗闇がやってきて、私を容赦なく覆い隠すだろう。あの時死んでいればよかったと、脳裏でうずくまり呟くだろう。それが私の病で、これからももう一人の自分と戦い続けるだろう。
思い出話にしてはあまりに重い。医療機関に寄りかかりながら、この世に適応する人間達には打ち明けられぬ人生を、ともすれば誰とも心を分かち合えぬ孤独を、蛇の尾のように引きずる。刹那の光と闇に揉まれ、暗い水底をゆったりと泳ぐ。静かに、誰にも知られず、時には仲間と共に、穏やかに。
海は広く、私は小さい。けれど生きている。まだ生きている。
4 notes
·
View notes
Text
iFontMaker - Supported Glyphs
Latin//Alphabet// ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 !"“”#$%&'‘’()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ Latin//Accent// ¡¢£€¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ Latin//Extension 1// ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſfffiflffifflſtst Latin//Extension 2// ƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿ Symbols//Web// –—‚„†‡‰‹›•…′″‾⁄℘ℑℜ™ℵ←↑→↓↔↵⇐⇑⇒⇓⇔∀∂∃∅∇∈∉∋∏∑−∗√∝∞∠∧∨∩∪∫∴∼≅≈≠≡≤≥⊂⊃⊄⊆⊇⊕⊗⊥⋅⌈⌉⌊⌋〈〉◊♠♣♥♦ Symbols//Dingbat// ✁✂✃✄✆✇✈✉✌✍✎✏✐✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛✜✝✞✟✠✡✢✣✤✥✦✧✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❍❏❐❑❒❖❘❙❚❛❜❝❞❡❢❣❤❥❦❧❨❩❪❫❬❭❮❯❰❱❲❳❴❵❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➔➘➙➚➛➜➝➞➟➠➡➢➣➤➥➦➧➨➩➪➫➬➭➮➯➱➲➳➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾ Japanese//かな// あいうえおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもやゆよらりるれろわゐゑをんぁぃぅぇぉっゃゅょゎゔ゛゜ゝゞアイウエオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダチヂツヅテデトドナニヌネノハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモヤユヨラリルレロワヰヱヲンァィゥェォッャュョヮヴヵヶヷヸヹヺヽヾ Japanese//小学一年// 一右雨円王音下火花貝学気九休玉金空月犬見五口校左三山子四糸字耳七車手十出女小上森人水正生青夕石赤千川先早草足村大男竹中虫町天田土二日入年白八百文木本名目立力林六 Japanese//小学二年// 引羽雲園遠何科夏家歌画回会海絵外角楽活間丸岩顔汽記帰弓牛魚京強教近兄形計元言原戸古午後語工公広交光考行高黄合谷国黒今才細作算止市矢姉思紙寺自時室社弱首秋週春書少場色食心新親図数西声星晴切雪船線前組走多太体台地池知茶昼長鳥朝直通弟店点電刀冬当東答頭同道読内南肉馬売買麦半番父風分聞米歩母方北毎妹万明鳴毛門夜野友用曜来里理話 Japanese//小学三年// 悪安暗医委意育員院飲運泳駅央横屋温化荷開界階寒感漢館岸起期客究急級宮球去橋業曲局銀区苦具君係軽血決研県庫湖向幸港号根祭皿仕死使始指歯詩次事持式実写者主守取酒受州拾終習集住重宿所暑助昭消商章勝乗植申身神真深進世整昔全相送想息速族他打対待代第題炭短談着注柱丁帳調追定庭笛鉄転都度投豆島湯登等動童農波配倍箱畑発反坂板皮悲美鼻筆氷表秒病品負部服福物平返勉放味命面問役薬由油有遊予羊洋葉陽様落流旅両緑礼列練路和 Japanese//小学四年// 愛案以衣位囲胃印英栄塩億加果貨課芽改械害街各覚完官管関観願希季紀喜旗器機議求泣救給挙漁共協鏡競極訓軍郡径型景芸欠結建健験固功好候航康告差菜最材昨札刷殺察参産散残士氏史司試児治辞失借種周祝順初松笑唱焼象照賞臣信成省清静席積折節説浅戦選然争倉巣束側続卒孫帯隊達単置仲貯兆腸低底停的典伝徒努灯堂働特得毒熱念敗梅博飯飛費必票標不夫付府副粉兵別辺変便包法望牧末満未脈民無約勇要養浴利陸良料量輪類令冷例歴連老労録 Japanese//小学五〜六年// 圧移因永営衛易益液演応往桜恩可仮価河過賀快解格確額刊幹慣眼基寄規技義逆久旧居許境均禁句群経潔件券険検限現減故個護効厚耕鉱構興講混査再災妻採際在財罪���酸賛支志枝師資飼示似識質舎謝授修述術準序招承証条状常情織職制性政勢精製税責績接設舌絶銭祖素総造像増則測属率損退貸態団断築張提程適敵統銅導徳独任燃能破犯判版比肥非備俵評貧布婦富武復複仏編弁保墓報豊防貿暴務夢迷綿輸余預容略留領異遺域宇映延沿我灰拡革閣割株干巻看簡危机貴揮疑吸供���郷勤筋系敬警劇激穴絹権憲源厳己呼誤后孝皇紅降鋼刻穀骨困砂座済裁策冊蚕至私姿視詞誌磁射捨尺若樹収宗就衆従縦縮熟純処署諸除将傷障城蒸針仁垂推寸盛聖誠宣専泉洗染善奏窓創装層操蔵臓存尊宅担探誕段暖値宙忠著庁頂潮賃痛展討党糖届難乳認納脳派拝背肺俳班晩否批秘腹奮並陛閉片補暮宝訪亡忘棒枚幕密盟模訳郵優幼欲翌乱卵覧裏律臨朗論 Japanese//中学// 亜哀挨曖扱宛嵐依威為畏尉萎偉椅彙違維慰緯壱逸芋咽姻淫陰隠韻唄鬱畝浦詠影鋭疫悦越謁閲炎怨宴援煙猿鉛縁艶汚凹押旺欧殴翁奥憶臆虞乙俺卸穏佳苛架華菓渦嫁暇禍靴寡箇稼蚊牙瓦雅餓介戒怪拐悔皆塊楷潰壊懐諧劾崖涯慨蓋該概骸垣柿核殻郭較隔獲嚇穫岳顎掛括喝渇葛滑褐轄且釜鎌刈甘汗缶肝冠陥乾勘患貫喚堪換敢棺款閑勧寛歓監緩憾還環韓艦鑑含玩頑企伎忌奇祈軌既飢鬼亀幾棋棄毀畿輝騎宜偽欺儀戯擬犠菊吉喫詰却脚虐及丘朽臼糾嗅窮巨拒拠虚距御凶叫狂享況峡挟狭恐恭脅矯響驚仰暁凝巾斤菌琴僅緊錦謹襟吟駆惧愚偶遇隅串屈掘窟繰勲薫刑茎契恵啓掲渓蛍傾携継詣慶憬稽憩鶏迎鯨隙撃桁傑肩倹兼剣拳軒圏堅嫌献遣賢謙鍵繭顕懸幻玄弦舷股虎孤弧枯雇誇鼓錮顧互呉娯悟碁勾孔巧甲江坑抗攻更拘肯侯恒洪荒郊貢控梗喉慌硬絞項溝綱酵稿衡購乞拷剛傲豪克酷獄駒込頃昆恨婚痕紺魂墾懇沙唆詐鎖挫采砕宰栽彩斎債催塞歳載剤削柵索酢搾錯咲刹拶撮擦桟惨傘斬暫旨伺刺祉肢施恣脂紫嗣雌摯賜諮侍慈餌璽軸叱疾執湿嫉漆芝赦斜煮遮邪蛇酌釈爵寂朱狩殊珠腫趣寿呪需儒囚舟秀臭袖羞愁酬醜蹴襲汁充柔渋銃獣叔淑粛塾俊瞬旬巡盾准殉循潤遵庶緒如叙徐升召匠床抄肖尚昇沼宵症祥称渉紹訟掌晶焦硝粧詔奨詳彰憧衝償礁鐘丈冗浄剰畳壌嬢錠譲醸拭殖飾触嘱辱尻伸芯辛侵津唇娠振浸紳診寝慎審震薪刃尽迅甚陣尋腎須吹炊帥粋衰酔遂睡穂随髄枢崇据杉裾瀬是姓征斉牲凄逝婿誓請醒斥析脊隻惜戚跡籍拙窃摂仙占扇栓旋煎羨腺詮践箋潜遷薦繊鮮禅漸膳繕狙阻租措粗疎訴塑遡礎双壮荘捜挿桑掃曹曽爽喪痩葬僧遭槽踪燥霜騒藻憎贈即促捉俗賊遜汰妥唾堕惰駄耐怠胎泰堆袋逮替滞戴滝択沢卓拓託濯諾濁但脱奪棚誰丹旦胆淡嘆端綻鍛弾壇恥致遅痴稚緻畜逐蓄秩窒嫡抽衷酎鋳駐弔挑彫眺釣貼超跳徴嘲澄聴懲勅捗沈珍朕陳鎮椎墜塚漬坪爪鶴呈廷抵邸亭貞帝訂逓偵堤艇締諦泥摘滴溺迭哲徹撤添塡殿斗吐妬途渡塗賭奴怒到逃倒凍唐桃透悼盗陶塔搭棟痘筒稲踏謄藤闘騰洞胴瞳峠匿督篤凸突屯豚頓貪鈍曇丼那謎鍋軟尼弐匂虹尿妊忍寧捻粘悩濃把覇婆罵杯排廃輩培陪媒賠伯拍泊迫剝舶薄漠縛爆箸肌鉢髪伐抜罰閥氾帆汎伴畔般販斑搬煩頒範繁藩蛮盤妃彼披卑疲被扉碑罷避尾眉微膝肘匹泌姫漂苗描猫浜賓頻敏瓶扶怖附訃赴浮符普腐敷膚賦譜侮舞封伏幅覆払沸紛雰噴墳憤丙併柄塀幣弊蔽餅壁璧癖蔑偏遍哺捕舗募慕簿芳邦奉抱泡胞俸倣峰砲崩蜂飽褒縫乏忙坊妨房肪某冒剖紡傍帽貌膨謀頰朴睦僕墨撲没勃堀奔翻凡盆麻摩磨魔昧埋膜枕又抹慢漫魅岬蜜妙眠矛霧娘冥銘滅免麺茂妄盲耗猛網黙紋冶弥厄躍闇喩愉諭癒唯幽悠湧猶裕雄誘憂融与誉妖庸揚揺溶腰瘍踊窯擁謡抑沃翼拉裸羅雷頼絡酪辣濫藍欄吏痢履璃離慄柳竜粒隆硫侶虜慮了涼猟陵僚寮療瞭糧厘倫隣瑠涙累塁励戻鈴零霊隷齢麗暦劣烈裂恋廉錬呂炉賂露弄郎浪廊楼漏籠麓賄脇惑枠湾腕 Japanese//記号// ・ー~、。〃〄々〆〇〈〉《》「」『』【】〒〓〔〕〖〗〘〙〜〝〞〟〠〡〢〣〤〥〦〧〨〩〰〳〴〵〶 Greek & Coptic//Standard// ʹ͵ͺͻͼͽ;΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώϐϑϒϓϔϕϖϚϜϞϠϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬϭϮϯϰϱϲϳϴϵ϶ϷϸϹϺϻϼϽϾϿ Cyrillic//Standard// ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџѢѣѤѥѦѧѨѩѪѫѬѭѰѱѲѳѴѵѶѷѸѹҌҍҐґҒғҖҗҘҙҚқҜҝҠҡҢңҤҥҪҫҬҭҮүҰұҲҳҴҵҶҷҸҹҺһҼҽҾҿӀӁӂӇӈӏӐӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝӞӟӠӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹӾӿ Thai//Standard// กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮฯะัาำิีึืฺุู฿เแโใไๅๆ็่้๊๋์ํ๎๏๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๚๛
see also How to Edit a Glyph that is not listed on iFontMaker
#FAQ#ifontmaker2#Symbols#Dingbat#Cyrillic#Greek#Coptic#thai#character set#character sets#list#language
6 notes
·
View notes
Link
事実を知らしめることが親善に
豊田有恒(作家)
愛国の一方で政府批判
このところ、韓国の反日が常軌を逸したものになっている。いわゆる従軍慰安婦の問題は、日本の巨大新聞が、その強大な影響力を行使した結果、世界中にまき散らされた虚構なのだが、いわば韓国との連携のもとで、拡大した側面も見逃せない。
明らかに、韓国は、変わってきている。なぜなのだろうか? 私は、1970年代の初頭から、韓国へ通い始め、韓国語も学び、多くの著書を上梓してきた。しばしば、親韓派と目されてもきた。弁解になるが、これには、理由がある。70年代の当時、例の巨悪の源泉である新聞社は、北朝鮮一辺倒だったのである。今日では考えられないことだが、北朝鮮を「地上の楽園」と美化し、相対的に韓国を独裁政権と規定し貶(おとし)めてきたのである。
私は、もともと、小説家であり、思想的な背景はない。韓国へ行くようになったきっかけは、小説の取材のためでしかなかった。韓国は、あの新聞社が報じるように、独裁政権の国だと思いこんでいた。これは、おおかたの日本人の当時の平均的な理解だったろう。なにしろ、良心的と目されていた大新聞が、北朝鮮への帰国事業などを後援し、後にノーベル賞を受賞する有名作家や、国際無銭旅行で大ベストセラーを出した評論家などが、すっかり賛同しているのだから、実際に韓国へも北朝鮮へも行ったことのない人間は、そうだと信じこむしかなかった。
しかし、韓国へ通ううちに、日本の報道が、おかしいのではないかと、うすうす思いはじめた。三十代はじめで若かったせいだろう、フットワークが良かったから、取材目的の古代遺跡のほかにも、あちこち歩きまわる。ディスコで知り合ったディスクジョッキーをやっているという同年輩の韓国人と意気投合したが、この男、どこでも政府批判ばかり口にする。こちらが、心配になって、周囲を見回したほどだった。日本では、KCIA(韓国中央情報部)の悪行ばかりが報道されていたから、言論の自由はないという先入観にとらわれていたが、こうした報道が、変ではないかと感じはじめた。
また、一方では、政府批判もするが、この男、愛国心を口にする。ディスクジョッキーという軟らかい職業の男が、愛国心を口にすることに、違和感も持ったが、やや羨ましくもあった。当時、日本のマスコミは、左翼デマゴーグに牛耳られていたから、愛国心などと言えば、右翼と間違われかねないような風潮が、蔓延していた。しかし、韓国では、こうした言説は、この男だけではなかった。あちこちで、北朝鮮に偏している日本の報道がおかしいとする、多くの韓国人の批判を耳にするようになった。また、必ず日本に追いついて見せるという、愛国心をむき出しにした意見にも接した。
韓国の実情紹介に誹謗中傷
韓国語が判るようになると、行動範囲も広がってくる。こうした韓国人が、KCIAに監視されているから、点数かせぎに愛国心を口にしていたわけではないと、だんだん判ってきた。バイク・カーマニアだったので、現代(ヒョンデ)自動車(チャドンチャ)や大林産業(テーリムサノプ)のショールームに足を運んで、韓国の自動車・バイク事情に関心を持ちはじめた。
日本で報道されるような「暗く抑圧された独裁国」といったイメージでないことが、しだいに判ってきた。日本で、しばしば誤解されていることだが、反日の激しさから、韓国人に険しいイメージを持つ日本人が多い。一面では当たっていないこともないが、日常の生身の韓国人は、妙になれなれしく陽気で人懐(ひとなつ)こ��。
あの大新聞は、「暗く抑圧された独裁国」という疑似イベントを売りまくって、北朝鮮を美化し、韓国を貶める方向へ、日本国民をマインドコントロールしていたのだ。
韓国では、確かに日本より言論の自由が制限されていた。しかし、それは、金日成の個人崇拝による究極の独裁国家である北朝鮮と対峙するためであり、ある程度は強権政治を敷くしかなかったのである。当時、韓国では「誤判(オバン)」という表現が、しばしば使われていた。韓国国内が混乱していると見てとり、好機とばかりに北朝鮮が南進に踏み切るのではないかというわけだ。つまり、北朝鮮に誤判させないように、常に国内を安定させておかなければならなかったのだ。全ての韓国人が、ほん(・・)もの(・・)の(・)独裁国家である北朝鮮を恐れていたからだ。
こうした韓国の実情を、広く知らせたくなった。小説家という職業柄、書くメディアには、事欠かない。小説家の仕事ではないという躊躇(ためら)いもあったが、最初のノンフィクションとして「韓国の挑戦」(祥伝社)を上梓したのが、昭和53(78)年のことだった。書評では、これまでの日本の対韓認識を一変させたとまで、評された。当時の私には、巨悪と戦おうなどという大それた問題意識は、まったくなかった。
だが、ベストセラーにはなったものの、あれこれ、雑音が耳に入ってきた。この問題が、当時のマスコミ界では、タブーになっていると知ったのは、発売されてからだった。つまり、ほんとうのことを言ってしまったため、このタブーに抵触した。期せずして、あの大新聞と言う虎の尾を踏んでしまったわけだ。
朴政権に買収されている―は、まだしも上品なほうで、韓国に愛人がいるとか、韓国成り金だとか、いろいろ悪罵を聞かされることになった。そこで、子供たちもつれて、一家5人で毎年夏休みに韓国へ遊びにいき、印税を使い果たした。
日韓のため尽くした金思燁氏
あの大新聞が主導して、日本人を親北朝鮮、反韓国という方向へ誘導していたわけだが、最近は、かつての報道姿勢が嘘だったかのように、あの大新聞は、北朝鮮を賛美するようなこともなくなり、いつのまにか北朝鮮への批判を、臆面もなく展開するようになった。
それどころか、70年代当時あれほど嫌っていたはずの韓国に過剰に感情移入し、悪いのは全て日本人式の報道姿勢で、虚構に基づく従軍(・・)慰安婦(・・・)なる疑似イベントを垂れ流す始末である。多分、従軍(・・)慰安婦(・・・)報道についても、いったん非を認めたものの、真剣に謝罪するつもりなどなく、なし崩し的に、鉄面皮を決め込んで、風当たりが収まるのを待っているのだろう。
実際、当時、私は、韓国人の魅力にハマってもいた。日本人のように、控え目でなく、陽気に自己主張する姿勢が、一度も宮仕えしたことのない私のような一匹オオカミの作家には、波長が合っていると錯覚したせいでもある。
当時、知り合った韓国人のなかには、私の終生の師と仰ぐ人も、少なくなかった。東国大学の金思燁(キムサヨプ)先生とは、シンポジウムの席で知り合った。日韓バイリンガルの世代的な体験から、「日本書紀」「万葉集」を韓国語に、「三国(サムグク)史記(サギ)」「三国遺事(サムグンニュサ)」を日本語へ翻訳され、日韓古代史の研究におおいに貢献され、また、東国大学に日本学研究所を設立され、初代所長として、日本研究を韓国に定着させた功績は、おおいに評価されるべきだろう。
金先生に招かれ、東国大学で講演したこともある。最初、韓国語で話しはじめたのだが、見るに見かねて、助け船を出してくださったのは、先生の優しさだった。私のほうも、日本人を知る方々が物故して、日本語スピーカーが減っていることに危惧を覚え、毎年、拙著も含めた文庫本を教材として日本学研究所へ寄贈し、日韓親善に努めたものである。金先生は、私のささやかな協力に、研究所からの表彰という栄誉で応えてくださった。ほんとうに尊敬できる立派な方だった。
また、在日の人では、作家の故・金(キム)達(ダル)寿(ス)さんとは、古代史の会を通じて、親しくしていただいた。「日本の中の朝鮮文化」は、十数巻にわたる大著だが、日本全国に足を運んで、いわばライフワークとして書かれる際、金さんが自分に課していたことが、ひとつだけあった。韓国・朝鮮人の書いたものは、絶対に引用しないことだった。韓国・朝鮮人の書いたものなら、例の剣道の起源の捏造のように、なんでも朝鮮半島から渡来したと、こじつける文献が、いくらでも見つかるだろう。
おそらく、金さんは、韓国・朝鮮人の書いた文章を引用したいという誘惑に駆られたこともあったにちがいない。しかし、日本人が書いたものしか引用しないと、いわば、痩せ我慢のように、心に決めていたのだ。
金達寿さんとは、酒を呑んだり、旅行したり、また拙著の解説をお願いしたりしたこともある。艶福家で豪快な人だった。
今に伝わらぬ統治のプラス面
時の政権を批判して、亡命同様に日本へ渡り、「コリア評論」を主宰されていた金三(キムサム)圭(ギュ)さんとも、知り合った。何度か、同誌をお手伝いした記憶がある。金さんは、東亜(トンア)日報(イルボ)の主筆の体験を生かして、当時は画期的だったクロス承認方式を提唱して、健筆を奮っておられた。南北朝鮮の対立状況を解消するため、中ソ(当時)が韓国を、日米が北朝鮮を、それぞれ承認することによって、平和を担保するというアイデアだった。
しかし、その後の経緯を考えれば、中露は韓国を承認したが、日米は、北朝鮮と国交を持たないままである。あの当時は、かの大新聞の陰謀で、日本では伏せられていたが、北朝鮮という史上かつてない独裁国家の実像と戦略が、今や全世界で周知のものとなったからである。
例の大新聞は、韓国を独裁国家と決めつけて、あれこれ捏造報道を繰り返したが、まもなく馬脚をあらわすことになった。あまり、褒められた話ではないのだが、不純な動機ながら、多くの日本男性が、韓国を訪れるようになり、本物の韓国を実際に目で見るようになったからだ。
今も変わらぬ売春大国は、当時から有名だったのだ。空港などでは、団体旅行の男たちが、昨夜の女がどうのこうのと、聞えよがしに話しているのは、同じ日本人として、気が引ける思いだった。当時は、日本世代の韓国人が健在だったから、日本語を理解できる。あまりの傍若無人さに、舌打ちをしながら、露骨に「ウェノム」だの「チョッパリ」だの、差別用語を口にしている韓国人も、珍しくなかった。こうした日本人は、韓国語が判らないから、差別用語で呼ばれても、判らないのだから、おめでたい話だ。
しかし、不純な動機から訪韓しようと、実際の韓国を見てくれば、韓国が制限付きながら、自由主義の国だと判る人が増えてくる。とうとう、例の大新聞も、疑似イベントのような韓国=独裁国家論を、引っ込めるしかなくなったようである。
免税店などでは、日本世代の年配の女性が、若い人に日本語を教えているケースもあった。何度か訪れ、親しくなると、世間話のようなこともするようになる。さる女性は、つい最近(当時)、女学校の同窓会を行なったところ、多くの同窓生が日本から駆けつけてくれたと、嬉しそうに話してくれた。
当時、女子の高等教育は、日本でも朝鮮でも、まだ途上だった。女学校は、いわば最高学歴で、いい家の子女しか、通えなかった。したがって、この方の同窓生は、かつてソウルに住んでいた日本人が多かったわけだ。いや、この方も、元日本人であり、内地か朝鮮かなどと、出自を気にすることなく、自由に青春を共にしていたのである。
多くの悲劇も誤解も矛盾もあったが、こうした日本統治時代のプラス面が、日本でも韓国でも、今の世代に正確に伝わっていないことが、日韓の最大の問題なのだろう。
良好になりつつあった日韓関係
70~80年代にかけて、韓国では、慰安婦も歴史認識も、話題にすら昇ったことはなかった。その後、韓国を独裁政権扱いする報道も影をひそめ、日韓関係は、良好な方向へ向かいはじめた。もちろん、一部では、反日もあるにはあったものの、顕在化しなかった。
むしろ、日本人のほうが、韓国への好感度を増していった。「冬のソナタ」のヒットの影響もあったろう。元のタイトルは「冬(キョウル)恋歌(・ヨンガ)」である。主役の裴(ペ)勇(ヨン)俊(ジュン)の魅力もあったろうが、誰が訳したのか、ソナタという言葉が効いたせいもあるだろう。
70年代、日本世代の免税店のおばさんたちは、男ばかり来ないで、女性にも韓国へきてもらいたいと、いつもぼやいていた。家内を同行すると、おおいに喜ばれた。当時、ビーズのハンドバッグ、螺鈿(らでん)の漆器、絞り染めの生地など、男には価値の判らない土産物が、韓国では安く買えたのである。時代は、様変わりして、多くの中年女性が、日本から韓国を訪れるようになった。
私も個人的に、日韓親善に尽くしてきたつもりである。東国大学以外にも、たまたま知り合いができた祥(サン)明女子(ミョンヨジャ)大学(テーハク)など、いくつかの大学へ、文庫本を教材として寄贈しつづけた。韓国の日本語スピーカーを減らさないためである。
また、本業に関して言えば、日韓の推理作家協会の交流プロジェクトが、行なわれた際には、おおいに働いたと自負している。韓国では、減ったとはいっても、日本語で案内してくれる作家に、事欠かない。しかし、日本では、「韓国の独裁政権、やっつけろ」式の景気のいいスローガンをぶち上げる作家は、たくさんいたものの、韓国語で案内できる作家が、ほとんどいなかった。「あれ(イッチョ)に(ゲ・)見えます(ポイヌン・)建物(コンムル)は(・ン)、国会(クッケ)議事堂(ウィサタン)で(・イ)ございます(ムニダ)」などと、東京観光ではバスガイドのようなことも、しなければならなかった。
90年代には、日本人の韓国に対する関心と、好感度も高まり、韓国人の日本への興味、関心も、増していった。サッカーW杯の共同開催に向けて、日韓関係は、新たなステージに向かうかに見えた。
日韓離反狙う慰安婦捏造報道
だが、ここで、あの大新聞は、またしても、その強大な権力を行使して、日韓離反の挙に出た。
1991年、いわゆる従軍慰安婦なる虚構が、報道されたのである。この巨大新聞は、現在では、いちおう虚妄だったことを認めてはいる。だが、軍隊相手の売春婦である慰安婦と、勤労動員で働いた挺身隊を、混同した報道に関しては、当時は事実関係の研究が進んでいなかったためと、弁解している。
しかし、年齢の離れた姉が、あのころ女学生で、勤労動員により中島飛行機の工場へ、自転車で通っていたのを、私ははっきり覚えている。もちろん、慰安婦とは、何の関係もない。ことは、姉の名誉とも関わってくる。
平成に入って早々のころには、あの新聞社にも、私と同世代の社員が、まだ現役でたくさん働いていたはずである。知らないはずがない。二十数年も訂正することなく、頬かぶりをしてきたのは、単なる誤報などではなく、あの大新聞が仕掛けた日韓離反策の一環で、意図的なものだからなのだろう。
日韓離反を図る大きな意思は、あの新聞の言論支配のもうひとつの柱として、吉田某なる人物による、済州(チェジュ)島(ド)における日本官憲の女狩りという、とんでもない虚構を付け加えることによって、さらに拡大していく。
しかし、その後の十数年は、この大新聞の企みは、まだ功を奏さなかった。日本では、韓国ブームが続いていたからである。これまで訪韓したことのない、中年婦人層が、韓国を訪れることが多くなり、韓流にはまった韓国語学習者も、増えていった。そればかりでなく、男性のなかにも、韓流ドラマにはまる人が多くなった。韓国の大河ドラマ「朱蒙(チュモン)」は、高句麗の開祖朱蒙を主人公とした作品だが、私の近くのDVD店では、新作が十巻入っても、即日借りだされるほどの人気だった。
朱蒙は、もともと「三国(サムグク)史記(サギ)」に記録される神話上の人物なのだが、それを強引に歴史ドラマ風に、仕立て上げるところが、まさに韓国人である。元ネタが僅かしかないので、古今東西のエンタテインメントから、使えそうな要素を、流用している。水戸黄門のような部分も、大奥のような部分もあるが、臆面もなく、受けそうな要素を投入しているから、たしかに面白いことは面白い。
また、韓国側も経済力の伸長と共に、訪日して実際の日本を肌で知る人々が増えてきてもいた。別府の大ホテルなど、経営危機に陥った苦境を、韓国からの観光客の増大で乗り切ったほどである。国際化というスローガンが、しばしばマスコミを賑わすが、お互い知り合う以外に、国際理解が進むことはない。
慰安婦と同構造の原発報道
だが、挺身隊=慰安婦という虚妄、済州島女狩りという捏造は、徐々にボディブローのように効いていった。韓国では、従軍慰安婦像なるものが、日本大使館の前に設置され、アメリカ各地へ飛び火していく。あの像は、新聞報道にあった12歳の少女として造られている。挺身隊=勤労動員には、中学生、女学生も動員されたから、その年齢の生徒たちも少なくなかったが、軍隊相手の慰安婦に、その年代の少女がいたという記録もないし、事実もなかった。
韓国では、挺身隊問題対策協議会という団体が、活動し続けている。あまりにも長ったらしいので、挺(チョン)対(テ)協(ヒョ��)と略している。あの大新聞が垂れ流した挺身隊=慰安婦という虚構を、そのまま踏襲しているわけだ。語るに落ちるとは、このことだろう。
事実関係が、はっきりしたのだから、あの新聞の責任で、韓国側に訂正を求めるのが、筋だろう。だが、あの新聞は、それをしない。それどころか、慰安婦の存在は事実だから、これまでの方針に変わりないという態度を、とりつづけている。
なぜ、こうなるのだろうか? 韓国の問題と離れるが、私も筆禍に遭ったことがある。あの新聞社は、取材も検証もしないで、記事を書くことが、はっきり判った。私が受けた筆禍など、些細なことだが、問題の根は、共通している。
私は、本業のSF小説の未来エネルギーとして、昭和30年代から、原子力に興味を持っていた。そして、日本中の原発と、建設予定地の全てを、取材した。当時、人気の「朝日ジャーナル」誌が、特集を組んだなかに、私の名前も、名誉なことに入れてあった。その特集とは、「わたしたち(原発反対派)を未開人と罵った識者十人」というものだった。もしかしたら、原発反対派を未開人と罵った粗雑な人間が、その十人の中に、いたのかもしれない。
しかし、私は、そういうことを言ったこともないし、書いたこともない。それどころか、立地点の住民の反対を尊重すべきだと、常日頃から主張してきた。また、すでに物故したが、反対派の大立者の高木仁三郎は、私の中学の同級生で、同じ大学に入った間柄であり、かれが反対意見を発表できないような事態になったら、私と意見が異なってはいても、かれの言論の自由を守ると宣言してきた。さらに、原発に反対する自由のない国は、��発を建造すべきではないと、何度も書いたことがある。
ことは、原発賛成、反対という問題ではない。こうした報道をするからには、私をふくめて、そこに記された十人が、そういう発言をしたかどうかを、取材確認する必要がある。
ところが、私には、まったく取材は来ていない。そこで、私は、雑誌「諸君」のページを借りて、当時人気だった筑紫哲也編集長宛てに、私が、いつ、どんなメディアで、そういう発言をしたかと、問い合わせた。もちろん、そんな発言など、あるわけがない。筑紫編集長の回答は、のらりくらりと、話題をすりかえることに終始した。
韓国人と〝あの新聞〟の共通点
つまり、あの大新聞は、取材も検証もしないで、主義主張に基づくフィクションを、報道の形を借りて、読者に垂れ流しているわけだ。原発などに賛成し、傲慢な発言をする非国民が、十人必要になった。そこで、関係ない人間もふくめて、誌上でさらし者にしたわけだ。つまり、原発推進めいた意見を、圧殺する方針だったのだろう。
いわゆる従軍慰安婦の報道と、まったく同様の構造である。
従軍慰安婦なるフィクションを、あたかも事実であるかのように、売りまくって読者を欺いた責任は、まさに重大である。しかも、日韓関係を破壊したばかりでなく、全世界にわたって日本の名誉を泥にまみれさせた罪科は、きわめて悪質である。
誤報ではなく、明らかに意図的な捏造である。この捏造が,韓国に飛び火すると、さらに拡大していく。その意味では、この大新聞の離反策に、うまうまと乗せられた韓国も、いわば被害者と言えるかもしれない。主義主張を真っ向から掲げて、事実の確認も検証もしない韓国の国民性と、あの新聞の社是(?)は似ているかもしれない。
私は、過去四十数年にわたって、韓国と関わってきた。最初、自宅ちかくの笹塚の小さな教室で、韓国語を学びはじめた一人に産経新聞の黒田勝弘さんがいる。あちらは、ソウル在住が長いから、私など到底及ばないネィティブスピーカーに近い語学力だが、スタートは一緒だった。
以後、折々に韓国関係の著書を上梓してきたわけだが、その都度、親韓派、嫌韓派などと、勝手に分類されてきた。例の大新聞もふくめて、日本のマスコミが北朝鮮に淫していたころは、日本のマスコミ批判とともに、韓国擁護の論陣を張り、顰蹙を買った。また、韓国の反日が、度を過ぎたと思えば、遠慮なく韓国批判を展開してきたつもりである。
国際親善には、王道はないから、知る以外に近道はないと考え、「日本人と韓国人、ここが大違い」(文藝春秋)「いま韓国人は、なにを考えているのか」(青春出版社)など、比較文化論ふうの著書もあり、口はばったい話だが、日本人の韓国理解に貢献してきたつもりである。
もちろん、私の独断と偏見に堕す危険があるから、多くのコリア・ウォッチャー仲間から、助言や意見も頂戴し、拙著の間違いも指摘された。
転向左翼の韓国利用
いわゆる韓国病にはまりかけていたとき、早大名誉教授の鳥羽欽一郎先生から、たしなめられた。「豊田さん、日本人と韓国人は、おたがい外国人なのだから、同じ視点に立つということはできませんよ」と、確か、こんなことを言われた。そのときは、むっとしたが、先生は、韓国にのめりこみすぎている私に、ブレーキをかけてくださったのだ。
70年代、韓国にまじめに取り組もうという日本人は、それほど多くはなかった。田中明氏のような大先達のほか、外交評論の大御所岡崎久彦氏にも、お目にかかり、励ましを頂戴したことがある。外務省在勤中で、本名をはばかったのか、「隣の国で考えたこと」を、長坂覚のペンネームで、早い時期に刊行されている。現在は、本名で再版されているから、入手可能な名著である。
また、産経新聞の柴田穂さんも、大先達の一人だった。韓国関係の会合で、何度か、お目にかかり、アドバイスを頂戴したこともある。なにしろ、中国政府に批判的な記事を書き、産経新聞が北京支局の閉鎖に追いこまれたとき、支局長として残務を整理し、従容として北京を退去された剛直な方である。支局閉鎖という事態を招いたのだから、本来なら責任重大なはずだが、言論の自由を守ることを優先したのである。
それに引き換え、当時あの大新聞は、中国べったりの記事を、垂れ流しつづけていた。この新聞社には、Aという名物特派員がいた。中国通をもって自任していたはいいが、他社の記者まで、このA特派員に、お伺いを立てるようになったという。どこまで書いたら、中国政府の逆鱗にふれるか、A特派員に、判断を仰ぎに来たのだ。早い話が、あの大新聞が、日本の中国報道を検閲していたことになる。
70年代、北朝鮮一辺倒だった日本の文化ジャーナリズムの世界で、一つの伝説があった。いわゆる進歩的文化人は、自分の名前だけ、ハングルで書けたというのである。申し合わせたのかもしれないし、あるいは、あの大新聞の関与があったのかもしれない。現在からは、信じられない話だが、ハングルで名前を書いてみせるだけで、朝鮮問題(?)の権威扱いされたそうである。
しかし、現在の日韓の確執を眺めると、妙なねじれ現象がある。竹島問題にしても、従軍(・・)慰安婦(・・・)にしても、韓国側と共同歩調を取っているのは、70~80年代、あれほど韓国を独裁国家扱いして、忌み嫌っていた進歩的文化人なのである。節操もなにも、あったものではない。日本叩きに資する、あるいは、商売になると判ったら、かつて贔屓にした北朝鮮を見捨て、韓国に媚びるのだから、こういう世渡り上手と戦うのは、容易なことではない。
事実伝えることが真の親善に
翻って、現在の韓国である。反日は、狂気の沙汰の域に達している。これには、日本世代が現場から退き、あるいは物故したという事実が、おおいに関係している。私が、多くの教示を受けた方々は、もし存命なら、こんなことを言うと怒られるかもしれないが、日韓双方の美点を兼ね備えておられた。
もう一歩、踏み込んで言えば、日本の教育を受けた方々だった。立派な方というと、ややニュアンスがずれるが、韓国語でいう「アルンダウン・サラム」という方が多かった。こういう世代が亡くなり、反日が質量ともに、変わってしまった。まず、かれらが考える仮想の日本人に対して、際限なく敵意をむき出しにした、いわばバーチャル・リアリティの反日になっている。
日本では、韓国人は、険しいイメージでとらえられがちである。反日の激しさを見れば、間違いではないが、一面的に過ぎる。日頃の生身の韓国人は、お喋りで、陽気で、図々しいくらい人懐こい。日本人は、以心伝心を理想とする文化を生きているが、韓国人は、口にしたことが全てである。発信能力を磨かないと、生きていけない社会である。たとえ嘘でも、自分の主義主張を正面に掲げないと、たえず足をすくわれる危険に直面している。
そのため、国際的には、日本人より判りやすいと定評がある。よく見てもらえれば、日本人の誠意が通じるはずだが、韓国人のほうが声が大きいから、知らない人が聞くと本気にする、と言った程度には、説得力を持ってしまう。
大方の日本人の対韓姿勢は、「また、韓国人が騒いでおる。放っておくのが、大人の態度」といったものだろう。これが、日韓摩擦を拡大した主な原因のひとつである。日本からの反撃がないから、向こうは、さらに反日をエスカレートさせるのだ。
日本は、和の社会だとされる。これには、聖徳太子が引き合いに出されることが多いが、贔屓の引き倒しの面がある。有名な十七条憲法の第一条が、はきちがえられている。太子は、談合のような和を勧めているわけではない。あくまで論じてからと、なれあいを戒めている。
まさに韓国相手では、論じなければ駄目なのだ。相手は、合理的な議論が苦手だから、徹底して、論拠を上げて、言い負かすつもりで、追いつめなければ、非を認めない。一見、乱暴なようだが、反日が、高くつくという事実を、知らしめないかぎり、韓国の反日は、拡大するばかりで、絶対に解消しない。
現在の韓国は、日本世代がいなくなり、歯止めがかからなくなっている。さながら李朝時代の政争のような、権力闘争すら起こりはじめている。日本が、関わりを持つ以前の時代へ、先祖がえり(atavism)してしまった感がある。ここに乗じて、あの大新聞が、新たなテーマで反日の捏造を加えて、逆襲してくる畏れもある。いや、その萌芽は、すでに現れている。
私の「どの面下げての韓国人」(祥伝社)は、やや刺激的になるのを承知のうえで、出版社と協議して決めたタイトルである。さっそく、左翼弁護士が、噛みついてきた。ヘイトスピーチだというのである。しかし、ネットでは、すぐ反論されている。つまり読んでいないことを白状したようなものだというのである。なかには、あの本は韓国に同情しているのだ、とする感想もあった。こういう応援は、ありがたい。
私は、あるときは親韓派、あるときは嫌韓派というレッテルを、貼られてきた。私は、日本人であり、日本を愛している。その都度、批判すべきことは、日本であれ韓国であれ、批判してきたつもりである。
あの大新聞は、苦境を打破するため開き直って、韓国批判の本には、すべてヘイトスピーチだという烙印を押して、葬り去ろうというわけなのだろう。また、いわゆる従軍慰安婦の仕掛け人の元記者の就職先や自社に、脅迫があったという事実をもとに、言論の自由を盾にして、被害者の立場へ逃げこもうとしている。自分が、強大な権力をふりかざして、異なる言論を圧殺してきたことには、すっかり頬かぶりしている。
韓国には怒りを込めた反論を、あの大新聞には、厳しい追及の手を緩めてはならない。それが、ほんとうの日韓親善につながるからだ。
とよた・ありつね 昭和13年前橋市生まれ。父の医院を継ごうと医者をめざし、合格した東大を嫌い慶應大に入るも、目標が変わり武蔵大に入学。第1回日本SFコンテストなどに相次いで入賞して在学中の37年作家・シナリオライターとしてデビュー。手塚治虫のもとで「鉄腕アトム」のシナリオを二十数本担当。「スーパージェッタ―」「宇宙少年ソラン」の脚本も手掛ける。『倭王の末裔 小説・騎馬民族征服説』が46年にベストセラーとなる。47年東アジアの古代史を考える会創設に幹事として参画。50年「宇宙戦艦ヤマト」の企画原案、SF設定を担当。SF作家クラブ会長、島根県立大学教授などを歴任。63年オートバイ日本一周を達成。近著に『日本の原発技術が世界を変える』『どの面下げての韓国人』(ともに祥伝社新書)など。
※別冊正論23号「総復習『日韓併合』」 (日工ムック) より転載
3 notes
·
View notes
Text
『第六学舎』
窓からは密かに写真家たちがこぞって撮りに来る紅葉が綺麗だった。
その筋では著名な教授が高説を垂れている。授業中の静謐な空間はまさしく聖域で、何者にも邪魔されることはなかった。しかし一方で、自らに生まれるストレスや疲れという内的なエネミーに関しては別だった。連日課されるレポートの山に耐えうるだけの精神力がそろそろ尽きて来て、自分の方に眠気の悪魔が寄り掛かる幻想を見た。
あまり綺麗でない古いアパートに住んでもう三年半が過ぎた。家賃は月に五万と五千円、食費や光熱費を考えると更に支出は膨らむ。週四回のコンビニバイトと少しの仕送りでなんとか生きているが、そのコンビニでの仕事と難易度の高い専門分野のレポートをこなすと余暇はあまりに少ない。こうした状況の中で生じる休息の不足によって、なかなかに息の詰まる日々を送っている。
作る時間がなかったので、僕には友達がいな��った。完全に、といえば嘘になるだろうが、しかし交友関係は片手で指折り数えるくらいだった。だから、友達から過去問を貰うということもないし、友達と一緒に授業の課題に頭を悩ませるということもない。それがどうというわけではないのかもしれないし、それを言い訳にするのは違うのだろうが、──僕は単位取得率が極めて低い。親に成績低調者の家族向けの書類がやってきて、「これはどういうこと?」と冷たい声で電話越しに詰め寄られたのはそう遠い昔の話ではない。
しかし実際こうして授業を受けていても、何のことにもならないような無気力さがあった。予備校生のときは西京大学に入りたいという気持ちを持って勉強し見事合格、それから夢溢れる大学生活を想像していたものだ。
それが今はどうだろう。怠惰で自堕落な腐れ外道の大学生活。目的意識もなければ共に高みを目指す学友もいない。そういう日常の危うさを誰よりも自らが理解していながら、僕は何も解決しないでいた。
教授がチョークを持つ手を止め、籠ったマイク越しの声で一つ咳払いをしてから、こう言う。
「あの、眠いなら寝てきなさい。悪いことは言わないから」
僕のことを言われたのだろうか。しかし僕は知らん顔で目を伏せたまま、眠気に身体を任せたまま再開された授業に耳を傾けて……そのような態度だと周りに認められるかどうかはともかく、そうしていた。
眠りの世界にまた突入しようとした僕に教授はまたチョークで何かを書く手を止めた。
「君に言ってるんだよ。高校生じゃないんだから、もう注意しないよ」
ああ、別に何を言われても構わない。大学生なんだから、自分のことは自分で決めるさ。
人の目より自分のことの方が今は最優先だったので、そういう意味では高校生以下なのかもしれない……大学生になっても、歳をとっても何か変わるということは一切ないのではないかとすら思うのだ。そんな屁理屈をこねながら、僕は睡眠欲求に負けた。
それから目を覚ましたのは随分あとで、それは横にいる人間に肩を叩かれたのが主要因だった。
「先生、この人もう起きないんじゃないですか、寝かしてあげましょうよ。可哀想だし」
「……お、起きたようですよ。おはようございます。
貴方はこの研究室のメンバーではないはずですから、三限目からずっとこの教室で寝ていたんですね」
自分のロングスリーパーぶりに自分でも驚く羽目になるとは思わなかった。目の前にいたのは先の授業で弁を振るっていた落ち武者スタイルの教授ではなく、どこか弱々しい雰囲気を身にまといヨレヨレのスーツを着ていた名前も知らない先生だった。
「すみません、不躾な姿を晒してしまいました」
「いえいえ。何なら、今日だけでも私たちの話に参加していきませんか」
「嵯峨野先生、ちょっと、どうしたんですか。ずっと部屋にいたからって研究内容の話するんですか。第一、ここの研究内容って授業中から寝てるような人に理解できるんですか?」
ゼミ生だろうか、必死に教授の暴走を止めようとしている。僕は正直どっちでも良かったが、なんとなくすぐ終わるなら流されてもいいような気がしていた。
「心配いりませんよ。むしろ、面白くないですか? こんなに劣悪な環境で眠れる人間が世の中にはいるんですよ。寝ている最中も声は普通に飛び交っているし、横からたたき起こされるし。その中でこんなに図太くいられるというのは相当なものです」
「……何を言われているのかとか褒められているのかどうかとか、そういうところはさっぱりですが、僕は根本的に不真面目なので、先生のご高説を拝聴しても理解できるかどうか」
「なーに、そんなことは何も考えなくていい。なにせ、私も貴方の専攻に関しては素人でしょうからね。違うフィールドに立てば私が偉いということはなくなるので、気にしなくていいんですよ。さて」
嵯峨野先生は自分の世界に入られる方で、非常に落ち着き払っていた。そして、言葉を選びながら慎重に物事を筋立てていく研究者だということが僕にもすぐに分かった。
「我々の研究の第一義には『核エネルギーの利用』があります。もっとも、昨今は原子力発電の危険性が叫ばれていますから、そこまで声高にその利点や特性について何か語ることはしづらくなってきていますが、そもそも核融合を使った発電の仕組み自体知らない人が論説していることがあって、我々研究者としては非常に不本意な訳です」
「嵯峨野先生は、そういう核エネルギーについてもっと効率的で安全な利用法がないかどうかを研究する方で、普通のひとから見たらとてもじゃないけど心配性すぎてついていけないかもしれません」
「ちょっとどころじゃないよね、かなり変わってると思う」
嵯峨野先生がゼミ生たちからそこまでして言われるような教授には見えなかったが、人には表面を撫でただけではわからない多面性というのがあるのだろう。触るだけでは色の分からないルービックキューブだって六面あるんだから、人間はもっといろんな顔を持っていてもおかしくない。
「たとえば、原子力発電の問題で言えば、いわゆる「核のゴミ」といわれる放射性廃棄物を再利用する核燃料サイクルというのがありましたが、これは今では破綻しているという意見があります。これには、高速増殖炉という、いわば『使った燃料以上に燃料が出来るので、半永久器官化できる』と言われていたようなものが失敗に終わったり、使用済み燃料をウランと混ぜて燃やしたりというプルサーマル計画に穴があったり、と色んな背景があるわけなんですが、そうした問題をどのように軟着陸させ、違う形での核エネルギーを利用した発電方法とその安全性の確保をしていくかというのが、この研究室の諸課題なわけです。お分かりいただけたでしょうか?」
僕は、並べられた専門用語をいちいち質問するのは野暮だと思った。大筋は流し見していたニュースで見ていたことだから知っているし、その方向性でいいのかもしれない、ということも分かる。
「ええ、非常にわかりやすかったです」
「それは良かった。思わぬ来訪者でしたが、話してみて良かった。少し疲れたので脱線しますが……」
「あっ、先生。もしかして、気になっているのは『あの件』ですか?」
ゼミ生のひとり、三つ編みのツインテールという今どき流行らないヘアスタイルをした女子が言った。それにしても、僕は彼女のいう『あの件』を知らないのだが、それはなんなのだろうか。
「ええ。流石に冗談めかしてますからね。皆さんもまさか本気で受け取ってる人はいないと思いますが」
「あの。皆さんが仰っていることが分かりかねまして。僕は本気で友達がいないので、そういった学内で流行ってる話に疎いんですよ」
「何ですって、それはいけませんね。まあここからは無駄話ですから、つまらなくなったら帰ってもらって構いません。
……お、全員、帰らないんですか? そうですか、いいでしょう。それでは話しますからね。
皆さん、『西京大学は核実験を止めろ』という投稿は見たことがありますか」
「はい」
「もちろん。何ならネタにもなってますよ」
僕は不勉強でそんな不謹慎なことがあるのかともはや感心してしまった。まあ軽率なネタってだけで、教授が深刻にとらえることもない事柄だろう。
「その元ネタを探ると興味深いことがあったと、かつての卒業生から連絡があったんです」
「と、言いますのは?」
「この大学でも学生運動というのがあったんですよ──私はまだそのとき高校生なわけですが──その学生運動の看板を探していたら、似たような文字列を見つけたというんですね」
「なんで見つかったんでしょう。ただの卒業生の方なんですよね」
「そのへんは語ると長くなりますが、簡単に言うと演劇部のOBでいろいろ前衛的な芝居をやるにあたってそういう界隈を調べ漁ったら、出て来たらしいですね」
「あ、それ学祭でそれっぽいのやってた」
「そうそう、それが原形になった舞台を来月辺りにやるらしいですよ。あの子、宣伝上手なのは昔から変わらないですね」
学祭は毎年秋に盛大に行われ、四日にわたって学内、とくに模擬店や大きなステージはお祭り騒ぎとなる。僕は一年生の時に所属していた部活の手伝いに行ったっきり顔を出していないが、本当にその盛況といったらない。
「それは置いておいて……まあ、学生運動の看板に使われるほど古いネタがなんで再燃したか、ってのが本当に謎なんですよ。調べればすぐに出てきてミーム化するような言葉とも思えませんし。しかも、その時代はちょうど戦後体制への不信感が高まっていたとはいえ、大学で核実験を行っているという突飛な言説が出てくるというのも、いささか不自然なんですよね。まあ、私が深追いしていい問いとも思えなかったので、謎は謎のままにしておいたんですが」
教授は核の原理的説明やエネルギーの効率的な利用といった文脈にはもちろん文献をも凌駕する詳しさをお持ちなのだろうが、それ以上に核が置かれた文化的・社会的背景に詳しかったことに僕は驚いた。
「おみそれしました。僕なんて単なるネタで書かれてたんだろうと思ってたんですが」
「いや、当時の人たちだって、さすがに本気で核実験が学内で行われていたなんて思っていなかったでしょうからね。そんなに気にすることじゃあないんでしょうけど、そういう意味のある無駄なことを気にするのも面白くありませんか?」
僕が意識しないことを面白がるとき、こうやって理由を明確にして面白くないかと尋ねるのがそれからも教授との話では常になるのだった。
研究室で疲れた身体を癒す上級生が僕のいる教室に先生を呼びに来たついでに、帰り際の僕に声をかけた。
「知らない顔だね。どうしてここにいるんだ?」
「なんでっていうと、難しいんですけど。寝てたら何か巻き込まれました」
「……どういうこと?」
まあ、はじめから理解される気はない。
「ま、嵯峨野先生は言葉が足りないことはないから大丈夫だと思うけど、逆にうるさく感じてたら申し訳ない。止められない俺らが悪いわ」
「いえいえ。全然、成績が芳しくない僕でも話についていけるくらい丁寧でしたから」
「それだったら良かったけどさ。
でも、まあせっかくこの研究室に来たからには、ここで語り継がれている密かな噂のひとつでもしようじゃん」
「あの、『西京大学は核実験を止めろ』じゃないですよね?」
僕はまさかこの話をまたされるんじゃないだろうなと思って先回りをしたのだが、先輩は薄く笑って、ははは、と乾いた笑いを弄した。
「うーん、まあ、割と近いんじゃない?
じゃあ、『真夜中の虹』は知ってる?」
「昔の映画ですか。ロード・ムーヴィー風の。一度だけ見たことがあります」
「ごめん、それはたぶん違うよ。『真夜中の虹』ってのは、昔あった学校非公認の美術系団体で、よく問題を起こして学校から怒りの鉄槌を下されてたらしいんだけど、そこにいた人間のうちの一人が今でもテロ組織の指名手配犯になってるって話。『西京大学は核実験を止めろ』ってふざけた看板を作成したのは、その第一歩なんじゃないかっていうのが、この研究室にいた先輩たちの大方の見方だね。でも」
先輩はこう続けた。
「西京大学は核実験をしてたからって何か不味いことが当時あったんだろうかね? だから大っぴらに告発した、って線を消す必要はないんじゃないのってのが俺の、誰にも言ってない『諸説』だね」
「先輩、それ本気ですか」
「おいおい、俺はいつから君の先輩になったんだよ。気軽に『トモさん』とでも呼んでくれ」
彼は気軽に、構えないように、と僕に言った。彼にとってはパーソナルな関係の定義がとても広いのだろうと思った。
「それじゃ、トモさん、改めて聞きますけどその『諸説』は本気なんですか」
「ああ、本気だよ。別に根拠があるわけじゃないけれどね? こんな住宅地に近くて、その割に敷地面積が広いんだから、核実験施設の一つや二つは地下やどこかにあったって不思議じゃない」
……前言撤回。気軽に接しやすいというのではなく、ただの変人だった。
「あやふやすぎて、なんか、信じるに値しません」
「そんな風に言うなよ、これ��ただの思考実験なんだから。『もしも、西京大学が地下に核実験施設を持っていたら?』という問いが真だったら、どんな風な世界なんだろうね。西京大学にあるから、たとえば京大や東大にも核実験施設があったっておかしくないだろう──憲法か何かで禁止はされているだろうけど、そういうことは隠れて行われるから、まあ規律とかは所詮その程度のものってことだよ。ナンセンスだと思うかい?」
「……ええ、かなり」
「価値観の相違っていうのかね、こういうのは。嵯峨野先生が聞いたら怒りそうな話なのは確かだから、君も俺もそういう話はしないでおいたほうがいいというのは言っておくけれど。重大な価値観の相違があるから」
「嵯峨野先生って怒るんですか」
「一度だけ怒っているのを見たことがあるけど、意見の食い違った学者相手だったから俺しかその姿は知らないかもね。普段はもう仏よ」
トモさんの話は、友達のいない僕にとって、随分久しぶりに全く違う人生を歩んできた存在を見ているような気分になった。たった看板ひとつの話でここまで違う考え方の人間がいるとは、と思った。
「ああ、ただ、よく言ってるけど全然分からない言葉はいくつかあるよね」
「それってどんなのですか」
「『黙っていたら死んだことにされるぞ』とか、『意味のある無駄と意味のない無駄がある』とか、『核融合は本当はやりたくない』とか。もうどっちなんだよ、っていうことがいっぱいある」
「あーそういえば僕も、意味のある無駄なことを気にするのも面白くないか、みたいなこと言われました。あの先生、本当は唯物論者の哲学者なんじゃないですか?」
「そんな気がしてきたな」
トモさんは人の悪そうに笑った。
学祭の準備で学内が色めきだつ頃になった。銀杏の葉が落ち、実が道に転がる。あれ踏むと匂いが靴に付くから避けなきゃいけないんだよな、と思って避けていたら、人にぶつかった。
「あ、すみません」
「ごめんなさい、私が不注意で──あれ、この前の」
あの時代遅れっぽい三編みの子だ。こちらからすれば、なんだ、昭和の女学生か? と思っていただけなので特に印象とかはなかったのだが、この子からすると僕はロングスリーパーとして激烈な印象を与えていたのだろう。
「どうも。あれから嵯峨野先生は元気にしてるの?」
彼女は少し口籠っていた。僕の持っていた元々生ぬるいコーヒーが冷めていくのを感じて、焦れったくなって「どうした? なんかあったのか」と聞いたなら、ちょっと疑り深さを隠しきれない声で、
「嵯峨野先生、最近ちょっと様子がおかしくて」
と言うではないか。
僕は交友関係が相変わらず狭くてやっと反対側の手に付き合いの人数が拡がったくらいなので、そのあたりのことはやっぱり詳しくなかった。そして、他人にはやはりそんなに興味がない性格もまったく変わっていない。
しかし、一度でも深く長く面白い話をした人間の動向となれば、少し別になるのだろうか。まさかこんなところで核エネルギーの話をすることになるとは……僕はちょっと長話になるのを覚悟した。
「いいよ。話を聞きたいけど、少し肌寒くなったし、そこに入ろう」
僕は学内にあるチェーン展開された喫茶店を指した。しかし彼女はかぶりを振って、「そこだと都合が悪くて。私の部室に来てくれない? もうひとり、ウチの同期もいるし」と返した。普通にしていれば話を聞かれることもないだろうに、そこまで警戒する心理がなんとも分からないものだった。
「そんなに慎重に話さないといけないようなことか」
「どちらかというと、嵯峨野先生の名誉に関わることなんだよね。私だって別に喜んで他人のことを悪し様に言いたかないのよ」
「悪い話ってことなのは、今までの態度で分かった」
学内でも外れにある真っ白な団地じみた建物を上って二階の部室に辿り着くまでに、そんなに時間はかからなかった。珍妙な飾りつけでなんとも入るのには抵抗があったのだが、彼女がドアを開けたものだからそれについていくしかなかった。
「どうも、お邪魔します」
「まあ、ゆっくりしていってよ。同年代なんだから」
本当は僕がひとつ上だとはなかなか言い出しにくかった。
「彼女から事情は聞いた?」
「ああ、まったく事情を把握するには足らないけれど、嵯峨野先生があまり良くない状況に立たされてるのだけは分かった」
「それだけ理解できてたら全然大丈夫だよね、弓削」
「そうだけど──話をする前にひとつ。これは流石に教授が可哀想なので、他言無用で」
「ちょっと待った。そんな大事な話を、この前からちょくちょく会ってるだけの僕に話すんだ? 近況がよろしくないということが分かれば、僕にそこまで喋る必要なんてない」
「『真夜中の虹』」
そこで僕が沈黙を挟んだので、つむじ風が、びゅっと吹く音がした。
『真夜中の虹』が研究室の中でひとつの定説の根拠となっているのは理解しているが、なんで僕がトモさんにその話をされたことをこの人たちは知っているんだろうか。
「その感じは、やっぱり知ってるんだね。
じゃあ、この話は知ってるかな? 嵯峨野先生は『真夜中の虹』に所属していたこと。どうかな?」
あの理知的な姿勢を見せていた嵯峨野先生が、大学や政治を皮肉るような前衛的な芸術運動に関わるというのは、なかなか理解の及ばないことだった。
「ええ、もちろん知らない」
「だと思った。ちょっと安心したよ、既にその話が広まっていたらどうしようと思っていたから。やっぱり、偶然とはいえ、将来テロリストになる人間と同じ団体に入っていたというのは、核科学者としてはちょっと怖いどころの話じゃないし、いろいろとどうしても疑われそうだよね」
「嵯峨野先生が芸術肌だったのは、このせいか……」
「設立メンバーに誘われて加入してるから、もともと多感で影響されやすい人だったのは確かだと思うんだ。まあ、入っていながら『核実験をやめろ』看板を知らないってのは不思議なんだけど、これはあんまり重要じゃないね」
重要かそうでないかの区別が僕につくはずもなく、ただ同意してしまった。
「嵯峨野先生はどこかアヴァンギャルドな作品を作ってたらしいってどこかで聞いたんだけど、作品も見られないし忘れちゃったな。今でいうなら岡本太郎みたいな感じで」
ああ、岡本太郎か、彼なら核の戦禍、とりわけ原爆や水爆について描いていたと美術の教科書に書いてあったなと思い出した。その絵がとびきり気持ち悪くて、とびきり強烈だったから。
「それでね、そのときの共作相手を調べたら、……私、驚いて、何も言えなくなった」
「なんだよ。もったいぶらずに話してくれよ」
彼女が、何か話したいのに話せないときに見せる表情を、短いうちに分かってしまった。いったい、何が不安なのだろうと僕が推測するのもほとんど無駄だと思えた。
もう飲んでいなかったペットボトルの中のコーヒーは冷たかった。ひどく冷たくて、それが今��ら聞くことの衝撃をまた意識させた。
「朝香伯光──のちに、東光銀行の頭取を人質にしたテロ事件を起こした主犯格。小郡孝也──ハイジャック事件を起こし、のち逃走、現在も指名手配犯。松笠悠紀彦──のちに人気歌手になるも、有毒ガスを観客の待つ会場に充満させ死傷者多数の事件を起こし、現在は死刑を待つ」
これほどまでに、すらすらと言葉が出てくるだろうか。冷たく無表情で感情もない事実の羅列が頭を殴る。
「それは本当のことなのか?」
「共作も、犯行事実も、ともに正確性は高いと思うよ。それにしたって、こんなに社会に対して強烈な悪意を持つ人ばかりが共作相手になっているなんて、偶然ではまったく考えられない」
「それって」
「前衛的な美術団体なんてのはやっぱり化けの皮に過ぎないのかな、という結論に至ったのが、あなたと会ったちょうど一週間後」
その結論を材料に導き出されるのは、
「嵯峨野先生も、そういうことだったってことか」
「その可能性は高いんだろうね。だけど、それだけなら、俺たちが何か心配して、先生の暴走を止めようと騒いでいる、というのは少し無理があると思わないか?」
「どういうことだ」
「……それは、私から言わせて。私が最後に研究室を訪れたのは先月の物凄かった雨の日──そんな日は一日しかなかったから、わかるよね──だけど、そこに教授がいなかったの。……私は、ううん、私たちはそれから嵯峨野先生の姿を見てない」
嵯峨野先生が消えた? 今まで語られたこととの結びつきが怪しくて、あまりにどうも突拍子のないことだと思った。
「すまん、一つ聞きたい。今までの美術団体の話と嵯峨野先生の失踪はどんな関係があるっていうんだ?」
「関係はあるかもしれないし、ないかもしれない。だけど、研究室にはこんなものが残されていたんだよ」
三つ編みの彼女の同期といった筋肉質の男が説明しながら僕にスマホの写真を見せた。ピントのあっていない写真でも、それが何なのかはわかる。これは、壁画だ。それも、色彩感覚が非常に前面に出た、意味を含ませている恐ろしい絵だ。
「嵯峨野先生の失踪は、きっとこの壁画の写真に関係のあることがきっかけなんだろうと思う」
僕は、必死にその絵のことを思い出そうとした。そんなにアヴァンギャルドで、個人的な感覚と政治性を優先し、しかし有名になるほど普遍性を獲得した画家はいたのだろうか──いや、一人いる。
岡本太郎だ。
彼が残した作品の中で、そんな広い壁画はアレしかないだろう。
「それって、きっと『明日の神話』とかじゃないか?」
「ん? そんな作品あったっけ」
「あっただろ。俺もこいつも知ってるってことは、有名な作品には違いないだろう。しかし、なんでこんなものを置いて行ったんだ」
僕たちにその答えを出す能力は全くと言っていいほどなかった。
沈黙が流れるごとに、手持ち無沙汰な時間を使って自分の話していたことを整理するごとに、自分たちがやろうとしていることの恐ろしさと怖さに何か支配されそうになる。だけどそれを言葉にするのは難しかった。なぜ僕は恐れているのだろう。何を恐れているのだろう? 現実の何かが怖いのだろうか、それとも何かの意図に気が付くのが怖いのだろうか。
いや、僕たちはきっと空間の中にある僅かな気配だけを感じ取ろうとしているのだ。それは単なる恐れではない……人が生み出したものへの、畏怖だ。
「まったくの推論だし、根拠はないけど、繋がったのかもしれないしそうじゃないのかもしれない。ま、話だけでも聞いてくれ」
僕はへりくだったが、これは相当に自信のある結論だった。
嵯峨野先生は何をしようとしているのかということまで踏み込むつもりはなかったのだが、浅ましくもそういう話に立ち入らざるを得なくなったのだが、結論から言えば、嵯峨野先生もやはり何かの計画を実行しようとしているというものだった。その『何か』というのは、恐らく自らの専門分野である核反応についてのことなのだろうが、しかしそれを実行するだけの設備も覚悟も、ふつうのおじさんにしか見えない彼にあるようには見えない。
しかし、それがもし彼にある、と仮定したらどうだろう。
もしくはこう問を立ててもいい。もし、そのような『社会変革』を行えるだけの装置が身近にあったら、彼のような思想を持つものはどうするのだろうか。たとえ科学者の理性をもってしても止め難い何かに突き動かされるとすれば、答えは自ずと一意に決まるはずだった。
そんなことを僕は語ったのだった。
「どうだろう、別にすべて自分が正しいと思っているわけじゃないけど、話を聞く限りこういうことが言えるんじゃないか」
「それはまだ掘り下げが足りていないと、俺は思う」
彼がこういったのは、��っと状況証拠によってすべてを説明しようとしている僕に対し『証拠不十分』ということを突き付けたいようだったが、それを僕はこう切り返した。
「状況証拠だけで十分だろう。動機はあるんだ。やるかやらないかは先生の自由意志だけど、それをやる環境が整っているんじゃないかということを言っただけだ」
「……少し気になったんだけど、いい? もし仮にそうだったとして、他の『真夜中の虹』のメンバーみたいに若いころにテロ計画を起こさなかったのは、なんでだと思う?」
「それは、わかるんじゃないか? つまり、核実験装置が大学の中に密かにあったとしても、そのときは動機としては成り立ち得なかったが、母校の教授に就いて日が増すごとに、『これは有望だ』と思いながら実行の日を待ってたんじゃないか、ってこと」
「それだったなら、教授になった段階でテロが起こってもおかしくないんだよね。今、このタイミングで起こる必然性が証明できない」
話は同じポイントを堂々巡りするようにして展開する予感がしていた。それが不毛なことだと思っていても、既に僕たちの間で膨らんだ疑心それ自体は誰にも否定できないどころか、ますます拡大していた。
「何にせよ、細かい部分は間違っているかもしれないけれど、それは筋の悪い話ではないと思う。問題は、それを確かめるための手段だな」
「下手したら、死ぬからな」
「ま、私たちは責めるのが目的じゃないってのは忘れないようにね。現実問題、この時期に教授がいないのは色々と厄介だから」
「分かってるよ。上手くやる」
「それじゃ、周辺の人に嵯峨野教授へアプローチをとってみるよ」
「……ありがとう。ありがたいんだけど……嵯峨野教授と向かい合うのは僕に任せてくれないか」
僕は、嵯峨野教授に相対する役目を自分に担わせるように言った。そうすれば、他の誰かに傷も痛みも負わせずに済むし、一番嵯峨野教授に警戒されていないのは僕だろうから、と。
しかし、彼女は言葉を詰まらせたときと同じような、強く動揺したままの顔で反発した。
「はぁっ? 何でよ。私が行く方が、よっぽど信頼されているから話を聞いてもらえるかもしれない」
「弓削、それは甘い考えだ。相手は俺らが考えている以上の、社会に対する煮込み終わった悪意を持っているかもしれない。それで死ぬかもしれないのに、軽々しく自分が行く自分が行く、っていうもんじゃない。もちろんお前もだ、吉岡」
「分かってる」
「分かってる、分かってる、っていうけど、本当は分かっていないだろう。本当は俺だって怖いんだよ、お前の言ってることがもし本当に当たっていて、そのことで自分たちが死ぬというのが。こんなところで死にたいわけないだろう。嵯峨野教授の気持ちを知ってどうする。あの人がいつか起こすかもしれないことを止めてどうする。それで何になるっていうんだ」
それは僕が三年半の間起こしていた自分に対する恐れと似ていた。自分が何かすれば何が変わるということは別にない、それが現在であり、ずっと未来もそうなんだと思っていた。なるようになると生きていた。しかし現実は、自分が何かしなければ今まさに死ぬかもしれないという極限状態にまで追い詰められている。
今、畏れを抱いている相手の言葉を借りたくはないが、『沈黙を貫くことは、生きたまま死ぬということ』だとしか言えなかった。
「それでも、今止めなきゃいけないんだよ。嵯峨野教授がまだ何もしていないのは、実は僕は奇跡なんじゃないかとすら思っている。動機も凶器も、そして狂気も揃ってるときた。いつ何が起こってもおかしくない。……ふたりはまだ、あるだろう。ひとりじゃないだろう?」
「……いつから、そんなに自虐的になったんだ」
「生まれてからずっと。本当は反出生主義を取ってたんだけどな? おかしいな、こんなに人のことで熱くなるなんて」
「全然、吉岡君は矛盾なんかしてないでしょう。きっとそれが人の本心だよ。でも、放っておけないよ、ひとりでは行かせられない」
「──僕の話を聞いていたのか? 来るなと言っている!」
強い剣幕で扉を閉めた。
二人の驚愕する顔が脳裏に浮かぶが、それも仕方のないことだ。これは、何も背負っていなくて、偶然にも爆弾を踏んでしまった通りすがりの僕のやることであって、決して何の罪も罰も与えられていない彼らに押し付けていいことじゃないと思っていた。
『真夜中の虹』は、前衛的美術団体である。
学生運動の機運上昇とともに、西京大学の中にどこからともなく自然発生した団体である。創始者は小倉眞之介という文学部心理学専攻(現:社会科学部心理学専攻及び文学部心理学研究コース)に所属のしがない大学生であったが、徐々にその内実は政治的に過激な発想を美術の名のもとに解放していく、マリネッティさながらの未来派的な側面が強くあらわれることとなった。
さて、そこで嵯峨野教授──いや、嵯峨野氏は、創始から三年遅れて大学に入学し、『真夜中の虹』に所属していた高校の先輩からの誘いを受けてその団体に参加した。ちなみにこの先輩とは、弓削さんが言っていたハイジャック犯の小郡孝也である。
『真夜中の虹』のシンボルマークを作ったのは、嵯峨野教授である。といっても、大層なものではなく、ただの鰻の絵だ。しかしこの絵は、団体の活動最末期における地下的な破壊活動の集合日時を表すためのいわば隠語として機能したという。鰻といえば土用の丑の日。土用の丑の日の『真夜中の虹』。
そう、彼らはきまって毎週土曜日の午前二時に集まって、次のテロ活動について話し合うのだ。
そのことに気が付いた僕は忠実にその日時に合わせて、西京大学の一番離れた場所にある学生会館の前までやってきた。そこは不自然に高く、まるで小高い丘の上に不自然に会館だけがポツンと建っているようにしか見えなかった。
「すみません。──『明日の神話』を見たいんですが」
合言葉はそれだけで良かった。職員もグルらしいが、僕もそれに乗る。スーツ姿で出迎えた胡散臭いおばさんが、笑顔から一転して何も言わなくなったままに僕を二つ鍵を開けた先にある階段に導いた。
真っ暗だ。
正直何も見えないが、触覚だけが頼りになりそうだった。
暗いが、どうやら一つ目の扉を開けると鉄の重たく朽ちそうな音がする。ぎいっ、と。しかしそこには何もない。まだ真っすぐ行け、と空間に指図されているような気がしていた。
そして二つ目の扉を開けるとより厳重に閉じられたこれまた重たく冷たい扉がズ……ズズ……と開くのである。しかしまだ何もない。それで、さらに奥に進むことを命じられた気分になった。
三つ目の扉は先の二つよりもさらに固く、自分が普通に押しただけでは開こうともしなかったが、引くと開いた。こんなときにそんな間違いをするかという感じだが、自分が何か落ち着いていることを逆に確認することが出来た。
そして、四つ目の扉に辿り着いた。どこまで歩いたのか、どうやって戻るべきなのかも忘れてしまうくらいに、ここに来てから扉しか開けていなかったが、この扉は先の三つと比べればもう全く軽く、見せかけの扉に過ぎなかった。
ここなんだな……。
僕は覚悟を決めて、そこでノックをする。
「ようこそ、私の『第六学舎』へ」
西京大学には、第五学舎までしか存在しない。
つまり、というより、やはりそこにいたのは彼だった。目の前にはあの頼りなさそうな風貌だけが目に見えている。
「なるほど。やはり貴方でしたか。どうりで、変わった人だと思ったんですよ」
「何が、なるほど、なんですか。……すみません、言葉遣いが荒くなるのを失礼します。
あんた、何やってんだ!」
僕は、今までの冷静さとか、そういう身に纏って来た自分の業を忘れて棚に上げたうえで、力強く吠えた。それは恐れを含んでいたのかもしれない。
「今まで生きて来て、そして怨嗟を貯めて正解だった。ここまでぐちゃぐちゃになっていたら、世界は壊しがいがありますね」
「壊しがいのある世界なんて、存在しない」
「いいや、それは存在する。
これを、この無用の長物による圧倒的な破壊を、私の小さな恨みによるものだと断罪しますか。いいでしょう。そうだとして、それが社会を変える動機になってなぜいけないというんでしょう。あるいは言葉を変えて申し上げるのならば、社会を壊す動機になってなぜいけないというんでしょう。
……この核実験装置は、日本に投下された原爆の数千倍の威力を持つ、日本には存在しないはずの『兵器』です。いまから、私がそれを作ろうとした動機について説明しましょう。
私はまず、根本的に前衛的な美術に多大な影響を受けています。キュビズム、シュルレアリスム、未来派、そういった戦前からの系譜の上に、新たな芸術として我々も立脚しようと、先輩たちが『真夜中の虹』を創立されたわけです。ここに来たということは、もうご存じなのでしょうから、これ以上の説明は加えません。
そこで私はある作品が作成されていることを知りました。岡本太郎の『明日の神話』です。
『明日の神話』は、核爆発という凄惨な事態の後の世界を描いている作品で、一般的な解釈として、核爆発後の世界を生きることを表現していると言われたりするわけですが──私はこの描かれ方に少し異議申し立てをしたかったのです。つまりは、核兵器が炸裂し全てが崩壊した後の世界を、彼は一旦ネガティブに考えてから開き直ろうとする。
私は違いました、それは核研究について親和的であったからかもしれませんが。核兵器が爆裂したあとの世界は、全てが再構築される真っ白な世界として称えられるべきだと思ったんですね。
おかしいと思われますか。私にとってはそれがおかしいのです。
思えば、『真夜中の虹』という団体の名前を文字って、シンボルマークを作ったり色々なことを話し合う時間を取ったのは私な訳ですが、もっとも先輩たちから見れば、奇跡的にすべてが壊滅した後に残るものこそが希望だと捉えていたのかもしれません……これを答え合わせするには、随分時間が経ちすぎましたが。
おっと、いけない。思わず話しすぎてしまいました、核実験装置を作った動機に戻りましょう。
つまり、私がこれを作ったのは第一に美的精神の充足というやつです。しかしそれは単に美的なものを追い求めることに物足りず、圧倒的なまでの平穏を装っている社会に対する徹底的なプロテストとして作り上げたのです。腐敗した大学組織を崩壊させること、そしてこの忌々しき日常を破壊すること──それは私も貴方も同様に破壊されるということです。しかし、それがいい。それこそが、爆裂することで完成される芸術なのです。
……ここに誰かが来たら、このスイッチを押そうと決めていました。これを押すまでに、もう四十年も経つとは。随分と驚かされました。しかし、貴方が見つけたことによって、ついにこれも日の目を見ます。
それでは。沈黙を貫くことは恐怖です。生きたまま死ぬことを味わってください。
さようなら」
僕の目の前でその赤は炸裂した。瞬間、それは溶けていく。何もかもの境界線が揺らぐと、原子の中で全てが壊れていく音を聞いた。いつかの苦しみを今なら分かる気がする。こんな狂気の前に屈しなければならない今の自分の無力さは気にかかったが、それ以上に消滅するだろう世界にどうしようもなく贖罪の気持ちが湧きたつのだった。
目の前を彩る紅葉はどんな色だったろうか……。
そして僕と教授はともに灼け朽ちた。
彼の芸術は、こうして完成した。
0 notes
Text
Page 113 : 疑念
朝日が建物の隙間から差し、遠景の空は透く。
日の出を見る時刻は、車の往来も少なければ、人の出入りも殆ど無い。僅かな足音が妙に響くような静けさを伴っている。
アランは重い足取りで細い道をとぼとぼと歩く。
キリの地理には詳しくないが、探せる範囲はできるだけ足を伸ばした。大通り、湖の周囲、暗い路地も含めて、目を凝らし、呼び続けた。道行く人々の口から彼の噂が流れてくるのではと耳を澄ませ、時には尋ねて、捜索を続けたが、ついに手がかりを掴めなかった。万が一にも殺傷事件を重ねていれば多少なりとも耳に入ってきそうなものだが、アランもザナトアも足取りを追えないでいた。それは不幸中の幸いであると言えるかもしれない。しかし、まだ人目についていないだけで、闇夜に紛れた静寂なるうちに、誰の目にも止まらぬ場所で死体が転がっている可能性はあるのだった。たった一晩の間でそれが明らかになるとも限らない。
爽やかな陽光に照らされるアランの表情は暗かった。太陽に愛されたエーフィの足取りも流石に重い。ふらついた足はぽつんと誰もいない町を歩く。
見つけた電話ボックス。彼女が一人でこの町までやってきてまず入ったものと同じ。おもむろに入り、皺が増えてはじが破れかけているメモ用紙を開いた。以前スバメの足に括り付けられて運ばれた、所狭しと美麗な字が詰められた小さな手紙を、アランは一種の御守りのように持ち歩いている。
指先に触れる金属は冷たい。一つ一つ、番号を押していく。休息をできるだけ味わうように足下で寝転がるエーフィに彩りの無い視線を落としつつ、流れる音が途切れる時を待つ。まだ朝は早い。眠っているかもしれない。だが、遠慮を考えられるほどアランには余裕が残されてはいないのだろう。
やがて切れて、繋がる。
「はい」
彼は名乗らない。聞き慣れた、というにはまだ浅い。けれど今、縋る他ないその声に、アランは湿った吐息をついた。
「エクトルさん」
受話器を強く握りしめた。
「お願いしたいことがあるんです」
声に力は無かった。
そしてアランは、事の顛末を簡潔に説明した。以前から体調を崩していた様子だったブラッキーが、急に昨晩、野生のヤミカラスを襲ったこと。アランの声は一切届かず、彼から攻撃してきたこと。エーフィが身を張って暴走を止めようとしたが、失敗し、キリの町に姿を消したこと。夜を通して探しているが、手がかりすら掴めずにいること。
エクトルは特段動揺する様子も嘆く様子も無く、小さく相槌を打ちながら、アランの話に耳を傾けた。
「ブラッキーを見つけなくちゃならないんです。どこかでまた被害が出る前に」
「捜索を手伝ってほしいということですね」
長い前置きから先手を打たれ、アランは表情を引き締め、短く肯定した。
わかりました、とエクトルは静かに応える。
「まずは合流しましょう。今どこにおられますか?」
アランは逡巡し、宿泊しているホテルの名前を伝えた。現在地から遠くなく、アランが知っているキリに関する位置情報の中で、正確に伝えられるものである。同時に、ザナトアも泊まっている場所であり、縁が切れて久しい二人が出会う可能性が浮かぶのだが、アランはそれについては何も言わず、エクトルも勘付いているのか否か、普段と変わらぬ冷淡な調子で了承した。
電話を切ると、エーフィはたおやかな身体をするりと伸ばし、アランを不安げな顔で見上げた。疲労は隠せないが、立ち止まる余裕は無かった。エーフィもまたブラッキーを深く案じている。昨晩、ヤミカラスを屠る獣に対し、躊躇わずに電光石火で懐へ跳び込んだ彼女は、果たして彼の理性が弾ける可能性に気付いていたのか。今更想像を巡らせたとて、詮無きことだが。
「うん、行こう」
彼女達は並んで歩き始める。朝の陽光は僅かに明るくなっていき、町は青い影を纏い始めていた。
薄い光の中を急ぐと、既にエクトルは指定場所に立っていた。連絡をしてからそう時間は経っていないが、彼はまるでずっと待ち構えていたように、慌ただしい気配など一切感じさせず皺の無い黒いスーツを着こなしている。傍らには、やはりいつも傍に老いているネイティオが静かに鎮座して、まばたきもせずに正面を見つめている。過去と未来を見通すという、両のまなこには曇りが無い。体格のみでも圧倒する気難しげな男と、妙な存在感を放つネイティオの組み合わせは、どこにいても彼等と分かる、異様な雰囲気を作り出す。
性急な足音を耳に入れたのだろう、入り口からずれた壁に沿って立っていたエクトルは視線を動かす。
髪を乱し、息を切らしたアランに向けて、エクトルは黙って会釈する。若々しい肌に出来た隈がここ数日間の心労を克明に示しており、一瞬口を厳しく噤む。しかし、恐らくそう悠長に構えている暇は無いのだと、すぐに察した。
「詳細を聞いてもよろしいですか」
息が整ってきた頃合いを見計らって説明を求めると、重くかさついた口から改めて事のあらすじが語られた。首都を出て以来、ブラッキーの具合が悪かった点、それに卵屋の傍で死んだポッポにも触れる。
悪の波動を直接受けた腹部に自然と手があてられる。痛みはとうに消えている様子だったが、目に見えぬ傷は生々しいだろう。漠然とした不安に気を病むのも無理はない。
「ブラッキーが急に我を忘れて他のポケモンを襲ったことは、今まで無かったんですよね」
「はい」
勿論と言いたげに、アランは語調を強くする。
躊躇無く危機に跳び込む果敢な姿、鋭利な視線の強さは、彼の獣としての好戦的な本能を彷彿させる部分ではあった。しかし同時に、悲哀に寄り添う思慮深さや、一歩周囲から引いて達観している側面を持っており、突発的な暴走、ましてや主人や仲間のポケモン達に危害を加えるなど、正常からはかけ離れた行動だった。人懐っこいエーフィとは対照的に馴れ合いを拒む傾向があるが、情には熱い。
殆ど行動を共にしていないエクトルでも、漠然と彼等の性格や立ち位置は理解している。嘗てキリでもっと賑やかな一行であった時、子供とはいえ、主人に害を成す可能性は無いか、楽しげに時間を過ごす輪の外側から観察していたものだった。そのエクトルにとっても、今回のブラッキーの件は予想できぬものだっただろう。
可能性があるとすれば、もっと根本的な部分に由来する。
「性格や種族によって程度に差はあれど、そもそも、ポケモンには戦闘本能があります」
エクトルは話す。
だから、ポケモン同士を闘わせるポケモンバトルという文化が生まれ、発展してきている。此の国においては、スポーツと似た側面が強いが。相手を直接攻撃するということは、当然一歩間違えれば取り返しのつかない事態に陥る。不思議な生き物達の、未だはっきりとメカニズムの証明されていない技や進化といった神秘は、元来彼等が生き残り、子を残し種を繁栄させていくための潜在能力だ。時には戦い、そして生きるため。時には縄張りを守るため、群れを統率するため。単純に戦闘そのものを好む種もある。そして、生存のためには食事は必須であり、時には相手を喰らう目的で戦うことも、野生の世界ではなんらおかしいことではない。だが、人間に飼われている彼には本来その必要性が無い。たとえ強い敵意識が芽生えたとしても、本能を抑え付ける訓練も十分なされている。性格を考えても不可解な点は多い。
何故急にブラッキーが、理性を手放したのか。
「なんらかの条件が揃って戦闘本能が呼び起こされたと考えるのが自然ではありそうですが、心当たりは」
アランは考え込むように手を唇に当て、暫く黙り込む。
「……ありません」
ぽつりと応え、すぐに顔を上げた。
「原因も気になりますけど、まずは、ブラッキーを見つけたいです。ポッポの時は、一晩明けたら、誰かを襲うような様子はありませんでした。今も、どこかで冷静になっているかもしれません」
「貴方は、ポッポの件もブラッキーによるものだと考えているんですね」
アランは一呼吸を置き、頷く。昨晩は狼狽を隠せなかったが、既に冷静を取り戻していた。
「他に思い当たりませんから。勿論、野生のポケモンによるものという可能性は、捨てきれませんけど」
視線を下げてから、続ける。伸びた前髪に隠れた瞳に、黒い影が蹲っている。
「以前は、ザナトアさんは野生ポケモンを追い払うために用心棒のポケモンを用意していたんですよね」
アランの確認するような言いぶりに対しはじめエクトルは違和感を抱いたが、直後に理解する。彼女は、恐らくザナトアと自分の関係について、知っている。それを知っていて、敢えて尋ねるような口調を使った。
エクトルが答えずにいると、先にアランが口を開いた。
「でも、決して全く野生の対策をしていないわけではないんです。一応、育て屋を囲う柵は健在ですし、周囲には、刺激の強い香りを放つ植物が植えてあります。家にある資料に書いてありました。慣れてしまえば気にならなくなる程度みたいなんですが。林に棲み着いた野生ポケモンだとしても、林から建物は離れているうえ、わざわざ広い草原を渡って卵屋の方まで獲物を取りに来るでしょうか」
アランのポケモンに関する知識は付け焼き刃に等しい。それでも、彼女は考えていたのだった。ポッポの死の真相について。毎晩見張りながら、何も起こらぬ夜を過ごし、観察していた。
ザナトアが言うように、野生に命を奪われる事故は珍しくはないのだろう。しかし、今は育て屋を辞め、人のポケモンには触れず野生ポケモンの保護に尽力するようになった。
「あの付近には小麦畑や野菜畑もあります。卵屋でなくとも、食料はある。勿論、そうとは限らないという可能性があるというのも、解ってるんです。でも、そもそも、ポッポの死体が首だけを抉っていたというのが、おかしい気がして」
だって、と見上げたアランの瞳は、光に照らされてもなお暗がりを広げていた。
「食べるために襲ったのだとすれば、殆んなど食べずに放っておくなんて、変じゃないですか。それに、夜で殆どのポケモンが眠っていたとはいえ、外から敵がやってきて、少しも騒いでいないっていうのも。保護されているとはいえ、あの子達だって野生なのだから、敏感なはずだと思うんです。……見知った気配か、気配を消して近付くだけの賢さがないと」
それでもブラッキーだとは限らない。あくまで可能性の一つに過ぎない。
エクトルは何も言わなかった。正しくは、言えなかった。彼自身は現場を見ていないためでもあるが、アランの思考の流量に、目を見張っていた。ザナトアからすれば呆れたものだったが、ポッポの死に執着している中で、彼女は様々な可能性を浮かび上がらせては、否定し、繋ぎ合わせていたのだろう。
以前アランに再会した時の印象をもう一度彷彿させた。果たしてこんな人間であっただろうか、と。
「だから私は初め、誰かが何らかの理由で意図的にポッポを殺した可能性があると疑ってたんです」
黒の団の関与については、ポッポが死んで明けた朝、エーフィに対して疑念として打ち明けた。
「でも、その意図が全くわからない。……もしかしたら、ザナトアさんを恨んだ誰かの仕業かもしれない。脅迫のような。或いは、全く別かもしれない。でも、そうだとして、あのポッポを選んだのは、どうしてなのか、解らなかった。恨みでポッポを殺したのなら、その人はザナトアさんのことを解っていない。そんなことをしても、あの人は動じないです」
「……そうですね」
たった一匹の命が軽いものとはザナトアは言わないだろう。しかし、一匹が死んだことで、嘆きに囚われてしまうことはない。たとえ長く生活を共にしたポケモンだったとしても平等に扱う。死は必然として訪れる。ザナトアは身に沁みるほど知っているから動じない。
「ブラッキーだとしたら、辻褄が合うんです。私の中でも」
エクトルは目を細める。
「……他を疑ってきた中で、ブラッキーが犯人である可能性は、疑いようがないと言い切れるんですね」
「絶対じゃないですよ。もしかしたら、もう本当のことは解らないかもしれないです。でも、ブラッキーだったら……信じられないけれど、有り得てしまうのかもしれないって。それに、あの日がどうであろうと、ブラッキーが昨晩ヤミカラスを殺したのは事実です」
でも、とアランは不意に微笑んだ。
「だからといって、ブラッキーを見捨てたくはありませんから」
疲弊が滲んだ笑みに、エクトルは言葉を返せない。代わりに小さく首肯し、無言のうちに鞄を探った。
目当ての物はすぐ出てきて、アランに差し出される。大きな手に包まれて手渡されたものをアランは自らの掌で確認し、目を丸くした。
白いポケギアだ。型には彼女にも見覚えがある。旧式で、使い古された浅い傷が残っている。
「これは」
「お嬢様の私物でした。もう必要のないものです。貴方にお譲りします」
アランは言葉を続けられず、無言で操作する。自ら操作するのは初めてだったが、旧式である分構造もシンプルであり、機能もごく限られている。時計と、電話と、ラジオ。登録されている電話番号の一覧にはエクトルの名前のみが鎮座している。
「貰っていいんですか?」
「ええ。いずれ捨てる予定のものですから」
その理由は今更語るものでもない。アランは暫し沈黙した後、疑り深い視線を寄せた。
「これ、発信器がついてたんじゃ……」
エクトルは一瞬言葉に詰まる。
「そんなこと、覚えていらしたんですか。……不要な機能は除いています」
小さな狼狽は強固な面には表れない。アランはじっと見つめ、頷いた。
「ありがとうございます」
そう言って、すぐに取り出せるように上着のポケットに差し込んだ。
「一度、お休みになられてはいかがですか」
先程から妙に過敏な傾向もみられる。青い顔色も見かね、エクトルが慮るように提案すると、力無くアランは首を横に振る。
「少しでも早く、見つけないと」
「しかし……エーフィも疲れているでしょう」
ふとアランは足下を見やる。
陽気とまではいかずとも、いつも穏やかに明るく振る舞うエーフィも、流石に一睡もせずに町を走り回ったのは身に堪えるだろう。元気に動く二叉の���も、垂れ下がって沈黙している。
「急いては事を仕損じる、と言います」
隣国の諺ですが、とエクトルは補足する。
「いざブラッキーに相対した時、万が一に戦闘となればこちらもそれなりの心積もりでいなければならないでしょう。朝になれば通常ブラッキーは大人しくなります。一度休めて備えるのも一手かと」
アランは納得し難いように口を噤んだが、その間エクトルが町を詮索すると説得して、漸く頷いた。
「駄目ですね」
唐突に零した声音が自棄的であった。
「周りが見えなくて、焦ってばかりで」
「貴方は当事者ですから」
仕方ないでしょう、と言いかけたところを、アランは首を振る。
「大丈夫です。……お言葉に甘えて、少し休みます。何かあったら、連絡してください。すぐに出ます」
エーフィに声をかけ、アランは背後のホテルに戻っていく。エクトル自身も予想はしていたが、宿泊している場所だったようだ。ザナトアとエクトルが邂逅する可能性も零ではなかったが、老婆は最後まで姿を現さなかった。それを果たして彼女は解ったうえでこの場所を指定してきたのか、エクトルは危ない橋を渡っている感覚から脱せない。
あの様子では忠告を無視して捜索に乗り出してもおかしくはなかったが、彼女自身も疲弊は頂点に達していたのか、大人しくホテルの奥へ姿を消していったのを硝子越しに確認し、エクトルは踵を返した。
周りが見えない、と言う。エクトルからしてみれば彼女は若いというよりも幼く、それは当然のことだと片付けられた。だが、子供だと見くびっていると、思わぬ矛先が向けられることもある。
実際、あんなに冷酷な考えに至る子供だっただろうか、とエクトルは思う。
己が目撃したわけではない凶悪犯が、付き従えてきたポケモンだと断定することに、さほど躊躇は無いように見えた。むしろ、納得していた気配すらある。暴走の理由は解らないと言い淀みながらも、辻褄が合うとは不可解だ。彼女は重要な事項を隠しているのかもしれない。それゆえにブラッキーを疑っているのか。
まだ何も明らかにはなっていない。
エクトルは彼女について何も知らないも同然だ。ほんの少しだけクラリスと過ごしただけの、友達と呼べるのかも断言し難い、あまりに刹那であった夏の終わりの出来事に出会っただけの人間である。それでもエクトルには今の彼女が妙に冷たく感じられるのは、クラリスの境遇に対し強い抵抗感を示した彼女とも、楽しげに料理を囲んで笑っていた彼女とも重ならないからだ。あの訣別の朝、湖上を飛翔しクラリスの名を呼び続けたという熱意が思いがけず鮮烈であった印象でもある。終始凪いで他人を見張っている暗い顔つきをした現在からはかけ離れている。ポケモンの食嗜好と性格を結びつける、エクトルからすれば他愛も無い知識に対して目を輝かせた顔が懐かしい。
そういえば、あの時、彼女は言った。ポケモンが好きなんですね、と。
当時、濁りの無い言葉になんの感情も浮かび上がってはこなかった。
「ネイティオ」
隣に立つ存在を呼びかけると、特徴的な黒目のみが動きエクトルをぎょろりと捉えた。
「未来予知だ。彼女のブラッキーは記憶してるな。探し当てろ」
指示を受け、やや間を置いてからネイティオは頷いた。空白の時間に彼の頭で駆け巡ったのは、記憶の引き出しを一瞬で開いていく音だろう。ネイティオをできるだけ外に置いているのは、できるだけ視界に情報を与え、記憶させるためでもあった。不審な人物の行方を追う際に何度も使ってきた手法だ。クラリスでも知らないことだ。
エクトルはスーツの裾を捲り、腰のベルトに装着したボールを取り出す。紅白でデザインされた一般的なモンスターボールではなく、黒字に緑の円が重なった特殊なボールは、暗闇を生きる獣に対して効果的とされる種である。
まだ夜が明けたばかりの朝。伸びる影は濃く、夜の気配は残滓のように辺りに張り付いている。
隣でネイティオの黒い瞳に赤い光が浮かんだ。かの視界は時を渡る。瞬き一つせずに虚空を見つめ、エクトル達人間には見通すことのない世界を視る。
ポケモンの力は強大だ。不可能を可能にできる、異次元の世界が彼等の中には広がっている。それを全て意のままに操るなど、人間の傲慢に過ぎないだろう。しかし、クヴルールはその傲慢を払いのけ、不可能を可能にした。
人間の科学や想像力は、理想は、ポケモンの底知れぬ力すらねじ伏せるのか。しかし、自然に対する逆行が、良い方へ作用するとは限らない。ブラッキーの暴走に対し、エクトルは不吉な予感がしてならなかった。
*
アランがホテルの部屋に戻ると、ザナトアは既に起床し、ラジオをかけながら、身支度を整えているところだった。元々ザナトアの朝は始まるのが早い。普段も殆ど夜明けと共に目覚めて卵屋や広い放牧地に赴いてポケモン達の体調や環境を確認し、墓地を訪れるのが日課なのだった。場所が違えど習慣は身体に染みついている。だから、部屋に戻って一番にザナトアに会うこと自体に関して、アランには動揺は無かっただろう。
手前側のベッドの枕元を、まだ眠っているアメモースが占拠しており、些細なことで布など簡単に傷つけ破ってしまうフカマルは、テーブルに寄りかかって、持参した傷だらけのクッションに身を委ねて寝息を立てている。
ザナトアは開いた扉に立つアランを、驚く素振りもせずに振り返り、収穫は無かったのだとすぐに理解した。
「おかえり」
たった一言、いつも通り、つっけんどんに言うと、アランは頭を垂れた。
「見つからなかったかい」
解りきっていることだが、あえて尋ねる。きっと彼女からは言い出しづらいことだろう。慣れぬ町を深夜もうろつくとは、いくら彼女が旅で昼夜放浪しているとはいえ勧められたものではなかった。反対を押し切ったものの結果を出せなくては、気まずさもあるに違いない。
早朝のニュースを伝えるラジオ音声を背景に、静かな首肯を見て、ザナトアはアランに近付き背中を叩いた。
「今のところニュースにはなっていないようだよ。ブラッキーも今頃頭を冷やしているかもね」
励ますように言葉をかけてみるが、彼女の顔は晴れない。ザナトアは肩を落とす。
「少しおやすみよ。朝になってしまえばいつ探しても変わらないだろうさ」
アランの口元が僅かに緩んだ。師弟揃って似たようなことを言うものだった。
「……のんびりしていてもいいんでしょうか」
「はあ? のんびりしていいなんて誰も言ってないよ。英気を養えって言ってるんだ」
思わず突き放すように言うと、漸くアランの頬が上がる。何かが��に落ちたようだった。
「そうですね。のんびりはできません」
「そうだよ」
エーフィが我先にとベッドに乗り込むと、つられてアランも布団の上に転がった。瞬く間にまどろみが瞼にのしかかっていくのか、抵抗なく目を閉じた。
『――次のニュースです。またも火災事故です。昨夜未明、アレイシアリス・』
ラジオの音声が唐突に途切れる。ザナトアが電源を切ったためだ。沈黙の朝がむず痒く流していたものだが、眠りゆく者たちには弊害だろう。シャワーも浴びずに真っ先にベッドに倒れ込んだのだから、苦労は想像するまでもない。若さはそれだけで価値がある。多少の無理をしても身体がそう簡単には堪えない。老婆の手元からはとっくの昔に消えてしまったものだ。
空調が効いているとはいえ、秋も深まりつつある暁は冷える。布団もかけずに寝転がって、彼女はそのまま眠りにつこうとしていた。仕方無く、ザナトアは昨日羽織っていた上等な上着を彼女の肩からかけてやる。エーフィには、備え付けのブランケットをかけた。
アメモースに、エーフィに、アラン。一匹欠けてしまった彼女のパーティの侘しさが引き立つ。
窓辺に立ち、薄手のレースカーテンをそっと開ける。広い道路に面した窓辺からは磨かれた硝子を通して、突き抜けるような秋空が天にたたずみ、青い朝が一望できる。外にひとたび足を踏み入れれば、冷めた風が肌を撫でて身を引き締めるだろう。室内にいても容易に想像できるような、澄んだ朝である。
祭当日、ポッポレース本番としては、この上無くお膳立てされた空模様である。
今頃湖は昨日の雨を忘れて波一つ立てずに凪いでいることだろう。普段なら早朝に船を出して漁に励む男らがいるものだが、今日は祝日。季節の変わり目と、祭日に限っては、湖への侵入が暗黙の了解で禁じられている。
時間が立てばみるみる湖畔は人やポケモンで賑わうようになり、湖畔の一角を陣取る自然公園を中心に催しが繰り広げられ、収穫の秋に相応しく食材やその加工品といった出店が所狭しと並ぶ。花をあしらった目にも鮮やかな装飾品も名物の一つだ。明るいうちから大人は酒を呑み、子供は旬の食材を使ったお菓子を貰っては飛び回るように遊ぶ。朝から昼間にかけてポッポレースが開催されて大いに盛り上がり、場外ステージでは小規模ではあるが公式のポケモンバトル大会も行われる。そして夕方には、毎年、美しい夕陽に照らされて輝く湖の傍に集まって、空に向けて風船を飛ばす。その先端には羽や花が添えられ、人によっては誰かへ向けた手紙を付ける。暗くなっても賑やかに夜店が並び、盛大のうちに幕を下ろす。
楽しい祭を快く過ごせない事態になろうとは、ザナトアも予想していなかった。折角渡した駄賃も、残念ながら楽しむのに使うどころではない。
今のアランには、祭を楽しむ余裕など当然ないだろう。ブラッキーが早く見つかればいいのだが、見つかったとしても収集が着くのかは不明である。捜索に加わりたいのは山々だが、外付き合いというのは億劫なものだ。それに、日々訓練に励んでいた野生の子たちを放置するわけにもいかない。
しかし、ブラッキーの消失した夜が明け眠りから覚めて、ザナトアは一つ心に決めたことがあった。戸惑うだろうが、きっと理解してくれるだろう。
窓枠に手を添い、秋の恒例行事を想像する。
あのポッポが飛べなかった舞台、チルタリスやクロバットをはじめとして多くのポケモン達が味わえなかった舞台を、あのちいさき者達が羽ばたく。
その光景は、何にも代え難い。
可能ならば、アランにもその瞬間を見せてやりたかった。
無数の翼が希望を抱いた青空に向かって一気に飛翔する、圧巻の空間を共有させてやりたい。生命が叫ぶ瞬間である。あの瞬間、ザナトアは自分は翼を持たないにも関わらず、彼等に引っ張られるように、生きなければならないという高揚がみぞおちの底から湧いてくるのだ。驚いて泣き出す子供も少なからずいるくらいだが、喜怒哀楽が極端に薄い彼女にはむしろ驚かせるぐらいが丁度良いだろう。
今年もその日が遂にやってきたのだと、感慨に耽っていると、不意に落とした視線の先に、黒スーツの後ろ姿が見えた。あまりに遠く、黒い後頭部からは体格はおろか顔も判別がつかない。隣にはネイティオを従えていた。
それ以上ザナトアの視界に留まる間も無く、次瞬には跡形も無く姿を消した。恐らくは、ネイティオがテレポートを使ったのだろう。
まさかね。
絶縁となった彼に繋がっているというアランと生活をしているから、ここ数年は存在も殆ど頭から抜け落ちていたというのに、妙に思考を過るようになってしまった。そんな偶然がこうして簡単に起きるなら、同じキリに住んでいれば、もっと早く鉢合わせたっておかしくないだろう。
影も形も男の気配が残されていない地上からはすいと目を離し、カーテンを閉め、薄い陽光は遮断された。
*
彼方で花火のあがる音がした。三発、空砲のようなからりとした音である。その音をきっかけにしてアランは目が覚めた。つられて、他の二匹も身体を起こした。
まどろむ顔で浸っているうちに、町に住んでいるのであろう鳥ポケモンが硝子の向こうで小さく囀っている。
眠りにつくのは早かったが、深くは眠れていなかった。遠い音で簡単に起きてしまう。しかし、部屋に備え付けられた時計を確認すれば、二時間ほどが経過していた。
結んだままにしていた髪ゴムを取り、少し長くなった髪が垂れる。身だしなみを気にする生活をしていないから、奔放に伸びている。気怠げな所作ではあるが、その下の顔色は、格段に良くなっていた。
机の上に置かれたメモを確認し、ザナトアは先に会場へ向かったと知る。今の花火は祭の始まりを報せる合図だったのだろうか。
ポッポレースは午前中のうちに始まる。ヒノヤコマをはじめとしたザナトアのチームが飛ぶのは第二部。正午には終わるだろう。
メモの隣にはパンが二つ置いてある。ビニール袋に入れられたそれを出して、齧り付く。塩を混ぜ込んだ生地はとっくに冷めていたが、柔らかげな風合いを保っている。流し込むように一つ平らげたら、残りの一つはエーフィとアメモースに分け与えた。それだけではポケモン達は足りないから、持参した固形のポケモンフーズを取り出し、それぞれに食べさせる。
小さな咀嚼音を聞きながら、アランは視線を伏せる。
いつもの存在がいない朝は寂しさが漂う。喪失は突然やってくるものだと、彼女は既に身を以て痛感している。幾度も経験しては、時に驚き、嘆き、受け入れてきた。だが、喪失感��暮れる暇などはない。戸惑いは夜に置いてきたように、顔つきは引き締まっていた。
ザナトアの上着を丁寧に畳んでベッドに置くと、一つ深呼吸をした。
触角を上下させるアメモースを傷だらけのモンスターボールに戻し、鞄にしまいこむ。紺の上着を着直した時、ポケットの固さが気になったように手を入れると、譲り受けたポケギアをまじまじと見つめた。今後二度と会わないかもしれないというクラリスが使っていたという機械は丁寧に扱われており使用感がほとんど無いほどだったが、よく目を凝らすと、薄い傷がはじを静かに抉っていた。
「いける?」
エーフィに向けて言った。アイコンタクトと言葉での簡単な意思確認が交わされる。エーフィも活力が戻ったのだろう、力強く肯いた。
< index >
0 notes
Text
NOxAyumu

堀田歩
その日は、起きるのに少し苦労した。一度スマートフォンのアラームで起きて、エアコンを除湿でつけてぼんやりしていたらまた寝てしまった。前夜に寝付くまでラジオを聴こうと耳にしたイヤホンの紐が首にかかったまま意識が浮上してきて、寝ぼけながら一生懸命それを解こうとした。自分のんー、んーと唸る声で目が覚めてきた。古いアパートだから、上の階の忙しない足音が聞こえる。しばらく天井を見つめ耳を澄ましていると、豪快な施錠の音。
バタン、ガチャ。
もうそんな時間か。
エアコンですっかり冷えた腕をさすりながらベッドを出た。テレビを点けるとニュースが流れ、アナウンサーの真剣な顔を横目に耳だけそちらに向ける。
「えー、引き続き、昨日午後五時頃、○○県立第一高等学校で起きました、無差別殺傷事件の速報をお伝えしております」
ご飯はいいや、いや、食べられるかな。カップラーメンを食べよう。線まで水を入れて、電子レンジに入れて三分チンする。本当は、火花が散るため強く禁止されている横着だ。かつて友人に火事になるぞと言われて一時期やめたけれど、ついやってしまう。普通にお湯を沸かして三分待つことができなくなってしまった。
タバコも吸わない、彼女もいない、麻雀もやめたし、なるべく歩くし、お年寄りには席を譲り、未来ある青少年教育を担う。カップラーメンで電子レンジに火花を散らしたくらいじゃ、誰も怒らないでしょう。
芯の残った麺は、割り箸には重たい。啜りながらノートパソコンを開くと、喚くようなファンの音が耳に付く。夜中電源を切らなかったから、熱がこもってしまったんだ。ああ、また熱がこもる季節になってきたんだな。それとも、パソコンの寿命かな。メールをチェックしようとすると、机の上のスマホが震えた。
「はい、堀田です」
「あ、堀田先生おはよー」
「おはよう、さやか。どうしたの」
「あのさあ、体育館開いてないんだけどさあ、今日男バスの顧問が当番でしょ」
「え、職員室行った?前田先生居ないの」
「居ねー」
「居ねー、じゃねえだろ。じゃあ前田先生に連絡して、今から行くから。女子バスケ部の皆さんもういるの?外練できる?」
「うん。私らはいいけどさ、なんか男バスの一年の子居るよ」
「二年来たら外周しといてって伝えて」
「了解。じゃーね、早く来てね、ほったちゃん!」
「こら」
通話を切って、前田先生に連絡を入れた。自分も行かなくては。一歩踏み出すと、胃の中でラーメンがゆらりと揺れた。いつもなら軽くかき込んで出ていけるところが、なんとなく立ちすくんだ。いやだな、変なことしなきゃよかったな。内臓冷えてるところに追い打ちを掛けてしまった。後悔しながら、手にした残りのラーメンを、全て流しの三角コーナーに捨てた。ヒゲ剃って歯磨きもして、夏は上着が無くてシャツのシワが目立つから、一番綺麗に見えるシャツを羽織る。パソコンに刺さっていたUSBを勢いよく抜いて、部屋を飛び出した。
なんだか嫌な天気だ。もうじんわりと汗ばむのに、思ったよりも、全然夏じゃない。途方も無く白い薄暗ささえある。SF映画に出てくる恐怖の惑星のセットみたいだな、と目を細めて見ていた。さあ、行かなくちゃ。頼りないエンジン音を聞きながら、サイドブレーキを降ろす。
学校に近づくと、ちらほら我が校の制服を見かけるようになる。顔を伏せ気味に車を運転し、中庭に停め運転席を降りると、体育館前であぐらをかいている山賊のような生徒たちが何人か見えた。先ほど電話をかけてきた、女子バスケ部員たちだ。俺が男子高校生ならば、その迫力に大いにおののいた事だろう。
「ちょっと、あんたたち女子高生でしょ」
「ほった、おはよー!」
「堀田先生」
「ほった、早く鍵開けてよ」
「お前らあんまそういうこと言ってると前田先生にご報告ですからね」
「え、やめてやめてやめて、ほんっとうにやめて」
「授業も同じだからな、今日は小テスト落ちないでよ。さ、じゃ、職員室に鍵取りに行くから、ちょっと待っててね」
「もうあと一時間しか練習できな��んですけど!」
「ごめんって」
職員室は静かだった。普段あまり会話を交わさない年上の教諭や、コピーをせっせと取る非常勤職員がちらほら居るだけで、あとは二台の空調が部屋を冷やさんとごうごう音を立てていた。
今年の春に赴任してきて、三ヶ月。生徒の前では、当然他人行儀とか見知りとかなんて言っていられないし、慣れてなくても、教え子は愛情を持って下の名前で呼べば「そう言う感じ」の先生でスタートできるし、そうすれば先生の間でもあんまり目立たないし。上手にやれていた。無理はしてないし、仕方も知らない。抱えてきた荷物を自分の机に降ろせば、手の甲にひんやりと冷たい天板が触れた。
「おはようございます、あの、前田先生まだいらっしゃってないですかね」
校内の鍵は全て教頭先生の机の背面に管理されている。教頭先生に声を掛けると、眼鏡をずらしてこちらを見た。
「来てると思うよ。スクールカウンセラーのことで保健室の方に行かれてるんじゃないですかね」
「あ、なるほど。ありがとうございます」
「なにか御用でした?」
「あ、ちょっとご相談があって」
そう言いながら体育館の鍵に手を伸ばした。
体育館への昇降口は、塗り立てのペンキの匂いがした。太陽は雲の向こうにさんさんと照っているのに、そこには最悪な企みがあるような。ドアスコープの向こうから、笑みを浮かべてこっちを覗き込む影の不気味さに似た、信じきれない温もりに、ワイシャツがじっとり肌に吸い付く。
体育館の鍵を開けに行くと、女子バスケ部員の生徒たちが、手を叩いて笑っていた。
「先生」「ほったちゃんに聞いてみようよ」「ねえ先生」
「おまたせ」
体育館を解錠していると、背中から代わる代わる問いかけられる。
「先生さ、犯人とか捕まえられる?」
「は?」
「昨日一高で殺人事件あったじゃん」
「殺人っていうかね、あれはね」
無差別殺傷事件って言うんだよ。いや、殺人事件でもまあ間違えてはないけど。
「あれでさあ、なんか結局警察来るまで犯人の生徒そのままだったんでしょ?先生とかって生徒取り押さえられないの?」
「 さあ」
どうしてたんだろうね。
昨日、近隣の高校で、生徒による無差別殺傷事件が起きた。同校男子生徒が授業中に所持していた刃物を振り回し、今朝の時点で生徒四名、教師一名が搬送先の病院で息を引き取った。いや、「さあ」じゃなくて。
「君らさあ、簡単に言うけど先生も亡くなってるの知ってる?」
「あ、そうなの?」
「そういうのをね、自重というのだよ、君。モテたいなら化粧じゃなくて思慮深い発言するようにね」
「はあ?今日してねえし」
「ばか、毎日しねえんだよ。今日なな香部長は?」
体育館の重い扉を開け、「部長休み」と答えた生徒に体育倉庫の鍵を差し出す。
「え、今日顧問無し?」
「前田先生御用だから」
「いやほった副顧問でしょ、見てくれないの?」
「見てた方がいい?」
「いた方がいいよ」
からかうように笑いながら、体育館に駆け上がる子供たち。
かわいいな、と思う。
でも、命をかけられるかな。まだ出会って間もないこの子たちの無邪気な未来を守るために、この先の全てを投げ打てるかなあ。
立派だったと思う。亡くなった先生は。どう亡くなったのかはわからないけど、きっと勇敢だったに違いない。もしかしたら、一人目に刺されて、痛がる生徒の姿を見たら、お前!なんて、刃物の前に立ち塞がれるかも。書いて字のごとく、胸が痛い、想像すると、首元もぞくぞくと悪寒がする。お葬式、どうするんだろう。かわいい生徒たちが、みんな来て、泣いてくれるんだろうか。いや、こんなに一度に亡くなってしまったら。
深く刺さった、刃物を握る、他人の子供。進路相談も、模試も、朝礼もしたのに。たくさん単語が、構文が詰まった頭を抱えて、やっと振り絞った気持ちが、初めて、深々と刺さったんだろうな。いや、案外、スッと、頸動脈に刃物が当たっただけかも。あっけない、怖い。
体育館に響くドリブルの音は、カップラーメンすら受け付けなかったばかに繊細な胃の底を、力強く揺さぶった。
今日はいつもに増して欠席者が多い。午前中の授業を終え、職員室前の学級ごとの欠席者数報告に足を止めた。
うちの学校は、いわゆる田舎の進学校で、ゆとり教育の後に吹く強い風にちょうど晒される場所だ。大学入試の意義も体制も揺らぐ中、何だかよくわからないものを信じながら、生徒は生まれ育った家から何百キロとある遠い地の公立大学へ進学していく。不安を抱える生徒は少なくない。
自身のクラスの名簿を職員室で開く。
風呂蔵まりあ。久しぶりに出席に丸のついた名前にため息をついた。
「堀田先生」
「はい」
前田先生の声だ。立ち上がって振り返ると、おじさんが申し訳なさそうな顔をして立っていた。
「ちょっと」なんて、もの言いたそうに手招きするから、怖かった。
こう言う時のおじさんって怖いよな。俺はどう見られてるんだろう。促されるまま職員室のとなり、会議室の椅子へ腰を掛けた。昼休みに会議室を使う先生は結構多くて、別に聞かれても構わないけど「聞いて欲しくはない」ような背中をしている。生徒を叱っている先生もいるし、部費の計算をしている先生もいる。職員室でやればいいのに。
キョロキョロ癖、治らない。
視線を手元の長机に落とすと、前田先生は視界の隅へプリントを置いて俺の横に腰掛けた。
「今日ごめんね、朝練の面倒見てもらっちゃって」
「いえ、そんなそんな」
「あ、堀田先生お昼食べました?すみません、確認もせず。すぐ済むので」
「ああ、いえ、大丈夫です」
「これなんですけどね、言い訳がましくなっちゃうんですけど、市からスクールカウンセラーを増やすって連絡が来て。例の事件のことで、市の方でも対策を取ろうと言うところで」
「一高の、無差別殺傷事件ですか」
「そう。僕ね、ちょっとしばらくこっちの方担当しなくちゃならなくて、部活の方に行けなくなってしまうので、週末まで部活動を堀田先生にお願いしたくて」
「ああー!はい、是非是非。監督さんにも僕の方からお伝えしておきますね」
「いやあ、助かります。なんだかんだでここ最近女バスも男バスも僕の方で面倒見ちゃってたから」
「こちらこそ、むしろ前田先生お忙しいのに、ずっとお任せしっぱなしで」
「いやいや。それでね、これはまた別件なんだけど、堀田先生のクラスの…」
前田先生は、良くも悪くも癖の無い人だ。少し強面で、いつもジャージで、身体が大きくて、ちらほら白髪が混じっている。いわゆるよくいる体育の先生。同じ男子バスケ部の顧問として、それなりに活動を共にすることはあるけれど、特に大きな思い出はない。「はい」口半開きのまま、次の言葉を待つ。嫌な予感と言えば失礼だけれど、ちょっとどきどきした。
「あの、お話中すみません。堀田先生に保健室から内線入ってます」
背後から声をかけられて、振り返った。事務員の女性が腰を曲げて申し訳なさそうに職員室を指差していた。
前田先生の方をちらりと見ると、手でどうぞ、と促される。
「お待たせしました、堀田です」
「お忙しいところごめんなさい。保健室の仁科です。あの、風呂蔵さんがいらっしゃってます。午後は早退したいみたい」
「あー、だめそうですか」
額に手をやって、そのまま前髪を持ち上げた。クーラーの直風が生え際を撫でる。
「お昼休みに駆け込んで来た時はいつもと変わらない様子だったんだけど。逆にそれが気になったんですよ。昨日、結構ショッキングな事件があったでしょう」
「ああ、はい」
「私の方でちょっとお話を聞いてみてもいいんだけど、先生、午後どこかで保健室いらっしゃられますか」
「お昼休みの後になっちゃうんですが、五限にお伺いします」
「分かりました、あと、桝さんが風呂蔵さんとお昼一緒に食べようって来てくれてますよ」
「桝ですか、そっか。良かった。ありがたいです」
「はーい、じゃあ、失礼しますね。いらした時に私がいなくても、丸いテーブル使ってくださいね」
「はい。恐縮です」
受話器を戻し、自然と力のこもっていた首を左右に揺らした。
うちのクラスの風呂蔵まりあは、心が痛くなるほど普通の女子高生に見えた。
元々、学生時代の付き合いの中で、風呂蔵の姉と面識があった。確か名前は、風呂蔵いのりさん。姉の方は静かで人見知りのようだったから、この珍しい苗字でなければ気づかなかっただろう。風呂蔵まりあの担任になってすぐ、新年度のはじめは、クラスの中心になるグループの一員くらいに思っていた。昼休みはぎゃあぎゃあ騒いでる女子たちの一角に、お弁当を持ってそそくさと座り込んでいたし、教室を出る時も同じような女子たちと誘い合って出て行った。俺のことも、他と一緒になって「ほったちゃん」と茶化していた気がする。他人との境界をあまり感じない振る舞いもあり、そういう子、だと思ってた。
一方で、未提出の課題を催促したときや、遅刻を叱ったときは、心の底から後ろめたそうにして、ちょっと悲壮な表情にすら見えたのが強く印象に残った。この年頃の女子生徒が男の先生を茶化したりするのは、まあ仕方のないことだと思うし、高校まで来てそんなことを正そうとも思わない。ただ、自身が軽んじられやすいからか、風呂蔵の、普段の様子とは少し異質な「次は気をつけます」「明日出します」は、むしろこっちがたじろいだ。
根が真面目なんだな、と結論付けた。それでも、風呂蔵の未提出物や遅刻、居眠りは増えていって、クラスのグループ作りのざわつきは収まってきた時期、ちょっと心配になった。風呂蔵は昼ご飯を一人で食べるようになったから。
ぼんやりと立ち尽くしていると、前田先生が職員室へ入って来た。
「堀田先生、今の内線は風呂蔵さんのお話ですか?」
「あ、すみません、ぼんやりしてて。お話の途中だったのに」
「いや、仁科先生が朝、風呂蔵さんにカウンセリングを考えるよう堀田先生へ話してみて欲しいと言われて」
「はい」
「そんな感じなので、これ、カウンセラーの先生の出校表です。良い機会なのでと」
「ありがとうございます、助かります。すみません」
「こちらこそ、結局お呼び出しした意味がなくなっちゃって、すみませんね」
前田先生は、「風呂蔵さんは体育もあんまり出席が無くて」と切り出したが、会話を続けたいわけでは無さそうで、「ね」なんて言いながら自分の席へ戻って行った。
前田先生の後ろ姿は、やはりおじさんだった。昼休みが終わり、五限目の予鈴が鳴る。
授業は無いけど、片付けないとならない仕事が山ほどある。放課後がしばらく部活動にとられちゃうから、詰め詰めでやって行こう。でもその前に、風呂蔵…いや、六限に返す小テストの採点が先か。
俺も、学生時代は要領がいい方じゃなくて、特に優先順位を付けることが苦手だった。コンプレックスの変遷はいわゆる教科書通り、腰パン、チェーン、声変わり、ワックス、眉毛、女のこと。やりたいことと出来ないことの折り合いの中で、ふと気がつくと、周りの人には出来て当然のことが出来ない大人になっていた。時間ギリギリに来る、忘れ物をする、誤魔化し、嘘をつき、ほぞを噛み、夜更かしをした。
外に向けられていたコンプレックスが、内面に出現したことをくっきり感じ始めたのが教育学部に入りたての頃だったから、「みんなそんなもんだろ」では自分を誤魔化せなくなって、今度は自分こそ教育者になるべき人間だと、正当化した。弱者の気持ちが、分かるから。共感性を無くした閉塞的な学校王国の教師たちなんかより、出来ないことの辛さを知る俺は立派になれるはずだ。世の中に辟易してるのはみんな、俺みたいなやつで、自分が駄目であればあるほど、そういう子どもに救いの手を差し伸べることが出来るんじゃ無いかと、思った。
こうして根底に湧き出た自己肯定感は、めちゃくちゃな毒だったのだが、歳を取る以外にそれを知る術はない。恐らく。
採点が終わると、もう三十分も経っていた。一コマが五十五分だから、あと二十五分しかない。風呂蔵と十分くらいしか話せないかも知れないな。とりあえず、行ってみなきゃ。
職員室を出ると、外は蒸し暑かった。一階にある保健室へ階段を降りる足音も、どこかこもって響かない気がする。下駄箱を通り過ぎて、体育館へ向かう昇降口の手前に保健室がある。
「失礼します」
ドアを開けると仁科先生の姿は無く、窓から入る陽の光で白くぼんやりかすむ室内は、教会のようだった。クラスメイトたちが授業を受けているときにここで差し伸べられる救いの手、泣くほど嬉しいんじゃないか。でも、案外仁科先生怖いしな。
「まりあー?」
仁科先生が使っていいよと言ってくれた、パーテーションの中の丸テーブルに腰掛けながら、風呂蔵を呼んでみた。保健室という場所は、何故か妙に緊張するから、勝手に探し回るのもあれかな、なんて。しばらく耳を澄ましてみても、返事が無い。
「帰っちゃった?」
パーテーションから顔だけ出すと、準備室に続く扉から、「せんせー、カフェオレー」と、カップを片手にした風呂蔵が出てきた。黙って見ていると、顔を上げた風呂蔵と目があった。向こうは、誤魔化すような笑みを浮かべた。
「うわ」
「はい、まりあさん、こちらへどうぞ」
「えー!やです」
「やですじゃないです」
風呂蔵は渋々カップをすすぎ、流しに置いて、丸テーブルの向かい側へ腰掛けた。慣れたもんだな、おい。
「先生、暇そうだね」
茶化してくる。この、人とそつなくコミュニケーションを取ろうと言う切り出し方は、春の頃と変わらないのに。
「まりあこそ、暇そうじゃん。午後出ようよ」
「具合悪いの!」
「お前なあ」
「明日はちゃんと全部授業出る」
「勢いだけは良いんだよなあ。仮に家に帰るとして、親御さん居るの?」
「親は居ないけど、先生の初恋の人ならうちにいるから」
「あほ」
手にしていたファイルで頭を軽くはたく。痛いんですけど!と笑う。風呂蔵が「先生の初恋の人」と揶揄したのは、彼女自身の姉のこと。
「そういうの柏原くんから吹き込まれるわけ?」
柏原くんというのは、俺の大学時代の友人だ。俺が風呂蔵の姉と面識があったのも、その柏原が当時同じサークルの一つ後輩だった風呂蔵いのりさんと交際関係にあったからだ。面識があると言っても、柏原と遊ぶたびに惚気話ばかり聞かされていただけで、実際に��ったのは、大学祭の時の一度きりだ。
柏原とはいまもずっと連絡を取り合っているが、風呂蔵の姉とは今も続いているそうで、彼女の妹にあたるまりあに、俺の話をあることないこと吹き込んでいるらしい。
「でも柏原くん言ってたよ、堀田先生もうちのお姉ちゃんのこと好きだったって」
「あなたね、そう言うのを減らず口って言うんだよ。やっぱり元気じゃん。小テスト落ちてもいいから出なさいって」
言葉による返事はなかった。代わりに目は逸らされ、喉から絞り出すような笑い声が差し出された。
心が痛かった。大人と喋るのはちょっと怖いよね。でも、そんなに無理するもんじゃないよ。
仁科先生の声を頭に思い浮かべて、なるべく優しい声を出してみた。
「…まりあ」
自分の声が思いの外おじさんで、ちょっと気持ち悪かった。まりあの顔も心なしか引きつっているように見える。自分に違和感を感じながら続ける。いや、なんか気持ち悪い、本当にごめん。
「具合悪いのは、こう、学校に居ると心が辛い、みたいな感じかな。それとも、本当に体調悪い?」
「お腹痛い!私さ、生理痛重いんですよ」
間髪入れず返ってきた風呂蔵の言葉を、強がり、と言うのも憚られるほどに。
さあ、どうして、心が痛むんだろう。訳もなく晴れない、多感な時期の子どもの苦悩に直面しているから?
「最近の若い子って、そう言うのためらい無いわけ?」
違う。救いの手だと思って差し伸べているものが、見当違いかもしれないと言う不安。
自分は子供達にとって、救いの存在じゃ無いという確信。
先生なんて、生徒が一番、それなりにやり過ごす相手じゃないか。
前田先生の後ろ姿。あんな風に、俺も見られてるのかな。
慕われる先生って、こんな時どうするんだろう。
「てか、先生さ」
「はい」
「クラスの生徒のことって大事?」
「当然じゃん」
当然じゃん
「命かけて守ろうと思う?」
迷っているところとか、困っているところとか、あんまり教師が見せるもんじゃないだろうと、勝手に思っていた。少なくとも俺が生徒の立場だった記憶の中で、「先生」は毎度迷わず教科書通りでいてくれた。でも、それも、俺には出来ないことの一つだった。いつもいつも正しくはいられない。
「どうかなあ。学校って色んな人がいるから、命がけで守って欲しい人も、そんなことして欲しくない人もいるんじゃないかな」
「堀田先生っぽい」
「申し出に合わせると思う」
だってもう、本当に分かんねえもん。守って欲しいなら、差し伸べた手を掴んでよ。どうしたいの
「風呂蔵は」
「え」
風呂蔵が、まん丸の目をこっちに向ける。前髪で隠れたニキビ。乾いてささくれの一助となった色付きのリップ。十四時五分前、時計の真下。
何て言ったら正解なんだろう。何を言えば、風呂蔵は幸せになれるかな。
「命がけで守られたら、午後の授業出る?」
「今日は、本当に!」
両手の平を顔の前でピタリと併せて、そう言いながら立ち上がる。
「まだお話済んでませんよ」
「本当に!」
ごめんなさい、立ち上がりこうべを垂れる風呂蔵に、授業の終わりを告げるチャイムが降り注ぐ。
ガラス棚に光が射して、跳ね返った光線は、空中に舞う埃を縁取った。まりあって名前の由来、もしかしてマリアさま?
成長って言うのは、ままならないね。そんな泣きそうな顔しないでよ、こっちだって簡単に命なんて張らないからさ、なんとか今は耐えて、自分のなりたいように大人になってごらん。それを邪魔する奴からなら、喜んで守ってあげるよ。
なんて言ったら、キモい!とか言うんだろうなお前ら。
すり足でパーテーションの外側へ出て行こうとする風呂蔵を見て、思わず笑ってしまった。風呂蔵の表情が安堵に満ちたのが分かった。
「気をつけて帰れよ。ちゃんと仁科先生にご報告して、早退届には明日まとめてサインするから」
「ありがとうございまーす」
俺をやり過ごすことが、そんなに嬉しい?学生時代の俺がまさしく見たかった生徒の笑顔だけど、それ。
そのまま風呂蔵は準備室へと戻って行った。静かになった教室に背を向けて、自身も保健室を後にすべく、引き戸に手をかけた。ただ気まぐれで、風呂蔵が消えていった準備室へと続く扉に向かって大きな声を出した。
「また明日!」
神様の声は、もう聞こえなかった。
六限まで終わると、生徒たちは掃除と軽いホームルームをして、各々放課後の活動へと散っていく。
教室にポツポツと散る空席に、今日配布になった学園祭のお知らせを配って回る。風呂蔵の机にも同じようにお知らせを入れようとすると、「あの」と呼び止められる。
風呂蔵と親しい、桝莉花だ。
「あ、莉花、今日はありがとうね 」
「え?」
「お昼まりあのところへ行ってくれたでしょ」
「はい」
「まりあ、元気そうだった?」
「普通でした、割と」
でも、と髪の毛をいじる。上から見下げるのが申し訳なくなって、手近なまりあの椅子を引っ張って腰掛けた。
「お昼ご飯、買ってきてたのに、私が行ったら隠しちゃって」
「どういうこと?」
「ご飯食べてないのにご飯食べたって言ってました。あんまりそういうことないかも」
「あ、ほんと」
桝莉花は風呂蔵と仲が良くて、何かというとよく二人の世界に浸っているように見える。それは俺と柏原の仲の良さとは確実に違う、いわゆる女同士っぽい付き合い方だなと思っていた。教師になってから、クラスの関係性を様々見てきたけれど、まあ珍しくはないだろうと思った。ただ、やはり風呂蔵の方が学校を休みがちということもあり、桝が進んで面倒を見ている、という印象は少なからずあった。状況だけで判断しているつもりは無く、日頃、桝の振る舞いが、少なからずそう言った雰囲気を漂わせていた。
それは全然悪いことじゃない。桝は独特だけど、優しい子なんだ。
「先生、私、まりあにプリント届けに行きます」
「ほんと?じゃあお願いしようかな、莉花今日は部活は?」
「行きます、帰りに寄るので」
桝にお知らせを手渡すと、それをリュックの中に押し込んだ。
「ねえ、莉花さんさ、まりあといつから仲良しなの」
「このクラスになってからですよ」
「そうなんだ、でも二人家近いよね」
「まりあは幼稚園から中学まで大学附属に行ってたと思います。エスカレーターだけど高校までは行かなかったっぽい。私はずっと公立」
「あ、そうかそうか」
割と最近なんだ、それにしてはと思ったけど、人間の数だけ価値観や感性があることを念頭に置かなきゃだめだ。
桝は頭を下げて教室を出て行った。
風呂蔵の机は綺麗だった。お知らせが溜まっているわけでも無く、置き勉がしてあるわけでもない。
うちの生徒は、教科書、ノート、資料集、問題集、解答集、模試ノートなど、一つの教科でいくつもの教材を持ち歩く。そこに部活の道具、塾の教材、その他諸々…土曜の補講も含め毎日学校へ来ることを考えれば、自分の席やロッカーは私物化せざるを得ない。教師に注意されても、それなりに上手くやりながら、かいくぐることをお勧めしたいね。
今日休んだ他の生徒の席も、そうは言っても、それなりに生活感というか、あああいつの席だな、とわかるくらいの面影がある。それが風呂蔵の席にはない。いつ居なくなっても、何も困らないくらいに。
桝が一生懸命、お知らせや返却物を溜まらないようにしているからだろう。しかしその行為は、いつ来ても自分の居なかったラグを実感することはなく、変わらず目の前には空っぽの席があるだけということなんじゃないか。
そう思うと、少しゾッとした。
俺なら、プリントそのままにしておいて、って言うかもしれないな。
遠くから何かの楽器の高らかな音が飛んでくる。空っぽの教室の輪郭を滑り落ちていく。そろそろ部活に行かなきゃ。立ち上がって振り返ると、出て行ったはずの桝と目が合った。
「うわびっくりした。どうしたの」
「あ、忘れ物…」
桝は自分の席に小走りで近寄って、ペンケースを持って逃げるように出て行った。
桝の目は時々すごく鋭い。二者面談をするときや、個人的に話すとき、彼女の人当たりとは裏腹な眼光の鋭さがある。もともとの顔立ちのせいなのかもしれないが、言いたいことをぐっと堪えたりしてるようにも見える。振り返った時にぶつかった視線もまた、言葉にならない訴えで射抜くような強さがあった。
十九時前、部活動を終え、職員室へ戻った。
朝とはまた少し違った終業の慌ただしさや、疲れ切った空気感は嫌いじゃない。蛍光灯のショボさはノスタルジーを誘い、高校時代に夜遅くまで校舎に残っているような、無限の王国、夏休みの直前、地球最後の日、そんな気持ちになる。無論、真面目だった俺はそんな経験はないけれど、学校の特定の場所、特定の時間帯に訪れるセンチメンタルは、それらをとても優しく捏造してくれる。
「堀田先生、お疲れ様です」
隣の席の細倉先生がマスクをずらして会釈する。
「お疲れ様です」
「先生、どうすか。今日ご飯」
「あー…」
細倉先生は同い年で、気持ちのいい男の先生だ。俺もそれなりに、そこらの高校生には負けない背丈があるぞ、というのがなけなしの自慢だったけれど、細倉先生にはしっかり負ける。高校時代は剣道でインターハイまで行ったとか。さぞかしモテたことだろう。その勢いは衰えを知らず、今年度から細倉先生がこの学年の世界史を担当するようになってから、日本史を選択履修した女子が軒並み己を呪ったらしい。
「行きますかね…」
細倉先生は、よくご飯に誘ってくれる。ほとんど断ることはないのだが、快諾するたびに人懐っこそうな顔をするため、いつもお約束で迷うふりをする。こういうところが、やっぱり女性にもモテるし、俺も嬉しくなっちゃうんだよな。
「あ、でも細倉先生、何時に上がりますか?ちょっと今日遅くなっちゃうかもしれなくて」
「僕もう帰ろうかと思ってました」
「そっか。どうしようかな。というか、奥さん大丈夫なんですか」
「最近、ヨガのレッスンが入ってるとかで、あんまり夜家に居なくて」
「毎日ヨガ?」
「教えてる方ですよ、インストラクターなんで」
「へー」
「堀田先生は何時までお仕事なさるんですか」
「いや、やっぱり今日は帰ります、行きましょう」
「え、大丈夫ですか」
「はい。校務自体は終わっているんで」
「よっしゃ、じゃあ行きましょうか!で、あの、僕今日、自転車なんですけど」
「あ、載せて行きますか」
「えー!悪いなあ、でもありがとうございます!お言葉に甘えて!」
「初めからそのつもりだったくせに」
「あはは、じゃあ、すみません!お先に失礼します!」
「僕も失礼します」
細倉先生がまだちらほら残る上司たちに元気よく挨拶すると、遠くで難しい顔をした学年主任が片手をひらひらと振った。後に続くように自分も荷物を抱えて職員室を出る。
細倉先生はずるいね。すごくやりやすそう、色々と。
昼間、自分にこびりついたおじさんの残像にがっくりと肩を落とす。かといって、細倉先生のような先生が理想かというと少し違う。ドラマや漫画や実体験が就職のきっかけになっていない自分には、端から明確な理想像なんてなかったのかもしれない。でも、高校時代の、大学時代の、比較的鬱屈とした自分に問えば、めちゃくちゃ生意気な顔をしてこう言うだろう。
「ちょっと違うんだよな」
「え?」
「あ、いや」
俺の車の後部座席を倒して自身のロードバイクを一生懸命押し込む細倉先生は、バックミラー越しにこっちを見た。
「飯、どこ行きます?」
「駅前になんか有名なつけ麺のお店が出来たらしくて、そこ行きましょうよ!」
「駅前」
「駐車場無いんで、駅ビルの立体駐車場に止めましょ」
「はーい」
助手席に乗り込んで来る細倉先生に、「じゃあ出しますよ」とサイドブレーキを下ろす。スマートフォンの通知音が響いた。
ブルーライトに照らされた隣の細倉先生の横顔は、鳴ったのが自分のスマホの通知ではないと確認すると、わずかに左右に振れた。
「俺か」
サイドブレーキをもう一度引き、スマホの画面を確認すると、差出人が「柏原」のメッセージが数件来ていた。柏原か、まあ、後でいいかな。画面を暗くすると、今度こそ学校を出た。
「堀田、もう授業終わり?」
「今日まりあちゃんに会ったよ」
「飯行こうよ」
車で二十分くらいかかり、ようやく駅の駐車場で確認した柏原のメッセージはその三件だった。柏原は風呂蔵の姉に会いに行ったのか。そこで早退したまりあに会ったらしい。また風呂蔵と二人で俺の悪口でも言っていたのだろうか。飯に行こうというのも、その延長で俺に話したいことでもできたに違いない。
「ごめん、飯は同僚と食べるから」
そう送った俺の返事にすぐ繋げられた返信は、誤字だらけだった
「今ら?あ、終わってらの?大丈夫かなる」
酔ってるのか?そう打ちかけた時、送信されたメッセージは取り消され、画面上から消えた。代わりにまた違う文面が送られてきた。
「分かった、また連絡するよ」
嘘だろ。どう考えてもおかしいだろ。細倉先生がしおらしく、「大丈夫すか?」と覗き込んできた。メッセージ画面を見ると、すぐ首を引っ込めた。
「彼女さん?」
「残念ながら」
とりあえず、「またね」とだけ返して、駐車場の外階段へ繋がる出口を目指した。帰る時に迷わないよう、頭上に掲げられた三階B区画の表示を確認する。
コンクリートに閉じ込められた埃っぽい熱気の中に、誘導灯の緑がぼやける。階段の錆びたドアを開け、細倉先生を先に通すと、会釈と溢れた「うわ、全然涼しくねえな」もまた、内側に逆流して誘導灯と輪郭を曖昧にした。振り返ると緑色がべったりと反射した愛車が、不安げに佇む。夏の夜に、人工の緑は良くないな。全然心穏やかじゃない。
「堀田さん?」
一歩が跨げずにいると、細倉先生がカンカンと音を立てて階段を上り直してきた。
「あ、行きまーす」
外に出ると、動かない外気と夜景が広がる。それらもまた、どこまで行っても息苦しく滲んでいるように見えた。
「そういえば俺、朝も麺だったな」
「朝から麺?堀田さん料理なんてするんですか」
「そう、高級なアルデンテなんですけど」
「絶対に嘘だ」
「でも食べきれなくて流しに捨てちゃった」
「流しに…?あっ、わかった。カップ麺でしょ。僕も最近食が細くてエネルギー足りないし、帰り自転車に乗る気力も湧かない。堀田さんも結構少食ですよね」
「まあ、何だかんだ暑いですものね。でも今日のつけ麺は美味しかったです、毎日食べれそう」
「ね!うまかったですよね」
つけ麺屋はそれなりに混んでいたが、待つこともなくスムーズに食事をして出て来られた。スマートフォンを確認すると、時刻は二十時半前。立体駐車場の外階段を上りながら、前を行く細倉先生の背中から声が降ってくる。
「どうすか、クラス」
「どうって」
「僕のクラス、今日すごい休み多かったんですよ。朝、出欠確認した時、びっくりしちゃって。十人くらい居なかった」
「そりゃ、結構居ないですね」
「でしょ。そこからまた一人頭痛で早退しちゃって、寂しかったですよ」
細倉先生は先に三階まで辿り着き、踊り場で夜景を一生懸命見ている。錆びた手すりの向こうは確実に夜を迎え、黒く低い空と、無数の騒がしい光が向かい合わせに続いている。
風呂蔵も、数多いる遅刻、欠席、早退のうちの一人だった。きっとどうしても学校には居られなくて、申し訳ないと心を痛めながらも、家に帰るんだろうな。みんな自分が一番情けない、恥ずかしいって思うのかな。それとも、ラッキー、くらいなのかな。ここから見れば、別に大きな差はないのに。
三階にたどり着き、今度は細倉先生が駐車場へのドアを開けてくれた。
「お嫁さん、もう帰ってきてます?」
「まだだと思う。遅いんですよ」
車の鍵を開けると、そそくさと運転席側に回って今度は車のドアまで丁寧に開けてくれる。
「ご自宅まででよろしいですか」
「よろしくお願いします!」
俺が乗り込むと、静かにドアを閉め、自分のシートベルトを締めながら、愛想のいい笑顔が助手席に収まる。本当に同い年かと、しげしげと顔を眺めながらエンジンをかける。この人の、クラスでの様子がいまいち想像つかない。
駐車場を出て駅前のごたついた道を抜けると、細倉先生がぽつりと話し始めた。
「昨日、一高で事件があったでしょ」
「はい」
「あれで亡くなった先生ね、僕知り合いだったんですよ」
「あっ」
赤信号で思わず強めにブレーキを踏んでしまった。そうだ、そういえば、細倉先生って。
「僕、一個前の赴任先が一高で、そこで、クラスを二年持ち上げした時に、新任で入ってきたのがその先生。優しい先生でしたよ。すごくいい人。でもちょっとおっちょこちょいで、間違いとか誤魔化そうとするし、僕はあんまり反りが合わないなって思ってたんですけど」
赤信号に照らされる細倉先生の横顔を、横目で見ていた。その鼻筋がパッと緑に縁取られて、慌ててアクセルを踏んだ。
「僕がこっちの学校に転任してしばらく経って、メールが来たんですよ。生徒と上手く行かなくて困ってるって。僕、言ったんです、他に相談できる先生を学年で作れよって、あんまり一人で抱え込むんじゃないよって」
細倉先生の声は落ち着いていた。俺が黙っていると、「こんな話あります?」とちょっと笑った。
「その、上手くいっていなかった生徒っていうのが、例の?」
励ますとか、諭すとか、さまざまな選択肢が脳裏に浮かんだけれど、もう胸が痛み正解を選び出すような力はなく、純粋な疑問が隙間を埋めるように口から溢れた。
「そうみたいです。学校に来れてなかった子だったらしいんですけど、説得して少しづつ来れるようになったら今度は、その先生と衝突しちゃうことがすごく増えたみたいで。なんだったんでしょうね、いじめられてたのかなあ、僕にも想像がつかない。でも、本当に彼、しつこくしちゃったのかも。最後にやりとりした時は、その生徒とはもう言葉が通じないって言ってて」
細倉先生の家が近い。俺は道沿いのコンビニに車を停めた。わずかに震えるような、大きいため息に押し出されるようにして続きが語られる。
「でも僕、その子も、一生懸命助けを求めてたんじゃないかって、思って。先生も救ってあげようとして、学校へ連れてきて、それなのに、言葉が通じなくて、お互いに、苦しかっただろうなって。それでも、あいつがしたこと、間違ってなかったって、だれか言ってあげて欲しい。事件で亡くなった生徒さんも居るから、お葬式では言えないし、今となっては、もう、遅いんですけど」
きっと、隣で感情を押し殺しながら、いつも通りの毅然とした顔でいるんだろう。それでも、細倉先生の顔は見れず俯いていた。
「ちょっと、堀田さん!」
細倉先生に肩を叩かれた。
「堀田さんが泣いてるじゃないですか!」
ちょっと涙目、くらいだと思う。鼻の奥がツンと痛かったから、それを噛んで堪えていた。涙もろいタイプですか、と散々茶化してから、細倉先生も少し鼻をすすった気がした。
「だから、僕、今日、あまりにもクラスに子供が居なくて、本当にビビっちゃって」
次の言葉を待っていると、ちょっと考えてから、
「ビビっちゃった、と言うことでした。僕が学校休みたいくらいだよって、ねえ」
強引に話を終わらせ、笑った。
生徒のことも、先生のことも、何もかもが、かき混ぜた水槽の様に、順序なく頭の中を漂っていた。
その中で、最後のメールに、細倉先生はなんて返したんだろう、という疑問というか、きっと、本当は聞かなくても分かるんだけど、後悔の本当の理由みたいなものに触れていいのかどうかだけが、深く静かに沈んでいくのが分かった。
「細倉先生、大丈夫ですか」
「いやいや、ははは!まさかそんなにダメージ食らう人でした?逆に大丈夫ですか」
「俺が泣いちゃったから泣けなかったですか」
「え、なんじゃそりゃ!すみません本当、全然そんなことじゃなくて」
細倉先生は顎に手を当ててしばらく唸った。
「いや、自分でもよくわからねえな。でも本当に、言いたかったんだと思う、誰かに。嫁にはこんな話できないですよ」
本当のところがどうかは分からないけれど、疑うなといわんばかりの強い語気を取り戻していた。俺も居直って、今度はきちんと細倉先生の顔を見た。
「話してくれて、ありがとうございます。俺なんかで良かったんですかね、少しは役に立てたらいいけど」
「あはは、なんかあれっすね。堀田さんって、卑屈というか、真面目というか…。なんて言うんだろう、ギブアンドテイクの精神がすごい人ですね」
いつもと違う会話の切り口で、少しどぎまぎする。何を言っても、話が空振りする。三振でも取らんとするその小刻みな頷きはやめてくれ。いつもなら爽やかだな、くらいにしか思わない細倉先生の笑顔が、コンビニのサインのくっきりとした光で陰影が与えられ、ちょっとだけ違って見えた。
「別に、堀田先生になんか役に立って欲しくて話したわけじゃないというか。俺も泣きたいとか、励まされたいとか、そんな感じの性格じゃないし。でも堀田先生は自然と話しやすいんですよ、教師向きで羨ましい」
真っ直ぐになだめられ、絶句してしまった。
訝しんだ手前、いつのまにか自分の方が励まされている情けなさが、反論や肯定や、細倉先生こそ教師向いてますよ、みたいな言葉も全部霞ませた。でも、細倉先生のは、ちょっと嘘っぽい言葉だな。本当に、ずっと調子のいい奴だ。隠した心はボロボロかもしれないけど、まんまとこのペースに乗せてくる。というか、お嫁さんは、よくこんな食えない男を捕まえたよな。
自分がどんな顔をしていたかは分からない。でも、細倉先生は多分、俺の顔で笑っていた。
細倉先生の胸ポケットのスマートフォンに明かりが灯り、画面を確認すると、そのまま呟いた。
「あ、嫁帰ってきた」
「車出します」
「大丈夫ですか?運転代わりましょうか」
そんなに情けない顔をしていたのか。
「大丈夫です!」
すぐそこが細倉先生の住むマンションだ。駐車場に入れるのが面倒で、いつもエントランスの向かいの道路に停める。
「じゃ、ありがとうございます」
助手席を降りて、後ろに積んでいた自身のロードバイクの固定を解きながら、細倉先生が語りだす。それをバックミラーで見ていた。
「僕、堀田先生が話しやすいのって、同い年ってこともあるけど、他人に興味がなさそうだからだって思ってたんですよ。割り切ってるっ���いうか。そういうところは僕とちょっと似てるなあって思ってたんです。僕もあいつからメールもらって、ああ、オレみたいな適当に流せるやつって話しやすいよねー、って。でも、ちょっと違ったみたいですね。全然物事深く考えられない僕の分まで、すごく色々考えてくれそう。あんまり抱え込んじゃだめですよ」
人懐っこそうに笑いながら、じゃあまた明日、なんていつまでも手を振っているから、そそくさと車を出した。
俺がもし、どうしようも無くなったら、この人を頼るだろうか。俺みたいに、変にダメージ受けるような奴より、普通はこういう強い人を選ぶだろうな。でも。ここでふと自分の嫌なところが顔を出す。でも俺だったら、もっと的確なアドバイスが出来たかもしれない。細倉先生の持つ強さって、深入りしないところなんじゃないのか。色んな人の心地よいところで踏みとどまれるというか。いい意味で浅い。だからこそ、亡くなった例の先生ごと見知らぬ生徒まで救うような導きの一撃ができなかったんだろうな。
もしも、俺だったら。
というか、いい距離感でいたからこそ俺は細倉先生に気に入られてたのかな、似てるって言ってたしな。でも、俺の反応は予想外だっただろうから、引かれたかもかな。最悪だな。最後の捨て台詞が、急に三行半のように思えてきて、チクチクと胸を刺す。いや、でもあれは感情が揺さぶられない方がどうかしてるだろ。そもそも、突然決めつけで打ち明けてきたのはあっちだし。
禁煙してなかったら、今絶対に吸ってた。どいつもこいつも、子どものためになら考え続けろよ。逃げるんじゃない。
感情の名前はいくつか知っているけれど、そのどれでもない。苛立ちなら六秒でピークは過ぎ去っていくらしいけど、この感情は一生このままのような気さえする。細倉先生のマンションから俺の家までは三十分かからないくらいの距離だが、それでもさらに遠回りを目指し左折した。
思いのほかずっと、「もはやこれまで」のまま長生きしている。生きていることに対しての恥ずかしさはもうない。夜眠れなくても、息を吸っても、吐いても、あの頃の不安はもう分からない。暗号の、解き方だけを忘れたような。周波数の違う電波は全部ノイズになってしまうような。
環状線へ乗ると、急に独りぼっちが寂しくなった。空になった助手席には、沿道の光が色とりどりに反射して、誰も居ないシートを浮き彫りにする。案外、もう、どうしようもないのかもしれないな。誰に助けを求めようか。
家に着いたのは、二十二時前だった。車を駐車場に停め、不快な湿気と温度の中、しばらく放心した。身体がだるい。夏バテにしては早すぎる。重力に逆らえず、運転席に沈んだ。
スマートフォンの画面が光って、穏やかな着信音と共に学年主任の名前が表示される。
何かあったのだろうか。細倉先生とへらへら職員室を出た自分が思い出され、決まりが悪い。怒られたくないんだよ、今日はもう。なんなんだ、一体。ほうっておいてくれ。祈りを込めた一撃で、受話器のボタンをとんと叩く。
「はい、堀田です」
「もしもし、堀田先生、夜分遅くに失礼します。主任の篠原です」
ニュースキャスターのように優しい、穏やかな声だった。
「今、ご家族の方からご連絡がありまして、先生のクラスの風呂蔵まりあさんが、駅のホームから転落して病院に搬送され、先ほど、病院で息を引き取られたと」
あ、俺、風呂蔵にカウンセラーの出校表渡すの、忘れてた。
「ご家族に僕の方からご連絡入れるべきでしょうか」
「大丈夫ですよ。明日以降改めてご家族へのご挨拶と、クラスの生徒への対応を検討しましょう」
「はい」
「明日は早めに出勤できますか?」
「はい…あ」
「何かありますか?出来ればこちらを優先していただきたいのですが」
「いえ、あの、部活の朝練の監督を、前田先生がお忙しいので僕が代わるとお約束していて」
「ああ。でもそれは前田先生にお願いしましょう。堀田先生、七時に会議室にいらしてくださいね」
「は、はい」
駅のホームに流れる業務連絡のように、自分ではない誰かに向け左から右の遠い方へ、主任の声は逃げていく。
「眠れないかもしれませんが、しっかりと体を休めるようにしてください」
「はい」
「失礼します」
言葉にならない最後の返事を口の端からこぼして、通話を終える。焦点の定らないまま、車を降りて、駐車場を後にした。
部屋は温度が逃げ出したような奇妙な空気が静かに支配し、今朝捨てたカップラーメンの塩分の匂いだけが残っている。電気がまた、安っぽく部屋を照らす。俺の部屋はこんなにわざとらしい部屋だったか。B級映画のセットみたいだ。俺は、死ぬならここがいい。
ベッドに横になると、息を止めて、少しずつぼやける天井を眺めた。まぶたを閉じれば暗転する画面にかかる「カット」の声。息を吹き返して、笑って起き上がる。なんていうのは冗談で、閉じたままのまぶたに、まだまだ続く明日のことを思い浮かべた。
「あーあ」
どのタイミングで誰に何を言えばいいんだ。いつどんな仕事をすればいいんだ。持ち合わせない誠意を求められたら、どう示そう。個人的な後悔に襲われるのはいつだろう。報告書みたいなのがあるのか。警察へ行くこともあるだろう。クラスの子どもたちは、友達を一人失ってしまったことになる。学園祭、どうするんだ。クラス旗には風呂蔵の名前も入れてやろう。クラスTシャツは、風呂蔵の分も人数に入れて発注しよう。嫌がる子がいるかな。そうだ、風呂蔵と仲の良かった、桝。あいつには個人的に話した方がいいのか。大丈夫か。もう二度と友達に会えないことを、どう告げればいい。
次々と内に溢れる不安に身を任せて、朝まで漂うしかない。
投げやりに寝返りを打つと、指の先でスマートフォンの通知音が響いた。
「堀田、まりあちゃんの話聞いた?」
「今病院の駐車場にいる」
「落ち込んでる?」
柏原からのメッセージだった。こいつ、いつも三言打つ。
メッセージ画面を開くと、そのまますぐに通話ボタンを押した。呼び出し音の中で、深く胸が痛む。
桝は、もう風呂蔵と電話もできない、声を聞くことも、学校でいくら姿を探せど会うことも出来ない。風呂蔵へと繋がるはずの呼び出し音は永遠に止まない、これから彼女に訪れるのはそんな体験ばかりだろう。かわいそうでならない。
「あ、堀田?」
柏原の声は小声で、いつもの浮ついた口調とは違っていた。
「柏原」
「堀田ぁ、大変なことになったな」
「そうだね」
柏原の疲れたようなため息が遠くに聞こえた。タバコでも吸っているんだろう。
「疲れてるだろ、電話はいいからゆっくり休めよ。今日は自宅に帰れるの?」
「さあ、わからない。今は警察の人が来てる。というか、いやいや。疲れた声してんのはどっちよ、堀田。大丈夫?なんかさあ、こんな話したくないかもしれねえけど」
「いいよ」
「記者会見みたいなのするの?謝罪会見っていうのか、あれ」
「え?」
「テレビでよくやってるじゃん。自殺した子どもがいじめられてなかったか、キョーイクイインカイってのが調査するんだろ」
「あ、ああ…」
柏原はやや頭が悪い。大学の頃からずっとそういう振る舞いで、話が噛み合わないこともしばしばあるが、一生懸命会話をしようとするし、優しくて明るい、だらしなくてちょっと悪ガキ。友達が多くて、不思議と安心感がある。教壇に立ってしばらくしてから、柏原みたいなタイプを教員が妙に可愛がる気持ちをなんとなく理解した。その頃からずっと変わってない。
「やるのかなあ、わからないや。いじめは無かったと思うんだけど…、遺書とかが出てきて、内容にそういう旨が書かれていたら別だろうな。なあ、柏原。もしクラスでいじめがあって、気づいてないバカ教師だったら、俺は懲戒処分になると思う?」
「は、え?俺に聞くなよそんなこと。そういう法律とかがあるのか」
「知らない」
「うーん、でも、俺も、まりあちゃんがいじめられてるとは思わなかった。あの子、普通に明るい子だったじゃん」
「はは、そうだね」
「普通、分からねえよ。だって他人のことなんていちいち理解出来ねえし、なあ?」
柏原の言葉尻が少し荒い。もちろん、状況が状況であるから、全てが普段通りではないだろうが、こういう時に真っ先にしょぼくれるタイプの柏原に怒りがにじむのは、少し違和感がある。
「お前は悪くねえし、第一、なんでもかんでも先生が責任とるのはおかしいだろ」
柏原の声がもごもごした。タバコを咥えたのだろう。それでも、電話越しの声がだんだんと怒っていくのがわかった。
「柏原、怒ってる?」
「は?怒ってねえよ、別に」
怒っている。柏原は軽薄そうな見た目に似合わず声が低いため、ドスが効いてちょっと怖いなと思った。初めてだ、こんなこと。夕飯の前に送られてきた、変な誤変換だらけのメッセージのことを聞こうかと思っていたのも、触れないでおくことにした。
「風呂蔵はさ、その…遺書とか遺してたのか?」
「…さあ。俺は知らねえよ」
「じゃあ他殺の可能性もあるってこと?」
「いや、駅のホームの防犯カメラの映像で、まりあちゃん自分で飛び込んでるって、警察が。また明日警察行ってその映像を確認すんのよ、ひでえよな。いのりが無理そうなら俺が付き添いで行って、俺の確認で大丈夫だって言われたら俺が見る」
「ふーん…。いのりさんは、大丈夫?」
柏原は黙った。ひやひやしながら返事を待つ。
「だめだよ。もうずーっと泣きっぱなし。気の強いやつだけど、まあ、妹の面倒一生懸命見てきて最期は自殺って、そりゃ泣いても泣いても足りねえよ、無理もないんじゃねえの」
「あー」
胸が痛かった。形容し難いものが瞬く間に胸をいっぱいになって、今度は俺が黙った。
これからは、こういう気持ちを正面から受け止めることが仕事なのか。生徒の分、保護者の分、いのりさんの分、あと俺の分。俺の分?
ことと場合によっては世間の分。何なんだ一体。何の責任を果たせばいいんだ、何の秤にかけられてるんだ、何の受け皿になったんだ、俺は。どうして死んだんだ、風呂蔵。
素晴らしい明日はしばらく来ない、過去も変えられない、出席表の丸は二度とつかない。
「なあ、堀田」
「なに」
「元気出せよ。無職になったら、仕事紹介してやるから」
「はは…縁起でもないな」
縁起でもないってなんだ、大切な教え子が死んだのに。言葉はいつも使ってるものが出てくるもんだな。何十年もかけて馬鹿みたいに毎日使えば、そりゃそうか。
「とりあえず、また連絡するわ」
「うん、じゃあまた」
「またな」
「はい、またね。切っていいよ」
耳からスマートフォンを離し手元で画面を見ると、十分六秒、七秒、八秒…。通話時間は刻々と続いて行く。
「切れよ」
集音部分に口を近づけ、笑いながらそういうと、向こう側からも笑い声が漏れ聞こえ、プツリと切れた。
1 note
·
View note
Photo

🍪 ̖́- 今夜はオリジナルクッキー缶のデザインを担当してくださった @toraring さん についてご紹介させてください もともとtoraringさんのイラストが大好きで、ポストカードを集めさせてもらってました 愛するうさぎさんと草花が活き活きと優しく描かれ まさに求めていた世界観 いつかイラストをオーダーしたいなと思っていたんですが、このような形で依頼することになるとは ※にゃんこもとってもかわいく描かれます。にゃんこ好きの方もぜひtoraringさんのminneを覗かれてみてくださいね🐈 今回めちゃくちゃお世話になりまして オリジナル画の作成だけでなく印刷業者さんへのデータ出稿から何から何まで… 業者さんのミスで、まさかの不良品が届き toraringさんが間へ入ってくれなかったら泣き寝入りするところでした🫣 業者さんは部品から交換して全てやり直してくれて😮💨 おかげさまで美しすぎる、まるで芸術品のようなクッキー缶を納品することができました ほんとにありがとうございました😭 手にとった瞬間きっと笑顔がこぼれる そして封を開けた瞬間うさちゃんが飛びつく笑 素敵なクッキー缶に仕上がってます ✰︎こだわりの材料や制作風景をvlog形式でご紹介してます ハイライト【販売情報🍪】でご覧いただけますのでそちらをご参照ください`🤍´ #あんちゃん #うさぎ #うさぎら部 #うさぎのいる暮らし #ふわもこ部うさぎ課垂れ耳係 #うさぎのおやつ #チモシークッキー #rabbit #bunny #minilop #rabbitsofinstagram #instabunny #rabbitaccount #bunnytreats #토끼스타그램 (Hiroshima Japón) https://www.instagram.com/p/Cp7sHRJr0YH/?igshid=NGJjMDIxMWI=
#あんちゃん#うさぎ#うさぎら部#うさぎのいる暮らし#ふわもこ部うさぎ課垂れ耳係#うさぎのおやつ#チモシークッキー#rabbit#bunny#minilop#rabbitsofinstagram#instabunny#rabbitaccount#bunnytreats#토끼스타그램
0 notes
Text
ティーンエイジ・サイコプレイス
女子中学生になろうぜ!!!!!!!!!!!!!!!!
「終業式、探索者の通う学校で一人の少女の死が告げられる。
しかし痛ましく衝撃的なその事件は、ただの幕開けに過ぎなかった。」

中学二年生女子限定クトゥルフ神話TRPGオリジナルシナリオです。
boothにてダウンロード販売をしております。
NPC立ち絵、コピペ用テキストを同梱済。
所要時間:5~6時間程度
プレイ人数:2人
推奨技能:なし
NPC立ち絵 もりろ様 Twitter @365funeral
表紙デザイン、マップ TWEO様 Twitter @TEWOWET
シナリオページ https://sagimarisa.booth.pm/items/1647668
以下、本文サンプルとなります。
『ティーンエイジ・サイコプレイス』
【はじめに】
当シナリオは、現代日本、女子中学校を舞台としたものになります。PLは中学二年生の女子と言う前提で、クトゥルフ2010の学生探索者作成手順に従って探索者を製作してください。 また、このシナリオには推奨技能はありません。KPは推奨技能を提示せず、JC作成を見守って下さい。もしこの値は女子中学生らしくないと言う内容であれば、修正を促して下さい。
【セッション概要】
終業式、探索者の通う学校で一人の少女の死が告げられる。しかし衝撃的なその事件は、ただの幕開けに過ぎなかった。 幼い探索者達は変死事件の謎を解き、学校という閉じた世界に蔓延する恐怖から脱出することが出来るだろうか……?
所要時間:5~6時間程度
プレイ人数:2人
推奨技能:なし
難易度:中。JCvs宇宙的恐怖の片鱗なので若干死に易め
あると楽しいもの:お揃いの制服立ち絵とJCの心意気
【シナリオ利用規約】
OK:軽度の改変、ゲーム画面スクリーンショットの投稿、動画利用
NG:二次配布、多数の目に触れる場所でのシナリオのネタバレ、このシナリオ以外でのNPC立ち絵の利用
【導入 7月19日:一日目】
◎Phase day1:終業式
探索者は市立織塚女子中学校に通う、2年b組の生徒である。 今日は終業式、いつも通りに登校した生徒達はチャイムと同時に体育館へ集められ、式が始まるだろう。背の順に整列させられ「静かに」と風紀委員に念を押されたと同時に、探索者は教師陣がどこか深刻そうな面持ちであることに気付いてよい。何かあったのか、只ならぬ雰囲気に首を捻る中、校長が壇上に立ち、マイクを握る。
「皆さんに残念なお知らせがあります。昨夜、2-aの里木宵子さんが亡くなりました」
途端、体育館は中学生達の密やかな驚きで騒めく。え、と声を上げる者や冗談だろうという表情の者、泣き出してしまう生徒なども出るだろう。
探索者は「2-a 里木宵子(さときよいこ)」と同級生である。 アイデア:成功すれば彼女が、品行方正を形にしたと言ってもよい学級委員の手本の様な人間で、学年でもトップを争う成績の持ち主だったことを知っている。同級生の突然の死に、SANチェック1/1d2。またアイデアがクリティカルであれば彼女は探索者の親友だったことになる。その場合はSANチェック1/1d4。
校長は生徒を悼む言葉を告げて壇上を降り、他の教師が連絡事項を読み上げる。彼からは以下の内容が伝えられるだろう。
・給食室に入らない様にという注意、昨日昼前に誰かが入ったらしい
・二十三日に行われる織塚祭の準備への激励
織塚祭とは7月23日の夕方に行われる、この学校でやる夏祭りの様なものだ。吹奏楽の生演奏を交えた演劇部による演劇や、火を焚きながらの地元の神様の供養、外部の屋台が校庭へ出店して来る等、様々な事が行われる行事である。
これらの連絡を終えれば、ざわざわと不穏な雰囲気を残したまま終業式は終わり、生徒は教室へと帰される。
里木宵子の死に関しては深く語られない。しかしもし調べようとしたり教師達の話を聞き耳で盗み聞けば「裏山で転落死したらしいこと」「遺書らしきものを持っていたこと」「死体は犬猫に漁られたのか体が酷く破損していたこと」などの情報を得ることが出来る。SANチェック0/1。
◎Phase day 1:訪問者
夏休みに関しての連絡などが済み教室の掃除が始まると、隣のクラスから生徒が一人訪ねて来る。探索者達はふんわりと緩やかな巻き毛を垂らした彼女が「2-a 金乃井トメ(かねのいとめ)」であり、非常にお金持ちのお嬢様だと知っている。また、アイデアに成功すれば彼女が昨日まで軽い交通事故に遭い一週間ほど休んでいたことも知っている。
彼女は小さな紙袋を手に「杏奈は来ていないかしら」と探索者に尋ねてくる。杏奈、と言うのがクラスメイトの「2-b 釜内杏奈(かまないあんな)」であること、彼女が今日休みであることを探索者は知っているだろう。釜内が休みであることを伝えれば「そう…」と彼女は困ったような表情を浮かべ、探索者が何か聞いても「貴方達には関係無いわ」とその場を去って行く。 釜内は放送委員のクラスメイト。放送の県大会に出る程の実力者で、周りからは「釜内アナ」と呼ばれている。また、アイデアに成功すれば、昨日彼女が早退したことを知っている。
聞き耳:その欠席者、釜内について、近くの席の生徒が噂をしていることに気付く。「釜内さん、行方不明らしいよ」「えぇー、家出とかじゃない?」「かなぁ」
その後、終業式なので授業もなく午前中終了となる。明日からは午前のみの全員参加の補講が始まる。また今日から放課後の時間(13:00〜)は、織塚祭の準備をする様だ。下校時刻は基本16時である。
◎Phase day 1:不穏な放課後
放課後になると早速、織塚祭の準備が始まる。生徒たちは机を少し端に押しやり、真ん中で作業を始めるだろう。 生徒に任されているのは等身大の藁人形を作る仕事だ。握った藁束はしっかりしており、まとめるだけでもかなりの苦労を強いられる。クラス内で手分けして、人形に着せる和服や飾りなどの製作も行われている。周囲の同級生たちは「女子中なのによくこんな肉体労働させるよね~」と溜息を吐いている。
作りかけの藁人形に目星:資料をもとに作成しているが、体つきや装飾を見るに、女性の藁人形の様だ。
アイデア:この藁人形作りは2、3年の仕事なので今年が初めてである。二年生以上が各クラス一つずつ作ることになっている。
作業場に目星:祭りの手順の書かれた紙が置いてある。「三年生の代表が藁人形から少しずつ藁を抜き取り、丸に近い形に束ねて模造刀を突き刺す。突き刺した物を焚いている火にくべ、礼をする」
作業をしていると��中で藁が足りなくなってしまう。それに気付いた風紀委員の「2-b 清木音芽(きよきおとめ)」に頼まれ、探索者達は倉庫に取りに行く事になる。「ごめんちょっと、手が空いてるそこの二人、藁を取りに行ってくれない?」 倉庫は校舎から体育館へ向かう途中の道にあり、普段使わない運動会用の用具などが仕舞われている。もし余り親しくない探索者同士なら、この道中で少し会話をしてもらっても良いだろう。
保健室や家庭科室が並ぶ一階の廊下を歩いていると、出口の付近を何かが歩いている。ふらふらと進んでいるのは人影に見えるが、その体は不自然なほど左右に大きく揺れており、人の様な動きをしていない。それが一瞬こちらを振り返り、じっと探索者達を見つめた。 見つめる人影は釜内杏奈によく似ているが、その顔は赤黒いものに塗れ、額を突き破って角の様なものが生えている。
目星でクリティカルが出ればその爪が異様に伸びており、重々しい雰囲気を纏っていることもわかる。
探索者が立ち竦んでいると、どこかから教師の叱責する様な声が響き渡る。その騒ぎを耳にしたのか釜内(?)は逃げる様に飛び跳ねて倉庫の上に乗り、向こう側へと消えるだろう。一連の不可思議な出来事にSANチェック1/1d4+1。(追跡不可)
この後、もし教室に戻ってしまうならば「藁は?」と剣呑な表情をした清木に手ぶらであることを咎められる。探索者たちはどちらにしろ倉庫へと向かわなければならない。
鬼に動じず直接倉庫へ向かえば、変わった様子は特にない。中には運動会等の行事で使う道具と一緒に、藁が積み上げられている。倉庫に目星を振った場合、壁の一部が目に留まる。そこには何かが剥がされた様な跡があることに気付くだろう。
アイデア1/2:確かここには気味の悪いお札が貼ってあった様な記憶がある。
また倉から藁を取る最中、探索者の一人が壁から突き出ていた古い釘で足、もしくは腕を怪我してしまう。HP-1d2。応急手当をすることは可能だが、このままでは破傷風などの危険がある可能性を説明すること。探索者が保健室の存在を思い出さなければアイデアを振ってもらってもよいし、教室に戻ったあと、怪我を見つけた清木に保健室に行くように促されてもよい。
◎Phase day 1:保健室
足の怪我を手当てしに保健室へ行くと、そこに教師はおらず、代わりに「緑野」と書かれた名札を付けた保険委員長がいる。アイデアに成功すれば、長い黒髪を垂らしどこか妖艶な雰囲気を纏っている彼女が「3-a 緑野黒華(みどりのくろか)」である事を知っている。 彼女は文庫本を読んでいるが、探索者に気付くと「足の怪我かしら、じゃあそこに名前を書いて」と言って保健室の使用者名簿を出して来る。また、もしこの時彼女の読んでいる文庫本に注目するのであれば「火葬の歴史」と言う本であることが分かる。
保健室の使用者名簿は以下の通りである。
《保健室 使用者名簿》
7月15日:2-b 清木音芽 体調不良 早退
7月16日:1-b 田神真美 怪我
7月17日:2-b 清木音芽 体調不良
7月18日:1-a 控江めい 怪我 2-b 釜内杏奈 体調不良 早退
田神真美について「あぁ、ちょっと前に来たあの元気な子ね。膝小僧を両方綺麗に擦りむいていたわ。委員会とかは分からないけど……雰囲気は体育だったわね、実際のところどうなのかしら……?ごめんなさいね、あまり詳しくないの」アイデアに成功すれば、田神が放送委員の一年生で、釜内の後輩であることを知っている。
清木音芽について「最近体調が悪いみたいね。よく来ているわ。通院もしているみたい」
控江めいについて「図書委員の子、だったかしら。この子は手当てしてないけれど、たまに三年の廊下ですれ違うわ」
祭りの事には詳しくないが、何か調べている様だと知れば「レターデスク」について教えて貰える。「部室棟一階の端の廊下に机があるでしょう?あれ、レターデスクっていうの。引き出しに紙を入れておくとカミサマが返事を書いてくれる、なんて言われてる、知らない相手との交換日記みたいなものね。引き出しに何か書いたメモを入れてその机に付箋を貼る、そうしたら次の日くらいには机に丸の書いた自分の付箋が貼られていて、返事の書かれたメモがその引き出しに入っているわ。知らないこととか秘密とかおまじないとか、そこで聞く人が多いみたいよ。カミサマなんているのかしらね」
田神まみを探す、もしくはレターデスクに向かおうとするならば、その途中で清木と鉢合わせる。「ちょっと、どこ行くの!先に仕事よ!」と教室に引き戻されるだろう。 レターデスクを見る事が出来るのは下校時刻の直前となる。(田神は今日は既に帰宅している。)
◎Phase day 1:レターデスク
部室棟の隅にひっそりと置かれている机。引き出しに紙を入れておくとカミサマが返事を書いてくれる、と言われている。返事が欲しい紙を入れた時は机に付箋を貼っておく。引き出しが空の時は付箋を剥いでおく。カミサマからの返事があると、丸印が書かれた付箋が机に貼ってある。自分の付箋に丸の付いている返事しか見てはいけない暗黙のルール。 机に近づけば、丸の付いた付箋が貼られている事に気付く。中を見ると一枚のルーズリーフが入っており、この様なやり取りが書かれている。
「神様へ 遂行への手掛かりを下さい」
「鬼塚祭ヲ中止セヨ」
これらのイベントを終えた所で本日は下校時刻となる。無理やり学校に残ろうとした場合、教師から注意を受け下校させられるだろう。
※レターデスクのイベントが20日以降になる場合は後述。
0 notes
Text
Melting Edge
投稿するたびに久々の掌編。Breathless Breaktimeの契渡と良が、相変わらずの感じです。前作(?)の「出発」「帰宅」の続きなので目を通していただいた方が楽しめるかもしれませんが、これ単体でも特に問題ありません。では以下よりどうぞ。 【Melting Edge】 契渡が具合が悪いと言いだしたのは、ちょうど時計の短針がてっぺんを過ぎた頃だった。テレビから控えめに流れていた誰かの笑い声が不意にぷつりと消え、ちょうど明日提出の課題を終えてパソコンを閉じた良が振り向く。そうすれば否応なしに、テレビを消した張本人と目が合った。 「どうした、契渡。帰るのか?」 契渡が良の部屋で夜を過ごすことが日常茶飯事と化して久しいが、あまりそれを普通だと思うのも気が引けて、良はそう問うた。しかし、そういうことではないらしい。契渡は酷く億劫そうに、首を横に振った。 「違う。ねえ、良……」 「うん?」 「なんか、くらくらするの」 仮に身体が不調を来していたとして、それを契渡が良に、言葉という形で伝えることは極めて稀だった。それは彼が性格上やけに甘え下手だということとも無関係ではないのだろうが、おそらくそれ以前に、彼が人間とは少し、いやかなり違う類の生き物であることに由来していた。 契渡本人曰く、吸息魔というものは身体の感覚と快・不快のつながりが人間よりも薄いらしい。仮に体調を崩して身体がいつものように動かなくても、よっぽどでない限りそれが不快だとは思えないというのだ。だから、その状態を改善しようとか、誰かに伝えようとかする発想もない。たとえば真冬並みの寒さという天気予報を耳にしながら、部屋着にしていた半袖Tシャツ一枚で外出しようとする。寒いと分かっていても、ならばそれを防ごうという思考が、契渡には欠落していた。結果として顔面蒼白になった良が玄関先で慌ててそれを阻止し、必要以上に着膨れさせられた契渡がボクを雪だるまにするつもりかと唇を尖らせたのが、ほんの数日前のこと。 良としてはその思考回路の奇怪さを理解したいとは思っていなかったが、契渡との少しだけ複雑な関係性の都合上、放っておいていいという訳にはいかないだろう。それを抜きにしたって、何事につけ余りにも無防備な恋人――そう呼んでいいのか、未だに少し迷うことがあるけれど――の姿には、どこか胸をくすぐられるところがある。良は元来、世話焼きなのだ。 しかし、ともあれ今は、違った。契渡は確かに、誰に促されるでもなく、良に己の不調を訴えたのだ。眉を落としたその顔は、なぜか良の心をもざわつかせた。 「息が……」 薄く開いた唇から発せられた声が、さっきよりも掠れている。とりあえず横になれ、とベッドへ顎をしゃくって促せば、契渡は大人しく寝転がった。いつもならその雑な指示はなんだなどと煩く口を挟むくせに、こういうときに限って――勿論、こういうときだからこそなのだということは分かってはいた――、見せる従順さは普段の彼からはあまりにもかけ離れていて、良の調子を狂わせる。ざわつきが、酷くなる。 「ええと……吸えよ、いつもみたいにさ」 そう声をかけても、契渡は困惑した表情を崩さないまま、また首を横に振った。シーツの上に、淡い淡い色をした髪が、ぱらぱらと散らばって広がる。 「駄目、吸えない。無理だよ、うまくいかない」 確かに契渡は短い喘ぎを繰り返すばかりで、いつものように息を吸っている様子はない。取ろうとした白い腕は、ずるりと良の手から落ちた。良はベッドに乗り上がって、改めて契渡の姿を見下ろした。 はくはくと浅い呼吸で、眉を顰めて冷や汗をかいて、これ以上は助けを求めることもできずにいた。こうして話をしている間にも、明らかに具合が悪くなっているようだ。蒼ざめた顔で、目だけがこちらに向かって開かれている。何が起こっているのか、理解できていない顔だった。今までに見たことがないくらい、危うげな表情だった。どれくらい長く一緒にいたらそう言えるのか、よくわからないけれど。 「良、ボク、死ぬ?」 唐突にそう問われた瞬間、きっちり一拍分、鼓動が停止した。と思ったら、今度は煩いくらいにばくばくと動き始める。百メートル全速力で走ったときみたいに。きっと胸の上からでも、心臓の形がくっきり見えるだろうというくらいに。 「バカだな、そんなわけないだろ」 絞り出した台詞は、誰よりも自分のための言葉だった。契渡がバカだと思ったのなんて、後にも先にもこの一度だけだった。そして顎を掴んで引いて、力なく開いた唇を、躊躇いなく己のそれで塞いだ。 しかし吐息は、いつものように契渡の体内へと引き込まれはしなかった。まるで風船を膨らませるのに失敗したときのように、唇の合わせ目から、良の吐息が虚しく溢れる。掌を置いた喉が、ひくひくと震えている。契渡の言った通り、彼は吐息を吸うことができなかった。 ああ、どうしようなんて口に出して言ったら、何もかもおしまいになってしまう気がした。でもどうしたらいいのかなんて、分かるはずもなかった。息を与えてやる以外に自分にできることなんて何一つ思い浮かばなくて、ただ所在なさげに投げ出されている白い手に、自分の指を絡めた。契渡の瞳は今や煙って、人形と見紛うようだった。ああ、この眼は見たことがある。あの、寒かった夜に……。 そのときのことなら、今でもまるで昨日のように思い出せる。あの日の契渡はちょうど今みたいに、氷さながらの冷たい肌をしていた。ただ寒さの只中にあったからというだけではなくて、身体の内側から凍りついていたのだ。あのときはそう、この部屋の中で、長い間、たった一人で。何も食べず、何も考えず、ただ"在った"のだ。 ――どうして?どうして、そうなってしまった? あの夜はうやむやにしてしまった疑問が、はたと蘇る。契渡はあのとき、なんて言っていたっけ? 考えて、考えて、その台詞を思い出す。控え目な唇の動きを、ざらついた声を、記憶の底から引っ張り上げる。 《永い間、ずっとずっと目を瞑ってきたものに、今更向き合えない》 そう、契渡は、結局答えを言おうとはしなかった。でも、今なら分かる気がする。お前があの日、最後まで口にしなかったことは……。俺が、気付くべきだったことは……。 「寂しかったのか」 口をついて出たその言葉に、契渡は茫洋と溶けかけていた視線を揺らした。 「契渡、ちゃんと言え。ごまかさずに」 僅かに強くなった声色に、腕の中の身体が縮こまるのが分かる。 「勝手に一人になるな。生きようとしろ。意志を持て」 俺が、ここにいるのに。一人じゃないって、分かってるはずなのに。こんなにも近くにいるのに、どうして、どうして、離れていこうとする? 「お前と出会う前にお前がどんな風に生きてきたか知らないけど、今は、寂しいなんて思うな。今は、一人じゃないんだから」 ぐるぐると渦巻く思考の中で、先んじたのは怒りだった。腕の下で寝転んでいるこの小さな、生き物と言っていいのかすら怪しい存在への同情でも、憐憫でも、なかった。もはや悲哀ですらなかった。こんなに人の心を乱しておきながら、遠くへ遠くへと行ってしまおうとする契渡が、無性に腹立たしく思えた。急にむしゃくしゃして胃がひっくり返りそうになるのを治めようと、良はその手を契渡の髪の中に突っ込み、手荒に撫で始めた。 「一人になるな。俺のことも、一人にするな。誰だって知ってる、一人じゃ生きていけないって……なのに、お前ってヤツは、バカだからそんなことも知らないで、誰にも言わないで、勝手に黙ってるからこんな目に遭うんだ」 ひっくり返す前のホットケーキに浮かんでは消える泡のように、怒りやら不満やらがふつふつと込み上げる。だからそれらを言葉にして、ぶつけてやった。文句があるなら、言ってみればいい。お前が好きにするなら、俺だって好きにする……。ぶつぶつ言っていたら、契渡が不意に、良の手を握る指に力を込めた。 「怖いの」 たった一言、反らせた喉を震わせて出た台詞は、余りにも頼りなくて。それでも、表情を失った顔の中で大きく見開かれた瞳は、確かに良を見ていた。今では凍てついた湖面のようにさざなみ一つ立っていない、静かなそこに映る良は、驚いた顔をしている。その中の口がひとりでに動いて、言葉が溢れた。 「大丈夫、怖くない。ほら、ちゃんと俺がいるから……」 そう告げた瞬間、不意に湖面は波紋に揺れた。未だ映る良の顔を歪めたかと思うと、雫が一粒、目尻から音もなく垂れ落ちる。 「俺がいるから、もう怖くない。寂しくもない。ずっと、一緒にいるから」 良は、もう一度唇を寄せた――今度は契渡の口のではなく、額に。既にぐしゃぐしゃになってしまった髪を掻き上げて、冷たく、滑らかで傷のない、氷のような肌に、ただ触れるだけのキスをした。 キスをして、今度は��しく頭を撫でて、抱き締めて温めてやった。一人じゃないって、嫌でも分かるように。これからずっと、死ぬまで。 「ふふ……」 腕の中で、契渡がかすかに、笑う声がした。 「キミといると、泣き虫になってしまうよ。不本意だけどね」 次の日の朝、二人揃って部屋を出るとき、契渡が不意にぼそりと呟いた。あれからそのまま眠りに落ちてしまった契渡は、目の縁をほんのりと紅く染めていた。 「氷は溶けると、水になるからな」 「なんて?」 「なんでもないよ」 なんでもないことないでしょ、とごねる契渡の尖らせた唇に自分のそれを軽く触れた後で、良はにやりと笑ってみせた。我ながら、悪くない言い回しだと思ったのだ。 *** 数週間後、二人は昼食を学寮のテラスで食べていた。実際のところ食事をしているように見えたのは良だけで、契渡は何もしていないように見えていたのだが、そこで契渡がふと口を開いた。 「……それにしても、この間のあれは何だったんだろう。突然だったし、ああまで具合が悪くなるなんてさ」 契渡はあの夜の体調不良が気にかかっているようで、その後もしばしば話題に出していた。良は二つ目のサンドウィッチの包装を破りながら、何ということもなく言葉を返す。 「何かが変わった。変化した、だから身体が少し、戸惑っただけだろ」 そうは言ったものの、何が変わったわけでもなかった。ただ強いて言うならば、契渡自身を包む空気が変わったように、良には感じられていた。近寄るだけで皮膚を裂くかとすら思われた彼の鋭さは、確かにあの日を境に少しだけ、ほんの少しだけ薄れた。それはたとえばそう、氷を研いで作ったナイフがやがて溶けて、切っ先を丸くするようなもの。でもそんな風に感じているのはきっと自分だけで、それを証明することなんてできはしない。だから、契渡には何も言わなかった。ただ、自分だけが知っていればいい。あからさまに不満げな表情を浮かべている契渡の頭を、良はまた、くしゃくしゃとかき混ぜた。 おしまい。
1 note
·
View note
Text
世界にごめんなさい
あたし達は駅前の安っぽいチェーン店で、ハンバーガーを食べていた。この店は繁華街と通りを一本隔てた場所に建っている。横断歩道を渡れば、そこは猥雑な世界だ。ハイヒールのお姉さんが生足をブリブリ出して闊歩している。男どもが万札ばりばり言わして女を買いにきてる。まるで薄汚い森のようだ。あたし達はそんな大人の事情なんて知りませんよという顔をして、だらだら話をしていたんだ。制服から誇らしげに生やした太腿を、忙しなく組み替えながら。学校をさぼったわけではない。今はれっきとした放課後。ヤンチャが格好いいなんて価値観、もうダサいんだ。
「彼氏とのセックスが良くないんだよねえ」
とアコは言った。あたしは、
「当たり前じゃん」
と相槌をうつ。
「世の中、そういうもんなのだ」と、あたし。
「それでいいのだ」と、アコ。
「西から昇ったお日様が」
「違くて。そういうもんってどういうもんよ。ミイはすぐ煙に巻くような言い方するんだから」
「そういうもんなんだよ。愛に運命があるのと同じように、セックスにも運命があると思うのよね。あたしは二つ同時に当たりを引くなんてこと、まずないと思ってるの」
アコは「あ、そうなの」なんて、分かったような分かっていないような返事をする。仕方がない。アコは彼氏とのセックスの記憶をなぞるので忙しいのだ。あたしはアコに聞く。
「ていうかあんた、彼氏いたっけ?」
「向こうがそう言い張るからもしかして彼氏なのかなって」
「じゃあんたは心の底では、その人のことを彼氏だと思ってないんだ」
「めんどくさー。別にどうでもいいじゃん。彼氏なんてさ、セックスした相手に貼るレッテルよ」
そうね。ほんとそうだわ。あたし達はこの話題をゴミ箱に捨てた。
アコはチープな紙コップからコカコーラを啜っている。席を陣取るために飲み物頼んだのに、それじゃあすぐになくなっちゃうよ。それに見てみろ、このどす黒さ。見るからに不健康な色をしている。あたしは得体の知れない飲み物を美味しそうに啜ってるアコが信じられない。あたしはストローでオレンジジュースを掻き回しながら言う。
「そうして世の中回ってるのね。くるくるくるくる」
「だーかーら、それが分かんないの。全然納得いかないよ」
アコはぶりっと頬を膨らませる。可愛くねえ。
「あーあ、セックスがスーパーマン並に上手い男捕まえて、朝から晩までイかされたい。どっかにいると思うんだよね、そういうバカ野郎が」
「いねーよ」
あたし達はげらげら笑った。
アコは氷が溶けて地獄の釜のようになった紙コップをぐしゃっと握り潰した。あたし達はとっくに冷めてるテリヤキバーガーにかぶりつく。お腹は空いてないんだけど、それとこれとは関係がないんだ。あたし達は性欲のまま行きずりのサラリーマンとセックスするように、物を食べまくる。あたし達は満足するまで食べたいんだ。色んなものを。与えられるものがあったら、全部ぺろっとたいらげたいんだ。
「誰か与えてくれないかな。何かを」
あたしが呟くと、アコが神妙にうなずいた。おっかしいの。バンズの端っこから茶色い汁がこぼれ落ちる。アコはそれを人差し指ですくい上げ、べろっと舐める。
「アコ、あんたその仕草似合ってるよ」
「うそ。あたしエロい?」
「はは。それ、男の前で言えよ」
「そうねえ。確かに」
あたし達はしょっぱい唇をぺろぺろ舐めながら、チェーン店を後にした。
俗っぽい店に行った後は、こんな風景が頭に浮かぶ。ソースまみれの包み紙が、店員の手で無様に捨てられるの。あたしはその光景を思い浮かべると、少し興奮するんだ。それがあたしだったらいい。見知らぬ男のたくましい手で、骨まで丸めこまれて血みどろのまま捨てられたい。
「ねえねえ、あたしちょっとセックスしてくから、ミイ先に帰ってて」
目を離した隙に、アコは見知らぬサラリーマンと腕を組んでわくわくしている。いつもこんな調子だ。あたしは舌を出して言う。
「ばーか。殺されても知らないからな。えんじょこーさい、不倫、殺人事件だ、アホ」
「うわっ。ださー。九十年代的な退廃の香りがぷんぷんするよ」
「バブル崩壊の年ですからね、荒みもします。エヴァンゲリオン然り」
サラリーマンが口を挟む。うるせーお前は黙って七三になっていればいいんだよ。あたしはアコに囁く。
「その男、鞄に包丁忍ばせてるかもよ」
「な、何を言ってるんだ君は。ぼくは根っから真面目で爽やか彼女と妻を大事にする健全にスケベの……」
と、リーマン。うるせーっての。
「ホテル入った途端、後ろからぶすっ。あんたの動脈から血が噴き出るよ。ダブルベッドが血染め。大きな青いゴミ箱、満タンになっちゃうくらいの血液」
「うわあ、そしたらアコ、蝋人形みたいに青白くなっちゃうね。王子様のキスを待つ眠り姫みたい。最高にきれいじゃん。名前が可愛いからラプンツェルでもいいけどぉ」
「こいつはアコがあんまり美しいから、内臓ずるずる啜って、お尻の肉を持ち帰ってホルマリン漬けにして、毎日眺めながらオナニーしちゃうんだから」
「うひひ。何それ。あたしサイコホラー映画のヒロインになれるの? うれしー。ね、こいつのあだ名エド・ゲインにしようよ。3Pしながら羊たちの沈黙見よう?」
アコが背広に皺が寄るほど男の腕を抱きしめるから、サラリーマンはぎょっとして脂汗をかく。あたしはごめん、のポーズをする。
「遠慮しとく。想像したらお腹がもたれてきた」
「あそ。じゃね、ミイ。今日も黙って死ねよ」
「うん、アコも耳噛まれて死ねよ」
眠りって死と似てない? つまり、死ねはおやすみの挨拶。あたし達は毎日こうしてさよならするんだよ。年に何度も生命の終わりがくるのって、いいじゃん。
あたし達は壊れた人形みたいにぶらぶらと手を振りあった。男のよれよれした革靴と、アコの見せかけの純潔じみたピカピカのローファーが立ち去るのを見送りながら、あたしはコインパーキングにだらしなく生えてる雑草になりたいと思った。あーあ、めんどくさ。
兄ちゃんの部屋は男臭い。机にもベッドにも、わけ分からんものが山積み。兄ちゃん、教科書はどこにあんの? 辞書は? 鉛筆は? この人ちゃんと勉強してんのかなあ。山の中から煙草をパクってふかしていたら、兄ちゃんに後ろから蹴り飛ばされた。あたしは盛大にテーブルの角に頭をぶつける。
「いてーっ。死ねっ」
「オマエは二の句に死ね、だ。芸なし。つまんねー女」
「そりゃあんたの前ではつまんねー女だよ。面白さはとっておくんだ」
「知らん男のために? オマエの面白さって使い捨てなんだな」
「そりゃそうよ。言葉や価値観なんてツギハギで使い捨てなのよ。哲学者も心理学者もいっぱいいるんだから、どんな精神論だって替えがきくわよ。少し本読みゃね」
「まー確かに」
兄ちゃん拳骨であたしの後頭部を叩く。あたしはいてっと叫びながら、もっとしてと思う。あたしってヘンタイだ。
あたしってヘンタイだ。兄ちゃんに服を脱がされている。これからセックスするんだ。こういうのって気持ちいいんだよなあ。背徳的ってやつ? 法律なんてどうでもいい。こんなの当たり前だから。近親相姦なんて虐待や売春と同じで、常識という絨毯をめくれば白アリみたいにありふれてんだ。
「ねえ兄ちゃん」
「うるせー集中できないだろ」
頬を叩かれる。わーい、もっとして。
あたしの脱ぎ散らかしたスカートと兄ちゃんの学ランが、床の上で絡まりあっている。靴下の跡がかゆい。兄ちゃんの背中に腕を回す。熱くて湿ってる。何で兄ちゃんの背中はいつも湿っているんだろう? 一つ屋根の下に住んでいるのに、兄ちゃんって分かんないんだ。
兄ちゃんは眉間に皺を寄せてあたしを睨みながら交わる。だからあたしはいつも、兄ちゃんが気持ちいいのかそうでないのか分からなくなる。それでなくてもあたしは時々、観察されている気分になるんだよ。色んな人から標本みたいにね。
あたしは揺すぶられながら兄ちゃんを罵る。
「くず。くず。ばかばかばか。何十人もの彼女がいるのに妹と浮気する男のくず! バカ野郎、嬉しそうに腰ふってんじゃねーよ」
「そういうバカに抱かれて嬉しそうにしてるオマエは何なんだよ。ハツカネズミか。年中発情期か」
まあ性欲強いのは確かなことよ。真昼間の光の中で、あたしの体はよく見えているだろうか。あたしの肋や乳首やお尻のラインが、兄ちゃんの網膜に突き刺さって一生消えなくなればいい。兄ちゃんは制服のネクタイをあたしの首に巻きつけて、顔が鬱血するまでぎりぎり絞めあげる。
「兄ちゃん、こんなので興奮すんの? ヘンタイだね」
「悦んでるのはオマエじゃん」
「分かってらっしゃる」
「死ね、死ね、死ね。黙って死ね、このバカ女」
思いっきり絞め上げるから、あたしはげえげえ喘ぐ。色気も何もあったもんじゃない。けれども兄ちゃんだらだら汗かいてるし、まあいいか。
兄ちゃん、このまま殺してよ。あたしは誰からでもいい、愛されたまま死にたいんだ。目を瞑ってるうちにさ。抱きしめてもらってるうちにさ。あたしは人込みにいても、ぎゅうぎゅうの満員電車に乗っていても、体を冷たい風がひゅうひゅう通り抜けていくみたいなんだ。あたしの周りには常に小さな隙き間があって、それが疾風を呼び寄せる。
あたしは兄ちゃんの耳に頬を寄せて呟く。
「兄ちゃんも寂しい?」
「だからしたくねえやつとセックスしてんだよ」
ああ、兄ちゃん大好き。兄ちゃんの寂しさに包丁を突き立てて抉ってあげたい。兄ちゃんとあたしはキスして殴り合ってぶつかり合って静かにイきました。笑えます。
した後の朝日はだるい、ってどっかの歌人が詠んでたよ。あたしはセックスした後に朝日なんて見たことないな。だってするのってだいたい誰かのアパートかラブホテルか兄ちゃんの部屋だからさあ。アパートかホテルだったとしたら、さっさと家に帰ってだらだらして寝ちゃうからさあ。兄ちゃんと致す時は大抵お昼だしね。した後にピロートーク、そんな愛が詰まったお泊まりはしたことないんだ。
「愛なんていらねーよ」
ガン、また兄ちゃんからぶたれる。あたしは悦んでにこにこ笑いながら、心底、
「いらねーね」
と言う。あたしと兄ちゃんはこういうところで血が繋がっているんだなあ。神様いらんことしい。
兄ちゃんは毛布に包まって、まるで芋虫みたい。あたしはぐったりソファーに落ち着いている。お昼からどろどろに絡まり合うのって、気持ちのいいものなのよ。
明るい光に照らされて、身体中顕になるとあたしは、もう誤魔化しがきかないと思っちゃうんだ。あたしは紙の上のテリヤキバーガーで、色んなところから汁垂れ流しながら誰かに食べられる。兄ちゃんはあたしの肩を齧って歯型をつけるけれど、あたしは、そうされていると訳が分からなくなるんだ。あたしの腹に収納された小腸がもぞもぞもぞもぞ蠢き出すからさあ。
あたしは己の心の構造を突っつき回す度、いても立ってもいられなくなるんだ。あたしの心臓には歯がついていて、触れる人あらば噛みつこ��とする。いつだってかっちかっちと牙が鳴る音が、胸のあたりから聞こえてくる。兄ちゃんもあたしの胸に頭を乗せて聞いてみてよ。
兄ちゃんはあたしが腕を突っついても振り向いてくれない。分かっている。つれない男だ。あたしはセックスした相手が思い通りにならないことにイライラして、こいつの気を引くのを諦める。
そうこうしてるうちに凶暴な心臓はどんどん歯を鳴らし始め、犬歯が刃になって、舌が三十センチも伸びた。あたしの心臓は下品な獣のように、舌をべろべろ出しながら涎を垂れ流している。全身がわなわな震えだす。あたしはたまらず兄ちゃんの腕にしがみつく。
寂しい。寂しい。兄ちゃん。寂しいよ。
こういう時だけ兄ちゃんは優しくて頭を撫でてくれるけれど、しばらくすると煙草吸いにどっか行く。突然放り出されたあたしの両腕、ドチンと地面に落ちる。
あたしは汗も流さずに外に出た。セックスしてる間にアコから連絡が来てた。やり終わったから踊ろうって。アマチュアかプロか分からない人がイキってる、クラブという煙たい場所で。あたし達は繁華街で合流する。アコがつまらなそうに言う。
「なーんだ。まだ生きてたの?」
あたしもやり返す。
「あんたこそ。この死に損ないっ」
虫食いだらけの街路樹が、あたしの肩に葉を落とす。やだ、全然しゃれてないんだな。そもそもこいつら、兵士みたいでいけすかないんだ。どこぞのエラい建築家が、景観がどうのとうそぶいて植えたけれど、夏になれば虫食いで茶色くなるし、秋になれば銀杏が臭う。冬は落ち葉の大洪水だ。だからおせっかいな市の職員が、定期的に丸ハゲにしちゃう。その結果みっともなくぽちょぽちょと葉がついているだけなので、景観を整えるという前提そのものがどこかにいっちまってる。この辺に巣食う太った芋虫、見捨てられた街路樹を食いつくしてよ。食いつくしたらパワーアップして、ビルの鉄骨も食べつくして、モスラになって飛んでってしまえ。
あたしの思考の如くもつれた電線を見上げながら歩いてたら、アコがぺちゃくちゃ喋りだした。
「またミイ、兄ちゃんとセックスしたんだね。残り香で分かるよ」
「んー」
あの電線が切れた���いいのに。あたし、それを噛んで感電死したい。山田かまちみたいにかっこよく死にたい。アーティスティックに死ねる人こそ、真の芸術家。
「ね、ミイ。さっきのサラリーマンとのセックスだけどね。気持ちよかったけど気持ちよくなかった」
「どゆこと?」
「分かんない。あのさあセックスって、してる間は相手のこと凄く好きだって思うけど、終わるとサーッと冷めるよね」
「あんたは男か」
「そうだったらよかったなあ。だって簡単じゃん。終わったら何もかもスカッと忘れてさ、どこへだって行けちゃうんだよ。あたしたちって穴ポコだから、洞窟に潜むナメクジみたいにうじうじするしかないじゃん。それに愛液とひだの形がそこはかとなくあの虫と似てるし」
「ははは。ばーか」
信号が凶暴な赤を点滅させ始めたので、あたし達は青を待つ。あたしは横断歩道のサイケな白黒が、シマウマを連想させるから好きなんだ。あたし達もシマウマと同じだから。孤独という猛獣から逃れるために、制服を着て普通の女の子のふりをして、コンクリートジャングルに溶け込もうとしている。保護色を必要としているから、同じ。
信号待ちの間、あたしもアコも横目で男を品定めしていた。そいつらの顔見るだけであたし、セックスしてるところを想像しちゃうんだ。どういう強さであたしのこと押さえつけるのかな、とか。アコも絶対そうだよ。
「あたし生まれ変わったらかっこいい男になる。地上にいる全ての女の子とやりまくって、無様に捨ててやるんだ」
お、それいいね、と振り向く。アコは魔法みたいにどこからか取り出したリップを唇に塗りたくっていた。その赤いいな。思いっきり下品で。
どうしてクラブの壁ってどこもマットな黒なんだろう。病院みたいな白でもいいじゃんかねえ。ま、見た目がどうであろうが、豚骨ラーメン屋に似た油の臭いがしてようが、何もかもふっとばしてくれる爆音が鳴ってればそれでいいよ。そうでしょ?
パッと見何人か分からないオーナーは、いつもあたし達に酒を奢ってくれる。この人絶対あたし達が高校生だと知ってるよな。いいんだけどね。あたし達はこっそり二人でトイレに篭って、コップの中身を便器にぶちまける。おしっこみたいに流されてゆくビールを見ながら、ざまあみろってケタケタ笑う。余計な優しさなんてクソったれだ。壊すのって面白い。それが大事なものほどね。
あたし達は踊り狂う。踊り狂う。発情モードに入った男がグラマーな女の尻を眺め回している。ああいいな。あたしもあの男に見つめられたいな。あたしは常に誰かに恋される人間になりたくなっちゃうんだ。誰もが愛する理想の女になりたい。セックスの相手が変わる度、あたしの体も変形するのならよかったのにな。あたし、そういうラブドールならよかった。
スピーカーから音の水を浴びながら、あたし達は狂ったように笑う。何もかもどーってことないみたいに。どーってことないんだけどさ。深刻な悩みがあるわけじゃないし。ミラーボール以外は床も壁も黒だ。黒、黒、黒。あたし達の制服がくっきりと浮かびあがる。あたしこのまま、光になって消えちゃいたい。
あたしが寂しがる、消えたがる、殺されたがる理由なら、シンリガクの本読みゃ理解できるんじゃないかな。だいたいの本には親が原因って書いてるよ。そうでなけりゃ肛門がどうとか。昔の人もたいがいスケベだよねえ。髭生やした爺ちゃんが赤ちゃんの下半身にばっかり注目して。そんなのってどうでもいい。いっそあたし達、下半身だけの化け物になっちゃえばいいんじゃない?
アコがふざけてあたしの腹をぶった。あたしもぶちかえす。アコは言う。
「ねえ、こないだあたしの彼氏貸したじゃん。どうだった?気持ちよかった?」
「それって今の彼氏? それとも前の? それとも前の前の……」
「えーと、分かんなくなっちゃった。いっか。誰だって同じだし」
「やっぱあたしら気が合うな」
ヘドバンしてると頭に脳内物質が溢れて、ボルチオ突かれるより気持ちよくなれるんだ。クソみたいな曲でも、そうしちゃえばどれも同じだよ。あたしもあなたも恋も愛も、爆弾で吹っ飛ばして塵にしてやる。
「アコ、あたしの彼氏はどうだった?」
「どうだったろ。ていうかどれだっけ」
「どれ」だって。笑える。
「ミイ。あたし達も数々の男に『どれ』って呼ばれてるのかな?」
「女子高生A、Bみたいに?」
「そうそう」
「そうだったらいいね。あたし、そうなりたいなあ」
「あたしも。あたし達、消えちゃいたいね」
「うん。消えて、きれいな思い出になりたい」
「天気のいい日だけきらきらして見えるハウスダストみたいにね」
「普段は濁っているのに、台風の後だけ半透明になる川の水みたいに」
「あたし、雫くんになりたい。知ってる? 絵本だよ。雫くんがさ、川に流されて海に到着して蒸発して、また雨になるの」
「それって話が違くなってない?」
「あ、そう?」
あたし達は全然センチメンタルじゃないダブステに貫かれながら手を繫いだ。アコの手のひらだけがあったかい。
あたし達はフライヤーをハリセンのように折り曲げ、互いの頭をはたきながら帰った。夜のネオンっていいよね。泣いてる時に見える風景みたいに潤んでてさ。ネオンを見ながらしみじみしてると、ひょっとしたらあたしも純情な女子高生なんじゃって思えてくるんだ。肩書き的には正真正銘の女子高生なんだけど、すれっからしだから、あたし達は。アコはにかっと笑い、尖った八重歯を両手の親指で押した。
「あたし、死んでもいいくらい好きな人ができたら、八重歯をペンチで引っこ抜いてプレゼントしたいな。世界一大好きな人に抜歯した箇所の神経ぺろぺろ舐めてほしい」
システマチックな街灯の光が、アコの横顔を照らしている。彼女はぼやっと言った。
「あたし愛されたいんだ。本当はね。それなのになぜか行きずりの人と寝ちゃうんだよねえ。あたし好きな人ができても、隣に男の人いたらエッチしちゃうんだろうなあ」
「別にそんなこと考えなくてもよくない? 無意味だよ。してる間、気持ちよければいいじゃん。黙ってりゃ誰も傷つかないし」
「んーまあそうなんだけど。あたし時々ね、どっちなのか分かんなくなるんだ。エッチして自分を悦ばせているのか、傷つけているのかがさ」
「大丈夫だよ。誰もアコのことなんかそこまで気にしてないから」
アコは子犬みたいな目であたしを見た。あ、地雷踏んだかも。アコがチワワのようにぷるぷる震えだしたので、あたしは彼女をそっと抱き寄せ、おでこを優しく撫でてあげた。
「ごめんね。あたしだけだよ。アコの気持ちを知ってるの。あたしだけがアコを見守ってあげるね。きれいだって思ってあげるね。アコが何人もの男から忘れられようとも、あたしは覚えててあげる。あたしに八重歯くれたら、あんたの望み通り神経舐めつくしてあげるよ」
「ほんと?」
アコはあたしの胸に頭をすり寄せてくる。この子を絶対に不感症のロボットなんかにさせないんだから。あたしはありったけの体温でアコを包み込む。この子が気持ち良さそうに目を細めてくれたらいい。そしたらあたし久々に、幸せってやつを味わうことができるから。
「あたしねえ、アコとセックスしたいな」
「あたしもミイとセックスしたい」
「しよっか」
「いえーい」
わはは、なんて簡単なんだろう。
「あたし、ミイを愛してる」
あたしはうんと返事をしようとして、黙った。愛がどういうものなのか分からなかったから。
ラブホテルのベッドでアコの体を舐めながら、色白いなあ、と思う。
「ミイ女の子とするの初めて? あたしは初めて」
「ふーん」
いつもスマホに貼り付いてる親指をがじがじ齧る。あ、ここだけ爪のびてる。
「ミイはどういうの好みなの?」
「どういうのって?」
「体位とか」
「うーん、何だろ、分かんない」
「兄ちゃんとしてる時ってどんな感じ?」
「あたしが上に乗るの」
「へえー、意外」
「意外もクソもある?」
「分かんないけどさ」
アコの耳を齧る。皮膚が歯茎に気持ちいい。アコは、あんた歯が痒い犬みたいだねえ、なんて言ってる。あんたも一度人を噛んでみろ。あたしがアコの胸をむにむにしていると、彼女はまた喋りだす。あたしの涎が潤滑油になってんのか、この子の口はさあ。
「兄ちゃん、あんたにどんなことするの?」
「スリッパでぶつよ」
「えっ」
「枕で窒息死させようとしてくる」
「それって気持ちいいの?」
「どうでもいいの。されてる間はさ。どうでもいい方が気持ちいいんだ」
「ミイが自分を粗末にするのって、近親相姦してることに罪悪感があるから?」
「何フロイトみたいなこと言ってんの。あたし、そういうのって嫌いなんだ。中学生の頃に腐るほど心理学の本読んだけど、読めば読むほどあたしを狂わせた原因が憎らしくなってくるからさ」
「えっ、憎らしくなるように書かれてんじゃないの、ああいう本って」
「マジ?」
「マジマジ。きっと昔の人はあたし達に親殺しさせようと思ってあの本書いてんだよ」
「それマジかもねえ、だったら面白いし」
「きゃはきゃは」
あー、くだらねえ。
「ねえねえ、じゃあやってみてよ。あたしの首、絞めてみて」
あたしは自分がアコの言葉にぎょっとしたことに気がついて、奇妙な気持ちになった。ああ、あたしってまだぎょっとするんだなあ。色んなセックスしててもさ。あたしは目をきらきらさせてるアコが無償に「愛おしく」なっちゃったりして、彼女の胸に顔を押し付けた。
「アコにはできないよ」
彼女はあたしの珍しく真面目で優しい声に目を丸くした。
「どおして?」
「うーん」
「あんた誰にでも残酷なことしそうなのにね」
「そうなんだけどねえ」
「どうしてあたしにはしてくれないの? あたしとするのが気持ちよくないとか? それともあたしが嫌いなの?」
アコは、嫌いにならないで、と泣きそうになる。ああ、そうじゃない。今この瞬間、彼女と一つになれたらいい。物理的に一つになって、ぐちゃぐちゃになって、疲れ果てるまで喚きあいたい。ああ、あたし男だったらよかったのに。そしたらアコのこと、一時しのぎでも悦ばせてあげられたのに。今ほどこう思うことってないよ。あたしはとりあえずデタラメな文句パテにして、二人の隙き間を埋める。
「だってアコの肌ってふわふわしててきれいだからさ。傷つけたくないんだもん」
「それを言ったらミイだって、殴られたりしてるわりに肌きれいじゃん。だからあたしの首を絞めても大丈夫だよ」
「嫌」
「どうして?」
あたしはアコをぎゅっと抱きしめた。そうすることしかできなかった。
「ミイがあたしの超絶技巧スーパーマンになってよ」きゃはきゃは。
まだ言ってるこいつ。バカだなあ。
これを愛と呼ぶのかどうなのか。あたし、世に蔓延るほとんどの概念が嫌いだけど、「愛」は殊更に嫌いなんだ。だって得体が知れないんだもの。
あたしは感情ってやつが嫌い。思考ってやつも嫌い。人間が地球にのさばる繁殖菌であるのなら、知能なんかなければよかったんだ。子供を作る行為をするために些細なことに頭を悩ませるなんて、全く時間の無駄すぎるよ。それが人間のいいところなんてセリフ、よく言えたもんだ。人間は動物達を見下す限り、地球に優しくなんてなれない。本来の優しさは無駄がなく、システマチックなものなんだ。
そうでしょ? 兄ちゃん。
「うわ、指先紫になってる。いい感じに動脈つかまえたかも」
手首に巻かれた紙紐が食い込んで痛いけど、それがまた興奮するんだなあ。兄ちゃんガンガン口の中で動かすから、思わずえずきそうになる。ここでゲロ吐いたらどんなに気持ちいいかしら。兄ちゃんは咳き込むあたしを足で踏み付けて、死ね、死ね、シネって怒鳴る。あたしは毛だらけの兄ちゃんの足首に縋り付く。
「兄ちゃん。殺して。今すぐ包丁持ってきてあたしを殺して」
「はいはい」
兄ちゃんは白けた目であたしをいなす。彼の瞳から放たれるレーザービームで粉々になりたいわ、あたし。
「兄ちゃん。あたしの心臓どうにかして。兄ちゃんがこいつを握り潰してくれたら、あたし、あたし」
あたしの喉がひいっと鳴いた。あたしはバーガーソースみたいな涙を滴らせながらズルズル泣いた。兄ちゃんが濡れた頬をぺろぺろ舐めてくれたので、あたしは少し嬉しくなった。
兄ちゃんは今に包丁を持ってくる。兄ちゃんも本心では死にたいんでしょ? 知ってるんだから。二人で汗だくになって死のうよ。それであたしを、あたしだけのものにして。
あたしは愛という建前に摩耗しないため、行きずりの男に抱かれる自分が嫌いなんだ。あたしは愛を忘れたいんだ。忘れたらもう苦しまなくてすむもん。兄ちゃん、アコ、あたしは、あたしのこの心臓は、いつか満たされる日がくるのかなあ。たくさんの人とセックスしたら、寂しくなくなる日がくるのかなあ。誰かを愛しいと思える日がくるのかなあ。キスをしたら少し楽になれるから、誰彼構わずキスをねだることも、それで長く続いた友情をぶち壊すことも、先生から不倫を強要されることもなくなるのかなあ。
あたしの皮膚は涙と一緒にズルズル溶け落ちてゆく。兄ちゃんが思いも寄らぬ優しさであたしを抱きしめて「泣くな」なんて言うから、あたしはますます感動してしまう。けれどその昂りもすぐ「ばからしー」に冷まされる。お願い兄ちゃん、早く包丁、としゃくりあげながら、あたしはこのまま永遠に彼に頭を撫でられていたいと思った。
兄ちゃん、煙草吸いに行かないで。ずっとあたしの傍にいて。
けれど兄ちゃん煙草吸いにきっとどっか行く。
0 notes
Text
漫画のもと♯1「沈んだエンター」
公開しておく。プロットと思ったら小説になった今描きたい漫画の一話目。
第一話「沈んだエンター」
音量だけは申し分ない、薄っぺらな演奏が部屋を満たしている。メロディこそないが、あまりにも耳慣れた曲であるため、大して鳴らない口笛を吹きながら体を揺らす。おっと、アイラインはずれるといけない。
「例えばさ、そのとき付き合ってる人のことを歌った曲が大ヒットするじゃん。ライブで歌ってほしい曲ナンバーワンになったり、歌番組に出るときの十八番になったりする。でも実は別れてて思い出したくもありません! みたいな関係性にもうなっちゃってたとき、どんな気持ちで歌えるんだろうね?」
少し間があった後で、目を閉じたままの彼女は小さく笑った。
「……面白いこと言うね」
「あっ、これで最後だから目開けないで。こんなにラブラブなのに我に返る時がさ! 来るんだよ、実際この歌手も浮気されて離婚してんじゃん」
「そうなの?」
本来の目的以外のために使われているカラオケボックスの個室には、��子高生が二人。テーブルには使いっぱなしの化粧道具��いくつも転がり、それらの装飾部分を天井のミラーボールが機嫌よく照らし、まるで魔法の道具のように見える。化粧を施す佳奈子の眼の端では、頑丈そうな黒い細長い箱が存在感を主張している。
「ごめんね、土曜なのに呼び出して」
「ちょうどお互い課外あったし、気にするなって」
ちょっとミスったかも。カラオケの個室は外気よりずっと暖かくて、ちょっと暑すぎるくらいで佳奈子のむきだしの膝は喜んだけれど、橙色の照明と肌の上をちらちら通るミラーボールの光の中色を選んでは、太陽光の中で見たときに印象が変わってしまうかもしれない。まとい(・・・)を送り出す直前にトイレの白い照明でも確認しないとならないな、と思う。二人の通う高校の最寄り駅のトイレやフードコートで同じことをしてもよかったのだが、まといがあまりにも大荷物かつ着込んでいたので、なんとなくはばかられたのである。佳奈子は、最近動画で見たのと同じように、ベースの色を載せてから深いワイン色のアイシャドウをぼかし、少しだけモスグリーンを目尻に置いた。派手すぎないアクセントカラーが、まといの猫目を引き立ててくれると信じながら、さりげなく、慎重に。
「……まだ経験したことないからわかんないなあ」
「うん、もう一回言って?」
独り言のようなその言葉に反応が遅れた。
「佳奈子ちゃんのさっきの。わたしには大事な人がいた経験がないからわからない。けど、その瞬間瞬間の気持ちに正直な表現の方がずっと美しいと思うから」
脈絡がないようで、しかし先ほどの佳奈子の発言を踏まえた、まといの意見らしかった。
「どういうこと?」
「だってきっと、嫌でしょう。いつまで持つかな~この恋人と、って思いながら作る曲なんてかっこうよくないじゃない。聞き手も恋人も」
まといは変人だ。
*
今日がこんなことになっているのは、佳奈子がまといへ話しかけたことがきっかけである。もっとも、とっさに振り返り声をかけてしまうほどの強めの眼力を背後から飛ばしていたまといのせいである、と言い換えたい。修了式を行う体育館へ移動するにも前クラスの着席に時間がかかっているらしく、学年で最もケツ(・・)の一年H組は、長いこと廊下で出席番号順に整列させられていた。もとより苦手な人などいない佳奈子であったが、その日はやや精神が不安定な自分を察知し、イヤホンをして動画を観ることで、人とのつながりを遮断し、この後のクラスでの打ち上げやお別れムードに向けてエネルギーを備蓄していたのであった。
とはいえ、話しかけられるよりも視線のほうが協力で無視しがたい圧があることを、佳奈子は初めて知った。目算で一五センチほど佳奈子より上背のあるまといが、佳奈子のつむじのさらに奥を上からのぞき込もうとすれば、まず影になる。無礼にならないよう配慮しているのか、見たり見なかったり、やっぱり気になるのか見たり…とかかる影がゆらゆらと揺れればそちらの方が気になるものである。イヤホンを外し、やや怪訝な気持ちで振り向くと、出席番号が一つ後ろのまといがピクリと肩を揺らした。
「まといちゃん、どうかした?」
おいおい佳奈子を気にしていたのはそちらでしょう、視線を泳がせて言葉を発しないまといを佳奈子はじっと待ってみた。そしておもむろに発した言葉。
「佳奈子ちゃん、お化粧できる……?」
*
最後にかかったのは、長いこと人気曲ランキング上位のアニメソングだ。サビ前の激しいベース音が心地いいが、曲の盛り上がりにかき消されないように声を張る。
「まといちゃんさあ、正直こんな綺麗にして行くものじゃなくない? 老人ホームでしょ」
「いやいや。きっと喜んでくれるよ~、やっぱり非日常を感じられる方が気分も晴れるんじゃないかなあ」
どうやらまといは、ときどきボランティアでギター演奏を披露しているらしく、それは一年間出席番号が前後である仲だったにも関わらずずっと知らなかったことだった。まといと仲のいいクラスの子がそのことを知っているのかも定かではない。クラスでも、背筋の伸びた長身というだけで存在感はあった。ギターも似合うだろうなあと思う。クラスに中学からの友達が多かったのもあり、出席番号をきっかけに仲のいい子をつくらなかった佳奈子は、それが少々悔やまれるなあと思った。
数日前に佳奈子に化粧を頼んだまといが、いざ今日二人きりになると佳奈子より気まずそうにするものだからと、始めにBGMとしてデンモクの月間ラン���ングから適当に入れた。その五曲が流れ終わるのと同時に、濃い目に紅を引き、まといのメイクアップは無事完了した。
「できたよ。うわっ、我ながらいいんじゃない。まといちゃんって化粧映えする顔してるもんねえ。普段の自分のメイクより三倍くらいやりがいを感じましたね…。一応、まといちゃんがここ出るとき変じゃないかトイレで確認させて」
ほら、と手鏡を手渡すとこちらに向かって、まといがわかりやすく笑顔になる。佳奈子は息をのんだ。人を敬遠しているような普段の釣り目が垂れて、敵意をまるで感じさせないほどの柔らかく笑んだ。じっと見つめたまま動かず、佳奈子の耳には液晶の中でインタビューされるアーティストの声が徐々に聞こえてきた。まといほどじゃないけれど、佳奈子も少しのあいだ見惚れていたようだ。まといは唇を震わせて、目がうるんで、えっ、泣いちゃうの?
「すごい…きれい。生まれ変わったみたい。ありがとう」
そうつぶやいたきりいまだ自分の顔を見て恍惚とするまといが現実へ戻って来ないので、佳奈子はナルシストの語源となる神話なんかを思い出していた。自分の美しさに見惚れてもっと自分の映る川だか海だかの水面に近づこうと飛び込み死んでしまうナルキッソス。こんなに美しかったら、自分の映る水の中に飛び込んでしまうのも仕方ないよなあなどとぼんやり考えた。まといはついぞ泣かなかったけれど、その喜びように、じわじわと達成感が押し寄せてきて、まといに正面から抱き着いた。ひぃと引き笑いの途中のような声を上げ、まといが体を強張らせる。どうやら現実に戻ってきたらしい。よかった。佳奈子はさらに、まといにハイタッチを求める。
「そんなに喜んでもらえて光栄だなあ。わたし、メイクアップアーティストになるしかないなこれは! 素材がいいって最高だな……こちらこそ、カラオケ代払ってもらっちゃうし」
まといのここを発つ時間が迫るので、やりっぱなし状態の化粧品をポーチに戻す。
「佳奈子ちゃんはこのあともヒトカラしてくよね」
うんと頷くと、まといは学生二人・休日二時間分の料金を伝票の上に載せた。学生の分際でお金でのお礼はいやらしいぞ、と思いながらも対価なのでときかなかった。フワフワしているように見えて、そういうところはしっかりしているんだなあ、とやや失礼なことを思う。春の近づきを感じさせる若草色のハイネックリブニットとスキニージーンズは細身な体型を引き出しているし、佳奈子の淡いグレーのロングカーディガンは動きやすく、まといの演奏を邪魔しないだろう。残念なことに、長身のまといが着るとそれは膝上そこそこの丈になってしまったが。袖もやや短めに見えるが、不自然なほどではない。そもそもそれまでまともな私腹を持っていなかったらしいまといは、そんなことを一ミリも考えている様子はなかった。
「あ、じゃあ、また明日ね! いやその前に明日も課外あるよね?」
本当に言いたいことを口に出すか悩みながらも、佳奈子は別れを告げた。蛍光灯下での見え方の確認がてらカラオケ店の出口まで見送ると、ギターケースを下げたまといが振り向いた。
「行ってきます」
まといは変人だ。そして、まといは美しい。
「本当に言いたいこと」について、解決するのはすぐ翌日だった。すでに数人が教室にいるのに誰も電気をつけようとしないものだから、誰もつけないのかよ怖いなあ、ありがとう佳奈子様、などと軽口を応酬しながらボタンに近づくと、背後にたった今登校してきたまといがいた。思わずのけぞり、距離をとる。他の人の視線も痛い。自習を邪魔してごめん。
「まといちゃんせめて近づいてくるときに声かけて、びっくりするから!」
「おはよう」
「え、無視」
昨日二人でハグしたことも忘れたような距離感がなんとなく悲しいが、無言のまといが差し出す紙袋をのぞくと、貸していたカーディガンと一緒に、チラシが入っていた。黄色の蛍光ペンで、一か所だけ線が引いてある。
「これ何のチラシ?」
「服まで選んでくれて、すごいいっぱい声かけられた、から」
「それはわたしも楽しかったしいいよ」
ワンターンの会話では質問へ回答は貰えないらしい。仕方ないのでまといのペースに乗ることにする。
「来週の宣伝。お礼には足りないけど……合唱サークルの伴奏したあとで歌う時間貰えたから」
佳奈子は目を見開いた。頬の血色が良くなるのがわかる。
「本当⁉ わたし行っていいの」
「いいよ。でも人にはあまり言わないでね」
わたしもどんな歌を歌うのか興味があったの、とニヤニヤが止まらないまままといの手を握り締めると、人に言わないでって言ったんだけど、聞いてた? と訊かれるものだから、佳奈子はそれまといちゃんが言うの? 返した。昨日はカラオケに行ったにもかかわらずまといの歌声がどんなものか聴けなかったから、好奇心があったのだ。ギターを持っているというだけで、化粧をしているだけでさらに見栄えするまとい。どんなものでもいいから、聴いてみたかった。嬉しさの余り抱こうとしたまといの肩は高すぎて届かず、まといの膝がかくんと折らせることになった。まきかなこぉ、とにぎやかな集団の気配がしたので、「楽しみにしてる」と一言残し、佳奈子はまといのもとを去った。その集団に向けて、佳奈子はフルネームを呼び返した。
人の賑わいを見ているとわくわくしてしまう。今日だって、近隣の他県からもそこそこ集まるマラソン大会の裏側で、様々なパフォーマンスやら出店やらで、子どもから老人まで楽しそうな声が聞こえてくる。肌寒さはあるけれど、春始まりの空は大変に澄んでいて気持ちがいい。マラソン日和だ。肺にその冷たい空気をいっぱい吸い込む。
段の高さが低く幅の広い階段は屋外ステージのほうを向いており、十時のおやつかマラソン完走後のご褒美か、腰を下ろしてほおばる人の数は二クラス分ほどいそうだ。結構大きい舞台じゃないか、と思いながらまといの出番を待機していると、聞き覚えのあるゲラゲラ笑う声が聞こえた。振り向くと、指をさされている。
「まきかなこじゃん、何してんの」
「あらおはよ! 何って出待ちよ。早映と心愛はなんでいるの」
「早映が昨日うち泊まってたから、家からここに遅い朝ごはん食べにきた」
「そういえば実家この辺だっけね」
「それにしても佳奈子、めちゃくちゃ楽しんでるじゃん」
「そりゃ人生楽しむ天才だからね、わたしは」
防寒対策にレジャーシート、みたらし団子とのり団子、片手には甘酒。我が子の発表を待つ父兄にも勝るほどに準備万端、今日を楽しむ準備はばっちりである。楽しんでいるのは、もちろん佳奈子も例外ではないのであった。
今日はまといに化粧を断られてしまった。今日のまといの役割は合唱隊の伴奏がメインなので、目立ちすぎず、いつも通りでいいらしい。
「で、佳奈子はなに目当て?」
チラシを確認する。
「えっとね、カンレキーズの合唱……?」
「渋いな」
「身内出るのか」
「ネーミングセンスがない団体だな」
好き放題言われているのを流しながら、まといに言われたことを思い出す。人には言わないようにと念を押されたが、掲載されているのは合唱サークル名のみだ。まといの名前はなかったので、ばらしても問題はないということにしておこう。
「あっ、きたきた!」
幼稚園児たちのダンス発表が終わり、次のステージには平均年齢のぐんと上がり、おばさまとおじさまが十人ほどだ。そして間隔をあけて後に続くのはまぎれもなく、まといだ。ギターを抱えている。
――カンレキーズです! よろしくお願いします。毎年このステージには上がらせてもらってるんですが、今年も楽しみにしてきました――
はらはらするところの一切ない貫禄のあるMCの中、まといは用意されたパイプ椅子に静かに座った。大人たちと同じ白いブラウスに、浅葱色のギャザースカートを履いたまといは、自分の存在感を大人たちと違うところに移そうとしているように見えた。ブラウスの下は各自の私物なのか、派手な大判の花柄のスカートや、明度の高いパンツが多く、めいめいが目立つことを楽しんでいるふうだ。
――今回披露するのはジブリメドレーです。ギターの音に乗せて、ぜひお楽しみください――
ふいにスポットを当てられたまといは、わずかにびくっとしたようだったが、指揮者に合わせて優しく弦をなぜるように弾き始めた。まといはギターが上手かった。なるほどメンバーはなかなかのベテランらしい、ぴたりと重なり合うハーモニーに、一方まといも、
それを邪魔しないよう徹底した細やかで穏やかな演奏だった。
箒やお面などの小道具、軽やかなステップも最後までそろったひたすらに楽しい時間に、観客から放たれた拍手は盛大なものだった。
「すっごいねえ……」
ため息とともにつかれた佳奈子の言葉に、早映と心愛は「ガチ恋みたいだね」と絡もうとしたが、やめた。佳奈子ももれなく心を動かされ、放心状態だった。すごい。彼女は生み出せる人間だ。自らが生み出したもので人を幸せにできる人間だ。まといは部活にも入っていなかったから、普段どんなことをして過ごしているのか想像がつかなかったし、特に想像してもこなかった。佳奈子は自分が一番輝いているという自負が揺るがない、幸福な人間でもあった。世界が広がるような気持ちだった。
感動はまといの言葉を忘れかけるほどで、そろそろ行こうか、このあと遊ぼうと佳奈子の腕を引き立たせようとする二人の友人に反応しようとするが、引っかかるものがある。まといはなんて言ってたっけ。
――盛大な拍手、ありがとうございます。最後に、今回伴奏をしてくれたまといちゃんにバトンタッチして、終わろうと思います――
「そうじゃん! 待って、わたしこれ最後まで聴かなきゃ」
――このサークルの平均年齢をがくっと下げてくれているのが、まといちゃんですからね。いつも素敵な伴奏をしてくれるんですが、今日は彼女の作った曲を皆さんにも聴いていただけたらと思います――
慌ててもといた場所にしゃがみ直した。ステージに一人にされるまとい。あの変人は大丈夫か。佳奈子の心配をよそに、まといは安定した声であいさつをした。
「このような機会を貰えて嬉しいです。よろしくお願いします」
今日はポニーテールだった。毛束が丸い頭をするりと滑って前にくるほど、深々と礼をして椅子に腰かける。
「あれ、うちのクラスの的井さんじゃない?」
「えっまじか、ギター弾くんだ」
早映と心愛の気づきに構うはずもなく、まといは息を吸い込んだ。佳奈子は手に汗を握った。平坦で温かみの残った声だった。
「沈んだエンター」
喝采の中で、佳奈子は誰よりも拍手した。
0 notes
Text
マフィアパロ パーヴェ
1.
あらゆる贅を尽くした室内に無機質な機械音が響いている。まさしく豪華絢爛な部屋にふさわしい大きなサイズのベッドの横には硬質な医療器械がずらりと並んでおり、無機質な機械音はそこから発せられていた。
機械から伸びた無数のチューブは、ベッドの上に横たわる人物と繋がっていた。
黒いスーツを身に付けた赤髪の美丈夫はひとり静かにベッドのそばに佇んで、無数の管に繋がれ浅く呼吸をして横たわる男を見下ろしていた。
「――……パーシヴァル、…そこに、いる…のか…」
薄らとベッドに横たわる男の目が開き、掠れたいまにも掻き消えてしまいそうな声を洩らした。
「…はい、ボス」
パーシヴァル、とは赤髪の美丈夫の名だ。うめき声のようなちいさな声を漏らさず聞き届けたパーシヴァルは顔を近づけるように蹲み、しかと返事をする。
男の薄らと開かれている虚ろげな瞳にはパーシヴァルの顔どころかすでにほとんど何も映ってはいないことも、耳もあまり聞こえていないことも、パーシヴァルは知っていた。
微かに聞こえたのであろうパーシヴァルの声を辿って弱々しい腕が上がりすっかり細く骨のようになってしまった指先がパーシヴァルの頬をなぞる。
男は――ファミリーを束ねるボスであり、ファミリーの構成員は彼を父として慕っている。もちろんそれはパーシヴァルにとっても同じで、父のような存在だった。マフィアという世界だけではなく、この世界で生きる術を教えてくれた、今のパーシヴァルがあるのはすべて彼のおかげと言っても決して過言ではなかった。
彼は、病にかかるより前は岩のような大男だった。
面白がってよくパーシヴァルの頬をつついたり撫ぜてきた優しい指先もこんなに細くなかったし、さまざまな表情を彩っていた頬もこんなに痩けていなかった。声だっていつも少々ボリュームを落としてほしい正直思ったことがあるほどであったし、笑うときなんかそれはもう豪快に笑う人だった。
――それが、数年前に思い病を患ったことで彼はこんなにもやつれてしまった。
抗争で銃弾の雨を浴びても、暗殺まがいのことをされて腹に派手な風穴が空いても、しばらくすればひょっこり戻ってきて、やっちまったわ、とげらげら笑って心配していたパーシヴァルを笑い飛ばしていたような豪胆な男だった。“何度殺しても死なない男”と、別のファミリーからも恐れられていた。そんな彼が、病に負けるなんてこうなった今でもパーシヴァルは信じられなかった――信じたくなかった――。
もはやかつての面影は薄れおよそ威厳というものは感じられず、そうなっては下にいる構成員――ソルジャー――の不安を招き最悪内乱にだってなりかねない。それゆえほとんど表舞台に立つことはできなくなり、彼に会うことが叶っているのはそういった心配のない信用がおけるパーシヴァルと、幹部であるカポレジームの面々くらいだ。
「……俺ァ、もう長くはねェ……、ファミリーを、…ココを、…頼んだわ…」
「! ボス、それは――」
「…アンダーボス、の、おまえの……務めだろうがァ……、務めを果たせ、…パーシヴァル…」
パーシヴァルはその言葉に、途端に顔を強張らせる。
――アンダーボス。次期ボス。それが、パーシヴァルの、このファミリーにおいての役目だ。だから、ボスに何かあれば己がこのファミリーを束ねるのだという自覚はずっと前からあった。そのために様々学んできたつもりだった。
しかし、現実を目の前にすると途端にずしりとパーシヴァルの肩に重圧がのし掛かる。
そして、病に伏せりやつれはじめた頃から本当は薄ら感じてきた、彼の死という現実に血の気が引く。
「ハ、…かてえ、かてえ……、ああ…、おめえは頭はいい、が…ちいとばかり…かてえんだよなァ……」
彼の漏らした薄い呼気は、呼吸だったのか笑ったつもりだったのか判然としなかった。
けれど、呼気を洩らした唇はゆっくりコマ送りのように弧を描いた。
そして、パーシヴァルの頬に触れていた手はぽとんとベッドの上に落ち、薄ら開いていた瞳が瞼で覆われてしまった。…チューブを通して注がれる薬の副作用で、あまりボスは目を覚ますことはなく、ほとんど眠っている。深い、深い眠り。
ボスの病は治らない、もう手を尽くしてしまった。現状は…ただただ、細い糸のような命を繋ぎとめているのだ。
パーシヴァルはベッドの上に無造作に落ちた手をベッドの中に戻し、布団を整えて立ち上がった。
真面目すぎる、頭が硬い、甘い、とは彼からは言われ慣れた言葉の数々ではあったが、今この時言われることとは重みが違う。
今一度、彼を見下ろしてからパーシヴァルは踵を返した。
静かに部屋から出て扉を閉め、パーシヴァルは険しい顔でその場に立ち止まりつるりとよく磨かれている床の上に立つ、己の革靴の爪先を見つめた。
「ジークフリート」
おもむろに名を口にして半ば睨み付けるように見つめていた床から視線を動かすと、いつの間にか音もなく、離れた場所にパーシヴァルと同じようにスーツを着た男が立っていた。
まるで、気付かれたことが意外だとでもいうように、男――ジークフリートは、ひとつに結び横に流した緩やかにうねる茶髪を揺らし眼鏡の薄いレンズ越しの鼈甲色の瞳を丸めた。
「おまえに頼みたいことがある」
「俺に、か? 珍しい」
「コンシリエーレ、ジークフリート。おまえに相談がある」
そう呼ぶと、笑みさえ浮かべていたジークフリートは、穏やかに弧を描いていた唇を何か言いたげにわずかに開き、それからすぐに引き結び瞳を細めた。
“コンシリエーレ”、それがこのファミリーの中でのジークフリートという男に与えられた役割。
顧問とも呼ばれるコンシリエーレは主にソルジャーたちの相談役ではあるが、その存在はファミリーにとってはなくてはならない存在だ。他に誰もその役割につくこともなく、ジークフリートただひとりだけコンシリエーレという立場にいる。間違いなくファミリー内でのトップはボスただひとりだ。しかし、その次は誰なのかと言われれば、パーシヴァルはきっとジークフリートなのだと言う。アンダーボスである自分よりも、表だって出てくるわけではないがジークフリートはこのファミリーの中心にいる人物であろう、とそう思っている。
パーシヴァルがこのファミリーに入ったときには既に、ジークフリートはその位置にいた。ボスは、付き合いは長い、と言っていたが具体的にどういう繋がりなのか、どうしてこのファミリーにいるのか、彼が何をなしてきたのかは知らない。知る者も多くはないはずだ。
ジークフリートも無口なわけではないが決して雄弁なほうではないので、あまり語らない。パーシヴァルも進んで問うこともしない。この男の底知れぬ何かを、本能的に察しているのだ。
「暫く不在にする。その間、適当に繕っておいてほしい」
「…構わないが、知られたくない場所へ行くのか?」
「……今の、ファミリーを見たい。俺が普段、目の届いていないところに」
――いずれ、…いや、近いうちにボスは死んでしまう。そうなったときに、新たなボスとなるのはパーシヴァルなのだ。それを、先程ボスと言葉を交わして改めて自覚した。
肩にのしかかる重圧も、迫りくる彼の死という現実も、全てを乗り越えなければならない。彼が作り上げたこの大きなファミリーを、束ねなければならないのだ。
だからこれは、パーシヴァルの決意だ。
「では、それも俺の方でなんとかしよう。当てがある」
ジークフリートは更に問うでもなく、あっさりと承諾した。ボスがあのような状態になってから、裏で代わりをしていたのはほとんどパーシヴァルだ。もちろんジークフリートやカポレジームたちも動いてはいたが、次期ボスとしての責務として主はパーシヴァルに任されていた。ファミリーのためとはいえ…そのパーシヴァルが長く不在にするということは特にジークフリートへ負荷がかかってしまう。
それゆえ、反対のひとつやお小言でも飛んでくるものと思っていたから――あまりジークフリートらしい行動とは思えないが――、少々拍子抜けではある。
「――もう然程、時間はないだろうからな」
ぽつり、と扉を見つめ呟いたジークフリートの横顔は、普段となんら変わりないもののようでいて、少しさびしげであったように思えた。
パーシヴァルもその横顔を見つめ、それから同じように扉を見つめた。
2.
(……案外変わるものだな)
パーシヴァルは鏡に映る、少しだけ見慣れない自身の姿を眺めていた。
赤く綺麗だった髪は黒がかりくすみ、同じように赤い色だった瞳も変色している。パーシヴァルのようにはっきりとした赤い色の髪や瞳はこの辺りではあまり見ないから、という理由でジークフリートに毛染めと色のついているコンタクトを渡されたのだ。
はじめはたったこれだけで、と思ったが…髪の色や瞳の色が変わるだけでもこんなにも印象というものは変わるものか、と今ではいっそ関心さえ覚えている。
体躯を包んでいるのは普段身に着けている質の良い艶のある黒いスーツではなく、パーシヴァルのギリギリ許容範囲程度の質素な服だ。布も薄く、心もとなさに顔を顰めながら服を摘まむ。
ファミリーに入るより以前はこういう服を身に着けているのがふつうだったというのに、それが今では違和感を覚えてしまうようになったというのはなんとも皮肉な気がして、ちいさく自嘲ぎみに笑みを零す。
アンダーボスとなってから、ボスにスーツをもらった。全てフルオーダーなのだというそれの値段はパーシヴァルとて知らぬわけではなく、こんな高価なものをボス手ずからいただくなど、とパーシヴァルは焦ったものだが、ボスはアンダーボスになったからこそこういう服を着るべきなのだと言っていた。外見を着飾ることも、重要なことなのだと。
特にパーシヴァルは年若く、なかなかこの年齢で今のポストにいる人間というのはごく一握りであり、それ故古びた考えも持つ人間にはなめられやすいのだ。だから、スーツは防具であり、武具だった。
(そろそろ行くか…)
本邸ではなく、この潜入のために用意した街外れにある小さな家に付けられた時計を見上げる。
ジークフリートの言う当て、とやらが何を指しているのか知らないが、時間と場所を指定されたのだ。何故、と聞き返したら、行けばわかるさ、とだけ言われた。
パーシヴァルは今日から、ファミリーの新入りとして身分を隠し潜入することになる。下の者たちが今どのようにしてファミリーを支えているのか、――あるいはファミリーの規律を乱しているのか、パーシヴァルはそれをしっかり見定め、これから己がトップとなったときファミリーのためになる舵取りを考えなければならない。
「え、えーっと…今日から世話係になったヴェインだ! よろしくな!」
ジークフリート���指定された場所にいたのは、なんとも呑気な顔付きの男だった。明るい金色のふわふわしている毛がひよこか犬かのようで余計にその呑気さを増していて、パーシヴァルは思わず顔を顰めそうになったが、ぐっと堪えて笑みを張りつける。初日から自分の世話係とやらに噛み付く新入りはまずいないだろう。
だがそれにしたってこの男…ヴェインは、とても裏社会であるマフィアの一員にはあまり見えない。街中のどこにでもいる、平穏な陽の当たる生活をしていそうなごくごく普通の青年だ。
ボスやジークフリート、カポレジームや彼らが率いるソルジャー…みな、そういう雰囲気を持っている。みな性根が腐っているとまでは言わないが、良い人間とは言えないし汚いことに手を染めたこともある――陽のあたる場所にはいけない、そういう存在だ。……もちろん、パーシヴァルも。
「…パルツィです、よろしくお願いします」
きれいに張りつけた笑みのまま、差し出されたヴェインのごつごつしている無骨な手を握り返す。
本名でそのままいくわけにはいかないと思い、偽名を考えてはいたけれど…パーシヴァルの顔を見てピンとも怪しむでもなくにこにこ阿呆のように笑っていたこの男にそこまで警戒する必要はあるのだろうか、とも正直考えてしまう。それほどまでに、ヴェインからはおよそ警戒や疑心を感じなかった。この男は、純粋すぎるように思えてならない。その純粋さは普通の生活では然程問題にはならないだろうが、ことこの社会においてはその気質は食い物にしかされないだろう。
「わ、いや、敬語とかいいって、ほんとに…。たぶんそっちのほうが年上だろうしなあ……あと俺も入ったばっかで、ほとんど新入りみたいなもんだしさ…。なのに、急にコンシリエーレ? っていう役職の…ジークフリート、さん? に頼むって言われて……あんなすげー人が何で頼んできたのかわかんないんだけど、そもそももしかしてパルツィってジークフリートさんと知り合いなのか?」
何なんだ、この男は。パーシヴァルは張りつけた笑みのまま口元を僅かにひきつらせた。
初見から能天気そうな男だとは思ったが、妙に慣れ慣れしい上に先程からべらべらと怒涛の勢いで喋ってくるものだから、パーシヴァルは若干引いた。喧しい、とついいつものように言ってしまいそうなのをなんとか堪える。
――ヴェインと己の相性はともかく。ジークフリートの当てとやらがヴェインだとはどういう意図なのかわかりかねたが、ほとんど新入りなのだということでようやく納得した。
パーシヴァルが潜入したのは、カポレジームが率いる構成員であるソルジャーのところではなくそれより更に下の準構成員であるアソシエーテのところだ。
大きなファミリー故、ソルジャーでさえもすべてを把握しているわけではないが、それ以上にアソシエーテは更に未知数だ。人種もなにもかもごちゃまぜになっていて、それ故一番所属している人間が多いので、パーシヴァルは今まで接したことさえない。
その中で更に新入りともなれば、アンダーボスであるパーシヴァルの顔や容姿、その存在さえもあまり知らなくて当然と言えば当然かもしれない。
「……コンシリエーレとは、偶然拾っていただいたというそれだけだ」
当然これも嘘だ。そうでも言わないと、ファミリーのトップに近いジークフリートと入ったばかりの新入りが繋がっているのは怪しい。
拾われたという理由ならば多少は現実味がある。ファミリーには拾われたという人間も決して多いわけではないが、いることにはいる。拾われた、というのは正真正銘文字のまま拾われた者のことだ。街の中心部やその周辺はとても裕福でにぎわうこの街も、街外れに向かえば向かうほど治安が悪く、所謂スラムになっており、そこには家も何もかもを失った者たちが、限りなく死に近い状態で暮らしている。
そこから、ファミリーの者が気まぐれで目を付けて拾ってくることがあるのだ。だが、ただただ拾ってそれで終わりなのではなく、拾われた者の不始末は拾った者の責任となり同じように、血の掟により制裁を受けることになるのだ。だからあまり拾いたがる人間もいないのだが、ごく稀に情を移して拾ってくる人間もいる。
ジークフリートは、適当に言いつくろっておいてくれ、となんとも無責任なことを言ってきたので、唯一現実味がある嘘をついてしまったが、さすがのヴェインもこれは怪しむのではないだろうか…と、パーシヴァルはヴェインが怪しんできて発する言葉をいくつか脳内で浮かべ、その返答を何通りも思考しながらヴェインを見つめる。
「ふーん、そうなのかあ」
ひく、とパーシヴァルの顔が引きつる。……この男、能天気なだけではなく実はただの馬鹿なのだろう、そうはっきり確信した。へらへら笑って、すんなりパーシヴァルの言葉を一部も疑うこともなく受け入れてしまったのだ。ここまでくるといっそ末恐ろしささえ感じる。
「…コンシリエーレとの繋がりは、他の者へ余計な気をもたせてしまう。他言無用でお願いしたいのだが」
「おっけー」
またもヴェインは浮かべた笑顔を崩すこともなく即答だ。……軽い。果てしなく軽すぎる。パーシヴァルであれば、こんなふうに言われたら間違いなくその者をまず疑うだろう。ただ、その時にはヴェインのように了承はするだろうが、内心は疑心に満ちさてこいつをどう調べてやろうかと思考を巡らせる。――しかし、ヴェインからはやはり疑心を感じないのだ。
「おまえは俺のことを怪しいと思わないのか」
ヴェインがあまりにも能天気で、苛立ちさえ覚えてつい口走ってしまったことをパーシヴァルは口にしてから後悔した。ヴェインが能天気で人を疑う事を知らないのであれば尚の事、身分を隠したいパーシヴァルにとっては非常に扱いやすく都合が良いというのに、だ。これでは、ボスに甘いと言われるのも道理だ。
「え? なんで? だってパルツィって悪い人には見えねえし、ジークフリートさんもそう言ってたし。俺だって、信じていい奴と信じちゃいけない奴くらい区別つくんだぜ」
きょとんとしたヴェインは、言葉を躊躇するでもなくやはりすんなりと答え、むしろ胸さえ張るのだから、どうしようもない。
真っ直ぐに信頼を向けてもらえることに胸を躍らせるほど、パーシヴァルは純粋な心根は既になく、どこか冷えた心地でこいつはきっとこの社会では生きてはいけまい、と思った。騙し合いなど当たり前のようにあって、人を信じれば、なんて理論は通用しないし、善悪の判断など不要だった。周りも自分も、結局悪でしかないのだから。それをわからなければ、やはりこの男は食い物にされるだけだ。
“悪い人”ではない、などとよくも言えたもので、そもそもこのような場所に身を置く時点で“良い人”ではなくなるというのに。いっそこのまま、己の手を汚したすべてをぶちまけてしまおうか、そんな事さえ思う。やれることならばなんでもやった、人を手に掛けた事も何度もある。抵抗さえその内なくなって、気が付けばこんなところにいる。――腹の奥がぐるぐる気分が悪い。汚い言葉を遣ってしまえば、胸糞が悪い、ということなのだろう。
パーシヴァルは小さく舌打ちを零し、握ったままだったヴェインの手を振り払った。
「…パルツィ?」
どうかしたのか、とヴェインが気遣わしげに覗きこんでくる。
まだ染まりきっていない、真っ直ぐな瞳に己の姿が映っていることが耐えがたく、パーシヴァルはふいと視線を逸らした。
「おなかすいた?」
……やはりこいつとはウマが合わない、とパーシヴァルは深く溜息を零す。何をどう考えたらお腹が空いているのだと思うのか。いかにもな態度を取ったのはパーシヴァル自身ではあるが、あまりの度し難さに半分睨み付けるようにヴェインを再び見遣る。
すると、一瞬ヴェインの瞳が揺らいだ。怯え、かあるいは。…ただ、パーシヴァルはそういう瞳を見たことがあった。――他でもない、スラムで。
徴収でスラム街付近を通ったとき、パーシヴァルはいくつもの同じような瞳で見つめられた。風格が出てきたということだ、と周囲には言われたがパーシヴァルの胸中には釈然としない何かがあった。
スラムの人間を助けることはパーシヴァルの仕事でも、マフィアの仕事でもない。同情をしても、仕方がないことではある。けれど、パーシヴァルは――
「…これから世話になる身でありながら失礼な態度を取ったこと、許してほしい」
血が上った頭をゆっくり冷やす。パーシヴァルは何も新入りをいびりにきたわけでも威圧しにきたわけでもない。次期のボスになるために、このファミリーの実情を見に来たのだ。そして、ヴェインはいくらどうしようもなく能天気で阿呆だとしても、パーシヴァルにとっては貴重な協力者なのだから――もちろんヴェインはそんなことになっているとは微塵もおもっていないだろうが――、事を荒げず上手くやっていかなくてはならない。だから今は剣を収めるべきだ。
「いや俺のほうこそ、何か気障ることしたんだよな、ごめん」
謝る必要がないだろうがおまえには、と言いそうになる口をつぐむ。
街角のどこにでもいそうな青年に見えていたヴェインに、何か歪みのようなものを感じるのは何故だろう。
(……こんな世界に入るくらいだ、こいつにも何かがあるのだろう)
みな訳アリなのは当然のことだ。ただ、ほんの一瞬でも弱者の瞳を見せたこの男はこの弱肉強食の世界には向いていないと思った。
「…よし! じゃあ飯でも食おうぜ、俺の家すぐ近くなんだ」
「おい、仕事は――」
「んなの飯の後! 腹が減ってはなんとやらって言うだろ!」
わははは、と笑いすっかり明るい調子に戻ったヴェインはそう言ってさっさと歩いていってしまう。能天気なくせに度胸はある奴だ。仕事をさっさと熟さないで怒られるのはヴェインだろうに。
はあ、と今一度溜息を零しパーシヴァルはヴェインの後を追った。
3.
『どうだ、調子は』
影になっている建物の壁に背を預け、耳に当てた携帯から聞こえる久方ぶりのジークフリートの声に顔を顰める。
「……どうもこうも…」
振り返り、背を預けていた壁から顔をわずかばかり覗かせると、少し離れた場所にヴェインがソルジャーのひとりと話しているのが見える。
いつもパーシヴァルの前ではおしゃべりな口を噤ませ、眉を垂らし顔色があまり良くないことから察するに、おおかた説教か鬱憤を晴らすように言いがかりでも食らっているのだろう。
ソルジャーがやって来たのを察知して、パーシヴァルはうまいことヴェインに理由を言って――何を言ってもヴェインは許容するだろうが――その場から逃げおおせたのだが、ちょうどジークフリートから電話がかかってきたのだ。
パーシヴァルが潜入を始めて三日が経った。一番下のアソシエーテとだけあり渡される仕事はあまり緊張感のない、汗臭いものだった。みかじめ料や貸した金の徴収やらに方々街中歩き回ったりが主だ。時折密輸やら密造に関わることもあったが、それも結局力仕事をさせられるだけだ。
汗をぬぐいながら、アソシエーテに任せられる仕事は確かにこのくらいだろうなとパーシヴァルは思う。しかし、こういったものは異国では縁の下の力持ちと言ったか。やはりファミリーにとってなくてはならないものと言えよう。しかし、アソシエーテは人種が様々なせいか、非常に良い扱いを受けていないようだ。
今のヴェインのようにソルジャーに突っかかられるのは最早どうしようもないが、アソシエーテの面々にはこれからも励んでもらうために何か考えるのもいいかもしれない。鬱憤を晴らしたいのもわかるが、やはり素行がやや目立つ。今すぐ血の掟で粛清するほどのことでもないが、今後も監視は続けるべきだろう。
「――…それなりに成果はある、が……おまえの手配したあのヴェインとかいう男はなんとかならんのか」
『ヴェインか? ああ……良い青年じゃないか』
「…正気か? アレにはこの世界で生きることなど到底無理だ、誰だあんな男を拾ってきた阿呆は」
再び背を預けた壁を後ろ手にこつこつちいさな音を立て苛立たしげに指先で小突く。すると、暫しの沈黙の後電話越しに小さく笑う声が聞こえ、パーシヴァルは眉間にしわを寄せる。
「何がおかしい」
『…いいや、心配をしているようで…随分ヴェインと仲が良くなったようだと思ってな』
「な……」
心配している? あの男を? 何故俺が。そんな文句とも疑問とも言える言葉が一気に溢れだして、なんだと、という言葉は正確には吐き出せなかった。
ヴェインとの関係性は別段変わったこと���ない。ヴェインは相変わらず馴れ馴れしく、騒がしい。しかも、どんなに疲れ果てた日でも変わらず喧しいのだ、あの男は。
それと、どうしようもないくらい致命的に方向音痴ということも判明した――しかも本人は認めようとしない――。そのせいで徴収がまるで捗らず、単純計算で課された仕事を今日一日で終わるかどうか…と、とうとう耐えられなくなったパーシヴァルが逆方向へ歩いていくのを首根っこひっつかんで引き戻し、そのたびに溜息を洩らしたものだ。
正直、ヴェインといると平和ボケというべきか、調子が狂う。アンダーボスになり、ボスが病に伏せてからずっとパーシヴァルは息の詰まるような重圧と隣り合わせの日々を続けていたから、余計にヴェインといると気が抜けて嫌になる。
それに、ファミリーに入る前も後もあまりパーシヴァルの周囲にヴェインのような男がいなかったということもあり、接する度に疲労感さえ正直覚える。…ヴェインのような男がほいほいそこら中にいても困るだろうが――想像するだけで鼓膜が破れ頭が爆発しそうだ――。
敢えて言うのであれば。ヴェインは時折、あの時見せた顔色を窺うような弱々しい視線をこちらに向けてくるときがある。意識的にそうしているのか無意識なのか知ったことではないが、余程あのときのパーシヴァルの態度が響いたらしかった。ある種、恐怖を植え付けられて服従するという点では御しやすく組織的には一向に構わないのだが、パーシヴァルはヴェインのそういうところは気に入らなかった。
「っ、そんなことはどうでもいいだろう! そんなことを言うためにわざわざ電話をしたのか!」
自分でこの話題を振っておきながらこの言い方はないだろう、と恥じながら、しかしパーシヴァルはこれ以上何か言われることも、誤解されることもごめんだった。
『……そうだな、本題に入るが…例のファミリーに妙な動きがみられたと、つい今しがた報告があった』
途端に真剣な声音になりジークフリートが告げた内容に、パーシヴァルは眉を顰める。
「…ボスのことが勘付かれたか」
『可能性は否定できないが、少なくとも好機とは思われているだろうな。近いうちに仕掛けてくるのは間違いない』
よりにもよってこんなときに、とパーシヴァルは舌打ちを思わず零した。
“例のファミリー”とは、この都市に根付くパーシヴァルたちのファミリーとは別のもうひとつのファミリーだ。普通、ひとつの都市にファミリーが複数存在することは通常ありえないことだが、この都市には昔からふたつのファミリーが存在していた。
いままで、大きな争いもなくお互いの縄張りを守ってきたが…ボスが不在の今を狙ってくる可能性も考え、周辺を探らせ見張らせ警戒していた。長いこと何も諍いもなくやってきたから、まさかとは思うが念のため…と慎重になったのが功を奏したようだ。
ボスが健在であればこんな事態どうということもなかったかもしれないが…いいや、ボスがいても、これほどの規模になっているファミリー同士がぶつかる抗争となれば被害は相当なものになるはずだ。小競り合い程度ならば被害は最小限にとどめられるだろうが、総力戦となった場合は――。
「……わかった。引き続き見張らせ、また動きがあればすぐに知らせろ、いざと言うときは俺が指示を出す」
『ああ。俺のほうでもやれることはやっておく』
「! おい、ひとりで突っ走るなよ、ジークフリート。今回ばかりはおまえひとり動いてどうにかなるものでもあるまい」
『わかっている、情報収集をするだけだ。…それにしても……ふむ、ボスに似てきたなパーシヴァル』
妙にうれしそうなジークフリートの声音に、パーシヴァルは咄嗟に言葉をかえせず唸る。
たしかにボスはよく茶化すような声音で同じような事を言っていた。それというのも、ジークフリートは単独行動をするきらいがあり、裏で手を回しなんやかんや解決してしまうということがままあったからだ。
ジークフリートならばひとりでも問題はないのだろうが、それは絶対ではない。不測の事態が必ず起きないという保証だってないのだ。そして、ジークフリートはファミリーにかえがいない重要な人間で、ボスがいなくなろうかというこの時期に失うわけにはいかない。
それに、ボスだけではなくジークフリートまでいなくなってしまったら――と考えパーシヴァルはハッとする。
「っ茶化すな、ジークフリート」
『茶化したつもりはないが、すまなかった』
「くそ、謝っているように聞こえん! そろそろ切るが、何かあればすぐ連絡しろ、いいな」
『もちろんだ』
電話を切ると、遠くのほうでヴェインがパーシヴァルを呼ぶ声がちょうど聞こえてきた。
先程を同じようにこっそり振り返ると既にソルジャーの姿はなく、ヴェインが噴水を中心にした円形の広間の周囲をうろうろひとりで歩き回っていた。
このまま放置すれば、パーシヴァルをさがして当てもなく歩き出し、またどこぞかで迷子にでもなりそうな勢いだ。今日も方々歩き回りコキ使われたので、さっさと休みたいというのに更にヴェインをさがしまわるなんて御免こうむる。
「ここだ」
「あ、パーさん! どこまで行ってたんだよ、先に帰っちまったかと思っただろ」
呼ばれたその名で、パーシヴァルは眉間に皺を寄せる。当然ヴェインにもわかるよう露骨にそういう表情をしたのだが、ここ最近ではパーシヴァルのその表情には反応しなくなってきた。
パーシヴァルとて本気で怒りを覚えているわけでも苛立ちもしていないのだが、それを見ぬきだしてきたヴェインという男の抜け目のなさのようなものがやはり気に入らない。
能天気そうに見えて、ヴェインは存外人の機微に敏い男だ。顔色を窺っているように思えるが、どちらにしても見抜かれているような気分は心地よくはない。
しかしながらヴェインの気に入らない点などこのように上げ始めたらキリがないのだが、その中で一番パーシヴァルが気に入らないのは“パーさん”などという不名誉極まりないその呼び名だ。
「“パーさん”ではない。いい加減その間抜けな呼び方をやめろ」
なんとも腹立たしいことに、このやりとりはもう数えきれないほど繰り返しており初日からずっと続けているのだ。最早“パーさんではない”と“パーさんと呼ぶな”はまるでパーシヴァルの口癖のようになってしまっている。
はじめてヴェインと顔を合わせたあの日、結局郊外にあるヴェインの自宅で食事をしたのだが、そのときに“決めた!”とヴェインが突然声を上げ、“パーさんでいこう!”とこれまた突然言い出したのだ。
ヴェイン曰く、これからふたりで色々仕事をするんだから俺たちペアじゃんバディじゃん、とのことらしい。……意味がわからない。
そしてパーシヴァルが何度言ってもやめようとしないという謎のメンタルの強さに、パーシヴァルは苦戦を強いられているのだった。
「いいじゃん、友だちみたいで!」
「――友だと? おまえが俺の? ハッ、ごめんだな」
そもそもこの男は、マフィアがなんたるか正しく理解しているのだろうか。そんな友だのなんだの仲良しごっこをしていること自体おかしいのだと、何故わからない。
それを差し引いてもヴェインと友など考えられないが。
えー、といかにも納得がいっていなそうな声を上げたヴェインが不満げに唇を尖らせる。
「友などとのんきな奴だな、おまえには友人のひとりもいないのか」
「――…え、…あー…うん、まあ…そう、なるかな」
「なんだ、その他人事のような言い方は。自分のことだろうが?」
わかりやすくヴェインは困惑したような表情を見せ、返答に困ったのか歯切れの悪い言葉を返してきた。だが、何かを隠しているという風でもなく、どちらかと言えば自分のことであるはずなのに、誰か別の人間のことでも言っているかのようだ。
「……ま、まあいいだろ…。そんなこと、どうでも。パーさんと俺が友だちっていうのが今ジューヨーなことだろ!」
「だから友では……」
「よっしゃパーさん、今日も夕飯食べに来てくれよ! な! ほら行こうぜ!」
有無も言わさずがしりと肩に腕を回され、早々にヴェインが歩き出してしまったため、パーシヴァルはほとんど引きずられているのに近しい形で連行されていく。
ヴェインは見かけに相応しく馬鹿力で、さしものパーシヴァルもこれを振り払うのにはそれなりの体力を必要となる。それに、振り払ったら振り払ったでまたヴェインとまた延々とやり取りをすることになるだけなので、ここは素直にヴェインに合せてやっているのだ。
事あるごと…毎食ごとにパーシヴァルはヴェインの家に連行され、何故か食事を振る舞われていた。
これが最高にまずいのであればパーシヴァルは何が何でも抜け出すのだが、これは見かけに反してヴェインの料理は美味いので満更でもない……いや、美味な食事に罪はない、そういうことだ。それだけだ。
あとは食事中にヴェインが黙っていてくれさえすれば、郊外のボロ家の食事でもそれなりに楽しめるのだが。
(……しかしこいつに友人のひとりもいないとは)
パーシヴァルが素直についてくるのがわかったからかようやっと回されていた腕が外れて、やれやれと肩を回しつつ鼻歌をうたい上機嫌のヴェインの横顔を眺め、パーシヴァルはなんともなしにおもう。
パーシヴァルからすればウマの合わない男ではあるが、一般的に見てヴェインは“良い性格”なのだろう。性格に裏表がなく、優しい部類で面倒見も良い。人に対する共感性も、感受性も強い。誰かを率いるリーダーの資質があるわけではないだろうが――本人の性格的にも――、人の輪の中心にいるのが似合うような男だ。だから、そんなヴェインに友人がひとりもいないというのも不思議な話だった。
それに、先程の妙な態度……。友人が出来ない、もしくは、いない理由でもあるというのか。
(――いや、俺はなにを)
つい思考をまわし考え込むのは悪い癖か。だとしても、よりにもよって考えるのがヴェインのこととは。なんたる不覚、とパーシヴァルはひとり渋い顔をする。
パーシヴァルがいまなにより今一番考えなければならないのは、ジークフリートから連絡を受けた例のファミリーのことだ。
もし万が一、予想通りこちらを潰そうともくろみ準備を着々と進めているのであればどうするべきか。
パーシヴァルとしては、慎重になるべきだと思っている。抗争を避けられるのであれば避けるべきだ。たしかにもうひとつが潰れれば、ファミリーもさらに大きくなるかもしれないがその代償はあまりにも重い。むやみやたらと構成員たちの命を散らすことになる。
だが、これはあくまでもパーシヴァル一個人としての意見であり、実際ジークフリートや幹部であるカポレジームの面々の意見は違ってくるだろう。
特にカポレジームは古参も多く、いまだ若輩であるパーシヴァルが次期ボスであることに納得していない者もいる。そしてそういう者に限って、好戦的であったりするからまた厄介なのだ。
どうせ、パーシヴァルが抗争を避けるべき、と言えば、聞くに堪えない罵りが飛んでくるに違いない。
(…問題は山積みだな)
しかし、パーシヴァルにはやらねばならない、という強い意思がある。これしきで立ち止まってなどいたら、パーシヴァルに託すと言ってくれたボスに顔向けが出来ない。
だからヴェインに傾ける思考などパーシヴァルにはないはずなのに、そ��でも思考の片隅にちらつくこの男がひどく憎らしかった。
「うわ、すごい雨降ってきたなぁ。パーさん今日は泊まっていったら? 時間も結構遅くなっちまったし」
ちょうど食事を終えたところで、外からものすごい音が聞こえだしたので何かと思えばどうやら大雨が降ってきたらしい。
ヴェインが引いたカーテンの隙間から見える外はいつの間にか暗くなっており、雨粒は良く見えなかった。
「…………ああ、そうさせてもらおう。だが俺はパーさんでは」
「パーさん律儀だなあ、それもしかして毎回言う気かよ」
「…………」
ヴェインの家に泊まるなど、夜は果たして静かに寝かせてもらえるのだろうかと少々不安ではあるが、たしかにこの暗闇と大雨の中走るのは少々堪える。
「とりあえず、俺は風呂と部屋の準備してくるからパーさんはここでゆっくりしててくれ」
それじゃあ、とヴェインは言いたいことだけ言ってさっさと部屋の奥に消えて行った。
(……そういうところだけは妙に気が利くんだがな…)
ならばもう少し他のところも気が利いてほしいものだが。パーシヴァルは食後に出された温かいハーブティー――これもヴェインが自ら育てたハーブで淹れたものらしい。すっかりパーシヴァルのお気に入りになったもの――を飲みながら、ゆるゆると一息漏らす。
家人として客人をもてなすのは当然だと言わんばかりに、パーシヴァルが家にやってくるとヴェインはあれこれ気を利かせてくる。パーシヴァルはいつも、ただ椅子に座っているだけだ。
「パーさん、あんま背丈変わんないし俺のパジャマでもいけるよな?」
準備が終わったのか、ヴェインが手に何やら持って戻ってきた。
背丈はたしかにヴェインとパーシヴァルはあまり変わらない。ヴェインのほうが一、二センチ高いくらいだ。しかし、体の厚みやなにやらを比べるとあまり同じくらい、とは言い難いような気もする……というところまで考えると強烈に悔しいので、パーシヴァルは気を落ち着かせるためにひとまずもう一度ハーブティーを飲んでから、改めてヴェインの手元を見る。
「!? 貴様なんだその幼児が着るような柄は!」
ヴェインの手に乗っていたパジャマは、とてもヴェインのような成人もとっくに過ぎた筋肉盛りの男が着るとは思えぬ愛らしくデフォルメされた犬がまるで布の上をはしりまわっているようにあちこちにプリントされたなんとも可愛らしいもので、パーシヴァルは危うくふきだしそうになった。そしてそれをこれから自分が着るのだと思い、その姿を想像するだけでゾッとする。
「ん? ああでも確かにパーさんが着ると……っく、ぷ…ふ…」
「おい、今笑ったな!」
「パーさん顔いいから何でも似合うって! 」
ほらほらと言ってヴェインは手元に畳んであったパジャマを拡げ、目の前のパーシヴァルに当ててみせてくるのでパーシヴァルは椅子から立ち上がってそれを避ける。避けるとヴェインがまたパジャマをパーシヴァルのシルエットに当ててこようとするので、それをまた避けて――と狭い室内でふたり
「いや待ってくれよパーさん、ほら似合っ………、ッあー! だめだやっぱおかしい! すげえかわいいもん!」
「な…貴様ァ!」
とうとう堪えきれなくなったのか、ヴェインはひいひい笑いながら覚束ない足元でふらついて机に伏してばんばん叩きはじめた。
避けるパーシヴァルを追ってくるくる回っているときから、ハムスターか何かのように頬をパンパンに膨らませて今すぐにでも噴きだしそうな勢いではあったが、いざ実際ここまで大笑いされるとパーシヴァルも黙ってはいられない。
「そんなもの着るか! 裸で寝る!」
「ええ~…パーさん裸族かよ、えっちだなぁ~」
「…………」
ひく、と口元が引き攣り眉間に濃く皺が寄る。裸で寝ている人間などそこら中ごろごろいる。ヴェインはそれら全員を“えっち”であると言うつもりなのか。
そしてパーシヴァルは本来普段寝るときは、ナイトローブを着るか上半身だけ何も身に着けていないか全裸の三択だ。ヴェインのこの感覚からすると、その三択はすべて“えっち”と言われそうな気がしてならないのは何故だ。
しかしここ最近は、簡素なものではあるが上下共に着て寝ている。何故かといえば、まさしく今パーシヴァルの目の前でにやついた顔を向けてきているこの男のせいだ。
ヴェインは頼んでもいないのに朝は必ずパーシヴァルの家まで迎えに来るわけで、そんなときにうっかりとてもこの生活層に似つかわしくない上質な素材を使った肌触りの良いナイトローブなど着ているところなら見られた日には、さしものヴェインにも何か勘付かれてしまいそうだからそうせざるえなかった。
「冗談だって、ふつうの無地のやつもあるから」
「なんだと!? はじめからそちらを出せ!」
「だって面白いだろ」
「知るか!」
すっかりヴェインの調子に乗せられていたことに気付き、パーシヴァルは舌打ちをもらしながらどすりと再び椅子に腰を下ろす。
残っていたすこし冷えてしまったハーブティーを喉に流し込みティーカップを置くと、机の傍にしゃがみ机上に置いた腕の上に顎を乗せ、へらへらというよりゆるゆるにとろけた顔でヴェインがパーシヴァルを見上げてきていた。
「…なんだ、気味の悪い」
「ひでえなぁ、俺これでも先輩なんだけど」
「おまえが自分との間では上下関係を気にするなと言ったんだろうが」
「まあそうなんだけどさ。……へへ、なんか…いいなあって、こういうのすげー友だちみたいだな、って思って。俺、ずっと同じくらいの歳の友だちほしかったんだ」
先程の馬鹿笑いと違い、頬をほんのりと染めほどけるように零された吐息のようなほほえみは、嘘偽りがないことをわかりやすく示していた。ヴェインは本当にパーシヴァルを友だと思っていて、こんな些細なことに幸せを感じているのだ。――こんな、人の表情を見て偽りか否かから考えるような男であると知っても尚、それでもヴェインは友であってよかったのだと、幸福なのだと言えるだろうか。…そんなことを考える自分に辟易とする。
「……フン、知るか」
ばかばかしい、そう言うようにパーシヴァルは椅子から立ち上がって先程ヴェインが消えて行ったほうへと歩みを進める。
背から、お風呂右手側~、とヴェインの相変わらずゆるっゆるな声が投げかけられた。
今日も相変わらずヴェインに振り回されて疲れた。労働よりもよっぽどそちらのほうが疲れるかもしれない。はやいところ疲れを流して眠ってしまいたい。明日もどうせ同じような感じなのだろうし。
パーシヴァルは深く溜息を零しながらシャツを脱いでいく。しゅる、と音を立ててシャツがパーシヴァルの肩から滑り落ち、鏡にパーシヴァルの白めのすべらかな背の素肌が映る。
「――……」
鏡に映ったパーシヴァルの背――肩のあたりにはタトゥーが刻まれている。タトゥーにしては控えめな模様、ワンポイントのようなそれをパーシヴァルはちいさく振り返り見つめた。
「パーさんタオル渡すの忘れて――…あ、悪い」
どたどた扉の前までくる足音にハッと我に返り、ちょうどヴェインが扉を開けた瞬間パーシヴァルは肩からずり落ちていたシャツを手繰り寄せ背を隠した。
タイミングよく、パーシヴァルが脱いでいたシャツを着こんだのを目にしたヴェインはパーシヴァルが着替えを見られたくないのだと思ったようで、タオルを傍に置いてすぐに顔を逸らした。
「――早く出て行け」
「! ごめん」
低く唸るようなパーシヴァルの声に、肩をすくませたヴェインはちらりとパーシヴァルをうかがうように見つめる。はじめて会った日に見せた、弱者の瞳に苛立ちを覚える。――やめろ、俺をそんな目で見るな、と。
「…それとも。そんなに俺の裸体にでも興味があるのか、人のことを“えっち”などと言っておきながら、おまえのほうがよっぽど――」
嘲りというよりはからかうようにつらつら言葉を吐き出しながら、もう一度ヴェインを見やる。
元に戻ってかみついてくるかと思ったヴェインは、何故か顔を青ざめ強張らせて黙り込んでいた。まさか本当に俺の裸体に興味を持っているのか、などという考えは一瞬にして霧散する。そうであればヴェインは顔を赤らめるはずである。ヴェインはそういう男だ。
しかし、ヴェインは顔を青ざめさせている。何か、おそろしいことが気づかれてしまったかのような、顔。
実は同性愛者だとか? そういう趣味であるとか? さまざまな考えが浮かんではくるが、そのどれもヴェインの凍った表情の理由づけにはならないような気がした。
そうしてパーシヴァルが何も言葉を次げずにいると、ヴェインはまたちいさな声で“ごめん”と呟いて、ふらふらとした足取りで廊下に出て行ってしまった。
4.
「パーさん! パーさんってば、���きろって!」
「…っ…、なんだ、朝から……さわがしい…」
翌朝のことだ。ソファで寝ると言ったがヴェインが頑として聞かなかったのでヴェインが普段使っているというベッドで就寝していたパーシヴァルは、ヴェインに慌ただしく突然叩き起こされた。カーテンの隙間から見える外は、まだ薄暗く陽も上っていなかった。
いまだ重い瞼を持ち上げのっそり起き上がると、起こしてきたヴェインも余程焦っているのかまだ寝間着のままだ。
――ふと、昨晩風呂の前でのことを思い出し、パーシヴァルは心地悪い気まずさにヴェインから目を逸らした。
あの後もヴェインとは一言二言言葉を交わしたものの、ヴェインは気もそぞろといった様子で、こちらを見ようともしなかったのだ。
いや待てよ、とパーシヴァルは自身の咄嗟の行動に思考停止する。何故、パーシヴァルのほうが気まずさなど感じなければならないのか。そもそも、何の確認もせずに中に入ってきたヴェインのほうにも非は充分あるはず。それに、パーシヴァルは多少機嫌の悪さを見せたが、怒鳴ったわけでも威圧したつもりもなかった。ヴェインの反応は聊か大袈裟すぎたのだ。
しかも、そのヴェインが何故かいつも通りに戻って何事もなかったかのように接してきているのだから、パーシヴァルが気まずさを感じる必要など微塵もないのだろう。
はあ、と溜息を零し、寝起きで乱れている前髪を掻き上げながら改めて落ち着きのない様子のヴェインを見遣る。
「――こんな時間に起こしたんだ、余程の理由があるんだろうな?」
「お、おうそれはもちろん…! 今さっき連絡があって、ここのすぐ近くの街外れで喧嘩になってるみたいで…」
「……喧嘩? そんなもの好きにやらせてやればいいだろうが…」
どんな理由かと思えば、“喧嘩”。郊外の治安が悪いこの近辺では喧嘩などしょっちゅうだ。また、連絡があったということはファミリーの中でのことだろう。規律はあるがわけありな人間が集まった、ガラが良いとは言えない集団だ。喧嘩など起こるのも日常茶飯事ではある。しかしそれを諌めるのも、止めるのも、新入りのヴェインやパーシヴァルの役割ではない。無論、アンダーボスのパーシヴァルの役割でもない。トップであるパーシヴァルには内輪の揉めごとや喧嘩を禁ずる規律を作ることは出来るが、現場に毎度赴くことは役割ではない。そういったことは、どちらかと言えばソルジャーを直接まとめ上げているカポレジームの役割だろう。
第一新入りが止めに行ったところで、更に騒動が大きくなるだけだ。パーシヴァルは馬鹿らしい、とベッドにあげかけていた腰を下ろした。
「それが…内輪もめならいいんだけど、…俺たちのところと…もうひとつのとこが、喧嘩してるらしくって…。しかも最初は本当にただの喧嘩だったのに、どんどん人が集まってきてちょっとした小競り合いになってる、って…。これ、やばいよな」
「…なんだと?」
ヴェインの次の強張った固い声音で告げられた言���に、もう一度寝るかとさえ考えていたパーシヴァルは目を瞠る。
ヴェインの言う“もうひとつのとこ”はこの街に存在するもうひとつのマフィアのファミリーのことで間違いない。一瞬、おそれていた事態は既に起こってしまったかと背中に冷たいものが伝う。しかし、情報収集にもたけているジークフリートがそんな危機的状況に陥るまで見逃すとは思えない。であれば、偶然的に誘発されたものとみていいだろう。
だが、当然このまま放っておくわけにもいかない。このことをきっかけに一気に事が進んでしまうのだけはなんとしてでも阻止しなければ。
ヴェインがどれだけのことを把握して“やばい”と言っているのかは定かでないが、存外敏い男のことだ、同じ街にあるファミリー同士が小競り合いとはいえ暴力沙汰の喧嘩になっているということがどれだけ危険であるかを正しく理解しているようだった。
こいつのそういうところはなかなか見どころがある、とパーシヴァルは感心する。
「すぐに行くぞ」
「ああ! じゃあ俺着替えてくるから、パーさんも早めにな!」
パーシヴァルが腰をあげると、ヴェインはぱっと顔を輝かせ力強く頷くと部屋を飛び出して行った。
どたどたとヴェインの慌ただしい足音が遠くなったのを小耳に挟み、パーシヴァルは携帯を取り出した。既に画面にはジークフリートからの着信履歴とメッセージが入っている。
さすが情報は早いな、と遅れてしまったことを悔いる。しかし己の未熟さを見直し恥じ入るのは後からでもいい、今は一刻も早く事態をおさめなければならない。
着替えの準備をしながら、パーシヴァルは電話でジークフリートにこれから自分が直接現場に行くことを伝えておいた。
「よし、じゃあ行くぜパーさん!」
「おい待て、その前になんだこの車は! 本当に動くのか!」
「え? 動く動く! たぶん!」
狭い車内の助手席でパーシヴァルは顔を青ざめさせ、アシストグリップに掴まり声を上げた。
運転席に座るヴェインがいかにも気合十分、みたいな顔をしているのが余計にパーシヴァルの不安を煽る。しかも、“たぶん”とまで言い出す始末だ。
着替えを終えてまだ陽も上っていない薄暗い街に出たふたりは、連絡のあった場所を確認した。徒歩でも行けることには行けそうではあるが、時間がかかってしまいそうだった。
一分一秒でも早く辿りつきたい、という意見が一致したところでヴェインは車で行こう、と言い出したのだ。
これにはさすがのパーシヴァルも驚いた。もちろんパーシヴァルは自身の車を持っているが、当たり前のように高級車なので持ち出してくることは不可能だ。
しかし、ヴェインのように郊外にひっそりとちいさな家で暮らしているような男が、金のかかる車というものを持っていることは珍しい。持っているのか、と聞くと、もらった、と言っていた。……車をもらう? と不審を抱いたものの、さっさと行けるのならばそれで、と承諾したのだ。
――そして、現在に至る。家から少し離れたところに停めてあった車はもう何年も前に出たような型落ちとなったようなボロ車だった。これにはパーシヴァルもドン引きだ。
本当に走るのか怪しいし、走ったとしても途中でタイヤが破裂したり操作不能になったりする可能性だってある。現場に着く前にこっちが病院送りになってしまいそうだ。
「俺を信じろよ、パルツィ!」
渾身のキメ顔である。何をかっこいい台詞決まった、みたいな顔をしているのか、とパーシヴァルは胸を熱くするどころか冷えた面持ちの白い目でその顔を見返す。
しかしヴェインはそんなこと知らないと言った様子で、早々に車のエンジンを掛けた。まるで安心も信頼もしていないパーシヴァルが思わず止めようと、“待て”と言おうと口を開きかけた瞬間、がくんと車が揺れあろうことか急発進し、そのままのスピードで走り始めたのだ。
アシストグリップを掴んでいて本当によかった、そしてこんなボロ車でもアシストグリップがついていてよかった、と普段であれば然程その存在におもうことがないだろうに、パーシヴァルは深くその存在に感謝したのだった。
「着いたぜ、パーさん! 車停められそうなのここしかなかったから、ここからちょっと歩いて……ってパーさんすげー顔色! 生きてるか!?」
「…っく…ふざけるな貴様……もっとまともな運転技術を身に付けんか馬鹿者…」
「急いでたんだからしょうがないだろ、ほら早く!」
目的地に到着した頃には、パーシヴァルは顔面蒼白になっていた。
ヴェインは料理やその他家事が得意なようで、なかなか手先が器用な男だ。だから、こんなボロ車でも運転は上手ければ問題なかろう、とほんの僅か思っていたが大間違いだった。急いでいるから、という理由が通用しないほどヴェインの運転はまるで遊園地のジェットコースターのように壮絶に荒かったのだ。ボロ車のひどい走行具合と相まって車内で激しく揺られながらパーシヴァルはあまりのひどさに途中から怒号を飛ばすことさえままらなくなった。パーシヴァルにとって人生で初めての車酔いだった。
ヴェインに急かされるようにふらふら車からパーシヴァルが出ると、近くでつんざくような音が鳴り響いた。
「! 今の、って……銃声、だよな?」
「……そのようだな」
静かな街外れということもあり、余計にその音は大きく響いた。ふたりの間にも緊張が走る。
音がした方角はこれからふたりが向かおうとしているほうからだ。喧嘩、とは聞いていたがどうやら銃までもちだすところまで事は大きくなっているらしい。
下手をすれば命を落としている者もいるかもしれない。今の銃声だって、どちらのファミリーの者が撃ったか定かではないが、誰かを殺した音だったかもしれない――おそらくヴェインもそのことまで考えたのだろう、強張った顔に微かに緊張と共に恐怖を滲ませていた。
(…銃まで持ちだされてくるようなところには行ったことがないようだな)
先程までパーシヴァルを急かすほどだったヴェインはその場に固まってしまっているのを見て、当然のことを考える。アソシエーテの仕事はパーシヴァルの体験してきた通り、雑用的なことが多い印象な上、ここ最近目立った抗争もなく落ち着いていたので入ったばかりと言っていたヴェインがこういった場がはじめてなのは当然だろう。
いまでこそアンダーボスにまで上り詰めたパーシヴァルだが、ファミリーに入ったばかりのころ――ソルジャーであった頃には、銃が持ち出されたのを幾度か遭遇したことがある。それこそ別の街のマフィアと抗争になったときなどは、撃たれて相当な負傷もした。
しかし初めてのときは、パーシヴァルも内心相当恐怖したものだ。なにせ、死に直結しかねないものだ。恐怖を覚えるのは当然のことと言える。……そう考えると、銃弾の雨を浴びて尚笑っていられるボスはやはりとんでもない人なのだと、改めて思う。
「やめるか?」
どうあれパーシヴァルは行かなくてはならないが、ヴェインは何も無理をして行く必要はないのだ。それに、緊張や恐怖で強張った体ではまともな動きが出来まい。命をむざむざ捨てさせるようなことは、パーシヴァルも許容できない。
パーシヴァルが声をかけると、ヴェインはハッとした様子を見せ、呆然としていた己を叱咤するように両頬を叩きふるりと頭を振った。
「――大丈夫、行ける」
深く息を吸い吐き出してから顔を上げたヴェインには、既に先程までの恐怖や緊張はなくなっていた。
ようやくのぼりはじめてきた朝日に照られ輝く新緑色の瞳は真っ直ぐに前を向いており、強い意思を宿したその瞳をパーシヴァルはただただ、うつくしいと思った。
まさかこんな男にそのようなことをおもうとは、と内心笑えてはくるのだけれど、いまはその色を己の瞳に焼き付けておきたかった。
(――…あらかた落ち着いてきたか)
周囲を見回したパーシヴァルは深く吐息を吐き出した。
どのくらい時間が経ったかわからないが、なんとか事態は収束したようだ。パーシヴァルとヴェインが到着して暫くしてカポレジームの数人がやって来たということと、こちらと同じくして、あちらのファミリーも事態の収拾のためにやってきたと思われるメンバーが集まってきたおかげで、あまり被害を出さずに事は済んだ。騒動を起こした者もパーシヴァルやヴェインも含めた仲裁に入った者も、軽傷から重傷まで怪我をした者はそれなりの数だが、命を落とした者がいなかったことが唯一の救いか。
聞けば、事の始まりは酔っぱらい同士の諍いというなんとも間の抜けたもので、偶然にも同じ街にふたつファミリーがいるということに不満のようなものを持っていた者たちがその場に集まっていたというのも、ここまで大騒動に発展した要因だったようだ。
――始まりこそ、単純な酔っぱらい同士の暴走かもしれないが、実のところその根は深い。
今回、あちらのファミリーが本当に仕掛けてくる準備をしているにせよ、そうではなかったにせよ、パーシヴァルは少しずつ平穏が軋んできているように思えてならなかった。
今はどうであれ、近いうちに必ずこの均衡は崩れる。そのときパーシヴァルは、新たなボスとしてこのファミリーを必ず生き残らせなければならない。恩人であるボスのため、そして――己の目的のために。
(……、ヴェインはどこに)
ふと、騒動の渦中に飛び込んでからいつの間にか離れてしまった男の存在を思い出す。
死んでいる者はいないというのは確かな情報であるはずなので、怪我の有無はともかくにしてヴェインもとりあえずは無事だろうが……その姿をさがすべく、パーシヴァルはその場から歩き出した。
中心街から一番遠くの街外れにあたるこの一帯は、以前までは他と変わらず生活をする住民がいたはずなのだが、治安や生活環境などさまざまな理由から人が離れていき、気が付けばすっかり空家だらけになり、いまでは崩れかけた塀や家ばかりで人の気配もなくほとんど廃墟群のような状態になってしまったのだ。
既にこの辺りからはどちらのファミリーも引き上げていった後のようで、先程までの騒々しさから一転して再びもとの静けさを取り戻していた。
そんな廃墟と廃墟の隙間の壁にまるで隠れるように力なく座り込んで寄り掛かっている姿が視界に入る。金色のふわふわした髪はヴェインで間違いない。
「! ヴェイン、おい、大丈夫か」
一瞬見逃しそうになりパーシヴァルは数歩戻ってすぐに駆け寄り、どういう怪我をしているのかもわからないのであまり揺すらぬようにその肩にそっと手をやった。
「……ぱー、さん」
ゆるゆると気だるげにあげられた顔にはかすり傷や殴られたような痕があるものの、大した怪我ではないようで、ほっと安堵する。しかし妙にヴェインから力が感じられないので、目に見えないがどこか怪我をしているのかもしれない。早いところ診てもらったほうがいいだろう。
「肩を貸す、立てるか」
「…うん」
ひとまず車まで戻るためには、ヴェインに動いてもらわなくてはならない。パーシヴァルも力がないわけではないのだが、さすがに自分と同じくらいの背丈でがっしりとした体格のヴェインひとりを持ち上げて歩けるほどの力はない。
自身で歩けるようになるまで待ってやればいいのかもしれないが、今は暴れていた者たちをまとめているのか周囲に姿は見られないもののカポレジームの面々がいる関係上、パーシヴァルはなるべく早くこの場を去りたいのだ。
必ず正体を見抜かれる、というわけではないだろうが可能性は非常に高い。今日この現場に姿を見せたカポレジームの数名は比較的表だってパーシヴァルに噛み付いてくるわけではない穏健な面々だったことは幸いだが。
ヴェインは問いかけにうつろながらも、かくん、と首を揺らし、パーシヴァルに合せてその場から立ち上がり覚束ない足元でゆっくり歩きだした。
立ち上がったその姿を横目に見るが、やはりどこかほかに怪我をしている様子もない。簡素な白いTシャツ��血らし��ものが飛び散っているものの、ヴェインの傷の様子からそれはほとんど返り血でヴェイン自身の血ではなさそうだが……、何故こんなにぐったりしているのだこの男は。
(…気でも抜けたか?)
途中までは、ヴェインの動きはパーシヴァルからも見えていた。目に見えて気合の入りすぎであったので、その反動か何かだろうか。
姿を見失うまでのパーシヴァルが見ていたヴェインの動きを思い出す。その体格からもわかるように、相当鍛えている様子のヴェインはやはり身体能力は人並みより上だ。筋肉で盛り上がり重たそうに見える体は存外しなやかに軽やかで、それでいて力強い。
やや己の身を顧みないような突出や動きが見られはしたが、それ以外はおおむねパーシヴァルをうならせるには充分な腕だった。正直、アソシエーテにとどめるには勿体ないとさえ思うほどに。
この社会にはふさわしくない、生きてはいけない――初めて会ったときはそんな風にパーシヴァルは思ったが、性格やら考え方、思考はともかくにして…純粋な“力”という点においては、ヴェインを倒せる人間はそういないだろう。
自分がボスになったときに、ソルジャーか…いや、いっそ自分の傍付きにでもしてやるのもいいかもしれない。喧しいのが少々玉にきずではあるが…番犬くらいにはなるだろうし、争いごとが嫌ならば給仕係にしてもいい。何せヴェインの作る料理はあらゆる高級なものを口にしてきて舌を肥えらせてしまったパーシヴァルさえ虜になるほど美味いのだ。
共にいることが疲れる、とまで思い不満を漏らしていたはずなのに、自然と己の傍に置くような選択ばかり浮かべていることに、パーシヴァル自身気づきもせず己の良案にひどく満足げだ。
――そんなことを考えている内に、停めてあった車まで戻ってきた。
ヴェインは一言もしゃべらずやはり変わらずぐったりしているような様子なので、運転は難しいだろう。後部座席に寝かせておき、自分がヴェインの家まで運転してやるか、とヴェインのズボンのポケットを漁って車のキーを探る。
「んっ……、ぁ」
ヴェインを支えながらの片手のためなかなか見つけにくく、ポケットに手を突っ込んで中を弄っているせいか、ヴェインがぴくりと反応を示しちいさな声をもらした。
ヴェインの履いているズボンのポケットは、左右と後ろで合わせて四つだ。
ここに到着したときはパーシヴァルは車酔いでふらふらだったので、ヴェインが車から鍵を抜いてどこに入れていたかなんて見てもいなかったのだ。もちろん他に鞄などは持っていないし、上半身はTシャツだけなのでポケットもないから、消去法的にズボンのポケットに入れたのは間違いないだろう。ヴェインに聞けば早いが、どうせ四つしかないのだし。
「っ、…ぱーさん…、…」
「待て、今鍵を……」
余程体調が悪いのか、それかまさか催したか、と思うほどヴェインは妙にじれったそうな…急かすような声音でパーシヴァルの名前を呼ぶ。
くすぐったさもあるかもしれないが、そのように急かされても見つからないものは見つからないわけで――と、漁っているとついに後ろ側の最後のポケットにようやっと鍵を発見した。
ようやっと取り出せた目的の鍵は何もストラップなどついておらず、これでは見つけづらいわけだ、とパーシヴァルの己の手のひらの上に乗るちいさな鍵を見て眉間に皺を寄せる。
しかも、古い車ゆえの本当の過去の遺産のような鍵。今となっては、キーレスキーやスマートキーといった鍵を差さずに車を開けられるのが主流で…そうであったならばヴェインに肩を貸した状態でもすんなり開けられるというのに……どこまでもこの車はパーシヴァルを苛立たせる。
「……よし、おまえは後部座席で寝ていろ、すぐに着く」
なんとか鍵を差して開け、先にヴェインを後部座席になんとか押しこむ。
ごろりとされるがまま転がったヴェインの瞳にはなぜか涙が浮かんでおり、相変わらず息も荒く頬もほんのりと赤い。晒された首筋には汗も滴っている。
まさか…熱でも出しているんじゃなかろうか。ここに到着したときには何ともなさそうだったのに、何故こんなに急に…。まさか変な菌でも移ったか。たしかにおかしな菌のひとつでも漂っていてもおかしくないような雰囲気ではあるが、この辺りは。
「おい、ヴェイ――」
ともあれさしものパーシヴァルも気遣うような声音で、どれ熱でも測ってやるかと狭苦しい後部座席に入り近づくと、先程まで動かすことさえ億劫であるようにだらんとしていたのが嘘かのように、突然ヴェインの腕がパーシヴァルに向かって伸びてきた。
伸ばされたヴェインの腕は、熱を額に触れることではかろうと屈んでいたパーシヴァルの後頭部を捉え、節くれたった指はパーシヴァルの髪をも掴みぐんと一気に引き寄せてみせた。
当然、まさかそんなことをされるとは考えもしておらず、すっかり油断していたパーシヴァルの体はいとも簡単に何の抵抗もなく倒れるようにぐらりと傾く。
危ない、と反射的にヴェインの身体を避けて座席シートに手を付き、それからもう片方の手でシートの背を掴み倒れ込むことを回避したパーシヴァルではあったが――まるで時が止まってしまったかのようにその場に硬直してしまっていた。
何が起こっているのかわからず、目を見開いたままパーシヴァルは目の前の光景を呆然と見つめる。すぐ間近に、ヴェインの顔があり己のくちびるにはあたたかで柔らかい感触……、パーシヴァルはヴェインに唇を奪われたのだ。
「っ、お…い…、っ、…」
触れたくちびるが離れた合間になんとか抗議の声を上げるが、ヴェインの腕の力は強くなかなか引きはがすことが出来ず、また引き寄せられてすぐにその声もヴェインのくちびるに吸われる。
はむ、と食まれた唇の合間から肉厚な舌が無遠慮に入り込んできて、パーシヴァルの舌を絡め取った。
もぞもぞヴェインの舌が口内を蠢くと徐々に口内に血の味が広がり、パーシヴァルは鉄くさいそれに顔を顰める。おそらく、ヴェインの口内から送り込まれてきた唾液によるものだ。ヴェインの頬には殴られたような痕もあったので、口の中を切ったんだろう。
――それにしても、なんと色気のないキスか。パーシヴァルは嗜み的にそれなりに場数を踏んでこういう経験も少なくはないが…断トツで最悪のキスだ。最早“キス”とも呼びたくもない。こんなものを“キス”と呼んでたまるものか。
腕をまわされ抱きこまれるような格好ながら、パーシヴァルが離れようとしているせいで髪ごと後頭部を鷲掴みされて痛いし、埃くさく狭い車内……そもそも、一方的に攻められるのはパーシヴァルの性ではない。
瞬間、かちん、とパーシヴァルの中で火がついた。なにせ、パーシヴァルという男は実に負けず嫌いな性格だった。
(おまえが俺を好き勝手しようなど、何千何百、幾年かけようとも早いわ)
パーシヴァルの口内で好き勝手動き回っていたヴェインの厚い舌を、むしろこちらから絡め返してやる。抵抗されることは想定外だったのか、それとも気持ちいのかわからないが、ヴェインが瞳を細め間近で見れば存外長く繊細そうな睫毛を震わせた。
絡め取りかえせたのならばもう主導権はこちらのものだ。ざらついた舌の表面をぬるぬる擦りあわせながら、少しずつ自身の口内からヴェインの舌を押し返していく。じりじり押し返し、パーシヴァルはとうとう形勢逆転してみせた。
正直あまりにも簡単すぎて、まさか何かたくらんでいるのか、ともパーシヴァルは考えたがヴェインは抵抗する気配すらなくむしろ受け入れているような――逃げなければそれでいい、そんな感じだ。
こちらが優位に立ったというのに、まるでヴェインの思惑にのせられてしまったようでなんとも腹立たしい。
パーシヴァルは鬱憤を晴らすようにヴェインの口内を思う存分荒らしてやった。女性相手ならば丁寧さが求められようが、所詮相手はヴェインだ。しかも、強引に荒っぽく始めたのだってヴェインからなのだから、敢えてパーシヴァルが懇切丁寧にキスをしてやる義理はないだろう。
「ん、っ…、ん…ぅ、く…」
されるがまま。先程までの強引さはどこへいったのか、ヴェインはとんと大人しくなった。パーシヴァルの配慮が一切ない荒っぽいキスにさえうれしそうに喉を鳴らし、くちびるの合間から漏れる吐息は満足げで甘くなんともうっとりとしたものだった。
何なんだ、こいつは。一体何がしたかったんだ、とパーシヴァルは内心舌打ちを洩らす。
やはりヴェインは同性愛者なのだろうか。――とすれば、昨晩のことはパーシヴァルが考えていたよりもずっと単純なことだったのかもしれない。
(――こいつがあまりにも大袈裟な反応をするものだから、俺もつられたか)
それにしても顔まで青ざめさせ、足取りもふらふらにまでなるほどのことなのか――、一瞬また再び深く考えそうになった己を叱咤し、パーシヴァルは余程バレたくなかったとかそういうことだろう、と早々に思考を打ち切るように結論づけた。
パーシヴァルのキスですっかりとろりとしたヴェインはようやっと腕の力を弱めた。やれやれやっと解放された、とパーシヴァルは唇を離して、深く溜息を零しながらヴェインの腕を振りほどいて体を起こした。変な格好で身を屈めていたせいで腰が痛いではないか。腰の痛みを感じるなど、年寄にでもなった気分で最悪だ。
ふう、とパーシヴァルが扉に背を寄り掛からせた瞬間。先程まで、キスではあはあ荒い吐息を洩らしながら溶けて座席に沈んでいたヴェインはのっそり体を起こすと、その起き上がる速度とは比にならない手早さで今度はパーシヴァルのズボンをがしりと掴んだ。
「…!? 貴様ッ」
ずる、とパーシヴァルのズボンが僅かに腰から僅かにずれて下着がのぞく。
もちろんこのまま見過ごせるはずもなく、パーシヴァルはヴェインの手首を掴んで我慢ならず怒声を浴びせる。
キスくらいならば、まあ…戯れとして多少は許せる。しかし、ここから先はどう考えてもありえない。
世界は広いもので、男同士でセックスをする輩もいるそうだが――無論他人の趣味嗜好を否定するつもりはないにしても――、パーシヴァルは男に抱かれる趣味も、抱く趣味も一切ない。いくらなんでもそこまで悪食になれないだろう、さすがに。
パーシヴァルの怒声を浴びたヴェインはびくりと肩を竦めほんの一瞬だけ手を止めたものの、なおも力を緩めない。まったくこれだから馬鹿力は困る、怪我をしている可能性もあるからなるべく強引な手は打ちたくないのだけれど、最終手段は蹴り飛ばす他ないか。
パーシヴァルの腕力よりヴェインの腕力のほうが上であり、徐々にパーシヴァルのズボンはずり落ちていく見える下着の範囲が徐々に広がっていく。そろそろ蹴り飛ばすか、とパーシヴァルが足を動かすと、ヴェインはズボンを掴んだ手をそのままに身を屈めた。
「な、」
先程パーシヴァルが唾液塗れにしてやった艶めく唇が、下着に包まれているパーシヴァルのやわらかい陰茎を食んだ。なんとも形容しがたい唇の感触――。
「――…おさまら、なくて」
終始言葉を発しなかったヴェインが、ようやく口を開いた。その拍子に、はあ、と湿った吐息が股間部を撫で、パーシヴァルは眉間に皺を寄せヴェインを見下ろした。
「…興、奮して…………」
吐息混じりにぽろぽろ言葉を零しながら、何をいまさら恥じているのか眉を八の字にした弱々しい顔をこれでもかと赤らめたヴェインは、もぞりと己の下半身を揺らめかした。見るまでもなく、ソコは勃起でもしているのだろう。
……呆れた。なんて奴だ。先程のキスで、ということならばよかっただろうが…ヴェインの様子がおかしかったのは、つい先刻騒動が終わった後に座り込んでいるのを見つけたときからだ。思えばあの発熱のようなぐったりしたような状態は、ただ発情し興奮していただけだったのだ。
パーシヴァルには到底理解できぬことだが、殴り合いにせよ銃撃戦にせよ、そういったことで気が昂ぶってしまう者は一定数いる。そして、それが終わった後にも収まらないというのも、ままあることだろう。特に今回のような本気のものではなく、ただ止めるためだけに入った、力を加減したようなものでは余計だろう。
しかしまさかヴェインがその類の人間だったとは。嗜虐よりむしろ被虐のほうが納得できるし似合っていそうな――いや、その可能性もあるのか。幾らか殴られているようだし。
どちらにせよ、度し難いのは変わらないのだけれど。
「俺はおまえなぞに抱かれる趣味はないわけだが…」
襲いかかってきたものだからてっきりパーシヴァルを抱こうとしているのかとも思ったが、どうやらヴェインはそうではないらしい。パーシヴァルの言葉に、ヴェインはふるふる首を振った。
「…まあ当然男を抱く趣味もないが…、それは見ればわかるな」
現に、パーシヴァルの下半身は下着越しでもわかるようにまったく一切反応をしておらず、芯もなく柔らかい状態だ。ヴェインもさすがにわかっているようでちいさく頷く。
「――俺をその気にさせてみろ」
そうしたら抱いてやってもいい、そう言うと半ばあきらめていたヴェインは驚いたように目を丸めた顔をパーシヴァルに向けた。――いやまったく気でも狂ったか、と己の言葉にパーシヴァルは内心笑いさえ込み上げてくる。男を抱くにしても、ヴェインのように筋肉隆々とした男ではなく肉付きの薄い少々中性的な男のほうがまだマシというものだ。であれば、さっさと蹴り飛ばしてシートに沈めなおしてやればいいというのに、猶予をやるなどさすがに寛大すぎただろうか。
(まあ…その気になるかどうかはこいつ次第だが)
ある意味、その気にさせろ、というのは“その気になる可能性は低いが”、という意味合いも実のところ含んでいる。必ず向かない、という絶対的な自信ではないが、気が向く、というのもなかなか想像しがたい。
ヴェインは視線を泳がせ少々困惑したようであったが、決意は固まったようで再びパーシヴァルの股間に顔を埋めた。
パーシヴァルは阻止しようと掴んでいたヴェインの手首を離してやり、シートに片肘をついて己の足の間でもぞもぞ動くその様を眺める。
手を離してやったというのに、そこから更にズボンや下着をずり下げるでもなくヴェインはそのまま下着ごとパーシヴァルの陰茎を舐めはじめた。おかげで下着はヴェインの唾液で濡れ始め、既にパーシヴァルは気持ちが萎えている。するならするでさっさと直で舐めればいいだろうが、と溜息さえつきたい気分だ。まさかこの期に及んで直接舐めるのはちょっと…とでも言いたいのか。直接だろうが下着越しだろうが、同じ性である男の陰茎をくちびるで触れるなどパーシヴァルからすればどちらも正気の沙汰ではないと思うのだが。
じゅるじゅる唾液の音を立てながら、先程浮かべた困惑はどこへやらで夢中で舐めしゃぶっているその姿は抵抗感など皆無どころか、まるで大層な馳走にでもありつけたような喜色さえ見られる。……慣れている、そう感じるには充分すぎた。一体今まで何人の男の陰茎を同じようにくわえてきたのだ、と思うと不快感がこみあげてくる。しかしそれがヴェイン本人に対してなのか、それともそうさせた現実になのか…パーシヴァルも判然としなかった。そんな曖昧な己の感情さえ不快極まりなく、腹の奥底が煮えくり返る。
当然、そんな気分の中で陰茎が勃起するはずもなく、物理的な刺激でやや芯を持ったもののいまだ柔らかいまま下着の中に納まっている。
パーシヴァルが退屈そうに溜息を洩らすと、びくりと肩を竦めたヴェインの動きが止まった。しかしそれは一瞬のことで、すぐに動き出したヴェインによりようやっと下着がずり下ろされる。中途半端な膝あたりでとまっていたズボンと共に下着がシートの下に落とされた。
下着が取り払われ陰茎が外気に晒されて、車内とはいえまだ朝も早いので肌寒さにふる、と震えパーシヴァルの肌が粟立つ。
思っていた通り、パーシヴァルの陰茎は縮んで力なく垂れている。他者の前にそのような姿の陰茎を晒すなど男としては恥でしかないが、これは決してパーシヴァルが男として不能なのではなく、気分でないからというだけだ。
さあこれを見てヴェインはどう動くか。下着越しではあるが口で奉仕したにも関わらずこの萎えっぷりは、心が折れても仕方がないものだが――。
ヴェインは再び顔を寄せると、重く垂れる陰嚢に舌先をちょんと付け舐めはじめた。
…やはりヴェインは手馴れている。陰茎にせよフェラをするときにはそれなりに加減が必要であることに違いはないが、陰嚢は男の直接的な急所でありほんの少しの衝撃であろうとかなり痛いので更に慎重に扱ってもわねば困る場所だ――もちろん陰茎も歯を立てられるとかなり痛いが――。女性でもあまり、陰嚢を舐めるという行為をすすんでやる者はいないだろうと思う。現にパーシヴァルはそこを舐められたことは今まで一度もない。なにせ、下手だった場合はかなりの痛みを伴うわけで、余程信頼できる相手ではないと任せられないので、してほしいと望んだこともないわけで。
しかし、ヴェインは舐めるだけではなく唇で食んだり、吸ったり、手でやわやわ揉んだり――するのもあくまでもやさしく絶妙な力加減で、責める場所も迷いなく的確に選んでいる。
フェラだけならまだしも、陰嚢を舐めることまで会得しているとなると、やはりそれなりに経験があるのだろう。
「っ……、ふ、…、くそ…」
不快感は変わらないはずであるのに、ヴェインから与えられる刺激にパーシヴァルの唇から思わず乱れた吐息が洩れる。そのような趣味は皆無であるはずなのに、たしかに性的興奮を引き出されはじめていることは認めざるを得ず、パーシヴァルはちいさく悪態も零した。
重くだらんと脚の間に垂れ下がっていた陰嚢も徐々にきゅうと締まり持ち上がっていき、それに伴い先程まで微塵も反応を示さなかったはずの陰茎がぴくりと反応し上向きはじめた。――そうして気が付けば、すっかり陰茎は立派に勃起していた。
こんなことであっさり勃起してしまったことに悔しさのようなものを感じ顔を苦々しく顰めたパーシヴァルを、顔を上げたヴェインがしてやったりとにんまりいやらしくわらう。
本当に、この男はヴェインなのか…そう思ってしまうほど、虚ろ気味に揺蕩う緑の色も、そそりたつ陰茎に涎を垂らす口元も、これまで数日間見てきたヴェインとはあまりにもかけ離れている。
「んく、…む……、ん、は…ぁ…」
ぱくりとヴェインのおおきな口に陰茎がのまれる。肌寒い外気に晒されていた陰茎が生温かい肉に包み込まれ、温度差に腰がぶるりと震える。生温かい口内に招かれて歓喜するようにカウパーを垂れ流し、それがヴェインの唾液と空気とで混じってじゅぽじゅぽ不格好な水音が立つ。
「…、…ッ…ク、」
ふうふう堪えきれない吐息がパーシヴァルの唇から零れ落ち、じわりじわりと追い詰められるようにして射精欲がこみあげてくる。生温かい口内も、丁寧に舐めしゃぶる肉厚な舌も、存外柔らかい唇も、すべてが丁寧にパーシヴァルの陰茎を愛撫する。
思えば、ボスが病に伏してから何かと忙しく肉体的にも精神的にも余裕がなかったためこうした行為は随分久しい。そのせいだ、と言い訳をしなければならないほどパーシヴァルの高揚感はとめどなく高まっていく。
ぐしゃりと己の前髪を掻き上げたパーシヴァルがふと見下ろすと、ヴェインはパーシヴァルのモノを舐めしゃぶりながら己のズボンに手を突っ込んでいた。しかも、今尚勃起したままの前ではなく、尻に。
驚くべきことに、ヴェインは己の尻の穴に自らの指を入れていたのだ。
――パーシヴァルはその光景に、思わず見入っていた。男の陰茎を咥え、己の尻を弄るその姿のなんといやらしいこと。
やがて、ヴェインはゆっくり己の口の中から今にも弾けそうなパーシヴァルの陰茎をゆっくり取り出し、ゆらりと体を起こした。ヴェインの口の端から垂れるそれは唾液とパーシヴァルのカウパーだが、車窓から差し込んだ朝日で透けきらきら光りまるで繊細な糸のようだった。
微かな金属音を立て外されたヴェインのズボンが、シートの下に落ちている���ーシヴァルのズボンの上に重なる。
眼前に晒されたその素肌にパーシヴァルは目を丸める。
(――タトゥー)
パーシヴァルの上に跨ったその脚には、大きなタトゥーが大胆に深く刻まれていた。太腿から腰のあたりまで伸びるそれは、まるで肌の上を這いずりまわっているようだ。曲線が組み合わさった黒一色のタトゥーは実にシンプルで、種類としてはトライバルタトゥーに近いだろうか。
タトゥーを身に刻むことなど、今となっては普通のことだ。ファミリーに属している人間もそのほとんどがどこかしらにタトゥーを入れている。パーシヴァル自身もそうであるし、あのジークフリートだって入れているらしい。
しかし――ヴェインが、タトゥーを入れているという事実はパーシヴァルにとっては衝撃だったのだ。
「ぁ、ふ…っ、ぁあ……」
パーシヴァルが衝撃を受け固まっている間にヴェインは腰を沈め、己の指でほぐしたアナルにカウパーを垂らすパーシヴァルのそそり立つ陰茎を埋めた。
「! ぅ…ッ」
口内とは比にならず、また女性の膣内とも違う内部の熱と締め付けにようやっとパーシヴァルは我に返り、呻く。
ヴェインが腰を揺らめかす度にふたりの体重分、ボロ車がぎしりと揺れ傾く。
パーシヴァルが動くまでもなく、ヴェインは快楽を追って好き勝手腰を振り己の陰茎をも扱いて感じいっている。潤む瞳は変わらず虚ろげで、間違いなくパーシヴァルとセックスをしているはずなのに、パーシヴァルをまるで見ていない。
(――ふざけるな)
怒りで頭に血が上る。パーシヴァルは快楽を上回る感情の奔流のまま、己の上でなおも体をくねらせるヴェインの胸倉を掴みシートに半ば突き飛ばすように押し倒した。
どすん、とも、ぎしり、とも、車が悲鳴を上げる。ちいさなこの車では、体格の良い成人男子の体重が一気に片側に偏るだけであっさり傾いてしまう。
押し倒されたヴェインが、パーシヴァルを見上げる。それでも緑の瞳に輝きは戻らない。パーシヴァルの網膜に焼き付いた、うつくしい翠はどこにもない。パーシヴァルの姿さえ、映らない。
「――……パルツィ」
パーシヴァルの偽りの名が、ほろりとヴェインの唇から零れ落ちる。
ヴェインはあの晩のように徐々に顔色を青くし、ちいさく震えた。正気に返り、己のしでかしたことの大きさに気付きでもしたというのか。それとも、これがヴェインの気づかれたくない“おそろしいこと”だったのか。
「ぉ、おれ…っ、ァ…!? ぁ、待っ…!」
しかし、正気を失っていたにせよそうでなかったにせよここまで散々煽り好き放題人のモノを使ってほとんど自慰のような行為に付き合ってやったのだ、パーシヴァルはヴェインの言葉を待たずタトゥーの這う足をがっしりと抱きかかえ、ずん、と奥を突き上げた。
「っ、…ッ…! んんンッ、んく、ぅぅ…っ!」
ビク、と震えたヴェインはぱたた、と己の割れた腹に白濁を飛び散らした。たったひとつきでヴェインの高まった体はいとも簡単に達してしまったのだ。
本来であればさぞ高く啼いたであろう声は、すべてヴェインの宛がった手に吸われてしまった。
「ふ、…っ」
達した余韻でぎゅうぎゅうと中に締め付けられ、パーシヴァルも腰を震わせ白濁をヴェインの中に放った。
久方ぶりの快楽にずきずきと頭が痛む。眩暈のような心地の中、ゆっくりと瞬きをし見下ろすとヴェインは瞳を閉じぐったりと気を失っていた。
5.
「よ! おはよ、パーさん!」
「…………」
翌朝。今日は珍しくヴェインが家まで押しかけてこなかったので、本当だったらいつもの場所であるはず――初日に待ち合わせた場所だが翌日から毎日ヴェインが家に押しかけてきたのでここで待ち合わせるのは初日以来――の広間に行くと、ドン引きするほどいつも通りのヴェインに朗らかな笑顔で迎えられた。
すん、と無表情になったパー��ヴァルは内心“は?”である。
昨日は、結局ヴェインは気を失ったまま起きなかったので、パーシヴァルは後始末をしヴェインにしっかり服を着せ、それから車を運転しヴェインを家まで送りベッドに寝かせた。
――そうだ、昨日は正真正銘パーシヴァルとヴェインはセックスをしたはずなのだ。ヴェインも途中まではどうだか知らないが最後は正気に戻ってパーシヴァルを認識していた。
これでもパーシヴァルは、翌日ヴェインがどんな反応をしてくるのかと結構考えたのだ。あんなことがあったのだ、さぞ気まずかろう…そんな風に思ったというのに。先日の風呂場の件のときといい、この男いくらなんでも神経が図太すぎやしないだろうか。そしていつもいつも、何故パーシヴァルばかり気まずい思いをしなければならないのか。
そもそも、今回に至ってはどう考えてもヴェインに100%非がある。どんな事情があるのか知ったことではないが、ヴェインがパーシヴァルを襲ったという点においては間違いがないのだから。
「どうしたんだよパーさん! 顔色悪いぞ~? あ、さては朝飯食ってないんだろ!」
……馬鹿だ。こいつはやはり筋金入りの馬鹿なのだ。人が決して良いとは言えない顔をしているときは必ず腹が減っているとなぜ思えるのかいまだに不思議で仕方がない。パーシヴァルにはヴェインの思考は到底理解できるものではなかった。
(…馬鹿らしい)
理解しえない人間のことを気にするのも、正直ばかばかしくなってきた。パーシヴァルもまあ、昨日のことは犬にかまれたとでも思って流すことにしようと決める。常々、ヴェインは動物で例えるのならば犬であろうと思っていたのである意味ちょうどいい。しかも躾がされていない、吠えて煩い駄犬だ。我ながら良い例えだと内心得意げに頷く。
「この近くに、モーニングが美味しい店があるんだ。そこ行こうぜ!」
「――店?」
「うん、そう。あ、すげえ安いから安心しろよ! なんだったら俺のおごりでもいいし」
俺先輩だからな、とふふんと胸を張る姿に、馬鹿か、と素直な言葉を溜息と共に吐くとヴェインはむうと頬を膨らませた。こいつ俺が実はアンダーボスなのだと知ったら今までの己の発言と行動を振り返って卒倒するのではないか、となんともなしに思い、それはそれで面白そうだといずれ来る日のヴェインの反応にほくそ笑む。
それにしても、珍しいこともあるものだ。朝昼晩全てヴェインは自分の家までパーシヴァルを引きずり込んであれよこれよと振る舞ってきていたが、今日は店の気分のようだ。
微かな違和感を覚えながら、そういう日もあるのだろうと思い、あれほど美味い料理を作るヴェインが“美味い”と評する店へ期待に胸を膨らませるのだった。
――違和感は何日も続いた。ヴェインは朝昼必ずどこかしらの店に行こうとパーシヴァルを誘い、仕事が終わった夜はさっさとひとりで家へ足早に帰ってしまう。
(わかりやすく露骨に避けているな)
最早ここまで来ると、パーシヴァルもだいたいのことを察した。ヴェインはなんでもない振りをしていつも通りを装っているが、その実パーシヴァルを避けている。…いや、正確に言えばパーシヴァルとふたりきりになるのを避けているのだろう。
何故か、などというヴェインの心理など詳しくは察しようもないが、セックスをしてしまったことが原因であることだけは間違いない。
チ、と薄暗い自室に苛立たしげなパーシヴァルの舌打ちが虚しく響く。
何を苛立っているのかも今となってはわかりようもない。ヴェインがパーシヴァルとセックスしたことをなんてことのないようにしていることなのか、今までしつこい程にべたべたしてきたくせに今さら露骨に避けられどこかよそよそしくされていることなのか、確かに美味いはずの店の料理を口にしてヴェインの作った料理のほうが美味いと無意識に考えてしまった己になのか。
(――どうでもいい、そんなことは)
ばさりと布団をかけなおし、目がさえているが瞳を閉じて無理矢理寝入ることにした。
「――、――」
――誰かに呼ばれている。吐息をそっと吐き出すように囁くその声音にパーシヴァルは、ようやく眠れたというのに…と不満げに薄ら瞳を開ける。
「ぱーさん」
「……ヴェ、イン…?」
ぼやける視界に映るその姿は――ヴェインだった。衣服を何も身に着けていない全裸のヴェインがパーシヴァルの上に跨っていたのだ。
あまりにも突然のことで状況が理解できず呆然とした声を洩らし強張ったパーシヴァルの頬を、ヴェインの太い指が撫ぜる。
意味がわからず丸めた瞳で見上げると、ヴェインはうっそりと微笑みを返した。まさかまた発情でもしているのかと思ったが、その瞳は先日見た虚ろげなものではなくパーシヴァルがいっとううつくしいと思った爛々と輝く翠を宿していた。
ああそうだその瞳がほしかった――パーシヴァルが思わず手を伸ばすと、ぐちゅり、と下半身から鈍い水音が響いた。
「んあっ…ぁは……、ぱーさんの…っおっきくなった、ぁっ…」
「ッ…! き、さま…っ」
跨っている時点で疑うべきだったのだが…、まさかそんなことをされてはいまいと思っていた。しかし、ヴェインはいつも通りパーシヴァルの想像の斜め上をいくもので、パーシヴァルの陰茎はヴェインのナカにずっぷりと埋め込まれていた。
そして、興奮で膨れた陰茎にうっとりとした声を洩らし恍惚とした表情を浮かべるヴェインは己の腹をいとおしそうに撫ぜた。明け透けなその仕草にもあっさり質量を増した素直すぎる己の陰茎にも、パーシヴァルはカッと顔を赤くする。
「くそっ…、貴様は…!」
「ぅあッ…! ァ、ッ…あ、だめ、ぱぁさん、もっとゆっくり、ぃっ…!」
好き勝手されるのはやはり性に合わないのだ。くねるヴェインの腰を鷲掴みにすると思い切り腰を突き上げ、そのままがつがつと幾度も突き上げてやるとヴェインは根をあげるような言葉を喘ぎまじりに言うが、その声音は甘ったるくて、むしろもっとしてほしいと言っているようだった。
「くぅ、ンッ…! あうっ、ひ、ああ、やさしくして、っ、ね、ぱ、さんっ…」
とうとう膝を立てることさえ困難になったらしいヴェインは倒れ込むようにぺたりと上半身をパーシヴァルにくっつけて、うるうる潤んだ瞳で訴えかけてきた。ぱーさん、ぱーさん、と甘えるように何度も何度もパーシヴァルの名を呼ぶそのくちびるはいやらしく濡れて艶めいており、なんだかとても美味しそうに見えた。
ふらふらと吸い寄せられるようにしてパーシヴァルはヴェインの頭に手を回し、そのくちびるにかぶりついた。普段かさついているくちびるもこの時ばかりふにふに柔らかく、心地よくて馬鹿みたいに夢中になってくちびるをむさぼりながら、パーシヴァルは膝を立て緩めることなくヴェインの身体をゆさぶるように突き上げた。
「ん、ふっ…んン…あふ…」
くちびるの隙間からヴェインの吐息が洩れる。パーシヴァルが薄ら瞳を開くと、同じくらいのタイミングでヴェインも瞳を開いた。ヴェインの瞳には涙が滲んでおり、ほんの僅かに翠が薄くなって甘い色になっていた。ああ、その色もいいなと思うと下腹が痛いほど疼いた。
「ぁ、もぅ…っ、も、だめ…」
「ああ…っ、ク、おれも…」
くちびるを離すと、ヴェインは限界のようでふるりと首を振る。その兆しのようにきゅうきゅう締め付けるナカに絞られるパーシヴァルもそろそろ限界が近い。一緒に、とヴェインが囁くように耳元にくちびるを寄せていやらしくねだってきたので、パーシヴァルはヴェインのびくつく腰を撫でながら抱き寄せ、お互いの汗ばむ額をくっつけてこれ以上ないほど密着した。
そしてふたりは――、
「……。……! …!」
がば、とパーシヴァルは文字通り飛び起きた。――今、…今自分は何を見ていた? 動揺しながらパーシヴァルはぱさりと垂れ下がってきた己の前髪を、ざわつく己の胸中を落ち着かせるようにかき上げる。
何も身に着けていない裸体の上半身には僅かに汗が滴り、心臓はドクドクと全身に響く程高鳴っていた。そして、嫌な予感がしておそるおそる下半身を覆い隠している布団を捲りあげると、身に着けているズボンが僅かに変色しこんもりと盛り上がっている。
(――最悪だ……)
ひどい夢を見た。気分は最悪だ。よりにもよってヴェインとセックスをする夢を見るなどと……しかもその夢で、現実でも勃起してしまうなど。
いやらしい夢を見て興奮してしまうなど青臭い童貞のすることだ。とうの昔に欲求を暴走させることもなくあっさりとそんなものを捨てるようにして卒業したパーシヴァルは、腹の内でぐるぐる渦巻き暴れまわり落ち着かない己の欲求とはじめての経験に顔を苦々しく顰めさせた。
「…ッくそ…」
ひとり悪態を洩らしても、一度膨れ上がった股間が静まってくれる気配はない。そして、こんな現状で眠りにつくことも不可能だ。
何故俺がこんなことをしなければならんのだ、と苛立たしく舌打ちを零しながらズボンを下着ごと荒っぽくずり下ろす。すると、パーシヴァルの最悪な気分とは裏腹に陰茎はカウパーを漏らしながら元気にぶるりとまろび出た。
己の肉体の一部がこんなにも憎らしく思える日が来ようとは、と自嘲気味な笑みを零しながらパーシヴァルは手を伸ばし萎えることなく血管の筋を浮かばせる陰茎を握り込んだ。
「ク…、ッ…は、」
早く終わらせてしまおうと性急に上下に扱き上げる度、にちゃにちゃといやらしい水音が余計大きく立ち、パーシヴァルの羞恥が煽られる。
日頃自慰をまるでしない、というのはいくら欲求が薄かろうと男である以上無理なものだ。生理的な反応故、一般的かつ平均的な回数今までもしてきたが、あくまでも生理的な反応と割り切って事務処理のように淡々とこなしてきた。快楽に耽ったことも皆無――のはずだった。
ふわふわおかしな心地で腰が浮つく。擦り上げる度に痺れるような快楽が頭のてっぺんまで突き抜け、だしたくもない声と吐息が止めようもなく洩れる。
下ろした瞼の裏側に映るのは、パーシヴァルが過去にセックスの相手をした大層な美女たちのいずれでもなく、先程の夢に出てきたヴェインだった。
いくら強く握り込んでも、ヴェインのナカの締め付けや熱は再現できようもないが、まるで突き上げるように腰が勝手に揺らめく。熱で浮ついて麻痺する頭はたったそれだけで愉快な勘違いをしてしまう。
「ぅ…、ぁ、ハ…ッ」
どぷ、と精液が噴き出し溢れる。数度扱き上げ、残滓も残らず漏らしたところでパーシヴァルはゆっくりと瞳を開いた。
当然眼前には誰の姿もなく、静寂と暗闇に包まれた自室にパーシヴァルの荒い吐息だけが響いている。
射精後の冷めた心地で己の股間を見下ろすと、とろとろと白濁とした体液を零しながらも少しずつ擡げていた頭を垂らしていく。――終わったはずであるのに、パーシヴァルは動くでも眠るでもなく己の手に纏わりついた欲望の証である白濁をただただ見下ろしていた。
「…お、…パーさん…今日は一段と顔色悪いな…?」
あれから一睡も出来ぬまま朝を迎え、気分も体調も最悪のままヴェインと顔を合わせた。
待ち合わせ場所にパーシヴァルが現れると、いつも通りぱっと笑顔を浮かべて手を上げたヴェインもパーシヴァルの顔色の悪さに気付いたようで、怪訝そうな表情を浮かべた。
「……黙れ」
「――…あのさぁ……、いや別にいいけど…。じゃあ朝ご飯食べに行こうぜ」
今は正直ヴェインの顔を見ても苛々するだけだ。完全に八つ当たりでしかないこともパーシヴァル自身わかっていたが、それでも割り切れない部分があり唸るような声で吐き捨て、顔を逸らした。
ヴェインは不満そうに何か言いかけていたようだが、パーシヴァルの態度を見て結局何を言うでもなく口を噤み、会話を切り上げ踵を返してさっさと歩きだした。
何か文句でも言いたそうな感じではあったが、そんなこと知��たことではない。文句を言いたいのはこちらのほうだ、とパーシヴァルは歩き出したヴェインの背を睨み付けた。
結局、朝から一日険悪な雰囲気がふたりの間に流れ一言も言葉を交わすことなく、黙々と言いつけられた仕事をこなした。ヴェインが静かな分、パーシヴァルの本来の目的である調査に集中出来たのでよかったと言えばよかったけれど。
こういう時に限ってヴェインは道を間違えないので、もしかしてこいつ方向音痴なのは嘘なのではあるまいなと疑いそうになったものの、そんな器用なことをヴェインが出来るとは思えない。だが、こうしてみるといつも喋り出すのはヴェインからで、パーシヴァルから喋りかけたことは少なかったのだと気付かされる。ヴェインがとんと無口になると、ふたりから一切会話がなくなるのだということにも。
そうして夜になった。どうせこの後もヴェインはさっさと帰るのだろうと思いながら、街の中心部からお互いの家がある郊外への帰路を辿る。
「……あの、パーさん」
ふたりの家はほとんど真反対の方向にある。ちょうど分かれるところである丁字路を曲がろうとすると、背後からヴェインに声を掛けられる。
朝ぶりに聞いたヴェインの声に、パーシヴァルは足を止め返事をするでもなく振り返った。
「……これ」
気まずそうに顔を逸らしたヴェインが鞄から何やら取り出して、ずいと差しだしてきた。
何かと思い近づき、その手に乗っているものを受け取って見下ろす。ちいさな個包装に入っているのは花のようだった。黄色の中心部から細い白の花弁――乾燥されているカモミールだ。ヴェインがなんともなしに始めて続けていると言っていた家で栽培しているハーブティーになるひとつで、パーシヴァルも何度かヴェインの家で馳走になったことがある。
ヴェインの意図がわからず、パーシヴァルは何も言わずに視線を上げヴェインを見つめた。
「…あんま、寝れてないっぽかったから……それ、寝る前に飲むとよく寝れるから、だから……その」
そういえば昼間、ヴェインはほんの数十分程どこかへ姿を消していたが……これを自宅に取りに帰っていたのか。パーシヴァルがいかにも睡眠不足の顔をしていたから、わざわざこれを。
――何なんだ、この男は。ヴェインと出会ってからもう幾度も同じことを思った。しかしそれ以上に、説明のつかない何かが胸中に満ちパーシヴァルは何も言えずただその場に立ちすくんだ。
「っ~、そんだけ! じゃあな!」
沈黙が耐え切れなくなったのか、ヴェインは強引に切り上げると背を向けてずんずんと大股で歩いていってしまう。
パーシヴァルは掌に乗ったハーブティー用のカモミールが入った包装をもう一度見下ろす。中にはカモミールとは別に、ちいさなメモが入っており、少し袋を振って重なっているカモミールを端に寄せて書かれた文字を見る。どうやらメモはヴェインの手書きのようで、ハーブティーの淹れかたが事細かに書かれていた。
「……」
もう一度顔を上げると、大股で足早に歩くヴェインの背はいくらも遠くにあった。もうあといくらかすれば角を曲がって見えなくなるその背を、パーシヴァルはじっと見つめる。
――別に、ハーブティーをもらっただけだ。パーシヴァルは立場であり、容姿であり、それらからいくらだって他者から贈り物をされたこともある。そして、その中でヴェインからのものは一番地味で全く一切金銭価値がないものと言えるだろう。それに、ヴェインはパーシヴァルの本来の立場を知らないし、容姿が好みだというわけでもないはずだ。
ふと、ヴェインがよく口にしている“ともだち”という言葉が浮かぶ。そう、ヴェインは結局のところパーシヴァルを勝手に友だと思っているのだ。だから心配して、贈り物をした。ただ、それだけだ。
それだけなのに、どうしてか手の中のちいさな贈り物がパーシヴァルには何よりも尊く思えた。
――気が付けば、パーシヴァルは足早に自身の家とは真反対になる道を歩き出しヴェインの背を追っていた。何をやっているんだ俺は、と思いながら。
「おいヴェイン」
「! うわびっくりした! な、何だよパーさん道間違えんなよ、パーさん家反対だろいつも俺に道間違えんなとか言ってるくせに」
背に少し追いついたところで声を掛けると、ヴェインはビクと肩を揺らし少し振り返ると大袈裟な程大声を上げた。静かな夜にヴェインの大声はなかなかに響く上���散々な言われようにパーシヴァルは顔を顰める。
「貴様と一緒にするな、誰が間違えるか」
「へ、へー、あっそ」
じゃあ何故こっちに向かって歩いているのか、ということを尋ねない辺り、ヴェインはパーシヴァルが自分に着いてきているのだと気付いているはずだ。
何も問いはしないが、明らかに着いてきてほしくはないというように更に歩く速度を上げる。やはり、どうあってもヴェインはパーシヴァルに家に来てほしくはないらしい。歩く速度を上げたのはパーシヴァルを撒くためではなく、その来てほしくないということをアピールするためだろう。しかしわざと気づかないふりをしてパーシヴァルは黙々とヴェインの後ろをついて歩いた。夜も遅いため、周囲にはひと気がないが傍目に見れば男ふたりが縦に並んで足早に歩いている様は随分おかしいものであろう。
「じゃ、じゃあ、おやすみパーさん!」
「おい待て」
早足だったせいか普段よりも幾分か早くヴェインの自宅に着いた。ヴェインは扉の鍵を開けさっさと中に入ると、パーシヴァルの目の前で堂々と扉を閉めようとするのでその隙間に足を差し入れ阻止すると、ぎゃあ! とヴェインが喚いた。うるさい。
「人が家まで来てよくも扉を目の前で閉められるな、貴様」
「え、ええ…だってパーさんいつも俺の家くんの嫌そうにしたじゃん、渋々って感じだったし……」
「……」
そんなことはない、と言い切れないのはたしかだ。ヴェインは貴重な協力者だったがため仕方がなしに付き合ってやるか、と思っていたのでまさしく渋々だったのだ。
「ご、ごめん……今は、本当に無理なんだ……」
図星に他ならず黙り込んだパーシヴァルをなんだと思ったのか、ヴェインはちいさい声でぽつりとそう呟いて顔を逸らした。
「――俺と、セックスをしたのがそんなに気になるものか」
「……!」
はっきりと遠慮なしにパーシヴァルが核心をつくことを口にすると、ヴェインはびっくりしたように目を瞠ってパーシヴァルを、信じられないとでかでかと書かれたような顔で見た。パーシヴァルも避ける話題だとでも思っていたのだろうか。
特に表情を変えるでもなく真っ直ぐに見つめると、ヴェインはさっと再び顔を逸らした。
「そ、そうだよ! それ以外ないだろ! お、俺っ変で…、でも、そういうことしない限りは平気なはずなのにっ…パーさんと、ふたりっきりになるの、考えただけでまたおかしくなっちまいそうで…、パーさんだってあんなの二度とごめんだろ、だからっ!」
ヴェインが顔を上げた瞬間、パーシヴァルは開きかけている扉に手を掛け強引に押し開けると、そのままヴェインの言葉を遮り口を塞ぐようにしてキスをした。
あまりに突然のことだったせいか、ヴェインは目を見開いたままかちんこちんに固まってしまい、閉めようと掴んでいたドアノブからも手をぽろりと外してしまっている。これ幸いと、キスをしたままパーシヴァルはその身体を押しやり家の中に滑り込んだ。
背後で扉の閉まる音がするのと同時に、そっと唇を離す。大して長い間塞いでいたわけでもないのに、妙に荒いヴェインの吐息が静寂に満ちた空間に響く。
「だ、だめ、…だって……ぱーさん…はう」
たじろぐヴェインの腰に手を回し抱き寄せると、その身体はとっくに熱を帯びていて指先で撫ぜるだけで蕩けそうな声が上がる。
だが、パーシヴァルは気をやったヴェインを抱く気は毛頭ない。あのくすみ淀んだ瞳に用はないのだ。
パーシヴァルが何も言わず瞳を覗き込むと、まるで射竦められたようにヴェインがハッと息を呑んで瞳を瞠る。淀みかけていた瞳が再び正気に戻る。
車の中でしたときも、ヴェインは途中でたしかに我を取り戻したのだから、セックスをしている間中トんでいるわけではないのだろう。どうすれば戻ってくるかなどわかったことではないが、こうして今戻ってきたことが全てな気がしてパーシヴァルは褒美を与えるようにまた唇にかぶりついて、舌を絡めとってやった。
「――ぅ…やっぱむ、むり、どうしていいか、わか、んねえし……」
「…あの時散々してただろうが」
「あ、あれは! あれは…俺も、わかんない内に勝手にやってるっつーか、…ほら…酔っぱらってるときって、よく覚えてないだろ…そういう、感じなんだよ…」
玄関先からベッドルームに移動して、たんまりキスを堪能したあと服を脱がせ合ったふたりであったが……ヴェインはパーシヴァルへの口淫を渋っていた。
ヴェインは自分の尻のほぐしかたもよくわからなくなっているようなので、パーシヴァルも決して詳しいわけではないがあの時のヴェインの様子からしてそこまで困難ではなさそうなので、見よう見まねでやってやることにしたのだ。その間、口淫でもしてもらおうと寝転んだパーシヴァルの上に頭の位置を逆に四つん這いにさせたのだが、どうやらトんでいる状態の技術は正気のままのヴェインでは出来ないらしい。
酔っぱらっているときの状態を覚えていないというそれ自体がパーシヴァル自身にはまるでわからないが、酔っぱらって記憶を飛ばしている人間ならば確かに見たことはある。だとしてもあれが酔っぱらっている状態と同じと言われてもピンとこないが。
「…わかった、ならしなくていい」
下手にやらせて歯を立てられても正直困る。以前食事中にちらりと見えたヴェインの尖り気味の歯を思い出し、あれで齧られなどしたら――と考えると縮みそうだ、色々と。
しなくてもいいと珍しく優しい言葉を掛けてやったというのにヴェインはいまだううと諦め悪く唸っている。そんなヴェインを放っておき、パーシヴァルはヴェインの家に何故かあったローションを自身の手の上と眼前に晒されているヴェインの尻に垂らし早速準備をはじめることにした。
「んッ…」
尻にローションがかかり、ヴェインはびくりと肩を竦める。パーシヴァルも己の手にかかったローションのひんやりとした感触に、たしかにこれを尻にかけられたら冷たいだろうなと思う。
やはり最初は、小指辺りからいれるべきなのだろうか。女性とのセックスでは指でほぐすということもするにはするが、女性の膣は基本濡れるので余程のことでない限り実際に膣に指を入れて丹念にひろげるということはしない。前戯としてするだけで、必須事項ではないだろう。
しかし元々そういった行為のためにあるわけではない男の尻が濡れるわけがないので――むしろ濡れたら一大事だ――、指を入れてナカをローションで濡らすということは必要だ。
「ぁ、っ…ン…」
考えた結果、とりあえず中指を宛がう。すると、見る見るうちにパーシヴァルの細長い中指はヴェインのナカにのまれていくではないか。パーシヴァルの指を食んだナカの肉壁はうねうねとうねり懸命に縋りつき、入口の輪は健気にぴっちりと吸いついてくる。
しかも、ヴェインは痛がるどころか腰をぶるりと震わせ善がっている。
この男の身体は一体どうなってしまっているのだ、といっそ探究心が煽られる。
そもそもが、同じ状況に陥ると自身ではどうしようもなくなってしまう“パブロフの犬”のような状態になるほどなのだから、体もそうなっているのかもしれない。
「は、…ハ、は、ぅ…ぁ、…あ…」
パーシヴァルは好奇心のまま一本、また一本と指を次々とヴェインの中に収めていく。どこかで痛がればやめようと思ったのに、指を増やしてぎちぎちになった肉壁に指が触れる度にヴェインは体をよじらせ、嬌声をあげる。そしてその度に、陰茎を握っていたヴェインの手が力んできゅうと窄まり、湿っ���吐息がかかりパーシヴァルも僅かに息を詰める。
「ん、ん…っ、んむ…」
とうとう意を決したのか、ヴェインはパーシヴァルの指に翻弄されながらもおそるおそるといった様子ではあるがパーシヴァルの陰茎をくちびるでくわえた。
懸命に舐めているようだが…本人も言っていた通り、あの状態のときと違って舌使いはかなり拙い。ぺろぺろと幼児がアイスキャンデーでも舐めるような単調なそれに技術もへったくれもないが、むしろそれがパーシヴァルの劣情を煽るようだった。
(俺も焼きが回ったものだな)
すっかり下半身に熱を溜めたパーシヴァルは内心自身を笑いながら、ヴェインが苦しくなったのかぷはと陰茎から口を離した隙にするりと下から抜け出し、無防備な背を押してベッドに寝かせる。
「あ、ぱーさん…」
大人しくベッドに半身を埋め、そろりと肩ごしに振り返ったヴェインの顔には困惑と不安が浮かんでいるが、その奥にはありありと隠しきれない期待が滲んでいる。淀みもなく潤んだ瞳にパーシヴァルはうっそり微笑みかけながら、勃起した自身をヴェインのアナルに押しつけた。
「んっ…ん、く、ぅぅ…ッ!」
指がもう何本もあっさり飲みこんだアナルはパーシヴァルの陰茎もすぐに飲みこんだ。ずぷずぷと焦らすようにゆっくり押しこんでいくと、ヴェインは時折腰をへこませながらベッドシーツに皺が寄るほどしがみつき枕に顔を埋めた。
そのせいでヴェインの嬌声らしきものは全て枕に吸いこまれてしまった。車内でシたときといい……トんでるときはこれでもかといやらしく啼いてみせるくせ、どうやら正気のヴェインは声を何が何でも聞かせたくないらしい。
――ほうなるほど。パーシヴァルは、かわいそうなくらいぷるぷる震えながら枕に顔を埋めるヴェインを静かに見下ろす。
当然そんなことを許すパーシヴァルではなく、がしりと枕を鷲掴んでヴェインから強引に奪うと部屋の隅まで放り飛ばした。
「あっ! やだ、や、ぱーさッ…ぁあ…!」
「くぐもった声を聞かされるこちらの身にもなれ、馬鹿者」
「ひ、ぁ、ンッ…だ、だって…っ、ぱーさん、おんなの、ひとと、ハぅ、んく、いっぱいっ…えっちしてるだろぉ…っ!」
「…………は?」
以前のように手で口を塞がれぬように手首を掴んでベッドに押しつけ、ようやくこれで始められると満足して腰を動かし始めたパーシヴァルだったが、ヴェインの意味不明な発言に急激に力が抜けていくのを感じ、動きを止めてしまった。
…今、この男何を言ったのか?
「だ、だって、俺男だし! 女の人みたいにかわいい声だせねえもん! それで萎えたとか言われても、ヤだし…っ!」
「待てそれ以前に“いっぱい”しているという発言を訂正しろ」
「ううっ…だってパーさん顔いいし、ち、ちんこ強いし…女の人放っておけねえじゃん絶対!」
「ぐ…貴様と話していると頭が痛くなる!」
同時にパーシヴァルの知能まで同じように急激に下がっていくような気分になる。いちいち発言が馬鹿っぽいのだ、ヴェインは。しかしわざわざこんな時にまでその馬鹿っぽい発言はやめてほしいものだ。
ついでに言えば、断じて“いっぱい”しているわけではない。“ちんこが強い”というのは意味不明だが、実際パーシヴァルはその容姿から女性が放っておかないのは本当で、そういう誘いが多いのも確かだった。けれどその誘いに乗るかどうかはパーシヴァルのそのときの気分次第なわけで、大概が気分ではない。そこまで派手な夜遊びをするような性格ではないパーシヴァルは、嗜み程度にしかしてきていない。
「なんで!? 俺なんか間違ったこと言ったかよ?! パーさんのばか! ずる剥けちんこ!」
「なんだと!? 貴様は幼児か!」
よくもまあそんなことが言えたものだ。ヴェインはパーシヴァルのことばかり言うが、ヴェインのモノもなかなかに凶悪な大きさと太さだ。並の女性では勃起したそれを目の前にすれば一瞬怯むはずだ。
「っ…いいから大人しく俺の下で啼いていればいいんだ、貴様は」
「なにそれ横暴っ――…ひぁ、やあ…っ!」
逃がさぬようにベッドに押しつけていた両手を掴みあげヴェインの上半身を起こし上げながら、パーシヴァルが思い切り奥を突き上げると思いのほか大きな喘ぎ声が響く。
「あっぁ゛あ! うッや、ぁ、やあ、ぱーさ、ぱぁさん、も、ゆっく、んハ、り、ぃ…っ!」
膝立ちと手綱のように両手を引っ張られ逃げられない状態で、硬い陰茎に激しく貫き犯され、ヴェインはほろほろ涙を流しながら一生懸命パーシヴァルに訴えかけてくる。
「ハ、ッ…、はは…、もっとやさしく、か?」
――ああなんだかどこかで聞いたような言葉だ。まるで正夢のようでおかしくて、パーシヴァルは吐息と一緒に笑い声を零しながらヴェインの耳元に舐めるように囁きかける。
「ん! ん…ッ! おねが、おねがい、だから、ぁっ…ぱーさ、ぁんっ…」
こくこくと夢中に頷き懇願するその姿に満足して、許すように囁きかけた耳元をぞろりと舐めあげるとぶる、とヴェインが震え甘ったるい声を漏らした。同時に、ずっと放置されていたはずのヴェインの陰茎から精液が噴き出した。
「ふ、――……、ハ、…ああ…」
リクエストにこたえてゆっくりとした速度で何度か肉筒の中を行き来すると、パーシヴァルも深く息を吐き出しながら精液をヴェインのナカに放った。
「――俺さ、はじめてヤったのってスラムにいたころなんだよな」
――あれから数度交わり行為が終わり、後始末もシャワーも済ませ、再び寝室に戻り一息ついたころ――パーシヴァルの隣で寝転んでいたヴェインは天井を見上げぽろりと突然そう切り出した。
「……スラム出身だったのか」
「そう。…とか言って、パーさんの事だからなんとなく察してたんだろ、そんなこと」
「――それは…」
確信があったわけではない。ヴェインの弱々しい瞳をスラムにいる人間と重ねあわせてしまったのは事実だ。だが、それを除いてはヴェインはやはり普通のどこにでもいる青年で…、だから確信がなかったが、やはりヴェインはスラムの出身だったのだ。
「ハハ、だよなぁ……。まあ、それでさ…スラムで俺を育ててくれたじーちゃんが死んで、俺ひとりになって…天国のじーちゃんを心配させないためにも俺はひとりでもちゃんと生きてくぞー!って新しい明日に向かって踏み出したらあっさり。ボッコボコにされて何人かに押さえつけられて。朝にポイ捨てみたいに放っておかれたとき、ああ俺何してんだろって思った」
つらつらと明かされる話にパーシヴァルは顔を顰めるが、当の本人であるヴェインは
「スラムではその一回だけ。そっから暫くしてこのファミリーのひとに偶然拾われて、頑張って働くぞって気合入れた初日でまた、されて。喧嘩の鬱憤晴らしだなんだって言われて、毎回、毎回、何度もされた。んで、気付いたら喧嘩とかあーいうことすると、わけわかんないくらい身体が熱くなって気が遠くなっちまうようになって」
何と言葉をかけていいかわからず、パーシヴァルが口を噤んでヴェインを見下ろしているとヴェインは、よっとちいさく声に出して起き上がるとパーシヴァルの肩からずり落ちていたシャツを恭しくそっと直してまたごろんとベッドに寝転がった。
「――それも、無理矢理入れられたのか」
何の恥じらいもなく大胆に全裸で寝転んだつい先刻まで抱いていたその姿を見下ろすと、やはり脚に這うタトゥーが異質のように思えてならず、パーシヴァルは思わず言葉を零した。
「ん? あー、これ。タトゥー?これは俺の意思。スラムで色々開き直って“やんちゃ”してたからさ、そのときに入れちゃえーって」
タトゥーが刻まれた素足を行儀悪くぷらぷら上げてヴェインはにひりと笑う。
なんとなくではあるが、自身の意思で入れたというのはおそらくは事実なのだろう。無理矢理入れられたのだとしたら、輪姦に強姦とそれ以上に非道なことをされてきたことをあっさりと話したくらいだ、わざわざ隠す必要もない。
しかし、“やんちゃ”することを楽観的に語るのは嘘らしく思えた。スラム――あの世界で生きるためには、なりふり構っていられないのがふつうで、自分を育ててくれたひとのためにもひとりで強く生きなければと、強く願ったヴェインが生きるために何をしてきたのかは――
「パーさん?」
ヴェインが逞しく生きてきた証なのだと思うと、このタトゥーもそう悪いものではないのかもしれない――パーシヴァルはタトゥーの刻まれたヴェインの太腿を慈しむように手を這わせながらきょとんと間抜けな顔のヴェインを見下ろし、ぽっかり半開きの唇にキスを落とす。
「ぱーさ、んっ…ふふ、なに…どーしたんだよ」
数度そうして唇を触れあわせると、ヴェインはくすぐったそうにわらいながら身をよじながらパーシヴァルの頬を両手で包むように摩った。
どうした、などと言われても、そんなことパーシヴァルが一番知りたかった。何故だか、むしょうにこの男にキスをしたくなったのだ。
「…パーさんの髪って、光にあたると少しあかくて、綺麗だな」
頬を包み込んでいたヴェインの手が撫でるように滑り、パーシヴァルの少し長い髪を梳く。今は髪染めでくすんだ色をしているはずなのに、綺麗などとこの男の審美眼はどうやら狂っているらしい……なのに、心底そう思って眩しいものをみつめるように瞳を細めるヴェインにパーシヴァルは言葉を失う。
そして、ふと先刻己の上に跨っていたヴェインの姿を思い出し、カーテンの隙間から洩れた光に透けてきらきら陽の光のようにきらめいていたこの男の金糸こそうつくしい――、そう思ってしまった自分もどううやら審美眼が狂ってしまったらしかった。
0 notes
Text
エンドロールにはまだ早い(柴君)
∵背中に想う
長く降った雨に打たれ、今年の桜は既に散ってしまった。新緑の生い茂る木々の足元で、ほんの薄く色づいた花びらだけが、濡れたコンクリートにいつまでも張り付いている。
送別会ラッシュがひと段落したかと思えば、すぐに歓迎会が催される。何かと理由をつけて飲みに出かけたいのは、春の穏やかな気候がそうさせるからかもしれない。全くはた迷惑な話だな、と年中金欠の俺は心の中で悪態付く。それでもこうして律義に出席する事におそらく理由はない。が、あえて言うのならばやはり春のせいなのだろう。
よく晴れた金曜日だった。その日の夜は高校時代に所属したサッカー部のOBが集まる、いわゆる同窓会の予定があった。急な休講により午前で講義を終えてしまった俺は、大学の敷地内にある図書館で時間を潰したのち、人々で溢れかえる駅の改札を抜けた。同じく飲みに来たのであろう人の波を避けながら、先のほうで信号待ちをする集団の中に見覚えのある男の頭を見つけた。頭一つ分ほどの目線の高さに燃えるような赤い髪。派手な身なりの男はどこからどう見ても大柴喜一だ。幼馴染で、犬猿の仲。高校を卒業して二度目の春を迎えた今も、その関係は変わっていない。だから一瞬、変わらない懐かしい後ろ姿に声をかけるべきか迷っていた。だが追いつく手前で歩行者信号が青に変わると、大柴は足早に去ってゆき、それ以上近づくことは叶わなかった。
まずいな、とどこかぼんやりした頭で思う。成人してもなお酒も苦みも得意ではないので、“とりあえず”のビールを残すとすぐにカルピスハイへと切り替えた。だが今思えばそれがまずかったのかもしれない。いつものように何食わぬ顔でノンアルコールにしておけばよかったのに、今日に限ってそうしなかったのは、この場の雰囲気に流されたからに違いない。早々に回ったアルコールのせいで耳や頬がひどく熱かった。
いよいよまずいなと思ったのは、場所を変え、二軒目へと向かおうというときだった。皆が笑いながらゆっくりと歩く中、ふと、先頭にいたはずの大柴が立ち止まり、靴紐を結び直すためにその場に屈み込んだ。繁華街の雑踏の中、眩いほどのネオンライトが、きちんと鍛えられた背中の筋肉を浮き彫りにさせている。あいつの体なんて初めて見たわけでもない。それなのにその後ろ姿を捉えてから、ずっと大柴から視線が外せない。
どこの駅前にもあるようなチェーン店の安居酒屋の、寂れた座敷席で皆が胡座をかくなか、大柴だけがその高い背をきちんと伸ばして座っていたり、トマトスライスをつまむ箸使いは意外にも綺麗だと思った。昔からこんな感じだっただろうか、と酔いのまわった頭で考えても仕方がないことはわかっている。だがあれから二年たった今、俺も大柴も少しだけ大人になっていても何らおかしい話ではない。
一番遠い席に座る男を眺めていると、時折視線が合ったように思うのは気にし過ぎているだけだろうか。よそった焼きそばを半分ほど皿に残し、誤魔化すようにカルピスハイを口に含む。同窓会というものに浮かれているのは、案外自分も同じかもしれない。
終電が間もなくだという理由で、二軒目の会計を済ませると会は一旦お開きになった。道のど真ん中で「よし、次行く人~っ!」と叫ぶ灰原先輩はすこぶる機嫌がよく、飲み足りないらしい上級生たちは次の店を探すためにそれぞれがスマホと向き合っていた。
「もう面倒くせぇから、歩きながら適当に入ろうぜ」
誰かがそう言うと、散り散りになっていた男たちはあてもなく夜の街をゆっくりと歩き出した。その間にもメニューを持った客引きのアルバイトが「お兄さんたち、どう?」「飲み放題980円ですよ」とひっきりなしに声をかけてくる。
「えーっと、今何人だ」
「十ぐらいじゃね?」
「君下、お前は終電大丈夫なのか?」
唐突に声をかけてきたのは臼井だった。ぼんやりと自分の足元を眺めながら歩いていた俺は、その声に熱くなった顔を上げた。セーブしていたのか、あるいは酒に強いのか、普段とあまり変わらない様子の臼井はにこやかだった。
「明日休みなんで大丈夫っす」
「そうか、それならよかった」
そうは言ったものの、正直に言えばこの後どうするかなんて何も考えてはいなかった。都内の大学に進学した俺は、今も変わらず実家に住んでいる。走ればまだ終電には間に合うだろうが、急ぎで帰る予定もなければ、そうするだけの余力も残っていなかった。
(それに……)
ちらり、と斜め後ろを歩く大柴を見る。あいつもこのまま残るのだろうか。結局この日はまだ一言も口を聞いていなかった。とくに何かを期待しているわけではないが、このまま先輩たちに付き合ってだらだらと始発まで待つのも悪くない。
いつのまにか次の店が決まったらしく、店の入り口で水樹が両手を挙げて立っている。水樹は卒業後、以前より契約していた鹿島にそのまま入団した。明日の練習は大丈夫なのだろうか、とお節介なことを思っていると、店の前でふと、誰かに手首を掴まれて思わず立ち止まる。
「あ?」
勢いよく振り向くと、険しい表情をした大柴が俺の手首を掴んでいた。
「なっ……にすんだよ」
なんで、お前が。思いがけない人物に少し怯んだ俺の声は、威勢を失くしみっともなく尻すぼみになってしまった。掴まれた手首がじりじりと熱い。振り払おうと腕を振り回すが、俺よりも一回りほど大きな掌はそう簡単に放してくれず余計に力が込められて、触れられたそこが一層熱を持ったように思えた。
おかしい。今日の俺はどうかしている。嫌いなはずの男をじっと盗み見、触れられ、まるでそれを喜んでいるかのように頬や身体が熱い。先ほどから無駄に高鳴っている胸の鼓動ですらいつもと違っていた。こんなのはまるで俺じゃない。
「っ、気安く触んな」
「お前、もう帰れ」
その掌の温度とは裏腹に、冷めた声が棘のように胸に刺さる。素っ気ない物言いはいつのも大柴と同じなのに、なにかを堪えるようなその瞳は、はじめて見る表情だった。だから油断したのかもしれない。
「すんません、こいつ連れて帰ります」
俺の手首を掴んだまま、店の入り口で人数を数えていた臼井に向かい大柴がそう言った。臼井は一瞬驚いたような表情をしたが、すぐに「ああ、分かった。気をつけて帰れよ」といつもの笑みを浮かべて小さく手を振った。隣にいた水樹が俺と大柴を交互に見て、不思議そうに首を曲げていたがそれどころではなかった。お疲れ様っす、と軽く会釈をした大柴が、俺を掴んだまま駅とは反対方向へと歩き出したからだ。
「ちょ、待て! 放せバカ!」
嫌がる俺を引きずって道のど真ん中を進む大柴の表情は窺えない。が、なぜか怒っていることは雰囲気で察していた。まだ肌寒い春の夜にぴりぴりとした空気を纏い、あれから何も言わない大柴に俺は諦めて引きずられることにした。ここで揉めて運よく逃れられたとしても、ふらつく足で人の波をかき分けて、一体どこへ行くというのだろう。酔っぱらった男が引きずられているこの奇妙な光景に、街行く人々は何ら疑問に感じていないことだけが唯一の救いだった。
そこからは所々の記憶が曖昧だった。ひどく酔っていた、というよりも、あまり思い出したくないというのが本当かもしれない。
繁華街の眩いネオンがピンクや紫ばかりに変わり、怪しげなバーやホテルが立ち並ぶ。普段足を踏み入れることのないエリアにやってきたところでまさかとは思ったが、大柴の足は迷うことなく一軒のホテルへと吸い寄せられてゆく。ラブホテルにしてはシンプルな――言い換えれば味気のない――ここは大柴の行きつけなのだろうか、と思うと、なぜか胸のあたりがずきりとした。大柴はパネルの前で一度立ち止まり、何やら部屋を選んでいる様子だったがそんなことはどうでもよかった。こいつの意図がまるで読めない。今日一度も話しかけなかった男、それも犬猿の仲であるはずの俺を突然こんな場所へと連れ込んで、一体何がしたいのだろう。だが俺は不安になるどころか、むしろその先を想像してあり得ないと思いながらも秘かに期待してしまった。
壁に凭れ、うっすらと額にかいた汗を掌でぬぐうと、その腕はまたすぐに大柴の掌へと収まった。連れられたエレベーターの中で、暫くの間ぎこちない空気が流れる。俺の手首を握る大柴の手が湿っている。これは夢ではなく現実なのだと他人事のように思った。
⌘⌘⌘
翌朝、ひどい頭痛で目を覚ますと、頭の鈍い痛みよりも自分が素っ裸で眠っていたことに驚いた。起き上がろうとして腹筋に力を籠めるが、身体のあちこちに痛みが走り思うように力が入らない。
「……っ」
ひねり出した声も掠れ、張り付いた喉が渇きを訴える。おまけに昨日のコンタクトをしたままの視界はぼんやりとしていて、ここが自宅ではないことに気づくまでに随分と時間が掛かった。遠くでざあざあと水の流れる音が聞こえている。
俺は、あの後どうしたのだろう。肌触りのいいシーツに手を伸ばしながら、その感触を確かめる。ひんやりと冷たいそれはしっとりと濡れているようにも感じた。思考を巡らせすぐに思い出したのは、終電組を見送り、大柴に半ば無理やりここへと連れられたことと、あいつの怒ったような瞳の色。全身に触れた大柴の指。腰の痛み。俺の名を呼ぶ低い声。どれも朧気だが現実だという確信がある。
「起きたか?」
声のしたほうを振り向くと、真っ白なバスローブを羽織った大柴が立っていた。派手な赤い髪色も水分を含んだ今はやけに大人しく、垂れ下がった先端からぽたり、ぽたりと水滴を垂らし、バスルームへと続く絨毯を濡らしている。備え付けの冷蔵庫からミネラルウォーターを二本取り出すと、その一方をこちらに向かって投げてくる。
「……今何時だ」
「知らん。自分で見やがれ」
蓋を外し、ゴクゴクと喉を鳴らしてそのほとんどを飲み切った大柴は、俺のよく知る太々しい態度だった。急に自信のなくなった俺は、サイドテーブルに投げられていた自身のスマホを起動する。午前十一時半を過ぎたところだった。
「シャワー入るならさっさと入れ。ちなみに二時間延長しているから、これ以上はテメェで払えよ」
身体の痛みを堪えながら、時間内になんとかシャワーを済ませると、昨日の服をそのまま身に着けて外へ出た。高く上った太陽の光がやけに眩しい。あれだけたくさんのネオンが輝いていたこの街も、今は寂れたようにひっそりと息を殺して佇んでいる。道行くサラリーマンの視線が痛い。居心地の悪い中、どうやってこいつに別れを告げればいいのかがわからなくて、二人してぼうっと突っ立っていると突然、大柴の腹が鳴った。
「腹減ったな」
同意を求めた大柴の腹がもう一度鳴り、「ラーメンでも行くか」と勝手に歩き出す。別にこのまま別れてもよかったものの、その後ろ姿を追いかけてしまったのは、昨夜の残像が重なったせいなのかもしれない。結局これが何なのかわからないまま、俺はラーメン屋ののれんをくぐることになった。
「お前、ラーメンなんか食うんだな」
太めの麺を魚介のスープに浸しながら、カウンターの隣の席で豚骨ラーメンを啜る男の手元を盗み見ていた。昨日見た綺麗な箸使いは幻などではなく、硬めに茹でられた極細面を器用につまんでいる。
「あーまあ、大学の付き合いとかでたまに、な」
「友達いるのかよ」
「なっ、舐めんなよバカ君下! つーかお前こそ、どこで何してんだよ」
そう言われて初めて気が付いた。俺たちは幼馴染であるのに、高校を卒業して以来の互いのことを殆ど知らなかったのだ。少し呆気にとられながら、時間を埋めるようにぽつぽつと近況を話し始めると、ホテルを出たときに感じていたギスギスとした空気はいつの間にかなくなっていた。傍から見ればただの仲のいい友人のように見えるだろうか。今よりも更に若かった俺たちはいがみ合うばかりで、互いが他愛もない話を何の気づかいもなくできる相手だということをこれっぽっちも知りはしなかった。だから隣で笑う男に対し、まるで昨夜の出来事が最初からなかったかのように振舞った。
大柴は都内の私立大学に通っているらしく、今は一人暮らしだという。どうせ親の金で借りたマンションなのだろうと思ったが、それは口には出さなかった。俺も自分のことを聞かれたので、実家であるスポーツショップを手伝いながら、たまの空いた時間で家庭教師のアルバイトをしていると話した。
「じゃあここの会計はお前が払え」
「あ? 奢りって言ったじゃねぇか」
席を立ちながら、当たり前のように伝票を手渡してくる大柴を睨みつける。
「奢りだとは言ってねぇだろ」
「テメェ、嵌めやがったな」
「まあハメたと言えばそうだが」
「なっ……そっちじゃねぇだろ! このタワケが」
いきなり蒸し返された昨夜の失態に思わずお冷を吹きこぼしそうになる。袖で口元を拭い、目の前にあった腹にジャブをお見舞いしてやると、「いってぇなバカ!」と大柴が吠えた。
「チッ、せっかく人がなかったことにしてやろうと思ったのに」
結局その場は君下が支払った。ホテル代に比べれば大した額ではないが、口止め料ぐらいにはなるだろう。のれんをくぐり外へ出ると、いつの間にか太陽が真上に昇っている。相変わらず時間の感覚が曖昧だったが、家に帰って眠ればそのうち戻るだろうか。
「じゃあな」
「ああ、またな」
そう言うと、タクシーで帰るという大柴は大通りへ向かい歩いてゆく。
「またって何だよ」
小さくなってゆく後ろ姿を眺めながら、果たして次はあるのだろうかと、ふと思った。
∵好きだと言えない
見慣れない番号から連絡があったのは、あれからちょうど一週間たった金曜日の午後だった。机の上でうるさく鳴り続けるバイブレーションに負けて、電話を取ったのが運の尽きだった。
「テメェ、何回鳴らせば出やがるんだ!」
耳鳴りがしそうなほどの大声に、思わずスマホを耳から離した。それからもう一度画面を確認し、表示されている番号を速攻で着信拒否に設定した。
次に電話が鳴ったのはちょうど四限が終わった頃だった。またもや知らない番号から電話が掛かってきたが、嫌な予感しかしないそれを無視し続けた。今日はこの後家庭教師のバイトがある。着信が途切れた隙に、カレンダーに保存した住所を確認して地図アプリを開く。大学からほど遠くない場所にある一軒家で、中学生相手に中間試験対策を行う予定だった。
早歩きで校門を抜けると、目の前の通りに真っ赤なスポーツカーが停まっているのが視界に入った。半分開いた運転席から、車と同じ髪色の男がサングラスをかけて、こちらに向かい手を振っているのが窺える。
「嘘だろ」
鳴りっぱなしの電話の相手が目の前に現れたのだと悟ると、これ以上近づきたくはなかった。今からでも気づかないふりをしてどうにか逃げ切りたかったが、車の中の大柴は口をへの字に結んだまま、親指で助手席を指している――つまり、乗れということか。少し迷ったが、君下は素直に従うことにした。ここは自分の通う大学の目の前であり、万が一あいつの機嫌を損ねて騒がれても困るのは俺のほうだ。ただでさえ目立つ真っ赤なスポーツカーは、既にこの場に不似合いだった。��のラーメン屋で迂闊にも大学名を教えたことを後悔しながら、身を屈めて助手席――後部座席のドアに手をかけると鍵が掛かっていて開かなかった。止むを得ずだ――へと乗り込むと、車はすぐに発進する。
「おい、何処行きやがる」
今日はバイトが、と言おうとして、大柴の機嫌がすこぶる悪いことを察して口を噤んだ。むしろ怒りたいのはこちらだというのに、どうして俺が気を遣わなければいけないのだろう。大柴の前だと時々自分がわからなくなる。
「なんで電話に出ねぇんだ」
やはり拗ねていやがる。アポイントなしにやって来られるぐらいなら、せめて通話に出てやればよかったと少しだけ後悔した。
「授業中だぞ」
「知るか。俺も授業中だった」
「どんな学校だよお前のところは……つーか、わざわざここまで来て何の用だ」
信号に引っかかると大柴は短く舌打ちをし、ブレーキを踏んだままこちらを振り向く。サングラス越しに目が合い、なぜかあの日の夜を思い出して急に気恥ずかしくなった。あの日の出来事は何度も忘れようと試みたが、ふとした瞬間に大柴の温もりを思い出しては惨めな気持ちになっていた。こんなこと、二度と忘れられる訳がない。
「その……なんだ、お前と飯でも行こうと思って」
「は?」
「いいだろ飯ぐらい。たまには幼馴染と話したいこともあるだろうが」
幼馴染だと? どの口がそう言っているのだろうか。眉間に皺が寄るのと同時に、不自然に心臓が高鳴っている。
「生憎だが、俺は今からバイトなんだよ……あ、次の信号を右に曲がれ」
「じゃあ終わるまで待ってる。因みに俺の奢りだ」
奢りという言葉に嫌でも眉尻がピクリと反応した。それを見たのであろう大柴は余裕のある笑みを浮かべている。やはりこの男はいちいち気に食わない。
「当たり前だろうタワケが。八時に迎えに来い」
半信半疑で仕事を終えて外へ出てみると、暗闇の中でもその車体ははっきりと窺えた。運転席のシートを倒して眠りこける大柴の姿を認め、小さくため息をついたのち窓ガラスをノックする。
そこから車を走らせること数分で焼肉屋の駐車場に辿り着いた。「今日は肉の気分だな」と笑った男に俺はまだ少しだけ警戒心を抱いている。
当たり前だが運転してきた大柴は酒を飲まなかった。俺も翌日のことを考えて酒はビール一杯に留め、たわいも無い話をして二時間ばかりで店を出た。何も言わずとも実家まで送り届けた男は欠伸を噛み殺しながら「じゃあ、またな」と言った。やはり次もあるのか、と内心で思うだけにして、家の前で車が見えなくなるまで見送った。
そんなことが週に一度、あるいは二週に一度ほどのペースで続いている。俺のスマホの着信履歴には「バカ喜一」という名で登録された番号がずっと並んでいる。発信履歴には、未だその文字が一つもない。
⌘⌘⌘
雲一つなく晴れた火曜日だった。季節はいつの間にか夏から秋へと移り変わり、この奇妙な関係が始まって半年が過ぎていた。
あれ以来大柴と酒を飲むことはあっても、ひどく酔うこともベッドを共にすることもなかった。人当たりが決して良いわけではない君下にとって、大柴と過ごす時間は己を晒け出せる数少ない機会になっていた。正反対の性格とは、裏を返せば酷く似通った思考をしているということだ。その証拠にサッカーに関して言えば、同じピッチに立った二人の呼吸はぴたりと合う。そう考えると自分たちは決して相性が悪いわけではないらしい。近過ぎた距離だけが互いを嫌悪する理由だったのかもしれない、と今更になって思うのだった。
ともあれ俺は大柴に特別な感情を抱いている。これが恋なのかはわからないが、自覚するまでに大した時間は掛からなかった。
「珍しいな、お前から誘ってくるなんて」
柔らかな午後の日差しが差すテラスでアイスコーヒーを啜っていると、待ち合わせの時間よりも少し早くやってきた大柴が隣の席に腰掛けた。初めて俺から電話をかけて、まだ三十分も経っていない。手にしていた文庫に栞を挟み、テーブルの上のスマホと重ねて置き直した。
「まあな……早かったな」
「ちょうど風呂入ったところだった」
そう言われてみると、大柴の髪がまだ濡れているような気がした。少しだけ心拍数が上がるのを感じていると、「それで」と大柴が続きを促す。
「あまり奢られてばかりだと、あとで何言われるかわかんねぇからな。たまには俺が奢ってやる」
「うむ、よかろう」
今日大柴を誘ったのは、明日が十月十日――つまり大柴の誕生日だということも少なからず関係している。当日に予定を組まなかったのは我ながら女々しい考えだと思う。その日に都合よく誘いが来ると限らなければ、大柴に彼女がいるのではないかと勘ぐっている自分がいたからだ。今までそういった類の話をしなかったのは意図的なのかもしれない。一度だけ大柴に聞かれたことはあったが、「そういうお前はどうなんだ」と聞き返すだけの勇気はなかった。
思えば高校時代は部活に明け暮れていて、恋愛ごとなどに全く興味がなかった。幸いにもサッカー部は練習が忙しく、彼女がいる奴の方が少ない。自分のことで精一杯なのに、他人に気を遣い機嫌を取り、それが一体何になるのだろう。性欲処理なら自慰で済む。彼女だっていつかそのうち出来るだろう。当時は本気でそう思っていた。
だがそれが大学に進学し、サッカーを辞めた今でも変わることはなかった。放課後と休日の殆どを占めていたサッカーは、そのまま家の手伝いと細々とした家庭教師のアルバイト、そして勉強へと成り代わった。
珍しく電車で来たという大柴を連れて、待ち合わせをした駅前から続くゆるい坂道を上り、裏通りにあるスペイン料理店へと足を運ぶ。予約した時間よりも早めに着いたが、カウンターがメインの狭い店内は既に半分ほど席が埋まっていた。あたりを見渡しながら「よくこんな店選んだな」と感心したように言う大柴に、「ちょうどテレビでやってたんだよ」と教えてやる。通された一番奥の席に着いたところでウエイターがメニューを持ってやって来たので、とりあえずカヴァを二杯オーダーした。
人気店というだけあり、前菜にと頼んだスパニッシュオムレツが運ばれるころには店の前に軽く列ができていた。機嫌のよいたくさんの話し声、忙しなく鳴るグラスや食器のぶつかる音、薄暗い空間にぶら下がったあたたかな裸電球の色と陽気なギターが鳴るラテン音楽。舌を弾ける慣れない泡に気分はすっかり良くなり、塩気のきいた料理はどれも絶品だった。魚介のたっぷりと乗ったパエリアをつついている大柴も「お前にしては悪くないチョイスだ」とへらりと笑い上機嫌だった。本当に機嫌がいいらしくいつもよりもグラスを開けるペースも早く、いまは何杯目かのテンプラニーリョを舐めている。
「なあ、そろそろ付き合わねぇか」
まるで昨日の試合結果を伝えたかのような、何気ない口調だった。だから気分よく酔っていた君下は危うくその言葉を聞き流すところだった。
「そうだな……って待て、おい、今なんつった?」
「だから、付き合おうかって聞いてるんだよ」
やはり大柴は天気の話でもしているかのように言うものだから、話の内容が鈍った頭に入ってこない。言葉に詰まっていると、追い打ちをかけるようにワイングラスを持つ手を上から握られる。ああ畜生、なんてずるい奴だ。こうされてしまえば、その大きな手を振り解くことは難しい。悔しさにぐっと唇を噛みしめていると、それを見た大柴はにやりと勝ち誇った笑みを浮かべている。
「明日が俺様の誕生日だと知らなかったわけではあるまい。だからプレゼント代わりにお前をも貰ってやろうと言ってるんだ」
「っ! 畜生が」
「返事はイエス以外聞かねぇぞ」
「じゃあわざわざ聞くんじゃねぇよ」
分かっているくせに、とテーブルの横に下げてある伝票をひったくり、そそくさと席を立ちレジへと向かう。入り口付近の小さなパーテーションで会計をしていると、大柴が俺の背後を通り過ぎながら「俺の家な」と耳打ちした。
「クソ……やっぱり嵌められてんのかも」
俺は騙されているのだ。頭ではそう思っているが、素直にうれしいと思っている自分もいる。無意識ににやける口元をこれ以上誤魔化しきれそうにない。顔が妙に熱いのは、飲みすぎた赤ワインだけのせいではないような気がした。
∵切れない関係
なぜこいつなのだろう、と腰を動かしながら何度も思った。打ち付けるたびに君下の細い腰がびくり、と跳ね、だらし無く開いたままの唇がてらてらと濡れているのが視界に入る。正直に言うと、男は論外だと思っていた。突っ込まれる側なんて勿論無理だが、抱くことすら考えたことなどなかった。だが現実に今、同じ男である君下の中を貫く己の欲望は、はち切れそうなほどに張り詰めていた。
「んっ……もう、出そう……」
「ぐッ……あぁっ……」
思ったより限界は近い。一刻も早く欲を吐き出したくて、内壁を擦り上げるように性器を擦り付けた。ぢゅぷ、ちゅぷ、と音を立てるそこは何で濡れているのかも定かではない。そもそもここ小一時間ほどの記憶が曖昧だった。懐かしい顔ぶれで年に何度かの会合をしていたはずが、いつのまにか幼馴染と駅前のラブホテルの一室にいる。アルコールの影響でどろどろに溶けた思考のまま、自力で立つことすらままならない様子の君下を壁に押し付け、服もそのままに膨らませた股間を擦り付けた。俺以上に泥酔している君下の、苦しそうに息を吐く唇に吸い寄せられるように口づけ、気がついた頃にはこうなっていた。うつ伏せになった君下とシーツの間に左手を差し込むと柔らかいものに触れたが、同時に生温かい滑りを感じて君下がいつのまにか一度達したことを察した。別に否定したいわけではない。だがこれは、明らかに男同士のセックスだった。
正直に言って、あまり居心地のいい視線ではなかった。理由はわからないが、俺は君下に睨まれている。長年の付き合いで君下が俺を好ましく思っていないことは知っている。だがこうも判りやすい嫌悪を示されたことはなく、大抵は俺の存在自体を無視されることが多かった。だから睨まれていることに気づくと、必然的にその視線の意味を知りたくなった。
カルピスらしきものを飲む君下を盗み見る。長い前髪が邪魔をしてうまく表情は読み取れないが、一番遠いこの席から見てもわかるほどに、顔全体が赤く染まっていた。酒は弱いのだろうか。それとも顔に現れるタイプなのか。ともかくジョッキを握りしめたまま、誰と話すわけでもなくちびちびとそれを口に含み続けている。君下の隣に座る鈴木とたまに目が合うが、俺が君下を見ていたことは恐らく気づかれていないだろう。
結局何一つ答えを得ることができないまま、会はお開きになり、大げさに手を振りながら終電組が帰って行った。俺の住むマンションはここからそう遠くない。酔いも心地よい程度に留まっている。どうせタクシーで帰るのだ。今すぐ帰る理由も見当たらず、かといってこれ以上残る目的もない。帰りたくなれば適当に抜ければいいか、などと思いながら、なんとなく人の流れに乗って歩いていると、前を歩く臼井が君下に何かを話しかけている。
「明日休みなんで大丈夫っす」
大丈夫ではないことは、その不確かな足取りを見ればわかる。臼井もおそらく分かっているだろうが、本人の意思を尊���したのか、「それならよかった」と笑いかけるだけだった。いや、良くねぇだろう。そう思うと、俺の体は勝手に動いていた。
初めて身体を重ねた日から、ずっと君下のことが頭を離れなかった。かわいそうだと思ったわけではない。だがあの時、酔った君下を放っておけないと思ったのは紛れもない事実だった。本能に突き動かされるまま、適当に連れ込んだホテルで衝動的に身体を繋げた。俺も大概酔っていたのだろうが、壁に押し付けた君下を前に、俺の下半身はしっかりと反応を示していた。それでも誰でも良いわけではないことは、プライドの高い俺自身が一番よく判っている。俺はあの時たしかに、幼馴染である君下敦という男に欲情していたのだ。
⌘⌘⌘
君下が会計を済ませている間にタクシーを拾うと、行き先を告げて後部座席へと乗り込んだ。待ちわびた瞬間だった。まさか自分の誕生日の前日に食事に誘われるとは夢にも思わなかった。遅れてやっきた君下が隣へ乗り込むと、自動的に扉が閉まり、ゆっくりと車は夜の東京を滑り出す。緩やかな車の揺れに合わせて時折触れた肩だけが、これが夢ではなく現実なのだと俺に訴えかけていた。
そうして俺たちは晴れて恋人同士になったわけだが、思っていたよりも上手くいっていたと思う。付き合うとはいっても、俺は所属している大学のサッカー部の練習、君下はバイトと実家の手伝いで忙しい。会う頻度は付き合いはじめる以前と大して変わらなければ、行き先だっていつもの居酒屋か、俺の気に入っているバーだったり、そんなもんだった。デートらしいものをしたこともないが、あれほど仲の悪かった俺たちにしては大きな喧嘩もなかった。友情の延長線のような関係は気楽で、それでいてやることはやっているので性欲は満たされるが、その一方で何かが足りないような気もしていた。
互いに予定のない金曜の晩は、外で待ち合わせて軽く食事をしたのち、俺のマンションへと一緒に帰る。手間だからと一緒にシャワーを浴び、そのまま互いの性器を擦り合わせて軽く抜いた。風呂でやるとのぼせるから嫌だ、という君下の意見を酌み、濡れたままベッドルームまで運んでやると溺れるように身体を重ねた。本来ならばモノを受け入れる場所ではないそこは、初めて抱いた頃と比べると、随分と慣れた様子だった。恐らく君下には他にも男がいたのだろう。本人に直接聞いたわけではないので確信はなかったが、そう思うと胸のあたりがもやもやとした。これがいわゆる嫉妬だということに気づいてしまえば、どうしたってあの男を自分だけのものにしたいと思うのは人間の本能だ。存在すらわからない相手に嫉妬し、根拠のない怒りをぶちまけるかのように、ぐったりとした細身の身体を力任せに何度も突き上げた。
二度目のシャワーを浴び終えベッドへと戻ると、気を失っていたはずの君下が起きていた。俺の枕を抱えて力なく横たわっている。自分の放った精液にまみれていた白い腹も、いつの間にかきれいになっていた。
「一緒に住まねぇか」
ベッドの空いているスペースに腰かけながら、ずっと思っていたことを口にした。寝ぼけ眼だった君下の瞳が少し見開かれる。
「というかここに住め。特別に家賃は要らねぇし、家の世話をするなら今雇っている家政婦と同じ額を出してやる」
実家の手伝い以外にもバイトをしているということは、この男は相変わらず金に困っているのだろう。男二人暮らしの生活費を稼ぐために掛け持ちをしているというのに、さらに俺と会うためにバイトを増やされれば会う時間も今以上に限られてくる。そんなのは堪ったものではないだろう。
「えっこの家……家政婦なんていたのか」
「当たり前だろう。俺が家事をやると思ったか」
「まあ、確かに想像できねぇな」
「だろう。それに慌てて帰る必要もなくなる」
俺がただこいつをそばに置いておきたかっただけだ。これは俺のわがままなのだと、そんなことは分かっている。だがそれを素直に口にしたところで、この男が素直に従うという期待はしていなかった。一緒にいるための理由を必要としたのは、曖昧なこの関係を、何かで縛っておきたかったからなのかもしれない。そのぐらい俺たちの関係は、ひどく壊れやすいもののような気がしていた。
それからすぐに君下は、両手に荷物を提げて俺の住むマンションへとやってきた。古い旅行鞄はいつかの修学旅行で見たような気がする。くたびれたそれに入っていた殆どは大学で使うらしい参考書や難しい本だった。最小限の服も私物も、あっという間に俺の部屋の一部となった。
家事はある程度できるという君下に「とりあえず腹減ったから何か作れ」とリクエストをすると、「じゃあまずは買い出しに付き合え」と交換条件を言い渡された。ここの家賃は勿論、食費などの生活費もすべて俺が――正確には俺の親父が――支払うとの約束だった。
「冷蔵庫は酒か水しかねぇし、お前ちゃんと食ってるのかよ」
呆れた様子でほとんど使われていないシステムキッチンを確認した君下は、「うわ、鍋もフライパンもねぇな」と頭を抱えている。俺は食事の大抵を外食か、もしくは週に二度やってくる家政婦が作ってきたもので済ませていた。広いキッチンにはコンロのほかにオーブン機能付き電子レンジも備わっていたが、自分で使うのはドリップ式のコーヒーメーカーぐらいものだろう。
そのほかにもあれやこれやと君下が買い物リストを作り、行き先も近所のスーパーから少し離れたショッピングモールへと変更になった。広々とした店内で大きなカートを押して歩きながら、いかにもカップルらしいなとどこか他人事のように思った。
「もっと良いもの買えよ、どうせ俺の金だ」
俺がそう言ったのも何回目だろうか。貧乏性とは知ってはいたが、まさかここまでだとはさすがに思わなかった。どうでもいいものはいつまでも悩むくせに、よく使うような必需品は百円ショップなどで済ませようとする。現にいま君下が選んでいる包丁も、まるで子供のままごとに使うもののように安っぽい代物だった。
「これちゃんと切れんのか?」
「喜一、お前はわかってねぇな」
「あ? なんだと」
プラスチックの箱に入ったそれを籠へと放りながら、君下は得意げな顔で俺を見る。いつになく楽しそうな男は、「切れねぇ包丁で料理するのが主婦ってもんだろ」と訳の分からないことを言い、見下したように笑っていた。俺はその言葉の意味がいまいちわからなかったし、それを理解する日は一生来ないだろうと思った。切れない包丁を買ったその日、君下は案の定涙を流しながら玉ねぎを切っていた。頭がいい癖に意外とバカだというところも愛おしい。玉ねぎ入りの焼きそばを食べながら、いつのまにか心底こいつに惚れていることに気づかされた。
だが、そんな日々は半年も続かなかった。いつかこうなると分かっていたのに、どうして止められなかったのだろう。君下が毎日刻んでいた玉ねぎの香りは、もう思い出すことができない。
∵花が散る
いつのまにか桜が蕾をつけている。
君下と最初に寝たのも確か去年の春だったな、と教室から見える中庭の木々を眺めていると、ふいにポケットの中身が震えた。先月買い替えたばかりのスマートフォンを取り出すと、君下から「今日は実家に泊まる」と短いラインが入っていた。ロックを解除して「了解」とだけ返事をしながら、そういえば今日は練習がなかったのだと思い出す。まっすぐに帰宅してもどうせ夕食は外で摂ることになるだろう。
「あ、大柴くん。今日って結局来れるんだっけ」
退屈だった講義が終わり、荷物を纏めていると斜め後ろの席から声をかけられた。聞き覚えのある声に振り向くと、ミルクティーブラウンの長い髪をひとつにまとめた女がこちらを覗き込んでいる。確か同じサークルのミキだかそんなありきたりな名前だったはずだが、女の名前にいまいち自信はなかった。
「あー、たぶん行けるけど」
「よかった! 大柴くん最近来ないことが多かったから、ちょっと寂しかったってミキが言ってたよ」
「ああ……」
ミキはもう一人の連れのほうだったか……なんて失礼なことを思いながら、集合場所を聞いて一度その場で別れた。どのみち今夜は一人で食事をする予定だったので、それに人数と酒が少し加わる程度だ。思い返すと君下と一緒に暮らし始めてからは、籍だけ置いていたサークルにはほとんど顔を見せなくなっていたので、たまにはこういう日も悪くないのかもしれない。そう軽く見ていた俺が甘かったのだ。
時間を気にせずに酒を飲んだのは久しぶりで、情けないことに早い時間に潰れてしまった俺は、目を覚ますと見知らぬ天井が視界に入り大いに戸惑った。泥の中にいるように重たい身体と、どくどくと脈打つような頭の痛みにしばらく起き上がることも適わない。肌に当たる感覚から今俺はベッドの上にいて、そう広くはない部屋のどこかからはすうすうと規則正しい寝息が聞こえている。それも一つではなく、この空間に複数人いることはなんとなく察した。
これはものすごくまずい状況ではないか。ベッドに横たえたまま顔を動かすと、顔のすぐ隣に女の真っ白な太腿がある。花柄のスカートはめくれ上がり、布の隙間から薄桃色の下着が覗いていた。頭の痛みどころではないこの状況に飛びあがるようにベッドから降り、部屋を見渡すと、サキもミキもアサミもマリも服を乱し、誰だかわからない女と男がそこら中に横たわり眠りこけている。
「なんじゃこりゃ」
覚えのない光景に呆然としていると、ずるり、と前の開いたスラックスが落ちかけたので慌てて引き上げる。通していたはずのベルトは見当たらず、背中を嫌な汗が伝う。嘘だろう。まさか俺は――
慌ててチャックを引き上げると、布の上から財布もスマホもポケットに入っていることを確認して大慌てで部屋を出た。失くしたベルトなど今はどうでもいい。とにかくこの悪夢のような場所から一刻も早く立ち去りたくて、安っぽいホテルの廊下を一目散に駆け抜けた。
その日は幸いにも土曜日で大学に行く必要はなかった。だが夕方には練習があるので、面倒だが一度車を取りに戻ることにした。時刻はちょうど朝の八時を過ぎ、駅前には休日出勤のサラリーマンがちらほらと窺える。コンビニに寄り、水と頭痛薬を購入して飲み込むと、ホテルを出たころよりも幾分か冷静さを取り戻したような気がした。
一日ぶりの愛車を運転しながら、昨夜のことは考えないようにしていたがどうしても罪悪感がぬぐい切れない。何が起こったのか一切記憶はないが、所謂ラブホテルのような場所で目が覚めてしまえば、どんな馬鹿でも大方の予想はつく。ずっと大柴の隣に座っていたミキ――サキだったかもしれない――が、始終俺にべったりくっついていたことは覚えている。俺にその気がなくたって、何もなかったとはとてもじゃないが思えない。
ふらふらになりながら帰宅すると、玄関にはないはずの靴がきちんと脱ぎ揃えられていて、またもや嫌な汗が額に浮かぶ。まさかもう帰ってきたのか? あれからまっすぐに帰ったので、時刻はまだ九時にもなっていない。思わず独り言が零れたのと、寝室の扉が開くのはほぼ同時だった。
「よお……俺が居ねぇからって夜遊びか?」
靴を脱ぐために腰かけた俺の背中に、低い君下の声が刺さる。長い付き合いの中で君下の怒った声は何度も聞いているが、これは俺の知っている声とはだいぶ違っていた。ぞくり、と鳥肌が立ちそうなほどに冷たく、突き放すような声だった。振り向かなくとも君下が本気で怒っているのだと気づいた俺は、弁解したい気持ちを抑え、「急な集まりで飲みすぎて終電逃しちまった」とだけ報告した。暫くの沈黙が流れる。居心地の悪さを誤魔化すように、脱いだ靴をきちんと並べなおしていると、君下は「さっさと風呂入ってこい」と吐き捨てるように言うとリビングへと去って行った。
熱いシャワーを浴びながら、今回の件をどうやって切り抜けようかと考えていたが、リビングでコーヒーを飲んでいた君下に「女と寝ただろ」と先手を打たれてしまった。
「くせぇんだよ。如何にも頭からっぽです、みたいな品のない香水を振りまいてんじゃねぇよ」
自分では気づかなかったが、帰宅した当初から俺が纏っていた匂いがいつものそれではないと気づいていたようだった。君下の勘がいいのは昔からだが、ずばりと言い当てられて余計に居心地が悪くなる。
「お、俺は悪くねぇからな。何も覚えていないし、確かに同じ部屋に居はしたが、それだけで浮気とは限らねぇだろ!」
「誰が浮気って言ったんだ馬鹿が!」
「なっ……! テメェがカマかけるようなこと言ったじゃねぇか! それに浮気って、お前こそ他に男がいるんじゃねぇのかよ」
「あ? んだよそれ、自分のことは棚に上げて、よくそんなことが言えるな!」
「おい誤魔化すなよ!」
言い訳を重ねるうちに、つい熱くなってずっと気になっていたことを口にしてしまった。「本当は俺以外にも、男が居るんじゃねぇの?」そう言うと君下は、ひどく傷ついたような顔をした気がした。バン、と大きな音を立てて、君下の変な柄のマグカップがテーブルに叩きつけられる。その音にびくり、と肩を揺らしたが、次の瞬間、君下の眉が寄せられ、その切れ長の目に涙が浮かんでぎょっとした。見たこともないぐらいぐしゃぐしゃに顔を歪め、短い嗚咽を漏らしながら泣き始めた君下に、俺の怒りはあっという間にどこかへ消えてしまっていた。両手で顔を覆う君下を抱き寄せ、震える背を力強く抱きしめる。
「ごめん、ほんとに覚えてなくて……悪かった」
「うっ……ぐ、っ」
「もう二度としねぇよ。絶対に」
どうしてこんな大事な存在を傷つけることができるだろうか。こんなにも愛おしい奴を、俺はこいつ以外に知らないというのに。
顔を覆っていた手を引きはがし、赤く腫れた目尻に口づけを落とす。ちゅ、ちゅ、と何度も優しく触れたそこは、海のようなしょっぱい味がした。君下が泣き止むころには、いつの間にか頭痛はしなくなっていた。
それから一週間後、君下はこの家を出て行った。元々少なかった荷物はきれいになくなり、リビングのテーブルの上に「ごめん」とだけ書かれた付箋と、合鍵だけが残されていた。一度実家を訪ねてみたが、記憶の中より少し痩せた親父が出てきただけで、「あいつは秋からずっと友達の家にいるぞ」という情報しか手に入らなかった。大学の前で待ち伏せをしたことも何度かあったが、いつかのときのように、偶然に君下と遭遇できた試しは一度もない。
四月に入り、毎年恒例のOB会にも行ってみたが、案の定君下の姿はなかった。今年の幹事である鈴木に聞いてみたが、欠席の返信を貰って以降、さっぱり連絡が取れないらしい。「お前、なにかしたんだろ」臼井に似て勘のいい鈴木にそう問い詰められたが、俺たちの関係を知らないこいつらに何と説明すればいいのかすら浮かばず、「何もねぇよ」と言うことが精いっぱいだった。その年も桜はいつの間にか散ってしまっていた。いつか花見をしようと約束したが、叶うことはもうないだろう。
∵なすすべもない
「で? いつまでここに居るんだよ。あ、俺もウノだ」
手札から一枚を切り捨てた鈴木が、思い出したかのようにそう言った。
「分かんねぇ……あいつが諦めるまで? おい佐藤、はやくしろ」
「あ~~どうしよう、ちょっと待って。ちょっと考えてるから」
「何でもいいから出せよ栄樹、どうせその手札の量だと負けるぞ」
「うるせぇ! 今からでも十分ひっくり返せるぞ、っと、ワイルド」
「色は?」
「青」
「ん、あがりだ」
「サンキュー君下、俺もあがり」
「だあああああ!! 何なんだよお前らは!」
つうかもう帰してくれ! やけを起こしカードを巻き散らした佐藤が吠える。そうは言うがいつの間にかすっかり夜も更け、もう終電は走っていないだろう。
俺が大柴のマンションを出て向かったのは鈴木の家だった。一度遊びに行ったことのあるそこはこぢんまりとした学生向けのアパートで、広さはないがベッドのほかにどうにか寝れそうなサイズのソファーが置いてある。急に訪ねてきた俺に対し、鈴木は特に理由を求めることもせずに「ソファーなら貸してやる」と言ってあっさりと受け入れた。鈴木の住むアパートから大学までは少し距離があったが、大学を挟み大柴のマンションとは反対方面なので正面玄関を通らずに済む。
喜一のいない俺の日常は案外普通に戻ってきた。喜一に貰った金は貯めてあった上に、減らしていた家庭教師のアルバイトも再開すれば生活費には困らない。迷惑料として家賃の半分を鈴木に手渡すと「そんなの要らねぇから、ちゃんと理由だけ教えろ」と返されてしまったが。
「もう半年か? あいつ、びっくりするぐらいしょげてたぜ」
「ふん、野郎がそんなことで落ち込むたまかよ」
「でもあれはさすがに可哀そうだった。俺なんか危うく鈴木の家にいるって言いそうになったからなぁ」
「ハイハイお友達だな、泣けるぜ」
今年の春のOB会は幸運にも鈴木が幹事だった。うまく言い訳をしてくれたらしく、君下の不参加を誰も不思議に思わなかったのだろう。ただ一人を除いては。
「まああいつモテるからなぁ。ほら、顔だけはいいだろ」
「顔だけ、な」
「付き合ってたお前がそれを言ってやるなよ」
ぐしゃり、と握り潰したチューハイ缶をゴミ袋に投げ入れると、あくびをしながら佐藤は「もう寝るわ」と言って、寝床にしている床へと転がった。ローテーブルには食べかけのつまみや総菜などが残っていたが、十月じゃあもう腐る時期じゃねぇな、と理由をつけてそのままソファーへと寝転がった。
「栄太、でんき~」
「ったくお前らは……」
頭上でパチン、と音がして視界を暗闇が覆った。闇夜に浮かぶ残光性のまるい輪を見つめながら、まだ眠れそうにないなとぼんやりと思う。
覚悟はしていたつもりだった。だがその覚悟があっても、それを受け止めるだけの心が俺にはなかったのだ。要するに子供だったのだ。俺も喜一も。青春時代のすべてをサッカーに捧げ、とても恋愛どころではなかった俺たちの心はまだ思春期にも満たないのだろう。
大柴が女受けするというのは紛れもない事実だ。背が高く顔も良くてサッカーもできる、おまけに両親は医者で運転手付きの大豪邸に住んでいる。だが壊滅的にバカなので彼女ができない。俺にとってはどれも随分昔から知っていることだった。それでも彼氏ではない関係を求める女も一定数はいるはずだった。その可能性を甘く見ていた俺にも非があると思っている。男同士だなんてうまくいくわけがない。そう思ってしまうのは、俺もあいつも元々そういう趣味ではなかったというところにある。やっぱり女のほうがいい。そう言われてしまえば最後、俺にはもう成す術がない。そのことが一番恐ろしいと、あの日知ってしまったのだ。
実家に泊まると連絡したが、いざ自分のうすっぺらな布団で寝てみると急に寂しさがこみ上げてきた。馴染みのあるはずの布団が急に赤の他人のもののように思えたのだ。隣に感じない大柴の温もりを恋しく思い、あまり深く眠れないまま早朝に目を覚ますと、簡単な朝食とメモを残して実家を後にした。春の明け方はまだ肌寒い。それでも今頃家で寝ているであろう大柴の寝顔を思えば、寒さなど微塵も感じることはなかった。鍵を差し込み、起こさぬようにそっとドアを開けるといつもの靴が見当たらない。少しの違和感を覚えたが、寝室のドアを開けて余計に胸がざわついた。もしかしたら、もしかして――
「おい、それ、どうにかなんねぇのかよ」
うんざりしたような鈴木の声に、まどろんでいた君下ははっとした。息をしようとしてずっ、と鼻を啜り、そこでようやく自分が泣いていることに気づいた。
「悪い、へんな夢見てた」
「毎日か?」
「……」
毎日とは、と聞き返さなくても意味が分かった。おそらく俺は無意識のうちに、毎晩こうして悪い想像をしながら泣いていたのだろう。
「いい加減にちゃんと話し合えよ。案外あいつも同じ気持ちかもしれないだろ」
鈴木の言葉は全くの正論だった。俺は佐藤に差し出されたティッシュボックスから一枚を引き抜くと、思い切り鼻をかんでゴミ箱に向かって投げた。
「すまねぇな」
「そう思うならさっさと服着ろ。そんで荷物持って外に出ることだな」
徐に立ち上がり、部屋の明かりをつけた鈴木を目を細めながら見上げる。素っ気ない口調から怒っているのだと思っていたが、意外にもその口元は笑っていた。ぽかんとした表情で見上げていると、アパートの外から短いクラクションの音が鳴る。「お、早かったな」と呟いた佐藤はスマホで何かを打ち込んでいる。
「おい、まさか」
「迎えがきたぞ。さっさと帰るんだな」
∵エンドロールにはまだ早い
低いエンジン音が振動となって両脚を伝う。途中で買ったトールサイズのラテを飲みながら、落ち着かない気持ちをどうにか抑えようと試みていた。
佐藤から連絡があったのは先週の木曜日の午後だ。休講になった四限を車で寝て過ごし、練習へと向かおうとした時だった。寝ぼけ眼で電話を取り、「ふぁい」とあくび交じりに返事をすると、「お前、今日鈴木の家に来れるか」といきなり要件を伝えてきた。
「君下がいる。練習が終わったら来いよ」
君下が出て行って、既に半年が経っていた。
俺が悪いのだと分かっている。だが別れも告げずに急に消えた君下に対し、俺だって怒りがないのかと聞かれれば答えはノーだ。知り合いをつたって探し回ったが、一向に足取りがつかめない。これは誰かが嘘をついている可能性もあると思ったが、そうまでされるとあいつを連れ戻そうという気にはこれ以上なれなかった。
君下にはやはり男が居たのだろうか。あの時はつい頭に血が上り、かっとなってそんなことを口にしたが、思い返してみるとあいつがそれに明確な答えをしたかどうかは分からない。もしかしたら俺がほかの女に手を出したことをきっかけに、ただ俺と別れる理由を作りたかっただけなのかもしれない。いや、でも――。考えれば考えるほどに悪いイメージは浮かんでは消え、忘れようにも忘れられない。まさに悪循環だった。
君下がいない間、あのサークルの集まりには何度か顔を出した。寂しさを埋めたいだけなのか、あるいは自分を試したかったからなのか。黙っていれば女には困らない容姿をしている自覚はある。見てくれだけを狙っている馬鹿な女は案外あっさりと釣れた。
だが何度女の裸を前にしても、どうしても抱く気にはなれなかった。華奢な美女からむっちりとしたギャルまで様々を試してみたが、ただ目の前のそいつが君下ではないという現実を突き付けられるだけで、そのたびに無駄に張り手――もれなくインポという不名誉な称号付き――を食らう羽目に遭ってしまった。それはプライドの高い俺の心を傷つけるだけでなく、本気で不能になってしまう予感さえしていた。君下のいない今、唯一の友人である佐藤に泣きつくと、「俺も何かわかったら連絡するから」と毎度困った顔で慰められた。
そして佐藤はその約束を守ったらしい。
鈴木の住まいは何の変哲もない、いたって普通のアパートだった。住所を教えられたが今が夜だということもあり、この何の特徴もない建物を見つけるのに随分と時間が掛かってしまった。パッ、と短くクラクションを鳴らすと、佐藤から「今行く」とラインが入り、程なくして二階の角部屋から男が一人出てきたことが窺える。遠目で見てもわかる、長い黒髪の男は紛れもなく君下だった。
逃げられるかと思ったが、君下はまっすぐに俺の車へと歩いてくると、何も言わずに助手席へと腰かけた。大きな荷物は膝の上に抱えたまま、その眼はじっと前方を見据えている。
「帰るぞ、君下」
返事はないが、君下は大きなカバンの上からシートベルトを締めたのでそれを了解と取ることにした。まるで家出した息子を引き取りに来た親父のような気分だな、と呑気なことを思いながら、俺はゆっくりとアクセルを踏み込んだ。
深夜の道路は思ったよりも空いていて、互いに一言もしゃべらないままあっという間に自宅マンションへと辿り着いてしまった。地下駐車場に車を停め、エレベーターで六階へ昇る。隣の住人はまだ起きているらしく、玄関の外にまで深夜のバラエティ番組の声が聞こえていた。
靴を脱ごうと背を屈めると、急に背中に重みを感じてバランスを崩した。
「おわっ?!」
どすん、と派手な音を立てて俺は膝から転げ落ちた。すぐに受け身を取った上にマットレスのお陰で痛みはないが、急にのしかかってきた君下に「何だよ、危ねぇだろうが」と文句を言おうとした俺の唇に、あたたかなものが触れた。
「?!」
突然に口づけられ、無防備だった唇の隙間から舌が侵入してくる。歯列をなぞり、その奥で縮こまっていた俺の舌を探り当てるように、君下の舌がじゅ、ぢゅっ、と厭らしく音を立てながら吸い上げる。
「あっ、まへ……」
久しぶりの感覚に腰がじん、と痺れ、貪りあうような口づけの合間に吐息が漏れた。すべてを吸いつくすかのような、君下の積極的な舌遣いに柄にもなく翻弄されっぱなしだった。いつの間にか俺の両手は君下の腰を抱き、シャツの裾からやわらかな肌を探り当てようと伸びてゆく。
「はぁ……っ喜一、っ」
ここはまだ玄関先で、足元には靴を履いたまま君下はゆらゆらと腰を動かしている。俺の顔を両手で挟み、しっかりとその存在を確かめるように深く口付ける。忙しない接吻に口の端から唾液がこぼれるが、それすらも吸い尽くすように君下の赤い舌が俺の顎を這う。
「おい、どうした……らしく、ねぇじゃねぇか」
ようやく解放された唇は酸素を取り込み、久しぶりに深く呼吸をしたような気がした。上気しぼうっとした様子で膝立ちになる君下を抱き寄せる。柔らかな黒髪の隙間に指を差し込み、首筋に鼻先を埋めると久しぶりの君下の匂いがした。
「どこにも行くなよ」
ようやく捻り出した声はどこか頼りのない声だった。君下に会ったら、言ってやりたいことはたくさんあった。この半年間、どんな思いで俺がお前のいない家に住んでいたのか。必死に探して、誤解を解いて謝ろうとして、それでも見つからないお前のために、何度眠れない夜を過ごしたのだろう。言いたいことは山ほどあったはずなのに、いざ本人を目の前にしてしまうとそのどれもが無意味だった。伝えたいことはただ一つ。どんな形であれ俺のそばに居てほしい。たったそれだけだったのだ。
「去年の今日……お前が俺にくれたものを覚えているか」
きつく抱き寄せたまま、君下は何も言わない。俺の真横にある顔が、どんな表情をしているのかすら分からなかった。
「あの時のプレゼントを返せと言われても困るのだが」
「……クセェ奴だな」
「るせぇな、じゃあ言わせるなよ」
俺の肩で君下が震えている。泣いているのかと思ってぎょっとしたが、引き剥がしてみると目に涙を浮かべ、必死に笑いを堪えていた。
「テメェ、笑うか泣くかどっちかにしろよ」
「クク……っ。わ、笑ってんだろうがッ……ブフッ」
「あー信じらんねぇな、畜生。俺は誕生日だっていうのに」
もうとっくに日付は変わっている。十月十日――今日は俺の誕生日だ。まさかこうなることを狙ってわざと君下は戻ってきたのだろうか。そう思えなくもないし、それだけのことをやるほどこいつの性格が悪いことを俺はよく知っている。
「なあ、誕生日プレゼント、何が欲しい?」
半泣きの君下が俺に聞いた。
「あ? お前を貰うってさっき言ったじゃねぇかよ」
「それは去年やっただろ? 今年は何がいいかって聞いてやってんだよ」
確かに一度もらったものを返してもらっただけである。これで今年もお前を貰うと言えば、またこいつは居なくなり、来年の誕生日に戻ってくるかもしれない。我ながらそれを思いついたことにぞっとしたが、君下以外に欲しいものなんて今すぐには思いつかなかった。
「あ、そうだ。新しい包丁買ってくれよ」
「なんだそりゃ」
「ちゃんと切れるやつにしろよ。それでお前が俺に焼きそばを作ってくれ。春になったら一緒に桜を見に行こう。どうだ? これでいいだろう」
返事を聞く前にその唇を塞いでやる。どうか気が早いだなんて思わないでくれ。先のことは何一つわからないが、今はこのまま君下と繋がっていたかった。俺たちの物語は、エンドロールにはまだ早いのだ。
0 notes
Text
燭台切探偵事務所2
「ええっ、伽羅ちゃん文化祭なの?!」
「……言われてなかったのか?」
長谷部の住む6階建てのマンションの502号室……の隣には職業探偵の燭台切は住んでいる。ここから探偵事務所に出勤しているが、実際は帰ったり帰らなかったりとまちまちだ。燭台切の趣味は料理らしく、休みの日になる度に何か作っては、お裾分けと言って長谷部の家に上がり込んでくる。
そんな長谷部の自宅に大倶利伽羅は同居していた。というのも、大倶利伽羅の両親は海外赴任で現在日本にはいないのだ。そんな事情があり、紆余曲折を経て2人は同居生活を送っている。
そのため、燭台切と大倶利伽羅はよく知る間柄なのだが。
「聞いてないよ!言ってくれれば遊びに行ったのに……」
「そんなことだから言わなかったんじゃないか」
夏休みの事件から3ヶ月ほど経っていた。痛いほどの暑さはすっかり引いて、秋風が穏やかに流れている。テレビでは紅葉狩りの名所なんかが連日放送されているこの季節は、学生にとってはちょうど文化祭シーズンで、それは大倶利伽羅達の通う学校でも例外ではない。
もっとも、大倶利伽羅はこういったイベントごとは積極的ではないので、長谷部が聞いた文化祭の話も「日曜は学校で、月曜は振替休日だから」という事務報告だったのだが。
長谷部としても、その際に「行くべきか?」「来なくていい」という短い会話があり、行かないことにしていた。学生の行事なのだから、大人は要らないというのなら学生で完結させておくべきだろう、というのが長谷部の方針だった。
だが、燭台切はそうでもないらしい。
「そんなあ……あ、そういえば、伽羅ちゃんから国広くんのことって聞いてる?」
ギャグ漫画のようにわかりやすく項垂れた燭台切が、真剣な面持ちになる。ああ、仕事か。燭台切の切り替えの速さに長谷部は常々感心していた。
国広くんのこと。
長谷部にはその質問に思い当たる節がある。大倶利伽羅がここ最近、たまに特定の人物に対する近況報告をするようになった。それが"国広くん"だった。何故、と訊ねると、「文句は光忠に言え」と短く返されたのを思い出す。つまり、燭台切にその人物の様子を確認してほしいなどと頼まれたのだろう。
「特に問題があるようには見えないそうだが……。俺に聞くくらいなら自分で確認したらどうだ?俺は詮索するつもりはないし、守秘義務もあるだろう」
「そう、だけどさあ……彼、こちらが気にかけてると知るとそれはそれで気にしそうで」
「難儀なことだな」
この前の事件のときも、ずっと巻き込んでしまったって気にしてたし。そう呟いて、燭台切はかの夏の日を思い返す。きっかけは彼に届いた脅迫だった。そこで、ふと先日のことを思い出す。
「…ああ、そうだ!長義くんのことは伽羅ちゃんから聞いてる?彼も転校してきたんだよね、この前そこのコンビニで会ってさ」
何やら違う人物がでてきた。長谷部は燭台切の話の展開に眉根を寄せる。実はその人物についても、ちらりも大倶利伽羅の話にでてきてはいた。けれども、長谷部としてはもう、たまの休みの二度寝をしたい気分だったのだ。
「だから!気になるなら文化祭にでもなんでも行けと言っている!」
この男、いっそ学校に投げ飛ばしてしまいたい……。
とはいったものの、自分よりもガタイのいい燭台切を投げ飛ばすなんてことはできないので、ぐいぐいと玄関先まで押し出すことになる。燭台切はもともとはお裾分けを持ってきただけだったので、玄関まで行くと大人しく靴にはきかえた。
「ああ、長谷部くんが文化祭について教えてくれたってことは言わないから大丈夫だよ」
「俺以外どこから漏れる情報だというんだ……」
学園祭パンフレットを持たせると、ありがとうといいながら懐にしまい込んだ。パンフレットは学生用のものだ。大倶利伽羅が1部だけ置いていっていたもの。
「……全く。なんでもいいが、入れこみすぎるなよ」
「ははは、君がいえた義理じゃないなあ」
そう言い残して、燭台切は長谷部宅を出て行った。なんとなく腹立たしいが、なにか反応すると睡眠時間が減りそうなので、後ろ姿をじとりと睨む程度にとどめる。
「……さて、寝るか 」
長谷部はそう独り言を零すと、小さく欠伸をして部屋に戻っていった。
***
文化祭だ。
先日までは、休み時間や放課後、学級会、それから一部の授業も使って準備を進めてきた。昨日は準備日で、丸一日。今日も朝早くからきて準備に勤しんでいた連中もいる。その辺はもうどれくらい文化祭に入れ込むかといったところだろうか。
大倶利伽羅はというと、登校時間とされた8時半ぴったりにクラスのドアを開け、9時の開会式に出ると早々に静かな場所を探そうとあたりを付け始めた。文化祭とはいえ、外れに行けば意外な程ほどに喧騒の外だ。
大倶利伽羅が声をかけられたのは、ちょうどそんなことを考えていた時だった。相手はこの夏の一件でそれなりに話すようになった山姥切国広と、その一件の関係者の山姥切長義だった。2人はよく一緒にいるが、国広曰く「長義が思い出せと言うんだが……どうしてでも思い出せなくて……」とのことで、長義が国広に昔のこととやらを本気で思い出させようとあの手この手を使っているらしい。
とはいっても、何か無理のある関係ではなく(事件の蟠りもないようだ)、仲の良いクラスメイトのように見える。今日もそれは同じようで。
「大倶利伽羅のクラスはおばけ屋敷なんだよな。なら、やっぱり脅かし役とかするのか?」
「いや、準備に積極的に参加すればあとは自由と言われたんでね」
「へえ、じゃあ今日はほとんどフリーなんだ?」
「あ、そうか。それならうちのクラスに寄っていかないか?うちは模擬店なんだが……」
「ああ、それでその格好か」
2人の出で立ちは文化祭のドレスコードと言うべきか、少々コスプレっぽさのあるウェイターだった。高校生の文化祭らしいちゃちな作りではあるものの、それを感じさせないほどに似合っている。
「国広がね、早くパーカーに着替えたいと言って聞かないから、担当は午前だけなんだよ」
「だって、こんなの無理だ……」
「そういうわけだから、よろしく」
つまり、来るなら早めに来てくれ、ということらしい。聞けば、長義は国広のシフトにかなり合わせているらしく、残りの時間は2人で回る予定だという。なんとなく長義の内心を察してしまったものの、大倶利伽羅は何か言うつもりはなかった。
しかし、国広の方はあくまでクラスメイトと回る予定と捉えていたらしく、長義の思考はよそに、そうだ、と思いついたように声をあげる。
「大倶利伽羅も午後から一緒にどうだ?」
国広の提案に、はじめ大倶利伽羅は断ろうとした。馴れ合うつもりはないし、図書室辺りは静かだろうと考えていたところだったのだ。隣に立つ長義の顔にはわかりやすく「断れ」と書いてある。だが、「……迷惑、だろうか」と申し訳なさそうにする国広を見ていると、無碍にするのも気が引けた。断る理由も特にはないということもある。
「……少しなら」
「!……少しでもいいんだ、ありがとう」
結局、大倶利伽羅は国広の提案を断りきれなかった。ぱあっと、だが控えめに国広の表情が華やぐ。半分くらい付き合って、半分くらいは2人にさせてやろう、そう思いながら大倶利伽羅が長義をちらりとみると、長義は仕方ないかと息をつく。こちらとしても少し申し訳なく感じてしまった。
昼前に一度自分のクラスのバックヤードに戻ると、隣の模擬店の大盛況ぶりが伺えた。やたらと絵になるウェイターがいるとのことで、入店は女子生徒を中心に人が並ぶほどだった。ああは言われたものの、別に2人の接客を受けたいわけではないし、大倶利伽羅は一度も隣のクラスの模擬店には寄らなかったのだが、ここまで盛り上がっているとさすがに気になる。
教室のドアは抜かれており、画用紙に『出口』と書いている方から少し中を覗き込むと、件の2人が何やらきゃあきゃあ言われていた。長義の方は慣れたように対応しているが、国広の方はそういったことは苦手らしく、助けてくれとばかりに他のウェイター役に視線を送っている。
「……大変そうだな」
思わずそう零した時だった。
国広の視線が出口扉の方を向いて、大倶利伽羅の存在に気がつく。気が付いたかと思うと、今度はずんずんとこちらに向かってきた。
「大倶利伽羅!来てくれたんだな」
「……違う、俺は少し様子を見に来ただけで」
「そうなのか……でももう昼時だし、軽食ならあるから、折角だしよければ食べていかないか?」
パウンドケーキなんだ、とメニューを渡してくる国広は見るからにほっとしている。あの人集りを何とかできたからだろうか。大倶利伽羅は、国広の誘いに教室の外を改めて見てみた。やはり長蛇の列だ。
「並んでいるようだが。それに、席もないだろう」
「ん、それなら大丈夫だ」
あの人と相席というこ���で。そう言って国広が目で指した方向に顔を向けると、嬉しそうに手を振っている、昔からよく知る眼帯の男がいた。
***
午後1時30分。
長義と国広はいつもの制服(制服は自由なので、実際はなんちゃって制服というやつだが)に着替え、料理部の広島風お好み焼きを買って、大倶利伽羅が待つ中庭に向かう。そこにはすでに燭台切と大倶利伽羅が待っていた。
「すまない、待たせたかな」
「お疲れ様。二人とも大人気だったね」
大倶利伽羅が言うには、中庭は例年出し物がないため、文化祭の時は人が少ないらしい。しかし、木製の簡易テーブルと日陰棚があり、居心地は悪くない。実際、平時ならば昼休みには生徒もいる場所だ。
「だが、上手く出来た気がしない……」
「大丈夫、ちゃんとかっこよかったよ」
「パウンドケーキも悪くなかった」
「……!本当か!」
「あれ実は国広が兄弟からレシピを聞いたんだよ」
ね、と同意を求めると、国広ははにかみながら頷いた。評判が良いことがよほど嬉しいらしい。
「ほら、国広は兄弟大好きだから」
「兄弟の作るものは何でも美味しいんだ」
からかうように長義が言うも、国広の耳はそうとはとらなかったらしい。兄弟?と燭台切が訊ねると、養子先の兄弟なんだ、と国広はやはり楽しそうにしている。
「なるほど、好きな人のことを褒められると嬉しいものだよね」
「……ああ、嬉しい」
そんな会話をしながら、何となく空いている席に着く。がさり、とビニール袋をテーブルに置いたところで、長義と国広は互いに目を見合わせた。その様子を見ていた燭台切は、「僕らはもう食べちゃったから、遠慮せずに食べて」と人好きのする笑みで促す。長義がそれでは遠慮なく、とセットの割り箸を割ると、国広も遠慮がちに手を合わせ「いただきます」と声を揃えた。
「それにしても、国広くんも長義くんも元気そうで安心したよ」
暗に夏のことについて言っているのはわかった。国広が返答に困っている様子なので、長義は代わりに俺達は問題ないよ、と答える。
「だが、長義……」
「……はあ、わかってるよ」
長義の「問題ない」という言葉に、国広は抗議の目を向ける。長義は嫌そうにため息をついた。話したいことではないらしい。
「……一度母には会った」
「え、そうだったのかい?」
「あの、たしか鶴丸……だったね、彼にも会ったよ」
「鶴さん?どうだった?」
「元気そうだったよ」
「だろうな」
実際はそうでもないのかもしれないが、大倶利伽羅は元気ではない鶴丸を見たことはなかったため、そういうものだと思ってしまっているところがあった。まあ、本人もそう思われたくて、そのように振舞っているようだが。
事実だけを伝えて、長義は話を打ち切ろうとする。顛末は気になったものの、無理強いをするのも良くはないだろう。燭台切はそれ以上何かを尋ねることはせず、文化祭の話題へと話は流れていった。
「じゃあ僕はこれで、文化祭楽しんでね」
それから程なくして、会話の切れ目に燭台切は立ち上がり別れを切り出した。もともと文化祭そのものよりも、どちらかというとかつての依頼人達の様子を見に来ていたようで、もう用事は済んだのだろう。大倶利伽羅はそう推測しつつ横目で見る。
「ところで、俺は光忠に文化祭の日程は伝えてないはずだが」
「あ、ああ、その、たまたま通りかかって……?」
「そのパンフレット、学生用のものなんだがな」
大倶利伽羅の指摘に、燭台切が困ったように誤魔化しうとするも、あえなく追撃をくらう。別にどうでもいいが、と大倶利伽羅が返そうとした、ちょうどその時だった。
『3F音楽準備室で火事です。繰り返します、3F音楽準備室で火事です。校内にいる皆さんは、至急校庭に避難してください』
突然、文化祭は終わりを告げた。
学校が燃えてなくなる、などということはなかった。
当然と言えばそうだし、幸いと言えばそれもそれで一理あるのだが。
とはいえ、ことが起きてしまったということもまた事実で、文化祭は中止、明日は休み、振替休日も予定通り休みで、火曜日に片付けのために登校するという運びになった。今日ももう帰れ、というのが学校側からの通達だ。それも当然と言えば当然ではあるが、興を削がれた生徒のブーイングが出てしまうのもまた、もっともだろう。
「……でも、少し不思議じゃないか?」
「何が?」
「音楽準備室って火災が起きるようなところだろうか……」
帰れと言われているのだから帰るしかない。今度こそ燭台切と別れ(送ろうかと言われたがそれは断った)、三人は教室に戻り、教科書などの入っていない軽い鞄を手に玄関まで向かう。上履きを履き替えた所で、ふと国広が疑問の声をあげた。
言われてみれば、と長義は顎に手を当てて考えてみる。思い返せば、音楽準備室にあるのは楽器ばかりだ。近くにある美術室の方が、よほど燃えそうなものがたくさんあるように思う。あるいは、音楽室そのものなら、机や椅子は木製なので燃えるだろう。
一方で、大倶利伽羅は怪訝そうに国広を見ていた。思うところがあるらしい。
「……いや、燃えるだろ、楽譜とか」
「楽譜は火を起こせないだろう」
大倶利伽羅の言葉に国広はすかさず返す。たしかに楽譜は燃えやすい素材ではあるが、そういうことではないらしい。長義は改めて国広の言葉を反芻する。火を起こすもの、火種……。
「……つまり、国広は調理実習室や給湯室のある職員室ならともかく、そういったものがないところで起きたのが不思議ってこと?」
長義の考え込むような声に、国広がこくり、と頷く。大倶利伽羅も、そっちか、と呟いた。
「確かにそうだな……音楽準備室には窓もないから、光を集めてしまうこともない。それこそ楽器と音楽教師の私物くらいしか……」
「あ、それじゃないかな。教師の私物のライターとか」
音楽教師の保科は喫煙者だったはず、と長義は続けた。転校してわずか三ヶ月程度にもかかわらず、すっかり学校内のことは把握しているらしい。以前、そのことに対して、すごいな、と伝えたところ、大きい家ではそういうのの把握が大事だったからね、と何でもないように返されたのを国広は思い出した。住んでいた世界が違うとはこのことを言うのだろうか。時々、国広はそうやって長義との距離感を測りかねていた。長義はあまりそういったことは感じていないように見えるが。
「仮にそれだと、保科先生はどうなるんだ?」
「相応の処分をくらうんじゃないか」
あの人、悪い噂で有名だったからまた荒れそうだな、と大倶利伽羅は来る火曜日、水曜日にうんざりとした。騒がしいのは好きではない。ましてや、そういったあれこれで煩くなるのはごめんだ。
予定よりずっと早く家に着き、事情を話した長谷部に驚かれた後も、大倶利伽羅はの心のうちは靄がかったままだった。
***
ところが、予想に反して、保科は火曜日も水曜日も普通に学校にいた。
それどころか、生徒が一人自殺し、一人が捕まった。自殺したというのも、捕まったのも一年の生徒で、二人は保科に嫌がらせを受けていたらしい。らしい、というのは、自殺については朝礼で少し話があったが、捕まった云々の方は噂でしかなかったからである。嫌がらせについても、もちろん噂でしかない。
不確かな噂話を真に受けて騒ぎ立てるのは好きではない大倶利伽羅は、そういった話には積極的に参加する気にはなれず、なんとなく居心地が悪くなり休み時間は教室から離れるようになった。もともとつるまない性質なので特に違和感もない。大倶利伽羅が教室を出ると、ロッカーの荷物を整理している国広と目が合った。国広の方も、あまりそういった類の話は好きではないらしく、困ったように眉を下げた。
少し離れるか、という大倶利伽羅の提案に、国広も乗った。そのまま昼休みを過ごせるような場所を探し、廊下を弁当箱片手に適当に歩いていく。
「長義の方は?」
「……その、家の方で色々とあるんだそうだ、それで」
「休みなのか」
家の方、というのは恐らくは夏の事件に関することだろう。大倶利伽羅は目の前の国広と今はいない長義について考える。二人は確かに穏やかに、特に問題はなく過ごしている。しかし、絡んでいる問題というのはかなり強固なものだった。なるべく意識しないようにはしているものの、ふとした時にその時のことを思い出す。第三者である大倶利伽羅がそうなのだから、二人だって恐らくは似たようなものだろう。
事件の後、夏休みの間に会う機会があった際に、大倶利伽羅は国広に尋ねたことがあった。「両親について、とか、色々とあったが」と。大丈夫か、とは聞けなかった。国広は少し考えた後、「……本当の家族を知ったというのに、薄情かもしれないが」と前置きし、「今の家族が、俺の家族だと思っているんだ、それだけで十分なんだと、思う」と選んで乗せるにぽつりぽつりと言葉を置いていった。何も言わないと、いたたまれなくなったのか、国広は被っているパーカーをぎゅっと深く被りなおそうとするので、大倶利伽羅は「それでいいんじゃないか」と返した。
こちらは直接訊ねることはなかったのだが、きっと長義に関しても、きっと同じように思うところがあれど、自分なりに折り合いをつけてなんとかあの事件を飲み込んだ���だろう。
「大倶利伽羅、どうした?」
「……いや、」
少々ぼうっとしていたらしい。国広が心配そうに声をかけてくる。現実に引き戻され、なんでもないと小さく返した。
ふと目に留まった階段を見る。黄色いテープが張られているその先は音楽準備室、それからその先には屋上へと続く扉がある。
「……音楽準備室、か」
「しばらくは芸術選択は一律自習に変更になるそうだ」
「だろうな」
ここはここで居心地があまりよくない。移動するか、とどちらともなく言ってその場を去ろうとした。……が、呼び止める声でそれは叶わなかった。
「お二人は、この前のボヤ騒ぎ、やっぱりおかしいと思いませんか」
その声の主は、唐突にそう話しかけたかと思えば、次には「鯰尾っていいます、一年生です」と頭を下げてきた。
大倶利伽羅と国広の反応をみた鯰尾は、これは話を聞いてくれそうだと判断したのか、長話になるから放課後どうですか?と提案してきた。先日より、どこか違和感を持っていた二人は特に悩むでもなく頷く。
「決まりですね!じゃあ放課後、そうだなあ……」
「……あ、待ってくれ。今日の放課後には長義が帰ってくるんだ、報告することがあるかもしれないからあけておいてくれ、と言われている」
「本当にとんぼ返りだな」
「……その人、信頼に足る人ですか?」
「えっと……友人、だが……」
それなら別に一緒でもいいですよ、味方は多い方がいいので。にっこりと肯定する鯰尾に、すまないな、と国広が謝る。この場に長義がいなくてよかった、と大倶利伽羅はぼんやりと思った。友人だとはっきり言われるのは、なかなかに厳しいものがあるだろう。いや、長義のことだから、そのあたりは織り込み済みかもしれないが。
「……味方は多い方がいい、と言ったな」
「え、あ、はい、言いましたけど……」
「その道の奴がいる。そいつもその話に加わらせていいか」
いいのか?と小声で訊ねてくる国広に、問題はない、と返す。国広の心配事といえば、忙しいんじゃないかとか、お金はどうすればとか、そういったことだろうが、そのあたりに関して、大倶利伽羅には当てがあった。そもそも、困っている人を見ると手を貸してしまう世話焼きな性質の燭台切なので、言えば何を頼まずともついてくるだろうということが一つ。それから、先日猫探しに付き合った大倶利伽羅には、借りを返せといえば協力してくれるだろうということがもう一つ。それに、最近は少し仕事が暇らしく、お裾分けの回数が多いことがさらに一つ。
鯰尾が、いいですよと肯定するなり、大倶利伽羅はスマホを取り出し、燭台切あてにメッセージを送った。
***
長義は東京に戻ってくるなり、国広に言われ、学校近くの喫茶店まで足を運ぶことになった。本来ならば、何かと理由をつけて国広の放課後を手に入れようと、あわよくば、少しくらい意識させられないだろうかと画策している時間だったのだが、まあそれはいい、効果もあまり期待できないし。また、何かに巻き込まれるなり首を突っ込むなりしてしまったというところだろう。本人に自覚は恐らくないだろうが、国広はなかなか死に急ぐタイプだというのが、長義のここ最近の見解だった。
喫茶店は個人経営のもののようで、あまりがやがやとした雰囲気は感じさせない、悪く言えば少々暗い雰囲気の店だった。指定したのは大倶利伽羅というところだろうか。カラン、と音をたてたやや重い扉をくぐる。少し辺りを見回すと、すぐに目的のグループは見つかった。すでに役者は揃っているようだ。国広が振り返って小さく手招きをするので、やや小走りに長義は座席に向かった。
「噂になっている二人がいるでしょう?あれ、どっちも俺のクラスなんです」
「噂って?」
「そっか、燭台切さんは知らなくて当然ですよね。うちの学校から、一人自殺したっていう生徒がでて、それか��もう一人、例の文化祭でのボヤの犯人が捕まったっていうやつです。自殺の方は、ぼかされてはいますが朝礼で全員通達がありました」
初対面が半分という状況ではあったが、鯰尾本人がなるべく急ぎたいというので、挨拶もほどほどに本題にはいる。
燭台切に学校の現状を一通り共有すると、それから鯰尾は、「それで、ここからが話したいことなんですけどね」と一度区切った。
鯰尾が言うには、つまりこういうことらしい。自殺したという生徒はクラスメイトで、確かに音楽教師からの嫌がらせを受けていたし、それを苦にしていた。自殺した生徒の部屋には遺書のようなメモ書きがあったため、自殺した生徒が放火犯であると推測。しかし、その生徒には別の生徒によってアリバイがあった。文化祭の日、犯行時刻にあたる時間にその生徒と行動を共にしていた人物は、共犯もしくは庇いだてしている可能性が高いとして、警察に事情聴取を受けている。
「……なんだ」
「いや、慣れているな、と……」
「そういえば、以前も慣れた様子だったね」
「別に、大したことはしていない」
話がはじまるとすぐに鞄から小さいノートと筆記用具を取り出した大倶利伽羅を見て、右隣に座る国広が大倶利伽羅の飲み物をそっとずらす。そのまま簡単にメモを取りはじめるのを、国広と長義が両隣からのぞき込んでいた。視線のうるささに大倶利伽羅が訝しむと、二人は心底感心したというように声をもらす。
「あのー……話、続けても?」
「あ、ああ……すまない、ちゃんと聞いている」
話がすっかり逸れてしまっていた。先ほどから流れる様に話をしていた鯰尾が、いったん話を止めて、遠慮がちに前に座る三人に声をかける。国広が慌てて謝罪し続きを促すと、鯰尾は問題はないとふるふる首を横に振った。
「いえいえ、そんな、気にしてませんから。えっと、それで、月曜日はお休みだったじゃないですか。あの日、家に警察が来て、それからはもう、まるで犯人扱いなんですよ」
「ちょっと待って、家に?」
「ああ、そっか。捕まった生徒の方なんですけど、俺の兄弟なんです」
燭台切の疑問に、言ってなかったか、と思い出したように鯰尾は返す。返した言葉に、骨喰っていうんだけど、似てない双子ですね、とさらに鯰尾は付け足した。
骨喰は文化祭の日、ちょうど自殺したという生徒、早川と行動を共にしていた。鯰尾を含め、三人のクラスの出し物は演劇だったらしい。同じクラスの二人は、舞台のセットが甘いことに気付き、補強するためにあれこれ材料を取りに行っていたという。鯰尾が骨喰に問い質すと、犯行が起きたと推測される時間の間、骨喰と早川はずっと一緒にいたと証言したという。
「そんな彼女が死んじゃって、そこにメモがあって、だから彼女が犯人で、一緒にいたって言ってる骨喰も芋づる式で何か悪いことを一緒にしていたんじゃないかって、警察はそこを疑ってるんだと思う……」
鯰尾はテーブルの上に置いた拳を握り、わなわなと震えていた。ペンを走らせていた大倶利伽羅が顔をあげ鯰尾を見る。大倶利伽羅だけではない。テーブルの全員が何も言わず、次の言葉を待っていた。鯰尾は自分を落ち着けるように一呼吸おく。
「でも、あいつは、骨喰は、共犯とか、そんなことしないと思うんだ!確かに友達思いだし、優しいし、そのことは兄弟贔屓目を抜いたとしても俺は証明できる!でも、あいつは誰かが悪いことしてたら、それはちゃんとダメだっていうやつなんだ!だから……っ」
お願いします、骨喰の疑いを晴らしてほしいんです、と鯰尾はテーブルに額が付きそうなほどに深々と頭を下げた。
隣に座る燭台切が慌てて鯰尾の顔を上げさせる。それを確認したのち、大倶利伽羅はメモをテーブルの真ん中付近に置いて、ペンで指しながら情報を整理していく。ひとつひとつの事実問題に確認をとると、鯰尾は「はい、あってます。そうです」と言いながら頷いた。メモを再び眺めてみる。
「なあ、長義はどう思う?」
「まだなんとも。でも、骨喰の疑いを晴らそうというのなら、必然的に早川の疑いを晴らすことになる。そうなると、怪しいのは遺書と思われるメモ、かな」
「偽造の可能性があるということか?」
「まあ、そうかもね。遺書は騙られるものだよ」
「え、それドラマとかの話ですか」
「……いや実体験」
国広の問いに、大倶利伽羅の字で書かれた『早川→自殺?遺書がある?』という部分を指さしながら長義は答える。国広も特に異論はないようで、そうだな、と首肯し、遺書の偽造の可能性を提示してきた。その会話に疑問を持ったのはむしろ鯰尾の方で、長義に問いかけてみるも、反応しづらい答えが返ってくる。その様子を見て、長義は「なんてね、冗談だよ」と悪戯っぽい笑みを作って見せた。
「僕が気になったのはこの犯行時刻だね」
「犯行時刻?」
「まず、火災の発生時刻についてだけど、今回の場合火の手が回りにくいところで発生しているよね。そのうえで、放火の場合の発生時刻はそこまで正確には求まらないはずなんだ。たとえば、九時ごろ発生とあれば、九時台のどこか、というようにね」
燭台切の言葉に、鯰尾は困ったような表情になる。何が言いたいのかわからない、とわかりやすく顔に出ている鯰尾に、じゃあ質問、と燭台切は投げかけた。
「骨喰くんと早川さんが準備をしていたというのは、何時間もかかるようなものかい?」
「いえ……多分、あって数十分のものですけど……」
「それ以前や以降は二人だけで一緒にいた?」
「……あ、そうか」
燭台切の言葉に鯰尾は納得したようにぱん、と手をたたいた。それから、ちょっと紙とペン借りますね、といいながら、大倶利伽羅のメモの次のページに横線を引いていく。そして、引かれた線に短く切れ目を入れ、『犯行時刻』と記した。
「早川さんと骨喰がいたのが、ここ」
「今回の音楽準備室の火災は、隣の美術準備室まで火が回っていて、時間の特定が数十分単位で出来ないんだ。ですよね、燭台切さん」
その通り、と燭台切は答える。やった正解だ、などと鯰尾も楽しそうに返している。結構楽観的なところがあるのかもしれない。その様子を見ながら、国広は氷がほとんど解けたメロンソーダを一口飲んだ。炭酸も随分と抜けていて、甘い味だけが広がる。長くなると知りながら炭酸を頼むなんて失敗したな、とその時になって少し後悔した。
「……それなら、一度音楽準備室を探してみないか」
結局のところ、怪しいと思われた部分といえば、遺書の中身と犯行時刻くらいだった。しかし、それらは基本的に警察の管轄で、関係者でもない限りは蚊帳の外になってしまう。情報の開示だってしてくれないだろう。燭台切は一通り伝手をあたってくれるだろうが、生徒である自分たちにできることはもうないようだ。そう長義が結論付けたところに、国広が割って入ってくる。
「黄色いテープが張ってありますけど」
「……だが、全校集会の時に何も言われはしていない」
「なんだよ、その一休さんみたいな理屈は」
普通、黄色いテープが張ってあればそれは進入禁止を意味する。何も言われなくてもそういうものだと受け取るもの、暗黙の了解というやつだ。長義は呆れてため息をついた。しかし、鯰尾の方は、その言葉に「言われてみれば」などと思案し始める。大倶利伽羅はいつも通りの表情で黙っていた。これは悪くないときの反応だ。長義としては分が悪い。
「進入しちゃうのはさすがにまずいよ」
「……だよな」
助け舟となったのは燭台切の言葉だった。そういえば、初めて会った時も、大倶利伽羅と国広に死体をなるべく見せないように、だとか、そういったことをしていたな、と長義は思い出す。国広も、言ってはみたものの実行に移すことにはそこまで強く考えていたわけではなかったらしく、あっさり納得した。
しかし、その言葉に大倶利伽羅が反応する。
「……許可があれば、いいんだな」
***
「というわけだ、長谷部。日本号に許可を出してもらえるように頼めないか」
「何を言っているんだ、お前は」
久しぶりに保護者を頼ってきたと思えば、頼ってきたのは正確には日本号だった。長谷部は大倶利伽羅の言い分を聞きながら、少し嘆きたい気分になる。ため息も思わずついてしまった。
日本号は大倶利伽羅たちの通う学校で教員をしており、今は三年の副担任を二つのクラス分担当している。日本号自身は、きっと頼めばいくらでも入室許可を出してくれるタイプであるように見えるが、日本号の教師としての立場が生徒からの頼みという一点でのみ許さない。逆に言えば、保護者、養育者、そういった立場からの要請ならば、応えてくれるだろうという確信がある。また、日本号と長谷部は古くからの腐れ縁というやつらしく、付き合いも長い。
「……危険は」
「火災発生現場ではあるが、基本的には学校だ」
妙なところで燭台切の影響を受けたな……。
長谷部は再びため息をつく。あの男は、入れ込みすぎるなと忠告したにもかかわらず、また何かに首を突っ込んでいるようだ。しかも、大倶利伽羅もしっかりと巻き込んで。正確には巻き込んだのは大倶利伽羅で、巻き込まれたのは燭台切なのだが、それは長谷部の知るところではなかった。
「夜か」
「そうだな、夜中というわけにはいかないが、下校時刻が過ぎた後になる」
何か問題があればすぐに連絡をする、という大倶利伽羅の言い分に押され気味になっていく。もう一度、頼む、と静かに言われる。長谷部はそういった頼みには弱いところがあった。三度目となるため息を深くつく。それから長谷部は私用のスマホを手に取り、連絡表の『に』の欄を忌々しげに見つめる。「今回だけだ」と大倶利伽羅にとって通算何度目かわからない「今回だけ」を告げた後、通話ボタンをタップした。
***
「別に、送っていかなくてもいいのに」
「一秒でも長く居たいという気持ちが、お前にはわからないかな」
「そんなに思い出させたいのか。だが、その……」
「……そっちじゃない」
喫茶店を出るころには、すっかり日が落ちていた。喫茶店前で鯰尾とは別れ、それから駅で燭台切と大倶利伽羅とも別れ、電車には二人が残された。下車駅は二つ違い、同じ路線という比較的近隣に住んでいることが九月頭には判明し、それからは時間が合えば途中まで一緒に帰ることが多いのだが、今日は途中まで、ではなく国広の家まで送る、と長義が言い出した。
とはいえ、同い年の同性、特に送る意味が国広には見出せない。
「手続きは、一通り全部終わったよ」
「そう、か」
「……最初にDNA鑑定を見たときにね、正直に言うと、少しお前を憎んだんだ」
大通りから二本入った道を歩きながら長義はぽつりと呟くように切り出した。ひょっとしたら、国広に話しかけたわけではなかったかもしれない。国広の相槌を気にする様子もなく、長義は続ける。
「お前という存在で、俺の家はすっかり駄目になったんだって、そう思った」
「……それは」
「いや、お前を責めているわけじゃないよ。ただ、少しそう思ったことがあるというだけだ」
歩くスピードはいつの間にかゆっくりとしたものになっていた。少しだけ、並んで歩いていた距離に差ができてしまう。だから、国広には、少し前を歩く長義の表情をうかがうことが出来ない。長義も国広の方へと向こうとしない。
「でも、祖母がお前のことを『鬼子』と言って、まるでなかったことのように扱うのを目の当たりにして、考えを改めたよ。お前が家をどうこうしたんじゃない、あの家がお前を認めてはくれなかったんだと、今度はそう思った」
ゆっくりとした歩きが、ついにとまる。夜の電灯と家々から漏れる灯りが、少々心もとなくあたりを照らす。車の通りも少ない道路には、今は二人しか見当たらない。国広は、かける言葉が思いつかず、ただどうしたらいいのかと俯いてしまう。国広に気付いたか気付いていないのか、長義の独り言のような語りはさらに続いた。
「あの日、お前が現れて、なんで来たんだと思った。今更帰ってきても、お前はこの家にはとうにいないものになっている、俺も家の者としてはお前を認識してはいけなかった。本当なら、はじめに玄関先にいるのが見えたあの時に、もっとかける言葉があっただろうに。層が違うように、二度と会うことも話すこともない存在でないといけない、と考えていた」
あの日、というのは国広が村に来た当日のことだろう。玄関先ですぐに追い返されてしまったあの日。その時にはもう、長義は国広がいることに気が付いていた。「その、」と国広は思いつかない続きも放り投げて、聞こえないような小さな声で長義に呼びかける。聞こえていたかは定かではないが、その声とほぼ同時に、長義は国広の方へと振り返る。
「だからね、こうして今いるのは奇跡のような偶然だと思うんだ」
それは普段の様子からは想像がつかないほど穏やかな表情で、国広は息をのんだ。
言いたいことは色々とあるのに、言葉にはならない。
「……それは、その」
言葉が喉につっかえて出てこない。長義の言葉がなにを意味しているのか、なんとなくはわかってはいるのに、それを自分から口にすることが出来ない。そうやってしどろもどろにしている様子を、すぐにいつものような様相に戻った長義は何が面白いのか可笑しそうに笑いだす。
「まだわからないかな、好きだって言ってるんだよ」
考えておいてね、と言って、また明日と手を振り、そのまま真っすぐ来た道を歩いていく長義を、国広は茫然と眺めていた。
それから、きっともう家まではそれほど距離はなかったとは思うが、どうやって帰ったのか、国広は覚えていない。
(また明日って、明日からどんな顔して会えばいいんだ……)
気付かないフリをして、なんとか保っていたはずの均衡だったのに、長義はそれを許してくれないらしい。国広のささやかな打算は呆気なく崩れ去った。
夜になると、どうしてでもその日あったことだとか、些細なことをきっかけにして色々と考えが浮かんでしまう。ネガティブなことも。しかし、今日に限っては、数時間前のことで頭がいっぱいだった。
「……考えておけって、どうすればいいんだ」
誰かに相談したい、そう思ってメッセージアプリを開くも、こんなこと誰にいえるんだ、とすぐに閉じて、スマホをベッドサイドの充電器に差し込み、国広は逃げるように布団に潜り込んだ。
気が付いたらもう外は白んでいた。
「……あさ、」
目元をこすりながら時間を確認する。もう起床時間だ。国広は潜り込んでいた頭からかぶっていた布団から這い出した。気持ちの方が落ち着いていなくても、体は機械のように習慣通りに動いてくれるようで、制服に着替えて居間へと向かう。すでに起きている家族と挨拶を交わしご飯を口に運ぶ。さすがに挙動不審だったのだろう、兄弟に何かあったのかと尋ねられて、また昨日の夜を思い出してしまって顔が熱くなる。熱があるなら休もう、無理はしちゃダメだよ、と立て続けに言われてしまい、申し訳なさと居た堪れなさと気恥しさでいっぱいになる。熱じゃないから、心配ないから、などと国広は自分でも不思議なほどに必死に否定して家を飛び出した。
慌てて飛び出したからか、いつもよりもずっと早く着いてしまった。日直の生徒もまだ来ていない一人きりの教室。本来ならば一応は日直の仕事ではあるが、何かしていないと落ち着かないし、早く来たのに何もしないというのも気が引けた。国広は窓を開け換気を行い、黒板の日付を書き換え、教室の後ろにあるロッカーからほうきとちりとりを取り出してさっと辺りを掃除し始めた。しばらくすると日直の生徒が教室に入ってきて、入ってくるなり国広の姿を認め、何かあったのかと訊ねてくる。なぜ、と言えば、こんなに早く学校に来てるから、ともっともな意見を返されて、国広はなんでもない、なんとなくだ、とあやふやに返事をしてしまった。
それから日直の仕事を少し手伝いつつ、時間が過ぎるのを待った。日直の生徒は、いいよ別に、と言うのだが、ほとんど人のいない教室で、じっと机についているというのが、今日の国広にはどうにも出来そうにない。少しでも時間ができると、すぐに昨日のことを思い出しそうだった。
さらに時間が経ち、生徒の数が増えてくる。賑やかないつもの教室になると、ようやく気分が落ち着いてきた。そう思って、ほっと胸を撫で下ろしたのも束の間。
「おはよう、国広」
「……ああ、おは……よ、……っ?!」
誰かの挨拶に顔を上げて返そうとする。返そうとしたところで、驚いて声が出せなくなってしまった。
長義はいつも通りに教室に入り、いつも通りに鞄を置き、いつも通り隣に座る国広に声をかけたに過ぎない。それはわかっているのに、国広にはそのいつも通りが出来ない。『考えておいてね』という言葉が頭の中でリフレインしてしまう。
国広はガタン、と音を立てて立ち上がり、あと5分もなく1限目だというのに「……すまない、頭冷やしてくる!」と言い残して教室を走り去っていった。クラス中の注目が残された長義に向く。あいつに何したんだよ……と呆れるグループに、遂に何かあったんだな、と察して苦笑いするグループ。そんな面々をよそに、長義はにやける頬をなんとか抑えるのに必死になっていた。
もちろん、何の反応もないとは思っはいなかった。国広は色恋沙汰には鈍いように思うが、それでも直接の言葉を曲解するほどのものではない。けれども、あんなに意識されるとも長義は思っていなかった。
たとえば、普通に挨拶をすれば、向こうも昨日のことは夢か何かだと勝手に完結して終わるような、そういうものを予想していた。だから、あれは夢ではないのだと、今日の帰りにでも、もう一度念を押してみようかと昨夜は計画していたのに。
「……あんな反応、期待するだろう」
数分後、チャイムを聞いたのか慌てて教室に戻ってきた国広を、長義は見ることが出来なかった。
***
「音楽準備室についてなんだが……何かあったのか」
昼休み。教室の外が一気に騒がしくなる。二限と三限の間に来ていた、大倶利伽羅からグループメッセージの通り、長義と国広は文化祭の日に昼食を食べた中庭に向かった。授業が終わるや否や、国広が逃げるように教室から消えてしまったので、長義はひとりで中庭に向かうことになった。しかし、同じ教室から同じ場所に、しかも同じ人物を目的として向かうのだから、当然、早足で向かえば国広に追いつく。国広、と声をかけると、こちらを見ることなく、国広は早足になる。しまいには、中庭まで走ることになってしまい、四限は体育だったのかジャージ姿で先に来ていた大倶利伽羅は、妙に疲れた様子の二人を見て僅かに眉を寄せた。
「なん、でもないよ……ちょっと国広に逃げられただけで」
「に、逃げてはいない……!」
「声をかけたら走り出しただろう」
「う……急いでいたんだ、教室から中庭は少し遠いから……」
「俺が声をかけるまでは歩いていたのに?」
「どうでもいいが、長く続くようなら他所でやれ」
「……すまない」
堂々巡りになっている応酬に、大倶利伽羅が釘を刺す。売り言葉に買い言葉、あまり生産的ではないことに自覚はあった二人は、素直に黙って、先日とほぼ同じ日陰棚の下にある木製のテーブルに昼食を置いた。
程なくして、鯰尾が中庭まで駆けてくる。
「みなさんお揃いで!お待たせしてすみません」
ぺこり、と小さく頭を下げ、「じゃあ、えっと、お隣失礼しまーす」と空いている大倶利伽羅の隣に座り、弁当箱を置いた。
「……それで、音楽準備室がなんですか?」
「ああ、長谷部が……いや、これはいいか。結論を言うと、日本号から教師立ち会いの元ならば許可を出すと言われた」
「日本号先生?3年生の副担ですよね、どんなご縁が?」
「……知り合いの知り合い、のようなものだ」
「それもう全くの赤の他人ですよね」
鯰尾が大倶利伽羅の言葉にあけすけに返している間も、長義と国広は黙々と昼食に集中していた。話は聞いているらしく、頷いたり、声の方に視線を向けたり、といった反応は示している。一方で、たまにちらちらと隣を見ては、さっと目を逸らし、というのを続けているのが、大倶利伽羅にも鯰尾にもすぐにわかった。
「何かあったんですか?」
「……さあな。とにかく、今日の放課後に日本号立ち会いで音楽準備室を調べる……そこの2人、伝えたからな」
「えっ、あ……ああ……大丈夫だ、聞いてる、その、許可ありがとう……」
「……俺も、ちゃんと聞いてるから安心していいよ」
大倶利伽羅がやや強い口調で言えば、国広はびくりと肩を跳ねさせ、長義は少し忌々しげに放課後の音楽準備室調査を了承した。
***
放課後、下校時刻過ぎに音楽準備室へ続く階段前に全部で四人の人影があるのを確認した日本号は、「お前らが長谷部の言ってた燭台切の助手か」と尋ねた。戸惑いながら否定しようとする国広を遮って、大倶利伽羅は「そのようなものだ」と返す。
「高校生をスパイにして保科の浮気調査とは、燭台切のやつもなかなか……」
「え、そんなことになってるのか?」
「見ろ国広、あの顔は冗談言ってる顔だよ」
「……なんて、ちゃんと長谷部のやつから聞いてるよ。この前の放火で気になるところがあるんだろ?」
じゃあ行くか、そういうと、日本号は黄色いテープの端をハサミで切る。いいんですか?と国広が慌てると、日本号はあっけらかんとした態度で後で張りなおすさ、と答えた。
「しかしまあ、あの長谷部がこんなことを頼んでくるとはなぁ……」
あいつも丸くなったってことかね、と日本号は遠い目をした。日本号の知る昔の長谷部ならば、頼まれたから少し音楽準備室とやらを開放できないか、出来ることなら子守りも頼む、教師なのだから生徒の面倒を見ろ、などと言いだすはずがない。ルールはルール、そういってどんな意見でも一蹴していただろう。いや、どうだろうか。あの真面目馬鹿はそういった自分の真面目馬鹿さで散々なことになったことがある。その時の後悔が長谷部を変えたのかもしれない。いずれにせよ、悪いことではないように日本号は思っていた。
階段を上がる中、そのようにぼんやりと考えていた日本号に、鯰尾が声をかける。
「あの、すみません……でも俺、どうしてでも気になっちゃって」
「気にすんな。もしも俺がお前のような立場だったとしても、何かおかしいって言いだすだろうよ。でも、無理矢理物を開けようとしたり、壊したりはしないこと。いいな?」
「……当然だ」
「はーい、わかりました」
じきに着いた音楽準備室の鍵を日本号が回す。今日は保科はいない曜日なので、鍵は職員室にかけてあるものを使った。鍵は保科の持っているものと、職員室のものの二つがある。それは学校中で周知のものだった。音楽準備室は吹奏楽部もよく使うが、保科は快く鍵を貸さない性質であったため、必ず職員室から借りているのだ。
「じゃ、俺はここで待ってるから終わったら言ってくれや」
日本号がそう言って扉を開けると、籠った空気がふわりと漂ってきた。
「……さすがにもう、焦げ臭くはないですね」
「でも、結構見事に燃えてる」
「……保科の私物もかなりが燃えたんじゃないか。焦げが強いのが机のあたりだ」
「机のあたりなら、なおのこと本人のライターとか、その線が強くならないか?」
思い思いに感想を述べながら、音楽準備室に入っていく。その様子をドアの前で日本号は、これはこれで不思議な組み合わせだと考えながら見ていた。
教室というには準備室は狭い。楽器などはすべて移動されたため、もともとの音楽準備室に比べればずっと広いはずだが、それでも一つの教室を半分にした程度の広さしかない。もう半分は美術準備室になっているはずだ。いずれも、音楽室・美術室が広々としているためなのだろうか。荷物は多いはずなのだが、これに抗議が出たことはなさそうだった。
「でも、調べてみたところで、一応ここって警察も見てるはずだよね」
「……まあな。ダメでもともとだ」
一通り見た所で、手がかりが得られないような気がしてた。飽きてきたのか、残された棚を開けて、手で奥の方をまさぐりつつ、長義が誰に言うでもなく呟く。反応を帰した大倶利伽羅も、もう一度見てみるか、と案の定、鍵がかけられていいた保科の机に手をかけた。やはり変わらずしまっている。
「でも、火元が机側というのは大きいんじゃないか?この教室の最奥にあるから、入り口付近で火を放ったということはないことになる」
国広がやや前向きな意見を出したときだった。
「……あ!」
鯰尾が何かを見つけたのか、やや大きく声を上げた。
「……何かあったのか?」
近くにいた大倶利伽羅が声をかける。鯰尾は「手がかりかはわかりませんけど……見つけました」と言いながら、一枚の写真を渡した。
そこにいたのは、保科と、それから高校生くらいの生徒。
制服には校章があり、どこの学校かまでは潰れていて見えないものの、私服制服のこの学校とは違うものだとわかる。服装はセーラー、女子だった。
「心当たりは?」
「……あります。これ、早川さんの友達です。文化祭の日、うちのクラスに来てましたから」
「明日は骨喰についていたいので」
鯰尾とはそう言って昨日別れた。骨喰はあまり多くを語らないから、自分が見ていないとどうにも心配なんだと鯰尾は零していた。
「だって、ほら……SOSだって骨喰は言ってくれないから。信用されていないとは思わないんですけどね、それが骨喰にとっての当たり前だし。それなら、俺が骨喰のこともたくさん気付いて、拡声器になればいいんです」
それが俺達の在り方なんですよ、と鯰尾は笑っていた。
「大倶利伽羅もあまり喋らないよな」
「……何の話だ」
「昨日の」
国広が思い出したかのように話を始めたのは、放課後の空き教室で、昨日の写真のコピーを三人で囲んでいるときだった。大倶利伽羅も昨日のことを思い出したのか、国広の言葉に、ああ、と相槌を打つ。
「燭台切は、やっぱり大倶利伽羅が喋らない分を代弁していたりするのか?」
「光忠はそんなんじゃない」
「鯰尾たちの在り方と、大倶利伽羅たちの在り方は、やっぱり違うよ」
「……そう、か。そうだよな」
長義が大倶利伽羅の言葉に付け足すように言う。あ、と声を上げ、次にはすまない、と謝る国広に、大倶利伽羅は、謝るようなことか、と息をついた。はじめのうちは苛立っていた国広のこの態度も、夏の日から、まだそんなに長い付き合いではないのに、あっと言う間に大倶利伽羅には慣れたものとなっていた。
その間を割るように、長義は話を切り出す。
「鯰尾は、骨喰のために出来ることをやっている自分にその在り方を見出しているんだろうね」
世話焼き体質というところかな、と長義は続ける。その言葉を受けた国広は、在り方、と呟き、黙りこんでしまった。俯いてしまうと、長い前髪が目元を隠してしまい、二人には国広の表情が読めなくなってしまう。瞳は面白いほど感情を乗せるというのに、これでは何もわからない。長義は国広のこの仕草があまり好きではなかった。
***
今朝から妙に寒気があって、頭がぼうっとしていたからだろうか。普段なら気にしないようにできていたことが、妙に気にかかってしまう。昨日の帰りには気にならなかった鯰尾の言葉が気になったのもそのせいだろう。
国広は、二人の会話がどこか靄がかって遠くで聞こえる中で一人考え込んでいた。
今しがた発せられた長義の言葉を反芻する。
(……出来ること、在り方、か)
最初に国広が鯰尾の話を聞いて一番に思ったのは、自分の兄弟が同じように疑われていたら自分はどうするかということだった。
きっと、鯰尾のように誰かを味方につけようとは考えない、かもしれない。でも、兄弟が疑われるのはきっと見ていられない。途方に暮れるだろうか、一人でできることを探すかもしれない。思えば、あの夏の依頼も、友人に脅迫状を発見され、半ば無理矢理引っ張られたのだった。それがなければどうしていただろうか。少なくとも、長義とはこのような形で出会うことはなかったかもしれない。いや、ひょっとしたら今ここに自分はいないかもしれないほどだ。
国広には、大倶利伽羅のように探偵の知り合いもいなかったし、日本号に許可を取り付けたように別のあてもない。それだけではない。昨日の様子を見ていてもそうだったが、大倶利伽羅はずっと鯰尾のことを気にかけていた。クラスメイトが自殺し、兄弟が疑われている、気丈であろうとしてはいるが、焦燥はある。国広にもそれはわかっていた。しかし、自分が気にかけることで鯰尾に余計に気負わせてしまわないかと思うと、何もできなかった。大倶利伽羅は、相手を気負わせることなく、さり気なく気を遣うことが出来る。
長義はどうだろうか、と国広は大倶利伽羅と話している長義を見る。長義はあの夏、ひとりで秘密を抱えていた。『家の者としては』と長義は言っていた。自分が同じ立場なら、あんな風にはきっと振舞えない。
自分には、彼らのようにはなれない。彼らにできることが、自分にはとても出来そうにないから。まるで傾いた天秤のようだ、と国広は考えた。それが自分の在り方として、よいものだとは思えなかった。
(……そうだ、考えておけ、と言われたんだった。)
昨日の帰りまでは長義を見る度に思い出して、その度に心臓が跳ねるのを感じていたのに、今度は気分が沈んでいく。
今、告白を受けたところで、何となく長義に流されただけなのではないか、そう国広は考えてしまいそうになる。ずっと知っていた、何となく気付いていた視線に気付かぬ振りをしておきながら、いざ告白を受けたら馬鹿みたいに意識をして、それで付き合おうとなるのは、長義に対して不誠実な気がしてしまう。
「……ひ……ろ、国広!」
「……え?」
「え?じゃない。急に黙るな、心配するだろう?」
思考の海に沈んでいたところに、自分を呼ぶ声が響く。はっと我に返ると、国広の目の前には長義が、その少し後ろには大倶利伽羅が、どちらも心配そうにこちらを見ていた。
「……す、すまない……考え事をしていて……っうわ?!」
「顔色も悪い、と思ったら少し熱があるな……」
咄嗟に謝る国広に対して、有無を言わせず長義は国広の前髪を右手で避け、そのまま額を国広に押し付ける。驚く国広をよそに、額も手もさっと離れ、怪訝そうに眉を寄せた長義はぶつぶつと呟きつつ、国広の前髪を軽く整えた。国広が、熱?と聞き返す間もなく、今度は右腕を掴まれ、国広を椅子から立ち上がらせる。
「すまない、大倶利伽羅。今日はこいつを連れて帰る。明日以降にしよう」
「ああ、構わない」
「え、え……その、長義?」
「帰るよ」
そのまま長義は国広の座席にかけてある鞄と自分の鞄を持ち、国広を引っ張りながら教室から出て行った。残された教室で、大倶利伽羅はため息をついた。
「……喋らないのは、そっちだろ」
***
長義が黙ったままなのが、国広にはなぜか恐ろしく思えた。何か、自分の考えを見破られているような居心地の悪さを覚えてしまう。自分の考えを見破られて、そのことで軽蔑されているかのような感覚だった。
ぎゅうっと掴まれたままの腕が痛い。なのに、振りほどくのが怖い。
「……長義、あの」
校舎の玄関まで来たかというところで、小さく、痛い、と素直に告げると、あっさりと掴む腕はほどかれた。それどころか、長義はどこかバツの悪そうな顔をしている。そのためか、国広まで悪いことをした気になってくる。口癖のような謝罪が口をついて出てくるかといったところで、それを遮るように長義が話し始めた。
「……先に一応言っておくけど、国広が悪いわけではないから」
「え?」
「お前とは同じクラスだろう?朝の時点で、様子がおかしいのなら気が付けたはずなのに、気が付けなかった自分に苛立ってる。……すまない、お前にぶつけるつもりはなかった。自分でも、驚いてるくらいで……」
「そんな、俺は……」
自分でも長義に言われるまで体調に気が付かなかったくらいだし、今も大したことではないし、と国広は言葉を並べはじめる。それでも納得のいかない様子の長義は、そうじゃない、と国広を遮った。
「……鯰尾のこと」
「……ああ」
「いいな、と思ったんだよ……お前も、言わないから」
パタン、と靴箱になっている棚を閉めながら、そう言い出した長義の言葉に国広は首を傾げた。言わないとはなんのことだろう。そう思いながら自分も靴を履き替える。
言わない、言わない、と何度か繰り返して、告白のことか、と思いあたった。返事をせかされているのだろうか。毎日一緒にいて、何もアクションを起こさないのは、言われてみれば確かに、それはそれで不誠実な気がする。国広はそこまで考えて、それから一度息を吸った。
「……その、先日の夜のことだが」
嬉しくなかったわけじゃない、むしろ、自分でいいのかと思ったほどで。
でも、ダメだと思ってしまう。自分では、長義にとって最終的にはよくない。
「俺では、お前に応えられないと、思う」
***
白状しよう。
浮かれていた。今の今まで、勝利を確信していた。
だから、長義は国広の言葉が最初飲み込めな��った。何を言っているのかもよくわからなかったし、熱に浮かされてわけのわからない思考回路から結論を導いているんじゃないかと疑った。だが、国広は正気のように見える。少し顔色は悪く、先ほどから咳が混じるようになっているが、自分でも気が付かなかったというように意識の方はしっかりとしている様子だった。
昨日の朝のあれは、どう考えても、そういう反応だったのに。少ない経験からもあからさまにそうだと思えるほどにわかりやすかったのに。
だからこそ、長義は冷水を浴びせられたような感覚になってしまった。
「……それ、が……答え?」
「……すまない」
ずっと、どうやって告白を断ろうかと考えていたのだろうか。どうしてこのタイミングでそのようなことを言うのか。もしや、国広のことを気にかけてしまうことに対して、迷惑だとでも感じているというのか。
国広は申し訳なさそうに謝ってくる。国広の口癖のようなものだった。
「……はあ、どうして今言うかな」
「……、」
「ああもう、謝るな……こちらが惨めになる」
惨めにさせてくれるな、といえば、国広はまたも続けようとしていた謝罪の言葉を飲み込んで黙ってしまう。
「お前が迷惑に思っていたとしても、今日はお前を送り届けるから」
「迷惑、なんかじゃ……」
「……お前ね、病人が余計な気を遣うなよ」
「……」
国広は、とぼとぼと長義の少し後ろを歩く。大丈夫だから、と鞄は持たせてしまった。国広とて馬鹿ではない。体調があまり良くない今、無理にどこかへ行こうとはしない。長義が国広を送っていく意味もあまりない。
明日からどうしようか、大倶利伽羅は気が付く方だから、そっと察してくれるだろうか。長義はぼんやりと考えた。
家まで何も話すことなくたどりついてしまった。
国広が家に入っていくのを見届け、自分も踵を返す。そういえば、ここで話をしたんだった、と帰り道、一人になって考えた。
国広は最後まで謝っていた。そこまで悪いことをしたわけでもないのに、国広はすぐにその言葉が出てくる。あるいは、自分が悪いとでも本気で思っているのかもしれない。それは長義にはあずかり知らぬ国広の内面的な部分だ。
長義は、国広のそういった性質が嫌いで、それでいて存外気に入っていた。
『俺が骨喰のこともたくさん気付いて、拡声器になればいいんです』
鯰尾の言葉だ。長義は、これを悪くないと感じていた。
国広がああいう性質なのは、もう仕方のないことだ。変わらず自分だけが覚えている幼少期から、今ほどではないにせよ、引っ込み思案なきらいはあった。同い年なのに、少しばかり誕生日の早い自分は、まるで弟が出来たような気分にもなっていた。当時は、だが。
今こそ抱いている感情に変かはあれど、根本的に変わらないところもあった。簡単に人は変われないし、国広がどうしてそういう性質になってしまったのかも、長義にはどうでもいい。ただ、ああやって自分を押し込めてしまう国広の代わりに、自分が国広のことに気付いてやれれば、と思っていた。
結果的には、国広を困らせていたようだし、とんだ独善だったようだが。
はあ、ともう一度ため息をつく。いつまでもぐるぐると平行線をたどるようなことを考え続けるなど、自分らしくもない。
「ああクソ、やめだやめ……」
誰に聞かれるでもない日が落ちた住宅街。気持ちを切り替えようと独り言を声にしてみた。思ったよりも声は大きく響いたような気がしてしまって、思わずあたりを確認してしまった。聞こえているなんてありえないが、少なくとも、国広には聞かれたくはない。
「……あれは」
その時だった。長義は目の前に見覚えのある姿を見つけた。
その人はきょろきょろとあたりを見回している様子で、近くの公園へと入っていく。
例の写真の女性だった。
***
「……探し物ですか?」
「えっあ、は……いぃっ?!」
思わず声をかけてしまった。
公園へと入っていったその人は、どう考えても遊びに来ている様子ではなかった。公園の隅の方、花壇の陰、あらゆる死角を服が汚れるだろうことも気にすることなく、ごそごそと探し始めた。公園には彼女と、それから長義しかいない。その人は、長義の様子に気付くこともない。よほど集中しているようだった。
長義が声をかけると、その人は振り返り、それから自分の行動をみられていたことに気付いたのか、驚いて素っ頓狂な声を上げる。
「だ、誰ですか見てましたか見てましたよね?!」
「……ええ、と、まあ」
「わわ、忘れてください!」
「ああー……そういうわけにも、いかないかな」
それから、妙なハイテンションで長義に向ってまくしたてた。普段どちらかといえば静かな連中の方が周りには多いためか、どうにもそのテンションについていけず、ひるんでしまう。
しかし、忘れるわけにはいかない、といった長義の言葉に、その人はスッと一瞬で表情を、仕草を凍らせた。知られるわけにはいかない何かがある、ということだ。長義はその瞬間を見逃さなかった。
「……保科、という人間を知ってますね」
「貴方……一体、」
鞄の中にいれたままになっていた写真のコピーを取り出し、女性に見せる。女性の表情はますますこわばっていく。黙り続けていると、ついには、恐怖からか、ぽろぽろと涙を流し始めた。理由はわからないが、泣かせるつもりもなかった長義はさすがに戸惑った。何か言わなければ。そう思った長義が声をかけるより前に、女性が口を開く。
「……天使との、取引なんです」
「天使……?」
はい、天使です。聞き返した言葉に、はっきりとそう返されて、長義はどこか気が遠くなるのを感じた。
翌日。
どうにも気まずい。自分で蒔いた種だというのは理解している。だからこそ、どうしようもなかった。
大倶利伽羅とはまだ会っていない。鯰尾とも。長義は同クラスなので顔を合わせているが、会話は交わしていない。思わず目を逸らされてしまった。無理もない、結果的には長義から受けた告白を断るようなことをしてしまったのだから。きっと彼は自分に対していい感情を持たないだろうし、ひょっとしたら怒ってるかもしれない。
そう思っていた矢先のことだった。
「……山姥切」
「えっと、うち二人いるんですけど、どっちですか?」
「ああそうだったな、山姥切国広、ちょっと」
二限と三限の間の時間だった。ガラリと教室の扉が開いたと思ったら、呼び出しだった。ドアの近くにいた生徒が対応し、「国広くん、呼ばれてるよ」と自分を呼ぶ。何かあっただろうか、何かしただろうか、なんとなく不安に思いながら、「はい」と返事をする。顔を上げて、思わず固まってしまった。目の前にいたのは、音楽教師の保科だった。
「山姥切のやつ、いくらなんでも遅いな」
もう三限のチャイムなってだいぶ経つのに。そう呟く近くの生徒の声で、長義はようやく国広がいないことに気が付いた。違う。正確には、誰かに呼ばれて教室を出ていったということを事実としては知っていた。ただ、なるべく意識の外に彼をおくようにしていたから、鈍くなっていたのだ。
「国広、どうかしたの?」
「お前気付いてなかったのかよ」
生徒の一人に話しかけると、彼の方は、むしろなぜお前が気付いていないのかとでも言いたげに答える。次の時間は選択科目で、三限と四限は自習だった。先生はたまに見回りにくるくらいで、教室は授業中の時間帯にも関わず比較的騒がしい。
「……色々あってね。それで、国広は?」
「先生に呼ばれた」
適当に誤魔化しつつ、続きを促し、返ってきた答えに嫌な予感がした。
「先生って誰」
「え、何でお前が必死になってるんだ……?」
「いいから!」
「保科先生だけど……って長義?!」
次の瞬間には、長義は教室を飛び出していた。向かうは音楽準備室だ。あそこは、今は一応封鎖扱いだから、きっと人が寄り付かない。かつ自分のテリトリーでもある。自分が保科ならそこを選ぶ。急がないと、と思いながらも隣のクラスを横目で見る。大倶利伽羅はいつもの席にはいなかった。メッセージを開き、『音楽準備室』とだけ書いて送って、ポケットにスマホをしまう。
どこで漏れた?長義は音楽準備室へと続く階段へと向かいながら頭を働かせた。きっと国広が、保科について嗅ぎまわっていると思われている。間違ってはいない。だが、そこに長義は含まれていない。だから、国広だけを呼び出したのだろう。
「……だから、俺は知らないと言ってます!」
「知らないはずがない!あいつは、天使の話をしたと言っていたんだ!お前に!」
「……っ、本当に、知らない、昨日は早く帰って、それからずっと家に……」
「あいつに指定した場所はお前の家の近くだった、その上、山姥切と名乗ったと言っていた、お前以外に誰がいるというんだ!」
階段を駆け上がった先、すぐによく知った声が聞こえた。
すぐあとに、何かがぶつかる鈍い音もした。
慌てて扉を開ける。
保科と、それから痛みで小さく呻きながら蹲り、それでも目の前の男を睨む国広がいた。
***
「それで、天使って……?」
「そう、ね……貴方は、オペラ座の怪人って知ってる?」
「……ガストン・ルルーの?」
「そう、それ」
さすがに秋とはいえ、夜になると少し肌寒い。近くにあった自販機で、適当に温かい飲み物を探す。結局ホットココアを二本買って、ひとつを女性に手渡した。それから、公園のベンチに座り、女性に話の続きを促す。すると、女性の口から出てきたのは、かの有名な小説だった。
「私ね、舞台女優をやってるの……まあ、あんな大舞台ではないけれど」
大舞台に立つのは夢ね、スポットライトを浴びて死にたいと思うもの。女性が続ける言葉に、へえ、と長義は相槌を打つ。言われてみれば、確かに結構顔立ちは整っているし、言動はともかくとして、話し方もはっきりとしていた。舞台に立てば、それなりにスポットライトが映えるだろう。天使だなんだと突然言い出すことへは、不信感がどうにもぬぐえないが。
「でも、私、いまいち伸び悩んでいて」
「それは……オペラ座の怪人というほどなら、歌?」
オペラ座の怪人は、クリスティーヌに歌を教える『天使の声』と、オペラ座に住まう怪人の謎を巡った物語だ。長義も以前、一度だけ、今はもういない父に、東京まで突然連れられて観劇したことがあった。今にして思えば、ああいった父の態度は、自分への贖罪だったのか、あるいは……。
「……話が早いのね。そう。私はね、ファントムに歌を教わっているの。その代わりに、私はファントムの言うとおりにする……そうすれば、私は舞台に立てる」
だから取引か、と長義はようやく最初の言葉を理解した。
しかし、話はあわせつつも、長義からしてみれば頭の痛い話だった。きっとファントムというのは保科のことだ。彼は音楽教師だから、指導も当然できることだろう。言うとおりにするというのが何を意味しているのかは、はっきりとしないが、こんな時間に公園で一人、探し物をさせるくらいだから、どうせろくなことではない。
彼はファントムなのだろうが、エリックではない。彼女を愛しているとか、そういったことではきっとない。彼女も、わかっていて騙されているのだろう。ひどく、歪んだ関係に思えた。
「……そう。でも、今日はもう帰った方がいい。ほら、夜に女性が一人で出歩くのは危ないだろうし」
「あら、貴方結構紳士ね……ええと、名前……」
「……山姥切、だけど」
「珍しい苗字ね。ありがとう、山姥切くん。でも、私は大丈夫だから」
そう言って微笑む女性は確かに綺麗で、舞台女優としての貫禄のようなものが見えた気がした。その勢いに押され、結局は長義は早川さんについてのことを聞きそびれたまま、女性を見送ってしまった。ホットココアはもう、とっくに冷めていた。
***
「光忠……急いだほうがよさそうだ」
「え、ああ、ごめんね伽羅ちゃん。僕のことはいいから先に……」
「……音楽準備室、とメッセージが来ている。長義からだ。恐らく、国広もいるんだろう、どちらかか、あるいはどちらもか、とにかく危ない」
「え、ええっ?!なんで?!」
「俺が知るか」
昨夜のこと。
早川の母親から長谷部へ、それから燭台切へと手渡された懐中時計は、最終的には大倶利伽羅のもとへとたどり着いていた。
早川さんのお母さんには会えなくて、結局その時計だけが手がかりで……と言いながら、燭台切は大倶利伽羅に懐中時計を見せた。懐中時計を見るなりに、面倒がやってきたとばかりに険しい顔をする大倶利伽羅をよそに、燭台切はといえば、どうすればいいと思う?などと聞いてくる。
「ばらせばいいんじゃないか」
「僕、機械には弱いんだよ……知ってるでしょ?」
「はあ……貸せ」
道具ならあるよ、と言いながら、ミニ工具セットを取り出してきた燭台切に、またため息をついた。仕方ない、と受け取った懐中時計を電気にかざしたり、くるくると回してみたりする。妙な音がした。
「……これ、時計を合わせれば開くタイプの絡繰りなんじゃないか」
「ああ、そういうやつか……」
何度か針を回すと、特定の位置でカチ、カチと音が鳴る。針は短針と長針で、違うところでなっているようだった。
「……探偵、金庫を開けるのと同じ要領でいけそうだが」
「う……探偵がピッキングとか鍵開けにたけてるって、漫画の世界の話だよ」
まあやるけど。そう言いながら、燭台切は耳に懐中時計を押し当てながら、少しずつ針を回していく。しばらく経つと、カチャリと別の音がして、支えを失ったパーツの一つが、何か中に入っていた軽いものとともに床へと転がり落ちた。
「……紙、だな」
「ねえ、これって……例の遺書……?」
そこに書かれていたのは、告白文だった。
確かに、早川という生徒が、ボヤ騒ぎを引き起こした。そのことが書かれていた。
***
「骨喰、大丈夫?それとも結構きつい?」
「……『はい』か『いいえ』しか、言ってない気がする」
表情こそ大きく変わる様子はないものの、長年一緒に過ごしている鯰尾には、骨喰がひどく疲れていることくらいは、すぐに察しがついた。よほど疲れているのか、わかりやすい弱音も吐いていて、珍しいとか変わってやりたいとか、色々と感情がこみあげてくる。
「警察の人、なんか言ってたりした?」
「……思い当たることは、」
「だよねえ……」
骨喰は無関係だ。何を言われたところで、知りません、としか言えないし、何を聞いたところでわからない話だ。ひょっとしたら、色々と調べていた鯰尾の方が、事件について詳しいかもしれないくらいだった。
「……そうだ。早川、は」
「うん?」
「早川の遺言書は、切り取られたもの、らしい。残りは、見つかってないそうだ」
「うーん……どういうことだろう?」
「さあ……」
コンビニで買った肉まんを片手に、住宅街を歩く。ここは二人の通学路だった。自宅までほどなくしてたどり着く。
学校では散々だった。勿論、クラスの誰もが、いや、心の内では少しもということはないのかもしれないが、骨喰を疑ったり、骨喰に冷たく当たるようなことはしなかった。早川についても同じだ。死体蹴りをするのもどうかと思うし、何よりもつい数日前までは、みんなで文化祭の準備をしていたはずなのだ。手のひらを返すような態度をとる人がいないのは、当然と言えば当然なのかもしれない。
でも、警察で重要参考人として聴取を受け続けていた骨喰は、好奇の対象だった。つまり、質問責めに遭った。
「……山崎、香取、堀川、高橋、と」
早川の遺書について、少し考えてみた。しかし、考えてみても何も思い浮かばない。気晴らし程度に、公園沿いにある表札をなんとなく確認しながら歩く。とはいっても、特に変わり映えはしないのだが。鯰尾にとっては、ご近所さん、といえども、全く交流があるわけではない。小学校が同じ、とかそのくらい近しい関係の奴の家ならば、ある程度わかるが、その程度だった。
「……鯰尾」
「ん?どうしたの?」
「隠れる」
「えっ?!」
突然名前を呼ばれたと思ったら、腕をひかれ、二人で転がり込むように公園入口横の木々の間に潜る。骨喰の頭についた葉を落としながら、鯰尾がいきなりどうしたのかと訊ねると、骨喰は真っすぐ公園の奥、ベンチの陰辺りを指さした。
「保科だ」
「……本当だ、こんなところになんの用だろう」
そこにいたのは保科だった。小声で会話を交わす。といっても、さっきの音もだいぶ大きかったし、気付くならあの時点で気付いていそうだが。保科は、二人に気付くことなく、あたりを挙動不審気味にきょろきょろ見回しながら、木陰に何かを置いて、土を軽く被せた。
集中しているのか、逆にまったく集中できていないからか、相も変わらず誰かの気配などには気付くことなく、保科は公園をそそくさと離れていった。
「行ったみたいだ、行こう」
「ちょっと、骨喰!」
保科が公園から離れていくのを確認した途端、骨喰は立ち上がり、迷わずベンチの方向へと向かっていく。少し遅れて、鯰尾がそれを追いかけた。
少し土を掘り返すだけで、すぐにそれは現れた。なかなか体格のいい保科には、少し不似合いにも思える小さく可愛らしい小瓶だった。
「……これって、土に埋めるもの?」
「どちらかといえば、海だな」
「あ、中に紙が入ってる」
ますます海の方がいいんじゃないか、と言い合いながら、何度か小瓶を逆さにして振ると、あっさりと中のものは出てきた。小さく折りたたまれたメモ用紙だ。
「……これ、は」
「黒……」
「……だね」
互いに顔を見合わせる。それから、こくりと確かめるようにうなずき合った。
『明後日いつもの駅前ホテル八〇四号室』
中身は、誰かへの指示だった。
しかも、駅前のホテルについて、手元ですぐに調べたところ、明らかに高校生には不釣り合いで、不適切な場所だ。そんなところへ、誰かを行かせようという指示。
露骨なまでに黒だった。
さっと血の気が引くのを感じる。何か、大変な情報を手にしてしまったかのような。鯰尾は手早く小瓶をポケットにしまい込み、「行こう」ともう一度頷きあい、そのまま二人は急ぎ足で公園を後にした。
***
翌日。
鯰尾が三限の終わりにスマホを確認するとメッセージが入っていた。色々とあって、手を借りている先輩たちのグループだった。ちょうどよかった、お昼に小瓶を渡したい、そんな思いでメッセージを開く。すると、そこにあった文字は『音楽準備室』という長義からのメッセージ、それから、大倶利伽羅からの『お前たちは来るな』というメッセージだった。
「……え、音楽準備室……これって、やばいことになってるってことじゃ……」
言った方が絶対にいいはず。そう思い鯰尾は教室を出ようとする。しかし、それを止めたのは骨喰だった。
「……四限、はじまる」
「そう、だけど……ごめん!俺行かないと!」
鯰尾は骨喰の制止を振り切って教室を飛び出す。音楽準備室までは遠い。廊下は走るなよ、という教師の言葉も無視して、音楽準備室まで鯰尾は急いだ。
ピコン、と音がなる。
走りながら一応確認すると、再び大倶利伽羅からのものだった。中身はみずにポケットにしまい込む。あの人たちは、保科が公園で埋めたメモを知らない。
もしかしたら、彼らも危険かもしれない。
巻き込んだのは自分だ、自分だけが蚊帳の外にはなりたくなかった。
「先輩っ!無事です……か……?」
音楽準備室に飛び込むと、今にも暴れ出しそうな保科を取り押さえている燭台切と、近くのガムテープを長くとって切る大倶利伽羅と、頭を押さえている国広と、それからそんな国広に話しかけている長義の姿があった。
「……緊急事態、だったんだ。それは一応、解決したよ」
茫然とする鯰尾を見るなり、そういいながら、ははは、と力なく笑う燭台切は、すぐにまた保科を抑えるために力を込めなおした。大倶利伽羅は容赦なく抑えた腕から長く切ったガムテープを無言でぐるぐると巻いていく。
「頭、打ってただろう。いいから見せろ」
「長義は大袈裟なんだ、これくらい、何ともない」
「何ともなくはないんだよ、脳震盪を起こしているかもしれないし」
その横で何か言い争っている様子の長義と国広を見る。国広の方が先に鯰尾に気付いき、何か言おうと口を開いたと思ったら。すぐに閉じて視線を逸らした。
「じゃあ、皆さん無事なんですね」
「……ああ、まあ」
「それならよかったあ……ほっとしたら、力抜けちゃいました」
鯰尾がドアの前で座り込む。ちょうど、大倶利伽羅は保科の手足にガムテープを巻き付け終わったようだった。まだ何か喚いている様子の保科に、今度も容赦なくガムテープで口をふさぐ。ああ見えて、怒っているのかもしれない、鯰尾は安堵した思考でぼんやりと考えた。
燭台切が、場を切り替える様に、パンパン、と二度手を打つ。
「それじゃあ、真相解明といこうか」
その言葉で、全員の視線が燭台切に向いた。
***
「まずは、結論から言おう。先日、この教室に火をつけた人物。それは早川さんのお母さんだった。……トリックも何もないね、あの日は���化祭で、保護者の人も当然学校に来ている。いつもよりも人の出入りが多く、誰がどこにいるのかの把握が難しい。つまり、誰でも火をつけることは可能だった。でも、彼女はこの学校を燃やしたかったわけじゃない、燃やしたかったのは、写真だった」
「……写真?あ、もしかしてこの……」
「……残念だけど、そっちじゃない」
鯰尾がスマホに撮っておいた写真を見せようとする。燭台切はそれを静かに止めて、それから保科へと向き直り、話を続けた。
「保科さん、長谷部という人を知ってますか?」
大倶利伽羅がピクリと眉を動かす。どうして長谷部の名が出てくるのかとでも言いたげだ。しかし、反応を示したのは大倶利伽羅だけではなかった。保科も、目を見開いた。なぜその名前が出てくるのかと言わんばかりに。
「いえ、今は喋れませんよね。……ですが、今の反応は肯定と受け取ります。僕は長谷部くんの友人……っていったら怒るかな、まあ知人なんですよ。あなたが高校生の頃にやっていたことも、聞きました。早川さんのお母さんは、あなたと同級生。……貴方のやった売買の、被害者だった」
燭台切は、ほんの少し暈した物言いをした。周りにいるのはほとんどが未成年の高校生だったから、直接的な言葉を避けたかったのだろう。しかし、その場にいる全員が、保科の行動を理解していた。「最低だな」と侮蔑する声が国広のすぐそばから聞こえる。国広も、目線だけその声の主、長義の方へと向け、すぐに保科を睨んだ。似たような感情だった。
「保科さんは、売買の記録を丁寧に写真付きで残していましたね。……写真、残ってましたよ」
「今度こそ、この写真……?」
鯰尾は、早川の友人が写る写真を再び見た。独り言のつもりが、燭台切に拾われる。
「そう、その写真だ。あなたは今でもその売買を行っていた。長谷部くんがい言うには、結構曖昧に、当時は解決という形をとったらしいからね。貴方に何もお咎めなしだったことは十分に考えられる。そして、それからもこの学校を拠点に、活動を続けていた。……そんな折に、早川さんの友人に偶然手を出したことを、早川さんに知られてしまった」
「……早川への当たりは強かったと聞く。それが理由だな」
燭台切の流れるような話ぶりに、大倶利伽羅が補足を入れてくる。鯰尾は、ああ、と納得したように声を上げた。
「早川さんは、ことの大きさ故に、母親に相談したんだ。母親は、被害者だったから、その時のことには誰よりも詳しかったのかもしれない。最初は、あの先生には関わらない方がいいとでも言ったのだろうね。そうしたら、今度は、早川さんが独自で調査を始めてしまった。母親は、写真が残っていることを恐れたんだ。もう、一五年以上前になる、その写真があるかもしれないことを」
「……それで、火を?でも、それならおかしいだろう。写真さえ燃えればいい、そのような事情なら大事にもしたくはないはずだし、火事が起きるような事態にはならないんじゃないかな」
「そうだね。ここからが、運の悪いことだった。この教室にはね、早川さんが前日に細工をして帰ったんだよ。保科さんは、喫煙者だから、たとえば、煙草の火が着火の合図になるように、仕掛けることができるよね」
長義の疑問に、燭台切が答える。それに対して、返したのは国広の方だった。
「……そうか、油。隣は美術準備室で、ここは普段、結構臭いがきついから、多少のものなら気が付きにくい。煙草でも着火の危険があるほど撒いたのならば、当然、写真を燃やしていたら、火が移るようになる……」
「そう。意図せぬ大事故だった。そして、早川さんは、音楽準備室のある階段から降りてくる、母親の姿を見てしまったんだ。僕は早川さんじゃないから、全部の気持ちはわからないけど、きっと罪悪感とか、色々なものが押し寄せてきたのかもしれないね。自分が犯人だという遺言を残して、自殺した。これが、大まかな真相だよ……そして、ここからが保科さん、あなたの話だ。僕は、貴方に自首を勧めたい」
そういって、燭台切が保科の目の前に差し出したのは、一枚の紙だった。よく見えるわけではないが、国広にも、そして長義にも、鯰尾にも見覚えのないもの。大倶利伽羅は燭台切の話そうとしている内容まで把握しているのか、特に注視する様子はなかった。
「最初、僕は早川さんの自殺の話を聞いて、亡くなった場所は自宅の、もっと言えば自室辺りを想定していたんです。ですが、そうではなかった。亡くなった場所は、この学校ですね。普通、火災の騒動があって、犯行を自供した生徒が自殺とくれば、それなりにマスコミが取り上げます。ですが、彼らの話を聞いていてもそのことがひとつも出てこない……誰かが、圧力をかけているということになります。もちろん、学校の評判が落ちるので、教師とをしては避けたいところでしょう、でももっと避けたいことが、これがどこかから流出することだった」
それが、これです。そう言いながら、保科に見せつける様に燭台切は途中で破られた紙をその場にいる全員に見せる。確かに、そこには細かな字で、ことのあらましがすべて書かれているように見えた。
私が、音楽準備室ごと友人を騙すあの怪物を殺してしまおうと考えた。そうでないと、騙されやすい彼女は、ずっと騙される。彼女はアレをファントムだと信じている。けれど、彼はエリックなんかじゃないし、彼女もクリスティーヌではない。あいつはただの化物だ。彼女を愛してなんかいない、彼女の目を覚まさせるには、もうあの怪物をなんとか彼女の目の前から消してしまわないといけない。そう思って、あの音楽準備室細工をした。相談していた、お母さんも、あいつの被害者だとか、私がお母さんを追い詰めてしまっていたとか、そんなこと、かけらも思いつかなかった。
そこから先は、遺書の『ごめんなさい』に続くのだろう。
切羽詰まったような殴り書きが細かくされているそれは、確かに公になれば、すぐに保科の行動に疑いの目が向けられるようなものだった。
「調べてみれば、早川さんはこの近くには住んでいなかった。ですが、この学校の近くに住んでいる長谷部くんは、早川さんの母親に会っています。なんでもない平日に。母親が自殺した娘に関して学校に用があったことはわかりやすい。そして、その時に破られた遺書の残りを見つけた。……長谷部くんは学生時代に保科さんについて独自に調べていたそうですから、彼に希望を託したのでしょう。この残りの遺書が、懐中時計に入って、僕に渡されたんです。貴方の悪質な行為は一〇余年に及ぶ。……僕は、これを警察に届けます。ですが、出来ることなら自首してほしいんです」
燭台切が言い終えると、途端に教室内は静かになった。保科も、もう暴れる気力もないらしく、大人しくなっていた。燭台切が大倶利伽羅を呼ぶ。大倶利伽羅も、わかっているというように、口元のガムテープだけを剥がした。自由になった口で、保科は呻るような声で答える。
「……しょせんは想像、なんだろう?」
「……貴様、いい加減に」
その声に真っ先に反応を示したのは長義だった。先ほどまで話を聞きながら、話が進むたびにどんどん冷めた表情になっていったのを、誰より近くにいた国広は見ていた。今も、凍るような声色で言うものだから、国広の方が驚いてしまった。今まで見たことのないような怒り方をしていることが、それだけでもわかる。
「おい、長義……」
「あの、証拠ならありますよ」
長義が切れる前に止めなければ、と声をかけようとした矢先、出入り口に一番近いところにいた鯰尾が声を上げた。それから、二歩ほど前に歩いて、小瓶を床に置く。その横に、畳まれていたのであろう、折り目が多くついた紙を丁寧に広げて置いた。
「……昨日、帰るときに保科先生をみたんです。骨喰も一緒でした。保科先生は気付いてなかったみたいですけどね。それで、その時にこっそり写真をとって、それからこれを掘り起こしたんです。鯨のオブジェがある第一公園ってところなんですけど、知ってますよね」
「……うちの、近くだ」
「え、そうだったんですか?国広先輩ご近所さんだったんですね!……でも、山姥切なんてあの辺にあったかなあ……」
ぽつりと独り言のように呟いた国広の言葉に、鯰尾がいつもの軽い調子で返してしまう。
「鯰尾」
逸れかかった話題を戻したのは大倶利伽羅だった。無言で鯰尾を見ながら続きを促す。
「……んん、そ、それでですね、このホテル、調べたんですけど、その、そういうホテルみたいじゃないですか。……誰に、これは渡す予定だったんですか?」
保科は答えなかった。その様子を見ていた長義が、これ見よがしに納得したというような態度をとる。
「……ああ、なるほど。その渡す予定だった相手とは、俺がその日の夕方過ぎに会ってるよ。確かに、彼女はクリスティーヌだったかな」
舞台の道を志しているそうでね、と長義は続ける。あの女性は、何かを探していた。偶然、その日鯰尾たちが回収してしまったから、その情報伝達はうまくいかなかったということだ。そして、その女性から保科へも、情報伝達がうまくいかなかったのだろう、と長義は考えた。
「早川の友人か……昨日といえば、お前らが一緒に帰っていったな」
「……つまり、俺の家の近くで『山姥切』という生徒を見かけた、と言われたから、あんたは俺のことだと思った、ということか」
「まあ、居住している場所も、教師ならすぐにわかるだろうね。国広は、山姥切って表札の家には住んでないから、あの女性ではきっとわからないだろうし」
大倶利伽羅の言葉に、補足するように国広が続ける。さらに、長義が追い打ちをかけた。その言葉を聞き終えると、鯰尾が保科をじっと見つめる。それから、もう一度、ずいと小瓶と紙を動けない保科の前に差し出した。
「……と、いうことです。それで、誰に、この指令を渡すつもりだったのか、答えてくれませんか」
***
思ったよりも早く自白した。燭台切は自首を頼んでおきながら、実際のところは学校で手続きをしている間に警察を呼ぶように頼んでいたようで、警察はすぐにかけつけた。
証拠品をすべて警察の方に手渡すと、「こういうのは、すぐに警察に渡しなさい」と少しだけ注意を受け、その日はそのまま解放と相成った。
「……国広、やっぱり一度検査くらい」
「だから、頭を打つことくらい誰だってあるだろう……」
音楽準備室に入った長義は迷わず国広の前に出た。何か勘違いをしているらしい保科が、国広の何かを疑っていることは明らかだった。恐らく、本当の目的は自分の方であることも、何となくわかってしまった。もっと言えば、自分が急に前に出てくることで、隙ができると思ったのもあった。
実際、動きは止まった。その隙をついて、「逃げるぞ」というや否や、国広の手を引き教室の外へと走りだそうとした。頭を強かに打っているからか、昨日熱があったし、本調子ではないのか、国広の身体は少しだけ普段よりも重たく感じられた。「……長義」と力なく呼ぶ声に振り返ってしまう。それがせっかくのチャンスをふいにしてしまった。……かと思えば、ドアのすぐそこにいたのが燭台切と大倶利伽羅だった。燭台切は迷いのない動きであっという間に保科の動きを封じ、大倶利伽羅も一切の躊躇いなどなく、ガムテープを手にした。そこへ鯰尾も現れたのだった。
全員と別れ、再び二人の帰り道になっていた。鯰尾と国広は家が近いことがわかったというのに、鯰尾は長義と国広の間に何度か視線を動かすと、「今日は用事があったので」と言って走っていなくなってしまったのだ。気を遣われてしまった、と国広は少しだけ落ち込んだ。
「第一、何で呼び出されたときに俺も呼ばなかったんだよ」
「……気まずい、だろう。俺は、あんなこと言ってしまった翌日だったし……」
あんなこと、という国広の言葉で、長義もつい昨日の出来事を思い出してしまう。
「…��今なら、熱に浮かされていたことにするけど」
我ながら未練がましいような言い方をしてしまった。長義は自分のあまりの言い草に情けなくなってしまい口を噤む。どうしようもない沈黙がふたりを包んだ。ついさっきまでは、少々緊急事態だったということもあり、昨日のことなどなかったかのように接することが出来ていたというのに、いつの間にかまた、どう振る舞えばいいのかわからなくなってくる。
内心でクソ、と悪態をつく長義に対して、国広がぽつぽつと言葉を置くように話しだした。
「……違う、んだ。その、告白、されたことは嬉しかった」
「……え?」
「でも、どうして俺なんか、って思ったし、すごく、俺も戸惑っていて……それで、すまない、うまく言えない……」
予想外すぎる発言に、ぽかんと開いた口が塞がらない長義をよそに、首をゆるゆると静かに横に振って、国広はそう続けた。
隣には渦中になってしまった公園がある。昨日は全く意識していなかったが、たしかに目立つ鯨のオブジェがあった。存外可愛らしい造形をしているが、塗装はだいぶ剥げていて、それなりの年月を感じるものだ。
まだ言葉の出ない長義に対して、国広は変わらず独り言でも言うかのような声音で話を続ける。
「昨日の夜、ずっと考えてた。うまく言えないままでお前に応えるのは、すごく不誠実でよくないように思った……でも、今朝のお前を見て、ひどく傷つけてしまったんだろうなって思ったんだ……なあ、俺はどうしたらいい」
真っすぐに国広は長義を見つめた。家はすぐそこだというのに、まるで迷子のような瞳だった。
「……馬鹿じゃないのか」
「っ俺は真剣に!」
「……ふ、はは……馬鹿は俺も同じか」
「は……?」
その瞳に見つめられて、思わず笑いがこみあげてくる。可笑しい。馬鹿馬鹿しいったらない。態度の変化に、国広は怪訝な表情を隠せない。それでもなお、長義は面白おかしいとでも言うように、声を上げて笑い出した。
「……本当に、なんなんだよ、お前は」
「それはこっちのセリフなんだが……」
自惚れだと笑うなら笑えばいい。だが、今度こそ勝利を確信していた。長義は出来るだけ逃げ道をふさぐような物言いを、ぱっと二‐三考える。そのうち、一番国広の退路を塞げそうなものを選んで口にした。
「好きあうという意味でも、お前の気持ちが言葉になるまでという意味でも、俺はお前と付き合いたいと思ってる……それなら、お前も答えられる?」
「……だが、」
「迷うということは、その気があるということだと受け取るけど」
「……っ!……わ、わかった、こたえる、こたえるから!」
長義の有無を言わせない言い方に、国広は押し負けた。勢いでそのまま返答をしてしまう。それから、「うう……」と羞恥からか、勢いで答えてしまった罪悪感からか、俯いたまま長義よりも一歩斜め後ろを何も言わずに歩いて、家の前で止まった。
「じゃあ、また明日」
「……ああ、また明日」
いつも通りに言い合って、長義は国広が家の中に入るのを見届けてから、来た道を戻りだした。
正式なお付き合い、というのとはまた少し違ってしまっているけれど、これはこれで自分たちらしい関係かもしれない。そう思うと、悪くないようにも思える。あの様子では、恋人らしいことも当分は先の話だろうな、とも考えた。別に、そういう目的でもないから構わないのだけれど。
「……そっか、俺達、付き合うのか」
ぽつりと零してみて、改めて実感する。ただただ、単純に嬉しい。
くるりと振り返り、国広の家を見た。今頃国広は何を考えているだろうか。
クリスマスまで、あと一か月と少し。
0 notes