#ショーペンハウアー
Quote
アルトゥル・ショーペンハウアー 哲学者
思ったことをすぐに話したり、人の言うことを鵜呑みにしたりしてはいけない。むしろ、道徳面でも教養面でも、他人の言葉には多くを期待しないほうがいい。
他人 期待 名言
0 notes
Text

誰もが自分自身の視野の限界を、世界の限界だと思い込んでいる。
Every man takes the limits of his own field of vision for the limits of the world.
Arthur Schopenhauer
アルトゥル・ショーペンハウアー
89 notes
·
View notes
Text
ショーペンハウアーは言います
「心に思想を抱くことと...胸に恋人を抱く事は同じ様なものである」と
...何か"信じる"ものをそばに置いていれば時に癒されるが...時に傷つけられる事もあります
完璧なものなどありませんから
...それでも
"信じる"という気持ちがよいものです
「"信じたもの"が真実ではない
"信じる"とはもっとそれ以上のものなのだ
"信じること"そのものを真実にするのだ」
フランクルは言いました
疲れたなら休みましょう…
ここは今から倫理です。とてもよい
3 notes
·
View notes
Text
アルトゥル・ショーペンハウアーの『読書について』に、「読書とは他人にものを考えてもらうことである。一日を多読に費す勤勉な人間は次第に自分でものを考える力を失ってゆく」という一節がありますが、私の読書の姿勢に通じます。すなわち「考える主体は誰か」を見失ってはいけないということです。
5 notes
·
View notes
Quote
ショーペンハウアーの言葉を借りれば、
「良い本を読みたいなら、悪い本を避けるようにしなければならない。人生は短く、時間もエネルギーも限られているからです」
Modern Books are Trash. Read the Greats! | by Erik Rittenberry | Medium
2 notes
·
View notes
Note
ミシェル・ウェルベックの話をよくされていると思いますが、初めてウェルベックの本を読むとしたら、何が良いでしょうか。
ウェルベックじゃなくてウエルベックです(うるさい)。
『セロトニン』か『素粒子』からでどうでしょうか、文庫化したし。でも僕が一番好きなのは『ある島の可能性』です。個人主義がいくとこいっても犬は可愛いよねって話。初めて買ったのは『素粒子』でしたが最初挫折して、しばらく経って再チャレンジしたら読破できたのでそれから楽しくなって全部読みました。映画化してるので、そこから入るのもいいかもです。小説じゃないけど、ショーペンハウアーのやつも良いですよ。妙に縦長で本棚に嵌まらなくて困るけど。

8 notes
·
View notes
Text
2022年8月29日 身体が倒れることがたえず阻止されていること
「午後三時、砂糖がけのウェブ」という合同ウェブマガジンに、『「永遠」に一番近い色ランキング』という記事を寄稿しています。
タイトルになっている〈「永遠」に一番近い色ランキング〉の他にも、かなり個人的なランキングを4つ載せていて、〈行ってみたいところランキング〉みたいなのは、放っておくと忘れてしまう記憶を「ランキング」という形式でパッケージングしてしまおうということだし、〈赤ちゃんにつけるのにおすすめの名前ランキング〉とかは、異なる文脈上にある単語を、その意味や文脈を脱臼させながら全く別のレールに載せることで異化できたらな、という試みだったりする。
***
ショーペンハウアーは『意志と表象としての世界』第4巻で、「われわれの歩行とは、身体が倒れることがたえず阻止されていることにすぎない」と書いているらしいのだけど、この感覚がかなりよく分かる。というのも、朝(あるいは昼や夕方)に目が覚めて、そこから一切起き上がったり歩行したりできない、ということがよくあるし、朝に関して言うと、起きたばかりのその身体には一切の気力とかそういうものがなくて、それを動かす力がどこにもない、完全な無(でも、確かに重さだけがある)として感じられる。だから、起きてから元気に起きて何かをしている人を見ると、一体どうやって、何をどうすることで、身体を起き上がらせているんだろう、と思うし、ほんとうに、教えて欲しい。
ただ、もちろん、バイトがあったり学校があったら、重くて動かない身体も、何とか起き上がることができる。その強制力が、身体を駆動する力になるから。でも、逆に言えば、そういった強制力や暴力性がなければ身体は動くことがない。外部からやってくるその強制的な力によってだけ、身体は起き上がり、歩行することができる。身体の内部には、いかなる形でもそれを動かす精神的なエネルギーなんてものが存在しない。
だけど、普通に生きている人々を見ていると、まるでみんな、自分の身体の中にそれを動かす力とか気力とかそういうものが自然に��るみたいにして生きているような気がする。それに、自分だって、外に出て何かをしているときはきっとそう思われているだろうし、実際、そのときはそうなのかもしれない。
でも、何だか違和感がある。身体の内部のその感覚。身体を動かす、ということの感覚。自分が身体を思い通りに動かせているという感覚があまりない。「身体は常に重く、自分の意志では動かすこともままならない。でも、何か(締め切り、他者からの圧力、どうしようもないほどに強い感情、強い危機意識)に強制されたときだけに、身体の重さを忘れて立ち上がり、歩行し、どこかに向かっていけるという感覚。身体を自分の意志で動かすことなんてできず、何らかの圧力が外部から掛けられたときにだけ動く、という感覚。
もちろん、そういうものがなくても、ほんとうに一日中ただ横たわっているのもよくないから、それに、やらないといけないことはたくさんあるんだから、と思って、外に出て何かをしようとしてみることはある。でも、そうやって自分の意志で無理やりに身体を動かしても、身体はどうしようもなく重く、身体を引きずって、無理やり歩いているような感覚になる。身体を動かすための(精神的な)エネルギー源、のようなものがどこにもない。だから、常に音楽やラジオ(それは外部からやってくるものだから)を聴くことで、音を外部から摂取しながら起き上がり、歩行し、行動しているわけだけど、それも十分なものではない(マーク・フィッシャーが言っていた、鬱病的快楽状態、という言葉を思い出す。でも、別にそれは以上な状態ではなくて、本来、身体とはそういうものだったような気がする)。
そして、この身体の感覚は案外普通で、みんな意外とそういう重くてどうしようもない身体を引きずりながら社会の中で生きている、という可能性もあるけれど、一方では、自分以外のほとんどの人はもっと精神的エネルギーに満ち溢れていて、いつでも起き上がれていつでも歩行できる身体を持っているのかもしれない、と思う。自分の身体のその内的な感覚が、自分以外の人に伝わることは絶対にないし、逆に、自分以外の人の身体のその内的な感覚を、自分が知るということだって絶対にないわけだから、原理的にはそれを確かめることはできないわけだけど、一体どうなんだろう。
創作においてもそういう感覚はある。「スランプ」という言葉はいまいち調子が出ないとか、作品を作ったりできない状態のことを指すと思うけれど、自分の中では、「創作できる時期」がたくさんあって、その間にときどき「スランプ」がある、という構図ではなく、むしろほとんどの時期は「スランプ」であり、「スランプ」の間に「創作できる時期」がある、という構図だと思う。ほんとうに稀にやってくるある瞬間の光だけを頼りに創作をやっている。
そして、私たちにできるのは、その一瞬の光がやってくるのを待ち続けること。そして、その光がやってきたときに、決してそれを見逃さずに、その光すべてを捉えること。ただそれだけだと思う。
2 notes
·
View notes
Text
新国立劇場におけるヴァーグナーの《トリスタンとイゾルデ》の上演を観て
「闇に包まれた夜の国」から来て、今またそこへ還ろうとしている。深い傷を負ったトリスタンは、みずからの来し方と行く末をイゾルデにこう語りかけるが、その言葉は《トリスタンとイゾルデ》という楽劇そのものを暗示しているようにも聞こえる。チューリヒでのマティルデ・ヴェーゼンドンクとの出会いと、ショーペンハウアーの思想への共鳴のなかから生まれたヴァーグナーの作品を貫くのは、この「夜の国」の翳である。その闇は第二幕の「愛の二重唱」でも触れられるように、恋人たちを隠すと同時に、自他の区別も、個としての生命も溶解させる。それをつうじて一つになることの憧れを、ヴァーグナーの音楽は歌い続ける。
おそらくはこうしたことを踏まえながら、新国立劇場における《トリスタンとイゾルデ》の上演の舞台は、翳を基調としていたのだろう。2024年3月23日の公演における第二幕の終景と第三幕の最初の場���におけるトリスタンの歌に耳…

View On WordPress
#David McVicar#Egils Silins#Kazushi Ono#Liene Kinča#New National Theatre Tokyo#Opera Palace#Richard Wagner#Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra#Tristan und Isolde#Wilhelm Schwinghammer#Zoltán Nyári
0 notes
Text

同じ釜の飯を食べたら理解し合えると思ってーるんです日本人とのことよ 留学生が半数を占める学生寮で、異なる文化を持つ人たちをまとめるには?という委員長のお悩みに、ローティ ごっちゃにしないことです公私を
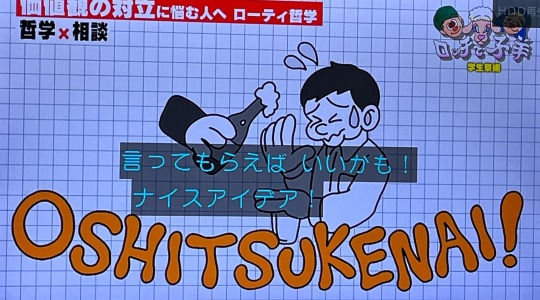

オシツケナイでも おしえてもいいよ そうだよね、はなから分担ではなく、規範が異なる以上は 相互的な意味まで真似し切れないから。留学生も まず周りを見て、どう言う意味合い?とか、聞き方が分かるかも。小さな気づきを噛み砕くように 教えてほしいと思ってもらえるかも。何に興味が向くかも一旦預けつつ、教えるほうも自国の言語の持つ構造に気づくかも。入り口があるね
似た物同士クラブではなく、バザールとして最低限のルールと、バザールゆえに実利を用意。 留学生の元に来てるであろう各国の仕送りの、ぶつぶつ交換とかしたらどう?と、なんか...ほんとにナイスアイデアかもだね ロッチすごい 来週ショーペンハウアー 現場で考えておる 自分てダメだなーも江戸っ子だからよぅも、会話が終わりになる可能性があり、現状追認や確認がそういう意味で渦中(禍中)にも円満にも問われて、だからこそ公やバザールとしての言語とは?のほうもやろう、でやっぱり良いんだけど。。この飲み会が安定開催して、仲良くなるor...としたら、、? 'グローバルな興味'を持つ、ってすごいことだし跨げるといいよな
この時のこれもあれやそれだったのかなとか
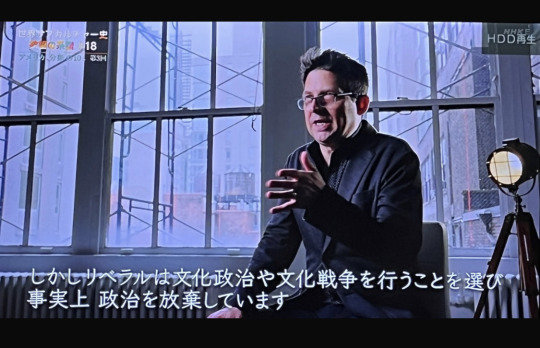
0 notes
Text
2024年2月9日に発売予定の翻訳書
2月9日(金)には28冊の翻訳書が発売予定です。 ハーパーコリンズ・ジャパンからは15冊。同社に次いで点数の多い(6点)風詠社は主に自費出版を手がけている会社です。
19世紀イタリア・フランス音楽史

ファブリツィオ・デッラ・セータ/著 園田みどり/訳
法政大学出版局
Mayo Clinicの症例から学ぶ臨床感染症
織田錬太郎/翻訳
メディカル・サイエンス・インターナショナル
王子ラセラス、幸福への彷徨
高橋昌久/翻訳 サミュエル・ジョンソン/著
風詠社
アメリカ人(上)
高橋昌久/翻訳 ヘンリー・ジェイムズ/著
風詠社
アメリカ人(下)
高橋昌久/翻訳 ヘンリー・ジェイムズ/著
風詠社
アンドレアス
高橋昌久/翻訳 フーゴ・フォン・ホフマンスタール/著
風詠社
回想録
高橋昌久/翻訳 エドワード・ギボン/著
風詠社
負けない方法、他二編
高橋昌久/翻訳 アルトゥール・ショーペンハウアー/著
風詠社
男の子をダメな大人にしないために、親のぼくができること
アーロン・グーヴェイア/著 上田勢子/翻訳
平凡社
公爵さま、それは誤解です
リン・メッシーナ/著 箸本すみれ/翻訳
原書房
霧に眠る殺意
アイリス・ジョハンセン/著 矢沢聖子/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
冬の白いバラ
アン・メイザー/著 長沢由美/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
純白のウエディング
ダイアナ・パーマー/著 山野紗織/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
裏切られた夏
リン・グレアム/著 小砂恵/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
夢一夜
シャーロット・ラム/著 大沢晶/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
涙は愛のために
ダイアナ・パーマー/著 仁嶋いずる/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
ボスを愛した罪
サラ・モーガン/著 山本翔子/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
アドニスと飛べない白鳥
スザンヌ・マーチャント/著 大田朋子/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
千年の愛を誓って
ミシェル・リード/著 柿原日出子/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
孤独な城主と誘惑の9カ月
ジェニー・ルーカス/著 新井ひろみ/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
炎のキスをもう一度
エマ・ダーシー/著 片山真紀/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
愛なき富豪と身重の家政婦
シャロン・ケンドリック/著 加納亜依/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
スター作家傑作選~シンデレラに情熱の花を~
ダイアナ・パーマー/著 松村和紀子/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
花嫁は偽りの愛を捨てられない
ミシェル・スマート/著 久保奈緒実/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
さまよう恋心
ベティ・ニールズ/著 桃里留加/翻訳
ハーパーコリンズ・ジャパン
つめて つめて!
カトリーナ・チャーマン/著 ギリェルメ・カルステン/イラスト 木坂涼/翻訳
BL出版
愛と心理療法 完訳版
M・スコット・ペック/著 氏原寛/翻訳 矢野隆子/翻訳
実務教育出版
レディ・ルーの秘密の手紙
ソフィ・ラポルト/著 旦紀子/翻訳
竹書房
0 notes
Text

ぢ
アルトゥール・ショーペンハウアーと孤独な人 Arthur Schopenhauer and the Lonely Man
ウポポ アナベベ チンポ チンポ Upopo Anabebe Cock Cock
私は死刑制度に反対です 殺されたから 人道に反して 国家が人を殺す また 人の命は平等です あなたは自分を選んで産まれてきましたか? 国家ですら奪っていいものではありません 命を奪ったからこその命を奪っていいというわけではないのが人道的だと思います 他の国の死刑はひどいと思いながら自分の国ではしっかり国家の力を借りて 死刑制度に乗っ取るのもどうでしょう 私は間違いだと思うのです I am against the death penalty. Even if you are killed, it is against humanity that the state kills people. Also, human life is equal. Did you choose yourself to be born? Even the state should not take away your life. I think it's humane that it's not okay to take someone's life just because someone took someone's life. I think it's not humane to think that capital punishment in other countries is terrible, but in your own country, with the help of the state, . I think it's a mistake
当たり前だよ そりゃそうなるだろ という人は疑問を持たないのだろうか…? I wonder if people who saying it's natural and that's how it happens don't have doubts…?
0 notes
Quote
●オッペンハイマー
「原子物理学の発見によって示された人間の理解力は、
必ずしもこれまで知られていなかったわけではない。
また、別段新しいというわけでもない。我々の文化にも先例があり、
仏教やヒンズー教では中心的な位置を占めていた。
原子物理学は、いにしえの智慧の正しさを例証し、強調し、純化するものだ」
●アインシュタイン
「現代科学に欠けているものを埋め合わせてくれる宗教があるとすれば、
それは『仏教』です」
「仏教は、近代科学と両立可能な唯一の宗教です」
●ニーチェ
「仏教はキリスト教に比べれば、100倍くらい現実的です」
「仏教は、歴史的に見て、ただ一つの
きちんと論理的にものを考える宗教と言っていいでしょう」
●ショーペンハウアー
「私は他のすべてのものより仏教に卓越性を認めざるをえない」
●バートランド・ラッセル
「今日の宗教では、仏教がベストだ。
その教えは深遠で、おおよそ合理的である」
●ユング
「仏教はこれまで世界の見た最も完璧な宗教であると確信する」
●H・G・ウェルズ
「現在では原典の研究で明らかになったように、
釈迦の根本的な教えは、明晰かつシンプル、
そして現代の思想に最も密接な調和を示す。
仏教は世界史上知られる最も透徹した知性の偉業である
ということに議論の余地はない」
【兵庫】「神様はアラーしかいない」「ここで祈るな」 ガンビア人の男、神社で暴れ賽銭箱など次々破壊…日本ムスリム協会が非難声明 ★5 [樽悶★]
5 notes
·
View notes
Text
満天の朝焼け
カントにおけるほど強力にロマン主義が表現されたことは、それまで一度もなかった。超越論的なものの必要性、あらゆるかたちでの無媒介的なものの不可能性、存在がその理解力と行動において示す活力に満ちたあらゆる形象を厄介払いすること―これが、カント哲学のライトモチーフなのである。このような視座からすると、アルトゥール・ショーペンハウアーを、カント主義とそのロマン主義的身振りをもっとも明瞭に見抜いた読者とみなすべきであるかもしれない。〔ショーペンハウアーは、カントを次のように読み解いたのだった。すなわち、〕事物の仮象と物自体を再結合することが不可能ではないにしても困難であるということは、苦と窮乏に満ちたこの世の災いのもとである。また、それゆえに、高貴かつ高尚な力が繁栄しうるようには、この世界はできていない、と。言葉を換えるなら、ショーペンハウアーは、人文主義的革命を決定的な仕方で清算するものとして、カント主義を理解したのである。-アントニオ・ネグリ、マイケル・ハート「〈帝国〉 グローバル化の世界秩序とマルチチュードの可能性」
東京都千代田区霞が関三丁目四番三号 特許庁総合庁舎7階〇〇課〇〇室
知っているな、と思った真司はウーバーイーツの配達車両に乗り込んだ。三年前に新品で買ったヤマハのトリシティ155である。彼はこれを愛着を持って使っており、北関東に遠出することもある。ちょっとした小旅行と呼ぶべきものではあるが、一流と呼ばれるような場所に泊まったこともある。すなわち一泊三万円を越えるような宿泊プランであった。
ここ、ピーザラ神田店から霞が関までは15分で着くだろう。多くの国内の者が想像するほど国の中核たる千代田区は交通量が多くなく、スクーターの運転はスイスイと終えることができる。そこらの県庁所在地よりは空いているほどである。それに彼は霞が関の省庁が立ち並ぶ雄大な眺めを愛してもいたので、上機嫌になってくるほどであった。天気は昨日から曇りが続く。
スクーターに乗る彼は動きやすい格好に黒の薄手のジャンパーである。そもそもこの国では私服の配送業者が目を引くことになる。
信号が赤になったので、スクーターを停める。右側の歩道を眺める。50代ぐらいの中年女性が歩いており、しかめ面を浮かべている。彼女とすれ違う作業服姿の40代ぐらいの先ほどよりは明らかに若い男性。すれ違った。こういう時に当該の人物��に何も起きなかったこと��真司はときどき意識することになる。彼らは道端でぶつかりもしなかった。それは一つの可能性である。そして、一つの不可能性でもある。通り魔で実刑判決を受けた人物が、囚人が、一度は思い浮かべるであろう不可能性のことだ。
うかうかしてはいられないので、前を向く。信号は赤のままだ。機械は大人しくプログラムをこなしてくれる。さながらたまたますれ違った二人に何事も起きないように。現在配達するピザは汁物のようにこぼれたりする心配が少なく、彼はほっとしていた。
霞が関、特許庁前。省庁の中には入ることもできるが受付の許可を得たうえで、持ち物検査を義務付けられるので、受付までで、配達業務を終えることにしている。こういう時に自己判断と現場の様子で仕事を終えられるのが、ウーバーであり、自由の国アメリカらしさといったところだろうか。
受付に近づく。
「こんにちはぁ、ウーバーイーツですがぁ」
少しフレンドリーに振舞ってみたつもりだ。
「どちらの階にお届けでしょうか」
女性の声が応じる。
「七階の、えぇ」
スマホの情報を確認する。
「〇〇課〇〇室の~さん宛ですね」
「はい、いいですよ」
女性の声がうなずく。
終わりか、と思い、配達物を置き、引き返すことにする。
「毎度、ありがとうございます」
建物を出て、腕時計を確認する。十一時五十五分。このまま、三件は回れそうだが、先に昼食にすることにする。麺類が食べたい。
家についてシャワーから出ると、もう午後六時だった。テレビを付けて、スマホの電源を入れる。テレビのボリュームを下げた。
スマホにメールが来ている。
「件名:ご質問です。」
件名に。(句点)を付けるのか、と真司はふと思った。
「個人的な悩みにお付き合いしてもらうことは可能でしょうか」
個人的な悩みか、何だろうと彼は思う。ところでこの女性は誰だたっか……。彼はこの女性の名前をした人物のことをよく覚えていないし、姿かたちもさだかではないのだ。名前は流川愛美(るかわまなみ)である。やはり、知らない人である。勢いで悩みに付き合ってやろうかとも思ったが思いとどまった。スパムメッセージの可能性もある。
テレビを五分ほどぼーっと眺めていたら、やはりあの時か、と思い当たる節があった。大学のシェイクスピア研究会の白井が紹介してくれた在学生の会員の内の一人であった。何度思い直してもそうである。
ならば、と思いメールに返信することにした。
「なんのごようでしょうか。シェイクスピア研究会の在学生ですよね」
数分後返信が来た。自由にスマホを操作できる状態なのだ。
「件名:枕詞が古臭くてちょっと笑ってしまいました(笑) 知り合いには相談しづらいことなのであなたに相談した次第なのですが、現在交際している男性のことです。厄介ごとに足を踏み入れたくなければお断りしていただいて構いません。シェイクスピア研究会所属でOBの白井さんの知り合いです」
0 notes
Text
TEDにて
ロバート・グプタ:音楽と医学のハイブリッドで
(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)
ロバート・グプタは、医師になるべきか!バイオリン奏者になるべきか!思い悩んでいた時、自分の進路は、その中間にあるのだと気づきました。
手にはバイオリンを持ち、心には社会的公正の意識を抱いて進むことにしたのです。
社会の周縁にいる人々と、従来の医学では、上手くいかない領域で成果を上げている音楽療法の力について語った感動的なスピーチです。
クラシック音楽による表現は、大きな癒しのパワーを伝えるためのパイプになれるということです。
医学が治すのが、体の部品だけではないのと同じように、交響曲などのようなクラシック音楽のもつ美しさは、エンターティンメントを超えたものです。
このような黄金比の美しさのきらめきは、希望へと形を変えるのです。
ゴッドフリードシュラーグ博士は、神経科学者でメロディックイントネーションセラピーという音楽療法の主唱者でもあります。コンサートというのは、何もコンサートホールだけで行う物ではないことがわかります。
ゴットフリード・シュラーグ博士は、ハーバード大学で音楽と脳の研究をしている優れた神経科学者でメロディック・イントネーション・セラピーという今では広く使われている音楽療法の主唱者でもあります。
シュラーグ博士が気づいたのは、脳梗塞を起こして失語症になり3,4語の文章ですら、発することができない患者でも曲の歌詞なら歌えるということでした。
「ハッピー・バースデー」やお気に入りのイーグルスやローリング・ストーンズの曲などです。
そして、70時間の歌の集中レッスンを受けると音楽が患者の脳神経をつなぎ直し、代替的な言語中枢を右脳に作り出し、損傷を受けた左脳を補完することを博士は発見したのです。
ステージも照明もなく、タキシードもないこうしたコンサート活動を通じて、気づいたのはコンサートホールになど、来ることができず、私たちが普段演奏するような音楽に接する機会のない人たちに対して
演奏家は、この音楽の持つ大きな癒しの力を伝えるパイプになれるということです。
音楽が表すのは、美学上の美しさだけではありません。ワーグナーのオペラやブラームスの交響曲。ベートーベンの室内楽を聴くとき、共有される感情体験には、私たちが共通の人間性や深い部分でつながった
共通の意識。共感の思いを持ち合わせていることを思い起こさずにはいられません。
精神神経科医のイアン・マギルクリストによると、こうした感情は人間の右脳に生まれつき備わっているものです。
精神疾患を抱えながら、ホームレスや囚人でいるというもっとも非人間的な状況で暮らす人にとって、音楽。そして、音楽が持つ美は、周囲の環境に関わらず
自分たちは、今でも美しいものを体験することができ、人々はまだ自分たちのことを忘れていないのだと気づかせる機会になります。
そして、そのような人間性や美のきらめきは希望へと形を変えるのです。
ショーペンハウアーも似たようなことを言っていますが、この思想が一部、科学的に証明された形です。
ドイツの哲学者。「意志と表象としての世界」の書籍が有名です。あるがままの仏教精神を思想として、インド哲学の精髄も同様に明確にヨーロッパ向けに語り尽くした思想家のひとり。
PTSD(心的外傷後ストレス障害)とは、危うく死ぬ。または、重症を負うような出来事の後に起こる、心に加えられた衝撃的な傷が元となる、様々なストレス障害を引き起こす疾患のこと。
<おすすめサイト>
マット・ルッソ:宇宙の音を探る音楽の旅
<提供>
東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント
独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです
東京都北区神谷のハイブリッドな直送ウェブサービス(Hybrid Synergy Service)高橋クリーニングFacebook版
#ロバート#グプタ#音楽#医者#バイオリン#意識#hybrid#wave#ハイブリッド#ヴァルハラ#ゲート#黄金比#PTSD#障害#脳#神経#シナプス#ニューロン#jwave#哲学#ショーペンハウアー#分子#生物学#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery
0 notes
Video
youtube
ヒトコトリのコトノハ vol.29
『幸福について ―人生論―』
ショーペンハウアー著/橋本文夫訳(1958)新潮社より
0 notes
Quote
哲学は人生を始めたばかりの若者のためのものではありません。哲学は「夕食に何を食べるか?」とまだ尋ねる人のためのものではありません。。だからこそ、夏の読書としてプラトンやショーペンハウアーを読むのは特権なのです。
I Hate Philosophy!. Philosophy is inherently useless. It is… | by Nurma Komala-Hadi | Medium
2 notes
·
View notes