#立平葺き
Photo

「PARALLEL」外観 ・ ガルバリウムカラー鋼板立平葺き(さざ波加工付き)と木板張りの組み合わせ。 庇部分は二階床から片持ち梁で跳ね出し、柱の無いポーチとして使い易い玄関回りとしています。 ネット通販が重要なツールとなった時代、宅配ボックスは断熱と気密を気にしない自立型とし、ポーチのアクセントとしています。 ・ 庭はL形した建物形状と、外物置+コンクリートフェンスを道路側に配置することにより、中庭状に囲まれたプライバシー感あるスペースとなりました。 ・ リビングの大窓は敢えて窓台を広くすることで猫の日向ぼっこ&休憩スペースともしたことで、いつも窓から外を覗いてくれています。 ・ 写真 酒井広司 ・ その他のphoto→@yosuke_tomiya_design_office ・ #富谷洋介建築設計#一級建築士事務所#設計事務所#建築家#北海道#江別市#注文住宅#PARALLEL#酒井広司#ガルバリウム#ガルバリウム鋼板#立平葺き#さざ波加工#スチール手摺#宅配ボックス#ボビカーゴ#猫スペース#猫と暮らす#日向ぼっこ#家づくりアイディア#マイホームアイディア #architect#architecture#design https://www.instagram.com/p/CfsvcWfLhBT/?igshid=NGJjMDIxMWI=
#富谷洋介建築設計#一級建築士事務所#設計事務所#建築家#北海道#江別市#注文住宅#parallel#酒井広司#ガルバリウム#ガルバリウム鋼板#立平葺き#さざ波加工#スチール手摺#宅配ボックス#ボビカーゴ#猫スペース#猫と暮らす#日向ぼっこ#家づくりアイディア#マイホームアイディア#architect#architecture#design
0 notes
Photo

越中国一宮氣多神社 国重要文化財指定の御本殿 戦国時代永禄年間(1558~1570)の再建と云われる三間社流造柿葺一間向拝付きです 全体的にシンプルな造ですが木組みが大きく荘厳な風体を醸し出しています 元は越中国総社とされ越中が能登に合併し天平宝字元年(757年)再び越中が分離独立の際、氣多大社より勘定したのが創祀とされています #気多神社 ⛩┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⛩ 気多神社(けたじんじゃ) 鎮座地:富山県高岡市伏木一宮1-10-1 主祭神:大己貴命、奴奈加波比売命 社格:式内名神大社 県社 巡拝:諸国一宮 #国指定重要文化財 ⛩┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⛩ #神社 #神社巡り #神社好き #神社好きな人と繋がりたい #recotrip #御朱印 #御朱印巡り #神社建築#神社仏閣 #パワースポット #高岡市 #一宮巡り #延喜式内社 #式内社 #富山県 #神社巡拝家 (気多神社) https://www.instagram.com/p/CmcBq8vPuFp/?igshid=NGJjMDIxMWI=
#気多神社#国指定重要文化財#神社#神社巡り#神社好き#神社好きな人と繋がりたい#recotrip#御朱印#御朱印巡り#神社建築#神社仏閣#パワースポット#高岡市#一宮巡り#延喜式内社#式内社#富山県#神社巡拝家
67 notes
·
View notes
Photo



[1]奈良国立博物館 仏教美術資料研究センター
Nara National Museum Buddhist Art Library
仏教を中心とする歴史と美術にかかわる学術資料の作成・収集・整理・保管・公開を目的に、昭和55年(1980)に博物館の一部門として設置され、平成元年(1989)より現在の建物にうつりました。
資料公開日: 毎週. 水曜日・金曜日
(国民の祝日・休日、12月26日から翌年1月4日までを除く
開館時間: 午前9時30分〜午後4時30分 (複写受付は午後4時まで)
公開している資料: 図書、雑誌、紀要、報告書、展覧会カタログ、両像資料等
サービス内容: 閲覧、複写、レファレンス
調査研究を目的とする利用者に対して資料を公開しています。利用を希望の方は左側のインターホンを押して係員をお呼び出して下さい (水曜日・金曜日の公開日のみ)。
[2]重要文化財
旧奈良県物産陳列所
昭和58年(1983)1月7日 指定
奈良市登大路町50番地1
この建物は明治35年(1902)に竣工し、同年奈良県物産陳列所として開館したもので、県下の殖産興業と物産の展示販売をおかなう施設として利用された。設計者は、帝国大学工科大学造家学科(東京大学工学部建築学科の前身)出身の建築史学者で、当時奈良県技師として古社寺建造物修理に尽力した関野貞博士(1867-1935)である。 木造桟瓦葺で、小屋組や河辺などに西洋建築の技術とりいれつつ、外観は和風を基調とする。唐破風造車寄を正面につけた入母屋造の中央楼から、東西に切妻造の翼部を延ばし、端には宝形造の楼をおいている。関野は大学在学中より宇治の平等院鳳凰堂を研究しており、屋根の形式や左右対称の優美な外観は鳳凰堂に範をとったものと思われる。また蟇股などのなどの細部には、飛鳥時代から鎌倉時代にかけての伝統的な建築様式を取り入れ、この建物の設計と奈良における古建築研究との密接な関係がうかがえる。その一方で窓にはイスラム風の意匠もみられる。構造・意匠に東西の要素を巧みに取り入れた明治中期を代表する近代和風建築として高く評価されている。
この建物は開館後、奈良県商品陳列所、奈良県商工館と名称を変え、昭和26(1951) に国に移管されて、昭和27年(1952)から55年(1980)まで間のに奈良国立文化財研究所春日野宇舎として利用された。昭和58年(1983)に重要文化財の指定を受け、同年奈良国立博物館が管理するところとなり、現在は当館の仏教美術資料研究センターとして活用されている。
平成23年7月 奈良国立博物館
Vocab
関わる (かかわる) to be concerned with, to have to do with
学術 (がくじゅつ) science, learning, scholarship
作成 (さくせい) making (a report, etc.)
収集 (しゅうしゅう) collection (of art, etc.)
整理 (せいり) sorting, organization
保管 (ほかん) charge, safekeeping, storage
公開 (こうかい) making available to the public, exhibiting
部門 (ぶもん) branch, division
元年 (がんねん) first year
祝日 (しゅくじつ) national holiday
翌年 (よくねん) following year
複写 (ふくしゃ) copying
図書 (としょ) books
紀要 (きよう) bulletin, memoirs
報告書 (ほうこくしょ) (written) report
物産 (ぶっさん)product
陳列 (ちんれつ)exhibition, display
登大路町 (のぼりおおじちょう)Noborioojichou
竣工 (しゅんこう)completion of construction
県下 (けんか)prefectural
殖産興業 (しょくさんこうぎょう)promotion of industry
設計者 (せっけいしゃ)designer
帝国大学 (ていこくだいがく)Imperial University (name of Tokyo University 1886-1897)
工科大学 (こうだいがく)engineering college
建築学 (けんちくがく)architecture
全身 (ぜんしん)previous existence, predecessor organization
出身 (しゅっしん)one’s origin (i.e. school)
史学者 (しがくしゃ)historian
技師 (ぎし)engineer, technician
古社寺 (こしゃじ)old shrines and temples
建造物 (けんぞうぶつ)structure, building
修理 (しゅうり)repair, mending
尽力 (じんりょく)efforts, exertion, services
関野貞 (せきの・ただし)Sekino Tadashi
木造 (もくぞう)wooden
桟瓦 (さんがわら)pantile
葺 (ぶき)roofing
小屋組 (こやぐみ)roof truss, room frame
河辺 (かわべ)riverside, riverbank
取り入れる (とりいれる)to adopt (e.g. an idea), borrow
つつ while; even though
外観 (がいかん)exterior appearance
基調 (きちょう)basic theme, underlying tone
唐破風 (からはふ)karahafu, bow-shaped eaves of a gabled roof
車寄 (くるまよせ)carriage porch, entranceway
入母屋造 (いりもやづくり)Irimoya; building with a gabled, hipped roof
楼 (ろう)tower, tall building
切妻造 (きりづまづくり)gabled roof construction
端 (はし)end, tip, edge
宝形造 (ほうぎょうづくり)pyramidal roof
在学 (���いがく)attending (school), enrolled
宇治 (うじ)Uji (city)
平等院 (びょうどういん)Byodo-in temple
鳳凰堂 (ほうおうどう)Pheonix Hall
左右対称 (さゆうたいしょう)bilateral symmetry
優美 (ゆうび)refinement, grace, elegance
範 (はん)example, model
蟇股 (かえるまた)curved wooden support on top of the main beam of a house (shape looks like a frog with open legs)
細部 (さいぶ)details, particulars
飛鳥時代 (あすかいじだい)Asuka period (550-710)
鎌倉時代 (かまくらじだい)Kamakura period (1185-1333)
にかけて till, over (a period), through
建築様式 (けんちくようしき)architectural styles
設計 (せっけい)plan, design, layout
における regarding
密接 (みっせつ)close (relationship, connection, etc.)
うかがう to guess, infer, surmise
意匠 (いしょう)design
構造 (こうぞう)structure, construction
巧み (たくみ)craftmanship, design
評価 (ひょうか)appreciation, recognition
商工 (しょうこう)commerce and industry
移管 (いかん)transfer of control
国立文化財研究所 (こくりつぶんかざいけんきゅうしょ)National Research Institute of Cultural Properties
春日野 (かすがの)Kasugano
庁舎 (ちょうしゃ)government office building
国立博物館 (こくりつはくぶつかん)national museum
管理 (かんり)control, management
#日本語#Japanese language#Japanese vocabulary#Japan#Nara#奈良#日本#日本歴史#Japanese history#Japanese architecture#日本建築
20 notes
·
View notes
Text
20230225 巨大こけし(東本願寺)
1日だけはたらいて、また、休日。国公立大学の二次入学試験日。京大には恒例の折田先生像がたつ。天神さんの日。ロシアのウクライナ侵攻から1年、習近平がウクライナ訪問か、というさなか、東本願寺前に巨大こけしを見物にいってきた。
23日にたまたまクルマで前を通って「なんじゃこりゃ」と感心したのだけど、2人組の現代アートユニットYottaの作品、ということらしい。いつまで置いてあるのかよく知らないが、なかなか楽しいイベントである。
なんでそんなに大きいものつくったんや、と思ってしまうが、背後の本願寺も相当にでかい。ずいぶん昔のことになるが、瓦葺き替えで寄進をもとめられたときが1枚たしか5万円だった。祇園で羽振り飲んでいる姿を見ているので、京都のひとはわりと坊さんには敬意をはらっていない傾向がある。功徳あるえらいぼんさんもいるだろうし、お地蔵さん、仏さんもたいせつにはしたいが、あとはだいたい、そこらの人とそんなに差はない、と見切っているように思う。
24日を休みにすれば4連休なので、もうちょっと人が押しよせてくるのかと思ったが、人出はさほどではなかった。晴れたり、ちらちらと雪の舞う日でもあった。
5 notes
·
View notes
Text

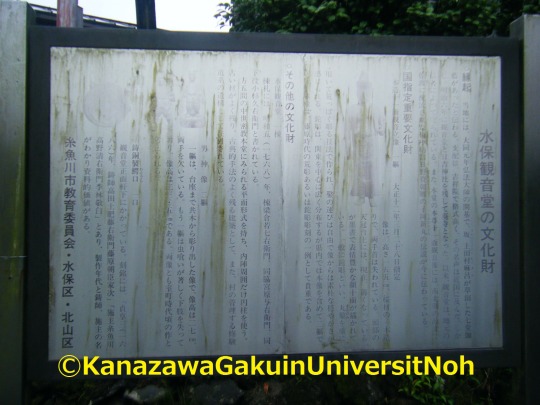





【新潟県謡曲古跡めぐり上越編】1日目9箇所目 2021/6/27ー28
能「壇風」「田村」
水俣観音堂
《 糸魚川市水俣 》
水保観音堂の創建は不詳ですが泰澄大師が養老年間(717~724年)に開いたとも弘法大師空海が大同元年(806)に開いたとも云われています。
その後、坂上田村麻呂が当地を訪れた際、境内が整えられ寺院として草創したそうです。当時は吉祥院に属し、信仰を広げ最盛期には七堂伽藍を備た大寺院として周囲にも大きな影響力を持ちました。古くから神仏習合し隣接する日吉神社の祭祀を担っていましたが明治時代初頭に発令された神仏分離令により吉祥院が廃寺となり日吉神社と観音堂だけが残され現在は宝伝寺の境外仏堂となり周囲の信者によって管理されています。
水保観音堂には棟札が残されていて明和5年(1768)に建てられ、棟梁が倉若七右衛門、脇棟梁が宮原与右衛門、下役が小杉久右衛門だったことがわかっています。水俣観音堂は木造平屋建て、寄棟、鉄板葺(旧茅葺)、桁行5間、梁間5間、平入、外壁は真壁造り板張り、四方浜縁、高欄付き、中世の密教寺院建築の特徴を残し地域に残る修験道場の遺構としても貴重な存在です。
寺宝には大正12年(1923)に国重要文化財に指定された「木造十一面観音立像」(平安時代中期~後期の作と推定、桜材の一木造、頭部の天冠台には様々な表情をした十一面が墨書、像高1.548m、鉈彫り、33年に一度の開帳、身をもって集落の火災を防いだという伝説が残っていて火伏の観音さまとして信仰の対象となり住民からは「水保の観音さん」と呼ばれています。)や男神像(2躯、室町時代作と推定、像高27㎝、23.5㎝)や鋳銅製鰐口(貞享3年作、鋳師:高田土肥藤右衛門藤原朝臣家次、施主:糸魚川高野清右衛門季林敬白)などがあります。
この仏像は、桜材の一木造りで、高さ1.548メートル。
平安時代中~後期(藤原時代)の作と推定されています。丸のみを横に用いて荒っぽく削る「鉈彫り」の技法で作られたものです。
この技法で彫られた例は新潟県には2例しかなく貴重な仏像です。
一般公開は33年に1回です。(平成16年8月27日~29日に一般公開されました)
又、水俣観音堂には鎌倉時代に後醍後天皇の倒幕に加担し佐渡に流され、本間一族に惨殺された日野資朝の子供阿新丸が十一面観音の霊力を受け父の敵を討ち果たし父の遺骨を境内に埋葬したという伝説があり資朝のもの思われる墓(五輪塔)もあります。毎年5月1日に行われる例大祭では日吉神社の神事の後、観音堂まで神輿渡御が行われ、さらに境内で神楽が奉納される神仏習合の名残が見られます。
能楽 #能 #Noh #申楽 #猿楽 #狂言 #風姿花伝 #世阿弥 #芸術論 #幽玄 #歌舞劇 #演劇 #能面 #マスク #文化 #旅行 #トラベル #名所旧跡 #神社 #寺院 #像 #碑 #巡礼 #古跡 #謡曲 #新潟 #上越 #伝統 #Travel #GoTo #ruins #wreckage #grave #Tomb #temple #Buddhist #image #Buddha #Buddhism #Slaughter #murder #massacre #massacre #Overthrow #noble #aristocracy #aristocrat #coup #惨殺 #貴族 #クーデター #倒幕 #鎌倉 #墓 #塔 #仏 #将軍
#Travel#Noh#GoTo#ruins#wreckage#grave#tomb#temple#buddhist#image#buddha#buddhism#slaughter#murder#massacre#overthrow#noble#aristocracy#artistocrat#coup#能楽#能#芸術#art#演劇#伝統#古典#芸能#古典芸能#伝統芸能
2 notes
·
View notes
Text
2022/8/27〜

8月27日
カスタムくんに会いに出かけた!
片道2時間の��し複雑な乗り換えを頭にたたき込んだ。あと少しのところで初めての路線乗り換え。そこでお財布を忘れていることに気がつく。え〜〜……!!と、でも、なんとも戻るしかない。そして戻ったらまた同じ道を出発する元気もないし、カスタム君の午後の部にも間に合わない。横浜駅構内にはブルーナカフェが入っていてナインチェかわいいけれど、心はすっかりカスタムくん。
合計3時間程の旅を0円でしてしまった。
戻りながら電車で日記の文字起こしをして、最果タヒの展覧会のオフィシャルブックを読む。もう1年以上私の部屋にある本だけれど、昨日、この本にマンスーンさんが寄稿していることを知り、もう一度読むことにした。
駅のホームでおじさんに話しかけられる。
私に顔を近づけて「一言、二言で終わるから!」と言われ、イヤホンを外すと「あなたは美人です。だからすてきな彼氏がいるんでしょう。そしてその人と結婚して、絶対に幸せになって下さい。」と言って、去って行った。(“絶対に”の位置が「“絶対に”その人と結婚して〜…」だったかも知れない。)
揶揄う相手を間違えている。
ヨドバシカメラで洗濯機をみる。
1人だとただの鑑賞会をして終わってしまうので友人に付き添ってもらった。ドラムより縦型の方が私の生活には合っていそう。コストダウンできた分で何かしようと思った。
友人がフィルムの現像を出していて嬉しかった。自分以外の人が写真を撮っていると嬉しい。

8月28日
夜にライブイベントに参加する予定があり、1日を、それまで体力を保たせて帰宅後もきちんと過ごせるように時間を過ごしていた。
夜の予定が本当に苦手になってしまう。
もともと、ライブには1人でよく行っていたけれど、チケットを取った時の喜びから、そのライブが近づくにつれて憂鬱になることばかり。ライブの中身より、その時間を耐えた開放感と夜の街にいる喜びに、ライブ=楽しい、という印象をもっていて、ライブって楽しい。
でも、いつもの日曜日をいろいろ終えて、そこからお出かけするのはなんかいい感じ。みんな帰っていく中でわたしはこれから!みたいな。
途中、ディズニー帰りのお姉さんが隣に座り、携帯で新幹線を予約している様子で、これから大阪まで帰るのか〜と眺めていた。

臨海副都心の街に久しぶりに降り立てて、しかも日暮れ時の涼しい夏の日曜の夜で最高だった。ライブ中も、外の景色とか今の空の暗さとかが気になって、元々終演までいるつもりはなかったけれど、早めに会場を後にした。
フットサルをしている人達、それ以外は、日暮れ時の公園の人達はみんないなくて、ビルの赤いランプが点々と映えていた。
夜の海沿いの首都高を眺めながら、ほとんど千葉なのでは?と思いながら、意外と日曜日もお仕事お疲れ様な人が多い、と思いながら、ライブ会場の粗悪なパイプ椅子から座って鑑賞することを想定されていない高さの舞台を見ることで痛めた身体を引きずりながら、涼しい夜を帰ってきた。

8月29日
実家へ少しだけ帰ってみる。
母と同じ時に京都にいたらしい。近所の梨園で無人販売を始めたらしく、梨を1袋買った。ちょうどもぎ取ったところで、その場で詰めてくれる。1,000円で5,6個入っていて、1つだけ貰ってあとは実家に置いてきた。

実家は色々家の補修を済ませていた。
庭の一部にコンクリートを打って通行しやすくしたり、かなり劣化していた木のデッキと縁側をプラスチックの擬木のデッキにして手入れしやすくしたり、施工不良でずり落ちた屋根を葺き替えたりしていた。
また駅まで車で送ってもらう。
昔、塾に行くために下車していた駅は、駅ビルがかなり充実していて、駅横のデパートはショッピングモールみたいになって格が落ちていた。
池袋のビッグカメラで洗濯機を買った!
他店で目星をつけた製品をもう一度紹介してもらい、その内、一つ前の型がかなりお買い得だった製品に決めた。満足のいく行程で購入まで漕ぎつけた、と思っていると、最後にポイントプレゼントキャンペーンの紹介(セールス?)。どこかの国の必殺技くらいにしか思っていなかった“格安SIM”のことが少しわかった。

帰宅して眼科へ。ペッパー君みたいなお兄さんに検査してもらう。使っているコンタクトのゴロゴロがつらくて、とても毎日装着できないことを伝えると「そうですよね〜、◯◯さん(私の名前)はかなり乱視が強いので違和感はあると思います。」と流れるように答えてくれてペッパー君。「目薬や装着液を使ってもあまり軽減しなくて…」と言うと、「え…?装着液ですか…?」と人間になってしまった。装着液ってハードコンタクトにしか使わないらしい。「(ゴロゴロするのは)慣れれば感じなくなりますかね〜」と言うと「慣れませんよ〜。ずっと違和感は残りますよ。」とペッパー君に戻った。
梨の皮を剥いて、カットして、今までで1番カットされた梨っぽい造形になって嬉しい!包丁を新しくして良かった。

8月30日
夕食のお誘いメールをもらった。
職場の飲み会が無くなったご時世でとても助かっている身だけれど、少人数の少し心落ち着ける人選の会だと、行きます!と返事をしてしまう。
(食事の席に変わりはないので、少しずつこれから憂鬱度が増していくのだろうな。)
でもお誘いメールに“参加してくれると嬉しいです。夕食を取らない派であれば飲み物だけのオーダーでも構いません。ご一緒できるのを楽しみにしています。”とあり、ならば!となったのかも知れない。
基本的に、他人から気を遣われてしまうタイプだと思っていて、(こんなにしたら逆に相手に悪いかな)と不安を抱かせてしまうくらい気を遣ってもらえると嬉しかったりする。(だから、家族や身内の無礼にしょんぼりするし、いつまでも引きずったりする。)
妹と喋れていた頃、その最後の方は彼女とそんな感じの関係でなんか良かった。祖母のお葬式を中抜けして一緒に帰った時、少しお互いの近況を話して、お葬式も大事だけど、テストや課題や明日の大事なことがあるよね、みたいな話をした気がする。
上司の思いつきで明後日は都庁へ行くことになった。昼食問題は自分に正直になって乗り越えよう。
職場で2日連続で病欠した人がいて「また病んでいるんじゃないか」「お前何かしたんじゃないか」みたいな会話が飛び交っていた。
その人がお休みすることで仕事が増えることの迷惑より、ただ何か面白がって言っている愚痴に聞こえて、とっても私は落ち込んだ。
明日で8月が終わる。暑中見舞いは2通お返事が来た。

8月31日
今日は何もなかった。
そんなことはないはず。だけど、今日は何もなかった。
9月1日
都庁へ行った。1階のエントランスの巨大なピロティが、何かの搬入口みたいな空間なのに人だけが通っていて不気味。
ロビーにはアルソックの警備ロボットがウロウロしていて可愛い。
ずっと閉鎖されていた45階の展望室は、なんと今日から再オープンのよう!警備員のおじさんが「ちょうど今日からなんですよ。」と教えてくれる。
用務まで東京観光案内所で23区と市区町村のパンフレットを眺めて、再来週行く予定の府中市のお散歩マップを手に入れた!
隣は全国都道府県の観光マップが揃っていて楽しい。月替わりショップは今日から山梨県で、オープンしたてなので信玄餅の入荷数を数えていた。
用務が終わり、昼食に行くみなさんを見送って展望室へ。新宿から眺める東京は、何かありそうで、特別何もなくて、意外と住宅街が細々とよく見える。
誰でも弾けるピアノに人がたくさん並んでいて、代わる代わるに上手に演奏していた。みなさん力強いタッチ。
午後から職場へ戻るため、中央線に乗る。
平日の昼間の中央線っていろんな人がいる。ビンテージっぽいTシャツとキャップ、短パンにサンダルを身につけて、手にはフライトの本があり、昨晩の音楽イベントのストーリーを投稿している男の人がいた。
職場に戻ると、昼食をとれない、人前で食べられないことを、また今日も明るみにしてしまい、そのことを話されているな〜小声で遠くで、というのを察知したりした。あと都庁のどこかに傘を忘れたことに気がついた。
帰り道で稲妻を5回見た!

9月2日
聴く・見る・読む、何を受け取っても、どこかで気持ち悪いレーダーが働いてしまう日。何も聴きたくない見たくない読みたくない。なので、自分の頭の中で健やかな都合の良いイメージやストーリーを流していた。
今日も何もなかった。
でも、以前同じ部署だった方にばったり会って「相変わらずかわいいですね〜」と言ってもらった。
「ヘッドホンおしゃれですね。」と言ってもらい、でもただのファッションなんです、ファッションといえば◯◯さん(相手の名前)のメガネっておしゃれですよね、といつも思っていたことを伝えることができた。「眼鏡はね、こだわりがあるんです。」と言っていた。眼鏡市場で買っているとのこと。
掃除をして爪を切って写真を撮って梨を剥いて花の水を換えて鏡を磨いてお香を焚いて洗濯をした。
場所性の本に、写真や芸術作品を作る人は場所の���イデンティティの要素をダイジェスト的に捉える、みたいな文があり、ある作家は、以前住んでいたプレーリーの土地を、グミの匂いの中に見出した、とあって、その作家の作品を観たくなった。

3 notes
·
View notes
Text
youtube
世界最大石灯籠製作 世界ギネス記録認定 念佛宗佛教之王堂 The Largest Stone Lanterns in the world The Buddhist Art of Nenbutsushu
念仏宗無量寿寺(念佛宗) 総本山 佛教之王堂
三国伝来の佛教美術 石灯籠
世界ギネス記録認定 概要 高さ:12m 幅:7.4m Height:12m Width:7.4m 本堂前 左右石灯籠 Stone Lantern The Guinness World Records ギネス世界記録認定 平成二十年四月二十八日 衆生の心を不断の光明で照らし、仏道へと導く。 世界最大の本堂につりあう灯籠を計画すると、灯篭も世界最大になった。
本堂前の二基の灯籠は高さ12 メートル(4 階建の高さ)、世界最大、ギネス世界記録認定となっている。
台座部分には「龍の阿吽形」、「鳳凰の阿吽形」が彫刻されている。
本堂 阿弥陀堂
高さ51.5m(基壇、棟飾り込)、桁行(幅)67.9m、梁間(奥行)58.2m 天井までの高さ約32m(11階建ての建物が入る)、天井大彫刻は48畳 破風 一辺25m、合計50m 平瓦 幅1.7尺、奥行1.9尺(世界最大) 十二万四千枚 畳数 888枚 欄間彫刻 堂内488点 柱など堂内は拭き漆仕上げ 上段は六手先総詰組様式、下段は四手先総詰組様式。 上層部に扇垂木を用いた日本建築史上初の佛教建築であり、屋根上に12万4千枚の瓦が敷かれている。 その瓦の波の頂上に聳える鬼瓦は、鬼師・梶川亮治氏制作。 (ギネス世界記録認定・平成19年2月28日公式認証・高さ9m、幅8.8m、先端部経之巻の直径91cm) 鬼の憤怒の形相が、衆生の心中に潜む煩悩を払い、清浄無垢な心を顕現させます。 軒下最上層部の周囲には、手先詰組の間に、釈迦如来像八十体が四方へ向かって遍く衆生済度を勧められ、その下層部には八十八体の龍、蟇股には、表に龍、内に等身大の飛天それぞれ百四体、また、本堂全体で十万枚を超える金色に輝く飾り金具が、荘麗なる浄土の世界を厳飾しています。 堂内には、金箔二重貼り、六手先総詰組、屋根葺面積226.2㎡、総数16,000枚の瓦を使用した宮殿(くうでん)(高さ19m、幅19.98m、奥行12.36m)、その中に在して、大慈悲の光明にて十方世界を照らすが如く輝きわたる本尊阿弥陀三尊佛は、中華人民共和国、工芸美術大師・佘國平佛師制作の総高8.45mの木彫佛像です。 伽藍全体で一万点以上の木彫群、宮殿上に配す幅22.6m、高さ3mの双龍彫刻、宮殿の両脇に四階建てビルの高さに匹敵する全高11mの彫刻が、鳳凰、松竹梅等を刻んで納められている。 また、本堂内壁は、三阪雅彦画伯により、総面積852.9平方メートルに及ぶ金箔襖に色彩豊かに描かれた鳳凰及び瑞雲、また、下部に描かれた蓮華が相俟って、浄土の光景を彷彿させる。
本堂全体で2,987点に及ぶ木彫群、百四十四枚の桟唐戸、また、本堂前に鎮座する一塊の巨岩を彫り込んだ巨大な天水鉢(全高2.2m、幅3.5m、奥行3.5m)等々、世界に二つとない彫刻・工芸の奥深い造形の数々は、どれほどの時をかけても見尽くすことができないものであり、それぞれが調和しつつ、妙なる浄土賛歌を奏でる情景は、参詣する者全てに御佛への畏敬の念を起こさせずにはおかない。
全世界 仏教徒の聖地 「佛教之王堂」念佛宗 総本山 無量壽寺 仏教美術の宝箱 故タイ法王猊下 世界各国の仏教最高指導者 並びに カンボジア王国 故ノロドム・シアヌーク国王陛下の御聖骨がお祀りされている寺院です。 佛教之王堂は佛法に基づいて建立され 建物全ての部位に、仏縁を結ぶ教えが込められています。
伽藍工事全体、およそ7年間で10,524点の彫刻、450,173点を超える彫金が製作されました。
The Royal Grand Hall of Buddhism - Nenbutsushu Buddhist Sect of Japan The sacred place for all Buddhists in the world The Royal Grand Hall of Buddhism
仏教美術の宝箱 Buddhist Art / nenbutsushubuddhistart
念佛宗公式 Official / royalgrandhallofbuddhism https://muryojyu.com
Buddhism has its origin in IndiaBuddhist cultures of China, Korea, and Japan are represented hereat the Royal Grand Hall of Buddhism. It is the first construction of an authentic full-scale Buddhist temple since the erection of the main temple of Obakushu Buddhist Sect in 1661.A total of roughly 3.5 million people joined forces to construct the Royal Grand Hall of Buddhism and completed the entire temple in only seven years without even a single accident.The Royal Grand Hall of Buddhism, in its vast precincts of over 180 hectares, has the Front Gate, the North Gate, the South Gate, the Main Gate, the Washstand, the Ksitigarbha Hall, the Prince Shotoku Hall, the Five-story Pagoda, the North Bell Tower, the South Bell Tower, the Main Halls including the Amida Hall and the Sakyamuni Hall and the Avalokitesvara Hall, the Sutra Hall, the Merit-transference Hall, the Okunoin Hall, the International Buddhist Conference Hall, the Sangha Hall, and the Main Building. All the buildings are decorated with 10,524 sculptures and statues and more than 450,173 metal carvings.
この動画は、個人が念佛宗の資料などを元に作成しており公式なものではありません
#念仏宗#念佛宗#世界一#Guinness World Records#nenbutsushu#buddhist temple#stonecaving#stone lantern#largest#Youtube
1 note
·
View note
Text

【かいわいの時】明治二十二年(1889)9月30日:天満紡績争議(大阪市史編纂所「今日は何の日」)
争議の発端
1889(明治22)年9月30日12時半、午後の就業をつげる汽笛が鳴りひびいても誰一人工場に出てこなかった。かねて職工は賃金引上げについて「寄々相談」を続けていたが、この30日、綛場 (綛部・綛締部)の女工300余名がまず朝9時の休憩時間、そして昼12時の食事時間に食堂で「今日こそは賃金引上げを要求しよう」と相談、ついに午後就業しなかったのである。米価が騰貴を続け、生活に難渋し(この当時女工は、近郊農村あるいはいわゆる細民社会のものがほとんどであった)、それに近くの堂島紡績の賃金の方が高い(綛機一枠、紹締部一玉に付2~3厘)ことからも、賃上げは決して無理な要求ではないというのが女工の主張であった。その他、上半季特別賞与の支払い(予定は9月20日迄に支払い)・待遇の公平も要求していた。その後、女工は、食堂の様子をうかがいにきた職工取締(役員)が後日の返答を約したことで、一応就業したが、午後5時半になると一斉に仕事をやめ(6時までが就業時間)門前にでて夜業職工を待ち受け「人毎に何か示し合わせし模様」だったが、この日はそれ以上の行動に出なかった。
その後の経過
30日以後女工たちは、返答を待ち仕事も手につかない有様だったという。返答がないのに業を煮やした女工約300名は、 10月2日午前7時頃、出勤途上の一職工取締にじか談判に及んだ。だが女工らが、その取締の説得に応じ会社内での話合いに入ろうとした途端、取締は態度を変え、即座に主唱者を解雇してしまった。憤激した女工たちは、午後三時頃には4~50名が先の要求に加えて、5年間契約書・積立金(双方とも職工の足留策)の返付をせまった。さらに翌3日には、 汽缶部の男工も、女工に同調する動きをみせた。このため、会社は3日まで操業を中止せざるをえなかった。 この3日には、会社は、女工300名募集の掲示を門前に出すとともに、社員が職工宅を歴訪し出社を説得するなど、争議の切崩しにかかった。対抗して、職工約400名は同日午後から、堀川監獄・島田硝子製造会社等の天満周辺に「集合して頻りに相談をなし」、「ややもすれば会社に押しかけんとする」勢いをみせた。この動きを察知した憲兵第六管区長柄駐屯所は、4名の憲兵を現場に派遣、職工を説諭、解散させた。ちなみに憲兵が争議に介入するのはこれが初めてである。警察・憲兵は、争議中の集会等にも干渉し、解散を命じていた。会社側はこれを背景に、「もし説諭に服さざれば解雇せん」と一層強硬な態度に出てきた。翌4日、会社は、争議の主唱者とみられる 男工60余名・女工20余名を厳重に取り調べた。5日までに、その職工らを解雇するかあるいは要求を受け入れるか、いずれかに決定する予定だったという。
警察・憲兵・会社の強硬な姿勢を前にして、5日には昼業職工400名はすべて就業してしまった。だが夜業職工のうち数百名はなおも説諭に服さず、「賃金の引上げを聞き入れぬとならば、我々に相当の前借を許された」と要求していた(結果不明)。
妥結
警察憲兵・会社の強硬な姿勢の前に、職工側の態勢が崩れ、争議を継続している職工も止むなく会社と妥協することとなった。その結果、会社側は、職工が「穏当」に出ればという条件つきで、「物価騰貴につき実際生活上困難なるべければ、就業の上勉強の者には賃金の値上げをなし、また本年上半季における特別賞与金は6月迄に入社せし者に限り来たる20日迄にそれぞれ配当する」ことを認めた。 また職工主任(職工配置、日給・請負額等の労働条件を決定し、また日常的に職工を監督する)から謝罪書をとることも認めている。この妥協案により、職工は7日から元の通り就業し争議は一応落着した。 当初の職工の要求のうち、賃上げ・特別賞与そして待遇の改善(主任の謝罪書)を曲がりなりにも獲得していることから、この争議は、解雇者が出たとはいえ、一応成功したものといってよいだろう(『大阪 朝日』明2・10・4、10・5、10・6、10・8)。
なお1889(明治22)年12月の天満紡の火災の際、この争議との関連を警察が調べていることからみて(無関係と判明)、その後も争議の余波は残っていたものと思われる(『大阪朝日』明22・12・ 4)。周知のように、この天満紡の争議を契機として、紡績連合会・各紡績会社の職工対策は整備されていく(立川健治)。『大阪労働運動史(第1巻)戦前編・上』1986より。※原文数字はすべて漢数字。
(写真)「赤レンガ館」1886築(中西金属工業)
赤レンガ館はもともと天満紡績の工場として完成、合併により1900(明治33)年に大阪合同紡績天満工場となった。1931(昭和6)年、大阪合同紡績が吸収された東洋紡績の工場となり、1938(昭和13)年に中西金属工業に移った。赤レンガ館と並んで本社棟も明治期の建物。1階が石造風、2階はタイル張り、屋根が寄棟造桟瓦葺という和風づくり。天井が高く、階段は急勾配、手すりまわりの古風な意匠などに、明治の香りが漂う(中西金属工業)。写真は、《西日本 近代建築万華鏡》より。
1 note
·
View note
Text
ムー旅 平将門巡り「胴と首をつなぐ」崇敬の旅 ・その1
6月18日(日)参加して参りました。ローソントラベルと月刊ムー編集部のコラボツアー第2段です。実は昨年の第1段も気になってはいたのですが、コロナ下ということと1泊ツアーだったこともあって断念😢
今回は元々が大好きな平将門さんなのと、パンフレットに作家の加門七海女史が寄稿されているということで、読んでみたい意欲も重なりまして。6月過ぎているというのに申し込みをポチってしまいました💦
集合場所は新宿センタービル。Twitter等の情報を見てなかったんですが、何か集合時間ギリギリになって最後に現れた方が松原タニシ氏のコスプレ?すごい似てるけどまさかな~😅
……そのまさかで、ご本人様でした💦💦
※後から松原タニシ氏の参加が、公式Twitterで告知されてるのを確認して脱力しました。何だよー、ちゃんと把握しとけよ😂>自分
さて、1時過ぎに定刻通り出発した🚍が向かった先は、茨城県の國王神社でした。
将門さんが討ち死にされた跡地?に創建された神社です。ここがめっちゃ居心地がいい😊💕空気が違うと言うか、清々しいんですね。糺の森クラス。



駐車場から境内に入ったのですが、ちょうど狛犬さん辺りからになるので、改めて⛩️をくぐって入ろうと思い、⛩️は何処だと見渡したら遥か彼方!!

参道長っ😳
急いで⛩️まで行って、改めて参道を歩いてから本殿に二礼二拍一礼しましたが、端から見たら多分変な人でしかなかったと思うの😰
ここから、郷土史家の方の簡単な将門さんの生涯と神社の縁起の説明がありまして、将門さんの三女の如蔵尼-ー歌舞伎の滝夜叉姫のモデルになった方ですねーーによる建立とのこと。御神体は如蔵尼自らが将門さんの三十三回忌に彫られた坐像だそうですが、盗難にあった関係で現在は本体は蔵に安置してあり写真のみパネルで公開。
余談ではありますが、私の家の氏神様というか守護神様?が谷保天神(ウチは神道なんで、祭礼関係をお願いしています)なんですが、由来がほぼ同じ💦💦
あちらも菅原道真さんの三男にあたる道武公が、配流先で薨去の知らせを聞いて刻んだ道真さんの坐像を鎮座したのが縁起なんですよねー。3番目の子供と坐像……ちなみに、将門さんが新皇と名乗るきっかけになった神託は道真さんが下したものなので、これも深い因縁があるように思えます。
境内には数々の石碑や、建立当時から植わっていた樹木があり、歴史が感じられました。



こちらの拝殿の屋根は茅葺きなんですが、所々傷みが……💦💦本来だと茅は数十年おきに葺き替えるのが常識です。京都のみやまのかやぶきの里でも岐阜の白川郷や五箇山でも、保存会の方々が総出で葺き替えている映像を見かけたことがあります。傷みがあれば、茅を継ぎ足します。こちらもそろそろ葺き替えの時期が来てると思うのですが、資金不足だそうで😰お詣りしたご縁もあるからと、些少ではありますが授与所で寄付をさせて頂きました。もっと早くに知っていれば、💴を下ろしていったのにーー😩
参拝を済ませ境内を散策した後、再び🚍に乗り込み次の目的地の神田山延命院へ。こちらには将門さんの胴塚があります。大体15分くらいで到着。🚍の前には畑と竹林が拡がり、こちらも落ち着いた��囲気の場所。

でもってですね。☝️を見て仰天。こちらの宗派は真言宗智山派ですと!?
何を隠そう、将門さんの調伏をしたとされる成田山新勝寺が同門なんですよ!!そういうこともあって、将門さんを信仰される方は新勝寺には行かないそうなんですが、よりによって何で同じ宗派に葬った!!
朝廷は調伏を全国の仏門に命じたそうなので、新勝寺がしたということはその宗派全体に命令が下っている筈なんですね。にも拘らず、胴塚が築かれている。何じゃそれ。
ともかく、境内に入ります。



将門さんの胴は、最初このカヤの巨木の根元に埋葬されたそうです。かなり存在感がある。胴塚にはペットボトルがたくさん置かれておりまして、信仰の篤さが伺えます。
神田明神もそうですが、神田山は元々はからだ山がなまってかど山⇒かんだ山となり、現在の山号になったそうです。将門山とも称するそうなので、かど山=将門さんの「かど」から来てるのかと思ってた😅その身体は何かと言えば、当然のことながら胴塚の胴ですね。
ちなみにこちらの石碑。

右の「南無阿弥陀仏」と書かれたものは、元々大手町の将門塚(首塚)にあったもので、それが盗難に遭い将門塚の方は新しく造り直して設置した後に戻ってきたそうで。既に設置し直したものを破棄する訳にもいかず、それならこちらの胴塚に奉納しようということで、将門塚保存会から寄贈されたとのこと。それはいいとして、何で浄土宗もしくは浄土真宗なんだろう🤔(南無阿弥陀仏は“阿弥陀仏に帰依する”ということで、浄土宗&浄土真宗の所謂「念仏」なんですよ)
旗の上にある九曜紋は、毘沙門天(多聞天)=大日如来を表すそうで……そういや、境内にちゃんと毘沙門天を祀ったお堂があったじゃん😭(画像撮らんかったんです)
この左の石碑、ん?と思う方もあるんじゃないかと。「大威徳将門明王」なのに、梵字がキリークではなく不動明王を表すカーンなんですよ(その辺りの考察は、高田崇史氏がQ.E.Dシリーズの御霊将門で書かれています😊)
ちなみにこちらの金堂は1964年(東京オリンピックの年ですね)に不審火で焼失してそのままだとか。胴塚のすぐ横の↓がその跡地になります。

こちらも信仰を集めている割にちょっと荒れているというか。國王神社と延命院、どちらも常駐の神主さん&住職さんが居られない😥正直うちの近所の村社とあまり変わりがなくて驚きました。
取りあえず前半戦はこの辺までで。
1 note
·
View note
Text
美しき故国④
六月三日、船はようやく港に入った。
実に二年ぶりの帰国である。
帰帆を知らせる狼煙を受け取った王府の役人や使節の家族がこぞって埠頭へ迎えに出向いていた。
船室の小さな窓から外を覗くと、出迎えでごった返す人出のうしろ、陸の奥には石造りの塀が連なり、その隙間には朱や灰褐色の瓦屋根の屋敷が並んでいる。遠くに見える青々とした緑の高台には板や茅葺きの民家がまばらに顔を出していた。
命がけの航海に身を固めて耐えていた人々は盛んに動きだし、積荷も外へ運び出されはじめると、船のなかに外の空気が入り込む。重く湿った夏の風は決して爽やかな心地とはいえないが、海では感じることのできない草木の薫りとこの地に染み付いた命のにおいを運んでくる。
―――美しき我が蔽国。
頭号船から順に下船がはじまり、二号船に乗っている朝明らが船を降りる頃には、入港から大分時間が経っていた。荷物の入った行李などは船員に運ばせ、身の回りの少ない荷物だけを携えて、朝明と己煥そして聡伴の三人はようやく故郷の地を踏んだ。 本格的に夏のはじまりを告げる刺すような陽の光をうけて、己煥は人がひしめき合うなかで仕方なく傘を開いて歩く。
「一生帰れなかったらどうしようかと思いましたよ!あぁ早く屋敷まで戻りたい……子供がですねぇ、生まれているはずなんですよ」
「それはめでたいな聡伴。私も旅役に就く直前に娘が生まれたが、どれほど大きく育っていることやら……」
「何人目だ?」
「それが長子なんです。男女の別は知りませんがはじめての子供が己の知らないうちにとっくに妻の腹のなかから出てきていて、もしかするともう四書を諳んじているかもしれないと思うと寂しいものがありますよ」
もう育つ余地のない大の大人とは違��て、幼子の時の流れは実に早くてその成長具合はとてつもなく大きいのだ。
「我が家に着くのが待ち遠しいですよ。ところで己煥様は本当にその猫をお持ち帰りになられるのですか?」
船底で暴れまわっていた虎猫は筆のようなしっぽを立て、己煥の足元にぴっちりと寄り添っている。あらためて船の外で見るその姿は、毛も瞳も陽の光を浴びて黄金に輝いていた。此奴が散々積荷を崩しまわったあと、船員に猫の出どころを訊いたが生憎誰も知らず、懐かれてしまった己煥がいつのまにか持ち帰ることになっていたのだ。
「まったく、散々暴れまわった挙句に良い人間に拾われるなんて運のいい奴め。お前が暴れ���から俺たちはよくわからない肉なんかを―――……」
「え?肉ってなんですか?」
「いや、なんでもない。それよりお前早く屋敷へ戻らないといけないだろう? 駕籠を使うか?馬でもいいぞ。呼ばせるか?」
「いやいやいやいや、なにをおっしゃっているんですか!屋敷までそこまで離れていませんから、家の者を待って帰りますよ!」
しかし、あれよあれよというまに、聡伴は朝明が呼び寄せた駕籠に詰め込まれ、彼の住まう四町へと送り出されていった。港の喧騒のなか、聡伴が去ったふたりの周りだけが、妙に寂しく感じられたのはきっと気のせいだろう。
朝明と己煥はゆっくりと人の流れに合わせながら 連れ立って歩くふたりだが、互いに交わす言葉はなくただ足だけを進めていた。
それはいつもの慣れ合ったふたりに時たま訪れる呼吸のような沈黙ではなかった。わずかに背の丈に差があることで己煥が差した傘の先が隣の朝明を突くことはないが、今このときだけはむしろ故意に突っつきたい。常日頃は堂々と己の意を主張してみせるこの幼馴染が、眉を八の字にしながらやたらにもごもごと口のなかに言葉を溜め込むのは、余計な気を揉んでいるときの癖だと己煥は知っていた。
喉の奥で唾液を飲み込んだ数が二十を超えたころ、耐えかねた朝明が先に口を開いた。
「己煥……あの肉は―――」
「あぁ、不味くはなかったな」
暗い船底でふたりの食指を誘う妖艶な輝きを放っていたあの肉切れは、口に入れた途端、味わう暇もなく一瞬にして蕩け、喉の奥へ消えていったのだ。
「口に入れるべきではなかった、と?」
「お前も感じただろう?あの肉を前にしたときの……」
あの奇妙な心の騒ぎようを。
「気のせいだ。その前に聡伴が林宗信の話をしていたからじゃないか。薬を買い込んだとかいないとか」
「己煥!」
「今のところ身体の調子はおかしくないし、毒の類ではなかったんだろう。それに、清冊に載っていない品であればこの先咎められることもないだろう」
女にしても仕事にしても、ことあるたびに要領良く綱渡りをし、たとえ綱から落ちようとも悪びれることもなく平然としている朝明だが、それらに己煥を巻き込むこととなればすこぶる落ち込むのだ。
「五良小、」
外ではあまり使うことのなくなった童名で朝明を呼んでやる。
「もう船旅は御免だが、今度仙薬でも探しに行こうか」
味のある、できれば美味で、陸の上で気持ちよく酔えるものが良い。
「……口当たりの優しい良薬を探しておくよ、煥小」
体よくはぐらかされたことは十分承知だが、まるめ込まれた朝明もこの話を続けるはなくなっていた。
「父上!」
雑踏のなかから、甲高い声が己煥を呼ぶ。
声の先には、幼子と欹髻前の少年の手を引いた女性、己煥の妻と屋敷の者たちがこちらへ合図を送っていた。住まいを異にしている朝明の息子も一緒だった。
「お迎えだな」
暗い船底で、あの肉を前にしたときの朝明、そして己煥自身も、きっとまっとうではなかった。胃が空になる勢いの船酔いに見舞われていたのだ。絹のように薄くても、とてもじゃあないが肉なんて腹に入れたくはなかったはずだ。それなのに、腹の底から心の底から、己煥はあの肉を欲していた。
それが、長きに渡った職務と航海の疲れからなのか、はたまたあの肉の仙力なのかはわからない。もしそうであったのなら、己のこの弱き身体を治してくれるというのなら、それは大変喜ばしいことなのではないだろうか。
「あの薬が真の仙薬であれば、お前の身体も少しは楽になるんだろうな」
「さすがにそんな都合の良い話はないだろう、世迷言はよせ」
こちらへ駆けてきた息子たちのほうへ、歩き出す。
それ以上、お互いあの肉について口に出すことはなかった。
死―――大国の帝ですらそれに抗おうとその世迷言に縋るのだ。
人間の生は短い。
たとえ俗伝だとしても、残酷なほどに過ぎ往く歳月に己を繋ぎとめようと必死になるのだ。
いつのまにか先へ進んでいた彼らに気づいた猫は、行き交う人間らの足元を上手に縫って、はぐれることなくついていった。
―――1683 美しき故国―――
0 notes
Photo

「斜光のガレージハウス」夕景外観 ・ 風景と光に向け斜めに配置された大きな窓を道路から見上げると迫力ある無垢材の梁表しの空間が透過します。 ハードな外観と優しいインテリアの対比が面白い見え方、設計中の模型でも検討したカットのイメージが形になっています。 ・ 素材はガルバリウム鋼板立平葺き、亜鉛メッキしたスチール、コンクリート打ち放しを組み合わせています。 ・ ガルバリウム鋼板はさざ波加工とすることで表面のペコつき感を抑えています。 ・ 写真 酒井広司 ・ その他のphoto→@yosuke_tomiya_design_office ・ #富谷洋介建築設計#一級建築士事務所#設計事務所#建築家#北海道#札幌#注文住宅#斜光のガレージハウス#梁あらわし#無垢梁 #ガルバリウム鋼板#ガルバリウム外壁#ガルバリウム#立平葺#さざ波 #建築模型#家づくり #マイホーム#architect#architecture#design (一級建築士事務所 富谷洋介建築設計) https://www.instagram.com/p/CgRyQqJvqTZ/?igshid=NGJjMDIxMWI=
#富谷洋介建築設計#一級建築士事務所#設計事務所#建築家#北海道#札幌#注文住宅#斜光のガレージハウス#梁あらわし#無垢梁#ガルバリウム鋼板#ガルバリウム外壁#ガルバリウム#立平葺#さざ波#建築模型#家づくり#マイホーム#architect#architecture#design
3 notes
·
View notes
Photo

蘇鉄と松に囲まれたご本殿 新庄八幡宮 瀬戸内の雨があんまり降らずあったかい気候に馴染む風貌ですね 備後沿岸でよくみかける入母屋平入千鳥破風唐破風に備前備中でよくみかける外削ぎ千木と二本の鰹木のハイブリッド本殿は総﨔造銅板葺で江戸時代末期文化二年の造営です 42代文武天皇の御代、大宝元年(701)に宇佐の宮より勧請し創建したと伝わります 宇佐神宮の創建を調べると45代聖武天皇の御代の神亀2年(725)と出てきますがこれは現在の社殿が建立された年です 創祀自体は29代欽明天皇の御代、大神比義命が創建し日本で初めての神職(祝職)に任ぜられ初代大宮司に就いています 大神神社の初代神主大田田根子命が初の神主といえますが職制としての神主は宇佐神宮が初めてのようです #新庄八幡宮 𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍 新庄八幡宮(しんじょうはちまんぐう) 鎮座地:岡山県倉敷市児島阿津2丁目18−1 主祭神:誉田別尊、足仲彦尊、息長帯姫命 社格:村社 𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍 #神社 #神社巡り #神社好き #神社好きな人と繋がりたい #神道 #神社仏閣 #shrine #shinto #日本の風景 #参拝 #神社巡拝家 #recotrip #御朱印 #御朱印巡り #御朱印好きな人と繋がりたい#神社建築 #神社仏閣 #パワースポット #岡山県 #倉敷市 (新庄八幡様) https://www.instagram.com/p/CoE6zGbPXBx/?igshid=NGJjMDIxMWI=
#新庄八幡宮#神社#神社巡り#神社好き#神社好きな人と繋がりたい#神道#神社仏閣#shrine#shinto#日本の風景#参拝#神社巡拝家#recotrip#御朱印#御朱印巡り#御朱印好きな人と繋がりたい#神社建築#パワースポット#岡山県#倉敷市
43 notes
·
View notes
Text
フワッとなせツアー。

きんなは散々雨が降り散らかしてくれました。おかげでうちのクズ屋根(茅葺き屋根の事ね、方言ね、口悪いよね)は雨漏りして大変。そんな時でもライフ ゴーズ オン。本日はなせ(初心者)ツアー也。

平日3日間の悪い大人の修学旅行に来た自営のお二人。当初のリクエストでは来たる明日のバフバフに備え、11線の楽しみ方を教えろコノヤローというものでした。リフトの運行情報が発表されるまでコーヒー飲みながら地図を見ていたのですが、程なくして終日運休のアナウンス。仕方あるめえ、プランBですな。

ゴンドラ乗り場で何やら寒気のする笑顔の二人組が。あ、黒田大先生とテリーダイチ氏!ステージⅡの試験中だそうです。テリーダイチは俺と同じ年にステージⅡを受けた仲。若いのにすでに講師とは。やりおるな。今年の受験生はなんと一名!うお〜、この二人に笑顔でしごかれるのか〜。なかなかメンタル的にキツそうですね。ご武運を!

入り口ですでに20cm程のニュースノー。こいつはええんちゃうん?
因みに以前もたいてのこらせ(中級コース)でご参加いただいてる二人なんですけど、今日はゆる〜く行きたいという事でなせツアーでエントリーしてきました。このパターンの人、最近多いな。

まあいいや、なせらしくのんびり歩きましょう。ふかふかなほうていに囲まれ笑顔を隠しきれません。

ハイクする度にタバコを辞めようと決意し、数分後にこの絶景で吸うからうめ〜んだよな〜と、のたまうゲスト。
ほんじゃもっと美味いほうていいただきましょうか。

スキーカットに反応もせずくっついていそう。そんじゃどーぞ!!

わっしゃっしゃーーーー!!

イヤッホ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜イ!!!

たまんねーーー!!
思わずほうていの大海原に身を投げ、全身で喜びを表現するゲスト。

いやあ〜、人も全然いねえし、最高だ〜。どうやら悪い大人の修学旅行は幸先いいスタートを切れた模様。

次のゆるふわツリーもいいと思いますよ〜。

ほらね〜。

結構なお手前でございました!
普通ならこれでゲレンデ滑って帰るんですけど、まだ時間あるし裏滑って帰ります?悪魔のささやきに二つ返事のゲスト。

がしかし、そうは問屋が卸さねえと来たもんだ。標高が下がると積雪が減った上に重て〜!

誰だ!こんなとこ行こうって言った奴は!
まあ、これなら11線行かなくて良かったすね!ナハハのハ〜。

それでも悪雪滑って修行できました!とのポジティヴなお言葉!
残りの二日間、気をつけて思いっきりハッチャケちゃってくださーい!!
お疲れ山でした!&おしょっ様でしたー!!

帰り際、ゲストがお土産に立派な牡蠣をくださいましたー!!
滅茶苦茶美味かったですー!!最大級のおしょっ様を!!!
0 notes
Text
御岳山、ロックガーデンと奥の院

剱岳の疲れが漸く取れた翌週末、山サークルで久々のリーダー山行。
台風の影響で天気予報が判断期限ギリギリまで微妙だったせいで、決行するかボルダリングに変更するかで大いに悩んだのですが…。
結局は雨の降り出しが午���からの予報に変わったので、予定した行程を全てこなす事が出来ました。
今回は初心者向け企画なので、往復ともに潔くケーブルカーを利用。
その代わり、天狗岩に登ったり奥の院峰にもチャレンジしたり、ゆったりとしたティータイムを設けるなどして変化に富んだ山行を楽しめたかと思います。
ケーブルかーを降りてどんどん歩いて行くと、神代欅の手前辺りにシュウカイドウ(秋海棠)の花が咲いていました。ベゴニアに似てますね。

先月も見たけど、神代欅。寿齢1000年だから、平安時代からここにある訳です。

昼から雨なら後回しにするつもりだった武蔵御嶽神社。
順路を考え、やっぱり先に行くことに。

長い階段を登って、もうすぐ山頂。 少し青空が見えて来ました♬

神社裏手にある奥宮遥拝所からは、午後に登る予定の奥の院が見えます。

御岳山の山頂は、本殿と遥拝所の間の微妙な場所(奧の屋根が遥拝所)。
標高929mの文字も読みづらい…。

石段の途中からエスケープルートを使って、七代の滝への道へ。

この道、こんなに長かったかなぁ?と思った頃に、沢に架かる橋が見えました。

「七代の滝(ななよのたき)」に到着!
マイナスイオンたっぷりで気持ち良い!

天狗岩へ向かう鉄階段。

そして根っこ道。

長い木段も。

木段が終わったら、天狗岩の鎖場を登っていきます!

岩の上には天狗像が二体。こちらはその①。

祠もあります。

さっきの鎖場の上は、こんな風に根っこに覆われています。

天狗像その②。

天狗岩の後は、ロックガーデンへ。

苔むした岩だらけ。
屋久島の白谷雲水峡を思い出します。
ロックガーデンは、やっぱりこれぐらいの季節が最高!

ロックガーデンでランチの後、綾広の滝へ。 沢沿い歩きはここでお終い。

名残惜しいので苔を1枚。

トイレを済ませて、さぁ奥の院峰へ!
ここからは急登ですが、無理せずじっくり歩けば初心者でも大丈夫。

私とSLが持参したトレッキングポールを初心者の方にお貸しして、使い方をレクチャーしつつ登りました。
立派なお社から左脇の岩場を更に登ると…

奥の院峰に到着です!標高1,077m。
ちなみにこの奥の道は鍋割山→芥場峠→大岳山へと続く上級者コース。
昔、その上級者コース(逆回りだったけど)を初心者のWちゃんを連れて歩いてしまったことがあったなぁ…猛省。

復路は、長尾平を目指して下ります。
途中の見晴らしポイントからは、西武ドームや副都心方面が見えました。

下りは最初こそやや急ですが、この辺りからは緩やかに。

天狗の腰掛け杉の分岐まで来ました。長尾平まではあと少し!

長尾平の奥のベンチで優雅にティータイム。
皆さん、フルーツやコーヒーなど、ありがとうございました!

帰りは茅葺き屋根の御師住宅の前を通って(食事やお茶も楽しめるようです)…

ビジターセンターにも入ってみました。
狸の剥製や、御岳山で見られる動物のフンなどが展示されています。

ケーブルカー乗り場の手前に咲いていた萩の花。秋ですね〜。
帰りは、御嶽駅前にある中古アウトドア用品店「マウンガ」へ立ち寄り、希望者のみで河辺温泉「梅の湯」へ。
最後まで雨にも降られず、一日を大満喫出来ました!
やっぱり低山も楽しいですね♬
0 notes
Text
youtube
来迎阿弥陀三尊佛 総高8.45m 製作 念佛宗総本山 佛教之王堂 本堂 The Buddhist Art & Architecture of Nenbutsushu 仏教美術 兵庫県加東市
堂内
金箔二重貼り、六手先総詰組、屋根葺面積226.2㎡、総数16,000枚の瓦を使用した宮殿(高さ19m、幅19.98m、奥行12.36m)、 その中に在して、大慈悲の光明にて十方世界を照らすが如く輝きわたる本尊阿弥陀三尊佛は、中華人民共和国、工��美術大師・佘國平佛師制作の総高8.45mの木彫佛像です。
全世界 仏教徒の聖地 「佛教之王堂」念佛宗 総本山 無量壽寺 仏教美術の宝箱 故タイ法王猊下 世界各国の仏教最高指導者 並びに カンボジア王国 故ノロドム・シアヌーク国王陛下の御聖骨がお祀りされている寺院です。
佛教之王堂は佛法に基づいて建立され 建物全ての部位に、仏縁を結ぶ教えが込められています
伽藍工事全体、およそ7年間で10,524点の彫刻、450,173点を超える彫金が製作されました。
The Royal Grand Hall of Buddhism - Nenbutsushu Buddhist Sect of Japan The sacred place for all Buddhists in the world
The Royal Grand Hall of Buddhism 仏教美術の宝箱 Buddhist Art
https://buddhistart18.com https://www.tumblr.com/nenbutsushuart
念佛宗公式 Official
https://muryojyu.com
Buddhism has its origin in IndiaBuddhist cultures of China, Korea, and Japan are represented hereat the Royal Grand Hall of Buddhism. It is the first construction of an authentic full-scale Buddhist temple since the erection of the main temple of Obakushu Buddhist Sect in 1661.A total of roughly 3.5 million people joined forces to construct the Royal Grand Hall of Buddhism and completed the entire temple in only seven years without even a single accident.The Royal Grand Hall of Buddhism, in its vast precincts of over 180 hectares, has the Front Gate, the North Gate, the South Gate, the Main Gate, the Washstand, the Ksitigarbha Hall, the Prince Shotoku Hall, the Five-story Pagoda, the North Bell Tower, the South Bell Tower, the Main Halls including the Amida Hall and the Sakyamuni Hall and the Avalokitesvara Hall, the Sutra Hall, the Merit-transference Hall, the Okunoin Hall, the International Buddhist Conference Hall, the Sangha Hall, and the Main Building. All the buildings are decorated with 10,524 sculptures and statues and more than 450,173 metal carvings.
#念仏宗#念仏宗無量寿寺#nenbutsushu#the royal grand hall of buddhism#buddhist temple#仏教美術#art#buddhist statue#仏像#釈迦#woodcarving#Youtube
1 note
·
View note
Photo

ミュージアムは12/29〜1/3はお休みですが、屋外古墳エリアは自由に見学できます。 【歴史の里 しだみ古墳群】 「体感!しだみ古墳群ミュージアムSHIDAMU」 名古屋市守山区大字上志段味字前山1367 2022年12月29日(木) 屋外古墳エリアは大小8基の古墳が点在している広い公園となっていて親子連れが遊んでいたり、犬の散歩の人などが訪れています。 https://youtu.be/JWK-rvVzM6c ミュージアムは志段味古墳群の「SHIDAMI(しだみ)」とミュージアムの「MU(みゅー)」を組み合わせて「SHIDAMU(しだみゅー)」 SHIDAMIのホームページより SHIDAMU基本情報 ■開館時間:午前9時~午後5時(展示室への最終入室午後4時30分) ■休館日:毎週月曜日(祝日の場合は翌平日)、12月29日~1月3日 ■入館料:無料(展示室のみ有料200円 ※中学生以下無料) ■駐車場:乗用車101台、大型バス4台(特定のイベント時のみ有料) 『<歴史の里しだみ古墳群について> 「歴史の里しだみ古墳群」は、名古屋市の北東端に位置する守山区上志段味に集積する、墳形および大きさとも様々な「しだみ古墳群」と埴輪作りや勾玉作りといった古代体験や古墳群から出土した貴重な遺物を展示した「体感!しだみ古墳群ミュージアム」で構成されています。 現在、名古屋市内には、約200基の古墳が確認されていますが、このうち古墳が最も集中しているのが「しだみ古墳群」がある上志段味(かみしだみ)です。 上志段味は、岐阜県から愛知県へ流れる一級河川である庄内川が濃尾平野へ流れ出る部分にあたり、多くの古墳が点在することから志段味古墳群と呼ばれ、国の史跡に指定されています。 志段味古墳群は尾張戸神社が鎮座する市内最高峰の東谷山頂から山裾、庄内川に沿って広がる河岸段丘に東西1.7km、南北1kmにわたって分布しています。 4世紀前半から7世紀にかけて、古墳が築かれない空白期間をはさみながらも、長期にわたって古墳が造営されており、空白期間を境に4世紀前半から中頃、5世紀中頃から6世紀前半、6世紀後半から7世紀の3つの時期に分けることができます。その特徴は、全時期を通して、規模・形の異なる様々な古墳が、起伏の富んだ狭い地形に築かれており、「日本の古墳時代の縮図」と言えるところにあります。 墳丘の平面形や葺石の特徴、石英を用いた墳丘装飾、埴輪の形態・製法技法、墳丘上の祭祀行為、埋葬施設内の副葬品などから、古墳群の被葬者たちがヤマト王権と密接な関係にあったことがうかがえる貴重な古墳群であると言えます。』 #志段味古墳群 #志段味大塚古墳 #しだみ古墳群ミュージアム #SHIDAMU #帆立貝式古墳 (歴史の里 しだみ古墳群) https://www.instagram.com/p/CmxuLeJP15E/?igshid=NGJjMDIxMWI=
0 notes